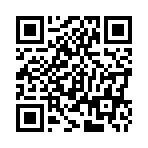2009年12月30日
海洋・沿岸域政策大綱 洋産業振興
急がれるわが国の海洋政策と海洋産業振興
―海洋産業を支える海洋情報インフラとは―
国土交通省海洋・沿岸域政策大綱 平成18年6月
目次
?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識
?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題
1.国際的な動向と課題
2.海洋及び沿岸域の現状と課題
?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進
1.海上における安全を確保する
2.国土の保全と防災対策を推進する
3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する
4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す
5.海洋・沿岸域の利用を推進する
6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する
7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する
8.国際社会との協調及び協力関係を確立する
9.施策を推進するに当たっての基本的考え方
?.施策の推進体制
?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識
我が国は、四方を海に囲まれた「海洋国家」であるとともに、典型的な「島嶼国」EEZ でもある。領海及び排他的経済水域( )の面積は国土面積の約12 倍にあたる約447万km2(うち領海は43 万km2)、海岸線の延長は約35,000km にも達する。日本人は、はるか昔から人や文化の往来、物の輸送、産業、生活等の分野において、海と深く関わってきた。
毎年7月の第3月曜日は、海の恩恵に感謝するとともに海洋国家、日本の繁栄を願う国民の祝日「海の日」と定められているが、そのことは、我が国が海洋とのつながりが特に深い国であることを示すものである。
一方、我が国の海洋・沿岸域を巡っては、海上交通の安全の確保、不審船、密輸・密航等の保安対策の強化、海上災害の防止、海洋汚染の防止、海岸等における防災対策の強化、海洋資源の開発の推進、海上輸送の安定化・活性化といった課題や、沿岸域や閉鎖性水域を中心とした、海岸侵食や砂浜等の消失、埋立等による藻場や干潟の減少、漂流・漂着ゴミの増大や減らない放置艇、赤潮や青潮の発生といった問題が山積している。
他方、国連海洋法条約(1994 年発効)及びリオ地球サミット(1992 年)以来、アジアを含む世界の各国では、「海洋・沿岸域の総合管理」、「持続可能な開発」といった考え方を背景に、海洋・沿岸域に関する様々な施策を総合的に実施するための制度的枠組みを整えて、海洋政策に積極的に取り組むとともに、そうした制度体系を有する国々が連携、協働する流れが強まっている。
このような状況を踏まえ、近年、海洋・沿岸域に関する法制の強化が図られており、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の制定や、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の改正等とともに、「国土形成計画法」において、国土の形成を推進するための総合的かつ基本的な計画である国土形成計画の計画事項として「海域の利用及び保全」が明記され、海洋を貴重な国土空間として位置付けることとしたところである。
海洋・沿岸域を巡る様々な問題や課題は、それぞれが独立で存在するのではなく、相互に関係がある場合が多いことから、こうした問題や課題に取り組むためには、関連する施策を総合的に進めていくことが必要である。
このような観点から、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、海洋・沿岸域に関する施策を総合的に推進していくべく、2004 年9 月に、省内に関係部局の長を構成員とする「国土交通省海洋・沿岸域政策連絡会議」を設置し、海洋・沿岸域政策のあり方について検討を重ね、今回、「国土交通省海洋・沿岸域政策大綱」をまとめた。
国土交通省としては、今後、この大綱に基づき諸般の施策の総合的な推進を図る。
?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題
海洋とは一般には広々とした海を意味するが、この大綱においては、我が国の主権が及ぶ領海(内水を含む)並びに。主権的権利及び管轄権を有する排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚を海洋としている。
我が国は、太平洋の最北西部に位置し、オホーツク海、日本海及び東シナ海という3 つの半閉鎖海と太平洋に囲まれた弧状列島によって構成され、我が国の主権並びに主権的権利及び管轄権が及ぶ水域の面積は447 万km2(領海の43 万km2を含む。)と世界で第6位ともいわれる広さとなっている。また、離島が北方から南方まで広範囲にわたって6,847 島も分布しており、我が国の領土、領海、排他的経済水域等の保全、自然環境の保全等に重要な役割を担っている。
また、この大綱では、海岸線を挟む陸域及び海域(主に内水及び領海を念頭。)の総体を沿岸域としている(なお、この大綱では、海洋と沿岸域を総称して「海洋・沿岸域」としている。)。沿岸域は、水圏、地圏及び気圏の交わる空間であり、洪水、高潮、津波等の自然の脅威にさらされるとともに、自然の微妙なバランスの下、優れた景観や多様で豊かな生態系が形成される等貴重な資源と言える一方、産業、交通、物流、観光、レクリエーション等の様々な利用の要請が輻輳していると言える。
海洋・沿岸域については、未知の分野も多く、基礎となるデータや知見等が十分ではないと言われていることから、今後、更に調査や研究を継続的に進め、それを施策に反映させていくことが重要である。
1.国際的な動向と課題
(1) 各国の取組
1992 年の地球サミット(ブラジル、リオデジャネイロ)でのアジェンダ21 の採択と1994 年の国連海洋法条約の発効以降、アジアを含む世界各国では、海洋の持続可能な開発の推進の動きが進む一方、排他的経済水域や大陸棚等の海洋における自国の権益の確保のため、「海洋の囲い込み」という考え方が広まっており、これらが相まって、総合的な海洋政策の策定等の取組が積極的に進められている。
米国においては、2000 年に海洋法2000 を制定し、同法に基づき海洋政策審議会を設立している。2004 年には、同審議会において報告書「21 世紀の海洋の青写真」を策定し、議会及び大統領に提出した。同報告書は、持続可能性や生態系に基づく管理等を原則とし、政府の海洋管理体制の改善や、研究、観測及び教育の強化等広範にわたり、212 項目の具体的な勧告を行うものである。
これを受け、同年、具体的に実行するための行動計画として、「米国海洋行動計画」を策定した。
一方、沿岸域においては、沿岸域管理法(1972 年)に基づき、沿岸域に接する州が沿岸域管理計画を作成した場合、連邦政府がその推進を支援することとしている。
アジアにおいても中国、韓国が総合的な海洋政策の策定及び実施に力を入れている。中国では「中国海洋アジェンダ、21」(1996 年)を制定し、海洋資源の合理的かつ持続的な利用、海洋経済の一層の発展を促進すること目指している。
2002年には海域使用管理法を制定し、海域の国有を前提として、ゾーニング制度の導入、海域使用権の創設と競争入札制の導入、海域使用料の徴収等について規定し、持続可能な開発と海域管理を推進している。韓国では、先進海洋大国の実現を目指し、沿岸域管理、海洋環境保護、水産等を所掌する海洋水産部を設置し、海洋基本戦略「海洋コリア21」(2000 年)を策定しているほか、海洋水産発展基本法(2002 年)や沿岸域管理法(1999 年)を制定し、海洋管理に関する諸施策を進めている。
以上のほか、東アジア諸国においては、タイが「タイ国家海洋政策」を2003年に策定したほか、インドネシアが沿岸域管理法を、また、マレーシアが国の沿岸域管理政策を、それぞれ策定中である。また、他の地域でも、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、南アフリカ等多くの国が同様の取組みを行っている。(表参照)
(2) 海洋秩序の維持
2001 年の同時多発テロを受け、2003 年5 月、米国からPSI(大量破壊兵器、ミサイル及びその関連物質の拡散に対する安全保障構想) が提案された。現在、日1)本をはじめ60 カ国以上がPSI 活動を支持しており、参加国が共同して取り得るこれらの移転及び輸送の阻止のための海上訓練を合同で行う等多国間連携が行われている。
2005 年10 月にはSUA 条約(海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約) が改正され、犯罪に関与している疑いのある他国籍船舶への公海上2)での乗船や捜索が可能になるなど、ますます国際機関によるテロ防止対策も進んでいる。
また、東南アジア周辺海域における海賊等の多国間にまたがる海上犯罪等については、現在、各国が連携、協力し、これに取り組んでいるが、全ての沿岸国海上法執行機関が、組織、勢力、技術等の面で充分な状況にあるとは言えないため、我が
国からの支援が強く求められている。
一方、近隣諸国の海洋政策上の戦略が我が国周辺海域で競合し、日本海、東シナ海等多くの海域で排他的経済水域の境界が未だ画定していない。
その他にも東シナ海における日中地理的中間線付近における資源開発問題や中国人活動家による尖閣諸島における領有権主張活動、日本海においては竹島問題など我が国の海洋権益を脅かす問題が山積しており、これらに対する厳正かつ適切な対応が求められている。
2.海洋及び沿岸域の現状と課題
(1) 海上交通
? 貨物輸送
エネルギーの93 %(2004 年)及び食料の60 %(2004 年)を海外に依存する我が国においては、輸出入取扱貨物量の99 %以上(2004 年、重量ベース)を海上輸送に依存し、工業製品の輸出や食料及び資源の輸入等の貿易が我が国の経済及び国民生活を支えており、海上輸送は我が国の共通利益となる「物流生命線」であると言える。
全国の津々浦々に1,070 の港湾が配置され、港湾で取扱われている貨物量は、外貿は12 億トン強で、内貿は19 億トン強(2004 年、フレートトン)となっている。
外航海運についてみると、我が国の海上貿易量の世界に占めるシェアは15.7 %(2003 年)であり、中国、アメリカ合衆国に次いで世界第3 位となっている。
外航海運は、各国の経済情勢、さらにはテロや紛争等による影響を受けやすく、安定的な輸送の確保が課題となっている。
また、内航海運は、国内貨物輸送のうち約39 %(2003 年度、トンキロベース)を担っており、我が国の経済や国民生活を支える鉄鋼、石油等の産業物資については、その約8 割を輸送している。営業用トラックと比較してエネルギー効率のよい輸送であり、環境面で優れている一方で、供給面での機動性を欠くため、市況変動による輸送需要の変動に対応しにくく、船腹需給ギャップが生じやすい構造となっている。
? 旅客輸送
旅客輸送は、外航定期航路が15 航路で約45 万6 千人(2004 年、日本人のみ、対前年35.9 %増)、内航旅客が1574 航路で約1 億90 万人(2004 年、対前年6.0 %減)となっている。内航旅客のうち離島航路については、島外との連絡について私的交通の利用が容易でない離島住民の足として必要不可欠であるため、約3 割を公営及び第三セクターが運営しているが、経営状況は厳しく、航路の維持及び改善が課題となっている。
(2) 海上の安全及び海洋汚染
? 海難事故
我が国周辺海域において、救助を必要とする海難に遭遇した船舶(要救助船舶)の隻数は、2001 年から2005 年までの年平均で2,086 隻(死者及び行方不明者167 人)であり、それ以前の5 年間の年平均1,877 隻(同170 人)と比べ11 %増加しているものの、死者及び行方不明者数は約2 %減少している。
また、死者及び行方不明者のうち、約54 %が漁船、約18 %がプレジャーボート及び遊漁船によるものである。これら国民の人命、財産にかかる海難事故への対応として、海難防止のための諸施策を推進するとともに、沿岸海域におけるより迅速かつ的確な人命救助体制の充実強化を進めていくことが重要である。
特に、近年、40 ノット程度の高速で運航する超高速船(ジェットフォイル等)が航行中に障害物と衝突したとみられる事故が多発しており、多数の負傷者を出すケースもあることから、超高速船の安全運航の確保に係る方策の検討が喫緊の課題となっている。
? 海洋汚染及び海上災害
2005 年、海上保安庁は、海上における油、廃棄物、赤潮、青潮等の海洋汚染の発生を360 件確認している。また同庁が防除措置を実施した油排出事故は116 件あり、そのうち影響の大きいタンカーは8 件であった。また船舶火災が118 件発生したが、そのうち約66 %が漁船である。
また、港湾局では、海域環境を整備する日常の業務として、清掃兼油回収船により、日々、漂流3)油、流木、漂流ゴミ等を回収しており、その量は年間約8,000m3(2003 年から2005 年の平均)にのぼる。このような海洋汚染や海上災害の未然防止及び対処能力をより向上させることが必要である。
? 海上テロ及び海賊対策
2001 年9 月に発生した米国同時多発テロ事件発生以後、2002 年10 月には、イエメン沖においてフランス籍タンカー爆破事件が発生する等海上においてもテロが続発している。幸いにして我が国では発生していないものの、依然として我が国を巡るテロ情勢は予断を許さない状況である。
今後とも海上におけるテロの未然防止及び海上における公共の安全と治安維持に万全を期すため、国内外の関係機関と連携し、水際での間隙のない体制を構築、強化することが必要である。
また、2005 年の全世界における海賊事件の発生件数は276 件、そのうち東南アジアにおける発生件数は122 件となっている。これらは減少傾向にあるものの、2005 年3 月に発生した日本籍船舶「韋駄天(いだてん)」が襲撃された事件など、依然として誘拐等の凶悪な海賊事案が発生していることから、引き続き国内外の関係機関との連携や協力関係の強化が必要である。
? 海上犯罪
2005 年の海上保安庁による海上犯罪の送致件数は、6,256 件であり、2004年と比べ、1,395 件の増加となっている。その中でも、暴力団や悪質業者が関与する等組織的かつ広域的な海上環境事犯、我が国の水産資源を枯渇させ、地域経済にも大きな打撃を与えかねない組織的な密漁事犯や外国漁船による不法操業事犯の件数が増加している。
また、我が国周辺海域では、麻薬、覚せい剤等の密輸事犯や不法入国事犯等の国際的な組織犯罪も依然として後を絶たず、ますます悪質かつ巧妙化している。
これら海上犯罪を阻止するために、監視取締り体制の強化を図るとともに、国内外の関係機関との連携強化や各種対策に取り組むなど、海上犯罪対策の徹底を図る必要がある。
(3) 港湾及び航路
周囲を海に囲まれ、臨海部に人口、資産等が集積する我が国において、港湾及び航路は、物流や人流を支え、国民生活の向上や産業活動の発展に大きな役割を果たしている。国際社会と我が国の緊密な関わりの中で、我が国の経済安全保障を実現するためには、より一層の海上輸送の機能強化、安全確保を図ることが極めて重要である。
我が国港湾においては、引き続き物流改革を推進していくとともに、国際海上コンテナ輸送量の増大や船舶の大型化等に適切に対応しつつ、現在進めているスーパー中枢港湾プロジェクトにおいて、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現に向けた港湾整備を図ることや、関係機関と連携、協力した水際対策等危機管理体制の強化を行うこと等が喫緊の課題となっている。
国際海上輸送及び国内海上輸送を担う一連の航路において、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、関門海峡等では、航路や船舶航行が輻輳した湾口部や海峡部等が存在し、海上輸送の要衝、隘路となっている。このような場所で海難事故が発生すれば、長期にわたり航路が閉鎖する可能性が高く、その影響は我が国全体の国民生活や経済産業活動に重大なものとなる。
このため、我が国の経済安全保障を実現するため、船舶の航行水域管理のあり方や国と地方の役割分担について検討
を進める必要がある。
(4) 海洋に関するレクリエーション
海洋に関するレクリエーションには、プレジャーボート(モーターボート、水上オートバイ、ヨット等)、サーフィン、ダイビング、釣り等の「スポーツ型」、海水浴、潮干狩り、水族館等の「リゾート型」のほか、客船等によるクルーズ等がある。
これらの参加人口は、2003 年で海水浴1,890 万人(1995 年:3,000 万人)、釣り1,470 万人(同1,850 万人)、潮干狩り224 万人(同461 万人)、モーターボート及びヨット100 万人(同110 万人)であり、いずれも減少傾向にある。
また、プレジャーボートの保有隻数は、1995 年度の39.8 万隻(モーターボート30.0 万隻、水上オートバイ8.5 万隻、ヨット1.3 万隻)から増加し、1999 年度には43.8 万隻(同32.2 万、10.3 万、1.3 万隻)となったが、これをピークに減少し、2004年度は36.5 万隻(同26.8 万、8.5 万、1.2 万隻)となっている。また、小型船舶操縦士免許保有者数は、2005 年度末で303 万(1995 年度:226 万人)と年々増加している。
一方で、放置艇及び沈廃船の隻数は年で万隻( 年: 8万隻、河川区域含む。)にものぼっており、船舶航行や漁業活動への支障、流水の阻害、津波及び高潮時における艇の流出による被害、景観悪化等の問題が顕在化している。
(5) 鉱物及びエネルギー資源
我が国の領海、排他的経済水域及び大陸棚の海底や海底下には、鉱物資源や、石油、天然ガス、メタンハイドレートといったエネルギー資源の多量の埋蔵が確認されている。また、風力発電や海洋温度差発電といった新エネルギーの可能性も広が
っており、これらの開発及び利用の推進が、将来の我が国の経済活動にとって重要になっているとの指摘がなされている。
(6) 海岸
? 海岸の概要
島国であり、入り組んだ海岸地形をもつ我が国は、約35,000km もの海岸線を有しており、海岸の重要性は特に大きいものがある。
海岸は、自然海岸、半自然海岸及び人工海岸に分類されるが、1960 年当時、8割を占めた自然海岸が、現在は53 %にまで減少しており、半自然海岸が13 %、人工海岸が34 %となっている。
? 海岸侵食
海岸の砂浜は、河川における砂利採取、河川横断工作物の設置等による土砂供給量の減少及び各種構造物の設置等による沿岸方向土砂の流れの変化など、様々な要因により、全国各地で侵食が生じている。また、海砂利採取による侵食も懸念されている。近年は海岸侵食が早いペースで進行(1908 〜 1978 年:72ha/年→ 1978 〜 1992 年:160ha/年)しており、砂浜の減少が、利用空間の減少とともに海岸の景観や生態系を大きく変化させている。
? 災害と防災対策
我が国は、台風の常襲地帯にあり高潮が頻発し(2004 年:27 回)、地震多発地帯で津波の来襲も多い(2004 年:4 回)など、厳しい地理的、自然条件下にある。
また、海岸侵食も全国的に顕在化してきており、放置すれば貴重な国土が失われることから、その保全は極めて重要である。この他、地球温暖化により、今後100年間で海面が9 〜 88cm 上昇するとの予測もある(IPCC(気候変動に関する政府間パネル)による。)。
一方、防災対策としての海岸保全施設は、2004 年度末時点で要保全海岸延長の62 %に設置されているが、このうち約18 %が想定津波高より低く、また、約30 %が想定津波高との比較調査が行われていないほか、施設の老朽化も進んでいる。
? 海岸漂着ゴミ
海岸漂着ゴミは恒常的に発生しているため、景観の悪化や生態系への影響等が生じている。発生起源としては、海域から漂着したもの、河川から流出したもの及び陸域から持ち込まれたもの等であり、近年では海外からと思われる漂着ゴミも日本海側の海岸を中心に確認されている。今後、海岸漂着ゴミへの対応を強化するとともに、関係諸国とも協調、連携した取組を推進することが課題となっている。
(7) 沿岸域の利用状況
現在、国土面積の約3割を占める沿岸に位置する市町村には、総人口の約5割が集中しており、特に東京湾、伊勢湾、大阪湾の沿岸は、全国平均の約10倍もの人口密度となっている。
これらの三大湾と瀬戸内海は、海上交通、工業、物流、エネルギー、港湾、商業、水産業、レクリエーション、観光等で稠密に利用されている。産業の面でも沿岸に位置する市町村の工業製品出荷額は全国の約5割、商業年間販売額は全国の約6割を占める状況となっている。
近年まで、臨海部に集積する重厚長大型産業の移転、縮小等により産業の空洞化が進んでいたが、景気の回復、海外進出企業の国内回帰、物流の高度化等により、臨海部への企業進出が進み出しつつある。
(8) 沿岸域の環境
? 沿岸域に関する水質
我が国では、陸域からの汚濁負荷削減、海域における自然環境の再生や創出等を行い、海域の水質の改善に取り組んできた結果、COD の環境基準の達成率が2004 年で75.5%となっている。
しかし、内湾、内海等の閉鎖性水域では依然として達成率が低くなっており(東京湾63.2 %、伊勢湾50.0 %、瀬戸内海67.3 %)、赤潮や青潮の発生等も見られる(2003 年で東京湾59 件、伊勢湾60 件、瀬戸内海106 件の赤潮が発生)。
? 沿岸域に関する生態系
日本の海洋・沿岸域は、海流の特徴や南北に長い列島の影響により、多様な環境が形成され、同緯度の地中海や北米西岸に比べ豊富な生物相が形成されている(例:海産魚類約3,100 種、藻類約5,500 種)。しかしながら、浅海域では埋立等により藻場や干潟が減少(例:1945 〜 1994 年に4 割の干潟が減少)しているほか、琉球諸島等で海水温の上昇等によるサンゴ礁への影響が懸念されている。
河川及び海洋・沿岸域は、多くの生態系が重なり合って形成されており、特に川と海の接点である汽水域は、沿岸域の中でもすぐれた貴重な生態的価値を有している。
このため、アサリの稚貝やサンゴの幼生の移動等を踏まえた広域的な取組が必要であること、東京湾等の閉鎖性海域を一体として保全することが必要であること、関係者が情報を共有するとともに、科学的な解明を着実に推進し、実現可能な改善策を漸進的に実行する必要があること等が指摘されている。
(9) 沿岸域の総合的な管理
沿岸域に関する課題を解決するためには、沿岸域を自然の系として適切にとらえ、沿岸域の総合的な管理計画を策定し、各種事業、施策、利用等を総合的、計画的に推進することが重要であるとの考え方から、2000年に関係17省庁が「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」を策定し、これに基づきケーススタディ等を行ってきたが、全国的には進んでいないのが現実となっており、このような沿岸域の総合管理の推進をいかに図るかが課題となっている。
?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進
以上のような我が国の海洋・沿岸域を巡る現状及び課題を踏まえると、我が国として海洋・沿岸域に関する施策を総合的かつ戦略的に実施する必要がある。
このような中で、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、以下に掲げる施策を推進していくこととする。
1.海上における安全を確保する
? 海上交通の安全を確保する
海上輸送量の増大や船舶の大型化に対応した安全に航行できる船舶航行水域の確保、航行支援システムの構築、航路標識等の整備、海難事故の分析等を推進するとともに、安全上問題のある条約不適合船(サブスタンダード船)を排除するための措置を行い、海上交通の安全を確保する。
また、ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、事後チェック機能の強化等を図る。
○ 船舶の安全な航行を支援するため、航海用海図の作成や更新、電子海図の整備と普及、航路標識の高機能化、沿岸域情報提供システムの拡充、地震や津波に関する情報の迅速な提供等を推進するとともに、(船舶自動識別装置) AIS を活用した次世代型航行支援システムの構築、航空レーザー等を用いた浅海域の情報の整備、海洋短波レーダー網、(全地球測位システム)波浪計等も活用したGPS的確な漂流予測、航行ルートの選定等を推進。また、衝突回避に必要な他船舶の動向等を的確に表示するINT-NAV(先進安全航行支援システム) の調査研究を推進。
○ 船舶が安全に航行できる環境を確保するため、大型船舶に対応した航路水深の確保、障害物の除去、防波堤の配置等を図るとともに、開発保全航路の指定範囲の拡大や開発保全航路と港湾の間の水域の措置等を行い、これを促進。また、荒天
時に船舶が避難できる避難港の整備を図るとともに、無害通航の外国船舶が我が国の領海内において安全に航行できるよう可航水域を確保。
○ サブスタンダード船の排除等を推進するため、IMO(国際海事機関)加盟国監査を促進するとともにPSC ポートステートコントロールを的確に実施
○ ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、運航労務監理官による監査等の事後チェックの強化を図るとともに、ILO(国際労働機関)海事労働条約の批准に取り組む。
○ 船舶の大型化等が進展する中、海上交通の一層の安全を確保するため、水先人に係る等級別免許制の導入や免許更新要件の見直し等の水先制度改革を実施。
○ 海難事故の再発防止を図るため、海難の調査及び分析に基づく、積極的な勧告や提言を実施。
? 海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する
テロ関連情報の調査、分析体制の整備、海上及び港湾における警備体制を強化するとともに、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施し海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する。
○ 海賊及び海上テロを含む海上における不法行為対策について、アジア海上セキュリティ・イニシアティブ( ) 等に基2004 AMARSECTIVE2004 づき、関係国海上保安機関に対し海上犯罪取締り能力向上のための支援を実施。
○ 国際航海船舶及び国際埠頭施設の保安措置が適確に行われるよう、実施状況の確認や人材育成等を図り、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施するとともに、船舶接岸情報の活用、港湾施設への出入管理の高度化、内航も含めた旅客ターミナルの保安施設整備等を進め、船舶及び港湾の保安対策を強化。
○ 国が港湾施設管理者や税関等の関係機関と協働体制をとり、港湾の利用船舶に関する情報を収集して分析し、問題船等が明らかになった場合、警察機関への通報や港湾施設管理者に警戒指示を行う体制を整備。
○ 臨海部の原子力発電所、石油備蓄基地、米軍施設等の重要施設に対する警備やテロ情報調査体制を強化。
? 事故及び災害等対応の体制を強化する
船舶の衝突や乗揚事故による油の排出、有害液体物質や危険物の流出、火災等の船舶の事故による災害、原子力発電所等のエネルギー施設の事故による災害、台風や津波等の自然現象による災害等の多様な事故及び災害に迅速かつ的確に対応するとともに、地震等に伴う経済的損失の低減を図るため海上からの輸送を確保する体制を強化する。
○ ヘリコプターの機動性、高速性等を活用した機動救難体制の充実強化に努めるほか、特殊な海難への対応体制の強化、救急救命士の養成、洋上救急体制の充実等により救急救命体制を強化。
○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制や臨海部の施設の安全監督体制を一層強化するとともに、OPRC-HNS 議定書(2000 年の危険物質及び有害物による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議定書) に対応した体20)制を確立。
○ 大規模災害対応として、物流と人流の両面における海上−港湾−陸上を結ぶ輸送を確保する広域的な連携、協働体制を確立。
? 海上保安業務体制の充実を図る
海上における総合的な安全及び法秩序を確保するため、海上においてその実態を把握、監視し、直接施策を実施する海上保安業務体制の充実を図る。
○ 巡視船艇、航空機の老朽化や旧式化による業務上の支障の早期解消を図るとともに、海洋権益の保全、沿岸水域の警戒監視体制の構築、大規模災害等に対する救助体制の強化等の新たな業務課題に対応するため、老朽巡視船艇、航空機等の
緊急かつ計画的な代替整備を推進。
○ 携帯電話からの118 番通報による位置情報、コスパス・サーサット捜索救助衛星システムによる遭難警報、船舶に搭載された等から得られる我が国周 ?AIS辺海域の船舶動静情報等を、海上保安庁が保有する各種の情報と横断的に照合で
きるシステムを構築し、救難即応体制、海難防止対策等を向上。
2.国土の保全と防災対策を推進する
? 国民の生命や財産を保護する
安全性の確保が不十分な地域において引き続き防災や減災に取り組む。その際には、施設の耐震化、津波や高潮の予測をより正確かつ迅速に分かりやすく伝達する仕組みや、土地利用施策等の多様な対策を含めた総合的な取組を行う。
○ 海岸保全施設の重点緊急点検結果を受けた、壊滅的な被害が生じるおそれがある海岸における被害防止対策をはじめ、水門の自動化や遠隔操作化、堤防護岸の破堤防止、ハザードマップ作成支援等ハードとソフトが一体となった総合的な津波、高潮(ゼロメートル地帯)対策を推進。
○ 東海・東南海・南海地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による津波被害が想定される沿岸域やゼロメートル地帯における耐震性が十分でない海岸保全施設(堤防、護岸等)の耐震対策を推進。
○ 海岸ごとに潮位、波高、打ち上げ高等を的確かつきめ細かに予測する高潮情報システムの構築、津波警報の一層の迅速化及び精度向上、津波、高潮、高波に関する情報提供の充実や共有化を推進し、防災機関等での情報共有の高度化を推進。
○ 地震発生の予知に寄与する海底地殻変動観測や活断層の調査を実施するとともに、大規模地震に伴う津波の挙動を明らかにするため、津波シミュレーションを実施。また、海域火山活動の監視を行い、船舶航行や漁業活動等に関する災害の防止
を推進。
○ 津波時の放置プレジャーボートの陸への乗り上げ等の防止として、一般海域を含めた係留施設の台帳管理の徹底、係留施設の指定等を実施。
○ 大規模地震発生時の避難者や緊急物資の円滑な輸送の確保に資する港湾施設の耐震化とともに、海岸保全施設の耐震性を短時間かつ低コストで判定可能な「チャート式耐震診断システム」の開発を推進。
○ 地震や津波等の災害時における、海上からの住民の避難や物資輸送等を支援するため、沿岸域における防災情報図の整備を推進。
○ 東京湾及び大阪湾臨海部等において、基幹的広域防災拠点を整備するとともに「道の駅」の防災拠点化を推進。
○ 減災対策として、道路利用者への情報提供、避難路の整備及び救援活動や物資輸送を行う上で重要な役割を果たす緊急輸送道路の確保のため、道路橋の耐震補強や高規格幹線道路ネットワークを整備。さらに、被災を受けた道路について、障害物の除去や応急復旧等の迅速な啓開を実施。
○ 津波被害リスクのある地域において、生命や財産を守るため、津波防護機能を持ち合わせた防波堤の整備を推進。
○ 災害体験の継承、防災知識の蓄積や普及に必要な分かりやすい教材の作成、これらを多くの住民に分かりやすく伝えられる人材の育成、緊急時に備えた体制の構築と防災訓練を推進。
○ 海岸侵食や津波、高潮に対する沿岸域の安全性の低下を防止、軽減するため、関係者間の連携等の仕組みを構築。
? 国土を保全し、領海及び排他的経済水域等の海洋権益を確保する
海岸侵食等の対策を行うことや、外洋域における離島の交通、情報通信やエネルギー供給等に係る基盤の確保等に関する取組により、国境離島をはじめ、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の基線となる国土の保全を図るとともに、日本周辺海域についての適正な海図の作成のための調査や大陸棚の限界画定のための調査、的確な監視警戒等を行い、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の海洋権益の確保を図る。
○ 離島、奄美群島及び小笠原諸島において、交通基盤、産業基盤、生活環境、防災及び国土保全に係る施設等の整備や離島航路の維持及び改善に対する助成、産業や観光の振興、国内外との交流の促進、人材育成の支援等ソフトとハードを一体的に実施する総合的な施策を推進。
○ 我が国の領海及び排他的経済水域等を確保する上で、重要な拠点である国境離島に対して、万全な国土保全を推進するとともに、海象観測の実施等その活用を推進。
○ 大陸棚の限界画定のための調査等の推進や、国境離島の位置情報基盤の整備を推進。また、侵食対策等の海岸の適切な維持及び管理に資する低潮線の調査を実施。
○ 排他的経済水域が画定していない日本海、東シナ海等における海底地形や地質等の情報基盤を整備し、適正な海図の作成を推進。
○ 東シナ海等において顕在化している我が国の海洋権益に関する問題への対応として、機動力や監視能力等に優れた巡視船、航空機等を整備し、厳正かつ的確な監視警戒を実施。
○ 外国漁船による不法操業に対して、特に外国漁船が多数操業している日本海、東シナ海への巡視船艇や航空機の配備等により、効果的かつ厳正な取締りを実施。
3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する
? 海洋・沿岸域のモニター体制を強化する
継続的に海流、海水中の汚染物質、海底地盤の状況、気象、漂流・漂着ゴミ等に関する基礎データの整理、提供体制の強化等を実施し、海洋・沿岸域環境のモニター体制を強化する。
○ 国土交通省における海洋や沿岸域に関する各種情報の収集、整理、提供体制の強化を図るとともに、海域環境の順応的管理に資する波浪、潮位、水深、水質、底質等の効率的なモニタリングを行うことで、海洋や沿岸域のモニター体制を強化。
○ 地球環境に関連した海洋現象を総合的に診断し、「海洋の健康診断表」として提供。
○ 海岸を活動の場としている市民、NPO との協働により、海岸環境に関する情報の広範かつ継続的なモニタリング体制を構築。
○ 排他的経済水域や大陸棚から沿岸域までの海岸線、低潮線、海底地形、地質等の情報基盤を整備。
? 海洋汚染等に対する的確な対応を推進する
大規模油流出、漂流ゴミ、放置座礁船、流出流木及び大型構造物の漂流等が、環境や安全上の支障をきたす等の問題に対し、未然防止対策の推進及び漂着前後それぞれにおける積極的な防除の仕組みの構築等を図る。
○ 油や有害危険物質の流出、放置座礁船等による海洋・沿岸域の汚染に適切に対処するため、領海を越え、場合によっては公海上であっても大型油回収船、巡視船等を迅速に派遣する等国境を越境する海洋汚染について、積極的な防除の取組を推進するための体制等の強化や、保険や基金による被害者保護への的確な取組を実施。
○ 油流出事故が発生した際に迅速かつ的確な油防除措置等の実施に資するため、適切な漂流予測を実施するとともに、沿岸海域の自然的、社会的情報等をデータベース化した沿岸海域環境保全情報の整備を推進。
○ 漂流・漂着ゴミについて、関係省庁と連携して、その処理(回収、処分)、発生源対策を推進。
○ 海洋環境保全講習会や訪船指導等により、漁業者、海事関係者に対して海洋汚染の防止のための指導及び啓発を実施。
? 脆弱な海域の保護及び保全を推進する
船舶からの汚染を防止する必要性が高い海域を、海上輸送を確保しつつ、保護及び保全する。
○ 生態学的又は科学的理由により船舶からの汚染を防止する必要性の高い海域に対し、海上輸送を確保しつつ、これを未然に防止するための措置を導入。
4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す
? 海洋・沿岸域の自然環境を回復させる
埋め立て、沿岸構造物の設置、海岸の消失等により失われた自然環境の回復を図るため、干潟や藻場、サンゴ礁、湿地等の保全と再生、修復を図る。また、ヘドロ、ごみ、ダイオキシン等の有害物質等の堆積、埋立用材及び骨材の採取による深掘等により、元の生態系が失われた海底環境について底質環境を改善する。
○ 流砂系及び漂砂系の連続性を確保し、流入土砂による航路埋没、海岸侵食等の課題に対処するため、関係機関が協働して流砂系及び漂砂系における総合土砂管理を推進する体制を構築。
○ 埋立造成地、工場等からの土地利用転換地、廃棄物の埋立処分地等における緑地、湿地、干潟等の自然空間の再生や創出、砂浜、藻場、サンゴ礁等の回復、底質環境の改善等による自然環境の再生を推進。
○ 珊瑚付着型のブロックや干潟の再生に関する技術開発を推進し、港湾整備等への反映を推進。
○ ダイオキシン類等の有害化学物質による底質汚染の対策を推進。
○ 青潮等の原因とされる深掘跡の効率的な埋め戻し等を実施するため、浚渫土砂等の需給や品質を調整するシステムを構築。
? 海洋・沿岸域の自然環境及び景観の維持及び保全を図る
自然海岸や砂浜、干潟等の生態系への影響を最小化するため、十分な事前環境調査等を行い、沿岸域構造物と環境及び景観との調和を図る。また、多くの海岸で見られる漂着ゴミや放置されている船舶等を処理することや、船舶からの排出ガスの削減等により、自然環境及び景観の維持、保全を図る。
○ 人工海岸の整備、構造物の設置等に際して、環境との調和を一層重視し、石積堤や緩傾斜護岸等自然と共生する取組を実施。
○ 沿岸域にゴミが異常に漂流、漂着し、これを放置することにより船舶航行への支障、海岸保全施設の機能阻害、海岸環境の悪化等が生じているため、実効的な対策を推進。
○ 廃船(繊維強化プラスティック製廃船)の環境に優FRP しい処理と、FRP 廃27)船の不法投棄、放置艇の沈廃船化等の問題に対処するため、FRP 廃船のリサイクルシステムの普及を推進。
○ 海域への廃棄物不法投棄、汚水の不法排出等の海上環境事犯に対し、関係機関と悪質事業者等に係る情報共有体制を構築し、監視取締体制を効率化するとともに強化。
○ 船舶に石油類等を積み出す際に放出されるVOC(揮発性有機化合物質) 対策を実行していくため、放出規制港湾の指定や港湾における排出ガス処理施設の整備を促進。
○ 港湾に係留中の船舶に陸上側施設から電力を供給することで、船舶のアイドリングストップを推進。
○ 沿岸部における魅力ある空間の整備を推進、支援するため、海岸景観形成ガイドラインを踏まえた防災や利用と調和した良好な海岸景観形成を推進するとともに、景観計画の策定等景観法の制度活用について地方公共団体への助言を実施。
? 水質の保全及び回復を図る
下水道の整備及び河川の直接浄化による陸域からの汚濁負荷の削減並びに水質浄化能力を有する干潟や藻場の保全、再生等を行うことにより、依然として閉鎖性水域において、赤潮や青潮が発生している状況を改善する等水質の保全及び回復を図る。
○ 水質改善が進まない三大湾等の閉鎖性海域を中心に、「全国海の再生プロジェクト」として「海の再生」に向けた各種施策、海底の汚泥除去や覆砂による溶出抑制等の海洋・沿岸域の水質改善対策、合流式下水道の改善や高度処理の推進、河川浄
化対策、環境モニタリングを、一層、総合的かつ効果的に推進。
○ 東京湾、大阪湾以外の閉鎖性海域についても、順次再生行動計画の策定に向けた取組を推進。
5.海洋・沿岸域の利用を推進する
? 海上輸送の安定化・活性化を図る
外航海運について、適切な競争環境の確保等により、高質かつ効率的な輸送サービスを安定的に提供できる体制を整える。また、内航海運の経営基盤の強化等により、新造船舶への適切な代替を推進し、内航海運の活性化を図る。
○ 我が国商船隊による安定輸送を確保するための方策の充実・強化。
○ 経済効率、環境、安全等の課題を解決する新技術の開発と実用化を支援する枠組みを創設するとともに、環境問題への対応等社会的要請に応えることのできるスーパーエコシップの普及を促進。
○ 中小零細の多い内航海運事業者のグループ化、協業化を促進し、経営基盤を強化。
? 海洋・沿岸域の経済活動を活性化させる
貿易構造や荷役形態の変化に伴う陳腐化した施設や水際線を有する付加価値の高い低未利用地について、物流拠点や国際競争産業等の立地を推進する等有効利用すること等により、沿岸域の経済活動の活性化を図る。
○ 沿岸域の低未利用地に物流や国際競争産業等新しい機能立地を促し、それに併せて拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路の重点的な整備や、高度成長期時代の老朽化した運河や水路、護岸、防災・減災施設等のリニューアルを推進。
○ 「みなとオアシス」のような交流の場の形成を支援し、多目的拠点としての活用を推進。
○ 沿岸域における公共水域や港湾施設等既存ストックの適正かつ安全な活用促進に資する地域の取組に対し、フィージビリティの調査や規制等との調整等を実施し、これを支援。
? 海洋・沿岸域の新たな利用を推進する
新規航路の開拓、メガフロート等を活用した洋上発電や大陸棚海洋資源開発基地及び中小ガス田の活用を可能とする新たな輸送システムの構築等海洋の新たな利用を、技術の開発動向を踏まえ推進する。
○ 「リサイクルポート」の形成により、海上輸送による効率的な静脈物流ネットワークを構築し、循環資源の広域的な流動を促進。
○ 環境負荷の少ない内航海運による輸送への転換を促進するとともに、沿岸域ネットワーク、島や海の魅力を気軽に楽しむことができる国内旅客航路を活性化。
○ 拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路を重点的に整備。
○ 中小ガス田の活用が可能となるよう、NGH(天然ガスハイドレート)輸送船を活用した新たな輸送システムを構築。
○ 海洋における風力、海洋温度差等による発電といった新エネルギーの活用に向けた洋上発電プラットフォームや大陸棚海洋資源開発基地として、メガフロートの活用を推進。
? 海洋・沿岸域の利用に関する技術の開発等を推進する
環境修復や侵食防護、高潮や津波への対策、耐震性診断、低環境負荷の船舶等の技術の開発、実用化及び普及を推進するとともに、気象、海象、水路状況等の海洋情報の活用を推進し、海上輸送の高度化等を図る。
○ 経済的で環境にやさしい船舶であるスーパーエコシップ等新技術を活用した船舶、船舶からの排出ガスに含まれる硫黄酸化物を大幅に低減するACF(活性炭素繊維) を活用した舶用高機能排煙処理システム、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出を同時に削減する超臨界水を活用した舶用ディーゼル燃焼機関等の研究開発、実用化及び普及を推進。
○ 海上におけるインターネットやTV 電話、電子メール等の通信利用環境を改善する高速大容量の船陸間双方向通信を実現するため、海上ブロードバンドの有望な活用方策の検討、実現に向けて必要な取組の提案を実施。
○ GPS 波浪計、陸上GPS 基準局、船舶AIS 及び海洋短波レーダー等の情報のマッチングにより、船舶に対する各種航行支援情報のリアルタイムの発信を推進。
○ 環境モニタリング結果を活用しつつ、珊瑚付着型のブロックや干潟の再生等に関する技術の向上のための研究開発を持続的に実施。
○ 日本海洋データセンターが収集、管理し提供している各種海洋データを関係機関との連携により充実させ、海洋・沿岸域の基盤情報の整備を推進。
? 海洋・沿岸域の利用を支える船舶や船員を確保する
海上輸送の高度化に対応した船舶や船員を確保するため、造船技能者や優良な船員の育成を行う。
○ 海洋・沿岸域の安全確保、環境保全に資する船舶の供給を支える造船業を振興。また、造船業における技能者の世代交代に対応する造船に関する「匠」の技の円滑な伝承を推進。
○ 船員教育機関における船員養成やBRM 研修を始めとする実践的な技能の教授並びに各種の船員雇用施策により、優良な船員の確保及び育成を促進。
? 海洋・沿岸域の多様な利用を調和させる
沿岸域の利用の輻輳等を解消するため、一般と産業関連等との利用調整、国土保全と経済活動との利用調整を行い、相互に調和がとれるようにする。
○ 沿岸域の環境と産業、観光、レクリエーション等の利用との調整を図り、持続的な沿岸域の利用と保全を図るため、沿岸域の利用と保全に関する施策を国と地方及び利用者、NPO 等の適切な役割分担、相互の連携、協力、協働により、より一層
着実に実施。
○ 沿岸の大都市から排出される廃棄物最終残渣や災害時に発生する廃棄物の適切処分について、最終処分場の広域融通を推進。
6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する
? 人と海のふれあいを取り戻し、海辺のにぎわいを創出する
臨海部における親水空間の確保やアクセスの改善、プレジャーボート等による海洋スポーツやクルーズの活性化等ハード、ソフト両面において人と海のふれあいを取り戻すことにより、海辺のにぎわいを創出し、地域の活性化等に寄与する。
○ 臨海部の水辺空間が市民の親水空間、人と海の触れ合う場となるよう、臨海部の都市公園、港湾緑地、海岸等の整備を推進。
○ 水域を活用したプロムナードやビジター桟橋、水域にアクセスできる斜路や階段護岸等施設の一部として水域を効果的に取り込んだ港湾緑地の整備を行い、海辺のにぎわいを創出。
○ 港湾の資産を地域の視点から再評価するとともに、地域の産業、海に開かれた特性等港湾の資産を最大限に活用し、地元等の市民団体、地NPO 元市町村、港湾管理者、地元企業等の連携による港湾のにぎわいの創出を推進。
○ マリーナ及びフィッシャリーナ等を活用し、プレジャーボート等によるクルーズ、海洋スポーツ等のマリンレジャーの拠点や地域観光情報等の提供を行う「海の駅」の設置を地域と連携して支援し、ネットワーク化を推進。
○ 海洋におけるレクリエーションが安全かつ安心に楽しめる環境を整備するため、沿岸域の流況情報等の整備及び提供を推進。
? 海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る
海との共生について積極的な関心や協力を喚起するため、海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る。
○ 海洋・沿岸域教育に係る普及啓発活動や指導者育成、NPO 等活動団体のネットワーク化、ホームページの作成等の取組を更に拡充し、利用者からのアクセスしやすさの向上や団体同士の連携と協働をより一層促進。また、関連する基礎知識の体
系化や普及啓発の取組を推進。
7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する
海洋・沿岸域に関する施策を総合的、戦略的に実施するため、国家戦略的な視点を踏まえつつ、海洋・沿岸域の総合的管理について、国の施策の基本方向を定立するとともに、各地域において、関係者の共通認識の醸成を図り、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働による計画策定等の取組を着実に推進する。
○ 国の各種基本的な政策等との整合を図りつつ、沿岸域の安全の確保、多面的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自立的な地域の形成を図るため、関係者の共通認識の醸成を図りつつ、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働により、各地域の特性に応じて沿岸域圏の総合的な管理計画を策定するなど、各種事業、施策、利用等を総合的、戦略的に推進する。
8.国際社会との協調及び協力関係を確立する
海洋・沿岸域の安全確保や環境保全等を図るため、IMO等の国際機関の枠組みや、PSIをはじめ各種会合や訓練等海の安全や環境保全に係る国際的な取組に積極的に参画するとともに、SUA条約の改正等に伴う国内の体制の整備や、国土の水没問題等に苦慮している島嶼国への支援、国際的な沿岸防災対策への支援、日ASEAN交通連携プロジェクトの推進、ODAの活用等により、国際社会との協調及び協力関係を確立する。また、東南アジア諸国に対する海上保安機関の設立支援、海上犯罪取締能力や捜索救助技術等高度な技術や知識の移転等により、マラッカ・シンガポール海峡等を含む東南アジア海域の海上保安能力の全体的な向上を図る。
○ マラッカ・シンガポール海峡等日ASEAN 地域における海の安全や環境保全等のため、日ASEAN 海事セキュリティプログラムやOSPAR 計画等を推進。
○ 東南アジア周辺海域の海上の秩序を確保し、これを通じて我が国の海上交通の安全を確保すべく、フィリピン、インドネシア、マレーシア等へ専門家を派遣し、海上保安機関の設立支援や、東南アジア諸国への技術や知識の移転等を実施。
○ 海上阻止訓練に海上保安庁巡視船を参加させるなど、PSI の活動に積極的に参画。
○ 平成17 年10 月に採択されたSUA 条約の改正について、関係省庁の一員として批准に向けた国内体制の整備を推進。
○ PEMSEA(東アジア海域環境管理パートナーシップ) やNOWPAP(北西太平洋地域海行動計画) 等の取組に積極的に参画し、我が国の取組を東アジアに発信するとともに、日本海、黄海等の海洋環境の保全に積極的に取り組む。また、海洋汚染防止に関する取組について日仏協力会議を開催し、技術的、組織的な協力等を推進。
○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制を一層強化するとともに、OPRC − HNS 議定書に対応した体制を確立。
○ シップリサイクル(船舶の解撤)や目標指向の新造船構造基準、次世代航海システム等に関するにおける検討を積極的にリード。
○ IMO やMAIIF(国際海難調査官会議) における、国際的海難についての調査協力体制推進の議論に積極的に参加。
○ ODA を通じた海洋・沿岸域に関する国際協力を推進。
○ 国土の水没問題等に苦慮している島嶼国に対し、国土保全の手法等について情報提供等の支援を実施。
○ 北西太平洋域の各国に津波情報の提供を実施するとともに、インド洋の沿岸国に対しインド洋における津波警戒システムの構築支援及び暫定的な津波監視情報の提供を実施。
○ 船舶、ブイ、フロート等の海洋観測データを準リアルタイムで国際的に収集し、地球環境に関連する海洋の情報を作成して国内外の行政機関や研究機関へ提供。
9.施策を推進するに当たっての基本的考え方
海洋・沿岸域に関する施策については、国土交通省として以下の基本的考え方を十分踏まえ、推進していくこととする。
? 総合的、戦略的な取組
海洋・沿岸域に関する問題は、それぞれ個別に存在するのではなく、相互に関係するものが多く、また、例えば海岸侵食対策のように山地や河川から海岸に土砂を適正に供給する総合的な土砂管理が必要であるなど、陸域、河川等との関係で生じているものもある。
さらに、安全の確保や国土の保全のように中長期的な視点に立って施策を組み合わせて実施することが効果的なものもあることから、関係機関が連携し、関係する施策を総合的、戦略的に実施する。
? 国際的な視野に立った取組
我が国はすべての国境を海域で画し、海上における安全、離島管理、資源やエネルギーの利用及び開発、地球規模の環境問題等海洋に関する課題の中には、国際的な性格を帯び、その解決に当たって国際的な協力が不可欠であるものもあるため、国際的な視野に立った取組を進める。
また、海洋・沿岸域政策に関する幅広い分野に精通し、かつ、国際的枠組みに参加し、我が国の意見を発信していくことができるような人材の育成を図る。
? 国と地方の役割分担、連携及び協働
海洋・沿岸域に関する問題は多岐にわたり、地域的な問題として単独の市町村が取り組むべき問題から、複数の都府県にわたる広域の連携が必要な問題、排他的経済水域及び大陸棚における問題や国際競争力の根幹を担う海上輸送の確保のように国が取り組むことが必要な問題があることから、今後は、国際動向に応じた国の立場を踏まえ、国と地方、また、地域間の役割分担を明確にするとともに、重層的な取組が必要な分野について、連携、協働して取り組んでいく。
? コンセンサスの状況に応じた取組
海洋・沿岸域に関する問題については、多様な価値観が存在し、また、利害関係が複雑であることが多いことから、地方公共団体、漁業者、産業界、海運事業者、海洋レジャー関係者、各公物管理者、地域住民、環境保護団体その他のNPO等多くの関係者の間の情報共有や共通認識の醸成を図り、そのコンセンサスの形成状況に応じて、取組を進める。また、取組に当たっては、関係者の連携、協働の下、試行的に良好な環境を形成することによって理解と協力を得る等の方策も進める。
? 持続的な取組
海洋・沿岸域に関する問題の多く、例えば、干潟や藻場の回復といったことは、長期にわたる取組が必要であるとともに科学的、技術的に解明されていないものもあることから、持続的な取組を着実に推進していく。
? 先行的な取組
良好な環境はいったん損なわれると回復が困難となる場合が多いことから、海洋・沿岸域の海洋環境や自然環境を守るために、損なわれる前に環境のモニタリングや科学的、技術的な分析評価を十分に実施する等の先行的措置を講じる。
? 多様な主体の参画促進
沿岸域における問題については、現在でも地域住民やNPO が参画し、取組を行っているところであるが、特に環境の保全や、海を活用した地域づくり等を中心として、引き続き地域住民、NPO の力に期待するところは大きく、一層の参画を促す。
? 効率的、効果的な施策の実施
国及び地方公共団体とも要員や財源の確保が厳しい中、不断の組織体制の見直し等と併せて、事前の施策効果を見極め、担当部局間の連携、メリハリのある施策の展開、重点施策への要員の集中、民間やNPO との協働等により、効率的かつ効果的に施策を実施する。
本大綱にまとめた施策のうち、法制の整備が必要なものについては、海洋政策を巡る諸状況を踏まえつつ、その整備に向けて検討を進めることとする。
また、本大綱にまとめた施策のうち国土計画上重要な事項については、国土形成計画(全国計画及び広域地方計画)の案において、関係府省とも調整の上、位置付けを図るものとする。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010621_2/02.pdf
―海洋産業を支える海洋情報インフラとは―
国土交通省海洋・沿岸域政策大綱 平成18年6月
目次
?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識
?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題
1.国際的な動向と課題
2.海洋及び沿岸域の現状と課題
?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進
1.海上における安全を確保する
2.国土の保全と防災対策を推進する
3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する
4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す
5.海洋・沿岸域の利用を推進する
6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する
7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する
8.国際社会との協調及び協力関係を確立する
9.施策を推進するに当たっての基本的考え方
?.施策の推進体制
?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識
我が国は、四方を海に囲まれた「海洋国家」であるとともに、典型的な「島嶼国」EEZ でもある。領海及び排他的経済水域( )の面積は国土面積の約12 倍にあたる約447万km2(うち領海は43 万km2)、海岸線の延長は約35,000km にも達する。日本人は、はるか昔から人や文化の往来、物の輸送、産業、生活等の分野において、海と深く関わってきた。
毎年7月の第3月曜日は、海の恩恵に感謝するとともに海洋国家、日本の繁栄を願う国民の祝日「海の日」と定められているが、そのことは、我が国が海洋とのつながりが特に深い国であることを示すものである。
一方、我が国の海洋・沿岸域を巡っては、海上交通の安全の確保、不審船、密輸・密航等の保安対策の強化、海上災害の防止、海洋汚染の防止、海岸等における防災対策の強化、海洋資源の開発の推進、海上輸送の安定化・活性化といった課題や、沿岸域や閉鎖性水域を中心とした、海岸侵食や砂浜等の消失、埋立等による藻場や干潟の減少、漂流・漂着ゴミの増大や減らない放置艇、赤潮や青潮の発生といった問題が山積している。
他方、国連海洋法条約(1994 年発効)及びリオ地球サミット(1992 年)以来、アジアを含む世界の各国では、「海洋・沿岸域の総合管理」、「持続可能な開発」といった考え方を背景に、海洋・沿岸域に関する様々な施策を総合的に実施するための制度的枠組みを整えて、海洋政策に積極的に取り組むとともに、そうした制度体系を有する国々が連携、協働する流れが強まっている。
このような状況を踏まえ、近年、海洋・沿岸域に関する法制の強化が図られており、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の制定や、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の改正等とともに、「国土形成計画法」において、国土の形成を推進するための総合的かつ基本的な計画である国土形成計画の計画事項として「海域の利用及び保全」が明記され、海洋を貴重な国土空間として位置付けることとしたところである。
海洋・沿岸域を巡る様々な問題や課題は、それぞれが独立で存在するのではなく、相互に関係がある場合が多いことから、こうした問題や課題に取り組むためには、関連する施策を総合的に進めていくことが必要である。
このような観点から、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、海洋・沿岸域に関する施策を総合的に推進していくべく、2004 年9 月に、省内に関係部局の長を構成員とする「国土交通省海洋・沿岸域政策連絡会議」を設置し、海洋・沿岸域政策のあり方について検討を重ね、今回、「国土交通省海洋・沿岸域政策大綱」をまとめた。
国土交通省としては、今後、この大綱に基づき諸般の施策の総合的な推進を図る。
?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題
海洋とは一般には広々とした海を意味するが、この大綱においては、我が国の主権が及ぶ領海(内水を含む)並びに。主権的権利及び管轄権を有する排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚を海洋としている。
我が国は、太平洋の最北西部に位置し、オホーツク海、日本海及び東シナ海という3 つの半閉鎖海と太平洋に囲まれた弧状列島によって構成され、我が国の主権並びに主権的権利及び管轄権が及ぶ水域の面積は447 万km2(領海の43 万km2を含む。)と世界で第6位ともいわれる広さとなっている。また、離島が北方から南方まで広範囲にわたって6,847 島も分布しており、我が国の領土、領海、排他的経済水域等の保全、自然環境の保全等に重要な役割を担っている。
また、この大綱では、海岸線を挟む陸域及び海域(主に内水及び領海を念頭。)の総体を沿岸域としている(なお、この大綱では、海洋と沿岸域を総称して「海洋・沿岸域」としている。)。沿岸域は、水圏、地圏及び気圏の交わる空間であり、洪水、高潮、津波等の自然の脅威にさらされるとともに、自然の微妙なバランスの下、優れた景観や多様で豊かな生態系が形成される等貴重な資源と言える一方、産業、交通、物流、観光、レクリエーション等の様々な利用の要請が輻輳していると言える。
海洋・沿岸域については、未知の分野も多く、基礎となるデータや知見等が十分ではないと言われていることから、今後、更に調査や研究を継続的に進め、それを施策に反映させていくことが重要である。
1.国際的な動向と課題
(1) 各国の取組
1992 年の地球サミット(ブラジル、リオデジャネイロ)でのアジェンダ21 の採択と1994 年の国連海洋法条約の発効以降、アジアを含む世界各国では、海洋の持続可能な開発の推進の動きが進む一方、排他的経済水域や大陸棚等の海洋における自国の権益の確保のため、「海洋の囲い込み」という考え方が広まっており、これらが相まって、総合的な海洋政策の策定等の取組が積極的に進められている。
米国においては、2000 年に海洋法2000 を制定し、同法に基づき海洋政策審議会を設立している。2004 年には、同審議会において報告書「21 世紀の海洋の青写真」を策定し、議会及び大統領に提出した。同報告書は、持続可能性や生態系に基づく管理等を原則とし、政府の海洋管理体制の改善や、研究、観測及び教育の強化等広範にわたり、212 項目の具体的な勧告を行うものである。
これを受け、同年、具体的に実行するための行動計画として、「米国海洋行動計画」を策定した。
一方、沿岸域においては、沿岸域管理法(1972 年)に基づき、沿岸域に接する州が沿岸域管理計画を作成した場合、連邦政府がその推進を支援することとしている。
アジアにおいても中国、韓国が総合的な海洋政策の策定及び実施に力を入れている。中国では「中国海洋アジェンダ、21」(1996 年)を制定し、海洋資源の合理的かつ持続的な利用、海洋経済の一層の発展を促進すること目指している。
2002年には海域使用管理法を制定し、海域の国有を前提として、ゾーニング制度の導入、海域使用権の創設と競争入札制の導入、海域使用料の徴収等について規定し、持続可能な開発と海域管理を推進している。韓国では、先進海洋大国の実現を目指し、沿岸域管理、海洋環境保護、水産等を所掌する海洋水産部を設置し、海洋基本戦略「海洋コリア21」(2000 年)を策定しているほか、海洋水産発展基本法(2002 年)や沿岸域管理法(1999 年)を制定し、海洋管理に関する諸施策を進めている。
以上のほか、東アジア諸国においては、タイが「タイ国家海洋政策」を2003年に策定したほか、インドネシアが沿岸域管理法を、また、マレーシアが国の沿岸域管理政策を、それぞれ策定中である。また、他の地域でも、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、南アフリカ等多くの国が同様の取組みを行っている。(表参照)
(2) 海洋秩序の維持
2001 年の同時多発テロを受け、2003 年5 月、米国からPSI(大量破壊兵器、ミサイル及びその関連物質の拡散に対する安全保障構想) が提案された。現在、日1)本をはじめ60 カ国以上がPSI 活動を支持しており、参加国が共同して取り得るこれらの移転及び輸送の阻止のための海上訓練を合同で行う等多国間連携が行われている。
2005 年10 月にはSUA 条約(海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約) が改正され、犯罪に関与している疑いのある他国籍船舶への公海上2)での乗船や捜索が可能になるなど、ますます国際機関によるテロ防止対策も進んでいる。
また、東南アジア周辺海域における海賊等の多国間にまたがる海上犯罪等については、現在、各国が連携、協力し、これに取り組んでいるが、全ての沿岸国海上法執行機関が、組織、勢力、技術等の面で充分な状況にあるとは言えないため、我が
国からの支援が強く求められている。
一方、近隣諸国の海洋政策上の戦略が我が国周辺海域で競合し、日本海、東シナ海等多くの海域で排他的経済水域の境界が未だ画定していない。
その他にも東シナ海における日中地理的中間線付近における資源開発問題や中国人活動家による尖閣諸島における領有権主張活動、日本海においては竹島問題など我が国の海洋権益を脅かす問題が山積しており、これらに対する厳正かつ適切な対応が求められている。
2.海洋及び沿岸域の現状と課題
(1) 海上交通
? 貨物輸送
エネルギーの93 %(2004 年)及び食料の60 %(2004 年)を海外に依存する我が国においては、輸出入取扱貨物量の99 %以上(2004 年、重量ベース)を海上輸送に依存し、工業製品の輸出や食料及び資源の輸入等の貿易が我が国の経済及び国民生活を支えており、海上輸送は我が国の共通利益となる「物流生命線」であると言える。
全国の津々浦々に1,070 の港湾が配置され、港湾で取扱われている貨物量は、外貿は12 億トン強で、内貿は19 億トン強(2004 年、フレートトン)となっている。
外航海運についてみると、我が国の海上貿易量の世界に占めるシェアは15.7 %(2003 年)であり、中国、アメリカ合衆国に次いで世界第3 位となっている。
外航海運は、各国の経済情勢、さらにはテロや紛争等による影響を受けやすく、安定的な輸送の確保が課題となっている。
また、内航海運は、国内貨物輸送のうち約39 %(2003 年度、トンキロベース)を担っており、我が国の経済や国民生活を支える鉄鋼、石油等の産業物資については、その約8 割を輸送している。営業用トラックと比較してエネルギー効率のよい輸送であり、環境面で優れている一方で、供給面での機動性を欠くため、市況変動による輸送需要の変動に対応しにくく、船腹需給ギャップが生じやすい構造となっている。
? 旅客輸送
旅客輸送は、外航定期航路が15 航路で約45 万6 千人(2004 年、日本人のみ、対前年35.9 %増)、内航旅客が1574 航路で約1 億90 万人(2004 年、対前年6.0 %減)となっている。内航旅客のうち離島航路については、島外との連絡について私的交通の利用が容易でない離島住民の足として必要不可欠であるため、約3 割を公営及び第三セクターが運営しているが、経営状況は厳しく、航路の維持及び改善が課題となっている。
(2) 海上の安全及び海洋汚染
? 海難事故
我が国周辺海域において、救助を必要とする海難に遭遇した船舶(要救助船舶)の隻数は、2001 年から2005 年までの年平均で2,086 隻(死者及び行方不明者167 人)であり、それ以前の5 年間の年平均1,877 隻(同170 人)と比べ11 %増加しているものの、死者及び行方不明者数は約2 %減少している。
また、死者及び行方不明者のうち、約54 %が漁船、約18 %がプレジャーボート及び遊漁船によるものである。これら国民の人命、財産にかかる海難事故への対応として、海難防止のための諸施策を推進するとともに、沿岸海域におけるより迅速かつ的確な人命救助体制の充実強化を進めていくことが重要である。
特に、近年、40 ノット程度の高速で運航する超高速船(ジェットフォイル等)が航行中に障害物と衝突したとみられる事故が多発しており、多数の負傷者を出すケースもあることから、超高速船の安全運航の確保に係る方策の検討が喫緊の課題となっている。
? 海洋汚染及び海上災害
2005 年、海上保安庁は、海上における油、廃棄物、赤潮、青潮等の海洋汚染の発生を360 件確認している。また同庁が防除措置を実施した油排出事故は116 件あり、そのうち影響の大きいタンカーは8 件であった。また船舶火災が118 件発生したが、そのうち約66 %が漁船である。
また、港湾局では、海域環境を整備する日常の業務として、清掃兼油回収船により、日々、漂流3)油、流木、漂流ゴミ等を回収しており、その量は年間約8,000m3(2003 年から2005 年の平均)にのぼる。このような海洋汚染や海上災害の未然防止及び対処能力をより向上させることが必要である。
? 海上テロ及び海賊対策
2001 年9 月に発生した米国同時多発テロ事件発生以後、2002 年10 月には、イエメン沖においてフランス籍タンカー爆破事件が発生する等海上においてもテロが続発している。幸いにして我が国では発生していないものの、依然として我が国を巡るテロ情勢は予断を許さない状況である。
今後とも海上におけるテロの未然防止及び海上における公共の安全と治安維持に万全を期すため、国内外の関係機関と連携し、水際での間隙のない体制を構築、強化することが必要である。
また、2005 年の全世界における海賊事件の発生件数は276 件、そのうち東南アジアにおける発生件数は122 件となっている。これらは減少傾向にあるものの、2005 年3 月に発生した日本籍船舶「韋駄天(いだてん)」が襲撃された事件など、依然として誘拐等の凶悪な海賊事案が発生していることから、引き続き国内外の関係機関との連携や協力関係の強化が必要である。
? 海上犯罪
2005 年の海上保安庁による海上犯罪の送致件数は、6,256 件であり、2004年と比べ、1,395 件の増加となっている。その中でも、暴力団や悪質業者が関与する等組織的かつ広域的な海上環境事犯、我が国の水産資源を枯渇させ、地域経済にも大きな打撃を与えかねない組織的な密漁事犯や外国漁船による不法操業事犯の件数が増加している。
また、我が国周辺海域では、麻薬、覚せい剤等の密輸事犯や不法入国事犯等の国際的な組織犯罪も依然として後を絶たず、ますます悪質かつ巧妙化している。
これら海上犯罪を阻止するために、監視取締り体制の強化を図るとともに、国内外の関係機関との連携強化や各種対策に取り組むなど、海上犯罪対策の徹底を図る必要がある。
(3) 港湾及び航路
周囲を海に囲まれ、臨海部に人口、資産等が集積する我が国において、港湾及び航路は、物流や人流を支え、国民生活の向上や産業活動の発展に大きな役割を果たしている。国際社会と我が国の緊密な関わりの中で、我が国の経済安全保障を実現するためには、より一層の海上輸送の機能強化、安全確保を図ることが極めて重要である。
我が国港湾においては、引き続き物流改革を推進していくとともに、国際海上コンテナ輸送量の増大や船舶の大型化等に適切に対応しつつ、現在進めているスーパー中枢港湾プロジェクトにおいて、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現に向けた港湾整備を図ることや、関係機関と連携、協力した水際対策等危機管理体制の強化を行うこと等が喫緊の課題となっている。
国際海上輸送及び国内海上輸送を担う一連の航路において、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、関門海峡等では、航路や船舶航行が輻輳した湾口部や海峡部等が存在し、海上輸送の要衝、隘路となっている。このような場所で海難事故が発生すれば、長期にわたり航路が閉鎖する可能性が高く、その影響は我が国全体の国民生活や経済産業活動に重大なものとなる。
このため、我が国の経済安全保障を実現するため、船舶の航行水域管理のあり方や国と地方の役割分担について検討
を進める必要がある。
(4) 海洋に関するレクリエーション
海洋に関するレクリエーションには、プレジャーボート(モーターボート、水上オートバイ、ヨット等)、サーフィン、ダイビング、釣り等の「スポーツ型」、海水浴、潮干狩り、水族館等の「リゾート型」のほか、客船等によるクルーズ等がある。
これらの参加人口は、2003 年で海水浴1,890 万人(1995 年:3,000 万人)、釣り1,470 万人(同1,850 万人)、潮干狩り224 万人(同461 万人)、モーターボート及びヨット100 万人(同110 万人)であり、いずれも減少傾向にある。
また、プレジャーボートの保有隻数は、1995 年度の39.8 万隻(モーターボート30.0 万隻、水上オートバイ8.5 万隻、ヨット1.3 万隻)から増加し、1999 年度には43.8 万隻(同32.2 万、10.3 万、1.3 万隻)となったが、これをピークに減少し、2004年度は36.5 万隻(同26.8 万、8.5 万、1.2 万隻)となっている。また、小型船舶操縦士免許保有者数は、2005 年度末で303 万(1995 年度:226 万人)と年々増加している。
一方で、放置艇及び沈廃船の隻数は年で万隻( 年: 8万隻、河川区域含む。)にものぼっており、船舶航行や漁業活動への支障、流水の阻害、津波及び高潮時における艇の流出による被害、景観悪化等の問題が顕在化している。
(5) 鉱物及びエネルギー資源
我が国の領海、排他的経済水域及び大陸棚の海底や海底下には、鉱物資源や、石油、天然ガス、メタンハイドレートといったエネルギー資源の多量の埋蔵が確認されている。また、風力発電や海洋温度差発電といった新エネルギーの可能性も広が
っており、これらの開発及び利用の推進が、将来の我が国の経済活動にとって重要になっているとの指摘がなされている。
(6) 海岸
? 海岸の概要
島国であり、入り組んだ海岸地形をもつ我が国は、約35,000km もの海岸線を有しており、海岸の重要性は特に大きいものがある。
海岸は、自然海岸、半自然海岸及び人工海岸に分類されるが、1960 年当時、8割を占めた自然海岸が、現在は53 %にまで減少しており、半自然海岸が13 %、人工海岸が34 %となっている。
? 海岸侵食
海岸の砂浜は、河川における砂利採取、河川横断工作物の設置等による土砂供給量の減少及び各種構造物の設置等による沿岸方向土砂の流れの変化など、様々な要因により、全国各地で侵食が生じている。また、海砂利採取による侵食も懸念されている。近年は海岸侵食が早いペースで進行(1908 〜 1978 年:72ha/年→ 1978 〜 1992 年:160ha/年)しており、砂浜の減少が、利用空間の減少とともに海岸の景観や生態系を大きく変化させている。
? 災害と防災対策
我が国は、台風の常襲地帯にあり高潮が頻発し(2004 年:27 回)、地震多発地帯で津波の来襲も多い(2004 年:4 回)など、厳しい地理的、自然条件下にある。
また、海岸侵食も全国的に顕在化してきており、放置すれば貴重な国土が失われることから、その保全は極めて重要である。この他、地球温暖化により、今後100年間で海面が9 〜 88cm 上昇するとの予測もある(IPCC(気候変動に関する政府間パネル)による。)。
一方、防災対策としての海岸保全施設は、2004 年度末時点で要保全海岸延長の62 %に設置されているが、このうち約18 %が想定津波高より低く、また、約30 %が想定津波高との比較調査が行われていないほか、施設の老朽化も進んでいる。
? 海岸漂着ゴミ
海岸漂着ゴミは恒常的に発生しているため、景観の悪化や生態系への影響等が生じている。発生起源としては、海域から漂着したもの、河川から流出したもの及び陸域から持ち込まれたもの等であり、近年では海外からと思われる漂着ゴミも日本海側の海岸を中心に確認されている。今後、海岸漂着ゴミへの対応を強化するとともに、関係諸国とも協調、連携した取組を推進することが課題となっている。
(7) 沿岸域の利用状況
現在、国土面積の約3割を占める沿岸に位置する市町村には、総人口の約5割が集中しており、特に東京湾、伊勢湾、大阪湾の沿岸は、全国平均の約10倍もの人口密度となっている。
これらの三大湾と瀬戸内海は、海上交通、工業、物流、エネルギー、港湾、商業、水産業、レクリエーション、観光等で稠密に利用されている。産業の面でも沿岸に位置する市町村の工業製品出荷額は全国の約5割、商業年間販売額は全国の約6割を占める状況となっている。
近年まで、臨海部に集積する重厚長大型産業の移転、縮小等により産業の空洞化が進んでいたが、景気の回復、海外進出企業の国内回帰、物流の高度化等により、臨海部への企業進出が進み出しつつある。
(8) 沿岸域の環境
? 沿岸域に関する水質
我が国では、陸域からの汚濁負荷削減、海域における自然環境の再生や創出等を行い、海域の水質の改善に取り組んできた結果、COD の環境基準の達成率が2004 年で75.5%となっている。
しかし、内湾、内海等の閉鎖性水域では依然として達成率が低くなっており(東京湾63.2 %、伊勢湾50.0 %、瀬戸内海67.3 %)、赤潮や青潮の発生等も見られる(2003 年で東京湾59 件、伊勢湾60 件、瀬戸内海106 件の赤潮が発生)。
? 沿岸域に関する生態系
日本の海洋・沿岸域は、海流の特徴や南北に長い列島の影響により、多様な環境が形成され、同緯度の地中海や北米西岸に比べ豊富な生物相が形成されている(例:海産魚類約3,100 種、藻類約5,500 種)。しかしながら、浅海域では埋立等により藻場や干潟が減少(例:1945 〜 1994 年に4 割の干潟が減少)しているほか、琉球諸島等で海水温の上昇等によるサンゴ礁への影響が懸念されている。
河川及び海洋・沿岸域は、多くの生態系が重なり合って形成されており、特に川と海の接点である汽水域は、沿岸域の中でもすぐれた貴重な生態的価値を有している。
このため、アサリの稚貝やサンゴの幼生の移動等を踏まえた広域的な取組が必要であること、東京湾等の閉鎖性海域を一体として保全することが必要であること、関係者が情報を共有するとともに、科学的な解明を着実に推進し、実現可能な改善策を漸進的に実行する必要があること等が指摘されている。
(9) 沿岸域の総合的な管理
沿岸域に関する課題を解決するためには、沿岸域を自然の系として適切にとらえ、沿岸域の総合的な管理計画を策定し、各種事業、施策、利用等を総合的、計画的に推進することが重要であるとの考え方から、2000年に関係17省庁が「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」を策定し、これに基づきケーススタディ等を行ってきたが、全国的には進んでいないのが現実となっており、このような沿岸域の総合管理の推進をいかに図るかが課題となっている。
?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進
以上のような我が国の海洋・沿岸域を巡る現状及び課題を踏まえると、我が国として海洋・沿岸域に関する施策を総合的かつ戦略的に実施する必要がある。
このような中で、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、以下に掲げる施策を推進していくこととする。
1.海上における安全を確保する
? 海上交通の安全を確保する
海上輸送量の増大や船舶の大型化に対応した安全に航行できる船舶航行水域の確保、航行支援システムの構築、航路標識等の整備、海難事故の分析等を推進するとともに、安全上問題のある条約不適合船(サブスタンダード船)を排除するための措置を行い、海上交通の安全を確保する。
また、ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、事後チェック機能の強化等を図る。
○ 船舶の安全な航行を支援するため、航海用海図の作成や更新、電子海図の整備と普及、航路標識の高機能化、沿岸域情報提供システムの拡充、地震や津波に関する情報の迅速な提供等を推進するとともに、(船舶自動識別装置) AIS を活用した次世代型航行支援システムの構築、航空レーザー等を用いた浅海域の情報の整備、海洋短波レーダー網、(全地球測位システム)波浪計等も活用したGPS的確な漂流予測、航行ルートの選定等を推進。また、衝突回避に必要な他船舶の動向等を的確に表示するINT-NAV(先進安全航行支援システム) の調査研究を推進。
○ 船舶が安全に航行できる環境を確保するため、大型船舶に対応した航路水深の確保、障害物の除去、防波堤の配置等を図るとともに、開発保全航路の指定範囲の拡大や開発保全航路と港湾の間の水域の措置等を行い、これを促進。また、荒天
時に船舶が避難できる避難港の整備を図るとともに、無害通航の外国船舶が我が国の領海内において安全に航行できるよう可航水域を確保。
○ サブスタンダード船の排除等を推進するため、IMO(国際海事機関)加盟国監査を促進するとともにPSC ポートステートコントロールを的確に実施
○ ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、運航労務監理官による監査等の事後チェックの強化を図るとともに、ILO(国際労働機関)海事労働条約の批准に取り組む。
○ 船舶の大型化等が進展する中、海上交通の一層の安全を確保するため、水先人に係る等級別免許制の導入や免許更新要件の見直し等の水先制度改革を実施。
○ 海難事故の再発防止を図るため、海難の調査及び分析に基づく、積極的な勧告や提言を実施。
? 海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する
テロ関連情報の調査、分析体制の整備、海上及び港湾における警備体制を強化するとともに、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施し海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する。
○ 海賊及び海上テロを含む海上における不法行為対策について、アジア海上セキュリティ・イニシアティブ( ) 等に基2004 AMARSECTIVE2004 づき、関係国海上保安機関に対し海上犯罪取締り能力向上のための支援を実施。
○ 国際航海船舶及び国際埠頭施設の保安措置が適確に行われるよう、実施状況の確認や人材育成等を図り、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施するとともに、船舶接岸情報の活用、港湾施設への出入管理の高度化、内航も含めた旅客ターミナルの保安施設整備等を進め、船舶及び港湾の保安対策を強化。
○ 国が港湾施設管理者や税関等の関係機関と協働体制をとり、港湾の利用船舶に関する情報を収集して分析し、問題船等が明らかになった場合、警察機関への通報や港湾施設管理者に警戒指示を行う体制を整備。
○ 臨海部の原子力発電所、石油備蓄基地、米軍施設等の重要施設に対する警備やテロ情報調査体制を強化。
? 事故及び災害等対応の体制を強化する
船舶の衝突や乗揚事故による油の排出、有害液体物質や危険物の流出、火災等の船舶の事故による災害、原子力発電所等のエネルギー施設の事故による災害、台風や津波等の自然現象による災害等の多様な事故及び災害に迅速かつ的確に対応するとともに、地震等に伴う経済的損失の低減を図るため海上からの輸送を確保する体制を強化する。
○ ヘリコプターの機動性、高速性等を活用した機動救難体制の充実強化に努めるほか、特殊な海難への対応体制の強化、救急救命士の養成、洋上救急体制の充実等により救急救命体制を強化。
○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制や臨海部の施設の安全監督体制を一層強化するとともに、OPRC-HNS 議定書(2000 年の危険物質及び有害物による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議定書) に対応した体20)制を確立。
○ 大規模災害対応として、物流と人流の両面における海上−港湾−陸上を結ぶ輸送を確保する広域的な連携、協働体制を確立。
? 海上保安業務体制の充実を図る
海上における総合的な安全及び法秩序を確保するため、海上においてその実態を把握、監視し、直接施策を実施する海上保安業務体制の充実を図る。
○ 巡視船艇、航空機の老朽化や旧式化による業務上の支障の早期解消を図るとともに、海洋権益の保全、沿岸水域の警戒監視体制の構築、大規模災害等に対する救助体制の強化等の新たな業務課題に対応するため、老朽巡視船艇、航空機等の
緊急かつ計画的な代替整備を推進。
○ 携帯電話からの118 番通報による位置情報、コスパス・サーサット捜索救助衛星システムによる遭難警報、船舶に搭載された等から得られる我が国周 ?AIS辺海域の船舶動静情報等を、海上保安庁が保有する各種の情報と横断的に照合で
きるシステムを構築し、救難即応体制、海難防止対策等を向上。
2.国土の保全と防災対策を推進する
? 国民の生命や財産を保護する
安全性の確保が不十分な地域において引き続き防災や減災に取り組む。その際には、施設の耐震化、津波や高潮の予測をより正確かつ迅速に分かりやすく伝達する仕組みや、土地利用施策等の多様な対策を含めた総合的な取組を行う。
○ 海岸保全施設の重点緊急点検結果を受けた、壊滅的な被害が生じるおそれがある海岸における被害防止対策をはじめ、水門の自動化や遠隔操作化、堤防護岸の破堤防止、ハザードマップ作成支援等ハードとソフトが一体となった総合的な津波、高潮(ゼロメートル地帯)対策を推進。
○ 東海・東南海・南海地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による津波被害が想定される沿岸域やゼロメートル地帯における耐震性が十分でない海岸保全施設(堤防、護岸等)の耐震対策を推進。
○ 海岸ごとに潮位、波高、打ち上げ高等を的確かつきめ細かに予測する高潮情報システムの構築、津波警報の一層の迅速化及び精度向上、津波、高潮、高波に関する情報提供の充実や共有化を推進し、防災機関等での情報共有の高度化を推進。
○ 地震発生の予知に寄与する海底地殻変動観測や活断層の調査を実施するとともに、大規模地震に伴う津波の挙動を明らかにするため、津波シミュレーションを実施。また、海域火山活動の監視を行い、船舶航行や漁業活動等に関する災害の防止
を推進。
○ 津波時の放置プレジャーボートの陸への乗り上げ等の防止として、一般海域を含めた係留施設の台帳管理の徹底、係留施設の指定等を実施。
○ 大規模地震発生時の避難者や緊急物資の円滑な輸送の確保に資する港湾施設の耐震化とともに、海岸保全施設の耐震性を短時間かつ低コストで判定可能な「チャート式耐震診断システム」の開発を推進。
○ 地震や津波等の災害時における、海上からの住民の避難や物資輸送等を支援するため、沿岸域における防災情報図の整備を推進。
○ 東京湾及び大阪湾臨海部等において、基幹的広域防災拠点を整備するとともに「道の駅」の防災拠点化を推進。
○ 減災対策として、道路利用者への情報提供、避難路の整備及び救援活動や物資輸送を行う上で重要な役割を果たす緊急輸送道路の確保のため、道路橋の耐震補強や高規格幹線道路ネットワークを整備。さらに、被災を受けた道路について、障害物の除去や応急復旧等の迅速な啓開を実施。
○ 津波被害リスクのある地域において、生命や財産を守るため、津波防護機能を持ち合わせた防波堤の整備を推進。
○ 災害体験の継承、防災知識の蓄積や普及に必要な分かりやすい教材の作成、これらを多くの住民に分かりやすく伝えられる人材の育成、緊急時に備えた体制の構築と防災訓練を推進。
○ 海岸侵食や津波、高潮に対する沿岸域の安全性の低下を防止、軽減するため、関係者間の連携等の仕組みを構築。
? 国土を保全し、領海及び排他的経済水域等の海洋権益を確保する
海岸侵食等の対策を行うことや、外洋域における離島の交通、情報通信やエネルギー供給等に係る基盤の確保等に関する取組により、国境離島をはじめ、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の基線となる国土の保全を図るとともに、日本周辺海域についての適正な海図の作成のための調査や大陸棚の限界画定のための調査、的確な監視警戒等を行い、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の海洋権益の確保を図る。
○ 離島、奄美群島及び小笠原諸島において、交通基盤、産業基盤、生活環境、防災及び国土保全に係る施設等の整備や離島航路の維持及び改善に対する助成、産業や観光の振興、国内外との交流の促進、人材育成の支援等ソフトとハードを一体的に実施する総合的な施策を推進。
○ 我が国の領海及び排他的経済水域等を確保する上で、重要な拠点である国境離島に対して、万全な国土保全を推進するとともに、海象観測の実施等その活用を推進。
○ 大陸棚の限界画定のための調査等の推進や、国境離島の位置情報基盤の整備を推進。また、侵食対策等の海岸の適切な維持及び管理に資する低潮線の調査を実施。
○ 排他的経済水域が画定していない日本海、東シナ海等における海底地形や地質等の情報基盤を整備し、適正な海図の作成を推進。
○ 東シナ海等において顕在化している我が国の海洋権益に関する問題への対応として、機動力や監視能力等に優れた巡視船、航空機等を整備し、厳正かつ的確な監視警戒を実施。
○ 外国漁船による不法操業に対して、特に外国漁船が多数操業している日本海、東シナ海への巡視船艇や航空機の配備等により、効果的かつ厳正な取締りを実施。
3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する
? 海洋・沿岸域のモニター体制を強化する
継続的に海流、海水中の汚染物質、海底地盤の状況、気象、漂流・漂着ゴミ等に関する基礎データの整理、提供体制の強化等を実施し、海洋・沿岸域環境のモニター体制を強化する。
○ 国土交通省における海洋や沿岸域に関する各種情報の収集、整理、提供体制の強化を図るとともに、海域環境の順応的管理に資する波浪、潮位、水深、水質、底質等の効率的なモニタリングを行うことで、海洋や沿岸域のモニター体制を強化。
○ 地球環境に関連した海洋現象を総合的に診断し、「海洋の健康診断表」として提供。
○ 海岸を活動の場としている市民、NPO との協働により、海岸環境に関する情報の広範かつ継続的なモニタリング体制を構築。
○ 排他的経済水域や大陸棚から沿岸域までの海岸線、低潮線、海底地形、地質等の情報基盤を整備。
? 海洋汚染等に対する的確な対応を推進する
大規模油流出、漂流ゴミ、放置座礁船、流出流木及び大型構造物の漂流等が、環境や安全上の支障をきたす等の問題に対し、未然防止対策の推進及び漂着前後それぞれにおける積極的な防除の仕組みの構築等を図る。
○ 油や有害危険物質の流出、放置座礁船等による海洋・沿岸域の汚染に適切に対処するため、領海を越え、場合によっては公海上であっても大型油回収船、巡視船等を迅速に派遣する等国境を越境する海洋汚染について、積極的な防除の取組を推進するための体制等の強化や、保険や基金による被害者保護への的確な取組を実施。
○ 油流出事故が発生した際に迅速かつ的確な油防除措置等の実施に資するため、適切な漂流予測を実施するとともに、沿岸海域の自然的、社会的情報等をデータベース化した沿岸海域環境保全情報の整備を推進。
○ 漂流・漂着ゴミについて、関係省庁と連携して、その処理(回収、処分)、発生源対策を推進。
○ 海洋環境保全講習会や訪船指導等により、漁業者、海事関係者に対して海洋汚染の防止のための指導及び啓発を実施。
? 脆弱な海域の保護及び保全を推進する
船舶からの汚染を防止する必要性が高い海域を、海上輸送を確保しつつ、保護及び保全する。
○ 生態学的又は科学的理由により船舶からの汚染を防止する必要性の高い海域に対し、海上輸送を確保しつつ、これを未然に防止するための措置を導入。
4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す
? 海洋・沿岸域の自然環境を回復させる
埋め立て、沿岸構造物の設置、海岸の消失等により失われた自然環境の回復を図るため、干潟や藻場、サンゴ礁、湿地等の保全と再生、修復を図る。また、ヘドロ、ごみ、ダイオキシン等の有害物質等の堆積、埋立用材及び骨材の採取による深掘等により、元の生態系が失われた海底環境について底質環境を改善する。
○ 流砂系及び漂砂系の連続性を確保し、流入土砂による航路埋没、海岸侵食等の課題に対処するため、関係機関が協働して流砂系及び漂砂系における総合土砂管理を推進する体制を構築。
○ 埋立造成地、工場等からの土地利用転換地、廃棄物の埋立処分地等における緑地、湿地、干潟等の自然空間の再生や創出、砂浜、藻場、サンゴ礁等の回復、底質環境の改善等による自然環境の再生を推進。
○ 珊瑚付着型のブロックや干潟の再生に関する技術開発を推進し、港湾整備等への反映を推進。
○ ダイオキシン類等の有害化学物質による底質汚染の対策を推進。
○ 青潮等の原因とされる深掘跡の効率的な埋め戻し等を実施するため、浚渫土砂等の需給や品質を調整するシステムを構築。
? 海洋・沿岸域の自然環境及び景観の維持及び保全を図る
自然海岸や砂浜、干潟等の生態系への影響を最小化するため、十分な事前環境調査等を行い、沿岸域構造物と環境及び景観との調和を図る。また、多くの海岸で見られる漂着ゴミや放置されている船舶等を処理することや、船舶からの排出ガスの削減等により、自然環境及び景観の維持、保全を図る。
○ 人工海岸の整備、構造物の設置等に際して、環境との調和を一層重視し、石積堤や緩傾斜護岸等自然と共生する取組を実施。
○ 沿岸域にゴミが異常に漂流、漂着し、これを放置することにより船舶航行への支障、海岸保全施設の機能阻害、海岸環境の悪化等が生じているため、実効的な対策を推進。
○ 廃船(繊維強化プラスティック製廃船)の環境に優FRP しい処理と、FRP 廃27)船の不法投棄、放置艇の沈廃船化等の問題に対処するため、FRP 廃船のリサイクルシステムの普及を推進。
○ 海域への廃棄物不法投棄、汚水の不法排出等の海上環境事犯に対し、関係機関と悪質事業者等に係る情報共有体制を構築し、監視取締体制を効率化するとともに強化。
○ 船舶に石油類等を積み出す際に放出されるVOC(揮発性有機化合物質) 対策を実行していくため、放出規制港湾の指定や港湾における排出ガス処理施設の整備を促進。
○ 港湾に係留中の船舶に陸上側施設から電力を供給することで、船舶のアイドリングストップを推進。
○ 沿岸部における魅力ある空間の整備を推進、支援するため、海岸景観形成ガイドラインを踏まえた防災や利用と調和した良好な海岸景観形成を推進するとともに、景観計画の策定等景観法の制度活用について地方公共団体への助言を実施。
? 水質の保全及び回復を図る
下水道の整備及び河川の直接浄化による陸域からの汚濁負荷の削減並びに水質浄化能力を有する干潟や藻場の保全、再生等を行うことにより、依然として閉鎖性水域において、赤潮や青潮が発生している状況を改善する等水質の保全及び回復を図る。
○ 水質改善が進まない三大湾等の閉鎖性海域を中心に、「全国海の再生プロジェクト」として「海の再生」に向けた各種施策、海底の汚泥除去や覆砂による溶出抑制等の海洋・沿岸域の水質改善対策、合流式下水道の改善や高度処理の推進、河川浄
化対策、環境モニタリングを、一層、総合的かつ効果的に推進。
○ 東京湾、大阪湾以外の閉鎖性海域についても、順次再生行動計画の策定に向けた取組を推進。
5.海洋・沿岸域の利用を推進する
? 海上輸送の安定化・活性化を図る
外航海運について、適切な競争環境の確保等により、高質かつ効率的な輸送サービスを安定的に提供できる体制を整える。また、内航海運の経営基盤の強化等により、新造船舶への適切な代替を推進し、内航海運の活性化を図る。
○ 我が国商船隊による安定輸送を確保するための方策の充実・強化。
○ 経済効率、環境、安全等の課題を解決する新技術の開発と実用化を支援する枠組みを創設するとともに、環境問題への対応等社会的要請に応えることのできるスーパーエコシップの普及を促進。
○ 中小零細の多い内航海運事業者のグループ化、協業化を促進し、経営基盤を強化。
? 海洋・沿岸域の経済活動を活性化させる
貿易構造や荷役形態の変化に伴う陳腐化した施設や水際線を有する付加価値の高い低未利用地について、物流拠点や国際競争産業等の立地を推進する等有効利用すること等により、沿岸域の経済活動の活性化を図る。
○ 沿岸域の低未利用地に物流や国際競争産業等新しい機能立地を促し、それに併せて拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路の重点的な整備や、高度成長期時代の老朽化した運河や水路、護岸、防災・減災施設等のリニューアルを推進。
○ 「みなとオアシス」のような交流の場の形成を支援し、多目的拠点としての活用を推進。
○ 沿岸域における公共水域や港湾施設等既存ストックの適正かつ安全な活用促進に資する地域の取組に対し、フィージビリティの調査や規制等との調整等を実施し、これを支援。
? 海洋・沿岸域の新たな利用を推進する
新規航路の開拓、メガフロート等を活用した洋上発電や大陸棚海洋資源開発基地及び中小ガス田の活用を可能とする新たな輸送システムの構築等海洋の新たな利用を、技術の開発動向を踏まえ推進する。
○ 「リサイクルポート」の形成により、海上輸送による効率的な静脈物流ネットワークを構築し、循環資源の広域的な流動を促進。
○ 環境負荷の少ない内航海運による輸送への転換を促進するとともに、沿岸域ネットワーク、島や海の魅力を気軽に楽しむことができる国内旅客航路を活性化。
○ 拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路を重点的に整備。
○ 中小ガス田の活用が可能となるよう、NGH(天然ガスハイドレート)輸送船を活用した新たな輸送システムを構築。
○ 海洋における風力、海洋温度差等による発電といった新エネルギーの活用に向けた洋上発電プラットフォームや大陸棚海洋資源開発基地として、メガフロートの活用を推進。
? 海洋・沿岸域の利用に関する技術の開発等を推進する
環境修復や侵食防護、高潮や津波への対策、耐震性診断、低環境負荷の船舶等の技術の開発、実用化及び普及を推進するとともに、気象、海象、水路状況等の海洋情報の活用を推進し、海上輸送の高度化等を図る。
○ 経済的で環境にやさしい船舶であるスーパーエコシップ等新技術を活用した船舶、船舶からの排出ガスに含まれる硫黄酸化物を大幅に低減するACF(活性炭素繊維) を活用した舶用高機能排煙処理システム、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出を同時に削減する超臨界水を活用した舶用ディーゼル燃焼機関等の研究開発、実用化及び普及を推進。
○ 海上におけるインターネットやTV 電話、電子メール等の通信利用環境を改善する高速大容量の船陸間双方向通信を実現するため、海上ブロードバンドの有望な活用方策の検討、実現に向けて必要な取組の提案を実施。
○ GPS 波浪計、陸上GPS 基準局、船舶AIS 及び海洋短波レーダー等の情報のマッチングにより、船舶に対する各種航行支援情報のリアルタイムの発信を推進。
○ 環境モニタリング結果を活用しつつ、珊瑚付着型のブロックや干潟の再生等に関する技術の向上のための研究開発を持続的に実施。
○ 日本海洋データセンターが収集、管理し提供している各種海洋データを関係機関との連携により充実させ、海洋・沿岸域の基盤情報の整備を推進。
? 海洋・沿岸域の利用を支える船舶や船員を確保する
海上輸送の高度化に対応した船舶や船員を確保するため、造船技能者や優良な船員の育成を行う。
○ 海洋・沿岸域の安全確保、環境保全に資する船舶の供給を支える造船業を振興。また、造船業における技能者の世代交代に対応する造船に関する「匠」の技の円滑な伝承を推進。
○ 船員教育機関における船員養成やBRM 研修を始めとする実践的な技能の教授並びに各種の船員雇用施策により、優良な船員の確保及び育成を促進。
? 海洋・沿岸域の多様な利用を調和させる
沿岸域の利用の輻輳等を解消するため、一般と産業関連等との利用調整、国土保全と経済活動との利用調整を行い、相互に調和がとれるようにする。
○ 沿岸域の環境と産業、観光、レクリエーション等の利用との調整を図り、持続的な沿岸域の利用と保全を図るため、沿岸域の利用と保全に関する施策を国と地方及び利用者、NPO 等の適切な役割分担、相互の連携、協力、協働により、より一層
着実に実施。
○ 沿岸の大都市から排出される廃棄物最終残渣や災害時に発生する廃棄物の適切処分について、最終処分場の広域融通を推進。
6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する
? 人と海のふれあいを取り戻し、海辺のにぎわいを創出する
臨海部における親水空間の確保やアクセスの改善、プレジャーボート等による海洋スポーツやクルーズの活性化等ハード、ソフト両面において人と海のふれあいを取り戻すことにより、海辺のにぎわいを創出し、地域の活性化等に寄与する。
○ 臨海部の水辺空間が市民の親水空間、人と海の触れ合う場となるよう、臨海部の都市公園、港湾緑地、海岸等の整備を推進。
○ 水域を活用したプロムナードやビジター桟橋、水域にアクセスできる斜路や階段護岸等施設の一部として水域を効果的に取り込んだ港湾緑地の整備を行い、海辺のにぎわいを創出。
○ 港湾の資産を地域の視点から再評価するとともに、地域の産業、海に開かれた特性等港湾の資産を最大限に活用し、地元等の市民団体、地NPO 元市町村、港湾管理者、地元企業等の連携による港湾のにぎわいの創出を推進。
○ マリーナ及びフィッシャリーナ等を活用し、プレジャーボート等によるクルーズ、海洋スポーツ等のマリンレジャーの拠点や地域観光情報等の提供を行う「海の駅」の設置を地域と連携して支援し、ネットワーク化を推進。
○ 海洋におけるレクリエーションが安全かつ安心に楽しめる環境を整備するため、沿岸域の流況情報等の整備及び提供を推進。
? 海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る
海との共生について積極的な関心や協力を喚起するため、海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る。
○ 海洋・沿岸域教育に係る普及啓発活動や指導者育成、NPO 等活動団体のネットワーク化、ホームページの作成等の取組を更に拡充し、利用者からのアクセスしやすさの向上や団体同士の連携と協働をより一層促進。また、関連する基礎知識の体
系化や普及啓発の取組を推進。
7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する
海洋・沿岸域に関する施策を総合的、戦略的に実施するため、国家戦略的な視点を踏まえつつ、海洋・沿岸域の総合的管理について、国の施策の基本方向を定立するとともに、各地域において、関係者の共通認識の醸成を図り、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働による計画策定等の取組を着実に推進する。
○ 国の各種基本的な政策等との整合を図りつつ、沿岸域の安全の確保、多面的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自立的な地域の形成を図るため、関係者の共通認識の醸成を図りつつ、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働により、各地域の特性に応じて沿岸域圏の総合的な管理計画を策定するなど、各種事業、施策、利用等を総合的、戦略的に推進する。
8.国際社会との協調及び協力関係を確立する
海洋・沿岸域の安全確保や環境保全等を図るため、IMO等の国際機関の枠組みや、PSIをはじめ各種会合や訓練等海の安全や環境保全に係る国際的な取組に積極的に参画するとともに、SUA条約の改正等に伴う国内の体制の整備や、国土の水没問題等に苦慮している島嶼国への支援、国際的な沿岸防災対策への支援、日ASEAN交通連携プロジェクトの推進、ODAの活用等により、国際社会との協調及び協力関係を確立する。また、東南アジア諸国に対する海上保安機関の設立支援、海上犯罪取締能力や捜索救助技術等高度な技術や知識の移転等により、マラッカ・シンガポール海峡等を含む東南アジア海域の海上保安能力の全体的な向上を図る。
○ マラッカ・シンガポール海峡等日ASEAN 地域における海の安全や環境保全等のため、日ASEAN 海事セキュリティプログラムやOSPAR 計画等を推進。
○ 東南アジア周辺海域の海上の秩序を確保し、これを通じて我が国の海上交通の安全を確保すべく、フィリピン、インドネシア、マレーシア等へ専門家を派遣し、海上保安機関の設立支援や、東南アジア諸国への技術や知識の移転等を実施。
○ 海上阻止訓練に海上保安庁巡視船を参加させるなど、PSI の活動に積極的に参画。
○ 平成17 年10 月に採択されたSUA 条約の改正について、関係省庁の一員として批准に向けた国内体制の整備を推進。
○ PEMSEA(東アジア海域環境管理パートナーシップ) やNOWPAP(北西太平洋地域海行動計画) 等の取組に積極的に参画し、我が国の取組を東アジアに発信するとともに、日本海、黄海等の海洋環境の保全に積極的に取り組む。また、海洋汚染防止に関する取組について日仏協力会議を開催し、技術的、組織的な協力等を推進。
○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制を一層強化するとともに、OPRC − HNS 議定書に対応した体制を確立。
○ シップリサイクル(船舶の解撤)や目標指向の新造船構造基準、次世代航海システム等に関するにおける検討を積極的にリード。
○ IMO やMAIIF(国際海難調査官会議) における、国際的海難についての調査協力体制推進の議論に積極的に参加。
○ ODA を通じた海洋・沿岸域に関する国際協力を推進。
○ 国土の水没問題等に苦慮している島嶼国に対し、国土保全の手法等について情報提供等の支援を実施。
○ 北西太平洋域の各国に津波情報の提供を実施するとともに、インド洋の沿岸国に対しインド洋における津波警戒システムの構築支援及び暫定的な津波監視情報の提供を実施。
○ 船舶、ブイ、フロート等の海洋観測データを準リアルタイムで国際的に収集し、地球環境に関連する海洋の情報を作成して国内外の行政機関や研究機関へ提供。
9.施策を推進するに当たっての基本的考え方
海洋・沿岸域に関する施策については、国土交通省として以下の基本的考え方を十分踏まえ、推進していくこととする。
? 総合的、戦略的な取組
海洋・沿岸域に関する問題は、それぞれ個別に存在するのではなく、相互に関係するものが多く、また、例えば海岸侵食対策のように山地や河川から海岸に土砂を適正に供給する総合的な土砂管理が必要であるなど、陸域、河川等との関係で生じているものもある。
さらに、安全の確保や国土の保全のように中長期的な視点に立って施策を組み合わせて実施することが効果的なものもあることから、関係機関が連携し、関係する施策を総合的、戦略的に実施する。
? 国際的な視野に立った取組
我が国はすべての国境を海域で画し、海上における安全、離島管理、資源やエネルギーの利用及び開発、地球規模の環境問題等海洋に関する課題の中には、国際的な性格を帯び、その解決に当たって国際的な協力が不可欠であるものもあるため、国際的な視野に立った取組を進める。
また、海洋・沿岸域政策に関する幅広い分野に精通し、かつ、国際的枠組みに参加し、我が国の意見を発信していくことができるような人材の育成を図る。
? 国と地方の役割分担、連携及び協働
海洋・沿岸域に関する問題は多岐にわたり、地域的な問題として単独の市町村が取り組むべき問題から、複数の都府県にわたる広域の連携が必要な問題、排他的経済水域及び大陸棚における問題や国際競争力の根幹を担う海上輸送の確保のように国が取り組むことが必要な問題があることから、今後は、国際動向に応じた国の立場を踏まえ、国と地方、また、地域間の役割分担を明確にするとともに、重層的な取組が必要な分野について、連携、協働して取り組んでいく。
? コンセンサスの状況に応じた取組
海洋・沿岸域に関する問題については、多様な価値観が存在し、また、利害関係が複雑であることが多いことから、地方公共団体、漁業者、産業界、海運事業者、海洋レジャー関係者、各公物管理者、地域住民、環境保護団体その他のNPO等多くの関係者の間の情報共有や共通認識の醸成を図り、そのコンセンサスの形成状況に応じて、取組を進める。また、取組に当たっては、関係者の連携、協働の下、試行的に良好な環境を形成することによって理解と協力を得る等の方策も進める。
? 持続的な取組
海洋・沿岸域に関する問題の多く、例えば、干潟や藻場の回復といったことは、長期にわたる取組が必要であるとともに科学的、技術的に解明されていないものもあることから、持続的な取組を着実に推進していく。
? 先行的な取組
良好な環境はいったん損なわれると回復が困難となる場合が多いことから、海洋・沿岸域の海洋環境や自然環境を守るために、損なわれる前に環境のモニタリングや科学的、技術的な分析評価を十分に実施する等の先行的措置を講じる。
? 多様な主体の参画促進
沿岸域における問題については、現在でも地域住民やNPO が参画し、取組を行っているところであるが、特に環境の保全や、海を活用した地域づくり等を中心として、引き続き地域住民、NPO の力に期待するところは大きく、一層の参画を促す。
? 効率的、効果的な施策の実施
国及び地方公共団体とも要員や財源の確保が厳しい中、不断の組織体制の見直し等と併せて、事前の施策効果を見極め、担当部局間の連携、メリハリのある施策の展開、重点施策への要員の集中、民間やNPO との協働等により、効率的かつ効果的に施策を実施する。
本大綱にまとめた施策のうち、法制の整備が必要なものについては、海洋政策を巡る諸状況を踏まえつつ、その整備に向けて検討を進めることとする。
また、本大綱にまとめた施策のうち国土計画上重要な事項については、国土形成計画(全国計画及び広域地方計画)の案において、関係府省とも調整の上、位置付けを図るものとする。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010621_2/02.pdf
2009年12月29日
第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会
第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会
1.日時
平成21年3月3日(月)14時00分
2.場所
神戸市中央区下山手通5−1−16パレス神戸2階「大会議室」
3.出席者指名
?出席委員
糠善次/ 川本信義/ 山本正直/ 小田英一
福池昌広/ 高橋昭/ 前田健二/ 宮本憲二
藤本昭夫/ 坂井淳/ 原一郎/ 荒井修亮
以上12名
臨席者
水産庁資源管理部管理課課長木實谷浩史
課長補佐渡邉顕太郎
九州漁業調整事務所次長佐藤愁一
独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所部長岩本明雄
資源管理研究室長永井達樹
研究員片町太輔
中央水産研究所主任研究員石田実
和歌山海区漁業調整委員会事務局長田上伸治
大阪海区漁業調整委員会課長補佐狭間文雄
専門委員小菅弘夫
大阪府環境農林水産部水産課課長補佐亀井誠
兵庫県農政環境部農林水産局水産課資源管理係主査峰浩司
兵庫県農政環境部農林水産局水産課漁政係主査森本利晃
岡山海区漁業調整委員会次長佐藤二郎
広島海区漁業調整委員会専門員山根康幸
山口県農林水産部水産振興課主任岡田浩司
徳島県農林水産部水産課技師西岡智哉
香川海区漁業調整委員会副主幹宮川昌志
香川県農林水産部水産課課長補佐井口政紀
技師益井敏光
愛媛県農林水産部水産局水産課資源管理担当係長加藤利弘
愛媛県農林水産研究所主任研究員河本泉
主任研究員関信一郎
福岡県豊前海区漁業調整委員会事務主査竹馬悦子
大分海区漁業調整委員会事務局長日隈邦夫
大分県農林水産部水産振興課副主幹大塚猛
愛媛新聞社大阪支社編集部長芝充
瀬戸内海漁業調整事務所所長佐藤力生
調整課長馬場幸男
資源課長森春雄
指導課長小林一弘
資源管理計画官平松大介
資源保護管理指導官中奥美津子
調整課許可係長酒井仁
調整課調整係玉城哲平
資源課資源管理係長松本貴弘
資源課資源増殖係長萩原邦夫
資源課漁場整備係正岡克洋
4.議題
1.サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について
2.周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について
3.カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について
4.トラフグ資源管理の検討状況について
5.その他



5.議事の内容
(開会)
(馬場調整課長)
ただいまから第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会を
開催いたします。
それでは前田会長、議事進行をお願いいたします。
(挨拶)
(前田会長)
さて、本日の委員会ではサワラ瀬戸内海系群資源回復計画、周防灘小型機船底びき網漁
業対象種資源回復計画、燧灘カタクチイワシ資源回復計画について平成20年度取組の実
施状況と資源状況についての報告をしていただきまして、また平成21年度の取組などに
ついてご審議いただくことといたしております。
更にはトラフグ資源管理の検討状況、平成21年度予算についてもご報告いただくなど
盛りだくさんの内容となっております。
また、ご案内のとおり委員の皆様におかれましては現在の委員の任期が平成17年10
月1日から4年間、今年の9月末日までが任期となっております。緊急の予定がなければ
本日が最後の委員会になろうかと思います。委員の皆様におかれましては最後まで活発な
ご議論をお願い申し上げます。
(木實谷管理課長)
ご承知のとおり広域漁業調整委員会でございますけれども、都道府県の区域を越えて分
布回遊する資源の適切な管理を目的として設置されまして、国が作成する広域の資源回復
計画を中心としてご審議をいただいているところでございます。
現在、全国で18の広域計画そして46の地先計画が実施されておりまして資源回復の
ための取組が全国的に展開されてきているところでございます。瀬戸内海を管轄いただい
ております本委員会の関係では現在までに3つの広域計画が作成実施されているところで
ございますけれども、皆様方の不断のご努力により資源の回復が更に図られることを期待
しているところでございます。
改めて申し上げるまでもなく水産庁といたしましても、この資源回復計画につきまして
は主要施策の1つでございまして今後とも一層推進していくということにしているところ
でございます。現在取り組んでおります資源回復計画につきましては、徐々に回復が見ら
れ始めている計画もございまして、このような資源については将来的には漁業者がみずか
らの力で管理していくような方向にもっていくというのがこれからの課題ではないかとい
うふうに考えているところでございます。
一方で、漁業経営を取り巻く情勢につきましてはご承知のとおりいまだ予断を許さない
状況にございますけれども、適切な資源管理に取り組み水産資源の維持回復を行っていく
ことは、将来的に活力ある漁業構造の確立にもつながっていくものと考えておりまして、
資源管理を目的として設置されました広域漁業調整委員会の役割は一層期待されるものと
考えているところでございます。
なお、広域漁業調整委員会につきましては委員の皆様の任期が一期4年となっておりま
して、現在第2期目の最終年を迎えているということでございます。平成13年に漁業法
が改正され広域漁業調整委員会制度が設けられ、その中で資源回復計画を中心とした課題
に鋭意ご尽力を賜りました皆様のおかげで、資源回復計画も今や全国的な展開になってい
るところでございます。これまで各委員の皆様方が払ってこられましたご努力に対して重
ねて御礼申し上げますとともに、残されました半年の期間におきましても資源管理、漁業
調整といった課題に対しまして引きつづきご支援、ご協力をお願いする次第でございます。
本日はさわらの資源回復計画を始め、盛りだくさんの議題となっているというふうに承
知しております。皆様の有意義なご審議が行われまして、今後さらに瀬戸内海における資
源管理が推進されますよう祈念いたしまして、簡単ですけれども開会のあいさつとさせて
いただきます。
(資料確認)
(前田会長)
それでは、本日使用いたします資料の確認を行いたいと思います。事務局よろしくお願
いします。
(馬場調整課長)
それでは、お手元にお配りしております資料でございますが、まず議事次第、委員名簿、
出席者名簿それから本日の会議での資料としまして資料1−1から1−3までサワラの資
源回復計画関係の資料。資料2−1から資料2−3まで周防灘小型機船底びき網資源回復
計画の資料。資料3−1から3−3までがカタクチイワシ資源回復計画の資料。資料4ト
ラフグ資源管理に関する主な取組。資料5平成21年度予算関連資料がございます。それ
から参考資料といたしまして瀬戸内海で行っている広域種の資源回復計画等に関します資
料をホッチキスどめで配付しております。ざいます。
(議題1 サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について)
(前田会長)
それでは早速、議題1「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の一部変更について」に入り
ます。
まず始めに20年度の実施状況について事務局より報告していただき、次に瀬戸内海区
水産研究所からサワラの資源状況などについて説明をしていただきます。その後、21年
度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。
それでは本年度の実施状況について事務局から報告をお願いいたします。
(平松資源管理計画官)
瀬戸内海漁業調整事務所資源管理計画官をしております平松でございます。
まず資料1−1を用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。座って説明を
させていただきます。
サワラ資源回復計画の平成20年度の実施状況につきまして、資料1−1の表紙をめく
っていただきますと漁獲努力量削減措置実施状況図1ページがございます。こちらの実施
状況図から資料の5ページまで、種苗放流それから漁場整備等の実施状況につきましては
前回の委員会での報告内容と重複いたしますのでここではご説明を割愛させていただきま
す。
資料の6ページをご覧いただきたいと思います。こちらに平成20年の漁獲量の速報値
を載せてございます。6ページの1番の漁獲量の表の欄外、右側に速報値として括弧書き
で各年の数量を書いているところでございます。こちらの数値につきましては、農林水産
省の統計部が半年ごとに速報値として集計しております数値の平成20年の上半期、下半
期の合計の数字を掲載させていただいております。平成20年につきましては、瀬戸内海
の漁獲量が752トンということで集計をされてございます。これと同じ速報値の平成1
9年の数字を見ていただきますと803トンということで速報値の対前年比が94%、マ
イナス6%ということになってございます。私どもの事務所の方で各府県の担当の方から
漁獲状況を聞き取っております情報を整理いたしますと、やはり同様に数%前年を下回る
というような情報をお聞きしてございます。こちらにつきましては、確定値はもう少し時
間が経ってから出るということでございますが、平成20年は平成19年の漁獲量の確定
値1,081トンを若干下回るのではないかと想像をしているところでございます。
平成20年の漁獲量の統計の数字につきましては以上でございますが、6ページの2番、
下の方ですがこちらの方には当広域漁業調整委員会指示で漁獲量の上限が定められており
ます。はなつぎ網、さわら船曳網、サゴシ巾着網、こちらの漁獲量の報告が各県からござ
いましたので、その数値を掲載させていただいてございます。それぞれ表にございます制
限値以内での操業が実施されたというところでございます。
漁獲量については以上でございますが、次に資料の7ページに岡山県が今年度実施いた
しました試験操業調査の結果、それから8ページから9ページには同じく香川県で実施さ
れました試験操業調査の結果を載せてございます。
まず、7ページの岡山県の調査結果でございますが今年度、昨年の10月に試験操業が
3回実施されてございます。真ん中の2番の試験操業結果のところの平成20年の欄をご
覧ください。3回の試験操業によりましてサゴシが197尾漁獲されております。その下、
1隻あたりのCPUEも65.7ということで、それぞれ平成19年の結果を上回る結果
となってございます。197尾の漁獲されたサゴシのうち、放流魚がどれだけ含まれてい
たかというものにつきまして7ページ一番下の表3に漁獲サゴシのデータと右側に放流さ
れたサワラのデータの結果を載せております。平成20年につきましては、197尾のう
ち放流されたものが1尾ということで混獲率は0.5%という結果になってございます。
昨年、一昨年と比べて混獲率が非常に低い結果というのが今年の特徴でございます。
同様に8ページから9ページの香川県の調査結果も傾向といたしましては、ただいまの
岡山県と同様の傾向となってございまして、まず8ページの2番の漁獲状況の1番下の右
端、平成20年の結果といたしまして3回の試験操業で107尾のサゴシが漁獲され、1
隻あたりの漁獲実数も17.8尾ということでそれぞれ前年を上回っているという結果で
ございます。また9ページに漁獲されたもののうち放流されたサワラがどれだけ含まれて
いたかということで表になってございますが、こちらの平成20年のところをご覧いただ
くと、左側の漁獲サゴシ107に対して放流サワラの尾数が1尾ということで混入率が約
1%という形になってございます。それぞれ傾向といたしましては、先ほどの岡山県と同
様な傾向になっているというところでございます。
このように両県とも試験操業での漁獲は昨年よりも多いということ、それから全体の漁
獲の中に占める放流されたサワラの割合が少ないということ、相対的に見ると全体の天然
のサワラ加入が多いということを示す結果となってございます。ただ、近年では加入が卓
越いたしました平成14年ほどの結果にはなっていないというところがございます。若干
漁獲がいいのではないかというような推定もしておりますが、これらの加入状況につきま
してはまた後ほど瀬戸内海区水産研究所の方からの報告にも触れられますのでそちらに譲
りたいと思います。
岡山県、香川県の両県で実施されております試験操業こちらにつきましては、播磨灘の
休漁期間に実施されるものということで、本委員会指示との関係により事前に委員会へ調
査計画の報告、また結果の報告を行うということにされております。平成21年度につき
ましても今年度と同様に調査が計画されておりまして、資料の10ページ、11ページに
それぞれ来年度の調査計画が提出をされていることをご報告いたします。
それから平成20年度の実施状況、最後になりますが資料の12ページ一番後ろでござ
いますが、TAE管理の実施状況を取りまとめてございます。府県別に数字が書かれてお
ります表の一番右端に全体の合計値といたしまして、設定された努力量が12万3,67
4隻日に対しまして平成20年度のTAE管理期間での操業隻日数が2段目の1万5,9
13隻日となってございます。設定値に対する割合といたしましては13%となっており
まして、こちらの出漁隻日数につきましては平成15年度にこのTAE管理を開始して以
降、最も少ない値ということになってございます。
簡単ではございますが平成20年度、本年度のサワラ計画の実施状況についての説明は
以上でございます。
(前田会長)
ただいまの報告につきまして何かご質問はございませんでしょうか。
それではご質問もないようですので、つづきましてサワラの資源状況につきまして瀬戸
内海区水産研究所の永井室長さんより説明をお願いいたします。
(永井室長)
図は漁獲量の経年推移です。横軸が年、縦軸が千トン単位で示した漁獲量です。青が瀬
戸内海の東部、紀伊水道から備讃瀬戸まで、赤が燧灘から伊予灘、あるいは周防灘までの
西部を示します。漁獲量は一番多いときで6千トンを超えましたが、1986年をピーク
に減ってきました。1998年に香川県、岡山県、兵庫県が自主規制を始めてから、徐々
に漁獲量は回復してきて、2000年からは資源回復計画が行われているところです。
2007年の漁獲量は図では1,108トンと記入しておりますが、先ほどの平松さん
の説明で新しい推定値は1,081トンとなっています。漁獲物の年齢を見ますと昔は3
歳、4歳をとっていたのですが、1980年代に入ってから2歳、3歳、1990年代に
入ると1歳、2歳が中心となり、漁獲物の低年齢化が進んいます。とり方としては悪くな
ってきています。
次に資源量の推移ですが、縦軸に漁獲物の年齢組成を基に資源計算して求めた資源量の
経年推移を示しました。一番多いとき1987年で1万6千トンくらいあったものがずっ
と減ってきて、2007年には2,282トンと1987年の14%に減っています。そ
の後、資源量は少し回復してきましたが、ここ4年ほどやや減少ぎみで推移しています。
一時の悪いときは脱したけれど、やや減りぎみで推移しています。
それから資源量に対してどのくらい漁獲しているかという漁獲割合を赤で示しておりま
すが、一時に比べてその割合が高くなってきており、漁獲圧力が増してきています。
次に親魚量(トン)と加入尾数の関係です。横軸に親の資源量をとりまして、縦軸にそ
の年に生まれて秋に加入したサゴシの資源尾数をとっています。図を見ると、親が多いほ
ど子供も多く加入していることがうかがわれます。両者に直線の関係を当てはめると青い
ラインになります。最近年の1998年以降を切り出してみると右の図ですが、同じブル
ーの直線で示していますが、これは2つの図で同じものです。要するに親が多いと子供も
多い、ただ2002年というのは親がそれほど多くなかった割には加入がよかった、強い
年級が生まれてきた。これに対し2004年は親が多かったけれど、期待したほど子供が
生まれてこなかったわけです。いずれにしても最近はこの直線より少し上に点がくるいい
傾向があるのですが、それが親の増加につながっていない。というのは0歳秋から1歳の
間の魚がまだ小さいうちに漁獲されて、親の増加につながっていないと言えると思います。
先ほど2004年は親が多かった割に子供の生き残りが悪かったということを言いまし
たが、その理由として1つ考えられるのはこの年には御承知のように6月から10月に台
風が10個来襲して史上最高ということがありました。この年サワラの卵が多かったとい
うことがネット調査でわかっておりますが、仔魚が少なかった。小さいうちに海が時化て
魚の生き残りが悪かったのかなと思っています。
それから2006年については、2005年の12月から40年ぶりの低温という厳し
い冬でして、表面の水温がこれは大阪湾の例ですけど例年に比べて5度くらい低かった。
その影響がずっとサワラの産卵期まで持ち越してきまして、サワラの産卵時期は開始が遅
れましたが、逆に低温のため産卵の終わりが細く長く続いたという特徴があります。漁獲
の経過や年齢別の漁獲の状況から見て、2006年は非常に低温で、産卵に影響は受けた
が、結果として細く長くつづいた産卵で2006年の加入はそれほど悪くなかったと理解
しています。
いろいろと環境が不安定な例を示します。図の横軸が1月から12月の平年の水温の平
均値ですが、それに対して2006年とか2007年がどうかと比べました。香川県の1
0メートル水温の平年偏差ですが、海域は幾つかあります。3つほどまとめて言いますと、
特徴として2006年は先ほど言ったように平年を下回る水温がずっと続き、3月に平年
値を少し超える時がありますが、低温の年でした。2007年は逆に平年より非常に暑く
て、一番高い時は平年偏差より2度くらい高い場合も見られました。魚の場合1度水温が
高いと人間で言えば5度とか10度に相当すると言われています。水温がかなり高いとい
うことがサワラの仔稚魚の生産率を低下させていないか、つまり2007年生まれの生き
残りがどうだったかということを考える上で、水温が高かった影響を考えていかないとい
けないと思います。
資源評価のまとめとして、2007年の資源量は2,282トンで1987年に比べて
14%と低位です。それから2007年の資源水準は低位で過去5年の動向は減少、生物
学的に望ましい漁獲の係数であるF30%は、現状の漁獲の係数に比べて41%、つまり
現状の漁獲圧力が望ましい状態に比べて非常に高い。望ましいというのは生物学的にサワ
ラにとって優しいという意味なんです。現状はちょっと漁獲圧力が高いと評価しています。
それから2007年の加入は生き残りが悪かったかもしれないということで少ない恐れが
あると考えています。このように特徴的な年の状況を言いましたが、環境が不安定に推移
することが多いので、加入が環境の影響を受けやすいということが最近続いていると考え
ています。
次は漁獲量の動向を図にしたものですが、2008年の東西別漁獲量、左側の柱が春漁、
右側が秋漁、高さが漁獲量、それから赤が全年を下回っている場合、青が前年を上回って
いる場合を示しています。ですから東部の場合春漁は前年を上回って1.1倍、秋漁は0.
6倍でした。西部の場合は1.0の赤ですから前年をやや下回ったもののほとんど1に近
い、秋は1.8倍と秋が良かったことを示します。
図は春漁、秋漁を府県別に示したものです。瀬戸内海の内の方で春も秋も青のところが
見られますが、外側では秋が青だけれども、なかには例えば徳島県のように前年比秋が0.
6倍というところもあります。兵庫県は春も秋も0.6倍、大阪府は0.2倍、0.4倍
で、大阪湾あるいは播磨灘のあたりはよくなかったことが分かります。
次は4月から7月を春漁と定義しまして、その東西別の割合を示しています。今度は左
側がサワラ銘柄、右側がサゴシ銘柄の漁獲量です。東部では春にサワラは1.1倍、サゴ
シは1.0倍、合計163トンでした。西部ではサワラが1.1倍、サゴシが0.5倍で、
春サゴシが西部で悪かった。次の図は府県別に示したものですが、サワラでは香川、広島
で前年を上回って、大阪、兵庫などで下回った。サゴシでは香川、岡山、広島で前年を上
回り、兵庫、愛媛で下回った。
次に8月から12月を秋漁として示しています。8月から12月には東部のサワラで前
年を下回り0.4倍でした。サゴシは前年を上回り3.0倍でした。西部についてはサワ
ラもサゴシも前年を上回って1.1倍と6.7倍です。この2008年はサゴシの銘柄が
東部で3.0倍、西部で6.7倍と前年比で高い値が得られているのが特徴です。それを
府県別に示したものが次の図ですが、サゴシでは大阪と大分で前年を下回ったほかは大体
前年を上回るところが多かった。
それでは次に2008年の秋の漁獲の動向について説明します。
これは大阪府の資料ですが、南部の標本組合の機船船びき網漁業の漁獲量を示していま
す。一番上はシラスの漁獲量、縦軸がトンで横軸が1月から12月まで。ヒストグラムが
平年で赤が2008年、青が2007年、黒が2006年の直近3年ですが、平年と比べ
て2008年は10月にシラスが割と多かったというのが特徴的です。
カタクチイワシについては8月、9月がピークですが、前2年に比べて2008年はち
ょっと悪かった。
サワラについては2006年、7年に比べてピークが余りはっきりしない。10月が一
応低いピークなんですが、余りよくなかったということになります。カタクチが余りよく
なかったということでサワラもよくなかったのかと思われます。ただ10月にシラスがと
れたというところが目新しいと思います。
サワラの尾叉長組成の方ですが、これも大阪府の資料ですが、流網の尾叉長組成が主で
す。9月から12月まです。一番上は曳網でして、9月に曳網でとれたものは46センチ
程度で例年に比べて魚体がやや小さかった。小さかったので、これが流網にかかってこな
かった。50センチより小さかったということであまり流網にはかかってこず、9月は1
歳魚、同じく10月、11月も大阪では1歳魚主体の漁獲であり、0歳魚、その年生まれ
のサゴシがとれたのは12月に入ってからだった。
2008年生まれのサゴシは多いんだとか、それほどでもないという情報がいろいろあ
るわけですが、これについてちょっと御説明しますと、2008年の秋のサゴシの漁獲は
香川県の資料では東部の引田で、これが2008年の秋のサゴシですが、加入が非常によ
かった2002年、それからそれ以降比較的よかった2005年に比べて、2008年は
2002年ほどではないけれども2005年並みであるという数字となっています。それ
から西の方の香川県の伊吹の資料では2005年に比べてもやや小さい半分以下の数字に
なっております。それから高松中央卸売市場での9月から12月の香川県産のサゴシの入
荷量、取扱量は2005年あるいは2002年並みの数字になっております。先ほど御紹
介があったように試験漁獲では2002年の0.4倍、2005年の0.8倍ですから、
2002年に比べるとやはりそれほど多くないが、その次に比較的よかった2005年と
同じかやや下回る程度じゃないかという数字になっています。
愛媛県のサワラとサゴシの資料を分析しますと、2008年秋のサゴシの豊度、1隻1
日あたりの漁獲尾数あるいはキログラム数、川之江と埴生ではキログラム、西条と河原津
では尾数です。2002年から2008年について色別に示しておりますが、2008年
のCPUEで見ると川之江と埴生では2002年並み、2002年というのは図で黒です。
西条と河原津では2002年を下回る。このように、2008年が2002年ほどではな
いということで、良いという情報と悪いという情報が半ばとなっています。
それから、同じ愛媛県でも伊予灘では、月別の漁獲量で図はないのですが、サゴシにつ
いて数字を整理したものを県からいただいたのですが、2005年の漁獲量を1としまし
て、2006、2007、2008年の漁獲量はそれぞれ1.5倍、2.2倍、1.9倍
となりまして、2005年に比べて2008年のサゴシは2倍近い漁獲量で、サゴシが比
較的とれています。
管理方策への提言として、毎年70万尾の加入がないと資源は持続しない。親の資源は
2歳魚主体で若齢化しておりまして、年齢構成も単純化している。そのために環境が悪く、
再生産において仔稚魚の生残が悪い年があると、資源が大きな打撃を受ける恐れがあると
考えています。ですから、サゴシの漁獲を抑えて親を残して、加入動向を見守ることが重
要です。そして、環境や加入、再生産の不安定さを考慮しますと資源回復計画での取り組
みの強化が望まれると考えております。
それから、次は補足なんですが平成20年度第1回サワラブロック漁業者協議会、9月
24日の会議で各県の漁業者の方々から研究サイドへいろいろ要望が出ました。大きなも
のとしては3つほど出たんですが、それに対して私の方でできる範囲で資料を整理して回
答したので、簡単にご紹介したいと思います。
1番目は地域別の放流効果、放流しているが、地域別に漁獲量への反映がどうなってい
るのか示してほしいということです。2番目はサワラがどうして播磨灘に入ってこないか
説明してほしいということです。これに対して非常に説明は難しい、なかなかいい説明が
できないのですが、後でお見せする図の2や小路・益田両先生の講演要旨を見てください
と説明しました。それから、3番目に海の変化、瀬戸内海の海の変化とか温暖化に関する
情報を提供してほしいということで、これについては後で表1をお見せしますが、東シナ
海とか日本海、瀬戸内海に関しての状況を私の方でまとめさせてもらいました。参考資料
として委員の先生のところには「海洋と生物について瀬戸内海の魚類生産に変化はあった
か」というテーマで私が書いたものをお配りしております。これはブロック漁業者協議会
でもお配りしたものです。
サワラの放流魚については、ご承知のように内部標識として小さい卵とか仔魚の段階で
赤い標識を入れております。ですから成魚あるいはサゴシでも、漁獲して頭の中の耳石を
調べたら放流物か天然物かがわかります。その天然物に対して放流物の割合が何%かを海
域別、それから年齢別、それから年別に放流魚の混入率としてまとめました。御覧になっ
てわかるように0歳のところでは混入率が非常に高いです。ただ年齢が高くなるほど値は
低くなっています。図には播磨灘の兵庫県、播磨灘の岡山県、播磨灘の香川県などでの混
入率の数字がありまして、これに漁獲物の年齢組成を別に持っておりますので、両者をか
けてどのくらい放流魚が漁獲されているかというのを直近の3年について推定して図中に
数字としてあげています。
ここでちょっと分かりにくいんですが、赤い色は瀬戸内海、兵庫県の播磨灘で再捕され
たものですが、西部放流分を示しています。図では厚みをもっていませんので1尾とか2
尾なんですが、西から東に来たものが再捕されています。それから瀬戸内海西部なんです
が、燧灘、香川県沖、愛媛沖、安芸灘、伊予灘での特徴として、安芸灘、伊予灘では混入
率が低い、放流物の再捕がない。それからもう1つの特徴は香川沖でも愛媛沖でも燧灘に
ついては、この緑色は厚みをもっていますので、瀬戸内海東部で放したものが備讃瀬戸を
通って西部の方にかなりきていることを示します。ただ、東に比べると西では混入率はそ
れほど高くはないということが特徴です。いずれにしても地域別、年別、年齢別にこのよ
うな混入率となっており、それが漁獲量にどう反映しているかをブロック漁業者協議会で
お示ししました。
それから、後で読んでもらえばいいんですが広島大学小路先生、京都大学益田先生、こ
ういった先生方の指摘として、瀬戸内海のサワラを増やすにはやはりカタクチイワシをは
じめとするサワラの餌となりうる資源の管理をきちんとしないと本格的な回復はないんじ
ゃないかという指摘がなされています。
それについて同じようなことなんですが、灘別にカタクチシラスの漁獲量とかシラスと
カタクチイワシの漁獲量の比、そういったものを灘別に私の方で整理しています。言いた
いことは、シラスの漁獲量が瀬戸内海東部の方で多いものですから、資源としては安定し
ていてもカタクチイワシの影を見ることがどうしても少なくなる。カタクチイワシがいれ
ば、2004年の春に五色で見られたように、カタクチイワシにサワラがつくというふう
なことがありますので、やはりシラスで先取りしてカタクチイワシの影が薄いと、サワラ
が滞留する機会というのは少なくなってくるのだろうと考えています。ただ、シラスとい
うのは非常に大きな漁業を支え、商業的にも価値が高いですから、そっちの方が重要だと
考える行政の方もいるし、漁業者の方もいるわけで、なかなかその辺が難しいところだと
思います。
あと東シナ海、日本海についてはどういった異常現象が見られるかということで1つだ
け言いますと、サワラの東シナ海系群に見られる漁獲量の北への偏りは1999年以降に
日本海の北区で始まりまして、2000年以降太平洋北区、要するに青森の三沢の方や福
島の方で漁獲がかなりあがってきているという情報があります。もう1つ言えば例えば従
来沖縄の魚であるグルクン、これが沖縄での漁獲量が減って、2005年から長崎とか宮
崎で漁獲量が増えていたのが、2008年には福岡で増えているというふうに魚の分布が
更に北へ上がってきているような傾向があります。以上こういったことを瀬戸内海ブロッ
ク漁業者協議会で報告させていただきました。
以上です。
(前田会長)
どうもありがとうございました。
ただいまの説明によりますと、サワラの資源状況につきましては平成19年の資源水準
は低位で動向は減少傾向にあるとのことです。また親魚資源は2歳魚が主体で若齢化し年
齢構成が単純化しているため、再生産や稚魚の生産が悪いと資源に大きな影響を与える恐
れがあるとのことでございます。このため環境や加入の不安定さを考慮すると資源回復計
画での取組強化が望まれるとのご報告でございました。
何かこのご報告に対して質問等がございませんでしょうか。
それではないようですので次に移ります。平成21年度の取組の審議に移ります。
昨年10月の委員会におきまして、休漁期間の変更に関する検討状況の報告がありまし
た。それによりますと伊予灘関係県で休漁期間変更に関する検討を進め、ブロック漁業者
協議会において意見集約を図り、本日の委員会で計画変更について審議したいとのことで
した。
まず事務局より伊予灘の休漁期間の取り扱いを含めた平成21年度の取組について説明
していただきまして、その後、配付資料には含まれておりませんけれども新たな資源管理
体制の構築に向けた検討を行っているということでございますので、その検討条件につい
て報告していただきます。それでは事務局、よろしくお願いします。
(平松計画官)
では、資料につきましてはサワラ資料の1−3でございます。
まず始めに、先ほど会長の方からもございましたとおり伊予灘の休漁期間の変更に関す
る検討状況、検討結果でございますが、前回の委員会では試験操業ですとか既存の研究デ
ータを基にした行政研究担当者会議の検討結果といたしまして、休漁期間を変更しても現
状より漁獲量が増加する可能性が低いということが考えられる等の報告を行い、またこれ
らの結果を踏まえまして伊予灘の関係県におきまして休漁期間の変更案に対する検討を進
めるとご報告いたしました。それらを2月に開催されますブロック漁業者協議会で持ち寄
り、検討を加えて意見の集約を行うということでその後の取組の方針を説明させていただ
きました。
これにつきまして昨年の10月以降、伊予灘関係県の方で検討が行われてきたわけでご
ざいます。2月にブロック漁業者協議会が開催されましたが、その場で伊予灘の関係県と
いたしまして山口県それから大分県、こちらの漁業者協議会の代表委員の方から県内の協
議状況についてご報告がございました。両県ともこの休漁の期間変更については了解する
ということでございました。これらを受けまして2月10日に開催されましたブロック漁
業者協議会におきましては、この伊予灘の休漁期間を15日間後ろの方へずらすという変
更案について了解が得られたというところでございます。これらを踏まえまして本日、来
年度のサワラ計画の取組案ということでまとめさせていただいてございます。
それでは、資料1−3表紙をめくっていただきまして、1ページの漁獲努力量削減措置
(平成21年度案)という地図のページをご覧ください。
内容につきましては、ただいま申し上げましたとおり伊予灘海域での休漁期間につきま
してサワラ流し網漁業(山口・愛媛・大分)としているところですが、こちらの休漁期間
5月16日から6月15日ということにさせていただいております。これが、本年度5月
1日から5月31日までとしていたところからの変更箇所でございます。
その他の海域につきましては、本年度と全く同様の休漁期間として実施したいと考えて
ございます。また、瀬戸内海全域での流し網の目合い規制10.6センチにつきましても
今年度と同様の内容となってございます。来年度の漁獲努力量削減措置につきましては伊
予灘を変更した形でこのような取組で進めたいと考えてございます。
つづきまして、2ページめくっていただきまして種苗生産・中間育成・受精卵放流の取
組、来年度の実施予定を載せてございます。
同様に3ページには広域漁場整備及び漁場環境保全の来年度の事業の実施予定を取りま
とめてございます。放流それから漁場整備、両方につきましておおむね今年度と同じ内容
の実施予定をしてございます。来年度の漁獲努力量削減措置、種苗放流、漁場整備につき
ましてはただいまご説明申し上げました内容で実施したいと考えてございます。
このうち、休漁期間に係ります漁獲努力量の削減措置につきましては休漁期間変更とい
うことでございますので、資源回復計画本文の変更が必要になってまいります。こちらに
つきまして資料の4ページから8ページにかけまして、サワラ瀬戸内海系群資源回復計画
一部変更案という形で新旧対照表のスタイルで載せております。表の右側が現在の回復計
画の文章、左側が変更案になってございます。資料の4ページ、新旧対照表になる部分で
すが、こちらの一番下のところ、漁獲努力量の削減措置の表にあります伊予灘の部分でご
ざいますが、こちらにつきまして現行の5月1日から5月31日という期間を表の左側の
5月16日から6月15日というふうに変更をさせていただきたいと考えてございます。
また、規制措置の内容の変更はこの点のみですが今回の一部変更に併せまして7ページ
にございます海域の定義の中の灯台名につきまして通称名から正式名称に改めさせていた
だくという措置を1ヶ所させていただきたいと考えてございます。変更箇所はその2ヶ所
でございます。
それから資源回復計画におけます休漁等の措置につきましては、これらの措置を担保す
るための瀬戸内海広域漁業調整委員会指示につきましては資料の9ページから11ページ
に案を載せてございます。
こちらの内容につきましては、11ページをご覧いただきたいんですが先ほどご説明い
たしました伊予灘の休漁期間、こちらにつきまして変更後の休漁期間に対応した内容での
設定を考えてございます。
以上が平成21年度のサワラ資源回復計画の措置案でございます。
それから、これから資料はございませんので口頭での説明をさせていただきたいと思い
ますが、このほかに現在資源管理体制の構築に向けた検討といたしまして2つ行ってござ
います。
1つは資源回復計画の取組の強化に関すること、それから2つ目が平成23年度以降の
放流体制の検討に関してでございます。
まず1つ目の回復計画の取組強化に関しましては、サワラ資源の回復に必要な産卵親魚
の確保につきまして、現在の資源水準から考えますと一律に漁獲量を減らすような取組と
いうものは、少ない漁獲量を更に減らすということになるため実現性が困難と考えてござ
います。従いまして、卓越年級群の発生など例年以上の漁獲が見込まれる場合を想定いた
しまして、あらかじめ未成魚の保護による親魚量のかさ上げについて、これらの方法につ
きまして検討しておくことが重要と考えているところでございます。
また、平成20年級群につきましてはある程度の加入量が期待できるということもござ
いまして、早急にそれらの検討を進める必要があると考えているところでございます。こ
のような考え方によりまして、1つの例といたしまして好漁日、漁獲のいい日が2日連続
すれば3日目を臨時休漁にするという取組を想定いたしまして、それらの取組よってどの
ような効果が発現するか、また実際の漁獲の減少がどの程度かというようなことについて
これらの漁獲増加の取り控え効果というものについて検討をしてございます。現在、各地
域の実情に見合った方法というものにつきまして、各府県、地域での検討を行っていただ
くよう行政研究担当者会議、またブロック漁業者協議会において各府県に要請していると
いう状況でございます。これが1つ目の取組強化に関する検討の状況のご報告でございま
す。
つづきまして2つ目のサワラ種苗放流体制の検討状況という部分でございますが、サワ
ラ資源回復計画におきまして種苗放流は漁獲努力量の抑制との一体的な推進が必要とされ
ているところでございます。現在の種苗放流の体制に当たりましては、水研センターの関
与が大きいところでございますが、その水研センターの取組の根拠となります水研センタ
ーの中期計画というものが平成22年度で終了するということ。また、サワラのような広
域回遊種についての国の関与、栽培、放流に対する国の関与を定めております栽培に関す
る基本方針につきましても、平成21年度で終了するということになってございます。
このような状況から、これらの次の基本方針、次期の水研センターの中期計画に瀬戸内海と
しての要望内容等が反映されるよう今年度1月26日の行政研究担当者会議からこの種苗
放流体制、23年度以降の種苗放流体制のあり方について検討を始めたというところでご
ざいます。まだ、検討を始めたばかりでございますので、その具体的内容について、現時
点でご報告できるまでには至っておりませんが、今後、水産庁の本庁また水研センターの
これらの関係する動きを注視しつつ検討の進捗状況に応じまして、適宜ご報告できればと
考えているところでございます。
以上2点口頭でのご報告になりますが、資源管理体制の構築に向けた検討状況について
ご報告しました。これらを含めました来年度、平成21年度の資源回復措置、サワラ回復
計画の取組案と考えてございます。来年度の取組案につきまして、ご審議よろしくお願い
いたします。
(前田会長)
平成21年度の取組の案につきましては、伊予灘の休漁期間についてこれまでの検討を
踏まえ5月1日から5月31日の休漁期間を5月16日から6月15日までに変更したい
とのことでございました。これに伴いまして、資源回復計画を一部変更し本委員会指示に
つきましても変更後の休漁期間に対応した内容により設定するとともに種苗放流等の取組
については本年度と同様の内容で実施したいとのことでございます。
また、後半の新たな資源管理体制の構築に向けた検討につきましては、資源回復計画の
取組の強化及び種苗放流体制の検討に関して行政研究担当者会議等での検討状況及び今後
の検討の進め方について報告がございました。
なお、紀伊水道外域につきましては、2月24日に開催されました「和歌山・徳島連合
海区漁業調整委員会」におきまして、本委員会指示の案が決議されれば本年度と同様の連
合海区委員会指示に従うことが決議されております。
また、宇和海につきましても3月12日に開催予定の愛媛海区漁業調整委員会において
本年度と同様の海区委員会指示を決議する予定となっております。
これから質疑に入りますけれども、まず始めに平成21年度の取組の案につきまして何
かご質問等がございましたらお願いいたします。
ご意見もございませんようですので、それでは「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平
成21年度取組(案、本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員) 会指示(案)につ
いて」承認したいと考えますがよろしいでしょうか。
それでは委員会として「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平成、21年度取組(案)、
本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員会指示(案)について」承認をいたします。
引きつづきまして、第2点目の新たな資源管理体制の構築に向けた検討が行われている
資源回復計画の取組強化及び種苗放流体制の検討状況についての報告がございましたけれ
ども、これにつきましてご質問等がございませんでしょうか。
(高橋委員)
この問題につきましては、この委員会で擁護するというのがいいのかどうかよくわから
ないままに申し上げたいと思います。
行政の方でも将来的な取組というのを検討なさるというようなことでありましたけれど
も、この資源管理についての取組というのは漁業者自身、我々もある意味ではそうだとは
思うんですけれども、今の取組がやっとこさよちよち歩きの状態なんです。これで計画期
間が終わったからおしまいよというのでは、せっかく取り組んだのがほっぽり出されると
いうような気がしてならない。そういう意味では、やはり行政からも当然そういうご意見
が出るんだと思うんですけれども、これは続けてやっていただかないと、せっかく今まで
取り組んできたのが終わってしまうというような気がしますので、国におかれてもこの問
題についてはどうぞ息の長い取組をお願いしたい。
(前田会長)
今後とも水産庁と言いますか、行政サイドでの取組も今までと同様の指導してほしいと
の要望でございます。
何か事務局の方でございますか。
(平松計画官)
今おっしゃられたのは平成23年度まで今の計画期間、5年延長した第2期の計画期間
がございまして、先ほど放流につきましてはそれ以降の体制についていろいろ関係の長期
計画等の進捗に合わせて検討を進めたいという報告をさせていただいております。
後ほど予算の説明の中で本庁から今後の制度的な話も予定しておりますが、サワラにつ
きましても放流だけでなく全体の取組を今後どうしていくかというのは、当然現在の取組
期間の終わりに向けてしかるべきときに具体的な検討を進めていかないといけないとは認
識してございます。その中で一番いいやり方、どのようにやっていくかということを十分
関係の機関とも検討しながら進めていきたいと考えます。
以上でございます。
(前田会長)
どうもありがとうございました。よろしいですか。
ほかにございませんか。
- 17 -
(荒井委員)
回復計画の取組を強化するということで、今1つのアイデアをご提示されましたけれど
も、2日続けていい漁があれば1日休むと、それも1つのアイデアだと思うんですけれど
も、他の魚種あるいは他の海区でこういった取組をやってうまくいってると、あるいはう
まくいくんじゃないかどうかという事例があればちょっとご紹介していただければと思う
んですけれども。
(前田会長)
ございますか、事務局の方で。
(佐藤所長)
実は私ども資源回復計画を最初に立ち上げたときに、これは白書にも載ってますけれども
太平洋のマサバである程度成果が出たんですけれども、要するに魚を増やすということは
獲り控えをするということです。獲り控えをすると何が起こるかというと、ぎりぎりの経
営をやっているというところで更に取るなと、これを要求していかざるを得ない。ところ
が、うまいことに自然の中でたまにボーナスが出ると言ったら変ですが、実は経営に負担
を与えないで資源を回復する道が時々あるんです。それが実は卓越年級群が出たときに、
そのボーナスをできるだけ手をつけないで貯金しておくと。普通の生活費でぎりぎりして
いる人に魚を取るなというのはこれは非常に難しいんです。特に今年さっきの報告にもあ
りましたように、地域によっては相当漁獲量が減っております。平均ですると前年度より
ちょっとかもしれません。だけど播磨灘のように過去に比べて非常に減ってるところ、さ
らに、中間育成までやっている漁業者にとっては、とてもじゃないですけれども受け入れ
られない。そう見ると資源を回復するには、誰に獲る量を減らしてもらうのか。やっぱり
ある程度取れて生活が維持できる人にそこの負担をしてもらおうじゃないかと。それと、
先ほど言いましたように、もしかすると本年度とか20年度に卓越年級群が発生している
可能性がある。そうすれば過去と同じ獲り方をすればたくさん残せるため、昨年と同程度
に我慢をしようと。そういう発想で実は太平洋のマサバのときも経営の維持をすると同時
に、もう一方のボーナスが出たときに欲というものをいかに抑えるか。そこである一定以
上取れた翌日は確実に休むと、それを連続してやったわけです。その成果として漁獲量は
減らないけれど大きな魚が残って翌年から、収益が上がってきたという1つの事例があり
ます。だから、そういう経営と資源の回復をうまくマッチングするタイミングが今回出て
きたんではないかということで、それに期待しているということになりますので、以上で
ございます。
(前田会長)
ありがとうございます。ほかにございませんか。
それでは、サワラ資源回復計画は種苗放流と資源管理の取組を大きな柱としております。
サワラ資源が減少傾向にある中で今後この取組をどうすべきかは、重要なテーマであると
考えますので事務局におかれましては引きつづき検討を進めるようお願いを申し上げたい
と思います。
なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正
式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部
分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承お願い申し上
げます。
(議題2 周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について)
(前田会長)
それでは、再開いたしたいと思います。
つづきまして、議題2の「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部変更
について」に入らせていただきます。
本計画につきましては、前回の委員会で計画延長の骨子について承認しておりますので、
今回は計画延長を内容とした資源回復計画の一部変更について審議を行うこととなってお
ります。
まず、始めに事務局より平成20年の漁獲状況及び本計画の延長について説明していた
だいたあと、計画の一部変更の案についてご審議いただきたいと思います。それでは事務
局から説明をお願いいたします。
(平松計画官)
それでは、周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画に関しまして、資料は資料
番号の2−1から2−3までが関連の資料でございます。
まず始めに資料2−1に基づきまして漁獲状況のご報告、それから資料2−2と2−3
を用いまして延長計画の内容について続けてご説明をさせていただきます。
資料2−1をご覧ください。平成20年の漁獲状況につきまして、先ほどサワラの漁獲
量でもご報告申し上げました平成20年下半期の速報値が2月に公表されましたので、上
半期の数字と合わせまして平成20年の速報値ということでまとめさせていただいており
ます。
こちらによりますと、平成20年は1,751トンということで19年の速報値1,8
70トンに比べまして約6%減少という結果になってございます。それぞれ周防灘計画の
対象魚種ごとの内訳が資料の2−1の下の魚種別の表に載せているとおりでございます。
この中で前年よりも漁獲量が増えておりますのがクルマエビとガザミでございます。一方、
漁獲量が特に減少が大きいのがシャコでございまして320トンが207トンに減少して
いるということでございます。周防灘につきましては漁法別の漁獲量の集計がちょっと時
間を要するということで、確定値は平成18年までということでございまして表に数字を
記載しているとおりでございます。20年の漁獲状況につきましては簡単でございますが、
以上でございます。
つづきまして、計画延長につきまして考え方のご説明をさせていただいて、計画変更案
についてご審議いただきたいと思っております。
まず計画延長の内容につきまして取組の基本的な方針、内容につきまして資料2−2「周
防灘資源回復計画の延長について」という資料にまとめてございます。こちらの資料1ペ
ージをご覧ください。1番といたしまして資源回復措置の継続の必要性ということで、こ
れまでの骨子等でまとめさせていただいた内容を簡単に整理をさせていただいてございま
す。回復計画に取り組んできておりますが、効果も上がっている部分もございますが、引
きつづき取組の継続というものが重要なポイントになっていると考えてございます。この
ような考え方のもと、計画を延長して進めたいということでございますが、まず1ページ
の2番のところに資源回復の目標といたしまして、実施期間と計画の目標を載せてござい
ます。
まず実施期間につきましては(1)にございますように本計画の実施期間は平成25年
度までとするということで、現在の計画が16年11月に作成されて5年間ということで
すので、21年の11月に5年間期間が満了するということでございますが、これを更に
延長するという考えでございます。前回の委員会で骨子の了解をいただいたときにはここ
は平成23年度までとさせていただいておりましたが、回復計画の実施期間が25年度ま
でこの制度としての実施期間が延びるということで、それにあわせて25年度までの延長
としたいと考えてございます。従いまして来年度、21年度からちょうど5年間の取組に
つきまして第2期の取組というような位置づけで今後2ページ以降に記載してございます
内容を中心に進めてまいりたいと考えてございます。
それから、資源回復の目標につきましては現在の計画の目標でございます平成16年の
漁獲量の水準、数字で言いますと2,123トンということになりますがこちらの維持と
いう目標を引きつづき掲げて取り組んでいきたいと考えているところでございます。
それでは、ページをめくっていただきまして2ページ目以降に実際にどのような取組を
行っていくかということで3番の資源回復のために講じる措置というところ以降に取りま
とめてございます。
まず(1)の漁獲努力量の削減措置につきましては、まず?の小型魚の水揚げ制限、こ
れは現在取り組んでおります制限サイズを引きつづき継続実施すると考えてございます。
2つ目の取組といたしまして、シャワー設備の導入がございますがこちらのところで資
料の中にアンダーラインを引いている部分、こちらがこれまでの取組にプラスした部分、
検討の方向性も含めまして今回の計画延長に当たりましてこのような観点の取組を進めて
いくという部分の追加部分をアンダーラインをしております。シャワー設備の導入でいき
ますと、これまでの再放流魚の生残率の向上というものに加えて、持ち帰り出荷する漁獲
物の鮮度維持というもの、これをシャワー設備の導入の目的の中に位置づけとして追加す
るということで取り組んでいきたいと考えております。
現在、山口県、福岡県、大分県の3県のうち大分、福岡が導入済みということで山口県の方で今、順次導入しているという
ところでございますので、未導入船につきまして先ほど言いました再放流魚の生産率の向
上に加えた、漁獲物の鮮度保持というものを目的に加えまして導入促進を推進していきた
いと考えているところでございます。また鮮度維持ということに関しまして現在、夏場に
機能を発揮します簡易冷却装置の現場での応用試験というものも進められておりますの
で、これらの取組も推進していきたいと考えております。それらを含めて効果的なシャワ
ーの活用方法というものも考えつつ、効果的なシャワーの利用というふうなものを推進し
たいと思っているところでございます。
それから、産卵親魚の保護といたしまして実施しております抱卵ガザミの再放流につき
ましては、現在取り組んでいるとおり継続していくということ、また休漁期間の設定につ
きましてはこちらは海底清掃等の漁場環境改善の取組とあわせて実施するという考えを今
後も継続するということで考えてございます。
?といたしまして、漁具の改良がございます。これはこれまでの取組の中でも進めてま
いりましたが、それら試験研究をより推進することを考えておりまして現在幼稚魚の混獲
防止漁具の性能試験も実施されておりますので、このような取組について実用化に向けた
推進を行ってまいりたいと考えているところでございます。
以上が漁獲努力量の削減措置でございますが、回復計画の2つ目の柱でございます資源
の積極的培養措置ということで、これは主に種苗の放流というものになりますがこちらに
つきまして2ページから3ページに記載しております。この回復計画を進めるに当たって
今年度から事業として立ち上がりました資源管理アドバイザー制度等を活用しつつ、この
3県の連携、協力というものによる放流体制の構築というものを推進していきたいと考え
てございます。特にクルマエビにつきましては、山口、福岡、大分の3県で共同した事業
も実施してございますので、これらの事業の推進というものを図っていきたいと考えてご
ざいます。
3つ目の柱として漁場環境の保全措置ということでございますが、こちらは水産基盤整
備事業等の漁場環境改善の事業について取組を引きつづき行いたいと考えております。
資源回復のための措置といたしましては、以上3本柱の内容でございます。次に資料の
3ページの4番にございます漁業経営安定の取組ということでこちらは今後この資源回復
計画によりまして、資源の回復、漁獲の増大というものを進めていく取組にあわせまして
経営的な観点での検討を並行して実施していく。これは今回新たに盛り込んだ内容でござ
います。
大きな柱としましては2つございまして1つがコストの削減ということでございます。
燃油につきましては昨年度非常に高騰いたしまして、こういうコスト削減、特に燃油の使
用の抑制等の取組というものの重要性が出てきておるわけでございますが、このような観
点での操業コストの低減策ということについて検討するというのが1 つでございます。
2つ目といたしまして先ほどのシャワー設備のところでも申し上げましたが、漁獲物の付
加価値向上、単価アップ等に向けた取組ということについて、各種検討をあわせて実施し
ていきたいと考えているところでございます。これら、資源回復措置の取組プラス漁業経
営安定の取組という観点で来年度以降の取組を進めたいと考えているところでございます。
その他、3ページの中段以降にございます5番の公的担保措置、6番の支援策等につき
ましては従前どおりの体制で進めていきたいと考えているところでございます。
最後、資料は4ページになりますがその他といたしまして、これは今までの回復計画の
中でも取組として進めてきたところでございますが、他漁業への取組の拡大というような
部分につきましては現在、カニ籠漁業のカニ籠目合いの適正化試験というものも実施され
て小さなカニ、ガザミですがこれを漁獲しないようにするための検討ということが進めら
れてございますので、そのような取組をこの関連漁業へのアプローチというようなことで
進めていきたいと、このような取組を推進していきたいと考えてございます。このような
考え方のもと、来年度以降の5ヵ年間の取組を第2期の取組として進めていきたいと考え
てございます。
回復計画につきましては今申し上げましたとおり実施期間の延長ということになります
ので、計画変更が必要になります。そちらにつきましては資料2−3、1 枚資料、裏表印
刷しているものでございます。こちらも新旧対照表によります変更案ということで、表の
右側が現行の計画、左側が変更案ということで整理をしてございます。変更箇所としまし
ては、資料2−3の1ページのちょうど中ほどの行に当たりますが、資源回復目標の中で
実施機関に係る部分、現行では当面の5年間としている部分を平成25年度までの間とい
うふうに改めたいと思っております。また、平成16年の漁獲量が統計の数値が公表され
ておりますので2,123トンという具体的な数字を盛り込むということにしてございます。
変更内容は以上の2点ですが、実施期間につきましては1ページ目の一番下の2行にご
ざいますように、もう1ヶ所実施機関が当面の5年間が平成25年度までの間というふう
に記載されている部分がございます。
変更箇所は以上でございますが、2ページ目にございます海域の定義の基点のところに
つきましても市町村合併に伴う市町村名の修正と、灯台等の名称を正式名称に改めるとい
うことで一部記載内容が変わってございますが、実際の基点そのものにつきましては変更
ございません。表現方法の変更をこの計画変更にあわせて行いたいと考えてございます。
周防灘計画の延長の取組内容・方針、それから資源回復計画の一部変更案につきまして
は、以上でございます。
(前田会長)
計画の延長につきましては実施機関を平成25年度までとし、現在実施している漁獲努
力量の削減措置を継続しつつ漁獲物の鮮度維持等の漁業経営安定の取組に検討を進めてい
るとのことでございました。
それでは、ただいまの説明につきましてご質問がございませんでしょうか。
それでは、ないようですので「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部
変更(案)について」承認したいと思いますがよろしいでしょうか。
ありがとうございました。それでは、委員会といたしまして「周防灘小型機船底びき網
漁業対象種資源回復計画の一部変更(案)について」承認をいたします。
なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正
式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部
分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承をお願い申し
上げます。各関係、各委員におかれましては本計画の適切な実施について、よろしくご指
導お願い申し上げます。
(議題3 カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について)
(前田会長)
「つづきまして議題3のカタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について」
に入ります。
まず、20年度の実施状況と資源状況などについて事務局より報告していただきまして、
引きつづいて21年度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。
また、計画作成後4年が経過し、来年3月で計画期間満了を迎える本計画の評価という
ことで事務局より報告していただきます。それでは、本年度の実施状況などにつきまして
事務局から報告お願いいたします。
(中奥資源保護管理指導官)
瀬戸内海漁業調整事務所、中奥です。よろしくお願いいたします。
それでは着席させていただきましてご説明させていただきます。
では、20年度の取組について資料3−1をご覧ください。対象漁業の許可期間は1ペ
ージの(1)に示すとおりでございます。これに対しまして資源回復措置としましては(2)
にあります休漁期間と(3)にあります定期休漁日を設定し取り組まれました。本年度定
期休漁日につきましては広島県が燃油高騰の要因もあり、従来の木曜日に加えて日曜日も
追加実施されました。20年度の操業実績といたしまして(4)にありますとおり瀬戸内
海機船船びき網につきましては広島県は6月13日から10月10日まで、香川県は6月
10日から9月10日まで、愛媛県は6月10日から9月10まで、愛媛県のいわし機船
船びき網では6月10日から8月17日までとなっております。
次に燧灘のカタクチイワシの資源状況です、2ページをご覧ください。資源状況につき
ましては関係3県の広島県、香川県、愛媛県の水産試験研究担当者の方々により資源解析
が行われた結果です。
(1)は漁獲量の動向です。平成18年までは農林水産統計から、平成19年、20年
は共販量からの推定量をグラフにしました。平成20年の漁獲量はカタクチイワシとシラ
スを合わせて1万4,540トンと前年の108%となっております。
(2)は初期資源尾数の動向です。本計画の目標は回復計画開始当初の資源尾数水準、
これは平成12年から16年の平均で346億尾です。この水準と計画期間終了後に同程
度維持することとしております。その基準である資源尾数は、春季発生群の初期資源尾数
を用いることとしています。グラフはその動向について示しております。平成20年につ
いては水準より若干低い値、340億尾で目標の98%となっております。
(3)は初期資源尾数の漁獲率の動向を示しております。グラフのとおり資源量に対す
る漁獲率は(2)の資源尾数をベースに出しているため、このように高い値となります。
それを踏まえて見てみますと、例年86%前後で推移し平成20年も平年並みの値となっ
ております。
(4)は資源状況の考察です。3県の水産試験研究担当者の資源解析、燧灘のカタクチ
イワシ漁獲量及び瀬戸内海系群カタクチイワシの資源評価結果から判断して、資源水準は
中位、動向は横ばいとの評価が出ております。
次に、脂イワシ調査結果について3ページに取りまとめております。本調査は19年度
から関係3県と瀬戸内水研が協力して調査を開始したものです。19年度の結果報告から
脂質含有量と製品単価の急低下との関連から脂質含有量が2%以上のものを脂イワシと仮
定義したことから、今年度も引きつづき調査を行い図1のように脂質含有量と肥満度の間
に正の相関が見られたことから、脂イワシの判定指標として肥満度が利用できると判定し
ました。図1の脂質含有量2%のときの肥満度は約10であり、肥満度10を脂イワシの
発生警戒値とする結果を得ました。
20年度の取組状況については以上です。
(前田会長)
ただいまの説明によりますと、本年度は広島県の定期休漁日について従来の木曜日に加
えて日曜日も追加して実施されたとのことでございました。また、燧灘のカタクチイワシ
の資源水準は中位、動向は横ばいとのことでございます。ただいまの報告について、何か
ご質問等がございませんでしょうか。
ないようですので、つづきまして平成21年度の取組について事務局から説明をお願い
いたします。
(中奥資源保護管理指導官)
21年度の取組案につきましては、資料3−2をご覧ください。
1ページ目、平成21年度の資源回復措置の取組としまして2と3にあります漁期始め
及び漁期終期の休漁、定期休漁日の設定につきまして従来と同様に継続することとしてお
ります。また、漁期始め及び漁期終期の休漁期間の担保措置としまして本委員会指示を平
成20年度と同様の内容で設定したいと考えております。本委員会指示の対象海域は2ペ
ージの図に示しております。3ページには本委員会指示の案を添付しております。なお、
2月12日に開催されましたカタクチイワシブロック漁業者協議会において21年度取組
案及び本委員会指示案につきましては了解が得られております。また、20年度取組でご
紹介しました脂イワシに関する調査につきましても引きつづき瀬戸内水研と関係3県が協
力して続けることにしております。
21年度の取組案につきましては以上です。よろしくご審議お願いいたします。
(前田会長)
平成21年度は引きつづきまして従来と同様の資源回復措置を実施し、本委員会指示に
つきましても本年度と同様の内容で行いたいとのことでございます。また、脂イワシに関
する調査についても引きつづき行われるとのことでございました。
ただいまの説明に対してご質問等ございませんでしょうか。
、「( それではないようですので平成21年度取組案)及びこれに係る本委員会指示(案)
について」承認したいと考えますがよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声)
(前田会長)
委員会として「平成21年度取組(案)及びこれに係る本委員会指示(案)について」
承認をいたします。
それでは、次に本計画も計画作成から4年が経過し、来年度が最終年度となっておりま
す。こうした状況を踏まえまして、事務局から本計画のこれまでの取組に対する評価につ
いて報告していただきたいと思います。では、事務局よろしくお願いいたします。
(中奥資源保護管理指導官)
4年間の取組状況を評価にまとめておりますので資料3−3をご覧ください。
まず、計画の概要といたしましては1ページの2にあるとおり瀬戸内海海域におけるカ
タクチイワシに対する漁獲圧力は経年的に高い傾向であり、現在の比較的安定した加入状
況が悪化すれば資源悪化や漁獲量減少を招く恐れがあるため、現状の水準を下回らないよ
うに資源量を維持する必要があります。そのために、資源回復の目標としまして5年間の
計画期間後に燧灘のカタクチイワシの資源尾数水準を計画開始前の平成12年から16年
の平均と同程度に維持することを目標にしました。講じている措置は休漁期間の設定と、
定期休漁日の設定となっております。
次の3の計画実施状況ですが、6ページ以降に添付しております図表をご覧いただきな
がらお聞きください。まず、漁獲努力量削減措置の実施状況を6ページの表1と表2にま
とめております。
表1では本計画で定められた休漁期間に加えて自主休漁が取り組まれておりますので、
その内容を整理しております。まず、広島県の瀬戸内海機船船びき網漁業の17年度を例
に説明しますと、表にあります操業開始日とは計画上6月10日から操業できるところを
実際に操業を開始された日が6月13日であり、定められた休漁期間に加えて6月10、
11、12と3日間の自主休漁を実施されたことから(A)の自主、休漁日数3という整
理をしています。同様に操業終漁日では11月30日まで操業できるところを実際は10
月31日で終漁されたということなので、定められた休漁期間に加えて30日の自主休漁
を実施され(B)の自主休漁日数30で、17年度の広島県の合計自主休漁日数は33日
となります。そのほか、表にまとめた以外にも天候や魚の状態で臨時休漁も適宜実施され
ております。
表2では定期休漁日について取りまとめました。平成20年度の広島県は先ほども報告
しましたとおり、燃油高騰の要因もあり木曜日のほか暫定的に日曜日が追加されました。
なお、本計画に定められました休漁期間に対しては本委員会指示が毎年設定されておりま
す。また、平成19年度に愛媛県宮窪町漁協所属のいわし機船船びき網漁業1ヵ統の本計
画参加により、対象海域拡大の一部変更を行いました。5ページの図1が拡大しました対
象海域になっております。
次に、支援事業について7ページ表3にまとめたとおり愛媛県で平成18年度から延べ
54隻日、494万6千円の休漁漁船活用支援事業で漁場監視が実施されております。以
上が漁獲努力量削減措置に関する実施状況です。
次に関連調査としまして、資源評価については関係3県と瀬戸内海区水産研究所が協力
して行っており、8ページの表4にあるとおり卵稚仔調査や表5の脂イワシに関する調査
が実施されております。餌料環境調査、脂質含有量調査、発生要因分析などを行い、基礎
データの収集や肥満度を利用した脂イワシの判定指標の検討など研究が行われておりま
す。
次に資源動向と漁獲量の推移ですが、9ページの図2をご覧ください。燧灘のカタクチ
イワシの資源動向は春季発生群の初期資源尾数について平成5年以降のデータをもとに推
定されております。グラフに示すとおり平成5年以降は減少傾向で、平成8年に138億
尾と最低の水準になりましたが、その後、回復傾向で平成12年以降は300億から40
0億尾の水準を維持しております。
次に漁獲量ですが、10ページの左上の図3をご覧ください。燧灘での近年のシラスを
含む漁獲量は1万1千トンから1万7千トンで推移しており、平成12年から20年の平
均漁獲量は1万4千トン程度となっています。
次に県別に見ますと、図4の広島県では平成15年に3千トンを超えましたが、その後
は1千トン前後で推移し、図5の香川県では平成17年に1万トンを超えましたが、その
後はおおむね7千トンで推移しております。図6の愛媛県では3千トンから5千トンで推
移しております。
また、各県の銘柄別共販量とその割合から漁獲の主体を見てみますと、瀬戸内海機船船
びき網漁業では11ページの図7からご覧ください。上段のグラフが銘柄別の漁獲量、下
段が銘柄別の構成割合になっております。図7の広島県ではチリメンを主体に漁獲してお
り、図8の香川県では中羽を主体に小羽から大羽を漁獲、12ページの図9の愛媛県では
中小羽を主体に小羽から大羽を漁獲、図10のいわし機船船びき漁業ではカエリを主体に
チリメンを漁獲しています。このことから、漁獲対象が広島県はチリメン主体、香川県及
び愛媛県は煮干加工向けのサイズを主体に、いわし機船船びき網漁業においてはカエリ、
小羽を主体にそれぞれ漁獲しているようです。
次に目標達成状況ですが、戻りますが9ページの図2をご覧ください。本計画の資源回
復目標は、5年間の計画期間後に燧灘のカタクチイワシの資源尾数水準を計画開始前の5
年間、平成12年から16年の平均と同程度に維持することとしております。この指標と
して用いる資源尾数は、燧灘の資源評価で算定された初期資源尾数です。図2に引いてお
ります破線は回復目標の指標であります平成12年から16年の平均値である346億尾
を示し、計画開始後の平成17年から折れ線を太線で表しております。達成状況について
はご覧いただいているとおり、平成20年の資源尾数は340億尾で目標である346億
尾の98%であり目標水準で安定しております。
最後に評価と今後の課題としてまとめておりますので、本文4ページをご覧ください。
本計画を4年間実施してきた評価として、現時点でカタクチイワシは産卵親魚量と加入量
の間に明瞭な関係が認められていないため、資源管理措置の効果を定量的に判断すること
はできませんが、初期資源尾数が安定的に確保され漁獲量が一時期の低水準より回復し安
定していることから措置はおおむね妥当であると考えます。また、瀬戸内海区水産研究所
の指導のもと、関係3県の協力で資源評価体制が確立され、またその体制により脂イワシ
の判別法で化学分析を必要としない簡易な肥満度を活用できることが明らかにされたとこ
ろであり、操業方法の改善に寄与することも期待できます。
次に今後の課題ですが、漁獲努力量削減措置は評価で述べましたとおり一定の効果があ
ったと考えますが、今後の資源量の維持、安定を考えますと資源予測の精度を高め資源動
向に即した措置について検討が必要であります。また漁獲動向や脂イワシの発生により製
品価格の年変動が大きいため脂イワシ発生のメカニズム解明に期待されていますが、その
研究成果をいかに現場で活用していくかが重要であります。更に、脂イワシの発生による
価格低下から漁獲金額の向上の取組として、漁獲物の付加価値向上や操業及び加工コスト
の削減などについて検討を行い漁業経営の安定に向けた取組を推進することが重要である
と考えます。以上が本計画の評価ということで、4年間の取組状況を取りまとめ最後に評
価と今後の課題としてまとめました。
本計画の計画期間は来年度末までとなっておりますが、今後の課題にありますように、
燧灘のカタクチイワシに関する資源管理については引きつづき検討していきたいと考えて
おりますので、関係県や漁業者の方々と今後話し合いを深めていく予定としております。
(前田会長)
説明していただきましたけれども、現行の計画の評価を簡単にまとめますと、初期資源
尾数が安定的に確保されたこと及び漁獲量が一時期の低水準より回復し安定しているこ
と、また本計画によりいわし機船船びき網漁業者を加えた体制が整えられたなどの評価を
行うとともに、今後の課題としては資源量の維持、安定に加えて漁業経営の安定に向けた
取組の推進が重要であると以上のような内容であったかと思います。
ただいまの説明につきましてご質問がございましたら。
ご意見等もございませんか。それでは事務局におかれましては今後、関係県、漁業者等
と十分協議をしていただきまして22年度以降の燧灘におけるカタクチイワシの資源管理
について、よろしく検討をお願いいたしたいと思います。
(議題4 トラフグ資源管理の検討状況について(報告))
(前田会長)
つづきまして、議題4「トラフグ資源管理の検討状況について(報告)」につきまして、
事務局より報告していただきたいと思います。
(森資源課長)
瀬戸内海漁業調整事務所で資源課長を担当しております森と申します。
資料4を用いましてトラフグ資源管理の検討状況についてご報告いたします。座ってご
報告させていただきます。
「トラフグ資源管理に関する主な取組」としまして、まず「瀬戸内海関係府県との会議
等」でございます。この中の「関係県との意見交換会」についてでございますが、瀬戸内
海のトラフグ資源管理の検討は、トラフグ資源量が多く重要度が高い愛媛県、山口県、大
分県、広島県の瀬戸内海西部4 県から進めてはどうかとの瀬戸内海区水産研究所担当者
からの助言を受けまして、瀬戸内海西部4 県と意見交換会を開催することにしております。
なお、意見交換を終えた大分県、愛媛県、山口県3県においては今後トラフグの資源管
理につき何らかの対応をしていかざるを得ないとの認識であり、引き続き関係漁業者の意
見等を聞くため浜回りを行う方向で検討中です。
その下、「瀬戸内海区水産研究所との打合せ」につきましては、昨年11月と12月に
2回実施しております。瀬戸内海区水産研究所担当者からは情報提供や助言をいただいて
おります。主なところをご紹介しますと、1つ目はトラフグの資源水準は極めて悪いとい
うこと、2つ目は九州・山口北西海域では既に資源回復計画に取組んでおり、同じ系群を
漁獲している瀬戸内海においても資源管理を進めることが重要であること、3つ目は九州、
山口関係県からは瀬戸内海における資源管理の取組への要望が大きいこと、最後に特に漁
獲量の多い愛媛県、山口県、大分県、広島県の資源管理の取組が重要であることなどです。
次に「九州・山口北西海域関係機関との会議等」でございますが、まず「九州漁業調整
事務所との情報交換」についてですが、昨年の12月、九州漁業調整事務所で実施いたし
ました。九州漁業調整事務所担当者から、九州・山口北西海域のトラフグ資源回復計画の
取組状況等について説明を受けるとともに、今後は更に一層、両事務所が情報交換を密に
していくことを確認しております。
最後に「トラフグWG会議関連」と、一番下の「九州・山口北西海域トラフグ資源回復
計画に係る行政担当者会議」についてですが、九州・山口北西海域においては研究者の会
議であるトラフグWG会議と行政担当者会議が開催されておりますが、九州・山口北西海
域におけるトラフグ資源の状況や資源回復計画の取組状況等を把握するため、これらの会
議には瀬戸内海漁業調整事務所から担当者が出席しております。
平成20年10月21日開催の第17回瀬戸内海広域漁業調整委員会以降の主な取組は
以上のとおりでございます。
引きつづき、他海域の状況も把握しつつ、また関係県のご協力を得つつ、更には関係漁
業者のご意見を踏まえつつ検討を進めてまいりたいと考えております。また検討状況につ
きましては適宜本委員会に報告を行いたいと考えております。
(前田会長)
ただいまの報告につきまして何かご意見、ご質問はございませんか。
それでは、トラフグの資源水準は低位横ばいとの資源評価がなされております。トラフ
グの資源管理につきましては、こうした資源評価を踏まえまして引きつづき検討を進めて
いただくようお願いを申し上げます。
(議題5 平成21年度予算について)
(前田会長)
それではつづきまして、議題5の「平成21年度予算について」に入ります。水産庁管
理課さんより説明がございます、よろしくお願いいたします。
(渡邉管理課課長補佐)
水産庁管理課の渡辺と申します。
私から平成21年度予算につきましてご説明申し上げます。資料の5の1ページをご覧
ください。
21年度予算に関しましては、その前提となる資源回復計画につきまして新たな方向性
が確定をいたしました。先ほど高橋委員からもご発言がありましたけれども、今回この2
1年度予算に関しましては、この資源回復計画の今後の展開についてということを中心に
ご説明を申し上げます。
まずこの1ページ目の一番左側をご覧いただきたいんですが、現行の資源回復計画、今
平成14年から取組の開始をいたしまして現在64計画で実施中、5計画で作成中という
ことでございまして、資源の回復が必要な魚種等を対象に漁獲努力量の削減等を実施して
いくということで取り組んできております。計画開始から時間が大分たってきておりまし
て、中には資源の回復の兆しが見られつつある計画も出てきているところでございまして、
そうしたものについてはこの資料の一番右側にございますけれども、最終的には経営支援
を行わない形で自立的に、漁業者、あと行政、研究者がともに資源管理を行っていくとい
うものが最終的な理想になるわけでございます。とは言っても、いきなり自立といっても
さまざまな課題があります。そうした課題も踏まえまして、水産庁としてはどのような形
で取り組んでいけば最終的に自立というようなものが有効に、効果的に達成できるのかと
いうものを当然考えていかなければならないという課題があると考えております。そうし
たことを踏まえて今回、新たに一番右側の右から1つ戻っていただいたところにポスト資
源回復計画というものがございますけれども、最終的に自立に向けた準備期間ということ
でより効果的な取組というのもどのようなものがあるのかというものを考えながら、これ
までと同様の取組、そしてこれまでと同様の形で支援を行う準備期間として、ポスト資源
回復計画というものを新たに位置づけて推進をしていきたいと考えてございます。
中にポスト資源回復計画のところにも書いてありますけれども、基本的に実施機関は原
則5年間取り組んでいきたいと考えておりまして、繰り返しますけれどもポスト資源回復
計画の下の部分に矢印が出ておりますが、これまでと同様に漁獲努力量の削減措置である
とか種苗放流の積極的な推進、漁場環境の保全措置等に対する支援を引きつづきやってい
きたいと考えております。
また、こうしたことに加えまして、これまで既存の資源回復計画につきましても現在の
ところ平成18年度に着手したものに作成を限るということにしておったわけでございま
すけれども、これまでさまざまな作成に対する要望等もございましたので、そうしたこと
も踏まえまして今後また新たに資源回復計画の作成についても可能にしていくことといた
しましたのであわせてご報告をいたします。
資源回復計画につきましても、努力量の削減措置等に対する支援というものを当然なが
らこれまでと同じように行っていきたいと考えております。
なお、ポスト資源回復計画に移行するに当たってこれまでにやってきた取り組みがどう
だったのか、また今後最終的な自立に向けてどのような取組が有効でかつ取り組み可能な
のかというようなものを当然評価検討していかなければいけませんので、そうしたことを
するために左側の2つ目のところにポスト資源回復計画移行調査というものがございます
けれども、そのための予算というものも今回新たに確保をいたしましたのであわせてご報
告をいたします。
このほか平成21年度予算につきましては、繰り返しますがこれまでと同様に漁業者協
議会の開催であるとか、資源回復計画の普及・啓発の取組、また漁獲努力量の削減、種苗
放流、漁場環境保全といったものに対す支援措置というものも引きつづき確保をいたしま
したので、引きつづきご活用をいただければと思っております。
また、2ページ以降にはそうした各事業のPR判を添付しておりますのでご参照いただ
ければと思います。
以上、簡単ではございますけれども平成21年度予算につきましてご説明を終わります。
以上でございます。
(前田会長)
どうもありがとうございました。
何かご質問といいますか、ございませんでしょうか。
(議題6 その他)
(前田会長)
ございませんか、それでは議題5の「その他」に入りますけれども、せっかくの委員会
でございますので何か取り上げる事項等はございませんでしょうか。
よろしいですか。それでは事務局の方から委員の任期及び次回の委員会の開催予定など
についてご説明お願いいたします。
(馬場調整課長)
瀬戸内海広域漁業調整委員会の現在の委員の任期は平成17年10月1日から4年間、
今年の9月末日までが任期となっており、次回の委員会につきましては緊急開催の必要が
なければ例年どおり10月ごろに開催したいと考えております。
委員につきましては、海区委員の代表については改めて選定していただき、また大臣選
任委員につきましても改めて選任し直した上で開催させていただく予定です。
委員の皆さまには大変お世話になり、まことにありがとうございました。
なお次回の委員会の日時、場所等につきましては改めて事務局より新委員さんに連絡さ
せていただきます。以上でございます。
(閉会)
(前田会長)
ありがとうございました。
馬場課長さんからお話がございましたとおり、今日、出席していただいておりますメン
バーでの委員会はこれで最後になろうかと思います。委員の皆様方、4年間大変ご苦労さ
までございました。この4年間に当委員会で取り上げられましたいろいろな課題に取り組
んでまいりました。そして、その課題に対しましてそれぞれ一定の成果を上げることがで
きました。これ、一重に委員皆様方のご尽力の賜であると感謝を申し上げる次第でござい
ます。
今後とも委員皆様方にはご健勝で、そしてまたそれぞれのお立場、またそれぞれの分野
でご活躍していただくことを心からご祈念申し上げるものでございます。
それでは、これで本日の会を閉じたいと思いますが、各委員さん、また、ご臨席の皆様
には本委員会の開催へのご協力ありがとうございました。
また、議事録署名人の山本委員さん、原委員さんにおかれましては後日議事録が送付さ
れると思いますのでよろしくお願いを申し上げます。
それではこれをもちまして、第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会を閉会いたしたいと
思います。どうもありがとうございました。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/s_kouiki/setouti/pdf/s_18.pdf
1.日時
平成21年3月3日(月)14時00分
2.場所
神戸市中央区下山手通5−1−16パレス神戸2階「大会議室」
3.出席者指名
?出席委員
糠善次/ 川本信義/ 山本正直/ 小田英一
福池昌広/ 高橋昭/ 前田健二/ 宮本憲二
藤本昭夫/ 坂井淳/ 原一郎/ 荒井修亮
以上12名
臨席者
水産庁資源管理部管理課課長木實谷浩史
課長補佐渡邉顕太郎
九州漁業調整事務所次長佐藤愁一
独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所部長岩本明雄
資源管理研究室長永井達樹
研究員片町太輔
中央水産研究所主任研究員石田実
和歌山海区漁業調整委員会事務局長田上伸治
大阪海区漁業調整委員会課長補佐狭間文雄
専門委員小菅弘夫
大阪府環境農林水産部水産課課長補佐亀井誠
兵庫県農政環境部農林水産局水産課資源管理係主査峰浩司
兵庫県農政環境部農林水産局水産課漁政係主査森本利晃
岡山海区漁業調整委員会次長佐藤二郎
広島海区漁業調整委員会専門員山根康幸
山口県農林水産部水産振興課主任岡田浩司
徳島県農林水産部水産課技師西岡智哉
香川海区漁業調整委員会副主幹宮川昌志
香川県農林水産部水産課課長補佐井口政紀
技師益井敏光
愛媛県農林水産部水産局水産課資源管理担当係長加藤利弘
愛媛県農林水産研究所主任研究員河本泉
主任研究員関信一郎
福岡県豊前海区漁業調整委員会事務主査竹馬悦子
大分海区漁業調整委員会事務局長日隈邦夫
大分県農林水産部水産振興課副主幹大塚猛
愛媛新聞社大阪支社編集部長芝充
瀬戸内海漁業調整事務所所長佐藤力生
調整課長馬場幸男
資源課長森春雄
指導課長小林一弘
資源管理計画官平松大介
資源保護管理指導官中奥美津子
調整課許可係長酒井仁
調整課調整係玉城哲平
資源課資源管理係長松本貴弘
資源課資源増殖係長萩原邦夫
資源課漁場整備係正岡克洋
4.議題
1.サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について
2.周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について
3.カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について
4.トラフグ資源管理の検討状況について
5.その他



5.議事の内容
(開会)
(馬場調整課長)
ただいまから第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会を
開催いたします。
それでは前田会長、議事進行をお願いいたします。
(挨拶)
(前田会長)
さて、本日の委員会ではサワラ瀬戸内海系群資源回復計画、周防灘小型機船底びき網漁
業対象種資源回復計画、燧灘カタクチイワシ資源回復計画について平成20年度取組の実
施状況と資源状況についての報告をしていただきまして、また平成21年度の取組などに
ついてご審議いただくことといたしております。
更にはトラフグ資源管理の検討状況、平成21年度予算についてもご報告いただくなど
盛りだくさんの内容となっております。
また、ご案内のとおり委員の皆様におかれましては現在の委員の任期が平成17年10
月1日から4年間、今年の9月末日までが任期となっております。緊急の予定がなければ
本日が最後の委員会になろうかと思います。委員の皆様におかれましては最後まで活発な
ご議論をお願い申し上げます。
(木實谷管理課長)
ご承知のとおり広域漁業調整委員会でございますけれども、都道府県の区域を越えて分
布回遊する資源の適切な管理を目的として設置されまして、国が作成する広域の資源回復
計画を中心としてご審議をいただいているところでございます。
現在、全国で18の広域計画そして46の地先計画が実施されておりまして資源回復の
ための取組が全国的に展開されてきているところでございます。瀬戸内海を管轄いただい
ております本委員会の関係では現在までに3つの広域計画が作成実施されているところで
ございますけれども、皆様方の不断のご努力により資源の回復が更に図られることを期待
しているところでございます。
改めて申し上げるまでもなく水産庁といたしましても、この資源回復計画につきまして
は主要施策の1つでございまして今後とも一層推進していくということにしているところ
でございます。現在取り組んでおります資源回復計画につきましては、徐々に回復が見ら
れ始めている計画もございまして、このような資源については将来的には漁業者がみずか
らの力で管理していくような方向にもっていくというのがこれからの課題ではないかとい
うふうに考えているところでございます。
一方で、漁業経営を取り巻く情勢につきましてはご承知のとおりいまだ予断を許さない
状況にございますけれども、適切な資源管理に取り組み水産資源の維持回復を行っていく
ことは、将来的に活力ある漁業構造の確立にもつながっていくものと考えておりまして、
資源管理を目的として設置されました広域漁業調整委員会の役割は一層期待されるものと
考えているところでございます。
なお、広域漁業調整委員会につきましては委員の皆様の任期が一期4年となっておりま
して、現在第2期目の最終年を迎えているということでございます。平成13年に漁業法
が改正され広域漁業調整委員会制度が設けられ、その中で資源回復計画を中心とした課題
に鋭意ご尽力を賜りました皆様のおかげで、資源回復計画も今や全国的な展開になってい
るところでございます。これまで各委員の皆様方が払ってこられましたご努力に対して重
ねて御礼申し上げますとともに、残されました半年の期間におきましても資源管理、漁業
調整といった課題に対しまして引きつづきご支援、ご協力をお願いする次第でございます。
本日はさわらの資源回復計画を始め、盛りだくさんの議題となっているというふうに承
知しております。皆様の有意義なご審議が行われまして、今後さらに瀬戸内海における資
源管理が推進されますよう祈念いたしまして、簡単ですけれども開会のあいさつとさせて
いただきます。
(資料確認)
(前田会長)
それでは、本日使用いたします資料の確認を行いたいと思います。事務局よろしくお願
いします。
(馬場調整課長)
それでは、お手元にお配りしております資料でございますが、まず議事次第、委員名簿、
出席者名簿それから本日の会議での資料としまして資料1−1から1−3までサワラの資
源回復計画関係の資料。資料2−1から資料2−3まで周防灘小型機船底びき網資源回復
計画の資料。資料3−1から3−3までがカタクチイワシ資源回復計画の資料。資料4ト
ラフグ資源管理に関する主な取組。資料5平成21年度予算関連資料がございます。それ
から参考資料といたしまして瀬戸内海で行っている広域種の資源回復計画等に関します資
料をホッチキスどめで配付しております。ざいます。
(議題1 サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について)
(前田会長)
それでは早速、議題1「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の一部変更について」に入り
ます。
まず始めに20年度の実施状況について事務局より報告していただき、次に瀬戸内海区
水産研究所からサワラの資源状況などについて説明をしていただきます。その後、21年
度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。
それでは本年度の実施状況について事務局から報告をお願いいたします。
(平松資源管理計画官)
瀬戸内海漁業調整事務所資源管理計画官をしております平松でございます。
まず資料1−1を用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。座って説明を
させていただきます。
サワラ資源回復計画の平成20年度の実施状況につきまして、資料1−1の表紙をめく
っていただきますと漁獲努力量削減措置実施状況図1ページがございます。こちらの実施
状況図から資料の5ページまで、種苗放流それから漁場整備等の実施状況につきましては
前回の委員会での報告内容と重複いたしますのでここではご説明を割愛させていただきま
す。
資料の6ページをご覧いただきたいと思います。こちらに平成20年の漁獲量の速報値
を載せてございます。6ページの1番の漁獲量の表の欄外、右側に速報値として括弧書き
で各年の数量を書いているところでございます。こちらの数値につきましては、農林水産
省の統計部が半年ごとに速報値として集計しております数値の平成20年の上半期、下半
期の合計の数字を掲載させていただいております。平成20年につきましては、瀬戸内海
の漁獲量が752トンということで集計をされてございます。これと同じ速報値の平成1
9年の数字を見ていただきますと803トンということで速報値の対前年比が94%、マ
イナス6%ということになってございます。私どもの事務所の方で各府県の担当の方から
漁獲状況を聞き取っております情報を整理いたしますと、やはり同様に数%前年を下回る
というような情報をお聞きしてございます。こちらにつきましては、確定値はもう少し時
間が経ってから出るということでございますが、平成20年は平成19年の漁獲量の確定
値1,081トンを若干下回るのではないかと想像をしているところでございます。
平成20年の漁獲量の統計の数字につきましては以上でございますが、6ページの2番、
下の方ですがこちらの方には当広域漁業調整委員会指示で漁獲量の上限が定められており
ます。はなつぎ網、さわら船曳網、サゴシ巾着網、こちらの漁獲量の報告が各県からござ
いましたので、その数値を掲載させていただいてございます。それぞれ表にございます制
限値以内での操業が実施されたというところでございます。
漁獲量については以上でございますが、次に資料の7ページに岡山県が今年度実施いた
しました試験操業調査の結果、それから8ページから9ページには同じく香川県で実施さ
れました試験操業調査の結果を載せてございます。
まず、7ページの岡山県の調査結果でございますが今年度、昨年の10月に試験操業が
3回実施されてございます。真ん中の2番の試験操業結果のところの平成20年の欄をご
覧ください。3回の試験操業によりましてサゴシが197尾漁獲されております。その下、
1隻あたりのCPUEも65.7ということで、それぞれ平成19年の結果を上回る結果
となってございます。197尾の漁獲されたサゴシのうち、放流魚がどれだけ含まれてい
たかというものにつきまして7ページ一番下の表3に漁獲サゴシのデータと右側に放流さ
れたサワラのデータの結果を載せております。平成20年につきましては、197尾のう
ち放流されたものが1尾ということで混獲率は0.5%という結果になってございます。
昨年、一昨年と比べて混獲率が非常に低い結果というのが今年の特徴でございます。
同様に8ページから9ページの香川県の調査結果も傾向といたしましては、ただいまの
岡山県と同様の傾向となってございまして、まず8ページの2番の漁獲状況の1番下の右
端、平成20年の結果といたしまして3回の試験操業で107尾のサゴシが漁獲され、1
隻あたりの漁獲実数も17.8尾ということでそれぞれ前年を上回っているという結果で
ございます。また9ページに漁獲されたもののうち放流されたサワラがどれだけ含まれて
いたかということで表になってございますが、こちらの平成20年のところをご覧いただ
くと、左側の漁獲サゴシ107に対して放流サワラの尾数が1尾ということで混入率が約
1%という形になってございます。それぞれ傾向といたしましては、先ほどの岡山県と同
様な傾向になっているというところでございます。
このように両県とも試験操業での漁獲は昨年よりも多いということ、それから全体の漁
獲の中に占める放流されたサワラの割合が少ないということ、相対的に見ると全体の天然
のサワラ加入が多いということを示す結果となってございます。ただ、近年では加入が卓
越いたしました平成14年ほどの結果にはなっていないというところがございます。若干
漁獲がいいのではないかというような推定もしておりますが、これらの加入状況につきま
してはまた後ほど瀬戸内海区水産研究所の方からの報告にも触れられますのでそちらに譲
りたいと思います。
岡山県、香川県の両県で実施されております試験操業こちらにつきましては、播磨灘の
休漁期間に実施されるものということで、本委員会指示との関係により事前に委員会へ調
査計画の報告、また結果の報告を行うということにされております。平成21年度につき
ましても今年度と同様に調査が計画されておりまして、資料の10ページ、11ページに
それぞれ来年度の調査計画が提出をされていることをご報告いたします。
それから平成20年度の実施状況、最後になりますが資料の12ページ一番後ろでござ
いますが、TAE管理の実施状況を取りまとめてございます。府県別に数字が書かれてお
ります表の一番右端に全体の合計値といたしまして、設定された努力量が12万3,67
4隻日に対しまして平成20年度のTAE管理期間での操業隻日数が2段目の1万5,9
13隻日となってございます。設定値に対する割合といたしましては13%となっており
まして、こちらの出漁隻日数につきましては平成15年度にこのTAE管理を開始して以
降、最も少ない値ということになってございます。
簡単ではございますが平成20年度、本年度のサワラ計画の実施状況についての説明は
以上でございます。
(前田会長)
ただいまの報告につきまして何かご質問はございませんでしょうか。
それではご質問もないようですので、つづきましてサワラの資源状況につきまして瀬戸
内海区水産研究所の永井室長さんより説明をお願いいたします。
(永井室長)
図は漁獲量の経年推移です。横軸が年、縦軸が千トン単位で示した漁獲量です。青が瀬
戸内海の東部、紀伊水道から備讃瀬戸まで、赤が燧灘から伊予灘、あるいは周防灘までの
西部を示します。漁獲量は一番多いときで6千トンを超えましたが、1986年をピーク
に減ってきました。1998年に香川県、岡山県、兵庫県が自主規制を始めてから、徐々
に漁獲量は回復してきて、2000年からは資源回復計画が行われているところです。
2007年の漁獲量は図では1,108トンと記入しておりますが、先ほどの平松さん
の説明で新しい推定値は1,081トンとなっています。漁獲物の年齢を見ますと昔は3
歳、4歳をとっていたのですが、1980年代に入ってから2歳、3歳、1990年代に
入ると1歳、2歳が中心となり、漁獲物の低年齢化が進んいます。とり方としては悪くな
ってきています。
次に資源量の推移ですが、縦軸に漁獲物の年齢組成を基に資源計算して求めた資源量の
経年推移を示しました。一番多いとき1987年で1万6千トンくらいあったものがずっ
と減ってきて、2007年には2,282トンと1987年の14%に減っています。そ
の後、資源量は少し回復してきましたが、ここ4年ほどやや減少ぎみで推移しています。
一時の悪いときは脱したけれど、やや減りぎみで推移しています。
それから資源量に対してどのくらい漁獲しているかという漁獲割合を赤で示しておりま
すが、一時に比べてその割合が高くなってきており、漁獲圧力が増してきています。
次に親魚量(トン)と加入尾数の関係です。横軸に親の資源量をとりまして、縦軸にそ
の年に生まれて秋に加入したサゴシの資源尾数をとっています。図を見ると、親が多いほ
ど子供も多く加入していることがうかがわれます。両者に直線の関係を当てはめると青い
ラインになります。最近年の1998年以降を切り出してみると右の図ですが、同じブル
ーの直線で示していますが、これは2つの図で同じものです。要するに親が多いと子供も
多い、ただ2002年というのは親がそれほど多くなかった割には加入がよかった、強い
年級が生まれてきた。これに対し2004年は親が多かったけれど、期待したほど子供が
生まれてこなかったわけです。いずれにしても最近はこの直線より少し上に点がくるいい
傾向があるのですが、それが親の増加につながっていない。というのは0歳秋から1歳の
間の魚がまだ小さいうちに漁獲されて、親の増加につながっていないと言えると思います。
先ほど2004年は親が多かった割に子供の生き残りが悪かったということを言いまし
たが、その理由として1つ考えられるのはこの年には御承知のように6月から10月に台
風が10個来襲して史上最高ということがありました。この年サワラの卵が多かったとい
うことがネット調査でわかっておりますが、仔魚が少なかった。小さいうちに海が時化て
魚の生き残りが悪かったのかなと思っています。
それから2006年については、2005年の12月から40年ぶりの低温という厳し
い冬でして、表面の水温がこれは大阪湾の例ですけど例年に比べて5度くらい低かった。
その影響がずっとサワラの産卵期まで持ち越してきまして、サワラの産卵時期は開始が遅
れましたが、逆に低温のため産卵の終わりが細く長く続いたという特徴があります。漁獲
の経過や年齢別の漁獲の状況から見て、2006年は非常に低温で、産卵に影響は受けた
が、結果として細く長くつづいた産卵で2006年の加入はそれほど悪くなかったと理解
しています。
いろいろと環境が不安定な例を示します。図の横軸が1月から12月の平年の水温の平
均値ですが、それに対して2006年とか2007年がどうかと比べました。香川県の1
0メートル水温の平年偏差ですが、海域は幾つかあります。3つほどまとめて言いますと、
特徴として2006年は先ほど言ったように平年を下回る水温がずっと続き、3月に平年
値を少し超える時がありますが、低温の年でした。2007年は逆に平年より非常に暑く
て、一番高い時は平年偏差より2度くらい高い場合も見られました。魚の場合1度水温が
高いと人間で言えば5度とか10度に相当すると言われています。水温がかなり高いとい
うことがサワラの仔稚魚の生産率を低下させていないか、つまり2007年生まれの生き
残りがどうだったかということを考える上で、水温が高かった影響を考えていかないとい
けないと思います。
資源評価のまとめとして、2007年の資源量は2,282トンで1987年に比べて
14%と低位です。それから2007年の資源水準は低位で過去5年の動向は減少、生物
学的に望ましい漁獲の係数であるF30%は、現状の漁獲の係数に比べて41%、つまり
現状の漁獲圧力が望ましい状態に比べて非常に高い。望ましいというのは生物学的にサワ
ラにとって優しいという意味なんです。現状はちょっと漁獲圧力が高いと評価しています。
それから2007年の加入は生き残りが悪かったかもしれないということで少ない恐れが
あると考えています。このように特徴的な年の状況を言いましたが、環境が不安定に推移
することが多いので、加入が環境の影響を受けやすいということが最近続いていると考え
ています。
次は漁獲量の動向を図にしたものですが、2008年の東西別漁獲量、左側の柱が春漁、
右側が秋漁、高さが漁獲量、それから赤が全年を下回っている場合、青が前年を上回って
いる場合を示しています。ですから東部の場合春漁は前年を上回って1.1倍、秋漁は0.
6倍でした。西部の場合は1.0の赤ですから前年をやや下回ったもののほとんど1に近
い、秋は1.8倍と秋が良かったことを示します。
図は春漁、秋漁を府県別に示したものです。瀬戸内海の内の方で春も秋も青のところが
見られますが、外側では秋が青だけれども、なかには例えば徳島県のように前年比秋が0.
6倍というところもあります。兵庫県は春も秋も0.6倍、大阪府は0.2倍、0.4倍
で、大阪湾あるいは播磨灘のあたりはよくなかったことが分かります。
次は4月から7月を春漁と定義しまして、その東西別の割合を示しています。今度は左
側がサワラ銘柄、右側がサゴシ銘柄の漁獲量です。東部では春にサワラは1.1倍、サゴ
シは1.0倍、合計163トンでした。西部ではサワラが1.1倍、サゴシが0.5倍で、
春サゴシが西部で悪かった。次の図は府県別に示したものですが、サワラでは香川、広島
で前年を上回って、大阪、兵庫などで下回った。サゴシでは香川、岡山、広島で前年を上
回り、兵庫、愛媛で下回った。
次に8月から12月を秋漁として示しています。8月から12月には東部のサワラで前
年を下回り0.4倍でした。サゴシは前年を上回り3.0倍でした。西部についてはサワ
ラもサゴシも前年を上回って1.1倍と6.7倍です。この2008年はサゴシの銘柄が
東部で3.0倍、西部で6.7倍と前年比で高い値が得られているのが特徴です。それを
府県別に示したものが次の図ですが、サゴシでは大阪と大分で前年を下回ったほかは大体
前年を上回るところが多かった。
それでは次に2008年の秋の漁獲の動向について説明します。
これは大阪府の資料ですが、南部の標本組合の機船船びき網漁業の漁獲量を示していま
す。一番上はシラスの漁獲量、縦軸がトンで横軸が1月から12月まで。ヒストグラムが
平年で赤が2008年、青が2007年、黒が2006年の直近3年ですが、平年と比べ
て2008年は10月にシラスが割と多かったというのが特徴的です。
カタクチイワシについては8月、9月がピークですが、前2年に比べて2008年はち
ょっと悪かった。
サワラについては2006年、7年に比べてピークが余りはっきりしない。10月が一
応低いピークなんですが、余りよくなかったということになります。カタクチが余りよく
なかったということでサワラもよくなかったのかと思われます。ただ10月にシラスがと
れたというところが目新しいと思います。
サワラの尾叉長組成の方ですが、これも大阪府の資料ですが、流網の尾叉長組成が主で
す。9月から12月まです。一番上は曳網でして、9月に曳網でとれたものは46センチ
程度で例年に比べて魚体がやや小さかった。小さかったので、これが流網にかかってこな
かった。50センチより小さかったということであまり流網にはかかってこず、9月は1
歳魚、同じく10月、11月も大阪では1歳魚主体の漁獲であり、0歳魚、その年生まれ
のサゴシがとれたのは12月に入ってからだった。
2008年生まれのサゴシは多いんだとか、それほどでもないという情報がいろいろあ
るわけですが、これについてちょっと御説明しますと、2008年の秋のサゴシの漁獲は
香川県の資料では東部の引田で、これが2008年の秋のサゴシですが、加入が非常によ
かった2002年、それからそれ以降比較的よかった2005年に比べて、2008年は
2002年ほどではないけれども2005年並みであるという数字となっています。それ
から西の方の香川県の伊吹の資料では2005年に比べてもやや小さい半分以下の数字に
なっております。それから高松中央卸売市場での9月から12月の香川県産のサゴシの入
荷量、取扱量は2005年あるいは2002年並みの数字になっております。先ほど御紹
介があったように試験漁獲では2002年の0.4倍、2005年の0.8倍ですから、
2002年に比べるとやはりそれほど多くないが、その次に比較的よかった2005年と
同じかやや下回る程度じゃないかという数字になっています。
愛媛県のサワラとサゴシの資料を分析しますと、2008年秋のサゴシの豊度、1隻1
日あたりの漁獲尾数あるいはキログラム数、川之江と埴生ではキログラム、西条と河原津
では尾数です。2002年から2008年について色別に示しておりますが、2008年
のCPUEで見ると川之江と埴生では2002年並み、2002年というのは図で黒です。
西条と河原津では2002年を下回る。このように、2008年が2002年ほどではな
いということで、良いという情報と悪いという情報が半ばとなっています。
それから、同じ愛媛県でも伊予灘では、月別の漁獲量で図はないのですが、サゴシにつ
いて数字を整理したものを県からいただいたのですが、2005年の漁獲量を1としまし
て、2006、2007、2008年の漁獲量はそれぞれ1.5倍、2.2倍、1.9倍
となりまして、2005年に比べて2008年のサゴシは2倍近い漁獲量で、サゴシが比
較的とれています。
管理方策への提言として、毎年70万尾の加入がないと資源は持続しない。親の資源は
2歳魚主体で若齢化しておりまして、年齢構成も単純化している。そのために環境が悪く、
再生産において仔稚魚の生残が悪い年があると、資源が大きな打撃を受ける恐れがあると
考えています。ですから、サゴシの漁獲を抑えて親を残して、加入動向を見守ることが重
要です。そして、環境や加入、再生産の不安定さを考慮しますと資源回復計画での取り組
みの強化が望まれると考えております。
それから、次は補足なんですが平成20年度第1回サワラブロック漁業者協議会、9月
24日の会議で各県の漁業者の方々から研究サイドへいろいろ要望が出ました。大きなも
のとしては3つほど出たんですが、それに対して私の方でできる範囲で資料を整理して回
答したので、簡単にご紹介したいと思います。
1番目は地域別の放流効果、放流しているが、地域別に漁獲量への反映がどうなってい
るのか示してほしいということです。2番目はサワラがどうして播磨灘に入ってこないか
説明してほしいということです。これに対して非常に説明は難しい、なかなかいい説明が
できないのですが、後でお見せする図の2や小路・益田両先生の講演要旨を見てください
と説明しました。それから、3番目に海の変化、瀬戸内海の海の変化とか温暖化に関する
情報を提供してほしいということで、これについては後で表1をお見せしますが、東シナ
海とか日本海、瀬戸内海に関しての状況を私の方でまとめさせてもらいました。参考資料
として委員の先生のところには「海洋と生物について瀬戸内海の魚類生産に変化はあった
か」というテーマで私が書いたものをお配りしております。これはブロック漁業者協議会
でもお配りしたものです。
サワラの放流魚については、ご承知のように内部標識として小さい卵とか仔魚の段階で
赤い標識を入れております。ですから成魚あるいはサゴシでも、漁獲して頭の中の耳石を
調べたら放流物か天然物かがわかります。その天然物に対して放流物の割合が何%かを海
域別、それから年齢別、それから年別に放流魚の混入率としてまとめました。御覧になっ
てわかるように0歳のところでは混入率が非常に高いです。ただ年齢が高くなるほど値は
低くなっています。図には播磨灘の兵庫県、播磨灘の岡山県、播磨灘の香川県などでの混
入率の数字がありまして、これに漁獲物の年齢組成を別に持っておりますので、両者をか
けてどのくらい放流魚が漁獲されているかというのを直近の3年について推定して図中に
数字としてあげています。
ここでちょっと分かりにくいんですが、赤い色は瀬戸内海、兵庫県の播磨灘で再捕され
たものですが、西部放流分を示しています。図では厚みをもっていませんので1尾とか2
尾なんですが、西から東に来たものが再捕されています。それから瀬戸内海西部なんです
が、燧灘、香川県沖、愛媛沖、安芸灘、伊予灘での特徴として、安芸灘、伊予灘では混入
率が低い、放流物の再捕がない。それからもう1つの特徴は香川沖でも愛媛沖でも燧灘に
ついては、この緑色は厚みをもっていますので、瀬戸内海東部で放したものが備讃瀬戸を
通って西部の方にかなりきていることを示します。ただ、東に比べると西では混入率はそ
れほど高くはないということが特徴です。いずれにしても地域別、年別、年齢別にこのよ
うな混入率となっており、それが漁獲量にどう反映しているかをブロック漁業者協議会で
お示ししました。
それから、後で読んでもらえばいいんですが広島大学小路先生、京都大学益田先生、こ
ういった先生方の指摘として、瀬戸内海のサワラを増やすにはやはりカタクチイワシをは
じめとするサワラの餌となりうる資源の管理をきちんとしないと本格的な回復はないんじ
ゃないかという指摘がなされています。
それについて同じようなことなんですが、灘別にカタクチシラスの漁獲量とかシラスと
カタクチイワシの漁獲量の比、そういったものを灘別に私の方で整理しています。言いた
いことは、シラスの漁獲量が瀬戸内海東部の方で多いものですから、資源としては安定し
ていてもカタクチイワシの影を見ることがどうしても少なくなる。カタクチイワシがいれ
ば、2004年の春に五色で見られたように、カタクチイワシにサワラがつくというふう
なことがありますので、やはりシラスで先取りしてカタクチイワシの影が薄いと、サワラ
が滞留する機会というのは少なくなってくるのだろうと考えています。ただ、シラスとい
うのは非常に大きな漁業を支え、商業的にも価値が高いですから、そっちの方が重要だと
考える行政の方もいるし、漁業者の方もいるわけで、なかなかその辺が難しいところだと
思います。
あと東シナ海、日本海についてはどういった異常現象が見られるかということで1つだ
け言いますと、サワラの東シナ海系群に見られる漁獲量の北への偏りは1999年以降に
日本海の北区で始まりまして、2000年以降太平洋北区、要するに青森の三沢の方や福
島の方で漁獲がかなりあがってきているという情報があります。もう1つ言えば例えば従
来沖縄の魚であるグルクン、これが沖縄での漁獲量が減って、2005年から長崎とか宮
崎で漁獲量が増えていたのが、2008年には福岡で増えているというふうに魚の分布が
更に北へ上がってきているような傾向があります。以上こういったことを瀬戸内海ブロッ
ク漁業者協議会で報告させていただきました。
以上です。
(前田会長)
どうもありがとうございました。
ただいまの説明によりますと、サワラの資源状況につきましては平成19年の資源水準
は低位で動向は減少傾向にあるとのことです。また親魚資源は2歳魚が主体で若齢化し年
齢構成が単純化しているため、再生産や稚魚の生産が悪いと資源に大きな影響を与える恐
れがあるとのことでございます。このため環境や加入の不安定さを考慮すると資源回復計
画での取組強化が望まれるとのご報告でございました。
何かこのご報告に対して質問等がございませんでしょうか。
それではないようですので次に移ります。平成21年度の取組の審議に移ります。
昨年10月の委員会におきまして、休漁期間の変更に関する検討状況の報告がありまし
た。それによりますと伊予灘関係県で休漁期間変更に関する検討を進め、ブロック漁業者
協議会において意見集約を図り、本日の委員会で計画変更について審議したいとのことで
した。
まず事務局より伊予灘の休漁期間の取り扱いを含めた平成21年度の取組について説明
していただきまして、その後、配付資料には含まれておりませんけれども新たな資源管理
体制の構築に向けた検討を行っているということでございますので、その検討条件につい
て報告していただきます。それでは事務局、よろしくお願いします。
(平松計画官)
では、資料につきましてはサワラ資料の1−3でございます。
まず始めに、先ほど会長の方からもございましたとおり伊予灘の休漁期間の変更に関す
る検討状況、検討結果でございますが、前回の委員会では試験操業ですとか既存の研究デ
ータを基にした行政研究担当者会議の検討結果といたしまして、休漁期間を変更しても現
状より漁獲量が増加する可能性が低いということが考えられる等の報告を行い、またこれ
らの結果を踏まえまして伊予灘の関係県におきまして休漁期間の変更案に対する検討を進
めるとご報告いたしました。それらを2月に開催されますブロック漁業者協議会で持ち寄
り、検討を加えて意見の集約を行うということでその後の取組の方針を説明させていただ
きました。
これにつきまして昨年の10月以降、伊予灘関係県の方で検討が行われてきたわけでご
ざいます。2月にブロック漁業者協議会が開催されましたが、その場で伊予灘の関係県と
いたしまして山口県それから大分県、こちらの漁業者協議会の代表委員の方から県内の協
議状況についてご報告がございました。両県ともこの休漁の期間変更については了解する
ということでございました。これらを受けまして2月10日に開催されましたブロック漁
業者協議会におきましては、この伊予灘の休漁期間を15日間後ろの方へずらすという変
更案について了解が得られたというところでございます。これらを踏まえまして本日、来
年度のサワラ計画の取組案ということでまとめさせていただいてございます。
それでは、資料1−3表紙をめくっていただきまして、1ページの漁獲努力量削減措置
(平成21年度案)という地図のページをご覧ください。
内容につきましては、ただいま申し上げましたとおり伊予灘海域での休漁期間につきま
してサワラ流し網漁業(山口・愛媛・大分)としているところですが、こちらの休漁期間
5月16日から6月15日ということにさせていただいております。これが、本年度5月
1日から5月31日までとしていたところからの変更箇所でございます。
その他の海域につきましては、本年度と全く同様の休漁期間として実施したいと考えて
ございます。また、瀬戸内海全域での流し網の目合い規制10.6センチにつきましても
今年度と同様の内容となってございます。来年度の漁獲努力量削減措置につきましては伊
予灘を変更した形でこのような取組で進めたいと考えてございます。
つづきまして、2ページめくっていただきまして種苗生産・中間育成・受精卵放流の取
組、来年度の実施予定を載せてございます。
同様に3ページには広域漁場整備及び漁場環境保全の来年度の事業の実施予定を取りま
とめてございます。放流それから漁場整備、両方につきましておおむね今年度と同じ内容
の実施予定をしてございます。来年度の漁獲努力量削減措置、種苗放流、漁場整備につき
ましてはただいまご説明申し上げました内容で実施したいと考えてございます。
このうち、休漁期間に係ります漁獲努力量の削減措置につきましては休漁期間変更とい
うことでございますので、資源回復計画本文の変更が必要になってまいります。こちらに
つきまして資料の4ページから8ページにかけまして、サワラ瀬戸内海系群資源回復計画
一部変更案という形で新旧対照表のスタイルで載せております。表の右側が現在の回復計
画の文章、左側が変更案になってございます。資料の4ページ、新旧対照表になる部分で
すが、こちらの一番下のところ、漁獲努力量の削減措置の表にあります伊予灘の部分でご
ざいますが、こちらにつきまして現行の5月1日から5月31日という期間を表の左側の
5月16日から6月15日というふうに変更をさせていただきたいと考えてございます。
また、規制措置の内容の変更はこの点のみですが今回の一部変更に併せまして7ページ
にございます海域の定義の中の灯台名につきまして通称名から正式名称に改めさせていた
だくという措置を1ヶ所させていただきたいと考えてございます。変更箇所はその2ヶ所
でございます。
それから資源回復計画におけます休漁等の措置につきましては、これらの措置を担保す
るための瀬戸内海広域漁業調整委員会指示につきましては資料の9ページから11ページ
に案を載せてございます。
こちらの内容につきましては、11ページをご覧いただきたいんですが先ほどご説明い
たしました伊予灘の休漁期間、こちらにつきまして変更後の休漁期間に対応した内容での
設定を考えてございます。
以上が平成21年度のサワラ資源回復計画の措置案でございます。
それから、これから資料はございませんので口頭での説明をさせていただきたいと思い
ますが、このほかに現在資源管理体制の構築に向けた検討といたしまして2つ行ってござ
います。
1つは資源回復計画の取組の強化に関すること、それから2つ目が平成23年度以降の
放流体制の検討に関してでございます。
まず1つ目の回復計画の取組強化に関しましては、サワラ資源の回復に必要な産卵親魚
の確保につきまして、現在の資源水準から考えますと一律に漁獲量を減らすような取組と
いうものは、少ない漁獲量を更に減らすということになるため実現性が困難と考えてござ
います。従いまして、卓越年級群の発生など例年以上の漁獲が見込まれる場合を想定いた
しまして、あらかじめ未成魚の保護による親魚量のかさ上げについて、これらの方法につ
きまして検討しておくことが重要と考えているところでございます。
また、平成20年級群につきましてはある程度の加入量が期待できるということもござ
いまして、早急にそれらの検討を進める必要があると考えているところでございます。こ
のような考え方によりまして、1つの例といたしまして好漁日、漁獲のいい日が2日連続
すれば3日目を臨時休漁にするという取組を想定いたしまして、それらの取組よってどの
ような効果が発現するか、また実際の漁獲の減少がどの程度かというようなことについて
これらの漁獲増加の取り控え効果というものについて検討をしてございます。現在、各地
域の実情に見合った方法というものにつきまして、各府県、地域での検討を行っていただ
くよう行政研究担当者会議、またブロック漁業者協議会において各府県に要請していると
いう状況でございます。これが1つ目の取組強化に関する検討の状況のご報告でございま
す。
つづきまして2つ目のサワラ種苗放流体制の検討状況という部分でございますが、サワ
ラ資源回復計画におきまして種苗放流は漁獲努力量の抑制との一体的な推進が必要とされ
ているところでございます。現在の種苗放流の体制に当たりましては、水研センターの関
与が大きいところでございますが、その水研センターの取組の根拠となります水研センタ
ーの中期計画というものが平成22年度で終了するということ。また、サワラのような広
域回遊種についての国の関与、栽培、放流に対する国の関与を定めております栽培に関す
る基本方針につきましても、平成21年度で終了するということになってございます。
このような状況から、これらの次の基本方針、次期の水研センターの中期計画に瀬戸内海と
しての要望内容等が反映されるよう今年度1月26日の行政研究担当者会議からこの種苗
放流体制、23年度以降の種苗放流体制のあり方について検討を始めたというところでご
ざいます。まだ、検討を始めたばかりでございますので、その具体的内容について、現時
点でご報告できるまでには至っておりませんが、今後、水産庁の本庁また水研センターの
これらの関係する動きを注視しつつ検討の進捗状況に応じまして、適宜ご報告できればと
考えているところでございます。
以上2点口頭でのご報告になりますが、資源管理体制の構築に向けた検討状況について
ご報告しました。これらを含めました来年度、平成21年度の資源回復措置、サワラ回復
計画の取組案と考えてございます。来年度の取組案につきまして、ご審議よろしくお願い
いたします。
(前田会長)
平成21年度の取組の案につきましては、伊予灘の休漁期間についてこれまでの検討を
踏まえ5月1日から5月31日の休漁期間を5月16日から6月15日までに変更したい
とのことでございました。これに伴いまして、資源回復計画を一部変更し本委員会指示に
つきましても変更後の休漁期間に対応した内容により設定するとともに種苗放流等の取組
については本年度と同様の内容で実施したいとのことでございます。
また、後半の新たな資源管理体制の構築に向けた検討につきましては、資源回復計画の
取組の強化及び種苗放流体制の検討に関して行政研究担当者会議等での検討状況及び今後
の検討の進め方について報告がございました。
なお、紀伊水道外域につきましては、2月24日に開催されました「和歌山・徳島連合
海区漁業調整委員会」におきまして、本委員会指示の案が決議されれば本年度と同様の連
合海区委員会指示に従うことが決議されております。
また、宇和海につきましても3月12日に開催予定の愛媛海区漁業調整委員会において
本年度と同様の海区委員会指示を決議する予定となっております。
これから質疑に入りますけれども、まず始めに平成21年度の取組の案につきまして何
かご質問等がございましたらお願いいたします。
ご意見もございませんようですので、それでは「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平
成21年度取組(案、本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員) 会指示(案)につ
いて」承認したいと考えますがよろしいでしょうか。
それでは委員会として「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平成、21年度取組(案)、
本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員会指示(案)について」承認をいたします。
引きつづきまして、第2点目の新たな資源管理体制の構築に向けた検討が行われている
資源回復計画の取組強化及び種苗放流体制の検討状況についての報告がございましたけれ
ども、これにつきましてご質問等がございませんでしょうか。
(高橋委員)
この問題につきましては、この委員会で擁護するというのがいいのかどうかよくわから
ないままに申し上げたいと思います。
行政の方でも将来的な取組というのを検討なさるというようなことでありましたけれど
も、この資源管理についての取組というのは漁業者自身、我々もある意味ではそうだとは
思うんですけれども、今の取組がやっとこさよちよち歩きの状態なんです。これで計画期
間が終わったからおしまいよというのでは、せっかく取り組んだのがほっぽり出されると
いうような気がしてならない。そういう意味では、やはり行政からも当然そういうご意見
が出るんだと思うんですけれども、これは続けてやっていただかないと、せっかく今まで
取り組んできたのが終わってしまうというような気がしますので、国におかれてもこの問
題についてはどうぞ息の長い取組をお願いしたい。
(前田会長)
今後とも水産庁と言いますか、行政サイドでの取組も今までと同様の指導してほしいと
の要望でございます。
何か事務局の方でございますか。
(平松計画官)
今おっしゃられたのは平成23年度まで今の計画期間、5年延長した第2期の計画期間
がございまして、先ほど放流につきましてはそれ以降の体制についていろいろ関係の長期
計画等の進捗に合わせて検討を進めたいという報告をさせていただいております。
後ほど予算の説明の中で本庁から今後の制度的な話も予定しておりますが、サワラにつ
きましても放流だけでなく全体の取組を今後どうしていくかというのは、当然現在の取組
期間の終わりに向けてしかるべきときに具体的な検討を進めていかないといけないとは認
識してございます。その中で一番いいやり方、どのようにやっていくかということを十分
関係の機関とも検討しながら進めていきたいと考えます。
以上でございます。
(前田会長)
どうもありがとうございました。よろしいですか。
ほかにございませんか。
- 17 -
(荒井委員)
回復計画の取組を強化するということで、今1つのアイデアをご提示されましたけれど
も、2日続けていい漁があれば1日休むと、それも1つのアイデアだと思うんですけれど
も、他の魚種あるいは他の海区でこういった取組をやってうまくいってると、あるいはう
まくいくんじゃないかどうかという事例があればちょっとご紹介していただければと思う
んですけれども。
(前田会長)
ございますか、事務局の方で。
(佐藤所長)
実は私ども資源回復計画を最初に立ち上げたときに、これは白書にも載ってますけれども
太平洋のマサバである程度成果が出たんですけれども、要するに魚を増やすということは
獲り控えをするということです。獲り控えをすると何が起こるかというと、ぎりぎりの経
営をやっているというところで更に取るなと、これを要求していかざるを得ない。ところ
が、うまいことに自然の中でたまにボーナスが出ると言ったら変ですが、実は経営に負担
を与えないで資源を回復する道が時々あるんです。それが実は卓越年級群が出たときに、
そのボーナスをできるだけ手をつけないで貯金しておくと。普通の生活費でぎりぎりして
いる人に魚を取るなというのはこれは非常に難しいんです。特に今年さっきの報告にもあ
りましたように、地域によっては相当漁獲量が減っております。平均ですると前年度より
ちょっとかもしれません。だけど播磨灘のように過去に比べて非常に減ってるところ、さ
らに、中間育成までやっている漁業者にとっては、とてもじゃないですけれども受け入れ
られない。そう見ると資源を回復するには、誰に獲る量を減らしてもらうのか。やっぱり
ある程度取れて生活が維持できる人にそこの負担をしてもらおうじゃないかと。それと、
先ほど言いましたように、もしかすると本年度とか20年度に卓越年級群が発生している
可能性がある。そうすれば過去と同じ獲り方をすればたくさん残せるため、昨年と同程度
に我慢をしようと。そういう発想で実は太平洋のマサバのときも経営の維持をすると同時
に、もう一方のボーナスが出たときに欲というものをいかに抑えるか。そこである一定以
上取れた翌日は確実に休むと、それを連続してやったわけです。その成果として漁獲量は
減らないけれど大きな魚が残って翌年から、収益が上がってきたという1つの事例があり
ます。だから、そういう経営と資源の回復をうまくマッチングするタイミングが今回出て
きたんではないかということで、それに期待しているということになりますので、以上で
ございます。
(前田会長)
ありがとうございます。ほかにございませんか。
それでは、サワラ資源回復計画は種苗放流と資源管理の取組を大きな柱としております。
サワラ資源が減少傾向にある中で今後この取組をどうすべきかは、重要なテーマであると
考えますので事務局におかれましては引きつづき検討を進めるようお願いを申し上げたい
と思います。
なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正
式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部
分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承お願い申し上
げます。
(議題2 周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について)
(前田会長)
それでは、再開いたしたいと思います。
つづきまして、議題2の「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部変更
について」に入らせていただきます。
本計画につきましては、前回の委員会で計画延長の骨子について承認しておりますので、
今回は計画延長を内容とした資源回復計画の一部変更について審議を行うこととなってお
ります。
まず、始めに事務局より平成20年の漁獲状況及び本計画の延長について説明していた
だいたあと、計画の一部変更の案についてご審議いただきたいと思います。それでは事務
局から説明をお願いいたします。
(平松計画官)
それでは、周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画に関しまして、資料は資料
番号の2−1から2−3までが関連の資料でございます。
まず始めに資料2−1に基づきまして漁獲状況のご報告、それから資料2−2と2−3
を用いまして延長計画の内容について続けてご説明をさせていただきます。
資料2−1をご覧ください。平成20年の漁獲状況につきまして、先ほどサワラの漁獲
量でもご報告申し上げました平成20年下半期の速報値が2月に公表されましたので、上
半期の数字と合わせまして平成20年の速報値ということでまとめさせていただいており
ます。
こちらによりますと、平成20年は1,751トンということで19年の速報値1,8
70トンに比べまして約6%減少という結果になってございます。それぞれ周防灘計画の
対象魚種ごとの内訳が資料の2−1の下の魚種別の表に載せているとおりでございます。
この中で前年よりも漁獲量が増えておりますのがクルマエビとガザミでございます。一方、
漁獲量が特に減少が大きいのがシャコでございまして320トンが207トンに減少して
いるということでございます。周防灘につきましては漁法別の漁獲量の集計がちょっと時
間を要するということで、確定値は平成18年までということでございまして表に数字を
記載しているとおりでございます。20年の漁獲状況につきましては簡単でございますが、
以上でございます。
つづきまして、計画延長につきまして考え方のご説明をさせていただいて、計画変更案
についてご審議いただきたいと思っております。
まず計画延長の内容につきまして取組の基本的な方針、内容につきまして資料2−2「周
防灘資源回復計画の延長について」という資料にまとめてございます。こちらの資料1ペ
ージをご覧ください。1番といたしまして資源回復措置の継続の必要性ということで、こ
れまでの骨子等でまとめさせていただいた内容を簡単に整理をさせていただいてございま
す。回復計画に取り組んできておりますが、効果も上がっている部分もございますが、引
きつづき取組の継続というものが重要なポイントになっていると考えてございます。この
ような考え方のもと、計画を延長して進めたいということでございますが、まず1ページ
の2番のところに資源回復の目標といたしまして、実施期間と計画の目標を載せてござい
ます。
まず実施期間につきましては(1)にございますように本計画の実施期間は平成25年
度までとするということで、現在の計画が16年11月に作成されて5年間ということで
すので、21年の11月に5年間期間が満了するということでございますが、これを更に
延長するという考えでございます。前回の委員会で骨子の了解をいただいたときにはここ
は平成23年度までとさせていただいておりましたが、回復計画の実施期間が25年度ま
でこの制度としての実施期間が延びるということで、それにあわせて25年度までの延長
としたいと考えてございます。従いまして来年度、21年度からちょうど5年間の取組に
つきまして第2期の取組というような位置づけで今後2ページ以降に記載してございます
内容を中心に進めてまいりたいと考えてございます。
それから、資源回復の目標につきましては現在の計画の目標でございます平成16年の
漁獲量の水準、数字で言いますと2,123トンということになりますがこちらの維持と
いう目標を引きつづき掲げて取り組んでいきたいと考えているところでございます。
それでは、ページをめくっていただきまして2ページ目以降に実際にどのような取組を
行っていくかということで3番の資源回復のために講じる措置というところ以降に取りま
とめてございます。
まず(1)の漁獲努力量の削減措置につきましては、まず?の小型魚の水揚げ制限、こ
れは現在取り組んでおります制限サイズを引きつづき継続実施すると考えてございます。
2つ目の取組といたしまして、シャワー設備の導入がございますがこちらのところで資
料の中にアンダーラインを引いている部分、こちらがこれまでの取組にプラスした部分、
検討の方向性も含めまして今回の計画延長に当たりましてこのような観点の取組を進めて
いくという部分の追加部分をアンダーラインをしております。シャワー設備の導入でいき
ますと、これまでの再放流魚の生残率の向上というものに加えて、持ち帰り出荷する漁獲
物の鮮度維持というもの、これをシャワー設備の導入の目的の中に位置づけとして追加す
るということで取り組んでいきたいと考えております。
現在、山口県、福岡県、大分県の3県のうち大分、福岡が導入済みということで山口県の方で今、順次導入しているという
ところでございますので、未導入船につきまして先ほど言いました再放流魚の生産率の向
上に加えた、漁獲物の鮮度保持というものを目的に加えまして導入促進を推進していきた
いと考えているところでございます。また鮮度維持ということに関しまして現在、夏場に
機能を発揮します簡易冷却装置の現場での応用試験というものも進められておりますの
で、これらの取組も推進していきたいと考えております。それらを含めて効果的なシャワ
ーの活用方法というものも考えつつ、効果的なシャワーの利用というふうなものを推進し
たいと思っているところでございます。
それから、産卵親魚の保護といたしまして実施しております抱卵ガザミの再放流につき
ましては、現在取り組んでいるとおり継続していくということ、また休漁期間の設定につ
きましてはこちらは海底清掃等の漁場環境改善の取組とあわせて実施するという考えを今
後も継続するということで考えてございます。
?といたしまして、漁具の改良がございます。これはこれまでの取組の中でも進めてま
いりましたが、それら試験研究をより推進することを考えておりまして現在幼稚魚の混獲
防止漁具の性能試験も実施されておりますので、このような取組について実用化に向けた
推進を行ってまいりたいと考えているところでございます。
以上が漁獲努力量の削減措置でございますが、回復計画の2つ目の柱でございます資源
の積極的培養措置ということで、これは主に種苗の放流というものになりますがこちらに
つきまして2ページから3ページに記載しております。この回復計画を進めるに当たって
今年度から事業として立ち上がりました資源管理アドバイザー制度等を活用しつつ、この
3県の連携、協力というものによる放流体制の構築というものを推進していきたいと考え
てございます。特にクルマエビにつきましては、山口、福岡、大分の3県で共同した事業
も実施してございますので、これらの事業の推進というものを図っていきたいと考えてご
ざいます。
3つ目の柱として漁場環境の保全措置ということでございますが、こちらは水産基盤整
備事業等の漁場環境改善の事業について取組を引きつづき行いたいと考えております。
資源回復のための措置といたしましては、以上3本柱の内容でございます。次に資料の
3ページの4番にございます漁業経営安定の取組ということでこちらは今後この資源回復
計画によりまして、資源の回復、漁獲の増大というものを進めていく取組にあわせまして
経営的な観点での検討を並行して実施していく。これは今回新たに盛り込んだ内容でござ
います。
大きな柱としましては2つございまして1つがコストの削減ということでございます。
燃油につきましては昨年度非常に高騰いたしまして、こういうコスト削減、特に燃油の使
用の抑制等の取組というものの重要性が出てきておるわけでございますが、このような観
点での操業コストの低減策ということについて検討するというのが1 つでございます。
2つ目といたしまして先ほどのシャワー設備のところでも申し上げましたが、漁獲物の付
加価値向上、単価アップ等に向けた取組ということについて、各種検討をあわせて実施し
ていきたいと考えているところでございます。これら、資源回復措置の取組プラス漁業経
営安定の取組という観点で来年度以降の取組を進めたいと考えているところでございます。
その他、3ページの中段以降にございます5番の公的担保措置、6番の支援策等につき
ましては従前どおりの体制で進めていきたいと考えているところでございます。
最後、資料は4ページになりますがその他といたしまして、これは今までの回復計画の
中でも取組として進めてきたところでございますが、他漁業への取組の拡大というような
部分につきましては現在、カニ籠漁業のカニ籠目合いの適正化試験というものも実施され
て小さなカニ、ガザミですがこれを漁獲しないようにするための検討ということが進めら
れてございますので、そのような取組をこの関連漁業へのアプローチというようなことで
進めていきたいと、このような取組を推進していきたいと考えてございます。このような
考え方のもと、来年度以降の5ヵ年間の取組を第2期の取組として進めていきたいと考え
てございます。
回復計画につきましては今申し上げましたとおり実施期間の延長ということになります
ので、計画変更が必要になります。そちらにつきましては資料2−3、1 枚資料、裏表印
刷しているものでございます。こちらも新旧対照表によります変更案ということで、表の
右側が現行の計画、左側が変更案ということで整理をしてございます。変更箇所としまし
ては、資料2−3の1ページのちょうど中ほどの行に当たりますが、資源回復目標の中で
実施機関に係る部分、現行では当面の5年間としている部分を平成25年度までの間とい
うふうに改めたいと思っております。また、平成16年の漁獲量が統計の数値が公表され
ておりますので2,123トンという具体的な数字を盛り込むということにしてございます。
変更内容は以上の2点ですが、実施期間につきましては1ページ目の一番下の2行にご
ざいますように、もう1ヶ所実施機関が当面の5年間が平成25年度までの間というふう
に記載されている部分がございます。
変更箇所は以上でございますが、2ページ目にございます海域の定義の基点のところに
つきましても市町村合併に伴う市町村名の修正と、灯台等の名称を正式名称に改めるとい
うことで一部記載内容が変わってございますが、実際の基点そのものにつきましては変更
ございません。表現方法の変更をこの計画変更にあわせて行いたいと考えてございます。
周防灘計画の延長の取組内容・方針、それから資源回復計画の一部変更案につきまして
は、以上でございます。
(前田会長)
計画の延長につきましては実施機関を平成25年度までとし、現在実施している漁獲努
力量の削減措置を継続しつつ漁獲物の鮮度維持等の漁業経営安定の取組に検討を進めてい
るとのことでございました。
それでは、ただいまの説明につきましてご質問がございませんでしょうか。
それでは、ないようですので「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部
変更(案)について」承認したいと思いますがよろしいでしょうか。
ありがとうございました。それでは、委員会といたしまして「周防灘小型機船底びき網
漁業対象種資源回復計画の一部変更(案)について」承認をいたします。
なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正
式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部
分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承をお願い申し
上げます。各関係、各委員におかれましては本計画の適切な実施について、よろしくご指
導お願い申し上げます。
(議題3 カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について)
(前田会長)
「つづきまして議題3のカタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について」
に入ります。
まず、20年度の実施状況と資源状況などについて事務局より報告していただきまして、
引きつづいて21年度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。
また、計画作成後4年が経過し、来年3月で計画期間満了を迎える本計画の評価という
ことで事務局より報告していただきます。それでは、本年度の実施状況などにつきまして
事務局から報告お願いいたします。
(中奥資源保護管理指導官)
瀬戸内海漁業調整事務所、中奥です。よろしくお願いいたします。
それでは着席させていただきましてご説明させていただきます。
では、20年度の取組について資料3−1をご覧ください。対象漁業の許可期間は1ペ
ージの(1)に示すとおりでございます。これに対しまして資源回復措置としましては(2)
にあります休漁期間と(3)にあります定期休漁日を設定し取り組まれました。本年度定
期休漁日につきましては広島県が燃油高騰の要因もあり、従来の木曜日に加えて日曜日も
追加実施されました。20年度の操業実績といたしまして(4)にありますとおり瀬戸内
海機船船びき網につきましては広島県は6月13日から10月10日まで、香川県は6月
10日から9月10日まで、愛媛県は6月10日から9月10まで、愛媛県のいわし機船
船びき網では6月10日から8月17日までとなっております。
次に燧灘のカタクチイワシの資源状況です、2ページをご覧ください。資源状況につき
ましては関係3県の広島県、香川県、愛媛県の水産試験研究担当者の方々により資源解析
が行われた結果です。
(1)は漁獲量の動向です。平成18年までは農林水産統計から、平成19年、20年
は共販量からの推定量をグラフにしました。平成20年の漁獲量はカタクチイワシとシラ
スを合わせて1万4,540トンと前年の108%となっております。
(2)は初期資源尾数の動向です。本計画の目標は回復計画開始当初の資源尾数水準、
これは平成12年から16年の平均で346億尾です。この水準と計画期間終了後に同程
度維持することとしております。その基準である資源尾数は、春季発生群の初期資源尾数
を用いることとしています。グラフはその動向について示しております。平成20年につ
いては水準より若干低い値、340億尾で目標の98%となっております。
(3)は初期資源尾数の漁獲率の動向を示しております。グラフのとおり資源量に対す
る漁獲率は(2)の資源尾数をベースに出しているため、このように高い値となります。
それを踏まえて見てみますと、例年86%前後で推移し平成20年も平年並みの値となっ
ております。
(4)は資源状況の考察です。3県の水産試験研究担当者の資源解析、燧灘のカタクチ
イワシ漁獲量及び瀬戸内海系群カタクチイワシの資源評価結果から判断して、資源水準は
中位、動向は横ばいとの評価が出ております。
次に、脂イワシ調査結果について3ページに取りまとめております。本調査は19年度
から関係3県と瀬戸内水研が協力して調査を開始したものです。19年度の結果報告から
脂質含有量と製品単価の急低下との関連から脂質含有量が2%以上のものを脂イワシと仮
定義したことから、今年度も引きつづき調査を行い図1のように脂質含有量と肥満度の間
に正の相関が見られたことから、脂イワシの判定指標として肥満度が利用できると判定し
ました。図1の脂質含有量2%のときの肥満度は約10であり、肥満度10を脂イワシの
発生警戒値とする結果を得ました。
20年度の取組状況については以上です。
(前田会長)
ただいまの説明によりますと、本年度は広島県の定期休漁日について従来の木曜日に加
えて日曜日も追加して実施されたとのことでございました。また、燧灘のカタクチイワシ
の資源水準は中位、動向は横ばいとのことでございます。ただいまの報告について、何か
ご質問等がございませんでしょうか。
ないようですので、つづきまして平成21年度の取組について事務局から説明をお願い
いたします。
(中奥資源保護管理指導官)
21年度の取組案につきましては、資料3−2をご覧ください。
1ページ目、平成21年度の資源回復措置の取組としまして2と3にあります漁期始め
及び漁期終期の休漁、定期休漁日の設定につきまして従来と同様に継続することとしてお
ります。また、漁期始め及び漁期終期の休漁期間の担保措置としまして本委員会指示を平
成20年度と同様の内容で設定したいと考えております。本委員会指示の対象海域は2ペ
ージの図に示しております。3ページには本委員会指示の案を添付しております。なお、
2月12日に開催されましたカタクチイワシブロック漁業者協議会において21年度取組
案及び本委員会指示案につきましては了解が得られております。また、20年度取組でご
紹介しました脂イワシに関する調査につきましても引きつづき瀬戸内水研と関係3県が協
力して続けることにしております。
21年度の取組案につきましては以上です。よろしくご審議お願いいたします。
(前田会長)
平成21年度は引きつづきまして従来と同様の資源回復措置を実施し、本委員会指示に
つきましても本年度と同様の内容で行いたいとのことでございます。また、脂イワシに関
する調査についても引きつづき行われるとのことでございました。
ただいまの説明に対してご質問等ございませんでしょうか。
、「( それではないようですので平成21年度取組案)及びこれに係る本委員会指示(案)
について」承認したいと考えますがよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声)
(前田会長)
委員会として「平成21年度取組(案)及びこれに係る本委員会指示(案)について」
承認をいたします。
それでは、次に本計画も計画作成から4年が経過し、来年度が最終年度となっておりま
す。こうした状況を踏まえまして、事務局から本計画のこれまでの取組に対する評価につ
いて報告していただきたいと思います。では、事務局よろしくお願いいたします。
(中奥資源保護管理指導官)
4年間の取組状況を評価にまとめておりますので資料3−3をご覧ください。
まず、計画の概要といたしましては1ページの2にあるとおり瀬戸内海海域におけるカ
タクチイワシに対する漁獲圧力は経年的に高い傾向であり、現在の比較的安定した加入状
況が悪化すれば資源悪化や漁獲量減少を招く恐れがあるため、現状の水準を下回らないよ
うに資源量を維持する必要があります。そのために、資源回復の目標としまして5年間の
計画期間後に燧灘のカタクチイワシの資源尾数水準を計画開始前の平成12年から16年
の平均と同程度に維持することを目標にしました。講じている措置は休漁期間の設定と、
定期休漁日の設定となっております。
次の3の計画実施状況ですが、6ページ以降に添付しております図表をご覧いただきな
がらお聞きください。まず、漁獲努力量削減措置の実施状況を6ページの表1と表2にま
とめております。
表1では本計画で定められた休漁期間に加えて自主休漁が取り組まれておりますので、
その内容を整理しております。まず、広島県の瀬戸内海機船船びき網漁業の17年度を例
に説明しますと、表にあります操業開始日とは計画上6月10日から操業できるところを
実際に操業を開始された日が6月13日であり、定められた休漁期間に加えて6月10、
11、12と3日間の自主休漁を実施されたことから(A)の自主、休漁日数3という整
理をしています。同様に操業終漁日では11月30日まで操業できるところを実際は10
月31日で終漁されたということなので、定められた休漁期間に加えて30日の自主休漁
を実施され(B)の自主休漁日数30で、17年度の広島県の合計自主休漁日数は33日
となります。そのほか、表にまとめた以外にも天候や魚の状態で臨時休漁も適宜実施され
ております。
表2では定期休漁日について取りまとめました。平成20年度の広島県は先ほども報告
しましたとおり、燃油高騰の要因もあり木曜日のほか暫定的に日曜日が追加されました。
なお、本計画に定められました休漁期間に対しては本委員会指示が毎年設定されておりま
す。また、平成19年度に愛媛県宮窪町漁協所属のいわし機船船びき網漁業1ヵ統の本計
画参加により、対象海域拡大の一部変更を行いました。5ページの図1が拡大しました対
象海域になっております。
次に、支援事業について7ページ表3にまとめたとおり愛媛県で平成18年度から延べ
54隻日、494万6千円の休漁漁船活用支援事業で漁場監視が実施されております。以
上が漁獲努力量削減措置に関する実施状況です。
次に関連調査としまして、資源評価については関係3県と瀬戸内海区水産研究所が協力
して行っており、8ページの表4にあるとおり卵稚仔調査や表5の脂イワシに関する調査
が実施されております。餌料環境調査、脂質含有量調査、発生要因分析などを行い、基礎
データの収集や肥満度を利用した脂イワシの判定指標の検討など研究が行われておりま
す。
次に資源動向と漁獲量の推移ですが、9ページの図2をご覧ください。燧灘のカタクチ
イワシの資源動向は春季発生群の初期資源尾数について平成5年以降のデータをもとに推
定されております。グラフに示すとおり平成5年以降は減少傾向で、平成8年に138億
尾と最低の水準になりましたが、その後、回復傾向で平成12年以降は300億から40
0億尾の水準を維持しております。
次に漁獲量ですが、10ページの左上の図3をご覧ください。燧灘での近年のシラスを
含む漁獲量は1万1千トンから1万7千トンで推移しており、平成12年から20年の平
均漁獲量は1万4千トン程度となっています。
次に県別に見ますと、図4の広島県では平成15年に3千トンを超えましたが、その後
は1千トン前後で推移し、図5の香川県では平成17年に1万トンを超えましたが、その
後はおおむね7千トンで推移しております。図6の愛媛県では3千トンから5千トンで推
移しております。
また、各県の銘柄別共販量とその割合から漁獲の主体を見てみますと、瀬戸内海機船船
びき網漁業では11ページの図7からご覧ください。上段のグラフが銘柄別の漁獲量、下
段が銘柄別の構成割合になっております。図7の広島県ではチリメンを主体に漁獲してお
り、図8の香川県では中羽を主体に小羽から大羽を漁獲、12ページの図9の愛媛県では
中小羽を主体に小羽から大羽を漁獲、図10のいわし機船船びき漁業ではカエリを主体に
チリメンを漁獲しています。このことから、漁獲対象が広島県はチリメン主体、香川県及
び愛媛県は煮干加工向けのサイズを主体に、いわし機船船びき網漁業においてはカエリ、
小羽を主体にそれぞれ漁獲しているようです。
次に目標達成状況ですが、戻りますが9ページの図2をご覧ください。本計画の資源回
復目標は、5年間の計画期間後に燧灘のカタクチイワシの資源尾数水準を計画開始前の5
年間、平成12年から16年の平均と同程度に維持することとしております。この指標と
して用いる資源尾数は、燧灘の資源評価で算定された初期資源尾数です。図2に引いてお
ります破線は回復目標の指標であります平成12年から16年の平均値である346億尾
を示し、計画開始後の平成17年から折れ線を太線で表しております。達成状況について
はご覧いただいているとおり、平成20年の資源尾数は340億尾で目標である346億
尾の98%であり目標水準で安定しております。
最後に評価と今後の課題としてまとめておりますので、本文4ページをご覧ください。
本計画を4年間実施してきた評価として、現時点でカタクチイワシは産卵親魚量と加入量
の間に明瞭な関係が認められていないため、資源管理措置の効果を定量的に判断すること
はできませんが、初期資源尾数が安定的に確保され漁獲量が一時期の低水準より回復し安
定していることから措置はおおむね妥当であると考えます。また、瀬戸内海区水産研究所
の指導のもと、関係3県の協力で資源評価体制が確立され、またその体制により脂イワシ
の判別法で化学分析を必要としない簡易な肥満度を活用できることが明らかにされたとこ
ろであり、操業方法の改善に寄与することも期待できます。
次に今後の課題ですが、漁獲努力量削減措置は評価で述べましたとおり一定の効果があ
ったと考えますが、今後の資源量の維持、安定を考えますと資源予測の精度を高め資源動
向に即した措置について検討が必要であります。また漁獲動向や脂イワシの発生により製
品価格の年変動が大きいため脂イワシ発生のメカニズム解明に期待されていますが、その
研究成果をいかに現場で活用していくかが重要であります。更に、脂イワシの発生による
価格低下から漁獲金額の向上の取組として、漁獲物の付加価値向上や操業及び加工コスト
の削減などについて検討を行い漁業経営の安定に向けた取組を推進することが重要である
と考えます。以上が本計画の評価ということで、4年間の取組状況を取りまとめ最後に評
価と今後の課題としてまとめました。
本計画の計画期間は来年度末までとなっておりますが、今後の課題にありますように、
燧灘のカタクチイワシに関する資源管理については引きつづき検討していきたいと考えて
おりますので、関係県や漁業者の方々と今後話し合いを深めていく予定としております。
(前田会長)
説明していただきましたけれども、現行の計画の評価を簡単にまとめますと、初期資源
尾数が安定的に確保されたこと及び漁獲量が一時期の低水準より回復し安定しているこ
と、また本計画によりいわし機船船びき網漁業者を加えた体制が整えられたなどの評価を
行うとともに、今後の課題としては資源量の維持、安定に加えて漁業経営の安定に向けた
取組の推進が重要であると以上のような内容であったかと思います。
ただいまの説明につきましてご質問がございましたら。
ご意見等もございませんか。それでは事務局におかれましては今後、関係県、漁業者等
と十分協議をしていただきまして22年度以降の燧灘におけるカタクチイワシの資源管理
について、よろしく検討をお願いいたしたいと思います。
(議題4 トラフグ資源管理の検討状況について(報告))
(前田会長)
つづきまして、議題4「トラフグ資源管理の検討状況について(報告)」につきまして、
事務局より報告していただきたいと思います。
(森資源課長)
瀬戸内海漁業調整事務所で資源課長を担当しております森と申します。
資料4を用いましてトラフグ資源管理の検討状況についてご報告いたします。座ってご
報告させていただきます。
「トラフグ資源管理に関する主な取組」としまして、まず「瀬戸内海関係府県との会議
等」でございます。この中の「関係県との意見交換会」についてでございますが、瀬戸内
海のトラフグ資源管理の検討は、トラフグ資源量が多く重要度が高い愛媛県、山口県、大
分県、広島県の瀬戸内海西部4 県から進めてはどうかとの瀬戸内海区水産研究所担当者
からの助言を受けまして、瀬戸内海西部4 県と意見交換会を開催することにしております。
なお、意見交換を終えた大分県、愛媛県、山口県3県においては今後トラフグの資源管
理につき何らかの対応をしていかざるを得ないとの認識であり、引き続き関係漁業者の意
見等を聞くため浜回りを行う方向で検討中です。
その下、「瀬戸内海区水産研究所との打合せ」につきましては、昨年11月と12月に
2回実施しております。瀬戸内海区水産研究所担当者からは情報提供や助言をいただいて
おります。主なところをご紹介しますと、1つ目はトラフグの資源水準は極めて悪いとい
うこと、2つ目は九州・山口北西海域では既に資源回復計画に取組んでおり、同じ系群を
漁獲している瀬戸内海においても資源管理を進めることが重要であること、3つ目は九州、
山口関係県からは瀬戸内海における資源管理の取組への要望が大きいこと、最後に特に漁
獲量の多い愛媛県、山口県、大分県、広島県の資源管理の取組が重要であることなどです。
次に「九州・山口北西海域関係機関との会議等」でございますが、まず「九州漁業調整
事務所との情報交換」についてですが、昨年の12月、九州漁業調整事務所で実施いたし
ました。九州漁業調整事務所担当者から、九州・山口北西海域のトラフグ資源回復計画の
取組状況等について説明を受けるとともに、今後は更に一層、両事務所が情報交換を密に
していくことを確認しております。
最後に「トラフグWG会議関連」と、一番下の「九州・山口北西海域トラフグ資源回復
計画に係る行政担当者会議」についてですが、九州・山口北西海域においては研究者の会
議であるトラフグWG会議と行政担当者会議が開催されておりますが、九州・山口北西海
域におけるトラフグ資源の状況や資源回復計画の取組状況等を把握するため、これらの会
議には瀬戸内海漁業調整事務所から担当者が出席しております。
平成20年10月21日開催の第17回瀬戸内海広域漁業調整委員会以降の主な取組は
以上のとおりでございます。
引きつづき、他海域の状況も把握しつつ、また関係県のご協力を得つつ、更には関係漁
業者のご意見を踏まえつつ検討を進めてまいりたいと考えております。また検討状況につ
きましては適宜本委員会に報告を行いたいと考えております。
(前田会長)
ただいまの報告につきまして何かご意見、ご質問はございませんか。
それでは、トラフグの資源水準は低位横ばいとの資源評価がなされております。トラフ
グの資源管理につきましては、こうした資源評価を踏まえまして引きつづき検討を進めて
いただくようお願いを申し上げます。
(議題5 平成21年度予算について)
(前田会長)
それではつづきまして、議題5の「平成21年度予算について」に入ります。水産庁管
理課さんより説明がございます、よろしくお願いいたします。
(渡邉管理課課長補佐)
水産庁管理課の渡辺と申します。
私から平成21年度予算につきましてご説明申し上げます。資料の5の1ページをご覧
ください。
21年度予算に関しましては、その前提となる資源回復計画につきまして新たな方向性
が確定をいたしました。先ほど高橋委員からもご発言がありましたけれども、今回この2
1年度予算に関しましては、この資源回復計画の今後の展開についてということを中心に
ご説明を申し上げます。
まずこの1ページ目の一番左側をご覧いただきたいんですが、現行の資源回復計画、今
平成14年から取組の開始をいたしまして現在64計画で実施中、5計画で作成中という
ことでございまして、資源の回復が必要な魚種等を対象に漁獲努力量の削減等を実施して
いくということで取り組んできております。計画開始から時間が大分たってきておりまし
て、中には資源の回復の兆しが見られつつある計画も出てきているところでございまして、
そうしたものについてはこの資料の一番右側にございますけれども、最終的には経営支援
を行わない形で自立的に、漁業者、あと行政、研究者がともに資源管理を行っていくとい
うものが最終的な理想になるわけでございます。とは言っても、いきなり自立といっても
さまざまな課題があります。そうした課題も踏まえまして、水産庁としてはどのような形
で取り組んでいけば最終的に自立というようなものが有効に、効果的に達成できるのかと
いうものを当然考えていかなければならないという課題があると考えております。そうし
たことを踏まえて今回、新たに一番右側の右から1つ戻っていただいたところにポスト資
源回復計画というものがございますけれども、最終的に自立に向けた準備期間ということ
でより効果的な取組というのもどのようなものがあるのかというものを考えながら、これ
までと同様の取組、そしてこれまでと同様の形で支援を行う準備期間として、ポスト資源
回復計画というものを新たに位置づけて推進をしていきたいと考えてございます。
中にポスト資源回復計画のところにも書いてありますけれども、基本的に実施機関は原
則5年間取り組んでいきたいと考えておりまして、繰り返しますけれどもポスト資源回復
計画の下の部分に矢印が出ておりますが、これまでと同様に漁獲努力量の削減措置である
とか種苗放流の積極的な推進、漁場環境の保全措置等に対する支援を引きつづきやってい
きたいと考えております。
また、こうしたことに加えまして、これまで既存の資源回復計画につきましても現在の
ところ平成18年度に着手したものに作成を限るということにしておったわけでございま
すけれども、これまでさまざまな作成に対する要望等もございましたので、そうしたこと
も踏まえまして今後また新たに資源回復計画の作成についても可能にしていくことといた
しましたのであわせてご報告をいたします。
資源回復計画につきましても、努力量の削減措置等に対する支援というものを当然なが
らこれまでと同じように行っていきたいと考えております。
なお、ポスト資源回復計画に移行するに当たってこれまでにやってきた取り組みがどう
だったのか、また今後最終的な自立に向けてどのような取組が有効でかつ取り組み可能な
のかというようなものを当然評価検討していかなければいけませんので、そうしたことを
するために左側の2つ目のところにポスト資源回復計画移行調査というものがございます
けれども、そのための予算というものも今回新たに確保をいたしましたのであわせてご報
告をいたします。
このほか平成21年度予算につきましては、繰り返しますがこれまでと同様に漁業者協
議会の開催であるとか、資源回復計画の普及・啓発の取組、また漁獲努力量の削減、種苗
放流、漁場環境保全といったものに対す支援措置というものも引きつづき確保をいたしま
したので、引きつづきご活用をいただければと思っております。
また、2ページ以降にはそうした各事業のPR判を添付しておりますのでご参照いただ
ければと思います。
以上、簡単ではございますけれども平成21年度予算につきましてご説明を終わります。
以上でございます。
(前田会長)
どうもありがとうございました。
何かご質問といいますか、ございませんでしょうか。
(議題6 その他)
(前田会長)
ございませんか、それでは議題5の「その他」に入りますけれども、せっかくの委員会
でございますので何か取り上げる事項等はございませんでしょうか。
よろしいですか。それでは事務局の方から委員の任期及び次回の委員会の開催予定など
についてご説明お願いいたします。
(馬場調整課長)
瀬戸内海広域漁業調整委員会の現在の委員の任期は平成17年10月1日から4年間、
今年の9月末日までが任期となっており、次回の委員会につきましては緊急開催の必要が
なければ例年どおり10月ごろに開催したいと考えております。
委員につきましては、海区委員の代表については改めて選定していただき、また大臣選
任委員につきましても改めて選任し直した上で開催させていただく予定です。
委員の皆さまには大変お世話になり、まことにありがとうございました。
なお次回の委員会の日時、場所等につきましては改めて事務局より新委員さんに連絡さ
せていただきます。以上でございます。
(閉会)
(前田会長)
ありがとうございました。
馬場課長さんからお話がございましたとおり、今日、出席していただいておりますメン
バーでの委員会はこれで最後になろうかと思います。委員の皆様方、4年間大変ご苦労さ
までございました。この4年間に当委員会で取り上げられましたいろいろな課題に取り組
んでまいりました。そして、その課題に対しましてそれぞれ一定の成果を上げることがで
きました。これ、一重に委員皆様方のご尽力の賜であると感謝を申し上げる次第でござい
ます。
今後とも委員皆様方にはご健勝で、そしてまたそれぞれのお立場、またそれぞれの分野
でご活躍していただくことを心からご祈念申し上げるものでございます。
それでは、これで本日の会を閉じたいと思いますが、各委員さん、また、ご臨席の皆様
には本委員会の開催へのご協力ありがとうございました。
また、議事録署名人の山本委員さん、原委員さんにおかれましては後日議事録が送付さ
れると思いますのでよろしくお願いを申し上げます。
それではこれをもちまして、第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会を閉会いたしたいと
思います。どうもありがとうございました。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/s_kouiki/setouti/pdf/s_18.pdf
2009年12月27日
平成21 年2月20 日大阪市底質対策等技術検討会
大阪市底質対策等技術検討会会議要旨
1 日 時 平成21 年2月20 日(金) 午後1時30 分〜午後2時50 分
2 場 所 環境局第11〜13 会議室(WTCコスモタワービル36 階)
3 出席者
(委 員)
大阪大学名誉教授 村岡 浩爾
大阪人間科学大学人間科学部教授 福永 勲
摂南大学薬学部准教授 上野 仁
京都大学原子炉実験所准教授 藤川 陽子
(事務局)
大阪市環境局・港湾局・建設局
(オブザーバ)
大阪府都市整備部河川室、大阪府環境農林水産部環境管理室、
大阪府環境農林水産総合研究所、大阪市立環境科学研究所水環境担当
4 議 題
(1) 委員長の選出
(2) 報告案件
? 平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
? 大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策について
? 大阪市管理河川(道頓堀川等)における底質浄化対策について
5 議事要旨
(1) 委員長の選出について
要綱の規定に基づき、委員の互選により村岡委員が委員長として選出された。また、村岡委員長の指名により、福永委員が委員長の職務代行を行うこととなった。
(2) 平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
事務局(環境局)から、大阪市域における平成15〜19 年度までの5年間の水質・底質に係るダイオキシン類濃度測定結果及び水質に係る代表的な汚濁指標であるBOD やCOD の汚濁状況について報告を行った。
(3) 大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策について
事務局(港湾局)から、平成18 年度から着手している大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策に伴う環境対策の概要(浚渫場所周辺における事前・日常的な水質環境監視や処分地(夢洲)及びその周辺おける水質環境調査結果など)の報告を行うとともに、平成19 年度に着手した港区尻無川(水門上流)堤防工事における環境対策の概要(工事場所周辺における事前・日常的な水質環境監視や固化処理による封じ込め効果を確認するための水質調査の実施結果など)について報告を行った。
(4) 大阪市管理河川(道頓堀川等)における底質浄化対策について
事務局(建設局)から、道頓堀川水辺整備事業のうち、湊町右岸工区における遊歩道の設置に係る工事概要、浚渫土の処理、工事中の環境監視結果などについて報告を行った。
【結果】
(2)〜(4)について、事務局からの報告内容について、各委員からご理解をいただいたが、底質ダイオキシン類溶出量の測定値の評価に関して、「底質ダイオキシン類に関する分析手法を含めた統一的な取り扱いの確立に向け、今後、府市等関係機関が連携すること」などが要望として出された。
6 会議資料:
(1)資料1 :平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
(2)資料2 :大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策及び港区尻無川(水門上流)堤防工事における環境対策について
(3)資料3 :大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策について
(4)参考資料:大阪市底質対策等技術検討会開催要綱
7 問い合わせ先
大阪市環境局環境保全部土壌水質担当
Tel:06-6615-7984、FAX:06-6615-7949、E-mail:ja0040@city.osaka.lg.jp
大阪市底質対策等技術検討会会議録
発言者(事務局及びオブザーバ)
・環境局環境保全部長 西山健一郎
・環境局環境保全部土壌水質担当課長 大石 一裕
・環境局環境保全部土壌水質担当課長代理 前田 和男
・環境局環境保全部環境情報担当課長代理 黒木 隆司
・環境局環境保全部担当係長 宮本 敏之(司会者)
・港湾局計画整備部環境保全担当課長代理 有門 貴
・建設局下水道河川部河川担当課長代理 三村 経雄
・大阪市立環境科学研究所水環境担当研究主任 先山 孝則
議事内容:次のとおり
西山環境保全部長
さて、大阪市では、これまで「大阪市底質対策技術検討会」におきまして、市内の河川並びに海域における底質汚染などに関しまして、その汚染要因や浄化対策につきまして検討するとともに、市域内における土壌汚染、また、地下水汚染に係ります調査・対策に関しましては、別途「大阪市土壌汚染対策専門委員会」を設置させていただき、学識者の先生方より検討をいただいたところでございます。
今般、大阪市では、これらの2つの委員会をより総合的に運用いたしまして、大阪市域内の公共用水域に係ります有害な底質、また、市域内の土壌汚染・地下水汚染など、水環境分野と地盤環境の分野の対策を一体的に推進いたしますため、平成20 年7月に底質の委員会に土壌の委員会を整理・統合させていただいたところでございます。
本日は、これまで「底質対策技術検討会」でご検討いただきました大阪港湾区域並びに本市の管理河川におけます底質浄化対策の進捗の状況、また、環境監視の結果などにつきまして、ご検討いただきたいと考えてございます。
本市といたしましては、今後とも、良好な都市環境を確保するとともに、水環境、また、地盤環境をはじめ、各種の環境施策をより一層、推進していく所存でございますので、委員の先生方におかれましては、引き続き、お力添えを賜りますようお願い申しあげまして、簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。
大阪市では、これまで「大阪市底質対策技術検討会」におきまして、底質汚染問題について、また、「大阪市土壌汚染対策専門委員会」では、土壌汚染や地下水汚染問題について、それぞれ検討を行ってまいりましたが、今後の環境施策を円滑に推進していくために、この2つの委員会を統合いたしまして、参考資料に示しますとおり、要綱改訂を行ってきたところです。
本検討会の委員につきましては、村岡先生、福永先生には再任させていただきますとともに、新たに上野先生、藤川先生には委員にご就任いただき、検討を進めていくこととなりました。
村岡委員長
委員の先生方から、ご賛同を得ましたので、この検討会の委員長を務めさせていただきます。
この検討会は、先ほど西山部長からも、ご説明ありましたように、これまでの2つの委員会を統合した新たな委員会となっています。これまで扱ってきました内容は、底質汚染、土壌汚染、地下水汚染であります。これらの内容については、相互に関係する場合もあり、独立して考えなければならない場合もあります。
この3つの汚染は、対策という面から扱っていく拠り所となる法律は3つとも別であります。ということで、これを行政サイドから扱われるにしても、環境局、港湾局、建設局と3つに分かれているわけです。
今回、統合的に検討するということになりまして、ある意味では、行政の縦割りを除いた総合的な検討ができる場であるということで、好ましい形になってきたのではないかと思います。
委員の先生方にも、それぞれご専門があるわけですが、この際、ご自分の専門以外に関連することが多いでしょうから、そういったところから広く総合的にご議論いただくことが望ましいと思いますので、その点、ご協力の方よろしくお願いいたします。
それでは、早速、議事に入りますが、本日の議題は、報告案件だけ3つあるようでございます。
まず、第1の議案ですけれども、「平成19 年度 ダイオキシン類環境調査結果」についてでございます。
事務局(環境局前田課長代理)
お手元の資料1に基づきまして、「平成19 年度ダイオキシン類調査結果」について、ご説明させていただきます。平成19 年度のダイオキシン類の水質・底質調査地点及び環境基準の適合状況を表しております。大阪市の地図上に、水質・底質のダイオキシン類の調査地点と環境基準の適合・不適合を示しております。各地点ごとに円がありますが、円の上半分が赤い場合は水質の環境基準不適合を、下半分が赤い場合は、底質の環境基準が不適合を、全体が赤い場合は、水質・底質両方とも環境基準不適合であることを表しております。
平成19 年度、水質につきましては、古川の徳栄橋、神崎川の小松橋、東横堀川の本町橋の3箇所で環境基準不適合となっております。
事務局(環境局前田課長代理)
また、底質につきましては、古川の徳栄橋、六軒家川の春日出橋、住吉川の住之江大橋下流1,100mの地点で環境基準不適合となっております。
こちらの表−1でございますが、水質のダイオキシン類濃度の経年変化を示しております。経年変化としましては、平成15 年度から19年度までのデータで示しております。
環境基準を超える又は高めのデータが出ている地点につきましては、調査回数を多く設定するというように、年度・地点により、調査回数が異なっております。複数回、測定を行う地点につきましては、データを範囲で示しております。
青色の網掛けをしており、下線を引いておりますのは、環境基準値1pg-TEQ/L を超えたところです。道頓堀川の大黒橋、古川の徳栄橋、東横堀川の本町橋、寝屋川の今津橋、京橋、神崎川の小松橋において、環境基準不適合となる傾向にあります。
資料の3枚目をご覧いただきたいのですが、こちらの方は、底質のダイオキシン類濃度の経年変化を示したものでございます。水質と同様に、平成15 年度から19 年度までのデータでお示ししております。
水質と同様、網をかけて下線を引いておりますところが、環境基準値150pg-TEQ/g を超えたところであります。道頓堀川の大黒橋、古川の徳栄橋の他、木津川、神崎川の河口部において、環境基準が不適合となる傾向が続いております。
ダイオキシン類の汚染要因でありますが、大阪府、大阪市で設置しております「河川及び港湾の底質浄化対策検討委員会」において検討されておりまして、大阪府及び大阪市の河川及び港湾におけるダイオキシン類の汚染は、主にPCB 製剤、並びに農薬、燃焼由来の要因が複合したものであり、個々の発生源の影響を特定することは困難であると結論づけられております。
底質浄化対策についてですが、まず、本市管理河川についてご説明させていただきますと、道頓堀川、東横堀川につきましては、既存の測定結果におきまして、すでに底質ダイオキシン類の環境基準の超過が判明しておりますので、大阪市建設局が詳細調査を行い、ダイオキシン類による底質汚染を確認しております。底質浄化対策につきましては、平成19 年度に同局が両河川の一部の区間で浚渫による浄化対策を実施しております。
港湾区域につきましては、同じく既存の測定結果におきまして、既に底質ダイオキシン類の環境基準の超過が判明しておりますので、大阪市港湾局が平成15 年度から17 年度にかけまして、正蓮寺川、尻無川、木津川、木津川運河等の大阪港湾区域の河川、港湾重複7区域におきまして、底質ダイオキシン類の汚染範囲等の調査を行っております。
事務局
(環境局前田課長代理)
底質浄化対策につきましては、平成18 年度から、木津川運河の一部区域、大正内港の一部区域で、同局が浚渫による浄化対策に着手しているところでございます。
さらに、大阪市以外の管理河川につきましては、神崎川、古川におきまして検討がなされているところでありますが、神崎川につきましては、大阪府におきまして、本川で平成18 年度以降、浚渫と覆砂による底質対策が行われているところでございます。
また、神崎川上流の水路で高濃度の底質ダイオキシン類が検出されているということで、大阪府の方で汚染底質の除去及び底質除去後の環境モニタリングが実施されております。
特に、古川につきましては、大阪府と大阪市が連携いたしまして、ダイオキシン類による底質汚染原因究明のための追跡調査を行い、上流に環境基準を超える底質があることが判明いたしました。その後、古川の河川管理者である大阪府の方で、詳細調査が行われ、上流域の水路に高濃度の底質があることが判明いたしました。そのため、大阪府では優先順位を上げて、古川の浄化対策に取り組むこととし、平成20 年度中にも、一部の区間で浚渫による浄化対策に着手されるものと聞いております。
最後に、水質の汚濁状況についてですが、資料3枚目のペーパーをめくっていただきまして、裏面をご覧ください。
こちらは、平成19 年度の大阪市内の水質調査地点と河川のBOD 及び海域のCOD の汚濁状況を示しております。先ほどのダイオキシン類の調査結果と同様、大阪市の地図に水質の調査地点とBOD,COD の測定結果を示しています。
円の横に数字がございますが、上段が年平均値、下段が環境基準の評価を行うための75%値であります。円の大きさが、地点により異なっておりますが、大きさは年平均値の数値に比例しておりまして、円内にメッシュがあるところは、環境基準を超過していることを示しています。
平成19 年度の調査結果では、寝屋川の今津橋、古川の徳栄橋、平野川の安泰橋等寝屋川水系の6地点で環境基準を超過しております。
最後の資料の4枚目でございますが、河川BOD 及び海域COD の環境基準の評価を行うための75%値につきまして、平成15 年度から19年度までの経年変化を示しております。表中の1から38 番までが河川域でありBOD の測定値を示しています。39 から50 番までが海域ということでCOD の測定値となっています。
神崎川、大和川におきましても、環境基準の不適合はみられますけでれども、改善傾向にあることがうかがわれます。これに対しまして、寝屋川、平野川等の寝屋川水域の各地点では、引き続き、環境基準不適合の状況が続いていることがうかがわれます。
寝屋川、平野川等の河川の水質につきましては、上流域の影響を受けやすいことから、流域の自治体や河川管理者等との連携した取組が重要であると考えまして、生活排水対策や底質対策等につきまして、大阪府や寝屋川流域の市等で構成いたします「寝屋川流域協議会」等の関係機関と連携を図っていく所存であります。
以上で、ご説明を終わらせていただきます。
村岡委員長
ただいまのご説明に関しまして、何かご質問やご意見等はありますでしょうか?
福永委員
全体の評価として、特に、この数字をどうみるかということですが、底質においては変動幅が大きく、サンプリングのばらつきが考えられるのですが、サンプルのばらつきの範囲内で、特に例年と異なるような異常な値は見られなかったと評価していいでしょうか?
事務局(環境局前田課長代理)
先生のおっしゃるとおり、例年の変動の範囲内で収まっているものと考えております。地点によりましては、環境基準近傍のところもありますので、環境基準を超えたり、下回ったりということもございますが、概ね、例年の変動の範囲内で、データが推移しているものと考えております。
村岡委員長
他に、何かありますでしょうか?
藤川委員
底質ダイオキシンと水質ダイオキシンの濃度を比較していたのですが、16、18、20 番の3地点ですが、底質の濃度と水質の濃度の比率が著しく他の地点と異なりまして、底質濃度が低いにもかかわらず、水質中の濃度が高く出ていますが、これは何か理由があるのでしょうか?
もしかすると、水質と底質の採取ポイントが異なっているのでしょうか?
事務局(環境局黒木課長代理)
サンプリング地点において、底質が実際に採れない地点については、場所を移動して採取している関係がございます。16 番の本町橋でございますが、底質は平野橋で、20 番の小松橋では、底質は江口橋でサンプリングしております。
ということで、水質とは調査地点が異なっております。
藤川委員
18 番については、どうでしょうか?
事務局(環境局黒木課長代理)
18 番につきましては、水質も底質も今津橋でサンプリングしております。
藤川委員
普通、底質の場合は、ダイオキシンを濃縮すると思うのですが、通常の河川の状況であれば、底質からの微量の脱着か巻き上げで水質に反映されると思いますので、例えば他の地点は、底質と水質の比率ですが、水が1なら底質が200 くらいになっていますが、この3地点中2地点は同じ場所で採られているのに、水質濃度と底質濃度の状況が異なるということは、どこか異なるところに汚染源があるのか又は底質の採取状況に問題があるのか、又は分析上、何かがあるのかなと思います。
これについては、安全がどうこうというよりは、やはり、そういう傾向があるのであれば把握しておかれた方が、今後の対策のためにもいいのではないかと思います。
村岡委員長
今の問題は、要するに同じ地点における水質と底質の濃度の関係で、それが関連する現象として起こっているのか或いは、そうではないのかということですよね。
水の場合は、おそらく一過性で流れていってしまうと思いますので、必ずしも、そこの底質が溶出してきて、ダイオキシンの水質が悪くなるということは、ちょっと考えにくいケースもあると思います。
しかしながら、これだけ地点で差があるということは、何か他に原因があるのではないかということだと思うので、その点に注目されておく必要があるのではないかと思われます。
もう1つは、何年も汚染が長引いている地点があるわけですが、そうしますと、こういったことについては、当然、その汚染源がどこかという汚染源の特定についても、これまで調査されてきたはずだと思いますが、…
その汚染源を特定する作業の結果としては、原因不明ということですか?
事務局(環境局大石課長)
大阪市としましては、原因不明と考えております。
村岡委員長
水質についてもですか?
事務局(環境局大石課長)
そうです。
村岡委員長
BODについてもですか?
事務局(環境局大石課長)
BODにつきましては、本日、大阪府さんも来られているわけですが、大阪府さんと連携協力しながら、いろいろ調査もしておりますし、また、対策についても、上流域の自治体の方にも、ご要望させていただいております。
市内河川は、長期的には改善傾向にあると思っておりますが、まだ、6箇所ほど寝屋川流域で環境基準を超えているところがございますので、今後とも、連携を密にしながら、対策に努めてまいりたいと考えております。
村岡委員長
水質の方は、流れていってしまいますのでともかく、底質の問題が長引いているということは、そこの底質を除去する以外に、対策はないと断言していいのですか?
事務局(環境局大石課長)
私どもとしましては、特に寝屋川のところで、水質なり底質が市域内で環境基準を超えているということで、先ほど前田の方から説明しましたように、大阪府さんと連携しながら追跡調査を実施してきて、結果として、ご案内のとおり門真の第8水路で、高濃度のダイオキシン類を含む底質が溜まっていることがわかってまいりました。
それで、門真第八水路につきましては、門真市の方で、今年度、詳細調査をやられて、対策をどうしていくかを決められるというふうに聞いております。
古川本川の方では、大阪府河川室さんの方で、今年度、一部浚渫されると聞いております。
我々としては、その結果を期待しているところですが、今後ともモニタリング等を適宜行いまして、対策の効果を把握してまいりたいと考えております。
村岡委員長
他にございませんか?
福永委員
藤川先生の意見に対する私なりの考えなのですが、16、17、18 番の数値が低いのは、川でwet な底質が採れずに砂質的な底質が採れた場合は、数値としては小さなものとなるのではないか?だから、サンプリング場所の橋のたもとに泥がたまらず、砂混じりのサンプリングでは、このような結果になるのではないかと私は思っております。
村岡委員長
ただいまの福永先生の意見につきまして、何かございますか?他にご意見がないようですので、市の方でも、これらの貴重なご意見を参考にして、今後の検討の中に採り入れていただきたいと思います。
それでは、次の議題に移ります。
次も報告事項ですが、「大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策」について、ご説明をお願いします。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料2を用いまして、大阪港湾区域におけます底質浄化対策及び港区尻無川堤防工事におけます環境対策につきまして、ご説明させていただきます。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料2の表紙をめくっていただきますと地図がございますが、今回説明させていただきます右下の方の赤い丸印2つが、平成18 年度から行っております大阪港湾区域の底質ダイオキシン類浄化対策の工事箇所でございます。その右上の方に青い丸印がありますが、これが19 年度から20 年度にかけて対策を行いました尻無川の工事箇所でございます。
図面をめくっていただきますと、1頁から12 頁までが、大阪港湾区域における底質ダイオキシン類浄化対策に伴う環境対策についてということで、平成18 年度から行っているものでございます。
また、この対策は、平成18 年3月に策定いたしました「大阪港湾区域におけます底質ダイオキシン類浄化対策方針」に基づいて実施しておりますもので、対策方針自体を参考資料として10 頁から12 頁に添付しております。
平成18 年度の浄化対策の概要ですが、実施場所は、木津川運河の一部区域及び大正内港の一部区域です。
対策土量は、それぞれ100m3、50m3 となっております。 ????
対象としました底質は、1000pg-TEQ/g から3000pg-TEQ/g の範囲で、いわゆる中濃度レベルでございます。浚渫除去しました底質を近傍の管理型処分地であります夢洲1区まで運搬しまして、そこで袋詰脱水処理を行いまして、同じく夢洲1区に処分したというものです。
環境対策でございますが、大阪府・市の河川及び港湾の底質ダイオキシン類対策検討委員会の「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル(案)」等に準拠いたしまして、次の3項目の対策を行っております。
1.浚渫場所における防止枠及び防止膜による汚濁防止対策
2.工事施工へのフィードバック等を実施するため、浚渫場所周辺における事前調査及び日常的な水質環境監視の実施
3.浚渫土砂処分地であります夢洲における水質環境調査の実施でございます。浚渫場所に関わります水質環境監視調査でございますが、調査地点としましては、工事箇所の上流側、下流側それぞれに放流箇所に近い順に補助監視点、基準監視点を、一番遠いところにバックグランド点を設置してございます。
調査地点は、次頁の図2に示すとおりです。それぞれの調査地点を設定し、浚渫工事の実施にあたりましては、水質環境監視調査を実施いたしました。
調査内容は、4頁の表2に示すとおりでありまして、日々の工事の監視に用います濁度は、基本監視点におきまして、深度方向に水深50cm から1m間隔の各層で測定いたしました。最下層は底面から1mの深さのところでございます。ダイオキシン類や生活環境項目などの採水測定は、それぞれの基本監視点で水深約2割程度の深さで行いました。
また、バックグランド点の濁りの測定も、同じく水深の2割程度の深さで行いました。
事務局(港湾局有門課長代理)
工事前に、現地で実施いたしました事前調査結果を基に、濁度等の日々の工事の環境監視基準を設定いたしました。その内容が、4頁にございます表2に示すとおりでございます。
濁度等の環境監視基準の設定は、事前調査データが少なかったこと等、精度的なことを勘案いたしまして、事前の水質調査結果のダイオキシン類濃度と濁度の平均値を利用いたしまして、比例的に監視基準を設定したということでございます。
工事中の水質環境監視調査結果につきましては、5頁の表3のとおりでございます。表3-1 は、木津川運河の濁度の監視結果で週平均値を記載しております。
次の頁の表3-2 が、大正内港の濁度の監視結果で、同じく週平均値を記載しております。その下の表3-3 がダイオキシン類等の採水分析結果です。採水は、水深の約2割程度の深さで行っております。
結果といたしましては、異常なにごりや油膜の発生もなく、全ての地点で、水質環境監視基準(週平均値)において適合している状況でございました。ただ、濁度につきましては、補助監視点で超過した地点もございますが、同時期の基準監視点では適合しておりますので、問題はないものと考えております。
資料の7頁でございます。浚渫した底質は、夢洲1区で袋詰脱水した後、夢洲1区の管理型処分場において処分いたしました。処分先の夢洲及びその周辺の水質環境調査を行っておりますが、脱水した排出水については水質調査を実施し、ダイオキシン類に係る排水監視基準に適合していることを確認したうえで、夢洲1区のとなりにあります夢洲3区へ放流いたしました。
写真等につきましては、12頁以降に掲載しております。夢洲3区への放流水の調査結果につきま
しては、表4のとおり基準に適合しております。
この排出水は、夢洲3区からその南側にございます2区を経由いたしまして、2区の余水吐から海域に放流してございます。その際の水質調査結果は、7頁の表5のとおり排水基準に適合している状況でございます。
以上が、平成18 年度に行いました内容でございまして、平成19年度は夢洲1区側における作業を行ってございまして、平成20 年度は、現在、浄化対策工事を実施しておりまして、同様の環境対策を行っているところでございます。実際の実施場所は2箇所ありまして、18 年度と同様に、木津川運河に引き続き大正内港においても実施しておりますが、大正内港につきましては、18 年度の地点とは異なる場所で行っております。
対象としておりますダイオキシン類の濃度は、150〜1000 pg-TEQ/gといういわゆる低濃度及び1000〜3000pg-TEQ/g までのいわゆる中濃度を対象としております。
以上が、大阪港湾区域における底質浄化対策の実施結果でございます。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料の13 頁でございますが、尻無川右岸の堤防工事における環境対策について説明させていただきます。この工事は、堤防におけます耐震補強工事を行っているものですが、本工事区域内に、ダイオキシン類及びPCB の環境基準を超過した底質が確認されましたことから、工事に際しての環境対策を行ったものです。
平成19 年度から20 年度にかけて実施いたしました。次の頁ですが、対策土量としましては、約1700m3 でございます。ダイオキシン類の濃度は、160〜970pg-TEQ/g ということで、いわゆる低濃度といわれるものです。
PCB につきましては17〜37mg/kg ということでございます。対策方法といたしましては、底質を現地でセメントを加えることに
より固化処理を行い、原位置で矢板内に封じ込めを行うというものでございます。
環境対策につきましては、先ほど説明いたしました水質の浄化対策のものとほぼ同様でございます。調査内容につきましては、15 頁の表1のとおりでございます。
また、水質環境監視調査地点等につきましても、16 頁にございます図2のとおりでございます。
現地で事前に行いました環境調査結果を用いまして、濁度とダイオキシン類濃度との相関から17 頁の表2に示しております濁度等の水質環境監視基準を設定してございます。相関図を下につけているところです。
工事中の水質環境監視結果につきましては、18 頁の表3に示すとおりでございます。表3-1 は、濁度の監視結果でございます。本文にも記載させていただいておりますが、5月から6月の梅雨の時期には河川上流からの濁水の流入による影響から濃度が高くなる傾向が見られ、一部の個別測定値が超過いたしましたが、週平均値を超過することはありませんでした。
また、採水分析結果といたしましては、SS が1回基準値を超過してございますが、工事施工箇所からみて、流れの上流側でございまして、下流側におきましては基準値以下でございましたので、工事以外の影響によるものと考えてございます。また、DO につきましても、1回基準値を下回っておりますが、一般的に夏場に低くなる傾向がございますので、一時的に数値が低下したのではないかと考えております。
同日において、工事施行箇所の上流側、下流側ともに基準値を下回っていることから、工事の影響ではないものと考えております。
また、表3-2 は採水分析結果を示しておりまして、採水箇所は水深の約2割程度の深さで行っております。20 頁ですが、この工事の場合、原位置で底質にセメントを加えて固化処理を行うということでございますので、この固化処理効果の確認というものを実施しております。事前に配合試験を行いました。
その結果が表4でございます。この結果を基に、固化剤でありますセメントをどれだけ加えるかという混入量を決定いたしました。
事務局(港湾局有門課長代理)
また、実際に、現地で固化処理を行いました底質につきましても、溶出試験を行っております。その結果が表5及び表6でございます。
表5は、六価クロムについて、表4の結果を受け、決めました添加量を底質に加えまして、大丈夫かどうかをみるために行ったものであります。実際の現地における固化物の溶出試験結果は、表5及び表6のとおり基準値以下の内容となってございます。
合わせまして、当委員会の前身でございます委員会におけるご指摘を踏まえまして、溶出試験につきましては、水銀、六価クロムについても行っているところでございます。
表7につきましては、事後の水質調査の概要を記載しておりますが、工事完了が1月ということもございまして、採水は2月に実施しておりますので、現在、分析中でございます。3月中旬には結果が判明するものと思われます。
最後に、尻無川右岸の堤防工事に関する写真を最後の頁に掲載しております。以上が、港湾局からの報告でございます。
村岡委員長
先ほど同様に、何かご質問等はありませんでしょうか?
村岡委員長
17 頁の相関図ですが、いつ頃、どの場所のデータでしょうか?
事務局(港湾局有門課長代理)
実際の対策工事は、春から行っているわけですが、事前調査につきましては、前の年の秋(9月〜10 月頃)のデータでございます。
村岡委員長
現実に、濁度との相関において、監視するということも必要になってくるでしょうから、相関をとるものについては、今後もデータを蓄積される方がいいのでは…と思います。
他に何かございませんか?よろしいでしょうか?ありがとうございました。それでは、この件についても、ご理解いただいたということで、次の3つめですが、大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策について、ご説明いただきたいと思います。
事務局(建設局三村課長代理)
資料3の大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策についてでございますが、工事名としましては、「道頓堀川水辺整備その他工事(湊町右岸工区)」に関わります浄化対策ということでございます。本件につきましては、本会議の前回に開かれました平成19 年9月に、ご報告させていただいた状況を審議していただいたという工事でございます。
1頁は、工事概要ですが、道頓堀川の水辺整備ということで、ミナミを東西に流れます道頓堀川に遊歩道を設置していくという事業でございます。1-1 の構造ですが、位置的には下の図にありますように四ツ橋筋のすぐ西側の北沿いです。住所でいいますと、西区南堀江というところでございます。
延長としましては約130mほどあり、遊歩道を建設するのですが、河川の中に新しい護岸を作って、河川の中を埋め立てる形式となっております。
遊歩道の幅は、大体9〜13mとなっておりまして、河川内に鋼矢板又は鋼管矢板を打設してまいります。
今回の対象となります土量は、約4000m3 となっております。これにつきましては、ヘドロ層を除去した後に、底質の入れ替えを行っていきます。
下に、図-1 として地図が出ております。1頁めくっていただきまして、2頁でございます。若干小さくて見づらくて申し訳ありませんが、左側が施行する前の現況図でございまして、護岸即ち大きなコンクリートの壁でございますが、その前に鋼矢板の護岸があります。右側の方は計画となっておりますが、大きな護岸であるコンクリート上部を撤去いたしまして、川の中に鋼矢板
を立てますが、幅は狭いところでは9mから13mほどございます。
次の3頁のところには、非常に見づらいですが、平面図が載っておりますが、図のように矢板、鋼矢板を打っている状況でございます。
次の4頁に出ておりますのが、前回の平成19 年9月のときに、ご報告させていただきましたこの工事現場における底質の状況でございます。
?の概略調査ということで、含有量と溶出量それぞれ2地点で測定した結果を示しております。含有量につきましては、220、230pg-TEQ/gということで環境基準を超えています。また、溶出量につきましても、いわゆる海洋汚染防止法の基準をオーバーしております。この概略調査といいますのは、工事現場内の概ね真ん中に位置する2地点を選んで、その表層の土をとりましたが、次の?の詳細調査では、平面的に8地点を選びまして、それぞれについて鉛直方向についても、ヘドロ層50cm おきに砂層のところまで、溶出及び含有量について、再度詳細に調査いたしました。
その結果でございますが、ダイオキシン類の含有につきましては、概略調査とさほど変わらない数字であり、最高で470 という数字が出ております。
事務局(建設局三村課長代理)
それから、ダイオキシン類の溶出ですが、概略調査の時には、44や21 pg-TEQ/L でございましたが、全て10 未満となっている状況でございます。
その他に、一部の箇所では溶出ですが、総水銀や鉛について、若干基準を超えるものが出ております。6頁ですが、図が小さくて恐縮ですが、真ん中に赤い点が2つございます。これは、一番最初に行いました概略調査の地点でございます。
それから、黒い点が8地点ありますが、これが概略調査の土を採った箇所でございます。
我々といたしましては、概略調査の時に出てまいりました溶出量が、通常時の数値よりも若干大きいということもございまして、前回の会議の時に、おはかりさせていただきましたが、一番最初の概略調査の地図周辺の4スミを囲むように、再度調査をしたということで、7頁に平面的な位置が出ております。
概略調査の赤い点のまわり4スミを、再度調査させていただくということと、念のために、その他に3点の合計11 地点、検体数としては16 検体となると思いますが、鉛直方向にも調査させていただきました。その結果が8頁にございます。
8頁には、ダイオキシンの含有あるいは溶出について記載しておりますが、含有量といたしましては、前回または前々回に調査いたしましたような数値でございまして、今回の場合には最高で330 pg-TEQ/gというような数字が出ております。溶出量につきましては、海洋汚染防止法基準、これは埋立が可能かどうかの基準ですが、10 未満の数字ばかりでございまして、最高で6.5 というような数字となっております。
これによりまして、北港に埋立処分する土は約2,800m3、溶出量を再チェックした形で、鉛、水銀というものが混ざっているということで、海洋投棄できないという土量はセメント原料として、セメント工場に運搬しましたのが、1,200m3 というような形で確定させていただきました。
9頁でございますが、工事中の環境監視ということで、前回の会議の時に、事前の水質調査の結果を報告させていただいております。10頁には水質環境基準ということで、その下側に出てまいりますが、pH,BOD,SS,DO、濁度が記載されております。この中で、濁度でございますが、濁度の週平均値は10.0 度、個別測定値は22.3 度で、事前の水質調査結果から設定されております。週平均値の10.0 度でございますが、事前の水質調査結果の段階でダイオキシン類の水質が3.6pg-TEQ/L ということでございまして、この10.0 度という数値につきましては、事前の水質調査結果に関して、現状より悪化させないという形の監視基準としております。
11 頁については、監視状況の結果を掲載しております。11 頁は、濁度の測定結果でございます。これは、週平均値の数字
を載せさせていただいておりまして、その下に個々の数字の最大・最小値を記載しております。
事務局(建設局三村課長代理)
個々の数値及び週平均値につきましても、環境監視基準値を上回るところはございませんでした。pH,BOD,SS,DO等の生活環境項目の測定でございますが、DO とBOD につきましては、一部の期間で監視基準を上回るあるいは下回るようなところが出てまいりまして、その期間につきましては、DO の場合は、矢板の打設や鋼管矢板の打設という時期でありまして、若干、矢板の打設速度を遅らせるというかゆっくりさせるというようなことで対応しました。
BOD の場合は、埋め立ての時、土を締切内に入れる時の状況でございますが、この時につきましても、若干、土砂の掘削あるいは投入に係るスピードを落とさせていただいたということでございます。
今回の工事につきましては、以上のような結果となっています。
村岡委員長
ご質問やご意見がありましたら、お願いします。
上野委員
ダイオキシン類の溶出量ですが、2回目の測定時点でも、若干、まだ数値が高いような気がするのですが、浚渫土中の特徴としては何かあるのでしょうか?あるいは溶出液が、若干濁っているとかはあるのでしょうか?
オブザーバ
(大阪市立環境科学研究所先山主任)
私は、本データを事前に見せていただきましたので、その印象からご説明させていただきます。先生がおっしゃるように、底質の2回目の測定データにつきましても、若干高いかなという気がしますが、まず、1回目の方が非常に高いということで、溶出量が多くなるような状況にあった泥なのかどうかということをみる指標がないかというご相談で、事前に見せていただきました。
しかし、その時点では、そのことを判断するようなデータの採取がなされていないということで、すでに、この時の泥が存在しない段階では、その判断はできませんでした。
2回目のデータにつきましては、平均の粒子径などは若干、データとしてとられていましたので、それを見せていただきまた。そうすると、この底質は、ダイオキシンも高いですけれども、かなりヘドロ化しているということで、平均粒子径が0.05mm を下回るようなものもたくさんありまして、非常に微粒子の底質が多いという状況がうかがえると思います。
ですから、ろ過操作等のバラツキというものが、結構、大きく効いてくるのではないかという判断を私はいたしました。
村岡委員長
このろ過操作というのは、現在のところ、どのような基準でやっておられるのですか?
オブザーバ
(大阪市立環境科学研究所先山主任)
ろ過操作につきましては、海洋汚染防止法で、ご存知のように孔径という表現がなされているわけですが、前回の委員会でも若干、説明させていただいたのですが、私が調べたところによりますと、市販品ではガラス繊維ろ紙で、仕様上、そのような表現がなされているものは存在しません。
現実には、様々なメーカーにより表現方法が異なるということで、その孔径に値するそれぞれの表現が、どの程度かとい
うことは、メーカーによってばらついております。
それを使用するときに、孔径と置き換えて読むのか、それよりも孔径の方が小さいということで、1μmよりも小さなものを使用するかということで、かなりろ過操作にバラツキが出る可能性があります。
しかし、公式には孔径という表現がされておりますので、孔径をどのように分析する側が解釈するかということで、結果に大きな違いが出ているのではないかと思います。具体的には、孔径と同じような意味で使われているメーカーさんのものでしたら、粒子保持能という表現があり、ろ過の初期段階でその粒子径以上のものが98%以上止められるという表現をされているところもあります。
もう一方では、保留粒子径ということで、「1μmのものを止めようとしますと、さらにその半分くらいの0.4〜0.6μmのものを使わないとダメですよ。」ということがカタログ上では示されていますので、その辺、混同して使用している可能性があるのかなと思います。
ですので、どのようなものを使うかということは、いずれ公式の委員会の場で承認を得て、標準的な操作の仕方というのを用いないと、なかなか説明がつかないデータが出てくる可能性があると考えられます。
村岡委員長
何か関連して、ご意見ありませんでしょうか?
福永委員
後で、この件に関して、お願いしようかなと思っていたのですが、前回の委員会でも、かなり問題になって、結局ばらついたデータが出てきて、議論に困るというようなことが多いと思うのですけれども、環境科学研究所さんの方で、大阪府さんとも調整していただきながら、誰が行っても同じ答えが出るというふうなフロー、いわば、今法令的には定められているんですけれども、必ずしも十分ではないので、人によって異なった答えが出るということですから、この委員会にデータとして出すという時には必ずこの方法で行えば、間違いない安定した数値が出るというフローを考えていただければ、この委員会としてはありがたいのではないかと思いますので、お願いしたいと思います。
事務局(環境局大石課長)
福永先生のご指摘の点ですが、先般、環境省の方から底質の調査方法に関わりまして、アンケート調査がまいりました。その時に、私どもの回答の中に、分析に用いるろ紙の規格をはっきりと明記してほしいということをお返ししております。いずれにいたしましても、前回以降、村岡先生にもご指摘をいただきながら、府市で、きちんと統一的な取り扱いを決めるようにというご指摘もありましたので、今後、大阪府の底質委員会の事務局とも調整をしながら、また、本市環境科学研究所、大阪府環境農林水産総合研究所とも、ご相談しながら、統一的な取り扱いができるかどうかも含めまして検討を進めてまいりたいと考えております。
村岡委員長
その点につきましては、ぜひスタンダードな測定値をもとに議論ができるように進めてほしいと思います。
藤川委員
濁度とダイオキシンの関係を0.1pg-TEQ/L だというのが、先ほどの回帰分析の結果ですけれども、今回の方では、濁度との関係を3.6pg-TEQ/L というふうにおっしゃっていただいたのですが、濁度1が0.1 なのか0.36 なのかというので、そういうデータは蓄積していただくのは、妥当だと思うのですが、ただ、この時の濁度10 で3.6pg-TEQ/L とおっしゃった時のろ過方法は、どのようなものだったのかを教えていただきたいのが第1点です。
もう1つは、ダイオキシン類については溶出量と含有量を両方測ると思いますが、普通、ダイオキシン類は溶出量は低いでしょうから、例えば、この溶出量と含有量の比が含有量5に対して溶出量が1というデータが出た時点で、直ちに環境科学研究所さんから、現場の方にご相談いただくなり、再分析に回すなりの対応をしていただくと早いと思うのです。
だから、そういうことを現場で徹底していただいたらどうかなというのが第2点です。
不自然なデータが出れば、すぐに追加のサンプリングはもちろんですけれども、再分析ということも考えられると思います。
事務局(建設局三村課長代理)
事前の水質調査を行った時には、2回目の詳細調査と同じ方法で行っております。一番最初の概略調査あるいは次の詳細調査、それから事前の水質調査という段階を経まして、事前の水質調査と詳細調査はほぼ同じような時期になっておりますが、一番最初の概略調査と次の詳細調査と次の詳細調査あるいは事前水質調査とは若干、違うような形であると聞いております。
私どもは、工事を発注してから、水質調査あるいは底質調査を行っておりますので、これからはちょっと考え直さなくてはいけないのですが、当時の工事期間中にそういうふうな状況が出てまいりますので、結果が出るまで少なくとも1カ月、2カ月ほどかかりますので、若干、その辺のところが、我々としては考え直さなくてはならないところではあると思います。
事務局(環境局大石課長)
2点目のご指摘でございますが、我々といたしましては、これからもデータの蓄積につきましては、統一的に、今後も進めていきたいと考えております。
また、検討会の事務局を、大阪市的にも港湾局、環境局、建設局、オブザーバとして環境科学研究所さんにも入っていただいておりますので、うまく機能させていきながら連絡体制をとっていきたいと考えております。
村岡委員長
今の問題は、すぐに解決できるものとは思えないですし、その時、その時に判断しないといけない大変難しい問題ですが、是非ともいい値が出るように、「正しい値が出て、正しい判断ができるように」努力をしてくださいということですから、その辺のところをよろしくお願いいたします。
他にございますか?
それでは、ご意見がないようでございますので、本日の議題である3つの報告について、委員の先生方、いろいろご指摘いただきましたので、これで全て終わったというわけではありませんが、ともかく、この報告の中身について、十分確認できたということにさせていただきます。
合わせまして、これに基づいて、また、作業が進められると思いますので、ぜひ、それが円滑に、いい効果が上げられますようにお願いしたいと思います。
それでは、以上をもちまして、議事を終わりたいと思います。後、進行を事務局にお願いします。
大阪市底質対策等技術検討会
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000019399.html
1 日 時 平成21 年2月20 日(金) 午後1時30 分〜午後2時50 分
2 場 所 環境局第11〜13 会議室(WTCコスモタワービル36 階)
3 出席者
(委 員)
大阪大学名誉教授 村岡 浩爾
大阪人間科学大学人間科学部教授 福永 勲
摂南大学薬学部准教授 上野 仁
京都大学原子炉実験所准教授 藤川 陽子
(事務局)
大阪市環境局・港湾局・建設局
(オブザーバ)
大阪府都市整備部河川室、大阪府環境農林水産部環境管理室、
大阪府環境農林水産総合研究所、大阪市立環境科学研究所水環境担当
4 議 題
(1) 委員長の選出
(2) 報告案件
? 平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
? 大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策について
? 大阪市管理河川(道頓堀川等)における底質浄化対策について
5 議事要旨
(1) 委員長の選出について
要綱の規定に基づき、委員の互選により村岡委員が委員長として選出された。また、村岡委員長の指名により、福永委員が委員長の職務代行を行うこととなった。
(2) 平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
事務局(環境局)から、大阪市域における平成15〜19 年度までの5年間の水質・底質に係るダイオキシン類濃度測定結果及び水質に係る代表的な汚濁指標であるBOD やCOD の汚濁状況について報告を行った。
(3) 大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策について
事務局(港湾局)から、平成18 年度から着手している大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策に伴う環境対策の概要(浚渫場所周辺における事前・日常的な水質環境監視や処分地(夢洲)及びその周辺おける水質環境調査結果など)の報告を行うとともに、平成19 年度に着手した港区尻無川(水門上流)堤防工事における環境対策の概要(工事場所周辺における事前・日常的な水質環境監視や固化処理による封じ込め効果を確認するための水質調査の実施結果など)について報告を行った。
(4) 大阪市管理河川(道頓堀川等)における底質浄化対策について
事務局(建設局)から、道頓堀川水辺整備事業のうち、湊町右岸工区における遊歩道の設置に係る工事概要、浚渫土の処理、工事中の環境監視結果などについて報告を行った。
【結果】
(2)〜(4)について、事務局からの報告内容について、各委員からご理解をいただいたが、底質ダイオキシン類溶出量の測定値の評価に関して、「底質ダイオキシン類に関する分析手法を含めた統一的な取り扱いの確立に向け、今後、府市等関係機関が連携すること」などが要望として出された。
6 会議資料:
(1)資料1 :平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
(2)資料2 :大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策及び港区尻無川(水門上流)堤防工事における環境対策について
(3)資料3 :大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策について
(4)参考資料:大阪市底質対策等技術検討会開催要綱
7 問い合わせ先
大阪市環境局環境保全部土壌水質担当
Tel:06-6615-7984、FAX:06-6615-7949、E-mail:ja0040@city.osaka.lg.jp
大阪市底質対策等技術検討会会議録
発言者(事務局及びオブザーバ)
・環境局環境保全部長 西山健一郎
・環境局環境保全部土壌水質担当課長 大石 一裕
・環境局環境保全部土壌水質担当課長代理 前田 和男
・環境局環境保全部環境情報担当課長代理 黒木 隆司
・環境局環境保全部担当係長 宮本 敏之(司会者)
・港湾局計画整備部環境保全担当課長代理 有門 貴
・建設局下水道河川部河川担当課長代理 三村 経雄
・大阪市立環境科学研究所水環境担当研究主任 先山 孝則
議事内容:次のとおり
西山環境保全部長
さて、大阪市では、これまで「大阪市底質対策技術検討会」におきまして、市内の河川並びに海域における底質汚染などに関しまして、その汚染要因や浄化対策につきまして検討するとともに、市域内における土壌汚染、また、地下水汚染に係ります調査・対策に関しましては、別途「大阪市土壌汚染対策専門委員会」を設置させていただき、学識者の先生方より検討をいただいたところでございます。
今般、大阪市では、これらの2つの委員会をより総合的に運用いたしまして、大阪市域内の公共用水域に係ります有害な底質、また、市域内の土壌汚染・地下水汚染など、水環境分野と地盤環境の分野の対策を一体的に推進いたしますため、平成20 年7月に底質の委員会に土壌の委員会を整理・統合させていただいたところでございます。
本日は、これまで「底質対策技術検討会」でご検討いただきました大阪港湾区域並びに本市の管理河川におけます底質浄化対策の進捗の状況、また、環境監視の結果などにつきまして、ご検討いただきたいと考えてございます。
本市といたしましては、今後とも、良好な都市環境を確保するとともに、水環境、また、地盤環境をはじめ、各種の環境施策をより一層、推進していく所存でございますので、委員の先生方におかれましては、引き続き、お力添えを賜りますようお願い申しあげまして、簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。
大阪市では、これまで「大阪市底質対策技術検討会」におきまして、底質汚染問題について、また、「大阪市土壌汚染対策専門委員会」では、土壌汚染や地下水汚染問題について、それぞれ検討を行ってまいりましたが、今後の環境施策を円滑に推進していくために、この2つの委員会を統合いたしまして、参考資料に示しますとおり、要綱改訂を行ってきたところです。
本検討会の委員につきましては、村岡先生、福永先生には再任させていただきますとともに、新たに上野先生、藤川先生には委員にご就任いただき、検討を進めていくこととなりました。
村岡委員長
委員の先生方から、ご賛同を得ましたので、この検討会の委員長を務めさせていただきます。
この検討会は、先ほど西山部長からも、ご説明ありましたように、これまでの2つの委員会を統合した新たな委員会となっています。これまで扱ってきました内容は、底質汚染、土壌汚染、地下水汚染であります。これらの内容については、相互に関係する場合もあり、独立して考えなければならない場合もあります。
この3つの汚染は、対策という面から扱っていく拠り所となる法律は3つとも別であります。ということで、これを行政サイドから扱われるにしても、環境局、港湾局、建設局と3つに分かれているわけです。
今回、統合的に検討するということになりまして、ある意味では、行政の縦割りを除いた総合的な検討ができる場であるということで、好ましい形になってきたのではないかと思います。
委員の先生方にも、それぞれご専門があるわけですが、この際、ご自分の専門以外に関連することが多いでしょうから、そういったところから広く総合的にご議論いただくことが望ましいと思いますので、その点、ご協力の方よろしくお願いいたします。
それでは、早速、議事に入りますが、本日の議題は、報告案件だけ3つあるようでございます。
まず、第1の議案ですけれども、「平成19 年度 ダイオキシン類環境調査結果」についてでございます。
事務局(環境局前田課長代理)
お手元の資料1に基づきまして、「平成19 年度ダイオキシン類調査結果」について、ご説明させていただきます。平成19 年度のダイオキシン類の水質・底質調査地点及び環境基準の適合状況を表しております。大阪市の地図上に、水質・底質のダイオキシン類の調査地点と環境基準の適合・不適合を示しております。各地点ごとに円がありますが、円の上半分が赤い場合は水質の環境基準不適合を、下半分が赤い場合は、底質の環境基準が不適合を、全体が赤い場合は、水質・底質両方とも環境基準不適合であることを表しております。
平成19 年度、水質につきましては、古川の徳栄橋、神崎川の小松橋、東横堀川の本町橋の3箇所で環境基準不適合となっております。
事務局(環境局前田課長代理)
また、底質につきましては、古川の徳栄橋、六軒家川の春日出橋、住吉川の住之江大橋下流1,100mの地点で環境基準不適合となっております。
こちらの表−1でございますが、水質のダイオキシン類濃度の経年変化を示しております。経年変化としましては、平成15 年度から19年度までのデータで示しております。
環境基準を超える又は高めのデータが出ている地点につきましては、調査回数を多く設定するというように、年度・地点により、調査回数が異なっております。複数回、測定を行う地点につきましては、データを範囲で示しております。
青色の網掛けをしており、下線を引いておりますのは、環境基準値1pg-TEQ/L を超えたところです。道頓堀川の大黒橋、古川の徳栄橋、東横堀川の本町橋、寝屋川の今津橋、京橋、神崎川の小松橋において、環境基準不適合となる傾向にあります。
資料の3枚目をご覧いただきたいのですが、こちらの方は、底質のダイオキシン類濃度の経年変化を示したものでございます。水質と同様に、平成15 年度から19 年度までのデータでお示ししております。
水質と同様、網をかけて下線を引いておりますところが、環境基準値150pg-TEQ/g を超えたところであります。道頓堀川の大黒橋、古川の徳栄橋の他、木津川、神崎川の河口部において、環境基準が不適合となる傾向が続いております。
ダイオキシン類の汚染要因でありますが、大阪府、大阪市で設置しております「河川及び港湾の底質浄化対策検討委員会」において検討されておりまして、大阪府及び大阪市の河川及び港湾におけるダイオキシン類の汚染は、主にPCB 製剤、並びに農薬、燃焼由来の要因が複合したものであり、個々の発生源の影響を特定することは困難であると結論づけられております。
底質浄化対策についてですが、まず、本市管理河川についてご説明させていただきますと、道頓堀川、東横堀川につきましては、既存の測定結果におきまして、すでに底質ダイオキシン類の環境基準の超過が判明しておりますので、大阪市建設局が詳細調査を行い、ダイオキシン類による底質汚染を確認しております。底質浄化対策につきましては、平成19 年度に同局が両河川の一部の区間で浚渫による浄化対策を実施しております。
港湾区域につきましては、同じく既存の測定結果におきまして、既に底質ダイオキシン類の環境基準の超過が判明しておりますので、大阪市港湾局が平成15 年度から17 年度にかけまして、正蓮寺川、尻無川、木津川、木津川運河等の大阪港湾区域の河川、港湾重複7区域におきまして、底質ダイオキシン類の汚染範囲等の調査を行っております。
事務局
(環境局前田課長代理)
底質浄化対策につきましては、平成18 年度から、木津川運河の一部区域、大正内港の一部区域で、同局が浚渫による浄化対策に着手しているところでございます。
さらに、大阪市以外の管理河川につきましては、神崎川、古川におきまして検討がなされているところでありますが、神崎川につきましては、大阪府におきまして、本川で平成18 年度以降、浚渫と覆砂による底質対策が行われているところでございます。
また、神崎川上流の水路で高濃度の底質ダイオキシン類が検出されているということで、大阪府の方で汚染底質の除去及び底質除去後の環境モニタリングが実施されております。
特に、古川につきましては、大阪府と大阪市が連携いたしまして、ダイオキシン類による底質汚染原因究明のための追跡調査を行い、上流に環境基準を超える底質があることが判明いたしました。その後、古川の河川管理者である大阪府の方で、詳細調査が行われ、上流域の水路に高濃度の底質があることが判明いたしました。そのため、大阪府では優先順位を上げて、古川の浄化対策に取り組むこととし、平成20 年度中にも、一部の区間で浚渫による浄化対策に着手されるものと聞いております。
最後に、水質の汚濁状況についてですが、資料3枚目のペーパーをめくっていただきまして、裏面をご覧ください。
こちらは、平成19 年度の大阪市内の水質調査地点と河川のBOD 及び海域のCOD の汚濁状況を示しております。先ほどのダイオキシン類の調査結果と同様、大阪市の地図に水質の調査地点とBOD,COD の測定結果を示しています。
円の横に数字がございますが、上段が年平均値、下段が環境基準の評価を行うための75%値であります。円の大きさが、地点により異なっておりますが、大きさは年平均値の数値に比例しておりまして、円内にメッシュがあるところは、環境基準を超過していることを示しています。
平成19 年度の調査結果では、寝屋川の今津橋、古川の徳栄橋、平野川の安泰橋等寝屋川水系の6地点で環境基準を超過しております。
最後の資料の4枚目でございますが、河川BOD 及び海域COD の環境基準の評価を行うための75%値につきまして、平成15 年度から19年度までの経年変化を示しております。表中の1から38 番までが河川域でありBOD の測定値を示しています。39 から50 番までが海域ということでCOD の測定値となっています。
神崎川、大和川におきましても、環境基準の不適合はみられますけでれども、改善傾向にあることがうかがわれます。これに対しまして、寝屋川、平野川等の寝屋川水域の各地点では、引き続き、環境基準不適合の状況が続いていることがうかがわれます。
寝屋川、平野川等の河川の水質につきましては、上流域の影響を受けやすいことから、流域の自治体や河川管理者等との連携した取組が重要であると考えまして、生活排水対策や底質対策等につきまして、大阪府や寝屋川流域の市等で構成いたします「寝屋川流域協議会」等の関係機関と連携を図っていく所存であります。
以上で、ご説明を終わらせていただきます。
村岡委員長
ただいまのご説明に関しまして、何かご質問やご意見等はありますでしょうか?
福永委員
全体の評価として、特に、この数字をどうみるかということですが、底質においては変動幅が大きく、サンプリングのばらつきが考えられるのですが、サンプルのばらつきの範囲内で、特に例年と異なるような異常な値は見られなかったと評価していいでしょうか?
事務局(環境局前田課長代理)
先生のおっしゃるとおり、例年の変動の範囲内で収まっているものと考えております。地点によりましては、環境基準近傍のところもありますので、環境基準を超えたり、下回ったりということもございますが、概ね、例年の変動の範囲内で、データが推移しているものと考えております。
村岡委員長
他に、何かありますでしょうか?
藤川委員
底質ダイオキシンと水質ダイオキシンの濃度を比較していたのですが、16、18、20 番の3地点ですが、底質の濃度と水質の濃度の比率が著しく他の地点と異なりまして、底質濃度が低いにもかかわらず、水質中の濃度が高く出ていますが、これは何か理由があるのでしょうか?
もしかすると、水質と底質の採取ポイントが異なっているのでしょうか?
事務局(環境局黒木課長代理)
サンプリング地点において、底質が実際に採れない地点については、場所を移動して採取している関係がございます。16 番の本町橋でございますが、底質は平野橋で、20 番の小松橋では、底質は江口橋でサンプリングしております。
ということで、水質とは調査地点が異なっております。
藤川委員
18 番については、どうでしょうか?
事務局(環境局黒木課長代理)
18 番につきましては、水質も底質も今津橋でサンプリングしております。
藤川委員
普通、底質の場合は、ダイオキシンを濃縮すると思うのですが、通常の河川の状況であれば、底質からの微量の脱着か巻き上げで水質に反映されると思いますので、例えば他の地点は、底質と水質の比率ですが、水が1なら底質が200 くらいになっていますが、この3地点中2地点は同じ場所で採られているのに、水質濃度と底質濃度の状況が異なるということは、どこか異なるところに汚染源があるのか又は底質の採取状況に問題があるのか、又は分析上、何かがあるのかなと思います。
これについては、安全がどうこうというよりは、やはり、そういう傾向があるのであれば把握しておかれた方が、今後の対策のためにもいいのではないかと思います。
村岡委員長
今の問題は、要するに同じ地点における水質と底質の濃度の関係で、それが関連する現象として起こっているのか或いは、そうではないのかということですよね。
水の場合は、おそらく一過性で流れていってしまうと思いますので、必ずしも、そこの底質が溶出してきて、ダイオキシンの水質が悪くなるということは、ちょっと考えにくいケースもあると思います。
しかしながら、これだけ地点で差があるということは、何か他に原因があるのではないかということだと思うので、その点に注目されておく必要があるのではないかと思われます。
もう1つは、何年も汚染が長引いている地点があるわけですが、そうしますと、こういったことについては、当然、その汚染源がどこかという汚染源の特定についても、これまで調査されてきたはずだと思いますが、…
その汚染源を特定する作業の結果としては、原因不明ということですか?
事務局(環境局大石課長)
大阪市としましては、原因不明と考えております。
村岡委員長
水質についてもですか?
事務局(環境局大石課長)
そうです。
村岡委員長
BODについてもですか?
事務局(環境局大石課長)
BODにつきましては、本日、大阪府さんも来られているわけですが、大阪府さんと連携協力しながら、いろいろ調査もしておりますし、また、対策についても、上流域の自治体の方にも、ご要望させていただいております。
市内河川は、長期的には改善傾向にあると思っておりますが、まだ、6箇所ほど寝屋川流域で環境基準を超えているところがございますので、今後とも、連携を密にしながら、対策に努めてまいりたいと考えております。
村岡委員長
水質の方は、流れていってしまいますのでともかく、底質の問題が長引いているということは、そこの底質を除去する以外に、対策はないと断言していいのですか?
事務局(環境局大石課長)
私どもとしましては、特に寝屋川のところで、水質なり底質が市域内で環境基準を超えているということで、先ほど前田の方から説明しましたように、大阪府さんと連携しながら追跡調査を実施してきて、結果として、ご案内のとおり門真の第8水路で、高濃度のダイオキシン類を含む底質が溜まっていることがわかってまいりました。
それで、門真第八水路につきましては、門真市の方で、今年度、詳細調査をやられて、対策をどうしていくかを決められるというふうに聞いております。
古川本川の方では、大阪府河川室さんの方で、今年度、一部浚渫されると聞いております。
我々としては、その結果を期待しているところですが、今後ともモニタリング等を適宜行いまして、対策の効果を把握してまいりたいと考えております。
村岡委員長
他にございませんか?
福永委員
藤川先生の意見に対する私なりの考えなのですが、16、17、18 番の数値が低いのは、川でwet な底質が採れずに砂質的な底質が採れた場合は、数値としては小さなものとなるのではないか?だから、サンプリング場所の橋のたもとに泥がたまらず、砂混じりのサンプリングでは、このような結果になるのではないかと私は思っております。
村岡委員長
ただいまの福永先生の意見につきまして、何かございますか?他にご意見がないようですので、市の方でも、これらの貴重なご意見を参考にして、今後の検討の中に採り入れていただきたいと思います。
それでは、次の議題に移ります。
次も報告事項ですが、「大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策」について、ご説明をお願いします。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料2を用いまして、大阪港湾区域におけます底質浄化対策及び港区尻無川堤防工事におけます環境対策につきまして、ご説明させていただきます。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料2の表紙をめくっていただきますと地図がございますが、今回説明させていただきます右下の方の赤い丸印2つが、平成18 年度から行っております大阪港湾区域の底質ダイオキシン類浄化対策の工事箇所でございます。その右上の方に青い丸印がありますが、これが19 年度から20 年度にかけて対策を行いました尻無川の工事箇所でございます。
図面をめくっていただきますと、1頁から12 頁までが、大阪港湾区域における底質ダイオキシン類浄化対策に伴う環境対策についてということで、平成18 年度から行っているものでございます。
また、この対策は、平成18 年3月に策定いたしました「大阪港湾区域におけます底質ダイオキシン類浄化対策方針」に基づいて実施しておりますもので、対策方針自体を参考資料として10 頁から12 頁に添付しております。
平成18 年度の浄化対策の概要ですが、実施場所は、木津川運河の一部区域及び大正内港の一部区域です。
対策土量は、それぞれ100m3、50m3 となっております。 ????
対象としました底質は、1000pg-TEQ/g から3000pg-TEQ/g の範囲で、いわゆる中濃度レベルでございます。浚渫除去しました底質を近傍の管理型処分地であります夢洲1区まで運搬しまして、そこで袋詰脱水処理を行いまして、同じく夢洲1区に処分したというものです。
環境対策でございますが、大阪府・市の河川及び港湾の底質ダイオキシン類対策検討委員会の「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル(案)」等に準拠いたしまして、次の3項目の対策を行っております。
1.浚渫場所における防止枠及び防止膜による汚濁防止対策
2.工事施工へのフィードバック等を実施するため、浚渫場所周辺における事前調査及び日常的な水質環境監視の実施
3.浚渫土砂処分地であります夢洲における水質環境調査の実施でございます。浚渫場所に関わります水質環境監視調査でございますが、調査地点としましては、工事箇所の上流側、下流側それぞれに放流箇所に近い順に補助監視点、基準監視点を、一番遠いところにバックグランド点を設置してございます。
調査地点は、次頁の図2に示すとおりです。それぞれの調査地点を設定し、浚渫工事の実施にあたりましては、水質環境監視調査を実施いたしました。
調査内容は、4頁の表2に示すとおりでありまして、日々の工事の監視に用います濁度は、基本監視点におきまして、深度方向に水深50cm から1m間隔の各層で測定いたしました。最下層は底面から1mの深さのところでございます。ダイオキシン類や生活環境項目などの採水測定は、それぞれの基本監視点で水深約2割程度の深さで行いました。
また、バックグランド点の濁りの測定も、同じく水深の2割程度の深さで行いました。
事務局(港湾局有門課長代理)
工事前に、現地で実施いたしました事前調査結果を基に、濁度等の日々の工事の環境監視基準を設定いたしました。その内容が、4頁にございます表2に示すとおりでございます。
濁度等の環境監視基準の設定は、事前調査データが少なかったこと等、精度的なことを勘案いたしまして、事前の水質調査結果のダイオキシン類濃度と濁度の平均値を利用いたしまして、比例的に監視基準を設定したということでございます。
工事中の水質環境監視調査結果につきましては、5頁の表3のとおりでございます。表3-1 は、木津川運河の濁度の監視結果で週平均値を記載しております。
次の頁の表3-2 が、大正内港の濁度の監視結果で、同じく週平均値を記載しております。その下の表3-3 がダイオキシン類等の採水分析結果です。採水は、水深の約2割程度の深さで行っております。
結果といたしましては、異常なにごりや油膜の発生もなく、全ての地点で、水質環境監視基準(週平均値)において適合している状況でございました。ただ、濁度につきましては、補助監視点で超過した地点もございますが、同時期の基準監視点では適合しておりますので、問題はないものと考えております。
資料の7頁でございます。浚渫した底質は、夢洲1区で袋詰脱水した後、夢洲1区の管理型処分場において処分いたしました。処分先の夢洲及びその周辺の水質環境調査を行っておりますが、脱水した排出水については水質調査を実施し、ダイオキシン類に係る排水監視基準に適合していることを確認したうえで、夢洲1区のとなりにあります夢洲3区へ放流いたしました。
写真等につきましては、12頁以降に掲載しております。夢洲3区への放流水の調査結果につきま
しては、表4のとおり基準に適合しております。
この排出水は、夢洲3区からその南側にございます2区を経由いたしまして、2区の余水吐から海域に放流してございます。その際の水質調査結果は、7頁の表5のとおり排水基準に適合している状況でございます。
以上が、平成18 年度に行いました内容でございまして、平成19年度は夢洲1区側における作業を行ってございまして、平成20 年度は、現在、浄化対策工事を実施しておりまして、同様の環境対策を行っているところでございます。実際の実施場所は2箇所ありまして、18 年度と同様に、木津川運河に引き続き大正内港においても実施しておりますが、大正内港につきましては、18 年度の地点とは異なる場所で行っております。
対象としておりますダイオキシン類の濃度は、150〜1000 pg-TEQ/gといういわゆる低濃度及び1000〜3000pg-TEQ/g までのいわゆる中濃度を対象としております。
以上が、大阪港湾区域における底質浄化対策の実施結果でございます。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料の13 頁でございますが、尻無川右岸の堤防工事における環境対策について説明させていただきます。この工事は、堤防におけます耐震補強工事を行っているものですが、本工事区域内に、ダイオキシン類及びPCB の環境基準を超過した底質が確認されましたことから、工事に際しての環境対策を行ったものです。
平成19 年度から20 年度にかけて実施いたしました。次の頁ですが、対策土量としましては、約1700m3 でございます。ダイオキシン類の濃度は、160〜970pg-TEQ/g ということで、いわゆる低濃度といわれるものです。
PCB につきましては17〜37mg/kg ということでございます。対策方法といたしましては、底質を現地でセメントを加えることに
より固化処理を行い、原位置で矢板内に封じ込めを行うというものでございます。
環境対策につきましては、先ほど説明いたしました水質の浄化対策のものとほぼ同様でございます。調査内容につきましては、15 頁の表1のとおりでございます。
また、水質環境監視調査地点等につきましても、16 頁にございます図2のとおりでございます。
現地で事前に行いました環境調査結果を用いまして、濁度とダイオキシン類濃度との相関から17 頁の表2に示しております濁度等の水質環境監視基準を設定してございます。相関図を下につけているところです。
工事中の水質環境監視結果につきましては、18 頁の表3に示すとおりでございます。表3-1 は、濁度の監視結果でございます。本文にも記載させていただいておりますが、5月から6月の梅雨の時期には河川上流からの濁水の流入による影響から濃度が高くなる傾向が見られ、一部の個別測定値が超過いたしましたが、週平均値を超過することはありませんでした。
また、採水分析結果といたしましては、SS が1回基準値を超過してございますが、工事施工箇所からみて、流れの上流側でございまして、下流側におきましては基準値以下でございましたので、工事以外の影響によるものと考えてございます。また、DO につきましても、1回基準値を下回っておりますが、一般的に夏場に低くなる傾向がございますので、一時的に数値が低下したのではないかと考えております。
同日において、工事施行箇所の上流側、下流側ともに基準値を下回っていることから、工事の影響ではないものと考えております。
また、表3-2 は採水分析結果を示しておりまして、採水箇所は水深の約2割程度の深さで行っております。20 頁ですが、この工事の場合、原位置で底質にセメントを加えて固化処理を行うということでございますので、この固化処理効果の確認というものを実施しております。事前に配合試験を行いました。
その結果が表4でございます。この結果を基に、固化剤でありますセメントをどれだけ加えるかという混入量を決定いたしました。
事務局(港湾局有門課長代理)
また、実際に、現地で固化処理を行いました底質につきましても、溶出試験を行っております。その結果が表5及び表6でございます。
表5は、六価クロムについて、表4の結果を受け、決めました添加量を底質に加えまして、大丈夫かどうかをみるために行ったものであります。実際の現地における固化物の溶出試験結果は、表5及び表6のとおり基準値以下の内容となってございます。
合わせまして、当委員会の前身でございます委員会におけるご指摘を踏まえまして、溶出試験につきましては、水銀、六価クロムについても行っているところでございます。
表7につきましては、事後の水質調査の概要を記載しておりますが、工事完了が1月ということもございまして、採水は2月に実施しておりますので、現在、分析中でございます。3月中旬には結果が判明するものと思われます。
最後に、尻無川右岸の堤防工事に関する写真を最後の頁に掲載しております。以上が、港湾局からの報告でございます。
村岡委員長
先ほど同様に、何かご質問等はありませんでしょうか?
村岡委員長
17 頁の相関図ですが、いつ頃、どの場所のデータでしょうか?
事務局(港湾局有門課長代理)
実際の対策工事は、春から行っているわけですが、事前調査につきましては、前の年の秋(9月〜10 月頃)のデータでございます。
村岡委員長
現実に、濁度との相関において、監視するということも必要になってくるでしょうから、相関をとるものについては、今後もデータを蓄積される方がいいのでは…と思います。
他に何かございませんか?よろしいでしょうか?ありがとうございました。それでは、この件についても、ご理解いただいたということで、次の3つめですが、大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策について、ご説明いただきたいと思います。
事務局(建設局三村課長代理)
資料3の大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策についてでございますが、工事名としましては、「道頓堀川水辺整備その他工事(湊町右岸工区)」に関わります浄化対策ということでございます。本件につきましては、本会議の前回に開かれました平成19 年9月に、ご報告させていただいた状況を審議していただいたという工事でございます。
1頁は、工事概要ですが、道頓堀川の水辺整備ということで、ミナミを東西に流れます道頓堀川に遊歩道を設置していくという事業でございます。1-1 の構造ですが、位置的には下の図にありますように四ツ橋筋のすぐ西側の北沿いです。住所でいいますと、西区南堀江というところでございます。
延長としましては約130mほどあり、遊歩道を建設するのですが、河川の中に新しい護岸を作って、河川の中を埋め立てる形式となっております。
遊歩道の幅は、大体9〜13mとなっておりまして、河川内に鋼矢板又は鋼管矢板を打設してまいります。
今回の対象となります土量は、約4000m3 となっております。これにつきましては、ヘドロ層を除去した後に、底質の入れ替えを行っていきます。
下に、図-1 として地図が出ております。1頁めくっていただきまして、2頁でございます。若干小さくて見づらくて申し訳ありませんが、左側が施行する前の現況図でございまして、護岸即ち大きなコンクリートの壁でございますが、その前に鋼矢板の護岸があります。右側の方は計画となっておりますが、大きな護岸であるコンクリート上部を撤去いたしまして、川の中に鋼矢板
を立てますが、幅は狭いところでは9mから13mほどございます。
次の3頁のところには、非常に見づらいですが、平面図が載っておりますが、図のように矢板、鋼矢板を打っている状況でございます。
次の4頁に出ておりますのが、前回の平成19 年9月のときに、ご報告させていただきましたこの工事現場における底質の状況でございます。
?の概略調査ということで、含有量と溶出量それぞれ2地点で測定した結果を示しております。含有量につきましては、220、230pg-TEQ/gということで環境基準を超えています。また、溶出量につきましても、いわゆる海洋汚染防止法の基準をオーバーしております。この概略調査といいますのは、工事現場内の概ね真ん中に位置する2地点を選んで、その表層の土をとりましたが、次の?の詳細調査では、平面的に8地点を選びまして、それぞれについて鉛直方向についても、ヘドロ層50cm おきに砂層のところまで、溶出及び含有量について、再度詳細に調査いたしました。
その結果でございますが、ダイオキシン類の含有につきましては、概略調査とさほど変わらない数字であり、最高で470 という数字が出ております。
事務局(建設局三村課長代理)
それから、ダイオキシン類の溶出ですが、概略調査の時には、44や21 pg-TEQ/L でございましたが、全て10 未満となっている状況でございます。
その他に、一部の箇所では溶出ですが、総水銀や鉛について、若干基準を超えるものが出ております。6頁ですが、図が小さくて恐縮ですが、真ん中に赤い点が2つございます。これは、一番最初に行いました概略調査の地点でございます。
それから、黒い点が8地点ありますが、これが概略調査の土を採った箇所でございます。
我々といたしましては、概略調査の時に出てまいりました溶出量が、通常時の数値よりも若干大きいということもございまして、前回の会議の時に、おはかりさせていただきましたが、一番最初の概略調査の地図周辺の4スミを囲むように、再度調査をしたということで、7頁に平面的な位置が出ております。
概略調査の赤い点のまわり4スミを、再度調査させていただくということと、念のために、その他に3点の合計11 地点、検体数としては16 検体となると思いますが、鉛直方向にも調査させていただきました。その結果が8頁にございます。
8頁には、ダイオキシンの含有あるいは溶出について記載しておりますが、含有量といたしましては、前回または前々回に調査いたしましたような数値でございまして、今回の場合には最高で330 pg-TEQ/gというような数字が出ております。溶出量につきましては、海洋汚染防止法基準、これは埋立が可能かどうかの基準ですが、10 未満の数字ばかりでございまして、最高で6.5 というような数字となっております。
これによりまして、北港に埋立処分する土は約2,800m3、溶出量を再チェックした形で、鉛、水銀というものが混ざっているということで、海洋投棄できないという土量はセメント原料として、セメント工場に運搬しましたのが、1,200m3 というような形で確定させていただきました。
9頁でございますが、工事中の環境監視ということで、前回の会議の時に、事前の水質調査の結果を報告させていただいております。10頁には水質環境基準ということで、その下側に出てまいりますが、pH,BOD,SS,DO、濁度が記載されております。この中で、濁度でございますが、濁度の週平均値は10.0 度、個別測定値は22.3 度で、事前の水質調査結果から設定されております。週平均値の10.0 度でございますが、事前の水質調査結果の段階でダイオキシン類の水質が3.6pg-TEQ/L ということでございまして、この10.0 度という数値につきましては、事前の水質調査結果に関して、現状より悪化させないという形の監視基準としております。
11 頁については、監視状況の結果を掲載しております。11 頁は、濁度の測定結果でございます。これは、週平均値の数字
を載せさせていただいておりまして、その下に個々の数字の最大・最小値を記載しております。
事務局(建設局三村課長代理)
個々の数値及び週平均値につきましても、環境監視基準値を上回るところはございませんでした。pH,BOD,SS,DO等の生活環境項目の測定でございますが、DO とBOD につきましては、一部の期間で監視基準を上回るあるいは下回るようなところが出てまいりまして、その期間につきましては、DO の場合は、矢板の打設や鋼管矢板の打設という時期でありまして、若干、矢板の打設速度を遅らせるというかゆっくりさせるというようなことで対応しました。
BOD の場合は、埋め立ての時、土を締切内に入れる時の状況でございますが、この時につきましても、若干、土砂の掘削あるいは投入に係るスピードを落とさせていただいたということでございます。
今回の工事につきましては、以上のような結果となっています。
村岡委員長
ご質問やご意見がありましたら、お願いします。
上野委員
ダイオキシン類の溶出量ですが、2回目の測定時点でも、若干、まだ数値が高いような気がするのですが、浚渫土中の特徴としては何かあるのでしょうか?あるいは溶出液が、若干濁っているとかはあるのでしょうか?
オブザーバ
(大阪市立環境科学研究所先山主任)
私は、本データを事前に見せていただきましたので、その印象からご説明させていただきます。先生がおっしゃるように、底質の2回目の測定データにつきましても、若干高いかなという気がしますが、まず、1回目の方が非常に高いということで、溶出量が多くなるような状況にあった泥なのかどうかということをみる指標がないかというご相談で、事前に見せていただきました。
しかし、その時点では、そのことを判断するようなデータの採取がなされていないということで、すでに、この時の泥が存在しない段階では、その判断はできませんでした。
2回目のデータにつきましては、平均の粒子径などは若干、データとしてとられていましたので、それを見せていただきまた。そうすると、この底質は、ダイオキシンも高いですけれども、かなりヘドロ化しているということで、平均粒子径が0.05mm を下回るようなものもたくさんありまして、非常に微粒子の底質が多いという状況がうかがえると思います。
ですから、ろ過操作等のバラツキというものが、結構、大きく効いてくるのではないかという判断を私はいたしました。
村岡委員長
このろ過操作というのは、現在のところ、どのような基準でやっておられるのですか?
オブザーバ
(大阪市立環境科学研究所先山主任)
ろ過操作につきましては、海洋汚染防止法で、ご存知のように孔径という表現がなされているわけですが、前回の委員会でも若干、説明させていただいたのですが、私が調べたところによりますと、市販品ではガラス繊維ろ紙で、仕様上、そのような表現がなされているものは存在しません。
現実には、様々なメーカーにより表現方法が異なるということで、その孔径に値するそれぞれの表現が、どの程度かとい
うことは、メーカーによってばらついております。
それを使用するときに、孔径と置き換えて読むのか、それよりも孔径の方が小さいということで、1μmよりも小さなものを使用するかということで、かなりろ過操作にバラツキが出る可能性があります。
しかし、公式には孔径という表現がされておりますので、孔径をどのように分析する側が解釈するかということで、結果に大きな違いが出ているのではないかと思います。具体的には、孔径と同じような意味で使われているメーカーさんのものでしたら、粒子保持能という表現があり、ろ過の初期段階でその粒子径以上のものが98%以上止められるという表現をされているところもあります。
もう一方では、保留粒子径ということで、「1μmのものを止めようとしますと、さらにその半分くらいの0.4〜0.6μmのものを使わないとダメですよ。」ということがカタログ上では示されていますので、その辺、混同して使用している可能性があるのかなと思います。
ですので、どのようなものを使うかということは、いずれ公式の委員会の場で承認を得て、標準的な操作の仕方というのを用いないと、なかなか説明がつかないデータが出てくる可能性があると考えられます。
村岡委員長
何か関連して、ご意見ありませんでしょうか?
福永委員
後で、この件に関して、お願いしようかなと思っていたのですが、前回の委員会でも、かなり問題になって、結局ばらついたデータが出てきて、議論に困るというようなことが多いと思うのですけれども、環境科学研究所さんの方で、大阪府さんとも調整していただきながら、誰が行っても同じ答えが出るというふうなフロー、いわば、今法令的には定められているんですけれども、必ずしも十分ではないので、人によって異なった答えが出るということですから、この委員会にデータとして出すという時には必ずこの方法で行えば、間違いない安定した数値が出るというフローを考えていただければ、この委員会としてはありがたいのではないかと思いますので、お願いしたいと思います。
事務局(環境局大石課長)
福永先生のご指摘の点ですが、先般、環境省の方から底質の調査方法に関わりまして、アンケート調査がまいりました。その時に、私どもの回答の中に、分析に用いるろ紙の規格をはっきりと明記してほしいということをお返ししております。いずれにいたしましても、前回以降、村岡先生にもご指摘をいただきながら、府市で、きちんと統一的な取り扱いを決めるようにというご指摘もありましたので、今後、大阪府の底質委員会の事務局とも調整をしながら、また、本市環境科学研究所、大阪府環境農林水産総合研究所とも、ご相談しながら、統一的な取り扱いができるかどうかも含めまして検討を進めてまいりたいと考えております。
村岡委員長
その点につきましては、ぜひスタンダードな測定値をもとに議論ができるように進めてほしいと思います。
藤川委員
濁度とダイオキシンの関係を0.1pg-TEQ/L だというのが、先ほどの回帰分析の結果ですけれども、今回の方では、濁度との関係を3.6pg-TEQ/L というふうにおっしゃっていただいたのですが、濁度1が0.1 なのか0.36 なのかというので、そういうデータは蓄積していただくのは、妥当だと思うのですが、ただ、この時の濁度10 で3.6pg-TEQ/L とおっしゃった時のろ過方法は、どのようなものだったのかを教えていただきたいのが第1点です。
もう1つは、ダイオキシン類については溶出量と含有量を両方測ると思いますが、普通、ダイオキシン類は溶出量は低いでしょうから、例えば、この溶出量と含有量の比が含有量5に対して溶出量が1というデータが出た時点で、直ちに環境科学研究所さんから、現場の方にご相談いただくなり、再分析に回すなりの対応をしていただくと早いと思うのです。
だから、そういうことを現場で徹底していただいたらどうかなというのが第2点です。
不自然なデータが出れば、すぐに追加のサンプリングはもちろんですけれども、再分析ということも考えられると思います。
事務局(建設局三村課長代理)
事前の水質調査を行った時には、2回目の詳細調査と同じ方法で行っております。一番最初の概略調査あるいは次の詳細調査、それから事前の水質調査という段階を経まして、事前の水質調査と詳細調査はほぼ同じような時期になっておりますが、一番最初の概略調査と次の詳細調査と次の詳細調査あるいは事前水質調査とは若干、違うような形であると聞いております。
私どもは、工事を発注してから、水質調査あるいは底質調査を行っておりますので、これからはちょっと考え直さなくてはいけないのですが、当時の工事期間中にそういうふうな状況が出てまいりますので、結果が出るまで少なくとも1カ月、2カ月ほどかかりますので、若干、その辺のところが、我々としては考え直さなくてはならないところではあると思います。
事務局(環境局大石課長)
2点目のご指摘でございますが、我々といたしましては、これからもデータの蓄積につきましては、統一的に、今後も進めていきたいと考えております。
また、検討会の事務局を、大阪市的にも港湾局、環境局、建設局、オブザーバとして環境科学研究所さんにも入っていただいておりますので、うまく機能させていきながら連絡体制をとっていきたいと考えております。
村岡委員長
今の問題は、すぐに解決できるものとは思えないですし、その時、その時に判断しないといけない大変難しい問題ですが、是非ともいい値が出るように、「正しい値が出て、正しい判断ができるように」努力をしてくださいということですから、その辺のところをよろしくお願いいたします。
他にございますか?
それでは、ご意見がないようでございますので、本日の議題である3つの報告について、委員の先生方、いろいろご指摘いただきましたので、これで全て終わったというわけではありませんが、ともかく、この報告の中身について、十分確認できたということにさせていただきます。
合わせまして、これに基づいて、また、作業が進められると思いますので、ぜひ、それが円滑に、いい効果が上げられますようにお願いしたいと思います。
それでは、以上をもちまして、議事を終わりたいと思います。後、進行を事務局にお願いします。
大阪市底質対策等技術検討会
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000019399.html
2009年12月06日
日本弁護士連合会水俣病被害実態調査 結果報告書
水俣病被害実態調査 結果報告書
2008年10月
日本弁護士連合会
第1 調査の概要
1 調査の目的
2 調査の方法
3 調査の概要
4 調査結果を見る上での注意点
第2 調査分析
1 基本情報について
2 現在の健康被害の内容について
3 居住歴,生活歴等について
4 昭和20年代から昭和40年代まで不知火海の魚介類の摂取状況
5 家族構成・同居していた家族について
6 水俣病関係の認定申請について
7 家族の申請状況について
8 胎児性世代,小児性世代の健康被害について
9 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決後に水俣病認定申請をした方のきっかけ
10 新保険手帳の申請をされた方のきっかけ
11 不知火海沿岸全域の健康調査について
12 水俣病の認定(公健法)基準について
13 今回の調査に関する自由記載
第1 調査の概要
1 調査の目的
日本弁護士連合会は,1977年の人権擁護大会において「公害被害者の救済に関する決議」
を採択し,それ以降,水俣病問題についての調査研究を重ね,被害者の方の即時・完全救済等
を求める決議,具体的方策の提言などを行ってきた。
そして,2007年7月に「与党水俣病問題に関するプロジェクトチーム」が公表した「水
俣病に係る新たな救済策について(中間取りまとめ)」を受け,同年9月14日に「水俣病問
題について抜本的な救済策を求める意見書」を発表した。同意見書では,公健法に基づく救済
策を抜本的に改め,新たに総合的な救済施策を講じるべきであることを提案するとともに,新
たな救済施策の具体的内容として,水俣病認定基準の抜本的改定,水俣病患者に対する十分な
補償,水俣病患者に対する医療面,福祉面に対する恒久対策,国及び熊本県による経済的負担
等の事項を提示した。また,水俣病患者の実効的な救済を図るために,不知火海岸沿岸の健康
調査を早急かつ網羅的に行うべきことを提案した。
その後,与党水俣病問題に関するプロジェクトチームが救済策の実現に向けて検討を重ねて
いるが,依然として公健法に基づく認定基準を堅持する態度を変えておらず,また,一時金の
金額も関西水俣病訴訟最高裁判決の水準額(400万円から800万円)を大幅に下回る金額
(150万円)しか提示していないなど,当連合会が発表している提言からすると未だ不十分
なものにとどまっていると言わざるを得ない。また,国による不知火沿岸の健康調査も未だに
実施されていない。
そこで,当連合会としては,現地を訪れて水俣病患者の被害実態を調査することにより,具
体的なあるべき救済施策を研究し,今後も引き続き国に対して提言をしていく必要があると考
え,九州弁護士会連合会及び熊本県弁護士会の協力を得て,水俣病問題に関する被害実態調査
を実施した。
2 調査の方法
(1)調査対象
水俣病患者団体に実態調査協力の依頼をし,107名から協力を得られた。
(2)調査期間
2008年6月14日から同月15日まで。
(3)調査方法
調査事項書自己記入後,弁護士による個別面接調査。
なお,実態調査に携わった弁護士は,日本弁護士連合会人権擁護委員会委員5名,人権救済
調査室嘱託1名,同公害対策・環境保全委員会委員3名,九州弁護士会連合会人権擁護委員会
委員10名,熊本県弁護士会会員3名の合計22名である。
3 水俣病実態調査の概要
調査結果の概要は以下の通りである。
(1)現在の健康被害の内容について
今回の調査対象者は,実際にはほとんどの者が公健法上の水俣病患者としては認定されてい
ないが,次のとおり,四肢抹消優位の感覚障害,運動失調,視野狭窄のいずれについても異常
を訴えている者が多く存在した。
○感覚の異常である手足のしびれについては,すべての調査対象者が何らかの異常を訴えていた。
○手足の感覚麻痺については,調査対象者107名のうち93名が何らかの異常を訴えていた。
○上下肢の運動症状については,ほとんどの調査対象者が,つまずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいなど何らかの異常を訴えていた。
○視野狭窄については,調査対象者107名のうち93名が何らかの異常を訴えていた。
このデータから,感覚麻痺の有無だけを基準にするだけでは割り切れない患者が多数存在す
ることが窺われ,また,厳密な診察をすれば相当程度の者が水俣病と認定されるのではないか
と推測されるという結果が得られた。
(2)日常生活や仕事への影響について
日常生活上については,すべての調査対象者が何らかの支障を訴えていた。具体的には,足
のこむらがえり,常時疲れやすい,関節が痛い,耳鳴りがひどいなど身体的な症状を訴えてい
たり,茶碗を落として割ったりする,車の運転をしているとき横がまともに見えない,風呂の
湯加減が分からないなどの日常生活上の支障を訴えていた。
仕事面については,漁業に携わっている人が多い関係から,重い船具を持つことができない,
荷物を運ぼうとすると落としてしまう,網の修理が苦手であるなどの支障を訴える者が多かっ
た。そのほか,立ちくらみ,めまいのため仕事がしにくい,目を使う仕事ができない,補助的
な仕事に限定される,脚立など高い所へあがれないなどの支障も観られた。
日常生活や仕事面での差別等については,特にないと回答した者も多く存在したが,様々な
不利益,差別を受けたことがあると回答した者も多かった。具体的には,「大した症状もない
のにお金をもらっている」と悪口を言われる,医療費を支払わないことについて詐病ではない
かと言われる,見合いをしても水俣病の話が出ると相手から断られるなどの差別が見られた。
(3)病院での診察について
ほとんどの調査対象者がこれまで病院にかかったことがあったと回答しているが,水俣病あ
るいは水俣病の疑いとの診断を受けた者は,60代〜70代では約54%であったが,40代
〜50代では約30%にとどまった。治療内容については,保険適用外となるものも少なくな
く,はり,きゅう,マッサージ,電気治療,湿布,漢方治療薬などを利用している者も多く存
在した。
(4)公健法上の水俣病の認定申請について
公健法上の水俣病の認定申請を行っていた者は56名であり,そのうち,平成16年10月
15日の関西水俣病訴訟最高裁判決まで公健法上の水俣病の認定申請を行っていなかった者は
37名であった。認定申請をしていなかった理由については,「自分や家族に差別(結婚,就
職,近所付き合い)などの不利益が生じると思った」「自分が水俣病であることが分からなか
った」などが多く,依然として差別や偏見が根強く残っていること,水俣病に関する情報が十
分に周知徹底されていないことが窺われた。
(5)不知火海沿岸の健康調査について
調査対象者の約82%が不知火海沿岸の健康調査について,国,県の負担で実施すべきであ
ると回答をし,調査対象者の約72%が,今から調査をすれば健康被害の実態は分かると回答
しており,多くの者が実態調査を希望していることが判明した。
(6)認定基準について
調査対象者の約82%が現行の公健法上の水俣病の認定基準は厳しすぎると回答し,約7
6%が現行の基準を変えるべきであると回答していた。多くの者が,被害状況に応じた救済が
なされていないと感じていることが窺われた。
4 調査結果を見る上での注意点
今回の実態調査にあたっては,無作為抽出的に対象者を選出するのではなく,既存の水俣病
患者団体に実態調査協力の依頼をし,各水俣病患者団体において患者を選定してもらっている。
調査対象者数も僅か107名であることから,今回の調査結果が水俣病患者の全体の実態を反
映しているとは限らない。
また,今回の実態調査では,例えば「公健法上の水俣病の認定申請」について自分が申請を
しているか否かが不明であったり,過去の状況について一部記憶が定かでなかったりする事例
も見られた。限られた時間の聞き取り調査であったため,設問の内容によっては,必ずしも統
計的に正しいデータが得られていない可能性があることを付言しておく。そこで,今回の実態
調査においては,正確な数字よりも,患者の状況や特徴についての傾向を把握する趣旨で見て
いただければ幸いである。
なお,質問項目の中には,「いつ頃から症状が出ているのですか。」というような個々の患
者によって状況が異なり,集計が困難なものもある。そのような場合,集計結果を省略させて
頂いている点をご容赦されたい。
また,集計は,弁護士による個別面談を経て修正,加筆された調査事項書を基にしている。
第2 調査分析
以下,調査事項書の質問事項順に集計結果を記載する。
なお,前述のとおり集計が困難な質問項目については,記載を省略している。
1 基本情報について
<調査結果の補足説明>
?の手足のしびれについて
手足のしびれについては調査対象者107名全員が感覚の異常である手足のしびれを訴え
ていたということになる。40代〜50代の胎児性世代,小児性世代の患者と60代〜70
代の患者とでは,その傾向はほとんど変わらなかった。
?つまずきやすい,転びやすい・?細かい作業がしにくいについて
つまずきやすい,転びやすいは下肢運動症状に,?細かい作業がしにくいは上肢運動症状
に該当する。
つまずきやすい,転びやすいは,年代に関わらず,ほとんどの調査対象者が症状の異常を
訴えている。
また,細かい作業がしにくいという症状についても,年代に関わらず,ほとんどの調査対
象者が症状の異常を訴えていた。
なお,つまずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいという症状について,いずれ
もなしと答えている者はおらず,すべての調査対象者が何らかの異常を訴えていた。
<コメント>
?の手足の感覚麻痺について
手足の感覚麻痺については調査対象者107名のうち,93名が何らかの異常を訴えてい
た。そのうち,40代〜50代では,感覚麻痺が「常時」と回答した者よりも「時々」と回
答した者の方が多かったが,60代〜70代では,「常時」と回答した者が「時々」と回答し
た者の2倍となっていた。今回の調査だけでははっきりとしたことは言えないが,40代〜
50代と60代〜70代との間で感覚麻痺について「常時」と「時々」との間に差があると
いうことに関して,一定の有意性が認められる可能性がある。
なお,今回の調査では40代〜50代の患者のうち,感覚麻痺についてなしと答えた者が
4名いた。しかしながら,前述した?のとおり,40代〜50代の調査対象者の全てが,つ
まずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいなどという症状を訴えており,感覚麻痺
はないものの,運動症状に何らかの異常を来している者も相当数存在していると考えられる。
このようなことから,感覚麻痺の有無だけを基準にするだけでは割り切れない症状の患者が
相当数存在することが窺われた。
?の全身の感覚麻痺について
全身の感覚麻痺については調査対象者107名のうち半数近くの者が何らかの異常を訴え
ていた。
但し,例えば手足の先ではなく腕の部分に感覚麻痺を感じた場合に,回答する側からする
と,これが全身性の感覚麻痺なのか,四肢末梢の感覚麻痺なのかは判然としない場合も少な
くなかったようである。全身性か末梢の感覚障害かは厳密に専門の医者の検査によって判断
しないと誤るおそれがあると言えよう。言い換えれば,水俣病の診断基準のうち「感覚障害」
の取り方には十分に注意して行う必要があるということになる。
?視野狭窄について
視野狭窄の何らかの異常を訴えている者の割合は,全部で93名と約87%であり,40
代〜50代でも異常を訴えるのは53名中44名と約83%である。今回の調査では視野狭
窄を訴えている者の割合がかなり高い。これは,調査対象者の選別について比較的重症の患
者が選択されたのではないかと推測される。
○健康被害についての総合的なコメント
前記内容を総合し,40代〜50代の調査対象者で,?感覚障害(感覚麻痺),?運動失調,
?視野狭窄について複数の異常を訴えている人たちがどれくらいいるのかという統計を出し
たところ,次のような結果が得られた。
?の感覚障害については,常時か時々の別はあるものの,全員が手足のしびれを訴えてお
り(?の「手足のしびれ」),また,約87%の人が手足の感覚麻痺を訴えている(?の「手
足の感覚麻痺」)。従って何らかの手足の感覚障害という意味では,全員が異常を訴えている
ということになる。
?の運動失調については,上肢と下肢に若干の違いがあるが,常時,時々を含めて何らか
の運動失調がある者は全員である(?のつまずきやすい,転びやすいが下肢に関する運動失
調。?の細かい作業がしにくいが上肢に関する運動失調)。
?視野狭窄については,40代〜50代の患者の53名のうち44名が常時または時々の
異常を訴えている(?の視野狭窄)。
すなわち,今回の調査対象者については,実際には,ほとんどの者が公健法上の水俣病患
者としては認定されていないが(6項?参照),四肢抹消優位の感覚障害,運動失調,視野狭
窄のいずれについても異常を訴えている者が大多数であることを考えると,厳密な診察をす
れば相当程度の者が水俣病と認定されるのではないかと推測される。
(2)いつ頃から症状が出ているのですか。
症状や回答者によって異なる回答であった。但し,症状の種類を問わず,年齢を重ねるごとに症状が悪化している傾向にあるようであった。
(3)上記の症状による日常生活や仕事への影響についてお聞きします。
? 日常生活においてどのような支障が生じていますか。
今回の調査対象者の全員が,日常生活上の何らの支障を訴えている。以下に,具体例を紹介する。
・足のこむらがえり。
・常時疲れやすい。
・人の支えがないと歩くのが困難。
・関節が痛い。
・手足のしびれ。
・小さい物をうまくつまめない。
・手足のしびれのため,例えば,けがをしてもあまり痛みを感じないので,いつ,どこで怪我をしたのかが分からない。血が出ているのを見て初めて気が付く程度。
・夜よく寝られない。
・カラス曲がりなど日常茶飯事で,ひどいときは30分,40分つりっぱなしの時もある。
・耳鳴りがひどく,人の声が聞こえないので,自分もついつい大声で話してしまう。
・心臓に不整脈がある(ニトロを持っている)。
・茶碗を落として割ったりする。
・1人で布団も干せない。
・箸がうまく使えない。
・言葉がどもり,人に挨拶などができない。
・人間関係が作れない。子ども時代から症状があり友達ができなかった。
・物をつかんでいる感覚がない。
・手がふるえるのでお茶を出すのが嫌。
・味付けが濃すぎたり,薄すぎたりする。
・車の運転をしているとき,横がまともに見えない。
・細かい仕事がつらい(手の震え)。
・脱いだつもりのつっかけが脱げなくて,そのまま上ってしまう。段差に躓いて,転倒し,骨折した。
・一番困るのは眼。手術のしようがないと言われている。新聞は読めない。目薬は1日1本必要。
・風呂に入るとき心臓から下までしか浸かれない。
・風呂の湯加減がわからない。
・怖くて水泳ができない。
・長く座っているのが苦痛。長く座っていると足がしびれて固まって立ち上がれなくなる。あぐらが長時間できない。座敷の食事等がつらく,早く終わってくれないかと思ってしまう。
・忘れてしまって何度も尋ねることがある。
・家の外にはほとんど出ない。テレビも見ない。本も読まない。家では掃除,洗濯をしているが頭が痛かったりだるかったりするので,掃除,洗濯を毎日することはできない。他は何もしていない。
・左右の視力が違い,また,視力も変わってくるため眼鏡が合わない。そのため,頭痛がする。
・何を食べてもおいしくない。等
? 仕事面で何か不都合や被害を受けたりしていますか。
仕事への支障についての訴えのみならず,それによる周囲からの反応について回答するものも見られた。以下に,具体例を紹介する。
・仕事に就いたことがない。
・補助的な仕事に限定される。スーパーのレジの仕事などしかできない。
・目を使う仕事ができない。
・長期間機械を扱うと,調子が悪くなる(腕など)。疲れやすいとは思う。
・指先にとげなどが刺さっていても気づかない。
・仕事中に休むことが多くなった。細かい作業ができないので困ることがある。同じ状態でいられない。重い物を抱えると,つって,しばらく腕をのばせない。
・立ちくらみ,めまいのため仕事がしにくい。県外で仕事しているとき,水俣出身ということがわかると「あなたも泡をふくんじゃないの?」などと言われた。
・パートに出たが,水俣病のことを言われた。私は申請中とは言わず黙っていたが,居づらくなり辞めてしまいまった。農作業も身体が痛く,していない。
・細かい作業が出来ない。文字を書けないのが,一番つらい。
・ひざが曲がらないので座るときは足を投げ出さないといけない。和式トイレが使えない。草むしりができない。
・手に力が入らないので,雑巾が絞れず,仕事の手伝いができなくなった。
・脚立など高い所へ上がれない。
・手が震えてハンダ付けができないときがある。
・手の感覚がないので,痛みを感じない。水俣病報道でよく登場したこともあり,会社から「お前はなぜ自分が水俣病だと言うのか」「お前の血は青いんだろう」「神経が通っていないんだろう」と言われた。
・物忘れ。商品の陳列がうまくできず,時間がかかる。
・高校卒業後,国鉄の試験を受けたが,耳鳴りのために面接,身体検査で落ちた。
・声が聞き取りにくいのですぐに返答できない。電話対応に困る。
・何か言われていることはわかるが,中身がわからないので何度も聞き直す。
・網を引く作業が船の上なので,すぐ転んで青あざができてしまう。手の握力も17〜18kgしかない。
・船の修理の仕事をしている。仕事に関してお客から信用を失いつつある。なくなっているかもしれない。仕事の集中力というか取り組みにむらがある。
・重たい船具(2kg)を持てないことがある。
・海上タクシーの仕事をしているが,荷物を運ぼうとすると落としてしまう。弁償することもあった。
・若い頃から漁業の網の修理が苦手だった。道具に糸が通らない。
・漁は2人でする仕事なので,自分が休めば夫も漁に行けず仕事が出来ない。よって収入減となる。子どもを育てるためには毎日漁に行かねばならない。
・農作業中にハサミ,のこを落とす。
・腰痛や肩こりがひどくなり痛み止めの注射を打つことが多く,通院しながらの農作業で仕事も進まない事も多い。人に代わってもらうことも多い。
・建設関係の仕事をしているが,手足のしびれがあるため測量作業がうまくできないことが多く,他の人から「他の人に代われ」と言われることがある。
・建設関係の仕事なので段差のある足場での作業(上り下り)がきつい。
・靴下工場で細かい作業だったので大変でした。
・手足が自由でないために,作業中に指を切断した。等
? 日常生活や仕事の面で不利益を生じたり,差別を受けたりしたことがありますか。
特にないと回答したものも多く存在したが,様々な不利益,差別を受けたりしたことがあると回答しているものも多かった。具体的な不利益,差別事例についての訴えを紹介する。
・高卒後,大阪で過ごしていたところ,テレビで水俣病のニュースが流れると「あなたの郷里
が映っている」等と言われ恥ずかしかった。夫の母が福岡の病院で手術を受けた。母は医療
手帳を持っていたので医療費がかからないが,看護師は医療手帳を見て,「これ何ですか!」
と驚いた。他の患者は支払をしているのに母だけ払わない扱いを説明するのに大変だった。
・差別についてあるとは思うが「大した症状もないのにお金をもらっている」「お金をほしが
っている」と悪口を言われる。だから自分も友達にもいえない。
・水俣病について活動(ビラ配り)をしていると,通行人の女性から「ニセ患者」と言われた。
・いとこが認定患者で胎児性患者を産んでいるが,差別を受けているのを見てきた。身内に漁
業関係者がいて,迷惑がられた。汽車では水俣で窓を閉めていた。
・自分ではないが,妹が「そんな身体なら家の人も早くいなくなればいいと思う」などと心な
い言葉をかけられた。
・薬剤師から,「認定患者だけが本当の患者だ,薬のありがたみが分かっていない,薬のお金
を払っていない,自分たちが払った税金が使われている」などと言われた。
・医療費を支払わないことについて,詐病ではないかと言われたことがある。「あんた達はよ
かなー,手帳もらえてなー,医療費がただで!」
・子どもが結婚前だったから申請しなかった。差別されるから。それまで手足のしびれはない
と言って隠していた。
・集会場などで声が聞きづらく困る。耳が聞こえないことで「つんぼ」とか言われる。隣家の
人が,結婚が破談になったという話を聞いた。
・お金目当てと言われる。
・水俣病だとお嫁に行けないなどと言われていたし,あえて調べようとは思っていなかった。
今までは,ただの神経痛ではないかと思っていたが,平成16年頃に水俣病のことを知って,
平成7年の政治解決の時もまさか自分が水俣病だとは思わなかった。
・裁判をしているので,「金がほしくてやっている,それくらいは誰でも身体に異常はある」
という悪口を言われる。父が認定されたときもニセ患者と言われた。
・ある人から「指輪など似合わない手だ」と言われた。口をつぐんで通行したり,けがらわし
いなどといわれた。行政からの正確な情報提供がないため。
・自分も見合いをしたが,水俣病の話が出ると,相手が断ってきたりした。結局,水俣病のこ
とをよく知らない外国人の女性と結婚した。
・テレビに出たあと差別を受けた。今の職場もいつ辞めさせられるか分からない。
・実家から送ってくる魚をおすそわけすると,「水俣からきたものだから嫌だ」と言われたこ
とはある。
・今現在はそうでもないが,幼小時期は冷たい目でみられたこともある。島外に出ていて結婚
していた際,県営住宅にいたとき,「笑わない人がきた」とか色々なことをいわれた。
・学校生活のときいじめられた。但し,水俣病との自覚はなく,トロイのが原因でいじめられ
ていると思っていた。
・小学校,中学校のとき悪口を言われた。近所のおばさんに会った際に父,母,妹だけに声を
かけて,自分に声をかけないということもあった。腹も立つし,とても悲しい。今でもそう
である。
・無理な仕事ができなくなった(手先や目を使う仕事ができない)。
・仕事中でもよくころぶことがある。高所のよう壁から足を踏み外して落ちたこともある。そ
のつど,「ボケか」と言われたりして,人からさげすまされているという思いがする。
・表だってはないが,何かを理由にして仕事がどんどん減っている。
・感覚がなく荷物を落としたり壊したりするため,職場の人からすごく言われる。
・仕事ができないことの理由がわかってもらえない。
・チッソの昭和50年度の採用試験を受けたときのこと。筆記試験が終わり,面接試験を受け
ていた時,面接試験の最後の質問で,「チッソが水俣病を起こしたことがよいか悪いか答え
なさい」と言われました。その時に,「それは悪い」と言ったら,面接官が「悪いだな」と
確認し,面接が終わった。結果は不採用だった。
・午前中しか仕事ができない。漁師なので潮加減があるが,夕方までの長時間の仕事ができな
い。
・手に力がなく配送中に店の商品を落とし,ビン類など割って弁償したりしている。
・親が認定されたとたん,縁談が破談になった人が近所にいた(相手は県外の人で,相手の両
親の反対のため)。
・仕事ができないために上司に解雇を申し渡され,職安に行こうとしたこともある。
等
水俣病以外の診断結果としてあげられていたものでは,「手足のしびれ」,「めまい」,「頭痛」,「腰痛」,「関節痛」,「原因不明」,「仕事上の疲労」等の回答があった。
<コメント>
手足のしびれというのは感覚障害の典型的な症状であり,水俣病患者には頭痛や腰痛,関
節痛などを訴える者も多くいる。診察を受けたときに,医師の側に,これらの症状が水俣病
の症状であるという理解がなかった可能性もある。
? いつ頃から病院に通っていますか。
40代〜50代の胎児性世代,小児性世代では子どものころから病院通いをしている人が多い。その一方で,最近になって通院を始めた者もいる。
<コメント>
症状によって発症の時期が異なること,複数の症状を訴える者が大半であるということ等
の事情によるものと思われる。
? どのような治療を受けていますか。
はり,きゅう,マッサージ,電気治療,湿布,漢方治療薬などといった回答が多く見られ
た。
<コメント>
これらの治療方法は保険適用外となることも多く,別途,医療費や医療手当の支給の必要
性が高いものである。
? 病院に通うことでの不都合があれば教えてください。
病院まで遠くて通院に時間がかかる,交通の便が悪いといった病院までのアクセスに関す
る回答や,1人で通院が出来ないという身体面での不都合を訴える回答,交通費や治療費な
どの経済的負担が大きいといった費用面での回答のほか,通院によって仕事に支障が生じる,
仕事を休めないので通院できない,医師の紹介が必要など不便といった回答があった。
<コメント>
未回答にはその年代には出生していなかったり幼児期であったために記憶が定かでなかった
りするものも含まれる。そのため,昭和20年代については未回答の割合が高くなっているも
のの,同年代に魚介類を摂取していないということではない。また,その年代に出生していな
い場合でも,母親が魚介類を摂取していれば胎児性の水銀暴露の問題が生じうる。
汚染地域を離れても家族から魚介類を送られてくることによってその魚介類を多食したとい
う例もあり,汚染地域を離れたことが魚介類の摂食と切り離されるとは一概には言えない。
さらに,地域によっては山間部や汚染地域と離れているような地区に居住していても行商か
ら購入したという例も見られた。
?ほぼ毎日?1週間に1回?1ヶ月に数回?ほとんど食べていない未回答
6 水俣病関係の認定申請について
(1)あなたはこれまで水俣病関係の認定申請をしたことがありますか。
ある 90名
ない 17名
(2)前項で「ある」と答えた方は下記にご回答ください。
? 認定申請(公健法)
水俣病関係の認定申請をしたことがあると回答した90名のうち,56名が公健法上の認
定申請に関しての申請状況を回答した。
結果の内訳は,認定2名,保留12名,棄却16名,申請中(審査中)8名,その他・回
答不明19名であった(1名は2回申請し,1回が棄却,1回が保留)。
? 総合対策医療事業
省略
? 政治解決(平成7年)のときの総合対策医療事業
省略
? 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決まで認定申請(公健法)をしたことがなかった
(公健法上の認定申請に関しての申請状況を回答した対象者について集計)
したことがない 37名
したことがある 19名
(3)平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決まで申請しなかった理由についてお聞きします。
(公健法上の認定申請に関しての申請状況を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴
訟最高裁判決まで認定申請をしたことがなかったと回答した対象者37名について集計。複
数回答可能。)
? 申請しても認定されないと思ったから。…5名
? 自分や家族に差別(結婚,就職,近所付き合い)などの不利益が生じると思ったから。…18名
? 認定申請についてのやり方がわからなかったから。…7名
? 自分が水俣病であることがわからなかったから。…18名
? 自分が水俣病であることを周囲に知られたくなかったから。…7名
? その他…10名
未回答…2名
<コメント>
?の差別などの不利益が生じると思ったとの回答や,?の自分が水俣病であることを周囲に
知られたくなかったという回答からは,依然として水俣病に対する差別や偏見が根強く残って
いることが窺われる。
?の申請しても認定されないと思ったというのは,現行の認定審査基準の審査が厳しすぎて,
殆どの患者が認定されないという基準の不合理性を患者が感じていることを示していると思わ
れる。
?の認定申請についてのやり方が分からなかったというのは,行政からの情報提供が不十分
であるということを示している。また,?の自分が水俣病であることが分からなかったと回答
する者も多かった(約半数)。
なお,その他の理由として,
・有機水銀による健康被害を受けていることは自覚していたが,救済を受けることができる「水
俣病」とは思わなかった。
・祖母から恥ずかしいから申請するなと言われた。近所から水俣病の人と接触するとうつるか
ら行くな等と言われていた。認定されると子どもまで差別されるかもしれないと思った。
・母親にも,歩行障害,手足のふるえ,よだれ(口回りのしびれ)の症状が強くあったが,差
別のおそれ(妹の結婚など)から申請は拒否していた。(母親自身と妹の意向)
・親戚,友人等にチッソの関係者が多いため対人関係の悪化を懸念して見送っていた。
・認定,申請方法などの制度説明は役所からもされたことは全くない。
・申請が出来ることを知らなかった。もう終わったこと,過去のことと思っていた。
・若かったので重く考えてなかった。歳を増すごとに酷くなった。
・他の都道府県に居住していたので関心を持たなかった。
等の回答があった。(但し,集計対象者外の人の回答も含む)
(4)前項で?(自分が水俣病であることがわからなかった)に○をつけた方にお聞きします。
どうして自分が水俣病であると思わなかったのですか。
(公健法上の認定申請に関しての申請情報を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴
訟最高裁判決まで認定申請をしたことがなく,その理由について「自分が水俣病であること
がわからなかったから」を選択した対象者18名について集計。複数回答可能。)
? 手足のしびれなどの感覚障害を感じなかった。…0名
? 生まれたときから手足のしびれなどの感覚障害があり,自分の症状が水俣病であるとは思わなかった。…4名
? いわゆる急性劇症型の人が水俣病であり,自分は水俣病であるとは思わなかった。…18名
? 魚を多食しておらず,水俣病になったとは思わなかった。…1名
? その他…1名
<コメント>
本項の質問の対象者全員(18名)が,?のいわゆる急性劇症型の人が水俣病であり自分が
水俣病であるとは思わなかったとの理由を選択しており,これは,水俣病に対する情報開示が
不十分であったことを示すものと言える。(なお,集計対象者外の人についても,かなりの人
数がこの選択肢を理由にあげており,有効な回答ではないが,「水俣病=急性劇症型」という
とらえ方がかなり根深く浸透していたことが窺われる。)
?の生まれたときから手足のしびれなどの感覚障害があり,自分の症状が水俣病であると思
わなかったとの回答についても,?と同様に水俣病に関する情報提供が十分になされていなか
ったことを推測させるものである。
なお,その他の理由として,
・症状が出てきたのが後からで,明確な診断がなかった。
・平成7年当時,他県にいたので,政治解決を知らなかった。行政からは何も情報提供はなかった。
・診察に行かなかったから,はっきりわからなかった。
・行政から情報提供もなかったので水俣病であるとの認識がなかった。
・他人と比較しないので,分からなかった。
・テレビで見るひどい状態の人だけが水俣病と思っていた。
等の回答があった。(但し,集計対象者外の人の回答も含む)
7 家族の申請状況について
(1)あなたの家族で,これまで水俣病の申請をした方はいますか。
いる 92名
いない 15名
(2)その方はあなたとはどのような関係の人ですか。
省略
(3)申請した結果はどうでしたか。
省略
(4)申請した時期はいつごろですか。
省略
(5)その家族の症状はどのようなものでしたか。
家族の症状についての回答は,手足のしびれやカラス曲がりなどが主であった。
(6)あなたの症状と具体的に違っていたところを述べてください。
省略
8 胎児性世代,小児性世代の健康被害について
(1)胎児性世代,小児性世代の人たち(40代,50代)と60才以上の人たちとの間で,健康被害に違いがあると思いますか。
?はい 20名
?いいえ 12名
?わからない 70名
未回答 5名
(2)そのように考えられる理由について述べて下さい。
省略
(3)手足のしびれなどについて違いがあると思いますか。
?はい 16名
?いいえ 12名
?わからない 67名
未回答 12名
(4)その理由について述べてください。
省略
(5)胎児性世代と小児性世代には何か違いがあると思いますか。
?はい 7名
?いいえ 4名
?わからない 89名
未回答 7名
9 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決後に水俣病認定申請をした方のきっかけ
(公健法上の認定申請に関しての申請情報を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴訟
最高裁判決まで認定申請(公健法)をしたことがなかったと回答した対象者37名について集計。複数回答可能。)
?知人,友人に勧められた 14名
?病院,医師に勧められた 3名
?被害者団体に勧められた 9名
?新聞報道やテレビ等を見て 2名
?家族や親戚に勧められた 11名
?その他 3名
未回答 5名
10 新保険手帳の申請をされた方のきっかけ
?知人,友人に勧められた 18名
?病院,医師に勧められた 2名
?被害者団体に勧められた 7名
?新聞報道やテレビ等を見て 0名
?家族や親戚に勧められた 13名
11 不知火海沿岸全域の健康調査について
(1)国,県の費用負担で調査を実施すべきである。(○をつけてください)
?はい 88名
?いいえ 7名
?どちらでもない 12名
(2)今から調査して健康被害の実態はわかると思いますか。(○をつけてください)
?はい 77名
?いいえ 19名
?どちらでもない 11名
(3)また,その理由について答えてください。
? 調査が必要であると回答した理由
早期解決のために国などによる健康調査の必要性に言及するもの,水俣病が未解決であるに
もかかわらず,一般には「終わったもの」と受けとめられているものに言及するもの等が多く
見られた。
・汚染地域の人たちが水俣病ということで差別されると思い,申請さえもできないでいる人が
まだ多くいる。調査をすれば実態が分かる。
・行政が健康診断のように行えば,多くの人が診断を受けると思う。
・現実に被害があって苦しんでいる人がたくさんいる。家庭訪問も取り入れるべきである。
・まだ水俣病であると気づいていない患者も多い。
・診断基準に納得ができない。症状に応じて判断されていないと思う。
・後から症状が出てきている人もいるので,調査には意味がある。
・感覚障害等が水俣病であるという情報は全く得られず,行政からも情報提供はなされなかった。
・あれだけの水銀を食べさせられていても「偽患者」と言われる。きちんと調査をしてほしい。
?調査を実施すべきであるか,健康被害の実態は分かるか,について「いいえ」あるいは「どちらでもない」と回答した理由
・調べる側のさじ加減次第。良くなるとは思わない。
・調査手法に疑問。
・水俣病であると偽った人がいた。本当に水俣病であることが分かるのか疑わしい。
・健康被害のある人は,既に各自が病院で検査済み。
・今頃,という感じ。遅すぎる。
・チッソ関係の仕事をしている人からは嫌がられることがある。
・今になって調査にお金をかけるのではなく,補償に回して欲しい。
12 水俣病の認定(公健法)基準について
(1)基準についてどのように考えていますか。(○をつけてください)
?きびしすぎる 88名
?妥当である 6名
?どちらでもない 13名
(2)そのように考える理由について述べて下さい。
基準がきびしすぎるとする理由としては,ほとんど申請が認められない,昭和52年より以
前の判断基準にすべきである,とするものが多数を占めた。中には,胎児性,小児性について
もっと解明すべきとするものも見られた。
一方,基準は妥当であるとする理由としては,きちんと検査をすれば自分が水俣病であるこ
とは分かるはず(認定審査会の運用の問題点を指摘する趣旨で述べられている)とするものが
見られた。
(3)基準を改訂すべきであると思いますか。
?きびしすぎる(はい) 81名
?妥当である(いいえ) 5名
?どちらでもない 14名
未回答 7名
(4)そのように考える理由について述べてください。
基準を改訂すべきであるとする理由としては,被害状況に応じ被害者を救済すべきとの趣旨
の回答が多数を占め,その他,関西水俣訴訟最高裁判決に準ずべきとの趣旨の回答も見られた。
一方,基準を改訂する必要はないとする理由としては,きちんと検査をすれば自分が水俣病
であることは分かるはず(認定審査会の運用の問題点を指摘する趣旨で述べられている)とす
るものが見られた。
13 今回の調査に関する自由記載
自由記載欄には患者の様々な思いが綴られていた。その内の一部を紹介することとする。
・水俣病はまだ終わっていない。水俣病患者はまだ救済されていないということを全国の皆さ
んに知っていただきたい。劇症型の水俣病で,軽いのはニセ患者だと思っている人が非常に
多いが,正しく水俣病のことを知ってほしい。水俣病の全面救済を1日も早くしてほしい。
全面救済をするには汚染地区の住民の全部の健康調査をしなければならない。
・平成7年の時に申請していない。ちょうどこのころからしびれを感じ始めた。水俣病の症状
を当時あまり知らなかった。水俣病の申請ができるとは思わなかった。
・もっと掘り下げて調べて欲しい。水俣病は終わったと思っている人が多い。多くの人に水俣
病について知って欲しい。
・子どもの頃から水俣病の症状に苦しめられてきた。私の母も同じ。母が水俣病だったか私に
は分かりませんが,私と同じ症状で苦しめられながら亡くなりました。もし,チッソの水銀
が原因でこうなったのであれば,チッソには責任をとってもらいたい。チッソの利益のため
に,私たちは何も知らずに自分の人生を台無しにされました。それを切りがないはないでし
ょう。最後の1人まで補償するのは当たり前のことです。たとえ,過失であっても,もし私
がチッソの立場だったら責任を取らされていますよ。
・この世に生まれる前から母胎の中で水銀にまみれ,生まれ落ちてすぐから命をつなぐため,
水銀に汚染された母親の母乳を飲まされて,生きなければならなかった赤ん坊。何も知らな
いで,愛しいわが子のために毒の入ったお乳を飲ませた母親。何の疑いも持たないで,無心
にお乳を飲み続けた末に水銀に身体をむしばまれて生きるしかない子どもたちが存在してい
るという現状をちゃんと見て欲しいと思う。50年以上の人生を水銀に苦しめられながら生
きてきて,これからもそれはもっと酷くなって続いていくという現実があることをしっかり
と認めて欲しい。
・汚染のことは聞いていたが,魚屋で売っているものだからと思って食べた。症状の重い人は
長年食べているからで,自分は未だ症状は出ないだろうと思った。申請した人に対する中傷
として,「申請されたとよー,まだ若いかモンのそがんことのあるもんか」という話を聞い
ていた。自分も申請したら同じように言われると思った。嫁ぎ先の両親も否定的だった。当
初は劇症型だけが「水俣病」だと思っていたが,新聞等で感覚障害でも「水俣病」であり,
メチル水銀が原因と報道されているので,そうであれば,自分も水俣病ではないかと思うよ
うになった。
・水俣湾だけの話だと思っていた。獅子島でも水俣患者がいることは平成18年になって始めて知った。悔しい,残念,どうして早く教えてくれなかったのかと。水俣病についての知識はあったが,自分の症状が水俣病だとは思っていなかった。昨年の12月に友人が水俣病の話があるので行くように誘われた。その際に「症状」を聞いた所,自分の症状とあっていることに驚いた。市役所に照会し,患者団体を紹介された。それ以前は関心もなかった。水俣病の患者は特別の人だろうと思っていた。
・胎児性世代についてちゃんと検査してほしい。漁師で毎日魚を食べていて「棄却」では納得できない。現在,手足の多少の麻痺(転びやすい),足のしびれ,カラス曲がりなどで障害も多いのに,まったく認定の外とはおかしい。自分が水俣病でないというのはどう考えてもおかしい。どうしても進展しなければ裁判も考えている。将来が不安。症状はひどくなっている感じがする。
・目に見えない症状をもっている人に対してもしっかり理解してあげるべきだ。苦しんでいる人は多くいる。自分でもよく分からないことが多く,判断できない。
・自分は早いうちから水俣病のおそれありと言われていたが,なかなか認定されなかった。同じ症状のある人でも認定に差があるのはおかしいのではないか。会社は責任を認めて,できる限り救済してもらいたい。
・チッソの対応に不満がある。テレビ等で見聞きするチッソの態度や意見に腹が立つ。
・水俣病の調査は行政がすべきものである。行政がきちんと住民の健康調査を行い,水俣病の全面的な救済をすべきである。
・不知火海沿岸の住民の健康調査を実施して,早くすべての人々を救済してほしい。そうしないと再び何回も裁判等の問題が今後起こってくると思う。
・何回も同じような調査をされている。社会に反映されていないのではないか。
・医者の検診の時は2〜3分見ただけで「ここはどうですか」って聞かれて「えぇ」ていったらそれでおしまい。「ここがおかしい」と言ったら 「そのようなことは言わなくてよい。聞いていることだけ答えろ」と言われた。これが実情。これでは検診とは言えない。
・打ち切られても今後水俣病の人が出てくる可能性が極めて高い。水俣病は年をとって気づくことが多いので。
・水俣病の重さによって,例えば5段階で認定して重さに応じて補償をすべきではないか。オール・オア・ナッシングは不当。裁判をしている高齢者は苦しんでいる。国に対策を望む。
・いろいろな調査が度重なっているので,現実的な救済を早期にしてほしい。チッソにはこの問題から逃げることなく,責任をとって救済に取り組んでほしい。
・基準を考え直してほしい。疫学を重視すべきである。行政から情報がきたことはない。行政の怠慢である。高齢化しており,早く解決してほしい。医師も経験がなく,診断能力がない。
・症状は人によって様々である。検査もそれにマッチしたものにしてほしい。今回の調査が,基準見直し,患者切り捨てでない方向に行くためのきっかけとなることを望む。
・被害者も高齢化しており,早く解決し,救済してほしい。救済が進まないことについて,特にチッソの対応については腹立たしい。調査を進め,救済してほしい。
・現在被害者団体に入り少しずつ水俣病のことについて分かるようになったが,若いときから関係があったとは思いもしなかった。いとこたちがたくさんいて,水俣病であったことは知っていたが,自分も同じ水俣病であることが分かったのがあまりにも遅すぎた。残念でならない。でも,この機会に自分たちが水俣病であることが分かったことは幸いであった。遅くなったとはいえ自分たちがやらなければいけないこと,出来ることは進んで参加し,みんなで協力して頑張りたいと思う。
・今,申請している人たちの中にも1800万円に相当する重い被害者はたくさんいる。150万で一律救済ならば全員救済にしてほしい。程度の差に応じて補償する制度を作るべき。行政側が,税金が高くなったのは水俣病患者が多く出てきたせいだとあちこちで言っている。そのせいで町民が水俣病のせいでと思うようになっている傾向もある。
・このままだと地球が危ない。大変苦労してきた。後がない。
・生きているうちに補償してほしい。それが一番。自分が死んだ後に残される娘のことがとても心配。娘は水俣病が一番ひどかったときに生まれた。
・水俣病は終わりではないので弁護士の方も力を貸して下さい。1人でも多くの人を救済してください。
・日弁連の調査はありがたい。この調査結果を国・県は,重く受け止めて水俣病解決に努めてほしい。
・被害者の相談には乗ってくれた弁護士に頑張ってもらっていることで心強い,一緒に頑張ってほしい。チッソの分社化は被害者にとってマイナスになるのでは。
・聞き取りがあったことで,これまで言いにくかったことをみんなに伝えて,理解してもらえることがよかった。以前より,基準が緩和されているように思える。申請しやすくなっているように思える。
以 上
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/minamata_houkokusyo_000.pdf
2008年10月
日本弁護士連合会
第1 調査の概要
1 調査の目的
2 調査の方法
3 調査の概要
4 調査結果を見る上での注意点
第2 調査分析
1 基本情報について
2 現在の健康被害の内容について
3 居住歴,生活歴等について
4 昭和20年代から昭和40年代まで不知火海の魚介類の摂取状況
5 家族構成・同居していた家族について
6 水俣病関係の認定申請について
7 家族の申請状況について
8 胎児性世代,小児性世代の健康被害について
9 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決後に水俣病認定申請をした方のきっかけ
10 新保険手帳の申請をされた方のきっかけ
11 不知火海沿岸全域の健康調査について
12 水俣病の認定(公健法)基準について
13 今回の調査に関する自由記載
第1 調査の概要
1 調査の目的
日本弁護士連合会は,1977年の人権擁護大会において「公害被害者の救済に関する決議」
を採択し,それ以降,水俣病問題についての調査研究を重ね,被害者の方の即時・完全救済等
を求める決議,具体的方策の提言などを行ってきた。
そして,2007年7月に「与党水俣病問題に関するプロジェクトチーム」が公表した「水
俣病に係る新たな救済策について(中間取りまとめ)」を受け,同年9月14日に「水俣病問
題について抜本的な救済策を求める意見書」を発表した。同意見書では,公健法に基づく救済
策を抜本的に改め,新たに総合的な救済施策を講じるべきであることを提案するとともに,新
たな救済施策の具体的内容として,水俣病認定基準の抜本的改定,水俣病患者に対する十分な
補償,水俣病患者に対する医療面,福祉面に対する恒久対策,国及び熊本県による経済的負担
等の事項を提示した。また,水俣病患者の実効的な救済を図るために,不知火海岸沿岸の健康
調査を早急かつ網羅的に行うべきことを提案した。
その後,与党水俣病問題に関するプロジェクトチームが救済策の実現に向けて検討を重ねて
いるが,依然として公健法に基づく認定基準を堅持する態度を変えておらず,また,一時金の
金額も関西水俣病訴訟最高裁判決の水準額(400万円から800万円)を大幅に下回る金額
(150万円)しか提示していないなど,当連合会が発表している提言からすると未だ不十分
なものにとどまっていると言わざるを得ない。また,国による不知火沿岸の健康調査も未だに
実施されていない。
そこで,当連合会としては,現地を訪れて水俣病患者の被害実態を調査することにより,具
体的なあるべき救済施策を研究し,今後も引き続き国に対して提言をしていく必要があると考
え,九州弁護士会連合会及び熊本県弁護士会の協力を得て,水俣病問題に関する被害実態調査
を実施した。
2 調査の方法
(1)調査対象
水俣病患者団体に実態調査協力の依頼をし,107名から協力を得られた。
(2)調査期間
2008年6月14日から同月15日まで。
(3)調査方法
調査事項書自己記入後,弁護士による個別面接調査。
なお,実態調査に携わった弁護士は,日本弁護士連合会人権擁護委員会委員5名,人権救済
調査室嘱託1名,同公害対策・環境保全委員会委員3名,九州弁護士会連合会人権擁護委員会
委員10名,熊本県弁護士会会員3名の合計22名である。
3 水俣病実態調査の概要
調査結果の概要は以下の通りである。
(1)現在の健康被害の内容について
今回の調査対象者は,実際にはほとんどの者が公健法上の水俣病患者としては認定されてい
ないが,次のとおり,四肢抹消優位の感覚障害,運動失調,視野狭窄のいずれについても異常
を訴えている者が多く存在した。
○感覚の異常である手足のしびれについては,すべての調査対象者が何らかの異常を訴えていた。
○手足の感覚麻痺については,調査対象者107名のうち93名が何らかの異常を訴えていた。
○上下肢の運動症状については,ほとんどの調査対象者が,つまずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいなど何らかの異常を訴えていた。
○視野狭窄については,調査対象者107名のうち93名が何らかの異常を訴えていた。
このデータから,感覚麻痺の有無だけを基準にするだけでは割り切れない患者が多数存在す
ることが窺われ,また,厳密な診察をすれば相当程度の者が水俣病と認定されるのではないか
と推測されるという結果が得られた。
(2)日常生活や仕事への影響について
日常生活上については,すべての調査対象者が何らかの支障を訴えていた。具体的には,足
のこむらがえり,常時疲れやすい,関節が痛い,耳鳴りがひどいなど身体的な症状を訴えてい
たり,茶碗を落として割ったりする,車の運転をしているとき横がまともに見えない,風呂の
湯加減が分からないなどの日常生活上の支障を訴えていた。
仕事面については,漁業に携わっている人が多い関係から,重い船具を持つことができない,
荷物を運ぼうとすると落としてしまう,網の修理が苦手であるなどの支障を訴える者が多かっ
た。そのほか,立ちくらみ,めまいのため仕事がしにくい,目を使う仕事ができない,補助的
な仕事に限定される,脚立など高い所へあがれないなどの支障も観られた。
日常生活や仕事面での差別等については,特にないと回答した者も多く存在したが,様々な
不利益,差別を受けたことがあると回答した者も多かった。具体的には,「大した症状もない
のにお金をもらっている」と悪口を言われる,医療費を支払わないことについて詐病ではない
かと言われる,見合いをしても水俣病の話が出ると相手から断られるなどの差別が見られた。
(3)病院での診察について
ほとんどの調査対象者がこれまで病院にかかったことがあったと回答しているが,水俣病あ
るいは水俣病の疑いとの診断を受けた者は,60代〜70代では約54%であったが,40代
〜50代では約30%にとどまった。治療内容については,保険適用外となるものも少なくな
く,はり,きゅう,マッサージ,電気治療,湿布,漢方治療薬などを利用している者も多く存
在した。
(4)公健法上の水俣病の認定申請について
公健法上の水俣病の認定申請を行っていた者は56名であり,そのうち,平成16年10月
15日の関西水俣病訴訟最高裁判決まで公健法上の水俣病の認定申請を行っていなかった者は
37名であった。認定申請をしていなかった理由については,「自分や家族に差別(結婚,就
職,近所付き合い)などの不利益が生じると思った」「自分が水俣病であることが分からなか
った」などが多く,依然として差別や偏見が根強く残っていること,水俣病に関する情報が十
分に周知徹底されていないことが窺われた。
(5)不知火海沿岸の健康調査について
調査対象者の約82%が不知火海沿岸の健康調査について,国,県の負担で実施すべきであ
ると回答をし,調査対象者の約72%が,今から調査をすれば健康被害の実態は分かると回答
しており,多くの者が実態調査を希望していることが判明した。
(6)認定基準について
調査対象者の約82%が現行の公健法上の水俣病の認定基準は厳しすぎると回答し,約7
6%が現行の基準を変えるべきであると回答していた。多くの者が,被害状況に応じた救済が
なされていないと感じていることが窺われた。
4 調査結果を見る上での注意点
今回の実態調査にあたっては,無作為抽出的に対象者を選出するのではなく,既存の水俣病
患者団体に実態調査協力の依頼をし,各水俣病患者団体において患者を選定してもらっている。
調査対象者数も僅か107名であることから,今回の調査結果が水俣病患者の全体の実態を反
映しているとは限らない。
また,今回の実態調査では,例えば「公健法上の水俣病の認定申請」について自分が申請を
しているか否かが不明であったり,過去の状況について一部記憶が定かでなかったりする事例
も見られた。限られた時間の聞き取り調査であったため,設問の内容によっては,必ずしも統
計的に正しいデータが得られていない可能性があることを付言しておく。そこで,今回の実態
調査においては,正確な数字よりも,患者の状況や特徴についての傾向を把握する趣旨で見て
いただければ幸いである。
なお,質問項目の中には,「いつ頃から症状が出ているのですか。」というような個々の患
者によって状況が異なり,集計が困難なものもある。そのような場合,集計結果を省略させて
頂いている点をご容赦されたい。
また,集計は,弁護士による個別面談を経て修正,加筆された調査事項書を基にしている。
第2 調査分析
以下,調査事項書の質問事項順に集計結果を記載する。
なお,前述のとおり集計が困難な質問項目については,記載を省略している。
1 基本情報について
<調査結果の補足説明>
?の手足のしびれについて
手足のしびれについては調査対象者107名全員が感覚の異常である手足のしびれを訴え
ていたということになる。40代〜50代の胎児性世代,小児性世代の患者と60代〜70
代の患者とでは,その傾向はほとんど変わらなかった。
?つまずきやすい,転びやすい・?細かい作業がしにくいについて
つまずきやすい,転びやすいは下肢運動症状に,?細かい作業がしにくいは上肢運動症状
に該当する。
つまずきやすい,転びやすいは,年代に関わらず,ほとんどの調査対象者が症状の異常を
訴えている。
また,細かい作業がしにくいという症状についても,年代に関わらず,ほとんどの調査対
象者が症状の異常を訴えていた。
なお,つまずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいという症状について,いずれ
もなしと答えている者はおらず,すべての調査対象者が何らかの異常を訴えていた。
<コメント>
?の手足の感覚麻痺について
手足の感覚麻痺については調査対象者107名のうち,93名が何らかの異常を訴えてい
た。そのうち,40代〜50代では,感覚麻痺が「常時」と回答した者よりも「時々」と回
答した者の方が多かったが,60代〜70代では,「常時」と回答した者が「時々」と回答し
た者の2倍となっていた。今回の調査だけでははっきりとしたことは言えないが,40代〜
50代と60代〜70代との間で感覚麻痺について「常時」と「時々」との間に差があると
いうことに関して,一定の有意性が認められる可能性がある。
なお,今回の調査では40代〜50代の患者のうち,感覚麻痺についてなしと答えた者が
4名いた。しかしながら,前述した?のとおり,40代〜50代の調査対象者の全てが,つ
まずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいなどという症状を訴えており,感覚麻痺
はないものの,運動症状に何らかの異常を来している者も相当数存在していると考えられる。
このようなことから,感覚麻痺の有無だけを基準にするだけでは割り切れない症状の患者が
相当数存在することが窺われた。
?の全身の感覚麻痺について
全身の感覚麻痺については調査対象者107名のうち半数近くの者が何らかの異常を訴え
ていた。
但し,例えば手足の先ではなく腕の部分に感覚麻痺を感じた場合に,回答する側からする
と,これが全身性の感覚麻痺なのか,四肢末梢の感覚麻痺なのかは判然としない場合も少な
くなかったようである。全身性か末梢の感覚障害かは厳密に専門の医者の検査によって判断
しないと誤るおそれがあると言えよう。言い換えれば,水俣病の診断基準のうち「感覚障害」
の取り方には十分に注意して行う必要があるということになる。
?視野狭窄について
視野狭窄の何らかの異常を訴えている者の割合は,全部で93名と約87%であり,40
代〜50代でも異常を訴えるのは53名中44名と約83%である。今回の調査では視野狭
窄を訴えている者の割合がかなり高い。これは,調査対象者の選別について比較的重症の患
者が選択されたのではないかと推測される。
○健康被害についての総合的なコメント
前記内容を総合し,40代〜50代の調査対象者で,?感覚障害(感覚麻痺),?運動失調,
?視野狭窄について複数の異常を訴えている人たちがどれくらいいるのかという統計を出し
たところ,次のような結果が得られた。
?の感覚障害については,常時か時々の別はあるものの,全員が手足のしびれを訴えてお
り(?の「手足のしびれ」),また,約87%の人が手足の感覚麻痺を訴えている(?の「手
足の感覚麻痺」)。従って何らかの手足の感覚障害という意味では,全員が異常を訴えている
ということになる。
?の運動失調については,上肢と下肢に若干の違いがあるが,常時,時々を含めて何らか
の運動失調がある者は全員である(?のつまずきやすい,転びやすいが下肢に関する運動失
調。?の細かい作業がしにくいが上肢に関する運動失調)。
?視野狭窄については,40代〜50代の患者の53名のうち44名が常時または時々の
異常を訴えている(?の視野狭窄)。
すなわち,今回の調査対象者については,実際には,ほとんどの者が公健法上の水俣病患
者としては認定されていないが(6項?参照),四肢抹消優位の感覚障害,運動失調,視野狭
窄のいずれについても異常を訴えている者が大多数であることを考えると,厳密な診察をす
れば相当程度の者が水俣病と認定されるのではないかと推測される。
(2)いつ頃から症状が出ているのですか。
症状や回答者によって異なる回答であった。但し,症状の種類を問わず,年齢を重ねるごとに症状が悪化している傾向にあるようであった。
(3)上記の症状による日常生活や仕事への影響についてお聞きします。
? 日常生活においてどのような支障が生じていますか。
今回の調査対象者の全員が,日常生活上の何らの支障を訴えている。以下に,具体例を紹介する。
・足のこむらがえり。
・常時疲れやすい。
・人の支えがないと歩くのが困難。
・関節が痛い。
・手足のしびれ。
・小さい物をうまくつまめない。
・手足のしびれのため,例えば,けがをしてもあまり痛みを感じないので,いつ,どこで怪我をしたのかが分からない。血が出ているのを見て初めて気が付く程度。
・夜よく寝られない。
・カラス曲がりなど日常茶飯事で,ひどいときは30分,40分つりっぱなしの時もある。
・耳鳴りがひどく,人の声が聞こえないので,自分もついつい大声で話してしまう。
・心臓に不整脈がある(ニトロを持っている)。
・茶碗を落として割ったりする。
・1人で布団も干せない。
・箸がうまく使えない。
・言葉がどもり,人に挨拶などができない。
・人間関係が作れない。子ども時代から症状があり友達ができなかった。
・物をつかんでいる感覚がない。
・手がふるえるのでお茶を出すのが嫌。
・味付けが濃すぎたり,薄すぎたりする。
・車の運転をしているとき,横がまともに見えない。
・細かい仕事がつらい(手の震え)。
・脱いだつもりのつっかけが脱げなくて,そのまま上ってしまう。段差に躓いて,転倒し,骨折した。
・一番困るのは眼。手術のしようがないと言われている。新聞は読めない。目薬は1日1本必要。
・風呂に入るとき心臓から下までしか浸かれない。
・風呂の湯加減がわからない。
・怖くて水泳ができない。
・長く座っているのが苦痛。長く座っていると足がしびれて固まって立ち上がれなくなる。あぐらが長時間できない。座敷の食事等がつらく,早く終わってくれないかと思ってしまう。
・忘れてしまって何度も尋ねることがある。
・家の外にはほとんど出ない。テレビも見ない。本も読まない。家では掃除,洗濯をしているが頭が痛かったりだるかったりするので,掃除,洗濯を毎日することはできない。他は何もしていない。
・左右の視力が違い,また,視力も変わってくるため眼鏡が合わない。そのため,頭痛がする。
・何を食べてもおいしくない。等
? 仕事面で何か不都合や被害を受けたりしていますか。
仕事への支障についての訴えのみならず,それによる周囲からの反応について回答するものも見られた。以下に,具体例を紹介する。
・仕事に就いたことがない。
・補助的な仕事に限定される。スーパーのレジの仕事などしかできない。
・目を使う仕事ができない。
・長期間機械を扱うと,調子が悪くなる(腕など)。疲れやすいとは思う。
・指先にとげなどが刺さっていても気づかない。
・仕事中に休むことが多くなった。細かい作業ができないので困ることがある。同じ状態でいられない。重い物を抱えると,つって,しばらく腕をのばせない。
・立ちくらみ,めまいのため仕事がしにくい。県外で仕事しているとき,水俣出身ということがわかると「あなたも泡をふくんじゃないの?」などと言われた。
・パートに出たが,水俣病のことを言われた。私は申請中とは言わず黙っていたが,居づらくなり辞めてしまいまった。農作業も身体が痛く,していない。
・細かい作業が出来ない。文字を書けないのが,一番つらい。
・ひざが曲がらないので座るときは足を投げ出さないといけない。和式トイレが使えない。草むしりができない。
・手に力が入らないので,雑巾が絞れず,仕事の手伝いができなくなった。
・脚立など高い所へ上がれない。
・手が震えてハンダ付けができないときがある。
・手の感覚がないので,痛みを感じない。水俣病報道でよく登場したこともあり,会社から「お前はなぜ自分が水俣病だと言うのか」「お前の血は青いんだろう」「神経が通っていないんだろう」と言われた。
・物忘れ。商品の陳列がうまくできず,時間がかかる。
・高校卒業後,国鉄の試験を受けたが,耳鳴りのために面接,身体検査で落ちた。
・声が聞き取りにくいのですぐに返答できない。電話対応に困る。
・何か言われていることはわかるが,中身がわからないので何度も聞き直す。
・網を引く作業が船の上なので,すぐ転んで青あざができてしまう。手の握力も17〜18kgしかない。
・船の修理の仕事をしている。仕事に関してお客から信用を失いつつある。なくなっているかもしれない。仕事の集中力というか取り組みにむらがある。
・重たい船具(2kg)を持てないことがある。
・海上タクシーの仕事をしているが,荷物を運ぼうとすると落としてしまう。弁償することもあった。
・若い頃から漁業の網の修理が苦手だった。道具に糸が通らない。
・漁は2人でする仕事なので,自分が休めば夫も漁に行けず仕事が出来ない。よって収入減となる。子どもを育てるためには毎日漁に行かねばならない。
・農作業中にハサミ,のこを落とす。
・腰痛や肩こりがひどくなり痛み止めの注射を打つことが多く,通院しながらの農作業で仕事も進まない事も多い。人に代わってもらうことも多い。
・建設関係の仕事をしているが,手足のしびれがあるため測量作業がうまくできないことが多く,他の人から「他の人に代われ」と言われることがある。
・建設関係の仕事なので段差のある足場での作業(上り下り)がきつい。
・靴下工場で細かい作業だったので大変でした。
・手足が自由でないために,作業中に指を切断した。等
? 日常生活や仕事の面で不利益を生じたり,差別を受けたりしたことがありますか。
特にないと回答したものも多く存在したが,様々な不利益,差別を受けたりしたことがあると回答しているものも多かった。具体的な不利益,差別事例についての訴えを紹介する。
・高卒後,大阪で過ごしていたところ,テレビで水俣病のニュースが流れると「あなたの郷里
が映っている」等と言われ恥ずかしかった。夫の母が福岡の病院で手術を受けた。母は医療
手帳を持っていたので医療費がかからないが,看護師は医療手帳を見て,「これ何ですか!」
と驚いた。他の患者は支払をしているのに母だけ払わない扱いを説明するのに大変だった。
・差別についてあるとは思うが「大した症状もないのにお金をもらっている」「お金をほしが
っている」と悪口を言われる。だから自分も友達にもいえない。
・水俣病について活動(ビラ配り)をしていると,通行人の女性から「ニセ患者」と言われた。
・いとこが認定患者で胎児性患者を産んでいるが,差別を受けているのを見てきた。身内に漁
業関係者がいて,迷惑がられた。汽車では水俣で窓を閉めていた。
・自分ではないが,妹が「そんな身体なら家の人も早くいなくなればいいと思う」などと心な
い言葉をかけられた。
・薬剤師から,「認定患者だけが本当の患者だ,薬のありがたみが分かっていない,薬のお金
を払っていない,自分たちが払った税金が使われている」などと言われた。
・医療費を支払わないことについて,詐病ではないかと言われたことがある。「あんた達はよ
かなー,手帳もらえてなー,医療費がただで!」
・子どもが結婚前だったから申請しなかった。差別されるから。それまで手足のしびれはない
と言って隠していた。
・集会場などで声が聞きづらく困る。耳が聞こえないことで「つんぼ」とか言われる。隣家の
人が,結婚が破談になったという話を聞いた。
・お金目当てと言われる。
・水俣病だとお嫁に行けないなどと言われていたし,あえて調べようとは思っていなかった。
今までは,ただの神経痛ではないかと思っていたが,平成16年頃に水俣病のことを知って,
平成7年の政治解決の時もまさか自分が水俣病だとは思わなかった。
・裁判をしているので,「金がほしくてやっている,それくらいは誰でも身体に異常はある」
という悪口を言われる。父が認定されたときもニセ患者と言われた。
・ある人から「指輪など似合わない手だ」と言われた。口をつぐんで通行したり,けがらわし
いなどといわれた。行政からの正確な情報提供がないため。
・自分も見合いをしたが,水俣病の話が出ると,相手が断ってきたりした。結局,水俣病のこ
とをよく知らない外国人の女性と結婚した。
・テレビに出たあと差別を受けた。今の職場もいつ辞めさせられるか分からない。
・実家から送ってくる魚をおすそわけすると,「水俣からきたものだから嫌だ」と言われたこ
とはある。
・今現在はそうでもないが,幼小時期は冷たい目でみられたこともある。島外に出ていて結婚
していた際,県営住宅にいたとき,「笑わない人がきた」とか色々なことをいわれた。
・学校生活のときいじめられた。但し,水俣病との自覚はなく,トロイのが原因でいじめられ
ていると思っていた。
・小学校,中学校のとき悪口を言われた。近所のおばさんに会った際に父,母,妹だけに声を
かけて,自分に声をかけないということもあった。腹も立つし,とても悲しい。今でもそう
である。
・無理な仕事ができなくなった(手先や目を使う仕事ができない)。
・仕事中でもよくころぶことがある。高所のよう壁から足を踏み外して落ちたこともある。そ
のつど,「ボケか」と言われたりして,人からさげすまされているという思いがする。
・表だってはないが,何かを理由にして仕事がどんどん減っている。
・感覚がなく荷物を落としたり壊したりするため,職場の人からすごく言われる。
・仕事ができないことの理由がわかってもらえない。
・チッソの昭和50年度の採用試験を受けたときのこと。筆記試験が終わり,面接試験を受け
ていた時,面接試験の最後の質問で,「チッソが水俣病を起こしたことがよいか悪いか答え
なさい」と言われました。その時に,「それは悪い」と言ったら,面接官が「悪いだな」と
確認し,面接が終わった。結果は不採用だった。
・午前中しか仕事ができない。漁師なので潮加減があるが,夕方までの長時間の仕事ができな
い。
・手に力がなく配送中に店の商品を落とし,ビン類など割って弁償したりしている。
・親が認定されたとたん,縁談が破談になった人が近所にいた(相手は県外の人で,相手の両
親の反対のため)。
・仕事ができないために上司に解雇を申し渡され,職安に行こうとしたこともある。
等
水俣病以外の診断結果としてあげられていたものでは,「手足のしびれ」,「めまい」,「頭痛」,「腰痛」,「関節痛」,「原因不明」,「仕事上の疲労」等の回答があった。
<コメント>
手足のしびれというのは感覚障害の典型的な症状であり,水俣病患者には頭痛や腰痛,関
節痛などを訴える者も多くいる。診察を受けたときに,医師の側に,これらの症状が水俣病
の症状であるという理解がなかった可能性もある。
? いつ頃から病院に通っていますか。
40代〜50代の胎児性世代,小児性世代では子どものころから病院通いをしている人が多い。その一方で,最近になって通院を始めた者もいる。
<コメント>
症状によって発症の時期が異なること,複数の症状を訴える者が大半であるということ等
の事情によるものと思われる。
? どのような治療を受けていますか。
はり,きゅう,マッサージ,電気治療,湿布,漢方治療薬などといった回答が多く見られ
た。
<コメント>
これらの治療方法は保険適用外となることも多く,別途,医療費や医療手当の支給の必要
性が高いものである。
? 病院に通うことでの不都合があれば教えてください。
病院まで遠くて通院に時間がかかる,交通の便が悪いといった病院までのアクセスに関す
る回答や,1人で通院が出来ないという身体面での不都合を訴える回答,交通費や治療費な
どの経済的負担が大きいといった費用面での回答のほか,通院によって仕事に支障が生じる,
仕事を休めないので通院できない,医師の紹介が必要など不便といった回答があった。
<コメント>
未回答にはその年代には出生していなかったり幼児期であったために記憶が定かでなかった
りするものも含まれる。そのため,昭和20年代については未回答の割合が高くなっているも
のの,同年代に魚介類を摂取していないということではない。また,その年代に出生していな
い場合でも,母親が魚介類を摂取していれば胎児性の水銀暴露の問題が生じうる。
汚染地域を離れても家族から魚介類を送られてくることによってその魚介類を多食したとい
う例もあり,汚染地域を離れたことが魚介類の摂食と切り離されるとは一概には言えない。
さらに,地域によっては山間部や汚染地域と離れているような地区に居住していても行商か
ら購入したという例も見られた。
?ほぼ毎日?1週間に1回?1ヶ月に数回?ほとんど食べていない未回答
6 水俣病関係の認定申請について
(1)あなたはこれまで水俣病関係の認定申請をしたことがありますか。
ある 90名
ない 17名
(2)前項で「ある」と答えた方は下記にご回答ください。
? 認定申請(公健法)
水俣病関係の認定申請をしたことがあると回答した90名のうち,56名が公健法上の認
定申請に関しての申請状況を回答した。
結果の内訳は,認定2名,保留12名,棄却16名,申請中(審査中)8名,その他・回
答不明19名であった(1名は2回申請し,1回が棄却,1回が保留)。
? 総合対策医療事業
省略
? 政治解決(平成7年)のときの総合対策医療事業
省略
? 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決まで認定申請(公健法)をしたことがなかった
(公健法上の認定申請に関しての申請状況を回答した対象者について集計)
したことがない 37名
したことがある 19名
(3)平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決まで申請しなかった理由についてお聞きします。
(公健法上の認定申請に関しての申請状況を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴
訟最高裁判決まで認定申請をしたことがなかったと回答した対象者37名について集計。複
数回答可能。)
? 申請しても認定されないと思ったから。…5名
? 自分や家族に差別(結婚,就職,近所付き合い)などの不利益が生じると思ったから。…18名
? 認定申請についてのやり方がわからなかったから。…7名
? 自分が水俣病であることがわからなかったから。…18名
? 自分が水俣病であることを周囲に知られたくなかったから。…7名
? その他…10名
未回答…2名
<コメント>
?の差別などの不利益が生じると思ったとの回答や,?の自分が水俣病であることを周囲に
知られたくなかったという回答からは,依然として水俣病に対する差別や偏見が根強く残って
いることが窺われる。
?の申請しても認定されないと思ったというのは,現行の認定審査基準の審査が厳しすぎて,
殆どの患者が認定されないという基準の不合理性を患者が感じていることを示していると思わ
れる。
?の認定申請についてのやり方が分からなかったというのは,行政からの情報提供が不十分
であるということを示している。また,?の自分が水俣病であることが分からなかったと回答
する者も多かった(約半数)。
なお,その他の理由として,
・有機水銀による健康被害を受けていることは自覚していたが,救済を受けることができる「水
俣病」とは思わなかった。
・祖母から恥ずかしいから申請するなと言われた。近所から水俣病の人と接触するとうつるか
ら行くな等と言われていた。認定されると子どもまで差別されるかもしれないと思った。
・母親にも,歩行障害,手足のふるえ,よだれ(口回りのしびれ)の症状が強くあったが,差
別のおそれ(妹の結婚など)から申請は拒否していた。(母親自身と妹の意向)
・親戚,友人等にチッソの関係者が多いため対人関係の悪化を懸念して見送っていた。
・認定,申請方法などの制度説明は役所からもされたことは全くない。
・申請が出来ることを知らなかった。もう終わったこと,過去のことと思っていた。
・若かったので重く考えてなかった。歳を増すごとに酷くなった。
・他の都道府県に居住していたので関心を持たなかった。
等の回答があった。(但し,集計対象者外の人の回答も含む)
(4)前項で?(自分が水俣病であることがわからなかった)に○をつけた方にお聞きします。
どうして自分が水俣病であると思わなかったのですか。
(公健法上の認定申請に関しての申請情報を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴
訟最高裁判決まで認定申請をしたことがなく,その理由について「自分が水俣病であること
がわからなかったから」を選択した対象者18名について集計。複数回答可能。)
? 手足のしびれなどの感覚障害を感じなかった。…0名
? 生まれたときから手足のしびれなどの感覚障害があり,自分の症状が水俣病であるとは思わなかった。…4名
? いわゆる急性劇症型の人が水俣病であり,自分は水俣病であるとは思わなかった。…18名
? 魚を多食しておらず,水俣病になったとは思わなかった。…1名
? その他…1名
<コメント>
本項の質問の対象者全員(18名)が,?のいわゆる急性劇症型の人が水俣病であり自分が
水俣病であるとは思わなかったとの理由を選択しており,これは,水俣病に対する情報開示が
不十分であったことを示すものと言える。(なお,集計対象者外の人についても,かなりの人
数がこの選択肢を理由にあげており,有効な回答ではないが,「水俣病=急性劇症型」という
とらえ方がかなり根深く浸透していたことが窺われる。)
?の生まれたときから手足のしびれなどの感覚障害があり,自分の症状が水俣病であると思
わなかったとの回答についても,?と同様に水俣病に関する情報提供が十分になされていなか
ったことを推測させるものである。
なお,その他の理由として,
・症状が出てきたのが後からで,明確な診断がなかった。
・平成7年当時,他県にいたので,政治解決を知らなかった。行政からは何も情報提供はなかった。
・診察に行かなかったから,はっきりわからなかった。
・行政から情報提供もなかったので水俣病であるとの認識がなかった。
・他人と比較しないので,分からなかった。
・テレビで見るひどい状態の人だけが水俣病と思っていた。
等の回答があった。(但し,集計対象者外の人の回答も含む)
7 家族の申請状況について
(1)あなたの家族で,これまで水俣病の申請をした方はいますか。
いる 92名
いない 15名
(2)その方はあなたとはどのような関係の人ですか。
省略
(3)申請した結果はどうでしたか。
省略
(4)申請した時期はいつごろですか。
省略
(5)その家族の症状はどのようなものでしたか。
家族の症状についての回答は,手足のしびれやカラス曲がりなどが主であった。
(6)あなたの症状と具体的に違っていたところを述べてください。
省略
8 胎児性世代,小児性世代の健康被害について
(1)胎児性世代,小児性世代の人たち(40代,50代)と60才以上の人たちとの間で,健康被害に違いがあると思いますか。
?はい 20名
?いいえ 12名
?わからない 70名
未回答 5名
(2)そのように考えられる理由について述べて下さい。
省略
(3)手足のしびれなどについて違いがあると思いますか。
?はい 16名
?いいえ 12名
?わからない 67名
未回答 12名
(4)その理由について述べてください。
省略
(5)胎児性世代と小児性世代には何か違いがあると思いますか。
?はい 7名
?いいえ 4名
?わからない 89名
未回答 7名
9 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決後に水俣病認定申請をした方のきっかけ
(公健法上の認定申請に関しての申請情報を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴訟
最高裁判決まで認定申請(公健法)をしたことがなかったと回答した対象者37名について集計。複数回答可能。)
?知人,友人に勧められた 14名
?病院,医師に勧められた 3名
?被害者団体に勧められた 9名
?新聞報道やテレビ等を見て 2名
?家族や親戚に勧められた 11名
?その他 3名
未回答 5名
10 新保険手帳の申請をされた方のきっかけ
?知人,友人に勧められた 18名
?病院,医師に勧められた 2名
?被害者団体に勧められた 7名
?新聞報道やテレビ等を見て 0名
?家族や親戚に勧められた 13名
11 不知火海沿岸全域の健康調査について
(1)国,県の費用負担で調査を実施すべきである。(○をつけてください)
?はい 88名
?いいえ 7名
?どちらでもない 12名
(2)今から調査して健康被害の実態はわかると思いますか。(○をつけてください)
?はい 77名
?いいえ 19名
?どちらでもない 11名
(3)また,その理由について答えてください。
? 調査が必要であると回答した理由
早期解決のために国などによる健康調査の必要性に言及するもの,水俣病が未解決であるに
もかかわらず,一般には「終わったもの」と受けとめられているものに言及するもの等が多く
見られた。
・汚染地域の人たちが水俣病ということで差別されると思い,申請さえもできないでいる人が
まだ多くいる。調査をすれば実態が分かる。
・行政が健康診断のように行えば,多くの人が診断を受けると思う。
・現実に被害があって苦しんでいる人がたくさんいる。家庭訪問も取り入れるべきである。
・まだ水俣病であると気づいていない患者も多い。
・診断基準に納得ができない。症状に応じて判断されていないと思う。
・後から症状が出てきている人もいるので,調査には意味がある。
・感覚障害等が水俣病であるという情報は全く得られず,行政からも情報提供はなされなかった。
・あれだけの水銀を食べさせられていても「偽患者」と言われる。きちんと調査をしてほしい。
?調査を実施すべきであるか,健康被害の実態は分かるか,について「いいえ」あるいは「どちらでもない」と回答した理由
・調べる側のさじ加減次第。良くなるとは思わない。
・調査手法に疑問。
・水俣病であると偽った人がいた。本当に水俣病であることが分かるのか疑わしい。
・健康被害のある人は,既に各自が病院で検査済み。
・今頃,という感じ。遅すぎる。
・チッソ関係の仕事をしている人からは嫌がられることがある。
・今になって調査にお金をかけるのではなく,補償に回して欲しい。
12 水俣病の認定(公健法)基準について
(1)基準についてどのように考えていますか。(○をつけてください)
?きびしすぎる 88名
?妥当である 6名
?どちらでもない 13名
(2)そのように考える理由について述べて下さい。
基準がきびしすぎるとする理由としては,ほとんど申請が認められない,昭和52年より以
前の判断基準にすべきである,とするものが多数を占めた。中には,胎児性,小児性について
もっと解明すべきとするものも見られた。
一方,基準は妥当であるとする理由としては,きちんと検査をすれば自分が水俣病であるこ
とは分かるはず(認定審査会の運用の問題点を指摘する趣旨で述べられている)とするものが
見られた。
(3)基準を改訂すべきであると思いますか。
?きびしすぎる(はい) 81名
?妥当である(いいえ) 5名
?どちらでもない 14名
未回答 7名
(4)そのように考える理由について述べてください。
基準を改訂すべきであるとする理由としては,被害状況に応じ被害者を救済すべきとの趣旨
の回答が多数を占め,その他,関西水俣訴訟最高裁判決に準ずべきとの趣旨の回答も見られた。
一方,基準を改訂する必要はないとする理由としては,きちんと検査をすれば自分が水俣病
であることは分かるはず(認定審査会の運用の問題点を指摘する趣旨で述べられている)とす
るものが見られた。
13 今回の調査に関する自由記載
自由記載欄には患者の様々な思いが綴られていた。その内の一部を紹介することとする。
・水俣病はまだ終わっていない。水俣病患者はまだ救済されていないということを全国の皆さ
んに知っていただきたい。劇症型の水俣病で,軽いのはニセ患者だと思っている人が非常に
多いが,正しく水俣病のことを知ってほしい。水俣病の全面救済を1日も早くしてほしい。
全面救済をするには汚染地区の住民の全部の健康調査をしなければならない。
・平成7年の時に申請していない。ちょうどこのころからしびれを感じ始めた。水俣病の症状
を当時あまり知らなかった。水俣病の申請ができるとは思わなかった。
・もっと掘り下げて調べて欲しい。水俣病は終わったと思っている人が多い。多くの人に水俣
病について知って欲しい。
・子どもの頃から水俣病の症状に苦しめられてきた。私の母も同じ。母が水俣病だったか私に
は分かりませんが,私と同じ症状で苦しめられながら亡くなりました。もし,チッソの水銀
が原因でこうなったのであれば,チッソには責任をとってもらいたい。チッソの利益のため
に,私たちは何も知らずに自分の人生を台無しにされました。それを切りがないはないでし
ょう。最後の1人まで補償するのは当たり前のことです。たとえ,過失であっても,もし私
がチッソの立場だったら責任を取らされていますよ。
・この世に生まれる前から母胎の中で水銀にまみれ,生まれ落ちてすぐから命をつなぐため,
水銀に汚染された母親の母乳を飲まされて,生きなければならなかった赤ん坊。何も知らな
いで,愛しいわが子のために毒の入ったお乳を飲ませた母親。何の疑いも持たないで,無心
にお乳を飲み続けた末に水銀に身体をむしばまれて生きるしかない子どもたちが存在してい
るという現状をちゃんと見て欲しいと思う。50年以上の人生を水銀に苦しめられながら生
きてきて,これからもそれはもっと酷くなって続いていくという現実があることをしっかり
と認めて欲しい。
・汚染のことは聞いていたが,魚屋で売っているものだからと思って食べた。症状の重い人は
長年食べているからで,自分は未だ症状は出ないだろうと思った。申請した人に対する中傷
として,「申請されたとよー,まだ若いかモンのそがんことのあるもんか」という話を聞い
ていた。自分も申請したら同じように言われると思った。嫁ぎ先の両親も否定的だった。当
初は劇症型だけが「水俣病」だと思っていたが,新聞等で感覚障害でも「水俣病」であり,
メチル水銀が原因と報道されているので,そうであれば,自分も水俣病ではないかと思うよ
うになった。
・水俣湾だけの話だと思っていた。獅子島でも水俣患者がいることは平成18年になって始めて知った。悔しい,残念,どうして早く教えてくれなかったのかと。水俣病についての知識はあったが,自分の症状が水俣病だとは思っていなかった。昨年の12月に友人が水俣病の話があるので行くように誘われた。その際に「症状」を聞いた所,自分の症状とあっていることに驚いた。市役所に照会し,患者団体を紹介された。それ以前は関心もなかった。水俣病の患者は特別の人だろうと思っていた。
・胎児性世代についてちゃんと検査してほしい。漁師で毎日魚を食べていて「棄却」では納得できない。現在,手足の多少の麻痺(転びやすい),足のしびれ,カラス曲がりなどで障害も多いのに,まったく認定の外とはおかしい。自分が水俣病でないというのはどう考えてもおかしい。どうしても進展しなければ裁判も考えている。将来が不安。症状はひどくなっている感じがする。
・目に見えない症状をもっている人に対してもしっかり理解してあげるべきだ。苦しんでいる人は多くいる。自分でもよく分からないことが多く,判断できない。
・自分は早いうちから水俣病のおそれありと言われていたが,なかなか認定されなかった。同じ症状のある人でも認定に差があるのはおかしいのではないか。会社は責任を認めて,できる限り救済してもらいたい。
・チッソの対応に不満がある。テレビ等で見聞きするチッソの態度や意見に腹が立つ。
・水俣病の調査は行政がすべきものである。行政がきちんと住民の健康調査を行い,水俣病の全面的な救済をすべきである。
・不知火海沿岸の住民の健康調査を実施して,早くすべての人々を救済してほしい。そうしないと再び何回も裁判等の問題が今後起こってくると思う。
・何回も同じような調査をされている。社会に反映されていないのではないか。
・医者の検診の時は2〜3分見ただけで「ここはどうですか」って聞かれて「えぇ」ていったらそれでおしまい。「ここがおかしい」と言ったら 「そのようなことは言わなくてよい。聞いていることだけ答えろ」と言われた。これが実情。これでは検診とは言えない。
・打ち切られても今後水俣病の人が出てくる可能性が極めて高い。水俣病は年をとって気づくことが多いので。
・水俣病の重さによって,例えば5段階で認定して重さに応じて補償をすべきではないか。オール・オア・ナッシングは不当。裁判をしている高齢者は苦しんでいる。国に対策を望む。
・いろいろな調査が度重なっているので,現実的な救済を早期にしてほしい。チッソにはこの問題から逃げることなく,責任をとって救済に取り組んでほしい。
・基準を考え直してほしい。疫学を重視すべきである。行政から情報がきたことはない。行政の怠慢である。高齢化しており,早く解決してほしい。医師も経験がなく,診断能力がない。
・症状は人によって様々である。検査もそれにマッチしたものにしてほしい。今回の調査が,基準見直し,患者切り捨てでない方向に行くためのきっかけとなることを望む。
・被害者も高齢化しており,早く解決し,救済してほしい。救済が進まないことについて,特にチッソの対応については腹立たしい。調査を進め,救済してほしい。
・現在被害者団体に入り少しずつ水俣病のことについて分かるようになったが,若いときから関係があったとは思いもしなかった。いとこたちがたくさんいて,水俣病であったことは知っていたが,自分も同じ水俣病であることが分かったのがあまりにも遅すぎた。残念でならない。でも,この機会に自分たちが水俣病であることが分かったことは幸いであった。遅くなったとはいえ自分たちがやらなければいけないこと,出来ることは進んで参加し,みんなで協力して頑張りたいと思う。
・今,申請している人たちの中にも1800万円に相当する重い被害者はたくさんいる。150万で一律救済ならば全員救済にしてほしい。程度の差に応じて補償する制度を作るべき。行政側が,税金が高くなったのは水俣病患者が多く出てきたせいだとあちこちで言っている。そのせいで町民が水俣病のせいでと思うようになっている傾向もある。
・このままだと地球が危ない。大変苦労してきた。後がない。
・生きているうちに補償してほしい。それが一番。自分が死んだ後に残される娘のことがとても心配。娘は水俣病が一番ひどかったときに生まれた。
・水俣病は終わりではないので弁護士の方も力を貸して下さい。1人でも多くの人を救済してください。
・日弁連の調査はありがたい。この調査結果を国・県は,重く受け止めて水俣病解決に努めてほしい。
・被害者の相談には乗ってくれた弁護士に頑張ってもらっていることで心強い,一緒に頑張ってほしい。チッソの分社化は被害者にとってマイナスになるのでは。
・聞き取りがあったことで,これまで言いにくかったことをみんなに伝えて,理解してもらえることがよかった。以前より,基準が緩和されているように思える。申請しやすくなっているように思える。
以 上
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/minamata_houkokusyo_000.pdf
2009年11月11日
由良・生石宣言
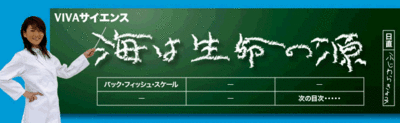



国際シンポジウム 「沿岸域の生態系を重視した持続可能な発展に向けて」由良・生石宣言
00/05
http://www.osakawan.or.jp/sub7-01.htm
はじめに
地球人口は、約60億人に達し、さらに増加しつつある。2025年には、地球人口が約80億人となり、そのうち約60億人が沿岸域に住むと予想されている。海陸が一体の空間であり、多様な生命の源泉である沿岸域は、現状においても様々な問題を抱えているが、近い将来、世界中で人間活動と生物・生態系の調和に関する極めて重大な問題に直面することと予想される。
大阪湾沿岸域は、これまでの歴史過程において、人口増加と人間活動の拡大に起因する様々な沿岸域問題を発生させてきたが、近年、歴史過程における教訓を踏まえ、沿岸域問題の解決に向けた幾つかの先導的な取組みが進展しつつあり、それらをさらに発展させるとともに、海からの視点による新たな取組みを加え、世界の沿岸域に対して将来モデルを提示していくことが望まれている。それは、沿岸域の生態系を重視した持続可能な発展のモデルと言うべきものである。
大阪湾沿岸域の要衝を占める洲本市南部の由良・生石研究村地域は、海陸の豊かな自然、自然とのかかわりを重視した優れた生活文化を残しており、沿岸域の生態系を重視した持続可能な発展を語るにふさわしい場所である。ここに、内外の叡智を結集して、1999年4月17日〜18日、沿岸域の将来に向けた議論を展開した。
貴重な海浜植物「ハマボウ」(由良・生石研究村の成ヶ島地区)
1.沿岸域の特性と沿岸域問題
(1) 沿岸域の特性
沿岸域は、海岸線を挟んで一定範囲の海域と陸域から成る空間である。沿岸域では、海域側からの作用と陸域側からの作用が様々にぶつかり合い、相互に利益や不利益を生じさせ、また、物質を循環させている。
ぶつかり合いの最前線となる海岸線では、砂浜、岩場、干潟など多様な自然形態が生まれ、河口域では、森林から流れてきた淡水と海水が混ざり合って汽水域が形成される。そして、このような特別な環境のもとで、多様な生命が育まれる。陸域からもたらされる栄養塩や有用微量成分が海藻や植物プランクトンの生命を育み、それらは高次生物に転生し、豊かな生態系が生まれるという森と海の連続性が存在する。
一方、沿岸陸域は、人々の生活、産業活動、レクリエーションなどにとって望ましい空間であるため、多くの人間活動が集積している。
人々は、沿岸海域に食糧や資源、レクリエーションの場を求めている。そして、沿岸陸域は、他の陸域の人間活動と海を介して深く結びついており、活発な交易が行われ、異質な価値や文化の交流があり、新たな価値や文化が生まれている。
(2) 沿岸域の諸問題と沿岸海域
世界中で沿岸域は、過密居住と生活環境の悪化、生物・生態系に配慮しない計画と急速な開発による環境負荷の増大、沿岸域利用者間における各種の軋轢、海洋汚染、海岸浸食や自然災害、資源枯渇など様々な範囲に及ぶ問題を抱えるに至っている。
人間社会の発展は、沿岸陸域への人口と産業の集中に伴う様々な環境悪化をもたらした。その環境悪化は、最近まで、主として陸域の人間生活環境の悪化に焦点が絞られていたが、それと同時に、陸域の様々な生命の生息環境ならびに沿岸海域の環境問題に焦点を当てなければならないことが明らかになってきた。
沿岸海域、特に多くの人間活動が集中する臨海部に面する海域は、陸域の問題を隠蔽するための役割を担わされてきた。下排水やゴミの処理・処分、用地不足を補うための埋立てなどが典型例である。また、陸側の安全確保を安価にあげるために、強固な垂直護岸で海岸線を覆ってきた。沿岸域においては、海域の特性や海側からの視点を全く考慮せず、陸側の視点で海域を都合よく利用し、あるいは海陸を分け隔ててきた。
世界各国において、都市化・工業化の急激な進展は、沿岸陸域の人口急増をもたらした。また、地域によっては、観光客の大巾な増加がある。
このような状況は、沿岸陸域のみならず沿岸海域の埋立による工業施設等の立地、港湾やマリーナの開発、養殖場の設置、ホテル等観光施設の立地などの開発・利用を加速した。そして、海域への廃棄物の大量放出、漁業資源の過剰な収奪などの問題とともに沿岸域の荒廃をもたらしている。
世界各国の沿岸海域では、長い年月をかけて形成されてきた砂浜・岩場・干潟・湿地帯など自然海岸やマングローブ林が破壊され、浅場や藻場が消滅しつつある。自然海岸、マングローブ林、浅場や藻場は、生物にとって重要な発生・生息環境であり、それらが失われれば、生物・生態系が損なわれ、それに依っていた物質循環が阻害され、自然浄化機能も当然のことながら消滅する。
そこへ、陸域から大量の窒素やリンがもたらされることにより、沿岸海域では、生態系内での生産・消費・分解のバランスが崩れ、一次生産が過大となり、赤潮や底層水の貧酸素化など環境の悪化をきたす。こうして、海域環境が悪化すれば、その海域の生物相は貧困となる。さらに、陸域から排出された有害重金属や化学物質は、生物濃縮現象へと結びつき、また内分泌攪乱物質(環境ホルモン)等として水生生物の生殖活動の異常を引き起こしている。
私達が持続可能な発展を実現するためには、海からの視点を据えておかなければならない。沿岸海域に常に焦点を当てていなければならない。生物・生態系との共生を忘れた人間活動のツケの総てが沿岸海域に凝縮してしまうからである。環境財としての沿岸海域の機能を失ってしまっては、私達自身の生存も危うくなる。
2.沿岸域の生態系を重視した持続可能な発展に向けての基本戦略
(1) 持続可能な社会システムの構築
沿岸域が持続可能な発展を達成するためには、まず沿岸陸域の社会システムを環境(生物・生態系)と共生するシステムに変える必要がある。近年、生活者、生産者ともに環境意識の高まりが見られるが、持続可能な社会システムの構築に向けての活動は緒についたばかりである。
生活者にあっては、生活と生物・生態系との関わりを学び、身近な環境問題から積極的な対応を進めていかなければならない。
生産者にあっては、生物・生態系の視点と生活者の視点を内包し、廃棄物を出さない、資源が循環利用される産業システムの構築を行う必要がある。
一方、交通・物流、都市開発、廃棄物処理等の分野においては、行政をはじめ社会全体が意識を集中し知識を結集して、環境を最優先した問題解決への取組みを行うことが必要となる。
なお、この時、海洋環境教育・研究・評価・情報交流の基盤となる施設は、海域生物の視点を含めた海からの視点を社会にインプットする極めて重要な役割を担うこととなる。
(2) 沿岸域の物質循環メカニズムの重視と沿岸海域環境の保全・創造
沿岸域へは、様々な物質が陸域から流入してくる。一部分は外洋に流出していくが、多くの物質は、沿岸海域、特に内湾域ではそこに留まり、水質ならびに底質を悪化させている。かつては、自然と人間の共同作業により、沿岸海域に留まった物質を再び陸域に戻す「循環」が行われていたため、深刻な汚染問題、特に富栄養化の問題などは生じなかった。
つまり、沿岸海域に流入した様々な物質は、海域生物に取り込まれ、最終的には魚介類を通して人間に、また底生生物を通して鳥類に食べられることにより、陸域に回帰していた。かつての沿岸海域は、魚類の産卵場であり生育場である藻場が見られ、漁業生産性が高く、干潟は鳥類の生息場所であった。しかし、藻場があり、漁業が健全に営まれ、鳥類が羽を休め餌を啄む干潟がある沿岸海域は、人間活動の拡大とともに減少してしまった。
栄養塩が陸域へ戻されるメカニズムが機能していたことにより、人間は豊かな生物・生態系と共生していたことの重要性を再認識すべきであり、私達は今後、多くの海洋生物の再生産を妨げないことはもとより、再生産に役立ち、豊かな生物・生態系が維持されることを助ける必要がある。また、人間活動に都合の良い様々な基盤施設のために生態系が破壊された沿岸海域では、その回復に役立つ機能をもつ基盤施設に造り変えていくことが必要である。
(3) 総合的な沿岸域管理(生態的沿岸域管理)
これまでの沿岸海域は、沿岸陸域の発展のために利用することが中心命題として捉えられてきた。沿岸陸域は強大な自然力により甚大な被害をこうむることも多く、沿岸海域と沿岸陸域を対立概念でとらえてきた時期がある。その結果、沿岸海域は海から切り取られ、陸域の都合を優先して利用する場、処理・処分のために使う場としてのみ位置づけられ、陸域からの栄養塩を吸収しつつ生命が発生・生育するインキュベータとしての機能、その生命が水圏、地圏と密接に関連して生態系を構築し、陸域に食糧や学習・レクリエーションの機会を提供するとともに、陸域からの排出物の分解・浄化を行うことなどを通して、陸域と共生する関係にあることが軽視されてきた。
そして、沿岸域に人間活動の中心が移るとともに山間部の荒廃も進行し、森が海の生物を育むという関係が閉じられてしまった。これによって沿岸域の荒廃が加速されてくることにも注意を払わなくてはならない。
私達は、沿岸海域が陸域にとって極めて重要な環境財であることを再確認しなければならない。海域の生物の視点を含めた海からの視点を据えて、海陸が共に発展していくための総合的な沿岸域管理を行う必要がある。これは、生態的沿岸域管理とも呼ぶべきものである。
この生態的沿岸域管理を具体的に展開していくためには、森と川と海を一体的な環境圏ととらえ、生態系のメカニズムを解明すること、砂浜、岩場、干潟などのなぎさの環境研究や藻場の環境研究を積極的に進めること、これらを通して望ましい環境とは何かを明らかにすること、さらに、現場主義の姿勢で観察・調査を続け、環境財としての目録を作成し、それを踏まえて環境を正確に把握・評価しつつ、環境の保全・創造の具体策をみつけていくことが必要となる。
その具体策としては、保護・保存されるべきところ、積極的に修復・回復・創造すべきところ、生物・生態系と共生しつつ適切に利活用を図るところを明確にし、そのための具体的方法と適用する技術、市民参加を含む管理プログラム、必要な財源とその源泉などが示されなければならない。なお、この時、環境評価手法の研究、生態的沿岸域管理計画手法の研究、生物・生態系環境の保全・創造のための技術開発が積極的に進められていなければならない。
行政においては、総合的な沿岸域管理(生態的沿岸域管理)を、持続可能な発展に向けての最も重要な戦略のひとつと強く認識し、研究機関等における所要の研究や技術開発を十分に支援するとともに、広く叡智を結集し、市民の協力と理解を得つつ、具体策を立案していく必要がある。

将来モデルとしての大阪湾沿岸域と由良・生石研究村の発展に向けて
1.大阪湾沿岸域の発展方向と取組み課題
大阪湾沿岸域においては、大阪湾が社会経済基盤としての重要な役割を果し続けているが、大阪湾は、陸域からの排出物の影響を受けやすい閉鎖性海域であり、陸域の諸活動の拡大に伴って、生物多様性の喪失、水質・底質の汚濁など環境を悪化させてきた。大阪湾においては、特に湾奥部において環境悪化が顕著であり、陸域からの負荷の削減、砂浜、岩場、干潟、藻場等の創造によって、生物生育環境の回復を急がなければならない。紀淡海峡海域においては、自然形態の多様性、生物種の多様性が保たれており、良好な環境を適切に維持・更新していく必要がある。
一方、大阪湾沿岸陸域は、関係自治体による環境基本計画の策定をはじめ環境と調和するまちづくりの方向へと展開しつつあるが、1995年1月17日未明に発生した兵庫県南部地震は、局所集中型の大都市圏構造の問題点を露呈し、新たなネットワーク型構造への転換を重要な命題として提示した。同時に、防災と環境の保全・創造が両立したまちづくりが強く求められることが明らかになった。
大阪湾沿岸陸域は、古代から日本の経済・文化の中心として繁栄した地域でもあり、国土の先導拠点として、またアジアのさらなる発展の中核としての役割を果たすとともに、自然環境と共生する空間として甦ることが強く望まれている。
大阪湾沿岸域においては、1,000年後の未来において人類文明が高度な発展を続けるモデルとなるように、その時、大阪湾が今から1,000年昔、即ち平安時代中期の美しさとロマンに満ちた状況を復活させていることを目標として、沿岸域の環境保全・創造とワイズ・ユースを追求する必要がある。そのために、今から取組むべきことは、次のように示される。
? 大阪湾を構成する個別海域および沿岸陸域の生態的・社会的特性を生かし、大阪湾沿岸域全体として多様性に富み、かつ調和のとれたまとまりのある空間を構築するとともに、総合的な沿岸域管理(生態的沿岸域管理)を実現するための大阪湾沿岸域環境グランドプランを作成する。このプランは、行政の枠を越えて広域的に、かつ長期的展望に基づいて作成し、大阪湾沿岸域の市民、企業、行政の共有指針とすべきである。
? 将来の状況変化に弾力的に対応できる環境管理システムを構築すべきである。そのベースとして、大阪湾の海況、水質、底質、生物等のモニタリングを継続実施し、環境および生態系に関するデータバンクを整備しておく必要がある。
? 漁業、海上輸送、観光、マリンスポーツ、自然観察、環境研究など様々な海域利用の総合的調整システムを構築する。なお、この時、例えば港湾区域や企業により囲い込まれた埋立地の海岸であっても、できるだけ多様な生物が生息できる空間の創造に取組むこと、また、本来の目的に支障をきたさない範囲で、市民が海と親しめ、漁業者が漁をできる余地を残す、あるいは積極的に目的が異なる活動を取り込んでいくことが必要である。
? 大阪湾沿岸域の各都市の都市計画において、持続的な未来を見通した沿岸域環境修復を基軸とする都市計画マスタープランおよび土地利用計画を策定し、大阪湾臨海地域開発整備法とも結びつけて実現を図る長期的な取組みへの着手を早急に開始することを提言する。
2.由良・生石研究村の特性と取組み課題
洲本市南部の由良から上灘にかけての海陸5,000haに及ぶ由良・生石研究村地域においては、人々が海・山とのかかわりの強い歴史文化や生活文化を今に伝えている。自然とのつき合い方においても、生物・生態系を荒らさず適切に維持・更新する漁業や人々のレクリエーションのスタイルが残されており、貴重な文化的資産をもっていると言える。
そして、この地域の自然環境は多様性に富んでいる。つまり、次のように自然形態が多様で、生物種も多様である。
?大阪湾で数少なくなった砂浜、岩場、干潟があり、特徴的な海域生物が存在し、特に熊田地区では、様々な海藻や付着生物、稚仔魚の群れが見られる。
?成ヶ島には、貴重な海浜植物が残され、広い意味でのマングローブの一種とも言われるハマボウは、夏にさわやかな黄色の花を咲かせ、ハママツナは、干潟の一部を柔らかく構成している。
?陸域では、複雑な地形に豊かな森が残り、ナガサキアゲハや古代からの姿を残すヒメハルゼミなどの昆虫の種類が多く、イノシシ、シカ、サルといった大型動物も生息している。
?研究村一帯は、ハヤブサ、ハチクマ、サシバのような猛禽類をはじめ、ルリビタキ、カワセミ、アオバズク、チュウサギ、シロチドリ等々、多様な鳥類の楽園でもある。
一方、大阪湾の中では、由良・生石研究村海域(紀淡海峡海域)が最も優れた海域環境をもっている。一部で砂浜の減少、藻場の減少、水質の悪化、漂着ゴミの大量堆積が見られるなど、環境悪化傾向も現れているが、海域環境の特徴は、次のように言える。
?紀伊水道・太平洋と大阪湾・瀬戸内海の海水交換の重要な場所となっている。
?砂浜、岩場、干潟等の多様で複雑な自然海岸と良好な藻場が残されている。
?自然度の高い山林が残り、陸域から海域への栄養塩と鉄分等の有用微量成分供給がある、森と海の連続性のモデル地域である。
?生石・熊田の海岸、由良湾等は、魚介類の産卵場、稚仔魚のナーサリーとして知られている。
?内外交流種の重要な通り道であり、魚種が豊富で沿岸漁業が盛んであり、高級魚が捕れる。
このように、由良・生石研究村では、比較的狭い範囲に、異なる性格を持つ生物・生態系がそれぞれ相互に関連し、接触あるいは近接して数多く存在している。このことが由良・生石研究村の生物・生態系の重要さであり、それゆえ私達は、生物・生態系とそこにおける人間の諸活動を探究するつきせぬ興味を覚える。
異なる性格をもつ生物・生態系が数多く存在する沿岸域においては、個別の生物・生態系の特性を生かし、かつ全体の生態系を生かす方向で、地域の発展を成し遂げなければならない。このことが沿岸域の生態系を重視した持続可能な発展である。由良・生石研究村においては、次の取組みが必要である。
? 異なる性格をもつ個別の生物・生態系の存在を地理的・特性的に同定し、各生物・生態系における持続可能な発展のあり方を検討する。
? 生態系全体について持続可能な発展のあり方を検討する。また、その具体策を立案する。
? 上記を前提として、研究村の将来像、環境共生・環境活用型産業の開発方向を明らかにする。
国際シンポジウム 「沿岸域の生態系を重視した持続可能な発展に向けて」
由良・生石宣言 おわりに
古代から、共生を旨とする日本文化を育んできた大阪湾沿岸域のゲートウェイであり、豊かな自然と生活文化を残す由良・生石研究村地域において、沿岸域の生態系を重視した持続可能な発展について議論できたことには感慨深いものがある。
本シンポジウムの成果を踏まえ、私達は、大阪湾沿岸域の環境保全・創造に関係する大学や行政、また市民の支援と協力を得つつ、世界の友人との情報交流を大切にしつつ、来るべき1,000年の始まりに向け、次の活動を開始することとする。
? 由良・生石研究村をフィ-ルドとした、海陸一体の環境のメカニズムの解明と総合的な沿岸域管理(生態的沿岸域管理)のモデルづくり
? 大阪湾沿岸域環境グランドプランの提案
? 本シンポジウム成果の発信と関係者の協力・共働の場づくりに向けシンポジウムの定期開催の準備
http://www.osakawan.or.jp/sub7-01.htm#book4

女性はおおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌・底質研究会の藤原きよみさんです(環境カウンセラー)。
2009年11月10日
日本周辺海域における海洋汚染の現状
平成21年10月20日
「日本周辺海域における海洋汚染の現状(海洋環境モニタリング調査結果(1998〜2007年度))」の発表について
環境省が1998年度から毎年実施している「海洋環境モニタリング調査」の結果を中心として、日本周辺海域の沿岸域から沖合域における、主として有害化学物質による汚染の現状を整理し、学識経験者による評価を踏まえ、「日本周辺海域における海洋汚染の現状(海洋環境モニタリング調査結果(1998〜2007年))」として取りまとめました。
1 海洋環境モニタリング調査の概要
陸域起源の汚染の把握を目的とする、内湾や沿岸域から沖合域にかけての汚染物質分布や濃度勾配の調査と、海洋投棄による汚染の把握を目的とする、海水、堆積物、海洋生物の汚染状況を把握する調査を実施。具体的な調査項目等は、以下のとおり。
○海水、堆積物について、重金属類のほかPOPs条約対象物質であるPCBやダイオキシン類、有機スズ化合物等を調査。
○沿岸から沖合域に分布する底生生物群集の状況及び5種類の海洋生物(イガイ類、底生性サメ類、イカ類、タラ類、甲殻類)により、PCB、ダイオキシン類等の汚染物質の蓄積状況を調査。
○浮遊性プラスチック類の調査
2 結果概要
○重金属類、PCB、ダイオキシンともに沿岸域の堆積物から検出されており、大都市圏からの負荷が沿岸域に影響していることが示唆された。また、PCB、ダイオキシンについては沖合域の堆積物でも低レベルながら検出された。 ○紀伊水道周辺海域堆積物から比較的高濃度のPCBが、紀伊・四国沖及び日本海西部海域の堆積物からバックグランドより高い濃度の有機スズ化合物が検出された。
○一部の沿岸域において、貧酸素化に起因する底生生物の組成の変化が観測されたが、有害物質との関係は認められなかった。また、海洋生物体内のダイオキシン類及びPCBの濃度は有意な減少傾向を示していないことが分かった。 ○沖合域までプラスチック類が分布していることが明らかになった。 以上により、いずれの海域においても、人の健康に影響を及ぼすおそれはないと判断しているものの、人為的な影響が沿岸域から沖合域まで及んでいると言える。
3 今後の調査予定
海洋生態系保全を含む海洋環境保全の観点から、今後も引き続き海洋環境モニタリングを定期的に実施し、汚染状況の監視を続けていくことにしている。また、新たにPOPs条約の対象物質として追加されるPFOS等の監視や紀伊水道周辺海域等比較的高濃度の汚染が見つかった海域での継続監視等を行っていく必要がある。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11688
日本周辺海域における海洋汚染の現状(海洋環境モニタリング調査結果(1998〜2007 年度))(概要版)
平成2 1 年1 0 月2 0 日
環境省地球環境局環境保全対策課
環境省においては、1998 年度から我が国の排他的経済水域の環境保全のため、海洋環境
モニタリング調査を開始した。1998〜2007 年度の10 年間において、3〜5年で一巡する
ことを前提とした調査の二巡の調査(フェーズ1、フェーズ2)が終了したところである。
これを受け、日本周辺海域の海洋環境の実態についての総合的な評価と国際的にも活用
されるよう日本周辺海域の海洋環境の現状についての積極的な情報提供を行うことを目的
とし、調査の結果を中心として、日本周辺海域の沿岸域から外洋域における、有害化学物
質による汚染の現状の整理及び評価を行い、ステータスレポートとして取りまとめた。今
回これを公表するもの。
公表内容の概要については、以下のとおり。
(1)調査概要
陸域起源の汚染を対象とし、特に大きな汚染負荷が存在すると考えられる内湾や沿岸
域からその沖合域にかけての汚染物質の分布や濃度勾配を把握する調査と、海洋投棄によ
る汚染を対象とし、投入処分?・?海域(旧B・C 海域)において、海水、堆積物、海洋生
物の汚染状況を把握する調査を実施している。また、従来からの人の健康保護あるいは生
活環境の保全という観点に加え、海洋生態系を保全するという観点から、生態濃度調査に
加え生物群集調査も実施している。
本モニタリング調査の特徴は以下の通りである。
? 沿岸域のみならず、沖合域の水深4000m 級の海域において、海水(栄養塩および
重金属類は各層採水)、堆積物、底生生物群集、浮遊性プラスチック類の調査を実施。
? 従来の汚染物質である重金属類の他、POPs 条約対象物質であるPCB やダイオキ
シン類、有機スズ化合物等を対象としている。
? 沿岸域から沖合域に分布する5 種類の海洋生物(イガイ類、底生性サメ類、イカ
類、タラ類、甲殻類)により、海洋生物体内の汚染物質を調査している。
? 定期的な調査に加えて、その結果検出された高濃度の汚染に対応した詳細調査を
実施している。
(2)調査結果と評価
調査結果概要とその評価を次表に示す。
表日本周辺海域の海洋環境の評価結果
評価 項目 現状の評価施策の効果と今後のモニタリング
陸域起源の汚染堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度ダイオキシン類
・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間において一部の海域・生物種では減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
・ダイオキシン特措法(1999 年)等により、近年の主要な排出源である焼却施設に由来する排出量は大幅に減少したものの、難分解性および高蓄積性のため、過去に放出されたものの影響が継続している。
・POPs 条約(2004 年発効)により国際的な削減が進められており、近隣諸国からの越境汚染も含め、今後も継続監視が必要である。
PCB
・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間における海洋生物体内の濃度は、統計的に有意な減少傾向を示していない。
・化審法によりPCB の製造・使用・輸入が1974 年に原則禁止されたことに伴い、環境中のPCB 濃度は減少したものの、近年はその傾向が緩やかになっている。
・PCB 特措法によるPCB 廃棄物の処理が2004 年より開始されたことに伴い、環境中への流出は減少しつつあると考えられるものの、難分解性よび高蓄積性のため、その効果が堆積物や海洋生物に濃度減少として現れるには至っていない。
・POPs 条約において国際的な削減が進められており、近隣諸国からの越境汚染も含め、今後も継続監視が必要である。
ブチルスズ化合物
・主として外国船舶の航行に由来すると考えられる負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間において一部の海域・生物種について減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
・化審法による規制(1988〜1990 年)および自主規制に伴い、開放系用途の出荷量は減少したと推定されており、その結果、海洋生物体内の濃度は減少した。
近年におけるその減少は緩やかになっており、汚染の解消にはしばらく時間がかかると考えられる。
・AFS 条約が2008 年に発効し、これに伴い、わが国に入港する外国船舶に対し有機スズ化合物を含む船底防汚塗料の使用が禁止された。
重金属類
・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。
・わが国に由来する汚染は減少した一方、近隣諸国の経済発展に伴う越境汚染の増大が懸念され、それに合域においては人為的負荷が認められるレベルではない。
・一部の沿岸域においては、貧酸素環境に起因するメイオベントス群集の組成の変化が観測された。一方、有害化学物質汚染とメイオベントス群集の個体数や組成の変化との関係は認められなかった。
・わが国周辺の4000m 級までの海域におけるメイオベントス群集のベースラインデータが得られた。今後、その経時的変化を把握し、底生生物群集への影響を監視する。
栄養塩類
・一部の沿岸域では陸域からの負荷の影響が認められたが、その影響は沖合域まで広がっていなかった。
・今後もモニタリングを継続することが必要であるが、水質総量規制を含む排水規制により、負荷は削減されており、今後頻度削減の検討が可能である。
プラスチック類
・沖合域までプラスチック類が分布していることが明らかとなった。一旦環境中に流出したプラスチック類は容易には分解されず、長期にわたる生物への潜在的な影響が懸念される。
・近年、国内の削減方策の検討や、NOWPAP における各国の連携が図られるようになった。プラスチック生産量は世界では増加傾向にあり、これらを注視することが必要である。
海洋投棄由来の汚染・赤泥の投入処分点においては、許可申請時の事前環境影響評価で想定された範囲内で底生生物群集の個体数がバックグラウンドより減少していた。それ以外の投入処分地点においては、適正な投入処分に由来すると考えられる底質あるいは水質への特段の影響は認められなかった。
・わが国の投入処分に対する環境保全対策には、一定の効果が確認された。さらに海洋投入処分に係る許可制度の新設(2007 年)により、今後著しい汚染が生じる可能性は低いものの、引き続き、法に基づく投入処分の適切性を確認することが重要である。
特定の汚染海域(ホットスポット)の発見
・限られた調査の中で、底質より沖合域としては高い濃度の汚染を検出した。これらは人為的な影響であると判断された。いずれも人の健康に影響を及ぼすレベルではないと判断されたものの、海洋環境保全の観点から注視すべきものである。
・これまでに発見されたホットスポットについては継続的な監視を行うとともに、このような人為的汚染を防止するために、未調査海域についても適宜モニタリングを実施する必要がある。
(3)ホットスポットについて
海洋環境モニタリングにより、以下の三つの海域において沖合域の堆積物としては高い濃度の汚染が明らかとなった。
(1)紀伊水道周辺海域
紀伊水道周辺海域において堆積物からバックグラウンドよりも高濃度のPCB を検
出した。調査の結果、海底付近にPCB 負荷源が存在しており、1970 年前後から少
なくとも近年まで継続的な負荷があったと考えられる。また、負荷源は単一の性状
のものではない可能性が高いことを明らかにした。
(2)紀伊・四国沖
紀伊・四国沖の投入処分?海域および?海域(水深4000〜4500m 程度)において、
堆積物から高濃度のブチルおよびフェニルスズ化合物を検出した。
(3)日本海西部
日本海西部の投入処分?海域を中心とした広範囲の海域において、堆積物から高
濃度のブチルスズ化合物を検出した。
いずれの海域においても、人の健康に影響を及ぼすおそれはないと判断している
ものの、人為的な影響が沖合域に及んでいると言え、海洋生態系保全を含む海洋環
境保全の観点から、今後も引き続き監視を続けていくことが必要である。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14426&hou_id=11688
日本周辺海域における海洋汚染の現状
―主として海洋環境モニタリング調査結果(1998〜2007 年度)を踏まえて―
2009 年10 月
環境省
目次
1. 目的...........................................................1
2. 海洋環境モニタリング調査の概要....................2
2.1. 日本周辺の海域と海流............................2
2.2. 海洋環境モニタリング調査の概要..............4
3. 海洋環境の総合評価...................................5
3.1. 陸域起源の汚染の影響...........................8
3.1.1. 堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度....8
3.1.2. 底生生物群集への影響.....................17
3.1.3. 栄養塩類.........................................18
3.1.4. プラスチック類の汚染.........................18
3.2. 投入処分に起因する汚染の影響...............21
3.3. 特定の汚染海域(ホットスポット)の発見......23
3.4. 今後の対策に向けて................................24
4. 参考文献.....................................................26
海洋環境モニタリング調査検討会
検討員(敬称略、50 音順)
石坂丞二長崎大学水産学部教授
小城春雄北海道大学水産学部名誉教授
白山義久京都大学フィールド科学教育研究センター長
田辺信介愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授
中田英昭長崎大学大学院生産科学研究科長(座長)
西田周平東京大学海洋研究所浮遊生物分野教授
野尻幸宏独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター副センター長
二ツ町悟海上保安庁海洋情報部環境調査課海洋汚染調査室長
牧秀明独立行政法人国立環境研究所
水土壌圏環境研究領域海洋環境研究室主任研究員
注:検討員および所属は2009 年3 月時点のもの
本報告書の作成にあたっては、上記検討員の方々にご協力いただいた。
1. 目的
国連海洋法条約が1996 年7 月に発効したことを受け、わが国は排他的経済水域の環境保
全に責任を負うこととなり、これに対処するため環境省は海洋環境モニタリング調査検討
会(座長:中田英昭長崎大学教授)の指導の下、「海洋環境モニタリング指針」(環境庁,
1998)に基づく新たなモニタリング(海洋環境モニタリング調査)を1998 年度に開始した。
本モニタリングが対象としている海域は広大であることから、当該調査海域を3〜5 年で
一巡することを原則とした計画を立て、1998〜2007 年度の10 年間において、二巡の調査(フ
ェーズ1、フェーズ2)が終了したところである。同モニタリングでは、日本周辺海域を一
巡するごとに、海洋環境の実態について総合的な評価を行うこととしている。
一方、近年、北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)や地球海洋アセスメント(GMA)
等において、地域的、世界的に海洋環境の現状をとりまとめたステータスレポートが作成
されており、広域的な情報収集が活発化している。わが国においても、海洋環境の現状に
ついて積極的に情報提供を行い、国際的な貢献を果たすべきと考えられる。
上記の状況を踏まえ、ここでは、海洋環境モニタリング調査の結果を中心に、日本周辺
の沿岸から外洋域における、主として重金属類、PCB、ダイオキシン類等の有害化学物質に
よる汚染の現状を解析・評価し、ステータスレポートとしてまとめた。
2. 海洋環境モニタリング調査の概要
2.1. 日本周辺の海域と海流
わが国は四方を海で囲まれており、東側には海洋全体のほぼ半分を占める太平洋(平均
水深は4,282 m)がある。また、わが国周辺の沿海として、東シナ海、日本海、オホーツク
海がある。東シナ海は広い陸棚を有し、最大水深は2,719 m と深いものの、平均水深は188
m と極めて浅い海である。一方、日本海は最大水深3,796m、平均水深1,350 m と深くて閉
鎖的な海域である。オホーツク海の最大水深は3,372 m、平均水深は838 m であり、東シナ
海と日本海の中間的な性格を有しており、沿岸に沿って大陸棚が発達している(文部科学
省, 2002)。以上のように、わが国周辺海域は、一部に比較的発達した陸棚があるものの、
全体的にその面積は狭く、深い海に囲まれ、内湾以外に浅い海をほとんど持たない特徴を
有する(図2.1)。
日本周辺の海域の主な海流としては、暖流である黒潮及び対馬海流、寒流の親潮及びリ
マン海流がある(図2.2)。黒潮は、輸送する水の量が毎秒5,000 万トンにも達し、高温・
高塩・貧栄養の海水である。プランクトンが少ないため、透明度は高く、世界でも有数の
流れの強い海流として知られている。親潮は、オホーツク海やベーリング海の冷たい水が
起源となっており、栄養分を豊富に含んでいる。プランクトンが多いため、透明度は比較
的低い。この黒潮と親潮との潮境*は日本東方の海域に位置しており、水温が高く、栄養分
が豊富で魚類が多く集まることから、世界有数の漁場となっている(海上保安庁HP,2009)。
* 黒潮と親潮などのように温度や性質の違った水塊間の境目をいう。
※水深は200m ピッチ
図2.1 日本周辺の海底地形(海洋情報研究センターのデータより作成)
W:暖水、C:冷水
?黒潮、?黒潮続流、?黒潮反流、?対馬海流、?津軽暖流、?宗谷暖流、?親潮、?リマン海流
図2.2 日本周辺の主な海流(宇野木・久保田, 1996)
2.2. 海洋環境モニタリング調査の概要
日本国内では、行政、研究所、大学等の関係機関により様々なモニタリングが行われて
いる。環境省の海洋環境モニタリング調査の他、同省が実施している化学物質環境実態調
査、公共用水域調査、広域総合水質調査、及び他省庁としては、海上保安庁の海洋汚染調
査、気象庁の大気・海洋環境観測等があげられる。
海洋環境モニタリング調査では、発生源に着目し、陸域起源の汚染を対象とした調査と
海洋投棄による汚染を対象とした調査を実施している。
陸域起源の汚染を対象とした調査は、特に大きな汚染負荷が存在すると考えられる内湾
や沿岸域から、その沖合にかけての汚染物質の分布や濃度勾配を把握することで、陸域起
源の汚染負荷が海洋環境に及ぼす影響の把握を目的としている。
廃棄物等の海洋投入処分による汚染を対象とした調査は、近年において相当量の処分が
実施されている投入処分?・?海域(旧B・C 海域)において、海水、堆積物、海洋生物の
汚染状況を把握することを目的としている。
ヒトの健康保護あるいは生活環境の保全という従来からの観点に加え、海洋生態系を保
全するという観点から、環境基準よりもはるかに低い汚染物質濃度であっても、海洋生物
や海洋生態系に影響を及ぼしている可能性があることを考慮し、生体濃度調査および生物
群集調査を実施している。
本モニタリング調査の特徴は以下のとおりである。
? 沿岸域のみならず、沖合域の水深4000m 級の海域を対象として、海水(栄養塩および重金属類は各層採水)、堆積物、海洋生物、底生生物群集、浮遊性プラスチック類等に関する包括的な調査を実施している。
? 重金属類に加えて、POPs 条約対象物質であるPCB やダイオキシン類、有機スズ化合物など多様な有害物質を対象に含めている。
? 行政上規制あるいは要監視対象にはなっていない、主に下水汚泥に由来すると考えられるコプロスタノールや直鎖アルキルベンゼン等のマーカー物質も併せて測定を行っている。
? 沿岸域から沖合域にかけて分布する5 種類の海洋生物(イガイ類、底生性サメ類、イカ類、タラ類、甲殻類)を供試することにより、海洋生物体内のPCB やダイオキシン類等の汚染物質濃度の包括的なモニタリングを実施している。
? 定期的な調査に加え、その過程で判明した高濃度汚染に即応した詳細調査を実施している。
? 各測点における各測定対象物の過去数年間における変遷が把握されている。
3. 海洋環境の総合評価
日本周辺海域の海洋環境の現状および近年10 年間の傾向について、「海洋環境モニタリング調査」の結果を中心に、既存の研究調査結果も加味し、専門家による総合評価を行った。その概要は表3.1 に示した通りである。詳細を以下に述べる。
表3.1 日本周辺海域の海洋環境の評価結果(1)
評価項目現状の評価施策の効果と今後のモニタリング
陸域起源の汚染堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度ダイオキシン類
・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間において一部の海域・生物種では減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
・ダイオキシン特措法(1999 年)等により、近年の主要な排出源である焼却施設に由来する排出量は大幅に減少したものの、難分解性および高蓄積性のため、過去に放出されたものの影響が継続している。
・POPs 条約(2004 年発効)により国際的な削減が進められており、近隣諸国からの越境汚染も含め、今後も継続監視が必要である。PCB ・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間における海洋生物体内の濃度は、統計的に有意な減少傾向を示していない。
・化審法によりPCB の製造・使用・輸入が1974 年に原則禁止されたことに伴い、環境中のPCB 濃度は減少したものの、近年はその傾向が緩やかになっている。
・PCB 特措法によるPCB 廃棄物の処理が2004 年より開始されたことに伴い、環境中への流出は減少しつつあると考えられるものの、難分解性よび高蓄積性のため、その効果が堆積物や海洋生物に濃度減少として現れるには至っていない。
・POPs 条約において国際的な削減が進められており、近隣諸国からの越境汚染も含め、今後も継続監視が必要である。
ブチルスズ化合物
・主として外国船舶の航行に由来すると考えられる負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間において一部の海域・生物種について減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
・化審法による規制(1988〜1990 年)および自主規制に伴い、開放系用途の出荷量は減少したと推定されており、その結果、海洋生物体内の濃度は減少した。近年におけるその減少は緩やかになっており、汚染の解消にはしばらく時間がかかると考えられる。
・AFS 条約が2008 年に発効し、これに伴い、わが国に入港する外国船舶に対し有機スズ化合物を含む船底防汚塗料の使用が禁止された。この効果を今後継続的に検証する必要がある。
表3.1 日本周辺海域の海洋環境の評価結果(2)
評価項目現状の評価施策の効果と今後のモニタリング
陸域起源の汚染堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度重金属類・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。元来、自然に存在するものであり、沖合域においては人為的負荷が認められるレベルではない。
・わが国に由来する汚染は減少した一方、近隣諸国の経済発展に伴う越境汚染の増大が懸念され、それに対応した調査の実施が必要である。
底生生物群集への影響
・一部の沿岸域においては、貧酸素環境に起因するメイオベントス群集の組成の変化が観測された。一方、有害化学物質汚染とメイオベントス群集の個体数や組成の変化との関係は認められなかった。
・わが国周辺の4000m 級までの海域におけるメイオベントス群集のベースラインデータが得られた。今後、その経時的変化を把握し、底生生物群集への影響を監視する。
栄養塩類
・一部の沿岸域では陸域からの負荷の影響が認められたが、その影響は沖合域まで広がっていなかった。
・今後もモニタリングを継続することが必要であるが、水質総量規制を含む排水規制により、負荷は削減されており、今後、頻度削減の検討が可能である。
プラスチック類
・沖合域までプラスチック類が分布していることが明らかとなった。一旦環境中に流出したプラスチック類は容易には分解されず、長期にわたる生物への潜在的な影響が懸念される
・近年、国内の削減方策の検討や、NOWPAP における各国の連携が図られるようになった。プラスチック生産量は世界では増加傾向にあり、これらを注視することが必要である。
海洋投棄由来の汚染
・赤泥の投入処分点においては、許可申請時の事前環境影響評価で想定された範囲内で底生生物群集の個体数がバックグラウンドより減少していた。それ以外の投入処分地点においては、適正な投入処分に由来すると考えられる底質あるいは水質への特段の影響は認められなかった。
・わが国の投入処分に対する環境保全対策には、一定の効果が確認された。さらに海洋投入処分に係る許可制度の新(2007 年)により、今後著しい汚染が生じる可能性は低いものの、引き続き、法に基づく投入処分の適切性を確認することが重要である。
特定の汚染海域(ホットスポット)の発見
・限られた調査の中で、底質より沖合域としては高い濃度の汚染を検出した。これらは人為的な影響であると判断された。いずれも人の健康に影響を及ぼすレベルではないと判断されたものの、海洋環境保全の観点から注視すべきものである。
・これまでに発見されたホットスポットについては継続的な監視を行うとともに、このような人為的汚染を防止するために、未調査海域についても適宜モニタリングを実施する必要がある。
3.1. 陸域起源の汚染の影響
3.1.1. 堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度
(1) 総論
大きな汚染負荷が存在すると考えられる内湾や沿岸域から、その沖合にかけての汚染
物質の分布や濃度勾配を把握することで、陸域起源の汚染負荷が海洋環境に及ぼす影響
を把握することができる。堆積物中の汚染物質濃度のうち、内湾・沿岸域で高く沖合域
で低い傾向を示したものは以下のとおりである。PCB やブチルスズ化合物などの人工化
学物質は、本来自然には存在しない物質であり、ブチルスズ化合物を除いては、陸域か
らの汚染負荷の影響を示していると考えられる。
仙台湾〜沖合域:カドミウム、総水銀、PCB
東京湾〜沖合域:カドミウム、総水銀、鉛、PCB、ダイオキシン類、ブチルスズ化合物
伊勢湾〜沖合域:カドミウム、PCB
大阪湾〜沖合域:総水銀、鉛、PCB、ダイオキシン類、ブチルスズ化合物
富山湾〜沖合域:鉛、PCB、ダイオキシン類
ブチルスズ化合物については主要な用途は防汚塗料であり、陸域起源というよりは、
船舶の航行量が多いことに由来するものと推察される。これらを総合すると、大都市あ
るいは大工業地帯からの汚染負荷が沿岸域に影響を及ぼしていると考えられる。
これら物質の沖合域における濃度は低いものの、検出限界値以上の濃度で検出されて
おり、沿岸域の環境のみならず、沖合域においても影響を及ぼしている可能性がある。
以下、汚染の動向が注目されるものとして、ダイオキシン類、PCB、ブチルスズ化合物
をとりあげ、海洋環境モニタリングのデータに基づき、その汚染の現状と最近10 年間の
トレンドについて概説した上で、他のモニタリングや研究の結果も踏まえて、これまで
の経緯、長期トレンド、施策とその効果(評価)について述べる。
(2) ダイオキシン類
1)海洋環境モニタリングの調査結果
海洋環境モニタリング調査のデータによれば、堆積物中のダイオキシン類は大都市圏
を背後に抱える内湾・沿岸域で高く、沖合域で低いという傾向を示している(図3.1)。
このことは、陸域からの負荷が沿岸域に集積していることを示唆している。
海洋生物中のダイオキシン類については、一部の海域・生物種(東京湾のサメ類(肝
臓、筋肉)、黒潮域のイカ類(肝臓)、親潮域のイカ類(筋肉)、日本海域のタラ類(肝臓))
について統計的に有意な減少傾向が認められたものの(p<0.05)、全体としては明瞭な減
少傾向は認められない(図3.2)。
図3.1 表層堆積物中のダイオキシン類濃度の地理的分布(pg-TEQ/g dry wt)
図3.2 イカ類(肝臓)中のダイオキシン類濃度の経年変動(pg-TEQ/g wet wt)
2)これまでの施策の評価
わが国においては、ダイオキシン類の排出量のうち、特にPCDD 及びPCDF について
は、その約9 割が産業廃棄物の焼却時に排出されると推定されている(環境省,2005b)。
そこで、1997 年12 月から、大気汚染防止法や廃棄物処理法によって、焼却施設の煙突な
どから排出されるダイオキシン類の規制やごみ焼却施設の改善などの対策が進められて
きた。次いで1999 年3 月にダイオキシン対策推進基本指針が策定され、「今後4 年以内
に全国のダイオキシン類の排出総量を1997 年に比べ約9 割削減する」方針が打ち出され
た(ダイオキシン対策関係閣僚会議,1999)。また、ダイオキシン類対策特別措置法が1999
年7 月に成立、2000 年1 月に施行され、排出ガスおよび排出水に関する規制等が行われ
ている。
その結果、ダイオキシン類の総排出量は2007 年には1997 年から約96%減少した(環
境省,2008a)。これに伴い、排出量削減の効果が最も早く現れると考えられる大気中のダ
イオキシン類の濃度は急速に減少し、1997 年から2007 年の間に約92%減少した(環境
省,2008b)(図3.3)。その一方で、排出量削減の効果が現れるのが最も遅いと考えられ
る海洋生物中のダイオキシン類については、上述したとおり、一部の海域・生物種につ
いては減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
図3.3 ダイオキシン類の排出総量と大気中濃度の推移
(環境省2008a;2008b より作成)
東京湾における柱状堆積物(1993 年に採取)の分析結果によると、ダイオキシン類濃
度の推移は、ダイオキシン類対策特別措置法が施行された2000 年以前の1970 年頃をピ
ークとして、その後減少している(図3.4;益永ら,2001)。東京湾の調査結果では、1960
年代〜1970 年代を中心として使用された農薬に不純物として含まれていたダイオキシン
類の影響が大きいとする見解が報告されている(益永,2004)。
柱状堆積物の平均年代
PCDD/DFs(ng/g-dry)
図3.4 東京湾の柱状堆積物におけるダイオキシン類濃度の変遷(益永ら,2001 を改変)
ダイオキシン類は環境中で分解しにくく(難分解性)、食物連鎖を通して生物体内に濃
縮される(高蓄積性)ため、過去に放出されたダイオキシン類の影響が現在でも継続し
ており、近年の主要な排出源である焼却施設に由来するダイオキシン類の排出量が減少
しても、海洋生物体内の濃度は速やかには減少しない可能性がある。
(3) PCB
1)海洋環境モニタリングの調査結果
海洋環境モニタリング調査のデータによれば、堆積物中のPCB は大都市圏を背後に抱
える内湾・沿岸域で高く、沖合域で低いという傾向を示している(図3.5)。このことは、
そのような海域においては、陸域からの負荷が沿岸域に集積しやすいことを示唆している。
海洋生物中のPCB については、最近10 年間において統計的に有意な減少傾向は認めら
れていない(p>0.05)(図3.6)。
2)これまでの施策の評価
わが国におけるPCB の使用は1954 年に開始された後、年々増加し1970 年にピークを
迎えたが、1972 年に生産が中止され(図3.7)、1974 年に化審法の第一種特定化学物質に
指定されてその使用が原則禁止された。
東京湾奥における柱状堆積物(1993 年に採取)の分析結果(奥田ら,2000)によると、
PCB 濃度は1960 年代に急増し1970 年頃をピークに減少に転じており、その使用量の推
移とよく対応している(図3.8)。その一方で、PCB の生産は1972 年に中止されたにも関
わらず、1980 年代半ば以降1993 年までは、最高値の30%程度の濃度で推移している。
また、魚類および貝類のPCB 濃度(全国平均)は、1970 年代末から減少傾向にあるが(環
境省,2007)、2000 年代はほぼ横ばいの状態で推移している(図3.9)。
※値のない縦軸は凡例と同じスケール
図3.5 表層堆積物中のPCB 濃度の地理的分布(ng/g dry wt)
図3.6 底生性サメ類(肝臓)中のPCB 濃度の経年変動(ng/g wet wt)
図3.7 PCB 使用量の推移(磯野,1975 より作成)
図3.8 東京湾の柱状堆積物におけるPCB の鉛直分布(奥田ら,2000 を改変)
PCB類
生物(pg/g-wet)
貝類魚類
定量[検出]下限値(pg/g-wet)
図3.9 生物体内のPCB 濃度の長期的推移(環境省,2007 より作成)
PCB が化審法の第一種特定化学物質に指定された後、既に生産されたPCB やそれを含
む製品は回収・保管されることとなったが、回収されたPCB の処理はスムーズに進展し
なかった。一方、長期にわたるPCB 廃棄物の保管は、その不明・紛失をもたらしており
(PCB 廃棄物処理事業評価検討会,2003)、それに由来する環境へのPCB の流出が懸念されている。
POPs 条約においてPCB の適切な処理を2028 年までに行うことが義務づけされたこと
もあり、わが国では「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置
法」(PCB 特措法)が2001 年に成立し、2016 年7 月までにPCB 廃棄物の処理を終えると
いう目標のもと、2004 年12 月より、化学処理法による無害化処理が順次進められている。
PCB は環境中で分解しにくく(難分解性)、食物連鎖を通して生物体内に濃縮・蓄積しや
すい(高蓄積性)ため、PCB 廃棄物の処理に伴う環境中への流出量の低減が、堆積物や
海洋生物の濃度の減少として未だ現れるには至っていない。
(4) ブチルスズ化合物
1)海洋環境モニタリングの調査結果
海洋環境モニタリング調査によれば、堆積物中のブチルスズ化合物は大都市圏の内
湾・沿岸域で高く、沖合域で低いという傾向を示している(図3.10)。ブチルスズ化合物
の主要な用途は防汚塗料であり、これは陸域起源というよりは、船舶の航行量が多いこ
とに由来するものと推察される。なお、後述するように、わが国ではブチルスズ化合物
を含む防汚塗料の使用は既に禁止されていることから、主たる負荷源は外国船舶の航行
と考えられる。
海洋生物中のブチルスズ化合物については、一部の海域・生物種(仙台湾および富山
湾のイガイ類(軟体部)、東京湾および有明海のサメ類(肝臓))について統計的に有意
な減少傾向が認められたものの(p<0.05)、全体としては明瞭な減少傾向を示していない
(図3.11)。
2)これまでの施策の評価
ブチルスズ化合物は1960 年代から防汚塗料(船底塗料や漁網防汚剤)として広く使用
されてきたが、1980 年代半ばに、わが国において有機スズ化合物による海洋汚染が社会
問題となった。これに伴い、わが国では化審法において、1990 年1 月にブチルスズ化合
物のうちトリブチルスズオキシド(TBTO)が第一種特定化学物質に指定され、製造、使
用、輸入が原則禁止された。同年9 月にはその他のトリブチルスズ(TBT)化合物が第二
種特定化学物質に指定され、製造、輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ、製造、
輸入量が規制された。これと前後して、関連業界において防汚塗料の製造・使用が自主
規制された。TBT の推定開放系用途出荷量は1980 年代末をピークに急速に減少しており
(図3.12)、これは上記の規制の効果を示していると考えられる。
※値のない縦軸は凡例と同じスケール
図3.10 表層堆積物中のブチルスズ化合物濃度の地理的分布(ng/g dry wt)
図3.11 底生性サメ類(肝臓)中のブチルスズ化合物濃度の経年変動(ng/g wet wt)
図3.12 TBT の推定開放系用途出荷量(化学原料用を除く;TBT 基換算値)(中西・堀口,2006)
生物(ng/g-wet)
貝類魚類
定量[検出]下限値(ng/g-wet)
・幾何平均算出に際し、ndは検出下限値の1/2とした。
図3.13 生物体内のTBT 濃度の長期的推移(環境省,2007 より作成)
魚類および貝類のTBT 濃度は、環境省の化学物質環境実態調査が開始された1985 年か
ら長期的に減少する傾向を示している(図3.13; 環境省,2007)。これは、上記の政策の
効果が現れているものと考えられるが、その一方で、1998 年以降は減少が緩やかになっ
ている。また、海洋環境モニタリング調査の海洋生物体内の濃度についても、前述のと
おり、一部の海域・生物種について有意な減少傾向が認められたものの、全体としては
明瞭な減少傾向が見られなかった。これらの結果を総合的に解析すると、海洋生物体内
のトリブチルスズ化合物の汚染が解消するには、しばらく時間がかかると考えられる。
2008 年に、船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約(AFS 条約)が発効した。
これに伴い、わが国に入港する外国船舶に対し有機スズ化合物を含む船底防汚塗料の使
用が禁止されるため、海域への負荷は減少することが期待される。
3.1.2. 底生生物群集への影響
様々な人間活動の海洋環境への影響は、最終的に海洋生態系の変化という形で現れる
と考えられる。海洋環境モニタリングでは、そのような観点から、メイオベントス群集
の調査を実施した。その結果、水深最大5000m 程度までの海域におけるデータが蓄積さ
れた(図3.14)。
一部の内湾域においては、貧酸素環境に由来すると考えられるメイオベントス群集の
組成の変化が確認された。一方、有害化学物質汚染とメイオベントス群集の個体数や組
成の変化との関係は認められなかった。
現時点では今後の評価の基礎となるベースラインデータが得られた段階であり、さら
にデータが蓄積されれば、環境への影響の評価も可能になると考えられる。
※棒グラフは個体数、折れ線グラフは水深を示す。
図3.14 メイオベントスの個体数の分布(個体/10cm2)
3.1.3. 栄養塩類
主要な湾のうち陸域からの負荷が大きい東京湾及び大阪湾において、沿岸域では湾奥
の表層の値が高く、河川水に由来すると推測される陸域から水質への人為的負荷の影響
が認められた。一方、沖合域では表層で低く、中層にピークのある鉛直分布が認められ、
既存の知見(才野,1995)と同様の傾向を示していることから、沿岸域の負荷の影響は
沖合域まで広がってはいなかったことが確認された(図3.15)。
図3.15 東京湾(2002 年12 月)及び大阪湾(2003 年12 月)から沖合域にかけての硝酸態窒素(μM)の鉛直分布
3.1.4. プラスチック類の汚染
1)海洋環境モニタリングの調査結果
海洋環境モニタリング調査の結果から、沿岸域のみならず、沖合域においてもプラス
チック類が分布していることが明らかとなった(図3.16)。一部の海域では、沿岸域で高
く沖合域で低いデータが得られているが、そのような明瞭な傾向を示すデータは少ない。
また、時空間的に不均一性が大きく、局所的に、また調査年により分布個数の多い測点
見られた。
図3.16 2004〜2006 年度のプラスチック類の分布(千個/km2)
2)既存の知見と国際的な取組
レジンペレットやプラスチック破片は、海鳥などの海洋生物が誤飲することが知られ
ている。生物体内に取り込まれたレジンペレット等のプラスチック類から有害物質が溶
出し、生物体内のそれらの濃度が有意に増加していることも報告されている(Teuten et al.,
2009)。一旦環境中に流出したプラスチック類は容易には分解されないこと、日本周辺海
域の広範囲にわたってプラスチック類が分布していることから、長期にわたる生物への
潜在的な生物影響が懸念される。
小城・福本(2000)は、1994〜95 年に北海道南東部沿岸域にプラスチック粒子が平均
49 万個/km2(範囲0〜989 万個/km2)分布していたことを報告している。海洋環境モニ
タリング調査では、同一の測点でも調査年により分布個数が大きく異なっていることか
ら、このデータとの比較だけでは経年的な増加あるいは減少の傾向を判断することは困難である。
近年、海洋ゴミの国内における削減に向けた方策の検討が行われるとともに、NOWPAP
において海洋ゴミの流出防止、モニタリング、除去および処理のための行動計画(RAP
MALI)が日中韓ロにより策定されている。その一方で、世界におけるプラスチックの生
産量は増加傾向にあり(図3.17)、環境への負荷は今後増大する可能性がある。
図3.17 プラスチック生産量の推移(日本プラスチック工業連盟HP,2008 より作成)
3.2. 投入処分に起因する汚染の影響
わが国における廃棄物の海洋投入処分は、海洋汚染防止法及び廃棄物処理法により規制
されている。これにより、国際条約であるロンドン条約及びその「1996 年の議定書」(96
年議定書)に定める内容が担保されている。
2007 年4 月以前においてわが国では、廃棄物海洋投入処分海域として、A、B、C、F 海
域が設定されていた(図3.18)。それぞれの海域については以下に述べるような廃棄物が投
入処分可能なものとして定められている。なお、A 海域はB 海域に、B 海域はC 海域に包
含され、F 海域は実質的にすべての海域である。
A 海域(現在のI 海域(未設定))は、2007 年以前は有害性の大きい物質を固化した廃棄
物の投入処分海域であったが、実際には1981 年以降、このような廃棄物の投入処分は実施
されておらず、2007 年の海洋汚染防止法改正後には、投入処分が禁止されている。B 海域
(現在の?海域)に投入処分されていた廃棄物は、主として非水溶性無機性汚泥である。
具体的な廃棄物の品目としては赤泥や建設汚泥が挙げられる。C 海域(現在の?海域)では、
有機性の廃棄物が投入処分されていた。具体的な品目としては、し尿及びし尿浄化槽汚泥
や有機性汚泥、廃酸・廃アルカリ、動植物性残さ、家畜ふん尿等が挙げられる。F 海域(現
在の?海域)においては水底土砂の投入処分が可能とされていた。
海洋投入処分にあたっては、有害化学物質が混入する恐れのある廃棄物については判定
基準が定められており、この基準を満たしたものだけを投入処分することができる。旧海
洋汚染防止法においては、国が包括的な環境影響評価を実施して、海洋投入処分できる廃
棄物を定め、及び適切な排出海域を設定した。これに対して、現行の海洋汚染防止法は、
廃棄物の排出を行う個々の事業者に対して、国の指定する排出海域内にて具体的な排出場
所を選定し、事前の環境影響評価や事後の監視を実施することが義務付けられている。
これまでの海洋環境モニタリング調査の結果によれば、?海域では投入処分の影響は検
出されていない。また、?および?海域については、房総・伊豆沖合の?海域では、投入
点において赤泥に由来する物質が検出され、メイオベントスに対する影響が認められたも
のの事前の環境影響評価で想定された範囲内であり、他のほとんどの海域においては、法
に基づいた投入処分による影響は検出されなかった。その一方で、一部の投入処分海域に
おいては、原因が明らかでない汚染も検出されている。これは不法投棄による影響の可能
性もあり、その汚染源の把握が必要と考えられる(3.3 参照)。
2007 年4 月1 日以降は、96 年議定書に対応した海洋汚染防止法の一部改正に伴い、廃棄
物の海洋投入処分に係る許可制度が新設された。これに伴い、海洋環境に及ぼす影響に関
し、排出事業者による事前の評価が行われることとなった。このため、今後、著しい汚染
が生じる可能性は低いものの、今後も引き続き、法に基づいた投入処分が適切に実施され
る確認作業が必要である。
図3.18 海洋投入処分海域図(環境法令研究会,2004 より作成)
3.3. 特定の汚染海域(ホットスポット)の発見
海洋環境モニタリング調査により、以下の三つの海域において沖合域の堆積物としては
他の海域でみられない高濃度汚染が明らかとなった。
(
1)紀伊水道周辺海域
紀伊水道周辺海域において、堆積物からバックグラウンドよりも高濃度のPCB を検出
した。調査の結果、海底付近にPCB 負荷源が存在しており、1970 年前後から少なくとも
近年まで継続的な負荷があったと考えられる。また、負荷源は単一の性状のものではな
い可能性が高いことが分かった。
(2)紀伊・四国沖
紀伊・四国沖の投入処分?海域および?海域(水深4000〜4500m 程度)において、堆
積物から高濃度のブチルおよびフェニルスズ化合物が検出された。
(3)日本海西部
日本海西部の投入処分?海域を中心とした広範囲の海域において、堆積物から高濃度
のブチルスズ化合物が検出された。
いずれの海域においても、人の健康に影響を及ぼすおそれはないと判断されるものの、
これらの事例は人為的な影響が沖合域に及んでいることを示しており、海洋環境及び生態
系の保全の観点から、今後も引き続き監視を続けることが必要である。
これまでのモニタリング調査では、このように深海底における汚染が検出されており、
人為的な汚染を抑止する観点から、これまでに調査を行っていない海域も含めて広範囲に
わたるモニタリング調査を今後も実施していく必要がある。
3.4. 今後の対策に向けて
先に述べたとおり、ダイオキシン類では法規制によりこの10 年間で排出量が1/10 以下に
減少した。それに伴い、大気中の濃度は急速に減少したが、その一方で、海洋生物中の濃
度については一部に減少傾向が認められるものの、全体としては減少傾向が明瞭ではない。
このように、いったん海洋に流出した汚染物質は、規制の効果がなかなか現れにくいと
いう特徴がある。海洋汚染の防止に関しては、このような海洋の特性を踏まえた、未然防
止先や保全対策が求められる。そうした観点も含め、以下に海洋環境モニタリング調査が
今後取り組むべき課題をとりまとめた。
(1)新たに汚染が懸念される物質の監視
PCB やダイオキシン類など残留性有機汚染物質(POPs)は、2004 年5 月に発効したPOPs
条約により、その生産・使用の廃絶や排出削減、適正処理等の対策が国際レベルで推進
されている。一方、現在流通・利用している化学物質の中にも既存のPOPs と類似の物理
化学性を有し、地球規模での汚染拡大や影響が懸念される物質群(POPs 候補物質)があ
り、2009 年5 月に開催された第4 回締約国会議においてPBDE(4〜7 臭素化体)やPFOS
等の物質が新たな対象物質となった。POPs 条約では、地球規模での環境モニタリングデ
ータをもとに、6 年ごとに条約の有効性評価が行われることとなっており、それに資する
データを集積するために、対象物質について長期的な監視が必要である。
(2)越境汚染に対応した調査の実施
近隣諸国の経済発展に伴い、これらの国々から海洋を通じた越境汚染の増大が懸念さ
れる。そのため、近隣諸国からの汚染物質の流入の早期発見に資する調査を実施すると
ともに、国際協力の枠組みを活用しながら、各国のモニタリングデータを入手し比較検
討することが必要である。
(3)投入処分規制の枠組みの変更に対応した調査の実施
海洋汚染防止法の一部改正に伴い、廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度が新設され、
投入処分されているものの種類、量、位置を事前に正確に把握することが可能となった。
また、排出事業者による監視報告が義務付けられ、大量に投入処分される廃棄物につい
ては排出事業者によるフィールド調査が実施される見込みである。今後も継続的な投入
処分が実施される海域について、排出事業者による監視報告の妥当性、すなわち海洋環
境の汚染や影響を未然に防ぐモニタリングシステムの構築が必要である。
(4) CO2 海底下地層貯留の海洋環境への影響の監視
ロンドン条約96 年議定書附属書?改正案の採択により、CO2 海底下地層貯留が可能と
なった。わが国において、今後、実用化に向け沿岸域海底下における実証試験が実施さ
れる見込みである。CO2 海底下地層貯留の海洋環境への影響防止に向けて、海洋汚染防止
法に基づき廃棄物の海洋投入処分と同様の許可発給の枠組みが構築されており、今後実
際の事業実施段階における事業者による監視報告の妥当性、すなわち海洋環境への著し
い影響が生じていないことを国として検証することが必要である。
(5)特定汚染海域(ホットスポット)の継続監視
これまでの調査で明らかとされた紀伊水道周辺海域の堆積物中のPCB、紀伊・四国沖
の堆積物中の有機スズ化合物、日本海西部の堆積物中のブチルスズ化合物について、継
続的な監視を実施する必要がある。加えて、このような人為的汚染の事態を把握するた
めに、未調査海域についても適宜モニタリングを行う必要がある。
(6)オールジャパン体制での海洋環境の評価の実施
海洋環境の評価は近年、エコシステム・アプローチの観点から統合アセスメントを実
施する方向に向かっている。例えば英国では、関係省庁が協力してナショナルレポート
(Defra, 2005)を作成している。
わが国では2007 年7 月に海洋基本法が施行され、総理大臣を本部長とする総合海洋政
策本部が内閣に設置された。海洋基本計画が策定され、生態系、海洋汚染物質等の海洋
環境に関する科学的知見の充実を図ることや、海洋調査の推進が盛り込まれた。今回は、
環境省の海洋環境モニタリング調査の結果と他の既存の知見等も踏まえ海洋汚染に係る
評価を実施したが、今後、関係省庁が協力して、海洋生物や生息地のリスク評価、乱獲
等による水産資源への影響、気候変動に伴う海洋生態系への影響等も含めた、日本周辺
の海洋環境の包括的な評価の実現に向けて進んでいくことが望ましい。
(7)定期的な海洋環境の評価の実施
海洋環境モニタリング調査はおおむね5〜8 年で日本周辺海域の調査を実施する計画で
あり、2008 年度からフェーズ3 に移行している。各フェーズごとに、それまでに得られ
たデータに加え、国内外の関連するモニタリングデータを用いて、海洋環境の現状や政
策の効果等について定期的な評価を実施することにしている。
その結果を、わが国の海洋環境保全のための施策の立案・見直しに活かすと同時に、
NOWPAP のリージョナルアセスメントやGMA(地球海洋アセスメント)のグローバルア
セスメント等に活用していく。
海洋の連続性や大気を経由した広域の汚染の広がりを考慮すれば、海洋環境の保全を各
国が単独で実施するだけでは不十分であり、各国が協調して取り組んでいく必要があると
の認識が広まっている。NOWPAP、POPs 条約、GMA などの海洋環境保全のための国際協
調の枠組みを十分に活用しながら、海洋環境モニタリング調査をさらに充実させることに
より、わが国周辺海域を含む海洋環境の保全に大きく貢献していきたいと考えている。
4. 参考文献
磯野直秀(1975):化学物質と人間−PCB の過去・現在・未来.中央公論社.
宇野木早苗、久保田雅久(1996):海洋の波と流れの科学.東海大学出版会.
小城春雄・福本由利(2000):海洋表層浮遊,および砂浜海岸漂着廃棄プラスチック微小粒子のソーティング方法.北海道大學水産學部研究彙報51(2),71-93.
奥田啓司・中田典秀・磯部友彦・西山肇・真田幸尚・佐藤太・高田秀重(2000):東京湾堆積物中の環境ホルモン物質−過去50 年間の歴史変遷−.沿岸海洋研究37(2),97-106.
海上保安庁ホームページ(2009 年アクセス)海水温・海流の知識.
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/kaikyo/knowledge/index.html
環境庁(1998):海洋環境モニタリング調査指針等作成調査.(指針部分は、環日本海環境協力センター編(2000):海洋環境モニタリング指針.大蔵省印刷局.として市販されている。)
環境省(2005):ダイオキシン2005.関係省庁共通パンフレット.
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph/2005.pdf
環境省(2007):平成18 年度化学物質と環境.
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2006/shosai.html
環境省(2008a):ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー).
http://www.env.go.jp/air/report/h20-08/
環境省(2008b):平成19 年度ダイオキシン類に係る環境調査結果.
http://www.env.go.jp/air/report/h20-06/
環境法令研究会(2004):環境六法(平成16 年版).中央法規出版株式会社.
才野敏郎(1995)栄養塩と生物活動.月刊海洋,号外No.8,20-27.
ダイオキシン対策関係閣僚会議(1999)ダイオキシン対策推進基本指針.
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/law/kihonsisin.html
中西準子・堀口文男(2006):トリブチルスズ,詳細リスク評価書シリーズ8.丸善.
日本プラスチック工業連盟HP(2008 アクセス):世界のプラスチック統計.
http://www.jpif.gr.jp/5topics/conts/world2_c.htm
PCB 廃棄物処理事業評価検討会(2003):PCB 廃棄物処理事業評価検討会〜中間とりまとめ〜.
http://www.env.go.jp/recycle/poly/kento_r/index.html
益永茂樹(2004):東京湾のダイオキシン類汚染の変遷.海洋と生物,26(5),403-409.
益永茂樹・姚元・高田秀重・桜井健郎・中西準子(2001):東京湾のダイオキシン汚染,組成と汚染源推定.地球化学,35,159-168.
文部科学省国立天文台編(2002):理科年表CD-ROM 2002.丸善株式会社.
Defra (2005): Charting progress: an integrated assessment of the state of UK seas.
Teuten EL, Saquing JM, Knappe DRU., Barlaz MA, Jonsson S, Bjorn A, Rowland SJ, Thompson
RC, Galloway TS, Yamashita R, Ochi D,Watanuki Y, Moore C, Viet PH, Tana TS, Prudente
M, Boonyatumanond R, Zakaria MP, Akkhavong K, Ogata Y, Hirai H, Iwasa S, Mizukawa K,
Hagino Y, Imamura A, Saha M, Takada H (2009):Transport and release of chemicals from
plastics to the environment and to wildlife.Philosophical Transactions of The Royal Society B 364 (1526), 2027-2045.
海洋環境モニタリング調査の結果は下記に掲載している。
http://www.env.go.jp/earth/kaiyo/monitoring.html
海洋環境モニタリング調査のデータは下記よりダウンロード可能。
http://www-gis4.nies.go.jp/kaiyo/
―――――――――――――――――――――――――
環境省地球環境局環境保全対策課
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
TEL:03-3581-3351(代表)(内線6748)
03-5521-8245(直通)
FAX:03-3581-3348
http://www.env.go.jp
―――――――――――――――――――――――――
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14427&hou_id=11688
「日本周辺海域における海洋汚染の現状(海洋環境モニタリング調査結果(1998〜2007年度))」の発表について
環境省が1998年度から毎年実施している「海洋環境モニタリング調査」の結果を中心として、日本周辺海域の沿岸域から沖合域における、主として有害化学物質による汚染の現状を整理し、学識経験者による評価を踏まえ、「日本周辺海域における海洋汚染の現状(海洋環境モニタリング調査結果(1998〜2007年))」として取りまとめました。
1 海洋環境モニタリング調査の概要
陸域起源の汚染の把握を目的とする、内湾や沿岸域から沖合域にかけての汚染物質分布や濃度勾配の調査と、海洋投棄による汚染の把握を目的とする、海水、堆積物、海洋生物の汚染状況を把握する調査を実施。具体的な調査項目等は、以下のとおり。
○海水、堆積物について、重金属類のほかPOPs条約対象物質であるPCBやダイオキシン類、有機スズ化合物等を調査。
○沿岸から沖合域に分布する底生生物群集の状況及び5種類の海洋生物(イガイ類、底生性サメ類、イカ類、タラ類、甲殻類)により、PCB、ダイオキシン類等の汚染物質の蓄積状況を調査。
○浮遊性プラスチック類の調査
2 結果概要
○重金属類、PCB、ダイオキシンともに沿岸域の堆積物から検出されており、大都市圏からの負荷が沿岸域に影響していることが示唆された。また、PCB、ダイオキシンについては沖合域の堆積物でも低レベルながら検出された。 ○紀伊水道周辺海域堆積物から比較的高濃度のPCBが、紀伊・四国沖及び日本海西部海域の堆積物からバックグランドより高い濃度の有機スズ化合物が検出された。
○一部の沿岸域において、貧酸素化に起因する底生生物の組成の変化が観測されたが、有害物質との関係は認められなかった。また、海洋生物体内のダイオキシン類及びPCBの濃度は有意な減少傾向を示していないことが分かった。 ○沖合域までプラスチック類が分布していることが明らかになった。 以上により、いずれの海域においても、人の健康に影響を及ぼすおそれはないと判断しているものの、人為的な影響が沿岸域から沖合域まで及んでいると言える。
3 今後の調査予定
海洋生態系保全を含む海洋環境保全の観点から、今後も引き続き海洋環境モニタリングを定期的に実施し、汚染状況の監視を続けていくことにしている。また、新たにPOPs条約の対象物質として追加されるPFOS等の監視や紀伊水道周辺海域等比較的高濃度の汚染が見つかった海域での継続監視等を行っていく必要がある。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11688
日本周辺海域における海洋汚染の現状(海洋環境モニタリング調査結果(1998〜2007 年度))(概要版)
平成2 1 年1 0 月2 0 日
環境省地球環境局環境保全対策課
環境省においては、1998 年度から我が国の排他的経済水域の環境保全のため、海洋環境
モニタリング調査を開始した。1998〜2007 年度の10 年間において、3〜5年で一巡する
ことを前提とした調査の二巡の調査(フェーズ1、フェーズ2)が終了したところである。
これを受け、日本周辺海域の海洋環境の実態についての総合的な評価と国際的にも活用
されるよう日本周辺海域の海洋環境の現状についての積極的な情報提供を行うことを目的
とし、調査の結果を中心として、日本周辺海域の沿岸域から外洋域における、有害化学物
質による汚染の現状の整理及び評価を行い、ステータスレポートとして取りまとめた。今
回これを公表するもの。
公表内容の概要については、以下のとおり。
(1)調査概要
陸域起源の汚染を対象とし、特に大きな汚染負荷が存在すると考えられる内湾や沿岸
域からその沖合域にかけての汚染物質の分布や濃度勾配を把握する調査と、海洋投棄によ
る汚染を対象とし、投入処分?・?海域(旧B・C 海域)において、海水、堆積物、海洋生
物の汚染状況を把握する調査を実施している。また、従来からの人の健康保護あるいは生
活環境の保全という観点に加え、海洋生態系を保全するという観点から、生態濃度調査に
加え生物群集調査も実施している。
本モニタリング調査の特徴は以下の通りである。
? 沿岸域のみならず、沖合域の水深4000m 級の海域において、海水(栄養塩および
重金属類は各層採水)、堆積物、底生生物群集、浮遊性プラスチック類の調査を実施。
? 従来の汚染物質である重金属類の他、POPs 条約対象物質であるPCB やダイオキ
シン類、有機スズ化合物等を対象としている。
? 沿岸域から沖合域に分布する5 種類の海洋生物(イガイ類、底生性サメ類、イカ
類、タラ類、甲殻類)により、海洋生物体内の汚染物質を調査している。
? 定期的な調査に加えて、その結果検出された高濃度の汚染に対応した詳細調査を
実施している。
(2)調査結果と評価
調査結果概要とその評価を次表に示す。
表日本周辺海域の海洋環境の評価結果
評価 項目 現状の評価施策の効果と今後のモニタリング
陸域起源の汚染堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度ダイオキシン類
・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間において一部の海域・生物種では減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
・ダイオキシン特措法(1999 年)等により、近年の主要な排出源である焼却施設に由来する排出量は大幅に減少したものの、難分解性および高蓄積性のため、過去に放出されたものの影響が継続している。
・POPs 条約(2004 年発効)により国際的な削減が進められており、近隣諸国からの越境汚染も含め、今後も継続監視が必要である。
PCB
・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間における海洋生物体内の濃度は、統計的に有意な減少傾向を示していない。
・化審法によりPCB の製造・使用・輸入が1974 年に原則禁止されたことに伴い、環境中のPCB 濃度は減少したものの、近年はその傾向が緩やかになっている。
・PCB 特措法によるPCB 廃棄物の処理が2004 年より開始されたことに伴い、環境中への流出は減少しつつあると考えられるものの、難分解性よび高蓄積性のため、その効果が堆積物や海洋生物に濃度減少として現れるには至っていない。
・POPs 条約において国際的な削減が進められており、近隣諸国からの越境汚染も含め、今後も継続監視が必要である。
ブチルスズ化合物
・主として外国船舶の航行に由来すると考えられる負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間において一部の海域・生物種について減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
・化審法による規制(1988〜1990 年)および自主規制に伴い、開放系用途の出荷量は減少したと推定されており、その結果、海洋生物体内の濃度は減少した。
近年におけるその減少は緩やかになっており、汚染の解消にはしばらく時間がかかると考えられる。
・AFS 条約が2008 年に発効し、これに伴い、わが国に入港する外国船舶に対し有機スズ化合物を含む船底防汚塗料の使用が禁止された。
重金属類
・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。
・わが国に由来する汚染は減少した一方、近隣諸国の経済発展に伴う越境汚染の増大が懸念され、それに合域においては人為的負荷が認められるレベルではない。
・一部の沿岸域においては、貧酸素環境に起因するメイオベントス群集の組成の変化が観測された。一方、有害化学物質汚染とメイオベントス群集の個体数や組成の変化との関係は認められなかった。
・わが国周辺の4000m 級までの海域におけるメイオベントス群集のベースラインデータが得られた。今後、その経時的変化を把握し、底生生物群集への影響を監視する。
栄養塩類
・一部の沿岸域では陸域からの負荷の影響が認められたが、その影響は沖合域まで広がっていなかった。
・今後もモニタリングを継続することが必要であるが、水質総量規制を含む排水規制により、負荷は削減されており、今後頻度削減の検討が可能である。
プラスチック類
・沖合域までプラスチック類が分布していることが明らかとなった。一旦環境中に流出したプラスチック類は容易には分解されず、長期にわたる生物への潜在的な影響が懸念される。
・近年、国内の削減方策の検討や、NOWPAP における各国の連携が図られるようになった。プラスチック生産量は世界では増加傾向にあり、これらを注視することが必要である。
海洋投棄由来の汚染・赤泥の投入処分点においては、許可申請時の事前環境影響評価で想定された範囲内で底生生物群集の個体数がバックグラウンドより減少していた。それ以外の投入処分地点においては、適正な投入処分に由来すると考えられる底質あるいは水質への特段の影響は認められなかった。
・わが国の投入処分に対する環境保全対策には、一定の効果が確認された。さらに海洋投入処分に係る許可制度の新設(2007 年)により、今後著しい汚染が生じる可能性は低いものの、引き続き、法に基づく投入処分の適切性を確認することが重要である。
特定の汚染海域(ホットスポット)の発見
・限られた調査の中で、底質より沖合域としては高い濃度の汚染を検出した。これらは人為的な影響であると判断された。いずれも人の健康に影響を及ぼすレベルではないと判断されたものの、海洋環境保全の観点から注視すべきものである。
・これまでに発見されたホットスポットについては継続的な監視を行うとともに、このような人為的汚染を防止するために、未調査海域についても適宜モニタリングを実施する必要がある。
(3)ホットスポットについて
海洋環境モニタリングにより、以下の三つの海域において沖合域の堆積物としては高い濃度の汚染が明らかとなった。
(1)紀伊水道周辺海域
紀伊水道周辺海域において堆積物からバックグラウンドよりも高濃度のPCB を検
出した。調査の結果、海底付近にPCB 負荷源が存在しており、1970 年前後から少
なくとも近年まで継続的な負荷があったと考えられる。また、負荷源は単一の性状
のものではない可能性が高いことを明らかにした。
(2)紀伊・四国沖
紀伊・四国沖の投入処分?海域および?海域(水深4000〜4500m 程度)において、
堆積物から高濃度のブチルおよびフェニルスズ化合物を検出した。
(3)日本海西部
日本海西部の投入処分?海域を中心とした広範囲の海域において、堆積物から高
濃度のブチルスズ化合物を検出した。
いずれの海域においても、人の健康に影響を及ぼすおそれはないと判断している
ものの、人為的な影響が沖合域に及んでいると言え、海洋生態系保全を含む海洋環
境保全の観点から、今後も引き続き監視を続けていくことが必要である。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14426&hou_id=11688
日本周辺海域における海洋汚染の現状
―主として海洋環境モニタリング調査結果(1998〜2007 年度)を踏まえて―
2009 年10 月
環境省
目次
1. 目的...........................................................1
2. 海洋環境モニタリング調査の概要....................2
2.1. 日本周辺の海域と海流............................2
2.2. 海洋環境モニタリング調査の概要..............4
3. 海洋環境の総合評価...................................5
3.1. 陸域起源の汚染の影響...........................8
3.1.1. 堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度....8
3.1.2. 底生生物群集への影響.....................17
3.1.3. 栄養塩類.........................................18
3.1.4. プラスチック類の汚染.........................18
3.2. 投入処分に起因する汚染の影響...............21
3.3. 特定の汚染海域(ホットスポット)の発見......23
3.4. 今後の対策に向けて................................24
4. 参考文献.....................................................26
海洋環境モニタリング調査検討会
検討員(敬称略、50 音順)
石坂丞二長崎大学水産学部教授
小城春雄北海道大学水産学部名誉教授
白山義久京都大学フィールド科学教育研究センター長
田辺信介愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授
中田英昭長崎大学大学院生産科学研究科長(座長)
西田周平東京大学海洋研究所浮遊生物分野教授
野尻幸宏独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター副センター長
二ツ町悟海上保安庁海洋情報部環境調査課海洋汚染調査室長
牧秀明独立行政法人国立環境研究所
水土壌圏環境研究領域海洋環境研究室主任研究員
注:検討員および所属は2009 年3 月時点のもの
本報告書の作成にあたっては、上記検討員の方々にご協力いただいた。
1. 目的
国連海洋法条約が1996 年7 月に発効したことを受け、わが国は排他的経済水域の環境保
全に責任を負うこととなり、これに対処するため環境省は海洋環境モニタリング調査検討
会(座長:中田英昭長崎大学教授)の指導の下、「海洋環境モニタリング指針」(環境庁,
1998)に基づく新たなモニタリング(海洋環境モニタリング調査)を1998 年度に開始した。
本モニタリングが対象としている海域は広大であることから、当該調査海域を3〜5 年で
一巡することを原則とした計画を立て、1998〜2007 年度の10 年間において、二巡の調査(フ
ェーズ1、フェーズ2)が終了したところである。同モニタリングでは、日本周辺海域を一
巡するごとに、海洋環境の実態について総合的な評価を行うこととしている。
一方、近年、北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)や地球海洋アセスメント(GMA)
等において、地域的、世界的に海洋環境の現状をとりまとめたステータスレポートが作成
されており、広域的な情報収集が活発化している。わが国においても、海洋環境の現状に
ついて積極的に情報提供を行い、国際的な貢献を果たすべきと考えられる。
上記の状況を踏まえ、ここでは、海洋環境モニタリング調査の結果を中心に、日本周辺
の沿岸から外洋域における、主として重金属類、PCB、ダイオキシン類等の有害化学物質に
よる汚染の現状を解析・評価し、ステータスレポートとしてまとめた。
2. 海洋環境モニタリング調査の概要
2.1. 日本周辺の海域と海流
わが国は四方を海で囲まれており、東側には海洋全体のほぼ半分を占める太平洋(平均
水深は4,282 m)がある。また、わが国周辺の沿海として、東シナ海、日本海、オホーツク
海がある。東シナ海は広い陸棚を有し、最大水深は2,719 m と深いものの、平均水深は188
m と極めて浅い海である。一方、日本海は最大水深3,796m、平均水深1,350 m と深くて閉
鎖的な海域である。オホーツク海の最大水深は3,372 m、平均水深は838 m であり、東シナ
海と日本海の中間的な性格を有しており、沿岸に沿って大陸棚が発達している(文部科学
省, 2002)。以上のように、わが国周辺海域は、一部に比較的発達した陸棚があるものの、
全体的にその面積は狭く、深い海に囲まれ、内湾以外に浅い海をほとんど持たない特徴を
有する(図2.1)。
日本周辺の海域の主な海流としては、暖流である黒潮及び対馬海流、寒流の親潮及びリ
マン海流がある(図2.2)。黒潮は、輸送する水の量が毎秒5,000 万トンにも達し、高温・
高塩・貧栄養の海水である。プランクトンが少ないため、透明度は高く、世界でも有数の
流れの強い海流として知られている。親潮は、オホーツク海やベーリング海の冷たい水が
起源となっており、栄養分を豊富に含んでいる。プランクトンが多いため、透明度は比較
的低い。この黒潮と親潮との潮境*は日本東方の海域に位置しており、水温が高く、栄養分
が豊富で魚類が多く集まることから、世界有数の漁場となっている(海上保安庁HP,2009)。
* 黒潮と親潮などのように温度や性質の違った水塊間の境目をいう。
※水深は200m ピッチ
図2.1 日本周辺の海底地形(海洋情報研究センターのデータより作成)
W:暖水、C:冷水
?黒潮、?黒潮続流、?黒潮反流、?対馬海流、?津軽暖流、?宗谷暖流、?親潮、?リマン海流
図2.2 日本周辺の主な海流(宇野木・久保田, 1996)
2.2. 海洋環境モニタリング調査の概要
日本国内では、行政、研究所、大学等の関係機関により様々なモニタリングが行われて
いる。環境省の海洋環境モニタリング調査の他、同省が実施している化学物質環境実態調
査、公共用水域調査、広域総合水質調査、及び他省庁としては、海上保安庁の海洋汚染調
査、気象庁の大気・海洋環境観測等があげられる。
海洋環境モニタリング調査では、発生源に着目し、陸域起源の汚染を対象とした調査と
海洋投棄による汚染を対象とした調査を実施している。
陸域起源の汚染を対象とした調査は、特に大きな汚染負荷が存在すると考えられる内湾
や沿岸域から、その沖合にかけての汚染物質の分布や濃度勾配を把握することで、陸域起
源の汚染負荷が海洋環境に及ぼす影響の把握を目的としている。
廃棄物等の海洋投入処分による汚染を対象とした調査は、近年において相当量の処分が
実施されている投入処分?・?海域(旧B・C 海域)において、海水、堆積物、海洋生物の
汚染状況を把握することを目的としている。
ヒトの健康保護あるいは生活環境の保全という従来からの観点に加え、海洋生態系を保
全するという観点から、環境基準よりもはるかに低い汚染物質濃度であっても、海洋生物
や海洋生態系に影響を及ぼしている可能性があることを考慮し、生体濃度調査および生物
群集調査を実施している。
本モニタリング調査の特徴は以下のとおりである。
? 沿岸域のみならず、沖合域の水深4000m 級の海域を対象として、海水(栄養塩および重金属類は各層採水)、堆積物、海洋生物、底生生物群集、浮遊性プラスチック類等に関する包括的な調査を実施している。
? 重金属類に加えて、POPs 条約対象物質であるPCB やダイオキシン類、有機スズ化合物など多様な有害物質を対象に含めている。
? 行政上規制あるいは要監視対象にはなっていない、主に下水汚泥に由来すると考えられるコプロスタノールや直鎖アルキルベンゼン等のマーカー物質も併せて測定を行っている。
? 沿岸域から沖合域にかけて分布する5 種類の海洋生物(イガイ類、底生性サメ類、イカ類、タラ類、甲殻類)を供試することにより、海洋生物体内のPCB やダイオキシン類等の汚染物質濃度の包括的なモニタリングを実施している。
? 定期的な調査に加え、その過程で判明した高濃度汚染に即応した詳細調査を実施している。
? 各測点における各測定対象物の過去数年間における変遷が把握されている。
3. 海洋環境の総合評価
日本周辺海域の海洋環境の現状および近年10 年間の傾向について、「海洋環境モニタリング調査」の結果を中心に、既存の研究調査結果も加味し、専門家による総合評価を行った。その概要は表3.1 に示した通りである。詳細を以下に述べる。
表3.1 日本周辺海域の海洋環境の評価結果(1)
評価項目現状の評価施策の効果と今後のモニタリング
陸域起源の汚染堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度ダイオキシン類
・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間において一部の海域・生物種では減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
・ダイオキシン特措法(1999 年)等により、近年の主要な排出源である焼却施設に由来する排出量は大幅に減少したものの、難分解性および高蓄積性のため、過去に放出されたものの影響が継続している。
・POPs 条約(2004 年発効)により国際的な削減が進められており、近隣諸国からの越境汚染も含め、今後も継続監視が必要である。PCB ・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間における海洋生物体内の濃度は、統計的に有意な減少傾向を示していない。
・化審法によりPCB の製造・使用・輸入が1974 年に原則禁止されたことに伴い、環境中のPCB 濃度は減少したものの、近年はその傾向が緩やかになっている。
・PCB 特措法によるPCB 廃棄物の処理が2004 年より開始されたことに伴い、環境中への流出は減少しつつあると考えられるものの、難分解性よび高蓄積性のため、その効果が堆積物や海洋生物に濃度減少として現れるには至っていない。
・POPs 条約において国際的な削減が進められており、近隣諸国からの越境汚染も含め、今後も継続監視が必要である。
ブチルスズ化合物
・主として外国船舶の航行に由来すると考えられる負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。沖合域堆積物中の濃度レベルは低いが、依然として検出されている。
・最近10 年間において一部の海域・生物種について減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
・化審法による規制(1988〜1990 年)および自主規制に伴い、開放系用途の出荷量は減少したと推定されており、その結果、海洋生物体内の濃度は減少した。近年におけるその減少は緩やかになっており、汚染の解消にはしばらく時間がかかると考えられる。
・AFS 条約が2008 年に発効し、これに伴い、わが国に入港する外国船舶に対し有機スズ化合物を含む船底防汚塗料の使用が禁止された。この効果を今後継続的に検証する必要がある。
表3.1 日本周辺海域の海洋環境の評価結果(2)
評価項目現状の評価施策の効果と今後のモニタリング
陸域起源の汚染堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度重金属類・大都市圏からの負荷が沿岸域の堆積物に影響を及ぼしている。元来、自然に存在するものであり、沖合域においては人為的負荷が認められるレベルではない。
・わが国に由来する汚染は減少した一方、近隣諸国の経済発展に伴う越境汚染の増大が懸念され、それに対応した調査の実施が必要である。
底生生物群集への影響
・一部の沿岸域においては、貧酸素環境に起因するメイオベントス群集の組成の変化が観測された。一方、有害化学物質汚染とメイオベントス群集の個体数や組成の変化との関係は認められなかった。
・わが国周辺の4000m 級までの海域におけるメイオベントス群集のベースラインデータが得られた。今後、その経時的変化を把握し、底生生物群集への影響を監視する。
栄養塩類
・一部の沿岸域では陸域からの負荷の影響が認められたが、その影響は沖合域まで広がっていなかった。
・今後もモニタリングを継続することが必要であるが、水質総量規制を含む排水規制により、負荷は削減されており、今後、頻度削減の検討が可能である。
プラスチック類
・沖合域までプラスチック類が分布していることが明らかとなった。一旦環境中に流出したプラスチック類は容易には分解されず、長期にわたる生物への潜在的な影響が懸念される
・近年、国内の削減方策の検討や、NOWPAP における各国の連携が図られるようになった。プラスチック生産量は世界では増加傾向にあり、これらを注視することが必要である。
海洋投棄由来の汚染
・赤泥の投入処分点においては、許可申請時の事前環境影響評価で想定された範囲内で底生生物群集の個体数がバックグラウンドより減少していた。それ以外の投入処分地点においては、適正な投入処分に由来すると考えられる底質あるいは水質への特段の影響は認められなかった。
・わが国の投入処分に対する環境保全対策には、一定の効果が確認された。さらに海洋投入処分に係る許可制度の新(2007 年)により、今後著しい汚染が生じる可能性は低いものの、引き続き、法に基づく投入処分の適切性を確認することが重要である。
特定の汚染海域(ホットスポット)の発見
・限られた調査の中で、底質より沖合域としては高い濃度の汚染を検出した。これらは人為的な影響であると判断された。いずれも人の健康に影響を及ぼすレベルではないと判断されたものの、海洋環境保全の観点から注視すべきものである。
・これまでに発見されたホットスポットについては継続的な監視を行うとともに、このような人為的汚染を防止するために、未調査海域についても適宜モニタリングを実施する必要がある。
3.1. 陸域起源の汚染の影響
3.1.1. 堆積物・海洋生物中の汚染物質濃度
(1) 総論
大きな汚染負荷が存在すると考えられる内湾や沿岸域から、その沖合にかけての汚染
物質の分布や濃度勾配を把握することで、陸域起源の汚染負荷が海洋環境に及ぼす影響
を把握することができる。堆積物中の汚染物質濃度のうち、内湾・沿岸域で高く沖合域
で低い傾向を示したものは以下のとおりである。PCB やブチルスズ化合物などの人工化
学物質は、本来自然には存在しない物質であり、ブチルスズ化合物を除いては、陸域か
らの汚染負荷の影響を示していると考えられる。
仙台湾〜沖合域:カドミウム、総水銀、PCB
東京湾〜沖合域:カドミウム、総水銀、鉛、PCB、ダイオキシン類、ブチルスズ化合物
伊勢湾〜沖合域:カドミウム、PCB
大阪湾〜沖合域:総水銀、鉛、PCB、ダイオキシン類、ブチルスズ化合物
富山湾〜沖合域:鉛、PCB、ダイオキシン類
ブチルスズ化合物については主要な用途は防汚塗料であり、陸域起源というよりは、
船舶の航行量が多いことに由来するものと推察される。これらを総合すると、大都市あ
るいは大工業地帯からの汚染負荷が沿岸域に影響を及ぼしていると考えられる。
これら物質の沖合域における濃度は低いものの、検出限界値以上の濃度で検出されて
おり、沿岸域の環境のみならず、沖合域においても影響を及ぼしている可能性がある。
以下、汚染の動向が注目されるものとして、ダイオキシン類、PCB、ブチルスズ化合物
をとりあげ、海洋環境モニタリングのデータに基づき、その汚染の現状と最近10 年間の
トレンドについて概説した上で、他のモニタリングや研究の結果も踏まえて、これまで
の経緯、長期トレンド、施策とその効果(評価)について述べる。
(2) ダイオキシン類
1)海洋環境モニタリングの調査結果
海洋環境モニタリング調査のデータによれば、堆積物中のダイオキシン類は大都市圏
を背後に抱える内湾・沿岸域で高く、沖合域で低いという傾向を示している(図3.1)。
このことは、陸域からの負荷が沿岸域に集積していることを示唆している。
海洋生物中のダイオキシン類については、一部の海域・生物種(東京湾のサメ類(肝
臓、筋肉)、黒潮域のイカ類(肝臓)、親潮域のイカ類(筋肉)、日本海域のタラ類(肝臓))
について統計的に有意な減少傾向が認められたものの(p<0.05)、全体としては明瞭な減
少傾向は認められない(図3.2)。
図3.1 表層堆積物中のダイオキシン類濃度の地理的分布(pg-TEQ/g dry wt)
図3.2 イカ類(肝臓)中のダイオキシン類濃度の経年変動(pg-TEQ/g wet wt)
2)これまでの施策の評価
わが国においては、ダイオキシン類の排出量のうち、特にPCDD 及びPCDF について
は、その約9 割が産業廃棄物の焼却時に排出されると推定されている(環境省,2005b)。
そこで、1997 年12 月から、大気汚染防止法や廃棄物処理法によって、焼却施設の煙突な
どから排出されるダイオキシン類の規制やごみ焼却施設の改善などの対策が進められて
きた。次いで1999 年3 月にダイオキシン対策推進基本指針が策定され、「今後4 年以内
に全国のダイオキシン類の排出総量を1997 年に比べ約9 割削減する」方針が打ち出され
た(ダイオキシン対策関係閣僚会議,1999)。また、ダイオキシン類対策特別措置法が1999
年7 月に成立、2000 年1 月に施行され、排出ガスおよび排出水に関する規制等が行われ
ている。
その結果、ダイオキシン類の総排出量は2007 年には1997 年から約96%減少した(環
境省,2008a)。これに伴い、排出量削減の効果が最も早く現れると考えられる大気中のダ
イオキシン類の濃度は急速に減少し、1997 年から2007 年の間に約92%減少した(環境
省,2008b)(図3.3)。その一方で、排出量削減の効果が現れるのが最も遅いと考えられ
る海洋生物中のダイオキシン類については、上述したとおり、一部の海域・生物種につ
いては減少傾向が認められたものの、全体としては明瞭な減少傾向を示していない。
図3.3 ダイオキシン類の排出総量と大気中濃度の推移
(環境省2008a;2008b より作成)
東京湾における柱状堆積物(1993 年に採取)の分析結果によると、ダイオキシン類濃
度の推移は、ダイオキシン類対策特別措置法が施行された2000 年以前の1970 年頃をピ
ークとして、その後減少している(図3.4;益永ら,2001)。東京湾の調査結果では、1960
年代〜1970 年代を中心として使用された農薬に不純物として含まれていたダイオキシン
類の影響が大きいとする見解が報告されている(益永,2004)。
柱状堆積物の平均年代
PCDD/DFs(ng/g-dry)
図3.4 東京湾の柱状堆積物におけるダイオキシン類濃度の変遷(益永ら,2001 を改変)
ダイオキシン類は環境中で分解しにくく(難分解性)、食物連鎖を通して生物体内に濃
縮される(高蓄積性)ため、過去に放出されたダイオキシン類の影響が現在でも継続し
ており、近年の主要な排出源である焼却施設に由来するダイオキシン類の排出量が減少
しても、海洋生物体内の濃度は速やかには減少しない可能性がある。
(3) PCB
1)海洋環境モニタリングの調査結果
海洋環境モニタリング調査のデータによれば、堆積物中のPCB は大都市圏を背後に抱
える内湾・沿岸域で高く、沖合域で低いという傾向を示している(図3.5)。このことは、
そのような海域においては、陸域からの負荷が沿岸域に集積しやすいことを示唆している。
海洋生物中のPCB については、最近10 年間において統計的に有意な減少傾向は認めら
れていない(p>0.05)(図3.6)。
2)これまでの施策の評価
わが国におけるPCB の使用は1954 年に開始された後、年々増加し1970 年にピークを
迎えたが、1972 年に生産が中止され(図3.7)、1974 年に化審法の第一種特定化学物質に
指定されてその使用が原則禁止された。
東京湾奥における柱状堆積物(1993 年に採取)の分析結果(奥田ら,2000)によると、
PCB 濃度は1960 年代に急増し1970 年頃をピークに減少に転じており、その使用量の推
移とよく対応している(図3.8)。その一方で、PCB の生産は1972 年に中止されたにも関
わらず、1980 年代半ば以降1993 年までは、最高値の30%程度の濃度で推移している。
また、魚類および貝類のPCB 濃度(全国平均)は、1970 年代末から減少傾向にあるが(環
境省,2007)、2000 年代はほぼ横ばいの状態で推移している(図3.9)。
※値のない縦軸は凡例と同じスケール
図3.5 表層堆積物中のPCB 濃度の地理的分布(ng/g dry wt)
図3.6 底生性サメ類(肝臓)中のPCB 濃度の経年変動(ng/g wet wt)
図3.7 PCB 使用量の推移(磯野,1975 より作成)
図3.8 東京湾の柱状堆積物におけるPCB の鉛直分布(奥田ら,2000 を改変)
PCB類
生物(pg/g-wet)
貝類魚類
定量[検出]下限値(pg/g-wet)
図3.9 生物体内のPCB 濃度の長期的推移(環境省,2007 より作成)
PCB が化審法の第一種特定化学物質に指定された後、既に生産されたPCB やそれを含
む製品は回収・保管されることとなったが、回収されたPCB の処理はスムーズに進展し
なかった。一方、長期にわたるPCB 廃棄物の保管は、その不明・紛失をもたらしており
(PCB 廃棄物処理事業評価検討会,2003)、それに由来する環境へのPCB の流出が懸念されている。
POPs 条約においてPCB の適切な処理を2028 年までに行うことが義務づけされたこと
もあり、わが国では「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置
法」(PCB 特措法)が2001 年に成立し、2016 年7 月までにPCB 廃棄物の処理を終えると
いう目標のもと、2004 年12 月より、化学処理法による無害化処理が順次進められている。
PCB は環境中で分解しにくく(難分解性)、食物連鎖を通して生物体内に濃縮・蓄積しや
すい(高蓄積性)ため、PCB 廃棄物の処理に伴う環境中への流出量の低減が、堆積物や
海洋生物の濃度の減少として未だ現れるには至っていない。
(4) ブチルスズ化合物
1)海洋環境モニタリングの調査結果
海洋環境モニタリング調査によれば、堆積物中のブチルスズ化合物は大都市圏の内
湾・沿岸域で高く、沖合域で低いという傾向を示している(図3.10)。ブチルスズ化合物
の主要な用途は防汚塗料であり、これは陸域起源というよりは、船舶の航行量が多いこ
とに由来するものと推察される。なお、後述するように、わが国ではブチルスズ化合物
を含む防汚塗料の使用は既に禁止されていることから、主たる負荷源は外国船舶の航行
と考えられる。
海洋生物中のブチルスズ化合物については、一部の海域・生物種(仙台湾および富山
湾のイガイ類(軟体部)、東京湾および有明海のサメ類(肝臓))について統計的に有意
な減少傾向が認められたものの(p<0.05)、全体としては明瞭な減少傾向を示していない
(図3.11)。
2)これまでの施策の評価
ブチルスズ化合物は1960 年代から防汚塗料(船底塗料や漁網防汚剤)として広く使用
されてきたが、1980 年代半ばに、わが国において有機スズ化合物による海洋汚染が社会
問題となった。これに伴い、わが国では化審法において、1990 年1 月にブチルスズ化合
物のうちトリブチルスズオキシド(TBTO)が第一種特定化学物質に指定され、製造、使
用、輸入が原則禁止された。同年9 月にはその他のトリブチルスズ(TBT)化合物が第二
種特定化学物質に指定され、製造、輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ、製造、
輸入量が規制された。これと前後して、関連業界において防汚塗料の製造・使用が自主
規制された。TBT の推定開放系用途出荷量は1980 年代末をピークに急速に減少しており
(図3.12)、これは上記の規制の効果を示していると考えられる。
※値のない縦軸は凡例と同じスケール
図3.10 表層堆積物中のブチルスズ化合物濃度の地理的分布(ng/g dry wt)
図3.11 底生性サメ類(肝臓)中のブチルスズ化合物濃度の経年変動(ng/g wet wt)
図3.12 TBT の推定開放系用途出荷量(化学原料用を除く;TBT 基換算値)(中西・堀口,2006)
生物(ng/g-wet)
貝類魚類
定量[検出]下限値(ng/g-wet)
・幾何平均算出に際し、ndは検出下限値の1/2とした。
図3.13 生物体内のTBT 濃度の長期的推移(環境省,2007 より作成)
魚類および貝類のTBT 濃度は、環境省の化学物質環境実態調査が開始された1985 年か
ら長期的に減少する傾向を示している(図3.13; 環境省,2007)。これは、上記の政策の
効果が現れているものと考えられるが、その一方で、1998 年以降は減少が緩やかになっ
ている。また、海洋環境モニタリング調査の海洋生物体内の濃度についても、前述のと
おり、一部の海域・生物種について有意な減少傾向が認められたものの、全体としては
明瞭な減少傾向が見られなかった。これらの結果を総合的に解析すると、海洋生物体内
のトリブチルスズ化合物の汚染が解消するには、しばらく時間がかかると考えられる。
2008 年に、船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約(AFS 条約)が発効した。
これに伴い、わが国に入港する外国船舶に対し有機スズ化合物を含む船底防汚塗料の使
用が禁止されるため、海域への負荷は減少することが期待される。
3.1.2. 底生生物群集への影響
様々な人間活動の海洋環境への影響は、最終的に海洋生態系の変化という形で現れる
と考えられる。海洋環境モニタリングでは、そのような観点から、メイオベントス群集
の調査を実施した。その結果、水深最大5000m 程度までの海域におけるデータが蓄積さ
れた(図3.14)。
一部の内湾域においては、貧酸素環境に由来すると考えられるメイオベントス群集の
組成の変化が確認された。一方、有害化学物質汚染とメイオベントス群集の個体数や組
成の変化との関係は認められなかった。
現時点では今後の評価の基礎となるベースラインデータが得られた段階であり、さら
にデータが蓄積されれば、環境への影響の評価も可能になると考えられる。
※棒グラフは個体数、折れ線グラフは水深を示す。
図3.14 メイオベントスの個体数の分布(個体/10cm2)
3.1.3. 栄養塩類
主要な湾のうち陸域からの負荷が大きい東京湾及び大阪湾において、沿岸域では湾奥
の表層の値が高く、河川水に由来すると推測される陸域から水質への人為的負荷の影響
が認められた。一方、沖合域では表層で低く、中層にピークのある鉛直分布が認められ、
既存の知見(才野,1995)と同様の傾向を示していることから、沿岸域の負荷の影響は
沖合域まで広がってはいなかったことが確認された(図3.15)。
図3.15 東京湾(2002 年12 月)及び大阪湾(2003 年12 月)から沖合域にかけての硝酸態窒素(μM)の鉛直分布
3.1.4. プラスチック類の汚染
1)海洋環境モニタリングの調査結果
海洋環境モニタリング調査の結果から、沿岸域のみならず、沖合域においてもプラス
チック類が分布していることが明らかとなった(図3.16)。一部の海域では、沿岸域で高
く沖合域で低いデータが得られているが、そのような明瞭な傾向を示すデータは少ない。
また、時空間的に不均一性が大きく、局所的に、また調査年により分布個数の多い測点
見られた。
図3.16 2004〜2006 年度のプラスチック類の分布(千個/km2)
2)既存の知見と国際的な取組
レジンペレットやプラスチック破片は、海鳥などの海洋生物が誤飲することが知られ
ている。生物体内に取り込まれたレジンペレット等のプラスチック類から有害物質が溶
出し、生物体内のそれらの濃度が有意に増加していることも報告されている(Teuten et al.,
2009)。一旦環境中に流出したプラスチック類は容易には分解されないこと、日本周辺海
域の広範囲にわたってプラスチック類が分布していることから、長期にわたる生物への
潜在的な生物影響が懸念される。
小城・福本(2000)は、1994〜95 年に北海道南東部沿岸域にプラスチック粒子が平均
49 万個/km2(範囲0〜989 万個/km2)分布していたことを報告している。海洋環境モニ
タリング調査では、同一の測点でも調査年により分布個数が大きく異なっていることか
ら、このデータとの比較だけでは経年的な増加あるいは減少の傾向を判断することは困難である。
近年、海洋ゴミの国内における削減に向けた方策の検討が行われるとともに、NOWPAP
において海洋ゴミの流出防止、モニタリング、除去および処理のための行動計画(RAP
MALI)が日中韓ロにより策定されている。その一方で、世界におけるプラスチックの生
産量は増加傾向にあり(図3.17)、環境への負荷は今後増大する可能性がある。
図3.17 プラスチック生産量の推移(日本プラスチック工業連盟HP,2008 より作成)
3.2. 投入処分に起因する汚染の影響
わが国における廃棄物の海洋投入処分は、海洋汚染防止法及び廃棄物処理法により規制
されている。これにより、国際条約であるロンドン条約及びその「1996 年の議定書」(96
年議定書)に定める内容が担保されている。
2007 年4 月以前においてわが国では、廃棄物海洋投入処分海域として、A、B、C、F 海
域が設定されていた(図3.18)。それぞれの海域については以下に述べるような廃棄物が投
入処分可能なものとして定められている。なお、A 海域はB 海域に、B 海域はC 海域に包
含され、F 海域は実質的にすべての海域である。
A 海域(現在のI 海域(未設定))は、2007 年以前は有害性の大きい物質を固化した廃棄
物の投入処分海域であったが、実際には1981 年以降、このような廃棄物の投入処分は実施
されておらず、2007 年の海洋汚染防止法改正後には、投入処分が禁止されている。B 海域
(現在の?海域)に投入処分されていた廃棄物は、主として非水溶性無機性汚泥である。
具体的な廃棄物の品目としては赤泥や建設汚泥が挙げられる。C 海域(現在の?海域)では、
有機性の廃棄物が投入処分されていた。具体的な品目としては、し尿及びし尿浄化槽汚泥
や有機性汚泥、廃酸・廃アルカリ、動植物性残さ、家畜ふん尿等が挙げられる。F 海域(現
在の?海域)においては水底土砂の投入処分が可能とされていた。
海洋投入処分にあたっては、有害化学物質が混入する恐れのある廃棄物については判定
基準が定められており、この基準を満たしたものだけを投入処分することができる。旧海
洋汚染防止法においては、国が包括的な環境影響評価を実施して、海洋投入処分できる廃
棄物を定め、及び適切な排出海域を設定した。これに対して、現行の海洋汚染防止法は、
廃棄物の排出を行う個々の事業者に対して、国の指定する排出海域内にて具体的な排出場
所を選定し、事前の環境影響評価や事後の監視を実施することが義務付けられている。
これまでの海洋環境モニタリング調査の結果によれば、?海域では投入処分の影響は検
出されていない。また、?および?海域については、房総・伊豆沖合の?海域では、投入
点において赤泥に由来する物質が検出され、メイオベントスに対する影響が認められたも
のの事前の環境影響評価で想定された範囲内であり、他のほとんどの海域においては、法
に基づいた投入処分による影響は検出されなかった。その一方で、一部の投入処分海域に
おいては、原因が明らかでない汚染も検出されている。これは不法投棄による影響の可能
性もあり、その汚染源の把握が必要と考えられる(3.3 参照)。
2007 年4 月1 日以降は、96 年議定書に対応した海洋汚染防止法の一部改正に伴い、廃棄
物の海洋投入処分に係る許可制度が新設された。これに伴い、海洋環境に及ぼす影響に関
し、排出事業者による事前の評価が行われることとなった。このため、今後、著しい汚染
が生じる可能性は低いものの、今後も引き続き、法に基づいた投入処分が適切に実施され
る確認作業が必要である。
図3.18 海洋投入処分海域図(環境法令研究会,2004 より作成)
3.3. 特定の汚染海域(ホットスポット)の発見
海洋環境モニタリング調査により、以下の三つの海域において沖合域の堆積物としては
他の海域でみられない高濃度汚染が明らかとなった。
(
1)紀伊水道周辺海域
紀伊水道周辺海域において、堆積物からバックグラウンドよりも高濃度のPCB を検出
した。調査の結果、海底付近にPCB 負荷源が存在しており、1970 年前後から少なくとも
近年まで継続的な負荷があったと考えられる。また、負荷源は単一の性状のものではな
い可能性が高いことが分かった。
(2)紀伊・四国沖
紀伊・四国沖の投入処分?海域および?海域(水深4000〜4500m 程度)において、堆
積物から高濃度のブチルおよびフェニルスズ化合物が検出された。
(3)日本海西部
日本海西部の投入処分?海域を中心とした広範囲の海域において、堆積物から高濃度
のブチルスズ化合物が検出された。
いずれの海域においても、人の健康に影響を及ぼすおそれはないと判断されるものの、
これらの事例は人為的な影響が沖合域に及んでいることを示しており、海洋環境及び生態
系の保全の観点から、今後も引き続き監視を続けることが必要である。
これまでのモニタリング調査では、このように深海底における汚染が検出されており、
人為的な汚染を抑止する観点から、これまでに調査を行っていない海域も含めて広範囲に
わたるモニタリング調査を今後も実施していく必要がある。
3.4. 今後の対策に向けて
先に述べたとおり、ダイオキシン類では法規制によりこの10 年間で排出量が1/10 以下に
減少した。それに伴い、大気中の濃度は急速に減少したが、その一方で、海洋生物中の濃
度については一部に減少傾向が認められるものの、全体としては減少傾向が明瞭ではない。
このように、いったん海洋に流出した汚染物質は、規制の効果がなかなか現れにくいと
いう特徴がある。海洋汚染の防止に関しては、このような海洋の特性を踏まえた、未然防
止先や保全対策が求められる。そうした観点も含め、以下に海洋環境モニタリング調査が
今後取り組むべき課題をとりまとめた。
(1)新たに汚染が懸念される物質の監視
PCB やダイオキシン類など残留性有機汚染物質(POPs)は、2004 年5 月に発効したPOPs
条約により、その生産・使用の廃絶や排出削減、適正処理等の対策が国際レベルで推進
されている。一方、現在流通・利用している化学物質の中にも既存のPOPs と類似の物理
化学性を有し、地球規模での汚染拡大や影響が懸念される物質群(POPs 候補物質)があ
り、2009 年5 月に開催された第4 回締約国会議においてPBDE(4〜7 臭素化体)やPFOS
等の物質が新たな対象物質となった。POPs 条約では、地球規模での環境モニタリングデ
ータをもとに、6 年ごとに条約の有効性評価が行われることとなっており、それに資する
データを集積するために、対象物質について長期的な監視が必要である。
(2)越境汚染に対応した調査の実施
近隣諸国の経済発展に伴い、これらの国々から海洋を通じた越境汚染の増大が懸念さ
れる。そのため、近隣諸国からの汚染物質の流入の早期発見に資する調査を実施すると
ともに、国際協力の枠組みを活用しながら、各国のモニタリングデータを入手し比較検
討することが必要である。
(3)投入処分規制の枠組みの変更に対応した調査の実施
海洋汚染防止法の一部改正に伴い、廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度が新設され、
投入処分されているものの種類、量、位置を事前に正確に把握することが可能となった。
また、排出事業者による監視報告が義務付けられ、大量に投入処分される廃棄物につい
ては排出事業者によるフィールド調査が実施される見込みである。今後も継続的な投入
処分が実施される海域について、排出事業者による監視報告の妥当性、すなわち海洋環
境の汚染や影響を未然に防ぐモニタリングシステムの構築が必要である。
(4) CO2 海底下地層貯留の海洋環境への影響の監視
ロンドン条約96 年議定書附属書?改正案の採択により、CO2 海底下地層貯留が可能と
なった。わが国において、今後、実用化に向け沿岸域海底下における実証試験が実施さ
れる見込みである。CO2 海底下地層貯留の海洋環境への影響防止に向けて、海洋汚染防止
法に基づき廃棄物の海洋投入処分と同様の許可発給の枠組みが構築されており、今後実
際の事業実施段階における事業者による監視報告の妥当性、すなわち海洋環境への著し
い影響が生じていないことを国として検証することが必要である。
(5)特定汚染海域(ホットスポット)の継続監視
これまでの調査で明らかとされた紀伊水道周辺海域の堆積物中のPCB、紀伊・四国沖
の堆積物中の有機スズ化合物、日本海西部の堆積物中のブチルスズ化合物について、継
続的な監視を実施する必要がある。加えて、このような人為的汚染の事態を把握するた
めに、未調査海域についても適宜モニタリングを行う必要がある。
(6)オールジャパン体制での海洋環境の評価の実施
海洋環境の評価は近年、エコシステム・アプローチの観点から統合アセスメントを実
施する方向に向かっている。例えば英国では、関係省庁が協力してナショナルレポート
(Defra, 2005)を作成している。
わが国では2007 年7 月に海洋基本法が施行され、総理大臣を本部長とする総合海洋政
策本部が内閣に設置された。海洋基本計画が策定され、生態系、海洋汚染物質等の海洋
環境に関する科学的知見の充実を図ることや、海洋調査の推進が盛り込まれた。今回は、
環境省の海洋環境モニタリング調査の結果と他の既存の知見等も踏まえ海洋汚染に係る
評価を実施したが、今後、関係省庁が協力して、海洋生物や生息地のリスク評価、乱獲
等による水産資源への影響、気候変動に伴う海洋生態系への影響等も含めた、日本周辺
の海洋環境の包括的な評価の実現に向けて進んでいくことが望ましい。
(7)定期的な海洋環境の評価の実施
海洋環境モニタリング調査はおおむね5〜8 年で日本周辺海域の調査を実施する計画で
あり、2008 年度からフェーズ3 に移行している。各フェーズごとに、それまでに得られ
たデータに加え、国内外の関連するモニタリングデータを用いて、海洋環境の現状や政
策の効果等について定期的な評価を実施することにしている。
その結果を、わが国の海洋環境保全のための施策の立案・見直しに活かすと同時に、
NOWPAP のリージョナルアセスメントやGMA(地球海洋アセスメント)のグローバルア
セスメント等に活用していく。
海洋の連続性や大気を経由した広域の汚染の広がりを考慮すれば、海洋環境の保全を各
国が単独で実施するだけでは不十分であり、各国が協調して取り組んでいく必要があると
の認識が広まっている。NOWPAP、POPs 条約、GMA などの海洋環境保全のための国際協
調の枠組みを十分に活用しながら、海洋環境モニタリング調査をさらに充実させることに
より、わが国周辺海域を含む海洋環境の保全に大きく貢献していきたいと考えている。
4. 参考文献
磯野直秀(1975):化学物質と人間−PCB の過去・現在・未来.中央公論社.
宇野木早苗、久保田雅久(1996):海洋の波と流れの科学.東海大学出版会.
小城春雄・福本由利(2000):海洋表層浮遊,および砂浜海岸漂着廃棄プラスチック微小粒子のソーティング方法.北海道大學水産學部研究彙報51(2),71-93.
奥田啓司・中田典秀・磯部友彦・西山肇・真田幸尚・佐藤太・高田秀重(2000):東京湾堆積物中の環境ホルモン物質−過去50 年間の歴史変遷−.沿岸海洋研究37(2),97-106.
海上保安庁ホームページ(2009 年アクセス)海水温・海流の知識.
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/kaikyo/knowledge/index.html
環境庁(1998):海洋環境モニタリング調査指針等作成調査.(指針部分は、環日本海環境協力センター編(2000):海洋環境モニタリング指針.大蔵省印刷局.として市販されている。)
環境省(2005):ダイオキシン2005.関係省庁共通パンフレット.
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph/2005.pdf
環境省(2007):平成18 年度化学物質と環境.
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2006/shosai.html
環境省(2008a):ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー).
http://www.env.go.jp/air/report/h20-08/
環境省(2008b):平成19 年度ダイオキシン類に係る環境調査結果.
http://www.env.go.jp/air/report/h20-06/
環境法令研究会(2004):環境六法(平成16 年版).中央法規出版株式会社.
才野敏郎(1995)栄養塩と生物活動.月刊海洋,号外No.8,20-27.
ダイオキシン対策関係閣僚会議(1999)ダイオキシン対策推進基本指針.
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/law/kihonsisin.html
中西準子・堀口文男(2006):トリブチルスズ,詳細リスク評価書シリーズ8.丸善.
日本プラスチック工業連盟HP(2008 アクセス):世界のプラスチック統計.
http://www.jpif.gr.jp/5topics/conts/world2_c.htm
PCB 廃棄物処理事業評価検討会(2003):PCB 廃棄物処理事業評価検討会〜中間とりまとめ〜.
http://www.env.go.jp/recycle/poly/kento_r/index.html
益永茂樹(2004):東京湾のダイオキシン類汚染の変遷.海洋と生物,26(5),403-409.
益永茂樹・姚元・高田秀重・桜井健郎・中西準子(2001):東京湾のダイオキシン汚染,組成と汚染源推定.地球化学,35,159-168.
文部科学省国立天文台編(2002):理科年表CD-ROM 2002.丸善株式会社.
Defra (2005): Charting progress: an integrated assessment of the state of UK seas.
Teuten EL, Saquing JM, Knappe DRU., Barlaz MA, Jonsson S, Bjorn A, Rowland SJ, Thompson
RC, Galloway TS, Yamashita R, Ochi D,Watanuki Y, Moore C, Viet PH, Tana TS, Prudente
M, Boonyatumanond R, Zakaria MP, Akkhavong K, Ogata Y, Hirai H, Iwasa S, Mizukawa K,
Hagino Y, Imamura A, Saha M, Takada H (2009):Transport and release of chemicals from
plastics to the environment and to wildlife.Philosophical Transactions of The Royal Society B 364 (1526), 2027-2045.
海洋環境モニタリング調査の結果は下記に掲載している。
http://www.env.go.jp/earth/kaiyo/monitoring.html
海洋環境モニタリング調査のデータは下記よりダウンロード可能。
http://www-gis4.nies.go.jp/kaiyo/
―――――――――――――――――――――――――
環境省地球環境局環境保全対策課
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
TEL:03-3581-3351(代表)(内線6748)
03-5521-8245(直通)
FAX:03-3581-3348
http://www.env.go.jp
―――――――――――――――――――――――――
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14427&hou_id=11688
2009年11月07日
高砂西港盛立地のPCB 汚染土に係る報告書BK
平成19 年9 月
高砂西港盛立地のPCB 汚染土に係る
技術検討専門委員会
高砂西港盛立地のPCB 汚染土に係る報告書
はじめに
提 言 P2
【参考】
1 委員会の概要 P10
1.1 委員会設立の経緯
1.2 委員会審議の経緯
2 盛立地の概要 P12
2.1 盛立地の造成
2.2 PCB 関連法規の適用関係
3 盛立地の安全性の検証 P19
3.1 現地調査
3.2 盛立地の環境面の検討結果
3.3 盛立地の構造面の検討結果
4 今後の対策と課題 P27
4.1 擁壁補強
4.2 恒久対策と検討事項
4.3 盛立地の恒久対策と課題
4.3.1 A1 全量撤去+分解処理方式
4.3.2 A2 全量撤去+直接埋め立て処分方式
4.3.3 B 分解処理+現地埋め戻し(又は搬出)方式
4.3.4 C1 上部被覆方式
4.3.5 C2 上部被覆+遮水性地下土留め壁方式
【添付資料】
はじめに
東播磨港高砂地区高砂西岸壁に面する港(以下高砂西港という。)の北側に位
置する(株)カネカ高砂工業所と三菱製紙(株)高砂工場の敷地内に、広さ約5ヘ
クタール高さ約5メートルのアスファルトで覆われた人工の巨大な丘(以下盛
立地という。)がある。
この盛立地は、昭和40 年代後半、高砂西港の底質土砂がPCB で汚染されてい
ることが明らかになった際、これらを浚渫し、固化処理後、このような形に造
成したものである。
平成18 年3月に高砂市から兵庫県に対し、盛立地のあり方を検討するための
専門家委員会の設置について依頼があり、平成18 年5 月に「高砂西港盛立地の
PCB 汚染土に係る技術検討専門委員会」が設立されて以来、7 回にわたり審議を
重ねてきたところである。
この報告書は、今後のまちづくりにおいて、この盛立地をいかに取り扱うか
検討するため、過去の工事工程などの資料やPCB に係る各種調査結果などをも
とに、必要となる事項を環境科学及び土木工学の観点からとりまとめたもので
ある。
とりまとめに当たっては、単に技術上の観点だけからではなく、現実的にど
のように対処すべきかに意を配したところであり、今後関係者間で具体化を図
る際の基礎資料として生かしていただきたい。
高砂西港盛立地のPCB 汚染土に係る技術検討専門委員会
委員長 藤 田 正 憲
提 言
委員会では、次の事項を検証するとともに、これらを踏まえ「恒久対策」
即ち将来にわたって安全性をより確実にするための方策を提言としてとり
まとめた。
(1)検証事項及びその結果
? 環境への漏洩
? 現時点での構造面の安全性
盛立土本体ではないが、最外周部の擁壁の一部に補強を
要する箇所がある。
? 地震等の自然災害に対する安全性
大規模地震により下層地盤が液状化した場合には盛立土の斜面の一部が崩壊する可能性がある。
(2)今後の恒久対策
上記の??により、現状における安全性を確認したが、さらに安全
性を確実にするため、上記?〜?を踏まえて、恒久対策として次の3
つの方策を検討した。
対策 内容
盛立土を全量搬出し、分解処理し、最終処分場に埋め立てる方法
A全量撤去
盛立土を全量搬出し、最終処分場に直接埋め立てる方法
盛立土を全量掘削し、近傍で分解処理した後、現地に埋め戻す方法
B現地分解処理
盛立土を全量掘削し、近傍で分解処理した後、最終処分場に埋め立てる方法
C現地封じ込め
盛立土を現状のまま、安全性をより確実なものとして封じ込める方法
恒久対策の選定に当たっては、次の条件に適合する必要がある。
? 確立された技術であり、かつ盛立地の対策として適用可能であること。
? 周辺への影響が小さいこと。
? 実現性が高いこと。
なお、最外周部の擁壁の一部の補強については、周辺の道路交通
の安全を確保するという観点から、いずれの恒久対策をとる場合で
も必ず実施すべき対策である。
(擁壁の補強)
盛立地の最外周部に設置されているコンクリート製の擁壁の一部
(通常時においては東側擁壁のみ、地震時においては西側擁壁と北側
擁壁も)について、強度不足があることが判明した。破損したとして
も盛立土の安全性に影響を与えることはないが、擁壁内側の盛立土造
成以前の下層土砂などが道路に崩れ出る可能性があることから、道路
交通の安全性を確保するため、補強が必要である。
盛立地イメージ図
2 期工事PCB 含有固化土
1)A全量撤去対策
PCB 含有固化土を全量搬出することにより、現地から盛立土自体を
なくしてしまう方法である。
? A1 全量撤去+分解処理方式
この対策を採用するためには、PCB を含有している大量の盛立土
(覆土量含む、283,000m3)を分解処理することができる実用規模の既
存施設の存在が前提となる。
しかし、現時点で大規模の分解処理施設は稼働していない。(分解
処理施設については、B現地分解処理対策を参照)
なお、100 ?/日程度の受け入れが可能な分解処理施設を建設する
と仮定した場合でも、対策工事期間は、新たな施設の建設を含め概
ね20 年である。
? A2 全量撤去+直接埋め立て処分方式
この対策を採用するためには、分解処理をしないPCB 含有固化土
を大量に受け入れできる最終処分場の確保が課題となる。
この方式は、高濃度のPCB を含有した固化土と処分場の雨水など
が接触することから、PCB を含む排水を処理する施設が必要である。
また、仮に搬入できるとして、200 ?/日程度の受け入れ量を仮定
しても対策工事期間は概ね10 年である。(10 ?トラック20 台/日)
Aの対策を採用するためには、次の環境対策が必要である。
・ 盛立土を掘削するため、PCB 含有固化土由来の粉じんなどの飛散防止対策が重要となる。
・ 掘削作業中は、掘削場所をテントなどで覆蓋し、飛散防止対策
をとることとなるが、長期にわたりPCB 含有固化土由来の粉じん
などの周辺環境への飛散リスクが継続することから、場合によっ
ては、周辺住民の移転などを考慮する必要がある。
以上のことから、この全量撤去対策を採用するには、これらの課題
を解決する必要がある。
2)B現地分解処理対策
現地近傍にPCB 分解処理施設を設置し、盛立土全量を分解処理後現
地に埋め戻す、又は別の場所の最終処分場に埋め立てる方法である。
ア PCB 等の汚染土壌の分解処理技術としては、高温分解法などが開
発されており、小規模ではあるが実用に供されている。
しかし、PCB を含有している大量の盛立土(283,000m3)を処理する
には、さらに処理能力の大きな施設の建設が必要となる。
現在、北九州で建設中のPCB 廃棄物処理施設の能力は、5?/日である。
イ 仮に10 ?/日の処理能力を有する施設を10 基設置し、100 ?/日
の処理能力と仮定すると、対策工事期間は施設の建設も含め概ね20
年である。
ウ 今回対象となるPCB 含有固化土は、通常の汚染土壌とは性状が異
なることから、この対策を採用する場合には、事前に実サンプルを
使った実証実験により処理効果を確認する必要がある。
エ この対策を採用する場合には、分解処理施設建設のための用地確
保が必要である。
オ この対策を採用する場合には、次の環境対策が必要である。
・ 盛立土を掘削し、処理施設まで運搬した後、分解処理を行うた
め、PCB 含有固化土由来の粉じんなどの飛散防止対策が重要となる。
・ 分解処理施設の稼働時には、処理施設から排ガスなどの対策も
行う必要がある。
・ 掘削作業中は、掘削場所をテントなどで覆蓋し、飛散防止対策
をとることとなるが、長期にわたりPCB 含有固化土由来の粉じん
などの周辺環境への飛散リスクが継続することから、場合によっ
ては、周辺住民の移転などを考慮する必要がある。
以上のことから、この現地分解処理対策を採用するには、これら
の課題を解決する必要がある。
3)C現地封じ込め対策
盛立土を現状のまま、安全性をより確実なものとして封じ込める方
法であり、以下の2つが考えられる。
? 遮水シートなどによる上部被覆方式
? 遮水シートなどによる上部被覆+遮水性地下土留め壁方式
??の対策はいずれも最終処分場遮水工事、地下構造物築造工事な
どで多数の実績があり、技術上の問題はない。
また、現地封じ込め対策は盛立土を掘削・運搬しないので、PCB 含
有固化土由来の粉じんなどが飛散するリスクはない。
なお、対策実施後も適切に盛立地を管理し続けていく必要がある。
? C1 上部被覆方式
盛立土上部(周囲の法面を含む。)には、現状でも覆土及びアスフ
ァルト被覆が施されており、その安全性を確認しているが、さらに
遮水シート、不織布などにより盛立土上部を被覆することにより、
雨水などの浸入を防止し盛立土への遮水効果を高め、封じ込め効果
を確実にすることができる。
ただし、大規模地震(震度6強)が発生し、盛立地の下層地盤が液
状化した場合には、この上部被覆方式のみでは盛立土の斜面の一部
が崩壊する可能性がある。
? C2 上部被覆+遮水性地下土留め壁方式
現状でも周辺へのPCB の漏洩はなく、盛立土上面は、遮水のため
に50mm のアスファルト被覆がなされており、さらに、下層はカーバ
イド滓及びアスファルト層により遮水されていることから、安全性
を確認している。
しかし、アスファルトの劣化による地下水の浸透、地震時の対策
として、遮水性地下土留め壁を盛立土の周囲の地下地盤に施工する。
この対策を行うことにより、大規模地震(震度6強)が発生し、盛
立地の下層地盤が液状化した場合でも、盛立土の斜面の崩壊を防止
することが可能となる。
また、盛立土下層地盤にある地下水と周辺地下水の間を遮断し、
PCB の漏洩を更に確実に防止することが可能となる。
本方式は、想定した大規模地震等に対しても安全性を確保できる
対策である。
現地封じ込め対策イメージ図
2 期工事PCB 含有固化土
(3)まとめ
1)検討内容
過去の工事記録、調査結果及び新たに実施した各種の調査結果など
を踏まえ、今後想定される大規模地震等の自然災害に対しても安全性が
確保できる恒久対策を検討した。
検討した対策は、A全量撤去対策(さらにA1、A2に区分)、B現地
分解処理対策、C現地封じ込め対策(さらにC1、C2に区分)である。
各対策技術の現状、工期及び事業費の試算をもとに検討し、総合評価
などを次表のとおり整理した。
2)結論
? A全量撤去対策
受け入れ可能な施設の確保が課題である。また、この対策を採用
した場合には、長期にわたりPCB 含有固化土由来の粉じん等が周辺
環境へ飛散するリスクは避けられない。
? B現地分解処理対策
大規模の分解処理施設の建設が課題である。また、この対策を採
用した場合には、A対策と同様、長期にわたりPCB 含有固化土由来
の粉じん等が周辺環境へ飛散するリスクは避けられない。
? C現地封じ込め対策
この対策は、PCB 含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散
リスクがなく、上部被覆と遮水性土留め壁方式を採用すれば、盛立
土の封じ込め効果が高く、大規模地震等に対しても安全性を確保で
き、さらに万が一のPCB 漏洩にも対応できる。
「C現地封じ込め対策」は、周辺への影響が少なく、現状で確立さ
れた技術であることから、盛立地の対策として適用可能な技術である。
中でも今後想定される大規模地震等にも対応できる「C2上部被覆
+遮水性地下土留め壁方式」は、盛立地の安全性をより確実にするも
のである。
【参考】
1 委員会の概要
1.1 委員会設立の経緯
平成17 年7月に兵庫県において、「高砂みなとまちづくり構想」がとり
まとめられ、同年10 月には、構想の実現に向けた検討を行うため、高砂
市において、「高砂みなとまちづくり構想推進協議会」が設立された。こ
の協議会設立を機に、盛立地のあり方を検討するための専門家の立場から
の知見が必要であるとの意見があり、高砂市から兵庫県に対し、専門委員
会の設置について依頼があった。
このため、兵庫県では、「高砂西港盛立地のPCB 汚染土に係る技術検討
専門委員会」を設置し、盛立地の環境面と構造面に関する安全性について
技術的な観点から検討してきたところである。
(1)委員会の構成
委員は、環境工学、環境化学、廃棄物処理及び土木工学の各分野の学識
経験者5名で構成している。
委員長:藤田正憲 大阪大学名誉教授、高知工業高等専門学校長
委 員:金原和秀 岡山大学資源生物科学研究所准教授
〃 :常田賢一 大阪大学大学院工学研究科教授
〃 :野馬幸生 国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター
物質管理研究室長
〃 :道奥康治 神戸大学大学院工学研究科教授
1.2 委員会審議の経緯
(1)第1回技術検討専門委員会
開催日:平成18 年6月30 日(高砂市内)
審議事項:
・盛立地の概要、現地視察
・関係法令
・審議の基本方針及びスケジュール
(2) 第2回技術検討専門委員会
開催日:平成18 年9月8日(神戸市内)
審議事項:
・既存資料の確認及び補完すべき追加調査
・PCB 汚染土の処理事例・処理技術
(3)第3回技術検討専門委員会
開催日:平成18 年12 月20 日(高砂市内)
審議事項:
・現状での盛立地の安全性
・各種対処方法
(4)第4回技術検討専門委員会
開催日:平成19 年2月7日(神戸市内)
審議事項:
・現状での盛立地の安全性
・各種対処方法
(5)第5回技術検討専門委員会
開催日:平成19 年3月24 日(高砂市内)
審議事項:
・地震、高潮など自然災害に対する安全性の検討
・恒久対策について
・委員会の延長決定
(6)第6回技術検討委員会
開催日:平成19 年6月19 日(神戸市内)
審議事項
・恒久対策について
・提言に当たっての方針
(7)第7回技術検討委員会
開催日:平成19 年9月10 日(神戸市内)
審議事項
・提言の内容
・報告書の取りまとめ
2 盛立地の概要
2.1 盛立地の造成
(1)高砂西港底質調査と浚渫・固化処理工事の実施
兵庫県では、昭和47 年に高砂西港の底質土砂からPCB が検出されたこ
とから、昭和48 年6月「PCB 対策本部」を設置し、対策に着手した。
当時実施された高砂西港の底質土砂の調査結果は、表2.1-1 のとおり
である。
これらの底質土砂は、(株)カネカ高砂工業所及び三菱製紙(株)高砂工
場が事業主体となって、「底質の処理・処分等に関する暫定指針」(昭和
49 年環水管第113 号環境庁水質保全局長通知)に基づいて、兵庫県及び高
砂市の監視のもとに、昭和49 年9月から昭和51 年8月までに浚渫・固
化工事が実施され、現地に盛り立てられた。(盛立地位置及び断面の構造
を図2.1-1、図2.1-2 に示す。)
工事は、表2.1-2 のとおり第1期工事(昭和49 年9月〜昭和50 年3
月)及び第2期工事(昭和50 年8月〜昭和51 年8月)に分けて実施さ
れた。(図2.1-2)
第1期工事は、ガット船により浚渫し、陸揚、トラック搬送、貯泥・
固化処理後、ダンプにて搬出し、造成が行われた。
第2期工事は、ウーザーポンプ浚渫船により浚渫し、固化処理プラン
トにより混練固化後、送泥管にて搬送し、造成が行われた。
盛立土は表面を成形後、アスファルトで被覆し、法面には良質な覆土に
芝生を植栽した。
表 2.1−1 高砂西港底質土砂調査結果
調査期間 昭和47 年6月20 日〜昭和48 年4月6日
調査地点数 24 地点
PCB 濃度
(単位:mg/kg)
4〜3,300
− 1 3 −
表 2.1−2 工事期間と浚渫土量
図2.1-1 高砂西港盛立地位置図
出典:国土地理院 空中写真サービス(撮影1999 年)を元に作成
項目 第1期工事 第2期工事 合計
浚渫工事開始年月 昭和49 年9 月27 日昭和50 年8 月13 日 −
浚渫工事完了年月 昭和50 年2 月5 日昭和50 年12 月27 日 −
全工事完了年月 昭和50 年3 月19 日昭和51 年8 月23 日 −
浚渫面積 m3 45,000 194,000 239,000
浚渫計画土量 m3 110,000 170,000 280,000
浚渫土量(有姿)m3 112,000 189,000 301,000
盛立土量 m3 − − 224,000
盛立土量(覆土含む) m3 − − 283,000
図2.1-2 高砂西港盛立地の断面構造
図2.1-3 盛立工事の工程
(2)浚渫・固化処理後の底質調査
浚渫・固化処理工事後の調査結果は以下のとおりであった。
1)高砂西港のPCB 底質調査など
? 第2期工事浚渫終了直後の底質調査
第2期工事浚渫終了直後の昭和51 年1月に高砂西港内で底質の含
有試験を実施した。その結果は、40 地点において定量下限値(0.01
mg/kg)未満〜12mg/kg であり、4交点平均値で判定すると0.02〜
4.53mg/kg となり、底質の暫定除去基準(昭和50 年環水管第119 号
環境庁水質管理局長通知)10mg/kg 以下であった。
結果(mg/kg) 測定箇所数(全40 地点)
ND 8 地点
0.01〜0.1 11 地点
0.11〜1.0 14 地点
1.1〜2.0 4 地点
2.1〜3.0 2 地点
〜12 1 地点
注)ND:PCB 含有量定量下限値(0.01mg/kg)未満
? 高砂市のPCB 底質調査
高砂市は昭和56 年度以降、現在に至るまで高砂西港内の1地点で
年1回底質含有試験を実施している。その結果は、定量下限値(0.01
mg/kg)未満〜9mg/kg の範囲内であった。
? 兵庫県の水質及び底質調査
兵庫県は、平成16 年9月13 日に水質及び底質の調査を実施した。
水質については、2地点とも定量下限値(0.0005mg/L)未満であ
った。
底質については、高砂西港内の底質6地点で含有試験を実施して
おり、その結果は、0.036〜7.5mg/kg 、平均2.13mg/kg であった。
2.2 PCB 関連法規の適用関係
盛立地の工事は「底質の処理・処分等に関する暫定指針」に適合した工
法で実施されている。
しかしながら、当時から30 年以上が経過して、関係法令が整備されて
きていることから、再度、現行の関係法令の適用について整理を行った。
盛立地の対策の検討に当たっては、たとえ関係法令の直接の適用はなく
ても、現行法令の基準に適合した対策をとるべきであるという考え方に立
つものである。
検討対象の法令は、「環境基本法」、「土壌汚染対策法」、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進
に関する特別措置法」及び「ポリ塩化ビフェニル等の取扱いの規制に関す
る条例」である。
(1)環境基本法(平成5年法律第91 号)
第16 条に基づく「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年
環境庁告示第46 号)では、「PCB の環境基準は、溶出量で検出されな
いこと(0.0005mg/L 未満)」とされている。しかしながら、同告示に
おいて、「環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らか
であると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋め立て地そ
の他の環境基準に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として
現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。」
とされている。
さらに「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年環水土第
116 号環境庁水質保全局長通知)では、「「底質の処理・処分等に関す
る暫定指針」により除去底質を埋め立てる場所、「海洋汚染及び海上災
害の防止に関する法律」に基づいて行われる水底土砂の埋め立て場所
など対象物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している
ものと認められる施設に係る土壌には環境基準を適用しないこととす
る。」とされている。
このため、高砂西港盛立地に環境基準は適用されないが、周辺環境
には適用される。
(2)土壌汚染対策法(平成14 年法律第53 号)
この法律では、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合は、「指
定区域」として指定(法第5条)するとともに、汚染土壌の撤去などの
措置を講じることなどを定めているが、「土壌汚染対策法の施行につい
て」(平成15 年環水土第20 号環境省環境管理局水環境部長通知)では、
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある土地の調査に関し、「土
壌環境基準が適用されないこととなっている土壌については、それが
適切に管理されている限りにおいて、特定有害物質を含んでいたとし
ても人が摂取する可能性はないと考えられることから、調査の命令な
どの対象とはならない。」とされている。
このため、高砂西港盛立地は土壌汚染対策法の対象外であるが、分
解処理する場合の評価のための基準値として、指定基準で判断するこ
ととした。
また、PCB の溶出試験方法として、土壌汚染対策法に基づく測定方
法(平成15 年環境省告示第18 号)を採用した。
(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(昭和46 年
10 月環整第43 号厚生省環境衛生局長通知)では、「港湾、河川のしゅ
んせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは、廃棄物処理法
の対象となる廃棄物でない。」としていることから、高砂西港盛立土は、
同法で定める廃棄物には該当しない。
(4)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13 年法律第65 号)
第2条では、「この法律において、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」
とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩
化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたも
のが廃棄物(廃棄物処理法第2 条第1 項に規定する廃棄物をいう。)
となったものをいう。」としている。
高砂西港盛立土は、廃棄物処理法で定める廃棄物でないことから、
この法律で規定するPCB 廃棄物に該当しない。
(5)ポリ塩化ビフェニール等の取扱いの規制に関する条例(昭和48 年条例第54 号)
この条例では、PCB を含有する廃棄物その他の物で知事が指定す
るものについて適切な管理などを 義務付けている。
知事が指定するものの一つに、排水施設その他の施設の堆積物で
PCB を含有するものがある。
盛立土については、高砂西港内に堆積していたPCB 含有底質土砂
を浚渫し、PCB が溶出しないよう固化処理を行ったものであることか
ら、知事が指定するPCB 又はPCB 製品には該当しない。
3 盛立地の安全性の検証
本委員会では、現時点での盛立地の安全性を検証するとともに、さらに今
後起こりうる地震などの自然災害を想定し、専門的な見地から安全性を検証
した。
安全性を検証するにあたり、地震時の液状化などに関する検討を行うため
に、測量、ボーリングなどの現地調査を実施した。
3.1 現地調査
調査は、平成18 年11 月21 日〜12 月20 日に実施した。
(1)測量及びボーリング調査(添付資料2参照)
盛立地及びその周辺に工事基準点を6箇所設け、平面測量(99,000
?)及び横断測量(5,000 ?)を行うとともに、盛立土本体2地点及び
外周部6地点でボーリング調査を実施した。
図3.1-1 ボーリング位置図
(2)盛立土の土質及びPCB 分析調査
盛立土法面の2地点においてボーリングを実施し、1期工事部分、2
期工事部分及び覆土の土質調査(土質定数など)を行うとともに、採
取した覆土及びPCB 含有固化土のPCB 分析を実施した。
土質調査については、盛立土の原位置での試験及び室内試験により、
安定解析に必要な土質定数を設定した。
(3)盛立地外周部の調査
盛立地外周部6 地点について15〜20m の深さまでボーリングを行い、
土質柱状図を作成し、土質定数の設定を行った。さらに採取した土壌
のPCB 分析を行った。
また、盛立土下部のカーバイド滓層、沖積粘性土層などの土質構成
を確認し、東西2ヶ所及び南北2ヶ所の地層横断面図を作成した。
3.2 盛立地の環境面の検討結果
PCB は、化学的に安定した物質であり、難水溶性かつ脂溶性である。
PCB は、難水溶性であることから地下水などを通じて外部に漏洩する可
能性は小さいが、安全性を高めるためには、盛立土と外部の水を遮断する
ことが重要である。そこで、周辺への漏洩を防ぐため、以下のように盛立
土の遮水状況を評価した。
(1)盛立土の遮水状況
? 盛立土上面及び法面の状況
盛立土上面は、遮水のために50mm のアスファルト被覆がなされてお
り、さらに、関係企業が継続して補修工事を行ってきていることから、
現時点で盛立土上部の遮水性については問題ない。
また、法面の覆土の下にアスファルト被覆があることを現地調査に
て確認している。
? 盛立土の下の状況
盛立土の下は、難透水性の厚さ1.8m のカーバイド滓層(透水係数
8.57×10-7cm /秒)であり、さらにその下に厚さ1.3〜3m の沖積粘性
土層(透水係数3.86×10-7cm /秒)が確認された。これらは土壌汚染
対策法に基づく封じ込め対策として遮水性があると認められる基準
(透水係数1×10-5cm /秒:厚さ5m)を元に換算すると、カーバイド
滓層は21m 及び沖積粘性土層は34m〜78m に相当する。
従って、盛立土の下の遮水性は非常に高いと判断できる。
(2)盛立地と地下水位
盛立地は地上部にあり、盛立地周辺の地下水位は、盛立土より1.5m
以上低いことが判明した。従って、地下水が盛立土と直接接触すること
はなく、周辺地下水と盛立土の間の物質移動はほとんどないと判断でき
る。
(3)PCB 分析結果
1)過去からの調査結果(添付資料1参照)
? 高砂市による調査
高砂市は、昭和51 年1月から現在に至るまで、盛立地周辺について、
年2回環境調査を実施している。(調査地点は図3.2-1)
調査内容は 盛立地周辺の水路1地点、雨水2地点、地下水7地点、
大気3地点、高砂西港内の水質3地点であり、その結果は、すべて定
量下限値(水質:0.0005mg/L、大気:0.05μg/m3)未満であった。
? 関係企業によるPCB 調査
(株)カネカ及び三菱製紙(株)は「高砂西港盛立地の管理に関する確
約書」に基づき、昭和52 年度から現在に至るまで、年2回盛立地周辺
の雨水2地点、地下水3地点、大気2地点で周辺環境調査を実施して
いる。(調査地点は図3.2-1)
その結果は、すべて定量下限値(水質:0.0005mg/L、大気:0.05μg/
m3)未満であった。
2)今回の調査結果
? PCB 含有固化土及び覆土のPCB 分析結果
現在の盛立土中のPCB 濃度を確認するため、今回実施したボーリン
グにより採取したPCB 固化土及び覆土中のPCB を分析した。
第1期工事部分の、PCB 溶出量(※1)は0.0006〜0.0024mg/L、PCB
含有量(※2)は280〜470mg/kg であった。
同様に第2期工事部分のPCB 溶出量は定量下限値未満、PCB 含有量
は22〜31mg/kg であった。
なお、覆土については、溶出量、含有量とも定量下限値未満であっ
た。
表3.2-1 PCB 含有固化土及び覆土のPCB 分析結果
ボーリングポイント 分析個所 溶出量
(mg/L)
含有量
(mg/kg)
覆土 ND ND
南西側法面部 第2期工事部分PCB 含有固化土 ND 22
第1期工事部分PCB 含有固化土 0.0006 280
覆土 ND ND
南東側法面部 第2期工事部分PCB 含有固化土 ND 31
第1期工事部分PCB 含有固化土 0.0024 470
注)ND:PCB 溶出量定量下限値(0.0005mg/L)未満、PCB 含有量定量下限値(0.05mg/kg)未満
※1 PCB 溶出量分析:平成15 年環境省告示第18 号による。
溶出試験 :水と対象土壌を混ぜ、6 時間振とうし、溶け出したPCB を測定する試
験をいう。
※2 PCB 含有量分析:底質調査方法(昭和63 年環水管第127 号環境庁水質保全局長通知)に
よる。
含有試験:対象土壌をアルカリにて1 時間分解した後、溶媒と混合し、PCB の全
量を測定する試験をいう。
? 盛立地周辺のPCB 分析結果
周辺土壌へのPCB の漏洩の有無を確認するため、盛立地周辺で今回実
施したボーリングにより採取した深度別の土壌についてPCB 分析(溶出
試験及び含有試験)を行った。
その結果(表3.2-2)は、いずれの深度でも定量下限値未満であった。
第2期工事終了後実施されてきた周辺地下水のモニタリング調査で
もPCB は検出しておらず、地下水を通じての周辺環境への漏洩がないこ
とを再確認した。
(4)まとめ
盛立土の上面、法面ともにアスファルトで被覆されている。
また、盛立土は、地面よりさらに上部に盛り立てられていることから、地下水と接触することはない。
さらにこれまでの周辺環境調査、今回の盛立土法面覆土調査及び周辺ボ
ーリング土壌調査においてPCB は検出されていない。
このように、盛立土から周辺へのPCB の漏洩が認められないこと、PCB
含有固化土の上面、法面及び下面が遮水されていることから、現時点にお
いてPCB の漏洩の可能性はない。
3.3 盛立地の構造面の検討結果(添付資料3参照)
盛立地は、現在まで安定を保っており、問題は生じていないが、今回、
「港湾の施設の技術上の基準・同解説」((社)日本港湾協会)などに基づき、
地震、液状化、高潮、大雨などの自然災害が発生した場合を想定して盛立
地の安定性を検討した。
(1)盛立土のすべり
地震時においても液状化が起こらなければ、盛立土にすべりは生
じないことが判明した。
一方、液状化判定の結果、内陸直下型やプレート型の大規模地震(兵
庫県地域防災計画で震度6強が想定されている山崎断層地震など)が起こ
った場合は、盛立土下部及び周辺地盤は液状化の可能性が高いことが判明
した。
この場合、盛立土法面肩部から法先部にかけてすべりが生じる可能性が
あることが判明した。ただし、水際線から離れていること及び液状化しや
すい厚さ5m 以上の地層が連続していないため、液状化によって起こる地
盤流動により盛立地が受ける影響は小さいと判断した。
(2)盛立地の沈下
現在、盛立土の施工後30 年が経過していること、及び今回実施した測
量結果などから、盛立地の圧密沈下は既にほぼ完了していると判断できる。
このために、残留沈下はほとんどなく、将来の不等沈下を考慮する必要は
ないと考えられる。
(3)津波時の盛立地の安全性
盛立地は、播磨灘に面しており、外洋で発生した津波の影響は小さい。
兵庫県沿岸域における津波被害想定調査報告書(平成13 年3月)による
と当該地区の津波高さはTP(東京湾平均海面)+1.8m が想定されているの
に対し、盛立地周辺地盤高さは概ねTP+4〜5m である。津波時の予想津
波高さと盛立地の地盤高さを比較検討し、安全であることを確認した。
(4)高潮時の盛立地の安全性
高潮ハザードマップ(平成18 年3月兵庫県)によると当該地区の高潮潮
位はTP+4.2m が想定されているのに対し、盛立地周辺地盤高さがTP+4.2m
より低いところは、西側道路沿いの法尻部のみであった。西側道路沿いの
最も低い地点でTP+4.03mであるので、最大浸水深さは17cm、流速は0.2
〜0.5m/秒と推定されることから、法面覆土が大きく浸食される心配もな
く、安全と考えられる。
(5)大雨時の盛立地の安全性
盛立地は、雨水を早期に排除できる構造となっており、形状や排水勾配
を考慮すると当該地区の100 年確率降雨強度の降雨(66.2mm/時)によっ
て法面覆土が浸食される可能性はないことが判明した。
一方、高潮と大雨が同時に起こった場合は、盛立地内の排水路が水没す
るため、盛立土周辺の法面の一部が冠水することが想定されるが、盛立土
覆土が冠水することはないことが判明した。
これらのことから大雨時についても、安全と考えられる。
(6)擁壁の安定性
当時の設計資料を現在の「道路土工擁壁工指針」((社)日本道路協会)
に基づき検討したところ、通常時は、敷地西側・北側の擁壁は問題ない
ことが確認されたが、東側擁壁については、鉄筋が不足していることが
判明した。
また、地震時は、敷地西側・北側擁壁について地盤の支持力が不足し
ていることが判明した。
なお、南側擁壁については、通常時、地震時においても問題がないこ
とを確認した。
なお、擁壁が破損した場合の土砂崩壊範囲は、擁壁の背後6m までで
あり、擁壁から盛立土までは16m 以上離れていることから、擁壁が破壊
しても直接盛立土に影響はない。ただし、土砂崩壊の拡大を防ぐための
応急処置として、崩壊土砂を除去し、斜面を土嚢及び遮水性シートで保
護するなどの対策を速やかに講じることが必要であり、そのための、擁
壁の変化の状態を早期に検知し、応急措置をとるための体制を整えてお
く必要がある。
(7)まとめ
検討の結果、盛立土は、地震(液状化が起こらない場合)、津波、高潮、
大雨に対して安全であることを確認した。しかし、大規模な地震により
液状化が起こった場合には、盛立土の一部が崩壊することが判明した。
また、盛立地最外周部の一部擁壁については、破損する可能性がある
ことが判明したが、擁壁の破損は小規模で影響範囲が限定的であること
から、盛立土本体の安全性に影響を与えるものではない。
4 今後の対策と課題
これまでの継続的な周辺環境のモニタリング及び今回の追加調査により、
周辺環境へのPCB の漏洩がないこと、地震(液状化が起こらない場合)、津波、
高潮、大雨に対して安全であることを確認した。
委員会では、将来にわたって盛立地の安全性をより確実にするための方策
を検討した。
恒久対策として、「全量撤去対策」、「現地分解処理対策」及び「現地封じ込
め対策」について、次の3つの視点から整理した。
? 確立された技術であり、盛立地の対策として適用可能であること。
? 周辺への影響が小さいこと。
? 実現性が高いこと。
なお、最外周部の擁壁の補強については、周辺の道路交通の安全を守る
という観点から、いずれの恒久対策をとる場合でも必ず実施すべき対策で
ある。
4.1 擁壁補強
盛立地最外周部の一部擁壁については、安定性を確保できていないこ
とが判明したが、破損しても盛立土の安全性に影響を与えることはない。
ただし、隣接する道路の安全性を確保する観点から、補強を行う必要
がある。
この補強工事は、どのような恒久対策をとる場合も実施されるべきである。
(1)工事内容
当時の設計資料及び土質調査結果を用いて最外周の擁壁の安定性に
ついて、「道路土工擁壁工指針」に基づき検討した。
この結果、東側擁壁は、鉄筋が不足していることが判明した。
さらに地震時には、敷地西側・北側擁壁について地盤の支持力が不足
していることが判明した。
このため、隣接道路の安全を確保するため、補強を行う必要がある。
西側、北側擁壁の補強例としては、a)擁壁背後の土砂を除去する、b)
底版を延長するなどが考えられる。
東側擁壁の補強例としては、a)擁壁背後の土砂を除去する、c) 水路
の蓋を固定して梁機能をもたせる、d)コンクリートを増し打ちするな
どが考えられる。
なお、対策の実施のために、さらに詳細な調査が必要である。
<西側・北側擁壁の例> ネットフェンス
<東側擁壁の例> ネットフェンス
(2)検討課題
擁壁補強は通常技術で対応できるが、工事に際してはPCB 盛立土に
影響を与えないよう慎重に行う必要がある。また、補強が施されるま
での間、擁壁の変化の状態を早期に検知し、応急措置をとるための体
制を整えておく必要がある。
水路
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおりである
? 工期
1年
内訳
・準備工事 :5ヶ月
・擁壁補修工事 :7ヶ月
? 概算事業費
2億円
表4.1-1 擁壁補強の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
擁壁補強工事 擁壁補強: 仮設フェンス、北側・東側・西
側擁壁の底版コンクリート増し打
ち工事など
2億円
4.2 恒久対策と検討事項
考えられる各恒久対策(表4.2-1)について、工法の実用化レベルや実
績、工事中のPCB 漏洩に対する安全性の確保などについて検討するととも
に、参考として工期及び事業費を試算した。(表4.2-2)
4.3 盛立地の恒久対策と課題
4.3.1 A1 全量撤去+分解処理方式
盛立土全量を現地から撤去し、大量のPCB 含有固化土を分解処理でき
る受け入れ先へ搬出し、分解処理する方法である。
(1)工事内容
盛立土の掘削場所を覆蓋し、全量を掘削して場外へ搬出し、分解処
理できる施設を保有する事業場に持ち込んで土壌汚染対策法の指定基
準値以下まで分解処理する。
(2)検討課題
? 受入先分解処理施設の確保
この対策を採用するためには、PCB を含有している大量の盛立土
(283,000m3)を分解処理することができる実用規模の既存施設の存
在が前提となる。
しかし、現時点で大規模の分解処理施設は稼働していない。
(分解処理施設については、B分解処理+現地埋め戻し(又は搬
出)方式を参照)
? 工事期間中の環境対策
盛立土を掘削し、分解処理施設へ運搬する際に、掘削した盛立土
の表面が乾燥し、粉じんが周辺へ飛散することが考えられる。
また、台風や降雨の対策として、盛立土掘削作業場所を強固なテ
ントなどにより覆蓋し、高性能の大容量集じん機を設置する必要が
ある。
図4.3.1-1 掘削場所覆蓋イメージ図
? 盛立土の運搬
掘削した盛立土は、有蓋ダンプ車など密閉構造の車両にて輸送を
行う必要がある。
図4.3.1-2 有蓋ダンプ車10 ?車
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおり。
? 工期
20 年
内訳:
・飛散防止工事など 1年
・搬出(搬出量283,000m3 ) 17 年
(搬出先300km 圏、受け入れ能力100 ?/日として、有
蓋10 ?トラックで250 日/年稼動で搬出した場合を想定した。)
・施設建設 2年
? 概算事業費
1,570 億円
表4.3.1-1 A1(全量撤去+分解処理方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
1掘削、搬出 移動式テント40m×40m×2 基、集じん
機(1,200m3/分)×2 基、アスファル
ト撤去、掘削・場内運搬、事前土壌分
析、10 ?ダンプトラック×10 台=100
?/日場外搬出
350 億円
2分解処理 分解処理施設600 億円、分解処理費600
億円。(環境対策、環境監視、分析費を含む。)
1,200 億円
3分解処理土の埋め立て
分解処理土搬出費、埋め立て処分費 20 億円
概算事業費総額 1,570 億円
(4)対策後のモニタリング
盛立土を全量撤去するので、現地でのモニタリングは不要となる。
4.3.2 A2 全量撤去+直接埋め立て処分方式
盛立土全量を現地から撤去し、直接最終処分場へ搬入する方法である。
(1)対策工事内容
盛立土の掘削場所を覆蓋し、全量を掘削して場外へ搬出し、最終処
分場へ持ち込んで埋め立て処分する。
(2)検討課題
? 受け入れ先の確保
この対策を採用するためには、分解処理をしないPCB 含有固化土
を大量に受け入れできる最終処分場の確保が課題となる。
また、埋め立て処分先として検討した「大阪湾広域臨海環境整備
センター」の最終処分場は、高濃度のPCB を含有する土壌の搬入を
想定しておらず、高濃度のPCB を含有した固化土を受け入れできる
設備を有していない。
? 工事期間中の環境対策
A1(全量撤去+分解処理方式)と同じ対策が必要。
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業は次のとおり。
? 工期
10 年
内訳:
・飛散防止工事など 1年
・搬出(搬出量283,000m3) 9年
(受け入れ能力200 ?/日として、有蓋10 ?トラック20
台/日×250 日/年で搬出した場合を想定した。)
? 概算事業費
400 億円
表4.3.2-1 A2(全量撤去+直接埋め立て処分方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
1掘削、搬出 A1対策と同じ 350 億円
2埋め立て 「大阪湾広域臨海環境整備センター」
と仮定した場合
50 億円
概算事業費総額 400 億円
(4)対策後のモニタリング
盛立土を全量撤去するので、現地でのモニタリングは不要となる。
図4.3.2-1 大阪湾広域臨海環境整備センター
神戸沖埋め立て処分場
出典:大阪湾広域臨海環境整備センターホームページ
4.3.3 B 分解処理+現地埋め戻し(又は搬出)方式
現在の盛立地近傍において、盛立土を土壌汚染対策法の指定基準値以
下まで分解処理し、現地へ埋め戻し又は場外に搬出し、最終処分場で埋
め立て処分を行う。
そこで、現在の分解処理技術の開発状況や実績のほか、掘削、分解処
理中の環境を検討するとともに工期及び事業費について試算した。
(1)工事内容
現地近傍に分解処理施設を設置し、掘削場所を覆蓋する。
盛立土を掘削して分解処理施設まで運搬し、盛立土を土壌汚染対策法
の指定基準値以下まで分解処理する。分解処理された盛立土は、再度現
地に埋め戻すか、又は最終処分場へ搬出する。
? 分解処理施設の建設
PCB 含有固化土を土壌汚染対策法の指定基準値以下に分解処理す
る方法を選定し、施設を建設する。
現在開発されている分解処理方法を表4.3.3-1 に示す。
表4.3.3-1 PCB 汚染土壌等処理技術の開発
分解処理方法 概要
還元加熱分離法+金
属ナトリウム分散体法
汚染土壌を窒素雰囲気下で間接加熱(500〜600℃)し、ガス
化によりPCB を分解・分離する。さらに金属ナトリウム分
散体により脱塩素化する。
間接熱脱着+水蒸気分解法
汚染土壌を間接加熱(400〜700℃)し、ガス化によりPCB を
分解・分離する。さらに水蒸気雰囲気下で間接加熱(1100℃
以上)により加熱分解する。
高温分解・焼成処理法
汚染土壌を高温乾燥処理(800〜900℃)し、ガス化により
PCB を分解・分離する。
さらにガスを2次燃焼(1100℃以上)にて加熱分解する。
減圧還元加熱処理法 汚染土壌を還元熱処理(600℃)し、還元脱塩素分解及びガ
ス化によりPCB を分解・分離する。さらにガスを2次燃焼
(1100 度以上)にて加熱分解する。
間接加熱酸化分解法 汚染土壌を間接加熱(450〜600℃)し、PCB を脱塩素化・分
解する。
水洗分解処理法 汚染土壌に水と空気を加え洗浄することによりPCB を分
離・濃縮する。さらに高温分解法で溶融分解する。
湿式酸化ラジカル法 汚染土壌を低酸素雰囲気下で間接加熱(600℃)し、PCB を分
解・除去する。さらに金属ナトリウム分散体にて脱塩素化
する。
溶剤抽出法 汚染土壌スラリーを加温加圧下(150〜200℃、1〜2MPa)で
水に溶出させ、OH ラジカルにて酸化分解する。
高温分解法 PCB に汚染された土壌等に電気を流すことによって高温溶
融(1,600℃以上)し、有害物を分解・無害化する。
(2)検討課題
? PCB 汚染土壌の分解処理の実績
全国の汚染土壌処理事例を調査したところ、現時点では、小規模
な分解処理施設の事例(10m3/日未満)はあるが、今回のような大
量のPCB 含有固化処理土を処理した事例はない。
表4.3.3-2 汚染土壌分解処理事例
処理場所 対象土壌 処理量
(トン)
完了年月 分解方法
和歌山県橋本市 ダイオキシン 汚染土壌 3,900 H16.9 高温分解
東京都大田区大森 ダイオキシン 汚染土壌 1,500 H18.3 溶剤抽出
大阪府能勢町 ダイオキシン 汚染土壌 9,000 H18.12 間接熱脱着+高温分解
? 工事期間中の環境対策
盛立土を掘削し、分解処理施設へ運搬する際に、掘削した盛立土
の表面が乾燥し、粉じんが周辺へ飛散することが考えられる。
また、台風や降雨の対策として、盛立土掘削作業場所を強固なテ
ントなどにより覆蓋し、高性能の大容量集じん機を設置する必要がある。
また、分解処理施設から排出される排ガスなどについては、活性
炭などによる高効率の処理装置が必要となる。
? PCB などの分析
工事期間中は、排ガスや周辺環境のモニタリングを適切に実施す
る必要がある。
分解処理施設を適正に運転するため、処理前処理後のPCB 含有量
を適切な頻度で把握する必要がある。
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおり。
? 工期
20 年
内訳:
・実証試験と技術の選定 1年
・施設建設(10 ?/日×10 基) 2年
・分解処理(処理量283,000m3) 17 年
? 概算事業費
1,500 億円
表4.3.3-3 B(分解処理+現地埋め戻し(又は搬出)方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
1掘削・埋め戻し(又は搬出)
移動式テント40m×40m×2 基、集じん機
(1,200m3/分)×2 基、アスファルト撤去、
掘削、場内運搬、事前土壌分析、埋め戻し工
事(又は搬出)
300 億円
2分解処理 分解処理施設600 億円、分解処理費600 億円。
(環境対策、環境監視、分析費を含む。)
1,200 億円
概算事業費総額 1,500 億円
(4)対策後のモニタリング
盛立土は全量分解処理されているので、対策後のモニタリングは不要
である。
4.3.4 C1 上部被覆方式
盛立土上部(周囲の法面を含む。)には、現状でも覆土及びアスファル
ト被覆が施されており、その安全性を確認しているが、さらに盛立土の
遮水効果を高め、封じ込め効果を確実にすることができる。
(1)工事内容
盛立土と外部との遮断を将来にわたって確実なものとするために、図
4.3.4-1 に示すとおり、現在のアスファルト被覆上を保護土で覆い、そ
の上を不織布と遮水シートで覆い、さらに1m 程度覆土する方法などがある。
図4.3.4-1 被覆構造と被覆工事の事例
(2)検討課題
? 保守点検
不織布及び遮水性シートの選定など上部被覆の構造設計に当たっ
ては、日常点検の方法や、災害、劣化などにより破損が生じた場合の
補修方法に配慮する必要がある。
? 地震などについて
上部被覆対策のみを実施する場合は、盛立地の下層地盤が液状化
するような大規模地震(震度6強)が発生した時には、盛立土の地斜
面の一部が崩落する可能性がある。
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおりである。
? 工期
2年
内訳
・準備工事 :5ヶ月
・上部被覆工事その他関連工事 :17 ヶ月
・片付工事 :2ヶ月
? 概算事業費
40 億円
表4.3.4-1 C1(上部被覆方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
上部被覆工事 覆土、シート設置、排水工事ほか 40 億円
(4)対策後のモニタリングなど
対策後は、現状よりさらに安全性が高められるが、適切な頻度でモ
ニタリングを継続する必要がある。
また、新たに設置する上部被覆シートなどを含め、適切に管理してい
く必要がある。
4.3.5 C2 上部被覆+遮水性地下土留め壁方式
盛立地の安全性の検証により、現状の盛立地の構造では大規模な地震
時に液状化が起こった場合には課題があることが判明した。
そのため、ここでは、現状の盛立地の液状化に対する対策と地下地盤
の遮水性を確保する対策を同時に検討した。
(1)対策工事内容
上部被覆については、4.3.4 と同様の内容とする。
さらに遮水性地下土留め壁を盛立土の周囲に施工することにより、液
状化対策及び盛立土の遮水性を高める対策となる。
大規模な地震により液状化が起こった場合、盛立土肩部から盛立土法
面にかけてすべり現象が発生する可能性が高いため、これを防止する対
策として、遮水性地下土留め壁を盛立土周囲の地下地盤に施工すること
が有効と考えられる。遮水性地下土留め壁の構造は、例えば、SMW 工法
(ソイルセメント壁工法)では、下図のように地中にセメントミルクを
注入しながら掘削した穴にH鋼を挿入して連続壁を形成するものであ
る。
図4.3.5-1 遮水性地下土留め壁工事のイメージ図
(2)検討課題
? 上部被覆工事
C1と同じ。
? 遮水性地下土留め壁工事
遮水性地下土留め壁を設計施工するに当たっては、土質定数の
ために振動三軸試験を実施し、液状化時の対策のために地震応答
解析やすべり変形解析を実施するなどさらに詳しく調査する必要
がある。
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおりである。
? 工期
2年
内訳
・準備工事 :5ヶ月
・遮水性地下土留め壁工事及び
上部被覆工事その他関連工事 :17 ヶ月
・片付工事 :2ヶ月
? 概算事業費
75 億円
表4.3.5-1 C2(上部被覆+遮水性地下土留め壁方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
1上部被覆工事 覆土、シート設置、排水工事ほか 40 億円
2遮水性地下土留め壁工事
遮水性地下土留め壁工事 35 億円
概算事業費総額 75 億円
(4)対策後のモニタリングなど
対策後は、現状よりさらに安全性が高められるが、適切な頻度でモ
ニタリングを継続する必要がある。
また、新たに設置する上部被覆シートなどを含め、適切に管理してい
く必要がある。
B 現地分解処理対策擁壁補強
A1 全量撤去+分解処理方式A2 全量撤去+直接埋め立て処分方式B 分解処理→現地埋め戻し(又は搬出)方式C1 上部被覆方式C2 上部被覆+遮水性地下土留め壁方式いずれの対策にも必要
・盛立土を全量搬出し、別の場所で分解処理する。・盛立土を全量搬出し、別の最終処分場に直接埋め立てる。
・現地近傍に分解処理施設を設置し、盛立土を全量掘
削し、分解処理施設で環境基準値以下のレベルまで分解処理する。
・処理後物は、再び現地に埋め戻す。(又は搬出)
・盛立土へ雨水の浸入を防止するため、遮水シート、
不織布等により、盛立土の上部(周囲の法面含む)に
遮水工事を行う。
・C1の上部被覆に加えて、盛立土周囲の地下地盤に
遮水性地下土留め壁工事を行う。
・盛立地の周辺に設置されている擁壁の一部で、通常
時でも強度が不足している箇所の補強を行う。
?背面土砂の除去による土圧低減
?コンクリート増打ちあるいは底版の延長
?上記??の組み合わせ
1
対策技術
の現状
・盛立土を掘削搬出する技術については土壌汚染対策
工事等多くの実績があり技術的な課題はない。
・分解処理技術については、汚染土壌の小規模な処理
設備はあるが、大規模な処理施設は稼働していない。
・盛立土を掘削搬出する技術については、A1と同じ。
・受入先の有無を事前に調査する必要がある。
・汚染土壌の小規模な処理設備はあるが、大規模な処
理施設は稼働していない。
また、固化処理土では、実証実験の実施例がない。
・遮水工事は、最終処分場の遮水対策など多数の実
績がある。
・遮水性地下土留め壁は、護岸工事、地下構造物築
造工事、最終処分場遮水工事など、日本全国で多数
の実績があり、技術的な問題はない。
・遮水性地下土留め壁を施工するに当たっては、さら
に詳細に解析等を行う必要がある。
・多数の実績があり、技術上の問題はない。
2 工期
20年
1.飛散防止工事等:1年
2.掘削・搬出:17年(100トン/日で想定)
3.施設建設:2年
10年
1.飛散防止工事等:1年
2.掘削・搬出:9年(200トン/日で想定)
20年
1.実証試験と技術の選定:1年
2.施設建設:2年
3.分解処理:17年
2年
1.上部被覆工事:2年
2年
1.遮水性地下土留め壁工事:2年
(上部被覆工事も同時施工可能)
1年
1.準備工事:5ヶ月
2.補強工事:7ヶ月
3
事業費の
試算
(概算)
1,570億円
(内訳)
1.掘削・運搬費:350億円
2.処理施設償却費:600億円
3.分解処理費:600億円
4.埋立て処分費:20億円
400億円
(内訳)
1.掘削・運搬費:350億円
2.埋立て処分費:50億円
1,500億円
(内訳)
1.掘削盛立て費等:300億円
2.処理施設建設費:600億円
3.分解処理費:600億円
《参考》
北九州PCB廃棄物処理施設の建設費
約300億円(5t/日) 60億円/t
40億円
(内訳)
1.上部被覆工事費:40億円
75億円
(内訳)
1.上部被覆工事費:約40億円
2.遮水性地下土留め壁工事費:35億円
2億円
(内訳)
1.擁壁補強工事費:2億円
恒久対策一覧
総合評価
・上部被覆の面積、構造等はC1と同じ
・遮水性地下土留め壁の全延長は1,250mとする。
・遮水性地下土留め壁の構造は、φ850、L=18mの
ソイルセメント壁とする。
積算の
前提条件
・外周道路に対する安全対策
・補強が施されるまでの間、擁壁の点検や応急措置を
とるための体制が必要。
・盛立土の掘削を行うため、掘削中に長期にわたり
PCB含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散
リスクが継続する。
・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。
・受け入れ可能な最終処分場の確保が課題である。
・盛立土の掘削を行うため、掘削中に長期にわたり
PCB含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散
リスクが継続する。
・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。
・受け入れ可能な施設の確保が課題である。
・工期が長期にわたるため、別途対策が必要である。
(大規模地震時の液状化対策工事などを事前に実施
しておく必要がある。)
・盛立土の掘削を行うため、掘削中及び処理施設での
処理中に長期にわたりPCB含有固化土由来の粉じん
等の周辺環境への飛散リスクが継続する。
・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。
・大規模処理施設の建設が必要。
・処理施設の設置場所の用地確保が必要。
・PCB含有固化土の処理実績はない。
・盛立土の掘削がないため、PCB含有固化土由来の
粉じん等が飛散するリスクはない。
・工事終了後、モニタリングと適切な管理が必要であ
る。
・盛立地の地下地盤が液状化した場合でも、盛立土
の滑りを防止し、盛立土の封じ込め効果が高く、万が
一のPCB漏洩にも対応できる。
・盛立土の掘削がないため、PCB含有固化土由来の
粉じん等が飛散するリスクはない。
・工事終了後、モニタリングと適切な管理が必要であ
る。
・震度6強の大規模地震時には、地盤が液状化して
盛立地斜面に滑りが生じる可能性がある。
事業概要
・擁壁解体時の掘削残土は一般残土として処分できる
ものとする。
・盛立地東側、北側及び西側の擁壁の底版にコンク
リート増打ち等を実施する。
A 全量撤去対策
・盛立土の数量はA1と同じ。
・搬出は、10トンダンプトラック20台/日。
・搬出日数は、250日/年(土日祝除く)
・盛立土は管理型処分場で埋立処分できるものとす
る。
・盛立土の数量は283,000m3とする。
・盛立土はH17環境省公募PCB処理法等で分解処理で
きるものとする。
・処理能力は、10t/日規模の施設を10台設置し、365日
24時間連続運転で稼働効率を7割として想定。
・処理費はダイオキシン汚染土壌処理実績およびH17
環境省公募処理法公開資料から試算。
・盛立土掘削箇所に粉じん飛散防止のための仮設テン
トを設置できるものとする。
・分解処理前の土壌分析は、PCB溶出・含有を100t当
り1検体とする。
・分解処理後の土壌分析は、土壌汚染対策法の指定
基準項目すべての溶出とPCB含有を100t当り1検体と
する。
・盛立土の単位体積重量は1.5t/m3とする。
・搬出は、10トンダンプトラック10台/日。
・搬出日数は、250日/年(土日祝除く)
・盛立土の数量は283,000m3とする。
・盛立土はH17環境省公募PCB処理法等で分解処理で
きるものとする。
・処理費はダイオキシン汚染土壌処理実績およびH17
環境省公募処理法公開資料から試算。
・盛立土掘削箇所に粉じん飛散防止のための仮設テン
トを設置できるものとする。
・盛立土の単位体積重量は1.5t/m3とする。掘削、分解
処理についてはBに同じ。
C 現地封じ込め対策
・上部被覆の面積は55,436m2とする。
・上部被覆の構造は、盛立土上の既設アスファルトの
上に、下から順番に保護土(粘性土)0.75m、不織布、
遮水シート、不織布、良質土とする。
・盛立地天端面の覆土はTP+14mまでとする。
【添付資料】
1 盛立地の周辺環境調査結果
2 土質調査資料
(1)盛立地平面図(1/1,500)
(2)盛立地土層断面図(1/1,500)
3 安定性検討資料
(1)安定性検討の概要
(2)盛立土(固化処理土、覆土)のすべり検討
(3)擁壁の検討
(4)擁壁の検討結果
(5)液状化の検討
(6)液状化時の現象
(7)沈下の検討
(8)津波に関する検討
(9)大雨に関する検討(排水能力、流域図)
http://www.city.takasago.hyogo.jp/index.cfm/8,3862,c,html/3862/20080108-100507.pdf
高砂西港盛立地のPCB 汚染土に係る
技術検討専門委員会
高砂西港盛立地のPCB 汚染土に係る報告書
はじめに
提 言 P2
【参考】
1 委員会の概要 P10
1.1 委員会設立の経緯
1.2 委員会審議の経緯
2 盛立地の概要 P12
2.1 盛立地の造成
2.2 PCB 関連法規の適用関係
3 盛立地の安全性の検証 P19
3.1 現地調査
3.2 盛立地の環境面の検討結果
3.3 盛立地の構造面の検討結果
4 今後の対策と課題 P27
4.1 擁壁補強
4.2 恒久対策と検討事項
4.3 盛立地の恒久対策と課題
4.3.1 A1 全量撤去+分解処理方式
4.3.2 A2 全量撤去+直接埋め立て処分方式
4.3.3 B 分解処理+現地埋め戻し(又は搬出)方式
4.3.4 C1 上部被覆方式
4.3.5 C2 上部被覆+遮水性地下土留め壁方式
【添付資料】
はじめに
東播磨港高砂地区高砂西岸壁に面する港(以下高砂西港という。)の北側に位
置する(株)カネカ高砂工業所と三菱製紙(株)高砂工場の敷地内に、広さ約5ヘ
クタール高さ約5メートルのアスファルトで覆われた人工の巨大な丘(以下盛
立地という。)がある。
この盛立地は、昭和40 年代後半、高砂西港の底質土砂がPCB で汚染されてい
ることが明らかになった際、これらを浚渫し、固化処理後、このような形に造
成したものである。
平成18 年3月に高砂市から兵庫県に対し、盛立地のあり方を検討するための
専門家委員会の設置について依頼があり、平成18 年5 月に「高砂西港盛立地の
PCB 汚染土に係る技術検討専門委員会」が設立されて以来、7 回にわたり審議を
重ねてきたところである。
この報告書は、今後のまちづくりにおいて、この盛立地をいかに取り扱うか
検討するため、過去の工事工程などの資料やPCB に係る各種調査結果などをも
とに、必要となる事項を環境科学及び土木工学の観点からとりまとめたもので
ある。
とりまとめに当たっては、単に技術上の観点だけからではなく、現実的にど
のように対処すべきかに意を配したところであり、今後関係者間で具体化を図
る際の基礎資料として生かしていただきたい。
高砂西港盛立地のPCB 汚染土に係る技術検討専門委員会
委員長 藤 田 正 憲
提 言
委員会では、次の事項を検証するとともに、これらを踏まえ「恒久対策」
即ち将来にわたって安全性をより確実にするための方策を提言としてとり
まとめた。
(1)検証事項及びその結果
? 環境への漏洩
? 現時点での構造面の安全性
盛立土本体ではないが、最外周部の擁壁の一部に補強を
要する箇所がある。
? 地震等の自然災害に対する安全性
大規模地震により下層地盤が液状化した場合には盛立土の斜面の一部が崩壊する可能性がある。
(2)今後の恒久対策
上記の??により、現状における安全性を確認したが、さらに安全
性を確実にするため、上記?〜?を踏まえて、恒久対策として次の3
つの方策を検討した。
対策 内容
盛立土を全量搬出し、分解処理し、最終処分場に埋め立てる方法
A全量撤去
盛立土を全量搬出し、最終処分場に直接埋め立てる方法
盛立土を全量掘削し、近傍で分解処理した後、現地に埋め戻す方法
B現地分解処理
盛立土を全量掘削し、近傍で分解処理した後、最終処分場に埋め立てる方法
C現地封じ込め
盛立土を現状のまま、安全性をより確実なものとして封じ込める方法
恒久対策の選定に当たっては、次の条件に適合する必要がある。
? 確立された技術であり、かつ盛立地の対策として適用可能であること。
? 周辺への影響が小さいこと。
? 実現性が高いこと。
なお、最外周部の擁壁の一部の補強については、周辺の道路交通
の安全を確保するという観点から、いずれの恒久対策をとる場合で
も必ず実施すべき対策である。
(擁壁の補強)
盛立地の最外周部に設置されているコンクリート製の擁壁の一部
(通常時においては東側擁壁のみ、地震時においては西側擁壁と北側
擁壁も)について、強度不足があることが判明した。破損したとして
も盛立土の安全性に影響を与えることはないが、擁壁内側の盛立土造
成以前の下層土砂などが道路に崩れ出る可能性があることから、道路
交通の安全性を確保するため、補強が必要である。
盛立地イメージ図
2 期工事PCB 含有固化土
1)A全量撤去対策
PCB 含有固化土を全量搬出することにより、現地から盛立土自体を
なくしてしまう方法である。
? A1 全量撤去+分解処理方式
この対策を採用するためには、PCB を含有している大量の盛立土
(覆土量含む、283,000m3)を分解処理することができる実用規模の既
存施設の存在が前提となる。
しかし、現時点で大規模の分解処理施設は稼働していない。(分解
処理施設については、B現地分解処理対策を参照)
なお、100 ?/日程度の受け入れが可能な分解処理施設を建設する
と仮定した場合でも、対策工事期間は、新たな施設の建設を含め概
ね20 年である。
? A2 全量撤去+直接埋め立て処分方式
この対策を採用するためには、分解処理をしないPCB 含有固化土
を大量に受け入れできる最終処分場の確保が課題となる。
この方式は、高濃度のPCB を含有した固化土と処分場の雨水など
が接触することから、PCB を含む排水を処理する施設が必要である。
また、仮に搬入できるとして、200 ?/日程度の受け入れ量を仮定
しても対策工事期間は概ね10 年である。(10 ?トラック20 台/日)
Aの対策を採用するためには、次の環境対策が必要である。
・ 盛立土を掘削するため、PCB 含有固化土由来の粉じんなどの飛散防止対策が重要となる。
・ 掘削作業中は、掘削場所をテントなどで覆蓋し、飛散防止対策
をとることとなるが、長期にわたりPCB 含有固化土由来の粉じん
などの周辺環境への飛散リスクが継続することから、場合によっ
ては、周辺住民の移転などを考慮する必要がある。
以上のことから、この全量撤去対策を採用するには、これらの課題
を解決する必要がある。
2)B現地分解処理対策
現地近傍にPCB 分解処理施設を設置し、盛立土全量を分解処理後現
地に埋め戻す、又は別の場所の最終処分場に埋め立てる方法である。
ア PCB 等の汚染土壌の分解処理技術としては、高温分解法などが開
発されており、小規模ではあるが実用に供されている。
しかし、PCB を含有している大量の盛立土(283,000m3)を処理する
には、さらに処理能力の大きな施設の建設が必要となる。
現在、北九州で建設中のPCB 廃棄物処理施設の能力は、5?/日である。
イ 仮に10 ?/日の処理能力を有する施設を10 基設置し、100 ?/日
の処理能力と仮定すると、対策工事期間は施設の建設も含め概ね20
年である。
ウ 今回対象となるPCB 含有固化土は、通常の汚染土壌とは性状が異
なることから、この対策を採用する場合には、事前に実サンプルを
使った実証実験により処理効果を確認する必要がある。
エ この対策を採用する場合には、分解処理施設建設のための用地確
保が必要である。
オ この対策を採用する場合には、次の環境対策が必要である。
・ 盛立土を掘削し、処理施設まで運搬した後、分解処理を行うた
め、PCB 含有固化土由来の粉じんなどの飛散防止対策が重要となる。
・ 分解処理施設の稼働時には、処理施設から排ガスなどの対策も
行う必要がある。
・ 掘削作業中は、掘削場所をテントなどで覆蓋し、飛散防止対策
をとることとなるが、長期にわたりPCB 含有固化土由来の粉じん
などの周辺環境への飛散リスクが継続することから、場合によっ
ては、周辺住民の移転などを考慮する必要がある。
以上のことから、この現地分解処理対策を採用するには、これら
の課題を解決する必要がある。
3)C現地封じ込め対策
盛立土を現状のまま、安全性をより確実なものとして封じ込める方
法であり、以下の2つが考えられる。
? 遮水シートなどによる上部被覆方式
? 遮水シートなどによる上部被覆+遮水性地下土留め壁方式
??の対策はいずれも最終処分場遮水工事、地下構造物築造工事な
どで多数の実績があり、技術上の問題はない。
また、現地封じ込め対策は盛立土を掘削・運搬しないので、PCB 含
有固化土由来の粉じんなどが飛散するリスクはない。
なお、対策実施後も適切に盛立地を管理し続けていく必要がある。
? C1 上部被覆方式
盛立土上部(周囲の法面を含む。)には、現状でも覆土及びアスフ
ァルト被覆が施されており、その安全性を確認しているが、さらに
遮水シート、不織布などにより盛立土上部を被覆することにより、
雨水などの浸入を防止し盛立土への遮水効果を高め、封じ込め効果
を確実にすることができる。
ただし、大規模地震(震度6強)が発生し、盛立地の下層地盤が液
状化した場合には、この上部被覆方式のみでは盛立土の斜面の一部
が崩壊する可能性がある。
? C2 上部被覆+遮水性地下土留め壁方式
現状でも周辺へのPCB の漏洩はなく、盛立土上面は、遮水のため
に50mm のアスファルト被覆がなされており、さらに、下層はカーバ
イド滓及びアスファルト層により遮水されていることから、安全性
を確認している。
しかし、アスファルトの劣化による地下水の浸透、地震時の対策
として、遮水性地下土留め壁を盛立土の周囲の地下地盤に施工する。
この対策を行うことにより、大規模地震(震度6強)が発生し、盛
立地の下層地盤が液状化した場合でも、盛立土の斜面の崩壊を防止
することが可能となる。
また、盛立土下層地盤にある地下水と周辺地下水の間を遮断し、
PCB の漏洩を更に確実に防止することが可能となる。
本方式は、想定した大規模地震等に対しても安全性を確保できる
対策である。
現地封じ込め対策イメージ図
2 期工事PCB 含有固化土
(3)まとめ
1)検討内容
過去の工事記録、調査結果及び新たに実施した各種の調査結果など
を踏まえ、今後想定される大規模地震等の自然災害に対しても安全性が
確保できる恒久対策を検討した。
検討した対策は、A全量撤去対策(さらにA1、A2に区分)、B現地
分解処理対策、C現地封じ込め対策(さらにC1、C2に区分)である。
各対策技術の現状、工期及び事業費の試算をもとに検討し、総合評価
などを次表のとおり整理した。
2)結論
? A全量撤去対策
受け入れ可能な施設の確保が課題である。また、この対策を採用
した場合には、長期にわたりPCB 含有固化土由来の粉じん等が周辺
環境へ飛散するリスクは避けられない。
? B現地分解処理対策
大規模の分解処理施設の建設が課題である。また、この対策を採
用した場合には、A対策と同様、長期にわたりPCB 含有固化土由来
の粉じん等が周辺環境へ飛散するリスクは避けられない。
? C現地封じ込め対策
この対策は、PCB 含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散
リスクがなく、上部被覆と遮水性土留め壁方式を採用すれば、盛立
土の封じ込め効果が高く、大規模地震等に対しても安全性を確保で
き、さらに万が一のPCB 漏洩にも対応できる。
「C現地封じ込め対策」は、周辺への影響が少なく、現状で確立さ
れた技術であることから、盛立地の対策として適用可能な技術である。
中でも今後想定される大規模地震等にも対応できる「C2上部被覆
+遮水性地下土留め壁方式」は、盛立地の安全性をより確実にするも
のである。
【参考】
1 委員会の概要
1.1 委員会設立の経緯
平成17 年7月に兵庫県において、「高砂みなとまちづくり構想」がとり
まとめられ、同年10 月には、構想の実現に向けた検討を行うため、高砂
市において、「高砂みなとまちづくり構想推進協議会」が設立された。こ
の協議会設立を機に、盛立地のあり方を検討するための専門家の立場から
の知見が必要であるとの意見があり、高砂市から兵庫県に対し、専門委員
会の設置について依頼があった。
このため、兵庫県では、「高砂西港盛立地のPCB 汚染土に係る技術検討
専門委員会」を設置し、盛立地の環境面と構造面に関する安全性について
技術的な観点から検討してきたところである。
(1)委員会の構成
委員は、環境工学、環境化学、廃棄物処理及び土木工学の各分野の学識
経験者5名で構成している。
委員長:藤田正憲 大阪大学名誉教授、高知工業高等専門学校長
委 員:金原和秀 岡山大学資源生物科学研究所准教授
〃 :常田賢一 大阪大学大学院工学研究科教授
〃 :野馬幸生 国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター
物質管理研究室長
〃 :道奥康治 神戸大学大学院工学研究科教授
1.2 委員会審議の経緯
(1)第1回技術検討専門委員会
開催日:平成18 年6月30 日(高砂市内)
審議事項:
・盛立地の概要、現地視察
・関係法令
・審議の基本方針及びスケジュール
(2) 第2回技術検討専門委員会
開催日:平成18 年9月8日(神戸市内)
審議事項:
・既存資料の確認及び補完すべき追加調査
・PCB 汚染土の処理事例・処理技術
(3)第3回技術検討専門委員会
開催日:平成18 年12 月20 日(高砂市内)
審議事項:
・現状での盛立地の安全性
・各種対処方法
(4)第4回技術検討専門委員会
開催日:平成19 年2月7日(神戸市内)
審議事項:
・現状での盛立地の安全性
・各種対処方法
(5)第5回技術検討専門委員会
開催日:平成19 年3月24 日(高砂市内)
審議事項:
・地震、高潮など自然災害に対する安全性の検討
・恒久対策について
・委員会の延長決定
(6)第6回技術検討委員会
開催日:平成19 年6月19 日(神戸市内)
審議事項
・恒久対策について
・提言に当たっての方針
(7)第7回技術検討委員会
開催日:平成19 年9月10 日(神戸市内)
審議事項
・提言の内容
・報告書の取りまとめ
2 盛立地の概要
2.1 盛立地の造成
(1)高砂西港底質調査と浚渫・固化処理工事の実施
兵庫県では、昭和47 年に高砂西港の底質土砂からPCB が検出されたこ
とから、昭和48 年6月「PCB 対策本部」を設置し、対策に着手した。
当時実施された高砂西港の底質土砂の調査結果は、表2.1-1 のとおり
である。
これらの底質土砂は、(株)カネカ高砂工業所及び三菱製紙(株)高砂工
場が事業主体となって、「底質の処理・処分等に関する暫定指針」(昭和
49 年環水管第113 号環境庁水質保全局長通知)に基づいて、兵庫県及び高
砂市の監視のもとに、昭和49 年9月から昭和51 年8月までに浚渫・固
化工事が実施され、現地に盛り立てられた。(盛立地位置及び断面の構造
を図2.1-1、図2.1-2 に示す。)
工事は、表2.1-2 のとおり第1期工事(昭和49 年9月〜昭和50 年3
月)及び第2期工事(昭和50 年8月〜昭和51 年8月)に分けて実施さ
れた。(図2.1-2)
第1期工事は、ガット船により浚渫し、陸揚、トラック搬送、貯泥・
固化処理後、ダンプにて搬出し、造成が行われた。
第2期工事は、ウーザーポンプ浚渫船により浚渫し、固化処理プラン
トにより混練固化後、送泥管にて搬送し、造成が行われた。
盛立土は表面を成形後、アスファルトで被覆し、法面には良質な覆土に
芝生を植栽した。
表 2.1−1 高砂西港底質土砂調査結果
調査期間 昭和47 年6月20 日〜昭和48 年4月6日
調査地点数 24 地点
PCB 濃度
(単位:mg/kg)
4〜3,300
− 1 3 −
表 2.1−2 工事期間と浚渫土量
図2.1-1 高砂西港盛立地位置図
出典:国土地理院 空中写真サービス(撮影1999 年)を元に作成
項目 第1期工事 第2期工事 合計
浚渫工事開始年月 昭和49 年9 月27 日昭和50 年8 月13 日 −
浚渫工事完了年月 昭和50 年2 月5 日昭和50 年12 月27 日 −
全工事完了年月 昭和50 年3 月19 日昭和51 年8 月23 日 −
浚渫面積 m3 45,000 194,000 239,000
浚渫計画土量 m3 110,000 170,000 280,000
浚渫土量(有姿)m3 112,000 189,000 301,000
盛立土量 m3 − − 224,000
盛立土量(覆土含む) m3 − − 283,000
図2.1-2 高砂西港盛立地の断面構造
図2.1-3 盛立工事の工程
(2)浚渫・固化処理後の底質調査
浚渫・固化処理工事後の調査結果は以下のとおりであった。
1)高砂西港のPCB 底質調査など
? 第2期工事浚渫終了直後の底質調査
第2期工事浚渫終了直後の昭和51 年1月に高砂西港内で底質の含
有試験を実施した。その結果は、40 地点において定量下限値(0.01
mg/kg)未満〜12mg/kg であり、4交点平均値で判定すると0.02〜
4.53mg/kg となり、底質の暫定除去基準(昭和50 年環水管第119 号
環境庁水質管理局長通知)10mg/kg 以下であった。
結果(mg/kg) 測定箇所数(全40 地点)
ND 8 地点
0.01〜0.1 11 地点
0.11〜1.0 14 地点
1.1〜2.0 4 地点
2.1〜3.0 2 地点
〜12 1 地点
注)ND:PCB 含有量定量下限値(0.01mg/kg)未満
? 高砂市のPCB 底質調査
高砂市は昭和56 年度以降、現在に至るまで高砂西港内の1地点で
年1回底質含有試験を実施している。その結果は、定量下限値(0.01
mg/kg)未満〜9mg/kg の範囲内であった。
? 兵庫県の水質及び底質調査
兵庫県は、平成16 年9月13 日に水質及び底質の調査を実施した。
水質については、2地点とも定量下限値(0.0005mg/L)未満であ
った。
底質については、高砂西港内の底質6地点で含有試験を実施して
おり、その結果は、0.036〜7.5mg/kg 、平均2.13mg/kg であった。
2.2 PCB 関連法規の適用関係
盛立地の工事は「底質の処理・処分等に関する暫定指針」に適合した工
法で実施されている。
しかしながら、当時から30 年以上が経過して、関係法令が整備されて
きていることから、再度、現行の関係法令の適用について整理を行った。
盛立地の対策の検討に当たっては、たとえ関係法令の直接の適用はなく
ても、現行法令の基準に適合した対策をとるべきであるという考え方に立
つものである。
検討対象の法令は、「環境基本法」、「土壌汚染対策法」、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進
に関する特別措置法」及び「ポリ塩化ビフェニル等の取扱いの規制に関す
る条例」である。
(1)環境基本法(平成5年法律第91 号)
第16 条に基づく「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年
環境庁告示第46 号)では、「PCB の環境基準は、溶出量で検出されな
いこと(0.0005mg/L 未満)」とされている。しかしながら、同告示に
おいて、「環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らか
であると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋め立て地そ
の他の環境基準に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として
現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。」
とされている。
さらに「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年環水土第
116 号環境庁水質保全局長通知)では、「「底質の処理・処分等に関す
る暫定指針」により除去底質を埋め立てる場所、「海洋汚染及び海上災
害の防止に関する法律」に基づいて行われる水底土砂の埋め立て場所
など対象物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している
ものと認められる施設に係る土壌には環境基準を適用しないこととす
る。」とされている。
このため、高砂西港盛立地に環境基準は適用されないが、周辺環境
には適用される。
(2)土壌汚染対策法(平成14 年法律第53 号)
この法律では、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合は、「指
定区域」として指定(法第5条)するとともに、汚染土壌の撤去などの
措置を講じることなどを定めているが、「土壌汚染対策法の施行につい
て」(平成15 年環水土第20 号環境省環境管理局水環境部長通知)では、
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある土地の調査に関し、「土
壌環境基準が適用されないこととなっている土壌については、それが
適切に管理されている限りにおいて、特定有害物質を含んでいたとし
ても人が摂取する可能性はないと考えられることから、調査の命令な
どの対象とはならない。」とされている。
このため、高砂西港盛立地は土壌汚染対策法の対象外であるが、分
解処理する場合の評価のための基準値として、指定基準で判断するこ
ととした。
また、PCB の溶出試験方法として、土壌汚染対策法に基づく測定方
法(平成15 年環境省告示第18 号)を採用した。
(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(昭和46 年
10 月環整第43 号厚生省環境衛生局長通知)では、「港湾、河川のしゅ
んせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは、廃棄物処理法
の対象となる廃棄物でない。」としていることから、高砂西港盛立土は、
同法で定める廃棄物には該当しない。
(4)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13 年法律第65 号)
第2条では、「この法律において、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」
とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩
化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたも
のが廃棄物(廃棄物処理法第2 条第1 項に規定する廃棄物をいう。)
となったものをいう。」としている。
高砂西港盛立土は、廃棄物処理法で定める廃棄物でないことから、
この法律で規定するPCB 廃棄物に該当しない。
(5)ポリ塩化ビフェニール等の取扱いの規制に関する条例(昭和48 年条例第54 号)
この条例では、PCB を含有する廃棄物その他の物で知事が指定す
るものについて適切な管理などを 義務付けている。
知事が指定するものの一つに、排水施設その他の施設の堆積物で
PCB を含有するものがある。
盛立土については、高砂西港内に堆積していたPCB 含有底質土砂
を浚渫し、PCB が溶出しないよう固化処理を行ったものであることか
ら、知事が指定するPCB 又はPCB 製品には該当しない。
3 盛立地の安全性の検証
本委員会では、現時点での盛立地の安全性を検証するとともに、さらに今
後起こりうる地震などの自然災害を想定し、専門的な見地から安全性を検証
した。
安全性を検証するにあたり、地震時の液状化などに関する検討を行うため
に、測量、ボーリングなどの現地調査を実施した。
3.1 現地調査
調査は、平成18 年11 月21 日〜12 月20 日に実施した。
(1)測量及びボーリング調査(添付資料2参照)
盛立地及びその周辺に工事基準点を6箇所設け、平面測量(99,000
?)及び横断測量(5,000 ?)を行うとともに、盛立土本体2地点及び
外周部6地点でボーリング調査を実施した。
図3.1-1 ボーリング位置図
(2)盛立土の土質及びPCB 分析調査
盛立土法面の2地点においてボーリングを実施し、1期工事部分、2
期工事部分及び覆土の土質調査(土質定数など)を行うとともに、採
取した覆土及びPCB 含有固化土のPCB 分析を実施した。
土質調査については、盛立土の原位置での試験及び室内試験により、
安定解析に必要な土質定数を設定した。
(3)盛立地外周部の調査
盛立地外周部6 地点について15〜20m の深さまでボーリングを行い、
土質柱状図を作成し、土質定数の設定を行った。さらに採取した土壌
のPCB 分析を行った。
また、盛立土下部のカーバイド滓層、沖積粘性土層などの土質構成
を確認し、東西2ヶ所及び南北2ヶ所の地層横断面図を作成した。
3.2 盛立地の環境面の検討結果
PCB は、化学的に安定した物質であり、難水溶性かつ脂溶性である。
PCB は、難水溶性であることから地下水などを通じて外部に漏洩する可
能性は小さいが、安全性を高めるためには、盛立土と外部の水を遮断する
ことが重要である。そこで、周辺への漏洩を防ぐため、以下のように盛立
土の遮水状況を評価した。
(1)盛立土の遮水状況
? 盛立土上面及び法面の状況
盛立土上面は、遮水のために50mm のアスファルト被覆がなされてお
り、さらに、関係企業が継続して補修工事を行ってきていることから、
現時点で盛立土上部の遮水性については問題ない。
また、法面の覆土の下にアスファルト被覆があることを現地調査に
て確認している。
? 盛立土の下の状況
盛立土の下は、難透水性の厚さ1.8m のカーバイド滓層(透水係数
8.57×10-7cm /秒)であり、さらにその下に厚さ1.3〜3m の沖積粘性
土層(透水係数3.86×10-7cm /秒)が確認された。これらは土壌汚染
対策法に基づく封じ込め対策として遮水性があると認められる基準
(透水係数1×10-5cm /秒:厚さ5m)を元に換算すると、カーバイド
滓層は21m 及び沖積粘性土層は34m〜78m に相当する。
従って、盛立土の下の遮水性は非常に高いと判断できる。
(2)盛立地と地下水位
盛立地は地上部にあり、盛立地周辺の地下水位は、盛立土より1.5m
以上低いことが判明した。従って、地下水が盛立土と直接接触すること
はなく、周辺地下水と盛立土の間の物質移動はほとんどないと判断でき
る。
(3)PCB 分析結果
1)過去からの調査結果(添付資料1参照)
? 高砂市による調査
高砂市は、昭和51 年1月から現在に至るまで、盛立地周辺について、
年2回環境調査を実施している。(調査地点は図3.2-1)
調査内容は 盛立地周辺の水路1地点、雨水2地点、地下水7地点、
大気3地点、高砂西港内の水質3地点であり、その結果は、すべて定
量下限値(水質:0.0005mg/L、大気:0.05μg/m3)未満であった。
? 関係企業によるPCB 調査
(株)カネカ及び三菱製紙(株)は「高砂西港盛立地の管理に関する確
約書」に基づき、昭和52 年度から現在に至るまで、年2回盛立地周辺
の雨水2地点、地下水3地点、大気2地点で周辺環境調査を実施して
いる。(調査地点は図3.2-1)
その結果は、すべて定量下限値(水質:0.0005mg/L、大気:0.05μg/
m3)未満であった。
2)今回の調査結果
? PCB 含有固化土及び覆土のPCB 分析結果
現在の盛立土中のPCB 濃度を確認するため、今回実施したボーリン
グにより採取したPCB 固化土及び覆土中のPCB を分析した。
第1期工事部分の、PCB 溶出量(※1)は0.0006〜0.0024mg/L、PCB
含有量(※2)は280〜470mg/kg であった。
同様に第2期工事部分のPCB 溶出量は定量下限値未満、PCB 含有量
は22〜31mg/kg であった。
なお、覆土については、溶出量、含有量とも定量下限値未満であっ
た。
表3.2-1 PCB 含有固化土及び覆土のPCB 分析結果
ボーリングポイント 分析個所 溶出量
(mg/L)
含有量
(mg/kg)
覆土 ND ND
南西側法面部 第2期工事部分PCB 含有固化土 ND 22
第1期工事部分PCB 含有固化土 0.0006 280
覆土 ND ND
南東側法面部 第2期工事部分PCB 含有固化土 ND 31
第1期工事部分PCB 含有固化土 0.0024 470
注)ND:PCB 溶出量定量下限値(0.0005mg/L)未満、PCB 含有量定量下限値(0.05mg/kg)未満
※1 PCB 溶出量分析:平成15 年環境省告示第18 号による。
溶出試験 :水と対象土壌を混ぜ、6 時間振とうし、溶け出したPCB を測定する試
験をいう。
※2 PCB 含有量分析:底質調査方法(昭和63 年環水管第127 号環境庁水質保全局長通知)に
よる。
含有試験:対象土壌をアルカリにて1 時間分解した後、溶媒と混合し、PCB の全
量を測定する試験をいう。
? 盛立地周辺のPCB 分析結果
周辺土壌へのPCB の漏洩の有無を確認するため、盛立地周辺で今回実
施したボーリングにより採取した深度別の土壌についてPCB 分析(溶出
試験及び含有試験)を行った。
その結果(表3.2-2)は、いずれの深度でも定量下限値未満であった。
第2期工事終了後実施されてきた周辺地下水のモニタリング調査で
もPCB は検出しておらず、地下水を通じての周辺環境への漏洩がないこ
とを再確認した。
(4)まとめ
盛立土の上面、法面ともにアスファルトで被覆されている。
また、盛立土は、地面よりさらに上部に盛り立てられていることから、地下水と接触することはない。
さらにこれまでの周辺環境調査、今回の盛立土法面覆土調査及び周辺ボ
ーリング土壌調査においてPCB は検出されていない。
このように、盛立土から周辺へのPCB の漏洩が認められないこと、PCB
含有固化土の上面、法面及び下面が遮水されていることから、現時点にお
いてPCB の漏洩の可能性はない。
3.3 盛立地の構造面の検討結果(添付資料3参照)
盛立地は、現在まで安定を保っており、問題は生じていないが、今回、
「港湾の施設の技術上の基準・同解説」((社)日本港湾協会)などに基づき、
地震、液状化、高潮、大雨などの自然災害が発生した場合を想定して盛立
地の安定性を検討した。
(1)盛立土のすべり
地震時においても液状化が起こらなければ、盛立土にすべりは生
じないことが判明した。
一方、液状化判定の結果、内陸直下型やプレート型の大規模地震(兵
庫県地域防災計画で震度6強が想定されている山崎断層地震など)が起こ
った場合は、盛立土下部及び周辺地盤は液状化の可能性が高いことが判明
した。
この場合、盛立土法面肩部から法先部にかけてすべりが生じる可能性が
あることが判明した。ただし、水際線から離れていること及び液状化しや
すい厚さ5m 以上の地層が連続していないため、液状化によって起こる地
盤流動により盛立地が受ける影響は小さいと判断した。
(2)盛立地の沈下
現在、盛立土の施工後30 年が経過していること、及び今回実施した測
量結果などから、盛立地の圧密沈下は既にほぼ完了していると判断できる。
このために、残留沈下はほとんどなく、将来の不等沈下を考慮する必要は
ないと考えられる。
(3)津波時の盛立地の安全性
盛立地は、播磨灘に面しており、外洋で発生した津波の影響は小さい。
兵庫県沿岸域における津波被害想定調査報告書(平成13 年3月)による
と当該地区の津波高さはTP(東京湾平均海面)+1.8m が想定されているの
に対し、盛立地周辺地盤高さは概ねTP+4〜5m である。津波時の予想津
波高さと盛立地の地盤高さを比較検討し、安全であることを確認した。
(4)高潮時の盛立地の安全性
高潮ハザードマップ(平成18 年3月兵庫県)によると当該地区の高潮潮
位はTP+4.2m が想定されているのに対し、盛立地周辺地盤高さがTP+4.2m
より低いところは、西側道路沿いの法尻部のみであった。西側道路沿いの
最も低い地点でTP+4.03mであるので、最大浸水深さは17cm、流速は0.2
〜0.5m/秒と推定されることから、法面覆土が大きく浸食される心配もな
く、安全と考えられる。
(5)大雨時の盛立地の安全性
盛立地は、雨水を早期に排除できる構造となっており、形状や排水勾配
を考慮すると当該地区の100 年確率降雨強度の降雨(66.2mm/時)によっ
て法面覆土が浸食される可能性はないことが判明した。
一方、高潮と大雨が同時に起こった場合は、盛立地内の排水路が水没す
るため、盛立土周辺の法面の一部が冠水することが想定されるが、盛立土
覆土が冠水することはないことが判明した。
これらのことから大雨時についても、安全と考えられる。
(6)擁壁の安定性
当時の設計資料を現在の「道路土工擁壁工指針」((社)日本道路協会)
に基づき検討したところ、通常時は、敷地西側・北側の擁壁は問題ない
ことが確認されたが、東側擁壁については、鉄筋が不足していることが
判明した。
また、地震時は、敷地西側・北側擁壁について地盤の支持力が不足し
ていることが判明した。
なお、南側擁壁については、通常時、地震時においても問題がないこ
とを確認した。
なお、擁壁が破損した場合の土砂崩壊範囲は、擁壁の背後6m までで
あり、擁壁から盛立土までは16m 以上離れていることから、擁壁が破壊
しても直接盛立土に影響はない。ただし、土砂崩壊の拡大を防ぐための
応急処置として、崩壊土砂を除去し、斜面を土嚢及び遮水性シートで保
護するなどの対策を速やかに講じることが必要であり、そのための、擁
壁の変化の状態を早期に検知し、応急措置をとるための体制を整えてお
く必要がある。
(7)まとめ
検討の結果、盛立土は、地震(液状化が起こらない場合)、津波、高潮、
大雨に対して安全であることを確認した。しかし、大規模な地震により
液状化が起こった場合には、盛立土の一部が崩壊することが判明した。
また、盛立地最外周部の一部擁壁については、破損する可能性がある
ことが判明したが、擁壁の破損は小規模で影響範囲が限定的であること
から、盛立土本体の安全性に影響を与えるものではない。
4 今後の対策と課題
これまでの継続的な周辺環境のモニタリング及び今回の追加調査により、
周辺環境へのPCB の漏洩がないこと、地震(液状化が起こらない場合)、津波、
高潮、大雨に対して安全であることを確認した。
委員会では、将来にわたって盛立地の安全性をより確実にするための方策
を検討した。
恒久対策として、「全量撤去対策」、「現地分解処理対策」及び「現地封じ込
め対策」について、次の3つの視点から整理した。
? 確立された技術であり、盛立地の対策として適用可能であること。
? 周辺への影響が小さいこと。
? 実現性が高いこと。
なお、最外周部の擁壁の補強については、周辺の道路交通の安全を守る
という観点から、いずれの恒久対策をとる場合でも必ず実施すべき対策で
ある。
4.1 擁壁補強
盛立地最外周部の一部擁壁については、安定性を確保できていないこ
とが判明したが、破損しても盛立土の安全性に影響を与えることはない。
ただし、隣接する道路の安全性を確保する観点から、補強を行う必要
がある。
この補強工事は、どのような恒久対策をとる場合も実施されるべきである。
(1)工事内容
当時の設計資料及び土質調査結果を用いて最外周の擁壁の安定性に
ついて、「道路土工擁壁工指針」に基づき検討した。
この結果、東側擁壁は、鉄筋が不足していることが判明した。
さらに地震時には、敷地西側・北側擁壁について地盤の支持力が不足
していることが判明した。
このため、隣接道路の安全を確保するため、補強を行う必要がある。
西側、北側擁壁の補強例としては、a)擁壁背後の土砂を除去する、b)
底版を延長するなどが考えられる。
東側擁壁の補強例としては、a)擁壁背後の土砂を除去する、c) 水路
の蓋を固定して梁機能をもたせる、d)コンクリートを増し打ちするな
どが考えられる。
なお、対策の実施のために、さらに詳細な調査が必要である。
<西側・北側擁壁の例> ネットフェンス
<東側擁壁の例> ネットフェンス
(2)検討課題
擁壁補強は通常技術で対応できるが、工事に際してはPCB 盛立土に
影響を与えないよう慎重に行う必要がある。また、補強が施されるま
での間、擁壁の変化の状態を早期に検知し、応急措置をとるための体
制を整えておく必要がある。
水路
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおりである
? 工期
1年
内訳
・準備工事 :5ヶ月
・擁壁補修工事 :7ヶ月
? 概算事業費
2億円
表4.1-1 擁壁補強の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
擁壁補強工事 擁壁補強: 仮設フェンス、北側・東側・西
側擁壁の底版コンクリート増し打
ち工事など
2億円
4.2 恒久対策と検討事項
考えられる各恒久対策(表4.2-1)について、工法の実用化レベルや実
績、工事中のPCB 漏洩に対する安全性の確保などについて検討するととも
に、参考として工期及び事業費を試算した。(表4.2-2)
4.3 盛立地の恒久対策と課題
4.3.1 A1 全量撤去+分解処理方式
盛立土全量を現地から撤去し、大量のPCB 含有固化土を分解処理でき
る受け入れ先へ搬出し、分解処理する方法である。
(1)工事内容
盛立土の掘削場所を覆蓋し、全量を掘削して場外へ搬出し、分解処
理できる施設を保有する事業場に持ち込んで土壌汚染対策法の指定基
準値以下まで分解処理する。
(2)検討課題
? 受入先分解処理施設の確保
この対策を採用するためには、PCB を含有している大量の盛立土
(283,000m3)を分解処理することができる実用規模の既存施設の存
在が前提となる。
しかし、現時点で大規模の分解処理施設は稼働していない。
(分解処理施設については、B分解処理+現地埋め戻し(又は搬
出)方式を参照)
? 工事期間中の環境対策
盛立土を掘削し、分解処理施設へ運搬する際に、掘削した盛立土
の表面が乾燥し、粉じんが周辺へ飛散することが考えられる。
また、台風や降雨の対策として、盛立土掘削作業場所を強固なテ
ントなどにより覆蓋し、高性能の大容量集じん機を設置する必要が
ある。
図4.3.1-1 掘削場所覆蓋イメージ図
? 盛立土の運搬
掘削した盛立土は、有蓋ダンプ車など密閉構造の車両にて輸送を
行う必要がある。
図4.3.1-2 有蓋ダンプ車10 ?車
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおり。
? 工期
20 年
内訳:
・飛散防止工事など 1年
・搬出(搬出量283,000m3 ) 17 年
(搬出先300km 圏、受け入れ能力100 ?/日として、有
蓋10 ?トラックで250 日/年稼動で搬出した場合を想定した。)
・施設建設 2年
? 概算事業費
1,570 億円
表4.3.1-1 A1(全量撤去+分解処理方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
1掘削、搬出 移動式テント40m×40m×2 基、集じん
機(1,200m3/分)×2 基、アスファル
ト撤去、掘削・場内運搬、事前土壌分
析、10 ?ダンプトラック×10 台=100
?/日場外搬出
350 億円
2分解処理 分解処理施設600 億円、分解処理費600
億円。(環境対策、環境監視、分析費を含む。)
1,200 億円
3分解処理土の埋め立て
分解処理土搬出費、埋め立て処分費 20 億円
概算事業費総額 1,570 億円
(4)対策後のモニタリング
盛立土を全量撤去するので、現地でのモニタリングは不要となる。
4.3.2 A2 全量撤去+直接埋め立て処分方式
盛立土全量を現地から撤去し、直接最終処分場へ搬入する方法である。
(1)対策工事内容
盛立土の掘削場所を覆蓋し、全量を掘削して場外へ搬出し、最終処
分場へ持ち込んで埋め立て処分する。
(2)検討課題
? 受け入れ先の確保
この対策を採用するためには、分解処理をしないPCB 含有固化土
を大量に受け入れできる最終処分場の確保が課題となる。
また、埋め立て処分先として検討した「大阪湾広域臨海環境整備
センター」の最終処分場は、高濃度のPCB を含有する土壌の搬入を
想定しておらず、高濃度のPCB を含有した固化土を受け入れできる
設備を有していない。
? 工事期間中の環境対策
A1(全量撤去+分解処理方式)と同じ対策が必要。
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業は次のとおり。
? 工期
10 年
内訳:
・飛散防止工事など 1年
・搬出(搬出量283,000m3) 9年
(受け入れ能力200 ?/日として、有蓋10 ?トラック20
台/日×250 日/年で搬出した場合を想定した。)
? 概算事業費
400 億円
表4.3.2-1 A2(全量撤去+直接埋め立て処分方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
1掘削、搬出 A1対策と同じ 350 億円
2埋め立て 「大阪湾広域臨海環境整備センター」
と仮定した場合
50 億円
概算事業費総額 400 億円
(4)対策後のモニタリング
盛立土を全量撤去するので、現地でのモニタリングは不要となる。
図4.3.2-1 大阪湾広域臨海環境整備センター
神戸沖埋め立て処分場
出典:大阪湾広域臨海環境整備センターホームページ
4.3.3 B 分解処理+現地埋め戻し(又は搬出)方式
現在の盛立地近傍において、盛立土を土壌汚染対策法の指定基準値以
下まで分解処理し、現地へ埋め戻し又は場外に搬出し、最終処分場で埋
め立て処分を行う。
そこで、現在の分解処理技術の開発状況や実績のほか、掘削、分解処
理中の環境を検討するとともに工期及び事業費について試算した。
(1)工事内容
現地近傍に分解処理施設を設置し、掘削場所を覆蓋する。
盛立土を掘削して分解処理施設まで運搬し、盛立土を土壌汚染対策法
の指定基準値以下まで分解処理する。分解処理された盛立土は、再度現
地に埋め戻すか、又は最終処分場へ搬出する。
? 分解処理施設の建設
PCB 含有固化土を土壌汚染対策法の指定基準値以下に分解処理す
る方法を選定し、施設を建設する。
現在開発されている分解処理方法を表4.3.3-1 に示す。
表4.3.3-1 PCB 汚染土壌等処理技術の開発
分解処理方法 概要
還元加熱分離法+金
属ナトリウム分散体法
汚染土壌を窒素雰囲気下で間接加熱(500〜600℃)し、ガス
化によりPCB を分解・分離する。さらに金属ナトリウム分
散体により脱塩素化する。
間接熱脱着+水蒸気分解法
汚染土壌を間接加熱(400〜700℃)し、ガス化によりPCB を
分解・分離する。さらに水蒸気雰囲気下で間接加熱(1100℃
以上)により加熱分解する。
高温分解・焼成処理法
汚染土壌を高温乾燥処理(800〜900℃)し、ガス化により
PCB を分解・分離する。
さらにガスを2次燃焼(1100℃以上)にて加熱分解する。
減圧還元加熱処理法 汚染土壌を還元熱処理(600℃)し、還元脱塩素分解及びガ
ス化によりPCB を分解・分離する。さらにガスを2次燃焼
(1100 度以上)にて加熱分解する。
間接加熱酸化分解法 汚染土壌を間接加熱(450〜600℃)し、PCB を脱塩素化・分
解する。
水洗分解処理法 汚染土壌に水と空気を加え洗浄することによりPCB を分
離・濃縮する。さらに高温分解法で溶融分解する。
湿式酸化ラジカル法 汚染土壌を低酸素雰囲気下で間接加熱(600℃)し、PCB を分
解・除去する。さらに金属ナトリウム分散体にて脱塩素化
する。
溶剤抽出法 汚染土壌スラリーを加温加圧下(150〜200℃、1〜2MPa)で
水に溶出させ、OH ラジカルにて酸化分解する。
高温分解法 PCB に汚染された土壌等に電気を流すことによって高温溶
融(1,600℃以上)し、有害物を分解・無害化する。
(2)検討課題
? PCB 汚染土壌の分解処理の実績
全国の汚染土壌処理事例を調査したところ、現時点では、小規模
な分解処理施設の事例(10m3/日未満)はあるが、今回のような大
量のPCB 含有固化処理土を処理した事例はない。
表4.3.3-2 汚染土壌分解処理事例
処理場所 対象土壌 処理量
(トン)
完了年月 分解方法
和歌山県橋本市 ダイオキシン 汚染土壌 3,900 H16.9 高温分解
東京都大田区大森 ダイオキシン 汚染土壌 1,500 H18.3 溶剤抽出
大阪府能勢町 ダイオキシン 汚染土壌 9,000 H18.12 間接熱脱着+高温分解
? 工事期間中の環境対策
盛立土を掘削し、分解処理施設へ運搬する際に、掘削した盛立土
の表面が乾燥し、粉じんが周辺へ飛散することが考えられる。
また、台風や降雨の対策として、盛立土掘削作業場所を強固なテ
ントなどにより覆蓋し、高性能の大容量集じん機を設置する必要がある。
また、分解処理施設から排出される排ガスなどについては、活性
炭などによる高効率の処理装置が必要となる。
? PCB などの分析
工事期間中は、排ガスや周辺環境のモニタリングを適切に実施す
る必要がある。
分解処理施設を適正に運転するため、処理前処理後のPCB 含有量
を適切な頻度で把握する必要がある。
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおり。
? 工期
20 年
内訳:
・実証試験と技術の選定 1年
・施設建設(10 ?/日×10 基) 2年
・分解処理(処理量283,000m3) 17 年
? 概算事業費
1,500 億円
表4.3.3-3 B(分解処理+現地埋め戻し(又は搬出)方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
1掘削・埋め戻し(又は搬出)
移動式テント40m×40m×2 基、集じん機
(1,200m3/分)×2 基、アスファルト撤去、
掘削、場内運搬、事前土壌分析、埋め戻し工
事(又は搬出)
300 億円
2分解処理 分解処理施設600 億円、分解処理費600 億円。
(環境対策、環境監視、分析費を含む。)
1,200 億円
概算事業費総額 1,500 億円
(4)対策後のモニタリング
盛立土は全量分解処理されているので、対策後のモニタリングは不要
である。
4.3.4 C1 上部被覆方式
盛立土上部(周囲の法面を含む。)には、現状でも覆土及びアスファル
ト被覆が施されており、その安全性を確認しているが、さらに盛立土の
遮水効果を高め、封じ込め効果を確実にすることができる。
(1)工事内容
盛立土と外部との遮断を将来にわたって確実なものとするために、図
4.3.4-1 に示すとおり、現在のアスファルト被覆上を保護土で覆い、そ
の上を不織布と遮水シートで覆い、さらに1m 程度覆土する方法などがある。
図4.3.4-1 被覆構造と被覆工事の事例
(2)検討課題
? 保守点検
不織布及び遮水性シートの選定など上部被覆の構造設計に当たっ
ては、日常点検の方法や、災害、劣化などにより破損が生じた場合の
補修方法に配慮する必要がある。
? 地震などについて
上部被覆対策のみを実施する場合は、盛立地の下層地盤が液状化
するような大規模地震(震度6強)が発生した時には、盛立土の地斜
面の一部が崩落する可能性がある。
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおりである。
? 工期
2年
内訳
・準備工事 :5ヶ月
・上部被覆工事その他関連工事 :17 ヶ月
・片付工事 :2ヶ月
? 概算事業費
40 億円
表4.3.4-1 C1(上部被覆方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
上部被覆工事 覆土、シート設置、排水工事ほか 40 億円
(4)対策後のモニタリングなど
対策後は、現状よりさらに安全性が高められるが、適切な頻度でモ
ニタリングを継続する必要がある。
また、新たに設置する上部被覆シートなどを含め、適切に管理してい
く必要がある。
4.3.5 C2 上部被覆+遮水性地下土留め壁方式
盛立地の安全性の検証により、現状の盛立地の構造では大規模な地震
時に液状化が起こった場合には課題があることが判明した。
そのため、ここでは、現状の盛立地の液状化に対する対策と地下地盤
の遮水性を確保する対策を同時に検討した。
(1)対策工事内容
上部被覆については、4.3.4 と同様の内容とする。
さらに遮水性地下土留め壁を盛立土の周囲に施工することにより、液
状化対策及び盛立土の遮水性を高める対策となる。
大規模な地震により液状化が起こった場合、盛立土肩部から盛立土法
面にかけてすべり現象が発生する可能性が高いため、これを防止する対
策として、遮水性地下土留め壁を盛立土周囲の地下地盤に施工すること
が有効と考えられる。遮水性地下土留め壁の構造は、例えば、SMW 工法
(ソイルセメント壁工法)では、下図のように地中にセメントミルクを
注入しながら掘削した穴にH鋼を挿入して連続壁を形成するものであ
る。
図4.3.5-1 遮水性地下土留め壁工事のイメージ図
(2)検討課題
? 上部被覆工事
C1と同じ。
? 遮水性地下土留め壁工事
遮水性地下土留め壁を設計施工するに当たっては、土質定数の
ために振動三軸試験を実施し、液状化時の対策のために地震応答
解析やすべり変形解析を実施するなどさらに詳しく調査する必要
がある。
(3)工期及び概算事業費
工期及び概算事業費は次のとおりである。
? 工期
2年
内訳
・準備工事 :5ヶ月
・遮水性地下土留め壁工事及び
上部被覆工事その他関連工事 :17 ヶ月
・片付工事 :2ヶ月
? 概算事業費
75 億円
表4.3.5-1 C2(上部被覆+遮水性地下土留め壁方式)の概算事業費
工事内容 概算見積条件 概算事業費
1上部被覆工事 覆土、シート設置、排水工事ほか 40 億円
2遮水性地下土留め壁工事
遮水性地下土留め壁工事 35 億円
概算事業費総額 75 億円
(4)対策後のモニタリングなど
対策後は、現状よりさらに安全性が高められるが、適切な頻度でモ
ニタリングを継続する必要がある。
また、新たに設置する上部被覆シートなどを含め、適切に管理してい
く必要がある。
B 現地分解処理対策擁壁補強
A1 全量撤去+分解処理方式A2 全量撤去+直接埋め立て処分方式B 分解処理→現地埋め戻し(又は搬出)方式C1 上部被覆方式C2 上部被覆+遮水性地下土留め壁方式いずれの対策にも必要
・盛立土を全量搬出し、別の場所で分解処理する。・盛立土を全量搬出し、別の最終処分場に直接埋め立てる。
・現地近傍に分解処理施設を設置し、盛立土を全量掘
削し、分解処理施設で環境基準値以下のレベルまで分解処理する。
・処理後物は、再び現地に埋め戻す。(又は搬出)
・盛立土へ雨水の浸入を防止するため、遮水シート、
不織布等により、盛立土の上部(周囲の法面含む)に
遮水工事を行う。
・C1の上部被覆に加えて、盛立土周囲の地下地盤に
遮水性地下土留め壁工事を行う。
・盛立地の周辺に設置されている擁壁の一部で、通常
時でも強度が不足している箇所の補強を行う。
?背面土砂の除去による土圧低減
?コンクリート増打ちあるいは底版の延長
?上記??の組み合わせ
1
対策技術
の現状
・盛立土を掘削搬出する技術については土壌汚染対策
工事等多くの実績があり技術的な課題はない。
・分解処理技術については、汚染土壌の小規模な処理
設備はあるが、大規模な処理施設は稼働していない。
・盛立土を掘削搬出する技術については、A1と同じ。
・受入先の有無を事前に調査する必要がある。
・汚染土壌の小規模な処理設備はあるが、大規模な処
理施設は稼働していない。
また、固化処理土では、実証実験の実施例がない。
・遮水工事は、最終処分場の遮水対策など多数の実
績がある。
・遮水性地下土留め壁は、護岸工事、地下構造物築
造工事、最終処分場遮水工事など、日本全国で多数
の実績があり、技術的な問題はない。
・遮水性地下土留め壁を施工するに当たっては、さら
に詳細に解析等を行う必要がある。
・多数の実績があり、技術上の問題はない。
2 工期
20年
1.飛散防止工事等:1年
2.掘削・搬出:17年(100トン/日で想定)
3.施設建設:2年
10年
1.飛散防止工事等:1年
2.掘削・搬出:9年(200トン/日で想定)
20年
1.実証試験と技術の選定:1年
2.施設建設:2年
3.分解処理:17年
2年
1.上部被覆工事:2年
2年
1.遮水性地下土留め壁工事:2年
(上部被覆工事も同時施工可能)
1年
1.準備工事:5ヶ月
2.補強工事:7ヶ月
3
事業費の
試算
(概算)
1,570億円
(内訳)
1.掘削・運搬費:350億円
2.処理施設償却費:600億円
3.分解処理費:600億円
4.埋立て処分費:20億円
400億円
(内訳)
1.掘削・運搬費:350億円
2.埋立て処分費:50億円
1,500億円
(内訳)
1.掘削盛立て費等:300億円
2.処理施設建設費:600億円
3.分解処理費:600億円
《参考》
北九州PCB廃棄物処理施設の建設費
約300億円(5t/日) 60億円/t
40億円
(内訳)
1.上部被覆工事費:40億円
75億円
(内訳)
1.上部被覆工事費:約40億円
2.遮水性地下土留め壁工事費:35億円
2億円
(内訳)
1.擁壁補強工事費:2億円
恒久対策一覧
総合評価
・上部被覆の面積、構造等はC1と同じ
・遮水性地下土留め壁の全延長は1,250mとする。
・遮水性地下土留め壁の構造は、φ850、L=18mの
ソイルセメント壁とする。
積算の
前提条件
・外周道路に対する安全対策
・補強が施されるまでの間、擁壁の点検や応急措置を
とるための体制が必要。
・盛立土の掘削を行うため、掘削中に長期にわたり
PCB含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散
リスクが継続する。
・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。
・受け入れ可能な最終処分場の確保が課題である。
・盛立土の掘削を行うため、掘削中に長期にわたり
PCB含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散
リスクが継続する。
・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。
・受け入れ可能な施設の確保が課題である。
・工期が長期にわたるため、別途対策が必要である。
(大規模地震時の液状化対策工事などを事前に実施
しておく必要がある。)
・盛立土の掘削を行うため、掘削中及び処理施設での
処理中に長期にわたりPCB含有固化土由来の粉じん
等の周辺環境への飛散リスクが継続する。
・場合によっては、近隣住民の移転等が必要である。
・大規模処理施設の建設が必要。
・処理施設の設置場所の用地確保が必要。
・PCB含有固化土の処理実績はない。
・盛立土の掘削がないため、PCB含有固化土由来の
粉じん等が飛散するリスクはない。
・工事終了後、モニタリングと適切な管理が必要であ
る。
・盛立地の地下地盤が液状化した場合でも、盛立土
の滑りを防止し、盛立土の封じ込め効果が高く、万が
一のPCB漏洩にも対応できる。
・盛立土の掘削がないため、PCB含有固化土由来の
粉じん等が飛散するリスクはない。
・工事終了後、モニタリングと適切な管理が必要であ
る。
・震度6強の大規模地震時には、地盤が液状化して
盛立地斜面に滑りが生じる可能性がある。
事業概要
・擁壁解体時の掘削残土は一般残土として処分できる
ものとする。
・盛立地東側、北側及び西側の擁壁の底版にコンク
リート増打ち等を実施する。
A 全量撤去対策
・盛立土の数量はA1と同じ。
・搬出は、10トンダンプトラック20台/日。
・搬出日数は、250日/年(土日祝除く)
・盛立土は管理型処分場で埋立処分できるものとす
る。
・盛立土の数量は283,000m3とする。
・盛立土はH17環境省公募PCB処理法等で分解処理で
きるものとする。
・処理能力は、10t/日規模の施設を10台設置し、365日
24時間連続運転で稼働効率を7割として想定。
・処理費はダイオキシン汚染土壌処理実績およびH17
環境省公募処理法公開資料から試算。
・盛立土掘削箇所に粉じん飛散防止のための仮設テン
トを設置できるものとする。
・分解処理前の土壌分析は、PCB溶出・含有を100t当
り1検体とする。
・分解処理後の土壌分析は、土壌汚染対策法の指定
基準項目すべての溶出とPCB含有を100t当り1検体と
する。
・盛立土の単位体積重量は1.5t/m3とする。
・搬出は、10トンダンプトラック10台/日。
・搬出日数は、250日/年(土日祝除く)
・盛立土の数量は283,000m3とする。
・盛立土はH17環境省公募PCB処理法等で分解処理で
きるものとする。
・処理費はダイオキシン汚染土壌処理実績およびH17
環境省公募処理法公開資料から試算。
・盛立土掘削箇所に粉じん飛散防止のための仮設テン
トを設置できるものとする。
・盛立土の単位体積重量は1.5t/m3とする。掘削、分解
処理についてはBに同じ。
C 現地封じ込め対策
・上部被覆の面積は55,436m2とする。
・上部被覆の構造は、盛立土上の既設アスファルトの
上に、下から順番に保護土(粘性土)0.75m、不織布、
遮水シート、不織布、良質土とする。
・盛立地天端面の覆土はTP+14mまでとする。
【添付資料】
1 盛立地の周辺環境調査結果
2 土質調査資料
(1)盛立地平面図(1/1,500)
(2)盛立地土層断面図(1/1,500)
3 安定性検討資料
(1)安定性検討の概要
(2)盛立土(固化処理土、覆土)のすべり検討
(3)擁壁の検討
(4)擁壁の検討結果
(5)液状化の検討
(6)液状化時の現象
(7)沈下の検討
(8)津波に関する検討
(9)大雨に関する検討(排水能力、流域図)
http://www.city.takasago.hyogo.jp/index.cfm/8,3862,c,html/3862/20080108-100507.pdf
2009年11月07日
用 語 集 等(化学物質の環境リスク評価)
用 語 集 等
1.用語説明
(1) 略語
ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.(米国産業衛生専門家会議)
米国の産業衛生の専門家の組織で、職業上及び環境上の健康についての管理及び技術的な分
野を扱っている。毎年、化学物質や物理的作用及びバイオモニタリングについて職業上の許容
濃度の勧告値(TLV:Threshold Limit Value)や化学物質の発がん性のランクを公表し、世界的
にも重要視されている。
ADI:Acceptable Daily Intake(許容1 日摂取量)
健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重
1 kg 当たりの摂取量。コストと便益にもとづいた概念で、農薬や食品添加物の残留基準の設定
に用いられ、ここまでなら許容できる量を示すもの。
AQUIRE:AQUatic toxicity Information Retrieval (http://www.epa.gov/ecotox/)
米国環境保護庁 (U.S. EPA) が水生生物や水生植物に対する化学物質の毒性影響の知見を基に
構築しているデータベース。1970 年以降に発表された大半の論文を収録しており、定期的にデ
ータを追加している。2001 年10 月31 日改訂時の収録化学物質数は7,964 物質、収録文献数は
17,717 文献である。AQUIRE (水生生物)、PHYTOTOX (陸生植物)、TERRETOX (野生動物)を統
合したものをECOTOX と呼んでいる。
ATSDR:Agency for Toxic Substances and Disease Registry (米国有害物質・疾病登録局)
米国保健福祉省に属する機関であり、有害物質へのばく露や関連する疾病を防ぐために信頼
できる情報提供を行っている。
BMD, BMC:Benchmark Dose (BMD) , Concentration (BMC)(ベンチマーク用量、濃度)
用量−反応関係の曲線から計算されるある割合の有害影響を発現する用量(あるいはその上
側信頼限界値)をベンチマーク量として、無毒性量や最小無毒性量の代わりに用いる方法である。
CERHR:Center for The Evaluation of Risks to Human Reproduction (ヒト生殖リスク評価センター)
米国国立環境衛生研究所(NIEHS:National Institute of Environmental Health Science)によって
1998 年にNTP(National Toxicology Program)のもとに設立した機関。ヒトがばく露する可能性の
ある化学物質によって引き起こされる生殖に関する有害な影響を、タイムリーに公平に科学的
に評価することを目的としている。
CICAD:Concise International Chemical Assessment Document(国際簡潔評価文書)
国際化学物質安全性計画(IPCS)の出版物のうち、最も新しいシリーズである。既存の化学
物質の健康と生態系への影響について国際機関における評価作業との重複を省きつつ、これら
を基にして国際的に利用可能な簡潔な新たな安全性評価文書を作成するもので、主要な目的は
化学物質のばく露による有害性の解析と、量−影響の定量的な記述にある。
DFG:Deutsche Forschungsgemeinschaft (ドイツ学術協会)
ドイツの非政府機関であり、政府からの資金を受けて、人文・自然科学の学問領域における
研究プロジェクトに寄与し、政府への助言を行う。化学物質の職場環境における許容濃度等、発
がん性の分類について情報提供を行っている。
EC50:Median Effective Concentration(半数影響濃度)
ばく露期間中試験生物の50%に(有害)影響を及ぼすと予想される濃度。影響内容が、
生長(成長)や遊泳阻害、繁殖など死亡以外の時に用いられる。
EHC:Environmental Health Criteria(WHO環境保健クライテリア)
国連環境計画(UNEP)、国際労働機関(ILO)および世界保健機関(WHO)により設立され
た国際化学物質安全性計画(IPCS)の中核事業として作成されているモノグラフで、ヒトの健
康と環境に対して有害な影響を与えないように、化学物質の管理を適切に行うための判断の基
礎となる科学的知見を物質毎にまとめた評価文書のシリーズ。化学物質の評価について、多く
の国際協力事業がある中で、WHO を中心とするIPCS は評価が高く、また、権威のある評価文
書の作成事業として知られている。
EPI:Exposure/Potency Index(ばく露量/発がん強度比率)
カナダの環境省(Environment Canada)及び厚生省(Health Canada)の優先物質リスト(Priority
Substance List Assessment Report)で使用されている化学物質の発がん性のリスクを表す指数。動
物の慢性ばく露実験において過剰な腫瘍発生率が5 %となる用量(TD05)あるいは濃度(TC05)
を用いてばく露量との比を計算する。なお、TD05はTD0.05、TC05 はTC0.05 として表記される場合
もある。
GDWQ:Guideline of Drinking Water Quality(WHO 飲料水水質ガイドライン)
ヒトの健康を保護することを目的として、飲料水中に含まれる潜在的に有害な成分の濃度あ
るいは飲料水の性状について定めたWHOのガイドライン。健康に影響を及ぼすことが知られて
いる飲料水中の汚染物質について、各国で飲料水の安全性を保証する水質基準を策定するため
の基礎として使用されることを意図している。
HEAST:EPA's Health Effects Assessment Summary Tables(EPA健康影響評価要約表)
米国環境保護庁(米国EPA)により、大気清浄法修正条項(1990 年)で指定された大気汚染
物質(一部の物質を除く)のハザード、ばく露情報、毒性情報(一般毒性、生殖・発生毒性、発
がん性)等の要約および出典を提供している。
IARC:International Agency for Research on Cancer(国際がん研究機関)
WHO により1965 年に設立された国際的な機関。ヒトのがんの原因に関する研究及び方向性
の提示並びにがんを科学的に制御するための方策を研究することを目的とし、ヒトに対する化
学物質の発がん性について以下に示す5 段階で分類評価を行っている。
1:ヒトに対して発がん性が有る。
2A:ヒトに対して恐らく発がん性が有る。
2B:ヒトに対して発がん性が有るかもしれない。
3:ヒトに対する発がん性については分類できない。
4:ヒトに対して恐らく発がん性がない。
IPCS:International Programme on Chemical Safety(国際化学物質安全性計画)
WHO、ILO、UNEP の共同事業で、化学物質による健康障害を未然に防ぐために化学物質の
安全性に関する正当な評価を取りまとめ、環境保健クライテリア(EHC)、国際化学物質安全
性カード(ICSC)等を発行している。また、アジェンダ21 の決定に基づき、化学物質の危険有
害性の分類等について国際的調和をはかっている。
IRIS:Integrated Risk Information System
米国環境保護庁(U.S. EPA)により、化学物質のリスク評価やリスク管理に利用することを
目的として作成されている化学物質のデータベースシステム。化学物質によるヒトへの健康影
響に関する情報(慢性毒性評価、発がん性評価)が個々の化学物質ごとに収集されている。
JECFA:FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives(FAO/WHO合同食品添加物専門家
会議)
FAO とWHO により設置された食品添加物等の安全性評価等を行う国際機関。各国の添加物
規格に関する専門家及び毒性学者からなり、各国によって実施された添加物の安全性試験の結果
を評価し、一日摂取許容量(ADI)を決定しており、会議報告は、WHO テクニカルレポートシ
リーズとして毎年公表されている。
JMPR:JOINT FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues(FAO/WHO 合同残留農薬会議)
WHO とFAO が共同して1963 年に設置した機関。農薬の使用による食品への残留について検
討するFAO Panel と農薬の毒性面について検討するWHO Expert Group から構成される。FAO
Panel では、適切な農薬規範に従って有効な散布量を最小限用いた場合に作物に残留するレベル
として最大残留基準を設定し、WHO Expert Group では、毒性関連データに基づいて農薬のADI
について審議を行っている。最大残留基準は、残留農薬規格委員会の検討を経て国際食品基準
となり、ADI は各国で安全評価を進める際の参考とされる。
LC50:Lethal Concentration 50, Median Lethal Concentration(半数致死濃度)
1 回のばく露(通常1 時間から4 時間)で1 群の実験動物の50%を死亡させると予想さ
れる濃度。生態毒性試験においては、ばく露期間中試験生物の50%を死亡させると予想さ
れる濃度のことをいう。
LCLo:Lethal Concentration Lowest(最小致死濃度)
特定のばく露時間での吸入によりヒトまたは動物を致死させたばく露濃度の最小値。関連し
た報告値の中での最小の致死濃度(Lowest Published Lethal Concentration)の意味に用いられるこ
ともある。
LD50:Lethal Dose 50(半数致死量)
1 回の投与で1 群の実験動物の50%を死亡させると予想される投与量。
LDLo:Lethal Dose Lowest(最小致死量)
ヒトまたは動物を致死させた吸入ばく露以外の経路による投与量の最小値。関連した報告値
の中での最小の致死量(Lowest Published Lethal Dose)の意味に用いられることもある。
LOEC : Lowest Observed Effect Concentration (最小影響濃度)
最小作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な(有害)影響を及ぼす最も低
い濃度のこと。
LOAEL:Lowest Observed Adverse Effect Level(最小毒性量)
毒性試験において有害な影響が認められた最低のばく露量。
LOEL:Lowest Observed Effect Level(最小影響量)
最小作用量ともいう。毒性試験において何らかの影響が認められる最低のばく露量。影響の
中には有害、無害両方を含むので、一般にはLOAELに等しいかそれより低い値である。
MATC:Maximum Acceptable Toxicant Concentration(最大許容濃度)
最大許容毒性物質濃度ともいう。NOEC とLOECの間にあると仮定される毒性の閾値を
指し、両者の幾何平均濃度として算出される。
MOE:Margin of Exposure
今のばく露量がヒトのNOAELに対してどれだけ離れているかを示す係数でNOAEL/ばく露
量により算出する。この値が大きいほど安全への余地があるということを示している。なお、
動物実験の結果から求められたNOAELの場合には、NOAEL/ばく露量/10 により算出する。
NCI:National Cancer Institute(米国国立がん研究所)
米国保健福祉省(DHHS:Department of Health and Human Services)に所属する機関で、がんの
原因と予防、診断・処置およびがん患者のリハビリテーション等を研究している。
NIOSH:National Institute for Occupational Safety and Health(国立労働安全衛生研究所)
職業上の疾病や傷害を防ぐための研究や勧告を行う米国保健福祉省疾病予防管理センターに
所属する機関。約15 万の化学物質の毒性情報を収載したRTECS データベース(Registry of Toxic
Effects of Chemical Substances)を編纂している。
NOAEL:No Observed Adverse Effect Level(無毒性量)
無副作用量、最大有害無作用レベル、最大無毒性量と訳すこともある。何段階かの投与用量
群を用いた毒性試験において有害影響が観察されなかった最高のばく露量のことである。この
値に安全係数や不確定係数を乗じて、ADI やTDI を求めることがある。
NOEC : No Observed Effect Concentration (無影響濃度)
最大無影響濃度、最大無作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な(有害)
影響が認められなかった最高濃度であり、LOECのすぐ下の濃度区である。
NOEL:No Observed Effect Level(無影響量)
毒性試験において影響が認められない最高のばく露量。影響の中には有害、無害両方を含む
ので、一般にはNOAELに等しいかそれより低い値である。
NTP:National Toxicology Program(米国国家毒性プログラム)
米国保健福祉省(DHHS)により1978 年に設置された事業。米国の各省庁が実施している化
学物質の毒性研究をまとめ、発がん性物質の分類、試験を行っている。NTP が発行している発
がん性年報のデータは、情報提供のみを目的としたものである。
PEC:Predicted Environmental Concentration (予測環境中濃度)
予測される環境中の化学物質濃度を指す。実測データを基に決めているが、データが少ない
場合には生産量や排出量などから推定する。生態リスク評価は、このPEC とPNEC を比較して
行う。
PMR:Proportional Mortality Ratio(特定死因死亡比)
一定の集団において、特定原因による観察死亡数の割合を、標準人口における同じ原因によ
る期待死亡数の割合で除して求められる値。
PNEC:Predicted No Effect Concentration (予測無影響濃度)
水生生物への影響が表れないと予測される濃度を指す。環境中の全生物種への影響を捉える
ことは困難なため、試験生物種の毒性濃度から全生物種への影響を推定した値である。
SIDS:Screening Information DataSet(初期評価データセット)
OECD 加盟国のいずれか1 ヵ国又はEU 加盟国全体での年間生産量及び輸入量が1,000 トンを
超える既存化学物質について、安全性評価を行うために必須な最小限のデータセットについて
情報を収集し、この情報が欠如している場合には試験を行った上で、環境生物への影響、ヒト
への健康影響についての初期評価を加盟国が分担してまとめている。
SIR:Standardized Incident Ratio(標準化罹患比)
ある特定の状況下にある対象集団の罹患数と、その集団が罹患率の分かっている標準人口と
同じ罹患率を有すると仮定したときに期待される罹患数との比。
)(標準人口の年齢別罹患率対象集団の年齢別人口の総和
ある期間に対象集団で観察された罹患数
´
SIR =
SMR:Standardized Mortality Ratio(標準化死亡比)
対象集団における観察死亡数と、対象集団の年齢別死亡率が標準人口のそれと等しいと仮定
したときに期待される死亡数との比。
(標準人口の年齢別死亡率対象集団の年齢別人口)の総和
対象集団の観察死亡数
´
SMR =
TCLo:Toxic Concentration Lowest(最小中毒濃度)
ヒトまたは動物に中毒症状を引き起こさせた吸入によるばく露濃度のうちの最小値。
TDI:Tolerable Daily Intake(耐容1 日摂取量)
健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重
1 kg 当たりの摂取量。
TDLo:Toxic Dose Lowest(最小中毒量)
ヒトまたは実験動物に中毒症状をおこさせた吸入ばく露以外の経路による投与量の最小値。
TLV:Threshold Limit Value(作業環境許容濃度)
ほとんどすべての作業者が毎日繰り返しばく露しても、有害な健康影響が現れないと考えら
れる化学物質の気中濃度についてのACGIHによる勧告値。産業界の経験、ヒトや動物による試
験・研究等の利用可能な情報に基づいている。これら情報の量と質は物質によって異なるため、
TLV の精度には幅があり、また、TLV は安全濃度と危険濃度の間のはっきりした線ではないし、
毒性の相対的な指標でもない。TLV は時間加重平均(TWA)等で示される。
TWA:Time Weighted Average(時間加重平均)
通常の1 日8 時間、週40 時間労働の時間加重平均濃度。
WHO:World Health Organization(世界保健機関)
世界の公衆衛生の向上や、伝染病対策、環境問題等を取り扱っている国際機関。「すべての
人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的に掲げている。
(2) 用語
アセスメント係数
生態リスク評価において、限られた試験データから化学物質の予測無影響濃度(PNEC)を求
めるために用いる係数で、感受性の種間差、急性毒性値と慢性毒性値の違い、実験生物から野外
生物への毒性値の外挿等を考慮して設定されている。
in vitro、in vivo
in vitro は、人工的な器具内で行われる生物学的な反応に関して使われる言葉で、「試験管内」
を意味する。多くの場合、生物体機能の一部を試験管内において行わせることを指す。一方、in
vivo は、生きている細胞あるいは生体内に置かれている状態を指す語で、「生体内」を意味し、
対象とする生体の機能や反応が生体内で発現される状態を示す。たとえば、心臓細胞の収縮が
動物体内で起こればin vivo、試験管内で行われていればin vitro における機能発現である。
一日ばく露量:daily exposure
ヒトの1 日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ15 m3、2 L及び2000 g と仮定し、体重を
50 kg と仮定した場合の一日あたり体重1 kg あたりのばく露量(μg/kg/day)を示す。
一般毒性:general toxicity
急性毒性、亜急性毒性(亜慢性毒性)、慢性毒性をまとめて、一般毒性と言う。これらは、
毒性学の領域において、もっとも基本的なもので、化学物質の危険性を知るための基礎を提供
する。
一本鎖切断: single-strand breaks
二本鎖DNAにおいて、両鎖のうち一つの鎖のみ切れ目が入っているが、両鎖は互いに切り離
されていない状態。
遺伝子突然変異:gene mutation
DNA 塩基の置換、欠失、挿入などにより、単一遺伝子または調節遺伝子の塩基配列に生じた
恒久的な変化のこと。
遺伝子変換:gene conversion
相同染色体間及び対立遺伝子間の交換を指す。相同なDNA配列(対立遺伝子あるいは非対立
遺伝子)間の遺伝的情報の非相互的な組換えを行うこと。
遺伝的組換え:genetic recombination
2つ以上の形質に関して、遺伝子型が異なる両親の遺伝物質が交配などにより1つの個体に持
ち込まれたとき、いずれの親にも見られなかった新しい遺伝子の組合せを持った子孫が突然変異
によらずに生じること。すなわち、同一染色体上にある遺伝子の組合せが交叉によって組換えら
れる現象をいう。
遺伝毒性、遺伝子毒性(遺伝子傷害性):genetic toxicity, genotoxicity
化学物質や物理的要因の遺伝的過程に対する傷害で、染色体の異数性、付加・欠失・再結合
等の染色体異常及び遺伝子突然変異に起因する。遺伝物質に対する毒性の総称であり、DNA 傷
害性、突然変異誘発性、染色体異常誘発性を包含する。
内環境
ある環境がより小さい領域の環境を取り囲む構造(入れ子構造)を持つ多媒体モデルにおいて
は、内側を内環境、その外側を外環境と呼ぶ。入れ子構造を持つ多媒体モデルとしては、例
えばBrandes LJ et al. (1996)のSimpleBox2.0 がある。
環境リスク初期評価では、内環境は都道府県を、外環境には日本全国から内環境を差し引い
た環境を設定している。
hprt 遺伝子座位:hprt locus
ヒポキサンチン ホスフォリボシル転移酵素をコードする遺伝子座位。X染色体上にある。hprt
遺伝子の欠損変異は、6−チオグアニン抵抗性を標識として容易に選別できることから、突然変
異頻度の測定手段として用いられている。
疫学:epidemiology
ヒトの集団を対象として、ヒトの健康およびその異常の原因を、病因、環境等の各面から包
括的に考察する学問分野で、健常者を含めたヒトの集団全員を対象にして、主に疾病の予防方
法を研究する。
エームス試験:Ames test
遺伝毒性試験の一つであり、B. N. Ames が開発したネズミチフス菌を用いて復帰突然変異を
検出する試験系。化学物質の遺伝毒性の検出、がん原性のスクリーニングとして広く用いられる。
塩基対置換:base (pair) substitution
DNA中の特定の塩基対が他の塩基対に置換されること。これにより、DNA分子としての機能
に変化が生じる。
感作性:sensitization
免疫機能を障害し、アレルギーを起こさせる性質のこと。アレルギー誘発性ともいう。
急性毒性:acute toxicity
動物あるいはヒトに化学物質等を単回投与あるいは短時間中(1 日以内)に持続注入あるいは
反復投与した場合に投与開始直後から1〜2 週間以内に現れる毒性。急性毒性試験では、症状の
種類、程度、持続時間、死亡の状態等を指標として、中毒量や致死量を算出する。急性毒性の
最も明確な毒性指標としてはLD50(半数致死量)がある。
ケースコントロール研究:case control study
患者対照研究のことで、研究対象とする疾病をもつ人の群と、その疾病をもたない適切な対
照群とを用いた観察的疫学研究方法。患者と非患者それぞれについて、ある属性がどの程度であ
るかを比較することによって、その属性と当該疾病との関連性を検討する。文字どおりケース(研
究対象としている患者)とコントロール(対照)の群を設定して、過去の関心ある危険因子に関
する記録を調査し、その関連を検討するものである。限られた時間内に研究が行えるので実際的
な研究方法である。代表的な研究例としては肺がんの研究が有名である。しかしながら、ケース
とコントロールの比較の背後には潜在的に多くのバイアスが存在し、得られた結果の解釈が容易
でない場合が少なくない。
限度試験:limit test
環境中ある濃度以上に被験物質が存在することがないか、その濃度以上での影響は無視
しうると考えられる場合、その濃度区のみの試験をすることを限度試験という。毒性値を
求めるのではなく、その濃度における影響の有無を調べる。通常生態毒性試験では、100mg/L
または水溶解限度のより低い方の濃度となる。
コホート調査:cohort study
疫学研究方法の一つ。疾病発生に関連していると考えられる仮説因子の有無もしくはばく露
の程度が確認できる集団を一定期間観察し、その間の疾病発生頻度を仮説因子の有無もしくは
ばく露の程度別に比較する方法。
催奇形性:teratogenicity
化学物質等が次世代に対して、先天異常を引き起こす性質。
細胞形質転換:cell transformation
培養細胞が放射線、ウイルス、化学物質などによってその形態や機能をかえ、腫瘍細胞類似
の性質を備えること。
細胞遺伝学:cytogenetics
染色体の構造や形態、染色体に存在する遺伝子の行動と形質発現など、細胞学的な特徴から
遺伝現象を明らかにしようとする遺伝学の一分野。遺伝毒性試験の中でin vitro、 in vivo 染色体
異常試験、小核試験、及び優性致死試験などは細胞遺伝学試験とよばれている。
姉妹染色分体交換:sister chromatid exchange, SCE
姉妹染色分体の部分的な交換(2本の姉妹染色分体の間で同じ部位が入れ替わること)。こ
れを利用して遺伝毒性を検出する方法がある。SCE は、染色体の構造異常とは異なる現象である。
宿主経由試験:host-mediated assay
宿主動物の腹腔内に微生物を注入した後に、被験物質を投与し、回収した微生物の突然変異
頻度を調べることにより、哺乳類の代謝物の変異誘発性を評価する試験。
小核:micronucleus
染色体の構造異常または分裂装置の損傷により、細胞分裂後に細胞質中に取り残された染色
体断片、あるいは1〜数本の染色体に由来する小さな核。小核の誘発を検出する試験を小核試験
といい、げっ歯類の骨髄あるいは末梢血の塗抹標本を観察して、小核を有する幼若赤血球の出現
頻度より、被験物質の染色体異常誘発性を調べる。
数的異常:numerical aberration
染色体異常の分類の一つで染色体の数の変化を指す。数的異常には異数性(aneuploidy)と倍
数性(polyploidy)があり、前者は染色体の数が1〜数本増加または減少するもので、後者は染
色体基本数(n)が整数倍化する現象をいう。
スロープファクター:slope factor
体重1 kg あたり1 mg の化学物質を、毎日、生涯にわたって経口摂取した場合の過剰発がんリ
スク推定値。
がんの過剰発生率=スロープファクター(mg/kg/day) -1× 経口ばく露量(mg/kg/day)
生殖・発生毒性:reproductive and developmental toxicity
化学物質等の環境要因が生殖・発生の過程に有害な反応を引き起こす性質。親世代からみれ
ば生殖毒性(reproductive toxicity)、次世代を中心にみると発生毒性(developmental toxicity)で
ある。両者については研究者によってそれぞれ概念がことなるが、一般には生殖毒性は受胎能
の障害、発生毒性は生殖細胞の形成から受精、出生を経て、個体の死に至る発生の何れかの時
期に作用して、発生障害(早期死亡、発育遅滞、形態異常、機能異常)を引き起こす性質と定
義される。
線形多段階モデル:linearized multistage model
発がんに至るには多段階のステップが関与することを考慮に入れた数学モデルであり、実際
にヒトがばく露されるような低濃度においては、高次の項目は無視し得ることになるため、用量
の1次式(線形)で表せることになる。このモデルにおいて直線の傾き「q* 」(一般に95%信
頼区間上限値)を発がん性の強さの指標とし、スロープファクターと呼ぶ。
2
p(D) =1 - exp{-q0 - q1D - q 2D …… q D } , qi 0
k
k >
p(D) :用量Dにおける生涯の発がん率 D :用量
用量が低い場合の線形多段階モデル近似式
p(D) = q* ´ D
染色体異常:chromosomal aberration
染色体の数もしくは形態に変化をきたす損傷をいう。染色体異常は細胞周期のDNA合成期(S
期)で頻度が高い。
相互転座:reciprocal translocation
染色体型異常の中の染色体間交換の一つ。2 本の染色体に生じた切断端の相互交換が対称型
に、すなわち動原体を持った部分と持たない部分との間に交換が行われたものであり、2つの転
座染色体が形成される。
外環境
“内環境”参照
体細胞突然変異:somatic mutation
生殖細胞以外の体細胞に生じる突然変異。細胞のがん化に深く関与している。
代謝活性化:metabolic activation
前駆型変異原(promutagen)が薬物代謝酵素により変異原に変換されること。通常、in vitro 遺伝
毒性試験においては、代謝活性系として、ラット肝臓のホモジネートのS9 画分(9000×g、10
分の遠沈上清)と補酵素から成るS9mix を用いる。
多媒体モデル:multimedia model
多媒体環境モデル(multimedia environmental model)と呼ばれることがある。大気、水質、土壌、
底質等の複数の媒体間での化学物質の移流、分配、媒体間輸送(湿性沈着等)等を、媒体内では分
解等も考慮する環境運命予測モデルで各媒体中の化学物質濃度予測に用いる。
仮定する媒体間の物質移動機構、分解の有無等により、Mackay はLevel?〜?のクラス分け
を行っている。媒体間においては、Level?は分配のみ、Level?では移流も考慮する。Level?及
び?では分配は仮定せず、移流及び媒体間輸送を考慮する。化学物質の分解(生分解やOH ラジ
カル反応等)はLevel?のみ考慮しない。Level?〜?は定常状態を仮定し、化学物質の排出速度
が一定で無限時間経過後に達成される濃度が、Level?では非定常を仮定し、排出速度や濃度の
時間変化を考慮した濃度が予測される。
断面調査:cross-sectional study
疫学研究方法の一つ。ある一時点での仮説因子の存在状況と特定の疾病の有病状況の類似性
を調査し、仮説因子と疾病との間の関連性を確かめる方法。
遅発性毒性:delayed toxicity
化学物質を生体に単回投与後、ある時間の経過後に現れる作用。例えば、化学物質の発がん
作用や遅発性の神経毒性があげられる。
伴性劣性致死突然変異:sex-linked recessive lethal mutation
X 染色体に起こる劣性の致死突然変異。
p53 遺伝子:p53 gene
がん抑制遺伝子の一つ。遺伝子が傷害されたときにp53 遺伝子が誘導され、DNAの修復酵素、
細胞周期を停止させるp21 遺伝子およびアポトーシス促進因子Bax を発現させる。
復帰突然変異:reverse mutation
変異を起こしている細胞が、もとの表現型に戻るような突然変異。これに対して最初の突然
変異を前進突然変異(forward mutation)とよぶ。
不定期DNA 合成:unscheduled DNA synthesis (UDS)
真核生物の細胞では、細胞周期のS 期(DNA 合成期)にのみDNA の合成が起きるため、培
養細胞に化学物質を加えたとき、細胞周期の間期にDNA合成が起こっていると、加えた化学物
質がDNAに損傷を与えたため、損傷の除去修復が進行しているものと考えることができる。
フレームシフト:frame shift (mutation)
DNA分子中に1 または3n±1 の塩基対が新たに挿入、もしくは失欠すること。その結果、そ
の部位以降のコドンは新しい組み合わせになり、本来とはアミノ酸組成の異なったペプチドが作
られる。
慢性毒性:chronic toxicity
長期間の継続ばく露(反復ばく露)により引き起こされる毒性。慢性毒性試験は、3 ヶ月以上
の長期間にわたって反復投与して、中毒症状を引き起こす用量とその経過を明らかにし、その
化学物質を使用する場合の安全量を推定することを目的に行われ、血液生化学的検査や肝機
能・腎機能の検査等、確立されている検査のほとんどを行う。なお、3 ヶ月ないし6 ヶ月以内の
ものを亜急性毒性、あるいは亜慢性毒性試験といわれる。
優性致死試験:Dominant lethal test
化学物質の遺伝毒性を検出する in vivo 試験の一つ。一般に雄マウスに被験物質を投与し、無
処理雌と交配する。減数分裂後に雄の生殖細胞(精子細胞〜精子)に染色体異常が生じると、胚
の初期死亡及び不着床を引き起こすので、これを指標とする。また、減数分裂前の精原細胞及び
精母細胞に染色体異常が生じると、減数分裂の過程で死滅して精子数の減少をきたし、不妊ある
いは不受精卵が増加する。
ユニットリスク:unit risk
大気中1 μg/m3 の化学物質に、生涯にわたって吸入ばく露したときの過剰発がんリスク推定値。
なお、飲料水中1 μg/L の化学物質を生涯、経口摂取したときの過剰発がんリスク推定値の場合
も指す。
がんの過剰発生率=ユニットリスク(μg/m3) -1× 吸入ばく露量(μg/m3)
lac?遺伝子座位:lac?locus
大腸菌の遺伝子の一つであり、プロモーター、オペレーター領域の上流側に位置する。lac リ
プレッサー単量体(タンパク質)をコードする。変異したlac?遺伝子を遺伝子工学的にマウス
に導入し(トランスジェニックマウス)、変異原性のある化学物質をばく露させると、突然変異
の箇所(lac?遺伝子座位)がもとに戻り突然変異の頻度も把握することができる。
ras 遺伝子:ras gene
ras 遺伝子は、受容体チロシンキナーゼから核へのシグナルを中継し、細胞の増殖や分化の促
進に係わるシグナル蛋白(ras 蛋白)をコードする遺伝子である。この遺伝子が変異して過剰活
性型ras 遺伝子となると、変異型遺伝子の産物が細胞の増殖や分化に対する正常な調節を阻害し
てがん発生を促進する。
2.無毒性量(NOAEL)等の性格および利用上の注意
(1) 無毒性量(NOAEL)等とは、NOAEL(NOEL)から、またはLOAEL(LOEL)を10で除して
変換したNOAEL(NOEL)から、時間補正のみを行って求めた数値をいう。
(2) 無毒性量(NOAEL)等は、ヒトの健康影響等についての十分な知識を基に、活用すること
が望ましい。
(3) 無毒性量(NOAEL)等を決定するに当たって、ヒトにおける調査及び動物実験等から得ら
れた多様な知見を考慮しているが、これらの情報の質、量は物質によって大きく異なってい
る。従って、無毒性量(NOAEL)等の数値を、有害物質間の相対的な毒性強度の比較に用
いることについては注意を要する。また、有害物質等への感受性は個人毎に異なるので、無
毒性量(NOAEL)等以下のばく露であっても、不快や既存の健康異常の悪化、あるいは新
たな健康異常の発生を防止できない場合もある。
(4) 無毒性量(NOAEL)等は安全と危険を判断する上でのおおよその目安であり、ヒトに何ら
かの健康異常がみられた場合、無毒性量(NOAEL)等を越えたことのみを理由として、そ
の物質による健康影響と判断してはならない。またその逆に、無毒性量(NOAEL)等を越
えていないことのみを理由として、その物質による健康影響ではないと判断してはならない。
(5) 無毒性量(NOAEL)等は、有害物質および健康影響に関する知識の増加、情報の蓄積、新
たな物質の使用等に応じて改訂・追加するものとする。
3.生物名一覧
学名 和名・属名 科・目名等 生物群
Acartia tonsa アカルチア属 アカルチア科(カイアシ類) 甲殻類
Aedes aegypti ネッタイシマカ カ科 その他
Aedes taeniorhynchus ヤブカ属 カ科 その他
Alburnus alburnus コイ科 魚 類
Americamysis bahia
(=Mysidopsis bahia)
アミ科 甲殻類
Amphilochus likelike 端脚目 甲殻類
Anabaena flos-aquae アナベナ属 ノストック科(藍藻類) 藻 類
Aplexa hypnorum ホタルヒダリマキガイ サカマキガイ科(巻貝) その他
Artemia salina アルテミア属 ホウネンエビ目 甲殻類
Australorbis glabratus ヒラマキガイ科(巻貝) その他
Balanus balanoides フジツボ科 甲殻類
Bufo marinus オオヒキガエル ヒキガエル科 その他
Caenorhabditis elegans
カンセンチュウ科
(線形動物)
その他
Callinectes sapidus ブルークラブ ワタリガニ科 甲殻類
Cancer magister ホクヨウイチョウガニ イチョウガニ科 甲殻類
Carassius auratus キンギョ コイ科 魚 類
Ceriodaphnia cf. dubia ニセネコゼミジンコと同属ミジンコ科 甲殻類
Ceriodaphnia dubia ニセネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類
Chaetogammarus marinus ヨコエビ科 甲殻類
Chironomus riparius ドブユスリカ ユスリカ科 その他
Chlamydomonas angulosa クラミドモナス属 クラミドモナス科(緑藻類) 藻 類
Chlamydomonas eugametos クラミドモナス属 クラミドモナス科(緑藻類) 藻 類
Chlorella pyrenoidosa クロレラ属 オーキスチス科 (緑藻類) 藻 類
Chlorella vulgaris クロレラ属 オーキスチス科 (緑藻類) 藻 類
Colpidium colpoda ミズケムシ目(繊毛虫) その他
Crinia insignifera カメガエル科 その他
Culex pipiens アカイエカ カ科 その他
Culex quinquefasciatus ナミカ属 カ科 その他
Culex restuans ナミカ属 カ科 その他
Cyclotella meneghiniana キクロテラ属
コスキノジスクス科
(珪藻類)
藻 類
Cyprinodon variegatus
キプリノドン科
(カダヤシ目)
魚 類
Cyprinus carpio コイ コイ科 魚 類
14
学名 和名・属名 科・目名等 生物群
Danio rerio
(=Brachydanio rerio)
ゼブラフィッシュ コイ科 魚 類
Daphnia magna オオミジンコ ミジンコ科 甲殻類
Daphnia pulex ミジンコ ミジンコ科 甲殻類
Desmodesmus subspicatus
(旧名Scenedesmus subspicatus*1)
デスモデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Dunaliella tertiolecta ドゥナリエラ属 ドゥナリエラ科(緑藻類) 藻 類
Elasmopus pectinicrus ヨコエビ科 甲殻類
Entosiphon sulcatum エントシフォン属 ペラネマ科(ユウグレナ目) その他
Fundulus heteroclitus マミチョグ Fundulidae(カダヤシ目) 魚 類
Fungia scutaria クサビライシ
クサビライシ科
(イシサンゴ目)
その他
Gadus morhua マダラ属 タラ科 魚 類
Gambusia affinis カダヤシ カダヤシ科 魚 類
Gammarus pulex ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類
Hyalella azteca ヨコエビ科 甲殻類
Hydra oligactis ヒドラ属 ヒドラ科 その他
Ictalurus punctatus アメリカナマズ ナマズ目 魚 類
Idus idus melanotus コイ科 魚 類
Lemna gibba イボウキクサ ウキクサ科 その他
Lemna minor コウキクサ ウキクサ科 その他
Lepomis macrochirus ブルーギル サンフィッシュ科(スズキ目) 魚 類
Leuciscus idus コイ科 魚 類
Leuciscus idus melanotus コイ科 魚 類
Libinia dubia クモガニ科 甲殻類
Litoria adelaidensis アマガエル科 その他
Lymnaea stagnalis モノアラガイ科(巻貝) その他
Microcystis aeruginosa ミクロキスティス属 クロオコックス科(藍藻類) 藻 類
Moina macrocopa タマミジンコ ミジンコ科 甲殻類
Mulinia lateralis バカガイ科(二枚貝) その他
Mytilus edulis ムラサキイガイ イガイ科(二枚貝) その他
Navicula pelliculosa ナビクラ属 ナビクラ科(珪藻類) 藻 類
Nitocra spinipes ナミミズベソコミジンコ
ソコミジンコ(ハルパクチ
クス)目
甲殻類
Oithona davisae オイトナ属 オイトナ科(カイアシ類) 甲殻類
Oncorhynchus kisutch ギンザケ サケ科 魚 類
Oncorhynchus mykiss ニジマス サケ科 魚 類
15
学名 和名・属名 科・目名等 生物群
(=Salmo gairdneri)
Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類
Pagrus major マダイ タイ科 魚 類
Palaemonetes kadiakensis テナガエビ科 甲殻類
Palaemonetes pugio テナガエビ科 甲殻類
Panopeus herbstii イソオウギガニ科 甲殻類
Paramecium caudatum ゾウリムシ ミズケムシ目 その他
Paramecium trichium
パラメシウム属
(ゾウリムシと同属)
ミズケムシ目 その他
Paratanytarsus parthenogeneticus ニセヒゲユスリカ属 ユスリカ科 その他
Paratanytarsus sp. ニセヒゲユスリカ属 ユスリカ科 その他
Pecten opercularis イタヤガイ科(二枚貝) その他
Pimephales promelas ファットヘッドミノー コイ科 魚 類
Platichthys flesus ヌマガレイ属 カレイ科 魚 類
Platynereis dumeralii ゴカイ科(多毛類) その他
Pleuronectes flesus ツノガレイ属 カレイ科 魚 類
Poecilia reticulata グッピー カダヤシ科 魚 類
Portunus pelagicus タイワンガザミ ワタリガニ科 甲殻類
Pseudokirchneriella subcapitata
(旧名Selenastrum capricornutum*2)
プセウドキルクネリエラ属オーキスチス科 (緑藻類) 藻 類
Rana catesbeiana ウシガエル アカガエル科 その他
Rana pipiens アカガエル科 その他
Rasbora heteromorpha ラスボラ属 コイ科 魚 類
Salmo trutta ブラウントラウト サケ科 魚 類
Scenedesmus obliquus セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Scenedesmus opoliensis セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Scenedesmus pannonicus セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Scenedesmus quadricauda セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Scenedesmus vacuolatus セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Skeletonema costatum スケレトネマ属 タラシオシラ科(珪藻類) 藻 類
Solea solea
ササウシノシタ科
(カレイ目)
魚類
Tetrahymena elliotti テトラヒメナ属 ミズケムシ目 その他
Tetrahymena pyriformis テトラヒメナ属 ミズケムシ目 その他
Tetrahymena thermophila テトラヒメナ属 ミズケムシ目 その他
Utterbackia imbecillis イシガイ科(二枚貝) その他
Xenopus laevis アフリカツメガエル ピパ(コモリガエル)科 その他
*1 OECD テストガイドラインNo.201 における記述に準じて、ここでは旧名と表記した
http://www.env.go.jp/chemi/report/h21-01/index.html
1.用語説明
(1) 略語
ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.(米国産業衛生専門家会議)
米国の産業衛生の専門家の組織で、職業上及び環境上の健康についての管理及び技術的な分
野を扱っている。毎年、化学物質や物理的作用及びバイオモニタリングについて職業上の許容
濃度の勧告値(TLV:Threshold Limit Value)や化学物質の発がん性のランクを公表し、世界的
にも重要視されている。
ADI:Acceptable Daily Intake(許容1 日摂取量)
健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重
1 kg 当たりの摂取量。コストと便益にもとづいた概念で、農薬や食品添加物の残留基準の設定
に用いられ、ここまでなら許容できる量を示すもの。
AQUIRE:AQUatic toxicity Information Retrieval (http://www.epa.gov/ecotox/)
米国環境保護庁 (U.S. EPA) が水生生物や水生植物に対する化学物質の毒性影響の知見を基に
構築しているデータベース。1970 年以降に発表された大半の論文を収録しており、定期的にデ
ータを追加している。2001 年10 月31 日改訂時の収録化学物質数は7,964 物質、収録文献数は
17,717 文献である。AQUIRE (水生生物)、PHYTOTOX (陸生植物)、TERRETOX (野生動物)を統
合したものをECOTOX と呼んでいる。
ATSDR:Agency for Toxic Substances and Disease Registry (米国有害物質・疾病登録局)
米国保健福祉省に属する機関であり、有害物質へのばく露や関連する疾病を防ぐために信頼
できる情報提供を行っている。
BMD, BMC:Benchmark Dose (BMD) , Concentration (BMC)(ベンチマーク用量、濃度)
用量−反応関係の曲線から計算されるある割合の有害影響を発現する用量(あるいはその上
側信頼限界値)をベンチマーク量として、無毒性量や最小無毒性量の代わりに用いる方法である。
CERHR:Center for The Evaluation of Risks to Human Reproduction (ヒト生殖リスク評価センター)
米国国立環境衛生研究所(NIEHS:National Institute of Environmental Health Science)によって
1998 年にNTP(National Toxicology Program)のもとに設立した機関。ヒトがばく露する可能性の
ある化学物質によって引き起こされる生殖に関する有害な影響を、タイムリーに公平に科学的
に評価することを目的としている。
CICAD:Concise International Chemical Assessment Document(国際簡潔評価文書)
国際化学物質安全性計画(IPCS)の出版物のうち、最も新しいシリーズである。既存の化学
物質の健康と生態系への影響について国際機関における評価作業との重複を省きつつ、これら
を基にして国際的に利用可能な簡潔な新たな安全性評価文書を作成するもので、主要な目的は
化学物質のばく露による有害性の解析と、量−影響の定量的な記述にある。
DFG:Deutsche Forschungsgemeinschaft (ドイツ学術協会)
ドイツの非政府機関であり、政府からの資金を受けて、人文・自然科学の学問領域における
研究プロジェクトに寄与し、政府への助言を行う。化学物質の職場環境における許容濃度等、発
がん性の分類について情報提供を行っている。
EC50:Median Effective Concentration(半数影響濃度)
ばく露期間中試験生物の50%に(有害)影響を及ぼすと予想される濃度。影響内容が、
生長(成長)や遊泳阻害、繁殖など死亡以外の時に用いられる。
EHC:Environmental Health Criteria(WHO環境保健クライテリア)
国連環境計画(UNEP)、国際労働機関(ILO)および世界保健機関(WHO)により設立され
た国際化学物質安全性計画(IPCS)の中核事業として作成されているモノグラフで、ヒトの健
康と環境に対して有害な影響を与えないように、化学物質の管理を適切に行うための判断の基
礎となる科学的知見を物質毎にまとめた評価文書のシリーズ。化学物質の評価について、多く
の国際協力事業がある中で、WHO を中心とするIPCS は評価が高く、また、権威のある評価文
書の作成事業として知られている。
EPI:Exposure/Potency Index(ばく露量/発がん強度比率)
カナダの環境省(Environment Canada)及び厚生省(Health Canada)の優先物質リスト(Priority
Substance List Assessment Report)で使用されている化学物質の発がん性のリスクを表す指数。動
物の慢性ばく露実験において過剰な腫瘍発生率が5 %となる用量(TD05)あるいは濃度(TC05)
を用いてばく露量との比を計算する。なお、TD05はTD0.05、TC05 はTC0.05 として表記される場合
もある。
GDWQ:Guideline of Drinking Water Quality(WHO 飲料水水質ガイドライン)
ヒトの健康を保護することを目的として、飲料水中に含まれる潜在的に有害な成分の濃度あ
るいは飲料水の性状について定めたWHOのガイドライン。健康に影響を及ぼすことが知られて
いる飲料水中の汚染物質について、各国で飲料水の安全性を保証する水質基準を策定するため
の基礎として使用されることを意図している。
HEAST:EPA's Health Effects Assessment Summary Tables(EPA健康影響評価要約表)
米国環境保護庁(米国EPA)により、大気清浄法修正条項(1990 年)で指定された大気汚染
物質(一部の物質を除く)のハザード、ばく露情報、毒性情報(一般毒性、生殖・発生毒性、発
がん性)等の要約および出典を提供している。
IARC:International Agency for Research on Cancer(国際がん研究機関)
WHO により1965 年に設立された国際的な機関。ヒトのがんの原因に関する研究及び方向性
の提示並びにがんを科学的に制御するための方策を研究することを目的とし、ヒトに対する化
学物質の発がん性について以下に示す5 段階で分類評価を行っている。
1:ヒトに対して発がん性が有る。
2A:ヒトに対して恐らく発がん性が有る。
2B:ヒトに対して発がん性が有るかもしれない。
3:ヒトに対する発がん性については分類できない。
4:ヒトに対して恐らく発がん性がない。
IPCS:International Programme on Chemical Safety(国際化学物質安全性計画)
WHO、ILO、UNEP の共同事業で、化学物質による健康障害を未然に防ぐために化学物質の
安全性に関する正当な評価を取りまとめ、環境保健クライテリア(EHC)、国際化学物質安全
性カード(ICSC)等を発行している。また、アジェンダ21 の決定に基づき、化学物質の危険有
害性の分類等について国際的調和をはかっている。
IRIS:Integrated Risk Information System
米国環境保護庁(U.S. EPA)により、化学物質のリスク評価やリスク管理に利用することを
目的として作成されている化学物質のデータベースシステム。化学物質によるヒトへの健康影
響に関する情報(慢性毒性評価、発がん性評価)が個々の化学物質ごとに収集されている。
JECFA:FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives(FAO/WHO合同食品添加物専門家
会議)
FAO とWHO により設置された食品添加物等の安全性評価等を行う国際機関。各国の添加物
規格に関する専門家及び毒性学者からなり、各国によって実施された添加物の安全性試験の結果
を評価し、一日摂取許容量(ADI)を決定しており、会議報告は、WHO テクニカルレポートシ
リーズとして毎年公表されている。
JMPR:JOINT FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues(FAO/WHO 合同残留農薬会議)
WHO とFAO が共同して1963 年に設置した機関。農薬の使用による食品への残留について検
討するFAO Panel と農薬の毒性面について検討するWHO Expert Group から構成される。FAO
Panel では、適切な農薬規範に従って有効な散布量を最小限用いた場合に作物に残留するレベル
として最大残留基準を設定し、WHO Expert Group では、毒性関連データに基づいて農薬のADI
について審議を行っている。最大残留基準は、残留農薬規格委員会の検討を経て国際食品基準
となり、ADI は各国で安全評価を進める際の参考とされる。
LC50:Lethal Concentration 50, Median Lethal Concentration(半数致死濃度)
1 回のばく露(通常1 時間から4 時間)で1 群の実験動物の50%を死亡させると予想さ
れる濃度。生態毒性試験においては、ばく露期間中試験生物の50%を死亡させると予想さ
れる濃度のことをいう。
LCLo:Lethal Concentration Lowest(最小致死濃度)
特定のばく露時間での吸入によりヒトまたは動物を致死させたばく露濃度の最小値。関連し
た報告値の中での最小の致死濃度(Lowest Published Lethal Concentration)の意味に用いられるこ
ともある。
LD50:Lethal Dose 50(半数致死量)
1 回の投与で1 群の実験動物の50%を死亡させると予想される投与量。
LDLo:Lethal Dose Lowest(最小致死量)
ヒトまたは動物を致死させた吸入ばく露以外の経路による投与量の最小値。関連した報告値
の中での最小の致死量(Lowest Published Lethal Dose)の意味に用いられることもある。
LOEC : Lowest Observed Effect Concentration (最小影響濃度)
最小作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な(有害)影響を及ぼす最も低
い濃度のこと。
LOAEL:Lowest Observed Adverse Effect Level(最小毒性量)
毒性試験において有害な影響が認められた最低のばく露量。
LOEL:Lowest Observed Effect Level(最小影響量)
最小作用量ともいう。毒性試験において何らかの影響が認められる最低のばく露量。影響の
中には有害、無害両方を含むので、一般にはLOAELに等しいかそれより低い値である。
MATC:Maximum Acceptable Toxicant Concentration(最大許容濃度)
最大許容毒性物質濃度ともいう。NOEC とLOECの間にあると仮定される毒性の閾値を
指し、両者の幾何平均濃度として算出される。
MOE:Margin of Exposure
今のばく露量がヒトのNOAELに対してどれだけ離れているかを示す係数でNOAEL/ばく露
量により算出する。この値が大きいほど安全への余地があるということを示している。なお、
動物実験の結果から求められたNOAELの場合には、NOAEL/ばく露量/10 により算出する。
NCI:National Cancer Institute(米国国立がん研究所)
米国保健福祉省(DHHS:Department of Health and Human Services)に所属する機関で、がんの
原因と予防、診断・処置およびがん患者のリハビリテーション等を研究している。
NIOSH:National Institute for Occupational Safety and Health(国立労働安全衛生研究所)
職業上の疾病や傷害を防ぐための研究や勧告を行う米国保健福祉省疾病予防管理センターに
所属する機関。約15 万の化学物質の毒性情報を収載したRTECS データベース(Registry of Toxic
Effects of Chemical Substances)を編纂している。
NOAEL:No Observed Adverse Effect Level(無毒性量)
無副作用量、最大有害無作用レベル、最大無毒性量と訳すこともある。何段階かの投与用量
群を用いた毒性試験において有害影響が観察されなかった最高のばく露量のことである。この
値に安全係数や不確定係数を乗じて、ADI やTDI を求めることがある。
NOEC : No Observed Effect Concentration (無影響濃度)
最大無影響濃度、最大無作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な(有害)
影響が認められなかった最高濃度であり、LOECのすぐ下の濃度区である。
NOEL:No Observed Effect Level(無影響量)
毒性試験において影響が認められない最高のばく露量。影響の中には有害、無害両方を含む
ので、一般にはNOAELに等しいかそれより低い値である。
NTP:National Toxicology Program(米国国家毒性プログラム)
米国保健福祉省(DHHS)により1978 年に設置された事業。米国の各省庁が実施している化
学物質の毒性研究をまとめ、発がん性物質の分類、試験を行っている。NTP が発行している発
がん性年報のデータは、情報提供のみを目的としたものである。
PEC:Predicted Environmental Concentration (予測環境中濃度)
予測される環境中の化学物質濃度を指す。実測データを基に決めているが、データが少ない
場合には生産量や排出量などから推定する。生態リスク評価は、このPEC とPNEC を比較して
行う。
PMR:Proportional Mortality Ratio(特定死因死亡比)
一定の集団において、特定原因による観察死亡数の割合を、標準人口における同じ原因によ
る期待死亡数の割合で除して求められる値。
PNEC:Predicted No Effect Concentration (予測無影響濃度)
水生生物への影響が表れないと予測される濃度を指す。環境中の全生物種への影響を捉える
ことは困難なため、試験生物種の毒性濃度から全生物種への影響を推定した値である。
SIDS:Screening Information DataSet(初期評価データセット)
OECD 加盟国のいずれか1 ヵ国又はEU 加盟国全体での年間生産量及び輸入量が1,000 トンを
超える既存化学物質について、安全性評価を行うために必須な最小限のデータセットについて
情報を収集し、この情報が欠如している場合には試験を行った上で、環境生物への影響、ヒト
への健康影響についての初期評価を加盟国が分担してまとめている。
SIR:Standardized Incident Ratio(標準化罹患比)
ある特定の状況下にある対象集団の罹患数と、その集団が罹患率の分かっている標準人口と
同じ罹患率を有すると仮定したときに期待される罹患数との比。
)(標準人口の年齢別罹患率対象集団の年齢別人口の総和
ある期間に対象集団で観察された罹患数
´
SIR =
SMR:Standardized Mortality Ratio(標準化死亡比)
対象集団における観察死亡数と、対象集団の年齢別死亡率が標準人口のそれと等しいと仮定
したときに期待される死亡数との比。
(標準人口の年齢別死亡率対象集団の年齢別人口)の総和
対象集団の観察死亡数
´
SMR =
TCLo:Toxic Concentration Lowest(最小中毒濃度)
ヒトまたは動物に中毒症状を引き起こさせた吸入によるばく露濃度のうちの最小値。
TDI:Tolerable Daily Intake(耐容1 日摂取量)
健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重
1 kg 当たりの摂取量。
TDLo:Toxic Dose Lowest(最小中毒量)
ヒトまたは実験動物に中毒症状をおこさせた吸入ばく露以外の経路による投与量の最小値。
TLV:Threshold Limit Value(作業環境許容濃度)
ほとんどすべての作業者が毎日繰り返しばく露しても、有害な健康影響が現れないと考えら
れる化学物質の気中濃度についてのACGIHによる勧告値。産業界の経験、ヒトや動物による試
験・研究等の利用可能な情報に基づいている。これら情報の量と質は物質によって異なるため、
TLV の精度には幅があり、また、TLV は安全濃度と危険濃度の間のはっきりした線ではないし、
毒性の相対的な指標でもない。TLV は時間加重平均(TWA)等で示される。
TWA:Time Weighted Average(時間加重平均)
通常の1 日8 時間、週40 時間労働の時間加重平均濃度。
WHO:World Health Organization(世界保健機関)
世界の公衆衛生の向上や、伝染病対策、環境問題等を取り扱っている国際機関。「すべての
人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的に掲げている。
(2) 用語
アセスメント係数
生態リスク評価において、限られた試験データから化学物質の予測無影響濃度(PNEC)を求
めるために用いる係数で、感受性の種間差、急性毒性値と慢性毒性値の違い、実験生物から野外
生物への毒性値の外挿等を考慮して設定されている。
in vitro、in vivo
in vitro は、人工的な器具内で行われる生物学的な反応に関して使われる言葉で、「試験管内」
を意味する。多くの場合、生物体機能の一部を試験管内において行わせることを指す。一方、in
vivo は、生きている細胞あるいは生体内に置かれている状態を指す語で、「生体内」を意味し、
対象とする生体の機能や反応が生体内で発現される状態を示す。たとえば、心臓細胞の収縮が
動物体内で起こればin vivo、試験管内で行われていればin vitro における機能発現である。
一日ばく露量:daily exposure
ヒトの1 日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ15 m3、2 L及び2000 g と仮定し、体重を
50 kg と仮定した場合の一日あたり体重1 kg あたりのばく露量(μg/kg/day)を示す。
一般毒性:general toxicity
急性毒性、亜急性毒性(亜慢性毒性)、慢性毒性をまとめて、一般毒性と言う。これらは、
毒性学の領域において、もっとも基本的なもので、化学物質の危険性を知るための基礎を提供
する。
一本鎖切断: single-strand breaks
二本鎖DNAにおいて、両鎖のうち一つの鎖のみ切れ目が入っているが、両鎖は互いに切り離
されていない状態。
遺伝子突然変異:gene mutation
DNA 塩基の置換、欠失、挿入などにより、単一遺伝子または調節遺伝子の塩基配列に生じた
恒久的な変化のこと。
遺伝子変換:gene conversion
相同染色体間及び対立遺伝子間の交換を指す。相同なDNA配列(対立遺伝子あるいは非対立
遺伝子)間の遺伝的情報の非相互的な組換えを行うこと。
遺伝的組換え:genetic recombination
2つ以上の形質に関して、遺伝子型が異なる両親の遺伝物質が交配などにより1つの個体に持
ち込まれたとき、いずれの親にも見られなかった新しい遺伝子の組合せを持った子孫が突然変異
によらずに生じること。すなわち、同一染色体上にある遺伝子の組合せが交叉によって組換えら
れる現象をいう。
遺伝毒性、遺伝子毒性(遺伝子傷害性):genetic toxicity, genotoxicity
化学物質や物理的要因の遺伝的過程に対する傷害で、染色体の異数性、付加・欠失・再結合
等の染色体異常及び遺伝子突然変異に起因する。遺伝物質に対する毒性の総称であり、DNA 傷
害性、突然変異誘発性、染色体異常誘発性を包含する。
内環境
ある環境がより小さい領域の環境を取り囲む構造(入れ子構造)を持つ多媒体モデルにおいて
は、内側を内環境、その外側を外環境と呼ぶ。入れ子構造を持つ多媒体モデルとしては、例
えばBrandes LJ et al. (1996)のSimpleBox2.0 がある。
環境リスク初期評価では、内環境は都道府県を、外環境には日本全国から内環境を差し引い
た環境を設定している。
hprt 遺伝子座位:hprt locus
ヒポキサンチン ホスフォリボシル転移酵素をコードする遺伝子座位。X染色体上にある。hprt
遺伝子の欠損変異は、6−チオグアニン抵抗性を標識として容易に選別できることから、突然変
異頻度の測定手段として用いられている。
疫学:epidemiology
ヒトの集団を対象として、ヒトの健康およびその異常の原因を、病因、環境等の各面から包
括的に考察する学問分野で、健常者を含めたヒトの集団全員を対象にして、主に疾病の予防方
法を研究する。
エームス試験:Ames test
遺伝毒性試験の一つであり、B. N. Ames が開発したネズミチフス菌を用いて復帰突然変異を
検出する試験系。化学物質の遺伝毒性の検出、がん原性のスクリーニングとして広く用いられる。
塩基対置換:base (pair) substitution
DNA中の特定の塩基対が他の塩基対に置換されること。これにより、DNA分子としての機能
に変化が生じる。
感作性:sensitization
免疫機能を障害し、アレルギーを起こさせる性質のこと。アレルギー誘発性ともいう。
急性毒性:acute toxicity
動物あるいはヒトに化学物質等を単回投与あるいは短時間中(1 日以内)に持続注入あるいは
反復投与した場合に投与開始直後から1〜2 週間以内に現れる毒性。急性毒性試験では、症状の
種類、程度、持続時間、死亡の状態等を指標として、中毒量や致死量を算出する。急性毒性の
最も明確な毒性指標としてはLD50(半数致死量)がある。
ケースコントロール研究:case control study
患者対照研究のことで、研究対象とする疾病をもつ人の群と、その疾病をもたない適切な対
照群とを用いた観察的疫学研究方法。患者と非患者それぞれについて、ある属性がどの程度であ
るかを比較することによって、その属性と当該疾病との関連性を検討する。文字どおりケース(研
究対象としている患者)とコントロール(対照)の群を設定して、過去の関心ある危険因子に関
する記録を調査し、その関連を検討するものである。限られた時間内に研究が行えるので実際的
な研究方法である。代表的な研究例としては肺がんの研究が有名である。しかしながら、ケース
とコントロールの比較の背後には潜在的に多くのバイアスが存在し、得られた結果の解釈が容易
でない場合が少なくない。
限度試験:limit test
環境中ある濃度以上に被験物質が存在することがないか、その濃度以上での影響は無視
しうると考えられる場合、その濃度区のみの試験をすることを限度試験という。毒性値を
求めるのではなく、その濃度における影響の有無を調べる。通常生態毒性試験では、100mg/L
または水溶解限度のより低い方の濃度となる。
コホート調査:cohort study
疫学研究方法の一つ。疾病発生に関連していると考えられる仮説因子の有無もしくはばく露
の程度が確認できる集団を一定期間観察し、その間の疾病発生頻度を仮説因子の有無もしくは
ばく露の程度別に比較する方法。
催奇形性:teratogenicity
化学物質等が次世代に対して、先天異常を引き起こす性質。
細胞形質転換:cell transformation
培養細胞が放射線、ウイルス、化学物質などによってその形態や機能をかえ、腫瘍細胞類似
の性質を備えること。
細胞遺伝学:cytogenetics
染色体の構造や形態、染色体に存在する遺伝子の行動と形質発現など、細胞学的な特徴から
遺伝現象を明らかにしようとする遺伝学の一分野。遺伝毒性試験の中でin vitro、 in vivo 染色体
異常試験、小核試験、及び優性致死試験などは細胞遺伝学試験とよばれている。
姉妹染色分体交換:sister chromatid exchange, SCE
姉妹染色分体の部分的な交換(2本の姉妹染色分体の間で同じ部位が入れ替わること)。こ
れを利用して遺伝毒性を検出する方法がある。SCE は、染色体の構造異常とは異なる現象である。
宿主経由試験:host-mediated assay
宿主動物の腹腔内に微生物を注入した後に、被験物質を投与し、回収した微生物の突然変異
頻度を調べることにより、哺乳類の代謝物の変異誘発性を評価する試験。
小核:micronucleus
染色体の構造異常または分裂装置の損傷により、細胞分裂後に細胞質中に取り残された染色
体断片、あるいは1〜数本の染色体に由来する小さな核。小核の誘発を検出する試験を小核試験
といい、げっ歯類の骨髄あるいは末梢血の塗抹標本を観察して、小核を有する幼若赤血球の出現
頻度より、被験物質の染色体異常誘発性を調べる。
数的異常:numerical aberration
染色体異常の分類の一つで染色体の数の変化を指す。数的異常には異数性(aneuploidy)と倍
数性(polyploidy)があり、前者は染色体の数が1〜数本増加または減少するもので、後者は染
色体基本数(n)が整数倍化する現象をいう。
スロープファクター:slope factor
体重1 kg あたり1 mg の化学物質を、毎日、生涯にわたって経口摂取した場合の過剰発がんリ
スク推定値。
がんの過剰発生率=スロープファクター(mg/kg/day) -1× 経口ばく露量(mg/kg/day)
生殖・発生毒性:reproductive and developmental toxicity
化学物質等の環境要因が生殖・発生の過程に有害な反応を引き起こす性質。親世代からみれ
ば生殖毒性(reproductive toxicity)、次世代を中心にみると発生毒性(developmental toxicity)で
ある。両者については研究者によってそれぞれ概念がことなるが、一般には生殖毒性は受胎能
の障害、発生毒性は生殖細胞の形成から受精、出生を経て、個体の死に至る発生の何れかの時
期に作用して、発生障害(早期死亡、発育遅滞、形態異常、機能異常)を引き起こす性質と定
義される。
線形多段階モデル:linearized multistage model
発がんに至るには多段階のステップが関与することを考慮に入れた数学モデルであり、実際
にヒトがばく露されるような低濃度においては、高次の項目は無視し得ることになるため、用量
の1次式(線形)で表せることになる。このモデルにおいて直線の傾き「q* 」(一般に95%信
頼区間上限値)を発がん性の強さの指標とし、スロープファクターと呼ぶ。
2
p(D) =1 - exp{-q0 - q1D - q 2D …… q D } , qi 0
k
k >
p(D) :用量Dにおける生涯の発がん率 D :用量
用量が低い場合の線形多段階モデル近似式
p(D) = q* ´ D
染色体異常:chromosomal aberration
染色体の数もしくは形態に変化をきたす損傷をいう。染色体異常は細胞周期のDNA合成期(S
期)で頻度が高い。
相互転座:reciprocal translocation
染色体型異常の中の染色体間交換の一つ。2 本の染色体に生じた切断端の相互交換が対称型
に、すなわち動原体を持った部分と持たない部分との間に交換が行われたものであり、2つの転
座染色体が形成される。
外環境
“内環境”参照
体細胞突然変異:somatic mutation
生殖細胞以外の体細胞に生じる突然変異。細胞のがん化に深く関与している。
代謝活性化:metabolic activation
前駆型変異原(promutagen)が薬物代謝酵素により変異原に変換されること。通常、in vitro 遺伝
毒性試験においては、代謝活性系として、ラット肝臓のホモジネートのS9 画分(9000×g、10
分の遠沈上清)と補酵素から成るS9mix を用いる。
多媒体モデル:multimedia model
多媒体環境モデル(multimedia environmental model)と呼ばれることがある。大気、水質、土壌、
底質等の複数の媒体間での化学物質の移流、分配、媒体間輸送(湿性沈着等)等を、媒体内では分
解等も考慮する環境運命予測モデルで各媒体中の化学物質濃度予測に用いる。
仮定する媒体間の物質移動機構、分解の有無等により、Mackay はLevel?〜?のクラス分け
を行っている。媒体間においては、Level?は分配のみ、Level?では移流も考慮する。Level?及
び?では分配は仮定せず、移流及び媒体間輸送を考慮する。化学物質の分解(生分解やOH ラジ
カル反応等)はLevel?のみ考慮しない。Level?〜?は定常状態を仮定し、化学物質の排出速度
が一定で無限時間経過後に達成される濃度が、Level?では非定常を仮定し、排出速度や濃度の
時間変化を考慮した濃度が予測される。
断面調査:cross-sectional study
疫学研究方法の一つ。ある一時点での仮説因子の存在状況と特定の疾病の有病状況の類似性
を調査し、仮説因子と疾病との間の関連性を確かめる方法。
遅発性毒性:delayed toxicity
化学物質を生体に単回投与後、ある時間の経過後に現れる作用。例えば、化学物質の発がん
作用や遅発性の神経毒性があげられる。
伴性劣性致死突然変異:sex-linked recessive lethal mutation
X 染色体に起こる劣性の致死突然変異。
p53 遺伝子:p53 gene
がん抑制遺伝子の一つ。遺伝子が傷害されたときにp53 遺伝子が誘導され、DNAの修復酵素、
細胞周期を停止させるp21 遺伝子およびアポトーシス促進因子Bax を発現させる。
復帰突然変異:reverse mutation
変異を起こしている細胞が、もとの表現型に戻るような突然変異。これに対して最初の突然
変異を前進突然変異(forward mutation)とよぶ。
不定期DNA 合成:unscheduled DNA synthesis (UDS)
真核生物の細胞では、細胞周期のS 期(DNA 合成期)にのみDNA の合成が起きるため、培
養細胞に化学物質を加えたとき、細胞周期の間期にDNA合成が起こっていると、加えた化学物
質がDNAに損傷を与えたため、損傷の除去修復が進行しているものと考えることができる。
フレームシフト:frame shift (mutation)
DNA分子中に1 または3n±1 の塩基対が新たに挿入、もしくは失欠すること。その結果、そ
の部位以降のコドンは新しい組み合わせになり、本来とはアミノ酸組成の異なったペプチドが作
られる。
慢性毒性:chronic toxicity
長期間の継続ばく露(反復ばく露)により引き起こされる毒性。慢性毒性試験は、3 ヶ月以上
の長期間にわたって反復投与して、中毒症状を引き起こす用量とその経過を明らかにし、その
化学物質を使用する場合の安全量を推定することを目的に行われ、血液生化学的検査や肝機
能・腎機能の検査等、確立されている検査のほとんどを行う。なお、3 ヶ月ないし6 ヶ月以内の
ものを亜急性毒性、あるいは亜慢性毒性試験といわれる。
優性致死試験:Dominant lethal test
化学物質の遺伝毒性を検出する in vivo 試験の一つ。一般に雄マウスに被験物質を投与し、無
処理雌と交配する。減数分裂後に雄の生殖細胞(精子細胞〜精子)に染色体異常が生じると、胚
の初期死亡及び不着床を引き起こすので、これを指標とする。また、減数分裂前の精原細胞及び
精母細胞に染色体異常が生じると、減数分裂の過程で死滅して精子数の減少をきたし、不妊ある
いは不受精卵が増加する。
ユニットリスク:unit risk
大気中1 μg/m3 の化学物質に、生涯にわたって吸入ばく露したときの過剰発がんリスク推定値。
なお、飲料水中1 μg/L の化学物質を生涯、経口摂取したときの過剰発がんリスク推定値の場合
も指す。
がんの過剰発生率=ユニットリスク(μg/m3) -1× 吸入ばく露量(μg/m3)
lac?遺伝子座位:lac?locus
大腸菌の遺伝子の一つであり、プロモーター、オペレーター領域の上流側に位置する。lac リ
プレッサー単量体(タンパク質)をコードする。変異したlac?遺伝子を遺伝子工学的にマウス
に導入し(トランスジェニックマウス)、変異原性のある化学物質をばく露させると、突然変異
の箇所(lac?遺伝子座位)がもとに戻り突然変異の頻度も把握することができる。
ras 遺伝子:ras gene
ras 遺伝子は、受容体チロシンキナーゼから核へのシグナルを中継し、細胞の増殖や分化の促
進に係わるシグナル蛋白(ras 蛋白)をコードする遺伝子である。この遺伝子が変異して過剰活
性型ras 遺伝子となると、変異型遺伝子の産物が細胞の増殖や分化に対する正常な調節を阻害し
てがん発生を促進する。
2.無毒性量(NOAEL)等の性格および利用上の注意
(1) 無毒性量(NOAEL)等とは、NOAEL(NOEL)から、またはLOAEL(LOEL)を10で除して
変換したNOAEL(NOEL)から、時間補正のみを行って求めた数値をいう。
(2) 無毒性量(NOAEL)等は、ヒトの健康影響等についての十分な知識を基に、活用すること
が望ましい。
(3) 無毒性量(NOAEL)等を決定するに当たって、ヒトにおける調査及び動物実験等から得ら
れた多様な知見を考慮しているが、これらの情報の質、量は物質によって大きく異なってい
る。従って、無毒性量(NOAEL)等の数値を、有害物質間の相対的な毒性強度の比較に用
いることについては注意を要する。また、有害物質等への感受性は個人毎に異なるので、無
毒性量(NOAEL)等以下のばく露であっても、不快や既存の健康異常の悪化、あるいは新
たな健康異常の発生を防止できない場合もある。
(4) 無毒性量(NOAEL)等は安全と危険を判断する上でのおおよその目安であり、ヒトに何ら
かの健康異常がみられた場合、無毒性量(NOAEL)等を越えたことのみを理由として、そ
の物質による健康影響と判断してはならない。またその逆に、無毒性量(NOAEL)等を越
えていないことのみを理由として、その物質による健康影響ではないと判断してはならない。
(5) 無毒性量(NOAEL)等は、有害物質および健康影響に関する知識の増加、情報の蓄積、新
たな物質の使用等に応じて改訂・追加するものとする。
3.生物名一覧
学名 和名・属名 科・目名等 生物群
Acartia tonsa アカルチア属 アカルチア科(カイアシ類) 甲殻類
Aedes aegypti ネッタイシマカ カ科 その他
Aedes taeniorhynchus ヤブカ属 カ科 その他
Alburnus alburnus コイ科 魚 類
Americamysis bahia
(=Mysidopsis bahia)
アミ科 甲殻類
Amphilochus likelike 端脚目 甲殻類
Anabaena flos-aquae アナベナ属 ノストック科(藍藻類) 藻 類
Aplexa hypnorum ホタルヒダリマキガイ サカマキガイ科(巻貝) その他
Artemia salina アルテミア属 ホウネンエビ目 甲殻類
Australorbis glabratus ヒラマキガイ科(巻貝) その他
Balanus balanoides フジツボ科 甲殻類
Bufo marinus オオヒキガエル ヒキガエル科 その他
Caenorhabditis elegans
カンセンチュウ科
(線形動物)
その他
Callinectes sapidus ブルークラブ ワタリガニ科 甲殻類
Cancer magister ホクヨウイチョウガニ イチョウガニ科 甲殻類
Carassius auratus キンギョ コイ科 魚 類
Ceriodaphnia cf. dubia ニセネコゼミジンコと同属ミジンコ科 甲殻類
Ceriodaphnia dubia ニセネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類
Chaetogammarus marinus ヨコエビ科 甲殻類
Chironomus riparius ドブユスリカ ユスリカ科 その他
Chlamydomonas angulosa クラミドモナス属 クラミドモナス科(緑藻類) 藻 類
Chlamydomonas eugametos クラミドモナス属 クラミドモナス科(緑藻類) 藻 類
Chlorella pyrenoidosa クロレラ属 オーキスチス科 (緑藻類) 藻 類
Chlorella vulgaris クロレラ属 オーキスチス科 (緑藻類) 藻 類
Colpidium colpoda ミズケムシ目(繊毛虫) その他
Crinia insignifera カメガエル科 その他
Culex pipiens アカイエカ カ科 その他
Culex quinquefasciatus ナミカ属 カ科 その他
Culex restuans ナミカ属 カ科 その他
Cyclotella meneghiniana キクロテラ属
コスキノジスクス科
(珪藻類)
藻 類
Cyprinodon variegatus
キプリノドン科
(カダヤシ目)
魚 類
Cyprinus carpio コイ コイ科 魚 類
14
学名 和名・属名 科・目名等 生物群
Danio rerio
(=Brachydanio rerio)
ゼブラフィッシュ コイ科 魚 類
Daphnia magna オオミジンコ ミジンコ科 甲殻類
Daphnia pulex ミジンコ ミジンコ科 甲殻類
Desmodesmus subspicatus
(旧名Scenedesmus subspicatus*1)
デスモデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Dunaliella tertiolecta ドゥナリエラ属 ドゥナリエラ科(緑藻類) 藻 類
Elasmopus pectinicrus ヨコエビ科 甲殻類
Entosiphon sulcatum エントシフォン属 ペラネマ科(ユウグレナ目) その他
Fundulus heteroclitus マミチョグ Fundulidae(カダヤシ目) 魚 類
Fungia scutaria クサビライシ
クサビライシ科
(イシサンゴ目)
その他
Gadus morhua マダラ属 タラ科 魚 類
Gambusia affinis カダヤシ カダヤシ科 魚 類
Gammarus pulex ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類
Hyalella azteca ヨコエビ科 甲殻類
Hydra oligactis ヒドラ属 ヒドラ科 その他
Ictalurus punctatus アメリカナマズ ナマズ目 魚 類
Idus idus melanotus コイ科 魚 類
Lemna gibba イボウキクサ ウキクサ科 その他
Lemna minor コウキクサ ウキクサ科 その他
Lepomis macrochirus ブルーギル サンフィッシュ科(スズキ目) 魚 類
Leuciscus idus コイ科 魚 類
Leuciscus idus melanotus コイ科 魚 類
Libinia dubia クモガニ科 甲殻類
Litoria adelaidensis アマガエル科 その他
Lymnaea stagnalis モノアラガイ科(巻貝) その他
Microcystis aeruginosa ミクロキスティス属 クロオコックス科(藍藻類) 藻 類
Moina macrocopa タマミジンコ ミジンコ科 甲殻類
Mulinia lateralis バカガイ科(二枚貝) その他
Mytilus edulis ムラサキイガイ イガイ科(二枚貝) その他
Navicula pelliculosa ナビクラ属 ナビクラ科(珪藻類) 藻 類
Nitocra spinipes ナミミズベソコミジンコ
ソコミジンコ(ハルパクチ
クス)目
甲殻類
Oithona davisae オイトナ属 オイトナ科(カイアシ類) 甲殻類
Oncorhynchus kisutch ギンザケ サケ科 魚 類
Oncorhynchus mykiss ニジマス サケ科 魚 類
15
学名 和名・属名 科・目名等 生物群
(=Salmo gairdneri)
Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類
Pagrus major マダイ タイ科 魚 類
Palaemonetes kadiakensis テナガエビ科 甲殻類
Palaemonetes pugio テナガエビ科 甲殻類
Panopeus herbstii イソオウギガニ科 甲殻類
Paramecium caudatum ゾウリムシ ミズケムシ目 その他
Paramecium trichium
パラメシウム属
(ゾウリムシと同属)
ミズケムシ目 その他
Paratanytarsus parthenogeneticus ニセヒゲユスリカ属 ユスリカ科 その他
Paratanytarsus sp. ニセヒゲユスリカ属 ユスリカ科 その他
Pecten opercularis イタヤガイ科(二枚貝) その他
Pimephales promelas ファットヘッドミノー コイ科 魚 類
Platichthys flesus ヌマガレイ属 カレイ科 魚 類
Platynereis dumeralii ゴカイ科(多毛類) その他
Pleuronectes flesus ツノガレイ属 カレイ科 魚 類
Poecilia reticulata グッピー カダヤシ科 魚 類
Portunus pelagicus タイワンガザミ ワタリガニ科 甲殻類
Pseudokirchneriella subcapitata
(旧名Selenastrum capricornutum*2)
プセウドキルクネリエラ属オーキスチス科 (緑藻類) 藻 類
Rana catesbeiana ウシガエル アカガエル科 その他
Rana pipiens アカガエル科 その他
Rasbora heteromorpha ラスボラ属 コイ科 魚 類
Salmo trutta ブラウントラウト サケ科 魚 類
Scenedesmus obliquus セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Scenedesmus opoliensis セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Scenedesmus pannonicus セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Scenedesmus quadricauda セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Scenedesmus vacuolatus セネデスムス属 セネデスムス科(緑藻類) 藻 類
Skeletonema costatum スケレトネマ属 タラシオシラ科(珪藻類) 藻 類
Solea solea
ササウシノシタ科
(カレイ目)
魚類
Tetrahymena elliotti テトラヒメナ属 ミズケムシ目 その他
Tetrahymena pyriformis テトラヒメナ属 ミズケムシ目 その他
Tetrahymena thermophila テトラヒメナ属 ミズケムシ目 その他
Utterbackia imbecillis イシガイ科(二枚貝) その他
Xenopus laevis アフリカツメガエル ピパ(コモリガエル)科 その他
*1 OECD テストガイドラインNo.201 における記述に準じて、ここでは旧名と表記した
http://www.env.go.jp/chemi/report/h21-01/index.html
2009年10月25日
底質環境基準
'''底質の環境基準'''(ていしつのかんきょうきじゅん)とは、水底の底質について国が定めている環境基準のこと。現在、ダイオキシン類(150pg-TEQ/g)についてのみが定められている。底質には有害物質が蓄積されており食物連鎖を通じて人への健康被害が生じており、生態系への顕著な影響が知られている。重金属や環境ホルモン等の有害物質に基準が求められている。
== 内容 ==
[[ダイオキシン類]]のみが定められている。
=== ダイオキシン類 ===
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、ダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準である。
* 媒体:水底の底質
* 基準:150pg-TEQ/g以下
* 測定方法:水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
== 底質の環境中の濃度に係るその他の基準 ==
=== 暫定除去基準 ===
「底質暫定除去基準」として水銀とポリ塩化ビフェニル(PCB)が定められている。
=== 水産用水基準による底質の基準 ===
*河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。
*海域では乾泥として化学的酸素要求量(COD)(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること
*微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、[[種苗]]の着生、発生あるいはその発育を妨げないことなどとされている。
*海域では乾泥としてCODOH(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること。
*海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については、水産用水基準の基準値の10倍を下回ること。ただし、カドミウム、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の検出下限値を下回ること。
*ダイオキシン類の濃度は150pgTEQ/gを下回ること。
=== 水底土砂判定基準 ===
環境中の濃度を示すものではないが、浚渫した土砂(底質)を海面[[埋立]]または[[海洋投入]]するにあたって定められている基準として、「水底土砂に係る判定基準」がある。
== 底質の環境基準の必要性 ==
底質汚染は水俣病の事例のように食物連鎖を通してヒトの健康被害が懸念されている。今後、早急に鉛やヒ素などの重金属類やテトラクロロエチレンなどの揮発性有機化合物さらにPOPs農薬などの有害物質に関する底質環境基準を定めることが必要であるとされている。
== 底質の環境中の濃度の評価について ==
=== 土壌環境基準との比較 ===
底質を浚渫して陸上に上げると土壌となる。底質は土壌の一部であるという考え方もあるが、統一されていない。
しかし、底質汚染が土壌汚染と比べて健康リスクは高いが、人の健康の保護に関する水質環境基準に定められている物質について、地下水の水質汚濁に係る環境基準や、土壌の汚染に係る環境基準が定められているのに対し、現在底質の環境基準は定められていない。
なお、土壌の汚染に係る環境基準は、汚染された土壌から地下水等への溶出の観点から上記の溶出量の基準が定められているほか、農作物に対する影響および農作物に蓄積して人の健康に影響を及ぼす観点から含有量の基準が定められている。
ダイオキシン類については、土壌環境基準値が1,000pg-TEQ/gとなっており、底質環境基準値がその15%となっている。
=== 底生生物と有害物質の関係 ===
平成14年に港湾底泥調査が国の機関により実施され、[[重金属]]濃度と[[底生生物]]の種類数との相関関係が公開されている。底生生物の種類が比較的豊富である限界の濃度であるERLの含有量値を下記に示す。
水銀:0.1mg/kg乾泥
カドミウム:1mg/kg乾泥
銅:34mg/kg乾泥
鉛:46.7mg/kg乾泥
ニッケル:20mg/kg乾泥
クロム:80mg/kg乾泥
亜鉛:150mg/kg乾泥
特に、カドミウム・鉛・水銀についてはERLを超過した底質には底生生物が激減することが公開されている。含有量値と溶出量値との明確な相関関係は認められないが、底生生物が水生生物と同程度の感受性を持ち、エラからの吸収による影響が主体的であれば水産用水基準水質環境基準の近似値が一つの目標となる。
ERL(effects range-low):悪影響があるとした報告例のうち低濃度側から10 パーセンタイル値の濃度(最小影響範囲:底生生物の種類が豊富である限界の濃度)
ERM(effects range-median):悪影響があるとした報告例のうち低濃度側から10 パーセンタイル値の濃度(確実な影響範囲:底生生物がほとんどいない濃度)
ERL以上ERM未満の濃度は潜在影響範囲と呼ばれている。
この手法は底質評価のガイドライン値を提供するものであり、カナダ国家底質ガイドラインおよび、フロリダ州の底質ガイドライン開発の基礎として利用されているほかロサンゼルス・ロングビーチ港で適用されている。
=== 溶出量値 ===
前述したERLにおける含有量値と溶出量値との明確な相関関係は認められないが、底生生物が水生生物と同程度の感受性を持ち、エラからの吸収による影響が主体的であれば水産用水基準(水質環境基準の近似値)が一つの目標となる。
なお、亜鉛の水生生物保全のための環境基準は0.02mg/Lである。|また、河川や港湾の底から地下水へ浸透しているので、地下水の環境基準を基本とした土壌環境基準を底質の環境基準として取り組んでる。
== 外部リンク ==
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準
化学物質と環境(年次報告書)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)
4 . 基準値(1)基本的考え方 底質中ダイオキシン類が人の健康に影響を及ぼす恐れは、魚介類への取り込み並びに底質から水への巻き上げ及び溶出の2つの影響経路からが考えられる。
?魚介類への取り込みを考慮する方式について
ダイオキシン類については国民摂取実態から魚介類を経由した摂取が多いことが既知の事実であり、また、平成11年度に環境庁が行った調査では、底質中ダイオキシン類濃度と魚介類中ダイオキシン類濃度との関係においては、相関係数が小さいながらも有意な正の相関があることが分かっている。
他方、ダイオキシン類については、国民の平均的なダイオキシン類摂取量が耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake。以下「TDI」という。)に比較して小さく、バランスのとれた食事が大切と整理されている。また、食品としての魚介類の許容上限値が定められていない。
このため、現時点では、対策実施のための底質環境基準の設定において、基準値導出に必要な諸条件が不足しており、この観点から数値を設定することは困難な状況にある。
?水への影響を考慮する方式について
底質中ダイオキシン類は、ダイオキシン類の水への供給源(汚染源)となっており、その影響の程度を勘案して設定するという方式については、底泥中の間隙水の濃度に着目して底質濃度を規定する分配平衡法と、実際にダイオキシン類に汚染された底泥を用いて水への振とう分配試験を行い、水質への影響を考慮する方法の2種類がある。
他にも様々な手法が考えられるが、現時点でデータが得られており、算定が可能な手法として、本報告では、これら両者の手法を勘案して環境基準値を設定することとした。
(2)設定手法
?分配平衡法
底質の間隙水中の化学物質濃度は底質の固相における濃度と平衡状態を形成しており、底質固相の濃度は底質の有機物濃度によって変動する。
つまり、平衡条件下にある底質と水との間の化学物質の分配係数は、?固相中濃度と間隙水濃度との比、及び?有機炭素と水との分配係数と、底質の有機炭素の割合との積、の2つの方法で表すことができる。模式的には、下記の(1)式の様に書くことができる。
Kp = Cs / Cd = foc・Koc (1)
Kp : 底質中、固相と間隙水の分配係数
Cs : 固相の化学物質濃度
Cd : 間隙水中の化学物質濃度
foc : 有機炭素割合(%)
Koc : 有機炭素と水との分配係数(cm3/g org.C)
log Kocは、log Kow(オクタノール-水分配係数)を変数として換算式から算定することができる。換算式としては複数の学説があるが、本報告では、
?PCBのlog Kowの値を主に解析しており、
?諸外国で底質基準値を水質環境基準
値から導出する際に実際に用いられている、下記の式を用いるものとした。
log Koc = 1.03 × log Kow ― 0.61
log Kowの値は、ダイオキシン類の異性体ごとに異なっており、概ね6〜8であるが、本報告では、米Federal Register(1995年3月23日付)に掲載された、栄養連鎖上、濃縮係数が最も大きいとされるlog Kowの数値である6.9を用いるものとする。
log Koc = 6.50
(1)式は下記の様に書くことができる。
( Cs×(1/foc) )/ Cd = Koc (2)
間隙水濃度に水質環境基準値である1pg-TEQ/L(1×10-3pg-TEQ/ml)、有機炭素濃度を5%(同手法を用いる独仏と同じ数値)とし、代入すると、
Cs = 157 pg-TEQ/g
となり、概ね、150pg-TEQ/gとなる。
※ 平成11年度に環境庁が実施した調査結果では、例えば、東京湾の調査地点(20地点)の底質に含まれるダイオキシン類について、異性体ごとに毒性等量換算後の重み付けをして計算したところ、log Kow の数値の範囲は6.9〜7.2であった。
※ 間隙水濃度については、底質からの水への移行のみを考えた場合に水質濃度は底質間隙水濃度を超えないこと、また、底生生物への影響を考慮し、水質環境基準濃度とした。
? 振とう分配試験結果
高濃度のダイオキシン類を含む底質からの、水質への巻き上げ及び溶出の程度を把握するため、平成13年度に環境省において高濃度の底泥の振とう分配試験を実施し、その結果を検討した。
試験対象底泥として、国内の海域及び河川からそれぞれ2検体を採取し、振とう分配試験を行い、試験水中のSS濃度を通常状態まで低減させた場合を計算した。この結果、試験水濃度が水質環境基準である1pg-TEQ/Lに対応する底質濃度の全試験結果の平均値は196pg-TEQ/g であった。
(3)数値
(2)?及び?の結果を比較すると、?の振とう分配試験結果から導出した数値は、?の分配平衡法で導出した値と比較して大きい数値である。
一方、振とう分配試験結果の解析は現時点で得られているデータに基づくものであり、多様な底泥の全てを代表しているとは断言できないことを勘案し、?及び?の結果から、ダイオキシン類の底質環境基準値は150pg-TEQ/g とすることが適当である。
(4)一日摂取量との関係
ダイオキシン類については、食品としての魚介類の許容上限値が定められていないが、他方、国民の平均的なダイオキシン類摂取量については毎年調査が実施されていることから、これらの結果を用いて、本報告で提案する底質環境基準値まで対策を実施した場合の、ダイオキシン類の一日摂取量の試算を行った。
平成12年度におけるダイオキシン類常時監視結果から、底質150pg-TEQ/g 以上の濃度地点について、提案している基準値150pg-TEQ/g まで濃度を低減させた場合、全体の底質濃度の平均値は、計算上、現行の9.6 pg-TEQ/gから7.8pg-TEQ/g となる。
魚介類摂取量のうち、内海魚及び外海魚のダイオキシン類の平均濃度を平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告及び野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告から計算する。
更に、内海魚と外海魚の摂取割合を仮定し、また、内海魚からの摂取量が底質濃度の低減に比して低減すると仮定した場合の、魚介類を経由したダイオキシン類の平均一日摂取量を計算、この結果から、食品経由でのダイオキシン類の平均一日摂取量を推定すると、1.7pg-TEQ/kg/day となる。
※ これらの計算には下記の数値を用いた。
?内海魚及び外海魚平均濃度
平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告における野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告に示された個別食品毎の濃度結果から計算し、内海魚平均2.0pg-TEQ/g、外海魚平均1.2pg-TEQ/g とした。この場合、摂取重量割合を勘案した平均値は1.4pg-TEQ/g となる。
なお、平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告によれば、魚介類からの摂取量は71pg-TEQ/day であり、単純に魚介類一日摂取重量の3カ年平均値でこの数値を除すと、0.74pg-TEQ/g となる。
?内海魚と外海魚の摂取重量割合
内海魚4分の1、外海魚4分の3とした。
?1日魚介類平均摂取量
平成9〜11年国民栄養調査結果から、平均96gとした。
?体重
50kgとした。
?魚介類からのダイオキシン類の摂取割合
平成12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告から、76%とした。
5.適用
ダイオキシン類の底質環境基準については、人の健康の保護という観点から見た場合、間接的に飲料水及び魚介類経由の食物摂取による影響を考慮する必要があることから、他の健康項目同様、河川、湖沼、海域を問わず、全公共用水域に適用することが適当である。
6.達成期間
ダイオキシン類については、多様な経路を経て人体に摂取されるため、環境媒体間における移行による時間的遅れ等の要素を考慮すれば、「可及的速やかにその達成維持に努める」等とすることが適当である。
参考となるパワーポイント底質汚染対策の過去・現在・将来 有害物質に関する基準と底質対策
このパワーポイントは、「環境技術支援ネットワーク」及び「おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会」主催のセミナーで、東京農工大学細見正明教授が2007年に講演されたものです。
http://www.ts-net.or.jp/files/070601_teisitsu.pdf
重金属による底質汚染と重金属底質環境基準のありかた
おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会オフシャルブログより
底生生物が明らかに減少する重金属濃度は下記の通りです。
水 銀:0.15mg/kg
カドミウム:1.2mg/kgを
ク ロ ム:81mg/kg
亜 鉛:150mg/kg
ダイオキシン類:21.5pg-TEQ/g
http://atcwsr.earthblog.jp/e110975.html
== 内容 ==
[[ダイオキシン類]]のみが定められている。
=== ダイオキシン類 ===
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、ダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準である。
* 媒体:水底の底質
* 基準:150pg-TEQ/g以下
* 測定方法:水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
== 底質の環境中の濃度に係るその他の基準 ==
=== 暫定除去基準 ===
「底質暫定除去基準」として水銀とポリ塩化ビフェニル(PCB)が定められている。
=== 水産用水基準による底質の基準 ===
*河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。
*海域では乾泥として化学的酸素要求量(COD)(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること
*微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、[[種苗]]の着生、発生あるいはその発育を妨げないことなどとされている。
*海域では乾泥としてCODOH(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること。
*海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については、水産用水基準の基準値の10倍を下回ること。ただし、カドミウム、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の検出下限値を下回ること。
*ダイオキシン類の濃度は150pgTEQ/gを下回ること。
=== 水底土砂判定基準 ===
環境中の濃度を示すものではないが、浚渫した土砂(底質)を海面[[埋立]]または[[海洋投入]]するにあたって定められている基準として、「水底土砂に係る判定基準」がある。
== 底質の環境基準の必要性 ==
底質汚染は水俣病の事例のように食物連鎖を通してヒトの健康被害が懸念されている。今後、早急に鉛やヒ素などの重金属類やテトラクロロエチレンなどの揮発性有機化合物さらにPOPs農薬などの有害物質に関する底質環境基準を定めることが必要であるとされている。
== 底質の環境中の濃度の評価について ==
=== 土壌環境基準との比較 ===
底質を浚渫して陸上に上げると土壌となる。底質は土壌の一部であるという考え方もあるが、統一されていない。
しかし、底質汚染が土壌汚染と比べて健康リスクは高いが、人の健康の保護に関する水質環境基準に定められている物質について、地下水の水質汚濁に係る環境基準や、土壌の汚染に係る環境基準が定められているのに対し、現在底質の環境基準は定められていない。
なお、土壌の汚染に係る環境基準は、汚染された土壌から地下水等への溶出の観点から上記の溶出量の基準が定められているほか、農作物に対する影響および農作物に蓄積して人の健康に影響を及ぼす観点から含有量の基準が定められている。
ダイオキシン類については、土壌環境基準値が1,000pg-TEQ/gとなっており、底質環境基準値がその15%となっている。
=== 底生生物と有害物質の関係 ===
平成14年に港湾底泥調査が国の機関により実施され、[[重金属]]濃度と[[底生生物]]の種類数との相関関係が公開されている。底生生物の種類が比較的豊富である限界の濃度であるERLの含有量値を下記に示す。
水銀:0.1mg/kg乾泥
カドミウム:1mg/kg乾泥
銅:34mg/kg乾泥
鉛:46.7mg/kg乾泥
ニッケル:20mg/kg乾泥
クロム:80mg/kg乾泥
亜鉛:150mg/kg乾泥
特に、カドミウム・鉛・水銀についてはERLを超過した底質には底生生物が激減することが公開されている。含有量値と溶出量値との明確な相関関係は認められないが、底生生物が水生生物と同程度の感受性を持ち、エラからの吸収による影響が主体的であれば水産用水基準水質環境基準の近似値が一つの目標となる。
ERL(effects range-low):悪影響があるとした報告例のうち低濃度側から10 パーセンタイル値の濃度(最小影響範囲:底生生物の種類が豊富である限界の濃度)
ERM(effects range-median):悪影響があるとした報告例のうち低濃度側から10 パーセンタイル値の濃度(確実な影響範囲:底生生物がほとんどいない濃度)
ERL以上ERM未満の濃度は潜在影響範囲と呼ばれている。
この手法は底質評価のガイドライン値を提供するものであり、カナダ国家底質ガイドラインおよび、フロリダ州の底質ガイドライン開発の基礎として利用されているほかロサンゼルス・ロングビーチ港で適用されている。
=== 溶出量値 ===
前述したERLにおける含有量値と溶出量値との明確な相関関係は認められないが、底生生物が水生生物と同程度の感受性を持ち、エラからの吸収による影響が主体的であれば水産用水基準(水質環境基準の近似値)が一つの目標となる。
なお、亜鉛の水生生物保全のための環境基準は0.02mg/Lである。|また、河川や港湾の底から地下水へ浸透しているので、地下水の環境基準を基本とした土壌環境基準を底質の環境基準として取り組んでる。
== 外部リンク ==
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準
化学物質と環境(年次報告書)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)
4 . 基準値(1)基本的考え方 底質中ダイオキシン類が人の健康に影響を及ぼす恐れは、魚介類への取り込み並びに底質から水への巻き上げ及び溶出の2つの影響経路からが考えられる。
?魚介類への取り込みを考慮する方式について
ダイオキシン類については国民摂取実態から魚介類を経由した摂取が多いことが既知の事実であり、また、平成11年度に環境庁が行った調査では、底質中ダイオキシン類濃度と魚介類中ダイオキシン類濃度との関係においては、相関係数が小さいながらも有意な正の相関があることが分かっている。
他方、ダイオキシン類については、国民の平均的なダイオキシン類摂取量が耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake。以下「TDI」という。)に比較して小さく、バランスのとれた食事が大切と整理されている。また、食品としての魚介類の許容上限値が定められていない。
このため、現時点では、対策実施のための底質環境基準の設定において、基準値導出に必要な諸条件が不足しており、この観点から数値を設定することは困難な状況にある。
?水への影響を考慮する方式について
底質中ダイオキシン類は、ダイオキシン類の水への供給源(汚染源)となっており、その影響の程度を勘案して設定するという方式については、底泥中の間隙水の濃度に着目して底質濃度を規定する分配平衡法と、実際にダイオキシン類に汚染された底泥を用いて水への振とう分配試験を行い、水質への影響を考慮する方法の2種類がある。
他にも様々な手法が考えられるが、現時点でデータが得られており、算定が可能な手法として、本報告では、これら両者の手法を勘案して環境基準値を設定することとした。
(2)設定手法
?分配平衡法
底質の間隙水中の化学物質濃度は底質の固相における濃度と平衡状態を形成しており、底質固相の濃度は底質の有機物濃度によって変動する。
つまり、平衡条件下にある底質と水との間の化学物質の分配係数は、?固相中濃度と間隙水濃度との比、及び?有機炭素と水との分配係数と、底質の有機炭素の割合との積、の2つの方法で表すことができる。模式的には、下記の(1)式の様に書くことができる。
Kp = Cs / Cd = foc・Koc (1)
Kp : 底質中、固相と間隙水の分配係数
Cs : 固相の化学物質濃度
Cd : 間隙水中の化学物質濃度
foc : 有機炭素割合(%)
Koc : 有機炭素と水との分配係数(cm3/g org.C)
log Kocは、log Kow(オクタノール-水分配係数)を変数として換算式から算定することができる。換算式としては複数の学説があるが、本報告では、
?PCBのlog Kowの値を主に解析しており、
?諸外国で底質基準値を水質環境基準
値から導出する際に実際に用いられている、下記の式を用いるものとした。
log Koc = 1.03 × log Kow ― 0.61
log Kowの値は、ダイオキシン類の異性体ごとに異なっており、概ね6〜8であるが、本報告では、米Federal Register(1995年3月23日付)に掲載された、栄養連鎖上、濃縮係数が最も大きいとされるlog Kowの数値である6.9を用いるものとする。
log Koc = 6.50
(1)式は下記の様に書くことができる。
( Cs×(1/foc) )/ Cd = Koc (2)
間隙水濃度に水質環境基準値である1pg-TEQ/L(1×10-3pg-TEQ/ml)、有機炭素濃度を5%(同手法を用いる独仏と同じ数値)とし、代入すると、
Cs = 157 pg-TEQ/g
となり、概ね、150pg-TEQ/gとなる。
※ 平成11年度に環境庁が実施した調査結果では、例えば、東京湾の調査地点(20地点)の底質に含まれるダイオキシン類について、異性体ごとに毒性等量換算後の重み付けをして計算したところ、log Kow の数値の範囲は6.9〜7.2であった。
※ 間隙水濃度については、底質からの水への移行のみを考えた場合に水質濃度は底質間隙水濃度を超えないこと、また、底生生物への影響を考慮し、水質環境基準濃度とした。
? 振とう分配試験結果
高濃度のダイオキシン類を含む底質からの、水質への巻き上げ及び溶出の程度を把握するため、平成13年度に環境省において高濃度の底泥の振とう分配試験を実施し、その結果を検討した。
試験対象底泥として、国内の海域及び河川からそれぞれ2検体を採取し、振とう分配試験を行い、試験水中のSS濃度を通常状態まで低減させた場合を計算した。この結果、試験水濃度が水質環境基準である1pg-TEQ/Lに対応する底質濃度の全試験結果の平均値は196pg-TEQ/g であった。
(3)数値
(2)?及び?の結果を比較すると、?の振とう分配試験結果から導出した数値は、?の分配平衡法で導出した値と比較して大きい数値である。
一方、振とう分配試験結果の解析は現時点で得られているデータに基づくものであり、多様な底泥の全てを代表しているとは断言できないことを勘案し、?及び?の結果から、ダイオキシン類の底質環境基準値は150pg-TEQ/g とすることが適当である。
(4)一日摂取量との関係
ダイオキシン類については、食品としての魚介類の許容上限値が定められていないが、他方、国民の平均的なダイオキシン類摂取量については毎年調査が実施されていることから、これらの結果を用いて、本報告で提案する底質環境基準値まで対策を実施した場合の、ダイオキシン類の一日摂取量の試算を行った。
平成12年度におけるダイオキシン類常時監視結果から、底質150pg-TEQ/g 以上の濃度地点について、提案している基準値150pg-TEQ/g まで濃度を低減させた場合、全体の底質濃度の平均値は、計算上、現行の9.6 pg-TEQ/gから7.8pg-TEQ/g となる。
魚介類摂取量のうち、内海魚及び外海魚のダイオキシン類の平均濃度を平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告及び野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告から計算する。
更に、内海魚と外海魚の摂取割合を仮定し、また、内海魚からの摂取量が底質濃度の低減に比して低減すると仮定した場合の、魚介類を経由したダイオキシン類の平均一日摂取量を計算、この結果から、食品経由でのダイオキシン類の平均一日摂取量を推定すると、1.7pg-TEQ/kg/day となる。
※ これらの計算には下記の数値を用いた。
?内海魚及び外海魚平均濃度
平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告における野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告に示された個別食品毎の濃度結果から計算し、内海魚平均2.0pg-TEQ/g、外海魚平均1.2pg-TEQ/g とした。この場合、摂取重量割合を勘案した平均値は1.4pg-TEQ/g となる。
なお、平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告によれば、魚介類からの摂取量は71pg-TEQ/day であり、単純に魚介類一日摂取重量の3カ年平均値でこの数値を除すと、0.74pg-TEQ/g となる。
?内海魚と外海魚の摂取重量割合
内海魚4分の1、外海魚4分の3とした。
?1日魚介類平均摂取量
平成9〜11年国民栄養調査結果から、平均96gとした。
?体重
50kgとした。
?魚介類からのダイオキシン類の摂取割合
平成12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告から、76%とした。
5.適用
ダイオキシン類の底質環境基準については、人の健康の保護という観点から見た場合、間接的に飲料水及び魚介類経由の食物摂取による影響を考慮する必要があることから、他の健康項目同様、河川、湖沼、海域を問わず、全公共用水域に適用することが適当である。
6.達成期間
ダイオキシン類については、多様な経路を経て人体に摂取されるため、環境媒体間における移行による時間的遅れ等の要素を考慮すれば、「可及的速やかにその達成維持に努める」等とすることが適当である。
参考となるパワーポイント底質汚染対策の過去・現在・将来 有害物質に関する基準と底質対策
このパワーポイントは、「環境技術支援ネットワーク」及び「おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会」主催のセミナーで、東京農工大学細見正明教授が2007年に講演されたものです。
http://www.ts-net.or.jp/files/070601_teisitsu.pdf
重金属による底質汚染と重金属底質環境基準のありかた
おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会オフシャルブログより
底生生物が明らかに減少する重金属濃度は下記の通りです。
水 銀:0.15mg/kg
カドミウム:1.2mg/kgを
ク ロ ム:81mg/kg
亜 鉛:150mg/kg
ダイオキシン類:21.5pg-TEQ/g
http://atcwsr.earthblog.jp/e110975.html
2009年10月25日
底質暫定除去基準''
'''底質暫定除去基準'''(ていしつざんていじょきょきじゅん)は、1975年(昭和50年)に定められた、水銀及びポリ塩化ビフェニル(PCB) に汚染された底質を除去する範囲を定める場合の基準である。
== 調査方法 ==
調査の方法は、「底質調査方法」[http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000178 底質方法の改定について ](昭和63年9月8日付け環水管第127号)に基づく。
底質を除去する範囲を定める調査の方法は、「底質調査方法」に基づき、メッシュの通常4つの交点の測定値の平均値を当該メッシュ内の平均濃度として考える。
== 基準値 ==
水銀及びポリ塩化ビフェニル (PCB)について、定められている。
===水銀===
水銀を含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、海域においては次式により算出した値(C)以上、河川及び湖沼においては25ppm以上である。
ただし、潮汐の影響を強く受ける河口部においては海域に準じ、沿岸流の強い海域においては河川及び湖沼に準ずるとされる。
:C=0.18・(△H/J)・(1/S) (ppm)
:*△H=平均潮差(m)
:*J=溶出率
:*S=安全率
*平均潮差△H(m)は、当該水域の平均潮差とする。ただし、潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては、平均潮差に代えて次式によって算出した値とする。
:△H=副振動の平均振幅(m)×(12×60(分))/(平均周期(分))
*溶出率Jは、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる四地点以上の底質について、「底質調査方法」の溶出試験により溶出率を求め、その平均値を当該水域の底質の溶出率とする。
*安全率Sは、当該水域及びその周辺の漁業の実態に応じて、次の区分により定めた数値とする。なお、地域の食習慣等の特殊事情に応じて安全率を更に見込むことは差し支えない。
**漁業が行われていない水域においては、10とする。
**漁業が行われている水域で、底質及び底質に付着している生物を摂取する魚介類(エビ、カニ、シャコ、ナマコ、ボラ、巻貝類等)の漁獲量の総漁獲量に対する割合が、おおむね2分の1以下である水域においては50、おおむね2分の1を超える水域においては100とする。
<単位>
10 ppm = 10 mg/kg
- *土壌の環境基準値は溶出量値として、総水銀は0.0005mg/L以下であり、アルキル水銀は「検液中に検出されないこと」である。
- *土壌汚染対策法における指定基準は含有量として、土壌1kgにつき15mg以下となっている。ただし、土壌汚染対策法における試験方法が真水を使うのに対し、底質調査法は強酸を使用して試料に含まれる水銀を分析するので単純に比較できない。なお、土壌汚染対策法の分析方法は底質調査法より数分の1の値しかでないことが知られている。
- *海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律による水底土砂の判定基準は「水銀又はその化合物」の溶出量値は銀0.005mg/L以下である。
===PCB===
PCBを含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、10ppm以上である。
==他の基準値との比較==
===水銀===
25ppmは、25mg/kgとも表記できる。
*土壌の環境基準において、溶出量値として、総水銀は0.0005mg/L以下であり、アルキル水銀は「検液中に検出されないこと」である。
*土壌汚染対策法における指定基準は含有量として、土壌1kgにつき15mg以下となっている。ただし、土壌汚染対策法における試験方法が真水を使うのに対し、底質調査法は強酸を使用して試料に含まれる水銀を分析するので単純には比較できない。なお、土壌汚染対策法の分析方法は底質調査法より数分の1の値しかでないことが知られている。
*海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律による水底土砂に係る判定基準において、「水銀又はその化合物」の溶出量値は銀0.005mg/L以下である。
===PCB===
10ppmは10mg/kg、10,000,000pg/gとも表記できる。
PCBのうち、コプラナーPCB(塩素原子が分子の外側を向き平面状分子となっているもの、一般のPCBに比べて毒性が高い。)はダイオキシン類の一部に分類されている。
現在のダイオキシン類の底質環境基準は150 pg-TEQ/gであり、10ppm(=10,000,000pg/g)と大きな差があるように見えるが、対象となる物質が異なるとともに分析方法や毒性等量|毒性等価係数等の差コプラナーPCBの毒性等価係数(TEF)は、0.1〜0.00003である。[http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/mamoru/kanshi/dioxin/tef.html 横浜市 環境創造局 環境監視センター :毒性等価係数(TEF)]があることから単純には比較できない。
底質の環境中におけるPCBとダイオキシンの濃度について、PCBについては平成19年度版「化学物質と環境」[http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/ 「化学物質と環境」]によれば、平成18年度の各調査地点の年間平均値が36〜670,000pg/g-dry、その幾何平均値が7,600pg/g-dryであり、ダイオキシン類については[[ダイオキシン法]]に基づくモニタリングデータ[http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h20/html/hj08020503.html#n2_5_3_3 平成20年版環境白書]によれば平成18年の各調査地点の年間平均値は0.056〜750pg-TEQ/g、その幾何平均値が6.7pg-TEQ/gとなっている。
PCB濃度が2ppmを超過すると多くの場合で、ダイオキシン類濃度が150pg-TEQ/gを超過することを各河川・港湾管理者が公開している。
10 ppm = 10 mg/kg = 10,000,000 pg/g
- PCBのうち、コプラナーPCB(塩素原子が分子の外側を向き平面状分子となっているもの、一般のPCBに比べて毒性が高い。)はダイオキシン類の一部に分類されている。現在のダイオキシン類の底質環境基準は150 pg-TEQ/gである。分析方法や毒性等価係数等の差はあるにしても上記のように、本基準は現在のダイオキシン類底質環境基準を大きく離れている。
== 外部リンク ==
底質の暫定除去基準について]
環境基準について(環境省)]
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)]
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第18号)]
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第19号)]
要調査項目について(環境省)
== 調査方法 ==
調査の方法は、「底質調査方法」[http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000178 底質方法の改定について ](昭和63年9月8日付け環水管第127号)に基づく。
底質を除去する範囲を定める調査の方法は、「底質調査方法」に基づき、メッシュの通常4つの交点の測定値の平均値を当該メッシュ内の平均濃度として考える。
== 基準値 ==
水銀及びポリ塩化ビフェニル (PCB)について、定められている。
===水銀===
水銀を含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、海域においては次式により算出した値(C)以上、河川及び湖沼においては25ppm以上である。
ただし、潮汐の影響を強く受ける河口部においては海域に準じ、沿岸流の強い海域においては河川及び湖沼に準ずるとされる。
:C=0.18・(△H/J)・(1/S) (ppm)
:*△H=平均潮差(m)
:*J=溶出率
:*S=安全率
*平均潮差△H(m)は、当該水域の平均潮差とする。ただし、潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては、平均潮差に代えて次式によって算出した値とする。
:△H=副振動の平均振幅(m)×(12×60(分))/(平均周期(分))
*溶出率Jは、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる四地点以上の底質について、「底質調査方法」の溶出試験により溶出率を求め、その平均値を当該水域の底質の溶出率とする。
*安全率Sは、当該水域及びその周辺の漁業の実態に応じて、次の区分により定めた数値とする。なお、地域の食習慣等の特殊事情に応じて安全率を更に見込むことは差し支えない。
**漁業が行われていない水域においては、10とする。
**漁業が行われている水域で、底質及び底質に付着している生物を摂取する魚介類(エビ、カニ、シャコ、ナマコ、ボラ、巻貝類等)の漁獲量の総漁獲量に対する割合が、おおむね2分の1以下である水域においては50、おおむね2分の1を超える水域においては100とする。
<単位>
10 ppm = 10 mg/kg
- *土壌の環境基準値は溶出量値として、総水銀は0.0005mg/L以下であり、アルキル水銀は「検液中に検出されないこと」である。
- *土壌汚染対策法における指定基準は含有量として、土壌1kgにつき15mg以下となっている。ただし、土壌汚染対策法における試験方法が真水を使うのに対し、底質調査法は強酸を使用して試料に含まれる水銀を分析するので単純に比較できない。なお、土壌汚染対策法の分析方法は底質調査法より数分の1の値しかでないことが知られている。
- *海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律による水底土砂の判定基準は「水銀又はその化合物」の溶出量値は銀0.005mg/L以下である。
===PCB===
PCBを含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、10ppm以上である。
==他の基準値との比較==
===水銀===
25ppmは、25mg/kgとも表記できる。
*土壌の環境基準において、溶出量値として、総水銀は0.0005mg/L以下であり、アルキル水銀は「検液中に検出されないこと」である。
*土壌汚染対策法における指定基準は含有量として、土壌1kgにつき15mg以下となっている。ただし、土壌汚染対策法における試験方法が真水を使うのに対し、底質調査法は強酸を使用して試料に含まれる水銀を分析するので単純には比較できない。なお、土壌汚染対策法の分析方法は底質調査法より数分の1の値しかでないことが知られている。
*海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律による水底土砂に係る判定基準において、「水銀又はその化合物」の溶出量値は銀0.005mg/L以下である。
===PCB===
10ppmは10mg/kg、10,000,000pg/gとも表記できる。
PCBのうち、コプラナーPCB(塩素原子が分子の外側を向き平面状分子となっているもの、一般のPCBに比べて毒性が高い。)はダイオキシン類の一部に分類されている。
現在のダイオキシン類の底質環境基準は150 pg-TEQ/gであり、10ppm(=10,000,000pg/g)と大きな差があるように見えるが、対象となる物質が異なるとともに分析方法や毒性等量|毒性等価係数等の差コプラナーPCBの毒性等価係数(TEF)は、0.1〜0.00003である。[http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/mamoru/kanshi/dioxin/tef.html 横浜市 環境創造局 環境監視センター :毒性等価係数(TEF)]があることから単純には比較できない。
底質の環境中におけるPCBとダイオキシンの濃度について、PCBについては平成19年度版「化学物質と環境」[http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/ 「化学物質と環境」]によれば、平成18年度の各調査地点の年間平均値が36〜670,000pg/g-dry、その幾何平均値が7,600pg/g-dryであり、ダイオキシン類については[[ダイオキシン法]]に基づくモニタリングデータ[http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h20/html/hj08020503.html#n2_5_3_3 平成20年版環境白書]によれば平成18年の各調査地点の年間平均値は0.056〜750pg-TEQ/g、その幾何平均値が6.7pg-TEQ/gとなっている。
PCB濃度が2ppmを超過すると多くの場合で、ダイオキシン類濃度が150pg-TEQ/gを超過することを各河川・港湾管理者が公開している。
10 ppm = 10 mg/kg = 10,000,000 pg/g
- PCBのうち、コプラナーPCB(塩素原子が分子の外側を向き平面状分子となっているもの、一般のPCBに比べて毒性が高い。)はダイオキシン類の一部に分類されている。現在のダイオキシン類の底質環境基準は150 pg-TEQ/gである。分析方法や毒性等価係数等の差はあるにしても上記のように、本基準は現在のダイオキシン類底質環境基準を大きく離れている。
== 外部リンク ==
底質の暫定除去基準について]
環境基準について(環境省)]
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)]
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第18号)]
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第19号)]
要調査項目について(環境省)
2009年10月25日
工事中:(Wikipedia)より詳しく正確な底質汚染
底質汚染
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に加筆訂正

底質汚染(ていしつおせん)とは底質が汚染されていることをいう。底質とは海域、港湾、河川、水路、湖沼などの水底の土砂やヘドロ等のことである。狭義には底質の環境基準はダイオキシン類のみ(150pg-TEQ/g)が定められておりこの基準を超過するもの(詳しくは底質の環境基準を参照)のこと。 なお、PCBや水銀には底質暫定除去基準が定められており、対策は一旦行われた水域もあるが、依然として環境基準を大きく超過する底質が大量に存在している。
目次
1 概要
2 各地での底質汚染の取組み
3 各省庁の底質汚染の取組み
4 汚染原因の特定
5 浚渫土問題
6 水底ゴミ問題
7 底質浄化費用負担
8 法的規制
9 底質汚染の取組の歴史
10 出典
11 参照資料
12 関連項目
13 外部リンク
13.1 国土交通省
13.2 環境省
13.3 地方自治体
13.4 その他
13.5 関係法令
概要
環境白書に底質についての言及が現れたのは昭和46年版公害白書であり、それまでは典型公害として、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭の6種を公害の対象として捕らえていたが、冷却用水等による温排水問題やヘドロ問題に対処すれる為に「水底の底質の悪化」を公害の対象として認識するようになった。
ここで言う「ヘドロ問題」とは東京湾、大阪湾、田子の浦港、洞海湾、伊予三島港のヘドロである。問題にしているのはCOD(生物の大量死)や硫化物量(悪臭)が主であるが、東京湾と洞海湾ではカドミウム、クロム、水銀、鉛なども底質中に検出されているが、この頃は生物の大量死や藻類の異常繁茂が問題視されていた為、底質の多量の有機物に注目が集まっていた。
第2-2-11表ヘドロ問題発生主要水域のヘドロ状況(註昭和46年当時)
地域 測定年度 COD 硫化物 カドミウム クロム 全水銀 鉛
東京湾(鶴見付近) 昭和45 6.2mg/g - 0.009mg/g 0.01mg/g 0.018mg/g 0.25mg/g
東京湾(横浜本牧付近) 昭和45 4.9mg/g - 0.001mg/g 0.006mg/g 0.023mg/g 0.03mg/g
大阪湾(大坂港口) 昭和42 18.9mg/g 1.3mg/g - - - -
大阪湾(神戸港沖) 昭和42 25.2mg/g 0.3mg/g - - - -
田子の浦港 昭和44 11.4mg/g 2.1mg/g - - - -
洞海湾(湾口) 昭和44 16.4mg/g - 0.012mg/g 0.055mg/g - -
洞海湾(湾奥) 昭和44 21.6mg/g - 0.122mg/g 0.051mg/g - -
伊予三島港 昭和39 13.6mg/g 0.6mg/g - - - -
1972年(昭和47年)に初めて底質のPCB汚染の実態調査が全国1,445地点において実施されたその結果工場近接水域の4箇所については水質で0.011ppm以上底質で500ppm以上のPCBを検出し「PCB取扱い工場周辺の公共用水域の底質がかなり汚染されていることが明らかになった。」と環境白書では総括している。[3]
1970年(昭和45年)12月に「公害防止事業費事業者負担法」が制定され、1971年(昭和46年)5月10日から施行されている。5年後の1975年(昭和50年)2月末までにこの法律に従い静岡県・田子の浦湾(有機物堆積汚泥浚渫)、福岡県・中の川水系(PCB含有堆積汚泥浚渫)などの総計17件の底質汚染防止対策事業が実施されることとなる。[4]
この様に底質汚染除去事業が開始され、水銀に係る底質汚染については48年度底質調査では27水域で暫定除去基準値を超えたものが昭和49 - 52年度では暫定除去基準値を超える水域は42水域中7水域に減少した。PCBに係る底質汚染については昭和47 - 52年度の調査で除去等の対策を講じる必要がある69水域中54水域の除去事業が完了することになる。[5]
その約十年後の1987年(昭和62年)には水銀による底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある42水域中41水域が事業を完了し、PCBによる底質汚染底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある71水域はすべて事業を完了している[6]。
ダイオキシン類についての底質汚染は昭和62年度の調査よりモニタリングが開始され、低濃度ではあるが0.001 - 0.006ppbの2,3,7,8-TCDFが18箇の検体より検出されている。[7]約十年後の平成11年版環境白書においても「海、川、湖の底質、生物についてもこれまで10年以上にわたって毎年調査しているが、ダイオキシン類濃度に特段大きな変化は認められない。
しかし、環境中から広く検出されており、引き続き調査が必要である。」と環境白書で総括されている[8]その後平成14年度にダイオキシン類の環境基準を変更し、底質ダイオキシン類については757地点中18点で環境基準(150pg-TEQ/g)を超えることとなった。(平均11pg-TEQ/g)[9]
各地での底質汚染の取組み
2007年の国土交通省の発表によると汚染土量が把握されているのは7港湾であり、1港湾当たりの汚染土量の頻度分布を1港湾当たりの汚染土量は250,000m3 以下が3港湾と最も多く、250,000m3超が4港湾とされている。-*具体的な港名、汚染面積、汚染体積、汚染濃度を下記の通り公開している。
- **千葉港 、140ha、1,700千m3、〜15,000pg-TEQ/g
- **伏木富山港、41ha、 286千m3、〜10,000pg-TEQ/g
- **大阪港 、56ha、 925千m3、〜 7,200pg-TEQ/g
- **東京港 、0.7ha、 4.5千m3、〜 280pg-TEQ/g
- **田子の浦港、35ha、 542千m3、〜 3,600pg-TEQ/g
- **水俣港 、0.3ha、 12千m3、〜 920pg-TEQ/g
- **宇部港 、0.4ha、 5.6千m3、〜 2,700pg-TEQ/g

以下に各地の取組み状況を示す。
埼玉県:古綾瀬川において委員会を組織し取り組んでいる。
千葉県:市原港で高濃度の底質ダイオキシン類 (15,000pg-TEQ/g) の公開すると共に、汚染原因特定についても取り組んでいる。
東京都:横十軒川や隅田川河口部などの底質汚染について対策がなされている。水銀やダイオキシン類による食品汚染調査結果を公開している。豊洲貯木場でダイオキシン類による底質汚染が検出され屋形船係留施設の計画を変更した。
横浜市:横浜港などの底質汚染について対策が検討されている。
静岡県富士市[田子の浦港]底質(ダイオキシン類)浄化対策事業を港管理事務所が中心となって取り組んでいる。
京都府:「舞鶴引揚記念館周辺地域における環境問題専門家会議」で舞鶴湾の底質について議論し、鉛溶出量が0.1mg/L以上の範囲の対策として、浚渫及び覆砂を行うことが適当であるとし公開されている。また阿蘇海においても取り組んでいる。
大阪府:神崎川など大阪府が管理する河川について委員会を組織して取り組んでおり、公害防止事業費事業者負担法に従い三箇牧水路の汚染対策費用を汚染原因者が負担する計画を作成した。

大阪市:市内河川の底質汚染についてデータを公開し取り組んでいる。また、港湾部についても調査を進めている。
神戸市:遠矢浜北側水域の底質におけるダイオキシン類の環境基準超過について委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。また、2008年から浚渫だけでなく無害化処理等の無害化を含めた浄化対策を行っている。
高砂市:高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。
島根県:馬潟団地に周辺水路において委員会を組織して、公害防止事業費事業者負担法を適用し取り組んでいる。
北九州市:洞海湾の底質汚染について取り組んでいる。
環境省の発表では底質ダイオキシン類の検出は年を経るごとに減少し、平成17年度の調査[10]によると底質のダイオキシン類で環境基準150pg-TEQ/gを超えている地点は下記の6か所であったとされている。
東京都:横十間川 280pg-TEQ/g
大阪府:六軒家川 320pg-TEQ/g、木津川運河 190pg-TEQ/g、神崎川 510pg-TEQ/g、古川 300pg-TEQ/g
和歌山県・和歌山下津港 160pg-TEQ/g
しかしながら、各自治体は独自に底質ダイオキシン類濃度を測定しており、環境省が発表した値より高濃度の底質汚染があることをホームページで公表している。
千葉県市原市市原港 12,000pg-TEQ/g(2001年6月)
東京都・横十間川 19,000pg-TEQ/g(公表2004年9月)
大阪府
古川 25,000pg-TEQ/g(公表2008年2月 門真第八水路)
木津川運河 7,200pg-TEQ/g(2006年6月)
神崎川 7,000pg-TEQ/g(糸田川合流点左岸)
三箇牧水路 44,000pg-TEQ/g(2005年11月)
和歌山県・和歌山下津港 1,800pg-TEQ/g(2004年9月)
島根県馬潟工業団地 7,000pg-TEQ/g(2008年4月)
福岡県北九州市洞海湾 4,600pg-TEQ/g(2005年11月)
浄化対策は多額の費用を要するので余り進んでいないが、試験施工等が実施されていることが公表されている。
各省庁の底質汚染の取組み
環境省:
底質の環境基準や底質汚染の状況を調査をしている。
国土交通省:
監視マニュアルや対策マニュアルを作成している。北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所が実証実験をして底質ダイオキシン類無害化に関するデーターをまとめている。本省河川局河川環境課は底質のダイオキシン類対策技術資料集を2007年にとりまとめた。また、鶴見川遊水地でも無害化の取り組みが進んでいる。
独立行政法人港湾空港技術研究所などが底生生物と有害金属の相関関係のデーターを整理し発表している。
農林水産省:
魚介類に含まれる水銀やダイオキシン類について資料を公開している。
厚生労働省:
魚介類等に含まれる水銀について資料を公開している。
汚染原因の特定
ダイオキシン類の総毒性等量のみ議論だけでなく、ダイオキシン類の異性体パターンやケミカルマスバランス等の環境鑑識学の発展によりにより汚染物質の同定や汚染原因者の寄与率算定により汚染原因者に対し、公害防止事業費事業者負担法に従い、合法的な汚染原因者費用負担額が算定され鳥取県の中海地域の企業が応分の費用負担に応じている。
浚渫土問題
底質暫定除去基準によりPCBや水銀が高濃度で含まれている水域の浚渫が過去に実施された。その浚渫土は無害化されずに仮置きされたり、埋立てに利用されている。
環境リスクや人の健康被害防止の観点から十分な検討が必要であり、例えば、兵庫県高砂市では学識経験者等による検討会を開催し議論が進んでいる。
水底ゴミ問題
水底には多くのゴミがあり、特に瀬戸内海や東京湾・大阪湾・伊勢湾等の閉鎖性海域には多く沈んでいる。水底ゴミは水底環境を悪化させるだけでなく底質汚染対策の妨げにもなっている。
底質浄化費用負担
底質汚染の浄化には多額の費用が必要となる。公害防止事業費事業者負担法により汚染原因者がその費用を負担することになる事例が増えている。近年では島根県の馬潟工業団地付近において廃棄物処理業者等が費用を負担している。
法的規制
永年の不要な物質や有害物質の蓄積である底質汚染には多くの法規制が適用されることになる。まず、ダイオキシン類の底質環境基準が挙げられる。ダイオキシン類対策特別措置法により都道府県知事は底質等に含まれるダイオキシン類を測定し基準を超過している場合は浄化計画を策定し措置する義務があり対策に取り組んでいる地域がある。
なお、水質に定められているように人の健康被害に関する環境基準に定める水銀・鉛・ヒ素・シアン・六価クロムなどの有害物質に関する底質環境基準は定められていないが、地下水汚染リスクや浚渫後の土壌汚染の観点から土壌環境基準を援用することが多い。
水質汚濁防止法や海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律さらに廃棄物処理法が汚染原因者に対して適用されるべきであるが、現場確認や時効の問題もあり適用される事例は多くない。しかし、汚染者負担原則から公害防止事業費事業者負担法により汚染原因者に応分の負担を求める事例が増えている。なお、外部リンク欄に関係法規制を示す。
底質汚染の取組の歴史
2008年
11月 大阪府が「三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について」(部会報告)をとりまとめる
5月 国土交通省が「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」を改訂
2007年
横須賀で底質汚染等を理由とする浚渫工事の差止裁判が提訴される
11月北九州市港湾空港局が洞海湾の底質ダイオキシン類汚染を発表(濃度:環境基準の30倍 体積:62,000m3)。
9月 大阪府が三箇牧水路底質汚染対策を一旦完了し報告書をとりまとめ
3月 国土交通省の河川環境課が「底質のダイオキシン類対策技術資料集」をとりまとめ
3月 国土交通省が「底質ダイオキシン類対策検討調査報告書」と「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」をとりまとめ
2006年
水俣病公式確認50年を迎える
2005年
河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)改定
国土交通省の新潟港湾空港技術調査事務所が底質ダイオキシン類分解無害化処理技術]をとりまとめ
2004年
国土交通省が河川、湖沼等における底質ダイオキシン類簡易測定マニュアル(案)をとりまとめ
国土交通省が「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル」(案)
「市原港」で高濃度(12,000pg-TEQ/g)のダイオキシン類が検出され、「市原港」全域にダイオキシン類による高濃度汚染の確認
2002年
7月 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準が施行される
6月 中央環境審議会、ダイオキシン類の底質環境基準値を答申
2000年
ダイオキシン対策特別措置法施行規則及びダイオキシン類による水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準施行
ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル
1998年 古綾瀬川松江新橋地点の底質から過去最高濃度(当時)の720[pg-TEQ/g]が検出
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行
1995年東京湾内の浦賀港内において住友重機械工業がおこなった浚渫工事において多額の漁業被害発生
1979年 酒田港、徳島湾、大江川、水俣湾、敦賀港、高砂西港等において底質の除去等の対策を実施
1975年
底質暫定除去基準
1974年
水銀やPCB等に汚染された高砂本港、北九州市洞海湾、岩国市の地先海域等における汚でいの浚渫(しゅんせつ)作業の実施
1973年
瀬戸内海環境保全特別措置法の制定
1970年
水質汚濁防止法の制定
田子の浦ヘドロ公害で富士市住民が製紙会社と静岡県知事を告発
1969年
全国的にも汚濁の著しい東京都の隅田川、大阪市の神崎川、名古屋市の堀川、福岡市の御笠川、尼崎市の庄下川、横浜市の帷子川、和歌山市の和歌川のしゅんせつの実施
出典
^ 「第4章 第4節 1 公害対策の進展」『昭和46年版公害白書』総理府・厚生省
^ 「第2章 水質汚濁 第3節 最近における水質汚濁の新しい問題 2 ヘドロ問題」『昭和46年版公害白書』総理府・厚生省
^ 「第4章 第7節 2 PCB汚染対策」『昭和48年版環境白書』環境庁
^ 「第9章 第4節 公害防止事業費の事業者負担」『昭和50年版環境白書』環境庁
^ 「第3章 第3節 9 水銀、PCBによる底質除去対策」『昭和55年版環境白書』環境庁
^ 「第3章 第3節 7 水銀、PCBによる汚染底質除去対策」『昭和50年版環境白書』環境庁
^ 「第1-1-18表ダイオキシン類による環境汚染状況(昭和62年度)」「第1章 第1節 9 化学物質」『平成元年版環境白書』環境庁
^ 「第2章 第2節 3 ダイオキシン問題について」『平成11年版環境白書』環境庁
^ 「表5-3-1平成14年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(モニタリングデータ)(概要)」「第5章 第3節 3 ダイオキシン類問題への取組」『平成16年版 環境白書』環境省
^ 平成17年度ダイオキシン類に係る環境調査結果PDF 環境省
参照資料
環境白書〈環境庁、環境省〉
公害白書〈総務庁、環境庁〉
参考文献
国土交通省
「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂(2008年5月)
「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」のとりまとめについて(2007年7月)
底質ダイオキシン類対策検討調査報告書(2007年3月 国土交通省 港湾局)
底質ダイオキシン類対策の基本的考え方(2007年3月 国土交通省)
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年)
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年5月修正国土交通省)
浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針 資料(2006年国土交通省)
河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)(2005年3月国土交通省)
「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂について(2003年12月国土交通省)
新潟港湾空港技術調査事務所 底質ダイオキシン類分解無害化処理技術
環境省
ダイオキシン類の水底の底質等の汚染に係る環境基準
底質の暫定除去基準
環境基準について(環境省)
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)
要調査項目について(環境省)
化学物質と環境(年次報告書)
環境基準について(環境省)
地方自治体
東京都横十間川の底質のダイオキシン類対策
古綾瀬川の底質ダイオキシン類汚染対策について(埼玉県)
阿蘇海環境づくり協働会議(京都府)
大阪府河川底質浄化対策
大阪府三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について
大阪府三箇牧水路底質汚染に関する検討結果報告書
島根県馬潟工業団地周辺ダイオキシン類対策
その他
東京都臨海域における埋立地造成の歴史
日本の地球化学図(産業技術総合研究所)
関係法令
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁( 水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5 条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令
底質の処理・処分等に関する指針について

底質汚染文法
'''底質汚染'''(ていしつおせん)とは底質が汚染されていることをいう。底質とは海域、港湾、河川、水路、湖沼などの水底の土砂やヘドロ等のことである。狭義には底質の環境基準はダイオキシン類のみ(150pg-毒性等量TEQ/g)が定められておりこの基準を超過するもの(詳しくは底質の環境基準を参照)のこと。 なお、ポリ塩化ビフェニル(PCB)や水銀には底質暫定除去基準が定められており、対策は一旦行われた水域もある。
== 概要 ==
環境白書に底質についての言及が現れたのは昭和46年版公害白書であり、それまでは典型公害として、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭の6種を公害の対象として捕らえていたが、冷却用水等による温排水問題やヘドロ問題に対処すれる為に「水底の底質の悪化」を公害の対象として認識するようになった。
「第4章 第4節 1 公害対策の進展」『昭和46年版公害白書』総理府・厚生省>ここで言う「ヘドロ問題」とは東京湾、大阪湾、田子の浦(|田子の浦港)、洞海湾、伊予三島市(伊予三島港)のヘドロである。問題にしているのは化学的酸素要求量(COD)(生物の大量死)や硫化物量(悪臭)が主であるが、東京湾と洞海湾ではカドミウム、クロム、水銀、鉛なども底質中に検出されているが、この頃は生物の大量死や藻類の異常繁茂が問題視されていた為、底質の多量の有機物に注目が集まっていた。
{
{{和暦|s|47}}に初めて底質の[[PCB]]汚染の実態調査が全国1,445地点において実施されたその結果工場近接水域の4箇所については水質で0.011ppm以上底質で500ppm以上のPCBを検出し「PCB取扱い工場周辺の公共用水域の底質がかなり汚染されていることが明らかになった。」と[[環境白書]]では総括している。「第4章 第7節 2 PCB汚染対策」『昭和48年版環境白書』環境庁
{{和暦|s|45}}12月に「[[公害防止事業費事業者負担法]]」が制定され、{{和暦|s|46}}5月10日から施行されている。5年後の{{和暦|s|50}}2月末までにこの法律に従い静岡県・田子の浦湾(有機物堆積汚泥浚渫)、福岡県・中の川水系(PCB含有堆積汚泥浚渫)などの総計17件の底質汚染防止対策事業が実施されることとなる。「第9章 第4節 公害防止事業費の事業者負担」『昭和50年版環境白書』環境庁
この様に底質汚染除去事業が開始され、水銀に係る底質汚染については48年度底質調査では27水域で暫定除去基準値を超えたものが昭和49 - 52年度では暫定除去基準値を超える水域は42水域中7水域に減少した。PCBに係る底質汚染については昭和47 - 52年度の調査で除去等の対策を講じる必要がある69水域中54水域の除去事業が完了することになる。「第3章 第3節 9 水銀、PCBによる底質除去対策」『昭和55年版環境白書』環境庁その約十年後の{{和暦|s|62}}には水銀による底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある42水域中41水域が事業を完了し、PCBによる底質汚染底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある71水域はすべて事業を完了している「第3章 第3節 7 水銀、PCBによる汚染底質除去対策」『昭和50年版環境白書』環境庁。
[[ダイオキシン類]]についての底質汚染は昭和62年度の調査よりモニタリングが開始され、低濃度ではあるが0.001 - 0.006ppbの2,3,7,8-TCDFが18箇の検体より検出されている。「第1-1-18表ダイオキシン類による環境汚染状況(昭和62年度)」「第1章 第1節 9 化学物質」『平成元年版環境白書』環境庁約十年後の平成11年版環境白書においても「海、川、湖の底質、生物についてもこれまで10年以上にわたって毎年調査しているが、ダイオキシン類濃度に特段大きな変化は認められない。しかし、環境中から広く検出されており、引き続き調査が必要である。」と環境白書で総括されている「第2章 第2節 3 ダイオキシン問題について」『平成11年版環境白書』環境庁その後平成14年度にダイオキシン類の[[環境基準]]を変更し、底質ダイオキシン類については757地点中18点で環境基準(150pg-TEQ/g)を超えることとなった。(平均11pg-TEQ/g)「表5-3-1平成14年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(モニタリングデータ)(概要)」「第5章 第3節 3 ダイオキシン類問題への取組」『平成16年版 環境白書』環境省
== 各地での底質汚染の取組み ==
2007年の国土交通省の発表によると汚染土量が把握されているのは7港湾であり、1港湾当たりの汚染土量の頻度分布を1港湾当たりの汚染土量は250,000m3 以下が3港湾と最も多く、250,000m3超が4港湾とされている。以下に各地の取組み状況を示す。
* [[埼玉県]]:[[古綾瀬川]]において委員会を組織し取り組んでいる。
* [[千葉県]]:[[市原]]港で高濃度の底質[[ダイオキシン類]] (15,000pg-TEQ/g) の公開すると共に、汚染原因特定についても取り組んでいる。
* [[東京都]]:[[横十軒川]]や[[隅田川]]河口部などの底質汚染について対策がなされている。[[水銀]]や[[ダイオキシン類]]による[[食品汚染]]調査結果を公開している。豊洲貯木場でダイオキシン類による底質汚染が検出され屋形船係留施設の計画を変更した。
* [[横浜市]]:[[横浜港]]などの底質汚染について対策が検討されている。
* [[静岡県]][[富士市]][田子の浦港]底質(ダイオキシン類)浄化対策事業を港管理事務所が中心となって取り組んでいる。
* [[京都府]]:「[[舞鶴引揚記念館]]周辺地域における環境問題専門家会議」で舞鶴湾の底質について議論し、鉛溶出量が0.1mg/L以上の範囲の対策として、浚渫及び覆砂を行うことが適当であるとし公開されている。また阿蘇海においても取り組んでいる。
* [[大阪府]]:[[神崎川]]など[[大阪府]]が管理する[[河川]]について委員会を組織して取り組んでおり、[[公害防止事業費事業者負担法]]に従い三箇牧水路の汚染対策費用を汚染原因者が負担する計画を作成した。
* [[大阪市]]:市内河川の底質汚染についてデータを公開し取り組んでいる。また、[[港湾]]部についても調査を進めている。
* [[神戸市]]:[[遠矢浜]]北側水域の底質におけるダイオキシン類の環境基準超過について委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。また、2008年から浚渫だけでなく無害化処理等の無害化を含めた浄化対策を行っている。
* [[高砂市]]:[[高砂]]西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。
* [[島根県]]:[[馬潟]]団地に周辺水路において委員会を組織して、[[公害防止事業費事業者負担法]]を適用し取り組んでいる。
*[[北九州市]]:[[洞海湾]]の底質汚染について取り組んでいる。
環境省の発表では底質ダイオキシン類の検出は年を経るごとに減少し、平成17年度の調査{{PDFlink|[
http://www.env.go.jp/air/report/h18-08/ap_2.pdf
平成17年度ダイオキシン類に係る環境調査結果]}} 環境省によると底質の[[ダイオキシン類]]で環境基準150pg-TEQ/gを超えている地点は下記の6か所であったとされている。
* [[東京都]]・[[横十間川]] 280pg-TEQ/g
* [[大阪府]]・[[六軒家川]] 320pg-TEQ/g、[[木津川運河]] 190pg-TEQ/g、[[神崎川]] 510pg-TEQ/g、[[古川]] 300pg-TEQ/g
* [[和歌山県]]・[[和歌山下津港]] 160pg-TEQ/g
しかしながら、各自治体は独自に底質ダイオキシン類濃度を測定しており、環境省が発表した値より高濃度の底質汚染があることをホームページで公表している。
* 千葉県市原市市原港 12,000pg-TEQ/g(2001年6月)
* 東京都・[[横十間川]] 19,000pg-TEQ/g(公表2004年9月)
* 大阪府
** 古川 25,000pg-TEQ/g(公表2008年2月 門真第八水路)
** [[木津川運河]] 7,200pg-TEQ/g(2006年6月)
** 神崎川 7,000pg-TEQ/g(糸田川合流点左岸)
** [[三箇牧水路]] 44,000pg-TEQ/g(2005年11月)
* 和歌山県・[[和歌山下津港]] 1,800pg-TEQ/g(2004年9月)
* 島根県馬潟工業団地 7,000pg-TEQ/g(2008年4月)
* 福岡県北九州市洞海湾 4,600pg-TEQ/g(2005年11月)
浄化対策は多額の費用を要するので余り進んでいないが、試験施工等が実施されていることが公表されている。
== 各省庁の底質汚染の取組み ==
* [[環境省]]:底質の[[環境基準]]や底質汚染の状況を調査をしている。
* [[国土交通省]]:監視マニュアルや対策マニュアルを作成している。北陸[[地方整備局]]新潟港湾空港技術調査事務所が実証実験をして底質ダイオキシン類無害化に関するデーターをまとめている。本省[[河川局]]河川環境課は底質のダイオキシン類対策技術資料集を2007年にとりまとめた。また、鶴見川遊水地でも無害化の取り組みが進んでいる。
**独立行政法人港湾空港技術研究所などが底生生物と有害金属の相関関係のデーターを整理し発表している。
* [[農林水産省]]:魚介類に含まれる[[水銀]]や[[ダイオキシン類]]について資料を公開している。
* [[厚生労働省]]:魚介類等に含まれる水銀について資料を公開している。
== 汚染原因の特定 ==
ダイオキシン類の総[[毒性等量]]のみ議論だけでなく、[[ダイオキシン類]]の[[異性体]]パターンや[[ケミカルマスバランス]]等の環境[[鑑識]]学の発展によりにより[[汚染]]物質の[[同定]]や[[汚染]][[原因]]者の[[寄与]]率算定により汚染原因者に対し、[[公害防止事業費事業者負担法]]に従い、合法的な[[汚染]]原因者費用負担額が算定され鳥取県の[[中海]]地域の企業が応分の費用負担に応じている。
== 浚渫土問題 ==
[[底質暫定除去基準]]により[[PCB]]や[[水銀]]が高濃度で含まれている水域の[[浚渫]]が過去に実施された。その浚渫土は無害化されずに仮置きされたり、埋立てに利用されている。
環境リスクや人の[[健康]]被害防止の観点から十分な検討が必要であり、例えば、兵庫県[[高砂市]]では学識経験者等による検討会を開催し議論が進んでいる。
== 水底ゴミ問題 ==
水底には多くのゴミがあり、特に[[瀬戸内海]]や[[東京湾]]・[[大阪湾]]・[[伊勢湾]]等の閉鎖性海域には多く沈んでいる。水底ゴミは水底環境を悪化させるだけでなく底質汚染対策の妨げにもなっている。
== 底質浄化費用負担 ==
底質汚染の浄化には多額の費用が必要となる。[[公害防止事業費事業者負担法]]により[[汚染原因者]]がその費用を負担することになる事例が増えている。近年では[[島根県]]の[[馬潟工業団地]]付近において[[廃棄物]]処理業者等が費用を負担している。
== 法的規制 ==
永年の不要な物質や有害物質の蓄積である底質汚染には多くの法規制が適用されることになる。まず、ダイオキシン類の底質環境基準が挙げられる。[[ダイオキシン類対策特別措置法]]により都道府県知事は底質等に含まれるダイオキシン類を測定し基準を超過している場合は浄化計画を策定し措置する義務があり対策に取り組んでいる地域がある。なお、水質に定められているように人の健康被害に関する[[環境基準]]に定める[[水銀]]・[[鉛]]・[[ヒ素]]・[[シアン]]・[[六価クロム]]などの[[有害物質]]に関する底質環境基準は定められていないが、地下水汚染リスクや浚渫後の土壌汚染の観点から土壌環境基準を援用することが多い。
[[水質汚濁防止法]]や[[海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]]さらに[[廃棄物処理法]]が汚染原因者に対して適用されるべきであるが、現場確認や時効の問題もあり適用される事例は多くない。しかし、[[汚染者負担原則]]から[[公害防止事業費事業者負担法]]により汚染原因者に応分の負担を求める事例が増えている。なお、外部リンク欄に関係法規制を示す。
== 底質汚染の取組の歴史 ==
* [[2008年]]
**11月 大阪府が「三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について」(部会報告)をとりまとめる
**5月 国土交通省が「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」を改訂
* [[2007年]] [[横須賀]]で底質汚染等を理由とする浚渫工事の差止裁判が提訴される
** 11月北九州市港湾空港局が[[洞海湾]]の底質ダイオキシン類汚染を発表(濃度:環境基準の30倍 体積:62,000m3)。
** 9月 大阪府が三箇牧水路底質汚染対策を一旦完了し報告書をとりまとめ
** 3月 国土交通省の河川環境課が「底質のダイオキシン類対策技術資料集」をとりまとめ
** 3月 国土交通省が「底質ダイオキシン類対策検討調査報告書」と「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」をとりまとめ
* [[2006年]] [[水俣病]]公式確認50年を迎える
* [[2005年]] [[河川]]、[[湖沼]]等における[[底質]][[ダイオキシン類]]対策[[マニュアル]](案)改定
* [[2005年]] [[国土交通省]]の新潟[[港湾空港技術調査事務所]]が[[底質]][[ダイオキシン類]]分解無害化処理技術]をとりまとめ
* [[2004年]] 国土交通省が[[河川]]、[[湖沼]]等における[[底質]][[ダイオキシン類]][[簡易測定]][[マニュアル]](案)をとりまとめ
** 国土交通省が「河川、湖沼等におけるダイオキシン類[[常時監視]]マニュアル」(案)
** 「[[市原]]港」で高濃度(12,000pg-TEQ/g)のダイオキシン類が検出され、「市原港」全域に[[ダイオキシン類]]による高濃度汚染の確認

* [[2002年]]
**7月 [[ダイオキシン類対策特別措置法]]に基づく底質環境基準が施行される
**6月 中央環境審議会、ダイオキシン類の底質環境基準値を答申
* [[2000年]]
**ダイオキシン対策特別措置法施行規則及びダイオキシン類による水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準施行
**ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル
* [[1998年]] 古[[綾瀬川]]松江新橋地点の底質から過去最高濃度(当時)の720[pg-[[TEQ]]/g]が検出
** [[ダイオキシン類対策特別措置法]]に基づく[[底質]][[環境基準]]の施行
* [[1995年]]東京湾内の浦賀港内において住友重機械工業がおこなった浚渫工事において多額の漁業被害発生
* [[1979年]] [[酒田港]]、[[徳島湾]]、[[大江川]]、[[水俣湾]]、[[敦賀港]]、[[高砂西港]]等において底質の除去等の対策を実施
* [[1975年]] [[底質暫定除去基準]]
* [[1974年]] [[水銀]]や[[ポリ塩化ビフェニル|PCB]]等に汚染された[[高砂]]本港、[[北九州市]][[洞海湾]]、[[岩国市]]の地先海域等における汚でいの[[浚渫]](しゅんせつ)作業の実施
* [[1973年]] [[瀬戸内海環境保全特別措置法]]の制定
* [[1970年]] [[水質汚濁防止法]]の制定
** [[田子の浦]][[ヘドロ]][[公害]]で[[富士市]]住民が[[製紙会社]]と静岡県知事を告発
* [[1969年]] 全国的にも汚濁の著しい[[東京都]]の[[隅田川]]、[[大阪市]]の[[神崎川]]、[[名古屋市]]の[[堀川]]、福岡市の[[御笠川]]、[[尼崎市]]の[[庄下川]]、[[横浜市]]の[[帷子川]]、和歌山市の[[和歌川]]のしゅんせつの実施
== 出典 ==
== 参照資料 ==
* 環境白書〈環境庁、環境省〉
* 公害白書〈総務庁、環境庁〉
== 関連項目 ==
* [[底質]]、[[ヘドロ]]
* [[底質暫定除去基準]] [[底質の環境基準]]
* [[環境省]] [[国土交通省]]
* [[環境白書]]
* [[公害]]、[[公害病#四大公害病|四大公害病]]
* [[環境法]]、[[環境基本法]]、[[環境基準]]、[[水質汚濁防止法]]、[[土壌汚染対策法]]、 [[ダイオキシン類対策特別措置法]]、 [[海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]]、[[公害防止事業費事業者負担法]]、
* [[汚染者負担原則]]
* [[水質汚染]]、[[大気汚染]]、[[土壌汚染]]、[[地下水汚染]]
* [[環境問題関連の記事一覧]]
* [[環境運動]]
* [[地球環境問題]]
* [[環境学]]
== 外部リンク ==
=== 国土交通省 ===
* [
http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000002.html
「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂(2008年5月)]
* [
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/11/110720_.html
「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」のとりまとめについて(2007年7月)]
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/11/110720/03.pdf
底質ダイオキシン類対策検討調査報告書(2007年3月 国土交通省 港湾局)]}}
link|[http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/11/110720/02.pdf
底質ダイオキシン類対策の基本的考え方(2007年3月 国土交通省)]}}
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/05/050413/02.pdf
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年)]}}
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/river/press/200701_06/070413-1/pdf/070413-1shiryou.pdf
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年5月修正国土交通省)]}}
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/11/110619/02.pdf
浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針 資料(2006年国土交通省)]}}
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/05/050330_3/02.pdf
河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)(2005年3月国土交通省)]}}
* [
http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/daiokisin.html
「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂について(2003年12月国土交通省)]
* [
http://www.gicho.pa.hrr.mlit.go.jp/gyomu/gijutsu/teidai.html
新潟港湾空港技術調査事務所 底質ダイオキシン類分解無害化処理技術]
=== 環境省 ===
* [
http://www.env.go.jp/kijun/dioxin.html
ダイオキシン類の水底の底質等の汚染に係る環境基準]
* [
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000037
底質の暫定除去基準]
* [
http://www.env.go.jp/kijun/
環境基準について(環境省)]
* [
http://www.env.go.jp/water/impure/kanshi.html
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)]
* [
http://www.env.go.jp/water/chosa/
要調査項目について(環境省)]
* [
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/
化学物質と環境(年次報告書)]
* [
http://www.env.go.jp/kijun/
環境基準について(環境省)]

=== 地方自治体 ===
* [
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kasen/yokoju_dxn/
東京都横十間川の底質のダイオキシン類対策]
* [
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BG00/huruayase/huruayase.html
古綾瀬川の底質ダイオキシン類汚染対策について](埼玉県)
* [
http://www.pref.kyoto.jp/tango/ki-kikaku/1211259080561.html
阿蘇海環境づくり協働会議](京都府)
* [
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/kasen/kankyo/purification/dioxin/index.html
大阪府河川底質浄化対策]
*{{PDFlink|[
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kannosomu/kankyo_singikai/kai/giji/37/2-2.pdf
大阪府三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について]}}
* {{PDFlink|[
http://www.pref.osaka.jp/fumin/doc/houdou_siryou2_17035.pdf
大阪府三箇牧水路底質汚染に関する検討結果報告書]}}
* [
http://www.pref.shimane.lg.jp/environment/kankyo/kankyo/kagaku/
島根県馬潟工業団地周辺ダイオキシン類対策]
=== その他 ===
* {{PDFlink|[
http://www.geog.or.jp/journal/back/pdf113-6/p785-801.pdf
東京都臨海域における埋立地造成の歴史]}}
* [
http://www.gsj.jp/Map/JP/docs/geochemical/geochemical.html
日本の地球化学図]([[産業技術総合研究所]])
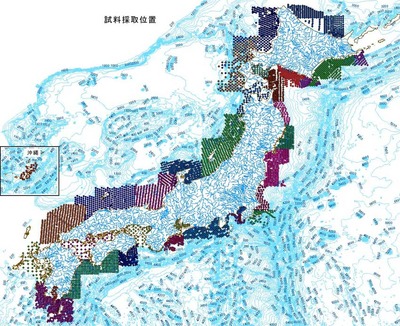

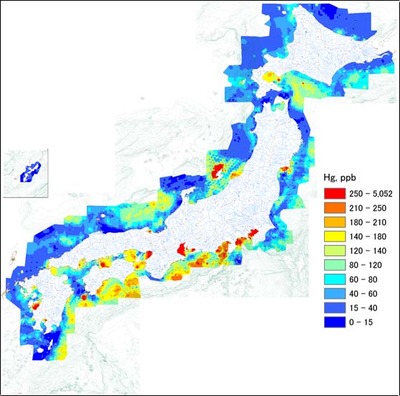
=== 関係法令 ===
* [
http://www.env.go.jp/kijun/dioxin.html
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁( 水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html
ダイオキシン類対策特別措置法]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE433.html
ダイオキシン類対策特別措置法施行令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03101000067.html
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03102004002.html
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO086.html
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO136.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE201.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03901000038.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000006.html
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5 条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03101000038.html
余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令]
* [
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000090
底質の処理・処分等に関する指針について]
{{DEFAULTSORT:ていしつおせん}}
{{sci-stub}}
[[Category:水質汚染]]
ノート:底質汚染提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
底質汚染の中の「各地での底質汚染の取組み」を訂正した方はダイオキシン類の単位も分からず訂正しています。 技術的に極めて稚拙ですので速やかな訂正が必要です。?以上の署名の無いコメントは、60.236.204.155(会話・履歴)さんが 2007年12月9日 (日) 13:12 (UTC) に投稿したものです(青山コロハ 2007年12月9日 (日) 13:14 (UTC)による付記)。
2007年9月18日 (火) 02:34の版 (編集) (取り消し)Dr jimmyで致命的なミスがあります。ダイオキシン類が少し知っている方なら直ぐに分かる初歩的なミスを犯しています。
出展を示しても削除されています。出展は検索すれば直ぐに分かりますがその努力もぜすに底質汚染の書き込みを直ちに削除するのはなぜでしょうか?。底質汚染という不都合な真実を認めたくないのでしょうか。21世紀初頭に生きるヒトは底質汚染に時間やお金を使わなくても一生を終えることができるかもしれませんが、未来の地球はどうでしょうか?「環境は子孫からの預かりも」のでございます。?以上の署名の無いコメントは、211.135.236.251(会話・履歴)さんによるものです。
相変わらずですねぇ。基本方針と記事削除の基準は別物です。無条件に削除するにはWikipedia:削除の方針かWikipedia:即時削除の方針に該当する場合のみです。それ以外は単に執筆者の意見の対立にすぎず、合意なしでは削除の可否は決定されません。したがって、ルールを守らないから消されたのではなく単に消したい人が消しただけの話にすぎないと考えます。--あら金 2008年1月21日 (月) 18:57 (UTC)
ホント相変わらずですねぇ。Wikipedia:削除の方針もWikipedia:即時削除の方針も、ページ・画像の削除に関する方針であり、記事の一部分の削除についての方針ではありません。しかも、無条件でもありません。--Dr.Jimmy 2008年1月22日 (火) 02:14 (UTC)
揚げ足とって申し訳ないんだが、履歴ごと消すのが削除でそれ以外は編集除去。使い分けをきちんとしないと、すれ違うだけです。
また、削除の方針or即時削除の方針に合致するのであれば、無条件で削除対象です。コミュニティの審議を経るのは条件に合致するのかどうかを確認するためで、各方針に合致すれば管理者は削除しなければならないのです。--Kodai99 2008年1月22日 (火) 12:15 (UTC)
Wikipedia:編集方針「記事の一部でも除去するときは、以下の理由に該当するものにしてください。重複 、関係のない内容 、無意味な記述 、著作権侵害 、検証不可能な内容」(註、「検証不可能な内容」を「出典がない」と読み替えた時点ですでに類推である)
Wikipedia:中立的な観点「ある記述が偏った見方から書かれているという事実だけでは、その記述を即削除してしまう理由としては不十分だと考えます。もしもその記述が完全に妥当な情報を含んでいるなら、それを活かすべく編集されるべきで、削除されるべきではありません。」
したがって対象が「ページ削除」であろうと「部分削除」であろうと、Dr.Jimmy氏の提示した論証は類推にすぎず、それゆえ個人的な意見にすぎません。 であるならば同意が形成されていない状態では単に消したい人が消しているだけです。--あら金 2008年1月25日 (金) 15:37 (UTC)
あの方は音楽がご専門のようですね、ご専門に専念される方が社会のためになるかも知れません。もっと社会に役立つのは環境について勉強されて、消すべきものとそうでないもの区別がつくようになれば・・・・。意外と環境は難しいですね!?以上の署名の無いコメントは、60.238.118.155(会話/Whois)さんが 2008年1月28日 (月) 21:57 に投稿したものです。
Dr.Jimmyさんは今までに、この記事やこの記事以外で環境問題を理由にして一回あるいは複数回に分けて特定者の版の編集を根こそぎ削除しておられますが、これは特定の版の削除と同じことをされているわけです。実際、Dr.Jimmyさん以外の方は風評被害等が懸念される場合は、即時削除あるいは特定の版の削除申請されて合意を取り付けて削除しています。そのような合意形成プロセスも経ないのであれは、GNU Free Documentation Licenseはあなたの消した編集をどのようにでも上書き編集することを認めています。したがって、合意形成がなければ消したい人が消しているだけなので書きたい人は書くのです。
GNU Free Documentation Licenseは個々の版の著作権は執筆者が保持しつづけます。したがって、合意形成する以外に復活をやめてもらい内容を合意した範囲で固定するしか方法はないのです。合意以外の方法で他人の著作権行使を妨害するものは「1.ウィキペディア (Wikipedia) に文書を投稿する場合はすべて、GNU Free Documentation License (GFDL) (非公式日本語訳)およびそのウィキペディアでの解釈に同意するものとみなされます。あなたの文章が他人によって自由に編集・配布されることを望まないならば、投稿を控えてください。 」と書かれているように、Wikipediaに(削除編集)投稿すべきではありません。なぜならばボタンには「上記の記述を完全に理解し同意した上で投稿する」と書かれているのでDr.Jimmyさんは既に他人の編集を許可しているのですよ。中立性にしろ風評被害にしろ検証可能性にしろ、丸ごと消したらなにが問題なのか他人が分かるはずがないじゃないですか?以前より説明、説得が要約欄やノートに「発言明瞭、意味不明」な感想を書くだけで、それで同意してもらえると考えるのは楽天的に過ぎると感想を持っていましたので、「あいかわらずですねぇ」ともうしあげました。--あら金 2008年2月1日 (金) 06:00 (UTC)
私の意見をWikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成であると強弁するのであれば、少なくとも引用元の論旨と私の意見との論旨の不整合か反対意見に対する証拠の引用が必要です。
いままで幾度となくこのページや他のページでも証拠引用をDr.Jimmy氏に求めておりますがいまだかつて根拠の引用とそのご自分の解釈の説明をご提示いたいておりませんのでDr.Jimmy氏は感想文をお書きになっておられると判断せざるを得ません。
感想文をお書きになられるのはご勝手ですが、感想文を元に他人の行動を非難したり、自己の行動が正当化されると期待されても「子供だまし」な説得であり、人によってはDr.Jimmy氏が恫喝していると誤解されかねないと存じます。
なによりも「口(議論)よりも先に手を(行動を起こす)出されている」のはDr.Jimmy氏の自由意思による行動です。すべてご自分のおこなった行動が引き起こしたことなので、第三者の私は支持も同情も致して居りません。Dr.Jimmy氏に何が起ころうと、わたくしとしてはどうでもよいのですが、理なくして義が通るはずもなくさらに人徳が足らないと悲惨なことがおきますねぇ。--あら金 2008年2月8日 (金) 12:14 (UTC)
(コメント)複数の方針抜粋がありますが、GFDL違反(履歴不継承)の可能性があります(以下の編集が該当する可能性があり)。
--Dr.Jimmy 2008年1月21日 (月) 14:14 (UTC)
あら金 2008年1月25日 (金) 15:37 (UTC)
--Kc1477 2008年2月24日 (日) 15:10 (UTC)
(コメント)出典元は不十分ながらも示されており、妥当な引用と見なせると思います。--スのG 2008年2月24日 (日) 15:19 (UTC)
目次 [非表示]
1 提案
2 みんなの川や海はみんなで知ろう
3 底質ダイオキシン類汚染の不都合な真実
4 一般環境把握調査と汚染調査とは別
5 底質汚染に関する意見が出尽くしたようですが
6 ウィキペディアを良くするために
7 行政資料や関係法規制
提案 [編集]
ええと。一番上でIP氏が指摘された単位の誤りですが、単位が pg-TEQ/gではなく -TEQ/g となっている箇所があるのが不自然であることに対しての異論はノートを見ている限りないように思います。単純な誤記の修正として、管理者伝言板を通して管理者の方に編集していただくわけにはいかないのでしょうか?--朱月朱音 2008年2月8日 (金) 12:20 (UTC)
誤記があることを確認しました。私が管理者権限を行使するのは差し障りがありましょうから、賛成だけいたします。場所は「各地での底質汚染の取組み」の節の
東京都・横十間川 280-TEQ/g
大阪府・六軒家川 320-TEQ/g、木津川運河 190-TEQ/g、神崎川 510-TEQ/g、古川 300-TEQ/g
和歌山県・和歌山下津港 160-TEQ/g
(以上、記事より引用)の部分だけでしょうか。まだありますか?--スのG 2008年2月8日 (金) 12:28 (UTC)
もう一回一通り見てみましたが、その部分だけだと思います。--朱月朱音 2008年2月8日 (金) 12:33 (UTC)
お手間をおかけします。筆者敬白--あら金 2008年2月8日 (金) 12:36 (UTC)
では、その部分の6箇所の明らかな誤記「-TEQ/g」を「pg-TEQ/g」に置き換えることに賛成します。--スのG 2008年2月8日 (金) 12:37 (UTC)
提案より三日以上経過し、反対意見がなかったため、管理者伝言板に依頼しました。--朱月朱音 2008年2月11日 (月) 14:22 (UTC)
みんなの川や海はみんなで知ろう [編集]
また、編集可能なようになりました。行政のホームページからの情報をもとに追記されています。 Vaiotechnologyは「プロパガンダの取り消し」としてなんの議論も無く取り消しをしておられますが、現実を正しく見たうえでのことでしょうか?真面目な議論を封じ込める一方的な削除と思わざるを得ません。 Vaiotechnologyは遺伝子組み換え作物や農薬関係にも加筆訂正されていらっしゃるようなので、有害物質の人や生態系に与える環境リスクを考えることの出来る方とご推察いたします。
底質汚染において加筆した内容は、行政のホームページで公開されてる内容なので、検証可能であり、中立的な観点で記載されています。独自の研究でもなんでもありません。みんなの川や海の底が汚れているから、みんなで考える事は当たり前のことです。
行政が公表している内容を確認した上で取り消す必要があればこのノートで議論してから取り消せばいいことです。
蛇足ですが、環境を美しくしようと思えば、汚れているところを直視して、汚れているところの対策をしなければなりません。 底質汚染を考える事は、「臭いものにはフタをする」や「嫌な事は水に流して忘れよう」という日本人的な感情とは逆の思考が必要です。
環境は子孫からの預かり物です。底質汚染に関する真面目な議論を期待します。
環境に関する論議や環境浄化推進を目的として、Wikipediaに参加するのはご遠慮下さい。Wikipedia:ウィキペディアは何でないかの1.3をお読み下さい。百科事典作成のみの目的をもってご参加下さい。百科事典的でなく、環境浄化推進のみの観点で書かれた文章は差し戻されることがあります。--Los688 2008年2月24日 (日) 04:04 (UTC)
「みんなの川や海はみんなできれいにしよう」を「みんなの川や海はみんなで知ろう」
に訂正しました。
自分の主義主張を宣伝するためにウィキペディアを利用することは絶対に許されません。ましてや貴方は投稿ブロック中ではないですか。川や海を知るよりもまず貴方がルールを知ることです。--Vaiotechnology 2008年2月25日 (月) 00:43 (UTC)
>自分の主義主張を宣伝するためにウィキペディアを利用することは絶対に許されません。
とのご主張ですが、どのような記載が「Vaiotechnologyさん」のおっしゃる「主義や主張」なのでしょうか? 行政が公開している法規制等やデータを分かりやすく記載するのに「主義や主張」は不要です。 「Vaiotechnologyさん」が底質汚染についてあまりご存知では無いようですね! もう少し日本の環境法規制や、底質汚染について中央省庁や地方自治体が公開している内容ををまず知ることです。
それとも、行政が公開している法規制等やデータが記載されているウィキペディアは全て削除すべきとは思いませんが・・・? 宣伝した「主義主張」が具体的に明確にならないのであれば、速やかに復帰すべきです。?以上の署名の無いコメントは、221.171.175.169(会話/Whois)さんが 2008年2月26日 (火) 14:04 (UTC) に投稿したものです。
何を仰りたいのか良くわかりません。他にもあるだろうというのであれば、平成17年度の結果を並べて「これもあるから6箇所じゃないよ」といえばよいでしょう?項目をずらずらと並べるのは誰にでもできます。根拠は掲載を望む側が提出するのがWikipediaのルールです。--Kodai99 2008年2月29日 (金) 23:37 (UTC)
下記の通り「これもあるから6箇所じゃないよ!」項目をずらずらと並べててあります。これについて反論は無いのでしょうかの?
逐次回答は面倒なので、港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針に記述されていないことに関してご質問ください。不都合である為に隠されていると問題点称されていることは平成14年以来隠されることなく公開されてきたことが明確になると存じます。--あら金 2008年3月26日 (水) 00:27 (UTC)
「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」より平成19年3月に国土交通省の港湾局と河川局が合同で発行した「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」の方がまとまっております。その表紙には以下の記載があります。「底質のダイオキシン類対策については、大都市の港湾・河川において環境基準を超えるダイオキシン類含有汚泥が確認されているにもかかわらず、膨大な対策費用や処分場確保が困難という問題のほか、効率的・経済的な処理工法も確立されていない等の理由により本格的な処理が進展しておらず、早急な対応が求められている。」即ち、基準を超える底質汚染を確認しているが、対策が遅れており、早く対応しなければならないことを国土交通省は公にしているのです。平成20年4月27日
底質ダイオキシン類汚染の不都合な真実 [編集]
ウィキペディアの底質汚染に関する下記の文書があります。
「環境省の発表では底質ダイオキシン類の検出は年を経るごとに減少し、平成17年度の調査[10]によると底質のダイオキシン類で環境基準150pg-TEQ/gを超えている地点は6か所であった。東京都・横十間川 280pg-TEQ/g 、大阪府・六軒家川 320pg-TEQ/g、木津川運河 190pg-TEQ/g、神崎川 510pg-TEQ/g、古川 300pg-TEQ/g 、和歌山県・和歌山下津港 160pg-TEQ/g」
しかし、誤解が生じるといけないので、6ヶ所だけなのでしょうか? 下記に示す公共水域は環境基準を超過する底質ダイオキシン類が検出されていることを国土交通省や各自治体が公表しています。
宮城県:長沼
埼玉県:古綾瀬川・伝右川
千葉県:市原市市原港
東京都:堅川・旧中川・高浜運河・北十間川・綾瀬川
富山県:富岸運河
神奈川県:桜掘運河先・南渡田運河先、
山梨県:濁川
静岡県:田子の浦・巴川
大阪府:正蓮寺川・大正内港・木津川・旧住吉川・尻無川・三十間堀川・住吉川・東横堀川・道頓堀川・恩智川・平野川
兵庫県:神戸市遠矢浜、
和歌山県:海南地区・山田川・和歌川・有本川
島根県馬潟工業団地
福岡県:北九州市洞海湾等
以上のとおり全国でダイオキシン類による底質汚染が生じているヶ所数は6ヶ所だけで無く、数え方にもよりますが全国で30ヶ所は確認できています。
また、底質ダイオキシン類濃度の低い場所を環境省が発表していますが、詳細調査した結果を各自治体は公表しています。
東京都・横十間川 280pg-TEQ/g というのは低いところで、濃いところは19,000pg-TEQ/g(公表平成16年9月)
木津川運河 190pg-TEQ/g、というのは低いところで、濃いところは7,200pg-TEQ/g(公表平成18年6月)
神崎川 510pg-TEQ/gというのは低いところで、濃いところは7,000pg-TEQ/g(糸田川合流点左岸)
古川 300pg-TEQ/g というのは低いところで、濃いところは25,000pg-TEQ/g(公表平成20年2月 門真第八水路)
和歌山県・和歌山下津港 160pg-TEQ/gというのは低いところで、濃いところは1,800pg-TEQ/g(平成16年9月)
なお、下記の底質ダイオキシン類汚染濃度が公開されています。
大阪府の三箇牧水路44,000pg-TEQ/g(調査平成17年11月)
千葉県市原市市原港12,000pg-TEQ/g(平成13年6月)
島根県馬潟工業団地7,000pg-TEQ/g(平成20年4月)
福岡県北九州市洞海湾:4,600pg-TEQ/g(平成17年11月)
ウィキペディアの底質汚染の本文を読むと
「環境基準の2倍程度の底質汚染がで全国に数ヶ所あるだけ」 のように思ってしまいますが、実は
「環境基準の数十倍、場所によっては数百倍程度の底質汚染が全国に数十ヶ所確認されている」 のです。
底質汚染は時間と共に蓄積されるか、又は拡散して食物連鎖で濃縮されヒトが食べることになります。
底質汚染の現実を知ることは快くないでしょうが、底質汚染の現実は不都合な真実です。2007年3月2日IP
現状のウィキペディアの底質汚染に関する本文は「中立的な環境科学」から逸脱しており、読者に誤解を与える可能性があります。上記内容を本文に書き加えるべきと思います。
どなたか上記の記述に対して、反論される方はいらっしゃらないのでしょうか?
同一時点(すくなくとも同一年度)でのデータを列挙していないので「全国各地で高濃度の底質ダイオキシンが検出されたことがある」という以上の意味を持ちません。「全国各地で高濃度の底質ダイオキシンが検出された」という記述の為には過去にさかのぼって全データをウィキペディアに示す必要はなく代表値として最も価値のある最新状況以外はリンクも不要と考えます。地方自治体のデータは監督官庁の環境省へ報告されるので同一年度の代表値として二重である必然はなく環境省公報のみで十分と考えます。(Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディアは単なる知識ベースではありませんが根拠)--あら金 2008年3月2日 (日) 19:05 (UTC)
ここは底質汚染に関することを書く所です。環境省公報は底質で書いて書いて欲しいものです。全国各地で高濃度の底質ダイオキシンが検出されたことは、過去の問題ではなく、ほとんどが現在も高濃度の汚染がそのまま残っている不都合な現実ががあります。
たとえば、大気汚染も土壌汚染も環境省の公報の値は汚染がほとんど見つかりません。底質汚染を語るには何処にどのような基準を超えた汚染があることを議論すべきです。
汚染の無い空間分布や同じ場所の経時変化以外は底質汚染を考える上で無価値です。底質汚染がある現実は単なる知識ベースではなく永年にわたり、人類が汚染物質を少し毎排出しその有害物質が蓄積している現実を多くの人々が知ることが必要です。また、高濃度の底質汚染が検出され速やかに対策されれば、ニュース速報になり、百科辞典の記事としては不適切でしょうが、高濃度の汚染底質に対しほとんどが対策されず放置されている現実があるので、ニュース速報ではありません。
高濃度の輩出派あら金様は高濃度底質汚染が
最も価値ある最新状況は古川では25,000pg-TEQ/gですね?
底質ダイオキシンはサンプリング位置が1mずれれば千倍も濃度が違うことはざらです。したがって汚染総量を見るには平均値を見るしかないです。生物濃縮を問題にされるているようならばなおさらです。動物は餌を求めて動き回るものですから、一か所だけ濃度が高くても動き回ることで蓄積量は平均化されます。あなたがそこの特別濃いところの底質をスプーンですくってすするようならば重大な影響がでると考えますが、そのような極端な状況の健康被害は普通は想定しないので平均値で十分です。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)
古川の25,000pg-TEQ/g最新データーとしての意味があります。また、底質ダイオキシンはサンプリング位置が1mずれれば千倍も濃度が違うことがよくあることのようですが、このような具体例は何処でしょうか?2008年3月20日
地方自治体のデーターは監督官庁の環境省に報告されているのですか?その根拠は?なぜ大阪の底質汚染のあるいくつかの河川のデータを環境省は公開しないのでしょうね?
変動が大きすぎて、そのまま発表すると統計的に確からしくない結論を発表することになり恥をかくからです。したがってデータを幾つかの統計的手法などを活用して汚染量の推定値を出すのが普通です。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)
統計的に確からしくない結論とな何を意味するのでしょうか?現実に高濃度のデータがーあれば隠蔽すると言う意味と解釈することになります。汚染量の推定値を出すために、幾つかの統計的手法などを活用するとのことですが、どのような統計的手法でしょうか?汚染量=(汚染面積)×(汚染深度)で算出されます。2008年3月20日
あら金様のご説明に沿って考えた場合、過去に高濃度のダイオキシン類がふくまれていた底質は何処に行ったのでしょうか?
たまたままったく同じ場所にサンプリングの棒を突き立てることができなかったか、泥がかきまぜられて濃度が低下しただけだと考えます。川底の土砂は流速の二乗から三乗位に比例して移動することは土木工学的に知られているので台風などの増水で流量が増えるイベントがあると、当然泥がかきまぜられて濃度が低下します。あるいは増水で上流から汚染されていない泥が覆いかぶさりサンプリングの深さよりも堆積して覆い隠したのかもしれません。増水のタイミングも汚染のタイミングもそれぞれですから毎日垂れ流すようでなければ一時的に減る場合もあるでしょう。なのである時点の一か所だけの高濃度は評価する上で価値がないのです。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)
泥がかき混ぜられて濃度が低下し周辺に広がることはよくあります。底質は流れがあれば移動しますが、汚染が検出されてる東京都内運河・富岸運河、河口部は流量が少なく、潮の満ち引きを受けて逆流しているところがほとんどです。平成200年3月20日
あら金様のお名前を挙げて恐縮ですが、あら金様の回答を読むと矛盾が沢山でてきます。ご説明下さいますようお願いいたします。
以上、ご説明を申し上げました。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)
あら金様、ご説明ご苦労様でした。かなり勉強されたのですが、残念ながら、ある一面の知識で底質汚染全体を論じておられる
とと思います。地方行政の委員会などを傍聴されると不都合な現実がが良く分かるとと思います。
底質について勉強されたことに対して敬意を表しますが、水の底の汚染は難しく、蓄積性があります。ドブさらえは小まめにやっておかないと、汚い物が溜まるばっかりなので、大変な事になります。2008年3月20日
一般環境把握調査と汚染調査とは別
平成18年度ダイオキシン類に係る環境調査結果が環境省から発表されています。ここで、土壌は 1,505地点中超過したのは0地点ですが、ニュースで東京・大阪・九州で土壌にダイオキシン類が高濃度で含まれていることが報道されています。 底質 1,548地点中超過したのは4地点と発表されています。注意書きに「土壌については、環境の一般的状況を調査した結果(一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査)した結果であり、汚染範囲を確定するための調査等の結果は含まない。」と記載されています。底質についても略同じことが言えます。一般環境把握と汚染範囲を確定するための調査とは別の目的で実施されています。この ウィキペディア「底質汚染」について記載されており、一般的な「底質」は別にあります。よってこの底質汚染の本文は、底質汚染が何処でどれくらい生じているかなどを検証可能なデーター等を分かりやすく整理した百科辞典であるべきと思いますので、全国の現実の汚染の状態を記載すべきと思います。平成2000年3月20日(ドブさらえ)
早く保護を解除して欲しいですね!
勘違いされているようですが、本文の保護テンプレートに書かれているとおり誰かが保護解除依頼を出さないかぎり永久に保護のままです。また本文で編集合戦が起きないという確証がなければ提出された依頼は却下されます。ノートを見る限り編集合戦しないという合意に関する議論は皆無なので現状では無期限保護であると存じます。--あら金 2008年3月26日 (水) 00:05 (UTC)
底質汚染に関する意見が出尽くしたようですが [編集]
あら金様やVaiotechnology様などからの底質汚染に関する意見が無いようですが如何されたのでしょうか?底質汚染に関する現状と課題などは理解されたのでしょうか?まじめな議論を求めます。平成20年4月27日
口頭の発言とは異なり見解は空に消えるわけでもなくすべて履歴に残りますので二度同じ内容を発言する必要はないと存じます。(この発言)つまり不都合な真実なるものは存在しない根拠も提示いたしましたし、編集ロック解除に必要なことは何かも提示しました。質問があっても回答済みである以上、議論は加筆されないし、ロック解除もされないのは当たり前と存じます。--あら金 2008年4月27日 (日) 14:20 (UTC)
国土交通省から「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂が発表されています。また、環境省から「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」の改定や「平成18年度ダイオキシン類に係る環境調査結果」も発表されています。これは本文に掲載すべきと思います。
編集ロックの解除がなければ無理ですね。編集合戦が起こらないという根拠と「…すべき」とは無関係なので現状では当面(年単位で)はこのままと考えます。--あら金 2008年5月20日 (火) 00:17 (UTC)
底質汚染は現在の子作りの終わった人間にとっては差し迫った危険が無いと思います。しかし、これから子供を産む人には大きな問題になる可能性を否定できません。ダイオキシン類等の有害物質の排出量は減りましたが、底質にダイオキシン類等の有害物質が大量に蓄積されています。先祖から生かされた自分の世代だけを守るのであれば、底質は逃げればすむことかもしれませんが、将来世代(子・孫・ひ孫・・)を考えると、自分が生まれた頃の底質に戻すことが、私の使命だと思います。2008年8月お盆?以上の署名の無いコメントは、218.227.217.30(会話/Whois)さんが 2008年8月9日 (土) 12:53 に投稿したものです。
ウィキペディアを良くするために [編集]
信頼できる行政の情報等を分かりやすく載せることが必要と思います。無知な御仁が参加した編集合戦があればウィキペディアは相手にされなくなる可能性があります。?以上の署名の無いコメントは、218.227.215.81(会話・履歴)さんによるものです。
Wikipedia:ガイドブックを拝読させていただきました。(2008年9月2日218.227.217.30などと同一人)
外部リンクの『底質のダイオキシン類対策技術資料集(平成19年5月修正国土交通省)』 がリンク切れです。?以上の署名の無いコメントは、60.237.78.178(会話・履歴)さんによるものです。
行政資料や関係法規制 [編集]
行政が発表した資料に基づく事実や、関係法規制を多くの人が分かりやすいように記載したら何故削除されるのでしょうか? 下記のアドレスで差が分かります。
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BA%95%E8%B3%AA%E6%B1%9A%E6%9F%93&diff=23656010&oldid=23649867
食品水土 080103
重金属の底質汚染の現状が産業技術総合研究所のホームページで掲載されました。東京湾付近の大学や国土交通省から底質に含まれる重金属と底生生物の相関関係のデータが示されました。IP??080303
「
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%BA%95%E8%B3%AA%E6%B1%9A%E6%9F%93
」より作成
2009年10月17日
2009年6月23日大阪市 環境対策特別委員会 底質汚染
大阪市 環境対策特別委員会 底質汚染 2009年6月23日


◆矢達幸委員
日本共産党、矢達でございます。
ダイオキシン類対策の問題について若干質疑をさせていただきたいと思います。
報告があったわけですけども、このダイオキシン類というのは、過去は何ら問題視されなかったんですね。焼却やいろんなことでダイオキシン類は副産物のようにしてばらまかれてきました。しかし、ここ最近になってその毒性が非常に怖いものであるということを科学者が指摘をいたしまして、対策が立てられるようになりました。
まず、ダイオキシン類の毒性というのはどういうものか、その特徴についてお答えください。

◎小西環境局環境保全部土壌水質担当課長
お答えいたします。
ダイオキシン類は、低濃度でも慢性毒性があると言われており、慢性毒性に係るダイオキシン類の安全性を評価するため、我が国では人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響があらわれないと判断される1日体重1キログラム当たりの摂取量、耐容一日摂取量を4ピコグラム−−1兆分の1グラムという単位でございますが−−と設定しております。
一方、大阪市域における平成20年度の人のダイオキシン類の一日摂取量は1.14ピコグラムと推定されており、耐容一日摂取量4ピコグラムを下回っております。
また、ダイオキシン類は、動物実験では発がんを促進する作用、甲状腺機能の低下、生殖器官の重さや精子形成の減少、免疫機能の低下を引き起こすことが報告されております。
◆矢達幸委員
特徴は、遅発性なんですね。サリンの2倍の毒性があると言われておりますけれども、一気に毒性が出て死に至るというんではなしに、その一生涯、あるいは子供、孫まで影響していくというふうに言われております。そういう点では、非常におくれて出てくる、長引くという、一生涯と先ほど言われましたけど。
それともう一つは、水質や底質の問題では植物連鎖がするんですね。先ほど、私、ちょっと高木部長の説明で気になるんですけども、河川の汚染の箇所が2カ所基準値オーバーしてるところありますけども、これについて、飲用に使うものではないから大丈夫だと、直ちに影響はないとの説明だったけども、それは私はちょっと違うと思うんですよ。
やはり植物連鎖ですから、これは魚が食べる、回遊魚はですね、これは魚を通じて人間の体に入ってきますから、だからそういう点ではダイオキシンというのは世の中から全部なくしていかないかんという性格のものであって、直ちに影響はないというふうな甘い見方は私はするべきじゃないというふうに思います。
そういう点で、私がきょう一つ問題にいたしたいのは、港湾地区の汚染の問題です。資料配付お願いします。
○山崎誠二委員長
矢達委員より、質疑の参考に資するため資料の配付の申し出がありますので、これを許します。
◆矢達幸委員
港湾局が独自に平成15年から17年の間に、特に大阪湾の河口付近、あるいは堀、こういうところの底質のダイオキシンの汚染状況の調査を実施しております。資料に配付いたしておりますように、非常に高濃度の汚染物質が堆積してるということが明らかでございます。
これがなぜ本日報告されないし、環境白書にも載らないかということで、これまた後で議論いたしますけれども、この内容について港湾局はどう考えておるんかちょっとまず答えてくれますか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
お答えいたします。
港湾局におきましては、平成15年から17年度におきまして、底質のモニタリング調査においてダイオキシンの疑いがある箇所について調査をいたしました結果、この表にございますように、この7地域において環境基準である150ピコグラム以上の底質が確認されております。これは港湾局のほうでこの浄化対策を行うために、その量を確定するために実施した調査でございます。
◆矢達幸委員
スクリューで底質を巻き上げているのも見かけております。当然、魚類へのダイオキシンの汚染が進んでるんではないかというように私は気になるんですけどもですね、こういう高濃度の汚染されてるという状況を危険視されて開始されるということだと思うんですけどね。どのような対策を立てておるのか、全体計画及びその進捗状況はどうですか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
お答えいたします。
この15年から17年の調査におきまして、大阪港の河川下流部におきまして、環境基準を超える底質量は、純汚泥量で193万立米となってございます。これは汚れを含めますと約110万立米となります。そのうち、低濃度であります150ピコから1,000ピコまでの土量が約95%を占めておりまして、残りの5%が中高濃度の1,000ピコグラムを超える底質となってございます。
現在、18年度以降、この底質の除去対策を実施しておりますが、本年度を入れまして4年間で約7,000立米の除去を予定いたしております。
◆矢達幸委員
全体計画ですから、いつまでに終わるのかね。また、18年度から始めた予算規模はどの程度なのか。全体の予算は幾らかかりますか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
この110万立米の浄化対策でございますが、これは今後の技術開発等によりまして、その事業費が下げられる可能性はございますが、現在想定しておりますのは約150億円を想定してございます。それで、毎年の事業規模でございますけども、平成18年度以降約1億円ずつの事業費となってございます。
それで、完了時期でございますけども、これにつきましては大阪市の底質対策技術検討会の中で速やかに浄化対策を完了させるということになっておりますが、本市も非常に厳しい財政状況の中ではありますので、ちょっと今明確にその時期というのを申し上げることはできません。
◆矢達幸委員
これ評価委員会の評価書に書いてあるでしょう。完成年度はちゃんと明示されてる。それを答えなさい。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
それ、委員お持ちのやつは事業評価委員会のやつでしょうか。そこに書いてある数字ということになりますと、ここでいいます速やかに浄化対策を完了させるということで17年度に申しておりましたんで、速やかに浄化対策を完了させるというのはどれぐらいかということで、おおむね10年ぐらいということで表記されているものかと思います。

◆矢達幸委員
平成27年度が完了予定になってるんですね。ところが、予算が150億円かかると。それで、平年ペースでは1億円しか予算とれませんから、150年かかるわけですな、150年。これはもう我々の世代を過ぎて次の世代でもまだ終わらへんという、こういう大変な事業量になってしまうわけですよね。
ところが、こういう高濃度汚染を放置しておくと非常に危険な状況になるという、一方ではこれはありますからね。まさに過去の大阪市のいろんな負の資産ありますけれども、これも一つのそういうもんじゃないかというふうに思うんです。市民の健康や安全、特に食の安全というこういう立場からいうと、これは金をかけてでも早期に解決せないかんというふうに思います。
事業評価委員会のこの内容でも、事業進捗状況はわずか3%ですよね、今まで。これではとても間尺に合いません。27年度までに仮に終わらそうとすると、30億円ぐらいは毎年とらないかん。国の公害対策の補助金も半分出るそうですけども、そういう点でも大変な事業量にふやさなきゃならんというふうに思いますが、これは1部局、港湾局や部局ではできる問題じゃないと。
市長のこういう決裁が必要になってくるんじゃないかということで、きょう平松市長においでいただいてますんでね。こういうこと、ダイオキシンという重大な毒性のものがこんなに大量に大阪港の河口に沈んでおると、底質としてあるという、こういう事実なんですね。これはもう明らかになりましたので、早急に除却処理されるように市長の見解をお聞きしたいというふうに思います。
◎平松市長
お答えいたします。
港湾地域のダイオキシン類につきましては、先ほど来報告させていただきまして、毎年水質モニタリング調査というのを実施しております。これによりますと、直ちに健康被害が生じる状況ではないという報告は受けております。ただ、委員御指摘のように、ダイオキシン問題、ダイオキシン類の浄化をという問題に関しましては、市民の健康にかかわる重要な課題であり、学識経験者からなる大阪市底質対策技術検討会の審議においても、御指摘のように速やかに浄化対策を行うこととされております。
このため、これまでも国の補助を得て港湾工事等にあわせて浄化対策を実施してきておりますけれども、今申し上げましたように多額の事業費を必要とすることから、今後とも引き続き財政的な支援の強化、これを国に積極的に要望してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
◆矢達幸委員
国だけやなしに大阪市も頑張らなあかんですからね。これは公害対策で半分持ちですからね、こういうことになりますから。もちろん国の補助金を大幅にふやすということは重要ですけども、しかし現在のペースではとても間尺に合いません。これ、急速にこの問題を強めていただきたいということで、市長におきましても奮闘いただきますようよろしくお願いします。市長、どうもありがとうございます。
こういう問題で、特に私気になりますのは、大阪市の環境白書に一切これ載ってないんですね。環境白書や現況と対策を見ますと、港湾地帯、湾岸地帯を調べてないのかといえば、そうじゃないんですよ。ちゃんと定点ポイントで調べてるんですね。一定の2カ所ほど底質でオーバーしてるという問題がありながら、こういう問題に一切触れないという、こういうことは何でですか。なぜこういうことを、大阪の環境白書に載らないのかということをまずお聞きしたいんですが、どうですか。なぜ載せないんですか。
◎小西環境局環境保全部土壌水質担当課長
お答えいたします。
環境白書は、大阪市環境基本条例第9条に基づき、環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策並びに実施状況を明らかにした年次報告として、毎年ダイオキシン類のモニタリング結果を公表しております。
一方、ダイオキシン類による汚染状況の詳細調査結果につきましては、港湾局がプレス発表を行うとともに、対策の進捗状況含めてホームページで公表しているところでございます。
港湾局のダイオキシン調査結果につきましては、今後掲載する方向で検討してまいりたいと思います。
◆矢達幸委員
今後掲載する方向でということで改めるということなんで、これ以上私言いませんけども、大阪の環境はこの白書に一切掲載されなきゃならんですね。どこの部局であろうと、どういう調査であろうと。現況はこうですということはここに、これに一切網羅されなきゃあかんわけですね。そういう意味では、縦割りで、あるいは港湾局の仕事だと、向こうのホームページで公開されてるというんじゃだめですね。これは市民に公開されたことになりません。そういう意味で、こんだけ高濃度汚染地域が横たわっておるという状況では、これはぜひとも今後この白書にも載せ、また現況と対策で、非常に大変な費用のかかるこういう対策です。
しかし、しっかりと対応して、対策して解決していただきたいというふうに思いますし、我々も市民もこの進捗状況をしっかりと監視していきたいというふうに思います。
[大阪市域の水環境中ダイオキシン類の調査]
河川水中のダイオキシン類濃度(平成12年〜15年度の平均濃度)
大阪市は多くの都市域を流れる河川の最下流に位置しており、市内での勾配が小さいため、河川の流れが緩やかな「水の都」として有名です。
これまでの様々な調査から、大阪市域の水環境中ダイオキシン類の分布が明らかになってきました。そして、その状況から大阪市域では、河川上流から懸濁物とともに運ばれてきたダイオキシン類が、河口域で底質へと沈降、堆積していると予想されます。
このようなダイオキシン類の状況が明らかになったことから、大阪市では河口域底質の浄化対策や周辺自治体との連携による調査や対策を進めようとしています。
グリーンニューディール政策を

ATCセミナーレポート 緑のニューディール政策がもたらす環境ビジネス
■講師
大阪大学大学院工学研究科 准教授 加藤悟氏
緑のニューディール政策は、オバマ大統領の就任後有名になりましたが、以前から、国内外で考えられていた政策です。まずは緑のニューディール政策の言葉の元となった「ニューディール政策」について振り返ってみたいと思います。
1.ニューディール政策とは何か
ニューディール政策は、1929年10月24日に発生した世界大恐慌の後、大統領となったフランクリン・ルーズベルトが行った政策です。ニューディールの“ディール”とはトランプ用語で、新規で持ち札をかえる、という意味。つまり、ゼロベースで予算配分をするということを表します。
世界恐慌の三大原因となったのは、
(1)第一次世界大戦後の農産物価格下落による市場の購買力低下、
(2)過剰な設備投資による過剰生産、
(3)各国の高関税政策による貿易縮小だと言われています。
その結果、ニューヨーク株式取引所で株価が大暴落し、各国で企業・銀行が倒産し、失業者が増大、ドイツもアメリカ資本撤退で資本不足になりました。
そんな中、フランクリン・ルーズベルトは恐慌対策を確約して大統領選に勝利しました。就任後すぐに「テネシー川流域開発公社(TVA)」を設立、またニューディール政策の基礎となる法律、「全国産業復興法(NIRA))と「農業調整法(AAA)」を制定。政府が積極的に経済に介入して景気回復に努め、善隣外交により、中南米と友好を深めました。アメリカで唯一、四選された大統領で、1945年、任期中に病死しました。
彼の政治理論を支えていたのはイギリスの経済学者、ケインズです。彼は国家の経済への介入を肯定する修正資本主義を提唱、著書「雇用・利子および貨幣の一般理論」において、一国全体における生産水準がどのように決定されるかを考案しました。これは現在、マクロ経済学と呼ばれています。
ニューディール政策の目玉の1つであるテネシー川流域開発公社(TVA)は、1933年5月に設立され、電力生産の多目的ダムを建設し、土壌保全・河川整備等の事業を行うことで、地域経済振興や住民流出防止に努めました。また電力価格を低下させて物価を引き下げ、雇用を創出しましたが、民間電力業を圧迫するという批判もありました。
一方、全国産業復興法(NIRA)では、企業の生産を規制して適正な利潤を確保、労働者には団結権や団体交渉権を認め、最低賃金を確保し、生産力や購買力の向上を目指しましたが、景気回復を促進するためカルテル的な協定締結を認めたことで、合衆国最高裁判所が違憲判決を下し、2年足らずで廃止することとなりました。
また農業調整法(AAA)では、農業部門の慢性的過剰生産恐慌の事態に対し、小麦や綿花など7項目について、作付け割り当て計画による生産管理を行いました。
しかし、一連の政策をもってしても失業率は高いまま推移し、雇用もGNPも目立った変化は見られませんでした。その後、第二次世界大戦による軍需の拡大により、アメリカ経済は回復し、失業も解消されました。皮肉なことに、アメリカを救ったのは戦争だったという意見も少なくありません。ですが、これらの政策により、それまでの古典的自由主義的経済政策から、政府が経済へ関与する社会民主主義的な政策へ転換が行われ、アメリカの政治・経済が大きく変わったことは間違いありません。
2.グリーン・ニューディール政策とは何か
2008年7月21日、「グリーン・ニューディール・グループ」により、提唱された“グリーン・ニューディール”という言葉は、1年足らずで広く知られるようになりました。
2008年7月に発表された「グリーン・ニューディール:信用危機・気候変動・原油価格高騰の三大危機を解決するための政策集」は、化石燃料に依存しないエネルギーを確保するという、エネルギーセキュリティーに重きをおいており、それと並行して気候変動対策や経済対策を行っていくという考え方です。具体的には省エネルギー技術とマイクロジェネレーション(マイクロ発電技術)への政府主導の投資、メガバンクの分割とグリーンバンキング化などの政策があります。
同年10月にUNEPが発表したグリーン経済イニシアチブでも、世界経済をクリーン技術や自然のインフラ(森林や土壌など)への投資に向かわせることが21世紀の新の成長につながるという考え方が述べられています。
その後、オバマ大統領は、2008年10月の大統領選勝利演説にて、2050年までに温室効果ガス排出量を80%削減、今後10年間でクリーンエネルギーに1500億ドルを投資し、500万人分の雇用を創出するという計画を披露しました。それに引き続く形で、世界経済フォーラム(ダボス会議)において国連の潘事務総長が、現在の経済危機を利用して、再生可能エネルギーと技術開発の投資により雇用を創出し、地球温暖化問題に取り組むべきと呼びかけました。
また2009年2月にUNEPが発表した“グローバル・グリーン・ニューディール”では、現在、景気刺激策として予定されている約2兆5千億ドルのうち3分の1はグリーン経済の実現のための投資とすべきだと強調しています。その例として、クリーンな技術開発による雇用促進や、化石燃料に対する補助金の削減、温室効果ガスを削減、生態系の悪化防止、水の安全保障等が挙げられています。
そんな中、アメリカのグリーン・ニューディール政策は非常にはっきりしており、ひとつは今後の原油高騰を見据えたエネルギー安全保障のための自然エネルギー対策、次にプラグインハイブリッド100万台によるビッグ3の復活という2本柱と、研究開発として、マイクロジェネレーションや超伝導送電、大型二次電池による蓄電等のエネルギー技術開発の取り組みを行っています。
3.日本におけるグリーン・ニューディール政策
日本におけるグリーン・ニューディール政策は、2008年9月の麻生総理の所信表明演説にて「我が国が強みを持つ環境・エネルギー技術は新たな需要と雇用を生む力がある。」と述べられているほか、環境省は2009年1月に「緑の経済と社会の変革」という構想を発表しました。この構想において、2006年現在の環境ビジネスの市場規模約70兆円、雇用者数約140万人を、近い将来飛躍的に拡大すること、そして世界で先頭をゆく環境・省エネ国家として、世界で最初に不況を脱出するという目標が掲げられています。その基本的な考え方としては、エコ改造(省庁や学校へ太陽光発電を設置する等)、エコグッズ(省エネ家電等の普及)、エコファイナンス(エコ投資)の大きく3点があげられています。
日本のグリーン・ニューディール政策に対する有識者の意見としては、太陽エネルギー社会の構築や持続可能な社会地域物質循環システム構築といった、環境白書でも述べられている基本的な提案のほか、環境エネルギー技術の促進や、特徴的な意見として途上国にむけ技術移転を行うこと、カーボンフットプリント等の見える化の促進、大学生等若い世代への働きかけ等が述べられました。
日本経団連や経済同友会でも、日本版グリーン・ニューディールの推進が推奨されており、脱化石燃料および、循環型社会へ向けた取り組みが示されています。中でも経済同友会の取り組みの中で特徴的なのは、排出権制度やグリーン税制などの、インセンティブ制度・投融資制度の導入でしょう。
日本のグリーン・ニューディール政策は、アメリカと違い、エコ改修、緑の消費への変革、緑の地域コミュニティーの変革、緑の投資への変革等、幅広いですが、地球温暖化対策とあまり差がありません。そういうところが日本らしいと言えるかもしれません。
4.環境の産業化と産業の環境化
世界での環境産業の市場規模は増加傾向にあります。企業の環境配慮における3つの発展段階として、「(1)規制追随型・受動的な環境配慮」から、「(2)事前対応型・予防的な環境配慮」になり、さらに付加価値を追求し、「(3)機会追求型・戦略的な環境配慮」と変化してきています。
環境ビジネスをOECDによる分類で分けると、大気汚染や水質汚濁等の防止・処理にかかる装置の製造や設置にかかるビジネスが「環境汚染防止」、環境負荷低減および省資源化のための技術、プロセスの提供、配慮した製品に関するビジネスは「環境負荷低減技術および製品」、最後に、環境負荷低減および省資源化を直接的な目的としないが、その効果が期待できる関連産業が「資源有効利用」に分類されます。たとえば、再生可能エネルギー施設や、省エネルギー関連ビジネス、エコツーリズム等も資源有効利用に分類されるビジネスです。
日本における環境ビジネスの市場規模も、2020年には2000年の2倍の規模になることが期待されています。日本の環境ビジネスとしては、以下の10分野の産業の環境化、および環境の産業化が考えられます。
1.廃棄物関連ビジネス(3R、廃棄物処理関連)、
2.地球温暖化(省エネルギー・新エネルギー)、
3.環境浄化(土壌汚染、アスベスト)、
4.観光(エコツーリズム)、
5.金融・保険(社会的責任投資、環境リスクの商品化)、
6.情報通信(効率化や情報による脱物質化)、
7.農業(エコファーマー、バイオマス利用)、
8.林業(持続可能な森林経営)、
9.水産業(自然管理・育成型漁業)、
10.貿易(フェアトレード)
5.大きな政府と小さな政府
ニューディール政策の思想は、大きな政府なのか、小さな政府なのかを考えてみましょう。
大きな政府とは、ゆりかごから墓場まで国が全部面倒を見てくれる政府です。一方、小さな政府は、警察や防衛など国として最低限の仕事だけを行い、経済活動等は放任する政府のことです。小さな政府の場合、自由放任主義が行き詰まって、貧富の差が大きくなります。そして政府は経済や社会のさまざまな領域に介入せざるをえなくなり、社会福祉立法や少数派保護法によって平等化の推進に努めることとなります。社会はイノベーションや競争の力で前へ進みますが、競争の中で生じる勝ち負けのバランスをとるのが政治の役割です。
アメリカでは小さな政府が破たんし、大きな政府への移行が進んでいます。非常時の公共投資による一時的なばらまきや経済への介入は、半永久的な大きな政府への移行とは異なります。
一方、大きな政府の弊害は、競争による効率性やイノベーション活動の低下が挙げられます。どちらが良いかではなく、そのバランスが重要です。
ここで、注意しておきたいのが、高福祉国家は大きな政府か?ということです。北欧は税金も高く、子持ちの女性が就労する世帯への手厚い補助や福祉が充実していますが、中央政府の権限は最小限に限定されており、地方では地元住民に大きな権限があります。さらに投資環境ランキングで上位常連、つまり自由経済がすすんでいると言えます。これらのことからも、北欧は高福祉国家ですが、大きな政府ではないと言えます。
では、アメリカは小さな政府か?というと、軍事予算や財政赤字は、小さくなるどころか増加の一途をたどっており、「通貨ばらまき」政策のため、国際決済通貨としての米ドルの地位は年々低下しています。また防災や地方に交付される予算は削減されています。
このような流れの中、私は、グリーン・ニューディールの目指すべきものは地方分権と自立型都市の確立だと考えています。地域が自立した産業を育成するためには、投資活動が円滑に行われるべきでしょう。そうなると、エネルギーや資源も地産地消が良いのでは、という考えに至ります。となると、家電や大規模太陽光発電に投資するのではなく、持続可能な農林水産業やエコハウスの建設、植物工場などの実現こそが、いま求められている環境投資、環境ビジネスではないでしょうか。
環境モデル都市として採択された北海道の下川町の「緑の経済と社会の変革」の例では、地域資源・地域雇用を生かし、地域で消費する、さらに地域の中で投資も進んでいるという、まさにグリーン・ニューディールのお手本となるモデルです。
まとめ
ニューディール政策とは、生産規制と公共投資、雇用確保についての政策でした。そしてグリーン・ニューディール政策は、本当の意味でグリーンではなく、信用危機や原油価格高騰とともに気候変動対策を行うという政策で、アメリカでは原油価格高騰対策とビッグ3に焦点がしぼられています。
一方、日本のグリーン・ニューディール政策では、省エネ家電と太陽光発電が2本柱となっています。また産業の環境化および環境の産業化については、従来の環境浄化型産業から事前対応型産業への移行が今後も進んでいくでしょう。
最後に、大きな政府と小さな政府という観点においては、自立型で競争原理とセイフティーネットを併せ持つ、小さな政府を目指したインフラ整備の改革を進めることが、グリーン・ニューディールの本来の姿なのではないかと思います。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/210501/index.html


◆矢達幸委員
日本共産党、矢達でございます。
ダイオキシン類対策の問題について若干質疑をさせていただきたいと思います。
報告があったわけですけども、このダイオキシン類というのは、過去は何ら問題視されなかったんですね。焼却やいろんなことでダイオキシン類は副産物のようにしてばらまかれてきました。しかし、ここ最近になってその毒性が非常に怖いものであるということを科学者が指摘をいたしまして、対策が立てられるようになりました。
まず、ダイオキシン類の毒性というのはどういうものか、その特徴についてお答えください。

◎小西環境局環境保全部土壌水質担当課長
お答えいたします。
ダイオキシン類は、低濃度でも慢性毒性があると言われており、慢性毒性に係るダイオキシン類の安全性を評価するため、我が国では人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響があらわれないと判断される1日体重1キログラム当たりの摂取量、耐容一日摂取量を4ピコグラム−−1兆分の1グラムという単位でございますが−−と設定しております。
一方、大阪市域における平成20年度の人のダイオキシン類の一日摂取量は1.14ピコグラムと推定されており、耐容一日摂取量4ピコグラムを下回っております。
また、ダイオキシン類は、動物実験では発がんを促進する作用、甲状腺機能の低下、生殖器官の重さや精子形成の減少、免疫機能の低下を引き起こすことが報告されております。
◆矢達幸委員
特徴は、遅発性なんですね。サリンの2倍の毒性があると言われておりますけれども、一気に毒性が出て死に至るというんではなしに、その一生涯、あるいは子供、孫まで影響していくというふうに言われております。そういう点では、非常におくれて出てくる、長引くという、一生涯と先ほど言われましたけど。
それともう一つは、水質や底質の問題では植物連鎖がするんですね。先ほど、私、ちょっと高木部長の説明で気になるんですけども、河川の汚染の箇所が2カ所基準値オーバーしてるところありますけども、これについて、飲用に使うものではないから大丈夫だと、直ちに影響はないとの説明だったけども、それは私はちょっと違うと思うんですよ。
やはり植物連鎖ですから、これは魚が食べる、回遊魚はですね、これは魚を通じて人間の体に入ってきますから、だからそういう点ではダイオキシンというのは世の中から全部なくしていかないかんという性格のものであって、直ちに影響はないというふうな甘い見方は私はするべきじゃないというふうに思います。
そういう点で、私がきょう一つ問題にいたしたいのは、港湾地区の汚染の問題です。資料配付お願いします。
○山崎誠二委員長
矢達委員より、質疑の参考に資するため資料の配付の申し出がありますので、これを許します。
◆矢達幸委員
港湾局が独自に平成15年から17年の間に、特に大阪湾の河口付近、あるいは堀、こういうところの底質のダイオキシンの汚染状況の調査を実施しております。資料に配付いたしておりますように、非常に高濃度の汚染物質が堆積してるということが明らかでございます。
これがなぜ本日報告されないし、環境白書にも載らないかということで、これまた後で議論いたしますけれども、この内容について港湾局はどう考えておるんかちょっとまず答えてくれますか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
お答えいたします。
港湾局におきましては、平成15年から17年度におきまして、底質のモニタリング調査においてダイオキシンの疑いがある箇所について調査をいたしました結果、この表にございますように、この7地域において環境基準である150ピコグラム以上の底質が確認されております。これは港湾局のほうでこの浄化対策を行うために、その量を確定するために実施した調査でございます。
◆矢達幸委員
スクリューで底質を巻き上げているのも見かけております。当然、魚類へのダイオキシンの汚染が進んでるんではないかというように私は気になるんですけどもですね、こういう高濃度の汚染されてるという状況を危険視されて開始されるということだと思うんですけどね。どのような対策を立てておるのか、全体計画及びその進捗状況はどうですか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
お答えいたします。
この15年から17年の調査におきまして、大阪港の河川下流部におきまして、環境基準を超える底質量は、純汚泥量で193万立米となってございます。これは汚れを含めますと約110万立米となります。そのうち、低濃度であります150ピコから1,000ピコまでの土量が約95%を占めておりまして、残りの5%が中高濃度の1,000ピコグラムを超える底質となってございます。
現在、18年度以降、この底質の除去対策を実施しておりますが、本年度を入れまして4年間で約7,000立米の除去を予定いたしております。
◆矢達幸委員
全体計画ですから、いつまでに終わるのかね。また、18年度から始めた予算規模はどの程度なのか。全体の予算は幾らかかりますか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
この110万立米の浄化対策でございますが、これは今後の技術開発等によりまして、その事業費が下げられる可能性はございますが、現在想定しておりますのは約150億円を想定してございます。それで、毎年の事業規模でございますけども、平成18年度以降約1億円ずつの事業費となってございます。
それで、完了時期でございますけども、これにつきましては大阪市の底質対策技術検討会の中で速やかに浄化対策を完了させるということになっておりますが、本市も非常に厳しい財政状況の中ではありますので、ちょっと今明確にその時期というのを申し上げることはできません。
◆矢達幸委員
これ評価委員会の評価書に書いてあるでしょう。完成年度はちゃんと明示されてる。それを答えなさい。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
それ、委員お持ちのやつは事業評価委員会のやつでしょうか。そこに書いてある数字ということになりますと、ここでいいます速やかに浄化対策を完了させるということで17年度に申しておりましたんで、速やかに浄化対策を完了させるというのはどれぐらいかということで、おおむね10年ぐらいということで表記されているものかと思います。

◆矢達幸委員
平成27年度が完了予定になってるんですね。ところが、予算が150億円かかると。それで、平年ペースでは1億円しか予算とれませんから、150年かかるわけですな、150年。これはもう我々の世代を過ぎて次の世代でもまだ終わらへんという、こういう大変な事業量になってしまうわけですよね。
ところが、こういう高濃度汚染を放置しておくと非常に危険な状況になるという、一方ではこれはありますからね。まさに過去の大阪市のいろんな負の資産ありますけれども、これも一つのそういうもんじゃないかというふうに思うんです。市民の健康や安全、特に食の安全というこういう立場からいうと、これは金をかけてでも早期に解決せないかんというふうに思います。
事業評価委員会のこの内容でも、事業進捗状況はわずか3%ですよね、今まで。これではとても間尺に合いません。27年度までに仮に終わらそうとすると、30億円ぐらいは毎年とらないかん。国の公害対策の補助金も半分出るそうですけども、そういう点でも大変な事業量にふやさなきゃならんというふうに思いますが、これは1部局、港湾局や部局ではできる問題じゃないと。
市長のこういう決裁が必要になってくるんじゃないかということで、きょう平松市長においでいただいてますんでね。こういうこと、ダイオキシンという重大な毒性のものがこんなに大量に大阪港の河口に沈んでおると、底質としてあるという、こういう事実なんですね。これはもう明らかになりましたので、早急に除却処理されるように市長の見解をお聞きしたいというふうに思います。
◎平松市長
お答えいたします。
港湾地域のダイオキシン類につきましては、先ほど来報告させていただきまして、毎年水質モニタリング調査というのを実施しております。これによりますと、直ちに健康被害が生じる状況ではないという報告は受けております。ただ、委員御指摘のように、ダイオキシン問題、ダイオキシン類の浄化をという問題に関しましては、市民の健康にかかわる重要な課題であり、学識経験者からなる大阪市底質対策技術検討会の審議においても、御指摘のように速やかに浄化対策を行うこととされております。
このため、これまでも国の補助を得て港湾工事等にあわせて浄化対策を実施してきておりますけれども、今申し上げましたように多額の事業費を必要とすることから、今後とも引き続き財政的な支援の強化、これを国に積極的に要望してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
◆矢達幸委員
国だけやなしに大阪市も頑張らなあかんですからね。これは公害対策で半分持ちですからね、こういうことになりますから。もちろん国の補助金を大幅にふやすということは重要ですけども、しかし現在のペースではとても間尺に合いません。これ、急速にこの問題を強めていただきたいということで、市長におきましても奮闘いただきますようよろしくお願いします。市長、どうもありがとうございます。
こういう問題で、特に私気になりますのは、大阪市の環境白書に一切これ載ってないんですね。環境白書や現況と対策を見ますと、港湾地帯、湾岸地帯を調べてないのかといえば、そうじゃないんですよ。ちゃんと定点ポイントで調べてるんですね。一定の2カ所ほど底質でオーバーしてるという問題がありながら、こういう問題に一切触れないという、こういうことは何でですか。なぜこういうことを、大阪の環境白書に載らないのかということをまずお聞きしたいんですが、どうですか。なぜ載せないんですか。
◎小西環境局環境保全部土壌水質担当課長
お答えいたします。
環境白書は、大阪市環境基本条例第9条に基づき、環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策並びに実施状況を明らかにした年次報告として、毎年ダイオキシン類のモニタリング結果を公表しております。
一方、ダイオキシン類による汚染状況の詳細調査結果につきましては、港湾局がプレス発表を行うとともに、対策の進捗状況含めてホームページで公表しているところでございます。
港湾局のダイオキシン調査結果につきましては、今後掲載する方向で検討してまいりたいと思います。
◆矢達幸委員
今後掲載する方向でということで改めるということなんで、これ以上私言いませんけども、大阪の環境はこの白書に一切掲載されなきゃならんですね。どこの部局であろうと、どういう調査であろうと。現況はこうですということはここに、これに一切網羅されなきゃあかんわけですね。そういう意味では、縦割りで、あるいは港湾局の仕事だと、向こうのホームページで公開されてるというんじゃだめですね。これは市民に公開されたことになりません。そういう意味で、こんだけ高濃度汚染地域が横たわっておるという状況では、これはぜひとも今後この白書にも載せ、また現況と対策で、非常に大変な費用のかかるこういう対策です。
しかし、しっかりと対応して、対策して解決していただきたいというふうに思いますし、我々も市民もこの進捗状況をしっかりと監視していきたいというふうに思います。
[大阪市域の水環境中ダイオキシン類の調査]

河川水中のダイオキシン類濃度(平成12年〜15年度の平均濃度)
大阪市は多くの都市域を流れる河川の最下流に位置しており、市内での勾配が小さいため、河川の流れが緩やかな「水の都」として有名です。
これまでの様々な調査から、大阪市域の水環境中ダイオキシン類の分布が明らかになってきました。そして、その状況から大阪市域では、河川上流から懸濁物とともに運ばれてきたダイオキシン類が、河口域で底質へと沈降、堆積していると予想されます。
このようなダイオキシン類の状況が明らかになったことから、大阪市では河口域底質の浄化対策や周辺自治体との連携による調査や対策を進めようとしています。
グリーンニューディール政策を

ATCセミナーレポート 緑のニューディール政策がもたらす環境ビジネス
■講師
大阪大学大学院工学研究科 准教授 加藤悟氏
緑のニューディール政策は、オバマ大統領の就任後有名になりましたが、以前から、国内外で考えられていた政策です。まずは緑のニューディール政策の言葉の元となった「ニューディール政策」について振り返ってみたいと思います。
1.ニューディール政策とは何か
ニューディール政策は、1929年10月24日に発生した世界大恐慌の後、大統領となったフランクリン・ルーズベルトが行った政策です。ニューディールの“ディール”とはトランプ用語で、新規で持ち札をかえる、という意味。つまり、ゼロベースで予算配分をするということを表します。
世界恐慌の三大原因となったのは、
(1)第一次世界大戦後の農産物価格下落による市場の購買力低下、
(2)過剰な設備投資による過剰生産、
(3)各国の高関税政策による貿易縮小だと言われています。
その結果、ニューヨーク株式取引所で株価が大暴落し、各国で企業・銀行が倒産し、失業者が増大、ドイツもアメリカ資本撤退で資本不足になりました。
そんな中、フランクリン・ルーズベルトは恐慌対策を確約して大統領選に勝利しました。就任後すぐに「テネシー川流域開発公社(TVA)」を設立、またニューディール政策の基礎となる法律、「全国産業復興法(NIRA))と「農業調整法(AAA)」を制定。政府が積極的に経済に介入して景気回復に努め、善隣外交により、中南米と友好を深めました。アメリカで唯一、四選された大統領で、1945年、任期中に病死しました。
彼の政治理論を支えていたのはイギリスの経済学者、ケインズです。彼は国家の経済への介入を肯定する修正資本主義を提唱、著書「雇用・利子および貨幣の一般理論」において、一国全体における生産水準がどのように決定されるかを考案しました。これは現在、マクロ経済学と呼ばれています。
ニューディール政策の目玉の1つであるテネシー川流域開発公社(TVA)は、1933年5月に設立され、電力生産の多目的ダムを建設し、土壌保全・河川整備等の事業を行うことで、地域経済振興や住民流出防止に努めました。また電力価格を低下させて物価を引き下げ、雇用を創出しましたが、民間電力業を圧迫するという批判もありました。
一方、全国産業復興法(NIRA)では、企業の生産を規制して適正な利潤を確保、労働者には団結権や団体交渉権を認め、最低賃金を確保し、生産力や購買力の向上を目指しましたが、景気回復を促進するためカルテル的な協定締結を認めたことで、合衆国最高裁判所が違憲判決を下し、2年足らずで廃止することとなりました。
また農業調整法(AAA)では、農業部門の慢性的過剰生産恐慌の事態に対し、小麦や綿花など7項目について、作付け割り当て計画による生産管理を行いました。
しかし、一連の政策をもってしても失業率は高いまま推移し、雇用もGNPも目立った変化は見られませんでした。その後、第二次世界大戦による軍需の拡大により、アメリカ経済は回復し、失業も解消されました。皮肉なことに、アメリカを救ったのは戦争だったという意見も少なくありません。ですが、これらの政策により、それまでの古典的自由主義的経済政策から、政府が経済へ関与する社会民主主義的な政策へ転換が行われ、アメリカの政治・経済が大きく変わったことは間違いありません。
2.グリーン・ニューディール政策とは何か
2008年7月21日、「グリーン・ニューディール・グループ」により、提唱された“グリーン・ニューディール”という言葉は、1年足らずで広く知られるようになりました。
2008年7月に発表された「グリーン・ニューディール:信用危機・気候変動・原油価格高騰の三大危機を解決するための政策集」は、化石燃料に依存しないエネルギーを確保するという、エネルギーセキュリティーに重きをおいており、それと並行して気候変動対策や経済対策を行っていくという考え方です。具体的には省エネルギー技術とマイクロジェネレーション(マイクロ発電技術)への政府主導の投資、メガバンクの分割とグリーンバンキング化などの政策があります。
同年10月にUNEPが発表したグリーン経済イニシアチブでも、世界経済をクリーン技術や自然のインフラ(森林や土壌など)への投資に向かわせることが21世紀の新の成長につながるという考え方が述べられています。
その後、オバマ大統領は、2008年10月の大統領選勝利演説にて、2050年までに温室効果ガス排出量を80%削減、今後10年間でクリーンエネルギーに1500億ドルを投資し、500万人分の雇用を創出するという計画を披露しました。それに引き続く形で、世界経済フォーラム(ダボス会議)において国連の潘事務総長が、現在の経済危機を利用して、再生可能エネルギーと技術開発の投資により雇用を創出し、地球温暖化問題に取り組むべきと呼びかけました。
また2009年2月にUNEPが発表した“グローバル・グリーン・ニューディール”では、現在、景気刺激策として予定されている約2兆5千億ドルのうち3分の1はグリーン経済の実現のための投資とすべきだと強調しています。その例として、クリーンな技術開発による雇用促進や、化石燃料に対する補助金の削減、温室効果ガスを削減、生態系の悪化防止、水の安全保障等が挙げられています。
そんな中、アメリカのグリーン・ニューディール政策は非常にはっきりしており、ひとつは今後の原油高騰を見据えたエネルギー安全保障のための自然エネルギー対策、次にプラグインハイブリッド100万台によるビッグ3の復活という2本柱と、研究開発として、マイクロジェネレーションや超伝導送電、大型二次電池による蓄電等のエネルギー技術開発の取り組みを行っています。
3.日本におけるグリーン・ニューディール政策
日本におけるグリーン・ニューディール政策は、2008年9月の麻生総理の所信表明演説にて「我が国が強みを持つ環境・エネルギー技術は新たな需要と雇用を生む力がある。」と述べられているほか、環境省は2009年1月に「緑の経済と社会の変革」という構想を発表しました。この構想において、2006年現在の環境ビジネスの市場規模約70兆円、雇用者数約140万人を、近い将来飛躍的に拡大すること、そして世界で先頭をゆく環境・省エネ国家として、世界で最初に不況を脱出するという目標が掲げられています。その基本的な考え方としては、エコ改造(省庁や学校へ太陽光発電を設置する等)、エコグッズ(省エネ家電等の普及)、エコファイナンス(エコ投資)の大きく3点があげられています。
日本のグリーン・ニューディール政策に対する有識者の意見としては、太陽エネルギー社会の構築や持続可能な社会地域物質循環システム構築といった、環境白書でも述べられている基本的な提案のほか、環境エネルギー技術の促進や、特徴的な意見として途上国にむけ技術移転を行うこと、カーボンフットプリント等の見える化の促進、大学生等若い世代への働きかけ等が述べられました。
日本経団連や経済同友会でも、日本版グリーン・ニューディールの推進が推奨されており、脱化石燃料および、循環型社会へ向けた取り組みが示されています。中でも経済同友会の取り組みの中で特徴的なのは、排出権制度やグリーン税制などの、インセンティブ制度・投融資制度の導入でしょう。
日本のグリーン・ニューディール政策は、アメリカと違い、エコ改修、緑の消費への変革、緑の地域コミュニティーの変革、緑の投資への変革等、幅広いですが、地球温暖化対策とあまり差がありません。そういうところが日本らしいと言えるかもしれません。
4.環境の産業化と産業の環境化
世界での環境産業の市場規模は増加傾向にあります。企業の環境配慮における3つの発展段階として、「(1)規制追随型・受動的な環境配慮」から、「(2)事前対応型・予防的な環境配慮」になり、さらに付加価値を追求し、「(3)機会追求型・戦略的な環境配慮」と変化してきています。
環境ビジネスをOECDによる分類で分けると、大気汚染や水質汚濁等の防止・処理にかかる装置の製造や設置にかかるビジネスが「環境汚染防止」、環境負荷低減および省資源化のための技術、プロセスの提供、配慮した製品に関するビジネスは「環境負荷低減技術および製品」、最後に、環境負荷低減および省資源化を直接的な目的としないが、その効果が期待できる関連産業が「資源有効利用」に分類されます。たとえば、再生可能エネルギー施設や、省エネルギー関連ビジネス、エコツーリズム等も資源有効利用に分類されるビジネスです。
日本における環境ビジネスの市場規模も、2020年には2000年の2倍の規模になることが期待されています。日本の環境ビジネスとしては、以下の10分野の産業の環境化、および環境の産業化が考えられます。
1.廃棄物関連ビジネス(3R、廃棄物処理関連)、
2.地球温暖化(省エネルギー・新エネルギー)、
3.環境浄化(土壌汚染、アスベスト)、
4.観光(エコツーリズム)、
5.金融・保険(社会的責任投資、環境リスクの商品化)、
6.情報通信(効率化や情報による脱物質化)、
7.農業(エコファーマー、バイオマス利用)、
8.林業(持続可能な森林経営)、
9.水産業(自然管理・育成型漁業)、
10.貿易(フェアトレード)
5.大きな政府と小さな政府
ニューディール政策の思想は、大きな政府なのか、小さな政府なのかを考えてみましょう。
大きな政府とは、ゆりかごから墓場まで国が全部面倒を見てくれる政府です。一方、小さな政府は、警察や防衛など国として最低限の仕事だけを行い、経済活動等は放任する政府のことです。小さな政府の場合、自由放任主義が行き詰まって、貧富の差が大きくなります。そして政府は経済や社会のさまざまな領域に介入せざるをえなくなり、社会福祉立法や少数派保護法によって平等化の推進に努めることとなります。社会はイノベーションや競争の力で前へ進みますが、競争の中で生じる勝ち負けのバランスをとるのが政治の役割です。
アメリカでは小さな政府が破たんし、大きな政府への移行が進んでいます。非常時の公共投資による一時的なばらまきや経済への介入は、半永久的な大きな政府への移行とは異なります。
一方、大きな政府の弊害は、競争による効率性やイノベーション活動の低下が挙げられます。どちらが良いかではなく、そのバランスが重要です。
ここで、注意しておきたいのが、高福祉国家は大きな政府か?ということです。北欧は税金も高く、子持ちの女性が就労する世帯への手厚い補助や福祉が充実していますが、中央政府の権限は最小限に限定されており、地方では地元住民に大きな権限があります。さらに投資環境ランキングで上位常連、つまり自由経済がすすんでいると言えます。これらのことからも、北欧は高福祉国家ですが、大きな政府ではないと言えます。
では、アメリカは小さな政府か?というと、軍事予算や財政赤字は、小さくなるどころか増加の一途をたどっており、「通貨ばらまき」政策のため、国際決済通貨としての米ドルの地位は年々低下しています。また防災や地方に交付される予算は削減されています。
このような流れの中、私は、グリーン・ニューディールの目指すべきものは地方分権と自立型都市の確立だと考えています。地域が自立した産業を育成するためには、投資活動が円滑に行われるべきでしょう。そうなると、エネルギーや資源も地産地消が良いのでは、という考えに至ります。となると、家電や大規模太陽光発電に投資するのではなく、持続可能な農林水産業やエコハウスの建設、植物工場などの実現こそが、いま求められている環境投資、環境ビジネスではないでしょうか。
環境モデル都市として採択された北海道の下川町の「緑の経済と社会の変革」の例では、地域資源・地域雇用を生かし、地域で消費する、さらに地域の中で投資も進んでいるという、まさにグリーン・ニューディールのお手本となるモデルです。
まとめ
ニューディール政策とは、生産規制と公共投資、雇用確保についての政策でした。そしてグリーン・ニューディール政策は、本当の意味でグリーンではなく、信用危機や原油価格高騰とともに気候変動対策を行うという政策で、アメリカでは原油価格高騰対策とビッグ3に焦点がしぼられています。
一方、日本のグリーン・ニューディール政策では、省エネ家電と太陽光発電が2本柱となっています。また産業の環境化および環境の産業化については、従来の環境浄化型産業から事前対応型産業への移行が今後も進んでいくでしょう。
最後に、大きな政府と小さな政府という観点においては、自立型で競争原理とセイフティーネットを併せ持つ、小さな政府を目指したインフラ整備の改革を進めることが、グリーン・ニューディールの本来の姿なのではないかと思います。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/210501/index.html
2009年07月20日
重金属による底質汚染と重金属底質環境基準のありかた

現在、私たち人類の文明の発達などよって自然界に生態系のバランスが崩れ、本来あるはずの食物連鎖のかたちが崩れかけている現状ですっ。
海に親しむ私たち釣り人の身近な問題といえば、赤潮、青潮の大量発やカワウの数が増えた事でせっかく放流した稚魚が食べられちゃう事など…。
現在も未来も豊富な資源に恵まれた美しい地球でありますように。
いつまでもマリンレジャーが楽しめますように。
たくさん魚が釣れるフィッシングパラダイス、ニッポン!を本気で目指すためにも、これから私もみなさまと一緒に海の知識を学んでゆきたいと思いますっ。
まずは魚の生態や保護、増やすための海の知識が今の私たちに必要なのかな?
釣る、という観点を180度変えてみて海洋学の視点から考えてみましょう!
研究者によって解明された事実は意外にも釣果に深い関係があったりしてお役立ち知識も!?
それらを名づけてビバ!フィッシングサイエンス
ではまず、食物連鎖の底辺にあるプランクトンのお勉強のために、底質汚染についてイントロを説明します。
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 底質汚染分科会は大阪府神崎川の底質ダイオキシン類汚染の公表を契機に発足しました。
水の底の蓄積された底質汚染は多くの人に理解されている訳ではありませんが、食物連鎖を通しての人の健康リスクや生物多様性への影響など多くの問題が抱えています。
当分科会は行政や学識経験者を招いて底質汚染に関するセミナーを開催してきました。この間、全国の底質汚染の現状が徐々に明らかになり、底質汚染による底生生物の影響や汚染原因解明手法も分かってきました。
底質汚染分科会の特別会員である環境カウンセラーの藤原きよみの主張する「三世代先の海いつまでも」に良く表れているように、環境は子孫からの預かりものでございます。この数十年で大変悪くなった底質汚染ですが、汚染濃度が高いところは低下傾向にありますが、底質汚染の拡散とも考えることができるのではないでしょうか。
ブログ「底質汚染ラーニング」で多くの底質汚染の情報を収集してきました。また、その情報を下記のホームページに掲載しています。
全国の底質汚染
底質汚染の歴史
私たちの時代に、底質環境を保全し、健康リスクを低減させると共に、恵み豊かな海の再生を図ることが現代人の使命ではないでしょうか。
それでは底質汚染について勉強しましょう。
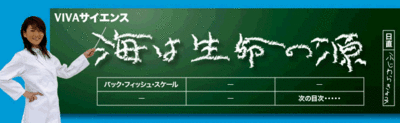
はじまり ハジマリ パチハチパチ!
日本の地球化学図や「港湾底泥中の粒子状金属の濃度レベルとその底生生物への影響」から主な資料を引用して説明します。
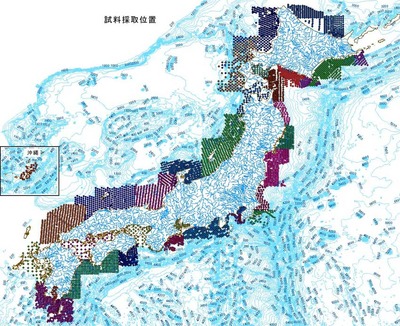
上図は日本沿岸の海の底と試料採取場所の図です。
水銀と底生生物の説明をします。
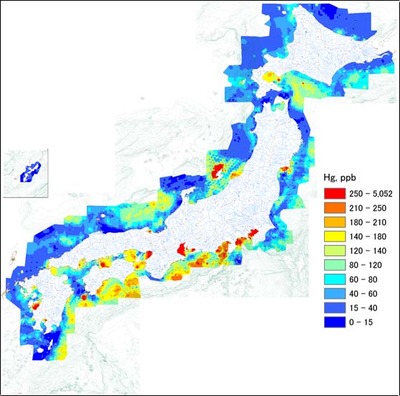
全国的に見ると佐渡島、宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、大阪、瀬戸内海、水俣等が高くなっています。

仙台も水銀が高くなっています。

東京湾(東京・千葉・市原・木更津・横須賀・君津・鎌倉・茅ヶ崎・小田原・熱海が高い)

伊勢湾も水銀が高いですね

大阪湾(大阪湾奥を汚染源とした東半分、阿南から御坊を結んだ線の北側。淡路島の南および西側は水銀が高い。)

瀬戸内海(大阪・神戸・堺・岸和田・姫路・和歌山・徳島・淡路島の五色の浜沖・新居浜沖・岩国等が水銀が高い)

九州(水俣・鹿児島国分・宿毛沖が水銀高い)
上図は底質に含まれる水銀を表しています。赤色は0.25〜126mg/kg、黄色は0.14〜0.18mg/kgで、 下の図に示すよう水銀含有量が0.15mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなります。
佐渡島、宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、大阪、瀬戸内海、水俣等が高いです。橙色〜赤色のところは底生生物が水銀により大きく影響を受けていることになります。

鉛と底生生物の説明をします。

東京湾・大阪湾・富山湾・瀬戸内海・新潟が高いですね。

東京湾の鉛底質汚染は赤色の横浜の奥の東京・市原・木更津ということになります。

大阪湾東3分の1が特に鉛底質汚染が進んでいます。

赤 色:45mg/kg
オレンジ色:45〜40mg/kg
橙 色:40〜35mg/kg
黄 色:35〜30mg/kg
下の図に示すように、鉛含有量が47mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなるとのことですので、鉛により底生生物がほとんどいなくなるっている範囲は赤色で、大阪・神戸・堺・岸和田・姫路・赤穂・倉敷・徳山・尾道・徳島・淡路島の五色の浜沖・新居浜沖・岩国等が、鉛の影響を受けて底生生物がほとんどいないことになります。


海の底にも有害物質が蓄積されています。
カドミウムと底生生物の説明をします。

赤色は1.4〜0.3mg/kgを示します。カドミウム含有量が1.2mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなります。東京湾・伊勢湾・大阪湾・周防灘が高いですね。赤い所のうち濃いところが底生生物がほとんどいないことになります。

赤色はカドミウムが1.4〜0.3mg/kgの濃度です。カドミウムの含有量が1.2mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなるとのことですので、カドミウムにより底生生物がほとんどいなくなるっている範囲は赤色である東京湾全域と銚子沖ということになります。



赤色:1.4〜0.3mg/kg
カドミウムの含有量が1.2mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなるとのことですので、カドミウムにより底生生物がほとんどいなくなるっている範囲は赤色である大阪湾の東4分の1程度ということになります。

赤は1.3〜0.3mg/kgですので、赤色の中心部分の 大阪や周防灘・姫路・岡山・岩国・自衛隊築城基地・苅田が高く、カドミウムにより底生生物が棲めなくなっているようです。
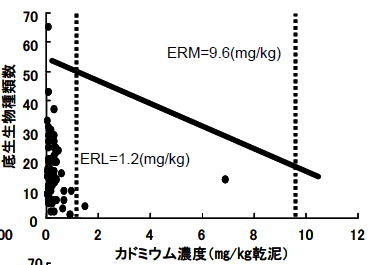
クロムと底生生物の説明をします。

クロムは北海道、宮城、千葉、東京、静岡、富山等で高くなっています。

赤色は334〜100mg/kg、黄は77〜66mg/kgクロムが含まれています。クロム含有量が81mg/kgを超えると底生生物はあまりいなくなりますので、橙色〜赤色のところの横浜・東京・船橋・千葉・市原などがクロムの影響で底生生物が少なくなっているようです。

赤色:334〜100mg/kg
橙色:99〜78mg/kg
黄色:77〜66mg/kg
橙色〜赤色のところの横浜・東京・船橋・千葉・市原などがクロムの影響で底生生物が少なくなっているようです。


赤:334〜100mg/kg
黄:77〜66mg/kg
クロム含有量81mg/kgを超えると底生生物はあまりいなくなります。赤色や橙色のところの大阪湾奥を汚染源とする大阪湾東半分や、徳島・小松島付近が汚染源と思われる淡路島西南部や高松から阿南の間の沖ではクロムの影響で底生生物が少なくなっているようです。淡路島西側はクロムが高いですね。

赤:334〜100mg/kg黄:77〜66mg/kg
橙色のところの大阪・淡路島南西部・徳島・新浜沖・高知・須崎がクロムの影響で底生生物が少なくなっているようです。
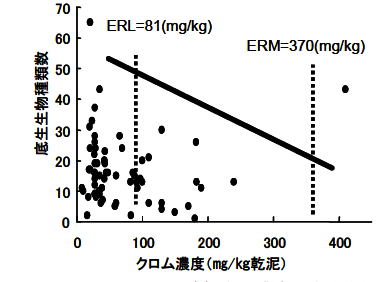
クロム含有量が81mg/kgを超えると底生生物はあまりいなくなることが分かりますね。
亜鉛と底生生物の説明をします。
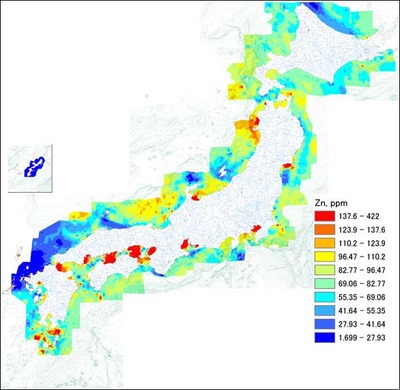
亜鉛含有量が150mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなります。
秋田、宮城、千葉、東京、富山、愛知、三重、福井、鹿児島などが高いです。赤い所は底生生物がほとんどいないことになります。


赤:422〜138mg/kg
赤くなっている東京湾や横須賀・茅ヶ崎・銚子などは亜鉛の影響で底生生物が少なくなっています。


赤いところは422〜138mg/kgです。 亜鉛含有量が150mg/kgを超えると底生生物はほとんどいなくなります。
赤くなっている大阪湾や和歌山・徳島・香川・播州・岡山は底生生物が少なくなっています。
赤くなっている伊勢湾や、海南市から阿南市を結んだ線の北側や姫路・高松付近も底生生物が少なくなっています。

赤:422〜138mg/kg
大阪・多奈川・神戸・姫路・岡山・小豆島・豊島・和歌山・海南・福良・高松・観音寺・水島・福山・尾道・広島・岩国・四国中央・新浜・西条・大分・中津・宇部・小野田など瀬戸内海全体の亜鉛が高く底生生物の棲息が妨げられている。

むつかしくなってきました。

次はダイオキシン類や環境ホルモンです。
ホルモン焼きではありません。
下の表は港湾における底質汚染の濃度と量です。(国土交通省提供)
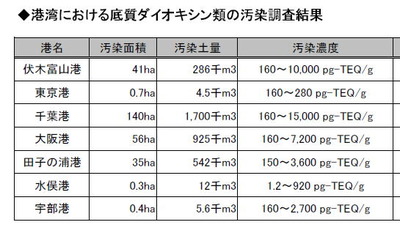
千葉港がもっとも汚れていて、たくさんのダイオキシン類汚染底質があります。2位は大阪港です。
下の図は千葉市原港の底質ダイオキシン類汚染の図面です。

見にくいのでリンク元(市原市地先海域におけるダイオキシン類の調査結果)をご覧ください。
下図は「内分泌かく乱物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理プロジェクト」内分泌かく乱化学物質のリスク評価と管理のための統合情報システムについては、GIS上の高詳細環境モデル(G-CIEMS)を完成させ、ダイオキシン類の河川水中濃度、ベンゼン・ダイオキシンの大気中濃度を推定し、実測値と比較した(図5)。

図5 G-CIEMSモデルによる河川水中濃度の推定結果の例
鳥羽港のあたりが一番高く京浜地域や高知も高い ですね。
鳥羽では、PCB類、 HCB(ヘキサクロロベンゼン)、アルドリン、ディルドリン等の環境ホルモンが高くなっています。エンドリン日本一高濃度です。伊勢の海女さんはご存知だったかも知れません。
「化学物質と環境2005年度調査」より底質における環境ホルモンの高いところ」で分かりやすく書いています。
下図は底質に含まれるダイオキシン類と底生生物の種類や重量の関係を示した図です。
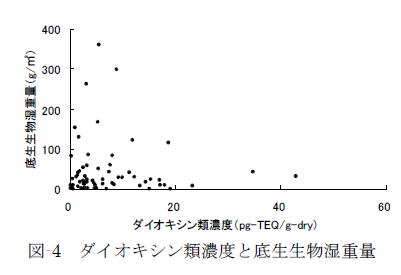
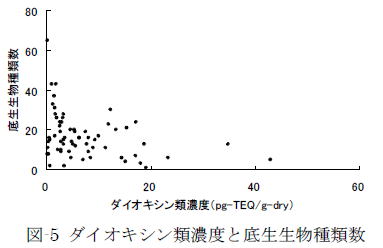
ダイオキシン類濃度と底生生物の関係には、 「米国NOAA から示されている底質ガイドラインでは,PEL 値(底生生物が少なくなる値)として,21.5pg-TEQ/g を与えており,環境基準値以下であっても,何らかの生物への影響を排除することはできないと考えられる。本調査の結果からは,底生生物湿重量,底生生物種類数ともに,ダイオキシン類濃度が高い場合には,生物棲息環境が貧弱になる傾向があった。特に,ダイオキシン類濃度が20 pg-TEQ/g を超過した場合,存在した底生生物は,二枚貝網,多毛類網,花虫網などであり,種類数が少なかった。」と記載されています。
ダイオシン類の底質環境基準は150pg−TEQ/gですが、底生生物を保全し豊かな海を守るには20pg-TEQ/gを基準に考えるべきだということになります。
大人には健康被害が無くても、胎児や小さな生物には影響があります。また、海の生物には環境ホルモンが蓄積されていることと有害化学物質の生物への蓄積
でまとめています。

三世代先の海、いつまでも。 / 藤原きよみ
島育ちの父は私が幼少の頃からよく海につれていってくれました。夏休みは家族8人で必ず海でキャンプです。幼すぎて場所はわからないけど磯場が多く海の生き物がたくさんいて楽しかった。
おてんばな私はフジツボで手足を切ったりなんてあたりまえ^^。急な突風、天候の変化、高波、雷雨。。。「自然は楽しい反面怖い」 子供だったけど無茶はしちゃいけないって感じました。
楽しかった子供のころの海の想い出。
私くらいの年齢の夫婦の子供達が大人になってまた子供を産んで。。。その三世代先の海がいつまでも健康であってほしい。
未来の海を大切に思うから、未来をつくる今の子供達の命の大切さを。
三世代先には私はもちろん生きてはないけどその時の子供達が豊かな自然恵みを受ける事ができたらいいなって。。。そのために今私達、大人が出来る事ってなんだろう。