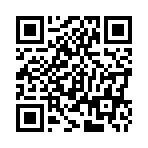2009年10月22日
(工事中)H20農薬飛散リスク評価手法確立調査
平成20年度農薬飛散リスク評価手法確立調査モニタリング調査業務
結果報告書
平成21年3月
社団法人 農林水産航空協会
要 約
市街地における街路樹や公園の花木類等管理のために散布される農薬の飛散リスクの影響を評価・管理する手法を確立するため、平成18年度及び平成19年度モニタリング調査結果を踏まえて、農薬飛散範囲調査、農薬検出期間調査および除草剤散布後気中濃度等調査を実施した。
農薬飛散範囲調査は、立木1本に対して水を散布し、樹高、樹形、風の条件、散布方向の違いについて、周辺への飛散状況を調査した。調査は、樹の中心から8方位に、樹高の条件により10mまたは15mまでの距離で調査地点に感水調査紙を設置して行った。感水調査紙は、画像処理ソフトウエアにより、被覆面積率および付着液量の推定を行った。
飛散状況は、樹が高いほど、また、枝葉が繁茂しているほど多かった。樹高4m 程度の樹に対しては、手の届く範囲で近距離からの散布ができることから、飛散が少なかったものと考えられる。枝葉が繁茂した樹形は散布水量が多くなることから、その分飛散のリスクが増えるものと考えられた。
しかし、風の強い条件では、散布方法より風の影響の方が強いと考えられ、平均風速が2m/s 程度であっても、風下側では15m 先へも飛散する可能性が十分にあると考えられた。
付着液量の推定は、1 樹当たりの散布水量と、8 方位の距離別にブロック分けした場所においての付着液量の比率の風下側最遠調査地点での最大値は、平方メートルあたり0.03%であった。
農薬検出期間調査は、公園等での使用実績のあるフェニトロチオン、トリクロルホン、エトフェンプロックス及びイソキサチオンの4 剤を混用して、調査対象の樹木林に散布し、気中濃度濃度調査、土壌中濃度調査及び葉への付着量調査を実施した。気中濃度は、調査農薬により検出された値に違いは見られたが、それら農薬の蒸気圧等の物理化学的性状が影響をあたえて
いのではないかと考えられた。
土壌中濃度で散布直後の濃度と比較して1/2 の濃度となったのは、フェニトロチオンで散布14 日後、ジクロルボスで散布7 日後、エトフェンプロックス及びイソキサチオンでは散布14 日後以降であると推察された。葉への付着量では、フェニトロチオン、トリクロルホン及びジクロルボスは同じようなに減少する傾向が見られ、散布14日後で1/80、1/20 及び1/50 まで減少し、当初の濃度が低かったイソキサチオンとエトフェンプロックスは散布14 日後で1/3 及び3/5 と減少は少なかった。
除草剤散布後気中濃度等調査は、使用実績のあるグリホサートの散布後に気中濃度調査、土壌中濃度調査及び葉中濃度調査を実施した。気中濃度では、散布区域内の高さ0.2mの地点で散布当日の13 時のみに検出されたことは、一度散布された農薬が蒸散した結果と考えるには、最も値が高いはずの散布直後に検出されていないことと、その検出濃度などから、植物体を経由したカラムの汚染による可能性が高いのではないかと考えられる。土壌中濃度は、散布直後と散布30 日後の濃度に違いは見られなかった。葉中濃度は、散布直後に高い濃度が検出され、散布1 日後に大きく減少した。
Summary
Based on the results of serial monitoring studies conducted in 2006 and 2007,dispersion range, duration of detection period, and concentrations in air of heirbicide after spraying were
investigated to establish the methods for evaluation and management of dispersal risks of
agrochemicals applied for maintenance of greenery on roadside tree or in parks.
For the purpose of estimation of dispersion range, a tree was sprayed with water and profiled
for the water dispersion toward surrounding area. The results were analyzed in terms of height
and shape of trees,wind condition,difference of spraying orientation. Sheets of water-sensitive
paper were placed 10 to 15 m from the center of a tree depending on height of trees in eight
azimuth directions. Ratio of the covered area and amount of attached solution were estimated
by measuring the wet area on the water sensitive papers using image analysis software.
The extent of dispersion was increased in accordance with the height of trees and the density
of branches and foliages. Trees as low as 4 m in height showed less dispersion probably due
to the spraying from closer distance within the reach of equipment. The elevated amount of
sprayed agrochemicals required for trees with dense branches and foliages seemed to give rise
to risk of dispersion. However, wind effect prevailed over spraying method especially under
strong wind condition. The downwind dispersion as far as 15 m can be observed even at the
wind speed of 2 m/s.
On spraying a tree, a ratio of the amount of attached solution versus that of sprayed solution
was calculated at each sampling point in eight azimuth directions differing in distance from
the sprayed site. The maximum ratio at the furthest downwind sampling point was estimated
to 0.03% per square meter.
Four agrochemicals with past application records in parks such as fenitrothion, trichlorphon,
etofenprox,and isoxathion were selected and adopted for determining the duration of detection
period. The combined agrochemicals were sprayed over trees and concentration in air,soil
concentration,and deposit on foliage were measured. The difference in concentration in air of
the individual agrochemicals could be ascribed to physicochemical characters such as vapor
pressure. Half-lives of fenitrothion, etofenprox, and isoxathion in soil were estimated to 14
days, 7 days, and 14 days, respectively. Fenitrothion, trichlorphon, and dichlorvos on leaves
showed the same decaying tendency, and the amount of the each substance decreased to
1/80-fold, 1/20-fold, and 1/50-fold of the primary amounts after 14 days from application.
Isoxathion and etofenprox with less primary attachment to leaves decreased to 1/3 and 3/5 of
the primary concentration after 14 days from application.
Glyphosate which has the solid past application records was adopted for the study of
post-application monitoring of herbicides. After spraying, glyphosate concentrations in the air,
in soil, and in leaves were monitored. The sole detection of concentrations in air was observed
at 13:00 on the day of spraying. The concentrations in air were not detected immediately after
spraying and the concentration of the detected glyphosate was too low. Therefore the
detection of glyphosate was most likely due to contamination of the trapping column in
contact with sprayed plants, rather than the evaporation of glyphosate. There was no
significant difference between glyphosate concentration in soil of immediate aftermath of
spraying and that of 30 days after spraying. In leaves, large amount of glyphosate was
detected immediately after spraying, while significant decrease of glyphosate was recognized
a day after spraying.
はじめに
この報告書は、環境省大気局農薬環境管理課から社団法人農林水産航空協会に委託された「平成20年度農薬飛散リスク評価手法確立調査(モニタリング調査業務)」の実施成果をとりまとめたものである。
本調査は、市街地における街路樹や公園の花木類等管理のために散布される農薬の飛散リスクの影響を評価・管理する手法を確立するに当たって、公園等を利用する一般市民及び公園等周辺住民の健康を保護する観点から、公園内及び周辺における農薬の気中濃度及び飛散等による曝露実態を把握するために実施した平成18年度及び平成19年度モニタリング調査結果を踏まえて、農薬飛散範囲調査、農薬検出期間調査および除草剤散布後気中濃度等調査を実施した。
平成21年3月
東京都千代田区平河町2−7−1 塩崎ビル3階
社団法人 農林水産航空協会 会 長 関 口 洋 一
目 次
?.農薬飛散範囲調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
?.農薬検出期間調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
?.除草剤散布後気中濃度等調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
要 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114
平成20 年度農薬飛散リスク評価手法確立調査(モニタリング調査業務)
[目的]
環境省では平成17 年度から農薬飛散リスク評価手法確立調査を開始し、街路樹や公園等の市街地において使用される農薬の飛散リスクの評価・管理手法について検討しているところであり、これまでに、国内外における農薬飛散リスクの評価・管理手法に関する文献調査、自治体での防除実態を把握するためのアンケート調査(平成17 年度)、実際の農薬散布場
面におけるモニタリング調査(平成18・19 年度)と、蒸気圧等の要因別の影響調査を含む基礎調査(平成19 年度)を実施し、農薬の飛散による暴露実態を把握するための基礎資料を得た。
平成20 年度の本業務では平成19 年度までの結果を踏まえた上でモニタリング調査を実施し、農薬の飛散による暴露実態を把握するうえでの基礎資料を得る。
[調査項目]
?.農薬飛散範囲調査
樹木等に対して通常用いられる農薬散布用器具を用いて水を散布し、感水紙を用いて、周囲への到達落下範囲を調査する。
?.農薬検出期間調査
農薬散布にあたり最も高濃度が検出される地点において十分減衰するまでの期間が立ち入り禁止期間となると考える。
したがって、高木が複数存在する区域を設定して調査地点を置き、農薬散布後の気中濃度低減の調査を行うとともに、当該地点における葉及び土壌での残留量を計測する。
?.除草剤散布後気中濃度等調査
雑草等が生えている場所に除草剤(グリホサート)を散布した場合、その周囲への飛散の程度、気中濃度、及び散布地点の土壌の残留について調査を行うこととする。
?.農薬飛散範囲調査
[調査内容]
1.調査実施場所
(社)農林水産航空協会 農林航空技術センター敷地内(長野県小諸市)
2.調査方法
(1)調査樹
樹種:オウシュウトウヒ(ドイツトウヒ)
樹高:中木4.2m、高木?(疎密)8.3m、高木?(繁茂)8.7m の3 形態(写真1)。
(2)調査の組み合わせ
樹高・樹形:中木、高木?(枝葉疎密)と高木?(枝葉繁茂)の比較。
ノズル:慣行と飛散低減の比較。
風速:平穏〜軽風(0〜1.5m/s)と軽風(1.6〜3.3m/s)の比較。
散布方向:高木?において、下からの吹上げと横方向からの散布の比較。
各調査は反復を2 回とした。
(3)感水紙の設置
調査対象となる樹木を中心に、8 方向に、樹木から3m、5m、10m の距離に地上高50 ?の高さに感水紙を水平に設置し、散布した水の飛散状況を調査した。なお、軽風条件下においては15m 地点にも設置した。
感水紙は、WATER SENSITEVE PAPER(スプレーイングシステム株式会社製)を使用した。
(4)感水紙の解析方法
感水紙は、散布開始前から散布終了後5 分まで設置し、変色量を画像解析ソフト、ImageJ(バイオアーツ株式会社製)を用い、被覆面積率を測定した。
感水紙の一部については、画像解析ソフト、まいA のーど(ノズルネットワーク株式会社製)により、付着液量の推定を行った。
なお、感水紙の画像の解像度は、1 ドット約64 ?(約400dpi)であった。
(5)散布方法
動力噴霧機:セット動噴MS253(株式会社丸山製作所製)
散布ノズル
慣行ノズル:アルミズームα900 型(ヤマホ工業株式会社製)噴霧粒径95〜360μm(写真2)
飛散低減ノズル:キリナシズーム900 型(ヤマホ工業株式会社製)
噴霧粒径380〜710μm(写真2)
*圧力1.5MPa での平均粒径(データはヤマホ工業株式会社提供)圧力:全て1.5MPa
(6)風向風速の計測
風向風速は、デジタルハンド風向風速計26D-B?(株式会社太田計器製作所製)で測定した。
[調査結果]
1.散布状況
調査に使用したノズルは、2 種とも、手元のグリップを回転させることにより遠距離噴霧(狭角)と近距離噴霧(広角)の調節ができるため、高木?、?の吹き上げ散布は、遠距離噴霧で、中木および高木?の横方向からの散布は近距離噴霧で行った。
中木は、手の届く範囲で概ね横方向からの散布となった。
高木?の横方向からの散布は、長さ4m の直管にノズルを取り付け行った。
散布水量は、予め練習散布で枝葉が十分に濡れ水が滴り落ちる程度を十分量と定め、噴霧時間を合わせることにより散布量が一定となるようにした。
散布は、条件を統一にするため、風向にかかわらずに散布者が樹の周囲を移動し、全周方向から行った。
2.飛散状況
飛散状況調査は、表2 の組み合わせで行い、その結果を表3 及び図1〜図16 に示した。
全体の飛散程度を検討するため、表3 より距離ごとに8 方位の感水紙における飛散の被
覆面積率(以下「被覆面積率」という)の合計値と飛散が確認された感水紙数を取りまと
め、表4 に示した。
樹高の影響については風の条件ごとに比較し図17 に、樹形の影響については高木につい
て風の条件を比較し図18 に、ノズルの影響、散布方向の影響については風の条件と樹高・
樹形を比較し図19 に、風速の影響については樹高・樹形と散布方法を比較し図20 に、風
向の影響については地点ごとの被覆面積率を比較し図1〜16 に示した。
(3)ノズルの影響について
中木では、平穏〜軽風の条件で飛散低減ノズルの被覆面積率の値が5m、10m で低かった。
軽風では飛散低減ノズルの値が3m、5m で低かった。
高木では、軽風で散布方法が吹上の条件では、3m 地点では慣行ノズルの値が低かったが、
10m、15m 地点では、低減ノズルの値が低かった。それ以外の条件では明らかな飛散程度の差
は認められなかった。
(4)散布方向の影響について(図19)
平穏〜軽風で低減ノズルの条件では、横方向からの散布が吹上での散布に比べて値が低か
った。軽風条件では、散布方向による明らかな差は認められなかった。
横方向からの散布はより上方へ到達する水量が、吹上での散布に比べ少ないと考えられる
ことから、飛散が低減されるものと考えられるが、風が強い場合は、風の影響の方が大きい
ものと考えられる。
図19 ノズル・散布方向の影響
(5)風速の影響について
中木では、3m、5m、10m では軽風に比べ平穏〜軽風の被覆面積率の値が明らかに低く、10m
以上で大きく値が減少した。
高木では、平穏〜軽風では3m での値が高く、5m、10m で大きく値が減少している。軽風で
は、3m と5m の値に大きな差が無く、飛散が認められた。
高木?、?ともに吹上散布では、平穏〜軽風の条件では風下方向に限らず、全周に飛散す
る傾向が認められた。軽風条件では、風上では3m の地点でも飛散はほとんど認められなかっ
た。目視では、吹き上げ散布はノズル先端より5m 以上吹き上げており、その結果より高い位
置で広範囲に飛散してしまうため、特に風の弱い状況においては、散布位置の周辺に多く飛
散することが観察された。風が強い場合は、ほとんどが風により風下方向に流されていた。
図20 風の影響
(6)風向の影響について
風下方向では、調査を行った最遠地点の10m(平穏〜軽風)、15m(軽風)まで飛散が認められ
た(図1〜16)。
高木?、?ともに吹上散布では、平穏〜軽風の条件では風下方向に限らず、全周に飛散す
る傾向が認められた(図3〜6)。軽風条件では、風上では3m の地点でも飛散はほとんど認め
られなかった(図11〜14)。
3.飛散量の推定
(1)感水紙の付着液量の推定
画像解析ソフト「まいA のーど」により、感水紙に付着した液量の推定を行った結果を
表5 に示し、被覆面積率と付着液量の関係を図21 に示し、得られた推定式
y=0.0003x2+0.0165x により換算した付着液量を表6 に示した。
また、感水紙の飛散状況(水滴が付着した部分が青色に変色する)の一例を写真5 に示した。
なお、本解析方法では、感水紙上の液滴痕跡が、多く重なったり、つながったりしてい
る状態では、精度が落ちるため、被覆面積率が概ね25%以下のサンプルについてのみ解析
を行った。表6 においても、被覆面積率が25%以上のものについては、換算から除外した。
表5 被覆面積率と付着液量の推定値
(2)総散布量に対する付着液量の割合
被覆面積率から換算した感水紙の付着液量をもとに、図22 に示すように方位ごと距離別
にブロック分けし総散布液量(1 樹当たりの散布水量)に対するブロック全体の面積で換算
した付着液量比率を算出し表6 に示した。
算出にあたっては、3m 地点と5m 地点での付着量の平均値を3m から5m までの範囲の付
着量の平均値、5m 地点と10m 地点での付着量の平均値を5m から10m までの範囲の付着量
の平均値、10m 地点と15m 地点での付着量の平均値を10m から15m までの範囲の付着量の
平均値として換算した。平穏〜軽風の10m から15m までの範囲の付着量の平均値は、10m
地点の1/2 の値とし、同じく軽風の15m から20m までの範囲の付着量の平均値は、15m 地
点の1/2 の値として換算した。
平穏から軽風条件では、総散布量に対する付着液量の割合の最大値は、高木繁茂、横方
向、通常ノズル散布の風下側10m から15m ブロックで0.65%で、平方メートルあたりでは、
0.03%であった。また軽風条件の最大値は、高木疎密、吹上、通常ノズル散布の風下側15m
から20m ブロックで0.93%で、平方メートルあたりでは、0.03%であった。
図22 総散布量に対する付着液量の割合算出における方位・距離別ブロック
[まとめ]
1.飛散状況調査
今回の調査は、立木1 本に対しての散布において、樹高、樹形、風の条件、散布方向の違いについて、周辺への飛散状況を調査したものである。
樹高4m 程度の中木に対しては、手の届く範囲で近距離からの散布ができるのに対し、8m程度の高木は、高いところまで勢い良く吹上る必要があり、その分飛散のリスクが増えるものと考える。
このことは高木で、吹上による散布よりも横方向から散布する方法の方が、飛散程度が少なかったことからも言える。しかし、風の強い条件では、散布方法より風の影響の方が強いと考えられた。
また、繁茂した樹形の方が、疎密のものより飛散程度が多かったことから、散布水量が多いことによると考えられる。
以上のことから、散布時の飛散リスクには、樹高及び風の条件が最も重要であり、次に散布量の影響が見られる。なお、平均風速が2m/s 程度であっても、風下側では15m 先へも飛散する可能性が十分にあると考えられる。
2.飛散量の推定
感水紙の画像解析による付着液量の推定調査については、感水紙上の痕跡が粒子状であり、重なりが少ないほど精度が良いと考えられる。このため本調査においては、被覆面積率が25%以下のサンプルについてのみ解析を行った。
本調査において、被覆面積率と画像処理ソフトにより測定した付着液量の間には、一定の相関が認められ、推定式により、被覆面積率から感水紙の付着液量の推定が可能であると考えられた。1 樹当たりの散布水量と、8 方位の距離別にブロック分けした場所においての付着液量の比率の風下側最遠調査地点での最大値は、平方メートルあたり0.03%であった。
ただし、本結果は、本調査における画像解析に係る機器、ソフトウエアの組み合わせで得られたものであり、他の組み合わせについては別に検討が必要である。
?.農薬検出期間調査
[調査内容]
1.調査場所
(社)農林水産航空協会 農林航空技術センター敷地内(長野県小諸市)
2.調査実施期間
平成20 年8 月11 日(散布前日)〜8 月26 日(散布14 日後)
3.散布概要
散布面積:およそ1,000 ?
散布農薬の概要を下表に示した。
散布諸元
ポンプ:動力噴霧器 MS903(株式会社丸山製作所製)
エンジン:ブリッグス20HP(ブリッグス&ストラットンジャパン製)
使用ノズル: 松喰虫ノズル(株式会社永田製作所製)
噴霧形状:高木樹が多いため直射噴霧とし、低木へは圧を弱めやや広角に散布
圧力:30kgf/c ?(3.0MPa)
散布量(4 農薬を混用):400 ?/1000 ?(葉から滴り落ちる程度)
4.調査農薬成分
フェニトロチオン
トリクロルホン
ジクロルボス(トリクロルホンの代謝物)
エトフェンプロックス
イソキサチオン
5.調査項目
(1)気中濃度調査
調査は、「航空防除農薬環境影響評価検討会報告書(平成9 年12 月、環境庁水質保全局)の測定方法に準じた手法を用いて行った。
1)調査地点
3 地点A、B、C を設定し、各地点で1.5mの高さ及び0.2mの高さとした。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布中、散布直後、散布1 時間後、3 時間後及び6 時間後)及び散布1 日後の所定の時間に行った。
3)捕集時間と捕集量
捕集時間は毎分3 ?の吸入速度で散布前は1 時間とし、散布中及び散布直後の調査時は30 分間、それ以降はすべて1 時間とした。また、散布中の調査は対象樹木への散布が開始された時から30 分間とし、散布直後の調査は「散布中調査」の後
に引き続き30 分間として行った。
大気の捕集は、高度1.5mでは自動大気捕集装置及び高度0.2mではミニポンプとガスメーターを組み合わせた捕集装置を使用した。
4)捕集装置
?自動大気捕集装置 AS-5000 型(株式会社メテク)
?ミニポンプ MP-500Σ(柴田科学株式会社)
乾式ガスメーター:DC-1C(株式会社シナガワ)
5)捕集カラム
?捕集剤 テナックスTA(60/80 mesh) 0.5g充填
?カラム 自動大気捕集装置:内径10mm、全長190mm(捕集剤充填部140mm)ガラス管に捕集剤を充填した。
ミニポンプ:内径12.7mm のポリプロピレンのチューブに捕集剤を充填した。
なお、ミニポンプに使用したカラムは、太陽光などによる影響を避けるため捕集
剤を充填した部分をアルミ箔で覆った。
6)捕集方法
?自動大気捕集装置
各調査地点に捕集カラムをセットした自動大気捕集装置を配置し、所定時間大気を吸引採取した。なお、この装置の吸引口の高さは地上1.5mとなる。
?ミニポンプ
捕集カラムを下向きにし、吸引口は地上0.2mの高さに固定し、ミニポンプで所定時間大気を採取した。吸引量は乾式ガスメーターを用いて測定した。
上記装置により採取された捕集カラムは、直ちに両端を密栓し冷却されたクーラーボックスに保管し分析機関へ送付し、ガスクロマトグラフにより調査対象農薬を分析した。
(2)土壌中濃度調査
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、C の近辺に3 地点A、B、C を設定した。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布直後)、散布1 日後、2 日後、5 日後、7 日後及び14日後の所定の時間に行った。
3)採取方法
ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成20 年3 月改正環境省水・大気環境局土壌環境課)に準じ、区域内より深さ5cm で5 点混合方式にて土壌を採取し、混合したものを分析試料とした。
(3)葉中濃度調査(葉への付着量)
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、C周辺に3地点A、B、Cを設定した。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布直後)、散布1 日後、2 日後、5 日後、7 日後及び14日後の所定の時間に行った。
3)試料採取
気中濃度調査の調査地点A、B、C周辺の散布した樹木から、高さ70cm程度にある葉を20g程度採取し、表面積及び重量を測定した後、混合したものを分析した。
(4)落下量調査
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、Cの近辺に3地点A、B、Cを設定した。
2)調査期間
散布当日(散布中)において行った。
3)定量調査
各調査地点に直径9cm のろ紙(ADVANTEC FILTER PAPER No.5A)2 枚を取り付けた調査板を設置した。調査板の高さは地上より1.5mとし、支柱等を利用して水平に設置した。
ろ紙は各調査時間に30 分間設置し回収した。2 枚のろ紙の表側が重なるように折りチャック付きのポリ袋に入れ回収した。試料は冷却されたクーラーボックスに保管し分析機関へ送付し、ガスクロマトグラフにより調査対象農薬を分析した。
なお、同一調査地点における、ろ紙2枚を合わせて1試料とし分析試料とした。
(5)気象観測
調査期間中の温度、降雨量及び日照時間を調査する(1時間間隔)。また、気中濃度測定時には温度、湿度、風向及び風速(平均及び最大)を10 分おきに測定した。
(6)樹木状況等
平成18年度及び平成19年度の調査結果から、散布区域の樹木の密集度合いや樹幹の大きさや枝ぶり等による「うっぺい度合い」、散布方法(散布方向、使用ノズル・噴霧形状等)の違い及び散布時の風向・風速、これらが飛散状況等の結果に影響を及ぼすことから、散布区域の樹木の樹種・樹高等の調査を行った。
(7)目標とする定量下限値
いずれの農薬についても、気中濃度で0.01μg/m3、土壌中濃度で0.01μg/g 及び葉中濃度(葉への付着量)で0.0002μg/cm2 を目標値とした。
[調査結果]
1.農薬分析法の概要
(1)分析農薬及び物理化学的性状
フェニトロチオン(MEP):O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate
トリクロルホン(DEP):dimethyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate
ジクロルボス(DDVP):2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate
エトフェンプロックス:2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
イソキサチオン:O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-yl phosphorothioate
2.調査地点の概況
散布区域は、南西側から北東側に高くなっていく傾斜地であり、散布区域内に分散させて調査地点A、B、Cを設置した(図1、写真1及び写真2)。
3.散布区域の樹木状況
散布区域は自然の雑木林および一部植栽の樹木であり、その状況は表1 及び図1 に示し
たとおりであった(写真3)。下層土壌の土質は褐色森林土壌でシルト質壌土であった。
散布区域の樹種は高木のカラマツ(10〜15m)、中木のコナラ(7〜8m)、ニセアカシア
(7m)、クリ(7m)、ソメイヨシノ(6〜7m)、低木のガマズミ(3m)であった。確認し
た小潅木はマルバハギ(1m)、ヤマザクラ(幼木)などであった。
4.薬剤散布状況
散布作業は、散布区域の北西側にあるクリの木付近から開始し、散布区域脇の道路を
バックする形で移動しながら散布を行い、続けて南西側にあるクリとコナラの木の間を
散布区域北側の地点C 付近まで入って、同じようにバックする形で移動しながら散布を
行った。次に散布区域の南側にあるカラマツおよびクリ付近から北側にあるコナラ方向
に移動しながら散布が行われた。散布時間は7 時より7 時10 分までの10 分間であった
(写真3 及び写真4)。
散布区域の面積はおよそ1000 ?であり、散布量は希釈液で400 ?であった。区域内の
高木および中木数はおよそ40 本であったことから、散布区域に均一に散布されたと考え
ると樹木当りでは10 ?/本であった。
5.気象概況
調査場所は標高800mの高原台地に位置し、夏季においても平野部の気温よりは低い気
象状況であった。
主に散布区域の南西地点において行い、その気象概況を表2 に示した。また、調査期
間中の日射量、日照時間及び雨量を表3 に示した。
(1)天候、温度及び湿度
8 月11 日(散布前日)から8 月26 日(散布14 日後)の調査期間中の調査時間帯に
おける天候は概ね晴れ、温度は22〜30℃、湿度は52〜89%であった。
(2)風向・風速
調査期間中の気中濃度調査実施時(散布当日及び散布1 日後)の風向は、南東から
南西であり、斜面となっている散布区域内を南西側から北東側に風が抜ける形となっ
た。
散布中(7:00〜7:30)、 散布直後(7:30〜8:00)、1 時間後(8:30〜9:00)、3 時間後
(10:30〜11:30)及び6 時間後(13:30〜14:30)の風向は主に南西〜南東、平均風速は0.4
〜1.9m/s であった。散布1 日後から散布14 日後の風向は主に南東または北東、平均
風速は0.0〜2.9m/s であった。
(3)日射量及び雨量
調査期間中の天候は概ね晴天であったため、日射量は高い状況が続いていた。1 日
後の夕方及び夜間(計2.2mm)、2 日後の夕方(計0.2mm)、3 日後の早朝(計0.2mm)、
4 日後の昼間及び夜間(計2.2mm)、7 日後の昼間から夕方(計5.0mm)、12 日後の朝
から昼間及び夜間(計5.2mm)、13 日後の朝(計0.4mm)に降雨があった(表3)。た
だし、調査時間帯においての降雨はなかった。
6.気中濃度調査
(1)大気の捕集状況
調査状況(捕集時刻と吸引量等)を表4 に示した。
(2)気中濃度
各調査地点における各調査農薬の気中濃度の結果を表5 及び図2 に示した。
1)フェニトロチオン(MEP)
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.90〜3.58μg/m3)、散布直後(2.35〜4.63μg/m3)、1 時間後(2.21〜5.08
μg/m3)及び3 時間後(0.93〜3.61μg/m3)の気中濃度はほぼ同程度であったが、6
時間後(0.63〜1.36μg/m3)から徐々に減少し、散布1 日後(0.06〜0.28μg/m3)で
はおよそ1/10〜1/30 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
2)トリクロルホン(DEP)
気中濃度は、散布1 日後の地点C の高さ1.5mで検出限界未満であったことを除き、
散布中から散布1 日後の調査において検出された。
散布中(1.9〜5.5μg/m3)、散布直後(4.0〜12μg/m3)、1 時間後(2.2〜4.6μg/m3)
及び3 時間後(1.8〜3.6μg/m3)の気中濃度はほぼ同程度であったが、6 時間後(0.7
〜3.2μg/m3)から徐々に減少し、散布1 日後(<0.1〜0.3μg/m3)ではおよそ1/10〜
1/60 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
3)ジクロルボス(DDVP)
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.71〜4.30μg/m3)及び散布直後(1.35〜2.85μg/m3)の気中濃度はほぼ
同程度であったが、1 時間後(0.61〜1.30μg/m3)から徐々に減少し、3 時間後(0.25
〜1.02μg/m3)には1/4〜1/7、6 時間後(0.03〜0.21μg/m3)には1/8〜1/108、散布 1
日後(0.02〜0.04μg/m3)ではおよそ1/70〜1/160 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
4)エトフェンプロックス
気中濃度は、散布中(0.03〜0.13μg/m3)、6 時間後(0.03μg/m3)及び散布1 日後
(0.02μg/m3)に検出された以外すべて検出されなかった。
高さ別の気中濃度は、検出された濃度が低いため差が判然としなかった。
5)イソキサチオン
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.24〜0.97μg/m3)、散布直後(0.32〜0.75μg/m3)、1 時間後(0.42〜1.35
μg/m3)、3 時間後(0.24〜1.19μg/m3)及び6 時間後(0.07〜0.96μg/m3)の気中濃
度はほぼ同程度であったが、散布1 日後(0.05〜0.29μg/m3)ではおよそ1/4〜1/10
に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
7.土壌中濃度調査
各調査地点における各調査農薬の土壌中濃度の結果を表6 及び図3 に示した。
(1)フェニトロチオン(MEP)
土壌中の残留濃度は、散布5 日後までほとんど減少は見られなかった。散布14 日では1/2 程度まで減少した。
(2)トリクロルホン(DEP)
土壌中の残留濃度は、すべて検出限界値未満であった。
(3)ジクロルボス(DDVP)
土壌中の残留濃度は、散布5 日後では減少は見られなかった。散布7 日後で1/2、散布14 日後では1/10 程度まで減少した。
(4)エトフェンプロックス
土壌中の残留濃度は、散布14 日後でもほとんど減少は見られなかった。
(5)イソキサチオン
土壌中の残留濃度は、散布14 日後でもほとんど減少は見られなかった。
8.葉中濃度調査(葉への付着量)
各調査地点における各調査農薬の濃度、葉の分析重量及び表面積(片面)、それらから算出した単位面積当たりの換算付着量を表7 及び図4 に示した。
(1)フェニトロチオン(MEP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/4、散布2 日後に1/7、散布7日後に1/30、散布14 日後には1/80 に減少した。
(2)トリクロルホン(DEP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/4、散布2 日後に1/7、散布7日後に1/20 に減少し、散布14 日後では1/20 であった。
(3)ジクロルボス(DDVP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/6、散布2 日後に1/13、散布5日後に1/50 に減少し、散布14 日後でも1/50 であった。
(4)エトフェンプロックス
葉への付着量は、散布直後、散布1 日後及び散布2 日後ではほぼ同程度であり、散布5 日後にわずかに減少が見られたが、その後は減少せず散布14 日後でも同程度であった。
(5)イソキサチオン
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後にわずかに減少し、散布2 日後及び散布5 日後には1/2 と減少が見られた。その後は散布7 日後及び散布14 日後に1/3程度に減少した。
9.落下量調査
各調査地点における各調査農薬の散布中の落下量の結果を表8 示した。
[まとめ]
1.気中濃度調査
表5 に示した各調査農薬の気中濃度から高さ0.2m及び高さ1.5mの平均値を求め表
9 及び図5 に示した。
フェニトロチオン及びトリクロルホンは、検出された濃度に違いは見られたが、散
布中または散布直後に最高濃度を示し、その後減少する傾向が見られた。これらの農
薬については、蒸気圧は同程度であるが、水に対する溶解性が違うために検出される
濃度に違いが現れたのではないかと考えられる。
ジクロルボスは、散布中及び散布直後に最高濃度を示し、その後減少する傾向が見
られた。トリクロルホンの代謝物であるため、検出された濃度が低くなったのではと
推察される。
イソキサチオンは、散布中から6 時間後までは同じ濃度が続き、散布1 日後に減少
する傾向が見られた。
エトフェンプロックスは、散布中のみ検出された。6 時間後及び散布1 日後に検出
されたことは、土壌などの舞い上がりを捕捉したことによると考えられる。
高さ別の気中濃度は、散布直後よりほとんど検出されなかったエトフェンプロック
スを除き、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。6 時間後では高さ1.5m
が高さ0.2mより高い傾向が見られたのは、土壌及び周辺樹木に付着している農薬の
揮散による影響と考えられる。
今回の調査結果から成分投下量が同じであったフェニトロチオン及びイソキサチオ
ン、それより少ないトリクロルホンの気中濃度には明らかに違いが見られた。このこ
とは、蒸気圧等の物理化学的性状が影響をあたえているのではないかと考えられる。
また、斎藤ら5)は農業の農薬散布現場において、散布中から散布後3 時間までの落
下量を30 分ずつ連続で調査し、噴霧粒子は散布中に約90%落下していると報告して
いる。このことから、散布中の気中濃度は散布された噴霧粒子(ミスト)を捕らえて
いると考えられる。
2.土壌中濃度調査
表6 に示した各調査農薬の土壌中濃度から平均値を求め、表10 及び図6 に示した。フェニトロチオン、エトフェンプロックス及びイソキサチオンは、検出された濃度に違いは見られたが、減少の傾向は同じであったと思われる。
このことは、これら農薬の土壌中半減期がほぼ同じであることによるかは定かではない。イソキサチオンの濃度が散布14 日後に高くなったことは、フェニトロチオン及びエトフェンプロックスの地点においても見られていることから、土壌採取場所のバラツキ及び散布12 日後及び13 日後における降雨の影響があったのではないかと考えられる。
トリクロルホンは、すべて検出限界値未満であった。これは、速やかに分解するという土壌半減期のため減少したのではないかと考えられる。
今回の調査結果から散布直後の濃度と比較して1/2 の濃度となったのは、フェニトロチオンで散布14 日後及びジクロルボスで散布7 日後であり、エトフェンプロックス及びイソキサチオンでは散布14 日後以降であると推察される。
3.葉中濃度調査(葉への付着量)
表7 に示した各調査農薬の葉への付着量から平均値を求め、表11 及び図7 に示した。フェニトロチオン、トリクロルホン及びジクロルボスは、検出された濃度に違いは見られたが、散布1 日後には大きく減少し、その後も同じように減少する傾向が見ら
れた。
エトフェンプロックスは、ほとんど減少が見られなかったが、その要因については定かではない。
イソキサチオンは、散布7 日後より14 日後に少し高くなったが、落下量のバラツキ及び葉採取場所の違いによるものと考えられる。
参考文献
1)農薬ハンドブック2005 年版(改訂新版)社団法人日本植物防疫協会
2)環境省環境保健部環境リスク評価室:化学物質の環境リスク評価第2 巻(2003 年3 月)第1編 ?.(?)[9]イソキサチオン、[28]ジクロルボス、[53]フェニトロチオン
3)国立医薬品食品衛生研究所:トリクロルホン、環境保健クライテリア(EnvironmentalHealth Criteria)132 日本語抄訳(原著162 頁、1992 年発行)
4)トレボン乳剤、製品安全データシート(MSDS):サンケイ化学株式会社(改訂2007年4 月26 日)
5)斎藤ら:地上防除及び無人ヘリ防除における有機リン系農薬の気中濃度・落下量、第28 回農薬製剤・施用法研究会、技術研究発表T5、2008(平成20 年)
http://www.env.go.jp/water/report/h21-02/full.pdf
結果報告書
平成21年3月
社団法人 農林水産航空協会
要 約
市街地における街路樹や公園の花木類等管理のために散布される農薬の飛散リスクの影響を評価・管理する手法を確立するため、平成18年度及び平成19年度モニタリング調査結果を踏まえて、農薬飛散範囲調査、農薬検出期間調査および除草剤散布後気中濃度等調査を実施した。
農薬飛散範囲調査は、立木1本に対して水を散布し、樹高、樹形、風の条件、散布方向の違いについて、周辺への飛散状況を調査した。調査は、樹の中心から8方位に、樹高の条件により10mまたは15mまでの距離で調査地点に感水調査紙を設置して行った。感水調査紙は、画像処理ソフトウエアにより、被覆面積率および付着液量の推定を行った。
飛散状況は、樹が高いほど、また、枝葉が繁茂しているほど多かった。樹高4m 程度の樹に対しては、手の届く範囲で近距離からの散布ができることから、飛散が少なかったものと考えられる。枝葉が繁茂した樹形は散布水量が多くなることから、その分飛散のリスクが増えるものと考えられた。
しかし、風の強い条件では、散布方法より風の影響の方が強いと考えられ、平均風速が2m/s 程度であっても、風下側では15m 先へも飛散する可能性が十分にあると考えられた。
付着液量の推定は、1 樹当たりの散布水量と、8 方位の距離別にブロック分けした場所においての付着液量の比率の風下側最遠調査地点での最大値は、平方メートルあたり0.03%であった。
農薬検出期間調査は、公園等での使用実績のあるフェニトロチオン、トリクロルホン、エトフェンプロックス及びイソキサチオンの4 剤を混用して、調査対象の樹木林に散布し、気中濃度濃度調査、土壌中濃度調査及び葉への付着量調査を実施した。気中濃度は、調査農薬により検出された値に違いは見られたが、それら農薬の蒸気圧等の物理化学的性状が影響をあたえて
いのではないかと考えられた。
土壌中濃度で散布直後の濃度と比較して1/2 の濃度となったのは、フェニトロチオンで散布14 日後、ジクロルボスで散布7 日後、エトフェンプロックス及びイソキサチオンでは散布14 日後以降であると推察された。葉への付着量では、フェニトロチオン、トリクロルホン及びジクロルボスは同じようなに減少する傾向が見られ、散布14日後で1/80、1/20 及び1/50 まで減少し、当初の濃度が低かったイソキサチオンとエトフェンプロックスは散布14 日後で1/3 及び3/5 と減少は少なかった。
除草剤散布後気中濃度等調査は、使用実績のあるグリホサートの散布後に気中濃度調査、土壌中濃度調査及び葉中濃度調査を実施した。気中濃度では、散布区域内の高さ0.2mの地点で散布当日の13 時のみに検出されたことは、一度散布された農薬が蒸散した結果と考えるには、最も値が高いはずの散布直後に検出されていないことと、その検出濃度などから、植物体を経由したカラムの汚染による可能性が高いのではないかと考えられる。土壌中濃度は、散布直後と散布30 日後の濃度に違いは見られなかった。葉中濃度は、散布直後に高い濃度が検出され、散布1 日後に大きく減少した。
Summary
Based on the results of serial monitoring studies conducted in 2006 and 2007,dispersion range, duration of detection period, and concentrations in air of heirbicide after spraying were
investigated to establish the methods for evaluation and management of dispersal risks of
agrochemicals applied for maintenance of greenery on roadside tree or in parks.
For the purpose of estimation of dispersion range, a tree was sprayed with water and profiled
for the water dispersion toward surrounding area. The results were analyzed in terms of height
and shape of trees,wind condition,difference of spraying orientation. Sheets of water-sensitive
paper were placed 10 to 15 m from the center of a tree depending on height of trees in eight
azimuth directions. Ratio of the covered area and amount of attached solution were estimated
by measuring the wet area on the water sensitive papers using image analysis software.
The extent of dispersion was increased in accordance with the height of trees and the density
of branches and foliages. Trees as low as 4 m in height showed less dispersion probably due
to the spraying from closer distance within the reach of equipment. The elevated amount of
sprayed agrochemicals required for trees with dense branches and foliages seemed to give rise
to risk of dispersion. However, wind effect prevailed over spraying method especially under
strong wind condition. The downwind dispersion as far as 15 m can be observed even at the
wind speed of 2 m/s.
On spraying a tree, a ratio of the amount of attached solution versus that of sprayed solution
was calculated at each sampling point in eight azimuth directions differing in distance from
the sprayed site. The maximum ratio at the furthest downwind sampling point was estimated
to 0.03% per square meter.
Four agrochemicals with past application records in parks such as fenitrothion, trichlorphon,
etofenprox,and isoxathion were selected and adopted for determining the duration of detection
period. The combined agrochemicals were sprayed over trees and concentration in air,soil
concentration,and deposit on foliage were measured. The difference in concentration in air of
the individual agrochemicals could be ascribed to physicochemical characters such as vapor
pressure. Half-lives of fenitrothion, etofenprox, and isoxathion in soil were estimated to 14
days, 7 days, and 14 days, respectively. Fenitrothion, trichlorphon, and dichlorvos on leaves
showed the same decaying tendency, and the amount of the each substance decreased to
1/80-fold, 1/20-fold, and 1/50-fold of the primary amounts after 14 days from application.
Isoxathion and etofenprox with less primary attachment to leaves decreased to 1/3 and 3/5 of
the primary concentration after 14 days from application.
Glyphosate which has the solid past application records was adopted for the study of
post-application monitoring of herbicides. After spraying, glyphosate concentrations in the air,
in soil, and in leaves were monitored. The sole detection of concentrations in air was observed
at 13:00 on the day of spraying. The concentrations in air were not detected immediately after
spraying and the concentration of the detected glyphosate was too low. Therefore the
detection of glyphosate was most likely due to contamination of the trapping column in
contact with sprayed plants, rather than the evaporation of glyphosate. There was no
significant difference between glyphosate concentration in soil of immediate aftermath of
spraying and that of 30 days after spraying. In leaves, large amount of glyphosate was
detected immediately after spraying, while significant decrease of glyphosate was recognized
a day after spraying.
はじめに
この報告書は、環境省大気局農薬環境管理課から社団法人農林水産航空協会に委託された「平成20年度農薬飛散リスク評価手法確立調査(モニタリング調査業務)」の実施成果をとりまとめたものである。
本調査は、市街地における街路樹や公園の花木類等管理のために散布される農薬の飛散リスクの影響を評価・管理する手法を確立するに当たって、公園等を利用する一般市民及び公園等周辺住民の健康を保護する観点から、公園内及び周辺における農薬の気中濃度及び飛散等による曝露実態を把握するために実施した平成18年度及び平成19年度モニタリング調査結果を踏まえて、農薬飛散範囲調査、農薬検出期間調査および除草剤散布後気中濃度等調査を実施した。
平成21年3月
東京都千代田区平河町2−7−1 塩崎ビル3階
社団法人 農林水産航空協会 会 長 関 口 洋 一
目 次
?.農薬飛散範囲調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
?.農薬検出期間調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
?.除草剤散布後気中濃度等調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
要 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114
平成20 年度農薬飛散リスク評価手法確立調査(モニタリング調査業務)
[目的]
環境省では平成17 年度から農薬飛散リスク評価手法確立調査を開始し、街路樹や公園等の市街地において使用される農薬の飛散リスクの評価・管理手法について検討しているところであり、これまでに、国内外における農薬飛散リスクの評価・管理手法に関する文献調査、自治体での防除実態を把握するためのアンケート調査(平成17 年度)、実際の農薬散布場
面におけるモニタリング調査(平成18・19 年度)と、蒸気圧等の要因別の影響調査を含む基礎調査(平成19 年度)を実施し、農薬の飛散による暴露実態を把握するための基礎資料を得た。
平成20 年度の本業務では平成19 年度までの結果を踏まえた上でモニタリング調査を実施し、農薬の飛散による暴露実態を把握するうえでの基礎資料を得る。
[調査項目]
?.農薬飛散範囲調査
樹木等に対して通常用いられる農薬散布用器具を用いて水を散布し、感水紙を用いて、周囲への到達落下範囲を調査する。
?.農薬検出期間調査
農薬散布にあたり最も高濃度が検出される地点において十分減衰するまでの期間が立ち入り禁止期間となると考える。
したがって、高木が複数存在する区域を設定して調査地点を置き、農薬散布後の気中濃度低減の調査を行うとともに、当該地点における葉及び土壌での残留量を計測する。
?.除草剤散布後気中濃度等調査
雑草等が生えている場所に除草剤(グリホサート)を散布した場合、その周囲への飛散の程度、気中濃度、及び散布地点の土壌の残留について調査を行うこととする。
?.農薬飛散範囲調査
[調査内容]
1.調査実施場所
(社)農林水産航空協会 農林航空技術センター敷地内(長野県小諸市)
2.調査方法
(1)調査樹
樹種:オウシュウトウヒ(ドイツトウヒ)
樹高:中木4.2m、高木?(疎密)8.3m、高木?(繁茂)8.7m の3 形態(写真1)。
(2)調査の組み合わせ
樹高・樹形:中木、高木?(枝葉疎密)と高木?(枝葉繁茂)の比較。
ノズル:慣行と飛散低減の比較。
風速:平穏〜軽風(0〜1.5m/s)と軽風(1.6〜3.3m/s)の比較。
散布方向:高木?において、下からの吹上げと横方向からの散布の比較。
各調査は反復を2 回とした。
(3)感水紙の設置
調査対象となる樹木を中心に、8 方向に、樹木から3m、5m、10m の距離に地上高50 ?の高さに感水紙を水平に設置し、散布した水の飛散状況を調査した。なお、軽風条件下においては15m 地点にも設置した。
感水紙は、WATER SENSITEVE PAPER(スプレーイングシステム株式会社製)を使用した。
(4)感水紙の解析方法
感水紙は、散布開始前から散布終了後5 分まで設置し、変色量を画像解析ソフト、ImageJ(バイオアーツ株式会社製)を用い、被覆面積率を測定した。
感水紙の一部については、画像解析ソフト、まいA のーど(ノズルネットワーク株式会社製)により、付着液量の推定を行った。
なお、感水紙の画像の解像度は、1 ドット約64 ?(約400dpi)であった。
(5)散布方法
動力噴霧機:セット動噴MS253(株式会社丸山製作所製)
散布ノズル
慣行ノズル:アルミズームα900 型(ヤマホ工業株式会社製)噴霧粒径95〜360μm(写真2)
飛散低減ノズル:キリナシズーム900 型(ヤマホ工業株式会社製)
噴霧粒径380〜710μm(写真2)
*圧力1.5MPa での平均粒径(データはヤマホ工業株式会社提供)圧力:全て1.5MPa
(6)風向風速の計測
風向風速は、デジタルハンド風向風速計26D-B?(株式会社太田計器製作所製)で測定した。
[調査結果]
1.散布状況
調査に使用したノズルは、2 種とも、手元のグリップを回転させることにより遠距離噴霧(狭角)と近距離噴霧(広角)の調節ができるため、高木?、?の吹き上げ散布は、遠距離噴霧で、中木および高木?の横方向からの散布は近距離噴霧で行った。
中木は、手の届く範囲で概ね横方向からの散布となった。
高木?の横方向からの散布は、長さ4m の直管にノズルを取り付け行った。
散布水量は、予め練習散布で枝葉が十分に濡れ水が滴り落ちる程度を十分量と定め、噴霧時間を合わせることにより散布量が一定となるようにした。
散布は、条件を統一にするため、風向にかかわらずに散布者が樹の周囲を移動し、全周方向から行った。
2.飛散状況
飛散状況調査は、表2 の組み合わせで行い、その結果を表3 及び図1〜図16 に示した。
全体の飛散程度を検討するため、表3 より距離ごとに8 方位の感水紙における飛散の被
覆面積率(以下「被覆面積率」という)の合計値と飛散が確認された感水紙数を取りまと
め、表4 に示した。
樹高の影響については風の条件ごとに比較し図17 に、樹形の影響については高木につい
て風の条件を比較し図18 に、ノズルの影響、散布方向の影響については風の条件と樹高・
樹形を比較し図19 に、風速の影響については樹高・樹形と散布方法を比較し図20 に、風
向の影響については地点ごとの被覆面積率を比較し図1〜16 に示した。
(3)ノズルの影響について
中木では、平穏〜軽風の条件で飛散低減ノズルの被覆面積率の値が5m、10m で低かった。
軽風では飛散低減ノズルの値が3m、5m で低かった。
高木では、軽風で散布方法が吹上の条件では、3m 地点では慣行ノズルの値が低かったが、
10m、15m 地点では、低減ノズルの値が低かった。それ以外の条件では明らかな飛散程度の差
は認められなかった。
(4)散布方向の影響について(図19)
平穏〜軽風で低減ノズルの条件では、横方向からの散布が吹上での散布に比べて値が低か
った。軽風条件では、散布方向による明らかな差は認められなかった。
横方向からの散布はより上方へ到達する水量が、吹上での散布に比べ少ないと考えられる
ことから、飛散が低減されるものと考えられるが、風が強い場合は、風の影響の方が大きい
ものと考えられる。
図19 ノズル・散布方向の影響
(5)風速の影響について
中木では、3m、5m、10m では軽風に比べ平穏〜軽風の被覆面積率の値が明らかに低く、10m
以上で大きく値が減少した。
高木では、平穏〜軽風では3m での値が高く、5m、10m で大きく値が減少している。軽風で
は、3m と5m の値に大きな差が無く、飛散が認められた。
高木?、?ともに吹上散布では、平穏〜軽風の条件では風下方向に限らず、全周に飛散す
る傾向が認められた。軽風条件では、風上では3m の地点でも飛散はほとんど認められなかっ
た。目視では、吹き上げ散布はノズル先端より5m 以上吹き上げており、その結果より高い位
置で広範囲に飛散してしまうため、特に風の弱い状況においては、散布位置の周辺に多く飛
散することが観察された。風が強い場合は、ほとんどが風により風下方向に流されていた。
図20 風の影響
(6)風向の影響について
風下方向では、調査を行った最遠地点の10m(平穏〜軽風)、15m(軽風)まで飛散が認められ
た(図1〜16)。
高木?、?ともに吹上散布では、平穏〜軽風の条件では風下方向に限らず、全周に飛散す
る傾向が認められた(図3〜6)。軽風条件では、風上では3m の地点でも飛散はほとんど認め
られなかった(図11〜14)。
3.飛散量の推定
(1)感水紙の付着液量の推定
画像解析ソフト「まいA のーど」により、感水紙に付着した液量の推定を行った結果を
表5 に示し、被覆面積率と付着液量の関係を図21 に示し、得られた推定式
y=0.0003x2+0.0165x により換算した付着液量を表6 に示した。
また、感水紙の飛散状況(水滴が付着した部分が青色に変色する)の一例を写真5 に示した。
なお、本解析方法では、感水紙上の液滴痕跡が、多く重なったり、つながったりしてい
る状態では、精度が落ちるため、被覆面積率が概ね25%以下のサンプルについてのみ解析
を行った。表6 においても、被覆面積率が25%以上のものについては、換算から除外した。
表5 被覆面積率と付着液量の推定値
(2)総散布量に対する付着液量の割合
被覆面積率から換算した感水紙の付着液量をもとに、図22 に示すように方位ごと距離別
にブロック分けし総散布液量(1 樹当たりの散布水量)に対するブロック全体の面積で換算
した付着液量比率を算出し表6 に示した。
算出にあたっては、3m 地点と5m 地点での付着量の平均値を3m から5m までの範囲の付
着量の平均値、5m 地点と10m 地点での付着量の平均値を5m から10m までの範囲の付着量
の平均値、10m 地点と15m 地点での付着量の平均値を10m から15m までの範囲の付着量の
平均値として換算した。平穏〜軽風の10m から15m までの範囲の付着量の平均値は、10m
地点の1/2 の値とし、同じく軽風の15m から20m までの範囲の付着量の平均値は、15m 地
点の1/2 の値として換算した。
平穏から軽風条件では、総散布量に対する付着液量の割合の最大値は、高木繁茂、横方
向、通常ノズル散布の風下側10m から15m ブロックで0.65%で、平方メートルあたりでは、
0.03%であった。また軽風条件の最大値は、高木疎密、吹上、通常ノズル散布の風下側15m
から20m ブロックで0.93%で、平方メートルあたりでは、0.03%であった。
図22 総散布量に対する付着液量の割合算出における方位・距離別ブロック
[まとめ]
1.飛散状況調査
今回の調査は、立木1 本に対しての散布において、樹高、樹形、風の条件、散布方向の違いについて、周辺への飛散状況を調査したものである。
樹高4m 程度の中木に対しては、手の届く範囲で近距離からの散布ができるのに対し、8m程度の高木は、高いところまで勢い良く吹上る必要があり、その分飛散のリスクが増えるものと考える。
このことは高木で、吹上による散布よりも横方向から散布する方法の方が、飛散程度が少なかったことからも言える。しかし、風の強い条件では、散布方法より風の影響の方が強いと考えられた。
また、繁茂した樹形の方が、疎密のものより飛散程度が多かったことから、散布水量が多いことによると考えられる。
以上のことから、散布時の飛散リスクには、樹高及び風の条件が最も重要であり、次に散布量の影響が見られる。なお、平均風速が2m/s 程度であっても、風下側では15m 先へも飛散する可能性が十分にあると考えられる。
2.飛散量の推定
感水紙の画像解析による付着液量の推定調査については、感水紙上の痕跡が粒子状であり、重なりが少ないほど精度が良いと考えられる。このため本調査においては、被覆面積率が25%以下のサンプルについてのみ解析を行った。
本調査において、被覆面積率と画像処理ソフトにより測定した付着液量の間には、一定の相関が認められ、推定式により、被覆面積率から感水紙の付着液量の推定が可能であると考えられた。1 樹当たりの散布水量と、8 方位の距離別にブロック分けした場所においての付着液量の比率の風下側最遠調査地点での最大値は、平方メートルあたり0.03%であった。
ただし、本結果は、本調査における画像解析に係る機器、ソフトウエアの組み合わせで得られたものであり、他の組み合わせについては別に検討が必要である。
?.農薬検出期間調査
[調査内容]
1.調査場所
(社)農林水産航空協会 農林航空技術センター敷地内(長野県小諸市)
2.調査実施期間
平成20 年8 月11 日(散布前日)〜8 月26 日(散布14 日後)
3.散布概要
散布面積:およそ1,000 ?
散布農薬の概要を下表に示した。
散布諸元
ポンプ:動力噴霧器 MS903(株式会社丸山製作所製)
エンジン:ブリッグス20HP(ブリッグス&ストラットンジャパン製)
使用ノズル: 松喰虫ノズル(株式会社永田製作所製)
噴霧形状:高木樹が多いため直射噴霧とし、低木へは圧を弱めやや広角に散布
圧力:30kgf/c ?(3.0MPa)
散布量(4 農薬を混用):400 ?/1000 ?(葉から滴り落ちる程度)
4.調査農薬成分
フェニトロチオン
トリクロルホン
ジクロルボス(トリクロルホンの代謝物)
エトフェンプロックス
イソキサチオン
5.調査項目
(1)気中濃度調査
調査は、「航空防除農薬環境影響評価検討会報告書(平成9 年12 月、環境庁水質保全局)の測定方法に準じた手法を用いて行った。
1)調査地点
3 地点A、B、C を設定し、各地点で1.5mの高さ及び0.2mの高さとした。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布中、散布直後、散布1 時間後、3 時間後及び6 時間後)及び散布1 日後の所定の時間に行った。
3)捕集時間と捕集量
捕集時間は毎分3 ?の吸入速度で散布前は1 時間とし、散布中及び散布直後の調査時は30 分間、それ以降はすべて1 時間とした。また、散布中の調査は対象樹木への散布が開始された時から30 分間とし、散布直後の調査は「散布中調査」の後
に引き続き30 分間として行った。
大気の捕集は、高度1.5mでは自動大気捕集装置及び高度0.2mではミニポンプとガスメーターを組み合わせた捕集装置を使用した。
4)捕集装置
?自動大気捕集装置 AS-5000 型(株式会社メテク)
?ミニポンプ MP-500Σ(柴田科学株式会社)
乾式ガスメーター:DC-1C(株式会社シナガワ)
5)捕集カラム
?捕集剤 テナックスTA(60/80 mesh) 0.5g充填
?カラム 自動大気捕集装置:内径10mm、全長190mm(捕集剤充填部140mm)ガラス管に捕集剤を充填した。
ミニポンプ:内径12.7mm のポリプロピレンのチューブに捕集剤を充填した。
なお、ミニポンプに使用したカラムは、太陽光などによる影響を避けるため捕集
剤を充填した部分をアルミ箔で覆った。
6)捕集方法
?自動大気捕集装置
各調査地点に捕集カラムをセットした自動大気捕集装置を配置し、所定時間大気を吸引採取した。なお、この装置の吸引口の高さは地上1.5mとなる。
?ミニポンプ
捕集カラムを下向きにし、吸引口は地上0.2mの高さに固定し、ミニポンプで所定時間大気を採取した。吸引量は乾式ガスメーターを用いて測定した。
上記装置により採取された捕集カラムは、直ちに両端を密栓し冷却されたクーラーボックスに保管し分析機関へ送付し、ガスクロマトグラフにより調査対象農薬を分析した。
(2)土壌中濃度調査
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、C の近辺に3 地点A、B、C を設定した。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布直後)、散布1 日後、2 日後、5 日後、7 日後及び14日後の所定の時間に行った。
3)採取方法
ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成20 年3 月改正環境省水・大気環境局土壌環境課)に準じ、区域内より深さ5cm で5 点混合方式にて土壌を採取し、混合したものを分析試料とした。
(3)葉中濃度調査(葉への付着量)
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、C周辺に3地点A、B、Cを設定した。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布直後)、散布1 日後、2 日後、5 日後、7 日後及び14日後の所定の時間に行った。
3)試料採取
気中濃度調査の調査地点A、B、C周辺の散布した樹木から、高さ70cm程度にある葉を20g程度採取し、表面積及び重量を測定した後、混合したものを分析した。
(4)落下量調査
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、Cの近辺に3地点A、B、Cを設定した。
2)調査期間
散布当日(散布中)において行った。
3)定量調査
各調査地点に直径9cm のろ紙(ADVANTEC FILTER PAPER No.5A)2 枚を取り付けた調査板を設置した。調査板の高さは地上より1.5mとし、支柱等を利用して水平に設置した。
ろ紙は各調査時間に30 分間設置し回収した。2 枚のろ紙の表側が重なるように折りチャック付きのポリ袋に入れ回収した。試料は冷却されたクーラーボックスに保管し分析機関へ送付し、ガスクロマトグラフにより調査対象農薬を分析した。
なお、同一調査地点における、ろ紙2枚を合わせて1試料とし分析試料とした。
(5)気象観測
調査期間中の温度、降雨量及び日照時間を調査する(1時間間隔)。また、気中濃度測定時には温度、湿度、風向及び風速(平均及び最大)を10 分おきに測定した。
(6)樹木状況等
平成18年度及び平成19年度の調査結果から、散布区域の樹木の密集度合いや樹幹の大きさや枝ぶり等による「うっぺい度合い」、散布方法(散布方向、使用ノズル・噴霧形状等)の違い及び散布時の風向・風速、これらが飛散状況等の結果に影響を及ぼすことから、散布区域の樹木の樹種・樹高等の調査を行った。
(7)目標とする定量下限値
いずれの農薬についても、気中濃度で0.01μg/m3、土壌中濃度で0.01μg/g 及び葉中濃度(葉への付着量)で0.0002μg/cm2 を目標値とした。
[調査結果]
1.農薬分析法の概要
(1)分析農薬及び物理化学的性状
フェニトロチオン(MEP):O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate
トリクロルホン(DEP):dimethyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate
ジクロルボス(DDVP):2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate
エトフェンプロックス:2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
イソキサチオン:O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-yl phosphorothioate
2.調査地点の概況
散布区域は、南西側から北東側に高くなっていく傾斜地であり、散布区域内に分散させて調査地点A、B、Cを設置した(図1、写真1及び写真2)。
3.散布区域の樹木状況
散布区域は自然の雑木林および一部植栽の樹木であり、その状況は表1 及び図1 に示し
たとおりであった(写真3)。下層土壌の土質は褐色森林土壌でシルト質壌土であった。
散布区域の樹種は高木のカラマツ(10〜15m)、中木のコナラ(7〜8m)、ニセアカシア
(7m)、クリ(7m)、ソメイヨシノ(6〜7m)、低木のガマズミ(3m)であった。確認し
た小潅木はマルバハギ(1m)、ヤマザクラ(幼木)などであった。
4.薬剤散布状況
散布作業は、散布区域の北西側にあるクリの木付近から開始し、散布区域脇の道路を
バックする形で移動しながら散布を行い、続けて南西側にあるクリとコナラの木の間を
散布区域北側の地点C 付近まで入って、同じようにバックする形で移動しながら散布を
行った。次に散布区域の南側にあるカラマツおよびクリ付近から北側にあるコナラ方向
に移動しながら散布が行われた。散布時間は7 時より7 時10 分までの10 分間であった
(写真3 及び写真4)。
散布区域の面積はおよそ1000 ?であり、散布量は希釈液で400 ?であった。区域内の
高木および中木数はおよそ40 本であったことから、散布区域に均一に散布されたと考え
ると樹木当りでは10 ?/本であった。
5.気象概況
調査場所は標高800mの高原台地に位置し、夏季においても平野部の気温よりは低い気
象状況であった。
主に散布区域の南西地点において行い、その気象概況を表2 に示した。また、調査期
間中の日射量、日照時間及び雨量を表3 に示した。
(1)天候、温度及び湿度
8 月11 日(散布前日)から8 月26 日(散布14 日後)の調査期間中の調査時間帯に
おける天候は概ね晴れ、温度は22〜30℃、湿度は52〜89%であった。
(2)風向・風速
調査期間中の気中濃度調査実施時(散布当日及び散布1 日後)の風向は、南東から
南西であり、斜面となっている散布区域内を南西側から北東側に風が抜ける形となっ
た。
散布中(7:00〜7:30)、 散布直後(7:30〜8:00)、1 時間後(8:30〜9:00)、3 時間後
(10:30〜11:30)及び6 時間後(13:30〜14:30)の風向は主に南西〜南東、平均風速は0.4
〜1.9m/s であった。散布1 日後から散布14 日後の風向は主に南東または北東、平均
風速は0.0〜2.9m/s であった。
(3)日射量及び雨量
調査期間中の天候は概ね晴天であったため、日射量は高い状況が続いていた。1 日
後の夕方及び夜間(計2.2mm)、2 日後の夕方(計0.2mm)、3 日後の早朝(計0.2mm)、
4 日後の昼間及び夜間(計2.2mm)、7 日後の昼間から夕方(計5.0mm)、12 日後の朝
から昼間及び夜間(計5.2mm)、13 日後の朝(計0.4mm)に降雨があった(表3)。た
だし、調査時間帯においての降雨はなかった。
6.気中濃度調査
(1)大気の捕集状況
調査状況(捕集時刻と吸引量等)を表4 に示した。
(2)気中濃度
各調査地点における各調査農薬の気中濃度の結果を表5 及び図2 に示した。
1)フェニトロチオン(MEP)
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.90〜3.58μg/m3)、散布直後(2.35〜4.63μg/m3)、1 時間後(2.21〜5.08
μg/m3)及び3 時間後(0.93〜3.61μg/m3)の気中濃度はほぼ同程度であったが、6
時間後(0.63〜1.36μg/m3)から徐々に減少し、散布1 日後(0.06〜0.28μg/m3)で
はおよそ1/10〜1/30 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
2)トリクロルホン(DEP)
気中濃度は、散布1 日後の地点C の高さ1.5mで検出限界未満であったことを除き、
散布中から散布1 日後の調査において検出された。
散布中(1.9〜5.5μg/m3)、散布直後(4.0〜12μg/m3)、1 時間後(2.2〜4.6μg/m3)
及び3 時間後(1.8〜3.6μg/m3)の気中濃度はほぼ同程度であったが、6 時間後(0.7
〜3.2μg/m3)から徐々に減少し、散布1 日後(<0.1〜0.3μg/m3)ではおよそ1/10〜
1/60 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
3)ジクロルボス(DDVP)
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.71〜4.30μg/m3)及び散布直後(1.35〜2.85μg/m3)の気中濃度はほぼ
同程度であったが、1 時間後(0.61〜1.30μg/m3)から徐々に減少し、3 時間後(0.25
〜1.02μg/m3)には1/4〜1/7、6 時間後(0.03〜0.21μg/m3)には1/8〜1/108、散布 1
日後(0.02〜0.04μg/m3)ではおよそ1/70〜1/160 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
4)エトフェンプロックス
気中濃度は、散布中(0.03〜0.13μg/m3)、6 時間後(0.03μg/m3)及び散布1 日後
(0.02μg/m3)に検出された以外すべて検出されなかった。
高さ別の気中濃度は、検出された濃度が低いため差が判然としなかった。
5)イソキサチオン
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.24〜0.97μg/m3)、散布直後(0.32〜0.75μg/m3)、1 時間後(0.42〜1.35
μg/m3)、3 時間後(0.24〜1.19μg/m3)及び6 時間後(0.07〜0.96μg/m3)の気中濃
度はほぼ同程度であったが、散布1 日後(0.05〜0.29μg/m3)ではおよそ1/4〜1/10
に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
7.土壌中濃度調査
各調査地点における各調査農薬の土壌中濃度の結果を表6 及び図3 に示した。
(1)フェニトロチオン(MEP)
土壌中の残留濃度は、散布5 日後までほとんど減少は見られなかった。散布14 日では1/2 程度まで減少した。
(2)トリクロルホン(DEP)
土壌中の残留濃度は、すべて検出限界値未満であった。
(3)ジクロルボス(DDVP)
土壌中の残留濃度は、散布5 日後では減少は見られなかった。散布7 日後で1/2、散布14 日後では1/10 程度まで減少した。
(4)エトフェンプロックス
土壌中の残留濃度は、散布14 日後でもほとんど減少は見られなかった。
(5)イソキサチオン
土壌中の残留濃度は、散布14 日後でもほとんど減少は見られなかった。
8.葉中濃度調査(葉への付着量)
各調査地点における各調査農薬の濃度、葉の分析重量及び表面積(片面)、それらから算出した単位面積当たりの換算付着量を表7 及び図4 に示した。
(1)フェニトロチオン(MEP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/4、散布2 日後に1/7、散布7日後に1/30、散布14 日後には1/80 に減少した。
(2)トリクロルホン(DEP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/4、散布2 日後に1/7、散布7日後に1/20 に減少し、散布14 日後では1/20 であった。
(3)ジクロルボス(DDVP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/6、散布2 日後に1/13、散布5日後に1/50 に減少し、散布14 日後でも1/50 であった。
(4)エトフェンプロックス
葉への付着量は、散布直後、散布1 日後及び散布2 日後ではほぼ同程度であり、散布5 日後にわずかに減少が見られたが、その後は減少せず散布14 日後でも同程度であった。
(5)イソキサチオン
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後にわずかに減少し、散布2 日後及び散布5 日後には1/2 と減少が見られた。その後は散布7 日後及び散布14 日後に1/3程度に減少した。
9.落下量調査
各調査地点における各調査農薬の散布中の落下量の結果を表8 示した。
[まとめ]
1.気中濃度調査
表5 に示した各調査農薬の気中濃度から高さ0.2m及び高さ1.5mの平均値を求め表
9 及び図5 に示した。
フェニトロチオン及びトリクロルホンは、検出された濃度に違いは見られたが、散
布中または散布直後に最高濃度を示し、その後減少する傾向が見られた。これらの農
薬については、蒸気圧は同程度であるが、水に対する溶解性が違うために検出される
濃度に違いが現れたのではないかと考えられる。
ジクロルボスは、散布中及び散布直後に最高濃度を示し、その後減少する傾向が見
られた。トリクロルホンの代謝物であるため、検出された濃度が低くなったのではと
推察される。
イソキサチオンは、散布中から6 時間後までは同じ濃度が続き、散布1 日後に減少
する傾向が見られた。
エトフェンプロックスは、散布中のみ検出された。6 時間後及び散布1 日後に検出
されたことは、土壌などの舞い上がりを捕捉したことによると考えられる。
高さ別の気中濃度は、散布直後よりほとんど検出されなかったエトフェンプロック
スを除き、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。6 時間後では高さ1.5m
が高さ0.2mより高い傾向が見られたのは、土壌及び周辺樹木に付着している農薬の
揮散による影響と考えられる。
今回の調査結果から成分投下量が同じであったフェニトロチオン及びイソキサチオ
ン、それより少ないトリクロルホンの気中濃度には明らかに違いが見られた。このこ
とは、蒸気圧等の物理化学的性状が影響をあたえているのではないかと考えられる。
また、斎藤ら5)は農業の農薬散布現場において、散布中から散布後3 時間までの落
下量を30 分ずつ連続で調査し、噴霧粒子は散布中に約90%落下していると報告して
いる。このことから、散布中の気中濃度は散布された噴霧粒子(ミスト)を捕らえて
いると考えられる。
2.土壌中濃度調査
表6 に示した各調査農薬の土壌中濃度から平均値を求め、表10 及び図6 に示した。フェニトロチオン、エトフェンプロックス及びイソキサチオンは、検出された濃度に違いは見られたが、減少の傾向は同じであったと思われる。
このことは、これら農薬の土壌中半減期がほぼ同じであることによるかは定かではない。イソキサチオンの濃度が散布14 日後に高くなったことは、フェニトロチオン及びエトフェンプロックスの地点においても見られていることから、土壌採取場所のバラツキ及び散布12 日後及び13 日後における降雨の影響があったのではないかと考えられる。
トリクロルホンは、すべて検出限界値未満であった。これは、速やかに分解するという土壌半減期のため減少したのではないかと考えられる。
今回の調査結果から散布直後の濃度と比較して1/2 の濃度となったのは、フェニトロチオンで散布14 日後及びジクロルボスで散布7 日後であり、エトフェンプロックス及びイソキサチオンでは散布14 日後以降であると推察される。
3.葉中濃度調査(葉への付着量)
表7 に示した各調査農薬の葉への付着量から平均値を求め、表11 及び図7 に示した。フェニトロチオン、トリクロルホン及びジクロルボスは、検出された濃度に違いは見られたが、散布1 日後には大きく減少し、その後も同じように減少する傾向が見ら
れた。
エトフェンプロックスは、ほとんど減少が見られなかったが、その要因については定かではない。
イソキサチオンは、散布7 日後より14 日後に少し高くなったが、落下量のバラツキ及び葉採取場所の違いによるものと考えられる。
参考文献
1)農薬ハンドブック2005 年版(改訂新版)社団法人日本植物防疫協会
2)環境省環境保健部環境リスク評価室:化学物質の環境リスク評価第2 巻(2003 年3 月)第1編 ?.(?)[9]イソキサチオン、[28]ジクロルボス、[53]フェニトロチオン
3)国立医薬品食品衛生研究所:トリクロルホン、環境保健クライテリア(EnvironmentalHealth Criteria)132 日本語抄訳(原著162 頁、1992 年発行)
4)トレボン乳剤、製品安全データシート(MSDS):サンケイ化学株式会社(改訂2007年4 月26 日)
5)斎藤ら:地上防除及び無人ヘリ防除における有機リン系農薬の気中濃度・落下量、第28 回農薬製剤・施用法研究会、技術研究発表T5、2008(平成20 年)
http://www.env.go.jp/water/report/h21-02/full.pdf