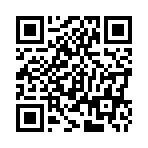2010年11月11日
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判
2010年10月12日(火)13時30分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で住民訴訟第一次(3世帯)第22回口頭弁論(公開)が実施されました。
被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。(13:34~14:47、証人A尋問)、(14:48~15:22、証人B尋問)。


被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
A証人(乙第24号証)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2010/2/7
B証人(乙第27号証)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2010/2/15
として、そのとき提出されています。
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
今回、原告住民は証拠資料として「甲第32号証」(岡山市水道局の回答書(原本))、「甲第33号証」(廃白土について(写し))、「甲第34号証」(廃掃法の運用に伴う通知(写し))を提出しました。
尋問の方法は、第14回裁判で原告本人尋問が行われた時と同じです。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2009/12/23
被告(両備)主尋問は、証人陳述書の内容を確認するものがほとんどでした。尋問内容の一部を記述します。
裁判長が、まず証人2名を証人台に呼び氏名等の確認をし、注意事項を述べ、宣誓文を唱和させた後、“A証人には主尋問30分反対尋問20分、B証人には主尋問30分反対尋問15分の予定で行います。”、と予定時間の説明がありました。
原告河田弁護士から、B証人の反対尋問は短く、その分A証人に時間をあてて反対尋問をしたい、と発言がありました。
A証人の主尋問です。
(被告足立弁護士)
この件であなたはどのような仕事を担当しましたか。
(A証人)
本件不動産を「旭油化」から即決和解で取得した当時、会社側の担当をしていました。「旭油化」との交渉は代理人の杉本弁護士にお願いしていたので、私が直接交渉したのではなく代理人との会社側の窓口として仕事をしていました。
(被告足立弁護士)
他に担当していた人は?
(A証人)
私一人で担当していました。
(被告足立弁護士)
(旭油化の操業による悪臭公害について)当時マスコミ報道はありましたか?
(A証人)
ありません。
(被告足立弁護士)
陳述書文中に「廃白土」とあるが、あなたは意味を知っていますか?
(A証人)
廃白土とはどういうものか当時は知らなかった。
(被告足立弁護士)
「旭油化」と被告会社との和解調書で、和解条項に記載しているように、廃白土等を「旭油化」は取り除いたのか?

(A証人)
「旭油化」は取り除けなかった。そのため油っぽい土と、土の中に埋まっているものを搬出しなければと思い、処理を外注した。油っぽい土と、土の中に埋まっているドラム缶の処理は東山工務店に搬出依頼したが搬出先は聞いていない。消臭工事はナップに依頼した。石灰で攪拌して臭いを消す工事をしていた。
(被告足立弁護士)
それで臭いは無くなりましたか?
(A証人)
臭いはわずかに残っていた。住宅地として販売するのに「気にならない」とは思っていなかった。臭いに敏感な人であれば気になる臭いがあった。しかし臭いの原因は除去したので年数がたてば収まると思っていた。
宅地開発は3年程度おいて着手した。3年ぐらいすれば臭いもなくなるだろうと思っていた。公害の発生した土地という感覚はなかった。臭いだけと思っていた。20年近くたってこのようなことになるとは認識してなかった。
A証人の主尋問は以上。
A証人の反対尋問です。
(原告河田弁護士)
「旭油化」との即決和解を担当されていますが、あなたの職務はどのようなものでしたか?
(A証人)
開発開始の職務と総務的な仕事をしていました。ただ決定権限は上司でした。
(原告河田弁護士)
この問題を解決するために即決和解を選択されたが、即決和解とはどのようなものかご存知ですよね?
まとまらないので和解をするために、当事者間で話を取りまとめて裁判所に持ち込む方法ですが、あなたが話をとりまとめたのですか?
(A証人)
杉本弁護士に委託していたので、この内容でという相談があり、決めた(昭和57年7月当時)。実際の交渉は1年ぐらい前からで、長い間交渉してもらった。
(原告河田弁護士)
この問題はたびたび新聞等で取り上げられ、和解を担当している者としては、「旭油化」のニュースは気になるのでは?
(A証人)
直接タッチしてないので気にはならなかった。
(原告河田弁護士)
「甲1号証の1」は昭和57年6月4日付けの山陽新聞で、岡山県が「旭油化」に対して工場内たい積汚泥の除去命令を出した記事ですが、この記事は知っていましたか?
(A証人)
知らなかった。
(原告河田弁護士)
「旭油化」の直接担当者として知らなかった?会社は当然知っていますよね?
(被告菊地弁護士)
異議あり。今の尋問は証人に推測を求めています。
(裁判長)
原告代理人は質問の方法を変えて下さい。
(原告河田弁護士)
分かりました。では、会社からそのニュースは知らされなかった?
(A証人)
知らされなかった。
(原告河田弁護士)
新聞記事、旭油化の産業廃棄物処理業免許の取得、廃白土とは、などの情報も会社から知らされなかった?
(A証人)
知らされなかった。
(原告河田弁護士)
そうですか。では即決和解についてお聞きします。旭油化跡地を取得して金銭支払いは総額いくらだったのですか?
(A証人)
詳しくは覚えていないが、2億を超えていたと思う。
(原告河田弁護士)
誰に支払った?
(A証人)
名義は小寺さん名義(旭油化の社長)であった。
(原告河田弁護士)
「旭油化」が自力で廃棄物を処理する能力が無く、あなたの会社で処理するしかなかったのでは?
(A証人)
能力がなかったとは記憶してない。
(原告河田弁護士)
「旭油化」が廃棄物を除去できなかったのに、和解条項違反の損害賠償金8000万円の問題で、紛争は起きなかったのですか?
(A証人)
紛争は起きなかった。
(原告河田弁護士)
訴訟が起きたのではないですか?
(A証人)
残金は支払った。
(原告河田弁護士)
訴訟は?
(A証人)
裁判はあった。条件どおりに出来ていないので。正式には覚えていない。引き渡し時期がきて残金は支払ったと思う。
(原告河田弁護士)
条件どおりに支払った?
(A証人)
・・・
(原告河田弁護士)
どんな状況で、引き渡された?
(A証人)
更地に近い状況で引き渡されたと思う。特に目立ったことはない。それなりの状態だった。「旭油化」がそこまでしたと思う。
(原告河田弁護士)
取得した土地はどのように利用しようと思っていた?
(A証人)
できれば住宅地として利用できないかと思っていた。
(原告河田弁護士)
宅地造成して、水道管が、(通常使用されない)鉛管を使用することになったことをあなたは知っていましたか?
(被告菊地弁護士)
異議あり。主尋問から離れた反対尋問は適切でない。このような質問は改めて証人申請して尋問すべき。また、前もって準備書面で明らかにして主張すべきである。
(裁判長)
準備書面で出来ることですね。今なにを確認したいのですか?
(原告河田弁護士)
土壌について、今回原告が提出した32号証(鉛管使用について岡山市水道局からの回答書)にあるように、鉛管を使用しなければならないほどの認識がなかったのか確認する手続きをしています。
(被告菊地弁護士)
してないでしょう!
≪法廷は、しばし騒然!≫
(原告河田弁護士)
今の鉛管が使用された件はどうですか?
(A証人)
知らなかった。
(原告河田弁護士)
あなたは住民説明会に出席していますね。何回出席しましたか?
(A証人)
二度出席したと思いますが、責任者としてではない。
(原告河田弁護士)
そのとき、ドラム缶が埋まっていたとか、「旭油化」が廃油を垂れ流ししていた、というような説明をしませんでしたか?
(A証人)
何度か話をしたことはあるが、それは撤去しているはず。担当してから引き渡しの間に見たことはない。
(原告河田弁護士)
すべて撤去してないのでは?
(A証人)
記憶してない。
(原告河田弁護士)
外注業者の計画書には記載されて無いのか?
(A証人)
計画書はない。
(原告河田弁護士)
尋問を終わります。
(裁判長)
裁判所から質問します。あなたは外注先の東山工務店・ナップが作業をしているところを見た事はありますか?
(A証人)
1~2度あります。進捗状況を確認するために。
(裁判長)
どのような状況でしたか?臭いは?
(A証人)
臭いはしていました。土の色は黒っぽい土だったと思います。
(被告足立弁護士)
現職と当時の状況を。
(B証人)
現職は4月から営業部部長。
当時担当していたのは、平成2年から平成4年に営業課主任として現在の「小鳥が丘団地」の物件の営業をしていた。ちょうど第1期の販売が終わり第2期開始の頃。
「小鳥が丘団地」になる前の現地に、初めて行ったのは、隣接する小鳥の森団地の営業を担当していた昭和60年から61年頃で、更地になっていて造成前で建物はなかった。
当時小鳥の森団地の事務所にも臭いはしていた。
平成2年ころはいくらか臭いはあったがずいぶん弱くなっていた。臭うのは夏場の雨上がりの時など一部からで場所は決まっていた。
(被告足立弁護士)
地図がありますので示して下さい。
(B証人)
(地図で示しながら)私が臭いを感じたのは、岩野邸北側道路の堺と擁壁のあるところです。
平成2年に第1期取得者から雨上がりの水たまりに油の膜ができるという話は聞いたことがあるが、お客様と顔を合わせたとき世間話の間に出た程度で、クレームではなかった。会社にもクレームの連絡はなかった。
(被告足立弁護士)
第2期分譲の販売方法は?
(B証人)
新聞広告(地元紙、山陽新聞)や、近隣にパンフレットを配った。
お客は地元の人がほとんどで、「旭油化」は多くの方が認識していて、まともな会社ではないことは地元には広く知られていた。お客から「旭油化」はどこに行ったのかと聞かれることもあったので、地域の要請に応えて旭油化跡地を買い取り、宅地開発したと説明していた。
上司から「旭油化」は食品油を使用し石けん油を製造していたと聞いていたので、お客の質問にはそのように答えていた。だから販売に際しては値引きするようなことはなく近隣相場で販売していた。
(被告足立弁護士)
土はどんな状態?
(B証人)
黒っぽい土が出てきたことはあるが黒い水はない。土は乾いた状態であり、黒い土は部分的に出てきた。
(被告足立弁護士)
黒い土はどこから?
(B証人)
私が見たのは、竹中邸の掘り抜きの駐車場を造るときと、川上邸の浄化槽の穴を掘ったとき。
(被告足立弁護士)
(平成20年の裁判所現地視察時撮影の写真を提示しながら)このような状態ではなかった?
(B証人)
このような真っ黒でドロドロした状態は見たことがない。水分はなかったし、土の色は灰色だった。他の箇所からも出てきたかもしれないが、それは私には分からない。
(裁判長)
環境基準を検討しようと思っていますが、客観的な資料をどちらか提出してもらえませんか?もちろん一般的な資料は裁判所でも収集しますが。
討議の結果、双方の立場で環境基準の資料を提出することになった。
(原告河田弁護士)
原告は次回最終準備書面をまとめたい。
(裁判長)
被告はどうですか?
(被告足立弁護士)
被告も同じ。ただ原告準備書面が提出されて相当程度期間をおいた後でないと。
(原告河田弁護士)
新たな主張をするものではありません。
(裁判長)
原告の準備書面はいつ頃?
(原告河田弁護士)
1か月半から2か月程度あとに。
<日程調整討議をする。>
(裁判長)
では、次回は12月21日(火)10:00から弁論を行い、終結予定とします。12月14日までにそれぞれ準備書面を提出してください。
裁判終了時刻、15時27分。

第22回口頭弁論に訴訟第一次(3世帯)原告住民が提出した10月12日付け証拠資料
事件番号 平成19年(ワ)第1352号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
証拠説明書
平成22年10月12日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河 田 英 正
番号 標 目(原本写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 備考
32 回答書 原本 H18.2.14 岡山市水道事業管理者 被告に当初から廃油工場跡地を造成するとの認識のあった事実
33 「廃白土」について 写し H22.10.10 前橋工科大学梅津研究室(ホームページから) 廃白土は廃油精製の工程で排出される処理の困難な産業廃棄物であること
34 廃掃法の運用に伴う通知 写し S46.10.25(公布) H14.5.21 廃白土は汚泥に分類され、廃油との混合物として取り扱われていて、産業廃棄物として厳格に処理が必要とされている事実。
(甲第)32(号証)
岡山市水道局の回答書(原本)
「小鳥が丘団地救済協議会」ホームページメニュー
「不思議な岡山市水道局の工事」内の<岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書>として掲載したもの。
<抜粋>、平成18年2月14日付け回答書
【質問】
なぜ、小鳥が丘団地に鉛製給水管を使用したのか
【回答】
小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから、樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認したものです。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/suidoukyoku01.html
(甲第)33(号証)廃白土について(写し)
該当ホームページ
1、廃白土の処理
油の精製過程で広く使用されている白土は、含油廃白土として排出される。
廃油精製の工程で、オリバーフィルタによって油中から分離された廃白土は、通常40%前後の油分を含む。
したがって、そのままの形状で投棄することはできず、廃白土中の油分は除去しなければならない。
廃白土中の油分を除去する方法としては、
① 溶剤によって油分を抽出し、白土の再生と油分の回収をはかる。
② 含油廃白土中の油分を焼却する。
①の溶剤抽出法は設備費、およびランニングコストがかさむため、回収される油の付加価値を考慮して採用される。
この方法で白土中の油分を抽出し、白土の再生利用をはかっても、何回か繰り返すうちに、白土は活性を失うので含油廃白土として排出される。
②の焼却法は廃白土中の油分を燃焼室で焼却する方法であり、①の溶剤抽出法で排出される含油廃白土の処理とあわせて投棄するために必要な処理方法である。
2、廃白土の焼却
油の処理過程で得られる廃白土中には水分もなく、発熱量も3000kcal/kg以上あるので自燃可能である。
含油廃白土は100μ以下の白土粉末に油が二次的に含浸したものであるから、石灰系の粉体燃料と比較して流動性がはるかに悪く、手で軽く押さえつけるだけで簡単に固まる。
流動性の悪い廃白土の焼却にはロータリキルンや、立て形多段焼却炉がある。が、設備費がかさむ割には燃焼に長時間を要する。また、廃油と混合してスラリー状として高圧噴霧し、微粒化させて焼却する噴霧燃焼法などがある。
廃白土の燃焼の際、とくに留意すべきことは、燃焼時にダスト(白土)が飛散することである。
白土の微粒子は燃焼ガスに同伴してきわめて飛散しやすいため、排ガス中のダスト除去対策を十分考慮しなければならない。
参考文献:廃棄物の処理・再利用
http://oo.spokon.net/mutou/hp/haihakudo.html
(甲第)34(号証)廃掃法の運用に伴う通知(写し)該当ホームページ
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】
公布日:昭和46年10月25日
環整45号
平成一四年五月二一日 環廃産二九四号
(各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて 厚生雀環境衛生局環境整備課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行については、下記の事項に留意して運用されたく通知する。
記
第一 廃棄物の範囲等に関すること
1 廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
法第二条第一項の規定は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行つたものであること。
2 廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあつては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によつて措置されるものであること。
なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。
3 産業廃棄物は、事業活動に伴つて生ずる廃棄物であり、事業活動というのは反覆継続して行なわれるものであるから、排出源において単一の産業廃棄物としてとらえられる場合が比較的多いものであるが、産業廃棄物がいくつか混合した状態で排出された場合には、廃棄物処理法第二条第四項に規定する六種類の産業廃棄物及び廃棄物処理法施行令第二条に規定する十三種類の産業廃棄物が複合した形態で排出されたものとみなしてとらえるものとし、たとえば「硫酸ピッチ」にあつては、廃酸と廃油の混合物としてとらえるものとすること。
また、定義の不明な事業活動に伴つて生ずる廃棄物にあつては、排出源、排出されるに至る過程、排出された時点での物の組成内容等を明記した上で、当局と協議し、その運用の円滑な推進を期するものであること。
4 廃棄物処理法第二条第四項及び令第二条に規定された産業廃棄物の内容は、別紙に示すとおりであること。
5 下水道法に規定する下水道から除去した汚でいは、産業廃棄物として取り扱うものであること。
第二 産業廃棄物処理施設の範囲に関すること
1 令第七条第一号、第二号及び第三号に掲げる施設は、汚でいの処理を行なうための施設であつて、それぞれ汚でいの脱水、乾燥及び焼却を目的とする施設であること。
2 令第七条第四号及び第五号に掲げる施設は、廃油の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃油の油水分離及び焼却を目的とする施設であること。
3 令第七条第六号に掲げる施設は、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、廃酸又は廃アルカリの中和を目的とする施設であり、中和槽を有するものであること。ただし、放流を目的とする一般の廃水処理に係る中和施設は除くものとする。
4 令第七条第七号及び第八号に掲げる施設は、廃プラスチック類の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃プラスチック類の破砕及び焼却を目的とする施設であること。
5 令第七条第九号に掲げる施設は、令別表下欄に掲げる有害物質を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でいをコンクリート固型化し、汚でい中に含まれる有害物質が漏れないように加工することを目的とする施設であること。
6 令第七条第十号に掲げる施設は、水銀又はその化合物を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でい中に含まれる水銀又はその化合物をばい焼により硫化物とし、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令における処分の態様に応じて定める判定基準に適合させることを目的とする施設であるが、水銀又はその化合物から水銀蒸気となつて水銀が気散する部分は捕集し、回収できる構造を有する施設であること。
7 令第七条第十一号に掲げる施設は、シアン化合物を含む汚でい、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、熱分解、電気分解、アルカリ塩素法分解等によつて処理し、汚でいを判定基準に適合するものにし、又は廃酸若しくは廃アルカリにシアン化合物が含まれないようにすることを目的とする施設であること。
8 令第七条第十二号の二に掲げる施設は、廃PCB等又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、脱塩素化法又は超臨界水酸化法による分解によって処理し、廃PCB等又はPCB処理物にPCBが含まれないようにすることを目的とする施設であること。
9 令第七条第十三号に掲げる施設は、PCB汚染物又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、PCBを除去することを目的とする施設であること。
10 令第七条第十三号の二に掲げる施設は、汚泥、廃油又は廃プラスチック以外の産業廃棄物の処理を行うための施設であって、当該産業廃棄物の焼却を目的とする施設であること。
11 令第七条第十四号に掲げる施設は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分を目的とする施設であること。
12 令第七条に規定する産業廃棄物処理施設は、いずれも独立した施設としてとらえ得るものであつて、工場又は事業場内のプラントの一部として組み込まれたものは含まないものであること。
13 令第七条に掲げる施設の処理能力は、その施設が標準運転時間に処理できる廃棄物の量をもつて表わすもので、いわゆる施設の公称能力である。したがつて、たとえば一日の標準運転時間が八時間のものは、一時間当りの処理能力の八時間ぶんをもつて表わす。
第四 産業廃棄物処理施設の維持管理等に関すること。
産業廃棄物処理施設の維持管理に関しては、次の点に留意するよう関係者を指導されたいこと。
1 産業廃棄物は、円形状、でい状及び液状を呈し、その種類は多様であり、かっ、有害物質を含むものもすくなくないので、焼却、ばい焼、中和、コンクリート固形化等による安全化又は安定化及び焼却、脱水、乾燥、破砕、圧縮等による減量化に努めなければならないこと。
このような処分は、その操作に伴なつて大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等を惹起する可能性があるので、施設の設計段階でこの点について考慮するとともに、技術管理者は、施設の基本設計と運転仕様を熟知し、規則第十二条の六及び第十二条の七の維持管理基準を遵守しなければならないものであること。
なお、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等他の公害防止関係法令による基準が設定されている場合は、これらの基準の遵守を目標に維持管理等を行なわなければならないこと。
2 規則第十二条の六第七項において規定している排水にあたつての放流水の水質基準は、その放流水が直接に公共の水域に排出される単独施設の場合に適用されるものであつて、水質汚濁防止法第二条第四項に規定する特定事業場内において他の排水と混合して放流される場合には、水質汚濁防止法第三条の規定に基づく排水基準に従うことはいうまでもないこと。
3 規則第十二条第一項の機能点検は毎月一回以上行なうこと。
4 以上のほか、第三の2、3、4及び6に準じて行なうようにすること。
(別紙)
(1) 燃えがら 電気事業等の事業活動に伴つて生ずる石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物等が代表的なものであり、集じん装置に捕捉されたものはダスト類として令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物として取り扱うものであること。
その他熱エネルギー源を物の燃焼に依存している場合の焼却残灰、炉清掃掃出物等についても同様の取扱いとするものであること。
(2) 汚でい
工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであつて、有機質の多分に混入したどろのみを指すのではなく、有機性及び無機性のもののすべてを含むものであること。有機性汚でいの代表的なものとしては、活性汚でい法による処理後の汚でい、パルブ廃液から生ずる汚でい、その他動植物性原料を使用する各種製造業の廃水処理後に生ずる汚でい、ビルピット汚でいがあること。
無機性汚でいの代表的なものとしては、赤でい、けい藻土かす、炭酸カルシウムかす、廃白土、浄水場の沈でん池より生ずる汚でいがあること。ただし、赤でいにあつては、廃アルカリとの混合物として、廃白土にあつては、廃油との混合物として取り扱うものであること。
(3) 廃 油
鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油を含むものとし、潤滑油系、絶縁油糸、洗浄用油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類(常温において固形状を呈するものに限る。)があること。硫酸ピッチ及びタンクスラッジは、それぞれ廃油と廃酸の混合物及び廃油と汚でいの混合物として取り扱うものであること。
(4) 廃 酸
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類をはじめ酸性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、アルコール又は食用のアミノ酸の製造に伴つて生じた発酵廃液は廃酸に該当するものであること。廃酸は、液状の産業廃棄物であるが、水素イオン濃度指数を五・八以上八・六以下に調整した場合に生ずる沈でん物は汚でいと同様に取り扱つて差し支えないものであること。
(5) 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せつけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、カーバイトかすは、廃アルカリとしてではなく汚でいとして取り扱い、埋立処分にあたつては、浸出液の処理を行なうこと。廃アルカリの水素イオソ濃度指数を調整した場合に生ずる沈でん物の取扱いは、廃酸の場合と同様とするものであること。なお、工場廃液は、(4)若しくは(5)又は(4)及び(5)の混合物として取り扱うものであること。
(6) 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むものであること。
(7) 令第二条第一号に掲げる産業廃棄物 「紙くず」という。
産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる紙くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一八、小分類一九一のうち新聞巻取紙を使用して印刷発行を行なう細分類一九一一、細分類一九二一のうち印刷出版を行なうもの、細分類一九五一及び一九五二に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる紙くずであつて、壁紙、障子、紙、板紙等の古紙が含まれるものであること。
(8) 令第二条第二号に掲げる産業廃棄物 「木くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くずであつて工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴つて生じたもの、中分類一六、小分類一七一及び一八ーに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くず並びに輸入木材の輸入を業務の一部又は全部として行なつている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くずであつておがくず、バーク類等が含まれるものであること。
(9) 令第二条第三号に掲げる産業廃棄物 「繊維くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる繊維くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一四に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる繊維くずであつて、畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずが含まれるものであること。
(10) 令第二条第四号に掲げる産業廃棄物 「動植物性残さ」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による中分類一二及び一三(小分類一三五を除く。)、小分類二〇六及び細分類二〇九三に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動植物性残さであって、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等が含まれるものであること。魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物として取り扱うものであること。
(11) 令第二条第四号の二に掲げる産業廃棄物 「動物系固形不要物」という。と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等により生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要とされるものが含まれるものであること。
なお、家畜の解体等に伴い発生する血液等の液体の不要物は、産業廃棄物たる廃酸又は廃アルカリとして扱うこと。
(12) 令第二条第五号に掲げる産業廃棄物 天然ゴムくずが含まれるものであること。
(13) 令第二条第六号に掲げる産業廃棄物 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等が含まれるものであること。
(14) 令第二条第七号に掲げる産業廃棄物 「ガラスくず」という。ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず、陶磁器くず等が含まれるものであること。ただし、コンクリートくずについては、令第二条第九号に掲げる産業廃棄物に含まれるものは除かれること。
(15) 令第二条第八号に掲げる産業廃棄物 高炉、平炉等の残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等が含まれるものであること。
(16) 令第二条第九号に掲げる産業廃棄物 「がれき類」という。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他各種の廃材の混合物を含むものであって、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じた物を除くものであること。ただし、地下鉄の工事現場等から排出される含水率が高く、粒子の微細なでい状のものにあっては、無機性の汚でいとして取り扱うものであること。
(17) 令第二条第十号に掲げる産業廃棄物 「家畜ふん尿」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物のふん尿(畜舎廃水を含む。)であって、牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿が含まれるものであること。なお、家畜ふん尿を動物のふん尿処理施設において処理した後に生じるでい状物は、汚でいに該当するものであること。
(18) 令第二条第十一号に掲げる産業廃棄物 「家畜の死体」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物の死体であって、動物の種類は、ふん尿の場合と同様であること。
(19) 令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物 「ダスト類」という。産業廃棄物に該当するものは、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において発生するばいじんであつて、集じん施設において捕捉されたものであること。なお、集じん施設の集じん方法は、乾式、湿式のいずれの方法であるかは問わないものであること。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000510
原告が提出した10月12日付け証拠資料以上。
第22回口頭弁論は、13時29分に始まり15時27分に終わりました。
裁判を終わっての感想です。
今回、原告(住民)が証拠資料として提出した、「甲第32号証(岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書(原本))」、
『小鳥が丘団地の鉛製給水管使用について(回答)』
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/suidoukyoku01.html
にあるように、
開発当時の、「小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であった」、ことが明らかであり、「両備」の主張する食品油を使用した石けん製造工場の跡地というよりも、水道局の回答書でも、「廃油工場跡地」、とはっきり記載されています。
開発当時の給水協議で、水道管を鉛管にすることが決定されており、ディベロッパー(宅地開発業者)の「両備」がそれを知らないはずはないと思います。
また、宅地に埋設する上水道管として、「樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認した」、土地であることを開発業者の「両備」は認識していたと思われます。
最後に、原告代理人河田弁護士のブログに、この日のことが書いてありましたので、紹介します。
「河田英正のブログ」、2010年10月17日付、下段に感想が載っています。
小鳥が丘団地の土壌汚染問題に関して,会社側の証人尋問を行った。当時,新聞報道にされて公の事実となっていたことでさえ,会社側の当時の事件処理担当者だった証人は,そのような事実は知らなかったという証言であった。一社員として,あくまでも会社を守ろうとして,頑なに事実を語ろうとしない証言態度には,かつての公害裁判でどの裁判においても企業利益を優先する態度をとってきたことが思い起こされ,「企業は悪者」という図式に変わることはないことを思い知らされた。
http://www.d-mc.ne.jp/blog/kawada/article.php?id=1250
次回第23回口頭弁論は、2010年12月21日(火)10時00分~、岡山地方裁判所で(公開)実施の予定で、原告・被告双方の最終答弁 (終結予定)です。
以上。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後6年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(訴訟第一次)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(訴訟第二次)も続いて提訴し係争中です。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/51343668.html
鉛製給水管について
1.水質基準の強化
鉛の水質基準は、平成4年に0.1mg/リットル以下から0.05mg/リットル以下に改められました。この値は、毎日水道水を飲用しても日本人の健康に問題がないとして制定されていましたが、平成15年度からWHO(世界保健機構)の「飲料水のガイドライン」にあわせ、0.01mg/リットル以下へと強化されました。
2.鉛製給水管の使用経過
鉛は金属としては柔らかい材質であるため、加工しやすく給水管などの材質として広く普及していましたが、硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の普及に伴い、岡山市では昭和53年3月以降鉛管の使用を中止しました。したがって、それ以前から水道を利用されている場合には、鉛製給水管が使用されている可能性があります。
http://www.water.okayama.okayama.jp/guest/kyusui4.htm
岡山市水道局へ「小鳥が丘の鉛管使用について」下記の公開質問状提出したところ
「小鳥が丘団地が開発された昭和62年当時岡山市はすでに鉛管の使用を止めていたのに何故当団地で使用したのか?」
同月14日、下記の回答書受領した。
「開発当時の給水協議に際し廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから樹脂系のポリエチレン管は変質する恐れがあり鉛管の使用を承認した。」
両備ホールディングス環 境 方 針
両備ホールディングス株式会社は、事業活動を通じて、環境保全活動に取組み、安全と高品質なサービスを提供することにより、 地域の発展と自然環境の保護に努めます。
両備ホールディングス株式会社 取締役社長 小 嶋 光 信


被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。(13:34~14:47、証人A尋問)、(14:48~15:22、証人B尋問)。


被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
A証人(乙第24号証)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2010/2/7
B証人(乙第27号証)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2010/2/15
として、そのとき提出されています。
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
今回、原告住民は証拠資料として「甲第32号証」(岡山市水道局の回答書(原本))、「甲第33号証」(廃白土について(写し))、「甲第34号証」(廃掃法の運用に伴う通知(写し))を提出しました。
尋問の方法は、第14回裁判で原告本人尋問が行われた時と同じです。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2009/12/23
被告(両備)主尋問は、証人陳述書の内容を確認するものがほとんどでした。尋問内容の一部を記述します。
裁判長が、まず証人2名を証人台に呼び氏名等の確認をし、注意事項を述べ、宣誓文を唱和させた後、“A証人には主尋問30分反対尋問20分、B証人には主尋問30分反対尋問15分の予定で行います。”、と予定時間の説明がありました。
原告河田弁護士から、B証人の反対尋問は短く、その分A証人に時間をあてて反対尋問をしたい、と発言がありました。
A証人の主尋問です。
(被告足立弁護士)
この件であなたはどのような仕事を担当しましたか。
(A証人)
本件不動産を「旭油化」から即決和解で取得した当時、会社側の担当をしていました。「旭油化」との交渉は代理人の杉本弁護士にお願いしていたので、私が直接交渉したのではなく代理人との会社側の窓口として仕事をしていました。
(被告足立弁護士)
他に担当していた人は?
(A証人)
私一人で担当していました。
(被告足立弁護士)
(旭油化の操業による悪臭公害について)当時マスコミ報道はありましたか?
(A証人)
ありません。
(被告足立弁護士)
陳述書文中に「廃白土」とあるが、あなたは意味を知っていますか?
(A証人)
廃白土とはどういうものか当時は知らなかった。
(被告足立弁護士)
「旭油化」と被告会社との和解調書で、和解条項に記載しているように、廃白土等を「旭油化」は取り除いたのか?

(A証人)
「旭油化」は取り除けなかった。そのため油っぽい土と、土の中に埋まっているものを搬出しなければと思い、処理を外注した。油っぽい土と、土の中に埋まっているドラム缶の処理は東山工務店に搬出依頼したが搬出先は聞いていない。消臭工事はナップに依頼した。石灰で攪拌して臭いを消す工事をしていた。
(被告足立弁護士)
それで臭いは無くなりましたか?
(A証人)
臭いはわずかに残っていた。住宅地として販売するのに「気にならない」とは思っていなかった。臭いに敏感な人であれば気になる臭いがあった。しかし臭いの原因は除去したので年数がたてば収まると思っていた。
宅地開発は3年程度おいて着手した。3年ぐらいすれば臭いもなくなるだろうと思っていた。公害の発生した土地という感覚はなかった。臭いだけと思っていた。20年近くたってこのようなことになるとは認識してなかった。
A証人の主尋問は以上。
A証人の反対尋問です。
(原告河田弁護士)
「旭油化」との即決和解を担当されていますが、あなたの職務はどのようなものでしたか?
(A証人)
開発開始の職務と総務的な仕事をしていました。ただ決定権限は上司でした。
(原告河田弁護士)
この問題を解決するために即決和解を選択されたが、即決和解とはどのようなものかご存知ですよね?
まとまらないので和解をするために、当事者間で話を取りまとめて裁判所に持ち込む方法ですが、あなたが話をとりまとめたのですか?
(A証人)
杉本弁護士に委託していたので、この内容でという相談があり、決めた(昭和57年7月当時)。実際の交渉は1年ぐらい前からで、長い間交渉してもらった。
(原告河田弁護士)
この問題はたびたび新聞等で取り上げられ、和解を担当している者としては、「旭油化」のニュースは気になるのでは?
(A証人)
直接タッチしてないので気にはならなかった。
(原告河田弁護士)
「甲1号証の1」は昭和57年6月4日付けの山陽新聞で、岡山県が「旭油化」に対して工場内たい積汚泥の除去命令を出した記事ですが、この記事は知っていましたか?
(A証人)
知らなかった。
(原告河田弁護士)
「旭油化」の直接担当者として知らなかった?会社は当然知っていますよね?
(被告菊地弁護士)
異議あり。今の尋問は証人に推測を求めています。
(裁判長)
原告代理人は質問の方法を変えて下さい。
(原告河田弁護士)
分かりました。では、会社からそのニュースは知らされなかった?
(A証人)
知らされなかった。
(原告河田弁護士)
新聞記事、旭油化の産業廃棄物処理業免許の取得、廃白土とは、などの情報も会社から知らされなかった?
(A証人)
知らされなかった。
(原告河田弁護士)
そうですか。では即決和解についてお聞きします。旭油化跡地を取得して金銭支払いは総額いくらだったのですか?
(A証人)
詳しくは覚えていないが、2億を超えていたと思う。
(原告河田弁護士)
誰に支払った?
(A証人)
名義は小寺さん名義(旭油化の社長)であった。
(原告河田弁護士)
「旭油化」が自力で廃棄物を処理する能力が無く、あなたの会社で処理するしかなかったのでは?
(A証人)
能力がなかったとは記憶してない。
(原告河田弁護士)
「旭油化」が廃棄物を除去できなかったのに、和解条項違反の損害賠償金8000万円の問題で、紛争は起きなかったのですか?
(A証人)
紛争は起きなかった。
(原告河田弁護士)
訴訟が起きたのではないですか?
(A証人)
残金は支払った。
(原告河田弁護士)
訴訟は?
(A証人)
裁判はあった。条件どおりに出来ていないので。正式には覚えていない。引き渡し時期がきて残金は支払ったと思う。
(原告河田弁護士)
条件どおりに支払った?
(A証人)
・・・
(原告河田弁護士)
どんな状況で、引き渡された?
(A証人)
更地に近い状況で引き渡されたと思う。特に目立ったことはない。それなりの状態だった。「旭油化」がそこまでしたと思う。
(原告河田弁護士)
取得した土地はどのように利用しようと思っていた?
(A証人)
できれば住宅地として利用できないかと思っていた。
(原告河田弁護士)
宅地造成して、水道管が、(通常使用されない)鉛管を使用することになったことをあなたは知っていましたか?
(被告菊地弁護士)
異議あり。主尋問から離れた反対尋問は適切でない。このような質問は改めて証人申請して尋問すべき。また、前もって準備書面で明らかにして主張すべきである。
(裁判長)
準備書面で出来ることですね。今なにを確認したいのですか?
(原告河田弁護士)
土壌について、今回原告が提出した32号証(鉛管使用について岡山市水道局からの回答書)にあるように、鉛管を使用しなければならないほどの認識がなかったのか確認する手続きをしています。
(被告菊地弁護士)
してないでしょう!
≪法廷は、しばし騒然!≫
(原告河田弁護士)
今の鉛管が使用された件はどうですか?
(A証人)
知らなかった。
(原告河田弁護士)
あなたは住民説明会に出席していますね。何回出席しましたか?
(A証人)
二度出席したと思いますが、責任者としてではない。
(原告河田弁護士)
そのとき、ドラム缶が埋まっていたとか、「旭油化」が廃油を垂れ流ししていた、というような説明をしませんでしたか?
(A証人)
何度か話をしたことはあるが、それは撤去しているはず。担当してから引き渡しの間に見たことはない。
(原告河田弁護士)
すべて撤去してないのでは?
(A証人)
記憶してない。
(原告河田弁護士)
外注業者の計画書には記載されて無いのか?
(A証人)
計画書はない。
(原告河田弁護士)
尋問を終わります。
(裁判長)
裁判所から質問します。あなたは外注先の東山工務店・ナップが作業をしているところを見た事はありますか?
(A証人)
1~2度あります。進捗状況を確認するために。
(裁判長)
どのような状況でしたか?臭いは?
(A証人)
臭いはしていました。土の色は黒っぽい土だったと思います。
(被告足立弁護士)
現職と当時の状況を。
(B証人)
現職は4月から営業部部長。
当時担当していたのは、平成2年から平成4年に営業課主任として現在の「小鳥が丘団地」の物件の営業をしていた。ちょうど第1期の販売が終わり第2期開始の頃。
「小鳥が丘団地」になる前の現地に、初めて行ったのは、隣接する小鳥の森団地の営業を担当していた昭和60年から61年頃で、更地になっていて造成前で建物はなかった。
当時小鳥の森団地の事務所にも臭いはしていた。
平成2年ころはいくらか臭いはあったがずいぶん弱くなっていた。臭うのは夏場の雨上がりの時など一部からで場所は決まっていた。
(被告足立弁護士)
地図がありますので示して下さい。
(B証人)
(地図で示しながら)私が臭いを感じたのは、岩野邸北側道路の堺と擁壁のあるところです。
平成2年に第1期取得者から雨上がりの水たまりに油の膜ができるという話は聞いたことがあるが、お客様と顔を合わせたとき世間話の間に出た程度で、クレームではなかった。会社にもクレームの連絡はなかった。
(被告足立弁護士)
第2期分譲の販売方法は?
(B証人)
新聞広告(地元紙、山陽新聞)や、近隣にパンフレットを配った。
お客は地元の人がほとんどで、「旭油化」は多くの方が認識していて、まともな会社ではないことは地元には広く知られていた。お客から「旭油化」はどこに行ったのかと聞かれることもあったので、地域の要請に応えて旭油化跡地を買い取り、宅地開発したと説明していた。
上司から「旭油化」は食品油を使用し石けん油を製造していたと聞いていたので、お客の質問にはそのように答えていた。だから販売に際しては値引きするようなことはなく近隣相場で販売していた。
(被告足立弁護士)
土はどんな状態?
(B証人)
黒っぽい土が出てきたことはあるが黒い水はない。土は乾いた状態であり、黒い土は部分的に出てきた。
(被告足立弁護士)
黒い土はどこから?
(B証人)
私が見たのは、竹中邸の掘り抜きの駐車場を造るときと、川上邸の浄化槽の穴を掘ったとき。
(被告足立弁護士)
(平成20年の裁判所現地視察時撮影の写真を提示しながら)このような状態ではなかった?
(B証人)
このような真っ黒でドロドロした状態は見たことがない。水分はなかったし、土の色は灰色だった。他の箇所からも出てきたかもしれないが、それは私には分からない。
(裁判長)
環境基準を検討しようと思っていますが、客観的な資料をどちらか提出してもらえませんか?もちろん一般的な資料は裁判所でも収集しますが。
討議の結果、双方の立場で環境基準の資料を提出することになった。
(原告河田弁護士)
原告は次回最終準備書面をまとめたい。
(裁判長)
被告はどうですか?
(被告足立弁護士)
被告も同じ。ただ原告準備書面が提出されて相当程度期間をおいた後でないと。
(原告河田弁護士)
新たな主張をするものではありません。
(裁判長)
原告の準備書面はいつ頃?
(原告河田弁護士)
1か月半から2か月程度あとに。
<日程調整討議をする。>
(裁判長)
では、次回は12月21日(火)10:00から弁論を行い、終結予定とします。12月14日までにそれぞれ準備書面を提出してください。
裁判終了時刻、15時27分。
第22回口頭弁論に訴訟第一次(3世帯)原告住民が提出した10月12日付け証拠資料
事件番号 平成19年(ワ)第1352号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
証拠説明書
平成22年10月12日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河 田 英 正
番号 標 目(原本写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 備考
32 回答書 原本 H18.2.14 岡山市水道事業管理者 被告に当初から廃油工場跡地を造成するとの認識のあった事実
33 「廃白土」について 写し H22.10.10 前橋工科大学梅津研究室(ホームページから) 廃白土は廃油精製の工程で排出される処理の困難な産業廃棄物であること
34 廃掃法の運用に伴う通知 写し S46.10.25(公布) H14.5.21 廃白土は汚泥に分類され、廃油との混合物として取り扱われていて、産業廃棄物として厳格に処理が必要とされている事実。
(甲第)32(号証)
岡山市水道局の回答書(原本)
「小鳥が丘団地救済協議会」ホームページメニュー
「不思議な岡山市水道局の工事」内の<岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書>として掲載したもの。
<抜粋>、平成18年2月14日付け回答書
【質問】
なぜ、小鳥が丘団地に鉛製給水管を使用したのか
【回答】
小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから、樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認したものです。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/suidoukyoku01.html
(甲第)33(号証)廃白土について(写し)
該当ホームページ
1、廃白土の処理
油の精製過程で広く使用されている白土は、含油廃白土として排出される。
廃油精製の工程で、オリバーフィルタによって油中から分離された廃白土は、通常40%前後の油分を含む。
したがって、そのままの形状で投棄することはできず、廃白土中の油分は除去しなければならない。
廃白土中の油分を除去する方法としては、
① 溶剤によって油分を抽出し、白土の再生と油分の回収をはかる。
② 含油廃白土中の油分を焼却する。
①の溶剤抽出法は設備費、およびランニングコストがかさむため、回収される油の付加価値を考慮して採用される。
この方法で白土中の油分を抽出し、白土の再生利用をはかっても、何回か繰り返すうちに、白土は活性を失うので含油廃白土として排出される。
②の焼却法は廃白土中の油分を燃焼室で焼却する方法であり、①の溶剤抽出法で排出される含油廃白土の処理とあわせて投棄するために必要な処理方法である。
2、廃白土の焼却
油の処理過程で得られる廃白土中には水分もなく、発熱量も3000kcal/kg以上あるので自燃可能である。
含油廃白土は100μ以下の白土粉末に油が二次的に含浸したものであるから、石灰系の粉体燃料と比較して流動性がはるかに悪く、手で軽く押さえつけるだけで簡単に固まる。
流動性の悪い廃白土の焼却にはロータリキルンや、立て形多段焼却炉がある。が、設備費がかさむ割には燃焼に長時間を要する。また、廃油と混合してスラリー状として高圧噴霧し、微粒化させて焼却する噴霧燃焼法などがある。
廃白土の燃焼の際、とくに留意すべきことは、燃焼時にダスト(白土)が飛散することである。
白土の微粒子は燃焼ガスに同伴してきわめて飛散しやすいため、排ガス中のダスト除去対策を十分考慮しなければならない。
参考文献:廃棄物の処理・再利用
http://oo.spokon.net/mutou/hp/haihakudo.html
(甲第)34(号証)廃掃法の運用に伴う通知(写し)該当ホームページ
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】
公布日:昭和46年10月25日
環整45号
平成一四年五月二一日 環廃産二九四号
(各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて 厚生雀環境衛生局環境整備課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行については、下記の事項に留意して運用されたく通知する。
記
第一 廃棄物の範囲等に関すること
1 廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
法第二条第一項の規定は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行つたものであること。
2 廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあつては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によつて措置されるものであること。
なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。
3 産業廃棄物は、事業活動に伴つて生ずる廃棄物であり、事業活動というのは反覆継続して行なわれるものであるから、排出源において単一の産業廃棄物としてとらえられる場合が比較的多いものであるが、産業廃棄物がいくつか混合した状態で排出された場合には、廃棄物処理法第二条第四項に規定する六種類の産業廃棄物及び廃棄物処理法施行令第二条に規定する十三種類の産業廃棄物が複合した形態で排出されたものとみなしてとらえるものとし、たとえば「硫酸ピッチ」にあつては、廃酸と廃油の混合物としてとらえるものとすること。
また、定義の不明な事業活動に伴つて生ずる廃棄物にあつては、排出源、排出されるに至る過程、排出された時点での物の組成内容等を明記した上で、当局と協議し、その運用の円滑な推進を期するものであること。
4 廃棄物処理法第二条第四項及び令第二条に規定された産業廃棄物の内容は、別紙に示すとおりであること。
5 下水道法に規定する下水道から除去した汚でいは、産業廃棄物として取り扱うものであること。
第二 産業廃棄物処理施設の範囲に関すること
1 令第七条第一号、第二号及び第三号に掲げる施設は、汚でいの処理を行なうための施設であつて、それぞれ汚でいの脱水、乾燥及び焼却を目的とする施設であること。
2 令第七条第四号及び第五号に掲げる施設は、廃油の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃油の油水分離及び焼却を目的とする施設であること。
3 令第七条第六号に掲げる施設は、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、廃酸又は廃アルカリの中和を目的とする施設であり、中和槽を有するものであること。ただし、放流を目的とする一般の廃水処理に係る中和施設は除くものとする。
4 令第七条第七号及び第八号に掲げる施設は、廃プラスチック類の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃プラスチック類の破砕及び焼却を目的とする施設であること。
5 令第七条第九号に掲げる施設は、令別表下欄に掲げる有害物質を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でいをコンクリート固型化し、汚でい中に含まれる有害物質が漏れないように加工することを目的とする施設であること。
6 令第七条第十号に掲げる施設は、水銀又はその化合物を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でい中に含まれる水銀又はその化合物をばい焼により硫化物とし、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令における処分の態様に応じて定める判定基準に適合させることを目的とする施設であるが、水銀又はその化合物から水銀蒸気となつて水銀が気散する部分は捕集し、回収できる構造を有する施設であること。
7 令第七条第十一号に掲げる施設は、シアン化合物を含む汚でい、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、熱分解、電気分解、アルカリ塩素法分解等によつて処理し、汚でいを判定基準に適合するものにし、又は廃酸若しくは廃アルカリにシアン化合物が含まれないようにすることを目的とする施設であること。
8 令第七条第十二号の二に掲げる施設は、廃PCB等又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、脱塩素化法又は超臨界水酸化法による分解によって処理し、廃PCB等又はPCB処理物にPCBが含まれないようにすることを目的とする施設であること。
9 令第七条第十三号に掲げる施設は、PCB汚染物又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、PCBを除去することを目的とする施設であること。
10 令第七条第十三号の二に掲げる施設は、汚泥、廃油又は廃プラスチック以外の産業廃棄物の処理を行うための施設であって、当該産業廃棄物の焼却を目的とする施設であること。
11 令第七条第十四号に掲げる施設は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分を目的とする施設であること。
12 令第七条に規定する産業廃棄物処理施設は、いずれも独立した施設としてとらえ得るものであつて、工場又は事業場内のプラントの一部として組み込まれたものは含まないものであること。
13 令第七条に掲げる施設の処理能力は、その施設が標準運転時間に処理できる廃棄物の量をもつて表わすもので、いわゆる施設の公称能力である。したがつて、たとえば一日の標準運転時間が八時間のものは、一時間当りの処理能力の八時間ぶんをもつて表わす。
第四 産業廃棄物処理施設の維持管理等に関すること。
産業廃棄物処理施設の維持管理に関しては、次の点に留意するよう関係者を指導されたいこと。
1 産業廃棄物は、円形状、でい状及び液状を呈し、その種類は多様であり、かっ、有害物質を含むものもすくなくないので、焼却、ばい焼、中和、コンクリート固形化等による安全化又は安定化及び焼却、脱水、乾燥、破砕、圧縮等による減量化に努めなければならないこと。
このような処分は、その操作に伴なつて大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等を惹起する可能性があるので、施設の設計段階でこの点について考慮するとともに、技術管理者は、施設の基本設計と運転仕様を熟知し、規則第十二条の六及び第十二条の七の維持管理基準を遵守しなければならないものであること。
なお、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等他の公害防止関係法令による基準が設定されている場合は、これらの基準の遵守を目標に維持管理等を行なわなければならないこと。
2 規則第十二条の六第七項において規定している排水にあたつての放流水の水質基準は、その放流水が直接に公共の水域に排出される単独施設の場合に適用されるものであつて、水質汚濁防止法第二条第四項に規定する特定事業場内において他の排水と混合して放流される場合には、水質汚濁防止法第三条の規定に基づく排水基準に従うことはいうまでもないこと。
3 規則第十二条第一項の機能点検は毎月一回以上行なうこと。
4 以上のほか、第三の2、3、4及び6に準じて行なうようにすること。
(別紙)
(1) 燃えがら 電気事業等の事業活動に伴つて生ずる石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物等が代表的なものであり、集じん装置に捕捉されたものはダスト類として令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物として取り扱うものであること。
その他熱エネルギー源を物の燃焼に依存している場合の焼却残灰、炉清掃掃出物等についても同様の取扱いとするものであること。
(2) 汚でい
工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであつて、有機質の多分に混入したどろのみを指すのではなく、有機性及び無機性のもののすべてを含むものであること。有機性汚でいの代表的なものとしては、活性汚でい法による処理後の汚でい、パルブ廃液から生ずる汚でい、その他動植物性原料を使用する各種製造業の廃水処理後に生ずる汚でい、ビルピット汚でいがあること。
無機性汚でいの代表的なものとしては、赤でい、けい藻土かす、炭酸カルシウムかす、廃白土、浄水場の沈でん池より生ずる汚でいがあること。ただし、赤でいにあつては、廃アルカリとの混合物として、廃白土にあつては、廃油との混合物として取り扱うものであること。
(3) 廃 油
鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油を含むものとし、潤滑油系、絶縁油糸、洗浄用油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類(常温において固形状を呈するものに限る。)があること。硫酸ピッチ及びタンクスラッジは、それぞれ廃油と廃酸の混合物及び廃油と汚でいの混合物として取り扱うものであること。
(4) 廃 酸
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類をはじめ酸性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、アルコール又は食用のアミノ酸の製造に伴つて生じた発酵廃液は廃酸に該当するものであること。廃酸は、液状の産業廃棄物であるが、水素イオン濃度指数を五・八以上八・六以下に調整した場合に生ずる沈でん物は汚でいと同様に取り扱つて差し支えないものであること。
(5) 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せつけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、カーバイトかすは、廃アルカリとしてではなく汚でいとして取り扱い、埋立処分にあたつては、浸出液の処理を行なうこと。廃アルカリの水素イオソ濃度指数を調整した場合に生ずる沈でん物の取扱いは、廃酸の場合と同様とするものであること。なお、工場廃液は、(4)若しくは(5)又は(4)及び(5)の混合物として取り扱うものであること。
(6) 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むものであること。
(7) 令第二条第一号に掲げる産業廃棄物 「紙くず」という。
産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる紙くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一八、小分類一九一のうち新聞巻取紙を使用して印刷発行を行なう細分類一九一一、細分類一九二一のうち印刷出版を行なうもの、細分類一九五一及び一九五二に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる紙くずであつて、壁紙、障子、紙、板紙等の古紙が含まれるものであること。
(8) 令第二条第二号に掲げる産業廃棄物 「木くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くずであつて工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴つて生じたもの、中分類一六、小分類一七一及び一八ーに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くず並びに輸入木材の輸入を業務の一部又は全部として行なつている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くずであつておがくず、バーク類等が含まれるものであること。
(9) 令第二条第三号に掲げる産業廃棄物 「繊維くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる繊維くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一四に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる繊維くずであつて、畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずが含まれるものであること。
(10) 令第二条第四号に掲げる産業廃棄物 「動植物性残さ」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による中分類一二及び一三(小分類一三五を除く。)、小分類二〇六及び細分類二〇九三に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動植物性残さであって、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等が含まれるものであること。魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物として取り扱うものであること。
(11) 令第二条第四号の二に掲げる産業廃棄物 「動物系固形不要物」という。と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等により生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要とされるものが含まれるものであること。
なお、家畜の解体等に伴い発生する血液等の液体の不要物は、産業廃棄物たる廃酸又は廃アルカリとして扱うこと。
(12) 令第二条第五号に掲げる産業廃棄物 天然ゴムくずが含まれるものであること。
(13) 令第二条第六号に掲げる産業廃棄物 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等が含まれるものであること。
(14) 令第二条第七号に掲げる産業廃棄物 「ガラスくず」という。ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず、陶磁器くず等が含まれるものであること。ただし、コンクリートくずについては、令第二条第九号に掲げる産業廃棄物に含まれるものは除かれること。
(15) 令第二条第八号に掲げる産業廃棄物 高炉、平炉等の残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等が含まれるものであること。
(16) 令第二条第九号に掲げる産業廃棄物 「がれき類」という。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他各種の廃材の混合物を含むものであって、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じた物を除くものであること。ただし、地下鉄の工事現場等から排出される含水率が高く、粒子の微細なでい状のものにあっては、無機性の汚でいとして取り扱うものであること。
(17) 令第二条第十号に掲げる産業廃棄物 「家畜ふん尿」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物のふん尿(畜舎廃水を含む。)であって、牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿が含まれるものであること。なお、家畜ふん尿を動物のふん尿処理施設において処理した後に生じるでい状物は、汚でいに該当するものであること。
(18) 令第二条第十一号に掲げる産業廃棄物 「家畜の死体」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物の死体であって、動物の種類は、ふん尿の場合と同様であること。
(19) 令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物 「ダスト類」という。産業廃棄物に該当するものは、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において発生するばいじんであつて、集じん施設において捕捉されたものであること。なお、集じん施設の集じん方法は、乾式、湿式のいずれの方法であるかは問わないものであること。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000510
原告が提出した10月12日付け証拠資料以上。
第22回口頭弁論は、13時29分に始まり15時27分に終わりました。
裁判を終わっての感想です。
今回、原告(住民)が証拠資料として提出した、「甲第32号証(岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書(原本))」、
『小鳥が丘団地の鉛製給水管使用について(回答)』
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/suidoukyoku01.html
にあるように、
開発当時の、「小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であった」、ことが明らかであり、「両備」の主張する食品油を使用した石けん製造工場の跡地というよりも、水道局の回答書でも、「廃油工場跡地」、とはっきり記載されています。
開発当時の給水協議で、水道管を鉛管にすることが決定されており、ディベロッパー(宅地開発業者)の「両備」がそれを知らないはずはないと思います。
また、宅地に埋設する上水道管として、「樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認した」、土地であることを開発業者の「両備」は認識していたと思われます。
最後に、原告代理人河田弁護士のブログに、この日のことが書いてありましたので、紹介します。
「河田英正のブログ」、2010年10月17日付、下段に感想が載っています。
小鳥が丘団地の土壌汚染問題に関して,会社側の証人尋問を行った。当時,新聞報道にされて公の事実となっていたことでさえ,会社側の当時の事件処理担当者だった証人は,そのような事実は知らなかったという証言であった。一社員として,あくまでも会社を守ろうとして,頑なに事実を語ろうとしない証言態度には,かつての公害裁判でどの裁判においても企業利益を優先する態度をとってきたことが思い起こされ,「企業は悪者」という図式に変わることはないことを思い知らされた。
http://www.d-mc.ne.jp/blog/kawada/article.php?id=1250
次回第23回口頭弁論は、2010年12月21日(火)10時00分~、岡山地方裁判所で(公開)実施の予定で、原告・被告双方の最終答弁 (終結予定)です。
以上。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後6年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(訴訟第一次)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(訴訟第二次)も続いて提訴し係争中です。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/51343668.html
鉛製給水管について
1.水質基準の強化
鉛の水質基準は、平成4年に0.1mg/リットル以下から0.05mg/リットル以下に改められました。この値は、毎日水道水を飲用しても日本人の健康に問題がないとして制定されていましたが、平成15年度からWHO(世界保健機構)の「飲料水のガイドライン」にあわせ、0.01mg/リットル以下へと強化されました。
2.鉛製給水管の使用経過
鉛は金属としては柔らかい材質であるため、加工しやすく給水管などの材質として広く普及していましたが、硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の普及に伴い、岡山市では昭和53年3月以降鉛管の使用を中止しました。したがって、それ以前から水道を利用されている場合には、鉛製給水管が使用されている可能性があります。
http://www.water.okayama.okayama.jp/guest/kyusui4.htm
岡山市水道局へ「小鳥が丘の鉛管使用について」下記の公開質問状提出したところ
「小鳥が丘団地が開発された昭和62年当時岡山市はすでに鉛管の使用を止めていたのに何故当団地で使用したのか?」
同月14日、下記の回答書受領した。
「開発当時の給水協議に際し廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから樹脂系のポリエチレン管は変質する恐れがあり鉛管の使用を承認した。」
両備ホールディングス環 境 方 針
両備ホールディングス株式会社は、事業活動を通じて、環境保全活動に取組み、安全と高品質なサービスを提供することにより、 地域の発展と自然環境の保護に努めます。
両備ホールディングス株式会社 取締役社長 小 嶋 光 信