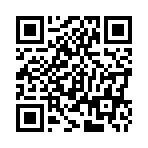2009年10月31日
チッソ水俣病 損害賠償,仮執行の原状回復等請求上告
事件番号 平成13(オ)1194
事件名 損害賠償,仮執行の原状回復等請求上告,同附帯上告事件
判示事項
1 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
2 熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
3 水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例
裁判要旨
1 国が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,同工場の排水に含まれる微量の水銀の定量分析をすることが可能であったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律に基づいて,指定水域の指定,水質基準及び特定施設の定めをし,上記製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,同施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
2 熊本県が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,旧熊本県漁業調整規則に基づいて,上記製造施設からの工場排水につき除害に必要な設備の設置を命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
3 水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となる。
参照法条
国家賠償法1条1項,公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの)1条,
公共用水域の水質の保全に関する法律5条,
工場排水等の規制に関する法律1条,
裁判年月日 平成16年10月15日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成6(ネ)1950
原審裁判年月日 平成13年04月27日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=
dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25100&hanreiKbn=01
主 文
1 原判決のうち,被上告人X22,同X23,同X53,同X54,同X55,同X64,同X65,同X66,同X67及び同X68の上告人らに対する請求を認容した部分を破棄する。
2 前項の部分につき,上記被上告人らの控訴をいずれも棄却する。
3 原判決のうち,被上告人X36,同X51及び同X52の上告人らに対する請求に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 上告人らは,各自,被上告人X36,同X51及び同X52に対し,各25万円及びこれに対する昭和57年12月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被上告人X36,同X51及び同X52の上告人らに対するその余の控訴をいずれも棄却する。
4 上告人らのその余の上告及び附帯上告人らの附帯上告をいずれも棄却する。
5 第1項記載の部分に関する控訴費用及び上告費用は同項記載の被上告人らの負担とし,第3項記載の部分に関する訴訟の総費用は,これを10分し,その1を上告人らの,その余を同項記載の被上告人らの各負担とし,前項の部分に関する上告費用は上告人らの負担とし,附帯上告費用は附帯上告人らの負担とする。
理 由
第1 事案の概要
1 被上告人らは,水俣病の患者であると主張する者(原判決別紙「結果一覧表」の患者氏名欄記載の58名のうち,患者番号13〜15,28,41,42,44,46,47,52,53,58,59の13名を除く45名。以下「本件患者」と総称する。)又はその承継人である。本件は,被上告人らが,上告人らは水俣病の発生及び被害拡大の防止のために規制権限を行使することを怠ったことにつき国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うなどと主張して,上告人らに対し,損害賠償を請求する訴訟である。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 水俣病は,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を多量に摂取したことによって起こる中毒性中枢神経疾患である。
その主要な症状としては,感覚障害,運動失調,求心性視野狭さく,聴力障害,言語障害等がある。
個々の患者には重症例から軽症例まで多様な形態がみられ,症状が重篤なときは,死亡するに至る。
水俣病の原因物質は,有機水銀化合物の一種であるメチル水銀化合物であり,これは,チッソ株式会社(昭和40年に商号を変更する前の商号は,新日本窒素肥料株式会社。以下「チッソ」という。)水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成され,同工場の排水に含まれて工場外に流出したものであった。水俣病は,このメチル水銀化合物が,魚介類の体内に蓄積され,その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれ,大脳,小脳等に蓄積し,神経細胞に障害を与えることによって引き起こされた疾病である。
(2) 本件患者らは,かつて水俣湾周辺地域に居住し,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取していた。本件患者らのうち,A(患者番号16),X23(同17),X36(同24),X51(同32),X52(同33),B(同34),C(同45),X68(同49)は昭和34年12月末までに,それ以外の者は昭和35年1月以降に,関西方面に転居した。
(3) 昭和31年5月1日,チッソ水俣工場附属病院の医師が,水俣保健所に対し,水俣市内において脳症状を呈する原因不明の患者が発生した旨の報告をした。公的機関が水俣病の存在を認識したのはこれが初めてであり,この時が水俣病の「公式発見」と呼ばれる。この報告を受けた水俣保健所等が調査をしたところ,昭和28年ころから同様の症状を呈する患者が発生していたこと,昭和32年1月の時点で54名の患者が発生し,うち17名が死亡していたことが判明した。
(4) 水俣病の原因については,上記公式発見以降,水俣保健所,熊本大学医学部の水俣病医学研究班(以下「熊大研究班」という。),厚生省(以下,省庁名,官職名等は,いずれも当時のものである。)の厚生科学研究班等により,調査や研究が行われた。原因究明は困難を極めたが,昭和31年11月開催の熊大研究班の研究報告会において魚介類との関係が一応疑われるとの報告がされ,昭和32年1月開催の国立公衆衛生院での上告人国,上告人県の関係者も参加した合同研究発表会において魚介類の摂取が原因であるとの一応の結論に達した。
上告人県は,水俣市の住民に対して水俣湾の魚介類を摂取しないように呼び掛けるとともに,湾内での漁業を自粛するよう,地元の漁業協同組合に申し入れた。このような行政指導の結果,昭和31年12月以降,しばらくの間は,新たな患者の発生がみられなくなった。
昭和32年7月開催の厚生科学研究班の研究報告会において,水俣病は,感染症ではなく,中毒症であり,何らかの化学物質によって汚染された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであるとの結論が示されたが,原因物質が何であるかは不明のままであり,当時は,マンガン,タリウム,セレン等の物質が疑われていた。
昭和33年6月開催の参議院社会労働委員会において,厚生省環境衛生部長は,水俣病の原因物質は水俣市の肥料工場から流失したと推定されるとの発言をした。
また,同年7月,同省公衆衛生局長は,関係省庁及び上告人県に対して発した文書により,水俣病はある種の化学毒物によって有毒化された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであり,肥料工場の廃棄物によって魚介類が有毒化されると推定した上で,水俣病の対策について一層効率的な措置を講ずることを要望した。
他方,通商産業省(以下「通産省」という。)軽工業局長は,同年9月ころ,厚生省に対し,水俣病の原因が確定していない現段階において断定的な見解を述べることがないよう申し入れた。
(5) 昭和33年8月,新たな水俣病患者の発生が確認された。この患者は,水俣湾の魚介類を自ら捕獲して,多量に摂取したものであった。
上告人県は,水俣湾の魚介類を摂取しないことを周知徹底させるべく,住民に対して改めて広報活動を行うとともに,地元の漁業協同組合に対し漁業を自粛するよう申し入れた。
(6) 昭和33年9月,チッソは,アセトアルデヒド製造施設からの排水の放出経路を,水俣湾内にある百間港から湾外の水俣川河口付近へと変更した。その結果,昭和34年3月以降,水俣湾外の海域で漁獲された魚介類を多食していた者についても水俣病の発症が確認され,湾外の魚介類も危険視されることとなった。
(7) 昭和34年3月刊行の熊大研究班の報告書に,水俣病の症状が有機水銀中毒の症状(いわゆるハンター・ラッセル症候群)と一致する旨を述べた論文が掲載された。
熊大研究班は,その後も調査研究を続け,同年7月22日に開催された研究報告会において,水俣病は現地の魚介類を摂取することによって引き起こされる神経系疾患であり,魚介類を汚染する毒物としては水銀が極めて注目されるに至ったと発表した。
また,厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会の特別部会として昭和34年1月に発足した水俣食中毒部会は,同年10月6日,水俣病は有機水銀中毒症に酷似しており,その原因物質としては水銀が最も重要視されるとの中間報告を行った。
同年11月12日,食品衛生調査会は,この中間報告に基づいて,水俣病の主因を成すものはある種の有機水銀化合物であるとの結論を出し,厚生大臣に対してその旨を答申した。
水俣食中毒部会は,この答申によりその目的を達したとして,そのころ解散した。その後,水俣病の原因についての総合的な調査研究は,経済企画庁が中心となり,厚生省,通産省及び水産庁が分担して行うものとされた。
なお,昭和34年10月ころ,チッソ水俣工場附属病院の医師が行った実験により,チッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設の排水を経口投与したネコに水俣病と同様の症状が現れることが認められた。
ところが,チッソは,実験の続行を中止し,この実験結果を公表しなかった。
(8) 上告人らが把握していた昭和34年8月現在の水俣病患者の発生状況は,患者数71名,死亡者28名であった。通産省は,そのころ,水俣病が現地において極めて深刻な問題となっている状況にかんがみ,チッソ水俣工場に対し,口頭で,水俣川河口への排水路を廃止すること,排水処理装置の完備を急ぐこと,原因究明のための調査に十分協力することを求める行政指導を行った。
また,通産省は,同年10月末から11月にかけて,厚生省公衆衛生局長,水産庁長官等から,チッソ水俣工場の排水に対して適切な処置を至急講ずるよう求める旨の要望を受けたので,チッソの社長あてに文書を送付して,一刻も早く排水処理施設を
完備することなどを求めた。
昭和34年12月,サイクレーター,セディフローターを主体とする排水浄化装置がチッソ水俣工場に設置された。チッソは,これによって工場排水が浄化される旨を強調したが,この装置は水銀の除去を目的とするものではなかった。
そのことは,多少の化学知識のある者が,上記装置の設計図等を見れば,容易に知ることができた。
(9) 昭和34年12月,熊本県知事らのあっせんにより,チッソと熊本県漁業協同組合連合会との間に漁業補償に関する契約が,水俣病患者家庭互助会との間に見舞金の支払に関する契約が,それぞれ締結された。
(10) 昭和34年当時の総水銀(有機水銀化合物に加え,金属水銀,無機水銀化合物を含むもの)の一般的な定量分析技術においては,0.01ppmが定量分析の限界であるとされていたが,工業技術院東京工業試験所は,同年11月下旬ころには,独自に工夫した方法によって総水銀について0.001ppmレベルまで定量分析し得る技術を有していた。同試験所は,そのころから昭和35年8月までの間,通産省の依頼を受けて,チッソ水俣工場の排水中の総水銀を定量分析し,0.002〜0.084ppmの総水銀が検出されたとの検査結果を報告した。
(11) 上告人らは,遅くとも昭和34年11月末ころまでには,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であること,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあった。
また,上告人らにおいて,そのころまでには,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析は可能であったし,チッソが整備した上記排水浄化施設が水銀の除去を目的としたものではなかったことも容易に知ることができた。
(12) 昭和43年5月,チッソは,水俣工場におけるアセトアルデヒドの製造を取りやめた。これにより,同工場からメチル水銀化合物が排出されることはなくなった。
同年9月,上告人国は,水俣病はチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成されたメチル水銀化合物が原因で発生したものである旨の政府見解を発表した。昭和44年,水俣湾及びその周辺海域について,後述する水質二法に基づく指定水域の指定等がされた。
第2 平成13年(オ)第1194号上告代理人都築弘ほかの上告理由について
1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
2 所論にかんがみ,職権により判断する。
前記の事実関係の下において,上告人らが,昭和35年1月以降,チッソ水俣工場の排水に関して規制権限を行使しなかったことが違法であり,上告人らは,同月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害の拡大があった者に対して国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,後述のとおり,正当として是認することができる。そうすると,本件患者らのうち,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域からその地域外へ転居した者については,水俣病となったことによる
損害を受けているとしても,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係を認めることはできない。ところが,原審は,本件患者らのうちA,X23,X36,X51,X52,B,C,X68について,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域から転居したとの事実を認定しながら,上記8名の本件患者に係る損害賠償請求を一部認容したものであって,原判決には,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係の存否の判断につき,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるといわざるを得ない。
したがって,原判決のうち,上記8名の本件患者ら又はその承継人である被上告人X22,同X23,同X36,同X51,同X52,同X53,同X54,同X55,同X64,同X65,同X66,同X67及び同X68の上告人らに対する請求(ただし,被上告人X36,同X51及び同X52については,D(患者番号31)の承継人として請求する部分を除く。)を認容した部分は,破棄を免れない。
そして,同部分に係る上記被上告人らの請求を棄却した第1審判決は,結論において是認することができるから,同部分についての上記被上告人らの控訴はいずれも棄却されるべきものである。
第3 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第3及び第4について
1 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの。以下「水質保全法」という。)及び工場排水等の規制に関する法律(以下「工場排水規制法」という。また,水質保全法と併せて,「水質二法」という。)は,昭和33年12月25日に公布され,昭和34年3月1日に施行された(その後,水質二法は,昭和45年12月に公布された水質汚濁防止法の施行に伴って廃止された。)。
水質保全法は,公共用水域の水質の保全を図るなどのために必要な事項を定め,もって産業の相互協和と公衆衛生の向上
に寄与することを目的とするものであり(同法1条),工場排水規制法は,製造業等における事業活動に伴って発生する汚水等の処理を適切にすることにより,公共用水域の水質の保全を図ることを目的とするものである(同法1条)。
水質二法による工場排水規制の概要は,次のとおりである。
経済企画庁長官は,公共用水域のうち,水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の被害が生じ,若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを「指定水域」として指定するとともに(水質保全法5条1項),当該指定水域に係る「水質基準」を定めるものとされている(同条2項)。
水質基準とは,「特定施設」を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度であり(同法3条2項),特定施設とは,製造業等の用に供する施設のうち,汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出するもので政令で定めるものである(工場排水規制法2条2項)。また,主務大臣(特定施設の種類ごとに,政令により定められる。同法21条1項)は,工場排水の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは,これを排出する者に対し,汚水等の処理方法に関する計画の変更,特定施設の設置に関する計画の変更等を命ずること(同法7条),汚水等の処理方法の改善,特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を執るべき旨を命ずること(同法12条)等の,特定施設から排出される工場排水に関して規制を
行う権限を有するものとされており,主務大臣の上記命令に違反した者は,罰則を科される(同法23条)。
2 熊本県漁業調整規則は,漁業法65条及び水産資源保護法4条の規定に基づいて制定されたものであり,水産動植物の繁殖保
護,漁業取締りその他漁業調整を図り,併せて漁業秩序の確立を期するため,必要な事項を定めることを目的とするものである(県漁業調整規則1条)。
県漁業調整規則は,何人も水産動植物の繁殖保護に有害な物を遺棄し,又は漏せつするおそれのあるものを放置してはならない旨を定め,これに違反する者があるときは,熊本県知事は,その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ,又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができるものとされている(同規則32条)。上記の規定又は命令に違反した者に対しては罰則が科される(同58条)。
3 原審は,前記の事実関係の下において,チッソ水俣工場の排水につき,上告人国においては上記の水質二法に基づく規制権限を,上告人県においては上記の県漁業調整規則に基づく規制権限を,それぞれ行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,昭和35年1月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害が拡大した者に対して,同項による損害賠償責任を負うと判断した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,水質二法,県漁業調整規則の関係規定及び国家賠償法1条1項の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
4 そこで,以下,この点について検討する。
(1) 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6号1600頁参照)。
(2) これを本件についてみると,まず,上告人国の責任については,次のとおりである。
ア 水質二法所定の前記規制は,
? 特定の公共用水域の水質の汚濁が原因となって,関係産業に相当の損害が生じたり,公衆衛生上看過し難い影響が生じたりしたとき,又はそれらのおそれがあるときに,当該水域を指定水域に指定し,この指定水域に係る水質基準(特定施設を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度)を定めること,汚水等を排出する施設を特定施設として政令で定めることといった水質二法所定の手続が執られたことを前提として,
? 主務大臣が,工場排水規制法7条,12条に基づき,特定施設から排出される工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないときに,その水質を保全するため,工場排水についての処理方法の改善,当該特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を命ずる等の規制権限を行使するものである。そして,この権限は,当該水域の水質の悪化にかかわりのある周辺住民の生命,健康の保護をその主要な目的の一つとして,適時にかつ適切に行使されるべきものである。
イ 【要旨1】
前記の事実関係によれば,昭和34年11月末の時点で,
? 昭和31年5月1日の水俣病の公式発見から起算しても既に約3年半が経過しており,その間,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取する住民の生命,健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続していたのであって,上告人国は,現に多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていることを認識していたこと,
? 上告人国においては,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,
? 上告人国にとって,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析をすることは可能であったことといった事情を認めることができる。なお,チッソが昭和34年12月に整備した前記排水浄化装置が水銀の除去を目的としたものではなかったことを容易に知り得たことも,前記認定のとおりである。
そうすると,同年11月末の時点において,水俣湾及びその周辺海域を指定水域に指定すること,当該指定水域に排出される工場排水から水銀又はその化合物が検出されないという水質基準を定めること,アセトアルデヒド製造施設を特定施設に定めることという上記規制権限を行使するために必要な水質二法所定の手続を直ちに執ることが可能であり,また,そうすべき状況にあったものといわなければならない。
そして,この手続に要する期間を考慮に入れても,同年12月末には,主務大臣として定められるべき通商産業大臣において,上記規制権限を行使して,チッソに対し水俣工場のアセトアルデヒド製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,当該施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずることが可能であり,しかも,水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると,直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当である。
また,この時点で上記規制権限が行使されていれば,それ以降の水俣病の被害拡大を防ぐことができたこと,ところが,実際には,その行使がされなかったために,被害が拡大する結果となったことも明らかである。
ウ 本件における以上の諸事情を総合すると,昭和35年1月以降,水質二法に基づく上記規制権限を行使しなかったことは,上記規制権限を定めた水質二法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法というべきである。
したがって,同項による上告人国の損害賠償責任を認めた原審の判断は,正当として是認することができる。この点に関する上告人国の論旨は採用することができない。
(3) 次に,【要旨2】
上告人県の責任についてみると,以上説示したところによれば,前記事実関係の下において,熊本県知事は,水俣病にかかわる前記諸事情について上告人国と同様の認識を有し,又は有し得る状況にあったのであり,同知事には,昭和34年12月末までに県漁業調整規則32条に基づく規制権限を行使すべき作為義務があり,昭和35年1月以降,この権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くものであるとして,上告人県が国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,同規則が,水産動植物の繁殖保護等を直接の目的とするものではあるが,それを摂取する者の健康の保持等をもその究極の目的とするものであると解されることからすれば,是認することができる。
この点に関する上告人県の論旨を採用することはできない。
第4 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第5について
1 被上告人らの上告人らに対する請求(前記第2で判示したところにより棄却されるべき部分を除く。)については,国家賠償法4条,民法724条後段所定の除斥期間の適用の有無が問題となるところ,原審は,その適用を否定した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,上記各規定の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
2 そこで,以下,この点について検討する。
(1) 民法724条後段所定の除斥期間は,「不法行為ノ時ヨリ二十年」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となると考えられる。
しかし,身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解するのが相当である。
このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間が進行することを認めることは,被害者にとって著しく酷であるだけでなく,加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過した後に損害が発生し,被害者から損害賠償の請求を受けることがあることを予期すべきであると考えられるからである。原審の判断は,以上の趣旨をいうものとして,是認することができる。論旨は採用することができない。
(2) 【要旨3】
上記見解に立って本件をみると,本件患者のそれぞれが水俣湾周辺地域から他の地域へ転居した時点が各自についての加害行為の終了した時であるが,水俣病患者の中には,潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては,水俣湾又はその周辺海域の魚介類の摂取を中止してから4年以内に水俣病の症状が客観的に現れることなど,原審の認定した事実関係の下では,上記転居から遅くとも4年を経過した時点が本件における除斥期間の起算点となるとした原審の判断も,是認し得るものということができる。この点に関する上告人らの論旨も採用することができない。
第5 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかのその余の上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
第6 平成13年(オ)第1196号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告理由について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件附帯上告の理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
第7 平成13年(受)第1174号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
第8 結論
以上によれば,上告人らの上告は,前記第2の限度で理由があるから,主文第1項記載の部分につき原判決を破棄し,同第3項記載の部分につき原判決を変更すべきものであるが,その余の上告はいずれも理由がないので,これを棄却することとする。また,附帯上告人らの附帯上告には理由がないので,これを棄却する。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田 博 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/67930C1EA789333049257029002690BE.pdf

「奇病のかげに」は、熊本県の水俣病を工場公害ではないかと告発した
踊り回る猫(3コマ目)の姿は「奇病」の本質をとらえた。小倉一郎の作品。

事件名 損害賠償,仮執行の原状回復等請求上告,同附帯上告事件
判示事項
1 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
2 熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
3 水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例
裁判要旨
1 国が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,同工場の排水に含まれる微量の水銀の定量分析をすることが可能であったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律に基づいて,指定水域の指定,水質基準及び特定施設の定めをし,上記製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,同施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
2 熊本県が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,旧熊本県漁業調整規則に基づいて,上記製造施設からの工場排水につき除害に必要な設備の設置を命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
3 水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となる。
参照法条
国家賠償法1条1項,公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの)1条,
公共用水域の水質の保全に関する法律5条,
工場排水等の規制に関する法律1条,
裁判年月日 平成16年10月15日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成6(ネ)1950
原審裁判年月日 平成13年04月27日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=
dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25100&hanreiKbn=01
主 文
1 原判決のうち,被上告人X22,同X23,同X53,同X54,同X55,同X64,同X65,同X66,同X67及び同X68の上告人らに対する請求を認容した部分を破棄する。
2 前項の部分につき,上記被上告人らの控訴をいずれも棄却する。
3 原判決のうち,被上告人X36,同X51及び同X52の上告人らに対する請求に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 上告人らは,各自,被上告人X36,同X51及び同X52に対し,各25万円及びこれに対する昭和57年12月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被上告人X36,同X51及び同X52の上告人らに対するその余の控訴をいずれも棄却する。
4 上告人らのその余の上告及び附帯上告人らの附帯上告をいずれも棄却する。
5 第1項記載の部分に関する控訴費用及び上告費用は同項記載の被上告人らの負担とし,第3項記載の部分に関する訴訟の総費用は,これを10分し,その1を上告人らの,その余を同項記載の被上告人らの各負担とし,前項の部分に関する上告費用は上告人らの負担とし,附帯上告費用は附帯上告人らの負担とする。
理 由
第1 事案の概要
1 被上告人らは,水俣病の患者であると主張する者(原判決別紙「結果一覧表」の患者氏名欄記載の58名のうち,患者番号13〜15,28,41,42,44,46,47,52,53,58,59の13名を除く45名。以下「本件患者」と総称する。)又はその承継人である。本件は,被上告人らが,上告人らは水俣病の発生及び被害拡大の防止のために規制権限を行使することを怠ったことにつき国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うなどと主張して,上告人らに対し,損害賠償を請求する訴訟である。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 水俣病は,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を多量に摂取したことによって起こる中毒性中枢神経疾患である。
その主要な症状としては,感覚障害,運動失調,求心性視野狭さく,聴力障害,言語障害等がある。
個々の患者には重症例から軽症例まで多様な形態がみられ,症状が重篤なときは,死亡するに至る。
水俣病の原因物質は,有機水銀化合物の一種であるメチル水銀化合物であり,これは,チッソ株式会社(昭和40年に商号を変更する前の商号は,新日本窒素肥料株式会社。以下「チッソ」という。)水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成され,同工場の排水に含まれて工場外に流出したものであった。水俣病は,このメチル水銀化合物が,魚介類の体内に蓄積され,その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれ,大脳,小脳等に蓄積し,神経細胞に障害を与えることによって引き起こされた疾病である。
(2) 本件患者らは,かつて水俣湾周辺地域に居住し,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取していた。本件患者らのうち,A(患者番号16),X23(同17),X36(同24),X51(同32),X52(同33),B(同34),C(同45),X68(同49)は昭和34年12月末までに,それ以外の者は昭和35年1月以降に,関西方面に転居した。
(3) 昭和31年5月1日,チッソ水俣工場附属病院の医師が,水俣保健所に対し,水俣市内において脳症状を呈する原因不明の患者が発生した旨の報告をした。公的機関が水俣病の存在を認識したのはこれが初めてであり,この時が水俣病の「公式発見」と呼ばれる。この報告を受けた水俣保健所等が調査をしたところ,昭和28年ころから同様の症状を呈する患者が発生していたこと,昭和32年1月の時点で54名の患者が発生し,うち17名が死亡していたことが判明した。
(4) 水俣病の原因については,上記公式発見以降,水俣保健所,熊本大学医学部の水俣病医学研究班(以下「熊大研究班」という。),厚生省(以下,省庁名,官職名等は,いずれも当時のものである。)の厚生科学研究班等により,調査や研究が行われた。原因究明は困難を極めたが,昭和31年11月開催の熊大研究班の研究報告会において魚介類との関係が一応疑われるとの報告がされ,昭和32年1月開催の国立公衆衛生院での上告人国,上告人県の関係者も参加した合同研究発表会において魚介類の摂取が原因であるとの一応の結論に達した。
上告人県は,水俣市の住民に対して水俣湾の魚介類を摂取しないように呼び掛けるとともに,湾内での漁業を自粛するよう,地元の漁業協同組合に申し入れた。このような行政指導の結果,昭和31年12月以降,しばらくの間は,新たな患者の発生がみられなくなった。
昭和32年7月開催の厚生科学研究班の研究報告会において,水俣病は,感染症ではなく,中毒症であり,何らかの化学物質によって汚染された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであるとの結論が示されたが,原因物質が何であるかは不明のままであり,当時は,マンガン,タリウム,セレン等の物質が疑われていた。
昭和33年6月開催の参議院社会労働委員会において,厚生省環境衛生部長は,水俣病の原因物質は水俣市の肥料工場から流失したと推定されるとの発言をした。
また,同年7月,同省公衆衛生局長は,関係省庁及び上告人県に対して発した文書により,水俣病はある種の化学毒物によって有毒化された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであり,肥料工場の廃棄物によって魚介類が有毒化されると推定した上で,水俣病の対策について一層効率的な措置を講ずることを要望した。
他方,通商産業省(以下「通産省」という。)軽工業局長は,同年9月ころ,厚生省に対し,水俣病の原因が確定していない現段階において断定的な見解を述べることがないよう申し入れた。
(5) 昭和33年8月,新たな水俣病患者の発生が確認された。この患者は,水俣湾の魚介類を自ら捕獲して,多量に摂取したものであった。
上告人県は,水俣湾の魚介類を摂取しないことを周知徹底させるべく,住民に対して改めて広報活動を行うとともに,地元の漁業協同組合に対し漁業を自粛するよう申し入れた。
(6) 昭和33年9月,チッソは,アセトアルデヒド製造施設からの排水の放出経路を,水俣湾内にある百間港から湾外の水俣川河口付近へと変更した。その結果,昭和34年3月以降,水俣湾外の海域で漁獲された魚介類を多食していた者についても水俣病の発症が確認され,湾外の魚介類も危険視されることとなった。
(7) 昭和34年3月刊行の熊大研究班の報告書に,水俣病の症状が有機水銀中毒の症状(いわゆるハンター・ラッセル症候群)と一致する旨を述べた論文が掲載された。
熊大研究班は,その後も調査研究を続け,同年7月22日に開催された研究報告会において,水俣病は現地の魚介類を摂取することによって引き起こされる神経系疾患であり,魚介類を汚染する毒物としては水銀が極めて注目されるに至ったと発表した。
また,厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会の特別部会として昭和34年1月に発足した水俣食中毒部会は,同年10月6日,水俣病は有機水銀中毒症に酷似しており,その原因物質としては水銀が最も重要視されるとの中間報告を行った。
同年11月12日,食品衛生調査会は,この中間報告に基づいて,水俣病の主因を成すものはある種の有機水銀化合物であるとの結論を出し,厚生大臣に対してその旨を答申した。
水俣食中毒部会は,この答申によりその目的を達したとして,そのころ解散した。その後,水俣病の原因についての総合的な調査研究は,経済企画庁が中心となり,厚生省,通産省及び水産庁が分担して行うものとされた。
なお,昭和34年10月ころ,チッソ水俣工場附属病院の医師が行った実験により,チッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設の排水を経口投与したネコに水俣病と同様の症状が現れることが認められた。
ところが,チッソは,実験の続行を中止し,この実験結果を公表しなかった。
(8) 上告人らが把握していた昭和34年8月現在の水俣病患者の発生状況は,患者数71名,死亡者28名であった。通産省は,そのころ,水俣病が現地において極めて深刻な問題となっている状況にかんがみ,チッソ水俣工場に対し,口頭で,水俣川河口への排水路を廃止すること,排水処理装置の完備を急ぐこと,原因究明のための調査に十分協力することを求める行政指導を行った。
また,通産省は,同年10月末から11月にかけて,厚生省公衆衛生局長,水産庁長官等から,チッソ水俣工場の排水に対して適切な処置を至急講ずるよう求める旨の要望を受けたので,チッソの社長あてに文書を送付して,一刻も早く排水処理施設を
完備することなどを求めた。
昭和34年12月,サイクレーター,セディフローターを主体とする排水浄化装置がチッソ水俣工場に設置された。チッソは,これによって工場排水が浄化される旨を強調したが,この装置は水銀の除去を目的とするものではなかった。
そのことは,多少の化学知識のある者が,上記装置の設計図等を見れば,容易に知ることができた。
(9) 昭和34年12月,熊本県知事らのあっせんにより,チッソと熊本県漁業協同組合連合会との間に漁業補償に関する契約が,水俣病患者家庭互助会との間に見舞金の支払に関する契約が,それぞれ締結された。
(10) 昭和34年当時の総水銀(有機水銀化合物に加え,金属水銀,無機水銀化合物を含むもの)の一般的な定量分析技術においては,0.01ppmが定量分析の限界であるとされていたが,工業技術院東京工業試験所は,同年11月下旬ころには,独自に工夫した方法によって総水銀について0.001ppmレベルまで定量分析し得る技術を有していた。同試験所は,そのころから昭和35年8月までの間,通産省の依頼を受けて,チッソ水俣工場の排水中の総水銀を定量分析し,0.002〜0.084ppmの総水銀が検出されたとの検査結果を報告した。
(11) 上告人らは,遅くとも昭和34年11月末ころまでには,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であること,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあった。
また,上告人らにおいて,そのころまでには,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析は可能であったし,チッソが整備した上記排水浄化施設が水銀の除去を目的としたものではなかったことも容易に知ることができた。
(12) 昭和43年5月,チッソは,水俣工場におけるアセトアルデヒドの製造を取りやめた。これにより,同工場からメチル水銀化合物が排出されることはなくなった。
同年9月,上告人国は,水俣病はチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成されたメチル水銀化合物が原因で発生したものである旨の政府見解を発表した。昭和44年,水俣湾及びその周辺海域について,後述する水質二法に基づく指定水域の指定等がされた。
第2 平成13年(オ)第1194号上告代理人都築弘ほかの上告理由について
1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
2 所論にかんがみ,職権により判断する。
前記の事実関係の下において,上告人らが,昭和35年1月以降,チッソ水俣工場の排水に関して規制権限を行使しなかったことが違法であり,上告人らは,同月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害の拡大があった者に対して国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,後述のとおり,正当として是認することができる。そうすると,本件患者らのうち,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域からその地域外へ転居した者については,水俣病となったことによる
損害を受けているとしても,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係を認めることはできない。ところが,原審は,本件患者らのうちA,X23,X36,X51,X52,B,C,X68について,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域から転居したとの事実を認定しながら,上記8名の本件患者に係る損害賠償請求を一部認容したものであって,原判決には,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係の存否の判断につき,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるといわざるを得ない。
したがって,原判決のうち,上記8名の本件患者ら又はその承継人である被上告人X22,同X23,同X36,同X51,同X52,同X53,同X54,同X55,同X64,同X65,同X66,同X67及び同X68の上告人らに対する請求(ただし,被上告人X36,同X51及び同X52については,D(患者番号31)の承継人として請求する部分を除く。)を認容した部分は,破棄を免れない。
そして,同部分に係る上記被上告人らの請求を棄却した第1審判決は,結論において是認することができるから,同部分についての上記被上告人らの控訴はいずれも棄却されるべきものである。
第3 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第3及び第4について
1 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの。以下「水質保全法」という。)及び工場排水等の規制に関する法律(以下「工場排水規制法」という。また,水質保全法と併せて,「水質二法」という。)は,昭和33年12月25日に公布され,昭和34年3月1日に施行された(その後,水質二法は,昭和45年12月に公布された水質汚濁防止法の施行に伴って廃止された。)。
水質保全法は,公共用水域の水質の保全を図るなどのために必要な事項を定め,もって産業の相互協和と公衆衛生の向上
に寄与することを目的とするものであり(同法1条),工場排水規制法は,製造業等における事業活動に伴って発生する汚水等の処理を適切にすることにより,公共用水域の水質の保全を図ることを目的とするものである(同法1条)。
水質二法による工場排水規制の概要は,次のとおりである。
経済企画庁長官は,公共用水域のうち,水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の被害が生じ,若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを「指定水域」として指定するとともに(水質保全法5条1項),当該指定水域に係る「水質基準」を定めるものとされている(同条2項)。
水質基準とは,「特定施設」を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度であり(同法3条2項),特定施設とは,製造業等の用に供する施設のうち,汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出するもので政令で定めるものである(工場排水規制法2条2項)。また,主務大臣(特定施設の種類ごとに,政令により定められる。同法21条1項)は,工場排水の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは,これを排出する者に対し,汚水等の処理方法に関する計画の変更,特定施設の設置に関する計画の変更等を命ずること(同法7条),汚水等の処理方法の改善,特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を執るべき旨を命ずること(同法12条)等の,特定施設から排出される工場排水に関して規制を
行う権限を有するものとされており,主務大臣の上記命令に違反した者は,罰則を科される(同法23条)。
2 熊本県漁業調整規則は,漁業法65条及び水産資源保護法4条の規定に基づいて制定されたものであり,水産動植物の繁殖保
護,漁業取締りその他漁業調整を図り,併せて漁業秩序の確立を期するため,必要な事項を定めることを目的とするものである(県漁業調整規則1条)。
県漁業調整規則は,何人も水産動植物の繁殖保護に有害な物を遺棄し,又は漏せつするおそれのあるものを放置してはならない旨を定め,これに違反する者があるときは,熊本県知事は,その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ,又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができるものとされている(同規則32条)。上記の規定又は命令に違反した者に対しては罰則が科される(同58条)。
3 原審は,前記の事実関係の下において,チッソ水俣工場の排水につき,上告人国においては上記の水質二法に基づく規制権限を,上告人県においては上記の県漁業調整規則に基づく規制権限を,それぞれ行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,昭和35年1月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害が拡大した者に対して,同項による損害賠償責任を負うと判断した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,水質二法,県漁業調整規則の関係規定及び国家賠償法1条1項の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
4 そこで,以下,この点について検討する。
(1) 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6号1600頁参照)。
(2) これを本件についてみると,まず,上告人国の責任については,次のとおりである。
ア 水質二法所定の前記規制は,
? 特定の公共用水域の水質の汚濁が原因となって,関係産業に相当の損害が生じたり,公衆衛生上看過し難い影響が生じたりしたとき,又はそれらのおそれがあるときに,当該水域を指定水域に指定し,この指定水域に係る水質基準(特定施設を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度)を定めること,汚水等を排出する施設を特定施設として政令で定めることといった水質二法所定の手続が執られたことを前提として,
? 主務大臣が,工場排水規制法7条,12条に基づき,特定施設から排出される工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないときに,その水質を保全するため,工場排水についての処理方法の改善,当該特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を命ずる等の規制権限を行使するものである。そして,この権限は,当該水域の水質の悪化にかかわりのある周辺住民の生命,健康の保護をその主要な目的の一つとして,適時にかつ適切に行使されるべきものである。
イ 【要旨1】
前記の事実関係によれば,昭和34年11月末の時点で,
? 昭和31年5月1日の水俣病の公式発見から起算しても既に約3年半が経過しており,その間,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取する住民の生命,健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続していたのであって,上告人国は,現に多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていることを認識していたこと,
? 上告人国においては,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,
? 上告人国にとって,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析をすることは可能であったことといった事情を認めることができる。なお,チッソが昭和34年12月に整備した前記排水浄化装置が水銀の除去を目的としたものではなかったことを容易に知り得たことも,前記認定のとおりである。
そうすると,同年11月末の時点において,水俣湾及びその周辺海域を指定水域に指定すること,当該指定水域に排出される工場排水から水銀又はその化合物が検出されないという水質基準を定めること,アセトアルデヒド製造施設を特定施設に定めることという上記規制権限を行使するために必要な水質二法所定の手続を直ちに執ることが可能であり,また,そうすべき状況にあったものといわなければならない。
そして,この手続に要する期間を考慮に入れても,同年12月末には,主務大臣として定められるべき通商産業大臣において,上記規制権限を行使して,チッソに対し水俣工場のアセトアルデヒド製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,当該施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずることが可能であり,しかも,水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると,直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当である。
また,この時点で上記規制権限が行使されていれば,それ以降の水俣病の被害拡大を防ぐことができたこと,ところが,実際には,その行使がされなかったために,被害が拡大する結果となったことも明らかである。
ウ 本件における以上の諸事情を総合すると,昭和35年1月以降,水質二法に基づく上記規制権限を行使しなかったことは,上記規制権限を定めた水質二法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法というべきである。
したがって,同項による上告人国の損害賠償責任を認めた原審の判断は,正当として是認することができる。この点に関する上告人国の論旨は採用することができない。
(3) 次に,【要旨2】
上告人県の責任についてみると,以上説示したところによれば,前記事実関係の下において,熊本県知事は,水俣病にかかわる前記諸事情について上告人国と同様の認識を有し,又は有し得る状況にあったのであり,同知事には,昭和34年12月末までに県漁業調整規則32条に基づく規制権限を行使すべき作為義務があり,昭和35年1月以降,この権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くものであるとして,上告人県が国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,同規則が,水産動植物の繁殖保護等を直接の目的とするものではあるが,それを摂取する者の健康の保持等をもその究極の目的とするものであると解されることからすれば,是認することができる。
この点に関する上告人県の論旨を採用することはできない。
第4 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第5について
1 被上告人らの上告人らに対する請求(前記第2で判示したところにより棄却されるべき部分を除く。)については,国家賠償法4条,民法724条後段所定の除斥期間の適用の有無が問題となるところ,原審は,その適用を否定した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,上記各規定の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
2 そこで,以下,この点について検討する。
(1) 民法724条後段所定の除斥期間は,「不法行為ノ時ヨリ二十年」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となると考えられる。
しかし,身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解するのが相当である。
このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間が進行することを認めることは,被害者にとって著しく酷であるだけでなく,加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過した後に損害が発生し,被害者から損害賠償の請求を受けることがあることを予期すべきであると考えられるからである。原審の判断は,以上の趣旨をいうものとして,是認することができる。論旨は採用することができない。
(2) 【要旨3】
上記見解に立って本件をみると,本件患者のそれぞれが水俣湾周辺地域から他の地域へ転居した時点が各自についての加害行為の終了した時であるが,水俣病患者の中には,潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては,水俣湾又はその周辺海域の魚介類の摂取を中止してから4年以内に水俣病の症状が客観的に現れることなど,原審の認定した事実関係の下では,上記転居から遅くとも4年を経過した時点が本件における除斥期間の起算点となるとした原審の判断も,是認し得るものということができる。この点に関する上告人らの論旨も採用することができない。
第5 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかのその余の上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
第6 平成13年(オ)第1196号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告理由について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件附帯上告の理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
第7 平成13年(受)第1174号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
第8 結論
以上によれば,上告人らの上告は,前記第2の限度で理由があるから,主文第1項記載の部分につき原判決を破棄し,同第3項記載の部分につき原判決を変更すべきものであるが,その余の上告はいずれも理由がないので,これを棄却することとする。また,附帯上告人らの附帯上告には理由がないので,これを棄却する。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田 博 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/67930C1EA789333049257029002690BE.pdf

「奇病のかげに」は、熊本県の水俣病を工場公害ではないかと告発した
踊り回る猫(3コマ目)の姿は「奇病」の本質をとらえた。小倉一郎の作品。

2009年10月31日
工事騒音・粉塵の判例 慰謝料10万円
建物解体工事により約3か月の間,散発的に,ある程度継続的に解体工事敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認め,音源から居住地が離れることによる騒音の減衰を考慮し,居住地の敷地において85デシベルを越える騒音被害を受けていたと認められる原告らにつき,民法709条に基づき,解体工事施工業者に各自10万円の慰謝料支払責任を認めた事案。
(85mで距離減衰9デシベル)慰謝料10万円
主文
1 被告木内建設株式会社は,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告
X5,原告X6,原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,
原告X12,原告X13,原告X14,原告X15,原告X16,原告X17
及び原告X18に対し,それぞれ10万円及びこれに対する平成19年1月3
0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
, , , ,
2 原告X1 原告X2 原告X3 原告X4 原告X5,原告X6,原告X7,
原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12,原告X13,原
告X14,原告X15,原告X16,原告X17及び原告X18の被告木内建
設株式会社に対するその余の請求及び被告三菱地所株式会社に対する請求をい
ずれも棄却する。
3 原告X19及び原告X20の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告X19及び原告X20に生じた費用と被告らに生じた費用
の10分の1を原告X19及び原告X20の負担とし,その余の原告らに生じ
た費用の2分の1,被告三菱地所株式会社に生じた費用の10分の9,被告木
内建設株式会社に生じた費用の20分の9をその余の原告らの負担とし,その
余の原告らに生じた費用の2分の1と被告木内建設に生じた費用の20分の9
を被告木内建設株式会社の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告ら各自に対し,連帯して20万円及びこれに対する平成19年1月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告らが,被告ら各自に対し,被告らが行った建物解体工事(以下「本件工事」という。)の際のアスベスト飛散,騒音・振動,粉じん飛散などにより近隣住民の原告らが健康被害を受けたとして,不法行為に基づき,原告ら各自が相当慰謝料額である50万円のうち20万円(合計400万円)及びこれに対する不法行為日後である平成19年1月30日(公害調停の申立日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(証拠〔枝番があるものは特にことわらない限り,これを含む。以下同じ〕を掲記しない事実は,当事者間に争いが。ない。)
(1) 当事者
ア 原告らは,本件工事現場付近に居住する者である。原告らは,本件工事当時,当事者目録の番号欄と対応する別紙図面(省略)の各番号の位置に居住していた。(甲12,丙3)
イ 被告三菱地所株式会社(以下「被告三菱地所」という。)は,本件工事で解体した建物(甲7。鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建事務所〔延べ床面積2368.72?〕。以下「本件建物」という。)の所有者であり,かつ,本件工事事業者である。
ウ 被告木内建設株式会社(以下「被告木内建設」という。)は,本件工事の施工業者である。
(2) 本件工事について
ア 被告三菱地所は,被告木内建設を施工業者として,さいたま市中央区a の宅地の敷地(以下「本件敷地」という。)上に18階建てのマンション(以下「本件マンション」という。)を新築する計画(以下「本件マンション建築計画」という。)を立てた。
イ 被告三菱地所は,本件マンション建築計画のために,東京海上日動株式会社から,本件敷地及びその上に建設されていた本件建物を買い取り,平成18年10月4日(原告主張によれば11月7日)ころから本件建物の解体工事に着手した。
ウ 本件工事は,平成19年7月11日に終了した。(乙1)
2 争点
( ) 本件工事の違法性(争点1 (1))
(原告ら)
ア 原告らは,人格権,環境権として,居住地で静謐で健康的な生活を送る権利を有している。
イ 説明義務違反について
(ア)本件建物には,アスベストを含有する断熱材がボイラー室を中心に32
4φ×5.9メートルの量で使用されている。被告らは,アスベスト除去
工事を平成18年11月7日から同月21日にかけて実施した。
(イ)被告らがアスベストの除去工事をする前には工事内容を原告らに告知,
周知し,原告ら自身で健康被害の対策ができるようにすべきであったが,
被告らはそのようなことをせずに秘密裏に除去工事をなした。アスベスト
除去工事についての説明図書の配布は同月15日であり,説明会は同年1
2月であり,事前の説明がなされていない。
(ウ)大気汚染防止法18条の14及び同法施行規則16条の4では,アスベ
スト除去工事をする場合には一定の事項を掲示しなければならないと定め
られているが,被告らはそれを行っていない違法がある。被告らは,アス
ベスト除去工事に関し,近隣住民に掲示板を設置するなどして情報提供を
行う義務があったが,掲示板が設置されたのは平成18年12月過ぎであ
り,アスベスト除去工事後である。
(エ)大気汚染防止法は,アスベスト除去作業時に十分な散水をするよう定め
ているが,行われていない違法がある。
ウ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)被告らは,本件工事で激しい騒音・振動を発生させた。平成19年1月
17日になってようやく騒音・振動計が設置された。同年1月24日午前
9時過ぎには,さいたま市騒音防止条例(以下「条例」という。)に違反
する94デシベルの騒音を発生させた。
(イ)本件工事による騒音・振動については,条例に違反している。さらに,
防音シート,防音壁を十分使用する,低騒音・振動の工事機械を使用した
り,手で壊す,ゆっくりと時間をかけて機械を使用して壊す,十分休み時
間をおいて振動の激しい作業を連続させないなどの騒音・振動を低減させ
る対策を取ることなく,経済的利益を追及し,早急な工事が行われている。
また,被告らは原告らに十分な説明や,工程表の配布等をせずに工事を行
っている。これらは,受忍限度を超えている。
(ウ)被告らは,十分な散水をして粉じんの発生を防止する措置を執らず,ま
た,年末年始にコンクリート屑等の有害物質の飛散が予想されることから
十分瓦礫に散水したり,解体搬出したり,シートによる養生をしておくべ
きであったが,その実行を怠り瓦礫を飛散させた。
エ誠実義務違反
原告らの被告らに対する騒音・振動・粉じんに関する危惧や苦情に対し,
被告らは対策を講じなかった。具体的には,騒音振動計を現地敷地の境界線
上と変更すること,防音シート等を充分な範囲で設置すること,昼休みには
一切の工事を休んで騒音・振動を発生させないこと,散水を充分すること,
重機が倒壊する危険に対し対策を採ることなどの要望を無視し,工事協定書
の締結を拒否し,さいたま簡易裁判所公害調停において調停委員会が助言し
た400万円の支払を拒否した。
(被告三菱地所)
ア説明義務違反について
(ア)原告は大気汚染防止法施行規則16条の4に基づき説明義務を負うかの
主張をしているが,被告三菱地所は「特定粉じん排出等作業」(大気汚染
防止法2条12項)を行うものではないから,大気汚染防止法に基づく責
任を負わない。
(イ)同規則16条の4の掲示義務から住民に対する説明義務は発生しない。
法が定める掲示義務は履行されている。
イ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)騒音については,受忍限度の範囲内である。
(イ)振動は,規制値を超えておらず,受忍限度の範囲内である。
(ウ)粉じん発生は,事実が不明である。また,散水による飛散防止措置は講
じられていた。
ウ誠実義務違反について
誠実義務なるものの内容は不明である。
(被告木内建設)
ア説明義務違反について
(ア)大気汚染防止法施行規則16条の4に掲示義務があることは認めるが,
住民に対する説明義務はない。
(イ)アスベスト除去工事の際十分散水する義務があるというのは争う。散水
による飛散防止は,薬液等による湿潤化作業等による飛散防止措置ができ
ない状況の防止策として許容されているものである。
(ウ)本件解体工事に関する届出書で「近隣周知」との記載をしたこ, とは認
めるが,これにより説明会の開催義務が生じるわけではない。
(エ)平成18年12月に開かれた説明会は,解体工事ではなく,新築工事の
説明会である。
(オ)本件のアスベスト除去工事は国土交通省が発表している資料によると,
「塔屋階段天井材」及び「屋上クーリングタワーパッキン」の石綿除
去作業はレベル3(発じん性が比較的低い)に属する作業で,「煙突内部
断熱材」の石綿除去作業はレベル2(発じん性が高い)に属する作業で
あるが,外界から隔離した区画内で適切に行っている。
イ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)平成18年1月24日に94デシベルの騒音を記録したことは認めるが,
これは遮音性の低い東側の道路境界面で測定したためである。
(イ)公法上の規制に違反することが直ちに私法上の不法行為責任が生じるこ
とにはならない。概ね,音源と各原告の居住地との距離の事情に反比例す
るといわれている。
(ウ)音は音源を中心として球状に伝達するから,音源からの距離を半径(r)
とすれば,音のエネルギー量は音の表面積=4×円周率(π)×rの二乗
となるので,距離が音源から2倍となったときエネルギー量は距離の二乗
に反比例する結果4分の1となる。デシベルとは音のエネルギー量を表す
ものであり,10デシベルの差は10倍のエネルギー量の差を意味すると
ころ,仮に音源からの距離が約3倍になれば,エネルギー量は約9分の1
となり,騒音計の数値は約10デシベル低下することになる。原告らは居
住地を異にしているから,同一に論じることはできない。
(エ)また,建物の遮音性能は,少なくとも約25デシベルある。
(オ)条例の規制値を85デシベルとしても,騒音計指針値の最大値の90パ
ーセントがその値であるから,85デシベルを90パーセントで除した9
4デシベルを超えると,規制値を超えたことになる。さらに,本件工事現
場に一番近い原告X12宅でも,基準距離の2倍ないし3倍はあるから,
距離減衰により6ないし9デシベルは低下することになる。したがって,
100ないし103デシベルの指針値を超えたのでなければ,違反とはな
らない。原告らの多くは,基準距離の3倍以上は離れているので,106
デシベル以上の騒音であることが必要である。加えて,建物の透過損失に
より25デシベル以上の低下もあるから,受忍限度の範囲内である。
(カ)粉じん被害の主張は,争う。
ウ誠実義務違反について
争う。
( ) 被告三菱地所が不法行為責任を負うか(争点2 。(2))
(原告ら)
被告三菱地所は,被告木内建設の使用者として,民法715条に基づき使用者責任を負う。
また,被告木内建設とともに民法719条に基づき共同不法行為責任を負う。
(被告三菱地所)
被告三菱地所は被告木内建設の使用者ではないから,民法715条による
責任を負わない。
また,被告らに不法行為責任がないから,民法719条の主張は失当であ
る。
(3) 原告らに生じた損害の程度(争点(3))
(原告ら)
原告らは,被告らの下記の本件工事によるアスベスト,コンクリート屑等
の飛散と騒音・振動により,精神的・身体的被害を受けた。具体的には,身
体的に血圧が上昇したり,不眠となったり,ぜんそくが悪化したり,動悸が
したり,自律神経が失調したりするなどの顕在化した被害や,顕在化しない
程度の生活妨害を受けた。この被害による慰謝料は,原告ら各自につき50
万円を下らないので,そのうち20万円の支払を求める。
(被告ら)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。(以下,特に断りがない場合,9月から12月は平成18年,1月から8月は平成19年の日時を指す。)
( ) 本件工事の工程等(1 甲2)
ア 本件工事の途中で被告らが開示した工程表(甲4。以下「本件工程表」という。)によると,本件工事は,工事が始まる順番に,仮設工事,内装解体,ハツリ工事,進入路確保工事,アスベスト除去工事,PCB撤去工事,レッカー作業,塔屋,5F,4F,3F,2F,1F,山留め工事,地下解体,基礎解体,アスファルト解体,外構解体,整地,杭抜き工事という20の工
種に分解されている。本件工程表では,10月4日から3月17日までを工期と予定しており,アスベスト除去工事は10月23日から11月2日の10日間(作業日数。以下同じ。),塔屋解体工事は11月4日から同月9日の5日間,5F解体工事は11月10日から同月16日の6日間,4F解体工事は11月17日から同月25日の7日間,3F解体工事は11月27日から12月4日の7日間,2F解体工事は12月4日から同月9日の6日間,1F解体工事は12月9日から同月16日の7日間,地下解体工事は12月18日から1月26日の30日間,基礎解体工事は1月22日から2月3日の12日間,アスファルト解体工事は2月5日から同月16日の10日間,外構解体工事は2月5日から同月16日の10日間,杭抜き工事は2月13日から3月17日の29日間となっている。
また,使用重機,アタッチメントの予定表によれば,仮設工事・内装工事は10月10日から11月2日までの21日,建家解体工事は11月4日から1月10日までの47日間,地下解体工事は1月11日から2月17日までの32日間,基礎解体工事は2月19日から同月28日までの9日間となっている。(甲33の10)
イ 9月8日ころ,被告三菱地所は,さいたま市長に対し,建設工事に係る資材の再資源化に関する法律10条1項の規定により,本件解体工事の届出書(甲3。以下「本件解体工事届出書」という。)を提出した。
本件解体工事届出書には,「建築物に関する調査の内容の結果」として,「その他」欄に「。, 煙突内部にカポスタック吹付有り現在ステンレスで覆い飛散防止済。」,
「工事着手前に実施する措置の内容」として,「作業の確保」欄に「敷地内作業スペース十分有り。」,「その他」欄に「近隣周知。」と記載し,工事着手の時期を,「平成18年9月19日」と記載している。また,「工程ごとの作業内容及び解体方法」として,「外装材・上部構造部分の取り壊し」,「基礎・基礎杭の取り壊し」,「その他の取り壊し」を「手作業」ではなく,「手
作業・機械作業の併用」の「分別解体等の方法」により行う旨記載している。(甲3)
ウ 被告木内建設は,10月4日,本件工事に着手した。本件工事の内容は,地上5階建て鉄骨鉄筋コンクリートビルの取壊と,地下室の取壊及び地下室周辺の障壁の解体,搬出及び地中杭4本(長さ約34メートル,直径は1300ミリメートル1本,1400ミリメートル1本,1500ミリメートル2本。)の抜き取りと現場解体,敷地外搬出である。
エ 本件工事の際,本件敷地と,周囲の道路や隣地との境界線上には,ほぼ全面に1800ミリメートル×5400ミリメートルで鉛を含有する重量50キログラム程度の防音シートが張られていた。また,本件敷地のうち,本件建物があった東側部分の敷地四方には,西側南部分を除き,高さ3メートルの安全鋼板仮囲が設置されていた。本件敷地の東側には道路b があり,道路b
から本件敷地への搬入路としては,東側の仮設搬入路と,北東側の搬入搬出口の2か所があった。
このうち,東側の仮設搬入路の部分は,防音シートや安全鋼板仮囲がなく,防音性能の乏しいシートが張られていた。(丙10)
オ 10月30日,被告木内建設は,さいたま市長に対し,本件工事につき日曜・祭日を除く10月17日から2月28日の期間に,さく岩機作業(解体)による騒音規制法の定める特定建設作業を,ブレーカー(解体)による振動規制法の定める特定建設作業を,それぞれ行うとして,特定建設作業実施届出書(丙5,6)を提出した。
いずれも,騒音・振動の防止方法の一つとして,行程・作業内容等を近隣住民に説明することを記載している(。丙5,6)
カ 本件建物には,?塔屋階段の天井材,?屋上クーリングタワーのパッキン,?煙突内部の断熱材に,石綿が含有されている。?については,ボイラー室を中心に,アスベストを含有する断熱材が,324ミリメートル×5.9メートルの量使用されている。
このうち,?は,被告木内建設から請け負った株式会社東京ビルド(以下「東京ビルド」という。)が,10月23日,2
4日に湿潤化させた上,極力割らないように撤去し,袋詰めを行い,10月24日に搬出した。
?は,東京ビルド,?は練馬建設工業株式会社(以下「練馬建設」という。)が,11月7日から同月21日まで除去作業を行い,実際には11月9日のさいたま市役所の養生検査済後,除去作業に取りかかり,11月21日に作業を完了し,12月11日に搬出した。?に関して,東京ビルドは,10月24日,さいたま市長に対し,「特定粉じん排出等作業実施届出書」(乙5。以下「本件届出書」という。)を提出し,10月31日,「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」と題する掲示板(乙6の?な
し?がその写真である。以下「本件掲示板」という。)を,本件工事の現場西側の安全鋼板仮囲の側面2か所に設置し,練馬建設は,本件届出書提出から14日後である11月7日から本件石綿除去工事を開始した。(甲19,乙5,6,11)
キ 12月29日から1月8日の年末年始にかけて,被告木内建設は工事を中断していたが,その際,散水やシートによる養生などで,瓦礫の飛散を防止する措置を講じていない。年末年始のシートによる養生について,さいたま市環境経済局環境部環境管理事務所(以下「さいたま市環境管理事務所」という。)の担当者と被告木内建設の現場所長との間の電話で,シート養生をする方法での埃等の飛散防止の方法が話題に出たことがある。
ク 本件工事により,本件敷地東側の道路b に24メートルほどにわたって亀裂が生じ,4月4日ころ,補修工事が行われた(甲48,54。の4)
ケ 本件工事は,3月ころまでは1週間遅れが出る程度でほぼ予定通りに進み,既存杭引抜作業を残す段階に来ていたが,杭引抜機械の故障や新たな地中障害物の発見により,5月中旬から下旬までかかる見込みとなったため,被告木内建設は,3月20日ころ,近隣住民にこのことを文書で周知した。
さらに,既存杭引抜作業は予定以上に時間がかかり,4本中2本は工法も変更して行うこととしたため,被告木内建設は,5月7日,本件工事の完了予定を6月中旬と変更し,近隣住民に文書で周知した。予定変更以降の作業で見込まれる騒音や振動について,被告木内建設は,3月に行われている既存杭引抜作業と同程度と予想している。(甲48)
コ 7月11日,重機が搬出され,本件工事は終了した。(乙1)
サ 本件工事による騒音は,周辺住民の感覚としては,上部構造の解体工事,地下室の解体工事,杭抜き工事のときが大きかった。(原告X3(以下「原告X3」という。),原告X20(以下「原告X20」という。))
(2) 原告らと被告らの交渉状況等
ア 11月15日,被告らは,本件工事後に予定している本件マンション建築計画に関する説明文書を近隣住民に配布し,12月5日午後7時30分から,本件マンション建築計画に関する第1回近隣説明会を実施した。(甲8の1)
イ 12月19日,被告らは,本件マンション建築計画の第2回近隣説明会を実施した。この際,本件工事について,データを保存できる騒音計・振動計の設置が要望された。(甲8の2)
ウ 1月11日,被告らは,本件マンション建築計画の第3回近隣説明会を実施した。この際,さいたま市環境管理事務所との間で被告木内建設が約束した年末年始の粉じん飛散防止のためのシート養生がなされていなかったことが議題に出て,被告木内建設はシート養生の指導を受けた認識がない旨答えた。
また,被告らは,1階の解体工事について,確たる数値ではないが,70ないし75デシベル程度と思う旨答えた。そして,騒音・振動計の設置が決まった(甲8。の3)
エ 1月17日,第3回近隣説明会の合意に基づき,被告木内建設は,工事現場近くに騒音振動計(以下「本件騒音振動計」という。)を設置した。
本件騒音振動計の記録紙は,1目盛りを1デシベルとし,90デシベルを目盛りの上端としている。本件工事により記録された記録紙(甲32)には,90デシベルを超えた数値が記録されているところもあるが,その部分の数値が
単純に超過した長さ1目盛り分につき1デシベルといえるか,不明であるし,本件騒音振動計の構造上(甲48),際限なく大きな数値が記録されることはない。
オ 1月22日,被告らは,本件マンション建築計画の第4回近隣説明会を実施した。その日の朝に,ターンテーブルの解体をしたため,特に大きな振動が出たことが話題に出た。(甲8の4)
カ 1月24日午前9時過ぎ,原告本人兼原告ら代理人弁護士X1(以下「X1弁護士」という。)が本件騒音振動計を本件敷地東側境界上の防音シートのないところに移すと,94デシベルの騒音が記録された。(当事者間に争いがない。)
キ 2月16日,さいたま市環境管理事務所が本件工事現場の騒音及び振動を測定した。その際,騒音について,測定値の90パーセントレンジの上端値が,85デシベルという測定結果であり,振動について,測定値の80パーセントレンジの上端値が,61デシベルという測定結果であった。
この測定の際は,まずさいたま市環境管理事務所の者が一度本件工事の現場に訪れて工事関係者に騒音及び振動の測定をすることを伝えた後,一度現場を離れ,数十分後に再度来てから測定を開始しており,普段よりも控えめな騒音・振
動で工事が行われていた。(丙7,原告X3)
2 争点(1)(本件工事の違法性)について
( ) 説明義務違反に1 ついて
ア 大気汚染防止法18条の14及び同法施行規則16条の4は,作業基準としてアスベスト除去工事を行う場合の一定の事項の掲示義務を定めており,作業基準を遵守しない場合には都道府県知事が作業基準適合命令等を行うことができるとし(同法18条の18),当該命令に従わない場合には行為者に6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則を定め(同法33条の2第1項2号),同額の罰金の両罰規定も定めている(同法36条)。
しかしながら,この法令の定めにより,直ちに被告木内建設が近隣住民等に対する私法上の説明義務を負うと解することはできない。
イ また,原告らは,本件解体工事届出書に「近隣周知。」と記載したことにより,被告木内建設は原告らへアスベスト除去工事の説明義務を負う旨主張する。
本件解体工事届出書は,建設工事に係る資源の再資源化に関する法律10条1項に基づく届出であるところ,同法は,当該届出に虚偽記載をした場合には20万円以下の罰金という罰則を定め(同法51条1項1号),同額の罰金の両罰規定も定めている(同法52条)。
届出た計画が法令が定める基準に適合しないと認めるときは,都道府県知事は計画の変更その他必要な措置を命ずることができ(同法10条3項),命令に違反したときには30万円以下の罰金という罰則を定め(同法50条1号),同額の罰金の両罰
規定も定めている(同法52条)。
しかし,この法令の定めにより,直ちに被告木内建設が近隣住民等に対する私法上の義務を負うと解することはでき
ない。
ウ その他,以上に認定説示したところ及び弁論の全趣旨により認められる事情を考慮しても,被告木内建設が原告らに対し説明義務を負うとは認められない。
エ また,大気汚染防止法等で規定する掲示義務に違反したところで,原告らに損害が生じるとも認められない。
オ したがって,原告らの説明義務違反の主張は理由がない。
( ) 騒音・振動の発生に2 ついて
ア 社会生活を営む上である程度の騒音や振動は発生するものであるから,互いに受忍すべきものであるが,騒音や振動を体感することにより,その種類・程度等によっては,人は不快感を覚え,精神的・身体的に健康を害されることがあるから,騒音や振動が受忍限度を超える場合には,違法な騒音ないし振動として,不法行為が成立することがあるというべきである。
そして,いかなる騒音や振動が不快感を及ぼすかは,個人差もあると考えられるが,騒音規制法は,特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,85デシベルを超える大きさを規制基準としていること(乙8),振動規制法は,特定建設作業の振動が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,75デシベルを超える大きさを規制基準としていること(振動規制法施行規則11条),本件敷地の周辺は第1種住居地域ないし第2種住居地域であり(甲45),平常時の工場・事業場等の騒音・振動規制について,騒音規制法,振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例上,午前8時から午後7時までの間,工場・事業場の敷地境界において,騒音は55デシベル,振動は60デシベルを規制基準としていること(甲46),特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準は,騒音の大きさの決定方法について,指示値が変動しないときは指示値を,周期的又は間欠的に変動し,最大値がおおむね一定の時は指示値の最大値の
平均値を,指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は測定値の90パーセントレンジの上端の数値を,周期的又は間欠的に変動し,最大値が一定でない場合は指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値を,それぞれ騒音の大きさと定めていること(乙8),振動規制法施行規則は,振動レベルの決定方法について,測定器の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値を,測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値を,測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,5秒間隔,100個又はこれに準ずる間隔,個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値を,それぞれ振動の大きさと定めていること(振動規制法施行規則別表第1備考4)などの事情からすると,騒音については,ある程度継続的に85デシベルを超える騒音や,騒音の程度は一定ではないが一時的にでも94.44デシベル(85デシベルを0.9で除した数値)を超える騒音を,振動については,ある程度継続的に75デシベルを超える振動や,振動の程度は一定ではないが,一時的にでも93.75デシベル(75デシベルを0.8で除した数値)を超える振動を,特段の事情がない限り,受忍限度を超える違法な騒音や振動というべきである。
イ もっとも,騒音や振動は距離が離れるに連れて弱まるものであり(距離減衰,騒音について見ると,その程度は距離の二乗に反比例し,音の) 発生源から測定位置までの距離をX,発生源から被害地までの距離をYとすると,20× log(Y÷X)の式により減殺されるデシベルの数値が算出される(弁論の全趣旨)。したがって,原告らの敷地境界線上において,距離減衰を考
慮した上で,上記違法な騒音や振動が発生していた場合に,不法行為の成立を認めるのが相当である。
ウ まず,振動については,本件工事により継続的にどの程度の振動が発生していたか証拠上明らかでない上,平成19年2月16日に行われたさいたま市環境管理事務所の測定結果時,騒音が規制基準と同数値の85デシベルという測定結果だったのに対し,振動は規制基準の75デシベルを下回る61デシベルであったことからすると(丙7),一時的に大きな振動が発生することがあったとしても(甲48),受忍限度を超える違法な振動が発生していたと認めることはできない。なお,原告らは,道路や家屋のひび割れを指摘するが,これは振動の影響なのか,本件解体工事による地盤沈下の影響なのか,その他の原因なのか証拠上不明であり,これらをもって振動の強さを判断することはできない。したがって,本件工事の振動による不法行為は,
認められない。
エ 次に,被告木内建設が本件工事により発生させていた騒音について認定事実も踏まえて検討する。
(ア)平成19年1月19日から同年2月28日までの騒音については,別紙騒音一覧表(省略)の「該当日付」の日に,概ね「1日合計分」の分数程度,90デシベルを超える騒音が発生していたと認められる(甲5の1及び4,甲32)。
(イ)平成19年2月16日午前8時35分から午前10時26分まで,さいたま市環境管理事務所が行った騒音の測定結果は,東側敷地境界において,測定値の90パーセントレンジの上端値で,85デシベルであった。(乙9)
(ウ)騒音計の記録(甲32)によれば,1月24日,2月8日,2月13日ないし15日,2月22日ないし24日,2月26日などの日は(いずれも平成19年),平成19年2月16日午前8時35分から午前10時26分までの騒音と比較し,大きな騒音,長期間の騒音が出されている。騒音計の計測条件は,平成19年1月24日に防音性の比較的低いところで計測されたと認められる点を除き,特段の違いは見当たらない(丙10)。
(エ)本件騒音振動計の記録用紙は1目盛りを1デシベルとし,90デシベルを上限としていて,それを振り切った場合の数値は不明であるが,平成18年2月24日に94デシベルを記録したことに当事者間に争いはなく,振れ幅の大きさ上,それと同程度の騒音を記録しているところは平成19年2月22日ないし24日,同月26日などにもあるから,本件工事により,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認めるのが相当である。そして,本件騒音振動計が設置されていなかった時期の騒音の程度は客観的な数値としては明らかではないが,原告らは個人差があるもののいずれの工事も騒音がうるさかった旨供述していること 引抜工事までの解体工事については,使用している重機を見ても工事の種類ごとに騒音の程度が大きく異なるとは認められないことなどから,本件工事のうち平成18年11月21日にアスベスト除去工事が終了し,本件建物の解体工事が始まった平成18年11月末ころから,既存杭引抜工事前の本件建物及び地下室の解体工事が終了した平成19年2月28日までの間,散発的に,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認める。
他方,既存杭引抜工事については,解体工事がコンクリート等を破壊する作業であるのに対し,杭を引き抜くという異なる作業であること,騒音の客観的な数値が不明であることから,引き抜いた杭を本件敷地内で壊していたとしても,受忍限度を超える違法な騒音が発生していたとは認められない。
オ 以上のとおり,本件工事により,平成18年11月末ころから平成19年2月28日までの間,散発的に,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたことを前提に,それらが各原告らに対する受忍限度を超える違法な騒音といえるか,検討する。
(ア)本件敷地は,東側が約35メートル,南側が約26メートル超,北側が約15メートルの長さである。また,本件建物は,本件敷地の東側に,1階から6階は東西方向に12メートル,南北方向に31.7メートルの長さで建っており,その南側に東西方向に12メートル,南北方向に15.85メートルの長さの地階があった。(甲14,弁論の全趣旨)
(イ)本件工事による騒音の発生源は一定せず,本件騒音振動計も一定していないが,平均すると,本件建物の中心地から騒音は発生していたと考えられ,本件騒音振動計は本件建物の北側に設置されていた期間が多かったことから,上記記載の本件建物や本件敷地の状況を考慮し,本件騒音振動計は,音源から30メートル離れたところで記録されたものと認めるのが相
当である。
(ウ)そうすると,本件工事により本件敷地境界線部分で94デシベルの騒音が発生したと認められるから,距離減衰により9デシベルの騒音低下が生じれば,騒音は受忍限度の範囲内といえる85デシベルの範囲内に収まることになる。そして,上記距離減衰の式によると,音源から85メートル離れることにより,9.04デシベル(=20× ( ))騒音log 85/30 は低下することになる。
(エ)本件工事による騒音の発生源は一定していなかったことは既述のとおりであるが,本件敷地内のどの場所からも騒音が発生していた可能性があるから,距離減衰との関係では,本件敷地境界線から原告らの敷地までの距離で距離減衰を考えるのが相当である。
(オ)なお,被告木内建設は,家屋の壁などによる透過減衰も主張するが,仮に透過減衰の量を25デシベルとしても,85デシベルを超える騒音から透過減衰を考慮しても60デシベルとなり,平常時の規制基準である55デシベルを超えているから,受忍限度を超えるという判断には影響しないというべきである。
(カ)以上の考えに基づき,本件敷地から85メートルの範囲内に敷地が含まれる原告らを判別すると,別紙原告ら居住地(省略)記載のとおり,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6,原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12,原告X13,原告X14,原告X15,原告X16,原告X17,原告X18(以下「範囲内原告」という。)となる。
これらの原告は,被告木内建設に対し,騒音被害による不法行為に基づき,損害賠償請求権を有しているというべきである。
これに対し,原告X19及び原告X20(以下「範囲外原告」という。)は,受忍限度内の騒音被害であったというべきであり,被告木内建設に対し,騒音被害による不法行為に基づき,損害賠償請求権を有しない。
( ) 粉じんの発生に3 ついて
ア 原告らは,本件工事による粉じんの発生で苦痛を被ったと主張する。
イ 確かに,証拠によると,本件工事によりある程度の粉じんが発生したことが認められるが(甲11,48,原告X3),本件敷地の外に粉じんが飛散したか否か,どの程度飛散したか,粉じんの飛散により原告らに損害が発生したのか等,不明であるといわざるをえない。
ウ また,被告木内建設が,原告らに対し,通常の不法行為責任を超えて,粉じんを飛散させないように注意すべき特段の法的義務を負っていたと認めることはできない。
エ よって,原告らの粉じんの発生による不法行為の主張は,理由がない。
(4) 誠実義務違反について
原告らは,被告木内建設が原告らの本件工事に対する要望に誠実に対応しなかったことなどをもって,誠実義務違反と主張するが,本件事実関係の下で,被告木内建設が,原告らが主張するような法的義務を負っていたとはいえない。
よって,原告らの誠実義務違反の主張は,理由がない。
3 争点(2)(被告三菱地所が不法行為責任を負うか。)について
(1) 使用者責任について
ア 原告らは,被告三菱地所が使用者責任を負う旨主張するが,使用者責任が生じるためには使用者とされる者が被用者とされる者を指揮監督する使用関係が必要である。
イ 被告三菱地所と被告木内建設の本件工事についての関係は,請負契約であることに争いはなく,被告三菱地所から被告木内建設に対し工事の方法等につき特段の指揮監督がなされていたと認めるに足りる証拠はない。
請負契約における注文者は,注文又は指図についてその注文者に過失があったときでなければ,請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないのであって(民法716条,本件では具体的に被告三菱地) 所の注文又は指図に過失があったとは認められないことも併せ考慮すると,被告三菱地所が使用者責任を負うとはいえない。
(2) 共同不法行為責任について
原告らは,被告三菱地所が共同不法行為責任を負う旨主張するが,被告三菱地所が被告木内建設と共同して本件工事を行ったとは認められず,本件工事について主観的な関連共同関係があったとも認められないから,被告三菱地所が共同不法行為責任を負うとはいえない。
(3) よって,原告らの被告三菱地所に対する請求は,すべて理由がない。
4 争点(3)(原告らに生じた損害の程度)について
(1) 既に認定したとおり,本件工事により範囲内原告に対し不法行為を構成するのは,平成18年11月末ころから平成19年2月末ころまで,散発的に生じる,ある程度継続的に94デシベルに達する騒音である。
騒音が発生していたのは約3か月間の月曜日から土曜日の午前8時から午後5時ころであったこと,違法な騒音は毎日発生するとは限らず,発生する日も1日中違法な騒音が続いたわけではないことなどからすると(甲11,32,原告X3,原告X20),慰謝料は,一人当たり10万円が相当である。
(2) なお,原告X3は,神経性胃炎,胃けいれん,不安神経症,不眠症,血圧上昇という診断書を提出するが(甲11の4の2),医師の診断を受けたのは2年ぶりであるなどと供述しており,本件工事との相当因果関係は認められない。
第4 結論
よって,範囲内原告の被告木内建設に対する請求は,慰謝料各10万円及びこれに対する不法行為後である平成19年1月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これらを認容することとし,範囲内原告の被告木内建設に対するその余の請求,被告三菱地所に対する請求,範囲外原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がないので,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第5民事部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090528150644.pdf
(85mで距離減衰9デシベル)慰謝料10万円
主文
1 被告木内建設株式会社は,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告
X5,原告X6,原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,
原告X12,原告X13,原告X14,原告X15,原告X16,原告X17
及び原告X18に対し,それぞれ10万円及びこれに対する平成19年1月3
0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
, , , ,
2 原告X1 原告X2 原告X3 原告X4 原告X5,原告X6,原告X7,
原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12,原告X13,原
告X14,原告X15,原告X16,原告X17及び原告X18の被告木内建
設株式会社に対するその余の請求及び被告三菱地所株式会社に対する請求をい
ずれも棄却する。
3 原告X19及び原告X20の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告X19及び原告X20に生じた費用と被告らに生じた費用
の10分の1を原告X19及び原告X20の負担とし,その余の原告らに生じ
た費用の2分の1,被告三菱地所株式会社に生じた費用の10分の9,被告木
内建設株式会社に生じた費用の20分の9をその余の原告らの負担とし,その
余の原告らに生じた費用の2分の1と被告木内建設に生じた費用の20分の9
を被告木内建設株式会社の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告ら各自に対し,連帯して20万円及びこれに対する平成19年1月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告らが,被告ら各自に対し,被告らが行った建物解体工事(以下「本件工事」という。)の際のアスベスト飛散,騒音・振動,粉じん飛散などにより近隣住民の原告らが健康被害を受けたとして,不法行為に基づき,原告ら各自が相当慰謝料額である50万円のうち20万円(合計400万円)及びこれに対する不法行為日後である平成19年1月30日(公害調停の申立日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(証拠〔枝番があるものは特にことわらない限り,これを含む。以下同じ〕を掲記しない事実は,当事者間に争いが。ない。)
(1) 当事者
ア 原告らは,本件工事現場付近に居住する者である。原告らは,本件工事当時,当事者目録の番号欄と対応する別紙図面(省略)の各番号の位置に居住していた。(甲12,丙3)
イ 被告三菱地所株式会社(以下「被告三菱地所」という。)は,本件工事で解体した建物(甲7。鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建事務所〔延べ床面積2368.72?〕。以下「本件建物」という。)の所有者であり,かつ,本件工事事業者である。
ウ 被告木内建設株式会社(以下「被告木内建設」という。)は,本件工事の施工業者である。
(2) 本件工事について
ア 被告三菱地所は,被告木内建設を施工業者として,さいたま市中央区a の宅地の敷地(以下「本件敷地」という。)上に18階建てのマンション(以下「本件マンション」という。)を新築する計画(以下「本件マンション建築計画」という。)を立てた。
イ 被告三菱地所は,本件マンション建築計画のために,東京海上日動株式会社から,本件敷地及びその上に建設されていた本件建物を買い取り,平成18年10月4日(原告主張によれば11月7日)ころから本件建物の解体工事に着手した。
ウ 本件工事は,平成19年7月11日に終了した。(乙1)
2 争点
( ) 本件工事の違法性(争点1 (1))
(原告ら)
ア 原告らは,人格権,環境権として,居住地で静謐で健康的な生活を送る権利を有している。
イ 説明義務違反について
(ア)本件建物には,アスベストを含有する断熱材がボイラー室を中心に32
4φ×5.9メートルの量で使用されている。被告らは,アスベスト除去
工事を平成18年11月7日から同月21日にかけて実施した。
(イ)被告らがアスベストの除去工事をする前には工事内容を原告らに告知,
周知し,原告ら自身で健康被害の対策ができるようにすべきであったが,
被告らはそのようなことをせずに秘密裏に除去工事をなした。アスベスト
除去工事についての説明図書の配布は同月15日であり,説明会は同年1
2月であり,事前の説明がなされていない。
(ウ)大気汚染防止法18条の14及び同法施行規則16条の4では,アスベ
スト除去工事をする場合には一定の事項を掲示しなければならないと定め
られているが,被告らはそれを行っていない違法がある。被告らは,アス
ベスト除去工事に関し,近隣住民に掲示板を設置するなどして情報提供を
行う義務があったが,掲示板が設置されたのは平成18年12月過ぎであ
り,アスベスト除去工事後である。
(エ)大気汚染防止法は,アスベスト除去作業時に十分な散水をするよう定め
ているが,行われていない違法がある。
ウ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)被告らは,本件工事で激しい騒音・振動を発生させた。平成19年1月
17日になってようやく騒音・振動計が設置された。同年1月24日午前
9時過ぎには,さいたま市騒音防止条例(以下「条例」という。)に違反
する94デシベルの騒音を発生させた。
(イ)本件工事による騒音・振動については,条例に違反している。さらに,
防音シート,防音壁を十分使用する,低騒音・振動の工事機械を使用した
り,手で壊す,ゆっくりと時間をかけて機械を使用して壊す,十分休み時
間をおいて振動の激しい作業を連続させないなどの騒音・振動を低減させ
る対策を取ることなく,経済的利益を追及し,早急な工事が行われている。
また,被告らは原告らに十分な説明や,工程表の配布等をせずに工事を行
っている。これらは,受忍限度を超えている。
(ウ)被告らは,十分な散水をして粉じんの発生を防止する措置を執らず,ま
た,年末年始にコンクリート屑等の有害物質の飛散が予想されることから
十分瓦礫に散水したり,解体搬出したり,シートによる養生をしておくべ
きであったが,その実行を怠り瓦礫を飛散させた。
エ誠実義務違反
原告らの被告らに対する騒音・振動・粉じんに関する危惧や苦情に対し,
被告らは対策を講じなかった。具体的には,騒音振動計を現地敷地の境界線
上と変更すること,防音シート等を充分な範囲で設置すること,昼休みには
一切の工事を休んで騒音・振動を発生させないこと,散水を充分すること,
重機が倒壊する危険に対し対策を採ることなどの要望を無視し,工事協定書
の締結を拒否し,さいたま簡易裁判所公害調停において調停委員会が助言し
た400万円の支払を拒否した。
(被告三菱地所)
ア説明義務違反について
(ア)原告は大気汚染防止法施行規則16条の4に基づき説明義務を負うかの
主張をしているが,被告三菱地所は「特定粉じん排出等作業」(大気汚染
防止法2条12項)を行うものではないから,大気汚染防止法に基づく責
任を負わない。
(イ)同規則16条の4の掲示義務から住民に対する説明義務は発生しない。
法が定める掲示義務は履行されている。
イ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)騒音については,受忍限度の範囲内である。
(イ)振動は,規制値を超えておらず,受忍限度の範囲内である。
(ウ)粉じん発生は,事実が不明である。また,散水による飛散防止措置は講
じられていた。
ウ誠実義務違反について
誠実義務なるものの内容は不明である。
(被告木内建設)
ア説明義務違反について
(ア)大気汚染防止法施行規則16条の4に掲示義務があることは認めるが,
住民に対する説明義務はない。
(イ)アスベスト除去工事の際十分散水する義務があるというのは争う。散水
による飛散防止は,薬液等による湿潤化作業等による飛散防止措置ができ
ない状況の防止策として許容されているものである。
(ウ)本件解体工事に関する届出書で「近隣周知」との記載をしたこ, とは認
めるが,これにより説明会の開催義務が生じるわけではない。
(エ)平成18年12月に開かれた説明会は,解体工事ではなく,新築工事の
説明会である。
(オ)本件のアスベスト除去工事は国土交通省が発表している資料によると,
「塔屋階段天井材」及び「屋上クーリングタワーパッキン」の石綿除
去作業はレベル3(発じん性が比較的低い)に属する作業で,「煙突内部
断熱材」の石綿除去作業はレベル2(発じん性が高い)に属する作業で
あるが,外界から隔離した区画内で適切に行っている。
イ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)平成18年1月24日に94デシベルの騒音を記録したことは認めるが,
これは遮音性の低い東側の道路境界面で測定したためである。
(イ)公法上の規制に違反することが直ちに私法上の不法行為責任が生じるこ
とにはならない。概ね,音源と各原告の居住地との距離の事情に反比例す
るといわれている。
(ウ)音は音源を中心として球状に伝達するから,音源からの距離を半径(r)
とすれば,音のエネルギー量は音の表面積=4×円周率(π)×rの二乗
となるので,距離が音源から2倍となったときエネルギー量は距離の二乗
に反比例する結果4分の1となる。デシベルとは音のエネルギー量を表す
ものであり,10デシベルの差は10倍のエネルギー量の差を意味すると
ころ,仮に音源からの距離が約3倍になれば,エネルギー量は約9分の1
となり,騒音計の数値は約10デシベル低下することになる。原告らは居
住地を異にしているから,同一に論じることはできない。
(エ)また,建物の遮音性能は,少なくとも約25デシベルある。
(オ)条例の規制値を85デシベルとしても,騒音計指針値の最大値の90パ
ーセントがその値であるから,85デシベルを90パーセントで除した9
4デシベルを超えると,規制値を超えたことになる。さらに,本件工事現
場に一番近い原告X12宅でも,基準距離の2倍ないし3倍はあるから,
距離減衰により6ないし9デシベルは低下することになる。したがって,
100ないし103デシベルの指針値を超えたのでなければ,違反とはな
らない。原告らの多くは,基準距離の3倍以上は離れているので,106
デシベル以上の騒音であることが必要である。加えて,建物の透過損失に
より25デシベル以上の低下もあるから,受忍限度の範囲内である。
(カ)粉じん被害の主張は,争う。
ウ誠実義務違反について
争う。
( ) 被告三菱地所が不法行為責任を負うか(争点2 。(2))
(原告ら)
被告三菱地所は,被告木内建設の使用者として,民法715条に基づき使用者責任を負う。
また,被告木内建設とともに民法719条に基づき共同不法行為責任を負う。
(被告三菱地所)
被告三菱地所は被告木内建設の使用者ではないから,民法715条による
責任を負わない。
また,被告らに不法行為責任がないから,民法719条の主張は失当であ
る。
(3) 原告らに生じた損害の程度(争点(3))
(原告ら)
原告らは,被告らの下記の本件工事によるアスベスト,コンクリート屑等
の飛散と騒音・振動により,精神的・身体的被害を受けた。具体的には,身
体的に血圧が上昇したり,不眠となったり,ぜんそくが悪化したり,動悸が
したり,自律神経が失調したりするなどの顕在化した被害や,顕在化しない
程度の生活妨害を受けた。この被害による慰謝料は,原告ら各自につき50
万円を下らないので,そのうち20万円の支払を求める。
(被告ら)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。(以下,特に断りがない場合,9月から12月は平成18年,1月から8月は平成19年の日時を指す。)
( ) 本件工事の工程等(1 甲2)
ア 本件工事の途中で被告らが開示した工程表(甲4。以下「本件工程表」という。)によると,本件工事は,工事が始まる順番に,仮設工事,内装解体,ハツリ工事,進入路確保工事,アスベスト除去工事,PCB撤去工事,レッカー作業,塔屋,5F,4F,3F,2F,1F,山留め工事,地下解体,基礎解体,アスファルト解体,外構解体,整地,杭抜き工事という20の工
種に分解されている。本件工程表では,10月4日から3月17日までを工期と予定しており,アスベスト除去工事は10月23日から11月2日の10日間(作業日数。以下同じ。),塔屋解体工事は11月4日から同月9日の5日間,5F解体工事は11月10日から同月16日の6日間,4F解体工事は11月17日から同月25日の7日間,3F解体工事は11月27日から12月4日の7日間,2F解体工事は12月4日から同月9日の6日間,1F解体工事は12月9日から同月16日の7日間,地下解体工事は12月18日から1月26日の30日間,基礎解体工事は1月22日から2月3日の12日間,アスファルト解体工事は2月5日から同月16日の10日間,外構解体工事は2月5日から同月16日の10日間,杭抜き工事は2月13日から3月17日の29日間となっている。
また,使用重機,アタッチメントの予定表によれば,仮設工事・内装工事は10月10日から11月2日までの21日,建家解体工事は11月4日から1月10日までの47日間,地下解体工事は1月11日から2月17日までの32日間,基礎解体工事は2月19日から同月28日までの9日間となっている。(甲33の10)
イ 9月8日ころ,被告三菱地所は,さいたま市長に対し,建設工事に係る資材の再資源化に関する法律10条1項の規定により,本件解体工事の届出書(甲3。以下「本件解体工事届出書」という。)を提出した。
本件解体工事届出書には,「建築物に関する調査の内容の結果」として,「その他」欄に「。, 煙突内部にカポスタック吹付有り現在ステンレスで覆い飛散防止済。」,
「工事着手前に実施する措置の内容」として,「作業の確保」欄に「敷地内作業スペース十分有り。」,「その他」欄に「近隣周知。」と記載し,工事着手の時期を,「平成18年9月19日」と記載している。また,「工程ごとの作業内容及び解体方法」として,「外装材・上部構造部分の取り壊し」,「基礎・基礎杭の取り壊し」,「その他の取り壊し」を「手作業」ではなく,「手
作業・機械作業の併用」の「分別解体等の方法」により行う旨記載している。(甲3)
ウ 被告木内建設は,10月4日,本件工事に着手した。本件工事の内容は,地上5階建て鉄骨鉄筋コンクリートビルの取壊と,地下室の取壊及び地下室周辺の障壁の解体,搬出及び地中杭4本(長さ約34メートル,直径は1300ミリメートル1本,1400ミリメートル1本,1500ミリメートル2本。)の抜き取りと現場解体,敷地外搬出である。
エ 本件工事の際,本件敷地と,周囲の道路や隣地との境界線上には,ほぼ全面に1800ミリメートル×5400ミリメートルで鉛を含有する重量50キログラム程度の防音シートが張られていた。また,本件敷地のうち,本件建物があった東側部分の敷地四方には,西側南部分を除き,高さ3メートルの安全鋼板仮囲が設置されていた。本件敷地の東側には道路b があり,道路b
から本件敷地への搬入路としては,東側の仮設搬入路と,北東側の搬入搬出口の2か所があった。
このうち,東側の仮設搬入路の部分は,防音シートや安全鋼板仮囲がなく,防音性能の乏しいシートが張られていた。(丙10)
オ 10月30日,被告木内建設は,さいたま市長に対し,本件工事につき日曜・祭日を除く10月17日から2月28日の期間に,さく岩機作業(解体)による騒音規制法の定める特定建設作業を,ブレーカー(解体)による振動規制法の定める特定建設作業を,それぞれ行うとして,特定建設作業実施届出書(丙5,6)を提出した。
いずれも,騒音・振動の防止方法の一つとして,行程・作業内容等を近隣住民に説明することを記載している(。丙5,6)
カ 本件建物には,?塔屋階段の天井材,?屋上クーリングタワーのパッキン,?煙突内部の断熱材に,石綿が含有されている。?については,ボイラー室を中心に,アスベストを含有する断熱材が,324ミリメートル×5.9メートルの量使用されている。
このうち,?は,被告木内建設から請け負った株式会社東京ビルド(以下「東京ビルド」という。)が,10月23日,2
4日に湿潤化させた上,極力割らないように撤去し,袋詰めを行い,10月24日に搬出した。
?は,東京ビルド,?は練馬建設工業株式会社(以下「練馬建設」という。)が,11月7日から同月21日まで除去作業を行い,実際には11月9日のさいたま市役所の養生検査済後,除去作業に取りかかり,11月21日に作業を完了し,12月11日に搬出した。?に関して,東京ビルドは,10月24日,さいたま市長に対し,「特定粉じん排出等作業実施届出書」(乙5。以下「本件届出書」という。)を提出し,10月31日,「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」と題する掲示板(乙6の?な
し?がその写真である。以下「本件掲示板」という。)を,本件工事の現場西側の安全鋼板仮囲の側面2か所に設置し,練馬建設は,本件届出書提出から14日後である11月7日から本件石綿除去工事を開始した。(甲19,乙5,6,11)
キ 12月29日から1月8日の年末年始にかけて,被告木内建設は工事を中断していたが,その際,散水やシートによる養生などで,瓦礫の飛散を防止する措置を講じていない。年末年始のシートによる養生について,さいたま市環境経済局環境部環境管理事務所(以下「さいたま市環境管理事務所」という。)の担当者と被告木内建設の現場所長との間の電話で,シート養生をする方法での埃等の飛散防止の方法が話題に出たことがある。
ク 本件工事により,本件敷地東側の道路b に24メートルほどにわたって亀裂が生じ,4月4日ころ,補修工事が行われた(甲48,54。の4)
ケ 本件工事は,3月ころまでは1週間遅れが出る程度でほぼ予定通りに進み,既存杭引抜作業を残す段階に来ていたが,杭引抜機械の故障や新たな地中障害物の発見により,5月中旬から下旬までかかる見込みとなったため,被告木内建設は,3月20日ころ,近隣住民にこのことを文書で周知した。
さらに,既存杭引抜作業は予定以上に時間がかかり,4本中2本は工法も変更して行うこととしたため,被告木内建設は,5月7日,本件工事の完了予定を6月中旬と変更し,近隣住民に文書で周知した。予定変更以降の作業で見込まれる騒音や振動について,被告木内建設は,3月に行われている既存杭引抜作業と同程度と予想している。(甲48)
コ 7月11日,重機が搬出され,本件工事は終了した。(乙1)
サ 本件工事による騒音は,周辺住民の感覚としては,上部構造の解体工事,地下室の解体工事,杭抜き工事のときが大きかった。(原告X3(以下「原告X3」という。),原告X20(以下「原告X20」という。))
(2) 原告らと被告らの交渉状況等
ア 11月15日,被告らは,本件工事後に予定している本件マンション建築計画に関する説明文書を近隣住民に配布し,12月5日午後7時30分から,本件マンション建築計画に関する第1回近隣説明会を実施した。(甲8の1)
イ 12月19日,被告らは,本件マンション建築計画の第2回近隣説明会を実施した。この際,本件工事について,データを保存できる騒音計・振動計の設置が要望された。(甲8の2)
ウ 1月11日,被告らは,本件マンション建築計画の第3回近隣説明会を実施した。この際,さいたま市環境管理事務所との間で被告木内建設が約束した年末年始の粉じん飛散防止のためのシート養生がなされていなかったことが議題に出て,被告木内建設はシート養生の指導を受けた認識がない旨答えた。
また,被告らは,1階の解体工事について,確たる数値ではないが,70ないし75デシベル程度と思う旨答えた。そして,騒音・振動計の設置が決まった(甲8。の3)
エ 1月17日,第3回近隣説明会の合意に基づき,被告木内建設は,工事現場近くに騒音振動計(以下「本件騒音振動計」という。)を設置した。
本件騒音振動計の記録紙は,1目盛りを1デシベルとし,90デシベルを目盛りの上端としている。本件工事により記録された記録紙(甲32)には,90デシベルを超えた数値が記録されているところもあるが,その部分の数値が
単純に超過した長さ1目盛り分につき1デシベルといえるか,不明であるし,本件騒音振動計の構造上(甲48),際限なく大きな数値が記録されることはない。
オ 1月22日,被告らは,本件マンション建築計画の第4回近隣説明会を実施した。その日の朝に,ターンテーブルの解体をしたため,特に大きな振動が出たことが話題に出た。(甲8の4)
カ 1月24日午前9時過ぎ,原告本人兼原告ら代理人弁護士X1(以下「X1弁護士」という。)が本件騒音振動計を本件敷地東側境界上の防音シートのないところに移すと,94デシベルの騒音が記録された。(当事者間に争いがない。)
キ 2月16日,さいたま市環境管理事務所が本件工事現場の騒音及び振動を測定した。その際,騒音について,測定値の90パーセントレンジの上端値が,85デシベルという測定結果であり,振動について,測定値の80パーセントレンジの上端値が,61デシベルという測定結果であった。
この測定の際は,まずさいたま市環境管理事務所の者が一度本件工事の現場に訪れて工事関係者に騒音及び振動の測定をすることを伝えた後,一度現場を離れ,数十分後に再度来てから測定を開始しており,普段よりも控えめな騒音・振
動で工事が行われていた。(丙7,原告X3)
2 争点(1)(本件工事の違法性)について
( ) 説明義務違反に1 ついて
ア 大気汚染防止法18条の14及び同法施行規則16条の4は,作業基準としてアスベスト除去工事を行う場合の一定の事項の掲示義務を定めており,作業基準を遵守しない場合には都道府県知事が作業基準適合命令等を行うことができるとし(同法18条の18),当該命令に従わない場合には行為者に6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則を定め(同法33条の2第1項2号),同額の罰金の両罰規定も定めている(同法36条)。
しかしながら,この法令の定めにより,直ちに被告木内建設が近隣住民等に対する私法上の説明義務を負うと解することはできない。
イ また,原告らは,本件解体工事届出書に「近隣周知。」と記載したことにより,被告木内建設は原告らへアスベスト除去工事の説明義務を負う旨主張する。
本件解体工事届出書は,建設工事に係る資源の再資源化に関する法律10条1項に基づく届出であるところ,同法は,当該届出に虚偽記載をした場合には20万円以下の罰金という罰則を定め(同法51条1項1号),同額の罰金の両罰規定も定めている(同法52条)。
届出た計画が法令が定める基準に適合しないと認めるときは,都道府県知事は計画の変更その他必要な措置を命ずることができ(同法10条3項),命令に違反したときには30万円以下の罰金という罰則を定め(同法50条1号),同額の罰金の両罰
規定も定めている(同法52条)。
しかし,この法令の定めにより,直ちに被告木内建設が近隣住民等に対する私法上の義務を負うと解することはでき
ない。
ウ その他,以上に認定説示したところ及び弁論の全趣旨により認められる事情を考慮しても,被告木内建設が原告らに対し説明義務を負うとは認められない。
エ また,大気汚染防止法等で規定する掲示義務に違反したところで,原告らに損害が生じるとも認められない。
オ したがって,原告らの説明義務違反の主張は理由がない。
( ) 騒音・振動の発生に2 ついて
ア 社会生活を営む上である程度の騒音や振動は発生するものであるから,互いに受忍すべきものであるが,騒音や振動を体感することにより,その種類・程度等によっては,人は不快感を覚え,精神的・身体的に健康を害されることがあるから,騒音や振動が受忍限度を超える場合には,違法な騒音ないし振動として,不法行為が成立することがあるというべきである。
そして,いかなる騒音や振動が不快感を及ぼすかは,個人差もあると考えられるが,騒音規制法は,特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,85デシベルを超える大きさを規制基準としていること(乙8),振動規制法は,特定建設作業の振動が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,75デシベルを超える大きさを規制基準としていること(振動規制法施行規則11条),本件敷地の周辺は第1種住居地域ないし第2種住居地域であり(甲45),平常時の工場・事業場等の騒音・振動規制について,騒音規制法,振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例上,午前8時から午後7時までの間,工場・事業場の敷地境界において,騒音は55デシベル,振動は60デシベルを規制基準としていること(甲46),特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準は,騒音の大きさの決定方法について,指示値が変動しないときは指示値を,周期的又は間欠的に変動し,最大値がおおむね一定の時は指示値の最大値の
平均値を,指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は測定値の90パーセントレンジの上端の数値を,周期的又は間欠的に変動し,最大値が一定でない場合は指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値を,それぞれ騒音の大きさと定めていること(乙8),振動規制法施行規則は,振動レベルの決定方法について,測定器の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値を,測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値を,測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,5秒間隔,100個又はこれに準ずる間隔,個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値を,それぞれ振動の大きさと定めていること(振動規制法施行規則別表第1備考4)などの事情からすると,騒音については,ある程度継続的に85デシベルを超える騒音や,騒音の程度は一定ではないが一時的にでも94.44デシベル(85デシベルを0.9で除した数値)を超える騒音を,振動については,ある程度継続的に75デシベルを超える振動や,振動の程度は一定ではないが,一時的にでも93.75デシベル(75デシベルを0.8で除した数値)を超える振動を,特段の事情がない限り,受忍限度を超える違法な騒音や振動というべきである。
イ もっとも,騒音や振動は距離が離れるに連れて弱まるものであり(距離減衰,騒音について見ると,その程度は距離の二乗に反比例し,音の) 発生源から測定位置までの距離をX,発生源から被害地までの距離をYとすると,20× log(Y÷X)の式により減殺されるデシベルの数値が算出される(弁論の全趣旨)。したがって,原告らの敷地境界線上において,距離減衰を考
慮した上で,上記違法な騒音や振動が発生していた場合に,不法行為の成立を認めるのが相当である。
ウ まず,振動については,本件工事により継続的にどの程度の振動が発生していたか証拠上明らかでない上,平成19年2月16日に行われたさいたま市環境管理事務所の測定結果時,騒音が規制基準と同数値の85デシベルという測定結果だったのに対し,振動は規制基準の75デシベルを下回る61デシベルであったことからすると(丙7),一時的に大きな振動が発生することがあったとしても(甲48),受忍限度を超える違法な振動が発生していたと認めることはできない。なお,原告らは,道路や家屋のひび割れを指摘するが,これは振動の影響なのか,本件解体工事による地盤沈下の影響なのか,その他の原因なのか証拠上不明であり,これらをもって振動の強さを判断することはできない。したがって,本件工事の振動による不法行為は,
認められない。
エ 次に,被告木内建設が本件工事により発生させていた騒音について認定事実も踏まえて検討する。
(ア)平成19年1月19日から同年2月28日までの騒音については,別紙騒音一覧表(省略)の「該当日付」の日に,概ね「1日合計分」の分数程度,90デシベルを超える騒音が発生していたと認められる(甲5の1及び4,甲32)。
(イ)平成19年2月16日午前8時35分から午前10時26分まで,さいたま市環境管理事務所が行った騒音の測定結果は,東側敷地境界において,測定値の90パーセントレンジの上端値で,85デシベルであった。(乙9)
(ウ)騒音計の記録(甲32)によれば,1月24日,2月8日,2月13日ないし15日,2月22日ないし24日,2月26日などの日は(いずれも平成19年),平成19年2月16日午前8時35分から午前10時26分までの騒音と比較し,大きな騒音,長期間の騒音が出されている。騒音計の計測条件は,平成19年1月24日に防音性の比較的低いところで計測されたと認められる点を除き,特段の違いは見当たらない(丙10)。
(エ)本件騒音振動計の記録用紙は1目盛りを1デシベルとし,90デシベルを上限としていて,それを振り切った場合の数値は不明であるが,平成18年2月24日に94デシベルを記録したことに当事者間に争いはなく,振れ幅の大きさ上,それと同程度の騒音を記録しているところは平成19年2月22日ないし24日,同月26日などにもあるから,本件工事により,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認めるのが相当である。そして,本件騒音振動計が設置されていなかった時期の騒音の程度は客観的な数値としては明らかではないが,原告らは個人差があるもののいずれの工事も騒音がうるさかった旨供述していること 引抜工事までの解体工事については,使用している重機を見ても工事の種類ごとに騒音の程度が大きく異なるとは認められないことなどから,本件工事のうち平成18年11月21日にアスベスト除去工事が終了し,本件建物の解体工事が始まった平成18年11月末ころから,既存杭引抜工事前の本件建物及び地下室の解体工事が終了した平成19年2月28日までの間,散発的に,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認める。
他方,既存杭引抜工事については,解体工事がコンクリート等を破壊する作業であるのに対し,杭を引き抜くという異なる作業であること,騒音の客観的な数値が不明であることから,引き抜いた杭を本件敷地内で壊していたとしても,受忍限度を超える違法な騒音が発生していたとは認められない。
オ 以上のとおり,本件工事により,平成18年11月末ころから平成19年2月28日までの間,散発的に,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたことを前提に,それらが各原告らに対する受忍限度を超える違法な騒音といえるか,検討する。
(ア)本件敷地は,東側が約35メートル,南側が約26メートル超,北側が約15メートルの長さである。また,本件建物は,本件敷地の東側に,1階から6階は東西方向に12メートル,南北方向に31.7メートルの長さで建っており,その南側に東西方向に12メートル,南北方向に15.85メートルの長さの地階があった。(甲14,弁論の全趣旨)
(イ)本件工事による騒音の発生源は一定せず,本件騒音振動計も一定していないが,平均すると,本件建物の中心地から騒音は発生していたと考えられ,本件騒音振動計は本件建物の北側に設置されていた期間が多かったことから,上記記載の本件建物や本件敷地の状況を考慮し,本件騒音振動計は,音源から30メートル離れたところで記録されたものと認めるのが相
当である。
(ウ)そうすると,本件工事により本件敷地境界線部分で94デシベルの騒音が発生したと認められるから,距離減衰により9デシベルの騒音低下が生じれば,騒音は受忍限度の範囲内といえる85デシベルの範囲内に収まることになる。そして,上記距離減衰の式によると,音源から85メートル離れることにより,9.04デシベル(=20× ( ))騒音log 85/30 は低下することになる。
(エ)本件工事による騒音の発生源は一定していなかったことは既述のとおりであるが,本件敷地内のどの場所からも騒音が発生していた可能性があるから,距離減衰との関係では,本件敷地境界線から原告らの敷地までの距離で距離減衰を考えるのが相当である。
(オ)なお,被告木内建設は,家屋の壁などによる透過減衰も主張するが,仮に透過減衰の量を25デシベルとしても,85デシベルを超える騒音から透過減衰を考慮しても60デシベルとなり,平常時の規制基準である55デシベルを超えているから,受忍限度を超えるという判断には影響しないというべきである。
(カ)以上の考えに基づき,本件敷地から85メートルの範囲内に敷地が含まれる原告らを判別すると,別紙原告ら居住地(省略)記載のとおり,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6,原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12,原告X13,原告X14,原告X15,原告X16,原告X17,原告X18(以下「範囲内原告」という。)となる。
これらの原告は,被告木内建設に対し,騒音被害による不法行為に基づき,損害賠償請求権を有しているというべきである。
これに対し,原告X19及び原告X20(以下「範囲外原告」という。)は,受忍限度内の騒音被害であったというべきであり,被告木内建設に対し,騒音被害による不法行為に基づき,損害賠償請求権を有しない。
( ) 粉じんの発生に3 ついて
ア 原告らは,本件工事による粉じんの発生で苦痛を被ったと主張する。
イ 確かに,証拠によると,本件工事によりある程度の粉じんが発生したことが認められるが(甲11,48,原告X3),本件敷地の外に粉じんが飛散したか否か,どの程度飛散したか,粉じんの飛散により原告らに損害が発生したのか等,不明であるといわざるをえない。
ウ また,被告木内建設が,原告らに対し,通常の不法行為責任を超えて,粉じんを飛散させないように注意すべき特段の法的義務を負っていたと認めることはできない。
エ よって,原告らの粉じんの発生による不法行為の主張は,理由がない。
(4) 誠実義務違反について
原告らは,被告木内建設が原告らの本件工事に対する要望に誠実に対応しなかったことなどをもって,誠実義務違反と主張するが,本件事実関係の下で,被告木内建設が,原告らが主張するような法的義務を負っていたとはいえない。
よって,原告らの誠実義務違反の主張は,理由がない。
3 争点(2)(被告三菱地所が不法行為責任を負うか。)について
(1) 使用者責任について
ア 原告らは,被告三菱地所が使用者責任を負う旨主張するが,使用者責任が生じるためには使用者とされる者が被用者とされる者を指揮監督する使用関係が必要である。
イ 被告三菱地所と被告木内建設の本件工事についての関係は,請負契約であることに争いはなく,被告三菱地所から被告木内建設に対し工事の方法等につき特段の指揮監督がなされていたと認めるに足りる証拠はない。
請負契約における注文者は,注文又は指図についてその注文者に過失があったときでなければ,請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないのであって(民法716条,本件では具体的に被告三菱地) 所の注文又は指図に過失があったとは認められないことも併せ考慮すると,被告三菱地所が使用者責任を負うとはいえない。
(2) 共同不法行為責任について
原告らは,被告三菱地所が共同不法行為責任を負う旨主張するが,被告三菱地所が被告木内建設と共同して本件工事を行ったとは認められず,本件工事について主観的な関連共同関係があったとも認められないから,被告三菱地所が共同不法行為責任を負うとはいえない。
(3) よって,原告らの被告三菱地所に対する請求は,すべて理由がない。
4 争点(3)(原告らに生じた損害の程度)について
(1) 既に認定したとおり,本件工事により範囲内原告に対し不法行為を構成するのは,平成18年11月末ころから平成19年2月末ころまで,散発的に生じる,ある程度継続的に94デシベルに達する騒音である。
騒音が発生していたのは約3か月間の月曜日から土曜日の午前8時から午後5時ころであったこと,違法な騒音は毎日発生するとは限らず,発生する日も1日中違法な騒音が続いたわけではないことなどからすると(甲11,32,原告X3,原告X20),慰謝料は,一人当たり10万円が相当である。
(2) なお,原告X3は,神経性胃炎,胃けいれん,不安神経症,不眠症,血圧上昇という診断書を提出するが(甲11の4の2),医師の診断を受けたのは2年ぶりであるなどと供述しており,本件工事との相当因果関係は認められない。
第4 結論
よって,範囲内原告の被告木内建設に対する請求は,慰謝料各10万円及びこれに対する不法行為後である平成19年1月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これらを認容することとし,範囲内原告の被告木内建設に対するその余の請求,被告三菱地所に対する請求,範囲外原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がないので,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第5民事部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090528150644.pdf
2009年10月31日
桃花台の地盤沈下と土壌汚染
******************************
ウィキメディアより
桃花台の地盤沈下と土壌汚染
■地盤沈下■
愛知県が造成し都市再生機構(旧 住宅・都市整備公団)が販売した、ニュータウン南部の城山5丁目地区にある住宅で地盤沈下が発覚し、問題となっている。
問題の発覚は2001年、同地区の2軒の住宅に住む住人から、都市再生機構に対し「家が傾いてきた」との苦情が届いた事に始まる。その後都市再生機構が調査したところ、2軒の住宅とも家が沈下している事が判明。2軒の住宅は都市再生機構が買取り、後に解体された。
2軒の住宅から突然家主が引っ越した事を不審に思った近所の住民が、都市再生機構に問い合わせたところ、地盤沈下の事実を知る。2005年にはこの2軒の住宅周辺の住民からも、都市再生機構に対し「家が傾いてきた」などの苦情が相次いで届くようになる。
その結果都市再生機構がそれらの住宅を調査したところ、数軒で地盤沈下が判明する。2006年2月都市再生機構は、問題となっている地域のボーリング調査を開始する。
すると、さらに十数軒の住宅が沈下している事が判明。この事は、マスメディアによって大きく報じられる事となる。

有害物質の埋設が確認された場所(桃花台ニュータウン)
問題となっている土地は、
1957年に王春工業の会長が購入し、王子製紙春日井工場などから出る産業廃棄物を10年以上にわたって廃棄していた事がわかっている(当時は廃棄物処理に関する法律がなかったため、この件で王春工業の責任を問うことはできない)。
1971年7月、愛知県が小牧市の仲介でこの土地を購入し、造成工事を行っている。この造成工事の際、産業廃棄物と見られる粘土が大量に堆積していた事を、当時の愛知県庁職員が確認している。そのため「これらを撤去した」としているが、「全て撤去できなかった可能性もある」とも証言している。
その後愛知県は、この土地を旧住宅・都市整備公団に売却。
住宅・都市整備公団は住宅を建築し、1988年に販売している。
2006年7月都市再生機構は、地盤沈下の原因を探るべく、解体した2軒の住宅跡地の地下の土壌の調査分析を開始。同年11月に結果を公表している。それによると、「問題となっている土地は産業廃棄物が層となって残っており、その上にさらに土が盛られている状態であった。
この産業廃棄物層の上にある土の層が造成の際十分踏み固められておらず、雨水が浸透。その結果その層が沈下し、さらにその重みに絶えられず、産業廃棄物層が沈下した。」と言うものであった。
■土壌汚染■
土壌汚染が発覚した城山地区の土地は1957年に王春工業の会長が購入し、王子製紙春日井工場などから出る産業廃棄物を10年以上にわたって廃棄していた事がわかっている。
2006年11月に公表された都市再生機構の調査結果では、産業廃棄物が現存している事が確認されている。 また同調査では、環境基準値の170倍の鉛を含む5種類の有害物質や、油分、木片、ガラス片、ビニール袋なども確認されている。
同年8月住民からの要請を受けた小牧市は、市独自の調査を開始する。都市再生機構の調査地点から土壌サンプルを回収し、同年10月に分析結果を公表している。それによると、「土壌には環境基準を上回る有害物質(ヒ素:3.6倍、ジクロロメタン:約1.9倍)が含まれており、通常の土壌ではほとんど検出されない油分も検出された」となっている。この調査結果を受けて小牧市は、愛知県と都市再生機構に対し、適切な対応を求める要望書を提出している。
同年8月住民は愛知県に対し、県独自の調査を要請している。それに対し愛知県は、「都市再生機構側に責任がある」として、要請を断っている。
しかしその一方で、愛知県庁の職員が都市再生機構の調査地点から土壌サンプルを回収。同年10月に小牧市とともに分析結果を公表している 。それによると、小牧市の調査では環境基準を上回る有害物質が見つかっているの対し、愛知県の調査結果は「環境基準を上回る有害物質は見つからなかった」と言うものであった。
■問題地域の拡大■
新たな問題として同年11月に開かれた住民説明会で、愛知県は、問題となっている地域の土壌がニュータウン内の3つの学校(大城小学校、光ヶ丘小学校、光ヶ丘中学校)のグラウンドに持ち込まれて埋められた事を公表した。そして調査対象地区を学校グラウンドにも拡大し、改めて調査を行った。
その結果、光ヶ丘小学校と大城小学校の敷地内で、環境基準の1.1〜2.2倍の鉛が見つかった。一方住宅地からは、1.3〜6.9倍の鉛と1.2倍の総水銀、そして1.5倍のヒ素が見つかった。さらに黒い土が見つかった全ての地点からは、油分が検出された。
この調査結果に対し愛知県は、環境基準を超えた物質が見つかった場所は全て1.2〜2.5mの土で覆われており、地下水の飲用利用もないため、「人体への影響は無い」としている。また「(環境基準を超えた物質が)検出された原因は判らない」としたうえで、県の責任を否定している。
また2008年4月には、古雅地区に整備される予定の住宅地「エコーガーデン桃花台」の土地の一部の地下からも、環境基準を上回る有害物質(基準約7倍のヒ素、基準をやや上回るフッ素)が見つかっている。これは他地区で土壌汚染が相次いで発覚した事を受けて、整備を行っている愛知県住宅供給公社が2007年10月から行った土壌調査で明らかとなった。
問題が発覚した土地は、1970年代に愛知県が購入。1989年頃まで暫定調整池として利用されていた。1999年3月に、愛知県が県住宅供給公社に売却。その後駐車場などとして利用されていたが、2007年4月から住宅地の整備工事が始められていた。
なお、なぜ有害物質が見つかったかについては、不明としている。
■裁判■
■都市再生機構による損害賠償請求
この問題の責任を巡って、2006年8月都市再生機構は「地盤沈下の原因は愛知県の責任である」として、住民への補償費用やこれまでかかった調査費用などを求める裁判を名古屋地方裁判所に起こした。都市再生機構側は「(愛知県から)大量の廃棄物が持ち込まれた場所だったとは聞いていない。廃棄物があれば購入していない。」と主張。
それに対し愛知県側は「土地売買の際、資料のやりとりはあったはず。旧住宅・都市整備公団には、住宅の売り手として、地盤をよく調べる義務がある。基礎を頑丈にした近隣の住宅では、問題は起きていない。」と主張した。
判決が出たのは2009年3月26日。「地盤調査する責任は都市再生機構にあった」として、都市再生機構側の訴えは棄却された。
■住民による損害賠償請求
2007年10月、問題が起こっている城山地区に住む5人の住民が、住宅の購入費用の返還を求めた裁判を名古屋地方裁判所に起こした。訴えられた側は愛知県と都市再生機構。賠償請求額は総額約9,300万円。
その後2008年11月にも、同地区に住む別の住民12人が、同じく愛知県と都市再生機構を相手取って有害物質の除去や損害賠償を求める裁判を起こしている。賠償請求額は総額約1億2千万円。[16]
■公害調停
住民は県の公害審議会に対し、2008年3月に公害紛争処理法に基づく公害調停を申請。住民側は委員に対し、原因究明や第三者機関による土壌調査を要請した。
これに対し愛知県側は、調停の打ち切りを要請。都市再生機構も自らの責任を否定したうえで、調停には応じない構えを見せた。
その後3回の調停が行われたが、結局3者相容れず。同年8月の3回目の調停で、打ち切りが決定した。
■今後の対策や調査■
■都市再生機構
都市再生機構は、地盤沈下の対策については「これ以上両層とも沈下する可能性は低い」として、一軒ごとに住宅を調べたうえで場合によってはジャッキアップ工法で修復工事を行うとしている。
それに対して住民は、「それでは不十分だ」として産業廃棄物の完全撤去を求める意見を出している。しかし、都市再生機構は産業廃棄物に関して「愛知県の調査結果を待ってから検討する」としている。
■愛知県
愛知県は土壌汚染の範囲を測定するため、「2006年中に調査を開始し、翌2007年3月には結論をまとめる」としている。調査の詳細は、「すでに解体された2軒の住宅を中心に同心円状に1軒1軒ボーリング調査をしていく」と言うものである。また新たな問題として浮上したニュータウン内の3つの学校のグラウンドへの問題となっている土壌の埋設に対応する為に、「これらの学校のグラウンドも調査する」としている。
なお愛知県は、現在も産業廃棄物の存在を認めていない。問題となっている土壌については、「粘土質の土壌」、「黒っぽい土」などとしており、あくまで自然の土であると言う立場である。これに対し住民は、「土壌からは木片やガラス、油分などが見つかっており、明らかに産業廃棄物だ」と愛知県の認識を非難している。
一方地盤沈下に関する対応について愛知県は、2006年11月に行われた住民説明会で、都市再生機構との裁判を理由に曖昧な対応をした。
そのため住民からは、「住民より裁判を重視するのか」と非難が相次いだ。結果、その翌日に行われた県知事の定例記者会見でもこの問題が取り上げられた。その際神田真秋愛知県知事は、あくまで「地盤沈下の責任は、都市再生機構にある」としながらも、土壌調査の際に得られる地盤沈下に関する情報(地耐力データ)の住民への公開を示唆した。
■その他の機関■
■小牧市
小牧市は2007年6月の議会で、問題が起こっている城山地区の一部住民に対し、過去数年間の固定資産税減免措置実施を表明している。
愛知県住宅供給公社
愛知県住宅供給公社は、古雅地区のエコーガーデン桃花台内で見つかった有害物質が含まれる全ての土壌を撤去し、新しい土と入れ替えるとしている。
■亜炭鉱
ニュータウンを含めた一帯では、江戸時代から第二次大戦後しばらくにかけて、石炭の一種である「亜炭」と呼ばれる鉱物が掘り出されていた。そのため、一部報道機関では「地盤沈下の原因は、亜炭鉱が崩れたからではないか」と報じられた。
■年 表■
・1957年 - 王春工業が、一帯の土地(当時は山林)を購入。愛知県へと土地を売却するまでの間、王子製紙春日井工場などから出る産業廃棄物を投棄。
・1971年7月 - 小牧市の仲介で、愛知県が土地を購入。
・1983年〜1985年 - 愛知県による造成工事。「造成地に廃棄物と見られる大量の粘土の堆積を確認し、除去した。しかし完全には取り除けなかった可能性もある。」(愛知県庁職員OB談)。
住宅・都市整備公団が、愛知県から土地を購入。
・1988年 - 住宅・都市整備公団が、城山5丁目の住宅販売開始。
・2001年 - 城山5丁目にある2軒の住宅から、住宅・都市整備公団に対し「家が傾いてきた」との苦情。調査の結果、地盤沈下発覚。
・2005年 - 地盤沈下が発覚した住宅の周辺住民からも、都市再生機構(旧住宅・都市整備公団)に苦情相次ぐ。調査の結果、その内の数軒でも地盤沈下発覚。
・2006年2月 - 都市再生機構が、苦情のあった地域のボーリング調査開始。
・2006年3月 - マスメディアが「桃花台ニュータウンで地盤沈下が発生」と報じる。
・2006年4月16日 - 都市再生機構が地盤沈下が起こっている地域の一部住民に対し、説明会開催。ボーリング調査の結果や今後の対応などを公表。「さらに十数軒の住宅でも、地盤沈下が起こっていた事」を公表。
・2006年7月 - 都市再生機構が、最初に地盤沈下が発覚してすでに解体された、2軒の住宅跡地下の土壌調査を開始。
・2006年8月18日 - 住民が愛知県に対し、地盤沈下に関する独自調査を要請。愛知県は、「責任は都市再生機構にある」としてそれを拒否。
・2006年8月23日 - 都市再生機構が、調査地点を住民に公開。小牧市が住民の要請に従い、地盤沈下の調査開始。土壌サンプルを入手。
・2006年8月30日 - 都市再生機構が愛知県に対し、地盤沈下の対応で掛かった費用を請求する裁判を起こす。
・2006年8月31日 - 都市再生機構が、調査地点の埋め戻しを開始。都市再生機構が記者会見で、愛知県への損害賠償請求額が「現状で8億円」である事を公表。また「今後もし住民からの請求が増えたり、調査費用が増えれば、その分また損害賠償請求する」事も示唆。
・2006年9月4日 - 神田真秋愛知県知事が定例記者会見で、都市再生機構の訴訟を批判。「売り主(都市再生機構)が買い主(住民)に対し責任を取るのは、当たり前」と知事が発言。
・2006年9月15日 - 住民が愛知県知事に対し、公開質問状を提出。「県が造成の際、なぜ地盤の問題を放置したか」についての原因究明を求める。
・2006年10月6日 - 愛知県が住民に対し、公開質問状に対する回答を提示。「産業廃棄物処分場跡地という認識がなかった」、「造成工事の時には、軟弱ではなかった。また問題も起きなかった。」と、県の責任を否定。
・2006年10月19日 - 都市再生機構が起こした裁判が始まる。
・2006年10月26日 - 愛知県と小牧市が、それぞれの土壌調査の結果を公表。愛知県側の結果が「環境基準を上回る有害物質は見つからなかった」のに対し、小牧市側は「環境基準を上回る有害物質(ヒ素とジクロロメタン)と、通常見られない油分を検出した」であった。小牧市は県と都市再生機構に対し、要望書を提出。住民側は県に対し、再度調査を要請。
・2006年11月6日 - 愛知県知事が定例記者会見で、県独自による調査を明言。
・2006年11月19日 - 愛知県が城山地区住民を対象とした土壌調査結果の説明会を開催。調査結果と今後の県独自の調査予定を公表。また問題となっている地域の造成時の残土を、ニュータウン内の小中学校グランドに運んだ事も発表。これら学校も、調査範囲に。
・2006年11月20日 - 愛知県知事が定例記者会見で、土壌調査の際に得られる地盤沈下に関する情報の住民への公開を示唆。
・2006年11月26日 - 都市再生機構が住民説明会開催。土壌分析の結果公表。地盤沈下の原因を特定。産業廃棄物が埋設されている科学的証拠を公表。基準値の170倍の鉛を含む5種類の有害物質が土壌に含まれていた事を公表。今後の地盤沈下対策を公表。
・2007年4月12日 - 愛知県が土壌調査の結果を公表。環境基準を上回る鉛や総水銀、ヒ素などが見つかる。
・2007年4月29日 - 愛知県が城山地区住民を対象とした土壌調査結果の説明会を開催。
・2007年6月 - 小牧市が城山地区の一部住民に対し、固定資産税の減免措置実施を発表。
・2007年7月6日 - 住民が愛知県知事に対し、公開質問状を再度提出。
・2007年10月12日 - 住民が愛知県と都市再生機構に対し、購入した住宅に対する損害賠償を求める裁判を起こす。
・2007年11月7日〜11月9日 - 愛知県が城山地区と光ヶ丘・大城両小学校の地下水調査のため観測用の井戸から取水。
・2007年11月29日 - 城山地区と光ヶ丘・大城両小学校の1回目の地下水調査結果を愛知県が公表。有害物質はまったく検出されず。
・2008年2月6日 - 城山地区と光ヶ丘・大城両小学校の2回目の地下水調査の取水。
・2008年3月7日 - 城山地区と光ヶ丘・大城両小学校の2回目の地下水調査の結果公表。最大で環境基準の3.4倍の総水銀が城山地区で検出。
・2008年3月18日 - 第1回公害調停
・2008年4月 - 愛知県住宅供給公社がニュータウン内に整備中の土地(古雅地区)から、環境基準の7倍のヒ素などが検出。
・2008年4月18日 - 城山地区の3回目の地下水調査の取水。
・2008年5月21日 - 城山地区の3回目の地下水調査結果を愛知県が公表。最大で環境基準の3倍の総水銀検出。更に今まで総水銀が検出されなかった地点からも総水銀が検出される。
・2008年6月25日・6月26日 - 城山地区(4回目)と光ヶ丘・大城両小学校(3回目)の地下水取水。
・2008年8月11日 - 城山地区(4回目)と光ヶ丘・大城両小学校(3回目)の地下水調査結果発表。城山地区の3地点で最大で環境基準の6.6倍の総水銀が検出。
・2008年8月22日 - 第3回公害調停。調停打ち切りが決定する。
・2008年9月30日 - 城山地区(5回目)と光ヶ丘・大城両小学校(4回目)の地下水取水。
・2008年11月10日 - 別の住民が愛知県と都市再生機構に対し、購入した住宅に対する損害賠償を求める裁判を起こす。
・2008年11月11日 - 城山地区(5回目)と光ヶ丘・大城両小学校(4回目)の地下水調査結果発表。城山地区の2地点で最大で環境基準の7.6倍の総水銀が検出。

愛知県議会議員「天野まさき」さんのブログより
・2009年3月18日 - 城山地区(6回目)の地下水調査結果発表。1地点で最大で環境基準の7.8倍の総水銀が検出。
・2009年3月26日 - 都市再生機構が愛知県に対し損害賠償を求めていた裁判が決着。機構側の訴えが棄却された。[14]
■参考資料■
・愛知県庁:桃花台城山地区及び小中学校における土壌調査結果について
・中日新聞:小牧・桃花台で基準超すヒ素 分譲予定、県公社が土壌入れ替え:愛知
・団地地盤沈下:都市再生機構の請求棄却 名地裁判決 - 毎日jp(毎日新聞)
・読売新聞 (2007-11-04). "地盤沈下 桃花台住民が提訴". 2008-02-01 閲覧。
・中日新聞:桃花台訴訟、新たに住民12人提訴 愛知県と機構に損賠請求
・桃花台地盤沈下 調停を打ち切り(読売新聞)
・桃花台城山地区及び小学校における地下水調査結果について 平成19年11月29日(木曜日)発表
・桃花台城山地区及び小学校における地下水調査結果について 平成20年3月7日(金曜日)発表
・桃花台城山地区における地下水調査結果について 平成20年5月21日(水曜日)発表
・桃花台城山地区及び小学校における地下水調査結果について | 愛知県
・桃花台城山地区及び小学校における地下水調査結果について | 愛知県
・桃花台城山地区における地下水調査結果について | 愛知県
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%83%E8%8A%B1%E5%8F%B0%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3
******************************
桃花台ニュータウンの軟弱地層及び産業廃棄物による沈下問題に関する愛知県知事への公開質問状
掲載日2006年9月17日
平成18年9月15日
愛知県知事
神田真秋殿
小牧市城山●●●●●●●
城山第五区長 木下 博
小牧市城山●●●●●●●
考える会代表 丸山 直希
公 開 質 問 状
8月18日に知事殿に、何点かの要望・疑問点を提起しご回答をいただけるよう要望書を提出しました。ご回答を頂く前に貴下のもとで職務担当者が要望事項に反するような発言をしておりましたので、8月21日知事殿には真実を知っていただくため上申書及び現地に残存しておる産業廃棄物をお届けし、適切な行政判断指導をお願いし回答していただけるよう「考える会」として要望しておりましたところ、8月22日環境課職員、8月23日計画課職員、8月24日環境課(計画課?)職員が現地を訪れるといった慌ただしい動きがみえ、問題早期解決に心を痛め悩み抜いていた我々住民はなにがしかの進展があるものと信じて疑いませんでした。
ところが回答を頂く前に、都市再生機構より提訴をされたと聞き、非常に残念に思っております。提訴当日8月30日早朝、時間外にも拘らず(早朝8:00)計画課職員数名と都市再生機構社員数名が現地にて打ち合わせを行っていた事により、問題解決に向けての進展がより早くなるものと思った矢先の提訴でした。これにより、我々住民の愛知県及び都市再生機構への不信感・疑いはより強くなったものです。
都市再生機構の記者会見発表では「機構の請求権を保存する必要から提訴した」とありました。この請求権保存の言葉から推察すると平成17年に2宅地の買取りに対する賠償請求権保存それに調査費用がプラスされた金額とも受け取れ、我々住民無視の提訴といった内容かと思われます。都市再生機構は我々住民との間で対策・賠償について何らの合意もされていないことにより上記事項を伺い知ることが出来ます。
以上のようなことから、早急に下記質問事項にお答え願います。
(新住宅市街地開発法に関連した質問事項)
(1)桃花台ニュータウンは「健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする」と規定された国の「新住宅市街地開発法」にもとづきつくられた住宅であり、県としても住民の被害と不安にたいし、誠実に対応することが必要不可欠です。今回の問題についての対応を是非お答え下さい。
(2)「新住宅市街地開発法」第24条 処分計画においては、造成宅地等の処分価額は、……当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。 とされております。 油分が含まれた状態の廃棄物の品位をどのように捉え造成され、処分されたのでしょうか。
(3)「新住宅市街地開発法」第40条 ……国土交通大臣に対して、新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。とされております。愛知県においては技術的援助を求められたのでしょうか。
(4)「都市計画法」第9条に 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。とあります。油分が含まれた状態の土地が、良好な住居の環境と言えるのでしょうか。
(5)「都市計画法」第12条の5
地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。とされています。
産業廃棄物処分場跡地を地区整備計画に含めたことは、どんな見解をもってされたのでしょうか。
(6)「都市計画法」第33条の7
開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがおおい土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められている。今回の沈下場所は、軟弱な土地であり、また産業廃棄物が含まれていました。設計に定められた必要な措置はどのように講じられたのでしょうか。
(土壌汚染対策法に関連した質問事項)
(1)「土壌汚染対策法」第1条、第2条
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
今回、UR都市機構開示の「土壌調査結果報告書」に鉛、砒素、トリクロロエチレンその他有害物質が検出されております。鉛は基準値をオーバーしており、その他有害物質は基準値以下とされておりますが、自然界に存在しない成分が多数検出されております。自然界に存在しない物質、即ち産業活動により排出された物質、これが産業廃棄物ではないのでしょうか。
「土壌汚染」 「産業廃棄物」でない根拠、見解をお答え下さい。また愛知県環境部では「土壌調査結果報告書」をチェックできる職員は不在なのでしょうか。
(2)「土壌汚染対策法」第4条の2
都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報
告を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査をしないときは、当該調査を自らおこなう旨を、あらかじめ、広告しなければならない。
現在、UR都市機構のUR都市機構の調査方法・説明は信頼できるものではありません。このことは「土壌汚染対策法」第4条の2による、これを放置することが著しく公益に反すると認められるに該当するのではないでしょうか。
(3)「土壌汚染対策法」第7条
都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染により、…………当該土地の所有者以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者に汚染の除去等の措置を講じさせることができる。
今回の城山地区の汚染は、当該土地の所有者以外の者の行為によって汚染が生じたことは明らかであります。当然、汚染の除去等の措置を講じることが法に沿った解決方法ではないでしょうか。
(4)「土壌汚染対策法」第8条の2
当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求する請求権は、当該汚染の除去等の措置を講じ、かつ、その行為をした者を知ったときから三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該汚染の除去等の措置を講じたときから二十年を経過したときも、同様とする。
この法律を盾にし、実際には除去していない(除去していない事は明白です)にもかかわらず、愛知県は責任回避のため当時除去したと説明をしたうえで、時効(二十年)を迎えようとしたのでしょうか。
(5)「土壌汚染対策法」第9条
土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施工方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
テストピット調査掘削土を、産業廃棄物処理場(浄化施設)に運搬し、埋め戻し土を客土にてするようにしております。これは形質の変更ではないのでしょうか。届け出された環境省令で定める事項を示してください。
このことは愛知県の指導によるものと聞いております。この状態では、客土が更に汚染され、汚染土壌の増加だけの結果となってしまいます。どの様な見解を持って、指導されたのでしょうか。「汚染土壌」 「産業廃棄物」なのでしょうか。
(6)「土壌汚染対策法」第29条
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、…………職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。愛知県においては、この法律は無縁のものなのでしょうか。
(7)「土壌汚染対策法施行規則」環境省告示第20号
第二溶出基準に適合しない汚染状態にある土壌は、「産業廃棄物遮断型処分場」に 搬入すること。第二溶出基準に適合する汚染状態にある土壌は、「産業廃棄物管理型処分場」に搬出すること。とされております。当初UR都市機構は、汚染土壌の浄化施設に搬出する予定でおりました。搬出する汚染土壌が第二溶出基準に適合する土壌であったのか、適合しない土壌であったのか、愛知県の判断の基となった資料及び説明を求めます。
(8)「土壌汚染対策法施行規則」環境省告示第21号
搬出する汚染土壌の処分に係る確認方法について、「搬出汚染土壌管理票」を作成、搬出汚染土壌確認報告書の提出が義務づけられております。報告書の提出が済み次第、報告書の開示を求めます。
(9)「土壌汚染対策法施行規則」の概要
揮発性有機化合物は、土壌ガス調査及び土壌溶出量調査とする。開示されたUR都市機構実施調査では、土壌ガス調査が行われていません。サンプリング地点の数は、100?に1点とし、土壌汚染の可能性が低い場所は900?に1点とする。
UR都市機構実施調査では、土壌汚染の可能性が高い場所において約400?に1点、可能性の低い場所においては全く調査をしておりません。
愛知県の見解では、「土壌汚染対策法施行規則」を無視した調査方法が妥当なも
のであると認識されておるのでしょうか。
(油汚染対策ガイドラインに関連した質問事項)
(1)ガイドラインで油臭や油膜の報告例は鉱油類によるものがほとんどであるとされているが、UR都市機構の説明は、自然界に存在しない成分、鉱油、香油と2転3転している。
現物を見られた知事及び担当部署職員の見解では、どちらなのでしょうか。
(2)UR都市機構が設定した、影響範囲外の宅地において油臭があり、雨後に洗濯物を干すと臭いが付着するため、室内に洗濯物を干す家があります。UR都市機構に調査依頼をしても、これ以上の調査は行いませんとの返答だったため、住民で掘削調査を行った結果、油膜が生じました。その結果をUR都市機構に説明、再度調査依頼をするも同じ返答でした。
庭で子供が遊び、地表の土に触れます。UR都市機構の判断は正しいものと、愛知県も思っておられるのでしょうか。
(3)対策として、戸建て住宅や公園など、土地を裸地のまま利用することが普通である土地利用については、油臭や油膜の原因となる油含有土壌の掘削除去や浄化が必要となる。あるいは裸地ではない土地利用方法への変更も考えられる。
愛知県としては、どう考えられているのでしょうか。
(4)地下水の汚染を確認するため、周辺地下水・井戸水のモニタリング、観測井戸等の措置が全くなされておりません。
愛知県としても、必要ないと考えられるのでしょうか。
(その他質問事項)
(1)知事及び愛知県担当部署職員の方々は、残存している産業廃棄物を見られたにもかかわらず、都市再生機構より提訴されたこの時点に至っても、まだ「黒っぽい粘土」と捉えておられるのでしょうか。明確かつ簡潔にお答え願います。
(2)県職員は「産業廃棄物ではなく粘土」・「機構とは情報交換するつもりだが、同じ調査を繰り返しても意味がない」と発言されておりました。情報交換をするつもりだったはずが、提訴された今後どう対応されるのかお聞かせ願いたい。
(3)都市再生機構が調査費用の請求をしましたが、環境調査においては愛知県が土壌汚染対策法に基づいて指導する立場にあり、都市再生機構より適正な調査方法・判断を下すことが出来るものと我々住民は思っております。
愛知県においては、今でも都市再生機構の調査方法が適正なものであると信じ、今後も都市再生機構に調査を委ねたままとするのでしょうか。
(4)ある新聞紙面に県側のコメントとして「提訴は想定の範囲内。訴状を見て対応を検討したい」とありました。想定の範囲内とはどう云うことですか。
この言葉は前回コメント「周辺住民が燃料として使っていた。」 「造成時には無くなっていた」「黒っぽい粘土があっただけ」と大きく矛盾した言葉となっています。産業廃棄物は存在しない姿勢を取りながら提訴を想定していたとの発言。どこに整合性があるのでしょうか。
(5)周辺住民が燃料として使っていた物とは何であるのか、当然燃料として使われていた物ですから目視でどのような廃棄物だったのか容易に想像できたと思います。当時存在していた状態、固形物か・液体物か・固形物に液体が含まれた物か詳細かつ明確に何であったのかお答えいただきたい。そのうえで、その物が産業廃棄物でなかった理由も併せて明確にお答えいただきたい。
(6)当時周辺には住宅が存在しませんでした。愛知県担当部署の方が判断される周辺地域とはどこまでの範囲なのか、また周辺地域の方とは何方を示されておるのか、明快かつ端的にお知らせ下さい。
(7)産業廃棄物処理は許可事業です。許可は当然ご存じのように県が許可を与えるものです。その愛知県が許可の範囲・許可事業内容を一番良くご存じのはずです。なぜ範囲特定の作業に着手していただけないのか理由をお聞かせ下さい。
(8)日本国内において管理産業廃棄物処分場跡地(造成時に稼働していたらしいことから跡地とは呼べない?)に土地情報の告知もせず、分譲住宅を売り出した自治体が愛知県以外にあったのかどうか、また知らせる必要がなかったとされる根拠について教えていただきたい。
(9)産業廃棄物処分場を復旧することは廃棄物事業者に責任があります。跡地を造成名目で愛知県が処理されたとするならば、どの様な見解に基づいて処理されたのでしょうか。また売買契約は処理費用を含んだ金額で適正に行われたのでしょうか。
(10)UR都市機構の提訴金額は8億円とのことでした。2宅地補償金(対策費用と説明)と調査費用のみで8億円の賠償請求が生じるのでしょうか。今後の調査如何で最終金額は不明とのことでした。裁判費用・損害賠償費用他全て県民の税金です。県民の納得出来る状態で損害賠償請求に応じるべきではないでしょうか。
(11)UR都市機構の検討委員会には、環境の専門家、不動産評価の専門家がおりません。地質及び建築の専門家のみで構成されております。愛知県としては、指導していただけたのでしょうか。愛知県の見解をお答え
下さい。
(12)知事は9月4日、定例記者会見で、「一義的には分譲した売主(都市再生機構)が買い主の住人にきちんと対応するのが当たり前」と発言されております。きちんと対応していない都市再生機構に、どのような指導をおこなっているのでしょうか。また分譲した都市再生機構に、土地を造成、売却したのは愛知県です。この重大責任事項に言及しないことは非常に不自然なことに思えますが、愛知県は土地を造成、売却した責任をどう考えておられるのでしょうか。
(13)知事は9月4日、定例記者会見で、8月下旬に土壌のサンプルを採取し、調査していることを挙げ「土壌が産廃なのではという住民の声もあり、不安が解消されるようにしたい」と発言されておりました。サンプルを採取したのは8月22日でしたが、8月25日県職員が現地に来た際「再調査はしない」と言っておりました。未だに知事と担当部署職員との間で、意志疎通がはかられていないのでしょうか。
(14)上記発言は、一番問題となっている「何故産廃があるのか」、「地歴調査をして範囲の特定をするのか」、「調査方法は公正で正しいのか」といった問題から、記者の注目を遠ざける目的で発せられた言葉なのでしょうか。現物を見られた知事及び造成当時の職員ならなら、その物が何であるか十分わかっておられるはずです。
以上 新住宅市街地開発法に関連した質問事項6項目
土壌汚染対策法に関連した質問事項9項目
油汚染対策ガイドラインに関連した質問事項4項目
その他質問事項14項目
※ 上記33項目及び要望書・上申書事項について書面回答して下さい。
※ 回答期日: 9月22日
http://eritokyo.jp/independent/komaki-col0001.html
******************************
愛知県庁:知事の記者会見:2006年11月20日 桃花台ニュータウンの地盤沈下問題について
桃花台ニュータウンの地盤沈下問題について
【記者】
小牧市の桃花台ニュータウンの地盤沈下の件ですけれども、昨日、県の説明会がありまして、調査の方法を説明しておりました。その中で、土壌汚染だけではなく、地耐力をボーリングをする中でもデータはとれるだろうと言っていたのですが、そのデータを住民に公表するといった姿勢が見られませんでした。要するに、裁判の材料のために、そのデータを使うのだというようにしか聞こえないものの言い方でした。
知事は、先だって環境汚染に関しては、住民の安心、安全、不安を取り除くためにやるのだとおっしゃいました。県の説明会の住民への回答の中では、そこのところの言及が全然ないのです。裁判を気にして、そういうことに取り組まないというものの言い方をする行政とはいかがなものか、お考えがありましたらお願いします。
【知事】
職員がどういう言い方をしたのか、詳細までは私はわかりませんけれども、誤解の無いようにしていただきたいのは、裁判の材料にするためなどとは、毛頭考えておりません。
今回の地盤沈下は地盤のいわゆる耐力の問題ですね。それから、土壌の中に黒っぽい粘土質のものがあって、その成分が環境基準を一部オーバーするものがあったということです。これは環境汚染の問題で、厳密に言えば、ちょっと別の問題になろうかと思います。地盤沈下との問題も全く無関係ではありませんけれども、今回、たまたま都市再生機構側が調査したときのサンプルを、県と小牧市も取得し、小牧市の調査分析の中で若干そういうものが出てきたので、その状況を地元の皆様方にご説明するだけではなく、当然、不安をお持ちでありますので、これからあの地域の各住宅ごとに調査をしたいということで、その依頼も含めて説明会をしたものでございます。
したがって、あくまでも土壌汚染、環境汚染を主眼に置いており、耐力を測るための目的のものではないということが一つございます。
しかし、そういうことも、いろいろな材料がこれから結果として出てくるのかもわかりませんが、それは私どもなりに、また分析をしなければならないと思っておりますけれども、裁判は向こうから起こされてきた問題ですし、地盤沈下の問題は売り主としての責任は当然機構側にあるわけでありますので、その耐力の問題も含め、機構側がどのようなデータで、これからどのような調査を進めていかれるのか、これは県としても見極めていかなければならない問題であります。
くどくなって恐縮ですが、裁判のためにというようなことは、目的としては持っていません。裁判の中でも、もちろん県の正当性などを主張しながら進めていくわけで、そこへ活用することは当然あると思います。それは、もう少しいろいろなものが出てきて分析したり、調査してみないとわからないと思っております。
【記者】
住民の不安を取り除くためには、住民にそのデータの公表は考えられないのですか。
【知事】
どんなものが出てくるのか、まだちょっとわかりませんけれども、先ほど申し上げたとおり、住民の不安を解消するということも、もちろん重要なことだと思っておりますので、必要なものについて開示することは、やぶさかではございません。
ただ、ご承知のとおり、現に裁判を起こされておりまして、裁判というのは、主張、立証責任というのは、お互いに分配し合いながら、やっていることでありますので、本来、そのことは機構がきちんとやることでもありますので、今ここで、その材料をどうするかということは、断言的に申し上げことはできないと思っております。努力はいたします。
http://www.pref.aichi.jp/koho/kaiken/2006/11.20.html#7
ウィキメディアより
桃花台の地盤沈下と土壌汚染
■地盤沈下■
愛知県が造成し都市再生機構(旧 住宅・都市整備公団)が販売した、ニュータウン南部の城山5丁目地区にある住宅で地盤沈下が発覚し、問題となっている。
問題の発覚は2001年、同地区の2軒の住宅に住む住人から、都市再生機構に対し「家が傾いてきた」との苦情が届いた事に始まる。その後都市再生機構が調査したところ、2軒の住宅とも家が沈下している事が判明。2軒の住宅は都市再生機構が買取り、後に解体された。
2軒の住宅から突然家主が引っ越した事を不審に思った近所の住民が、都市再生機構に問い合わせたところ、地盤沈下の事実を知る。2005年にはこの2軒の住宅周辺の住民からも、都市再生機構に対し「家が傾いてきた」などの苦情が相次いで届くようになる。
その結果都市再生機構がそれらの住宅を調査したところ、数軒で地盤沈下が判明する。2006年2月都市再生機構は、問題となっている地域のボーリング調査を開始する。
すると、さらに十数軒の住宅が沈下している事が判明。この事は、マスメディアによって大きく報じられる事となる。

有害物質の埋設が確認された場所(桃花台ニュータウン)
問題となっている土地は、
1957年に王春工業の会長が購入し、王子製紙春日井工場などから出る産業廃棄物を10年以上にわたって廃棄していた事がわかっている(当時は廃棄物処理に関する法律がなかったため、この件で王春工業の責任を問うことはできない)。
1971年7月、愛知県が小牧市の仲介でこの土地を購入し、造成工事を行っている。この造成工事の際、産業廃棄物と見られる粘土が大量に堆積していた事を、当時の愛知県庁職員が確認している。そのため「これらを撤去した」としているが、「全て撤去できなかった可能性もある」とも証言している。
その後愛知県は、この土地を旧住宅・都市整備公団に売却。
住宅・都市整備公団は住宅を建築し、1988年に販売している。
2006年7月都市再生機構は、地盤沈下の原因を探るべく、解体した2軒の住宅跡地の地下の土壌の調査分析を開始。同年11月に結果を公表している。それによると、「問題となっている土地は産業廃棄物が層となって残っており、その上にさらに土が盛られている状態であった。
この産業廃棄物層の上にある土の層が造成の際十分踏み固められておらず、雨水が浸透。その結果その層が沈下し、さらにその重みに絶えられず、産業廃棄物層が沈下した。」と言うものであった。
■土壌汚染■
土壌汚染が発覚した城山地区の土地は1957年に王春工業の会長が購入し、王子製紙春日井工場などから出る産業廃棄物を10年以上にわたって廃棄していた事がわかっている。
2006年11月に公表された都市再生機構の調査結果では、産業廃棄物が現存している事が確認されている。 また同調査では、環境基準値の170倍の鉛を含む5種類の有害物質や、油分、木片、ガラス片、ビニール袋なども確認されている。
同年8月住民からの要請を受けた小牧市は、市独自の調査を開始する。都市再生機構の調査地点から土壌サンプルを回収し、同年10月に分析結果を公表している。それによると、「土壌には環境基準を上回る有害物質(ヒ素:3.6倍、ジクロロメタン:約1.9倍)が含まれており、通常の土壌ではほとんど検出されない油分も検出された」となっている。この調査結果を受けて小牧市は、愛知県と都市再生機構に対し、適切な対応を求める要望書を提出している。
同年8月住民は愛知県に対し、県独自の調査を要請している。それに対し愛知県は、「都市再生機構側に責任がある」として、要請を断っている。
しかしその一方で、愛知県庁の職員が都市再生機構の調査地点から土壌サンプルを回収。同年10月に小牧市とともに分析結果を公表している 。それによると、小牧市の調査では環境基準を上回る有害物質が見つかっているの対し、愛知県の調査結果は「環境基準を上回る有害物質は見つからなかった」と言うものであった。
■問題地域の拡大■
新たな問題として同年11月に開かれた住民説明会で、愛知県は、問題となっている地域の土壌がニュータウン内の3つの学校(大城小学校、光ヶ丘小学校、光ヶ丘中学校)のグラウンドに持ち込まれて埋められた事を公表した。そして調査対象地区を学校グラウンドにも拡大し、改めて調査を行った。
その結果、光ヶ丘小学校と大城小学校の敷地内で、環境基準の1.1〜2.2倍の鉛が見つかった。一方住宅地からは、1.3〜6.9倍の鉛と1.2倍の総水銀、そして1.5倍のヒ素が見つかった。さらに黒い土が見つかった全ての地点からは、油分が検出された。
この調査結果に対し愛知県は、環境基準を超えた物質が見つかった場所は全て1.2〜2.5mの土で覆われており、地下水の飲用利用もないため、「人体への影響は無い」としている。また「(環境基準を超えた物質が)検出された原因は判らない」としたうえで、県の責任を否定している。
また2008年4月には、古雅地区に整備される予定の住宅地「エコーガーデン桃花台」の土地の一部の地下からも、環境基準を上回る有害物質(基準約7倍のヒ素、基準をやや上回るフッ素)が見つかっている。これは他地区で土壌汚染が相次いで発覚した事を受けて、整備を行っている愛知県住宅供給公社が2007年10月から行った土壌調査で明らかとなった。
問題が発覚した土地は、1970年代に愛知県が購入。1989年頃まで暫定調整池として利用されていた。1999年3月に、愛知県が県住宅供給公社に売却。その後駐車場などとして利用されていたが、2007年4月から住宅地の整備工事が始められていた。
なお、なぜ有害物質が見つかったかについては、不明としている。
■裁判■
■都市再生機構による損害賠償請求
この問題の責任を巡って、2006年8月都市再生機構は「地盤沈下の原因は愛知県の責任である」として、住民への補償費用やこれまでかかった調査費用などを求める裁判を名古屋地方裁判所に起こした。都市再生機構側は「(愛知県から)大量の廃棄物が持ち込まれた場所だったとは聞いていない。廃棄物があれば購入していない。」と主張。
それに対し愛知県側は「土地売買の際、資料のやりとりはあったはず。旧住宅・都市整備公団には、住宅の売り手として、地盤をよく調べる義務がある。基礎を頑丈にした近隣の住宅では、問題は起きていない。」と主張した。
判決が出たのは2009年3月26日。「地盤調査する責任は都市再生機構にあった」として、都市再生機構側の訴えは棄却された。
■住民による損害賠償請求
2007年10月、問題が起こっている城山地区に住む5人の住民が、住宅の購入費用の返還を求めた裁判を名古屋地方裁判所に起こした。訴えられた側は愛知県と都市再生機構。賠償請求額は総額約9,300万円。
その後2008年11月にも、同地区に住む別の住民12人が、同じく愛知県と都市再生機構を相手取って有害物質の除去や損害賠償を求める裁判を起こしている。賠償請求額は総額約1億2千万円。[16]
■公害調停
住民は県の公害審議会に対し、2008年3月に公害紛争処理法に基づく公害調停を申請。住民側は委員に対し、原因究明や第三者機関による土壌調査を要請した。
これに対し愛知県側は、調停の打ち切りを要請。都市再生機構も自らの責任を否定したうえで、調停には応じない構えを見せた。
その後3回の調停が行われたが、結局3者相容れず。同年8月の3回目の調停で、打ち切りが決定した。
■今後の対策や調査■
■都市再生機構
都市再生機構は、地盤沈下の対策については「これ以上両層とも沈下する可能性は低い」として、一軒ごとに住宅を調べたうえで場合によってはジャッキアップ工法で修復工事を行うとしている。
それに対して住民は、「それでは不十分だ」として産業廃棄物の完全撤去を求める意見を出している。しかし、都市再生機構は産業廃棄物に関して「愛知県の調査結果を待ってから検討する」としている。
■愛知県
愛知県は土壌汚染の範囲を測定するため、「2006年中に調査を開始し、翌2007年3月には結論をまとめる」としている。調査の詳細は、「すでに解体された2軒の住宅を中心に同心円状に1軒1軒ボーリング調査をしていく」と言うものである。また新たな問題として浮上したニュータウン内の3つの学校のグラウンドへの問題となっている土壌の埋設に対応する為に、「これらの学校のグラウンドも調査する」としている。
なお愛知県は、現在も産業廃棄物の存在を認めていない。問題となっている土壌については、「粘土質の土壌」、「黒っぽい土」などとしており、あくまで自然の土であると言う立場である。これに対し住民は、「土壌からは木片やガラス、油分などが見つかっており、明らかに産業廃棄物だ」と愛知県の認識を非難している。
一方地盤沈下に関する対応について愛知県は、2006年11月に行われた住民説明会で、都市再生機構との裁判を理由に曖昧な対応をした。
そのため住民からは、「住民より裁判を重視するのか」と非難が相次いだ。結果、その翌日に行われた県知事の定例記者会見でもこの問題が取り上げられた。その際神田真秋愛知県知事は、あくまで「地盤沈下の責任は、都市再生機構にある」としながらも、土壌調査の際に得られる地盤沈下に関する情報(地耐力データ)の住民への公開を示唆した。
■その他の機関■
■小牧市
小牧市は2007年6月の議会で、問題が起こっている城山地区の一部住民に対し、過去数年間の固定資産税減免措置実施を表明している。
愛知県住宅供給公社
愛知県住宅供給公社は、古雅地区のエコーガーデン桃花台内で見つかった有害物質が含まれる全ての土壌を撤去し、新しい土と入れ替えるとしている。
■亜炭鉱
ニュータウンを含めた一帯では、江戸時代から第二次大戦後しばらくにかけて、石炭の一種である「亜炭」と呼ばれる鉱物が掘り出されていた。そのため、一部報道機関では「地盤沈下の原因は、亜炭鉱が崩れたからではないか」と報じられた。
■年 表■
・1957年 - 王春工業が、一帯の土地(当時は山林)を購入。愛知県へと土地を売却するまでの間、王子製紙春日井工場などから出る産業廃棄物を投棄。
・1971年7月 - 小牧市の仲介で、愛知県が土地を購入。
・1983年〜1985年 - 愛知県による造成工事。「造成地に廃棄物と見られる大量の粘土の堆積を確認し、除去した。しかし完全には取り除けなかった可能性もある。」(愛知県庁職員OB談)。
住宅・都市整備公団が、愛知県から土地を購入。
・1988年 - 住宅・都市整備公団が、城山5丁目の住宅販売開始。
・2001年 - 城山5丁目にある2軒の住宅から、住宅・都市整備公団に対し「家が傾いてきた」との苦情。調査の結果、地盤沈下発覚。
・2005年 - 地盤沈下が発覚した住宅の周辺住民からも、都市再生機構(旧住宅・都市整備公団)に苦情相次ぐ。調査の結果、その内の数軒でも地盤沈下発覚。
・2006年2月 - 都市再生機構が、苦情のあった地域のボーリング調査開始。
・2006年3月 - マスメディアが「桃花台ニュータウンで地盤沈下が発生」と報じる。
・2006年4月16日 - 都市再生機構が地盤沈下が起こっている地域の一部住民に対し、説明会開催。ボーリング調査の結果や今後の対応などを公表。「さらに十数軒の住宅でも、地盤沈下が起こっていた事」を公表。
・2006年7月 - 都市再生機構が、最初に地盤沈下が発覚してすでに解体された、2軒の住宅跡地下の土壌調査を開始。
・2006年8月18日 - 住民が愛知県に対し、地盤沈下に関する独自調査を要請。愛知県は、「責任は都市再生機構にある」としてそれを拒否。
・2006年8月23日 - 都市再生機構が、調査地点を住民に公開。小牧市が住民の要請に従い、地盤沈下の調査開始。土壌サンプルを入手。
・2006年8月30日 - 都市再生機構が愛知県に対し、地盤沈下の対応で掛かった費用を請求する裁判を起こす。
・2006年8月31日 - 都市再生機構が、調査地点の埋め戻しを開始。都市再生機構が記者会見で、愛知県への損害賠償請求額が「現状で8億円」である事を公表。また「今後もし住民からの請求が増えたり、調査費用が増えれば、その分また損害賠償請求する」事も示唆。
・2006年9月4日 - 神田真秋愛知県知事が定例記者会見で、都市再生機構の訴訟を批判。「売り主(都市再生機構)が買い主(住民)に対し責任を取るのは、当たり前」と知事が発言。
・2006年9月15日 - 住民が愛知県知事に対し、公開質問状を提出。「県が造成の際、なぜ地盤の問題を放置したか」についての原因究明を求める。
・2006年10月6日 - 愛知県が住民に対し、公開質問状に対する回答を提示。「産業廃棄物処分場跡地という認識がなかった」、「造成工事の時には、軟弱ではなかった。また問題も起きなかった。」と、県の責任を否定。
・2006年10月19日 - 都市再生機構が起こした裁判が始まる。
・2006年10月26日 - 愛知県と小牧市が、それぞれの土壌調査の結果を公表。愛知県側の結果が「環境基準を上回る有害物質は見つからなかった」のに対し、小牧市側は「環境基準を上回る有害物質(ヒ素とジクロロメタン)と、通常見られない油分を検出した」であった。小牧市は県と都市再生機構に対し、要望書を提出。住民側は県に対し、再度調査を要請。
・2006年11月6日 - 愛知県知事が定例記者会見で、県独自による調査を明言。
・2006年11月19日 - 愛知県が城山地区住民を対象とした土壌調査結果の説明会を開催。調査結果と今後の県独自の調査予定を公表。また問題となっている地域の造成時の残土を、ニュータウン内の小中学校グランドに運んだ事も発表。これら学校も、調査範囲に。
・2006年11月20日 - 愛知県知事が定例記者会見で、土壌調査の際に得られる地盤沈下に関する情報の住民への公開を示唆。
・2006年11月26日 - 都市再生機構が住民説明会開催。土壌分析の結果公表。地盤沈下の原因を特定。産業廃棄物が埋設されている科学的証拠を公表。基準値の170倍の鉛を含む5種類の有害物質が土壌に含まれていた事を公表。今後の地盤沈下対策を公表。
・2007年4月12日 - 愛知県が土壌調査の結果を公表。環境基準を上回る鉛や総水銀、ヒ素などが見つかる。
・2007年4月29日 - 愛知県が城山地区住民を対象とした土壌調査結果の説明会を開催。
・2007年6月 - 小牧市が城山地区の一部住民に対し、固定資産税の減免措置実施を発表。
・2007年7月6日 - 住民が愛知県知事に対し、公開質問状を再度提出。
・2007年10月12日 - 住民が愛知県と都市再生機構に対し、購入した住宅に対する損害賠償を求める裁判を起こす。
・2007年11月7日〜11月9日 - 愛知県が城山地区と光ヶ丘・大城両小学校の地下水調査のため観測用の井戸から取水。
・2007年11月29日 - 城山地区と光ヶ丘・大城両小学校の1回目の地下水調査結果を愛知県が公表。有害物質はまったく検出されず。
・2008年2月6日 - 城山地区と光ヶ丘・大城両小学校の2回目の地下水調査の取水。
・2008年3月7日 - 城山地区と光ヶ丘・大城両小学校の2回目の地下水調査の結果公表。最大で環境基準の3.4倍の総水銀が城山地区で検出。
・2008年3月18日 - 第1回公害調停
・2008年4月 - 愛知県住宅供給公社がニュータウン内に整備中の土地(古雅地区)から、環境基準の7倍のヒ素などが検出。
・2008年4月18日 - 城山地区の3回目の地下水調査の取水。
・2008年5月21日 - 城山地区の3回目の地下水調査結果を愛知県が公表。最大で環境基準の3倍の総水銀検出。更に今まで総水銀が検出されなかった地点からも総水銀が検出される。
・2008年6月25日・6月26日 - 城山地区(4回目)と光ヶ丘・大城両小学校(3回目)の地下水取水。
・2008年8月11日 - 城山地区(4回目)と光ヶ丘・大城両小学校(3回目)の地下水調査結果発表。城山地区の3地点で最大で環境基準の6.6倍の総水銀が検出。
・2008年8月22日 - 第3回公害調停。調停打ち切りが決定する。
・2008年9月30日 - 城山地区(5回目)と光ヶ丘・大城両小学校(4回目)の地下水取水。
・2008年11月10日 - 別の住民が愛知県と都市再生機構に対し、購入した住宅に対する損害賠償を求める裁判を起こす。
・2008年11月11日 - 城山地区(5回目)と光ヶ丘・大城両小学校(4回目)の地下水調査結果発表。城山地区の2地点で最大で環境基準の7.6倍の総水銀が検出。

愛知県議会議員「天野まさき」さんのブログより
・2009年3月18日 - 城山地区(6回目)の地下水調査結果発表。1地点で最大で環境基準の7.8倍の総水銀が検出。
・2009年3月26日 - 都市再生機構が愛知県に対し損害賠償を求めていた裁判が決着。機構側の訴えが棄却された。[14]
■参考資料■
・愛知県庁:桃花台城山地区及び小中学校における土壌調査結果について
・中日新聞:小牧・桃花台で基準超すヒ素 分譲予定、県公社が土壌入れ替え:愛知
・団地地盤沈下:都市再生機構の請求棄却 名地裁判決 - 毎日jp(毎日新聞)
・読売新聞 (2007-11-04). "地盤沈下 桃花台住民が提訴". 2008-02-01 閲覧。
・中日新聞:桃花台訴訟、新たに住民12人提訴 愛知県と機構に損賠請求
・桃花台地盤沈下 調停を打ち切り(読売新聞)
・桃花台城山地区及び小学校における地下水調査結果について 平成19年11月29日(木曜日)発表
・桃花台城山地区及び小学校における地下水調査結果について 平成20年3月7日(金曜日)発表
・桃花台城山地区における地下水調査結果について 平成20年5月21日(水曜日)発表
・桃花台城山地区及び小学校における地下水調査結果について | 愛知県
・桃花台城山地区及び小学校における地下水調査結果について | 愛知県
・桃花台城山地区における地下水調査結果について | 愛知県
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%83%E8%8A%B1%E5%8F%B0%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3
******************************
桃花台ニュータウンの軟弱地層及び産業廃棄物による沈下問題に関する愛知県知事への公開質問状
掲載日2006年9月17日
平成18年9月15日
愛知県知事
神田真秋殿
小牧市城山●●●●●●●
城山第五区長 木下 博
小牧市城山●●●●●●●
考える会代表 丸山 直希
公 開 質 問 状
8月18日に知事殿に、何点かの要望・疑問点を提起しご回答をいただけるよう要望書を提出しました。ご回答を頂く前に貴下のもとで職務担当者が要望事項に反するような発言をしておりましたので、8月21日知事殿には真実を知っていただくため上申書及び現地に残存しておる産業廃棄物をお届けし、適切な行政判断指導をお願いし回答していただけるよう「考える会」として要望しておりましたところ、8月22日環境課職員、8月23日計画課職員、8月24日環境課(計画課?)職員が現地を訪れるといった慌ただしい動きがみえ、問題早期解決に心を痛め悩み抜いていた我々住民はなにがしかの進展があるものと信じて疑いませんでした。
ところが回答を頂く前に、都市再生機構より提訴をされたと聞き、非常に残念に思っております。提訴当日8月30日早朝、時間外にも拘らず(早朝8:00)計画課職員数名と都市再生機構社員数名が現地にて打ち合わせを行っていた事により、問題解決に向けての進展がより早くなるものと思った矢先の提訴でした。これにより、我々住民の愛知県及び都市再生機構への不信感・疑いはより強くなったものです。
都市再生機構の記者会見発表では「機構の請求権を保存する必要から提訴した」とありました。この請求権保存の言葉から推察すると平成17年に2宅地の買取りに対する賠償請求権保存それに調査費用がプラスされた金額とも受け取れ、我々住民無視の提訴といった内容かと思われます。都市再生機構は我々住民との間で対策・賠償について何らの合意もされていないことにより上記事項を伺い知ることが出来ます。
以上のようなことから、早急に下記質問事項にお答え願います。
(新住宅市街地開発法に関連した質問事項)
(1)桃花台ニュータウンは「健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする」と規定された国の「新住宅市街地開発法」にもとづきつくられた住宅であり、県としても住民の被害と不安にたいし、誠実に対応することが必要不可欠です。今回の問題についての対応を是非お答え下さい。
(2)「新住宅市街地開発法」第24条 処分計画においては、造成宅地等の処分価額は、……当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。 とされております。 油分が含まれた状態の廃棄物の品位をどのように捉え造成され、処分されたのでしょうか。
(3)「新住宅市街地開発法」第40条 ……国土交通大臣に対して、新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。とされております。愛知県においては技術的援助を求められたのでしょうか。
(4)「都市計画法」第9条に 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。とあります。油分が含まれた状態の土地が、良好な住居の環境と言えるのでしょうか。
(5)「都市計画法」第12条の5
地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。とされています。
産業廃棄物処分場跡地を地区整備計画に含めたことは、どんな見解をもってされたのでしょうか。
(6)「都市計画法」第33条の7
開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがおおい土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められている。今回の沈下場所は、軟弱な土地であり、また産業廃棄物が含まれていました。設計に定められた必要な措置はどのように講じられたのでしょうか。
(土壌汚染対策法に関連した質問事項)
(1)「土壌汚染対策法」第1条、第2条
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
今回、UR都市機構開示の「土壌調査結果報告書」に鉛、砒素、トリクロロエチレンその他有害物質が検出されております。鉛は基準値をオーバーしており、その他有害物質は基準値以下とされておりますが、自然界に存在しない成分が多数検出されております。自然界に存在しない物質、即ち産業活動により排出された物質、これが産業廃棄物ではないのでしょうか。
「土壌汚染」 「産業廃棄物」でない根拠、見解をお答え下さい。また愛知県環境部では「土壌調査結果報告書」をチェックできる職員は不在なのでしょうか。
(2)「土壌汚染対策法」第4条の2
都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報
告を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査をしないときは、当該調査を自らおこなう旨を、あらかじめ、広告しなければならない。
現在、UR都市機構のUR都市機構の調査方法・説明は信頼できるものではありません。このことは「土壌汚染対策法」第4条の2による、これを放置することが著しく公益に反すると認められるに該当するのではないでしょうか。
(3)「土壌汚染対策法」第7条
都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染により、…………当該土地の所有者以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者に汚染の除去等の措置を講じさせることができる。
今回の城山地区の汚染は、当該土地の所有者以外の者の行為によって汚染が生じたことは明らかであります。当然、汚染の除去等の措置を講じることが法に沿った解決方法ではないでしょうか。
(4)「土壌汚染対策法」第8条の2
当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求する請求権は、当該汚染の除去等の措置を講じ、かつ、その行為をした者を知ったときから三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該汚染の除去等の措置を講じたときから二十年を経過したときも、同様とする。
この法律を盾にし、実際には除去していない(除去していない事は明白です)にもかかわらず、愛知県は責任回避のため当時除去したと説明をしたうえで、時効(二十年)を迎えようとしたのでしょうか。
(5)「土壌汚染対策法」第9条
土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施工方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
テストピット調査掘削土を、産業廃棄物処理場(浄化施設)に運搬し、埋め戻し土を客土にてするようにしております。これは形質の変更ではないのでしょうか。届け出された環境省令で定める事項を示してください。
このことは愛知県の指導によるものと聞いております。この状態では、客土が更に汚染され、汚染土壌の増加だけの結果となってしまいます。どの様な見解を持って、指導されたのでしょうか。「汚染土壌」 「産業廃棄物」なのでしょうか。
(6)「土壌汚染対策法」第29条
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、…………職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。愛知県においては、この法律は無縁のものなのでしょうか。
(7)「土壌汚染対策法施行規則」環境省告示第20号
第二溶出基準に適合しない汚染状態にある土壌は、「産業廃棄物遮断型処分場」に 搬入すること。第二溶出基準に適合する汚染状態にある土壌は、「産業廃棄物管理型処分場」に搬出すること。とされております。当初UR都市機構は、汚染土壌の浄化施設に搬出する予定でおりました。搬出する汚染土壌が第二溶出基準に適合する土壌であったのか、適合しない土壌であったのか、愛知県の判断の基となった資料及び説明を求めます。
(8)「土壌汚染対策法施行規則」環境省告示第21号
搬出する汚染土壌の処分に係る確認方法について、「搬出汚染土壌管理票」を作成、搬出汚染土壌確認報告書の提出が義務づけられております。報告書の提出が済み次第、報告書の開示を求めます。
(9)「土壌汚染対策法施行規則」の概要
揮発性有機化合物は、土壌ガス調査及び土壌溶出量調査とする。開示されたUR都市機構実施調査では、土壌ガス調査が行われていません。サンプリング地点の数は、100?に1点とし、土壌汚染の可能性が低い場所は900?に1点とする。
UR都市機構実施調査では、土壌汚染の可能性が高い場所において約400?に1点、可能性の低い場所においては全く調査をしておりません。
愛知県の見解では、「土壌汚染対策法施行規則」を無視した調査方法が妥当なも
のであると認識されておるのでしょうか。
(油汚染対策ガイドラインに関連した質問事項)
(1)ガイドラインで油臭や油膜の報告例は鉱油類によるものがほとんどであるとされているが、UR都市機構の説明は、自然界に存在しない成分、鉱油、香油と2転3転している。
現物を見られた知事及び担当部署職員の見解では、どちらなのでしょうか。
(2)UR都市機構が設定した、影響範囲外の宅地において油臭があり、雨後に洗濯物を干すと臭いが付着するため、室内に洗濯物を干す家があります。UR都市機構に調査依頼をしても、これ以上の調査は行いませんとの返答だったため、住民で掘削調査を行った結果、油膜が生じました。その結果をUR都市機構に説明、再度調査依頼をするも同じ返答でした。
庭で子供が遊び、地表の土に触れます。UR都市機構の判断は正しいものと、愛知県も思っておられるのでしょうか。
(3)対策として、戸建て住宅や公園など、土地を裸地のまま利用することが普通である土地利用については、油臭や油膜の原因となる油含有土壌の掘削除去や浄化が必要となる。あるいは裸地ではない土地利用方法への変更も考えられる。
愛知県としては、どう考えられているのでしょうか。
(4)地下水の汚染を確認するため、周辺地下水・井戸水のモニタリング、観測井戸等の措置が全くなされておりません。
愛知県としても、必要ないと考えられるのでしょうか。
(その他質問事項)
(1)知事及び愛知県担当部署職員の方々は、残存している産業廃棄物を見られたにもかかわらず、都市再生機構より提訴されたこの時点に至っても、まだ「黒っぽい粘土」と捉えておられるのでしょうか。明確かつ簡潔にお答え願います。
(2)県職員は「産業廃棄物ではなく粘土」・「機構とは情報交換するつもりだが、同じ調査を繰り返しても意味がない」と発言されておりました。情報交換をするつもりだったはずが、提訴された今後どう対応されるのかお聞かせ願いたい。
(3)都市再生機構が調査費用の請求をしましたが、環境調査においては愛知県が土壌汚染対策法に基づいて指導する立場にあり、都市再生機構より適正な調査方法・判断を下すことが出来るものと我々住民は思っております。
愛知県においては、今でも都市再生機構の調査方法が適正なものであると信じ、今後も都市再生機構に調査を委ねたままとするのでしょうか。
(4)ある新聞紙面に県側のコメントとして「提訴は想定の範囲内。訴状を見て対応を検討したい」とありました。想定の範囲内とはどう云うことですか。
この言葉は前回コメント「周辺住民が燃料として使っていた。」 「造成時には無くなっていた」「黒っぽい粘土があっただけ」と大きく矛盾した言葉となっています。産業廃棄物は存在しない姿勢を取りながら提訴を想定していたとの発言。どこに整合性があるのでしょうか。
(5)周辺住民が燃料として使っていた物とは何であるのか、当然燃料として使われていた物ですから目視でどのような廃棄物だったのか容易に想像できたと思います。当時存在していた状態、固形物か・液体物か・固形物に液体が含まれた物か詳細かつ明確に何であったのかお答えいただきたい。そのうえで、その物が産業廃棄物でなかった理由も併せて明確にお答えいただきたい。
(6)当時周辺には住宅が存在しませんでした。愛知県担当部署の方が判断される周辺地域とはどこまでの範囲なのか、また周辺地域の方とは何方を示されておるのか、明快かつ端的にお知らせ下さい。
(7)産業廃棄物処理は許可事業です。許可は当然ご存じのように県が許可を与えるものです。その愛知県が許可の範囲・許可事業内容を一番良くご存じのはずです。なぜ範囲特定の作業に着手していただけないのか理由をお聞かせ下さい。
(8)日本国内において管理産業廃棄物処分場跡地(造成時に稼働していたらしいことから跡地とは呼べない?)に土地情報の告知もせず、分譲住宅を売り出した自治体が愛知県以外にあったのかどうか、また知らせる必要がなかったとされる根拠について教えていただきたい。
(9)産業廃棄物処分場を復旧することは廃棄物事業者に責任があります。跡地を造成名目で愛知県が処理されたとするならば、どの様な見解に基づいて処理されたのでしょうか。また売買契約は処理費用を含んだ金額で適正に行われたのでしょうか。
(10)UR都市機構の提訴金額は8億円とのことでした。2宅地補償金(対策費用と説明)と調査費用のみで8億円の賠償請求が生じるのでしょうか。今後の調査如何で最終金額は不明とのことでした。裁判費用・損害賠償費用他全て県民の税金です。県民の納得出来る状態で損害賠償請求に応じるべきではないでしょうか。
(11)UR都市機構の検討委員会には、環境の専門家、不動産評価の専門家がおりません。地質及び建築の専門家のみで構成されております。愛知県としては、指導していただけたのでしょうか。愛知県の見解をお答え
下さい。
(12)知事は9月4日、定例記者会見で、「一義的には分譲した売主(都市再生機構)が買い主の住人にきちんと対応するのが当たり前」と発言されております。きちんと対応していない都市再生機構に、どのような指導をおこなっているのでしょうか。また分譲した都市再生機構に、土地を造成、売却したのは愛知県です。この重大責任事項に言及しないことは非常に不自然なことに思えますが、愛知県は土地を造成、売却した責任をどう考えておられるのでしょうか。
(13)知事は9月4日、定例記者会見で、8月下旬に土壌のサンプルを採取し、調査していることを挙げ「土壌が産廃なのではという住民の声もあり、不安が解消されるようにしたい」と発言されておりました。サンプルを採取したのは8月22日でしたが、8月25日県職員が現地に来た際「再調査はしない」と言っておりました。未だに知事と担当部署職員との間で、意志疎通がはかられていないのでしょうか。
(14)上記発言は、一番問題となっている「何故産廃があるのか」、「地歴調査をして範囲の特定をするのか」、「調査方法は公正で正しいのか」といった問題から、記者の注目を遠ざける目的で発せられた言葉なのでしょうか。現物を見られた知事及び造成当時の職員ならなら、その物が何であるか十分わかっておられるはずです。
以上 新住宅市街地開発法に関連した質問事項6項目
土壌汚染対策法に関連した質問事項9項目
油汚染対策ガイドラインに関連した質問事項4項目
その他質問事項14項目
※ 上記33項目及び要望書・上申書事項について書面回答して下さい。
※ 回答期日: 9月22日
http://eritokyo.jp/independent/komaki-col0001.html
******************************
愛知県庁:知事の記者会見:2006年11月20日 桃花台ニュータウンの地盤沈下問題について
桃花台ニュータウンの地盤沈下問題について
【記者】
小牧市の桃花台ニュータウンの地盤沈下の件ですけれども、昨日、県の説明会がありまして、調査の方法を説明しておりました。その中で、土壌汚染だけではなく、地耐力をボーリングをする中でもデータはとれるだろうと言っていたのですが、そのデータを住民に公表するといった姿勢が見られませんでした。要するに、裁判の材料のために、そのデータを使うのだというようにしか聞こえないものの言い方でした。
知事は、先だって環境汚染に関しては、住民の安心、安全、不安を取り除くためにやるのだとおっしゃいました。県の説明会の住民への回答の中では、そこのところの言及が全然ないのです。裁判を気にして、そういうことに取り組まないというものの言い方をする行政とはいかがなものか、お考えがありましたらお願いします。
【知事】
職員がどういう言い方をしたのか、詳細までは私はわかりませんけれども、誤解の無いようにしていただきたいのは、裁判の材料にするためなどとは、毛頭考えておりません。
今回の地盤沈下は地盤のいわゆる耐力の問題ですね。それから、土壌の中に黒っぽい粘土質のものがあって、その成分が環境基準を一部オーバーするものがあったということです。これは環境汚染の問題で、厳密に言えば、ちょっと別の問題になろうかと思います。地盤沈下との問題も全く無関係ではありませんけれども、今回、たまたま都市再生機構側が調査したときのサンプルを、県と小牧市も取得し、小牧市の調査分析の中で若干そういうものが出てきたので、その状況を地元の皆様方にご説明するだけではなく、当然、不安をお持ちでありますので、これからあの地域の各住宅ごとに調査をしたいということで、その依頼も含めて説明会をしたものでございます。
したがって、あくまでも土壌汚染、環境汚染を主眼に置いており、耐力を測るための目的のものではないということが一つございます。
しかし、そういうことも、いろいろな材料がこれから結果として出てくるのかもわかりませんが、それは私どもなりに、また分析をしなければならないと思っておりますけれども、裁判は向こうから起こされてきた問題ですし、地盤沈下の問題は売り主としての責任は当然機構側にあるわけでありますので、その耐力の問題も含め、機構側がどのようなデータで、これからどのような調査を進めていかれるのか、これは県としても見極めていかなければならない問題であります。
くどくなって恐縮ですが、裁判のためにというようなことは、目的としては持っていません。裁判の中でも、もちろん県の正当性などを主張しながら進めていくわけで、そこへ活用することは当然あると思います。それは、もう少しいろいろなものが出てきて分析したり、調査してみないとわからないと思っております。
【記者】
住民の不安を取り除くためには、住民にそのデータの公表は考えられないのですか。
【知事】
どんなものが出てくるのか、まだちょっとわかりませんけれども、先ほど申し上げたとおり、住民の不安を解消するということも、もちろん重要なことだと思っておりますので、必要なものについて開示することは、やぶさかではございません。
ただ、ご承知のとおり、現に裁判を起こされておりまして、裁判というのは、主張、立証責任というのは、お互いに分配し合いながら、やっていることでありますので、本来、そのことは機構がきちんとやることでもありますので、今ここで、その材料をどうするかということは、断言的に申し上げことはできないと思っております。努力はいたします。
http://www.pref.aichi.jp/koho/kaiken/2006/11.20.html#7
2009年10月27日
環境省&地方自治体&会員の土壌汚染に関する意見交換会1119


「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html


各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html


2009年10月27日
ISO 9000って???
--------------------------------------------------------------------------------
ISO 9000
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ISO 9000:2000
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000
ISO 9000(広義)、規格群「ISO 9000シリーズ」を省略して「ISO 9000s」と表記。
ISO 9000は、国際標準化機構による品質マネジメントシステム関係の国際規格群。1994年版から2000年版への改正によって、それまでの「製品品質を保証するための規格」から、「品質保証を含んだ、顧客満足の向上を目指すための規格」へと位置付けが変わっている。さらに2008年版では・・・
目次
1 改定履歴
2 規格要求事項
2.1 JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
3 ISO 9001:2008(2008年改訂版)
4 課題
5 関連項目
改定履歴
1987年にISO 9000の規格が制定されてから、1994年と2000年さらに2008年にそれぞれ規格改定が行われた。
ISO 9000:1987
ISO 9000:1994 「94年版」と呼ばれる。
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000 「2000年版」と呼ばれる(ISO 9001)。
「2000年版」と呼ばれる規格
ISO 9000:2005 品質マネジメントシステム―基本及び用語
ISO 9001:2000 品質マネジメントシステム―要求事項
国内での批准翻訳的な規格は、JIS Q 9000:2006 / JIS Q 9001:2000などがある。
2008年版の改正は主に要求事項の明確化とISO 14001 との整合性の向上を目的として行われた。
規格要求事項
ISO 9001(品質マネジメントシステム―要求事項)の目次の一部を下に示す。
JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
JISQ9001:2008(ISO9001:2008)規格解釈
目 次
1.2 適用
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
4.2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一般
4.2.2 品質マニュアル
4.2.3 文書管理
4.2.4 記録の管理
5.経営者の責任5.1 経営者のコミットメント
5.2 顧客重視
5.3 品質方針
5.4 計画
5.4.1 品質目標
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
5.5.2 管理責任者
5.5.3 内部コミュニケーション
5.6 マネジメントレビュー
5.6.1 一般
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
5.6.2 マネジメントレビューからのアウトプット
6.資源の運営管理6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.2.1 一般
6.2.2 力量、教育・訓練及び認識
6.3 インフラストラクチャー
6.4 作業環境
7.製品実現7.1 製品実現の計画
7.2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
7.3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
7.3.2 設計・開発へのインプット
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
7.3.4 設計・開発のレビュー
7.3.5 設計・開発の検証
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
7.3.7 設計・開発の変更管理
7.4 購買
7.4.1 購買プロセス
7.4.2 購買情報
7.4.3 購買製品の検証
7.5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
7.5.4 顧客の所有物
7.5.5 製品の保存
7.6 監視機器及び測定機器の管理
8. 測定、分析及び改善
8.1 一般
8.2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
8.2.2 内部監査
8.2.3 プロセスの監視及び測定
8.2.4 製品の監視及び測定
8.3 不適合製品の管理
8.4 データの分析
8.5 改善
8.5.1 継続的改善
8.5.2 是正処置
8.5.3 予防処置
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
第1章 ISO 9000 規格の解説
第1節 ISO9000規格とは
1 ISO9000規格の成立ち
(1) ISOについて
国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)は1947年に設立された民間の非営利組織で本部はスイスのジュネーブにあります。ISOという略称の由来はギリシャ語の「相等しい」「同一の」を意味する“ISOS”から来ているとも言われています。
ISOは、製品やサービスにおける科学技術や経済活動などの国際標準規格を制定する機関です。日本からは日本工業標準調査会(JISC)が参加しています。
日本のISOの窓口は、経済産業省産業技術環境局です。また、ISO規格の入手等に関する問い合わせ窓口は(財)日本規格協会となっています。
1976年 : ISOに関する委員会TC176が設置され、規格作成の活動が開始。
1987年 : ISO9000、9001〜9003、9004制定
1994年 : ISO9000s1994年版発行(JIS Z 9900s:1994発行)
1998年 :(JIS Z 9900s:1998発行)
2000年12月: ISO9000s:2000発行(JIS Q 9000s:2000発行)
(3) 日本の動き
1991年10月にISO9000規格の翻訳規格として、JIS Z 9900規格が発行されました。1993年11月には、JIS Z 9900(ISO9000)規格の審査登録制度の体制確立と、この制度の整備普及を促進するため、経済団体連合会を構成する産業界が約1年の審議検討を行い、自ら基金を拠出し、(財)日本品質システム審査登録認定協会(JAB:現(財)日本適合性認定協会 http://www.jab.or.jp/)を設立しました。
【品質マネジメントの8原則】
a)顧客重視
組織はその顧客に依存しており、そのために、現在及び将来の顧客ニーズを理解し、顧客要求事項を満たし、顧客の期待を越えるように努力すべきである。
b)リーダーシップ
リーダーは、組織の目的及び方向を一致させる。リーダーは、人々が組織の目標を達することに十分に参画できる内部環境を創りだし、維持すべきである。
c)人々の参画
すべての階層の人々は組織にとって根本的要素であり、その全面的な参画によって、組織の便益のためにその能力を活用することが可能となる。
d)プロセスアプローチ
活動及び関連する資源が一つのプロセスとして運営管理されるとき、望まれる結果がより効率よく達成される。
e)マネジメントへのシステムアプローチ
相互の関連するプロセスを一つのシステムとして、明確にし、理解し、運営管理することが組織の目標を効果的で効率よく達成することに寄与する。
f)継続的改善
組織の総合的パフォーマンスの継続的改善を組織の永遠の目標とすべきである。
g)意思決定への事実に基づくアプローチ
効果的な意思決定は、データ及び情報の分析に基づいている。
h)供給者との互恵関係
組織及びその供給者は独立しており、両者の互恵関係は両者の価値創造能力を高める。
(JIS Q 9004 4. 3より)
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/iso/files/iso.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。 組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善に
かかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
ISO 9001:2008(2008年改訂版)
ISO(国際標準化機構)が、規格の内容の明確化等を目的に平成20年11月15日付けでISO 9001 の改正版を発行したことによって、経済産業省は平成20 年12月20日付けで、JIS Q 9001(品質マネジメントシステム規格)を改正した。今回の改正は、JIS Q 9001 の規格の内容の明確化等を目的とするものであり、組織に要求される事項を追加・変更するものでない。主な改正点は以下のとおり。
(1)規格要求事項の明確化
品質マネジメントシステム:一般要求事項【4.1】アウトソースしたプロセスの管理について、本文の中に“組織は「管理の方式及び程度」を定めなければならない”とするとともに、注記に、「管理の方式及び程度」は以下の3 つの要因により影響されうると説明を追加した。
・アウトソースしたプロセスの適合製品を供給するという組織の能力への影響の可能性
・アウトソースしたプロセスの管理への組織の関与の度合い
・購買管理を遂行する組織の能力
改善:是正処置【8.5.2】及び予防処置【8.5.3】現行版の本文にある“是正処置において実施した活動のレビュー”を、“とった是正処置の有効性のレビュー”と修文することで、ここにおけるレビューとは「実施した是正処置の結果の確認を含む」ことであることを明確にした。
(2)JIS Q 14001 との整合性の向上
記録の管理に関する要求事項【4.2.4】について、JIS Q 14001 との記述順序を揃えることで整合性を向上させた。
課題
ISO 9000シリーズは品質管理を管理する規格であり、品質管理そのものと混同すると形骸化が発生するなどの課題がある。第二次世界大戦後に敗戦国から世界に冠たるものづくり大国になった日本国の品質管理手法と同一視するには無理がある。
関連項目
国際標準化機構
ISO 9004:2000 - 品質マネジメントシステム-パフォーマンス改善の指針
ISO 19011 - 内部監査の規格
ISO 10006 - 品質管理-プロジェクト管理における品質の指針
ISO 14000 - 環境マネジメントシステムの国際規格(IS)
ISO 13485 - 医療機器の規制目的の品質マネジメントシステム
ISO/TS 16949 - 自動車の品質マネジメントシステム
品質管理
プロセスアプローチ
Quality Management System(英語)
ISO
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
4. 2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一般
(1)品質マネジメントシステムの文書には,次の事項を含めなければならない。
a)文書化した,品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c)この規格が要求する“文書化された手順”及び記録
d)組織内のプロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実に実施するために,組織が必要と決定した記録を含む文書
注記1
この規格で“文書化された手順”という用語を使う場合には,その手順が確立され,文書化され,実施され,維持されていることを意味する。一つの文書で,一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。“文書化された手順”の要求事項は,複数の文書で対応してもよい。
注記2
品質マネジメントシステムの文書化の程度は,次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
注記3
文書の様式及び媒体の種類は,どのようなものでもよい。
4.2.2 品質マニュアル
(1)組織は,次の事項を含む品質マニュアルを作成し,維持しなければならない。
a)品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には,除外の詳細,及び除外を正当とする理由。(1.2 参照)
b)品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報
c)品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3 文書管理
(1)品質マネジメントシステムで必要とされる文書は,管理しなければならない。ただし,記録は文書の一種ではあるが,4.2.4 に規定する要求事項に従って管理しなければならない。
(2)次の事項に必要な管理を規定するために,文書化された手順”を確立しなければならない。
a)発行前に,適切かどうかの観点から文書を承認する。
b)文書をレビューする。また,必要に応じて更新し,再承認する。
c)文書の変更の識別及び現在有効な版の識別を確実にする。
d)該当する文書の適切な版が,必要なときに,必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e)文書は,読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f)品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし,その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また,これらを何らかの目的で保持する場合には,適切な識別をする。
4.2.4 記録の管理
(1)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成された記録を,管理しなければならない。
(2)組織は,記録の識別,保管,保護,検索,保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)記録は,読みやすく,容易に識別可能かつ検索可能でなければならない。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
4. 2 文書化に関する要求事項4.2.1 一般
(1)品質マネジメントシステムの文書には,次の事項を含めなければならない。
a)文書化した,品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c)この規格が要求する“文書化された手順”及び記録
d)組織内のプロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実に実施するために,組織が必要と決定した記録を含む文書
注記1
この規格で“文書化された手順”という用語を使う場合には,その手順が確立され,文書化され,実施され,維持されていることを意味する。一つの文書で,一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。“文書化された手順”の要求事項は,複数の文書で対応してもよい。
注記2
品質マネジメントシステムの文書化の程度は,次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
注記3
文書の様式及び媒体の種類は,どのようなものでもよい。
4.2.2 品質マニュアル
(1)組織は,次の事項を含む品質マニュアルを作成し,維持しなければならない。
a)品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には,除外の詳細,及び除外を正当とする理由。(1.2 参照)
b)品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報
c)品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3 文書管理
(1)品質マネジメントシステムで必要とされる文書は,管理しなければならない。ただし,記録は文書の一種ではあるが,4.2.4 に規定する要求事項に従って管理しなければならない。
(2)次の事項に必要な管理を規定するために,文書化された手順”を確立しなければならない。
a)発行前に,適切かどうかの観点から文書を承認する。
b)文書をレビューする。また,必要に応じて更新し,再承認する。
c)文書の変更の識別及び現在有効な版の識別を確実にする。
d)該当する文書の適切な版が,必要なときに,必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e)文書は,読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f)品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし,その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また,これらを何らかの目的で保持する場合には,適切な識別をする。
4.2.4 記録の管理
(1)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成された記録を,管理しなければならない。
(2)組織は,記録の識別,保管,保護,検索,保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)記録は,読みやすく,容易に識別可能かつ検索可能でなければならない。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
5.経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
(1)トップマネジメントは,品質マネジメントシステムの構築及び実施,並びにその有効性を継続的に改善することに対するコミットメントの証拠を,次の事項によって示さなければならない。
a)法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして,顧客要求事項を満たすことの重要性を組織内に周知する。
b)品質方針を設定する。
c)品質目標が設定されることを確実にする。
d)マネジメントレビューを実施する。
e)資源が使用できることを確実にする。
5.2 顧客重視
(1)顧客満足の向上を目指して,トップマネジメントは,顧客要求事項が決定され,満たされていることを確実にしなければならない(7.2.1 及び8.2.1 参照)。
5.3 品質方針
(1)トップマネジメントは,品質方針について,次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の目的に対して適切である。
b)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミットメントを含む。
c)品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。
d)組織全体に伝達され,理解される。
e)適切性の持続のためにレビューされる。
5. 4 計画
5.4.1 品質目標
(1)トップマネジメントは,組織内のしかるべき部門及び階層で,品質目標が設定されていることを確実にしなければならない。
(2)その品質目標には,製品要求事項を満たすために必要なものを含む品質目標[7.1.a]参照]が設定されていることを確実にしなければならない。
(3)品質目標は,その達成度が判定可能で,品質方針との整合がとれていなければならない。
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
(1)トップマネジメントは,次の事項を確実にしなければならない。
a)品質目標に加えて,4.1 に規定する要求事項を満たすために,品質マネジメントシステムの計画を策定する。
b)品質マネジメントシステムの変更を計画し,実施する場合には,品質マネジメントシステムを“完全に整っている状態”(integrity)に維持する。
5. 5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
(1)トップマネジメントは,責任及び権限が定められ,組織全体に周知されていることを確実にしなければならない。
5.5.2 管理責任者
(1)トップマネジメントは,組織の管理層の中から管理責任者を任命しなければならない。
(2)管理責任者は,与えられている他の責任とかかわりなく,次に示す責任及び権限をもたなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立,実施及び維持を確実にする。
b)品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について,トップマネジメントに報告する。
c)組織全体にわたって,顧客要求事項に対する認識を高めることを確実にする。
注記1
管理青任者の責任には,品質マネジメントシステムに関する事項について外部と連絡をとることも含めることができる。
注記2
管理責任者は,上記の責任及び権限をもつ限り,一人である必要はない。
5.5.3 内部コミュニケーション
(1)トップマネジメントは,組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にしなければならない。
(2)また,品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にしなければならない。
5. 6 マネジメントレビュー5.6.1 一般
(1)トップマネジメントは,組織の品質マネジメントシステムが,引き続き,適切,妥当かつ有効であることを確実にするために,あらかじめ定められた間隔で品質マネジメントシステムをレビューしなければならない。
(2)このレビューでは,品質マネジメントシステムの改善の機会の評価,並びに品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行わなければならない。
(3)マネジメントレビューの結果の記録は,維持しなければならない。(4.2.4 参照)。
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
(1)マネジメントレビューへのインプットには,次の情報を含めなければならない。
a)監査の結果
b)顧客からのフィードバック
c)プロセスの成果を含む実施状況及び製品の適合性
d)予防処置及び是正処置の状況
e)前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
f)品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
g)改善のための提案
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
(1)マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項に関する決定及び処置すべてを含めなければならない。
a)品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b)顧客要求事項にかかわる,製品の改善
c)資源の必要性
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
(1)マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項に関する決定及び処置すべてを含めなければならない。
a)品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b)顧客要求事項にかかわる,製品の改善
c)資源の必要性
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
6.資源の運営管理
6.1 資源の提供
(1)組織は,次の事項に必要な資源を明確にし,提供しなければならない。
a)品質マネジメントシステムを実施し,維持する。また,その有効性を継続的に改善する。
b)顧客満足を、顧客要求事項を満たすことによって向上する。
6. 2 人的資源6.2.1 一般
(1)製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員は,適切な教育,訓練,技能及び経験を判断の根拠として力量がなければならない。
注記
製品要求事項への適合は,品質マネジメントシステム内の作業に従事する要員によって,直接的に又は間接的に影響を受ける可能性がある。
6.2.2 力量,認識及び教育・訓練
(1)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量を明確にする。
b)該当する場合には(必要な力量が不足している場合には),その必要な力量に到達することができるように教育・訓練を行うか,又は他の処置をとる。
c)教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。
d)組織の要員が,自らの活動のもつ意味及び重要性を認識し,品質目標の達成に向けて自らがどのように貢献できるかを認識することを確実にする。
e)教育,訓練,技能及び経験について該当する記録を維持する(4.2.4 参照)。
6.3 インフラストラクチャー
(1)組織は,製品要求事項への適合を達成するうえで必要とされるインフラストラクチャーを明確にし,提供し,維持しなければならない。インフラストラクチャーとしては,次のようなものが該当する場合がある。
a)建物,作業場所及び関連するユーティリティー(例えば,電気,ガス又は水)
b)設備(ハードウェア及びソフトウェア)
c)支援体制(例えば,輸送,通信又は情報システム)
6.4 作業環境
(1)組織は,製品要求事項への適合を達成するために必要な作業環境を明確にし,運営管理しなければならない。
注記
“作業環境”という用語は,物理的,環境的及びその他の要因を含む(例えば,騒音,気温,湿度,照明又は天候),作業が行われる状態と関連している。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
7.製品実現
7.1 製品実現の計画
(1)組織は,製品実現のために必要なプロセスを計画し,構築しなければならない。
(2)製品実現の計画は,品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合がとれていなければならない(4.1 参照)。
(3)組織は,製品実現の計画に当たって,次の各事項について適切に明確化しなければならない。
a)製品に対する品質目標及び要求事項
b)製品に特有な,プロセス及び文書の確立の必要性,並びに資源の提供の必要性
c)その製品のための検証,妥当性確認,監視,測定,検査及び試験活動,並びに製品合否判定基準
d)製品実現のプロセス及びその結果としての製品が,要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録(4.2.4 参照)
(4)この計画のアウトプットは,組織の運営方法に適した形式でなければならない。
注記1
特定の製品,プロジェクト又は契約に適用される品質マネジメントシステムのプロセス(製品実現のプロセスを含む。)及び資源を規定する文書を,品質計画書と呼ぶことがある。
注記2
組織は,製品実現のプロセスの構築に当たって,7.3 に規定する要求事項を適用してもよい。
7. 2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化
(1)組織は,次の事項を明確にしなければならない。
a)顧客が規定した要求事項。これには引渡し及び引渡し後の活動に関する要求事項を含む。
b)顧客が明示してはいないが,指定された用途又は意図された用途が既知である場合,それらの用途に応じた要求事項
c)製品に適用される法令・規制要求事項
d)組織が必要と判断する追加要求事項すべて
注記
引渡し後の活動には,例えば,保証に関する取決め,メンテナンスサービスのような契約義務,及びリサイクル又は最終廃棄のような補助的サービスのもとでの活動を含む。
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
(1)組織は,製品に関連する要求事項をレビューしなければならない。
(2)このレビューは,組織が顧客に製品を提供することに対するコミットメント(例:提案書の提出,契約又は注文の受諾,契約又は注文への変更の受諾)をする前に実施しなければならない。
(3)レビューでは,次の事項を確実にしなければならない。
a)製品要求事項が定められている。
b)契約又は注文の要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には,それについて解決されている。
c)組織が,定められた要求事項を満たす能力をもっている。
(4)このレビューの結果の記録,及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
(5)顧客がその要求事項を書面で示さない場合には,組織は顧客要求事項を受諾する前に確認しなければならない。
(6)製品要求事項が変更された場合には,組織は,関連する文書を修正しなければならない。
(7)また,変更後の要求事項が,関連する要員に理解されていることを確実にしなければならない。
注記
インターネット販売などでは,個別の注文に対する正式なレビューの実施は非現実的である。このような場合のレビューでは,カタログ又は宣伝広告資料のような関連する製品情報をその対象とすることもできる。
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
(1)組織は,次の事項に関して顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を明確にし,実施しなければならない。
a)製品情報
b)引き合い,契約若しくは注文,又はそれらの変更
c)苦情を含む顧客からのフィードバック
7. 3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
(1)組織は,製品の設計・開発の計画を策定し,管理しなければならない。
(2)設計・開発の計画において,組織は,次の事項を明確にしなければならない。
a)設計・開発の段階
b)設計・開発の各段階に適したレビュー,検証及び妥当性確認
c)設計・開発に関する責任及び権限
(3)組織は,効果的なコミュニケーション及び責任の明確な割当てを確実にするために,設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理しなければならない。
(4)設計・開発の進行に応じて,策定した計画を適切に更新しなければならない。
注記
設計・開発のレビュー,検証及び妥当性確認は,異なった目的を持っている。それらは,製品及び組織に適するように,個々に又はどのような組み合わせでも,実施し,記録することができる。
7.3.2 設計・開発へのインプット
(1)製品要求事項に関連するインプットを明確にし,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。インプットには,次の事項を含めなければならない。
a)機能及び性能に関する要求事項
b)適用される法令・規制要求事項
c)適用可能な場合には,以前の類似した設計から得られた情報
d)設計・開発に不可欠なその他の要求事項
(2)製品要求事項に関連するインプットについては,その適切性をレビューしなければならない。要求事項は,漏れがなく,あいまい(曖昧)でなく,相反することがあってはならない。
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
(1)設計・開発からのアウトプットは,設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式でなければならない。
(2)また,リリースの前に,承認を受けなければならない。
(3)設計・開発からのアウトプットは,次の状態でなければならない。
a)設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
b)購買,製造及びサービス提供に対して適切な情報を提供する。
c)製品の合否判定基準を含むか,又はそれを参照している。
d)安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性を明確にする。
注記
製造及びサービス提供に対する情報には,製品の保存に関する詳細を含めることができる。
7.3.4 設計・開発のレビュー
(1)設計・開発の適切な段階において,次の事項を目的として,計画されたとおりに(7.3.1 参照)体系的なレビューを行わなければならない。
a)設計・開発の結果が要求事項を満たせるかどうかを評価する。
b)問題を明確にし,必要な処置を提案する。
(2)レビューへの参加者には,レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表する者が含まれていなければならない。
(3)このレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない。(4.2.4 参照)
7.3.5 設計・開発の検証
(1)設計・開発からのアウトプットが,設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために,計画されたとおりに(7.3.1参照)検証を実施しなければならない。
(2)この検証の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない。(4.2.4 参照)
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
(1)結果として得られる製品が,指定された用途又は意図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするために,計画した方法(7.3.1 参照)に従って,設計・開発の妥当性確認を実施しなければならない。
(2)実行可能な湯合にはいつでも,製品の引渡し又は提供の前に,妥当性確認を完了しなければならない。
(3)妥当性確認の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
7.3.7 設計・開発の変更管理
(1)設計・開発の変更を明確にし,記録を維持しなければならない。
(2)変更に対して,レビュー,検証及び妥当性確認を適切に行い,その変更を実施する前に承認しなければならない。
(3)設計・開発の変更のレビューには,その変更が,製品を構成する要素及び既に引き渡されている製品に及ぼす影響の評価を含めなければならない。
(4)変更のレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
注記
“変更のレビュー”とは,変更に対して適切に行われたレビュー,検証及び妥当性確認のことである。
7. 4 購買
7.4.1 購買プロセス
(1)組織は,規定された購買要求事項に,購買製品が適合することを確実にしなければならない。
(2)供給者及び購買した製品に対する管理の方式及び程度は,購買製品が,その後の製品実現のプロセス又は最終製品に及ぼす影響に応じて定めなければならない。
(3)組織は,供給者が組織の要求事項に従って製品を供給する能力を判断の根拠として,供給者を評価し,選定しなければならない。選定,評価及び再評価の基準を定めなければならない。
(4)評価の結果の記録,及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
7.4.2 購買情報
(1)購買情報では購買製品に関する情報を明確にし,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。
a)製品,手順,プロセス及び設備の承認に関する要求事項
b)要員の適格性確認に関する要求事項
c)品質マネジメントシステムに関する要求事項
(2)組織は,供給者に伝達する前に,規定した購買要求事項が妥当であることを確実にしなければならない。
7.4.3 購買製品の検証
(1)組織は,購買製品が,規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために,必要な検査又はその他の活動を定めて,実施しなければならない。
(2)組織又はその顧客が,供給者先で検証を実施することにした場合には,組織は,その検証の要領及び購買製品のリリースの方法を購買情報の中で明確にしなければならない。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
7. 5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
(1)組織は,製造及びサービス提供を計画し,管理された状態で実行しなければならない。
(2)管理された状態には,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。
a)製品の特性を述べた情報が利用できる。
b)必要に応じて,作業手順が利用できる。
c)適切な設備を使用している。
d)監視機器及び測定機器が利用でき,使用している。
e)監視及び測定が実施されている。
f)製品のリリース,顧客への引渡し及び引渡し後の活動が実施されている。
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
(1)製造及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットが,それ以降の監視又は測定で検証することが不可能で,その結果,製品が使用され,又はサービスが提供された後でしか不具合が顕在化しない場合には,組織は,その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行わなければならない。
(2)妥当性確認によって,これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証しなければならない。
(3)組織は,これらのプロセスについて,次の事項のうち該当するものを含んだ手続を確立しなければならない。
a)プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準
b)設備の承認及び要員の適格性確認
c)所定の方法及び手順の適用
d)記録に関する要求事項(4. 2. 4 参照)
e)妥当性の再確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
(1)必要な場合には,組織は,製品実現の全過程において適切な手段で製品を識別しなければならない。
(2)組織は,製品実現の全過程において,監視及び測定の要求事項に関連して,製品の状態を識別しなければならない。
(3)トレーサビリティが要求事項となっている場合には,組織は,製品について一意の識別を管理し,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
注記
ある産業分野では,構成管理(configuration management)が識別及びトレーサビリティを維持する手段である。
7.5.4 顧客の所有物
(1)組織は,顧客の所有物について,それが組織の管理下にある間,又は組織がそれを使用している間は,注意を払わなければならない。
(2)組織は,使用するため又は製品に組み込むために提供された顧客の所有物の識別,検証及び保護・防護を実施しなければならない。
(3)顧客の所有物を紛失若しくは損傷した場合又は使用には適さないとわかった場合には,組織は,顧客に報告し,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。注記 顧客の所有物には,知的財産及び個人情報を含めることができる。
7.5.5 製品の保存
(1)組織は,内部処理から指定納入先への引渡しまでの間,要求事項への適合を維持するように製品を保存しなければならない。
(2)この保存には,該当する場合,識別,取扱い,包装,保管及び保護を含めなければならない。保存は,製品を構成する要素にも適用しなければならない。
注記 内部処理とは,組織が運営管理している製品実現のプロセスにおける活動をいう。
7.6 監視機器及び測定機器の管理
(1)定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために,組織は,実施すべき監視及び測定を明確にしなければならない。また,そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にしなければならない。
(2)組織は,監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立しなければならない。
(3)測定値の正当性が保証されなければならない場合には,測定機器に関し,次の事項を満たさなければならない。
a)定められた間隔又は使用前に,国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証,又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には,校正又は検証に用いた基準を記録する(4.2.4 参照)。
b)機器の調整をする,又は必要に応じて再調整する。
c)校正の状態を明確にするために識別を行う。
d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
e)取扱い,保守及び保管において,損傷及び劣化しないように保護する。
(4)さらに,測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には,組織は,その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し,記録しなければならない。
(5)組織は,その機器,及び影響を受けた製品すべてに対して,適切な処置をとらなければならない。校正及び検証の結果の記録を維持しなければならない(4.2.4参照)。
(6)規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には,そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認しなければならない。
(7)この確認は,最初に使用するのに先立って実施しなければならない。
(8)また,必要に応じて再確認しなければならない。
注記
意図した用途を満たすコンピュータソフトウェアの能力の確認には,通常,その使用の適切性を維持するための検証及び構成管理も含まれる。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
8.測定、分析及び改善
8.1 一般
(1)組織は,次の事項のために必要となる監視,測定,分析及び改善のプロセスを計画し,実施しなければならない。
a)製品要求事項への適合性を実証する。
b)品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。
c)品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。
(2)これには,統計的手法を含め,適用可能な方法,及びその使用の程度を決定することを含めなければならない。
8. 2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
(1)組織は,品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして,顧客要求事項を満足しているかどうかに関して顧客がどのように受けとめているかについての情報を監視しなければならない。
(2)この情報の入手及び使用の方法を定めなければならない。
注記
顧客がどのように受け止めているかの監視には,顧客満足度調査,提供された製品の品質に関する顧客からのデータ,ユーザ意見調査,失注分析,顧客からの賛辞,補償請求,ディーラ報告などの情報源から得たインプットを含めることができる。
8.2.2 内部監査
(1)組織は,品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明確にするために,あらかじめ定められた間隔で内部監査を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムが,個別製品の実現の計画(7.1 参照)に適合しているか,この規格の要求事項に適合しているか,及び組織が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合しているか。
b)品質マネジメントシステムが効果的に実施され,維持されているか。
(2)組織は,監査の対象となるプロセス及び領域の状態及び重要性,並びにこれまでの監査結果を考慮して,監査プログラムを策定しなければならない。
(3)監査の基準,範囲,頻度及び方法を規定しなければならない。
(4)監査員の選定及び監査の実施においては,監査プロセスの客観性及び公平性を確保しなければならない。
(5)監査員は自らの仕事は監査してはならない。
(6)監査の計画及び実施,記録の作成及び結果の報告に関する責任,並びに要求事項を規定するために“文書化された手順”を確立しなければならない。監査及びその結果の記録は,維持しなければならない(4.2.4 参照)。
(7)監査された領域に責任をもつ管理者は,検出された不適合及びその原因を除去するために遅滞なく,必要な修正及び是正処置すべてがとられることを確実にしなければならない。
(8)フォローアップには,とられた処置の検証及び検証結果の報告を含めなければならない(8.5.2 参照)。
注記 JIS Q 19011 参照。
8.2.3 プロセスの監視及び測定
(1)組織は,品質マネジメントシステムのプロセスの監視,及び適用可能な場合に行う測定には,適切な方法を適用しなければならない。
(2)これらの方法は,プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するものでなければならない。
(3)計画どおりの結果が達成できない場合には,適切に,修正及び是正処置をとらなければならない。
注記
適切な方法を決定するとき,組織は,製品要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性への影響に応じて,個々のプロセスに対する適切な監視又は測定の方式及び程度を考慮することを推奨する。
8.2.4 製品の監視及び測定
(1)組織は,製品要求事項が満たされていることを検証するために,製品の特性を監視し,測定しなければならない。
(2)監視及び測定は,個別製品の実現の計画(7.1 参照)に従って,製品実現の適切な段階で実施すしなければならない。
(3)合否判定基準への適合の証拠を維持しなければならない。
(4)顧客への引渡しのための製品のリリースを正式に許可した人を,記録しておかなければならない(4.2.4 参照)。
(5)個別製品の実現の計画(7.1 参照)で決めたことが問題なく完了するまでは,顧客への製品のリリース及びサービスの提供は行ってはならない。ただし,当該の権限をもつ者が承認したとき,及び該当する場合に顧客が承認したときは,この限りではない。
8.3 不適合製品の管理
(1)組織は,製品要求事項に適合しない製品が誤って使用されたり,又は引き渡されることを防ぐために,それらを識別し,管理することを確実にしなければならない。
(2)不適合製品の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)該当する場合には,組織は,次の一つ又はそれ以上の方法で,不適合製品を処理しなければならない。
a)発見された不適合を除去するための処置をとる。
b)当該の権限をもつ者,及び該当する場合に顧客が,特別採用によって,その使用,リリース,又は合格と判定することを正式に許可する。
c)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。
d)引渡し後又は使用開始後に不適合製品が検出された場合には,その不適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。
注記
“c)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる”とは“廃棄すること”を含む。
(4)不適合製品に修正を施した場合には,要求事項への適合を実証するための再検証を行わなければならない。
(5)不適合の性質の記録,及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
8.4 データの分析
(1)組織は,品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため,また,品質マネジメントシステムの継続的な改善の可能性を評価するために適切なデータを明確にし,それらのデータを収集し,分析しなければならない。
(2)この中には,監視及び測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の該当する情報源からのデータを含めなければならない。
(3)データの分析によって,次の事項に関連する情報を提供しなければならない。
a)顧客満足(8.2.1 参照)
b)製品要求事項への適合(8.2.4 参照)
c)予防処置の機会を得ることを含む,プロセス及び製品の,特性及び傾向(8.2.3及び8.2.4 参照)
d)供給者(7.4 参照)
8. 5 改善
8.5.1 継続的改善(1)組織は,品質方針,品質目標,監査結果,データの分析,是正処置,予防処置及びマネジメントレビューを通じて,品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
8.5.2 是正処置
(1)組織は,再発防止のため,不適合の原因を除去する処置をとらなければならない。
(2)是正処置は,検出された不適合のもつ影響に応じたものでなければならない。
(3)次の事項に関する要求事項を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
a)不適合(顧客からの苦情を含む)の内容確認
b)不適合の原因の特定
c)不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価
d)必要な処置の決定及び実施
e)とった処置の結果の記録(4. 2. 4 参照)
f)とった是正処置の有効性のレビュー
注記
f)における“とった是正処置”とは,a)〜e)のことである。
8.5.3 予防処置
(1)組織は,起こり得る不適合が発生することを防止するために,その原因を除去する処置を決めなければならない。
(2)予防処置は,起こり得る問題の影響に応じたものでなければならない。
(3)次の事項に関する要求事項を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
a)起こり得る不適合及びその原因の特定
b)不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価
c)必要な処置の決定及び実施
d)とった処置の結果の記録(4.2.4 参照)
e)とった予防処置の有効性のレビュー
注記 e)における“とった予防処置”とは,a)〜d)のことである。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
ISO 9000
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ISO 9000:2000
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000
ISO 9000(広義)、規格群「ISO 9000シリーズ」を省略して「ISO 9000s」と表記。
ISO 9000は、国際標準化機構による品質マネジメントシステム関係の国際規格群。1994年版から2000年版への改正によって、それまでの「製品品質を保証するための規格」から、「品質保証を含んだ、顧客満足の向上を目指すための規格」へと位置付けが変わっている。さらに2008年版では・・・
目次
1 改定履歴
2 規格要求事項
2.1 JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
3 ISO 9001:2008(2008年改訂版)
4 課題
5 関連項目
改定履歴
1987年にISO 9000の規格が制定されてから、1994年と2000年さらに2008年にそれぞれ規格改定が行われた。
ISO 9000:1987
ISO 9000:1994 「94年版」と呼ばれる。
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000 「2000年版」と呼ばれる(ISO 9001)。
「2000年版」と呼ばれる規格
ISO 9000:2005 品質マネジメントシステム―基本及び用語
ISO 9001:2000 品質マネジメントシステム―要求事項
国内での批准翻訳的な規格は、JIS Q 9000:2006 / JIS Q 9001:2000などがある。
2008年版の改正は主に要求事項の明確化とISO 14001 との整合性の向上を目的として行われた。
規格要求事項
ISO 9001(品質マネジメントシステム―要求事項)の目次の一部を下に示す。
JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
JISQ9001:2008(ISO9001:2008)規格解釈
目 次
1.2 適用
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
4.2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一般
4.2.2 品質マニュアル
4.2.3 文書管理
4.2.4 記録の管理
5.経営者の責任5.1 経営者のコミットメント
5.2 顧客重視
5.3 品質方針
5.4 計画
5.4.1 品質目標
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
5.5.2 管理責任者
5.5.3 内部コミュニケーション
5.6 マネジメントレビュー
5.6.1 一般
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
5.6.2 マネジメントレビューからのアウトプット
6.資源の運営管理6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.2.1 一般
6.2.2 力量、教育・訓練及び認識
6.3 インフラストラクチャー
6.4 作業環境
7.製品実現7.1 製品実現の計画
7.2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
7.3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
7.3.2 設計・開発へのインプット
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
7.3.4 設計・開発のレビュー
7.3.5 設計・開発の検証
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
7.3.7 設計・開発の変更管理
7.4 購買
7.4.1 購買プロセス
7.4.2 購買情報
7.4.3 購買製品の検証
7.5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
7.5.4 顧客の所有物
7.5.5 製品の保存
7.6 監視機器及び測定機器の管理
8. 測定、分析及び改善
8.1 一般
8.2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
8.2.2 内部監査
8.2.3 プロセスの監視及び測定
8.2.4 製品の監視及び測定
8.3 不適合製品の管理
8.4 データの分析
8.5 改善
8.5.1 継続的改善
8.5.2 是正処置
8.5.3 予防処置
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
第1章 ISO 9000 規格の解説
第1節 ISO9000規格とは
1 ISO9000規格の成立ち
(1) ISOについて
国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)は1947年に設立された民間の非営利組織で本部はスイスのジュネーブにあります。ISOという略称の由来はギリシャ語の「相等しい」「同一の」を意味する“ISOS”から来ているとも言われています。
ISOは、製品やサービスにおける科学技術や経済活動などの国際標準規格を制定する機関です。日本からは日本工業標準調査会(JISC)が参加しています。
日本のISOの窓口は、経済産業省産業技術環境局です。また、ISO規格の入手等に関する問い合わせ窓口は(財)日本規格協会となっています。
1976年 : ISOに関する委員会TC176が設置され、規格作成の活動が開始。
1987年 : ISO9000、9001〜9003、9004制定
1994年 : ISO9000s1994年版発行(JIS Z 9900s:1994発行)
1998年 :(JIS Z 9900s:1998発行)
2000年12月: ISO9000s:2000発行(JIS Q 9000s:2000発行)
(3) 日本の動き
1991年10月にISO9000規格の翻訳規格として、JIS Z 9900規格が発行されました。1993年11月には、JIS Z 9900(ISO9000)規格の審査登録制度の体制確立と、この制度の整備普及を促進するため、経済団体連合会を構成する産業界が約1年の審議検討を行い、自ら基金を拠出し、(財)日本品質システム審査登録認定協会(JAB:現(財)日本適合性認定協会 http://www.jab.or.jp/)を設立しました。
【品質マネジメントの8原則】
a)顧客重視
組織はその顧客に依存しており、そのために、現在及び将来の顧客ニーズを理解し、顧客要求事項を満たし、顧客の期待を越えるように努力すべきである。
b)リーダーシップ
リーダーは、組織の目的及び方向を一致させる。リーダーは、人々が組織の目標を達することに十分に参画できる内部環境を創りだし、維持すべきである。
c)人々の参画
すべての階層の人々は組織にとって根本的要素であり、その全面的な参画によって、組織の便益のためにその能力を活用することが可能となる。
d)プロセスアプローチ
活動及び関連する資源が一つのプロセスとして運営管理されるとき、望まれる結果がより効率よく達成される。
e)マネジメントへのシステムアプローチ
相互の関連するプロセスを一つのシステムとして、明確にし、理解し、運営管理することが組織の目標を効果的で効率よく達成することに寄与する。
f)継続的改善
組織の総合的パフォーマンスの継続的改善を組織の永遠の目標とすべきである。
g)意思決定への事実に基づくアプローチ
効果的な意思決定は、データ及び情報の分析に基づいている。
h)供給者との互恵関係
組織及びその供給者は独立しており、両者の互恵関係は両者の価値創造能力を高める。
(JIS Q 9004 4. 3より)
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/iso/files/iso.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。 組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善に
かかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
ISO 9001:2008(2008年改訂版)
ISO(国際標準化機構)が、規格の内容の明確化等を目的に平成20年11月15日付けでISO 9001 の改正版を発行したことによって、経済産業省は平成20 年12月20日付けで、JIS Q 9001(品質マネジメントシステム規格)を改正した。今回の改正は、JIS Q 9001 の規格の内容の明確化等を目的とするものであり、組織に要求される事項を追加・変更するものでない。主な改正点は以下のとおり。
(1)規格要求事項の明確化
品質マネジメントシステム:一般要求事項【4.1】アウトソースしたプロセスの管理について、本文の中に“組織は「管理の方式及び程度」を定めなければならない”とするとともに、注記に、「管理の方式及び程度」は以下の3 つの要因により影響されうると説明を追加した。
・アウトソースしたプロセスの適合製品を供給するという組織の能力への影響の可能性
・アウトソースしたプロセスの管理への組織の関与の度合い
・購買管理を遂行する組織の能力
改善:是正処置【8.5.2】及び予防処置【8.5.3】現行版の本文にある“是正処置において実施した活動のレビュー”を、“とった是正処置の有効性のレビュー”と修文することで、ここにおけるレビューとは「実施した是正処置の結果の確認を含む」ことであることを明確にした。
(2)JIS Q 14001 との整合性の向上
記録の管理に関する要求事項【4.2.4】について、JIS Q 14001 との記述順序を揃えることで整合性を向上させた。
課題
ISO 9000シリーズは品質管理を管理する規格であり、品質管理そのものと混同すると形骸化が発生するなどの課題がある。第二次世界大戦後に敗戦国から世界に冠たるものづくり大国になった日本国の品質管理手法と同一視するには無理がある。
関連項目
国際標準化機構
ISO 9004:2000 - 品質マネジメントシステム-パフォーマンス改善の指針
ISO 19011 - 内部監査の規格
ISO 10006 - 品質管理-プロジェクト管理における品質の指針
ISO 14000 - 環境マネジメントシステムの国際規格(IS)
ISO 13485 - 医療機器の規制目的の品質マネジメントシステム
ISO/TS 16949 - 自動車の品質マネジメントシステム
品質管理
プロセスアプローチ
Quality Management System(英語)
ISO
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
4. 2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一般
(1)品質マネジメントシステムの文書には,次の事項を含めなければならない。
a)文書化した,品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c)この規格が要求する“文書化された手順”及び記録
d)組織内のプロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実に実施するために,組織が必要と決定した記録を含む文書
注記1
この規格で“文書化された手順”という用語を使う場合には,その手順が確立され,文書化され,実施され,維持されていることを意味する。一つの文書で,一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。“文書化された手順”の要求事項は,複数の文書で対応してもよい。
注記2
品質マネジメントシステムの文書化の程度は,次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
注記3
文書の様式及び媒体の種類は,どのようなものでもよい。
4.2.2 品質マニュアル
(1)組織は,次の事項を含む品質マニュアルを作成し,維持しなければならない。
a)品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には,除外の詳細,及び除外を正当とする理由。(1.2 参照)
b)品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報
c)品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3 文書管理
(1)品質マネジメントシステムで必要とされる文書は,管理しなければならない。ただし,記録は文書の一種ではあるが,4.2.4 に規定する要求事項に従って管理しなければならない。
(2)次の事項に必要な管理を規定するために,文書化された手順”を確立しなければならない。
a)発行前に,適切かどうかの観点から文書を承認する。
b)文書をレビューする。また,必要に応じて更新し,再承認する。
c)文書の変更の識別及び現在有効な版の識別を確実にする。
d)該当する文書の適切な版が,必要なときに,必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e)文書は,読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f)品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし,その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また,これらを何らかの目的で保持する場合には,適切な識別をする。
4.2.4 記録の管理
(1)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成された記録を,管理しなければならない。
(2)組織は,記録の識別,保管,保護,検索,保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)記録は,読みやすく,容易に識別可能かつ検索可能でなければならない。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
4. 2 文書化に関する要求事項4.2.1 一般
(1)品質マネジメントシステムの文書には,次の事項を含めなければならない。
a)文書化した,品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c)この規格が要求する“文書化された手順”及び記録
d)組織内のプロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実に実施するために,組織が必要と決定した記録を含む文書
注記1
この規格で“文書化された手順”という用語を使う場合には,その手順が確立され,文書化され,実施され,維持されていることを意味する。一つの文書で,一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。“文書化された手順”の要求事項は,複数の文書で対応してもよい。
注記2
品質マネジメントシステムの文書化の程度は,次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
注記3
文書の様式及び媒体の種類は,どのようなものでもよい。
4.2.2 品質マニュアル
(1)組織は,次の事項を含む品質マニュアルを作成し,維持しなければならない。
a)品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には,除外の詳細,及び除外を正当とする理由。(1.2 参照)
b)品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報
c)品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3 文書管理
(1)品質マネジメントシステムで必要とされる文書は,管理しなければならない。ただし,記録は文書の一種ではあるが,4.2.4 に規定する要求事項に従って管理しなければならない。
(2)次の事項に必要な管理を規定するために,文書化された手順”を確立しなければならない。
a)発行前に,適切かどうかの観点から文書を承認する。
b)文書をレビューする。また,必要に応じて更新し,再承認する。
c)文書の変更の識別及び現在有効な版の識別を確実にする。
d)該当する文書の適切な版が,必要なときに,必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e)文書は,読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f)品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし,その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また,これらを何らかの目的で保持する場合には,適切な識別をする。
4.2.4 記録の管理
(1)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成された記録を,管理しなければならない。
(2)組織は,記録の識別,保管,保護,検索,保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)記録は,読みやすく,容易に識別可能かつ検索可能でなければならない。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
5.経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
(1)トップマネジメントは,品質マネジメントシステムの構築及び実施,並びにその有効性を継続的に改善することに対するコミットメントの証拠を,次の事項によって示さなければならない。
a)法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして,顧客要求事項を満たすことの重要性を組織内に周知する。
b)品質方針を設定する。
c)品質目標が設定されることを確実にする。
d)マネジメントレビューを実施する。
e)資源が使用できることを確実にする。
5.2 顧客重視
(1)顧客満足の向上を目指して,トップマネジメントは,顧客要求事項が決定され,満たされていることを確実にしなければならない(7.2.1 及び8.2.1 参照)。
5.3 品質方針
(1)トップマネジメントは,品質方針について,次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の目的に対して適切である。
b)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミットメントを含む。
c)品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。
d)組織全体に伝達され,理解される。
e)適切性の持続のためにレビューされる。
5. 4 計画
5.4.1 品質目標
(1)トップマネジメントは,組織内のしかるべき部門及び階層で,品質目標が設定されていることを確実にしなければならない。
(2)その品質目標には,製品要求事項を満たすために必要なものを含む品質目標[7.1.a]参照]が設定されていることを確実にしなければならない。
(3)品質目標は,その達成度が判定可能で,品質方針との整合がとれていなければならない。
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
(1)トップマネジメントは,次の事項を確実にしなければならない。
a)品質目標に加えて,4.1 に規定する要求事項を満たすために,品質マネジメントシステムの計画を策定する。
b)品質マネジメントシステムの変更を計画し,実施する場合には,品質マネジメントシステムを“完全に整っている状態”(integrity)に維持する。
5. 5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
(1)トップマネジメントは,責任及び権限が定められ,組織全体に周知されていることを確実にしなければならない。
5.5.2 管理責任者
(1)トップマネジメントは,組織の管理層の中から管理責任者を任命しなければならない。
(2)管理責任者は,与えられている他の責任とかかわりなく,次に示す責任及び権限をもたなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立,実施及び維持を確実にする。
b)品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について,トップマネジメントに報告する。
c)組織全体にわたって,顧客要求事項に対する認識を高めることを確実にする。
注記1
管理青任者の責任には,品質マネジメントシステムに関する事項について外部と連絡をとることも含めることができる。
注記2
管理責任者は,上記の責任及び権限をもつ限り,一人である必要はない。
5.5.3 内部コミュニケーション
(1)トップマネジメントは,組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にしなければならない。
(2)また,品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にしなければならない。
5. 6 マネジメントレビュー5.6.1 一般
(1)トップマネジメントは,組織の品質マネジメントシステムが,引き続き,適切,妥当かつ有効であることを確実にするために,あらかじめ定められた間隔で品質マネジメントシステムをレビューしなければならない。
(2)このレビューでは,品質マネジメントシステムの改善の機会の評価,並びに品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行わなければならない。
(3)マネジメントレビューの結果の記録は,維持しなければならない。(4.2.4 参照)。
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
(1)マネジメントレビューへのインプットには,次の情報を含めなければならない。
a)監査の結果
b)顧客からのフィードバック
c)プロセスの成果を含む実施状況及び製品の適合性
d)予防処置及び是正処置の状況
e)前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
f)品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
g)改善のための提案
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
(1)マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項に関する決定及び処置すべてを含めなければならない。
a)品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b)顧客要求事項にかかわる,製品の改善
c)資源の必要性
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
(1)マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項に関する決定及び処置すべてを含めなければならない。
a)品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b)顧客要求事項にかかわる,製品の改善
c)資源の必要性
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
6.資源の運営管理
6.1 資源の提供
(1)組織は,次の事項に必要な資源を明確にし,提供しなければならない。
a)品質マネジメントシステムを実施し,維持する。また,その有効性を継続的に改善する。
b)顧客満足を、顧客要求事項を満たすことによって向上する。
6. 2 人的資源6.2.1 一般
(1)製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員は,適切な教育,訓練,技能及び経験を判断の根拠として力量がなければならない。
注記
製品要求事項への適合は,品質マネジメントシステム内の作業に従事する要員によって,直接的に又は間接的に影響を受ける可能性がある。
6.2.2 力量,認識及び教育・訓練
(1)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量を明確にする。
b)該当する場合には(必要な力量が不足している場合には),その必要な力量に到達することができるように教育・訓練を行うか,又は他の処置をとる。
c)教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。
d)組織の要員が,自らの活動のもつ意味及び重要性を認識し,品質目標の達成に向けて自らがどのように貢献できるかを認識することを確実にする。
e)教育,訓練,技能及び経験について該当する記録を維持する(4.2.4 参照)。
6.3 インフラストラクチャー
(1)組織は,製品要求事項への適合を達成するうえで必要とされるインフラストラクチャーを明確にし,提供し,維持しなければならない。インフラストラクチャーとしては,次のようなものが該当する場合がある。
a)建物,作業場所及び関連するユーティリティー(例えば,電気,ガス又は水)
b)設備(ハードウェア及びソフトウェア)
c)支援体制(例えば,輸送,通信又は情報システム)
6.4 作業環境
(1)組織は,製品要求事項への適合を達成するために必要な作業環境を明確にし,運営管理しなければならない。
注記
“作業環境”という用語は,物理的,環境的及びその他の要因を含む(例えば,騒音,気温,湿度,照明又は天候),作業が行われる状態と関連している。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
7.製品実現
7.1 製品実現の計画
(1)組織は,製品実現のために必要なプロセスを計画し,構築しなければならない。
(2)製品実現の計画は,品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合がとれていなければならない(4.1 参照)。
(3)組織は,製品実現の計画に当たって,次の各事項について適切に明確化しなければならない。
a)製品に対する品質目標及び要求事項
b)製品に特有な,プロセス及び文書の確立の必要性,並びに資源の提供の必要性
c)その製品のための検証,妥当性確認,監視,測定,検査及び試験活動,並びに製品合否判定基準
d)製品実現のプロセス及びその結果としての製品が,要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録(4.2.4 参照)
(4)この計画のアウトプットは,組織の運営方法に適した形式でなければならない。
注記1
特定の製品,プロジェクト又は契約に適用される品質マネジメントシステムのプロセス(製品実現のプロセスを含む。)及び資源を規定する文書を,品質計画書と呼ぶことがある。
注記2
組織は,製品実現のプロセスの構築に当たって,7.3 に規定する要求事項を適用してもよい。
7. 2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化
(1)組織は,次の事項を明確にしなければならない。
a)顧客が規定した要求事項。これには引渡し及び引渡し後の活動に関する要求事項を含む。
b)顧客が明示してはいないが,指定された用途又は意図された用途が既知である場合,それらの用途に応じた要求事項
c)製品に適用される法令・規制要求事項
d)組織が必要と判断する追加要求事項すべて
注記
引渡し後の活動には,例えば,保証に関する取決め,メンテナンスサービスのような契約義務,及びリサイクル又は最終廃棄のような補助的サービスのもとでの活動を含む。
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
(1)組織は,製品に関連する要求事項をレビューしなければならない。
(2)このレビューは,組織が顧客に製品を提供することに対するコミットメント(例:提案書の提出,契約又は注文の受諾,契約又は注文への変更の受諾)をする前に実施しなければならない。
(3)レビューでは,次の事項を確実にしなければならない。
a)製品要求事項が定められている。
b)契約又は注文の要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には,それについて解決されている。
c)組織が,定められた要求事項を満たす能力をもっている。
(4)このレビューの結果の記録,及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
(5)顧客がその要求事項を書面で示さない場合には,組織は顧客要求事項を受諾する前に確認しなければならない。
(6)製品要求事項が変更された場合には,組織は,関連する文書を修正しなければならない。
(7)また,変更後の要求事項が,関連する要員に理解されていることを確実にしなければならない。
注記
インターネット販売などでは,個別の注文に対する正式なレビューの実施は非現実的である。このような場合のレビューでは,カタログ又は宣伝広告資料のような関連する製品情報をその対象とすることもできる。
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
(1)組織は,次の事項に関して顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を明確にし,実施しなければならない。
a)製品情報
b)引き合い,契約若しくは注文,又はそれらの変更
c)苦情を含む顧客からのフィードバック
7. 3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
(1)組織は,製品の設計・開発の計画を策定し,管理しなければならない。
(2)設計・開発の計画において,組織は,次の事項を明確にしなければならない。
a)設計・開発の段階
b)設計・開発の各段階に適したレビュー,検証及び妥当性確認
c)設計・開発に関する責任及び権限
(3)組織は,効果的なコミュニケーション及び責任の明確な割当てを確実にするために,設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理しなければならない。
(4)設計・開発の進行に応じて,策定した計画を適切に更新しなければならない。
注記
設計・開発のレビュー,検証及び妥当性確認は,異なった目的を持っている。それらは,製品及び組織に適するように,個々に又はどのような組み合わせでも,実施し,記録することができる。
7.3.2 設計・開発へのインプット
(1)製品要求事項に関連するインプットを明確にし,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。インプットには,次の事項を含めなければならない。
a)機能及び性能に関する要求事項
b)適用される法令・規制要求事項
c)適用可能な場合には,以前の類似した設計から得られた情報
d)設計・開発に不可欠なその他の要求事項
(2)製品要求事項に関連するインプットについては,その適切性をレビューしなければならない。要求事項は,漏れがなく,あいまい(曖昧)でなく,相反することがあってはならない。
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
(1)設計・開発からのアウトプットは,設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式でなければならない。
(2)また,リリースの前に,承認を受けなければならない。
(3)設計・開発からのアウトプットは,次の状態でなければならない。
a)設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
b)購買,製造及びサービス提供に対して適切な情報を提供する。
c)製品の合否判定基準を含むか,又はそれを参照している。
d)安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性を明確にする。
注記
製造及びサービス提供に対する情報には,製品の保存に関する詳細を含めることができる。
7.3.4 設計・開発のレビュー
(1)設計・開発の適切な段階において,次の事項を目的として,計画されたとおりに(7.3.1 参照)体系的なレビューを行わなければならない。
a)設計・開発の結果が要求事項を満たせるかどうかを評価する。
b)問題を明確にし,必要な処置を提案する。
(2)レビューへの参加者には,レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表する者が含まれていなければならない。
(3)このレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない。(4.2.4 参照)
7.3.5 設計・開発の検証
(1)設計・開発からのアウトプットが,設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために,計画されたとおりに(7.3.1参照)検証を実施しなければならない。
(2)この検証の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない。(4.2.4 参照)
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
(1)結果として得られる製品が,指定された用途又は意図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするために,計画した方法(7.3.1 参照)に従って,設計・開発の妥当性確認を実施しなければならない。
(2)実行可能な湯合にはいつでも,製品の引渡し又は提供の前に,妥当性確認を完了しなければならない。
(3)妥当性確認の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
7.3.7 設計・開発の変更管理
(1)設計・開発の変更を明確にし,記録を維持しなければならない。
(2)変更に対して,レビュー,検証及び妥当性確認を適切に行い,その変更を実施する前に承認しなければならない。
(3)設計・開発の変更のレビューには,その変更が,製品を構成する要素及び既に引き渡されている製品に及ぼす影響の評価を含めなければならない。
(4)変更のレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
注記
“変更のレビュー”とは,変更に対して適切に行われたレビュー,検証及び妥当性確認のことである。
7. 4 購買
7.4.1 購買プロセス
(1)組織は,規定された購買要求事項に,購買製品が適合することを確実にしなければならない。
(2)供給者及び購買した製品に対する管理の方式及び程度は,購買製品が,その後の製品実現のプロセス又は最終製品に及ぼす影響に応じて定めなければならない。
(3)組織は,供給者が組織の要求事項に従って製品を供給する能力を判断の根拠として,供給者を評価し,選定しなければならない。選定,評価及び再評価の基準を定めなければならない。
(4)評価の結果の記録,及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
7.4.2 購買情報
(1)購買情報では購買製品に関する情報を明確にし,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。
a)製品,手順,プロセス及び設備の承認に関する要求事項
b)要員の適格性確認に関する要求事項
c)品質マネジメントシステムに関する要求事項
(2)組織は,供給者に伝達する前に,規定した購買要求事項が妥当であることを確実にしなければならない。
7.4.3 購買製品の検証
(1)組織は,購買製品が,規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために,必要な検査又はその他の活動を定めて,実施しなければならない。
(2)組織又はその顧客が,供給者先で検証を実施することにした場合には,組織は,その検証の要領及び購買製品のリリースの方法を購買情報の中で明確にしなければならない。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
7. 5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
(1)組織は,製造及びサービス提供を計画し,管理された状態で実行しなければならない。
(2)管理された状態には,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。
a)製品の特性を述べた情報が利用できる。
b)必要に応じて,作業手順が利用できる。
c)適切な設備を使用している。
d)監視機器及び測定機器が利用でき,使用している。
e)監視及び測定が実施されている。
f)製品のリリース,顧客への引渡し及び引渡し後の活動が実施されている。
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
(1)製造及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットが,それ以降の監視又は測定で検証することが不可能で,その結果,製品が使用され,又はサービスが提供された後でしか不具合が顕在化しない場合には,組織は,その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行わなければならない。
(2)妥当性確認によって,これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証しなければならない。
(3)組織は,これらのプロセスについて,次の事項のうち該当するものを含んだ手続を確立しなければならない。
a)プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準
b)設備の承認及び要員の適格性確認
c)所定の方法及び手順の適用
d)記録に関する要求事項(4. 2. 4 参照)
e)妥当性の再確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
(1)必要な場合には,組織は,製品実現の全過程において適切な手段で製品を識別しなければならない。
(2)組織は,製品実現の全過程において,監視及び測定の要求事項に関連して,製品の状態を識別しなければならない。
(3)トレーサビリティが要求事項となっている場合には,組織は,製品について一意の識別を管理し,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
注記
ある産業分野では,構成管理(configuration management)が識別及びトレーサビリティを維持する手段である。
7.5.4 顧客の所有物
(1)組織は,顧客の所有物について,それが組織の管理下にある間,又は組織がそれを使用している間は,注意を払わなければならない。
(2)組織は,使用するため又は製品に組み込むために提供された顧客の所有物の識別,検証及び保護・防護を実施しなければならない。
(3)顧客の所有物を紛失若しくは損傷した場合又は使用には適さないとわかった場合には,組織は,顧客に報告し,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。注記 顧客の所有物には,知的財産及び個人情報を含めることができる。
7.5.5 製品の保存
(1)組織は,内部処理から指定納入先への引渡しまでの間,要求事項への適合を維持するように製品を保存しなければならない。
(2)この保存には,該当する場合,識別,取扱い,包装,保管及び保護を含めなければならない。保存は,製品を構成する要素にも適用しなければならない。
注記 内部処理とは,組織が運営管理している製品実現のプロセスにおける活動をいう。
7.6 監視機器及び測定機器の管理
(1)定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために,組織は,実施すべき監視及び測定を明確にしなければならない。また,そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にしなければならない。
(2)組織は,監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立しなければならない。
(3)測定値の正当性が保証されなければならない場合には,測定機器に関し,次の事項を満たさなければならない。
a)定められた間隔又は使用前に,国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証,又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には,校正又は検証に用いた基準を記録する(4.2.4 参照)。
b)機器の調整をする,又は必要に応じて再調整する。
c)校正の状態を明確にするために識別を行う。
d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
e)取扱い,保守及び保管において,損傷及び劣化しないように保護する。
(4)さらに,測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には,組織は,その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し,記録しなければならない。
(5)組織は,その機器,及び影響を受けた製品すべてに対して,適切な処置をとらなければならない。校正及び検証の結果の記録を維持しなければならない(4.2.4参照)。
(6)規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には,そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認しなければならない。
(7)この確認は,最初に使用するのに先立って実施しなければならない。
(8)また,必要に応じて再確認しなければならない。
注記
意図した用途を満たすコンピュータソフトウェアの能力の確認には,通常,その使用の適切性を維持するための検証及び構成管理も含まれる。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
8.測定、分析及び改善
8.1 一般
(1)組織は,次の事項のために必要となる監視,測定,分析及び改善のプロセスを計画し,実施しなければならない。
a)製品要求事項への適合性を実証する。
b)品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。
c)品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。
(2)これには,統計的手法を含め,適用可能な方法,及びその使用の程度を決定することを含めなければならない。
8. 2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
(1)組織は,品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして,顧客要求事項を満足しているかどうかに関して顧客がどのように受けとめているかについての情報を監視しなければならない。
(2)この情報の入手及び使用の方法を定めなければならない。
注記
顧客がどのように受け止めているかの監視には,顧客満足度調査,提供された製品の品質に関する顧客からのデータ,ユーザ意見調査,失注分析,顧客からの賛辞,補償請求,ディーラ報告などの情報源から得たインプットを含めることができる。
8.2.2 内部監査
(1)組織は,品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明確にするために,あらかじめ定められた間隔で内部監査を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムが,個別製品の実現の計画(7.1 参照)に適合しているか,この規格の要求事項に適合しているか,及び組織が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合しているか。
b)品質マネジメントシステムが効果的に実施され,維持されているか。
(2)組織は,監査の対象となるプロセス及び領域の状態及び重要性,並びにこれまでの監査結果を考慮して,監査プログラムを策定しなければならない。
(3)監査の基準,範囲,頻度及び方法を規定しなければならない。
(4)監査員の選定及び監査の実施においては,監査プロセスの客観性及び公平性を確保しなければならない。
(5)監査員は自らの仕事は監査してはならない。
(6)監査の計画及び実施,記録の作成及び結果の報告に関する責任,並びに要求事項を規定するために“文書化された手順”を確立しなければならない。監査及びその結果の記録は,維持しなければならない(4.2.4 参照)。
(7)監査された領域に責任をもつ管理者は,検出された不適合及びその原因を除去するために遅滞なく,必要な修正及び是正処置すべてがとられることを確実にしなければならない。
(8)フォローアップには,とられた処置の検証及び検証結果の報告を含めなければならない(8.5.2 参照)。
注記 JIS Q 19011 参照。
8.2.3 プロセスの監視及び測定
(1)組織は,品質マネジメントシステムのプロセスの監視,及び適用可能な場合に行う測定には,適切な方法を適用しなければならない。
(2)これらの方法は,プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するものでなければならない。
(3)計画どおりの結果が達成できない場合には,適切に,修正及び是正処置をとらなければならない。
注記
適切な方法を決定するとき,組織は,製品要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性への影響に応じて,個々のプロセスに対する適切な監視又は測定の方式及び程度を考慮することを推奨する。
8.2.4 製品の監視及び測定
(1)組織は,製品要求事項が満たされていることを検証するために,製品の特性を監視し,測定しなければならない。
(2)監視及び測定は,個別製品の実現の計画(7.1 参照)に従って,製品実現の適切な段階で実施すしなければならない。
(3)合否判定基準への適合の証拠を維持しなければならない。
(4)顧客への引渡しのための製品のリリースを正式に許可した人を,記録しておかなければならない(4.2.4 参照)。
(5)個別製品の実現の計画(7.1 参照)で決めたことが問題なく完了するまでは,顧客への製品のリリース及びサービスの提供は行ってはならない。ただし,当該の権限をもつ者が承認したとき,及び該当する場合に顧客が承認したときは,この限りではない。
8.3 不適合製品の管理
(1)組織は,製品要求事項に適合しない製品が誤って使用されたり,又は引き渡されることを防ぐために,それらを識別し,管理することを確実にしなければならない。
(2)不適合製品の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)該当する場合には,組織は,次の一つ又はそれ以上の方法で,不適合製品を処理しなければならない。
a)発見された不適合を除去するための処置をとる。
b)当該の権限をもつ者,及び該当する場合に顧客が,特別採用によって,その使用,リリース,又は合格と判定することを正式に許可する。
c)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。
d)引渡し後又は使用開始後に不適合製品が検出された場合には,その不適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。
注記
“c)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる”とは“廃棄すること”を含む。
(4)不適合製品に修正を施した場合には,要求事項への適合を実証するための再検証を行わなければならない。
(5)不適合の性質の記録,及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
8.4 データの分析
(1)組織は,品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため,また,品質マネジメントシステムの継続的な改善の可能性を評価するために適切なデータを明確にし,それらのデータを収集し,分析しなければならない。
(2)この中には,監視及び測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の該当する情報源からのデータを含めなければならない。
(3)データの分析によって,次の事項に関連する情報を提供しなければならない。
a)顧客満足(8.2.1 参照)
b)製品要求事項への適合(8.2.4 参照)
c)予防処置の機会を得ることを含む,プロセス及び製品の,特性及び傾向(8.2.3及び8.2.4 参照)
d)供給者(7.4 参照)
8. 5 改善
8.5.1 継続的改善(1)組織は,品質方針,品質目標,監査結果,データの分析,是正処置,予防処置及びマネジメントレビューを通じて,品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
8.5.2 是正処置
(1)組織は,再発防止のため,不適合の原因を除去する処置をとらなければならない。
(2)是正処置は,検出された不適合のもつ影響に応じたものでなければならない。
(3)次の事項に関する要求事項を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
a)不適合(顧客からの苦情を含む)の内容確認
b)不適合の原因の特定
c)不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価
d)必要な処置の決定及び実施
e)とった処置の結果の記録(4. 2. 4 参照)
f)とった是正処置の有効性のレビュー
注記
f)における“とった是正処置”とは,a)〜e)のことである。
8.5.3 予防処置
(1)組織は,起こり得る不適合が発生することを防止するために,その原因を除去する処置を決めなければならない。
(2)予防処置は,起こり得る問題の影響に応じたものでなければならない。
(3)次の事項に関する要求事項を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
a)起こり得る不適合及びその原因の特定
b)不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価
c)必要な処置の決定及び実施
d)とった処置の結果の記録(4.2.4 参照)
e)とった予防処置の有効性のレビュー
注記 e)における“とった予防処置”とは,a)〜d)のことである。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
2009年10月26日
ATC土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会


「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html


各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html


2009年10月25日
底質環境基準
'''底質の環境基準'''(ていしつのかんきょうきじゅん)とは、水底の底質について国が定めている環境基準のこと。現在、ダイオキシン類(150pg-TEQ/g)についてのみが定められている。底質には有害物質が蓄積されており食物連鎖を通じて人への健康被害が生じており、生態系への顕著な影響が知られている。重金属や環境ホルモン等の有害物質に基準が求められている。
== 内容 ==
[[ダイオキシン類]]のみが定められている。
=== ダイオキシン類 ===
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、ダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準である。
* 媒体:水底の底質
* 基準:150pg-TEQ/g以下
* 測定方法:水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
== 底質の環境中の濃度に係るその他の基準 ==
=== 暫定除去基準 ===
「底質暫定除去基準」として水銀とポリ塩化ビフェニル(PCB)が定められている。
=== 水産用水基準による底質の基準 ===
*河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。
*海域では乾泥として化学的酸素要求量(COD)(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること
*微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、[[種苗]]の着生、発生あるいはその発育を妨げないことなどとされている。
*海域では乾泥としてCODOH(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること。
*海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については、水産用水基準の基準値の10倍を下回ること。ただし、カドミウム、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の検出下限値を下回ること。
*ダイオキシン類の濃度は150pgTEQ/gを下回ること。
=== 水底土砂判定基準 ===
環境中の濃度を示すものではないが、浚渫した土砂(底質)を海面[[埋立]]または[[海洋投入]]するにあたって定められている基準として、「水底土砂に係る判定基準」がある。
== 底質の環境基準の必要性 ==
底質汚染は水俣病の事例のように食物連鎖を通してヒトの健康被害が懸念されている。今後、早急に鉛やヒ素などの重金属類やテトラクロロエチレンなどの揮発性有機化合物さらにPOPs農薬などの有害物質に関する底質環境基準を定めることが必要であるとされている。
== 底質の環境中の濃度の評価について ==
=== 土壌環境基準との比較 ===
底質を浚渫して陸上に上げると土壌となる。底質は土壌の一部であるという考え方もあるが、統一されていない。
しかし、底質汚染が土壌汚染と比べて健康リスクは高いが、人の健康の保護に関する水質環境基準に定められている物質について、地下水の水質汚濁に係る環境基準や、土壌の汚染に係る環境基準が定められているのに対し、現在底質の環境基準は定められていない。
なお、土壌の汚染に係る環境基準は、汚染された土壌から地下水等への溶出の観点から上記の溶出量の基準が定められているほか、農作物に対する影響および農作物に蓄積して人の健康に影響を及ぼす観点から含有量の基準が定められている。
ダイオキシン類については、土壌環境基準値が1,000pg-TEQ/gとなっており、底質環境基準値がその15%となっている。
=== 底生生物と有害物質の関係 ===
平成14年に港湾底泥調査が国の機関により実施され、[[重金属]]濃度と[[底生生物]]の種類数との相関関係が公開されている。底生生物の種類が比較的豊富である限界の濃度であるERLの含有量値を下記に示す。
水銀:0.1mg/kg乾泥
カドミウム:1mg/kg乾泥
銅:34mg/kg乾泥
鉛:46.7mg/kg乾泥
ニッケル:20mg/kg乾泥
クロム:80mg/kg乾泥
亜鉛:150mg/kg乾泥
特に、カドミウム・鉛・水銀についてはERLを超過した底質には底生生物が激減することが公開されている。含有量値と溶出量値との明確な相関関係は認められないが、底生生物が水生生物と同程度の感受性を持ち、エラからの吸収による影響が主体的であれば水産用水基準水質環境基準の近似値が一つの目標となる。
ERL(effects range-low):悪影響があるとした報告例のうち低濃度側から10 パーセンタイル値の濃度(最小影響範囲:底生生物の種類が豊富である限界の濃度)
ERM(effects range-median):悪影響があるとした報告例のうち低濃度側から10 パーセンタイル値の濃度(確実な影響範囲:底生生物がほとんどいない濃度)
ERL以上ERM未満の濃度は潜在影響範囲と呼ばれている。
この手法は底質評価のガイドライン値を提供するものであり、カナダ国家底質ガイドラインおよび、フロリダ州の底質ガイドライン開発の基礎として利用されているほかロサンゼルス・ロングビーチ港で適用されている。
=== 溶出量値 ===
前述したERLにおける含有量値と溶出量値との明確な相関関係は認められないが、底生生物が水生生物と同程度の感受性を持ち、エラからの吸収による影響が主体的であれば水産用水基準(水質環境基準の近似値)が一つの目標となる。
なお、亜鉛の水生生物保全のための環境基準は0.02mg/Lである。|また、河川や港湾の底から地下水へ浸透しているので、地下水の環境基準を基本とした土壌環境基準を底質の環境基準として取り組んでる。
== 外部リンク ==
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準
化学物質と環境(年次報告書)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)
4 . 基準値(1)基本的考え方 底質中ダイオキシン類が人の健康に影響を及ぼす恐れは、魚介類への取り込み並びに底質から水への巻き上げ及び溶出の2つの影響経路からが考えられる。
?魚介類への取り込みを考慮する方式について
ダイオキシン類については国民摂取実態から魚介類を経由した摂取が多いことが既知の事実であり、また、平成11年度に環境庁が行った調査では、底質中ダイオキシン類濃度と魚介類中ダイオキシン類濃度との関係においては、相関係数が小さいながらも有意な正の相関があることが分かっている。
他方、ダイオキシン類については、国民の平均的なダイオキシン類摂取量が耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake。以下「TDI」という。)に比較して小さく、バランスのとれた食事が大切と整理されている。また、食品としての魚介類の許容上限値が定められていない。
このため、現時点では、対策実施のための底質環境基準の設定において、基準値導出に必要な諸条件が不足しており、この観点から数値を設定することは困難な状況にある。
?水への影響を考慮する方式について
底質中ダイオキシン類は、ダイオキシン類の水への供給源(汚染源)となっており、その影響の程度を勘案して設定するという方式については、底泥中の間隙水の濃度に着目して底質濃度を規定する分配平衡法と、実際にダイオキシン類に汚染された底泥を用いて水への振とう分配試験を行い、水質への影響を考慮する方法の2種類がある。
他にも様々な手法が考えられるが、現時点でデータが得られており、算定が可能な手法として、本報告では、これら両者の手法を勘案して環境基準値を設定することとした。
(2)設定手法
?分配平衡法
底質の間隙水中の化学物質濃度は底質の固相における濃度と平衡状態を形成しており、底質固相の濃度は底質の有機物濃度によって変動する。
つまり、平衡条件下にある底質と水との間の化学物質の分配係数は、?固相中濃度と間隙水濃度との比、及び?有機炭素と水との分配係数と、底質の有機炭素の割合との積、の2つの方法で表すことができる。模式的には、下記の(1)式の様に書くことができる。
Kp = Cs / Cd = foc・Koc (1)
Kp : 底質中、固相と間隙水の分配係数
Cs : 固相の化学物質濃度
Cd : 間隙水中の化学物質濃度
foc : 有機炭素割合(%)
Koc : 有機炭素と水との分配係数(cm3/g org.C)
log Kocは、log Kow(オクタノール-水分配係数)を変数として換算式から算定することができる。換算式としては複数の学説があるが、本報告では、
?PCBのlog Kowの値を主に解析しており、
?諸外国で底質基準値を水質環境基準
値から導出する際に実際に用いられている、下記の式を用いるものとした。
log Koc = 1.03 × log Kow ― 0.61
log Kowの値は、ダイオキシン類の異性体ごとに異なっており、概ね6〜8であるが、本報告では、米Federal Register(1995年3月23日付)に掲載された、栄養連鎖上、濃縮係数が最も大きいとされるlog Kowの数値である6.9を用いるものとする。
log Koc = 6.50
(1)式は下記の様に書くことができる。
( Cs×(1/foc) )/ Cd = Koc (2)
間隙水濃度に水質環境基準値である1pg-TEQ/L(1×10-3pg-TEQ/ml)、有機炭素濃度を5%(同手法を用いる独仏と同じ数値)とし、代入すると、
Cs = 157 pg-TEQ/g
となり、概ね、150pg-TEQ/gとなる。
※ 平成11年度に環境庁が実施した調査結果では、例えば、東京湾の調査地点(20地点)の底質に含まれるダイオキシン類について、異性体ごとに毒性等量換算後の重み付けをして計算したところ、log Kow の数値の範囲は6.9〜7.2であった。
※ 間隙水濃度については、底質からの水への移行のみを考えた場合に水質濃度は底質間隙水濃度を超えないこと、また、底生生物への影響を考慮し、水質環境基準濃度とした。
? 振とう分配試験結果
高濃度のダイオキシン類を含む底質からの、水質への巻き上げ及び溶出の程度を把握するため、平成13年度に環境省において高濃度の底泥の振とう分配試験を実施し、その結果を検討した。
試験対象底泥として、国内の海域及び河川からそれぞれ2検体を採取し、振とう分配試験を行い、試験水中のSS濃度を通常状態まで低減させた場合を計算した。この結果、試験水濃度が水質環境基準である1pg-TEQ/Lに対応する底質濃度の全試験結果の平均値は196pg-TEQ/g であった。
(3)数値
(2)?及び?の結果を比較すると、?の振とう分配試験結果から導出した数値は、?の分配平衡法で導出した値と比較して大きい数値である。
一方、振とう分配試験結果の解析は現時点で得られているデータに基づくものであり、多様な底泥の全てを代表しているとは断言できないことを勘案し、?及び?の結果から、ダイオキシン類の底質環境基準値は150pg-TEQ/g とすることが適当である。
(4)一日摂取量との関係
ダイオキシン類については、食品としての魚介類の許容上限値が定められていないが、他方、国民の平均的なダイオキシン類摂取量については毎年調査が実施されていることから、これらの結果を用いて、本報告で提案する底質環境基準値まで対策を実施した場合の、ダイオキシン類の一日摂取量の試算を行った。
平成12年度におけるダイオキシン類常時監視結果から、底質150pg-TEQ/g 以上の濃度地点について、提案している基準値150pg-TEQ/g まで濃度を低減させた場合、全体の底質濃度の平均値は、計算上、現行の9.6 pg-TEQ/gから7.8pg-TEQ/g となる。
魚介類摂取量のうち、内海魚及び外海魚のダイオキシン類の平均濃度を平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告及び野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告から計算する。
更に、内海魚と外海魚の摂取割合を仮定し、また、内海魚からの摂取量が底質濃度の低減に比して低減すると仮定した場合の、魚介類を経由したダイオキシン類の平均一日摂取量を計算、この結果から、食品経由でのダイオキシン類の平均一日摂取量を推定すると、1.7pg-TEQ/kg/day となる。
※ これらの計算には下記の数値を用いた。
?内海魚及び外海魚平均濃度
平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告における野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告に示された個別食品毎の濃度結果から計算し、内海魚平均2.0pg-TEQ/g、外海魚平均1.2pg-TEQ/g とした。この場合、摂取重量割合を勘案した平均値は1.4pg-TEQ/g となる。
なお、平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告によれば、魚介類からの摂取量は71pg-TEQ/day であり、単純に魚介類一日摂取重量の3カ年平均値でこの数値を除すと、0.74pg-TEQ/g となる。
?内海魚と外海魚の摂取重量割合
内海魚4分の1、外海魚4分の3とした。
?1日魚介類平均摂取量
平成9〜11年国民栄養調査結果から、平均96gとした。
?体重
50kgとした。
?魚介類からのダイオキシン類の摂取割合
平成12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告から、76%とした。
5.適用
ダイオキシン類の底質環境基準については、人の健康の保護という観点から見た場合、間接的に飲料水及び魚介類経由の食物摂取による影響を考慮する必要があることから、他の健康項目同様、河川、湖沼、海域を問わず、全公共用水域に適用することが適当である。
6.達成期間
ダイオキシン類については、多様な経路を経て人体に摂取されるため、環境媒体間における移行による時間的遅れ等の要素を考慮すれば、「可及的速やかにその達成維持に努める」等とすることが適当である。
参考となるパワーポイント底質汚染対策の過去・現在・将来 有害物質に関する基準と底質対策
このパワーポイントは、「環境技術支援ネットワーク」及び「おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会」主催のセミナーで、東京農工大学細見正明教授が2007年に講演されたものです。
http://www.ts-net.or.jp/files/070601_teisitsu.pdf
重金属による底質汚染と重金属底質環境基準のありかた
おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会オフシャルブログより
底生生物が明らかに減少する重金属濃度は下記の通りです。
水 銀:0.15mg/kg
カドミウム:1.2mg/kgを
ク ロ ム:81mg/kg
亜 鉛:150mg/kg
ダイオキシン類:21.5pg-TEQ/g
http://atcwsr.earthblog.jp/e110975.html
== 内容 ==
[[ダイオキシン類]]のみが定められている。
=== ダイオキシン類 ===
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、ダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準である。
* 媒体:水底の底質
* 基準:150pg-TEQ/g以下
* 測定方法:水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
== 底質の環境中の濃度に係るその他の基準 ==
=== 暫定除去基準 ===
「底質暫定除去基準」として水銀とポリ塩化ビフェニル(PCB)が定められている。
=== 水産用水基準による底質の基準 ===
*河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。
*海域では乾泥として化学的酸素要求量(COD)(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること
*微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、[[種苗]]の着生、発生あるいはその発育を妨げないことなどとされている。
*海域では乾泥としてCODOH(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること。
*海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については、水産用水基準の基準値の10倍を下回ること。ただし、カドミウム、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の検出下限値を下回ること。
*ダイオキシン類の濃度は150pgTEQ/gを下回ること。
=== 水底土砂判定基準 ===
環境中の濃度を示すものではないが、浚渫した土砂(底質)を海面[[埋立]]または[[海洋投入]]するにあたって定められている基準として、「水底土砂に係る判定基準」がある。
== 底質の環境基準の必要性 ==
底質汚染は水俣病の事例のように食物連鎖を通してヒトの健康被害が懸念されている。今後、早急に鉛やヒ素などの重金属類やテトラクロロエチレンなどの揮発性有機化合物さらにPOPs農薬などの有害物質に関する底質環境基準を定めることが必要であるとされている。
== 底質の環境中の濃度の評価について ==
=== 土壌環境基準との比較 ===
底質を浚渫して陸上に上げると土壌となる。底質は土壌の一部であるという考え方もあるが、統一されていない。
しかし、底質汚染が土壌汚染と比べて健康リスクは高いが、人の健康の保護に関する水質環境基準に定められている物質について、地下水の水質汚濁に係る環境基準や、土壌の汚染に係る環境基準が定められているのに対し、現在底質の環境基準は定められていない。
なお、土壌の汚染に係る環境基準は、汚染された土壌から地下水等への溶出の観点から上記の溶出量の基準が定められているほか、農作物に対する影響および農作物に蓄積して人の健康に影響を及ぼす観点から含有量の基準が定められている。
ダイオキシン類については、土壌環境基準値が1,000pg-TEQ/gとなっており、底質環境基準値がその15%となっている。
=== 底生生物と有害物質の関係 ===
平成14年に港湾底泥調査が国の機関により実施され、[[重金属]]濃度と[[底生生物]]の種類数との相関関係が公開されている。底生生物の種類が比較的豊富である限界の濃度であるERLの含有量値を下記に示す。
水銀:0.1mg/kg乾泥
カドミウム:1mg/kg乾泥
銅:34mg/kg乾泥
鉛:46.7mg/kg乾泥
ニッケル:20mg/kg乾泥
クロム:80mg/kg乾泥
亜鉛:150mg/kg乾泥
特に、カドミウム・鉛・水銀についてはERLを超過した底質には底生生物が激減することが公開されている。含有量値と溶出量値との明確な相関関係は認められないが、底生生物が水生生物と同程度の感受性を持ち、エラからの吸収による影響が主体的であれば水産用水基準水質環境基準の近似値が一つの目標となる。
ERL(effects range-low):悪影響があるとした報告例のうち低濃度側から10 パーセンタイル値の濃度(最小影響範囲:底生生物の種類が豊富である限界の濃度)
ERM(effects range-median):悪影響があるとした報告例のうち低濃度側から10 パーセンタイル値の濃度(確実な影響範囲:底生生物がほとんどいない濃度)
ERL以上ERM未満の濃度は潜在影響範囲と呼ばれている。
この手法は底質評価のガイドライン値を提供するものであり、カナダ国家底質ガイドラインおよび、フロリダ州の底質ガイドライン開発の基礎として利用されているほかロサンゼルス・ロングビーチ港で適用されている。
=== 溶出量値 ===
前述したERLにおける含有量値と溶出量値との明確な相関関係は認められないが、底生生物が水生生物と同程度の感受性を持ち、エラからの吸収による影響が主体的であれば水産用水基準(水質環境基準の近似値)が一つの目標となる。
なお、亜鉛の水生生物保全のための環境基準は0.02mg/Lである。|また、河川や港湾の底から地下水へ浸透しているので、地下水の環境基準を基本とした土壌環境基準を底質の環境基準として取り組んでる。
== 外部リンク ==
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準
化学物質と環境(年次報告書)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)
4 . 基準値(1)基本的考え方 底質中ダイオキシン類が人の健康に影響を及ぼす恐れは、魚介類への取り込み並びに底質から水への巻き上げ及び溶出の2つの影響経路からが考えられる。
?魚介類への取り込みを考慮する方式について
ダイオキシン類については国民摂取実態から魚介類を経由した摂取が多いことが既知の事実であり、また、平成11年度に環境庁が行った調査では、底質中ダイオキシン類濃度と魚介類中ダイオキシン類濃度との関係においては、相関係数が小さいながらも有意な正の相関があることが分かっている。
他方、ダイオキシン類については、国民の平均的なダイオキシン類摂取量が耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake。以下「TDI」という。)に比較して小さく、バランスのとれた食事が大切と整理されている。また、食品としての魚介類の許容上限値が定められていない。
このため、現時点では、対策実施のための底質環境基準の設定において、基準値導出に必要な諸条件が不足しており、この観点から数値を設定することは困難な状況にある。
?水への影響を考慮する方式について
底質中ダイオキシン類は、ダイオキシン類の水への供給源(汚染源)となっており、その影響の程度を勘案して設定するという方式については、底泥中の間隙水の濃度に着目して底質濃度を規定する分配平衡法と、実際にダイオキシン類に汚染された底泥を用いて水への振とう分配試験を行い、水質への影響を考慮する方法の2種類がある。
他にも様々な手法が考えられるが、現時点でデータが得られており、算定が可能な手法として、本報告では、これら両者の手法を勘案して環境基準値を設定することとした。
(2)設定手法
?分配平衡法
底質の間隙水中の化学物質濃度は底質の固相における濃度と平衡状態を形成しており、底質固相の濃度は底質の有機物濃度によって変動する。
つまり、平衡条件下にある底質と水との間の化学物質の分配係数は、?固相中濃度と間隙水濃度との比、及び?有機炭素と水との分配係数と、底質の有機炭素の割合との積、の2つの方法で表すことができる。模式的には、下記の(1)式の様に書くことができる。
Kp = Cs / Cd = foc・Koc (1)
Kp : 底質中、固相と間隙水の分配係数
Cs : 固相の化学物質濃度
Cd : 間隙水中の化学物質濃度
foc : 有機炭素割合(%)
Koc : 有機炭素と水との分配係数(cm3/g org.C)
log Kocは、log Kow(オクタノール-水分配係数)を変数として換算式から算定することができる。換算式としては複数の学説があるが、本報告では、
?PCBのlog Kowの値を主に解析しており、
?諸外国で底質基準値を水質環境基準
値から導出する際に実際に用いられている、下記の式を用いるものとした。
log Koc = 1.03 × log Kow ― 0.61
log Kowの値は、ダイオキシン類の異性体ごとに異なっており、概ね6〜8であるが、本報告では、米Federal Register(1995年3月23日付)に掲載された、栄養連鎖上、濃縮係数が最も大きいとされるlog Kowの数値である6.9を用いるものとする。
log Koc = 6.50
(1)式は下記の様に書くことができる。
( Cs×(1/foc) )/ Cd = Koc (2)
間隙水濃度に水質環境基準値である1pg-TEQ/L(1×10-3pg-TEQ/ml)、有機炭素濃度を5%(同手法を用いる独仏と同じ数値)とし、代入すると、
Cs = 157 pg-TEQ/g
となり、概ね、150pg-TEQ/gとなる。
※ 平成11年度に環境庁が実施した調査結果では、例えば、東京湾の調査地点(20地点)の底質に含まれるダイオキシン類について、異性体ごとに毒性等量換算後の重み付けをして計算したところ、log Kow の数値の範囲は6.9〜7.2であった。
※ 間隙水濃度については、底質からの水への移行のみを考えた場合に水質濃度は底質間隙水濃度を超えないこと、また、底生生物への影響を考慮し、水質環境基準濃度とした。
? 振とう分配試験結果
高濃度のダイオキシン類を含む底質からの、水質への巻き上げ及び溶出の程度を把握するため、平成13年度に環境省において高濃度の底泥の振とう分配試験を実施し、その結果を検討した。
試験対象底泥として、国内の海域及び河川からそれぞれ2検体を採取し、振とう分配試験を行い、試験水中のSS濃度を通常状態まで低減させた場合を計算した。この結果、試験水濃度が水質環境基準である1pg-TEQ/Lに対応する底質濃度の全試験結果の平均値は196pg-TEQ/g であった。
(3)数値
(2)?及び?の結果を比較すると、?の振とう分配試験結果から導出した数値は、?の分配平衡法で導出した値と比較して大きい数値である。
一方、振とう分配試験結果の解析は現時点で得られているデータに基づくものであり、多様な底泥の全てを代表しているとは断言できないことを勘案し、?及び?の結果から、ダイオキシン類の底質環境基準値は150pg-TEQ/g とすることが適当である。
(4)一日摂取量との関係
ダイオキシン類については、食品としての魚介類の許容上限値が定められていないが、他方、国民の平均的なダイオキシン類摂取量については毎年調査が実施されていることから、これらの結果を用いて、本報告で提案する底質環境基準値まで対策を実施した場合の、ダイオキシン類の一日摂取量の試算を行った。
平成12年度におけるダイオキシン類常時監視結果から、底質150pg-TEQ/g 以上の濃度地点について、提案している基準値150pg-TEQ/g まで濃度を低減させた場合、全体の底質濃度の平均値は、計算上、現行の9.6 pg-TEQ/gから7.8pg-TEQ/g となる。
魚介類摂取量のうち、内海魚及び外海魚のダイオキシン類の平均濃度を平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告及び野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告から計算する。
更に、内海魚と外海魚の摂取割合を仮定し、また、内海魚からの摂取量が底質濃度の低減に比して低減すると仮定した場合の、魚介類を経由したダイオキシン類の平均一日摂取量を計算、この結果から、食品経由でのダイオキシン類の平均一日摂取量を推定すると、1.7pg-TEQ/kg/day となる。
※ これらの計算には下記の数値を用いた。
?内海魚及び外海魚平均濃度
平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告における野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告に示された個別食品毎の濃度結果から計算し、内海魚平均2.0pg-TEQ/g、外海魚平均1.2pg-TEQ/g とした。この場合、摂取重量割合を勘案した平均値は1.4pg-TEQ/g となる。
なお、平成10〜12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告によれば、魚介類からの摂取量は71pg-TEQ/day であり、単純に魚介類一日摂取重量の3カ年平均値でこの数値を除すと、0.74pg-TEQ/g となる。
?内海魚と外海魚の摂取重量割合
内海魚4分の1、外海魚4分の3とした。
?1日魚介類平均摂取量
平成9〜11年国民栄養調査結果から、平均96gとした。
?体重
50kgとした。
?魚介類からのダイオキシン類の摂取割合
平成12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告から、76%とした。
5.適用
ダイオキシン類の底質環境基準については、人の健康の保護という観点から見た場合、間接的に飲料水及び魚介類経由の食物摂取による影響を考慮する必要があることから、他の健康項目同様、河川、湖沼、海域を問わず、全公共用水域に適用することが適当である。
6.達成期間
ダイオキシン類については、多様な経路を経て人体に摂取されるため、環境媒体間における移行による時間的遅れ等の要素を考慮すれば、「可及的速やかにその達成維持に努める」等とすることが適当である。
参考となるパワーポイント底質汚染対策の過去・現在・将来 有害物質に関する基準と底質対策
このパワーポイントは、「環境技術支援ネットワーク」及び「おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会」主催のセミナーで、東京農工大学細見正明教授が2007年に講演されたものです。
http://www.ts-net.or.jp/files/070601_teisitsu.pdf
重金属による底質汚染と重金属底質環境基準のありかた
おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会オフシャルブログより
底生生物が明らかに減少する重金属濃度は下記の通りです。
水 銀:0.15mg/kg
カドミウム:1.2mg/kgを
ク ロ ム:81mg/kg
亜 鉛:150mg/kg
ダイオキシン類:21.5pg-TEQ/g
http://atcwsr.earthblog.jp/e110975.html
2009年10月25日
底質暫定除去基準''
'''底質暫定除去基準'''(ていしつざんていじょきょきじゅん)は、1975年(昭和50年)に定められた、水銀及びポリ塩化ビフェニル(PCB) に汚染された底質を除去する範囲を定める場合の基準である。
== 調査方法 ==
調査の方法は、「底質調査方法」[http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000178 底質方法の改定について ](昭和63年9月8日付け環水管第127号)に基づく。
底質を除去する範囲を定める調査の方法は、「底質調査方法」に基づき、メッシュの通常4つの交点の測定値の平均値を当該メッシュ内の平均濃度として考える。
== 基準値 ==
水銀及びポリ塩化ビフェニル (PCB)について、定められている。
===水銀===
水銀を含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、海域においては次式により算出した値(C)以上、河川及び湖沼においては25ppm以上である。
ただし、潮汐の影響を強く受ける河口部においては海域に準じ、沿岸流の強い海域においては河川及び湖沼に準ずるとされる。
:C=0.18・(△H/J)・(1/S) (ppm)
:*△H=平均潮差(m)
:*J=溶出率
:*S=安全率
*平均潮差△H(m)は、当該水域の平均潮差とする。ただし、潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては、平均潮差に代えて次式によって算出した値とする。
:△H=副振動の平均振幅(m)×(12×60(分))/(平均周期(分))
*溶出率Jは、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる四地点以上の底質について、「底質調査方法」の溶出試験により溶出率を求め、その平均値を当該水域の底質の溶出率とする。
*安全率Sは、当該水域及びその周辺の漁業の実態に応じて、次の区分により定めた数値とする。なお、地域の食習慣等の特殊事情に応じて安全率を更に見込むことは差し支えない。
**漁業が行われていない水域においては、10とする。
**漁業が行われている水域で、底質及び底質に付着している生物を摂取する魚介類(エビ、カニ、シャコ、ナマコ、ボラ、巻貝類等)の漁獲量の総漁獲量に対する割合が、おおむね2分の1以下である水域においては50、おおむね2分の1を超える水域においては100とする。
<単位>
10 ppm = 10 mg/kg
- *土壌の環境基準値は溶出量値として、総水銀は0.0005mg/L以下であり、アルキル水銀は「検液中に検出されないこと」である。
- *土壌汚染対策法における指定基準は含有量として、土壌1kgにつき15mg以下となっている。ただし、土壌汚染対策法における試験方法が真水を使うのに対し、底質調査法は強酸を使用して試料に含まれる水銀を分析するので単純に比較できない。なお、土壌汚染対策法の分析方法は底質調査法より数分の1の値しかでないことが知られている。
- *海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律による水底土砂の判定基準は「水銀又はその化合物」の溶出量値は銀0.005mg/L以下である。
===PCB===
PCBを含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、10ppm以上である。
==他の基準値との比較==
===水銀===
25ppmは、25mg/kgとも表記できる。
*土壌の環境基準において、溶出量値として、総水銀は0.0005mg/L以下であり、アルキル水銀は「検液中に検出されないこと」である。
*土壌汚染対策法における指定基準は含有量として、土壌1kgにつき15mg以下となっている。ただし、土壌汚染対策法における試験方法が真水を使うのに対し、底質調査法は強酸を使用して試料に含まれる水銀を分析するので単純には比較できない。なお、土壌汚染対策法の分析方法は底質調査法より数分の1の値しかでないことが知られている。
*海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律による水底土砂に係る判定基準において、「水銀又はその化合物」の溶出量値は銀0.005mg/L以下である。
===PCB===
10ppmは10mg/kg、10,000,000pg/gとも表記できる。
PCBのうち、コプラナーPCB(塩素原子が分子の外側を向き平面状分子となっているもの、一般のPCBに比べて毒性が高い。)はダイオキシン類の一部に分類されている。
現在のダイオキシン類の底質環境基準は150 pg-TEQ/gであり、10ppm(=10,000,000pg/g)と大きな差があるように見えるが、対象となる物質が異なるとともに分析方法や毒性等量|毒性等価係数等の差コプラナーPCBの毒性等価係数(TEF)は、0.1〜0.00003である。[http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/mamoru/kanshi/dioxin/tef.html 横浜市 環境創造局 環境監視センター :毒性等価係数(TEF)]があることから単純には比較できない。
底質の環境中におけるPCBとダイオキシンの濃度について、PCBについては平成19年度版「化学物質と環境」[http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/ 「化学物質と環境」]によれば、平成18年度の各調査地点の年間平均値が36〜670,000pg/g-dry、その幾何平均値が7,600pg/g-dryであり、ダイオキシン類については[[ダイオキシン法]]に基づくモニタリングデータ[http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h20/html/hj08020503.html#n2_5_3_3 平成20年版環境白書]によれば平成18年の各調査地点の年間平均値は0.056〜750pg-TEQ/g、その幾何平均値が6.7pg-TEQ/gとなっている。
PCB濃度が2ppmを超過すると多くの場合で、ダイオキシン類濃度が150pg-TEQ/gを超過することを各河川・港湾管理者が公開している。
10 ppm = 10 mg/kg = 10,000,000 pg/g
- PCBのうち、コプラナーPCB(塩素原子が分子の外側を向き平面状分子となっているもの、一般のPCBに比べて毒性が高い。)はダイオキシン類の一部に分類されている。現在のダイオキシン類の底質環境基準は150 pg-TEQ/gである。分析方法や毒性等価係数等の差はあるにしても上記のように、本基準は現在のダイオキシン類底質環境基準を大きく離れている。
== 外部リンク ==
底質の暫定除去基準について]
環境基準について(環境省)]
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)]
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第18号)]
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第19号)]
要調査項目について(環境省)
== 調査方法 ==
調査の方法は、「底質調査方法」[http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000178 底質方法の改定について ](昭和63年9月8日付け環水管第127号)に基づく。
底質を除去する範囲を定める調査の方法は、「底質調査方法」に基づき、メッシュの通常4つの交点の測定値の平均値を当該メッシュ内の平均濃度として考える。
== 基準値 ==
水銀及びポリ塩化ビフェニル (PCB)について、定められている。
===水銀===
水銀を含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、海域においては次式により算出した値(C)以上、河川及び湖沼においては25ppm以上である。
ただし、潮汐の影響を強く受ける河口部においては海域に準じ、沿岸流の強い海域においては河川及び湖沼に準ずるとされる。
:C=0.18・(△H/J)・(1/S) (ppm)
:*△H=平均潮差(m)
:*J=溶出率
:*S=安全率
*平均潮差△H(m)は、当該水域の平均潮差とする。ただし、潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては、平均潮差に代えて次式によって算出した値とする。
:△H=副振動の平均振幅(m)×(12×60(分))/(平均周期(分))
*溶出率Jは、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる四地点以上の底質について、「底質調査方法」の溶出試験により溶出率を求め、その平均値を当該水域の底質の溶出率とする。
*安全率Sは、当該水域及びその周辺の漁業の実態に応じて、次の区分により定めた数値とする。なお、地域の食習慣等の特殊事情に応じて安全率を更に見込むことは差し支えない。
**漁業が行われていない水域においては、10とする。
**漁業が行われている水域で、底質及び底質に付着している生物を摂取する魚介類(エビ、カニ、シャコ、ナマコ、ボラ、巻貝類等)の漁獲量の総漁獲量に対する割合が、おおむね2分の1以下である水域においては50、おおむね2分の1を超える水域においては100とする。
<単位>
10 ppm = 10 mg/kg
- *土壌の環境基準値は溶出量値として、総水銀は0.0005mg/L以下であり、アルキル水銀は「検液中に検出されないこと」である。
- *土壌汚染対策法における指定基準は含有量として、土壌1kgにつき15mg以下となっている。ただし、土壌汚染対策法における試験方法が真水を使うのに対し、底質調査法は強酸を使用して試料に含まれる水銀を分析するので単純に比較できない。なお、土壌汚染対策法の分析方法は底質調査法より数分の1の値しかでないことが知られている。
- *海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律による水底土砂の判定基準は「水銀又はその化合物」の溶出量値は銀0.005mg/L以下である。
===PCB===
PCBを含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、10ppm以上である。
==他の基準値との比較==
===水銀===
25ppmは、25mg/kgとも表記できる。
*土壌の環境基準において、溶出量値として、総水銀は0.0005mg/L以下であり、アルキル水銀は「検液中に検出されないこと」である。
*土壌汚染対策法における指定基準は含有量として、土壌1kgにつき15mg以下となっている。ただし、土壌汚染対策法における試験方法が真水を使うのに対し、底質調査法は強酸を使用して試料に含まれる水銀を分析するので単純には比較できない。なお、土壌汚染対策法の分析方法は底質調査法より数分の1の値しかでないことが知られている。
*海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律による水底土砂に係る判定基準において、「水銀又はその化合物」の溶出量値は銀0.005mg/L以下である。
===PCB===
10ppmは10mg/kg、10,000,000pg/gとも表記できる。
PCBのうち、コプラナーPCB(塩素原子が分子の外側を向き平面状分子となっているもの、一般のPCBに比べて毒性が高い。)はダイオキシン類の一部に分類されている。
現在のダイオキシン類の底質環境基準は150 pg-TEQ/gであり、10ppm(=10,000,000pg/g)と大きな差があるように見えるが、対象となる物質が異なるとともに分析方法や毒性等量|毒性等価係数等の差コプラナーPCBの毒性等価係数(TEF)は、0.1〜0.00003である。[http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/mamoru/kanshi/dioxin/tef.html 横浜市 環境創造局 環境監視センター :毒性等価係数(TEF)]があることから単純には比較できない。
底質の環境中におけるPCBとダイオキシンの濃度について、PCBについては平成19年度版「化学物質と環境」[http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/ 「化学物質と環境」]によれば、平成18年度の各調査地点の年間平均値が36〜670,000pg/g-dry、その幾何平均値が7,600pg/g-dryであり、ダイオキシン類については[[ダイオキシン法]]に基づくモニタリングデータ[http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h20/html/hj08020503.html#n2_5_3_3 平成20年版環境白書]によれば平成18年の各調査地点の年間平均値は0.056〜750pg-TEQ/g、その幾何平均値が6.7pg-TEQ/gとなっている。
PCB濃度が2ppmを超過すると多くの場合で、ダイオキシン類濃度が150pg-TEQ/gを超過することを各河川・港湾管理者が公開している。
10 ppm = 10 mg/kg = 10,000,000 pg/g
- PCBのうち、コプラナーPCB(塩素原子が分子の外側を向き平面状分子となっているもの、一般のPCBに比べて毒性が高い。)はダイオキシン類の一部に分類されている。現在のダイオキシン類の底質環境基準は150 pg-TEQ/gである。分析方法や毒性等価係数等の差はあるにしても上記のように、本基準は現在のダイオキシン類底質環境基準を大きく離れている。
== 外部リンク ==
底質の暫定除去基準について]
環境基準について(環境省)]
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)]
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第18号)]
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第19号)]
要調査項目について(環境省)
2009年10月25日
工事中:(Wikipedia)より詳しく正確な底質汚染
底質汚染
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に加筆訂正

底質汚染(ていしつおせん)とは底質が汚染されていることをいう。底質とは海域、港湾、河川、水路、湖沼などの水底の土砂やヘドロ等のことである。狭義には底質の環境基準はダイオキシン類のみ(150pg-TEQ/g)が定められておりこの基準を超過するもの(詳しくは底質の環境基準を参照)のこと。 なお、PCBや水銀には底質暫定除去基準が定められており、対策は一旦行われた水域もあるが、依然として環境基準を大きく超過する底質が大量に存在している。
目次
1 概要
2 各地での底質汚染の取組み
3 各省庁の底質汚染の取組み
4 汚染原因の特定
5 浚渫土問題
6 水底ゴミ問題
7 底質浄化費用負担
8 法的規制
9 底質汚染の取組の歴史
10 出典
11 参照資料
12 関連項目
13 外部リンク
13.1 国土交通省
13.2 環境省
13.3 地方自治体
13.4 その他
13.5 関係法令
概要
環境白書に底質についての言及が現れたのは昭和46年版公害白書であり、それまでは典型公害として、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭の6種を公害の対象として捕らえていたが、冷却用水等による温排水問題やヘドロ問題に対処すれる為に「水底の底質の悪化」を公害の対象として認識するようになった。
ここで言う「ヘドロ問題」とは東京湾、大阪湾、田子の浦港、洞海湾、伊予三島港のヘドロである。問題にしているのはCOD(生物の大量死)や硫化物量(悪臭)が主であるが、東京湾と洞海湾ではカドミウム、クロム、水銀、鉛なども底質中に検出されているが、この頃は生物の大量死や藻類の異常繁茂が問題視されていた為、底質の多量の有機物に注目が集まっていた。
第2-2-11表ヘドロ問題発生主要水域のヘドロ状況(註昭和46年当時)
地域 測定年度 COD 硫化物 カドミウム クロム 全水銀 鉛
東京湾(鶴見付近) 昭和45 6.2mg/g - 0.009mg/g 0.01mg/g 0.018mg/g 0.25mg/g
東京湾(横浜本牧付近) 昭和45 4.9mg/g - 0.001mg/g 0.006mg/g 0.023mg/g 0.03mg/g
大阪湾(大坂港口) 昭和42 18.9mg/g 1.3mg/g - - - -
大阪湾(神戸港沖) 昭和42 25.2mg/g 0.3mg/g - - - -
田子の浦港 昭和44 11.4mg/g 2.1mg/g - - - -
洞海湾(湾口) 昭和44 16.4mg/g - 0.012mg/g 0.055mg/g - -
洞海湾(湾奥) 昭和44 21.6mg/g - 0.122mg/g 0.051mg/g - -
伊予三島港 昭和39 13.6mg/g 0.6mg/g - - - -
1972年(昭和47年)に初めて底質のPCB汚染の実態調査が全国1,445地点において実施されたその結果工場近接水域の4箇所については水質で0.011ppm以上底質で500ppm以上のPCBを検出し「PCB取扱い工場周辺の公共用水域の底質がかなり汚染されていることが明らかになった。」と環境白書では総括している。[3]
1970年(昭和45年)12月に「公害防止事業費事業者負担法」が制定され、1971年(昭和46年)5月10日から施行されている。5年後の1975年(昭和50年)2月末までにこの法律に従い静岡県・田子の浦湾(有機物堆積汚泥浚渫)、福岡県・中の川水系(PCB含有堆積汚泥浚渫)などの総計17件の底質汚染防止対策事業が実施されることとなる。[4]
この様に底質汚染除去事業が開始され、水銀に係る底質汚染については48年度底質調査では27水域で暫定除去基準値を超えたものが昭和49 - 52年度では暫定除去基準値を超える水域は42水域中7水域に減少した。PCBに係る底質汚染については昭和47 - 52年度の調査で除去等の対策を講じる必要がある69水域中54水域の除去事業が完了することになる。[5]
その約十年後の1987年(昭和62年)には水銀による底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある42水域中41水域が事業を完了し、PCBによる底質汚染底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある71水域はすべて事業を完了している[6]。
ダイオキシン類についての底質汚染は昭和62年度の調査よりモニタリングが開始され、低濃度ではあるが0.001 - 0.006ppbの2,3,7,8-TCDFが18箇の検体より検出されている。[7]約十年後の平成11年版環境白書においても「海、川、湖の底質、生物についてもこれまで10年以上にわたって毎年調査しているが、ダイオキシン類濃度に特段大きな変化は認められない。
しかし、環境中から広く検出されており、引き続き調査が必要である。」と環境白書で総括されている[8]その後平成14年度にダイオキシン類の環境基準を変更し、底質ダイオキシン類については757地点中18点で環境基準(150pg-TEQ/g)を超えることとなった。(平均11pg-TEQ/g)[9]
各地での底質汚染の取組み
2007年の国土交通省の発表によると汚染土量が把握されているのは7港湾であり、1港湾当たりの汚染土量の頻度分布を1港湾当たりの汚染土量は250,000m3 以下が3港湾と最も多く、250,000m3超が4港湾とされている。-*具体的な港名、汚染面積、汚染体積、汚染濃度を下記の通り公開している。
- **千葉港 、140ha、1,700千m3、〜15,000pg-TEQ/g
- **伏木富山港、41ha、 286千m3、〜10,000pg-TEQ/g
- **大阪港 、56ha、 925千m3、〜 7,200pg-TEQ/g
- **東京港 、0.7ha、 4.5千m3、〜 280pg-TEQ/g
- **田子の浦港、35ha、 542千m3、〜 3,600pg-TEQ/g
- **水俣港 、0.3ha、 12千m3、〜 920pg-TEQ/g
- **宇部港 、0.4ha、 5.6千m3、〜 2,700pg-TEQ/g

以下に各地の取組み状況を示す。
埼玉県:古綾瀬川において委員会を組織し取り組んでいる。
千葉県:市原港で高濃度の底質ダイオキシン類 (15,000pg-TEQ/g) の公開すると共に、汚染原因特定についても取り組んでいる。
東京都:横十軒川や隅田川河口部などの底質汚染について対策がなされている。水銀やダイオキシン類による食品汚染調査結果を公開している。豊洲貯木場でダイオキシン類による底質汚染が検出され屋形船係留施設の計画を変更した。
横浜市:横浜港などの底質汚染について対策が検討されている。
静岡県富士市[田子の浦港]底質(ダイオキシン類)浄化対策事業を港管理事務所が中心となって取り組んでいる。
京都府:「舞鶴引揚記念館周辺地域における環境問題専門家会議」で舞鶴湾の底質について議論し、鉛溶出量が0.1mg/L以上の範囲の対策として、浚渫及び覆砂を行うことが適当であるとし公開されている。また阿蘇海においても取り組んでいる。
大阪府:神崎川など大阪府が管理する河川について委員会を組織して取り組んでおり、公害防止事業費事業者負担法に従い三箇牧水路の汚染対策費用を汚染原因者が負担する計画を作成した。

大阪市:市内河川の底質汚染についてデータを公開し取り組んでいる。また、港湾部についても調査を進めている。
神戸市:遠矢浜北側水域の底質におけるダイオキシン類の環境基準超過について委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。また、2008年から浚渫だけでなく無害化処理等の無害化を含めた浄化対策を行っている。
高砂市:高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。
島根県:馬潟団地に周辺水路において委員会を組織して、公害防止事業費事業者負担法を適用し取り組んでいる。
北九州市:洞海湾の底質汚染について取り組んでいる。
環境省の発表では底質ダイオキシン類の検出は年を経るごとに減少し、平成17年度の調査[10]によると底質のダイオキシン類で環境基準150pg-TEQ/gを超えている地点は下記の6か所であったとされている。
東京都:横十間川 280pg-TEQ/g
大阪府:六軒家川 320pg-TEQ/g、木津川運河 190pg-TEQ/g、神崎川 510pg-TEQ/g、古川 300pg-TEQ/g
和歌山県・和歌山下津港 160pg-TEQ/g
しかしながら、各自治体は独自に底質ダイオキシン類濃度を測定しており、環境省が発表した値より高濃度の底質汚染があることをホームページで公表している。
千葉県市原市市原港 12,000pg-TEQ/g(2001年6月)
東京都・横十間川 19,000pg-TEQ/g(公表2004年9月)
大阪府
古川 25,000pg-TEQ/g(公表2008年2月 門真第八水路)
木津川運河 7,200pg-TEQ/g(2006年6月)
神崎川 7,000pg-TEQ/g(糸田川合流点左岸)
三箇牧水路 44,000pg-TEQ/g(2005年11月)
和歌山県・和歌山下津港 1,800pg-TEQ/g(2004年9月)
島根県馬潟工業団地 7,000pg-TEQ/g(2008年4月)
福岡県北九州市洞海湾 4,600pg-TEQ/g(2005年11月)
浄化対策は多額の費用を要するので余り進んでいないが、試験施工等が実施されていることが公表されている。
各省庁の底質汚染の取組み
環境省:
底質の環境基準や底質汚染の状況を調査をしている。
国土交通省:
監視マニュアルや対策マニュアルを作成している。北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所が実証実験をして底質ダイオキシン類無害化に関するデーターをまとめている。本省河川局河川環境課は底質のダイオキシン類対策技術資料集を2007年にとりまとめた。また、鶴見川遊水地でも無害化の取り組みが進んでいる。
独立行政法人港湾空港技術研究所などが底生生物と有害金属の相関関係のデーターを整理し発表している。
農林水産省:
魚介類に含まれる水銀やダイオキシン類について資料を公開している。
厚生労働省:
魚介類等に含まれる水銀について資料を公開している。
汚染原因の特定
ダイオキシン類の総毒性等量のみ議論だけでなく、ダイオキシン類の異性体パターンやケミカルマスバランス等の環境鑑識学の発展によりにより汚染物質の同定や汚染原因者の寄与率算定により汚染原因者に対し、公害防止事業費事業者負担法に従い、合法的な汚染原因者費用負担額が算定され鳥取県の中海地域の企業が応分の費用負担に応じている。
浚渫土問題
底質暫定除去基準によりPCBや水銀が高濃度で含まれている水域の浚渫が過去に実施された。その浚渫土は無害化されずに仮置きされたり、埋立てに利用されている。
環境リスクや人の健康被害防止の観点から十分な検討が必要であり、例えば、兵庫県高砂市では学識経験者等による検討会を開催し議論が進んでいる。
水底ゴミ問題
水底には多くのゴミがあり、特に瀬戸内海や東京湾・大阪湾・伊勢湾等の閉鎖性海域には多く沈んでいる。水底ゴミは水底環境を悪化させるだけでなく底質汚染対策の妨げにもなっている。
底質浄化費用負担
底質汚染の浄化には多額の費用が必要となる。公害防止事業費事業者負担法により汚染原因者がその費用を負担することになる事例が増えている。近年では島根県の馬潟工業団地付近において廃棄物処理業者等が費用を負担している。
法的規制
永年の不要な物質や有害物質の蓄積である底質汚染には多くの法規制が適用されることになる。まず、ダイオキシン類の底質環境基準が挙げられる。ダイオキシン類対策特別措置法により都道府県知事は底質等に含まれるダイオキシン類を測定し基準を超過している場合は浄化計画を策定し措置する義務があり対策に取り組んでいる地域がある。
なお、水質に定められているように人の健康被害に関する環境基準に定める水銀・鉛・ヒ素・シアン・六価クロムなどの有害物質に関する底質環境基準は定められていないが、地下水汚染リスクや浚渫後の土壌汚染の観点から土壌環境基準を援用することが多い。
水質汚濁防止法や海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律さらに廃棄物処理法が汚染原因者に対して適用されるべきであるが、現場確認や時効の問題もあり適用される事例は多くない。しかし、汚染者負担原則から公害防止事業費事業者負担法により汚染原因者に応分の負担を求める事例が増えている。なお、外部リンク欄に関係法規制を示す。
底質汚染の取組の歴史
2008年
11月 大阪府が「三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について」(部会報告)をとりまとめる
5月 国土交通省が「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」を改訂
2007年
横須賀で底質汚染等を理由とする浚渫工事の差止裁判が提訴される
11月北九州市港湾空港局が洞海湾の底質ダイオキシン類汚染を発表(濃度:環境基準の30倍 体積:62,000m3)。
9月 大阪府が三箇牧水路底質汚染対策を一旦完了し報告書をとりまとめ
3月 国土交通省の河川環境課が「底質のダイオキシン類対策技術資料集」をとりまとめ
3月 国土交通省が「底質ダイオキシン類対策検討調査報告書」と「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」をとりまとめ
2006年
水俣病公式確認50年を迎える
2005年
河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)改定
国土交通省の新潟港湾空港技術調査事務所が底質ダイオキシン類分解無害化処理技術]をとりまとめ
2004年
国土交通省が河川、湖沼等における底質ダイオキシン類簡易測定マニュアル(案)をとりまとめ
国土交通省が「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル」(案)
「市原港」で高濃度(12,000pg-TEQ/g)のダイオキシン類が検出され、「市原港」全域にダイオキシン類による高濃度汚染の確認
2002年
7月 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準が施行される
6月 中央環境審議会、ダイオキシン類の底質環境基準値を答申
2000年
ダイオキシン対策特別措置法施行規則及びダイオキシン類による水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準施行
ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル
1998年 古綾瀬川松江新橋地点の底質から過去最高濃度(当時)の720[pg-TEQ/g]が検出
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行
1995年東京湾内の浦賀港内において住友重機械工業がおこなった浚渫工事において多額の漁業被害発生
1979年 酒田港、徳島湾、大江川、水俣湾、敦賀港、高砂西港等において底質の除去等の対策を実施
1975年
底質暫定除去基準
1974年
水銀やPCB等に汚染された高砂本港、北九州市洞海湾、岩国市の地先海域等における汚でいの浚渫(しゅんせつ)作業の実施
1973年
瀬戸内海環境保全特別措置法の制定
1970年
水質汚濁防止法の制定
田子の浦ヘドロ公害で富士市住民が製紙会社と静岡県知事を告発
1969年
全国的にも汚濁の著しい東京都の隅田川、大阪市の神崎川、名古屋市の堀川、福岡市の御笠川、尼崎市の庄下川、横浜市の帷子川、和歌山市の和歌川のしゅんせつの実施
出典
^ 「第4章 第4節 1 公害対策の進展」『昭和46年版公害白書』総理府・厚生省
^ 「第2章 水質汚濁 第3節 最近における水質汚濁の新しい問題 2 ヘドロ問題」『昭和46年版公害白書』総理府・厚生省
^ 「第4章 第7節 2 PCB汚染対策」『昭和48年版環境白書』環境庁
^ 「第9章 第4節 公害防止事業費の事業者負担」『昭和50年版環境白書』環境庁
^ 「第3章 第3節 9 水銀、PCBによる底質除去対策」『昭和55年版環境白書』環境庁
^ 「第3章 第3節 7 水銀、PCBによる汚染底質除去対策」『昭和50年版環境白書』環境庁
^ 「第1-1-18表ダイオキシン類による環境汚染状況(昭和62年度)」「第1章 第1節 9 化学物質」『平成元年版環境白書』環境庁
^ 「第2章 第2節 3 ダイオキシン問題について」『平成11年版環境白書』環境庁
^ 「表5-3-1平成14年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(モニタリングデータ)(概要)」「第5章 第3節 3 ダイオキシン類問題への取組」『平成16年版 環境白書』環境省
^ 平成17年度ダイオキシン類に係る環境調査結果PDF 環境省
参照資料
環境白書〈環境庁、環境省〉
公害白書〈総務庁、環境庁〉
参考文献
国土交通省
「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂(2008年5月)
「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」のとりまとめについて(2007年7月)
底質ダイオキシン類対策検討調査報告書(2007年3月 国土交通省 港湾局)
底質ダイオキシン類対策の基本的考え方(2007年3月 国土交通省)
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年)
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年5月修正国土交通省)
浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針 資料(2006年国土交通省)
河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)(2005年3月国土交通省)
「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂について(2003年12月国土交通省)
新潟港湾空港技術調査事務所 底質ダイオキシン類分解無害化処理技術
環境省
ダイオキシン類の水底の底質等の汚染に係る環境基準
底質の暫定除去基準
環境基準について(環境省)
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)
要調査項目について(環境省)
化学物質と環境(年次報告書)
環境基準について(環境省)
地方自治体
東京都横十間川の底質のダイオキシン類対策
古綾瀬川の底質ダイオキシン類汚染対策について(埼玉県)
阿蘇海環境づくり協働会議(京都府)
大阪府河川底質浄化対策
大阪府三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について
大阪府三箇牧水路底質汚染に関する検討結果報告書
島根県馬潟工業団地周辺ダイオキシン類対策
その他
東京都臨海域における埋立地造成の歴史
日本の地球化学図(産業技術総合研究所)
関係法令
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁( 水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5 条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令
底質の処理・処分等に関する指針について

底質汚染文法
'''底質汚染'''(ていしつおせん)とは底質が汚染されていることをいう。底質とは海域、港湾、河川、水路、湖沼などの水底の土砂やヘドロ等のことである。狭義には底質の環境基準はダイオキシン類のみ(150pg-毒性等量TEQ/g)が定められておりこの基準を超過するもの(詳しくは底質の環境基準を参照)のこと。 なお、ポリ塩化ビフェニル(PCB)や水銀には底質暫定除去基準が定められており、対策は一旦行われた水域もある。
== 概要 ==
環境白書に底質についての言及が現れたのは昭和46年版公害白書であり、それまでは典型公害として、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭の6種を公害の対象として捕らえていたが、冷却用水等による温排水問題やヘドロ問題に対処すれる為に「水底の底質の悪化」を公害の対象として認識するようになった。
「第4章 第4節 1 公害対策の進展」『昭和46年版公害白書』総理府・厚生省>ここで言う「ヘドロ問題」とは東京湾、大阪湾、田子の浦(|田子の浦港)、洞海湾、伊予三島市(伊予三島港)のヘドロである。問題にしているのは化学的酸素要求量(COD)(生物の大量死)や硫化物量(悪臭)が主であるが、東京湾と洞海湾ではカドミウム、クロム、水銀、鉛なども底質中に検出されているが、この頃は生物の大量死や藻類の異常繁茂が問題視されていた為、底質の多量の有機物に注目が集まっていた。
{
{{和暦|s|47}}に初めて底質の[[PCB]]汚染の実態調査が全国1,445地点において実施されたその結果工場近接水域の4箇所については水質で0.011ppm以上底質で500ppm以上のPCBを検出し「PCB取扱い工場周辺の公共用水域の底質がかなり汚染されていることが明らかになった。」と[[環境白書]]では総括している。「第4章 第7節 2 PCB汚染対策」『昭和48年版環境白書』環境庁
{{和暦|s|45}}12月に「[[公害防止事業費事業者負担法]]」が制定され、{{和暦|s|46}}5月10日から施行されている。5年後の{{和暦|s|50}}2月末までにこの法律に従い静岡県・田子の浦湾(有機物堆積汚泥浚渫)、福岡県・中の川水系(PCB含有堆積汚泥浚渫)などの総計17件の底質汚染防止対策事業が実施されることとなる。「第9章 第4節 公害防止事業費の事業者負担」『昭和50年版環境白書』環境庁
この様に底質汚染除去事業が開始され、水銀に係る底質汚染については48年度底質調査では27水域で暫定除去基準値を超えたものが昭和49 - 52年度では暫定除去基準値を超える水域は42水域中7水域に減少した。PCBに係る底質汚染については昭和47 - 52年度の調査で除去等の対策を講じる必要がある69水域中54水域の除去事業が完了することになる。「第3章 第3節 9 水銀、PCBによる底質除去対策」『昭和55年版環境白書』環境庁その約十年後の{{和暦|s|62}}には水銀による底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある42水域中41水域が事業を完了し、PCBによる底質汚染底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある71水域はすべて事業を完了している「第3章 第3節 7 水銀、PCBによる汚染底質除去対策」『昭和50年版環境白書』環境庁。
[[ダイオキシン類]]についての底質汚染は昭和62年度の調査よりモニタリングが開始され、低濃度ではあるが0.001 - 0.006ppbの2,3,7,8-TCDFが18箇の検体より検出されている。「第1-1-18表ダイオキシン類による環境汚染状況(昭和62年度)」「第1章 第1節 9 化学物質」『平成元年版環境白書』環境庁約十年後の平成11年版環境白書においても「海、川、湖の底質、生物についてもこれまで10年以上にわたって毎年調査しているが、ダイオキシン類濃度に特段大きな変化は認められない。しかし、環境中から広く検出されており、引き続き調査が必要である。」と環境白書で総括されている「第2章 第2節 3 ダイオキシン問題について」『平成11年版環境白書』環境庁その後平成14年度にダイオキシン類の[[環境基準]]を変更し、底質ダイオキシン類については757地点中18点で環境基準(150pg-TEQ/g)を超えることとなった。(平均11pg-TEQ/g)「表5-3-1平成14年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(モニタリングデータ)(概要)」「第5章 第3節 3 ダイオキシン類問題への取組」『平成16年版 環境白書』環境省
== 各地での底質汚染の取組み ==
2007年の国土交通省の発表によると汚染土量が把握されているのは7港湾であり、1港湾当たりの汚染土量の頻度分布を1港湾当たりの汚染土量は250,000m3 以下が3港湾と最も多く、250,000m3超が4港湾とされている。以下に各地の取組み状況を示す。
* [[埼玉県]]:[[古綾瀬川]]において委員会を組織し取り組んでいる。
* [[千葉県]]:[[市原]]港で高濃度の底質[[ダイオキシン類]] (15,000pg-TEQ/g) の公開すると共に、汚染原因特定についても取り組んでいる。
* [[東京都]]:[[横十軒川]]や[[隅田川]]河口部などの底質汚染について対策がなされている。[[水銀]]や[[ダイオキシン類]]による[[食品汚染]]調査結果を公開している。豊洲貯木場でダイオキシン類による底質汚染が検出され屋形船係留施設の計画を変更した。
* [[横浜市]]:[[横浜港]]などの底質汚染について対策が検討されている。
* [[静岡県]][[富士市]][田子の浦港]底質(ダイオキシン類)浄化対策事業を港管理事務所が中心となって取り組んでいる。
* [[京都府]]:「[[舞鶴引揚記念館]]周辺地域における環境問題専門家会議」で舞鶴湾の底質について議論し、鉛溶出量が0.1mg/L以上の範囲の対策として、浚渫及び覆砂を行うことが適当であるとし公開されている。また阿蘇海においても取り組んでいる。
* [[大阪府]]:[[神崎川]]など[[大阪府]]が管理する[[河川]]について委員会を組織して取り組んでおり、[[公害防止事業費事業者負担法]]に従い三箇牧水路の汚染対策費用を汚染原因者が負担する計画を作成した。
* [[大阪市]]:市内河川の底質汚染についてデータを公開し取り組んでいる。また、[[港湾]]部についても調査を進めている。
* [[神戸市]]:[[遠矢浜]]北側水域の底質におけるダイオキシン類の環境基準超過について委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。また、2008年から浚渫だけでなく無害化処理等の無害化を含めた浄化対策を行っている。
* [[高砂市]]:[[高砂]]西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。
* [[島根県]]:[[馬潟]]団地に周辺水路において委員会を組織して、[[公害防止事業費事業者負担法]]を適用し取り組んでいる。
*[[北九州市]]:[[洞海湾]]の底質汚染について取り組んでいる。
環境省の発表では底質ダイオキシン類の検出は年を経るごとに減少し、平成17年度の調査{{PDFlink|[
http://www.env.go.jp/air/report/h18-08/ap_2.pdf
平成17年度ダイオキシン類に係る環境調査結果]}} 環境省によると底質の[[ダイオキシン類]]で環境基準150pg-TEQ/gを超えている地点は下記の6か所であったとされている。
* [[東京都]]・[[横十間川]] 280pg-TEQ/g
* [[大阪府]]・[[六軒家川]] 320pg-TEQ/g、[[木津川運河]] 190pg-TEQ/g、[[神崎川]] 510pg-TEQ/g、[[古川]] 300pg-TEQ/g
* [[和歌山県]]・[[和歌山下津港]] 160pg-TEQ/g
しかしながら、各自治体は独自に底質ダイオキシン類濃度を測定しており、環境省が発表した値より高濃度の底質汚染があることをホームページで公表している。
* 千葉県市原市市原港 12,000pg-TEQ/g(2001年6月)
* 東京都・[[横十間川]] 19,000pg-TEQ/g(公表2004年9月)
* 大阪府
** 古川 25,000pg-TEQ/g(公表2008年2月 門真第八水路)
** [[木津川運河]] 7,200pg-TEQ/g(2006年6月)
** 神崎川 7,000pg-TEQ/g(糸田川合流点左岸)
** [[三箇牧水路]] 44,000pg-TEQ/g(2005年11月)
* 和歌山県・[[和歌山下津港]] 1,800pg-TEQ/g(2004年9月)
* 島根県馬潟工業団地 7,000pg-TEQ/g(2008年4月)
* 福岡県北九州市洞海湾 4,600pg-TEQ/g(2005年11月)
浄化対策は多額の費用を要するので余り進んでいないが、試験施工等が実施されていることが公表されている。
== 各省庁の底質汚染の取組み ==
* [[環境省]]:底質の[[環境基準]]や底質汚染の状況を調査をしている。
* [[国土交通省]]:監視マニュアルや対策マニュアルを作成している。北陸[[地方整備局]]新潟港湾空港技術調査事務所が実証実験をして底質ダイオキシン類無害化に関するデーターをまとめている。本省[[河川局]]河川環境課は底質のダイオキシン類対策技術資料集を2007年にとりまとめた。また、鶴見川遊水地でも無害化の取り組みが進んでいる。
**独立行政法人港湾空港技術研究所などが底生生物と有害金属の相関関係のデーターを整理し発表している。
* [[農林水産省]]:魚介類に含まれる[[水銀]]や[[ダイオキシン類]]について資料を公開している。
* [[厚生労働省]]:魚介類等に含まれる水銀について資料を公開している。
== 汚染原因の特定 ==
ダイオキシン類の総[[毒性等量]]のみ議論だけでなく、[[ダイオキシン類]]の[[異性体]]パターンや[[ケミカルマスバランス]]等の環境[[鑑識]]学の発展によりにより[[汚染]]物質の[[同定]]や[[汚染]][[原因]]者の[[寄与]]率算定により汚染原因者に対し、[[公害防止事業費事業者負担法]]に従い、合法的な[[汚染]]原因者費用負担額が算定され鳥取県の[[中海]]地域の企業が応分の費用負担に応じている。
== 浚渫土問題 ==
[[底質暫定除去基準]]により[[PCB]]や[[水銀]]が高濃度で含まれている水域の[[浚渫]]が過去に実施された。その浚渫土は無害化されずに仮置きされたり、埋立てに利用されている。
環境リスクや人の[[健康]]被害防止の観点から十分な検討が必要であり、例えば、兵庫県[[高砂市]]では学識経験者等による検討会を開催し議論が進んでいる。
== 水底ゴミ問題 ==
水底には多くのゴミがあり、特に[[瀬戸内海]]や[[東京湾]]・[[大阪湾]]・[[伊勢湾]]等の閉鎖性海域には多く沈んでいる。水底ゴミは水底環境を悪化させるだけでなく底質汚染対策の妨げにもなっている。
== 底質浄化費用負担 ==
底質汚染の浄化には多額の費用が必要となる。[[公害防止事業費事業者負担法]]により[[汚染原因者]]がその費用を負担することになる事例が増えている。近年では[[島根県]]の[[馬潟工業団地]]付近において[[廃棄物]]処理業者等が費用を負担している。
== 法的規制 ==
永年の不要な物質や有害物質の蓄積である底質汚染には多くの法規制が適用されることになる。まず、ダイオキシン類の底質環境基準が挙げられる。[[ダイオキシン類対策特別措置法]]により都道府県知事は底質等に含まれるダイオキシン類を測定し基準を超過している場合は浄化計画を策定し措置する義務があり対策に取り組んでいる地域がある。なお、水質に定められているように人の健康被害に関する[[環境基準]]に定める[[水銀]]・[[鉛]]・[[ヒ素]]・[[シアン]]・[[六価クロム]]などの[[有害物質]]に関する底質環境基準は定められていないが、地下水汚染リスクや浚渫後の土壌汚染の観点から土壌環境基準を援用することが多い。
[[水質汚濁防止法]]や[[海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]]さらに[[廃棄物処理法]]が汚染原因者に対して適用されるべきであるが、現場確認や時効の問題もあり適用される事例は多くない。しかし、[[汚染者負担原則]]から[[公害防止事業費事業者負担法]]により汚染原因者に応分の負担を求める事例が増えている。なお、外部リンク欄に関係法規制を示す。
== 底質汚染の取組の歴史 ==
* [[2008年]]
**11月 大阪府が「三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について」(部会報告)をとりまとめる
**5月 国土交通省が「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」を改訂
* [[2007年]] [[横須賀]]で底質汚染等を理由とする浚渫工事の差止裁判が提訴される
** 11月北九州市港湾空港局が[[洞海湾]]の底質ダイオキシン類汚染を発表(濃度:環境基準の30倍 体積:62,000m3)。
** 9月 大阪府が三箇牧水路底質汚染対策を一旦完了し報告書をとりまとめ
** 3月 国土交通省の河川環境課が「底質のダイオキシン類対策技術資料集」をとりまとめ
** 3月 国土交通省が「底質ダイオキシン類対策検討調査報告書」と「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」をとりまとめ
* [[2006年]] [[水俣病]]公式確認50年を迎える
* [[2005年]] [[河川]]、[[湖沼]]等における[[底質]][[ダイオキシン類]]対策[[マニュアル]](案)改定
* [[2005年]] [[国土交通省]]の新潟[[港湾空港技術調査事務所]]が[[底質]][[ダイオキシン類]]分解無害化処理技術]をとりまとめ
* [[2004年]] 国土交通省が[[河川]]、[[湖沼]]等における[[底質]][[ダイオキシン類]][[簡易測定]][[マニュアル]](案)をとりまとめ
** 国土交通省が「河川、湖沼等におけるダイオキシン類[[常時監視]]マニュアル」(案)
** 「[[市原]]港」で高濃度(12,000pg-TEQ/g)のダイオキシン類が検出され、「市原港」全域に[[ダイオキシン類]]による高濃度汚染の確認

* [[2002年]]
**7月 [[ダイオキシン類対策特別措置法]]に基づく底質環境基準が施行される
**6月 中央環境審議会、ダイオキシン類の底質環境基準値を答申
* [[2000年]]
**ダイオキシン対策特別措置法施行規則及びダイオキシン類による水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準施行
**ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル
* [[1998年]] 古[[綾瀬川]]松江新橋地点の底質から過去最高濃度(当時)の720[pg-[[TEQ]]/g]が検出
** [[ダイオキシン類対策特別措置法]]に基づく[[底質]][[環境基準]]の施行
* [[1995年]]東京湾内の浦賀港内において住友重機械工業がおこなった浚渫工事において多額の漁業被害発生
* [[1979年]] [[酒田港]]、[[徳島湾]]、[[大江川]]、[[水俣湾]]、[[敦賀港]]、[[高砂西港]]等において底質の除去等の対策を実施
* [[1975年]] [[底質暫定除去基準]]
* [[1974年]] [[水銀]]や[[ポリ塩化ビフェニル|PCB]]等に汚染された[[高砂]]本港、[[北九州市]][[洞海湾]]、[[岩国市]]の地先海域等における汚でいの[[浚渫]](しゅんせつ)作業の実施
* [[1973年]] [[瀬戸内海環境保全特別措置法]]の制定
* [[1970年]] [[水質汚濁防止法]]の制定
** [[田子の浦]][[ヘドロ]][[公害]]で[[富士市]]住民が[[製紙会社]]と静岡県知事を告発
* [[1969年]] 全国的にも汚濁の著しい[[東京都]]の[[隅田川]]、[[大阪市]]の[[神崎川]]、[[名古屋市]]の[[堀川]]、福岡市の[[御笠川]]、[[尼崎市]]の[[庄下川]]、[[横浜市]]の[[帷子川]]、和歌山市の[[和歌川]]のしゅんせつの実施
== 出典 ==
== 参照資料 ==
* 環境白書〈環境庁、環境省〉
* 公害白書〈総務庁、環境庁〉
== 関連項目 ==
* [[底質]]、[[ヘドロ]]
* [[底質暫定除去基準]] [[底質の環境基準]]
* [[環境省]] [[国土交通省]]
* [[環境白書]]
* [[公害]]、[[公害病#四大公害病|四大公害病]]
* [[環境法]]、[[環境基本法]]、[[環境基準]]、[[水質汚濁防止法]]、[[土壌汚染対策法]]、 [[ダイオキシン類対策特別措置法]]、 [[海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]]、[[公害防止事業費事業者負担法]]、
* [[汚染者負担原則]]
* [[水質汚染]]、[[大気汚染]]、[[土壌汚染]]、[[地下水汚染]]
* [[環境問題関連の記事一覧]]
* [[環境運動]]
* [[地球環境問題]]
* [[環境学]]
== 外部リンク ==
=== 国土交通省 ===
* [
http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000002.html
「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂(2008年5月)]
* [
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/11/110720_.html
「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」のとりまとめについて(2007年7月)]
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/11/110720/03.pdf
底質ダイオキシン類対策検討調査報告書(2007年3月 国土交通省 港湾局)]}}
link|[http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/11/110720/02.pdf
底質ダイオキシン類対策の基本的考え方(2007年3月 国土交通省)]}}
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/05/050413/02.pdf
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年)]}}
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/river/press/200701_06/070413-1/pdf/070413-1shiryou.pdf
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年5月修正国土交通省)]}}
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/11/110619/02.pdf
浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針 資料(2006年国土交通省)]}}
* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/05/050330_3/02.pdf
河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)(2005年3月国土交通省)]}}
* [
http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/daiokisin.html
「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂について(2003年12月国土交通省)]
* [
http://www.gicho.pa.hrr.mlit.go.jp/gyomu/gijutsu/teidai.html
新潟港湾空港技術調査事務所 底質ダイオキシン類分解無害化処理技術]
=== 環境省 ===
* [
http://www.env.go.jp/kijun/dioxin.html
ダイオキシン類の水底の底質等の汚染に係る環境基準]
* [
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000037
底質の暫定除去基準]
* [
http://www.env.go.jp/kijun/
環境基準について(環境省)]
* [
http://www.env.go.jp/water/impure/kanshi.html
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)]
* [
http://www.env.go.jp/water/chosa/
要調査項目について(環境省)]
* [
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/
化学物質と環境(年次報告書)]
* [
http://www.env.go.jp/kijun/
環境基準について(環境省)]

=== 地方自治体 ===
* [
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kasen/yokoju_dxn/
東京都横十間川の底質のダイオキシン類対策]
* [
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BG00/huruayase/huruayase.html
古綾瀬川の底質ダイオキシン類汚染対策について](埼玉県)
* [
http://www.pref.kyoto.jp/tango/ki-kikaku/1211259080561.html
阿蘇海環境づくり協働会議](京都府)
* [
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/kasen/kankyo/purification/dioxin/index.html
大阪府河川底質浄化対策]
*{{PDFlink|[
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kannosomu/kankyo_singikai/kai/giji/37/2-2.pdf
大阪府三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について]}}
* {{PDFlink|[
http://www.pref.osaka.jp/fumin/doc/houdou_siryou2_17035.pdf
大阪府三箇牧水路底質汚染に関する検討結果報告書]}}
* [
http://www.pref.shimane.lg.jp/environment/kankyo/kankyo/kagaku/
島根県馬潟工業団地周辺ダイオキシン類対策]
=== その他 ===
* {{PDFlink|[
http://www.geog.or.jp/journal/back/pdf113-6/p785-801.pdf
東京都臨海域における埋立地造成の歴史]}}
* [
http://www.gsj.jp/Map/JP/docs/geochemical/geochemical.html
日本の地球化学図]([[産業技術総合研究所]])
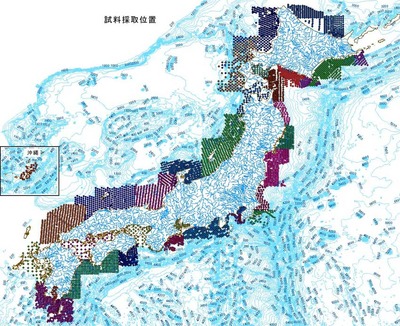

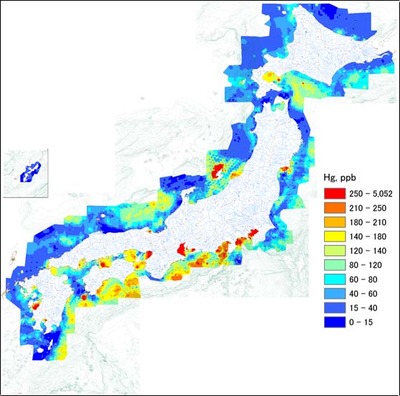
=== 関係法令 ===
* [
http://www.env.go.jp/kijun/dioxin.html
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁( 水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html
ダイオキシン類対策特別措置法]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE433.html
ダイオキシン類対策特別措置法施行令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03101000067.html
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03102004002.html
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO086.html
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO136.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE201.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03901000038.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000006.html
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5 条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03101000038.html
余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令]
* [
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000090
底質の処理・処分等に関する指針について]
{{DEFAULTSORT:ていしつおせん}}
{{sci-stub}}
[[Category:水質汚染]]
ノート:底質汚染提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
底質汚染の中の「各地での底質汚染の取組み」を訂正した方はダイオキシン類の単位も分からず訂正しています。 技術的に極めて稚拙ですので速やかな訂正が必要です。?以上の署名の無いコメントは、60.236.204.155(会話・履歴)さんが 2007年12月9日 (日) 13:12 (UTC) に投稿したものです(青山コロハ 2007年12月9日 (日) 13:14 (UTC)による付記)。
2007年9月18日 (火) 02:34の版 (編集) (取り消し)Dr jimmyで致命的なミスがあります。ダイオキシン類が少し知っている方なら直ぐに分かる初歩的なミスを犯しています。
出展を示しても削除されています。出展は検索すれば直ぐに分かりますがその努力もぜすに底質汚染の書き込みを直ちに削除するのはなぜでしょうか?。底質汚染という不都合な真実を認めたくないのでしょうか。21世紀初頭に生きるヒトは底質汚染に時間やお金を使わなくても一生を終えることができるかもしれませんが、未来の地球はどうでしょうか?「環境は子孫からの預かりも」のでございます。?以上の署名の無いコメントは、211.135.236.251(会話・履歴)さんによるものです。
相変わらずですねぇ。基本方針と記事削除の基準は別物です。無条件に削除するにはWikipedia:削除の方針かWikipedia:即時削除の方針に該当する場合のみです。それ以外は単に執筆者の意見の対立にすぎず、合意なしでは削除の可否は決定されません。したがって、ルールを守らないから消されたのではなく単に消したい人が消しただけの話にすぎないと考えます。--あら金 2008年1月21日 (月) 18:57 (UTC)
ホント相変わらずですねぇ。Wikipedia:削除の方針もWikipedia:即時削除の方針も、ページ・画像の削除に関する方針であり、記事の一部分の削除についての方針ではありません。しかも、無条件でもありません。--Dr.Jimmy 2008年1月22日 (火) 02:14 (UTC)
揚げ足とって申し訳ないんだが、履歴ごと消すのが削除でそれ以外は編集除去。使い分けをきちんとしないと、すれ違うだけです。
また、削除の方針or即時削除の方針に合致するのであれば、無条件で削除対象です。コミュニティの審議を経るのは条件に合致するのかどうかを確認するためで、各方針に合致すれば管理者は削除しなければならないのです。--Kodai99 2008年1月22日 (火) 12:15 (UTC)
Wikipedia:編集方針「記事の一部でも除去するときは、以下の理由に該当するものにしてください。重複 、関係のない内容 、無意味な記述 、著作権侵害 、検証不可能な内容」(註、「検証不可能な内容」を「出典がない」と読み替えた時点ですでに類推である)
Wikipedia:中立的な観点「ある記述が偏った見方から書かれているという事実だけでは、その記述を即削除してしまう理由としては不十分だと考えます。もしもその記述が完全に妥当な情報を含んでいるなら、それを活かすべく編集されるべきで、削除されるべきではありません。」
したがって対象が「ページ削除」であろうと「部分削除」であろうと、Dr.Jimmy氏の提示した論証は類推にすぎず、それゆえ個人的な意見にすぎません。 であるならば同意が形成されていない状態では単に消したい人が消しているだけです。--あら金 2008年1月25日 (金) 15:37 (UTC)
あの方は音楽がご専門のようですね、ご専門に専念される方が社会のためになるかも知れません。もっと社会に役立つのは環境について勉強されて、消すべきものとそうでないもの区別がつくようになれば・・・・。意外と環境は難しいですね!?以上の署名の無いコメントは、60.238.118.155(会話/Whois)さんが 2008年1月28日 (月) 21:57 に投稿したものです。
Dr.Jimmyさんは今までに、この記事やこの記事以外で環境問題を理由にして一回あるいは複数回に分けて特定者の版の編集を根こそぎ削除しておられますが、これは特定の版の削除と同じことをされているわけです。実際、Dr.Jimmyさん以外の方は風評被害等が懸念される場合は、即時削除あるいは特定の版の削除申請されて合意を取り付けて削除しています。そのような合意形成プロセスも経ないのであれは、GNU Free Documentation Licenseはあなたの消した編集をどのようにでも上書き編集することを認めています。したがって、合意形成がなければ消したい人が消しているだけなので書きたい人は書くのです。
GNU Free Documentation Licenseは個々の版の著作権は執筆者が保持しつづけます。したがって、合意形成する以外に復活をやめてもらい内容を合意した範囲で固定するしか方法はないのです。合意以外の方法で他人の著作権行使を妨害するものは「1.ウィキペディア (Wikipedia) に文書を投稿する場合はすべて、GNU Free Documentation License (GFDL) (非公式日本語訳)およびそのウィキペディアでの解釈に同意するものとみなされます。あなたの文章が他人によって自由に編集・配布されることを望まないならば、投稿を控えてください。 」と書かれているように、Wikipediaに(削除編集)投稿すべきではありません。なぜならばボタンには「上記の記述を完全に理解し同意した上で投稿する」と書かれているのでDr.Jimmyさんは既に他人の編集を許可しているのですよ。中立性にしろ風評被害にしろ検証可能性にしろ、丸ごと消したらなにが問題なのか他人が分かるはずがないじゃないですか?以前より説明、説得が要約欄やノートに「発言明瞭、意味不明」な感想を書くだけで、それで同意してもらえると考えるのは楽天的に過ぎると感想を持っていましたので、「あいかわらずですねぇ」ともうしあげました。--あら金 2008年2月1日 (金) 06:00 (UTC)
私の意見をWikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成であると強弁するのであれば、少なくとも引用元の論旨と私の意見との論旨の不整合か反対意見に対する証拠の引用が必要です。
いままで幾度となくこのページや他のページでも証拠引用をDr.Jimmy氏に求めておりますがいまだかつて根拠の引用とそのご自分の解釈の説明をご提示いたいておりませんのでDr.Jimmy氏は感想文をお書きになっておられると判断せざるを得ません。
感想文をお書きになられるのはご勝手ですが、感想文を元に他人の行動を非難したり、自己の行動が正当化されると期待されても「子供だまし」な説得であり、人によってはDr.Jimmy氏が恫喝していると誤解されかねないと存じます。
なによりも「口(議論)よりも先に手を(行動を起こす)出されている」のはDr.Jimmy氏の自由意思による行動です。すべてご自分のおこなった行動が引き起こしたことなので、第三者の私は支持も同情も致して居りません。Dr.Jimmy氏に何が起ころうと、わたくしとしてはどうでもよいのですが、理なくして義が通るはずもなくさらに人徳が足らないと悲惨なことがおきますねぇ。--あら金 2008年2月8日 (金) 12:14 (UTC)
(コメント)複数の方針抜粋がありますが、GFDL違反(履歴不継承)の可能性があります(以下の編集が該当する可能性があり)。
--Dr.Jimmy 2008年1月21日 (月) 14:14 (UTC)
あら金 2008年1月25日 (金) 15:37 (UTC)
--Kc1477 2008年2月24日 (日) 15:10 (UTC)
(コメント)出典元は不十分ながらも示されており、妥当な引用と見なせると思います。--スのG 2008年2月24日 (日) 15:19 (UTC)
目次 [非表示]
1 提案
2 みんなの川や海はみんなで知ろう
3 底質ダイオキシン類汚染の不都合な真実
4 一般環境把握調査と汚染調査とは別
5 底質汚染に関する意見が出尽くしたようですが
6 ウィキペディアを良くするために
7 行政資料や関係法規制
提案 [編集]
ええと。一番上でIP氏が指摘された単位の誤りですが、単位が pg-TEQ/gではなく -TEQ/g となっている箇所があるのが不自然であることに対しての異論はノートを見ている限りないように思います。単純な誤記の修正として、管理者伝言板を通して管理者の方に編集していただくわけにはいかないのでしょうか?--朱月朱音 2008年2月8日 (金) 12:20 (UTC)
誤記があることを確認しました。私が管理者権限を行使するのは差し障りがありましょうから、賛成だけいたします。場所は「各地での底質汚染の取組み」の節の
東京都・横十間川 280-TEQ/g
大阪府・六軒家川 320-TEQ/g、木津川運河 190-TEQ/g、神崎川 510-TEQ/g、古川 300-TEQ/g
和歌山県・和歌山下津港 160-TEQ/g
(以上、記事より引用)の部分だけでしょうか。まだありますか?--スのG 2008年2月8日 (金) 12:28 (UTC)
もう一回一通り見てみましたが、その部分だけだと思います。--朱月朱音 2008年2月8日 (金) 12:33 (UTC)
お手間をおかけします。筆者敬白--あら金 2008年2月8日 (金) 12:36 (UTC)
では、その部分の6箇所の明らかな誤記「-TEQ/g」を「pg-TEQ/g」に置き換えることに賛成します。--スのG 2008年2月8日 (金) 12:37 (UTC)
提案より三日以上経過し、反対意見がなかったため、管理者伝言板に依頼しました。--朱月朱音 2008年2月11日 (月) 14:22 (UTC)
みんなの川や海はみんなで知ろう [編集]
また、編集可能なようになりました。行政のホームページからの情報をもとに追記されています。 Vaiotechnologyは「プロパガンダの取り消し」としてなんの議論も無く取り消しをしておられますが、現実を正しく見たうえでのことでしょうか?真面目な議論を封じ込める一方的な削除と思わざるを得ません。 Vaiotechnologyは遺伝子組み換え作物や農薬関係にも加筆訂正されていらっしゃるようなので、有害物質の人や生態系に与える環境リスクを考えることの出来る方とご推察いたします。
底質汚染において加筆した内容は、行政のホームページで公開されてる内容なので、検証可能であり、中立的な観点で記載されています。独自の研究でもなんでもありません。みんなの川や海の底が汚れているから、みんなで考える事は当たり前のことです。
行政が公表している内容を確認した上で取り消す必要があればこのノートで議論してから取り消せばいいことです。
蛇足ですが、環境を美しくしようと思えば、汚れているところを直視して、汚れているところの対策をしなければなりません。 底質汚染を考える事は、「臭いものにはフタをする」や「嫌な事は水に流して忘れよう」という日本人的な感情とは逆の思考が必要です。
環境は子孫からの預かり物です。底質汚染に関する真面目な議論を期待します。
環境に関する論議や環境浄化推進を目的として、Wikipediaに参加するのはご遠慮下さい。Wikipedia:ウィキペディアは何でないかの1.3をお読み下さい。百科事典作成のみの目的をもってご参加下さい。百科事典的でなく、環境浄化推進のみの観点で書かれた文章は差し戻されることがあります。--Los688 2008年2月24日 (日) 04:04 (UTC)
「みんなの川や海はみんなできれいにしよう」を「みんなの川や海はみんなで知ろう」
に訂正しました。
自分の主義主張を宣伝するためにウィキペディアを利用することは絶対に許されません。ましてや貴方は投稿ブロック中ではないですか。川や海を知るよりもまず貴方がルールを知ることです。--Vaiotechnology 2008年2月25日 (月) 00:43 (UTC)
>自分の主義主張を宣伝するためにウィキペディアを利用することは絶対に許されません。
とのご主張ですが、どのような記載が「Vaiotechnologyさん」のおっしゃる「主義や主張」なのでしょうか? 行政が公開している法規制等やデータを分かりやすく記載するのに「主義や主張」は不要です。 「Vaiotechnologyさん」が底質汚染についてあまりご存知では無いようですね! もう少し日本の環境法規制や、底質汚染について中央省庁や地方自治体が公開している内容ををまず知ることです。
それとも、行政が公開している法規制等やデータが記載されているウィキペディアは全て削除すべきとは思いませんが・・・? 宣伝した「主義主張」が具体的に明確にならないのであれば、速やかに復帰すべきです。?以上の署名の無いコメントは、221.171.175.169(会話/Whois)さんが 2008年2月26日 (火) 14:04 (UTC) に投稿したものです。
何を仰りたいのか良くわかりません。他にもあるだろうというのであれば、平成17年度の結果を並べて「これもあるから6箇所じゃないよ」といえばよいでしょう?項目をずらずらと並べるのは誰にでもできます。根拠は掲載を望む側が提出するのがWikipediaのルールです。--Kodai99 2008年2月29日 (金) 23:37 (UTC)
下記の通り「これもあるから6箇所じゃないよ!」項目をずらずらと並べててあります。これについて反論は無いのでしょうかの?
逐次回答は面倒なので、港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針に記述されていないことに関してご質問ください。不都合である為に隠されていると問題点称されていることは平成14年以来隠されることなく公開されてきたことが明確になると存じます。--あら金 2008年3月26日 (水) 00:27 (UTC)
「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」より平成19年3月に国土交通省の港湾局と河川局が合同で発行した「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」の方がまとまっております。その表紙には以下の記載があります。「底質のダイオキシン類対策については、大都市の港湾・河川において環境基準を超えるダイオキシン類含有汚泥が確認されているにもかかわらず、膨大な対策費用や処分場確保が困難という問題のほか、効率的・経済的な処理工法も確立されていない等の理由により本格的な処理が進展しておらず、早急な対応が求められている。」即ち、基準を超える底質汚染を確認しているが、対策が遅れており、早く対応しなければならないことを国土交通省は公にしているのです。平成20年4月27日
底質ダイオキシン類汚染の不都合な真実 [編集]
ウィキペディアの底質汚染に関する下記の文書があります。
「環境省の発表では底質ダイオキシン類の検出は年を経るごとに減少し、平成17年度の調査[10]によると底質のダイオキシン類で環境基準150pg-TEQ/gを超えている地点は6か所であった。東京都・横十間川 280pg-TEQ/g 、大阪府・六軒家川 320pg-TEQ/g、木津川運河 190pg-TEQ/g、神崎川 510pg-TEQ/g、古川 300pg-TEQ/g 、和歌山県・和歌山下津港 160pg-TEQ/g」
しかし、誤解が生じるといけないので、6ヶ所だけなのでしょうか? 下記に示す公共水域は環境基準を超過する底質ダイオキシン類が検出されていることを国土交通省や各自治体が公表しています。
宮城県:長沼
埼玉県:古綾瀬川・伝右川
千葉県:市原市市原港
東京都:堅川・旧中川・高浜運河・北十間川・綾瀬川
富山県:富岸運河
神奈川県:桜掘運河先・南渡田運河先、
山梨県:濁川
静岡県:田子の浦・巴川
大阪府:正蓮寺川・大正内港・木津川・旧住吉川・尻無川・三十間堀川・住吉川・東横堀川・道頓堀川・恩智川・平野川
兵庫県:神戸市遠矢浜、
和歌山県:海南地区・山田川・和歌川・有本川
島根県馬潟工業団地
福岡県:北九州市洞海湾等
以上のとおり全国でダイオキシン類による底質汚染が生じているヶ所数は6ヶ所だけで無く、数え方にもよりますが全国で30ヶ所は確認できています。
また、底質ダイオキシン類濃度の低い場所を環境省が発表していますが、詳細調査した結果を各自治体は公表しています。
東京都・横十間川 280pg-TEQ/g というのは低いところで、濃いところは19,000pg-TEQ/g(公表平成16年9月)
木津川運河 190pg-TEQ/g、というのは低いところで、濃いところは7,200pg-TEQ/g(公表平成18年6月)
神崎川 510pg-TEQ/gというのは低いところで、濃いところは7,000pg-TEQ/g(糸田川合流点左岸)
古川 300pg-TEQ/g というのは低いところで、濃いところは25,000pg-TEQ/g(公表平成20年2月 門真第八水路)
和歌山県・和歌山下津港 160pg-TEQ/gというのは低いところで、濃いところは1,800pg-TEQ/g(平成16年9月)
なお、下記の底質ダイオキシン類汚染濃度が公開されています。
大阪府の三箇牧水路44,000pg-TEQ/g(調査平成17年11月)
千葉県市原市市原港12,000pg-TEQ/g(平成13年6月)
島根県馬潟工業団地7,000pg-TEQ/g(平成20年4月)
福岡県北九州市洞海湾:4,600pg-TEQ/g(平成17年11月)
ウィキペディアの底質汚染の本文を読むと
「環境基準の2倍程度の底質汚染がで全国に数ヶ所あるだけ」 のように思ってしまいますが、実は
「環境基準の数十倍、場所によっては数百倍程度の底質汚染が全国に数十ヶ所確認されている」 のです。
底質汚染は時間と共に蓄積されるか、又は拡散して食物連鎖で濃縮されヒトが食べることになります。
底質汚染の現実を知ることは快くないでしょうが、底質汚染の現実は不都合な真実です。2007年3月2日IP
現状のウィキペディアの底質汚染に関する本文は「中立的な環境科学」から逸脱しており、読者に誤解を与える可能性があります。上記内容を本文に書き加えるべきと思います。
どなたか上記の記述に対して、反論される方はいらっしゃらないのでしょうか?
同一時点(すくなくとも同一年度)でのデータを列挙していないので「全国各地で高濃度の底質ダイオキシンが検出されたことがある」という以上の意味を持ちません。「全国各地で高濃度の底質ダイオキシンが検出された」という記述の為には過去にさかのぼって全データをウィキペディアに示す必要はなく代表値として最も価値のある最新状況以外はリンクも不要と考えます。地方自治体のデータは監督官庁の環境省へ報告されるので同一年度の代表値として二重である必然はなく環境省公報のみで十分と考えます。(Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディアは単なる知識ベースではありませんが根拠)--あら金 2008年3月2日 (日) 19:05 (UTC)
ここは底質汚染に関することを書く所です。環境省公報は底質で書いて書いて欲しいものです。全国各地で高濃度の底質ダイオキシンが検出されたことは、過去の問題ではなく、ほとんどが現在も高濃度の汚染がそのまま残っている不都合な現実ががあります。
たとえば、大気汚染も土壌汚染も環境省の公報の値は汚染がほとんど見つかりません。底質汚染を語るには何処にどのような基準を超えた汚染があることを議論すべきです。
汚染の無い空間分布や同じ場所の経時変化以外は底質汚染を考える上で無価値です。底質汚染がある現実は単なる知識ベースではなく永年にわたり、人類が汚染物質を少し毎排出しその有害物質が蓄積している現実を多くの人々が知ることが必要です。また、高濃度の底質汚染が検出され速やかに対策されれば、ニュース速報になり、百科辞典の記事としては不適切でしょうが、高濃度の汚染底質に対しほとんどが対策されず放置されている現実があるので、ニュース速報ではありません。
高濃度の輩出派あら金様は高濃度底質汚染が
最も価値ある最新状況は古川では25,000pg-TEQ/gですね?
底質ダイオキシンはサンプリング位置が1mずれれば千倍も濃度が違うことはざらです。したがって汚染総量を見るには平均値を見るしかないです。生物濃縮を問題にされるているようならばなおさらです。動物は餌を求めて動き回るものですから、一か所だけ濃度が高くても動き回ることで蓄積量は平均化されます。あなたがそこの特別濃いところの底質をスプーンですくってすするようならば重大な影響がでると考えますが、そのような極端な状況の健康被害は普通は想定しないので平均値で十分です。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)
古川の25,000pg-TEQ/g最新データーとしての意味があります。また、底質ダイオキシンはサンプリング位置が1mずれれば千倍も濃度が違うことがよくあることのようですが、このような具体例は何処でしょうか?2008年3月20日
地方自治体のデーターは監督官庁の環境省に報告されているのですか?その根拠は?なぜ大阪の底質汚染のあるいくつかの河川のデータを環境省は公開しないのでしょうね?
変動が大きすぎて、そのまま発表すると統計的に確からしくない結論を発表することになり恥をかくからです。したがってデータを幾つかの統計的手法などを活用して汚染量の推定値を出すのが普通です。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)
統計的に確からしくない結論とな何を意味するのでしょうか?現実に高濃度のデータがーあれば隠蔽すると言う意味と解釈することになります。汚染量の推定値を出すために、幾つかの統計的手法などを活用するとのことですが、どのような統計的手法でしょうか?汚染量=(汚染面積)×(汚染深度)で算出されます。2008年3月20日
あら金様のご説明に沿って考えた場合、過去に高濃度のダイオキシン類がふくまれていた底質は何処に行ったのでしょうか?
たまたままったく同じ場所にサンプリングの棒を突き立てることができなかったか、泥がかきまぜられて濃度が低下しただけだと考えます。川底の土砂は流速の二乗から三乗位に比例して移動することは土木工学的に知られているので台風などの増水で流量が増えるイベントがあると、当然泥がかきまぜられて濃度が低下します。あるいは増水で上流から汚染されていない泥が覆いかぶさりサンプリングの深さよりも堆積して覆い隠したのかもしれません。増水のタイミングも汚染のタイミングもそれぞれですから毎日垂れ流すようでなければ一時的に減る場合もあるでしょう。なのである時点の一か所だけの高濃度は評価する上で価値がないのです。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)
泥がかき混ぜられて濃度が低下し周辺に広がることはよくあります。底質は流れがあれば移動しますが、汚染が検出されてる東京都内運河・富岸運河、河口部は流量が少なく、潮の満ち引きを受けて逆流しているところがほとんどです。平成200年3月20日
あら金様のお名前を挙げて恐縮ですが、あら金様の回答を読むと矛盾が沢山でてきます。ご説明下さいますようお願いいたします。
以上、ご説明を申し上げました。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)
あら金様、ご説明ご苦労様でした。かなり勉強されたのですが、残念ながら、ある一面の知識で底質汚染全体を論じておられる
とと思います。地方行政の委員会などを傍聴されると不都合な現実がが良く分かるとと思います。
底質について勉強されたことに対して敬意を表しますが、水の底の汚染は難しく、蓄積性があります。ドブさらえは小まめにやっておかないと、汚い物が溜まるばっかりなので、大変な事になります。2008年3月20日
一般環境把握調査と汚染調査とは別
平成18年度ダイオキシン類に係る環境調査結果が環境省から発表されています。ここで、土壌は 1,505地点中超過したのは0地点ですが、ニュースで東京・大阪・九州で土壌にダイオキシン類が高濃度で含まれていることが報道されています。 底質 1,548地点中超過したのは4地点と発表されています。注意書きに「土壌については、環境の一般的状況を調査した結果(一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査)した結果であり、汚染範囲を確定するための調査等の結果は含まない。」と記載されています。底質についても略同じことが言えます。一般環境把握と汚染範囲を確定するための調査とは別の目的で実施されています。この ウィキペディア「底質汚染」について記載されており、一般的な「底質」は別にあります。よってこの底質汚染の本文は、底質汚染が何処でどれくらい生じているかなどを検証可能なデーター等を分かりやすく整理した百科辞典であるべきと思いますので、全国の現実の汚染の状態を記載すべきと思います。平成2000年3月20日(ドブさらえ)
早く保護を解除して欲しいですね!
勘違いされているようですが、本文の保護テンプレートに書かれているとおり誰かが保護解除依頼を出さないかぎり永久に保護のままです。また本文で編集合戦が起きないという確証がなければ提出された依頼は却下されます。ノートを見る限り編集合戦しないという合意に関する議論は皆無なので現状では無期限保護であると存じます。--あら金 2008年3月26日 (水) 00:05 (UTC)
底質汚染に関する意見が出尽くしたようですが [編集]
あら金様やVaiotechnology様などからの底質汚染に関する意見が無いようですが如何されたのでしょうか?底質汚染に関する現状と課題などは理解されたのでしょうか?まじめな議論を求めます。平成20年4月27日
口頭の発言とは異なり見解は空に消えるわけでもなくすべて履歴に残りますので二度同じ内容を発言する必要はないと存じます。(この発言)つまり不都合な真実なるものは存在しない根拠も提示いたしましたし、編集ロック解除に必要なことは何かも提示しました。質問があっても回答済みである以上、議論は加筆されないし、ロック解除もされないのは当たり前と存じます。--あら金 2008年4月27日 (日) 14:20 (UTC)
国土交通省から「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂が発表されています。また、環境省から「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」の改定や「平成18年度ダイオキシン類に係る環境調査結果」も発表されています。これは本文に掲載すべきと思います。
編集ロックの解除がなければ無理ですね。編集合戦が起こらないという根拠と「…すべき」とは無関係なので現状では当面(年単位で)はこのままと考えます。--あら金 2008年5月20日 (火) 00:17 (UTC)
底質汚染は現在の子作りの終わった人間にとっては差し迫った危険が無いと思います。しかし、これから子供を産む人には大きな問題になる可能性を否定できません。ダイオキシン類等の有害物質の排出量は減りましたが、底質にダイオキシン類等の有害物質が大量に蓄積されています。先祖から生かされた自分の世代だけを守るのであれば、底質は逃げればすむことかもしれませんが、将来世代(子・孫・ひ孫・・)を考えると、自分が生まれた頃の底質に戻すことが、私の使命だと思います。2008年8月お盆?以上の署名の無いコメントは、218.227.217.30(会話/Whois)さんが 2008年8月9日 (土) 12:53 に投稿したものです。
ウィキペディアを良くするために [編集]
信頼できる行政の情報等を分かりやすく載せることが必要と思います。無知な御仁が参加した編集合戦があればウィキペディアは相手にされなくなる可能性があります。?以上の署名の無いコメントは、218.227.215.81(会話・履歴)さんによるものです。
Wikipedia:ガイドブックを拝読させていただきました。(2008年9月2日218.227.217.30などと同一人)
外部リンクの『底質のダイオキシン類対策技術資料集(平成19年5月修正国土交通省)』 がリンク切れです。?以上の署名の無いコメントは、60.237.78.178(会話・履歴)さんによるものです。
行政資料や関係法規制 [編集]
行政が発表した資料に基づく事実や、関係法規制を多くの人が分かりやすいように記載したら何故削除されるのでしょうか? 下記のアドレスで差が分かります。
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BA%95%E8%B3%AA%E6%B1%9A%E6%9F%93&diff=23656010&oldid=23649867
食品水土 080103
重金属の底質汚染の現状が産業技術総合研究所のホームページで掲載されました。東京湾付近の大学や国土交通省から底質に含まれる重金属と底生生物の相関関係のデータが示されました。IP??080303
「
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%BA%95%E8%B3%AA%E6%B1%9A%E6%9F%93
」より作成
2009年10月22日
土壌汚染に関する行政と民間との意見交換会


「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html


各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html


2009年10月22日
(工事中)H20農薬飛散リスク評価手法確立調査
平成20年度農薬飛散リスク評価手法確立調査モニタリング調査業務
結果報告書
平成21年3月
社団法人 農林水産航空協会
要 約
市街地における街路樹や公園の花木類等管理のために散布される農薬の飛散リスクの影響を評価・管理する手法を確立するため、平成18年度及び平成19年度モニタリング調査結果を踏まえて、農薬飛散範囲調査、農薬検出期間調査および除草剤散布後気中濃度等調査を実施した。
農薬飛散範囲調査は、立木1本に対して水を散布し、樹高、樹形、風の条件、散布方向の違いについて、周辺への飛散状況を調査した。調査は、樹の中心から8方位に、樹高の条件により10mまたは15mまでの距離で調査地点に感水調査紙を設置して行った。感水調査紙は、画像処理ソフトウエアにより、被覆面積率および付着液量の推定を行った。
飛散状況は、樹が高いほど、また、枝葉が繁茂しているほど多かった。樹高4m 程度の樹に対しては、手の届く範囲で近距離からの散布ができることから、飛散が少なかったものと考えられる。枝葉が繁茂した樹形は散布水量が多くなることから、その分飛散のリスクが増えるものと考えられた。
しかし、風の強い条件では、散布方法より風の影響の方が強いと考えられ、平均風速が2m/s 程度であっても、風下側では15m 先へも飛散する可能性が十分にあると考えられた。
付着液量の推定は、1 樹当たりの散布水量と、8 方位の距離別にブロック分けした場所においての付着液量の比率の風下側最遠調査地点での最大値は、平方メートルあたり0.03%であった。
農薬検出期間調査は、公園等での使用実績のあるフェニトロチオン、トリクロルホン、エトフェンプロックス及びイソキサチオンの4 剤を混用して、調査対象の樹木林に散布し、気中濃度濃度調査、土壌中濃度調査及び葉への付着量調査を実施した。気中濃度は、調査農薬により検出された値に違いは見られたが、それら農薬の蒸気圧等の物理化学的性状が影響をあたえて
いのではないかと考えられた。
土壌中濃度で散布直後の濃度と比較して1/2 の濃度となったのは、フェニトロチオンで散布14 日後、ジクロルボスで散布7 日後、エトフェンプロックス及びイソキサチオンでは散布14 日後以降であると推察された。葉への付着量では、フェニトロチオン、トリクロルホン及びジクロルボスは同じようなに減少する傾向が見られ、散布14日後で1/80、1/20 及び1/50 まで減少し、当初の濃度が低かったイソキサチオンとエトフェンプロックスは散布14 日後で1/3 及び3/5 と減少は少なかった。
除草剤散布後気中濃度等調査は、使用実績のあるグリホサートの散布後に気中濃度調査、土壌中濃度調査及び葉中濃度調査を実施した。気中濃度では、散布区域内の高さ0.2mの地点で散布当日の13 時のみに検出されたことは、一度散布された農薬が蒸散した結果と考えるには、最も値が高いはずの散布直後に検出されていないことと、その検出濃度などから、植物体を経由したカラムの汚染による可能性が高いのではないかと考えられる。土壌中濃度は、散布直後と散布30 日後の濃度に違いは見られなかった。葉中濃度は、散布直後に高い濃度が検出され、散布1 日後に大きく減少した。
Summary
Based on the results of serial monitoring studies conducted in 2006 and 2007,dispersion range, duration of detection period, and concentrations in air of heirbicide after spraying were
investigated to establish the methods for evaluation and management of dispersal risks of
agrochemicals applied for maintenance of greenery on roadside tree or in parks.
For the purpose of estimation of dispersion range, a tree was sprayed with water and profiled
for the water dispersion toward surrounding area. The results were analyzed in terms of height
and shape of trees,wind condition,difference of spraying orientation. Sheets of water-sensitive
paper were placed 10 to 15 m from the center of a tree depending on height of trees in eight
azimuth directions. Ratio of the covered area and amount of attached solution were estimated
by measuring the wet area on the water sensitive papers using image analysis software.
The extent of dispersion was increased in accordance with the height of trees and the density
of branches and foliages. Trees as low as 4 m in height showed less dispersion probably due
to the spraying from closer distance within the reach of equipment. The elevated amount of
sprayed agrochemicals required for trees with dense branches and foliages seemed to give rise
to risk of dispersion. However, wind effect prevailed over spraying method especially under
strong wind condition. The downwind dispersion as far as 15 m can be observed even at the
wind speed of 2 m/s.
On spraying a tree, a ratio of the amount of attached solution versus that of sprayed solution
was calculated at each sampling point in eight azimuth directions differing in distance from
the sprayed site. The maximum ratio at the furthest downwind sampling point was estimated
to 0.03% per square meter.
Four agrochemicals with past application records in parks such as fenitrothion, trichlorphon,
etofenprox,and isoxathion were selected and adopted for determining the duration of detection
period. The combined agrochemicals were sprayed over trees and concentration in air,soil
concentration,and deposit on foliage were measured. The difference in concentration in air of
the individual agrochemicals could be ascribed to physicochemical characters such as vapor
pressure. Half-lives of fenitrothion, etofenprox, and isoxathion in soil were estimated to 14
days, 7 days, and 14 days, respectively. Fenitrothion, trichlorphon, and dichlorvos on leaves
showed the same decaying tendency, and the amount of the each substance decreased to
1/80-fold, 1/20-fold, and 1/50-fold of the primary amounts after 14 days from application.
Isoxathion and etofenprox with less primary attachment to leaves decreased to 1/3 and 3/5 of
the primary concentration after 14 days from application.
Glyphosate which has the solid past application records was adopted for the study of
post-application monitoring of herbicides. After spraying, glyphosate concentrations in the air,
in soil, and in leaves were monitored. The sole detection of concentrations in air was observed
at 13:00 on the day of spraying. The concentrations in air were not detected immediately after
spraying and the concentration of the detected glyphosate was too low. Therefore the
detection of glyphosate was most likely due to contamination of the trapping column in
contact with sprayed plants, rather than the evaporation of glyphosate. There was no
significant difference between glyphosate concentration in soil of immediate aftermath of
spraying and that of 30 days after spraying. In leaves, large amount of glyphosate was
detected immediately after spraying, while significant decrease of glyphosate was recognized
a day after spraying.
はじめに
この報告書は、環境省大気局農薬環境管理課から社団法人農林水産航空協会に委託された「平成20年度農薬飛散リスク評価手法確立調査(モニタリング調査業務)」の実施成果をとりまとめたものである。
本調査は、市街地における街路樹や公園の花木類等管理のために散布される農薬の飛散リスクの影響を評価・管理する手法を確立するに当たって、公園等を利用する一般市民及び公園等周辺住民の健康を保護する観点から、公園内及び周辺における農薬の気中濃度及び飛散等による曝露実態を把握するために実施した平成18年度及び平成19年度モニタリング調査結果を踏まえて、農薬飛散範囲調査、農薬検出期間調査および除草剤散布後気中濃度等調査を実施した。
平成21年3月
東京都千代田区平河町2−7−1 塩崎ビル3階
社団法人 農林水産航空協会 会 長 関 口 洋 一
目 次
?.農薬飛散範囲調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
?.農薬検出期間調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
?.除草剤散布後気中濃度等調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
要 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114
平成20 年度農薬飛散リスク評価手法確立調査(モニタリング調査業務)
[目的]
環境省では平成17 年度から農薬飛散リスク評価手法確立調査を開始し、街路樹や公園等の市街地において使用される農薬の飛散リスクの評価・管理手法について検討しているところであり、これまでに、国内外における農薬飛散リスクの評価・管理手法に関する文献調査、自治体での防除実態を把握するためのアンケート調査(平成17 年度)、実際の農薬散布場
面におけるモニタリング調査(平成18・19 年度)と、蒸気圧等の要因別の影響調査を含む基礎調査(平成19 年度)を実施し、農薬の飛散による暴露実態を把握するための基礎資料を得た。
平成20 年度の本業務では平成19 年度までの結果を踏まえた上でモニタリング調査を実施し、農薬の飛散による暴露実態を把握するうえでの基礎資料を得る。
[調査項目]
?.農薬飛散範囲調査
樹木等に対して通常用いられる農薬散布用器具を用いて水を散布し、感水紙を用いて、周囲への到達落下範囲を調査する。
?.農薬検出期間調査
農薬散布にあたり最も高濃度が検出される地点において十分減衰するまでの期間が立ち入り禁止期間となると考える。
したがって、高木が複数存在する区域を設定して調査地点を置き、農薬散布後の気中濃度低減の調査を行うとともに、当該地点における葉及び土壌での残留量を計測する。
?.除草剤散布後気中濃度等調査
雑草等が生えている場所に除草剤(グリホサート)を散布した場合、その周囲への飛散の程度、気中濃度、及び散布地点の土壌の残留について調査を行うこととする。
?.農薬飛散範囲調査
[調査内容]
1.調査実施場所
(社)農林水産航空協会 農林航空技術センター敷地内(長野県小諸市)
2.調査方法
(1)調査樹
樹種:オウシュウトウヒ(ドイツトウヒ)
樹高:中木4.2m、高木?(疎密)8.3m、高木?(繁茂)8.7m の3 形態(写真1)。
(2)調査の組み合わせ
樹高・樹形:中木、高木?(枝葉疎密)と高木?(枝葉繁茂)の比較。
ノズル:慣行と飛散低減の比較。
風速:平穏〜軽風(0〜1.5m/s)と軽風(1.6〜3.3m/s)の比較。
散布方向:高木?において、下からの吹上げと横方向からの散布の比較。
各調査は反復を2 回とした。
(3)感水紙の設置
調査対象となる樹木を中心に、8 方向に、樹木から3m、5m、10m の距離に地上高50 ?の高さに感水紙を水平に設置し、散布した水の飛散状況を調査した。なお、軽風条件下においては15m 地点にも設置した。
感水紙は、WATER SENSITEVE PAPER(スプレーイングシステム株式会社製)を使用した。
(4)感水紙の解析方法
感水紙は、散布開始前から散布終了後5 分まで設置し、変色量を画像解析ソフト、ImageJ(バイオアーツ株式会社製)を用い、被覆面積率を測定した。
感水紙の一部については、画像解析ソフト、まいA のーど(ノズルネットワーク株式会社製)により、付着液量の推定を行った。
なお、感水紙の画像の解像度は、1 ドット約64 ?(約400dpi)であった。
(5)散布方法
動力噴霧機:セット動噴MS253(株式会社丸山製作所製)
散布ノズル
慣行ノズル:アルミズームα900 型(ヤマホ工業株式会社製)噴霧粒径95〜360μm(写真2)
飛散低減ノズル:キリナシズーム900 型(ヤマホ工業株式会社製)
噴霧粒径380〜710μm(写真2)
*圧力1.5MPa での平均粒径(データはヤマホ工業株式会社提供)圧力:全て1.5MPa
(6)風向風速の計測
風向風速は、デジタルハンド風向風速計26D-B?(株式会社太田計器製作所製)で測定した。
[調査結果]
1.散布状況
調査に使用したノズルは、2 種とも、手元のグリップを回転させることにより遠距離噴霧(狭角)と近距離噴霧(広角)の調節ができるため、高木?、?の吹き上げ散布は、遠距離噴霧で、中木および高木?の横方向からの散布は近距離噴霧で行った。
中木は、手の届く範囲で概ね横方向からの散布となった。
高木?の横方向からの散布は、長さ4m の直管にノズルを取り付け行った。
散布水量は、予め練習散布で枝葉が十分に濡れ水が滴り落ちる程度を十分量と定め、噴霧時間を合わせることにより散布量が一定となるようにした。
散布は、条件を統一にするため、風向にかかわらずに散布者が樹の周囲を移動し、全周方向から行った。
2.飛散状況
飛散状況調査は、表2 の組み合わせで行い、その結果を表3 及び図1〜図16 に示した。
全体の飛散程度を検討するため、表3 より距離ごとに8 方位の感水紙における飛散の被
覆面積率(以下「被覆面積率」という)の合計値と飛散が確認された感水紙数を取りまと
め、表4 に示した。
樹高の影響については風の条件ごとに比較し図17 に、樹形の影響については高木につい
て風の条件を比較し図18 に、ノズルの影響、散布方向の影響については風の条件と樹高・
樹形を比較し図19 に、風速の影響については樹高・樹形と散布方法を比較し図20 に、風
向の影響については地点ごとの被覆面積率を比較し図1〜16 に示した。
(3)ノズルの影響について
中木では、平穏〜軽風の条件で飛散低減ノズルの被覆面積率の値が5m、10m で低かった。
軽風では飛散低減ノズルの値が3m、5m で低かった。
高木では、軽風で散布方法が吹上の条件では、3m 地点では慣行ノズルの値が低かったが、
10m、15m 地点では、低減ノズルの値が低かった。それ以外の条件では明らかな飛散程度の差
は認められなかった。
(4)散布方向の影響について(図19)
平穏〜軽風で低減ノズルの条件では、横方向からの散布が吹上での散布に比べて値が低か
った。軽風条件では、散布方向による明らかな差は認められなかった。
横方向からの散布はより上方へ到達する水量が、吹上での散布に比べ少ないと考えられる
ことから、飛散が低減されるものと考えられるが、風が強い場合は、風の影響の方が大きい
ものと考えられる。
図19 ノズル・散布方向の影響
(5)風速の影響について
中木では、3m、5m、10m では軽風に比べ平穏〜軽風の被覆面積率の値が明らかに低く、10m
以上で大きく値が減少した。
高木では、平穏〜軽風では3m での値が高く、5m、10m で大きく値が減少している。軽風で
は、3m と5m の値に大きな差が無く、飛散が認められた。
高木?、?ともに吹上散布では、平穏〜軽風の条件では風下方向に限らず、全周に飛散す
る傾向が認められた。軽風条件では、風上では3m の地点でも飛散はほとんど認められなかっ
た。目視では、吹き上げ散布はノズル先端より5m 以上吹き上げており、その結果より高い位
置で広範囲に飛散してしまうため、特に風の弱い状況においては、散布位置の周辺に多く飛
散することが観察された。風が強い場合は、ほとんどが風により風下方向に流されていた。
図20 風の影響
(6)風向の影響について
風下方向では、調査を行った最遠地点の10m(平穏〜軽風)、15m(軽風)まで飛散が認められ
た(図1〜16)。
高木?、?ともに吹上散布では、平穏〜軽風の条件では風下方向に限らず、全周に飛散す
る傾向が認められた(図3〜6)。軽風条件では、風上では3m の地点でも飛散はほとんど認め
られなかった(図11〜14)。
3.飛散量の推定
(1)感水紙の付着液量の推定
画像解析ソフト「まいA のーど」により、感水紙に付着した液量の推定を行った結果を
表5 に示し、被覆面積率と付着液量の関係を図21 に示し、得られた推定式
y=0.0003x2+0.0165x により換算した付着液量を表6 に示した。
また、感水紙の飛散状況(水滴が付着した部分が青色に変色する)の一例を写真5 に示した。
なお、本解析方法では、感水紙上の液滴痕跡が、多く重なったり、つながったりしてい
る状態では、精度が落ちるため、被覆面積率が概ね25%以下のサンプルについてのみ解析
を行った。表6 においても、被覆面積率が25%以上のものについては、換算から除外した。
表5 被覆面積率と付着液量の推定値
(2)総散布量に対する付着液量の割合
被覆面積率から換算した感水紙の付着液量をもとに、図22 に示すように方位ごと距離別
にブロック分けし総散布液量(1 樹当たりの散布水量)に対するブロック全体の面積で換算
した付着液量比率を算出し表6 に示した。
算出にあたっては、3m 地点と5m 地点での付着量の平均値を3m から5m までの範囲の付
着量の平均値、5m 地点と10m 地点での付着量の平均値を5m から10m までの範囲の付着量
の平均値、10m 地点と15m 地点での付着量の平均値を10m から15m までの範囲の付着量の
平均値として換算した。平穏〜軽風の10m から15m までの範囲の付着量の平均値は、10m
地点の1/2 の値とし、同じく軽風の15m から20m までの範囲の付着量の平均値は、15m 地
点の1/2 の値として換算した。
平穏から軽風条件では、総散布量に対する付着液量の割合の最大値は、高木繁茂、横方
向、通常ノズル散布の風下側10m から15m ブロックで0.65%で、平方メートルあたりでは、
0.03%であった。また軽風条件の最大値は、高木疎密、吹上、通常ノズル散布の風下側15m
から20m ブロックで0.93%で、平方メートルあたりでは、0.03%であった。
図22 総散布量に対する付着液量の割合算出における方位・距離別ブロック
[まとめ]
1.飛散状況調査
今回の調査は、立木1 本に対しての散布において、樹高、樹形、風の条件、散布方向の違いについて、周辺への飛散状況を調査したものである。
樹高4m 程度の中木に対しては、手の届く範囲で近距離からの散布ができるのに対し、8m程度の高木は、高いところまで勢い良く吹上る必要があり、その分飛散のリスクが増えるものと考える。
このことは高木で、吹上による散布よりも横方向から散布する方法の方が、飛散程度が少なかったことからも言える。しかし、風の強い条件では、散布方法より風の影響の方が強いと考えられた。
また、繁茂した樹形の方が、疎密のものより飛散程度が多かったことから、散布水量が多いことによると考えられる。
以上のことから、散布時の飛散リスクには、樹高及び風の条件が最も重要であり、次に散布量の影響が見られる。なお、平均風速が2m/s 程度であっても、風下側では15m 先へも飛散する可能性が十分にあると考えられる。
2.飛散量の推定
感水紙の画像解析による付着液量の推定調査については、感水紙上の痕跡が粒子状であり、重なりが少ないほど精度が良いと考えられる。このため本調査においては、被覆面積率が25%以下のサンプルについてのみ解析を行った。
本調査において、被覆面積率と画像処理ソフトにより測定した付着液量の間には、一定の相関が認められ、推定式により、被覆面積率から感水紙の付着液量の推定が可能であると考えられた。1 樹当たりの散布水量と、8 方位の距離別にブロック分けした場所においての付着液量の比率の風下側最遠調査地点での最大値は、平方メートルあたり0.03%であった。
ただし、本結果は、本調査における画像解析に係る機器、ソフトウエアの組み合わせで得られたものであり、他の組み合わせについては別に検討が必要である。
?.農薬検出期間調査
[調査内容]
1.調査場所
(社)農林水産航空協会 農林航空技術センター敷地内(長野県小諸市)
2.調査実施期間
平成20 年8 月11 日(散布前日)〜8 月26 日(散布14 日後)
3.散布概要
散布面積:およそ1,000 ?
散布農薬の概要を下表に示した。
散布諸元
ポンプ:動力噴霧器 MS903(株式会社丸山製作所製)
エンジン:ブリッグス20HP(ブリッグス&ストラットンジャパン製)
使用ノズル: 松喰虫ノズル(株式会社永田製作所製)
噴霧形状:高木樹が多いため直射噴霧とし、低木へは圧を弱めやや広角に散布
圧力:30kgf/c ?(3.0MPa)
散布量(4 農薬を混用):400 ?/1000 ?(葉から滴り落ちる程度)
4.調査農薬成分
フェニトロチオン
トリクロルホン
ジクロルボス(トリクロルホンの代謝物)
エトフェンプロックス
イソキサチオン
5.調査項目
(1)気中濃度調査
調査は、「航空防除農薬環境影響評価検討会報告書(平成9 年12 月、環境庁水質保全局)の測定方法に準じた手法を用いて行った。
1)調査地点
3 地点A、B、C を設定し、各地点で1.5mの高さ及び0.2mの高さとした。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布中、散布直後、散布1 時間後、3 時間後及び6 時間後)及び散布1 日後の所定の時間に行った。
3)捕集時間と捕集量
捕集時間は毎分3 ?の吸入速度で散布前は1 時間とし、散布中及び散布直後の調査時は30 分間、それ以降はすべて1 時間とした。また、散布中の調査は対象樹木への散布が開始された時から30 分間とし、散布直後の調査は「散布中調査」の後
に引き続き30 分間として行った。
大気の捕集は、高度1.5mでは自動大気捕集装置及び高度0.2mではミニポンプとガスメーターを組み合わせた捕集装置を使用した。
4)捕集装置
?自動大気捕集装置 AS-5000 型(株式会社メテク)
?ミニポンプ MP-500Σ(柴田科学株式会社)
乾式ガスメーター:DC-1C(株式会社シナガワ)
5)捕集カラム
?捕集剤 テナックスTA(60/80 mesh) 0.5g充填
?カラム 自動大気捕集装置:内径10mm、全長190mm(捕集剤充填部140mm)ガラス管に捕集剤を充填した。
ミニポンプ:内径12.7mm のポリプロピレンのチューブに捕集剤を充填した。
なお、ミニポンプに使用したカラムは、太陽光などによる影響を避けるため捕集
剤を充填した部分をアルミ箔で覆った。
6)捕集方法
?自動大気捕集装置
各調査地点に捕集カラムをセットした自動大気捕集装置を配置し、所定時間大気を吸引採取した。なお、この装置の吸引口の高さは地上1.5mとなる。
?ミニポンプ
捕集カラムを下向きにし、吸引口は地上0.2mの高さに固定し、ミニポンプで所定時間大気を採取した。吸引量は乾式ガスメーターを用いて測定した。
上記装置により採取された捕集カラムは、直ちに両端を密栓し冷却されたクーラーボックスに保管し分析機関へ送付し、ガスクロマトグラフにより調査対象農薬を分析した。
(2)土壌中濃度調査
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、C の近辺に3 地点A、B、C を設定した。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布直後)、散布1 日後、2 日後、5 日後、7 日後及び14日後の所定の時間に行った。
3)採取方法
ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成20 年3 月改正環境省水・大気環境局土壌環境課)に準じ、区域内より深さ5cm で5 点混合方式にて土壌を採取し、混合したものを分析試料とした。
(3)葉中濃度調査(葉への付着量)
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、C周辺に3地点A、B、Cを設定した。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布直後)、散布1 日後、2 日後、5 日後、7 日後及び14日後の所定の時間に行った。
3)試料採取
気中濃度調査の調査地点A、B、C周辺の散布した樹木から、高さ70cm程度にある葉を20g程度採取し、表面積及び重量を測定した後、混合したものを分析した。
(4)落下量調査
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、Cの近辺に3地点A、B、Cを設定した。
2)調査期間
散布当日(散布中)において行った。
3)定量調査
各調査地点に直径9cm のろ紙(ADVANTEC FILTER PAPER No.5A)2 枚を取り付けた調査板を設置した。調査板の高さは地上より1.5mとし、支柱等を利用して水平に設置した。
ろ紙は各調査時間に30 分間設置し回収した。2 枚のろ紙の表側が重なるように折りチャック付きのポリ袋に入れ回収した。試料は冷却されたクーラーボックスに保管し分析機関へ送付し、ガスクロマトグラフにより調査対象農薬を分析した。
なお、同一調査地点における、ろ紙2枚を合わせて1試料とし分析試料とした。
(5)気象観測
調査期間中の温度、降雨量及び日照時間を調査する(1時間間隔)。また、気中濃度測定時には温度、湿度、風向及び風速(平均及び最大)を10 分おきに測定した。
(6)樹木状況等
平成18年度及び平成19年度の調査結果から、散布区域の樹木の密集度合いや樹幹の大きさや枝ぶり等による「うっぺい度合い」、散布方法(散布方向、使用ノズル・噴霧形状等)の違い及び散布時の風向・風速、これらが飛散状況等の結果に影響を及ぼすことから、散布区域の樹木の樹種・樹高等の調査を行った。
(7)目標とする定量下限値
いずれの農薬についても、気中濃度で0.01μg/m3、土壌中濃度で0.01μg/g 及び葉中濃度(葉への付着量)で0.0002μg/cm2 を目標値とした。
[調査結果]
1.農薬分析法の概要
(1)分析農薬及び物理化学的性状
フェニトロチオン(MEP):O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate
トリクロルホン(DEP):dimethyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate
ジクロルボス(DDVP):2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate
エトフェンプロックス:2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
イソキサチオン:O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-yl phosphorothioate
2.調査地点の概況
散布区域は、南西側から北東側に高くなっていく傾斜地であり、散布区域内に分散させて調査地点A、B、Cを設置した(図1、写真1及び写真2)。
3.散布区域の樹木状況
散布区域は自然の雑木林および一部植栽の樹木であり、その状況は表1 及び図1 に示し
たとおりであった(写真3)。下層土壌の土質は褐色森林土壌でシルト質壌土であった。
散布区域の樹種は高木のカラマツ(10〜15m)、中木のコナラ(7〜8m)、ニセアカシア
(7m)、クリ(7m)、ソメイヨシノ(6〜7m)、低木のガマズミ(3m)であった。確認し
た小潅木はマルバハギ(1m)、ヤマザクラ(幼木)などであった。
4.薬剤散布状況
散布作業は、散布区域の北西側にあるクリの木付近から開始し、散布区域脇の道路を
バックする形で移動しながら散布を行い、続けて南西側にあるクリとコナラの木の間を
散布区域北側の地点C 付近まで入って、同じようにバックする形で移動しながら散布を
行った。次に散布区域の南側にあるカラマツおよびクリ付近から北側にあるコナラ方向
に移動しながら散布が行われた。散布時間は7 時より7 時10 分までの10 分間であった
(写真3 及び写真4)。
散布区域の面積はおよそ1000 ?であり、散布量は希釈液で400 ?であった。区域内の
高木および中木数はおよそ40 本であったことから、散布区域に均一に散布されたと考え
ると樹木当りでは10 ?/本であった。
5.気象概況
調査場所は標高800mの高原台地に位置し、夏季においても平野部の気温よりは低い気
象状況であった。
主に散布区域の南西地点において行い、その気象概況を表2 に示した。また、調査期
間中の日射量、日照時間及び雨量を表3 に示した。
(1)天候、温度及び湿度
8 月11 日(散布前日)から8 月26 日(散布14 日後)の調査期間中の調査時間帯に
おける天候は概ね晴れ、温度は22〜30℃、湿度は52〜89%であった。
(2)風向・風速
調査期間中の気中濃度調査実施時(散布当日及び散布1 日後)の風向は、南東から
南西であり、斜面となっている散布区域内を南西側から北東側に風が抜ける形となっ
た。
散布中(7:00〜7:30)、 散布直後(7:30〜8:00)、1 時間後(8:30〜9:00)、3 時間後
(10:30〜11:30)及び6 時間後(13:30〜14:30)の風向は主に南西〜南東、平均風速は0.4
〜1.9m/s であった。散布1 日後から散布14 日後の風向は主に南東または北東、平均
風速は0.0〜2.9m/s であった。
(3)日射量及び雨量
調査期間中の天候は概ね晴天であったため、日射量は高い状況が続いていた。1 日
後の夕方及び夜間(計2.2mm)、2 日後の夕方(計0.2mm)、3 日後の早朝(計0.2mm)、
4 日後の昼間及び夜間(計2.2mm)、7 日後の昼間から夕方(計5.0mm)、12 日後の朝
から昼間及び夜間(計5.2mm)、13 日後の朝(計0.4mm)に降雨があった(表3)。た
だし、調査時間帯においての降雨はなかった。
6.気中濃度調査
(1)大気の捕集状況
調査状況(捕集時刻と吸引量等)を表4 に示した。
(2)気中濃度
各調査地点における各調査農薬の気中濃度の結果を表5 及び図2 に示した。
1)フェニトロチオン(MEP)
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.90〜3.58μg/m3)、散布直後(2.35〜4.63μg/m3)、1 時間後(2.21〜5.08
μg/m3)及び3 時間後(0.93〜3.61μg/m3)の気中濃度はほぼ同程度であったが、6
時間後(0.63〜1.36μg/m3)から徐々に減少し、散布1 日後(0.06〜0.28μg/m3)で
はおよそ1/10〜1/30 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
2)トリクロルホン(DEP)
気中濃度は、散布1 日後の地点C の高さ1.5mで検出限界未満であったことを除き、
散布中から散布1 日後の調査において検出された。
散布中(1.9〜5.5μg/m3)、散布直後(4.0〜12μg/m3)、1 時間後(2.2〜4.6μg/m3)
及び3 時間後(1.8〜3.6μg/m3)の気中濃度はほぼ同程度であったが、6 時間後(0.7
〜3.2μg/m3)から徐々に減少し、散布1 日後(<0.1〜0.3μg/m3)ではおよそ1/10〜
1/60 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
3)ジクロルボス(DDVP)
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.71〜4.30μg/m3)及び散布直後(1.35〜2.85μg/m3)の気中濃度はほぼ
同程度であったが、1 時間後(0.61〜1.30μg/m3)から徐々に減少し、3 時間後(0.25
〜1.02μg/m3)には1/4〜1/7、6 時間後(0.03〜0.21μg/m3)には1/8〜1/108、散布 1
日後(0.02〜0.04μg/m3)ではおよそ1/70〜1/160 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
4)エトフェンプロックス
気中濃度は、散布中(0.03〜0.13μg/m3)、6 時間後(0.03μg/m3)及び散布1 日後
(0.02μg/m3)に検出された以外すべて検出されなかった。
高さ別の気中濃度は、検出された濃度が低いため差が判然としなかった。
5)イソキサチオン
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.24〜0.97μg/m3)、散布直後(0.32〜0.75μg/m3)、1 時間後(0.42〜1.35
μg/m3)、3 時間後(0.24〜1.19μg/m3)及び6 時間後(0.07〜0.96μg/m3)の気中濃
度はほぼ同程度であったが、散布1 日後(0.05〜0.29μg/m3)ではおよそ1/4〜1/10
に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
7.土壌中濃度調査
各調査地点における各調査農薬の土壌中濃度の結果を表6 及び図3 に示した。
(1)フェニトロチオン(MEP)
土壌中の残留濃度は、散布5 日後までほとんど減少は見られなかった。散布14 日では1/2 程度まで減少した。
(2)トリクロルホン(DEP)
土壌中の残留濃度は、すべて検出限界値未満であった。
(3)ジクロルボス(DDVP)
土壌中の残留濃度は、散布5 日後では減少は見られなかった。散布7 日後で1/2、散布14 日後では1/10 程度まで減少した。
(4)エトフェンプロックス
土壌中の残留濃度は、散布14 日後でもほとんど減少は見られなかった。
(5)イソキサチオン
土壌中の残留濃度は、散布14 日後でもほとんど減少は見られなかった。
8.葉中濃度調査(葉への付着量)
各調査地点における各調査農薬の濃度、葉の分析重量及び表面積(片面)、それらから算出した単位面積当たりの換算付着量を表7 及び図4 に示した。
(1)フェニトロチオン(MEP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/4、散布2 日後に1/7、散布7日後に1/30、散布14 日後には1/80 に減少した。
(2)トリクロルホン(DEP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/4、散布2 日後に1/7、散布7日後に1/20 に減少し、散布14 日後では1/20 であった。
(3)ジクロルボス(DDVP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/6、散布2 日後に1/13、散布5日後に1/50 に減少し、散布14 日後でも1/50 であった。
(4)エトフェンプロックス
葉への付着量は、散布直後、散布1 日後及び散布2 日後ではほぼ同程度であり、散布5 日後にわずかに減少が見られたが、その後は減少せず散布14 日後でも同程度であった。
(5)イソキサチオン
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後にわずかに減少し、散布2 日後及び散布5 日後には1/2 と減少が見られた。その後は散布7 日後及び散布14 日後に1/3程度に減少した。
9.落下量調査
各調査地点における各調査農薬の散布中の落下量の結果を表8 示した。
[まとめ]
1.気中濃度調査
表5 に示した各調査農薬の気中濃度から高さ0.2m及び高さ1.5mの平均値を求め表
9 及び図5 に示した。
フェニトロチオン及びトリクロルホンは、検出された濃度に違いは見られたが、散
布中または散布直後に最高濃度を示し、その後減少する傾向が見られた。これらの農
薬については、蒸気圧は同程度であるが、水に対する溶解性が違うために検出される
濃度に違いが現れたのではないかと考えられる。
ジクロルボスは、散布中及び散布直後に最高濃度を示し、その後減少する傾向が見
られた。トリクロルホンの代謝物であるため、検出された濃度が低くなったのではと
推察される。
イソキサチオンは、散布中から6 時間後までは同じ濃度が続き、散布1 日後に減少
する傾向が見られた。
エトフェンプロックスは、散布中のみ検出された。6 時間後及び散布1 日後に検出
されたことは、土壌などの舞い上がりを捕捉したことによると考えられる。
高さ別の気中濃度は、散布直後よりほとんど検出されなかったエトフェンプロック
スを除き、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。6 時間後では高さ1.5m
が高さ0.2mより高い傾向が見られたのは、土壌及び周辺樹木に付着している農薬の
揮散による影響と考えられる。
今回の調査結果から成分投下量が同じであったフェニトロチオン及びイソキサチオ
ン、それより少ないトリクロルホンの気中濃度には明らかに違いが見られた。このこ
とは、蒸気圧等の物理化学的性状が影響をあたえているのではないかと考えられる。
また、斎藤ら5)は農業の農薬散布現場において、散布中から散布後3 時間までの落
下量を30 分ずつ連続で調査し、噴霧粒子は散布中に約90%落下していると報告して
いる。このことから、散布中の気中濃度は散布された噴霧粒子(ミスト)を捕らえて
いると考えられる。
2.土壌中濃度調査
表6 に示した各調査農薬の土壌中濃度から平均値を求め、表10 及び図6 に示した。フェニトロチオン、エトフェンプロックス及びイソキサチオンは、検出された濃度に違いは見られたが、減少の傾向は同じであったと思われる。
このことは、これら農薬の土壌中半減期がほぼ同じであることによるかは定かではない。イソキサチオンの濃度が散布14 日後に高くなったことは、フェニトロチオン及びエトフェンプロックスの地点においても見られていることから、土壌採取場所のバラツキ及び散布12 日後及び13 日後における降雨の影響があったのではないかと考えられる。
トリクロルホンは、すべて検出限界値未満であった。これは、速やかに分解するという土壌半減期のため減少したのではないかと考えられる。
今回の調査結果から散布直後の濃度と比較して1/2 の濃度となったのは、フェニトロチオンで散布14 日後及びジクロルボスで散布7 日後であり、エトフェンプロックス及びイソキサチオンでは散布14 日後以降であると推察される。
3.葉中濃度調査(葉への付着量)
表7 に示した各調査農薬の葉への付着量から平均値を求め、表11 及び図7 に示した。フェニトロチオン、トリクロルホン及びジクロルボスは、検出された濃度に違いは見られたが、散布1 日後には大きく減少し、その後も同じように減少する傾向が見ら
れた。
エトフェンプロックスは、ほとんど減少が見られなかったが、その要因については定かではない。
イソキサチオンは、散布7 日後より14 日後に少し高くなったが、落下量のバラツキ及び葉採取場所の違いによるものと考えられる。
参考文献
1)農薬ハンドブック2005 年版(改訂新版)社団法人日本植物防疫協会
2)環境省環境保健部環境リスク評価室:化学物質の環境リスク評価第2 巻(2003 年3 月)第1編 ?.(?)[9]イソキサチオン、[28]ジクロルボス、[53]フェニトロチオン
3)国立医薬品食品衛生研究所:トリクロルホン、環境保健クライテリア(EnvironmentalHealth Criteria)132 日本語抄訳(原著162 頁、1992 年発行)
4)トレボン乳剤、製品安全データシート(MSDS):サンケイ化学株式会社(改訂2007年4 月26 日)
5)斎藤ら:地上防除及び無人ヘリ防除における有機リン系農薬の気中濃度・落下量、第28 回農薬製剤・施用法研究会、技術研究発表T5、2008(平成20 年)
http://www.env.go.jp/water/report/h21-02/full.pdf
結果報告書
平成21年3月
社団法人 農林水産航空協会
要 約
市街地における街路樹や公園の花木類等管理のために散布される農薬の飛散リスクの影響を評価・管理する手法を確立するため、平成18年度及び平成19年度モニタリング調査結果を踏まえて、農薬飛散範囲調査、農薬検出期間調査および除草剤散布後気中濃度等調査を実施した。
農薬飛散範囲調査は、立木1本に対して水を散布し、樹高、樹形、風の条件、散布方向の違いについて、周辺への飛散状況を調査した。調査は、樹の中心から8方位に、樹高の条件により10mまたは15mまでの距離で調査地点に感水調査紙を設置して行った。感水調査紙は、画像処理ソフトウエアにより、被覆面積率および付着液量の推定を行った。
飛散状況は、樹が高いほど、また、枝葉が繁茂しているほど多かった。樹高4m 程度の樹に対しては、手の届く範囲で近距離からの散布ができることから、飛散が少なかったものと考えられる。枝葉が繁茂した樹形は散布水量が多くなることから、その分飛散のリスクが増えるものと考えられた。
しかし、風の強い条件では、散布方法より風の影響の方が強いと考えられ、平均風速が2m/s 程度であっても、風下側では15m 先へも飛散する可能性が十分にあると考えられた。
付着液量の推定は、1 樹当たりの散布水量と、8 方位の距離別にブロック分けした場所においての付着液量の比率の風下側最遠調査地点での最大値は、平方メートルあたり0.03%であった。
農薬検出期間調査は、公園等での使用実績のあるフェニトロチオン、トリクロルホン、エトフェンプロックス及びイソキサチオンの4 剤を混用して、調査対象の樹木林に散布し、気中濃度濃度調査、土壌中濃度調査及び葉への付着量調査を実施した。気中濃度は、調査農薬により検出された値に違いは見られたが、それら農薬の蒸気圧等の物理化学的性状が影響をあたえて
いのではないかと考えられた。
土壌中濃度で散布直後の濃度と比較して1/2 の濃度となったのは、フェニトロチオンで散布14 日後、ジクロルボスで散布7 日後、エトフェンプロックス及びイソキサチオンでは散布14 日後以降であると推察された。葉への付着量では、フェニトロチオン、トリクロルホン及びジクロルボスは同じようなに減少する傾向が見られ、散布14日後で1/80、1/20 及び1/50 まで減少し、当初の濃度が低かったイソキサチオンとエトフェンプロックスは散布14 日後で1/3 及び3/5 と減少は少なかった。
除草剤散布後気中濃度等調査は、使用実績のあるグリホサートの散布後に気中濃度調査、土壌中濃度調査及び葉中濃度調査を実施した。気中濃度では、散布区域内の高さ0.2mの地点で散布当日の13 時のみに検出されたことは、一度散布された農薬が蒸散した結果と考えるには、最も値が高いはずの散布直後に検出されていないことと、その検出濃度などから、植物体を経由したカラムの汚染による可能性が高いのではないかと考えられる。土壌中濃度は、散布直後と散布30 日後の濃度に違いは見られなかった。葉中濃度は、散布直後に高い濃度が検出され、散布1 日後に大きく減少した。
Summary
Based on the results of serial monitoring studies conducted in 2006 and 2007,dispersion range, duration of detection period, and concentrations in air of heirbicide after spraying were
investigated to establish the methods for evaluation and management of dispersal risks of
agrochemicals applied for maintenance of greenery on roadside tree or in parks.
For the purpose of estimation of dispersion range, a tree was sprayed with water and profiled
for the water dispersion toward surrounding area. The results were analyzed in terms of height
and shape of trees,wind condition,difference of spraying orientation. Sheets of water-sensitive
paper were placed 10 to 15 m from the center of a tree depending on height of trees in eight
azimuth directions. Ratio of the covered area and amount of attached solution were estimated
by measuring the wet area on the water sensitive papers using image analysis software.
The extent of dispersion was increased in accordance with the height of trees and the density
of branches and foliages. Trees as low as 4 m in height showed less dispersion probably due
to the spraying from closer distance within the reach of equipment. The elevated amount of
sprayed agrochemicals required for trees with dense branches and foliages seemed to give rise
to risk of dispersion. However, wind effect prevailed over spraying method especially under
strong wind condition. The downwind dispersion as far as 15 m can be observed even at the
wind speed of 2 m/s.
On spraying a tree, a ratio of the amount of attached solution versus that of sprayed solution
was calculated at each sampling point in eight azimuth directions differing in distance from
the sprayed site. The maximum ratio at the furthest downwind sampling point was estimated
to 0.03% per square meter.
Four agrochemicals with past application records in parks such as fenitrothion, trichlorphon,
etofenprox,and isoxathion were selected and adopted for determining the duration of detection
period. The combined agrochemicals were sprayed over trees and concentration in air,soil
concentration,and deposit on foliage were measured. The difference in concentration in air of
the individual agrochemicals could be ascribed to physicochemical characters such as vapor
pressure. Half-lives of fenitrothion, etofenprox, and isoxathion in soil were estimated to 14
days, 7 days, and 14 days, respectively. Fenitrothion, trichlorphon, and dichlorvos on leaves
showed the same decaying tendency, and the amount of the each substance decreased to
1/80-fold, 1/20-fold, and 1/50-fold of the primary amounts after 14 days from application.
Isoxathion and etofenprox with less primary attachment to leaves decreased to 1/3 and 3/5 of
the primary concentration after 14 days from application.
Glyphosate which has the solid past application records was adopted for the study of
post-application monitoring of herbicides. After spraying, glyphosate concentrations in the air,
in soil, and in leaves were monitored. The sole detection of concentrations in air was observed
at 13:00 on the day of spraying. The concentrations in air were not detected immediately after
spraying and the concentration of the detected glyphosate was too low. Therefore the
detection of glyphosate was most likely due to contamination of the trapping column in
contact with sprayed plants, rather than the evaporation of glyphosate. There was no
significant difference between glyphosate concentration in soil of immediate aftermath of
spraying and that of 30 days after spraying. In leaves, large amount of glyphosate was
detected immediately after spraying, while significant decrease of glyphosate was recognized
a day after spraying.
はじめに
この報告書は、環境省大気局農薬環境管理課から社団法人農林水産航空協会に委託された「平成20年度農薬飛散リスク評価手法確立調査(モニタリング調査業務)」の実施成果をとりまとめたものである。
本調査は、市街地における街路樹や公園の花木類等管理のために散布される農薬の飛散リスクの影響を評価・管理する手法を確立するに当たって、公園等を利用する一般市民及び公園等周辺住民の健康を保護する観点から、公園内及び周辺における農薬の気中濃度及び飛散等による曝露実態を把握するために実施した平成18年度及び平成19年度モニタリング調査結果を踏まえて、農薬飛散範囲調査、農薬検出期間調査および除草剤散布後気中濃度等調査を実施した。
平成21年3月
東京都千代田区平河町2−7−1 塩崎ビル3階
社団法人 農林水産航空協会 会 長 関 口 洋 一
目 次
?.農薬飛散範囲調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
?.農薬検出期間調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
?.除草剤散布後気中濃度等調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
要 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114
平成20 年度農薬飛散リスク評価手法確立調査(モニタリング調査業務)
[目的]
環境省では平成17 年度から農薬飛散リスク評価手法確立調査を開始し、街路樹や公園等の市街地において使用される農薬の飛散リスクの評価・管理手法について検討しているところであり、これまでに、国内外における農薬飛散リスクの評価・管理手法に関する文献調査、自治体での防除実態を把握するためのアンケート調査(平成17 年度)、実際の農薬散布場
面におけるモニタリング調査(平成18・19 年度)と、蒸気圧等の要因別の影響調査を含む基礎調査(平成19 年度)を実施し、農薬の飛散による暴露実態を把握するための基礎資料を得た。
平成20 年度の本業務では平成19 年度までの結果を踏まえた上でモニタリング調査を実施し、農薬の飛散による暴露実態を把握するうえでの基礎資料を得る。
[調査項目]
?.農薬飛散範囲調査
樹木等に対して通常用いられる農薬散布用器具を用いて水を散布し、感水紙を用いて、周囲への到達落下範囲を調査する。
?.農薬検出期間調査
農薬散布にあたり最も高濃度が検出される地点において十分減衰するまでの期間が立ち入り禁止期間となると考える。
したがって、高木が複数存在する区域を設定して調査地点を置き、農薬散布後の気中濃度低減の調査を行うとともに、当該地点における葉及び土壌での残留量を計測する。
?.除草剤散布後気中濃度等調査
雑草等が生えている場所に除草剤(グリホサート)を散布した場合、その周囲への飛散の程度、気中濃度、及び散布地点の土壌の残留について調査を行うこととする。
?.農薬飛散範囲調査
[調査内容]
1.調査実施場所
(社)農林水産航空協会 農林航空技術センター敷地内(長野県小諸市)
2.調査方法
(1)調査樹
樹種:オウシュウトウヒ(ドイツトウヒ)
樹高:中木4.2m、高木?(疎密)8.3m、高木?(繁茂)8.7m の3 形態(写真1)。
(2)調査の組み合わせ
樹高・樹形:中木、高木?(枝葉疎密)と高木?(枝葉繁茂)の比較。
ノズル:慣行と飛散低減の比較。
風速:平穏〜軽風(0〜1.5m/s)と軽風(1.6〜3.3m/s)の比較。
散布方向:高木?において、下からの吹上げと横方向からの散布の比較。
各調査は反復を2 回とした。
(3)感水紙の設置
調査対象となる樹木を中心に、8 方向に、樹木から3m、5m、10m の距離に地上高50 ?の高さに感水紙を水平に設置し、散布した水の飛散状況を調査した。なお、軽風条件下においては15m 地点にも設置した。
感水紙は、WATER SENSITEVE PAPER(スプレーイングシステム株式会社製)を使用した。
(4)感水紙の解析方法
感水紙は、散布開始前から散布終了後5 分まで設置し、変色量を画像解析ソフト、ImageJ(バイオアーツ株式会社製)を用い、被覆面積率を測定した。
感水紙の一部については、画像解析ソフト、まいA のーど(ノズルネットワーク株式会社製)により、付着液量の推定を行った。
なお、感水紙の画像の解像度は、1 ドット約64 ?(約400dpi)であった。
(5)散布方法
動力噴霧機:セット動噴MS253(株式会社丸山製作所製)
散布ノズル
慣行ノズル:アルミズームα900 型(ヤマホ工業株式会社製)噴霧粒径95〜360μm(写真2)
飛散低減ノズル:キリナシズーム900 型(ヤマホ工業株式会社製)
噴霧粒径380〜710μm(写真2)
*圧力1.5MPa での平均粒径(データはヤマホ工業株式会社提供)圧力:全て1.5MPa
(6)風向風速の計測
風向風速は、デジタルハンド風向風速計26D-B?(株式会社太田計器製作所製)で測定した。
[調査結果]
1.散布状況
調査に使用したノズルは、2 種とも、手元のグリップを回転させることにより遠距離噴霧(狭角)と近距離噴霧(広角)の調節ができるため、高木?、?の吹き上げ散布は、遠距離噴霧で、中木および高木?の横方向からの散布は近距離噴霧で行った。
中木は、手の届く範囲で概ね横方向からの散布となった。
高木?の横方向からの散布は、長さ4m の直管にノズルを取り付け行った。
散布水量は、予め練習散布で枝葉が十分に濡れ水が滴り落ちる程度を十分量と定め、噴霧時間を合わせることにより散布量が一定となるようにした。
散布は、条件を統一にするため、風向にかかわらずに散布者が樹の周囲を移動し、全周方向から行った。
2.飛散状況
飛散状況調査は、表2 の組み合わせで行い、その結果を表3 及び図1〜図16 に示した。
全体の飛散程度を検討するため、表3 より距離ごとに8 方位の感水紙における飛散の被
覆面積率(以下「被覆面積率」という)の合計値と飛散が確認された感水紙数を取りまと
め、表4 に示した。
樹高の影響については風の条件ごとに比較し図17 に、樹形の影響については高木につい
て風の条件を比較し図18 に、ノズルの影響、散布方向の影響については風の条件と樹高・
樹形を比較し図19 に、風速の影響については樹高・樹形と散布方法を比較し図20 に、風
向の影響については地点ごとの被覆面積率を比較し図1〜16 に示した。
(3)ノズルの影響について
中木では、平穏〜軽風の条件で飛散低減ノズルの被覆面積率の値が5m、10m で低かった。
軽風では飛散低減ノズルの値が3m、5m で低かった。
高木では、軽風で散布方法が吹上の条件では、3m 地点では慣行ノズルの値が低かったが、
10m、15m 地点では、低減ノズルの値が低かった。それ以外の条件では明らかな飛散程度の差
は認められなかった。
(4)散布方向の影響について(図19)
平穏〜軽風で低減ノズルの条件では、横方向からの散布が吹上での散布に比べて値が低か
った。軽風条件では、散布方向による明らかな差は認められなかった。
横方向からの散布はより上方へ到達する水量が、吹上での散布に比べ少ないと考えられる
ことから、飛散が低減されるものと考えられるが、風が強い場合は、風の影響の方が大きい
ものと考えられる。
図19 ノズル・散布方向の影響
(5)風速の影響について
中木では、3m、5m、10m では軽風に比べ平穏〜軽風の被覆面積率の値が明らかに低く、10m
以上で大きく値が減少した。
高木では、平穏〜軽風では3m での値が高く、5m、10m で大きく値が減少している。軽風で
は、3m と5m の値に大きな差が無く、飛散が認められた。
高木?、?ともに吹上散布では、平穏〜軽風の条件では風下方向に限らず、全周に飛散す
る傾向が認められた。軽風条件では、風上では3m の地点でも飛散はほとんど認められなかっ
た。目視では、吹き上げ散布はノズル先端より5m 以上吹き上げており、その結果より高い位
置で広範囲に飛散してしまうため、特に風の弱い状況においては、散布位置の周辺に多く飛
散することが観察された。風が強い場合は、ほとんどが風により風下方向に流されていた。
図20 風の影響
(6)風向の影響について
風下方向では、調査を行った最遠地点の10m(平穏〜軽風)、15m(軽風)まで飛散が認められ
た(図1〜16)。
高木?、?ともに吹上散布では、平穏〜軽風の条件では風下方向に限らず、全周に飛散す
る傾向が認められた(図3〜6)。軽風条件では、風上では3m の地点でも飛散はほとんど認め
られなかった(図11〜14)。
3.飛散量の推定
(1)感水紙の付着液量の推定
画像解析ソフト「まいA のーど」により、感水紙に付着した液量の推定を行った結果を
表5 に示し、被覆面積率と付着液量の関係を図21 に示し、得られた推定式
y=0.0003x2+0.0165x により換算した付着液量を表6 に示した。
また、感水紙の飛散状況(水滴が付着した部分が青色に変色する)の一例を写真5 に示した。
なお、本解析方法では、感水紙上の液滴痕跡が、多く重なったり、つながったりしてい
る状態では、精度が落ちるため、被覆面積率が概ね25%以下のサンプルについてのみ解析
を行った。表6 においても、被覆面積率が25%以上のものについては、換算から除外した。
表5 被覆面積率と付着液量の推定値
(2)総散布量に対する付着液量の割合
被覆面積率から換算した感水紙の付着液量をもとに、図22 に示すように方位ごと距離別
にブロック分けし総散布液量(1 樹当たりの散布水量)に対するブロック全体の面積で換算
した付着液量比率を算出し表6 に示した。
算出にあたっては、3m 地点と5m 地点での付着量の平均値を3m から5m までの範囲の付
着量の平均値、5m 地点と10m 地点での付着量の平均値を5m から10m までの範囲の付着量
の平均値、10m 地点と15m 地点での付着量の平均値を10m から15m までの範囲の付着量の
平均値として換算した。平穏〜軽風の10m から15m までの範囲の付着量の平均値は、10m
地点の1/2 の値とし、同じく軽風の15m から20m までの範囲の付着量の平均値は、15m 地
点の1/2 の値として換算した。
平穏から軽風条件では、総散布量に対する付着液量の割合の最大値は、高木繁茂、横方
向、通常ノズル散布の風下側10m から15m ブロックで0.65%で、平方メートルあたりでは、
0.03%であった。また軽風条件の最大値は、高木疎密、吹上、通常ノズル散布の風下側15m
から20m ブロックで0.93%で、平方メートルあたりでは、0.03%であった。
図22 総散布量に対する付着液量の割合算出における方位・距離別ブロック
[まとめ]
1.飛散状況調査
今回の調査は、立木1 本に対しての散布において、樹高、樹形、風の条件、散布方向の違いについて、周辺への飛散状況を調査したものである。
樹高4m 程度の中木に対しては、手の届く範囲で近距離からの散布ができるのに対し、8m程度の高木は、高いところまで勢い良く吹上る必要があり、その分飛散のリスクが増えるものと考える。
このことは高木で、吹上による散布よりも横方向から散布する方法の方が、飛散程度が少なかったことからも言える。しかし、風の強い条件では、散布方法より風の影響の方が強いと考えられた。
また、繁茂した樹形の方が、疎密のものより飛散程度が多かったことから、散布水量が多いことによると考えられる。
以上のことから、散布時の飛散リスクには、樹高及び風の条件が最も重要であり、次に散布量の影響が見られる。なお、平均風速が2m/s 程度であっても、風下側では15m 先へも飛散する可能性が十分にあると考えられる。
2.飛散量の推定
感水紙の画像解析による付着液量の推定調査については、感水紙上の痕跡が粒子状であり、重なりが少ないほど精度が良いと考えられる。このため本調査においては、被覆面積率が25%以下のサンプルについてのみ解析を行った。
本調査において、被覆面積率と画像処理ソフトにより測定した付着液量の間には、一定の相関が認められ、推定式により、被覆面積率から感水紙の付着液量の推定が可能であると考えられた。1 樹当たりの散布水量と、8 方位の距離別にブロック分けした場所においての付着液量の比率の風下側最遠調査地点での最大値は、平方メートルあたり0.03%であった。
ただし、本結果は、本調査における画像解析に係る機器、ソフトウエアの組み合わせで得られたものであり、他の組み合わせについては別に検討が必要である。
?.農薬検出期間調査
[調査内容]
1.調査場所
(社)農林水産航空協会 農林航空技術センター敷地内(長野県小諸市)
2.調査実施期間
平成20 年8 月11 日(散布前日)〜8 月26 日(散布14 日後)
3.散布概要
散布面積:およそ1,000 ?
散布農薬の概要を下表に示した。
散布諸元
ポンプ:動力噴霧器 MS903(株式会社丸山製作所製)
エンジン:ブリッグス20HP(ブリッグス&ストラットンジャパン製)
使用ノズル: 松喰虫ノズル(株式会社永田製作所製)
噴霧形状:高木樹が多いため直射噴霧とし、低木へは圧を弱めやや広角に散布
圧力:30kgf/c ?(3.0MPa)
散布量(4 農薬を混用):400 ?/1000 ?(葉から滴り落ちる程度)
4.調査農薬成分
フェニトロチオン
トリクロルホン
ジクロルボス(トリクロルホンの代謝物)
エトフェンプロックス
イソキサチオン
5.調査項目
(1)気中濃度調査
調査は、「航空防除農薬環境影響評価検討会報告書(平成9 年12 月、環境庁水質保全局)の測定方法に準じた手法を用いて行った。
1)調査地点
3 地点A、B、C を設定し、各地点で1.5mの高さ及び0.2mの高さとした。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布中、散布直後、散布1 時間後、3 時間後及び6 時間後)及び散布1 日後の所定の時間に行った。
3)捕集時間と捕集量
捕集時間は毎分3 ?の吸入速度で散布前は1 時間とし、散布中及び散布直後の調査時は30 分間、それ以降はすべて1 時間とした。また、散布中の調査は対象樹木への散布が開始された時から30 分間とし、散布直後の調査は「散布中調査」の後
に引き続き30 分間として行った。
大気の捕集は、高度1.5mでは自動大気捕集装置及び高度0.2mではミニポンプとガスメーターを組み合わせた捕集装置を使用した。
4)捕集装置
?自動大気捕集装置 AS-5000 型(株式会社メテク)
?ミニポンプ MP-500Σ(柴田科学株式会社)
乾式ガスメーター:DC-1C(株式会社シナガワ)
5)捕集カラム
?捕集剤 テナックスTA(60/80 mesh) 0.5g充填
?カラム 自動大気捕集装置:内径10mm、全長190mm(捕集剤充填部140mm)ガラス管に捕集剤を充填した。
ミニポンプ:内径12.7mm のポリプロピレンのチューブに捕集剤を充填した。
なお、ミニポンプに使用したカラムは、太陽光などによる影響を避けるため捕集
剤を充填した部分をアルミ箔で覆った。
6)捕集方法
?自動大気捕集装置
各調査地点に捕集カラムをセットした自動大気捕集装置を配置し、所定時間大気を吸引採取した。なお、この装置の吸引口の高さは地上1.5mとなる。
?ミニポンプ
捕集カラムを下向きにし、吸引口は地上0.2mの高さに固定し、ミニポンプで所定時間大気を採取した。吸引量は乾式ガスメーターを用いて測定した。
上記装置により採取された捕集カラムは、直ちに両端を密栓し冷却されたクーラーボックスに保管し分析機関へ送付し、ガスクロマトグラフにより調査対象農薬を分析した。
(2)土壌中濃度調査
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、C の近辺に3 地点A、B、C を設定した。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布直後)、散布1 日後、2 日後、5 日後、7 日後及び14日後の所定の時間に行った。
3)採取方法
ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成20 年3 月改正環境省水・大気環境局土壌環境課)に準じ、区域内より深さ5cm で5 点混合方式にて土壌を採取し、混合したものを分析試料とした。
(3)葉中濃度調査(葉への付着量)
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、C周辺に3地点A、B、Cを設定した。
2)調査期間
散布前、散布当日(散布直後)、散布1 日後、2 日後、5 日後、7 日後及び14日後の所定の時間に行った。
3)試料採取
気中濃度調査の調査地点A、B、C周辺の散布した樹木から、高さ70cm程度にある葉を20g程度採取し、表面積及び重量を測定した後、混合したものを分析した。
(4)落下量調査
1)調査地点
気中濃度調査の調査地点A、B、Cの近辺に3地点A、B、Cを設定した。
2)調査期間
散布当日(散布中)において行った。
3)定量調査
各調査地点に直径9cm のろ紙(ADVANTEC FILTER PAPER No.5A)2 枚を取り付けた調査板を設置した。調査板の高さは地上より1.5mとし、支柱等を利用して水平に設置した。
ろ紙は各調査時間に30 分間設置し回収した。2 枚のろ紙の表側が重なるように折りチャック付きのポリ袋に入れ回収した。試料は冷却されたクーラーボックスに保管し分析機関へ送付し、ガスクロマトグラフにより調査対象農薬を分析した。
なお、同一調査地点における、ろ紙2枚を合わせて1試料とし分析試料とした。
(5)気象観測
調査期間中の温度、降雨量及び日照時間を調査する(1時間間隔)。また、気中濃度測定時には温度、湿度、風向及び風速(平均及び最大)を10 分おきに測定した。
(6)樹木状況等
平成18年度及び平成19年度の調査結果から、散布区域の樹木の密集度合いや樹幹の大きさや枝ぶり等による「うっぺい度合い」、散布方法(散布方向、使用ノズル・噴霧形状等)の違い及び散布時の風向・風速、これらが飛散状況等の結果に影響を及ぼすことから、散布区域の樹木の樹種・樹高等の調査を行った。
(7)目標とする定量下限値
いずれの農薬についても、気中濃度で0.01μg/m3、土壌中濃度で0.01μg/g 及び葉中濃度(葉への付着量)で0.0002μg/cm2 を目標値とした。
[調査結果]
1.農薬分析法の概要
(1)分析農薬及び物理化学的性状
フェニトロチオン(MEP):O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate
トリクロルホン(DEP):dimethyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate
ジクロルボス(DDVP):2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate
エトフェンプロックス:2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
イソキサチオン:O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-yl phosphorothioate
2.調査地点の概況
散布区域は、南西側から北東側に高くなっていく傾斜地であり、散布区域内に分散させて調査地点A、B、Cを設置した(図1、写真1及び写真2)。
3.散布区域の樹木状況
散布区域は自然の雑木林および一部植栽の樹木であり、その状況は表1 及び図1 に示し
たとおりであった(写真3)。下層土壌の土質は褐色森林土壌でシルト質壌土であった。
散布区域の樹種は高木のカラマツ(10〜15m)、中木のコナラ(7〜8m)、ニセアカシア
(7m)、クリ(7m)、ソメイヨシノ(6〜7m)、低木のガマズミ(3m)であった。確認し
た小潅木はマルバハギ(1m)、ヤマザクラ(幼木)などであった。
4.薬剤散布状況
散布作業は、散布区域の北西側にあるクリの木付近から開始し、散布区域脇の道路を
バックする形で移動しながら散布を行い、続けて南西側にあるクリとコナラの木の間を
散布区域北側の地点C 付近まで入って、同じようにバックする形で移動しながら散布を
行った。次に散布区域の南側にあるカラマツおよびクリ付近から北側にあるコナラ方向
に移動しながら散布が行われた。散布時間は7 時より7 時10 分までの10 分間であった
(写真3 及び写真4)。
散布区域の面積はおよそ1000 ?であり、散布量は希釈液で400 ?であった。区域内の
高木および中木数はおよそ40 本であったことから、散布区域に均一に散布されたと考え
ると樹木当りでは10 ?/本であった。
5.気象概況
調査場所は標高800mの高原台地に位置し、夏季においても平野部の気温よりは低い気
象状況であった。
主に散布区域の南西地点において行い、その気象概況を表2 に示した。また、調査期
間中の日射量、日照時間及び雨量を表3 に示した。
(1)天候、温度及び湿度
8 月11 日(散布前日)から8 月26 日(散布14 日後)の調査期間中の調査時間帯に
おける天候は概ね晴れ、温度は22〜30℃、湿度は52〜89%であった。
(2)風向・風速
調査期間中の気中濃度調査実施時(散布当日及び散布1 日後)の風向は、南東から
南西であり、斜面となっている散布区域内を南西側から北東側に風が抜ける形となっ
た。
散布中(7:00〜7:30)、 散布直後(7:30〜8:00)、1 時間後(8:30〜9:00)、3 時間後
(10:30〜11:30)及び6 時間後(13:30〜14:30)の風向は主に南西〜南東、平均風速は0.4
〜1.9m/s であった。散布1 日後から散布14 日後の風向は主に南東または北東、平均
風速は0.0〜2.9m/s であった。
(3)日射量及び雨量
調査期間中の天候は概ね晴天であったため、日射量は高い状況が続いていた。1 日
後の夕方及び夜間(計2.2mm)、2 日後の夕方(計0.2mm)、3 日後の早朝(計0.2mm)、
4 日後の昼間及び夜間(計2.2mm)、7 日後の昼間から夕方(計5.0mm)、12 日後の朝
から昼間及び夜間(計5.2mm)、13 日後の朝(計0.4mm)に降雨があった(表3)。た
だし、調査時間帯においての降雨はなかった。
6.気中濃度調査
(1)大気の捕集状況
調査状況(捕集時刻と吸引量等)を表4 に示した。
(2)気中濃度
各調査地点における各調査農薬の気中濃度の結果を表5 及び図2 に示した。
1)フェニトロチオン(MEP)
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.90〜3.58μg/m3)、散布直後(2.35〜4.63μg/m3)、1 時間後(2.21〜5.08
μg/m3)及び3 時間後(0.93〜3.61μg/m3)の気中濃度はほぼ同程度であったが、6
時間後(0.63〜1.36μg/m3)から徐々に減少し、散布1 日後(0.06〜0.28μg/m3)で
はおよそ1/10〜1/30 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
2)トリクロルホン(DEP)
気中濃度は、散布1 日後の地点C の高さ1.5mで検出限界未満であったことを除き、
散布中から散布1 日後の調査において検出された。
散布中(1.9〜5.5μg/m3)、散布直後(4.0〜12μg/m3)、1 時間後(2.2〜4.6μg/m3)
及び3 時間後(1.8〜3.6μg/m3)の気中濃度はほぼ同程度であったが、6 時間後(0.7
〜3.2μg/m3)から徐々に減少し、散布1 日後(<0.1〜0.3μg/m3)ではおよそ1/10〜
1/60 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
3)ジクロルボス(DDVP)
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.71〜4.30μg/m3)及び散布直後(1.35〜2.85μg/m3)の気中濃度はほぼ
同程度であったが、1 時間後(0.61〜1.30μg/m3)から徐々に減少し、3 時間後(0.25
〜1.02μg/m3)には1/4〜1/7、6 時間後(0.03〜0.21μg/m3)には1/8〜1/108、散布 1
日後(0.02〜0.04μg/m3)ではおよそ1/70〜1/160 に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
4)エトフェンプロックス
気中濃度は、散布中(0.03〜0.13μg/m3)、6 時間後(0.03μg/m3)及び散布1 日後
(0.02μg/m3)に検出された以外すべて検出されなかった。
高さ別の気中濃度は、検出された濃度が低いため差が判然としなかった。
5)イソキサチオン
気中濃度は、散布中から散布1 日後の調査においてすべて検出された。
散布中(0.24〜0.97μg/m3)、散布直後(0.32〜0.75μg/m3)、1 時間後(0.42〜1.35
μg/m3)、3 時間後(0.24〜1.19μg/m3)及び6 時間後(0.07〜0.96μg/m3)の気中濃
度はほぼ同程度であったが、散布1 日後(0.05〜0.29μg/m3)ではおよそ1/4〜1/10
に減少した。
高さ別の気中濃度は、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。
7.土壌中濃度調査
各調査地点における各調査農薬の土壌中濃度の結果を表6 及び図3 に示した。
(1)フェニトロチオン(MEP)
土壌中の残留濃度は、散布5 日後までほとんど減少は見られなかった。散布14 日では1/2 程度まで減少した。
(2)トリクロルホン(DEP)
土壌中の残留濃度は、すべて検出限界値未満であった。
(3)ジクロルボス(DDVP)
土壌中の残留濃度は、散布5 日後では減少は見られなかった。散布7 日後で1/2、散布14 日後では1/10 程度まで減少した。
(4)エトフェンプロックス
土壌中の残留濃度は、散布14 日後でもほとんど減少は見られなかった。
(5)イソキサチオン
土壌中の残留濃度は、散布14 日後でもほとんど減少は見られなかった。
8.葉中濃度調査(葉への付着量)
各調査地点における各調査農薬の濃度、葉の分析重量及び表面積(片面)、それらから算出した単位面積当たりの換算付着量を表7 及び図4 に示した。
(1)フェニトロチオン(MEP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/4、散布2 日後に1/7、散布7日後に1/30、散布14 日後には1/80 に減少した。
(2)トリクロルホン(DEP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/4、散布2 日後に1/7、散布7日後に1/20 に減少し、散布14 日後では1/20 であった。
(3)ジクロルボス(DDVP)
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後に1/6、散布2 日後に1/13、散布5日後に1/50 に減少し、散布14 日後でも1/50 であった。
(4)エトフェンプロックス
葉への付着量は、散布直後、散布1 日後及び散布2 日後ではほぼ同程度であり、散布5 日後にわずかに減少が見られたが、その後は減少せず散布14 日後でも同程度であった。
(5)イソキサチオン
葉への付着量は、散布直後に比べ、散布1 日後にわずかに減少し、散布2 日後及び散布5 日後には1/2 と減少が見られた。その後は散布7 日後及び散布14 日後に1/3程度に減少した。
9.落下量調査
各調査地点における各調査農薬の散布中の落下量の結果を表8 示した。
[まとめ]
1.気中濃度調査
表5 に示した各調査農薬の気中濃度から高さ0.2m及び高さ1.5mの平均値を求め表
9 及び図5 に示した。
フェニトロチオン及びトリクロルホンは、検出された濃度に違いは見られたが、散
布中または散布直後に最高濃度を示し、その後減少する傾向が見られた。これらの農
薬については、蒸気圧は同程度であるが、水に対する溶解性が違うために検出される
濃度に違いが現れたのではないかと考えられる。
ジクロルボスは、散布中及び散布直後に最高濃度を示し、その後減少する傾向が見
られた。トリクロルホンの代謝物であるため、検出された濃度が低くなったのではと
推察される。
イソキサチオンは、散布中から6 時間後までは同じ濃度が続き、散布1 日後に減少
する傾向が見られた。
エトフェンプロックスは、散布中のみ検出された。6 時間後及び散布1 日後に検出
されたことは、土壌などの舞い上がりを捕捉したことによると考えられる。
高さ別の気中濃度は、散布直後よりほとんど検出されなかったエトフェンプロック
スを除き、高さ0.2mが高さ1.5mより高い傾向が見られた。6 時間後では高さ1.5m
が高さ0.2mより高い傾向が見られたのは、土壌及び周辺樹木に付着している農薬の
揮散による影響と考えられる。
今回の調査結果から成分投下量が同じであったフェニトロチオン及びイソキサチオ
ン、それより少ないトリクロルホンの気中濃度には明らかに違いが見られた。このこ
とは、蒸気圧等の物理化学的性状が影響をあたえているのではないかと考えられる。
また、斎藤ら5)は農業の農薬散布現場において、散布中から散布後3 時間までの落
下量を30 分ずつ連続で調査し、噴霧粒子は散布中に約90%落下していると報告して
いる。このことから、散布中の気中濃度は散布された噴霧粒子(ミスト)を捕らえて
いると考えられる。
2.土壌中濃度調査
表6 に示した各調査農薬の土壌中濃度から平均値を求め、表10 及び図6 に示した。フェニトロチオン、エトフェンプロックス及びイソキサチオンは、検出された濃度に違いは見られたが、減少の傾向は同じであったと思われる。
このことは、これら農薬の土壌中半減期がほぼ同じであることによるかは定かではない。イソキサチオンの濃度が散布14 日後に高くなったことは、フェニトロチオン及びエトフェンプロックスの地点においても見られていることから、土壌採取場所のバラツキ及び散布12 日後及び13 日後における降雨の影響があったのではないかと考えられる。
トリクロルホンは、すべて検出限界値未満であった。これは、速やかに分解するという土壌半減期のため減少したのではないかと考えられる。
今回の調査結果から散布直後の濃度と比較して1/2 の濃度となったのは、フェニトロチオンで散布14 日後及びジクロルボスで散布7 日後であり、エトフェンプロックス及びイソキサチオンでは散布14 日後以降であると推察される。
3.葉中濃度調査(葉への付着量)
表7 に示した各調査農薬の葉への付着量から平均値を求め、表11 及び図7 に示した。フェニトロチオン、トリクロルホン及びジクロルボスは、検出された濃度に違いは見られたが、散布1 日後には大きく減少し、その後も同じように減少する傾向が見ら
れた。
エトフェンプロックスは、ほとんど減少が見られなかったが、その要因については定かではない。
イソキサチオンは、散布7 日後より14 日後に少し高くなったが、落下量のバラツキ及び葉採取場所の違いによるものと考えられる。
参考文献
1)農薬ハンドブック2005 年版(改訂新版)社団法人日本植物防疫協会
2)環境省環境保健部環境リスク評価室:化学物質の環境リスク評価第2 巻(2003 年3 月)第1編 ?.(?)[9]イソキサチオン、[28]ジクロルボス、[53]フェニトロチオン
3)国立医薬品食品衛生研究所:トリクロルホン、環境保健クライテリア(EnvironmentalHealth Criteria)132 日本語抄訳(原著162 頁、1992 年発行)
4)トレボン乳剤、製品安全データシート(MSDS):サンケイ化学株式会社(改訂2007年4 月26 日)
5)斎藤ら:地上防除及び無人ヘリ防除における有機リン系農薬の気中濃度・落下量、第28 回農薬製剤・施用法研究会、技術研究発表T5、2008(平成20 年)
http://www.env.go.jp/water/report/h21-02/full.pdf
2009年10月22日
(工事中)汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
1.汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令の概要
(1)制定の趣旨
改正法附則第2条(汚染土壌処理業の許可の申請の手続に係る規定)については、本年10月23日までの政令で定める日から施行するとされているところ。土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令により、同条の施行日が本年10月23日とされたことに伴い、当該許可申請に必要となる手続の細目のほか、当該許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める必要があることから、そのための省令の制定を行うもの。
(2)省令の内容
[1] 汚染土壌処理施設の種類(第1条関係)
改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第22条第2項第3号において、汚染土壌処理施設の種類が申請書の記載事項として定められていることから、汚染土壌処理施設について、当該汚染土壌処理施設における汚染土壌の処理方法に応じて類型化を行い、それぞれについて定義を定めることとする。
[2] 汚染土壌処理業の許可の申請の手続(第2条及び第3条関係)
汚染土壌処理業の許可の申請の手続に必要な申請書の様式、当該申請書の添付書類及び図面並びに新法第22条第2項第1号から第4号までに規定する事項以外の当該申請書の記載事項について定めることとする。
[3] 汚染土壌処理業の許可の基準(第4条関係)
都道府県知事が[2]の申請に応じて汚染土壌処理業の許可を与える際の基準について、汚染土壌処理施設に係るものと申請者の能力に係るものに分けて定めることとする。 [4]汚染土壌の処理に関する基準(第5条関係)
汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理を行うに当たっての基準について定めることとする。 (3)施行
改正法の施行の日(平成22年4月1日)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11694
○環境省令第十号
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
(汚染土壌処理施設の種類)第一条
(汚染土壌処理業の許可の申請)第二条
(汚染土壌処理業の許可の基準)第四条
(汚染土壌の処理に関する基準)第五条
(施行期日)附則
○環境省令第十号
土壌汚染対策法 第二十二条第二項、第三項第一号及び第六項並びに第二十八条の規定に基づき、並びに第二十二条第一項の規定を実施するため、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令を次のように定める。
平成二十一年十月二十二日環境大臣小沢鋭仁
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令

(汚染土壌処理施設の種類)
第一条 土壌汚染対策法 第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 浄化等処理施設汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(以下「規則」という。)第十八条第一項及び
第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二 セメント製造施設汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三 埋立処理施設汚染土壌の埋立てを行うための施設
四 分別等処理施設汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設
(汚染土壌処理業の許可の申請)
第二条 法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 汚染土壌の処理工程図
五 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六 埋立処理施設にあっては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う場合における当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
七 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
九 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十三 申請者が法第二十二条第三項第二号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
十四 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十五 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十六 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第四条第一号ト、第五条第十三号において同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法 第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。第四条第一号チ及び第五条第十四号において同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十七 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類
十八 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
十九 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヌからまでに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。次条第二号において「令」という。)第一条第七号、第十一号、第十二号、第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十 法第二十七条第一項に規定する措置(次号及び第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面
二十一 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しないときの法第十四条第一項の申請を行うことについての当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
二十二 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合における当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該処理を受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書類
3 法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第七号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。
第三条 法第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
二 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
三 汚染土壌の処理の方法
四 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
五 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
六 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の氏名及び住所
七 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
イ 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力

(汚染土壌処理業の許可の基準)
第四条 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に関する基準
イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体、汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
ト 排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第十三号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備及びに掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備?
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(
ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
チ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。排水口における排出水の水質を下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第十二条の二第三項の規定により同令第九条の五第一項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第十四号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
下水道法施行令第九条の四第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第十四号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備
リ 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第十五号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヌ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次のからまでに掲げる大気有害物質の量が当該からまでに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び
環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、、、及びに掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
カドミウム及びその化合物一・〇ミリグラム
塩素三十ミリグラム
塩化水素七百ミリグラム
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素十ミリグラム
鉛及びその化合物二十ミリグラム
窒素酸化物二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄
化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
二 申請者の能力に関する基準
イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者
(1)汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有する者として次に掲げる者
(2)大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
・技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る。)
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者からまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
からまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
(汚染土壌の処理に関する基準)
第五条 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
三 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
四 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第五条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第十八条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第二十四条第一項第一号に規定する第二溶出量基準をいう。第八号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
五 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国
民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
六 浄化等処理施設にあっては、申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
七 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
八 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。
九 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
十 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
十一 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十二 汚水を地下に浸透させてはならないこと。
十三 排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第一号ト及びに掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
?
十四 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
十五 汚染土壌処理施設が設置されている場所にある地下水の下流側の当該汚染土壌処理施設の周縁において、三月に一回以上地下水を採取し、当該地下水の水質を規則第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第六条第一項に規定する地下水基準をいう。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
十六 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ 前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質の量が、排出口において、温度が零度であって、
?
圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該からまでに掲げる許容限度を超える大気有害物質を排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、大気有害物質(前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質を除く。)の量を一年に一回以上、同号ヌの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
十七 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、法第十六条第一項の環境省令で定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合しているものを搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
十八 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
十九 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者にあっては、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、当該処理を終了したときは、法第二十条第四項の規定の例により、当該処理を委託した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
二十 前号の処理を委託した汚染土壌処理業者にあっては、同号の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者にその写しを送付しなければならないこと。
二十一 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二十二 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
二十三 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第三条 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定
(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
2 改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14432&hou_id=11694



(1)制定の趣旨
改正法附則第2条(汚染土壌処理業の許可の申請の手続に係る規定)については、本年10月23日までの政令で定める日から施行するとされているところ。土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令により、同条の施行日が本年10月23日とされたことに伴い、当該許可申請に必要となる手続の細目のほか、当該許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める必要があることから、そのための省令の制定を行うもの。
(2)省令の内容
[1] 汚染土壌処理施設の種類(第1条関係)
改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第22条第2項第3号において、汚染土壌処理施設の種類が申請書の記載事項として定められていることから、汚染土壌処理施設について、当該汚染土壌処理施設における汚染土壌の処理方法に応じて類型化を行い、それぞれについて定義を定めることとする。
[2] 汚染土壌処理業の許可の申請の手続(第2条及び第3条関係)
汚染土壌処理業の許可の申請の手続に必要な申請書の様式、当該申請書の添付書類及び図面並びに新法第22条第2項第1号から第4号までに規定する事項以外の当該申請書の記載事項について定めることとする。
[3] 汚染土壌処理業の許可の基準(第4条関係)
都道府県知事が[2]の申請に応じて汚染土壌処理業の許可を与える際の基準について、汚染土壌処理施設に係るものと申請者の能力に係るものに分けて定めることとする。 [4]汚染土壌の処理に関する基準(第5条関係)
汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理を行うに当たっての基準について定めることとする。 (3)施行
改正法の施行の日(平成22年4月1日)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11694
○環境省令第十号
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
(汚染土壌処理施設の種類)第一条
(汚染土壌処理業の許可の申請)第二条
(汚染土壌処理業の許可の基準)第四条
(汚染土壌の処理に関する基準)第五条
(施行期日)附則
○環境省令第十号
土壌汚染対策法 第二十二条第二項、第三項第一号及び第六項並びに第二十八条の規定に基づき、並びに第二十二条第一項の規定を実施するため、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令を次のように定める。
平成二十一年十月二十二日環境大臣小沢鋭仁
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令

(汚染土壌処理施設の種類)
第一条 土壌汚染対策法 第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 浄化等処理施設汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(以下「規則」という。)第十八条第一項及び
第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二 セメント製造施設汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三 埋立処理施設汚染土壌の埋立てを行うための施設
四 分別等処理施設汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設
(汚染土壌処理業の許可の申請)
第二条 法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 汚染土壌の処理工程図
五 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六 埋立処理施設にあっては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う場合における当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
七 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
九 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十三 申請者が法第二十二条第三項第二号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
十四 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十五 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十六 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第四条第一号ト、第五条第十三号において同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法 第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。第四条第一号チ及び第五条第十四号において同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十七 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類
十八 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
十九 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヌからまでに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。次条第二号において「令」という。)第一条第七号、第十一号、第十二号、第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十 法第二十七条第一項に規定する措置(次号及び第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面
二十一 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しないときの法第十四条第一項の申請を行うことについての当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
二十二 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合における当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該処理を受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書類
3 法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第七号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。
第三条 法第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
二 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
三 汚染土壌の処理の方法
四 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
五 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
六 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の氏名及び住所
七 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
イ 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力

(汚染土壌処理業の許可の基準)
第四条 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に関する基準
イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体、汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
ト 排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第十三号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備及びに掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備?
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(
ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
チ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。排水口における排出水の水質を下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第十二条の二第三項の規定により同令第九条の五第一項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第十四号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
下水道法施行令第九条の四第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第十四号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備
リ 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第十五号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヌ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次のからまでに掲げる大気有害物質の量が当該からまでに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び
環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、、、及びに掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
カドミウム及びその化合物一・〇ミリグラム
塩素三十ミリグラム
塩化水素七百ミリグラム
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素十ミリグラム
鉛及びその化合物二十ミリグラム
窒素酸化物二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄
化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
二 申請者の能力に関する基準
イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者
(1)汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有する者として次に掲げる者
(2)大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
・技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る。)
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者からまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
からまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
(汚染土壌の処理に関する基準)
第五条 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
三 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
四 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第五条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第十八条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第二十四条第一項第一号に規定する第二溶出量基準をいう。第八号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
五 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国
民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
六 浄化等処理施設にあっては、申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
七 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
八 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。
九 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
十 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
十一 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十二 汚水を地下に浸透させてはならないこと。
十三 排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第一号ト及びに掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
?
十四 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
十五 汚染土壌処理施設が設置されている場所にある地下水の下流側の当該汚染土壌処理施設の周縁において、三月に一回以上地下水を採取し、当該地下水の水質を規則第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第六条第一項に規定する地下水基準をいう。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
十六 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ 前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質の量が、排出口において、温度が零度であって、
?
圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該からまでに掲げる許容限度を超える大気有害物質を排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、大気有害物質(前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質を除く。)の量を一年に一回以上、同号ヌの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
十七 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、法第十六条第一項の環境省令で定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合しているものを搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
十八 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
十九 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者にあっては、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、当該処理を終了したときは、法第二十条第四項の規定の例により、当該処理を委託した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
二十 前号の処理を委託した汚染土壌処理業者にあっては、同号の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者にその写しを送付しなければならないこと。
二十一 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二十二 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
二十三 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第三条 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定
(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
2 改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14432&hou_id=11694



2009年10月20日
「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内

「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html


各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html

2009年10月19日
工事中 水循環基本法要綱案&政策大綱案 意見募集
水循環基本法要綱案(原案)
前文
水は、「生命」の基本である。地球上の水は、海洋と太陽エネルギーによつて絶えず循環を繰り返し、多様な生命に思恵を与え続けてきた。
現代においては、水循環系は人間の営為によって不断に直接的・問接的に影響を受けるという点で社会的システムであると言えよう。私たちは、地球上に人為的影響を受けない水循県系は最早存在しないことに深く思いを致し、改変された水循環系を持続可能なシステムに再生する努力を払わなければならない。
国上の70パーセントが森林で覆われ水に恵まれたわが国でも、かつての高度経済成長にともなう国上開発と都市化、工業化、さらに生活の利便性の追求による水循環系への直接的影響によって、生態系保全を伴う水循環系は撹乱され、国土保全力を極度に弱めてきた。
地球温暖化は、このような直接的影響と相侯つて水循乗系の大変動を誘発させ、異常な洪水や極端な渇水をもたらし、生命と生活を脅かす。化学物質による水の汚染は、微量であっても食物連鎖・生物濃縮によつて生命の危険を増大させ、とくに胎児への悪影響に警告が発せられている。
日本人が様々な水の脅威を克服し、日本の水を大切にし、日本の水を飲み、日本の水を使うようにするためには、水循環系に影響を与える人間の営為そのものを適正に制御することによつて、撹乱された水循環系を水量、水質、生態系の面から持続可能なシステムに再構築し、健全な水循環型社会を創出して、それを将来世代に継承しなければならない。このため、水循環基本法を制定することにした。
第一 総則・目的
この法律は、健全で持続可能な水循環型社会の形成について基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、水循環総合基本方針の策定その他の水循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、水循環型社会の形成に関する統合的水管理施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、将来の世代に健全な国上を継承することを目的とする。
,定義(注:今後さらに検討を重ねる。必要語句を追加する。)
〈水循環〉
水循環とは、人間の営為の影響を受けつつ地表水及び地下水となり、蒸発し再び降水となり、あるいは地表での滞留や貯留、土壌への浸透など様々な過程を経て絶えず繰り返す水の循県の過程を言う。
〈統合的水管理〉
統合的水管理とは、現在の縦割型水管理を排し、河川流域を一貫した地表水及び地下水の水量管理、水質管理、生態系管理及び水環境管理を統合した総合的な水管理を言う。
〈河川流域〉
河川流域とは、河川及びその集水域を媒介として、森林、農村、都市、海が結ばれたまとまりのある国上の単位を言う。
(水環境〉
統合的水管理によつて形成され、将来の世代に継承され、国民の全てがその思恵を享受する水の環境で、水量、水質、生態系の面から持統可能な水循環系によつてもたらされたものを言う。
第二 基本理念
(1)地表水及び地下水は公共水であること
地表水及び地下水は、共に公共水であり、流域別水循環計画に基づいて統合的に管理されなければならない。
(2)水循環保全義務と水環境享受権
現在の国民は、現在及び将来の国民のために、持続可能な水循環系を保持する義務を担う。現在及び将来の国民は、水量、水質、生態系の面から持続可能な水循環系によつてもたらされる健全な水環境の思恵を享受する基本的権利を有する。
(3)流域圏の統合的管理
水循環管理は、河川流域を原則的単位として統合的かつ地域主権的に行われなければならない。河川流域を構成する地方公共団体は、相互に協力し、河川及び河川流域を上流の森林や農地から河日沿岸域までを含めて統合的かつ地域主権的に管理する主体である「流域連合」を組織しなければならない。ここで、流域圏の範囲については、複数河川流域に亘る広域生活圏においては当該の全河川流域を包含したものとする。
(4)持続可能な水循環型社会の再生と将来世代への継承
持続可能な水循環型社会の形成は、健全な国土とその上に生活する国民の健康で文化的な生活と幸福追求に不可欠である。このため、これを再生し、将来世代に継承しなければならない。
(5)持続可能な水循環系保全のための公平な役割分担
持続的な水循環系の保全のための行動は、国民、事業者、地方公共団体(流域連合)、国等によつて公平な役割分担の下に行われなければならない。
(6)拡大汚染者責任の原則
通常の生活者が処理処分できない有害物質の生産者、通常の生活者の排出する各種の感染症の原因となる病原菌やウイルス、微量な医薬品や有害化学物質を含む排水の処理に当る事業者及び地方公共団体は、汚染防止について第一次的な責任を有する。
(7)未然防止と予防原則
水循環によつて生じる悪影響は、未然に防止されなければならない。このためには、科学的知見の充実を図るとともに、予防原則の適用を躊躇してはならない。
第二 関係者の責務等・国の責務
国は、「第二 基本理念」にのっとり、水循環の道正化に関する基本的かつ総合的な施策の基本方針を策定し、その推進に努める責務を有する。また、流域連合の自主性を尊重することを前提とした上で、流域連合による河川及び河川流域の管理が基本理念に則していないと判断される場合は必要な処置を勧告することができる。
・地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのつとり、国の定める基本方針に基づき、流域連合を組織し、互いに協力して、施策を策定し、及び実施する責務を有する9地方公共団体は、この際、流域内の事業者及び住民の意見を聞かなければならない。
・事業者の責務
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に当つては、水循環系の支障とならないよう必要な措置を講じなければならない。支障が生じた場合は、その責は事業者に帰すものとする。
・国民の責務
国民は、基本理念を共有するとともに、水循環系への支障を防止するため、その日常生活に伴う水循乗系を撹乱する恐れのある負荷の低減に努めなければならない。また、国民は、水循環系の適正化に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する施策の推進に主体的に参加する責務を有する。
・関係者相互の連携及び協力
国、地方公共団体、事業者、国民及び水循環系に関わる非営利公益団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力することに努めなければならない。
このために情報公開の徹底を期すとともに、広く情報が利用されるように広報活動を強化する。
・水循環の日
事業者及び国民の間に広く水循環系の再生と保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に活動を行う意欲を高めるため、O月○ 日を水循環の口とする。
・法制上の措置等
国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならない。さらに国は、縦割の制度と組織を廃し、水循環系の道正化に関する施策を実施するため必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講じなければならない。また、地方公共団体においても縦割の制度と組織を廃するために必要な措置を行わなければならない。
・年次報告等
政府は、毎年、国会に基本方針の実施状況を報告し、その促進に必要な措置を明らかにした文書を提出しなければならない。また、国会に報告した内容及び提出した文書を公表する。
第四 基本方針口基本計画等
・水循環総合基本方針
国は、基本理念に基づき「第五基本的施策」の基礎となり、流域連合が策定する「流域別水循環計画」の前提となる基本方針を策定し、流域連合が円滑に実施できるよう支援・調整しなければならない。
基本方針には、基本的施策の推進に関する方針その他の必要な事項を定め、閣議の決定を求め、決定後遅滞無く公表するとともに国会に報告するものとする。
,流域別水循環計画
「流域連合」は、国の基本方針に基づき、河川流域毎に水循環アセスメントを行い、流域別水循環計画を当該流域に適合した最上位計画として策定する。
計画の策定から決定までのプロセスは、下記の通りである。
流域を構成する地方公共団体によつて結成された「流域連合」が「流域水循環審議会」に計画策定を諮問する。計画策定に当つては、流域住民の意見を聞き、誠実に対応しなければならない。流域連合は、答申された計画案を「流域連合議会」に諮り、議決を得て決定する。
第五 基本的施策
国は、下記の基本的施策に関する基本方針を示し、河川流域を構成する地方公共団体は、流域連合を結成し、流域別水循環計画に基づいてこれらの基本的施策を講じるものとする。
(1)流域治水対策の推進
想定した規模の洪水をダム等洪水調節施設と河道で処理するという従来の治水から、森林や農地による保水、流域による貯留、土地利用に応じた浸水の受け入れによる洪水氾濫の分散、河川、下水道、農業用水路等の一体的整備等、河川流域全体で洪水対策を行う流域治水へと転換する。
このため、河川法で想定されている基本高水流量等の設定に基づく治水計画を根本的に見直す。 流域治水へ転換することによつて、河川堤防のかさ上げとダム建設への過度な依存体制が克服でき、今後は、緑のダムとしての森林の持つ保水機能や土砂流出防止機能の活用、保水型・耐水型都市の再生、公園緑地や田畑の持つ遊水機能の活用、さらに雨水の地下浸透、滞留や貯留の計画的推進、水と緑の豊かなネットワーク都市の再生を進めることになる。
流域治水の推進のためには、浸水危険区域、遊水可能区域、水と緑の酒養区域などの土地利用計画を公表し、農業政策や都市計画とあいまった土地利用の適正な規制と誘導を図ることが不可欠になる。国民ひとリー人がこうして、流域治水に参加することになる。
(2)水環境管理の道正化及び水循環系の再生と保全
水環境管理の要諦は、河川管理と水環境管理の統合及びこれに伴う水環境基準と排水基準の適正化の推進である。これまでの縦割制度の下で達成されなかった両者の統合と諸基準の全面的改正を進め、同時に多様な生物の棲息・生育環境の再生・保全やギ硼十1の自然回帰と復元、環境用水の確保とその維持を図る。
さらに水循兵系の再生と地下水の保全のために、雨水の浸透・貯留機能の保全・回復あるいは雨水の利用を進める。何人も、水循環を妨げ、雨水の地下浸透を阻害する行為を行つてはならず、このために適切な土地不1用規制を図る。
(3)第二者機関による公正な水環境監視
縦割の所管部門がそれぞれ水質監視を行うこれまでの監視体制から脱却し、公正な第二者機関が排水源の放流水質及び受容水域の水環境の諸側面(水量、水質、生態系など)を監視する。
この第二者機関が違反者に対する是正勧告権を持つと同時に、法的な処置を講じることを可能にする。
(4)利水システムの合理化の促進
過剰な水利用を誘発したこれまでの利水システムを改め、節水型都市及び産業の創出に努め、新規水資源開発の抑制に向けた構造転換を図る。さらに、農業用水を含めた水利用合理化総合計画の策定、水利権転用(工業用水、農業用水)、水融通の促進、水利用量削減目標設定、水利権システムの整備(譲渡契約の認可主体=流域連合)などを進める。さらに、利水システムの一環として、 雨水利用及び下水処理水の再利用等の促進を図る。
(5)地下水の保全と利用の適正化の推進
地下水の保全と利用の適正化を図るため、同一地下水盆における地下水情報の共有化、モニタリング体制、緊急時体制を整備すると共に、地下水の涵養と保全のため、都市の公園や緑地、農地や森林などを有効に活用する。地方公共団体は、条例の定めるところにより、地下水利用適正化計画の策定、地下水酒養区域及び地下水汚染防止区域の設定並びに地下水採取料の徴収を行うことができる。
(6)河川と森林との統合管理の推進
河川管理と森林管理の統合は、水循環系の健全化の視点から極めて重要である。両者の統合によつて、放置林による山地災害や洪水時の大量の流木流出による被害拡大の防止対策を推進する。
また、地球温暖化は水循県系を撹乱させる元凶であるため、二酸化炭素吸収源としての森林の役割その他の森林の多面的機能を維持拡大させる措置を講じる。これらの対策を進めるために森林の所有者以外の者が管理行為を行うことが出来るようにし、併せて所得補償制度を導入する。
また、水源地域の土地の外国資本に封する売却を禁止する処置を採る。
(7)農地の保全と活用
農地を遊水地として保全し、冠水補償を実施する。体耕農地に湛水し、地下水の涵養及び生物多様性保全のためのビオトープとして活用することについて一定の補償を実施する。
(8)水道及び水循宋保全施設の流域圏統合経営の推進
水道及び下水道・浄化槽・し尿処理施設等の水循環保全施設は、排水源におけるきめ細かな対応とともに、流域圏ベースの広域経営を可能にすることによって経営の合理化とサービス水準の向上を図るとともに、処理水準の高度化を推進し、水環境の更なる清浄を確保する。このため、本来同一の機能を果す下水道、浄化槽、し尿処理等の施設は、一体的に整備と管理を進める。
さらに、これらの施設は、流域住民全ての生活に不可欠な社会的共通資本であることに鑑み、社会的事業としてその設置から維持管理までを含め、一貫した経営の合理化を進める。
(9)老朽化施設の更新と機能の向上並びに異常渇水や震災などに備える非常時対応
戦後60数年、経済復興期、高度経済成長期、安定成長期を通じて莫大な公共投資が進められた結果、治水施設、水資源施設、水道施設及び水循環保全施設等の社会的ストックは膨大な資産となって現在それなりに役割を果している。
今後は、これらの資産の更新と機能の向上が大きな課題となるため、アセットアセスメントを進め、合理的な更新と機能の向上に努める。
さらに、今後予想される異常な渇水や大震災に対応する非常時の水供給、水環境保全対策、環境衛生対策
を進める。
(10)財政制度の見直し
国は、従来の財政処置の方式を抜本的に再検討し、流域連合の創設及び同連合による事業の円滑な推進が可能なように地方公共団体とも協議しつつ、財政制度を再構築する。
流域連合の財源は、分担金、賦課金、課徴金、原因者負担金、水循環目的税、地下水使用料等で構成される。
(11)科学技術の振興及び国際協調の推進
水循環の適正化という視点での技術開発は、ハード、ソフト両面で研究課題が山積している。 縦割体制の下では、技術体系も歪みを生じ、合理性を欠く結果となる。今後は横につながる適正技術が志向される。国際援助においてもかかる技術が望まれるが、この面ではわが国は後進的と言える。
また、後発開発途上国の支援体制を抜本的に見直し、強化する。
第六 中央政府の行政組織及びその再編整備
・中央政府の行政組織
(案1)水循環庁の設置
内閣府の外局として水循環庁を設置し、水循環に関わる全ての行政組織を統合する。(水循環庁設置法を新たに制定)
水循環庁は、基本理念にのっとり、水循環社会の実現に向けて基本的施策の推進のための全ての事務を所掌する。水循環庁は、この任務の達成のため、水循環に関わる現行の個別制度の全てを所管し、統合的水管理体制に移行させる。
ただし、「水循環庁」は、将来の道州制の導入も踏まえ、全国的視野で行うことが求められる政策の企画、調整等に権限を限定し、政策の実施権限の多くを広域連合である「流域連合」に委譲することとする。
(問題点)
・関係各省庁及び族議員の抵抗が予想される。
・抜本的な行政改革になるので、実現可能性を危惧し、消極に流れる恐れがある。
(案2)水循環社会推進委員会の設置
内閣府の外局として、独立した行政委員会を設置し、水循環に関わる基本的な行政を所掌させる。(水循環社会推進委員会設置法を新たに
中央政府に於ける水行政の権能を大胆に簡素化させ、中央政府に残される基本的権限のみを所掌する体制を想定した場合、独立行政委員会の設置は適切であると考えられる。なお、委員長及び委員の人事を国会の承認案件とすることで、独立性を保持するものとする。
(問題点)基本的に(案1)と同じ。
道州制が導入された場合、中央政府が所掌する行政権能の範囲
(注)現行法制上、独立行政委員会は、内閣から一定の独立性の確保が求められる行政事務を処理する場合に設置されている。大臣の分担管理の原則(国家行政組織法第5条、内閣法第3条)に鑑み、水管理行政がこれになじむか否かという問題がある。
(案3)水循環政策本部の設置
水循環政策を推進するため、内閣府に水循秦政策本部を設置する。(内閣府設置法の改正)本部は、水循環政策の推進に関する基本方針の作成及びその実施に関すること、関係行政機関の総合調整にかんすること、その他水循環施策で重要なものの企画、立案及び総合調整に当る。
(問題点)
・縦割制度・体制の打破に限界がある。(現行の制度、組織がそのまま残る)
・結果的に関係各省の出向者によつて組織され、現状と変わらない。
・道州制が導入された場合でも縦割制度と体制とが温存される可能性が高い。
・中央水循環審議会
上記組織とは別に、本法に基づく水循環政策の基本方針の審議、水循環政策の進捗状況その他基本的事項を調査審議するために中央水循環審議会を設置する。なお、審議会は、学識経験者及び国民の代表によつて構成される。(設置法による規定が必要)
第七 「流城連合」の設置等、地方公共団体の行政組織及びその再編整備
・流域連合
河川流域を構成する地方公共団体(市町村と都道府県)は、基本理念に基づき水循環政策を推進するため、河川流域の統合的管理主体(地方公共団体の連合組織)である流域連合を設置しなければならない。(注)中央政府の出先地方組織は廃止される。
国は、速やかに流域連合を結成するよう、関係する地方公共団体に勧告することができる。
・流域連合議会
流域連合に関わる立法機関として予算、組織、人事などに関わる諸議案を議決し、流域水循環条例その他の諸規定を制定するため、地方公共団体及び流域住民代表で構成される流域連合議会を設ける。
・流域水循環審議会
水循環アセスメント、流域別水循環計画の調査審議、流域連合の水循環政策の進捗状況のチェックや各種の勧告を行うため、流域連合に諮問機関として流域水循環審議会を設ける。
・流域連合監理・監査
流域連合及び同議会の業務監理に当る組織として、地方公共団体代表者及び流域住民代表者で構成される流域連合監査機構を設ける。同監査機構は、業務監査、情報公開、住民の苦情対応等にも対応するものとする。
第八 流増住民との協働・流域住民との協働体制/・情報公開と監査への参加
行政と流域住民ネットワークは、連携・協働して政策形成を行うことが望まれる。このため、両者のパートナーシップによる協働体制を倉J出し、地域ガバナンスを確立することが必要であり、水の公共性、コモンズとしての性格及びオーフス条約等を考えれば、当然の措置でもある。
このため、流域水循環審議会、流域連合議会、流域連合監査機構には、一定割合の流域住民代表者の参加が前提条件となる。なお、現行河川法に基づく淀川流域委員会は、8月3日をもつて機能停止した。これは、現行河川法の住民参加規定(河川法第16条の2)の曖昧さ(住民の意見聴取の実施の有無、方法等については河川管理者の裁量に委ねていること)に起因するものである。
第九 雑則
・原状回復命令等
水循乗に悪影響を及ばす行為により、現実に支障が生じた場合、原因者の負担において支障の回復・軽減の措置を講じることを命令し、命令の牌怠、不履行に対しては間接強制、汚染者負担の原則の適用を可能とする制度を設ける。
第十 付則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、流域連合など第七、第人に関わる規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行する。
http://mizuseidokaikaku.com/report/report17_tenpu6.pdf
水循環政策大綱案(原案)
1.水循環型社会の再生と将来世代への継承
水は、「生命」の基本である。地球上の水は、海洋と太陽エネルギーによつて絶えず循環を繰り返えし、多様な生命に恩恵を与え続けてきた。
現代においては、水循環系は人間の営為によつて不断に直接的・聞接的に影響を受けているという点で社会的システムであると言えよう。私たちは、地球上に人為的影響を受けない水循環系は最早存在しないことに深く思いを致し、改変された水循環系を持続可能なシステムに再生する努力を払わなければならない。
国上の70パーセントが森林で覆われ水に恵まれたわが国でも、かつての高度経済成長に伴う国上開発、都市化、工業化、さらに生活の利便性の追求による水循環系への直接的影響によつて、生態系保全を伴う水循環系は撹乱され、国土保全力を極度に弱めてきた。
地球温暖化は、このような直接的影響と相侯って水循環系の大変動を誘発させ、異常な洪水や極端な渇水をもたらし、生命と生活を脅かす。化学物質による水の汚染は、微量であつても食物連鎖・生物濃縮によつて生命の危険を増大させ、とくに胎児への悪影響に警告が発せられている。
日本人が様々な水の脅威を克服し、日本の水を大切にし、日本の水を飲み、日本の水を使うようにするためには、水循環系に悪影響を与える人間の営為そのものを適正に制御することによつて、境乱された水循環系を水量、水質、生態系の面から持続可能なシステムに再構築し、健全な水循環型社会の創出を期さなければならない。そこで、水循環系の統合的管理体制を構築し、持統可能な水循兵型社会を創出して、それを将来世代に継承するために水循秦政策大綱を定める。
2.水循環基本法の制定
(1)水循環政策の基本理念
水は、生命の根源であるにもかかわらず、河川等の公共水域の表流水のみを公水とし、その他の水は土地に付随した水として私水と位置づけられてきた。さらに水は、様々な管理者の下で局時的局所的な個別管理に委ねられてきた。河川水が公水であると位置づけられていても、あたかも河サII管理者の私物であるかのように扱われ、そこには国民の姿が全く見えない。 水循環系が歪められ、寸断され、破綻した理由は、一にかかる制度にあつた。
水は、地表水も地下水も水循環系によつて結ばれた一体の存在であり、生命の根源であるという意味において、現在と将来の人々の生存に不可欠な共同資源である。このような水は、水循環系の全ての過程を一体として統合的に管理されなければならない。 全ての人々は、このために水循環系を守る義務を担うべきものである。
この視点に立ち、水循環政策の基本理念は、次の七つの原則的な考え方で構成される。
(1)地表水及び地下水は公共水であること
地表水及び地下水は、共に公共水であり、統合的に管理されなければならない。
(2)水循環保全義務と水環境享受権
現在の国民は、現在及び将来の国民のために、持続可能な水循環系を保持する義務を担う。現在及び将来の国民は、持統可能な水循環系によつてもたらされる健全な水環境の恩恵を享受する基本的権利を有する。
(3)流域圏の統合的管理
水管理は、河)「1流域を原則的単位として統合的かつ地域主権的に行われなければならない。河川流域を構成する地方公共団体は、相互に協力し、河川及び河川流域を上流の森林や農地から河口沿岸域までを含めて統合的かつ地域主権的に管理する主体である「流域連合」を組織しなければならない。
(4)持統可能な水循環型社会の再生と将来世代への継承
持続可能な水循秦型社会の形成は、健全な国土とその上に生活する国民の健康で文化的な生活と幸福の追求に不可欠である。このため、これを再生し、将来世代に継承しなければならない。
(5)持続可能な水循環系保全のための公平な役割分担
持続的な水循環系の保全のための行動は、国民、事業者、地方公共団体(流域連合)、国等によつて、公平な役割分担の下に行われなければならない。
(6)拡大汚染者責任の原則
通常の生活者が処理できない有害物質の生産者、通常の生活者の排出する病原菌やタイルス、微量な医薬品や有害化学物質を含む排水の処理に当る事業者及び地方公共団体は、一次的汚染防止責任を負う。
(7)未然防止と予防原則
水循乗によつて生じる悪影響は、未然に防止されなければならない。このためには、科学的知見の充実を図るとともに、予防原則の適用を躊踏してはならない。
(2)水循環墓本法の制定
わが国の水行政は、これまで経済成長や生活の利便性の向上という観点に立って、水循環系の部分毎に異なる事業制度と組織体制の下で対症療法的に進められて来た。このため、もつばら個別的事業法が存在するのみで、前項の基本理念を定めた基本法は制定されていない。
そこで、水循環基本法を制定し、健全で持続可能な水循環型社会の形成について基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の水循環
型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、統合的水管理施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、将来の世代に健全な国上を継承する制度的処置を講じるものである。
(3〕水循環に関する主要施策
国は、下記の基本的施策に関する基本方針を示し、河川流域を構成する地方公共団体は、流域連合を結成し、流域別水循環計画に基づいてこれらの基本的施策を講じるものとする。
(1)流域治水対策の推進
想定した規模の洪水をダム等洪水調節施設と河道で処理するという従来の治水から、河川流域全体で洪水対策を行う流域治水へと転換する。流域治水の推進のためには、浸水危険区域、遊水可能区域、水と緑の涵養区域などの土地利用計画を公表し、土地利用の適正な規制と誘導を図ることが不可欠になる。
国民ひとリー人がこうして、流域治水に参加することになる。
(2)水環境管理の適正化及び水循環系の再生と保全
水環境管理の要諦は、河川管理と水環境管理の統合及びこれに伴う水環境基準と排水基準の適正化の推進である。同時に多様な生物の棲息・生育環境の再生・保全や河川の自然回帰と復元、環境用水の確保とその維持を図る。さらに水循環系の再生と地下水の保全のために、雨水の浸透・貯留機能の保全・回復あるいは雨水の利用を進める。
(3)第二者機関による公正な水環境監視
縦割の所管部門がそれぞれ水質監視を行うこれまでの監視体制から脱却し、公正な第二者機関が排水源の放流水質及び受容水域の水環境の諸側面(水量、水質、生態系など)を監視する。
(4)利水システムの合理化の促進
過剰な水利用を誘発したこれまでの利水システムを改め、節水型都市及び産業の倉J出????に努め、新規水資源開発の抑制に向けた構造転換を図る。
(5)地下水の保全と利用の適正化の推進
地下水の保全と利用の適正化を図るため、同一地下水盆における地下水情報の共有化、モニタリング体制、緊急時体制を整備すると共に、地下水の涵養と保全の対策を進める。
地方公共団体は、条例の定めるところにより、地下水涵養区域の設定、地下水利用適正化計画の策定及び地下水汚染防止区域の設定を行うことができる。また、条例の定めるところにより、地下水採取料を徴収することができる。
(6)河川と森林との統合管理の推進
河川管理と森林管理の統合によつて、放置林による山地災害や洪水時の大量の流木流出による被害拡大の防止対策を推進する。また地球温暖化は水循環系を撹乱させる元凶であるため、二酸化炭素吸収源としての森林の役割その他の森林の多面的機能を維持拡大させる措置を講じる。
(7)農地の保全と活用
農地を遊水地として保全し、冠水補償を実施する。休耕農地に湛水し、地下水の涵養及び生物多様性保全のためのビオトープとして活用することについて一定の補償を実施する。
(8)水道及び水循環保全施設の流域圏統合経営の推進
水道及び下水道・浄化槽。し尿処理施設等の水循環保全施設は、流域圏ベースの広域経営を可能にすることによつて経営の合理化とサービスの向上を図るとともに、処理水準の高度化を推進し、水環境の更なる清浄を確保する。
(9)老朽化施設の更新と機能の向上並びに異常渇水や震災などに備える非常時対応
戦後60数年を通じて莫大な公共投資が進められた。今後は、これらの資産の更新と機能の向上が大きな課題となるため、アセットアセスメントを進め、合理的な更新と機能の向上に努める。
(10)財政制度の見直し ・
国は、従来の財政処置の方式を抜本的に再検討し、事業の円滑な推進が可能なように地方公共団体とも協議しつつ、財政制度を再構築する。流域連合の財源は、分担金、賦課金、課徴金、原因者負担金、水循環目的税、地下水使用料等で構成される。
(11)科学技術の振興及び国際協調の推進
縦割体制の下では、技術体系も歪みを生じ、合理性を欠く結果となっている。今後は横につながる道正代誉技術が志向される。また、後発開発途上国の支援を抜本的に見直し、強化する。
3.山紫水明の国づくり〜行政組織の再編と流域住民との協働
水循環系を再生し、山紫水明の国づくりを推進するためには、前述の基本理念に則り、これまでの制度と組織を抜本的に改革し、中央政府の権限を大幅に地方政府に委譲するとともに、地方公共団体を越えた河川流域ベースの体制に構築し直さなければならない。さらに、水が国民ひとリー人の生命の源であり、国民の共同資源としての公共水であるという視点から、流域住民が水循環に関わる様々な意思決定に参画するシステムの構築もまた必要不可欠であり、勇断を持って
推進しなければならない。
(1)中央政府の行政組織の再編
改革案としては、三案が考えられる。
[案1]
水循環庁の創設は、最も適切であろう。内閣府の外局として水循環庁を創設すれば、水行政に関わる全ての行政部門を一挙に統合し、整理合理化を断行できる。なお、この場合においても、「水循環庁」は、全国的視点で行うことが求められる政策の企画、調整等に権限を限定し、Я在???、国土交通省その他の省庁が有している権限の多くを「流域連合」に委譲するものとする。
道州制を早期に導入する場合は、道州を超える問題や道州間の調整など限られた重要課題に対
応する
[案2]水循環委員会の設置が考えられる。委員会は独立行政委員会であるが、この場合も[案1]と同じように内閣府の外局となる。委員長などの人事を国会の議決事案とすることで独立性を確保させたい。
(ただし、[案2]には現行法制上、国家行政組織法第3条に基づく委員会が現在の大臣の分担管理原則(国家行政組織法第5条、内閣法第3条)に鑑み、水管理行政になじむか否かの問題が残る。消費者庁の設置に際しても、中立性を確保する行政委員会型組織が遡上に上ったが、最終的に「消費者庁及び消費者委員会」が設けられた。)
[案3]
水循環政策本部の設置は、現段階では現実的と考えられなくも無い。海洋行政分野に有力な事例があるが、水循環行政においては内容的に曖味で、行政改革につながらないと考える。
なお、上記組織とは別に、本法に基づく水循環政策の基本方針の審議、水循環政策の進捗状況その他基本的事項を調査審議するために中央水循兵審議会を設置する。
(2)「流域連合」の設置等、地方公共団体の行政組織の再編
水循環系の保全は、基本理念に基づき流域を一貫して、流域住民に近い所で、流域住民の参加を得て推進すべきである。個々の地方公共団体が個別に行う従来の体制を脱し、流域圏をベースに推進できる行政組織に再構築するため、国は流域連合、同議会の創設を推進するとともに、国の権限を大幅に流域連合に移管する。なお、学識経験者や流域住民の意見を反映させるため、流域水循環審議会を設け、さらに事業推進の透明性を確保するため、流域連合監査機構を設ける。.
[流域連合]
河川流域を構成する地方公共団体(市町村と都道府県)は、基本理念に基づき水循環政策を推進するため、流域圏の統合的管理主体(地方公共団体の連合組織)である流域連合(地方自治法上の広域連合)を設置しなければならない。(注)中央政府の出先地方組織は廃止される。
[流域連合議会]
流域連合に関わる立法機関として予算、組織、人事などに関わる諸議案を議決し、流域水循環条例その他の諸規定を制定するため、地方公共団体及び流域住民代表で構成される流域連合議会を設ける。
[流域水循環審議会]
水循環アセスメント、流域別水循環計画の調査審議、流域連合の水循環政策の進捗状況のチ
ェックや各種の勧告を行うため、流域連合に諮問機関として流域水循環審議会を設ける。
[流域連合監査機構]
流域連合及び同議会の業務監理に当る組織として、地方公共団体代表者及び流域住民代表者
で構成される流域連合監査機構を設ける。同監査機構は、業務監査、情報公開、住民の苦情対応
等にも対応するものとする。
(3)流域住民との協働体制
行政と流域住民ネットワークとが連携,協働して政策形成を行うことが望まれる。このため、両者のパートナーシンプによる協働体制を創出し、地域ガバナンスを確立することが必要である。
水の公共性、コモンズとしての性格及びオーフス条約等を考えれば、当然の措置でもある。このため、流域水循環審議会、流域連合議会、流域連合監査機構には、一定割合の流域住民代表者の参加が前提条件となる。なお、現行河川法に基づく淀川流域委員会は、8月3日をもつて機能停止した。これは、現行河川法の住民参加規定(河川法第16条の2)の曖味さ(住民意見聴取の実施の有無、方法等については河川管理者の裁量に委ねていること)に起因するものである
http://mizuseidokaikaku.com/report/report17_tenpu5.pdf
水循環政策大綱案(原案)と基本法要綱案(原案)にご意見をお寄せください
(2009年10月14日)
水循環基本法研究会の第10回会合(2009年10月9日開催)において、起草委員会でまとめた 「水循環政策大綱案(原案)」と 「水循環基本法要綱案(原案)」を提案いたしました。10月22日まで両原案に対する修正意見をお受けしております。下記2点についてご意見をおまとめいただき、文書にてお送りいただけますようお願いいたします。こちらの回答用紙をご利用ください。
【第1点】
水循環基本法要綱案(原案)の「第六 中央政府の行政組織及びその再編整備―中央政府の行政組織」(6ページ目)において示している3つの案について、どれが適当と考えますか。その理由は何ですか。また、別案がありましたらお示しください。
(案1)
内閣府の外局として水循環庁を設置し、水循環に関わるすべての行政組織を統合する
(案2)
内閣府の外局として、独立した行政委員会(水循環社会推進委員会)を設置し、水循環に関わる基本的な行政を掌握させる
(案3)
水循環政策を推進するため、内閣府に水循環政策本部を設置する
【第2点】
原案に対する修正意見について、該当個所とその対案及び理由をお示しください。
●メールの送付先 qqyg4fv9k★peace.ocn.ne.jp(★印を@に変えてお送りください)
●Faxの送付先 075-722-5295
http://mizuseidokaikaku.com/report/report18.html
ATCグリーンエコプラザセミナーレポート 世界の水問題と日本
■講師
東京大学 生産技術研究所 教授 沖大幹氏
はじめに
世界の水問題は、大きく3種類に分けられます。安全な飲み水(indispensable water)、農業生産、工業生産の水(profitable water)最後に、人と生態系を維持するため、快適に生きるための水(comfortable water)です。1km以内に、1日1人当たり20リットルの水が得られることが、安全な飲み水へのアクセスがあることを意味しますが、世界人口の5分の1は、それがなく、水の確保のためだけに毎日の貴重な時間を費やしています。
これらの3種類の水問題は、質・量も異なれば、貨幣価値も違います。水の様々な側面で懸念事項があるということをお伝えしなければなりません。
農業・工業生産のための水は、今後使用が増えることが懸念されており、地球温暖化が進まなくとも、都市化の進展と人口集中により、洪水・渇水被害は深刻化するでしょう。さらに、数十年後には、水問題は国際的紛争の引き金になるという研究者もいます。
ではまず、水資源は循環資源で、地球上には水がふんだんにあるのに、どうして水不足が生じるのかということをおさらいしましょう。
地球上の水に対して、淡水の占める割合は水全体の約2.5%にすぎず、中でも地下水、氷河などを除いた水資源として利用しやすい淡水は約0.02%しかないため、水不足が生じると説明されることがありますが、そうではありません。
水資源は、ストックではなくフローだと考えるべきです。ある瞬間、世界中の河川の水の総量は、2000 km?に対して、人間が年間使う水は4000 km?だから足りない、という比較の仕方は間違っています。実際は、陸から海へ流れる水の流量の合計は、年間約4万km?。その水循環の一部が、人間の社会の中を通っていると考えなければなりません。では、年間流量のうち、人間が使うのはたったの約10%だから水不足になるわけがないかというと、それも誤りです。
数値モデルによる世界の河川の日流量シミュレーション結果によると、水は、地理的、時間的に偏在することがわかります。極地や、熱帯雨林地帯は年中湿潤なのに対し、砂漠は常に乾燥しており、一方でモンスーン地帯は雨季・乾季で、流量に大きな差があります。全世界の年間流量が足りているからといって、個々の場所で足りているとは限らないのです。
物質の重さ当たりの単価と市場規模について比較してみると、水は、廃品回収の古紙よりもはるかに単価が安いことがわかります。ちなみにミネラルウォーターは嗜好品で、清涼飲料水と同じと考えられるためいわゆる水問題とは切り離して考えるべきでしょう。
ミネラルウォーターは500mlで150円、1m?で30万円ですが、水道水は、1m?で140円〜400円です。都民の水瓶として知られる、奥多摩の小河内ダムの貯水容量1.85億m?の水は、約300億円に相当します。しかし、それは、金塊にすると、たった1m?に過ぎません。つまり、水資源は安くてかさばり、かつ大量に必要なものであり、必要なときに必要な場所、必要な質の水資源がないと、貯蔵、輸送コストが相対的に高すぎて経済的に引き合いません。
21世紀における世界の水資源アセスメント
21世紀の人口増加と経済発展による水需要の変化と、気候変動による水資源賦在量の変化、つまり温暖化による気候変動で使用できる水の量がどう変化するかについて、IPCCで使用しているSRESシナリオに沿って推計した結果をお話したいと思います。
Aは経済行動成長を重視したシナリオ、Bが環境保全を重視したシナリオ。かつ、1はグローバリゼーションが進んだ場合、2は地域化が進んだ場合、という4通りの組み合わせのシナリオで将来推計を行いました。
まず人口の将来展望について、もっとも高くなるのはA2、つまり各地域が交流なく経済発展を目指すと、もっとも人口が増加します。A1B1は共通のカーブを描き、世界的に価値観や技術移転が共通して進む場合、人口は2050年をピークに減少します。地域化、および環境保全重視型のB2シナリオは、人口は増加しますが、指数関数的に増えるわけではなく、ある程度で増加スピードは落ち着くという結果となっています。
このように最近の推計では、人口は増え続けるわけではないというのが一般的になりつつあり、今世紀中に来るであろう環境負荷のピークを乗り切れば、持続可能社会も作れるのではないかと考えています。
次に世界の食料生産と供給についてですが、1960年から2004年の間に、人口は約2倍に増えましたが、その間、農地の面積はわずか10%増に留まっています。しかし、緑の革命と言われる農業分野の技術の発展と、大量の水の使用により、単位面積あたりの収穫量は2.3倍となり、一日一人あたりの摂取カロリーは25%増えています。しかし、そんな中でも現在8億人は飢餓に苦しんでいると言われています。これも水と同様に、物理的な量の問題ではなく、社会における分配の問題でしょう。
工業用水取水量と工業分野のGDPとの関係は、大体線形関係にあります。しかし日本は海外諸国よりも格段に低い取水量を保っており、工業用水の約80%を再生利用しています。
“将来工業用水量”は、“現在工業用水量”*“工業規模増加率”*“用水効率改善係数”により求められます。中国など途上国の工業規模増加は今後も見込まれるため、工業用水の再利用による用水効率改善係数により、将来の工業用水量は大幅に変わってくることが予想されます。
水需要の話をしてきましたが、では、水の供給はどう変化するのでしょうか?これは温暖化の予測となります。
地球温暖化とは気候が変動するということであり、単純に気温が上がるだけでなく、気圧配置が変わり、雨の降り方が変わります。気温上昇による影響と、気候変動による水循環の変化は分けて考える必要があります。
まず温度上昇の直接的影響には、氷河・氷床の融解に伴う流量の一時的増加があります。一見流量が増えていても、それは氷河という水資源の貯金をとりくずしているにすぎず、今世紀末にはやがてなくなって必ず減少します。人間の生活にとっては、流量の一次的な増加ではなく、普段の流量が大切です。氷河がなくなれば、雨が降ったときと、降っていないときの流量の差が非常に大きくなり、ダムを作らなければ、全世界人口の6分の1が深刻な影響を受けると言われています。同時に、水温上昇により水質も変わり、生態系も大きな影響を受けるでしょう。
次に、雨の降り方が変わることによる間接的影響としては、極域と湿潤地帯での水資源の増加、熱帯・亜熱帯乾燥域で減少が予測されています。つまり乾燥域での旱魃地帯がさらに広がり、湿潤地帯においては激しい降水による洪水リスクが増大します。
私は、IPCC第4次報告書第2作業部会、影響評価を調査するグループに参加していました。ほとんどが欧米系なので、水不足の話が中心になりますが、仮にアジアの人がいれば、洪水の話ももっと前面に出ていたと思います。
さらに国交省が行った日本の気候変動予測によると、温暖化が進んだ100年後、雪が雨として降るため、冬の間の河川流出量が増え、同時に雪解けが早まるため、本来、ダム貯水量が満水になるべき代かき期などの需要期に、流量が不足してしまう恐れがあります。
21世紀における深刻な水ストレス下の人口予測のシミュレーションを、先ほどと同様のSRESシナリオで行いました。ここでの水ストレスのある人とは、年によっては渇水で困窮したり、食物生産が落ちて影響を受ける可能性がある状態にある人ということでお考えください。2050年までは、どのシナリオでも水ストレス人口は増えます。しかしそれ以降、A2(経済行動成長重視・地域化)はさらに増えますが、A1、B1では横ばい、あるいは減るという結果になりました。つまり、今後どのような社会になるかによって、必ずしも悲観的な未来ばかりではないと考えられるでしょう。
IPCCでは、prediction(予測)という言葉は使わないように心がけています。人間の力が及ばない天気などの予報とは違い、50年、100年後の未来は、人間社会が今後どの程度温室効果ガスを排出するかという緩和策や、気候変動の悪影響を最小限にしようとする適応策にどの程度取り組むかにより変わります。私たちが行っているのは、ある仮定の下の計算に過ぎません。これらのシミュレーションから、環境配慮型の社会に変えていくことによって、水に困らない社会が出来るということを示すことができればと思います。
将来展望まとめ
21世紀における水需給において、温暖化の影響による逼迫が予想されるのは、地中海沿岸ヨーロッパ、アメリカ西部です。しかしこの地域は、おそらく適応策を講じることができるため、あまり心配の必要はないでしょう。一方、中近東、西・南アジア地域は、社会経済変化、特に経済発展と人口増により逼迫の恐れがあります。また、サハラ以南のアフリカ、中南米は、今後の経済発展や社会の変化により、逼迫が懸念されます。日本にも、これらの脆弱性と気候変動リスクに対する国際的な支援が期待されています。
ヴァーチャルウォーターと、ウォーターフットプリント
食料の輸出入に伴って生じる水資源の量を表す言葉として、ヴァーチャルウォーターとウォーターフットプリントという2種類があります。ヴァーチャルウォーター(仮想水)は、たとえば、食料を輸入するとき、実際使用された水の量は関係なく、自国内で生産するときに必要となる水の量をあらわすのに対し、ウォーターフットプリントは、輸出物質を生産するために実際消費された水の量を指します。
日本人は、1日に一人当たり250リットルの水を使っています。そのうち、飲み水は2〜3リットルにすぎません。その用途は、風呂、トイレなど、ほとんどが洗浄のためであり、水を飲むことすら、体の汚れを運んでもらうという意味では洗浄といえます。つまり、水を使うこととは、水に汚れを運んでもらうことを意味しています。
一方、食料を作るために使っている水は、重さ比で、とうもろこしは食べられる量の2000倍です。大豆は2500倍、米は3600倍、牛肉は約2万倍もの水が必要となります。これらのデータに基づき計算すると、日本が海外から輸入している主要な食料を日本で作った場合は、約年間640億トンの水が必要であり、日本国内の農業用水570億トンと同じくらいの量の水を海外から輸入していることになります。
その輸入品目の内訳は、家畜の飼料となるとうもろこし、大豆、小麦、牛肉、豚肉などが大半を占めます。つまり食料の輸入の大半は、肉食のためのものなのです。輸入してから肉にするか、肉として輸入するかの違いに過ぎません。
私たちが1日に使っている水は、飲み水が2〜3リットル、それに対して水道水は約200〜300リットル、一方、食料のために使用されている水は2000リットル〜3000リットルです。実は一番、たくさんの量が必要なのは、食料生産のための水です。水不足が起こったときは、飲み水不足の前に、食料不足が起こることが容易に想像できます。
ヴァーチャルウォーターの各地域間の貿易をみると、オーストラリア、アメリカから、北アフリカや中近東の取引が顕著です。水が少なく石油を持つ国が、食料という形で水を買っています。水をヴァーチャルウォーターに、つまり食料という形にすれば、重さが1000分の1になります。世界で水危機が起こったときは、食料として水を動かせば輸送コストがかからず経済的です。現在も、水は戦略物質として食料という形で世界をめぐっており、その流れを握っているのは、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランスという限られた国々です。これらの国はG8など世界でも力を持っています。
しかしヴァーチャルウォーターでは、実際その国でどのくらいの量の水が使われたか、また取水源も特定できません。それを推計できるのが、ウォーターフットプリントです。
取水源とされる水の中には天水(雨水)と灌漑水があります。灌漑水の中には、河川水と、ダム・貯水池・ため池、そして、非循環型の地下水(化石水)があります。
私たち東京大学は、国立環境研究所との共同研究により、全世界的な農地の水利用量を、作物の種類や作付けの時期・場所などから計算、またダムの働きや規模も考慮して取水源を推定する全球統合水資源モデルを開発しました。
まず、世界の農地の水消費量、地下水取水量について、推定値と、近年の研究による統計結果と比較したところ、大きな違いはなく、まずまず妥当な結果となりました。
そうして算出した日本のウォーターフットプリントは、年間427億トン。一方ヴァーチャルウォーターは年間約627億トンです。水効率が良い国で生産したものを、水効率が悪い国が輸入するため、ウォーターフットプリントはヴァーチャルウォーターよりも少なくなります。その取水源は、灌漑水起源が73億トンで、全体の20%弱に過ぎず、ウォーターフットプリントの8割は、雨水起源だということがわかりました。しかし、灌漑水の中でも29億トンの水は、河川水、ため池などの灌漑水では足りず、非循環の地下水(化石水)を利用していると考えられます。
品目別の水源をみてみると、牛肉の大半は雨水起源となりました。これは家畜は牧草を食べて育つためだと考えられます。一方、米は中規模貯水池が使われ、大豆、小麦などは、灌漑水では足りず、非循環地下水を比較的多く(全体の約10〜15%程度)使っていることがわかりました。
ヴァーチャルウォーターは、日本では、水資源問題への一般認識を高めるためにもよく利用されますが、実際は、より現実的な水資源アセスメントや、将来の食料需給の推定に利用される概念です。しかし、問題は、他の生産手段の制約を考えていないことです。例えば日本が飼料用穀物を大量に輸入しているのは、牧草を大量に育てる土地が不足しているためであり、水不足の中近東とは理由が異なっています。他の制約による食料輸入にVWが入ってきてしまっていることになります。
まとめ
持続可能な社会を作るためには、水だけ切り離すのではなく、食料とエネルギーと水は、三位一体で考えなければいけません。本日お話しましたように、ヴァーチャルウォータートレードにより、水不足の地域で食料を輸入することは、食料を生産するための水を大幅に節約でき、逆に、食料を作るときは多くの水が使われています。またエネルギーと水は海水淡水化、水力発電によりお互いを生み出すことが出来ます。一方、食物をバイオ燃料などのエネルギーにすることもでき、そして大量のエネルギーがなければ食料は作れません。これら3つはそれぞれがチェンジャブルな関係にあり、少ない方を補うことができます。広い視点から持続可能を捉えるためには、これらを一体化して考えなければなりません。
中国には、「飲水思源」という言葉があります。水を飲むときにはその井戸を掘った人を忘れるなという意味だそうですが、それに倣い、これからは「飲食思水」、食べ物を食べるときには、水は簡単にどこでも手に入るものではなく、食べ物を作るときにたくさん水が使われているということを思い出していただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/200501/index.html
前文
水は、「生命」の基本である。地球上の水は、海洋と太陽エネルギーによつて絶えず循環を繰り返し、多様な生命に思恵を与え続けてきた。
現代においては、水循環系は人間の営為によって不断に直接的・問接的に影響を受けるという点で社会的システムであると言えよう。私たちは、地球上に人為的影響を受けない水循県系は最早存在しないことに深く思いを致し、改変された水循環系を持続可能なシステムに再生する努力を払わなければならない。
国上の70パーセントが森林で覆われ水に恵まれたわが国でも、かつての高度経済成長にともなう国上開発と都市化、工業化、さらに生活の利便性の追求による水循環系への直接的影響によって、生態系保全を伴う水循環系は撹乱され、国土保全力を極度に弱めてきた。
地球温暖化は、このような直接的影響と相侯つて水循乗系の大変動を誘発させ、異常な洪水や極端な渇水をもたらし、生命と生活を脅かす。化学物質による水の汚染は、微量であっても食物連鎖・生物濃縮によつて生命の危険を増大させ、とくに胎児への悪影響に警告が発せられている。
日本人が様々な水の脅威を克服し、日本の水を大切にし、日本の水を飲み、日本の水を使うようにするためには、水循環系に影響を与える人間の営為そのものを適正に制御することによつて、撹乱された水循環系を水量、水質、生態系の面から持続可能なシステムに再構築し、健全な水循環型社会を創出して、それを将来世代に継承しなければならない。このため、水循環基本法を制定することにした。
第一 総則・目的
この法律は、健全で持続可能な水循環型社会の形成について基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、水循環総合基本方針の策定その他の水循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、水循環型社会の形成に関する統合的水管理施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、将来の世代に健全な国上を継承することを目的とする。
,定義(注:今後さらに検討を重ねる。必要語句を追加する。)
〈水循環〉
水循環とは、人間の営為の影響を受けつつ地表水及び地下水となり、蒸発し再び降水となり、あるいは地表での滞留や貯留、土壌への浸透など様々な過程を経て絶えず繰り返す水の循県の過程を言う。
〈統合的水管理〉
統合的水管理とは、現在の縦割型水管理を排し、河川流域を一貫した地表水及び地下水の水量管理、水質管理、生態系管理及び水環境管理を統合した総合的な水管理を言う。
〈河川流域〉
河川流域とは、河川及びその集水域を媒介として、森林、農村、都市、海が結ばれたまとまりのある国上の単位を言う。
(水環境〉
統合的水管理によつて形成され、将来の世代に継承され、国民の全てがその思恵を享受する水の環境で、水量、水質、生態系の面から持統可能な水循環系によつてもたらされたものを言う。
第二 基本理念
(1)地表水及び地下水は公共水であること
地表水及び地下水は、共に公共水であり、流域別水循環計画に基づいて統合的に管理されなければならない。
(2)水循環保全義務と水環境享受権
現在の国民は、現在及び将来の国民のために、持続可能な水循環系を保持する義務を担う。現在及び将来の国民は、水量、水質、生態系の面から持続可能な水循環系によつてもたらされる健全な水環境の思恵を享受する基本的権利を有する。
(3)流域圏の統合的管理
水循環管理は、河川流域を原則的単位として統合的かつ地域主権的に行われなければならない。河川流域を構成する地方公共団体は、相互に協力し、河川及び河川流域を上流の森林や農地から河日沿岸域までを含めて統合的かつ地域主権的に管理する主体である「流域連合」を組織しなければならない。ここで、流域圏の範囲については、複数河川流域に亘る広域生活圏においては当該の全河川流域を包含したものとする。
(4)持続可能な水循環型社会の再生と将来世代への継承
持続可能な水循環型社会の形成は、健全な国土とその上に生活する国民の健康で文化的な生活と幸福追求に不可欠である。このため、これを再生し、将来世代に継承しなければならない。
(5)持続可能な水循環系保全のための公平な役割分担
持続的な水循環系の保全のための行動は、国民、事業者、地方公共団体(流域連合)、国等によつて公平な役割分担の下に行われなければならない。
(6)拡大汚染者責任の原則
通常の生活者が処理処分できない有害物質の生産者、通常の生活者の排出する各種の感染症の原因となる病原菌やウイルス、微量な医薬品や有害化学物質を含む排水の処理に当る事業者及び地方公共団体は、汚染防止について第一次的な責任を有する。
(7)未然防止と予防原則
水循環によつて生じる悪影響は、未然に防止されなければならない。このためには、科学的知見の充実を図るとともに、予防原則の適用を躊躇してはならない。
第二 関係者の責務等・国の責務
国は、「第二 基本理念」にのっとり、水循環の道正化に関する基本的かつ総合的な施策の基本方針を策定し、その推進に努める責務を有する。また、流域連合の自主性を尊重することを前提とした上で、流域連合による河川及び河川流域の管理が基本理念に則していないと判断される場合は必要な処置を勧告することができる。
・地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのつとり、国の定める基本方針に基づき、流域連合を組織し、互いに協力して、施策を策定し、及び実施する責務を有する9地方公共団体は、この際、流域内の事業者及び住民の意見を聞かなければならない。
・事業者の責務
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に当つては、水循環系の支障とならないよう必要な措置を講じなければならない。支障が生じた場合は、その責は事業者に帰すものとする。
・国民の責務
国民は、基本理念を共有するとともに、水循環系への支障を防止するため、その日常生活に伴う水循乗系を撹乱する恐れのある負荷の低減に努めなければならない。また、国民は、水循環系の適正化に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する施策の推進に主体的に参加する責務を有する。
・関係者相互の連携及び協力
国、地方公共団体、事業者、国民及び水循環系に関わる非営利公益団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力することに努めなければならない。
このために情報公開の徹底を期すとともに、広く情報が利用されるように広報活動を強化する。
・水循環の日
事業者及び国民の間に広く水循環系の再生と保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に活動を行う意欲を高めるため、O月○ 日を水循環の口とする。
・法制上の措置等
国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならない。さらに国は、縦割の制度と組織を廃し、水循環系の道正化に関する施策を実施するため必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講じなければならない。また、地方公共団体においても縦割の制度と組織を廃するために必要な措置を行わなければならない。
・年次報告等
政府は、毎年、国会に基本方針の実施状況を報告し、その促進に必要な措置を明らかにした文書を提出しなければならない。また、国会に報告した内容及び提出した文書を公表する。
第四 基本方針口基本計画等
・水循環総合基本方針
国は、基本理念に基づき「第五基本的施策」の基礎となり、流域連合が策定する「流域別水循環計画」の前提となる基本方針を策定し、流域連合が円滑に実施できるよう支援・調整しなければならない。
基本方針には、基本的施策の推進に関する方針その他の必要な事項を定め、閣議の決定を求め、決定後遅滞無く公表するとともに国会に報告するものとする。
,流域別水循環計画
「流域連合」は、国の基本方針に基づき、河川流域毎に水循環アセスメントを行い、流域別水循環計画を当該流域に適合した最上位計画として策定する。
計画の策定から決定までのプロセスは、下記の通りである。
流域を構成する地方公共団体によつて結成された「流域連合」が「流域水循環審議会」に計画策定を諮問する。計画策定に当つては、流域住民の意見を聞き、誠実に対応しなければならない。流域連合は、答申された計画案を「流域連合議会」に諮り、議決を得て決定する。
第五 基本的施策
国は、下記の基本的施策に関する基本方針を示し、河川流域を構成する地方公共団体は、流域連合を結成し、流域別水循環計画に基づいてこれらの基本的施策を講じるものとする。
(1)流域治水対策の推進
想定した規模の洪水をダム等洪水調節施設と河道で処理するという従来の治水から、森林や農地による保水、流域による貯留、土地利用に応じた浸水の受け入れによる洪水氾濫の分散、河川、下水道、農業用水路等の一体的整備等、河川流域全体で洪水対策を行う流域治水へと転換する。
このため、河川法で想定されている基本高水流量等の設定に基づく治水計画を根本的に見直す。 流域治水へ転換することによつて、河川堤防のかさ上げとダム建設への過度な依存体制が克服でき、今後は、緑のダムとしての森林の持つ保水機能や土砂流出防止機能の活用、保水型・耐水型都市の再生、公園緑地や田畑の持つ遊水機能の活用、さらに雨水の地下浸透、滞留や貯留の計画的推進、水と緑の豊かなネットワーク都市の再生を進めることになる。
流域治水の推進のためには、浸水危険区域、遊水可能区域、水と緑の酒養区域などの土地利用計画を公表し、農業政策や都市計画とあいまった土地利用の適正な規制と誘導を図ることが不可欠になる。国民ひとリー人がこうして、流域治水に参加することになる。
(2)水環境管理の道正化及び水循環系の再生と保全
水環境管理の要諦は、河川管理と水環境管理の統合及びこれに伴う水環境基準と排水基準の適正化の推進である。これまでの縦割制度の下で達成されなかった両者の統合と諸基準の全面的改正を進め、同時に多様な生物の棲息・生育環境の再生・保全やギ硼十1の自然回帰と復元、環境用水の確保とその維持を図る。
さらに水循兵系の再生と地下水の保全のために、雨水の浸透・貯留機能の保全・回復あるいは雨水の利用を進める。何人も、水循環を妨げ、雨水の地下浸透を阻害する行為を行つてはならず、このために適切な土地不1用規制を図る。
(3)第二者機関による公正な水環境監視
縦割の所管部門がそれぞれ水質監視を行うこれまでの監視体制から脱却し、公正な第二者機関が排水源の放流水質及び受容水域の水環境の諸側面(水量、水質、生態系など)を監視する。
この第二者機関が違反者に対する是正勧告権を持つと同時に、法的な処置を講じることを可能にする。
(4)利水システムの合理化の促進
過剰な水利用を誘発したこれまでの利水システムを改め、節水型都市及び産業の創出に努め、新規水資源開発の抑制に向けた構造転換を図る。さらに、農業用水を含めた水利用合理化総合計画の策定、水利権転用(工業用水、農業用水)、水融通の促進、水利用量削減目標設定、水利権システムの整備(譲渡契約の認可主体=流域連合)などを進める。さらに、利水システムの一環として、 雨水利用及び下水処理水の再利用等の促進を図る。
(5)地下水の保全と利用の適正化の推進
地下水の保全と利用の適正化を図るため、同一地下水盆における地下水情報の共有化、モニタリング体制、緊急時体制を整備すると共に、地下水の涵養と保全のため、都市の公園や緑地、農地や森林などを有効に活用する。地方公共団体は、条例の定めるところにより、地下水利用適正化計画の策定、地下水酒養区域及び地下水汚染防止区域の設定並びに地下水採取料の徴収を行うことができる。
(6)河川と森林との統合管理の推進
河川管理と森林管理の統合は、水循環系の健全化の視点から極めて重要である。両者の統合によつて、放置林による山地災害や洪水時の大量の流木流出による被害拡大の防止対策を推進する。
また、地球温暖化は水循県系を撹乱させる元凶であるため、二酸化炭素吸収源としての森林の役割その他の森林の多面的機能を維持拡大させる措置を講じる。これらの対策を進めるために森林の所有者以外の者が管理行為を行うことが出来るようにし、併せて所得補償制度を導入する。
また、水源地域の土地の外国資本に封する売却を禁止する処置を採る。
(7)農地の保全と活用
農地を遊水地として保全し、冠水補償を実施する。体耕農地に湛水し、地下水の涵養及び生物多様性保全のためのビオトープとして活用することについて一定の補償を実施する。
(8)水道及び水循宋保全施設の流域圏統合経営の推進
水道及び下水道・浄化槽・し尿処理施設等の水循環保全施設は、排水源におけるきめ細かな対応とともに、流域圏ベースの広域経営を可能にすることによって経営の合理化とサービス水準の向上を図るとともに、処理水準の高度化を推進し、水環境の更なる清浄を確保する。このため、本来同一の機能を果す下水道、浄化槽、し尿処理等の施設は、一体的に整備と管理を進める。
さらに、これらの施設は、流域住民全ての生活に不可欠な社会的共通資本であることに鑑み、社会的事業としてその設置から維持管理までを含め、一貫した経営の合理化を進める。
(9)老朽化施設の更新と機能の向上並びに異常渇水や震災などに備える非常時対応
戦後60数年、経済復興期、高度経済成長期、安定成長期を通じて莫大な公共投資が進められた結果、治水施設、水資源施設、水道施設及び水循環保全施設等の社会的ストックは膨大な資産となって現在それなりに役割を果している。
今後は、これらの資産の更新と機能の向上が大きな課題となるため、アセットアセスメントを進め、合理的な更新と機能の向上に努める。
さらに、今後予想される異常な渇水や大震災に対応する非常時の水供給、水環境保全対策、環境衛生対策
を進める。
(10)財政制度の見直し
国は、従来の財政処置の方式を抜本的に再検討し、流域連合の創設及び同連合による事業の円滑な推進が可能なように地方公共団体とも協議しつつ、財政制度を再構築する。
流域連合の財源は、分担金、賦課金、課徴金、原因者負担金、水循環目的税、地下水使用料等で構成される。
(11)科学技術の振興及び国際協調の推進
水循環の適正化という視点での技術開発は、ハード、ソフト両面で研究課題が山積している。 縦割体制の下では、技術体系も歪みを生じ、合理性を欠く結果となる。今後は横につながる適正技術が志向される。国際援助においてもかかる技術が望まれるが、この面ではわが国は後進的と言える。
また、後発開発途上国の支援体制を抜本的に見直し、強化する。
第六 中央政府の行政組織及びその再編整備
・中央政府の行政組織
(案1)水循環庁の設置
内閣府の外局として水循環庁を設置し、水循環に関わる全ての行政組織を統合する。(水循環庁設置法を新たに制定)
水循環庁は、基本理念にのっとり、水循環社会の実現に向けて基本的施策の推進のための全ての事務を所掌する。水循環庁は、この任務の達成のため、水循環に関わる現行の個別制度の全てを所管し、統合的水管理体制に移行させる。
ただし、「水循環庁」は、将来の道州制の導入も踏まえ、全国的視野で行うことが求められる政策の企画、調整等に権限を限定し、政策の実施権限の多くを広域連合である「流域連合」に委譲することとする。
(問題点)
・関係各省庁及び族議員の抵抗が予想される。
・抜本的な行政改革になるので、実現可能性を危惧し、消極に流れる恐れがある。
(案2)水循環社会推進委員会の設置
内閣府の外局として、独立した行政委員会を設置し、水循環に関わる基本的な行政を所掌させる。(水循環社会推進委員会設置法を新たに
中央政府に於ける水行政の権能を大胆に簡素化させ、中央政府に残される基本的権限のみを所掌する体制を想定した場合、独立行政委員会の設置は適切であると考えられる。なお、委員長及び委員の人事を国会の承認案件とすることで、独立性を保持するものとする。
(問題点)基本的に(案1)と同じ。
道州制が導入された場合、中央政府が所掌する行政権能の範囲
(注)現行法制上、独立行政委員会は、内閣から一定の独立性の確保が求められる行政事務を処理する場合に設置されている。大臣の分担管理の原則(国家行政組織法第5条、内閣法第3条)に鑑み、水管理行政がこれになじむか否かという問題がある。
(案3)水循環政策本部の設置
水循環政策を推進するため、内閣府に水循秦政策本部を設置する。(内閣府設置法の改正)本部は、水循環政策の推進に関する基本方針の作成及びその実施に関すること、関係行政機関の総合調整にかんすること、その他水循環施策で重要なものの企画、立案及び総合調整に当る。
(問題点)
・縦割制度・体制の打破に限界がある。(現行の制度、組織がそのまま残る)
・結果的に関係各省の出向者によつて組織され、現状と変わらない。
・道州制が導入された場合でも縦割制度と体制とが温存される可能性が高い。
・中央水循環審議会
上記組織とは別に、本法に基づく水循環政策の基本方針の審議、水循環政策の進捗状況その他基本的事項を調査審議するために中央水循環審議会を設置する。なお、審議会は、学識経験者及び国民の代表によつて構成される。(設置法による規定が必要)
第七 「流城連合」の設置等、地方公共団体の行政組織及びその再編整備
・流域連合
河川流域を構成する地方公共団体(市町村と都道府県)は、基本理念に基づき水循環政策を推進するため、河川流域の統合的管理主体(地方公共団体の連合組織)である流域連合を設置しなければならない。(注)中央政府の出先地方組織は廃止される。
国は、速やかに流域連合を結成するよう、関係する地方公共団体に勧告することができる。
・流域連合議会
流域連合に関わる立法機関として予算、組織、人事などに関わる諸議案を議決し、流域水循環条例その他の諸規定を制定するため、地方公共団体及び流域住民代表で構成される流域連合議会を設ける。
・流域水循環審議会
水循環アセスメント、流域別水循環計画の調査審議、流域連合の水循環政策の進捗状況のチェックや各種の勧告を行うため、流域連合に諮問機関として流域水循環審議会を設ける。
・流域連合監理・監査
流域連合及び同議会の業務監理に当る組織として、地方公共団体代表者及び流域住民代表者で構成される流域連合監査機構を設ける。同監査機構は、業務監査、情報公開、住民の苦情対応等にも対応するものとする。
第八 流増住民との協働・流域住民との協働体制/・情報公開と監査への参加
行政と流域住民ネットワークは、連携・協働して政策形成を行うことが望まれる。このため、両者のパートナーシップによる協働体制を倉J出し、地域ガバナンスを確立することが必要であり、水の公共性、コモンズとしての性格及びオーフス条約等を考えれば、当然の措置でもある。
このため、流域水循環審議会、流域連合議会、流域連合監査機構には、一定割合の流域住民代表者の参加が前提条件となる。なお、現行河川法に基づく淀川流域委員会は、8月3日をもつて機能停止した。これは、現行河川法の住民参加規定(河川法第16条の2)の曖昧さ(住民の意見聴取の実施の有無、方法等については河川管理者の裁量に委ねていること)に起因するものである。
第九 雑則
・原状回復命令等
水循乗に悪影響を及ばす行為により、現実に支障が生じた場合、原因者の負担において支障の回復・軽減の措置を講じることを命令し、命令の牌怠、不履行に対しては間接強制、汚染者負担の原則の適用を可能とする制度を設ける。
第十 付則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、流域連合など第七、第人に関わる規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行する。
http://mizuseidokaikaku.com/report/report17_tenpu6.pdf
水循環政策大綱案(原案)
1.水循環型社会の再生と将来世代への継承
水は、「生命」の基本である。地球上の水は、海洋と太陽エネルギーによつて絶えず循環を繰り返えし、多様な生命に恩恵を与え続けてきた。
現代においては、水循環系は人間の営為によつて不断に直接的・聞接的に影響を受けているという点で社会的システムであると言えよう。私たちは、地球上に人為的影響を受けない水循環系は最早存在しないことに深く思いを致し、改変された水循環系を持続可能なシステムに再生する努力を払わなければならない。
国上の70パーセントが森林で覆われ水に恵まれたわが国でも、かつての高度経済成長に伴う国上開発、都市化、工業化、さらに生活の利便性の追求による水循環系への直接的影響によつて、生態系保全を伴う水循環系は撹乱され、国土保全力を極度に弱めてきた。
地球温暖化は、このような直接的影響と相侯って水循環系の大変動を誘発させ、異常な洪水や極端な渇水をもたらし、生命と生活を脅かす。化学物質による水の汚染は、微量であつても食物連鎖・生物濃縮によつて生命の危険を増大させ、とくに胎児への悪影響に警告が発せられている。
日本人が様々な水の脅威を克服し、日本の水を大切にし、日本の水を飲み、日本の水を使うようにするためには、水循環系に悪影響を与える人間の営為そのものを適正に制御することによつて、境乱された水循環系を水量、水質、生態系の面から持続可能なシステムに再構築し、健全な水循環型社会の創出を期さなければならない。そこで、水循環系の統合的管理体制を構築し、持統可能な水循兵型社会を創出して、それを将来世代に継承するために水循秦政策大綱を定める。
2.水循環基本法の制定
(1)水循環政策の基本理念
水は、生命の根源であるにもかかわらず、河川等の公共水域の表流水のみを公水とし、その他の水は土地に付随した水として私水と位置づけられてきた。さらに水は、様々な管理者の下で局時的局所的な個別管理に委ねられてきた。河川水が公水であると位置づけられていても、あたかも河サII管理者の私物であるかのように扱われ、そこには国民の姿が全く見えない。 水循環系が歪められ、寸断され、破綻した理由は、一にかかる制度にあつた。
水は、地表水も地下水も水循環系によつて結ばれた一体の存在であり、生命の根源であるという意味において、現在と将来の人々の生存に不可欠な共同資源である。このような水は、水循環系の全ての過程を一体として統合的に管理されなければならない。 全ての人々は、このために水循環系を守る義務を担うべきものである。
この視点に立ち、水循環政策の基本理念は、次の七つの原則的な考え方で構成される。
(1)地表水及び地下水は公共水であること
地表水及び地下水は、共に公共水であり、統合的に管理されなければならない。
(2)水循環保全義務と水環境享受権
現在の国民は、現在及び将来の国民のために、持続可能な水循環系を保持する義務を担う。現在及び将来の国民は、持統可能な水循環系によつてもたらされる健全な水環境の恩恵を享受する基本的権利を有する。
(3)流域圏の統合的管理
水管理は、河)「1流域を原則的単位として統合的かつ地域主権的に行われなければならない。河川流域を構成する地方公共団体は、相互に協力し、河川及び河川流域を上流の森林や農地から河口沿岸域までを含めて統合的かつ地域主権的に管理する主体である「流域連合」を組織しなければならない。
(4)持統可能な水循環型社会の再生と将来世代への継承
持続可能な水循秦型社会の形成は、健全な国土とその上に生活する国民の健康で文化的な生活と幸福の追求に不可欠である。このため、これを再生し、将来世代に継承しなければならない。
(5)持続可能な水循環系保全のための公平な役割分担
持続的な水循環系の保全のための行動は、国民、事業者、地方公共団体(流域連合)、国等によつて、公平な役割分担の下に行われなければならない。
(6)拡大汚染者責任の原則
通常の生活者が処理できない有害物質の生産者、通常の生活者の排出する病原菌やタイルス、微量な医薬品や有害化学物質を含む排水の処理に当る事業者及び地方公共団体は、一次的汚染防止責任を負う。
(7)未然防止と予防原則
水循乗によつて生じる悪影響は、未然に防止されなければならない。このためには、科学的知見の充実を図るとともに、予防原則の適用を躊踏してはならない。
(2)水循環墓本法の制定
わが国の水行政は、これまで経済成長や生活の利便性の向上という観点に立って、水循環系の部分毎に異なる事業制度と組織体制の下で対症療法的に進められて来た。このため、もつばら個別的事業法が存在するのみで、前項の基本理念を定めた基本法は制定されていない。
そこで、水循環基本法を制定し、健全で持続可能な水循環型社会の形成について基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の水循環
型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、統合的水管理施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、将来の世代に健全な国上を継承する制度的処置を講じるものである。
(3〕水循環に関する主要施策
国は、下記の基本的施策に関する基本方針を示し、河川流域を構成する地方公共団体は、流域連合を結成し、流域別水循環計画に基づいてこれらの基本的施策を講じるものとする。
(1)流域治水対策の推進
想定した規模の洪水をダム等洪水調節施設と河道で処理するという従来の治水から、河川流域全体で洪水対策を行う流域治水へと転換する。流域治水の推進のためには、浸水危険区域、遊水可能区域、水と緑の涵養区域などの土地利用計画を公表し、土地利用の適正な規制と誘導を図ることが不可欠になる。
国民ひとリー人がこうして、流域治水に参加することになる。
(2)水環境管理の適正化及び水循環系の再生と保全
水環境管理の要諦は、河川管理と水環境管理の統合及びこれに伴う水環境基準と排水基準の適正化の推進である。同時に多様な生物の棲息・生育環境の再生・保全や河川の自然回帰と復元、環境用水の確保とその維持を図る。さらに水循環系の再生と地下水の保全のために、雨水の浸透・貯留機能の保全・回復あるいは雨水の利用を進める。
(3)第二者機関による公正な水環境監視
縦割の所管部門がそれぞれ水質監視を行うこれまでの監視体制から脱却し、公正な第二者機関が排水源の放流水質及び受容水域の水環境の諸側面(水量、水質、生態系など)を監視する。
(4)利水システムの合理化の促進
過剰な水利用を誘発したこれまでの利水システムを改め、節水型都市及び産業の倉J出????に努め、新規水資源開発の抑制に向けた構造転換を図る。
(5)地下水の保全と利用の適正化の推進
地下水の保全と利用の適正化を図るため、同一地下水盆における地下水情報の共有化、モニタリング体制、緊急時体制を整備すると共に、地下水の涵養と保全の対策を進める。
地方公共団体は、条例の定めるところにより、地下水涵養区域の設定、地下水利用適正化計画の策定及び地下水汚染防止区域の設定を行うことができる。また、条例の定めるところにより、地下水採取料を徴収することができる。
(6)河川と森林との統合管理の推進
河川管理と森林管理の統合によつて、放置林による山地災害や洪水時の大量の流木流出による被害拡大の防止対策を推進する。また地球温暖化は水循環系を撹乱させる元凶であるため、二酸化炭素吸収源としての森林の役割その他の森林の多面的機能を維持拡大させる措置を講じる。
(7)農地の保全と活用
農地を遊水地として保全し、冠水補償を実施する。休耕農地に湛水し、地下水の涵養及び生物多様性保全のためのビオトープとして活用することについて一定の補償を実施する。
(8)水道及び水循環保全施設の流域圏統合経営の推進
水道及び下水道・浄化槽。し尿処理施設等の水循環保全施設は、流域圏ベースの広域経営を可能にすることによつて経営の合理化とサービスの向上を図るとともに、処理水準の高度化を推進し、水環境の更なる清浄を確保する。
(9)老朽化施設の更新と機能の向上並びに異常渇水や震災などに備える非常時対応
戦後60数年を通じて莫大な公共投資が進められた。今後は、これらの資産の更新と機能の向上が大きな課題となるため、アセットアセスメントを進め、合理的な更新と機能の向上に努める。
(10)財政制度の見直し ・
国は、従来の財政処置の方式を抜本的に再検討し、事業の円滑な推進が可能なように地方公共団体とも協議しつつ、財政制度を再構築する。流域連合の財源は、分担金、賦課金、課徴金、原因者負担金、水循環目的税、地下水使用料等で構成される。
(11)科学技術の振興及び国際協調の推進
縦割体制の下では、技術体系も歪みを生じ、合理性を欠く結果となっている。今後は横につながる道正代誉技術が志向される。また、後発開発途上国の支援を抜本的に見直し、強化する。
3.山紫水明の国づくり〜行政組織の再編と流域住民との協働
水循環系を再生し、山紫水明の国づくりを推進するためには、前述の基本理念に則り、これまでの制度と組織を抜本的に改革し、中央政府の権限を大幅に地方政府に委譲するとともに、地方公共団体を越えた河川流域ベースの体制に構築し直さなければならない。さらに、水が国民ひとリー人の生命の源であり、国民の共同資源としての公共水であるという視点から、流域住民が水循環に関わる様々な意思決定に参画するシステムの構築もまた必要不可欠であり、勇断を持って
推進しなければならない。
(1)中央政府の行政組織の再編
改革案としては、三案が考えられる。
[案1]
水循環庁の創設は、最も適切であろう。内閣府の外局として水循環庁を創設すれば、水行政に関わる全ての行政部門を一挙に統合し、整理合理化を断行できる。なお、この場合においても、「水循環庁」は、全国的視点で行うことが求められる政策の企画、調整等に権限を限定し、Я在???、国土交通省その他の省庁が有している権限の多くを「流域連合」に委譲するものとする。
道州制を早期に導入する場合は、道州を超える問題や道州間の調整など限られた重要課題に対
応する
[案2]水循環委員会の設置が考えられる。委員会は独立行政委員会であるが、この場合も[案1]と同じように内閣府の外局となる。委員長などの人事を国会の議決事案とすることで独立性を確保させたい。
(ただし、[案2]には現行法制上、国家行政組織法第3条に基づく委員会が現在の大臣の分担管理原則(国家行政組織法第5条、内閣法第3条)に鑑み、水管理行政になじむか否かの問題が残る。消費者庁の設置に際しても、中立性を確保する行政委員会型組織が遡上に上ったが、最終的に「消費者庁及び消費者委員会」が設けられた。)
[案3]
水循環政策本部の設置は、現段階では現実的と考えられなくも無い。海洋行政分野に有力な事例があるが、水循環行政においては内容的に曖味で、行政改革につながらないと考える。
なお、上記組織とは別に、本法に基づく水循環政策の基本方針の審議、水循環政策の進捗状況その他基本的事項を調査審議するために中央水循兵審議会を設置する。
(2)「流域連合」の設置等、地方公共団体の行政組織の再編
水循環系の保全は、基本理念に基づき流域を一貫して、流域住民に近い所で、流域住民の参加を得て推進すべきである。個々の地方公共団体が個別に行う従来の体制を脱し、流域圏をベースに推進できる行政組織に再構築するため、国は流域連合、同議会の創設を推進するとともに、国の権限を大幅に流域連合に移管する。なお、学識経験者や流域住民の意見を反映させるため、流域水循環審議会を設け、さらに事業推進の透明性を確保するため、流域連合監査機構を設ける。.
[流域連合]
河川流域を構成する地方公共団体(市町村と都道府県)は、基本理念に基づき水循環政策を推進するため、流域圏の統合的管理主体(地方公共団体の連合組織)である流域連合(地方自治法上の広域連合)を設置しなければならない。(注)中央政府の出先地方組織は廃止される。
[流域連合議会]
流域連合に関わる立法機関として予算、組織、人事などに関わる諸議案を議決し、流域水循環条例その他の諸規定を制定するため、地方公共団体及び流域住民代表で構成される流域連合議会を設ける。
[流域水循環審議会]
水循環アセスメント、流域別水循環計画の調査審議、流域連合の水循環政策の進捗状況のチ
ェックや各種の勧告を行うため、流域連合に諮問機関として流域水循環審議会を設ける。
[流域連合監査機構]
流域連合及び同議会の業務監理に当る組織として、地方公共団体代表者及び流域住民代表者
で構成される流域連合監査機構を設ける。同監査機構は、業務監査、情報公開、住民の苦情対応
等にも対応するものとする。
(3)流域住民との協働体制
行政と流域住民ネットワークとが連携,協働して政策形成を行うことが望まれる。このため、両者のパートナーシンプによる協働体制を創出し、地域ガバナンスを確立することが必要である。
水の公共性、コモンズとしての性格及びオーフス条約等を考えれば、当然の措置でもある。このため、流域水循環審議会、流域連合議会、流域連合監査機構には、一定割合の流域住民代表者の参加が前提条件となる。なお、現行河川法に基づく淀川流域委員会は、8月3日をもつて機能停止した。これは、現行河川法の住民参加規定(河川法第16条の2)の曖味さ(住民意見聴取の実施の有無、方法等については河川管理者の裁量に委ねていること)に起因するものである
http://mizuseidokaikaku.com/report/report17_tenpu5.pdf
水循環政策大綱案(原案)と基本法要綱案(原案)にご意見をお寄せください
(2009年10月14日)
水循環基本法研究会の第10回会合(2009年10月9日開催)において、起草委員会でまとめた 「水循環政策大綱案(原案)」と 「水循環基本法要綱案(原案)」を提案いたしました。10月22日まで両原案に対する修正意見をお受けしております。下記2点についてご意見をおまとめいただき、文書にてお送りいただけますようお願いいたします。こちらの回答用紙をご利用ください。
【第1点】
水循環基本法要綱案(原案)の「第六 中央政府の行政組織及びその再編整備―中央政府の行政組織」(6ページ目)において示している3つの案について、どれが適当と考えますか。その理由は何ですか。また、別案がありましたらお示しください。
(案1)
内閣府の外局として水循環庁を設置し、水循環に関わるすべての行政組織を統合する
(案2)
内閣府の外局として、独立した行政委員会(水循環社会推進委員会)を設置し、水循環に関わる基本的な行政を掌握させる
(案3)
水循環政策を推進するため、内閣府に水循環政策本部を設置する
【第2点】
原案に対する修正意見について、該当個所とその対案及び理由をお示しください。
●メールの送付先 qqyg4fv9k★peace.ocn.ne.jp(★印を@に変えてお送りください)
●Faxの送付先 075-722-5295
http://mizuseidokaikaku.com/report/report18.html
ATCグリーンエコプラザセミナーレポート 世界の水問題と日本
■講師
東京大学 生産技術研究所 教授 沖大幹氏
はじめに
世界の水問題は、大きく3種類に分けられます。安全な飲み水(indispensable water)、農業生産、工業生産の水(profitable water)最後に、人と生態系を維持するため、快適に生きるための水(comfortable water)です。1km以内に、1日1人当たり20リットルの水が得られることが、安全な飲み水へのアクセスがあることを意味しますが、世界人口の5分の1は、それがなく、水の確保のためだけに毎日の貴重な時間を費やしています。
これらの3種類の水問題は、質・量も異なれば、貨幣価値も違います。水の様々な側面で懸念事項があるということをお伝えしなければなりません。
農業・工業生産のための水は、今後使用が増えることが懸念されており、地球温暖化が進まなくとも、都市化の進展と人口集中により、洪水・渇水被害は深刻化するでしょう。さらに、数十年後には、水問題は国際的紛争の引き金になるという研究者もいます。
ではまず、水資源は循環資源で、地球上には水がふんだんにあるのに、どうして水不足が生じるのかということをおさらいしましょう。
地球上の水に対して、淡水の占める割合は水全体の約2.5%にすぎず、中でも地下水、氷河などを除いた水資源として利用しやすい淡水は約0.02%しかないため、水不足が生じると説明されることがありますが、そうではありません。
水資源は、ストックではなくフローだと考えるべきです。ある瞬間、世界中の河川の水の総量は、2000 km?に対して、人間が年間使う水は4000 km?だから足りない、という比較の仕方は間違っています。実際は、陸から海へ流れる水の流量の合計は、年間約4万km?。その水循環の一部が、人間の社会の中を通っていると考えなければなりません。では、年間流量のうち、人間が使うのはたったの約10%だから水不足になるわけがないかというと、それも誤りです。
数値モデルによる世界の河川の日流量シミュレーション結果によると、水は、地理的、時間的に偏在することがわかります。極地や、熱帯雨林地帯は年中湿潤なのに対し、砂漠は常に乾燥しており、一方でモンスーン地帯は雨季・乾季で、流量に大きな差があります。全世界の年間流量が足りているからといって、個々の場所で足りているとは限らないのです。
物質の重さ当たりの単価と市場規模について比較してみると、水は、廃品回収の古紙よりもはるかに単価が安いことがわかります。ちなみにミネラルウォーターは嗜好品で、清涼飲料水と同じと考えられるためいわゆる水問題とは切り離して考えるべきでしょう。
ミネラルウォーターは500mlで150円、1m?で30万円ですが、水道水は、1m?で140円〜400円です。都民の水瓶として知られる、奥多摩の小河内ダムの貯水容量1.85億m?の水は、約300億円に相当します。しかし、それは、金塊にすると、たった1m?に過ぎません。つまり、水資源は安くてかさばり、かつ大量に必要なものであり、必要なときに必要な場所、必要な質の水資源がないと、貯蔵、輸送コストが相対的に高すぎて経済的に引き合いません。
21世紀における世界の水資源アセスメント
21世紀の人口増加と経済発展による水需要の変化と、気候変動による水資源賦在量の変化、つまり温暖化による気候変動で使用できる水の量がどう変化するかについて、IPCCで使用しているSRESシナリオに沿って推計した結果をお話したいと思います。
Aは経済行動成長を重視したシナリオ、Bが環境保全を重視したシナリオ。かつ、1はグローバリゼーションが進んだ場合、2は地域化が進んだ場合、という4通りの組み合わせのシナリオで将来推計を行いました。
まず人口の将来展望について、もっとも高くなるのはA2、つまり各地域が交流なく経済発展を目指すと、もっとも人口が増加します。A1B1は共通のカーブを描き、世界的に価値観や技術移転が共通して進む場合、人口は2050年をピークに減少します。地域化、および環境保全重視型のB2シナリオは、人口は増加しますが、指数関数的に増えるわけではなく、ある程度で増加スピードは落ち着くという結果となっています。
このように最近の推計では、人口は増え続けるわけではないというのが一般的になりつつあり、今世紀中に来るであろう環境負荷のピークを乗り切れば、持続可能社会も作れるのではないかと考えています。
次に世界の食料生産と供給についてですが、1960年から2004年の間に、人口は約2倍に増えましたが、その間、農地の面積はわずか10%増に留まっています。しかし、緑の革命と言われる農業分野の技術の発展と、大量の水の使用により、単位面積あたりの収穫量は2.3倍となり、一日一人あたりの摂取カロリーは25%増えています。しかし、そんな中でも現在8億人は飢餓に苦しんでいると言われています。これも水と同様に、物理的な量の問題ではなく、社会における分配の問題でしょう。
工業用水取水量と工業分野のGDPとの関係は、大体線形関係にあります。しかし日本は海外諸国よりも格段に低い取水量を保っており、工業用水の約80%を再生利用しています。
“将来工業用水量”は、“現在工業用水量”*“工業規模増加率”*“用水効率改善係数”により求められます。中国など途上国の工業規模増加は今後も見込まれるため、工業用水の再利用による用水効率改善係数により、将来の工業用水量は大幅に変わってくることが予想されます。
水需要の話をしてきましたが、では、水の供給はどう変化するのでしょうか?これは温暖化の予測となります。
地球温暖化とは気候が変動するということであり、単純に気温が上がるだけでなく、気圧配置が変わり、雨の降り方が変わります。気温上昇による影響と、気候変動による水循環の変化は分けて考える必要があります。
まず温度上昇の直接的影響には、氷河・氷床の融解に伴う流量の一時的増加があります。一見流量が増えていても、それは氷河という水資源の貯金をとりくずしているにすぎず、今世紀末にはやがてなくなって必ず減少します。人間の生活にとっては、流量の一次的な増加ではなく、普段の流量が大切です。氷河がなくなれば、雨が降ったときと、降っていないときの流量の差が非常に大きくなり、ダムを作らなければ、全世界人口の6分の1が深刻な影響を受けると言われています。同時に、水温上昇により水質も変わり、生態系も大きな影響を受けるでしょう。
次に、雨の降り方が変わることによる間接的影響としては、極域と湿潤地帯での水資源の増加、熱帯・亜熱帯乾燥域で減少が予測されています。つまり乾燥域での旱魃地帯がさらに広がり、湿潤地帯においては激しい降水による洪水リスクが増大します。
私は、IPCC第4次報告書第2作業部会、影響評価を調査するグループに参加していました。ほとんどが欧米系なので、水不足の話が中心になりますが、仮にアジアの人がいれば、洪水の話ももっと前面に出ていたと思います。
さらに国交省が行った日本の気候変動予測によると、温暖化が進んだ100年後、雪が雨として降るため、冬の間の河川流出量が増え、同時に雪解けが早まるため、本来、ダム貯水量が満水になるべき代かき期などの需要期に、流量が不足してしまう恐れがあります。
21世紀における深刻な水ストレス下の人口予測のシミュレーションを、先ほどと同様のSRESシナリオで行いました。ここでの水ストレスのある人とは、年によっては渇水で困窮したり、食物生産が落ちて影響を受ける可能性がある状態にある人ということでお考えください。2050年までは、どのシナリオでも水ストレス人口は増えます。しかしそれ以降、A2(経済行動成長重視・地域化)はさらに増えますが、A1、B1では横ばい、あるいは減るという結果になりました。つまり、今後どのような社会になるかによって、必ずしも悲観的な未来ばかりではないと考えられるでしょう。
IPCCでは、prediction(予測)という言葉は使わないように心がけています。人間の力が及ばない天気などの予報とは違い、50年、100年後の未来は、人間社会が今後どの程度温室効果ガスを排出するかという緩和策や、気候変動の悪影響を最小限にしようとする適応策にどの程度取り組むかにより変わります。私たちが行っているのは、ある仮定の下の計算に過ぎません。これらのシミュレーションから、環境配慮型の社会に変えていくことによって、水に困らない社会が出来るということを示すことができればと思います。
将来展望まとめ
21世紀における水需給において、温暖化の影響による逼迫が予想されるのは、地中海沿岸ヨーロッパ、アメリカ西部です。しかしこの地域は、おそらく適応策を講じることができるため、あまり心配の必要はないでしょう。一方、中近東、西・南アジア地域は、社会経済変化、特に経済発展と人口増により逼迫の恐れがあります。また、サハラ以南のアフリカ、中南米は、今後の経済発展や社会の変化により、逼迫が懸念されます。日本にも、これらの脆弱性と気候変動リスクに対する国際的な支援が期待されています。
ヴァーチャルウォーターと、ウォーターフットプリント
食料の輸出入に伴って生じる水資源の量を表す言葉として、ヴァーチャルウォーターとウォーターフットプリントという2種類があります。ヴァーチャルウォーター(仮想水)は、たとえば、食料を輸入するとき、実際使用された水の量は関係なく、自国内で生産するときに必要となる水の量をあらわすのに対し、ウォーターフットプリントは、輸出物質を生産するために実際消費された水の量を指します。
日本人は、1日に一人当たり250リットルの水を使っています。そのうち、飲み水は2〜3リットルにすぎません。その用途は、風呂、トイレなど、ほとんどが洗浄のためであり、水を飲むことすら、体の汚れを運んでもらうという意味では洗浄といえます。つまり、水を使うこととは、水に汚れを運んでもらうことを意味しています。
一方、食料を作るために使っている水は、重さ比で、とうもろこしは食べられる量の2000倍です。大豆は2500倍、米は3600倍、牛肉は約2万倍もの水が必要となります。これらのデータに基づき計算すると、日本が海外から輸入している主要な食料を日本で作った場合は、約年間640億トンの水が必要であり、日本国内の農業用水570億トンと同じくらいの量の水を海外から輸入していることになります。
その輸入品目の内訳は、家畜の飼料となるとうもろこし、大豆、小麦、牛肉、豚肉などが大半を占めます。つまり食料の輸入の大半は、肉食のためのものなのです。輸入してから肉にするか、肉として輸入するかの違いに過ぎません。
私たちが1日に使っている水は、飲み水が2〜3リットル、それに対して水道水は約200〜300リットル、一方、食料のために使用されている水は2000リットル〜3000リットルです。実は一番、たくさんの量が必要なのは、食料生産のための水です。水不足が起こったときは、飲み水不足の前に、食料不足が起こることが容易に想像できます。
ヴァーチャルウォーターの各地域間の貿易をみると、オーストラリア、アメリカから、北アフリカや中近東の取引が顕著です。水が少なく石油を持つ国が、食料という形で水を買っています。水をヴァーチャルウォーターに、つまり食料という形にすれば、重さが1000分の1になります。世界で水危機が起こったときは、食料として水を動かせば輸送コストがかからず経済的です。現在も、水は戦略物質として食料という形で世界をめぐっており、その流れを握っているのは、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランスという限られた国々です。これらの国はG8など世界でも力を持っています。
しかしヴァーチャルウォーターでは、実際その国でどのくらいの量の水が使われたか、また取水源も特定できません。それを推計できるのが、ウォーターフットプリントです。
取水源とされる水の中には天水(雨水)と灌漑水があります。灌漑水の中には、河川水と、ダム・貯水池・ため池、そして、非循環型の地下水(化石水)があります。
私たち東京大学は、国立環境研究所との共同研究により、全世界的な農地の水利用量を、作物の種類や作付けの時期・場所などから計算、またダムの働きや規模も考慮して取水源を推定する全球統合水資源モデルを開発しました。
まず、世界の農地の水消費量、地下水取水量について、推定値と、近年の研究による統計結果と比較したところ、大きな違いはなく、まずまず妥当な結果となりました。
そうして算出した日本のウォーターフットプリントは、年間427億トン。一方ヴァーチャルウォーターは年間約627億トンです。水効率が良い国で生産したものを、水効率が悪い国が輸入するため、ウォーターフットプリントはヴァーチャルウォーターよりも少なくなります。その取水源は、灌漑水起源が73億トンで、全体の20%弱に過ぎず、ウォーターフットプリントの8割は、雨水起源だということがわかりました。しかし、灌漑水の中でも29億トンの水は、河川水、ため池などの灌漑水では足りず、非循環の地下水(化石水)を利用していると考えられます。
品目別の水源をみてみると、牛肉の大半は雨水起源となりました。これは家畜は牧草を食べて育つためだと考えられます。一方、米は中規模貯水池が使われ、大豆、小麦などは、灌漑水では足りず、非循環地下水を比較的多く(全体の約10〜15%程度)使っていることがわかりました。
ヴァーチャルウォーターは、日本では、水資源問題への一般認識を高めるためにもよく利用されますが、実際は、より現実的な水資源アセスメントや、将来の食料需給の推定に利用される概念です。しかし、問題は、他の生産手段の制約を考えていないことです。例えば日本が飼料用穀物を大量に輸入しているのは、牧草を大量に育てる土地が不足しているためであり、水不足の中近東とは理由が異なっています。他の制約による食料輸入にVWが入ってきてしまっていることになります。
まとめ
持続可能な社会を作るためには、水だけ切り離すのではなく、食料とエネルギーと水は、三位一体で考えなければいけません。本日お話しましたように、ヴァーチャルウォータートレードにより、水不足の地域で食料を輸入することは、食料を生産するための水を大幅に節約でき、逆に、食料を作るときは多くの水が使われています。またエネルギーと水は海水淡水化、水力発電によりお互いを生み出すことが出来ます。一方、食物をバイオ燃料などのエネルギーにすることもでき、そして大量のエネルギーがなければ食料は作れません。これら3つはそれぞれがチェンジャブルな関係にあり、少ない方を補うことができます。広い視点から持続可能を捉えるためには、これらを一体化して考えなければなりません。
中国には、「飲水思源」という言葉があります。水を飲むときにはその井戸を掘った人を忘れるなという意味だそうですが、それに倣い、これからは「飲食思水」、食べ物を食べるときには、水は簡単にどこでも手に入るものではなく、食べ物を作るときにたくさん水が使われているということを思い出していただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/200501/index.html
2009年10月18日
「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内

「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html


各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html

2009年10月18日
転載マンション事業における土壌汚染対策に関する留意事項等
マンション事業における土壌汚染対策に関する留意事項等
一部加筆訂正する場合があります
1.土地利用の履歴等調査 −情報収集―
マンション事業用地の取得に際しては、売主に対し、土壌汚染に関する詳細な情報の提供を求めるとともに、自らも実査、地図、登記簿、航空写真、指定区域台帳等の閲覧、近隣、売主、行政等からのヒアリング等によって土地利用の履歴等の調査を行い、土壌汚染に関する情報を収集する。
土地を宅地建物取引業者の仲介により取得する場合には、受託業者がこれらの方法により土地利用の履歴等の調査を行い、土壌汚染に関する情報を収集し、その結果を委託者に報告することを、媒介契約に明記することが望ましい。
* 平成15年2月から土壌汚染対策法(以下、「法律」という)が施行される予定である。同法に基づき都道府県等に備えられる指定区域台帳には、指定区域として指定された土地に関し、帳簿と図面により、土壌汚染の状態、汚染の除去等の措置が行われた場合はその措置の内容および土地の形質の変更等の履歴が記載される。
また、東京都では平成13年10月より都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という)が実施され3,000?以上の土地の改変について改変者(ディベロッパー等)による土地利用の履歴等調査が義務付けられている。
・ 売買契約の前に、詳細な情報の提供を売主に対して求める。
・ 買主自らも、土地の履歴等の調査により、土壌汚染に関する情報の収集を行う。
・ 宅地建物取引業者の仲介により土地を取得する場合には、土壌汚染に関する情報の収集を受託業者が行う旨を媒介契約に明記することが望ましい。
2.汚染状況の調査
マンション事業用地については、土地利用の履歴等調査等により汚染がないことが確実な場合を除いて、土壌汚染に関する状況の調査を行う。
調査は、原則として引渡しまでに売主が行うこととし、その旨を売買契約に約定すべきであるが、事情によりやむを得ず買主が行う場合もある。
いずれの場合においても、売主の責任を明確化するため、売買契約に土壌汚染に関する瑕疵担保責任や汚染の処理に関する特約等を必ず規定することとすべきである。
なお、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見された場合には、売主の瑕疵担保責任を判断する上で買主にとって不利な状況を招くおそれがあるため、この場合についても、売主に対し責任を追及し得る旨 の特約を明確に約定する。
* 法律は、?有害物質特定施設に係る工場・事業場の使用廃止時または?土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときに、都道府県等が土壌汚染調査を命じることとしている。その場合の調査主体は、いずれも土地の所有者、管理者または占有者(以下、「所有者等」という)である。
法律によれば、調査の必要な特定有害物質は、鉛、砒素、トリクロロエチレン等25物質であり、調査方法等は施行令および施行規則等に定められる予定である。
なお、土壌汚染対策法とは別に、地方自治体が独自に土壌汚染について条例を定めている場合があり、注意を要する。
東京都では、平成13年10月からの環境確保条例により、3,000?以上の土地の改変について、改変者による土地利用の履歴等調査の結果、汚染または汚染のおそれがある場合に、汚染状況の調査の実施を義務付けている。また、埼玉県においても今年の4月より東京都と同様の「生活環境保全条例」が施行されている。板橋区では1,000?以上、戸数30戸以上の開発には、履歴等調査の結果により、調査物質、調査サンプル数等で都の基準を上回る土壌汚染調査が義務付けられ、江東区でも1,000?以上の建築計画について六価クロムの調査が求められる等、自治体によって別個の基準があることに注意を要する。
・ マンション事業用地の売買契約においては、土地利用の履歴等調査により汚染されていないことが確実な場合を除いて、土壌汚染に関する汚染状況の調査を原則として引渡し日までに売主の負担と責任において実施する旨を約定する。
・ やむを得ず買主が汚染状況の調査を行う場合は、買主は売主に対しその費用を請求することができる旨を約定する。
・ また、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見された場合についても、売主に対し責任を追及し得る旨の特約を明確に約定する。
・ 調査基準は、土壌汚染対策法施行令および施行規則等による。地方自治体が別途調査基準を定めている場合はその基準も満たす必要がある。
3.浄化処理・汚染拡散防止措置等
浄化処理・汚染拡散防止措置等は、原則として引渡しまでに売主が行うこととし、その旨を売買契約に約定すべきであるが、事情によりやむを得ず買主が行う場合もある。
土壌汚染の浄化処理・汚染拡散防止措置等については、売買契約書にその主体となる者、費用の負担、処理期限等について規定するか、または同様の内容の合意書・覚書等を締結する。
上記「1.土地利用の履歴等調査」、「2.汚染状況の調査」において発見されなかった土壌汚染が引渡し後に発見されることを想定して、売買契約には土壌汚染に関する瑕疵担保責任の条項や浄化措置の実施等に関する特約を必ず記載する。
なお、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見され、買主が浄化等の措置を行った場合についても、調査および措置に要した費用ならびに損害の賠償を売主に対し請求することができる旨を明確に約定する。
* 法律では、調査の結果汚染が判明した場合、都道府県知事等は当該土地を指定区域に指定し、汚染の除去等の措置を命ずることができるとしている。措置の方法としては、地下水の水質の測定、土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、土壌入れ換え、盛土、立入禁止および舗装の11種類が定められている。完全浄化等により指定の事由がなくなった場合、指定区域の指定は解除される。汚染除去等の措置の実施主体は、土地の所有者、管理者または占有者である。
但し、汚染原因者が明らかであり、汚染原因者に措置を講じさせることに土地所有者等に異議がない場合は、汚染原因者である。土地所有者等が措置を実施し、後で汚染原因者が判明した場合、要した費用を原因者に請求できるとしている。また、東京都では平成13年10月より条例で3,000?以上の土地の改変について、改変者による汚染状況の調査の結果、汚染されまたは汚染されているおそれがある場合に、浄化処理・汚染拡散防止措置等を実施することが義務付けられている。(この場合の浄化処理・汚染拡散防止措置等は、東京都条例・同施行規則および土壌汚染対策指針による。)
・ マンション事業用地の土壌汚染については、売買契約において、浄化処理・汚染拡散防止措置等を売主の負担と責任において引渡し日までに実施する旨を約定する。
・ やむを得ず買主が、汚染浄化処理・汚染拡散防止措置等の措置を実施する場合には、売主に対しその費用を請求することができる旨を約定する。
・ また、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見され、買主が浄化等の措置を行った場合についても、調査および措置に要した費用ならびに損害の賠償を売主に対し請求することができる旨を明確に約定する。
・ 処理基準は、土壌汚染対策法施行令および施行規則等による。地方自治体が別途処理基準を定める場合はその基準も満たす必要がある。
4.土地売買契約の締結
以上により、土地売買契約には、売主による土地の引渡し日を期限とする土壌汚染の状況調査および浄化処理・汚染拡散防止措置等の実施、土地の引渡し後に発見される土壌汚染に関する売主の瑕疵担保責任(?売買契約の目的が達することができない場合の契約解除および?その他の場合の損害賠償請求)および売主による引渡し後の浄化措置等の実施について約定することとすべきである。
なお、法律は、調査および浄化・拡散防止措置等の実施主体について、汚染原因者が明らかな場合を除いて土地所有者等であると規定しており、買主としては、所有権移転の時期を明確に定めることがとくに重要である*。
* とくに定めをしない場合、民法第176条により売買契約と同時に所有権が移転し,調査および浄化・拡散防止措置等の責務が買主に移転するおそれが生じる。
・ 土地の引渡し後の土壌汚染の発見に備え、売買契約書には、所有権の移転時期、土壌汚染に関する瑕疵担保責任(契約解除および損害賠償請求)および売主による引渡し後の浄化措置の実施義務等の条項を必ず記載する。
・ 所有権移転の時期は、調査および浄化・拡散防止措置等を売主の負担と責任において完了した後とする旨を約定する。
【参考:土壌汚染対策法−要旨】
1.土壌汚染状況調査
(1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場であった土地の調査
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、指定調査機関に調査をさせて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。(土地利用の方法からみて人の健康被害を生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときを除く。)
(2) 土壌汚染による健康被害を生ずるおそれがある土地の調査
都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害を生ずるおそれがある土地があると認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2.指定区域等の指定、指定区域台帳の調製
都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、その区域を指定区域として指定・公示するとともに、指定区域の台帳を調製し、閲覧に供する。
3.土壌汚染による健康被害の防止措置
(1) 汚染の除去等の措置命令
? 都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
? 汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、?によらず、都道府県知事は、汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(2) 汚染の除去等の措置に要した費用の請求
(1)?の命令を受けて土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対し、これに要した費用を請求することができる。
(3) 土地の形質変更の届出および計画変更命令
指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。都道府県知事は、その施行方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
【参考:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例−環境確保条例−】
―東京都内での土地売買契約について−
・対象面積3,000?以上
工場等を廃止、除却する以前の土地の場合は、条例第116条により有害物質取扱事業者等が汚染状況の調査、汚染拡散防止措置等を行い、それらの処理の実施後に「調査および処理についての記録」(第118条)とともに引渡しを受ける。有害物質取扱事業者等が汚染状況等の調査を行わず土地を譲渡した場合は、譲受人が行う必要がある。
更地の場合は、条例第117条によって改変者に土地利用の履歴等調査、汚染状況調査、浄化処理・拡散防止措置等が発生する。要した費用については汚染原因者に対して求償できる(第121条)。
・対象面積3,000?未満
条例の範囲外であるが、土壌汚染によるリスクを考慮し、原則、土壌汚染に関する汚染状況調査および浄化処理・拡散防止措置等は売主の負担と責任において引渡し日までに実施する旨を約定する。ただし、買主が汚染状況調査および浄化処理・拡散防止措置等を行う場合は、売主がその費用を負担する旨を約定する。
【環境確保条例と土壌汚染対策法との関係】
・来年施行される法は、環境確保条例と比べ、有害物質の項目数や調査方法について一般に基準が厳しい。一方条例では、3,000?以上の土地の改変については土地の履歴調査が義務付けられている。
5.マンションの分譲・販売
汚染された敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を行ったマンションの分譲および販売については、購入後のトラブルを未然に防止するために、その内容を購入者および購入予定者を対象として積極的に説明する必要があるが、専門的知識が必要とされる分野に関する詳細な説明については、購入者の誤解を避けるためにも土壌処理会社等により行う。
説明の具体的方法としては、モデルルームには必ず具体的説明資料を備えることとし、来場者に対して必要に応じて開示する。ただし、販売担当者からの説明は、購入予定者の誤解を避けるため、重要事項説明書に記載された内容に即して行う。
さらに、購入後のトラブルを未然に防止する観点から、土壌汚染に関する説明は、詳細かつ遺漏のないように実施する必要があり、重要事項説明書に基づいた販売担当者からの説明に加えて、土壌汚染処理会社等からの専門的かつ詳細な説明がなされる機会を設けることが望ましい。
重要事項説明書には、従前の所有者・土地の使用状態、調査の基準・方法等、検出された有害物質および浄化処理・汚染拡散防止措置等の基準・方法等を必要に応じて記載する。
また、浄化処理・汚染拡散防止措置等の処理会社等の報告書は、その写しを購入者に対して交付するとともに、報告書の原本については、管理組合設立後、管理組合に対して引渡す。
東京都では、平成13年10月から、環境確保条例第116条および第117条に該当する土地については、同条第118条によって改変者が実施した調査および処理についての記録を土地の譲受者へと継承することが義務付けられている。
・ 敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を実施した場合は、購入者および購入予定者に対し、モデルルーム等で重要事項説明書に基づいて正確に説明する。
・ さらに、土壌汚染処理会社等による専門的かつ詳細な説明を行う機会を設けることが望ましい。
・ 重要事項説明書には、従前の所有者・土地の使用状態、調査の基準・方法等、検出された有害物質、浄化処理・汚染拡散防止措置等の基準・方法等について、必要に応じて記載する。
・ 購入者に浄化処理・汚染拡散防止措置等の処理会社等の報告書(写)を交付し、併せて管理組合に原本を引き渡す。
【参考:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例−環境確保条例−】
−東京都内でのマンション分譲について−
改変者が実施した調査および処理についての記録は、平成13年10月から、条例第118条によって土地の譲受者へと継承することが義務付けられている。
【参考:宅地建物取引業法施行令の改正】
法の施行に合わせて、宅地建物取引業法施行令が改正され、土壌汚染に関し重要事項説明を要する項目が追加される見通しである。追加される項目は、売買等の対象土地が指定区域に指定されていること、および指定された土地を改変する場合は、都道府県知事に届け出る必要があること、についてである。
重要事項説明を要するとして宅地建物取引業法施行令に列挙された項目は例示であると解されることから、汚染された敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を行ったマンションの分譲および販売するについては、上記のように、従前の所有者、土地の使用状態、調査の基準・方法等、検出された有害物質および浄化処理・汚染拡散防止措置等の基準・方法等を必要に応じて記載することとすべきである。
また、対象地がかつて指定区域に指定され、浄化等により指定区域から解除された土地である場合についても、かつて指定された指定区域の状況、および消除された場合の内容についても、それぞれ判明した範囲で記載する必要がある。
http://www.fdk.or.jp/k_environment/pdf/guideline.pdf#search='土壌汚染 マンション'
一部加筆訂正する場合があります
1.土地利用の履歴等調査 −情報収集―
マンション事業用地の取得に際しては、売主に対し、土壌汚染に関する詳細な情報の提供を求めるとともに、自らも実査、地図、登記簿、航空写真、指定区域台帳等の閲覧、近隣、売主、行政等からのヒアリング等によって土地利用の履歴等の調査を行い、土壌汚染に関する情報を収集する。
土地を宅地建物取引業者の仲介により取得する場合には、受託業者がこれらの方法により土地利用の履歴等の調査を行い、土壌汚染に関する情報を収集し、その結果を委託者に報告することを、媒介契約に明記することが望ましい。
* 平成15年2月から土壌汚染対策法(以下、「法律」という)が施行される予定である。同法に基づき都道府県等に備えられる指定区域台帳には、指定区域として指定された土地に関し、帳簿と図面により、土壌汚染の状態、汚染の除去等の措置が行われた場合はその措置の内容および土地の形質の変更等の履歴が記載される。
また、東京都では平成13年10月より都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という)が実施され3,000?以上の土地の改変について改変者(ディベロッパー等)による土地利用の履歴等調査が義務付けられている。
・ 売買契約の前に、詳細な情報の提供を売主に対して求める。
・ 買主自らも、土地の履歴等の調査により、土壌汚染に関する情報の収集を行う。
・ 宅地建物取引業者の仲介により土地を取得する場合には、土壌汚染に関する情報の収集を受託業者が行う旨を媒介契約に明記することが望ましい。
2.汚染状況の調査
マンション事業用地については、土地利用の履歴等調査等により汚染がないことが確実な場合を除いて、土壌汚染に関する状況の調査を行う。
調査は、原則として引渡しまでに売主が行うこととし、その旨を売買契約に約定すべきであるが、事情によりやむを得ず買主が行う場合もある。
いずれの場合においても、売主の責任を明確化するため、売買契約に土壌汚染に関する瑕疵担保責任や汚染の処理に関する特約等を必ず規定することとすべきである。
なお、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見された場合には、売主の瑕疵担保責任を判断する上で買主にとって不利な状況を招くおそれがあるため、この場合についても、売主に対し責任を追及し得る旨 の特約を明確に約定する。
* 法律は、?有害物質特定施設に係る工場・事業場の使用廃止時または?土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときに、都道府県等が土壌汚染調査を命じることとしている。その場合の調査主体は、いずれも土地の所有者、管理者または占有者(以下、「所有者等」という)である。
法律によれば、調査の必要な特定有害物質は、鉛、砒素、トリクロロエチレン等25物質であり、調査方法等は施行令および施行規則等に定められる予定である。
なお、土壌汚染対策法とは別に、地方自治体が独自に土壌汚染について条例を定めている場合があり、注意を要する。
東京都では、平成13年10月からの環境確保条例により、3,000?以上の土地の改変について、改変者による土地利用の履歴等調査の結果、汚染または汚染のおそれがある場合に、汚染状況の調査の実施を義務付けている。また、埼玉県においても今年の4月より東京都と同様の「生活環境保全条例」が施行されている。板橋区では1,000?以上、戸数30戸以上の開発には、履歴等調査の結果により、調査物質、調査サンプル数等で都の基準を上回る土壌汚染調査が義務付けられ、江東区でも1,000?以上の建築計画について六価クロムの調査が求められる等、自治体によって別個の基準があることに注意を要する。
・ マンション事業用地の売買契約においては、土地利用の履歴等調査により汚染されていないことが確実な場合を除いて、土壌汚染に関する汚染状況の調査を原則として引渡し日までに売主の負担と責任において実施する旨を約定する。
・ やむを得ず買主が汚染状況の調査を行う場合は、買主は売主に対しその費用を請求することができる旨を約定する。
・ また、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見された場合についても、売主に対し責任を追及し得る旨の特約を明確に約定する。
・ 調査基準は、土壌汚染対策法施行令および施行規則等による。地方自治体が別途調査基準を定めている場合はその基準も満たす必要がある。
3.浄化処理・汚染拡散防止措置等
浄化処理・汚染拡散防止措置等は、原則として引渡しまでに売主が行うこととし、その旨を売買契約に約定すべきであるが、事情によりやむを得ず買主が行う場合もある。
土壌汚染の浄化処理・汚染拡散防止措置等については、売買契約書にその主体となる者、費用の負担、処理期限等について規定するか、または同様の内容の合意書・覚書等を締結する。
上記「1.土地利用の履歴等調査」、「2.汚染状況の調査」において発見されなかった土壌汚染が引渡し後に発見されることを想定して、売買契約には土壌汚染に関する瑕疵担保責任の条項や浄化措置の実施等に関する特約を必ず記載する。
なお、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見され、買主が浄化等の措置を行った場合についても、調査および措置に要した費用ならびに損害の賠償を売主に対し請求することができる旨を明確に約定する。
* 法律では、調査の結果汚染が判明した場合、都道府県知事等は当該土地を指定区域に指定し、汚染の除去等の措置を命ずることができるとしている。措置の方法としては、地下水の水質の測定、土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、土壌入れ換え、盛土、立入禁止および舗装の11種類が定められている。完全浄化等により指定の事由がなくなった場合、指定区域の指定は解除される。汚染除去等の措置の実施主体は、土地の所有者、管理者または占有者である。
但し、汚染原因者が明らかであり、汚染原因者に措置を講じさせることに土地所有者等に異議がない場合は、汚染原因者である。土地所有者等が措置を実施し、後で汚染原因者が判明した場合、要した費用を原因者に請求できるとしている。また、東京都では平成13年10月より条例で3,000?以上の土地の改変について、改変者による汚染状況の調査の結果、汚染されまたは汚染されているおそれがある場合に、浄化処理・汚染拡散防止措置等を実施することが義務付けられている。(この場合の浄化処理・汚染拡散防止措置等は、東京都条例・同施行規則および土壌汚染対策指針による。)
・ マンション事業用地の土壌汚染については、売買契約において、浄化処理・汚染拡散防止措置等を売主の負担と責任において引渡し日までに実施する旨を約定する。
・ やむを得ず買主が、汚染浄化処理・汚染拡散防止措置等の措置を実施する場合には、売主に対しその費用を請求することができる旨を約定する。
・ また、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見され、買主が浄化等の措置を行った場合についても、調査および措置に要した費用ならびに損害の賠償を売主に対し請求することができる旨を明確に約定する。
・ 処理基準は、土壌汚染対策法施行令および施行規則等による。地方自治体が別途処理基準を定める場合はその基準も満たす必要がある。
4.土地売買契約の締結
以上により、土地売買契約には、売主による土地の引渡し日を期限とする土壌汚染の状況調査および浄化処理・汚染拡散防止措置等の実施、土地の引渡し後に発見される土壌汚染に関する売主の瑕疵担保責任(?売買契約の目的が達することができない場合の契約解除および?その他の場合の損害賠償請求)および売主による引渡し後の浄化措置等の実施について約定することとすべきである。
なお、法律は、調査および浄化・拡散防止措置等の実施主体について、汚染原因者が明らかな場合を除いて土地所有者等であると規定しており、買主としては、所有権移転の時期を明確に定めることがとくに重要である*。
* とくに定めをしない場合、民法第176条により売買契約と同時に所有権が移転し,調査および浄化・拡散防止措置等の責務が買主に移転するおそれが生じる。
・ 土地の引渡し後の土壌汚染の発見に備え、売買契約書には、所有権の移転時期、土壌汚染に関する瑕疵担保責任(契約解除および損害賠償請求)および売主による引渡し後の浄化措置の実施義務等の条項を必ず記載する。
・ 所有権移転の時期は、調査および浄化・拡散防止措置等を売主の負担と責任において完了した後とする旨を約定する。
【参考:土壌汚染対策法−要旨】
1.土壌汚染状況調査
(1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場であった土地の調査
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、指定調査機関に調査をさせて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。(土地利用の方法からみて人の健康被害を生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときを除く。)
(2) 土壌汚染による健康被害を生ずるおそれがある土地の調査
都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害を生ずるおそれがある土地があると認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2.指定区域等の指定、指定区域台帳の調製
都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、その区域を指定区域として指定・公示するとともに、指定区域の台帳を調製し、閲覧に供する。
3.土壌汚染による健康被害の防止措置
(1) 汚染の除去等の措置命令
? 都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
? 汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、?によらず、都道府県知事は、汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(2) 汚染の除去等の措置に要した費用の請求
(1)?の命令を受けて土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対し、これに要した費用を請求することができる。
(3) 土地の形質変更の届出および計画変更命令
指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。都道府県知事は、その施行方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
【参考:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例−環境確保条例−】
―東京都内での土地売買契約について−
・対象面積3,000?以上
工場等を廃止、除却する以前の土地の場合は、条例第116条により有害物質取扱事業者等が汚染状況の調査、汚染拡散防止措置等を行い、それらの処理の実施後に「調査および処理についての記録」(第118条)とともに引渡しを受ける。有害物質取扱事業者等が汚染状況等の調査を行わず土地を譲渡した場合は、譲受人が行う必要がある。
更地の場合は、条例第117条によって改変者に土地利用の履歴等調査、汚染状況調査、浄化処理・拡散防止措置等が発生する。要した費用については汚染原因者に対して求償できる(第121条)。
・対象面積3,000?未満
条例の範囲外であるが、土壌汚染によるリスクを考慮し、原則、土壌汚染に関する汚染状況調査および浄化処理・拡散防止措置等は売主の負担と責任において引渡し日までに実施する旨を約定する。ただし、買主が汚染状況調査および浄化処理・拡散防止措置等を行う場合は、売主がその費用を負担する旨を約定する。
【環境確保条例と土壌汚染対策法との関係】
・来年施行される法は、環境確保条例と比べ、有害物質の項目数や調査方法について一般に基準が厳しい。一方条例では、3,000?以上の土地の改変については土地の履歴調査が義務付けられている。
5.マンションの分譲・販売
汚染された敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を行ったマンションの分譲および販売については、購入後のトラブルを未然に防止するために、その内容を購入者および購入予定者を対象として積極的に説明する必要があるが、専門的知識が必要とされる分野に関する詳細な説明については、購入者の誤解を避けるためにも土壌処理会社等により行う。
説明の具体的方法としては、モデルルームには必ず具体的説明資料を備えることとし、来場者に対して必要に応じて開示する。ただし、販売担当者からの説明は、購入予定者の誤解を避けるため、重要事項説明書に記載された内容に即して行う。
さらに、購入後のトラブルを未然に防止する観点から、土壌汚染に関する説明は、詳細かつ遺漏のないように実施する必要があり、重要事項説明書に基づいた販売担当者からの説明に加えて、土壌汚染処理会社等からの専門的かつ詳細な説明がなされる機会を設けることが望ましい。
重要事項説明書には、従前の所有者・土地の使用状態、調査の基準・方法等、検出された有害物質および浄化処理・汚染拡散防止措置等の基準・方法等を必要に応じて記載する。
また、浄化処理・汚染拡散防止措置等の処理会社等の報告書は、その写しを購入者に対して交付するとともに、報告書の原本については、管理組合設立後、管理組合に対して引渡す。
東京都では、平成13年10月から、環境確保条例第116条および第117条に該当する土地については、同条第118条によって改変者が実施した調査および処理についての記録を土地の譲受者へと継承することが義務付けられている。
・ 敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を実施した場合は、購入者および購入予定者に対し、モデルルーム等で重要事項説明書に基づいて正確に説明する。
・ さらに、土壌汚染処理会社等による専門的かつ詳細な説明を行う機会を設けることが望ましい。
・ 重要事項説明書には、従前の所有者・土地の使用状態、調査の基準・方法等、検出された有害物質、浄化処理・汚染拡散防止措置等の基準・方法等について、必要に応じて記載する。
・ 購入者に浄化処理・汚染拡散防止措置等の処理会社等の報告書(写)を交付し、併せて管理組合に原本を引き渡す。
【参考:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例−環境確保条例−】
−東京都内でのマンション分譲について−
改変者が実施した調査および処理についての記録は、平成13年10月から、条例第118条によって土地の譲受者へと継承することが義務付けられている。
【参考:宅地建物取引業法施行令の改正】
法の施行に合わせて、宅地建物取引業法施行令が改正され、土壌汚染に関し重要事項説明を要する項目が追加される見通しである。追加される項目は、売買等の対象土地が指定区域に指定されていること、および指定された土地を改変する場合は、都道府県知事に届け出る必要があること、についてである。
重要事項説明を要するとして宅地建物取引業法施行令に列挙された項目は例示であると解されることから、汚染された敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を行ったマンションの分譲および販売するについては、上記のように、従前の所有者、土地の使用状態、調査の基準・方法等、検出された有害物質および浄化処理・汚染拡散防止措置等の基準・方法等を必要に応じて記載することとすべきである。
また、対象地がかつて指定区域に指定され、浄化等により指定区域から解除された土地である場合についても、かつて指定された指定区域の状況、および消除された場合の内容についても、それぞれ判明した範囲で記載する必要がある。
http://www.fdk.or.jp/k_environment/pdf/guideline.pdf#search='土壌汚染 マンション'
2009年10月18日
バックアップ小鳥が丘救済協議会の掲示板

ATCグリーンエコプラザで講演した桃花台や小鳥が丘の住民達
大阪市大の畑明郎先生と環境カウンセラーの藤原きよみさん
1.(untitled) 名前:小鳥が丘救済協議会 日付:7月5日(水)
ここに何でもお書き下さい
-----------------------------------------------------------
45.EICネット Q&A 参考まで 名前:シノギサバキは健康第一 日付:8月24日
貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24006
46.Re: EICネット Q&A 参考まで 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:8月25日
情報ありがとうございます。
全部は読み終えていないのですが、小鳥が丘団地土壌汚染問題とかなり共通点が有り、色々と参考になりそうです。
後で精読して参考にしたいと思います。
私たちの窮状に手を差し伸べてくれる方がいるという事に感謝いたします。
とりあえず御礼まで。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
41.(untitled) 名前:とある技術士 日付:8月9日(木) 9時21分
誰もがより良い環境を同等に享受できる権利の行使。1972年の国連人間環境会議で採択された人間環境宣言の中でも、「良好な環境の享受は、市民の権利である」とされている。
日本においても環境権は、憲法第25条(生存権)や憲法第13条(幸福追求権)として認められるものであり、法的保護下に置かれるべきであるという主張もある。がんばりましょう!!
42.Re: (untitled) 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:8月9日(木) 21時35分
ありがとうございます。
先日、土壌調査指定機関の民間会社に、岩野邸の建物近くの表層土調査を依頼し、結果が分かりました。
基準値を超えるものとしては、表層土壌ガス調査では発ガン性のベンゼンが、表層土壌調査(溶出量試験)ではベンゼン・猛毒のシアン・発ガン性のある鉛や砒素が検出されました。
学者に意見を伺うと、危険で有害な土壌であるとの事。
汚染発覚当初、宅地造成販売業者の両備バス?が、団地内、各戸の表層土調査を行い、当然、岩野邸も含まれていたのですが、結果は問題なし、でした。
私たちが依頼した調査結果との違いは、何なのでしょうか?益々このままにしておく事は出来ません。幸か不幸か、スコップで掘っても有害物質が出てくる場所が有るので、あきらめずに訴えていけば、隠す事は出来ないと思います。
ただ、汚染物質の直ぐ上に住宅が有り、生活しているので、危険回避の自己防衛には気を付けなければなりません。行政や議員に訴えても、実態を明らかにしようとしないので、民事訴訟を準備しています。
私たちには、解決に向かって前に進むしか、方法が無いのですから。励ましていただき、また勇気がでました。アドバイス等ありましたら、また宜しくお願いします。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
39.土壌第三者評価が大切 名前:研究会会員 日付:7月14日(土) 17時44分
絶対勝てそうな論点だけを土壌第三者評価委員会
http://www.e-being.jp/3party/index.htm
のようなところで評価してもらって勝ってから、全体の勝利に向けた裁判を起こすのはどうでしょうか?
40.Re: 土壌第三者評価が大切 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:7月14日(土) 23時34分
ご意見ありがとうございます。このような委員会の事は初めて知りました。教えて貰ったサイトで調べて検討します。有難うございました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
-----------------------------------------------------------------
37.法4条調査命令をかけさせるのは(案) 名前:某自治体担当者 日付:5月6日(日) 19時41分
某自治体で土壌汚染対策法事務を担当するものです。ここってVOC系の汚染があるのは分かるのですが、有害物質の項目の何が基準超過しているのか分かりません。
その中で含有量基準を超過している項目はありませんか。それがあれば、いろいろ理由をつけて岡山市長に法4条の調査命令をかけさせるのはいかがでしょう。土地所有者が調査することにはなりますが、汚染原因者との関係も明確になり、かえって住民側に有利にことが運ぶ可能性があります。
あと今、指定区域でなければ、そこから出る土壌を法の指定区域から出る土壌と全く同一に処理する必要はないと思います。(同等に処理しろとの法の施行通知はありますが…)岡山市って結構及び腰ですね。
38.Re: 法4条調査命令をかけさせるのは(案) 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:5月12日
ご提案ありがとうございます。そのような方法が有るのですね。検討してみます。
またアドバイスがありましたら宜しくお願いします。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
------------------------------------------------------------------
36.緊急連絡!岩野氏倒れる!! 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:10月14日
自宅庭の土壌を移動中、ガス中毒か!?
10月13日午後3時頃、小鳥が丘団地住民の岩野さんが自宅庭で倒れているのを、近くの住民が発見、119番通報し、救急車で病院に搬送された。
近所の住民や、帰宅中の学生などで現場は一時騒然とした。現場は今年6月、硫酸ピッチとみられる刺激臭のある黒い土壌が発見された自宅庭で、通報した住民によると、庭に駐車する場所を確保しようと、掘削跡の埋め戻しや堆積した土壌を移動中だったという。
今年6月に倉庫を建てるため業者が庭の土壌を掘削中、刺激臭のある黒い土壌が浅い場所から発見され、宅地を開発分譲した両備不動産に現地確認を求めたところ拒否され、業者の現地確認が済まないので現在まで、そのままの状態だったという。
通報した住民は「掘削跡に雨水が溜まっていて、堆積した黒い土壌と反応して発生したガスを吸い込んだ可能性がある。今まで危険性を訴えてきたが、誰も動かない。こうなれば、是が非でも後には引けない。」と言っている。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka
63.土壌汚染で県警に告訴状 住民、殺人未遂 名前:未必の故意 日付:10月19日
土壌汚染ヒ素汚染で県警に告訴状 神栖住民、殺人未遂などで
(共同通信) - 8月3日
茨城県神栖市の井戸水のヒ素汚染問題で、健康被害を受けた住民5人が3日、被疑者不詳のまま殺人未遂容疑で汚染源とみられるコンクリート塊の投棄を指示した人物と、業務上過失傷害容疑で現場の土地を埋め戻した同市内の業者の告訴状を県警に提出した。県警は受理する見通し。
告訴状は、投棄を指示した人物は旧日本軍の毒ガス原料にも使われた有機ヒ素化合物のジフェニルアルシン酸(DPAA)約180キロを含むコンクリート塊を現場に廃棄させ、溶出したDPAAが混入した井戸水を飲んだ近くの○○○○さん(28)の長男(3つ)に発達障害を生じさせるなど5人に健康被害をもたらした、としている。
代理人の弁護士は「コンクリート塊には毒性が極めて強いDPAAを固化処理しようとしたような跡がある。この人物は含有を知っており、摂取した人が死んでもやむを得ないという未必の故意があった」としている。(共同通信)
http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=1579;id=sikousakugo
-------------------------------------------------------------------
231.岡山市長は、小鳥が丘団地の宅地詐欺販売から手を引く宣言をすべきです 日付:8月20日
両備バス私設委員会『南古都?環境対策員会』の委員の研究課題・専門分野を、岡山大学ホームページを閲覧したら、(オブザーバー中瀬克己医師についてはYahoo検索によって、『中瀬克己』と入力して検索したら)、毒物や農薬や土壌有害物質の中毒や健康被害の専門医師は居ないことを、私のブログ http://blog.goo.ne.jp/jp280 の記事(2009年08月10日)に書いたので、ご覧ください。
--------------------------------------------------------------------
230.両備バスひどくないですか? 名前:通行人 日付:6月15日(月) 14時37分
企業責任が問われるべきです!
---------------------------------------------------------------
228.小鳥が丘団地の固定資産税の減免 名前:相川哲弥 日付:2月19日(木) 19時3分
『固定資産税額』=『固定資産評価額』×『税率』によって決まる。固定資産税の減免は、次の2方法がある。
方法1。上の計算式で普通の土地として税額を計算した上で、減免する。
方法2。協議会ホームページ記述によると、ある住民が銀行から、『廃棄物処理工場跡地は資産価値ゼロ』と言われたそうだから、『固定資産評価額』をそのように決めて、税額を、上の式で計算する。
方法1は、議員が既に市議会で質問している。方法2のために、市の固定資産評価審査委員会に不服申し立てしたらどうか(まだしていないなら)。私のブログ http://blog.goo.ne.jp/jp280 の2009年2月15日記事の17節に関連の話が書いてあります。
229.Re: 小鳥が丘団地の固定資産税の減免 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:2月20日(金)
アドバイスありがとうございます。平成17年5月に多数の「小鳥が丘団地住民」が岡山市固定資産評価審査委員会に「固定資産評価審査申出書」を提出しました。しかし平成17年7月に委員会から「申出却下」の決定通知書が郵送されてきました。
岡山市固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査決定書
主文;本件土地及び家屋に係る審査申出はこれを却下する。
理由は、価格に関する審査の申出のできる事項に当たらないと言うものです。
地方税法第432条第1項(中の第411条第3項及び第349条第2項第1号、同条同項ただし書、第3項ただし書、又は第5項ただし書)により本件申出は「地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情」に当たらないものと本委員会は判断する。
と記載されています。(説明一部省略)できないことを詳しく説明して審査を断ったのだと思っています。
---------------------------------------------------------------
226.住宅・宅地の購入・新築時の注意点 日付:1月16日
既に土地・住宅を買った人は、重要事項説明書に地番や仲介不動産屋の名前・住所が書いてあるか。。これから買う人は。買う前に登記を見よ。司法書士の選び方。最初に土地の履歴を付近住民に聞き合わせる。小鳥が丘団地住民の被害に学ぶ。
について、私のホームページ(ブログ) http://blog.goo.ne.jp/jp280 の記事『住宅・宅地の購入・新築時の注意点』(2009年01月16日)に書いたので、皆様、ご覧ください。
---------------------------------------------------------------
224.小鳥が丘住宅団地問題の住民に有利な判決例(2008.12.16) 日付:12月17日(水)
東京都の足立区土地開発公社が、平成3年に、会社から買った土地が、平成14年に新規制定された法律と都条例によって、フッ素が有害物質に成って、『フッ素を除去した費用を会社が払え』と命じた東京高裁判決の解説を、私のブログ http://blog.goo.ne.jp/jp280 の2008年12月15日の記事『小鳥が丘住宅団地問題の住民に有利な判決例』に書いたので、ご覧ください。
225.Re: 小鳥が丘住宅団地問題の住民に有利な判決例(2008.12.16) 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:12月17日(水) 21時28分
相川さんのブログ拝見しました。勇気づけられる判例です。小鳥が丘団地土壌汚染裁判は長くかかりそうですが、希望が湧いてきました。これからも根気よく私たちの主張をしていきます。
ありがとうございました。今後もご支援お願いします。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
--------------------------------------------------------------
223.5%以上は明らかに廃棄物処理法違反 名前:油売り 日付:11月25日(火)
財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)』2005年3月(乙第18号証)によれば、ヘキサン抽出物質量(油分)が0.1〜10%検出され、含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。つまり、油分、水分、塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20081124
---------------------------------------------------------------
208.平成20年5月30日 名前:ゴミゼロ 日付:4月12日(土) 11時12分
平成20年のゴミゼロの日は5月30日ですね!何か地球を美しくするイベントでもあれば良いのですが・・・
ごみゼロの日 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%94%E3%81%BF%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%AE%E6%97%A5
210.Re: 平成20年5月30日 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:4月13日(日) 11時13分
サイトトップページのニュース欄に掲載しましたが、裁判所による「小鳥が丘団地」現地検証が5月30日に行われる事になりました。(13:30〜15:30)
ゴミゼロの日とは、言われるまで気付きませんでした。裁判所も粋な日を選んだものですね。住宅地土壌汚染問題に関心のある方は、当日参加して実際自分の目で見聞きし、体感してみてください。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
219.Re: 平成20年ゴミゼロの日 裁判官現地検分 名前:裁判官が試験掘りに立会 日付:5月31日(土)
竹永みつえ議員のブログで現地検分の様子が掲載されています。下記は引用ですが
明らかにその当時の工場の頃の電線がでてきたり、ガスが充満しているという証拠の泡が湧いているのが目視できました。
そして何よりも頭が痛くなるほどの異臭。これで体に異変がないというのは間違いだと今日立ち会った誰もがわかったのではないでしょうか?今日は団地のなか3箇所と機械もいれて1箇所、あわせて4箇所で調査が行なわれました。
http://okjcp.jp/t/?p=950
220.Re: 平成20年5月30日 名前:毎日新聞転載 日付:6月1日
損賠訴訟:岡山・小鳥が丘団地の土壌汚染、地裁裁判官ら現地調査 /岡山
環境基準を超す有害物質が検出された宅地を十分な対策を取らずに販売したとして、岡山市南古都・楢原の「小鳥が丘団地」住民23人が「両備ホールディングス」を相手取り、約14億円の損害賠償を求めている訴訟で30日、岡山地裁の近下秀明裁判長ら2人の裁判官と書記官1人が現地を視察した。
住民が重機やスコップで宅地を掘ると約70センチ下の地中から黒や灰色の土が露出。同時に鼻につく化学臭が漂った。また住宅前の側溝にはガスが発生し、住民によると、メタンガスらしい。
http://mainichi.jp/area/okayama/news/20080531ddlk33040679000c.html
221.Re: 平成20年5月30日 名前:機関紙赤旗 日付:6月7日(土)
竹永みつえblog ≫ Blog Archive ≫ 小鳥が丘団地汚染訴訟を「赤旗」が ...
小鳥が丘団地汚染訴訟を「赤旗」が伝える
「しんぶん赤旗」(6月6日および6月7日付中国四国版)は、「岡山・小鳥が丘団地 汚染訴訟 」として、現地調査のようすなどを伝えています。
http://okjcp.jp/t/?p=1864
222.Re: 平成20年ゴミゼロの日
名前:環境新聞読者 日付:6月9日(月) 20時34分
小鳥が丘団地土壌汚染で強い臭気を確認――岡山地裁が現地視察
2008年06月09日
岡山市内の小鳥が丘団地住民が同団地を開発した両備バス(現・両備ホールディングス)を相手取り民事訴訟を起こしている土壌汚染問題について岡山地方裁判所は5月30日、同団地土壌汚染の現地視察を行った。
http://eco.goo.ne.jp/news/files_daily/daily_20080609_1112.html
--------------------------------------------------------
217.川崎市に48億円賠償命令 公調委が最高額裁 名前:公害等調整 日付:5月8日
転記 川崎市に48億円賠償命令 公調委が最高額裁定 土壌汚染 責任認める
2008年5月8日 朝刊
川崎市宮前区で購入した土地の土壌汚染は、同市が搬入したごみの焼却灰などが原因として、東京急行電鉄(東京都渋谷区)が同市に損害賠償を求めた問題で、国の公害等調整委員会は七日、市に約四十八億円を支払うよう命じる裁定をした。市は裁定を不服として、債務不存在の確認を求め提訴する方針。
公調委によると、裁定で命じた支払額としては過去最高で、土壌汚染の責任を認定したのは初めてという。
問題の土地は、東急電鉄が一九九二年に購入、二〇〇〇年にマンション用地として開発業者に売却した。〇三年、環境基準を超える鉛やトリクロロエチレンなどが検出される土壌汚染が発覚したため、東急電鉄は土地を買い戻して、汚染対策工事を実施。〇五年、市に約五十二億円の賠償を求める申請をした。
裁定では、市が六八−七〇年に隣の私有地に搬入した焼却灰などを、市の委託業者が土地の埋め立てに使ったのが原因と認定。東急電鉄が〇四年八月、市に土壌汚染処理計画を申請した時点で、市に汚染を除去する義務があったとした。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008050802009460.html
218.Re: 丸紅に被害者住民が土壌汚染公害調停申請へ 名前:公害等調停 日付:5月10日(土)
工場跡地異臭 住民、公害調停申請へ
神戸市中央区の62人開発の商社に5600万円求め
神戸市中央区脇浜町の香料原料製造会社「日本テルペン化学」神戸工場の解体現場で発生した異臭で「健康被害を受けた」とする周辺住民62人が近く、跡地でマンション開発を行う大手商社「丸紅」(東京)に計約5600万円の損害賠償を求め、県公害審査会に公害調停を申請する方針を固めた。同社は健康被害との因果関係を否定しているが、住民側は「同社は、治療費や慰謝料を支払うべきだ」と主張している。
住民や同社によると、2006年4月〜07年2月に同社が跡地の土壌改良工事を実施した際、異臭が発生。近くにある阪神大震災復興住宅の住民らから「せきがひどい」「涙や鼻水が止まらない」などの苦情が相次いだ。市の大気調査では、健康被害を及ぼすほどの有害物質は検出されなかったが、異臭軽減などを求めて行政指導。同社は薬剤を散布し、相談窓口を設置した。
しかし、その後も体調不良を訴える住民が相次ぎ、住民側が補償を要求。同社が1世帯約5000円、総額約500万円の迷惑料支払いを提案して交渉を進めてきたが、62人とは折り合いが付かなかった。
マンションは14階建てで現在建設中。同社は「不快な思いをさせたことは申し訳なく、誠意ある対応をしてきたつもりだ。公害調停申請についてはコメントできない」としている。
◇
公害調停の申請に踏み切ることを決めた住民は読売新聞の取材に対し、深刻な被害を訴えた。
長女(10)が気管支ぜんそくになったという女性(46)は「風邪もひかなかった子が、運動会や音楽会の練習にさえ参加できなくなった」と唇をかむ。医師の診断は「化学物質過敏症の疑い」。せきを抑える薬が手放せなくなった。「医者には完治しないと言われた。丸紅はきちんと説明してほしい」。女性は語気を強めた。
気管支炎と診断された別の女性(76)は好きだった登山ができなくなったという。「せきが苦しくて寝られないこともある。私たちがこんなに苦しんでいるのに、責任を認めない会社の姿勢にあきれてしまう」と憤った。
東京都杉並区の不燃ごみ圧縮施設の周辺住民が目やのどの痛みを訴えた「杉並病」問題で、住民を支援した旧通産省工業技術院(独立行政法人・産業技術総合研究所)元主任研究員、津谷裕子さんは「市の大気調査はデータの取り方に問題があり、不十分。同社が健康被害の原因を突きとめ、住民に説明責任を果たすべきだ」と指摘している。
(2008年4月27日 読売新聞)
--------------------------------------------------------
61.南古都? 環境対策員会 名前:大学の正義と学術 日付:10月18日(木)
南古都? 環境対策員会
設立年月日 平成16年10月15日
委員長 千葉喬三 岡山大学 副学長
委 員 河原長美 〃 保健環境センター教授
笹岡英司 〃 環境理工学部教授
西垣誠 〃 環境理工学部教授
西村伸一 〃 保健環境センター助教授
竹内文章 〃 保健環境センター助教授
山本秀樹 〃 医学部 講師
オブザーバー
金安利和 岡山市環境保全部 部長
中瀬克己 保健所 所長
委員会は基本的に非公開で開催し、必要に応じてプレスリリースさせて頂きます
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/ryoubiiinkai.html
68.岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結 名前:企業からの献金を増やす 日付:10月23日(火)
岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結について
両備グループ代表 小嶋 光信
写真:千葉学長(左)と小嶋代表
・・・まさしく開かれた大学として、地域産業にいかに貢献するかが大学の使命であり、またそうしなければ企業からの献金を増やすことが出来ず、大学は経営難になるなど、地域の発展が即大学の経営に反映してくるのです。・・・
http://www.ryobi.gr.jp/message/message01.html
166.Re: 岡山大学における情報開示について 名前:大学のコンプライアンス 日付:12月22日(土)
情報公開制度とは?
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするため、国民のみなさまに法人文書を開示する制度です。
開示請求ができる人は?
国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。
http://www.okayama-u.ac.jp/japanese/know/information_disclosure01.html
213.Re: 首相辞任の背景 名前:事情通 日付:4月20日(日) 8時48分
岡山大学 OB 六晋会 脱税 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=+%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%A6+OB+%E5%85%AD%E6%99%8B%E4%BC%9A+%E8%84%B1%E7%A8%8E&lr=
-------------------------------------------------------
12.土壌汚染対策法 名前:おほ! 日付:8月20日(日) 3時4分
現在の法律で、対策を取ろうとすると土壌汚染対策法しかないんではないでしょうか。ただし、その場合周辺で地下水利用に影響が出ていることが条件になるのかな。
そして、対策を講ずべき者は、土地の所有者だったような気もします。そのバイは、自爆??!!
13.Re: 土壌汚染対策法 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:8月21日(月)
私たちは、小鳥が丘団地土壌汚染問題を土壌汚染対策法で考えてはいません。それ以前の問題だと思っています。土壌汚染対策法の目的は、工場跡地等の土壌汚染から周辺の人の健康被害を防止し、土壌汚染地をそのまま、人の健康被害の危険が高くなる住宅等用途変更させない事にあると思います。
今後、安易な土壌汚染を許さない為の法律だと思います。この法律以外で考える場合
・瑕疵担保責任(不動産のキズ、不具合)
・債務不履行(重要事項説明を説明せず売却)
・不法行為(詐欺)
・殺人未遂(他人の生命を危険に曝しているにもかかわらず費用負担を避けるため傍観している)
など考えられますが、現法律では時効が成立しているか、時効を経過しつつあると思います。また、時効の発生時点がいつか、も考えさせられる問題です。土壌汚染の様な問題の場合、地中深くに原因がある場合が多いので、問題が発覚した時はすでに時効が成立している方が多いでしょう。
現在の土壌汚染対策法は汚染土壌の上で人間が生活している事を想定してない様に思えます。
小鳥が丘団地の場合、岡山市は土壌汚染対策法を参照し周辺に汚染が拡大しているかどうかだけを調査しているのであり、最も影響を受けていると推定される団地内の調査は、考えていません。
岡山市等行政は、目先の当てはまりそうな法律を追い、最も基本的な住民の生命・財産を守り、環境は良好なまま,子孫へと手渡していくことを目指して行う、という行政の基本理念から目を背けていると思います。
また、両備不動産は、時効が切れて法的責任が及ばなければ正当だと考えているフシがあり、口先では顧客が大事だといくら言っても、今後の本音では企業の社会的責任を果たそうとしないでしょう。
質問のように当団地住民の一部も、公になれば対策は土地所有者になるかもしれないと考えて活動するのをタメラッテいる人も居ると思われますが、それは問題を先送りするだけで、将来汚染が拡大したときには一層解決が難しくなると思います。
今でも行政に汚染発生時の文書開示請求をしても保管期限が来て処分したとの回答が少なくないし、数十年後では当時の証人も居なくなります。
そうなれば、土壌汚染対策法に言う「対策を講ずべき者は汚染原因者であり、不明などの場合は土地所有者」の現実的解決法を取らざるを得なくなる恐れが多くなると思います。
よって、問題を明らかにするのは、汚染が発覚した今をおいて無く、後では遅いと思います。
またとりあえず対策を講じた後の責任は土地所有者になる可能性が大きくなると思います。
今後、同じ様な事例が全国各地で発覚すると思われますが、公平で社会が容認できる解決策を創って行かなくてはならないのでは。
その時ババをつかんだ住民が悪いという論理が通って、住民が関係各社機関を道連れに自爆する事が無いようにしなければならないと思います。
小鳥が丘団地土壌汚染の様な問題の解決策は、未だ事例が無く、定まって無いと思われます。
皆さんはどうお考えですか?意見があれば、聞かせてください。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka
51.Re: 土壌汚染対策法8条 名前:本人の健康と周りの人の団結がなにより 日付:10月30日(火)
まず両備に対して時効停止の手続きを行う事が必要では無いでしょうか?一般に民事20年と言われますが、土壌汚染対策法においても良く似た条文があります。
支援制度を利用するにしても4分の1は自己負担になりますので最低限この額は貰わないといけません。しかし、健康被害や精神的苦痛はもっと大きいことでしょう。
下記に土壌汚染対策法の条文を転機いたします。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 前条第一項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。
ただし、その行為をした者が既に当該汚染の除去等の措置に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該汚染の除去等の措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該汚染の除去等の措置を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html
97.Re: 土壌汚染対策法に基づく指定支援法人 名前:民法・刑法・宅建業法・ 日付:12月31日(月) 1時27分
> 現在の法律で、対策を取ろうとすると土壌汚染対策法しかないんではないでしょうか。
いいえ、民法の損害賠償があります。
土地の瑕疵担保責任や不法行為責任もあり、土壌汚染対策法が返って汚染原因者負担の原則を分かりにくくしています。
詐欺罪の適用も一部で検討されているようですが、まだ適用されていません。今後、土壌汚染の知識が一般化すると詐欺罪適用の可能性もあります。
宅地建物取引業法は時効で適用され無かったとのことですが、時効で逃げるのは一番後味が悪いですね、先々どこかで仇を取られる可能性があります。
> ただし、その場合周辺で地下水利用に影響が出ていることが条件になるのかな。
いいえ、油を含んでる場合には「宅地として通常有すべき性状を備えないとして、土地の瑕疵に当たるというべきである」との判決が確定しています。
つまり、油があれば基準を超えていなくても「土地の瑕疵」にあたり損害賠償の対象になります。
http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/zennichi_kaiin/knowledge/business/database/data02.htm
> そして、対策を講ずべき者は、土地の所有者だったような気もします。
いいえ、汚染原因者が費用を負担します。また、廃油を扱っていた産業廃棄物処理施設なので、PCB由来によるダイオキシン類が心配されますので、ダイオキシン類が検出された場合にはダイオキシン類特別措置法に基づき行政が中心となって対策を進めることになります。
> そのバイは、自爆??!!
そう!両備ホールデングが自爆することになるかも知れません。企業が土壌汚染のある土地を一般住民に売却した場合には社会的制裁が厳しい状況下にあります。
両備ホールデングが住民からの訴えを甘く見ていると企業の存続に関わる重大な問題に発展する可能性があります。
両備が自爆しないように、過去の全ての情報を開示した上で、汚染調査を実施し、データは全て公開し、公的支援の活用なども視野に入れながら住民の健康を守る事を第一に考えて解決すべきです。
参考までに土壌汚染対策法に基づく指定支援法人のアドレス↓
http://www.jeas.or.jp/dojo/index.html
判例のアドレス↓
http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/zennichi_kaiin/knowledge/business/database/data02.htm
131.Re: 時効停止と民事訴訟 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月19日(月)
アドバイスありがとうございます。私たちも時効の事を考え、弁護士と相談のうえ汚染発覚から3年が迫り来る2007年7月13日付けで「通知・催告書」を内容証明郵便で両備バスに送付し、承諾しない旨の回答書を受け、2007年8月31日に民事訴訟しました。
結局私たちの問題は、いまの法律では最後は民事訴訟しかないのですね。今後もアドバイスよろしくお願いします。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
---------------------------------------------------------
211.Re: 無過失責任制度 名前:(財)環境情報普及センターのファン 日付:4月19日(土)
事業者が大気汚染および水質汚濁等により健康被害を引き起こした場合には、過失の有無を問わず賠償責任を認める制度。
事業者の責任を強化して被害者の円滑な救済を図るため、1972年に民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法(1968)および水質汚濁防止法(1970)で導入されたもの。
被害者が民法の規定によって損害賠償を請求するためには、損害の発生、原因行為と結果発生との間の因果関係、違法性及び加害者の故意又は過失を立証しなければならない。しかし、大気汚染等の分野ではこれらのうち故意過失の立証をしなくてもよいこととされた。
無過失責任の例は、イタイイタイ病裁判で使われた鉱業法や、国際法の分野でも宇宙損害賠償条約、原子力損害に関する諸条約、油濁民事責任条約等にみられる。刑事法の分野でも、公害罪法は公害により人を死傷させた者を一定の場合について過失の有無を問わず処罰することとし、法人の両罰規定も置いている。
アメリカ法でも公害、麻薬、食品、商標等に関するいわゆる公共的犯罪については故意も過失も要件としない厳格責任(strict liability)が認められている。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2531
212.Re: 無過失賠償責任 名前:土壌汚染は環境省水・大気環境局が担当 日付:4月19日(土)
汚染原因者としての企業責任について、大気汚染と水質汚濁に係る健康被害に関して企業の無過失賠償責任を法制的に確立したもの。
1972年の公害関係法の改正以前においては、公害の被害者が加害者に対し損害賠償を請求するには、不法行為の成立要件を充足させることが必要であった。
しかし、公害の特殊性を考えるとき、原因行為の違法性や原因者の故意又は過失を立証し、因果関係を確定することが非常に困難であり、被害者が公害発生者の不法行為責任を追究することは、決して容易なことではない。
このため1972年に整備された公害関係法においては、伝統的な不法行為理論を修正し、無過失賠償責任論に基づく原則が採用された。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2532
--------------------------------------------------------
55.はじめまして 返信 引用 名前:東急不買 日付:9月2日(日)
開発業者の無責任さには憤りを覚えます。売ったら売りっぱなしの無責任ですね
http://ameblo.jp/tokyufubai/
202.Re: はじめまして 名前:マイホームパパ 日付:1月6日(日) 10時54分
>開発業者の無責任さには憤りを覚えます。
>売ったら売りっぱなしの無責任ですね
マイホーム購入は庶民一生の夢であり、一大イベントです。
マイホームの問題に巻き込まれると、24時間中、心が穏やかではいられない。
--------------------------------------------------------
209.Re: はじめまして 名前:消費者相談 日付:4月12日(土)
社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 西日本支部
のような団体が土壌汚染についても相談に乗ってくれれば良いのですが・・・
http://www.nacs.or.jp/nishi/index.html
--------------------------------------------------------
88.今後の土壌環境施策に関する基本的な方針 返信 引用 名前:健康被害の防止 日付:10月27日(土) 22時9分
土壌環境施策のあり方についての論点(案)
1.今後の土壌環境施策に関する基本的な方針
○ 土壌汚染による健康被害を防止するため、土壌汚染地を的確に把握し、汚染の状況に応じた対策を円滑に推進することが必要。
このため土壌汚染の可能性のある土地について、汚染の状況や実態が明らかにされることが必要である。その上で、汚染状況に応じて健康被害の防止のための対策が行われることが必要である。
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/04/mat07.pdf
89.Re: 土壌環境施策に関するあり方懇談会 名前:健康被害の防止 日付:10月27日(土)
土壌環境施策に関するあり方懇談会
1.趣旨
我が国で土壌汚染対策法が平成15年2月に施行されてから5年目を迎えます。
この間、法律に基づく土壌汚染の調査、対策が行われ、さらに一般の土地取引でも土壌汚染の調査・対策が広く実施されるようになっています。
一方で、土壌汚染対策法の施行を通して浮かび上がってきた課題や法制定時に指摘された課題を整理検討することが必要な時期を迎えています。
また、土壌汚染は土地の資産価値に影響を与える問題でもあり、経済社会の各方面の実態をよく把握していくことが重要です。
このため、こうした土壌汚染に関する現状を把握し、それを踏まえて土壌汚染対策の新たな施策のあり方の検討を今後行っていくこととし、施策展開に向けた現状把握、課題の整理等を行っていくため懇談会を開催します。
2.懇談会について
「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を環境省水・大気環境局長諮問により開催します。
懇談会は、土壌環境や法律に関する学識経験者、調査・対策の専門家、不動産、金融、事業者等の関係者、自治体等により構成します。
<土壌環境施策に関するあり方懇談会委員名簿>
氏名 所属
石渡秀雄 東京都環境局環境改善部長
大塚直 早稲田大学法学学術院教授
荻原勉(社) 土壌環境センター会長代理((株)清水建設常務執行役員)
奥村彰(社) 日本経済団体連合会環境安全委員会環境リスク対策部会環境管理WG座長(住友化学(株)レスポンシブルケア室主幹)
神谷文吾 全国鍍金工業組合連合会常任理事((株)神谷理研代表取締役社長)
嘉門雅史 京都大学地球環境学堂長
栗原明広 (社)不動産協会事務局長代理
佐藤泉 佐藤泉法律事務所弁護士
佐藤雄也 中央大学理工学部教授
正保剛 (社)日本鉄鋼連盟環境・エネルギー政策委員会環境保全委員会土壌・水質分科会主査(住友金属工業(株)環境部環境室長)
鈴木一男 千葉県環境生活部次長
?橋滋 一橋大学大学院法学研究科教授
中杉修身 上智大学地球環境学研究科教授
早瀬保行 三井住友銀行投融資企画部長
廣田裕二 (財)日本不動産研究所環境プロジェクト室長
藤井良広 上智大学大学院地球環境学研究科教授
細見正明 東京農工大学大学院教授
前川統一郎 (株)国際航業常務執行役員
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/04/mat01.pdf
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/04/mat01.pdf
205.鉛害撲滅へ、鉛の怖さと鉛ゼロ化を実現した理由 名前:読者 日付:1月27日(日)
以下
http://news.livedoor.com/article/detail/3472162/
からの転載です。
■鉛による害とは
鉛は自然界に元々存在する物質であり、それだけでは環境に害があるとはいえません。しかし、人体に対しては有害物質であることも知られています。
鉛は食材にも存在しますが、通常の状態であれば尿と一緒に排泄されるために必要以上の鉛が体内に蓄積することはありません。
四エチル鉛のような有機化合物を摂取してしまったり、何らかの体質・代謝の異常により鉛が排泄できず大量の鉛を蓄積すると毒性を持つようになります。
呼吸器系統や消化器系統から人体に吸収されると腹痛や貧血などの「鉛中毒」の症状が現れます。鉛は最終的には骨と結びついて長く人体に蓄積されます。幼児の「慢性鉛中毒」は、大脳の成熟障害や精神薄弱や骨発育障害などを引き起こします。
アメリカにおける調査報告(David research center)では7歳児の血中鉛濃度が高い児童はIQ値が低いという結果も報告されています。
■生活の中で広まった鉛害
古代ギリシャのヒポクラテスの記述から古代ローマ時代は膨大な量の鉛が生産され、陶磁器の上薬、料理器具、配管などにも使われていました。このためローマ人には死産、奇形、脳障害といった鉛中毒が一般的だったと考えられています。
現代の日本では、1970年代まで水道の家庭への引き込み管に鉛製の水道管が使われていたことから水道水に含まれる鉛が問題となり、浄水器などが売られています。
このような直接体内に摂取することのほか、昔のオクタン価向上のために鉛を混入していたガソリンを使用した自動車の排ガスから鉛が空気、土壌、水に溶け込み危険な状態になりました。
http://news.livedoor.com/article/detail/3472162/
207.Re: 6万人追跡アトピー調査、化学物質の影響探る 名前:不思議なアトピー 日付:3月22日(土)
環境省は新年度から、日常生活の中で触れる化学物質が子どもの健康や発育に与える影響を、出生前から12歳ごろまで追跡調査する事業に乗り出す。
対象者数は約6万人と国内では最大規模で、漠然と不安がられてきた化学物質の影響を明らかにするのが狙いだ。
調査では、妊婦の血液や出産時のさい帯血を採取し、ダイオキシンや有機フッ素化合物など、体内に蓄積されやすく胎盤を通りやすい化学物質の有無や量を分析する。その後、数千人については、血液や毛髪の分析、家庭や地域環境の聞き取り、身体・精神面の発達のチェックなどを定期的に実施。残りの約5万人もアンケート調査を行う。
胎児や子どもは化学物質の影響を大人よりも受けやすく、アトピー、アレルギー、学習障害などの異常が、化学物質の影響と指摘されることも多い。だが、過去にさかのぼって原因を特定することは難しいため、調査実施を決めた。
(2008年3月22日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20080322-OYT8T00241.htm
-------------------------------------------------------
206.社会的責任の点から早期に問題解決を図るべきと判断した 日付:3月21日(金)
南海側が費用大半負担
大阪市購入の工場跡地土壌汚染 調停案に双方合意
南海電鉄から購入した土地の土壌汚染が発覚したため、大阪市が同社に対策工事費の全額負担を求めて府公害審査会に調停を申し立てていた問題で、市は19日、総額3億1370万円のうち、同社が2億6670万円を負担する内容の調停案に双方が合意したことを明らかにした。市議会の承認を経て、調印される見通し。
土地は西成区の工場跡地約1・5ヘクタール。当時誘致を目指していた五輪の競技会場用として市が2001年に購入したが、事前に土壌調査を求めておらず、契約にも汚染判明時の売り主側の責任を明記していなかった。04年に基準の最大52倍の鉛が検出され、06年4月に調停を申し立てていた。
調停案は、将来予想される最終対策工事費の一部など4700万円を市が負担する形だが、市は「売り主の責任を求めてきた主張がほぼ認められた」と説明。同社は「社会的責任の点から早期に問題解決を図るべきと判断した」とのコメントを出した。
(2008年3月20日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20080320-OYT8T00105.htm
---------------------------------------------------------
186.空中写真 名前:空中写真閲覧サービスファン 日付:12月31日(月)
昭和49年度 CKK-74-12 400dpi
右下の拡大ボタンをクリック
http://w3land.mlit.go.jp/Air/photo400/74/ckk-74-12/c13/ckk-74-12_c13_8.jpg
187.Re: 空中写真 名前:空からパチリ 日付:12月31日(月)
昭和55年
工場がくっきりスッキリ見えます
http://w3land.mlit.go.jp/Air/photo400/80/ccg-80-2/c10/ccg-80-2_c10_21.jpg
199.Re: 空中写真 名前:国土画像情報 日付:1月6日(日)
岡山県岡山市南古都の空中写真の選択画面
http://w3land.mlit.go.jp/cgi-bin/WebGIS2/WF_AirMapMain.cgi?CMD=52&IT=p&DT=n&CX=482577.1&CY=124929.1&STR=%b2%ac%bb%b3%b8%a9%b2%ac%bb%b3%bb%d4%c6%ee%b8%c5%c5%d4%a3%b5%a3%b7%a3%b4
204.Re: 空中写真 名前:クッキリ工場があります 日付:1月16日(水)
CCG-80-2
高解像度の画像をご覧になるには 400dpi
緯度 34°42′10″
経度 134°3′7″
昭和55年度
高解像度の画像をご覧になるには 400dpi
右下のボタンで拡大します。
http://w3land.mlit.go.jp/cgi-bin/WebGIS2/WC_AirPhoto.cgi?IT=p&DT=n&PFN=CCG-80-2&PCN=C10&IDX=21
-------------------------------------------------------
24.もう一つの大事な目的! 返信 引用 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:9月2日(土) 19時10分
私たちは、今回のgoogleの件で、事実の情報発信を阻害される、怖さを考えさせられました。
よって、土壌問題解決の目的と同時に、事実を伝える為に多くの人にアクセスしていただくことも大事な目的と認識し、努力して行こうと思います。
今後、私たちの体験したことは、公開できるものはすべて紹介したいと思います。
昨日夕方から、今度は「ヤフー検索」でトラブルがありました。
前は(小鳥が丘)と検索すれば「Yahooジオシティーズ環境と自然」が表示され、そこをクリックすると、「小鳥が丘団地救済協議会」が表示されていたのですが、そこをクリックしても「小鳥が丘団地救済協議会」はでてこなくなりました。
私達の思いは有りますが、本来の目的以外で、脱線していると眉をしかめられる方もいらっしゃるでしょうから、事実を記述するに留めておきます。
私達も本題の土壌汚染の問題を議論したいのです。検索の事を取り上げるのは、私達の本意ではありません。
ただ静かにホームページの検索が出来なくなりつつ、ある事だけは事実です。
私達は、そんな事はあるはずは無い、と考えないで、あらゆる可能性を否定しない立場で物を考える事は、これからも続けていこうと思っています。
皆さんのおかげで、当ホームページは徐々にでは有りますが、アクセスが増えています。
私たちは、微力では有りますが、多くの人にアクセスしていただく機会を奪われないよう、労苦を惜しまず、あらゆる方法を考えていきます。
私たちは、このホームページを多くの人に見ていただく為に、全力を傾けます。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka
---------------------------------------------------------
73.Re: インターネット情報操作 名前:google検索が1700件から548 件に激減 日付:10月27日(土)
2007年10月27日に Googleで「小鳥が丘」を検索した結果 約 548 件しかヒットしなくなりました。
2007年10月25日には1700件以上ヒットしていたのですが?
3分の1もの大幅減少です。
情報統制をおこなっているのでしょうか?
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%e5%b0%8f%e9%b3%a5%e3%81%8c%e4%b8%98
201.Re: もう一つの大事な目的! 名前:グーぐると5000件 日付:1月6日(日) 10時50分
小鳥が丘 の検索結果 約 5,030 件
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%e5%b0%8f%e9%b3%a5%e3%81%8c%e4%b8%98
203.Re: もう一つの大事な目的! 名前:傍観者 日付:1月8日(火) 9時3分
住民の皆さんの大変な気苦労をお察しします。
目に見えない圧力と戦っておられると、色々な事が疑わしく見えることかと思います。
しかし、妄想で第三者からの印象を悪くする必要はないと思います。
-------------------------------------------------------
151.「土壌汚染と健康被害の勉強会ブログ」様へ 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月26日(月) 11時38分
標記のブログで(小鳥が丘土壌汚染の歴史)年表を作成されていて、
http://beauty.geocities.jp/oecacasa/kotorigaokanorekisi.htm
2005年(H17年)3月28日の環境対策検討委員会意見書の内容を質問されていますので、配付された意見書を掲載します。
平成17年3月28日
意見書
南古都?環境対策検討委員会
委員長 千葉 喬三
先に行った電気探査において低比抵抗値を示した場所に存在する物質の化学的分析の結果について検討を加えた。また、本団地における調査は今回をもって完結したと考えられるので、これまでに行った調査結果をも参考にして、対策案を提案する。
1.土壌化学性状分析について
これまでに行われた土壌調査、土中ガス調査及び地下電気探査調査の各結果より、調査対象地内にパッチ状に特異な地層(団塊)の存在が推定されたことから、それら部分の性状を把握することを目的とした。電気探査調査において低比抵抗値を示した部分の内の2ヶ所についてボーリングを実施し、採取した不攪乱試料(コアサンプル)について必要な化学的性状分析を実施した。その結果の詳細は、添付した環境保全事業団の報告書のとおりである。
2ヶ所のコアサンプルの含水量、含イオン濃度、ECの測定の結果、当該部分には通常の土壌には含有されない物質が存在することがわかった。これは、先に実施された電気探査調査の結果と一致し、当該部分が何らかの人為的攪乱を受けていることは明らかとなった。電気探査調査における低い比抵抗値は、当該部分が電気を通しやすくなっていることを表しており、今回の調査のサンプルの含イオン濃度、ECの測定結果はそのことを裏付けている。すなわち、当該部分になんらかの電解物質(たとえば食塩など)が相当量混入し(投棄され)、そのことにより比抵抗値が低下していると推測される。
また、サンプルの有機物含量(強熱減量値)が高く、これは何らかの有機物材料(たとえば石けん材料の油脂物質)が投棄混入されていることを推測させる。このような有機物は水の移動を抑制するため、含水率が高くなり、比抵抗値を下げる一因にもなっている可能性がある。混入有機物は比較的深部に埋没されたかたちになっているので、嫌気的な微生物分解をうけつつ減量している過程にあるものと考えられる。また、硫黄を含む物質は比較的地表に近いところに多く存在するので、硫黄臭に関しては有機物臭よりも短期間で消失することが期待できる。
2.居住環境の改善対策
以上の調査結果より、当委員会が提示する対策工の案は別紙のとおりである。工法の選定にあたっては、当該地が住宅団地であることを考慮し、住民の日々の生活を阻害しないことに重点を置いた。
対策の目的は、土中のガスを揮散させ、臭気の低減を図ることにより、住民の不快感ならびに不安感を解消することである。そのため、対策工は住民の大多数が不快感を抱かなくなるまで継続することが望ましい。
なお、当委員会はこの対策工の提案をもって役割を終えるが、工事の実施にあたって技術的な助言が必要であれば別途意見を申し述べることとする。
これまでの調査によって、現状の生活環境においては臭気による不快感はあるものの、健康への影響が直ちに懸念されるものではないことは、既に申しあげたとおりです。しかし、よりよい居住環境を現出するため、ここに提案しました対策工案を参考にされ、できるだけ早く改善対策を実施されることをお奨めします。
以
以上ご確認ください。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
159.Re: ECが高いほど一般的には汚い水 名前:EC(電気伝導度)とは 日付:12月16日(日) 16時40分
EC(イーシー)(電気伝導度)
電気伝導度(electrical conductivity)は、電気の通しやすさの尺度(しゃくど)で、水中に溶(と)けているる物質の量を短時間で測定できる。
電気伝導度が高い値ほど、水にさまざまな物質が溶けていることになり、一般的には汚い水といえる。単位はミリジーメンス毎メートル[mS/m]。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/38967576.html
162.Re: 小鳥が丘団地は「日本第一級の土壌汚染」と言われて― 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:12月17日(月) 13時47分
小鳥が丘団地民家の庭を2メートルぐらい穴を掘って土壌調査をしたことがありました。
掘り始めると周囲に悪臭が漂い、掘るにつれて段々悪臭が強くなり、臭いというより刺激臭で鼻が痛くなり、気持ちが悪くなりました。
とてもその場で見ていられなくなり、飛んで逃げるような状態でした。学者の先生が穴に扇風機を入れ悪臭を飛ばしながら、ハシゴをかけて穴に入り調査をしました。
土壌の断層は、表層以下10センチぐらいまで汚染土壌を隠すお化粧用のマサ土になっていて、それ以下35センチぐらい灰黒色の層があり(HPトップページの写真)、それ以下は真っ黒の土壌が広がっていました。
灰黒色の土壌は真っ黒の汚染土壌とマサ土が混ざった土壌ということでした。
いくら行政指導が無かったとは言え、汚染土壌の上に住宅を建てる場合、汚染土壌と表層のマサ土の間に粘土層を敷き詰め有害ガスの被害を抑える事ぐらいはするそうなのですが、ここはそれさえも有りませんでした。
私たちは今までの聞き取り調査や地歴調査から小鳥が丘団地の土壌は相当汚染されていると覚悟していたのですが、調査結果は、「日本第一級の土壌汚染」だと言われて、何とも言えない気持ちになりました。
ガス抜き程度の対策で、このまま住み続けていく事など出来ないと一層強く思うようになりました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
200.Re: 意見書 名前:有害電解物質 日付:1月6日(日) 10時48分
>なんらかの電解物質(たとえば食塩など)
食塩を撒いたのでしょうか?
トリクロロエチレンがジクロロエチレンに脱塩素反応で分解していく過程で、トリクロロエチレン塩素イオンが分離します。
鉛イオンなどの重金属イオンも電解質です。
-----------------------------------------------------------
57.団地の土壌汚染で住民が提訴 名前:安すぎる 日付:9月8日(土) 10時34分
団地の土壌汚染で住民が提訴
8/31 11:46
岡山市内の団地の土壌から環境基準値を超える有害物質が検出された問題で、住民側が今日、土壌汚染を知りながら宅地を分譲したなどとして分譲した会社に対し総額2億2千700万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。
提訴したのは岡山市南古都の小鳥が丘団地の住民など4人で今朝、岡山地裁を訪れ訴状を提出しました。
この問題は3年前に住宅団地の土から最高で環境基準値の27倍のトリクロロエチレンやベンゼンなどの有害物質が検出されたものです。
訴えの中で住民側は宅地分譲を行なった両備ホールディングスが団地の土壌汚染を認識していたにも関わらず販売したなどと指摘し、総額2億2千789万円あまりの損害賠償を求めています。
一方、両備グループは「事実と異なる主張で裁判で決着をつけたい」としています。
167.Re: 汚染原因者様に書籍紹介 名前:公害・環境問題の真の解決策を提言 日付:12月23日(日) 19時43分
公害湮滅の構造と環境問題
四大鉱害事件や四大公害事件なのでの「公害を湮滅(湮滅)しようとする構造」は、最近の大気汚染、土壌汚染、廃棄物問題などの公害・環境問題でも、相変わらず繰り返されている。
1990年代以降、環境問題化した地球温暖化やダイオキシン・環境ホルモンに対しても、問題を湮滅しようとする「環境問題まきかえし」キャンペーンが意図的に展開されている。本書は、両者が共通する背景を有することに注目し、諸事例の分析を通して、公害・環境問題の真の解決策を提言する。
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=31872891
174.Re: 団地の土壌汚染でさらに住民が提訴 名前:ハイソーホー昭和51年改正 日付:1月1日(火) 19時54分
提訴:宅地の土壌汚染で住民らが−−岡山・小鳥が丘団地 /岡山
12月28日15時0分配信 毎日新聞
環境基準を超す有害物質が検出された宅地を十分な対策を取らずに販売したとして、岡山市南古都、同楢原の「小鳥が丘団地」住民18世帯23人が27日、「両備ホールディングス」(岡山市)を相手取り、総額11億8800万円の賠償を求めて岡山地裁に提訴した。
訴状によると、同社の前身の「両備バス」が87年に、せっけん工場跡地に団地を造成。04年、水道工事の際に黒い土が見つかり、同社が調査したところ、有害物質のベンゼンが基準値の26倍、トリクロロエチレンが27・3倍検出されるなどした。
住民側は「工場操業時に悪臭や水質汚濁の苦情があったにもかかわらず、調査・対策が不十分なまま販売したため、異臭や植物の枯死に悩まされ、不動産価値も下がった」としている。
両備ホールディングスは「(提訴内容は)事実と違う。裁判で真実を明らかにしていきたい」としている。
12月28日朝刊
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071228-00000177-mailo-l33
--------------------------------------------------------------------------------
103.開発許可制度 名前:国交省HP閲覧マニア 日付:11月17日(土) 7時22分
<開発許可制度>
安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに市街地が形成されるといった弊害が起きました。
開発許可制度は、土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。
<宅地造成規制法による宅地防災等>
一旦災害が起きるとその被害は、被災した宅地ばかりでなく周辺にも及ぶため、宅地造成に伴う工事等をチェックし災害を防止するため、宅地造成等規制法が定められています。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/index.htm
104.Re: 宅地擁壁の危険度判定 名前:計画・設計・施工段階の問題 日付:11月17日(土) 8時3分
宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/index.htm
5.宅地擁壁に対する危険度判定評価
5.3.3 構造諸元
水抜き穴及び排水施設の状況を分類し、配点を行います。
<良いと判定>
3m2に1ヶ所で内径75mm以上の水抜き穴及び排水施設があるかまたは、天端付近雨水の地盤への浸透が阻止されている場合。
<悪いと判定>
水抜き穴が設置されていないか、3m2に1ヶ所で内径75mm以上を満たしていない場合で雨水が浸透しやすい状況である場合。
宅地の水位が上がるのは「構造が悪い」と判定されます。数十センチ掘ると地下水が溜まるような土地では植栽もできませんし、地盤がブヨブヨします。草も生えないことがあります。宅地としては当然有すべき機能が欠けていることになります。また、適正な宅地造成工事を行っていない可能性があります。
地下水位が高いと地震時には地盤が液状化が生じたり小さな地震でも家が大きく揺れる可能性があります。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/02_hantei.htm#t-3
105.Re:我が家の擁壁チェックシート(案) 名前:計画・設計・施工段階の問題 日付:11月17日(土) 7時52分
我が家の擁壁は大丈夫でしょうか?チェックはどうするの?
それでは具体的にチェックしてみましょう!総合評価をしてみましょう!
1 周辺環境条件等のチェック(A)
?水抜き穴
水抜き穴が設置されていない。
2 擁壁のタイプは何でしょうか?擁壁に変状がありますか?
(1)練石積・コンクリートブロック積擁壁の場合
?ふくらみについて
ふくらみが更に大きくなり途中の積石間に隙間が生じている
以上の結果、総合評価が5点以上の場合には最寄りの自治体にご相談下さい
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/pdf/check.pdf
106.Re: 宅地耐震化
名前:地下水位低下は汚染対策と耐震化&地盤沈下に注意 日付:11月17日(土) 8時8分
地下水排除工の例
過剰間隙水圧消散工の例
http://www.mlit.go.jp/crd/web/jigyo/jigyo.htm
107.Re: 業者と市に共同不法行為が成立するとした事例 名前:最高裁〜判例検索システム閲覧マニア 日付:11月17日(土) 9時13分
排水路に隣接する一団の土地上に建設された11軒の建物に,ひび割れ,傾き等の損傷が生じたのは,同土地上に建物を建設した業者が,必要な軟弱地盤対策を怠ったことによるとして,業者に地盤改良義務違反の過失を認め,
また,11軒のうち,9軒の建物については,隣接する場所で市が実施した排水路改良工事において,市が不適切な工法を選択したことにより,建物の損傷が拡大したとして,市に適切な工法選択義務違反の過失を認め,業者と市に共同不法行為が成立するとした事例。
(被告京都市及び被告業者の主張)
争う。
第3 当裁判所の判断
2 本件各土地・・には隠れた瑕疵があるか
・・本件が法令の基準を満たしていなかったとまで認めるのは困難である。
(しかし、)・・売買の対象である敷地が,・・軟弱地盤であることは,・・買主が通常の注意を用いても発見できないというべきであるから,このことは,本件各土地建物の隠れた瑕疵というべきである。(31/60)
3 被告業者に・・義務違反の過失があるか
被告業者は,・・軽信し,地盤調査をせず,地盤の状態を把握しないまま・・建物を建築したものであり,この点において,過失があるとの評価を免れず,被告業者は,不法行為責任を負うというべきである。
4 本件工事について京都市の過失の有無
被告京都市は,本件工事施工に当たり,本件各土地に軟弱地盤対策が講じられていないことまで予見する義務はなく,本件工事によって軟弱地盤上の建物に損害が生じたとしても,その責任は,軟弱地盤対策を怠った先行工事者が負担すべきであると主張する。
しかしながら,被告京都市が,本件各土地に軟弱地盤対策が講じられていると認識していたことについては証拠がない。かえって,被告京都市は,本件各土地がN値3程度の軟弱地盤であることを把握していた上に,本件事前調査によって,建築後間もない原告建物に相当の損傷を生じていることを知っていたから,本件各土地に軟弱地盤対策がなされていないことを知り得たというべきである。
土木工事を施工するに当たっては,これを施工する土地毎の具体的な特性を把握して,周辺土地や周辺建物に損害を与えないよう施工すべきは当然であるから,被告京都市の上記主張は採用できない。(37/60)
8 結論
以上の検討の結果によれば,原告の本訴各請求は,京都市及び業者の被告らに対し,連帯して,別表の金員及び遅延損害金の支払を求める限度で正当として認容すべき
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35351&hanreiKbn=03
116.Re: 地下水が異常に高い 名前:排水不良 日付:11月17日(土) 18時31分
小鳥が丘救済協議会ホームページを見ると晴れた日も黒い水が地下20cm程度で湧いていますね。
宅地は道路より50cm〜100cm高いのが普通だから、宅地の地下水位は道路の高さより高いのですね!
こんな宅地を見るのは初めてです。暗渠や、基礎砕石・裏込栗石等を正しく施工ていれば、このような高い地下水位にならなです。
常識では考えられ無い程高い地下水位ですね!
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/top03.html
117.Re: 国民の生命及び財産の保護 名前:地下水の異常上昇 日付:11月18日(日) 10時18分
岡山市開発指導課業務内容
宅地造成等規制法とは
宅地造成に関する工事等について災害の防止のための必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。
岡山市都市整備局開発指導課
TEL 086−803−1451,1452
FAX 086−803−1743
E−Mail kaihatsushidouka@city.okayama.okayama.jp
http://www.city.okayama.okayama.jp/toshi/kaihatu/toshikeikaku.htm
118.Re: 岡山県開発許可制度 名前:地下水の異常上昇 日付:11月18日(日) 10時25分
宅地造成等を行う場合には許可が必要です
・切土、盛土、擁壁の設置などの造成行為がある場合
・道路、排水施設などの公共施設を整備する場合
※土地の区画形質の変更とは?
問合わせ先 : 岡山県土木部都市局建築指導課開発指導班
TEL 086−224−2111 内線3539
FAX 086−231−9354
E-mail kensido@pref.okayama.lg.jp
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kensido/kaihatsu/home.htm
119.Re: 開発行為許可書添付図面は? 名前:地下水の異常上昇 日付:11月18日(日) 14時6分
宅地を造成する時には、宅地の水はけを良くするためや、擁壁が不安定にならないように、地下水を排水する構造にすることが宅地造成規制法等に明記されています。
開発行為許可書に添付してある図面に、暗渠や、擁壁の裏込砕石・栗石、水抜きパイプ、(内径:75mmかつ、3m2当たり1本以上)等が明記されているでしょうか?
もし、排水設備が無ければ宅地造成規制法等に反していることになりますね。
宅地造成工事許可基準↓(擁壁水抜きパイプ:7/24頁)↓
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/takuchi/takuzo/tebiki/takutebi21.pdf
127.地下水位と開発行為許可書 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月18日(日) 22時30分
異常に高い地下水位との事ですが、掘削した後、埋め戻すまで4か月間ずっと池のようになっていましたから、地下水位は高いと思います。それに掘削したときホースやパイプの切れ端が沢山出てきました。
開発行為許可書に添付してある図面との事ですが、重要事項説明書に開発行為許可書のコピーは添付してありますが図面は土地の寸法・面積を記載した確定測量図しかありません。
岡山市に開示請求した「開発登録簿(調書)」にも「土地利用計画平面図」しか添付されていません。
団地西側は崖の様になっていてコンクリート擁壁があり、雨水排水口の様な孔が開いているのですが、水が流れた形跡がありません。ある土木関係の人に聞いた時、油で目詰まりしているので水が流れないのでは?と言われました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
128.Re: 油が拡散しないように排水設備をしていなければ行政も含めた問題かも 名前:宅地造成等規制法違反かも? 日付:11月19日(月) 0時41分
>掘削した後、埋め戻すまで4か月間ずっと池のようになっていましたから、地下水位は高いと思います。
排水が非常に悪い宅地と判断せざるを得ません。
>掘削したときホースやパイプの切れ端が沢山出てきました。
廃棄物埋めていますね、廃棄物処理法との関係がでてきます。
>開発行為許可書に添付してある図面との事ですが・・岡山市に開示請求した「開発登録簿(調書)」にも「土地利用計画平面図」しか添付されていません。
擁壁の構造図を添付しなければ開発許可は下りないはずですが・・・
擁壁の裏込砕石や裏込栗石の記載のある図面があると思うのですが・・・
図面が無ければ懐中電灯で水抜き穴を覗いたり、鉄の棒で突いてみて音や手ごたえ確認する方法があるかも知れません。
>ある土木関係の人に聞いた時、油で目詰まりしているので水が流れないのでは?
昔から「水と油の関係」は混ざらないものです。油の混ざった土の上に行き場の無い雨水などが溜まり、土の中の油が浮き上がってきたかもしれません。
油は水より軽いのが普通です。トルエン・キシレンは水より軽いので水面近くに浮いてきます。しかし、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレン、ジクロロエチレンは水より重たいので地下深くに浸透します。
住民の方はシックハウスのような症状を訴えておられますので、地下水位を下げることで、ベンゼンやトルエンなどから距離をおくことが、症状をやわらげることになるかもしれません。
>団地西側は崖の様になっていてコンクリート擁壁があり、雨水排水口の様な孔が開いているのですが、水が流れた形跡がありません。
開発事業者や行政が汚染のある事を知った上で、油が周辺の川に流れ出さない様に、法律で定められている排水設備を設置していなければ大きな問題になる可能性があります。
造成検査は開発許可を行った県や市が現場確認をするのが普通です。
宅地造成等規制法施行令
(擁壁の水抜穴)
第十条 第六条の規定による擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE016.html
136.わざわざ、平地を「傾斜のある丘」に宅地造成 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月20日(火) 12時11分
小鳥が丘団地の地形は前から「丘」だと思っていました。それ故に団地の名前を決める時も「丘」の文字を入れました。
しかし造成前の公害工場操業時の写真を見ると、周辺地域や隣接する道路と同じ高さの平地でした。
わざわざ平地を傾斜地の丘のように宅地造成したことになります。
何か不自然な気がします。
ちなみに、小鳥が丘団地は2つの川に挟まれていますが、一級河川旭川水系「砂川」の堤防に接する団地南側(以前建設省が所有、両備バス?所有地となった工場跡地の一部と昭和58年12月の境界確定協議により交換して宅地造成)が一番高く、用水路のような「沼川」に接する北側が低く、また団地奥である西側が少し高く、団地入口の一般道路に接する東側で低く、一番低い所でも一般道路より高くなっています。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
137.わざわざ、平地を「傾斜のある丘」に宅地造成の追伸 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月20日(火)
なお、公害工場の旭油化工業は、「砂川」の河川敷を不法占拠して廃油を垂れ流していた、という証言があります。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
139.Re: 開発許可制度 名前:廃掃法の違反の罰金は法人1億 日付:11月20日(火) 21時28分
>わざわざ平地を傾斜地の丘のように宅地造成したことになります。
何か不自然な気がします。
とのことですが、
丘にしたほうが水はけは良くなりますが・・・
>小鳥が丘団地は2つの川に挟まれていますが、・・・
油が川に流れたら川がよごれますよね!
水は正直ですから地下水も方に流れます。
>一級河川旭川水系「砂川」の堤防に接する団地南側が一番高く、用水路のような「沼川」に接する北側が低く、
とのことですが、
砂川と沼川の水位はどちらが低いのでしょうか?
水は正直ですから地下水も低い方に流れるはずです
低い北側の沼川の方に向かって土に浸み込んだ水が地下水になって流れるはずです。
地下水の圧力がかかって擁壁がはらみだしたりしていませんでしょうか?
>一番低い所でも一般道路より高くなっています。
宅地に水が溜まらないように宅地の高さは道路より高いことが普通です。
もし、道路の高さより宅地における地下水が高い場合はおかしいですね
なお、地下水の流れは複雑ですが、井戸による揚水やがあれば井戸に向かって流れるでしょう。
また、山の水が地下から湧き上がることがありますが、そこは砂利などの水を良く通す地層が地下深くまである場合におきるとおもいますが・・・
地下水 (ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4
140.以前から護岸擁壁の一部がはらみ、油がにじみ出ています。 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月21日(水)
砂川と沼川の水位は、北側の沼川の方が低いです。
推測された通り、沼川の護岸擁壁の一部は真中が膨らみブロックの隙間から黒い廃油と白い石灰のようなものが流れ出しています。
写真は以下のサイトをご覧ください。
団地風景写真の中央にある川が沼川です。川の左側が「小鳥が丘団地」で、団地入口側の一般道路から撮影した写真です。団地奥左の護岸擁壁がはらみだしています。
いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!インターネット新聞『JanJan』
http://www.news.janjan.jp/area/0703/0703220137/1.php
(掲示板127)の末尾2行に記載した団地西側の「崖のようになったコンクリート擁壁」の映像は、以下のサイトの「ある塀では手が入るほどの亀裂が走った。その補修の後」の写真です。
産廃に沈む住宅地
http://homepage2.nifty.com/kasida/environment/frame-sizumu.htm
近くに飲料用の井戸が無いので岡山市環境課は離れた飲料用井戸を調査したようですが、詳しい位置は分かりません。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
146.Re: 擁壁のふくらみ
名前:最寄りの自治体にご相談下さい 日付:11月23日(金) 8時55分
>沼川の護岸擁壁の一部は真中が膨らみブロックの隙間から黒い廃油と白い石灰のようなものが流れ出しています。
とのことですが、
擁壁が膨らんでいる範囲はどの場所でしょうか?
?対岸の擁壁は膨らんでいますか?
?同じ時期に工事した擁壁全てが同じように膨れていますか?
?昔廃油工場があった付近の擁壁が膨れていますか?
なぜ擁壁は膨らんでくる一般的な理由は下記のようなものです。
?擁壁の壁の強度が低い:ブロックの裏のコンクリートの厚みが少ない。
?背面の水位が上昇して水圧の力がかかっている:宅地造成規制法に定められている排水パイプや、壁の背面の水はけを良くする為の砂利などが入っていない。
その膨らんでいる擁壁の背面に下水管等が通っていた場合は、下水管からの水漏れが擁壁に水圧を与えている場合があります。
また、擁壁が少し動くと下水管からの水漏れが一気に多くなり、付近の土を川に流しだしてしまう可能性があります。
国土交通省の「擁壁チェックシート(案)」では
「ふくらみが大きくなり途中の積石間に隙間が生じている」状態になれば、「最寄りの自治体にご相談下さい」とで発表しています。
大きな災害にならない前に対策をしてもらった方が良いでしょう。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/pdf/check.pdf
147.Re: 護岸擁壁のふくらみと黒い廃油のにじみ出し 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月24日(土) 11時26分
いつもアドバイスありがとうございます。
<擁壁が膨らんでいる範囲>
団地奥端の沼川護岸擁壁が横幅15メートルぐらい膨らんでいます。
?対岸の擁壁は膨らんでいません。
?一部の擁壁が膨らんでいます。
?昔廃油工場があったのは団地全域です。そのなかでも廃油を垂れ流していた場所は何カ所かあるらしいのですが(土壌に廃油を吸わせていたり、廃油ドラム缶を埋没した)、宅地造成した後では推定するしかありません。ガス中毒で倒れた人の宅地の場所も、その一カ所と関係者の証言がありました。
<擁壁は膨らんでくる一般的な理由>
私たちの地域では、まだ公共下水道は設置されていません。下水は雑排水として側溝を流れていて大きな側溝の水漏れ現象は見られません。
何カ所かある黒い廃油のにじみ出し部分と、擁壁の膨らんでいる範囲はおおむね一致します。
その箇所付近の団地内道路をボーリング調査した時、表面のアスファルトと下の土壌との間に隙間が生じていました。
前から対岸の擁壁に比べて小鳥が丘団地側の擁壁は明らかに全体が黒っぽくなっていましたが、両備バスが汚染調査をし環境基準値を超える有害物質が検出されたボーリング調査後に、黒い廃油のにじみ出しが顕著に見られるようになり、特に白い石灰のようなものが流れ出したのは以前には無いことでした。
どうもボーリングで地下水の流れが変わり、内包されて留まっていたこの部分の廃油や石灰が流出し、流れの途中にある道路を空洞にしつつあるような気がしてなりません。
沼川の擁壁から廃油が流れていて膨らんでいる事は自治体に相談しました。
?平成19年2月5日に岡山市環境課に相談するが、川は県の管轄と言われる。
?同日岡山県備前県民局建設部に相談し翌日現場確認。・・・団地土壌が原因と思われるので、岡山市に住民から依頼して欲しい。道路地下から水の流れる音がする。
?岡山市に依頼。翌2月7日に西大寺支所建設課が現地調査。・・・普通の道路保全だけでは無いので(土壌汚染の関係もあるので)事情を確認してから連絡する。
?連絡がないので督促すると、6月25日来訪したので空洞化の確認を要請。・・・近くを通る時はチェックしている。県民局職員は水の流れる音は聞いてないとの事。現時点では心配ない。継続的に監視する。
自治体が手を付けないという事は、直ちに陥没の危険はないということでしょう。(将来は別にして!)
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
--------------------------------------------------------------------------------
148.Re: 開発許可制度 名前:水圧は土圧より大きい 日付:11月24日(土) 15時48分
>何カ所かある黒い廃油のにじみ出し部分と、擁壁の膨らんでいる範囲はおおむね一致します。
とのことですが、擁壁の後ろの地下水が上がってきて、地下水に含まれている油分がにじみ出しているとおもわれます。地下水が上がってきたので水の圧力も擁壁に加わることにより、擁壁が膨らんでいると一般的には考えられます。
だから、黒い廃油のにじみ出し部分と、擁壁の膨らんでいる範囲はおおむね一致するのでしょう。
擁壁が壊れないようにするには、擁壁背面の地下水を下げて、擁壁に加わる力を少なくすることが、一般的と思われます。
>その(擁壁がふくらんでいる)箇所付近の団地内道路をボーリング調査した時、表面のアスファルトと下の土壌との間に隙間が生じていました。
とのことですが、擁壁がふくらんだ分の土が舗装の下から回り込むことがあります。
>ボーリング調査後に、黒い廃油のにじみ出しが顕著に見られるようになり
とのことですが、ボーリングは何m掘ったのでしょうか?
下のほうから川砂や川砂利のようなもので出てきたのでしょうか?
川の横の砂や砂利は水を通しやすくものです。水は正直ですから山の上ほうの水圧がかかって水が泉のように沸いてくる場合があります。
>白い石灰のようなものが流れ出したのは以前には無いことでした
白い石灰のようなものは石灰でしょうか?またはセメントが、もろくなって溶け出しているのでしょうか?これは判定が難しいですが・・・
セメントだとコンクリートの強さがだんだん減っていきます。
>自治体が手を付けないという事は、直ちに陥没の危険はないということでしょう。
あまり心配すると体が持たないのでほどほどにしたほうが良いと思います。
しかし、念のため、国土交通省は「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」を出しているので、このマニュアルに従って行政の詳しい方にでも調べてもらう方が良いかもしれません。
やり方は「湧水の状況」、「排水施設等の設置状況」、「排水施設の障害の程度」、「劣化障害の程度」、「白色生成物障害の程度」、「擁壁の変状」、「擁壁の危険度評価」をマニュアルに従い点数を付けて評価します。
宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)↓
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/02_hantei.htm
--------------------------------------------------------------------------------
150.Re: 水圧は土圧より大きい 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月24日(土) 21時38分
ありがとうございます。
私たちも護岸ブロックの崩れより土壌汚染や健康被害の方が心配なので、ほどほどにしておきます。
ボーリングは7〜8mまで掘りました。
私たちは出来るだけ深く掘るよう要請しましたが、廃油や悪臭のためボーリング作業者が怖がって、それ以上掘りませんでした。
採取したサンプル土壌は黒く変質していて川砂や川砂利があったかどうか分かりません。
流れ出した白いものは、両備バスが宅地造成のとき廃油を石灰で凝固させたと言っているので、私たちは石灰だと思っています。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
--------------------------------------------------------------------------------
185.Re: 排水路改良工事では市に過失を認め共同不法行為が成立する 名前:各認容額欄記載の金員と遅延損害金を認容 日付:12月31日(月)
排水路に隣接する一団の土地上に建設された11軒の建物に,ひび割れ,傾き等の損傷が生じたのは,同土地上に建物を建設した業者が,必要な軟弱地盤対策を怠ったことによるとして,業者に地盤改良義務違反の過失を認め,また,11軒のうち,9軒の建物については,隣接する場所で市が実施した排水路改良工事において,市が不適切な工法を選択したことにより,建物の損傷が拡大したとして,市に適切な工法選択義務違反の過失を認め,業者と市に共同不法行為が成立するとした事例
8 結論
以上の検討の結果によれば,本訴各請求は,被告らに対し,連帯して,各認容額欄記載の金員及びこれらに対する各不法行為の日,即ち本件工事が終了した日である平成15年5月から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で正当として認容すべきであり,
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=35351&hanreiKbn=03
--------------------------------------------------------------------------------
168.廃棄物処理法 名前:昭和45年法律第137号 日付:12月26日(水) 20時53分
廃棄物処理法 小鳥が丘 の検索結果 約 666 件http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E5%87%A6%E7%90%86%E6%B3%95%E3%80%80%E5%B0%8F%E9%B3%A5%E3%81%8C%E4%B8%98&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw7.htm
169.Re: 廃棄物処理法 名前:昭和45年法律第137号 日付:12月26日(水) 21時13分
産業廃棄物が埋められている土地の売買 土壌汚染対策法と廃棄物処理法
廃棄物の最終処分場が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって位置づけられたのは1976年の同法改正によってです。
したがって、それ以前は、自分の敷地に廃棄物を埋めるような処分がなされており、そうした土地は全国至るところにあると考えられています。もちろん、法改正後は、たとえ自社の敷地であろうとも、廃棄物を最終処分(埋立て)することは許されません。
1976年改正以前であれば、『この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による』とされているため、遡及しません。
http://blog.goo.ne.jp/o-gyousei/e/4de65966b666f2f2252d9a55c9590039
173.Re: 廃棄物処理法(環境法令ウオッチング) 名前:1976年(昭和51年)改正 日付:12月29日(土) 8時43分
産業廃棄物が埋められている土地の売買 土壌汚染防止法と廃棄物処理法
2006年10月23日
鹿児島地裁で、旧知事公舎跡地の購入後に産業廃棄物や墓石などが大量に埋まっていたことが露見したとして、土地購入者が県に対して損害賠償を請求した訴訟の判決がありました。
http://blog.goo.ne.jp/o-gyousei/e/dbe3912c7341112bc9f1dec13d28e8e1
175.Re: 廃棄物処理法改正のポイント 名前:昭和51年改正 日付:12月29日(土) 8時51分
廃棄物処理法改正(昭和51年) 昭和46年の「廃棄物処理法」制定後も、廃棄物を適切に処理するための様々な基準が制定されました。
その一例として、
「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」
「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」 などの判定基準の策定があります。
しかしながら、当時はまだ廃棄物処理の社会的システムが不完全な状態でした。
産業廃棄物では、無許可業者による不法投棄や、周囲の環境に悪影響を及ぼす不適切な処理
一般廃棄物では、「東京ごみ戦争」に象徴される、処理施設の立地を巡った住民や自治体間での紛争が頻発していました。
昭和50年には、東京都内で、ある六価クロム化合物製造工場が、六価クロム含有鉱さいを工場周辺で埋立処分した結果、工場周囲の住民や工場労働者に健康被害が発生していたことが明らかになり、大きな社会問題となりました。
この六価クロム不適正処理事件を契機とし、昭和51年、初めての「廃棄物処理法」改正が行われました。
昭和51年改正のポイントは、下記に示すとおりです。
・措置命令規定の創設
・産業廃棄物処理業の委託基準の設定(再委託の禁止)
・産業廃棄物処理責任者による処理記録の記録保存
http://www.haikibutsu.org/kaisei/
176.Re: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の主な改正経緯 名前:ハイソーホー昭和51年改正 日付:12月29日(土)
特に産業廃棄物に関. して不法投棄等の違法. 処分や無許可の処理業. 者が多く、全体として事. 業者処理責任の原則が. 徹底していなかったこと ...
http://www.pref.miyagi.jp/gyokei/gyokei-ser/kensyo/siryou5.pdf
177.Re: 旧法第一六条第一項不法投棄に該当するか 名前:不法投棄に該当する 日付:12月30日(日) 7時31分
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について 】
公布日:平成4年9月18日生衛901号
(佐賀県保健環境部長から厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)
標記の法律に関して次の各事項について疑義が生じたので、至急御回答をお願いします。
記
(1) 中間処理施設敷地内の地表下二〜三メートルの穴の中に、廃油付着のドラム缶及び前処理した廃油混じりの土砂を入れ(埋め立て)、覆土をせず、その上に同様に前処理した廃油混じりの土砂を野積みの状態にしていた行為は、旧法第一六条第一項の不法投棄に該当するか。
(2) (1)の場合、廃油混じり土砂の廃油及びドラム缶付着の廃油の油分が五パーセント未満である場合はどうか。〔昭五一・一一・一八環水企一八一、環産一七通知(油分を含むでい状物の取扱いについて)との関係はどうか。〕
(4) (3)のとおり最終処分場で流出事故が起きたため、県は業者の願い出により、その付近の場所を、場内の汚でい等の仮置場とすることを承認したが、この仮置場内に当該業者が廃油付着のドラム缶を埋め立てた場合、旧法第一六条第一項の不法投棄に該当するか。
(平成四年一〇月一五日)(衛産第六九号)
(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長から佐賀県保健環境部長あて回答)
平成四年九月一八日付け生衛第九〇一号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。
記
1 (1)について
当該行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「旧法」という。)第一六条第一項の不法投棄に該当する。
2 (2)について
昭和五一年一一月一八日付け環水企第一八一号、環産第一七号環境庁水質保全局企画課長及び厚生省環境衛生局水道環境部参事官連名通知「油分を含むでい状物の取扱いについて」は、油分を含むでい状物(以下「油でい」という。)について、油でいが排出された時点における廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の取扱いを示したものであり、廃油に土砂を混合させることにより生じた混合物の油分が五パーセント未満になったものを土砂として取扱うこととしたものではない。
したがって、廃油に土砂を混合したもの及び廃油が付着したドラム缶について(1)の行為を行った場合、当該行為は旧法第一六条第一項の不法投棄に該当する。
4 照会事項(4)について
当該行為は、旧法第一六法第一項の不法投棄に該当する。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000198
178.Re: 昭和46年各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて 名前:留意して運用されたく通知する 日付:12月30日(日)
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】公布日:昭和46年10月25日環整45号
[改定]平成10年5月7日 衛環37号
厚生省環境衛生局環境整備課長から各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の施行については、別途厚生事務次官通知(厚生省環第784号)及び環境衛生局長通知(環整第43号)により指示されたところであるが、なお、下記の事項に留意して運用されたく通知する。
記
第1 廃棄物の範囲等に関すること。
1 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
4 廃棄物処理法第2条第4項及び令第2条に規定された産業廃棄物の内容は、別紙に示すとおりであること。
第2 産業廃棄物処理施設の範囲に関すること
第4 産業廃棄物処理施設の維持管理等に関すること。
産業廃棄物処理施設の維持管理に関しては、次の点に留意するよう関係者を指導されたいこと。
2 規則第12条の6第7項において規定している排水にあたっての放流水の水質基準は、その放流水が直接に公共の水域に排出される単独施設の場合に適用されるものであって、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する特定事業場内において他の排水と混合して放流される場合には、水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準に従うことはいうまでもないこと。
(別紙)
(2) 汚でい…… ・・廃白土にあっては、廃油との混合物として取り扱うものであること。
(3) 廃油……鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油を含むものとし、潤滑油系、絶縁油系、洗浄用油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類(常温において固形状を呈するものに限る。)があること。
(4) 廃酸……
(5) 廃アルカリ……
(10) 令第2条第4号に掲げる産業廃棄物……「動植物性残さ」という。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000023
183.Re: 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり 名前:廃棄物による土地造成は埋立処分に該当 日付:12月31日(月)
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について 】
公布日:昭和57年6月14日環産21号・・・
(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
標記については、昭和五六年一〇月三〇日付け環産第四七号をもって通知したところであるが、この程同通知の訂正通知をとりまとめたので、参考とされたい。
なお、使用する法令の略称は次のとおりである。
法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)
令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)
規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)
共同命令:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府・厚生省令第一号)
(クリーニング汚でい)
問2 クリーニング業の洗濯工程から排出されるクリーニング汚でい(パークレンと繊毛かすの混合したもの)は何か。
答 性状により廃油又は汚でいである。
(地盤改良剤かす)
問6 地盤改良工事で排出されるアルカリ性を呈する地盤改良剤かすは何か。
答 汚でいと廃アルカリの混合物である。
(閉鎖された最終処分場の掘削物)
問10 最終処分場が閉鎖された後に当該土地で掘削工事が行われる場合、当該工事に伴って生ずる廃棄物の排出者は当該工事を行う者であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
(地下工作物の埋め殺し)
問11 地下工作物が老朽化したのでこれを埋め殺すという計画を有している事業者がいる。この計画のままでは生活環境の保全上の支障が想定されるが、いつの時点から法を適用していけばよいか。
答 地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり法の適用を受ける。
(土地造成)
問19 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり、この者は「自ら利用」するのであるから法が適用されないと主張するが、廃棄物の埋立処分であり法が適用されると解してよいか。
答 お見込みのとおり。なお、次の点に留意されたい。「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しない。
また、土地造成は廃棄物・有価物たるとを問わず固形状、でい状であれば可能であるが、廃棄物による土地造成は埋立処分に該当する。
4 第一五条関係(産業廃棄物処理施設)
(薬剤による脱水・乾燥)
問62 汚でいに薬剤を投入して発熱反応により水分を除去する施設は令第七条第一号又は第二号に掲げる施設に該当するか。
答 お見込みのとおり。
5 第一六条関係(不法投棄)
(廃油)
問80 廃油(タールピッチ類を除く。)が不法投棄された場合、当該廃油の油分の程度を問わず令第七条の四第五号に規定する産業廃棄物に該当すると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000120
50.土壌汚染問題 和解金3億3千3百万ドル ノンフィクションビデオ 名前:日本の心を美しくするテンサイ 日付:12月31日(月)
土壌汚染問題で大企業相手にたたかって300億円の和解金を手にしたノンフィクション映画を紹介します。
映画のように上手くいかなくても、闘いのヒントや元気がもらえるかもしれません。
以下は「日本の心を美しくする 今月の当会推薦映画」の転載です。
映画『エリン・ブロコビッチ』 〜人を救うこと〜
和解金3億3千3百万ドル
「全米史上最高額の和解金を手にした女」
電力会社PG&E社からの全米史上最高額といわれる和解金3億3千3百万ドルを手にしたのは、その公害の被害者である600人を超える原告団であり、彼女はその死の恐怖におびえる被害者達の希望となり、獅子奮迅の活躍をした女性のヒューマンストーリーであり、実際にあった物語なのであります。
「六価クロム」なる化合物は、強力な酸化剤として働き、金属の洗浄、防食等に用いられますが、その毒性は強く、消化器や肺から吸収され、ガン、潰瘍などを生じます。
日本でも昭和48年に東京の地下鉄工事中に化学工場の跡地から六価クロム化合物を含む鉱さいが発見され、土壌汚染問題が大きな社会問題となりました。
映画の中では、ロサンゼルス郊外にあるヒンクリーという砂漠地帯にあるPG&E社の工場近辺に住む住民にその「六価クロム」の被害が及びます。
体の不調、ガンなどに犯される住民が増えますが、住民はこの企業によるずさんな水質管理が原因とは思いも寄りません。
企業はその事実を公表せず、水質汚染調査書類などを抹消し、3価クロムは体に影響はないなどと住民に虚偽の報告をし、隠ぺい工作を図っているからであります。
その上、住民の土地を格安で買い取り、証拠の隠滅を企んでいるという、企業倫理など微塵もない、まったくひどい話です。
この彼女の情熱の源となったのは、彼らから信頼されていく中で、裁判に勝利することにより病に倒れていく住民たちの無念を晴らすべく、彼らの希望としての使命を担うという、心の「満足感」でありましょう。
勇気と正義、生きることの真なる喜びを彼女はこの仕事の中で味わっていたことでありましょうし、光り輝いていたことでしょう。
賠償金の額という結果よりも、他を救うことにより、 「自分自身を救う」 という結果をもたらしたストーリーにこそ、面白みのある映画でありましょう。
http://www.j-mind.com/book/erin.htm
182.Re: 土壌汚染問題 和解金3億3千3百万ドル ノンフィクションビデオ 名前:通りすがり 日付:12月30日(日)
両備グル―プといえば思い出すのは「グレ―スタワ―」。両備マンションになぜ20億円も税金投入か!?という話。旧出石小跡地もまた両備がマンションを計画中。萩原前市長の両備びいきは目に余るものでした。いや、瘉着というのでは…という厳しい声もきこえてきます。
ともかく、特定企業優遇は市政のゆがみです。正さなくてはなりません。
http://okjcp.web.infoseek.co.jp/s/archives/2005/11/post_3.html
--------------------------------------------------------------------------------
180.人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 名前:過失犯 二年以下の懲役 両罰 日付:12月30日(日) 10時0分
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百四十二号)
(目的)
第一条 この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。
(故意犯)
第二条 工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
(過失犯)
第三条 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(推定)
第五条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。
(公訴の時効期間)
第六条 第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
(第一審の裁判権)
第七条 この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
附 則
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO142.html
181.Re: 法務省刑事局長から検事総長・検事長・検事正あて 名前:積極的に取締るべきである。 日付:12月30日(日)
【 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の施行について 】
公布日:昭和46年6月30日法務省刑事(刑)92号
法務省刑事局長から検事総長・検事長・検事正あて
過般の第六四回臨時国会において成立した標記法律は、昭和四五年一二月二五日法律第一四二号として公布され、きたる七月一日から施行されることとなつた。
・・・
なお、この法律の制定に際し、衆議院及び参議院の各法務委員会において別紙(一)及び(二)の附帯決議がなされているので、了知されたく、また、各規定に関する当局の解釈等については、既配布の検察資料一五五号「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律解説」を参照されたい。
右命により通達する。
別紙(一)
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案に対する附帯決議
(衆議院法務委員会昭和四五、一二、一〇)
1 政府は、複雑多岐にわたる公害の実情にかんがみ、不断の努力によりいやしくも企業責任が現場責任者のみに転嫁されることのなきよう努める等適切な運用をはかるとともに、今後公害の状況に応じ必要により関係法令について所要の改正措置を講じ、将来いわゆる食品薬品公害等の防止についても規制措置を検討するなど公害の防止に万全を期すること。
2 政府は、公害監視につき適切な措置を講ずることによりいわゆる公害事犯の未然防止及びその的確な把握に努めるとともにこの種の事件の迅速かつ適正な処理に資するため裁判、検察その他関係機関について人的物的両面にわたりその整備強化をはかること。
右決議する。
別紙(二)
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律に対する附帯決議
(参議院法務委員会昭和四五、一二、一八)
いわゆる複合公害についても、刑法の共犯の条件がみたされる場合には、本法の適用がある。
よつて、政府においては、この種の事件についても積極的に取締るべきである。
右決議する。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=16000002
--------------------------------------------------------------------------------
75.岡山の地下水調査は汚染のあるところを外しているのでは? 返信 引用 名前:汚染井戸周辺地区調査 日付:10月27日(土)
岡山市環境局環境保全課水質係
http://www.city.okayama.okayama.jp/kankyou/kankyoukisei/
公共用水域の健康項目は水質測定結果はどこにあるのでしょうか?
岡山県 生活環境部 > 環境管理課 > 水環境の概況
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=4325
環境省地下水質測定結果
http://www.env.go.jp/water/chikasui/index.html
環境省は汚染井戸周辺地区調査ぐらいはしてくれるかもしれません。
http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html
76.Re: 今後の地下水質モニタリングのあり方について(中間報告) 名前:汚染井戸周辺地区調査して欲しい 日付:10月27日(土)
4.汚染判明時の対応について
<現状>
環境基準を超過する汚染が発見された場合の対応については、「地下水の水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて」(平成9 年3 月13 日付け環水管第80 号 環境庁水質保全局長通知)にて、「人の健康を保護する観点からまず飲用指導等利用面から措置を講じるとともに、汚染範囲の確認、汚染源の特定等の調査を行うこととされたい。」とされている。
また、同通知には、「一時的にではあっても基準値を超過した測定結果が得られた場合には、必要に応じ直ちに関係機関との連携を図り、推移の適切な監視及び対策を検討することとされたい。」と記述されている。
また、処理基準においては、環境基準値を超える測定値が得られた場合には、速やかに環境省に報告することとされているほか、処理基準が引用している地下水質調査方法において、汚染井戸周辺地区調査は、汚染発見後、できるだけ早急に行うこととされている。
しかしながら、近年、概況調査で汚染が判明した場合でも、汚染井戸周辺地区調査等による汚染範囲の把握が適切に行われていない例も一部確認される。
住民の健康影響の防止のためには、汚染された地下水が飲用されることを防止することが最優先であり、このためには、汚染範囲の速やかな把握と周知が重要である。
<当面の対応>
? 汚染範囲の確定については、汚染井戸周辺地区調査の位置づけや実施方法等を改めて整理すべきである。具体的には、
ア.概況調査はもとより、事業者からの報告等により新たな汚染が判明した場合には、可能な限り速やかに汚染井戸周辺地区調査を行うべきであること
イ.水平方向だけでなく、鉛直方向(帯水層別)の汚染範囲の把握も重要であること等を明確にすべきである。詳細については、別紙のとおりである。
? 汚染が判明した後の関係者への周知や原因究明に関する望ましいあり方を整理すべきである。
具体的には、衛生部局や関係地方公共団体(必要に応じて、隣接する都道府県)、対策を講じる上で重要となる関係他部局との連携を一層緊密にし、把握された汚染の存在と広がりが利水上の関係者(井戸所有者等)に確実に周知されるよう留意することや、様々な方法で効率的に原因究明調査を行うこと等を改めて徹底する必要がある。
平成17年度地下水質モニタリングのあり方に関する検討会検討員名簿
(五十音順、敬称略)
飯田和義 神奈川県環境農政部大気水質課長
稲葉一穂 国立環境研究所水土壌圏環境研究領域地下環境研究室長
大岩敏男 山形県環境科学研究センター水環境部長
高橋孝治 島根県環境生活部環境政策課長
中杉修身 上智大学大学院地球環境学研究科教授
早瀬隆司 長崎大学環境科学部教授
山田欣也 愛知県環境部水環境課長
http://www.env.go.jp/water/report/h17-02.pdf
77.Re: 平成17年度地下水質測定結果について 名前:汚染井戸周辺地区調査して欲しい 日付:10月27日(土)
平成18年12月21日
平成17年度地下水質測定結果について
環境省は、平成17年度に国及び地方公共団体が水質汚濁防止法に基づいて実施した、全国の地下水質の測定結果をとりまとめた。
概況調査(地域の全体的な状況を把握する)の結果、全体の環境基準超過率は6.3%(前年度7.8%)であった。項目別の環境基準超過率は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が4.2%(前年度5.5%)で最も高かった。
定期モニタリング調査(汚染が確認された後の監視等を行う)の結果、1,950本(前年度1,894本)の井戸において環境基準超過が見られた。
項目別の環境基準超過本数は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が651本(前年度637本)で最も多かった。
水・大気環境局行政資料
平成17年度地下水質測定結果(冊子版)
http://www.env.go.jp/water/report/h18-08/index.html
添付資料
平成17年度地下水質測定結果(概要版) [PDF 89KB]
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=8918&hou_id=7838
連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
地下水・地盤環境室
代表:03−3581−3351
室長:藤塚 哲朗 (内線6670)
室長補佐:佐藤 郁太郎(内線6671)
担当:坂井 美穂子(内線6675)
兼平 進一 (内線6674)
http://www.env.go.jp/water/report/h17-02.pdf
81.Re: 常時監視だけでなく汚染付近モニタリングも 名前:水環境保全 日付:10月27日(土) 17時44分
岡山県 生活環境部 > 環境管理課 > 水環境の概況
地下水は容易に利用できるため、飲用以外にも農業用水や工業用水などに使われてきました。
しかしながら、近年、新たな化学物質による地下水汚染が懸念されるようになったため、県でも常時監視を行っています。
過去に汚染が確認された地点の継続監視(定期モニタリング調査)を実施した。
水質保全班086-226-7304
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=4325
126.Re: 地下水をきれいにするために 名前:地下水質の常時監視・有害物質の地下浸透の禁止・浄化 日付:11月18日(日)
揮発性有機化合物による地下水汚染対策に関するパンフレット
「地下水をきれいにするために」
1.地下水汚染のしくみ
地下水は、いったん汚染されると浄化することが容易ではありません。また、物質の種類によって程度は異なりますが汚染が拡散することもあるので、早期の調査と対策が必要ですし有害物質の地下浸透を未然に防止することが何よりも重要です。
VOCは難分解性で土壌に吸着されにくいため土壌中を容易に浸透し、地下水の流れによって広範囲に汚染が広がるおそれがあります。また、土壌中に原液状で溜まったり、地質の状況によっては地下深部にまで汚染が広がることもあります。・・・
3.1 水質汚濁防止法による地下水保全対策のしくみ
地下水質の常時監視
都道府県知事等が地下水質の常時監視を行い、結果は公表されます。
有害物質の地下浸透の禁止
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の有害物質を含む水の地下浸透は禁止されています
汚染された地下水の浄化
都道府県知事等が、汚染原因者に対して、汚染地下水の浄化措置を命令できることとなっています。・・・・
平成15年度 地下水浄化汎用装置開発普及等調査検討会
委 員 国吉克広 千葉市 環境局環境保全部環境規制課主査補
委 員 駒井武 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門グループ長
委 員 津田信吾 秦野市 環境農政部環境保全課特定技幹
委 員 中杉修身 国立環境研究所センター長
委 員 平田健正 和歌山大学システム工学部教授
委 員 吉岡昌徳 兵庫県立健康環境科学研究センター安全科学部長
http://www.env.go.jp/water/chikasui/panf/index.html
179.Re: トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針 名前:公布昭和59年8月 地下浸透の防止 日付:12月30日(日)
【 トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針の設定について 】
公布日:昭和59年8月22日 環水管127・環水規148
[改定]昭和62年 環水管65・環水規99
(都道府県知事・十大政令市長あて環境庁水質保全局長通知)
トリクロロエチレン等による地下水の汚染については、環境庁の昭和五七年度地下水汚染実態調査によりその広範な汚染が判明したほか、各地において汚染事例が確認されている。
地下水の汚染メカニズムについては、必ずしも十分に解明されるには至つていないが、トリクロロエチレン等を含む水の地下浸透に起因する地下水の汚染を防止し、あわせて公共用水域に排出されるトリクロロエチレン等の抑制を図る必要があることにかんがみ、別添のとおり、トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針を定めたので、当面、これに基づき工場及び事業場の指導に当たられたい。
なお、関係部局間の連絡を密にする等により円滑な指導の実施に十分配意されたい。
別表
トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針
一 指導の対象
本指針を適用する工場及び事業場は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一・一・一―トリクロロエタン(以下「トリクロロエチレン等」という。)並びにトリクロロエチレン等を含む物を取り扱う工場及び事業場とする。
二 地下浸透の防止
トリクロロエチレン等及びトリクロロエチレン等を含む水については、地下へしみこむこととならないよう適切な措置を講じなければならないものとし、トリクロロエチレン等の濃度が常に別表一の管理目標に適合する水を除いて、地下浸透は行つてはならないものとする。
トリクロロエチレン ○・○三mg/一以下
テトラクロロエチレン ○・○一mg/一以下
一・一・一―トリクロロエタン ○・三mg/一以下
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000048
--------------------------------------------------------------------------------
100.11月13日に初公判が岡山地方裁判所であります 名前:〜 傍聴歓迎 〜 日付:11月4日(日) 21時32分
★★ 予告ニュース ★★
今回提訴した初公判が平成19年11月13日(火)10:15分から岡山地方裁判所であります。
〜 傍聴歓迎 〜
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
130.Re: 2007年12月11日に第二回口頭弁論が岡山地方裁判所であります 名前:傍聴歓迎 学力向上します 日付:11月19日(月)
第2回口頭弁論がH19年12月11日(火)10:15分から岡山地方裁判所であります。
(住民3名が、両備ホールディングス?(旧両備バス?)を提訴)
〜 傍聴歓迎 〜
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
161.Re: 第3回口頭弁論がH20年1月29日(火) 名前:傍聴歓迎 日付:12月16日(日) 16時45分
第3回口頭弁論がH20年1月29日(火)10:20分から岡山地方裁判所であります。
--------------------------------------------------------------------------------
154. 岡山の環境問題総合政策ネツトワークの構築が急務です!名前:浦島 文男 日付:12月10日(月) 0時23分
名前を聞くと素晴らしい『小鳥が丘』。
随分前から、問題が起きていたのですね。岡山県の環境問題・土壌・大気
水質などでこのほかにも多くの課題が有ります。
児島湖・金甲山不法投棄・工場廃水たれながし・など多くの重大課題があります。
おかやま環境ネツトワーク(当時の理事長・千葉喬三さん)は、二年ほ
ど前から、公害問題などを扱う「第三部会」は閉鎖状態になりました。
当時、わたくしが部会長として、事務局に抗議をしました。今もつて
開かれず、総会も公式には開かれていません。
岡山県から、こうした課題が解決されるには、『良識のある』すべて
のみなさんが参加する環境問題のネツトワークを構築するべきです。
わたくしのブログは今は、全国のみなさまが見ていてくださいます。
ときどきの投稿は、みなさまが拝見してくださいます。
今、私は、地球温暖化防止活動推進員、岡山環境カウンンセラー協会
に所属しています。広葉樹の森つくりの取り組みをしています。
環境・再生の課題は、みんなの問題です。岡山県・岡山市も解決へむけ
た取り組みが緊急に必要でしょう。
皆さん、知恵を出しましょう!
http://blog.goo.ne.jp/goo1941-004/
155.Re: 岡山の環境問題総合政策ネツトワークの構築が急務です! 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:12月10日(月)
小鳥が丘団地土壌汚染問題にいつも関心を持って頂いてありがとうございます。
私たちも当事者になっていろいろ調べていくうちに岡山県内に多くの土壌・水・大気汚染問題があると知る事になりました。
ただ目に見えないので被害の実態がなかなか伝わらないのでしょう。
それに日々の生活に追われる我々一般庶民にとって環境問題に参加することはなかなか難しいのかもしれない。
また、環境問題は企業(特に大企業)の論理が優先し、ツケを生活者に押し付け、汚染実態を隠そうとする力が働いていると思います。
労働者でもある生活者は、組織のシガラミから脱却するのを躊躇しているように思えます。
提唱されている「環境問題のネットワーク」は非常に重要で効果のある取り組みだと思います。
これが出来たら環境問題はかなり進展するでしょう。
ただ、小鳥が丘団地内の汚染状況は場所により被害状況も各家庭でそれぞれ違いがあり、土壌汚染被害者である小鳥が丘団地住民でさえ十人十色の意見があり、全員一致の団結は出来ていません。
私たちも活動していて、相手方との交渉や行政への働きかけ以上に一番難しい課題です。
しかしいま係争中の住民以外に十数名の住民が裁判の準備をしています。
この輪が広まっていけば、やがて住民が団結する時が来るかもしれません。
係争中の裁判の第2回口頭弁論が、明日2007年12月11日(火)10時15分から岡山地方裁判所であります。
いまはこの裁判の行方を注視したいと思います。
今後もご協力をお願いします。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
--------------------------------------------------------------------------------
152.小鳥が丘土壌汚染問題の経緯 名前:リスコミ 日付:12月2日(日) 9時56分
失礼します。
「小鳥が丘土壌汚染問題の経緯」 というページがありましたのでお知らせします。
http://beauty.geocities.jp/oecacasa/kotorigaokanorekisi.htm
よろしくお願いします。
153.Re: 小鳥が丘土壌汚染問題の経緯 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:12月2日(日) 18時16分
ありがとうございます。
ホームページメニューに追加掲載いたしました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
--------------------------------------------------------------------------------
59.役員人事 名前:企業の社会的責任が重要な時代 日付:11月18日(日) 17時48分
役員人事
[新任]
常務取締役 阿部 泰裕 (現 両備経営サポートカンパニー長)
常勤監査役 藤井 捷爾 (前 取締役財務一部部長)
執行役員 近藤 定正 (両備テクノカンパニー長 就任)
[昇任]
常務執行役員 小坂 貞昭 (前 執行役員両備フェリーカンパニー長)
[退任]
専務取締役 佐藤 允彦 (?中国バス専務取締役 兼 両備グループ監査室長 就任)
常務取締役 窪田 新治 (両備グループ監査室主任監査役 就任)
常務取締役 山崎 茂幸 (両備フェリーカンパニー非常勤相談役 就任)
取締役 福間 和興 (両備グループ監査室分析統括監査役 就任)
取締役相談役 庭瀬 欣一郎(相談役就任)
非常勤監査役 大森 寿夫
常勤監査役 桑原 彰一郎(両備グループ監査室主任監査役 就任)
執行役員 渡辺 明正 (両備テクノカンパニー相談役 就任)
http://www.ryobi.gr.jp/news/07/070628holdings.htm
125.Re: 両備が岡山大学に献金
名前:両備ホームページ読者 日付:11月18日(日) 17時53分
岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結について
・・・地域産業にいかに貢献するかが大学の使命であり、またそうしなければ企業からの献金を増やすことが出来ず、大学は経営難になるなど、地域の発展が即大学の経営に反映してくるのです。
写真:千葉学長(左)と小嶋代表
http://www.ryobi.gr.jp/message/message01.html
132.Re: 支援法人のパンフレット 名前:リスコミが大切 日付:11月20日(火) 6時56分
土壌汚染とリスクコミュニケーション 1
各役割が分かりやすく書かれています。
パンフレットが請求できます。
http://www.jeas.or.jp/dojo/pdf/pamph/14.pdf
133.Re: リスコミが大切 ツヅキのリンク 名前:支援法人のパンフレット 日付:11月20日(火) 6時58分
土壌汚染とリスクコミュニケーション 2
各役割が分かりやすく書かれています。
パンフレットが請求できます。
http://www.jeas.or.jp/dojo/pdf/pamph/15.pdf
134.Re: 分かりやすいパンフレット請求できます 名前:支援法人のパンフレット 日付:11月20日(火) 7時3分
土壌汚染による環境リスクを正しく
1 土にはどんな役割があるの?
2 土壌汚染ってなに?
・土壌汚染とは
・土壌汚染の特徴
3 土が汚染されるとどうなるの?
・その1
・その2
4 汚染された土についてどんな対策をしてきたの?
・土壌汚染の現状とこれまでの対策
5 土壌汚染対策法ってどんな法律?
・土壌汚染対策法の概要
6 土壌汚染による環境リスクとは?
・土壌汚染による環境リスクの管理方法
7 土壌汚染とリスクコミュニケーション
・その1
・その2
http://www.jeas.or.jp/dojo/pamph_02.html
135.Re: 土壌汚染を正しく理解するための資料 名前:支援法人のパンフレット 日付:11月20日(火) 7時26分
土壌汚染のパンフレットの請求方法
工事事業者向け
13セット(52冊で590円)
一般向け
土壌汚染対策法のしくみ(30冊 450円)
土壌汚染による健康リスクを理解するために(30冊450円)
http://www.jeas.or.jp/dojo/pamph.html
149.Re: リスクコミュニケーションガイドライン 名前:情報の共有 日付:11月24日(土) 16時0分
「自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン(案)」について
○リスクコミュニケーションとは
本ガイドラインでは、リスクコミュニケーションを「住民、事業者、自治体といった全ての利害関係者がリスク等に関する情報を共有し、相互に意志疎通を図って土壌汚染対策を円滑に進めていくための手段」と位置づけます。
これは、汚染された土壌から生じる健康リスクについて、汚染源の事業者や汚染の報告を受ける自治体だけではなく、その影響を受けるリスクがある周辺住民も含めて全ての利害関係者が情報を共有し、リスクを低減するための具体的な方法について特に住民の理解を得た上で、汚染除去等の措置を実施していく過程を指します。
リスクコミュニケーションは、相手を説得し、自分の言い分を受け入れてもらうことが目的ではありません。
利害関係者が情報を共有し、意見交換を行って健康リスクや対策への理解を深め、より良い対策を選択し、実行していくことです。
土壌汚染リスクコミュニケーションのあり方に関する検討会委員名簿
〔委 員〕
大塚 直 早稲田大学法学部教授
古賀 剛志 富士通(株)環境本部本部長
坂部 孝夫※ 愛知県環境部水環境課地盤環境室長
田村 栄一 同上
佐藤 泉 弁護士、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議常任幹事、日本地質汚染審査機構理事
○ 中杉 修身 横浜国立大学共同研究推進センター客員教授
樋山 隆久 栃木県氏家町環境課長
前川 統一郎 国際航業(株)地盤環境エンジニアリング事業部長
森 千里 千葉大学大学院医学研究院環境生命医学教授
盛岡 通 大阪大学大学院工学研究科教授
吉田 一明※ 山形県米沢市市民環境部環境生活課長
佐藤 博 同上
(○ 座長)
〔オブザーバー〕
奥村 知一 (財)日本環境協会 専務理事
佐藤 雄也 (社)土壌環境センター 専務理事
堀江 宏隆 全国町村会 財政部副部長
http://www.env.go.jp/water/dojo/guide/index.html
--------------------------------------------------------------------------------
143.環境省不法投棄ホットラインHP 名前:不都合な真実 日付:11月22日(木) 6時28分
環境省廃棄物・リサイクル対策部
大量の産業廃棄物の不法投棄など緊急に対応を要する事案についての情報を国民から直接受ける窓口として、環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室に、次のとおり、通報専用のメールボックス及びFAXを設けます。
[1] 電子メール:
sanpai110@env.go.jp (産廃110番)
[2] FAX:
0120− 537( ゴミなし )−381( さんぱい ) (ゴミなし産廃)
送信表はこちらからダウンロードできます。
http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/fax.pdf
[3] 携帯:
次のサイトから携帯電話で直接メールを送信することも可能です。
http://www.env.go.jp/k/recycle/s110.html ( iモード 、 EZweb 、 Yahoo!ケータイ 対応)
大規模な産業廃棄物の不法投棄を防止するためには、不法投棄の早期発見、拡大防止に努めることが必要です。
http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/hotline.html
144.Re: 岡山県警は産業廃棄物の不法投棄情報募集中です! 名前:不都合な真実 日付:11月22日(木) 6時26分
岡山県警「産業廃棄物の不法投棄情報募集中」のHP
廃棄物の処理をめぐっては、生活環境に有害な影響を与えるような、悪質な不法投棄事犯が依然として後を絶たず、大きな社会問題になっています。
岡山県警察では、悪質・巧妙化する産業廃棄物の不正処理に対処するため本部内に
「 廃 棄 物 対 策 係 」
を設置し、悪質な不法投棄事犯や野外焼却(野焼き)事犯を重点に取締りを強化していますが、インターネットや生活環境110番電話を通じて広く県民の方からの情報提供をお願いしています。
廃棄物とは、大きく分けて、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。 産業廃棄物とは、家屋の解体工事や建築工事などの各種工事、工場にある機械の洗浄等の事業活動に伴って発生するもので、具体的には
・ コンクリート片
・ がれき類
・ 廃油
・ 汚泥
・ 木くず
・ 廃プラスチック
などがあります。
一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しないものとなります。
これらを、許可を受けた処分場等で適正に処理することなく、人目に付かない山中などへ捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反になります。 廃棄物に関する情報は 【生活環境110番】
086−231−9449
またはE−MAIL
pseikan@pref.okayama.jp
でお願いします。
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/seian/seikan/seikan4/haikibutu.htm
145.Re: 環境省、岡山県警不法投棄ホットラインHP 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月22日(木) 12時31分
環境省には2006年11月17日付けで質問状を出し土壌環境課から12月1日付けで事務連絡回答書を頂いていますが、地域の土壌環境行政を所管する岡山市に相談をというもので、岡山市が積極的に動かない以上事態は進展しません。
警察へは何度も相談しましたが、私たちの事件は過去に産廃が不法投棄された土地であり、宅地分譲され戸建て住宅が建設された団地なので、私たちが建物を撤去して大掛かりな土壌調査をし、確実な証拠を挙げなければ捜査できないことがよく分かりました。
しかしアドバイス頂いた環境省・岡山県警の部署にはまだ相談していないのでメールボックスに再度要望してみます。
私たちは、まず民事訴訟で決着をつける覚悟を固めました。
その結果を得て再度、各省庁・官庁に相談をするつもりです。そうでないと障害が多すぎて容易に動けないのだと思います。
情報ありがとうございました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
--------------------------------------------------------------------------------
93.シックハウスを考える会 返信 引用 名前:シックハウス症候群 日付:10月28日(日) 7時2分
シックハウスを考える会
住居から発生する有害物質で悩む人をなくすためにつくられたNPOです。
http://www.sickhouse-sa.com/
94.Re: シックハウスを考える会 名前:シックハウス症候群 日付:10月28日(日) 7時4分
シックハウスを考える会 eグループ
グループの説明:このメーリングリストはシックハウスに関する情報交換のためのものです。
http://groups.yahoo.co.jp/group/sickhouse-sa/
95.Re: 岡山県土木部 > 住宅課 > シックハウス関係のHP 名前:シックハウス症候群 日付:10月28日(日) 7時13分
住まい(住宅)が、住んでいる私たちを病気にしてしまうことがあります。
この病気は、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
下記HPでは、あなたの住まいを「シックハウス症候群」から防ぐための原因と対策等について説明しています。
公営住宅班 086-226-7526
計画融資班 086-226-7527
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=7469
96.Re: 岡山県保健福祉部 > 生活衛生課 > 現代の住まいとシックハウス症候群 名前:シックハウス症候群 日付:10月28日(日) 7時11分
住まい(住宅)が、住んでいる私たちを病気にしてしまうことがあります。
生活営業指導班
086-226-7335
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=4173
101.化学物質ファクトシート―2006年度版は送料のみでもらえます 名前:環境省HP閲覧マニア 日付:11月14日(水)
平成19年11月1日
「化学物質ファクトシート―2006年度版―」の作成・公表について
環境省では、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」の対象となっている化学物質について、専門的で分かりにくい情報を分かりやすく整理し、専門家以外の方にもよく理解していただけるよう簡潔にまとめた「化学物質ファクトシート」を作成しています。
このたび、2005年度版に収録していた159物質についての情報を最新の情報に更新するとともに、新たに50物質についての情報を追加した「化学物質ファクトシート―2006年度版―」が完成いたしましたので、ホームページ(http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html)にて公表いたします。また、御希望の方には本ファクトシートの冊子を無料(送料は自己負担)で配布いたします。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8985
102.シックハウス症候群に関する医学的知見の整理 名前:厚生労働省省HP閲覧マニア 日付:11月14日(水) 19時49分
「室内空気質健康影響研究会報告書:
〜シックハウス症候群に関する医学的知見の整理〜」
の公表について
近年のシックハウス症候群を始めとする室内空気質による健康影響への関心の高まりを受け、厚生労働省健康局生活衛生課では、有識者からなる「室内空気質健康影響研究会」を平成15年5月から3回にわたり開催し、室内空気質の健康影響について、厚生労働科学研究等を通じてこれまでに得られた医学的知見の整理をお願いしてきた。
今般、その報告書が取りまとめられたので公表することとする(概要:別紙参照)。
○ 研究会のメンバー 相澤 好治 (北里大学医学部教授)
秋山 一男 (国立相模原病院臨床研究センター長)
荒記 俊一 (独立行政法人産業医学総合研究所理事長)
石川 哲 (北里研究所病院臨床環境医学センター長)
石川 睦男 (旭川医科大学教授)
糸山 泰人 (東北大学大学院医学系研究科教授)
岩月 啓氏 (岡山大学大学院医歯学総合研究科教授)
小田島安平 (昭和大学医学部助教授)
加藤 貴彦 (宮崎大学医学部教授)
加藤 進昌 (東京大学大学院医学系研究科教授)
岸 玲子 (北海道大学大学院医学研究科教授)
熊野 宏昭 (東京大学大学院医学系研究科助教授)
名和田 新 (九州大学大学院医学研究院教授)
西間 三馨 (国立療養所南福岡病院院長)
古川 仞 (金沢大学医学部大学院医学系研究科教授)
宮坂 信之 (東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授)
※ 宮本 昭正 (財団法人日本アレルギー協会理事長)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/02/h0227-1.html
120.Re: 室内空気質健康影響研究会報告書 名前:岡山大学は室内空気質健康影響に詳しいはずだが 日付:11月18日(日)
室内空気質健康影響研究会報告書の概要
発症関連因子としての化学物質
シックハウス症候群の主な発症関連因子として、建材や内装材などから放散されるホルムアルデヒドや、トルエンをはじめとする揮発性有機化合物がこれまで指摘されている。
室内空気質健康影響研究会のメンバー
岩月 啓氏 (岡山大学大学院医歯学総合研究科教授) 他
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/02/h0227-1.html
121.Re: トルエンはもっとも排出量が多い化学物質(報告下限値0.006 mg/L) 名前:化学物質ファクトシート2006 日付:11月18日(日)
化学物質ファクトシート2006 トルエン
http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html
・トルエンは、さまざまな化学物質の原料として使われるほか、油性塗料や接着剤などの溶剤として使われています。
・2005 年度のPRTR データでは、環境中への排出量は約180,000 トンで、もっとも排出量が多い化学物質でした
・トルエンは水に溶けにくく、油などを溶かす性質があります。
・同じような性質があるベンゼンに比べて毒性が低く、安価なことから、油性塗料や印刷インキ、油性接着剤などの溶剤と
しても幅広く使われています。
・接着剤や塗料のうすめ液などに使用されるシンナーはトルエンを
主成分としているほか、油性のペンキ、ニス・ラッカー、マニキュアなど、身のまわりにもトルエンを含む製品があります。
・トルエンを長期間にわたって体内に取り込んだ結果、視野狭さく、眼のふるえ、運動障害、記憶障害などの神経系の障害のほか、腎臓、肝臓や血液への障害が認められています。
・トルエンはシックハウス症候群との関連性が疑われていることから、厚生労働省ではトルエンの室内空気濃度の指針値を0.26 mg/m3(0.07 ppm)と設定しています。
・水道法:水道水質管理目標値0.2 mg/L 以下
・水質要監視項目:指針値0.6 mg/L 以下
・住宅の品質確保の促進等に関する法律:住宅性能表示制度における室内空気中濃度の特定測定物質
http://ceis.sppd.ne.jp/fs2006/factsheet/data/1-227.html
122.Re: キシレンは2番目に多い化学物質(報告下限値:0.04 mg/L) 名前:化学物質ファクトシート2006 日付:11月18日(日)
・キシレンは、ほとんどが他の化学物質の原料として使われているほか、油性塗料や接着剤などの溶剤としても使われています。
・2005年度のPRTRデータでは、環境中への排出量は約12万トンで、トルエンについで2番目に多い化学物質でした。
・キシレンのほとんどは、他の化学物質の原料として使われています。
・この他、混合物キシレンと呼ばれる製品の形で、油性塗料、接着剤、印刷インキ、シンナー、農薬などの溶剤に使われています。
・灯油、軽油、ガソリンなどにも各異性体のキシレンが含まれています。
・高濃度のキシレンは、眼やのどなどに対する刺激性や、中枢神経へ影響を与えることが報告されています。
・シックハウス症候群との関連が疑われていることから、厚生労働省ではキシレンの室内空気濃度の指針値を0.87 mg/m3 (0.2 ppm) と定めています。
・公共用水域水質測定(要監視項目):指針値超過数0/708地点(報告下限値0.04 mg/L);[2005年度,環境省]
・地下水質測定(要監視項目):指針値超過数0/422地点(報告下限値0.04 mg/L);[2005年度,環境省]
http://ceis.sppd.ne.jp/fs2006/factsheet/data/1-063.html
123.Re: エチルベンゼン(地下水:検出最大濃度0.00015 mg/L) 名前:化学物質ファクトシート2006 日付:11月18日(日)
・エチルベンゼンは、ほとんどがスチレンの原料として使われているほか、溶剤として使用されています。
・エチルベンゼンはシックハウス症候群との関連性が疑われていることから、厚生労働省ではエチルベンゼンの室内空気濃度の指針値を3.8 mg/m3(0.88 ppm)と定めています。
・国際がん研究機関(IARC)はエチルベンゼンをグループ2B (人に対して発がん性があるかもしれない)に分類しています。
・地下水:要調査項目存在状況調査:検出数2/23地点,最大濃度0.00015 mg/L;[1999年度,環境省]
http://ceis.sppd.ne.jp/fs2006/factsheet/data/1-040.html
124.Re: BTEXは分析対象 名前:フリー百科事典(ウィキペディア)マニア 日付:11月18日(日) 17時45分
・BTEX はベンゼン (benzene)・トルエン (toluene)・エチルベンゼン (ethylbenzene)・キシレン (xylene) の頭文字を表し、主に石油業界や土壌汚染関連で使用される略語である。
・トルエン、エチルベンゼン、キシレンの各化合物は中枢神経系への影響が指摘されている。
・ガソリンスタンド跡地などにおける土壌や地下水の油汚染でもBTEXは専ら分析対象とされている。
・石油業界では各社独自の基準を設けている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/BTEX#.E9.96.A2.E9.80.A3.E9.A0.85.E7.9B.AE
129.Re: 化学物質ファクトシート2006年度版とは 名前:化学物質による環境リスクの削減 日付:11月19日(月) 0時22分
化学物質ファクトシートとは
◆ 目的
化学物質とその環境リスクの問題は、日常生活における身近な環境問題として社会的に関心が高いものの1つです。
その一方で、化学物質に関して提供されるさまざまな情報は専門的かつ断片的なものが多いため、専門家以外の人々にとって正確に理解することが難しく、誤解に基づく無用な不安を引き起こしてしまう恐れがあるばかりでなく、私たちが普段の生活の中で行うことのできる環境リスクの削減のための取組を進める上でも障害になっています。
この化学物質ファクトシートは、2003年度から引き続く環境省請負事業として実施したもので、下記の専門家からなる作成委員会を設置してご意見を頂きながら作業を進めています。
委員長 中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科 教授
委 員 有田 芳子 主婦連合会
石崎 直温 (社)日本化学工業協会環境安全部 部長
内山 巌雄 京都大学大学院工学研究科 教授
大歳 幸男 (社)環境情報科学センター 特別研究員
小林 剛 横浜国立大学 安心・安全の科学研究教育センター 助教授
黒川 幸郷 (社)日本化学会総務部 部長
白石 寛明 (独)国立環境研究所 環境リスク研究センター長
中地 重晴 環境監視研究所長
早川 敏幸 日本生活協同組合連合会 安全政策推進室
安井 至 国際連合大学 副学長
協 力 日本化学工業協会、日本鉱業協会、農薬工業会、日本無機薬品協会
化学構造式(監修) 野村 祐次郎 東京大学名誉教授
http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html
--------------------------------------------------------------------------------
108.岡山市の情報公開のページ 名前:情報公開請求マニア 日付:11月17日(土) 17時38分
情報公開制度とは、岡山市が保有する情報を広く公開する制度です。 この制度は、市民の知る権利を保障するとともに市政について市民に説明する責任を果たし,市民の積極的な参加による開かれた市政を実現することを目的にしています。
http://www.city.okayama.okayama.jp/soumu/bunsho/jouhoukoukaiseido/jouhoukoukaitop.htm
109.Re: 岡山市情報公開及び個人情報保護審査会委員 名前:情報公開請求マニア 日付:11月17日(土) 17時40分
岡山市情報公開及び個人情報保護審査会委員
平成18年6月1日現在
氏 名 職 業 等 備 考
小田廸子 元岡山市監査委員
恩田英宜 司法書士
佐藤洋子 弁 護 士
平井昭夫 弁 護 士
山口和秀 岡山大学大学院教授 会長
http://www.city.okayama.okayama.jp/soumu/bunsho/jouhoukoukaiseido/contentsu/iinkaimeibo.htm
110.Re: 南古都? 環境対策員会 委員名簿 名前:天知る地知る自分知る 日付:11月17日(土) 17時44分
南古都? 環境対策員会
設立年月日 平成16年10月15日
委員長 千葉喬三 岡山大学 副学長
委 員 河原長美 〃 保健環境センター教授
笹岡英司 〃 環境理工学部教授
西垣誠 〃 環境理工学部教授
西村伸一 〃 保健環境センター助教授
竹内文章 〃 保健環境センター助教授
山本秀樹 〃 医学部 講師
オブザーバー
金安利和 岡山市環境保全部 部長
中瀬克己 保健所 所長
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/sisetsuiinkai01.html
111.Re: 岡山県の情報公開のページ 名前:公僕 日付:11月17日(土) 17時48分
行政情報の公開
県政情報室(総務学事課行政情報班)では、県民の皆様に様々な行政情報の提供を行っています。
公文書の開示、岡山県が保有する個人情報の開示等、各種行政資料の閲覧・貸出しを希望される方は、県庁4階の県政情報室(総務学事課行政情報班)へお越しください。
http://www.pref.okayama.jp/somu/gakuji/gakuji-5.htm
112.Re: 岡山県行政情報公開審査会委員 名前:公僕 日付:11月17日(土) 17時50分
岡山県行政情報公開審査会委員
・任期 2年(現委員の任期 H17.3.1〜H19.2.28)
・委員名簿
会長 神山 敏雄 (甲南大学 法科大学院 教授)
委員 清野 幸代 (弁護士)
委員 宇佐美 英司(弁護士)
委員 森 義郎 (岡山県農業信用基金協会 専務理事)
委員 進藤 貴子 (川崎医療福祉大学 医療福祉学部 助教授)
http://www.pref.okayama.lg.jp/somu/gakuji/gyosei-joho/shingikai/johokokai.htm
113.Re: 広島国税局へのご意見・ご要望 名前:マルサ 日付:11月17日(土) 17時53分
広島国税局へのご意見・ご要望
http://www.nta.go.jp/hiroshima/kohyo/iken/index.htm
114.Re: 刑事訴訟法第239条 名前:主権在民 日付:11月17日(土) 18時13分
刑事訴訟法第239条 公務員の告発義務
第2号 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM
115.Re: 日本国憲法 第17条 国家賠償 名前:法治国家の民 日付:11月17日(土) 18時20分
日本国憲法/第3章 国民の権利及び義務
第17条〔国家賠償〕
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
--------------------------------------------------------------------------------
43.おおさかATCグリーンエコプラザ 土壌地下水汚染セミナーのご案内 返信 引用
名前:ATCMD研究会会員 日付:8月11日(土) 7時9分
失礼します。
おおさかATC「土壌・地下水汚染の課題と展望」セミナー 〜東京豊洲・大阪OAP等を例に学ぶ〜 のご紹介をさせていただきます。
今回のセミナーでは、今までに日本で社会的な話題になった(なっている)汚染の事例や問題点を真正面から学び、土壌・地下水汚染の現状の課題を真摯に考え、さらに、今後の土壌・地下水汚染についての展望を皆様と共に開く機会にしたいと思っておりますので、奮って、お申し込みください。
<開催日>
平成19年8月23日(木)14:00〜17:30
<プログラム>
講演1:「東京・築地市場移転先、豊洲の土壌・地下水汚染問題」
講師:日本環境学会 畑明郎会長
http://www.jaes.sakura.ne.jp/
講演2:「市民ができる市民のための地質汚染完全浄化」
講師:NPO法人日本地質汚染審査機構 楡井 久 理事長
http://homepage1.nifty.com/npo-geopol/index.htm
発表:大阪アメニティパーク土壌・地下水汚染と土壌汚染対策法の問題点
講師:NPO法人 職員 安田 圭奈江 氏
<主 催>
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会水・土壌汚染対策研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html
<会 場>
ビオトープ・プラザ(ITM棟11FATCグリーンエコプラザ内)
http://www.ecoplaza.gr.jp/
<交流会>
会場:ATCビルITM棟6F ピア6
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html
17:40〜18:50(会費制:2000円/1人)
(小鳥が丘住民代表の方が参加されました。)
44.Re: おおさかATCグリーンエコプラザ 土壌地下水汚染セミナーのご案内 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:8月12日(日)
情報ありがとうございます。
さっそく参加申込みいたしました。
よろしくお願いします。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
--------------------------------------------------------------------------------
99.Re: ATC「土壌・地下水汚染に関する無料相談」 名前:EICネット イベント情報 読者 日付:10月31日(水) 4時50分
ATC「土壌・地下水汚染に関する無料相談」のご案内
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会「水・土壌汚染対策研究部会」は、土壌汚染相談窓口を、設置しております。
土壌・地下水汚染に関連する事項(法令関連、調査・浄化、環境管理、リスクコミュニケーション等)について、ご質問、ご相談がございましたら、当研究部会アドバイザー(技術士、環境計量士、環境カウンセラー、宅地建物取引主任者、地質調査技士、土壌環境監理士等)が第三者の立場で無料でご相談に応じます。
<開催日時>
(木)15時00分〜16時30分
<主 催>
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会 http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
ブログ:http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk
<相 談 料>
無料
<場 所>
おおさかATCグリーンエコプラザ内 土壌汚染相談窓口コーナ
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
<相談例>
・土壌汚染調査報告書の内容が良く理解できない
・汚染地下水が地下駐車場に漏れ出した
・自社工場敷地の廃棄物が埋まっている
・汚染のある土地を利用したい
・タンクから油が漏れた
・近所に廃棄物を埋められた
・土壌汚染対策工事で健康被害が心配
・適当な業者を紹介して欲しい
・この商品は土壌地下水汚染に使えないか?
・土壌汚染調査会社を作りたい
・土壌汚染浄化施設を作りたい
・調査や対策の費用はどれくらいかかるのか?
・アスベストの調査や対策について?
・土壌・地下水汚染に関するセミナーを開催したい 等
<お申し込み>
相談概要や連絡先等を申し込み用紙
http://beauty.geocities.jp/atcmdk/atcmdkSOUDAN.doc
に記入して下記宛にお申し込み下さい。
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会 「水・土壌汚染に関する相談窓口」係
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
TEL06-6615-5887 FAX06-6614-1801 E-mail:md@e-being.jp
なお、メールやFAXでも相談を行っております。
<詳しくは下記をご覧下さい>
「水・土壌汚染に関する相談窓口」の設置
相談窓口↓
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/MYBLOG/yblog.html?fid=1318201&m=lc
申し込み用紙案がリンクできます
http://www.eic.or.jp/event/?act=view&serial=13321
--------------------------------------------------------------------------------
90.油汚染対策ガイドライン 名前:油臭油膜の無い事 日付:10月28日(日) 6時22分
平成18年3月22日
本ガイドラインは、鉱油類を含む土壌に起因して、その土壌が存在する土地の地表、あるいはその土地にある井戸の水や池・水路等の水に油臭や油膜が生じているときに、土地の所有者等が、その土地においてどのような調査や対策を行えばよいかなどについて、基本的な考え方と、取り得る方策を選択する際の考え方などを取りまとめたものです。
本ガイドラインについては、3月31日に開催される同部会に報告され、今後のフォローアップのあり方について審議される予定です。
なお、環境省は、本ガイドラインの周知を図るため、本日付で本ガイドラインを都道府県・土壌汚染対策法政令市に通知します。
環境省水・大気環境局土壌環境課
課長:鏑木 儀郎(6650)
課長補佐:太田 志津子(6652)
課長補佐:佐藤 宏昭(6651)
担当:山添 泰一(6656)
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/04/mat01.pdf
91.Re: 油汚染対策ガイドライン 名前:油臭油膜の無い事 日付:10月28日(日)
油汚染対策ガイドライン
このガイドラインをお読みになる方に
前略
例えば地面が油臭い、あるいは井戸水に油膜があるというときに、日ごろから油を扱っているプラントや設備の状況を頭の中に入れてある技術者なら、すぐに調べなければならないことがいくつも頭に浮かぶことでしょう。
このガイドラインには、油汚染問題に対応する際の考え方や、油汚染問題が生じている現場で調査や対策を行う際に参考となる事項を取りまとめています。
また、技術的な参考資料として、現時点で得られている様々な技術情報を収録していますので、調査や対策工事を実施する場面では大いに参考にして頂きたいと思います。
このガイドラインが様々な場面で、油臭や油膜の問題に直面した人たちに、それぞれの実情に応じて適切に利用されることを願っています。
http://www.env.go.jp/water/dojo/oil/full.pdf
92.Re: 土壌汚染技術基準等専門委員会 委員名簿 名前:油汚染対策ガイドライン 日付:10月28日(日) 6時29分
中央環境審議会土壌農薬部会 土壌汚染技術基準等専門委員会 委員名簿
(平成18年3月8日現在)
委員長 森田昌敏 独立行政法人国立環境研究所客員研究官
委員 大塚 直 早稲田大学法学部教授
〃 佐藤 洋 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科教授
臨時委員 浅野直人 福岡大学法学部教授
〃 櫻井治彦 中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長
〃 中杉修身 上智大学大学院地球環境学研究科教授
〃 細見正明 国立大学法人東京農工大学工学部化学システム工学科教授
〃 眞柄泰基 国立大学法人北海道大学創成科学共同研究機構特任教授
専門委員 鈴木規之 独立行政法人国立環境研究所内分泌かく乱物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理プロジェクトグループ総合化研究チーム総合研究官
〃 冨永 衞 独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター副センター長
〃 平田健正 国立大学法人和歌山大学システム工学部環境システム工学科教授
〃 三木博史 独立行政法人土木研究所技術推進本部総括研究官
(敬称略)
http://www.env.go.jp/water/dojo/oil/kanmatu.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
86.通常有すべき性状を備えないものとして土地の瑕疵にあたる 名前:財産管理に関する法律相談事例集読者 日付:10月27日(土)
東京地方裁判所平成4年10月28日判決
「地中に土以外の異物が存在する場合一般が、直ちに土地の瑕疵を構成するものではないことは言うまでもないが、その土地上に建物を建築するについて支障となる質・量の異物が地中に存在するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備・改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合には、建築用土地として通常有すべき性状を備えないものとして土地の瑕疵になるものと解すべきである。
本件の場合、大量の材木片等の産業廃棄物、広い範囲にわたる厚さ約15?のコンクリート土間および最長約2mのコンクリート基礎10個が地中に存在し、これらを除去するために相当の費用を要する特別の工事をしなければならなかったのであるから、これらの存在は土地の瑕疵にあたるものというべきである。」とされている。
(29/37)ページ下のほうにあります
http://www.zam.go.jp/p00/pdf/801/00000004.pdf
87.Re: 土壌汚染の関連判例 名前:ネットサーファー 日付:10月27日(土) 20時55分
取扱裁判案件の主要分野
第2 土壌汚染の実務
1 土壌汚染の問題点
2 買主の採りうる法律的手段について
3 手続について
第3 関連判例
1 東京地方裁判所平成4年10月28日判決
2 東京地方裁判所平成14年9月27日判決
http://www.sosho.jp/service/3-6-3.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
85.公害防止事業費事業者負担法 名前:汚染原因者負担の原則 日付:10月27日(土) 17時57分
公害防止事業費事業者負担法(フリー百科事典ウィキペディア)
この法律は、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めるものとする。(法1条)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E8%B2%A0%E6%8B%85%E6%B3%95
--------------------------------------------------------------------------------
65.環境基準を下回る土壌汚染(オイル)の瑕疵担保責任を認めた事例 名前:全日不動産協会東京都本部HP読者 日付:10月21日(日)
土の中の油は瑕疵になる判例の転載です
分譲マンションを建築する目的で土地を購入した宅建業者が、土地の引渡しを受けた後に建築工事に着手したところ、地中から建物のコンクリート基礎やオイルタンクの残骸等及び現場全体でオイル類に汚染された土壌が発見されたが、汚染された土壌が環境基準に抵触するような量の有害物質を含有していないことから、当該土壌汚染についての瑕疵担保責任が争われた事案において、売主の瑕疵担保責任を認容した事例(東京地裁平成14年9月27日判決 確定 ホームページ下級裁主要判決情報登載)
一 事案の概要
オイル類を含んだ土、はコンクリート製のオイルタンクの残骸が発見され、現場全体でオイル類により黒く汚染されて泥状になった土壌が見つかった。この汚染された土壌は、環境基準に抵触するような量の有害物質を含有していなかったが、水を含むと強い悪臭を発した。
二 判決の要旨
これに対して、裁判所は次のように判断を下した。
(1)本件汚染土壌の存在が、本件土地に瑕疵があるといえるか否かについて
本件土地における土壌汚染は、マンション建設の基礎工事途中で発見される程度に浅い位置において、多量のオイル類を含有し、しかも、容易に悪臭を発生し得るような状態にあったというのであるから、本件土地に基礎を置き、多数の住民を迎え入れることになるマンションを建設することを妨げる程度に至っており、特別に費用をかけてでも処理する必要があるといわざるを得ない。
したがって、本件土地は、取引通念上有すべき品質、性能を欠くというべきであり、本土壌汚染は本件土地の瑕疵に当たると認めるのが相当である。
三 まとめ
建物を建築するについて支障となる質、量の異物が地中に存在するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備、改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合は、宅地として通常有すべき性状を備えないとして、土地の瑕疵に当たるというべきであると判示している。
http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/zennichi_kaiin/knowledge/business/database/data02.htm
66.Re: 環境基準を下回る土壌汚染(オイル)の瑕疵担保責任を認めた事例 名前:地面から油が出てきたら瑕疵 日付:10月22日(月)
土壌汚染対策法の指定基準を超えても超えなくても地面から油がでてきたら、土地の瑕疵として損害賠償しなければならないのですね。
小鳥が丘はしっかり油がでてきています。当然、損害賠償してもらいましょう!!
69.Re:土地の欠陥を補正するために当然必要な措置である 名前:取引通念上通常有すべき性状を欠く 日付:10月23日(火)
平成14年9月27日判決言渡 平成13年(ワ)第19581号 損害賠償請求事件
主 文
1 被告は,原告に対し,金4594万円及びこれに対する平成13年9月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
<事実及び理由>
第2 事案の概要
本件は,マンションを建設するために被告から土地を購入した原告が,土地の引渡し後に,地中から建物のコンクリート基礎やオイル類といった障害物が発見されたため,それらを撤去,処理する費用や,マンション建設の遅れを取り戻すための突貫工事費用等の負担を余儀なくされたとして,被告に対し,瑕疵担保責任特約に基づく損害賠償及び遅延損害金を請求した事案である。
中略
民法570条にいう「瑕疵」とは,売買の目的物が,その種類のものとして取引通念上通常有すべき性状を欠いていることをいう。
そして,宅地の売買において,地中に土以外の異物が存在することが即土地の瑕疵に当たるとはいえないのは当然であるが,その土地上に建物を建築するについて支障となる質,量の異物が地中に存在するために,その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備,改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合は,宅地として通常有すべき性状を備えないものとして,土地の瑕疵に当たるというべきである。
これを本件についてみるに,前記前提となる事実及び証拠によれば,本件土地は,東京都江東区に所在する地積約800平方メートルの宅地であり,比較的大規模の建物を建築できるものであること,原告は,分
譲用マンションを建設する目的で本件土地を購入したものであり,被告もこれを了解していたこと,オイル類によって汚染された土壌は,大和建設がマンション建築のための基礎工事(根伐工事)を行っている際に発見されたこと,汚染土壌は,量にして合計1200立方メートルにのぼり,その形状は黒色で部分的には泥状になっているところもあったこと,汚染土壌が雨等によって水分を含むと,強い悪臭が発生したこと,オイル類によって汚染されて悪臭を発するような土壌は,産業廃棄物に該当するため,これを処分するためには,通常の残土処分に比べてかなり高額の廃棄費用を負担しなければならないこと,以上の諸事実が認められる。
してみると,本件土地における土壌汚染は,マンション建設の基礎工事途中で発見される程度に浅い位置において,多量のオイル類を含有し,しかも,容易に悪臭を発生し得るような状態にあったというのであるから,本件土地に基礎を置き,多数の住民を迎え入れることになるマンションを建設することを妨げる程度に至っており,特別に費用をかけてでも処理する必要があるといわざるを得ない。
したがって,本件土地は,取引通念上通常有すべき品質,性能を欠くというべきであり,土壌汚染は本件土地の瑕疵に当たると認めるのが相当である。
エ これに対し,被告は,本件土地の地中に存在したオイル類は,環境基本法に基づく環境基準値を全項目において下回っているのであるから,原告は本件土地内のオイル類を処分しなければならない法的な義務を負わず,したがって,本件土地に瑕疵があるとはいえないとし,原告が汚染土壌を処理したのは,単なる土地の改良にすぎない旨主張する。
しかしながら,売買目的物に関する瑕疵の有無の判断は,オイル類の処分をしなければならないかどうかという買主の法的義務の存否によって定められるのではなく,対象物が取引通念上通常有すべき性状を欠くか否かによって決定されるべきものであるところ,本件土地上にマンション建物を建築,販売するにあたって,その地中の比較的浅い部分に多量のオイル類が存在しているということは,買手に建物ひいては本件土地の安全性,快適性に対する疑念を生じさせ,購買意欲及び価格のマイナス要因となることは明らかである。
したがって,本件土地には,取引通念上通常有すべき性状が欠けており,原告が本件土地の汚染土壌を処理したことは,本件土地の欠陥を補正するために当然必要な措置であるというべきであるから,被告の主張は採用できない。
オ よって,・・原告の主張は理由がある。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ADFCB82106BA86E449256CAE0022C7C4.pdf
70.ツヅキRe: 環境基準を下回る土壌汚染(オイル)の瑕疵担保責任を認めた事例 名前:取引通念上通常有すべき性状を欠く 日付:10月23日(火)
中略
よって,争点に関する原告の主張は,損害を障害物の撤去及び土壌廃棄費用4594万円とする限度で理由がある。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は,金4594万3629円及びこれに対する平成13年9月26日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ADFCB82106BA86E449256CAE0022C7C4.pdf
84.Re: オイルは環境基準以下での土壌汚染も売主の負担 名前:日経アーキテクチュア読者 日付:10月27日(土)
環境基準以下での土壌汚染も売主の負担
2003年に土壌汚染対策法が施行されました。マンション用地等については厳しいチェックがされるようになっています。ただ土壌汚染紛争はその性格上、裁判ではなく当事者間で決着を図られることが多く、裁判事例はほとんどないようです。
790平方メートル3億円余のマンション用地で,着工後に土壌がオイルで汚染されていることが判明しました。
この土壌廃棄費用に数千万円を要することになり、この負担が争いとなります。イル類の汚染は環境基準を下回っていると売主は主張。売主が汚染の事実を知らずまた無過失だったことは裁判所も認めます。
しかし2002年9月27日東京地裁の判決は、この土壌汚染によりマンション用地としての適性が欠けていたものとなっているのであり、たとえ環境基準を超えていなくても土地の瑕疵だとして、売主に費用の負担を命じました。
(日経アーキテクチュア 2004.10.4号)
http://www.bird-net.co.jp/rp/MM041105.html
--------------------------------------------------------------------------------
83.信義則上の説明義務の不履行があると判断 名前:東京地裁平18・9・5判決 日付:10月27日(土)
売買された土地について後日 鉛等により土壌汚染されていることが判明した場合、売主に土地の来歴や従前からの使用方法について説明すべき信義則上の付随義務とその義務違反による損害賠償責任が認められた事例 東京地裁平18・9・5判決(判例時報 1973号 84項)
(売主が)交付した同土地の重要事項説明書に、同土地の来歴や使用状況についての詳細を記載しなかったのであるから、信義則上の説明義務の不履行があると判断し、本件請求を一部認容した。
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi-fujimura/siryou/minnpou/sousoku/dojouosennsingisoku191017.html
--------------------------------------------------------------------------------
82.土地の瑕疵を理由とした契約解除を認めた事例 返信 引用
名前:居住目的を達することができない 日付:10月27日(土)
土地の瑕疵を理由とした契約解除を認めた事例釧路地裁帯広支部平成15年3月31日判決
これまで、土地の瑕疵ということは、十分に論じられてきませんでしたが、土地の瑕疵という概念は理論上も実際上も問題となり得るのだということを再認識した事件でした。
契約解除ができるための条件は「居住目的を達することができない」という要件が必要ですが、その一事例として参考になると思います。
(欠陥住宅全国ネット機関紙「ふぉあ・すまいる」第11号〔2004年4月28日発行〕より)
http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/2-6-11-10-1=tochinokashiniyorukaijo-kushirochi-obhihiroshiH150331(kawai).htm
--------------------------------------------------------------------------------
67.OAPの和解案 25%キャッシュバック&土壌入れ替え+地下水浄化 名前:OAPコンソーシアム 日付:10月22日(月)
和解案の概要は、
?継続所有を希望する所有者に対しては購入価格の25%を支払う
さらに、土壌入れ替えや、有害物質が上がってこないよう地下にシートを貼ったり、ご近所に迷惑をかけないよう周辺の地下水も綺麗にしてくれます。
http://www.cc.toin.ac.jp/crc/cc/05/p140-144.pdf
78.Re: 大阪アメニティパーク(OAP)土壌・地下水対策工事等の決定 名前:汚れた土地住民から綺麗な土地の住民へ 日付:10月27日(土) 9時53分
2006年1月29日
大阪アメニティパーク(OAP)土壌・地下水対策工事等の決定に関するお知らせ
大阪アメニティパーク(大阪市北区天満橋所在、以下「OAP」という)における土壌・地下水問題に関する対策工事につきましては、本日、OAPレジデンスタワー管理組合と当社を含む事業者4社は、合意に達し、協定書を締結しましたので、お知らせ致します。
対策工事につきましては、昨年7月より学識者、コンサルタント、住民、事業者で構成する技術評価検討会において議論を重ね、12月に工事案が提示されておりましたが、本日の管理組合臨時総会において同案が承認されたものです。
工事の概要は以下の通りです。
?表層土壌対策 ・・・ 表層2mまでの土壌の入れ替え
?汚染の周辺拡散防止対策 ・・・ 敷地周辺部に深さ23mの遮水壁を設置
?封じ込め内部の対策 ・・・ 汚染土壌の濃度が高い箇所について表層5mまでの土壌入れ替え
http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/oap/oap20060129.html
79.Re: OAP敷地周辺調査結果は地下水汚染 セレン400倍 名前:ご近所に汚染の迷惑をお掛けしません 日付:10月27日(土)
2006年9月10日
OAP(大阪アメニティパーク)敷地周辺調査結果と対策について
OAPの環境問題に関しましては、本年6月からOAP敷地内の対策工事に着手しておりますが、今般、OAP敷地周辺への影響の有無を確認するため、当社旧大阪製錬所敷地(OAP敷地)外となる事業者用地等4地点において環境調査を実施し、下記のとおり調査結果がまとまりましたのでお知らせいたします。
当社では、本調査結果に関する近隣住民の方々の疑問やご相談に応じられるよう窓口を設け、ご不安の解消に努めるなど誠意を持って対応してまいります。
中略
5.今後の計画
汚染源から周辺への拡散防止のための工事等を実施しており、この対策工事によって周辺への汚染拡散は防止されますが、今後新たに次を実施する予定としております。
(1) No.1、No.2エリアについては、当該箇所に隣接するOAP敷地境界部において拡散防止ならびに浄化を目的とした地下水の揚水を実施します。
(2) 今回設置した観測井を用いてモニタリングを実施します。
http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/oap/oap20060910.html
80.Re: OAPの和解案 住むなら25%キャッシュバック 売るなら汚染が無い評価で10%上乗せ 名前:汚染があって金銭的には得 日付:10月27日(土)
2005年5月8日
OAP(大阪アメニティパーク)事業に係る和解提案に関するお知らせ
大阪アメニティパーク(OAP)の土壌・地下水問題に関し、早期かつ包括的な解決を図るため、当社、三菱地所(株)、(株)大林組及び三菱マテリアル不動産(株)の事業者4社は、平成17年5月8日付をもってOAPレジデンスタワー管理組合法人との間で、同マンションの現所有者の皆様に対し今後事業者が金銭的解決等に関する提案を行うことについて確認書を締結いたしました。
提案の概要は、継続して所有を希望される所有者の皆様に対しては、購入価格の25%を支払い、売却を希望される所有者の皆様に対しては、双方が合意した不動産鑑定士に土壌・地下水問題がないことを前提とした鑑定評価を依頼し、その鑑定価格による買い取りを行うとともに、買い取り価格の10%を支払うことなどです。
今後、本確認書の内容をガイドラインとして各所有者の皆様の意向を確認した上、個別に交渉を行い、具体的な支払金額、支払方法、支払時期等について取り決めていくこととしております。
http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/oap/oap20050508.html
--------------------------------------------------------------------------------
74.工場の詳しい資料は? 名前:土地利用履歴等調査 日付:10月27日(土) 8時54分
昭和57年に、行政も関与し両備不動産が買い取るという事で操業を停止し、旭油化工業と両備不動産の間で売買契約が成立しましたとのことですが、当時の詳しい資料はないのでしょうか?
土壌汚染の調査を行う場合には過去の操業の記録や工場の施設配置などが非常に参考になります。
また、排水の分析記録や廃棄物受け入れの記録などもあれば参考になるのですが・・・
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/asahiyukahyou.html
--------------------------------------------------------------------------------
72.土対法8条より民法570条 返信 引用 名前:土対法は汚染原因者の免罪符か? 日付:10月23日(火)
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 前条第一項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。
ただし、その行為をした者が既に当該汚染の除去等の措置に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該汚染の除去等の措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該汚染の除去等の措置を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html
--------------------------------------------------------------------------------
71.産廃が埋めれているのを公開するのは名誉毀損にならない 名前:悪い奴が名誉毀損と開き直るのは常套手段 日付:10月23日(火)
主文
1 原告(市会議員)の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告(市会議員)の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告(新聞社)は,原告(市会議員)に対し,金1000万円等を支払え。
2 被告は,株式会社東奥日報社発行の東奥日報及び株式会社陸奥新報社発行の陸奥新報の,各朝刊最終版に,別紙記載の謝罪広告を別紙記載の条件で各1回掲載せよ。
<被告(新聞社)の主張>
ア 以下に述べるとおり,原告は,産業廃棄物が本件ゴルフ練習場付近の土地に不法に投棄されたのを黙認し,むしろ,原告自身が,あえて業者に産業廃棄物の投棄を勧めていたものであって,被告の産廃不法投棄発言は真実である。
中略
<原告(市会議員)の主張>
ア 被告の産廃不法投棄発言は,以下のとおり真実ではない。
? 原告が,真実,産業廃棄物を不法投棄した,ないし不法投棄に関与したのであれば,遅くとも,被告が行政当局に通報し,当局の調査が入った平成14年12月以後に,原告が告発されたり,原告に対して何らかの命令が出されたりする事態に至っているはずである。
中略
第4 結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告(市会議員)の請求はいずれも理由がないから棄却する。
青森地方裁判所弘前支部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/CF86A8C4001DA5B049256EA8001A9379.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
64.土地の瑕疵担保責任による高知県の事例 名前:民法570条 日付:10月21日(日) 10時1分
以下引用
ダイオキシン汚染土壌の土壌調査と汚染土壌の処理にかかった費用について
http://www.pref.kochi.jp/~toseibi/dioxin/chotei/chotei.htm
ダイオキシン汚染土壌の処理について、平成15年5月19日に成立した調停に基づき、土地の売り主から、紛争解決金として金3000万円を県に支払っていただきました。
1.処理費用の問題
ダイオキシンに汚染された土壌の処理は平成13年6月12日をもって完了しましたが、このために要した土壌調査や汚染土壌の処理費用はどうするのかが問題として残りました。
2.売り主への支払い請求
この土地は、連続立体交差事業で立ち退きを余儀なくされる高齢者の方々などを受け入れるために、県営住宅を建設する目的で買収したものですが、ダイオキシンの汚染がなければこれらの処理費用等は不用になるものでした。
そこで県は、土地の売り主に対して土壌調査費や汚染土壌の処理費用等を損害賠償として支払うよう求めることとしました。
3.相手方との交渉方針
当初、県は売り主に支払いの請求を何度もしてきましたが、売り主から任意交渉には応じられないとの返事が繰り返し返ってきましたので、裁判所で解決することにしました。
ツヅク↓
http://www.pref.kochi.jp/~toseibi/dioxin/chotei/chotei.htm
--------------------------------------------------------------------------------
62.「土壌汚染対策法」に基づく指定支援法人 返信 引用 名前:土壌汚染対策基金16億円余っています 日付:10月19日(金)
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
http://www.jeas.or.jp/dojo/index.html
土壌汚染対策法に基づき実施する土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置についてのご質問・ご相談
http://www.jeas.or.jp/dojo/form/form.php
土壌汚染対策基金の助成交付に係るご相談
http://www.jeas.or.jp/dojo/kikin_jyosei.html
土壌汚染対策基金について
http://www.jeas.or.jp/dojo/kikin_gaiyo.html
土壌汚染対策基金(助成事業交付実績なし)
16億円の基金が余っています。
http://www.jeas.or.jp/disc/pdf18/18ksk7.pdf
http://www.jeas.or.jp/activ/soil.html
-------------------------------------------------------------------------------
60.ダイオキシン類対策特別措置法 名前:対策地域 日付:10月18日(木) 19時45分
(ダイオキシン類土壌汚染対策計画)
第三十一条 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)を定めなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html
--------------------------------------------------------------------------------

58.フオーラム・小鳥か丘団地土壌汚染問題 転載 名前:ネットサーファー 日付:9月30日(日) 0時53分
「小鳥が丘団地で何が起きた!」の転載
http://blog.goo.ne.jp/goo1941-004/e/1e5c59a642994a9b5f37ee44c191d132
なにか、楽しい団地の物語かな?
小鳥の物語で無いようです。素敵な団地の地下に「豊島」の産廃があるようなことだそうです。
残土の基準を悪いように拡張されています。住宅団地の造成で、産廃まがいの残土が投入されたようです。今は、どこも同じようなことになりだしています。
ゴルフ場にも有ります。二重に利益を上げているのです。テレビ・新聞で放送される原発の高レベル放射性廃棄物も、危険ですし、低レベル物質は残土として、造成地、グランドなどに投入されだしています。
さて、、、今回、フオーラムガ開催されます。〈情報提供〉
日 時 2007・10・28 13:30〜16:30
場 所 岡山市・上道公民館 〈電話/086-297−2377 〉
内 容
「フオーラム・小鳥か丘団地土壌汚染問題」
講師・畑 明郎〈日本環境学会会長〉
司会・石井 亨 〈前・香川県議〉
主催 小鳥が丘団地救済協議会
http://blog.goo.ne.jp/goo1941-004/e/1e5c59a642994a9b5f37ee44c191d132
--------------------------------------------------------------------------------
48.岡山 両備 小鳥が丘土壌汚染リンク集 名前:国民の健康を守る 日付:8月29日(水) 22時46分
<当事者のページ>
小鳥が丘団地救済協議会
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
小鳥が丘団地救済協議会のブログ
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka
小鳥が丘救済協議会の掲示板
http://www3.ezbbs.net/35/kotorigaoka/
<支援者など>
日本共産党 岡山市議 竹永みつえ 個人質問 2005 年6 月議会(転記)
http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/36088471.html
小鳥が丘団地で土壌汚染! (小笠原賢二さんの活動日記)
http://www.ogaken.net/kotori.htm
小鳥が丘の土壌汚染について(下市このみ) 2004年10月30日
http://blog.livedoor.jp/simoitikonomi/archives/cat_386343.html
<マスコミなど>
いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染! 2007/03/23 (janjan)
http://www.janjan.jp/area/0703/0703220137/1.php
有害物質:土壌から検出 小鳥が丘団地住民、公害調停を申請 /岡山(毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/okayama/news/20070711ddlk33040412000c.html
<その他>
身近な場所で起きてる汚染
http://schreiben.jugem.jp/?eid=99
いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!(ENVIROASIA)
http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J07032301J
--------------------------------------------------------------------------------
47.監査室 佐藤允彦室長 窪田新治主任監査役 桑原彰一郎 福間和興 名前:将を射んとせば、まず馬を射よ 日付:8月26日(日)
両備HD 監査室を新設 室長に佐藤氏
両備ホールディングス(岡山市)は、役員人事と組織改革を発表した。 両備グループ監査室を23日付で新設し、グループ48社の業績、改善、人材育成などの執行状況をチェックする。専務取締役から中国バス専務取締役に22日付で就いた佐藤允彦氏を室長に起用。主任監査役には元常務取締役の窪田新治氏、元常勤監査役の桑原彰一郎氏、分析統括監査役には元取締役の福間和興氏をあてた。 http://okanichi.co.jp/20070627124948.html
両備 佐藤允彦 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E4%B8%A1%E5%82%99%E3%80%80%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%85%81%E5%BD%A6&lr=
窪田新治の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E7%AA%AA%E7%94%B0%E6%96%B0%E6%B2%BB&lr=
福間和興の検索結果
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%e7%a6%8f%e9%96%93%e5%92%8c%e8%88%88

2009年10月18日
土地有効利用の土壌汚染情報検討会中間とりまとめ
土地の有効利用のための土壌汚染情報等に関する検討会中間とりまとめ
一部追加しています。



目 次
1.はじめに
2.土壌汚染関連情報の提供に係る現状と諸問題・取組
2.1 土壌汚染関連情報の提供に係る現状認識
2.1.1 土壌汚染関連情報の提供の現状
2.1.2 土壌汚染調査と情報収集
2.2 土壌汚染関連情報
2.2.1 人為的汚染
2.2.2 自然的原因による土壌の基準値超過
2.2.3 その他
2.3 土壌汚染関連情報の提供の目的と期待される効果
2.3.1 情報提供によるリスクの回避・低減
2.3.2 土壌汚染調査の効率化と標準化への貢献
2.3.3 土壌環境に係る土地の制度的管理
2.3.4 自治体の業務効率化
2.3.5 土壌汚染地に係る保険の普及
2.3.6 土壌汚染地の資産評価
2.4 国内における土壌汚染関連情報の提供に係る制度・取組
2.4.1 土壌汚染対策法
2.4.2 自治体の取組
2.4.3 その他
2.5 諸外国における土壌汚染関連情報の提供に係る制度・取組
2.5.1 アメリカにおける取組
2.5.2 ドイツにおける取組
3.事業所立地履歴マップ
3.1 マップの作成方法
3.1.1 作成手順概要
3.1.2 作成方法
3.1.3 収集データの種別
3.1.4 データの収集例
3.2 マップの表現方法
3.2.1 事業所立地履歴マップの表示種別
3.2.2 事業所立地履歴マップの表示方法についての考え方
3.3 事業所立地履歴マップの公開・活用
3.3.1 事業所立地履歴マップの全体像
3.3.2 マップの活用方法
3.3.2 事業所立地履歴マップを公開・活用する際の論点整理
4.自然由来重金属類分布マップ
4.1 マップの作成方法
4.1.1 マップ作成の目的
4.1.2 作成手順
4.1.3 作成方法
4.1.4 表現方法
4.2 マップの活用方法
4.2.1 マップの活用方法
4.2.2 自然由来重金属類分布マップの活用マニュアル(案)
4.2.3 自然由来重金属類分布マップ例(仮想案)
5.関係者等意見
5.1 検討会委員意見
5.2 ヒアリング結果
6.汚染された土地の有効利用促進等に向けた情報提供の方向性と課題
6.1 土壌汚染情報のデータベース化
6.1.1 人的活動に起因する土壌汚染データベース構築の方向性と課題
6.1.2 自然的原因による土壌の基準値超過に係るデータベースの構築の方向性と課題
6.2 土壌汚染の正確な知識の周知とリスクコミュニケーション
1 はじめに

我が国の限られた国土において、 土地は国民共通の財産といえるものであり、その適正かつ有効な利用を実現することが不可欠である。そのためには、土地を有効利用しようとする者が円滑に土地を取得し、利用を開始しやすくすることが必要である。
しかしながら、高度成長期を経て我が国の社会経済情勢が安定化する中で、産業構造の変化に伴う工場跡地の他用途利用
や、住商混在型のまちづくり、事業所等が相当程度点在する街なかの再開発等の増加が見られ、これらの局面で土壌汚染が判明し、しばしばトラブルとなった結果、当該土地の有効利用が阻害されるケースが生じている。
土壌汚染問題については、国民の健康保護を目的として、平成14 年5月に土壌汚染対策法が制定(翌年2月施行)され、また、土地取引市場においても、そのリスクが強く意識されるようになっていたことから、国土交通省では、平成14 年10 月に「宅地公共用地に関する土壌汚染対策研究会」を設置し、翌年6 月、土地取引の安全性と円滑化の確保を目的とした土地売買契約に当たっての留意事項や、土地建物取引業者の留意事項に関する基本的な事項等を体系的にとりまとめ、公表した。
しかしながら、土壌汚染の判明した土地については、依然として土地取引が忌避され、土地の有効利用や再開発、まちづくりにおいて支障が生じる事態になっている。この最大の要因として、国民や市場が土壌汚染問題について正しい認識を有しないことによる過剰な反応・対応が指摘されているところであり、それが土地所有者を汚染事実の公表について消極化させ、市場にそれらの情報が集積されない結果、さらに国民の過剰反応を促すという悪循環にあると思われる。
こうした問題意識を踏まえ、国土交通省において、土地取引の円滑化による土地の有効利用促進等の観点から、土壌汚染土地について現状と課題を整理し、具体的な方策につながる検討を行うことを目的として、平成20 年に「土壌汚染地における土地の有効利用等に関する研究会」が設置され、同年4月、土壌汚染地における土地の有効利用方策を検討する際の様々な課題等について、「中間とりまとめ」として整理が行われた。
その中で土壌汚染に関する情報の提供が、土壌汚染に対する国民の理解を改善し得るものであるとともに、それが根幹的な課題であることから、本年度は、土地の有効利用促進の観点からの土壌汚染に関する情報の提供のあり方に焦点を当て、特に土壌汚染に関連する情報のマッピングについて試作・検討することを目的として「土地の有効利用のための土壌汚染情報等に関する検討会」を設置し、4回の会合を開催した。
今般の「中間とりまとめ」はその成果であり、この種のマップを作成・公表することについての意義や課題、作成方法等を整理したものである。本年は土壌汚染対策法の改正が議論されており、その成立と政省令の整理の状況も考慮し、今後、自治体あるいは市場において積極的な情報提供を進める際の参考となることを期待する。
2.土壌汚染関連情報の提供についての現状と諸問題・取組
2.1 土壌汚染関連情報の提供に係る現状認識

2.1.1 土壌汚染関連情報の提供の現状
土壌汚染問題に対する一般的理解が不足していることから、我が国においては土壌汚染に関する情報は秘匿されがちであり、容易に公にはならず、一般社会では土壌汚染が特別なものだと認識されている。
その結果として、土壌汚染が報道等で取り上げられた場合、その汚染の程度が重篤なものでなくとも、世の中においては過剰に反応される傾向がある。
また、この風潮により土地所有者等は公表を拒みがちとなり、結果的に悪循環となっている。
しかしながら、我が国が火山国であることに由来する、重金属の自然含有レベルの高い土壌の存在や、過去の人為的活動により重金属等が河川などを通じて移動・濃縮した底泥などで構成されていることが多い臨海の埋立地の存在、水質汚濁防止法等公害対策が講じられる以前の工場等の跡地利用など、土壌汚染は決して特別なものではない。
それらの土地を健康リスクの観点から見た場合、多くは過剰反応するほどの大きなものでなく、合理的な対策により十分対応可能なレベルであると考えられる。
土壌汚染が社会問題化するのは、土壌汚染自体が比較的新しい概念であり、これまで通常存在するリスクの一つとして扱われなかった商習慣等の下で土地利用や土地取引が行われてきたことが背景にある。すなわち、対象とする物質が工場内等で取り扱われてきたことについて一般的には積極的にオープンにされていなかったにもかかわらず、近年土地利用や土地取引において急速にそれらの情報を求める局面が増加したためである。
前述したとおり、基本的な土壌汚染関連情報が不在又はアクセス困難であるため、マンション購入後に土壌汚染が発覚し問題となるケースや、再開発計画を着手後に見直さざるを得なくなるケース等の支障が生じている。
しかしながら、土壌汚染関連情報は、土壌汚染地の周辺住民や購入者にとっても利害関係を有するという意味では、土地の安全性に関する情報として公益的な側面を有するものであるため、広く共有されることが望ましい。
これを踏まえると、我が国でも、全国的な土壌汚染関連情報をデータベース化し、インターネット等によりその時点の状況を誰もが閲覧できる仕組が存在すれば、土地取引の円滑化や浄化措置の促進・早期化等に資することになるとも考えられる。
一方でこのようなデータベースの構築には様々な課題が存在するとともに、データ量も膨大となること等から、実現に相当の時間を要することが想定される。そこで、現実的に対応が可能と考えられる手法の一つとして、過去に工場が立地していた等の理由により、汚染されているおそれが高いサイトや地区を地図上に記載した「事業所立地履歴マップ」等を作成することが有効であると考えられる。
「事業所立地履歴マップ」等の作成・公表により土壌汚染関連情報の一部が世の中に浸透すれば、土壌汚染に関する情報を公開することに抵抗を感じにくい風土の醸成につながり、土地取引・土地利用における土壌汚染の存在を特別視しないで行えることが期待される。
結果として、比較的スムーズに土壌汚染情報データベースが世の中に受け入れられ、より効率的な土壌汚染への対応が可能になるものと考えられる。
ただし、こういったデータベースを構築・公表する場合、そもそも情報の入手手段が限られており、また、情報の正確性に細心の注意を図る必要があることから、引き続き、関係行政機関が連携し、情報の入手源や入手方法について検討するとともに、その情報の元となる調査の信頼性及び正確性をいかに担保するかという点や万が一公表した情報が誤っていた場合に、当該データベース作成者の責任の射程及び当該情報を利用した結果他者に危害を与えてしまった者の責任の射程についても併せて検討しておく必要がある。
なお、土壌汚染情報データベースの一類型として、浄化が完了したサイトに関し、当該サイトの土質や浄化が完了した旨を公表するようなデータベースを構築することも、土地取引の円滑化等に資すると考えられることから、こうした点についても検討する必要がある。

2.1.2 土壌汚染調査と情報収集
土壌汚染調査は、土壌が汚染されているかどうか、汚染されている場合にどの程度の汚染であるかを把握するために行われるものである。しかし、土地取引や対策計画立案など、調査実施主体が調査結果を使用する目的に応じて、調査の内容・手法や必要とする精度は異なる。
このため、法や条例に基づかない民間の自主的な土壌汚染調査は、法令に基づく調査に準拠して進められることが多いが、必ずしも統一された基準のもとに実施されているわけではない。一般的な土壌汚染調査のフローを図2.1.1 に示す。
地歴等調査(フェーズ?)は、土地利用履歴調査(登記簿、閉鎖謄本、古地図、空中写真等)、地形・地質に関する調査(ボーリングデータ、地形図等)、現地視察調査(周辺状況や対象地の現況を把握)などに基づき、土壌汚染のおそれの有無について定性的に判断する調査である。
我が国では、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)が土地取引時に作成されるエンジニアリングレポート(ER)のガイドラインを定め、その中で土壌汚染のフェーズ?調査手法を提案するなどの取組があるが、統一された土壌汚染調査仕様が規定されるに至っていない。
法令等に準じたフェーズ?調査を実施することによって、土壌汚染リスクが回避されるという一般認識が存在している。簡易なフェーズ?調査で土壌汚染の可能性が完全に否定される場合を除き、フェーズ?調査による評価が求められる傾向が強い。
地歴等調査(フェーズ?)
・既存資料調査
・現地踏査
・ヒアリング等調査
概況調査(フェーズ?)
・重金属等は表層部分での試料採取・試験
・VOCs は土壌ガス調査
・1,000 ?で1 地点調査
詳細調査(フェーズ?)
・ボーリング調査
・地下水調査
・ヒアリング等調査
・汚染範囲内100 ?で1 地点調査対策の策定と工事
モニタリング
・汚染の有無を判定
汚染の可能性のない場合は終了
汚染のない場合は終了
・汚染の平面的な広がりを調査
・汚染の範囲・深さ・程度を調査
・汚染の広がりを3 次元的に把握
・対策の必要性・範囲の設定
・汚染の可能性を調査
土壌汚染対策法に基づく汚染状況調査
(土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説)
・土壌含有量調査
・土壌溶出量調査
・土壌ガス調査
・汚染のおそれのあるエリアは100 ?で1 地点調査
図2.1.1 一般的な土壌汚染調査フロー
フェーズ?調査を実施する際には現地踏査やインタビュー、依頼者から提供される書類記録等のレビューの他に、公的機関が保有する環境情報を精査する。アメリカでは、汚染サイトや浄化中のサイト、埋立地や処分場、貯蔵タンク等の情報が法令等によって登録されており、フェーズ?調査の実施時にはこれらの情報を評価の材料としている。
一方、我が国でも同様の手法でフェーズ?調査が実施されているが、アメリカのような法令等がない。環境省と一部の自治体は、それぞれ土壌汚染対策法と条例が適用された土壌汚染地の調査・改善措置に関する情報を収集し、情報提供しているケースもあるが、これらの情報を制度的に集約する機関がないため、公的機関から多くの環境情報を得ることは困難である。
また、法や条例の適用を受けず、自主的に実施された調査や改善措置が、土壌汚染調査実施数の大半を占めているものの、それらに関する情報を共有できる仕組が構築されていないことも課題である。
土壌汚染に関して参照できる情報、資料の蓄積が少ないため、調査の案件毎に始めから調査を実施する必要が生じているのが現状である。
調査を実施して汚染が判明すると、対策の実施や公表を迫られ、企業の会計への影響やイメージの低下につながる事態をおそれて、調査を実施しないケースも存在する。土壌汚染に対する社会的な見方は変わりつつあるとはいえ、自主的な調査の結果の提供については、企業サイドも消極的となることが想定される中で、効果的な情報収集を図ることが重要である。
フェーズ?調査を実施する際には、住宅地図、不動産登記簿、土壌汚染に係る地域の基礎的情報(土地利用履歴、過去の地形図、漏出事故・汚染記録、潜在的汚染源の位置、地下水水質等の環境情報など)のほか、地方自治体や各省庁が所管する基礎的情報が活用される。
これらの情報は、未整備もしくは個別に収集・管理されているために、データ収集の非効率が生じており、アクセスしやすいように整備されることが望ましい。
土壌汚染に関する情報インフラが整備されることによる効果は、前述のとおりフェーズ?調査の品質確保や効率的な調査に資するものであり、生産性の向上にも結びつくものである。
そして、土地取引等に当たっての保険活用や担保評価に資する有用な情報となる。また、情報インフラが整備されることにより、土壌汚染地の譲渡等があった場合でも、次の管理者等が当該土地の情報を円滑に引き継ぐことができる。これにより土壌汚染による環境リスクの管理についても、次の管理者等へ承継できることとなる。
2.2 土壌汚染関連情報
2.2.1 人為的汚染
人為的な土壌汚染の代表的な発生原因としては、以下の5つである。
? 工場等で使用していた有害物質が、不適切な取扱いや老朽化等による施設、設備の破損により漏えい、流出、飛散して土壌に浸透するという、事業活動が原因の汚染
? 産業廃棄物が埋立処分された土地で発生するという、廃棄物が原因の汚染
? 事故や災害により施設、設備が故障、破損等することにより有害物質が漏えい、流出、飛散等して土壌に浸透するという、事故や災害が起因の汚染
? 土地造成により上記の汚染土壌を搬入したことが原因の汚染
? 土地造成により自然の土壌中に存在する自然由来の汚染を搬入したことが原因の汚染
上記の?、?については、土地利用履歴に関する情報が重要となる。立地した事業所の業種、使用化学物質、操業時期等が当該情報を構成する。
?については、同様に廃棄物処分場の立地履歴等が情報となる。
一方、?のケースの土壌汚染については、関連する情報の収集が困難である。事業所としての土地利用履歴が確認されないケースにおいて、造成盛土内から土壌汚染が検出されている事例も多い。
?については、過去に埋め立てられた臨海部の土地について、砒素などが含まれる河川や浅海域の底質の浚渫土砂等が埋め立てに使われていることが多いことから、基準値超過の可能性が指摘されている。また、臨海部以外の低・平地部の埋立造成地においても、持ち込まれた土が原因の基準値超過が見つかっている。
なお、浚渫された水底土砂による埋立地については、海洋汚染防止法の規定により、昭和48 年3月以降は、同法に基づく基準を満たした水底土砂とそうでない水底土砂を分けて埋め立て、後者については海水の流出防止措置や放流水の処理を講じることが義務付けられている。
また、土壌汚染は1 箇所にとどまるものではないため、隣接地を発生源とするもらい汚染の可能性がある。したがって、調査対象敷地のみならず、隣接地や周辺土地の利用履歴等についても、人為的汚染に係る情報として有用である。
2.2.2 自然的原因による土壌の基準値超過
自然に存在する岩石や地層に含まれる重金属が風化や水の流出に伴って拡散し、低・平地部に自然堆積した場合や、これらを含む河床や海底での堆積土砂などにより埋め立てられた場合であって、基準値を超過しているときは、自然的原因による土壌の基準値超過とみなされる。自然的原因の可能性のある物質として、砒素、鉛、フッ素、ホウ素、水銀、カドミウム、セレン、六価クロムなどがある。
自然的原因による土壌の基準値超過を判断することは技術的には不可能ではないが、人為的汚染と混在した場合にそれを区分することは相当の作業が必要となる。その区分を把握するためには、自然的原因による土壌の基準値超過は含有量が一定の範囲内にあり、広域で観測されて局在性がないなどの特色を持っていることから、広域的な視点からバックグラウンド濃度などのデータを収集して分布特性等を見て判断していくことが必要である。
こうした観点で、環境省や一部の自治体では、自然状態の土壌のレベルを把握するために、データの収集を始めている。
2.2.3 その他
上記の情報のほかに、土壌汚染の状況把握のためには、地盤の地層構成、有機物含有量、地下水面の位置など地下水に関する情報が、汚染の広がりを評価する場合には重要である。
また、土壌汚染が確認された土地について、土壌汚染対策法に基づく区域指定の有無、調査結果、対策の進捗状況なども収集し、一括整理することが望ましい。
2.3 土壌汚染関連情報の提供の目的と期待される効果
2.3.1 情報提供によるリスクの回避・低減

土壌汚染によるリスクについては、人の健康リスクが重要であることは言うまでもない。
しかしながら、土壌汚染地の取引に関連して、その資産価値に係るリスクも予測が困難であり、そのリスクが顕在化した場合の影響は大きい。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が土地価格を上回るケースもある。汚染を完全に除去しなければ、土地に残る土壌汚染の管理が必要となり、将来、想定外のコストが発生したり、将来売却する場合に想定以上の減価が生じる懸念もある。
さらに将来の法改正で、規制対象物質が増えたり、基準が強化され、予測できない大きな負担が生じる可能性がある。実際の土地取引においては、人の健康リスクよりも、むしろ資産価値に係るリスクが問題となることが多い。
行政が土壌汚染に関連して知り得る情報を提供することによって、国民や企業は土壌汚染によるリスクを特別なコストなしに概略把握することが可能となり、土地利用や土地取引を安心して行うことができる。
企業であれば、事業構想初期段階で、ER作成前の概略情報として活用することも可能である。すなわち、土壌汚染によるリスクを、効果的に回避・低減することができる可能性が高くなるものと期待される。
2.3.2 土壌汚染調査の効率化と標準化への貢献
土壌汚染対策法の規定に基づく調査は、環境大臣(地方環境事務所長)が指定する指定調査機関が実施することとされており、平成20 年12 月5 日現在、1,639 機関が指定されている。東京都等自治体の条例に基づく土壌汚染状況調査についても、原則として土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に実施させることが定められている。
ただし、指定調査機関の認定要件は届出による簡易な書面審査が中心であることに加え、土壌汚染対策法や条例が適用さ
れない調査では、土壌汚染の専門家以外でも調査の実施が可能なことから、調査結果の信頼性を問題視する意見もある。
2.1.2で述べたようにアメリカなどでは、汚染サイトや浄化中のサイト、埋立地や処分場、貯蔵タンク等の情報が法令等によって登録されており、フェーズ?調査の実施時にはこれらの情報を評価の材料としている。情報が提供されることによって、調査者が情報を収集整理するコストを低減できる。
加えて、最低限確認されるべき情報を調査発注者も容易に確認できるため、最低限の水準を満たさないような調査結果を排除し、上述のような問題点の解決に資するものと期待される。

2.3.3 土壌環境に係る土地の制度的管理
土壌汚染が発見された場合、そこに土地取引が絡む場合には、売り手側や買い手側の要望から実態として完全除去されることが多いが、土壌汚染対策法や条例では、すべてのケースについて完全な除去まで求めているわけではない。
当該敷地及び敷地以外の周辺環境において、人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれが顕在化していなければ、完全除去ではなく、土壌汚染が周辺環境に影響を及ぼさないように汚染拡散防止措置を実施することで足りる。そして、法や条例の適用対象とならない場合にも、この基本的な考え方は適用できる。
土壌汚染を残置することによって、土地所有者は土壌汚染リスクを将来にわたって適切に管理することが求められるが、経済合理的な対策を選択できる余地が広がることとなる。
掘削除去以外の対策により汚染が残存している場合、汚染土壌の継続的なリスク管理が必要となり、所有権の移転があれば、その役割は新しい所有者に適切に引き継がれなければならないが、個人レベルでは不安のあるところである。また、個人レベルで、土壌汚染の存在することによる土地資産の減価リスクの適切な判断が求められる。
これらの点においても、土壌汚染に関する情報の整備・提供というシステムは重要な役割を果たし得る。
2.3.4 自治体の業務効率化
特定の土地の土壌汚染に関する問い合わせに自治体が対応する際に参照可能な情報となるものであり、業務の効率化に資することが期待される。上記の土壌汚染土地の管理に加え、飲用井戸の管理体制の構築にも活用可能である。
また、都市計画や公共施設の計画において、初期の事業構想段階で環境情報、コスト要因を概略把握することも可能となり、事業進捗後の予期しない深刻なコストオーバーランのリスク回避に繋がるものと期待される。
2.3.5 土壌汚染に係る保険の普及
日本国内では、土壌汚染に関連した保険の普及が進んでいない。普及が進まない最大の理由は、保険料の高さと保険引受条件の厳しさにあるようである。仮に数を集めたところで発生要件の規則性が見いだせない(=大数の法則が成立しない)からこそ保険料が高くなり、加えて、逆選択(土壌汚染のリスクを抱えているのが明確な人ほど保険に入ろうとする)が生じ、最悪の場合モラルハザードにつながるため、保険の利用が進まないという側面がある。
そして、保険の利用が進まないために、大数の法則の適用が困難となり、結果として保険料が高くなり、引受条件が厳しくなるという悪循環が生じている。さらに、保険料に加えて、保険引受のための高額の調査費用も被保険者において負担することが一般的となっており、このことも保険が利用されていない一因となっている。
リスクを定量化するためのデータの蓄積は、保険商品の開発にとって重要である。土壌汚染リスクに関する情報が提供・整備されることにより正しい理解が進むことになるであろうことから、保険市場の創出に繋がる可能性もあるものと考えられる。

2.3.6 土壌汚染地の資産評価
資産除去債務の導入に伴い、融資や企業買収に際しての調査や、企業自らの資産評価を目的として、企業所有不動産の土壌汚染に係る状況を概略把握するニーズは増すものと想定される。土壌汚染に係るデータベース構築は、土壌汚染地の資産評価を必要とするシステムが適切に運用されるための前提条件ともなり得るものであり、概略情報を把握する目的で重要
な役割を果たすものと期待される。
2.4 国内における土壌汚染関連情報の提供に係る制度・取組
2.4.1 土壌汚染対策法
土壌が有害物質により汚染されると、汚染土壌の直接摂取や、汚染土壌から有害物質が溶出した地下水の飲用等により人の健康に影響を及ぼすおそれがある。汚染原因者等の責任の明確化と土壌汚染による健康被害の防止が求められる中、土壌汚染対策の法的な拠り所として、平成15 年に土壌汚染対策法が施行された。
同法のもとでは、次のとおり、特定の有害物質を取り扱った工場や事業所の敷地であった土地の所有者に対し、土壌汚染の調査とその結果の報告が義務づけられている。しかし、土壌汚染対策法は、民間の事業者が自主的に行った調査結果の届け出を義務付けていない。
【土壌汚染対策法に基づく調査の概要】
(目的) 国民の健康保護
(対象物質) 特定有害物質(重金属、揮発性有機化合物等25 項目)
(対象:調査の契機)
? 使用が廃止された「特定有害物質の製造、使用または処理をする水質汚濁防止法の特定施設」に係る工場・事業所の敷地であった土地
? 都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると認める土地
2.4.2 自治体の取組
土壌汚染対策法が平成15 年2 月に施行されて以後、多くの自治体で条例や要綱等が制定・改正され、その中に土壌汚染に関する調査・対策の実施義務や届出措置が盛り込まれた。
また、独自に条例において、土壌汚染調査に関して、より厳格な規定を設けている自治体もある。例えば、東京都は、環境確保条例において土壌汚染に関する規定を設け、3000 ?以上の土地の改変を行う場合又は有害物質取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合、調査を実施し報告することを義務付けている。しかし、土壌汚染の自主調査結果については、汚染が確認された場合の届け出を義務付けた上で公開するところ(三重県等)、できるだけ届け出るよう指導するところ(名古屋市等)、そもそも届け出を義務付けていないところなど、自治体によって取扱いが異なっている。
2.4.3 その他
(1)土地利用マップの公開・頒布
大阪市では土地利用現況の情報をマッピングして頒布するとともに、図2.4.1 に示すようにインターネットを通じて無償公開している。当該情報は、各土地利用を土壌汚染リスクと関連付けて読み取り、理解した場合には、土壌汚染リスクを示すマップとして機能するものと考えられる。
土地利用状況 一戸建て住宅 長屋住宅 共同住宅 販売商業施設 業務施設 文教施設
医療厚生施設 遊興・娯楽・サービス施設 宿泊施設 工業施設 供給施設 運輸通信施設
官公署施設 その他施設 公園・緑地・お墓 建物のない土地
【出典】大阪市土地利用現況情報提供インターネットサービス

図2.4.1 事業所位置情報の提供例
(2)自然的原因による土壌の基準値超過に係る情報提供の取組
自然的原因による土壌の基準値超過については、種々の資料もあり、データがあれば正確な判断と基準設定も可能であると考えられる。例えば、鉱床地帯・その周辺などの鉱染地帯や変質岩帯の地域から道路工事等により発生し得る基準値超過土壌については、広域地質図、一部の地域の鉱染マップ、採石資源分布図を使って類推できる。一方、都市部の土壌を考えると、本来の自然的原因による基準値超過土壌と、過去の人為(不特定多数の人為を含む。)に起因する汚染者特定不可能な汚染土壌などが混在しており、汚染者負担の観点からは慎重な判断が求められる。
前述のとおり、自然的原因による基準値超過土壌の判断基準については、さらなる科学的データの蓄積・公開が重要である。こうした視点で、地質情報、自然起源汚染情報、人為汚染情報などの全国規模の各種地圏情報をGIS 化して情報提供するシステムである「地圏環境インフォマティクス」の構築が東北大学を中心に進められている。この中では、日本の重金属バックグラウンドの把握、地域によるバックグラウンドの差異の把握方法の開発、地質と環境因子との関連性の把握と、これらを共通のプラットフォームで把握する取組が進められている。
(3)各種ハザードマップの作成・公表
土壌汚染に関する情報ではないが、同様の安全に係るリスク情報として、自治体では、様々なハザードマップを整備、公表している。国土地理院が整備するハザードマップポータルサイトによれば、洪水、内水、高潮、津波、土砂災害、火山、そして地震防災に関するハザードマップが整備、公表されている。
洪水ハザードマップを例にとれば、全国で878 の市町村が印刷物の配布等により公表しており、社会的な認知が進んでいる。
2.5 諸外国における土壌汚染関連情報の提供に係る制度・取組
2.5.1 アメリカにおける取組

アメリカでは、土壌汚染情報は土地の安全性に係る公益的な情報と位置づけられ、多くの州が自ら情報を収集し、届け出や問い合わせがあった情報を元にして、土壌汚染情報のデータベースを作成し、ウェブサイトでの一般公開を行っている。
(1)ニューヨーク市
ニューヨーク市のブラウンフィールド問題への取組の一つとして、次の目的で「潜在的なブラウンフィールドを把握するための過去からの土地利用のテータベースの作成」が掲げられる。
・ 潜在的でかつ優先的な取組が必要なブラウンフィールドを見つけること
・ 地区毎のブラウンフィールドの再開発計画への基本的な情報を提供すること
・ すべての土壌汚染地の浄化と再利用活動の目標を明確にすること
データベースは、以下の2つの方法で作成されている。
・ 各種情報の収集(環境関連の発行物・データベース、歴史的な地図、電話帳、財務記録などからの情報収集)
・ 年毎のブラウンフィールド関連環境アセスメントへの要望についての問い合わせ
(2)オクラホマ州
社会環境の保全のためにブラウンフィールドの制度的管理が重要であるとの認識の下に、オクラホマ州環境局では、ブラウンフィールドを含めた土地利用の管理に向けて法制度を整備している。
土地利用管理の具体的な内容として、ブラウンフィールドの制度的管理についてのデータベースをくまなく蓄積している。
(3)マサチューセッツ州
マサチューセッツ州では、全米でもいち早く土壌汚染の制度的管理手法を導入している。AUL(Activity and Use Limitations)と呼ばれている活動用途制限を設けている。このAULは、現在及び将来の土地所有者に対してその土地で許容される活動や利用が示されており、許容されていない用途に変更する場合は、新しい用途に応じたリスクの評価と追加的な浄化
が求められる。
用途制限されている土地のAUL に係る情報は、州環境保護局のほかに自治体と郡不動産登記所で管理しており、この土地の再開発や土地取引に際しては、環境通知書によって土壌汚染の扱いが確認されている。
(4)カリフォルニア州
カリフォルニア州毒物管理局(DISC)では、すべての浄化修復活動を長期間管理する方針であり、以下の事項について実施している。
浄化修復用地の用途制限については、いろいろなメディアを用いて、情報を公表しており、もし、用途制限をする必要がないレベルまで浄化修復された場合は、用地リストから除外し、逆に用途に見合ったレベルまで浄化修復されていない場合は、必要なレベルまでの浄化修復を行う財政的な裏付けを要求する。
また、浄化修復活動が完了していない場合は、継続的に浄化修復活動を行っているかどうか定期的に検査する。
(5)ルイジアナ州
ルイジアナ州環境管理局(DEQ)では、用途制限のある自主的な浄化修復活動については、インターネット上で公表できるデータベースにより追跡的に監視している。
このデータベースでは、当該サイトの住所、用途制限、過去からの土地所有者、用途の履歴とともに危険物取扱いの有無の情報が、土地所有者からの届出に基づき登録されており、DEQ の承認が無ければデータベースから除外できない。
また、正確な情報が登録されていない場合は、当該サイトの取引契約を買い手側が解約できる根拠ともなる。
(6)ウースター市
ウースター市においては、プロジェクトに応じて様々なスキームでブラウンフィールド再生に取り組んでいる。その一つとして、2002 年から市役所の技術サービス部門を中心に、ブラウンフィールド再開発データベース構想としてデータベースの整備が行われている。
データベースは図2.5.1 のような3つの段階に分けて構築された。ウースター市役所は、2005 年までに200 以上のブラウンフィールド・サイトを確認している。これらのブラウンフィールド情報のデータベース構築によって、市役所は、より強固な情報基盤を持つことが可能となり、計画立案の過程において的確な意思決定が行えるようになると考えている。
2.5.2 ドイツにおける取組
ドイツにおいては、土壌汚染が存在するために開発がストップしているサイトに関する情報のみならず、産業跡地である等の理由により土壌汚染が存在するおそれがあるサイトに関する情報も収集し、地図上に落とし込んで公表している。
ドイツにおいては、都市計画決定の権限や土壌汚染地の浄化修復についての自治体の役割は極めて大きい。このため、土地利用計画の安定性を担保するためにも、土壌汚染情報の収集は重要となっている。土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動しているため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしている。
具体的には、自治体レベルで土壌汚染の可能性のあるサイトを把握して土壌汚染情報をマップに落として公表しており、また、土壌汚染に関する統計データも自治体から、州、連邦政府へと段階的に上げられて整備され、公表されている。
統計によれば、ドイツにおいては、ブラウンフィールドは最終処分場跡地と産業跡地という広い意味で用いられている。
【統計データにおける「土壌汚染」の分類】
・ ブラウンフィールドが疑われるサイト
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち旧堆積場
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち産業跡地
・ ブラウンフィールド
・ 浄化完了サイト
・ リスク評価完了サイト
・ 浄化中サイト
・ モニタリング中サイト
第一段階(基本的な情報を収集してGIS化する)
・情報収集(州政府・自治体・その他の情報源) ・データベースの構築
・データベースをGI Sへ移行・サイトプロフィールの設計
・データの分析・維持・更新手順の設計
第二段階(サイトの開発可能性を指標化)
・技術的なブラウンフィールドの定義・格付けの指標を検討
・時間軸による分析・詳細なケース・スタディを実行
・調査された補助金・パートナーシップ・イニシアチブ
第三段階(再開発の可能性を詳細に調査)
・土地利用分析・情報資源を再生プロジェクトと結びつける
・環境面の課題を評価・再開発の可能性を決定
・開発を誘引・再開発可能なサイトを突き止める

図2.5.1 ウースター市のGIS を用いたブラウンフィールド情報の整理と評価


3.事業所立地履歴マップ
前述したとおり、現時点において、自主調査結果など直接的な土壌汚染情報を全国網羅的に収集・整理することは極めて困難であるため、フェーズ?調査の一過程でもある事業所立地履歴をマッピングすることについて検討・整理した。なお、事業所立地履歴マップは、土壌汚染の可能性を示唆する情報であり、土壌汚染そのものの状況を示すものではない。
3.1 マップの作成方法
3.1.1 作成手順概要
マップの作成手順の概要を下のフローに示す。
基図の用意 現状の立地事業所 リストの作成 廃止事業所のリストへの追加 住所から緯度経度の取得
重複データの整理等
● 自治体が把握する届出施設
【水濁法(下水道法)特定事業場、PRTR届出施設、廃棄物処理業者等】
基図上へのプロット プロット位置の調整 作図
● 取得した緯経度は、街区レベルのデータであり、街区中心に位置するため、各敷地にデータを移動調整する。
● 住宅地図とリストに不整合がある場合は、Web情報などを活用して確認する。土壌汚染対策法 指定区域のリスト化

図3.1.1 マップ作成手順フロー
3.1.2 作成方法
(1)作成範囲

市町村単位で作成するものとする。人的活動が土壌環境に与える影響可能性を示すマップであるため、原則として市街地を対象とする。
(2)対象物質
「土壌汚染」状況は千差万別であり、サイト毎に最適な調査・対策方法を検討し、実施していくことが重要である。また、「土壌汚染対策法」が対象とする土壌汚染は、特定有害物質25 項目(鉛、砒素など重金属等14 項目 、及びトリクロロエチレンなど揮発性有機化合物11 項目)であるが、その他の規制物質や規制はされていなくとも土地利用の障害となり得る物質もあり、注意が必要である。
ガソリン、重油、潤滑油、灯油等の油分、ダイオキシン類、その他の化学物質(条例等において特に規制されている物質、臭気の強い物質及び色のある物質等)、要監視項目(22 項目)等の規制対象候補の物質などが調査対象となり得る。土地取引に際しての調査では、購入用途が住宅系である場合、履歴にかかわらず「特定有害物質(農薬類を除く)」「油分」「ダイオキシン類」を調査対象とするケースが多い。
不動産鑑定評価基準等を踏まえて策定された(社)日本不動産鑑定協会の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」では、「特定有害物質を中心に各自冶体の条例等及びダイオキシン類対策特別措置法において対象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば価格形成に大きな影響があるものとする。」とし、法令等による調査義務がないことのみで土壌汚染が無いとはできないとしている。
したがって、土壌汚染対策法の対象とする特定有害物質26 項目に限定せず、広く影響可能性を把握することとする。特定有害物質以外の人の健康や資産価値に対するリスク要因となる物質も念頭に置き、マップ作成のための事業所情報等を収集、整理する。
(3)基図の用意
基図としては、自治体が庁内で使用するGIS地図データの都市計画基図(1/2500 データ)を活用する。
(4)データ収集
【事業所データ】
土壌環境に影響を及ぼすおそれのある事業所のデータを収集・整理の対象とし、公表されている次のデータを活用するものとする。
? 水質汚濁防止法(下水道法)に係る特定事業場(ただし、し尿処理施設と指定浄化槽は含まない)
? PRTR届出施設
? 廃棄物処理・運搬業(一般廃棄物は廃棄物処理業のみ)
? 消防法に係る届出給油施設
? 日本工場通覧、工場名鑑、事業所リスト
【土壌汚染調査結果、措置状況データ】
土壌汚染対策法に基づく指定区域や調査猶予地についての情報、さらには届け出のあった土壌汚染調査結果及び措置の状況について、随時整理・更新する。GISシステムを活用することによって、マップ上の位置情報と詳細な調査結果を関連付けることも可能である。※
※ 自治体が庁内での使用を前提に、包括的な情報管理を目的として非公表のデータ(例えば措置対策が終了し指定区域が解除された土地に関する情報)をマップに表示することも可能である。しかしながら、この場合、当該マップについての情報公開請求への対応に留意しておくことが重要である。
なお、収集したデータについては、可能な限り実態と乖離しないように定期的に更新することが望ましい。異なる部局が管理するデータ更新状況を集約する体制の構築は、マップ情報の効率的な更新に資するものである。
3.1.3 収集データの種別
? 水質汚濁防止法(下水道法)に係る特定事業場
自治体が把握する水質汚濁防止法(下水道法)に係る特定事業場を整理する。特定事業場は、現状に加え、過去の立地状況も調査する。
特定事業場に関する情報としては、特定施設番号、特定事業場名、届出者、住所、放流先、排水量、有害物質排出の有無などのデータが、河川等の公共用水域の水質を管理する自治体の担当課に届け出られており、利用可能である。
水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するものである。したがって、公共用水域への排出水のない施設は規制の対象とならない。また、環境省中央環境審議会土壌農薬部会第3回土壌制度小委員会によると、有害物質使用特定施設以外で194件の土壌汚染が顕在化したとしている。これらを把握するためには、他の情報源からデータを入手整理する必要がある。
なお、ここでは、し尿処理施設(特定施設番号72)と指定浄化槽については土壌汚染と直接の可能性が小さいことから整理対象外とした。
また、特定有害物質の使用が届けられていない事業場を図示するかの議論はあるが、有害物質使用特定施設以外においても土壌汚染が顕在化していることを踏まえ、表示する方針とする。
? PRTR届出施設
PRTR届出制度は、下記の23業種、354物質が対象となる。データベースが提供されており、これを活用することができる。ただし、従業員数が21人未満の事業所は対象とならない。
なお、PRTR届出が制度化されてから年数も浅い(法律制定は平成11年7月)ため、現状データの整理のみとする。
個別事業所のPRTRに関する情報(化学物質排出把握管理促進法第11条に基づき開示するファイル記録事項)は、環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/kaiji/index.html)からダウンロード可能である。企業名、事業所名、住所、産業分類、排出物質、排出量などのデータを入手することができる。
【有害物質使用特定施設】
有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設のことをいう。水質汚濁防止法は、工場等から排出される水の排水及び地下に浸透する水の浸透を規制する法律であり、工場排水が川や海などの公共用水域に排出される場合に適用される。公共下水道が普及し、工場排水の排出先が下水道となる場合は、下水道法が適用される。下水道法でも水質汚濁防止法上の特定施設をそのまま規制対象の施設として規定されている。
土壌汚染対策法は、有害物質使用特定施設が廃止された場合は、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、 その結果を都道府県知事に報告しなければならないと規定している。
土壌汚染対策法で規制されていない物質について整理し、マップに表現することが適切であるかが論点となる。PRTR制度は環境への排出を把握するための制度であり、人の健康を対象とした土壌環境対策法とは法の趣旨が異なる。しかし、土地取引という視点では、資産価値の低減に繋がる物質の存在は表現する方針とする。
? 廃棄物処理・運搬業
自治体が把握する一般廃棄物処理業許可業者(ごみ処分業に限る)、及び産廃事業所の立地を整理する。情報は、業者名、所在地、区分(処理業、収集運搬業、処分業の区分)から構成される。
し尿処理運搬業などは、土壌汚染と直接の可能性が小さいと考えられるため、除外することが適切であると考えられる。PRTR届出制度の対象と同様に、一般廃棄物処理業は、ごみ処分業に限る。
なお、警察等が把握する廃棄物の投棄箇所に関するデータなども、それが明確なものであれば、自治体の判断で収集整理することができる。
? 消防法に係る届出給油施設
給油施設を把握するために消防法に係る届出施設リストを活用する。データは、自治体の消防担当が管理している。
? 工場名鑑、事業所リスト
戦後発行されている工場名鑑、商工名鑑、事業所リストに基づき、工場、事業場の位置、業種などのデータを、過去に遡り収集、整理する。日本工場通覧は従業員数が10人以上の製造業を掲載しており、1931年以降1997年までほぼ毎年発行されており、国会図書館で閲覧できる(図3.1.2 参照)。
工場名鑑は自治体単位で作成されている場合があり、一定以上の規模の工場を掲載している(図3.1.3 参照)。しかしながら、整理した事業所の位置関係を確認するための資料として活用する住宅地図については1970年より前のデータが入手困難となっている市街地も多いので、それ以前の正確な場所の特定に困難を生じる場合がある。
【PRTR届出制度】
「化学物質排出把握管理促進法」にて定義されている第一種指定化学物質(揮発性炭化水素、有機塩素系化合物、農薬、金属化合物、オゾン層破壊物質、アスベスト等の計354 物質)を使用する以下の対象23 業種の中で、従業員数が21 人以上で、対象化学物質の年間取扱量が1トン以上(カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ダイオキシン類、砒素及びその無機化合物、ベンゼン等、12 の特定第一種指定化学物質は0.5 トン以上)となる事業所は、環境への排出量(大気、公共水域、土壌)及び廃棄物や下水に含まれて移動する量を届け出ることが義務付けられている。
・金属鉱業 ・原油・天然ガス鉱業 ・製造業 ・電気業
・ガス業 ・下水道業 ・熱供給業 ・鉄道業
・倉庫業 ・石油卸売業 ・鉄スクラップ卸売業 ・自動車卸売業
・燃料小売業 ・洗濯業 ・写真業 ・自動車整備業
・機械修理業 ・商品検査業 ・計量証明業(一般計量証明業を除く。)
・一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る) ・産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処理業含む。)
・高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。) ・自然科学研究所

図3.1.2 日本工場通覧(1992 年)より抜粋

図3.1.3 千葉県工場名鑑平成15 年度版より抜粋
整理した事業所データの関係を以下の図に示す。

3.1.4 データの収集例
産業立地の見られる都市部の自治体として、札幌市西区と市川市を対象に、前記のデータ収集を試行した。次表に整理されたデータ数を示す。

上記には今回の資料調査で廃止が確認された事業所(市川市83 事業所、札幌市125 事業所)を含む。
?有害物質使用
特定事業場
日本工場通覧、工場名鑑、
事業所リスト
水濁法(下水道法)特定事業場
【し尿処理施設と指定浄化槽を除く】
消防法届出給油施設
PRTR 届出施設
廃棄物処理・運搬業
(産業廃棄物処理、運搬業、一般廃棄物処理業)
【一般廃棄物収集・運搬業を除く】
3.2 マップの表現方法
3.2.1 事業所立地履歴マップの表示種別
データの表示については、次の表示方法が考えられる。
1)事業所の立地履歴をシンボルで表示
2)事業所立地履歴のシンボルに加え、事業所の立地街区を網掛けで表示
3)事業所立地履歴のシンボルに加え、事業所の立地したメッシュを表示
4)事業所の立地街区を網掛けで表示
5)事業所の立地したメッシュを表示
3.2.2 事業所立地履歴マップの表示方法についての考え方
○ マップには土壌汚染対策法の指定区域を示すものとする。条例により土壌汚染に係る区域が指定され公開される場合には、当該土地についても表示する。なお、土壌汚染対策法第3 条第1項但書で調査が猶予されている土地、及び調査対策済みの事業所については、個別事業所の情報開示に係る自治体ごとのスタンスに応じて記載の可否を判断することになると思われる。
また、過去に自治体への報告があった自主調査結果については、原則として公定法(平成3年環境庁告示第46 号別表の測定方法の欄に掲げる方法をいう。)に基づいて行われた調査の結果であって、公開されているものに限り表示することが望まし
く、それ以外の情報の表示については自治体の判断によるものと考えられる。
なお、中央環境審議会「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)」(平成20 年12月)においては、「土壌汚染に関する情報について、埋没させることなく、関係者が容易に入手し、適切に活用することができ、適切に承継される仕組みが必要である。
また、対策が行われて解除がなされたという情報や調査の結果土壌汚染が発見されなかったという情報も含め、地方公共団体において、土壌汚染の状況を把握し、汚染原因の解明、汚染状況の履歴調査等に有効に活用すべきである。」としている。
○ 使用(保管)物質の届出を行っている事業場が少ないため、届出使用(保管)物質を示すマップの表示は行わない。ただし、十分な注意書きを付す等により、有害物質の使用(保管)届出記録の無い施設について、業種から潜在的汚染を想定し表示する方法も代替案として考えられる。
○ 事業所については、マップの対象物質を直接的に使用する業種や、間接的に使用する業種がある。表3.2.1 は、自治体が把握する業種別の土壌汚染調査基準値超過事例数を整理したものである。
このように、業種によって汚染原因者となる可能性は大きく異なるが、環境省中央環境審議会土壌農薬部会第3回土壌制度小委員会によると、直接的に使用する業種だけ汚染原因者となっているわけではない。
したがって、フェーズ1調査の支援というマップの位置づけを踏まえ、製造業は全ての業種を表示する方針とし、リスクの大小に応じて異なる表示方法を用いる。(本調査では、製造業について、総事業所数に対する累積基準超過件数が0.1%未満の食料品製造業等を、土壌汚染リスクは小さいと評価した。)
同様に、水質汚濁防止法の施行以前に事業所が立地した土地は、土壌汚染リスクが高くなると考えられるので異なる表示をする。?
○ 注意喚起を目的として、事業所が存在する区域を網掛けして表示する場合の境界は、街区レベルを基本とするが、対象区域を碁盤目状にメッシュで区切り、その中に存在する事業所の数で色の濃淡を変えて表示することなども可能である。メッシュで表示する場合には、事業所立地履歴がある街区とは異なる周辺土地まで表示範囲となり得ることについて
使用上の配慮を要する。
○ GIS を活用してマップを作成することによって、事業所に関する様々な情報(事業所名、使用物質名と使用量、設立・廃止時期、事業所連絡先、関係条例の届出の有無と内容など)を付随データとして記録する。これらのデータは、アクセス権限があれば必要に応じて参照することができる。




3.3 事業所立地履歴マップの公開・活用
3.3.1 事業所立地履歴マップの全体像
事業所立地履歴マップ活用の方法や管理のあり方について、作成過程も含め、図3.3.1 に図示する。
3.3.2 マップの活用方法
事業所立地履歴マップについては、「2.3土壌汚染関連情報の提供の目的と期待される効果」で整理した事項を踏まえ、以下に示すような活用方法が考えられる。自治体の判断によっては、マップの公開は行わず、?に示す目的で、行政内部に限定して活用することも想定される。
? 行政による活用
・ 市民や事業者からの土地の土壌汚染に関する問い合わせに対応する際に参照可能な情報となるものであり、業務の効率化に資することが期待される。
・ 土壌汚染土地の管理、特に制度的管理を行う土地の情報の承継において重要な役割を担う。加えて、飲用井戸の管理体制の構築に活用できる。
・ 民間から提出された土壌調査報告書に対して、内容をチェックする際のサポート資料としての活用が想定される。
・ 都市計画や公共施設の計画において、初期の事業構想段階で環境情報、コスト要因を概略把握するために活用できる。
? 土地所有者による活用
・ 企業であれば、自社所有不動産の売却等に絡む事業構想初期段階で、ER作成前の概略情報として活用することも可能である。
? 不動産取得を検討する者による活用
・ 国民や企業は土壌汚染によるリスクを特別なコストなしに概略把握することが可能となり、土地利用や土地取引を安心して行うことができる。
? デベロッパー等による活用
・ 事業構想初期段階で、ER作成前の概略情報として活用することも可能である。
? 調査会社及び調査発注者による活用
・ 調査者が情報の収集整理を効率的に行うことができる。加えて最低限確認されるべき情報を調査発注者も容易に確認できるため、最低限の水準を満たさないような調査結果を排除し、調査結果の信頼性向上が期待される。
? 金融機関及び保険会社による活用
・ 資産価値評価の予備的な検討に活用されるものと期待する。
3.3.3 事業所立地履歴マップを公開・活用する際の論点整理
事業所立地履歴マップに関する論点は、大局的には
?「作成の是非」、
?「公開の是非」、
?「公開する場合のプロセス、留意点」に整理することができる。
以下、これらに係る内容について、想定される主要な論点を整理する。

?「作成の是非」
ア) マップ活用の可能性
マップの使用者と活用方法が適切に想定されるべきである。また、行政が作成する場合は、一部特定企業の商目的使用が、マップ活用の主用途となるべきではないと考える。
イ) 費用対効果
マップの精度向上は重要である。一方、特定の土地の取引は頻繁に行われるものではないにも関わらず、全体を網羅し情報の精度向上を図ると、マップ作成コストが増大する。マップ作成に適正な費用対効果の見通しが求められる。
ウ) 土壌汚染対策法改正の動きとの関連性
中央環境審議会「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)」(平成20 年12 月)は、「土壌汚染に関する情報について、埋没させることなく、関係者が容易に入手し、適切に活用することができ、適切に承継される仕組みが必要」としており、マップの作成、公開が有効となる。
?「公開の是非」
エ) 知らずに不動産を取得する事態の回避
事業所立地履歴マップを公開することは、土壌汚染リスクのあることを知らずに土地を購入する等の可能性の低減に資するものである。
オ) 代替物出現の可能性
マップの作成に当たって使用した情報は、届出給油施設等の一部の情報を除き、一般に公開されている。したがって、行政でなくとも、研究目的や営利目的で大学や企業が同様のマップを作成することは難しくない。(同じ論拠により、一般市民でも土壌汚染に係る情報を入手する意志さえあれば、マップはなくとも情報入手が可能。)
カ) 自治体の責任の範囲

マップに示された情報の不完全性あるいは誤記が原因となり、マップ活用者に損失が生じた場合について、作成者や公開者の責任の範囲について留意する必要がある。
キ) 資産価値への影響可能性
マップの公開が、不動産価格に対して影響を与える可能性は否定できない。マップを公開することによる資産価値への影響が社会的に認容できる範囲であることが求められる。(ただし、汚染土地の資産価値がリスクや対策費を織り込んだ値まで低下する状況については、その原因をマップの公開に帰するべきではなく、過剰な影響について論点とすべき。)
ク) 貸し渋りの可能性
マップを公開することによって、土壌汚染そのものを表すものと誤解された場合には、金融機関が不動産の担保価値を低く査定し、いわゆる貸し渋りのような状況が生じ得ることも否定できない。
ケ) 自主調査の公開と所有権移転
仮に調査時点で所有者が、自主調査を行った土地について、情報のマップ表示を許諾しても、別の者に当該土地の所有権が移転することもある。新しい所有者が情報の開示を認める保証はなく、自主調査の情報についてマップ表示する場合には、慎重に対応する必要がある。
?「公開する場合のプロセス、留意点」
コ) 公開のタイミングとリスクコミュニケーションの必要性
公開を前提とした場合、適切な体制と手順で公開することによって、負の影響を低減することも可能であると考えられる。マップの公開に当たって、行政は、いたずらに住民の不安を煽らないよう、土壌汚染のもたらす意味、リスク等を正確に説明することが必要。

事業所立地履歴
データベース
住宅地図
? 水質汚濁防止法(下水道法)特定事業場ただし、し尿処理施設と指定浄化槽含まず
? PRTR届出施設
? 廃棄物処理・運搬業(一般廃棄物は廃棄物処理業のみ)
? 消防法に係る届出給油施設
? 日本工場通覧、工場名鑑、事業所リスト事業所立地履歴マップ(網掛け表示)
事業所立地履歴マップ
(シンボル表示)
基図
● 土壌汚染の潜在的原因者となる事業所が立地する(した)エリアを網掛け表示
● 該当するエリアの表示方法
【1案】 街区を表示
【2案】 100メートルメッシュの碁盤目表示
● 事業所の立地履歴をシンボルで表示
● 土壌汚染対策法に基づく指定区域、調査済み土地、対策済み土地、調査猶予土地を表示
【一般への公開を想定】
● 不動産業者、不動産購入予定の一般市民による利用
◇ 不動産取引に際しての土壌汚染リスクの概略把握
● 土地所有者による利用
◇ 所有地の土地改変検討にあたっての状況把握
● 金融機関、保険会社による利用
【自治体が公開情報として管理】
● 年1回程度の定期的な更新
【行政内部の利用を想定】
● 土壌汚染担当部局による利用
◇ 一般からの特定の土地に関する問合せ対応
◇ 汚染土地(土壌)の管理、飲用井戸の規制
● 都市計画部局、建設関連部局等による利用
◇ 都市計画や事業計画を策定する上での概略の環境情報、コスト情報
◇ 土壌汚染リスクに応じた土地利用の推奨
【自治体が内部情報として管理】
● データベース更新時にマップも更新するシステムの構築
● 調査対策済み情報を反映
作図処理
作図処理
(位置情報取得)
土壌汚染調査、
対策実施状況
データベース
位置確認
土壌汚染対策法等に係る情報追加
? 土壌汚染対策法指定区域
? 調査猶予施設
? 自主調査結果届出施設
? 調査、対策済み施設
図3.3.1 マップの作成、管理、利用方法(案)
【期待される効果】
● 土壌汚染土地に関する情報管理、及び適正な都市計画、公共施設配置に向けた検討の効率化
● 公共事業コストの低減
● 完全掘削除去以外の対策と制度管理の普及
【期待される効果】
● 事業構想段階でのフィージビリティ検討の効率化
● 不適切なERの減少
● 不動産入札における逆選択の減少
● 安心感の創出
4.自然由来重金属類分布マップ
4.1 マップの作成方法
4.1.1 マップ作成の目的
自然由来重金属類分布マップは、地盤の中に自然に存在する重金属類の濃度等を基に、表層地質区分別に、今後の調査等において確認を必要とするレベルを表示したものである。
このマップ作成の目的は、地下水の適正な管理と土壌の移動の管理にあり、エリア内で情報がないままに地下水を利用し続けることを防止することや、自然由来の含有量が元々高い土壌が他のエリアに安易に移動してしまうことを防止することにある。
自然由来重金属類分布マップは、ここでは4つのランク区分で表示することとしているが、その土壌の重金属含有量の絶対値を示すものでない。
このマップを活用することにより、今後の土地改変や何らかの調査の機会を捉え、土壌を適正に管理をすることや、更なる情報の蓄積を促進しようというものである。
本マップは、上記の目的以外の、現状の土地利用、周辺住民、土地価格などに影響を与えることを意図するものではない。
以上のことを、土地所有者や住民に対して十分に周知するとともに、開発業者、建設業者等に対して土地改変等の機会を捉えて地歴調査や簡易な土壌分析を実施すること等を推奨するものである。
4.1.2 作成手順
自然由来重金属類分布マップの作成の手順を図4.1.1 に示す。

図4.1.1 自然由来重金属類分布マップ作成の手順
マップ作成の対象物質、対象区域設定
基図及び地質図の準備
対象物質に係る土壌調査データ収集
対象物質に係る地下水調査データ収集
対象物質に係る土壌調査データ整理・分析
対象物質に係る地下水調査データ整理
対象物質の含有量及び溶出量の基準の超過データ整理
対象物質の地下水基準の超過データ整理
基図及び地質図へ基準超過場所のプロット
基準超過物質に係るランク区分の考え方・基準の検討
自然由来重金属類分マップの作成
4.1.3 作成方法
(1)マップ作成の対象区域
自然由来重金属類分布マップを作成するエリアを設定する。自然界に存在する有害物質については、広域的な視野から状況を把握する必要があるため、行政区域等を参考に可能な限り広域エリアを対象区域として設定する。
(2)対象物質
土壌汚染対策法に基づく有害物質のうち、自然界に存在する物質として、砒素(As)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、セレン(Se)及びクロム(Cr)の重金属、及びふっ素(F)、ほう素(B)を対象とする。
(3)基図
基図は地形図及び地質図との重ね図を用いる。
地形図は、対象物質が地質構造と深く関係していることから地質図と重ね合わせの可能な1/5 万のスケールの国土地理院発行の数値地図を用いる。
地質図は、独立行政法人産業技術研究所地質調査総合センター作成の「20 万分の1 日本シームレス地質図」のデータが収納されている東北大学大学院環境科学研究科が作成した「地圏環境インフォマティクス(GENIUS)」を用いる。この地圏環境インフォマティクスは、地質情報、重金属等の各種地圏情報を全国規模でGIS 化して情報提供するシステムである。
また、国土交通省で土地分類調査として1/5 万表層地質図、土壌図等の基礎情報が整備されており、市町村レベルのエリアであればこれらの活用も可能である。

図4.1.2 基図(1/5 万地形図と地質図との重ね図)の例
地形図:国土地理院の数値地図50000(地図情報)
地質図:東北大学大学院環境科学研究科「地圏環境インフォマティクス(GENIUS)」
(4)データ収集
対象区域において、過去に実施された対象物質に係る土壌調査結果及び地下水調査結果のデータを収集する。(表4.1.1 及び表4.1.2 に例を示す。)
また、参考として、地域において対象物質に係るバックグラウンドレベルを表すと考えられている産業技術総合研究所地質調査総合センター発行の「日本の地球化学図」(2004 年)を用いる。
この資料では、砒素、カドミウム、鉛、水銀など有害物質を含む約50 元素について、日本全国の約3,000 試料(試料は河川堆積物、1 試料10km×10km)を用いて地球化学図(元素の濃度分布図)を作成しており、全国的な濃度分布が把握できる。(表4.1.3 に例を示す。)










(5)土壌調査データの整理及び分析
土壌調査データについては、土地改変の可能性の高い地下0〜3m の表層地質を対象範囲とし、地質図の表層地質区分別に土壌調査データを整理した上で、対象物質に係る含有量、溶出量の平均値と標準偏差、及びそれぞれの自然的原因による含有量の上限値の目安及び溶出量基準の超過頻度等について検討する。

なお、重金属類に係る基準超過については、自然的原因と人為的原因とに判別する必要があるが、判別するには十分な資料と検討が必要であることから、ここでは判別は行わない。これまでの検討資料等において、自然由来と考えられているデータを取り上げる。
(6)地下水調査データの整理
地下水調査結果から、地下水基準を超過している地点の濃度データを整理する。土壌汚染は地下水汚染の原因の一つとなっており、地下水汚染がある場合には近傍での土壌汚染の存在が疑われるが、地下水は複雑な地下の中を広い範囲で流動していることから、その汚染の原因を特定することは相当に困難である。
地下水汚染がある場合には周辺での土壌汚染のあるおそれがあることから、参考として地下水汚染の位置及び濃度をマップに表示することとする。
(7)基準超過地点のプロット図の作成
土壌汚染対策法の指定基準等と照らして、重金属類の自然的原因による含有量の上限値の目安及び溶出量基準の超過地点、地下水基準の超過地点をそれぞれ抽出して、基図にプロットする。
(8)自然由来重金属類のランク区分の考え方
基準超過の見られる対象物質について、表層地質別に自然由来重金属類のランク区分の考え方・基準について検討する。
例えば、砒素の場合、表層地質別にランク区分を行うために、
?全含有量の平均値、
?自然的原因による含有量の上限値の目安(39mg/kg)の超過率、
?溶出量基準の超過の有無、
?地下水基準の超過の有無、の4 つの指標を用いることとする。
4 つの指標について、表4.1.4 に示すように配点し、表層地質別にそのスコアを合計する。この配点については、砒素の全含有量の平均値を基本指標として、その他の指標について基準超過の有無等により加点する方式としており、リスク面を考慮している。

表4.1.4 砒素に係るランク区分に用いる指標とスコア
全含有量の指標
?平均値
?自然的原因による上限値の目安(39mg/kg)の超過率
?溶出量指定基準の超過の有無地下水基準超過の有無
砒素の場合、表層地層別のスコア合計値により、表4.1.5 に示すとおり区分する。

(9)自然由来重金属類分布マップの作成
自然由来重金属類分布マップの作成については、一般に土地改変の深さは地上から−3mまでの範囲が大部分であることから、深さ0〜3mの表層地質を対象とする。
対象区域の表層地質別に(8)に示す基準に基づいて検討を行い、マップを作成する。
4.1.4 表現方法
自然由来重金属類分布マップは、1/5 万地形図及び地質図の重ね図を用いて以下のように表現する。
? 自然由来重金属類分布マップにおいては、ランク区分別に表層地質を色分けする。
? 土壌調査地点や地下水調査地点をプロットし、また土壌環境基準や地下水基準を超過している場合や自然的原因による上限値の目安の値を超過している場合は、その地点を○印で表示することがマップをよりわかりやすくするため、このような表示を行うこととする。
? さらに、基準超過地点においては、含有量や溶出量、地下水濃度を数値で表示することが考えられる。

表4.1.6 自然由来重金属類分布マップの色区分の例
ランク区分 ランク区分の考え方
A 自然由来の含有量が高いレベルで予想され、かつ基準超過のリスクが考えられる地層エリア
B 自然由来の含有量が中程度に予想され、かつ基準超過のリスクが少し考えられる地層エリア
C 自然由来の含有量が低く、自然由来の上限値の目安の超過や基準超過が低い頻度で予想される地層エリア
表示なし 自然由来の上限値の目安の超過がほとんどないと予想される地層エリア
4.2 マップの活用方法
4.2.1 マップの活用方法
自然由来重金属類分布マップについては、以下に示すような活用方法が考えられる。
? 行政のサポート資料
・ 地域における土壌環境に係る潜在的なポテンシャルを把握することが可能である。
・ 市民や事業者に対する地域の土壌環境に関する情報提供や啓発に活用するとともに、市民等からの相談等にスムーズに対応することが可能となる。
・ 民間から提出された土壌調査報告書に対して、自然由来の基準超過かどうかの判断の際のサポート資料として活用することが考えられる。
例えば、以下のような要件に適合した場合には、自然由来と判断できる。
1)自然由来の基準超過の可能性のあるエリア内にあること
2)地歴調査の結果、対象物質を使用した経歴がないこと
3)対象物質の検出値が一定の範囲内にあること
? 土地所有者への情報提供による注意喚起
・ 土地所有者に自然由来重金属類分布マップに関する情報を提供することにより、土地所有者は自己所有地のある周辺地域一帯における土壌環境の状況を把握することが可能である。
・ 土地所有者は、あらかじめ所有地の自然由来重金属類の潜在可能性を把握できるため、リスクが比較的高いエリアでは土地改変や用地売却などの際に土壌環境についての留意が必要
である旨の認識を持つことができる。
・ このため、域外へ土壌の搬出を行う際には、リスク評価に応じて土壌調査を実施するなどの対応を行いやすくなる。もし、調査より自然由来の基準超過がみられる場合には、域外へ土壌をできるかぎり持ち出さないように敷地内で封じ込めなどの措置を行い、土壌の拡散や健康被害の発生を防止することにつなげることができる。
? デベロッパー・工事事業者への拡散防止に関する啓発
・ デベロッパーや工事事業者に対して、自然由来重金属類分布マップに関する情報を提供し、開発や工事を実施しようとする土地についての注意喚起を促すことができるため、工事の際の事前の対策や拡散防止に役立つ。
? 市民等への情報提供による理解の向上
市民や事業者等に自然由来重金属類分布マップに関する情報を提供することにより、市民等は地域一帯における自然由来の土壌環境の状況について把握し、より理解を深めることができる。
4.2.2 自然由来重金属類分布マップの活用マニュアル(案)
(1)行政サイドとしての活用
土地売買や土地改変の際に、開発事業者、調査業者や土地所有者から土壌調査についての事前相談を受けた場合や、提出された土壌調査報告書に対して、行政サイドとして以下に示すような手順で対応することが考えられる。
なお、以下に示す推奨、助言等の手続きは、法律の根拠を伴わない行政指導となる場合が多いことに留意する必要がある。
1)A又はBのエリア内にあって調査が行われていない場合
A又はBのエリア内にあって調査が行われていない場合は、自然由来重金属類分布マップ情報を提供するとともに、調査の目的によって追加の調査(例えば砒素が調査項目に入っていない場合)などの実施を推奨する。
→ 土地取引の際にバックグラウンド調査の実施を推奨する(人為汚染でなく自然由来であると証明した方がよい場合)
→ 工場管理などにおいて、土地改変や土量搬出の際にバックグラウンド調査の実施を推奨する
2)調査が実施され報告されてきた場合
土壌調査が実施され調査結果が報告されてきた場合に、行政サイドとしては図4.2.1 に示すフローで対応することが考えられる。
(2)各者への周知
行政サイドとして各者に対して広報誌、HPなどを使って周知していく。
? 開発事業者、調査業者、不動産業者及び土地所有者自然由来重金属類分布マップは、地盤に元来存在する重金属類について、表層の地質単位でのランク区分を表示したものである。このマップ作成の目的は、地下水の管理と土壌の移動管理にあり、エリア内で情報がないままに地下水を利用し続けることを防止することや、元々含有量が高い土壌が他のエリアに安易に移動してしまうことを防止することにある。
開発業者、調査業者及び土地所有者に対しては、上記の目的を理解していただいて、土地取引や土地改変の機会をとらえ、履歴調査やサンプリング分析等の実施と結果報告を行うことが望ましいことを助言していく。
また、土地取引の仲介を行う不動産業者に対しても、調査記録の有無等など土壌汚染に関する情報の収集を行うことが望ましいことを助言していく。
? 一般住民(土地売買や形質変更の予定のない土地所有者を含む)住民や土地所有者に対しては、自然的な土壌環境の状況に関する情報を提供して、認識や理解をより深めてもらい、エリア内で情報がないままに地下水を利用し続けることを防止す
ることや、元々含有量が高い土壌が他のエリアに安易に移動しないように防止していく。

図4.2.1 行政サイドでの活用・対応の手順(土壌調査が実施されている場合)
土壌調査が実施され、調査結果が報告されてきた場合
自然由来重金属類のランク区分がA又はBのエリア内
自然由来重金属類のランク区分がC又は無印のエリア内
含有量が自然的原因の上限値の目安の範囲内
含有量が自然的原因の上限値の目安の範囲を超過(明らかに大幅に超過)
過去に砒素等の使用履歴がなく、土地造成時に持ち込まれていないことを十分に調査している場合
溶出量基準の範囲内、かつ近傍に地下水汚染がない
ケース1
指示はなし(搬出土チェック)
ケース2
認識されない地下水使用の有無の精査と地下水汚染がある場合は詳細調査の実施を指示
溶出量基準を超過し、その地層で現れる範囲を超えており、かつ近傍に地下水汚染がある
過去に砒素等の使用履歴がなく、土地造成時に持ち込まれていないことを調査していない場合
ケース3
人為汚染がある場合はそのボーダーを明確にする調査の実施を誘導
自然由来かどうかの判断を求められた場合は、過去に砒素等の使用履歴がないこと、土地造成時に持ち込まれていないこ
とを再調査で確認することを指示(調査されている合でも再検討が妥当)
ケース4
再調査の結果、人為汚染がなければ、行政として地下水管理を実施するエリアとする
砒素は調査項目に入っていない、又は行われていてもCか無印の範囲内
特に砒素の使用履歴がないこと、土地造成時に持ち込まれていないことを調査で確認している
含有量が自然的原因の上限値の目安を超過
自然由来かどうかの判断を求められた場合は、過去に砒素等の使用履歴土地造成時に持ち込まれていないことをすることを指示(調査されている場合でも再検討が妥当)
ケース6
再調査の結果、人為汚染がなければ、行政として地下水管理を実施するエリアとする。
必要に応じて評価図を修正
ケース5
指示はなし
(溶出量値が極端な異常値でない限り)溶出量基準を超過し、その地層で現れる範囲を超えている使用履歴等の調査を指示
4.2.3 自然由来重金属類分布マップ例(仮想案)

【参考資料】

参考1.自然由来重金属類の概要と基準等
(1)自然由来重金属類とは
・ 自然的原因により基準超過の可能性のある有害物質として、砒素(As)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、セレン(Se)及びクロム(Cr)の重金属、及びふっ素(F)、ほう素(B)があり、温泉や鉱染帯地域、岩石中などに含まれて自然界に広く存在している。
・ 海域ではふっ素(F)及びほう素(B)が基準を超過して検出されやすいため、ふっ素(F)及びほう素(B)は海域では環境基準が適用されない。
・ 多くの都市部の浚渫土砂による埋立地では、鉛、砒素、ふっ素が基準を超過して検出されるケースがある。
・ 土壌汚染対策法では、第二種特定有害物質(砒素などの重金属とほう素、ふっ素)の自然由来の基準超過については対象外とされているため、人為的な汚染と識別する必要がある。
(2)特徴
・ 含有量が一定の範囲内である、溶出量も少ない場合が多い
・ 一般に広域で観測され、人為由来を示す局在性がない
・ 平面や深度調査でも同程度の濃度が観測される場合が多い
・ 調査地域の堆積環境と対象物質の因果関係が認められる
(3)自然由来重金属類の基準等
自然由来重金属類については自然的原因による含有量の上限値の目安や指定基準等がある。
・ 指定基準とは、土壌汚染対策法において土壌汚染がある土地として評価される指定区域の指定に係る基準であり、土壌溶出量基準と土壌含有量基準がある。土壌溶出量基準は環境基本法に基づく環境基準と同じ値である。
・ 第二種特定有害物質(重金属類)については土壌溶出量調査と土壌含有量調査を行う。

参考2.土壌溶出量基準に適合しない場合の判定基準
環境省「土壌汚染対策法の施行について(環水土第20 号、平成15 年2 月4 日)」における「(別紙1)土壌中の特定有害物質が自然的原因によるものかどうかの判定方法」において、自然地盤上に発見された基準超過であって、土壌溶出量基準に適合しない場合の判定基準として、以下の3 つの観点からの検討を行い、そのすべてについて以下の条件を満たすときは、
自然的原因によるものと判断することとしている。
(1)特定有害物質の種類等
自然地盤上に存在し、土壌溶出量基準に適合しない可能性のある特定有害物質は、砒素、鉛、ふっ素、ほう素、水銀、カドミウム、セレン、六価クロムの8 種類のいずれかとされ、土地の履歴、周辺の事例や地質的状況、海域との関係等を総合的に勘案し、次の事項を踏まえつつ判断する必要がある。
?)砒素、鉛、ふっ素及びほう素については、自然的原因により土壌溶出量基準に適合しない可能性が高いこと
?)溶出量基準の10 倍を超える場合は人為的原因である可能性が比較的高くなり、自然的原因であるかどうかの判断材料になり得ること(しかし、自然的原因である場合もあり得ることに留意が必要)
(2)特定有害物質の含有量の範囲等
特定有害物質の含有量が概ね表4.2.2 に示す濃度の範囲にあることとする。その際の含有量の測定方法は、土壌汚染状況調査における含有量調査の測定方法によらず、全量分析による。なお、表4.2.2 に示す濃度の範囲を超える場合でも、バックグラウンド濃度との比較又は化合物形態等の確認から、自然的原因によるものと確認できる場合は、自然的原因と判断する。

表4.2.2 自然的原因による含有量の上限値の目安
特定有害物質
砒素 鉛 ふっ素 ほう素 水銀 カドミウ セレン 六価クロム 上限値の目安 (mg/kg)
39 140 700 100 1.4 1.4 2.0 −
(注)含有量の上限値の目安の値は、全国主要10 都市で採取した市街地の土壌中の特定有害物質の含有量を全量分析によって測定した全量値で、統計解析から求めた値(平均値+3σ)である。なお、鉱脈・鉱床の分布地帯等の地質条件によっては、この上限値の目安を超える場合があり得ることに留意する必要がある。
(3)特定有害物質の分布特性
特定有害物質の含有量分布に、当該特定有害物質の使用履歴のある場所等との関連性を示す局在性が認められないこととする。
5.関係者意見等
前掲の3.及び4.で示した作成方法等を基に、本検討会委員や利害の及ぶ可能性のある業界等関係者から意見を聴取したところ、以下に示すとおりであった。
5.1 検討会委員意見
(1)マップ作成の必要性・メリットについて
?マップの作成と活用の必要性
一般論として、このようなマップが使われることは賛成である。まさにヨーロッパではこのような事業所立地履歴マップが提供されており、また自然由来のマップは作成している最中であるが、それなりに整備している。
このようなマップがあると、冷静な議論ができ、浄化の目標もすべて掘削除去ではなく、環境リスクの観点からベストな対策の選定についての合理的な判断ができる。また、事業所があれば土地は汚れていて当たり前という世論が醸成されることになる。
?土壌汚染対策法の改正によりマップの必要性が高まる
土壌汚染対策法の改正による平成22 年からの施行予定に併せて、土壌環境に係るマップの必要性が高まり、全国レベルでこのようなツールを持たなければならないことになる。
環境行政にとっても、このようなマップが平成22 年以降は一定程度必要になる。
?自然由来のマップの必要性
自然由来のマップは基本的に歓迎すべきことで、全国中で作成を促進すべきである。これまで、このようなマップがないために現場は非常に困っている。まず、このようなマップが共有化されることが必要で、これを基に議論ができる下地がないと、自治体によっては自然由来というだけでは受け付けないところもある。このような現状を少しでも変えていくために、このようなインフラが必要と考えられる。
また、工事の掘削土壌に自然由来による基準超過のおそれがあるかどうか事前に把握できるので、基準超過土壌処分に係る工事費の追加発生や工事期間延長といった問題も回避できる。
公共事業では、自然由来の重金属データがないと頓挫し、余計な経費が大きく発生することはもう目に見えていて、ある地域の地下鉄建設では砒素、カドミウムの問題が事前にわかっていたため、技術検討会で議論した結果を公開して適切な処置を講じたゆえに、工事費が数十億円も圧縮できた例がある。
現在では、自然由来の重金属データの調査・収集は不可欠となっており、どういう公開の仕方が社会にとって適切なのかという議論を行うべき段階に来ている。
(2)公開のデメリット
?土壌汚染マップと誤解されるおそれ
事業所の履歴情報をプロットしたはずのマップが、いつの間にか土壌汚染マップと誤解を生じてしまうおそれがあるのではないか。こうしたおそれがあると、このマップが公表された場合にどのような影響が生じるのか全く読めない。
?自然由来の汚染のある地域として悪いイメージが定着するおそれ
地域一帯が自然由来のリスクの高い地域として悪いイメージが定着すると、域外に土を搬出する場合はすべて色がついたものというレッテルを張られる懸念がある。
?住宅等を購入した土地所有者への影響

土地の履歴を知らずに住宅等を購入した土地所有者にとって、事業所立地履歴マップに色がついていることは全く寝耳に水の話で、調査して基準超過が判明した場合は、直接売主にクレームがいくことになる。このようなケースが多く出てくると、100 ?程度の小さな土地の調査でもリスクコミュニケーションは大変であり、この面で対応できる調査会社や専門家がいると
は思えないので、事業所立地履歴マップにはこのような面でのリスクもある。
?自治体への過度な負担
土壌汚染対策法の改正で対象範囲が拡大すると、自治体に多くの案件が持ち込まれて負担が大きくなることに加えて、このマップへの対応も求められるため、自治体にとって相当な負担となるおそれがある。
土地取引では、1週間以内で行政の了解をとって決済する必要がある場合もあり、行政がこれに対応できる容量がなければ売買に支障をきたすことになり、実体マーケットへの影響が懸念される。
(3)公開の是非と理由
【公開に賛成の意見】
?環境問題については情報公開が大切
環境問題は、基本的に情報公開することが大切という認識であり、情報公開するという姿勢はよいことである。また、情報公開により新規の土地購入者が汚染の可能性のある土地を購入してしまうリクスや、汚染を知らずに地下水を飲み続けるという健康被害を回避することができる。
?事業所立地履歴マップの公開
事業所立地履歴マップは公開されている既存のデータを用いてわかりやすく表示するものであるので、公開してもよい。
?自然由来重金属類分布マップの公開
民間の立場からは自然由来重金属類分布マップをどんどん公開してほしい。自然由来の判断についての行政協議のサポート資料となる。
【公開に反対の意見】
?公開請求を受けた場合にデータが一人歩きするおそれ
情報公開請求等でマップが出ていったときにどのように扱われるのかについても十分留意する必要がある。条例で原則公開となっているので、非公開の資料も請求を受ければそのまま公開される可能性がある。内部資料といえども、データがひとり歩きをしかねない危惧が懸念される。
?今すぐ公開するのは金融面でもリスクがある
今すぐ公開するのは、金融面からもリスクがあると思われる。金融庁による金融検査マニュアルにより土壌汚染を含めた環境汚染を評価しなければならないが、土壌汚染リスクをどう担保評価に反映するかは、銀行によって差異がある。土壌汚染対策法で指定区域になると相当厳しく差し引くけれども、そうではない土地は、調査等のコストもかかるので、金融機関にとっ
ても対応に差がある。
?公開については土壌汚染対策法が改正された後でよい
マップを広く知らせることはよいが、いきなり出てしまった場合に土地所有者や近隣の所有者に与えるデメリットはかなりある。土壌汚染対策法が改正され、ある程度整備された後に対応するということでも遅くはない。
?自然由来重金属類分布マップは自治体での検討結果と齟齬が生じるおそれ
自然的原因の砒素の判定方法の確立のために自治体側で委員会を設けて、表層土壌調査を加えて詳細に検討している最中であるため、自然由来重金属類分布マップが委員会での検討結果と異なる可能性があることから、自然由来重金属類分布マップは非公開とするのがよい。
また、マップについて、地層のどの深さまで見るかとか、金融面でのリスクとかを厳密に把握・整理してからでないと、かなりの混乱が予想されるので、当面は公開しないのがよい。
?公開については各自治体の判断
マップを行政内部だけに留保しておくのか、公開するのかは、個々の自治体の事情に応じて判断せざるを得ない部分があり、自治体の判断に任せるのがよい。
(4)公開する場合の条件
?データの信頼性が重要
マップの公開に際してはデータの信頼性が重要であり、公表されているデータを集約・整理して利用していくことはよい。
?公開に際して市民との十分なリスクコミュニケーションが必要

この化学物質はどういうものか、土壌、地質はどういう構成をしているのか、こういった面については、市民のみならず不動産業者もきちっと理解していないケースが多々ある。
土壌汚染についての情報公開の仕方によっては、市民に誤解を与えるおそれがあるため、ただ公開するというだけではなく、その下地として、十分なリスクコミュニケーションを通じて市民に基礎的な知識を提供することも必要である。
?公開するためには行政側の体制整備が必要
土壌汚染対策法の政令市のように、保健所行政とも一体的に連携できる体制がある場合はよいが、そうでない場合は、情報公開と同時に一体的にやれないという課題がある。
今後、土壌汚染対策法の改正の動きに併せて行政側の体制を整備する必要がある。
?要調査マップでないことを説明することが必要
事業所立地履歴マップは、(法律上調査が必要という意味での)土壌汚染の要調査マップではなく、全く土壌汚染対策法の対象になっていないものも含まれる事業所の立地マップであることから、マップに掲載されたとしても調査する義務はない。従って、フェーズ1調査をサポートするマップとして活用できるように、公開していく必要性があると考えられる。
要調査マップではないことをきちんと明記し、説明していく必要がある。
(5)公開の仕方
?自然由来から情報を公開
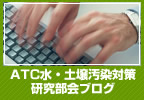
自然由来については、情報をある程度公開していく方向が重要で、まず自然由来の堆積状況から伝えていく。地方自治体では、自然由来の堆積物の判断に関していろいろな問題が生じている。日本の国土の地層は大きな特質があることを認識した上で、自然堆積物をはれものにさわるという扱いでなく、きちんと説明した上で土地取引をすべきである。
土地売買において重要な役割を果たす宅地建物取引主任者が、重要事項説明の中で、日本の国土についてある範囲できちんと説明して、市民も理解することをしていかない限り、土壌汚染リスクに対する過大な反応がいつまでも続くことになる。現場では、土壌汚染を全くゼロにしろといわれるけれども、ゼロにすることは本当にナンセンスなことである。
?行政で一斉に公開するのがよい
特定の都市のみで先行的に公開してリスクを抱えるよりは、行政側が一斉に実施することがよい。
?公表するタイミングが重要
マップづくりは大変すばらしいことでも、公表のタイミングは相当に慎重でないと、中小企業に対して、貸しはがしまで及ぶかどうかはわからないが、何らかの影響が出るのは避けられない。
?自然由来重金属類分布マップの公開の仕方
仮に自然由来重金属類分布マップを公開する場合でも、このマップを踏まえて自治体でも詳細に検討されており、新たにきちんとしたものが自治体から出される形になっていることを注記することが必要である。そうしないと、大変齟齬が生じることになる。

?段階的な公開
マップがいろいろ活用されて新しいビジネスや市場が生まれることは、大変いいことと評価する一方で、どのように使われるかわからない面もあるため、何か悪い影響が生じたら直ちに直していくというように、少しずつ段階的に公開していく方がよい。
いきなり公開するとハレーションがあるとすれば、とりあえず新たな被害を防ぐ観点から始めて、土壌汚染に対する認識が進んだ上で公開していく。
(6)事業所立地履歴マップの作成に関する意見
?街区単位よりもメッシュ単位のマップがよい
メッシュ又は街区単位で着色したマップは、場所によってかなり面積の大きさに違いがあるので、随分印象が変わる。街区単位よりもメッシュ単位で表した方が、ある意味平等である。
また、メッシュ図は、街区単位の図と比較して、面積が小さくなっている印象を与えるので、二者択一であれば、メッシュ図のほうがよい。
なお、100m メッシュ図についてきちんと説明がされないと、土地所有者がなぜ色がついているのか理解に苦しむといった懸念がある。
?目的によって対象とするデータの範囲が異なる
マップ作成の目的が、土地取引のためか、環境リスク把握のためかによって取り扱う事業所データの範囲が明確に異なってくる。土壌汚染対策法の改正の議論の中で、地歴調査で調べるべき範囲が設定されれば、その範囲の施設に限定してリスト化すればよいが、ここでの情報はそれを超える可能性がある。土壌汚染対策法が今回改正されても、ダイオキシンは対象になら
ないが、土地取引の実態ではダイオキシンまで対象としていると考えられるので、そのギャップをどう扱うかの話は残る。
?マップ作成の精度の問題
事業所立地履歴マップの精度について、10m メッシュ程度で行えば正確になるが、費用対効果の問題もあるのでどこまで詳細にできるのか、精度の問題がある。
(7)自然由来重金属類分布マップの作成に関する意見
?自然的原因の上限値の目安の全国一律的な基準値の見直し
環境省において、自然的原因の上限値の目安の全国一律の値を変えることについて現在検討中である。全国一律的な基準値(砒素の場合は39mg/kg)について、札幌市が独自の基準をどう出すかについては非常に興味があるところであるが、全国一律基準がそもそも成り立たないという共通認識を持つべきであり、それに対してどう評価すべきかというふうに発想を変えていかないと、混乱が生じることになる。
?全国的なマップづくりには多くのデータ数が必要
全国的にマップづくりを進めるには、データを増やすことが不可欠である。今回のように地質図をベースにしてデータを集積して、スコアをつけてリスクをカテゴライズしていく方法論は、おそらくその方向に向かうと考えられる。ただし、詳細な数値をどうす
るかという議論はあるが、例えば、10、20、30 という区切りの数値はこれから経験値を積み上げることによって修正していけばよい。
?担保評価の中に日本の地質的な特性を考慮すべき
これまで日本の土地の地質的特性を考慮されずに不動産取引をされてきたことの方が異常である。もともとこの地域は砒素が高目に出るところであるから、調査で砒素が高いからといって、この土地の担保は差し引くべきでないというコンセンサスが得られるようにしていくべきである。
?自治体の判断をフォローするガイドラインが必要
自然由来重金属類分布マップと事業者から提出された土壌調査報告書を踏まえて、自治体が自然由来かどうかを判断することになるので、逆にそれを判断した自治体を守ってあげるような制度設計も必要ではないか。自然由来と判断した責任を行政官がすべて負わなければいけないということは怖いことであり、技術的にここの線でこの地層には出る可能性が高いという整理をしてマップ化することは賛成である。
それを運用するときに、受け手側の自治体がしっかり判断できるガイドラインをつくらないと、安全サイドに流れて、今と変わらなくなる。
?土壌汚染対策法改正に向けた準備が必要
改正土壌汚染対策法の平成22 年運用に向けてこれから準備をしていくことが必要であり、行政側が特例区域(*)なのかどうかという判断を迫られるため、環境部局としては自然由来マップを持つことが必要な時を迎えるというふうに認識せざるを得ない。
実際自然由来については、日本の大都市の多くで砒素や鉛、ふっ素等が確認されており、そこは特例区域として妥当と判断すれば、土地所有者は調査しなくてよいとするのがねらいである。そこのエリアがどの範囲までか、既存の情報や地質図から一定程度類推したものを持っていないと、判断がつかなくなる。
(*)特例区域とは:中央環境審議会答申「今後の土壌汚染対策の在り方について」(平成20 年12 月19 日)において、海面埋立地の敷地はふっ素等の海水に含まれる自然由来成分やその埋め立てられた物質により指定基準を超過することが多いが、汚染土壌の搬出時の措置、形質変更時の土壌の飛散の防止措置を講じていれば、人の健康に被害が生じるおそれがないことから、土地所有者等の申立てにより土壌汚染があると見なす区域として特例区域の指定が盛り込まれていた。しかし、閣議決定された土壌汚染対策法改正案ではこの制度は盛り込まれなかった。
?臨海部埋立地の取り扱いの問題
例えば砒素の基準(0.01mg/L)はかなり厳しくなっており、海岸部において昭和30〜40 年代頃に埋め立てたときは合法であったが、今では基準超過となっており、埋立地は人為的汚染と考えるべきであろうが、その取り扱いについては明確な結論が出ていない。実際にフッ素の濃度は、海域の土壌による埋立てで、この土地全体が海に近いような値になっている状況もあ
る。
?札幌市では自然的原因の砒素に関して詳細に検討中
今回の自然由来重金属類分布マップは表層地質ごとであるが、札幌市ではさらに土質区分、河川の流域区分、深度区分、それから行政区区分など、多面的に検討している。
また、環境省が示している自然的原因の砒素の上限値の目安(39mg/kg)について、札幌市では、道内屈指の温泉や大きな旧鉱山が2つあるという地域特性に合わせた札幌市版の上限値の目安についても検討している。
この結果について札幌市としての判定区分を公開し、これによって土壌調査結果を判定していくことを考えている。また、併せて圏外に搬出するための札幌市版の搬出基準等に関する事項についても今後検討していく予定である。
5.2 ヒアリング結果
各業界関係者にマップの公開のメリット、デメリット、公開の是非、公開に際しての要件等についてヒアリングした結果の概要は以下に示すとおりである。
(1)中小企業関係団体
【公開のメリット】
?土地所有者にとって早期から適切な対応が可能
中小企業にとって事前に所有地の状況を把握することができれば、早期から負担等に適切に対応することができるので、廃業時などに土壌汚染の危惧から土地をそのまま放置することが少なくなる。
?中小企業にとって経営判断やシンビジネスの立ち上げに有力な情報
中小企業にとって、土地という重要な経営資源についての情報が増えるのは大変よいことで、速く、容易に情報を把握できることは大きなメリットである。とりわけ、転廃業や事業再生等を行う際の経営判断に有益である。
また、創業者が新ビジネスをスタートアップする際に、土壌汚染リスクの高い土地での創業を回避することが可能である。イメージ戦略で創業する場合に、自然由来による汚染が存する土地に立地しているなどと言われると、いきなりダメージを受けるので、スタートアップ時の経営が大変不安定な状況の中で、このような情報はメリットになる。
【公開のデメリット】
?所有地に係る情報を公開されることに対する抵抗感
土地所有者にとって、一般の人々が自分の土地についての情報を持つのは大変嫌なことであるという、心理的な抵抗感がある。
?近隣とのトラブル発生など操業への影響のおそれ
土壌汚染の可能性があると、すぐ近隣問題になって風評被害が生じるおそれがある。マスコミ等から子どもの健康を害するのではという記事が出ると、操業できなくなるおそれや町内会などコミュニティに影響するおそれがある。

?業界にとってのイメージダウン
マップの中に「クリーニング」、「ガソリンスタンド」という固有の業界が特出しされると、業界のイメージダウンになるおそれがある。
ガソリンスタンドは土壌汚染対策法の対象外であり、施設ごとに土壌汚染の可能性や対象物質が異なるので、他の業種と同じように一律に表示されることについては工夫が必要である。
?土地の担保価値低下による資金繰りの困難性
今までにない大変な景気悪化の状況下で、中小企業が直面している一番の問題は貸し渋り、要するに資金繰りの問題であり、土壌汚染のおそれにより土地の担保価値が下がって、貸し渋りの一助になることは一番不幸なシナリオである。
【公開の是非】
?当面は行政内部用としての扱い
マップの公開は時期尚早であり、当面は行政内部用の扱いがよい。
【公開する場合の要件と公開の仕方】
?ディテールも含めた正確な広報が必要
マップを公開する場合、ディテールも含めた正確な広報が大変重要である。このようなマップは活用の仕方がいろいろ考えられるが、マスコミを中心とする情報のひとり歩きは大変困ることになり、地域住民が土壌汚染として捉えた場合は、健康被害がなくても学校やPTAで大きな問題として取り上げることもあり得る。
?中小企業に対する十分な配慮が必要
中小企業は地域のコミュニティを維持するためにいろいろ苦労しているので、特に初期の段階で「土壌汚染マップ」などとネーミングされないように、十分な注意を払う必要がある。最初のイメージにとらわれて、そのまま固定観念で流れることを大変懸念する。
中小企業や家族操業の零細企業に対して十分に配慮しているというメッセージが伝わるような形でマップを公開していくべき。
?段階的な公開
マップがいろいろ活用されて新しいビジネスや市場が生まれることは、大変いいことと評価する一方で、どのように使われるかわからない面もあるため、何か悪い影響が生じたら直ちに直していくというように、少しずつ段階的に公開していく方がよい。
(2)石油輸送会社
【公開のメリット】
?フェーズ1調査の簡略化が可能
不動産取引時のフェーズ1 調査で、土地の履歴がわからず苦労しており、費用がかかるとか、結局明確な経歴がわからないことがある。このようなマップがあれば、フェーズ1調査における作業が簡略化できて有効である。

?自然由来の判定に有力な情報
自然由来かどうかの証明で、自治体と協議をする際に、このような情報があれば、大変有効に活用できるのではないか。また、工事の掘削土壌に自然由来による基準超過のおそれがあるかどうか事前に把握できるので、汚染土壌処分に係る工事費の追加発生や工事期間延長といった問題も回避できる。
【公開のデメリット】
?ガソリンスタンドへの配慮
ガソリンスタンドは、現状は土壌汚染対策法の対象外で、施設ごとに土壌汚染の可能性とか対象物が違うので、他の業種と一律同じように表示されることについては工夫が必要である。
?土地評価へのマイナス影響や土壌調査が必要な土地となるおそれ
マップに色塗りして公開された土地は、土地評価額が下がるとか、必ず土壌調査をしないと売れない土地になる可能性がある。
街区単位での色塗りの場合は、その隣も同じ色で塗られるので、隣からクレームがつけられる可能性がある。例えば、有害物質の使用経歴がないにもかかわらず、売却の際に土壌調査をしなければならいという場合に、隣から土壌調査費用の負担を求められる可能性が生じる。
?対策済みの土地も一律に色塗りされることは問題
不動産売買時に自主的な土壌調査・対策を既に実施した土地についても、一律同じ色で塗られることは問題である。調査・対策の実施状況を反映できる仕組みが必要である。
【公開の是非】
?行政内部用として使われるのがよい
情報公開請求等でその資料が出ていったときにどういうふうに扱われるのか。その辺も十分注意が必要である。マップの公開は時期尚早と考えられる。
【公開する場合の条件と公開の仕方】
?土壌汚染リスクに関する一般への周知が必要
マップ公開については、土壌汚染のリスクを一般の方に広く十分に周知した上で行うべきである。
?過去の調査・対策の実施結果を反映
過去の土壌調査・対策の実施結果を反映できるような仕組みとすべきである。
?ゾーン表示よりも施設の種類別表示がよい
街区やメッシュのエリアの単純な色塗りでは不安を広げることになるので、どういう施設がどこにあったかという実態を示すようにした方がよい。
(3)損害保険会社
【公開のメリット】
?リスク回避に有益な情報
マップに係る情報が開示されて土地汚染の可能性が示唆されれば、新規の土地購入者が汚染の可能性のある土地を購入してしまうリスクや、汚染を知らずに地下水を飲み続けるという健康リスクを回避することができる。
【公開の是非】
?時期尚早
事業所立地履歴マップは新しいデータを公表するのではなく、既存のデータを整備して分かりやすくしたものであるが、土壌汚染に対して十分な理解が進んでいない現状の社会環境下でいきなり公開することのデメリットは大きい。
当面のボトムラインは土壌汚染の存在を知らない新たな被害者の発生を防ぐことにあり、そうであれば当面は不動産売買時に売り手は立地履歴の提示を義務付けるという対策でもよいのではないか。
【公開する場合の条件と公開の仕方】
?行政用と公開用との区分は必要ない
もともと公開されているデータを整理してマップとして開示しているため、公開に当たって、行政用のものと一般開示用のものとを区分する必要はない。
?自然由来重金属類分布マップについて
自然由来の重金属類分布マップについては、科学的な検証がされた上でのクラス分けになるべきだろうと考えている。
(4)環境コンサルティング会社
【事業所立地履歴マップについて】
?事業者にとって歓迎であるが、住民にとってはデメリットが大きい
このマップは、コンサル、不動産関係、金融関係の事業者サイドにとっては非常にありがたく、メリットしか思いつかない。しかし、住民の立場からすれば、健康リスクのみならず経済リスクも負いかねないという意味では、公開することによるデメリットの方が大きい。自然由来重金属類マップ以上に綿密なリスクコミュニケーションが必要である。
行政内部用と公開用で分けているが、公開用だけあれば良いと思う。土壌汚染対策法の改正により自治体がフェーズ?についての判断を行うことが増えることが想定されるが、行政内部用を作ったにしても、そこに掲載されている情報が100%で無い場合は、結局担当者が調査を行うことになる場合もあると思われる。せっかく作ったマップでも、信頼がないと使われなくなる可能性も考えられる。
【自然由来重金属類分布マップについて】
?自然由来重金属類分布マップは必要
このようなマップを作成することはすばらしいことであり、行政が整備してくれると助かる。ただし、公開に当たってはリスクコミュニケーションが不可欠である。国土交通省と自治体双方の担当者がマップの意義や趣旨・目的、自然由来の基準超過には通常存在する量では健康リスクが無いこと等をしっかりと住民に対して説明出来る必要がある。
なお、自然由来については、「掘ったら出てくる」こと、そもそも通常存在する量では健康上のリスクは無いことが重要なのであるから、自然由来と判断されたところについては1色で塗ればよいのではないか。
このようなマップが全国で整備出来ると良い。ただ、自然由来と判断する基準は(環境省が自然由来と判断する基準である)39mg/kg を基準にするのではなく、地域によって変えた方がいい。この基準自体、全国10 地点くらいの平均値であり、信頼の高いものではないので、現在環境省においても見直しがされている。
マップに入っている調査結果の数字については出さない方がよい。不要な誤解を招きかねない。
(5)不動産鑑定士
色塗りされたエリアに含まれた土地の評価を求められた場合、土壌汚染による影響が無いと言い切るためには、このマップに掲載された情報よりももう少し詳細な調査が必要になるが、それは依頼者の負担で行ってもらう必要がある。そうなると、評価を依頼する人の負担が現状よりも増えるとともに、中途半端な情報の下では鑑定評価の依頼を受けにくいことから、鑑定
評価ビジネスが縮小してしまうかもしれない。
また、「このマップで色が塗られていないのだから土壌汚染は存在しない」と、このマップに責任を押しつけて悪用する人(特に鑑定士や不動産業者など)が出てくるかもしれない。
6.汚染された土地の有効利用促進等に向けた情報提供の方向性と課題
6.1 土壌汚染情報のデータベース化
6.1.1 人的活動に起因する土壌汚染データベース構築の方向性と課題
中央環境審議会「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)」(平成20 年12 月)は、「土壌汚染に関する情報について、埋没させることなく、関係者が容易に入手し、適切に活用することができ、適切に承継される仕組みが必要」としており、土壌汚染に係るデータベースの構築が必要とされている。
データベースの構築は、土壌汚染対策法の一部改正の方向として想定される「都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に関する努力義務」に沿った具体策の一つであると位置付けることもできる。
上記の答申においては、一定規模以上の土地であって土壌汚染のおそれのある土地の形質変更時における都道府県知事による土壌汚染の調査命令や、自主調査において土壌汚染が判明した場合も含め規制対象区域として適切な管理を行うことが謳われている。
また、汚染物質の掘削除去を行わず、残置して封じ込める対策の採用検討が推奨されている。行政が管理すべき土壌汚染に係る情報量が増加する方向にある中で、情報を効率的に管理し、効果的に施策決定に結びつけるためには事業所立地履歴マップを含めたデータベースの構築が有効である。
また、行政が知り得た情報を開示せず、土壌汚染リスクの存在を認識することができないままに土地を購入する者がいるとすれば、不幸なことであり、そのような状況の発生を防ぐ必要がある。宅地建物取引業法では、隣地や取引対象土地の過去の使用履歴について、その時点で認識している以上に開示することは求めておらず、一般には積極的にその土地の過去の使用履
歴を調査することは行わない。
したがって、土地購入者が近傍の土壌汚染の存在を把握したうえでの土地取引を推進できるという意味でも、データベースの構築・公開は求められるところである。
事業計画当初に調査を実施しなかったり土壌汚染を発見できなかったりした土地について、工事途中など事業が進んだ段階で土壌汚染が発見された場合には、土地取引の契約取消しや想定外のコスト発生などの問題が生じている事例は多い。容易に参照できる情報が存在すれば、土壌環境の概略把握が可能となり、その後の段取りの効率的な進行や調査品質の確保に繋がることが期待される。
一方で、土壌汚染対策法の改正が検討されている最中であり今後の詳細な制度内容が不確定であるという問題を除いても、事業所立地履歴マップの公開については、次の二つの理由から現時点では避けるべきという意見があったことにも配慮する必要がある。
第一に、マップの公開の仕方によっては、住民の一部に不安を与えてしまうという可能性を否定しきれないであろうということである。単純にマップの公開のみであると、リスクを正しく認識しないことによるスティグマのため、土地価格に悪影響を与え得ることなどが懸念された。
第二に、企業活動への影響が懸念された。景気が著しく悪化し、企業の資金繰りが悪くなる中で、土地の担保価値下落に繋がるおそれのあるマップ公開は避けるべきということである。
このため、今般はマップの作成方法等を示すにとどめることとするが、上記答申を内容とする改正土壌汚染対策法が成立・施行された場合、上記のとおり自治体の負担はかなり増大する可能性があると考えられることから、少なくともそれを軽減し円滑な業務執行を成し得るよう、まずは行政内部での活用を目的として、各自治体において本とりまとめで示した作成方法等を
参考にしつつマップ作成に取り組むことが一助になると考える。
6.1.2 自然的原因による土壌の基準値超過に係るデータベースの構築の方向性と課題
自然的原因による土壌の基準値超過については、地質的に一定の地域内に幅広く分布する等の事情により、その地域固有の特性と考えて対応する必要がある。
したがって、人為的な土壌汚染として対策をすべき土地と、そうではない自然的原因による土壌の基準値超過土地の線引きを可能にするため、自然的原因による土壌の基準値超過についてデータベースを構築することは有用であると考えられる。また、これにより、汚染土壌による地下水への影響や残土の処理方法等を調査、検討することも可能になる。
そもそも自然的原因による土壌の基準値超過は、国土そのものの議論であり、人為的な汚染との区別が明確にできれば、行政的に地下水への影響をコントロールすることや搬出土壌の移動管理を施すべきもので、また、情報の公開によって影響を受ける関係者も少ないことが想定されるため、自然的原因による土壌の基準値超過データベースの構築・公開に対する抵
抗感は少ないものと考える。
自然的原因による土壌の基準値超過については、前述したようにある地域内の土地全体に当てはまる特性であることから、個別サイトごとの状況を考慮に入れれば足りる一般の土壌汚染の場合とは異なり、面的に土壌の状況を把握する必要がある。
現在、自然的原因による土壌の基準値超過については、環境省主導で全国の土壌のバックグラウンド値が収集整理されているほか、自治体や大学等の研究者により自然的原因による土壌の基準値超過の判定に係る研究が進められている。
したがって、それらの成果を踏まえ、各自治体の判断により、自然由来重金属類分布マップをデータベースの一つの形として公表することは可能であるとともに適切であると考える。
また、事業所立地履歴マップの場合と同様に、改正土壌汚染対策法の内容を踏まえれば、自治体の負担が増す可能性がある中で、予め各自治体においてその軽減に資するバックグラウンドデータを整備しておくことが一助になると考える。
6.2 土壌汚染の正確な知識の周知とリスクコミュニケーション

土壌汚染が社会問題化するのは、土壌汚染自体が比較的新しい概念であり、これまで通常存在するリスクの一つとして扱われなかった商習慣等の下で土地利用や土地取引が行われていることが背景にある。こうした状況下で事業所立地履歴マップを公開した場合に、国民の間に過剰反応が生じる悪影響が懸念された。この課題を払拭するためには、行政主導で公開に先立ち国民に啓発活動を実施するとともに、公開に当たっての体制やシナリオを検討しておく必要がある。
土壌汚染問題に対する一般的理解の不足により、汚染の程度が重篤なものでなくとも、世の中においては過剰に反応される傾向があり、また、この風潮により土地所有者等は公表を拒みがちとなるという悪循環となっている。
しかしながら、それらの土地を健康リスクの観点から見た場合、多くは過剰反応するほどの大きなものでなく、合理的な対策により十分対応可能なレベルであると考えられる。
また、そもそも土壌環境基準が意味する健康被害リスクが一般的に思い込まれている以上に低いレベルであることさえも一般的に認知されておらず、このような土壌汚染に関する正確な知識の欠如が、世の中に土壌汚染に対する過剰な嫌悪「スティグマ」を生んでいる。
そして、スティグマの存在が風評被害の可能性へとつながるために土壌環境に係るマップの公開の障壁となり、世の中に土壌環境に係る正確な情報が提供されないという悪い連鎖が生じている。

この悪い連鎖を断ち切るためには、土壌汚染リスクに係る正確な知識の普及が必要なことは当然であるが、その普及の見通しが不透明である現状においては、国が主導し、正確な知識の周知と併せて全国の土壌環境に係るマップの公開を促進することが重要である。
土壌環境基準を超過する土地が日本国中至る所に存在し、そこで人々が何不自由なく生活していることが理解されれば、スティグマも解消し円滑な土地取引が行われるものと期待される。
土壌環境に係るマップの公開は、土壌汚染に係る有効なリスクコミュニケーションの手段となり得るものである。
なお、リスクコミュニケーションにおいては、土壌汚染が判明した場合であっても過剰な対策・負担なしに対応が可能であることを認識してもらうことが重要であり、土壌環境に係るマップの公開に伴う上記の懸念を可能な限り低減させるためにもその種の方策を講じることが有効である。
このため、例えば、掘削除去以外の措置により計画的な土地利用を行っている実在の土壌汚染地について、その成功要因等を分析・研究し、「サクセスモデル」として公開すること等を検討すべきである。










一部追加しています。



目 次
1.はじめに
2.土壌汚染関連情報の提供に係る現状と諸問題・取組
2.1 土壌汚染関連情報の提供に係る現状認識
2.1.1 土壌汚染関連情報の提供の現状
2.1.2 土壌汚染調査と情報収集
2.2 土壌汚染関連情報
2.2.1 人為的汚染
2.2.2 自然的原因による土壌の基準値超過
2.2.3 その他
2.3 土壌汚染関連情報の提供の目的と期待される効果
2.3.1 情報提供によるリスクの回避・低減
2.3.2 土壌汚染調査の効率化と標準化への貢献
2.3.3 土壌環境に係る土地の制度的管理
2.3.4 自治体の業務効率化
2.3.5 土壌汚染地に係る保険の普及
2.3.6 土壌汚染地の資産評価
2.4 国内における土壌汚染関連情報の提供に係る制度・取組
2.4.1 土壌汚染対策法
2.4.2 自治体の取組
2.4.3 その他
2.5 諸外国における土壌汚染関連情報の提供に係る制度・取組
2.5.1 アメリカにおける取組
2.5.2 ドイツにおける取組
3.事業所立地履歴マップ
3.1 マップの作成方法
3.1.1 作成手順概要
3.1.2 作成方法
3.1.3 収集データの種別
3.1.4 データの収集例
3.2 マップの表現方法
3.2.1 事業所立地履歴マップの表示種別
3.2.2 事業所立地履歴マップの表示方法についての考え方
3.3 事業所立地履歴マップの公開・活用
3.3.1 事業所立地履歴マップの全体像
3.3.2 マップの活用方法
3.3.2 事業所立地履歴マップを公開・活用する際の論点整理
4.自然由来重金属類分布マップ
4.1 マップの作成方法
4.1.1 マップ作成の目的
4.1.2 作成手順
4.1.3 作成方法
4.1.4 表現方法
4.2 マップの活用方法
4.2.1 マップの活用方法
4.2.2 自然由来重金属類分布マップの活用マニュアル(案)
4.2.3 自然由来重金属類分布マップ例(仮想案)
5.関係者等意見
5.1 検討会委員意見
5.2 ヒアリング結果
6.汚染された土地の有効利用促進等に向けた情報提供の方向性と課題
6.1 土壌汚染情報のデータベース化
6.1.1 人的活動に起因する土壌汚染データベース構築の方向性と課題
6.1.2 自然的原因による土壌の基準値超過に係るデータベースの構築の方向性と課題
6.2 土壌汚染の正確な知識の周知とリスクコミュニケーション
1 はじめに

我が国の限られた国土において、 土地は国民共通の財産といえるものであり、その適正かつ有効な利用を実現することが不可欠である。そのためには、土地を有効利用しようとする者が円滑に土地を取得し、利用を開始しやすくすることが必要である。
しかしながら、高度成長期を経て我が国の社会経済情勢が安定化する中で、産業構造の変化に伴う工場跡地の他用途利用
や、住商混在型のまちづくり、事業所等が相当程度点在する街なかの再開発等の増加が見られ、これらの局面で土壌汚染が判明し、しばしばトラブルとなった結果、当該土地の有効利用が阻害されるケースが生じている。
土壌汚染問題については、国民の健康保護を目的として、平成14 年5月に土壌汚染対策法が制定(翌年2月施行)され、また、土地取引市場においても、そのリスクが強く意識されるようになっていたことから、国土交通省では、平成14 年10 月に「宅地公共用地に関する土壌汚染対策研究会」を設置し、翌年6 月、土地取引の安全性と円滑化の確保を目的とした土地売買契約に当たっての留意事項や、土地建物取引業者の留意事項に関する基本的な事項等を体系的にとりまとめ、公表した。
しかしながら、土壌汚染の判明した土地については、依然として土地取引が忌避され、土地の有効利用や再開発、まちづくりにおいて支障が生じる事態になっている。この最大の要因として、国民や市場が土壌汚染問題について正しい認識を有しないことによる過剰な反応・対応が指摘されているところであり、それが土地所有者を汚染事実の公表について消極化させ、市場にそれらの情報が集積されない結果、さらに国民の過剰反応を促すという悪循環にあると思われる。
こうした問題意識を踏まえ、国土交通省において、土地取引の円滑化による土地の有効利用促進等の観点から、土壌汚染土地について現状と課題を整理し、具体的な方策につながる検討を行うことを目的として、平成20 年に「土壌汚染地における土地の有効利用等に関する研究会」が設置され、同年4月、土壌汚染地における土地の有効利用方策を検討する際の様々な課題等について、「中間とりまとめ」として整理が行われた。
その中で土壌汚染に関する情報の提供が、土壌汚染に対する国民の理解を改善し得るものであるとともに、それが根幹的な課題であることから、本年度は、土地の有効利用促進の観点からの土壌汚染に関する情報の提供のあり方に焦点を当て、特に土壌汚染に関連する情報のマッピングについて試作・検討することを目的として「土地の有効利用のための土壌汚染情報等に関する検討会」を設置し、4回の会合を開催した。
今般の「中間とりまとめ」はその成果であり、この種のマップを作成・公表することについての意義や課題、作成方法等を整理したものである。本年は土壌汚染対策法の改正が議論されており、その成立と政省令の整理の状況も考慮し、今後、自治体あるいは市場において積極的な情報提供を進める際の参考となることを期待する。
2.土壌汚染関連情報の提供についての現状と諸問題・取組
2.1 土壌汚染関連情報の提供に係る現状認識

2.1.1 土壌汚染関連情報の提供の現状
土壌汚染問題に対する一般的理解が不足していることから、我が国においては土壌汚染に関する情報は秘匿されがちであり、容易に公にはならず、一般社会では土壌汚染が特別なものだと認識されている。
その結果として、土壌汚染が報道等で取り上げられた場合、その汚染の程度が重篤なものでなくとも、世の中においては過剰に反応される傾向がある。
また、この風潮により土地所有者等は公表を拒みがちとなり、結果的に悪循環となっている。
しかしながら、我が国が火山国であることに由来する、重金属の自然含有レベルの高い土壌の存在や、過去の人為的活動により重金属等が河川などを通じて移動・濃縮した底泥などで構成されていることが多い臨海の埋立地の存在、水質汚濁防止法等公害対策が講じられる以前の工場等の跡地利用など、土壌汚染は決して特別なものではない。
それらの土地を健康リスクの観点から見た場合、多くは過剰反応するほどの大きなものでなく、合理的な対策により十分対応可能なレベルであると考えられる。
土壌汚染が社会問題化するのは、土壌汚染自体が比較的新しい概念であり、これまで通常存在するリスクの一つとして扱われなかった商習慣等の下で土地利用や土地取引が行われてきたことが背景にある。すなわち、対象とする物質が工場内等で取り扱われてきたことについて一般的には積極的にオープンにされていなかったにもかかわらず、近年土地利用や土地取引において急速にそれらの情報を求める局面が増加したためである。
前述したとおり、基本的な土壌汚染関連情報が不在又はアクセス困難であるため、マンション購入後に土壌汚染が発覚し問題となるケースや、再開発計画を着手後に見直さざるを得なくなるケース等の支障が生じている。
しかしながら、土壌汚染関連情報は、土壌汚染地の周辺住民や購入者にとっても利害関係を有するという意味では、土地の安全性に関する情報として公益的な側面を有するものであるため、広く共有されることが望ましい。
これを踏まえると、我が国でも、全国的な土壌汚染関連情報をデータベース化し、インターネット等によりその時点の状況を誰もが閲覧できる仕組が存在すれば、土地取引の円滑化や浄化措置の促進・早期化等に資することになるとも考えられる。
一方でこのようなデータベースの構築には様々な課題が存在するとともに、データ量も膨大となること等から、実現に相当の時間を要することが想定される。そこで、現実的に対応が可能と考えられる手法の一つとして、過去に工場が立地していた等の理由により、汚染されているおそれが高いサイトや地区を地図上に記載した「事業所立地履歴マップ」等を作成することが有効であると考えられる。
「事業所立地履歴マップ」等の作成・公表により土壌汚染関連情報の一部が世の中に浸透すれば、土壌汚染に関する情報を公開することに抵抗を感じにくい風土の醸成につながり、土地取引・土地利用における土壌汚染の存在を特別視しないで行えることが期待される。
結果として、比較的スムーズに土壌汚染情報データベースが世の中に受け入れられ、より効率的な土壌汚染への対応が可能になるものと考えられる。
ただし、こういったデータベースを構築・公表する場合、そもそも情報の入手手段が限られており、また、情報の正確性に細心の注意を図る必要があることから、引き続き、関係行政機関が連携し、情報の入手源や入手方法について検討するとともに、その情報の元となる調査の信頼性及び正確性をいかに担保するかという点や万が一公表した情報が誤っていた場合に、当該データベース作成者の責任の射程及び当該情報を利用した結果他者に危害を与えてしまった者の責任の射程についても併せて検討しておく必要がある。
なお、土壌汚染情報データベースの一類型として、浄化が完了したサイトに関し、当該サイトの土質や浄化が完了した旨を公表するようなデータベースを構築することも、土地取引の円滑化等に資すると考えられることから、こうした点についても検討する必要がある。

2.1.2 土壌汚染調査と情報収集
土壌汚染調査は、土壌が汚染されているかどうか、汚染されている場合にどの程度の汚染であるかを把握するために行われるものである。しかし、土地取引や対策計画立案など、調査実施主体が調査結果を使用する目的に応じて、調査の内容・手法や必要とする精度は異なる。
このため、法や条例に基づかない民間の自主的な土壌汚染調査は、法令に基づく調査に準拠して進められることが多いが、必ずしも統一された基準のもとに実施されているわけではない。一般的な土壌汚染調査のフローを図2.1.1 に示す。
地歴等調査(フェーズ?)は、土地利用履歴調査(登記簿、閉鎖謄本、古地図、空中写真等)、地形・地質に関する調査(ボーリングデータ、地形図等)、現地視察調査(周辺状況や対象地の現況を把握)などに基づき、土壌汚染のおそれの有無について定性的に判断する調査である。
我が国では、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)が土地取引時に作成されるエンジニアリングレポート(ER)のガイドラインを定め、その中で土壌汚染のフェーズ?調査手法を提案するなどの取組があるが、統一された土壌汚染調査仕様が規定されるに至っていない。
法令等に準じたフェーズ?調査を実施することによって、土壌汚染リスクが回避されるという一般認識が存在している。簡易なフェーズ?調査で土壌汚染の可能性が完全に否定される場合を除き、フェーズ?調査による評価が求められる傾向が強い。
地歴等調査(フェーズ?)
・既存資料調査
・現地踏査
・ヒアリング等調査
概況調査(フェーズ?)
・重金属等は表層部分での試料採取・試験
・VOCs は土壌ガス調査
・1,000 ?で1 地点調査
詳細調査(フェーズ?)
・ボーリング調査
・地下水調査
・ヒアリング等調査
・汚染範囲内100 ?で1 地点調査対策の策定と工事
モニタリング
・汚染の有無を判定
汚染の可能性のない場合は終了
汚染のない場合は終了
・汚染の平面的な広がりを調査
・汚染の範囲・深さ・程度を調査
・汚染の広がりを3 次元的に把握
・対策の必要性・範囲の設定
・汚染の可能性を調査
土壌汚染対策法に基づく汚染状況調査
(土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説)
・土壌含有量調査
・土壌溶出量調査
・土壌ガス調査
・汚染のおそれのあるエリアは100 ?で1 地点調査
図2.1.1 一般的な土壌汚染調査フロー
フェーズ?調査を実施する際には現地踏査やインタビュー、依頼者から提供される書類記録等のレビューの他に、公的機関が保有する環境情報を精査する。アメリカでは、汚染サイトや浄化中のサイト、埋立地や処分場、貯蔵タンク等の情報が法令等によって登録されており、フェーズ?調査の実施時にはこれらの情報を評価の材料としている。
一方、我が国でも同様の手法でフェーズ?調査が実施されているが、アメリカのような法令等がない。環境省と一部の自治体は、それぞれ土壌汚染対策法と条例が適用された土壌汚染地の調査・改善措置に関する情報を収集し、情報提供しているケースもあるが、これらの情報を制度的に集約する機関がないため、公的機関から多くの環境情報を得ることは困難である。
また、法や条例の適用を受けず、自主的に実施された調査や改善措置が、土壌汚染調査実施数の大半を占めているものの、それらに関する情報を共有できる仕組が構築されていないことも課題である。
土壌汚染に関して参照できる情報、資料の蓄積が少ないため、調査の案件毎に始めから調査を実施する必要が生じているのが現状である。
調査を実施して汚染が判明すると、対策の実施や公表を迫られ、企業の会計への影響やイメージの低下につながる事態をおそれて、調査を実施しないケースも存在する。土壌汚染に対する社会的な見方は変わりつつあるとはいえ、自主的な調査の結果の提供については、企業サイドも消極的となることが想定される中で、効果的な情報収集を図ることが重要である。
フェーズ?調査を実施する際には、住宅地図、不動産登記簿、土壌汚染に係る地域の基礎的情報(土地利用履歴、過去の地形図、漏出事故・汚染記録、潜在的汚染源の位置、地下水水質等の環境情報など)のほか、地方自治体や各省庁が所管する基礎的情報が活用される。
これらの情報は、未整備もしくは個別に収集・管理されているために、データ収集の非効率が生じており、アクセスしやすいように整備されることが望ましい。
土壌汚染に関する情報インフラが整備されることによる効果は、前述のとおりフェーズ?調査の品質確保や効率的な調査に資するものであり、生産性の向上にも結びつくものである。
そして、土地取引等に当たっての保険活用や担保評価に資する有用な情報となる。また、情報インフラが整備されることにより、土壌汚染地の譲渡等があった場合でも、次の管理者等が当該土地の情報を円滑に引き継ぐことができる。これにより土壌汚染による環境リスクの管理についても、次の管理者等へ承継できることとなる。
2.2 土壌汚染関連情報
2.2.1 人為的汚染
人為的な土壌汚染の代表的な発生原因としては、以下の5つである。
? 工場等で使用していた有害物質が、不適切な取扱いや老朽化等による施設、設備の破損により漏えい、流出、飛散して土壌に浸透するという、事業活動が原因の汚染
? 産業廃棄物が埋立処分された土地で発生するという、廃棄物が原因の汚染
? 事故や災害により施設、設備が故障、破損等することにより有害物質が漏えい、流出、飛散等して土壌に浸透するという、事故や災害が起因の汚染
? 土地造成により上記の汚染土壌を搬入したことが原因の汚染
? 土地造成により自然の土壌中に存在する自然由来の汚染を搬入したことが原因の汚染
上記の?、?については、土地利用履歴に関する情報が重要となる。立地した事業所の業種、使用化学物質、操業時期等が当該情報を構成する。
?については、同様に廃棄物処分場の立地履歴等が情報となる。
一方、?のケースの土壌汚染については、関連する情報の収集が困難である。事業所としての土地利用履歴が確認されないケースにおいて、造成盛土内から土壌汚染が検出されている事例も多い。
?については、過去に埋め立てられた臨海部の土地について、砒素などが含まれる河川や浅海域の底質の浚渫土砂等が埋め立てに使われていることが多いことから、基準値超過の可能性が指摘されている。また、臨海部以外の低・平地部の埋立造成地においても、持ち込まれた土が原因の基準値超過が見つかっている。
なお、浚渫された水底土砂による埋立地については、海洋汚染防止法の規定により、昭和48 年3月以降は、同法に基づく基準を満たした水底土砂とそうでない水底土砂を分けて埋め立て、後者については海水の流出防止措置や放流水の処理を講じることが義務付けられている。
また、土壌汚染は1 箇所にとどまるものではないため、隣接地を発生源とするもらい汚染の可能性がある。したがって、調査対象敷地のみならず、隣接地や周辺土地の利用履歴等についても、人為的汚染に係る情報として有用である。
2.2.2 自然的原因による土壌の基準値超過
自然に存在する岩石や地層に含まれる重金属が風化や水の流出に伴って拡散し、低・平地部に自然堆積した場合や、これらを含む河床や海底での堆積土砂などにより埋め立てられた場合であって、基準値を超過しているときは、自然的原因による土壌の基準値超過とみなされる。自然的原因の可能性のある物質として、砒素、鉛、フッ素、ホウ素、水銀、カドミウム、セレン、六価クロムなどがある。
自然的原因による土壌の基準値超過を判断することは技術的には不可能ではないが、人為的汚染と混在した場合にそれを区分することは相当の作業が必要となる。その区分を把握するためには、自然的原因による土壌の基準値超過は含有量が一定の範囲内にあり、広域で観測されて局在性がないなどの特色を持っていることから、広域的な視点からバックグラウンド濃度などのデータを収集して分布特性等を見て判断していくことが必要である。
こうした観点で、環境省や一部の自治体では、自然状態の土壌のレベルを把握するために、データの収集を始めている。
2.2.3 その他
上記の情報のほかに、土壌汚染の状況把握のためには、地盤の地層構成、有機物含有量、地下水面の位置など地下水に関する情報が、汚染の広がりを評価する場合には重要である。
また、土壌汚染が確認された土地について、土壌汚染対策法に基づく区域指定の有無、調査結果、対策の進捗状況なども収集し、一括整理することが望ましい。
2.3 土壌汚染関連情報の提供の目的と期待される効果
2.3.1 情報提供によるリスクの回避・低減

土壌汚染によるリスクについては、人の健康リスクが重要であることは言うまでもない。
しかしながら、土壌汚染地の取引に関連して、その資産価値に係るリスクも予測が困難であり、そのリスクが顕在化した場合の影響は大きい。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が土地価格を上回るケースもある。汚染を完全に除去しなければ、土地に残る土壌汚染の管理が必要となり、将来、想定外のコストが発生したり、将来売却する場合に想定以上の減価が生じる懸念もある。
さらに将来の法改正で、規制対象物質が増えたり、基準が強化され、予測できない大きな負担が生じる可能性がある。実際の土地取引においては、人の健康リスクよりも、むしろ資産価値に係るリスクが問題となることが多い。
行政が土壌汚染に関連して知り得る情報を提供することによって、国民や企業は土壌汚染によるリスクを特別なコストなしに概略把握することが可能となり、土地利用や土地取引を安心して行うことができる。
企業であれば、事業構想初期段階で、ER作成前の概略情報として活用することも可能である。すなわち、土壌汚染によるリスクを、効果的に回避・低減することができる可能性が高くなるものと期待される。
2.3.2 土壌汚染調査の効率化と標準化への貢献
土壌汚染対策法の規定に基づく調査は、環境大臣(地方環境事務所長)が指定する指定調査機関が実施することとされており、平成20 年12 月5 日現在、1,639 機関が指定されている。東京都等自治体の条例に基づく土壌汚染状況調査についても、原則として土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に実施させることが定められている。
ただし、指定調査機関の認定要件は届出による簡易な書面審査が中心であることに加え、土壌汚染対策法や条例が適用さ
れない調査では、土壌汚染の専門家以外でも調査の実施が可能なことから、調査結果の信頼性を問題視する意見もある。
2.1.2で述べたようにアメリカなどでは、汚染サイトや浄化中のサイト、埋立地や処分場、貯蔵タンク等の情報が法令等によって登録されており、フェーズ?調査の実施時にはこれらの情報を評価の材料としている。情報が提供されることによって、調査者が情報を収集整理するコストを低減できる。
加えて、最低限確認されるべき情報を調査発注者も容易に確認できるため、最低限の水準を満たさないような調査結果を排除し、上述のような問題点の解決に資するものと期待される。

2.3.3 土壌環境に係る土地の制度的管理
土壌汚染が発見された場合、そこに土地取引が絡む場合には、売り手側や買い手側の要望から実態として完全除去されることが多いが、土壌汚染対策法や条例では、すべてのケースについて完全な除去まで求めているわけではない。
当該敷地及び敷地以外の周辺環境において、人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれが顕在化していなければ、完全除去ではなく、土壌汚染が周辺環境に影響を及ぼさないように汚染拡散防止措置を実施することで足りる。そして、法や条例の適用対象とならない場合にも、この基本的な考え方は適用できる。
土壌汚染を残置することによって、土地所有者は土壌汚染リスクを将来にわたって適切に管理することが求められるが、経済合理的な対策を選択できる余地が広がることとなる。
掘削除去以外の対策により汚染が残存している場合、汚染土壌の継続的なリスク管理が必要となり、所有権の移転があれば、その役割は新しい所有者に適切に引き継がれなければならないが、個人レベルでは不安のあるところである。また、個人レベルで、土壌汚染の存在することによる土地資産の減価リスクの適切な判断が求められる。
これらの点においても、土壌汚染に関する情報の整備・提供というシステムは重要な役割を果たし得る。
2.3.4 自治体の業務効率化
特定の土地の土壌汚染に関する問い合わせに自治体が対応する際に参照可能な情報となるものであり、業務の効率化に資することが期待される。上記の土壌汚染土地の管理に加え、飲用井戸の管理体制の構築にも活用可能である。
また、都市計画や公共施設の計画において、初期の事業構想段階で環境情報、コスト要因を概略把握することも可能となり、事業進捗後の予期しない深刻なコストオーバーランのリスク回避に繋がるものと期待される。
2.3.5 土壌汚染に係る保険の普及
日本国内では、土壌汚染に関連した保険の普及が進んでいない。普及が進まない最大の理由は、保険料の高さと保険引受条件の厳しさにあるようである。仮に数を集めたところで発生要件の規則性が見いだせない(=大数の法則が成立しない)からこそ保険料が高くなり、加えて、逆選択(土壌汚染のリスクを抱えているのが明確な人ほど保険に入ろうとする)が生じ、最悪の場合モラルハザードにつながるため、保険の利用が進まないという側面がある。
そして、保険の利用が進まないために、大数の法則の適用が困難となり、結果として保険料が高くなり、引受条件が厳しくなるという悪循環が生じている。さらに、保険料に加えて、保険引受のための高額の調査費用も被保険者において負担することが一般的となっており、このことも保険が利用されていない一因となっている。
リスクを定量化するためのデータの蓄積は、保険商品の開発にとって重要である。土壌汚染リスクに関する情報が提供・整備されることにより正しい理解が進むことになるであろうことから、保険市場の創出に繋がる可能性もあるものと考えられる。

2.3.6 土壌汚染地の資産評価
資産除去債務の導入に伴い、融資や企業買収に際しての調査や、企業自らの資産評価を目的として、企業所有不動産の土壌汚染に係る状況を概略把握するニーズは増すものと想定される。土壌汚染に係るデータベース構築は、土壌汚染地の資産評価を必要とするシステムが適切に運用されるための前提条件ともなり得るものであり、概略情報を把握する目的で重要
な役割を果たすものと期待される。
2.4 国内における土壌汚染関連情報の提供に係る制度・取組
2.4.1 土壌汚染対策法
土壌が有害物質により汚染されると、汚染土壌の直接摂取や、汚染土壌から有害物質が溶出した地下水の飲用等により人の健康に影響を及ぼすおそれがある。汚染原因者等の責任の明確化と土壌汚染による健康被害の防止が求められる中、土壌汚染対策の法的な拠り所として、平成15 年に土壌汚染対策法が施行された。
同法のもとでは、次のとおり、特定の有害物質を取り扱った工場や事業所の敷地であった土地の所有者に対し、土壌汚染の調査とその結果の報告が義務づけられている。しかし、土壌汚染対策法は、民間の事業者が自主的に行った調査結果の届け出を義務付けていない。
【土壌汚染対策法に基づく調査の概要】
(目的) 国民の健康保護
(対象物質) 特定有害物質(重金属、揮発性有機化合物等25 項目)
(対象:調査の契機)
? 使用が廃止された「特定有害物質の製造、使用または処理をする水質汚濁防止法の特定施設」に係る工場・事業所の敷地であった土地
? 都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると認める土地
2.4.2 自治体の取組
土壌汚染対策法が平成15 年2 月に施行されて以後、多くの自治体で条例や要綱等が制定・改正され、その中に土壌汚染に関する調査・対策の実施義務や届出措置が盛り込まれた。
また、独自に条例において、土壌汚染調査に関して、より厳格な規定を設けている自治体もある。例えば、東京都は、環境確保条例において土壌汚染に関する規定を設け、3000 ?以上の土地の改変を行う場合又は有害物質取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合、調査を実施し報告することを義務付けている。しかし、土壌汚染の自主調査結果については、汚染が確認された場合の届け出を義務付けた上で公開するところ(三重県等)、できるだけ届け出るよう指導するところ(名古屋市等)、そもそも届け出を義務付けていないところなど、自治体によって取扱いが異なっている。
2.4.3 その他
(1)土地利用マップの公開・頒布
大阪市では土地利用現況の情報をマッピングして頒布するとともに、図2.4.1 に示すようにインターネットを通じて無償公開している。当該情報は、各土地利用を土壌汚染リスクと関連付けて読み取り、理解した場合には、土壌汚染リスクを示すマップとして機能するものと考えられる。
土地利用状況 一戸建て住宅 長屋住宅 共同住宅 販売商業施設 業務施設 文教施設
医療厚生施設 遊興・娯楽・サービス施設 宿泊施設 工業施設 供給施設 運輸通信施設
官公署施設 その他施設 公園・緑地・お墓 建物のない土地
【出典】大阪市土地利用現況情報提供インターネットサービス

図2.4.1 事業所位置情報の提供例
(2)自然的原因による土壌の基準値超過に係る情報提供の取組
自然的原因による土壌の基準値超過については、種々の資料もあり、データがあれば正確な判断と基準設定も可能であると考えられる。例えば、鉱床地帯・その周辺などの鉱染地帯や変質岩帯の地域から道路工事等により発生し得る基準値超過土壌については、広域地質図、一部の地域の鉱染マップ、採石資源分布図を使って類推できる。一方、都市部の土壌を考えると、本来の自然的原因による基準値超過土壌と、過去の人為(不特定多数の人為を含む。)に起因する汚染者特定不可能な汚染土壌などが混在しており、汚染者負担の観点からは慎重な判断が求められる。
前述のとおり、自然的原因による基準値超過土壌の判断基準については、さらなる科学的データの蓄積・公開が重要である。こうした視点で、地質情報、自然起源汚染情報、人為汚染情報などの全国規模の各種地圏情報をGIS 化して情報提供するシステムである「地圏環境インフォマティクス」の構築が東北大学を中心に進められている。この中では、日本の重金属バックグラウンドの把握、地域によるバックグラウンドの差異の把握方法の開発、地質と環境因子との関連性の把握と、これらを共通のプラットフォームで把握する取組が進められている。
(3)各種ハザードマップの作成・公表
土壌汚染に関する情報ではないが、同様の安全に係るリスク情報として、自治体では、様々なハザードマップを整備、公表している。国土地理院が整備するハザードマップポータルサイトによれば、洪水、内水、高潮、津波、土砂災害、火山、そして地震防災に関するハザードマップが整備、公表されている。
洪水ハザードマップを例にとれば、全国で878 の市町村が印刷物の配布等により公表しており、社会的な認知が進んでいる。
2.5 諸外国における土壌汚染関連情報の提供に係る制度・取組
2.5.1 アメリカにおける取組

アメリカでは、土壌汚染情報は土地の安全性に係る公益的な情報と位置づけられ、多くの州が自ら情報を収集し、届け出や問い合わせがあった情報を元にして、土壌汚染情報のデータベースを作成し、ウェブサイトでの一般公開を行っている。
(1)ニューヨーク市
ニューヨーク市のブラウンフィールド問題への取組の一つとして、次の目的で「潜在的なブラウンフィールドを把握するための過去からの土地利用のテータベースの作成」が掲げられる。
・ 潜在的でかつ優先的な取組が必要なブラウンフィールドを見つけること
・ 地区毎のブラウンフィールドの再開発計画への基本的な情報を提供すること
・ すべての土壌汚染地の浄化と再利用活動の目標を明確にすること
データベースは、以下の2つの方法で作成されている。
・ 各種情報の収集(環境関連の発行物・データベース、歴史的な地図、電話帳、財務記録などからの情報収集)
・ 年毎のブラウンフィールド関連環境アセスメントへの要望についての問い合わせ
(2)オクラホマ州
社会環境の保全のためにブラウンフィールドの制度的管理が重要であるとの認識の下に、オクラホマ州環境局では、ブラウンフィールドを含めた土地利用の管理に向けて法制度を整備している。
土地利用管理の具体的な内容として、ブラウンフィールドの制度的管理についてのデータベースをくまなく蓄積している。
(3)マサチューセッツ州
マサチューセッツ州では、全米でもいち早く土壌汚染の制度的管理手法を導入している。AUL(Activity and Use Limitations)と呼ばれている活動用途制限を設けている。このAULは、現在及び将来の土地所有者に対してその土地で許容される活動や利用が示されており、許容されていない用途に変更する場合は、新しい用途に応じたリスクの評価と追加的な浄化
が求められる。
用途制限されている土地のAUL に係る情報は、州環境保護局のほかに自治体と郡不動産登記所で管理しており、この土地の再開発や土地取引に際しては、環境通知書によって土壌汚染の扱いが確認されている。
(4)カリフォルニア州
カリフォルニア州毒物管理局(DISC)では、すべての浄化修復活動を長期間管理する方針であり、以下の事項について実施している。
浄化修復用地の用途制限については、いろいろなメディアを用いて、情報を公表しており、もし、用途制限をする必要がないレベルまで浄化修復された場合は、用地リストから除外し、逆に用途に見合ったレベルまで浄化修復されていない場合は、必要なレベルまでの浄化修復を行う財政的な裏付けを要求する。
また、浄化修復活動が完了していない場合は、継続的に浄化修復活動を行っているかどうか定期的に検査する。
(5)ルイジアナ州
ルイジアナ州環境管理局(DEQ)では、用途制限のある自主的な浄化修復活動については、インターネット上で公表できるデータベースにより追跡的に監視している。
このデータベースでは、当該サイトの住所、用途制限、過去からの土地所有者、用途の履歴とともに危険物取扱いの有無の情報が、土地所有者からの届出に基づき登録されており、DEQ の承認が無ければデータベースから除外できない。
また、正確な情報が登録されていない場合は、当該サイトの取引契約を買い手側が解約できる根拠ともなる。
(6)ウースター市
ウースター市においては、プロジェクトに応じて様々なスキームでブラウンフィールド再生に取り組んでいる。その一つとして、2002 年から市役所の技術サービス部門を中心に、ブラウンフィールド再開発データベース構想としてデータベースの整備が行われている。
データベースは図2.5.1 のような3つの段階に分けて構築された。ウースター市役所は、2005 年までに200 以上のブラウンフィールド・サイトを確認している。これらのブラウンフィールド情報のデータベース構築によって、市役所は、より強固な情報基盤を持つことが可能となり、計画立案の過程において的確な意思決定が行えるようになると考えている。
2.5.2 ドイツにおける取組
ドイツにおいては、土壌汚染が存在するために開発がストップしているサイトに関する情報のみならず、産業跡地である等の理由により土壌汚染が存在するおそれがあるサイトに関する情報も収集し、地図上に落とし込んで公表している。
ドイツにおいては、都市計画決定の権限や土壌汚染地の浄化修復についての自治体の役割は極めて大きい。このため、土地利用計画の安定性を担保するためにも、土壌汚染情報の収集は重要となっている。土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動しているため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしている。
具体的には、自治体レベルで土壌汚染の可能性のあるサイトを把握して土壌汚染情報をマップに落として公表しており、また、土壌汚染に関する統計データも自治体から、州、連邦政府へと段階的に上げられて整備され、公表されている。
統計によれば、ドイツにおいては、ブラウンフィールドは最終処分場跡地と産業跡地という広い意味で用いられている。
【統計データにおける「土壌汚染」の分類】
・ ブラウンフィールドが疑われるサイト
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち旧堆積場
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち産業跡地
・ ブラウンフィールド
・ 浄化完了サイト
・ リスク評価完了サイト
・ 浄化中サイト
・ モニタリング中サイト
第一段階(基本的な情報を収集してGIS化する)
・情報収集(州政府・自治体・その他の情報源) ・データベースの構築
・データベースをGI Sへ移行・サイトプロフィールの設計
・データの分析・維持・更新手順の設計
第二段階(サイトの開発可能性を指標化)
・技術的なブラウンフィールドの定義・格付けの指標を検討
・時間軸による分析・詳細なケース・スタディを実行
・調査された補助金・パートナーシップ・イニシアチブ
第三段階(再開発の可能性を詳細に調査)
・土地利用分析・情報資源を再生プロジェクトと結びつける
・環境面の課題を評価・再開発の可能性を決定
・開発を誘引・再開発可能なサイトを突き止める

図2.5.1 ウースター市のGIS を用いたブラウンフィールド情報の整理と評価


3.事業所立地履歴マップ
前述したとおり、現時点において、自主調査結果など直接的な土壌汚染情報を全国網羅的に収集・整理することは極めて困難であるため、フェーズ?調査の一過程でもある事業所立地履歴をマッピングすることについて検討・整理した。なお、事業所立地履歴マップは、土壌汚染の可能性を示唆する情報であり、土壌汚染そのものの状況を示すものではない。
3.1 マップの作成方法
3.1.1 作成手順概要
マップの作成手順の概要を下のフローに示す。
基図の用意 現状の立地事業所 リストの作成 廃止事業所のリストへの追加 住所から緯度経度の取得
重複データの整理等
● 自治体が把握する届出施設
【水濁法(下水道法)特定事業場、PRTR届出施設、廃棄物処理業者等】
基図上へのプロット プロット位置の調整 作図
● 取得した緯経度は、街区レベルのデータであり、街区中心に位置するため、各敷地にデータを移動調整する。
● 住宅地図とリストに不整合がある場合は、Web情報などを活用して確認する。土壌汚染対策法 指定区域のリスト化

図3.1.1 マップ作成手順フロー
3.1.2 作成方法
(1)作成範囲

市町村単位で作成するものとする。人的活動が土壌環境に与える影響可能性を示すマップであるため、原則として市街地を対象とする。
(2)対象物質
「土壌汚染」状況は千差万別であり、サイト毎に最適な調査・対策方法を検討し、実施していくことが重要である。また、「土壌汚染対策法」が対象とする土壌汚染は、特定有害物質25 項目(鉛、砒素など重金属等14 項目 、及びトリクロロエチレンなど揮発性有機化合物11 項目)であるが、その他の規制物質や規制はされていなくとも土地利用の障害となり得る物質もあり、注意が必要である。
ガソリン、重油、潤滑油、灯油等の油分、ダイオキシン類、その他の化学物質(条例等において特に規制されている物質、臭気の強い物質及び色のある物質等)、要監視項目(22 項目)等の規制対象候補の物質などが調査対象となり得る。土地取引に際しての調査では、購入用途が住宅系である場合、履歴にかかわらず「特定有害物質(農薬類を除く)」「油分」「ダイオキシン類」を調査対象とするケースが多い。
不動産鑑定評価基準等を踏まえて策定された(社)日本不動産鑑定協会の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」では、「特定有害物質を中心に各自冶体の条例等及びダイオキシン類対策特別措置法において対象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば価格形成に大きな影響があるものとする。」とし、法令等による調査義務がないことのみで土壌汚染が無いとはできないとしている。
したがって、土壌汚染対策法の対象とする特定有害物質26 項目に限定せず、広く影響可能性を把握することとする。特定有害物質以外の人の健康や資産価値に対するリスク要因となる物質も念頭に置き、マップ作成のための事業所情報等を収集、整理する。
(3)基図の用意
基図としては、自治体が庁内で使用するGIS地図データの都市計画基図(1/2500 データ)を活用する。
(4)データ収集
【事業所データ】
土壌環境に影響を及ぼすおそれのある事業所のデータを収集・整理の対象とし、公表されている次のデータを活用するものとする。
? 水質汚濁防止法(下水道法)に係る特定事業場(ただし、し尿処理施設と指定浄化槽は含まない)
? PRTR届出施設
? 廃棄物処理・運搬業(一般廃棄物は廃棄物処理業のみ)
? 消防法に係る届出給油施設
? 日本工場通覧、工場名鑑、事業所リスト
【土壌汚染調査結果、措置状況データ】
土壌汚染対策法に基づく指定区域や調査猶予地についての情報、さらには届け出のあった土壌汚染調査結果及び措置の状況について、随時整理・更新する。GISシステムを活用することによって、マップ上の位置情報と詳細な調査結果を関連付けることも可能である。※
※ 自治体が庁内での使用を前提に、包括的な情報管理を目的として非公表のデータ(例えば措置対策が終了し指定区域が解除された土地に関する情報)をマップに表示することも可能である。しかしながら、この場合、当該マップについての情報公開請求への対応に留意しておくことが重要である。
なお、収集したデータについては、可能な限り実態と乖離しないように定期的に更新することが望ましい。異なる部局が管理するデータ更新状況を集約する体制の構築は、マップ情報の効率的な更新に資するものである。
3.1.3 収集データの種別
? 水質汚濁防止法(下水道法)に係る特定事業場
自治体が把握する水質汚濁防止法(下水道法)に係る特定事業場を整理する。特定事業場は、現状に加え、過去の立地状況も調査する。
特定事業場に関する情報としては、特定施設番号、特定事業場名、届出者、住所、放流先、排水量、有害物質排出の有無などのデータが、河川等の公共用水域の水質を管理する自治体の担当課に届け出られており、利用可能である。
水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するものである。したがって、公共用水域への排出水のない施設は規制の対象とならない。また、環境省中央環境審議会土壌農薬部会第3回土壌制度小委員会によると、有害物質使用特定施設以外で194件の土壌汚染が顕在化したとしている。これらを把握するためには、他の情報源からデータを入手整理する必要がある。
なお、ここでは、し尿処理施設(特定施設番号72)と指定浄化槽については土壌汚染と直接の可能性が小さいことから整理対象外とした。
また、特定有害物質の使用が届けられていない事業場を図示するかの議論はあるが、有害物質使用特定施設以外においても土壌汚染が顕在化していることを踏まえ、表示する方針とする。
? PRTR届出施設
PRTR届出制度は、下記の23業種、354物質が対象となる。データベースが提供されており、これを活用することができる。ただし、従業員数が21人未満の事業所は対象とならない。
なお、PRTR届出が制度化されてから年数も浅い(法律制定は平成11年7月)ため、現状データの整理のみとする。
個別事業所のPRTRに関する情報(化学物質排出把握管理促進法第11条に基づき開示するファイル記録事項)は、環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/kaiji/index.html)からダウンロード可能である。企業名、事業所名、住所、産業分類、排出物質、排出量などのデータを入手することができる。
【有害物質使用特定施設】
有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設のことをいう。水質汚濁防止法は、工場等から排出される水の排水及び地下に浸透する水の浸透を規制する法律であり、工場排水が川や海などの公共用水域に排出される場合に適用される。公共下水道が普及し、工場排水の排出先が下水道となる場合は、下水道法が適用される。下水道法でも水質汚濁防止法上の特定施設をそのまま規制対象の施設として規定されている。
土壌汚染対策法は、有害物質使用特定施設が廃止された場合は、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、 その結果を都道府県知事に報告しなければならないと規定している。
土壌汚染対策法で規制されていない物質について整理し、マップに表現することが適切であるかが論点となる。PRTR制度は環境への排出を把握するための制度であり、人の健康を対象とした土壌環境対策法とは法の趣旨が異なる。しかし、土地取引という視点では、資産価値の低減に繋がる物質の存在は表現する方針とする。
? 廃棄物処理・運搬業
自治体が把握する一般廃棄物処理業許可業者(ごみ処分業に限る)、及び産廃事業所の立地を整理する。情報は、業者名、所在地、区分(処理業、収集運搬業、処分業の区分)から構成される。
し尿処理運搬業などは、土壌汚染と直接の可能性が小さいと考えられるため、除外することが適切であると考えられる。PRTR届出制度の対象と同様に、一般廃棄物処理業は、ごみ処分業に限る。
なお、警察等が把握する廃棄物の投棄箇所に関するデータなども、それが明確なものであれば、自治体の判断で収集整理することができる。
? 消防法に係る届出給油施設
給油施設を把握するために消防法に係る届出施設リストを活用する。データは、自治体の消防担当が管理している。
? 工場名鑑、事業所リスト
戦後発行されている工場名鑑、商工名鑑、事業所リストに基づき、工場、事業場の位置、業種などのデータを、過去に遡り収集、整理する。日本工場通覧は従業員数が10人以上の製造業を掲載しており、1931年以降1997年までほぼ毎年発行されており、国会図書館で閲覧できる(図3.1.2 参照)。
工場名鑑は自治体単位で作成されている場合があり、一定以上の規模の工場を掲載している(図3.1.3 参照)。しかしながら、整理した事業所の位置関係を確認するための資料として活用する住宅地図については1970年より前のデータが入手困難となっている市街地も多いので、それ以前の正確な場所の特定に困難を生じる場合がある。
【PRTR届出制度】
「化学物質排出把握管理促進法」にて定義されている第一種指定化学物質(揮発性炭化水素、有機塩素系化合物、農薬、金属化合物、オゾン層破壊物質、アスベスト等の計354 物質)を使用する以下の対象23 業種の中で、従業員数が21 人以上で、対象化学物質の年間取扱量が1トン以上(カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ダイオキシン類、砒素及びその無機化合物、ベンゼン等、12 の特定第一種指定化学物質は0.5 トン以上)となる事業所は、環境への排出量(大気、公共水域、土壌)及び廃棄物や下水に含まれて移動する量を届け出ることが義務付けられている。
・金属鉱業 ・原油・天然ガス鉱業 ・製造業 ・電気業
・ガス業 ・下水道業 ・熱供給業 ・鉄道業
・倉庫業 ・石油卸売業 ・鉄スクラップ卸売業 ・自動車卸売業
・燃料小売業 ・洗濯業 ・写真業 ・自動車整備業
・機械修理業 ・商品検査業 ・計量証明業(一般計量証明業を除く。)
・一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る) ・産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処理業含む。)
・高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。) ・自然科学研究所

図3.1.2 日本工場通覧(1992 年)より抜粋

図3.1.3 千葉県工場名鑑平成15 年度版より抜粋
整理した事業所データの関係を以下の図に示す。

3.1.4 データの収集例
産業立地の見られる都市部の自治体として、札幌市西区と市川市を対象に、前記のデータ収集を試行した。次表に整理されたデータ数を示す。

上記には今回の資料調査で廃止が確認された事業所(市川市83 事業所、札幌市125 事業所)を含む。
?有害物質使用
特定事業場
日本工場通覧、工場名鑑、
事業所リスト
水濁法(下水道法)特定事業場
【し尿処理施設と指定浄化槽を除く】
消防法届出給油施設
PRTR 届出施設
廃棄物処理・運搬業
(産業廃棄物処理、運搬業、一般廃棄物処理業)
【一般廃棄物収集・運搬業を除く】
3.2 マップの表現方法
3.2.1 事業所立地履歴マップの表示種別
データの表示については、次の表示方法が考えられる。
1)事業所の立地履歴をシンボルで表示
2)事業所立地履歴のシンボルに加え、事業所の立地街区を網掛けで表示
3)事業所立地履歴のシンボルに加え、事業所の立地したメッシュを表示
4)事業所の立地街区を網掛けで表示
5)事業所の立地したメッシュを表示
3.2.2 事業所立地履歴マップの表示方法についての考え方
○ マップには土壌汚染対策法の指定区域を示すものとする。条例により土壌汚染に係る区域が指定され公開される場合には、当該土地についても表示する。なお、土壌汚染対策法第3 条第1項但書で調査が猶予されている土地、及び調査対策済みの事業所については、個別事業所の情報開示に係る自治体ごとのスタンスに応じて記載の可否を判断することになると思われる。
また、過去に自治体への報告があった自主調査結果については、原則として公定法(平成3年環境庁告示第46 号別表の測定方法の欄に掲げる方法をいう。)に基づいて行われた調査の結果であって、公開されているものに限り表示することが望まし
く、それ以外の情報の表示については自治体の判断によるものと考えられる。
なお、中央環境審議会「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)」(平成20 年12月)においては、「土壌汚染に関する情報について、埋没させることなく、関係者が容易に入手し、適切に活用することができ、適切に承継される仕組みが必要である。
また、対策が行われて解除がなされたという情報や調査の結果土壌汚染が発見されなかったという情報も含め、地方公共団体において、土壌汚染の状況を把握し、汚染原因の解明、汚染状況の履歴調査等に有効に活用すべきである。」としている。
○ 使用(保管)物質の届出を行っている事業場が少ないため、届出使用(保管)物質を示すマップの表示は行わない。ただし、十分な注意書きを付す等により、有害物質の使用(保管)届出記録の無い施設について、業種から潜在的汚染を想定し表示する方法も代替案として考えられる。
○ 事業所については、マップの対象物質を直接的に使用する業種や、間接的に使用する業種がある。表3.2.1 は、自治体が把握する業種別の土壌汚染調査基準値超過事例数を整理したものである。
このように、業種によって汚染原因者となる可能性は大きく異なるが、環境省中央環境審議会土壌農薬部会第3回土壌制度小委員会によると、直接的に使用する業種だけ汚染原因者となっているわけではない。
したがって、フェーズ1調査の支援というマップの位置づけを踏まえ、製造業は全ての業種を表示する方針とし、リスクの大小に応じて異なる表示方法を用いる。(本調査では、製造業について、総事業所数に対する累積基準超過件数が0.1%未満の食料品製造業等を、土壌汚染リスクは小さいと評価した。)
同様に、水質汚濁防止法の施行以前に事業所が立地した土地は、土壌汚染リスクが高くなると考えられるので異なる表示をする。?
○ 注意喚起を目的として、事業所が存在する区域を網掛けして表示する場合の境界は、街区レベルを基本とするが、対象区域を碁盤目状にメッシュで区切り、その中に存在する事業所の数で色の濃淡を変えて表示することなども可能である。メッシュで表示する場合には、事業所立地履歴がある街区とは異なる周辺土地まで表示範囲となり得ることについて
使用上の配慮を要する。
○ GIS を活用してマップを作成することによって、事業所に関する様々な情報(事業所名、使用物質名と使用量、設立・廃止時期、事業所連絡先、関係条例の届出の有無と内容など)を付随データとして記録する。これらのデータは、アクセス権限があれば必要に応じて参照することができる。




3.3 事業所立地履歴マップの公開・活用
3.3.1 事業所立地履歴マップの全体像
事業所立地履歴マップ活用の方法や管理のあり方について、作成過程も含め、図3.3.1 に図示する。
3.3.2 マップの活用方法
事業所立地履歴マップについては、「2.3土壌汚染関連情報の提供の目的と期待される効果」で整理した事項を踏まえ、以下に示すような活用方法が考えられる。自治体の判断によっては、マップの公開は行わず、?に示す目的で、行政内部に限定して活用することも想定される。
? 行政による活用
・ 市民や事業者からの土地の土壌汚染に関する問い合わせに対応する際に参照可能な情報となるものであり、業務の効率化に資することが期待される。
・ 土壌汚染土地の管理、特に制度的管理を行う土地の情報の承継において重要な役割を担う。加えて、飲用井戸の管理体制の構築に活用できる。
・ 民間から提出された土壌調査報告書に対して、内容をチェックする際のサポート資料としての活用が想定される。
・ 都市計画や公共施設の計画において、初期の事業構想段階で環境情報、コスト要因を概略把握するために活用できる。
? 土地所有者による活用
・ 企業であれば、自社所有不動産の売却等に絡む事業構想初期段階で、ER作成前の概略情報として活用することも可能である。
? 不動産取得を検討する者による活用
・ 国民や企業は土壌汚染によるリスクを特別なコストなしに概略把握することが可能となり、土地利用や土地取引を安心して行うことができる。
? デベロッパー等による活用
・ 事業構想初期段階で、ER作成前の概略情報として活用することも可能である。
? 調査会社及び調査発注者による活用
・ 調査者が情報の収集整理を効率的に行うことができる。加えて最低限確認されるべき情報を調査発注者も容易に確認できるため、最低限の水準を満たさないような調査結果を排除し、調査結果の信頼性向上が期待される。
? 金融機関及び保険会社による活用
・ 資産価値評価の予備的な検討に活用されるものと期待する。
3.3.3 事業所立地履歴マップを公開・活用する際の論点整理
事業所立地履歴マップに関する論点は、大局的には
?「作成の是非」、
?「公開の是非」、
?「公開する場合のプロセス、留意点」に整理することができる。
以下、これらに係る内容について、想定される主要な論点を整理する。

?「作成の是非」
ア) マップ活用の可能性
マップの使用者と活用方法が適切に想定されるべきである。また、行政が作成する場合は、一部特定企業の商目的使用が、マップ活用の主用途となるべきではないと考える。
イ) 費用対効果
マップの精度向上は重要である。一方、特定の土地の取引は頻繁に行われるものではないにも関わらず、全体を網羅し情報の精度向上を図ると、マップ作成コストが増大する。マップ作成に適正な費用対効果の見通しが求められる。
ウ) 土壌汚染対策法改正の動きとの関連性
中央環境審議会「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)」(平成20 年12 月)は、「土壌汚染に関する情報について、埋没させることなく、関係者が容易に入手し、適切に活用することができ、適切に承継される仕組みが必要」としており、マップの作成、公開が有効となる。
?「公開の是非」
エ) 知らずに不動産を取得する事態の回避
事業所立地履歴マップを公開することは、土壌汚染リスクのあることを知らずに土地を購入する等の可能性の低減に資するものである。
オ) 代替物出現の可能性
マップの作成に当たって使用した情報は、届出給油施設等の一部の情報を除き、一般に公開されている。したがって、行政でなくとも、研究目的や営利目的で大学や企業が同様のマップを作成することは難しくない。(同じ論拠により、一般市民でも土壌汚染に係る情報を入手する意志さえあれば、マップはなくとも情報入手が可能。)
カ) 自治体の責任の範囲

マップに示された情報の不完全性あるいは誤記が原因となり、マップ活用者に損失が生じた場合について、作成者や公開者の責任の範囲について留意する必要がある。
キ) 資産価値への影響可能性
マップの公開が、不動産価格に対して影響を与える可能性は否定できない。マップを公開することによる資産価値への影響が社会的に認容できる範囲であることが求められる。(ただし、汚染土地の資産価値がリスクや対策費を織り込んだ値まで低下する状況については、その原因をマップの公開に帰するべきではなく、過剰な影響について論点とすべき。)
ク) 貸し渋りの可能性
マップを公開することによって、土壌汚染そのものを表すものと誤解された場合には、金融機関が不動産の担保価値を低く査定し、いわゆる貸し渋りのような状況が生じ得ることも否定できない。
ケ) 自主調査の公開と所有権移転
仮に調査時点で所有者が、自主調査を行った土地について、情報のマップ表示を許諾しても、別の者に当該土地の所有権が移転することもある。新しい所有者が情報の開示を認める保証はなく、自主調査の情報についてマップ表示する場合には、慎重に対応する必要がある。
?「公開する場合のプロセス、留意点」
コ) 公開のタイミングとリスクコミュニケーションの必要性
公開を前提とした場合、適切な体制と手順で公開することによって、負の影響を低減することも可能であると考えられる。マップの公開に当たって、行政は、いたずらに住民の不安を煽らないよう、土壌汚染のもたらす意味、リスク等を正確に説明することが必要。

事業所立地履歴
データベース
住宅地図
? 水質汚濁防止法(下水道法)特定事業場ただし、し尿処理施設と指定浄化槽含まず
? PRTR届出施設
? 廃棄物処理・運搬業(一般廃棄物は廃棄物処理業のみ)
? 消防法に係る届出給油施設
? 日本工場通覧、工場名鑑、事業所リスト事業所立地履歴マップ(網掛け表示)
事業所立地履歴マップ
(シンボル表示)
基図
● 土壌汚染の潜在的原因者となる事業所が立地する(した)エリアを網掛け表示
● 該当するエリアの表示方法
【1案】 街区を表示
【2案】 100メートルメッシュの碁盤目表示
● 事業所の立地履歴をシンボルで表示
● 土壌汚染対策法に基づく指定区域、調査済み土地、対策済み土地、調査猶予土地を表示
【一般への公開を想定】
● 不動産業者、不動産購入予定の一般市民による利用
◇ 不動産取引に際しての土壌汚染リスクの概略把握
● 土地所有者による利用
◇ 所有地の土地改変検討にあたっての状況把握
● 金融機関、保険会社による利用
【自治体が公開情報として管理】
● 年1回程度の定期的な更新
【行政内部の利用を想定】
● 土壌汚染担当部局による利用
◇ 一般からの特定の土地に関する問合せ対応
◇ 汚染土地(土壌)の管理、飲用井戸の規制
● 都市計画部局、建設関連部局等による利用
◇ 都市計画や事業計画を策定する上での概略の環境情報、コスト情報
◇ 土壌汚染リスクに応じた土地利用の推奨
【自治体が内部情報として管理】
● データベース更新時にマップも更新するシステムの構築
● 調査対策済み情報を反映
作図処理
作図処理
(位置情報取得)
土壌汚染調査、
対策実施状況
データベース
位置確認
土壌汚染対策法等に係る情報追加
? 土壌汚染対策法指定区域
? 調査猶予施設
? 自主調査結果届出施設
? 調査、対策済み施設
図3.3.1 マップの作成、管理、利用方法(案)
【期待される効果】
● 土壌汚染土地に関する情報管理、及び適正な都市計画、公共施設配置に向けた検討の効率化
● 公共事業コストの低減
● 完全掘削除去以外の対策と制度管理の普及
【期待される効果】
● 事業構想段階でのフィージビリティ検討の効率化
● 不適切なERの減少
● 不動産入札における逆選択の減少
● 安心感の創出
4.自然由来重金属類分布マップ
4.1 マップの作成方法
4.1.1 マップ作成の目的
自然由来重金属類分布マップは、地盤の中に自然に存在する重金属類の濃度等を基に、表層地質区分別に、今後の調査等において確認を必要とするレベルを表示したものである。
このマップ作成の目的は、地下水の適正な管理と土壌の移動の管理にあり、エリア内で情報がないままに地下水を利用し続けることを防止することや、自然由来の含有量が元々高い土壌が他のエリアに安易に移動してしまうことを防止することにある。
自然由来重金属類分布マップは、ここでは4つのランク区分で表示することとしているが、その土壌の重金属含有量の絶対値を示すものでない。
このマップを活用することにより、今後の土地改変や何らかの調査の機会を捉え、土壌を適正に管理をすることや、更なる情報の蓄積を促進しようというものである。
本マップは、上記の目的以外の、現状の土地利用、周辺住民、土地価格などに影響を与えることを意図するものではない。
以上のことを、土地所有者や住民に対して十分に周知するとともに、開発業者、建設業者等に対して土地改変等の機会を捉えて地歴調査や簡易な土壌分析を実施すること等を推奨するものである。
4.1.2 作成手順
自然由来重金属類分布マップの作成の手順を図4.1.1 に示す。

図4.1.1 自然由来重金属類分布マップ作成の手順
マップ作成の対象物質、対象区域設定
基図及び地質図の準備
対象物質に係る土壌調査データ収集
対象物質に係る地下水調査データ収集
対象物質に係る土壌調査データ整理・分析
対象物質に係る地下水調査データ整理
対象物質の含有量及び溶出量の基準の超過データ整理
対象物質の地下水基準の超過データ整理
基図及び地質図へ基準超過場所のプロット
基準超過物質に係るランク区分の考え方・基準の検討
自然由来重金属類分マップの作成
4.1.3 作成方法
(1)マップ作成の対象区域
自然由来重金属類分布マップを作成するエリアを設定する。自然界に存在する有害物質については、広域的な視野から状況を把握する必要があるため、行政区域等を参考に可能な限り広域エリアを対象区域として設定する。
(2)対象物質
土壌汚染対策法に基づく有害物質のうち、自然界に存在する物質として、砒素(As)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、セレン(Se)及びクロム(Cr)の重金属、及びふっ素(F)、ほう素(B)を対象とする。
(3)基図
基図は地形図及び地質図との重ね図を用いる。
地形図は、対象物質が地質構造と深く関係していることから地質図と重ね合わせの可能な1/5 万のスケールの国土地理院発行の数値地図を用いる。
地質図は、独立行政法人産業技術研究所地質調査総合センター作成の「20 万分の1 日本シームレス地質図」のデータが収納されている東北大学大学院環境科学研究科が作成した「地圏環境インフォマティクス(GENIUS)」を用いる。この地圏環境インフォマティクスは、地質情報、重金属等の各種地圏情報を全国規模でGIS 化して情報提供するシステムである。
また、国土交通省で土地分類調査として1/5 万表層地質図、土壌図等の基礎情報が整備されており、市町村レベルのエリアであればこれらの活用も可能である。

図4.1.2 基図(1/5 万地形図と地質図との重ね図)の例
地形図:国土地理院の数値地図50000(地図情報)
地質図:東北大学大学院環境科学研究科「地圏環境インフォマティクス(GENIUS)」
(4)データ収集
対象区域において、過去に実施された対象物質に係る土壌調査結果及び地下水調査結果のデータを収集する。(表4.1.1 及び表4.1.2 に例を示す。)
また、参考として、地域において対象物質に係るバックグラウンドレベルを表すと考えられている産業技術総合研究所地質調査総合センター発行の「日本の地球化学図」(2004 年)を用いる。
この資料では、砒素、カドミウム、鉛、水銀など有害物質を含む約50 元素について、日本全国の約3,000 試料(試料は河川堆積物、1 試料10km×10km)を用いて地球化学図(元素の濃度分布図)を作成しており、全国的な濃度分布が把握できる。(表4.1.3 に例を示す。)










(5)土壌調査データの整理及び分析
土壌調査データについては、土地改変の可能性の高い地下0〜3m の表層地質を対象範囲とし、地質図の表層地質区分別に土壌調査データを整理した上で、対象物質に係る含有量、溶出量の平均値と標準偏差、及びそれぞれの自然的原因による含有量の上限値の目安及び溶出量基準の超過頻度等について検討する。

なお、重金属類に係る基準超過については、自然的原因と人為的原因とに判別する必要があるが、判別するには十分な資料と検討が必要であることから、ここでは判別は行わない。これまでの検討資料等において、自然由来と考えられているデータを取り上げる。
(6)地下水調査データの整理
地下水調査結果から、地下水基準を超過している地点の濃度データを整理する。土壌汚染は地下水汚染の原因の一つとなっており、地下水汚染がある場合には近傍での土壌汚染の存在が疑われるが、地下水は複雑な地下の中を広い範囲で流動していることから、その汚染の原因を特定することは相当に困難である。
地下水汚染がある場合には周辺での土壌汚染のあるおそれがあることから、参考として地下水汚染の位置及び濃度をマップに表示することとする。
(7)基準超過地点のプロット図の作成
土壌汚染対策法の指定基準等と照らして、重金属類の自然的原因による含有量の上限値の目安及び溶出量基準の超過地点、地下水基準の超過地点をそれぞれ抽出して、基図にプロットする。
(8)自然由来重金属類のランク区分の考え方
基準超過の見られる対象物質について、表層地質別に自然由来重金属類のランク区分の考え方・基準について検討する。
例えば、砒素の場合、表層地質別にランク区分を行うために、
?全含有量の平均値、
?自然的原因による含有量の上限値の目安(39mg/kg)の超過率、
?溶出量基準の超過の有無、
?地下水基準の超過の有無、の4 つの指標を用いることとする。
4 つの指標について、表4.1.4 に示すように配点し、表層地質別にそのスコアを合計する。この配点については、砒素の全含有量の平均値を基本指標として、その他の指標について基準超過の有無等により加点する方式としており、リスク面を考慮している。

表4.1.4 砒素に係るランク区分に用いる指標とスコア
全含有量の指標
?平均値
?自然的原因による上限値の目安(39mg/kg)の超過率
?溶出量指定基準の超過の有無地下水基準超過の有無
砒素の場合、表層地層別のスコア合計値により、表4.1.5 に示すとおり区分する。

(9)自然由来重金属類分布マップの作成
自然由来重金属類分布マップの作成については、一般に土地改変の深さは地上から−3mまでの範囲が大部分であることから、深さ0〜3mの表層地質を対象とする。
対象区域の表層地質別に(8)に示す基準に基づいて検討を行い、マップを作成する。
4.1.4 表現方法
自然由来重金属類分布マップは、1/5 万地形図及び地質図の重ね図を用いて以下のように表現する。
? 自然由来重金属類分布マップにおいては、ランク区分別に表層地質を色分けする。
? 土壌調査地点や地下水調査地点をプロットし、また土壌環境基準や地下水基準を超過している場合や自然的原因による上限値の目安の値を超過している場合は、その地点を○印で表示することがマップをよりわかりやすくするため、このような表示を行うこととする。
? さらに、基準超過地点においては、含有量や溶出量、地下水濃度を数値で表示することが考えられる。

表4.1.6 自然由来重金属類分布マップの色区分の例
ランク区分 ランク区分の考え方
A 自然由来の含有量が高いレベルで予想され、かつ基準超過のリスクが考えられる地層エリア
B 自然由来の含有量が中程度に予想され、かつ基準超過のリスクが少し考えられる地層エリア
C 自然由来の含有量が低く、自然由来の上限値の目安の超過や基準超過が低い頻度で予想される地層エリア
表示なし 自然由来の上限値の目安の超過がほとんどないと予想される地層エリア
4.2 マップの活用方法
4.2.1 マップの活用方法
自然由来重金属類分布マップについては、以下に示すような活用方法が考えられる。
? 行政のサポート資料
・ 地域における土壌環境に係る潜在的なポテンシャルを把握することが可能である。
・ 市民や事業者に対する地域の土壌環境に関する情報提供や啓発に活用するとともに、市民等からの相談等にスムーズに対応することが可能となる。
・ 民間から提出された土壌調査報告書に対して、自然由来の基準超過かどうかの判断の際のサポート資料として活用することが考えられる。
例えば、以下のような要件に適合した場合には、自然由来と判断できる。
1)自然由来の基準超過の可能性のあるエリア内にあること
2)地歴調査の結果、対象物質を使用した経歴がないこと
3)対象物質の検出値が一定の範囲内にあること
? 土地所有者への情報提供による注意喚起
・ 土地所有者に自然由来重金属類分布マップに関する情報を提供することにより、土地所有者は自己所有地のある周辺地域一帯における土壌環境の状況を把握することが可能である。
・ 土地所有者は、あらかじめ所有地の自然由来重金属類の潜在可能性を把握できるため、リスクが比較的高いエリアでは土地改変や用地売却などの際に土壌環境についての留意が必要
である旨の認識を持つことができる。
・ このため、域外へ土壌の搬出を行う際には、リスク評価に応じて土壌調査を実施するなどの対応を行いやすくなる。もし、調査より自然由来の基準超過がみられる場合には、域外へ土壌をできるかぎり持ち出さないように敷地内で封じ込めなどの措置を行い、土壌の拡散や健康被害の発生を防止することにつなげることができる。
? デベロッパー・工事事業者への拡散防止に関する啓発
・ デベロッパーや工事事業者に対して、自然由来重金属類分布マップに関する情報を提供し、開発や工事を実施しようとする土地についての注意喚起を促すことができるため、工事の際の事前の対策や拡散防止に役立つ。
? 市民等への情報提供による理解の向上
市民や事業者等に自然由来重金属類分布マップに関する情報を提供することにより、市民等は地域一帯における自然由来の土壌環境の状況について把握し、より理解を深めることができる。
4.2.2 自然由来重金属類分布マップの活用マニュアル(案)
(1)行政サイドとしての活用
土地売買や土地改変の際に、開発事業者、調査業者や土地所有者から土壌調査についての事前相談を受けた場合や、提出された土壌調査報告書に対して、行政サイドとして以下に示すような手順で対応することが考えられる。
なお、以下に示す推奨、助言等の手続きは、法律の根拠を伴わない行政指導となる場合が多いことに留意する必要がある。
1)A又はBのエリア内にあって調査が行われていない場合
A又はBのエリア内にあって調査が行われていない場合は、自然由来重金属類分布マップ情報を提供するとともに、調査の目的によって追加の調査(例えば砒素が調査項目に入っていない場合)などの実施を推奨する。
→ 土地取引の際にバックグラウンド調査の実施を推奨する(人為汚染でなく自然由来であると証明した方がよい場合)
→ 工場管理などにおいて、土地改変や土量搬出の際にバックグラウンド調査の実施を推奨する
2)調査が実施され報告されてきた場合
土壌調査が実施され調査結果が報告されてきた場合に、行政サイドとしては図4.2.1 に示すフローで対応することが考えられる。
(2)各者への周知
行政サイドとして各者に対して広報誌、HPなどを使って周知していく。
? 開発事業者、調査業者、不動産業者及び土地所有者自然由来重金属類分布マップは、地盤に元来存在する重金属類について、表層の地質単位でのランク区分を表示したものである。このマップ作成の目的は、地下水の管理と土壌の移動管理にあり、エリア内で情報がないままに地下水を利用し続けることを防止することや、元々含有量が高い土壌が他のエリアに安易に移動してしまうことを防止することにある。
開発業者、調査業者及び土地所有者に対しては、上記の目的を理解していただいて、土地取引や土地改変の機会をとらえ、履歴調査やサンプリング分析等の実施と結果報告を行うことが望ましいことを助言していく。
また、土地取引の仲介を行う不動産業者に対しても、調査記録の有無等など土壌汚染に関する情報の収集を行うことが望ましいことを助言していく。
? 一般住民(土地売買や形質変更の予定のない土地所有者を含む)住民や土地所有者に対しては、自然的な土壌環境の状況に関する情報を提供して、認識や理解をより深めてもらい、エリア内で情報がないままに地下水を利用し続けることを防止す
ることや、元々含有量が高い土壌が他のエリアに安易に移動しないように防止していく。

図4.2.1 行政サイドでの活用・対応の手順(土壌調査が実施されている場合)
土壌調査が実施され、調査結果が報告されてきた場合
自然由来重金属類のランク区分がA又はBのエリア内
自然由来重金属類のランク区分がC又は無印のエリア内
含有量が自然的原因の上限値の目安の範囲内
含有量が自然的原因の上限値の目安の範囲を超過(明らかに大幅に超過)
過去に砒素等の使用履歴がなく、土地造成時に持ち込まれていないことを十分に調査している場合
溶出量基準の範囲内、かつ近傍に地下水汚染がない
ケース1
指示はなし(搬出土チェック)
ケース2
認識されない地下水使用の有無の精査と地下水汚染がある場合は詳細調査の実施を指示
溶出量基準を超過し、その地層で現れる範囲を超えており、かつ近傍に地下水汚染がある
過去に砒素等の使用履歴がなく、土地造成時に持ち込まれていないことを調査していない場合
ケース3
人為汚染がある場合はそのボーダーを明確にする調査の実施を誘導
自然由来かどうかの判断を求められた場合は、過去に砒素等の使用履歴がないこと、土地造成時に持ち込まれていないこ
とを再調査で確認することを指示(調査されている合でも再検討が妥当)
ケース4
再調査の結果、人為汚染がなければ、行政として地下水管理を実施するエリアとする
砒素は調査項目に入っていない、又は行われていてもCか無印の範囲内
特に砒素の使用履歴がないこと、土地造成時に持ち込まれていないことを調査で確認している
含有量が自然的原因の上限値の目安を超過
自然由来かどうかの判断を求められた場合は、過去に砒素等の使用履歴土地造成時に持ち込まれていないことをすることを指示(調査されている場合でも再検討が妥当)
ケース6
再調査の結果、人為汚染がなければ、行政として地下水管理を実施するエリアとする。
必要に応じて評価図を修正
ケース5
指示はなし
(溶出量値が極端な異常値でない限り)溶出量基準を超過し、その地層で現れる範囲を超えている使用履歴等の調査を指示
4.2.3 自然由来重金属類分布マップ例(仮想案)

【参考資料】

参考1.自然由来重金属類の概要と基準等
(1)自然由来重金属類とは
・ 自然的原因により基準超過の可能性のある有害物質として、砒素(As)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、セレン(Se)及びクロム(Cr)の重金属、及びふっ素(F)、ほう素(B)があり、温泉や鉱染帯地域、岩石中などに含まれて自然界に広く存在している。
・ 海域ではふっ素(F)及びほう素(B)が基準を超過して検出されやすいため、ふっ素(F)及びほう素(B)は海域では環境基準が適用されない。
・ 多くの都市部の浚渫土砂による埋立地では、鉛、砒素、ふっ素が基準を超過して検出されるケースがある。
・ 土壌汚染対策法では、第二種特定有害物質(砒素などの重金属とほう素、ふっ素)の自然由来の基準超過については対象外とされているため、人為的な汚染と識別する必要がある。
(2)特徴
・ 含有量が一定の範囲内である、溶出量も少ない場合が多い
・ 一般に広域で観測され、人為由来を示す局在性がない
・ 平面や深度調査でも同程度の濃度が観測される場合が多い
・ 調査地域の堆積環境と対象物質の因果関係が認められる
(3)自然由来重金属類の基準等
自然由来重金属類については自然的原因による含有量の上限値の目安や指定基準等がある。
・ 指定基準とは、土壌汚染対策法において土壌汚染がある土地として評価される指定区域の指定に係る基準であり、土壌溶出量基準と土壌含有量基準がある。土壌溶出量基準は環境基本法に基づく環境基準と同じ値である。
・ 第二種特定有害物質(重金属類)については土壌溶出量調査と土壌含有量調査を行う。

参考2.土壌溶出量基準に適合しない場合の判定基準
環境省「土壌汚染対策法の施行について(環水土第20 号、平成15 年2 月4 日)」における「(別紙1)土壌中の特定有害物質が自然的原因によるものかどうかの判定方法」において、自然地盤上に発見された基準超過であって、土壌溶出量基準に適合しない場合の判定基準として、以下の3 つの観点からの検討を行い、そのすべてについて以下の条件を満たすときは、
自然的原因によるものと判断することとしている。
(1)特定有害物質の種類等
自然地盤上に存在し、土壌溶出量基準に適合しない可能性のある特定有害物質は、砒素、鉛、ふっ素、ほう素、水銀、カドミウム、セレン、六価クロムの8 種類のいずれかとされ、土地の履歴、周辺の事例や地質的状況、海域との関係等を総合的に勘案し、次の事項を踏まえつつ判断する必要がある。
?)砒素、鉛、ふっ素及びほう素については、自然的原因により土壌溶出量基準に適合しない可能性が高いこと
?)溶出量基準の10 倍を超える場合は人為的原因である可能性が比較的高くなり、自然的原因であるかどうかの判断材料になり得ること(しかし、自然的原因である場合もあり得ることに留意が必要)
(2)特定有害物質の含有量の範囲等
特定有害物質の含有量が概ね表4.2.2 に示す濃度の範囲にあることとする。その際の含有量の測定方法は、土壌汚染状況調査における含有量調査の測定方法によらず、全量分析による。なお、表4.2.2 に示す濃度の範囲を超える場合でも、バックグラウンド濃度との比較又は化合物形態等の確認から、自然的原因によるものと確認できる場合は、自然的原因と判断する。

表4.2.2 自然的原因による含有量の上限値の目安
特定有害物質
砒素 鉛 ふっ素 ほう素 水銀 カドミウ セレン 六価クロム 上限値の目安 (mg/kg)
39 140 700 100 1.4 1.4 2.0 −
(注)含有量の上限値の目安の値は、全国主要10 都市で採取した市街地の土壌中の特定有害物質の含有量を全量分析によって測定した全量値で、統計解析から求めた値(平均値+3σ)である。なお、鉱脈・鉱床の分布地帯等の地質条件によっては、この上限値の目安を超える場合があり得ることに留意する必要がある。
(3)特定有害物質の分布特性
特定有害物質の含有量分布に、当該特定有害物質の使用履歴のある場所等との関連性を示す局在性が認められないこととする。
5.関係者意見等
前掲の3.及び4.で示した作成方法等を基に、本検討会委員や利害の及ぶ可能性のある業界等関係者から意見を聴取したところ、以下に示すとおりであった。
5.1 検討会委員意見
(1)マップ作成の必要性・メリットについて
?マップの作成と活用の必要性
一般論として、このようなマップが使われることは賛成である。まさにヨーロッパではこのような事業所立地履歴マップが提供されており、また自然由来のマップは作成している最中であるが、それなりに整備している。
このようなマップがあると、冷静な議論ができ、浄化の目標もすべて掘削除去ではなく、環境リスクの観点からベストな対策の選定についての合理的な判断ができる。また、事業所があれば土地は汚れていて当たり前という世論が醸成されることになる。
?土壌汚染対策法の改正によりマップの必要性が高まる
土壌汚染対策法の改正による平成22 年からの施行予定に併せて、土壌環境に係るマップの必要性が高まり、全国レベルでこのようなツールを持たなければならないことになる。
環境行政にとっても、このようなマップが平成22 年以降は一定程度必要になる。
?自然由来のマップの必要性
自然由来のマップは基本的に歓迎すべきことで、全国中で作成を促進すべきである。これまで、このようなマップがないために現場は非常に困っている。まず、このようなマップが共有化されることが必要で、これを基に議論ができる下地がないと、自治体によっては自然由来というだけでは受け付けないところもある。このような現状を少しでも変えていくために、このようなインフラが必要と考えられる。
また、工事の掘削土壌に自然由来による基準超過のおそれがあるかどうか事前に把握できるので、基準超過土壌処分に係る工事費の追加発生や工事期間延長といった問題も回避できる。
公共事業では、自然由来の重金属データがないと頓挫し、余計な経費が大きく発生することはもう目に見えていて、ある地域の地下鉄建設では砒素、カドミウムの問題が事前にわかっていたため、技術検討会で議論した結果を公開して適切な処置を講じたゆえに、工事費が数十億円も圧縮できた例がある。
現在では、自然由来の重金属データの調査・収集は不可欠となっており、どういう公開の仕方が社会にとって適切なのかという議論を行うべき段階に来ている。
(2)公開のデメリット
?土壌汚染マップと誤解されるおそれ
事業所の履歴情報をプロットしたはずのマップが、いつの間にか土壌汚染マップと誤解を生じてしまうおそれがあるのではないか。こうしたおそれがあると、このマップが公表された場合にどのような影響が生じるのか全く読めない。
?自然由来の汚染のある地域として悪いイメージが定着するおそれ
地域一帯が自然由来のリスクの高い地域として悪いイメージが定着すると、域外に土を搬出する場合はすべて色がついたものというレッテルを張られる懸念がある。
?住宅等を購入した土地所有者への影響

土地の履歴を知らずに住宅等を購入した土地所有者にとって、事業所立地履歴マップに色がついていることは全く寝耳に水の話で、調査して基準超過が判明した場合は、直接売主にクレームがいくことになる。このようなケースが多く出てくると、100 ?程度の小さな土地の調査でもリスクコミュニケーションは大変であり、この面で対応できる調査会社や専門家がいると
は思えないので、事業所立地履歴マップにはこのような面でのリスクもある。
?自治体への過度な負担
土壌汚染対策法の改正で対象範囲が拡大すると、自治体に多くの案件が持ち込まれて負担が大きくなることに加えて、このマップへの対応も求められるため、自治体にとって相当な負担となるおそれがある。
土地取引では、1週間以内で行政の了解をとって決済する必要がある場合もあり、行政がこれに対応できる容量がなければ売買に支障をきたすことになり、実体マーケットへの影響が懸念される。
(3)公開の是非と理由
【公開に賛成の意見】
?環境問題については情報公開が大切
環境問題は、基本的に情報公開することが大切という認識であり、情報公開するという姿勢はよいことである。また、情報公開により新規の土地購入者が汚染の可能性のある土地を購入してしまうリクスや、汚染を知らずに地下水を飲み続けるという健康被害を回避することができる。
?事業所立地履歴マップの公開
事業所立地履歴マップは公開されている既存のデータを用いてわかりやすく表示するものであるので、公開してもよい。
?自然由来重金属類分布マップの公開
民間の立場からは自然由来重金属類分布マップをどんどん公開してほしい。自然由来の判断についての行政協議のサポート資料となる。
【公開に反対の意見】
?公開請求を受けた場合にデータが一人歩きするおそれ
情報公開請求等でマップが出ていったときにどのように扱われるのかについても十分留意する必要がある。条例で原則公開となっているので、非公開の資料も請求を受ければそのまま公開される可能性がある。内部資料といえども、データがひとり歩きをしかねない危惧が懸念される。
?今すぐ公開するのは金融面でもリスクがある
今すぐ公開するのは、金融面からもリスクがあると思われる。金融庁による金融検査マニュアルにより土壌汚染を含めた環境汚染を評価しなければならないが、土壌汚染リスクをどう担保評価に反映するかは、銀行によって差異がある。土壌汚染対策法で指定区域になると相当厳しく差し引くけれども、そうではない土地は、調査等のコストもかかるので、金融機関にとっ
ても対応に差がある。
?公開については土壌汚染対策法が改正された後でよい
マップを広く知らせることはよいが、いきなり出てしまった場合に土地所有者や近隣の所有者に与えるデメリットはかなりある。土壌汚染対策法が改正され、ある程度整備された後に対応するということでも遅くはない。
?自然由来重金属類分布マップは自治体での検討結果と齟齬が生じるおそれ
自然的原因の砒素の判定方法の確立のために自治体側で委員会を設けて、表層土壌調査を加えて詳細に検討している最中であるため、自然由来重金属類分布マップが委員会での検討結果と異なる可能性があることから、自然由来重金属類分布マップは非公開とするのがよい。
また、マップについて、地層のどの深さまで見るかとか、金融面でのリスクとかを厳密に把握・整理してからでないと、かなりの混乱が予想されるので、当面は公開しないのがよい。
?公開については各自治体の判断
マップを行政内部だけに留保しておくのか、公開するのかは、個々の自治体の事情に応じて判断せざるを得ない部分があり、自治体の判断に任せるのがよい。
(4)公開する場合の条件
?データの信頼性が重要
マップの公開に際してはデータの信頼性が重要であり、公表されているデータを集約・整理して利用していくことはよい。
?公開に際して市民との十分なリスクコミュニケーションが必要

この化学物質はどういうものか、土壌、地質はどういう構成をしているのか、こういった面については、市民のみならず不動産業者もきちっと理解していないケースが多々ある。
土壌汚染についての情報公開の仕方によっては、市民に誤解を与えるおそれがあるため、ただ公開するというだけではなく、その下地として、十分なリスクコミュニケーションを通じて市民に基礎的な知識を提供することも必要である。
?公開するためには行政側の体制整備が必要
土壌汚染対策法の政令市のように、保健所行政とも一体的に連携できる体制がある場合はよいが、そうでない場合は、情報公開と同時に一体的にやれないという課題がある。
今後、土壌汚染対策法の改正の動きに併せて行政側の体制を整備する必要がある。
?要調査マップでないことを説明することが必要
事業所立地履歴マップは、(法律上調査が必要という意味での)土壌汚染の要調査マップではなく、全く土壌汚染対策法の対象になっていないものも含まれる事業所の立地マップであることから、マップに掲載されたとしても調査する義務はない。従って、フェーズ1調査をサポートするマップとして活用できるように、公開していく必要性があると考えられる。
要調査マップではないことをきちんと明記し、説明していく必要がある。
(5)公開の仕方
?自然由来から情報を公開
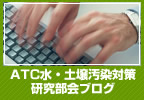
自然由来については、情報をある程度公開していく方向が重要で、まず自然由来の堆積状況から伝えていく。地方自治体では、自然由来の堆積物の判断に関していろいろな問題が生じている。日本の国土の地層は大きな特質があることを認識した上で、自然堆積物をはれものにさわるという扱いでなく、きちんと説明した上で土地取引をすべきである。
土地売買において重要な役割を果たす宅地建物取引主任者が、重要事項説明の中で、日本の国土についてある範囲できちんと説明して、市民も理解することをしていかない限り、土壌汚染リスクに対する過大な反応がいつまでも続くことになる。現場では、土壌汚染を全くゼロにしろといわれるけれども、ゼロにすることは本当にナンセンスなことである。
?行政で一斉に公開するのがよい
特定の都市のみで先行的に公開してリスクを抱えるよりは、行政側が一斉に実施することがよい。
?公表するタイミングが重要
マップづくりは大変すばらしいことでも、公表のタイミングは相当に慎重でないと、中小企業に対して、貸しはがしまで及ぶかどうかはわからないが、何らかの影響が出るのは避けられない。
?自然由来重金属類分布マップの公開の仕方
仮に自然由来重金属類分布マップを公開する場合でも、このマップを踏まえて自治体でも詳細に検討されており、新たにきちんとしたものが自治体から出される形になっていることを注記することが必要である。そうしないと、大変齟齬が生じることになる。

?段階的な公開
マップがいろいろ活用されて新しいビジネスや市場が生まれることは、大変いいことと評価する一方で、どのように使われるかわからない面もあるため、何か悪い影響が生じたら直ちに直していくというように、少しずつ段階的に公開していく方がよい。
いきなり公開するとハレーションがあるとすれば、とりあえず新たな被害を防ぐ観点から始めて、土壌汚染に対する認識が進んだ上で公開していく。
(6)事業所立地履歴マップの作成に関する意見
?街区単位よりもメッシュ単位のマップがよい
メッシュ又は街区単位で着色したマップは、場所によってかなり面積の大きさに違いがあるので、随分印象が変わる。街区単位よりもメッシュ単位で表した方が、ある意味平等である。
また、メッシュ図は、街区単位の図と比較して、面積が小さくなっている印象を与えるので、二者択一であれば、メッシュ図のほうがよい。
なお、100m メッシュ図についてきちんと説明がされないと、土地所有者がなぜ色がついているのか理解に苦しむといった懸念がある。
?目的によって対象とするデータの範囲が異なる
マップ作成の目的が、土地取引のためか、環境リスク把握のためかによって取り扱う事業所データの範囲が明確に異なってくる。土壌汚染対策法の改正の議論の中で、地歴調査で調べるべき範囲が設定されれば、その範囲の施設に限定してリスト化すればよいが、ここでの情報はそれを超える可能性がある。土壌汚染対策法が今回改正されても、ダイオキシンは対象になら
ないが、土地取引の実態ではダイオキシンまで対象としていると考えられるので、そのギャップをどう扱うかの話は残る。
?マップ作成の精度の問題
事業所立地履歴マップの精度について、10m メッシュ程度で行えば正確になるが、費用対効果の問題もあるのでどこまで詳細にできるのか、精度の問題がある。
(7)自然由来重金属類分布マップの作成に関する意見
?自然的原因の上限値の目安の全国一律的な基準値の見直し
環境省において、自然的原因の上限値の目安の全国一律の値を変えることについて現在検討中である。全国一律的な基準値(砒素の場合は39mg/kg)について、札幌市が独自の基準をどう出すかについては非常に興味があるところであるが、全国一律基準がそもそも成り立たないという共通認識を持つべきであり、それに対してどう評価すべきかというふうに発想を変えていかないと、混乱が生じることになる。
?全国的なマップづくりには多くのデータ数が必要
全国的にマップづくりを進めるには、データを増やすことが不可欠である。今回のように地質図をベースにしてデータを集積して、スコアをつけてリスクをカテゴライズしていく方法論は、おそらくその方向に向かうと考えられる。ただし、詳細な数値をどうす
るかという議論はあるが、例えば、10、20、30 という区切りの数値はこれから経験値を積み上げることによって修正していけばよい。
?担保評価の中に日本の地質的な特性を考慮すべき
これまで日本の土地の地質的特性を考慮されずに不動産取引をされてきたことの方が異常である。もともとこの地域は砒素が高目に出るところであるから、調査で砒素が高いからといって、この土地の担保は差し引くべきでないというコンセンサスが得られるようにしていくべきである。
?自治体の判断をフォローするガイドラインが必要
自然由来重金属類分布マップと事業者から提出された土壌調査報告書を踏まえて、自治体が自然由来かどうかを判断することになるので、逆にそれを判断した自治体を守ってあげるような制度設計も必要ではないか。自然由来と判断した責任を行政官がすべて負わなければいけないということは怖いことであり、技術的にここの線でこの地層には出る可能性が高いという整理をしてマップ化することは賛成である。
それを運用するときに、受け手側の自治体がしっかり判断できるガイドラインをつくらないと、安全サイドに流れて、今と変わらなくなる。
?土壌汚染対策法改正に向けた準備が必要
改正土壌汚染対策法の平成22 年運用に向けてこれから準備をしていくことが必要であり、行政側が特例区域(*)なのかどうかという判断を迫られるため、環境部局としては自然由来マップを持つことが必要な時を迎えるというふうに認識せざるを得ない。
実際自然由来については、日本の大都市の多くで砒素や鉛、ふっ素等が確認されており、そこは特例区域として妥当と判断すれば、土地所有者は調査しなくてよいとするのがねらいである。そこのエリアがどの範囲までか、既存の情報や地質図から一定程度類推したものを持っていないと、判断がつかなくなる。
(*)特例区域とは:中央環境審議会答申「今後の土壌汚染対策の在り方について」(平成20 年12 月19 日)において、海面埋立地の敷地はふっ素等の海水に含まれる自然由来成分やその埋め立てられた物質により指定基準を超過することが多いが、汚染土壌の搬出時の措置、形質変更時の土壌の飛散の防止措置を講じていれば、人の健康に被害が生じるおそれがないことから、土地所有者等の申立てにより土壌汚染があると見なす区域として特例区域の指定が盛り込まれていた。しかし、閣議決定された土壌汚染対策法改正案ではこの制度は盛り込まれなかった。
?臨海部埋立地の取り扱いの問題
例えば砒素の基準(0.01mg/L)はかなり厳しくなっており、海岸部において昭和30〜40 年代頃に埋め立てたときは合法であったが、今では基準超過となっており、埋立地は人為的汚染と考えるべきであろうが、その取り扱いについては明確な結論が出ていない。実際にフッ素の濃度は、海域の土壌による埋立てで、この土地全体が海に近いような値になっている状況もあ
る。
?札幌市では自然的原因の砒素に関して詳細に検討中
今回の自然由来重金属類分布マップは表層地質ごとであるが、札幌市ではさらに土質区分、河川の流域区分、深度区分、それから行政区区分など、多面的に検討している。
また、環境省が示している自然的原因の砒素の上限値の目安(39mg/kg)について、札幌市では、道内屈指の温泉や大きな旧鉱山が2つあるという地域特性に合わせた札幌市版の上限値の目安についても検討している。
この結果について札幌市としての判定区分を公開し、これによって土壌調査結果を判定していくことを考えている。また、併せて圏外に搬出するための札幌市版の搬出基準等に関する事項についても今後検討していく予定である。
5.2 ヒアリング結果
各業界関係者にマップの公開のメリット、デメリット、公開の是非、公開に際しての要件等についてヒアリングした結果の概要は以下に示すとおりである。
(1)中小企業関係団体
【公開のメリット】
?土地所有者にとって早期から適切な対応が可能
中小企業にとって事前に所有地の状況を把握することができれば、早期から負担等に適切に対応することができるので、廃業時などに土壌汚染の危惧から土地をそのまま放置することが少なくなる。
?中小企業にとって経営判断やシンビジネスの立ち上げに有力な情報
中小企業にとって、土地という重要な経営資源についての情報が増えるのは大変よいことで、速く、容易に情報を把握できることは大きなメリットである。とりわけ、転廃業や事業再生等を行う際の経営判断に有益である。
また、創業者が新ビジネスをスタートアップする際に、土壌汚染リスクの高い土地での創業を回避することが可能である。イメージ戦略で創業する場合に、自然由来による汚染が存する土地に立地しているなどと言われると、いきなりダメージを受けるので、スタートアップ時の経営が大変不安定な状況の中で、このような情報はメリットになる。
【公開のデメリット】
?所有地に係る情報を公開されることに対する抵抗感
土地所有者にとって、一般の人々が自分の土地についての情報を持つのは大変嫌なことであるという、心理的な抵抗感がある。
?近隣とのトラブル発生など操業への影響のおそれ
土壌汚染の可能性があると、すぐ近隣問題になって風評被害が生じるおそれがある。マスコミ等から子どもの健康を害するのではという記事が出ると、操業できなくなるおそれや町内会などコミュニティに影響するおそれがある。

?業界にとってのイメージダウン
マップの中に「クリーニング」、「ガソリンスタンド」という固有の業界が特出しされると、業界のイメージダウンになるおそれがある。
ガソリンスタンドは土壌汚染対策法の対象外であり、施設ごとに土壌汚染の可能性や対象物質が異なるので、他の業種と同じように一律に表示されることについては工夫が必要である。
?土地の担保価値低下による資金繰りの困難性
今までにない大変な景気悪化の状況下で、中小企業が直面している一番の問題は貸し渋り、要するに資金繰りの問題であり、土壌汚染のおそれにより土地の担保価値が下がって、貸し渋りの一助になることは一番不幸なシナリオである。
【公開の是非】
?当面は行政内部用としての扱い
マップの公開は時期尚早であり、当面は行政内部用の扱いがよい。
【公開する場合の要件と公開の仕方】
?ディテールも含めた正確な広報が必要
マップを公開する場合、ディテールも含めた正確な広報が大変重要である。このようなマップは活用の仕方がいろいろ考えられるが、マスコミを中心とする情報のひとり歩きは大変困ることになり、地域住民が土壌汚染として捉えた場合は、健康被害がなくても学校やPTAで大きな問題として取り上げることもあり得る。
?中小企業に対する十分な配慮が必要
中小企業は地域のコミュニティを維持するためにいろいろ苦労しているので、特に初期の段階で「土壌汚染マップ」などとネーミングされないように、十分な注意を払う必要がある。最初のイメージにとらわれて、そのまま固定観念で流れることを大変懸念する。
中小企業や家族操業の零細企業に対して十分に配慮しているというメッセージが伝わるような形でマップを公開していくべき。
?段階的な公開
マップがいろいろ活用されて新しいビジネスや市場が生まれることは、大変いいことと評価する一方で、どのように使われるかわからない面もあるため、何か悪い影響が生じたら直ちに直していくというように、少しずつ段階的に公開していく方がよい。
(2)石油輸送会社
【公開のメリット】
?フェーズ1調査の簡略化が可能
不動産取引時のフェーズ1 調査で、土地の履歴がわからず苦労しており、費用がかかるとか、結局明確な経歴がわからないことがある。このようなマップがあれば、フェーズ1調査における作業が簡略化できて有効である。

?自然由来の判定に有力な情報
自然由来かどうかの証明で、自治体と協議をする際に、このような情報があれば、大変有効に活用できるのではないか。また、工事の掘削土壌に自然由来による基準超過のおそれがあるかどうか事前に把握できるので、汚染土壌処分に係る工事費の追加発生や工事期間延長といった問題も回避できる。
【公開のデメリット】
?ガソリンスタンドへの配慮
ガソリンスタンドは、現状は土壌汚染対策法の対象外で、施設ごとに土壌汚染の可能性とか対象物が違うので、他の業種と一律同じように表示されることについては工夫が必要である。
?土地評価へのマイナス影響や土壌調査が必要な土地となるおそれ
マップに色塗りして公開された土地は、土地評価額が下がるとか、必ず土壌調査をしないと売れない土地になる可能性がある。
街区単位での色塗りの場合は、その隣も同じ色で塗られるので、隣からクレームがつけられる可能性がある。例えば、有害物質の使用経歴がないにもかかわらず、売却の際に土壌調査をしなければならいという場合に、隣から土壌調査費用の負担を求められる可能性が生じる。
?対策済みの土地も一律に色塗りされることは問題
不動産売買時に自主的な土壌調査・対策を既に実施した土地についても、一律同じ色で塗られることは問題である。調査・対策の実施状況を反映できる仕組みが必要である。
【公開の是非】
?行政内部用として使われるのがよい
情報公開請求等でその資料が出ていったときにどういうふうに扱われるのか。その辺も十分注意が必要である。マップの公開は時期尚早と考えられる。
【公開する場合の条件と公開の仕方】
?土壌汚染リスクに関する一般への周知が必要
マップ公開については、土壌汚染のリスクを一般の方に広く十分に周知した上で行うべきである。
?過去の調査・対策の実施結果を反映
過去の土壌調査・対策の実施結果を反映できるような仕組みとすべきである。
?ゾーン表示よりも施設の種類別表示がよい
街区やメッシュのエリアの単純な色塗りでは不安を広げることになるので、どういう施設がどこにあったかという実態を示すようにした方がよい。
(3)損害保険会社
【公開のメリット】
?リスク回避に有益な情報
マップに係る情報が開示されて土地汚染の可能性が示唆されれば、新規の土地購入者が汚染の可能性のある土地を購入してしまうリスクや、汚染を知らずに地下水を飲み続けるという健康リスクを回避することができる。
【公開の是非】
?時期尚早
事業所立地履歴マップは新しいデータを公表するのではなく、既存のデータを整備して分かりやすくしたものであるが、土壌汚染に対して十分な理解が進んでいない現状の社会環境下でいきなり公開することのデメリットは大きい。
当面のボトムラインは土壌汚染の存在を知らない新たな被害者の発生を防ぐことにあり、そうであれば当面は不動産売買時に売り手は立地履歴の提示を義務付けるという対策でもよいのではないか。
【公開する場合の条件と公開の仕方】
?行政用と公開用との区分は必要ない
もともと公開されているデータを整理してマップとして開示しているため、公開に当たって、行政用のものと一般開示用のものとを区分する必要はない。
?自然由来重金属類分布マップについて
自然由来の重金属類分布マップについては、科学的な検証がされた上でのクラス分けになるべきだろうと考えている。
(4)環境コンサルティング会社
【事業所立地履歴マップについて】
?事業者にとって歓迎であるが、住民にとってはデメリットが大きい
このマップは、コンサル、不動産関係、金融関係の事業者サイドにとっては非常にありがたく、メリットしか思いつかない。しかし、住民の立場からすれば、健康リスクのみならず経済リスクも負いかねないという意味では、公開することによるデメリットの方が大きい。自然由来重金属類マップ以上に綿密なリスクコミュニケーションが必要である。
行政内部用と公開用で分けているが、公開用だけあれば良いと思う。土壌汚染対策法の改正により自治体がフェーズ?についての判断を行うことが増えることが想定されるが、行政内部用を作ったにしても、そこに掲載されている情報が100%で無い場合は、結局担当者が調査を行うことになる場合もあると思われる。せっかく作ったマップでも、信頼がないと使われなくなる可能性も考えられる。
【自然由来重金属類分布マップについて】
?自然由来重金属類分布マップは必要
このようなマップを作成することはすばらしいことであり、行政が整備してくれると助かる。ただし、公開に当たってはリスクコミュニケーションが不可欠である。国土交通省と自治体双方の担当者がマップの意義や趣旨・目的、自然由来の基準超過には通常存在する量では健康リスクが無いこと等をしっかりと住民に対して説明出来る必要がある。
なお、自然由来については、「掘ったら出てくる」こと、そもそも通常存在する量では健康上のリスクは無いことが重要なのであるから、自然由来と判断されたところについては1色で塗ればよいのではないか。
このようなマップが全国で整備出来ると良い。ただ、自然由来と判断する基準は(環境省が自然由来と判断する基準である)39mg/kg を基準にするのではなく、地域によって変えた方がいい。この基準自体、全国10 地点くらいの平均値であり、信頼の高いものではないので、現在環境省においても見直しがされている。
マップに入っている調査結果の数字については出さない方がよい。不要な誤解を招きかねない。
(5)不動産鑑定士
色塗りされたエリアに含まれた土地の評価を求められた場合、土壌汚染による影響が無いと言い切るためには、このマップに掲載された情報よりももう少し詳細な調査が必要になるが、それは依頼者の負担で行ってもらう必要がある。そうなると、評価を依頼する人の負担が現状よりも増えるとともに、中途半端な情報の下では鑑定評価の依頼を受けにくいことから、鑑定
評価ビジネスが縮小してしまうかもしれない。
また、「このマップで色が塗られていないのだから土壌汚染は存在しない」と、このマップに責任を押しつけて悪用する人(特に鑑定士や不動産業者など)が出てくるかもしれない。
6.汚染された土地の有効利用促進等に向けた情報提供の方向性と課題
6.1 土壌汚染情報のデータベース化
6.1.1 人的活動に起因する土壌汚染データベース構築の方向性と課題
中央環境審議会「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)」(平成20 年12 月)は、「土壌汚染に関する情報について、埋没させることなく、関係者が容易に入手し、適切に活用することができ、適切に承継される仕組みが必要」としており、土壌汚染に係るデータベースの構築が必要とされている。
データベースの構築は、土壌汚染対策法の一部改正の方向として想定される「都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に関する努力義務」に沿った具体策の一つであると位置付けることもできる。
上記の答申においては、一定規模以上の土地であって土壌汚染のおそれのある土地の形質変更時における都道府県知事による土壌汚染の調査命令や、自主調査において土壌汚染が判明した場合も含め規制対象区域として適切な管理を行うことが謳われている。
また、汚染物質の掘削除去を行わず、残置して封じ込める対策の採用検討が推奨されている。行政が管理すべき土壌汚染に係る情報量が増加する方向にある中で、情報を効率的に管理し、効果的に施策決定に結びつけるためには事業所立地履歴マップを含めたデータベースの構築が有効である。
また、行政が知り得た情報を開示せず、土壌汚染リスクの存在を認識することができないままに土地を購入する者がいるとすれば、不幸なことであり、そのような状況の発生を防ぐ必要がある。宅地建物取引業法では、隣地や取引対象土地の過去の使用履歴について、その時点で認識している以上に開示することは求めておらず、一般には積極的にその土地の過去の使用履
歴を調査することは行わない。
したがって、土地購入者が近傍の土壌汚染の存在を把握したうえでの土地取引を推進できるという意味でも、データベースの構築・公開は求められるところである。
事業計画当初に調査を実施しなかったり土壌汚染を発見できなかったりした土地について、工事途中など事業が進んだ段階で土壌汚染が発見された場合には、土地取引の契約取消しや想定外のコスト発生などの問題が生じている事例は多い。容易に参照できる情報が存在すれば、土壌環境の概略把握が可能となり、その後の段取りの効率的な進行や調査品質の確保に繋がることが期待される。
一方で、土壌汚染対策法の改正が検討されている最中であり今後の詳細な制度内容が不確定であるという問題を除いても、事業所立地履歴マップの公開については、次の二つの理由から現時点では避けるべきという意見があったことにも配慮する必要がある。
第一に、マップの公開の仕方によっては、住民の一部に不安を与えてしまうという可能性を否定しきれないであろうということである。単純にマップの公開のみであると、リスクを正しく認識しないことによるスティグマのため、土地価格に悪影響を与え得ることなどが懸念された。
第二に、企業活動への影響が懸念された。景気が著しく悪化し、企業の資金繰りが悪くなる中で、土地の担保価値下落に繋がるおそれのあるマップ公開は避けるべきということである。
このため、今般はマップの作成方法等を示すにとどめることとするが、上記答申を内容とする改正土壌汚染対策法が成立・施行された場合、上記のとおり自治体の負担はかなり増大する可能性があると考えられることから、少なくともそれを軽減し円滑な業務執行を成し得るよう、まずは行政内部での活用を目的として、各自治体において本とりまとめで示した作成方法等を
参考にしつつマップ作成に取り組むことが一助になると考える。
6.1.2 自然的原因による土壌の基準値超過に係るデータベースの構築の方向性と課題
自然的原因による土壌の基準値超過については、地質的に一定の地域内に幅広く分布する等の事情により、その地域固有の特性と考えて対応する必要がある。
したがって、人為的な土壌汚染として対策をすべき土地と、そうではない自然的原因による土壌の基準値超過土地の線引きを可能にするため、自然的原因による土壌の基準値超過についてデータベースを構築することは有用であると考えられる。また、これにより、汚染土壌による地下水への影響や残土の処理方法等を調査、検討することも可能になる。
そもそも自然的原因による土壌の基準値超過は、国土そのものの議論であり、人為的な汚染との区別が明確にできれば、行政的に地下水への影響をコントロールすることや搬出土壌の移動管理を施すべきもので、また、情報の公開によって影響を受ける関係者も少ないことが想定されるため、自然的原因による土壌の基準値超過データベースの構築・公開に対する抵
抗感は少ないものと考える。
自然的原因による土壌の基準値超過については、前述したようにある地域内の土地全体に当てはまる特性であることから、個別サイトごとの状況を考慮に入れれば足りる一般の土壌汚染の場合とは異なり、面的に土壌の状況を把握する必要がある。
現在、自然的原因による土壌の基準値超過については、環境省主導で全国の土壌のバックグラウンド値が収集整理されているほか、自治体や大学等の研究者により自然的原因による土壌の基準値超過の判定に係る研究が進められている。
したがって、それらの成果を踏まえ、各自治体の判断により、自然由来重金属類分布マップをデータベースの一つの形として公表することは可能であるとともに適切であると考える。
また、事業所立地履歴マップの場合と同様に、改正土壌汚染対策法の内容を踏まえれば、自治体の負担が増す可能性がある中で、予め各自治体においてその軽減に資するバックグラウンドデータを整備しておくことが一助になると考える。
6.2 土壌汚染の正確な知識の周知とリスクコミュニケーション

土壌汚染が社会問題化するのは、土壌汚染自体が比較的新しい概念であり、これまで通常存在するリスクの一つとして扱われなかった商習慣等の下で土地利用や土地取引が行われていることが背景にある。こうした状況下で事業所立地履歴マップを公開した場合に、国民の間に過剰反応が生じる悪影響が懸念された。この課題を払拭するためには、行政主導で公開に先立ち国民に啓発活動を実施するとともに、公開に当たっての体制やシナリオを検討しておく必要がある。
土壌汚染問題に対する一般的理解の不足により、汚染の程度が重篤なものでなくとも、世の中においては過剰に反応される傾向があり、また、この風潮により土地所有者等は公表を拒みがちとなるという悪循環となっている。
しかしながら、それらの土地を健康リスクの観点から見た場合、多くは過剰反応するほどの大きなものでなく、合理的な対策により十分対応可能なレベルであると考えられる。
また、そもそも土壌環境基準が意味する健康被害リスクが一般的に思い込まれている以上に低いレベルであることさえも一般的に認知されておらず、このような土壌汚染に関する正確な知識の欠如が、世の中に土壌汚染に対する過剰な嫌悪「スティグマ」を生んでいる。
そして、スティグマの存在が風評被害の可能性へとつながるために土壌環境に係るマップの公開の障壁となり、世の中に土壌環境に係る正確な情報が提供されないという悪い連鎖が生じている。

この悪い連鎖を断ち切るためには、土壌汚染リスクに係る正確な知識の普及が必要なことは当然であるが、その普及の見通しが不透明である現状においては、国が主導し、正確な知識の周知と併せて全国の土壌環境に係るマップの公開を促進することが重要である。
土壌環境基準を超過する土地が日本国中至る所に存在し、そこで人々が何不自由なく生活していることが理解されれば、スティグマも解消し円滑な土地取引が行われるものと期待される。
土壌環境に係るマップの公開は、土壌汚染に係る有効なリスクコミュニケーションの手段となり得るものである。
なお、リスクコミュニケーションにおいては、土壌汚染が判明した場合であっても過剰な対策・負担なしに対応が可能であることを認識してもらうことが重要であり、土壌環境に係るマップの公開に伴う上記の懸念を可能な限り低減させるためにもその種の方策を講じることが有効である。
このため、例えば、掘削除去以外の措置により計画的な土地利用を行っている実在の土壌汚染地について、その成功要因等を分析・研究し、「サクセスモデル」として公開すること等を検討すべきである。










2009年10月18日
大阪湾見守りネット 関係 リンク
大阪湾見守りネット 関係 リンク

多様な市民や団体が参加しています。リンクには個人参加の所属団体等も含みます
行政
近畿地方環境事務所
国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾空港技術調査事務所
大阪府環境農林水産総合研究所
大阪府環境農林水産総合研究所 水産技術センター
大阪府環境農林水産部水産課
大阪府都市整備局安威川ダム建設事務所
大阪湾環境保全協議会
御前浜・香櫨園浜プロジェクト
環境活動拠点
おおさかATCグリーンエコプラザ
大阪市立自然史博物館
大阪市立自然史博物館友の会
大阪府立青少年海洋センター
貝塚市立自然遊学館のホームページ
きしわだ自然資料館ホームページ
神戸市立須磨海浜水族園
こども環境活動支援協会
西宮市貝類館
帆船「あこがれ」
教育機関
大阪アニマル&オーシャン専門学校
大阪コミュニケーションアート専門学校
大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科
大阪府立大学大学院海洋システム工学科
財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
日本大学生物資源科学部生物環境科学研究センター
阪南市立箱作小学校
NPO等団体
アマモ種子バンク
和泉葛城山 ブナ愛樹クラブ和泉葛城山 ブナ愛樹クラブ活動記録ブログ
海と船の博物館ネット
海守
NPOエコデザインネットワーク
大阪大学環境サークル GECS
大阪府釣りインストラクター連絡機構(JOFI−OSAKA)
大阪湾学習活動交流研究会
大阪湾ダイビングスポット創造プロジェクト調査
男里川の干潟を守る会
海藻押し葉クラブ 活動内容
海藻を通して、地球環境に関心を広げる学習支援をする
環境教育技術振興会
環境創生研究フォーラム
神戸 川と海を考える会
国立公園成ヶ島を美しくする会
近木川流域自然大学研究会
近畿みなとの達人HP
全日本釣り団体協議会
NPO釣り文化協会
西淀自然文化協会
日本野鳥の会大阪支部
日本ウミガメ協議会
日本水産学会
浜寺公園自然の会
Ecoact+本多俊之のホームページ
シグナス ヨットクラブ 新西宮ヨットハーバー
すがたの狩人 雑記帳 和泉葛城山ブナ愛樹クラブ
水辺環境浄化研究会
南大阪自然環境研究所
大阪湾海岸生物研究会
アマモ育成中!住吉川をきれいに!!
神戸川と海を考える会
兵庫運河を美しくする会
兵庫運河の水質の浄化と、周辺の景観の美化を通じて、地域社会に貢献することを目的とし・・・
兵庫県環境クリエイトセンター
NPO法人南港ウェットランドグループ
TEAM 魚っしょい!
(企業:個人参加の勤務先も含みます)
いであ
奥村組
海遊館
海洋生態研究所
近畿技術コンサルタンツ
シャトー海洋調査
総合化学
総合水研究所
地域計画建築研究所(アルパック)
日本ミクニヤ
阪神高速道路
パナソニック環境エンジニアリング株式会社
ユーエルアクアティクス
関係のないところも含まれます。

多様な市民や団体が参加しています。リンクには個人参加の所属団体等も含みます
行政
近畿地方環境事務所
国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾空港技術調査事務所
大阪府環境農林水産総合研究所
大阪府環境農林水産総合研究所 水産技術センター
大阪府環境農林水産部水産課
大阪府都市整備局安威川ダム建設事務所
大阪湾環境保全協議会
御前浜・香櫨園浜プロジェクト
環境活動拠点
おおさかATCグリーンエコプラザ
大阪市立自然史博物館
大阪市立自然史博物館友の会
大阪府立青少年海洋センター
貝塚市立自然遊学館のホームページ
きしわだ自然資料館ホームページ
神戸市立須磨海浜水族園
こども環境活動支援協会
西宮市貝類館
帆船「あこがれ」
教育機関
大阪アニマル&オーシャン専門学校
大阪コミュニケーションアート専門学校
大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科
大阪府立大学大学院海洋システム工学科
財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
日本大学生物資源科学部生物環境科学研究センター
阪南市立箱作小学校
NPO等団体
アマモ種子バンク
和泉葛城山 ブナ愛樹クラブ和泉葛城山 ブナ愛樹クラブ活動記録ブログ
海と船の博物館ネット
海守
NPOエコデザインネットワーク
大阪大学環境サークル GECS
大阪府釣りインストラクター連絡機構(JOFI−OSAKA)
大阪湾学習活動交流研究会
大阪湾ダイビングスポット創造プロジェクト調査
男里川の干潟を守る会
海藻押し葉クラブ 活動内容
海藻を通して、地球環境に関心を広げる学習支援をする
環境教育技術振興会
環境創生研究フォーラム
神戸 川と海を考える会
国立公園成ヶ島を美しくする会
近木川流域自然大学研究会
近畿みなとの達人HP
全日本釣り団体協議会
NPO釣り文化協会
西淀自然文化協会
日本野鳥の会大阪支部
日本ウミガメ協議会
日本水産学会
浜寺公園自然の会
Ecoact+本多俊之のホームページ
シグナス ヨットクラブ 新西宮ヨットハーバー
すがたの狩人 雑記帳 和泉葛城山ブナ愛樹クラブ
水辺環境浄化研究会
南大阪自然環境研究所
大阪湾海岸生物研究会
アマモ育成中!住吉川をきれいに!!
神戸川と海を考える会
兵庫運河を美しくする会
兵庫運河の水質の浄化と、周辺の景観の美化を通じて、地域社会に貢献することを目的とし・・・
兵庫県環境クリエイトセンター
NPO法人南港ウェットランドグループ
TEAM 魚っしょい!
(企業:個人参加の勤務先も含みます)
いであ
奥村組
海遊館
海洋生態研究所
近畿技術コンサルタンツ
シャトー海洋調査
総合化学
総合水研究所
地域計画建築研究所(アルパック)
日本ミクニヤ
阪神高速道路
パナソニック環境エンジニアリング株式会社
ユーエルアクアティクス
関係のないところも含まれます。
2009年10月18日
2010年 ATC水土壌汚染関係資格受験サークル
2010年 ATC水土壌汚染関係資格受験サークル
2010年 ATC水土壌汚染関係資格受験サークル
概要
土壌汚染は多くの分野の知識を集めて対応することが必要です。会員をはじめ参加希望者の資質やスキルアップのため、水・土壌汚染関係試験の受験希望者を対象に受験サークルを開催いたします。
サークルの進め方は参加者がプログラムを作成し、過去の土壌汚染関係試験の問題を参加者自らが回答を導き出すなどの手法を検討していますので受験勉強に適しています。
本年度は土壌汚染指定調査機関の管理技術者の受験者が多くなることが予想されますので、この資格の全員合格を目指してがんばることになりそうです。
ご意見や参加希望の方は、下記のお申込にご記入の上、FAXもしくはメールで事務局まで、お申込ください。試しに、1度参加してみようという方でも結構ですので、奮ってお申込ください。また、有資格者の方は自己啓発も兼ねて後進の指導にあたって下さるボランティアを募集します。
主 催
主催者は特にいません。
ATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会 有志がボランティアとしてアドバイスさせていただきます。
スケジュール 案
第1回 月 日(土)14:00〜17:00
講演:資格取得の方法・心構え
グループ分け・カリキュラム討議決定
過去問答え合わせ
第2回 月 日( )14:00〜17:00
各資格試験受験過去問答え合わせ
第3回 月 日( )14:00〜17:00
各資格試験受験勉強(技術士模擬試験)
第4回 月 日(土)14:00〜17:00
各資格模擬試験(環境カウンセラー試験説明)
参 加 料
?円/人
(資料代等に充当します。但し、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会員等は無料。)
会 場
おおさかATCビルITM棟11F ATCグリーンエコプラザ内ビオトープ・プラザ
大阪市住之江区南港北2丁目 地下鉄ニュートラムトレードセンター前駅下車すぐ
お申し込み
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会
「2010年土壌汚染関係資格受験サークル」係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp
案内チラシ
作成中
2010年 ATC水土壌汚染関係資格受験サークル
概要
土壌汚染は多くの分野の知識を集めて対応することが必要です。会員をはじめ参加希望者の資質やスキルアップのため、水・土壌汚染関係試験の受験希望者を対象に受験サークルを開催いたします。
サークルの進め方は参加者がプログラムを作成し、過去の土壌汚染関係試験の問題を参加者自らが回答を導き出すなどの手法を検討していますので受験勉強に適しています。
本年度は土壌汚染指定調査機関の管理技術者の受験者が多くなることが予想されますので、この資格の全員合格を目指してがんばることになりそうです。
ご意見や参加希望の方は、下記のお申込にご記入の上、FAXもしくはメールで事務局まで、お申込ください。試しに、1度参加してみようという方でも結構ですので、奮ってお申込ください。また、有資格者の方は自己啓発も兼ねて後進の指導にあたって下さるボランティアを募集します。
主 催
主催者は特にいません。
ATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会 有志がボランティアとしてアドバイスさせていただきます。
スケジュール 案
第1回 月 日(土)14:00〜17:00
講演:資格取得の方法・心構え
グループ分け・カリキュラム討議決定
過去問答え合わせ
第2回 月 日( )14:00〜17:00
各資格試験受験過去問答え合わせ
第3回 月 日( )14:00〜17:00
各資格試験受験勉強(技術士模擬試験)
第4回 月 日(土)14:00〜17:00
各資格模擬試験(環境カウンセラー試験説明)
参 加 料
?円/人
(資料代等に充当します。但し、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会員等は無料。)
会 場
おおさかATCビルITM棟11F ATCグリーンエコプラザ内ビオトープ・プラザ
大阪市住之江区南港北2丁目 地下鉄ニュートラムトレードセンター前駅下車すぐ
お申し込み
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会
「2010年土壌汚染関係資格受験サークル」係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp
案内チラシ
作成中