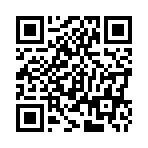2009年11月29日
地下水汚染 環境省 発表
地下水汚染
鉛 (23倍)東京都渋谷区上原
六価クロム (54倍)佐賀県鳥栖市原町
砒素 (44倍)兵庫県豊岡市若松
総水銀(36倍)福井県越前市家久
四塩化炭素 (180倍)千葉県千葉市稲毛区長沼町
1,2-ジクロロエタン (19倍)大阪府高槻市唐崎中
1,1-ジクロロエチレン (48倍)千葉県野田市木間ヶ瀬
シス-1,2-ジクロロエチレン (750倍)秋田県由利本荘市大浦
(228倍)新潟県上越市新光町
(158倍)大阪府高槻市桃園町
(120倍)新潟県燕市南
1,1,2-トリクロロエタン (11倍)宮崎県延岡市別府町
トリクロロエチレン(2733倍)秋田県井川町浜井川
(1467倍)福岡県福岡市香椎駅前
(1167倍)秋田県由利本荘市大浦
(400倍)愛知県豊田市神池町
(107倍)千葉県千葉市花見川区作新台4丁目
(103倍)滋賀県草津市矢倉
テトラクロロエチレン(2100倍)兵庫県明石市魚住町
(1100倍)千葉県松戸市紙敷
(430倍)福岡県福岡市香椎駅前
(430倍)福岡県福岡市田島
(190倍)愛知県名古屋市昭和区広見町
(160倍)宮城県栗原市築館萩沢
(160倍)福島県須賀川市小作田
(150倍)兵庫県明石市大久保町
(120倍)福岡県朝倉市屋永
(110倍)岩手県大船渡市下船渡
(110倍)兵庫県明石市大久保町
(110倍)兵庫県加東市高岡
(110倍)山口県岩国市下久原
(110倍)山口県周南市古市
(100倍)北海道旭川市大町
(100倍)滋賀県彦根市城北
ベンゼン (10倍)福井県越前市家久
ふっ素 (18倍)岐阜県御嵩町御嵩
ほう素 (9.9倍)福島県郡山市芳賀
酸性窒素及び亜硝酸性窒素
(12倍)栃木県藤岡町藤岡
(10倍)埼玉県深谷市櫛引
(10倍)神奈川県横浜市南区六ツ川
(8.5倍)茨城県つくば市上里
(8倍)長野県飯島町七久保
(7.2倍)青森県南部町平
(7倍)神奈川県海老名市本郷
(6倍)千葉県船橋市旭町6丁目
(6倍)群馬県館林市成島町
(6倍)茨城県板東市長須
http://www.env.go.jp/water/report/h21-03/full.pdf
鉛 (23倍)東京都渋谷区上原
六価クロム (54倍)佐賀県鳥栖市原町
砒素 (44倍)兵庫県豊岡市若松
総水銀(36倍)福井県越前市家久
四塩化炭素 (180倍)千葉県千葉市稲毛区長沼町
1,2-ジクロロエタン (19倍)大阪府高槻市唐崎中
1,1-ジクロロエチレン (48倍)千葉県野田市木間ヶ瀬
シス-1,2-ジクロロエチレン (750倍)秋田県由利本荘市大浦
(228倍)新潟県上越市新光町
(158倍)大阪府高槻市桃園町
(120倍)新潟県燕市南
1,1,2-トリクロロエタン (11倍)宮崎県延岡市別府町
トリクロロエチレン(2733倍)秋田県井川町浜井川
(1467倍)福岡県福岡市香椎駅前
(1167倍)秋田県由利本荘市大浦
(400倍)愛知県豊田市神池町
(107倍)千葉県千葉市花見川区作新台4丁目
(103倍)滋賀県草津市矢倉
テトラクロロエチレン(2100倍)兵庫県明石市魚住町
(1100倍)千葉県松戸市紙敷
(430倍)福岡県福岡市香椎駅前
(430倍)福岡県福岡市田島
(190倍)愛知県名古屋市昭和区広見町
(160倍)宮城県栗原市築館萩沢
(160倍)福島県須賀川市小作田
(150倍)兵庫県明石市大久保町
(120倍)福岡県朝倉市屋永
(110倍)岩手県大船渡市下船渡
(110倍)兵庫県明石市大久保町
(110倍)兵庫県加東市高岡
(110倍)山口県岩国市下久原
(110倍)山口県周南市古市
(100倍)北海道旭川市大町
(100倍)滋賀県彦根市城北
ベンゼン (10倍)福井県越前市家久
ふっ素 (18倍)岐阜県御嵩町御嵩
ほう素 (9.9倍)福島県郡山市芳賀
酸性窒素及び亜硝酸性窒素
(12倍)栃木県藤岡町藤岡
(10倍)埼玉県深谷市櫛引
(10倍)神奈川県横浜市南区六ツ川
(8.5倍)茨城県つくば市上里
(8倍)長野県飯島町七久保
(7.2倍)青森県南部町平
(7倍)神奈川県海老名市本郷
(6倍)千葉県船橋市旭町6丁目
(6倍)群馬県館林市成島町
(6倍)茨城県板東市長須
http://www.env.go.jp/water/report/h21-03/full.pdf
2009年11月15日
健全な地下水の保全・利用に向けて
健全な地下水の保全・利用に向けて−「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」報告−(抜粋)
平成19年3月
今後の地下水利用のあり方に関する懇談会
はじめに
近年、地下水を取り巻く環境は大きく変化してきている。かつて高度経済成長期に深刻であった地下水の過剰採取による地盤沈下は、一部現在も引き続き対策が必要な地域もあるが、地下水採取規制、代替水源の確保等により、沈静化しつつある。 一方で、かつては地盤沈下が深刻であった大都市地域で地下水採取規制等により地下水位が回復・上昇し、地下構造物や地下水環境への新たな悪影響・弊害を引き起こしている事例もある。また、地下水質の面で環境基準を超える浅層地下水汚染が顕在化している。
地下水は地球水循環系を構成する重要な要素であり、地下水の保全及び利用が水循環系全体に与える影響を把握していくことが重要である。
本懇談会は、平成10年に国土庁水資源部に設置され、“地下水の利用と制度のあり方”について、専門の立場より幅広く検討を進めてきた。平成12年3月には、地下水をめぐる現状、今後の地下水利用のあり方について中間報告としてとりまとめ
た。
つづいて平成15年3月に日本で開催された第3回世界水フォーラムにおいて「今後の地下水利用のあり方」をテーマに分科会を主催し国際的視野に立った議論を行った。
今般、地下水をめぐる最近の動向と保全・利用に向けた課題、地下水利用のあるべき基本的な考え方を整理し、今後の地下水利用のあり方に関する提言を報告書にまとめた。
本報告は、その前半では「地下水をめぐる現況、最近の国内外の動向、及び保全・利用に係る課題」を論点とし、後半で「今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法」に言及し、最後に、当初目指した「今後の地下水利用のあり方」を提言している。
その新しい視点は、地下水資源に軸足を置いてマネジメントする必要性に向けられている。これまでの永い地下水利用の歴史を踏まえて、地下水資源マネジメントの指針と方法をより実践的にまとめたものであり、今後、本提言が国や各地域での取り
組みに反映されることを期待するものである。
平成19年3月
今後の地下水利用のあり方に関する懇談会座長
埼玉大学名誉教授佐藤邦明
「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」委員
小尻利治京都大学防災研究所水資源研究センター教授
佐藤邦明埼玉大学名誉教授(座長)
七戸克彦九州大学大学院法学研究院教授
大東憲二大同工業大学工学部都市環境デザイン学科教授
田中正筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
中杉修身上智大学大学院地球環境学研究科教授
守田優芝浦工業大学工学部土木工学科教授
目 次
第1章 地下水をめぐる現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.1 地下水の特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2 地下水利用の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1.3 地下水障害・地下水水質・汚染の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
1.4 地下水に関する法制度の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第2章 地下水をめぐる最近の動向と地下水の保全・利用に係る課題・・・・ 29
2.1 わが国の水需給に関する動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
2.2 新たな地下水障害と地下水源開発の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
2.3 地震災害等、緊急水資源需要への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
2.4 水に関する世界情勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
2.5 地下水の保全・利用に向けた課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
第3章 今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法・・・・・・・・・・・・・・・ 55
3.1 健全な水循環系の構築における今後の地下水利用の基本的な考え方・・・・・・・・ 55
3.2 地下水資源マネジメントの考え方と手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
第4章 今後の地下水利用のあり方に関する提言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 4
4.1 地下水資源マネジメントの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
4.2 地下水資源マネジメントの運用方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
4.3 地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
第1章 地下水をめぐる現状
1.1 地下水の特性
(1)地下水の水循環上の特性
科学的にみると、地下水は陸水の地下にある水の総称である。それは、降水が地下に浸透して海洋へ地下流出するプロセスにある、いわゆる「地下水」と、陸地の地形・地質が形成される際に地下深くに閉じこめられた化石水や、岩石・溶岩の形成時に生成される初生水のように「循環に乏しい地下水」に分けられる。一般に、淡水資源や温泉水は、それらを持続的かつ健全に利用できる循環している地下水であることが前提となる。以下、このような視点に基づき、議論を展開する。
地下水の源は降水であり、地表水とともに水循環を構成する。降水の一部は、直接流出として河道に流出する。直接流出は、地表から河道に流れる表面流出と、一度地中に浸透した後に浅い地下水流として河道に流出する中間流出に分けることができる。直接流出しない降水は、窪地などに一時的に貯留されるか、土壌に浸透する。土壌に浸透した降水の一部は重力によって下方に浸透し、地下水となる。
地下水は地表水に比べて、地中をゆっくりと流れる。そして、やがて河川・湖沼や地表面に再び流出し、地表水に合流する。平均滞留時間は数百〜数千年といわれている(表1-1-1参照)。
このような水循環を図示したものが図1-1-1(○a ,○b )である。水循環の過程においては、大気事象や大地の影響を強く受けている。例えば、地下水涵養は降水量に支配され、地下水循環は地質や地形によって規定される。また、蒸発は気温や湿度、植生などの影響を受けている。さらに、採取量(揚水量)や土地利用などの人為的な要因も水循環に影響を与えている。

資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)をもとに加筆
図1-1-1 水循環とその規定要因の概念図
表1-1-1 地球の水量と滞留時間
貯留量(?3) 平均滞留時間
海 洋 1,349,929,000 3,200 年
氷 雪 24,230,000 9,600 年
地下水 10,100,000 830 年
土壌水 25,000 0.3 年
湖沼水 219,000 数年〜数百年
河川水 1,200 13 日
水蒸気 13,000 10 日
資料)建設産業調査会『改訂地下水ハンドブック』(1998 年)
(2)地下水の水資源としての潜在特性
一般に水資源としての地下水は、表1-1-2に示すように、利用の簡便性、経済性、良質な水質、恒温性という特性を有している。
表1-1-2 地下水の利用特性
このような地下水の自然特性を活かし、地下水は、生活用水(飲料用、調理用、浴用等)、工業用水(冷却用、洗浄用等)、農業用水(農作物栽培用等)、積雪地域の消雪用など多様な用途に利用されている(図1-1-2参照)。
図1-1-2 地下水特性からみた用途の内訳
1.北海道地方
(3)地下水の潜在分布状況
図1-1-3は、わが国における地下水盆の賦存地形類型と主な地下水区の分布を示している。わが国における地下水は、地形・地質上、平野型、盆地型等のいくつかに分類できる。

図1-1-3 わが国における地下水盆の類型と主な地下水文区
それぞれに分類される地下水の特徴を以下に要約する。
?堆積平野の地下水
a)平野・台地
関東平野など主要な地下水盆は、地質年代では新生代新第三紀末から第四紀の地層が堆積する平野、低平地に分布しており、特に第四紀完新世の沖積平野のうち、中〜上部更新統・完新統の新しい地質が主な帯水層となっている。地層が軟弱な沖積平野では、地下水の過剰なくみ上げが地盤沈下を引き起こしやすい。
b)盆地
わが国の盆地には、平野と同様に新生代新第三紀末から第四紀の地層が堆積しており、更新世末から完新世の地質をもつ段丘や扇状地が有力な帯水層となっている。盆地の帯水層は、豊富な地下水を有していることが多いが、地下水の過剰なくみ上げによって地下水位の低下や枯渇を起こすことがある。
?岩の地下水
地下水は溶岩体や深成岩地帯にれっか水(裂罅水:fissure water、「地質事典」平凡社、1990)や割れ目水として帯水している。
a)山地
山地では、造岩塊や固結岩の亀裂や浸透性の高い地層に地下水が含まれており、トンネル掘削時に湧水として流出することがあるが、環境への影響や採水の経済性を考慮すると、大規模な採取は困難である。
b)火山地域
火山地域は、溶岩・火山砕屑物など浸透性の高い地層から構成されているため、阿蘇カルデラ、シラス台地など有力な帯水層が多い。山麓部末端では湧水群が分布し、古くから農業用水、生活用水に利用されてきた。
c)石灰岩地帯
石灰岩中のれっかや鍾乳洞には地下水を有することが多く、日本では、例えば、栃木県の佐野市(弁天池)や山口県の秋吉台などに見られる。また、南西諸島では、琉球石灰岩が分布し、自然の地下水帯となっているため、近年、地下ダムによる地下水貯留が行われる例がある。
図1-1-4 日本の地質図
1.2 地下水利用の現状
(1)わが国における水使用量の推移
2003 年(平成15 年)におけるわが国の水使用量(取水ベース)は、都市用水と農業用水を合わせ、839 億m3 であり、そのうち、都市用水(生活用水と工業用水の合計)は282 億m3 である。都市用水の使用量は、図1-2-1に示すように1987 年(昭和62 年)以降、やや増加したが、その後微減の傾向にある。また、農業用水の使用量についても、昨今やや減少しており、2003 年は557 億m3となっている。
図1-2-1 全国の水使用量の推移
(2)わが国における地下水利用の特徴
?水使用量に占める地下水の割合
2003 年(平成15 年)における取水ベースの水使用量839 億m3 の水源内訳をみると、図1-2-2のように、河川水が735 億m3、地下水が104 億m3 であり、地下水依存率は約12.4%となっている。

図1-2-2 水使用量に占める地下水の割合
?地下水使用量の用途別割合
上述の地下水使用量104 億m3 に加え、養魚用水として約13 億m3/年、建築物用等として約7億m3/年の地下水が使用されており、全地下水使用量は約124億m3/年と推計されている。
2003 年(平成15 年)における地下水の用途別割合は、生活用水が35.5 億m3で全体の28.6%、工業用水が35.9 億m3 で28.9%、農業用水が33.0 億m3 で26.6%となっている(図1-2-3参照)。
用途別地下水使用量の推移をみると、図1-2-4に示すように、生活用水はほぼ横ばいであるが、工業用水は減少傾向にある。

図1-2-3 地下水の用途別割合
?用途別にみる地下水利用の地域性
地下水利用は、地形・地質や降水といった自然条件と、都市化や人口といった人的な条件の影響を強く受け、決して全国一律ではなく、地域性が多様である。以下、用途別に地下水源への依存の地域性を述べる。
□工業用水
地下水は、水質が良く、水温が一定であり、取水費用が安いという特徴から、工業用水に多く使用されており、特に、化学工業、鉄鋼業、パルプ・紙・食品加工など製造業で、製造、洗浄、冷却水などとして地下水使用量が多くなっている。
図1-2-5に示すように、工業用水の地下水依存率は、全国の合計でみると約3割(29.5%)である。地域別にみると、北陸で最も高く6割超(62.7%)である。また、近畿内陸(54.8%)、関東内陸(46.0%)、東海(45.0%)などでも高くなっている。
工業用水用の地下水は、戦後昭和20 年代以降、深井戸による被圧地下水が使われているが、工場等の立地は沖積平野に多いことから、地盤沈下、塩水化などの地下水障害を引き起こし、今日に至っている。
図1-2-5 地域別用途別地下水依存率(工業用水)
□生活用水
生活用水の地下水依存率は、全国の合計でみると2割強(22.1%)である。図1-2-6に示すように、地域別にみると、南九州(54.3%)や山陰地域(51.9%)で生活用水の地下水依存率が高く、5割を超えている。次いで、四国(41.5%)、関東内陸(41.0%)、北陸(39.8%)などでも高い。一方で、北海道(6.0%)、沖縄(8.5%)では、生活用水の地下水依存率が低い。
図1-2-6 地域別用途別地下水依存率(生活用水)
□農業用水
わが国では、農業用水として主に地表水が利用されてきた。地下水は、補助水源、渇水時の応急用水源として利用されてきたことから、農業用水に占める地下水の割合は概して低い(図1-2-7参照)。
図1-2-7 地域別用途別地下水依存率(農業用水)
□その他の用途
水産用にマス、ウナギなどの養殖で利用される地下水の量の統計では、上述の3つ(工業・生活・農業)の用途に次いで多く、個別的であるが、湧水、温泉水などが報告されている。
また、消雪用に地下水を利用する方法は、気温が氷点下にならない豪雪地で有効であり、消雪パイプは1961 年に新潟県長岡市で始まり、全国的には2004 年度の消雪パイプ使用水量の約83%(374 百万m3/年)が地下水を利用している。地下水は水温の季節変動が小さいため、消雪効果があり、東北、北陸などでも利用されている。しかし、狭い場所で集中的に大量の地下水をくみ上げるため、地下水位の低下、地盤沈下などの地下水障害をもたらした。
わが国では、温泉水として利用される地下水も多い。浴用以外にも、ハウス園芸用熱源、発電など多目的に利用される事例がある。井戸の掘削深度がかなり深く1,000m以上の深さのものもある。
1.3 地下水障害・地下水水質・汚染の現状
(1)地下水位の異常低下、井戸枯れ
わが国における地下水位の異常低下、井戸枯れは、戦後(1945 年)以後1950 年代後半〜1960年代前半にかけて最も激しい地下水被害をもたらした。高度成長期には地下水を大量に揚水したことによって、都市部を中心に地下水位の低下、井戸枯れが起こった。また、地下掘削工事やトンネル掘削によって、周辺の地下水位が低下し、井戸枯れが起こる例も見られた。
しかし、1950 年代後半〜1970 年代前半に揚水の法的規制等が行われたことにより採取量は減少し、全国的にみると地盤沈下は沈静化し、近年は地下水位が回復しているところもみられる。
(2)地盤沈下
(3)塩水化
わが国における地下水の塩水化は、ほとんどが海岸域で発生している(図1-1-1)。地下水の過剰なくみ上げが原因で、地下水位が海水面より低下し、帯水層に海水が浸入することによって発生する。1960 年以降、製紙業の盛んな静岡県富士市のほか多数の臨海域で発生しており、塩水化した地下水は、飲料水として利用できず、工業用水としての不適合、農作物への塩害などがみられた。八戸、石巻、気仙沼などでは、現在もその塩害が継続している。
表1-3-1 塩水化地域に対する対策の状況

(4)地下水の水質と汚染
?地下水質の評価指標
古来、地下水といえば、水温の安定した清廉な水という通念がある。地下水の水質は、地形・地質の成り立ちや地下水の由来、流動、気候、生態系などの自然条件の影響を受け、その地域性や深さによって大きく異なる。例えば、表1-3-2は日本の名水に指定されている水質の例を示す。地下水質は、主要溶存化学成分9項目、陽イオン(ナトリウムNa+、カリウムK+、カルシウムCa2+、マグネシウムMg2+)、陰イオン(重炭酸HCO3-、塩素Cl-、硫酸SO4-、硝酸NO3-、シリカSiO2)に加え、電気伝導度、水温、pH などにより判断され、必要に応じて用途や関係する水質(環境)基準項目を加味した上で評価される。
表1-3-2 名水の水質例
自然の地下水質は、元来多様な理化学的特性を持つ。言うまでもなく、ある地下水が水質上良いか悪いかを漠然と判断することはできない。通常、ある対象・目的に対して、人や環境に有害であると考えられる数値を水質評価指標(水質検査項目)の基準値(水質基準)として設定し、利用の可否を決めることになる。
したがって、自然のままで地下水質がある検査基準(例えば、水道水の検査基準)に適合しない場合がありうる(以下、仮に「自然由来の汚染」と呼ぶこととする)。なお、水質検査の項目自体も水質基準の種類(対象・目的)に応じて異なるものが必要となる。
一般に水質汚染とは、自然の地下水質が人為的に汚染された(=水質基準に不適合の検査項目がある)人為由来のものを指す。自然由来の汚染は主に深層の地下水で、人為由来の汚染は主に浅層の地下水で発生する。深層の地下水汚染は除去が困難であり、水資源として利用することができない。以下では、人為由来の地下水汚染を中心に述べる。
?地下水汚染に関する環境基準とその超過率
高度成長期以降、工場や事業所等が原因となって地下水汚染が発生し、化学合成物である揮発性有機塩素化合物による地下水汚染が深刻となった。
このため、1971 年(昭和46 年)に「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」の2つからなる「水質汚濁に係る環境基準」が定められた。「人の健康の保護に関する環境基準」は、全公共用水域に対し、カドミウム、シアン等9項目についての基準を定めていたが、1993 年(平成5年)3月に項目が追加され23 項目となった。さらに近年、農業、畜産排水による硝酸性窒素汚染が顕在化してきたことから、1999 年(平成11 年)には、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ほう素」及び「ふっ素」の3項目が追加され、現在では26 項目の基準が定められている。
国と都道府県では「地下水の水質汚濁に関わる環境基準」に定められた26 項目を調査対象物質として毎年地下水質測定を行っている(表1-3-3、図1-3-5参照)。
地下水は、一度汚染されると、汚染の継続は長期間に及ぶ。水資源の安全な利用の観点からも、地下水質の継続的な監視が求められることとなる。
表1-3-3 地下水の水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)
図1-3-5 環境基準超過率の推移
?揮発性有機塩素化合物による地下水汚染
揮発性有機塩素化合物は、土壌汚染や浅層地下水汚染を引き起こす原因となっている。その主要な原因となっているのは、金属関連産業や半導体産業などの洗浄溶剤として使用されるトリクロロエチレンと、クリーニングや金属等の脱脂洗浄、代替フロンの原料として使用されるテトラクロロエチレンであるが、近年、製造・使用量は減ってきており、環境基準超過率は減少傾向にある。
揮発性有機塩素化合物は、
?重い、
?水に溶けにくい、
?土壌に吸着しにくい、
?低粘性、
?揮発性が高い、
?分解されにくい、といった特徴を有しているため、いったん地下に進入すると、
鉛直方向には容易に重力浸透する。一方で、横方向への拡散は少ないため、高濃度の原液による局地的な地下水汚染、土壌汚染を引き起こす特徴を持っている。揮発性有機塩素化合物は、まず土壌に浸透し、少しずつその下の帯水層に重力沈降しつつ溶け出して地下水を汚染する。
溶解汚染した地下水の移流流動及び分散によって、汚染地域は拡大する。
揮発性有機塩素化合物は、麻痺や呼吸障害、貧血、肝臓障害、発ガン性があるなど、人体に悪影響を及ぼすことが分かっている。
?硝酸性窒素による地下水汚染
硝酸性窒素汚染は、農薬、畜産排水などが汚染源となっているため、野菜、果樹、茶の栽培に利用されることの多い扇状地や、畜産、野菜栽培に利用されることの多い火山山麓で拡大している。
環境基準では、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素ともに10mg/?と定められているが、基準を超える井戸も全国各地で見つかっている。
揮発性有機塩素化合物の汚染は汚染地域が局所的であるのに対し、硝酸性窒素汚染はその性格上、汚染地域が広範に及ぶ上、現状ではその改善に決定的に有効な対策が見当たらないことから、今後、被害の拡大も懸念されている。硝酸性窒素は過剰に摂取すると、乳児がメトヘモグロビン血症注) 等を起こすことが知られているが、日本ではそれによる発症例は報告されていない。

図1-3-6 平成9〜16 度(1997〜2004 年度)地下水汚染マップ(環境基準26 項目)
1.4 地下水に関する法制度の現状
わが国の現行法では、ヨーロッパの国々に見られる地下水の基本法や総合法(例えば、後述するEU水枠組み指令)のような上位法はなく、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(いわゆる「ビル用水法」)のような地盤沈下対策としての井戸揚水規制に関する法律、土壌汚染対策法や水質汚濁防止法、水質汚染防止に関する法律など、地下水に関連するさまざまな個別法が実効している。
多くの都道府県や市町村では、これら国の法律を受け、地域の実情に応じた独自の条例や要綱等を制定している。
(1)地下水揚水の規制
現在、地盤沈下対策としては「工業用水法」(1956 年(昭和31 年)施行、1962 年(昭和37 年)改正)及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(以下、「ビル用水法」、1962 年(昭和37年)施行)の2法が地下水揚水施設に適用されている。規制の対象となる指定地域は、表1-4-1及び表1-4-2に示すとおり、工業用水法は10 都府県、ビル用水法は4都府県にわたっている。
表1-4-1 「工業用水法」に基づく指定地域
(2)地盤沈下防止等対策要綱
法律や政省令ではないが、地盤沈下に伴う被害の著しい濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部の3地域については、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議(1981 年(昭和56 年)設置)において、「地盤沈下防止等対策要綱」が決定され、発効している。
これらの要綱は、指定3地域を対象とした重点的地下水の採取規制、代替水源の確保及び代替水の供給を行い、地下水を保全するとともに、地盤沈下によるたん水被害の防止及び被害の復旧等、地域の実情に応じた総合的な対策の根拠を与えている。
3地域の地盤沈下防止等対策要綱及び対象地域は表1-4-3に示すとおりである。
表1-4-3 地盤沈下防止等対策要綱の概要
また、各地域の近況は以下のとおりである。
□濃尾平野
2004 年度(平成16 年度)の地下水採取量は1.7 億m3 であり、目標採取量(2.7 億m3)を下回った。当該年度(2003 年11 月1 日〜2004 年11 月1 日)の水準測量結果によると、年間1?以上の地盤沈下が認められた面積は約9? 2 であった。
□筑後・佐賀平野
佐賀地区及び白石地区における2004 年度(平成16 年度)の地下水採取量はそれぞれ3.8 百万m3、4.2 百万m3 であり、佐賀地区では目標採取量(6百万m3)を下回ったものの白石地区では目標採取量(3 百万m3)を上回った。当該年度(2004 年2 月1 日〜2005 年2 月1 日)の水準測量結果によると、年間1cm 以上の地盤沈下はこれら両地区共に認められなかった。
□関東平野北部
2004 年度(平成16 年度)の年間採取量は4.9 億m3 であり、目標採取量(4.8 億m3)を上回った。当該年度(2004 年1 月1 日〜2005 年1 月1 日)の水準測量結果によると、地盤沈下は年間1?以上の沈下が認められた面積は約419 ? 2 であり、うち2?以上の沈下面積は約26 ? 2 であった。
(3)地方自治体における地下水に関する条例・要綱等の制定状況
地域の特性に応じ各地方自治体(都道府県、市町村)で、個別の地下水に関する条例・要綱等が制定されている。それらの法的性格は以下のとおり。
条 例:地方自治体の議会の議決などにより制定される法規で、法的拘束力を持つ。
要綱等:地方自治体が議会の議決を経ずに定める内規で、法的拘束力を持たない。
これらは、おおむね遵守されており、地域の特性に見合った地下水の利用・保全に大いに貢献していると考えられる。
ただし、同一の地下水盆が複数の地方自治体にまたがる場合、地方自治体によって規制の条件、条例・要綱等の内容が異なり、地下水盆全体としての整合した対応が必ずしもとれていない。
地方自治体の条例・要綱等による規制等の対象地域を定めても、対象地域以外では、たとえ同一の地下水盆であっても全くの自由に委ねられている点(いわゆる反対解釈)等の課題をもっているものもある。
?都道府県における制定状況
都道府県の地下水に関する条例・要綱等について、名称別に分類した(表1-4-4参照)。また、都道府県の62 件の条例・要綱等について、その名称と目的・対策等を地図上に示した(図1-4-1参照)。

表1-4-4 都道府県の地下水に関する条例・要綱等の名称による分類(2004 年7月現在)
図1-4-1 都道府県の地下水に関する条例・要綱等の制定状況と規定内容
これらのほとんどは、「公害防止条例」「生活環境保全条例」「環境基本条例」といった公害や環境全般を対象とする条例であり、地下水については、その一部として取り扱われている。
こうしたことから、地下水が、主に公害対策の一環として、地盤沈下対策の側面から規制の対象として取り扱われてきた経緯がうかがえる。一方、地下水そのものを主たる対象とする条例は5つ制定されている。それらは、以下のように要約される。
a)「公害防止条例」「環境条例」及びそれに類する条例における取り扱い(表1-4-4中の分類?〜?)
これらの中で、水質保全については、すべての都道府県において項目として掲げられ、その対策として汚水排出に関する規定が定められている。これは地下水の汚染にも関係するが、主に地表水の汚染との関わりが深い。一方、地盤沈下防止についてもすべての都道府県が目的として掲げているものの、その主要な対策である採取に関する許可・届出義務等の規定については、地域により規定のあるところと、そうでないところがある。
b)「地下水採取・地下水保全条例」及びそれに類する条例における取り扱い(表1-4-4中の分類?)
地下水の採取・保全に関する条例を制定しているのは、山形県、茨城県、富山県、静岡県、熊本県の5県である。その多くは「地下水の採取の適正化に関する条例」及びそれに類する名称を付し、熊本県のみが「地下水保全条例」の名称を持つ。これらのすべてが採取に関する許可・届出義務等の規定を定めており、公害や環境全般を対象とする条例を補完している。
c)地下水の採取に関する許可
公害や環境全般を対象とする条例もしくは地下水に関する条例において、採取に関する許可・届出義務等を規定している都道府県は、南東北、関東、北陸、東海地方に分布しているのに対し、北海道、北東北、甲信、近畿以西では、その選択的内容もしくは一部にとどまっている。
こうしたことから、採取に関する許可・届出義務等の規定は、人口が密集し、水需要の大きい大都市圏や、水資源における地下水依存率が高い関東内陸、北陸等、比較的広域的な対応の必要性の高い地域に制定されていることがわかる。
d)地下水涵養
地下水涵養の人為促進については、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、奈良県、熊本県の条例の中に規定があり、塩水化については、山形県、茨城県、富山県、静岡県、徳島県の5県で規定されている。
e)地下水に関する要綱等(表1-4-4中の分類?〜?)
要綱レベルのものでは、山梨県や徳島県において地下水の採取の適正化に関する要綱が定められているほか、埼玉県、千葉県、福井県において、地盤地下防止を目的とした要綱等が制定されている。埼玉県の「地盤沈下緊急時対策要綱」は、地盤沈下緊急時に知事が地下水利用者に対し、地下水の採取を抑制できるとするものであり、千葉県の「地盤沈下防止協定」は、天然ガスかん水地上排水基準等について県と天然ガス採取企業との間で個別的に締結された協定である。
?市町村における制定状況
市町村の地下水に関する条例・要綱等については、330 件の存在が確認できたが、その半数強の181 件は「公害防止条例」「生活環境保全条例」「環境基本条例」といった公害や環境全般を対象とする条例であり、地下水は、その一部の項目・内容で取り扱われている。
これらを除いた149 件は、名称別に分類した(表1-4-5参照)。また、分類対象とした149 件の市町村の条例・要綱等について、その名称と目的・対策等を地図上に示した(図1-4-2参照)。
表1-4-5 市町村の地下水に関する条例・要綱等の名称による分類(2004 年7月現在)
条例の名称 制定数
?地下水の採取・保全・保護に関する条例 76
?地下水の採取・保全・保護に関する要綱・規約 23
?水資源の保全・保護に関する条例 4
?水道水源の保全・保護に関する条例・要綱 12
?地盤沈下防止に関する要綱・指針 3
?自家用天然ガスの採取規制に関する条例 12
?地下水の汚染防止に関する条例 1
?水環境の保全に関する条例 1
?開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱 16
?地下水の涵養推進に関する要綱 1
合計 149
注)制定数は原則としてデータベース更新時のものであり、その後の市町村合併等による変更を反映していない。
資料)三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成
注)市町村名は2004 年7月現在のもの

図1-4-2 市町村における条例・要綱等の制定状況
a)名称による分類
分類対象とした条例・要綱等は、地下水採取の適正化や地下水の保全・保護、もしくはその双方を名称に含むもの(同じ内容の要件であっても重要度や取扱い方により違うもの)が多く、計99 件(うち条例が76、要綱・規約が23)が該当する。
水資源の側面からの条例・要綱等としては、地下水だけでなく、水資源や水道水源全般の保全・保護に関する条例・要綱で、地下水の採取に関する規定を含むものが計16 件ある。
また、地盤沈下防止に関する要綱・指針は3件あるが、このほか地盤沈下に関連して、自家用天然ガスの採取規制に関する条例が12 件制定されている。
地盤沈下以外の環境面に関するものとしては、地下水の汚染防止と水環境の保全に関する条例が各1件ある。また、開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱のうち、地下水の採取に関する規定を含むものが16 件ある。このほか、地下水の涵養推進に特化した要綱が1件制定されている。
b)条例・要綱の内容の概要
市町村の条例・要綱等について、その内容を概観すると、井戸の設置者や工場・事務所等の設置者に対し、地下水の採取について事前の届出等を義務づけたり、設備の設置基準等を定めたりするなど、採取に関する許可・届出義務や設備設置の基準に関する規定を定めるものがほとんどである。
これらの多くは地盤沈下防止もしくは水源保護を目的としているが、都道府県の場合と異なり、目的が明記されず、対策のみが定められているものも多い。また、一部の市町村では、採取に関する規定と併せて、汚水排出に関する規定や涵養に関する規定も定めている。
c)地域別の分類
地域別に制定状況をみると、新潟県が最も多く30 市町村、次いで、長野県が20 市町村、山梨県が17 市町村となっている。
このうち、新潟県については、自家用天然ガスの採取に関する条例が多いほか、地下水の採取に関する条例・要綱等の中で、消雪用地下水の保全や用水量の削減について規定しているものが多い。消雪に関する規定は豪雪地帯である石川県や福井県でもみられる。
また、長野県や山梨県では、開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱等において地下水に関する規定を設けているものが多く、リゾート開発等に対応したものと考えられる。
これ以外の条例・要綱等の制定状況を地域別にみると、山梨県や静岡県の富士山麓、山梨県や長野県の八ヶ岳山麓、長崎県の雲仙山麓、熊本県の阿蘇山麓など大規模な火山の山麓地域や、山梨県や京都府のような盆地地形の卓越する地域、鹿児島県や沖縄県の島嶼地域において、地下水に関する条例・要綱等を持つ市町村が多い。
国の地盤沈下防止等対策要綱や都道府県の条例の制定状況と合わせてみると、広域的な地下水利用が行われている大規模な平野等では、国もしくは都道府県レベルの条例・要綱等が制定され、盆地や火山山麓、島嶼など比較的狭い範囲での地下水利用が活発な地域や、消雪対策、天然ガス採取、リゾート開発など固有の問題への対応が必要な地域においては、
市町村レベルで条例・要綱等が独自に制定されている。
一方、北海道、北東北、中国、四国では、道県、市町村いずれのレベルにおいても、地下水に関する条例・要綱等の制定が少ない。
これまでにみたように、地方自治体(都道府県、市町村)では、さまざまな条例・要綱等が制定されており、それらの中には規制を伴うものもあるが、地域の実情に即した形で地元に定着し、地下水の地域特性に応じた地下水の保全・利用への取り組みに寄与しているものと考えられる。
第2章 地下水をめぐる最近の動向と地下水保全・利用に係る課題
ここでは、地下水をめぐる最近の動向を調査し、その結果を通して必要な課題を把握する。
まず、わが国の水をめぐる諸問題、水需給全般の状況や、近年の地下水障害等の状況について整理する。次いで、水に関する世界情勢とわが国との関係及び動向が整理される。
2.1 わが国の水需給に関する動向
(1)わが国の水需給動向
?水需給の見通し
わが国の水資源政策の推移をみると、食料の確保と国土の保全が最優先された戦後復興期を経て、高度成長期には、都市部の人口急増や急速な経済発展に伴い都市用水を中心として水需要が急増し、これに対応するために本格的な水資源開発が進められたが、水質汚染や地盤沈下等新たな公害や環境問題が発生した。水資源開発が需要に追いつかない状況は、わが国の経済が安定成長期に入った後も継続した。このように戦後のわが国の水資源政策には、一貫して需要増加に対応した供給拡大が求められてきた。
近年は、水資源施設の充実、人口増加率(出生率)の低下(図2-1-1、図2-1-2 参照)、経済の安定・成熟や国民生活の質的向上等に伴い、渇水等の異常気象時を除き平常時の水需給のギャップは縮小しつつある。また、総人口の減少局面を迎えたことから、水需給の将来に対し、短絡的に楽観視する声もある。
しかし、気象変動に伴う利水安全度の低下や、都市域への人口の緩やかな集中が続くことが予想されることから、平常時はもちろんのこと、特に異常渇水、災害等緊急時の対応の充実が必要である。さらに、水の重要性を国際的視点から鑑みれば、長期的に国家戦略として水資源を総合的かつ戦略的に確保・管理していく必要がある。
図2-1-1 わが国の総人口の推移と予測
図2-1-2 わが国の年齢3区分別人口割合の推移と予測(中位推計)
?安全で良質な水供給への要請
健康志向や安全・安心への関心の高まりの中で、安全で良質な水供給への国民の要請はさらに増大している。その要請の一つは飲料水の消費に現れている。最近、市販ミネラルウォーターの生産量と輸入量が急増している(図2-1-3 参照)。2004 年をみると、国内生産量と輸入量をあわせ1,627 千キロリットルが消費されており、10 年前の消費量の約3倍である。
これを一人あたりに換算すると、年間で一人約13 リットルのミネラルウォーターを使用していることとなる。一人一日あたり飲料水必要量を3リットル(市町村等で防災上必要な備蓄量の目安とされる値)として計算すると、年間の飲料水必要量の約1%に相当する。
図2-1-3 ミネラルウォーター類国内生産及び輸入量の推移
(2)水需給に関する安定性
?気象変動に伴う利水安全度の低下への対応
近年、少雨年と多雨年の変動幅が次第に増加し、渇水年の年降水量が減少傾向にあるのみならず、年最大連続無降雨日数(降水のない日が連続する最も長い期間)も長くなる傾向が認められている。こうしたことから、ダム等の水資源開発施設が計画された当時の開発水量を安定して供給できないなど、水供給の利水安全度(実力)が低下しており、気候変動が国内の水需給バランスに与える影響が顕在化しつつある(図2-1-4 参照)。
今後も、こうした降水特性の変化や地球温暖化等に起因する気候変動により、水供給の能力低下が一層加速する恐れがあるとともに、これまでの計画規模以上の渇水の危険度も増加している(図2-1-5 参照)。
図2-1-4 日本の年降水量の経年変化
図2-1-5 気象変化による水資源開発水量の利水安全度(実力)低下(木曽川水系の例)
?大都市圏域への人口集中への対応
わが国の総人口は、2025 年時点でも全国で1.2 億人前後と1980 年代の水準にあると予測されることから、年齢別人口構成の変動はあるものの生活の質の向上志向や都市型生活の利便性を容認する限り、水需要が急減することは考えにくい。現状の地方圏の実情では人口減少が避けられないだろうが、地方ブロックの中枢都市以上の大都市圏域では、統計資料の外挿の上で、人口の緩やかな集中が続くと予測されている(図2-1-6 参照)。
大都市圏域は、圏域内外より供給できる1人あたり水資源量が少ないことに加え、社会基盤の高度化や高齢化、生活様式の変化等により、給水制限や断水時の社会的影響も増大している。大都市圏域では、利水安全度の低下が高度化した都市機能の持続と維持に深刻な影響を及ぼす恐れがあり、危機管理の視点から対応の必要性が高まっている。
図2-1-6 都市と地方の人口の推移と予測
(3)地下水資源の需給見通し
これまでに述べたわが国の水需給状況と今後の動向を踏まえると、将来の地下水資源の需給見通しは以下のように考えられよう。
* 安全で良質な水供給の要請から地下水資源への需要が高まる可能性がある。
* 気象変動を踏まえた利水安全度の確保や、都市部の住民生活や都市機能の持続・維持の観点から、地下水資源への需要が高まる可能性がある。
2.2 新たな地下水障害と地下水源開発の動向
これまで地下水障害といえば、地下水の広域かつ長期にわたる揚水利用によって生じる地盤沈下、井戸枯れ、塩水化などを指したが、近年、渇水時の短期に集中する地下水利用に伴う地盤沈下が新たに問題となってきた。ここでは都市地下構造部への地下水の悪影響や新しい地下水開発・利用によるインパクト等も含め、主として量的側面に焦点を当てて広い視野で検討を加える。
(1)渇水時の地下水位(水頭)低下と地盤沈下
多くの地域では地盤沈下が沈静化し、地下水位・水頭(被圧帯水層)の大幅な低下はみられなくなってきているが、数年に一度生じる渇水時(図2-1-4)には、主要な都市域で短期的な低下がみられる(図2-2-2、図2-2-3参照)。これは、地表水が減少して河川水の取水制限が行われ、代替水源として地下水の利用量が増加することや、少雨により涵養量が少なくなることが要因と考えられている。
地下水位・水頭の低下は、地盤沈下などの不可逆かつ蓄積する障害を招く恐れがあり、一度生じると回復は容易ではなく、将来にわたる大きな問題となることから、渇水時には以下のように対応し、地下水位・水頭の低下を防ぐことが求められる。
1) 渇水時における地下水利用状況の把握・地下水位低下の要因特定
従来の年単位の地下水採取量の把握に加えて、渇水が起こりやすい地域、渇水が起こりやすい時期には、月単位などより詳細な地下水採取量の把握を行うとともに、地下水位の低下の要因を特定する必要がある。
2) 渇水時における地下水採取抑制・自粛の要請
渇水時における地下水位低下の要因を特定した上で、地下水利用の限界採取量あるいは管理基準地下水位を設定し、基準を超えた際には、利用者に対して地下水採取の抑制を要請する仕組みづくりが求められる。
例えば、生活用水の地下水依存率が高い福井県大野市では、扇状地の水田の水がなくなる11 月頃の地下水位が最も低くなり、これまでに大規模な井戸枯れが生じた経緯から、独自の地下水警報発令基準を設けている。近年、地下水位の低下が著しく、たびたび節水を呼びかける警報が出されている。
図2-2-1 渇水時の地下水位低下のメカニズム
図2-2-2 渇水年における地盤沈下の進行
図2-2-3 要綱地区(筑後・佐賀平野)における地盤沈下面積と地下水採取量
(2)地下水位(水頭)上昇による地下構造物への揚圧力による障害
揚水規制や地下水環境の保全意識の高まりにより、近年では、地盤沈下地域の数、面積ともに減少し、地盤沈下は沈静化しつつある。
しかし、首都圏では、地下水採取の法的規制によって、逆に地下水位が回復・上昇し、東京駅や上野駅などの鉄道駅の地下部分が浮き上がる等の新たな問題が発生し、JR東日本ではアンカーを埋めるなどの地下水位上昇対策工事(東京駅:1999 年、上野駅:1997年)を行った。また、大阪市では、地盤沈下を防ぐため地下水の採取を規制してきたが、現在は逆に地下水位が上昇し建物が浮いたり、地下街や地下鉄のトンネルへの湧水増等の事例が出てきている。
地下水位の上昇は地震災害時に液状化を引き起こす可能性など、防災上の問題も指摘されている。
このように、東京都や大阪市など大都市圏の限られた地域の問題ではあるものの、地下水位の上昇に伴い、地下水位が大幅に低下した時期に計画・建設された地下構造物が浮き上がるなどの障害がみられ、所有者や管理者による対策が実施されている。今後、このような国土の脆弱化をもたらす地下水位の上昇を防ぐために、地下水環境保全を促す地下水位を定めた上で、利用可能な範囲内で地下水採取を行うなど、一定の地下水位を維持する施策が求められる。
(3)ミネラルウォーターの生産拡大の動向
ミネラルウォーター市場の拡大に伴い、大手飲料メーカーだけでなく、全国各地で地下水を活用した飲料水ビジネスが活発化している。現在、国内で約400 社、450 銘柄のミネラルウォーターの飲料水があると推計されている。
現在、国内生産されているミネラルウォーターの生産量は、国内で使用されている地下水使用量全体(124.1 億?)の約0.01%にとどまり、現時点ではその占有率は低いが、大量採取が行われているような地域においては、この割合は今後高くなると想定される。
大手飲料メーカー等は山間部などの水源を確保し、地下水の大量採取を行っているが、現在のところ、この新たな地下水採取によって、周辺の地下水利用者への影響や、地下水障害等は特に報告されていない。この動向に対して行政は、水源地下水の状況や利用可能量を見極めた上で、必要な対応が求められる。
また、全国で最もミネラルウォーターの生産量が多い山梨県では、自治体が地域資源からの恩恵を受けている事業者に対して税負担(例えば、1リットルあたり0.5〜1円の税率で、2.5〜5億円の税収見込み)を求めることを検討した事例もある。
(4)地下水新ビジネスの参入
近年、水質改善膜ろ過技術や井戸の小口径高揚程ポンプの開発に伴い、企業、農漁業団体、サービス業、公的機関等の専用(自己)水道による地下水利用が新たに増加している。
特に、ホテルや病院、ショッピングセンターなど、緊急時の自己水源確保を求められる個別水道利用施設で導入が進んでいる。
この個別水道利用施設の地下水利用では、20〜30mの浅層家庭用井戸と異なり、100m以深の深井戸からのくみ上げが目立つ。浄水膜ろ過プラントは小型な設備であれば3,000万円程度の投資で済み、また、揚水機のリースであれば投資リスクを負う必要が無いなど、利用者にとって初期負担が比較的小さいことも普及の要因となっているものと思われる。
地下水の採取規制などがない地域では、利用者にとっては、水質に問題がなければ揚水コストを削減することができる。さらに、地震などの災害時に備え2つの自己水供給システムを有することができるというメリットもある。
現在のところ、これらに伴う地下水障害は顕在化していないが、規制対象から外れた地下水揚水施設については、現行法制度では利用実態の把握が困難であり、採取量が把握できない状況となっている。
また、水道事業を行う自治体において、この種の地下水採取に伴い、水道水の利用量減少による減収が懸念されている。
(5)深層地下水の開発
地下水資源は、淡水そのものを利用の対象とするのみならず、温泉・鉱業や深層水の新規開発にも拡大して目が向けられている。とりわけ都市型の商業施設や娯楽施設では深層地下水が多目的に活用されている。
(6)地下水の発展的利用・可能性へ向けた議論の動向
昨今、地下水の都市ヒートアイランド現象軽減のための利用など、いくつかの新しい発展的活用へ向けた議論がなされている。
2.3 地震災害等、緊急水資源需要への対応
(1)地震災害時における問題点
わが国では、1995 年の阪神・淡路大震災をはじめ、2004 年新潟中越地震、2005 年福岡県西方沖地震など、大きな被害を伴う大地震が発生している。これらの地震災害時には、各用途に応じた緊急的な水の確保が問題となった。阪神・淡路大震災においては、井戸や湧水を雑用水として利用したケースが報告された。また、震災時には揚水ポンプが停止し、急激な地下水帯水層の水圧力上昇により水があふれ出たが、この水が震災時のトイレ用水や復旧工事の際の散水などに活用された注)。
その他に新潟中越地震では、液状化による被害や消雪パイプの破損も問題となった。
表2-3-1 阪神・淡路大震災における水利用に関して報告された問題点
分類 分類 問題点
用途別 消火活動 ・消火栓が使用できず、消火活動の大きな障害になった。
医療活動 ・病院には特別に給水活動を行う必要があった。
飲料・炊事 ・市民は、飲料用水として、市販の水を確保した。
トイレ洗浄 ・量を必要とするトイレ用水は、その確保とともに運搬も大きな問題だった。
表2-3-2 新潟中越地震における水需要及び地下水利用に関する問題点
・被災地すべての避難所で県が実施した生活実態調査によると、「トイレが不便」という避難所が3割に達した。
・地震による液状化現象により、マンホールが浮き上がったり、路面が割れて盛り上がるなどの被害が生じている。これにより除雪車が走行できない等の問題が生じた。
・消雪パイプが破損したが、ガスや水道の復旧作業が優先されるため、消雪パイプの復旧が遅れ、雪対策が遅れる等の問題が生じた。
なお、地下水位の上昇による大地震発生時の液状化現象の危険拡大も指摘されている。液状化現象とは、地下水で満たされた地層(地盤)が地震動によりその体積を減じ、その分、間隙にあった水が上方に放出され、地盤内に余剰の水があふれた結果、地層が液状流動化することを言う。これにより、地上・地下のライフライン、構造物等が重大な被害を受ける可能性がある。
さらに、地球温暖化による海水面の上昇が、沿岸・臨海域の地下水位上昇や地盤の液状化強度の低下をもたらす可能性も指摘されている。
注)震災時の水の確保に関する研究会「大都市における大規模震災時の「水」の確保について(案)」(阪神・淡路大震災での状況)参照
(2)地震災害への対応
?緊急水需要
a)経過日数でみた水需要
大規模震災時に想定される水需要を、用途及び発生場所の点から経過日数に即して整理したものが図2-3-1 である。災害直後から3日目頃は消火用水、医療用水及び生命の維持に必要となる最小限の飲料水の確保が不可欠となる。また、被災生活が開始されると、飲料水だけでなく炊事、トイレなどのための水需要が発生するほか、入浴や洗濯のための生活用水が必要となる。
さらに、災害後概ね4日目以降で復旧作業が開始されると、生活用水の拡充とともに、産業復活や防塵、復旧工事用の水需要が発生する。
図2-3-1 地震被災時における水需要
b)用途別にみた水需要
地震災害時における水需要はその用途に応じて、必要となる水量や水質は異なる。例えば、災害直後に多量に必要となる消火活動や、生活用水の中でもトイレ洗浄用水は水質への要求度は高くない。一方、医療活動の水や飲料・炊事用水は清浄な水質が求められる。
表2-3-3 地震災害時における用途別にみた水需要
?応急水供給
地震災害時に利用が想定される、都市における水の所在は以下の通りとなっている。河川・池・湖沼水や海水などは大量に供給可能だが、水質が保証されず、取水ポイントが限定される。また、雨水や再生水は比較的良質な水であろうが、専用の設備が整備されていることが必要となる。
このような中で、地下水は、清浄な水質が期待できる身近な水資源として、飲料や医療用途に活用できる可能性があるが、事前の十分な水質検査や、地震時における地下水脈への影響等を考慮して利用する必要がある。
表2-3-4 地震災害時における水供給源別にみた特徴
2.4 水に関する世界情勢
情報、経済、物流のグローバル化が進む現在、それらを支える基盤である水資源や水政策が今後の日本でいかにあるべきかを考えることは、時代の要請と言えよう。ここでは世界的な水問題について、米国の水事情概況及び地表水・地下水を合わせた総合的な水資源管理をめざす欧州の取り組みを紹介する。
(1)世界的な水問題とわが国の関係
?世界的な水需要の拡大と地下水障害の発生
18 世紀産業革命以降の世界人口の増加や、農業、とりわけ灌漑農業の発展は、淡水の消費を飛躍的に増加させた。例えば、中国・黄河の過剰取水による流況異変、中央アジア・アラル海の灌漑取水による水位低下が招く湖面積の縮小など、世界各地で水が不足する状態を生じさせている。
米国は図2-4-1に示すように、西経100 度と120 度に挟まれた全国土(936.3 万k ?)の約4割が年降水量500mm 程度の乾燥地帯であり、西経100 度以東は降水量に恵まれた(例えば、ニューオーリンズの年降水量1,584mm)温帯多雨国土である。この東西を二分する気候は、地形と地質が相まって固有の農業を発展させてきた。図中の乾燥地帯はシェラネバダ山脈とロッキー山脈に挟まれた高地グレートベースンとロッキー山脈の東側グレートプレーンズに拡がり、小麦生産や遊牧業及び人工灌漑農業が広大な農地で行われた。
多量の水を必要とする灌漑農業には、化石水ともいえる深層地下水が利用されている。図中ではこの地域の水不足分布が概観されている。
地下水についても、米国・グレートプレーンズでは深刻な地下水位の低下が生じている。
この「センターピボット(Center Pivot)方式」では、1つの井戸で毎分10 ?の地下水を揚水し、井戸の本数が数千本にもなるため、年間約7,500 万?もの地下水を利用するが、涵養量は年間約800 万?にとどまるため、過去30 年間で地下水位は平均12m、最大30mも低下した。この結果、耕地面積は1978 年〜1988 年の10 年間で100 万ha 減少した。
図2-4-1 米国の水不足地域の分布状況
?世界的な水問題とわが国の関係
国連環境計画や国連人間居住委員会、ユネスコなど23 の国際機関などが共同で発表した「世界水開発報告書」(2003 年3月)によると、半世紀後には最悪の場合で世界人口の8割にあたる70 億人が淡水不足に直面すると予測しており、水問題は21 世紀の世界的な課題だと警告している。
島国日本は、当面、水需給ギャップが縮小傾向にあり、国際河川や国際湖沼も当然ながら存在しないため、直接的な水に係わる国際紛争はないが、無関心ではいられない。その理由は、例えば、水資源に直結するわが国の食料自給率は熱量換算で2000 年には約40%まで低下しており、フランス、アメリカ、ドイツなどの食料自給国と比較して非常に低い。
食料の生産には水が使用されることから、わが国は食料等の輸入を通じ間接的に海外の大量の水を消費しており、その総量は年間640 億?と見積られている(図2-4-3参照)。
世界的な水危機の状況が、今後ますます激化すると予想される中、これに関する世界の経済、社会活動の変化とりわけ食料問題は、物流・経済を通じて日本経済や社会問題に直結している。今後の水資源政策は、このような実情も視野に入れながら、より好ましい水資源を総合的かつ戦略的に確保、管理していかなければならない。
図2-4-3 日本の仮想投入水総輸入量
(2)EU政策「水枠組み指令」
世界的な水危機に伴い、総合的・戦略的な水資源政策が求められる中で、わが国の地下水保全・利用のあり方を検討する際の参考に資するため、ここでは、特に地下水利用の長い欧州における取り組みを紹介する。
欧州では、古代ローマ時代から地表水よりも地下水を優先して使用してきた経緯がある。その伝統は、現在でも特に生活用水において継承されており(鯖田、岩波新書、2001)、
その宗教的とも言える思想は、地下水源の保全に向けた欧州先進国の取り組みの中で継承されている。
近年、EUでは、加盟国に統一した指令として、流域単位での水管理を目指す「水枠組み指令」が新たに発効された。ここではそれに着目して、その背景や考え方、水政策と地下水に関する動向等について言及する。
?「水枠組み指令」(EU Water Framework Directive)の背景
a)EUの概要
欧州連合(EU:European Union)は、「経済的な統合を中心に発展してきた欧州共同体(EC)を基礎に、欧州連合条約(マーストリヒト条約)(1993 年発効)に従い、経済通貨統合を進めるとともに、共通外交安全保障政策、司法・内務協力等のより幅広い協力をも目指す政治・経済統合体」である。従来の国際機関などとは大きく異なり、構成国からの国家主権の一部の委譲を前提に、域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成し、政治的にも「一つの声」で発言する等、いわば連合国家に準ずる存在である点が大きな特徴である。
表2-4-1 EUの概要(2007 年1月現在)
b)欧州における水問題の状況
「水枠組み指令」制定の背景となった欧州における水問題の状況について、「水枠組み指令」では以下の各点があげられている。
*欧州連合の全地表水の20%は、深刻な汚染の危機にさらされている。
*欧州の飲料水の約65%は、地下水でまかなわれている。
*欧州の都市の60%は、地下水資源を過剰に採取している。
*湿地帯の50%は、地下水の過剰開発により「危機的状況」にある。
*1985 年以降、南欧の灌漑地が20%増加している。
EUにおいては、これまでにも主に水を保護するための政策や法律が策定されてきたが、「欧州連合の環境−1995」では、上記のような背景を踏まえ、EU内の水について、量的のみならず質的にも保護アクションが必要であることが指摘されている。
?「水枠組み指令」の概要
水域を良好な状況にすることを目的として制定された「水枠組み指令」(EU WaterFramework Directive)は、正式名称を「水政策分野での共同体アクション枠組みを構築する2000 年10 月23 日の欧州議会及び評議会指令2000/60/EC」(Directive 2000/60/EC ofthe European Parliament and of the Council establishing a framework for the Communityaction in the field of water policy)と言い、2000 年12 月に発効した。
「水枠組み指令」は、地表水や地下水などすべての水資源を対象としており、欧州全体で、地下水と地表水の統合的な管理を示した初の指令である。「水枠組み指令」を受けて、各EU加盟国は、地域性に応じたマネジメント計画等を作成し、それに基づく対策を講じることで、EU全体で水環境の保全・管理を進めていく仕組みとなっている。地下水の位置づけは地表水と同等であり、特に、第17 条では地下水に特化して汚染対策が記載されている。
「水枠組み指令」の特徴として、政治・行政的境界ではなく、河川流域単位での浄化及び管理の取り組みを導入していることがあげられる。各国はまず指令の対象となる河川流域を指定し、適切な管轄当局を含む行政整備を行うことが義務づけられている。国際河川流域についても、関係国間で調整し、同様の指定を行わなければならない。これらの河川流域には、言うまでもなく地下水が含まれる。
また、「水枠組み指令」では、水環境の維持と改善を目的としており、主な対象は水質である。水量のコントロールは水質対策の付随的な要素とされており、良質な水を確保するためには、各国で、質と同時に量に関する対策も実施すべきであるとされている。良好な地下水状態とは地下水の量的状態、化学的状態の両方が良好であることを指すとされて
いる。
以下に、「水枠組み指令」の構成及び概要を示す。
a)「水枠組み指令」の構成
「水枠組み指令」は以下のような条文から構成されている。
第1条 目的
第2条 定義
第3条 河川流域地区内での行政整備の調整
第4条 環境目的
第5条 河川流域の特徴、人間活動による環境影響のレビュー、水使用の経済分析
第6条 保護地区の登録
第7条 飲料水の対象とする水域
第8条 地表水状態、地下水状態、保護地域のモニタリング
第9条 水サービスの費用の回収
第10条 点源、拡散源についての組み合わせアプローチ
第11条 対策プログラム
第12条 加盟国のレベルで対処することができない問題
第13条 河川流域マネジメント計画
第14条 情報公開とコンサルティング
第15条 報告
第16条 水汚染に対する戦略
第17条 地下水の汚染防止、コントロールに関する戦略
第18条 委員会報告
第19条 将来の共同体対策計画
第20条 本指令に対する技術的な調整
第21条 規制委員会
第22条 廃止及び過渡的条項
第23条 罰則
第24条 実施
第25条 効力発生
第26条 送付先
付録
b)「水枠組み指令」の特徴
上述に構成されている「水枠組み指令」について、ここでは主な特徴を整理する。
■環境目的
主な環境目的は、すべての水域を2015 年までに良好な水質状態にすることである。
□地表水について
・加盟国は、地表水全体の劣化を防止するための必要な対策を実行しなければならない。
・加盟国は、すべての地表水体(bodies of surface water)を保護、整備、修復しなくてはならず、本指令発効(2000 年12 月)後少なくとも15 年間は良好な地表水状態を達成しなければならない。
・加盟国は、良好な生態的潜在力、良好な地表水化学状態を保つために、本指令発効後少なくとも15 年間は、人工的あるいは大幅に改良した地表水体を保護し整備しなくてはならない。
・加盟国は、重点物質による汚染を徐々に減らし、優先的危険物質の排出、放流、損害を排除、あるいは徐々に排除するために、必要な対策を講じなければならない。
□地下水について
・加盟国は、汚染物質が地下水に入ることを防ぎ、あるいは制限し、地下水全体の状態が悪化しないようにするために必要な対策を講じなければならない。
・加盟国は、本指令発効後少なくとも15 年間は良好な地下水状態を達成することを目的として、すべての地下水体を保護、整備、修復し、地下水の揚水量と涵養量のバランスを確実にしなくてはならない。
・加盟国は、地下水の汚染を徐々に減少させるために、人間活動の影響により地下水中の汚染物質の濃度が著しくあるいは持続的に増加する傾向にある場合、それを修復するために必要な対策を講じなければならない。
■現状把握
本指令を受けて、各河川流域地区で以下の事項を実施しなければならない。
○河川流域の特性把握
○地表水あるいは地下水に対する人間活動の影響の把握
○水使用の経済分析
○飲料水として抽出する水(1日平均供給量が10 ?超または50 人超に供給)または将来飲料水として使用される水のモニタリングなお、飲料水として抽出する水源は保護地域として登録が義務づけられる。
本指令を受けて、各国は2006 年までに(発効後6年以内)水状態のモニタリング・プログラムを設定し、実施しなければならない。地下水については、化学的状態及び量的状態の把握が求められている。
■水サービスのコスト
本指令では、水は商用製品とは異なり、むしろ遺産のように保護しなければならないとされているが、同時に水サービスコストの回収も考慮すべきと明記されている。加盟国は2010 年までに以下の実施が求められている。
?水料金政策によって水使用者が効率的使用を行った場合には、適切なインセンティブを与えられるようにして、環境目的に貢献するようにすること。
?経済分析に基づき、汚染者負担の原則を考慮して、産業、家庭、農業の異なる水利用者が、水サービスコストを適切に負担すること。
■対策
各国は、河川流域地区ごとに目的を達成するため、対策プログラムを実施しなければならない。このプログラムでは、国内レベルでの既存の法令に基づく対策の中から、本指令で求められている基準を定められた期限内に達成することができる活動を特定し、採用することができる。
■流域マネジメント計画
各国は、河川流域地区ごとに河川流域マネジメント計画を2009 年までに作成し、運用しなければならない。複数の国にまたがる国際河川流域マネジメント計画は単一の作成が義務づけられている。河川流域マネジメント計画は6年ごとにレビュー・更新される。その際には情報公開を徹底しなければならない。
■水汚染に対する戦略
欧州議会と欧州評議会は汚染物質あるいは汚染物質グループによる水汚染に対して対策を講じなければならない。欧州委員会は汚染の要因となる重点物質や重点危険物質を明確にし、それに対する対策について提案が義務づけられている。
これを受けて、欧州委員会は2001 年1月、新水枠組み指令の最初の規制対象として指定する32 種類の「優先物質」リストを提案、同年11 月に採択された。特定の有害物質については、20 年以内に水域への排出を段階的に停止することとされている。
地下水については、第17 条の中で記述され、地下水の汚染防止、コントロールに対する戦略として、欧州議会と評議会は、
?良好な地下水化学状態を評価するための基準、
?重大な継続的上昇傾向の確認及び傾向が逆転した地点の定義、を含む提案を行うこと
が義務づけられている。
また、第8条では、各国が策定する水状態のモニタリング・プログラムの対象として、地下水については化学的状態、量的状態があげられている。
■スケジュール
EU加盟各国は、2003 年12 月までに本指令の遵守に必要な法律、規制、行政条項の発効が義務づけられている。本指令の主要事項における期限は以下の通りである。
期限 内容
2003.12 ・本指令の遵守に必要な法律、規制、行政事項などを発効・流域連携の組織化
2004.12 ・水への影響分析を完了(経済分析を含む)
2006.12 ・水マネジメントの基盤となるモニタリング・プログラムの実施
2008.12 ・河川流域マネジメント計画が市民に公表される
2009.12 ・最初の河川流域マネジメント計画が発効される
2015.12 ・良質な状態の水となる
?「水枠組み指令」を補完する地下水に関する指令及び動向
2003 年9月、欧州委員会は、水枠組み指令の第17 条に基づき、地下水汚染防止に関するEU指令案(Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of groundwater against pollution 2003/0210(COD))(以下「地下水指令」)を発表した。「地下水指令」は加盟国に対し、地下水質のモニタリングを義務づけ、EUの既存の法令基準(窒素分、植物保護剤、殺生物性製品など)の遵守状況を把握するよう求めている。EUの法令で対象とされていない物質については、加盟国が2006年6月までに上限値を設定することとされている。汚染の程度が、「期間」と「環境上の重大性」の観点からみて、一定のレベルを超える場合には、加盟国は汚染悪化を防止する対策を講じなければならない。
水質基準値または上限値の75%を超える場合は、環境上重大な状況にあるとされる。この他、地下水汚染を防ぐため、有害物質の間接的な排出(地面や土壌中への排出)を禁止または制限する条項も盛り込まれている。
地下水指令の構成は以下の通りである。
第1条 内容
第2条 定義
第3条 地下水の良い化学状態を評価する基準
第4条 閾値いきち*1
第5条 重大かつ悪化傾向の判断基準及び修復を行う出発点の定義
第6条 地下水への間接的な排出を防ぐまたは制限する施策
第7条 過渡的なアレンジメント
第8条 技術的な適合
第9条 実施
第10条 効力発生
第11条 実施者
付録
備考*1)EU の各加盟国が定める、地下水帯に危険な影響を及ぼすと見なされる汚染物質の限界値。国レベル、流域レベルまたは地下水帯レベルで定めることができる。
このほか、「水枠組み指令」に基づく2005〜2006 年の作業プログラムとして、地下水、環境状況、統合的流域管理、調査報告をテーマとする4つのワーキンググループが設置され、水枠組み指令の実施にあたって解決すべき課題の検討がなされている。
?わが国の地下水利用のあり方への示唆
このように、EU「水枠組み指令」では地下水と地表水を総括した水資源全体での統合的な管理を推進している。地下水を含めた流域圏を一つの単位として、行政的な境界を超えて水資源管理を行うことが求められており、2009 年までに河川流域マネジメント計画を発効することが予定されている。
わが国においても複数の自治体にまたがる広域的な地下水マネジメントを実践する上で、行政計画策定や実践に向けた方法や手順策定の参考となろう。
2.5 地下水の保全・利用に向けた課題
(1)水資源需要多様化と地下水への期待
これまでに述べたように、わが国の水需給は、将来の人口減少や経済成長の鈍化に伴いおおむねバランスする方向にあり、一方で、安全で良質な水供給に対する要請はますます強まる動向にある。他方、少雨傾向など気候変動に伴う渇水が従来以上に頻発かつ大規模化する傾向があり、利水安全度の低下がより懸念される大都市圏域を中心として、危機管理の視点からの備えの必要性が高まっている。大規模地震災害時には、まず水の確保が重要な課題となるが、身近にある地下水は、それに即応できる重要な水源となりうる。
さらに、地球規模の水危機の深刻化にあって、安全保障の観点や食糧確保等を念頭に世界の水問題へ対応していく必要がある。
今日、淡水資源そのものを支える降水量とその地域分布が地球規模の気候変動によって大きく変容しつつある中で、水資源需給の多様化や安全性を満たす新しい水政策の構築が国家戦略として急務である。そのためには、河川水や湖沼水を含む地表水資源と地下水資源の量的・質的特性を活かしつつ、両者を調和的に利用しうる方法論が必要である。
ここでは、以上の観点から、過去の地下水過剰利用とその障害を教訓にしつつ、地球時代における地下水資源のあり方の議論に先行して、考えられる課題を以下に整理する。
(2)水資源としての地下水の保全・利用に向けた課題
地下水の保全・利用のあり方を考えるにあたって、まず、地下水が重要な水資源であることの共通認識が不可欠である。その上で、水循環系の構成要素として地表水と地下水のデータ整備や利用実態の把握を行うこと、水資源として保全と持続的利用の最適なマネジメントを考えること、また、地下水の分布や利用形態は地域的に多様性に富むことから、地域特性に即した保全・利用のあり方を実現していくことが大切である。
?水資源としての共通認識の醸成
わが国では、高度経済成長期に過剰な地下水の採取が深刻な地盤沈下を招いた経験から、それが広域的な地盤沈下の要因となることについては共通認識が得られている。しかし、地下水は地形・地質の構成要素であり、土地所有状況とは関係なく個別の地下水利用が多かれ少なかれ他に影響を及ぼすといった地下水資源特有の性質は十分理解されていない。
また、地下水は地表水と比較してデータ整備や実態把握が個別的であるため、地下水資源マネジメントに結びつく情報として定着していない。
こうしたことから、今後、地下水を水資源として捉え、その保全・利用を図っていくための共通認識を醸成していくことが課題である。
?水循環系の構成要素としての地下水に関するデータ整備・実態把握
降水を源とする地下水は、地表水とともに水循環系の構成要素であることから、水資源として重要であるだけでなく、流域地表水の基底流量の安定化や洪水流出の緩和に寄与したり、豊かな水辺環境の保全・再生に重要な役割を果たしたりするなど、水循環系において多面的な役割を担っている。
EU「水枠組み指令」(2000 年)によると、地表水や地下水などすべての水資源を対象として、流域単位での統合的な水の管理をめざす取り組みが進められている。一方、わが国でも「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」のもとで、流域全体を視野に入れた水循環系の健全化に向けた取り組みが芽生えている。
こうしたことから、水循環系の構成要素として地下水の保全・利用を行っていく必要はあるが、地下水は地表水と比較して各種定量データが十分に整備されておらず、行政上も組織的にデータ蓄積・分析する仕組みが確立されていないことから、現状では、水循環系全体として、地表水に呼応して地下水を統合的に保全・利用できる状況にはない。
このため、地下水に関する定量データを整備しうる仕組み、例えば、地下水の水資源と
しての基本データ(地下水位・水頭、採取量、地質柱状図、利用実態、水文等)の電子デ
ータ化の推進が時代の要請となっている。その定量データに基づき、科学的な地下水資源・
保全計画を立てて、水循環系の構成要素としての地下水の位置づけや特性を明らかにした
上で、適切な保全・利用を図っていくことが課題となる。
?持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現
地下水は、一般に水質が良好かつ水温変化が少なく、大規模な貯水・取水・給水施設を
必要とせず安価に利用できることから、わが国では、特に経済復興・高度成長期の水需要
に応え、大量に利用され、地盤沈下問題が深刻化した。その対策として国や地方自治体に
よるさまざまな取り組みが進められた結果、地盤沈下はおおむね沈静化している。
以下に示す観点から、今後とも地下水障害を未然に防止するための十分な配慮が必要で
ある。
1) 依然として、長期的には地盤沈下が沈静化している大都市でも、渇水時に短期的・
局所的な地下水位の低下が地盤沈下を招いた(平成6年渇水等)。近年、少雨年の
降水量が減少傾向にあることや、年最大連続無降雨日数(降水のない日が連続する
最も長い期間)が長くなる傾向が認められることから、今後も渇水に伴う地下水位
低下が懸念されている。
2) 深刻な地盤沈下を経験してきた地域(東京、名古屋、大阪等)は、地下水の採取量
を抑制してきた結果、地下水位が回復、上昇に転じ、地下街や地下駅などの既設地
下構造物が浮き上がる問題が生じている。
3) 地下水はいったん汚染されるとその浄化が困難であることから、有機塩素系溶剤や
硝酸性窒素など地下水汚染が多様化していることを踏まえた地下水資源の水質保全
について、特に留意が必要である。
4) ミネラルウォーター生産のための地下水利用、揚水・ろ過技術の新技術を背景とし
た個別水道利用施設における地下水利用等が拡大している。
地下水は水循環系において一般的に滞留時間が長く、地盤沈下や水質汚染などの地下水
障害は、いったん生じると復旧が不可能であるか、もしくは長い年月を要する。このこと
から、持続可能性という観点に立ち、地下水をめぐる新たな動向が及ぼす影響についての
解明も進めつつ、地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染等を生じさせず、地下水の保全と
利用の最適なマネジメントを実現していくことが課題となる。
?地域特性に即した保全・利用のあり方の実現
地下水資源の分布や利用形態は、地形、地質、気候、植生等の自然条件や、人口、土地
利用、産業、歴史・文化等の社会経済条件によって地域ごとに大きく異なっており、多様
性・固有性に富んでいる。
例えば、わが国では、主要な地下水盆は平野や盆地に分布しているが、関東平野のよう
に複数の都県にまたがる大規模なものから、単一市町村にとどまる小規模な平地や扇状地
まであり、このほかに火山地域や石灰岩地帯にも帯水層が存在し、それぞれで地下水が利
用されている。また、水利用全体における地下水への依存度や、生活用水、工業用水、農
業用水といった地下水利用の用途別割合も、地域によってさまざまである。
このように地下水資源の分布や利用形態が異なれば、地下水資源の開発可能性や地下水
障害・汚染等の発生状況も千差万別である。このため、地下水の保全・利用に向けた取り
組みにあたっては、それぞれの地域特性に則した考え方や方法・体制等に基づいて対応す
ることが重要な課題となる(図2-5-1参照)。
地下水への期待と動向
■水資源としての地下水への期待
* 安全で良質な水供給への要請
* 気候変動等に伴う利水安全度の低下への対応
* 大規模地震災害時の水源確保
* 長期的な安全保障の観点からの水資源確保の必要性
■地下水をめぐる最近の動向
* 広域的な地盤沈下は概ね沈静化
* 渇水時には短期的・局所的な地下水位低下、 地盤沈下が発生
* 一部地域では地下水位上昇により地下構造物への影響も発生
* 地下水質汚染
* 新たな地下水利用形態( ミネラルウォーター、 地下水ビジネス)の拡大 等地下水の保全・利用の課題
* 水資源としての共通認識の醸成
* 水循環系の構成要素としてのデータ整備・実態把握
* 持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現
* 地域特性に即した保全・利用のあり方の実現問題の所在
* 水資源としての地下水、 および水循環の構成要素としての地下水についての共通認識が得られていない
* 地下水の諸問題について、 科学的な見地からの実態解明・要因分析が十分になされていない
* 水資源としての地下水資源の保全と利用の調和の社会的合意や理念が形成されていない
* 地下水の現状・動向は、 地域ごとの多様性が高く、 全国画一的な対応が困難
図2-5-1 地下水の保全・利用に向けた課題の概観
第3章 今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法
第2章では、地下水資源の保全・利用に向けた課題として、水資源としての共通認識の醸成、水循環系の構成要素としてのデータ整備・実態把握、持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現、地域特性に即した保全・利用のあり方の実現、という4つが抽出された。
これらの解決における科学的論拠は「健全な水循環系の構築」(新しい全国総合水資源
計画(ウォータープラン21)、国土庁、1999 年)に置かれる。ここではまず、健全な水循
環系の構築における地下水の位置づけや、水循環系の構成要素としての地下水の特性を踏
まえ、課題解決に向けた基本的な考え方を示す。
次に、これらを踏まえた地下水の適正な保全・利用を実現するための新しい方法論とし
て、「地下水資源マネジメント」の考え方を提案し、その具体的な手順について述べる。
さらに、その計画・実践にあたり、地域ごとの多様性、地下水の特性、特に地域規模と
の関係に着目し、地域規模に基づく類型別「地下水資源マネジメント」を提唱する。
3.1 健全な水循環系の構築における今後の地下水利用の基本的な考え方
ここでは、健全な水循環系の構築にあたって地下水の位置づけを明らかにし、地下水の
特性を地表水と比較検討した後、これらを踏まえ、課題解決に向けた今後の地下水利用の
基本的な考え方を提示する。
(1)健全な水循環系の構築における地下水の位置づけ
?健全な水循環系構築の背景
「健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて」(2003 年10 月、健全な水循環系構
築に関する関係省庁連絡会議公表)では、「健全な水循環系」とは「流域を中心とした一連
の水の流れの過程において、人間社会の営みと環境の保全に果たす水の機能が、適切なバ
ランスの下にともに確保されている状態」と定義づけられている。その具体的な姿は地域
ごとに多様であり、例えば、地下水障害や地下水資源の枯渇を生じない範囲で地下水が最
大限利用されている状態や、歴史的・文化的に重要な湧水の復活・維持といったような目
標の設定や地域特性に依る。
近年の都市化の進展は、降水の浸透機能を低下させ、都市型水害や、地下水の涵養力低
下を招いている。また、地域の文化資産ともいえる古くからの湧水を枯渇させたり、河道
への地下水からの涵養を減少させ、平常時の河川流量の減少も招いている。地下水採取・
利用とも重なって、水循環系の健全性が損なわれている。
こうしたことから、今後の地下水資源の保全・利用のあり方を考える上で、健全な水循
環系の構築という視点の重要性がきわめて高くなっている。
?水循環系における地表水と地下水の特性比較
地表水と地下水はいずれも水循環系の構成要素であるが、今後の地下水資源の保全・利
用の検討にあたって、水循環系における地表水と地下水の特性の違いに留意する必要がある。
両者の特性を概略比較したものが表3-1-1であるが、地表水との比較における地下水の
重要な相違点として、滞留時間の長さと実態把握の困難さ(時間・経費増、遅れ等)があ
げられる。滞留時間の長さは、過剰揚水等による井戸枯れ・塩水化等の地下水障害や地下
水質の汚染が一度生じると、その回復・改善に長期間を要することの要因となる。また、
実態把握の困難性や遅れは、水循環系全体として、地表水に呼応して地下水を統合的に保
全・利用できない要因となっている。
表3-1-1 水循環系における地表水と地下水の特性比較
(2)今後の地下水利用の基本的な考え方
?地下水資源マネジメントの論点
地下水に関するマネジメント注)は、広域の地下水資源利用に焦点を当てた「地下水資源
マネジメント」と個別の土地開発や地下空間開発によって起こり得る地下水環境に与える
悪影響の防止・軽減を目的とする「地下水環境マネジメント」の2つに分けられる(図3-1-1
参照)。なお、地下水資源マネジメントは図3-1-1 青色に示す。
健全な水循環系の構成要素をなす地下水は、流域地下水文区のもつ水源地域から平野部
までさまざまな地域特性を踏まえ、量・質及び環境を考慮し、総合的な観点に立った検討
が必要である。
そこで、本報告書では、健全な水循環系の構築という視点から、主に量的な側面に軸足
を置いた「地下水資源マネジメント」について、今後の地下水利用の基本的な考え方を示
すこととする。今後、各地域で地下水資源マネジメントの取り組みをそれぞれの地域で具
体化・実践するにあたっては、各地域の諸条件や水需給に適合した検討が必要であること
は言うまでもない。以下の議論は日本で典型的な平野地形を念頭に置いている。
地下水マネジメント
地下水資源マネジメント地下水環境マネジメント
量的な側面における地下水資源マネジメント
*持続的に利用可能な範囲での利用
*地盤沈下等の地下水障害の未然防止等
地下水理・水文環境の保全
*湧水の保全・復活
*都市再開発
*地下空間開発
*大規模土地開発等
地下水質環境の保全
*汚染源・物質の特定
*汚染対策
*モニタリング等
質的な側面も含めた地下水資源マネジメント
*用途別の水質への要請を踏まえた利用等
図3-1-1 地下水資源マネジメントの主な検討対象
地下水も水資源の1つと見れば、こういった水資源マネジメントの考え方は思想上の符
号はあっても、地下水資源マネジメント(groundwater resource management)では、地表
水と同様のマネジメント手法には馴染まず、いくつか違った点がある。
1) 地下水は帯水層が自然の貯水池の役割を持つため、地表水のダムや人造湖のように
人工的な貯水施設を構築することはほとんどない(地下ダムや人工涵養施設は限ら
れた条件でしか効果を発揮しないため、事例は非常に少ない)。
2) 地下水の利用計画、管理、調整作業は、地下水盆の構造・地質の多様性や利用規則
欠如の面もあって、地表水に比べはるかに複雑である。
3) 地下水管理の要となる効果的な地下水モニタリングが地表水のそれと比べ容易でな
い。
以上を踏まえ、第2章で抽出された課題の解決に向けた今後の地下水利用の基本的な考
え方を以下に示す。
?地下水資源の最適なマネジメント実現に向けた方法論と指針の必要性
地下水は一般に水質が良好で水温の変化が少なく、大規模な貯水・取水・給水施設を要
しない等の優れた特性を有していることから、多用途に利用される重要な水資源となって
いる。今後も安定した水資源として、また災害時の緊急水源として保全・利用していくこ
とが期待されている。
地下水資源は水循環系における回復可能な水資源でもあり、地下水収支のバランス(あ
る区域内における一定期間内の地下水の流入・流出の均衡状態)が保たれる範囲内で持続
的に利用していくことが可能である。
一方、地下水資源の利用がかつて深刻な地盤沈下等の問題を招いたことから、行政によ
る採取規制とともに地表水への水源転換が積極的に進められてきた。今日、全国的にみて
地下水資源の利用による広域的な地盤沈下はおおむね沈静化しているが、渇水時等におけ
る短期的・局所的な地下水位の低下や地盤沈下等の地下水障害は、復旧に長い年月を要す。
こうしたことから、地下水資源と国土を保全することに加え、持続的に利用可能な範囲
内で利用し、地盤沈下や塩水化等の地下水障害を招かないように、地下水資源の保全・利
用をマネジメントしていくことが昨今の要請となっている。
一方、地下水資源のマネジメントを推進する前提として、地下水は同じ水循環系の構成
要素である地表水と比較して、適正に保全・利用すべき水資源としての認識が醸成されに
くく、データ整備や実態把握が十分に進んでいるとは言えない状況にある。
こうした状況にあって、地下水資源の保全と利用のマネジメントを推進していくために
は、その方法論を明らかにするとともに、地下水管理者となる地方自治体の計画担当者に
対して、どのようにして地下水に関する意識啓発や広報・指導、地下水のデータ整備や実
態把握を行い、必要な施策を計画・実践・運用していくべきかをわかりやすく示す指針(ガ
イドライン)が必要である。
?適正採取量に基づく地下水資源の保全・利用のマネジメント
地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染等を生じさせず、持続可能な形で地下水の保全と
利用を最適にマネジメントしていくためには、以下に述べる「適正採取量」に基づき、そ
の範囲内で地下水資源の保全と利用の最適なマネジメントを実現していくことが肝要であ
る。
ある地下水盆において、ある一定の期間に利用可能な地下水の量(おおむね涵養量より
小さく地下水障害を起こさない量)を「適正採取量」とすれば、適正採取量と(実際の)
採取量の関係は、図3-1-2上で説明できよう。採取量が適正採取量を上回る場合には地下
水障害や地下水資源の枯渇が懸念され、採取量が適正採取量を超えない範囲内で利用して
いくことが必要条件となる。一方で、地域によっては、地下水位が上がりすぎないように
マネジメントしていくことも重要な課題となる。
一般に、地下水は特段の規制をしなければ、安価な水資源として利用ニーズが拡大する
傾向を採る。このため、地下水の涵養能力や地下水障害の発生しやすさなどにより決まる
適正採取量より実際の採取量が少ない状態にあることが好ましい。また、地
下水の適正採取量そのものの維持・拡大には、地下水涵養策や地下水資源の保全策を実施
する必要がある。
図3-1-2 適正採取量と採取量の関係からみた地下水の保全と利用の説明
?地域規模等の類型に即した地下水資源のマネジメント
地域の地下水に関する状況は、自然条件(地形、地質、気候等)や社会経済条件(人口、
土地利用、産業、歴史・文化、法制度等)に応じて地域ごとの多様性・固有性がきわめて
強いことから、地域特性に即した対応が必要である。特に、適正採取量に基づく地下水資
源の保全・利用のマネジメントにあたっては、地下水盆や帯水層の規模が重要な尺度とな
る。その規模は1市町村内で完結するものから複数の都府県にまたがるものまで大小さま
ざまであり、こうした規模の違いによってマネジメントの目的や方法にも違いが生じる。
また、地下水資源のマネジメントでは、行政が中心的な役割を果たすことが期待される
ため、都道府県や市町村といった行政単位との関係も重要である。
こうしたことから、地下水盆や帯水層の規模と行政単位に着目していくつかの地域単位
の分類を設けることで、多種多様な地域特性を類型化し、地下水資源マネジメントの目的、
方法等を明らかにすることが可能となる。具体的には図3-1-3に示すように、局所(地区
レベル)・小規模(市町村レベル)・中規模(都府県レベル)・大規模(複数の都府県レ
ベル)という4つの類型が想定される。
資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)をもとに作成
図3-1-3 地域類型に応じた地下水資源マネジメント等の概観
3.2 地下水資源マネジメントの考え方と手順
ここでは、3.1節に述べた今後の地下水利用の基本的な考え方を踏まえ、地下水の保
全・利用の方法論として地下水資源マネジメントを提案し、その考え方と具体的な手順を
示す。
(1)地下水資源マネジメントの定義と特徴
「地下水資源マネジメント注1)」とは、3.1節に述べた今後の地下水利用の基本的な
考え方を具現化するための手段であり、「健全な地下水文循環にあって、地下水障害や枯
渇を発生させない範囲で、地下水を水資源として持続的に保全・利用しうる採取(揚水)・
運営・管理の方法」と定義する。
その特徴は、科学的な知見に基づき、実態把握、計画策定、揚水マネジメント、観測・
モニタリング、評価・見直しを定量的に行うことにあり、そのプロセスの中核を成すのは、
その適正配分数値シミュレーションモデルを活用した対象地下水盆の適正採取量の数量化
と地下水位に基づいた管理・モニタリングにある。また、もう1つの特徴として、PDC
Aサイクルに基づく継続的な見直しを行い、科学的・定量的なマネジメントの精度を向上
させていくことがあげられる。
?数値シミュレーションモデルを活用した適正採取量の数量化
地下水資源マネジメントにあたっては、持続的にどの程度の地下水が利用可能であるの
かの定量的把握に基づいた計画の作成が必要となる。そのためには対象地下水盆の数値シ
ミュレーションモデルを構築し、これを用いて地下水障害を発生させず、かつ健全な地下
水収支を保つ地下水位のもとで、総採取量とその地域配分を科学的な手法で数量化するこ
とが求められる。
このように、数値シミュレーションモデルは、地下水資源マネジメントの根幹を成すも
のであり、揚水事業者と地下水管理者 注2)(国や地方自治体)の両者が地下水の保全・利
用に関する計画を策定する際に有用である。
数値シミュレーションモデルの作成にあたっては、計画対象地域における地下水に関す
る各種データを経年的に収集し、地下水や水文の実態把握、地質調査・分析を行うことが
前提として必要となる。
?井内地下水位・水頭を用いた地下水管理・モニタリング
地下水の保全・利用に関する計画を実際に運用し、地下水の管理に役立てていくために
は、適切な管理・モニタリングの手法が必要となる。地下水位の変動と地下水採取量とが
密接に関係していることに注目すれば、テレメーターシステムを活用することにより、リ
アルタイムで地下水位をモニタリングして採取量を適正に制御できる。
こうした視点から、地下水資源マネジメントにおける地下水管理・モニタリングの指標
として井内地下水位を用いることが有効と考えられる。地下水位の常時観測を行い、その
変化に応じて地下水利用者に採取量の抑制を要請すること等により、過剰揚水を緩和し、
地盤沈下等の地下水障害を未然に防止ないし軽減することが可能となる。また、地下水位
を用いた地下水管理・モニタリングは、即時的かつ容易に対策を実施できるという点で優
れ、予想外の水需要に伴う緊急的対策にも対応可能である(例えば、渇水時の地下水採取
量急増による地下水位の短期異常低下の回避対策、既存の水源の水質事故に伴う振り替え
水源確保等)。さらに、地域によっては、地下水位が上がりすぎないよう適切に管理する
ことにも活用できる。
地下水位を用いた地下水管理・モニタリングは、渇水時等において地盤沈下防止のため
の地下水採取量を緊急抑制する施策にも適している。
?PDCAサイクルによる継続的な取り組みのプロセス
地下水資源マネジメントは、調査・計画(P)→実行・観測・モニタリング(D)→評価(C)
→見直し(A)というプロセス(PDCAサイクル)をある程度反復しながら、継続的に取り
組んでマネジメントの精度を高めていくことが必要となろう。
一般に、地下水に関するデータ整備や実態把握がどの地下水盆でも十分に進んでいると
は言えず、数値シミュレーションモデルを用いた地下水資源マネジメントの実践例も限ら
れていることから、地下水資源マネジメントの実施当初から精度の高い将来予測を行える
わけではない。また、地下水涵養量や帯水層水理パラメータの事前の把握は簡単ではなく、
推算せざるを得ないこともあり、シミュレーションモデルは、実際に運用しながら改良を
加えていくことで、精度を高めていく必要がある。
このため、地下水資源マネジメントの実施にあたっては、当初はある程度、実測値や経
験則に基づいて計画を策定し、実際に運用しながら評価・見直しを重ねていくことで、シ
ミュレーションモデルの精度を高めたり、計画の実効性を高めていったりするといった、
継続した取り組みが必要である。
(2)地域類型別にみた地下水資源マネジメントの方向性
地下水資源マネジメントのコンセプトは、地域特性に即した取り組みが重要であること
から、前述した地域規模による4つの地域類型(図3-1-3参照)に沿って以下に示す。
?局所規模レベルの地下水資源マネジメント
局所規模(1km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に小規模な地下水源の確保(井
戸のさく井)にあたって、個別の揚水井の配置や採取量の設定が対象となる。この場合、
対象となる地域の広がりは、地下水盆というより帯水層と呼ぶのが相応しい地区レベルの
規模である。
小規模な地下水源の確保においては、必要な採取量が継続的に確保できることと、地下
水資源開発による影響(周辺井戸の枯渇、地盤沈下の発生等)が周辺に及ばないようにす
ることの2点が重要である。
このため、既存の周辺井戸の影響や地盤沈下を防止しつつ、必要な採取量を確保するに
あたって、揚水井の適正深度や適正配置(適正な井戸間の距離)、個々の井戸の適正採取
量を算定し、井戸設置の申請に対してどのような許可制度や許可基準を設定するかという
ことが重要となる。これらの検討方法としては、水収支と水理学的な検討が求められ、揚
水井戸理論を用いた定量的検討が想定される。観測・モニタリングにあたっては、採取量、
地下水位、地盤変動量等が指標となる。
?小規模レベルの地下水資源マネジメント
小規模(数km2〜数十km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に市町村(単一の市町
村もしくは複数の市町村による組合等)の行政区域内で完結している地下水盆が対象とな
るが、近隣市町村にまたがる平野や盆地の一部地域が対象となることもある。
局所レベルのような個別井戸ごとではなく、一定の広がりをもつ地域を対象として、複
数の揚水井を集合体として捉え、対象地域内での地下水収支や地下水採取量の地域配分等
を取り扱うことになり、対象地域外の近隣市町村に地下水資源開発の影響を及ぼさないよ
うにしつつ、必要な採取量を確保することが地下水資源マネジメントの要点となる。
このため、地下水収支バランスの保たれる範囲内の適正採取量とともに、対象地域内で
の適正な地域配分や用途別配分、採取許可方法等を明らかにする必要がある。検討方法と
しては、数値シミュレーションモデルを用いて地下水盆や帯水層をモデル化した上で、水
需給の現状や将来見通しに基づくシミュレーションを用いて、利用可能地下水資源量や適
正採取量、揚水井の分布密度、安全地下水頭・採取量等を設定する。
また、観測・モニタリングの方法としては、テレメーターによって地下水位や地盤変動
量をリアルタイムで把握するとともに、渇水時等の短期的な地下水位低下に対する対応と
して、管理水位を設定し、警報・注意報の発令による地下水採取者への採取量抑制の要請
を行うこと等が考えられる。
?中規模レベルの地下水資源マネジメント
中規模(数十〜数百km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に都府県レベルで完結
している中規模な地下水盆(熊本地域等)が対象となる。
地下水資源マネジメントにあたっては、対象となる都府県の地域内において、地下水収
支バランスの保たれる範囲内で、かつ地下水資源開発に伴って地下水障害等の悪影響を防
止しつつ、必要な採取量を確保することが重要となる。
このため、計画においては、地下水資源量とその地域配分を適正化することや、広域的
な地下水の観測・モニタリング(地下水位、地盤変動量等)を通じた地盤沈下の防止対策
が重要な課題となる。検討方法については、?で述べた小規模地下水資源マネジメントの
定量的な延長検討とほぼ同様に考えることができる。
?大規模レベルの地下水資源マネジメント
大規模の地下水資源マネジメントにおいては、複数の都府県にまたがる広がりを持つ大
規模な地下水盆の分布する地域(関東平野、濃尾平野、大阪平野、筑後・佐賀平野等)が
対象となる。ここでの重点は中規模の地下水資源マネジメントとおおむね一致するが、都
府県をまたがる対応が必要となるため、国の関係府省と関係地方自治体が連携して対策を
行っている「地盤沈下防止等対策要綱」の対象地域のように、体制・制度面で広域的な取
り組みが必要となる。
(3)地下水資源マネジメントの企画・検討手順
地下水資源マネジメントの目的や手順は、その対象とする地下水盆の地形・地質特性、
特に地域の規模によって異なってくるが、ここでは地域特性にかかわらず共通する基本的
な企画・検討手順について、適宜代表的な事例を紹介しながら、図3-2-1に沿って示す。
資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)
図3-2-1 地下水資源マネジメントの企画・検討手順
?予備調査
a)対象・目的の設定
はじめに、地下水資源マネジメントを行う対象・目的の設定を行う。
対象となる地域は、局所的な1〜2k?の狭い範囲において個別の井戸の設置可否等を
対象とするような場合を除き、行政上の視点から設定されることが多いが、その規模は単
独の市町村にとどまるものから、同一都道府県内で複数の市町村にまたがるもの、複数の
都府県にまたがる盆地や平野規模までさまざまである。こうした対象地域は、地下水の保
全・利用に関する課題や問題意識を共有する圏域として設定され、地理的条件、特に帯水
層や地下水盆の分布状況・規模に応じた地域となる。
目的の設定は、地下水資源の保全、地盤沈下等の地下水障害の防止、地下水環境の保全
など、対象地下水盆における地下水の保全・利用上の課題や問題意識等に応じて設定され
る。また、地下水の保全・利用に関する総合的な計画の場合と、特定の課題に特化した計
画の場合で、目的の設定や力点が異なってくる。以下にその事例を示す。
【総合的な利用・保全の目的を掲げる事例】(熊本地域地下水総合保全管理計画)
生活用水をすべて地下水で賄っている熊本地域では、地下水資源を次世代に引き継ぐ
ことを目的に、地下水の保全を優先している。
本計画は地下水の保全・利用に関する総合的な計画であることから、計画で定めてい
る保全目標は、地下水資源の量・質両面での維持に加え、地域のシンボルともなってい
る豊かな湧水の維持・復元、地下水障害の防止等にも置かれている。
【特定課題の目的を掲げる事例】(埼玉県地盤沈下緊急時対策要綱)
かつて深刻な地盤沈下を経験し、現在も地盤沈下が懸念される埼玉県では、地下水の
過剰なくみ上げによる地盤沈下を防止することを、地下水対策の優先目的としている。
地下水の保全・利用全般については「埼玉県生活環境保全条例」に定められているこ
とから、本要綱では、緊急的な地盤沈下対策に特化して目的が設定されている。
b)調査内容・検討手順の検討
設定された対象・目的に基づき、実態把握や計画の策定、及び運用・評価にあたって必
要な調査内容や検討手順を構築する。その際には、地下水資源マネジメントの対象・目的
のほか、利用可能な予算、計画策定までの期間、取組体制等も考慮する。
?地下水に関する実態把握
対象・目的に応じた地下水・水文調査(地形・地質、水文、土地利用、水利用実態、地
下水障害、地下水流、地下水質、法制度等)を行い、対象地域の地下水に関する問題点の
要因分析を行うとともに、対象・目的に応じて適当な数値シミュレーションモデルを用い
ながら、地下水盆や帯水層をモデル化し、適正採取量の数量化を行う。
地下水資源マネジメントの実施にあたって、地下水に関する実態把握、特に採取量の把
握や地下水収支の数量化は、地下水の保全・利用に関する計画の策定・運用の前提となる
きわめて重要な要素である。同時に、実施にあたっては、適正採取量の数量化のために必
要な時間・労力と知識・経験の蓄積、また、地下水採取量把握にあたっての利用者の理解
と協力が必要である。
a)地下水・水文調査
地下水・水文調査の調査項目として、以下のようなものがあげられるが、実施する項目
や精度は、地下水資源マネジメントの対象・目的等に応じて、個別に設定する。
* 地形、地質、水文、土地利用、水利用実態
* 地下水障害、地下水流、地下水質、関係法令
【地下水・水文調査の調査項目の例】(熊本地域地下水総合調査)
「熊本地域地下水総合調査」では、以下の項目について調査を実施している。
・ 地形・地質:地質平面図・断面図、地下水位断面図等を作成
・ 土地利用:涵養域・非涵養域別土地利用、生産調整率(米作減反率)の推移を把握
・ 水利用実態:条例に基づき採取者から報告されたデータを活用
・ 地下水流:既存井戸の一斉測水調査を実施し、帯水層別地下水位等高線図を作成
・ 地下水質:水質汚染防止法に基づく地下水の水質汚濁状況の常時監視を170 地点あ
まりで実施するとともに、河川水5地点、湧水10 地点、地下水86 地点でイオン分
析を実施等
【地下水利用実態電子データの例】(茨城県)
以下に示す茨城県の検討例では、現行の揚水実態、井戸分布、地形・土地利用の情報
を一目で知ることができ、それぞれの井戸の地質情報や採取量が判る。
b)地下水数値シミュレーション解析による適正採取量の数量化
水収支は地表の水収支と地下の水収支が連成・構成されるが、地下水収支は、地下水の
涵養量と採取量によって地表水収支と結びついている。帯水層・地下水盆が対象地域を越
えて分布している場合には、隣接する地域との間において、地下水同士の流入・流出が生
じうるが、帯水層・地下水盆が対象地域内で閉じている場合には、涵養量と採取量が把握
できれば、地下水収支を数量化できることになる。
地下水収支モデルが検定・修正できれば、水需給の現状や将来見通しを外生的に入力し、
数値シミュレーションモデルを活用して地下水の挙動の将来予測を行うこと 注)、さらにそ
の現地適用への論拠とすることが可能となる。
* 地下水盆のモデル化
* 地下水涵養の数量化
* 水理定数
* 地下水流動解析・内挿検定・パラメータ同定
* 数値シミュレーションモデルによる適正採取量や水収支の数量化
* 将来予測
* 地下水採取量の適正配分・揚水井分布
* 安全水頭・採取量の設定
【地下水収支の数量化の例】(座間市地下水総合調査)
「座間市地下水総合調査」においては、過去20 年間におけるデータに基づき、地下
水収支シミュレーションモデルを構築し、揚水条件(地下水揚水量)、涵養条件(平水
年と渇水年の涵養量)、河川改修条件の組み合わせによって、7ケースについて地下水
位変動や水収支予測を行い、台地部、低地部、市全体のそれぞれについて、水収支が±
0となる揚水量を適正揚水量として設定している。
また、市内の代表観測井において地下水の揚水に支障のない地下水位として、第1段
階水位(注意)と第2段階水位(警戒)の2段階の管理水位を設定している。
?地下水の保全・利用に関する計画の策定
対象地域における地下水資源マネジメントの目的や枠組みに基づき、必要に応じて数値
シミュレーションモデルによる将来予測の結果を活用しながら、適正な地下水利用を実現
するための考え方、適正採取量、管理水位、利用規則や、地下水の観測・モニタリングの
方法、行政担当者向けの管理マニュアル等を検討・策定する。
a)地下水適正利用のあり方
数量化された地下水収支やその将来予測を参考にしながら、地下水の保全・利用に関す
る計画の根幹を成す地下水適正利用のあり方を検討する。
* 適正利用のコンセプト
地下水障害を招くことなく、地下水収支のバランスが保たれる範囲内で地下水資源
を保全しながら持続的に利用できること前提として、地下水資源の適正な利用にあ
たってのコンセプト、基本目標を設定する。地域内において、ある一定の期間に利
用可能な地下水の量(おおむね涵養量より小さく地下水障害を起こさない量)を「適
正採取量」とするとき、以下のようなケースが想定される。
<採取量が適正採取量を上回っていない場合>
採取量が適正採取量の範囲内にある状態を維持していくため、涵養量の維持に向け
た取り組みを行うとともに、規制・誘導等により採取量を抑制する必要がある。
<採取量が適正採取量を上回っている場合>
採取量の抑制と適正採取量の拡大が考えられるが、地下水涵養策による利用可能量
の拡大には限界があることから、主に規制・誘導等により採取量を適正採取量の範
囲内に抑制する方策が求められる。
* 用途別配分・利用方式
数値シミュレーションモデルによる適正採取量の将来予測結果や適正利用のコン
セプト、水資源の需給事情等に基づき、総採取量の中での利水用途別配分(農業用
水、工業用水、生活用水等)や、地下水の利用方式(各用途における地下水と地表
水の組み合わせ利用の考え方)等について検討する。
* 利用規則・井戸の設置許可等
必要に応じて、地下水の採取・利用にあたっての規則や揚水井の設置基準・設置条
件等のルール(法律・条例等)を検討する必要がある。例えば、茨城県地下水適正
利用条例では、新規の井戸設置は許可が必要である。
b)適正利用を実現するための方策
地下水適正利用のあり方の検討結果に基づき、これを実現させるための方策(地下水管
理の方式、具体的方法等)について検討する。
* 地下水管理の方式
気象の平穏な平常時、気象の不順な渇水期、自然災害時等の状況に応じた地下水管
理の方式を検討する。具体的には、総適正採取量の範囲で地下水位・水頭や地盤変
動、採取量等の各種データを総合的に分析して管理する方式や、経験的に得られた
採取量配分と地下水位の経時的な相関関係の分析に基づき、地下水位のモニタリン
グを通じて過剰揚水を抑制する方式(警報・注意報の発令による地下水採取者への
採取量抑制の要請等)が選定される。
* 観測井の構造・配置・数
地下水収支の数量化の結果等を踏まえ、地下水管理を行うために必要な地下水位・
水頭や地盤変動量等を観測する観測井の構造・配置・数を決定する。
近年ではテレメーターの実用化が進み、通信回線を活用して観測データをリアルタ
イムで観測・収集することが可能となっている。
* 管理マニュアル
担当者の異動等があっても継続的に地下水資源マネジメントが行えるよう、地下水
の保全・利用に関する計画の管理者や地下水採取者等が地下水管理をどのように行
っていくのかをまとめた管理マニュアルを作成する。
* 地下水管理者・採取者への情報伝達方法
地下水管理者となる地方自治体、地下水採取者となる企業、水道事業者、個人等に
対して、地下水資源マネジメントにあたって必要な情報を迅速に伝達する方法は、
インターネットをはじめとする電子媒体によることができる。
* 広報・指導
地下水資源は採取者や利用者が多岐・多数にわたることから、地下水資源マネジメ
ントにあたって重要な情報は、採取者のみならず、広く利用者一般に対して公表・
提供し、地下水の保全・利用に関する意識啓発を図る。
【適正利用を実現するための方策の事例】(埼玉県地盤沈下緊急時対策要綱)
埼玉県では、「埼玉県地盤沈下緊急対策要綱」に基づき、地下水位の著しい低下によ
り、地盤沈下が生じる恐れがあると認められる時には、一定量以上の地下水採取者に対
して、各地域の地下水位の程度に応じて、地下水採取の抑制等を要請する「地盤沈下注
意報」「地盤沈下警報」が発令される。
?地下水の保全・利用に関する計画の運用・評価
a)地下水の観測・モニタリング
計画に定められた適正利用を実現するための方策に基づき、地下水位、採取量、地盤変
動量についての報告を採取者に求めたり、観測井を用いて観測したりした上で、そのデー
タを収集・処理するとともに、必要に応じて地下水障害等を未然に防止するための対策(新
規揚水井の許可制等)を実施する。地下水資源マネジメントは、地下水位・水質、採取量、
降水、地下水障害(地盤沈下量等)といった観測データによってなされることから、観測
データの迅速かつ正確な収集・伝達・処理が重要である。
* 採取量・水位報告
地下水資源マネジメントには採取量や地下水位の把握が不可欠であることから、一
定量以上を採取する採取者に対して、記入書式を用意し、採取量や地下水位の報告
を義務づけること等により、これらを把握する。
b)計画の評価・見直し
地下水の観測・モニタリングを一定期間継続し、データの蓄積が図られた時点で、策定
した計画の妥当性、観測・モニタリングの有効性等を評価し、その結果に基づいて必要な
修正・変更を行う。特に、地下水収支の数量化と将来予測に用いる数値シミュレーション
モデルの精度を高めていくことが重要である。
* 評価
計画の評価は、地下水資源マネジメントのPDCAサイクルの「C」に相当し、計
画内容の有効性や成果を計る「政策評価」と、計画の執行段階での効率性や進捗度
を計る「執行評価」を適切に組み合わせて実施することが望ましい。
評価に用いる指標と、最低限達成すべき水準、おおむね成功と評価できる水準、可
能ならば達成したい水準というような目標を、計画策定段階で予め設定をしておく
ことで、評価の精度が高まる。
* 見直し
計画の見直しは、地下水資源マネジメントのPDCAサイクルの「A」に相当し、
上記の評価結果に基づいて行う。必要に応じて、地下水適正利用のあり方を見直す
とともに、適正利用を実現するための方策については、評価結果に応じ、継続・改
善・中止のいずれかを検討する。
【評価・見直しの例】(熊本市地下水量保全プラン)
「熊本市地下水量保全プラン」の場合、毎年度プランの評価・見直しを行い、その進
捗状況をホームページで公表することとしている。評価にあたっては、評価結果等の説
明や市民の意見聴取のため、「熊本市節水推進パートナーシップ会議」を設置している。
(4)地下水資源マネジメントの検討・策定方法と策定・運用主体
地下水資源マネジメントを円滑に実施・運用するためには、地下水利用事業者の参加及
び地下水管理者との共同歩調が欠かせない。したがって、行政だけでなく、対象地域の主
要な地下水採取者が参画し、地域全体が連携して取り組んでいくことができる体制づくり
が求められる。このため、計画の策定・運用主体は、地下水資源マネジメントを主体的か
つ効率的・効果的に実施できる体制を整備する必要がある。
現行の行政管理体制では、行政区画単位でのマネジメントが実用的と考えられることか
ら、行政や協議会の長が地下水管理者として、計画の策定・運用主体となろう。具体的に
は、対象地域が単独の市町村にとどまる場合、同一都道府県内で複数の市町村にまたがる
場合、複数の都府県にまたがる場合といったように、各地域の事情に即して個別に判断さ
れるべきである。なお、複数の都府県にまたがる「地盤沈下防止等対策要綱」の対象地域
については、国の関係府省連絡会議が設置されている。
第4章 今後の地下水利用のあり方に関する提言
本報告では、
?「健全な水循環系構築」のための計画づくりの一環において、地下水について計画作成担当者に向けた提言
?地下水障害を発生させないことを前提とした適正な管理により利用する仕組みの構築に向けた具体的な提言
?国際比較の中でのわが国の地下水の特性及び利用のあり方
の3点に重点を置いて検討してきた。
地下水は重要な水資源であり、水循環系の構成要素であることから、本来、地表水と一
体化させ、環境面を含めて捉え、計画的に保全・利用されるべきものと考えられる。これ
までは、水資源の需給バランスの相互補完や地下水障害等の直面する課題の解決の面から
のみ地下水が捉えられてきたが、今後は地下水と地表水の役割分担や最適な両者の利用配
分の実現をめざした施策展開が必要な段階になってきている。こういった今日的なニーズ
に応え、本報告は、地下水資源マネジメントの手法論を展開した。
ここでは、第1章から第3章で述べた検討の結果を踏まえ、今後の地下水利用のあり方
に関する基本的な考え方やその実現にあたって求められる取り組みを提言として以下にと
りまとめる。
国の関係府省、地方自治体、企業、利水受益者等、地下水の保全・利用にかかわる各関
係主体には、本提言を踏まえ、それぞれの立場から、健全な水循環系の構築と持続可能な
地下水の保全・利用に向けた積極的な取り組みが期待される。
4.1 地下水資源マネジメントの推進
(1)健全な水循環系の構築に向けた地下水資源マネジメントの必要性
現在、わが国では、都市域における雨水浸透機能の低下、地表水と地下水の自然相互依
存の阻害等といった水循環系の健全性が損なわれていることに起因して、平常時の河川流
量の減少、湧水の枯渇、各種排水による水質汚濁、都市型水害等の問題が顕著となってき
ている。地表水とともに水循環系の重要な構成要素である地下水においても、健全な水循
環系の構築が重要な課題となっている。さらに、多量の水資源を水文収支域外より集積し、
消費・排出する都市の人工水循環系の健全化・保全を推進していく必要がある。
そのため、適正採取量の数量化や将来予測に基づき、地下水に係わる地域の諸条件に応
じて、地盤沈下などの地下水障害を未然に防止し、地下水収支バランスが保たれる範囲内
で、持続的に地下水を水資源として利用していくための適正利用のあり方とその実現方策
を検討し、地下水保全・利用に関する計画を策定・運用する必要がある。計画の策定・実
践・運用にあたっては、実態把握、計画策定、観測・モニタリング、評価・見直しという
継続的な試行プロセスを通じて、地域の諸条件に応じた持続的な地下水資源の保全・利用
のあり方を実現していくという「地下水資源マネジメント」の考え方が重要である。
例えば、関東平野を例にとると、図4-1-1に示すように、昭和20 年代より広域地下水利
用がなされ、地下水位(水頭)は低下したが、法律の規制(昭和31 年以降)によって回復・
上昇し、今は過去の自然地下水位に近づきつつある。将来の地下水資源のマネジメントに
は、健全な地下水環境・国土保全を目標に、安全水位を管理値に保持するよう人工制御す
ることが目指すところとなる。
図4-1-1 地下水資源マネジメントの説明図
(2)地下水資源マネジメントの推進に向けた支援環境整備
地下水資源マネジメントの実践・普及に向けた支援環境整備として、以下のような取り
組みを進めるべきである。
?地下水の実態把握に向けた採取量をはじめとするデータ整備の推進
地下水資源マネジメントの実践にあたっては、地下水の実態把握や問題点の要因分析等
を行う必要がある。地下水に関する調査としては、
1)地下水位及び地盤変動に関する調査、
2)水質に関する調査、
3)採取量に関する調査、
4)地形・地質に関する調査等があるが、以上のような観測データは、その地域の地下水解析に欠くことのできないものであるため、精度の高い長期的な観測を継続する必要がある。しかし、地表水と異なり、地下水はその
実態把握に時間・労力・経費がかかり、地下水の実態把握を行うための各種観測データが
十分に整備されていない。特に、地下水採取量は、地下水収支の数量化や将来予測、計画
の運用、観測・モニタリング等のさまざまな面で有用であるにもかかわらず、データの収
集整備(特に電子データ化)が進んでいない地域も多い。
採取量をはじめとする各種観測データの収集には、利用者の協力が不可欠であることか
ら、関係者間での協議、条例等の制度面での対応、データ収集・処理体制の整備などにす
みやかに着手することが求められる。
国においては、各地域において収集されたデータを全国共通に活用できるよう、データ
の収集項目や定義、収集方法等についての統一的な基準を作成し、各地方自治体に対して
データ収集を積極的に取り組むよう、普及啓発活動を実施することが必要である。また、
収集されたデータを蓄積・活用するためのデータベースについては、一元的な電子データ
ベース化を図り、データの効果的・効率的・実践的な活用を推進していくことが期待され
る。地質情報を全国で共有するための全国電子地盤図システム構築の構想も動き始めてお
り、こうしたシステムの活用も検討する必要がある。
?地下水実態・観測の数値情報共有・活用の推進
地下水資源マネジメントの推進を図るため、地方自治体の担当者をはじめ、地下水資源
マネジメントに関係する人が、全国各地域で策定された地下水保全・利用計画やその運用
状況、地下水に関する各種データ(降水量、地質、地下水採取量等)、地方自治体の地下
水に関する条例・要綱等、各地域の取組事例を情報交換し、活用しやすくなるよう情報環
境整備が必要である。そうすることによって地域性に富み、かつ水需給事情の異なる地下
水資源採取者や管理者が、より適正な地下水資源開発計画や運用方策を実践することが出
来よう。地下水資源のように多数の採取者が分散して各自揚水している場合、そのマネジ
メントの実行主体は採取者の側にあることを銘記したい。したがって、採取者の理解と協
力がマネジメントの運用に不可欠である。その実施・推進にあたって、地下水資源の所管
(地方自治体や各種機関)を通じて、地下水資源マネジメントの趣旨や方法について地下
水採取者(例えば利用協議会等)に対する講習会やポスター配布等により予め周知する必
要がある。
?実証モデルケースによる地下水資源マネジメントの推進〜取り組みの牽引役として〜
すでにいくつかの地域で、地下水資源マネジメントの先駆となる取り組み(例えば、埼
玉県、熊本県、栃木県野木町等)が行われているものの、現状ではその数は限られている。
そこで、地下水資源マネジメントの考え方に基づき、地下水保全・利用計画を策定・運
用しようとしている地域(例えば、現行の地盤沈下防止等対策要綱の対象地域等)に実証
モデルケースを選定し、地下水管理者と揚水事業者の連携のもとで採取量の把握、地下水
収支の数量化と将来予測に支援された地下水資源マネジメントを試行・実践し、その応用
性の実証や問題の解決後、有効性を普及していく必要がある。
先進地下水資源マネジメントの事例や方法を公表・情報提供していくことで、より多く
の地域で地下水資源マネジメントの経験・実績・有効性が認識されるようになり、その前
提となる採取量の把握に向けた採取者の理解と協力も得やすくなっていくことが期待され
る。
国においては、地下水資源マネジメントを推進するための新たなモデル事業を先導し、
実証モデルケースとなる地域の取り組みに対して、財政面での支援や専門的見地からの助
言を行うとともに、その成果を広く情報提供することはもとより、解析作業の中核を成す
汎用性の高い数値シミュレーションモデルの普及(例えば、米国地質調査所(USGS)の
MODFLOW.2005 等が国際的に普及)を行うことが期待される。
4.2 地下水資源マネジメントの運用方策
地下水資源マネジメントには、管理する際不可欠なマネジメント条件(あるいは制約条
件)が課されることになるが、その条件や制約指標(例えば、観測地下水位、採取量、地
下水障害)は、次の5つが要点となる。
?ある対象地下水盆(あるいは地下水文区)に涵養される地下水総量より広域総採取
量が小さいこと(地下水収支条件)
?観測地下水位が管理目標限界地下水位より高いこと(あるいは、管理目標地下水位
の上限と下限の範囲内にあること)(安全地下水位保全条件)
?広域総採取量をその構成地域採取配分量の和とすると、それら配分量がそれぞれの
管理目標地域採取量を超えないこと(安全地下水採取量条件)
?地下水障害(地盤沈下、地下水塩水化等)の誘発防止(地下水障害防止条件)
?異常な井戸水位低下、井戸干渉を招かず、かつ揚水井間距離が適正であること
(揚水井適正配置条件)
以上の制約条件を満足させるよう地下水資源をマネジメントすることになるが、?と?
は健全な地下水環境を保証すべき必須条件であり、観測地下水位や採取量の適正化によっ
て満たされ、過去の経験や実測データ及び数値シミュレーションによって解析しうる。し
かし、即時的な地下水資源マネジメントの指標としては、観測地下水位が実用的である。
今日、?を満たすようマネジメントを行うことが運用しやすい。その具体的な仕様は以下
に示す。
地下水揚水の適正化とは、広域地下水盆における地表水と降水による涵養の範囲内で、地下水
障害が発生しない最適揚水量を地域ごとに決め、急激な揚水は避けながら地下水資源を効果的に
利用することにある。地下水揚水抑制の具体的な実践には、過去の地下水・地盤沈下の観測デー
タを解析し、従来の揚水実績を十分検討した上で、段階的に分けた管理基準(限界値)水位を予
め設定しておき、注意報・警報といった情報を地下水利用者の合意の下で実践するのが合理的と
考える。設定された(目標)基準(限界)水位を下回るような地下水揚水は回避されなければな
らない。
地下水位と地盤沈下の観測方法は、二重管構造の観測井を使用するのが主流で、地下水位はフ
ロート式で地盤沈下は管頭変位量を機械的に測定している。近年オンライン化されたテレメータ
観測システムを利用し、地盤沈下を防止しつつマネジメントする方法が開発されている。図4-2-1
はそのシステム概念を示す。最近、このシステムが地盤沈下対策のみならず、経済性向上や省力
化に向けた地下水資源の保全にも普及しつつある。
図4-2-1 テレメータによる地下水マネジメントシステム概念図
また、地下水位を用いた地下水管理をより推進するため、即時的かつ容易に対策を実施
できるという点で有利なテレメーターシステム等の導入が必要であり、財政面での支援を
行うとともに、その成果を広く全国に情報提供していくことが期待される。
4.3 地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項
地下水資源マネジメントの推進や地下水資源の利用にあたって重要と考えられる事項
を以下に提言する。
(1)水資源の視点からの地下水の水質確保・保全
地下水の水質面については、これまでの汚染対策としての視点に加え、水資源政策の視
点から捉え、多様な地下水の利用ニーズに対応した用途別の水質確保・保全のあり方につ
いて検討する必要がある。その際には、地下水資源マネジメントの実施にあたって、量的
な側面だけでなく、水質面もその対象とすることで地域の諸条件に応じた地下水利用のあ
り方を実現していくことが適切である。
また、その前提として、浅層のみならず深層も含めた水質汚染に関するデータや情報の
整備が求められることから、まずは量的な側面に限って地下水資源マネジメントを実施す
る際にも、水質面の観測・モニタリングを同時に行い、データ整備を進めていくことが欠
かせない。
(2)地下水の震災対策
大規模地震災害時において、水の確保が重要な課題であることがこれまでの震災の経験
から指摘されており、発生直後から時間の経過に応じた各種水需要に適切に対応するため、
利用可能な水源とその特徴(水量、水質、設備・運搬の必要性等)を踏まえた水利用シス
テムを検討・構築しておく必要がある。
地下水は、身近で入手の容易な水資源であり、一般に水質もよいことから、大規模地震
災害時の利活用性が高く、地域の特性に応じた地下水の利用方策(用途・利用方法・制度
等)を検討・構築する必要がある。その際には、シミュレーション結果に基づき、各避難
所に緊急時に使える井戸を積極的に設置するという地域の取り組み等も踏まえつつ、耐震
性の高い井戸の分布状況の把握、災害時に民間井戸を利用可能とする権限の担保方法、少
なくとも災害発生直後の緊急・応急水供給に向けた別水源への振り替えのあり方等に留意
し、安全・安心な災害時地下水利用システムを構築することが求められる。
(3)地下水資源マネジメントの社会的合意形成への取り組み
?社会的関心向上の必要性
これまでわが国においては、地下水の過剰採取が深刻な地盤沈下を招いた経験から、一
般に地下水は地盤沈下と結びついたイメージが強く定着し、地下水の採取が、採取者の所
有する土地内にとどまらず、広域的な地盤沈下の原因となることについては、共通の理解
が得られていると思われる。
今後、地下水を水資源として管理しながら利用していくにあたって、社会的な合意が必
要な内容(地下水は水資源として、また環境面においてどのような役割を担うべきか、地
下水は平常時・緊急時にそれぞれどの程度利用してよいか、等)を定量化し、その意義の
普及・啓発を図っていく必要がある。
?法制度に関する検討の必要性
現在、わが国では地下水に関する重要な紛争や係争が生じている状況にない。これは、
工業用水法などの個別法や条例の適切な運用に負うところも大きいと考えられる。
しかし、現在も長期的、短期的な地下水をめぐる課題が存在しており、また条例等を施
行する自治体においては、いわゆる反対解釈の問題や強制力の不足による公平性の確保の
困難さ等、施策の実効性不足の声も聞かれている。さらに、地下水に関する社会的合意を
具現化するため、わが国における地下水に関する法制度について、法制化を行うべきかど
うかも含め、検討を行うことも必要と考えられる。
その際、全国一律的な法律と、各地域の特性に応じた条例の関係については、地域によ
る多様性に富むという地下水の特性やこれまでの各地域における取り組みを踏まえつつ、
法の機能と特長をいかに適切に組み合わせていくかが重要な論点となる。
また、国外に目を転じると、EU(欧州連合)では、基本法とも言える水枠組み指令と
これに対応した各国の法律が制定されており、こうした海外の事例も参考にしながら、国
際的な視点に立って、わが国の自然特性や社会の実情に即した法制度のあり方を検討する
必要がある。
「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」報告要旨【平成19年3月】
地下水の特性と保全・利用に係る課題
・水循環系における滞留時間が長い
・涵養に時間がかかるが潜在賦存量は多い
・地下水資源利用の広域定着と安定化
・渇水時の揚水増による地下水位低下
・採取量等のデータ整備と実態把握の遅れ
・地下水の保全・利用に関する全般的取り組みの遅れ
・水収支バランスが保たれる範囲内での利用
・緊急時の応急水源としての利用方策
・広域地盤沈下は沈静化傾向のまま継続・残存
・短期的、集中的な地盤沈下は今後も懸念
・科学的、定量的処理と電子情報化が必要
・社会への啓発と関係者の意識向上
特性課題
・「持続的かつ健全に利用できる循環している地下水」が利用の前提
・一般に、水資源としての地下水は、利用の簡便性、経済性、良質な水質、恒温性を有する
・わが国の水使用量における地下水依存率は約12%
・各種法令による地下水採取規制等により、広域的な地盤沈下は概ね沈静化
・しかし、渇水時には短期的・局所的な地下水位低下、地盤沈下が発生
・一部地域では地下水位上昇により地下構造物への影響が発生
・地下水汚染の多様化
・新たな地下水利用形態(ミネラルウォーター、地下水ビジネス)の拡大
地下水をめぐる現状と最近の動向
?地下水資源マネジメントの推進
・地下水障害を未然に防止し、地下水収支バランスが保たれる範囲内で、持続的な地下水資源の適正利用のあり方とその実現方策を検討し、地下水保全・利用に関する計画を策定・運用する必要がある。
・計画に基づく施策の実施にあたっては、数値シミュレーションモデルの活用により地下水収支を定量化し、実態把握、計画策定、観測・モニタリング、評価・見直しのというプロセスを反復しながら継続的に取り組み、地域の諸条件に即した最適なマネジメントを実現することが重要である。
?地下水資源マネジメントの運用方策
・マネジメントにあたっては、目標とすべき地下水位を定め、地下水位を常時観測していくことにより管理していくことが実用的である。
・マネジメントの推進に必要となるデータを収集するため、観測井戸、観測機器、テレメーターシステム
等の整備が必要である。
?地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項
・水資源の視点からの地下水の水質確保・保全のあり方を検討する必要がある。
・大規模地震災害時における地下水の利用方策を検討する必要がある。
・地下水資源マネジメントの社会的合意形成への取り組みを推進する必要
http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/f_
groundwater/25/houkokusyo.pdf
平成19年3月
今後の地下水利用のあり方に関する懇談会
はじめに
近年、地下水を取り巻く環境は大きく変化してきている。かつて高度経済成長期に深刻であった地下水の過剰採取による地盤沈下は、一部現在も引き続き対策が必要な地域もあるが、地下水採取規制、代替水源の確保等により、沈静化しつつある。 一方で、かつては地盤沈下が深刻であった大都市地域で地下水採取規制等により地下水位が回復・上昇し、地下構造物や地下水環境への新たな悪影響・弊害を引き起こしている事例もある。また、地下水質の面で環境基準を超える浅層地下水汚染が顕在化している。
地下水は地球水循環系を構成する重要な要素であり、地下水の保全及び利用が水循環系全体に与える影響を把握していくことが重要である。
本懇談会は、平成10年に国土庁水資源部に設置され、“地下水の利用と制度のあり方”について、専門の立場より幅広く検討を進めてきた。平成12年3月には、地下水をめぐる現状、今後の地下水利用のあり方について中間報告としてとりまとめ
た。
つづいて平成15年3月に日本で開催された第3回世界水フォーラムにおいて「今後の地下水利用のあり方」をテーマに分科会を主催し国際的視野に立った議論を行った。
今般、地下水をめぐる最近の動向と保全・利用に向けた課題、地下水利用のあるべき基本的な考え方を整理し、今後の地下水利用のあり方に関する提言を報告書にまとめた。
本報告は、その前半では「地下水をめぐる現況、最近の国内外の動向、及び保全・利用に係る課題」を論点とし、後半で「今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法」に言及し、最後に、当初目指した「今後の地下水利用のあり方」を提言している。
その新しい視点は、地下水資源に軸足を置いてマネジメントする必要性に向けられている。これまでの永い地下水利用の歴史を踏まえて、地下水資源マネジメントの指針と方法をより実践的にまとめたものであり、今後、本提言が国や各地域での取り
組みに反映されることを期待するものである。
平成19年3月
今後の地下水利用のあり方に関する懇談会座長
埼玉大学名誉教授佐藤邦明
「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」委員
小尻利治京都大学防災研究所水資源研究センター教授
佐藤邦明埼玉大学名誉教授(座長)
七戸克彦九州大学大学院法学研究院教授
大東憲二大同工業大学工学部都市環境デザイン学科教授
田中正筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
中杉修身上智大学大学院地球環境学研究科教授
守田優芝浦工業大学工学部土木工学科教授
目 次
第1章 地下水をめぐる現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.1 地下水の特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2 地下水利用の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1.3 地下水障害・地下水水質・汚染の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
1.4 地下水に関する法制度の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第2章 地下水をめぐる最近の動向と地下水の保全・利用に係る課題・・・・ 29
2.1 わが国の水需給に関する動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
2.2 新たな地下水障害と地下水源開発の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
2.3 地震災害等、緊急水資源需要への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
2.4 水に関する世界情勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
2.5 地下水の保全・利用に向けた課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
第3章 今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法・・・・・・・・・・・・・・・ 55
3.1 健全な水循環系の構築における今後の地下水利用の基本的な考え方・・・・・・・・ 55
3.2 地下水資源マネジメントの考え方と手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
第4章 今後の地下水利用のあり方に関する提言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 4
4.1 地下水資源マネジメントの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
4.2 地下水資源マネジメントの運用方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
4.3 地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
第1章 地下水をめぐる現状
1.1 地下水の特性
(1)地下水の水循環上の特性
科学的にみると、地下水は陸水の地下にある水の総称である。それは、降水が地下に浸透して海洋へ地下流出するプロセスにある、いわゆる「地下水」と、陸地の地形・地質が形成される際に地下深くに閉じこめられた化石水や、岩石・溶岩の形成時に生成される初生水のように「循環に乏しい地下水」に分けられる。一般に、淡水資源や温泉水は、それらを持続的かつ健全に利用できる循環している地下水であることが前提となる。以下、このような視点に基づき、議論を展開する。
地下水の源は降水であり、地表水とともに水循環を構成する。降水の一部は、直接流出として河道に流出する。直接流出は、地表から河道に流れる表面流出と、一度地中に浸透した後に浅い地下水流として河道に流出する中間流出に分けることができる。直接流出しない降水は、窪地などに一時的に貯留されるか、土壌に浸透する。土壌に浸透した降水の一部は重力によって下方に浸透し、地下水となる。
地下水は地表水に比べて、地中をゆっくりと流れる。そして、やがて河川・湖沼や地表面に再び流出し、地表水に合流する。平均滞留時間は数百〜数千年といわれている(表1-1-1参照)。
このような水循環を図示したものが図1-1-1(○a ,○b )である。水循環の過程においては、大気事象や大地の影響を強く受けている。例えば、地下水涵養は降水量に支配され、地下水循環は地質や地形によって規定される。また、蒸発は気温や湿度、植生などの影響を受けている。さらに、採取量(揚水量)や土地利用などの人為的な要因も水循環に影響を与えている。

資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)をもとに加筆
図1-1-1 水循環とその規定要因の概念図
表1-1-1 地球の水量と滞留時間
貯留量(?3) 平均滞留時間
海 洋 1,349,929,000 3,200 年
氷 雪 24,230,000 9,600 年
地下水 10,100,000 830 年
土壌水 25,000 0.3 年
湖沼水 219,000 数年〜数百年
河川水 1,200 13 日
水蒸気 13,000 10 日
資料)建設産業調査会『改訂地下水ハンドブック』(1998 年)
(2)地下水の水資源としての潜在特性
一般に水資源としての地下水は、表1-1-2に示すように、利用の簡便性、経済性、良質な水質、恒温性という特性を有している。
表1-1-2 地下水の利用特性
このような地下水の自然特性を活かし、地下水は、生活用水(飲料用、調理用、浴用等)、工業用水(冷却用、洗浄用等)、農業用水(農作物栽培用等)、積雪地域の消雪用など多様な用途に利用されている(図1-1-2参照)。
図1-1-2 地下水特性からみた用途の内訳
1.北海道地方
(3)地下水の潜在分布状況
図1-1-3は、わが国における地下水盆の賦存地形類型と主な地下水区の分布を示している。わが国における地下水は、地形・地質上、平野型、盆地型等のいくつかに分類できる。

図1-1-3 わが国における地下水盆の類型と主な地下水文区
それぞれに分類される地下水の特徴を以下に要約する。
?堆積平野の地下水
a)平野・台地
関東平野など主要な地下水盆は、地質年代では新生代新第三紀末から第四紀の地層が堆積する平野、低平地に分布しており、特に第四紀完新世の沖積平野のうち、中〜上部更新統・完新統の新しい地質が主な帯水層となっている。地層が軟弱な沖積平野では、地下水の過剰なくみ上げが地盤沈下を引き起こしやすい。
b)盆地
わが国の盆地には、平野と同様に新生代新第三紀末から第四紀の地層が堆積しており、更新世末から完新世の地質をもつ段丘や扇状地が有力な帯水層となっている。盆地の帯水層は、豊富な地下水を有していることが多いが、地下水の過剰なくみ上げによって地下水位の低下や枯渇を起こすことがある。
?岩の地下水
地下水は溶岩体や深成岩地帯にれっか水(裂罅水:fissure water、「地質事典」平凡社、1990)や割れ目水として帯水している。
a)山地
山地では、造岩塊や固結岩の亀裂や浸透性の高い地層に地下水が含まれており、トンネル掘削時に湧水として流出することがあるが、環境への影響や採水の経済性を考慮すると、大規模な採取は困難である。
b)火山地域
火山地域は、溶岩・火山砕屑物など浸透性の高い地層から構成されているため、阿蘇カルデラ、シラス台地など有力な帯水層が多い。山麓部末端では湧水群が分布し、古くから農業用水、生活用水に利用されてきた。
c)石灰岩地帯
石灰岩中のれっかや鍾乳洞には地下水を有することが多く、日本では、例えば、栃木県の佐野市(弁天池)や山口県の秋吉台などに見られる。また、南西諸島では、琉球石灰岩が分布し、自然の地下水帯となっているため、近年、地下ダムによる地下水貯留が行われる例がある。
図1-1-4 日本の地質図
1.2 地下水利用の現状
(1)わが国における水使用量の推移
2003 年(平成15 年)におけるわが国の水使用量(取水ベース)は、都市用水と農業用水を合わせ、839 億m3 であり、そのうち、都市用水(生活用水と工業用水の合計)は282 億m3 である。都市用水の使用量は、図1-2-1に示すように1987 年(昭和62 年)以降、やや増加したが、その後微減の傾向にある。また、農業用水の使用量についても、昨今やや減少しており、2003 年は557 億m3となっている。
図1-2-1 全国の水使用量の推移
(2)わが国における地下水利用の特徴
?水使用量に占める地下水の割合
2003 年(平成15 年)における取水ベースの水使用量839 億m3 の水源内訳をみると、図1-2-2のように、河川水が735 億m3、地下水が104 億m3 であり、地下水依存率は約12.4%となっている。

図1-2-2 水使用量に占める地下水の割合
?地下水使用量の用途別割合
上述の地下水使用量104 億m3 に加え、養魚用水として約13 億m3/年、建築物用等として約7億m3/年の地下水が使用されており、全地下水使用量は約124億m3/年と推計されている。
2003 年(平成15 年)における地下水の用途別割合は、生活用水が35.5 億m3で全体の28.6%、工業用水が35.9 億m3 で28.9%、農業用水が33.0 億m3 で26.6%となっている(図1-2-3参照)。
用途別地下水使用量の推移をみると、図1-2-4に示すように、生活用水はほぼ横ばいであるが、工業用水は減少傾向にある。

図1-2-3 地下水の用途別割合
?用途別にみる地下水利用の地域性
地下水利用は、地形・地質や降水といった自然条件と、都市化や人口といった人的な条件の影響を強く受け、決して全国一律ではなく、地域性が多様である。以下、用途別に地下水源への依存の地域性を述べる。
□工業用水
地下水は、水質が良く、水温が一定であり、取水費用が安いという特徴から、工業用水に多く使用されており、特に、化学工業、鉄鋼業、パルプ・紙・食品加工など製造業で、製造、洗浄、冷却水などとして地下水使用量が多くなっている。
図1-2-5に示すように、工業用水の地下水依存率は、全国の合計でみると約3割(29.5%)である。地域別にみると、北陸で最も高く6割超(62.7%)である。また、近畿内陸(54.8%)、関東内陸(46.0%)、東海(45.0%)などでも高くなっている。
工業用水用の地下水は、戦後昭和20 年代以降、深井戸による被圧地下水が使われているが、工場等の立地は沖積平野に多いことから、地盤沈下、塩水化などの地下水障害を引き起こし、今日に至っている。
図1-2-5 地域別用途別地下水依存率(工業用水)
□生活用水
生活用水の地下水依存率は、全国の合計でみると2割強(22.1%)である。図1-2-6に示すように、地域別にみると、南九州(54.3%)や山陰地域(51.9%)で生活用水の地下水依存率が高く、5割を超えている。次いで、四国(41.5%)、関東内陸(41.0%)、北陸(39.8%)などでも高い。一方で、北海道(6.0%)、沖縄(8.5%)では、生活用水の地下水依存率が低い。
図1-2-6 地域別用途別地下水依存率(生活用水)
□農業用水
わが国では、農業用水として主に地表水が利用されてきた。地下水は、補助水源、渇水時の応急用水源として利用されてきたことから、農業用水に占める地下水の割合は概して低い(図1-2-7参照)。
図1-2-7 地域別用途別地下水依存率(農業用水)
□その他の用途
水産用にマス、ウナギなどの養殖で利用される地下水の量の統計では、上述の3つ(工業・生活・農業)の用途に次いで多く、個別的であるが、湧水、温泉水などが報告されている。
また、消雪用に地下水を利用する方法は、気温が氷点下にならない豪雪地で有効であり、消雪パイプは1961 年に新潟県長岡市で始まり、全国的には2004 年度の消雪パイプ使用水量の約83%(374 百万m3/年)が地下水を利用している。地下水は水温の季節変動が小さいため、消雪効果があり、東北、北陸などでも利用されている。しかし、狭い場所で集中的に大量の地下水をくみ上げるため、地下水位の低下、地盤沈下などの地下水障害をもたらした。
わが国では、温泉水として利用される地下水も多い。浴用以外にも、ハウス園芸用熱源、発電など多目的に利用される事例がある。井戸の掘削深度がかなり深く1,000m以上の深さのものもある。
1.3 地下水障害・地下水水質・汚染の現状
(1)地下水位の異常低下、井戸枯れ
わが国における地下水位の異常低下、井戸枯れは、戦後(1945 年)以後1950 年代後半〜1960年代前半にかけて最も激しい地下水被害をもたらした。高度成長期には地下水を大量に揚水したことによって、都市部を中心に地下水位の低下、井戸枯れが起こった。また、地下掘削工事やトンネル掘削によって、周辺の地下水位が低下し、井戸枯れが起こる例も見られた。
しかし、1950 年代後半〜1970 年代前半に揚水の法的規制等が行われたことにより採取量は減少し、全国的にみると地盤沈下は沈静化し、近年は地下水位が回復しているところもみられる。
(2)地盤沈下
(3)塩水化
わが国における地下水の塩水化は、ほとんどが海岸域で発生している(図1-1-1)。地下水の過剰なくみ上げが原因で、地下水位が海水面より低下し、帯水層に海水が浸入することによって発生する。1960 年以降、製紙業の盛んな静岡県富士市のほか多数の臨海域で発生しており、塩水化した地下水は、飲料水として利用できず、工業用水としての不適合、農作物への塩害などがみられた。八戸、石巻、気仙沼などでは、現在もその塩害が継続している。
表1-3-1 塩水化地域に対する対策の状況

(4)地下水の水質と汚染
?地下水質の評価指標
古来、地下水といえば、水温の安定した清廉な水という通念がある。地下水の水質は、地形・地質の成り立ちや地下水の由来、流動、気候、生態系などの自然条件の影響を受け、その地域性や深さによって大きく異なる。例えば、表1-3-2は日本の名水に指定されている水質の例を示す。地下水質は、主要溶存化学成分9項目、陽イオン(ナトリウムNa+、カリウムK+、カルシウムCa2+、マグネシウムMg2+)、陰イオン(重炭酸HCO3-、塩素Cl-、硫酸SO4-、硝酸NO3-、シリカSiO2)に加え、電気伝導度、水温、pH などにより判断され、必要に応じて用途や関係する水質(環境)基準項目を加味した上で評価される。
表1-3-2 名水の水質例
自然の地下水質は、元来多様な理化学的特性を持つ。言うまでもなく、ある地下水が水質上良いか悪いかを漠然と判断することはできない。通常、ある対象・目的に対して、人や環境に有害であると考えられる数値を水質評価指標(水質検査項目)の基準値(水質基準)として設定し、利用の可否を決めることになる。
したがって、自然のままで地下水質がある検査基準(例えば、水道水の検査基準)に適合しない場合がありうる(以下、仮に「自然由来の汚染」と呼ぶこととする)。なお、水質検査の項目自体も水質基準の種類(対象・目的)に応じて異なるものが必要となる。
一般に水質汚染とは、自然の地下水質が人為的に汚染された(=水質基準に不適合の検査項目がある)人為由来のものを指す。自然由来の汚染は主に深層の地下水で、人為由来の汚染は主に浅層の地下水で発生する。深層の地下水汚染は除去が困難であり、水資源として利用することができない。以下では、人為由来の地下水汚染を中心に述べる。
?地下水汚染に関する環境基準とその超過率
高度成長期以降、工場や事業所等が原因となって地下水汚染が発生し、化学合成物である揮発性有機塩素化合物による地下水汚染が深刻となった。
このため、1971 年(昭和46 年)に「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」の2つからなる「水質汚濁に係る環境基準」が定められた。「人の健康の保護に関する環境基準」は、全公共用水域に対し、カドミウム、シアン等9項目についての基準を定めていたが、1993 年(平成5年)3月に項目が追加され23 項目となった。さらに近年、農業、畜産排水による硝酸性窒素汚染が顕在化してきたことから、1999 年(平成11 年)には、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ほう素」及び「ふっ素」の3項目が追加され、現在では26 項目の基準が定められている。
国と都道府県では「地下水の水質汚濁に関わる環境基準」に定められた26 項目を調査対象物質として毎年地下水質測定を行っている(表1-3-3、図1-3-5参照)。
地下水は、一度汚染されると、汚染の継続は長期間に及ぶ。水資源の安全な利用の観点からも、地下水質の継続的な監視が求められることとなる。
表1-3-3 地下水の水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)
図1-3-5 環境基準超過率の推移
?揮発性有機塩素化合物による地下水汚染
揮発性有機塩素化合物は、土壌汚染や浅層地下水汚染を引き起こす原因となっている。その主要な原因となっているのは、金属関連産業や半導体産業などの洗浄溶剤として使用されるトリクロロエチレンと、クリーニングや金属等の脱脂洗浄、代替フロンの原料として使用されるテトラクロロエチレンであるが、近年、製造・使用量は減ってきており、環境基準超過率は減少傾向にある。
揮発性有機塩素化合物は、
?重い、
?水に溶けにくい、
?土壌に吸着しにくい、
?低粘性、
?揮発性が高い、
?分解されにくい、といった特徴を有しているため、いったん地下に進入すると、
鉛直方向には容易に重力浸透する。一方で、横方向への拡散は少ないため、高濃度の原液による局地的な地下水汚染、土壌汚染を引き起こす特徴を持っている。揮発性有機塩素化合物は、まず土壌に浸透し、少しずつその下の帯水層に重力沈降しつつ溶け出して地下水を汚染する。
溶解汚染した地下水の移流流動及び分散によって、汚染地域は拡大する。
揮発性有機塩素化合物は、麻痺や呼吸障害、貧血、肝臓障害、発ガン性があるなど、人体に悪影響を及ぼすことが分かっている。
?硝酸性窒素による地下水汚染
硝酸性窒素汚染は、農薬、畜産排水などが汚染源となっているため、野菜、果樹、茶の栽培に利用されることの多い扇状地や、畜産、野菜栽培に利用されることの多い火山山麓で拡大している。
環境基準では、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素ともに10mg/?と定められているが、基準を超える井戸も全国各地で見つかっている。
揮発性有機塩素化合物の汚染は汚染地域が局所的であるのに対し、硝酸性窒素汚染はその性格上、汚染地域が広範に及ぶ上、現状ではその改善に決定的に有効な対策が見当たらないことから、今後、被害の拡大も懸念されている。硝酸性窒素は過剰に摂取すると、乳児がメトヘモグロビン血症注) 等を起こすことが知られているが、日本ではそれによる発症例は報告されていない。

図1-3-6 平成9〜16 度(1997〜2004 年度)地下水汚染マップ(環境基準26 項目)
1.4 地下水に関する法制度の現状
わが国の現行法では、ヨーロッパの国々に見られる地下水の基本法や総合法(例えば、後述するEU水枠組み指令)のような上位法はなく、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(いわゆる「ビル用水法」)のような地盤沈下対策としての井戸揚水規制に関する法律、土壌汚染対策法や水質汚濁防止法、水質汚染防止に関する法律など、地下水に関連するさまざまな個別法が実効している。
多くの都道府県や市町村では、これら国の法律を受け、地域の実情に応じた独自の条例や要綱等を制定している。
(1)地下水揚水の規制
現在、地盤沈下対策としては「工業用水法」(1956 年(昭和31 年)施行、1962 年(昭和37 年)改正)及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(以下、「ビル用水法」、1962 年(昭和37年)施行)の2法が地下水揚水施設に適用されている。規制の対象となる指定地域は、表1-4-1及び表1-4-2に示すとおり、工業用水法は10 都府県、ビル用水法は4都府県にわたっている。
表1-4-1 「工業用水法」に基づく指定地域
(2)地盤沈下防止等対策要綱
法律や政省令ではないが、地盤沈下に伴う被害の著しい濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部の3地域については、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議(1981 年(昭和56 年)設置)において、「地盤沈下防止等対策要綱」が決定され、発効している。
これらの要綱は、指定3地域を対象とした重点的地下水の採取規制、代替水源の確保及び代替水の供給を行い、地下水を保全するとともに、地盤沈下によるたん水被害の防止及び被害の復旧等、地域の実情に応じた総合的な対策の根拠を与えている。
3地域の地盤沈下防止等対策要綱及び対象地域は表1-4-3に示すとおりである。
表1-4-3 地盤沈下防止等対策要綱の概要
また、各地域の近況は以下のとおりである。
□濃尾平野
2004 年度(平成16 年度)の地下水採取量は1.7 億m3 であり、目標採取量(2.7 億m3)を下回った。当該年度(2003 年11 月1 日〜2004 年11 月1 日)の水準測量結果によると、年間1?以上の地盤沈下が認められた面積は約9? 2 であった。
□筑後・佐賀平野
佐賀地区及び白石地区における2004 年度(平成16 年度)の地下水採取量はそれぞれ3.8 百万m3、4.2 百万m3 であり、佐賀地区では目標採取量(6百万m3)を下回ったものの白石地区では目標採取量(3 百万m3)を上回った。当該年度(2004 年2 月1 日〜2005 年2 月1 日)の水準測量結果によると、年間1cm 以上の地盤沈下はこれら両地区共に認められなかった。
□関東平野北部
2004 年度(平成16 年度)の年間採取量は4.9 億m3 であり、目標採取量(4.8 億m3)を上回った。当該年度(2004 年1 月1 日〜2005 年1 月1 日)の水準測量結果によると、地盤沈下は年間1?以上の沈下が認められた面積は約419 ? 2 であり、うち2?以上の沈下面積は約26 ? 2 であった。
(3)地方自治体における地下水に関する条例・要綱等の制定状況
地域の特性に応じ各地方自治体(都道府県、市町村)で、個別の地下水に関する条例・要綱等が制定されている。それらの法的性格は以下のとおり。
条 例:地方自治体の議会の議決などにより制定される法規で、法的拘束力を持つ。
要綱等:地方自治体が議会の議決を経ずに定める内規で、法的拘束力を持たない。
これらは、おおむね遵守されており、地域の特性に見合った地下水の利用・保全に大いに貢献していると考えられる。
ただし、同一の地下水盆が複数の地方自治体にまたがる場合、地方自治体によって規制の条件、条例・要綱等の内容が異なり、地下水盆全体としての整合した対応が必ずしもとれていない。
地方自治体の条例・要綱等による規制等の対象地域を定めても、対象地域以外では、たとえ同一の地下水盆であっても全くの自由に委ねられている点(いわゆる反対解釈)等の課題をもっているものもある。
?都道府県における制定状況
都道府県の地下水に関する条例・要綱等について、名称別に分類した(表1-4-4参照)。また、都道府県の62 件の条例・要綱等について、その名称と目的・対策等を地図上に示した(図1-4-1参照)。

表1-4-4 都道府県の地下水に関する条例・要綱等の名称による分類(2004 年7月現在)
図1-4-1 都道府県の地下水に関する条例・要綱等の制定状況と規定内容
これらのほとんどは、「公害防止条例」「生活環境保全条例」「環境基本条例」といった公害や環境全般を対象とする条例であり、地下水については、その一部として取り扱われている。
こうしたことから、地下水が、主に公害対策の一環として、地盤沈下対策の側面から規制の対象として取り扱われてきた経緯がうかがえる。一方、地下水そのものを主たる対象とする条例は5つ制定されている。それらは、以下のように要約される。
a)「公害防止条例」「環境条例」及びそれに類する条例における取り扱い(表1-4-4中の分類?〜?)
これらの中で、水質保全については、すべての都道府県において項目として掲げられ、その対策として汚水排出に関する規定が定められている。これは地下水の汚染にも関係するが、主に地表水の汚染との関わりが深い。一方、地盤沈下防止についてもすべての都道府県が目的として掲げているものの、その主要な対策である採取に関する許可・届出義務等の規定については、地域により規定のあるところと、そうでないところがある。
b)「地下水採取・地下水保全条例」及びそれに類する条例における取り扱い(表1-4-4中の分類?)
地下水の採取・保全に関する条例を制定しているのは、山形県、茨城県、富山県、静岡県、熊本県の5県である。その多くは「地下水の採取の適正化に関する条例」及びそれに類する名称を付し、熊本県のみが「地下水保全条例」の名称を持つ。これらのすべてが採取に関する許可・届出義務等の規定を定めており、公害や環境全般を対象とする条例を補完している。
c)地下水の採取に関する許可
公害や環境全般を対象とする条例もしくは地下水に関する条例において、採取に関する許可・届出義務等を規定している都道府県は、南東北、関東、北陸、東海地方に分布しているのに対し、北海道、北東北、甲信、近畿以西では、その選択的内容もしくは一部にとどまっている。
こうしたことから、採取に関する許可・届出義務等の規定は、人口が密集し、水需要の大きい大都市圏や、水資源における地下水依存率が高い関東内陸、北陸等、比較的広域的な対応の必要性の高い地域に制定されていることがわかる。
d)地下水涵養
地下水涵養の人為促進については、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、奈良県、熊本県の条例の中に規定があり、塩水化については、山形県、茨城県、富山県、静岡県、徳島県の5県で規定されている。
e)地下水に関する要綱等(表1-4-4中の分類?〜?)
要綱レベルのものでは、山梨県や徳島県において地下水の採取の適正化に関する要綱が定められているほか、埼玉県、千葉県、福井県において、地盤地下防止を目的とした要綱等が制定されている。埼玉県の「地盤沈下緊急時対策要綱」は、地盤沈下緊急時に知事が地下水利用者に対し、地下水の採取を抑制できるとするものであり、千葉県の「地盤沈下防止協定」は、天然ガスかん水地上排水基準等について県と天然ガス採取企業との間で個別的に締結された協定である。
?市町村における制定状況
市町村の地下水に関する条例・要綱等については、330 件の存在が確認できたが、その半数強の181 件は「公害防止条例」「生活環境保全条例」「環境基本条例」といった公害や環境全般を対象とする条例であり、地下水は、その一部の項目・内容で取り扱われている。
これらを除いた149 件は、名称別に分類した(表1-4-5参照)。また、分類対象とした149 件の市町村の条例・要綱等について、その名称と目的・対策等を地図上に示した(図1-4-2参照)。
表1-4-5 市町村の地下水に関する条例・要綱等の名称による分類(2004 年7月現在)
条例の名称 制定数
?地下水の採取・保全・保護に関する条例 76
?地下水の採取・保全・保護に関する要綱・規約 23
?水資源の保全・保護に関する条例 4
?水道水源の保全・保護に関する条例・要綱 12
?地盤沈下防止に関する要綱・指針 3
?自家用天然ガスの採取規制に関する条例 12
?地下水の汚染防止に関する条例 1
?水環境の保全に関する条例 1
?開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱 16
?地下水の涵養推進に関する要綱 1
合計 149
注)制定数は原則としてデータベース更新時のものであり、その後の市町村合併等による変更を反映していない。
資料)三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成
注)市町村名は2004 年7月現在のもの

図1-4-2 市町村における条例・要綱等の制定状況
a)名称による分類
分類対象とした条例・要綱等は、地下水採取の適正化や地下水の保全・保護、もしくはその双方を名称に含むもの(同じ内容の要件であっても重要度や取扱い方により違うもの)が多く、計99 件(うち条例が76、要綱・規約が23)が該当する。
水資源の側面からの条例・要綱等としては、地下水だけでなく、水資源や水道水源全般の保全・保護に関する条例・要綱で、地下水の採取に関する規定を含むものが計16 件ある。
また、地盤沈下防止に関する要綱・指針は3件あるが、このほか地盤沈下に関連して、自家用天然ガスの採取規制に関する条例が12 件制定されている。
地盤沈下以外の環境面に関するものとしては、地下水の汚染防止と水環境の保全に関する条例が各1件ある。また、開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱のうち、地下水の採取に関する規定を含むものが16 件ある。このほか、地下水の涵養推進に特化した要綱が1件制定されている。
b)条例・要綱の内容の概要
市町村の条例・要綱等について、その内容を概観すると、井戸の設置者や工場・事務所等の設置者に対し、地下水の採取について事前の届出等を義務づけたり、設備の設置基準等を定めたりするなど、採取に関する許可・届出義務や設備設置の基準に関する規定を定めるものがほとんどである。
これらの多くは地盤沈下防止もしくは水源保護を目的としているが、都道府県の場合と異なり、目的が明記されず、対策のみが定められているものも多い。また、一部の市町村では、採取に関する規定と併せて、汚水排出に関する規定や涵養に関する規定も定めている。
c)地域別の分類
地域別に制定状況をみると、新潟県が最も多く30 市町村、次いで、長野県が20 市町村、山梨県が17 市町村となっている。
このうち、新潟県については、自家用天然ガスの採取に関する条例が多いほか、地下水の採取に関する条例・要綱等の中で、消雪用地下水の保全や用水量の削減について規定しているものが多い。消雪に関する規定は豪雪地帯である石川県や福井県でもみられる。
また、長野県や山梨県では、開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱等において地下水に関する規定を設けているものが多く、リゾート開発等に対応したものと考えられる。
これ以外の条例・要綱等の制定状況を地域別にみると、山梨県や静岡県の富士山麓、山梨県や長野県の八ヶ岳山麓、長崎県の雲仙山麓、熊本県の阿蘇山麓など大規模な火山の山麓地域や、山梨県や京都府のような盆地地形の卓越する地域、鹿児島県や沖縄県の島嶼地域において、地下水に関する条例・要綱等を持つ市町村が多い。
国の地盤沈下防止等対策要綱や都道府県の条例の制定状況と合わせてみると、広域的な地下水利用が行われている大規模な平野等では、国もしくは都道府県レベルの条例・要綱等が制定され、盆地や火山山麓、島嶼など比較的狭い範囲での地下水利用が活発な地域や、消雪対策、天然ガス採取、リゾート開発など固有の問題への対応が必要な地域においては、
市町村レベルで条例・要綱等が独自に制定されている。
一方、北海道、北東北、中国、四国では、道県、市町村いずれのレベルにおいても、地下水に関する条例・要綱等の制定が少ない。
これまでにみたように、地方自治体(都道府県、市町村)では、さまざまな条例・要綱等が制定されており、それらの中には規制を伴うものもあるが、地域の実情に即した形で地元に定着し、地下水の地域特性に応じた地下水の保全・利用への取り組みに寄与しているものと考えられる。
第2章 地下水をめぐる最近の動向と地下水保全・利用に係る課題
ここでは、地下水をめぐる最近の動向を調査し、その結果を通して必要な課題を把握する。
まず、わが国の水をめぐる諸問題、水需給全般の状況や、近年の地下水障害等の状況について整理する。次いで、水に関する世界情勢とわが国との関係及び動向が整理される。
2.1 わが国の水需給に関する動向
(1)わが国の水需給動向
?水需給の見通し
わが国の水資源政策の推移をみると、食料の確保と国土の保全が最優先された戦後復興期を経て、高度成長期には、都市部の人口急増や急速な経済発展に伴い都市用水を中心として水需要が急増し、これに対応するために本格的な水資源開発が進められたが、水質汚染や地盤沈下等新たな公害や環境問題が発生した。水資源開発が需要に追いつかない状況は、わが国の経済が安定成長期に入った後も継続した。このように戦後のわが国の水資源政策には、一貫して需要増加に対応した供給拡大が求められてきた。
近年は、水資源施設の充実、人口増加率(出生率)の低下(図2-1-1、図2-1-2 参照)、経済の安定・成熟や国民生活の質的向上等に伴い、渇水等の異常気象時を除き平常時の水需給のギャップは縮小しつつある。また、総人口の減少局面を迎えたことから、水需給の将来に対し、短絡的に楽観視する声もある。
しかし、気象変動に伴う利水安全度の低下や、都市域への人口の緩やかな集中が続くことが予想されることから、平常時はもちろんのこと、特に異常渇水、災害等緊急時の対応の充実が必要である。さらに、水の重要性を国際的視点から鑑みれば、長期的に国家戦略として水資源を総合的かつ戦略的に確保・管理していく必要がある。
図2-1-1 わが国の総人口の推移と予測
図2-1-2 わが国の年齢3区分別人口割合の推移と予測(中位推計)
?安全で良質な水供給への要請
健康志向や安全・安心への関心の高まりの中で、安全で良質な水供給への国民の要請はさらに増大している。その要請の一つは飲料水の消費に現れている。最近、市販ミネラルウォーターの生産量と輸入量が急増している(図2-1-3 参照)。2004 年をみると、国内生産量と輸入量をあわせ1,627 千キロリットルが消費されており、10 年前の消費量の約3倍である。
これを一人あたりに換算すると、年間で一人約13 リットルのミネラルウォーターを使用していることとなる。一人一日あたり飲料水必要量を3リットル(市町村等で防災上必要な備蓄量の目安とされる値)として計算すると、年間の飲料水必要量の約1%に相当する。
図2-1-3 ミネラルウォーター類国内生産及び輸入量の推移
(2)水需給に関する安定性
?気象変動に伴う利水安全度の低下への対応
近年、少雨年と多雨年の変動幅が次第に増加し、渇水年の年降水量が減少傾向にあるのみならず、年最大連続無降雨日数(降水のない日が連続する最も長い期間)も長くなる傾向が認められている。こうしたことから、ダム等の水資源開発施設が計画された当時の開発水量を安定して供給できないなど、水供給の利水安全度(実力)が低下しており、気候変動が国内の水需給バランスに与える影響が顕在化しつつある(図2-1-4 参照)。
今後も、こうした降水特性の変化や地球温暖化等に起因する気候変動により、水供給の能力低下が一層加速する恐れがあるとともに、これまでの計画規模以上の渇水の危険度も増加している(図2-1-5 参照)。
図2-1-4 日本の年降水量の経年変化
図2-1-5 気象変化による水資源開発水量の利水安全度(実力)低下(木曽川水系の例)
?大都市圏域への人口集中への対応
わが国の総人口は、2025 年時点でも全国で1.2 億人前後と1980 年代の水準にあると予測されることから、年齢別人口構成の変動はあるものの生活の質の向上志向や都市型生活の利便性を容認する限り、水需要が急減することは考えにくい。現状の地方圏の実情では人口減少が避けられないだろうが、地方ブロックの中枢都市以上の大都市圏域では、統計資料の外挿の上で、人口の緩やかな集中が続くと予測されている(図2-1-6 参照)。
大都市圏域は、圏域内外より供給できる1人あたり水資源量が少ないことに加え、社会基盤の高度化や高齢化、生活様式の変化等により、給水制限や断水時の社会的影響も増大している。大都市圏域では、利水安全度の低下が高度化した都市機能の持続と維持に深刻な影響を及ぼす恐れがあり、危機管理の視点から対応の必要性が高まっている。
図2-1-6 都市と地方の人口の推移と予測
(3)地下水資源の需給見通し
これまでに述べたわが国の水需給状況と今後の動向を踏まえると、将来の地下水資源の需給見通しは以下のように考えられよう。
* 安全で良質な水供給の要請から地下水資源への需要が高まる可能性がある。
* 気象変動を踏まえた利水安全度の確保や、都市部の住民生活や都市機能の持続・維持の観点から、地下水資源への需要が高まる可能性がある。
2.2 新たな地下水障害と地下水源開発の動向
これまで地下水障害といえば、地下水の広域かつ長期にわたる揚水利用によって生じる地盤沈下、井戸枯れ、塩水化などを指したが、近年、渇水時の短期に集中する地下水利用に伴う地盤沈下が新たに問題となってきた。ここでは都市地下構造部への地下水の悪影響や新しい地下水開発・利用によるインパクト等も含め、主として量的側面に焦点を当てて広い視野で検討を加える。
(1)渇水時の地下水位(水頭)低下と地盤沈下
多くの地域では地盤沈下が沈静化し、地下水位・水頭(被圧帯水層)の大幅な低下はみられなくなってきているが、数年に一度生じる渇水時(図2-1-4)には、主要な都市域で短期的な低下がみられる(図2-2-2、図2-2-3参照)。これは、地表水が減少して河川水の取水制限が行われ、代替水源として地下水の利用量が増加することや、少雨により涵養量が少なくなることが要因と考えられている。
地下水位・水頭の低下は、地盤沈下などの不可逆かつ蓄積する障害を招く恐れがあり、一度生じると回復は容易ではなく、将来にわたる大きな問題となることから、渇水時には以下のように対応し、地下水位・水頭の低下を防ぐことが求められる。
1) 渇水時における地下水利用状況の把握・地下水位低下の要因特定
従来の年単位の地下水採取量の把握に加えて、渇水が起こりやすい地域、渇水が起こりやすい時期には、月単位などより詳細な地下水採取量の把握を行うとともに、地下水位の低下の要因を特定する必要がある。
2) 渇水時における地下水採取抑制・自粛の要請
渇水時における地下水位低下の要因を特定した上で、地下水利用の限界採取量あるいは管理基準地下水位を設定し、基準を超えた際には、利用者に対して地下水採取の抑制を要請する仕組みづくりが求められる。
例えば、生活用水の地下水依存率が高い福井県大野市では、扇状地の水田の水がなくなる11 月頃の地下水位が最も低くなり、これまでに大規模な井戸枯れが生じた経緯から、独自の地下水警報発令基準を設けている。近年、地下水位の低下が著しく、たびたび節水を呼びかける警報が出されている。
図2-2-1 渇水時の地下水位低下のメカニズム
図2-2-2 渇水年における地盤沈下の進行
図2-2-3 要綱地区(筑後・佐賀平野)における地盤沈下面積と地下水採取量
(2)地下水位(水頭)上昇による地下構造物への揚圧力による障害
揚水規制や地下水環境の保全意識の高まりにより、近年では、地盤沈下地域の数、面積ともに減少し、地盤沈下は沈静化しつつある。
しかし、首都圏では、地下水採取の法的規制によって、逆に地下水位が回復・上昇し、東京駅や上野駅などの鉄道駅の地下部分が浮き上がる等の新たな問題が発生し、JR東日本ではアンカーを埋めるなどの地下水位上昇対策工事(東京駅:1999 年、上野駅:1997年)を行った。また、大阪市では、地盤沈下を防ぐため地下水の採取を規制してきたが、現在は逆に地下水位が上昇し建物が浮いたり、地下街や地下鉄のトンネルへの湧水増等の事例が出てきている。
地下水位の上昇は地震災害時に液状化を引き起こす可能性など、防災上の問題も指摘されている。
このように、東京都や大阪市など大都市圏の限られた地域の問題ではあるものの、地下水位の上昇に伴い、地下水位が大幅に低下した時期に計画・建設された地下構造物が浮き上がるなどの障害がみられ、所有者や管理者による対策が実施されている。今後、このような国土の脆弱化をもたらす地下水位の上昇を防ぐために、地下水環境保全を促す地下水位を定めた上で、利用可能な範囲内で地下水採取を行うなど、一定の地下水位を維持する施策が求められる。
(3)ミネラルウォーターの生産拡大の動向
ミネラルウォーター市場の拡大に伴い、大手飲料メーカーだけでなく、全国各地で地下水を活用した飲料水ビジネスが活発化している。現在、国内で約400 社、450 銘柄のミネラルウォーターの飲料水があると推計されている。
現在、国内生産されているミネラルウォーターの生産量は、国内で使用されている地下水使用量全体(124.1 億?)の約0.01%にとどまり、現時点ではその占有率は低いが、大量採取が行われているような地域においては、この割合は今後高くなると想定される。
大手飲料メーカー等は山間部などの水源を確保し、地下水の大量採取を行っているが、現在のところ、この新たな地下水採取によって、周辺の地下水利用者への影響や、地下水障害等は特に報告されていない。この動向に対して行政は、水源地下水の状況や利用可能量を見極めた上で、必要な対応が求められる。
また、全国で最もミネラルウォーターの生産量が多い山梨県では、自治体が地域資源からの恩恵を受けている事業者に対して税負担(例えば、1リットルあたり0.5〜1円の税率で、2.5〜5億円の税収見込み)を求めることを検討した事例もある。
(4)地下水新ビジネスの参入
近年、水質改善膜ろ過技術や井戸の小口径高揚程ポンプの開発に伴い、企業、農漁業団体、サービス業、公的機関等の専用(自己)水道による地下水利用が新たに増加している。
特に、ホテルや病院、ショッピングセンターなど、緊急時の自己水源確保を求められる個別水道利用施設で導入が進んでいる。
この個別水道利用施設の地下水利用では、20〜30mの浅層家庭用井戸と異なり、100m以深の深井戸からのくみ上げが目立つ。浄水膜ろ過プラントは小型な設備であれば3,000万円程度の投資で済み、また、揚水機のリースであれば投資リスクを負う必要が無いなど、利用者にとって初期負担が比較的小さいことも普及の要因となっているものと思われる。
地下水の採取規制などがない地域では、利用者にとっては、水質に問題がなければ揚水コストを削減することができる。さらに、地震などの災害時に備え2つの自己水供給システムを有することができるというメリットもある。
現在のところ、これらに伴う地下水障害は顕在化していないが、規制対象から外れた地下水揚水施設については、現行法制度では利用実態の把握が困難であり、採取量が把握できない状況となっている。
また、水道事業を行う自治体において、この種の地下水採取に伴い、水道水の利用量減少による減収が懸念されている。
(5)深層地下水の開発
地下水資源は、淡水そのものを利用の対象とするのみならず、温泉・鉱業や深層水の新規開発にも拡大して目が向けられている。とりわけ都市型の商業施設や娯楽施設では深層地下水が多目的に活用されている。
(6)地下水の発展的利用・可能性へ向けた議論の動向
昨今、地下水の都市ヒートアイランド現象軽減のための利用など、いくつかの新しい発展的活用へ向けた議論がなされている。
2.3 地震災害等、緊急水資源需要への対応
(1)地震災害時における問題点
わが国では、1995 年の阪神・淡路大震災をはじめ、2004 年新潟中越地震、2005 年福岡県西方沖地震など、大きな被害を伴う大地震が発生している。これらの地震災害時には、各用途に応じた緊急的な水の確保が問題となった。阪神・淡路大震災においては、井戸や湧水を雑用水として利用したケースが報告された。また、震災時には揚水ポンプが停止し、急激な地下水帯水層の水圧力上昇により水があふれ出たが、この水が震災時のトイレ用水や復旧工事の際の散水などに活用された注)。
その他に新潟中越地震では、液状化による被害や消雪パイプの破損も問題となった。
表2-3-1 阪神・淡路大震災における水利用に関して報告された問題点
分類 分類 問題点
用途別 消火活動 ・消火栓が使用できず、消火活動の大きな障害になった。
医療活動 ・病院には特別に給水活動を行う必要があった。
飲料・炊事 ・市民は、飲料用水として、市販の水を確保した。
トイレ洗浄 ・量を必要とするトイレ用水は、その確保とともに運搬も大きな問題だった。
表2-3-2 新潟中越地震における水需要及び地下水利用に関する問題点
・被災地すべての避難所で県が実施した生活実態調査によると、「トイレが不便」という避難所が3割に達した。
・地震による液状化現象により、マンホールが浮き上がったり、路面が割れて盛り上がるなどの被害が生じている。これにより除雪車が走行できない等の問題が生じた。
・消雪パイプが破損したが、ガスや水道の復旧作業が優先されるため、消雪パイプの復旧が遅れ、雪対策が遅れる等の問題が生じた。
なお、地下水位の上昇による大地震発生時の液状化現象の危険拡大も指摘されている。液状化現象とは、地下水で満たされた地層(地盤)が地震動によりその体積を減じ、その分、間隙にあった水が上方に放出され、地盤内に余剰の水があふれた結果、地層が液状流動化することを言う。これにより、地上・地下のライフライン、構造物等が重大な被害を受ける可能性がある。
さらに、地球温暖化による海水面の上昇が、沿岸・臨海域の地下水位上昇や地盤の液状化強度の低下をもたらす可能性も指摘されている。
注)震災時の水の確保に関する研究会「大都市における大規模震災時の「水」の確保について(案)」(阪神・淡路大震災での状況)参照
(2)地震災害への対応
?緊急水需要
a)経過日数でみた水需要
大規模震災時に想定される水需要を、用途及び発生場所の点から経過日数に即して整理したものが図2-3-1 である。災害直後から3日目頃は消火用水、医療用水及び生命の維持に必要となる最小限の飲料水の確保が不可欠となる。また、被災生活が開始されると、飲料水だけでなく炊事、トイレなどのための水需要が発生するほか、入浴や洗濯のための生活用水が必要となる。
さらに、災害後概ね4日目以降で復旧作業が開始されると、生活用水の拡充とともに、産業復活や防塵、復旧工事用の水需要が発生する。
図2-3-1 地震被災時における水需要
b)用途別にみた水需要
地震災害時における水需要はその用途に応じて、必要となる水量や水質は異なる。例えば、災害直後に多量に必要となる消火活動や、生活用水の中でもトイレ洗浄用水は水質への要求度は高くない。一方、医療活動の水や飲料・炊事用水は清浄な水質が求められる。
表2-3-3 地震災害時における用途別にみた水需要
?応急水供給
地震災害時に利用が想定される、都市における水の所在は以下の通りとなっている。河川・池・湖沼水や海水などは大量に供給可能だが、水質が保証されず、取水ポイントが限定される。また、雨水や再生水は比較的良質な水であろうが、専用の設備が整備されていることが必要となる。
このような中で、地下水は、清浄な水質が期待できる身近な水資源として、飲料や医療用途に活用できる可能性があるが、事前の十分な水質検査や、地震時における地下水脈への影響等を考慮して利用する必要がある。
表2-3-4 地震災害時における水供給源別にみた特徴
2.4 水に関する世界情勢
情報、経済、物流のグローバル化が進む現在、それらを支える基盤である水資源や水政策が今後の日本でいかにあるべきかを考えることは、時代の要請と言えよう。ここでは世界的な水問題について、米国の水事情概況及び地表水・地下水を合わせた総合的な水資源管理をめざす欧州の取り組みを紹介する。
(1)世界的な水問題とわが国の関係
?世界的な水需要の拡大と地下水障害の発生
18 世紀産業革命以降の世界人口の増加や、農業、とりわけ灌漑農業の発展は、淡水の消費を飛躍的に増加させた。例えば、中国・黄河の過剰取水による流況異変、中央アジア・アラル海の灌漑取水による水位低下が招く湖面積の縮小など、世界各地で水が不足する状態を生じさせている。
米国は図2-4-1に示すように、西経100 度と120 度に挟まれた全国土(936.3 万k ?)の約4割が年降水量500mm 程度の乾燥地帯であり、西経100 度以東は降水量に恵まれた(例えば、ニューオーリンズの年降水量1,584mm)温帯多雨国土である。この東西を二分する気候は、地形と地質が相まって固有の農業を発展させてきた。図中の乾燥地帯はシェラネバダ山脈とロッキー山脈に挟まれた高地グレートベースンとロッキー山脈の東側グレートプレーンズに拡がり、小麦生産や遊牧業及び人工灌漑農業が広大な農地で行われた。
多量の水を必要とする灌漑農業には、化石水ともいえる深層地下水が利用されている。図中ではこの地域の水不足分布が概観されている。
地下水についても、米国・グレートプレーンズでは深刻な地下水位の低下が生じている。
この「センターピボット(Center Pivot)方式」では、1つの井戸で毎分10 ?の地下水を揚水し、井戸の本数が数千本にもなるため、年間約7,500 万?もの地下水を利用するが、涵養量は年間約800 万?にとどまるため、過去30 年間で地下水位は平均12m、最大30mも低下した。この結果、耕地面積は1978 年〜1988 年の10 年間で100 万ha 減少した。
図2-4-1 米国の水不足地域の分布状況
?世界的な水問題とわが国の関係
国連環境計画や国連人間居住委員会、ユネスコなど23 の国際機関などが共同で発表した「世界水開発報告書」(2003 年3月)によると、半世紀後には最悪の場合で世界人口の8割にあたる70 億人が淡水不足に直面すると予測しており、水問題は21 世紀の世界的な課題だと警告している。
島国日本は、当面、水需給ギャップが縮小傾向にあり、国際河川や国際湖沼も当然ながら存在しないため、直接的な水に係わる国際紛争はないが、無関心ではいられない。その理由は、例えば、水資源に直結するわが国の食料自給率は熱量換算で2000 年には約40%まで低下しており、フランス、アメリカ、ドイツなどの食料自給国と比較して非常に低い。
食料の生産には水が使用されることから、わが国は食料等の輸入を通じ間接的に海外の大量の水を消費しており、その総量は年間640 億?と見積られている(図2-4-3参照)。
世界的な水危機の状況が、今後ますます激化すると予想される中、これに関する世界の経済、社会活動の変化とりわけ食料問題は、物流・経済を通じて日本経済や社会問題に直結している。今後の水資源政策は、このような実情も視野に入れながら、より好ましい水資源を総合的かつ戦略的に確保、管理していかなければならない。
図2-4-3 日本の仮想投入水総輸入量
(2)EU政策「水枠組み指令」
世界的な水危機に伴い、総合的・戦略的な水資源政策が求められる中で、わが国の地下水保全・利用のあり方を検討する際の参考に資するため、ここでは、特に地下水利用の長い欧州における取り組みを紹介する。
欧州では、古代ローマ時代から地表水よりも地下水を優先して使用してきた経緯がある。その伝統は、現在でも特に生活用水において継承されており(鯖田、岩波新書、2001)、
その宗教的とも言える思想は、地下水源の保全に向けた欧州先進国の取り組みの中で継承されている。
近年、EUでは、加盟国に統一した指令として、流域単位での水管理を目指す「水枠組み指令」が新たに発効された。ここではそれに着目して、その背景や考え方、水政策と地下水に関する動向等について言及する。
?「水枠組み指令」(EU Water Framework Directive)の背景
a)EUの概要
欧州連合(EU:European Union)は、「経済的な統合を中心に発展してきた欧州共同体(EC)を基礎に、欧州連合条約(マーストリヒト条約)(1993 年発効)に従い、経済通貨統合を進めるとともに、共通外交安全保障政策、司法・内務協力等のより幅広い協力をも目指す政治・経済統合体」である。従来の国際機関などとは大きく異なり、構成国からの国家主権の一部の委譲を前提に、域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成し、政治的にも「一つの声」で発言する等、いわば連合国家に準ずる存在である点が大きな特徴である。
表2-4-1 EUの概要(2007 年1月現在)
b)欧州における水問題の状況
「水枠組み指令」制定の背景となった欧州における水問題の状況について、「水枠組み指令」では以下の各点があげられている。
*欧州連合の全地表水の20%は、深刻な汚染の危機にさらされている。
*欧州の飲料水の約65%は、地下水でまかなわれている。
*欧州の都市の60%は、地下水資源を過剰に採取している。
*湿地帯の50%は、地下水の過剰開発により「危機的状況」にある。
*1985 年以降、南欧の灌漑地が20%増加している。
EUにおいては、これまでにも主に水を保護するための政策や法律が策定されてきたが、「欧州連合の環境−1995」では、上記のような背景を踏まえ、EU内の水について、量的のみならず質的にも保護アクションが必要であることが指摘されている。
?「水枠組み指令」の概要
水域を良好な状況にすることを目的として制定された「水枠組み指令」(EU WaterFramework Directive)は、正式名称を「水政策分野での共同体アクション枠組みを構築する2000 年10 月23 日の欧州議会及び評議会指令2000/60/EC」(Directive 2000/60/EC ofthe European Parliament and of the Council establishing a framework for the Communityaction in the field of water policy)と言い、2000 年12 月に発効した。
「水枠組み指令」は、地表水や地下水などすべての水資源を対象としており、欧州全体で、地下水と地表水の統合的な管理を示した初の指令である。「水枠組み指令」を受けて、各EU加盟国は、地域性に応じたマネジメント計画等を作成し、それに基づく対策を講じることで、EU全体で水環境の保全・管理を進めていく仕組みとなっている。地下水の位置づけは地表水と同等であり、特に、第17 条では地下水に特化して汚染対策が記載されている。
「水枠組み指令」の特徴として、政治・行政的境界ではなく、河川流域単位での浄化及び管理の取り組みを導入していることがあげられる。各国はまず指令の対象となる河川流域を指定し、適切な管轄当局を含む行政整備を行うことが義務づけられている。国際河川流域についても、関係国間で調整し、同様の指定を行わなければならない。これらの河川流域には、言うまでもなく地下水が含まれる。
また、「水枠組み指令」では、水環境の維持と改善を目的としており、主な対象は水質である。水量のコントロールは水質対策の付随的な要素とされており、良質な水を確保するためには、各国で、質と同時に量に関する対策も実施すべきであるとされている。良好な地下水状態とは地下水の量的状態、化学的状態の両方が良好であることを指すとされて
いる。
以下に、「水枠組み指令」の構成及び概要を示す。
a)「水枠組み指令」の構成
「水枠組み指令」は以下のような条文から構成されている。
第1条 目的
第2条 定義
第3条 河川流域地区内での行政整備の調整
第4条 環境目的
第5条 河川流域の特徴、人間活動による環境影響のレビュー、水使用の経済分析
第6条 保護地区の登録
第7条 飲料水の対象とする水域
第8条 地表水状態、地下水状態、保護地域のモニタリング
第9条 水サービスの費用の回収
第10条 点源、拡散源についての組み合わせアプローチ
第11条 対策プログラム
第12条 加盟国のレベルで対処することができない問題
第13条 河川流域マネジメント計画
第14条 情報公開とコンサルティング
第15条 報告
第16条 水汚染に対する戦略
第17条 地下水の汚染防止、コントロールに関する戦略
第18条 委員会報告
第19条 将来の共同体対策計画
第20条 本指令に対する技術的な調整
第21条 規制委員会
第22条 廃止及び過渡的条項
第23条 罰則
第24条 実施
第25条 効力発生
第26条 送付先
付録
b)「水枠組み指令」の特徴
上述に構成されている「水枠組み指令」について、ここでは主な特徴を整理する。
■環境目的
主な環境目的は、すべての水域を2015 年までに良好な水質状態にすることである。
□地表水について
・加盟国は、地表水全体の劣化を防止するための必要な対策を実行しなければならない。
・加盟国は、すべての地表水体(bodies of surface water)を保護、整備、修復しなくてはならず、本指令発効(2000 年12 月)後少なくとも15 年間は良好な地表水状態を達成しなければならない。
・加盟国は、良好な生態的潜在力、良好な地表水化学状態を保つために、本指令発効後少なくとも15 年間は、人工的あるいは大幅に改良した地表水体を保護し整備しなくてはならない。
・加盟国は、重点物質による汚染を徐々に減らし、優先的危険物質の排出、放流、損害を排除、あるいは徐々に排除するために、必要な対策を講じなければならない。
□地下水について
・加盟国は、汚染物質が地下水に入ることを防ぎ、あるいは制限し、地下水全体の状態が悪化しないようにするために必要な対策を講じなければならない。
・加盟国は、本指令発効後少なくとも15 年間は良好な地下水状態を達成することを目的として、すべての地下水体を保護、整備、修復し、地下水の揚水量と涵養量のバランスを確実にしなくてはならない。
・加盟国は、地下水の汚染を徐々に減少させるために、人間活動の影響により地下水中の汚染物質の濃度が著しくあるいは持続的に増加する傾向にある場合、それを修復するために必要な対策を講じなければならない。
■現状把握
本指令を受けて、各河川流域地区で以下の事項を実施しなければならない。
○河川流域の特性把握
○地表水あるいは地下水に対する人間活動の影響の把握
○水使用の経済分析
○飲料水として抽出する水(1日平均供給量が10 ?超または50 人超に供給)または将来飲料水として使用される水のモニタリングなお、飲料水として抽出する水源は保護地域として登録が義務づけられる。
本指令を受けて、各国は2006 年までに(発効後6年以内)水状態のモニタリング・プログラムを設定し、実施しなければならない。地下水については、化学的状態及び量的状態の把握が求められている。
■水サービスのコスト
本指令では、水は商用製品とは異なり、むしろ遺産のように保護しなければならないとされているが、同時に水サービスコストの回収も考慮すべきと明記されている。加盟国は2010 年までに以下の実施が求められている。
?水料金政策によって水使用者が効率的使用を行った場合には、適切なインセンティブを与えられるようにして、環境目的に貢献するようにすること。
?経済分析に基づき、汚染者負担の原則を考慮して、産業、家庭、農業の異なる水利用者が、水サービスコストを適切に負担すること。
■対策
各国は、河川流域地区ごとに目的を達成するため、対策プログラムを実施しなければならない。このプログラムでは、国内レベルでの既存の法令に基づく対策の中から、本指令で求められている基準を定められた期限内に達成することができる活動を特定し、採用することができる。
■流域マネジメント計画
各国は、河川流域地区ごとに河川流域マネジメント計画を2009 年までに作成し、運用しなければならない。複数の国にまたがる国際河川流域マネジメント計画は単一の作成が義務づけられている。河川流域マネジメント計画は6年ごとにレビュー・更新される。その際には情報公開を徹底しなければならない。
■水汚染に対する戦略
欧州議会と欧州評議会は汚染物質あるいは汚染物質グループによる水汚染に対して対策を講じなければならない。欧州委員会は汚染の要因となる重点物質や重点危険物質を明確にし、それに対する対策について提案が義務づけられている。
これを受けて、欧州委員会は2001 年1月、新水枠組み指令の最初の規制対象として指定する32 種類の「優先物質」リストを提案、同年11 月に採択された。特定の有害物質については、20 年以内に水域への排出を段階的に停止することとされている。
地下水については、第17 条の中で記述され、地下水の汚染防止、コントロールに対する戦略として、欧州議会と評議会は、
?良好な地下水化学状態を評価するための基準、
?重大な継続的上昇傾向の確認及び傾向が逆転した地点の定義、を含む提案を行うこと
が義務づけられている。
また、第8条では、各国が策定する水状態のモニタリング・プログラムの対象として、地下水については化学的状態、量的状態があげられている。
■スケジュール
EU加盟各国は、2003 年12 月までに本指令の遵守に必要な法律、規制、行政条項の発効が義務づけられている。本指令の主要事項における期限は以下の通りである。
期限 内容
2003.12 ・本指令の遵守に必要な法律、規制、行政事項などを発効・流域連携の組織化
2004.12 ・水への影響分析を完了(経済分析を含む)
2006.12 ・水マネジメントの基盤となるモニタリング・プログラムの実施
2008.12 ・河川流域マネジメント計画が市民に公表される
2009.12 ・最初の河川流域マネジメント計画が発効される
2015.12 ・良質な状態の水となる
?「水枠組み指令」を補完する地下水に関する指令及び動向
2003 年9月、欧州委員会は、水枠組み指令の第17 条に基づき、地下水汚染防止に関するEU指令案(Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of groundwater against pollution 2003/0210(COD))(以下「地下水指令」)を発表した。「地下水指令」は加盟国に対し、地下水質のモニタリングを義務づけ、EUの既存の法令基準(窒素分、植物保護剤、殺生物性製品など)の遵守状況を把握するよう求めている。EUの法令で対象とされていない物質については、加盟国が2006年6月までに上限値を設定することとされている。汚染の程度が、「期間」と「環境上の重大性」の観点からみて、一定のレベルを超える場合には、加盟国は汚染悪化を防止する対策を講じなければならない。
水質基準値または上限値の75%を超える場合は、環境上重大な状況にあるとされる。この他、地下水汚染を防ぐため、有害物質の間接的な排出(地面や土壌中への排出)を禁止または制限する条項も盛り込まれている。
地下水指令の構成は以下の通りである。
第1条 内容
第2条 定義
第3条 地下水の良い化学状態を評価する基準
第4条 閾値いきち*1
第5条 重大かつ悪化傾向の判断基準及び修復を行う出発点の定義
第6条 地下水への間接的な排出を防ぐまたは制限する施策
第7条 過渡的なアレンジメント
第8条 技術的な適合
第9条 実施
第10条 効力発生
第11条 実施者
付録
備考*1)EU の各加盟国が定める、地下水帯に危険な影響を及ぼすと見なされる汚染物質の限界値。国レベル、流域レベルまたは地下水帯レベルで定めることができる。
このほか、「水枠組み指令」に基づく2005〜2006 年の作業プログラムとして、地下水、環境状況、統合的流域管理、調査報告をテーマとする4つのワーキンググループが設置され、水枠組み指令の実施にあたって解決すべき課題の検討がなされている。
?わが国の地下水利用のあり方への示唆
このように、EU「水枠組み指令」では地下水と地表水を総括した水資源全体での統合的な管理を推進している。地下水を含めた流域圏を一つの単位として、行政的な境界を超えて水資源管理を行うことが求められており、2009 年までに河川流域マネジメント計画を発効することが予定されている。
わが国においても複数の自治体にまたがる広域的な地下水マネジメントを実践する上で、行政計画策定や実践に向けた方法や手順策定の参考となろう。
2.5 地下水の保全・利用に向けた課題
(1)水資源需要多様化と地下水への期待
これまでに述べたように、わが国の水需給は、将来の人口減少や経済成長の鈍化に伴いおおむねバランスする方向にあり、一方で、安全で良質な水供給に対する要請はますます強まる動向にある。他方、少雨傾向など気候変動に伴う渇水が従来以上に頻発かつ大規模化する傾向があり、利水安全度の低下がより懸念される大都市圏域を中心として、危機管理の視点からの備えの必要性が高まっている。大規模地震災害時には、まず水の確保が重要な課題となるが、身近にある地下水は、それに即応できる重要な水源となりうる。
さらに、地球規模の水危機の深刻化にあって、安全保障の観点や食糧確保等を念頭に世界の水問題へ対応していく必要がある。
今日、淡水資源そのものを支える降水量とその地域分布が地球規模の気候変動によって大きく変容しつつある中で、水資源需給の多様化や安全性を満たす新しい水政策の構築が国家戦略として急務である。そのためには、河川水や湖沼水を含む地表水資源と地下水資源の量的・質的特性を活かしつつ、両者を調和的に利用しうる方法論が必要である。
ここでは、以上の観点から、過去の地下水過剰利用とその障害を教訓にしつつ、地球時代における地下水資源のあり方の議論に先行して、考えられる課題を以下に整理する。
(2)水資源としての地下水の保全・利用に向けた課題
地下水の保全・利用のあり方を考えるにあたって、まず、地下水が重要な水資源であることの共通認識が不可欠である。その上で、水循環系の構成要素として地表水と地下水のデータ整備や利用実態の把握を行うこと、水資源として保全と持続的利用の最適なマネジメントを考えること、また、地下水の分布や利用形態は地域的に多様性に富むことから、地域特性に即した保全・利用のあり方を実現していくことが大切である。
?水資源としての共通認識の醸成
わが国では、高度経済成長期に過剰な地下水の採取が深刻な地盤沈下を招いた経験から、それが広域的な地盤沈下の要因となることについては共通認識が得られている。しかし、地下水は地形・地質の構成要素であり、土地所有状況とは関係なく個別の地下水利用が多かれ少なかれ他に影響を及ぼすといった地下水資源特有の性質は十分理解されていない。
また、地下水は地表水と比較してデータ整備や実態把握が個別的であるため、地下水資源マネジメントに結びつく情報として定着していない。
こうしたことから、今後、地下水を水資源として捉え、その保全・利用を図っていくための共通認識を醸成していくことが課題である。
?水循環系の構成要素としての地下水に関するデータ整備・実態把握
降水を源とする地下水は、地表水とともに水循環系の構成要素であることから、水資源として重要であるだけでなく、流域地表水の基底流量の安定化や洪水流出の緩和に寄与したり、豊かな水辺環境の保全・再生に重要な役割を果たしたりするなど、水循環系において多面的な役割を担っている。
EU「水枠組み指令」(2000 年)によると、地表水や地下水などすべての水資源を対象として、流域単位での統合的な水の管理をめざす取り組みが進められている。一方、わが国でも「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」のもとで、流域全体を視野に入れた水循環系の健全化に向けた取り組みが芽生えている。
こうしたことから、水循環系の構成要素として地下水の保全・利用を行っていく必要はあるが、地下水は地表水と比較して各種定量データが十分に整備されておらず、行政上も組織的にデータ蓄積・分析する仕組みが確立されていないことから、現状では、水循環系全体として、地表水に呼応して地下水を統合的に保全・利用できる状況にはない。
このため、地下水に関する定量データを整備しうる仕組み、例えば、地下水の水資源と
しての基本データ(地下水位・水頭、採取量、地質柱状図、利用実態、水文等)の電子デ
ータ化の推進が時代の要請となっている。その定量データに基づき、科学的な地下水資源・
保全計画を立てて、水循環系の構成要素としての地下水の位置づけや特性を明らかにした
上で、適切な保全・利用を図っていくことが課題となる。
?持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現
地下水は、一般に水質が良好かつ水温変化が少なく、大規模な貯水・取水・給水施設を
必要とせず安価に利用できることから、わが国では、特に経済復興・高度成長期の水需要
に応え、大量に利用され、地盤沈下問題が深刻化した。その対策として国や地方自治体に
よるさまざまな取り組みが進められた結果、地盤沈下はおおむね沈静化している。
以下に示す観点から、今後とも地下水障害を未然に防止するための十分な配慮が必要で
ある。
1) 依然として、長期的には地盤沈下が沈静化している大都市でも、渇水時に短期的・
局所的な地下水位の低下が地盤沈下を招いた(平成6年渇水等)。近年、少雨年の
降水量が減少傾向にあることや、年最大連続無降雨日数(降水のない日が連続する
最も長い期間)が長くなる傾向が認められることから、今後も渇水に伴う地下水位
低下が懸念されている。
2) 深刻な地盤沈下を経験してきた地域(東京、名古屋、大阪等)は、地下水の採取量
を抑制してきた結果、地下水位が回復、上昇に転じ、地下街や地下駅などの既設地
下構造物が浮き上がる問題が生じている。
3) 地下水はいったん汚染されるとその浄化が困難であることから、有機塩素系溶剤や
硝酸性窒素など地下水汚染が多様化していることを踏まえた地下水資源の水質保全
について、特に留意が必要である。
4) ミネラルウォーター生産のための地下水利用、揚水・ろ過技術の新技術を背景とし
た個別水道利用施設における地下水利用等が拡大している。
地下水は水循環系において一般的に滞留時間が長く、地盤沈下や水質汚染などの地下水
障害は、いったん生じると復旧が不可能であるか、もしくは長い年月を要する。このこと
から、持続可能性という観点に立ち、地下水をめぐる新たな動向が及ぼす影響についての
解明も進めつつ、地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染等を生じさせず、地下水の保全と
利用の最適なマネジメントを実現していくことが課題となる。
?地域特性に即した保全・利用のあり方の実現
地下水資源の分布や利用形態は、地形、地質、気候、植生等の自然条件や、人口、土地
利用、産業、歴史・文化等の社会経済条件によって地域ごとに大きく異なっており、多様
性・固有性に富んでいる。
例えば、わが国では、主要な地下水盆は平野や盆地に分布しているが、関東平野のよう
に複数の都県にまたがる大規模なものから、単一市町村にとどまる小規模な平地や扇状地
まであり、このほかに火山地域や石灰岩地帯にも帯水層が存在し、それぞれで地下水が利
用されている。また、水利用全体における地下水への依存度や、生活用水、工業用水、農
業用水といった地下水利用の用途別割合も、地域によってさまざまである。
このように地下水資源の分布や利用形態が異なれば、地下水資源の開発可能性や地下水
障害・汚染等の発生状況も千差万別である。このため、地下水の保全・利用に向けた取り
組みにあたっては、それぞれの地域特性に則した考え方や方法・体制等に基づいて対応す
ることが重要な課題となる(図2-5-1参照)。
地下水への期待と動向
■水資源としての地下水への期待
* 安全で良質な水供給への要請
* 気候変動等に伴う利水安全度の低下への対応
* 大規模地震災害時の水源確保
* 長期的な安全保障の観点からの水資源確保の必要性
■地下水をめぐる最近の動向
* 広域的な地盤沈下は概ね沈静化
* 渇水時には短期的・局所的な地下水位低下、 地盤沈下が発生
* 一部地域では地下水位上昇により地下構造物への影響も発生
* 地下水質汚染
* 新たな地下水利用形態( ミネラルウォーター、 地下水ビジネス)の拡大 等地下水の保全・利用の課題
* 水資源としての共通認識の醸成
* 水循環系の構成要素としてのデータ整備・実態把握
* 持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現
* 地域特性に即した保全・利用のあり方の実現問題の所在
* 水資源としての地下水、 および水循環の構成要素としての地下水についての共通認識が得られていない
* 地下水の諸問題について、 科学的な見地からの実態解明・要因分析が十分になされていない
* 水資源としての地下水資源の保全と利用の調和の社会的合意や理念が形成されていない
* 地下水の現状・動向は、 地域ごとの多様性が高く、 全国画一的な対応が困難
図2-5-1 地下水の保全・利用に向けた課題の概観
第3章 今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法
第2章では、地下水資源の保全・利用に向けた課題として、水資源としての共通認識の醸成、水循環系の構成要素としてのデータ整備・実態把握、持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現、地域特性に即した保全・利用のあり方の実現、という4つが抽出された。
これらの解決における科学的論拠は「健全な水循環系の構築」(新しい全国総合水資源
計画(ウォータープラン21)、国土庁、1999 年)に置かれる。ここではまず、健全な水循
環系の構築における地下水の位置づけや、水循環系の構成要素としての地下水の特性を踏
まえ、課題解決に向けた基本的な考え方を示す。
次に、これらを踏まえた地下水の適正な保全・利用を実現するための新しい方法論とし
て、「地下水資源マネジメント」の考え方を提案し、その具体的な手順について述べる。
さらに、その計画・実践にあたり、地域ごとの多様性、地下水の特性、特に地域規模と
の関係に着目し、地域規模に基づく類型別「地下水資源マネジメント」を提唱する。
3.1 健全な水循環系の構築における今後の地下水利用の基本的な考え方
ここでは、健全な水循環系の構築にあたって地下水の位置づけを明らかにし、地下水の
特性を地表水と比較検討した後、これらを踏まえ、課題解決に向けた今後の地下水利用の
基本的な考え方を提示する。
(1)健全な水循環系の構築における地下水の位置づけ
?健全な水循環系構築の背景
「健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて」(2003 年10 月、健全な水循環系構
築に関する関係省庁連絡会議公表)では、「健全な水循環系」とは「流域を中心とした一連
の水の流れの過程において、人間社会の営みと環境の保全に果たす水の機能が、適切なバ
ランスの下にともに確保されている状態」と定義づけられている。その具体的な姿は地域
ごとに多様であり、例えば、地下水障害や地下水資源の枯渇を生じない範囲で地下水が最
大限利用されている状態や、歴史的・文化的に重要な湧水の復活・維持といったような目
標の設定や地域特性に依る。
近年の都市化の進展は、降水の浸透機能を低下させ、都市型水害や、地下水の涵養力低
下を招いている。また、地域の文化資産ともいえる古くからの湧水を枯渇させたり、河道
への地下水からの涵養を減少させ、平常時の河川流量の減少も招いている。地下水採取・
利用とも重なって、水循環系の健全性が損なわれている。
こうしたことから、今後の地下水資源の保全・利用のあり方を考える上で、健全な水循
環系の構築という視点の重要性がきわめて高くなっている。
?水循環系における地表水と地下水の特性比較
地表水と地下水はいずれも水循環系の構成要素であるが、今後の地下水資源の保全・利
用の検討にあたって、水循環系における地表水と地下水の特性の違いに留意する必要がある。
両者の特性を概略比較したものが表3-1-1であるが、地表水との比較における地下水の
重要な相違点として、滞留時間の長さと実態把握の困難さ(時間・経費増、遅れ等)があ
げられる。滞留時間の長さは、過剰揚水等による井戸枯れ・塩水化等の地下水障害や地下
水質の汚染が一度生じると、その回復・改善に長期間を要することの要因となる。また、
実態把握の困難性や遅れは、水循環系全体として、地表水に呼応して地下水を統合的に保
全・利用できない要因となっている。
表3-1-1 水循環系における地表水と地下水の特性比較
(2)今後の地下水利用の基本的な考え方
?地下水資源マネジメントの論点
地下水に関するマネジメント注)は、広域の地下水資源利用に焦点を当てた「地下水資源
マネジメント」と個別の土地開発や地下空間開発によって起こり得る地下水環境に与える
悪影響の防止・軽減を目的とする「地下水環境マネジメント」の2つに分けられる(図3-1-1
参照)。なお、地下水資源マネジメントは図3-1-1 青色に示す。
健全な水循環系の構成要素をなす地下水は、流域地下水文区のもつ水源地域から平野部
までさまざまな地域特性を踏まえ、量・質及び環境を考慮し、総合的な観点に立った検討
が必要である。
そこで、本報告書では、健全な水循環系の構築という視点から、主に量的な側面に軸足
を置いた「地下水資源マネジメント」について、今後の地下水利用の基本的な考え方を示
すこととする。今後、各地域で地下水資源マネジメントの取り組みをそれぞれの地域で具
体化・実践するにあたっては、各地域の諸条件や水需給に適合した検討が必要であること
は言うまでもない。以下の議論は日本で典型的な平野地形を念頭に置いている。
地下水マネジメント
地下水資源マネジメント地下水環境マネジメント
量的な側面における地下水資源マネジメント
*持続的に利用可能な範囲での利用
*地盤沈下等の地下水障害の未然防止等
地下水理・水文環境の保全
*湧水の保全・復活
*都市再開発
*地下空間開発
*大規模土地開発等
地下水質環境の保全
*汚染源・物質の特定
*汚染対策
*モニタリング等
質的な側面も含めた地下水資源マネジメント
*用途別の水質への要請を踏まえた利用等
図3-1-1 地下水資源マネジメントの主な検討対象
地下水も水資源の1つと見れば、こういった水資源マネジメントの考え方は思想上の符
号はあっても、地下水資源マネジメント(groundwater resource management)では、地表
水と同様のマネジメント手法には馴染まず、いくつか違った点がある。
1) 地下水は帯水層が自然の貯水池の役割を持つため、地表水のダムや人造湖のように
人工的な貯水施設を構築することはほとんどない(地下ダムや人工涵養施設は限ら
れた条件でしか効果を発揮しないため、事例は非常に少ない)。
2) 地下水の利用計画、管理、調整作業は、地下水盆の構造・地質の多様性や利用規則
欠如の面もあって、地表水に比べはるかに複雑である。
3) 地下水管理の要となる効果的な地下水モニタリングが地表水のそれと比べ容易でな
い。
以上を踏まえ、第2章で抽出された課題の解決に向けた今後の地下水利用の基本的な考
え方を以下に示す。
?地下水資源の最適なマネジメント実現に向けた方法論と指針の必要性
地下水は一般に水質が良好で水温の変化が少なく、大規模な貯水・取水・給水施設を要
しない等の優れた特性を有していることから、多用途に利用される重要な水資源となって
いる。今後も安定した水資源として、また災害時の緊急水源として保全・利用していくこ
とが期待されている。
地下水資源は水循環系における回復可能な水資源でもあり、地下水収支のバランス(あ
る区域内における一定期間内の地下水の流入・流出の均衡状態)が保たれる範囲内で持続
的に利用していくことが可能である。
一方、地下水資源の利用がかつて深刻な地盤沈下等の問題を招いたことから、行政によ
る採取規制とともに地表水への水源転換が積極的に進められてきた。今日、全国的にみて
地下水資源の利用による広域的な地盤沈下はおおむね沈静化しているが、渇水時等におけ
る短期的・局所的な地下水位の低下や地盤沈下等の地下水障害は、復旧に長い年月を要す。
こうしたことから、地下水資源と国土を保全することに加え、持続的に利用可能な範囲
内で利用し、地盤沈下や塩水化等の地下水障害を招かないように、地下水資源の保全・利
用をマネジメントしていくことが昨今の要請となっている。
一方、地下水資源のマネジメントを推進する前提として、地下水は同じ水循環系の構成
要素である地表水と比較して、適正に保全・利用すべき水資源としての認識が醸成されに
くく、データ整備や実態把握が十分に進んでいるとは言えない状況にある。
こうした状況にあって、地下水資源の保全と利用のマネジメントを推進していくために
は、その方法論を明らかにするとともに、地下水管理者となる地方自治体の計画担当者に
対して、どのようにして地下水に関する意識啓発や広報・指導、地下水のデータ整備や実
態把握を行い、必要な施策を計画・実践・運用していくべきかをわかりやすく示す指針(ガ
イドライン)が必要である。
?適正採取量に基づく地下水資源の保全・利用のマネジメント
地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染等を生じさせず、持続可能な形で地下水の保全と
利用を最適にマネジメントしていくためには、以下に述べる「適正採取量」に基づき、そ
の範囲内で地下水資源の保全と利用の最適なマネジメントを実現していくことが肝要であ
る。
ある地下水盆において、ある一定の期間に利用可能な地下水の量(おおむね涵養量より
小さく地下水障害を起こさない量)を「適正採取量」とすれば、適正採取量と(実際の)
採取量の関係は、図3-1-2上で説明できよう。採取量が適正採取量を上回る場合には地下
水障害や地下水資源の枯渇が懸念され、採取量が適正採取量を超えない範囲内で利用して
いくことが必要条件となる。一方で、地域によっては、地下水位が上がりすぎないように
マネジメントしていくことも重要な課題となる。
一般に、地下水は特段の規制をしなければ、安価な水資源として利用ニーズが拡大する
傾向を採る。このため、地下水の涵養能力や地下水障害の発生しやすさなどにより決まる
適正採取量より実際の採取量が少ない状態にあることが好ましい。また、地
下水の適正採取量そのものの維持・拡大には、地下水涵養策や地下水資源の保全策を実施
する必要がある。
図3-1-2 適正採取量と採取量の関係からみた地下水の保全と利用の説明
?地域規模等の類型に即した地下水資源のマネジメント
地域の地下水に関する状況は、自然条件(地形、地質、気候等)や社会経済条件(人口、
土地利用、産業、歴史・文化、法制度等)に応じて地域ごとの多様性・固有性がきわめて
強いことから、地域特性に即した対応が必要である。特に、適正採取量に基づく地下水資
源の保全・利用のマネジメントにあたっては、地下水盆や帯水層の規模が重要な尺度とな
る。その規模は1市町村内で完結するものから複数の都府県にまたがるものまで大小さま
ざまであり、こうした規模の違いによってマネジメントの目的や方法にも違いが生じる。
また、地下水資源のマネジメントでは、行政が中心的な役割を果たすことが期待される
ため、都道府県や市町村といった行政単位との関係も重要である。
こうしたことから、地下水盆や帯水層の規模と行政単位に着目していくつかの地域単位
の分類を設けることで、多種多様な地域特性を類型化し、地下水資源マネジメントの目的、
方法等を明らかにすることが可能となる。具体的には図3-1-3に示すように、局所(地区
レベル)・小規模(市町村レベル)・中規模(都府県レベル)・大規模(複数の都府県レ
ベル)という4つの類型が想定される。
資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)をもとに作成
図3-1-3 地域類型に応じた地下水資源マネジメント等の概観
3.2 地下水資源マネジメントの考え方と手順
ここでは、3.1節に述べた今後の地下水利用の基本的な考え方を踏まえ、地下水の保
全・利用の方法論として地下水資源マネジメントを提案し、その考え方と具体的な手順を
示す。
(1)地下水資源マネジメントの定義と特徴
「地下水資源マネジメント注1)」とは、3.1節に述べた今後の地下水利用の基本的な
考え方を具現化するための手段であり、「健全な地下水文循環にあって、地下水障害や枯
渇を発生させない範囲で、地下水を水資源として持続的に保全・利用しうる採取(揚水)・
運営・管理の方法」と定義する。
その特徴は、科学的な知見に基づき、実態把握、計画策定、揚水マネジメント、観測・
モニタリング、評価・見直しを定量的に行うことにあり、そのプロセスの中核を成すのは、
その適正配分数値シミュレーションモデルを活用した対象地下水盆の適正採取量の数量化
と地下水位に基づいた管理・モニタリングにある。また、もう1つの特徴として、PDC
Aサイクルに基づく継続的な見直しを行い、科学的・定量的なマネジメントの精度を向上
させていくことがあげられる。
?数値シミュレーションモデルを活用した適正採取量の数量化
地下水資源マネジメントにあたっては、持続的にどの程度の地下水が利用可能であるの
かの定量的把握に基づいた計画の作成が必要となる。そのためには対象地下水盆の数値シ
ミュレーションモデルを構築し、これを用いて地下水障害を発生させず、かつ健全な地下
水収支を保つ地下水位のもとで、総採取量とその地域配分を科学的な手法で数量化するこ
とが求められる。
このように、数値シミュレーションモデルは、地下水資源マネジメントの根幹を成すも
のであり、揚水事業者と地下水管理者 注2)(国や地方自治体)の両者が地下水の保全・利
用に関する計画を策定する際に有用である。
数値シミュレーションモデルの作成にあたっては、計画対象地域における地下水に関す
る各種データを経年的に収集し、地下水や水文の実態把握、地質調査・分析を行うことが
前提として必要となる。
?井内地下水位・水頭を用いた地下水管理・モニタリング
地下水の保全・利用に関する計画を実際に運用し、地下水の管理に役立てていくために
は、適切な管理・モニタリングの手法が必要となる。地下水位の変動と地下水採取量とが
密接に関係していることに注目すれば、テレメーターシステムを活用することにより、リ
アルタイムで地下水位をモニタリングして採取量を適正に制御できる。
こうした視点から、地下水資源マネジメントにおける地下水管理・モニタリングの指標
として井内地下水位を用いることが有効と考えられる。地下水位の常時観測を行い、その
変化に応じて地下水利用者に採取量の抑制を要請すること等により、過剰揚水を緩和し、
地盤沈下等の地下水障害を未然に防止ないし軽減することが可能となる。また、地下水位
を用いた地下水管理・モニタリングは、即時的かつ容易に対策を実施できるという点で優
れ、予想外の水需要に伴う緊急的対策にも対応可能である(例えば、渇水時の地下水採取
量急増による地下水位の短期異常低下の回避対策、既存の水源の水質事故に伴う振り替え
水源確保等)。さらに、地域によっては、地下水位が上がりすぎないよう適切に管理する
ことにも活用できる。
地下水位を用いた地下水管理・モニタリングは、渇水時等において地盤沈下防止のため
の地下水採取量を緊急抑制する施策にも適している。
?PDCAサイクルによる継続的な取り組みのプロセス
地下水資源マネジメントは、調査・計画(P)→実行・観測・モニタリング(D)→評価(C)
→見直し(A)というプロセス(PDCAサイクル)をある程度反復しながら、継続的に取り
組んでマネジメントの精度を高めていくことが必要となろう。
一般に、地下水に関するデータ整備や実態把握がどの地下水盆でも十分に進んでいると
は言えず、数値シミュレーションモデルを用いた地下水資源マネジメントの実践例も限ら
れていることから、地下水資源マネジメントの実施当初から精度の高い将来予測を行える
わけではない。また、地下水涵養量や帯水層水理パラメータの事前の把握は簡単ではなく、
推算せざるを得ないこともあり、シミュレーションモデルは、実際に運用しながら改良を
加えていくことで、精度を高めていく必要がある。
このため、地下水資源マネジメントの実施にあたっては、当初はある程度、実測値や経
験則に基づいて計画を策定し、実際に運用しながら評価・見直しを重ねていくことで、シ
ミュレーションモデルの精度を高めたり、計画の実効性を高めていったりするといった、
継続した取り組みが必要である。
(2)地域類型別にみた地下水資源マネジメントの方向性
地下水資源マネジメントのコンセプトは、地域特性に即した取り組みが重要であること
から、前述した地域規模による4つの地域類型(図3-1-3参照)に沿って以下に示す。
?局所規模レベルの地下水資源マネジメント
局所規模(1km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に小規模な地下水源の確保(井
戸のさく井)にあたって、個別の揚水井の配置や採取量の設定が対象となる。この場合、
対象となる地域の広がりは、地下水盆というより帯水層と呼ぶのが相応しい地区レベルの
規模である。
小規模な地下水源の確保においては、必要な採取量が継続的に確保できることと、地下
水資源開発による影響(周辺井戸の枯渇、地盤沈下の発生等)が周辺に及ばないようにす
ることの2点が重要である。
このため、既存の周辺井戸の影響や地盤沈下を防止しつつ、必要な採取量を確保するに
あたって、揚水井の適正深度や適正配置(適正な井戸間の距離)、個々の井戸の適正採取
量を算定し、井戸設置の申請に対してどのような許可制度や許可基準を設定するかという
ことが重要となる。これらの検討方法としては、水収支と水理学的な検討が求められ、揚
水井戸理論を用いた定量的検討が想定される。観測・モニタリングにあたっては、採取量、
地下水位、地盤変動量等が指標となる。
?小規模レベルの地下水資源マネジメント
小規模(数km2〜数十km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に市町村(単一の市町
村もしくは複数の市町村による組合等)の行政区域内で完結している地下水盆が対象とな
るが、近隣市町村にまたがる平野や盆地の一部地域が対象となることもある。
局所レベルのような個別井戸ごとではなく、一定の広がりをもつ地域を対象として、複
数の揚水井を集合体として捉え、対象地域内での地下水収支や地下水採取量の地域配分等
を取り扱うことになり、対象地域外の近隣市町村に地下水資源開発の影響を及ぼさないよ
うにしつつ、必要な採取量を確保することが地下水資源マネジメントの要点となる。
このため、地下水収支バランスの保たれる範囲内の適正採取量とともに、対象地域内で
の適正な地域配分や用途別配分、採取許可方法等を明らかにする必要がある。検討方法と
しては、数値シミュレーションモデルを用いて地下水盆や帯水層をモデル化した上で、水
需給の現状や将来見通しに基づくシミュレーションを用いて、利用可能地下水資源量や適
正採取量、揚水井の分布密度、安全地下水頭・採取量等を設定する。
また、観測・モニタリングの方法としては、テレメーターによって地下水位や地盤変動
量をリアルタイムで把握するとともに、渇水時等の短期的な地下水位低下に対する対応と
して、管理水位を設定し、警報・注意報の発令による地下水採取者への採取量抑制の要請
を行うこと等が考えられる。
?中規模レベルの地下水資源マネジメント
中規模(数十〜数百km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に都府県レベルで完結
している中規模な地下水盆(熊本地域等)が対象となる。
地下水資源マネジメントにあたっては、対象となる都府県の地域内において、地下水収
支バランスの保たれる範囲内で、かつ地下水資源開発に伴って地下水障害等の悪影響を防
止しつつ、必要な採取量を確保することが重要となる。
このため、計画においては、地下水資源量とその地域配分を適正化することや、広域的
な地下水の観測・モニタリング(地下水位、地盤変動量等)を通じた地盤沈下の防止対策
が重要な課題となる。検討方法については、?で述べた小規模地下水資源マネジメントの
定量的な延長検討とほぼ同様に考えることができる。
?大規模レベルの地下水資源マネジメント
大規模の地下水資源マネジメントにおいては、複数の都府県にまたがる広がりを持つ大
規模な地下水盆の分布する地域(関東平野、濃尾平野、大阪平野、筑後・佐賀平野等)が
対象となる。ここでの重点は中規模の地下水資源マネジメントとおおむね一致するが、都
府県をまたがる対応が必要となるため、国の関係府省と関係地方自治体が連携して対策を
行っている「地盤沈下防止等対策要綱」の対象地域のように、体制・制度面で広域的な取
り組みが必要となる。
(3)地下水資源マネジメントの企画・検討手順
地下水資源マネジメントの目的や手順は、その対象とする地下水盆の地形・地質特性、
特に地域の規模によって異なってくるが、ここでは地域特性にかかわらず共通する基本的
な企画・検討手順について、適宜代表的な事例を紹介しながら、図3-2-1に沿って示す。
資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)
図3-2-1 地下水資源マネジメントの企画・検討手順
?予備調査
a)対象・目的の設定
はじめに、地下水資源マネジメントを行う対象・目的の設定を行う。
対象となる地域は、局所的な1〜2k?の狭い範囲において個別の井戸の設置可否等を
対象とするような場合を除き、行政上の視点から設定されることが多いが、その規模は単
独の市町村にとどまるものから、同一都道府県内で複数の市町村にまたがるもの、複数の
都府県にまたがる盆地や平野規模までさまざまである。こうした対象地域は、地下水の保
全・利用に関する課題や問題意識を共有する圏域として設定され、地理的条件、特に帯水
層や地下水盆の分布状況・規模に応じた地域となる。
目的の設定は、地下水資源の保全、地盤沈下等の地下水障害の防止、地下水環境の保全
など、対象地下水盆における地下水の保全・利用上の課題や問題意識等に応じて設定され
る。また、地下水の保全・利用に関する総合的な計画の場合と、特定の課題に特化した計
画の場合で、目的の設定や力点が異なってくる。以下にその事例を示す。
【総合的な利用・保全の目的を掲げる事例】(熊本地域地下水総合保全管理計画)
生活用水をすべて地下水で賄っている熊本地域では、地下水資源を次世代に引き継ぐ
ことを目的に、地下水の保全を優先している。
本計画は地下水の保全・利用に関する総合的な計画であることから、計画で定めてい
る保全目標は、地下水資源の量・質両面での維持に加え、地域のシンボルともなってい
る豊かな湧水の維持・復元、地下水障害の防止等にも置かれている。
【特定課題の目的を掲げる事例】(埼玉県地盤沈下緊急時対策要綱)
かつて深刻な地盤沈下を経験し、現在も地盤沈下が懸念される埼玉県では、地下水の
過剰なくみ上げによる地盤沈下を防止することを、地下水対策の優先目的としている。
地下水の保全・利用全般については「埼玉県生活環境保全条例」に定められているこ
とから、本要綱では、緊急的な地盤沈下対策に特化して目的が設定されている。
b)調査内容・検討手順の検討
設定された対象・目的に基づき、実態把握や計画の策定、及び運用・評価にあたって必
要な調査内容や検討手順を構築する。その際には、地下水資源マネジメントの対象・目的
のほか、利用可能な予算、計画策定までの期間、取組体制等も考慮する。
?地下水に関する実態把握
対象・目的に応じた地下水・水文調査(地形・地質、水文、土地利用、水利用実態、地
下水障害、地下水流、地下水質、法制度等)を行い、対象地域の地下水に関する問題点の
要因分析を行うとともに、対象・目的に応じて適当な数値シミュレーションモデルを用い
ながら、地下水盆や帯水層をモデル化し、適正採取量の数量化を行う。
地下水資源マネジメントの実施にあたって、地下水に関する実態把握、特に採取量の把
握や地下水収支の数量化は、地下水の保全・利用に関する計画の策定・運用の前提となる
きわめて重要な要素である。同時に、実施にあたっては、適正採取量の数量化のために必
要な時間・労力と知識・経験の蓄積、また、地下水採取量把握にあたっての利用者の理解
と協力が必要である。
a)地下水・水文調査
地下水・水文調査の調査項目として、以下のようなものがあげられるが、実施する項目
や精度は、地下水資源マネジメントの対象・目的等に応じて、個別に設定する。
* 地形、地質、水文、土地利用、水利用実態
* 地下水障害、地下水流、地下水質、関係法令
【地下水・水文調査の調査項目の例】(熊本地域地下水総合調査)
「熊本地域地下水総合調査」では、以下の項目について調査を実施している。
・ 地形・地質:地質平面図・断面図、地下水位断面図等を作成
・ 土地利用:涵養域・非涵養域別土地利用、生産調整率(米作減反率)の推移を把握
・ 水利用実態:条例に基づき採取者から報告されたデータを活用
・ 地下水流:既存井戸の一斉測水調査を実施し、帯水層別地下水位等高線図を作成
・ 地下水質:水質汚染防止法に基づく地下水の水質汚濁状況の常時監視を170 地点あ
まりで実施するとともに、河川水5地点、湧水10 地点、地下水86 地点でイオン分
析を実施等
【地下水利用実態電子データの例】(茨城県)
以下に示す茨城県の検討例では、現行の揚水実態、井戸分布、地形・土地利用の情報
を一目で知ることができ、それぞれの井戸の地質情報や採取量が判る。
b)地下水数値シミュレーション解析による適正採取量の数量化
水収支は地表の水収支と地下の水収支が連成・構成されるが、地下水収支は、地下水の
涵養量と採取量によって地表水収支と結びついている。帯水層・地下水盆が対象地域を越
えて分布している場合には、隣接する地域との間において、地下水同士の流入・流出が生
じうるが、帯水層・地下水盆が対象地域内で閉じている場合には、涵養量と採取量が把握
できれば、地下水収支を数量化できることになる。
地下水収支モデルが検定・修正できれば、水需給の現状や将来見通しを外生的に入力し、
数値シミュレーションモデルを活用して地下水の挙動の将来予測を行うこと 注)、さらにそ
の現地適用への論拠とすることが可能となる。
* 地下水盆のモデル化
* 地下水涵養の数量化
* 水理定数
* 地下水流動解析・内挿検定・パラメータ同定
* 数値シミュレーションモデルによる適正採取量や水収支の数量化
* 将来予測
* 地下水採取量の適正配分・揚水井分布
* 安全水頭・採取量の設定
【地下水収支の数量化の例】(座間市地下水総合調査)
「座間市地下水総合調査」においては、過去20 年間におけるデータに基づき、地下
水収支シミュレーションモデルを構築し、揚水条件(地下水揚水量)、涵養条件(平水
年と渇水年の涵養量)、河川改修条件の組み合わせによって、7ケースについて地下水
位変動や水収支予測を行い、台地部、低地部、市全体のそれぞれについて、水収支が±
0となる揚水量を適正揚水量として設定している。
また、市内の代表観測井において地下水の揚水に支障のない地下水位として、第1段
階水位(注意)と第2段階水位(警戒)の2段階の管理水位を設定している。
?地下水の保全・利用に関する計画の策定
対象地域における地下水資源マネジメントの目的や枠組みに基づき、必要に応じて数値
シミュレーションモデルによる将来予測の結果を活用しながら、適正な地下水利用を実現
するための考え方、適正採取量、管理水位、利用規則や、地下水の観測・モニタリングの
方法、行政担当者向けの管理マニュアル等を検討・策定する。
a)地下水適正利用のあり方
数量化された地下水収支やその将来予測を参考にしながら、地下水の保全・利用に関す
る計画の根幹を成す地下水適正利用のあり方を検討する。
* 適正利用のコンセプト
地下水障害を招くことなく、地下水収支のバランスが保たれる範囲内で地下水資源
を保全しながら持続的に利用できること前提として、地下水資源の適正な利用にあ
たってのコンセプト、基本目標を設定する。地域内において、ある一定の期間に利
用可能な地下水の量(おおむね涵養量より小さく地下水障害を起こさない量)を「適
正採取量」とするとき、以下のようなケースが想定される。
<採取量が適正採取量を上回っていない場合>
採取量が適正採取量の範囲内にある状態を維持していくため、涵養量の維持に向け
た取り組みを行うとともに、規制・誘導等により採取量を抑制する必要がある。
<採取量が適正採取量を上回っている場合>
採取量の抑制と適正採取量の拡大が考えられるが、地下水涵養策による利用可能量
の拡大には限界があることから、主に規制・誘導等により採取量を適正採取量の範
囲内に抑制する方策が求められる。
* 用途別配分・利用方式
数値シミュレーションモデルによる適正採取量の将来予測結果や適正利用のコン
セプト、水資源の需給事情等に基づき、総採取量の中での利水用途別配分(農業用
水、工業用水、生活用水等)や、地下水の利用方式(各用途における地下水と地表
水の組み合わせ利用の考え方)等について検討する。
* 利用規則・井戸の設置許可等
必要に応じて、地下水の採取・利用にあたっての規則や揚水井の設置基準・設置条
件等のルール(法律・条例等)を検討する必要がある。例えば、茨城県地下水適正
利用条例では、新規の井戸設置は許可が必要である。
b)適正利用を実現するための方策
地下水適正利用のあり方の検討結果に基づき、これを実現させるための方策(地下水管
理の方式、具体的方法等)について検討する。
* 地下水管理の方式
気象の平穏な平常時、気象の不順な渇水期、自然災害時等の状況に応じた地下水管
理の方式を検討する。具体的には、総適正採取量の範囲で地下水位・水頭や地盤変
動、採取量等の各種データを総合的に分析して管理する方式や、経験的に得られた
採取量配分と地下水位の経時的な相関関係の分析に基づき、地下水位のモニタリン
グを通じて過剰揚水を抑制する方式(警報・注意報の発令による地下水採取者への
採取量抑制の要請等)が選定される。
* 観測井の構造・配置・数
地下水収支の数量化の結果等を踏まえ、地下水管理を行うために必要な地下水位・
水頭や地盤変動量等を観測する観測井の構造・配置・数を決定する。
近年ではテレメーターの実用化が進み、通信回線を活用して観測データをリアルタ
イムで観測・収集することが可能となっている。
* 管理マニュアル
担当者の異動等があっても継続的に地下水資源マネジメントが行えるよう、地下水
の保全・利用に関する計画の管理者や地下水採取者等が地下水管理をどのように行
っていくのかをまとめた管理マニュアルを作成する。
* 地下水管理者・採取者への情報伝達方法
地下水管理者となる地方自治体、地下水採取者となる企業、水道事業者、個人等に
対して、地下水資源マネジメントにあたって必要な情報を迅速に伝達する方法は、
インターネットをはじめとする電子媒体によることができる。
* 広報・指導
地下水資源は採取者や利用者が多岐・多数にわたることから、地下水資源マネジメ
ントにあたって重要な情報は、採取者のみならず、広く利用者一般に対して公表・
提供し、地下水の保全・利用に関する意識啓発を図る。
【適正利用を実現するための方策の事例】(埼玉県地盤沈下緊急時対策要綱)
埼玉県では、「埼玉県地盤沈下緊急対策要綱」に基づき、地下水位の著しい低下によ
り、地盤沈下が生じる恐れがあると認められる時には、一定量以上の地下水採取者に対
して、各地域の地下水位の程度に応じて、地下水採取の抑制等を要請する「地盤沈下注
意報」「地盤沈下警報」が発令される。
?地下水の保全・利用に関する計画の運用・評価
a)地下水の観測・モニタリング
計画に定められた適正利用を実現するための方策に基づき、地下水位、採取量、地盤変
動量についての報告を採取者に求めたり、観測井を用いて観測したりした上で、そのデー
タを収集・処理するとともに、必要に応じて地下水障害等を未然に防止するための対策(新
規揚水井の許可制等)を実施する。地下水資源マネジメントは、地下水位・水質、採取量、
降水、地下水障害(地盤沈下量等)といった観測データによってなされることから、観測
データの迅速かつ正確な収集・伝達・処理が重要である。
* 採取量・水位報告
地下水資源マネジメントには採取量や地下水位の把握が不可欠であることから、一
定量以上を採取する採取者に対して、記入書式を用意し、採取量や地下水位の報告
を義務づけること等により、これらを把握する。
b)計画の評価・見直し
地下水の観測・モニタリングを一定期間継続し、データの蓄積が図られた時点で、策定
した計画の妥当性、観測・モニタリングの有効性等を評価し、その結果に基づいて必要な
修正・変更を行う。特に、地下水収支の数量化と将来予測に用いる数値シミュレーション
モデルの精度を高めていくことが重要である。
* 評価
計画の評価は、地下水資源マネジメントのPDCAサイクルの「C」に相当し、計
画内容の有効性や成果を計る「政策評価」と、計画の執行段階での効率性や進捗度
を計る「執行評価」を適切に組み合わせて実施することが望ましい。
評価に用いる指標と、最低限達成すべき水準、おおむね成功と評価できる水準、可
能ならば達成したい水準というような目標を、計画策定段階で予め設定をしておく
ことで、評価の精度が高まる。
* 見直し
計画の見直しは、地下水資源マネジメントのPDCAサイクルの「A」に相当し、
上記の評価結果に基づいて行う。必要に応じて、地下水適正利用のあり方を見直す
とともに、適正利用を実現するための方策については、評価結果に応じ、継続・改
善・中止のいずれかを検討する。
【評価・見直しの例】(熊本市地下水量保全プラン)
「熊本市地下水量保全プラン」の場合、毎年度プランの評価・見直しを行い、その進
捗状況をホームページで公表することとしている。評価にあたっては、評価結果等の説
明や市民の意見聴取のため、「熊本市節水推進パートナーシップ会議」を設置している。
(4)地下水資源マネジメントの検討・策定方法と策定・運用主体
地下水資源マネジメントを円滑に実施・運用するためには、地下水利用事業者の参加及
び地下水管理者との共同歩調が欠かせない。したがって、行政だけでなく、対象地域の主
要な地下水採取者が参画し、地域全体が連携して取り組んでいくことができる体制づくり
が求められる。このため、計画の策定・運用主体は、地下水資源マネジメントを主体的か
つ効率的・効果的に実施できる体制を整備する必要がある。
現行の行政管理体制では、行政区画単位でのマネジメントが実用的と考えられることか
ら、行政や協議会の長が地下水管理者として、計画の策定・運用主体となろう。具体的に
は、対象地域が単独の市町村にとどまる場合、同一都道府県内で複数の市町村にまたがる
場合、複数の都府県にまたがる場合といったように、各地域の事情に即して個別に判断さ
れるべきである。なお、複数の都府県にまたがる「地盤沈下防止等対策要綱」の対象地域
については、国の関係府省連絡会議が設置されている。
第4章 今後の地下水利用のあり方に関する提言
本報告では、
?「健全な水循環系構築」のための計画づくりの一環において、地下水について計画作成担当者に向けた提言
?地下水障害を発生させないことを前提とした適正な管理により利用する仕組みの構築に向けた具体的な提言
?国際比較の中でのわが国の地下水の特性及び利用のあり方
の3点に重点を置いて検討してきた。
地下水は重要な水資源であり、水循環系の構成要素であることから、本来、地表水と一
体化させ、環境面を含めて捉え、計画的に保全・利用されるべきものと考えられる。これ
までは、水資源の需給バランスの相互補完や地下水障害等の直面する課題の解決の面から
のみ地下水が捉えられてきたが、今後は地下水と地表水の役割分担や最適な両者の利用配
分の実現をめざした施策展開が必要な段階になってきている。こういった今日的なニーズ
に応え、本報告は、地下水資源マネジメントの手法論を展開した。
ここでは、第1章から第3章で述べた検討の結果を踏まえ、今後の地下水利用のあり方
に関する基本的な考え方やその実現にあたって求められる取り組みを提言として以下にと
りまとめる。
国の関係府省、地方自治体、企業、利水受益者等、地下水の保全・利用にかかわる各関
係主体には、本提言を踏まえ、それぞれの立場から、健全な水循環系の構築と持続可能な
地下水の保全・利用に向けた積極的な取り組みが期待される。
4.1 地下水資源マネジメントの推進
(1)健全な水循環系の構築に向けた地下水資源マネジメントの必要性
現在、わが国では、都市域における雨水浸透機能の低下、地表水と地下水の自然相互依
存の阻害等といった水循環系の健全性が損なわれていることに起因して、平常時の河川流
量の減少、湧水の枯渇、各種排水による水質汚濁、都市型水害等の問題が顕著となってき
ている。地表水とともに水循環系の重要な構成要素である地下水においても、健全な水循
環系の構築が重要な課題となっている。さらに、多量の水資源を水文収支域外より集積し、
消費・排出する都市の人工水循環系の健全化・保全を推進していく必要がある。
そのため、適正採取量の数量化や将来予測に基づき、地下水に係わる地域の諸条件に応
じて、地盤沈下などの地下水障害を未然に防止し、地下水収支バランスが保たれる範囲内
で、持続的に地下水を水資源として利用していくための適正利用のあり方とその実現方策
を検討し、地下水保全・利用に関する計画を策定・運用する必要がある。計画の策定・実
践・運用にあたっては、実態把握、計画策定、観測・モニタリング、評価・見直しという
継続的な試行プロセスを通じて、地域の諸条件に応じた持続的な地下水資源の保全・利用
のあり方を実現していくという「地下水資源マネジメント」の考え方が重要である。
例えば、関東平野を例にとると、図4-1-1に示すように、昭和20 年代より広域地下水利
用がなされ、地下水位(水頭)は低下したが、法律の規制(昭和31 年以降)によって回復・
上昇し、今は過去の自然地下水位に近づきつつある。将来の地下水資源のマネジメントに
は、健全な地下水環境・国土保全を目標に、安全水位を管理値に保持するよう人工制御す
ることが目指すところとなる。
図4-1-1 地下水資源マネジメントの説明図
(2)地下水資源マネジメントの推進に向けた支援環境整備
地下水資源マネジメントの実践・普及に向けた支援環境整備として、以下のような取り
組みを進めるべきである。
?地下水の実態把握に向けた採取量をはじめとするデータ整備の推進
地下水資源マネジメントの実践にあたっては、地下水の実態把握や問題点の要因分析等
を行う必要がある。地下水に関する調査としては、
1)地下水位及び地盤変動に関する調査、
2)水質に関する調査、
3)採取量に関する調査、
4)地形・地質に関する調査等があるが、以上のような観測データは、その地域の地下水解析に欠くことのできないものであるため、精度の高い長期的な観測を継続する必要がある。しかし、地表水と異なり、地下水はその
実態把握に時間・労力・経費がかかり、地下水の実態把握を行うための各種観測データが
十分に整備されていない。特に、地下水採取量は、地下水収支の数量化や将来予測、計画
の運用、観測・モニタリング等のさまざまな面で有用であるにもかかわらず、データの収
集整備(特に電子データ化)が進んでいない地域も多い。
採取量をはじめとする各種観測データの収集には、利用者の協力が不可欠であることか
ら、関係者間での協議、条例等の制度面での対応、データ収集・処理体制の整備などにす
みやかに着手することが求められる。
国においては、各地域において収集されたデータを全国共通に活用できるよう、データ
の収集項目や定義、収集方法等についての統一的な基準を作成し、各地方自治体に対して
データ収集を積極的に取り組むよう、普及啓発活動を実施することが必要である。また、
収集されたデータを蓄積・活用するためのデータベースについては、一元的な電子データ
ベース化を図り、データの効果的・効率的・実践的な活用を推進していくことが期待され
る。地質情報を全国で共有するための全国電子地盤図システム構築の構想も動き始めてお
り、こうしたシステムの活用も検討する必要がある。
?地下水実態・観測の数値情報共有・活用の推進
地下水資源マネジメントの推進を図るため、地方自治体の担当者をはじめ、地下水資源
マネジメントに関係する人が、全国各地域で策定された地下水保全・利用計画やその運用
状況、地下水に関する各種データ(降水量、地質、地下水採取量等)、地方自治体の地下
水に関する条例・要綱等、各地域の取組事例を情報交換し、活用しやすくなるよう情報環
境整備が必要である。そうすることによって地域性に富み、かつ水需給事情の異なる地下
水資源採取者や管理者が、より適正な地下水資源開発計画や運用方策を実践することが出
来よう。地下水資源のように多数の採取者が分散して各自揚水している場合、そのマネジ
メントの実行主体は採取者の側にあることを銘記したい。したがって、採取者の理解と協
力がマネジメントの運用に不可欠である。その実施・推進にあたって、地下水資源の所管
(地方自治体や各種機関)を通じて、地下水資源マネジメントの趣旨や方法について地下
水採取者(例えば利用協議会等)に対する講習会やポスター配布等により予め周知する必
要がある。
?実証モデルケースによる地下水資源マネジメントの推進〜取り組みの牽引役として〜
すでにいくつかの地域で、地下水資源マネジメントの先駆となる取り組み(例えば、埼
玉県、熊本県、栃木県野木町等)が行われているものの、現状ではその数は限られている。
そこで、地下水資源マネジメントの考え方に基づき、地下水保全・利用計画を策定・運
用しようとしている地域(例えば、現行の地盤沈下防止等対策要綱の対象地域等)に実証
モデルケースを選定し、地下水管理者と揚水事業者の連携のもとで採取量の把握、地下水
収支の数量化と将来予測に支援された地下水資源マネジメントを試行・実践し、その応用
性の実証や問題の解決後、有効性を普及していく必要がある。
先進地下水資源マネジメントの事例や方法を公表・情報提供していくことで、より多く
の地域で地下水資源マネジメントの経験・実績・有効性が認識されるようになり、その前
提となる採取量の把握に向けた採取者の理解と協力も得やすくなっていくことが期待され
る。
国においては、地下水資源マネジメントを推進するための新たなモデル事業を先導し、
実証モデルケースとなる地域の取り組みに対して、財政面での支援や専門的見地からの助
言を行うとともに、その成果を広く情報提供することはもとより、解析作業の中核を成す
汎用性の高い数値シミュレーションモデルの普及(例えば、米国地質調査所(USGS)の
MODFLOW.2005 等が国際的に普及)を行うことが期待される。
4.2 地下水資源マネジメントの運用方策
地下水資源マネジメントには、管理する際不可欠なマネジメント条件(あるいは制約条
件)が課されることになるが、その条件や制約指標(例えば、観測地下水位、採取量、地
下水障害)は、次の5つが要点となる。
?ある対象地下水盆(あるいは地下水文区)に涵養される地下水総量より広域総採取
量が小さいこと(地下水収支条件)
?観測地下水位が管理目標限界地下水位より高いこと(あるいは、管理目標地下水位
の上限と下限の範囲内にあること)(安全地下水位保全条件)
?広域総採取量をその構成地域採取配分量の和とすると、それら配分量がそれぞれの
管理目標地域採取量を超えないこと(安全地下水採取量条件)
?地下水障害(地盤沈下、地下水塩水化等)の誘発防止(地下水障害防止条件)
?異常な井戸水位低下、井戸干渉を招かず、かつ揚水井間距離が適正であること
(揚水井適正配置条件)
以上の制約条件を満足させるよう地下水資源をマネジメントすることになるが、?と?
は健全な地下水環境を保証すべき必須条件であり、観測地下水位や採取量の適正化によっ
て満たされ、過去の経験や実測データ及び数値シミュレーションによって解析しうる。し
かし、即時的な地下水資源マネジメントの指標としては、観測地下水位が実用的である。
今日、?を満たすようマネジメントを行うことが運用しやすい。その具体的な仕様は以下
に示す。
地下水揚水の適正化とは、広域地下水盆における地表水と降水による涵養の範囲内で、地下水
障害が発生しない最適揚水量を地域ごとに決め、急激な揚水は避けながら地下水資源を効果的に
利用することにある。地下水揚水抑制の具体的な実践には、過去の地下水・地盤沈下の観測デー
タを解析し、従来の揚水実績を十分検討した上で、段階的に分けた管理基準(限界値)水位を予
め設定しておき、注意報・警報といった情報を地下水利用者の合意の下で実践するのが合理的と
考える。設定された(目標)基準(限界)水位を下回るような地下水揚水は回避されなければな
らない。
地下水位と地盤沈下の観測方法は、二重管構造の観測井を使用するのが主流で、地下水位はフ
ロート式で地盤沈下は管頭変位量を機械的に測定している。近年オンライン化されたテレメータ
観測システムを利用し、地盤沈下を防止しつつマネジメントする方法が開発されている。図4-2-1
はそのシステム概念を示す。最近、このシステムが地盤沈下対策のみならず、経済性向上や省力
化に向けた地下水資源の保全にも普及しつつある。
図4-2-1 テレメータによる地下水マネジメントシステム概念図
また、地下水位を用いた地下水管理をより推進するため、即時的かつ容易に対策を実施
できるという点で有利なテレメーターシステム等の導入が必要であり、財政面での支援を
行うとともに、その成果を広く全国に情報提供していくことが期待される。
4.3 地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項
地下水資源マネジメントの推進や地下水資源の利用にあたって重要と考えられる事項
を以下に提言する。
(1)水資源の視点からの地下水の水質確保・保全
地下水の水質面については、これまでの汚染対策としての視点に加え、水資源政策の視
点から捉え、多様な地下水の利用ニーズに対応した用途別の水質確保・保全のあり方につ
いて検討する必要がある。その際には、地下水資源マネジメントの実施にあたって、量的
な側面だけでなく、水質面もその対象とすることで地域の諸条件に応じた地下水利用のあ
り方を実現していくことが適切である。
また、その前提として、浅層のみならず深層も含めた水質汚染に関するデータや情報の
整備が求められることから、まずは量的な側面に限って地下水資源マネジメントを実施す
る際にも、水質面の観測・モニタリングを同時に行い、データ整備を進めていくことが欠
かせない。
(2)地下水の震災対策
大規模地震災害時において、水の確保が重要な課題であることがこれまでの震災の経験
から指摘されており、発生直後から時間の経過に応じた各種水需要に適切に対応するため、
利用可能な水源とその特徴(水量、水質、設備・運搬の必要性等)を踏まえた水利用シス
テムを検討・構築しておく必要がある。
地下水は、身近で入手の容易な水資源であり、一般に水質もよいことから、大規模地震
災害時の利活用性が高く、地域の特性に応じた地下水の利用方策(用途・利用方法・制度
等)を検討・構築する必要がある。その際には、シミュレーション結果に基づき、各避難
所に緊急時に使える井戸を積極的に設置するという地域の取り組み等も踏まえつつ、耐震
性の高い井戸の分布状況の把握、災害時に民間井戸を利用可能とする権限の担保方法、少
なくとも災害発生直後の緊急・応急水供給に向けた別水源への振り替えのあり方等に留意
し、安全・安心な災害時地下水利用システムを構築することが求められる。
(3)地下水資源マネジメントの社会的合意形成への取り組み
?社会的関心向上の必要性
これまでわが国においては、地下水の過剰採取が深刻な地盤沈下を招いた経験から、一
般に地下水は地盤沈下と結びついたイメージが強く定着し、地下水の採取が、採取者の所
有する土地内にとどまらず、広域的な地盤沈下の原因となることについては、共通の理解
が得られていると思われる。
今後、地下水を水資源として管理しながら利用していくにあたって、社会的な合意が必
要な内容(地下水は水資源として、また環境面においてどのような役割を担うべきか、地
下水は平常時・緊急時にそれぞれどの程度利用してよいか、等)を定量化し、その意義の
普及・啓発を図っていく必要がある。
?法制度に関する検討の必要性
現在、わが国では地下水に関する重要な紛争や係争が生じている状況にない。これは、
工業用水法などの個別法や条例の適切な運用に負うところも大きいと考えられる。
しかし、現在も長期的、短期的な地下水をめぐる課題が存在しており、また条例等を施
行する自治体においては、いわゆる反対解釈の問題や強制力の不足による公平性の確保の
困難さ等、施策の実効性不足の声も聞かれている。さらに、地下水に関する社会的合意を
具現化するため、わが国における地下水に関する法制度について、法制化を行うべきかど
うかも含め、検討を行うことも必要と考えられる。
その際、全国一律的な法律と、各地域の特性に応じた条例の関係については、地域によ
る多様性に富むという地下水の特性やこれまでの各地域における取り組みを踏まえつつ、
法の機能と特長をいかに適切に組み合わせていくかが重要な論点となる。
また、国外に目を転じると、EU(欧州連合)では、基本法とも言える水枠組み指令と
これに対応した各国の法律が制定されており、こうした海外の事例も参考にしながら、国
際的な視点に立って、わが国の自然特性や社会の実情に即した法制度のあり方を検討する
必要がある。
「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」報告要旨【平成19年3月】
地下水の特性と保全・利用に係る課題
・水循環系における滞留時間が長い
・涵養に時間がかかるが潜在賦存量は多い
・地下水資源利用の広域定着と安定化
・渇水時の揚水増による地下水位低下
・採取量等のデータ整備と実態把握の遅れ
・地下水の保全・利用に関する全般的取り組みの遅れ
・水収支バランスが保たれる範囲内での利用
・緊急時の応急水源としての利用方策
・広域地盤沈下は沈静化傾向のまま継続・残存
・短期的、集中的な地盤沈下は今後も懸念
・科学的、定量的処理と電子情報化が必要
・社会への啓発と関係者の意識向上
特性課題
・「持続的かつ健全に利用できる循環している地下水」が利用の前提
・一般に、水資源としての地下水は、利用の簡便性、経済性、良質な水質、恒温性を有する
・わが国の水使用量における地下水依存率は約12%
・各種法令による地下水採取規制等により、広域的な地盤沈下は概ね沈静化
・しかし、渇水時には短期的・局所的な地下水位低下、地盤沈下が発生
・一部地域では地下水位上昇により地下構造物への影響が発生
・地下水汚染の多様化
・新たな地下水利用形態(ミネラルウォーター、地下水ビジネス)の拡大
地下水をめぐる現状と最近の動向
?地下水資源マネジメントの推進
・地下水障害を未然に防止し、地下水収支バランスが保たれる範囲内で、持続的な地下水資源の適正利用のあり方とその実現方策を検討し、地下水保全・利用に関する計画を策定・運用する必要がある。
・計画に基づく施策の実施にあたっては、数値シミュレーションモデルの活用により地下水収支を定量化し、実態把握、計画策定、観測・モニタリング、評価・見直しのというプロセスを反復しながら継続的に取り組み、地域の諸条件に即した最適なマネジメントを実現することが重要である。
?地下水資源マネジメントの運用方策
・マネジメントにあたっては、目標とすべき地下水位を定め、地下水位を常時観測していくことにより管理していくことが実用的である。
・マネジメントの推進に必要となるデータを収集するため、観測井戸、観測機器、テレメーターシステム
等の整備が必要である。
?地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項
・水資源の視点からの地下水の水質確保・保全のあり方を検討する必要がある。
・大規模地震災害時における地下水の利用方策を検討する必要がある。
・地下水資源マネジメントの社会的合意形成への取り組みを推進する必要
http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/f_
groundwater/25/houkokusyo.pdf
2009年11月11日
最高濃度検出井戸の汚染原因と対策等
参考資料6 最高濃度検出井戸の汚染原因と対策等
項目調査区分 濃度 (mg/L) 都道府県等 飲用の有無 汚染原因対策等
全シアン 汚染井戸周辺 地区調査 0.10 大阪府 泉佐野市 無 事業場におけるシアンの不適切な管理等によると推定
平成15年度汚染井戸周辺地区調査実施済み。事業場の敷地外へ汚染の広がりがないことを確認済み。井戸所有者に対して
測定結果の通知及び使用方法を指導済み。飲用井戸の所有者に対しては水道水利用を指導済み。事業者に対しては事業
場内における浄化対策(現在検討中)及び継続したモニタリング調査の実施・報告を指導。
概況調査0.11
埼玉県三芳町 無
井戸所有者に対して測定結果の通知及び井戸水の使用方法の指導を実施済み。汚染井戸周辺地区調査では、全ての井戸で不検出。汚染状況の監視を継続。汚染井戸周辺
地区調査
0.041
茨城県千代川村
汚染井戸周辺地区調査では、当該井戸のほか、1井戸で基準を超過したが、計54井戸で不検出。当該地区は、水道給水区
域であり、基準超過井戸所有者には飲用しないよう指導済み。
大阪府高槻市
事業場における鉛の不適切な管理によるものと推定
飲用指導実施済み。事業場が平成11年度から地下水浄化対策を開始、現在も継続中。調査結果は公表済み。汚染状況の
監視を継続。
六価クロム
佐賀県基山町
過去に操業を終了した事業場における六価クロムの不適切な管理によるもの平成3年に汚染が判明し汚染井戸周辺地区調査、周辺住民に対する飲用停止等の指導、上水道への切り替え実施済み。汚染状況の監視を継続。
鉛
兵庫県猪名川町
周辺に飲用井戸がないことを確認済み。井戸所有者に対して測定結果を通知し、使用方法の指導を実施。今後は定期モニ
タリング調査に移行し、汚染状況の監視を継続。
福島県安達町
井戸の所有者に、飲用指導を実施済み。同地区には近々水道が布設される予定。
兵庫県豊岡市
周辺に飲用井戸がないことを確認済み。井戸所有者に対して測定結果を通知し、使用方法の指導を実施。今後も汚染状況
の監視を継続。
総水銀
福岡県春日市
汚染井戸周辺地区調査を実施。当該地区は水道給水区域であり、井戸所有者に対しては、使用方法について指導。又、現
状では飲用利用は無いものの、改めて飲用不可を伝えている。
ジクロロメタン
群馬県万場町
井戸所有者に対しては測定結果を知らせるとともに飲用指導を実施。汚染井戸周辺地区調査では当該井戸を含めすべての
井戸で基準超過はなし。汚染状態の監視を継続。
岐阜県各務原市
井戸所有者に対する飲用指導を実施済み。汚染原因究明調査として汚染井戸周辺地区調査、事業場等調査を実施した
が、原因は不明。汚染状況の監視を継続。
岩手県湯田町
汚染井戸周辺について調査を実施した結果、当該井戸以外からは、汚染は確認されない状況である。汚染井戸の所有者に対しては、飲用しないよう指導するとともに、周辺住民に対して情報提供を行った。今後は、定期モニタリング対象井戸として、継続的に汚染状況を確認することとしている。
福島県三春町
事業場における揮発性有機化合物の過去における不適切な管理によるものと推定住民説明会を開催し、井戸所有者は既に上水道に切替済み。
推定汚染原因者には、浄化対策を指導し、現在実施している。
四塩化炭素
砒素
群馬県万場町
井戸所有者に対しては測定結果を知らせるとともに飲用指導を実施。汚染井戸周辺地区調査では当該井戸を含めすべての
井戸で基準超過はなし。汚染状態の監視を継続。
大阪府高槻市
近隣の事業場における1,2−ジクロロエタンの不適切な管理等によると推定事業者が平成11年より地下水揚水による拡散防止対策を実施、今後も適切な浄化対策の指導及び定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
京都府福知山市
汚染井戸周辺地区調査実施済み。飲用井戸でないことを確認済み。定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
大阪府枚方市
汚染井戸周辺地区調査を実施済み。井戸所有者に対しては使用方法を指導済み。定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
奈良県御所市
汚染井戸周辺地区調査を実施したが全て検出しなかった。また、周辺の事業場調査でも当該物質を使用又は製造している
ものはなかった。飲用やその他の生活用水に使用している井戸ではないが、井戸所有者には注意を促した。今後は定期モニタ
リング調査を実施する予定。
千葉県市川市
近隣の事業所における揮発性有機化合物の過去における不適切な管理によるものと推定汚染井戸周辺地区調査実施。基準超過井戸所有者に対しては、測定結果を通知するとともに飲用指導済み。汚染状況の監視を継続。
秋田県本荘市
事業場における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定 汚染井戸周辺地区調査実施済み。県の指導により、原因者は地下水浄化対策(地下水揚水法)を強化。今後も適切な浄化対策を指導するとともに、定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
1,1,1-トリクロロエタン
大阪府枚方市
汚染井戸周辺地区調査を実施済み。井戸所有者に対しては使用方法を指導済み。定期モニタリング調査による汚染状況の監
視を継続。
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
宮崎県日向市
事業場における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定周辺住民への周知と共に飲用指導実施済み。汚染原因者は、井戸を設置し、地下水浄化対策(地下水揚水法)を実施中。汚染状況の監視を継続。
宮崎県延岡市
事業場における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定周辺住民への周知と共に飲用指導実施済み。汚染原因者は、井戸を設置し、地下水浄化対策(地下水揚水法)を実施中。汚染状況の監視を継続。
埼玉県秩父市
近隣事業所における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定周辺に飲用井戸がないことを確認済み。井戸所有者に対して測定結果の通知及び井戸水の使用方法の指導を実施済み。
汚染源の究明のため、周辺のトリクロロエチレン使用事業所に対して、敷地内の汚染状況調査等の実施及び報告を指導して
いる。汚染状況の監視を継続する。
埼玉県秩父市
近隣事業所における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定 周辺に飲用井戸がないことを確認済み。井戸所有者に対して測定結果の通知及び井戸水の使用方法の指導を実施済み。
汚染源の究明のため、周辺のトリクロロエチレン使用事業所に対して、敷地内の汚染状況調査等の実施及び報告を指導して
いる。
秋田県本荘市
事業場における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定
汚染井戸周辺地区調査実施済み。県の指導により、原因者は地下水浄化対策(地下水揚水法)を強化。今後も適切な浄化
対策を指導するとともに、定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
神奈川県平塚市
当該井戸所有者に対しては測定結果を知らせるとともに地下水の使用方法の指導を実施。汚染井戸周辺地区調査を実施し、検出地点には地下水の使用方法の指導を実施。周辺に汚染源と思われる事業場がないため、監視を継続。
北海道小樽市
平成15年度は定期モニタリング調査を実施し、汚染状況の監視を継続。飲用指導実施済み。周辺に当該物質を使用してい
る特定事業場があるが汚染原因は不明。
福島県須賀川市
事業場における揮発性有機化合物の過去における不適切な管理によるものと推定
井戸所有者に対しては、井戸の使用方法について指導済み。推定汚染原因者に対して浄化対策を指導し、現在実施中。
大阪府八尾市
井戸所有者に対して測定結果の通知及び飲用指導実施済み。引き続き周辺地区調査実施中。
千葉県沼南町
平成5年度の概況調査で、現環境基準(発見当時:旧評価基準)超過を発見及び飲用していない井戸と確認。当該井戸周
辺18本の井戸からは、当該物質は検出されず、また表層汚染調査、テレビカメラによる井戸内部調査でも汚染源は特定でき
なかった。現在まで、当該井戸を含めた地区の水質調査を毎年行っているが当該井戸のみで検出している。
青森県黒石市
井戸所有者に測定結果を通知し、地下水の飲用指導等実施済み。汚染井戸周辺地区調査を実施済み。汚染状況の監視を
継続。
セレン
茨城県日立市
当該地区は、水道給水区域であり、当該井戸所有者には飲用しないよう指導済み。平成15年度から定期モニタリング調査を
実施。
テトラクロロエチレン
ベンゼン
千葉県市川市
井戸所有者に測定結果を通知し、飲用指導の実施済み。市域において汚染地区を定め、汚染状況の監視を継続。
北海道端野町
平成15年度は定期モニタリング調査を実施し、汚染状況の監視を継続。飲用指導実施済み。
茨城県新治村
井戸所有者に測定結果を通知し、地下水を飲用しないよう指導済み。汚染井戸周辺地区調査を実施済み。汚染状況の監視を継続。
広島県広島市
有自然的要因と推定汚染井戸周辺地区調査を実施。飲用指導実施済み。汚染状況の監視を継続。
鳥取県鳥取市
温泉水の混入等の自然的要因の汚染と推定 汚染井戸周辺地区調査実施済み。井戸所有者に対して、測定結果の通知及び飲用指導を実施。
岐阜県土岐市
汚染井戸周辺地区調査、飲用指導実施済み。汚染状況の監視を継続。
千葉県富津市
市役所及び所轄保健所へ通報し飲用指導を行うとともに、汚染井戸周辺地区調査を実施した。しかし、汚染が確認されな
かったことから、当該井戸について県の研究機関で詳細調査を実施した。その結果、上総層群由来のものと推定された。平成
15年度からは当該井戸を定期モニタリング調査の対象とし、汚染状況を継続監視することとした。
鳥取県鳥取市
温泉水の混入等の自然的要因の汚染と推定
汚染井戸周辺地区調査実施済み。井戸所有者に対して、測定結果の通知及び飲用指導を実施。
大阪府泉南市
平成13年度に汚染井戸周辺地区調査を実施済み。汚染状況の監視を継続。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
ふっ素
ほう素
http://www.env.go.jp/water/chikasui/hokoku_h14/ref06.pdf
項目調査区分 濃度 (mg/L) 都道府県等 飲用の有無 汚染原因対策等
全シアン 汚染井戸周辺 地区調査 0.10 大阪府 泉佐野市 無 事業場におけるシアンの不適切な管理等によると推定
平成15年度汚染井戸周辺地区調査実施済み。事業場の敷地外へ汚染の広がりがないことを確認済み。井戸所有者に対して
測定結果の通知及び使用方法を指導済み。飲用井戸の所有者に対しては水道水利用を指導済み。事業者に対しては事業
場内における浄化対策(現在検討中)及び継続したモニタリング調査の実施・報告を指導。
概況調査0.11
埼玉県三芳町 無
井戸所有者に対して測定結果の通知及び井戸水の使用方法の指導を実施済み。汚染井戸周辺地区調査では、全ての井戸で不検出。汚染状況の監視を継続。汚染井戸周辺
地区調査
0.041
茨城県千代川村
汚染井戸周辺地区調査では、当該井戸のほか、1井戸で基準を超過したが、計54井戸で不検出。当該地区は、水道給水区
域であり、基準超過井戸所有者には飲用しないよう指導済み。
大阪府高槻市
事業場における鉛の不適切な管理によるものと推定
飲用指導実施済み。事業場が平成11年度から地下水浄化対策を開始、現在も継続中。調査結果は公表済み。汚染状況の
監視を継続。
六価クロム
佐賀県基山町
過去に操業を終了した事業場における六価クロムの不適切な管理によるもの平成3年に汚染が判明し汚染井戸周辺地区調査、周辺住民に対する飲用停止等の指導、上水道への切り替え実施済み。汚染状況の監視を継続。
鉛
兵庫県猪名川町
周辺に飲用井戸がないことを確認済み。井戸所有者に対して測定結果を通知し、使用方法の指導を実施。今後は定期モニ
タリング調査に移行し、汚染状況の監視を継続。
福島県安達町
井戸の所有者に、飲用指導を実施済み。同地区には近々水道が布設される予定。
兵庫県豊岡市
周辺に飲用井戸がないことを確認済み。井戸所有者に対して測定結果を通知し、使用方法の指導を実施。今後も汚染状況
の監視を継続。
総水銀
福岡県春日市
汚染井戸周辺地区調査を実施。当該地区は水道給水区域であり、井戸所有者に対しては、使用方法について指導。又、現
状では飲用利用は無いものの、改めて飲用不可を伝えている。
ジクロロメタン
群馬県万場町
井戸所有者に対しては測定結果を知らせるとともに飲用指導を実施。汚染井戸周辺地区調査では当該井戸を含めすべての
井戸で基準超過はなし。汚染状態の監視を継続。
岐阜県各務原市
井戸所有者に対する飲用指導を実施済み。汚染原因究明調査として汚染井戸周辺地区調査、事業場等調査を実施した
が、原因は不明。汚染状況の監視を継続。
岩手県湯田町
汚染井戸周辺について調査を実施した結果、当該井戸以外からは、汚染は確認されない状況である。汚染井戸の所有者に対しては、飲用しないよう指導するとともに、周辺住民に対して情報提供を行った。今後は、定期モニタリング対象井戸として、継続的に汚染状況を確認することとしている。
福島県三春町
事業場における揮発性有機化合物の過去における不適切な管理によるものと推定住民説明会を開催し、井戸所有者は既に上水道に切替済み。
推定汚染原因者には、浄化対策を指導し、現在実施している。
四塩化炭素
砒素
群馬県万場町
井戸所有者に対しては測定結果を知らせるとともに飲用指導を実施。汚染井戸周辺地区調査では当該井戸を含めすべての
井戸で基準超過はなし。汚染状態の監視を継続。
大阪府高槻市
近隣の事業場における1,2−ジクロロエタンの不適切な管理等によると推定事業者が平成11年より地下水揚水による拡散防止対策を実施、今後も適切な浄化対策の指導及び定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
京都府福知山市
汚染井戸周辺地区調査実施済み。飲用井戸でないことを確認済み。定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
大阪府枚方市
汚染井戸周辺地区調査を実施済み。井戸所有者に対しては使用方法を指導済み。定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
奈良県御所市
汚染井戸周辺地区調査を実施したが全て検出しなかった。また、周辺の事業場調査でも当該物質を使用又は製造している
ものはなかった。飲用やその他の生活用水に使用している井戸ではないが、井戸所有者には注意を促した。今後は定期モニタ
リング調査を実施する予定。
千葉県市川市
近隣の事業所における揮発性有機化合物の過去における不適切な管理によるものと推定汚染井戸周辺地区調査実施。基準超過井戸所有者に対しては、測定結果を通知するとともに飲用指導済み。汚染状況の監視を継続。
秋田県本荘市
事業場における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定 汚染井戸周辺地区調査実施済み。県の指導により、原因者は地下水浄化対策(地下水揚水法)を強化。今後も適切な浄化対策を指導するとともに、定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
1,1,1-トリクロロエタン
大阪府枚方市
汚染井戸周辺地区調査を実施済み。井戸所有者に対しては使用方法を指導済み。定期モニタリング調査による汚染状況の監
視を継続。
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
宮崎県日向市
事業場における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定周辺住民への周知と共に飲用指導実施済み。汚染原因者は、井戸を設置し、地下水浄化対策(地下水揚水法)を実施中。汚染状況の監視を継続。
宮崎県延岡市
事業場における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定周辺住民への周知と共に飲用指導実施済み。汚染原因者は、井戸を設置し、地下水浄化対策(地下水揚水法)を実施中。汚染状況の監視を継続。
埼玉県秩父市
近隣事業所における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定周辺に飲用井戸がないことを確認済み。井戸所有者に対して測定結果の通知及び井戸水の使用方法の指導を実施済み。
汚染源の究明のため、周辺のトリクロロエチレン使用事業所に対して、敷地内の汚染状況調査等の実施及び報告を指導して
いる。汚染状況の監視を継続する。
埼玉県秩父市
近隣事業所における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定 周辺に飲用井戸がないことを確認済み。井戸所有者に対して測定結果の通知及び井戸水の使用方法の指導を実施済み。
汚染源の究明のため、周辺のトリクロロエチレン使用事業所に対して、敷地内の汚染状況調査等の実施及び報告を指導して
いる。
秋田県本荘市
事業場における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定
汚染井戸周辺地区調査実施済み。県の指導により、原因者は地下水浄化対策(地下水揚水法)を強化。今後も適切な浄化
対策を指導するとともに、定期モニタリング調査による汚染状況の監視を継続。
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
神奈川県平塚市
当該井戸所有者に対しては測定結果を知らせるとともに地下水の使用方法の指導を実施。汚染井戸周辺地区調査を実施し、検出地点には地下水の使用方法の指導を実施。周辺に汚染源と思われる事業場がないため、監視を継続。
北海道小樽市
平成15年度は定期モニタリング調査を実施し、汚染状況の監視を継続。飲用指導実施済み。周辺に当該物質を使用してい
る特定事業場があるが汚染原因は不明。
福島県須賀川市
事業場における揮発性有機化合物の過去における不適切な管理によるものと推定
井戸所有者に対しては、井戸の使用方法について指導済み。推定汚染原因者に対して浄化対策を指導し、現在実施中。
大阪府八尾市
井戸所有者に対して測定結果の通知及び飲用指導実施済み。引き続き周辺地区調査実施中。
千葉県沼南町
平成5年度の概況調査で、現環境基準(発見当時:旧評価基準)超過を発見及び飲用していない井戸と確認。当該井戸周
辺18本の井戸からは、当該物質は検出されず、また表層汚染調査、テレビカメラによる井戸内部調査でも汚染源は特定でき
なかった。現在まで、当該井戸を含めた地区の水質調査を毎年行っているが当該井戸のみで検出している。
青森県黒石市
井戸所有者に測定結果を通知し、地下水の飲用指導等実施済み。汚染井戸周辺地区調査を実施済み。汚染状況の監視を
継続。
セレン
茨城県日立市
当該地区は、水道給水区域であり、当該井戸所有者には飲用しないよう指導済み。平成15年度から定期モニタリング調査を
実施。
テトラクロロエチレン
ベンゼン
千葉県市川市
井戸所有者に測定結果を通知し、飲用指導の実施済み。市域において汚染地区を定め、汚染状況の監視を継続。
北海道端野町
平成15年度は定期モニタリング調査を実施し、汚染状況の監視を継続。飲用指導実施済み。
茨城県新治村
井戸所有者に測定結果を通知し、地下水を飲用しないよう指導済み。汚染井戸周辺地区調査を実施済み。汚染状況の監視を継続。
広島県広島市
有自然的要因と推定汚染井戸周辺地区調査を実施。飲用指導実施済み。汚染状況の監視を継続。
鳥取県鳥取市
温泉水の混入等の自然的要因の汚染と推定 汚染井戸周辺地区調査実施済み。井戸所有者に対して、測定結果の通知及び飲用指導を実施。
岐阜県土岐市
汚染井戸周辺地区調査、飲用指導実施済み。汚染状況の監視を継続。
千葉県富津市
市役所及び所轄保健所へ通報し飲用指導を行うとともに、汚染井戸周辺地区調査を実施した。しかし、汚染が確認されな
かったことから、当該井戸について県の研究機関で詳細調査を実施した。その結果、上総層群由来のものと推定された。平成
15年度からは当該井戸を定期モニタリング調査の対象とし、汚染状況を継続監視することとした。
鳥取県鳥取市
温泉水の混入等の自然的要因の汚染と推定
汚染井戸周辺地区調査実施済み。井戸所有者に対して、測定結果の通知及び飲用指導を実施。
大阪府泉南市
平成13年度に汚染井戸周辺地区調査を実施済み。汚染状況の監視を継続。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
ふっ素
ほう素
http://www.env.go.jp/water/chikasui/hokoku_h14/ref06.pdf
2009年10月19日
工事中 水循環基本法要綱案&政策大綱案 意見募集
水循環基本法要綱案(原案)
前文
水は、「生命」の基本である。地球上の水は、海洋と太陽エネルギーによつて絶えず循環を繰り返し、多様な生命に思恵を与え続けてきた。
現代においては、水循環系は人間の営為によって不断に直接的・問接的に影響を受けるという点で社会的システムであると言えよう。私たちは、地球上に人為的影響を受けない水循県系は最早存在しないことに深く思いを致し、改変された水循環系を持続可能なシステムに再生する努力を払わなければならない。
国上の70パーセントが森林で覆われ水に恵まれたわが国でも、かつての高度経済成長にともなう国上開発と都市化、工業化、さらに生活の利便性の追求による水循環系への直接的影響によって、生態系保全を伴う水循環系は撹乱され、国土保全力を極度に弱めてきた。
地球温暖化は、このような直接的影響と相侯つて水循乗系の大変動を誘発させ、異常な洪水や極端な渇水をもたらし、生命と生活を脅かす。化学物質による水の汚染は、微量であっても食物連鎖・生物濃縮によつて生命の危険を増大させ、とくに胎児への悪影響に警告が発せられている。
日本人が様々な水の脅威を克服し、日本の水を大切にし、日本の水を飲み、日本の水を使うようにするためには、水循環系に影響を与える人間の営為そのものを適正に制御することによつて、撹乱された水循環系を水量、水質、生態系の面から持続可能なシステムに再構築し、健全な水循環型社会を創出して、それを将来世代に継承しなければならない。このため、水循環基本法を制定することにした。
第一 総則・目的
この法律は、健全で持続可能な水循環型社会の形成について基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、水循環総合基本方針の策定その他の水循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、水循環型社会の形成に関する統合的水管理施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、将来の世代に健全な国上を継承することを目的とする。
,定義(注:今後さらに検討を重ねる。必要語句を追加する。)
〈水循環〉
水循環とは、人間の営為の影響を受けつつ地表水及び地下水となり、蒸発し再び降水となり、あるいは地表での滞留や貯留、土壌への浸透など様々な過程を経て絶えず繰り返す水の循県の過程を言う。
〈統合的水管理〉
統合的水管理とは、現在の縦割型水管理を排し、河川流域を一貫した地表水及び地下水の水量管理、水質管理、生態系管理及び水環境管理を統合した総合的な水管理を言う。
〈河川流域〉
河川流域とは、河川及びその集水域を媒介として、森林、農村、都市、海が結ばれたまとまりのある国上の単位を言う。
(水環境〉
統合的水管理によつて形成され、将来の世代に継承され、国民の全てがその思恵を享受する水の環境で、水量、水質、生態系の面から持統可能な水循環系によつてもたらされたものを言う。
第二 基本理念
(1)地表水及び地下水は公共水であること
地表水及び地下水は、共に公共水であり、流域別水循環計画に基づいて統合的に管理されなければならない。
(2)水循環保全義務と水環境享受権
現在の国民は、現在及び将来の国民のために、持続可能な水循環系を保持する義務を担う。現在及び将来の国民は、水量、水質、生態系の面から持続可能な水循環系によつてもたらされる健全な水環境の思恵を享受する基本的権利を有する。
(3)流域圏の統合的管理
水循環管理は、河川流域を原則的単位として統合的かつ地域主権的に行われなければならない。河川流域を構成する地方公共団体は、相互に協力し、河川及び河川流域を上流の森林や農地から河日沿岸域までを含めて統合的かつ地域主権的に管理する主体である「流域連合」を組織しなければならない。ここで、流域圏の範囲については、複数河川流域に亘る広域生活圏においては当該の全河川流域を包含したものとする。
(4)持続可能な水循環型社会の再生と将来世代への継承
持続可能な水循環型社会の形成は、健全な国土とその上に生活する国民の健康で文化的な生活と幸福追求に不可欠である。このため、これを再生し、将来世代に継承しなければならない。
(5)持続可能な水循環系保全のための公平な役割分担
持続的な水循環系の保全のための行動は、国民、事業者、地方公共団体(流域連合)、国等によつて公平な役割分担の下に行われなければならない。
(6)拡大汚染者責任の原則
通常の生活者が処理処分できない有害物質の生産者、通常の生活者の排出する各種の感染症の原因となる病原菌やウイルス、微量な医薬品や有害化学物質を含む排水の処理に当る事業者及び地方公共団体は、汚染防止について第一次的な責任を有する。
(7)未然防止と予防原則
水循環によつて生じる悪影響は、未然に防止されなければならない。このためには、科学的知見の充実を図るとともに、予防原則の適用を躊躇してはならない。
第二 関係者の責務等・国の責務
国は、「第二 基本理念」にのっとり、水循環の道正化に関する基本的かつ総合的な施策の基本方針を策定し、その推進に努める責務を有する。また、流域連合の自主性を尊重することを前提とした上で、流域連合による河川及び河川流域の管理が基本理念に則していないと判断される場合は必要な処置を勧告することができる。
・地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのつとり、国の定める基本方針に基づき、流域連合を組織し、互いに協力して、施策を策定し、及び実施する責務を有する9地方公共団体は、この際、流域内の事業者及び住民の意見を聞かなければならない。
・事業者の責務
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に当つては、水循環系の支障とならないよう必要な措置を講じなければならない。支障が生じた場合は、その責は事業者に帰すものとする。
・国民の責務
国民は、基本理念を共有するとともに、水循環系への支障を防止するため、その日常生活に伴う水循乗系を撹乱する恐れのある負荷の低減に努めなければならない。また、国民は、水循環系の適正化に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する施策の推進に主体的に参加する責務を有する。
・関係者相互の連携及び協力
国、地方公共団体、事業者、国民及び水循環系に関わる非営利公益団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力することに努めなければならない。
このために情報公開の徹底を期すとともに、広く情報が利用されるように広報活動を強化する。
・水循環の日
事業者及び国民の間に広く水循環系の再生と保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に活動を行う意欲を高めるため、O月○ 日を水循環の口とする。
・法制上の措置等
国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならない。さらに国は、縦割の制度と組織を廃し、水循環系の道正化に関する施策を実施するため必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講じなければならない。また、地方公共団体においても縦割の制度と組織を廃するために必要な措置を行わなければならない。
・年次報告等
政府は、毎年、国会に基本方針の実施状況を報告し、その促進に必要な措置を明らかにした文書を提出しなければならない。また、国会に報告した内容及び提出した文書を公表する。
第四 基本方針口基本計画等
・水循環総合基本方針
国は、基本理念に基づき「第五基本的施策」の基礎となり、流域連合が策定する「流域別水循環計画」の前提となる基本方針を策定し、流域連合が円滑に実施できるよう支援・調整しなければならない。
基本方針には、基本的施策の推進に関する方針その他の必要な事項を定め、閣議の決定を求め、決定後遅滞無く公表するとともに国会に報告するものとする。
,流域別水循環計画
「流域連合」は、国の基本方針に基づき、河川流域毎に水循環アセスメントを行い、流域別水循環計画を当該流域に適合した最上位計画として策定する。
計画の策定から決定までのプロセスは、下記の通りである。
流域を構成する地方公共団体によつて結成された「流域連合」が「流域水循環審議会」に計画策定を諮問する。計画策定に当つては、流域住民の意見を聞き、誠実に対応しなければならない。流域連合は、答申された計画案を「流域連合議会」に諮り、議決を得て決定する。
第五 基本的施策
国は、下記の基本的施策に関する基本方針を示し、河川流域を構成する地方公共団体は、流域連合を結成し、流域別水循環計画に基づいてこれらの基本的施策を講じるものとする。
(1)流域治水対策の推進
想定した規模の洪水をダム等洪水調節施設と河道で処理するという従来の治水から、森林や農地による保水、流域による貯留、土地利用に応じた浸水の受け入れによる洪水氾濫の分散、河川、下水道、農業用水路等の一体的整備等、河川流域全体で洪水対策を行う流域治水へと転換する。
このため、河川法で想定されている基本高水流量等の設定に基づく治水計画を根本的に見直す。 流域治水へ転換することによつて、河川堤防のかさ上げとダム建設への過度な依存体制が克服でき、今後は、緑のダムとしての森林の持つ保水機能や土砂流出防止機能の活用、保水型・耐水型都市の再生、公園緑地や田畑の持つ遊水機能の活用、さらに雨水の地下浸透、滞留や貯留の計画的推進、水と緑の豊かなネットワーク都市の再生を進めることになる。
流域治水の推進のためには、浸水危険区域、遊水可能区域、水と緑の酒養区域などの土地利用計画を公表し、農業政策や都市計画とあいまった土地利用の適正な規制と誘導を図ることが不可欠になる。国民ひとリー人がこうして、流域治水に参加することになる。
(2)水環境管理の道正化及び水循環系の再生と保全
水環境管理の要諦は、河川管理と水環境管理の統合及びこれに伴う水環境基準と排水基準の適正化の推進である。これまでの縦割制度の下で達成されなかった両者の統合と諸基準の全面的改正を進め、同時に多様な生物の棲息・生育環境の再生・保全やギ硼十1の自然回帰と復元、環境用水の確保とその維持を図る。
さらに水循兵系の再生と地下水の保全のために、雨水の浸透・貯留機能の保全・回復あるいは雨水の利用を進める。何人も、水循環を妨げ、雨水の地下浸透を阻害する行為を行つてはならず、このために適切な土地不1用規制を図る。
(3)第二者機関による公正な水環境監視
縦割の所管部門がそれぞれ水質監視を行うこれまでの監視体制から脱却し、公正な第二者機関が排水源の放流水質及び受容水域の水環境の諸側面(水量、水質、生態系など)を監視する。
この第二者機関が違反者に対する是正勧告権を持つと同時に、法的な処置を講じることを可能にする。
(4)利水システムの合理化の促進
過剰な水利用を誘発したこれまでの利水システムを改め、節水型都市及び産業の創出に努め、新規水資源開発の抑制に向けた構造転換を図る。さらに、農業用水を含めた水利用合理化総合計画の策定、水利権転用(工業用水、農業用水)、水融通の促進、水利用量削減目標設定、水利権システムの整備(譲渡契約の認可主体=流域連合)などを進める。さらに、利水システムの一環として、 雨水利用及び下水処理水の再利用等の促進を図る。
(5)地下水の保全と利用の適正化の推進
地下水の保全と利用の適正化を図るため、同一地下水盆における地下水情報の共有化、モニタリング体制、緊急時体制を整備すると共に、地下水の涵養と保全のため、都市の公園や緑地、農地や森林などを有効に活用する。地方公共団体は、条例の定めるところにより、地下水利用適正化計画の策定、地下水酒養区域及び地下水汚染防止区域の設定並びに地下水採取料の徴収を行うことができる。
(6)河川と森林との統合管理の推進
河川管理と森林管理の統合は、水循環系の健全化の視点から極めて重要である。両者の統合によつて、放置林による山地災害や洪水時の大量の流木流出による被害拡大の防止対策を推進する。
また、地球温暖化は水循県系を撹乱させる元凶であるため、二酸化炭素吸収源としての森林の役割その他の森林の多面的機能を維持拡大させる措置を講じる。これらの対策を進めるために森林の所有者以外の者が管理行為を行うことが出来るようにし、併せて所得補償制度を導入する。
また、水源地域の土地の外国資本に封する売却を禁止する処置を採る。
(7)農地の保全と活用
農地を遊水地として保全し、冠水補償を実施する。体耕農地に湛水し、地下水の涵養及び生物多様性保全のためのビオトープとして活用することについて一定の補償を実施する。
(8)水道及び水循宋保全施設の流域圏統合経営の推進
水道及び下水道・浄化槽・し尿処理施設等の水循環保全施設は、排水源におけるきめ細かな対応とともに、流域圏ベースの広域経営を可能にすることによって経営の合理化とサービス水準の向上を図るとともに、処理水準の高度化を推進し、水環境の更なる清浄を確保する。このため、本来同一の機能を果す下水道、浄化槽、し尿処理等の施設は、一体的に整備と管理を進める。
さらに、これらの施設は、流域住民全ての生活に不可欠な社会的共通資本であることに鑑み、社会的事業としてその設置から維持管理までを含め、一貫した経営の合理化を進める。
(9)老朽化施設の更新と機能の向上並びに異常渇水や震災などに備える非常時対応
戦後60数年、経済復興期、高度経済成長期、安定成長期を通じて莫大な公共投資が進められた結果、治水施設、水資源施設、水道施設及び水循環保全施設等の社会的ストックは膨大な資産となって現在それなりに役割を果している。
今後は、これらの資産の更新と機能の向上が大きな課題となるため、アセットアセスメントを進め、合理的な更新と機能の向上に努める。
さらに、今後予想される異常な渇水や大震災に対応する非常時の水供給、水環境保全対策、環境衛生対策
を進める。
(10)財政制度の見直し
国は、従来の財政処置の方式を抜本的に再検討し、流域連合の創設及び同連合による事業の円滑な推進が可能なように地方公共団体とも協議しつつ、財政制度を再構築する。
流域連合の財源は、分担金、賦課金、課徴金、原因者負担金、水循環目的税、地下水使用料等で構成される。
(11)科学技術の振興及び国際協調の推進
水循環の適正化という視点での技術開発は、ハード、ソフト両面で研究課題が山積している。 縦割体制の下では、技術体系も歪みを生じ、合理性を欠く結果となる。今後は横につながる適正技術が志向される。国際援助においてもかかる技術が望まれるが、この面ではわが国は後進的と言える。
また、後発開発途上国の支援体制を抜本的に見直し、強化する。
第六 中央政府の行政組織及びその再編整備
・中央政府の行政組織
(案1)水循環庁の設置
内閣府の外局として水循環庁を設置し、水循環に関わる全ての行政組織を統合する。(水循環庁設置法を新たに制定)
水循環庁は、基本理念にのっとり、水循環社会の実現に向けて基本的施策の推進のための全ての事務を所掌する。水循環庁は、この任務の達成のため、水循環に関わる現行の個別制度の全てを所管し、統合的水管理体制に移行させる。
ただし、「水循環庁」は、将来の道州制の導入も踏まえ、全国的視野で行うことが求められる政策の企画、調整等に権限を限定し、政策の実施権限の多くを広域連合である「流域連合」に委譲することとする。
(問題点)
・関係各省庁及び族議員の抵抗が予想される。
・抜本的な行政改革になるので、実現可能性を危惧し、消極に流れる恐れがある。
(案2)水循環社会推進委員会の設置
内閣府の外局として、独立した行政委員会を設置し、水循環に関わる基本的な行政を所掌させる。(水循環社会推進委員会設置法を新たに
中央政府に於ける水行政の権能を大胆に簡素化させ、中央政府に残される基本的権限のみを所掌する体制を想定した場合、独立行政委員会の設置は適切であると考えられる。なお、委員長及び委員の人事を国会の承認案件とすることで、独立性を保持するものとする。
(問題点)基本的に(案1)と同じ。
道州制が導入された場合、中央政府が所掌する行政権能の範囲
(注)現行法制上、独立行政委員会は、内閣から一定の独立性の確保が求められる行政事務を処理する場合に設置されている。大臣の分担管理の原則(国家行政組織法第5条、内閣法第3条)に鑑み、水管理行政がこれになじむか否かという問題がある。
(案3)水循環政策本部の設置
水循環政策を推進するため、内閣府に水循秦政策本部を設置する。(内閣府設置法の改正)本部は、水循環政策の推進に関する基本方針の作成及びその実施に関すること、関係行政機関の総合調整にかんすること、その他水循環施策で重要なものの企画、立案及び総合調整に当る。
(問題点)
・縦割制度・体制の打破に限界がある。(現行の制度、組織がそのまま残る)
・結果的に関係各省の出向者によつて組織され、現状と変わらない。
・道州制が導入された場合でも縦割制度と体制とが温存される可能性が高い。
・中央水循環審議会
上記組織とは別に、本法に基づく水循環政策の基本方針の審議、水循環政策の進捗状況その他基本的事項を調査審議するために中央水循環審議会を設置する。なお、審議会は、学識経験者及び国民の代表によつて構成される。(設置法による規定が必要)
第七 「流城連合」の設置等、地方公共団体の行政組織及びその再編整備
・流域連合
河川流域を構成する地方公共団体(市町村と都道府県)は、基本理念に基づき水循環政策を推進するため、河川流域の統合的管理主体(地方公共団体の連合組織)である流域連合を設置しなければならない。(注)中央政府の出先地方組織は廃止される。
国は、速やかに流域連合を結成するよう、関係する地方公共団体に勧告することができる。
・流域連合議会
流域連合に関わる立法機関として予算、組織、人事などに関わる諸議案を議決し、流域水循環条例その他の諸規定を制定するため、地方公共団体及び流域住民代表で構成される流域連合議会を設ける。
・流域水循環審議会
水循環アセスメント、流域別水循環計画の調査審議、流域連合の水循環政策の進捗状況のチェックや各種の勧告を行うため、流域連合に諮問機関として流域水循環審議会を設ける。
・流域連合監理・監査
流域連合及び同議会の業務監理に当る組織として、地方公共団体代表者及び流域住民代表者で構成される流域連合監査機構を設ける。同監査機構は、業務監査、情報公開、住民の苦情対応等にも対応するものとする。
第八 流増住民との協働・流域住民との協働体制/・情報公開と監査への参加
行政と流域住民ネットワークは、連携・協働して政策形成を行うことが望まれる。このため、両者のパートナーシップによる協働体制を倉J出し、地域ガバナンスを確立することが必要であり、水の公共性、コモンズとしての性格及びオーフス条約等を考えれば、当然の措置でもある。
このため、流域水循環審議会、流域連合議会、流域連合監査機構には、一定割合の流域住民代表者の参加が前提条件となる。なお、現行河川法に基づく淀川流域委員会は、8月3日をもつて機能停止した。これは、現行河川法の住民参加規定(河川法第16条の2)の曖昧さ(住民の意見聴取の実施の有無、方法等については河川管理者の裁量に委ねていること)に起因するものである。
第九 雑則
・原状回復命令等
水循乗に悪影響を及ばす行為により、現実に支障が生じた場合、原因者の負担において支障の回復・軽減の措置を講じることを命令し、命令の牌怠、不履行に対しては間接強制、汚染者負担の原則の適用を可能とする制度を設ける。
第十 付則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、流域連合など第七、第人に関わる規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行する。
http://mizuseidokaikaku.com/report/report17_tenpu6.pdf
水循環政策大綱案(原案)
1.水循環型社会の再生と将来世代への継承
水は、「生命」の基本である。地球上の水は、海洋と太陽エネルギーによつて絶えず循環を繰り返えし、多様な生命に恩恵を与え続けてきた。
現代においては、水循環系は人間の営為によつて不断に直接的・聞接的に影響を受けているという点で社会的システムであると言えよう。私たちは、地球上に人為的影響を受けない水循環系は最早存在しないことに深く思いを致し、改変された水循環系を持続可能なシステムに再生する努力を払わなければならない。
国上の70パーセントが森林で覆われ水に恵まれたわが国でも、かつての高度経済成長に伴う国上開発、都市化、工業化、さらに生活の利便性の追求による水循環系への直接的影響によつて、生態系保全を伴う水循環系は撹乱され、国土保全力を極度に弱めてきた。
地球温暖化は、このような直接的影響と相侯って水循環系の大変動を誘発させ、異常な洪水や極端な渇水をもたらし、生命と生活を脅かす。化学物質による水の汚染は、微量であつても食物連鎖・生物濃縮によつて生命の危険を増大させ、とくに胎児への悪影響に警告が発せられている。
日本人が様々な水の脅威を克服し、日本の水を大切にし、日本の水を飲み、日本の水を使うようにするためには、水循環系に悪影響を与える人間の営為そのものを適正に制御することによつて、境乱された水循環系を水量、水質、生態系の面から持続可能なシステムに再構築し、健全な水循環型社会の創出を期さなければならない。そこで、水循環系の統合的管理体制を構築し、持統可能な水循兵型社会を創出して、それを将来世代に継承するために水循秦政策大綱を定める。
2.水循環基本法の制定
(1)水循環政策の基本理念
水は、生命の根源であるにもかかわらず、河川等の公共水域の表流水のみを公水とし、その他の水は土地に付随した水として私水と位置づけられてきた。さらに水は、様々な管理者の下で局時的局所的な個別管理に委ねられてきた。河川水が公水であると位置づけられていても、あたかも河サII管理者の私物であるかのように扱われ、そこには国民の姿が全く見えない。 水循環系が歪められ、寸断され、破綻した理由は、一にかかる制度にあつた。
水は、地表水も地下水も水循環系によつて結ばれた一体の存在であり、生命の根源であるという意味において、現在と将来の人々の生存に不可欠な共同資源である。このような水は、水循環系の全ての過程を一体として統合的に管理されなければならない。 全ての人々は、このために水循環系を守る義務を担うべきものである。
この視点に立ち、水循環政策の基本理念は、次の七つの原則的な考え方で構成される。
(1)地表水及び地下水は公共水であること
地表水及び地下水は、共に公共水であり、統合的に管理されなければならない。
(2)水循環保全義務と水環境享受権
現在の国民は、現在及び将来の国民のために、持続可能な水循環系を保持する義務を担う。現在及び将来の国民は、持統可能な水循環系によつてもたらされる健全な水環境の恩恵を享受する基本的権利を有する。
(3)流域圏の統合的管理
水管理は、河)「1流域を原則的単位として統合的かつ地域主権的に行われなければならない。河川流域を構成する地方公共団体は、相互に協力し、河川及び河川流域を上流の森林や農地から河口沿岸域までを含めて統合的かつ地域主権的に管理する主体である「流域連合」を組織しなければならない。
(4)持統可能な水循環型社会の再生と将来世代への継承
持続可能な水循秦型社会の形成は、健全な国土とその上に生活する国民の健康で文化的な生活と幸福の追求に不可欠である。このため、これを再生し、将来世代に継承しなければならない。
(5)持続可能な水循環系保全のための公平な役割分担
持続的な水循環系の保全のための行動は、国民、事業者、地方公共団体(流域連合)、国等によつて、公平な役割分担の下に行われなければならない。
(6)拡大汚染者責任の原則
通常の生活者が処理できない有害物質の生産者、通常の生活者の排出する病原菌やタイルス、微量な医薬品や有害化学物質を含む排水の処理に当る事業者及び地方公共団体は、一次的汚染防止責任を負う。
(7)未然防止と予防原則
水循乗によつて生じる悪影響は、未然に防止されなければならない。このためには、科学的知見の充実を図るとともに、予防原則の適用を躊踏してはならない。
(2)水循環墓本法の制定
わが国の水行政は、これまで経済成長や生活の利便性の向上という観点に立って、水循環系の部分毎に異なる事業制度と組織体制の下で対症療法的に進められて来た。このため、もつばら個別的事業法が存在するのみで、前項の基本理念を定めた基本法は制定されていない。
そこで、水循環基本法を制定し、健全で持続可能な水循環型社会の形成について基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の水循環
型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、統合的水管理施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、将来の世代に健全な国上を継承する制度的処置を講じるものである。
(3〕水循環に関する主要施策
国は、下記の基本的施策に関する基本方針を示し、河川流域を構成する地方公共団体は、流域連合を結成し、流域別水循環計画に基づいてこれらの基本的施策を講じるものとする。
(1)流域治水対策の推進
想定した規模の洪水をダム等洪水調節施設と河道で処理するという従来の治水から、河川流域全体で洪水対策を行う流域治水へと転換する。流域治水の推進のためには、浸水危険区域、遊水可能区域、水と緑の涵養区域などの土地利用計画を公表し、土地利用の適正な規制と誘導を図ることが不可欠になる。
国民ひとリー人がこうして、流域治水に参加することになる。
(2)水環境管理の適正化及び水循環系の再生と保全
水環境管理の要諦は、河川管理と水環境管理の統合及びこれに伴う水環境基準と排水基準の適正化の推進である。同時に多様な生物の棲息・生育環境の再生・保全や河川の自然回帰と復元、環境用水の確保とその維持を図る。さらに水循環系の再生と地下水の保全のために、雨水の浸透・貯留機能の保全・回復あるいは雨水の利用を進める。
(3)第二者機関による公正な水環境監視
縦割の所管部門がそれぞれ水質監視を行うこれまでの監視体制から脱却し、公正な第二者機関が排水源の放流水質及び受容水域の水環境の諸側面(水量、水質、生態系など)を監視する。
(4)利水システムの合理化の促進
過剰な水利用を誘発したこれまでの利水システムを改め、節水型都市及び産業の倉J出????に努め、新規水資源開発の抑制に向けた構造転換を図る。
(5)地下水の保全と利用の適正化の推進
地下水の保全と利用の適正化を図るため、同一地下水盆における地下水情報の共有化、モニタリング体制、緊急時体制を整備すると共に、地下水の涵養と保全の対策を進める。
地方公共団体は、条例の定めるところにより、地下水涵養区域の設定、地下水利用適正化計画の策定及び地下水汚染防止区域の設定を行うことができる。また、条例の定めるところにより、地下水採取料を徴収することができる。
(6)河川と森林との統合管理の推進
河川管理と森林管理の統合によつて、放置林による山地災害や洪水時の大量の流木流出による被害拡大の防止対策を推進する。また地球温暖化は水循環系を撹乱させる元凶であるため、二酸化炭素吸収源としての森林の役割その他の森林の多面的機能を維持拡大させる措置を講じる。
(7)農地の保全と活用
農地を遊水地として保全し、冠水補償を実施する。休耕農地に湛水し、地下水の涵養及び生物多様性保全のためのビオトープとして活用することについて一定の補償を実施する。
(8)水道及び水循環保全施設の流域圏統合経営の推進
水道及び下水道・浄化槽。し尿処理施設等の水循環保全施設は、流域圏ベースの広域経営を可能にすることによつて経営の合理化とサービスの向上を図るとともに、処理水準の高度化を推進し、水環境の更なる清浄を確保する。
(9)老朽化施設の更新と機能の向上並びに異常渇水や震災などに備える非常時対応
戦後60数年を通じて莫大な公共投資が進められた。今後は、これらの資産の更新と機能の向上が大きな課題となるため、アセットアセスメントを進め、合理的な更新と機能の向上に努める。
(10)財政制度の見直し ・
国は、従来の財政処置の方式を抜本的に再検討し、事業の円滑な推進が可能なように地方公共団体とも協議しつつ、財政制度を再構築する。流域連合の財源は、分担金、賦課金、課徴金、原因者負担金、水循環目的税、地下水使用料等で構成される。
(11)科学技術の振興及び国際協調の推進
縦割体制の下では、技術体系も歪みを生じ、合理性を欠く結果となっている。今後は横につながる道正代誉技術が志向される。また、後発開発途上国の支援を抜本的に見直し、強化する。
3.山紫水明の国づくり〜行政組織の再編と流域住民との協働
水循環系を再生し、山紫水明の国づくりを推進するためには、前述の基本理念に則り、これまでの制度と組織を抜本的に改革し、中央政府の権限を大幅に地方政府に委譲するとともに、地方公共団体を越えた河川流域ベースの体制に構築し直さなければならない。さらに、水が国民ひとリー人の生命の源であり、国民の共同資源としての公共水であるという視点から、流域住民が水循環に関わる様々な意思決定に参画するシステムの構築もまた必要不可欠であり、勇断を持って
推進しなければならない。
(1)中央政府の行政組織の再編
改革案としては、三案が考えられる。
[案1]
水循環庁の創設は、最も適切であろう。内閣府の外局として水循環庁を創設すれば、水行政に関わる全ての行政部門を一挙に統合し、整理合理化を断行できる。なお、この場合においても、「水循環庁」は、全国的視点で行うことが求められる政策の企画、調整等に権限を限定し、Я在???、国土交通省その他の省庁が有している権限の多くを「流域連合」に委譲するものとする。
道州制を早期に導入する場合は、道州を超える問題や道州間の調整など限られた重要課題に対
応する
[案2]水循環委員会の設置が考えられる。委員会は独立行政委員会であるが、この場合も[案1]と同じように内閣府の外局となる。委員長などの人事を国会の議決事案とすることで独立性を確保させたい。
(ただし、[案2]には現行法制上、国家行政組織法第3条に基づく委員会が現在の大臣の分担管理原則(国家行政組織法第5条、内閣法第3条)に鑑み、水管理行政になじむか否かの問題が残る。消費者庁の設置に際しても、中立性を確保する行政委員会型組織が遡上に上ったが、最終的に「消費者庁及び消費者委員会」が設けられた。)
[案3]
水循環政策本部の設置は、現段階では現実的と考えられなくも無い。海洋行政分野に有力な事例があるが、水循環行政においては内容的に曖味で、行政改革につながらないと考える。
なお、上記組織とは別に、本法に基づく水循環政策の基本方針の審議、水循環政策の進捗状況その他基本的事項を調査審議するために中央水循兵審議会を設置する。
(2)「流域連合」の設置等、地方公共団体の行政組織の再編
水循環系の保全は、基本理念に基づき流域を一貫して、流域住民に近い所で、流域住民の参加を得て推進すべきである。個々の地方公共団体が個別に行う従来の体制を脱し、流域圏をベースに推進できる行政組織に再構築するため、国は流域連合、同議会の創設を推進するとともに、国の権限を大幅に流域連合に移管する。なお、学識経験者や流域住民の意見を反映させるため、流域水循環審議会を設け、さらに事業推進の透明性を確保するため、流域連合監査機構を設ける。.
[流域連合]
河川流域を構成する地方公共団体(市町村と都道府県)は、基本理念に基づき水循環政策を推進するため、流域圏の統合的管理主体(地方公共団体の連合組織)である流域連合(地方自治法上の広域連合)を設置しなければならない。(注)中央政府の出先地方組織は廃止される。
[流域連合議会]
流域連合に関わる立法機関として予算、組織、人事などに関わる諸議案を議決し、流域水循環条例その他の諸規定を制定するため、地方公共団体及び流域住民代表で構成される流域連合議会を設ける。
[流域水循環審議会]
水循環アセスメント、流域別水循環計画の調査審議、流域連合の水循環政策の進捗状況のチ
ェックや各種の勧告を行うため、流域連合に諮問機関として流域水循環審議会を設ける。
[流域連合監査機構]
流域連合及び同議会の業務監理に当る組織として、地方公共団体代表者及び流域住民代表者
で構成される流域連合監査機構を設ける。同監査機構は、業務監査、情報公開、住民の苦情対応
等にも対応するものとする。
(3)流域住民との協働体制
行政と流域住民ネットワークとが連携,協働して政策形成を行うことが望まれる。このため、両者のパートナーシンプによる協働体制を創出し、地域ガバナンスを確立することが必要である。
水の公共性、コモンズとしての性格及びオーフス条約等を考えれば、当然の措置でもある。このため、流域水循環審議会、流域連合議会、流域連合監査機構には、一定割合の流域住民代表者の参加が前提条件となる。なお、現行河川法に基づく淀川流域委員会は、8月3日をもつて機能停止した。これは、現行河川法の住民参加規定(河川法第16条の2)の曖味さ(住民意見聴取の実施の有無、方法等については河川管理者の裁量に委ねていること)に起因するものである
http://mizuseidokaikaku.com/report/report17_tenpu5.pdf
水循環政策大綱案(原案)と基本法要綱案(原案)にご意見をお寄せください
(2009年10月14日)
水循環基本法研究会の第10回会合(2009年10月9日開催)において、起草委員会でまとめた 「水循環政策大綱案(原案)」と 「水循環基本法要綱案(原案)」を提案いたしました。10月22日まで両原案に対する修正意見をお受けしております。下記2点についてご意見をおまとめいただき、文書にてお送りいただけますようお願いいたします。こちらの回答用紙をご利用ください。
【第1点】
水循環基本法要綱案(原案)の「第六 中央政府の行政組織及びその再編整備―中央政府の行政組織」(6ページ目)において示している3つの案について、どれが適当と考えますか。その理由は何ですか。また、別案がありましたらお示しください。
(案1)
内閣府の外局として水循環庁を設置し、水循環に関わるすべての行政組織を統合する
(案2)
内閣府の外局として、独立した行政委員会(水循環社会推進委員会)を設置し、水循環に関わる基本的な行政を掌握させる
(案3)
水循環政策を推進するため、内閣府に水循環政策本部を設置する
【第2点】
原案に対する修正意見について、該当個所とその対案及び理由をお示しください。
●メールの送付先 qqyg4fv9k★peace.ocn.ne.jp(★印を@に変えてお送りください)
●Faxの送付先 075-722-5295
http://mizuseidokaikaku.com/report/report18.html
ATCグリーンエコプラザセミナーレポート 世界の水問題と日本
■講師
東京大学 生産技術研究所 教授 沖大幹氏
はじめに
世界の水問題は、大きく3種類に分けられます。安全な飲み水(indispensable water)、農業生産、工業生産の水(profitable water)最後に、人と生態系を維持するため、快適に生きるための水(comfortable water)です。1km以内に、1日1人当たり20リットルの水が得られることが、安全な飲み水へのアクセスがあることを意味しますが、世界人口の5分の1は、それがなく、水の確保のためだけに毎日の貴重な時間を費やしています。
これらの3種類の水問題は、質・量も異なれば、貨幣価値も違います。水の様々な側面で懸念事項があるということをお伝えしなければなりません。
農業・工業生産のための水は、今後使用が増えることが懸念されており、地球温暖化が進まなくとも、都市化の進展と人口集中により、洪水・渇水被害は深刻化するでしょう。さらに、数十年後には、水問題は国際的紛争の引き金になるという研究者もいます。
ではまず、水資源は循環資源で、地球上には水がふんだんにあるのに、どうして水不足が生じるのかということをおさらいしましょう。
地球上の水に対して、淡水の占める割合は水全体の約2.5%にすぎず、中でも地下水、氷河などを除いた水資源として利用しやすい淡水は約0.02%しかないため、水不足が生じると説明されることがありますが、そうではありません。
水資源は、ストックではなくフローだと考えるべきです。ある瞬間、世界中の河川の水の総量は、2000 km?に対して、人間が年間使う水は4000 km?だから足りない、という比較の仕方は間違っています。実際は、陸から海へ流れる水の流量の合計は、年間約4万km?。その水循環の一部が、人間の社会の中を通っていると考えなければなりません。では、年間流量のうち、人間が使うのはたったの約10%だから水不足になるわけがないかというと、それも誤りです。
数値モデルによる世界の河川の日流量シミュレーション結果によると、水は、地理的、時間的に偏在することがわかります。極地や、熱帯雨林地帯は年中湿潤なのに対し、砂漠は常に乾燥しており、一方でモンスーン地帯は雨季・乾季で、流量に大きな差があります。全世界の年間流量が足りているからといって、個々の場所で足りているとは限らないのです。
物質の重さ当たりの単価と市場規模について比較してみると、水は、廃品回収の古紙よりもはるかに単価が安いことがわかります。ちなみにミネラルウォーターは嗜好品で、清涼飲料水と同じと考えられるためいわゆる水問題とは切り離して考えるべきでしょう。
ミネラルウォーターは500mlで150円、1m?で30万円ですが、水道水は、1m?で140円〜400円です。都民の水瓶として知られる、奥多摩の小河内ダムの貯水容量1.85億m?の水は、約300億円に相当します。しかし、それは、金塊にすると、たった1m?に過ぎません。つまり、水資源は安くてかさばり、かつ大量に必要なものであり、必要なときに必要な場所、必要な質の水資源がないと、貯蔵、輸送コストが相対的に高すぎて経済的に引き合いません。
21世紀における世界の水資源アセスメント
21世紀の人口増加と経済発展による水需要の変化と、気候変動による水資源賦在量の変化、つまり温暖化による気候変動で使用できる水の量がどう変化するかについて、IPCCで使用しているSRESシナリオに沿って推計した結果をお話したいと思います。
Aは経済行動成長を重視したシナリオ、Bが環境保全を重視したシナリオ。かつ、1はグローバリゼーションが進んだ場合、2は地域化が進んだ場合、という4通りの組み合わせのシナリオで将来推計を行いました。
まず人口の将来展望について、もっとも高くなるのはA2、つまり各地域が交流なく経済発展を目指すと、もっとも人口が増加します。A1B1は共通のカーブを描き、世界的に価値観や技術移転が共通して進む場合、人口は2050年をピークに減少します。地域化、および環境保全重視型のB2シナリオは、人口は増加しますが、指数関数的に増えるわけではなく、ある程度で増加スピードは落ち着くという結果となっています。
このように最近の推計では、人口は増え続けるわけではないというのが一般的になりつつあり、今世紀中に来るであろう環境負荷のピークを乗り切れば、持続可能社会も作れるのではないかと考えています。
次に世界の食料生産と供給についてですが、1960年から2004年の間に、人口は約2倍に増えましたが、その間、農地の面積はわずか10%増に留まっています。しかし、緑の革命と言われる農業分野の技術の発展と、大量の水の使用により、単位面積あたりの収穫量は2.3倍となり、一日一人あたりの摂取カロリーは25%増えています。しかし、そんな中でも現在8億人は飢餓に苦しんでいると言われています。これも水と同様に、物理的な量の問題ではなく、社会における分配の問題でしょう。
工業用水取水量と工業分野のGDPとの関係は、大体線形関係にあります。しかし日本は海外諸国よりも格段に低い取水量を保っており、工業用水の約80%を再生利用しています。
“将来工業用水量”は、“現在工業用水量”*“工業規模増加率”*“用水効率改善係数”により求められます。中国など途上国の工業規模増加は今後も見込まれるため、工業用水の再利用による用水効率改善係数により、将来の工業用水量は大幅に変わってくることが予想されます。
水需要の話をしてきましたが、では、水の供給はどう変化するのでしょうか?これは温暖化の予測となります。
地球温暖化とは気候が変動するということであり、単純に気温が上がるだけでなく、気圧配置が変わり、雨の降り方が変わります。気温上昇による影響と、気候変動による水循環の変化は分けて考える必要があります。
まず温度上昇の直接的影響には、氷河・氷床の融解に伴う流量の一時的増加があります。一見流量が増えていても、それは氷河という水資源の貯金をとりくずしているにすぎず、今世紀末にはやがてなくなって必ず減少します。人間の生活にとっては、流量の一次的な増加ではなく、普段の流量が大切です。氷河がなくなれば、雨が降ったときと、降っていないときの流量の差が非常に大きくなり、ダムを作らなければ、全世界人口の6分の1が深刻な影響を受けると言われています。同時に、水温上昇により水質も変わり、生態系も大きな影響を受けるでしょう。
次に、雨の降り方が変わることによる間接的影響としては、極域と湿潤地帯での水資源の増加、熱帯・亜熱帯乾燥域で減少が予測されています。つまり乾燥域での旱魃地帯がさらに広がり、湿潤地帯においては激しい降水による洪水リスクが増大します。
私は、IPCC第4次報告書第2作業部会、影響評価を調査するグループに参加していました。ほとんどが欧米系なので、水不足の話が中心になりますが、仮にアジアの人がいれば、洪水の話ももっと前面に出ていたと思います。
さらに国交省が行った日本の気候変動予測によると、温暖化が進んだ100年後、雪が雨として降るため、冬の間の河川流出量が増え、同時に雪解けが早まるため、本来、ダム貯水量が満水になるべき代かき期などの需要期に、流量が不足してしまう恐れがあります。
21世紀における深刻な水ストレス下の人口予測のシミュレーションを、先ほどと同様のSRESシナリオで行いました。ここでの水ストレスのある人とは、年によっては渇水で困窮したり、食物生産が落ちて影響を受ける可能性がある状態にある人ということでお考えください。2050年までは、どのシナリオでも水ストレス人口は増えます。しかしそれ以降、A2(経済行動成長重視・地域化)はさらに増えますが、A1、B1では横ばい、あるいは減るという結果になりました。つまり、今後どのような社会になるかによって、必ずしも悲観的な未来ばかりではないと考えられるでしょう。
IPCCでは、prediction(予測)という言葉は使わないように心がけています。人間の力が及ばない天気などの予報とは違い、50年、100年後の未来は、人間社会が今後どの程度温室効果ガスを排出するかという緩和策や、気候変動の悪影響を最小限にしようとする適応策にどの程度取り組むかにより変わります。私たちが行っているのは、ある仮定の下の計算に過ぎません。これらのシミュレーションから、環境配慮型の社会に変えていくことによって、水に困らない社会が出来るということを示すことができればと思います。
将来展望まとめ
21世紀における水需給において、温暖化の影響による逼迫が予想されるのは、地中海沿岸ヨーロッパ、アメリカ西部です。しかしこの地域は、おそらく適応策を講じることができるため、あまり心配の必要はないでしょう。一方、中近東、西・南アジア地域は、社会経済変化、特に経済発展と人口増により逼迫の恐れがあります。また、サハラ以南のアフリカ、中南米は、今後の経済発展や社会の変化により、逼迫が懸念されます。日本にも、これらの脆弱性と気候変動リスクに対する国際的な支援が期待されています。
ヴァーチャルウォーターと、ウォーターフットプリント
食料の輸出入に伴って生じる水資源の量を表す言葉として、ヴァーチャルウォーターとウォーターフットプリントという2種類があります。ヴァーチャルウォーター(仮想水)は、たとえば、食料を輸入するとき、実際使用された水の量は関係なく、自国内で生産するときに必要となる水の量をあらわすのに対し、ウォーターフットプリントは、輸出物質を生産するために実際消費された水の量を指します。
日本人は、1日に一人当たり250リットルの水を使っています。そのうち、飲み水は2〜3リットルにすぎません。その用途は、風呂、トイレなど、ほとんどが洗浄のためであり、水を飲むことすら、体の汚れを運んでもらうという意味では洗浄といえます。つまり、水を使うこととは、水に汚れを運んでもらうことを意味しています。
一方、食料を作るために使っている水は、重さ比で、とうもろこしは食べられる量の2000倍です。大豆は2500倍、米は3600倍、牛肉は約2万倍もの水が必要となります。これらのデータに基づき計算すると、日本が海外から輸入している主要な食料を日本で作った場合は、約年間640億トンの水が必要であり、日本国内の農業用水570億トンと同じくらいの量の水を海外から輸入していることになります。
その輸入品目の内訳は、家畜の飼料となるとうもろこし、大豆、小麦、牛肉、豚肉などが大半を占めます。つまり食料の輸入の大半は、肉食のためのものなのです。輸入してから肉にするか、肉として輸入するかの違いに過ぎません。
私たちが1日に使っている水は、飲み水が2〜3リットル、それに対して水道水は約200〜300リットル、一方、食料のために使用されている水は2000リットル〜3000リットルです。実は一番、たくさんの量が必要なのは、食料生産のための水です。水不足が起こったときは、飲み水不足の前に、食料不足が起こることが容易に想像できます。
ヴァーチャルウォーターの各地域間の貿易をみると、オーストラリア、アメリカから、北アフリカや中近東の取引が顕著です。水が少なく石油を持つ国が、食料という形で水を買っています。水をヴァーチャルウォーターに、つまり食料という形にすれば、重さが1000分の1になります。世界で水危機が起こったときは、食料として水を動かせば輸送コストがかからず経済的です。現在も、水は戦略物質として食料という形で世界をめぐっており、その流れを握っているのは、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランスという限られた国々です。これらの国はG8など世界でも力を持っています。
しかしヴァーチャルウォーターでは、実際その国でどのくらいの量の水が使われたか、また取水源も特定できません。それを推計できるのが、ウォーターフットプリントです。
取水源とされる水の中には天水(雨水)と灌漑水があります。灌漑水の中には、河川水と、ダム・貯水池・ため池、そして、非循環型の地下水(化石水)があります。
私たち東京大学は、国立環境研究所との共同研究により、全世界的な農地の水利用量を、作物の種類や作付けの時期・場所などから計算、またダムの働きや規模も考慮して取水源を推定する全球統合水資源モデルを開発しました。
まず、世界の農地の水消費量、地下水取水量について、推定値と、近年の研究による統計結果と比較したところ、大きな違いはなく、まずまず妥当な結果となりました。
そうして算出した日本のウォーターフットプリントは、年間427億トン。一方ヴァーチャルウォーターは年間約627億トンです。水効率が良い国で生産したものを、水効率が悪い国が輸入するため、ウォーターフットプリントはヴァーチャルウォーターよりも少なくなります。その取水源は、灌漑水起源が73億トンで、全体の20%弱に過ぎず、ウォーターフットプリントの8割は、雨水起源だということがわかりました。しかし、灌漑水の中でも29億トンの水は、河川水、ため池などの灌漑水では足りず、非循環の地下水(化石水)を利用していると考えられます。
品目別の水源をみてみると、牛肉の大半は雨水起源となりました。これは家畜は牧草を食べて育つためだと考えられます。一方、米は中規模貯水池が使われ、大豆、小麦などは、灌漑水では足りず、非循環地下水を比較的多く(全体の約10〜15%程度)使っていることがわかりました。
ヴァーチャルウォーターは、日本では、水資源問題への一般認識を高めるためにもよく利用されますが、実際は、より現実的な水資源アセスメントや、将来の食料需給の推定に利用される概念です。しかし、問題は、他の生産手段の制約を考えていないことです。例えば日本が飼料用穀物を大量に輸入しているのは、牧草を大量に育てる土地が不足しているためであり、水不足の中近東とは理由が異なっています。他の制約による食料輸入にVWが入ってきてしまっていることになります。
まとめ
持続可能な社会を作るためには、水だけ切り離すのではなく、食料とエネルギーと水は、三位一体で考えなければいけません。本日お話しましたように、ヴァーチャルウォータートレードにより、水不足の地域で食料を輸入することは、食料を生産するための水を大幅に節約でき、逆に、食料を作るときは多くの水が使われています。またエネルギーと水は海水淡水化、水力発電によりお互いを生み出すことが出来ます。一方、食物をバイオ燃料などのエネルギーにすることもでき、そして大量のエネルギーがなければ食料は作れません。これら3つはそれぞれがチェンジャブルな関係にあり、少ない方を補うことができます。広い視点から持続可能を捉えるためには、これらを一体化して考えなければなりません。
中国には、「飲水思源」という言葉があります。水を飲むときにはその井戸を掘った人を忘れるなという意味だそうですが、それに倣い、これからは「飲食思水」、食べ物を食べるときには、水は簡単にどこでも手に入るものではなく、食べ物を作るときにたくさん水が使われているということを思い出していただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/200501/index.html
前文
水は、「生命」の基本である。地球上の水は、海洋と太陽エネルギーによつて絶えず循環を繰り返し、多様な生命に思恵を与え続けてきた。
現代においては、水循環系は人間の営為によって不断に直接的・問接的に影響を受けるという点で社会的システムであると言えよう。私たちは、地球上に人為的影響を受けない水循県系は最早存在しないことに深く思いを致し、改変された水循環系を持続可能なシステムに再生する努力を払わなければならない。
国上の70パーセントが森林で覆われ水に恵まれたわが国でも、かつての高度経済成長にともなう国上開発と都市化、工業化、さらに生活の利便性の追求による水循環系への直接的影響によって、生態系保全を伴う水循環系は撹乱され、国土保全力を極度に弱めてきた。
地球温暖化は、このような直接的影響と相侯つて水循乗系の大変動を誘発させ、異常な洪水や極端な渇水をもたらし、生命と生活を脅かす。化学物質による水の汚染は、微量であっても食物連鎖・生物濃縮によつて生命の危険を増大させ、とくに胎児への悪影響に警告が発せられている。
日本人が様々な水の脅威を克服し、日本の水を大切にし、日本の水を飲み、日本の水を使うようにするためには、水循環系に影響を与える人間の営為そのものを適正に制御することによつて、撹乱された水循環系を水量、水質、生態系の面から持続可能なシステムに再構築し、健全な水循環型社会を創出して、それを将来世代に継承しなければならない。このため、水循環基本法を制定することにした。
第一 総則・目的
この法律は、健全で持続可能な水循環型社会の形成について基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、水循環総合基本方針の策定その他の水循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、水循環型社会の形成に関する統合的水管理施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、将来の世代に健全な国上を継承することを目的とする。
,定義(注:今後さらに検討を重ねる。必要語句を追加する。)
〈水循環〉
水循環とは、人間の営為の影響を受けつつ地表水及び地下水となり、蒸発し再び降水となり、あるいは地表での滞留や貯留、土壌への浸透など様々な過程を経て絶えず繰り返す水の循県の過程を言う。
〈統合的水管理〉
統合的水管理とは、現在の縦割型水管理を排し、河川流域を一貫した地表水及び地下水の水量管理、水質管理、生態系管理及び水環境管理を統合した総合的な水管理を言う。
〈河川流域〉
河川流域とは、河川及びその集水域を媒介として、森林、農村、都市、海が結ばれたまとまりのある国上の単位を言う。
(水環境〉
統合的水管理によつて形成され、将来の世代に継承され、国民の全てがその思恵を享受する水の環境で、水量、水質、生態系の面から持統可能な水循環系によつてもたらされたものを言う。
第二 基本理念
(1)地表水及び地下水は公共水であること
地表水及び地下水は、共に公共水であり、流域別水循環計画に基づいて統合的に管理されなければならない。
(2)水循環保全義務と水環境享受権
現在の国民は、現在及び将来の国民のために、持続可能な水循環系を保持する義務を担う。現在及び将来の国民は、水量、水質、生態系の面から持続可能な水循環系によつてもたらされる健全な水環境の思恵を享受する基本的権利を有する。
(3)流域圏の統合的管理
水循環管理は、河川流域を原則的単位として統合的かつ地域主権的に行われなければならない。河川流域を構成する地方公共団体は、相互に協力し、河川及び河川流域を上流の森林や農地から河日沿岸域までを含めて統合的かつ地域主権的に管理する主体である「流域連合」を組織しなければならない。ここで、流域圏の範囲については、複数河川流域に亘る広域生活圏においては当該の全河川流域を包含したものとする。
(4)持続可能な水循環型社会の再生と将来世代への継承
持続可能な水循環型社会の形成は、健全な国土とその上に生活する国民の健康で文化的な生活と幸福追求に不可欠である。このため、これを再生し、将来世代に継承しなければならない。
(5)持続可能な水循環系保全のための公平な役割分担
持続的な水循環系の保全のための行動は、国民、事業者、地方公共団体(流域連合)、国等によつて公平な役割分担の下に行われなければならない。
(6)拡大汚染者責任の原則
通常の生活者が処理処分できない有害物質の生産者、通常の生活者の排出する各種の感染症の原因となる病原菌やウイルス、微量な医薬品や有害化学物質を含む排水の処理に当る事業者及び地方公共団体は、汚染防止について第一次的な責任を有する。
(7)未然防止と予防原則
水循環によつて生じる悪影響は、未然に防止されなければならない。このためには、科学的知見の充実を図るとともに、予防原則の適用を躊躇してはならない。
第二 関係者の責務等・国の責務
国は、「第二 基本理念」にのっとり、水循環の道正化に関する基本的かつ総合的な施策の基本方針を策定し、その推進に努める責務を有する。また、流域連合の自主性を尊重することを前提とした上で、流域連合による河川及び河川流域の管理が基本理念に則していないと判断される場合は必要な処置を勧告することができる。
・地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのつとり、国の定める基本方針に基づき、流域連合を組織し、互いに協力して、施策を策定し、及び実施する責務を有する9地方公共団体は、この際、流域内の事業者及び住民の意見を聞かなければならない。
・事業者の責務
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に当つては、水循環系の支障とならないよう必要な措置を講じなければならない。支障が生じた場合は、その責は事業者に帰すものとする。
・国民の責務
国民は、基本理念を共有するとともに、水循環系への支障を防止するため、その日常生活に伴う水循乗系を撹乱する恐れのある負荷の低減に努めなければならない。また、国民は、水循環系の適正化に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する施策の推進に主体的に参加する責務を有する。
・関係者相互の連携及び協力
国、地方公共団体、事業者、国民及び水循環系に関わる非営利公益団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力することに努めなければならない。
このために情報公開の徹底を期すとともに、広く情報が利用されるように広報活動を強化する。
・水循環の日
事業者及び国民の間に広く水循環系の再生と保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に活動を行う意欲を高めるため、O月○ 日を水循環の口とする。
・法制上の措置等
国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならない。さらに国は、縦割の制度と組織を廃し、水循環系の道正化に関する施策を実施するため必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講じなければならない。また、地方公共団体においても縦割の制度と組織を廃するために必要な措置を行わなければならない。
・年次報告等
政府は、毎年、国会に基本方針の実施状況を報告し、その促進に必要な措置を明らかにした文書を提出しなければならない。また、国会に報告した内容及び提出した文書を公表する。
第四 基本方針口基本計画等
・水循環総合基本方針
国は、基本理念に基づき「第五基本的施策」の基礎となり、流域連合が策定する「流域別水循環計画」の前提となる基本方針を策定し、流域連合が円滑に実施できるよう支援・調整しなければならない。
基本方針には、基本的施策の推進に関する方針その他の必要な事項を定め、閣議の決定を求め、決定後遅滞無く公表するとともに国会に報告するものとする。
,流域別水循環計画
「流域連合」は、国の基本方針に基づき、河川流域毎に水循環アセスメントを行い、流域別水循環計画を当該流域に適合した最上位計画として策定する。
計画の策定から決定までのプロセスは、下記の通りである。
流域を構成する地方公共団体によつて結成された「流域連合」が「流域水循環審議会」に計画策定を諮問する。計画策定に当つては、流域住民の意見を聞き、誠実に対応しなければならない。流域連合は、答申された計画案を「流域連合議会」に諮り、議決を得て決定する。
第五 基本的施策
国は、下記の基本的施策に関する基本方針を示し、河川流域を構成する地方公共団体は、流域連合を結成し、流域別水循環計画に基づいてこれらの基本的施策を講じるものとする。
(1)流域治水対策の推進
想定した規模の洪水をダム等洪水調節施設と河道で処理するという従来の治水から、森林や農地による保水、流域による貯留、土地利用に応じた浸水の受け入れによる洪水氾濫の分散、河川、下水道、農業用水路等の一体的整備等、河川流域全体で洪水対策を行う流域治水へと転換する。
このため、河川法で想定されている基本高水流量等の設定に基づく治水計画を根本的に見直す。 流域治水へ転換することによつて、河川堤防のかさ上げとダム建設への過度な依存体制が克服でき、今後は、緑のダムとしての森林の持つ保水機能や土砂流出防止機能の活用、保水型・耐水型都市の再生、公園緑地や田畑の持つ遊水機能の活用、さらに雨水の地下浸透、滞留や貯留の計画的推進、水と緑の豊かなネットワーク都市の再生を進めることになる。
流域治水の推進のためには、浸水危険区域、遊水可能区域、水と緑の酒養区域などの土地利用計画を公表し、農業政策や都市計画とあいまった土地利用の適正な規制と誘導を図ることが不可欠になる。国民ひとリー人がこうして、流域治水に参加することになる。
(2)水環境管理の道正化及び水循環系の再生と保全
水環境管理の要諦は、河川管理と水環境管理の統合及びこれに伴う水環境基準と排水基準の適正化の推進である。これまでの縦割制度の下で達成されなかった両者の統合と諸基準の全面的改正を進め、同時に多様な生物の棲息・生育環境の再生・保全やギ硼十1の自然回帰と復元、環境用水の確保とその維持を図る。
さらに水循兵系の再生と地下水の保全のために、雨水の浸透・貯留機能の保全・回復あるいは雨水の利用を進める。何人も、水循環を妨げ、雨水の地下浸透を阻害する行為を行つてはならず、このために適切な土地不1用規制を図る。
(3)第二者機関による公正な水環境監視
縦割の所管部門がそれぞれ水質監視を行うこれまでの監視体制から脱却し、公正な第二者機関が排水源の放流水質及び受容水域の水環境の諸側面(水量、水質、生態系など)を監視する。
この第二者機関が違反者に対する是正勧告権を持つと同時に、法的な処置を講じることを可能にする。
(4)利水システムの合理化の促進
過剰な水利用を誘発したこれまでの利水システムを改め、節水型都市及び産業の創出に努め、新規水資源開発の抑制に向けた構造転換を図る。さらに、農業用水を含めた水利用合理化総合計画の策定、水利権転用(工業用水、農業用水)、水融通の促進、水利用量削減目標設定、水利権システムの整備(譲渡契約の認可主体=流域連合)などを進める。さらに、利水システムの一環として、 雨水利用及び下水処理水の再利用等の促進を図る。
(5)地下水の保全と利用の適正化の推進
地下水の保全と利用の適正化を図るため、同一地下水盆における地下水情報の共有化、モニタリング体制、緊急時体制を整備すると共に、地下水の涵養と保全のため、都市の公園や緑地、農地や森林などを有効に活用する。地方公共団体は、条例の定めるところにより、地下水利用適正化計画の策定、地下水酒養区域及び地下水汚染防止区域の設定並びに地下水採取料の徴収を行うことができる。
(6)河川と森林との統合管理の推進
河川管理と森林管理の統合は、水循環系の健全化の視点から極めて重要である。両者の統合によつて、放置林による山地災害や洪水時の大量の流木流出による被害拡大の防止対策を推進する。
また、地球温暖化は水循県系を撹乱させる元凶であるため、二酸化炭素吸収源としての森林の役割その他の森林の多面的機能を維持拡大させる措置を講じる。これらの対策を進めるために森林の所有者以外の者が管理行為を行うことが出来るようにし、併せて所得補償制度を導入する。
また、水源地域の土地の外国資本に封する売却を禁止する処置を採る。
(7)農地の保全と活用
農地を遊水地として保全し、冠水補償を実施する。体耕農地に湛水し、地下水の涵養及び生物多様性保全のためのビオトープとして活用することについて一定の補償を実施する。
(8)水道及び水循宋保全施設の流域圏統合経営の推進
水道及び下水道・浄化槽・し尿処理施設等の水循環保全施設は、排水源におけるきめ細かな対応とともに、流域圏ベースの広域経営を可能にすることによって経営の合理化とサービス水準の向上を図るとともに、処理水準の高度化を推進し、水環境の更なる清浄を確保する。このため、本来同一の機能を果す下水道、浄化槽、し尿処理等の施設は、一体的に整備と管理を進める。
さらに、これらの施設は、流域住民全ての生活に不可欠な社会的共通資本であることに鑑み、社会的事業としてその設置から維持管理までを含め、一貫した経営の合理化を進める。
(9)老朽化施設の更新と機能の向上並びに異常渇水や震災などに備える非常時対応
戦後60数年、経済復興期、高度経済成長期、安定成長期を通じて莫大な公共投資が進められた結果、治水施設、水資源施設、水道施設及び水循環保全施設等の社会的ストックは膨大な資産となって現在それなりに役割を果している。
今後は、これらの資産の更新と機能の向上が大きな課題となるため、アセットアセスメントを進め、合理的な更新と機能の向上に努める。
さらに、今後予想される異常な渇水や大震災に対応する非常時の水供給、水環境保全対策、環境衛生対策
を進める。
(10)財政制度の見直し
国は、従来の財政処置の方式を抜本的に再検討し、流域連合の創設及び同連合による事業の円滑な推進が可能なように地方公共団体とも協議しつつ、財政制度を再構築する。
流域連合の財源は、分担金、賦課金、課徴金、原因者負担金、水循環目的税、地下水使用料等で構成される。
(11)科学技術の振興及び国際協調の推進
水循環の適正化という視点での技術開発は、ハード、ソフト両面で研究課題が山積している。 縦割体制の下では、技術体系も歪みを生じ、合理性を欠く結果となる。今後は横につながる適正技術が志向される。国際援助においてもかかる技術が望まれるが、この面ではわが国は後進的と言える。
また、後発開発途上国の支援体制を抜本的に見直し、強化する。
第六 中央政府の行政組織及びその再編整備
・中央政府の行政組織
(案1)水循環庁の設置
内閣府の外局として水循環庁を設置し、水循環に関わる全ての行政組織を統合する。(水循環庁設置法を新たに制定)
水循環庁は、基本理念にのっとり、水循環社会の実現に向けて基本的施策の推進のための全ての事務を所掌する。水循環庁は、この任務の達成のため、水循環に関わる現行の個別制度の全てを所管し、統合的水管理体制に移行させる。
ただし、「水循環庁」は、将来の道州制の導入も踏まえ、全国的視野で行うことが求められる政策の企画、調整等に権限を限定し、政策の実施権限の多くを広域連合である「流域連合」に委譲することとする。
(問題点)
・関係各省庁及び族議員の抵抗が予想される。
・抜本的な行政改革になるので、実現可能性を危惧し、消極に流れる恐れがある。
(案2)水循環社会推進委員会の設置
内閣府の外局として、独立した行政委員会を設置し、水循環に関わる基本的な行政を所掌させる。(水循環社会推進委員会設置法を新たに
中央政府に於ける水行政の権能を大胆に簡素化させ、中央政府に残される基本的権限のみを所掌する体制を想定した場合、独立行政委員会の設置は適切であると考えられる。なお、委員長及び委員の人事を国会の承認案件とすることで、独立性を保持するものとする。
(問題点)基本的に(案1)と同じ。
道州制が導入された場合、中央政府が所掌する行政権能の範囲
(注)現行法制上、独立行政委員会は、内閣から一定の独立性の確保が求められる行政事務を処理する場合に設置されている。大臣の分担管理の原則(国家行政組織法第5条、内閣法第3条)に鑑み、水管理行政がこれになじむか否かという問題がある。
(案3)水循環政策本部の設置
水循環政策を推進するため、内閣府に水循秦政策本部を設置する。(内閣府設置法の改正)本部は、水循環政策の推進に関する基本方針の作成及びその実施に関すること、関係行政機関の総合調整にかんすること、その他水循環施策で重要なものの企画、立案及び総合調整に当る。
(問題点)
・縦割制度・体制の打破に限界がある。(現行の制度、組織がそのまま残る)
・結果的に関係各省の出向者によつて組織され、現状と変わらない。
・道州制が導入された場合でも縦割制度と体制とが温存される可能性が高い。
・中央水循環審議会
上記組織とは別に、本法に基づく水循環政策の基本方針の審議、水循環政策の進捗状況その他基本的事項を調査審議するために中央水循環審議会を設置する。なお、審議会は、学識経験者及び国民の代表によつて構成される。(設置法による規定が必要)
第七 「流城連合」の設置等、地方公共団体の行政組織及びその再編整備
・流域連合
河川流域を構成する地方公共団体(市町村と都道府県)は、基本理念に基づき水循環政策を推進するため、河川流域の統合的管理主体(地方公共団体の連合組織)である流域連合を設置しなければならない。(注)中央政府の出先地方組織は廃止される。
国は、速やかに流域連合を結成するよう、関係する地方公共団体に勧告することができる。
・流域連合議会
流域連合に関わる立法機関として予算、組織、人事などに関わる諸議案を議決し、流域水循環条例その他の諸規定を制定するため、地方公共団体及び流域住民代表で構成される流域連合議会を設ける。
・流域水循環審議会
水循環アセスメント、流域別水循環計画の調査審議、流域連合の水循環政策の進捗状況のチェックや各種の勧告を行うため、流域連合に諮問機関として流域水循環審議会を設ける。
・流域連合監理・監査
流域連合及び同議会の業務監理に当る組織として、地方公共団体代表者及び流域住民代表者で構成される流域連合監査機構を設ける。同監査機構は、業務監査、情報公開、住民の苦情対応等にも対応するものとする。
第八 流増住民との協働・流域住民との協働体制/・情報公開と監査への参加
行政と流域住民ネットワークは、連携・協働して政策形成を行うことが望まれる。このため、両者のパートナーシップによる協働体制を倉J出し、地域ガバナンスを確立することが必要であり、水の公共性、コモンズとしての性格及びオーフス条約等を考えれば、当然の措置でもある。
このため、流域水循環審議会、流域連合議会、流域連合監査機構には、一定割合の流域住民代表者の参加が前提条件となる。なお、現行河川法に基づく淀川流域委員会は、8月3日をもつて機能停止した。これは、現行河川法の住民参加規定(河川法第16条の2)の曖昧さ(住民の意見聴取の実施の有無、方法等については河川管理者の裁量に委ねていること)に起因するものである。
第九 雑則
・原状回復命令等
水循乗に悪影響を及ばす行為により、現実に支障が生じた場合、原因者の負担において支障の回復・軽減の措置を講じることを命令し、命令の牌怠、不履行に対しては間接強制、汚染者負担の原則の適用を可能とする制度を設ける。
第十 付則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、流域連合など第七、第人に関わる規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行する。
http://mizuseidokaikaku.com/report/report17_tenpu6.pdf
水循環政策大綱案(原案)
1.水循環型社会の再生と将来世代への継承
水は、「生命」の基本である。地球上の水は、海洋と太陽エネルギーによつて絶えず循環を繰り返えし、多様な生命に恩恵を与え続けてきた。
現代においては、水循環系は人間の営為によつて不断に直接的・聞接的に影響を受けているという点で社会的システムであると言えよう。私たちは、地球上に人為的影響を受けない水循環系は最早存在しないことに深く思いを致し、改変された水循環系を持続可能なシステムに再生する努力を払わなければならない。
国上の70パーセントが森林で覆われ水に恵まれたわが国でも、かつての高度経済成長に伴う国上開発、都市化、工業化、さらに生活の利便性の追求による水循環系への直接的影響によつて、生態系保全を伴う水循環系は撹乱され、国土保全力を極度に弱めてきた。
地球温暖化は、このような直接的影響と相侯って水循環系の大変動を誘発させ、異常な洪水や極端な渇水をもたらし、生命と生活を脅かす。化学物質による水の汚染は、微量であつても食物連鎖・生物濃縮によつて生命の危険を増大させ、とくに胎児への悪影響に警告が発せられている。
日本人が様々な水の脅威を克服し、日本の水を大切にし、日本の水を飲み、日本の水を使うようにするためには、水循環系に悪影響を与える人間の営為そのものを適正に制御することによつて、境乱された水循環系を水量、水質、生態系の面から持続可能なシステムに再構築し、健全な水循環型社会の創出を期さなければならない。そこで、水循環系の統合的管理体制を構築し、持統可能な水循兵型社会を創出して、それを将来世代に継承するために水循秦政策大綱を定める。
2.水循環基本法の制定
(1)水循環政策の基本理念
水は、生命の根源であるにもかかわらず、河川等の公共水域の表流水のみを公水とし、その他の水は土地に付随した水として私水と位置づけられてきた。さらに水は、様々な管理者の下で局時的局所的な個別管理に委ねられてきた。河川水が公水であると位置づけられていても、あたかも河サII管理者の私物であるかのように扱われ、そこには国民の姿が全く見えない。 水循環系が歪められ、寸断され、破綻した理由は、一にかかる制度にあつた。
水は、地表水も地下水も水循環系によつて結ばれた一体の存在であり、生命の根源であるという意味において、現在と将来の人々の生存に不可欠な共同資源である。このような水は、水循環系の全ての過程を一体として統合的に管理されなければならない。 全ての人々は、このために水循環系を守る義務を担うべきものである。
この視点に立ち、水循環政策の基本理念は、次の七つの原則的な考え方で構成される。
(1)地表水及び地下水は公共水であること
地表水及び地下水は、共に公共水であり、統合的に管理されなければならない。
(2)水循環保全義務と水環境享受権
現在の国民は、現在及び将来の国民のために、持続可能な水循環系を保持する義務を担う。現在及び将来の国民は、持統可能な水循環系によつてもたらされる健全な水環境の恩恵を享受する基本的権利を有する。
(3)流域圏の統合的管理
水管理は、河)「1流域を原則的単位として統合的かつ地域主権的に行われなければならない。河川流域を構成する地方公共団体は、相互に協力し、河川及び河川流域を上流の森林や農地から河口沿岸域までを含めて統合的かつ地域主権的に管理する主体である「流域連合」を組織しなければならない。
(4)持統可能な水循環型社会の再生と将来世代への継承
持続可能な水循秦型社会の形成は、健全な国土とその上に生活する国民の健康で文化的な生活と幸福の追求に不可欠である。このため、これを再生し、将来世代に継承しなければならない。
(5)持続可能な水循環系保全のための公平な役割分担
持続的な水循環系の保全のための行動は、国民、事業者、地方公共団体(流域連合)、国等によつて、公平な役割分担の下に行われなければならない。
(6)拡大汚染者責任の原則
通常の生活者が処理できない有害物質の生産者、通常の生活者の排出する病原菌やタイルス、微量な医薬品や有害化学物質を含む排水の処理に当る事業者及び地方公共団体は、一次的汚染防止責任を負う。
(7)未然防止と予防原則
水循乗によつて生じる悪影響は、未然に防止されなければならない。このためには、科学的知見の充実を図るとともに、予防原則の適用を躊踏してはならない。
(2)水循環墓本法の制定
わが国の水行政は、これまで経済成長や生活の利便性の向上という観点に立って、水循環系の部分毎に異なる事業制度と組織体制の下で対症療法的に進められて来た。このため、もつばら個別的事業法が存在するのみで、前項の基本理念を定めた基本法は制定されていない。
そこで、水循環基本法を制定し、健全で持続可能な水循環型社会の形成について基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の水循環
型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、統合的水管理施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、将来の世代に健全な国上を継承する制度的処置を講じるものである。
(3〕水循環に関する主要施策
国は、下記の基本的施策に関する基本方針を示し、河川流域を構成する地方公共団体は、流域連合を結成し、流域別水循環計画に基づいてこれらの基本的施策を講じるものとする。
(1)流域治水対策の推進
想定した規模の洪水をダム等洪水調節施設と河道で処理するという従来の治水から、河川流域全体で洪水対策を行う流域治水へと転換する。流域治水の推進のためには、浸水危険区域、遊水可能区域、水と緑の涵養区域などの土地利用計画を公表し、土地利用の適正な規制と誘導を図ることが不可欠になる。
国民ひとリー人がこうして、流域治水に参加することになる。
(2)水環境管理の適正化及び水循環系の再生と保全
水環境管理の要諦は、河川管理と水環境管理の統合及びこれに伴う水環境基準と排水基準の適正化の推進である。同時に多様な生物の棲息・生育環境の再生・保全や河川の自然回帰と復元、環境用水の確保とその維持を図る。さらに水循環系の再生と地下水の保全のために、雨水の浸透・貯留機能の保全・回復あるいは雨水の利用を進める。
(3)第二者機関による公正な水環境監視
縦割の所管部門がそれぞれ水質監視を行うこれまでの監視体制から脱却し、公正な第二者機関が排水源の放流水質及び受容水域の水環境の諸側面(水量、水質、生態系など)を監視する。
(4)利水システムの合理化の促進
過剰な水利用を誘発したこれまでの利水システムを改め、節水型都市及び産業の倉J出????に努め、新規水資源開発の抑制に向けた構造転換を図る。
(5)地下水の保全と利用の適正化の推進
地下水の保全と利用の適正化を図るため、同一地下水盆における地下水情報の共有化、モニタリング体制、緊急時体制を整備すると共に、地下水の涵養と保全の対策を進める。
地方公共団体は、条例の定めるところにより、地下水涵養区域の設定、地下水利用適正化計画の策定及び地下水汚染防止区域の設定を行うことができる。また、条例の定めるところにより、地下水採取料を徴収することができる。
(6)河川と森林との統合管理の推進
河川管理と森林管理の統合によつて、放置林による山地災害や洪水時の大量の流木流出による被害拡大の防止対策を推進する。また地球温暖化は水循環系を撹乱させる元凶であるため、二酸化炭素吸収源としての森林の役割その他の森林の多面的機能を維持拡大させる措置を講じる。
(7)農地の保全と活用
農地を遊水地として保全し、冠水補償を実施する。休耕農地に湛水し、地下水の涵養及び生物多様性保全のためのビオトープとして活用することについて一定の補償を実施する。
(8)水道及び水循環保全施設の流域圏統合経営の推進
水道及び下水道・浄化槽。し尿処理施設等の水循環保全施設は、流域圏ベースの広域経営を可能にすることによつて経営の合理化とサービスの向上を図るとともに、処理水準の高度化を推進し、水環境の更なる清浄を確保する。
(9)老朽化施設の更新と機能の向上並びに異常渇水や震災などに備える非常時対応
戦後60数年を通じて莫大な公共投資が進められた。今後は、これらの資産の更新と機能の向上が大きな課題となるため、アセットアセスメントを進め、合理的な更新と機能の向上に努める。
(10)財政制度の見直し ・
国は、従来の財政処置の方式を抜本的に再検討し、事業の円滑な推進が可能なように地方公共団体とも協議しつつ、財政制度を再構築する。流域連合の財源は、分担金、賦課金、課徴金、原因者負担金、水循環目的税、地下水使用料等で構成される。
(11)科学技術の振興及び国際協調の推進
縦割体制の下では、技術体系も歪みを生じ、合理性を欠く結果となっている。今後は横につながる道正代誉技術が志向される。また、後発開発途上国の支援を抜本的に見直し、強化する。
3.山紫水明の国づくり〜行政組織の再編と流域住民との協働
水循環系を再生し、山紫水明の国づくりを推進するためには、前述の基本理念に則り、これまでの制度と組織を抜本的に改革し、中央政府の権限を大幅に地方政府に委譲するとともに、地方公共団体を越えた河川流域ベースの体制に構築し直さなければならない。さらに、水が国民ひとリー人の生命の源であり、国民の共同資源としての公共水であるという視点から、流域住民が水循環に関わる様々な意思決定に参画するシステムの構築もまた必要不可欠であり、勇断を持って
推進しなければならない。
(1)中央政府の行政組織の再編
改革案としては、三案が考えられる。
[案1]
水循環庁の創設は、最も適切であろう。内閣府の外局として水循環庁を創設すれば、水行政に関わる全ての行政部門を一挙に統合し、整理合理化を断行できる。なお、この場合においても、「水循環庁」は、全国的視点で行うことが求められる政策の企画、調整等に権限を限定し、Я在???、国土交通省その他の省庁が有している権限の多くを「流域連合」に委譲するものとする。
道州制を早期に導入する場合は、道州を超える問題や道州間の調整など限られた重要課題に対
応する
[案2]水循環委員会の設置が考えられる。委員会は独立行政委員会であるが、この場合も[案1]と同じように内閣府の外局となる。委員長などの人事を国会の議決事案とすることで独立性を確保させたい。
(ただし、[案2]には現行法制上、国家行政組織法第3条に基づく委員会が現在の大臣の分担管理原則(国家行政組織法第5条、内閣法第3条)に鑑み、水管理行政になじむか否かの問題が残る。消費者庁の設置に際しても、中立性を確保する行政委員会型組織が遡上に上ったが、最終的に「消費者庁及び消費者委員会」が設けられた。)
[案3]
水循環政策本部の設置は、現段階では現実的と考えられなくも無い。海洋行政分野に有力な事例があるが、水循環行政においては内容的に曖味で、行政改革につながらないと考える。
なお、上記組織とは別に、本法に基づく水循環政策の基本方針の審議、水循環政策の進捗状況その他基本的事項を調査審議するために中央水循兵審議会を設置する。
(2)「流域連合」の設置等、地方公共団体の行政組織の再編
水循環系の保全は、基本理念に基づき流域を一貫して、流域住民に近い所で、流域住民の参加を得て推進すべきである。個々の地方公共団体が個別に行う従来の体制を脱し、流域圏をベースに推進できる行政組織に再構築するため、国は流域連合、同議会の創設を推進するとともに、国の権限を大幅に流域連合に移管する。なお、学識経験者や流域住民の意見を反映させるため、流域水循環審議会を設け、さらに事業推進の透明性を確保するため、流域連合監査機構を設ける。.
[流域連合]
河川流域を構成する地方公共団体(市町村と都道府県)は、基本理念に基づき水循環政策を推進するため、流域圏の統合的管理主体(地方公共団体の連合組織)である流域連合(地方自治法上の広域連合)を設置しなければならない。(注)中央政府の出先地方組織は廃止される。
[流域連合議会]
流域連合に関わる立法機関として予算、組織、人事などに関わる諸議案を議決し、流域水循環条例その他の諸規定を制定するため、地方公共団体及び流域住民代表で構成される流域連合議会を設ける。
[流域水循環審議会]
水循環アセスメント、流域別水循環計画の調査審議、流域連合の水循環政策の進捗状況のチ
ェックや各種の勧告を行うため、流域連合に諮問機関として流域水循環審議会を設ける。
[流域連合監査機構]
流域連合及び同議会の業務監理に当る組織として、地方公共団体代表者及び流域住民代表者
で構成される流域連合監査機構を設ける。同監査機構は、業務監査、情報公開、住民の苦情対応
等にも対応するものとする。
(3)流域住民との協働体制
行政と流域住民ネットワークとが連携,協働して政策形成を行うことが望まれる。このため、両者のパートナーシンプによる協働体制を創出し、地域ガバナンスを確立することが必要である。
水の公共性、コモンズとしての性格及びオーフス条約等を考えれば、当然の措置でもある。このため、流域水循環審議会、流域連合議会、流域連合監査機構には、一定割合の流域住民代表者の参加が前提条件となる。なお、現行河川法に基づく淀川流域委員会は、8月3日をもつて機能停止した。これは、現行河川法の住民参加規定(河川法第16条の2)の曖味さ(住民意見聴取の実施の有無、方法等については河川管理者の裁量に委ねていること)に起因するものである
http://mizuseidokaikaku.com/report/report17_tenpu5.pdf
水循環政策大綱案(原案)と基本法要綱案(原案)にご意見をお寄せください
(2009年10月14日)
水循環基本法研究会の第10回会合(2009年10月9日開催)において、起草委員会でまとめた 「水循環政策大綱案(原案)」と 「水循環基本法要綱案(原案)」を提案いたしました。10月22日まで両原案に対する修正意見をお受けしております。下記2点についてご意見をおまとめいただき、文書にてお送りいただけますようお願いいたします。こちらの回答用紙をご利用ください。
【第1点】
水循環基本法要綱案(原案)の「第六 中央政府の行政組織及びその再編整備―中央政府の行政組織」(6ページ目)において示している3つの案について、どれが適当と考えますか。その理由は何ですか。また、別案がありましたらお示しください。
(案1)
内閣府の外局として水循環庁を設置し、水循環に関わるすべての行政組織を統合する
(案2)
内閣府の外局として、独立した行政委員会(水循環社会推進委員会)を設置し、水循環に関わる基本的な行政を掌握させる
(案3)
水循環政策を推進するため、内閣府に水循環政策本部を設置する
【第2点】
原案に対する修正意見について、該当個所とその対案及び理由をお示しください。
●メールの送付先 qqyg4fv9k★peace.ocn.ne.jp(★印を@に変えてお送りください)
●Faxの送付先 075-722-5295
http://mizuseidokaikaku.com/report/report18.html
ATCグリーンエコプラザセミナーレポート 世界の水問題と日本
■講師
東京大学 生産技術研究所 教授 沖大幹氏
はじめに
世界の水問題は、大きく3種類に分けられます。安全な飲み水(indispensable water)、農業生産、工業生産の水(profitable water)最後に、人と生態系を維持するため、快適に生きるための水(comfortable water)です。1km以内に、1日1人当たり20リットルの水が得られることが、安全な飲み水へのアクセスがあることを意味しますが、世界人口の5分の1は、それがなく、水の確保のためだけに毎日の貴重な時間を費やしています。
これらの3種類の水問題は、質・量も異なれば、貨幣価値も違います。水の様々な側面で懸念事項があるということをお伝えしなければなりません。
農業・工業生産のための水は、今後使用が増えることが懸念されており、地球温暖化が進まなくとも、都市化の進展と人口集中により、洪水・渇水被害は深刻化するでしょう。さらに、数十年後には、水問題は国際的紛争の引き金になるという研究者もいます。
ではまず、水資源は循環資源で、地球上には水がふんだんにあるのに、どうして水不足が生じるのかということをおさらいしましょう。
地球上の水に対して、淡水の占める割合は水全体の約2.5%にすぎず、中でも地下水、氷河などを除いた水資源として利用しやすい淡水は約0.02%しかないため、水不足が生じると説明されることがありますが、そうではありません。
水資源は、ストックではなくフローだと考えるべきです。ある瞬間、世界中の河川の水の総量は、2000 km?に対して、人間が年間使う水は4000 km?だから足りない、という比較の仕方は間違っています。実際は、陸から海へ流れる水の流量の合計は、年間約4万km?。その水循環の一部が、人間の社会の中を通っていると考えなければなりません。では、年間流量のうち、人間が使うのはたったの約10%だから水不足になるわけがないかというと、それも誤りです。
数値モデルによる世界の河川の日流量シミュレーション結果によると、水は、地理的、時間的に偏在することがわかります。極地や、熱帯雨林地帯は年中湿潤なのに対し、砂漠は常に乾燥しており、一方でモンスーン地帯は雨季・乾季で、流量に大きな差があります。全世界の年間流量が足りているからといって、個々の場所で足りているとは限らないのです。
物質の重さ当たりの単価と市場規模について比較してみると、水は、廃品回収の古紙よりもはるかに単価が安いことがわかります。ちなみにミネラルウォーターは嗜好品で、清涼飲料水と同じと考えられるためいわゆる水問題とは切り離して考えるべきでしょう。
ミネラルウォーターは500mlで150円、1m?で30万円ですが、水道水は、1m?で140円〜400円です。都民の水瓶として知られる、奥多摩の小河内ダムの貯水容量1.85億m?の水は、約300億円に相当します。しかし、それは、金塊にすると、たった1m?に過ぎません。つまり、水資源は安くてかさばり、かつ大量に必要なものであり、必要なときに必要な場所、必要な質の水資源がないと、貯蔵、輸送コストが相対的に高すぎて経済的に引き合いません。
21世紀における世界の水資源アセスメント
21世紀の人口増加と経済発展による水需要の変化と、気候変動による水資源賦在量の変化、つまり温暖化による気候変動で使用できる水の量がどう変化するかについて、IPCCで使用しているSRESシナリオに沿って推計した結果をお話したいと思います。
Aは経済行動成長を重視したシナリオ、Bが環境保全を重視したシナリオ。かつ、1はグローバリゼーションが進んだ場合、2は地域化が進んだ場合、という4通りの組み合わせのシナリオで将来推計を行いました。
まず人口の将来展望について、もっとも高くなるのはA2、つまり各地域が交流なく経済発展を目指すと、もっとも人口が増加します。A1B1は共通のカーブを描き、世界的に価値観や技術移転が共通して進む場合、人口は2050年をピークに減少します。地域化、および環境保全重視型のB2シナリオは、人口は増加しますが、指数関数的に増えるわけではなく、ある程度で増加スピードは落ち着くという結果となっています。
このように最近の推計では、人口は増え続けるわけではないというのが一般的になりつつあり、今世紀中に来るであろう環境負荷のピークを乗り切れば、持続可能社会も作れるのではないかと考えています。
次に世界の食料生産と供給についてですが、1960年から2004年の間に、人口は約2倍に増えましたが、その間、農地の面積はわずか10%増に留まっています。しかし、緑の革命と言われる農業分野の技術の発展と、大量の水の使用により、単位面積あたりの収穫量は2.3倍となり、一日一人あたりの摂取カロリーは25%増えています。しかし、そんな中でも現在8億人は飢餓に苦しんでいると言われています。これも水と同様に、物理的な量の問題ではなく、社会における分配の問題でしょう。
工業用水取水量と工業分野のGDPとの関係は、大体線形関係にあります。しかし日本は海外諸国よりも格段に低い取水量を保っており、工業用水の約80%を再生利用しています。
“将来工業用水量”は、“現在工業用水量”*“工業規模増加率”*“用水効率改善係数”により求められます。中国など途上国の工業規模増加は今後も見込まれるため、工業用水の再利用による用水効率改善係数により、将来の工業用水量は大幅に変わってくることが予想されます。
水需要の話をしてきましたが、では、水の供給はどう変化するのでしょうか?これは温暖化の予測となります。
地球温暖化とは気候が変動するということであり、単純に気温が上がるだけでなく、気圧配置が変わり、雨の降り方が変わります。気温上昇による影響と、気候変動による水循環の変化は分けて考える必要があります。
まず温度上昇の直接的影響には、氷河・氷床の融解に伴う流量の一時的増加があります。一見流量が増えていても、それは氷河という水資源の貯金をとりくずしているにすぎず、今世紀末にはやがてなくなって必ず減少します。人間の生活にとっては、流量の一次的な増加ではなく、普段の流量が大切です。氷河がなくなれば、雨が降ったときと、降っていないときの流量の差が非常に大きくなり、ダムを作らなければ、全世界人口の6分の1が深刻な影響を受けると言われています。同時に、水温上昇により水質も変わり、生態系も大きな影響を受けるでしょう。
次に、雨の降り方が変わることによる間接的影響としては、極域と湿潤地帯での水資源の増加、熱帯・亜熱帯乾燥域で減少が予測されています。つまり乾燥域での旱魃地帯がさらに広がり、湿潤地帯においては激しい降水による洪水リスクが増大します。
私は、IPCC第4次報告書第2作業部会、影響評価を調査するグループに参加していました。ほとんどが欧米系なので、水不足の話が中心になりますが、仮にアジアの人がいれば、洪水の話ももっと前面に出ていたと思います。
さらに国交省が行った日本の気候変動予測によると、温暖化が進んだ100年後、雪が雨として降るため、冬の間の河川流出量が増え、同時に雪解けが早まるため、本来、ダム貯水量が満水になるべき代かき期などの需要期に、流量が不足してしまう恐れがあります。
21世紀における深刻な水ストレス下の人口予測のシミュレーションを、先ほどと同様のSRESシナリオで行いました。ここでの水ストレスのある人とは、年によっては渇水で困窮したり、食物生産が落ちて影響を受ける可能性がある状態にある人ということでお考えください。2050年までは、どのシナリオでも水ストレス人口は増えます。しかしそれ以降、A2(経済行動成長重視・地域化)はさらに増えますが、A1、B1では横ばい、あるいは減るという結果になりました。つまり、今後どのような社会になるかによって、必ずしも悲観的な未来ばかりではないと考えられるでしょう。
IPCCでは、prediction(予測)という言葉は使わないように心がけています。人間の力が及ばない天気などの予報とは違い、50年、100年後の未来は、人間社会が今後どの程度温室効果ガスを排出するかという緩和策や、気候変動の悪影響を最小限にしようとする適応策にどの程度取り組むかにより変わります。私たちが行っているのは、ある仮定の下の計算に過ぎません。これらのシミュレーションから、環境配慮型の社会に変えていくことによって、水に困らない社会が出来るということを示すことができればと思います。
将来展望まとめ
21世紀における水需給において、温暖化の影響による逼迫が予想されるのは、地中海沿岸ヨーロッパ、アメリカ西部です。しかしこの地域は、おそらく適応策を講じることができるため、あまり心配の必要はないでしょう。一方、中近東、西・南アジア地域は、社会経済変化、特に経済発展と人口増により逼迫の恐れがあります。また、サハラ以南のアフリカ、中南米は、今後の経済発展や社会の変化により、逼迫が懸念されます。日本にも、これらの脆弱性と気候変動リスクに対する国際的な支援が期待されています。
ヴァーチャルウォーターと、ウォーターフットプリント
食料の輸出入に伴って生じる水資源の量を表す言葉として、ヴァーチャルウォーターとウォーターフットプリントという2種類があります。ヴァーチャルウォーター(仮想水)は、たとえば、食料を輸入するとき、実際使用された水の量は関係なく、自国内で生産するときに必要となる水の量をあらわすのに対し、ウォーターフットプリントは、輸出物質を生産するために実際消費された水の量を指します。
日本人は、1日に一人当たり250リットルの水を使っています。そのうち、飲み水は2〜3リットルにすぎません。その用途は、風呂、トイレなど、ほとんどが洗浄のためであり、水を飲むことすら、体の汚れを運んでもらうという意味では洗浄といえます。つまり、水を使うこととは、水に汚れを運んでもらうことを意味しています。
一方、食料を作るために使っている水は、重さ比で、とうもろこしは食べられる量の2000倍です。大豆は2500倍、米は3600倍、牛肉は約2万倍もの水が必要となります。これらのデータに基づき計算すると、日本が海外から輸入している主要な食料を日本で作った場合は、約年間640億トンの水が必要であり、日本国内の農業用水570億トンと同じくらいの量の水を海外から輸入していることになります。
その輸入品目の内訳は、家畜の飼料となるとうもろこし、大豆、小麦、牛肉、豚肉などが大半を占めます。つまり食料の輸入の大半は、肉食のためのものなのです。輸入してから肉にするか、肉として輸入するかの違いに過ぎません。
私たちが1日に使っている水は、飲み水が2〜3リットル、それに対して水道水は約200〜300リットル、一方、食料のために使用されている水は2000リットル〜3000リットルです。実は一番、たくさんの量が必要なのは、食料生産のための水です。水不足が起こったときは、飲み水不足の前に、食料不足が起こることが容易に想像できます。
ヴァーチャルウォーターの各地域間の貿易をみると、オーストラリア、アメリカから、北アフリカや中近東の取引が顕著です。水が少なく石油を持つ国が、食料という形で水を買っています。水をヴァーチャルウォーターに、つまり食料という形にすれば、重さが1000分の1になります。世界で水危機が起こったときは、食料として水を動かせば輸送コストがかからず経済的です。現在も、水は戦略物質として食料という形で世界をめぐっており、その流れを握っているのは、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランスという限られた国々です。これらの国はG8など世界でも力を持っています。
しかしヴァーチャルウォーターでは、実際その国でどのくらいの量の水が使われたか、また取水源も特定できません。それを推計できるのが、ウォーターフットプリントです。
取水源とされる水の中には天水(雨水)と灌漑水があります。灌漑水の中には、河川水と、ダム・貯水池・ため池、そして、非循環型の地下水(化石水)があります。
私たち東京大学は、国立環境研究所との共同研究により、全世界的な農地の水利用量を、作物の種類や作付けの時期・場所などから計算、またダムの働きや規模も考慮して取水源を推定する全球統合水資源モデルを開発しました。
まず、世界の農地の水消費量、地下水取水量について、推定値と、近年の研究による統計結果と比較したところ、大きな違いはなく、まずまず妥当な結果となりました。
そうして算出した日本のウォーターフットプリントは、年間427億トン。一方ヴァーチャルウォーターは年間約627億トンです。水効率が良い国で生産したものを、水効率が悪い国が輸入するため、ウォーターフットプリントはヴァーチャルウォーターよりも少なくなります。その取水源は、灌漑水起源が73億トンで、全体の20%弱に過ぎず、ウォーターフットプリントの8割は、雨水起源だということがわかりました。しかし、灌漑水の中でも29億トンの水は、河川水、ため池などの灌漑水では足りず、非循環の地下水(化石水)を利用していると考えられます。
品目別の水源をみてみると、牛肉の大半は雨水起源となりました。これは家畜は牧草を食べて育つためだと考えられます。一方、米は中規模貯水池が使われ、大豆、小麦などは、灌漑水では足りず、非循環地下水を比較的多く(全体の約10〜15%程度)使っていることがわかりました。
ヴァーチャルウォーターは、日本では、水資源問題への一般認識を高めるためにもよく利用されますが、実際は、より現実的な水資源アセスメントや、将来の食料需給の推定に利用される概念です。しかし、問題は、他の生産手段の制約を考えていないことです。例えば日本が飼料用穀物を大量に輸入しているのは、牧草を大量に育てる土地が不足しているためであり、水不足の中近東とは理由が異なっています。他の制約による食料輸入にVWが入ってきてしまっていることになります。
まとめ
持続可能な社会を作るためには、水だけ切り離すのではなく、食料とエネルギーと水は、三位一体で考えなければいけません。本日お話しましたように、ヴァーチャルウォータートレードにより、水不足の地域で食料を輸入することは、食料を生産するための水を大幅に節約でき、逆に、食料を作るときは多くの水が使われています。またエネルギーと水は海水淡水化、水力発電によりお互いを生み出すことが出来ます。一方、食物をバイオ燃料などのエネルギーにすることもでき、そして大量のエネルギーがなければ食料は作れません。これら3つはそれぞれがチェンジャブルな関係にあり、少ない方を補うことができます。広い視点から持続可能を捉えるためには、これらを一体化して考えなければなりません。
中国には、「飲水思源」という言葉があります。水を飲むときにはその井戸を掘った人を忘れるなという意味だそうですが、それに倣い、これからは「飲食思水」、食べ物を食べるときには、水は簡単にどこでも手に入るものではなく、食べ物を作るときにたくさん水が使われているということを思い出していただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/200501/index.html
2009年07月26日
地表水と地下水の一体的なマネジメント
地表水と地下水の一体的なマネジメント
・地下水は、民法上は土地所有権の範囲として私有財産的な扱い。
・地下水は流動し水循環の一形態として存在するが「公水」として管理する法律はなく
・公害防止の観点(地盤沈下、水質保全)から法律や条例等により規制。
地下水規制(国)《環境基本法》
・地下水の水質汚濁に係わる環境基準の設定
《水質汚濁防止法》
・排水の地下浸透に係わる排水基準
《工業用水法》
・工業用水の地下水利用を10都府県65市区町村が地域指定され規制
《建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)》
・建物用井戸について4都府県37市区町村が地域指定され採取を規制
《地盤沈下対策要綱》
・「関東平野北部」、「濃尾平野」、「筑後・佐賀平野」について地下水採取量の抑制対策(採取目標量の設定、代替水源の確保等)を実施
地下水を取りまく課題
・渇水時の地盤沈下
地下水採取の規制により、地盤沈下は沈静化傾向。但し、渇水時には水源の減少に伴い地下水が急激に揚水され、地盤沈下が発生。
・新たな地下水揚水施設が増加
法的規制対象外の地下水揚水施設(企業等の専用水道)が増大の傾向。
・地下水の塩水化
多数の臨海域で塩水化が発生し、現在も継続している地域が多い。
・新たな地下水障害
地下水位の回復に伴い、地下構造物に影響が発生。
・地下水汚染
地下水汚染は汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策も遅れている。
・緊急時の水源の確保
防災井戸の適正管理と運用ルールが確立していない。
渇水時の地盤沈下・地下水採取の法的規制等により全国的に地盤沈下は沈静化
・渇水時には、河川水源の減少に伴い地下水の急激な揚水が行われ、短期的な地盤沈下が発生
→ 適切な地下水管理による地盤沈下発生の予防が必要
新たな地下水障害・地下水位の回復に伴う地下構造物へ影響
・大都市圏(東京・大阪)では、地下水位の回復に伴い、地下水位が大幅に低下した時期に計画・建設された地下構造物の浮き上がり、湧水量の増大がみられる。また地震時の液状化の可能性が懸念
→ 管理地下水位(無害水位)を定め、利用可能な範囲内で地下水採取を行うなどの地下水位維持方策が必要
新たな地下水揚水施設が増加・法的規制対象外の地下水揚水施設が増加
・近年、小口径高程ポンプや水質改善膜ろ過技術の開発に伴い、専用水道による地下水利用が増大
(特に、ホテル、病院、ショッピングセンターなどの個別水道施設で導入が増加)
・専用水道は、地盤沈下防止等を目的とした法体系の規制対象外の施設が多く、揚水量の実態が不明
→ 地盤沈下への影響が懸念
★大阪市はH20年度より「水道事業供給条例」を改訂し、地下水等利用専用水道の設置者に対して水質管理を強化。併せて設置届書(給水量記載)の提出を義務化
地下水の塩水化・多数の臨海部では、地下水の過剰採取により帯水層に海水が浸入し、地下水が塩水化。
→ 飲用不適、工業用水水質の悪化、農作物への被害等が発生。
・地下水規制等により対策を実施しているが、現在も被害が認められる地域が多い(全国14地域)。また、いったん塩水化した地下水は自然回復に長い年月を要する。
・今後、気候変動等による海面上昇の影響により塩水化がさらに拡大することが懸念される。
→ モニタリング等の水質管理の徹底や遮水壁などのハード対策も検討が必要
地下水汚染・環境省は、毎年度、都道府県等を対象として、「地下水汚染に関するアンケート調査」を実施。






・地下水汚染は、汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策の実施も2割弱。
→ モニタリング等の水質管理の徹底や規制強化が必要
緊急時の水源として、適切な地下水利用の推進
・電力は地震発生から2日後に復旧完了→電気の復旧直後から地下水利用開始
・地震発生当日から給水車到着→飲料水は入手しやすいが、生活用水が不足
・柏崎市の約8割の井戸で地震後も利用が可能(注)→緊急時の水源として有効
今後の取り組み
1.地下水の情報共有化及び調査研究体制の整備
?地下水関連データの収集・整備と情報公開の推進
?流域単位の地下水情報の一元管理と体制整備
?流域単位の総合的な調査観測計画の策定と調査研究体制整備
?官民一体となった地下水動態とメカニズムの解明
2.地下水の適正な利用のための方策
?流域単位の地下水マネジメントのための体制整備
?流域単位の地下水の適正採取量・採取深度の検討方策の検討
?地下水と地表水の一体的なマネジメント方策の検討
3.地下水の適正な管理のための方策
?地下水動態を踏まえた観測・モニタリング体制の整備
?地下水管理水位の設定と緊急時の体制整備
?担当者のための管理マニュアルの作成
?地下水管理者・利用者への迅速な情報伝達方法
?地下水収支や利用を踏まえた地下水涵養対策の実施
?地震災害時等の緊急時に使用する防災井戸のガイドライン作成
4.地下水質の監視と保全
?地下水汚染に対して、監視体制の強化、情報共有対応体制の確立
?地球温暖化に向けた塩水化防止対策の検討
http://www.mlit.go.jp/common/000017998.pdf
・地下水は、民法上は土地所有権の範囲として私有財産的な扱い。
・地下水は流動し水循環の一形態として存在するが「公水」として管理する法律はなく
・公害防止の観点(地盤沈下、水質保全)から法律や条例等により規制。
地下水規制(国)《環境基本法》
・地下水の水質汚濁に係わる環境基準の設定
《水質汚濁防止法》
・排水の地下浸透に係わる排水基準
《工業用水法》
・工業用水の地下水利用を10都府県65市区町村が地域指定され規制
《建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)》
・建物用井戸について4都府県37市区町村が地域指定され採取を規制
《地盤沈下対策要綱》
・「関東平野北部」、「濃尾平野」、「筑後・佐賀平野」について地下水採取量の抑制対策(採取目標量の設定、代替水源の確保等)を実施
地下水を取りまく課題
・渇水時の地盤沈下
地下水採取の規制により、地盤沈下は沈静化傾向。但し、渇水時には水源の減少に伴い地下水が急激に揚水され、地盤沈下が発生。
・新たな地下水揚水施設が増加
法的規制対象外の地下水揚水施設(企業等の専用水道)が増大の傾向。
・地下水の塩水化
多数の臨海域で塩水化が発生し、現在も継続している地域が多い。
・新たな地下水障害
地下水位の回復に伴い、地下構造物に影響が発生。
・地下水汚染
地下水汚染は汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策も遅れている。
・緊急時の水源の確保
防災井戸の適正管理と運用ルールが確立していない。
渇水時の地盤沈下・地下水採取の法的規制等により全国的に地盤沈下は沈静化
・渇水時には、河川水源の減少に伴い地下水の急激な揚水が行われ、短期的な地盤沈下が発生
→ 適切な地下水管理による地盤沈下発生の予防が必要
新たな地下水障害・地下水位の回復に伴う地下構造物へ影響
・大都市圏(東京・大阪)では、地下水位の回復に伴い、地下水位が大幅に低下した時期に計画・建設された地下構造物の浮き上がり、湧水量の増大がみられる。また地震時の液状化の可能性が懸念
→ 管理地下水位(無害水位)を定め、利用可能な範囲内で地下水採取を行うなどの地下水位維持方策が必要
新たな地下水揚水施設が増加・法的規制対象外の地下水揚水施設が増加
・近年、小口径高程ポンプや水質改善膜ろ過技術の開発に伴い、専用水道による地下水利用が増大
(特に、ホテル、病院、ショッピングセンターなどの個別水道施設で導入が増加)
・専用水道は、地盤沈下防止等を目的とした法体系の規制対象外の施設が多く、揚水量の実態が不明
→ 地盤沈下への影響が懸念
★大阪市はH20年度より「水道事業供給条例」を改訂し、地下水等利用専用水道の設置者に対して水質管理を強化。併せて設置届書(給水量記載)の提出を義務化
地下水の塩水化・多数の臨海部では、地下水の過剰採取により帯水層に海水が浸入し、地下水が塩水化。
→ 飲用不適、工業用水水質の悪化、農作物への被害等が発生。
・地下水規制等により対策を実施しているが、現在も被害が認められる地域が多い(全国14地域)。また、いったん塩水化した地下水は自然回復に長い年月を要する。
・今後、気候変動等による海面上昇の影響により塩水化がさらに拡大することが懸念される。
→ モニタリング等の水質管理の徹底や遮水壁などのハード対策も検討が必要
地下水汚染・環境省は、毎年度、都道府県等を対象として、「地下水汚染に関するアンケート調査」を実施。






・地下水汚染は、汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策の実施も2割弱。
→ モニタリング等の水質管理の徹底や規制強化が必要
緊急時の水源として、適切な地下水利用の推進
・電力は地震発生から2日後に復旧完了→電気の復旧直後から地下水利用開始
・地震発生当日から給水車到着→飲料水は入手しやすいが、生活用水が不足
・柏崎市の約8割の井戸で地震後も利用が可能(注)→緊急時の水源として有効
今後の取り組み
1.地下水の情報共有化及び調査研究体制の整備
?地下水関連データの収集・整備と情報公開の推進
?流域単位の地下水情報の一元管理と体制整備
?流域単位の総合的な調査観測計画の策定と調査研究体制整備
?官民一体となった地下水動態とメカニズムの解明
2.地下水の適正な利用のための方策
?流域単位の地下水マネジメントのための体制整備
?流域単位の地下水の適正採取量・採取深度の検討方策の検討
?地下水と地表水の一体的なマネジメント方策の検討
3.地下水の適正な管理のための方策
?地下水動態を踏まえた観測・モニタリング体制の整備
?地下水管理水位の設定と緊急時の体制整備
?担当者のための管理マニュアルの作成
?地下水管理者・利用者への迅速な情報伝達方法
?地下水収支や利用を踏まえた地下水涵養対策の実施
?地震災害時等の緊急時に使用する防災井戸のガイドライン作成
4.地下水質の監視と保全
?地下水汚染に対して、監視体制の強化、情報共有対応体制の確立
?地球温暖化に向けた塩水化防止対策の検討
http://www.mlit.go.jp/common/000017998.pdf