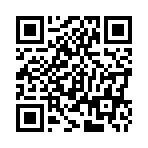2009年10月31日
チッソ水俣病 損害賠償,仮執行の原状回復等請求上告
事件番号 平成13(オ)1194
事件名 損害賠償,仮執行の原状回復等請求上告,同附帯上告事件
判示事項
1 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
2 熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
3 水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例
裁判要旨
1 国が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,同工場の排水に含まれる微量の水銀の定量分析をすることが可能であったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律に基づいて,指定水域の指定,水質基準及び特定施設の定めをし,上記製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,同施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
2 熊本県が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,旧熊本県漁業調整規則に基づいて,上記製造施設からの工場排水につき除害に必要な設備の設置を命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
3 水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となる。
参照法条
国家賠償法1条1項,公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの)1条,
公共用水域の水質の保全に関する法律5条,
工場排水等の規制に関する法律1条,
裁判年月日 平成16年10月15日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成6(ネ)1950
原審裁判年月日 平成13年04月27日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=
dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25100&hanreiKbn=01
主 文
1 原判決のうち,被上告人X22,同X23,同X53,同X54,同X55,同X64,同X65,同X66,同X67及び同X68の上告人らに対する請求を認容した部分を破棄する。
2 前項の部分につき,上記被上告人らの控訴をいずれも棄却する。
3 原判決のうち,被上告人X36,同X51及び同X52の上告人らに対する請求に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 上告人らは,各自,被上告人X36,同X51及び同X52に対し,各25万円及びこれに対する昭和57年12月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被上告人X36,同X51及び同X52の上告人らに対するその余の控訴をいずれも棄却する。
4 上告人らのその余の上告及び附帯上告人らの附帯上告をいずれも棄却する。
5 第1項記載の部分に関する控訴費用及び上告費用は同項記載の被上告人らの負担とし,第3項記載の部分に関する訴訟の総費用は,これを10分し,その1を上告人らの,その余を同項記載の被上告人らの各負担とし,前項の部分に関する上告費用は上告人らの負担とし,附帯上告費用は附帯上告人らの負担とする。
理 由
第1 事案の概要
1 被上告人らは,水俣病の患者であると主張する者(原判決別紙「結果一覧表」の患者氏名欄記載の58名のうち,患者番号13〜15,28,41,42,44,46,47,52,53,58,59の13名を除く45名。以下「本件患者」と総称する。)又はその承継人である。本件は,被上告人らが,上告人らは水俣病の発生及び被害拡大の防止のために規制権限を行使することを怠ったことにつき国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うなどと主張して,上告人らに対し,損害賠償を請求する訴訟である。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 水俣病は,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を多量に摂取したことによって起こる中毒性中枢神経疾患である。
その主要な症状としては,感覚障害,運動失調,求心性視野狭さく,聴力障害,言語障害等がある。
個々の患者には重症例から軽症例まで多様な形態がみられ,症状が重篤なときは,死亡するに至る。
水俣病の原因物質は,有機水銀化合物の一種であるメチル水銀化合物であり,これは,チッソ株式会社(昭和40年に商号を変更する前の商号は,新日本窒素肥料株式会社。以下「チッソ」という。)水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成され,同工場の排水に含まれて工場外に流出したものであった。水俣病は,このメチル水銀化合物が,魚介類の体内に蓄積され,その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれ,大脳,小脳等に蓄積し,神経細胞に障害を与えることによって引き起こされた疾病である。
(2) 本件患者らは,かつて水俣湾周辺地域に居住し,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取していた。本件患者らのうち,A(患者番号16),X23(同17),X36(同24),X51(同32),X52(同33),B(同34),C(同45),X68(同49)は昭和34年12月末までに,それ以外の者は昭和35年1月以降に,関西方面に転居した。
(3) 昭和31年5月1日,チッソ水俣工場附属病院の医師が,水俣保健所に対し,水俣市内において脳症状を呈する原因不明の患者が発生した旨の報告をした。公的機関が水俣病の存在を認識したのはこれが初めてであり,この時が水俣病の「公式発見」と呼ばれる。この報告を受けた水俣保健所等が調査をしたところ,昭和28年ころから同様の症状を呈する患者が発生していたこと,昭和32年1月の時点で54名の患者が発生し,うち17名が死亡していたことが判明した。
(4) 水俣病の原因については,上記公式発見以降,水俣保健所,熊本大学医学部の水俣病医学研究班(以下「熊大研究班」という。),厚生省(以下,省庁名,官職名等は,いずれも当時のものである。)の厚生科学研究班等により,調査や研究が行われた。原因究明は困難を極めたが,昭和31年11月開催の熊大研究班の研究報告会において魚介類との関係が一応疑われるとの報告がされ,昭和32年1月開催の国立公衆衛生院での上告人国,上告人県の関係者も参加した合同研究発表会において魚介類の摂取が原因であるとの一応の結論に達した。
上告人県は,水俣市の住民に対して水俣湾の魚介類を摂取しないように呼び掛けるとともに,湾内での漁業を自粛するよう,地元の漁業協同組合に申し入れた。このような行政指導の結果,昭和31年12月以降,しばらくの間は,新たな患者の発生がみられなくなった。
昭和32年7月開催の厚生科学研究班の研究報告会において,水俣病は,感染症ではなく,中毒症であり,何らかの化学物質によって汚染された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであるとの結論が示されたが,原因物質が何であるかは不明のままであり,当時は,マンガン,タリウム,セレン等の物質が疑われていた。
昭和33年6月開催の参議院社会労働委員会において,厚生省環境衛生部長は,水俣病の原因物質は水俣市の肥料工場から流失したと推定されるとの発言をした。
また,同年7月,同省公衆衛生局長は,関係省庁及び上告人県に対して発した文書により,水俣病はある種の化学毒物によって有毒化された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであり,肥料工場の廃棄物によって魚介類が有毒化されると推定した上で,水俣病の対策について一層効率的な措置を講ずることを要望した。
他方,通商産業省(以下「通産省」という。)軽工業局長は,同年9月ころ,厚生省に対し,水俣病の原因が確定していない現段階において断定的な見解を述べることがないよう申し入れた。
(5) 昭和33年8月,新たな水俣病患者の発生が確認された。この患者は,水俣湾の魚介類を自ら捕獲して,多量に摂取したものであった。
上告人県は,水俣湾の魚介類を摂取しないことを周知徹底させるべく,住民に対して改めて広報活動を行うとともに,地元の漁業協同組合に対し漁業を自粛するよう申し入れた。
(6) 昭和33年9月,チッソは,アセトアルデヒド製造施設からの排水の放出経路を,水俣湾内にある百間港から湾外の水俣川河口付近へと変更した。その結果,昭和34年3月以降,水俣湾外の海域で漁獲された魚介類を多食していた者についても水俣病の発症が確認され,湾外の魚介類も危険視されることとなった。
(7) 昭和34年3月刊行の熊大研究班の報告書に,水俣病の症状が有機水銀中毒の症状(いわゆるハンター・ラッセル症候群)と一致する旨を述べた論文が掲載された。
熊大研究班は,その後も調査研究を続け,同年7月22日に開催された研究報告会において,水俣病は現地の魚介類を摂取することによって引き起こされる神経系疾患であり,魚介類を汚染する毒物としては水銀が極めて注目されるに至ったと発表した。
また,厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会の特別部会として昭和34年1月に発足した水俣食中毒部会は,同年10月6日,水俣病は有機水銀中毒症に酷似しており,その原因物質としては水銀が最も重要視されるとの中間報告を行った。
同年11月12日,食品衛生調査会は,この中間報告に基づいて,水俣病の主因を成すものはある種の有機水銀化合物であるとの結論を出し,厚生大臣に対してその旨を答申した。
水俣食中毒部会は,この答申によりその目的を達したとして,そのころ解散した。その後,水俣病の原因についての総合的な調査研究は,経済企画庁が中心となり,厚生省,通産省及び水産庁が分担して行うものとされた。
なお,昭和34年10月ころ,チッソ水俣工場附属病院の医師が行った実験により,チッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設の排水を経口投与したネコに水俣病と同様の症状が現れることが認められた。
ところが,チッソは,実験の続行を中止し,この実験結果を公表しなかった。
(8) 上告人らが把握していた昭和34年8月現在の水俣病患者の発生状況は,患者数71名,死亡者28名であった。通産省は,そのころ,水俣病が現地において極めて深刻な問題となっている状況にかんがみ,チッソ水俣工場に対し,口頭で,水俣川河口への排水路を廃止すること,排水処理装置の完備を急ぐこと,原因究明のための調査に十分協力することを求める行政指導を行った。
また,通産省は,同年10月末から11月にかけて,厚生省公衆衛生局長,水産庁長官等から,チッソ水俣工場の排水に対して適切な処置を至急講ずるよう求める旨の要望を受けたので,チッソの社長あてに文書を送付して,一刻も早く排水処理施設を
完備することなどを求めた。
昭和34年12月,サイクレーター,セディフローターを主体とする排水浄化装置がチッソ水俣工場に設置された。チッソは,これによって工場排水が浄化される旨を強調したが,この装置は水銀の除去を目的とするものではなかった。
そのことは,多少の化学知識のある者が,上記装置の設計図等を見れば,容易に知ることができた。
(9) 昭和34年12月,熊本県知事らのあっせんにより,チッソと熊本県漁業協同組合連合会との間に漁業補償に関する契約が,水俣病患者家庭互助会との間に見舞金の支払に関する契約が,それぞれ締結された。
(10) 昭和34年当時の総水銀(有機水銀化合物に加え,金属水銀,無機水銀化合物を含むもの)の一般的な定量分析技術においては,0.01ppmが定量分析の限界であるとされていたが,工業技術院東京工業試験所は,同年11月下旬ころには,独自に工夫した方法によって総水銀について0.001ppmレベルまで定量分析し得る技術を有していた。同試験所は,そのころから昭和35年8月までの間,通産省の依頼を受けて,チッソ水俣工場の排水中の総水銀を定量分析し,0.002〜0.084ppmの総水銀が検出されたとの検査結果を報告した。
(11) 上告人らは,遅くとも昭和34年11月末ころまでには,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であること,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあった。
また,上告人らにおいて,そのころまでには,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析は可能であったし,チッソが整備した上記排水浄化施設が水銀の除去を目的としたものではなかったことも容易に知ることができた。
(12) 昭和43年5月,チッソは,水俣工場におけるアセトアルデヒドの製造を取りやめた。これにより,同工場からメチル水銀化合物が排出されることはなくなった。
同年9月,上告人国は,水俣病はチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成されたメチル水銀化合物が原因で発生したものである旨の政府見解を発表した。昭和44年,水俣湾及びその周辺海域について,後述する水質二法に基づく指定水域の指定等がされた。
第2 平成13年(オ)第1194号上告代理人都築弘ほかの上告理由について
1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
2 所論にかんがみ,職権により判断する。
前記の事実関係の下において,上告人らが,昭和35年1月以降,チッソ水俣工場の排水に関して規制権限を行使しなかったことが違法であり,上告人らは,同月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害の拡大があった者に対して国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,後述のとおり,正当として是認することができる。そうすると,本件患者らのうち,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域からその地域外へ転居した者については,水俣病となったことによる
損害を受けているとしても,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係を認めることはできない。ところが,原審は,本件患者らのうちA,X23,X36,X51,X52,B,C,X68について,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域から転居したとの事実を認定しながら,上記8名の本件患者に係る損害賠償請求を一部認容したものであって,原判決には,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係の存否の判断につき,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるといわざるを得ない。
したがって,原判決のうち,上記8名の本件患者ら又はその承継人である被上告人X22,同X23,同X36,同X51,同X52,同X53,同X54,同X55,同X64,同X65,同X66,同X67及び同X68の上告人らに対する請求(ただし,被上告人X36,同X51及び同X52については,D(患者番号31)の承継人として請求する部分を除く。)を認容した部分は,破棄を免れない。
そして,同部分に係る上記被上告人らの請求を棄却した第1審判決は,結論において是認することができるから,同部分についての上記被上告人らの控訴はいずれも棄却されるべきものである。
第3 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第3及び第4について
1 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの。以下「水質保全法」という。)及び工場排水等の規制に関する法律(以下「工場排水規制法」という。また,水質保全法と併せて,「水質二法」という。)は,昭和33年12月25日に公布され,昭和34年3月1日に施行された(その後,水質二法は,昭和45年12月に公布された水質汚濁防止法の施行に伴って廃止された。)。
水質保全法は,公共用水域の水質の保全を図るなどのために必要な事項を定め,もって産業の相互協和と公衆衛生の向上
に寄与することを目的とするものであり(同法1条),工場排水規制法は,製造業等における事業活動に伴って発生する汚水等の処理を適切にすることにより,公共用水域の水質の保全を図ることを目的とするものである(同法1条)。
水質二法による工場排水規制の概要は,次のとおりである。
経済企画庁長官は,公共用水域のうち,水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の被害が生じ,若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを「指定水域」として指定するとともに(水質保全法5条1項),当該指定水域に係る「水質基準」を定めるものとされている(同条2項)。
水質基準とは,「特定施設」を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度であり(同法3条2項),特定施設とは,製造業等の用に供する施設のうち,汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出するもので政令で定めるものである(工場排水規制法2条2項)。また,主務大臣(特定施設の種類ごとに,政令により定められる。同法21条1項)は,工場排水の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは,これを排出する者に対し,汚水等の処理方法に関する計画の変更,特定施設の設置に関する計画の変更等を命ずること(同法7条),汚水等の処理方法の改善,特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を執るべき旨を命ずること(同法12条)等の,特定施設から排出される工場排水に関して規制を
行う権限を有するものとされており,主務大臣の上記命令に違反した者は,罰則を科される(同法23条)。
2 熊本県漁業調整規則は,漁業法65条及び水産資源保護法4条の規定に基づいて制定されたものであり,水産動植物の繁殖保
護,漁業取締りその他漁業調整を図り,併せて漁業秩序の確立を期するため,必要な事項を定めることを目的とするものである(県漁業調整規則1条)。
県漁業調整規則は,何人も水産動植物の繁殖保護に有害な物を遺棄し,又は漏せつするおそれのあるものを放置してはならない旨を定め,これに違反する者があるときは,熊本県知事は,その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ,又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができるものとされている(同規則32条)。上記の規定又は命令に違反した者に対しては罰則が科される(同58条)。
3 原審は,前記の事実関係の下において,チッソ水俣工場の排水につき,上告人国においては上記の水質二法に基づく規制権限を,上告人県においては上記の県漁業調整規則に基づく規制権限を,それぞれ行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,昭和35年1月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害が拡大した者に対して,同項による損害賠償責任を負うと判断した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,水質二法,県漁業調整規則の関係規定及び国家賠償法1条1項の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
4 そこで,以下,この点について検討する。
(1) 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6号1600頁参照)。
(2) これを本件についてみると,まず,上告人国の責任については,次のとおりである。
ア 水質二法所定の前記規制は,
? 特定の公共用水域の水質の汚濁が原因となって,関係産業に相当の損害が生じたり,公衆衛生上看過し難い影響が生じたりしたとき,又はそれらのおそれがあるときに,当該水域を指定水域に指定し,この指定水域に係る水質基準(特定施設を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度)を定めること,汚水等を排出する施設を特定施設として政令で定めることといった水質二法所定の手続が執られたことを前提として,
? 主務大臣が,工場排水規制法7条,12条に基づき,特定施設から排出される工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないときに,その水質を保全するため,工場排水についての処理方法の改善,当該特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を命ずる等の規制権限を行使するものである。そして,この権限は,当該水域の水質の悪化にかかわりのある周辺住民の生命,健康の保護をその主要な目的の一つとして,適時にかつ適切に行使されるべきものである。
イ 【要旨1】
前記の事実関係によれば,昭和34年11月末の時点で,
? 昭和31年5月1日の水俣病の公式発見から起算しても既に約3年半が経過しており,その間,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取する住民の生命,健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続していたのであって,上告人国は,現に多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていることを認識していたこと,
? 上告人国においては,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,
? 上告人国にとって,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析をすることは可能であったことといった事情を認めることができる。なお,チッソが昭和34年12月に整備した前記排水浄化装置が水銀の除去を目的としたものではなかったことを容易に知り得たことも,前記認定のとおりである。
そうすると,同年11月末の時点において,水俣湾及びその周辺海域を指定水域に指定すること,当該指定水域に排出される工場排水から水銀又はその化合物が検出されないという水質基準を定めること,アセトアルデヒド製造施設を特定施設に定めることという上記規制権限を行使するために必要な水質二法所定の手続を直ちに執ることが可能であり,また,そうすべき状況にあったものといわなければならない。
そして,この手続に要する期間を考慮に入れても,同年12月末には,主務大臣として定められるべき通商産業大臣において,上記規制権限を行使して,チッソに対し水俣工場のアセトアルデヒド製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,当該施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずることが可能であり,しかも,水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると,直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当である。
また,この時点で上記規制権限が行使されていれば,それ以降の水俣病の被害拡大を防ぐことができたこと,ところが,実際には,その行使がされなかったために,被害が拡大する結果となったことも明らかである。
ウ 本件における以上の諸事情を総合すると,昭和35年1月以降,水質二法に基づく上記規制権限を行使しなかったことは,上記規制権限を定めた水質二法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法というべきである。
したがって,同項による上告人国の損害賠償責任を認めた原審の判断は,正当として是認することができる。この点に関する上告人国の論旨は採用することができない。
(3) 次に,【要旨2】
上告人県の責任についてみると,以上説示したところによれば,前記事実関係の下において,熊本県知事は,水俣病にかかわる前記諸事情について上告人国と同様の認識を有し,又は有し得る状況にあったのであり,同知事には,昭和34年12月末までに県漁業調整規則32条に基づく規制権限を行使すべき作為義務があり,昭和35年1月以降,この権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くものであるとして,上告人県が国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,同規則が,水産動植物の繁殖保護等を直接の目的とするものではあるが,それを摂取する者の健康の保持等をもその究極の目的とするものであると解されることからすれば,是認することができる。
この点に関する上告人県の論旨を採用することはできない。
第4 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第5について
1 被上告人らの上告人らに対する請求(前記第2で判示したところにより棄却されるべき部分を除く。)については,国家賠償法4条,民法724条後段所定の除斥期間の適用の有無が問題となるところ,原審は,その適用を否定した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,上記各規定の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
2 そこで,以下,この点について検討する。
(1) 民法724条後段所定の除斥期間は,「不法行為ノ時ヨリ二十年」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となると考えられる。
しかし,身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解するのが相当である。
このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間が進行することを認めることは,被害者にとって著しく酷であるだけでなく,加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過した後に損害が発生し,被害者から損害賠償の請求を受けることがあることを予期すべきであると考えられるからである。原審の判断は,以上の趣旨をいうものとして,是認することができる。論旨は採用することができない。
(2) 【要旨3】
上記見解に立って本件をみると,本件患者のそれぞれが水俣湾周辺地域から他の地域へ転居した時点が各自についての加害行為の終了した時であるが,水俣病患者の中には,潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては,水俣湾又はその周辺海域の魚介類の摂取を中止してから4年以内に水俣病の症状が客観的に現れることなど,原審の認定した事実関係の下では,上記転居から遅くとも4年を経過した時点が本件における除斥期間の起算点となるとした原審の判断も,是認し得るものということができる。この点に関する上告人らの論旨も採用することができない。
第5 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかのその余の上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
第6 平成13年(オ)第1196号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告理由について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件附帯上告の理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
第7 平成13年(受)第1174号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
第8 結論
以上によれば,上告人らの上告は,前記第2の限度で理由があるから,主文第1項記載の部分につき原判決を破棄し,同第3項記載の部分につき原判決を変更すべきものであるが,その余の上告はいずれも理由がないので,これを棄却することとする。また,附帯上告人らの附帯上告には理由がないので,これを棄却する。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田 博 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/67930C1EA789333049257029002690BE.pdf

「奇病のかげに」は、熊本県の水俣病を工場公害ではないかと告発した
踊り回る猫(3コマ目)の姿は「奇病」の本質をとらえた。小倉一郎の作品。

事件名 損害賠償,仮執行の原状回復等請求上告,同附帯上告事件
判示事項
1 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
2 熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
3 水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例
裁判要旨
1 国が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,同工場の排水に含まれる微量の水銀の定量分析をすることが可能であったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律に基づいて,指定水域の指定,水質基準及び特定施設の定めをし,上記製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,同施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
2 熊本県が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,旧熊本県漁業調整規則に基づいて,上記製造施設からの工場排水につき除害に必要な設備の設置を命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
3 水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となる。
参照法条
国家賠償法1条1項,公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの)1条,
公共用水域の水質の保全に関する法律5条,
工場排水等の規制に関する法律1条,
裁判年月日 平成16年10月15日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成6(ネ)1950
原審裁判年月日 平成13年04月27日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=
dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25100&hanreiKbn=01
主 文
1 原判決のうち,被上告人X22,同X23,同X53,同X54,同X55,同X64,同X65,同X66,同X67及び同X68の上告人らに対する請求を認容した部分を破棄する。
2 前項の部分につき,上記被上告人らの控訴をいずれも棄却する。
3 原判決のうち,被上告人X36,同X51及び同X52の上告人らに対する請求に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 上告人らは,各自,被上告人X36,同X51及び同X52に対し,各25万円及びこれに対する昭和57年12月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被上告人X36,同X51及び同X52の上告人らに対するその余の控訴をいずれも棄却する。
4 上告人らのその余の上告及び附帯上告人らの附帯上告をいずれも棄却する。
5 第1項記載の部分に関する控訴費用及び上告費用は同項記載の被上告人らの負担とし,第3項記載の部分に関する訴訟の総費用は,これを10分し,その1を上告人らの,その余を同項記載の被上告人らの各負担とし,前項の部分に関する上告費用は上告人らの負担とし,附帯上告費用は附帯上告人らの負担とする。
理 由
第1 事案の概要
1 被上告人らは,水俣病の患者であると主張する者(原判決別紙「結果一覧表」の患者氏名欄記載の58名のうち,患者番号13〜15,28,41,42,44,46,47,52,53,58,59の13名を除く45名。以下「本件患者」と総称する。)又はその承継人である。本件は,被上告人らが,上告人らは水俣病の発生及び被害拡大の防止のために規制権限を行使することを怠ったことにつき国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うなどと主張して,上告人らに対し,損害賠償を請求する訴訟である。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 水俣病は,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を多量に摂取したことによって起こる中毒性中枢神経疾患である。
その主要な症状としては,感覚障害,運動失調,求心性視野狭さく,聴力障害,言語障害等がある。
個々の患者には重症例から軽症例まで多様な形態がみられ,症状が重篤なときは,死亡するに至る。
水俣病の原因物質は,有機水銀化合物の一種であるメチル水銀化合物であり,これは,チッソ株式会社(昭和40年に商号を変更する前の商号は,新日本窒素肥料株式会社。以下「チッソ」という。)水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成され,同工場の排水に含まれて工場外に流出したものであった。水俣病は,このメチル水銀化合物が,魚介類の体内に蓄積され,その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれ,大脳,小脳等に蓄積し,神経細胞に障害を与えることによって引き起こされた疾病である。
(2) 本件患者らは,かつて水俣湾周辺地域に居住し,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取していた。本件患者らのうち,A(患者番号16),X23(同17),X36(同24),X51(同32),X52(同33),B(同34),C(同45),X68(同49)は昭和34年12月末までに,それ以外の者は昭和35年1月以降に,関西方面に転居した。
(3) 昭和31年5月1日,チッソ水俣工場附属病院の医師が,水俣保健所に対し,水俣市内において脳症状を呈する原因不明の患者が発生した旨の報告をした。公的機関が水俣病の存在を認識したのはこれが初めてであり,この時が水俣病の「公式発見」と呼ばれる。この報告を受けた水俣保健所等が調査をしたところ,昭和28年ころから同様の症状を呈する患者が発生していたこと,昭和32年1月の時点で54名の患者が発生し,うち17名が死亡していたことが判明した。
(4) 水俣病の原因については,上記公式発見以降,水俣保健所,熊本大学医学部の水俣病医学研究班(以下「熊大研究班」という。),厚生省(以下,省庁名,官職名等は,いずれも当時のものである。)の厚生科学研究班等により,調査や研究が行われた。原因究明は困難を極めたが,昭和31年11月開催の熊大研究班の研究報告会において魚介類との関係が一応疑われるとの報告がされ,昭和32年1月開催の国立公衆衛生院での上告人国,上告人県の関係者も参加した合同研究発表会において魚介類の摂取が原因であるとの一応の結論に達した。
上告人県は,水俣市の住民に対して水俣湾の魚介類を摂取しないように呼び掛けるとともに,湾内での漁業を自粛するよう,地元の漁業協同組合に申し入れた。このような行政指導の結果,昭和31年12月以降,しばらくの間は,新たな患者の発生がみられなくなった。
昭和32年7月開催の厚生科学研究班の研究報告会において,水俣病は,感染症ではなく,中毒症であり,何らかの化学物質によって汚染された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであるとの結論が示されたが,原因物質が何であるかは不明のままであり,当時は,マンガン,タリウム,セレン等の物質が疑われていた。
昭和33年6月開催の参議院社会労働委員会において,厚生省環境衛生部長は,水俣病の原因物質は水俣市の肥料工場から流失したと推定されるとの発言をした。
また,同年7月,同省公衆衛生局長は,関係省庁及び上告人県に対して発した文書により,水俣病はある種の化学毒物によって有毒化された魚介類を多量に摂取することによって発症するものであり,肥料工場の廃棄物によって魚介類が有毒化されると推定した上で,水俣病の対策について一層効率的な措置を講ずることを要望した。
他方,通商産業省(以下「通産省」という。)軽工業局長は,同年9月ころ,厚生省に対し,水俣病の原因が確定していない現段階において断定的な見解を述べることがないよう申し入れた。
(5) 昭和33年8月,新たな水俣病患者の発生が確認された。この患者は,水俣湾の魚介類を自ら捕獲して,多量に摂取したものであった。
上告人県は,水俣湾の魚介類を摂取しないことを周知徹底させるべく,住民に対して改めて広報活動を行うとともに,地元の漁業協同組合に対し漁業を自粛するよう申し入れた。
(6) 昭和33年9月,チッソは,アセトアルデヒド製造施設からの排水の放出経路を,水俣湾内にある百間港から湾外の水俣川河口付近へと変更した。その結果,昭和34年3月以降,水俣湾外の海域で漁獲された魚介類を多食していた者についても水俣病の発症が確認され,湾外の魚介類も危険視されることとなった。
(7) 昭和34年3月刊行の熊大研究班の報告書に,水俣病の症状が有機水銀中毒の症状(いわゆるハンター・ラッセル症候群)と一致する旨を述べた論文が掲載された。
熊大研究班は,その後も調査研究を続け,同年7月22日に開催された研究報告会において,水俣病は現地の魚介類を摂取することによって引き起こされる神経系疾患であり,魚介類を汚染する毒物としては水銀が極めて注目されるに至ったと発表した。
また,厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会の特別部会として昭和34年1月に発足した水俣食中毒部会は,同年10月6日,水俣病は有機水銀中毒症に酷似しており,その原因物質としては水銀が最も重要視されるとの中間報告を行った。
同年11月12日,食品衛生調査会は,この中間報告に基づいて,水俣病の主因を成すものはある種の有機水銀化合物であるとの結論を出し,厚生大臣に対してその旨を答申した。
水俣食中毒部会は,この答申によりその目的を達したとして,そのころ解散した。その後,水俣病の原因についての総合的な調査研究は,経済企画庁が中心となり,厚生省,通産省及び水産庁が分担して行うものとされた。
なお,昭和34年10月ころ,チッソ水俣工場附属病院の医師が行った実験により,チッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設の排水を経口投与したネコに水俣病と同様の症状が現れることが認められた。
ところが,チッソは,実験の続行を中止し,この実験結果を公表しなかった。
(8) 上告人らが把握していた昭和34年8月現在の水俣病患者の発生状況は,患者数71名,死亡者28名であった。通産省は,そのころ,水俣病が現地において極めて深刻な問題となっている状況にかんがみ,チッソ水俣工場に対し,口頭で,水俣川河口への排水路を廃止すること,排水処理装置の完備を急ぐこと,原因究明のための調査に十分協力することを求める行政指導を行った。
また,通産省は,同年10月末から11月にかけて,厚生省公衆衛生局長,水産庁長官等から,チッソ水俣工場の排水に対して適切な処置を至急講ずるよう求める旨の要望を受けたので,チッソの社長あてに文書を送付して,一刻も早く排水処理施設を
完備することなどを求めた。
昭和34年12月,サイクレーター,セディフローターを主体とする排水浄化装置がチッソ水俣工場に設置された。チッソは,これによって工場排水が浄化される旨を強調したが,この装置は水銀の除去を目的とするものではなかった。
そのことは,多少の化学知識のある者が,上記装置の設計図等を見れば,容易に知ることができた。
(9) 昭和34年12月,熊本県知事らのあっせんにより,チッソと熊本県漁業協同組合連合会との間に漁業補償に関する契約が,水俣病患者家庭互助会との間に見舞金の支払に関する契約が,それぞれ締結された。
(10) 昭和34年当時の総水銀(有機水銀化合物に加え,金属水銀,無機水銀化合物を含むもの)の一般的な定量分析技術においては,0.01ppmが定量分析の限界であるとされていたが,工業技術院東京工業試験所は,同年11月下旬ころには,独自に工夫した方法によって総水銀について0.001ppmレベルまで定量分析し得る技術を有していた。同試験所は,そのころから昭和35年8月までの間,通産省の依頼を受けて,チッソ水俣工場の排水中の総水銀を定量分析し,0.002〜0.084ppmの総水銀が検出されたとの検査結果を報告した。
(11) 上告人らは,遅くとも昭和34年11月末ころまでには,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であること,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあった。
また,上告人らにおいて,そのころまでには,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析は可能であったし,チッソが整備した上記排水浄化施設が水銀の除去を目的としたものではなかったことも容易に知ることができた。
(12) 昭和43年5月,チッソは,水俣工場におけるアセトアルデヒドの製造を取りやめた。これにより,同工場からメチル水銀化合物が排出されることはなくなった。
同年9月,上告人国は,水俣病はチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成されたメチル水銀化合物が原因で発生したものである旨の政府見解を発表した。昭和44年,水俣湾及びその周辺海域について,後述する水質二法に基づく指定水域の指定等がされた。
第2 平成13年(オ)第1194号上告代理人都築弘ほかの上告理由について
1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
2 所論にかんがみ,職権により判断する。
前記の事実関係の下において,上告人らが,昭和35年1月以降,チッソ水俣工場の排水に関して規制権限を行使しなかったことが違法であり,上告人らは,同月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害の拡大があった者に対して国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,後述のとおり,正当として是認することができる。そうすると,本件患者らのうち,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域からその地域外へ転居した者については,水俣病となったことによる
損害を受けているとしても,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係を認めることはできない。ところが,原審は,本件患者らのうちA,X23,X36,X51,X52,B,C,X68について,昭和34年12月末以前に水俣湾周辺地域から転居したとの事実を認定しながら,上記8名の本件患者に係る損害賠償請求を一部認容したものであって,原判決には,上告人らの上記の違法な不作為と損害との間の因果関係の存否の判断につき,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるといわざるを得ない。
したがって,原判決のうち,上記8名の本件患者ら又はその承継人である被上告人X22,同X23,同X36,同X51,同X52,同X53,同X54,同X55,同X64,同X65,同X66,同X67及び同X68の上告人らに対する請求(ただし,被上告人X36,同X51及び同X52については,D(患者番号31)の承継人として請求する部分を除く。)を認容した部分は,破棄を免れない。
そして,同部分に係る上記被上告人らの請求を棄却した第1審判決は,結論において是認することができるから,同部分についての上記被上告人らの控訴はいずれも棄却されるべきものである。
第3 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第3及び第4について
1 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの。以下「水質保全法」という。)及び工場排水等の規制に関する法律(以下「工場排水規制法」という。また,水質保全法と併せて,「水質二法」という。)は,昭和33年12月25日に公布され,昭和34年3月1日に施行された(その後,水質二法は,昭和45年12月に公布された水質汚濁防止法の施行に伴って廃止された。)。
水質保全法は,公共用水域の水質の保全を図るなどのために必要な事項を定め,もって産業の相互協和と公衆衛生の向上
に寄与することを目的とするものであり(同法1条),工場排水規制法は,製造業等における事業活動に伴って発生する汚水等の処理を適切にすることにより,公共用水域の水質の保全を図ることを目的とするものである(同法1条)。
水質二法による工場排水規制の概要は,次のとおりである。
経済企画庁長官は,公共用水域のうち,水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の被害が生じ,若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを「指定水域」として指定するとともに(水質保全法5条1項),当該指定水域に係る「水質基準」を定めるものとされている(同条2項)。
水質基準とは,「特定施設」を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度であり(同法3条2項),特定施設とは,製造業等の用に供する施設のうち,汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出するもので政令で定めるものである(工場排水規制法2条2項)。また,主務大臣(特定施設の種類ごとに,政令により定められる。同法21条1項)は,工場排水の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは,これを排出する者に対し,汚水等の処理方法に関する計画の変更,特定施設の設置に関する計画の変更等を命ずること(同法7条),汚水等の処理方法の改善,特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を執るべき旨を命ずること(同法12条)等の,特定施設から排出される工場排水に関して規制を
行う権限を有するものとされており,主務大臣の上記命令に違反した者は,罰則を科される(同法23条)。
2 熊本県漁業調整規則は,漁業法65条及び水産資源保護法4条の規定に基づいて制定されたものであり,水産動植物の繁殖保
護,漁業取締りその他漁業調整を図り,併せて漁業秩序の確立を期するため,必要な事項を定めることを目的とするものである(県漁業調整規則1条)。
県漁業調整規則は,何人も水産動植物の繁殖保護に有害な物を遺棄し,又は漏せつするおそれのあるものを放置してはならない旨を定め,これに違反する者があるときは,熊本県知事は,その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ,又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができるものとされている(同規則32条)。上記の規定又は命令に違反した者に対しては罰則が科される(同58条)。
3 原審は,前記の事実関係の下において,チッソ水俣工場の排水につき,上告人国においては上記の水質二法に基づく規制権限を,上告人県においては上記の県漁業調整規則に基づく規制権限を,それぞれ行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,昭和35年1月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害が拡大した者に対して,同項による損害賠償責任を負うと判断した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,水質二法,県漁業調整規則の関係規定及び国家賠償法1条1項の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
4 そこで,以下,この点について検討する。
(1) 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6号1600頁参照)。
(2) これを本件についてみると,まず,上告人国の責任については,次のとおりである。
ア 水質二法所定の前記規制は,
? 特定の公共用水域の水質の汚濁が原因となって,関係産業に相当の損害が生じたり,公衆衛生上看過し難い影響が生じたりしたとき,又はそれらのおそれがあるときに,当該水域を指定水域に指定し,この指定水域に係る水質基準(特定施設を設置する工場等から指定水域に排出される水の汚濁の許容限度)を定めること,汚水等を排出する施設を特定施設として政令で定めることといった水質二法所定の手続が執られたことを前提として,
? 主務大臣が,工場排水規制法7条,12条に基づき,特定施設から排出される工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないときに,その水質を保全するため,工場排水についての処理方法の改善,当該特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を命ずる等の規制権限を行使するものである。そして,この権限は,当該水域の水質の悪化にかかわりのある周辺住民の生命,健康の保護をその主要な目的の一つとして,適時にかつ適切に行使されるべきものである。
イ 【要旨1】
前記の事実関係によれば,昭和34年11月末の時点で,
? 昭和31年5月1日の水俣病の公式発見から起算しても既に約3年半が経過しており,その間,水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取する住民の生命,健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続していたのであって,上告人国は,現に多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていることを認識していたこと,
? 上告人国においては,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,
? 上告人国にとって,チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析をすることは可能であったことといった事情を認めることができる。なお,チッソが昭和34年12月に整備した前記排水浄化装置が水銀の除去を目的としたものではなかったことを容易に知り得たことも,前記認定のとおりである。
そうすると,同年11月末の時点において,水俣湾及びその周辺海域を指定水域に指定すること,当該指定水域に排出される工場排水から水銀又はその化合物が検出されないという水質基準を定めること,アセトアルデヒド製造施設を特定施設に定めることという上記規制権限を行使するために必要な水質二法所定の手続を直ちに執ることが可能であり,また,そうすべき状況にあったものといわなければならない。
そして,この手続に要する期間を考慮に入れても,同年12月末には,主務大臣として定められるべき通商産業大臣において,上記規制権限を行使して,チッソに対し水俣工場のアセトアルデヒド製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,当該施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずることが可能であり,しかも,水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると,直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当である。
また,この時点で上記規制権限が行使されていれば,それ以降の水俣病の被害拡大を防ぐことができたこと,ところが,実際には,その行使がされなかったために,被害が拡大する結果となったことも明らかである。
ウ 本件における以上の諸事情を総合すると,昭和35年1月以降,水質二法に基づく上記規制権限を行使しなかったことは,上記規制権限を定めた水質二法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法というべきである。
したがって,同項による上告人国の損害賠償責任を認めた原審の判断は,正当として是認することができる。この点に関する上告人国の論旨は採用することができない。
(3) 次に,【要旨2】
上告人県の責任についてみると,以上説示したところによれば,前記事実関係の下において,熊本県知事は,水俣病にかかわる前記諸事情について上告人国と同様の認識を有し,又は有し得る状況にあったのであり,同知事には,昭和34年12月末までに県漁業調整規則32条に基づく規制権限を行使すべき作為義務があり,昭和35年1月以降,この権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くものであるとして,上告人県が国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は,同規則が,水産動植物の繁殖保護等を直接の目的とするものではあるが,それを摂取する者の健康の保持等をもその究極の目的とするものであると解されることからすれば,是認することができる。
この点に関する上告人県の論旨を採用することはできない。
第4 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由第5について
1 被上告人らの上告人らに対する請求(前記第2で判示したところにより棄却されるべき部分を除く。)については,国家賠償法4条,民法724条後段所定の除斥期間の適用の有無が問題となるところ,原審は,その適用を否定した。
上告人らの論旨は,原審の上記判断は,上記各規定の解釈適用を誤ったものであり,法令に違反する旨を主張するものである。
2 そこで,以下,この点について検討する。
(1) 民法724条後段所定の除斥期間は,「不法行為ノ時ヨリ二十年」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となると考えられる。
しかし,身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解するのが相当である。
このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間が進行することを認めることは,被害者にとって著しく酷であるだけでなく,加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過した後に損害が発生し,被害者から損害賠償の請求を受けることがあることを予期すべきであると考えられるからである。原審の判断は,以上の趣旨をいうものとして,是認することができる。論旨は採用することができない。
(2) 【要旨3】
上記見解に立って本件をみると,本件患者のそれぞれが水俣湾周辺地域から他の地域へ転居した時点が各自についての加害行為の終了した時であるが,水俣病患者の中には,潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては,水俣湾又はその周辺海域の魚介類の摂取を中止してから4年以内に水俣病の症状が客観的に現れることなど,原審の認定した事実関係の下では,上記転居から遅くとも4年を経過した時点が本件における除斥期間の起算点となるとした原審の判断も,是認し得るものということができる。この点に関する上告人らの論旨も採用することができない。
第5 平成13年(受)第1172号上告代理人都築弘ほかのその余の上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
第6 平成13年(オ)第1196号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告理由について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件附帯上告の理由は,理由の不備及び食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。
第7 平成13年(受)第1174号附帯上告代理人松本健男ほかの附帯上告受理申立て理由について
所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り,上記事実関係の下においては,原審の判断は是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
第8 結論
以上によれば,上告人らの上告は,前記第2の限度で理由があるから,主文第1項記載の部分につき原判決を破棄し,同第3項記載の部分につき原判決を変更すべきものであるが,その余の上告はいずれも理由がないので,これを棄却することとする。また,附帯上告人らの附帯上告には理由がないので,これを棄却する。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田 博 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/67930C1EA789333049257029002690BE.pdf

「奇病のかげに」は、熊本県の水俣病を工場公害ではないかと告発した
踊り回る猫(3コマ目)の姿は「奇病」の本質をとらえた。小倉一郎の作品。

2009年10月31日
工事騒音・粉塵の判例 慰謝料10万円
建物解体工事により約3か月の間,散発的に,ある程度継続的に解体工事敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認め,音源から居住地が離れることによる騒音の減衰を考慮し,居住地の敷地において85デシベルを越える騒音被害を受けていたと認められる原告らにつき,民法709条に基づき,解体工事施工業者に各自10万円の慰謝料支払責任を認めた事案。
(85mで距離減衰9デシベル)慰謝料10万円
主文
1 被告木内建設株式会社は,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告
X5,原告X6,原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,
原告X12,原告X13,原告X14,原告X15,原告X16,原告X17
及び原告X18に対し,それぞれ10万円及びこれに対する平成19年1月3
0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
, , , ,
2 原告X1 原告X2 原告X3 原告X4 原告X5,原告X6,原告X7,
原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12,原告X13,原
告X14,原告X15,原告X16,原告X17及び原告X18の被告木内建
設株式会社に対するその余の請求及び被告三菱地所株式会社に対する請求をい
ずれも棄却する。
3 原告X19及び原告X20の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告X19及び原告X20に生じた費用と被告らに生じた費用
の10分の1を原告X19及び原告X20の負担とし,その余の原告らに生じ
た費用の2分の1,被告三菱地所株式会社に生じた費用の10分の9,被告木
内建設株式会社に生じた費用の20分の9をその余の原告らの負担とし,その
余の原告らに生じた費用の2分の1と被告木内建設に生じた費用の20分の9
を被告木内建設株式会社の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告ら各自に対し,連帯して20万円及びこれに対する平成19年1月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告らが,被告ら各自に対し,被告らが行った建物解体工事(以下「本件工事」という。)の際のアスベスト飛散,騒音・振動,粉じん飛散などにより近隣住民の原告らが健康被害を受けたとして,不法行為に基づき,原告ら各自が相当慰謝料額である50万円のうち20万円(合計400万円)及びこれに対する不法行為日後である平成19年1月30日(公害調停の申立日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(証拠〔枝番があるものは特にことわらない限り,これを含む。以下同じ〕を掲記しない事実は,当事者間に争いが。ない。)
(1) 当事者
ア 原告らは,本件工事現場付近に居住する者である。原告らは,本件工事当時,当事者目録の番号欄と対応する別紙図面(省略)の各番号の位置に居住していた。(甲12,丙3)
イ 被告三菱地所株式会社(以下「被告三菱地所」という。)は,本件工事で解体した建物(甲7。鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建事務所〔延べ床面積2368.72?〕。以下「本件建物」という。)の所有者であり,かつ,本件工事事業者である。
ウ 被告木内建設株式会社(以下「被告木内建設」という。)は,本件工事の施工業者である。
(2) 本件工事について
ア 被告三菱地所は,被告木内建設を施工業者として,さいたま市中央区a の宅地の敷地(以下「本件敷地」という。)上に18階建てのマンション(以下「本件マンション」という。)を新築する計画(以下「本件マンション建築計画」という。)を立てた。
イ 被告三菱地所は,本件マンション建築計画のために,東京海上日動株式会社から,本件敷地及びその上に建設されていた本件建物を買い取り,平成18年10月4日(原告主張によれば11月7日)ころから本件建物の解体工事に着手した。
ウ 本件工事は,平成19年7月11日に終了した。(乙1)
2 争点
( ) 本件工事の違法性(争点1 (1))
(原告ら)
ア 原告らは,人格権,環境権として,居住地で静謐で健康的な生活を送る権利を有している。
イ 説明義務違反について
(ア)本件建物には,アスベストを含有する断熱材がボイラー室を中心に32
4φ×5.9メートルの量で使用されている。被告らは,アスベスト除去
工事を平成18年11月7日から同月21日にかけて実施した。
(イ)被告らがアスベストの除去工事をする前には工事内容を原告らに告知,
周知し,原告ら自身で健康被害の対策ができるようにすべきであったが,
被告らはそのようなことをせずに秘密裏に除去工事をなした。アスベスト
除去工事についての説明図書の配布は同月15日であり,説明会は同年1
2月であり,事前の説明がなされていない。
(ウ)大気汚染防止法18条の14及び同法施行規則16条の4では,アスベ
スト除去工事をする場合には一定の事項を掲示しなければならないと定め
られているが,被告らはそれを行っていない違法がある。被告らは,アス
ベスト除去工事に関し,近隣住民に掲示板を設置するなどして情報提供を
行う義務があったが,掲示板が設置されたのは平成18年12月過ぎであ
り,アスベスト除去工事後である。
(エ)大気汚染防止法は,アスベスト除去作業時に十分な散水をするよう定め
ているが,行われていない違法がある。
ウ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)被告らは,本件工事で激しい騒音・振動を発生させた。平成19年1月
17日になってようやく騒音・振動計が設置された。同年1月24日午前
9時過ぎには,さいたま市騒音防止条例(以下「条例」という。)に違反
する94デシベルの騒音を発生させた。
(イ)本件工事による騒音・振動については,条例に違反している。さらに,
防音シート,防音壁を十分使用する,低騒音・振動の工事機械を使用した
り,手で壊す,ゆっくりと時間をかけて機械を使用して壊す,十分休み時
間をおいて振動の激しい作業を連続させないなどの騒音・振動を低減させ
る対策を取ることなく,経済的利益を追及し,早急な工事が行われている。
また,被告らは原告らに十分な説明や,工程表の配布等をせずに工事を行
っている。これらは,受忍限度を超えている。
(ウ)被告らは,十分な散水をして粉じんの発生を防止する措置を執らず,ま
た,年末年始にコンクリート屑等の有害物質の飛散が予想されることから
十分瓦礫に散水したり,解体搬出したり,シートによる養生をしておくべ
きであったが,その実行を怠り瓦礫を飛散させた。
エ誠実義務違反
原告らの被告らに対する騒音・振動・粉じんに関する危惧や苦情に対し,
被告らは対策を講じなかった。具体的には,騒音振動計を現地敷地の境界線
上と変更すること,防音シート等を充分な範囲で設置すること,昼休みには
一切の工事を休んで騒音・振動を発生させないこと,散水を充分すること,
重機が倒壊する危険に対し対策を採ることなどの要望を無視し,工事協定書
の締結を拒否し,さいたま簡易裁判所公害調停において調停委員会が助言し
た400万円の支払を拒否した。
(被告三菱地所)
ア説明義務違反について
(ア)原告は大気汚染防止法施行規則16条の4に基づき説明義務を負うかの
主張をしているが,被告三菱地所は「特定粉じん排出等作業」(大気汚染
防止法2条12項)を行うものではないから,大気汚染防止法に基づく責
任を負わない。
(イ)同規則16条の4の掲示義務から住民に対する説明義務は発生しない。
法が定める掲示義務は履行されている。
イ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)騒音については,受忍限度の範囲内である。
(イ)振動は,規制値を超えておらず,受忍限度の範囲内である。
(ウ)粉じん発生は,事実が不明である。また,散水による飛散防止措置は講
じられていた。
ウ誠実義務違反について
誠実義務なるものの内容は不明である。
(被告木内建設)
ア説明義務違反について
(ア)大気汚染防止法施行規則16条の4に掲示義務があることは認めるが,
住民に対する説明義務はない。
(イ)アスベスト除去工事の際十分散水する義務があるというのは争う。散水
による飛散防止は,薬液等による湿潤化作業等による飛散防止措置ができ
ない状況の防止策として許容されているものである。
(ウ)本件解体工事に関する届出書で「近隣周知」との記載をしたこ, とは認
めるが,これにより説明会の開催義務が生じるわけではない。
(エ)平成18年12月に開かれた説明会は,解体工事ではなく,新築工事の
説明会である。
(オ)本件のアスベスト除去工事は国土交通省が発表している資料によると,
「塔屋階段天井材」及び「屋上クーリングタワーパッキン」の石綿除
去作業はレベル3(発じん性が比較的低い)に属する作業で,「煙突内部
断熱材」の石綿除去作業はレベル2(発じん性が高い)に属する作業で
あるが,外界から隔離した区画内で適切に行っている。
イ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)平成18年1月24日に94デシベルの騒音を記録したことは認めるが,
これは遮音性の低い東側の道路境界面で測定したためである。
(イ)公法上の規制に違反することが直ちに私法上の不法行為責任が生じるこ
とにはならない。概ね,音源と各原告の居住地との距離の事情に反比例す
るといわれている。
(ウ)音は音源を中心として球状に伝達するから,音源からの距離を半径(r)
とすれば,音のエネルギー量は音の表面積=4×円周率(π)×rの二乗
となるので,距離が音源から2倍となったときエネルギー量は距離の二乗
に反比例する結果4分の1となる。デシベルとは音のエネルギー量を表す
ものであり,10デシベルの差は10倍のエネルギー量の差を意味すると
ころ,仮に音源からの距離が約3倍になれば,エネルギー量は約9分の1
となり,騒音計の数値は約10デシベル低下することになる。原告らは居
住地を異にしているから,同一に論じることはできない。
(エ)また,建物の遮音性能は,少なくとも約25デシベルある。
(オ)条例の規制値を85デシベルとしても,騒音計指針値の最大値の90パ
ーセントがその値であるから,85デシベルを90パーセントで除した9
4デシベルを超えると,規制値を超えたことになる。さらに,本件工事現
場に一番近い原告X12宅でも,基準距離の2倍ないし3倍はあるから,
距離減衰により6ないし9デシベルは低下することになる。したがって,
100ないし103デシベルの指針値を超えたのでなければ,違反とはな
らない。原告らの多くは,基準距離の3倍以上は離れているので,106
デシベル以上の騒音であることが必要である。加えて,建物の透過損失に
より25デシベル以上の低下もあるから,受忍限度の範囲内である。
(カ)粉じん被害の主張は,争う。
ウ誠実義務違反について
争う。
( ) 被告三菱地所が不法行為責任を負うか(争点2 。(2))
(原告ら)
被告三菱地所は,被告木内建設の使用者として,民法715条に基づき使用者責任を負う。
また,被告木内建設とともに民法719条に基づき共同不法行為責任を負う。
(被告三菱地所)
被告三菱地所は被告木内建設の使用者ではないから,民法715条による
責任を負わない。
また,被告らに不法行為責任がないから,民法719条の主張は失当であ
る。
(3) 原告らに生じた損害の程度(争点(3))
(原告ら)
原告らは,被告らの下記の本件工事によるアスベスト,コンクリート屑等
の飛散と騒音・振動により,精神的・身体的被害を受けた。具体的には,身
体的に血圧が上昇したり,不眠となったり,ぜんそくが悪化したり,動悸が
したり,自律神経が失調したりするなどの顕在化した被害や,顕在化しない
程度の生活妨害を受けた。この被害による慰謝料は,原告ら各自につき50
万円を下らないので,そのうち20万円の支払を求める。
(被告ら)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。(以下,特に断りがない場合,9月から12月は平成18年,1月から8月は平成19年の日時を指す。)
( ) 本件工事の工程等(1 甲2)
ア 本件工事の途中で被告らが開示した工程表(甲4。以下「本件工程表」という。)によると,本件工事は,工事が始まる順番に,仮設工事,内装解体,ハツリ工事,進入路確保工事,アスベスト除去工事,PCB撤去工事,レッカー作業,塔屋,5F,4F,3F,2F,1F,山留め工事,地下解体,基礎解体,アスファルト解体,外構解体,整地,杭抜き工事という20の工
種に分解されている。本件工程表では,10月4日から3月17日までを工期と予定しており,アスベスト除去工事は10月23日から11月2日の10日間(作業日数。以下同じ。),塔屋解体工事は11月4日から同月9日の5日間,5F解体工事は11月10日から同月16日の6日間,4F解体工事は11月17日から同月25日の7日間,3F解体工事は11月27日から12月4日の7日間,2F解体工事は12月4日から同月9日の6日間,1F解体工事は12月9日から同月16日の7日間,地下解体工事は12月18日から1月26日の30日間,基礎解体工事は1月22日から2月3日の12日間,アスファルト解体工事は2月5日から同月16日の10日間,外構解体工事は2月5日から同月16日の10日間,杭抜き工事は2月13日から3月17日の29日間となっている。
また,使用重機,アタッチメントの予定表によれば,仮設工事・内装工事は10月10日から11月2日までの21日,建家解体工事は11月4日から1月10日までの47日間,地下解体工事は1月11日から2月17日までの32日間,基礎解体工事は2月19日から同月28日までの9日間となっている。(甲33の10)
イ 9月8日ころ,被告三菱地所は,さいたま市長に対し,建設工事に係る資材の再資源化に関する法律10条1項の規定により,本件解体工事の届出書(甲3。以下「本件解体工事届出書」という。)を提出した。
本件解体工事届出書には,「建築物に関する調査の内容の結果」として,「その他」欄に「。, 煙突内部にカポスタック吹付有り現在ステンレスで覆い飛散防止済。」,
「工事着手前に実施する措置の内容」として,「作業の確保」欄に「敷地内作業スペース十分有り。」,「その他」欄に「近隣周知。」と記載し,工事着手の時期を,「平成18年9月19日」と記載している。また,「工程ごとの作業内容及び解体方法」として,「外装材・上部構造部分の取り壊し」,「基礎・基礎杭の取り壊し」,「その他の取り壊し」を「手作業」ではなく,「手
作業・機械作業の併用」の「分別解体等の方法」により行う旨記載している。(甲3)
ウ 被告木内建設は,10月4日,本件工事に着手した。本件工事の内容は,地上5階建て鉄骨鉄筋コンクリートビルの取壊と,地下室の取壊及び地下室周辺の障壁の解体,搬出及び地中杭4本(長さ約34メートル,直径は1300ミリメートル1本,1400ミリメートル1本,1500ミリメートル2本。)の抜き取りと現場解体,敷地外搬出である。
エ 本件工事の際,本件敷地と,周囲の道路や隣地との境界線上には,ほぼ全面に1800ミリメートル×5400ミリメートルで鉛を含有する重量50キログラム程度の防音シートが張られていた。また,本件敷地のうち,本件建物があった東側部分の敷地四方には,西側南部分を除き,高さ3メートルの安全鋼板仮囲が設置されていた。本件敷地の東側には道路b があり,道路b
から本件敷地への搬入路としては,東側の仮設搬入路と,北東側の搬入搬出口の2か所があった。
このうち,東側の仮設搬入路の部分は,防音シートや安全鋼板仮囲がなく,防音性能の乏しいシートが張られていた。(丙10)
オ 10月30日,被告木内建設は,さいたま市長に対し,本件工事につき日曜・祭日を除く10月17日から2月28日の期間に,さく岩機作業(解体)による騒音規制法の定める特定建設作業を,ブレーカー(解体)による振動規制法の定める特定建設作業を,それぞれ行うとして,特定建設作業実施届出書(丙5,6)を提出した。
いずれも,騒音・振動の防止方法の一つとして,行程・作業内容等を近隣住民に説明することを記載している(。丙5,6)
カ 本件建物には,?塔屋階段の天井材,?屋上クーリングタワーのパッキン,?煙突内部の断熱材に,石綿が含有されている。?については,ボイラー室を中心に,アスベストを含有する断熱材が,324ミリメートル×5.9メートルの量使用されている。
このうち,?は,被告木内建設から請け負った株式会社東京ビルド(以下「東京ビルド」という。)が,10月23日,2
4日に湿潤化させた上,極力割らないように撤去し,袋詰めを行い,10月24日に搬出した。
?は,東京ビルド,?は練馬建設工業株式会社(以下「練馬建設」という。)が,11月7日から同月21日まで除去作業を行い,実際には11月9日のさいたま市役所の養生検査済後,除去作業に取りかかり,11月21日に作業を完了し,12月11日に搬出した。?に関して,東京ビルドは,10月24日,さいたま市長に対し,「特定粉じん排出等作業実施届出書」(乙5。以下「本件届出書」という。)を提出し,10月31日,「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」と題する掲示板(乙6の?な
し?がその写真である。以下「本件掲示板」という。)を,本件工事の現場西側の安全鋼板仮囲の側面2か所に設置し,練馬建設は,本件届出書提出から14日後である11月7日から本件石綿除去工事を開始した。(甲19,乙5,6,11)
キ 12月29日から1月8日の年末年始にかけて,被告木内建設は工事を中断していたが,その際,散水やシートによる養生などで,瓦礫の飛散を防止する措置を講じていない。年末年始のシートによる養生について,さいたま市環境経済局環境部環境管理事務所(以下「さいたま市環境管理事務所」という。)の担当者と被告木内建設の現場所長との間の電話で,シート養生をする方法での埃等の飛散防止の方法が話題に出たことがある。
ク 本件工事により,本件敷地東側の道路b に24メートルほどにわたって亀裂が生じ,4月4日ころ,補修工事が行われた(甲48,54。の4)
ケ 本件工事は,3月ころまでは1週間遅れが出る程度でほぼ予定通りに進み,既存杭引抜作業を残す段階に来ていたが,杭引抜機械の故障や新たな地中障害物の発見により,5月中旬から下旬までかかる見込みとなったため,被告木内建設は,3月20日ころ,近隣住民にこのことを文書で周知した。
さらに,既存杭引抜作業は予定以上に時間がかかり,4本中2本は工法も変更して行うこととしたため,被告木内建設は,5月7日,本件工事の完了予定を6月中旬と変更し,近隣住民に文書で周知した。予定変更以降の作業で見込まれる騒音や振動について,被告木内建設は,3月に行われている既存杭引抜作業と同程度と予想している。(甲48)
コ 7月11日,重機が搬出され,本件工事は終了した。(乙1)
サ 本件工事による騒音は,周辺住民の感覚としては,上部構造の解体工事,地下室の解体工事,杭抜き工事のときが大きかった。(原告X3(以下「原告X3」という。),原告X20(以下「原告X20」という。))
(2) 原告らと被告らの交渉状況等
ア 11月15日,被告らは,本件工事後に予定している本件マンション建築計画に関する説明文書を近隣住民に配布し,12月5日午後7時30分から,本件マンション建築計画に関する第1回近隣説明会を実施した。(甲8の1)
イ 12月19日,被告らは,本件マンション建築計画の第2回近隣説明会を実施した。この際,本件工事について,データを保存できる騒音計・振動計の設置が要望された。(甲8の2)
ウ 1月11日,被告らは,本件マンション建築計画の第3回近隣説明会を実施した。この際,さいたま市環境管理事務所との間で被告木内建設が約束した年末年始の粉じん飛散防止のためのシート養生がなされていなかったことが議題に出て,被告木内建設はシート養生の指導を受けた認識がない旨答えた。
また,被告らは,1階の解体工事について,確たる数値ではないが,70ないし75デシベル程度と思う旨答えた。そして,騒音・振動計の設置が決まった(甲8。の3)
エ 1月17日,第3回近隣説明会の合意に基づき,被告木内建設は,工事現場近くに騒音振動計(以下「本件騒音振動計」という。)を設置した。
本件騒音振動計の記録紙は,1目盛りを1デシベルとし,90デシベルを目盛りの上端としている。本件工事により記録された記録紙(甲32)には,90デシベルを超えた数値が記録されているところもあるが,その部分の数値が
単純に超過した長さ1目盛り分につき1デシベルといえるか,不明であるし,本件騒音振動計の構造上(甲48),際限なく大きな数値が記録されることはない。
オ 1月22日,被告らは,本件マンション建築計画の第4回近隣説明会を実施した。その日の朝に,ターンテーブルの解体をしたため,特に大きな振動が出たことが話題に出た。(甲8の4)
カ 1月24日午前9時過ぎ,原告本人兼原告ら代理人弁護士X1(以下「X1弁護士」という。)が本件騒音振動計を本件敷地東側境界上の防音シートのないところに移すと,94デシベルの騒音が記録された。(当事者間に争いがない。)
キ 2月16日,さいたま市環境管理事務所が本件工事現場の騒音及び振動を測定した。その際,騒音について,測定値の90パーセントレンジの上端値が,85デシベルという測定結果であり,振動について,測定値の80パーセントレンジの上端値が,61デシベルという測定結果であった。
この測定の際は,まずさいたま市環境管理事務所の者が一度本件工事の現場に訪れて工事関係者に騒音及び振動の測定をすることを伝えた後,一度現場を離れ,数十分後に再度来てから測定を開始しており,普段よりも控えめな騒音・振
動で工事が行われていた。(丙7,原告X3)
2 争点(1)(本件工事の違法性)について
( ) 説明義務違反に1 ついて
ア 大気汚染防止法18条の14及び同法施行規則16条の4は,作業基準としてアスベスト除去工事を行う場合の一定の事項の掲示義務を定めており,作業基準を遵守しない場合には都道府県知事が作業基準適合命令等を行うことができるとし(同法18条の18),当該命令に従わない場合には行為者に6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則を定め(同法33条の2第1項2号),同額の罰金の両罰規定も定めている(同法36条)。
しかしながら,この法令の定めにより,直ちに被告木内建設が近隣住民等に対する私法上の説明義務を負うと解することはできない。
イ また,原告らは,本件解体工事届出書に「近隣周知。」と記載したことにより,被告木内建設は原告らへアスベスト除去工事の説明義務を負う旨主張する。
本件解体工事届出書は,建設工事に係る資源の再資源化に関する法律10条1項に基づく届出であるところ,同法は,当該届出に虚偽記載をした場合には20万円以下の罰金という罰則を定め(同法51条1項1号),同額の罰金の両罰規定も定めている(同法52条)。
届出た計画が法令が定める基準に適合しないと認めるときは,都道府県知事は計画の変更その他必要な措置を命ずることができ(同法10条3項),命令に違反したときには30万円以下の罰金という罰則を定め(同法50条1号),同額の罰金の両罰
規定も定めている(同法52条)。
しかし,この法令の定めにより,直ちに被告木内建設が近隣住民等に対する私法上の義務を負うと解することはでき
ない。
ウ その他,以上に認定説示したところ及び弁論の全趣旨により認められる事情を考慮しても,被告木内建設が原告らに対し説明義務を負うとは認められない。
エ また,大気汚染防止法等で規定する掲示義務に違反したところで,原告らに損害が生じるとも認められない。
オ したがって,原告らの説明義務違反の主張は理由がない。
( ) 騒音・振動の発生に2 ついて
ア 社会生活を営む上である程度の騒音や振動は発生するものであるから,互いに受忍すべきものであるが,騒音や振動を体感することにより,その種類・程度等によっては,人は不快感を覚え,精神的・身体的に健康を害されることがあるから,騒音や振動が受忍限度を超える場合には,違法な騒音ないし振動として,不法行為が成立することがあるというべきである。
そして,いかなる騒音や振動が不快感を及ぼすかは,個人差もあると考えられるが,騒音規制法は,特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,85デシベルを超える大きさを規制基準としていること(乙8),振動規制法は,特定建設作業の振動が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,75デシベルを超える大きさを規制基準としていること(振動規制法施行規則11条),本件敷地の周辺は第1種住居地域ないし第2種住居地域であり(甲45),平常時の工場・事業場等の騒音・振動規制について,騒音規制法,振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例上,午前8時から午後7時までの間,工場・事業場の敷地境界において,騒音は55デシベル,振動は60デシベルを規制基準としていること(甲46),特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準は,騒音の大きさの決定方法について,指示値が変動しないときは指示値を,周期的又は間欠的に変動し,最大値がおおむね一定の時は指示値の最大値の
平均値を,指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は測定値の90パーセントレンジの上端の数値を,周期的又は間欠的に変動し,最大値が一定でない場合は指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値を,それぞれ騒音の大きさと定めていること(乙8),振動規制法施行規則は,振動レベルの決定方法について,測定器の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値を,測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値を,測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,5秒間隔,100個又はこれに準ずる間隔,個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値を,それぞれ振動の大きさと定めていること(振動規制法施行規則別表第1備考4)などの事情からすると,騒音については,ある程度継続的に85デシベルを超える騒音や,騒音の程度は一定ではないが一時的にでも94.44デシベル(85デシベルを0.9で除した数値)を超える騒音を,振動については,ある程度継続的に75デシベルを超える振動や,振動の程度は一定ではないが,一時的にでも93.75デシベル(75デシベルを0.8で除した数値)を超える振動を,特段の事情がない限り,受忍限度を超える違法な騒音や振動というべきである。
イ もっとも,騒音や振動は距離が離れるに連れて弱まるものであり(距離減衰,騒音について見ると,その程度は距離の二乗に反比例し,音の) 発生源から測定位置までの距離をX,発生源から被害地までの距離をYとすると,20× log(Y÷X)の式により減殺されるデシベルの数値が算出される(弁論の全趣旨)。したがって,原告らの敷地境界線上において,距離減衰を考
慮した上で,上記違法な騒音や振動が発生していた場合に,不法行為の成立を認めるのが相当である。
ウ まず,振動については,本件工事により継続的にどの程度の振動が発生していたか証拠上明らかでない上,平成19年2月16日に行われたさいたま市環境管理事務所の測定結果時,騒音が規制基準と同数値の85デシベルという測定結果だったのに対し,振動は規制基準の75デシベルを下回る61デシベルであったことからすると(丙7),一時的に大きな振動が発生することがあったとしても(甲48),受忍限度を超える違法な振動が発生していたと認めることはできない。なお,原告らは,道路や家屋のひび割れを指摘するが,これは振動の影響なのか,本件解体工事による地盤沈下の影響なのか,その他の原因なのか証拠上不明であり,これらをもって振動の強さを判断することはできない。したがって,本件工事の振動による不法行為は,
認められない。
エ 次に,被告木内建設が本件工事により発生させていた騒音について認定事実も踏まえて検討する。
(ア)平成19年1月19日から同年2月28日までの騒音については,別紙騒音一覧表(省略)の「該当日付」の日に,概ね「1日合計分」の分数程度,90デシベルを超える騒音が発生していたと認められる(甲5の1及び4,甲32)。
(イ)平成19年2月16日午前8時35分から午前10時26分まで,さいたま市環境管理事務所が行った騒音の測定結果は,東側敷地境界において,測定値の90パーセントレンジの上端値で,85デシベルであった。(乙9)
(ウ)騒音計の記録(甲32)によれば,1月24日,2月8日,2月13日ないし15日,2月22日ないし24日,2月26日などの日は(いずれも平成19年),平成19年2月16日午前8時35分から午前10時26分までの騒音と比較し,大きな騒音,長期間の騒音が出されている。騒音計の計測条件は,平成19年1月24日に防音性の比較的低いところで計測されたと認められる点を除き,特段の違いは見当たらない(丙10)。
(エ)本件騒音振動計の記録用紙は1目盛りを1デシベルとし,90デシベルを上限としていて,それを振り切った場合の数値は不明であるが,平成18年2月24日に94デシベルを記録したことに当事者間に争いはなく,振れ幅の大きさ上,それと同程度の騒音を記録しているところは平成19年2月22日ないし24日,同月26日などにもあるから,本件工事により,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認めるのが相当である。そして,本件騒音振動計が設置されていなかった時期の騒音の程度は客観的な数値としては明らかではないが,原告らは個人差があるもののいずれの工事も騒音がうるさかった旨供述していること 引抜工事までの解体工事については,使用している重機を見ても工事の種類ごとに騒音の程度が大きく異なるとは認められないことなどから,本件工事のうち平成18年11月21日にアスベスト除去工事が終了し,本件建物の解体工事が始まった平成18年11月末ころから,既存杭引抜工事前の本件建物及び地下室の解体工事が終了した平成19年2月28日までの間,散発的に,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認める。
他方,既存杭引抜工事については,解体工事がコンクリート等を破壊する作業であるのに対し,杭を引き抜くという異なる作業であること,騒音の客観的な数値が不明であることから,引き抜いた杭を本件敷地内で壊していたとしても,受忍限度を超える違法な騒音が発生していたとは認められない。
オ 以上のとおり,本件工事により,平成18年11月末ころから平成19年2月28日までの間,散発的に,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたことを前提に,それらが各原告らに対する受忍限度を超える違法な騒音といえるか,検討する。
(ア)本件敷地は,東側が約35メートル,南側が約26メートル超,北側が約15メートルの長さである。また,本件建物は,本件敷地の東側に,1階から6階は東西方向に12メートル,南北方向に31.7メートルの長さで建っており,その南側に東西方向に12メートル,南北方向に15.85メートルの長さの地階があった。(甲14,弁論の全趣旨)
(イ)本件工事による騒音の発生源は一定せず,本件騒音振動計も一定していないが,平均すると,本件建物の中心地から騒音は発生していたと考えられ,本件騒音振動計は本件建物の北側に設置されていた期間が多かったことから,上記記載の本件建物や本件敷地の状況を考慮し,本件騒音振動計は,音源から30メートル離れたところで記録されたものと認めるのが相
当である。
(ウ)そうすると,本件工事により本件敷地境界線部分で94デシベルの騒音が発生したと認められるから,距離減衰により9デシベルの騒音低下が生じれば,騒音は受忍限度の範囲内といえる85デシベルの範囲内に収まることになる。そして,上記距離減衰の式によると,音源から85メートル離れることにより,9.04デシベル(=20× ( ))騒音log 85/30 は低下することになる。
(エ)本件工事による騒音の発生源は一定していなかったことは既述のとおりであるが,本件敷地内のどの場所からも騒音が発生していた可能性があるから,距離減衰との関係では,本件敷地境界線から原告らの敷地までの距離で距離減衰を考えるのが相当である。
(オ)なお,被告木内建設は,家屋の壁などによる透過減衰も主張するが,仮に透過減衰の量を25デシベルとしても,85デシベルを超える騒音から透過減衰を考慮しても60デシベルとなり,平常時の規制基準である55デシベルを超えているから,受忍限度を超えるという判断には影響しないというべきである。
(カ)以上の考えに基づき,本件敷地から85メートルの範囲内に敷地が含まれる原告らを判別すると,別紙原告ら居住地(省略)記載のとおり,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6,原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12,原告X13,原告X14,原告X15,原告X16,原告X17,原告X18(以下「範囲内原告」という。)となる。
これらの原告は,被告木内建設に対し,騒音被害による不法行為に基づき,損害賠償請求権を有しているというべきである。
これに対し,原告X19及び原告X20(以下「範囲外原告」という。)は,受忍限度内の騒音被害であったというべきであり,被告木内建設に対し,騒音被害による不法行為に基づき,損害賠償請求権を有しない。
( ) 粉じんの発生に3 ついて
ア 原告らは,本件工事による粉じんの発生で苦痛を被ったと主張する。
イ 確かに,証拠によると,本件工事によりある程度の粉じんが発生したことが認められるが(甲11,48,原告X3),本件敷地の外に粉じんが飛散したか否か,どの程度飛散したか,粉じんの飛散により原告らに損害が発生したのか等,不明であるといわざるをえない。
ウ また,被告木内建設が,原告らに対し,通常の不法行為責任を超えて,粉じんを飛散させないように注意すべき特段の法的義務を負っていたと認めることはできない。
エ よって,原告らの粉じんの発生による不法行為の主張は,理由がない。
(4) 誠実義務違反について
原告らは,被告木内建設が原告らの本件工事に対する要望に誠実に対応しなかったことなどをもって,誠実義務違反と主張するが,本件事実関係の下で,被告木内建設が,原告らが主張するような法的義務を負っていたとはいえない。
よって,原告らの誠実義務違反の主張は,理由がない。
3 争点(2)(被告三菱地所が不法行為責任を負うか。)について
(1) 使用者責任について
ア 原告らは,被告三菱地所が使用者責任を負う旨主張するが,使用者責任が生じるためには使用者とされる者が被用者とされる者を指揮監督する使用関係が必要である。
イ 被告三菱地所と被告木内建設の本件工事についての関係は,請負契約であることに争いはなく,被告三菱地所から被告木内建設に対し工事の方法等につき特段の指揮監督がなされていたと認めるに足りる証拠はない。
請負契約における注文者は,注文又は指図についてその注文者に過失があったときでなければ,請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないのであって(民法716条,本件では具体的に被告三菱地) 所の注文又は指図に過失があったとは認められないことも併せ考慮すると,被告三菱地所が使用者責任を負うとはいえない。
(2) 共同不法行為責任について
原告らは,被告三菱地所が共同不法行為責任を負う旨主張するが,被告三菱地所が被告木内建設と共同して本件工事を行ったとは認められず,本件工事について主観的な関連共同関係があったとも認められないから,被告三菱地所が共同不法行為責任を負うとはいえない。
(3) よって,原告らの被告三菱地所に対する請求は,すべて理由がない。
4 争点(3)(原告らに生じた損害の程度)について
(1) 既に認定したとおり,本件工事により範囲内原告に対し不法行為を構成するのは,平成18年11月末ころから平成19年2月末ころまで,散発的に生じる,ある程度継続的に94デシベルに達する騒音である。
騒音が発生していたのは約3か月間の月曜日から土曜日の午前8時から午後5時ころであったこと,違法な騒音は毎日発生するとは限らず,発生する日も1日中違法な騒音が続いたわけではないことなどからすると(甲11,32,原告X3,原告X20),慰謝料は,一人当たり10万円が相当である。
(2) なお,原告X3は,神経性胃炎,胃けいれん,不安神経症,不眠症,血圧上昇という診断書を提出するが(甲11の4の2),医師の診断を受けたのは2年ぶりであるなどと供述しており,本件工事との相当因果関係は認められない。
第4 結論
よって,範囲内原告の被告木内建設に対する請求は,慰謝料各10万円及びこれに対する不法行為後である平成19年1月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これらを認容することとし,範囲内原告の被告木内建設に対するその余の請求,被告三菱地所に対する請求,範囲外原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がないので,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第5民事部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090528150644.pdf
(85mで距離減衰9デシベル)慰謝料10万円
主文
1 被告木内建設株式会社は,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告
X5,原告X6,原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,
原告X12,原告X13,原告X14,原告X15,原告X16,原告X17
及び原告X18に対し,それぞれ10万円及びこれに対する平成19年1月3
0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
, , , ,
2 原告X1 原告X2 原告X3 原告X4 原告X5,原告X6,原告X7,
原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12,原告X13,原
告X14,原告X15,原告X16,原告X17及び原告X18の被告木内建
設株式会社に対するその余の請求及び被告三菱地所株式会社に対する請求をい
ずれも棄却する。
3 原告X19及び原告X20の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告X19及び原告X20に生じた費用と被告らに生じた費用
の10分の1を原告X19及び原告X20の負担とし,その余の原告らに生じ
た費用の2分の1,被告三菱地所株式会社に生じた費用の10分の9,被告木
内建設株式会社に生じた費用の20分の9をその余の原告らの負担とし,その
余の原告らに生じた費用の2分の1と被告木内建設に生じた費用の20分の9
を被告木内建設株式会社の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告ら各自に対し,連帯して20万円及びこれに対する平成19年1月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告らが,被告ら各自に対し,被告らが行った建物解体工事(以下「本件工事」という。)の際のアスベスト飛散,騒音・振動,粉じん飛散などにより近隣住民の原告らが健康被害を受けたとして,不法行為に基づき,原告ら各自が相当慰謝料額である50万円のうち20万円(合計400万円)及びこれに対する不法行為日後である平成19年1月30日(公害調停の申立日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(証拠〔枝番があるものは特にことわらない限り,これを含む。以下同じ〕を掲記しない事実は,当事者間に争いが。ない。)
(1) 当事者
ア 原告らは,本件工事現場付近に居住する者である。原告らは,本件工事当時,当事者目録の番号欄と対応する別紙図面(省略)の各番号の位置に居住していた。(甲12,丙3)
イ 被告三菱地所株式会社(以下「被告三菱地所」という。)は,本件工事で解体した建物(甲7。鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建事務所〔延べ床面積2368.72?〕。以下「本件建物」という。)の所有者であり,かつ,本件工事事業者である。
ウ 被告木内建設株式会社(以下「被告木内建設」という。)は,本件工事の施工業者である。
(2) 本件工事について
ア 被告三菱地所は,被告木内建設を施工業者として,さいたま市中央区a の宅地の敷地(以下「本件敷地」という。)上に18階建てのマンション(以下「本件マンション」という。)を新築する計画(以下「本件マンション建築計画」という。)を立てた。
イ 被告三菱地所は,本件マンション建築計画のために,東京海上日動株式会社から,本件敷地及びその上に建設されていた本件建物を買い取り,平成18年10月4日(原告主張によれば11月7日)ころから本件建物の解体工事に着手した。
ウ 本件工事は,平成19年7月11日に終了した。(乙1)
2 争点
( ) 本件工事の違法性(争点1 (1))
(原告ら)
ア 原告らは,人格権,環境権として,居住地で静謐で健康的な生活を送る権利を有している。
イ 説明義務違反について
(ア)本件建物には,アスベストを含有する断熱材がボイラー室を中心に32
4φ×5.9メートルの量で使用されている。被告らは,アスベスト除去
工事を平成18年11月7日から同月21日にかけて実施した。
(イ)被告らがアスベストの除去工事をする前には工事内容を原告らに告知,
周知し,原告ら自身で健康被害の対策ができるようにすべきであったが,
被告らはそのようなことをせずに秘密裏に除去工事をなした。アスベスト
除去工事についての説明図書の配布は同月15日であり,説明会は同年1
2月であり,事前の説明がなされていない。
(ウ)大気汚染防止法18条の14及び同法施行規則16条の4では,アスベ
スト除去工事をする場合には一定の事項を掲示しなければならないと定め
られているが,被告らはそれを行っていない違法がある。被告らは,アス
ベスト除去工事に関し,近隣住民に掲示板を設置するなどして情報提供を
行う義務があったが,掲示板が設置されたのは平成18年12月過ぎであ
り,アスベスト除去工事後である。
(エ)大気汚染防止法は,アスベスト除去作業時に十分な散水をするよう定め
ているが,行われていない違法がある。
ウ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)被告らは,本件工事で激しい騒音・振動を発生させた。平成19年1月
17日になってようやく騒音・振動計が設置された。同年1月24日午前
9時過ぎには,さいたま市騒音防止条例(以下「条例」という。)に違反
する94デシベルの騒音を発生させた。
(イ)本件工事による騒音・振動については,条例に違反している。さらに,
防音シート,防音壁を十分使用する,低騒音・振動の工事機械を使用した
り,手で壊す,ゆっくりと時間をかけて機械を使用して壊す,十分休み時
間をおいて振動の激しい作業を連続させないなどの騒音・振動を低減させ
る対策を取ることなく,経済的利益を追及し,早急な工事が行われている。
また,被告らは原告らに十分な説明や,工程表の配布等をせずに工事を行
っている。これらは,受忍限度を超えている。
(ウ)被告らは,十分な散水をして粉じんの発生を防止する措置を執らず,ま
た,年末年始にコンクリート屑等の有害物質の飛散が予想されることから
十分瓦礫に散水したり,解体搬出したり,シートによる養生をしておくべ
きであったが,その実行を怠り瓦礫を飛散させた。
エ誠実義務違反
原告らの被告らに対する騒音・振動・粉じんに関する危惧や苦情に対し,
被告らは対策を講じなかった。具体的には,騒音振動計を現地敷地の境界線
上と変更すること,防音シート等を充分な範囲で設置すること,昼休みには
一切の工事を休んで騒音・振動を発生させないこと,散水を充分すること,
重機が倒壊する危険に対し対策を採ることなどの要望を無視し,工事協定書
の締結を拒否し,さいたま簡易裁判所公害調停において調停委員会が助言し
た400万円の支払を拒否した。
(被告三菱地所)
ア説明義務違反について
(ア)原告は大気汚染防止法施行規則16条の4に基づき説明義務を負うかの
主張をしているが,被告三菱地所は「特定粉じん排出等作業」(大気汚染
防止法2条12項)を行うものではないから,大気汚染防止法に基づく責
任を負わない。
(イ)同規則16条の4の掲示義務から住民に対する説明義務は発生しない。
法が定める掲示義務は履行されている。
イ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)騒音については,受忍限度の範囲内である。
(イ)振動は,規制値を超えておらず,受忍限度の範囲内である。
(ウ)粉じん発生は,事実が不明である。また,散水による飛散防止措置は講
じられていた。
ウ誠実義務違反について
誠実義務なるものの内容は不明である。
(被告木内建設)
ア説明義務違反について
(ア)大気汚染防止法施行規則16条の4に掲示義務があることは認めるが,
住民に対する説明義務はない。
(イ)アスベスト除去工事の際十分散水する義務があるというのは争う。散水
による飛散防止は,薬液等による湿潤化作業等による飛散防止措置ができ
ない状況の防止策として許容されているものである。
(ウ)本件解体工事に関する届出書で「近隣周知」との記載をしたこ, とは認
めるが,これにより説明会の開催義務が生じるわけではない。
(エ)平成18年12月に開かれた説明会は,解体工事ではなく,新築工事の
説明会である。
(オ)本件のアスベスト除去工事は国土交通省が発表している資料によると,
「塔屋階段天井材」及び「屋上クーリングタワーパッキン」の石綿除
去作業はレベル3(発じん性が比較的低い)に属する作業で,「煙突内部
断熱材」の石綿除去作業はレベル2(発じん性が高い)に属する作業で
あるが,外界から隔離した区画内で適切に行っている。
イ騒音・振動・粉じんの発生について
(ア)平成18年1月24日に94デシベルの騒音を記録したことは認めるが,
これは遮音性の低い東側の道路境界面で測定したためである。
(イ)公法上の規制に違反することが直ちに私法上の不法行為責任が生じるこ
とにはならない。概ね,音源と各原告の居住地との距離の事情に反比例す
るといわれている。
(ウ)音は音源を中心として球状に伝達するから,音源からの距離を半径(r)
とすれば,音のエネルギー量は音の表面積=4×円周率(π)×rの二乗
となるので,距離が音源から2倍となったときエネルギー量は距離の二乗
に反比例する結果4分の1となる。デシベルとは音のエネルギー量を表す
ものであり,10デシベルの差は10倍のエネルギー量の差を意味すると
ころ,仮に音源からの距離が約3倍になれば,エネルギー量は約9分の1
となり,騒音計の数値は約10デシベル低下することになる。原告らは居
住地を異にしているから,同一に論じることはできない。
(エ)また,建物の遮音性能は,少なくとも約25デシベルある。
(オ)条例の規制値を85デシベルとしても,騒音計指針値の最大値の90パ
ーセントがその値であるから,85デシベルを90パーセントで除した9
4デシベルを超えると,規制値を超えたことになる。さらに,本件工事現
場に一番近い原告X12宅でも,基準距離の2倍ないし3倍はあるから,
距離減衰により6ないし9デシベルは低下することになる。したがって,
100ないし103デシベルの指針値を超えたのでなければ,違反とはな
らない。原告らの多くは,基準距離の3倍以上は離れているので,106
デシベル以上の騒音であることが必要である。加えて,建物の透過損失に
より25デシベル以上の低下もあるから,受忍限度の範囲内である。
(カ)粉じん被害の主張は,争う。
ウ誠実義務違反について
争う。
( ) 被告三菱地所が不法行為責任を負うか(争点2 。(2))
(原告ら)
被告三菱地所は,被告木内建設の使用者として,民法715条に基づき使用者責任を負う。
また,被告木内建設とともに民法719条に基づき共同不法行為責任を負う。
(被告三菱地所)
被告三菱地所は被告木内建設の使用者ではないから,民法715条による
責任を負わない。
また,被告らに不法行為責任がないから,民法719条の主張は失当であ
る。
(3) 原告らに生じた損害の程度(争点(3))
(原告ら)
原告らは,被告らの下記の本件工事によるアスベスト,コンクリート屑等
の飛散と騒音・振動により,精神的・身体的被害を受けた。具体的には,身
体的に血圧が上昇したり,不眠となったり,ぜんそくが悪化したり,動悸が
したり,自律神経が失調したりするなどの顕在化した被害や,顕在化しない
程度の生活妨害を受けた。この被害による慰謝料は,原告ら各自につき50
万円を下らないので,そのうち20万円の支払を求める。
(被告ら)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。(以下,特に断りがない場合,9月から12月は平成18年,1月から8月は平成19年の日時を指す。)
( ) 本件工事の工程等(1 甲2)
ア 本件工事の途中で被告らが開示した工程表(甲4。以下「本件工程表」という。)によると,本件工事は,工事が始まる順番に,仮設工事,内装解体,ハツリ工事,進入路確保工事,アスベスト除去工事,PCB撤去工事,レッカー作業,塔屋,5F,4F,3F,2F,1F,山留め工事,地下解体,基礎解体,アスファルト解体,外構解体,整地,杭抜き工事という20の工
種に分解されている。本件工程表では,10月4日から3月17日までを工期と予定しており,アスベスト除去工事は10月23日から11月2日の10日間(作業日数。以下同じ。),塔屋解体工事は11月4日から同月9日の5日間,5F解体工事は11月10日から同月16日の6日間,4F解体工事は11月17日から同月25日の7日間,3F解体工事は11月27日から12月4日の7日間,2F解体工事は12月4日から同月9日の6日間,1F解体工事は12月9日から同月16日の7日間,地下解体工事は12月18日から1月26日の30日間,基礎解体工事は1月22日から2月3日の12日間,アスファルト解体工事は2月5日から同月16日の10日間,外構解体工事は2月5日から同月16日の10日間,杭抜き工事は2月13日から3月17日の29日間となっている。
また,使用重機,アタッチメントの予定表によれば,仮設工事・内装工事は10月10日から11月2日までの21日,建家解体工事は11月4日から1月10日までの47日間,地下解体工事は1月11日から2月17日までの32日間,基礎解体工事は2月19日から同月28日までの9日間となっている。(甲33の10)
イ 9月8日ころ,被告三菱地所は,さいたま市長に対し,建設工事に係る資材の再資源化に関する法律10条1項の規定により,本件解体工事の届出書(甲3。以下「本件解体工事届出書」という。)を提出した。
本件解体工事届出書には,「建築物に関する調査の内容の結果」として,「その他」欄に「。, 煙突内部にカポスタック吹付有り現在ステンレスで覆い飛散防止済。」,
「工事着手前に実施する措置の内容」として,「作業の確保」欄に「敷地内作業スペース十分有り。」,「その他」欄に「近隣周知。」と記載し,工事着手の時期を,「平成18年9月19日」と記載している。また,「工程ごとの作業内容及び解体方法」として,「外装材・上部構造部分の取り壊し」,「基礎・基礎杭の取り壊し」,「その他の取り壊し」を「手作業」ではなく,「手
作業・機械作業の併用」の「分別解体等の方法」により行う旨記載している。(甲3)
ウ 被告木内建設は,10月4日,本件工事に着手した。本件工事の内容は,地上5階建て鉄骨鉄筋コンクリートビルの取壊と,地下室の取壊及び地下室周辺の障壁の解体,搬出及び地中杭4本(長さ約34メートル,直径は1300ミリメートル1本,1400ミリメートル1本,1500ミリメートル2本。)の抜き取りと現場解体,敷地外搬出である。
エ 本件工事の際,本件敷地と,周囲の道路や隣地との境界線上には,ほぼ全面に1800ミリメートル×5400ミリメートルで鉛を含有する重量50キログラム程度の防音シートが張られていた。また,本件敷地のうち,本件建物があった東側部分の敷地四方には,西側南部分を除き,高さ3メートルの安全鋼板仮囲が設置されていた。本件敷地の東側には道路b があり,道路b
から本件敷地への搬入路としては,東側の仮設搬入路と,北東側の搬入搬出口の2か所があった。
このうち,東側の仮設搬入路の部分は,防音シートや安全鋼板仮囲がなく,防音性能の乏しいシートが張られていた。(丙10)
オ 10月30日,被告木内建設は,さいたま市長に対し,本件工事につき日曜・祭日を除く10月17日から2月28日の期間に,さく岩機作業(解体)による騒音規制法の定める特定建設作業を,ブレーカー(解体)による振動規制法の定める特定建設作業を,それぞれ行うとして,特定建設作業実施届出書(丙5,6)を提出した。
いずれも,騒音・振動の防止方法の一つとして,行程・作業内容等を近隣住民に説明することを記載している(。丙5,6)
カ 本件建物には,?塔屋階段の天井材,?屋上クーリングタワーのパッキン,?煙突内部の断熱材に,石綿が含有されている。?については,ボイラー室を中心に,アスベストを含有する断熱材が,324ミリメートル×5.9メートルの量使用されている。
このうち,?は,被告木内建設から請け負った株式会社東京ビルド(以下「東京ビルド」という。)が,10月23日,2
4日に湿潤化させた上,極力割らないように撤去し,袋詰めを行い,10月24日に搬出した。
?は,東京ビルド,?は練馬建設工業株式会社(以下「練馬建設」という。)が,11月7日から同月21日まで除去作業を行い,実際には11月9日のさいたま市役所の養生検査済後,除去作業に取りかかり,11月21日に作業を完了し,12月11日に搬出した。?に関して,東京ビルドは,10月24日,さいたま市長に対し,「特定粉じん排出等作業実施届出書」(乙5。以下「本件届出書」という。)を提出し,10月31日,「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」と題する掲示板(乙6の?な
し?がその写真である。以下「本件掲示板」という。)を,本件工事の現場西側の安全鋼板仮囲の側面2か所に設置し,練馬建設は,本件届出書提出から14日後である11月7日から本件石綿除去工事を開始した。(甲19,乙5,6,11)
キ 12月29日から1月8日の年末年始にかけて,被告木内建設は工事を中断していたが,その際,散水やシートによる養生などで,瓦礫の飛散を防止する措置を講じていない。年末年始のシートによる養生について,さいたま市環境経済局環境部環境管理事務所(以下「さいたま市環境管理事務所」という。)の担当者と被告木内建設の現場所長との間の電話で,シート養生をする方法での埃等の飛散防止の方法が話題に出たことがある。
ク 本件工事により,本件敷地東側の道路b に24メートルほどにわたって亀裂が生じ,4月4日ころ,補修工事が行われた(甲48,54。の4)
ケ 本件工事は,3月ころまでは1週間遅れが出る程度でほぼ予定通りに進み,既存杭引抜作業を残す段階に来ていたが,杭引抜機械の故障や新たな地中障害物の発見により,5月中旬から下旬までかかる見込みとなったため,被告木内建設は,3月20日ころ,近隣住民にこのことを文書で周知した。
さらに,既存杭引抜作業は予定以上に時間がかかり,4本中2本は工法も変更して行うこととしたため,被告木内建設は,5月7日,本件工事の完了予定を6月中旬と変更し,近隣住民に文書で周知した。予定変更以降の作業で見込まれる騒音や振動について,被告木内建設は,3月に行われている既存杭引抜作業と同程度と予想している。(甲48)
コ 7月11日,重機が搬出され,本件工事は終了した。(乙1)
サ 本件工事による騒音は,周辺住民の感覚としては,上部構造の解体工事,地下室の解体工事,杭抜き工事のときが大きかった。(原告X3(以下「原告X3」という。),原告X20(以下「原告X20」という。))
(2) 原告らと被告らの交渉状況等
ア 11月15日,被告らは,本件工事後に予定している本件マンション建築計画に関する説明文書を近隣住民に配布し,12月5日午後7時30分から,本件マンション建築計画に関する第1回近隣説明会を実施した。(甲8の1)
イ 12月19日,被告らは,本件マンション建築計画の第2回近隣説明会を実施した。この際,本件工事について,データを保存できる騒音計・振動計の設置が要望された。(甲8の2)
ウ 1月11日,被告らは,本件マンション建築計画の第3回近隣説明会を実施した。この際,さいたま市環境管理事務所との間で被告木内建設が約束した年末年始の粉じん飛散防止のためのシート養生がなされていなかったことが議題に出て,被告木内建設はシート養生の指導を受けた認識がない旨答えた。
また,被告らは,1階の解体工事について,確たる数値ではないが,70ないし75デシベル程度と思う旨答えた。そして,騒音・振動計の設置が決まった(甲8。の3)
エ 1月17日,第3回近隣説明会の合意に基づき,被告木内建設は,工事現場近くに騒音振動計(以下「本件騒音振動計」という。)を設置した。
本件騒音振動計の記録紙は,1目盛りを1デシベルとし,90デシベルを目盛りの上端としている。本件工事により記録された記録紙(甲32)には,90デシベルを超えた数値が記録されているところもあるが,その部分の数値が
単純に超過した長さ1目盛り分につき1デシベルといえるか,不明であるし,本件騒音振動計の構造上(甲48),際限なく大きな数値が記録されることはない。
オ 1月22日,被告らは,本件マンション建築計画の第4回近隣説明会を実施した。その日の朝に,ターンテーブルの解体をしたため,特に大きな振動が出たことが話題に出た。(甲8の4)
カ 1月24日午前9時過ぎ,原告本人兼原告ら代理人弁護士X1(以下「X1弁護士」という。)が本件騒音振動計を本件敷地東側境界上の防音シートのないところに移すと,94デシベルの騒音が記録された。(当事者間に争いがない。)
キ 2月16日,さいたま市環境管理事務所が本件工事現場の騒音及び振動を測定した。その際,騒音について,測定値の90パーセントレンジの上端値が,85デシベルという測定結果であり,振動について,測定値の80パーセントレンジの上端値が,61デシベルという測定結果であった。
この測定の際は,まずさいたま市環境管理事務所の者が一度本件工事の現場に訪れて工事関係者に騒音及び振動の測定をすることを伝えた後,一度現場を離れ,数十分後に再度来てから測定を開始しており,普段よりも控えめな騒音・振
動で工事が行われていた。(丙7,原告X3)
2 争点(1)(本件工事の違法性)について
( ) 説明義務違反に1 ついて
ア 大気汚染防止法18条の14及び同法施行規則16条の4は,作業基準としてアスベスト除去工事を行う場合の一定の事項の掲示義務を定めており,作業基準を遵守しない場合には都道府県知事が作業基準適合命令等を行うことができるとし(同法18条の18),当該命令に従わない場合には行為者に6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則を定め(同法33条の2第1項2号),同額の罰金の両罰規定も定めている(同法36条)。
しかしながら,この法令の定めにより,直ちに被告木内建設が近隣住民等に対する私法上の説明義務を負うと解することはできない。
イ また,原告らは,本件解体工事届出書に「近隣周知。」と記載したことにより,被告木内建設は原告らへアスベスト除去工事の説明義務を負う旨主張する。
本件解体工事届出書は,建設工事に係る資源の再資源化に関する法律10条1項に基づく届出であるところ,同法は,当該届出に虚偽記載をした場合には20万円以下の罰金という罰則を定め(同法51条1項1号),同額の罰金の両罰規定も定めている(同法52条)。
届出た計画が法令が定める基準に適合しないと認めるときは,都道府県知事は計画の変更その他必要な措置を命ずることができ(同法10条3項),命令に違反したときには30万円以下の罰金という罰則を定め(同法50条1号),同額の罰金の両罰
規定も定めている(同法52条)。
しかし,この法令の定めにより,直ちに被告木内建設が近隣住民等に対する私法上の義務を負うと解することはでき
ない。
ウ その他,以上に認定説示したところ及び弁論の全趣旨により認められる事情を考慮しても,被告木内建設が原告らに対し説明義務を負うとは認められない。
エ また,大気汚染防止法等で規定する掲示義務に違反したところで,原告らに損害が生じるとも認められない。
オ したがって,原告らの説明義務違反の主張は理由がない。
( ) 騒音・振動の発生に2 ついて
ア 社会生活を営む上である程度の騒音や振動は発生するものであるから,互いに受忍すべきものであるが,騒音や振動を体感することにより,その種類・程度等によっては,人は不快感を覚え,精神的・身体的に健康を害されることがあるから,騒音や振動が受忍限度を超える場合には,違法な騒音ないし振動として,不法行為が成立することがあるというべきである。
そして,いかなる騒音や振動が不快感を及ぼすかは,個人差もあると考えられるが,騒音規制法は,特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,85デシベルを超える大きさを規制基準としていること(乙8),振動規制法は,特定建設作業の振動が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,75デシベルを超える大きさを規制基準としていること(振動規制法施行規則11条),本件敷地の周辺は第1種住居地域ないし第2種住居地域であり(甲45),平常時の工場・事業場等の騒音・振動規制について,騒音規制法,振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例上,午前8時から午後7時までの間,工場・事業場の敷地境界において,騒音は55デシベル,振動は60デシベルを規制基準としていること(甲46),特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準は,騒音の大きさの決定方法について,指示値が変動しないときは指示値を,周期的又は間欠的に変動し,最大値がおおむね一定の時は指示値の最大値の
平均値を,指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は測定値の90パーセントレンジの上端の数値を,周期的又は間欠的に変動し,最大値が一定でない場合は指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値を,それぞれ騒音の大きさと定めていること(乙8),振動規制法施行規則は,振動レベルの決定方法について,測定器の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値を,測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値を,測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,5秒間隔,100個又はこれに準ずる間隔,個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値を,それぞれ振動の大きさと定めていること(振動規制法施行規則別表第1備考4)などの事情からすると,騒音については,ある程度継続的に85デシベルを超える騒音や,騒音の程度は一定ではないが一時的にでも94.44デシベル(85デシベルを0.9で除した数値)を超える騒音を,振動については,ある程度継続的に75デシベルを超える振動や,振動の程度は一定ではないが,一時的にでも93.75デシベル(75デシベルを0.8で除した数値)を超える振動を,特段の事情がない限り,受忍限度を超える違法な騒音や振動というべきである。
イ もっとも,騒音や振動は距離が離れるに連れて弱まるものであり(距離減衰,騒音について見ると,その程度は距離の二乗に反比例し,音の) 発生源から測定位置までの距離をX,発生源から被害地までの距離をYとすると,20× log(Y÷X)の式により減殺されるデシベルの数値が算出される(弁論の全趣旨)。したがって,原告らの敷地境界線上において,距離減衰を考
慮した上で,上記違法な騒音や振動が発生していた場合に,不法行為の成立を認めるのが相当である。
ウ まず,振動については,本件工事により継続的にどの程度の振動が発生していたか証拠上明らかでない上,平成19年2月16日に行われたさいたま市環境管理事務所の測定結果時,騒音が規制基準と同数値の85デシベルという測定結果だったのに対し,振動は規制基準の75デシベルを下回る61デシベルであったことからすると(丙7),一時的に大きな振動が発生することがあったとしても(甲48),受忍限度を超える違法な振動が発生していたと認めることはできない。なお,原告らは,道路や家屋のひび割れを指摘するが,これは振動の影響なのか,本件解体工事による地盤沈下の影響なのか,その他の原因なのか証拠上不明であり,これらをもって振動の強さを判断することはできない。したがって,本件工事の振動による不法行為は,
認められない。
エ 次に,被告木内建設が本件工事により発生させていた騒音について認定事実も踏まえて検討する。
(ア)平成19年1月19日から同年2月28日までの騒音については,別紙騒音一覧表(省略)の「該当日付」の日に,概ね「1日合計分」の分数程度,90デシベルを超える騒音が発生していたと認められる(甲5の1及び4,甲32)。
(イ)平成19年2月16日午前8時35分から午前10時26分まで,さいたま市環境管理事務所が行った騒音の測定結果は,東側敷地境界において,測定値の90パーセントレンジの上端値で,85デシベルであった。(乙9)
(ウ)騒音計の記録(甲32)によれば,1月24日,2月8日,2月13日ないし15日,2月22日ないし24日,2月26日などの日は(いずれも平成19年),平成19年2月16日午前8時35分から午前10時26分までの騒音と比較し,大きな騒音,長期間の騒音が出されている。騒音計の計測条件は,平成19年1月24日に防音性の比較的低いところで計測されたと認められる点を除き,特段の違いは見当たらない(丙10)。
(エ)本件騒音振動計の記録用紙は1目盛りを1デシベルとし,90デシベルを上限としていて,それを振り切った場合の数値は不明であるが,平成18年2月24日に94デシベルを記録したことに当事者間に争いはなく,振れ幅の大きさ上,それと同程度の騒音を記録しているところは平成19年2月22日ないし24日,同月26日などにもあるから,本件工事により,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認めるのが相当である。そして,本件騒音振動計が設置されていなかった時期の騒音の程度は客観的な数値としては明らかではないが,原告らは個人差があるもののいずれの工事も騒音がうるさかった旨供述していること 引抜工事までの解体工事については,使用している重機を見ても工事の種類ごとに騒音の程度が大きく異なるとは認められないことなどから,本件工事のうち平成18年11月21日にアスベスト除去工事が終了し,本件建物の解体工事が始まった平成18年11月末ころから,既存杭引抜工事前の本件建物及び地下室の解体工事が終了した平成19年2月28日までの間,散発的に,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認める。
他方,既存杭引抜工事については,解体工事がコンクリート等を破壊する作業であるのに対し,杭を引き抜くという異なる作業であること,騒音の客観的な数値が不明であることから,引き抜いた杭を本件敷地内で壊していたとしても,受忍限度を超える違法な騒音が発生していたとは認められない。
オ 以上のとおり,本件工事により,平成18年11月末ころから平成19年2月28日までの間,散発的に,ある程度継続的に本件敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたことを前提に,それらが各原告らに対する受忍限度を超える違法な騒音といえるか,検討する。
(ア)本件敷地は,東側が約35メートル,南側が約26メートル超,北側が約15メートルの長さである。また,本件建物は,本件敷地の東側に,1階から6階は東西方向に12メートル,南北方向に31.7メートルの長さで建っており,その南側に東西方向に12メートル,南北方向に15.85メートルの長さの地階があった。(甲14,弁論の全趣旨)
(イ)本件工事による騒音の発生源は一定せず,本件騒音振動計も一定していないが,平均すると,本件建物の中心地から騒音は発生していたと考えられ,本件騒音振動計は本件建物の北側に設置されていた期間が多かったことから,上記記載の本件建物や本件敷地の状況を考慮し,本件騒音振動計は,音源から30メートル離れたところで記録されたものと認めるのが相
当である。
(ウ)そうすると,本件工事により本件敷地境界線部分で94デシベルの騒音が発生したと認められるから,距離減衰により9デシベルの騒音低下が生じれば,騒音は受忍限度の範囲内といえる85デシベルの範囲内に収まることになる。そして,上記距離減衰の式によると,音源から85メートル離れることにより,9.04デシベル(=20× ( ))騒音log 85/30 は低下することになる。
(エ)本件工事による騒音の発生源は一定していなかったことは既述のとおりであるが,本件敷地内のどの場所からも騒音が発生していた可能性があるから,距離減衰との関係では,本件敷地境界線から原告らの敷地までの距離で距離減衰を考えるのが相当である。
(オ)なお,被告木内建設は,家屋の壁などによる透過減衰も主張するが,仮に透過減衰の量を25デシベルとしても,85デシベルを超える騒音から透過減衰を考慮しても60デシベルとなり,平常時の規制基準である55デシベルを超えているから,受忍限度を超えるという判断には影響しないというべきである。
(カ)以上の考えに基づき,本件敷地から85メートルの範囲内に敷地が含まれる原告らを判別すると,別紙原告ら居住地(省略)記載のとおり,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6,原告X7,原告X8,原告X9,原告X10,原告X11,原告X12,原告X13,原告X14,原告X15,原告X16,原告X17,原告X18(以下「範囲内原告」という。)となる。
これらの原告は,被告木内建設に対し,騒音被害による不法行為に基づき,損害賠償請求権を有しているというべきである。
これに対し,原告X19及び原告X20(以下「範囲外原告」という。)は,受忍限度内の騒音被害であったというべきであり,被告木内建設に対し,騒音被害による不法行為に基づき,損害賠償請求権を有しない。
( ) 粉じんの発生に3 ついて
ア 原告らは,本件工事による粉じんの発生で苦痛を被ったと主張する。
イ 確かに,証拠によると,本件工事によりある程度の粉じんが発生したことが認められるが(甲11,48,原告X3),本件敷地の外に粉じんが飛散したか否か,どの程度飛散したか,粉じんの飛散により原告らに損害が発生したのか等,不明であるといわざるをえない。
ウ また,被告木内建設が,原告らに対し,通常の不法行為責任を超えて,粉じんを飛散させないように注意すべき特段の法的義務を負っていたと認めることはできない。
エ よって,原告らの粉じんの発生による不法行為の主張は,理由がない。
(4) 誠実義務違反について
原告らは,被告木内建設が原告らの本件工事に対する要望に誠実に対応しなかったことなどをもって,誠実義務違反と主張するが,本件事実関係の下で,被告木内建設が,原告らが主張するような法的義務を負っていたとはいえない。
よって,原告らの誠実義務違反の主張は,理由がない。
3 争点(2)(被告三菱地所が不法行為責任を負うか。)について
(1) 使用者責任について
ア 原告らは,被告三菱地所が使用者責任を負う旨主張するが,使用者責任が生じるためには使用者とされる者が被用者とされる者を指揮監督する使用関係が必要である。
イ 被告三菱地所と被告木内建設の本件工事についての関係は,請負契約であることに争いはなく,被告三菱地所から被告木内建設に対し工事の方法等につき特段の指揮監督がなされていたと認めるに足りる証拠はない。
請負契約における注文者は,注文又は指図についてその注文者に過失があったときでなければ,請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないのであって(民法716条,本件では具体的に被告三菱地) 所の注文又は指図に過失があったとは認められないことも併せ考慮すると,被告三菱地所が使用者責任を負うとはいえない。
(2) 共同不法行為責任について
原告らは,被告三菱地所が共同不法行為責任を負う旨主張するが,被告三菱地所が被告木内建設と共同して本件工事を行ったとは認められず,本件工事について主観的な関連共同関係があったとも認められないから,被告三菱地所が共同不法行為責任を負うとはいえない。
(3) よって,原告らの被告三菱地所に対する請求は,すべて理由がない。
4 争点(3)(原告らに生じた損害の程度)について
(1) 既に認定したとおり,本件工事により範囲内原告に対し不法行為を構成するのは,平成18年11月末ころから平成19年2月末ころまで,散発的に生じる,ある程度継続的に94デシベルに達する騒音である。
騒音が発生していたのは約3か月間の月曜日から土曜日の午前8時から午後5時ころであったこと,違法な騒音は毎日発生するとは限らず,発生する日も1日中違法な騒音が続いたわけではないことなどからすると(甲11,32,原告X3,原告X20),慰謝料は,一人当たり10万円が相当である。
(2) なお,原告X3は,神経性胃炎,胃けいれん,不安神経症,不眠症,血圧上昇という診断書を提出するが(甲11の4の2),医師の診断を受けたのは2年ぶりであるなどと供述しており,本件工事との相当因果関係は認められない。
第4 結論
よって,範囲内原告の被告木内建設に対する請求は,慰謝料各10万円及びこれに対する不法行為後である平成19年1月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これらを認容することとし,範囲内原告の被告木内建設に対するその余の請求,被告三菱地所に対する請求,範囲外原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がないので,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第5民事部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090528150644.pdf