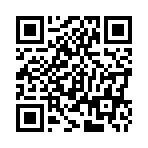2009年11月21日
土壌汚染地における土地の有効利用等に関する中間とりまとめ
土壌汚染地における土地の有効利用等に関する研究会中間とりまとめ
平成20 年4 月
国土交通省土地・水資源局 土地政策課土地市場企画室
中間とりまとめのポイント
土壌汚染が実際に存在する土地で、原則として掘削除去以外の浄化措置を行うとともにその後の土地利用の計画を策定した上で、その成功要因等を分析・研究するという「サクセスモデル」を構築・公開することが、土壌汚染地を有効活用するための有効策になりうる。
土壌汚染地の資産評価の適正化と土壌汚染地に係る安全かつ円滑な利用や取引を促進するため、土壌汚染の専門業者が行う調査の標準化とそれを通じた専門業者の標準化を進める必要がある。
不動産鑑定の実務面では運用指針の策定や研修等が行われているが、社会経済情勢の変化に対応しうるよう、引き続き不動産鑑定士が行うべき土壌汚染状況の確認範囲等を明確化し、鑑定評価に適切に反映するステップについて検討を深めていく必要がある。
また、スティグマについての評価方法や、掘削除去以外の措置を前提とした鑑定評価方法についてもさらに検討する必要がある。
個別の土壌汚染サイトに関する情報はなかなか公にならない現状があることから、下記の課題を検討するための前提として今後も企業や地方公共団体等へのヒアリングや調査等による情報収集が必要である。
更なる実態・状況の把握
土壌汚染情報は、土壌汚染地の近隣住民等も利害関係を有する情報であるから、全国的な土壌汚染情報をデータベース化し、広く情報を共有することができれば、土地取引の円滑化や浄化措置の促進及び早期化等に資することになる。
しかし、我が国においては土壌汚染情報の収集が十分でなく、情報の収集方法等も検討しなければならないため、すぐにはそういったデータベースの作成に取りかかることは困難であることから、公的なリーダーシップの元にフェーズ?程度の地歴調査を行った上で、過去に工場が立地している等の理由により土壌汚染の可能性が高いサイトや地区を地図上に記載した「土壌汚染要調査マップ」をひとまず作成することも有効と考えられる。
また、自然由来の土壌汚染についてデータベースを作成することも検討する必要がある。
土壌汚染情報のデータベース化
土壌汚染においては原因者負担が原則ではあるが、原因者に資力が無い場合や原因者が浄化しただけでは十分な開発が困難な場合であって、当該土地を活用して地域活性化等の施策を講じる必要が有る場合には、補助金や基金の創設、税制優遇等について検討することも考えられるので、実態把握の上、更なる検討・検証を進める。
公的支援の必要性
サクセスモデルの構築
資産評価の一層の適正化
その他の有効利用促進策
今後も市場の動向を注視しつつ、信託やファンド、保険等の活用については引き続き検討を進める必要がある。
また、土地所有者、開発業者、建設業者、さらには行政担当者等の関係者が土壌汚染について必要な知識を有していれば、必要に応じて調査等の対策を講じることが可能になるため、同業者の会合や講習等を通じ正確な知識を周知するとともに、土地取引に関する不正の防止に努める必要がある。
さらに、官民の連携を進めるため、自治体の環境部局のみならず、建築部局や都市開発部局といった関係部署においても土壌汚染が土地取引やまちづくり等の大きな阻害要因となっている旨を認識し、自治体内部で一丸となって取り組む態勢づくりが必要である。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030404/03.pdf
目 次
1.はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.土壌汚染の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1 土壌汚染の現状認識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1.1 現状認識
2.1.2 土壌汚染の可能性のある土地
2.2 土壌汚染の調査・対策の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2.2.1 土壌汚染対策法に基づく調査・対策の実施状況
2.2.2 条例・要綱等に基づく土壌汚染の調査・対策の実施状況
2.2.3 民間の自主的な調査・対策の実施状況
2.3 ヒアリング等による土壌汚染の実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2.3.1 土壌汚染の発生状況と対策
2.3.2 デベロッパー
2.3.3 ハウスメーカー
2.3.4 総合建設会社
2.3.5 外資系不動産ファンド
2.3.6 産業用不動産特化型REIT 運用会社
2.3.7 大規模土地所有企業
2.3.8 地方公共団体
3.土壌汚染に係る現行制度と諸問題・取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3.1 土壌汚染の調査と情報収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3.1.1 土壌汚染調査 /3.1.2 情報収集と活用
3.2 土壌汚染の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
3.2.1 用途別基準 /3.2.2 自然由来の汚染
3.3 土壌汚染の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
3.3.1 責任負担者
3.3.2 法令上の要求措置と実態の乖離
3.4 土壌汚染の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
3.5 土壌汚染がある土地取引のリスクと財政的支援・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
3.5.1 土壌汚染に係るリスクとリスク分担
3.5.2 低利融資等
3.5.3 保険
3.5.4 保証
3.5.5 買取り
3.5.6 信託
3.6 土壌汚染地の資産評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
3.6.1 土地の資産評価の枠組み
3.6.2 不動産鑑定評価の実務における土壌汚染地評価の基本的考え方
3.6.3 スティグマの評価
3.6.4 エンジニアリングレポートの重要性
3.6.5 課税関係
4.諸外国の制度・取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
4.1 米国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
4.1.1 スーパーファンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ
4.1.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み /4.1.3 浄化修復目標の設定
4.1.4 制度的管理
4.1.5 財政支援施策
4.1.6 環境負債免除制度
4.2 ドイツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
4.2.1 連邦土壌保護法制定の経緯
4.2.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
4.2.3 浄化修復目標の設定
4.2.4 制度的管理
4.2.5 公的関与
5.土壌汚染地における土地の有効利用促進等に向けた課題・・・・・・・・・・・・・・・ 63
5.1 更なる実態・影響の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
5.2 土壌汚染情報のデータベース化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
5.2.1 土壌汚染情報データベースの構築
5.2.2 土壌汚染要調査マップの作成
5.2.3 自然由来の土壌汚染データベースの構築
5.3 公的支援の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
5.4 サクセスモデルの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
5.4.1 サクセスモデルの構築 /5.4.2 官民の連携
5.5 資産評価の一層の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
5.6 その他の有効利用促進策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
5.6.1 信託、ファンド、保険等のリスク軽減策
5.6.2 土壌汚染の正確な知識の周知と土地取引の不正防止
1 はじめに
日本の限られた国土において、土地は国民共通の財産であり、土地の適切かつ有効な利用を
実現するためには、土地を有効利用しようとする者に対し円滑に土地を移転しやすくすること
を通じた土地取引の活性化を図ることが必要である。土地取引が円滑に行われることは、国土
の適正な利用につながると考えられる。
土壌汚染問題については、土壌汚染対策法施行後注目が集まっているところであり、土地取
引市場においても、そのリスクが近年強く意識されるようになっている。国土交通省では、土
壌汚染対策法施行以前の平成14 年10 月に「宅地公共用地に関する土壌汚染対策研究会」を設
置し、翌年6 月に土地取引の安全性と円滑化の確保を目的とした土地売買契約に当たっての留
意事項や、土地建物取引業者の留意事項に関する基本的な事項等を体系的にとりまとめ、公表
してきたところである。
しかしながら、土壌汚染の判明した土地については、依然として土地取引が忌避され、土地
の有効利用や再開発、まちづくりの観点から支障が生じる事態になっている。土壌汚染の問題
は、ともすれば土地所有者が汚染事実の公表に消極的となるので、土地の有効利用にとって、
どれだけ重要な問題であるかということが社会的に十分理解されていないのではないかという
指摘もある。実態として、土壌汚染が土地取引にどれだけの影響を与え、取引を阻害している
のかを、具体的なケースを含めて、調査、把握することが必要である。
さらには、土壌汚染土地の取引に係る様々な事項について、具体的な課題を抽出・整理し、
具体的な方策の検討につなげていくことが重要である。日本では、関係者が土壌汚染リスクに
敏感となり、法的には必ずしも要求されていない土壌汚染の完全除去を実施するケースが多く、
社会的コストの増加につながっている。また、土壌汚染土地の調査については、公的に利用可
能な情報基盤や調査・評価の枠組みに、整備改善の可能性があるという指摘が多い。土壌汚染
土地の取引に係るリスク分担を整理し、保険等のリスクヘッジのスキームを充実していくこと
が、土壌汚染土地の取引活性化につながるという意見もある。
一方、コンバージェンスの一環として、減損会計の導入等の時価会計への一本化等も進めら
れており、土壌汚染地における鑑定評価の重要性が高まるなど、土地政策の観点から土壌汚染
について検討することが強く求められている。
上記の問題意識を踏まえ、土地取引の円滑化による土地の有効利用促進等の観点から、土壌
汚染土地について現状と課題を整理し、具体的な方策につながる検討を行うことを目的として、
本研究会が設置された。本研究会においては、土壌汚染土地の取引に関係する民間企業や地方
自治体へのヒアリング、米国とドイツの事例の研究を行うと共に、本研究会委員及び土壌汚染
に関する専門的な知識を有する実務者からの発表を受けた議論を行い、今後、土壌汚染地にお
ける土地の有効利用方策を検討する際の課題を整理したところである。
2.土壌汚染の現状
2.1 土壌汚染の現状認識
2.1.1 現状認識
土壌汚染の現状に関して、土壌汚染対策法や各自治体の条例・要綱等に基づく調査・対策
の報告状況の他に、民間の自主的な実施状況に関するアンケート調査等の既存資料がある。
しかしながら、土地所有者等にとって、土壌汚染の判明は新たな調査・対策費用が必要と
なったり、近隣地域との軋轢が発生するおそれが高まったり、また土地資産評価の減価要因
になりうることなどから、自ら公表しづらいという問題を抱えているため、我が国では秘匿
されがちで、個別サイトに関する土壌汚染情報を入手することはきわめて困難な状況にある。
個別サイトに関する汚染情報を把握するためには、土壌汚染の土地を取り扱うデベロッパ
ーや不動産ファンド、このような土地を所有している企業、土壌汚染に関する相談・指導を
行う地方公共団体等に個別にヒアリング等を実施することが現状では有効と考えられる。
2.1.2 土壌汚染の可能性のある土地
? 土壌汚染の発生原因
土壌汚染の代表的な発生原因として、以下の4 つがある。
・工場などで使用していた有害物質が、不適切な取扱いや老朽化等による施設、設備の破損により漏えい、流出、飛散して土壌に浸透するという事業活動が原因の汚染
・産業廃棄物が埋立処分された土地で発生するという廃棄物が原因の汚染
・事故や災害により施設、設備が故障、破損等することにより有害物質が漏えい、流出、飛散等して土壌に浸透するという、事故や災害が起因の汚染
・重金属を含む岩石や地層が風化、流出して河川や平野部、海岸に堆積した自然の土壌中に存在する自然由来の汚染
? 工場等産業用地の土壌汚染
土壌汚染は日本の産業発展に伴って発生した過去の大きな負の遺産であり、水質汚濁防止
法による規制が行われる以前は、現在では汚染物質といわれる物質の一部も合法的に土壌に
浸透させることが可能であった。現在、有害物質使用特定施設として該当する土地は全国で
27,000 箇所といわれており、またカソリンスタンドやクリーニング事業等により土壌が汚染
されている可能性のある箇所は30 万箇所を越えるといわれている。
? 廃棄物処分地の土壌汚染
過去に廃棄物で埋め立てられた土地において、土壌汚染が見つかっている。
? 幹線道路沿道の土壌汚染
幹線道路沿道の土地では、自動車からの排気ガスに含まれている鉛などによる汚染が指摘
されており、土壌汚染は日常の生活空間のまわりで広く発生していると考えられる。
? 臨海部等埋立造成地の土壌汚染
過去に埋め立てられた臨海部の土地においては、砒素などが含まれる河川や浅海域の底質
の浚渫土砂等が埋め立てに使われていることが多いことから、土壌汚染の可能性が指摘され
ている。
臨海部以外の低・平地部の埋立造成地においても、持ち込まれた土が原因の汚染が見つか
っている。
なお、当該地域以外から持ち込まれた盛土材や廃棄物により埋立造成された場合には、土
壌汚染対策法の対象となる。
? 自然的原因の土壌汚染
自然に存在する岩石、地層に含まれる重金属が風化や水の流出に伴って拡散し、低・平地
部に自然堆積した場合や、これらを含む河床や海底での堆積土砂などにより埋め立てられた
場合は、自然的原因の土壌汚染と見なされる。自然的原因の可能性のある物質として、砒素、
鉛、フッ素、ホウ素、水銀、カドミウム、セレン、六価クロムなどがある。
自然的原因による高濃度の特定有害物質を含む土壌又は水底土砂が、周辺地域において盛
土や海面を埋め立てることにより造成された土地は、自然的原因により指定基準を超過した
ものとし、土壌汚染対策法の対象とはならないが、当該地域以外の土地から持ち込まれ、専
ら自然的原因により指定基準を超過する土壌は、土壌汚染対策法の対象となり、土壌を持ち
込んだ者が汚染原因者と見なされる。持ち込んだものが不明の場合は土地所有者が必要に応
じて措置を行うことになっている。
都市部においては、本来の河川堆積物による土壌汚染に、過去からの都市活動により河川
域の汚染原因者が不特定多数で特定できない人為的な汚染が混在しているという問題がある。
自然的原因による土壌汚染を判断することは可能であるが、人為的汚染と混在した場合に
それを区分することはかなり作業が必要となる。
その区分を把握するためには、自然的汚染は含有量が一定の範囲内にあり、広域で観測され
て局在性がないなどの特色を持っているこ
とから、広域的な視点からバックグラウンド濃度などのデータを収集して分布特性等を見て
判断していくことが必要である。
2.2 土壌汚染の調査・対策の実施状況
2.2.1 土壌汚染対策法に基づく調査・対策の実施状況
土壌汚染対策法が平成15 年2 月から施行されて以後の4 年間での法適用案件は622 件で
ある。このうち、土壌汚染の指定区域に指定されたものは172 件(28%)あり、措置済みが
91 件(15%)、措置実施中・検討中が69 件(11%)あり、未処置はわずかに12 件(2%)
である。
具体的に実施された措置としては、掘削除去が最も多く76%を占め、次いで原位置浄化が
18%、舗装措置が4%、立入禁止措置が3%の順である。
図2.2.1 指定区域の状況(平成15 年2 月15 日〜平成19 年2 月14 日)
(資料:環境省「平成19 年度版環境白書・循環型社会白書」)
2.2.2 条例・要綱等に基づく土壌汚染の調査・対策の実施状況
土壌汚染対策法が施行されて以降、多くの地方公共団体で条例や要綱等が改正され、その
中に土壌汚染に関する調査・対策の実施義務や届出措置が盛り込まれた。
都道府県調べによる年度別の土壌汚染調査件数及び判明件数は図2.2.2 に示すとおりであ
り、平成15 年2 月に土壌汚染対策法が施行されて以来、土壌汚染調査件数及び判明件数は大
きく増加している。
東京都条例に基づく土壌汚染調査の対象は、
・工場、指定作業所を設置して有害物質を取り扱い、又は取り扱った者、
・3,000 ?以上の敷地内で土地の切り盛り、掘削等土地の改変を行う者である。
また、新潟県では、平成16 年9 月から施行された新潟県生活環境の保全等に関する条例に
基づき有害物質を扱う事業所については5 年に1 回土壌汚染調査の実施を義務付けているが、
まだ届出件数はわずかである。
図2.2.2 年度別土壌汚染判明件数
(資料:環境省水・大気環境局「平成16 年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」)
2.2.3 民間の自主的な調査・対策の実施状況
? 民間の自主的な調査・対策の実施件数の増加傾向
土壌汚染の調査・対策は、健康被害を防止することよりも、むしろ土地資産価値の劣化を
防止する目的で実施されることが多い。土壌汚染対策法や条例・要綱によらない民間の自主
的な調査・対策の実施件数が増加してきており、(社)土壌環境センターの会員企業に対する
アンケート調査結果によれば、土壌汚染の調査及び対策の実施件数は平成17 年度で10,812
件に及んでおり、このうち土壌汚染調査の約8 割の件数が民間の自主的なものとなっている。
土壌汚染対策法や条例・要綱に基づく調査は約2 割である。
図2.2.3 土壌汚染調査の対象
? 土地取引を契機とした自主的な調査・対策が多い
調査及び対策の実施件数の多くは土地取引を契機としたものとなっており、土地取引に際
して土壌汚染の存在の有無の確認、存在する場合の調査・対策を求めるケースが増えている
ことがうかがえる。
図2.2.4 土壌汚染調査・対策の受託件数及び受託金額の推移
表2.2.1 土壌汚染調査・対策の契機となった理由
図2.2.5 自主調査を行う契機となった理由
図2.2.6 自主対策を行う契機となった理由
2.3 ヒアリング等による土壌汚染の実態
デベロッパー3 社、ハウスメーカー1 社、総合建設会社1 社、外資系不動産ファンド1 社、
産業用不動産特化型REIT 運用会社2 社、大規模土地所有企業3 社、地方公共団体6 団体に対
するヒアリング調査等から判明した土壌汚染の実態は、以下に示すとおりである。
2.3.1 土壌汚染の発生状況と対策
? 土壌汚染の発生状況
土壌汚染は、古くから操業を行っていた工場跡地、操業中の工場用地、市街地内のメッキ
工場やクリーニング工場、ガソリンスタンド、臨海部の埋立地、廃棄物により埋め立てられ
た土地、自然由来と思われる商業地等において判明している。
? 大都市と地方との比較
ア.大都市における土壌汚染と対策
東京のような大都市内においては、土地取引や都市開発の際に土壌汚染が判明しても、
土地価格が高いことから、掘削除去などの浄化対策費用を吸収可能であることから、ブラ
ウンフィールド化している事例はほとんど聞かれなかった。
マンション開発などの際には、土地所有者による掘削除去による対策がほとんどである。
なお、大都市内において、土地履歴調査で汚染のおそれのない土地において工事中の段
階で、搬出土調査等により汚染が判明するケースが出てきている。こうした場合は、売主
と買主との間で訴訟になるケースも見られた。
イ.地方における土壌汚染と対策
新潟市や盛岡市などの地方中核都市の市内においては、最近マンション開発などの際の
調査で土壌汚染が判明したケースが見られるが、その場合は主に掘削除去による浄化対策
が実施されており、土地取引や都市開発がストップしたような事例は聞かれなかった。
なお、新潟市内において、マンション開発の際に掘削除去と併せて封じ込め措置による
対策を併せて実施している事例もあり、また住宅以外の商業施設等の立地の場合は封じ込
め措置による対策も行われている。
しかし、それ以外のエリア、又は汚染の程度が広範囲に及んでいる場合は、土地価格に
比して相対的に土壌汚染対策費用が高いことから、汚染拡散防止措置のみを行っている事
例も見られた。こうした場合は、開発を断念したり、土地取引において買主と売主との間
でトラブルになるケースが生じている。
ウ.小規模な事業用地における土壌汚染と対策
地方都市内のメッキ工場やクリーニング用地において土壌汚染が判明した場合に、土地
所有者に対策コストを負担する資金的能力が低いことから、土地取引ができずにそのまま
となっている土地が存在しているケースが見られる。こうした土地では汚染拡散防止程度
の措置が実施されている。
クリーニング工場やメッキ工場などの小規模な事業所の汚染では、対策費用の比率が高
くなり、また資力もないことから、利用促進上のハードルが高くなって、ブラウンフィー
ルド化の懸念が高まっている。
大規模な再開発の中での小規模な土壌汚染の存在については、再開発事業の中で対処す
ることが考えられるが、市街地内で単独で残っている場合は、調査すらされずにそのまま
残されてしまうケースの発生が懸念される。
なお、ガソリンスタンドが廃止又は改修する際に油による土壌汚染が判明したケースが
あるが、系列の大手会社が前面に出て調査・対策を実施しているため、問題は生じていな
い。
? その他
ア.土壌汚染情報の秘匿
今回のヒアリングは、各企業や地方公共団体による土壌汚染問題への取組みを調べるの
みならず、個々のサイトの土壌汚染情報についても把握し、今後の検討に役立てることを
も意図したものだったが、あまり個別のサイトの土壌汚染情報は聞くことができなかった。
イ.土壌汚染が判明した場合の汚染原因者でない土地所有者の困惑
土地所有者が関与していない、いわゆる自然由来、埋立由来、もらい汚染と考えられる
土壌汚染が判明した場合に、とりわけ資金負担能力の低い土地所有者にとっては、対策を
行うことが困難であるため、相当深刻な事態となっている。
ウ.調査実施後に新たな汚染が判明したケースの発生
土地履歴調査を実施して汚染がないと判断して、土地を買収して開発する際に土壌汚染
が新たに判明したケースが生じており、売主と買主との間でトラブルになったり、デベロ
ッパー側に何らかの負担を強いられている。
2.3.2 デベロッパー3社
? 土壌汚染への対応
大手のデベロッパーは、事業用地の取得に際して土壌汚染に対処する独自の調査・判定ル
ールを設けて用地取得の可否を選別している。すべての案件についてフェーズ?調査は必須
としており、土壌汚染の可能性がある場合はフェーズ?調査を実施して、取得の可否を判断
している。
土壌汚染物件の住居系への開発・転売については、原則として掘削除去など完全浄化が可
能なものである場合が多い。但し、物流施設や商業施設への転用のケースでは法令要件を満
たせば、完全浄化でなくても受け入れるケースがある。
土地取得に際しては、自然由来による汚染も含め環境基準超過土壌は完全除去を行うこと
を基本としている。
? 特徴的な事例
ア.大都市内の都市開発可能用地において土壌汚染のため都市開発を断念したケース
大都市内の都市開発が可能な土地は、通常土地価格が高いことから、土壌汚染が判明し
ても掘削除去による対策費を吸収することが可能であるが、土壌汚染が重篤な場合や、土
壌汚染が相当にあると考えられリスク評価できない場合、周辺の状況から対策ができない
場合、また土地所有者が瑕疵担保責任を負わない場合には、開発を断念するケースがある。
イ.工事中の調査で新たな汚染が判明するケース
土地引渡し前の調査では土壌汚染が判明していないが、工事中の調査で汚染が見つかっ
たケースが出てきており、事前調査の信頼性が揺らいでいる。
こうした場合は売主・買主の間で責任の範囲についてトラブルに発展しやすい。瑕疵担
保期間が過ぎた場合や売主が全く知らない場合もあり、事業者側の新たな負担となる。ま
た、追加対策のために事業スケジュールが伸びると、契約期間内の引渡しが困難になる、
金利負担が増大するなどの影響がでる。
? 意見・感想等
ア.土壌汚染問題は地方都市ほど都市開発に影響を与えるため、対策面での工夫が必要
地方都市で、ブラウンフィールドが発生する可能性は高い。地方になればなるほど土地
価格が下がり、その対策費を土地価格で吸収できなくなる。掘削除去以外の封じ込めなど
の対策を模索していくことが必要となる。
札幌市や新潟市での開発事例(分譲マンション開発)では、土壌汚染対策費は土地価格
と同程度となって負担が大きく、掘削除去による対策では採算が合わない事態が生じてい
る。このため、深さ1m まで掘削除去、1m 以深の汚染については封じ込め措置を行って開
発したケースがある。購入者に対しては土壌汚染の調査・対策の状況を十分に説明して了
解を得ている。なお、封じ込め措置による土地価格の減価は行っていない。
イ.土壌汚染処理のための新たな基準づくりについて
現在の土壌汚染の環境基準では対策が過大になりがちで、そこまで浄化処理する必要が
あるのか、疑問の声が聞かれた。土地利用に合わせて、もっと緩やかな基準があってもよ
く、行政側で新たな基準づくりが行われることが望ましい。一般に広く理解が得られ、資
産評価にも影響しないようなものが出来るとよい。
法や条例の改正により新たな項目が環境基準に追加されると既存不適格となってしまう
土地が生じ、新たな対応が求められることになり、このような土地が多いことが指摘された。
ウ.土地取引のリスクを軽減する保険制度について
瑕疵担保保険は、保険料が高いため現在利用されていない。事業者のリスクを軽減でき
るような保険があればよいとする意見や、なくてもよいとする意見があった。
エ.地方や中小の工業等事業者への支援について
土壌汚染問題で身動きのとれないで困っている地方や中小の工業等事業者に対する支援
措置があれば、望ましい。
オ.土壌汚染地を開発する際のインセンティブ
土壌汚染地を開発する場合に、開発者側のリスクを緩和するような措置や自然由来の汚
染など原因者が不明の場合については固定資産税減免などの支援措置があれば、望ましい。
<参考>
(社)不動産協会作成の「マンション開発事業における土壌汚染対策に関する留意事項」
【マンション事業における土壌汚染対策に関する留意事項】(平成14 年11 月(社)不動産協会作成)
(社)不動産協会では、平成14 年11 月に、分譲マンション事業においてデベロッパーとし
てのリスク管理の観点から考え方を示したガイドラインである「マンション事業における土壌汚
染対策に関する留意事項」を定めた。詳細は以下のとおりである。
・ 土地履歴等調査については、売主に詳細な情報の提供を求めるとともに、買主自らも土壌汚
染情報の収集を行う。
・ マンション事業用地の売買契約において、土地履歴等調査で汚染がないことが確実な場合を
除いて、土壌汚染に関する調査を売主の負担と責任において約定し、また汚染が認められない
として引渡しを受けた後に買主の調査で汚染が発見された場合は、売主に対して責任を追及で
きる旨の特約を明確に約定する。
・ マンション事業用地の土壌汚染については、売買契約において浄化処理・汚染拡散防止措置
等を売主の負担と責任において引渡し日までに実施する旨、また引渡し後に買主の調査で汚染
が発見され、買主が浄化等の措置を行った場合についても、その費用並びに損害賠償を売主に
対して請求できる旨を明確に約定する。
・ 土地引渡し後の土壌汚染の発見に備えて、売買契約書には、所有権の移転時期、土壌汚染に
関する瑕疵担保責任及び売主による浄化措置の実施義務等の条項を必ず記載する。
・ 敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を実施した場合は、購入者に対して重要事項説
明書に基づいて正確に説明し、また購入者にその報告書(写)を交付し、併せて管理組合に原
本を引き渡す。
2.3.3 ハウスメーカー1社
? 土壌汚染への対応
大手の開発案件については、独自の調査マニュアルに基づき、すべての案件で土地履歴調
査を実施している。工場についてはすべてリスクありと判断し、また、資材置き場、倉庫、
作業場等についても詳細が不明な場合はリスクありと判断して土壌調査を実施している。
マンション用地では履歴上のリスクの有無にかかわらず全案件でより厳格なリスク評価を
行っており、汚染が判明した場合は原則として掘削除去等の完全浄化を実施している。年に
数件、汚染が重篤な場合や土地価格に見合わない場合として土地取得を断念している。
商業系や駐車場用途の場合で低濃度汚染の場合は、掘削除去以外の封じ込め又はバイオ手
法などによる長期浄化の対策もありうる。
土壌汚染リスクのある土地に対しては、跡地利用に併せて調査及び浄化対策を同時に検討
することにより、最適利用しましょうという提案をし始めている。
なお、汚染があった土地を販売する場合には、完全浄化後であっても重要事項として顧客
に説明を実施している。説明後の顧客の反応は比較的良好であった。汚染の程度が比較的低
濃度で対策も掘削除去とわかりやすい内容であったこと、積極的なリスクコミュニケーショ
ンを実施したこと等から、顧客の理解が得られた。
? 特徴的な事例
ア.建設時に新たな汚染が判明するケース
造成時の盛土や廃棄物埋設による汚染は土地履歴調査では発見することが困難であり、
マンション建設時の搬出残土の調査(残土条例や残土業者の自主調査)で汚染が判明する
事例が増えている。売買契約時に瑕疵担保を定めていても、売主の経済力などの問題で回
収できず、瑕疵担保が効果を発揮しないケースが増えてきている。
イ.施設建設後のモニタリング調査で汚染が判明するケース
特別なケースとして、過去に廃棄物により埋め立てられた土地を商業開発する際に土壌
汚染が判明したため、封じ込め措置を行って施設を建設したが、オープン後のモニタリン
グ調査で汚染地下水の流出が判明したことから、土地所有者が再度流出防止対策を実施し
た事例がある。
2.3.4 総合建設会社1社
土壌汚染を抱える開発案件の最近の情報や相談事例から、土壌汚染に関して以下のような
指摘があった。
? 土壌汚染地に対する土地所有者・土地購入者の意識
土地所有者の意識として、汚染があると買手が見つからないので、売却するためには完全
浄化をせざるをえないが、対策費用が工事費の30%を超えると、売却益が見込めなくなって
売却を断念するケースが多くなり、土地保有を継続して土地利用していくこととなる。
土地購入者としては、汚染がない、又は完全に浄化された土地を購入したい、という意識
が強い。背景として、土地利用上の制約がない、後々の問題を抱えたくない、風評が心配、
再売却時に問題を残したくない、という理由がある。
? 小規模事業所のブラウンフィールド化の懸念
大都市圏では、最近の土地価格の上昇傾向もあって土壌汚染対策費用を捻出できるケース
が大半である。しかし、クリーニング工場やメッキ工場などの小規模な事業所の汚染では、
対策費用の比率が高くなり、また資力もないことから、利用促進上のハードルが高くなって、
ブラウンフィールド化の懸念が高いケースがあるように感じられる。こうした場合では、調
査や対策もされずにそのまま残されてしまうような懸念がある。
? 商業施設や倉庫における封じ込め措置の例
商業施設や倉庫については、封じ込め措置により利用している事例が出てきている。
? 地方都市におけるブラウンフィールド化の事例
地方都市の工場等跡地において売却の際の自主調査で土壌汚染が判明し、土地価格に比し
て汚染対策費用が高額になるため、売却を断念して拡散防止措置のみを行ったうえで、駐車
場等に暫定利用又は放置されている、事例が数例ある。
・ 工場を閉鎖して土地を売却する際の自主調査で土壌汚染が判明しため、重金属による汚染
部分を掘削除去して、地下水汚染のない約半分の土地を売却し、残りの半分は売却を断念し
た事例
・ 工場跡地を購入して一部の土地を売却した後に自主調査により汚染が判明したが、対策費
用が多額になるため拡散防止対策(舗装及び揚水処理)のみを実施したが、新たな土地購入
者を確保できないため、駐車場として暫定利用している事例
・ 工場用地の一部を開発事業者に売却する際の自主調査で重金属汚染が判明したが、土地価
格に比して対策費用が過大になるため、売却を断念して舗装状態のままで利用用途を検討し
ている事例
・ 製油所跡地に公共的施設を誘致する際の自主調査で重金属、VOCs 及び油による広範囲な
土壌汚染が判明したが、土壌汚染対策費用が多額となるため、売却を断念してゴルフ練習場
などとして利用している事例
・ 工場跡地の売却の際の自主調査で重金属及びVOCs による汚染が判明したため、社会的責
任の見地から土地所有者は掘削除去を実施したが、土地の売却はやめて商業施設及び駐車場
として賃貸している事例
2.3.5 外資系不動産ファンド1社
? 土壌汚染への対応
受け入れ基準は厳格で、フェーズ?調査で土壌汚染の可能性が確認されれば、土地購入の
対象としていない。土地購入の対象となる不動産は汚染がない土地である。
今後の事業展開において、土壌汚染地を扱う可能性はあるとしているが、土壌汚染地を扱
う場合にはリスクを定量評価できることが必要であり、技術面のリスク・テイクをするゼネ
コン等の関与が必要である。
? 意見・感想等
フェーズ?調査のコスト低減、確度の向上につながる情報の開示は歓迎する。
2.3.6 産業用不動産特化型REIT 運用会社2社
? 土壌汚染への対応
商業・物流REIT では、汚染リスクが残置する物件を取得するケースもあるようである。
土壌汚染地の取得に関して自主基準に基づいて判断しており、ある社では、
?適切に対策され周囲への影響がないこと、
?将来の汚染対策費が予測可能であること、
?将来売却する場合に資産価値の大幅な下落がないこと、
の3 点を投資対象の要件としている。投資の持ち込み物件には土壌汚染地が多いが、
検討の優先順位は低くなる。
しかし、一方で投資の検討対象として土壌汚染地を避けて通るのは難しい。
? 特徴的な事例
産業用不動産については、産業用地としての利用の継続性が投資対象を選択する基準であ
ることから、掘削除去にこだわる必要はなく、その他の対策も実施可能である。
将来の改築の際に発生する汚染残土処理費用や土壌改良費を見込み、土地価格から減価す
ることで、土地取引を実施している例もある。
? 意見・感想等
ア.汚染情報の開示と活用について
元来REIT では、土壌汚染情報を開示する義務がある。検討対象物件の土壌汚染情報を
得られることは歓迎するが、コストが必要な場合はコスト・パフォーマンスで判断する。
イ.エンジニアリングレポート(ER)の信頼性の確保が必要
特別な資格を有しない者が作成するER に基づいて不動産鑑定士が土地評価を行うこと
には、問題があると思われる。
ウ.埋立由来や原因者が特定できない汚染の場合についての行政側の適切な支援
埋立由来や原因者が特定できない場合は行政側の適切な支援を行う制度の構築が望まし
い。
また、優遇税制、補助金などの制度化に向けての検討を期待する。
エ.政府による用途別基準づくり
土壌汚染地の土地取引についての自主基準は持っているが、政府による用途別の基準が
あることが望ましい。
2.3.7 大規模土地所有企業3社
? 土壌汚染への対応
所有地の土壌汚染については、自主的な調査・対策を実施している。
東京都内の工場跡地を都市開発する場合は、掘削除去による土壌汚染対策を実施している。
住民・マスコミ等風評リスクを恐れる企業も少なくなく、情報開示に必ずしも積極的では
ないという企業がある一方、自らホームページ等で公開に努めている企業もあった。
関西のある企業では、関西圏に広く散在している工場跡地の十数ヶ所で土壌汚染が判明し
たため、土壌汚染のリスク管理措置として、汚染拡散防止、地下水監視などの用地管理強化、
土壌の改善措置(盛土や舗装による表層追加被覆、汚染土壌中心部の掘削除去、土壌ガス吸
引などの原位置浄化)を実施している。
? 特徴的な事例
ア.土壌汚染地の自社利用等をしているケース
土壌汚染地については、掘削除去による浄化措置を実施して用地を売却した場合や、売
却しないで自社利用している場合がある。
後者については、汚染を残した状態では土地を売却できないものの、土壌汚染対策費が
高額になることから、やむをえず研究施設、倉庫、事務所、訓練所等として自社利用して
いる面もある。
関西のある企業が所有する京都市内の工場跡地のような立地条件の良い場所はグループ
会社で都市開発している。この場合も土地は売らずに施設を建設して賃貸している。建物
基礎部分は掘削除去を実施している。
イ.土壌汚染が土地活用を阻害しているケース
立地条件のよくない工場跡地では、土地利用ニーズがあまり期待できないことや土壌汚
染対策費がかかりすぎることがネックとなって土地活用の阻害要因となっていることがあ
る。
? 意見・感想等
ア.埋立地の土壌汚染対策に係る所有者責任について
臨海部の土地は埋立由来と考えられる汚染が必ずあり、土地を購入した所有者がすべて
対策をしなければならないことに対して、疑問を感じる。
イ.原因別、用途別の基準づくりが望まれる
現在の環境基準が厳しすぎるきらいがある。埋立由来や自然由来と思われる汚染、地下
水の直接摂取の可能性が低い汚染に対しては、基準に少し配慮があっても良いのではないか。
ウ.土壌汚染地を開発する際のインセンティブが望まれる
もらい汚染、埋立由来の汚染など土地所有者が原因者でなく、原因者が特定できない汚
染に対しては、対策費用の一部補助や税の減免措置などの支援が望ましい。
地方の土地価格の安い土地の汚染については、土地が売るに売れない厳しい環境にある
と思われるため、このような土地の有効利用を促進するための支援が望ましい。
エ.土壌汚染に対する心理的抵抗感の払拭が必要
土壌汚染に対して過剰反応しすぎる面があり、リスク管理措置でも大丈夫であるという
認識が広まるように努めてほしい。
2.3.8 地方公共団体
(1)岩手県、盛岡市
? 土壌汚染への対応
行政に報告されている土壌汚染については、法や条例に基づくもの以外の民間の自主調査
によって汚染が判明したものが多い。報告のあった件については、法や条例等に基づいて相
談・指導を実施している。なお、地下水汚染が判明した場合は、行政側で周辺の地下水調査
を実施して汚染の拡大の有無を確認している。
開発区域内のクリーニング工場跡地で溶剤漏出による汚染が判明したため、土壌浄化対策
を実施している。また、地下水モニタリングを実施する必要があることから、そのスケジュ
ールが遅延するおそれがある。
? 特徴的な事例
ア.市内のマンション開発を契機とした自主調査で土壌汚染が判明
盛岡市内でマンション開発が進んでおり、開発を契機とした民間の自主調査で土壌汚染
が判明したケースが出てきている。
マンション開発の場合は土地所有者が掘削除去で対処している。
また、かつて商用地として利用され、土地履歴で土壌汚染のおそれの少ない土地を買収
した後に、買主側の自主調査で土壌汚染が判明(盛土造成による汚染の可能性が高い)し
たケースもある。こういった場合、マンション開発のため全量掘削除去したくとも、その
対策費が多額になるため、費用負担の割合をめぐって売主と買主との間で訴訟になるおそ
れが生じている。
イ.油汚染の事例
自動車整備工場による油汚染の事例や灯油流出汚染の事例が報告されている。
? 意見・感想等
岩手県内(盛岡市除く)では、工場は継続操業されており、土壌汚染問題が生じている工
場跡地は今のところ見当たらない。工場の自主調査で土壌汚染が見つかった場合は必要な対
策が実施されている。
なお、盛岡市内を除いたエリアでは、都市開発ニーズが乏しいことから、工業の継続的な
土地利用が余儀なくされている面もあると考えられる。
(2)埼玉県
? 土壌汚染への対応
土壌汚染が見つかった場合は、事業者に公表を勧めている。事業所敷地外への地下水汚染
が考えられる場合には、行政側で周辺の地下水調査を実施している。
? 意見・感想
・ 土壌汚染対策法第3 条ただし書きで調査が猶予されているケースも多く、土壌汚染が発覚
しないことがあると思われる。土壌汚染の対策としては、掘削除去がほとんどである。
・ 小規模な事業所が多いクリーニング業は、調査が行われることが少ない。同じ小規模な事
業所でもガソリンスタンドは業界の補助金制度を活用して汚染を除去している例が見られる。
・ 埼玉県内の比較的交通便利な場所では、都市開発が進みつつあるが、土地価格の上昇によ
り掘削除去対策でも採算がとれるようになってきている。
(3)新潟県・新潟市
? 土壌汚染の状況と対応
新潟県生活環境の保全等に関する条例(平成16 年9 月施行)に基づき、有害物質を扱う事
業所については5 年に1 回土壌汚染調査を義務付けている。汚染が確認された場合は県等へ
の報告が必要であるが、まだ報告件数はわずかである。
調査義務対象外の事業場の自主調査により土壌汚染が判明し届出されたものは30 件以上
であるが、その調査の契機は土地取引に際してのものが多い。土壌汚染は、金属製品製造業
等によるものが多く、またガソリンスタンドの廃止又はタンク改修によるものも5〜6 件ある。
土壌汚染は、工場跡地に限らず、商業地等においても見られる。新潟市の場合は、地質の
特性から自然由来といわれる砒素などによる汚染が見られる。また、新潟地域には油田が埋
蔵されており、また石油産業の立地が多いため、先の地震による液状化の影響で油汚染が判
明する可能性がある。
マンションなど住宅開発の場合は掘削除去による対策が最も行われている。但し、マンシ
ョン開発の場合でも、汚染が敷地の広い範囲に及んでいるケースでは、建物基礎及び含有量
基準をオーバーしている汚染箇所を掘削除去し、溶出量基準をオーバーしている箇所等は封
じ込め措置がとられているケースがある。
住宅以外の商業施設、工業系施設の場合は、掘削除去は費用がかかるため、汚染拡散防止
措置がとられるケースが多い。敷地内の他の場所に汚染土壌を移動してアスファルト舗装等
による拡散防止措置が実施されている。
なお、新潟市内において、土壌汚染のために土地取引や土地利用が停滞しているような事
例は聞いていない。また、土壌汚染地の土地取引において問題が発生しているような事例も
見当たらない。
? 特徴的な事例
ア.工場跡地等で開発等がストップしている事例
・ 自治体がかなり以前に工場跡地を取得したが、土壌汚染が判明したため、土地利用が進
まないケースがある。原因者は撤退しており、汚染拡散防止のために土地所有者である自
治体が地下水モニタリングを実施しているが、土地は未利用のままである。
・ 工場が廃止された跡地に商業施設が立地し、その商業施設を改築する際に土壌汚染が判
明したため、商業施設が改築を断念、撤退して未利用地のまま残されているケースがある。
・ 小規模なメッキ工場の廃止に際して土壌汚染が判明したが、浄化対策を実施することは
困難であるため、土地は拡散防止程度の措置をして未利用のまま残されているケースがあ
る。借地していた工場側と土地所有者との間で原状回復についての話し合いが続けられている。
イ.小規模な工場用地等の汚染の事例
小規模な工場用地の汚染の事例として、金属製品製造業の用地の汚染、クリーニング工
場用地の汚染、ガソリンスタンドの汚染が発生している。
金属製品製造業の工場用地でトリクロロエチレンによる土壌汚染(地下水汚染もあり)
が判明しているが、対策費用の関係で浄化は無理で拡散防止措置を実施している。
クリーニング工場の廃止に伴って汚染が判明した事例は2 件あり、この内の1 件は立地
条件がよい場所であったため、掘削除去による対策を実施した後に土地を売却している。
他の1 件は浄化対策が実施されたという報告は受けていない。
ガソリンスタンドの廃止又はタンクの改修に際して、ベンゼン及び油による土壌汚染が
見つかっている事例が5〜6 件ある。ガソリンスタンドのほとんどは大手の系列店であり、
大手企業が前面に出て土壌汚染調査・対策を実施している。
? 意見・感想等
新潟県内では、金属製品等製造業の中小規模事業所が多いことから、今後土壌汚染が判明
しても、自前で浄化措置を実施できないケースが出てくることが想定される。また、浄化対
策に長期間かかることや費用面の問題から、工場の操業中から汚染対策を実施していかない
と、対策ができなくなる可能性がある。
自然由来など土壌汚染の原因者が不明の場合に、対策が実施できないようなケースが出て
くる可能性がある。
(4)福島県
? 土壌汚染の状況
民間の自主調査で土壌汚染が発見された場合については、自発的に県への報告を依頼して
いる。県への報告・相談の件数は、自主調査によるものが年間数件程度、土壌汚染対策法に
基づくものは、年間0〜3 件である。
報告があった事例については情報を保管しているが、情報の公開は難しい。土壌汚染情報
全般については、現在稼動している事業所など大企業は自主調査を行っているようだが、県
で全ての結果を把握しているわけではない。
? 特徴的な事例
ア.土壌汚染地の土地利用が円滑に進んでいない事例
住宅地開発の中で、一部の土壌汚染地が未利用のままとなっている事例がある。
従前の利用は資材置き場であったが、宅地開発を行う段階で土壌汚染が発見されたが、
汚染原因者と考えられる企業が倒産したため、汚染除去費用を開発者が負担すると事業が
成立しないので、立ち入り禁止措置がとられている。
イ.土壌汚染地の土地取引・土地利用に際して問題が生じた事例
・ 工場の移転の際の自主調査によりVOC 類の汚染が発見されたため、事業者による浄化
措置が完了した後、教育施設用地として福島県が購入した。その後、県が施設を建設する
工事を行う過程で新たにフッ素による汚染も発見されたが、フッ素は事業者が行った調査
の項目に含まれていなかった。県では、教育施設用地としての土地利用を考慮して安全性
を重視して掘削除去を実施したが、汚染浄化費用は事業者と福島県で折半された。
・ 駅前広場整備工事中に土壌汚染(地下水汚染はない)が発見されたが、用地取得が土壌
汚染対策法施行前で瑕疵担保による負担金を求めることが出来なかったため、福島県が掘
削除去による対策費用を負担した。
? 意見・感想等
福島県の制度として環境創造資金という名称で公害対策用の低利融資制度を設けているが、
市中の銀行とそれほど利子が変わらないこともあって、あまり利用されていない。土壌汚染
対策を推進するために、この融資制度を広く周知し、制度が効果的に利用されるように図っ
ていく必要がある。
今後、県が公共事業土地を購入する際には、工場などの場合は土壌汚染について確認して、
契約段階で土壌汚染の浄化を附則として盛り込むことが必要かもしれない。
3.土壌汚染に係る現行制度と諸問題・取組み
3.1 土壌汚染の調査と情報収集
3.1.1 土壌汚染調査
(1)土壌汚染調査の目的及び契機
土壌が有害物質により汚染されると、汚染土壌の直接摂取や、汚染土壌から有害物質が溶
出した地下水の飲用等により人の健康に影響を及ぼすおそれがある。汚染原因者等の責任の
明確化と土壌汚染による健康被害の防止が求められる中、土壌汚染対策の法的な拠り所とし
て、平成15 年に土壌汚染対策法が施行された。同法のもとでは、特定の有害物質を取り扱っ
た工場や、事業所の敷地であった土地の所有者に土壌汚染の調査と、その結果の報告が義務
づけられている。
また、独自に条例を定め、土壌汚染調査に関して、より厳格な規定を設け
ている自治体もある。たとえば、東京都は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
において土壌汚染に関する規定を設け、3000 ?以上の土地の改変を行う場合又は有害物質
取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合、調査を実施し報告することを
義務付けている。
しかし、前述の土壌汚染対策法や自治体の条例に基づく調査は、土壌汚染調査実施例の約
2 割を占めるにすぎない。土壌汚染対策法が施行されて以来、法や条例に基づかない民間の
自主的な土壌汚染調査が増えている。企業は、環境マネジメントや資産マネジメントにおけ
る重要な活動として、汚染の可能性のある土地の実態把握、自然由来やもらい汚染の可能性
の把握などを目的とした土壌汚染調査を実施している。また、不動産取引を契機とした土壌
汚染調査も、活発に実施されるようになった。
(2)土壌汚染調査の対象物質
「土壌汚染」状況は千差万別であり、サイト毎に最適な調査・対策方法を検討し、実施し
ていくことが重要である。また、「土壌汚染対策法」が 対象とする土壌汚染は、特定有害物
質26 項目(鉛、砒素など重金属等15 項目 、およびトリクロロエチレンなど揮発性有機化
合物11 項目)であるが、その他の規制物質や規制はされていなくとも土地利用の障害となり
うる可能性のある物質もあり、注意が必要である。ガソリン、重油、潤滑油、灯油等の油分、
ダイオキシン類、その他の化学物質(条例等において特に規制されている物質、臭気の強い
物質及び色のある物質等)、要監視項目(22 項目)等の規制対象候補の物質などが調査対象
となりうる。土地取引に際しての調査では、購入用途が住宅系である場合、履歴にかかわら
【土壌汚染対策法に基づく調査の概要】
(目的) 国民の健康保護
(対象物質) 特定有害物質(重金属、揮発性有機化合物等26 項目)
(対象:調査の契機)
? 使用がず「特定有害物質(農薬類を除く)」「油分」「ダイオキシン類」を調査対象とするケースが多
い。(社)日本不動産鑑定協会策定の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」では、
「特定有害物質を中心に各自冶体の条例等およびダイオキシン類対策特別措置法において対
象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば価格形成に大きな影響があるもの
とする。」とし、法令等による調査義務がないことのみで土壌汚染が無いとはできないとして
いる。
(3)土壌汚染調査の手順と標準化
土壌汚染調査は、土壌が汚染されているかどうか、さらに汚染されている場合にどの程度
の汚染であるか、を把握するために行われるものである。しかし、土地取引や対策計画立案
など、調査実施主体が調査結果を使用する目的に応じて、調査に必要とする精度や正確さは
異なる。したがって、日本において法や条例に基づかない民間の自主的な土壌汚染調査は、
法令に基づく調査に準拠して進められることが多いが、必ずしも統一された基準のもとに実
施されているわけではない。一般的な土壌汚染調査のフローを図3.1.1 に示す。
? フェーズ?調査
地歴等調査(フェーズ?)は、土地利用履歴調査(登記簿、閉鎖謄本、古地図、空中写真
等)、地形・地質に関する調査(ボーリングデータ、地形図等)、現地視察調査(周辺状況や
対象地の現況を把握)などに基づき、土壌汚染の有無について定性的に判断する調査である。
アメリカでは2005 年にEPA(連邦政府環境保護庁)がフェーズ?調査の標準となるAAI
(All Appropriate Inquiry:あらゆる適正な調査)を改め、これに基づきASTM(米国材料
検査協会)がフェーズ?調査の仕様を改定した。AAI とは、土地の所有者、新規購入予定者
がスーパーファンド法に基づき浄化義務を免れるために実施する必要がある調査である。
改定の目的は、浄化義務を免除された後で土壌汚染が顕在化するリスクを軽減するために、資
料等調査における質の向上及び調査内容(水準)における差異の低減を図ることであった。
AAI における従来標準からの重要な変更点は、環境専門家の資格明記、聞き取り調査の対象
者拡大、資料調査の対象拡大、土壌調査報告書の有効期限設定である。
一方、日本では、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)が土地取引時に作成され
るエンジニアリングレポート(ER)のガイドラインを定め、その中で土壌汚染のフェーズ?
調査手法を提案するなどの取り組みがあるが、統一された土壌汚染調査仕様が規定されるに
至っていない。法令等に準じたフェーズ?調査を実施することによって、土壌汚染リスクが
回避されるという一般認識が存在している。簡易なフェーズ?調査で土壌汚染の可能性が完
全に否定される場合を除き、フェーズ?調査による評価が求められる傾向が強い。したがっ
て、現状では、フェーズ?調査を実施することを想定し、日本におけるフェーズ?調査の水
準はAAI が要求する水準より低めに設定されている。
土壌汚染対策法の規定に基づく調査は、環境大臣(地方環境事務所長)が指定する指定調
査機関が実施することとされており、平成20 年1 月23 日現在、1,661 機関が指定されてい
る。東京都等の自治体の条例に基づく土壌汚染状況調査についても、原則として土壌汚染対
策法に基づく指定調査機関に実施させることが定められている。ただし、指定調査機関の認
定要件は届出による簡易な書面審査が中心であることに加え、土壌汚染対策法や条例が適用
されない調査では、土壌汚染の専門家以外でも調査の実施が可能なことから、調査結果の信
頼性を問題視する意見もある。
フェーズ?調査段階では、比較的簡単に入手できる情報のみに基づく調査であることから、
調査結果に不確実性が存在する。フェーズ?調査は、汚染の可能性を調査するものであるが、
汚染の可能性がないと判断した場合でも、不十分な調査により、対象地に存在する土壌汚染
を見逃している場合があり、留意する必要がある。ある不動産関連企業が独自に実施した調
査によれば、フェーズ?調査で汚染可能性が低いと判断した土地のうち、かなりの割合で土
壌汚染が検出された。特に、造成地において、外部から搬入された盛土部から検出されたと
想定される例が多くあり、フェーズ?調査の結果を評価する上での課題となっている。
? フェーズ?及びフェーズ?調査
フェーズ?調査で汚染の可能性があると判断された場合は、概況調査(フェーズ?)を実
施する。概況調査は、土壌汚染対策法に基づく汚染状況調査に相当するものであり、表層付
近のデータを採取し、汚染の存在を確認するとともに、平面的に汚染の存在するエリアを絞
り込むものである。この調査は、環境省監修・(社)土壌環境センター編「土壌汚染対策法に
基づく調査及び措置の技術的手法の解説」に示される方法に準じて、土壌ガス調査、5地点
混合法表層土壌調査が行われる。
詳細調査(フェーズ?)は、概況調査で絞り込んだエリアについて、ボーリングにより汚
染範囲を確定する。汚染対策の実施を前提として行われる調査であり、汚染の範囲・深さ・
程度を三次元的に把握して、対策の必要性、範囲を設定し、対策費用と期間を検討するため
に行うものである。汚染範囲が広い場合は、調査にかなりの費用と期間を要する。
土地利用の変更や土地取引に際して更地の状態で調査する場合には問題とはならないが、
開発検討段階の調査や権利置換型の事業では、調査段階で従前建物が存在(権利者が生活若
しくは営業)している場合が多い。このようなケースでは、可能な範囲でしか調査できない
ため、汚染リスクの見極めが困難となり、事業成立性の判断に影響を及ぼすことが懸念され
ている。
(4)土壌汚染調査の費用
調査のフェーズを重ねるごとに土壌汚染状況の把握の確実性は高まるが、それに伴って調
査費用も増大する。フェーズ?調査の費用は、40〜50 万円/物件であるが、フェーズ?調査
では対象範囲が大きいとその費用も多額になり、資金的余裕のない土地所有者にとっては大
きな負担となる。その費用は対象地を1,000 ?と仮定した場合、概況調査で1〜2 百万円/物
件、 詳細調査は数百万/物件となる。こうした高額の調査費用は、土地取引や開発計画を断
念したり、従来の土地利用をしたりする一因となる。また、不動産の競売入札において、土
壌汚染に関する調査を考慮に入れた上で入札する良い入札参加者ではなく、土壌汚染の可能
性を無視する悪い入札参加者が選ばれる逆選択の問題が生じているという懸念がある。
3.1.2 情報収集と活用
フェーズ?調査を実施する際には現地踏査やインタビュー、依頼者から提供される書類記
録等のレビューの他に、公的機関が保有する環境情報を精査する。次章で触れるように、ア
メリカでは、汚染サイトや浄化中のサイト、埋立地や処分場、貯蔵タンク等の情報が法や制
度によって登録されており、フェーズ?調査の実施時にはこれらの情報を評価の材料として
いる。
一方、日本でも同様の手法でフェーズ?調査が実施されているが、アメリカのような法や
制度がない。環境省と一部の自治体は、それぞれ土壌汚染対策法と自治体条例が適用された
土壌汚染地の調査・改善措置に関する情報を収集し、情報提供しているケースもあるが、こ
れらの情報を制度的に集約する機関がないため、公的機関から多くの環境情報を得ることは
できない。また、法や条例の適用を受けず、自主的に実施された調査や改善措置が、土壌汚
染調査実施数の大半を占めているものの、それらを共有できる仕組みが構築されていないこ
とも課題である。土壌汚染に関して参照できる情報、資料の蓄積が少ないため、調査の案件
毎に始めから調査を実施する必要が生じている。
調査を実施して汚染が判明すると、対策の実施や公表を迫られ、企業の業績への影響やイ
メージの低下につながる事態をおそれて、調査を実施しないケースも存在する。土壌汚染に
対する社会的な見方は変わりつつあるとはいえ、自主的な調査の結果の提供については、企
業サイドも消極的となることが想定される中で、効果的な情報収集を図ることが重要である。
フェーズ?調査を実施する際には、住宅地図、不動産登記簿、土壌汚染に係る地域の基礎
的情報(土地利用履歴、過去の地形図、漏出事故・汚染記録、潜在的汚染源の位置、地下水
水質等の環境情報など)、その他、地方自治体や各省庁が所管する基礎的情報が活用される。
これらの基礎的情報が、未整備もしくは個別に収集、管理されているために、データ収集の
非効率が生じている。これらの基礎的情報・データがアクセスしやすいように整備されるこ
とが望ましい。
土壌汚染に関する情報インフラが整備されることによる効果は、前述のとおりフェーズ?
調査の品質確保や効率的な調査に資するものであり、生産性の向上にも結びつくものである。
そして、土地取引等に当たっての保険活用や担保評価に資する有用な情報となる。また、情
報インフラが整備されることにより、土壌汚染地の譲渡等があった場合、次の管理者等が土
地の情報を引き継ぐことができる。これにより土壌汚染による環境リスクの制度的管理につ
いても、次の管理者等へ承継できる。
3.2 土壌汚染の基準
3.2.1 用途別基準
住宅や産業用地といった土地の用途に関わらず、土壌汚染が環境基準の数倍でも1,000 倍
でも、環境基準を超えていれば、土壌汚染地として同様に扱われることが、土壌汚染地対策
を非効率なものとしているという指摘が多い。健康被害の防止を前提として、土地利用と関
連付けた基準作りを望む意見も聞かれるところである。しかし、一方で、土地利用と関連付
けた基準の導入においては、土地の用途変更に際して対応する仕組みづくりが必要となる。
土壌・地下水汚染対策の目標は相当にレベルが高いため、目標水準まで浄化する場合の対
策費用は高額となる。将来、土地利用の用途に合わせた基準などが設定されれば、対策費用
の低減が可能になると考えられる。
3.2.2 自然由来の汚染
明確な自然的原因は、種々の資料もあり、データがあれば正確な判断と基準設定も可能で
あると考えられる。例えば、鉱床地帯・その周辺などの鉱染地帯や変質岩帯の地域から発生
する汚染土壌(道路工事など)については、広域地質図、一部の地域の鉱染マップ、採石資
源分布図を使って類推はできる。一方、都市部の土壌を考えると、本来の自然的原因の汚染
土壌と、過去の人間活動(不特定多数の人間活動を含む。)に起因する汚染者特定不可能な汚
染土壌などが混在しており、濃度的な問題や分布の問題の挙動が同じでも、汚染者負担の公
平性から考えると、負担者の面からも安易な分類ができない場合もある。
上記のとおり、自然由来の土壌汚染に対する基準については、さらなる科学的データの蓄
積、公開が重要である。こうした視点で、地質情報、自然起源汚染情報、人為汚染情報など
の全国規模の各種地圏情報をGIS 化して情報提供するシステムとしての「地圏環境インフォ
マティクス」構築の取り組みが東北大学を中心に行われている。この中では、日本の重金属
バックグラウンドの把握、地域によるバックグラウンドの差異の把握方法の開発、地質と環
境因子との関連性の把握と、これらを共通のプラットフォームで把握する試みが進められて
いる。
現行の法規制においては、自然的原因による有害物質含有の土壌は、「人の活動に伴って
生ずる相当範囲にわたる土壌汚染」(環境基本法第2条第3号)ではないことから、同号の「公
害」には該当せず、環境基準の適用においては「汚染が専ら自然的原因によることが明らか
であると認められる場所においては適用しない」こととされているため、中央環境審議会の
2002年1月答申「今後の土壌環境保全対策の在り方について」の中で、「自然的原因により
有害物質が含まれる土壌については、人の活動に伴って生じる土壌汚染ではなく、したがっ
て環境基本法で定める公害とは言えないことから、この制度の対象とはせず、別途検討され
るべき課題であると考える。」こととされている。
専ら自然的原因により高濃度の特定有害物質を含む土壌又は水底土砂が、同様の土壌又は水底土砂の存する周辺の地域において盛土や海面埋立等により土地の造成に用いられた場合には、造成された土地は自然的原因により基準に適合しなくなったものとされ、土壌汚染対策法や条例の適用対象とはならないものとされている。
一方、土地の造成に伴い当該地域とは異なる土地から持ち込まれた土壌については、それ
が専ら自然的原因により指定基準を超過するものであっても、平成15年2月15日環水土第24
号通知「指定区域以外の土地から搬出される汚染土壌の取扱指針について」の中で、土壌汚
染対策法の指定区域以外から搬出される汚染土壌についても、同法の考え方に即した取扱い
が望ましいこととされており、土壌を持ち込んだ者が汚染原因者と見なされる。持ち込んだ
者が不明等の場合には、土壌汚染対策法第7条第1項に基づき土地の所有者が必要に応じて措
置を行うこととされている。
土壌汚染が自然由来であるかについては、環境省が土壌汚染対策法施行時に地方公共団体
宛発出した「土壌汚染対策法の施行について(平成15年2月環水土第20号)」における「土
壌中の特定有害物質が自然的要因によるものかどうかの判定法」に基づいて判断が行われる。
具体的には土壌溶出量基準を超過する場合の判断基準として、
?対象物質の種類等、
?対象物質の含有量の範囲等、
?当該特定有害物質の分布特性、
の3項目から検討することとされ、また含有量基準を超過する場合の判断基準として、
?バックグラウンド濃度又は化合物形態等、
?使用履歴場所等との関連性、
の2項目から検討することとされている。
しかし、一般的に、土地取得に際しては、自然由来による汚染も含め環境基準超過土壌は
完全除去を行うことが原則とされている。自然由来による土壌汚染が深い部分まで及んでお
り、完全除去が事実上不可能もしくは売主に完全除去を求めることが不適当と判断される場
合は、建物の根切り深さに相当する一定の深さまでの除去を求め、それより深い部分の汚染
は免責とされるケースもある。
3.3 土壌汚染の対策
3.3.1 責任負担者
土壌汚染対策法では、汚染が判明した土壌は都道府県が「指定区域」として指定・公示し、
指定区域内の土壌が健康被害を招く恐れがある場合には、汚染原因者が特定できるケースを
除き、原則として土地所有者に対策を義務づけている。土壌汚染対策法では、土地所有者等
が汚染除去等の措置をした場合に、汚染原因者に対して措置費用の請求ができることとされ
ているが、汚染原因者が不明又は破産して費用負担できない場合には、土地所有者がすべて
対応しなければならない。
現在の諸制度は、使用者や用途が変更される通常の土地取引に対応したものである。昨今
不動産証券化にてよく行われているセール&リースバックにおいては、売買取引後のテナン
トによる汚染をモニタリングすることが重要である。モニタリングの手続きや内容は賃貸借
契約に反映されることとなるが、売主と売買取引後のテナントが異なるケースについて、売
主とテナントの間のリスク分担に係る対応が難しいという指摘がある。
3.3.2 法令上の要求措置と実態の乖離
汚染の除去等の措置には立ち入り禁止、覆土、舗装(直接摂取の場合)、汚染土壌の封じ込
め、掘削除去があるが、掘削除去が選択されることが多い。これは、土壌汚染対策法上「汚
染の除去等の措置」(同法第7 条第1 項)以外では台帳から指定地域の抹消をされないこと、
将来売却する場合に、掘削除去以外の措置では価格の減価程度が予測できないこと、土壌汚
染が完全に除去されないと、封じ込め等の措置が必要になり、その間の管理コストや土地利
用への影響があるなどの課題を長期間抱え込むことになるおそれがあることなどが、掘削除
去を求められる理由である。実に、国内で実施されている措置のうち80%強が「掘削除去」
か「現位置浄化」を選択している。
掘削除去は費用が高額となるため、土地の売却益の中で吸収できる場合は実施可能である
が、そうでない場合は厳しく、土地所有者にとって売却を断念せざるを得ない事態が生じる
可能性がある。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が土地価格を上回るケースもある。とり
わけ資金力のない中小事業者や土地価格の安い地方都市において、このような事態が生じる
可能性があり、いわゆるブラウンフィールドの発生につながると考えられる。
一方、土壌汚染対策法や自治体の条例は、掘削除去措置まで求めているわけではない。例
えば、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の第114条では、対象地内
の土壌汚染により「大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に係る被害が生じ、又は
生じるおそれがある」と認められる場合は、対象地内のすべての汚染土壌について指針の定
めるところにより汚染処理を行うこととされており、また、同条例に基づく東京都土壌汚染
対策指針において、周辺環境に土壌汚染の影響が顕在化していないこと、及び掘削する場所
以外に存在する汚染土壌が外部に拡散しないことを前提として、汚染拡散防止措置を行うも
のとされており、必ずしも掘削除去が求められていない。
なお、土地取引によらない場合は土地所有者が自己利用又は土地を賃貸することになるた
め対策コストの高い掘削除去よりは封じ込めなどの対策がしやすいものと考えられる。土壌
汚染の対策コストが多額で土地を売却できない場合には、汚染の封じ込め措置をして倉庫や
駐車場等として自己利用、又は土地を賃貸して商業施設や駐車場等への利用が見られる。ま
た、産業用途の不動産取引では、自主基準を作成し、それに沿った形で土壌汚染地取得の意
思決定が行われ、完全浄化を実施せず適切に管理している例も見られる。
3.4 土壌汚染の管理
土壌汚染が発見された場合、実態として完全除去されることが多いが、土壌汚染対策法や
自治体の条例では、完全な除去まで求めているわけではない。当該敷地および敷地以外の周
辺環境において、人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれが顕在化していなければ、
完全除去ではなく、土壌汚染が周辺環境に影響を及ぼさないように汚染拡散防止措置を実施
することで対策とすることができる。そして、法や条例の適用対象とならない場合にも、こ
の基本的な考え方は適用できる。土壌汚染を残置することによって、土地所有者は土壌汚染
リスクを将来にわたって適切に管理することが求められるが、経済的な対策を選択できる余
地が広がることとなる。
土地取引においては、土地購入者にとって、封じ込め措置などの汚染が残存する土地は割
安な価格で購入することが可能であるが、一方で封じ込めた汚染土壌に係る管理などに追加
費用を要することに加え、土地の使い勝手が大きく損なわれるおそれがある。したがって、
汚染土壌を一部エリアに封じ込める措置を採用する場合は、土地利用をあらかじめ考慮した
措置とすることによって、土地の利用価値低減をできるだけ限定的なものとすることが重要
であると考えられる。たとえば、土壌汚染地の地下利用制限などの部分的制限によって、掘
削除去以外の土壌汚染対策が容易になるだろう。また、将来、土壌汚染の封じ込め措置を行
った土地を売却する場合には、利用用途が限定される可能性があることから、売却先を探す
際にマイナス要因となりうることにも留意しなければならない。
このように、健康への潜在的な被害に考慮しつつ、土地の適切な利用を確保していくため
に、官民の間で取り決めを設ける手法は、制度的管理(Institutional Control)と呼ばれアメ
リカなどで活用されている。制度的管理は、土壌汚染された土地を、土地利用制限や継続的
モニタリングなどによって、適切に管理する手法である。制度的管理は、制度の特徴から、
土地利用用途別の基準と関連付けられることも多い。
日本での適用例は少ないが、豊中市のマンション敷地において、「深い基礎が必要な高い建
物は建てず、土壌汚染の事情を知らない第三者に転売しない」という協定を市と不動産業者
が結ぶことを条件に分譲するという方式が採用されている。また、倉庫等の産業用地を対象
とした不動産証券化ファンドにおいても、部分的な利用制限や将来の建て替え時の制限を設
け、完全浄化を行っていない例が増えている。
なお、本節で取り上げた土壌汚染の管理手法は、マンション用地など個人向け不動産に適
用する上では、十分な検討が必要となる。欧米では、管理された土壌汚染地は住宅等購入者
にとって、住宅等が比較的安く取得できるというメリットが認知されている。
しかし、掘削除去以外の対策により汚染が残存している場合は、汚染土壌の継続的なリスク管理が必要と
なり、その負担を個人に求めることができるのかという不安がある。当然のことながら、所
有権の移転があれば、その役割は新しい所有者に適切に引き継がれなければならない。また、
個人レベルで、土壌汚染の存在することによる土地資産の減価リスクの適切な判断が求められる。
3.5 土壌汚染がある土地取引のリスクと財政的支援
3.5.1 土壌汚染に係るリスクとリスク分担
(1)リスクの概要
土壌汚染によるリスクについては、人の健康リスクが重要であることは言うまでもない。
しかしながら、土壌汚染地の取引に関連して、その資産価値にかかるリスクも、予測が困難
であり、リスクが顕在化した場合の影響は大きい。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が
土地価格を上回るケースもある。汚染を完全に除去しなければ、土地に残る土壌汚染の管理
が必要となり、将来、想定外のコストが発生したり、将来売却する場合に想定以上の減価が
生じる懸念もある。さらに将来の法改正で、規制対象物質が増えたり、基準が強化され、予
測できない大きな負担が生じる可能性がある。
土壌汚染された土地に係るリスク
● 措置状態の管理/監視義務対応管理/監視結果の報告義務対応
● 第三者賠償請求(近隣住民の健康被害・財産権の侵害)
● 土地利用中の再措置命令対応(濃度上昇等による)やモニタリング井戸の追加等行政指導
● 再措置命令対応による休業損害補償
● 土地利用中の法規制の変更に伴う調査・措置の再実施に関わる費用負担
● 措置済み土地で計画する形質変更が実施できない、 あるいは計画変更を求められるリスク(計画遅延含む)
● 措置計画が行政および近隣住民からの同意が得られないリスク
● 風評リスク
(2)リスク分担
日本では、土壌汚染対策法で土地所有者等に汚染除去が求められており、同法では、土地
所有者等が対策を実施した場合に、汚染原因者に対して対策費用の請求ができることとされ
ている。しかし、汚染原因者が特定できない場合や、特定できても破産して費用負担できな
い場合には、土地所有者が負担しなければならないことになる。このように、土壌汚染があ
る土地の取引においては、土地所有者(売主)と買主が負担するリスクが大きく、円滑な取
引を阻害する要因となっている。
土地所有者(売主)と買主の間のリスク分担については、民法で瑕疵担保責任が規定され
ている。しかし、瑕疵担保責任は、二者間の契約で変更が可能であるため、土地所有者(売
主)と買主のリスク分担は、二者の関係によって変わることになる。したがって、土地所有
者(売主)が優位な場合には、無過失の買主がリスクを負担しなければならないこともある。
(3)リスク軽減の考え方
土壌汚染がある土地の取引において、リスクが顕在化した場合のコスト(つまり浄化費用)
は、莫大なものとなる可能性がある。アメリカで実際に導入されている事例からも、浄化融
資ファンドや公的な保険など、様々なタイプの支援や仕組みが、土地取引関係者のリスク軽
減とリスクヘッジに寄与するものと考えられる。零細汚染責任者のように責任者に責任を負
わせることができない場合について、修復の資金供給のための適切なメカニズムを構築する
ことを望む意見も聞かれるところである。たとえば、日本にも4万箇所以上のドライクリーニ
ング施設があり、経営主体は個人が約70%弱になる。経営規模は年間売り上げベースで3000
万円未満が8割と零細層が中心であり、対策は実質的に困難であると考えられる。こうした零
細企業の所有地を再開発する場合に、開発者にインセンティブを与えることは効果的である。
(4)リスク評価
土壌汚染に係るデータベースを用いて、統計的に土壌汚染による損失を評価する手法は、
一部の金融機関で実施されている。しかし、この手法は、金融機関の数多くの担保物件を対
象として、土壌汚染による減価の総額を把握する手法であり、個別物件のリスク評価に用い
るには精度的に不十分であった。これに対し、個別物件の土壌汚染リスクを評価するツール
開発の取り組みが行われている。
土壌汚染の可能性がある土地の取引や不動産開発を検討する際、土壌汚染の実態把握のた
めに、初期段階にて多大の費用がかかる調査等を行うと、事業リスクは大きくなる。また、
将来発生する詳細調査や対策の費用の不確実性が高いために、初期の調査に踏み出せず事業
自体が断念されるケースも多い。土地開発の採算性や実現可能性を検討するような構想段階
においては、多額の調査費用を費やし、詳細な土壌汚染調査を実施することは合理的ではな
い。むしろ、地歴調査、表土調査等の簡易調査に基づいて土壌汚染対策費用のリスク評価を
実施し、マーケットリスク等を含めて不動産開発の妥当性を検討することが必要である。
しかし、地歴調査、表土調査等の簡易調査のみが実施された段階で、土壌汚染の実態を確定的
に把握することは極めて困難であるため、特に初期構想段階では、土壌汚染に係るリスクを
評価し意思決定することが重要となる。
この点に関して、評価ツールとして期待値による評価と確率分布による評価が考えられる
が、期待値で評価をしても事業キャッシュフローに関する問題点が明確にならないケースも
ある。例えば、1000 分の1 の確率で100 億円の支出が生じる場合、期待値の上での影響は
1000 万円でしかない。しかし、ダウンサイドのリスクが顕在化し多額の資金需要が一度に生
じた場合、事業が頓挫する可能性もある。そこで、こうしたリスクを評価するためには期待
値ではなく、確率分布の形を評価することが有効である。また、人は確実に100 円の利益が
得られる場合と、期待値は100 円でもリスクのある場合とでは、その事象に見出す価値が異
なる。したがって、確率分布で理解することは、リスクコミュニケーションにおいても重要
となる。さらに、多様な資金調達や保険の活用、そして先進的な不動産プロジェクトで用い
られるようになったリアルオプションには分散に関する情報が不可欠であり、当該ツールに
よって得られる確率分布は極めて有効である。
3.5.2 低利融資等
土壌汚染対策に係る低利融資制度については、政府系金融機関(日本政策投資銀行)に
よる貸付制度がある。但し、この融資制度も包括的な制度設計に至っておらず、例えば調
査費用が対象とされなかったり、自主的な調査及び改善措置費用が対象とされなかったり
等、その適用範囲は限定的なものであるため、当該制度の利用実績は低調なものに留まっ
ている。
また、その他の公的支援制度として土壌汚染対策基金が挙げられる。この基金は、土壌汚
染対策法に基づき、汚染原因行為に関与していない資力に乏しい土地所有者等に対して汚染
の除去等の費用を助成するものであり、都道府県又は政令市を通じて実施される。
当該制度についても、資力の乏しい小規模事業者等にとっては有効な支援策であるものの、厳格な適
用要件等によりこれまでほとんど利用されてこなかった。
これら低利融資及び基金については、適用要件の緩和等、より弾力的な運用を施行するこ
とで、さらなる利用促進を図ることが望まれる。
3.5.3 保険
(1)土壌汚染地に関する保険の役割
保険の役割は、関係者または特定の土地に対し、通常の事業又は浄化工事請負作業中にお
いて、汚染が顕在化した場合の浄化費用を補償するものである。土壌汚染についてリスクを
負担することができない場合に、保険を付保することによって、リスクを移転することがで
き、費用を確定し収益性の判断がつけやすくなる。また、制度的管理(Institutional control)
を採用する場合には、潜在的な環境負債者の将来にわたる長期修繕費用の支払い能力が求め
られるが、もし適切な支払い能力がないと判断された場合、当事者は債権や保険等を利用し
て財政的な裏づけを確実に得ることもできる。アメリカでは、保険を活用することにより、
土壌汚染地の浄化を伴う再開発に民間資金が集まり、再開発が促進されるという効果を上げ
ている。
(2)土壌汚染に関する保険の種別
日本国内でも、海外と同様、汚染が顕在化した場合の浄化費用を補償する土壌浄化保険
をはじめとして、第三者土壌浄化賠償責任保険などの土壌汚染関連保険が開発されている。
これらの保険商品を分類すると、事業者に対して付保する保険と、土地に付保する保険がある。
事業者に対する保険は、開発、建築等の事業の過程で土壌汚染を発生させたことに起因
する賠償費用を補償するものや、土壌汚染対策などの請負作業において汚染を発生させた
場合に、賠償費用を補償するものがある。一方、土地に対する保険としては、結果として
土地所有者等が負担した対策費用に加え、地下水汚染等により発生する周辺住民の健康被
害などの対人、対物の損害賠償費用を補償するものがほとんどである。また、土壌汚染対
策費用の超過分を補償するコストキャップ保険(超過浄化費用保険)は、対策費の上限を
予測できるため有効である(3.5.4を参照)。
(3)土壌汚染保険の普及に向けた課題
日本国内では、土壌汚染に関連した保険の普及が進んでいない。普及が進まない最大の理
由は、保険料の高さと保険引受条件の厳しさにあるようである。仮に数を集めたところで発
生要件の規則性が見いだせない(=大数の法則が成立しない)からこそ保険料が高くなり、
加えて、逆選択(土壌汚染のリスクを抱えているのが明確な人ほど保険に入ろうとする)が
生じ、最悪の場合モラルハザードにつながるため、保険の利用が進まないという側面がある。
そして、保険の利用が進まないために、大数の法則の適用が困難となり、結果として保険料
が高くなり、引受条件が厳しくなるという悪循環が生じている。さらに、保険料に加えて、
保険引受のための高額の調査費用を、被保険者が負担することが一般的となっており、この
ことも保険が利用されていない一因となっている。
リスクを定量化するためのデータの蓄積は、保険商品の開発にとって重要である。しか
しながら、日本では、土壌汚染がある土地の調査事例や対策事例に関して、入手可能な情
報が不十分であることから、土壌汚染に関する事例の蓄積を進めていくことが必要である。
また、保険の利点や内容が理解されていないことも課題である。
(4)土壌汚染に関する保険の拡充
我が国では、土壌汚染保険やコストキャップ保険をはじめとする損害保険はあるものの、
情報の非対象性を一つの大きな理由として、必ずしも保険会社が積極的にリスクの引き受け
に応じていないのが実態であるが、海外では「ファイナイト(Finite)」といわれる従来型
の保険に代わるリスク移転手段が導入されている。
ファイナイトは、「リスクの保有」と「リスクの移転」を組み合わせ、企業と保険会社の間
でリスクをシェアする機能を有するリスク・ファイナンス手法であるといえる。ファイナイ
トにはニーズに応じた様々な形態があるが、土壌汚染問題に対する適用に関しては次の例を
想定することができる。
たとえば、ある工場の経営者が、当該工場の敷地に土壌汚染の存在が発覚したため、将来、
当該工場を閉鎖し、土地を売却する場合に備えて、その浄化費用の対策を考えた。売却の際
には、汚染地の浄化が必要になるが、その対策費が1 億円から7 億円の範囲内となることが
想定され、このときファイナイト契約を5 年間で構成することした。なお、5 年以内に当該
土地の売却・浄化してしまった場合でも契約は5 年間継続させるために、対象となる土地は
売却予定以外の複数の土地を含んだ契約となり、以下のようになる。
? 初の保険金支払い事由となる浄化工事の場合の支払限度額は7 億円、免責は1 億円、2
番目以降はそれぞれ3 億円、10 億円とする。また、毎年の保険料は1 億円で変更なしとする。
? 毎年の保険料が毎年積み立てられた場合5 年間で積立て額は5 億円となる。
? 仮に3 年目で土地の売却、浄化工事が行われ、その費用が5 億円であった場合、保険
会社から1 億円の免責額を除いた4 億円が保険金として支払われる。
? 契約は5 年目まで継続し、2 件目以降の保険金支払い事由の発生がない場合、保険料
の積立て額は5 億円、保険会社からの支払額は4 億円となる。この差額のある程度の
割合は予め約定された割合に基づき、契約者に優良戻しということで 返還されること
が多い。
? 仮に3 年目行われた浄化工事が8 億円かかった場合、保険料の積立て額は5 億円、一
方、保険金の受取額は7 億円となる。
ファイナイトのメリットは、浄化費用の発生タイミングと規模に係るリスクを抑えること
ができる点である。具体的には、積み立ての場合、積立て額は段階的にしか積み上がらない
のに対し、ファイナイトであれば1 年目から最大7 億円の浄化費用の手当てができる。また、
浄化費用の額についても、上記の例で8 億円までに収まった場合、保険料としての拠出額の
合計である5 億円に免責額の1 億円を加えた範囲内に抑えることができる。
保険会社からすると、保険料の積立て額が保険支払額よりも上回った場合は、その一部を
契約者に払い戻す構成としているため、契約者がリスクを軽減するモチベーションを持ち続
けることを期待することができるため、ある程度モラルハザードを抑制することが可能とな
る。
3.5.4 保証
保証は、保険と同様に、土壌汚染リスクをヘッジする目的で活用される。保証には、浄化
工事のコストの増加分を保証する「コストキャップ保証」型、フェーズ?調査後、汚染の可
能性が極めて低いと判断した土地に対し、調査会社が自社の調査に基づく土壌汚染がない旨
の評価に対して保証する「調査後のシロ保証型」、主として土地取引の契約書の記載事項を表
明保証する「表明保証」型などがある。
浄化工事の保証は、工事の請負契約に加え、対象地、対象期間、対象物質、工事請負金
額、工事の着工および完了予定時期、保証内容、免責事項などを記載した保証書を差し入
れることによってなされるのが一般的である。浄化工事の保証内容の例について、次に一
例を示す。
浄化工事の保証内容の例
・計画土量増加および処分時の比重増加に伴うコストの負担。
・高濃度汚染の存在などにより処理方法の変更、追加が生じた場合の費用の負担。
・対策計画の範囲内に存在する廃棄物や地中構造物の撤去に関わる費用の負担。
・地下水モニタリングに関わる費用一式の負担。
3.5.5 買取り
民間ファンド等が土壌汚染リスクのある不動産を買い取り、浄化を実施後に売却することに
よって、リスクヘッジするスキームも土壌汚染土地の取引活性化に有効であると考えられる。
土壌汚染がある土地の所有者(売主)にとっては、事業地を売却したくとも、調査費用や対策
費用の捻出が困難であったり、対策工事の工期の関係で困難であったりするケースや、風評
リスクが懸念され、売却をためらうケース、さらには、売却後の瑕疵担保責任を負いたくな
いようなケースも考えられるが、買取りスキームは、こうした土地所有者のニーズに応える
ものであり、土壌汚染調査と対策の実施負担が不要で、早期に売却収入が確定し、決済が可能
となるというメリットがある。
また、魅力的な物件だが、汚染が解消できなければ買収の意思決定ができないと躊躇う
買主側にとっても、浄化された土地として検討できるというメリット
がある。
さらには、買主と売主の双方にとって、土壌汚染に絡み流動化を阻害する問題が軽
減されることになる。ただし、民間ファンド等が中間的に買い取る行為が経済的に成立する
ためには、リスクを適切に評価することが可能であり、減価して買い取ることが条件となる。
3.5.6 信託
(1)信託の現状
信託は、委託者が、その保有する財産を受託者に引渡し、一定の目的(信託目的)に従い、
特定の受益者または公益のために、その財産(信託財産)を受託者に管理、処分してもらう
制度である。国内の信託財産残高は2007年3月末で744兆円と5年で1.9倍に増加し、この内、
不動産信託も5年間で残高3.8倍(6,257件)、件数9.0倍(22兆6千億円)と増加基調を示して
いる。(データ出典:(社)信託協会ホームページ)
不動産の信託においては、土壌汚染問題に受託者が直面することがある。例えば、
? 土地取引に際し土壌調査を行うことが慣行化する前に設定した信託受益権を信託期間中に譲渡す
る際に土壌調査を実施して、信託設定時に認識していなかった土壌汚染が発覚する場合、
?信託財産の隣接地等で実施された土壌調査によって、隣接地で汚染が見つかり、信託財産の
汚染が懸念されるような場合、
? 土壌調査の対象地に建物などがあったために汚染物質を見落とす場合、
?調査方法の選択ミスや精度の問題で、事前調査では分からなかった問題が発覚する場合等が想定される。
(2)旧信託法下での土壌汚染問題への対応方法
こうした場合に対応するため、旧信託法下においても「限定責任特約」を当事者間で締結
するというという方法があった。これは、受託者が信託事務に関する取引から生じた債務に
ついて、責任財産を信託財産に限定することを個別に特約として結ぶというものであったが、
土壌汚染に関しては、受託者に過失がなかった(無過失)としても受託者に対し以下の請求
が可能だったため、信託設定や信託財産の管理を適切に遂行したにもかかわらず、受託者が
最終的に個人負担する可能性があった。
・所有者の工作物(「汚染物質を放出した建物および構築物」)責任(民法717条)
・被害を受けた土地所有者からの妨害排除請求権に基づく汚染物質の排除請求
・受託者が土地の名義人であることによる土壌汚染対策法に基づく土壌改善等の措置命令
(土壌汚染対策法第7条第1項)
(3)改正信託法下での対応方法
そこで、仮に信託不動産に土壌汚染が存在することが発覚したとしても、その責任を限定
する手法として、平成19年に施行された改正信託法で制定された限定責任信託制度の利用が
考えられる。限定責任信託とは、「受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務につい
て信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託」(同法第2条第12項)のこ
とである。限定責任信託では、受託者の対外的な責任限定の対象者を拡大し、従来の責任限
定特約とは異なり、取引関係にない者との間でも限定責任が適用される。
しかしながら、同法第217条第1項において、「信託財産責任債務」から同法第21条第1項
第8号に掲げる権利に係る債務が除かれており、「受託者が信託事務を処理するについてした
不法行為によって生じた権利」に該当する行為の範囲が問題となるが、現時点で、土壌汚染
対策法等に基づく土壌汚染に関する責任(すなわち信託法に基づかない責任)が、信託財産
を充てるべき責任なのかどうか、又は、両者の責任が分断されるのかどうかといった点が明
確にされていないことから、現時点で土壌汚染に関する責任を限定する目的で限定責任信託
を活用するのは困難であると思われる。
仮に、信託法における責任と信託法に基づかない責任が分断できるとしても、大きな土壌
汚染に対する限定責任信託の活用については、社会的なコンセンサスを得られるのか疑問が
あり、今回の法改正で土壌汚染地の信託が急増することは想定し難いと考えられる。
3.6 土壌汚染地の資産評価
3.6.1 土地の資産評価の枠組み
現在、土地の資産価値の評価については、公の機関や業界団体が関わり、考え方や算定方
法などが規定されているものだけでも、以下に示すとおり多岐にわたっており、様々な分野
でその分野のニーズ・目的に応じた評価がなされている。それぞれ評価の目的が異なるため、
当然のことながら、土壌汚染に関しても異なる取り扱いが規定されている。民間企業によっ
ては、独自の考え方で評価を行い、内部の意思決定に活用していることもある。
3.6.2 不動産鑑定評価の実務における土壌汚染地評価の基本的考え方
平成15 年1 月1 日より、土壌汚染を土地の個別的要因の一つとして、評価項目に追加し
た改正不動産鑑定評価基準が施行された。土壌汚染調査が経済的・法的・物理的な物件調査
の1 項目として、明確に位置づけられたものであるといえる。
実務上は、原則として土壌汚染対策法第2 条第1 項に規定されている特定有害物質を中心
として、各自治体の条例等及びダイオキシン類対策特別措置法及び各自治体の環境条例等に
おいて対象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば、価格形成に大きな影響
を与える可能性が生ずると理解される。
上記の土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法及び各自治体の環境条例等は、人
の活動に伴う人への健康に係る被害の防止の観点から規定されている一方で、不動産鑑定評
価において考慮すべきは、土壌汚染が価格形成に影響を及ぼす場合であることから、自然に
由来する土壌汚染も考慮にいれる必要があり、法令等による調査等の義務がないことをもっ
て、土壌汚染がないということはできない。
現状では対策が掘削除去中心であることから鑑定評価もそれを前提にする場合が一般的で
あるが、今後掘削除去以外の措置が講じられるようになれば、それらを的確に反映するよう
な鑑定評価を行う必要があり、必要に応じた実務面の見直しと普及が必要である。
既に、 (社)日本不動産鑑定協会作成の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針
(以下「運用指針」という。)?、?」がガイドラインとして示されている。運用指針Iでは、
鑑定士が行うべき独自調査のあり方が記載されており、運用指針?では、土壌汚染地におけ
る対応のステップが示されている。
運用指針では、土壌汚染の疑いのある場合には、不動産鑑定士が独自調査を行った上で、
その結果と、既存の土壌汚染調査結果を明記し、汚染の分布状況、除去等に要する費用等を
他の専門家が行った調査結果等を活用して鑑定評価を行うものとされている。
これまでのところ、土壌汚染地の鑑定依頼件数は少なく、したがって土壌汚染土地の鑑定
評価の経験を積んだ不動産鑑定士は少ない。また、土壌汚染に関する鑑定評価が可能なレベ
ルの調査が実施されていない段階で、鑑定評価を依頼されるケースも多いのが現状である。
<参考>現在の取組み
・ 土壌汚染地に係る鑑定評価については、平成14 年の鑑定評価基準の改正時において、
土壌汚染が価格形成要因の一つに位置づけられたところである。実務面においても、(社)
日本不動産鑑定協会で「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」の策定・改定、
それに基づく研修等が実施されている。また、土壌汚染の鑑定評価の実務に関するワー
キンググループが設置され、継続的にケーススタディー等の検討が行われている。
3.6.3 スティグマの評価
土壌汚染の存在(過去に存在したこと)に起因する心理的な嫌悪感等から生ずる減価要因
をスティグマという。また、広義には、前述の心理的要因に加え、土壌汚染に起因して将来
追加コストが発生するリスクを加えた減価の根拠をいうこともある。土壌汚染地の資産評価
は、概念的には次式で表現されている。
個別の土壌汚染地及び評価時点により、スティグマの程度・内容は異なるので、評価ごと
に、求めるべきスティグマを勘案する必要性が生ずる。
日本におけるスティグマの調査事例としては、住宅用地に関する市民アンケート調査((財)
日本不動産研究所、明海大学2003 年実施)がある。当該調査結果によれば、いずれも浄化
後を想定した質問を行ったところ、汚染対策が行われたとしても購入を控えるという回答が
多く、スティグマが存在することがわかった。スティグマの大きさは、購入の場合も、賃貸
の場合も、20%から30%が最も多く、次に50%というものであった。
これに対し、デベロッパー、銀行、不動産仲介業者側は異なる考え方を示している。国土
交通省実施の「民間土地取引に係る土壌汚染地の取扱実態に関する調査」によれば、デベロ
ッパーは、マンションも、オフィスも原則として掘削除去を実施後スティグマなしで販売し
ており、スティグマを斟酌しない考え方が一般的である。また、マンション開発で、掘削除
去を実施していない場合においても、十分なリスクコミュニケーションを販売前に行うこと
によって、スティグマを考慮せずに販売価格を設定している例もある。
銀行は、担保評価上、浄化措置が前提であり、浄化後のスティグマに関しては、対応が分かれている。不動産仲介
業者は、用途等を踏まえて取扱い、浄化後スティグマを考慮に入れた上で対応を行っている。
以上のように、スティグマについては誰が土地を取り扱うかで対応が分かれており、不動
産市場で、スティグマによる減価の取扱いについて、今後のさらなる検討が必要である。
3.6.4 エンジニアリングレポートの重要性
平成19年4月に改正された不動産鑑定評価基準においては、証券化対象不動産の鑑定評価
にあたり、鑑定士は、土壌汚染について、エンジニアリングレポート(以下「ER」という。)
や鑑定士の独自調査により的確に判断しなければならないとされている。
一方、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)は、平成19年4月に新しいERのガ
イドラインを作成した。BELCAのガイドラインによれば、ERは「建物状況調査報告書」、「建
物環境リスク評価報告書(フェーズ?)」、「土壌汚染リスク評価報告書(フェーズ?)」、
「地震リスク評価報告書」の4つの報告書から構成される。
建物環境リスクにおいて、土壌汚染に関しては、フェーズ?調査が標準として位置づけ
られ、REC(Recognized Environmental Condition:使用履歴のある有害物質や石油製品
等が、現時点で漏洩している状態にある、過去に漏洩した履歴がある、あるいは将来にお
いて漏洩が発生することが十分に懸念され、土壌や地下水に影響を引き起こすような状況
のこと。)の有無及び内容を結論として提示することとされている。一方、証券化対象不
動産の鑑定評価においては、汚染リスクの価格に対する結論が要求される。
BELCAのガイドラインでは、フェーズ?でRECやデータギャップが指摘されたら、それ
を定量的に評価することとされており、これはフェーズ?で汚染がないことが完全に示さ
れない限り、フェーズ?が必要となるとも理解される。
しかしながら、BELCAのガイドラインには拘束力はなく、エンジニアリングレポートに
は様々なレベルのものが見受けられるため、鑑定評価に活用するという視点から必要とさ
れる内容等について検討し、整理していくことが必要である。
このため、(社)日本不動産鑑定協会において、エンジニアリングレポート関係者との
共同研究会や、エンジニアリングレポート関係者の協力による研修などが実施され、実務
面での取組みが進められており、今後は、これらの取組みを継続・発展させ、着実に実務
に反映させることが重要である。
この際、不動産鑑定とエンジニアリングレポートの制度面の差異やエンジニアリングレ
ポートの提出は鑑定士ではなく、鑑定評価の依頼者に対してであるなどの難しさはあるが、
両者の連携により、それらの課題を克服することが強く求められる。
3.6.5 課税関係
土壌汚染された土地についての課税関係における評価では、減額項目を見込むか否かの考
え方において税による差異が存在する。
固定資産税については、何万筆もの土地を同時に評価するという大量、一括性に特徴を有
すると同時に、課税のための評価であることから評価の均衡、公平の確保が重要である。「土
地に関する調査研究(平成18 年3 月)−土壌汚染対策法と固定資産税評価について−(資産
評価システム研究センター)」によれば、汚染の除去等の措置費用を減価要因とすることは必
ずしも適当ではなく、当該土壌汚染地の現況に着目し、当該土地の利用の制限を減価要素と
することとしている。また、心理的要因については、その影響の有無が不確定であること等
から、基本的には考慮しなくても一般的には差し支えないと考えられるとしている。
一方、相続税については、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」(平成16 年7
月5 日付国税庁課税部資産評価企画官情報第3 号、資産課税課情報第13 号)が示されてい
る。相続税における土壌汚染地の評価額は、土壌汚染がないものとした価額から、浄化費用、
使用収益制限による減価、心理的要因による減価を考慮することとされている。相続税等の
財産評価においては、課税時期において、評価対象地の土壌汚染の状況が判明している土地
を土壌汚染地としており、土壌汚染の可能性があるなどの潜在的な段階では土壌汚染地とし
て評価することはできないものとしている。
なお、相続税を公示価格を用いて評価する場合には、評価が公示価格の80%を基準として
いることから、減価は土壌汚染浄化額の80%としている。また、土壌汚染の原因が被相続人
であり、第三者からの損害賠償請求により債務が確定しているときは、債務として計上でき
る場合もある。相続開姶後に土壌汚染が判明した場合であって、土壌汚染の原因を第三者に
特定することができ、除去費用について、当該第三者に求償権を有するときは当該求償権を
資産計上する。
4.諸外国の制度・取り組み
諸外国として、土壌汚染問題関連の情報が比較的多く収集されている米国とドイツの二ヶ
国を対象とし、それぞれの国の土壌汚染問題への取り組み状況について、以下の5 つの視点
から分析整理した。
各国のはじめで、取り組み状況の分析整理の前提として、米国に関しては、スーパーファ
ンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ及びそれぞれの法制度の概要につい
て整理し、また、ドイツに関しては連邦土壌保護法制定の経緯について整理した。
なお、ドイツに関しては、「財政支援施策」及び「環境負債免除制度」の項目に関しては、
詳細な情報が不足しているため分析対象から除外した。
【分析整理の視点】
・ 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
・ 浄化修復目標の設定
・ 制度的管理
・ 財政支援施策
・ 環境負債免除制度
4.1 米国
4.1.1 スーパーファンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ
(1)スーパーファンド法
1)立法に至る背景
米国では、1970 年後半から有害廃棄物汚染による環境災害が立て続けに発生し、災害によ
っては国家非常事態宣言の発動もあった。しかし、それまでの法制度では、土壌、地下水、
地表、水、大気の汚染に対して、連邦政府が直接関与できる法的権限はなかった。このため、
有害物質汚染災害や土壌汚染から国民と環境を保護するための新たな法制度の整備が必要と
なり、1980 年に連邦議会が「包括的環境対処・補償・責任法」(以下「スーパーファンド法」
という。)を成立させた。これ以降、連邦環境保護庁(以下「EPA」という。)が主担当官庁
となって、連邦政府レベルでの取り組みを開始した。
その後、1986 年にスーパーファンド改正・再承認法(以下「SARA」 という。)が施行さ
れ、スーパーファンド法の立法内容の強化・拡充がなされている。
2)スーパーファンド法の概要 (注1)
? 汚染者負担主義
スーパーファンド法の基本的考え方は、汚染者負担主義であり、当該サイトの汚染に何ら
かの関わりがあったあらゆる個人ないし企業を潜在的責任当事者とし、サイトの浄化及び住
民の健康や自然環境に与えた損傷への補償責任を求めた。潜在的責任当事者とは、汚染物質
の排出者、運搬者、貯蔵者、投棄・処理者等有害物質の放出または放出のおそれに関与して
いる者をいい、判例により汚染物質を廃棄している施設の所有者や創業者に対して融資を行
っている金融機関等直接的に問題となる汚染に繋がっていない者も、汚染修復の資金負担責
任を抱えることになった。また、スーパーファンド法施行以前の関与の責任も負わねばなら
ないという極めて厳しい責任原則主義が基本となっていた。
? 財源の手当て
EPAは2つの財源を手当てしており、1つは責任者負担によるサイトの浄化と補償であり、
もう1つは責任主体に支払い能力が無い場合や責任主体が不在となる場合への対応のため、
危険物質を製造したり、あるいは利用する産業に目的税を課し、これを基金化(有害廃棄物
信託基金(トラスト資金))して、遊休地化したり、放棄されているサイトの浄化資金とした。
(ただし、この税制は制定後15 年間で失効した。)
? 措置の種類
スーパーファンド法では、有害物質のリスクの程度に応じ、短期又は長期のいずれかの対
応がなされる。
・ 除去措置(Removal Action):短期の対応。健康被害と緊急の環境リスクに対応するもの。
・ 浄化措置(Remedial Action):長期の対応。通常の浄化措置の流れを追って実施するもの。
? CERCRIS とNPL
CERCRIS(the Comprehensive Environmental Response, Compensation,and Liability
Information System)とは、米国内の有害物質による汚染の懸念のあるサイトと当該サイト
における調査等の状況が全て登録されている連邦政府作成のデータベースである。CERCRIS
に掲載されているサイトは、一定の手続きを経た後、連邦政府や州のスーパーファンドサイ
トとして登録される可能性のあるサイトである。
このうち、最も深刻な汚染サイトとして、早急に浄化措置を行うべきサイトに優先順位を
つけてリスト化したものがNPL(National Priority List:国家緊急リスト)である。
? スーパーファンド法による問題と対応
スーパーファンド法の責任原則に関連してさまざまな問題が発生し、それらの問題を改善
するために、さまざまな運用上の工夫や修正を加えて今日に至っている。
a.関係当事者間による訴訟の多発
汚染サイトの浄化コストが高額になるため、同じサイトの潜在的責任当事者同士に責任
分担の訴訟が多発し、訴訟問題で資金を浪費し、また、訴訟が長期化し、浄化事業の遅延
化を招いた。
この問題への対応として、1986 年に施行されたSARA において、小規模の当事者で、「寄
与割合が僅少の」または「寄与割合が極小の」当事者は、早期に和解できることとした。
「寄与割合が極小の」当事者については、負担無しで和解できることとした。
SARA のその他の主な改正内容は以下のとおりである。(注2)
・ 「無実の土地所有者保護措置」の創設とその適用要件としての「全ての適切な質問」の規定
・ 資金調達方法の改良(トラスト資金の増額)
・ 浄化に関する永続的な改良策の開発、利用の強調
・ 地域住民への重度汚染化学薬品の存在に関する情報公開の義務付け
b.環境リスクをカバーする保険商品の普及
潜在的責任当事者と保険会社の間でも浄化コストの資金的埋め合わせをめぐって訴訟が
多発したが、スーパーファンド法への対応について、保険の必要性も高まり、施設の被害、
浄化費用負担、プロジェクト遅延、ビジネス中断、担保価値下落、風評被害、契約不備等
のあらゆる環境リスクをカバーする保険商品が契約可能になっている。これらの保険商品
が開発されたことにより、リスクを潜在的に抱えているサイトの売買、浄化、開発が容易
になってきている。
c.不動産業界への影響
スーパーファンド法により不動産業界はネガティブな影響を大きく受けた。不動産開発
業者は、潜在的責任当事者になることを恐れて、環境リスクのある不動産取引を敬遠し、
汚染サイトの遊休地化、放置化が促進されてしまった。
この問題に対して、EPA と各州政府は、再開発を促進するために、税制や補助金、融資
などの財政支援の充実化や環境負債免除制度などの規制面の保護政策強化への対応措置を
講じてきている。これらの措置により、汚染サイトは、不動産業者にとって割安であり、
かつ立地条件も良いことなどから、経済的メリットのある開発適地へと蘇生される可能性
が高まる方向となった。
(2)ブラウンフィールド法
1)立法に至る背景
スーパーファンド法の施行以降、土壌浄化の汚染者負担原則及び浄化の義務付けが明確化
されたが、この法的責任に関連して、他の汚染主体との浄化コスト負担に関する訴訟の多発
や、浄化リスク発生を嫌って、土壌汚染サイトの土地取引の停滞等の問題が発生し、EPA で
はさまざまな改善策を講じてきたが、より効率的な浄化プロセスの構築と再開発促進を狙い
として、ブラウンフィールド法(小規模事業者の責任免除及びブラウンフィールド再活性化
法)が2002 年に施行された。
2)ブラウンフィールド法の概要 (注3)
ブラウンフィールド法では、浄化プロセス効率化の観点から、浄化修復事業の長期化・遅
延化の一因となっていた小規模零細企業の責任問題への対応を図り、また、ブラウンフィー
ルドの土地取引活性化への観点から、浄化後のサイト所有への免責保護の規定の明確化及び
財政支援策の拡充を図った。
? 小規模企業の浄化責任保護
スーパーファンドサイトの浄化責任を負っている企業のうち、以下の条件を満たす事業者
は免責される。
a.産業廃棄物の排出事業者または、収集運搬業者
有害物質の取り扱い量が液体100 ガロン、固体200 ポンド以下で、全ての廃棄、取り扱い、
輸送を2001 年4 月1 日以前に行っていた場合
b.生活系廃棄物(身の回りで出るごみ)の排出者以下の条件を満たす場合、免責される。
・住宅地の所有者、管理者、借地人である場合
・潜在的浄化責任の通知が届けられてから、さかのぼって3 年間の平均従業員数が100 人
以下で商業活動を営んでいて、かつ法律による小規模企業体に該当する場合
・廃棄物を発生させたNPO で、前の年の従業員数が100 人以下の場合
? ブラウンフィールド再活性化と環境修復
a.ブラウンフィールド再活性のための財政援助(補助金及びブラウンフィールド再活性化ファンド)
以下の財政支援関連施策が盛り込まれた。
・ 総額で年間2億ドルの財政援助(うち、5,000 万ドルまたは25%を石油関連物質のブラウンフィールドサイトに充当する)
・ ブラウンフィールドサイトの再定義
以下のように再定義し、ブラウンフィールドの範囲を拡張した。
「有害物質や汚染物質の存在、もしくは潜在的に存在しうることが確認されていること
により、増築や再開発、または再利用が困難と思われる土地」と定義し、産業用地以外の
土地、例えば住宅地や商用地等において過去の土地履歴等により土壌汚染が存在する可能
性がある場合の再開発時においても、財政支援の優遇措置を適用できることとなった。
・ ファンドの対象拡大
石油及び石油関連製品を対象に追加
・ ファンドから支出できる用途の拡大
サイト調査に対して20 万ドル以下、浄化に対して100 万ドル以下を対象として追加
b.ブラウンフィールド責任の明確化
以下の主体に対する責任を免除した。
・ 隣接所有者をスーパーファンド法の責任から免除(流れ汚染に対する保護措置)
・ スーパーファンドサイトの買い手の保護
・ 善意の土地所有者(適切な商習慣に従った土地の取得で、全ての適切な調査(AAI)を行っ
た上で土壌汚染の事実を知る余地がなかった場合)の保護
・ AAI の定義(AAI 自体はSARA で創設されたものであるが、何をどの程度行えばいいの
かが不明確であった。このため、ブラウンフィールド法が出来るまでのアメリカにおいて
は、環境アセスメントビジネスが発達し、フェーズ?調査として結実することとなる。)
c.州のブラウンフィールド対策プログラムへの支援
・ 毎年5,000 万ドルまでの補助金を州対策プログラムに支出
・ 対象サイトの拡大
4.1.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
土壌汚染情報は土地の安全性を知らせる公益的な情報として位置づけられ、米国では、
多くの州が土壌汚染情報に関するデータベースを作成し、ウェブサイトでの一般公開を行っ
ている。ここでは、ニューヨーク市とオクラホマ州の取り組みについて取り上げた。
(1)ニューヨーク市
ニューヨーク市のブラウンフィールド問題への取り組みの12 の具体的な内容の一つとし
て、「潜在的なブラウンフィールドを把握するための過去からの土地利用のテータベースの作
成」が掲げられている。
【目的】
以下の3 点が示されている。
・ 潜在的でかつ優先的な取り組みが必要なブラウンフィールドを見つけること
・ 地区ごとのブラウンフィールドの再開発計画への基本的な情報を提供すること
・ すべての土壌汚染地の浄化と再利用活動の目標を明確にすること
【データベース作成方法】
以下の2つの方法が示されている。
・ 各種情報の収集
(環境関連の発行物・データベース、歴史的な地図、電話帳、財務記録などからの情報収集)
・ 年ごとのブラウンフィールド関連環境アセスメントへの要望についての問い合わせ
(2)オクラホマ州
社会環境の保全のためにブラウンフィールドの制度的管理が重要であるとの認識の下に、
オクラホマ州環境局では、ブラウンフィールドを含めた土地利用の管理に向けて法制度を整
備している。
土地利用管理の具体的な内容として、ブラウンフィールドの制度的管理についてのデータ
ベースをくまなく蓄積している。
4.1.3 浄化修復目標の設定
ブラウンフィールドの浄化修復目標に関しては、汚染されている土壌の位置(地表からの
距離)、汚染の程度、その跡地における将来の用途などを考慮して、人体に対する曝露の危険
性(リスク)を計算し、そのリスクに応じて、環境浄化修復手法を選択する「リスクベース
基準」に基づき設定する方法が一般的になっている。
跡地が工場用途になる場合と幼稚園の砂場など子供が土で遊ぶ場所とでは、当然に浄化修
復レベルは異るという考え方をとっており、そのために必要な事業方法、費用も異なる。
このため、リスクベース基準の適用においては、跡地の用途が将来にわたって遵守される
必要があり、基準の設定とともに用途制限措置の設定が重要となる。
(1)浄化修復目標の設定及び適用方法に関する分類
米国の各州の浄化修復目標の設定及び適用方法は大きく、表4.1.1 に示す3つに分類され
る。また、それぞれの分類のうち、一つの州ずつ、内容の把握整理を行った。
表4.1.1 米国各州の浄化修復目標の設定及び適用方法の状況
(2)マサチューセッツ州
マサチューセッツ州の浄化修復目標の設定にあたっては、汚染された土壌や地下水の人体
及び環境への曝露の程度とともに、将来の跡地利用方法を密接に考慮して設定しており、こ
のため、土壌汚染が存在する土地に対して、その用途制限も行っている。
1)土壌の環境基準
土壌環境基準は3 つの土壌分類によって異なる基準が定められている。分類は、土壌に対
する可触可能性、受容者の存在の性質、土地の利用頻度、土地の利用の強さの4 つの土地固
有の要素によって分類される。これらの土壌分類は、土壌の受容者に対する曝露の程度を規
定しているものであり、これらの分類は互いに排他的である。
【マサチューセッツ州の土壌の環境基準】
S-1:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい(主に住宅・学校など)
現在又は将来において人間が摂取する野菜や果物を育てるため利用することができる
子供の頻繁な利用または、熱心な利用が行われる可能性が高い土壌はS-1 に準ずる
大人の頻繁かつ熱心な利用が行われる可能性が高い土壌はS-1 に準ずる
S-2:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい
子供の頻繁な利用も熱心な利用も双方とも行われる可能性が低い土壌はS-2に準ずる
子供が対象地に立ち入らず、大人の頻繁な利用又は熱心な利用が行われる可能性が高い土
壌はS-2 に準ずる
S-3:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい(駐車場の下など)
子供が対象地に立ち入らず、大人の頻繁な利用または熱心な利用が両方とも行われる可能
性が低い土壌はS-3 に準ずる
表4.1.2 マサチューセッツ州危機管理計画の土壌カテゴリー
2)地下水の環境基準
地下水環境基準は、地下水の汚染の結果に由来する異なる曝露の可能性を規定する3 つの
地下水分類によって定められている。これらの分類が異なる曝露の可能性を規定しているた
め、地下水の分類は互いに排他的ではない。すべての地下水は最終的に地表水に流れ出す可
能性があると考えられるため、すべての地下水はGW-3 の分類の水質基準を遵守する必要が
ある。土地固有の要素により、GW-1 やGW-2 に分類される可能性がある。
【マサチューセッツ州の地下水の環境基準】
GW-1:飲料水としての現在または将来の利用の可能性に基づき保護されるべき分類
GW-2:屋内の空気に対する揮発の水源となってもよいとされる分類
GW-3:石油や危険物質を地表水に対して放出する可能性がある分類
(2)カリフォルニア州
カリフォルニア州のブラウンフィールド浄化修復活動への要請事項は、NCP(国家石油及
び危険物汚染緊急対策)と連邦政府のスーパーファンド法の規定に準拠している。NCP の浄
化目標では、土壌別の基準というよりも発癌性の物質では10-4 から10-6 までの範囲に収まる
よう浄化修復を達成することといった基準であり、特定のサイトごとのリスク分析に基づい
て目標水準を設定し、跡地の土地利用に関係なく永続的な浄化修復を行うことを推奨している。
一方、EPA では、このような目標水準の実行可能性や、商業や産業用途の再開発が多い中
で、一律に住宅用途に対応した浄化修復を行うことは必要以上の対応であるとの判断を持っ
ており、跡地の土地利用に対応した浄化修復目標の設定を許容している。これは、リスクベ
ースのアプローチといわれており、浄化修復コストや健康リスク、跡地の土地利用、地域コ
ミュニティの許容性、技術的可能性などのさまざまな要因のバランスの下に浄化修復目標を
設定する方式である。
しかし、この方式は多くの環境上の判断を必要とし、恣意的に水準が適用される場合もあ
り、また、費用を節約するために必要とされる水準以下の浄化修復を行うことにより、汚染
物質が残存する問題も生じている。
これらの点から、カリフォルニア州としては、一律的な浄化修復目標水準の設定は難しい
と判断し、汚染地域の浄化修復事業に対して、以下の3 つの戦略により対応している。
【浄化修復目標水準設定の戦略】
a.バックグラウンドレベル(汚染されていない状態)までの浄化修復に向けての水準
バックグラウンドレベルについての一定不変の水準を持っている訳ではなく、各部局で
個別に設定している。
b.個別汚染地域ごとのリスクアセスメントに基づく浄化目標水準の設定
個別汚染地域ごとのリスクアセスメントに基づく浄化目標水準を設定し適用することを、
カリフォルニア州の基本的アプローチとしている。
c.州全体からのリスクベースの浄化目標水準の設定
以下の要因によるタイプ別リスクの想定に基づき、浄化目標水準を設定する。
開発事業者はまず、これらのタイプ別水準から控えめな水準との比較を行い、より高い
水準で比較する場合には、汚染地域ごとに実施するリスクアセスメントに基づく浄化目標
水準を適用する。
【タイプ別リスク設定の要因】
・汚染物質の人体への取り込みかた(摂取、吸入、皮膚からの感染)
・汚染源(土壌、空気、地下水)
・周辺土地利用(住宅地、商業地、工業地)
(3)ニュージャージー州
ニュージャージー州では浄化修復活動を行う上での目標水準として、リスクベースの基準
に基づき、以下の3 ケースに分けて、土壌と地下水に分けて設定している。
【浄化修復の目標水準】
a.無制限の跡地利用に対応する水準
b.条件付きの跡地利用に対応する水準
c.自然の自己回復力を考慮した条件付きの跡地利用に対応する水準
【浄化修復の目標水準の適用上の留意点】
・ これらのどの分類についても、汚染原因物質は除去されなければならない。
・ 土壌汚染物質については、発癌性のあるもの、非発癌性のものに分けて設定している。
・ 土壌の浄化修復においては、リスクアセスメントに基づいて設定された特定ケースの基
準の適用も認めている。
・ 適用される水準がそのサイトの周辺地区の水準よりも低い場合は、周辺地区の水準を適
用する。
・ そのサイトの土地利用が制限されている場合は、特別の注意書きを表示する必要がある。
4.1.4 制度的管理
制度的管理とは、ブラウンフィールドに対して、土地利用制限及び法的な管理により、健
康や自然環境への潜在的な被害を最小限にしつつ、ブラウンフィールドの有効利用を適切に
確保する法的措置等の取り決めを意味し、以下に示すブラウンフィールドの環境改善の一般
的プロセスのうち、段階5 に位置づけられる。
【環境改善の一般的プロセス】
段階1:地歴調査・聞き取り調査予備的な調査及び環境関連部局への通知と早期リスク削減措置の必要性の判断
段階2:包括的な土壌調査(アセスメント)、用途に対応したリスク影響調査アセスメントの実施により、汚染の原因、特性、程度、潜在的な影響の把握
段階3:環境改善計画の立案浄化計画とプロセスの評価、決定
段階4:浄化修復事業の実施
段階5:制度的管理継続的な浄化水準の維持管理
一部の州では、土壌汚染処理コストを低減させて土地の再利用、用途転換を円滑にするた
めに、人体の健康に対するリスクがない範囲において封じ込め等の部分的な処理を認めてい
る。このような完全浄化以外の対策が実施される場合には、土壌汚染による人体への暴露リ
スクを低減するために、一般の用途地区に上乗せするかたちで、土地利用制限などの制度的
管理が行われる。
制度的管理の目的は、土壌や地下水に含まれる未処理の汚染が人体に対して暴露する危険
性を管理するために、ブラウンフィールド再開発後の用途及び活動を限定して汚染土壌の封
じ込めを維持するためのものである。
(1)活動用途制限
マサチューセッツ州では、全米でもいち早く土壌汚染の制度的管理手法を導入しており、
AUL(Activity and Use Limitations)と呼ばれている活動用途制限を設けている。このAUL
は、現在及び将来の土地所有者に対してその土地で許容される活動や利用が示されており、
許容されていない用途に変更する場合は、新しい用途に応じたリスクの評価と追加的な浄化
が求められる。
この制度は、土壌汚染を全て除去するためには多額の費用がかかり、跡地利用にとって現
実的な解決策ではないため、汚染土壌を地下に残したまま人体に対して暴露されることを防
ぐために、土壌汚染が存在する土地に対して用途制限を行う制度である。
許容される土壌汚染の暴露の程度は汚染された土地の跡地利用によって異なるため、跡地
利用に応じて到達すべき浄化目標を設定して、その目標達成に適した方法で浄化を行う。こ
の浄化は、汚染自体の濃度を下げることのみでなく、汚染に対する暴露を取り除く、もしく
は最小化することでもよい。完全浄化によらず、汚染が残された場合には、活動利用制限を
設定して将来にわたり汚染の暴露状態が変わらないように継続的に土地を管理していくこと
になる。
マサチューセッツ州では、図4.1.1 に示す体制でAUL を実施している。用途制限されてい
る土地のAUL に係る情報は、州環境保護局のほかに自治体と郡不動産登記所で管理してお
り、この土地の再開発や土地取引に際しては、環境通知書によって土壌汚染の扱いが確認さ
れている。
図4.1.1 マサチューセッツ州の土壌環境情報管理体制
(2)制度的管理の実施方法に関する分類
米国の各州の制度的管理の実施方法で分類すると、多くの州では長期間モニタリングを実
施してブラウンフィールドを管理しているが、データベースを構築して経過追跡のみにとど
まっている州もみられる。表4.1.3 に示す分類のうち、カリフォルニア州及びルイジアナ州
における制度的管理の内容を以下に示す。
表4.1.3 米国各州の制度的管理の実施方法の状況
(3)カリフォルニア州の制度的管理の内容
カリフォルニア州毒物管理局(DISC)では、すべての浄化修復活動を長期間管理する方針
であり、以下の事項について実施している。
この中で、浄化修復用地の用途制限については、いろいろなメディアを用いて、情報を公
表しており、もし、用途制限をする必要がないレベルまで浄化修復された場合は、用地リス
トから除外し、逆に用途に見合ったレベルまで浄化修復されていない場合は、必要なレベル
までの浄化修復を行う財政的な裏付けを要求する。また、浄化修復活動が完了していない場
合は、継続的に浄化修復活動を行っているかどうか定期的に検査する。
【カリフォルニア州の制度的管理の内容】
・浄化修復活動完了時の検査
・モニタリング(契約事項の遵守徹底)
・インターネット上での浄化修復用地の用途制限の公表
・浄化修復用地周辺地区への掲示板での通知
・周辺住民への郵便による通知
・新聞紙上での注意広告
(4)ルイジアナ州の制度的管理の内容
ルイジアナ州環境管理局(DEQ)では、用途制限のある自主的な浄化修復活動については、
インターネット上で公表できるデータベースにより追跡的に監視している。
このデータベースでは、当該サイトの住所、用途制限、過去からの土地所有者、用途の履
歴とともに危険物取扱いの有無の情報が、土地所有者からの届出に基づき、登録されており、
DEQ の承認が無ければデータベースから除外できない。また、正確な情報が登録されていな
い場合は、当該サイトの取引契約を買い手側が解約できる根拠ともなる。
4.1.5 財政支援施策
ブラウンフィールドの浄化修復は、土地の安全性の改善や土地取引の活発化、都市の活性
化といった効果が見込まれる反面、多大な費用を要するため、当該用地の保有者が浄化修復
によるメリットが見込まれない場合は、そのまま土地利用の停滞状態が続く可能性もある。
このため、ブラウンフィールドの浄化修復を促進するために、用地の保有者や開発事業者
に財政的支援を講ずることは有効な施策となる。
ブラウンフィールド浄化修復再生事業に対する財政的な支援策としては、補助と融資、税
制措置に大別される。
ここでは、まず、米国の各州の財政支援策を総括的に捉え、次いで補助と融資について、
連邦政府の適用条件、主要な州の支援内容、適用条件について整理する。
(1)米国の財政支援策の分類
ブラウンフィールドの浄化修復事業への補助については、ブラウンフィールド再開発への
補助を行っている州が最も多い。融資については、零細事業者向けとして、ドライクリーニ
ング事業者への融資を行っている州が最も多い。また、税制措置に関しては、固定資産税の
軽減措置を講じている州が最も多い。
表4.1.4 米国各州の財政支援策の制定状況
(2)連邦政府のブラウンフィールド支援プログラム
連邦政府のブラウンフィールド支援プログラムは主にEPA(環境保護庁)とHUD(住宅
都市開発省)によって行われている。特にEPA は、常に連邦のブラウンフィールド政策のイ
ニシアチブをとり続けてきた機関であり、多くの支援プログラムを用意している。
1)EPA のブラウンフィールド補助プログラムの概要
地域に根ざした環境保護の手段としてブラウンフィールド問題に対応するために、1994 年
からEPA は、官民のパートナーシップを促進し、ブラウンフィールドサイトを評価した上で
浄化し、かつ、再開発するための革新的・創造的な方法の構築を促進することを目的として、
ブラウンフィールド問題に対応した補助金プログラムを開始した。EPA は「州・部族・自治
体の環境・経済開発職員が、ブラウンフィールド活動を概観し、また地域の問題に対して地
域固有の解決策を実行するための支援を行う」ことを目的としており、自治体を中心に自治
体・地域が主導するブラウンフィールド再生の取り組みを支援する姿勢に徹している。また、
EPA は、またブラウンフィールド再生による経済的な利益が地域に維持され続けるようにす
るため、地域の環境職業訓練プログラムを作成するための資金を提供している。
EPA のブラウンフィールド補助金は、以下の4 つが主要なものである。
・ アセスメント補助金
・ 浄化補助金
・ リボルビング・ローン・ファンド補助金
・ 職業訓練補助金
2)EPA のブラウンフィールド補助金の申請要件
【内容】
アセスメント
リボルビング・ファンド(RLF)
浄化対策
【規模】
2007 年10 月申請分 7,200 万ドル、200 件を予定
【対象】
a.ブラウンフィールド(危険物質や汚染の存在あるいは存在可能性により、再開発や再利
用に問題が生じうる不動産)
b.ブラウンフィールド以外の追加適用対象
・規制薬物によって汚染されたサイト
・石油または石油製品によって汚染されたサイト
・廃鉱など鉱物資源の跡が残るサイト
【資格要件】
a.申請者の要件
・ 浄化したいとする土地を所有している団体(大学やNPO を含む)
表4.1.5 補助対象別の申請者タイプ
b.適用除外土地
以下のサイトは、補助金受給資格を有さない。ただし、2)から5)については、個別判断に
基づき対象とすることができる。
1) NPL に現在リストされているか、リストに向け提案されている土地
2) CERCLA の下で計画あるいは進行中の浄化がある土地
3) 閉鎖計画または許認可に規定される要件に従い、RCRA 閉鎖通知を提出した処分場である土地
4) PCB の漏出があった施設
5) 漏出地下タンク信託基金から資金を受けている施設
【補助金の使用制限】
補助金は下記の支払いに使用できない
・ 罰金
・ 連邦経費分担要求(例えば他の連邦基金で要求される分担金)
・ 一般管理費
・ 潜在的責任者として対応するための費用
・ 土壌汚染浄化関連法以外の任意の連邦法に対する遵法費用
・ ロビー活動費用など
3)ブラウンフィールド・モデル地域
ブラウンフィールド・モデル地域(Brownfield Showcase Community)は、20 以上の連
邦機関のパートナーシップ(注4)のもとで1998 年から行われたブラウンフィールド再生のモ
デル事業である。環境修復から地域開発まで多岐にわたるブラウンフィールド問題を解決す
るための、省庁間協力の事例として注目される。
1997 年5 月に、ゴア副大統領は、15 を越える連邦機関の資源を集めるためにブラウンフ
ィールド連邦パートナーシップ(BFP)を発表、1998 年3 月に、この連邦パートナーシップ
は、ブラウンフィールド上の共同作業の利点を実証するモデルとして、16 ヶ所のブラウンフ
ィールド・モデル地域を選定した。さらに2000 年10 月には、イニシアチブの成功を継続す
るために12 の追加のブラウンフィールド・モデル地域を選定している。
選定は基本的に都市レベルまたは地域レベルで行われ、対象都市のなかでもブラウンフィ
ールドを多く抱える特定の地区に対して、特に重点的に資金を投入している。ブラウンフィ
ールド・モデル地域は規模、資源および地域のタイプなど多岐にわたるが、古い工業地帯が
広がる米国北東部に特に集中している。
図4.1.2 モデル地域事業に指定された自治体の位置
? モデル地域事業の目標
1.ブラウンフィールドのアセスメント、浄化および持続可能な再利用を通して環境保護お
よび回復、経済再開発、雇用創出、コミュニティ再生および公衆衛生保護を促進する。
2.ブラウンフィールドを修復し再利用する地域の努力を支援する連邦、州、地域・民間の
動きを結びつける。
3.ブラウンフィールドに取り組む際に、行政と民間が協働することによって、よい結果が
得られることを実証する全国的なモデルを開発する。
連邦政府が1980 年代から取り組んできたスーパーファンド法にはじまる環境修復の取り
組みが、土壌汚染をはじめとする環境浄化に主眼をおいてきたのに対し、90 年代のブラウン
フィールド再生事業には、単なる土壌汚染の浄化にとどまらず、環境問題に関する市民の教
育から、周辺地区の再生、地域の雇用創出に至るまで、多面的な取り組みが求められるよう
になってきた。
スーパーファンドサイト(注5)は、その多くは浄化の優先順位付けから資金確保・浄化の
管理に至るまで連邦直轄で行われてきたが、ブラウンフィールド再生事業はスーパーファン
ドほど汚染の程度は深刻ではなく、土壌汚染の浄化と同程度、もしくはそれ以上に都市・地
区の再生と経済開発に主眼が置かれている。結果として、その実施は連邦機関(特にEPA)
だけで実施できるものではなく、すべてのレベルの政府、民間部門および非政府組織の間に、
より多くの協力と調整が求められた。
モデル地域事業は、土壌汚染の浄化から工場跡地さらには疲弊した工業都市全体の再生を
目指すブラウンフィールド事業へと展開するためのノウハウを連邦・州・自治体が一体とな
って作り上げるための重要なプロセスであった。
? 対象地域の利点
ブラウンフィールド・モデル地域に指定されることで、自治体は連邦からの重点的な支援
を受けることができる。自治体は、ターゲットとされた技術的・財政的援助から直接的な利
益を得ることができる。
中でも連邦政府の職員(主にEPA の職員)が、対象の自治体に出向し、技術的・財政的援
助の調整を支援する制度である。政府間要員配置(IPA)スタッフと呼ばれ、環境面の知識
や制度・補助金に不慣れな自治体職員を助け、2 年から3 年にわたって、対象自治体の職員
として地域のブラウンフィールド再生に取り組んだことの意義が大きかった。(注6)
(3)主な州のブラウンフィールド関連財政支援策の概要
1)マサチューセッツ州の財政支援策
マサチューセッツ州では産業開発局や環境保護局などの部局ごとにさまざまなブラウンフ
ィールド関連の財政支援策が用意されているが、補助に関しては、対象が自治体または非営
利団体に限られており、一般のブラウンフィールドについては低利融資の利用に限定されて
いる。
VCP(自主浄化活動)サイト数は、2006 年7 月までに34,312 件のサイトが報告されてお
り、このうち、4,735 件は現在、実施中である。毎年、概ね1,800 件の新規サイトが申請さ
れる。
? マサチューセッツ州産業開発局(Mass Development)が管轄する助成策
a.ブラウンフィールド再開発基金(BRF)(融資)
再開発を伴うブラウンフィールドサイトに対して、以下の融資が提供されている。
【財政支援規模】
・連邦政府からのブラウンフィールド補助金の10%が、サイトを指定したアセスメントや
再開発を誘導する浄化事業(Cleaning Projects)に使われている。
・2006 年 7 月時点で、15 箇所のサイトの調査と2 箇所のサイトの浄化事業に取り組んで
いる。
【融資の内容】
・ブラウンフィールドサイトの調査への低利融資
サイトの調査に対しては、上限10 万ドルまでの低利融資が提供される。
〈資格要件〉
・EDA(Economically Distressed Areas)地域内に位置していること
以下のどれかの条件を満たすこと
・ETA(Economic Target Area)地域として指定された地域または自治体であること
・ETA 地域としては指定されていないが、ETA 指定条件を満たしていること
・以前の用途がガス製造プラントであったこと
・申請者はサイトの所有者か浄化の実施者であること
・マサチューセッツ州の規定により認可されたサイトであること
・浄化事業への低利融資
サイトの浄化、修復に対しては、上限 50 万ドルまでの低利融資が提供される。
特に、優先プロジェクトについては、調査と浄化事業に対して上限200 万ドルまで融資
される。
〈資格要件〉
・EDA 地域内に位置していること
・申請者はサイトの所有者であること
・抵当保証が設定できること
? マサチューセッツ州環境保護局(Mass DEP)が管轄する助成策
Mass DEP のブラウンフィールド関連の助成策としては、以下のように対象が限定される。
a.水質浄化リボルビングファンド(SRF)(融資)
水質を改善するプロジェクトを対象に,期間20 年の低利融資(2%)が提供される。
b.調査及び浄化事業への補助(補助)
連邦環境保護庁(EPA)の補助の下、自治体や非営利団体を対象として、荒地となって
いるサイトの調査及び浄化事業に補助される。
【財政支援規模】
・2006 年の上半期で、概算で600 万ドル支援
このうち、110 万ドルは連邦政府から指定されているサイト
・2006 年 7 月時点で、4,200 万ドルが契約中
・1983 年以降で、累計1 億8,300 万ドルを支援
? マサチューセッツ州住宅・コミュニティ開発局(DHCD)が管轄する助成策
DHCD は連邦政府の住宅都市開発省、コミュニティ開発基金プログラムを実施する機関で
あり、人口5 万人以下の市や町を対象とし、低所得者居住地区のスラム化や環境悪化の防止、
緊急対応事業などに助成する。
ブラウンフィールド関連の助成策は以下のとおりである。
a.コミュニティ開発基金(補助)
自治体を対象に、プランニング、予備的な開発計画の検討、用地の取得、調査、浄化事
業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
b.Mini−Entitlement Program(補助)
自治体のMini−Entitlement 事業を対象に、プランニング、予備的な開発計画の検討、
用地の取得、調査、浄化事業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
c.産業開発基金(補助)
自治体の産業開発事業に補助され、プランニング、予備的な開発計画の検討、用地の取
得、調査、浄化事業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
d.コミュニティ開発行動基金(補助)
自治体を対象に、市や町の経済活性化や投資の活発化、長期の雇用創出、低所得者居住
地区の環境改善に資するプロジェクトに補助され、市街地整備の様々な事業に使われる。
e.優先的開発基金(計画立案等への補助)
自治体を対象に、計画立案、ゾーニング、住宅整備への教育・指導などに上限で5 万ド
ルまで補助される。多くの市や町では、住宅開発を誘発する計画立案のコンサルタント費
用として使われている。
? マサチューセッツ州税務局(Mass DOR)が管轄する助成策
a.地下埋設タンクプログラム(補助)
自治体を対象に、地下埋設タンクからの漏洩対策や地下埋設タンクの閉鎖などの活動に
補助される。
2)カリフォルニア州の財政支援策
カリフォルニア州では、環境調査に関して連邦政府からの補助が受けられる。浄化事業に
関する補助は特定のプログラム(下記の?)に限定されている。一般事業者の浄化事業に関
しては、専ら低利融資が受けられる。
VCP(自主浄化活動)のサイト数について、カリフォルニア州毒物管理局(DTSC)は平
均して常に300 箇所のサイトを指導・監督している。また、毎年、平均して125 箇所のサイ
トの浄化事業を完了している。
? ブラウンフィールドサイトの環境調査への補助
連邦政府環境保護庁(EPA)から、カリフォルニア州毒物管理局(DTSC)の支援を通じて応
募者に環境調査費用への補助が行われる。
? 自主浄化事業(VCP)への低利融資
・融資額
サイトの特性把握:最大 10 万ドル
サイトの浄化活動:最大 250 万ドル
〈VCP として認定される資格要件〉
・連邦政府や州政府のスーパーファンド法による対策地域、軍事施設、DTSC の
管轄外のサイトでないこと
〈融資の適用条件〉
・事業用の用地であること
・産業、商業、非営利団体・スモールビジネスの立地が予定される再開発用地であること
? 浄化事業への補助等
以下のプログラムが用意されている。
・再開発局環境監視協定プログラム(EOA)
・学校用地の環境評価・浄化プログラム
・地下埋設タンク浄化基金プログラム(UST)
・毒物管理会計(TSCA)
3)ニュージャージー州の財政支援策
ニュージャージー州では、一般事業者の浄化事業に関しては、専ら低利融資が主要な助成
策となっている。革新的技術で浄化した場合などの特定の条件を満たす場合には、補助も行
われている。
以下の財政支援プログラムの下に、多数のサイトが浄化事業を実施中である。2002 年には、
危険物放出サイト修復基金では、156 サイトの浄化事業を完了しており、総額で1,500 万ド
ル以上の融資や補助が実施された。また、200 サイトが検査中である。
NJDEP では、常に23 千箇所の汚染サイトを監視しており、その内の1 万箇所は潜在的な
ブラウンフィールドサイトである。
? 危険物放出サイト修復基金(低利融資、補助)
・一般のサイト(低利融資)
危険性の高いサイトの修復に関しては、一般のサイトでは最大で100 万ドルまで融資
・地方自治体(補助)
地方自治体に対しては、所有者のはっきりしないサイトや無償譲渡されたサイトなどの浄
化のために、最大で200 万ドルまでの補助または融資
? 水資源関連のブラウンフィールドサイト浄化に対するニュージャージー州インフラ基金に
よる低利融資
? 革新的技術で浄化した場合や制限無しまたは一部制限付き再利用が可能なサイトの浄化費
用への補助(25%まで)
4.1.6 環境負債免除制度
米国における最初の土壌汚染に関する法律としてのスーパーファンド法(包括的環境対処
・補償責任法)は、不可逆的な環境汚染の拡散の防止のために、非常に厳しい規制を課して
いる。その最も厳しい点として、土壌汚染の浄化責任を現在及び過去の土地所有者に求めて
おり、現在の土地所有者が汚染の原因者でなくても浄化責任を求められる可能性があること
があげられるが、その影響として、土壌汚染浄化の可能性がある土地については浄化コスト
のリスクを伴うため、都市部の再開発から取り残されてしまうという問題を生じさせてしま
っていた。このような問題を改善し、土壌汚染地の開発を積極化していくための制度として、
以下の制度がつくられている。
○ 自発的修復制度(VCP:Voluntary Cleanup Program)
スーパーファンド法による浄化義務発生リスクを回避し、土壌汚染地の再開発を促進す
ることを目的としており、浄化修復事業は民間側が主導的にすすめることができるよう前
項で記述した各種財政支援策が用意されている。
○ 環境負債免除制度
民間側の浄化修復事業が事前に州当局と協議した計画に基づき実施され、完了した場合
に、州政府は修復完了を承認し、将来にわたる環境負債を免除するものとして、以下の証
明書を発行する。
・ 修復完了証(No-Further-Action letter)
浄化の完了及び追加的な浄化措置が不要であることを証明する
・ 訴追免除証(Covenants-Not-To-Sue)
将来にわたって同一理由による汚染修復責任を求める訴追を原則として受けなくてよい
ことを証明する
以下で各州の環境負債免除制度及び小規模事業者責任免除制度について把握整理する。
(1)環境負債免除制度
ブラウンフィールドへの取り組みとして、ほとんどの州が自発的修復制度及び環境負債免
除制度を関連法制度に盛り込んでいる。それらの州のうち、マサチューセッツ州、カリフォ
ルニア州について、その概要を整理する。
1)マサチューセッツ州の環境負債免除制度
マサチューセッツ州の環境負債免除制度の特徴は、責任軽減制度の導入と浄化管理の民間
化によって、効率的で迅速なプロセスを実現している点にある。マサチューセッツ州は、汚
染責任者に対して厳格な連帯責任を課している。汚染責任者は、自主的に土地を浄化するこ
とが認められており、もし自主的な浄化が行われない場合には、マサチューセッツ州開発局
(MADEP)が浄化を代行し、かかった費用を回収することができる。
実際に、自主的浄化の割合が95%と非常に高い。これは、マサチューセッツ州開発局の
担当者が、積極的にインセンティブ活用を推進するブラウンフィールド・コーディネーター
となり、民間事業者の側に立って自主浄化を促していることもあげられる。
? 責任免除制度の提供
責任免除制度は、民間事業者が再生事業に参加する際に最も重要になる制度である。マ
サチューセッツ州は、全米でも早い時期に責任免除制度を創設、提供を開始した州である。
? 訴訟免除契約書の発効
ウースター市のメディカル・シティ・プロジェクトの過程で、ウースター再開発公社か
ら、民間事業者に土地を売却する際に、州政府が発行したCNTS がその原型とされる。ブ
ラウンフィールド訴訟避止誓約書は、1998 年のブラウンフィールド法によって正式に制度
として認められた。現在はマサチューセッツ州法務局によって、各々の関係者に合わせた
責任免除措置が与えられている。
? 跡地利用制限がある場合の責任免除制度
土壌汚染がある土地を浄化する際に、経済的な理由から全ての汚染を除去せずに、一定
の汚染を残したまま、封じ込めなどの処理する場合がある。この場合、跡地の活動用途制
限(AUL)が土地に付加される。AUL のある土地に対してもAUL の変更を行なわない場
合、責任免除制度の適用が可能である。
2)カリフォルニア州の環境負債免除制度
カリフォルニア州のブラウンフィールド対策の基本として自発的修復制度(VCP)が位
置づけられている。浄化修復事業者は、浄化事業中はカリフォルニア州毒物管理局(DTSC)
の監督を受け、修復が完了した時点で、以下の2種類の証明書のどちらかを発行する。
しかし、これらの保証があっても将来時点で第三者機関による浄化活動を除外しない。ま
た、浄化活動が進行中であっても、事業の完了と維持管理が確保されるとの合意があれば保
証書は発行される。
・ 修復完了証(No-Further-Action letter)
一部、汚染が残っていても、人体や環境にほとんど影響が無いレベルまで浄化された場合に発行される
・ 完結終了証(Certificate of Completion)
浄化目標水準を完全に達成した場合に発行される
(2)小規模事業者責任免除制度
小規模事業者責任免除制度は、ブラウンフィールドプログラムのより効率的な実施と再開
発促進のため、連邦政府環境保護局により2002 年に法律が施行された。この法律での小規
模事業者とは、有害物質の保有量が液体100 ガロンまたは固体200 ポンド以下で、2001 年
4月1日以前にすべての有害物質の廃棄、取り扱い、輸送を行っていた事業者である。
各州の小規模事業者責任免除制度に対応する取り組みをみると、ドライクリーニング事業
者の汚染サイトに対する環境対策プログラムとして制度化されており、どの州でも財政イン
センティブが合わせて講じられている。
【小規模事業者責任免除制度を持つ州】
・ ウィスコンシン州 −ドライクリーニング環境対策プログラム
(ドライクリーニング環境対策ファンド)
・ サウスカロライナ州−ドライクリーニング事業者のための環境指導書
(ドライクリーニング修繕トラストファンド)
・ フロリダ州 −ドライクリーニング有機溶剤浄化プログラム
(ガソリンスタンド、ドライクリーニング店向け浄化ファンド)
・ カンザス州 −ドライクリーナー環境対策プログラム
(ドライクリーニングファンド)
・ テキサス州 −ドライクリーニングによる汚染サイト対策プログラム
(ドライクリーニング浄化支援プログラム)
・ ミズーリ州 −ドライクリーニングによる汚染サイトの再利用活性化支援プログラム
(ドライクリーニング信託投資ファンド)
4.2ドイツ
4.2.1 連邦土壌保護法制定の経緯
ドイツにおいても、1980 年代から土壌汚染問題への対応が本格化したが、当時は、個々の
法律(州レベルの土壌保護法、州レベルの廃棄物法など)ごとの個別的な対応であったり、
州ごとにばらばらな規制を行っていたりして、規制の不整合の問題が生じていた。しかし、
1999 年3 月に連邦土壌保護法、同年7月に連邦土壌保護土壌汚染令の施行により土壌汚染リ
スク管理が統一された。
4.2.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
ドイツにおいては、都市計画決定の権限や土壌汚染地の浄化修復についての自治体の役割
は極めて大きい。このため、土地利用計画の安定性を担保するためにも、土壌汚染情報の収
集は重要となっている。土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動してい
るため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしている。
具体的には、自治体レベルで土壌汚染の可能性のあるサイトを把握して土壌汚染情報をマ
ップに落として公表しており、また、土壌汚染に関する統計データも自治体から、州、連邦
政府へと段階的に上げられて整備され、公表されている。
ドイツにおいては、ブラウンフィールドは最終処分場跡地と産業跡地という広い意味で用
いられており、統計によれば、この該当サイトは231 千箇所あり、また土壌汚染が特定された
サイトは11 千箇所、浄化が終了しているサイトは14 千箇所、リスク評価が終了しているサ
イトは37 千箇所と集計されている。
ドイツにおいては、図4.2.1 に示すとおり法がカバーしている土壌汚染の範囲は広く、「予
防」段階から「危険防止」段階に分かれ、法的に対策が求められるのは「危険防止」段階以
上となる。ただし、「危険防止」段階でも、土地利用用途ごとの基準値と照らし合わせて、概
況調査で終わってよいもの、詳細調査まで進むべきものに分けられていく。
図4.2.1 土壌汚染の規制体系
【統計データにおける「土壌汚染」の分類】
・ ブラウンフィールドが疑われるサイト
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち旧堆積場
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち産業跡地
・ ブラウンフィールド
・ 浄化完了サイト
・ リスク評価完了サイト
・ 浄化中サイト
・ モニタリング中サイト
4.2.3 浄化修復目標の設定
ドイツにおいては、ブラウンフィールドサイト毎に「浄化計画」を作成し、目標水準は個
別に設定することを基本とする。その目標水準は、開発用途などを総合的に考慮して決定さ
れるため、米国の各州で基本的考え方となっているリスクベースの浄化修復目標水準の設定
と同様に経済合理性の視点が取り込まれている。
また、ドイツは都市計画決定に関して市町村が強力な権限を持っており、浄化修復目標の
設定や跡地の利用形態の決定に市町村が全面的に関与している。ブラウンフィールドに関連
して、健康的な居住や就労環境の確保は都市計画を定める中で、重要な配慮項目となってい
る。
(1)浄化計画と行政契約
土壌汚染の存在が確認された土地では、まず浄化のための概況調査が実施され、浄化目標、
浄化手段、費用などが定められた浄化計画が作成される。この浄化計画は、事業者側で作成
し、行政当局に提出して、公法上の手続きである行政契約によって合意形成される。
浄化後のネットバリューがマイナスになった場合、その相応額を行政が補助金で負担する。
また、浄化後の取引価格が顕著に上回った場合は、逆に費用返還請求できる制度となって
いる。
行政契約のメリットとして、行政手続きリスクの減少と手続きの迅速化があげられる。
浄化計画で定められる事項は以下のとおりであり、浄化方法、費用だけでなく、都市計画、
建築、水質保全、公害防止など都市開発に伴う関連許認可項目が網羅的に含まれている。
【タイプ別リスク設定の要因】
・ リスク評価の概要
・ 浄化対象用地の旧来そして将来の用途
・ 浄化目標
・ 費用見積り、資金計画
・ 浄化目標の達成に必要な除去、隔離、制限、自己管理措置 等
・ 浄化、品質保証のモニタリングコンセプト・一連の手続きに要する期間 等
(2)用途別基準の設定
ドイツでは詳細調査や浄化対策の必要性の判断を行うために、用途別基準が設定されてい
る。一度決められた土地利用計画は将来変わることは少ないと固定的にとらえられているた
め、経済合理性のある用途別基準が重みを持って用いられている。
調査値は、用途別汚染物質別に設定されているが、対策値はダイオキシン/フランのみし
か設定されていない。対策値は地域の特殊性を考慮して設定することが基本となっている。
【用途の分類】
・ 子供の遊び場
・ 住宅地域
・ 公園・レジャー施設
・ 工業、産業用地
4.2.4 制度的管理
ドイツでは、市町村が強力な都市計画決定権限を有しており、都市計画制度が土地利用用
途を厳格に管理している。F―プランといわれる行政内部の長期的な土地利用計画とB―プラ
ンといわれる私権を制限する強制力のある地区詳細計画があるが、計画策定に当たっては、
健康的な居住・就労環境の確保が重要な配慮事項とされている。各土壌汚染サイトの浄化レ
ベルは、開発用途等を総合的に勘案した上で個別に作成される浄化計画によって決められる
ため、都市計画と連結している。
また、浄化修復後の浄化水準チェックのためのモニタリングの方針を浄化計画に定める事
項としており、制度的管理においてモニタリングが重要な位置づけにある。
土壌汚染対策の流れは図4.2.2 に示すとおりであり、以下の点に特色がある。
・ 土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動しているため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしていること
・ リスク評価の段階で用途別の基準値を用いていること
・ 浄化とモニタリングの段階では目標が一律に定められておらず、それぞれのサイト毎に
浄化目標と浄化計画を定める浄化契約を自治体と結んで、対策及びモニタリングが実施さ
れていること
図4.2.2 土壌汚染対策の流れ図
4.2.5 公的関与
ブラウンフィールドの再開発において、採算がとりにくく民間が手を出しにくい土地に対し
ては官主導の色彩が濃くなり、自治体が基本的に公費で土壌汚染対策を実施して民間投資を誘
発して再開発を行い、開発後に得た開発利益を官民で分けている。フランクフルト西港開発の
事例では、市が土壌汚染を除去して用地をデベロッパーに売却し、開発・販売・分譲により得
た開発利益を市とデベロッパーとで折半する契約となっている。また、ノルトホルン再開発事
業の事例では、相当深刻な土壌汚染があって開発計画は一時頓挫していたが、市が様々な工夫
によって浄化対策を行って民間投資を呼び込んでいる。誘発された民間投資が大きいというこ
とで、市による公費投入が正当化されている。
(出所) Umweltbundesamt 資料、Osnabrueck 市資料より作成
5.土壌汚染地における土地の有効利用促進等に向けた課題
2.2でも述べたように、土壌汚染問題に対する一般的理解が不足していることから、我が国
においては土壌汚染に関する情報は秘匿されがちであり、容易に公にはならず、一般社会では土
壌汚染が特別なものだと思われている。その結果として、土壌汚染が公表された場合には、報道
等でことさら大きく取り上げられ、それが仮に軽微であっても、社会的には過剰反応しがちであ
る。また、この現象により土地所有者などは公表を拒むこととなり、結果的に悪循環となってい
る。
しかしながら、我が国は火山国である事から、重金属の自然含有レベルは高く、時に環境基準
を超過する土壌があることや、現在では汚染責任的には容易に対処のしようがない過去の含有レ
ベルの高い臨海の埋立地の土壌などの存在は、決して特別なものではない。それらの土地を健康
リスクの観点から見た場合、多くは他のリスクと比較して過剰反応するほどの大きなものでなく、
対応は充分可能なレベルであると考えられる。
土壌汚染が社会問題化するのは、土壌汚染自体が新しい概念であり、それらを大きな問題とし
ていない考え方や商習慣であった土地利用や土地取引への仕組みが充分に対応しきれていないこ
とによる。すなわち、対象とする物質は工場内等で管理されてきた事に対して一般的には積極的
にオープンにされていなかったにもかかわらず、その情報を求める必要性のある土地利用や土地
取引とのやりとりにまだ大きなギャップがあるまま、社会が動いてしまっているためである。
以上のような現象は、我が国よりも早くから土壌汚染の概念を導入してきた諸外国においても
見られており、それぞれの国の法令や、都市計画などの仕組みの中で対処されてきた事実も、本
年度の検討で明らかになった。特に安易に土壌汚染を放置することなく積極的に管理を行ってい
く取り組みはブラウンフィールドの対処法に関して多くの示唆があった。
現在我が国で起こっているギャップを埋めるためには、海外の取り組みも参考にしながら、単
なる規制ではなく、国民が土壌汚染の実態を認識した上で、土壌汚染の問題に対して適切な対応
をし、土地取引における問題の解消と我が国なりの法令、仕組みや国民性に適応した合理的な土
地利用を促進する必要がある。
5.1 更なる実態・影響の把握
土壌汚染に関する情報については、土壌汚染対策法が、民間の事業者が自主的に行った調査
結果の届け出を義務づけていないことに加え、自治体によって、自主調査結果についても届
け出を義務づけた上で公開するところ、できるだけ届け出るよう指導するところ、そもそも
届け出を義務づけていないところなど、そういった自主調査結果に対する取扱いが異なるこ
とから、個別の土壌汚染サイトに関する情報(調査、対策の状況やその所在地等)は、なか
なか公にならない現状がある。
土壌汚染に係る施策の必要性等を検討するためには、土壌汚染が土地取引や再開発等の支障
となっている事例を当該事例における土壌汚染の管理の実態と併せて可能な限り多く把握
し、その原因等を分析することが必要である。しかし、現時点ではそのような事例を十分に
把握しているとは言い難いことから、今後も企業や地方公共団体等へのヒアリングや調査等
を積み重ねていく必要がある。特に、どうしようもなく動かなくなった土地は商取引の場か
ら外れることにより非常に顕在化されにくいという意見が多く、5.2以下に掲げる課題を
検討し、次のステップに進むための前提としても、さらなる情報収集が必要である。
5.2 土壌汚染情報のデータベース化
5.2.1 土壌汚染情報データベースの構築
前述したとおり、基本的な土壌汚染情報が不在又はアクセス困難であるため、マンション購
入後に土壌汚染が発覚し問題となったり、再開発計画を着手後に見直さざるを得なくなる等
の支障が生じている。しかし、土壌汚染情報は、土壌汚染地の周辺住民や購入者にとっても
利害関係を有するという意味では、土地の安全性に関する情報として公益的な側面を有する
ものであるから、広く情報を共有することを検討すべきである。
この点米国では、4.1.2で述べたように、多くの州が自ら情報を収集したり、届け出や
問い合わせがあった情報を元にして、土壌汚染情報のデータベースを作成し、インターネッ
トで公開している。
これを踏まえわが国でも、全国的な土壌汚染情報をデータベース化し、インターネット等に
よりその時点の状況を誰もが閲覧できる仕組みが存在すれば、土地取引の円滑化や浄化措置
の促進・早期化等に資することになるとも考えられる。
ただし、こういったデータベースを構築・公表する場合、そもそも情報の入手手段が限られ
ており、また、情報の正確性に細心の注意を図る必要があることから、引き続き、情報の入
手源や入手方法について検討すると共に、その情報の元となる調査の信頼性及び正確性をい
かに担保するかという点や万が一公表した情報が誤っていた場合に、当該データベース作成
者の責任の射程及び当該情報を利用した結果他者に危害を与えてしまった者の責任の射程に
ついても併せて検討しておく必要がある。
なお、土壌汚染情報データベースの一類型として、浄化が完了したサイトに関し、当該サイ
トの土質や浄化が完了した旨を公表するようなデータベースを構築することも、土地取引の
円滑化等に資すると考えられることから、こうした点についても検討する必要がある。
5.2.2 土壌汚染要調査マップの作成
しかし、わが国においては、5.2.1で述べたように情報の収集方法等を検討しなければ
ならず、土壌汚染情報データベースの構築はすぐには開始できない。
この点ドイツにおいては、4.2.2で述べたように、土壌汚染が存在する結果開発がスト
ップしているサイトに関する情報のみならず、産業跡地である等の理由により土壌汚染が存
在する恐れがあるサイトに関する情報を収集し、地図上に落とし込んで公表している。
そこでわが国においても、個別サイトを対象にしたデータベースを構築するための前提とし
て、公的なリーダーシップのもとにフェーズ?程度の地歴調査を行ったうえで、過去に工場
が立地している等の理由により、土壌汚染されているおそれが高いサイトや地区を地図上に
記載した、「土壌汚染要調査マップ」をリスクアセスメント手法を活用しながらひとまず作
成することも有効であると考えられる。
「土壌汚染要調査マップ」の作成により土壌汚染要調査情報が世の中に浸透すれば、土壌汚
染に関する情報を公開することに抵抗を感じにくい土壌の醸成につながり、土地取引・土地
利用における土壌汚染の存在を特別視しないで行えることが期待される。結果として、比較
的スムーズに土壌汚染情報データベースが世の中に受け入れられ、より効率的な土壌汚染へ
の対応が可能になるものと考えられる。
5.2.3 自然由来の土壌汚染データベースの構築
自然由来の土壌汚染については、地質的に一定の地域内に幅広く分布する等の事情により、
その地域固有の特性と考えて対応する必要がある。すなわち、仮に掘削除去による完全浄化
をするとしても、どこまで掘っても汚染土壌が出てきてきりがないという場合がありうる。
したがって、対策をすべき土地とそうではない土地の線引きを可能にするため、自然由来の
土壌汚染についてデータベースを構築することは、有用であると考えられる。またこれによ
り、汚染土壌による地下水への影響や残土の処理方法等を調査、検討することも可能になる。
なお、自然由来の土壌汚染は、汚染原因者がいないことから、いわゆる「汚染者負担の原則」
により浄化費用等を負担させることは困難であるが、情報の公開によって影響を受ける関係
者も少ないことが想定されるため、自然由来の土壌汚染データベースの構築・公開に対する
抵抗感は少ないものと思われる。
しかし、自然由来の土壌汚染については、前述したようにある地域内の土地全体に当てはま
る特性であることから、個別サイトごとの状況を考慮に入れれば足りる一般の土壌汚染の場
合とは異なり、面的に土壌汚染の状況を把握する必要がある。
こうした点からすると、自然由来の土壌汚染に関する情報を収集するためには一般の土壌汚
染の場合とは異なった方法が必要であると考えられることから、引き続き検討をしていく必
要がある。
5.3 公的支援の必要性
米国等においては、土地取引の活発化や地域の活性化が図られると期待される場合には、土
壌汚染地に対し、公的主体が浄化費用の一部を補助し、また、土壌汚染地について浄化を開
始又は完了したような場合には固定資産税の軽減を行う等の財政的支援を行っている。
一方わが国においては、土壌汚染が土地取引や再開発やまちづくりに影響を与えていると考
えられる具体的局面として次の場合が挙げられる。
・ 一般的に、大都市部においては、地価が高いため対策費を拠出することが可能であり、
現時点では土壌汚染が土地取引や再開発の支障となっている事例は多くないようである
が、地方部においては対策費の負担が大きければ土地取引や再開発が断念され、地域活性
化を阻害するおそれがある。
・ 小規模事業所等の場合、土地所有者に資力がないことが多いため、調査及び対策が困難
となる結果、土地取引や再開発に支障が生じるおそれがある。
土壌汚染においては、原因者負担が原則ではあるが、原因者に資力が無い場合や原因者が浄
化しただけでは十分な開発等が困難な場合であって、なおかつ、当該土地を活用して地域活
性化等の施策を講ずる必要がある場合には、上記のような局面について、米国等の例を参考
に、補助金、公的資金を投入した基金、税制優遇、公的主体による浄化措置等を検討するこ
とも考えられる。しかしながら、本研究会では具体事例の収集が十分にできず、具体的な検
討には至らなかったところである。
今後検討する前提として、上記に掲げるようなケースごとの実態を十分に把握・分析した上
で、公的支援の公益性及び必要性について検証・検討し、問題点を明確化するとともに、背
景となる事情や制度が我が国と異なることに留意しつつ諸外国の事例を大いに参考にすべき
である。諸外国の事例を検討するに際しては、公的資金の投入等により浄化をした結果とし
ての雇用創出の程度や税収増の割合といった当該施策の効果についても分析を加え、より効
果的なものを参考にすることが望ましい。
なお、地域活性化等の観点から公的資金の投入が難しい場合であっても、地域住民に健康被
害が生じている場合等は、別の観点から検討をしていくことが必要である。
5.4 サクセスモデルの構築
5.4.1 サクセスモデルの構築
2.2.2で述べたように、現在、土壌汚染を浄化する際には、掘削除去による完全浄化が
ほとんどである。掘削除去には莫大な費用がかかることから、特に地方部においては、都市
部と比べて、掘削除去費用が地価を超えてしまうことも往々にしてあり得、結果として土壌
汚染の存在する土地が開発、利用されずに放置されてしまうという事態がありうる。
そこで、地方部においても土壌汚染が存在する土地の有効活用が少しでも図られるよう、土
壌汚染が実際に存在する土地を取り上げ、原則として掘削除去以外の浄化措置を行うと共に
その後の土地利用の計画を策定した上で、その成功要因等を分析・研究するという「サクセ
スモデル」を構築・公開し、その構築が一定程度完了した時点で当該モデルを「ひな型」と
してまとめ、公表することが、土壌汚染地の有効活用のための現実的な有効策となり得ると
考えられる。
この際、例えば、昔は工場等が集積していたが今後は住宅地・商業地として再開発の可能性
が高い一定の駅裏等を対象に、調査、データベースの整備・公開、非完全浄化を含めた対策
等の一連の対応を実験的に行うことの必要性や実現可能性について検討する必要がある。
なお、掘削除去以外の浄化方法を選択した上で再開発等を行った海外の事例について研究
し、場合によってはその事例自体を「サクセスモデル」の参考として提示することもあって
良いと考えられる。
5.4.2 官民の連携
なお、「サクセスモデル」の構築に当たっては、土地の開発、建築、浄化等を行う民間事業
者と土地利用の計画を策定する公共主体がそれぞれバラバラに取り組むのではなく、計画の
段階から実際に浄化した上で開発する段階、さらには土地利用の状況をモニタリングする段
階に至るまで官民一体となって両者が連携、協働することが必要である。
その際、浄化方法と土地利用の方法がどのように対応できるか等、民間業者と公的主体のそ
れぞれがノウハウを蓄積させるとともに、そのために必要な人材を育成していく必要がある。
5.5 資産評価の一層の適正化
時価会計への一本化や今後の資産除去債務の導入等社会経済情勢の変化に伴い、不動産の経
済的価値を正確に評価することが一層求められている。
このためには、土壌汚染の専門業者が行う調査の標準化とそれを通じた専門業者の標準化を
進める必要がある。これにより、土壌汚染地の資産評価の適正化と、さらには、土壌汚染地
に係る安全で円滑な利用や取引が促進される。
一般的に不動産鑑定士は、土壌汚染について専門の業者と同じレベルの知識は有していない
ため、土壌汚染地に係る鑑定評価においては、専門の業者が作成したER の活用が重要となる。
また、不動産鑑定の実務面においても、運用指針の策定や研修、さらなる研究・検討が行わ
れているところではあるが、社会経済情勢の変化に対応し得るよう、引き続き不動産鑑定士
が土壌汚染状況の確認範囲等を明確化し鑑定評価に適切に反映するステップについて検討を
深めていく必要がある。あわせて、様々な汚染状況や対策方法に応じた評価を一層客観的に
行うことを求められることが想定され、スティグマについての評価方法や、掘削除去以外の
措置を前提とした鑑定評価の方法についてもさらに検討する必要がある。
5.6 その他の有効利用促進策
5.6.1 信託、ファンド、保険等のリスク軽減策
なお、土壌汚染リスクの適切な移転・軽減を図る方策として、限定責任信託、土壌汚染地
を買い取った上で浄化するファンド、適切な保険料による保険商品等の活用が考えられる
が、土壌汚染の実態を把握するための十分な調査が行われていないことなどから、いずれも
現時点では具体的な提案をし得る検討状況にはない。しかしながら、いずれも重要なツール
であり、今後リスク評価が進み、具体的な方策を検討しうると考えられることから、今後も
引き続き市場における状況を注視しつつ、必要に応じ活用方策を検討する価値がある。
5.6.2 土壌汚染の正確な知識の周知と土地取引の不正防止
欧米と異なり、我が国では、例えば工業用地から住宅地への用途変更が容易であることか
ら、少なくともその機会を捉えた土壌汚染状況の確認を行うことが重要である。また、土壌
汚染の可能性がある土地について、土地取引が行われる場合には、必要な情報が新たな所有
者に十分伝達されない恐れがある。さらに、土壌汚染に関わる不公正な土地取引が散見され
るところである。
ここで、このような用途変更や土地取引に際して、土地所有者、開発業者、建設業者等の
関係者、さらにはこれに関係する行政担当者等が土壌汚染について必要な知識を有していれ
ば、必要に応じて調査その他の対策を講じることが可能となることから、これらの関係者に
対し、同業者の会合や必要に応じた講習等を通じ、土壌汚染についての正確な知識を周知す
るとともに、土地取引に関する不正の防止に努めていくことが必要である。
また、5.4.2で述べたような官民の連携を進めていく前提として、官の側も土壌汚染
について必要な知識をもつことが必要である。そこで、自治体の環境部局のみならず、建築
部局、都市開発部局といった関係部署においても、土壌汚染が土地取引やまちづくり等を行
う際に大きな阻害要因となっている旨を認識した上で、土壌汚染問題に適切な対応ができ、
ひいては民間に対しリーダーリップを発揮出来るよう、自治体内部で一丸となって取り組む
態勢づくりが必要である。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030404/02.pdf
平成20 年4 月
国土交通省土地・水資源局 土地政策課土地市場企画室
中間とりまとめのポイント
土壌汚染が実際に存在する土地で、原則として掘削除去以外の浄化措置を行うとともにその後の土地利用の計画を策定した上で、その成功要因等を分析・研究するという「サクセスモデル」を構築・公開することが、土壌汚染地を有効活用するための有効策になりうる。
土壌汚染地の資産評価の適正化と土壌汚染地に係る安全かつ円滑な利用や取引を促進するため、土壌汚染の専門業者が行う調査の標準化とそれを通じた専門業者の標準化を進める必要がある。
不動産鑑定の実務面では運用指針の策定や研修等が行われているが、社会経済情勢の変化に対応しうるよう、引き続き不動産鑑定士が行うべき土壌汚染状況の確認範囲等を明確化し、鑑定評価に適切に反映するステップについて検討を深めていく必要がある。
また、スティグマについての評価方法や、掘削除去以外の措置を前提とした鑑定評価方法についてもさらに検討する必要がある。
個別の土壌汚染サイトに関する情報はなかなか公にならない現状があることから、下記の課題を検討するための前提として今後も企業や地方公共団体等へのヒアリングや調査等による情報収集が必要である。
更なる実態・状況の把握
土壌汚染情報は、土壌汚染地の近隣住民等も利害関係を有する情報であるから、全国的な土壌汚染情報をデータベース化し、広く情報を共有することができれば、土地取引の円滑化や浄化措置の促進及び早期化等に資することになる。
しかし、我が国においては土壌汚染情報の収集が十分でなく、情報の収集方法等も検討しなければならないため、すぐにはそういったデータベースの作成に取りかかることは困難であることから、公的なリーダーシップの元にフェーズ?程度の地歴調査を行った上で、過去に工場が立地している等の理由により土壌汚染の可能性が高いサイトや地区を地図上に記載した「土壌汚染要調査マップ」をひとまず作成することも有効と考えられる。
また、自然由来の土壌汚染についてデータベースを作成することも検討する必要がある。
土壌汚染情報のデータベース化
土壌汚染においては原因者負担が原則ではあるが、原因者に資力が無い場合や原因者が浄化しただけでは十分な開発が困難な場合であって、当該土地を活用して地域活性化等の施策を講じる必要が有る場合には、補助金や基金の創設、税制優遇等について検討することも考えられるので、実態把握の上、更なる検討・検証を進める。
公的支援の必要性
サクセスモデルの構築
資産評価の一層の適正化
その他の有効利用促進策
今後も市場の動向を注視しつつ、信託やファンド、保険等の活用については引き続き検討を進める必要がある。
また、土地所有者、開発業者、建設業者、さらには行政担当者等の関係者が土壌汚染について必要な知識を有していれば、必要に応じて調査等の対策を講じることが可能になるため、同業者の会合や講習等を通じ正確な知識を周知するとともに、土地取引に関する不正の防止に努める必要がある。
さらに、官民の連携を進めるため、自治体の環境部局のみならず、建築部局や都市開発部局といった関係部署においても土壌汚染が土地取引やまちづくり等の大きな阻害要因となっている旨を認識し、自治体内部で一丸となって取り組む態勢づくりが必要である。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030404/03.pdf
目 次
1.はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.土壌汚染の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1 土壌汚染の現状認識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1.1 現状認識
2.1.2 土壌汚染の可能性のある土地
2.2 土壌汚染の調査・対策の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2.2.1 土壌汚染対策法に基づく調査・対策の実施状況
2.2.2 条例・要綱等に基づく土壌汚染の調査・対策の実施状況
2.2.3 民間の自主的な調査・対策の実施状況
2.3 ヒアリング等による土壌汚染の実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2.3.1 土壌汚染の発生状況と対策
2.3.2 デベロッパー
2.3.3 ハウスメーカー
2.3.4 総合建設会社
2.3.5 外資系不動産ファンド
2.3.6 産業用不動産特化型REIT 運用会社
2.3.7 大規模土地所有企業
2.3.8 地方公共団体
3.土壌汚染に係る現行制度と諸問題・取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3.1 土壌汚染の調査と情報収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3.1.1 土壌汚染調査 /3.1.2 情報収集と活用
3.2 土壌汚染の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
3.2.1 用途別基準 /3.2.2 自然由来の汚染
3.3 土壌汚染の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
3.3.1 責任負担者
3.3.2 法令上の要求措置と実態の乖離
3.4 土壌汚染の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
3.5 土壌汚染がある土地取引のリスクと財政的支援・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
3.5.1 土壌汚染に係るリスクとリスク分担
3.5.2 低利融資等
3.5.3 保険
3.5.4 保証
3.5.5 買取り
3.5.6 信託
3.6 土壌汚染地の資産評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
3.6.1 土地の資産評価の枠組み
3.6.2 不動産鑑定評価の実務における土壌汚染地評価の基本的考え方
3.6.3 スティグマの評価
3.6.4 エンジニアリングレポートの重要性
3.6.5 課税関係
4.諸外国の制度・取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
4.1 米国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
4.1.1 スーパーファンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ
4.1.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み /4.1.3 浄化修復目標の設定
4.1.4 制度的管理
4.1.5 財政支援施策
4.1.6 環境負債免除制度
4.2 ドイツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
4.2.1 連邦土壌保護法制定の経緯
4.2.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
4.2.3 浄化修復目標の設定
4.2.4 制度的管理
4.2.5 公的関与
5.土壌汚染地における土地の有効利用促進等に向けた課題・・・・・・・・・・・・・・・ 63
5.1 更なる実態・影響の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
5.2 土壌汚染情報のデータベース化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
5.2.1 土壌汚染情報データベースの構築
5.2.2 土壌汚染要調査マップの作成
5.2.3 自然由来の土壌汚染データベースの構築
5.3 公的支援の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
5.4 サクセスモデルの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
5.4.1 サクセスモデルの構築 /5.4.2 官民の連携
5.5 資産評価の一層の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
5.6 その他の有効利用促進策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
5.6.1 信託、ファンド、保険等のリスク軽減策
5.6.2 土壌汚染の正確な知識の周知と土地取引の不正防止
1 はじめに
日本の限られた国土において、土地は国民共通の財産であり、土地の適切かつ有効な利用を
実現するためには、土地を有効利用しようとする者に対し円滑に土地を移転しやすくすること
を通じた土地取引の活性化を図ることが必要である。土地取引が円滑に行われることは、国土
の適正な利用につながると考えられる。
土壌汚染問題については、土壌汚染対策法施行後注目が集まっているところであり、土地取
引市場においても、そのリスクが近年強く意識されるようになっている。国土交通省では、土
壌汚染対策法施行以前の平成14 年10 月に「宅地公共用地に関する土壌汚染対策研究会」を設
置し、翌年6 月に土地取引の安全性と円滑化の確保を目的とした土地売買契約に当たっての留
意事項や、土地建物取引業者の留意事項に関する基本的な事項等を体系的にとりまとめ、公表
してきたところである。
しかしながら、土壌汚染の判明した土地については、依然として土地取引が忌避され、土地
の有効利用や再開発、まちづくりの観点から支障が生じる事態になっている。土壌汚染の問題
は、ともすれば土地所有者が汚染事実の公表に消極的となるので、土地の有効利用にとって、
どれだけ重要な問題であるかということが社会的に十分理解されていないのではないかという
指摘もある。実態として、土壌汚染が土地取引にどれだけの影響を与え、取引を阻害している
のかを、具体的なケースを含めて、調査、把握することが必要である。
さらには、土壌汚染土地の取引に係る様々な事項について、具体的な課題を抽出・整理し、
具体的な方策の検討につなげていくことが重要である。日本では、関係者が土壌汚染リスクに
敏感となり、法的には必ずしも要求されていない土壌汚染の完全除去を実施するケースが多く、
社会的コストの増加につながっている。また、土壌汚染土地の調査については、公的に利用可
能な情報基盤や調査・評価の枠組みに、整備改善の可能性があるという指摘が多い。土壌汚染
土地の取引に係るリスク分担を整理し、保険等のリスクヘッジのスキームを充実していくこと
が、土壌汚染土地の取引活性化につながるという意見もある。
一方、コンバージェンスの一環として、減損会計の導入等の時価会計への一本化等も進めら
れており、土壌汚染地における鑑定評価の重要性が高まるなど、土地政策の観点から土壌汚染
について検討することが強く求められている。
上記の問題意識を踏まえ、土地取引の円滑化による土地の有効利用促進等の観点から、土壌
汚染土地について現状と課題を整理し、具体的な方策につながる検討を行うことを目的として、
本研究会が設置された。本研究会においては、土壌汚染土地の取引に関係する民間企業や地方
自治体へのヒアリング、米国とドイツの事例の研究を行うと共に、本研究会委員及び土壌汚染
に関する専門的な知識を有する実務者からの発表を受けた議論を行い、今後、土壌汚染地にお
ける土地の有効利用方策を検討する際の課題を整理したところである。
2.土壌汚染の現状
2.1 土壌汚染の現状認識
2.1.1 現状認識
土壌汚染の現状に関して、土壌汚染対策法や各自治体の条例・要綱等に基づく調査・対策
の報告状況の他に、民間の自主的な実施状況に関するアンケート調査等の既存資料がある。
しかしながら、土地所有者等にとって、土壌汚染の判明は新たな調査・対策費用が必要と
なったり、近隣地域との軋轢が発生するおそれが高まったり、また土地資産評価の減価要因
になりうることなどから、自ら公表しづらいという問題を抱えているため、我が国では秘匿
されがちで、個別サイトに関する土壌汚染情報を入手することはきわめて困難な状況にある。
個別サイトに関する汚染情報を把握するためには、土壌汚染の土地を取り扱うデベロッパ
ーや不動産ファンド、このような土地を所有している企業、土壌汚染に関する相談・指導を
行う地方公共団体等に個別にヒアリング等を実施することが現状では有効と考えられる。
2.1.2 土壌汚染の可能性のある土地
? 土壌汚染の発生原因
土壌汚染の代表的な発生原因として、以下の4 つがある。
・工場などで使用していた有害物質が、不適切な取扱いや老朽化等による施設、設備の破損により漏えい、流出、飛散して土壌に浸透するという事業活動が原因の汚染
・産業廃棄物が埋立処分された土地で発生するという廃棄物が原因の汚染
・事故や災害により施設、設備が故障、破損等することにより有害物質が漏えい、流出、飛散等して土壌に浸透するという、事故や災害が起因の汚染
・重金属を含む岩石や地層が風化、流出して河川や平野部、海岸に堆積した自然の土壌中に存在する自然由来の汚染
? 工場等産業用地の土壌汚染
土壌汚染は日本の産業発展に伴って発生した過去の大きな負の遺産であり、水質汚濁防止
法による規制が行われる以前は、現在では汚染物質といわれる物質の一部も合法的に土壌に
浸透させることが可能であった。現在、有害物質使用特定施設として該当する土地は全国で
27,000 箇所といわれており、またカソリンスタンドやクリーニング事業等により土壌が汚染
されている可能性のある箇所は30 万箇所を越えるといわれている。
? 廃棄物処分地の土壌汚染
過去に廃棄物で埋め立てられた土地において、土壌汚染が見つかっている。
? 幹線道路沿道の土壌汚染
幹線道路沿道の土地では、自動車からの排気ガスに含まれている鉛などによる汚染が指摘
されており、土壌汚染は日常の生活空間のまわりで広く発生していると考えられる。
? 臨海部等埋立造成地の土壌汚染
過去に埋め立てられた臨海部の土地においては、砒素などが含まれる河川や浅海域の底質
の浚渫土砂等が埋め立てに使われていることが多いことから、土壌汚染の可能性が指摘され
ている。
臨海部以外の低・平地部の埋立造成地においても、持ち込まれた土が原因の汚染が見つか
っている。
なお、当該地域以外から持ち込まれた盛土材や廃棄物により埋立造成された場合には、土
壌汚染対策法の対象となる。
? 自然的原因の土壌汚染
自然に存在する岩石、地層に含まれる重金属が風化や水の流出に伴って拡散し、低・平地
部に自然堆積した場合や、これらを含む河床や海底での堆積土砂などにより埋め立てられた
場合は、自然的原因の土壌汚染と見なされる。自然的原因の可能性のある物質として、砒素、
鉛、フッ素、ホウ素、水銀、カドミウム、セレン、六価クロムなどがある。
自然的原因による高濃度の特定有害物質を含む土壌又は水底土砂が、周辺地域において盛
土や海面を埋め立てることにより造成された土地は、自然的原因により指定基準を超過した
ものとし、土壌汚染対策法の対象とはならないが、当該地域以外の土地から持ち込まれ、専
ら自然的原因により指定基準を超過する土壌は、土壌汚染対策法の対象となり、土壌を持ち
込んだ者が汚染原因者と見なされる。持ち込んだものが不明の場合は土地所有者が必要に応
じて措置を行うことになっている。
都市部においては、本来の河川堆積物による土壌汚染に、過去からの都市活動により河川
域の汚染原因者が不特定多数で特定できない人為的な汚染が混在しているという問題がある。
自然的原因による土壌汚染を判断することは可能であるが、人為的汚染と混在した場合に
それを区分することはかなり作業が必要となる。
その区分を把握するためには、自然的汚染は含有量が一定の範囲内にあり、広域で観測され
て局在性がないなどの特色を持っているこ
とから、広域的な視点からバックグラウンド濃度などのデータを収集して分布特性等を見て
判断していくことが必要である。
2.2 土壌汚染の調査・対策の実施状況
2.2.1 土壌汚染対策法に基づく調査・対策の実施状況
土壌汚染対策法が平成15 年2 月から施行されて以後の4 年間での法適用案件は622 件で
ある。このうち、土壌汚染の指定区域に指定されたものは172 件(28%)あり、措置済みが
91 件(15%)、措置実施中・検討中が69 件(11%)あり、未処置はわずかに12 件(2%)
である。
具体的に実施された措置としては、掘削除去が最も多く76%を占め、次いで原位置浄化が
18%、舗装措置が4%、立入禁止措置が3%の順である。
図2.2.1 指定区域の状況(平成15 年2 月15 日〜平成19 年2 月14 日)
(資料:環境省「平成19 年度版環境白書・循環型社会白書」)
2.2.2 条例・要綱等に基づく土壌汚染の調査・対策の実施状況
土壌汚染対策法が施行されて以降、多くの地方公共団体で条例や要綱等が改正され、その
中に土壌汚染に関する調査・対策の実施義務や届出措置が盛り込まれた。
都道府県調べによる年度別の土壌汚染調査件数及び判明件数は図2.2.2 に示すとおりであ
り、平成15 年2 月に土壌汚染対策法が施行されて以来、土壌汚染調査件数及び判明件数は大
きく増加している。
東京都条例に基づく土壌汚染調査の対象は、
・工場、指定作業所を設置して有害物質を取り扱い、又は取り扱った者、
・3,000 ?以上の敷地内で土地の切り盛り、掘削等土地の改変を行う者である。
また、新潟県では、平成16 年9 月から施行された新潟県生活環境の保全等に関する条例に
基づき有害物質を扱う事業所については5 年に1 回土壌汚染調査の実施を義務付けているが、
まだ届出件数はわずかである。
図2.2.2 年度別土壌汚染判明件数
(資料:環境省水・大気環境局「平成16 年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」)
2.2.3 民間の自主的な調査・対策の実施状況
? 民間の自主的な調査・対策の実施件数の増加傾向
土壌汚染の調査・対策は、健康被害を防止することよりも、むしろ土地資産価値の劣化を
防止する目的で実施されることが多い。土壌汚染対策法や条例・要綱によらない民間の自主
的な調査・対策の実施件数が増加してきており、(社)土壌環境センターの会員企業に対する
アンケート調査結果によれば、土壌汚染の調査及び対策の実施件数は平成17 年度で10,812
件に及んでおり、このうち土壌汚染調査の約8 割の件数が民間の自主的なものとなっている。
土壌汚染対策法や条例・要綱に基づく調査は約2 割である。
図2.2.3 土壌汚染調査の対象
? 土地取引を契機とした自主的な調査・対策が多い
調査及び対策の実施件数の多くは土地取引を契機としたものとなっており、土地取引に際
して土壌汚染の存在の有無の確認、存在する場合の調査・対策を求めるケースが増えている
ことがうかがえる。
図2.2.4 土壌汚染調査・対策の受託件数及び受託金額の推移
表2.2.1 土壌汚染調査・対策の契機となった理由
図2.2.5 自主調査を行う契機となった理由
図2.2.6 自主対策を行う契機となった理由
2.3 ヒアリング等による土壌汚染の実態
デベロッパー3 社、ハウスメーカー1 社、総合建設会社1 社、外資系不動産ファンド1 社、
産業用不動産特化型REIT 運用会社2 社、大規模土地所有企業3 社、地方公共団体6 団体に対
するヒアリング調査等から判明した土壌汚染の実態は、以下に示すとおりである。
2.3.1 土壌汚染の発生状況と対策
? 土壌汚染の発生状況
土壌汚染は、古くから操業を行っていた工場跡地、操業中の工場用地、市街地内のメッキ
工場やクリーニング工場、ガソリンスタンド、臨海部の埋立地、廃棄物により埋め立てられ
た土地、自然由来と思われる商業地等において判明している。
? 大都市と地方との比較
ア.大都市における土壌汚染と対策
東京のような大都市内においては、土地取引や都市開発の際に土壌汚染が判明しても、
土地価格が高いことから、掘削除去などの浄化対策費用を吸収可能であることから、ブラ
ウンフィールド化している事例はほとんど聞かれなかった。
マンション開発などの際には、土地所有者による掘削除去による対策がほとんどである。
なお、大都市内において、土地履歴調査で汚染のおそれのない土地において工事中の段
階で、搬出土調査等により汚染が判明するケースが出てきている。こうした場合は、売主
と買主との間で訴訟になるケースも見られた。
イ.地方における土壌汚染と対策
新潟市や盛岡市などの地方中核都市の市内においては、最近マンション開発などの際の
調査で土壌汚染が判明したケースが見られるが、その場合は主に掘削除去による浄化対策
が実施されており、土地取引や都市開発がストップしたような事例は聞かれなかった。
なお、新潟市内において、マンション開発の際に掘削除去と併せて封じ込め措置による
対策を併せて実施している事例もあり、また住宅以外の商業施設等の立地の場合は封じ込
め措置による対策も行われている。
しかし、それ以外のエリア、又は汚染の程度が広範囲に及んでいる場合は、土地価格に
比して相対的に土壌汚染対策費用が高いことから、汚染拡散防止措置のみを行っている事
例も見られた。こうした場合は、開発を断念したり、土地取引において買主と売主との間
でトラブルになるケースが生じている。
ウ.小規模な事業用地における土壌汚染と対策
地方都市内のメッキ工場やクリーニング用地において土壌汚染が判明した場合に、土地
所有者に対策コストを負担する資金的能力が低いことから、土地取引ができずにそのまま
となっている土地が存在しているケースが見られる。こうした土地では汚染拡散防止程度
の措置が実施されている。
クリーニング工場やメッキ工場などの小規模な事業所の汚染では、対策費用の比率が高
くなり、また資力もないことから、利用促進上のハードルが高くなって、ブラウンフィー
ルド化の懸念が高まっている。
大規模な再開発の中での小規模な土壌汚染の存在については、再開発事業の中で対処す
ることが考えられるが、市街地内で単独で残っている場合は、調査すらされずにそのまま
残されてしまうケースの発生が懸念される。
なお、ガソリンスタンドが廃止又は改修する際に油による土壌汚染が判明したケースが
あるが、系列の大手会社が前面に出て調査・対策を実施しているため、問題は生じていな
い。
? その他
ア.土壌汚染情報の秘匿
今回のヒアリングは、各企業や地方公共団体による土壌汚染問題への取組みを調べるの
みならず、個々のサイトの土壌汚染情報についても把握し、今後の検討に役立てることを
も意図したものだったが、あまり個別のサイトの土壌汚染情報は聞くことができなかった。
イ.土壌汚染が判明した場合の汚染原因者でない土地所有者の困惑
土地所有者が関与していない、いわゆる自然由来、埋立由来、もらい汚染と考えられる
土壌汚染が判明した場合に、とりわけ資金負担能力の低い土地所有者にとっては、対策を
行うことが困難であるため、相当深刻な事態となっている。
ウ.調査実施後に新たな汚染が判明したケースの発生
土地履歴調査を実施して汚染がないと判断して、土地を買収して開発する際に土壌汚染
が新たに判明したケースが生じており、売主と買主との間でトラブルになったり、デベロ
ッパー側に何らかの負担を強いられている。
2.3.2 デベロッパー3社
? 土壌汚染への対応
大手のデベロッパーは、事業用地の取得に際して土壌汚染に対処する独自の調査・判定ル
ールを設けて用地取得の可否を選別している。すべての案件についてフェーズ?調査は必須
としており、土壌汚染の可能性がある場合はフェーズ?調査を実施して、取得の可否を判断
している。
土壌汚染物件の住居系への開発・転売については、原則として掘削除去など完全浄化が可
能なものである場合が多い。但し、物流施設や商業施設への転用のケースでは法令要件を満
たせば、完全浄化でなくても受け入れるケースがある。
土地取得に際しては、自然由来による汚染も含め環境基準超過土壌は完全除去を行うこと
を基本としている。
? 特徴的な事例
ア.大都市内の都市開発可能用地において土壌汚染のため都市開発を断念したケース
大都市内の都市開発が可能な土地は、通常土地価格が高いことから、土壌汚染が判明し
ても掘削除去による対策費を吸収することが可能であるが、土壌汚染が重篤な場合や、土
壌汚染が相当にあると考えられリスク評価できない場合、周辺の状況から対策ができない
場合、また土地所有者が瑕疵担保責任を負わない場合には、開発を断念するケースがある。
イ.工事中の調査で新たな汚染が判明するケース
土地引渡し前の調査では土壌汚染が判明していないが、工事中の調査で汚染が見つかっ
たケースが出てきており、事前調査の信頼性が揺らいでいる。
こうした場合は売主・買主の間で責任の範囲についてトラブルに発展しやすい。瑕疵担
保期間が過ぎた場合や売主が全く知らない場合もあり、事業者側の新たな負担となる。ま
た、追加対策のために事業スケジュールが伸びると、契約期間内の引渡しが困難になる、
金利負担が増大するなどの影響がでる。
? 意見・感想等
ア.土壌汚染問題は地方都市ほど都市開発に影響を与えるため、対策面での工夫が必要
地方都市で、ブラウンフィールドが発生する可能性は高い。地方になればなるほど土地
価格が下がり、その対策費を土地価格で吸収できなくなる。掘削除去以外の封じ込めなど
の対策を模索していくことが必要となる。
札幌市や新潟市での開発事例(分譲マンション開発)では、土壌汚染対策費は土地価格
と同程度となって負担が大きく、掘削除去による対策では採算が合わない事態が生じてい
る。このため、深さ1m まで掘削除去、1m 以深の汚染については封じ込め措置を行って開
発したケースがある。購入者に対しては土壌汚染の調査・対策の状況を十分に説明して了
解を得ている。なお、封じ込め措置による土地価格の減価は行っていない。
イ.土壌汚染処理のための新たな基準づくりについて
現在の土壌汚染の環境基準では対策が過大になりがちで、そこまで浄化処理する必要が
あるのか、疑問の声が聞かれた。土地利用に合わせて、もっと緩やかな基準があってもよ
く、行政側で新たな基準づくりが行われることが望ましい。一般に広く理解が得られ、資
産評価にも影響しないようなものが出来るとよい。
法や条例の改正により新たな項目が環境基準に追加されると既存不適格となってしまう
土地が生じ、新たな対応が求められることになり、このような土地が多いことが指摘された。
ウ.土地取引のリスクを軽減する保険制度について
瑕疵担保保険は、保険料が高いため現在利用されていない。事業者のリスクを軽減でき
るような保険があればよいとする意見や、なくてもよいとする意見があった。
エ.地方や中小の工業等事業者への支援について
土壌汚染問題で身動きのとれないで困っている地方や中小の工業等事業者に対する支援
措置があれば、望ましい。
オ.土壌汚染地を開発する際のインセンティブ
土壌汚染地を開発する場合に、開発者側のリスクを緩和するような措置や自然由来の汚
染など原因者が不明の場合については固定資産税減免などの支援措置があれば、望ましい。
<参考>
(社)不動産協会作成の「マンション開発事業における土壌汚染対策に関する留意事項」
【マンション事業における土壌汚染対策に関する留意事項】(平成14 年11 月(社)不動産協会作成)
(社)不動産協会では、平成14 年11 月に、分譲マンション事業においてデベロッパーとし
てのリスク管理の観点から考え方を示したガイドラインである「マンション事業における土壌汚
染対策に関する留意事項」を定めた。詳細は以下のとおりである。
・ 土地履歴等調査については、売主に詳細な情報の提供を求めるとともに、買主自らも土壌汚
染情報の収集を行う。
・ マンション事業用地の売買契約において、土地履歴等調査で汚染がないことが確実な場合を
除いて、土壌汚染に関する調査を売主の負担と責任において約定し、また汚染が認められない
として引渡しを受けた後に買主の調査で汚染が発見された場合は、売主に対して責任を追及で
きる旨の特約を明確に約定する。
・ マンション事業用地の土壌汚染については、売買契約において浄化処理・汚染拡散防止措置
等を売主の負担と責任において引渡し日までに実施する旨、また引渡し後に買主の調査で汚染
が発見され、買主が浄化等の措置を行った場合についても、その費用並びに損害賠償を売主に
対して請求できる旨を明確に約定する。
・ 土地引渡し後の土壌汚染の発見に備えて、売買契約書には、所有権の移転時期、土壌汚染に
関する瑕疵担保責任及び売主による浄化措置の実施義務等の条項を必ず記載する。
・ 敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を実施した場合は、購入者に対して重要事項説
明書に基づいて正確に説明し、また購入者にその報告書(写)を交付し、併せて管理組合に原
本を引き渡す。
2.3.3 ハウスメーカー1社
? 土壌汚染への対応
大手の開発案件については、独自の調査マニュアルに基づき、すべての案件で土地履歴調
査を実施している。工場についてはすべてリスクありと判断し、また、資材置き場、倉庫、
作業場等についても詳細が不明な場合はリスクありと判断して土壌調査を実施している。
マンション用地では履歴上のリスクの有無にかかわらず全案件でより厳格なリスク評価を
行っており、汚染が判明した場合は原則として掘削除去等の完全浄化を実施している。年に
数件、汚染が重篤な場合や土地価格に見合わない場合として土地取得を断念している。
商業系や駐車場用途の場合で低濃度汚染の場合は、掘削除去以外の封じ込め又はバイオ手
法などによる長期浄化の対策もありうる。
土壌汚染リスクのある土地に対しては、跡地利用に併せて調査及び浄化対策を同時に検討
することにより、最適利用しましょうという提案をし始めている。
なお、汚染があった土地を販売する場合には、完全浄化後であっても重要事項として顧客
に説明を実施している。説明後の顧客の反応は比較的良好であった。汚染の程度が比較的低
濃度で対策も掘削除去とわかりやすい内容であったこと、積極的なリスクコミュニケーショ
ンを実施したこと等から、顧客の理解が得られた。
? 特徴的な事例
ア.建設時に新たな汚染が判明するケース
造成時の盛土や廃棄物埋設による汚染は土地履歴調査では発見することが困難であり、
マンション建設時の搬出残土の調査(残土条例や残土業者の自主調査)で汚染が判明する
事例が増えている。売買契約時に瑕疵担保を定めていても、売主の経済力などの問題で回
収できず、瑕疵担保が効果を発揮しないケースが増えてきている。
イ.施設建設後のモニタリング調査で汚染が判明するケース
特別なケースとして、過去に廃棄物により埋め立てられた土地を商業開発する際に土壌
汚染が判明したため、封じ込め措置を行って施設を建設したが、オープン後のモニタリン
グ調査で汚染地下水の流出が判明したことから、土地所有者が再度流出防止対策を実施し
た事例がある。
2.3.4 総合建設会社1社
土壌汚染を抱える開発案件の最近の情報や相談事例から、土壌汚染に関して以下のような
指摘があった。
? 土壌汚染地に対する土地所有者・土地購入者の意識
土地所有者の意識として、汚染があると買手が見つからないので、売却するためには完全
浄化をせざるをえないが、対策費用が工事費の30%を超えると、売却益が見込めなくなって
売却を断念するケースが多くなり、土地保有を継続して土地利用していくこととなる。
土地購入者としては、汚染がない、又は完全に浄化された土地を購入したい、という意識
が強い。背景として、土地利用上の制約がない、後々の問題を抱えたくない、風評が心配、
再売却時に問題を残したくない、という理由がある。
? 小規模事業所のブラウンフィールド化の懸念
大都市圏では、最近の土地価格の上昇傾向もあって土壌汚染対策費用を捻出できるケース
が大半である。しかし、クリーニング工場やメッキ工場などの小規模な事業所の汚染では、
対策費用の比率が高くなり、また資力もないことから、利用促進上のハードルが高くなって、
ブラウンフィールド化の懸念が高いケースがあるように感じられる。こうした場合では、調
査や対策もされずにそのまま残されてしまうような懸念がある。
? 商業施設や倉庫における封じ込め措置の例
商業施設や倉庫については、封じ込め措置により利用している事例が出てきている。
? 地方都市におけるブラウンフィールド化の事例
地方都市の工場等跡地において売却の際の自主調査で土壌汚染が判明し、土地価格に比し
て汚染対策費用が高額になるため、売却を断念して拡散防止措置のみを行ったうえで、駐車
場等に暫定利用又は放置されている、事例が数例ある。
・ 工場を閉鎖して土地を売却する際の自主調査で土壌汚染が判明しため、重金属による汚染
部分を掘削除去して、地下水汚染のない約半分の土地を売却し、残りの半分は売却を断念し
た事例
・ 工場跡地を購入して一部の土地を売却した後に自主調査により汚染が判明したが、対策費
用が多額になるため拡散防止対策(舗装及び揚水処理)のみを実施したが、新たな土地購入
者を確保できないため、駐車場として暫定利用している事例
・ 工場用地の一部を開発事業者に売却する際の自主調査で重金属汚染が判明したが、土地価
格に比して対策費用が過大になるため、売却を断念して舗装状態のままで利用用途を検討し
ている事例
・ 製油所跡地に公共的施設を誘致する際の自主調査で重金属、VOCs 及び油による広範囲な
土壌汚染が判明したが、土壌汚染対策費用が多額となるため、売却を断念してゴルフ練習場
などとして利用している事例
・ 工場跡地の売却の際の自主調査で重金属及びVOCs による汚染が判明したため、社会的責
任の見地から土地所有者は掘削除去を実施したが、土地の売却はやめて商業施設及び駐車場
として賃貸している事例
2.3.5 外資系不動産ファンド1社
? 土壌汚染への対応
受け入れ基準は厳格で、フェーズ?調査で土壌汚染の可能性が確認されれば、土地購入の
対象としていない。土地購入の対象となる不動産は汚染がない土地である。
今後の事業展開において、土壌汚染地を扱う可能性はあるとしているが、土壌汚染地を扱
う場合にはリスクを定量評価できることが必要であり、技術面のリスク・テイクをするゼネ
コン等の関与が必要である。
? 意見・感想等
フェーズ?調査のコスト低減、確度の向上につながる情報の開示は歓迎する。
2.3.6 産業用不動産特化型REIT 運用会社2社
? 土壌汚染への対応
商業・物流REIT では、汚染リスクが残置する物件を取得するケースもあるようである。
土壌汚染地の取得に関して自主基準に基づいて判断しており、ある社では、
?適切に対策され周囲への影響がないこと、
?将来の汚染対策費が予測可能であること、
?将来売却する場合に資産価値の大幅な下落がないこと、
の3 点を投資対象の要件としている。投資の持ち込み物件には土壌汚染地が多いが、
検討の優先順位は低くなる。
しかし、一方で投資の検討対象として土壌汚染地を避けて通るのは難しい。
? 特徴的な事例
産業用不動産については、産業用地としての利用の継続性が投資対象を選択する基準であ
ることから、掘削除去にこだわる必要はなく、その他の対策も実施可能である。
将来の改築の際に発生する汚染残土処理費用や土壌改良費を見込み、土地価格から減価す
ることで、土地取引を実施している例もある。
? 意見・感想等
ア.汚染情報の開示と活用について
元来REIT では、土壌汚染情報を開示する義務がある。検討対象物件の土壌汚染情報を
得られることは歓迎するが、コストが必要な場合はコスト・パフォーマンスで判断する。
イ.エンジニアリングレポート(ER)の信頼性の確保が必要
特別な資格を有しない者が作成するER に基づいて不動産鑑定士が土地評価を行うこと
には、問題があると思われる。
ウ.埋立由来や原因者が特定できない汚染の場合についての行政側の適切な支援
埋立由来や原因者が特定できない場合は行政側の適切な支援を行う制度の構築が望まし
い。
また、優遇税制、補助金などの制度化に向けての検討を期待する。
エ.政府による用途別基準づくり
土壌汚染地の土地取引についての自主基準は持っているが、政府による用途別の基準が
あることが望ましい。
2.3.7 大規模土地所有企業3社
? 土壌汚染への対応
所有地の土壌汚染については、自主的な調査・対策を実施している。
東京都内の工場跡地を都市開発する場合は、掘削除去による土壌汚染対策を実施している。
住民・マスコミ等風評リスクを恐れる企業も少なくなく、情報開示に必ずしも積極的では
ないという企業がある一方、自らホームページ等で公開に努めている企業もあった。
関西のある企業では、関西圏に広く散在している工場跡地の十数ヶ所で土壌汚染が判明し
たため、土壌汚染のリスク管理措置として、汚染拡散防止、地下水監視などの用地管理強化、
土壌の改善措置(盛土や舗装による表層追加被覆、汚染土壌中心部の掘削除去、土壌ガス吸
引などの原位置浄化)を実施している。
? 特徴的な事例
ア.土壌汚染地の自社利用等をしているケース
土壌汚染地については、掘削除去による浄化措置を実施して用地を売却した場合や、売
却しないで自社利用している場合がある。
後者については、汚染を残した状態では土地を売却できないものの、土壌汚染対策費が
高額になることから、やむをえず研究施設、倉庫、事務所、訓練所等として自社利用して
いる面もある。
関西のある企業が所有する京都市内の工場跡地のような立地条件の良い場所はグループ
会社で都市開発している。この場合も土地は売らずに施設を建設して賃貸している。建物
基礎部分は掘削除去を実施している。
イ.土壌汚染が土地活用を阻害しているケース
立地条件のよくない工場跡地では、土地利用ニーズがあまり期待できないことや土壌汚
染対策費がかかりすぎることがネックとなって土地活用の阻害要因となっていることがあ
る。
? 意見・感想等
ア.埋立地の土壌汚染対策に係る所有者責任について
臨海部の土地は埋立由来と考えられる汚染が必ずあり、土地を購入した所有者がすべて
対策をしなければならないことに対して、疑問を感じる。
イ.原因別、用途別の基準づくりが望まれる
現在の環境基準が厳しすぎるきらいがある。埋立由来や自然由来と思われる汚染、地下
水の直接摂取の可能性が低い汚染に対しては、基準に少し配慮があっても良いのではないか。
ウ.土壌汚染地を開発する際のインセンティブが望まれる
もらい汚染、埋立由来の汚染など土地所有者が原因者でなく、原因者が特定できない汚
染に対しては、対策費用の一部補助や税の減免措置などの支援が望ましい。
地方の土地価格の安い土地の汚染については、土地が売るに売れない厳しい環境にある
と思われるため、このような土地の有効利用を促進するための支援が望ましい。
エ.土壌汚染に対する心理的抵抗感の払拭が必要
土壌汚染に対して過剰反応しすぎる面があり、リスク管理措置でも大丈夫であるという
認識が広まるように努めてほしい。
2.3.8 地方公共団体
(1)岩手県、盛岡市
? 土壌汚染への対応
行政に報告されている土壌汚染については、法や条例に基づくもの以外の民間の自主調査
によって汚染が判明したものが多い。報告のあった件については、法や条例等に基づいて相
談・指導を実施している。なお、地下水汚染が判明した場合は、行政側で周辺の地下水調査
を実施して汚染の拡大の有無を確認している。
開発区域内のクリーニング工場跡地で溶剤漏出による汚染が判明したため、土壌浄化対策
を実施している。また、地下水モニタリングを実施する必要があることから、そのスケジュ
ールが遅延するおそれがある。
? 特徴的な事例
ア.市内のマンション開発を契機とした自主調査で土壌汚染が判明
盛岡市内でマンション開発が進んでおり、開発を契機とした民間の自主調査で土壌汚染
が判明したケースが出てきている。
マンション開発の場合は土地所有者が掘削除去で対処している。
また、かつて商用地として利用され、土地履歴で土壌汚染のおそれの少ない土地を買収
した後に、買主側の自主調査で土壌汚染が判明(盛土造成による汚染の可能性が高い)し
たケースもある。こういった場合、マンション開発のため全量掘削除去したくとも、その
対策費が多額になるため、費用負担の割合をめぐって売主と買主との間で訴訟になるおそ
れが生じている。
イ.油汚染の事例
自動車整備工場による油汚染の事例や灯油流出汚染の事例が報告されている。
? 意見・感想等
岩手県内(盛岡市除く)では、工場は継続操業されており、土壌汚染問題が生じている工
場跡地は今のところ見当たらない。工場の自主調査で土壌汚染が見つかった場合は必要な対
策が実施されている。
なお、盛岡市内を除いたエリアでは、都市開発ニーズが乏しいことから、工業の継続的な
土地利用が余儀なくされている面もあると考えられる。
(2)埼玉県
? 土壌汚染への対応
土壌汚染が見つかった場合は、事業者に公表を勧めている。事業所敷地外への地下水汚染
が考えられる場合には、行政側で周辺の地下水調査を実施している。
? 意見・感想
・ 土壌汚染対策法第3 条ただし書きで調査が猶予されているケースも多く、土壌汚染が発覚
しないことがあると思われる。土壌汚染の対策としては、掘削除去がほとんどである。
・ 小規模な事業所が多いクリーニング業は、調査が行われることが少ない。同じ小規模な事
業所でもガソリンスタンドは業界の補助金制度を活用して汚染を除去している例が見られる。
・ 埼玉県内の比較的交通便利な場所では、都市開発が進みつつあるが、土地価格の上昇によ
り掘削除去対策でも採算がとれるようになってきている。
(3)新潟県・新潟市
? 土壌汚染の状況と対応
新潟県生活環境の保全等に関する条例(平成16 年9 月施行)に基づき、有害物質を扱う事
業所については5 年に1 回土壌汚染調査を義務付けている。汚染が確認された場合は県等へ
の報告が必要であるが、まだ報告件数はわずかである。
調査義務対象外の事業場の自主調査により土壌汚染が判明し届出されたものは30 件以上
であるが、その調査の契機は土地取引に際してのものが多い。土壌汚染は、金属製品製造業
等によるものが多く、またガソリンスタンドの廃止又はタンク改修によるものも5〜6 件ある。
土壌汚染は、工場跡地に限らず、商業地等においても見られる。新潟市の場合は、地質の
特性から自然由来といわれる砒素などによる汚染が見られる。また、新潟地域には油田が埋
蔵されており、また石油産業の立地が多いため、先の地震による液状化の影響で油汚染が判
明する可能性がある。
マンションなど住宅開発の場合は掘削除去による対策が最も行われている。但し、マンシ
ョン開発の場合でも、汚染が敷地の広い範囲に及んでいるケースでは、建物基礎及び含有量
基準をオーバーしている汚染箇所を掘削除去し、溶出量基準をオーバーしている箇所等は封
じ込め措置がとられているケースがある。
住宅以外の商業施設、工業系施設の場合は、掘削除去は費用がかかるため、汚染拡散防止
措置がとられるケースが多い。敷地内の他の場所に汚染土壌を移動してアスファルト舗装等
による拡散防止措置が実施されている。
なお、新潟市内において、土壌汚染のために土地取引や土地利用が停滞しているような事
例は聞いていない。また、土壌汚染地の土地取引において問題が発生しているような事例も
見当たらない。
? 特徴的な事例
ア.工場跡地等で開発等がストップしている事例
・ 自治体がかなり以前に工場跡地を取得したが、土壌汚染が判明したため、土地利用が進
まないケースがある。原因者は撤退しており、汚染拡散防止のために土地所有者である自
治体が地下水モニタリングを実施しているが、土地は未利用のままである。
・ 工場が廃止された跡地に商業施設が立地し、その商業施設を改築する際に土壌汚染が判
明したため、商業施設が改築を断念、撤退して未利用地のまま残されているケースがある。
・ 小規模なメッキ工場の廃止に際して土壌汚染が判明したが、浄化対策を実施することは
困難であるため、土地は拡散防止程度の措置をして未利用のまま残されているケースがあ
る。借地していた工場側と土地所有者との間で原状回復についての話し合いが続けられている。
イ.小規模な工場用地等の汚染の事例
小規模な工場用地の汚染の事例として、金属製品製造業の用地の汚染、クリーニング工
場用地の汚染、ガソリンスタンドの汚染が発生している。
金属製品製造業の工場用地でトリクロロエチレンによる土壌汚染(地下水汚染もあり)
が判明しているが、対策費用の関係で浄化は無理で拡散防止措置を実施している。
クリーニング工場の廃止に伴って汚染が判明した事例は2 件あり、この内の1 件は立地
条件がよい場所であったため、掘削除去による対策を実施した後に土地を売却している。
他の1 件は浄化対策が実施されたという報告は受けていない。
ガソリンスタンドの廃止又はタンクの改修に際して、ベンゼン及び油による土壌汚染が
見つかっている事例が5〜6 件ある。ガソリンスタンドのほとんどは大手の系列店であり、
大手企業が前面に出て土壌汚染調査・対策を実施している。
? 意見・感想等
新潟県内では、金属製品等製造業の中小規模事業所が多いことから、今後土壌汚染が判明
しても、自前で浄化措置を実施できないケースが出てくることが想定される。また、浄化対
策に長期間かかることや費用面の問題から、工場の操業中から汚染対策を実施していかない
と、対策ができなくなる可能性がある。
自然由来など土壌汚染の原因者が不明の場合に、対策が実施できないようなケースが出て
くる可能性がある。
(4)福島県
? 土壌汚染の状況
民間の自主調査で土壌汚染が発見された場合については、自発的に県への報告を依頼して
いる。県への報告・相談の件数は、自主調査によるものが年間数件程度、土壌汚染対策法に
基づくものは、年間0〜3 件である。
報告があった事例については情報を保管しているが、情報の公開は難しい。土壌汚染情報
全般については、現在稼動している事業所など大企業は自主調査を行っているようだが、県
で全ての結果を把握しているわけではない。
? 特徴的な事例
ア.土壌汚染地の土地利用が円滑に進んでいない事例
住宅地開発の中で、一部の土壌汚染地が未利用のままとなっている事例がある。
従前の利用は資材置き場であったが、宅地開発を行う段階で土壌汚染が発見されたが、
汚染原因者と考えられる企業が倒産したため、汚染除去費用を開発者が負担すると事業が
成立しないので、立ち入り禁止措置がとられている。
イ.土壌汚染地の土地取引・土地利用に際して問題が生じた事例
・ 工場の移転の際の自主調査によりVOC 類の汚染が発見されたため、事業者による浄化
措置が完了した後、教育施設用地として福島県が購入した。その後、県が施設を建設する
工事を行う過程で新たにフッ素による汚染も発見されたが、フッ素は事業者が行った調査
の項目に含まれていなかった。県では、教育施設用地としての土地利用を考慮して安全性
を重視して掘削除去を実施したが、汚染浄化費用は事業者と福島県で折半された。
・ 駅前広場整備工事中に土壌汚染(地下水汚染はない)が発見されたが、用地取得が土壌
汚染対策法施行前で瑕疵担保による負担金を求めることが出来なかったため、福島県が掘
削除去による対策費用を負担した。
? 意見・感想等
福島県の制度として環境創造資金という名称で公害対策用の低利融資制度を設けているが、
市中の銀行とそれほど利子が変わらないこともあって、あまり利用されていない。土壌汚染
対策を推進するために、この融資制度を広く周知し、制度が効果的に利用されるように図っ
ていく必要がある。
今後、県が公共事業土地を購入する際には、工場などの場合は土壌汚染について確認して、
契約段階で土壌汚染の浄化を附則として盛り込むことが必要かもしれない。
3.土壌汚染に係る現行制度と諸問題・取組み
3.1 土壌汚染の調査と情報収集
3.1.1 土壌汚染調査
(1)土壌汚染調査の目的及び契機
土壌が有害物質により汚染されると、汚染土壌の直接摂取や、汚染土壌から有害物質が溶
出した地下水の飲用等により人の健康に影響を及ぼすおそれがある。汚染原因者等の責任の
明確化と土壌汚染による健康被害の防止が求められる中、土壌汚染対策の法的な拠り所とし
て、平成15 年に土壌汚染対策法が施行された。同法のもとでは、特定の有害物質を取り扱っ
た工場や、事業所の敷地であった土地の所有者に土壌汚染の調査と、その結果の報告が義務
づけられている。
また、独自に条例を定め、土壌汚染調査に関して、より厳格な規定を設け
ている自治体もある。たとえば、東京都は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
において土壌汚染に関する規定を設け、3000 ?以上の土地の改変を行う場合又は有害物質
取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合、調査を実施し報告することを
義務付けている。
しかし、前述の土壌汚染対策法や自治体の条例に基づく調査は、土壌汚染調査実施例の約
2 割を占めるにすぎない。土壌汚染対策法が施行されて以来、法や条例に基づかない民間の
自主的な土壌汚染調査が増えている。企業は、環境マネジメントや資産マネジメントにおけ
る重要な活動として、汚染の可能性のある土地の実態把握、自然由来やもらい汚染の可能性
の把握などを目的とした土壌汚染調査を実施している。また、不動産取引を契機とした土壌
汚染調査も、活発に実施されるようになった。
(2)土壌汚染調査の対象物質
「土壌汚染」状況は千差万別であり、サイト毎に最適な調査・対策方法を検討し、実施し
ていくことが重要である。また、「土壌汚染対策法」が 対象とする土壌汚染は、特定有害物
質26 項目(鉛、砒素など重金属等15 項目 、およびトリクロロエチレンなど揮発性有機化
合物11 項目)であるが、その他の規制物質や規制はされていなくとも土地利用の障害となり
うる可能性のある物質もあり、注意が必要である。ガソリン、重油、潤滑油、灯油等の油分、
ダイオキシン類、その他の化学物質(条例等において特に規制されている物質、臭気の強い
物質及び色のある物質等)、要監視項目(22 項目)等の規制対象候補の物質などが調査対象
となりうる。土地取引に際しての調査では、購入用途が住宅系である場合、履歴にかかわら
【土壌汚染対策法に基づく調査の概要】
(目的) 国民の健康保護
(対象物質) 特定有害物質(重金属、揮発性有機化合物等26 項目)
(対象:調査の契機)
? 使用がず「特定有害物質(農薬類を除く)」「油分」「ダイオキシン類」を調査対象とするケースが多
い。(社)日本不動産鑑定協会策定の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」では、
「特定有害物質を中心に各自冶体の条例等およびダイオキシン類対策特別措置法において対
象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば価格形成に大きな影響があるもの
とする。」とし、法令等による調査義務がないことのみで土壌汚染が無いとはできないとして
いる。
(3)土壌汚染調査の手順と標準化
土壌汚染調査は、土壌が汚染されているかどうか、さらに汚染されている場合にどの程度
の汚染であるか、を把握するために行われるものである。しかし、土地取引や対策計画立案
など、調査実施主体が調査結果を使用する目的に応じて、調査に必要とする精度や正確さは
異なる。したがって、日本において法や条例に基づかない民間の自主的な土壌汚染調査は、
法令に基づく調査に準拠して進められることが多いが、必ずしも統一された基準のもとに実
施されているわけではない。一般的な土壌汚染調査のフローを図3.1.1 に示す。
? フェーズ?調査
地歴等調査(フェーズ?)は、土地利用履歴調査(登記簿、閉鎖謄本、古地図、空中写真
等)、地形・地質に関する調査(ボーリングデータ、地形図等)、現地視察調査(周辺状況や
対象地の現況を把握)などに基づき、土壌汚染の有無について定性的に判断する調査である。
アメリカでは2005 年にEPA(連邦政府環境保護庁)がフェーズ?調査の標準となるAAI
(All Appropriate Inquiry:あらゆる適正な調査)を改め、これに基づきASTM(米国材料
検査協会)がフェーズ?調査の仕様を改定した。AAI とは、土地の所有者、新規購入予定者
がスーパーファンド法に基づき浄化義務を免れるために実施する必要がある調査である。
改定の目的は、浄化義務を免除された後で土壌汚染が顕在化するリスクを軽減するために、資
料等調査における質の向上及び調査内容(水準)における差異の低減を図ることであった。
AAI における従来標準からの重要な変更点は、環境専門家の資格明記、聞き取り調査の対象
者拡大、資料調査の対象拡大、土壌調査報告書の有効期限設定である。
一方、日本では、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)が土地取引時に作成され
るエンジニアリングレポート(ER)のガイドラインを定め、その中で土壌汚染のフェーズ?
調査手法を提案するなどの取り組みがあるが、統一された土壌汚染調査仕様が規定されるに
至っていない。法令等に準じたフェーズ?調査を実施することによって、土壌汚染リスクが
回避されるという一般認識が存在している。簡易なフェーズ?調査で土壌汚染の可能性が完
全に否定される場合を除き、フェーズ?調査による評価が求められる傾向が強い。したがっ
て、現状では、フェーズ?調査を実施することを想定し、日本におけるフェーズ?調査の水
準はAAI が要求する水準より低めに設定されている。
土壌汚染対策法の規定に基づく調査は、環境大臣(地方環境事務所長)が指定する指定調
査機関が実施することとされており、平成20 年1 月23 日現在、1,661 機関が指定されてい
る。東京都等の自治体の条例に基づく土壌汚染状況調査についても、原則として土壌汚染対
策法に基づく指定調査機関に実施させることが定められている。ただし、指定調査機関の認
定要件は届出による簡易な書面審査が中心であることに加え、土壌汚染対策法や条例が適用
されない調査では、土壌汚染の専門家以外でも調査の実施が可能なことから、調査結果の信
頼性を問題視する意見もある。
フェーズ?調査段階では、比較的簡単に入手できる情報のみに基づく調査であることから、
調査結果に不確実性が存在する。フェーズ?調査は、汚染の可能性を調査するものであるが、
汚染の可能性がないと判断した場合でも、不十分な調査により、対象地に存在する土壌汚染
を見逃している場合があり、留意する必要がある。ある不動産関連企業が独自に実施した調
査によれば、フェーズ?調査で汚染可能性が低いと判断した土地のうち、かなりの割合で土
壌汚染が検出された。特に、造成地において、外部から搬入された盛土部から検出されたと
想定される例が多くあり、フェーズ?調査の結果を評価する上での課題となっている。
? フェーズ?及びフェーズ?調査
フェーズ?調査で汚染の可能性があると判断された場合は、概況調査(フェーズ?)を実
施する。概況調査は、土壌汚染対策法に基づく汚染状況調査に相当するものであり、表層付
近のデータを採取し、汚染の存在を確認するとともに、平面的に汚染の存在するエリアを絞
り込むものである。この調査は、環境省監修・(社)土壌環境センター編「土壌汚染対策法に
基づく調査及び措置の技術的手法の解説」に示される方法に準じて、土壌ガス調査、5地点
混合法表層土壌調査が行われる。
詳細調査(フェーズ?)は、概況調査で絞り込んだエリアについて、ボーリングにより汚
染範囲を確定する。汚染対策の実施を前提として行われる調査であり、汚染の範囲・深さ・
程度を三次元的に把握して、対策の必要性、範囲を設定し、対策費用と期間を検討するため
に行うものである。汚染範囲が広い場合は、調査にかなりの費用と期間を要する。
土地利用の変更や土地取引に際して更地の状態で調査する場合には問題とはならないが、
開発検討段階の調査や権利置換型の事業では、調査段階で従前建物が存在(権利者が生活若
しくは営業)している場合が多い。このようなケースでは、可能な範囲でしか調査できない
ため、汚染リスクの見極めが困難となり、事業成立性の判断に影響を及ぼすことが懸念され
ている。
(4)土壌汚染調査の費用
調査のフェーズを重ねるごとに土壌汚染状況の把握の確実性は高まるが、それに伴って調
査費用も増大する。フェーズ?調査の費用は、40〜50 万円/物件であるが、フェーズ?調査
では対象範囲が大きいとその費用も多額になり、資金的余裕のない土地所有者にとっては大
きな負担となる。その費用は対象地を1,000 ?と仮定した場合、概況調査で1〜2 百万円/物
件、 詳細調査は数百万/物件となる。こうした高額の調査費用は、土地取引や開発計画を断
念したり、従来の土地利用をしたりする一因となる。また、不動産の競売入札において、土
壌汚染に関する調査を考慮に入れた上で入札する良い入札参加者ではなく、土壌汚染の可能
性を無視する悪い入札参加者が選ばれる逆選択の問題が生じているという懸念がある。
3.1.2 情報収集と活用
フェーズ?調査を実施する際には現地踏査やインタビュー、依頼者から提供される書類記
録等のレビューの他に、公的機関が保有する環境情報を精査する。次章で触れるように、ア
メリカでは、汚染サイトや浄化中のサイト、埋立地や処分場、貯蔵タンク等の情報が法や制
度によって登録されており、フェーズ?調査の実施時にはこれらの情報を評価の材料として
いる。
一方、日本でも同様の手法でフェーズ?調査が実施されているが、アメリカのような法や
制度がない。環境省と一部の自治体は、それぞれ土壌汚染対策法と自治体条例が適用された
土壌汚染地の調査・改善措置に関する情報を収集し、情報提供しているケースもあるが、こ
れらの情報を制度的に集約する機関がないため、公的機関から多くの環境情報を得ることは
できない。また、法や条例の適用を受けず、自主的に実施された調査や改善措置が、土壌汚
染調査実施数の大半を占めているものの、それらを共有できる仕組みが構築されていないこ
とも課題である。土壌汚染に関して参照できる情報、資料の蓄積が少ないため、調査の案件
毎に始めから調査を実施する必要が生じている。
調査を実施して汚染が判明すると、対策の実施や公表を迫られ、企業の業績への影響やイ
メージの低下につながる事態をおそれて、調査を実施しないケースも存在する。土壌汚染に
対する社会的な見方は変わりつつあるとはいえ、自主的な調査の結果の提供については、企
業サイドも消極的となることが想定される中で、効果的な情報収集を図ることが重要である。
フェーズ?調査を実施する際には、住宅地図、不動産登記簿、土壌汚染に係る地域の基礎
的情報(土地利用履歴、過去の地形図、漏出事故・汚染記録、潜在的汚染源の位置、地下水
水質等の環境情報など)、その他、地方自治体や各省庁が所管する基礎的情報が活用される。
これらの基礎的情報が、未整備もしくは個別に収集、管理されているために、データ収集の
非効率が生じている。これらの基礎的情報・データがアクセスしやすいように整備されるこ
とが望ましい。
土壌汚染に関する情報インフラが整備されることによる効果は、前述のとおりフェーズ?
調査の品質確保や効率的な調査に資するものであり、生産性の向上にも結びつくものである。
そして、土地取引等に当たっての保険活用や担保評価に資する有用な情報となる。また、情
報インフラが整備されることにより、土壌汚染地の譲渡等があった場合、次の管理者等が土
地の情報を引き継ぐことができる。これにより土壌汚染による環境リスクの制度的管理につ
いても、次の管理者等へ承継できる。
3.2 土壌汚染の基準
3.2.1 用途別基準
住宅や産業用地といった土地の用途に関わらず、土壌汚染が環境基準の数倍でも1,000 倍
でも、環境基準を超えていれば、土壌汚染地として同様に扱われることが、土壌汚染地対策
を非効率なものとしているという指摘が多い。健康被害の防止を前提として、土地利用と関
連付けた基準作りを望む意見も聞かれるところである。しかし、一方で、土地利用と関連付
けた基準の導入においては、土地の用途変更に際して対応する仕組みづくりが必要となる。
土壌・地下水汚染対策の目標は相当にレベルが高いため、目標水準まで浄化する場合の対
策費用は高額となる。将来、土地利用の用途に合わせた基準などが設定されれば、対策費用
の低減が可能になると考えられる。
3.2.2 自然由来の汚染
明確な自然的原因は、種々の資料もあり、データがあれば正確な判断と基準設定も可能で
あると考えられる。例えば、鉱床地帯・その周辺などの鉱染地帯や変質岩帯の地域から発生
する汚染土壌(道路工事など)については、広域地質図、一部の地域の鉱染マップ、採石資
源分布図を使って類推はできる。一方、都市部の土壌を考えると、本来の自然的原因の汚染
土壌と、過去の人間活動(不特定多数の人間活動を含む。)に起因する汚染者特定不可能な汚
染土壌などが混在しており、濃度的な問題や分布の問題の挙動が同じでも、汚染者負担の公
平性から考えると、負担者の面からも安易な分類ができない場合もある。
上記のとおり、自然由来の土壌汚染に対する基準については、さらなる科学的データの蓄
積、公開が重要である。こうした視点で、地質情報、自然起源汚染情報、人為汚染情報など
の全国規模の各種地圏情報をGIS 化して情報提供するシステムとしての「地圏環境インフォ
マティクス」構築の取り組みが東北大学を中心に行われている。この中では、日本の重金属
バックグラウンドの把握、地域によるバックグラウンドの差異の把握方法の開発、地質と環
境因子との関連性の把握と、これらを共通のプラットフォームで把握する試みが進められて
いる。
現行の法規制においては、自然的原因による有害物質含有の土壌は、「人の活動に伴って
生ずる相当範囲にわたる土壌汚染」(環境基本法第2条第3号)ではないことから、同号の「公
害」には該当せず、環境基準の適用においては「汚染が専ら自然的原因によることが明らか
であると認められる場所においては適用しない」こととされているため、中央環境審議会の
2002年1月答申「今後の土壌環境保全対策の在り方について」の中で、「自然的原因により
有害物質が含まれる土壌については、人の活動に伴って生じる土壌汚染ではなく、したがっ
て環境基本法で定める公害とは言えないことから、この制度の対象とはせず、別途検討され
るべき課題であると考える。」こととされている。
専ら自然的原因により高濃度の特定有害物質を含む土壌又は水底土砂が、同様の土壌又は水底土砂の存する周辺の地域において盛土や海面埋立等により土地の造成に用いられた場合には、造成された土地は自然的原因により基準に適合しなくなったものとされ、土壌汚染対策法や条例の適用対象とはならないものとされている。
一方、土地の造成に伴い当該地域とは異なる土地から持ち込まれた土壌については、それ
が専ら自然的原因により指定基準を超過するものであっても、平成15年2月15日環水土第24
号通知「指定区域以外の土地から搬出される汚染土壌の取扱指針について」の中で、土壌汚
染対策法の指定区域以外から搬出される汚染土壌についても、同法の考え方に即した取扱い
が望ましいこととされており、土壌を持ち込んだ者が汚染原因者と見なされる。持ち込んだ
者が不明等の場合には、土壌汚染対策法第7条第1項に基づき土地の所有者が必要に応じて措
置を行うこととされている。
土壌汚染が自然由来であるかについては、環境省が土壌汚染対策法施行時に地方公共団体
宛発出した「土壌汚染対策法の施行について(平成15年2月環水土第20号)」における「土
壌中の特定有害物質が自然的要因によるものかどうかの判定法」に基づいて判断が行われる。
具体的には土壌溶出量基準を超過する場合の判断基準として、
?対象物質の種類等、
?対象物質の含有量の範囲等、
?当該特定有害物質の分布特性、
の3項目から検討することとされ、また含有量基準を超過する場合の判断基準として、
?バックグラウンド濃度又は化合物形態等、
?使用履歴場所等との関連性、
の2項目から検討することとされている。
しかし、一般的に、土地取得に際しては、自然由来による汚染も含め環境基準超過土壌は
完全除去を行うことが原則とされている。自然由来による土壌汚染が深い部分まで及んでお
り、完全除去が事実上不可能もしくは売主に完全除去を求めることが不適当と判断される場
合は、建物の根切り深さに相当する一定の深さまでの除去を求め、それより深い部分の汚染
は免責とされるケースもある。
3.3 土壌汚染の対策
3.3.1 責任負担者
土壌汚染対策法では、汚染が判明した土壌は都道府県が「指定区域」として指定・公示し、
指定区域内の土壌が健康被害を招く恐れがある場合には、汚染原因者が特定できるケースを
除き、原則として土地所有者に対策を義務づけている。土壌汚染対策法では、土地所有者等
が汚染除去等の措置をした場合に、汚染原因者に対して措置費用の請求ができることとされ
ているが、汚染原因者が不明又は破産して費用負担できない場合には、土地所有者がすべて
対応しなければならない。
現在の諸制度は、使用者や用途が変更される通常の土地取引に対応したものである。昨今
不動産証券化にてよく行われているセール&リースバックにおいては、売買取引後のテナン
トによる汚染をモニタリングすることが重要である。モニタリングの手続きや内容は賃貸借
契約に反映されることとなるが、売主と売買取引後のテナントが異なるケースについて、売
主とテナントの間のリスク分担に係る対応が難しいという指摘がある。
3.3.2 法令上の要求措置と実態の乖離
汚染の除去等の措置には立ち入り禁止、覆土、舗装(直接摂取の場合)、汚染土壌の封じ込
め、掘削除去があるが、掘削除去が選択されることが多い。これは、土壌汚染対策法上「汚
染の除去等の措置」(同法第7 条第1 項)以外では台帳から指定地域の抹消をされないこと、
将来売却する場合に、掘削除去以外の措置では価格の減価程度が予測できないこと、土壌汚
染が完全に除去されないと、封じ込め等の措置が必要になり、その間の管理コストや土地利
用への影響があるなどの課題を長期間抱え込むことになるおそれがあることなどが、掘削除
去を求められる理由である。実に、国内で実施されている措置のうち80%強が「掘削除去」
か「現位置浄化」を選択している。
掘削除去は費用が高額となるため、土地の売却益の中で吸収できる場合は実施可能である
が、そうでない場合は厳しく、土地所有者にとって売却を断念せざるを得ない事態が生じる
可能性がある。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が土地価格を上回るケースもある。とり
わけ資金力のない中小事業者や土地価格の安い地方都市において、このような事態が生じる
可能性があり、いわゆるブラウンフィールドの発生につながると考えられる。
一方、土壌汚染対策法や自治体の条例は、掘削除去措置まで求めているわけではない。例
えば、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の第114条では、対象地内
の土壌汚染により「大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に係る被害が生じ、又は
生じるおそれがある」と認められる場合は、対象地内のすべての汚染土壌について指針の定
めるところにより汚染処理を行うこととされており、また、同条例に基づく東京都土壌汚染
対策指針において、周辺環境に土壌汚染の影響が顕在化していないこと、及び掘削する場所
以外に存在する汚染土壌が外部に拡散しないことを前提として、汚染拡散防止措置を行うも
のとされており、必ずしも掘削除去が求められていない。
なお、土地取引によらない場合は土地所有者が自己利用又は土地を賃貸することになるた
め対策コストの高い掘削除去よりは封じ込めなどの対策がしやすいものと考えられる。土壌
汚染の対策コストが多額で土地を売却できない場合には、汚染の封じ込め措置をして倉庫や
駐車場等として自己利用、又は土地を賃貸して商業施設や駐車場等への利用が見られる。ま
た、産業用途の不動産取引では、自主基準を作成し、それに沿った形で土壌汚染地取得の意
思決定が行われ、完全浄化を実施せず適切に管理している例も見られる。
3.4 土壌汚染の管理
土壌汚染が発見された場合、実態として完全除去されることが多いが、土壌汚染対策法や
自治体の条例では、完全な除去まで求めているわけではない。当該敷地および敷地以外の周
辺環境において、人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれが顕在化していなければ、
完全除去ではなく、土壌汚染が周辺環境に影響を及ぼさないように汚染拡散防止措置を実施
することで対策とすることができる。そして、法や条例の適用対象とならない場合にも、こ
の基本的な考え方は適用できる。土壌汚染を残置することによって、土地所有者は土壌汚染
リスクを将来にわたって適切に管理することが求められるが、経済的な対策を選択できる余
地が広がることとなる。
土地取引においては、土地購入者にとって、封じ込め措置などの汚染が残存する土地は割
安な価格で購入することが可能であるが、一方で封じ込めた汚染土壌に係る管理などに追加
費用を要することに加え、土地の使い勝手が大きく損なわれるおそれがある。したがって、
汚染土壌を一部エリアに封じ込める措置を採用する場合は、土地利用をあらかじめ考慮した
措置とすることによって、土地の利用価値低減をできるだけ限定的なものとすることが重要
であると考えられる。たとえば、土壌汚染地の地下利用制限などの部分的制限によって、掘
削除去以外の土壌汚染対策が容易になるだろう。また、将来、土壌汚染の封じ込め措置を行
った土地を売却する場合には、利用用途が限定される可能性があることから、売却先を探す
際にマイナス要因となりうることにも留意しなければならない。
このように、健康への潜在的な被害に考慮しつつ、土地の適切な利用を確保していくため
に、官民の間で取り決めを設ける手法は、制度的管理(Institutional Control)と呼ばれアメ
リカなどで活用されている。制度的管理は、土壌汚染された土地を、土地利用制限や継続的
モニタリングなどによって、適切に管理する手法である。制度的管理は、制度の特徴から、
土地利用用途別の基準と関連付けられることも多い。
日本での適用例は少ないが、豊中市のマンション敷地において、「深い基礎が必要な高い建
物は建てず、土壌汚染の事情を知らない第三者に転売しない」という協定を市と不動産業者
が結ぶことを条件に分譲するという方式が採用されている。また、倉庫等の産業用地を対象
とした不動産証券化ファンドにおいても、部分的な利用制限や将来の建て替え時の制限を設
け、完全浄化を行っていない例が増えている。
なお、本節で取り上げた土壌汚染の管理手法は、マンション用地など個人向け不動産に適
用する上では、十分な検討が必要となる。欧米では、管理された土壌汚染地は住宅等購入者
にとって、住宅等が比較的安く取得できるというメリットが認知されている。
しかし、掘削除去以外の対策により汚染が残存している場合は、汚染土壌の継続的なリスク管理が必要と
なり、その負担を個人に求めることができるのかという不安がある。当然のことながら、所
有権の移転があれば、その役割は新しい所有者に適切に引き継がれなければならない。また、
個人レベルで、土壌汚染の存在することによる土地資産の減価リスクの適切な判断が求められる。
3.5 土壌汚染がある土地取引のリスクと財政的支援
3.5.1 土壌汚染に係るリスクとリスク分担
(1)リスクの概要
土壌汚染によるリスクについては、人の健康リスクが重要であることは言うまでもない。
しかしながら、土壌汚染地の取引に関連して、その資産価値にかかるリスクも、予測が困難
であり、リスクが顕在化した場合の影響は大きい。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が
土地価格を上回るケースもある。汚染を完全に除去しなければ、土地に残る土壌汚染の管理
が必要となり、将来、想定外のコストが発生したり、将来売却する場合に想定以上の減価が
生じる懸念もある。さらに将来の法改正で、規制対象物質が増えたり、基準が強化され、予
測できない大きな負担が生じる可能性がある。
土壌汚染された土地に係るリスク
● 措置状態の管理/監視義務対応管理/監視結果の報告義務対応
● 第三者賠償請求(近隣住民の健康被害・財産権の侵害)
● 土地利用中の再措置命令対応(濃度上昇等による)やモニタリング井戸の追加等行政指導
● 再措置命令対応による休業損害補償
● 土地利用中の法規制の変更に伴う調査・措置の再実施に関わる費用負担
● 措置済み土地で計画する形質変更が実施できない、 あるいは計画変更を求められるリスク(計画遅延含む)
● 措置計画が行政および近隣住民からの同意が得られないリスク
● 風評リスク
(2)リスク分担
日本では、土壌汚染対策法で土地所有者等に汚染除去が求められており、同法では、土地
所有者等が対策を実施した場合に、汚染原因者に対して対策費用の請求ができることとされ
ている。しかし、汚染原因者が特定できない場合や、特定できても破産して費用負担できな
い場合には、土地所有者が負担しなければならないことになる。このように、土壌汚染があ
る土地の取引においては、土地所有者(売主)と買主が負担するリスクが大きく、円滑な取
引を阻害する要因となっている。
土地所有者(売主)と買主の間のリスク分担については、民法で瑕疵担保責任が規定され
ている。しかし、瑕疵担保責任は、二者間の契約で変更が可能であるため、土地所有者(売
主)と買主のリスク分担は、二者の関係によって変わることになる。したがって、土地所有
者(売主)が優位な場合には、無過失の買主がリスクを負担しなければならないこともある。
(3)リスク軽減の考え方
土壌汚染がある土地の取引において、リスクが顕在化した場合のコスト(つまり浄化費用)
は、莫大なものとなる可能性がある。アメリカで実際に導入されている事例からも、浄化融
資ファンドや公的な保険など、様々なタイプの支援や仕組みが、土地取引関係者のリスク軽
減とリスクヘッジに寄与するものと考えられる。零細汚染責任者のように責任者に責任を負
わせることができない場合について、修復の資金供給のための適切なメカニズムを構築する
ことを望む意見も聞かれるところである。たとえば、日本にも4万箇所以上のドライクリーニ
ング施設があり、経営主体は個人が約70%弱になる。経営規模は年間売り上げベースで3000
万円未満が8割と零細層が中心であり、対策は実質的に困難であると考えられる。こうした零
細企業の所有地を再開発する場合に、開発者にインセンティブを与えることは効果的である。
(4)リスク評価
土壌汚染に係るデータベースを用いて、統計的に土壌汚染による損失を評価する手法は、
一部の金融機関で実施されている。しかし、この手法は、金融機関の数多くの担保物件を対
象として、土壌汚染による減価の総額を把握する手法であり、個別物件のリスク評価に用い
るには精度的に不十分であった。これに対し、個別物件の土壌汚染リスクを評価するツール
開発の取り組みが行われている。
土壌汚染の可能性がある土地の取引や不動産開発を検討する際、土壌汚染の実態把握のた
めに、初期段階にて多大の費用がかかる調査等を行うと、事業リスクは大きくなる。また、
将来発生する詳細調査や対策の費用の不確実性が高いために、初期の調査に踏み出せず事業
自体が断念されるケースも多い。土地開発の採算性や実現可能性を検討するような構想段階
においては、多額の調査費用を費やし、詳細な土壌汚染調査を実施することは合理的ではな
い。むしろ、地歴調査、表土調査等の簡易調査に基づいて土壌汚染対策費用のリスク評価を
実施し、マーケットリスク等を含めて不動産開発の妥当性を検討することが必要である。
しかし、地歴調査、表土調査等の簡易調査のみが実施された段階で、土壌汚染の実態を確定的
に把握することは極めて困難であるため、特に初期構想段階では、土壌汚染に係るリスクを
評価し意思決定することが重要となる。
この点に関して、評価ツールとして期待値による評価と確率分布による評価が考えられる
が、期待値で評価をしても事業キャッシュフローに関する問題点が明確にならないケースも
ある。例えば、1000 分の1 の確率で100 億円の支出が生じる場合、期待値の上での影響は
1000 万円でしかない。しかし、ダウンサイドのリスクが顕在化し多額の資金需要が一度に生
じた場合、事業が頓挫する可能性もある。そこで、こうしたリスクを評価するためには期待
値ではなく、確率分布の形を評価することが有効である。また、人は確実に100 円の利益が
得られる場合と、期待値は100 円でもリスクのある場合とでは、その事象に見出す価値が異
なる。したがって、確率分布で理解することは、リスクコミュニケーションにおいても重要
となる。さらに、多様な資金調達や保険の活用、そして先進的な不動産プロジェクトで用い
られるようになったリアルオプションには分散に関する情報が不可欠であり、当該ツールに
よって得られる確率分布は極めて有効である。
3.5.2 低利融資等
土壌汚染対策に係る低利融資制度については、政府系金融機関(日本政策投資銀行)に
よる貸付制度がある。但し、この融資制度も包括的な制度設計に至っておらず、例えば調
査費用が対象とされなかったり、自主的な調査及び改善措置費用が対象とされなかったり
等、その適用範囲は限定的なものであるため、当該制度の利用実績は低調なものに留まっ
ている。
また、その他の公的支援制度として土壌汚染対策基金が挙げられる。この基金は、土壌汚
染対策法に基づき、汚染原因行為に関与していない資力に乏しい土地所有者等に対して汚染
の除去等の費用を助成するものであり、都道府県又は政令市を通じて実施される。
当該制度についても、資力の乏しい小規模事業者等にとっては有効な支援策であるものの、厳格な適
用要件等によりこれまでほとんど利用されてこなかった。
これら低利融資及び基金については、適用要件の緩和等、より弾力的な運用を施行するこ
とで、さらなる利用促進を図ることが望まれる。
3.5.3 保険
(1)土壌汚染地に関する保険の役割
保険の役割は、関係者または特定の土地に対し、通常の事業又は浄化工事請負作業中にお
いて、汚染が顕在化した場合の浄化費用を補償するものである。土壌汚染についてリスクを
負担することができない場合に、保険を付保することによって、リスクを移転することがで
き、費用を確定し収益性の判断がつけやすくなる。また、制度的管理(Institutional control)
を採用する場合には、潜在的な環境負債者の将来にわたる長期修繕費用の支払い能力が求め
られるが、もし適切な支払い能力がないと判断された場合、当事者は債権や保険等を利用し
て財政的な裏づけを確実に得ることもできる。アメリカでは、保険を活用することにより、
土壌汚染地の浄化を伴う再開発に民間資金が集まり、再開発が促進されるという効果を上げ
ている。
(2)土壌汚染に関する保険の種別
日本国内でも、海外と同様、汚染が顕在化した場合の浄化費用を補償する土壌浄化保険
をはじめとして、第三者土壌浄化賠償責任保険などの土壌汚染関連保険が開発されている。
これらの保険商品を分類すると、事業者に対して付保する保険と、土地に付保する保険がある。
事業者に対する保険は、開発、建築等の事業の過程で土壌汚染を発生させたことに起因
する賠償費用を補償するものや、土壌汚染対策などの請負作業において汚染を発生させた
場合に、賠償費用を補償するものがある。一方、土地に対する保険としては、結果として
土地所有者等が負担した対策費用に加え、地下水汚染等により発生する周辺住民の健康被
害などの対人、対物の損害賠償費用を補償するものがほとんどである。また、土壌汚染対
策費用の超過分を補償するコストキャップ保険(超過浄化費用保険)は、対策費の上限を
予測できるため有効である(3.5.4を参照)。
(3)土壌汚染保険の普及に向けた課題
日本国内では、土壌汚染に関連した保険の普及が進んでいない。普及が進まない最大の理
由は、保険料の高さと保険引受条件の厳しさにあるようである。仮に数を集めたところで発
生要件の規則性が見いだせない(=大数の法則が成立しない)からこそ保険料が高くなり、
加えて、逆選択(土壌汚染のリスクを抱えているのが明確な人ほど保険に入ろうとする)が
生じ、最悪の場合モラルハザードにつながるため、保険の利用が進まないという側面がある。
そして、保険の利用が進まないために、大数の法則の適用が困難となり、結果として保険料
が高くなり、引受条件が厳しくなるという悪循環が生じている。さらに、保険料に加えて、
保険引受のための高額の調査費用を、被保険者が負担することが一般的となっており、この
ことも保険が利用されていない一因となっている。
リスクを定量化するためのデータの蓄積は、保険商品の開発にとって重要である。しか
しながら、日本では、土壌汚染がある土地の調査事例や対策事例に関して、入手可能な情
報が不十分であることから、土壌汚染に関する事例の蓄積を進めていくことが必要である。
また、保険の利点や内容が理解されていないことも課題である。
(4)土壌汚染に関する保険の拡充
我が国では、土壌汚染保険やコストキャップ保険をはじめとする損害保険はあるものの、
情報の非対象性を一つの大きな理由として、必ずしも保険会社が積極的にリスクの引き受け
に応じていないのが実態であるが、海外では「ファイナイト(Finite)」といわれる従来型
の保険に代わるリスク移転手段が導入されている。
ファイナイトは、「リスクの保有」と「リスクの移転」を組み合わせ、企業と保険会社の間
でリスクをシェアする機能を有するリスク・ファイナンス手法であるといえる。ファイナイ
トにはニーズに応じた様々な形態があるが、土壌汚染問題に対する適用に関しては次の例を
想定することができる。
たとえば、ある工場の経営者が、当該工場の敷地に土壌汚染の存在が発覚したため、将来、
当該工場を閉鎖し、土地を売却する場合に備えて、その浄化費用の対策を考えた。売却の際
には、汚染地の浄化が必要になるが、その対策費が1 億円から7 億円の範囲内となることが
想定され、このときファイナイト契約を5 年間で構成することした。なお、5 年以内に当該
土地の売却・浄化してしまった場合でも契約は5 年間継続させるために、対象となる土地は
売却予定以外の複数の土地を含んだ契約となり、以下のようになる。
? 初の保険金支払い事由となる浄化工事の場合の支払限度額は7 億円、免責は1 億円、2
番目以降はそれぞれ3 億円、10 億円とする。また、毎年の保険料は1 億円で変更なしとする。
? 毎年の保険料が毎年積み立てられた場合5 年間で積立て額は5 億円となる。
? 仮に3 年目で土地の売却、浄化工事が行われ、その費用が5 億円であった場合、保険
会社から1 億円の免責額を除いた4 億円が保険金として支払われる。
? 契約は5 年目まで継続し、2 件目以降の保険金支払い事由の発生がない場合、保険料
の積立て額は5 億円、保険会社からの支払額は4 億円となる。この差額のある程度の
割合は予め約定された割合に基づき、契約者に優良戻しということで 返還されること
が多い。
? 仮に3 年目行われた浄化工事が8 億円かかった場合、保険料の積立て額は5 億円、一
方、保険金の受取額は7 億円となる。
ファイナイトのメリットは、浄化費用の発生タイミングと規模に係るリスクを抑えること
ができる点である。具体的には、積み立ての場合、積立て額は段階的にしか積み上がらない
のに対し、ファイナイトであれば1 年目から最大7 億円の浄化費用の手当てができる。また、
浄化費用の額についても、上記の例で8 億円までに収まった場合、保険料としての拠出額の
合計である5 億円に免責額の1 億円を加えた範囲内に抑えることができる。
保険会社からすると、保険料の積立て額が保険支払額よりも上回った場合は、その一部を
契約者に払い戻す構成としているため、契約者がリスクを軽減するモチベーションを持ち続
けることを期待することができるため、ある程度モラルハザードを抑制することが可能とな
る。
3.5.4 保証
保証は、保険と同様に、土壌汚染リスクをヘッジする目的で活用される。保証には、浄化
工事のコストの増加分を保証する「コストキャップ保証」型、フェーズ?調査後、汚染の可
能性が極めて低いと判断した土地に対し、調査会社が自社の調査に基づく土壌汚染がない旨
の評価に対して保証する「調査後のシロ保証型」、主として土地取引の契約書の記載事項を表
明保証する「表明保証」型などがある。
浄化工事の保証は、工事の請負契約に加え、対象地、対象期間、対象物質、工事請負金
額、工事の着工および完了予定時期、保証内容、免責事項などを記載した保証書を差し入
れることによってなされるのが一般的である。浄化工事の保証内容の例について、次に一
例を示す。
浄化工事の保証内容の例
・計画土量増加および処分時の比重増加に伴うコストの負担。
・高濃度汚染の存在などにより処理方法の変更、追加が生じた場合の費用の負担。
・対策計画の範囲内に存在する廃棄物や地中構造物の撤去に関わる費用の負担。
・地下水モニタリングに関わる費用一式の負担。
3.5.5 買取り
民間ファンド等が土壌汚染リスクのある不動産を買い取り、浄化を実施後に売却することに
よって、リスクヘッジするスキームも土壌汚染土地の取引活性化に有効であると考えられる。
土壌汚染がある土地の所有者(売主)にとっては、事業地を売却したくとも、調査費用や対策
費用の捻出が困難であったり、対策工事の工期の関係で困難であったりするケースや、風評
リスクが懸念され、売却をためらうケース、さらには、売却後の瑕疵担保責任を負いたくな
いようなケースも考えられるが、買取りスキームは、こうした土地所有者のニーズに応える
ものであり、土壌汚染調査と対策の実施負担が不要で、早期に売却収入が確定し、決済が可能
となるというメリットがある。
また、魅力的な物件だが、汚染が解消できなければ買収の意思決定ができないと躊躇う
買主側にとっても、浄化された土地として検討できるというメリット
がある。
さらには、買主と売主の双方にとって、土壌汚染に絡み流動化を阻害する問題が軽
減されることになる。ただし、民間ファンド等が中間的に買い取る行為が経済的に成立する
ためには、リスクを適切に評価することが可能であり、減価して買い取ることが条件となる。
3.5.6 信託
(1)信託の現状
信託は、委託者が、その保有する財産を受託者に引渡し、一定の目的(信託目的)に従い、
特定の受益者または公益のために、その財産(信託財産)を受託者に管理、処分してもらう
制度である。国内の信託財産残高は2007年3月末で744兆円と5年で1.9倍に増加し、この内、
不動産信託も5年間で残高3.8倍(6,257件)、件数9.0倍(22兆6千億円)と増加基調を示して
いる。(データ出典:(社)信託協会ホームページ)
不動産の信託においては、土壌汚染問題に受託者が直面することがある。例えば、
? 土地取引に際し土壌調査を行うことが慣行化する前に設定した信託受益権を信託期間中に譲渡す
る際に土壌調査を実施して、信託設定時に認識していなかった土壌汚染が発覚する場合、
?信託財産の隣接地等で実施された土壌調査によって、隣接地で汚染が見つかり、信託財産の
汚染が懸念されるような場合、
? 土壌調査の対象地に建物などがあったために汚染物質を見落とす場合、
?調査方法の選択ミスや精度の問題で、事前調査では分からなかった問題が発覚する場合等が想定される。
(2)旧信託法下での土壌汚染問題への対応方法
こうした場合に対応するため、旧信託法下においても「限定責任特約」を当事者間で締結
するというという方法があった。これは、受託者が信託事務に関する取引から生じた債務に
ついて、責任財産を信託財産に限定することを個別に特約として結ぶというものであったが、
土壌汚染に関しては、受託者に過失がなかった(無過失)としても受託者に対し以下の請求
が可能だったため、信託設定や信託財産の管理を適切に遂行したにもかかわらず、受託者が
最終的に個人負担する可能性があった。
・所有者の工作物(「汚染物質を放出した建物および構築物」)責任(民法717条)
・被害を受けた土地所有者からの妨害排除請求権に基づく汚染物質の排除請求
・受託者が土地の名義人であることによる土壌汚染対策法に基づく土壌改善等の措置命令
(土壌汚染対策法第7条第1項)
(3)改正信託法下での対応方法
そこで、仮に信託不動産に土壌汚染が存在することが発覚したとしても、その責任を限定
する手法として、平成19年に施行された改正信託法で制定された限定責任信託制度の利用が
考えられる。限定責任信託とは、「受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務につい
て信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託」(同法第2条第12項)のこ
とである。限定責任信託では、受託者の対外的な責任限定の対象者を拡大し、従来の責任限
定特約とは異なり、取引関係にない者との間でも限定責任が適用される。
しかしながら、同法第217条第1項において、「信託財産責任債務」から同法第21条第1項
第8号に掲げる権利に係る債務が除かれており、「受託者が信託事務を処理するについてした
不法行為によって生じた権利」に該当する行為の範囲が問題となるが、現時点で、土壌汚染
対策法等に基づく土壌汚染に関する責任(すなわち信託法に基づかない責任)が、信託財産
を充てるべき責任なのかどうか、又は、両者の責任が分断されるのかどうかといった点が明
確にされていないことから、現時点で土壌汚染に関する責任を限定する目的で限定責任信託
を活用するのは困難であると思われる。
仮に、信託法における責任と信託法に基づかない責任が分断できるとしても、大きな土壌
汚染に対する限定責任信託の活用については、社会的なコンセンサスを得られるのか疑問が
あり、今回の法改正で土壌汚染地の信託が急増することは想定し難いと考えられる。
3.6 土壌汚染地の資産評価
3.6.1 土地の資産評価の枠組み
現在、土地の資産価値の評価については、公の機関や業界団体が関わり、考え方や算定方
法などが規定されているものだけでも、以下に示すとおり多岐にわたっており、様々な分野
でその分野のニーズ・目的に応じた評価がなされている。それぞれ評価の目的が異なるため、
当然のことながら、土壌汚染に関しても異なる取り扱いが規定されている。民間企業によっ
ては、独自の考え方で評価を行い、内部の意思決定に活用していることもある。
3.6.2 不動産鑑定評価の実務における土壌汚染地評価の基本的考え方
平成15 年1 月1 日より、土壌汚染を土地の個別的要因の一つとして、評価項目に追加し
た改正不動産鑑定評価基準が施行された。土壌汚染調査が経済的・法的・物理的な物件調査
の1 項目として、明確に位置づけられたものであるといえる。
実務上は、原則として土壌汚染対策法第2 条第1 項に規定されている特定有害物質を中心
として、各自治体の条例等及びダイオキシン類対策特別措置法及び各自治体の環境条例等に
おいて対象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば、価格形成に大きな影響
を与える可能性が生ずると理解される。
上記の土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法及び各自治体の環境条例等は、人
の活動に伴う人への健康に係る被害の防止の観点から規定されている一方で、不動産鑑定評
価において考慮すべきは、土壌汚染が価格形成に影響を及ぼす場合であることから、自然に
由来する土壌汚染も考慮にいれる必要があり、法令等による調査等の義務がないことをもっ
て、土壌汚染がないということはできない。
現状では対策が掘削除去中心であることから鑑定評価もそれを前提にする場合が一般的で
あるが、今後掘削除去以外の措置が講じられるようになれば、それらを的確に反映するよう
な鑑定評価を行う必要があり、必要に応じた実務面の見直しと普及が必要である。
既に、 (社)日本不動産鑑定協会作成の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針
(以下「運用指針」という。)?、?」がガイドラインとして示されている。運用指針Iでは、
鑑定士が行うべき独自調査のあり方が記載されており、運用指針?では、土壌汚染地におけ
る対応のステップが示されている。
運用指針では、土壌汚染の疑いのある場合には、不動産鑑定士が独自調査を行った上で、
その結果と、既存の土壌汚染調査結果を明記し、汚染の分布状況、除去等に要する費用等を
他の専門家が行った調査結果等を活用して鑑定評価を行うものとされている。
これまでのところ、土壌汚染地の鑑定依頼件数は少なく、したがって土壌汚染土地の鑑定
評価の経験を積んだ不動産鑑定士は少ない。また、土壌汚染に関する鑑定評価が可能なレベ
ルの調査が実施されていない段階で、鑑定評価を依頼されるケースも多いのが現状である。
<参考>現在の取組み
・ 土壌汚染地に係る鑑定評価については、平成14 年の鑑定評価基準の改正時において、
土壌汚染が価格形成要因の一つに位置づけられたところである。実務面においても、(社)
日本不動産鑑定協会で「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」の策定・改定、
それに基づく研修等が実施されている。また、土壌汚染の鑑定評価の実務に関するワー
キンググループが設置され、継続的にケーススタディー等の検討が行われている。
3.6.3 スティグマの評価
土壌汚染の存在(過去に存在したこと)に起因する心理的な嫌悪感等から生ずる減価要因
をスティグマという。また、広義には、前述の心理的要因に加え、土壌汚染に起因して将来
追加コストが発生するリスクを加えた減価の根拠をいうこともある。土壌汚染地の資産評価
は、概念的には次式で表現されている。
個別の土壌汚染地及び評価時点により、スティグマの程度・内容は異なるので、評価ごと
に、求めるべきスティグマを勘案する必要性が生ずる。
日本におけるスティグマの調査事例としては、住宅用地に関する市民アンケート調査((財)
日本不動産研究所、明海大学2003 年実施)がある。当該調査結果によれば、いずれも浄化
後を想定した質問を行ったところ、汚染対策が行われたとしても購入を控えるという回答が
多く、スティグマが存在することがわかった。スティグマの大きさは、購入の場合も、賃貸
の場合も、20%から30%が最も多く、次に50%というものであった。
これに対し、デベロッパー、銀行、不動産仲介業者側は異なる考え方を示している。国土
交通省実施の「民間土地取引に係る土壌汚染地の取扱実態に関する調査」によれば、デベロ
ッパーは、マンションも、オフィスも原則として掘削除去を実施後スティグマなしで販売し
ており、スティグマを斟酌しない考え方が一般的である。また、マンション開発で、掘削除
去を実施していない場合においても、十分なリスクコミュニケーションを販売前に行うこと
によって、スティグマを考慮せずに販売価格を設定している例もある。
銀行は、担保評価上、浄化措置が前提であり、浄化後のスティグマに関しては、対応が分かれている。不動産仲介
業者は、用途等を踏まえて取扱い、浄化後スティグマを考慮に入れた上で対応を行っている。
以上のように、スティグマについては誰が土地を取り扱うかで対応が分かれており、不動
産市場で、スティグマによる減価の取扱いについて、今後のさらなる検討が必要である。
3.6.4 エンジニアリングレポートの重要性
平成19年4月に改正された不動産鑑定評価基準においては、証券化対象不動産の鑑定評価
にあたり、鑑定士は、土壌汚染について、エンジニアリングレポート(以下「ER」という。)
や鑑定士の独自調査により的確に判断しなければならないとされている。
一方、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)は、平成19年4月に新しいERのガ
イドラインを作成した。BELCAのガイドラインによれば、ERは「建物状況調査報告書」、「建
物環境リスク評価報告書(フェーズ?)」、「土壌汚染リスク評価報告書(フェーズ?)」、
「地震リスク評価報告書」の4つの報告書から構成される。
建物環境リスクにおいて、土壌汚染に関しては、フェーズ?調査が標準として位置づけ
られ、REC(Recognized Environmental Condition:使用履歴のある有害物質や石油製品
等が、現時点で漏洩している状態にある、過去に漏洩した履歴がある、あるいは将来にお
いて漏洩が発生することが十分に懸念され、土壌や地下水に影響を引き起こすような状況
のこと。)の有無及び内容を結論として提示することとされている。一方、証券化対象不
動産の鑑定評価においては、汚染リスクの価格に対する結論が要求される。
BELCAのガイドラインでは、フェーズ?でRECやデータギャップが指摘されたら、それ
を定量的に評価することとされており、これはフェーズ?で汚染がないことが完全に示さ
れない限り、フェーズ?が必要となるとも理解される。
しかしながら、BELCAのガイドラインには拘束力はなく、エンジニアリングレポートに
は様々なレベルのものが見受けられるため、鑑定評価に活用するという視点から必要とさ
れる内容等について検討し、整理していくことが必要である。
このため、(社)日本不動産鑑定協会において、エンジニアリングレポート関係者との
共同研究会や、エンジニアリングレポート関係者の協力による研修などが実施され、実務
面での取組みが進められており、今後は、これらの取組みを継続・発展させ、着実に実務
に反映させることが重要である。
この際、不動産鑑定とエンジニアリングレポートの制度面の差異やエンジニアリングレ
ポートの提出は鑑定士ではなく、鑑定評価の依頼者に対してであるなどの難しさはあるが、
両者の連携により、それらの課題を克服することが強く求められる。
3.6.5 課税関係
土壌汚染された土地についての課税関係における評価では、減額項目を見込むか否かの考
え方において税による差異が存在する。
固定資産税については、何万筆もの土地を同時に評価するという大量、一括性に特徴を有
すると同時に、課税のための評価であることから評価の均衡、公平の確保が重要である。「土
地に関する調査研究(平成18 年3 月)−土壌汚染対策法と固定資産税評価について−(資産
評価システム研究センター)」によれば、汚染の除去等の措置費用を減価要因とすることは必
ずしも適当ではなく、当該土壌汚染地の現況に着目し、当該土地の利用の制限を減価要素と
することとしている。また、心理的要因については、その影響の有無が不確定であること等
から、基本的には考慮しなくても一般的には差し支えないと考えられるとしている。
一方、相続税については、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」(平成16 年7
月5 日付国税庁課税部資産評価企画官情報第3 号、資産課税課情報第13 号)が示されてい
る。相続税における土壌汚染地の評価額は、土壌汚染がないものとした価額から、浄化費用、
使用収益制限による減価、心理的要因による減価を考慮することとされている。相続税等の
財産評価においては、課税時期において、評価対象地の土壌汚染の状況が判明している土地
を土壌汚染地としており、土壌汚染の可能性があるなどの潜在的な段階では土壌汚染地とし
て評価することはできないものとしている。
なお、相続税を公示価格を用いて評価する場合には、評価が公示価格の80%を基準として
いることから、減価は土壌汚染浄化額の80%としている。また、土壌汚染の原因が被相続人
であり、第三者からの損害賠償請求により債務が確定しているときは、債務として計上でき
る場合もある。相続開姶後に土壌汚染が判明した場合であって、土壌汚染の原因を第三者に
特定することができ、除去費用について、当該第三者に求償権を有するときは当該求償権を
資産計上する。
4.諸外国の制度・取り組み
諸外国として、土壌汚染問題関連の情報が比較的多く収集されている米国とドイツの二ヶ
国を対象とし、それぞれの国の土壌汚染問題への取り組み状況について、以下の5 つの視点
から分析整理した。
各国のはじめで、取り組み状況の分析整理の前提として、米国に関しては、スーパーファ
ンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ及びそれぞれの法制度の概要につい
て整理し、また、ドイツに関しては連邦土壌保護法制定の経緯について整理した。
なお、ドイツに関しては、「財政支援施策」及び「環境負債免除制度」の項目に関しては、
詳細な情報が不足しているため分析対象から除外した。
【分析整理の視点】
・ 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
・ 浄化修復目標の設定
・ 制度的管理
・ 財政支援施策
・ 環境負債免除制度
4.1 米国
4.1.1 スーパーファンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ
(1)スーパーファンド法
1)立法に至る背景
米国では、1970 年後半から有害廃棄物汚染による環境災害が立て続けに発生し、災害によ
っては国家非常事態宣言の発動もあった。しかし、それまでの法制度では、土壌、地下水、
地表、水、大気の汚染に対して、連邦政府が直接関与できる法的権限はなかった。このため、
有害物質汚染災害や土壌汚染から国民と環境を保護するための新たな法制度の整備が必要と
なり、1980 年に連邦議会が「包括的環境対処・補償・責任法」(以下「スーパーファンド法」
という。)を成立させた。これ以降、連邦環境保護庁(以下「EPA」という。)が主担当官庁
となって、連邦政府レベルでの取り組みを開始した。
その後、1986 年にスーパーファンド改正・再承認法(以下「SARA」 という。)が施行さ
れ、スーパーファンド法の立法内容の強化・拡充がなされている。
2)スーパーファンド法の概要 (注1)
? 汚染者負担主義
スーパーファンド法の基本的考え方は、汚染者負担主義であり、当該サイトの汚染に何ら
かの関わりがあったあらゆる個人ないし企業を潜在的責任当事者とし、サイトの浄化及び住
民の健康や自然環境に与えた損傷への補償責任を求めた。潜在的責任当事者とは、汚染物質
の排出者、運搬者、貯蔵者、投棄・処理者等有害物質の放出または放出のおそれに関与して
いる者をいい、判例により汚染物質を廃棄している施設の所有者や創業者に対して融資を行
っている金融機関等直接的に問題となる汚染に繋がっていない者も、汚染修復の資金負担責
任を抱えることになった。また、スーパーファンド法施行以前の関与の責任も負わねばなら
ないという極めて厳しい責任原則主義が基本となっていた。
? 財源の手当て
EPAは2つの財源を手当てしており、1つは責任者負担によるサイトの浄化と補償であり、
もう1つは責任主体に支払い能力が無い場合や責任主体が不在となる場合への対応のため、
危険物質を製造したり、あるいは利用する産業に目的税を課し、これを基金化(有害廃棄物
信託基金(トラスト資金))して、遊休地化したり、放棄されているサイトの浄化資金とした。
(ただし、この税制は制定後15 年間で失効した。)
? 措置の種類
スーパーファンド法では、有害物質のリスクの程度に応じ、短期又は長期のいずれかの対
応がなされる。
・ 除去措置(Removal Action):短期の対応。健康被害と緊急の環境リスクに対応するもの。
・ 浄化措置(Remedial Action):長期の対応。通常の浄化措置の流れを追って実施するもの。
? CERCRIS とNPL
CERCRIS(the Comprehensive Environmental Response, Compensation,and Liability
Information System)とは、米国内の有害物質による汚染の懸念のあるサイトと当該サイト
における調査等の状況が全て登録されている連邦政府作成のデータベースである。CERCRIS
に掲載されているサイトは、一定の手続きを経た後、連邦政府や州のスーパーファンドサイ
トとして登録される可能性のあるサイトである。
このうち、最も深刻な汚染サイトとして、早急に浄化措置を行うべきサイトに優先順位を
つけてリスト化したものがNPL(National Priority List:国家緊急リスト)である。
? スーパーファンド法による問題と対応
スーパーファンド法の責任原則に関連してさまざまな問題が発生し、それらの問題を改善
するために、さまざまな運用上の工夫や修正を加えて今日に至っている。
a.関係当事者間による訴訟の多発
汚染サイトの浄化コストが高額になるため、同じサイトの潜在的責任当事者同士に責任
分担の訴訟が多発し、訴訟問題で資金を浪費し、また、訴訟が長期化し、浄化事業の遅延
化を招いた。
この問題への対応として、1986 年に施行されたSARA において、小規模の当事者で、「寄
与割合が僅少の」または「寄与割合が極小の」当事者は、早期に和解できることとした。
「寄与割合が極小の」当事者については、負担無しで和解できることとした。
SARA のその他の主な改正内容は以下のとおりである。(注2)
・ 「無実の土地所有者保護措置」の創設とその適用要件としての「全ての適切な質問」の規定
・ 資金調達方法の改良(トラスト資金の増額)
・ 浄化に関する永続的な改良策の開発、利用の強調
・ 地域住民への重度汚染化学薬品の存在に関する情報公開の義務付け
b.環境リスクをカバーする保険商品の普及
潜在的責任当事者と保険会社の間でも浄化コストの資金的埋め合わせをめぐって訴訟が
多発したが、スーパーファンド法への対応について、保険の必要性も高まり、施設の被害、
浄化費用負担、プロジェクト遅延、ビジネス中断、担保価値下落、風評被害、契約不備等
のあらゆる環境リスクをカバーする保険商品が契約可能になっている。これらの保険商品
が開発されたことにより、リスクを潜在的に抱えているサイトの売買、浄化、開発が容易
になってきている。
c.不動産業界への影響
スーパーファンド法により不動産業界はネガティブな影響を大きく受けた。不動産開発
業者は、潜在的責任当事者になることを恐れて、環境リスクのある不動産取引を敬遠し、
汚染サイトの遊休地化、放置化が促進されてしまった。
この問題に対して、EPA と各州政府は、再開発を促進するために、税制や補助金、融資
などの財政支援の充実化や環境負債免除制度などの規制面の保護政策強化への対応措置を
講じてきている。これらの措置により、汚染サイトは、不動産業者にとって割安であり、
かつ立地条件も良いことなどから、経済的メリットのある開発適地へと蘇生される可能性
が高まる方向となった。
(2)ブラウンフィールド法
1)立法に至る背景
スーパーファンド法の施行以降、土壌浄化の汚染者負担原則及び浄化の義務付けが明確化
されたが、この法的責任に関連して、他の汚染主体との浄化コスト負担に関する訴訟の多発
や、浄化リスク発生を嫌って、土壌汚染サイトの土地取引の停滞等の問題が発生し、EPA で
はさまざまな改善策を講じてきたが、より効率的な浄化プロセスの構築と再開発促進を狙い
として、ブラウンフィールド法(小規模事業者の責任免除及びブラウンフィールド再活性化
法)が2002 年に施行された。
2)ブラウンフィールド法の概要 (注3)
ブラウンフィールド法では、浄化プロセス効率化の観点から、浄化修復事業の長期化・遅
延化の一因となっていた小規模零細企業の責任問題への対応を図り、また、ブラウンフィー
ルドの土地取引活性化への観点から、浄化後のサイト所有への免責保護の規定の明確化及び
財政支援策の拡充を図った。
? 小規模企業の浄化責任保護
スーパーファンドサイトの浄化責任を負っている企業のうち、以下の条件を満たす事業者
は免責される。
a.産業廃棄物の排出事業者または、収集運搬業者
有害物質の取り扱い量が液体100 ガロン、固体200 ポンド以下で、全ての廃棄、取り扱い、
輸送を2001 年4 月1 日以前に行っていた場合
b.生活系廃棄物(身の回りで出るごみ)の排出者以下の条件を満たす場合、免責される。
・住宅地の所有者、管理者、借地人である場合
・潜在的浄化責任の通知が届けられてから、さかのぼって3 年間の平均従業員数が100 人
以下で商業活動を営んでいて、かつ法律による小規模企業体に該当する場合
・廃棄物を発生させたNPO で、前の年の従業員数が100 人以下の場合
? ブラウンフィールド再活性化と環境修復
a.ブラウンフィールド再活性のための財政援助(補助金及びブラウンフィールド再活性化ファンド)
以下の財政支援関連施策が盛り込まれた。
・ 総額で年間2億ドルの財政援助(うち、5,000 万ドルまたは25%を石油関連物質のブラウンフィールドサイトに充当する)
・ ブラウンフィールドサイトの再定義
以下のように再定義し、ブラウンフィールドの範囲を拡張した。
「有害物質や汚染物質の存在、もしくは潜在的に存在しうることが確認されていること
により、増築や再開発、または再利用が困難と思われる土地」と定義し、産業用地以外の
土地、例えば住宅地や商用地等において過去の土地履歴等により土壌汚染が存在する可能
性がある場合の再開発時においても、財政支援の優遇措置を適用できることとなった。
・ ファンドの対象拡大
石油及び石油関連製品を対象に追加
・ ファンドから支出できる用途の拡大
サイト調査に対して20 万ドル以下、浄化に対して100 万ドル以下を対象として追加
b.ブラウンフィールド責任の明確化
以下の主体に対する責任を免除した。
・ 隣接所有者をスーパーファンド法の責任から免除(流れ汚染に対する保護措置)
・ スーパーファンドサイトの買い手の保護
・ 善意の土地所有者(適切な商習慣に従った土地の取得で、全ての適切な調査(AAI)を行っ
た上で土壌汚染の事実を知る余地がなかった場合)の保護
・ AAI の定義(AAI 自体はSARA で創設されたものであるが、何をどの程度行えばいいの
かが不明確であった。このため、ブラウンフィールド法が出来るまでのアメリカにおいて
は、環境アセスメントビジネスが発達し、フェーズ?調査として結実することとなる。)
c.州のブラウンフィールド対策プログラムへの支援
・ 毎年5,000 万ドルまでの補助金を州対策プログラムに支出
・ 対象サイトの拡大
4.1.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
土壌汚染情報は土地の安全性を知らせる公益的な情報として位置づけられ、米国では、
多くの州が土壌汚染情報に関するデータベースを作成し、ウェブサイトでの一般公開を行っ
ている。ここでは、ニューヨーク市とオクラホマ州の取り組みについて取り上げた。
(1)ニューヨーク市
ニューヨーク市のブラウンフィールド問題への取り組みの12 の具体的な内容の一つとし
て、「潜在的なブラウンフィールドを把握するための過去からの土地利用のテータベースの作
成」が掲げられている。
【目的】
以下の3 点が示されている。
・ 潜在的でかつ優先的な取り組みが必要なブラウンフィールドを見つけること
・ 地区ごとのブラウンフィールドの再開発計画への基本的な情報を提供すること
・ すべての土壌汚染地の浄化と再利用活動の目標を明確にすること
【データベース作成方法】
以下の2つの方法が示されている。
・ 各種情報の収集
(環境関連の発行物・データベース、歴史的な地図、電話帳、財務記録などからの情報収集)
・ 年ごとのブラウンフィールド関連環境アセスメントへの要望についての問い合わせ
(2)オクラホマ州
社会環境の保全のためにブラウンフィールドの制度的管理が重要であるとの認識の下に、
オクラホマ州環境局では、ブラウンフィールドを含めた土地利用の管理に向けて法制度を整
備している。
土地利用管理の具体的な内容として、ブラウンフィールドの制度的管理についてのデータ
ベースをくまなく蓄積している。
4.1.3 浄化修復目標の設定
ブラウンフィールドの浄化修復目標に関しては、汚染されている土壌の位置(地表からの
距離)、汚染の程度、その跡地における将来の用途などを考慮して、人体に対する曝露の危険
性(リスク)を計算し、そのリスクに応じて、環境浄化修復手法を選択する「リスクベース
基準」に基づき設定する方法が一般的になっている。
跡地が工場用途になる場合と幼稚園の砂場など子供が土で遊ぶ場所とでは、当然に浄化修
復レベルは異るという考え方をとっており、そのために必要な事業方法、費用も異なる。
このため、リスクベース基準の適用においては、跡地の用途が将来にわたって遵守される
必要があり、基準の設定とともに用途制限措置の設定が重要となる。
(1)浄化修復目標の設定及び適用方法に関する分類
米国の各州の浄化修復目標の設定及び適用方法は大きく、表4.1.1 に示す3つに分類され
る。また、それぞれの分類のうち、一つの州ずつ、内容の把握整理を行った。
表4.1.1 米国各州の浄化修復目標の設定及び適用方法の状況
(2)マサチューセッツ州
マサチューセッツ州の浄化修復目標の設定にあたっては、汚染された土壌や地下水の人体
及び環境への曝露の程度とともに、将来の跡地利用方法を密接に考慮して設定しており、こ
のため、土壌汚染が存在する土地に対して、その用途制限も行っている。
1)土壌の環境基準
土壌環境基準は3 つの土壌分類によって異なる基準が定められている。分類は、土壌に対
する可触可能性、受容者の存在の性質、土地の利用頻度、土地の利用の強さの4 つの土地固
有の要素によって分類される。これらの土壌分類は、土壌の受容者に対する曝露の程度を規
定しているものであり、これらの分類は互いに排他的である。
【マサチューセッツ州の土壌の環境基準】
S-1:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい(主に住宅・学校など)
現在又は将来において人間が摂取する野菜や果物を育てるため利用することができる
子供の頻繁な利用または、熱心な利用が行われる可能性が高い土壌はS-1 に準ずる
大人の頻繁かつ熱心な利用が行われる可能性が高い土壌はS-1 に準ずる
S-2:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい
子供の頻繁な利用も熱心な利用も双方とも行われる可能性が低い土壌はS-2に準ずる
子供が対象地に立ち入らず、大人の頻繁な利用又は熱心な利用が行われる可能性が高い土
壌はS-2 に準ずる
S-3:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい(駐車場の下など)
子供が対象地に立ち入らず、大人の頻繁な利用または熱心な利用が両方とも行われる可能
性が低い土壌はS-3 に準ずる
表4.1.2 マサチューセッツ州危機管理計画の土壌カテゴリー
2)地下水の環境基準
地下水環境基準は、地下水の汚染の結果に由来する異なる曝露の可能性を規定する3 つの
地下水分類によって定められている。これらの分類が異なる曝露の可能性を規定しているた
め、地下水の分類は互いに排他的ではない。すべての地下水は最終的に地表水に流れ出す可
能性があると考えられるため、すべての地下水はGW-3 の分類の水質基準を遵守する必要が
ある。土地固有の要素により、GW-1 やGW-2 に分類される可能性がある。
【マサチューセッツ州の地下水の環境基準】
GW-1:飲料水としての現在または将来の利用の可能性に基づき保護されるべき分類
GW-2:屋内の空気に対する揮発の水源となってもよいとされる分類
GW-3:石油や危険物質を地表水に対して放出する可能性がある分類
(2)カリフォルニア州
カリフォルニア州のブラウンフィールド浄化修復活動への要請事項は、NCP(国家石油及
び危険物汚染緊急対策)と連邦政府のスーパーファンド法の規定に準拠している。NCP の浄
化目標では、土壌別の基準というよりも発癌性の物質では10-4 から10-6 までの範囲に収まる
よう浄化修復を達成することといった基準であり、特定のサイトごとのリスク分析に基づい
て目標水準を設定し、跡地の土地利用に関係なく永続的な浄化修復を行うことを推奨している。
一方、EPA では、このような目標水準の実行可能性や、商業や産業用途の再開発が多い中
で、一律に住宅用途に対応した浄化修復を行うことは必要以上の対応であるとの判断を持っ
ており、跡地の土地利用に対応した浄化修復目標の設定を許容している。これは、リスクベ
ースのアプローチといわれており、浄化修復コストや健康リスク、跡地の土地利用、地域コ
ミュニティの許容性、技術的可能性などのさまざまな要因のバランスの下に浄化修復目標を
設定する方式である。
しかし、この方式は多くの環境上の判断を必要とし、恣意的に水準が適用される場合もあ
り、また、費用を節約するために必要とされる水準以下の浄化修復を行うことにより、汚染
物質が残存する問題も生じている。
これらの点から、カリフォルニア州としては、一律的な浄化修復目標水準の設定は難しい
と判断し、汚染地域の浄化修復事業に対して、以下の3 つの戦略により対応している。
【浄化修復目標水準設定の戦略】
a.バックグラウンドレベル(汚染されていない状態)までの浄化修復に向けての水準
バックグラウンドレベルについての一定不変の水準を持っている訳ではなく、各部局で
個別に設定している。
b.個別汚染地域ごとのリスクアセスメントに基づく浄化目標水準の設定
個別汚染地域ごとのリスクアセスメントに基づく浄化目標水準を設定し適用することを、
カリフォルニア州の基本的アプローチとしている。
c.州全体からのリスクベースの浄化目標水準の設定
以下の要因によるタイプ別リスクの想定に基づき、浄化目標水準を設定する。
開発事業者はまず、これらのタイプ別水準から控えめな水準との比較を行い、より高い
水準で比較する場合には、汚染地域ごとに実施するリスクアセスメントに基づく浄化目標
水準を適用する。
【タイプ別リスク設定の要因】
・汚染物質の人体への取り込みかた(摂取、吸入、皮膚からの感染)
・汚染源(土壌、空気、地下水)
・周辺土地利用(住宅地、商業地、工業地)
(3)ニュージャージー州
ニュージャージー州では浄化修復活動を行う上での目標水準として、リスクベースの基準
に基づき、以下の3 ケースに分けて、土壌と地下水に分けて設定している。
【浄化修復の目標水準】
a.無制限の跡地利用に対応する水準
b.条件付きの跡地利用に対応する水準
c.自然の自己回復力を考慮した条件付きの跡地利用に対応する水準
【浄化修復の目標水準の適用上の留意点】
・ これらのどの分類についても、汚染原因物質は除去されなければならない。
・ 土壌汚染物質については、発癌性のあるもの、非発癌性のものに分けて設定している。
・ 土壌の浄化修復においては、リスクアセスメントに基づいて設定された特定ケースの基
準の適用も認めている。
・ 適用される水準がそのサイトの周辺地区の水準よりも低い場合は、周辺地区の水準を適
用する。
・ そのサイトの土地利用が制限されている場合は、特別の注意書きを表示する必要がある。
4.1.4 制度的管理
制度的管理とは、ブラウンフィールドに対して、土地利用制限及び法的な管理により、健
康や自然環境への潜在的な被害を最小限にしつつ、ブラウンフィールドの有効利用を適切に
確保する法的措置等の取り決めを意味し、以下に示すブラウンフィールドの環境改善の一般
的プロセスのうち、段階5 に位置づけられる。
【環境改善の一般的プロセス】
段階1:地歴調査・聞き取り調査予備的な調査及び環境関連部局への通知と早期リスク削減措置の必要性の判断
段階2:包括的な土壌調査(アセスメント)、用途に対応したリスク影響調査アセスメントの実施により、汚染の原因、特性、程度、潜在的な影響の把握
段階3:環境改善計画の立案浄化計画とプロセスの評価、決定
段階4:浄化修復事業の実施
段階5:制度的管理継続的な浄化水準の維持管理
一部の州では、土壌汚染処理コストを低減させて土地の再利用、用途転換を円滑にするた
めに、人体の健康に対するリスクがない範囲において封じ込め等の部分的な処理を認めてい
る。このような完全浄化以外の対策が実施される場合には、土壌汚染による人体への暴露リ
スクを低減するために、一般の用途地区に上乗せするかたちで、土地利用制限などの制度的
管理が行われる。
制度的管理の目的は、土壌や地下水に含まれる未処理の汚染が人体に対して暴露する危険
性を管理するために、ブラウンフィールド再開発後の用途及び活動を限定して汚染土壌の封
じ込めを維持するためのものである。
(1)活動用途制限
マサチューセッツ州では、全米でもいち早く土壌汚染の制度的管理手法を導入しており、
AUL(Activity and Use Limitations)と呼ばれている活動用途制限を設けている。このAUL
は、現在及び将来の土地所有者に対してその土地で許容される活動や利用が示されており、
許容されていない用途に変更する場合は、新しい用途に応じたリスクの評価と追加的な浄化
が求められる。
この制度は、土壌汚染を全て除去するためには多額の費用がかかり、跡地利用にとって現
実的な解決策ではないため、汚染土壌を地下に残したまま人体に対して暴露されることを防
ぐために、土壌汚染が存在する土地に対して用途制限を行う制度である。
許容される土壌汚染の暴露の程度は汚染された土地の跡地利用によって異なるため、跡地
利用に応じて到達すべき浄化目標を設定して、その目標達成に適した方法で浄化を行う。こ
の浄化は、汚染自体の濃度を下げることのみでなく、汚染に対する暴露を取り除く、もしく
は最小化することでもよい。完全浄化によらず、汚染が残された場合には、活動利用制限を
設定して将来にわたり汚染の暴露状態が変わらないように継続的に土地を管理していくこと
になる。
マサチューセッツ州では、図4.1.1 に示す体制でAUL を実施している。用途制限されてい
る土地のAUL に係る情報は、州環境保護局のほかに自治体と郡不動産登記所で管理してお
り、この土地の再開発や土地取引に際しては、環境通知書によって土壌汚染の扱いが確認さ
れている。
図4.1.1 マサチューセッツ州の土壌環境情報管理体制
(2)制度的管理の実施方法に関する分類
米国の各州の制度的管理の実施方法で分類すると、多くの州では長期間モニタリングを実
施してブラウンフィールドを管理しているが、データベースを構築して経過追跡のみにとど
まっている州もみられる。表4.1.3 に示す分類のうち、カリフォルニア州及びルイジアナ州
における制度的管理の内容を以下に示す。
表4.1.3 米国各州の制度的管理の実施方法の状況
(3)カリフォルニア州の制度的管理の内容
カリフォルニア州毒物管理局(DISC)では、すべての浄化修復活動を長期間管理する方針
であり、以下の事項について実施している。
この中で、浄化修復用地の用途制限については、いろいろなメディアを用いて、情報を公
表しており、もし、用途制限をする必要がないレベルまで浄化修復された場合は、用地リス
トから除外し、逆に用途に見合ったレベルまで浄化修復されていない場合は、必要なレベル
までの浄化修復を行う財政的な裏付けを要求する。また、浄化修復活動が完了していない場
合は、継続的に浄化修復活動を行っているかどうか定期的に検査する。
【カリフォルニア州の制度的管理の内容】
・浄化修復活動完了時の検査
・モニタリング(契約事項の遵守徹底)
・インターネット上での浄化修復用地の用途制限の公表
・浄化修復用地周辺地区への掲示板での通知
・周辺住民への郵便による通知
・新聞紙上での注意広告
(4)ルイジアナ州の制度的管理の内容
ルイジアナ州環境管理局(DEQ)では、用途制限のある自主的な浄化修復活動については、
インターネット上で公表できるデータベースにより追跡的に監視している。
このデータベースでは、当該サイトの住所、用途制限、過去からの土地所有者、用途の履
歴とともに危険物取扱いの有無の情報が、土地所有者からの届出に基づき、登録されており、
DEQ の承認が無ければデータベースから除外できない。また、正確な情報が登録されていな
い場合は、当該サイトの取引契約を買い手側が解約できる根拠ともなる。
4.1.5 財政支援施策
ブラウンフィールドの浄化修復は、土地の安全性の改善や土地取引の活発化、都市の活性
化といった効果が見込まれる反面、多大な費用を要するため、当該用地の保有者が浄化修復
によるメリットが見込まれない場合は、そのまま土地利用の停滞状態が続く可能性もある。
このため、ブラウンフィールドの浄化修復を促進するために、用地の保有者や開発事業者
に財政的支援を講ずることは有効な施策となる。
ブラウンフィールド浄化修復再生事業に対する財政的な支援策としては、補助と融資、税
制措置に大別される。
ここでは、まず、米国の各州の財政支援策を総括的に捉え、次いで補助と融資について、
連邦政府の適用条件、主要な州の支援内容、適用条件について整理する。
(1)米国の財政支援策の分類
ブラウンフィールドの浄化修復事業への補助については、ブラウンフィールド再開発への
補助を行っている州が最も多い。融資については、零細事業者向けとして、ドライクリーニ
ング事業者への融資を行っている州が最も多い。また、税制措置に関しては、固定資産税の
軽減措置を講じている州が最も多い。
表4.1.4 米国各州の財政支援策の制定状況
(2)連邦政府のブラウンフィールド支援プログラム
連邦政府のブラウンフィールド支援プログラムは主にEPA(環境保護庁)とHUD(住宅
都市開発省)によって行われている。特にEPA は、常に連邦のブラウンフィールド政策のイ
ニシアチブをとり続けてきた機関であり、多くの支援プログラムを用意している。
1)EPA のブラウンフィールド補助プログラムの概要
地域に根ざした環境保護の手段としてブラウンフィールド問題に対応するために、1994 年
からEPA は、官民のパートナーシップを促進し、ブラウンフィールドサイトを評価した上で
浄化し、かつ、再開発するための革新的・創造的な方法の構築を促進することを目的として、
ブラウンフィールド問題に対応した補助金プログラムを開始した。EPA は「州・部族・自治
体の環境・経済開発職員が、ブラウンフィールド活動を概観し、また地域の問題に対して地
域固有の解決策を実行するための支援を行う」ことを目的としており、自治体を中心に自治
体・地域が主導するブラウンフィールド再生の取り組みを支援する姿勢に徹している。また、
EPA は、またブラウンフィールド再生による経済的な利益が地域に維持され続けるようにす
るため、地域の環境職業訓練プログラムを作成するための資金を提供している。
EPA のブラウンフィールド補助金は、以下の4 つが主要なものである。
・ アセスメント補助金
・ 浄化補助金
・ リボルビング・ローン・ファンド補助金
・ 職業訓練補助金
2)EPA のブラウンフィールド補助金の申請要件
【内容】
アセスメント
リボルビング・ファンド(RLF)
浄化対策
【規模】
2007 年10 月申請分 7,200 万ドル、200 件を予定
【対象】
a.ブラウンフィールド(危険物質や汚染の存在あるいは存在可能性により、再開発や再利
用に問題が生じうる不動産)
b.ブラウンフィールド以外の追加適用対象
・規制薬物によって汚染されたサイト
・石油または石油製品によって汚染されたサイト
・廃鉱など鉱物資源の跡が残るサイト
【資格要件】
a.申請者の要件
・ 浄化したいとする土地を所有している団体(大学やNPO を含む)
表4.1.5 補助対象別の申請者タイプ
b.適用除外土地
以下のサイトは、補助金受給資格を有さない。ただし、2)から5)については、個別判断に
基づき対象とすることができる。
1) NPL に現在リストされているか、リストに向け提案されている土地
2) CERCLA の下で計画あるいは進行中の浄化がある土地
3) 閉鎖計画または許認可に規定される要件に従い、RCRA 閉鎖通知を提出した処分場である土地
4) PCB の漏出があった施設
5) 漏出地下タンク信託基金から資金を受けている施設
【補助金の使用制限】
補助金は下記の支払いに使用できない
・ 罰金
・ 連邦経費分担要求(例えば他の連邦基金で要求される分担金)
・ 一般管理費
・ 潜在的責任者として対応するための費用
・ 土壌汚染浄化関連法以外の任意の連邦法に対する遵法費用
・ ロビー活動費用など
3)ブラウンフィールド・モデル地域
ブラウンフィールド・モデル地域(Brownfield Showcase Community)は、20 以上の連
邦機関のパートナーシップ(注4)のもとで1998 年から行われたブラウンフィールド再生のモ
デル事業である。環境修復から地域開発まで多岐にわたるブラウンフィールド問題を解決す
るための、省庁間協力の事例として注目される。
1997 年5 月に、ゴア副大統領は、15 を越える連邦機関の資源を集めるためにブラウンフ
ィールド連邦パートナーシップ(BFP)を発表、1998 年3 月に、この連邦パートナーシップ
は、ブラウンフィールド上の共同作業の利点を実証するモデルとして、16 ヶ所のブラウンフ
ィールド・モデル地域を選定した。さらに2000 年10 月には、イニシアチブの成功を継続す
るために12 の追加のブラウンフィールド・モデル地域を選定している。
選定は基本的に都市レベルまたは地域レベルで行われ、対象都市のなかでもブラウンフィ
ールドを多く抱える特定の地区に対して、特に重点的に資金を投入している。ブラウンフィ
ールド・モデル地域は規模、資源および地域のタイプなど多岐にわたるが、古い工業地帯が
広がる米国北東部に特に集中している。
図4.1.2 モデル地域事業に指定された自治体の位置
? モデル地域事業の目標
1.ブラウンフィールドのアセスメント、浄化および持続可能な再利用を通して環境保護お
よび回復、経済再開発、雇用創出、コミュニティ再生および公衆衛生保護を促進する。
2.ブラウンフィールドを修復し再利用する地域の努力を支援する連邦、州、地域・民間の
動きを結びつける。
3.ブラウンフィールドに取り組む際に、行政と民間が協働することによって、よい結果が
得られることを実証する全国的なモデルを開発する。
連邦政府が1980 年代から取り組んできたスーパーファンド法にはじまる環境修復の取り
組みが、土壌汚染をはじめとする環境浄化に主眼をおいてきたのに対し、90 年代のブラウン
フィールド再生事業には、単なる土壌汚染の浄化にとどまらず、環境問題に関する市民の教
育から、周辺地区の再生、地域の雇用創出に至るまで、多面的な取り組みが求められるよう
になってきた。
スーパーファンドサイト(注5)は、その多くは浄化の優先順位付けから資金確保・浄化の
管理に至るまで連邦直轄で行われてきたが、ブラウンフィールド再生事業はスーパーファン
ドほど汚染の程度は深刻ではなく、土壌汚染の浄化と同程度、もしくはそれ以上に都市・地
区の再生と経済開発に主眼が置かれている。結果として、その実施は連邦機関(特にEPA)
だけで実施できるものではなく、すべてのレベルの政府、民間部門および非政府組織の間に、
より多くの協力と調整が求められた。
モデル地域事業は、土壌汚染の浄化から工場跡地さらには疲弊した工業都市全体の再生を
目指すブラウンフィールド事業へと展開するためのノウハウを連邦・州・自治体が一体とな
って作り上げるための重要なプロセスであった。
? 対象地域の利点
ブラウンフィールド・モデル地域に指定されることで、自治体は連邦からの重点的な支援
を受けることができる。自治体は、ターゲットとされた技術的・財政的援助から直接的な利
益を得ることができる。
中でも連邦政府の職員(主にEPA の職員)が、対象の自治体に出向し、技術的・財政的援
助の調整を支援する制度である。政府間要員配置(IPA)スタッフと呼ばれ、環境面の知識
や制度・補助金に不慣れな自治体職員を助け、2 年から3 年にわたって、対象自治体の職員
として地域のブラウンフィールド再生に取り組んだことの意義が大きかった。(注6)
(3)主な州のブラウンフィールド関連財政支援策の概要
1)マサチューセッツ州の財政支援策
マサチューセッツ州では産業開発局や環境保護局などの部局ごとにさまざまなブラウンフ
ィールド関連の財政支援策が用意されているが、補助に関しては、対象が自治体または非営
利団体に限られており、一般のブラウンフィールドについては低利融資の利用に限定されて
いる。
VCP(自主浄化活動)サイト数は、2006 年7 月までに34,312 件のサイトが報告されてお
り、このうち、4,735 件は現在、実施中である。毎年、概ね1,800 件の新規サイトが申請さ
れる。
? マサチューセッツ州産業開発局(Mass Development)が管轄する助成策
a.ブラウンフィールド再開発基金(BRF)(融資)
再開発を伴うブラウンフィールドサイトに対して、以下の融資が提供されている。
【財政支援規模】
・連邦政府からのブラウンフィールド補助金の10%が、サイトを指定したアセスメントや
再開発を誘導する浄化事業(Cleaning Projects)に使われている。
・2006 年 7 月時点で、15 箇所のサイトの調査と2 箇所のサイトの浄化事業に取り組んで
いる。
【融資の内容】
・ブラウンフィールドサイトの調査への低利融資
サイトの調査に対しては、上限10 万ドルまでの低利融資が提供される。
〈資格要件〉
・EDA(Economically Distressed Areas)地域内に位置していること
以下のどれかの条件を満たすこと
・ETA(Economic Target Area)地域として指定された地域または自治体であること
・ETA 地域としては指定されていないが、ETA 指定条件を満たしていること
・以前の用途がガス製造プラントであったこと
・申請者はサイトの所有者か浄化の実施者であること
・マサチューセッツ州の規定により認可されたサイトであること
・浄化事業への低利融資
サイトの浄化、修復に対しては、上限 50 万ドルまでの低利融資が提供される。
特に、優先プロジェクトについては、調査と浄化事業に対して上限200 万ドルまで融資
される。
〈資格要件〉
・EDA 地域内に位置していること
・申請者はサイトの所有者であること
・抵当保証が設定できること
? マサチューセッツ州環境保護局(Mass DEP)が管轄する助成策
Mass DEP のブラウンフィールド関連の助成策としては、以下のように対象が限定される。
a.水質浄化リボルビングファンド(SRF)(融資)
水質を改善するプロジェクトを対象に,期間20 年の低利融資(2%)が提供される。
b.調査及び浄化事業への補助(補助)
連邦環境保護庁(EPA)の補助の下、自治体や非営利団体を対象として、荒地となって
いるサイトの調査及び浄化事業に補助される。
【財政支援規模】
・2006 年の上半期で、概算で600 万ドル支援
このうち、110 万ドルは連邦政府から指定されているサイト
・2006 年 7 月時点で、4,200 万ドルが契約中
・1983 年以降で、累計1 億8,300 万ドルを支援
? マサチューセッツ州住宅・コミュニティ開発局(DHCD)が管轄する助成策
DHCD は連邦政府の住宅都市開発省、コミュニティ開発基金プログラムを実施する機関で
あり、人口5 万人以下の市や町を対象とし、低所得者居住地区のスラム化や環境悪化の防止、
緊急対応事業などに助成する。
ブラウンフィールド関連の助成策は以下のとおりである。
a.コミュニティ開発基金(補助)
自治体を対象に、プランニング、予備的な開発計画の検討、用地の取得、調査、浄化事
業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
b.Mini−Entitlement Program(補助)
自治体のMini−Entitlement 事業を対象に、プランニング、予備的な開発計画の検討、
用地の取得、調査、浄化事業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
c.産業開発基金(補助)
自治体の産業開発事業に補助され、プランニング、予備的な開発計画の検討、用地の取
得、調査、浄化事業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
d.コミュニティ開発行動基金(補助)
自治体を対象に、市や町の経済活性化や投資の活発化、長期の雇用創出、低所得者居住
地区の環境改善に資するプロジェクトに補助され、市街地整備の様々な事業に使われる。
e.優先的開発基金(計画立案等への補助)
自治体を対象に、計画立案、ゾーニング、住宅整備への教育・指導などに上限で5 万ド
ルまで補助される。多くの市や町では、住宅開発を誘発する計画立案のコンサルタント費
用として使われている。
? マサチューセッツ州税務局(Mass DOR)が管轄する助成策
a.地下埋設タンクプログラム(補助)
自治体を対象に、地下埋設タンクからの漏洩対策や地下埋設タンクの閉鎖などの活動に
補助される。
2)カリフォルニア州の財政支援策
カリフォルニア州では、環境調査に関して連邦政府からの補助が受けられる。浄化事業に
関する補助は特定のプログラム(下記の?)に限定されている。一般事業者の浄化事業に関
しては、専ら低利融資が受けられる。
VCP(自主浄化活動)のサイト数について、カリフォルニア州毒物管理局(DTSC)は平
均して常に300 箇所のサイトを指導・監督している。また、毎年、平均して125 箇所のサイ
トの浄化事業を完了している。
? ブラウンフィールドサイトの環境調査への補助
連邦政府環境保護庁(EPA)から、カリフォルニア州毒物管理局(DTSC)の支援を通じて応
募者に環境調査費用への補助が行われる。
? 自主浄化事業(VCP)への低利融資
・融資額
サイトの特性把握:最大 10 万ドル
サイトの浄化活動:最大 250 万ドル
〈VCP として認定される資格要件〉
・連邦政府や州政府のスーパーファンド法による対策地域、軍事施設、DTSC の
管轄外のサイトでないこと
〈融資の適用条件〉
・事業用の用地であること
・産業、商業、非営利団体・スモールビジネスの立地が予定される再開発用地であること
? 浄化事業への補助等
以下のプログラムが用意されている。
・再開発局環境監視協定プログラム(EOA)
・学校用地の環境評価・浄化プログラム
・地下埋設タンク浄化基金プログラム(UST)
・毒物管理会計(TSCA)
3)ニュージャージー州の財政支援策
ニュージャージー州では、一般事業者の浄化事業に関しては、専ら低利融資が主要な助成
策となっている。革新的技術で浄化した場合などの特定の条件を満たす場合には、補助も行
われている。
以下の財政支援プログラムの下に、多数のサイトが浄化事業を実施中である。2002 年には、
危険物放出サイト修復基金では、156 サイトの浄化事業を完了しており、総額で1,500 万ド
ル以上の融資や補助が実施された。また、200 サイトが検査中である。
NJDEP では、常に23 千箇所の汚染サイトを監視しており、その内の1 万箇所は潜在的な
ブラウンフィールドサイトである。
? 危険物放出サイト修復基金(低利融資、補助)
・一般のサイト(低利融資)
危険性の高いサイトの修復に関しては、一般のサイトでは最大で100 万ドルまで融資
・地方自治体(補助)
地方自治体に対しては、所有者のはっきりしないサイトや無償譲渡されたサイトなどの浄
化のために、最大で200 万ドルまでの補助または融資
? 水資源関連のブラウンフィールドサイト浄化に対するニュージャージー州インフラ基金に
よる低利融資
? 革新的技術で浄化した場合や制限無しまたは一部制限付き再利用が可能なサイトの浄化費
用への補助(25%まで)
4.1.6 環境負債免除制度
米国における最初の土壌汚染に関する法律としてのスーパーファンド法(包括的環境対処
・補償責任法)は、不可逆的な環境汚染の拡散の防止のために、非常に厳しい規制を課して
いる。その最も厳しい点として、土壌汚染の浄化責任を現在及び過去の土地所有者に求めて
おり、現在の土地所有者が汚染の原因者でなくても浄化責任を求められる可能性があること
があげられるが、その影響として、土壌汚染浄化の可能性がある土地については浄化コスト
のリスクを伴うため、都市部の再開発から取り残されてしまうという問題を生じさせてしま
っていた。このような問題を改善し、土壌汚染地の開発を積極化していくための制度として、
以下の制度がつくられている。
○ 自発的修復制度(VCP:Voluntary Cleanup Program)
スーパーファンド法による浄化義務発生リスクを回避し、土壌汚染地の再開発を促進す
ることを目的としており、浄化修復事業は民間側が主導的にすすめることができるよう前
項で記述した各種財政支援策が用意されている。
○ 環境負債免除制度
民間側の浄化修復事業が事前に州当局と協議した計画に基づき実施され、完了した場合
に、州政府は修復完了を承認し、将来にわたる環境負債を免除するものとして、以下の証
明書を発行する。
・ 修復完了証(No-Further-Action letter)
浄化の完了及び追加的な浄化措置が不要であることを証明する
・ 訴追免除証(Covenants-Not-To-Sue)
将来にわたって同一理由による汚染修復責任を求める訴追を原則として受けなくてよい
ことを証明する
以下で各州の環境負債免除制度及び小規模事業者責任免除制度について把握整理する。
(1)環境負債免除制度
ブラウンフィールドへの取り組みとして、ほとんどの州が自発的修復制度及び環境負債免
除制度を関連法制度に盛り込んでいる。それらの州のうち、マサチューセッツ州、カリフォ
ルニア州について、その概要を整理する。
1)マサチューセッツ州の環境負債免除制度
マサチューセッツ州の環境負債免除制度の特徴は、責任軽減制度の導入と浄化管理の民間
化によって、効率的で迅速なプロセスを実現している点にある。マサチューセッツ州は、汚
染責任者に対して厳格な連帯責任を課している。汚染責任者は、自主的に土地を浄化するこ
とが認められており、もし自主的な浄化が行われない場合には、マサチューセッツ州開発局
(MADEP)が浄化を代行し、かかった費用を回収することができる。
実際に、自主的浄化の割合が95%と非常に高い。これは、マサチューセッツ州開発局の
担当者が、積極的にインセンティブ活用を推進するブラウンフィールド・コーディネーター
となり、民間事業者の側に立って自主浄化を促していることもあげられる。
? 責任免除制度の提供
責任免除制度は、民間事業者が再生事業に参加する際に最も重要になる制度である。マ
サチューセッツ州は、全米でも早い時期に責任免除制度を創設、提供を開始した州である。
? 訴訟免除契約書の発効
ウースター市のメディカル・シティ・プロジェクトの過程で、ウースター再開発公社か
ら、民間事業者に土地を売却する際に、州政府が発行したCNTS がその原型とされる。ブ
ラウンフィールド訴訟避止誓約書は、1998 年のブラウンフィールド法によって正式に制度
として認められた。現在はマサチューセッツ州法務局によって、各々の関係者に合わせた
責任免除措置が与えられている。
? 跡地利用制限がある場合の責任免除制度
土壌汚染がある土地を浄化する際に、経済的な理由から全ての汚染を除去せずに、一定
の汚染を残したまま、封じ込めなどの処理する場合がある。この場合、跡地の活動用途制
限(AUL)が土地に付加される。AUL のある土地に対してもAUL の変更を行なわない場
合、責任免除制度の適用が可能である。
2)カリフォルニア州の環境負債免除制度
カリフォルニア州のブラウンフィールド対策の基本として自発的修復制度(VCP)が位
置づけられている。浄化修復事業者は、浄化事業中はカリフォルニア州毒物管理局(DTSC)
の監督を受け、修復が完了した時点で、以下の2種類の証明書のどちらかを発行する。
しかし、これらの保証があっても将来時点で第三者機関による浄化活動を除外しない。ま
た、浄化活動が進行中であっても、事業の完了と維持管理が確保されるとの合意があれば保
証書は発行される。
・ 修復完了証(No-Further-Action letter)
一部、汚染が残っていても、人体や環境にほとんど影響が無いレベルまで浄化された場合に発行される
・ 完結終了証(Certificate of Completion)
浄化目標水準を完全に達成した場合に発行される
(2)小規模事業者責任免除制度
小規模事業者責任免除制度は、ブラウンフィールドプログラムのより効率的な実施と再開
発促進のため、連邦政府環境保護局により2002 年に法律が施行された。この法律での小規
模事業者とは、有害物質の保有量が液体100 ガロンまたは固体200 ポンド以下で、2001 年
4月1日以前にすべての有害物質の廃棄、取り扱い、輸送を行っていた事業者である。
各州の小規模事業者責任免除制度に対応する取り組みをみると、ドライクリーニング事業
者の汚染サイトに対する環境対策プログラムとして制度化されており、どの州でも財政イン
センティブが合わせて講じられている。
【小規模事業者責任免除制度を持つ州】
・ ウィスコンシン州 −ドライクリーニング環境対策プログラム
(ドライクリーニング環境対策ファンド)
・ サウスカロライナ州−ドライクリーニング事業者のための環境指導書
(ドライクリーニング修繕トラストファンド)
・ フロリダ州 −ドライクリーニング有機溶剤浄化プログラム
(ガソリンスタンド、ドライクリーニング店向け浄化ファンド)
・ カンザス州 −ドライクリーナー環境対策プログラム
(ドライクリーニングファンド)
・ テキサス州 −ドライクリーニングによる汚染サイト対策プログラム
(ドライクリーニング浄化支援プログラム)
・ ミズーリ州 −ドライクリーニングによる汚染サイトの再利用活性化支援プログラム
(ドライクリーニング信託投資ファンド)
4.2ドイツ
4.2.1 連邦土壌保護法制定の経緯
ドイツにおいても、1980 年代から土壌汚染問題への対応が本格化したが、当時は、個々の
法律(州レベルの土壌保護法、州レベルの廃棄物法など)ごとの個別的な対応であったり、
州ごとにばらばらな規制を行っていたりして、規制の不整合の問題が生じていた。しかし、
1999 年3 月に連邦土壌保護法、同年7月に連邦土壌保護土壌汚染令の施行により土壌汚染リ
スク管理が統一された。
4.2.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
ドイツにおいては、都市計画決定の権限や土壌汚染地の浄化修復についての自治体の役割
は極めて大きい。このため、土地利用計画の安定性を担保するためにも、土壌汚染情報の収
集は重要となっている。土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動してい
るため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしている。
具体的には、自治体レベルで土壌汚染の可能性のあるサイトを把握して土壌汚染情報をマ
ップに落として公表しており、また、土壌汚染に関する統計データも自治体から、州、連邦
政府へと段階的に上げられて整備され、公表されている。
ドイツにおいては、ブラウンフィールドは最終処分場跡地と産業跡地という広い意味で用
いられており、統計によれば、この該当サイトは231 千箇所あり、また土壌汚染が特定された
サイトは11 千箇所、浄化が終了しているサイトは14 千箇所、リスク評価が終了しているサ
イトは37 千箇所と集計されている。
ドイツにおいては、図4.2.1 に示すとおり法がカバーしている土壌汚染の範囲は広く、「予
防」段階から「危険防止」段階に分かれ、法的に対策が求められるのは「危険防止」段階以
上となる。ただし、「危険防止」段階でも、土地利用用途ごとの基準値と照らし合わせて、概
況調査で終わってよいもの、詳細調査まで進むべきものに分けられていく。
図4.2.1 土壌汚染の規制体系
【統計データにおける「土壌汚染」の分類】
・ ブラウンフィールドが疑われるサイト
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち旧堆積場
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち産業跡地
・ ブラウンフィールド
・ 浄化完了サイト
・ リスク評価完了サイト
・ 浄化中サイト
・ モニタリング中サイト
4.2.3 浄化修復目標の設定
ドイツにおいては、ブラウンフィールドサイト毎に「浄化計画」を作成し、目標水準は個
別に設定することを基本とする。その目標水準は、開発用途などを総合的に考慮して決定さ
れるため、米国の各州で基本的考え方となっているリスクベースの浄化修復目標水準の設定
と同様に経済合理性の視点が取り込まれている。
また、ドイツは都市計画決定に関して市町村が強力な権限を持っており、浄化修復目標の
設定や跡地の利用形態の決定に市町村が全面的に関与している。ブラウンフィールドに関連
して、健康的な居住や就労環境の確保は都市計画を定める中で、重要な配慮項目となってい
る。
(1)浄化計画と行政契約
土壌汚染の存在が確認された土地では、まず浄化のための概況調査が実施され、浄化目標、
浄化手段、費用などが定められた浄化計画が作成される。この浄化計画は、事業者側で作成
し、行政当局に提出して、公法上の手続きである行政契約によって合意形成される。
浄化後のネットバリューがマイナスになった場合、その相応額を行政が補助金で負担する。
また、浄化後の取引価格が顕著に上回った場合は、逆に費用返還請求できる制度となって
いる。
行政契約のメリットとして、行政手続きリスクの減少と手続きの迅速化があげられる。
浄化計画で定められる事項は以下のとおりであり、浄化方法、費用だけでなく、都市計画、
建築、水質保全、公害防止など都市開発に伴う関連許認可項目が網羅的に含まれている。
【タイプ別リスク設定の要因】
・ リスク評価の概要
・ 浄化対象用地の旧来そして将来の用途
・ 浄化目標
・ 費用見積り、資金計画
・ 浄化目標の達成に必要な除去、隔離、制限、自己管理措置 等
・ 浄化、品質保証のモニタリングコンセプト・一連の手続きに要する期間 等
(2)用途別基準の設定
ドイツでは詳細調査や浄化対策の必要性の判断を行うために、用途別基準が設定されてい
る。一度決められた土地利用計画は将来変わることは少ないと固定的にとらえられているた
め、経済合理性のある用途別基準が重みを持って用いられている。
調査値は、用途別汚染物質別に設定されているが、対策値はダイオキシン/フランのみし
か設定されていない。対策値は地域の特殊性を考慮して設定することが基本となっている。
【用途の分類】
・ 子供の遊び場
・ 住宅地域
・ 公園・レジャー施設
・ 工業、産業用地
4.2.4 制度的管理
ドイツでは、市町村が強力な都市計画決定権限を有しており、都市計画制度が土地利用用
途を厳格に管理している。F―プランといわれる行政内部の長期的な土地利用計画とB―プラ
ンといわれる私権を制限する強制力のある地区詳細計画があるが、計画策定に当たっては、
健康的な居住・就労環境の確保が重要な配慮事項とされている。各土壌汚染サイトの浄化レ
ベルは、開発用途等を総合的に勘案した上で個別に作成される浄化計画によって決められる
ため、都市計画と連結している。
また、浄化修復後の浄化水準チェックのためのモニタリングの方針を浄化計画に定める事
項としており、制度的管理においてモニタリングが重要な位置づけにある。
土壌汚染対策の流れは図4.2.2 に示すとおりであり、以下の点に特色がある。
・ 土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動しているため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしていること
・ リスク評価の段階で用途別の基準値を用いていること
・ 浄化とモニタリングの段階では目標が一律に定められておらず、それぞれのサイト毎に
浄化目標と浄化計画を定める浄化契約を自治体と結んで、対策及びモニタリングが実施さ
れていること
図4.2.2 土壌汚染対策の流れ図
4.2.5 公的関与
ブラウンフィールドの再開発において、採算がとりにくく民間が手を出しにくい土地に対し
ては官主導の色彩が濃くなり、自治体が基本的に公費で土壌汚染対策を実施して民間投資を誘
発して再開発を行い、開発後に得た開発利益を官民で分けている。フランクフルト西港開発の
事例では、市が土壌汚染を除去して用地をデベロッパーに売却し、開発・販売・分譲により得
た開発利益を市とデベロッパーとで折半する契約となっている。また、ノルトホルン再開発事
業の事例では、相当深刻な土壌汚染があって開発計画は一時頓挫していたが、市が様々な工夫
によって浄化対策を行って民間投資を呼び込んでいる。誘発された民間投資が大きいというこ
とで、市による公費投入が正当化されている。
(出所) Umweltbundesamt 資料、Osnabrueck 市資料より作成
5.土壌汚染地における土地の有効利用促進等に向けた課題
2.2でも述べたように、土壌汚染問題に対する一般的理解が不足していることから、我が国
においては土壌汚染に関する情報は秘匿されがちであり、容易に公にはならず、一般社会では土
壌汚染が特別なものだと思われている。その結果として、土壌汚染が公表された場合には、報道
等でことさら大きく取り上げられ、それが仮に軽微であっても、社会的には過剰反応しがちであ
る。また、この現象により土地所有者などは公表を拒むこととなり、結果的に悪循環となってい
る。
しかしながら、我が国は火山国である事から、重金属の自然含有レベルは高く、時に環境基準
を超過する土壌があることや、現在では汚染責任的には容易に対処のしようがない過去の含有レ
ベルの高い臨海の埋立地の土壌などの存在は、決して特別なものではない。それらの土地を健康
リスクの観点から見た場合、多くは他のリスクと比較して過剰反応するほどの大きなものでなく、
対応は充分可能なレベルであると考えられる。
土壌汚染が社会問題化するのは、土壌汚染自体が新しい概念であり、それらを大きな問題とし
ていない考え方や商習慣であった土地利用や土地取引への仕組みが充分に対応しきれていないこ
とによる。すなわち、対象とする物質は工場内等で管理されてきた事に対して一般的には積極的
にオープンにされていなかったにもかかわらず、その情報を求める必要性のある土地利用や土地
取引とのやりとりにまだ大きなギャップがあるまま、社会が動いてしまっているためである。
以上のような現象は、我が国よりも早くから土壌汚染の概念を導入してきた諸外国においても
見られており、それぞれの国の法令や、都市計画などの仕組みの中で対処されてきた事実も、本
年度の検討で明らかになった。特に安易に土壌汚染を放置することなく積極的に管理を行ってい
く取り組みはブラウンフィールドの対処法に関して多くの示唆があった。
現在我が国で起こっているギャップを埋めるためには、海外の取り組みも参考にしながら、単
なる規制ではなく、国民が土壌汚染の実態を認識した上で、土壌汚染の問題に対して適切な対応
をし、土地取引における問題の解消と我が国なりの法令、仕組みや国民性に適応した合理的な土
地利用を促進する必要がある。
5.1 更なる実態・影響の把握
土壌汚染に関する情報については、土壌汚染対策法が、民間の事業者が自主的に行った調査
結果の届け出を義務づけていないことに加え、自治体によって、自主調査結果についても届
け出を義務づけた上で公開するところ、できるだけ届け出るよう指導するところ、そもそも
届け出を義務づけていないところなど、そういった自主調査結果に対する取扱いが異なるこ
とから、個別の土壌汚染サイトに関する情報(調査、対策の状況やその所在地等)は、なか
なか公にならない現状がある。
土壌汚染に係る施策の必要性等を検討するためには、土壌汚染が土地取引や再開発等の支障
となっている事例を当該事例における土壌汚染の管理の実態と併せて可能な限り多く把握
し、その原因等を分析することが必要である。しかし、現時点ではそのような事例を十分に
把握しているとは言い難いことから、今後も企業や地方公共団体等へのヒアリングや調査等
を積み重ねていく必要がある。特に、どうしようもなく動かなくなった土地は商取引の場か
ら外れることにより非常に顕在化されにくいという意見が多く、5.2以下に掲げる課題を
検討し、次のステップに進むための前提としても、さらなる情報収集が必要である。
5.2 土壌汚染情報のデータベース化
5.2.1 土壌汚染情報データベースの構築
前述したとおり、基本的な土壌汚染情報が不在又はアクセス困難であるため、マンション購
入後に土壌汚染が発覚し問題となったり、再開発計画を着手後に見直さざるを得なくなる等
の支障が生じている。しかし、土壌汚染情報は、土壌汚染地の周辺住民や購入者にとっても
利害関係を有するという意味では、土地の安全性に関する情報として公益的な側面を有する
ものであるから、広く情報を共有することを検討すべきである。
この点米国では、4.1.2で述べたように、多くの州が自ら情報を収集したり、届け出や
問い合わせがあった情報を元にして、土壌汚染情報のデータベースを作成し、インターネッ
トで公開している。
これを踏まえわが国でも、全国的な土壌汚染情報をデータベース化し、インターネット等に
よりその時点の状況を誰もが閲覧できる仕組みが存在すれば、土地取引の円滑化や浄化措置
の促進・早期化等に資することになるとも考えられる。
ただし、こういったデータベースを構築・公表する場合、そもそも情報の入手手段が限られ
ており、また、情報の正確性に細心の注意を図る必要があることから、引き続き、情報の入
手源や入手方法について検討すると共に、その情報の元となる調査の信頼性及び正確性をい
かに担保するかという点や万が一公表した情報が誤っていた場合に、当該データベース作成
者の責任の射程及び当該情報を利用した結果他者に危害を与えてしまった者の責任の射程に
ついても併せて検討しておく必要がある。
なお、土壌汚染情報データベースの一類型として、浄化が完了したサイトに関し、当該サイ
トの土質や浄化が完了した旨を公表するようなデータベースを構築することも、土地取引の
円滑化等に資すると考えられることから、こうした点についても検討する必要がある。
5.2.2 土壌汚染要調査マップの作成
しかし、わが国においては、5.2.1で述べたように情報の収集方法等を検討しなければ
ならず、土壌汚染情報データベースの構築はすぐには開始できない。
この点ドイツにおいては、4.2.2で述べたように、土壌汚染が存在する結果開発がスト
ップしているサイトに関する情報のみならず、産業跡地である等の理由により土壌汚染が存
在する恐れがあるサイトに関する情報を収集し、地図上に落とし込んで公表している。
そこでわが国においても、個別サイトを対象にしたデータベースを構築するための前提とし
て、公的なリーダーシップのもとにフェーズ?程度の地歴調査を行ったうえで、過去に工場
が立地している等の理由により、土壌汚染されているおそれが高いサイトや地区を地図上に
記載した、「土壌汚染要調査マップ」をリスクアセスメント手法を活用しながらひとまず作
成することも有効であると考えられる。
「土壌汚染要調査マップ」の作成により土壌汚染要調査情報が世の中に浸透すれば、土壌汚
染に関する情報を公開することに抵抗を感じにくい土壌の醸成につながり、土地取引・土地
利用における土壌汚染の存在を特別視しないで行えることが期待される。結果として、比較
的スムーズに土壌汚染情報データベースが世の中に受け入れられ、より効率的な土壌汚染へ
の対応が可能になるものと考えられる。
5.2.3 自然由来の土壌汚染データベースの構築
自然由来の土壌汚染については、地質的に一定の地域内に幅広く分布する等の事情により、
その地域固有の特性と考えて対応する必要がある。すなわち、仮に掘削除去による完全浄化
をするとしても、どこまで掘っても汚染土壌が出てきてきりがないという場合がありうる。
したがって、対策をすべき土地とそうではない土地の線引きを可能にするため、自然由来の
土壌汚染についてデータベースを構築することは、有用であると考えられる。またこれによ
り、汚染土壌による地下水への影響や残土の処理方法等を調査、検討することも可能になる。
なお、自然由来の土壌汚染は、汚染原因者がいないことから、いわゆる「汚染者負担の原則」
により浄化費用等を負担させることは困難であるが、情報の公開によって影響を受ける関係
者も少ないことが想定されるため、自然由来の土壌汚染データベースの構築・公開に対する
抵抗感は少ないものと思われる。
しかし、自然由来の土壌汚染については、前述したようにある地域内の土地全体に当てはま
る特性であることから、個別サイトごとの状況を考慮に入れれば足りる一般の土壌汚染の場
合とは異なり、面的に土壌汚染の状況を把握する必要がある。
こうした点からすると、自然由来の土壌汚染に関する情報を収集するためには一般の土壌汚
染の場合とは異なった方法が必要であると考えられることから、引き続き検討をしていく必
要がある。
5.3 公的支援の必要性
米国等においては、土地取引の活発化や地域の活性化が図られると期待される場合には、土
壌汚染地に対し、公的主体が浄化費用の一部を補助し、また、土壌汚染地について浄化を開
始又は完了したような場合には固定資産税の軽減を行う等の財政的支援を行っている。
一方わが国においては、土壌汚染が土地取引や再開発やまちづくりに影響を与えていると考
えられる具体的局面として次の場合が挙げられる。
・ 一般的に、大都市部においては、地価が高いため対策費を拠出することが可能であり、
現時点では土壌汚染が土地取引や再開発の支障となっている事例は多くないようである
が、地方部においては対策費の負担が大きければ土地取引や再開発が断念され、地域活性
化を阻害するおそれがある。
・ 小規模事業所等の場合、土地所有者に資力がないことが多いため、調査及び対策が困難
となる結果、土地取引や再開発に支障が生じるおそれがある。
土壌汚染においては、原因者負担が原則ではあるが、原因者に資力が無い場合や原因者が浄
化しただけでは十分な開発等が困難な場合であって、なおかつ、当該土地を活用して地域活
性化等の施策を講ずる必要がある場合には、上記のような局面について、米国等の例を参考
に、補助金、公的資金を投入した基金、税制優遇、公的主体による浄化措置等を検討するこ
とも考えられる。しかしながら、本研究会では具体事例の収集が十分にできず、具体的な検
討には至らなかったところである。
今後検討する前提として、上記に掲げるようなケースごとの実態を十分に把握・分析した上
で、公的支援の公益性及び必要性について検証・検討し、問題点を明確化するとともに、背
景となる事情や制度が我が国と異なることに留意しつつ諸外国の事例を大いに参考にすべき
である。諸外国の事例を検討するに際しては、公的資金の投入等により浄化をした結果とし
ての雇用創出の程度や税収増の割合といった当該施策の効果についても分析を加え、より効
果的なものを参考にすることが望ましい。
なお、地域活性化等の観点から公的資金の投入が難しい場合であっても、地域住民に健康被
害が生じている場合等は、別の観点から検討をしていくことが必要である。
5.4 サクセスモデルの構築
5.4.1 サクセスモデルの構築
2.2.2で述べたように、現在、土壌汚染を浄化する際には、掘削除去による完全浄化が
ほとんどである。掘削除去には莫大な費用がかかることから、特に地方部においては、都市
部と比べて、掘削除去費用が地価を超えてしまうことも往々にしてあり得、結果として土壌
汚染の存在する土地が開発、利用されずに放置されてしまうという事態がありうる。
そこで、地方部においても土壌汚染が存在する土地の有効活用が少しでも図られるよう、土
壌汚染が実際に存在する土地を取り上げ、原則として掘削除去以外の浄化措置を行うと共に
その後の土地利用の計画を策定した上で、その成功要因等を分析・研究するという「サクセ
スモデル」を構築・公開し、その構築が一定程度完了した時点で当該モデルを「ひな型」と
してまとめ、公表することが、土壌汚染地の有効活用のための現実的な有効策となり得ると
考えられる。
この際、例えば、昔は工場等が集積していたが今後は住宅地・商業地として再開発の可能性
が高い一定の駅裏等を対象に、調査、データベースの整備・公開、非完全浄化を含めた対策
等の一連の対応を実験的に行うことの必要性や実現可能性について検討する必要がある。
なお、掘削除去以外の浄化方法を選択した上で再開発等を行った海外の事例について研究
し、場合によってはその事例自体を「サクセスモデル」の参考として提示することもあって
良いと考えられる。
5.4.2 官民の連携
なお、「サクセスモデル」の構築に当たっては、土地の開発、建築、浄化等を行う民間事業
者と土地利用の計画を策定する公共主体がそれぞれバラバラに取り組むのではなく、計画の
段階から実際に浄化した上で開発する段階、さらには土地利用の状況をモニタリングする段
階に至るまで官民一体となって両者が連携、協働することが必要である。
その際、浄化方法と土地利用の方法がどのように対応できるか等、民間業者と公的主体のそ
れぞれがノウハウを蓄積させるとともに、そのために必要な人材を育成していく必要がある。
5.5 資産評価の一層の適正化
時価会計への一本化や今後の資産除去債務の導入等社会経済情勢の変化に伴い、不動産の経
済的価値を正確に評価することが一層求められている。
このためには、土壌汚染の専門業者が行う調査の標準化とそれを通じた専門業者の標準化を
進める必要がある。これにより、土壌汚染地の資産評価の適正化と、さらには、土壌汚染地
に係る安全で円滑な利用や取引が促進される。
一般的に不動産鑑定士は、土壌汚染について専門の業者と同じレベルの知識は有していない
ため、土壌汚染地に係る鑑定評価においては、専門の業者が作成したER の活用が重要となる。
また、不動産鑑定の実務面においても、運用指針の策定や研修、さらなる研究・検討が行わ
れているところではあるが、社会経済情勢の変化に対応し得るよう、引き続き不動産鑑定士
が土壌汚染状況の確認範囲等を明確化し鑑定評価に適切に反映するステップについて検討を
深めていく必要がある。あわせて、様々な汚染状況や対策方法に応じた評価を一層客観的に
行うことを求められることが想定され、スティグマについての評価方法や、掘削除去以外の
措置を前提とした鑑定評価の方法についてもさらに検討する必要がある。
5.6 その他の有効利用促進策
5.6.1 信託、ファンド、保険等のリスク軽減策
なお、土壌汚染リスクの適切な移転・軽減を図る方策として、限定責任信託、土壌汚染地
を買い取った上で浄化するファンド、適切な保険料による保険商品等の活用が考えられる
が、土壌汚染の実態を把握するための十分な調査が行われていないことなどから、いずれも
現時点では具体的な提案をし得る検討状況にはない。しかしながら、いずれも重要なツール
であり、今後リスク評価が進み、具体的な方策を検討しうると考えられることから、今後も
引き続き市場における状況を注視しつつ、必要に応じ活用方策を検討する価値がある。
5.6.2 土壌汚染の正確な知識の周知と土地取引の不正防止
欧米と異なり、我が国では、例えば工業用地から住宅地への用途変更が容易であることか
ら、少なくともその機会を捉えた土壌汚染状況の確認を行うことが重要である。また、土壌
汚染の可能性がある土地について、土地取引が行われる場合には、必要な情報が新たな所有
者に十分伝達されない恐れがある。さらに、土壌汚染に関わる不公正な土地取引が散見され
るところである。
ここで、このような用途変更や土地取引に際して、土地所有者、開発業者、建設業者等の
関係者、さらにはこれに関係する行政担当者等が土壌汚染について必要な知識を有していれ
ば、必要に応じて調査その他の対策を講じることが可能となることから、これらの関係者に
対し、同業者の会合や必要に応じた講習等を通じ、土壌汚染についての正確な知識を周知す
るとともに、土地取引に関する不正の防止に努めていくことが必要である。
また、5.4.2で述べたような官民の連携を進めていく前提として、官の側も土壌汚染
について必要な知識をもつことが必要である。そこで、自治体の環境部局のみならず、建築
部局、都市開発部局といった関係部署においても、土壌汚染が土地取引やまちづくり等を行
う際に大きな阻害要因となっている旨を認識した上で、土壌汚染問題に適切な対応ができ、
ひいては民間に対しリーダーリップを発揮出来るよう、自治体内部で一丸となって取り組む
態勢づくりが必要である。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030404/02.pdf