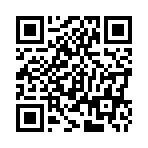2009年10月17日
2009年6月23日大阪市 環境対策特別委員会 底質汚染
大阪市 環境対策特別委員会 底質汚染 2009年6月23日


◆矢達幸委員
日本共産党、矢達でございます。
ダイオキシン類対策の問題について若干質疑をさせていただきたいと思います。
報告があったわけですけども、このダイオキシン類というのは、過去は何ら問題視されなかったんですね。焼却やいろんなことでダイオキシン類は副産物のようにしてばらまかれてきました。しかし、ここ最近になってその毒性が非常に怖いものであるということを科学者が指摘をいたしまして、対策が立てられるようになりました。
まず、ダイオキシン類の毒性というのはどういうものか、その特徴についてお答えください。

◎小西環境局環境保全部土壌水質担当課長
お答えいたします。
ダイオキシン類は、低濃度でも慢性毒性があると言われており、慢性毒性に係るダイオキシン類の安全性を評価するため、我が国では人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響があらわれないと判断される1日体重1キログラム当たりの摂取量、耐容一日摂取量を4ピコグラム−−1兆分の1グラムという単位でございますが−−と設定しております。
一方、大阪市域における平成20年度の人のダイオキシン類の一日摂取量は1.14ピコグラムと推定されており、耐容一日摂取量4ピコグラムを下回っております。
また、ダイオキシン類は、動物実験では発がんを促進する作用、甲状腺機能の低下、生殖器官の重さや精子形成の減少、免疫機能の低下を引き起こすことが報告されております。
◆矢達幸委員
特徴は、遅発性なんですね。サリンの2倍の毒性があると言われておりますけれども、一気に毒性が出て死に至るというんではなしに、その一生涯、あるいは子供、孫まで影響していくというふうに言われております。そういう点では、非常におくれて出てくる、長引くという、一生涯と先ほど言われましたけど。
それともう一つは、水質や底質の問題では植物連鎖がするんですね。先ほど、私、ちょっと高木部長の説明で気になるんですけども、河川の汚染の箇所が2カ所基準値オーバーしてるところありますけども、これについて、飲用に使うものではないから大丈夫だと、直ちに影響はないとの説明だったけども、それは私はちょっと違うと思うんですよ。
やはり植物連鎖ですから、これは魚が食べる、回遊魚はですね、これは魚を通じて人間の体に入ってきますから、だからそういう点ではダイオキシンというのは世の中から全部なくしていかないかんという性格のものであって、直ちに影響はないというふうな甘い見方は私はするべきじゃないというふうに思います。
そういう点で、私がきょう一つ問題にいたしたいのは、港湾地区の汚染の問題です。資料配付お願いします。
○山崎誠二委員長
矢達委員より、質疑の参考に資するため資料の配付の申し出がありますので、これを許します。
◆矢達幸委員
港湾局が独自に平成15年から17年の間に、特に大阪湾の河口付近、あるいは堀、こういうところの底質のダイオキシンの汚染状況の調査を実施しております。資料に配付いたしておりますように、非常に高濃度の汚染物質が堆積してるということが明らかでございます。
これがなぜ本日報告されないし、環境白書にも載らないかということで、これまた後で議論いたしますけれども、この内容について港湾局はどう考えておるんかちょっとまず答えてくれますか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
お答えいたします。
港湾局におきましては、平成15年から17年度におきまして、底質のモニタリング調査においてダイオキシンの疑いがある箇所について調査をいたしました結果、この表にございますように、この7地域において環境基準である150ピコグラム以上の底質が確認されております。これは港湾局のほうでこの浄化対策を行うために、その量を確定するために実施した調査でございます。
◆矢達幸委員
スクリューで底質を巻き上げているのも見かけております。当然、魚類へのダイオキシンの汚染が進んでるんではないかというように私は気になるんですけどもですね、こういう高濃度の汚染されてるという状況を危険視されて開始されるということだと思うんですけどね。どのような対策を立てておるのか、全体計画及びその進捗状況はどうですか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
お答えいたします。
この15年から17年の調査におきまして、大阪港の河川下流部におきまして、環境基準を超える底質量は、純汚泥量で193万立米となってございます。これは汚れを含めますと約110万立米となります。そのうち、低濃度であります150ピコから1,000ピコまでの土量が約95%を占めておりまして、残りの5%が中高濃度の1,000ピコグラムを超える底質となってございます。
現在、18年度以降、この底質の除去対策を実施しておりますが、本年度を入れまして4年間で約7,000立米の除去を予定いたしております。
◆矢達幸委員
全体計画ですから、いつまでに終わるのかね。また、18年度から始めた予算規模はどの程度なのか。全体の予算は幾らかかりますか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
この110万立米の浄化対策でございますが、これは今後の技術開発等によりまして、その事業費が下げられる可能性はございますが、現在想定しておりますのは約150億円を想定してございます。それで、毎年の事業規模でございますけども、平成18年度以降約1億円ずつの事業費となってございます。
それで、完了時期でございますけども、これにつきましては大阪市の底質対策技術検討会の中で速やかに浄化対策を完了させるということになっておりますが、本市も非常に厳しい財政状況の中ではありますので、ちょっと今明確にその時期というのを申し上げることはできません。
◆矢達幸委員
これ評価委員会の評価書に書いてあるでしょう。完成年度はちゃんと明示されてる。それを答えなさい。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
それ、委員お持ちのやつは事業評価委員会のやつでしょうか。そこに書いてある数字ということになりますと、ここでいいます速やかに浄化対策を完了させるということで17年度に申しておりましたんで、速やかに浄化対策を完了させるというのはどれぐらいかということで、おおむね10年ぐらいということで表記されているものかと思います。

◆矢達幸委員
平成27年度が完了予定になってるんですね。ところが、予算が150億円かかると。それで、平年ペースでは1億円しか予算とれませんから、150年かかるわけですな、150年。これはもう我々の世代を過ぎて次の世代でもまだ終わらへんという、こういう大変な事業量になってしまうわけですよね。
ところが、こういう高濃度汚染を放置しておくと非常に危険な状況になるという、一方ではこれはありますからね。まさに過去の大阪市のいろんな負の資産ありますけれども、これも一つのそういうもんじゃないかというふうに思うんです。市民の健康や安全、特に食の安全というこういう立場からいうと、これは金をかけてでも早期に解決せないかんというふうに思います。
事業評価委員会のこの内容でも、事業進捗状況はわずか3%ですよね、今まで。これではとても間尺に合いません。27年度までに仮に終わらそうとすると、30億円ぐらいは毎年とらないかん。国の公害対策の補助金も半分出るそうですけども、そういう点でも大変な事業量にふやさなきゃならんというふうに思いますが、これは1部局、港湾局や部局ではできる問題じゃないと。
市長のこういう決裁が必要になってくるんじゃないかということで、きょう平松市長においでいただいてますんでね。こういうこと、ダイオキシンという重大な毒性のものがこんなに大量に大阪港の河口に沈んでおると、底質としてあるという、こういう事実なんですね。これはもう明らかになりましたので、早急に除却処理されるように市長の見解をお聞きしたいというふうに思います。
◎平松市長
お答えいたします。
港湾地域のダイオキシン類につきましては、先ほど来報告させていただきまして、毎年水質モニタリング調査というのを実施しております。これによりますと、直ちに健康被害が生じる状況ではないという報告は受けております。ただ、委員御指摘のように、ダイオキシン問題、ダイオキシン類の浄化をという問題に関しましては、市民の健康にかかわる重要な課題であり、学識経験者からなる大阪市底質対策技術検討会の審議においても、御指摘のように速やかに浄化対策を行うこととされております。
このため、これまでも国の補助を得て港湾工事等にあわせて浄化対策を実施してきておりますけれども、今申し上げましたように多額の事業費を必要とすることから、今後とも引き続き財政的な支援の強化、これを国に積極的に要望してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
◆矢達幸委員
国だけやなしに大阪市も頑張らなあかんですからね。これは公害対策で半分持ちですからね、こういうことになりますから。もちろん国の補助金を大幅にふやすということは重要ですけども、しかし現在のペースではとても間尺に合いません。これ、急速にこの問題を強めていただきたいということで、市長におきましても奮闘いただきますようよろしくお願いします。市長、どうもありがとうございます。
こういう問題で、特に私気になりますのは、大阪市の環境白書に一切これ載ってないんですね。環境白書や現況と対策を見ますと、港湾地帯、湾岸地帯を調べてないのかといえば、そうじゃないんですよ。ちゃんと定点ポイントで調べてるんですね。一定の2カ所ほど底質でオーバーしてるという問題がありながら、こういう問題に一切触れないという、こういうことは何でですか。なぜこういうことを、大阪の環境白書に載らないのかということをまずお聞きしたいんですが、どうですか。なぜ載せないんですか。
◎小西環境局環境保全部土壌水質担当課長
お答えいたします。
環境白書は、大阪市環境基本条例第9条に基づき、環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策並びに実施状況を明らかにした年次報告として、毎年ダイオキシン類のモニタリング結果を公表しております。
一方、ダイオキシン類による汚染状況の詳細調査結果につきましては、港湾局がプレス発表を行うとともに、対策の進捗状況含めてホームページで公表しているところでございます。
港湾局のダイオキシン調査結果につきましては、今後掲載する方向で検討してまいりたいと思います。
◆矢達幸委員
今後掲載する方向でということで改めるということなんで、これ以上私言いませんけども、大阪の環境はこの白書に一切掲載されなきゃならんですね。どこの部局であろうと、どういう調査であろうと。現況はこうですということはここに、これに一切網羅されなきゃあかんわけですね。そういう意味では、縦割りで、あるいは港湾局の仕事だと、向こうのホームページで公開されてるというんじゃだめですね。これは市民に公開されたことになりません。そういう意味で、こんだけ高濃度汚染地域が横たわっておるという状況では、これはぜひとも今後この白書にも載せ、また現況と対策で、非常に大変な費用のかかるこういう対策です。
しかし、しっかりと対応して、対策して解決していただきたいというふうに思いますし、我々も市民もこの進捗状況をしっかりと監視していきたいというふうに思います。
[大阪市域の水環境中ダイオキシン類の調査]
河川水中のダイオキシン類濃度(平成12年〜15年度の平均濃度)
大阪市は多くの都市域を流れる河川の最下流に位置しており、市内での勾配が小さいため、河川の流れが緩やかな「水の都」として有名です。
これまでの様々な調査から、大阪市域の水環境中ダイオキシン類の分布が明らかになってきました。そして、その状況から大阪市域では、河川上流から懸濁物とともに運ばれてきたダイオキシン類が、河口域で底質へと沈降、堆積していると予想されます。
このようなダイオキシン類の状況が明らかになったことから、大阪市では河口域底質の浄化対策や周辺自治体との連携による調査や対策を進めようとしています。
グリーンニューディール政策を

ATCセミナーレポート 緑のニューディール政策がもたらす環境ビジネス
■講師
大阪大学大学院工学研究科 准教授 加藤悟氏
緑のニューディール政策は、オバマ大統領の就任後有名になりましたが、以前から、国内外で考えられていた政策です。まずは緑のニューディール政策の言葉の元となった「ニューディール政策」について振り返ってみたいと思います。
1.ニューディール政策とは何か
ニューディール政策は、1929年10月24日に発生した世界大恐慌の後、大統領となったフランクリン・ルーズベルトが行った政策です。ニューディールの“ディール”とはトランプ用語で、新規で持ち札をかえる、という意味。つまり、ゼロベースで予算配分をするということを表します。
世界恐慌の三大原因となったのは、
(1)第一次世界大戦後の農産物価格下落による市場の購買力低下、
(2)過剰な設備投資による過剰生産、
(3)各国の高関税政策による貿易縮小だと言われています。
その結果、ニューヨーク株式取引所で株価が大暴落し、各国で企業・銀行が倒産し、失業者が増大、ドイツもアメリカ資本撤退で資本不足になりました。
そんな中、フランクリン・ルーズベルトは恐慌対策を確約して大統領選に勝利しました。就任後すぐに「テネシー川流域開発公社(TVA)」を設立、またニューディール政策の基礎となる法律、「全国産業復興法(NIRA))と「農業調整法(AAA)」を制定。政府が積極的に経済に介入して景気回復に努め、善隣外交により、中南米と友好を深めました。アメリカで唯一、四選された大統領で、1945年、任期中に病死しました。
彼の政治理論を支えていたのはイギリスの経済学者、ケインズです。彼は国家の経済への介入を肯定する修正資本主義を提唱、著書「雇用・利子および貨幣の一般理論」において、一国全体における生産水準がどのように決定されるかを考案しました。これは現在、マクロ経済学と呼ばれています。
ニューディール政策の目玉の1つであるテネシー川流域開発公社(TVA)は、1933年5月に設立され、電力生産の多目的ダムを建設し、土壌保全・河川整備等の事業を行うことで、地域経済振興や住民流出防止に努めました。また電力価格を低下させて物価を引き下げ、雇用を創出しましたが、民間電力業を圧迫するという批判もありました。
一方、全国産業復興法(NIRA)では、企業の生産を規制して適正な利潤を確保、労働者には団結権や団体交渉権を認め、最低賃金を確保し、生産力や購買力の向上を目指しましたが、景気回復を促進するためカルテル的な協定締結を認めたことで、合衆国最高裁判所が違憲判決を下し、2年足らずで廃止することとなりました。
また農業調整法(AAA)では、農業部門の慢性的過剰生産恐慌の事態に対し、小麦や綿花など7項目について、作付け割り当て計画による生産管理を行いました。
しかし、一連の政策をもってしても失業率は高いまま推移し、雇用もGNPも目立った変化は見られませんでした。その後、第二次世界大戦による軍需の拡大により、アメリカ経済は回復し、失業も解消されました。皮肉なことに、アメリカを救ったのは戦争だったという意見も少なくありません。ですが、これらの政策により、それまでの古典的自由主義的経済政策から、政府が経済へ関与する社会民主主義的な政策へ転換が行われ、アメリカの政治・経済が大きく変わったことは間違いありません。
2.グリーン・ニューディール政策とは何か
2008年7月21日、「グリーン・ニューディール・グループ」により、提唱された“グリーン・ニューディール”という言葉は、1年足らずで広く知られるようになりました。
2008年7月に発表された「グリーン・ニューディール:信用危機・気候変動・原油価格高騰の三大危機を解決するための政策集」は、化石燃料に依存しないエネルギーを確保するという、エネルギーセキュリティーに重きをおいており、それと並行して気候変動対策や経済対策を行っていくという考え方です。具体的には省エネルギー技術とマイクロジェネレーション(マイクロ発電技術)への政府主導の投資、メガバンクの分割とグリーンバンキング化などの政策があります。
同年10月にUNEPが発表したグリーン経済イニシアチブでも、世界経済をクリーン技術や自然のインフラ(森林や土壌など)への投資に向かわせることが21世紀の新の成長につながるという考え方が述べられています。
その後、オバマ大統領は、2008年10月の大統領選勝利演説にて、2050年までに温室効果ガス排出量を80%削減、今後10年間でクリーンエネルギーに1500億ドルを投資し、500万人分の雇用を創出するという計画を披露しました。それに引き続く形で、世界経済フォーラム(ダボス会議)において国連の潘事務総長が、現在の経済危機を利用して、再生可能エネルギーと技術開発の投資により雇用を創出し、地球温暖化問題に取り組むべきと呼びかけました。
また2009年2月にUNEPが発表した“グローバル・グリーン・ニューディール”では、現在、景気刺激策として予定されている約2兆5千億ドルのうち3分の1はグリーン経済の実現のための投資とすべきだと強調しています。その例として、クリーンな技術開発による雇用促進や、化石燃料に対する補助金の削減、温室効果ガスを削減、生態系の悪化防止、水の安全保障等が挙げられています。
そんな中、アメリカのグリーン・ニューディール政策は非常にはっきりしており、ひとつは今後の原油高騰を見据えたエネルギー安全保障のための自然エネルギー対策、次にプラグインハイブリッド100万台によるビッグ3の復活という2本柱と、研究開発として、マイクロジェネレーションや超伝導送電、大型二次電池による蓄電等のエネルギー技術開発の取り組みを行っています。
3.日本におけるグリーン・ニューディール政策
日本におけるグリーン・ニューディール政策は、2008年9月の麻生総理の所信表明演説にて「我が国が強みを持つ環境・エネルギー技術は新たな需要と雇用を生む力がある。」と述べられているほか、環境省は2009年1月に「緑の経済と社会の変革」という構想を発表しました。この構想において、2006年現在の環境ビジネスの市場規模約70兆円、雇用者数約140万人を、近い将来飛躍的に拡大すること、そして世界で先頭をゆく環境・省エネ国家として、世界で最初に不況を脱出するという目標が掲げられています。その基本的な考え方としては、エコ改造(省庁や学校へ太陽光発電を設置する等)、エコグッズ(省エネ家電等の普及)、エコファイナンス(エコ投資)の大きく3点があげられています。
日本のグリーン・ニューディール政策に対する有識者の意見としては、太陽エネルギー社会の構築や持続可能な社会地域物質循環システム構築といった、環境白書でも述べられている基本的な提案のほか、環境エネルギー技術の促進や、特徴的な意見として途上国にむけ技術移転を行うこと、カーボンフットプリント等の見える化の促進、大学生等若い世代への働きかけ等が述べられました。
日本経団連や経済同友会でも、日本版グリーン・ニューディールの推進が推奨されており、脱化石燃料および、循環型社会へ向けた取り組みが示されています。中でも経済同友会の取り組みの中で特徴的なのは、排出権制度やグリーン税制などの、インセンティブ制度・投融資制度の導入でしょう。
日本のグリーン・ニューディール政策は、アメリカと違い、エコ改修、緑の消費への変革、緑の地域コミュニティーの変革、緑の投資への変革等、幅広いですが、地球温暖化対策とあまり差がありません。そういうところが日本らしいと言えるかもしれません。
4.環境の産業化と産業の環境化
世界での環境産業の市場規模は増加傾向にあります。企業の環境配慮における3つの発展段階として、「(1)規制追随型・受動的な環境配慮」から、「(2)事前対応型・予防的な環境配慮」になり、さらに付加価値を追求し、「(3)機会追求型・戦略的な環境配慮」と変化してきています。
環境ビジネスをOECDによる分類で分けると、大気汚染や水質汚濁等の防止・処理にかかる装置の製造や設置にかかるビジネスが「環境汚染防止」、環境負荷低減および省資源化のための技術、プロセスの提供、配慮した製品に関するビジネスは「環境負荷低減技術および製品」、最後に、環境負荷低減および省資源化を直接的な目的としないが、その効果が期待できる関連産業が「資源有効利用」に分類されます。たとえば、再生可能エネルギー施設や、省エネルギー関連ビジネス、エコツーリズム等も資源有効利用に分類されるビジネスです。
日本における環境ビジネスの市場規模も、2020年には2000年の2倍の規模になることが期待されています。日本の環境ビジネスとしては、以下の10分野の産業の環境化、および環境の産業化が考えられます。
1.廃棄物関連ビジネス(3R、廃棄物処理関連)、
2.地球温暖化(省エネルギー・新エネルギー)、
3.環境浄化(土壌汚染、アスベスト)、
4.観光(エコツーリズム)、
5.金融・保険(社会的責任投資、環境リスクの商品化)、
6.情報通信(効率化や情報による脱物質化)、
7.農業(エコファーマー、バイオマス利用)、
8.林業(持続可能な森林経営)、
9.水産業(自然管理・育成型漁業)、
10.貿易(フェアトレード)
5.大きな政府と小さな政府
ニューディール政策の思想は、大きな政府なのか、小さな政府なのかを考えてみましょう。
大きな政府とは、ゆりかごから墓場まで国が全部面倒を見てくれる政府です。一方、小さな政府は、警察や防衛など国として最低限の仕事だけを行い、経済活動等は放任する政府のことです。小さな政府の場合、自由放任主義が行き詰まって、貧富の差が大きくなります。そして政府は経済や社会のさまざまな領域に介入せざるをえなくなり、社会福祉立法や少数派保護法によって平等化の推進に努めることとなります。社会はイノベーションや競争の力で前へ進みますが、競争の中で生じる勝ち負けのバランスをとるのが政治の役割です。
アメリカでは小さな政府が破たんし、大きな政府への移行が進んでいます。非常時の公共投資による一時的なばらまきや経済への介入は、半永久的な大きな政府への移行とは異なります。
一方、大きな政府の弊害は、競争による効率性やイノベーション活動の低下が挙げられます。どちらが良いかではなく、そのバランスが重要です。
ここで、注意しておきたいのが、高福祉国家は大きな政府か?ということです。北欧は税金も高く、子持ちの女性が就労する世帯への手厚い補助や福祉が充実していますが、中央政府の権限は最小限に限定されており、地方では地元住民に大きな権限があります。さらに投資環境ランキングで上位常連、つまり自由経済がすすんでいると言えます。これらのことからも、北欧は高福祉国家ですが、大きな政府ではないと言えます。
では、アメリカは小さな政府か?というと、軍事予算や財政赤字は、小さくなるどころか増加の一途をたどっており、「通貨ばらまき」政策のため、国際決済通貨としての米ドルの地位は年々低下しています。また防災や地方に交付される予算は削減されています。
このような流れの中、私は、グリーン・ニューディールの目指すべきものは地方分権と自立型都市の確立だと考えています。地域が自立した産業を育成するためには、投資活動が円滑に行われるべきでしょう。そうなると、エネルギーや資源も地産地消が良いのでは、という考えに至ります。となると、家電や大規模太陽光発電に投資するのではなく、持続可能な農林水産業やエコハウスの建設、植物工場などの実現こそが、いま求められている環境投資、環境ビジネスではないでしょうか。
環境モデル都市として採択された北海道の下川町の「緑の経済と社会の変革」の例では、地域資源・地域雇用を生かし、地域で消費する、さらに地域の中で投資も進んでいるという、まさにグリーン・ニューディールのお手本となるモデルです。
まとめ
ニューディール政策とは、生産規制と公共投資、雇用確保についての政策でした。そしてグリーン・ニューディール政策は、本当の意味でグリーンではなく、信用危機や原油価格高騰とともに気候変動対策を行うという政策で、アメリカでは原油価格高騰対策とビッグ3に焦点がしぼられています。
一方、日本のグリーン・ニューディール政策では、省エネ家電と太陽光発電が2本柱となっています。また産業の環境化および環境の産業化については、従来の環境浄化型産業から事前対応型産業への移行が今後も進んでいくでしょう。
最後に、大きな政府と小さな政府という観点においては、自立型で競争原理とセイフティーネットを併せ持つ、小さな政府を目指したインフラ整備の改革を進めることが、グリーン・ニューディールの本来の姿なのではないかと思います。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/210501/index.html


◆矢達幸委員
日本共産党、矢達でございます。
ダイオキシン類対策の問題について若干質疑をさせていただきたいと思います。
報告があったわけですけども、このダイオキシン類というのは、過去は何ら問題視されなかったんですね。焼却やいろんなことでダイオキシン類は副産物のようにしてばらまかれてきました。しかし、ここ最近になってその毒性が非常に怖いものであるということを科学者が指摘をいたしまして、対策が立てられるようになりました。
まず、ダイオキシン類の毒性というのはどういうものか、その特徴についてお答えください。

◎小西環境局環境保全部土壌水質担当課長
お答えいたします。
ダイオキシン類は、低濃度でも慢性毒性があると言われており、慢性毒性に係るダイオキシン類の安全性を評価するため、我が国では人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響があらわれないと判断される1日体重1キログラム当たりの摂取量、耐容一日摂取量を4ピコグラム−−1兆分の1グラムという単位でございますが−−と設定しております。
一方、大阪市域における平成20年度の人のダイオキシン類の一日摂取量は1.14ピコグラムと推定されており、耐容一日摂取量4ピコグラムを下回っております。
また、ダイオキシン類は、動物実験では発がんを促進する作用、甲状腺機能の低下、生殖器官の重さや精子形成の減少、免疫機能の低下を引き起こすことが報告されております。
◆矢達幸委員
特徴は、遅発性なんですね。サリンの2倍の毒性があると言われておりますけれども、一気に毒性が出て死に至るというんではなしに、その一生涯、あるいは子供、孫まで影響していくというふうに言われております。そういう点では、非常におくれて出てくる、長引くという、一生涯と先ほど言われましたけど。
それともう一つは、水質や底質の問題では植物連鎖がするんですね。先ほど、私、ちょっと高木部長の説明で気になるんですけども、河川の汚染の箇所が2カ所基準値オーバーしてるところありますけども、これについて、飲用に使うものではないから大丈夫だと、直ちに影響はないとの説明だったけども、それは私はちょっと違うと思うんですよ。
やはり植物連鎖ですから、これは魚が食べる、回遊魚はですね、これは魚を通じて人間の体に入ってきますから、だからそういう点ではダイオキシンというのは世の中から全部なくしていかないかんという性格のものであって、直ちに影響はないというふうな甘い見方は私はするべきじゃないというふうに思います。
そういう点で、私がきょう一つ問題にいたしたいのは、港湾地区の汚染の問題です。資料配付お願いします。
○山崎誠二委員長
矢達委員より、質疑の参考に資するため資料の配付の申し出がありますので、これを許します。
◆矢達幸委員
港湾局が独自に平成15年から17年の間に、特に大阪湾の河口付近、あるいは堀、こういうところの底質のダイオキシンの汚染状況の調査を実施しております。資料に配付いたしておりますように、非常に高濃度の汚染物質が堆積してるということが明らかでございます。
これがなぜ本日報告されないし、環境白書にも載らないかということで、これまた後で議論いたしますけれども、この内容について港湾局はどう考えておるんかちょっとまず答えてくれますか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
お答えいたします。
港湾局におきましては、平成15年から17年度におきまして、底質のモニタリング調査においてダイオキシンの疑いがある箇所について調査をいたしました結果、この表にございますように、この7地域において環境基準である150ピコグラム以上の底質が確認されております。これは港湾局のほうでこの浄化対策を行うために、その量を確定するために実施した調査でございます。
◆矢達幸委員
スクリューで底質を巻き上げているのも見かけております。当然、魚類へのダイオキシンの汚染が進んでるんではないかというように私は気になるんですけどもですね、こういう高濃度の汚染されてるという状況を危険視されて開始されるということだと思うんですけどね。どのような対策を立てておるのか、全体計画及びその進捗状況はどうですか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
お答えいたします。
この15年から17年の調査におきまして、大阪港の河川下流部におきまして、環境基準を超える底質量は、純汚泥量で193万立米となってございます。これは汚れを含めますと約110万立米となります。そのうち、低濃度であります150ピコから1,000ピコまでの土量が約95%を占めておりまして、残りの5%が中高濃度の1,000ピコグラムを超える底質となってございます。
現在、18年度以降、この底質の除去対策を実施しておりますが、本年度を入れまして4年間で約7,000立米の除去を予定いたしております。
◆矢達幸委員
全体計画ですから、いつまでに終わるのかね。また、18年度から始めた予算規模はどの程度なのか。全体の予算は幾らかかりますか。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
この110万立米の浄化対策でございますが、これは今後の技術開発等によりまして、その事業費が下げられる可能性はございますが、現在想定しておりますのは約150億円を想定してございます。それで、毎年の事業規模でございますけども、平成18年度以降約1億円ずつの事業費となってございます。
それで、完了時期でございますけども、これにつきましては大阪市の底質対策技術検討会の中で速やかに浄化対策を完了させるということになっておりますが、本市も非常に厳しい財政状況の中ではありますので、ちょっと今明確にその時期というのを申し上げることはできません。
◆矢達幸委員
これ評価委員会の評価書に書いてあるでしょう。完成年度はちゃんと明示されてる。それを答えなさい。
◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長
それ、委員お持ちのやつは事業評価委員会のやつでしょうか。そこに書いてある数字ということになりますと、ここでいいます速やかに浄化対策を完了させるということで17年度に申しておりましたんで、速やかに浄化対策を完了させるというのはどれぐらいかということで、おおむね10年ぐらいということで表記されているものかと思います。

◆矢達幸委員
平成27年度が完了予定になってるんですね。ところが、予算が150億円かかると。それで、平年ペースでは1億円しか予算とれませんから、150年かかるわけですな、150年。これはもう我々の世代を過ぎて次の世代でもまだ終わらへんという、こういう大変な事業量になってしまうわけですよね。
ところが、こういう高濃度汚染を放置しておくと非常に危険な状況になるという、一方ではこれはありますからね。まさに過去の大阪市のいろんな負の資産ありますけれども、これも一つのそういうもんじゃないかというふうに思うんです。市民の健康や安全、特に食の安全というこういう立場からいうと、これは金をかけてでも早期に解決せないかんというふうに思います。
事業評価委員会のこの内容でも、事業進捗状況はわずか3%ですよね、今まで。これではとても間尺に合いません。27年度までに仮に終わらそうとすると、30億円ぐらいは毎年とらないかん。国の公害対策の補助金も半分出るそうですけども、そういう点でも大変な事業量にふやさなきゃならんというふうに思いますが、これは1部局、港湾局や部局ではできる問題じゃないと。
市長のこういう決裁が必要になってくるんじゃないかということで、きょう平松市長においでいただいてますんでね。こういうこと、ダイオキシンという重大な毒性のものがこんなに大量に大阪港の河口に沈んでおると、底質としてあるという、こういう事実なんですね。これはもう明らかになりましたので、早急に除却処理されるように市長の見解をお聞きしたいというふうに思います。
◎平松市長
お答えいたします。
港湾地域のダイオキシン類につきましては、先ほど来報告させていただきまして、毎年水質モニタリング調査というのを実施しております。これによりますと、直ちに健康被害が生じる状況ではないという報告は受けております。ただ、委員御指摘のように、ダイオキシン問題、ダイオキシン類の浄化をという問題に関しましては、市民の健康にかかわる重要な課題であり、学識経験者からなる大阪市底質対策技術検討会の審議においても、御指摘のように速やかに浄化対策を行うこととされております。
このため、これまでも国の補助を得て港湾工事等にあわせて浄化対策を実施してきておりますけれども、今申し上げましたように多額の事業費を必要とすることから、今後とも引き続き財政的な支援の強化、これを国に積極的に要望してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
◆矢達幸委員
国だけやなしに大阪市も頑張らなあかんですからね。これは公害対策で半分持ちですからね、こういうことになりますから。もちろん国の補助金を大幅にふやすということは重要ですけども、しかし現在のペースではとても間尺に合いません。これ、急速にこの問題を強めていただきたいということで、市長におきましても奮闘いただきますようよろしくお願いします。市長、どうもありがとうございます。
こういう問題で、特に私気になりますのは、大阪市の環境白書に一切これ載ってないんですね。環境白書や現況と対策を見ますと、港湾地帯、湾岸地帯を調べてないのかといえば、そうじゃないんですよ。ちゃんと定点ポイントで調べてるんですね。一定の2カ所ほど底質でオーバーしてるという問題がありながら、こういう問題に一切触れないという、こういうことは何でですか。なぜこういうことを、大阪の環境白書に載らないのかということをまずお聞きしたいんですが、どうですか。なぜ載せないんですか。
◎小西環境局環境保全部土壌水質担当課長
お答えいたします。
環境白書は、大阪市環境基本条例第9条に基づき、環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策並びに実施状況を明らかにした年次報告として、毎年ダイオキシン類のモニタリング結果を公表しております。
一方、ダイオキシン類による汚染状況の詳細調査結果につきましては、港湾局がプレス発表を行うとともに、対策の進捗状況含めてホームページで公表しているところでございます。
港湾局のダイオキシン調査結果につきましては、今後掲載する方向で検討してまいりたいと思います。
◆矢達幸委員
今後掲載する方向でということで改めるということなんで、これ以上私言いませんけども、大阪の環境はこの白書に一切掲載されなきゃならんですね。どこの部局であろうと、どういう調査であろうと。現況はこうですということはここに、これに一切網羅されなきゃあかんわけですね。そういう意味では、縦割りで、あるいは港湾局の仕事だと、向こうのホームページで公開されてるというんじゃだめですね。これは市民に公開されたことになりません。そういう意味で、こんだけ高濃度汚染地域が横たわっておるという状況では、これはぜひとも今後この白書にも載せ、また現況と対策で、非常に大変な費用のかかるこういう対策です。
しかし、しっかりと対応して、対策して解決していただきたいというふうに思いますし、我々も市民もこの進捗状況をしっかりと監視していきたいというふうに思います。
[大阪市域の水環境中ダイオキシン類の調査]

河川水中のダイオキシン類濃度(平成12年〜15年度の平均濃度)
大阪市は多くの都市域を流れる河川の最下流に位置しており、市内での勾配が小さいため、河川の流れが緩やかな「水の都」として有名です。
これまでの様々な調査から、大阪市域の水環境中ダイオキシン類の分布が明らかになってきました。そして、その状況から大阪市域では、河川上流から懸濁物とともに運ばれてきたダイオキシン類が、河口域で底質へと沈降、堆積していると予想されます。
このようなダイオキシン類の状況が明らかになったことから、大阪市では河口域底質の浄化対策や周辺自治体との連携による調査や対策を進めようとしています。
グリーンニューディール政策を

ATCセミナーレポート 緑のニューディール政策がもたらす環境ビジネス
■講師
大阪大学大学院工学研究科 准教授 加藤悟氏
緑のニューディール政策は、オバマ大統領の就任後有名になりましたが、以前から、国内外で考えられていた政策です。まずは緑のニューディール政策の言葉の元となった「ニューディール政策」について振り返ってみたいと思います。
1.ニューディール政策とは何か
ニューディール政策は、1929年10月24日に発生した世界大恐慌の後、大統領となったフランクリン・ルーズベルトが行った政策です。ニューディールの“ディール”とはトランプ用語で、新規で持ち札をかえる、という意味。つまり、ゼロベースで予算配分をするということを表します。
世界恐慌の三大原因となったのは、
(1)第一次世界大戦後の農産物価格下落による市場の購買力低下、
(2)過剰な設備投資による過剰生産、
(3)各国の高関税政策による貿易縮小だと言われています。
その結果、ニューヨーク株式取引所で株価が大暴落し、各国で企業・銀行が倒産し、失業者が増大、ドイツもアメリカ資本撤退で資本不足になりました。
そんな中、フランクリン・ルーズベルトは恐慌対策を確約して大統領選に勝利しました。就任後すぐに「テネシー川流域開発公社(TVA)」を設立、またニューディール政策の基礎となる法律、「全国産業復興法(NIRA))と「農業調整法(AAA)」を制定。政府が積極的に経済に介入して景気回復に努め、善隣外交により、中南米と友好を深めました。アメリカで唯一、四選された大統領で、1945年、任期中に病死しました。
彼の政治理論を支えていたのはイギリスの経済学者、ケインズです。彼は国家の経済への介入を肯定する修正資本主義を提唱、著書「雇用・利子および貨幣の一般理論」において、一国全体における生産水準がどのように決定されるかを考案しました。これは現在、マクロ経済学と呼ばれています。
ニューディール政策の目玉の1つであるテネシー川流域開発公社(TVA)は、1933年5月に設立され、電力生産の多目的ダムを建設し、土壌保全・河川整備等の事業を行うことで、地域経済振興や住民流出防止に努めました。また電力価格を低下させて物価を引き下げ、雇用を創出しましたが、民間電力業を圧迫するという批判もありました。
一方、全国産業復興法(NIRA)では、企業の生産を規制して適正な利潤を確保、労働者には団結権や団体交渉権を認め、最低賃金を確保し、生産力や購買力の向上を目指しましたが、景気回復を促進するためカルテル的な協定締結を認めたことで、合衆国最高裁判所が違憲判決を下し、2年足らずで廃止することとなりました。
また農業調整法(AAA)では、農業部門の慢性的過剰生産恐慌の事態に対し、小麦や綿花など7項目について、作付け割り当て計画による生産管理を行いました。
しかし、一連の政策をもってしても失業率は高いまま推移し、雇用もGNPも目立った変化は見られませんでした。その後、第二次世界大戦による軍需の拡大により、アメリカ経済は回復し、失業も解消されました。皮肉なことに、アメリカを救ったのは戦争だったという意見も少なくありません。ですが、これらの政策により、それまでの古典的自由主義的経済政策から、政府が経済へ関与する社会民主主義的な政策へ転換が行われ、アメリカの政治・経済が大きく変わったことは間違いありません。
2.グリーン・ニューディール政策とは何か
2008年7月21日、「グリーン・ニューディール・グループ」により、提唱された“グリーン・ニューディール”という言葉は、1年足らずで広く知られるようになりました。
2008年7月に発表された「グリーン・ニューディール:信用危機・気候変動・原油価格高騰の三大危機を解決するための政策集」は、化石燃料に依存しないエネルギーを確保するという、エネルギーセキュリティーに重きをおいており、それと並行して気候変動対策や経済対策を行っていくという考え方です。具体的には省エネルギー技術とマイクロジェネレーション(マイクロ発電技術)への政府主導の投資、メガバンクの分割とグリーンバンキング化などの政策があります。
同年10月にUNEPが発表したグリーン経済イニシアチブでも、世界経済をクリーン技術や自然のインフラ(森林や土壌など)への投資に向かわせることが21世紀の新の成長につながるという考え方が述べられています。
その後、オバマ大統領は、2008年10月の大統領選勝利演説にて、2050年までに温室効果ガス排出量を80%削減、今後10年間でクリーンエネルギーに1500億ドルを投資し、500万人分の雇用を創出するという計画を披露しました。それに引き続く形で、世界経済フォーラム(ダボス会議)において国連の潘事務総長が、現在の経済危機を利用して、再生可能エネルギーと技術開発の投資により雇用を創出し、地球温暖化問題に取り組むべきと呼びかけました。
また2009年2月にUNEPが発表した“グローバル・グリーン・ニューディール”では、現在、景気刺激策として予定されている約2兆5千億ドルのうち3分の1はグリーン経済の実現のための投資とすべきだと強調しています。その例として、クリーンな技術開発による雇用促進や、化石燃料に対する補助金の削減、温室効果ガスを削減、生態系の悪化防止、水の安全保障等が挙げられています。
そんな中、アメリカのグリーン・ニューディール政策は非常にはっきりしており、ひとつは今後の原油高騰を見据えたエネルギー安全保障のための自然エネルギー対策、次にプラグインハイブリッド100万台によるビッグ3の復活という2本柱と、研究開発として、マイクロジェネレーションや超伝導送電、大型二次電池による蓄電等のエネルギー技術開発の取り組みを行っています。
3.日本におけるグリーン・ニューディール政策
日本におけるグリーン・ニューディール政策は、2008年9月の麻生総理の所信表明演説にて「我が国が強みを持つ環境・エネルギー技術は新たな需要と雇用を生む力がある。」と述べられているほか、環境省は2009年1月に「緑の経済と社会の変革」という構想を発表しました。この構想において、2006年現在の環境ビジネスの市場規模約70兆円、雇用者数約140万人を、近い将来飛躍的に拡大すること、そして世界で先頭をゆく環境・省エネ国家として、世界で最初に不況を脱出するという目標が掲げられています。その基本的な考え方としては、エコ改造(省庁や学校へ太陽光発電を設置する等)、エコグッズ(省エネ家電等の普及)、エコファイナンス(エコ投資)の大きく3点があげられています。
日本のグリーン・ニューディール政策に対する有識者の意見としては、太陽エネルギー社会の構築や持続可能な社会地域物質循環システム構築といった、環境白書でも述べられている基本的な提案のほか、環境エネルギー技術の促進や、特徴的な意見として途上国にむけ技術移転を行うこと、カーボンフットプリント等の見える化の促進、大学生等若い世代への働きかけ等が述べられました。
日本経団連や経済同友会でも、日本版グリーン・ニューディールの推進が推奨されており、脱化石燃料および、循環型社会へ向けた取り組みが示されています。中でも経済同友会の取り組みの中で特徴的なのは、排出権制度やグリーン税制などの、インセンティブ制度・投融資制度の導入でしょう。
日本のグリーン・ニューディール政策は、アメリカと違い、エコ改修、緑の消費への変革、緑の地域コミュニティーの変革、緑の投資への変革等、幅広いですが、地球温暖化対策とあまり差がありません。そういうところが日本らしいと言えるかもしれません。
4.環境の産業化と産業の環境化
世界での環境産業の市場規模は増加傾向にあります。企業の環境配慮における3つの発展段階として、「(1)規制追随型・受動的な環境配慮」から、「(2)事前対応型・予防的な環境配慮」になり、さらに付加価値を追求し、「(3)機会追求型・戦略的な環境配慮」と変化してきています。
環境ビジネスをOECDによる分類で分けると、大気汚染や水質汚濁等の防止・処理にかかる装置の製造や設置にかかるビジネスが「環境汚染防止」、環境負荷低減および省資源化のための技術、プロセスの提供、配慮した製品に関するビジネスは「環境負荷低減技術および製品」、最後に、環境負荷低減および省資源化を直接的な目的としないが、その効果が期待できる関連産業が「資源有効利用」に分類されます。たとえば、再生可能エネルギー施設や、省エネルギー関連ビジネス、エコツーリズム等も資源有効利用に分類されるビジネスです。
日本における環境ビジネスの市場規模も、2020年には2000年の2倍の規模になることが期待されています。日本の環境ビジネスとしては、以下の10分野の産業の環境化、および環境の産業化が考えられます。
1.廃棄物関連ビジネス(3R、廃棄物処理関連)、
2.地球温暖化(省エネルギー・新エネルギー)、
3.環境浄化(土壌汚染、アスベスト)、
4.観光(エコツーリズム)、
5.金融・保険(社会的責任投資、環境リスクの商品化)、
6.情報通信(効率化や情報による脱物質化)、
7.農業(エコファーマー、バイオマス利用)、
8.林業(持続可能な森林経営)、
9.水産業(自然管理・育成型漁業)、
10.貿易(フェアトレード)
5.大きな政府と小さな政府
ニューディール政策の思想は、大きな政府なのか、小さな政府なのかを考えてみましょう。
大きな政府とは、ゆりかごから墓場まで国が全部面倒を見てくれる政府です。一方、小さな政府は、警察や防衛など国として最低限の仕事だけを行い、経済活動等は放任する政府のことです。小さな政府の場合、自由放任主義が行き詰まって、貧富の差が大きくなります。そして政府は経済や社会のさまざまな領域に介入せざるをえなくなり、社会福祉立法や少数派保護法によって平等化の推進に努めることとなります。社会はイノベーションや競争の力で前へ進みますが、競争の中で生じる勝ち負けのバランスをとるのが政治の役割です。
アメリカでは小さな政府が破たんし、大きな政府への移行が進んでいます。非常時の公共投資による一時的なばらまきや経済への介入は、半永久的な大きな政府への移行とは異なります。
一方、大きな政府の弊害は、競争による効率性やイノベーション活動の低下が挙げられます。どちらが良いかではなく、そのバランスが重要です。
ここで、注意しておきたいのが、高福祉国家は大きな政府か?ということです。北欧は税金も高く、子持ちの女性が就労する世帯への手厚い補助や福祉が充実していますが、中央政府の権限は最小限に限定されており、地方では地元住民に大きな権限があります。さらに投資環境ランキングで上位常連、つまり自由経済がすすんでいると言えます。これらのことからも、北欧は高福祉国家ですが、大きな政府ではないと言えます。
では、アメリカは小さな政府か?というと、軍事予算や財政赤字は、小さくなるどころか増加の一途をたどっており、「通貨ばらまき」政策のため、国際決済通貨としての米ドルの地位は年々低下しています。また防災や地方に交付される予算は削減されています。
このような流れの中、私は、グリーン・ニューディールの目指すべきものは地方分権と自立型都市の確立だと考えています。地域が自立した産業を育成するためには、投資活動が円滑に行われるべきでしょう。そうなると、エネルギーや資源も地産地消が良いのでは、という考えに至ります。となると、家電や大規模太陽光発電に投資するのではなく、持続可能な農林水産業やエコハウスの建設、植物工場などの実現こそが、いま求められている環境投資、環境ビジネスではないでしょうか。
環境モデル都市として採択された北海道の下川町の「緑の経済と社会の変革」の例では、地域資源・地域雇用を生かし、地域で消費する、さらに地域の中で投資も進んでいるという、まさにグリーン・ニューディールのお手本となるモデルです。
まとめ
ニューディール政策とは、生産規制と公共投資、雇用確保についての政策でした。そしてグリーン・ニューディール政策は、本当の意味でグリーンではなく、信用危機や原油価格高騰とともに気候変動対策を行うという政策で、アメリカでは原油価格高騰対策とビッグ3に焦点がしぼられています。
一方、日本のグリーン・ニューディール政策では、省エネ家電と太陽光発電が2本柱となっています。また産業の環境化および環境の産業化については、従来の環境浄化型産業から事前対応型産業への移行が今後も進んでいくでしょう。
最後に、大きな政府と小さな政府という観点においては、自立型で競争原理とセイフティーネットを併せ持つ、小さな政府を目指したインフラ整備の改革を進めることが、グリーン・ニューディールの本来の姿なのではないかと思います。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/210501/index.html
Posted by 大阪水・土壌研究会員 at 08:13│Comments(0)
│底質汚染分科会