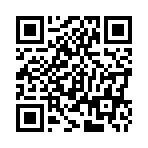2010年07月17日
土壌汚染対策法 ()無し要点
土壌汚染対策法
最終改正:平成二一年四月二四日法律第二三号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域(第六条―第十条)
第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
第三節 雑則(第十四条・第十五条)
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条
1 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条
1 土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条
1 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域
(要措置区域の指定等)
第六条
1 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(汚染の除去等の措置)
第七条
1 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の指示措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定める指示措置等を講じなければならない。
4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。
この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条
1 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(適用除外)
第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
第二節 形質変更時要届出区域
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条
1 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条
1 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(適用除外)
第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第三節 雑則
(指定の申請)
第十四条
1 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。
この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。
この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(台帳)
第十五条
1 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条
1 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(運搬に関する基準)
第十七条
1 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条
1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(措置命令)
第十九条
1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(管理票)
第二十条
1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した
者について準用する。
3 汚染土壌の運搬を運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理受託者は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したときは当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条
1 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第二節 汚染土壌処理業 略
第五章 指定調査機関
(指定の申請)
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三十二条
1 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
第三十三条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。
ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第三十七条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務規程を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示) 略
第六章 指定支援法人 略
第七章 雑則
(報告及び検査)
第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等) 略
(環境大臣の指示) 略
(国の援助)
第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六十条
1 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条
1 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 略
最終改正:平成二一年四月二四日法律第二三号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域(第六条―第十条)
第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
第三節 雑則(第十四条・第十五条)
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条
1 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条
1 土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条
1 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域
(要措置区域の指定等)
第六条
1 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(汚染の除去等の措置)
第七条
1 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の指示措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定める指示措置等を講じなければならない。
4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。
この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条
1 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(適用除外)
第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
第二節 形質変更時要届出区域
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条
1 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条
1 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(適用除外)
第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第三節 雑則
(指定の申請)
第十四条
1 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。
この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。
この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(台帳)
第十五条
1 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条
1 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(運搬に関する基準)
第十七条
1 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条
1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(措置命令)
第十九条
1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(管理票)
第二十条
1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した
者について準用する。
3 汚染土壌の運搬を運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理受託者は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したときは当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条
1 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第二節 汚染土壌処理業 略
第五章 指定調査機関
(指定の申請)
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三十二条
1 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
第三十三条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。
ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第三十七条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務規程を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示) 略
第六章 指定支援法人 略
第七章 雑則
(報告及び検査)
第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等) 略
(環境大臣の指示) 略
(国の援助)
第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六十条
1 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条
1 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 略
2010年07月12日
改正土壌汚染対策法施行通知 目次

改正土壌汚染対策法施行通知 目次
第1 法改正の経緯及び目的 1
第2 特定有害物質 2
第3 土壌汚染状況調査
1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地
(1) 趣旨
(2) 調査の実施主体
① 土地の所有者等
② 施設の設置者と土地の所有者等が異なる場合の手続
(3) 調査結果の報告の手続
① 報告の期限
② 報告すべき事項
③ 報告のない場合又は虚偽の報告の場合の命令
(4) 都道府県知事の確認による調査義務の一時的免除
① 趣旨
② 都道府県知事の確認の手続
③ 確認後の手続
④ 確認の取消し
(5) 調査の対象となる特定有害物質
(6) 土壌汚染状況調査の方法
① 考え方
② 調査対象地の範囲
③ 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握
④ 調査対象地の区画の方法及び区画ごとに行う試料採取等
⑤ 調査対象物質の種類ごとに行うべき試料採取等の種類
⑥ 土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の具体的な方法
⑦ 900平方メートル単位の試料採取等において土壌汚染が判明した場合
⑧ 土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合の追加調査
⑨ 土壌汚染の有無の判定
⑩ 法第5条第1項の命令の場合の特例
⑪ 土壌汚染状況調査における調査の過程の省略
⑫ 法施行前に行われた調査の結果の利用
2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査 20
(1) 趣旨
(2) 土地の形質の変更の届出
① 届出義務の対象となる土地の形質の変更
ア.軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
イ.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
② 届出義務者
③ 届出の際の添付図面及び書類
④ 届出義務の履行期限
(3) 調査の対象となる土地
① 土壌の特定有害物質汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令基準に適合しないことが明らかである土地
② 特定有害物質等が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地
③ 特定有害物質製造し、使用し、又は処理施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地
④ 特定有害物質等を施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地
⑤ ②から④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が
法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地
(4) 命令の手続
(5) 地歴調査により汚染のおそれがあることが判明した特定有害物質の種類と試料採
(6) 法第3条第1項の調査との関係
3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 26
(1) 趣旨
(2) 調査の対象となる土地の基準
① 土壌汚染の蓋然性が高く、かつ、人の暴露の可能性があること
② 調査の命令の対象とならない土地でないこと
(3) 命令の手続
(4) 都道府県知事による調査の実施等
第4 区域の指定等 31
1.要措置区域
(1) 趣旨
(2) 要措置区域の指定基準(汚染状態に関する基準)
(3) 要措置区域の指定基準(健康被害が生ずるおそれに関する基準)
① 人の暴露の可能性があること
② 汚染の除去等の措置が講じられている土地でないこと
(4) 要措置区域の指定の公示
(5) 要措置区域の指定の解除
(6) 汚染の除去等の措置
① 趣旨
② 指示の手続
③ 指示措置等の実施義務及び措置命令
④ 指示措置等に関する技術的基準
ア.指示措置の内容
イ.指示措置等の実施方法の具体的内容
ウ.実施後の効果の維持
エ.廃棄物埋立護岸において造成された土地の取扱い
オ.担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置
⑤ 汚染原因者に対する指示及び措置命令
ア.趣旨等
イ.汚染原因者の特定
ウ.指示の手続等
⑥ 都道府県知事による指示措置等の実施
(7) 汚染の除去等の措置に要した費用の汚染原因者への請求
(8) 土地の形質の変更の禁止
① 趣旨
② 土地の形質の変更の禁止の例外
ア.帯水層への影響を回避する方法等による土地の形質の変更
イ.指示措置等と一体となって行われる土地の形質の変更
ウ.地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている要措置区域内における土地の形質の変更
2.形質変更時要届出区域 50
(1) 趣旨
(2) 形質変更時要届出区域の指定及びその解除
① 形質変更時要届出区域の指定及びその解除の手続
② 解除の条件
③ 形質変更時要届出区域における摂取経路遮断状態の確認
(3) 土地の形質の変更の届出及び計画変更命令
① 趣旨
② 土地の形質の変更の届出
ア.届出の手続
イ.事前の届出を要しない土地の形質の変更
③ 計画変更命令
ア.計画変更命令
イ.土地の形質の変更の施行方法に関する基準
ウ.土地の形質の変更の後の手続
3.指定の申請 54
(1) 趣旨
(2) 指定の申請の手続
(3) 指定
(4) その他
4.台帳 56
(1) 台帳の調製
(2) 台帳の訂正及び消除
(3) 台帳の保管及び閲覧
第5 汚染土壌の搬出等に関する規制 58
1.汚染土壌の搬出時の措置
(1) 趣旨
(2) 汚染土壌の搬出の事前届出及び計画変更命令
① 汚染土壌の搬出の事前届出の手続
② 計画変更命令
(3) 要措置区域等内の土地の土壌を法の対象から外すための認定
① 調査方法
ア.掘削前調査
イ.掘削後調査
② 認定の申請及び認定
ア.掘削前調査
イ.掘削後調査
(4) 汚染土壌の搬出の事後届出
(5) 汚染土壌の運搬に関する基準及び処理の委託義務
① 運搬に関する基準
② 処理の委託義務
(6) 措置命令
(7) 管理票
2.汚染土壌処理業 65
(1) 趣旨
(2) 汚染土壌処理業の許可の申請の手続
(3) 汚染土壌の処理の基準
(4) 汚染土壌の処理の再委託の禁止
(5) 記録の保管及び閲覧
(6) 事故時の届出
(7) 変更の許可等
(8) 改善命令及び許可の取消し等
① 趣旨
② 要件
ア.法第22条第3項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき(法第25条第1号)
イ.汚染土壌処理施設又はその者の能力が法第22条第3項第1号の環境省令で定める基準に
適合しなくなったとき(法第25条第2号)
ウ.法第4章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき(法第25条第3号)
エ.不正の手段により法第22条第1項の許可又は法第23条第1項の変更の許可を
受けたとき(法第25条第4号)
③ 手続
④ 環境省への報告
(9) 名義貸しの禁止
(10) 許可の取消し等の場合の措置義務
第6 指定調査機関 71
1 指定調査機関に対する指導監督の充実強化
2 技術管理者に係る経過措置
第7 指定支援法人 72
1.指定支援法人の制度について
2.助成金の交付について
第8 雑則 73
1.報告及び検査
(1) 土壌汚染状況調査に係る土地等に関する報告徴収及び立入検査
(2) 汚染土壌の搬出及び運搬に関する報告徴収及び立入検査
(3) 汚染土壌の処理に関する報告徴収及び立入検査
2.公共の用に供する施設の管理を行う者との協議
3.その他
(1) 資料の提出の要求等
(2) 環境大臣の指示
(3) 国の援助
(4) 研究の推進等
(5) 国民の理解の増進
(6) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等
(7) 経過措置
(8) 政令で定める市の長による事務の処理
(9) 罰則
第9 施行期日等 77
1.施行期日
2.経過措置
3.検討
第10 法の施行に当っての配慮事項等
1.要措置区域等外の土地の基準不適合土壌等の取扱い
2.ダイオキシン類対策特別措置法との関係
3.都道府県が講ずる施策との関係
4.法の施行状況調査
http://www.env.go.jp/hourei/add/f005.pdf

2010年 おおさかATCグリーンエコプラザ
土壌汚染指定調査機関の技術管理者受験サークル
9月25日(土)14:00~17:00
10月23日(土)14:00~17:00
11月27日(土)14:00~17:00
12月11日(土)14:00~17:00
http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/59595388.html
2009年12月27日
第171回国会 環境委員会 畑明郎先生の発言
第171回国会 環境委員会 第5号
平成二十一年四月十四日(火曜日)
大阪市立大学大学院特任教授日本環境学会会長 畑 明郎君
本日の会議に付した案件
○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付)
○委員長(有村治子君)
ただいまから環境委員会を開会いたします。
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○参考人(畑明郎君)
大阪市立大学の畑と申します。
資料としましては、昨年十一月に日弁連の機関誌の「自由と正義」という雑誌があるんですけれども、それに土壌汚染対策法の特集がありまして、それの巻頭論文を付けております。二番目には大塚先生も書かれていますので、また参考にしていただければと思います。
元々、私は七年前にここに、法律できるときの、制定のときの参考人で、大野参考人と私とあと二人の方だったんですけれども。そのときに、ちょうど五月だったんですけれども、四月ですから今、似た時期ですけれども、非常に問題はいっぱいあるということで、当時は一応民主党の福山議員の紹介でこれ参加したわけですけれども、十五項目ぐらい問題あるということで、中でも大きな問題点は、二番目の、この法律はやっぱり土壌汚染の事後対策法である、未然防止法ではないということです。
それから、地下水の汚染の防止の観点がほとんどないと。土は人間が動かさないと動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますので、そこの防止の対策がこの法律では非常に問題があると。
それから、五番目の三条の調査対象ですね、これが一番問題なんですけれども、いわゆる水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止時、それも法律施行後の廃止時、さらに宅地等への転用する場合だけ、そういう形で非常に法対象を狭くしていると。それから、それ以外にも金属鉱山・製錬所、廃棄物処分場の跡地周辺、軍事基地等を対象外にしていることです。
それから七番目が、調査、対策を原則として汚染原因者でなく土地所有者等に義務付けている点です。
それから十番目が、対策は原則として覆土、つまり五十センチ以上の盛土でよしとする、土壌の浄化は特別な場合だと。これは保育園とか幼稚園とかそういう場合だけだという感じになっておりまして、この法律制定時から非常に問題があったと思っております。
とても土壌汚染問題の根本的解決につながる法律とは言えませんし、そればかりか、土壌汚染を覆土で隠ぺいし、言わば臭い物にふたをする、後世に負の遺産を残すことを合法化するざる法ではないかということで批判したわけです。
やはり法施行後五年、今六年ですけれども、たった現在、そのざる法性はますます明らかになったのではないかと思っております。
二番目のは、もう御存じのように、先ほど言われましたように、法対象が非常に、二%しかないとか、廃止工場の八割は調査を逃げている、つまり宅地等に用途を転用しないということで、ブラウンフィールド化している。
それから対策も二%しかないと。それから、四条の調査命令も、発動したのは五件。これは、環境省は課長会議の何か通達出していまして、一キロ以内ぐらいに直接水道の飲み水に使用している場合だけ発令しろ、それ以外発令するなというそういう通達を出しておりまして、結果的に五件しかないと。しかも、それは岩手県とか鳥取県とか、皆さん御存じの特定の知事がおられたときしか、県しか命令を出しておりません。そういうことで、非常に実効性の乏しいざる法となっていると思います。
それで、いわゆるこの法律自身は盛土、舗装等で摂取経路を遮断する対策で十分であると言っているんですけど、リスク管理といっておりますけど、汚染土壌が残っている限り半永久的に管理する必要があるわけですね。
特に問題なのは地下水の問題です。土壌が汚染されていますと、必ずそれに接触している地下水は汚染されます。その地下水は勝手に動きます。ということで、確かに直接都市部では飲み水にしていないんですけど、地下水によって汚染が拡散するという点で、その地下水のくみ上げ処理とか遮水壁で囲むとか幾つかの方法があるんですけど、一〇〇%水をカットすることは技術的には困難です。
幾らお金を掛けても困難です。ということで、こういうリスク管理には非常に問題があるということで、やはりリスクゼロ型の掘削除去の方が結果的には多く採用されているし、その方が私はいいと思っております。
当然それを掘削除去した汚染土壌については適正に処理することは当たり前のことでして、これは技術的に、最近、秋田とか川崎とか幾つかにその汚染土壌をきれいにするプラントもできておりますし、問題はコストですね、お金が掛かりますから。その負担をだれがするかという問題だと思っております。
それから三番目の、大野さんのおられる土環センターの調査によれば、いわゆる製造業だけじゃなくてサービス業も含めて九十三万か所ぐらい汚染地があるんではないかと推定されています。
これの調査費用が二兆円で、浄化費用が十一兆円で、合計十三兆円の土壌浄化ビジネスです。既に二〇〇七年でほぼ二千億円近い、年間二千億円の土壌浄化ビジネスになっております。二〇〇八年はちょっと景気の悪化で初めて落ち込むようですけど、それまではずっと右肩上がりで土壌浄化ビジネスの業界は成長しております。
それと、あと汚染地ですけど、基本的には東京、関東、近畿、中部の三大都市圏のいわゆるオールドエコノミーというか、そういう重化学工業の工場地帯のところに多いということです。
それから四番目は、私自身いろんな事件にかかわっているんですけど、基本的には市民、住民の依頼によってやってきたものが二十件以上あります。その中で法対象になったものは、この二十件のうちわずか三件です。
大阪のカネボウの中研の跡地、神戸の日本テルペン化学、川西の中央北地区、これは皮なめし工場です。ということで、大半が法施行前に廃止された工場、事業場や廃棄物処分場周辺の跡地です。ということで、法施行前に廃止された工場跡地、特に有害物質を取り扱っていた事業場をやっぱり法対象にする必要があるし、ドイツなんかでは廃棄物処分場の跡地周辺も法対象にしております。
あと、先ほど出ましたように、私はこの二番目の、?の大阪アメニティパークの、OAPの事件にかなり三年間ぐらいずっと住民に頼まれてかかわったんですけど、このときには土壌汚染対策法は全く役に立たなかったです。宅建業法でやっと三菱は対策とか調査をやったということになったわけですね。
それからあと、七番目以降、そこに滋賀県の例がありまして、私、滋賀県に住んでおりまして、有村委員長も滋賀県出身だそうなんですけど、守山、野洲とか信楽では、これは水道の飲み水の汚染が起こりました。
それから、住友大阪セメント、セメント工場もいろいろ問題あるんですけど、それから、今、滋賀県の知事が栗東の新幹線の駅止めましたけど、この産廃処分場の問題がもう一つありまして、そういう周辺で地下水汚染、土壌汚染が起こっております。
それから、このテルペン化学で、神戸の、非常に印象的だったんですけど、法対象になっているんですけど、法施行時に稼働していた施設では使っていた薬品だけの元素を、有害な元素を対象にしていまして、過去にあった施設の有害物質についてはこれは法対象にならないんだという解釈を神戸市、環境省がしておりまして、それは何かの間違いじゃないかと思ったんですけど、あくまで自主的調査だと。非常に法律自身を狭く運用していると。
いわゆるこういう土壌汚染というのは、一回汚染されますと十年、二十年、三十年、数十年間は蓄積します。そういう意味で、過去の汚染も考慮して調査、対策しないと意味がないと思うんですけど、非常に法律の運用が狭くなっている問題があると思っております。
それから、ここには書いていませんけど、武田薬品の神奈川の湘南工場の最近例知ったんですけど、これは工場の廃止は最近なんですけど、施設が法施行前に廃止されていた、だから法対象にならないと。神奈川県の条例でやっと対象になったという事例がございます。
あと、四日市の例のフェロシルト事件とか産廃処分場の問題とか、あと岐阜とかです。僕自身は、ずっとイタイイタイ病を起こした三井金属の神岡鉱山の排水・土壌汚染対策を四十年近くやっておりますけど、ここは一応今成功しましたけど、工場の下に汚染土壌が残っていまして、約九十トンぐらいカドミウムが残っているんですけど、完全に地下水くむまでに処理するには百年掛かると言われています。
そういう意味で、汚染土壌を残しますと非常に半永久的に処理コストが掛かるということです。結果的には取ってしまった方が安く上がる。これは産廃処分場でも一緒なんですけど、豊島とか青森、岩手のように全量撤去した方が後々ランニングコストというか排水処理とかいろんなリスク管理の費用が結果的には安く上がると思っております。
それから、皆さん御存じの築地市場の問題です。この問題につきまして、一応最近かかわっておりまして、もう御存じなので飛ばしますけど、これは面積的には日本最大の土壌汚染地になりますということで、一千億じゃなくて六百数十億円対策費が掛かる。
それも、二メートル土取って、汚染土壌は下に残ります。汚染地下水は半永久的にくみ上げて処理する、このコストがまた掛かります。そういう対策を東京都がやろうとしています。
今回の法律の件ですけど、僕は基本的にはやっぱりリスクゼロ型の掘削除去の土壌浄化対策の方がいいと思っていますし、盛土、封じ込め等は、こういう安易な対策は問題があると思っています。特に今回の法律はそういう点を、何か掘削除去を排して安易な対策、安上がりな対策を推進、推奨しようとしているということで問題があると思っています。
そういう意味で、東京都の条例とか滋賀県の条例のいわゆる一定規模以上の土地の改変、これは今回の法律には適用されているんですけど、問題はあとは、東京都、あと神奈川県横浜市、川崎市、大阪府等が採用しているんですけど、過去に有害物質を取り扱っていた工場、事業場については条例の対象にするということはやっぱり法律についてもやっていく必要があるんじゃないかと思っています。
それと、滋賀県の条例は、今回、環境省の委員会では全く取り上げられなかったんです。私は滋賀県に今住んでいるんですけど、一応、二〇〇七年に滋賀県の公害防止条例、一部を改正しまして、地下水汚染の未然防止、それから地下水汚染の早期発見と改善、法施行前に廃止された跡地を土壌調査の対象とするというこういう条例を定めて、もう施行しております。
こういうことをやっぱり全国の法律でもやってほしいなということです。やはり条例、要綱の方が進んでいると思いますし、進んだ条例、要綱を参考とした根本的な法改正をやっていただきたいと思っております。
終わりの部分はもう繰り返しになるんですけど、特に強調しますと、やはり法施行前、実際に僕が土壌汚染の問題にかかわっていると、ほとんどは法施行前の工場、事業場の跡地なんです。それも製造業だけじゃなくて、もちろんガソリンスタンドとかそういうサービス業なんかもあります。
そういう法施行前に有害物質を扱っていた工場跡地とか廃棄物処分場の跡地を法対象にする必要があるんじゃないかと思っております。これは日弁連の意見書でも提案されていますし、地方自治体、神奈川県とか先ほどの滋賀県とか東京都とか、条例ではそういうことを定めているところもあります。
それから、やっぱり土壌汚染の未然防止です。こういうことも今回全く入っていませんが、やはり長期的にはこれをやっておかないと、いったん汚染された土は、先ほど大野さん言われましたように、一〇〇%きれいにすることは技術的にはできません、多分幾らお金を掛けても。
そういう意味で、やっぱり汚染しないということが一番大事ですので、未然防止をやっていく必要がある。そのために、やっぱり操業中の工場、事業場についても滋賀県のように井戸を掘って調べる、常時監視するとかそういうことが大事ではないかと思っております。
そういう意味で、確かに今回の法改正は法対象を一定拡大するプラス面あるんですけれども、マイナス面もありまして、特に掘削除去を排するということは問題があるんじゃないかと思っています。
それと、築地市場の移転問題に関連しまして民主党が修正案を出しまして、衆議院で修正案が通ったようですけれども、いわゆる土壌汚染対策法施行以前の廃止工場、事業場であっても、公園、学校、市場等の、これは築地市場を完全に意識しているんですけれども、そういう公共施設等に利用する場合は法対象とするということが通ったことはそれなりに画期的だと思うんですけれども、私としてはやっぱりすべての施行前の有害物質を扱っていた廃止工場、事業場も法対象にすべきではないかと思っています。
そういう意味で、東京都環境条例とか滋賀県の条例とか、あと川崎市、横浜市、大阪府等の進んだ条例、要綱を参考にした抜本的な法改正を今後やっていただきたいと思っております。
あと、新聞記事を幾つか、朝日新聞とか、それから公明党さんの聖教新聞も頼まれまして、最近、三月に。これ百万か所ぐらい汚染用地がある、築地市場のことも書いてくれよということで少し写真とちょっとコメントが入っております。
それと、社民党の社会新報とか、赤旗とか東京新聞とか、あと毎日新聞とか朝日新聞等にも書いておりますし、あと、最後にちょっとありますように、中国の土壌汚染問題、最近中国は恐らく空気も水も土も食べ物も汚染されていまして、非常に問題がありまして、最近中国の土壌汚染のこともやっておりますので、また参考にしていただければと思っております。
○参考人(畑明郎君)
まず、附則三条につきましては、これはもう築地市場の移転問題で衆議院の川内議員なんかと私一緒にやっているんですけど、やはり法施行前の廃止工場、事業場をその法対象にしないという附則三条は取っ払うべきだと私は思っております。
それから、二番目の一定規模の問題ですけど、これはこれでそれなりに評価できるんですけど、ただ、規模だけでやっていいのかという問題があると思います。例えば、水質汚濁防止法の排水基準の適用の仕方なんですけど、有害物質を扱っている場合は排水量に関係ありません。
普通は排水量一日五十トン以上という場合に排水基準を掛けるんですけど、僕は以前京都市の公害の局におりましたけど、そのときには、有害物質を扱っている、それが出る、排水に出るところは排水量に関係なしに排水基準の規制を掛けております。
そういう意味で、やっぱり有害物質を扱っている工場、事業場については、規模についてはむしろ取っ払うべきだと私は思っております。
それから、民主党案の今回の、公共施設等に転用する場合に調査を義務付ける、これはこれでそれなりの意義は、築地市場の移転問題を法対象にするという意味で意義はあると思うんですけど、ただ、これだけではまだ問題があると思っています。
やはりさっき、何度も言うんですけど、過去に有害物質を扱っていた工場、事業場は基本的には汚染している可能性が強いですので、僕もいろいろ、大阪のUSJも住金の跡地なんですけど、あの場合なんかはほとんど工場の敷地内に産廃を埋めていたんです、それも大量に七十万トンという。それが今ジュラシック・パークという恐竜のパークになっているんですけど。
それで、過去に工場、事業場が工場敷地内に産廃を埋めたりとか、それから別に故意でなくても非意図的に液が漏れてしまった、それで床から、それから排水、例えばあとは排水溝です。必ず排水パイプというのは、時間がたちますと穴が空きます。だから、穴が空いて、そこから廃液が漏れてしまって汚染してしまう。
これは大学なんかでもそういう例はありますし、先ほどのカネボウの中央研究所なんかはほとんどその下水管の途中で液が漏れてしまって土壌汚染してしまったという例がありますので、そういう意味で、やっぱりその有害物質を扱っていた工場、事業場については汚染の危険が強いということで調査を義務付けるべきだと思っております。
○参考人(畑明郎君)
掘削除去の問題ですけど、いわゆる環境基準の設定の根拠なんですけど、よく行政とか企業は直ちに影響はないとかいう言い方するんですけど、元々環境基準等はどういう形で設定されたかといいますと、やはりイタイイタイ病とか水俣病のように非常に低濃度の有害物質を長期間暴露することによって被害が起こるわけです。そういう意味で、じわじわと来るものですから、目に見えてすぐ人が倒れるとかそういう急性中毒ではないんです。
そこを逆手に取って、影響はすぐないとか、出ていないとか、直ちに健康に影響はないという形ですぐ行政は逃げる場合が多いんですけど、やはり長期的な影響を考える必要があるということで、土壌の汚染とか地下水の汚染を残すということはやっぱり将来いろいろな問題が起こる可能性があるということで、掘削除去の方がいいと思いますし、それから費用対効果ですけど、これは時間スケールを考慮しないと駄目だと思うんですね。
例えば岩手県の例ですけど、旧松尾鉱山という硫黄鉱山があるんですけど、これ岩手県の方は御存じなんですけど、日本で一番大きい鉱山がありまして、いまだに酸性の水が出てくるんです。北上川を汚染するということで、非常にでっかい排水処理設備が造られています。これ半永久的に稼働しています。それを国とか岩手県は税金でやっているわけです。
そういうコストは莫大なコストになります。そういう意味で、青森・岩手県境の不法投棄のときに、当時の増田知事が、やはり長期的に見ると全量撤去した方が安上がりであると、この松尾鉱山の例を考慮して岩手県はそういう判断を取ったと聞いております。
そういう意味で、本当に、当面はそれは掘削除去はコストは掛かりますけど、長期的に見ると、そういう維持管理コストを考えるとそんなに高いものではないという場合もあるということです。
それから、覆土の問題ですけど、これは用途を非常に限定されます。例えば、通常、ビルなんかを建てる場合は基礎工事をやるわけです、くいを打ったりとかですね。下をかき混ぜますから、そういう工事をしたら、下に汚染土壌が残っているとその汚染土壌の対策も要りますし、五十センチぐらい覆土しても、これは豊洲の例ですけど、あそこは地下水位がほとんどゼロメートルのときがあるんですけど、土を多少上へ入れても、地下水が上昇してきて雨水と地下水が混ざり合ってまたその入れたきれいな土が再汚染される危険性が高いんです。
OAPでもこれは実際に起こったんですけれども、五年ぐらいでもう起こっちゃったんです。ということで、その五十センチぐらいの覆土では将来的には安全な対策にならないし、地下は触れなくなると、地下の倉庫とか地下の構造物を造れなくなる、造りにくくなるという問題はあります。
OAPにつきましてはどうするかといいますと、五十年後建て替えるときにやりますということで三菱は説明している。当面は、二メートル土入れ替えて、地下水はくみ上げて今延々と処理しているんです、コストを掛けて。取りあえずそういう、これは暫定的な対策だと私は思っております。恒久対策はやはりきれいにするということが大事じゃないかと思います。
○参考人(畑明郎君)
今、大塚先生言われましたように、これは廃棄物の問題と一緒でして、廃棄物処理法上いろんなマニフェストとかやっておりますけど、やはり不法投棄はなくなっておりませんし、僕自身も滋賀県の栗東とか四日市の日本最大の不法投棄の大矢知の問題にもかかわっているんですけど、これ同じことが起こり得ると思います。法律で幾ら汚染土壌のマニフェストを定めてフォローしたとしても、やはり限界はあると思います。
そういう意味で、やはりもう少し排出者責任をどう担保していくかという、これは廃棄物も一緒ですけど、取っていく必要あると思います。
これは残土についても一緒でして、残土も結構怪しいものがありまして、僕は汚染土壌も残土も廃棄物扱いというか、廃棄物処理法の対象にすべきだと思います。そういう意味で、もちろん廃棄物処理法ももっと強化しないと駄目なんですけど、強化した上で汚染土壌と残土等を管理していく。
最近でも残土に関連して、石原産業のフェロシルト事件というのがありましたけど、こういうことはついこの間も起こったばかりですよね。あれ、フェロシルトの回収に五百億円掛かるんですよ、これ石原産業が負担して、三年間赤字決算なんです。やっぱりいったんそういう不法投棄しますと非常にコストが掛かるという問題はありますので、この辺は、せっかく法律作ったんですから、きちっとそれは運用というか施行していってほしいなと思っております。
○参考人(畑明郎君)
これは日経新聞等でも拝見しましたけど、この環境債務ということをこういう企業の会計の中に入れていくことについては大賛成ですし、ストック型汚染と僕らは言っているんですけど、土壌汚染と産業廃棄物の問題というのがやっぱり現在はかなり先送りされていると。
言わば臭いものにふたをしてわざと調査しないとか、調査してもできるだけ安価な対策で終わらせて、将来世代にやっぱり負の遺産を送っているところがあると思いますので、やっぱり早めにそういう資産計上していくことはいいことだと思っていますし、非常に面白いのは、上場企業で一番環境債務たくさん計上しているのはOAP事件を起こした三菱マテリアルです。
それと、僕はイタイイタイ病のことをずっとやっているんですけど、結局、イタイイタイ病の場合、公害を出せば結果的に高く付いた例なんですけど、ほぼ掛かった費用が六百億円以上掛かっております。もちろん、死んだ人は、補償を出していますけど、帰ってこないということで、そういう絶対的な損失があるんですけど、経済的な損失という意味で六百億円以上掛かっています。やっとその汚染された農地の復元が来年ぐらいに終わります。
結局ほぼ四十年ぐらい掛かって、最近、三井金属の神岡の社長は朝日新聞に「私の視点」で書いていましたけど、結局四十年掛かって解決したと。そして、住民と企業が信頼関係ができたということで、結局、百億円の公害防止投資を事件が起こる前にやっておけば六百億円の被害は起こらなかったわけです。
結局、公害を出せば、後で非常に社会的コストも企業も負担が重くなるということで、やはり事前にそういう環境債務を計上して対処していくことが今後大事になるんじゃないかと思っております。
○市田忠義君 日本共産党の市田です。
畑参考人にお聞きいたします。
陳述の中でもお述べになりましたが、畑参考人は、リスクゼロ型の掘削除去等の土壌浄化対策、これを排して盛土や封じ込めなどの安易な対策の推奨に今度の法改正がなりかねないと、そう指摘をされています。
私も、今回の改正案で掘削除去の偏重ということが強調されて、現行の指定区域を要措置区域と要届出区域に分類をして、知事が技術的基準に基づいて指示する制度を新たに盛り込んでいると、これが掘削除去の抑制につながるのではないかという懸念をしております。
私事ですが、私は築地に四年前に住んでいまして、今、豊洲に住むという皮肉な、豊洲への移転には私は反対でありますけれども。
畑参考人は、東京ガスの豊洲工場跡地問題あるいは大阪アメニティパークなど多くの土壌・地下水汚染事例にかかわってこられたわけですが、先ほどもお述べになりましたけれども、このリスクゼロ型の掘削除去を抑制して覆土や封じ込めなどのリスク管理型を普及するということについて改めてもう少し詳しくお伺いしたいのと、若干他の参考人の方からも出されたことなんですが、掘削除去というのはかえって汚染地域が広がって汚染の拡大につながるのではないかという考え方についてどうお考えかと。
コスト問題はよく分かりました。中長期的に見れば、中途半端な処理はかえってお金が掛かるというのはよく分かりましたが、今の点について御意見をお伺いしたいと思います。
○参考人(畑明郎君)
確かに、今回の形質変更届管理区域、それから要措置区域ということで、従来の指定区域を二種類に分けて、結局対策を緩める。そして、掘削除去をできるだけやらさないという方向になるおそれは十分あると思っております。
それで、リスク管理という、これは言葉はいいんですけれども、元々この環境リスク論というのはどこから来たかといいますと、アメリカから来たものでして、これBSE問題が一番典型なんですけれども、いわゆる全頭検査なんか要らない、百万人に一人しかBSEにならないんだ、全頭検査のコストは無駄だと。
要は、アメリカの場合はリスクとベネフィットを比較してベネフィットの方が大きければリスクはある程度我慢すると。みんな飛行機とか自動車は交通事故の可能性があるけれども乗るでしょう、ベネフィットがあるから乗るでしょう、環境も一緒ですという形で、こういうことを中西準子なんかは言っているんですけれども、経産省もそういうスタンスなんですけれども、これは僕は全く間違っていると思います。
基本的には、僕はやっぱりEUが取っている予防原則、これは朝日新聞の知恵蔵に環境リスク論とEUの予防原則を比較して書いたことがあるんですけれども、やはり、今EUが進めているRoHS規制とかREACH規制という化学物質の規制は、言わばカドミウムとか水銀とか危ないものはもう製品に入れていかない、工業製品に入らなければできた廃棄物、廃製品も危ないものが入っていないということです。
鉛とか先ほどのカドミウム、水銀など、基本的には六物質に対してはもうやれている。日本のメーカーもEUに輸出はそれができている。自動車とか電気製品を輸出していますから、対応できるんです。
更にもっと、三万種類というすべての工業製品、化学物質に対して規制を掛けようとすると、従来は医薬品と同じように、医薬品だけが安全を証明しなければ販売できなかったんですけれども、すべての工業製品についてメーカーが安全を証明する義務を持たせるという、そういうREACH規制は今もうヨーロッパで始まっています。順次強化されていきますけれども。そういう動きがあります。
それから、やっぱりリスク管理というのは問題ありますし、本当にリスク管理できないんですよね。土壌は確かに人が動かさなければ動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますから、これはどこへ行くか分からないということで、何か法案にもちょっとありましたように、海辺の埋立地はいいんだと、汚染されていても。これはもう論外でして、やっぱり廃棄物処分場は山の中に造るか海に埋めているかどっちかなんですけれども、山の場合はもちろん排水は河川の上流に入ってきますし、海の場合もやはり、大阪湾のフェニックスとかありますけれども、東京湾の埋め立てていますけれども、やはり海の汚染を起こします。
完全にその汚染水を海に流さないことはできません。今、遮水していますけれども、あれは堤防だけ遮水していまして底は抜けていますので、必ず汚染が海に広がります。それで魚の汚染も起こりますし、そういう意味で問題があるということです。
それと、確かに掘削除去した土地をどう処理するかというのはもちろん問題なんですけれども、僕のかかわった京都府の日本最大のクレー射撃場、これは麻生首相が好きらしいんですけれども、要するに鉛の散弾、これを撃つんですよ。それで皿を割るらしいんですけれども。当然鉛の散弾がそこへ散らばって、クレー射撃場の中が鉛で土が全部汚染されちゃったんです。
その土、今京都府立の施設なんですけれども、京都府は十億円以上掛けて全部、秋田県の小坂にあるんですけれども、土壌処理施設で土をきれいにしてまた戻す、そういうことをちゃんとやっているんです。
そういう意味で、それは搬出土壌の処理の仕方、適正な処理をやっぱりどう担保するかという問題でして、これは産廃と一緒でして、ただ今の現状からいくともちろん産廃と同じように汚染土壌がどこへ行っているか分からぬという問題は起こり得ると思いますので、それは十分注意しながらやっていくしかないと思っております。ただ、技術的にはできると思います。
○参考人(畑明郎君)
だから、今回のもちろん一定規模以上の、多分三千平米ぐらいになると聞いておりますけれども、それはもちろん改善、今の法律の、ざる法のざるを少し目を埋める、目を小さくするということにはなると思いますけれども、完全にざるは目が埋まった状態ではないと思っております。
やはり法施行前の有害物質を扱っていた工場、事業場、これは水質汚濁防止法の特定施設以外にもいっぱい出ていますので、やっぱり有害物質を例えば運搬とか保管したところでも汚染は起こっていますので、それから交通機関とかそういうところなんかでも起こっていますので、やっぱり過去のこれは負の遺産だと。製造業の当初負の遺産という言葉が言われたんですけれども、土壌汚染は。過去の負の遺産をいつかの時点で一掃するためには、きちっとまずはやっぱり調査をすべきであると。
もちろん一〇〇%の工場が全部汚染されているとは僕は言いませんし、多分半分ぐらいだろうという土環センターの推定なんかもありますけれども、やっぱりやってみないと分かりませんから、調査はまずちゃんとすべきである。
これはカドミウム汚染米と一緒でして、ついちょっと前、一九九八年ぐらいに、五十ヘクタール単位にワンポイントでじゅうたん的に米を全部調査したら、またいっぱい準汚染米が出てきたという問題がありました。そういう意味で、やっぱり危ない可能性のある工場、事業場については調査を法的に義務付けてしていくべきであると。
あと、対策はどうするかというのは、やっぱりケース・バイ・ケースになると思いますけれども。
○参考人(畑明郎君)
私は元々の出身が京大の工学部の金属でして、それでずっと金属にこだわってやっているんですけど、金属というのは、確かに人間生活とかいろんな経済に役立っているんですけど、プラス面とマイナス面があって、金なんかは全く毒性がないんですけど、金以外の金属はほとんど何らかの毒性はあります。鉄なんかもたくさん取ったらやっぱり問題なんですけど。
確かに、それで必須金属で見ましても、多過ぎても少な過ぎても駄目なんですね。これは、生物は人間も含めて海から生まれた関係で海の中のやっぱり金属の濃度というのが影響しているんですけど、そういう意味で、例えばカドミウムとか水銀とか鉛とかは元々生物とか人間が利用しなかったんです。カルシウムとか鉄とか銅とか、こういうものは生物が利用したのでこれは必須金属になっているんですけど、全く利用しない不要な金属というのがあるんです。
そういうものの典型的なものが水銀であり、カドミウムであり、鉛とか六価クロムとか、そういう非常に有害な重金属なんです。そういうものはやっぱり基本的に、水銀は水俣病を起こしましたし、カドミウムはイタイイタイ病を起こしたと。鉛はもう古来からある毒物なんですけどね。これはもうギリシャ・ローマ時代からいろいろ毒ありますし、砒素なんかもそうですけど。
そういう明らかに人体に有害と分かっている金属についてはできるだけ使っていかないようにしようと、特に工業製品に使っていかないと。例えば、水銀なんかかて、昔はいろいろ、おしろいとかそれから不老長寿の薬とか、多分早く死んだと思うんですけど、そういうものに使われていたぐらいなんですけど。
それらは、明らかにやっぱり有害なものはできるだけ減らしていこうという意味で、僕の書いた本にはいろいろ書いてあるんですけど、やっぱりEUは、ヨーロッパが進めているこういう、元々これは北欧とかスウェーデンの方から始まったんですけど、有害な金属をやっぱり規制していく、工業製品には使っていかないと。そうすると、やっぱり安全な工業製品なので、後、環境汚染も少ないし、廃棄物についても処理、リサイクルしやすくなる。根本的にはそれやらないと。
それで、金属というのは基本的にはなくならない、地球上からなくならないんです。量は常に一定なんです。全部地下資源にあった分ですから、鉄はさびて酸化鉄になりますけど、鉄そのものの量は、地球上の存在量は変わらないです。隕鉄が降ってきて、その分は鉄が増えたかも分からないですけど。そういう意味で、絶対、金属はどこに行っても形変えるだけで、なくならないんですよ。
だから、有害な金属というのは、一回使うとどこかに行っちゃうんです。例えば、水銀でも今、石炭火力発電、石炭の中、少し水銀入っているんですけど、豊洲も石炭からガス造っていましたので水銀汚染あるんですけどね。そういうのは、火力発電は飛んでいるんですよ。アメリカなんかでは一番多いんですよ。中国からも今、水銀が飛んでいるという話もありますし。
そういう意味で、やっぱり危ないものが入っているものはできるだけ削減しよう、減らしていこうと。一遍にゼロにはできませんから。そういう動きというのはヨーロッパを中心に今始まっていますので、やっぱり日本も余りアメリカに追従するんじゃなくて、さっきのリスク論ですね、リスクとベネフィットを比較して、少々のリスクは我慢しろというんじゃなくて、やっぱり予防原則というか、安全なものにしていく、すべての消費するものとか物を、物資をですね。これは食べ物も含めてだと思いますけどね。
例えば農薬なんかも、結構昔は米にも水銀の農薬とか、それから今でも果樹、リンゴとかああいうものは砒素、鉛系の農薬なんかも使われていましたし、シロアリの駆除剤はあの和歌山のカレー事件で砒素が、亜砒酸が使われていましたし、そういうのがまだ使われているんですよね。そういうものをやっぱりどんどん減らしていくか代替のものに替えていく。
例えばカドミウムについては、昔はニッカド電池、まあ今も使われているんですけど、カドミウムはやっぱり問題があるということでだんだんリチウムイオン電池に切り替わっていっていますし、そういう代替のものがあるものについては替えていく。
ただ、自動車の鉛バッテリーは今代替はないんですよね。だから、リチウムイオン電池で自動車搭載型というのはまだ十分実用化されていませんので、そうなれば鉛バッテリーも使わなくて済むというようなことになると思います。
以上です。
○参考人(畑明郎君)
一番いい例はイタイイタイ病だと思うんですけど、先ほども少し紹介しましたけど。
僕は、だから、三井金属については評価しているんですけど。結局、カドミウムの排出量をほぼ四十年間で十分の一以下にしまして、神通川のカドミウムの水質は鉱山の上流も下流もほぼ一緒になったと。
もちろん、ゼロエミッション、ゼロ排出にはならないですね。ゼロにはできないんですけど、少しは出るんですけど。それで、ほぼ無視できるぐらいの濃度になって、自然界レベルになって神通川は清流に戻って、下流の農地も復元田ということで、千ヘクタールぐらい復元して、数百億円の費用が掛かったんですけど、来年終わると。また汚染物質流したらまた再汚染されますから、これも一種の未然防止だと思うんですけど。
それで、三井金属つぶれたかといいますと、決してつぶれていませんね。今、三井金属は先ほど言いました鉛の、自動車のバッテリーの日本最大のリサイクル工場になっているんです、神岡鉱山が。今、神岡鉱山は、鉱石は掘っていませんけど、自動車のバッテリーを回収して、それをまた鉛にして、自動車のバッテリーは非常にシンプルな製品でして、プラスチックの箱に鉛の電極が入っているだけです。
あと硫酸が入っていまして、まあ硫酸は処理したらいいので、プラスチックと鉛はまた再利用できるんです。あとそれ以外にも三井金属は、皆さん持っている携帯電話の中の銅の薄い箔というんですけれども、回路に使うんですけれども、これの世界トップシェアなんですよ。最近ちょっと何か経営苦しいようですけれども、それでも倒産はしていないし、神岡鉱山も操業を続けながらちゃんとそれなりの利益を出して、経済と環境の両立というのができたわけですね。
それで、この前、朝日新聞にも神岡の、まあ三井の取締役ですけれども、神岡の社長は「私の視点」に、今四十年たって成功したと、対策は。
これは、参議院の議員やられた近藤忠孝イタイイタイ病の弁護団長がNHKの「その時歴史が動いた」にも出ておられましたけれども、弁護団も被害者も企業を評価しているんですね、今。一応企業、経済活動と、上流の神岡鉱山は操業を続けています、工場。鉛、亜鉛造っているんですけれども。しかし、それで下流の農業も両立するということで、やっぱり経済と環境の両立はやればできるんだと。
アジアの問題ですけれども、一応このアジアの土壌汚染で私、最近、韓国とか台湾とか中国の調査やっているんですけれども、特に中国は皆さん御存じのようにひどい状況でして、僕は主に南の方の広東省とか湖南省の鉱山を見に行ったんですけれども、ほとんど排水は垂れ流し状態です。
もう鉄分を、真っ赤な水がそのまま垂れ流されて、谷間は全部泥の海になっていると。下流にがんの村が幾つかできていると。がんの原因もよく分からないんですよね、砒素なのか。多分、砒素でがんになっていると僕は思うんですけれども。あと、カドミウムによってイタイイタイ病みたいな患者も出ていまして。
そこの省の研究所の人がいろいろ調べていまして、その人に調査、案内してもらって、うちの中国の留学生がガイドしてくれたんですけれどもね。それで、日本にも一応中国の研究者を呼びまして、それで日本の富山とかイタイイタイ病の視察もやってもらいまして、これはテレビとか毎日新聞なんかに紹介されたんですけれども。
それで、復元の現場なんかも見せたんですけれども、それをそのまま中国に持っていくのは無理ですね。中国にそんなお金がないとか。やはり、日本の経験を生かしてほしいんですけれども、このままいくと中国は環境よりも経済成長優先でいっていますから、何か行くところまで行かないと反省しないのかなという気はあります。
だから、日本としては、やっぱりできるだけ日本の経験を知らせて、こういう解決の仕方をしたんだということでそれを紹介して、それを中国側がどうやって自分でやっていくかという、そのときに技術援助とか経済援助できることはやっぱり日本がやっていくべきだと思っております。
以上です。
○荒井広幸君 ありがとうございました。
○川田龍平君 川田龍平です。
土壌汚染対策法を始め環境関係法は市町村の役割が重要だと考えていますが、現実に地域で土壌汚染の問題が生じた場合に市区町村が住民への汚染状況の説明や緊急的な対応を行うことになると思いますが、環境省と都道府県、それから市区町村の相互に補完的な体制を整える必要があるかどうか、その点でこの法律が十分かどうかということ、あるいは課題があると考えているかどうかを参考人にお聞きしたいと思います。各参考人、お願いします。
○参考人(畑明郎君)
難しい問題なんですけれども、一応二つの事例で紹介したいと思いますけれども。
一つは、滋賀県の栗東の産廃問題ですけれども。栗東市は住民も含めて、僕はほとんど行政からは委員に呼ばれないんですけれども、珍しく栗東市の調査委員には住民推薦で入っていまして、それで栗東市としていろんな対策案の意見を出しているんですけれども。
それに対して滋賀県は、今、嘉田知事なんですけれども、嘉田知事は有名なんですけれども、新幹線の駅は止めたんですけれども、それからダムもある程度止めようとしているんですけれども、この産廃問題についてはからっきし駄目でして、今、栗東市とか周辺の住民の反発を食らっていまして、要は住民はやっぱり全量撤去を要求しているんですよね。確かに僕らも全量撤去が一番望ましいんですけれども、コスト的に二百数十億掛かるので無理なので。
ただ、県が考えている案は、要するに遮水壁で、ソイルセメントの遮水壁で囲って水をくみ上げて処理して産廃を残そうという、そういう案で四十五億円なんですけれどもね。僕らはそれよりも安い方法で効果的な対策ができますということで、底の粘土層が破壊されているんですけれども、その粘土層の修復と、明らかにドラム缶が三千本以上入っているのが分かっているので、そういう明らかに有害なものはやっぱり全部掘削して掘り起こす。
そういう対策は二十億円ぐらいで済むんですよね。そういう提案を栗東市として、その委員会として提案しているんですけれども、県の方はそれをつぶしに来ていまして、県の対策案を強引にやろうとしたんですけれども、結局は、周辺の住民の同意が得られない、自治会の同意は得られないし、七つの自治会のうち一つしか同意が得られなかったし、議会でも、多分これは自民党と共産党が反対してちょっと通らない可能性が強いので、結局、県案についてはちょっと棚上げになっているんですけれども。
そのときに環境省が果たした役割は非常に悪い役割をやっていまして、要は、環境省がどうも全量撤去をやるなと、現地封じ込めやれと。これは土壌汚染対策法と同じスタンスでして、土壌汚染対策法も掘削除去をやめろと、できるだけ現地封じ込めとか土かぶせて終わりにしろと、それと同じことがやられていますね。
これは、四日市の日本最大の不法投棄、百六十万、百七十万立方メートルが不法で、全部足すと三百万立方メートル、巨大なごみの山ができているんですけれども。そのときも、当初、県は不法投棄の部分については全量撤去をしますという案を出したんですけれども、それに対して環境省は、聞くところによると、環境省が圧力を掛けて、結局むちゃくちゃひどい対策なんですけれども、土かぶせて雨水だけ処理する、それで終わりにしようという。
岐阜の、あと椿洞の産廃の不法投棄事件でも、これは市長が当初、全量撤去をやりますということの方針を打ち出していたんですけれども、環境省がいろいろ圧力を掛けて一部撤去で百億円という形で決着ということで、そういう意味でやっぱり今、県とか環境省が市町村に対して果たしている役割というのは決して余り好ましくないという状況だと思っております。
○川田龍平君 ありがとうございます。
岡山市の小鳥が丘団地では、平成十六年に岡山市の水道局による水道管入替えの工事のときに土壌汚染が発見されて、これまで揮発性の有機化合物であるトリクロロエチレンが最大で環境基準の二十七倍、ベンゼンが二十六倍検出されるほどの状況にあると。
このため、窓を閉めていても異臭によって眠れない人であったりとか、頭痛や鼻炎などに悩まされる人であったり、中には住宅ローンが残っているにもかかわらず引っ越しを余儀なくされた人もいると聞いているんですが。
この土壌からの揮発経由による摂取、また住宅地における土壌汚染の場合というのがどうなのかという、長期的に濃度が高くない水準の暴露環境の中での暮らし、健康被害を受ける場合も考えられますが、こうした低濃度の長期暴露による健康被害について、参考人の意見を、答えられる方に答えていただきたいと思うんですが。
○参考人(畑明郎君)
これは私の資料にも書いていますように、私も三回ほど現地に行きまして、住民にも頼まれまして、それで今裁判にもなっております。
それで、この団地ってちっちゃい四十戸足らずの団地なんですけれども、団地の入口というか、道に入ると、川田議員も行かれたんですかね、もうぷうんと変な油臭いにおいがするんですよ。それで、二十四時間それを吸っていまして、多分外出した方が気分がいい、家にいると気分が悪くなると。実際に何かいろいろ発疹とかできものができたりとか。
台所の下に物入れがあるんですけれども、その床がコンクリートを張っていないところが何か噴火口みたいになっていまして、ガスが噴き出してきているんですね、メタンガスとかいろんなガスが。それから、庭の土がぶわぶわになっているんです。非常に軟らかくなっているんです。下から噴き出してきて、一部黒っぽい油そのものが出てきて、十センチ掘りますともう真っ黒けの油まみれの土なんですよ。これは元々何か廃油のリサイクル業者でして、そのかすをまた豊島に持っていったというんです。豊島の産廃業者と何かセットだったらしいんですけれども。
そういうところで健康被害がある、実際に健康被害が起こって裁判を起こしているんですけれども、全く行政の方は、もう岡山市も県も取り合おうとしないと。基準もないと。土壌汚染の大気の基準はないんですよね。土壌の溶出量とか含有量しかない、地下水の基準しかありませんからね。そういう意味でやっぱり裁判に訴えられない、裁判やってもこれは勝てるかどうか分からないと。
もう日常的にずっと、それで、外へ引っ越したいけれども、その家はもう銀行の担保価値ゼロなんですよ。全然お金も貸してくれない、売れない、その家ももういろいろマスコミに出ていますから。そういう悲惨な状況になっているところがあります。だから、実際に人が住んでいるところで日常的にVOC揮発していきますから、そういう大変なところの問題が起こったところがあるんですけれども、それに今の土壌汚染対策法は全く役に立たないという意味で、大気の基準なんかも設定要ると思います。
ただ、さっきの豊洲の問題でも、これ、ベンゼン、シアン、水銀は蒸発するんですよね、常温でも。それの基準はないという、やっぱりそういう問題はあると思います。大気汚染防止法で少し大気の環境基準はあるものはあるんですけれどもね。土壌汚染についてはないということで、問題あると思っています。
以上です。
○川田龍平君 ありがとうございます。
それから、今、汚染原因者の分社化を内容とする、水俣病についてなんですけれども、分社化を内容とするこの与党法案というのは今国会に提出されているんですが、汚染者負担の原則が今度薄くなる傾向にあるという印象を持っていますが、この土壌汚染法とこの汚染者負担の原則についての参考人の御意見を伺いたいと思います。これも答えられる方で結構です。
○参考人(畑明郎君)
だから、この汚染者負担原則ですね、基本的には従来の公害法はそれで貫かれているんですけれども、特に土壌汚染については、農用地の土壌汚染防止法はイタイイタイ病を契機として制定されたんですけど、これは基本的には汚染原因者負担です。だから、神岡鉱山、三井金属が土壌復元費用を、これは国の法律があって少し減額されていますけど、基本的には企業負担、人体被害の補償に農業被害の補償すべて、だから五百億円近い金額を企業は支払っているんです。
それが水俣病の場合、僕はチッソは非常にけしからぬと思うんですけど、三井金属はやっぱり、財閥系企業とそうでない企業の違いか、世間体があるのか知らないですけど、やっぱりきちっと三井金属は、三井財閥の一員だったし、対応を取って原因者負担を貫いているし。
この土壌汚染対策法が元々できたときに、やっぱりその汚染者負担原則は全く貫かれない、土地所有者責任主義と言われていましたけどね。それで、汚染原因者がオーケーしたら所有者が請求できますよと言っていますけど、普通はオーケーしないです。汚染原因者イコール土地所有者だったら問題ないんですけど、汚染原因者は必ず逃げますから。
それをまた証明しようとするとやっぱり裁判しかないとか、そういういっぱい、カネボウでもこれ裁判起こっているんですよ、企業同士が裁判やっているという。
やっぱりそういう意味で、土壌汚染対策法はPPPは貫かれていないということで問題はあると思っています。
本日はこれにて散会いたします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/171/0065/17104140065005a.html
平成二十一年四月十四日(火曜日)
大阪市立大学大学院特任教授日本環境学会会長 畑 明郎君
本日の会議に付した案件
○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付)
○委員長(有村治子君)
ただいまから環境委員会を開会いたします。
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○参考人(畑明郎君)
大阪市立大学の畑と申します。
資料としましては、昨年十一月に日弁連の機関誌の「自由と正義」という雑誌があるんですけれども、それに土壌汚染対策法の特集がありまして、それの巻頭論文を付けております。二番目には大塚先生も書かれていますので、また参考にしていただければと思います。
元々、私は七年前にここに、法律できるときの、制定のときの参考人で、大野参考人と私とあと二人の方だったんですけれども。そのときに、ちょうど五月だったんですけれども、四月ですから今、似た時期ですけれども、非常に問題はいっぱいあるということで、当時は一応民主党の福山議員の紹介でこれ参加したわけですけれども、十五項目ぐらい問題あるということで、中でも大きな問題点は、二番目の、この法律はやっぱり土壌汚染の事後対策法である、未然防止法ではないということです。
それから、地下水の汚染の防止の観点がほとんどないと。土は人間が動かさないと動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますので、そこの防止の対策がこの法律では非常に問題があると。
それから、五番目の三条の調査対象ですね、これが一番問題なんですけれども、いわゆる水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止時、それも法律施行後の廃止時、さらに宅地等への転用する場合だけ、そういう形で非常に法対象を狭くしていると。それから、それ以外にも金属鉱山・製錬所、廃棄物処分場の跡地周辺、軍事基地等を対象外にしていることです。
それから七番目が、調査、対策を原則として汚染原因者でなく土地所有者等に義務付けている点です。
それから十番目が、対策は原則として覆土、つまり五十センチ以上の盛土でよしとする、土壌の浄化は特別な場合だと。これは保育園とか幼稚園とかそういう場合だけだという感じになっておりまして、この法律制定時から非常に問題があったと思っております。
とても土壌汚染問題の根本的解決につながる法律とは言えませんし、そればかりか、土壌汚染を覆土で隠ぺいし、言わば臭い物にふたをする、後世に負の遺産を残すことを合法化するざる法ではないかということで批判したわけです。
やはり法施行後五年、今六年ですけれども、たった現在、そのざる法性はますます明らかになったのではないかと思っております。
二番目のは、もう御存じのように、先ほど言われましたように、法対象が非常に、二%しかないとか、廃止工場の八割は調査を逃げている、つまり宅地等に用途を転用しないということで、ブラウンフィールド化している。
それから対策も二%しかないと。それから、四条の調査命令も、発動したのは五件。これは、環境省は課長会議の何か通達出していまして、一キロ以内ぐらいに直接水道の飲み水に使用している場合だけ発令しろ、それ以外発令するなというそういう通達を出しておりまして、結果的に五件しかないと。しかも、それは岩手県とか鳥取県とか、皆さん御存じの特定の知事がおられたときしか、県しか命令を出しておりません。そういうことで、非常に実効性の乏しいざる法となっていると思います。
それで、いわゆるこの法律自身は盛土、舗装等で摂取経路を遮断する対策で十分であると言っているんですけど、リスク管理といっておりますけど、汚染土壌が残っている限り半永久的に管理する必要があるわけですね。
特に問題なのは地下水の問題です。土壌が汚染されていますと、必ずそれに接触している地下水は汚染されます。その地下水は勝手に動きます。ということで、確かに直接都市部では飲み水にしていないんですけど、地下水によって汚染が拡散するという点で、その地下水のくみ上げ処理とか遮水壁で囲むとか幾つかの方法があるんですけど、一〇〇%水をカットすることは技術的には困難です。
幾らお金を掛けても困難です。ということで、こういうリスク管理には非常に問題があるということで、やはりリスクゼロ型の掘削除去の方が結果的には多く採用されているし、その方が私はいいと思っております。
当然それを掘削除去した汚染土壌については適正に処理することは当たり前のことでして、これは技術的に、最近、秋田とか川崎とか幾つかにその汚染土壌をきれいにするプラントもできておりますし、問題はコストですね、お金が掛かりますから。その負担をだれがするかという問題だと思っております。
それから三番目の、大野さんのおられる土環センターの調査によれば、いわゆる製造業だけじゃなくてサービス業も含めて九十三万か所ぐらい汚染地があるんではないかと推定されています。
これの調査費用が二兆円で、浄化費用が十一兆円で、合計十三兆円の土壌浄化ビジネスです。既に二〇〇七年でほぼ二千億円近い、年間二千億円の土壌浄化ビジネスになっております。二〇〇八年はちょっと景気の悪化で初めて落ち込むようですけど、それまではずっと右肩上がりで土壌浄化ビジネスの業界は成長しております。
それと、あと汚染地ですけど、基本的には東京、関東、近畿、中部の三大都市圏のいわゆるオールドエコノミーというか、そういう重化学工業の工場地帯のところに多いということです。
それから四番目は、私自身いろんな事件にかかわっているんですけど、基本的には市民、住民の依頼によってやってきたものが二十件以上あります。その中で法対象になったものは、この二十件のうちわずか三件です。
大阪のカネボウの中研の跡地、神戸の日本テルペン化学、川西の中央北地区、これは皮なめし工場です。ということで、大半が法施行前に廃止された工場、事業場や廃棄物処分場周辺の跡地です。ということで、法施行前に廃止された工場跡地、特に有害物質を取り扱っていた事業場をやっぱり法対象にする必要があるし、ドイツなんかでは廃棄物処分場の跡地周辺も法対象にしております。
あと、先ほど出ましたように、私はこの二番目の、?の大阪アメニティパークの、OAPの事件にかなり三年間ぐらいずっと住民に頼まれてかかわったんですけど、このときには土壌汚染対策法は全く役に立たなかったです。宅建業法でやっと三菱は対策とか調査をやったということになったわけですね。
それからあと、七番目以降、そこに滋賀県の例がありまして、私、滋賀県に住んでおりまして、有村委員長も滋賀県出身だそうなんですけど、守山、野洲とか信楽では、これは水道の飲み水の汚染が起こりました。
それから、住友大阪セメント、セメント工場もいろいろ問題あるんですけど、それから、今、滋賀県の知事が栗東の新幹線の駅止めましたけど、この産廃処分場の問題がもう一つありまして、そういう周辺で地下水汚染、土壌汚染が起こっております。
それから、このテルペン化学で、神戸の、非常に印象的だったんですけど、法対象になっているんですけど、法施行時に稼働していた施設では使っていた薬品だけの元素を、有害な元素を対象にしていまして、過去にあった施設の有害物質についてはこれは法対象にならないんだという解釈を神戸市、環境省がしておりまして、それは何かの間違いじゃないかと思ったんですけど、あくまで自主的調査だと。非常に法律自身を狭く運用していると。
いわゆるこういう土壌汚染というのは、一回汚染されますと十年、二十年、三十年、数十年間は蓄積します。そういう意味で、過去の汚染も考慮して調査、対策しないと意味がないと思うんですけど、非常に法律の運用が狭くなっている問題があると思っております。
それから、ここには書いていませんけど、武田薬品の神奈川の湘南工場の最近例知ったんですけど、これは工場の廃止は最近なんですけど、施設が法施行前に廃止されていた、だから法対象にならないと。神奈川県の条例でやっと対象になったという事例がございます。
あと、四日市の例のフェロシルト事件とか産廃処分場の問題とか、あと岐阜とかです。僕自身は、ずっとイタイイタイ病を起こした三井金属の神岡鉱山の排水・土壌汚染対策を四十年近くやっておりますけど、ここは一応今成功しましたけど、工場の下に汚染土壌が残っていまして、約九十トンぐらいカドミウムが残っているんですけど、完全に地下水くむまでに処理するには百年掛かると言われています。
そういう意味で、汚染土壌を残しますと非常に半永久的に処理コストが掛かるということです。結果的には取ってしまった方が安く上がる。これは産廃処分場でも一緒なんですけど、豊島とか青森、岩手のように全量撤去した方が後々ランニングコストというか排水処理とかいろんなリスク管理の費用が結果的には安く上がると思っております。
それから、皆さん御存じの築地市場の問題です。この問題につきまして、一応最近かかわっておりまして、もう御存じなので飛ばしますけど、これは面積的には日本最大の土壌汚染地になりますということで、一千億じゃなくて六百数十億円対策費が掛かる。
それも、二メートル土取って、汚染土壌は下に残ります。汚染地下水は半永久的にくみ上げて処理する、このコストがまた掛かります。そういう対策を東京都がやろうとしています。
今回の法律の件ですけど、僕は基本的にはやっぱりリスクゼロ型の掘削除去の土壌浄化対策の方がいいと思っていますし、盛土、封じ込め等は、こういう安易な対策は問題があると思っています。特に今回の法律はそういう点を、何か掘削除去を排して安易な対策、安上がりな対策を推進、推奨しようとしているということで問題があると思っています。
そういう意味で、東京都の条例とか滋賀県の条例のいわゆる一定規模以上の土地の改変、これは今回の法律には適用されているんですけど、問題はあとは、東京都、あと神奈川県横浜市、川崎市、大阪府等が採用しているんですけど、過去に有害物質を取り扱っていた工場、事業場については条例の対象にするということはやっぱり法律についてもやっていく必要があるんじゃないかと思っています。
それと、滋賀県の条例は、今回、環境省の委員会では全く取り上げられなかったんです。私は滋賀県に今住んでいるんですけど、一応、二〇〇七年に滋賀県の公害防止条例、一部を改正しまして、地下水汚染の未然防止、それから地下水汚染の早期発見と改善、法施行前に廃止された跡地を土壌調査の対象とするというこういう条例を定めて、もう施行しております。
こういうことをやっぱり全国の法律でもやってほしいなということです。やはり条例、要綱の方が進んでいると思いますし、進んだ条例、要綱を参考とした根本的な法改正をやっていただきたいと思っております。
終わりの部分はもう繰り返しになるんですけど、特に強調しますと、やはり法施行前、実際に僕が土壌汚染の問題にかかわっていると、ほとんどは法施行前の工場、事業場の跡地なんです。それも製造業だけじゃなくて、もちろんガソリンスタンドとかそういうサービス業なんかもあります。
そういう法施行前に有害物質を扱っていた工場跡地とか廃棄物処分場の跡地を法対象にする必要があるんじゃないかと思っております。これは日弁連の意見書でも提案されていますし、地方自治体、神奈川県とか先ほどの滋賀県とか東京都とか、条例ではそういうことを定めているところもあります。
それから、やっぱり土壌汚染の未然防止です。こういうことも今回全く入っていませんが、やはり長期的にはこれをやっておかないと、いったん汚染された土は、先ほど大野さん言われましたように、一〇〇%きれいにすることは技術的にはできません、多分幾らお金を掛けても。
そういう意味で、やっぱり汚染しないということが一番大事ですので、未然防止をやっていく必要がある。そのために、やっぱり操業中の工場、事業場についても滋賀県のように井戸を掘って調べる、常時監視するとかそういうことが大事ではないかと思っております。
そういう意味で、確かに今回の法改正は法対象を一定拡大するプラス面あるんですけれども、マイナス面もありまして、特に掘削除去を排するということは問題があるんじゃないかと思っています。
それと、築地市場の移転問題に関連しまして民主党が修正案を出しまして、衆議院で修正案が通ったようですけれども、いわゆる土壌汚染対策法施行以前の廃止工場、事業場であっても、公園、学校、市場等の、これは築地市場を完全に意識しているんですけれども、そういう公共施設等に利用する場合は法対象とするということが通ったことはそれなりに画期的だと思うんですけれども、私としてはやっぱりすべての施行前の有害物質を扱っていた廃止工場、事業場も法対象にすべきではないかと思っています。
そういう意味で、東京都環境条例とか滋賀県の条例とか、あと川崎市、横浜市、大阪府等の進んだ条例、要綱を参考にした抜本的な法改正を今後やっていただきたいと思っております。
あと、新聞記事を幾つか、朝日新聞とか、それから公明党さんの聖教新聞も頼まれまして、最近、三月に。これ百万か所ぐらい汚染用地がある、築地市場のことも書いてくれよということで少し写真とちょっとコメントが入っております。
それと、社民党の社会新報とか、赤旗とか東京新聞とか、あと毎日新聞とか朝日新聞等にも書いておりますし、あと、最後にちょっとありますように、中国の土壌汚染問題、最近中国は恐らく空気も水も土も食べ物も汚染されていまして、非常に問題がありまして、最近中国の土壌汚染のこともやっておりますので、また参考にしていただければと思っております。
○参考人(畑明郎君)
まず、附則三条につきましては、これはもう築地市場の移転問題で衆議院の川内議員なんかと私一緒にやっているんですけど、やはり法施行前の廃止工場、事業場をその法対象にしないという附則三条は取っ払うべきだと私は思っております。
それから、二番目の一定規模の問題ですけど、これはこれでそれなりに評価できるんですけど、ただ、規模だけでやっていいのかという問題があると思います。例えば、水質汚濁防止法の排水基準の適用の仕方なんですけど、有害物質を扱っている場合は排水量に関係ありません。
普通は排水量一日五十トン以上という場合に排水基準を掛けるんですけど、僕は以前京都市の公害の局におりましたけど、そのときには、有害物質を扱っている、それが出る、排水に出るところは排水量に関係なしに排水基準の規制を掛けております。
そういう意味で、やっぱり有害物質を扱っている工場、事業場については、規模についてはむしろ取っ払うべきだと私は思っております。
それから、民主党案の今回の、公共施設等に転用する場合に調査を義務付ける、これはこれでそれなりの意義は、築地市場の移転問題を法対象にするという意味で意義はあると思うんですけど、ただ、これだけではまだ問題があると思っています。
やはりさっき、何度も言うんですけど、過去に有害物質を扱っていた工場、事業場は基本的には汚染している可能性が強いですので、僕もいろいろ、大阪のUSJも住金の跡地なんですけど、あの場合なんかはほとんど工場の敷地内に産廃を埋めていたんです、それも大量に七十万トンという。それが今ジュラシック・パークという恐竜のパークになっているんですけど。
それで、過去に工場、事業場が工場敷地内に産廃を埋めたりとか、それから別に故意でなくても非意図的に液が漏れてしまった、それで床から、それから排水、例えばあとは排水溝です。必ず排水パイプというのは、時間がたちますと穴が空きます。だから、穴が空いて、そこから廃液が漏れてしまって汚染してしまう。
これは大学なんかでもそういう例はありますし、先ほどのカネボウの中央研究所なんかはほとんどその下水管の途中で液が漏れてしまって土壌汚染してしまったという例がありますので、そういう意味で、やっぱりその有害物質を扱っていた工場、事業場については汚染の危険が強いということで調査を義務付けるべきだと思っております。
○参考人(畑明郎君)
掘削除去の問題ですけど、いわゆる環境基準の設定の根拠なんですけど、よく行政とか企業は直ちに影響はないとかいう言い方するんですけど、元々環境基準等はどういう形で設定されたかといいますと、やはりイタイイタイ病とか水俣病のように非常に低濃度の有害物質を長期間暴露することによって被害が起こるわけです。そういう意味で、じわじわと来るものですから、目に見えてすぐ人が倒れるとかそういう急性中毒ではないんです。
そこを逆手に取って、影響はすぐないとか、出ていないとか、直ちに健康に影響はないという形ですぐ行政は逃げる場合が多いんですけど、やはり長期的な影響を考える必要があるということで、土壌の汚染とか地下水の汚染を残すということはやっぱり将来いろいろな問題が起こる可能性があるということで、掘削除去の方がいいと思いますし、それから費用対効果ですけど、これは時間スケールを考慮しないと駄目だと思うんですね。
例えば岩手県の例ですけど、旧松尾鉱山という硫黄鉱山があるんですけど、これ岩手県の方は御存じなんですけど、日本で一番大きい鉱山がありまして、いまだに酸性の水が出てくるんです。北上川を汚染するということで、非常にでっかい排水処理設備が造られています。これ半永久的に稼働しています。それを国とか岩手県は税金でやっているわけです。
そういうコストは莫大なコストになります。そういう意味で、青森・岩手県境の不法投棄のときに、当時の増田知事が、やはり長期的に見ると全量撤去した方が安上がりであると、この松尾鉱山の例を考慮して岩手県はそういう判断を取ったと聞いております。
そういう意味で、本当に、当面はそれは掘削除去はコストは掛かりますけど、長期的に見ると、そういう維持管理コストを考えるとそんなに高いものではないという場合もあるということです。
それから、覆土の問題ですけど、これは用途を非常に限定されます。例えば、通常、ビルなんかを建てる場合は基礎工事をやるわけです、くいを打ったりとかですね。下をかき混ぜますから、そういう工事をしたら、下に汚染土壌が残っているとその汚染土壌の対策も要りますし、五十センチぐらい覆土しても、これは豊洲の例ですけど、あそこは地下水位がほとんどゼロメートルのときがあるんですけど、土を多少上へ入れても、地下水が上昇してきて雨水と地下水が混ざり合ってまたその入れたきれいな土が再汚染される危険性が高いんです。
OAPでもこれは実際に起こったんですけれども、五年ぐらいでもう起こっちゃったんです。ということで、その五十センチぐらいの覆土では将来的には安全な対策にならないし、地下は触れなくなると、地下の倉庫とか地下の構造物を造れなくなる、造りにくくなるという問題はあります。
OAPにつきましてはどうするかといいますと、五十年後建て替えるときにやりますということで三菱は説明している。当面は、二メートル土入れ替えて、地下水はくみ上げて今延々と処理しているんです、コストを掛けて。取りあえずそういう、これは暫定的な対策だと私は思っております。恒久対策はやはりきれいにするということが大事じゃないかと思います。
○参考人(畑明郎君)
今、大塚先生言われましたように、これは廃棄物の問題と一緒でして、廃棄物処理法上いろんなマニフェストとかやっておりますけど、やはり不法投棄はなくなっておりませんし、僕自身も滋賀県の栗東とか四日市の日本最大の不法投棄の大矢知の問題にもかかわっているんですけど、これ同じことが起こり得ると思います。法律で幾ら汚染土壌のマニフェストを定めてフォローしたとしても、やはり限界はあると思います。
そういう意味で、やはりもう少し排出者責任をどう担保していくかという、これは廃棄物も一緒ですけど、取っていく必要あると思います。
これは残土についても一緒でして、残土も結構怪しいものがありまして、僕は汚染土壌も残土も廃棄物扱いというか、廃棄物処理法の対象にすべきだと思います。そういう意味で、もちろん廃棄物処理法ももっと強化しないと駄目なんですけど、強化した上で汚染土壌と残土等を管理していく。
最近でも残土に関連して、石原産業のフェロシルト事件というのがありましたけど、こういうことはついこの間も起こったばかりですよね。あれ、フェロシルトの回収に五百億円掛かるんですよ、これ石原産業が負担して、三年間赤字決算なんです。やっぱりいったんそういう不法投棄しますと非常にコストが掛かるという問題はありますので、この辺は、せっかく法律作ったんですから、きちっとそれは運用というか施行していってほしいなと思っております。
○参考人(畑明郎君)
これは日経新聞等でも拝見しましたけど、この環境債務ということをこういう企業の会計の中に入れていくことについては大賛成ですし、ストック型汚染と僕らは言っているんですけど、土壌汚染と産業廃棄物の問題というのがやっぱり現在はかなり先送りされていると。
言わば臭いものにふたをしてわざと調査しないとか、調査してもできるだけ安価な対策で終わらせて、将来世代にやっぱり負の遺産を送っているところがあると思いますので、やっぱり早めにそういう資産計上していくことはいいことだと思っていますし、非常に面白いのは、上場企業で一番環境債務たくさん計上しているのはOAP事件を起こした三菱マテリアルです。
それと、僕はイタイイタイ病のことをずっとやっているんですけど、結局、イタイイタイ病の場合、公害を出せば結果的に高く付いた例なんですけど、ほぼ掛かった費用が六百億円以上掛かっております。もちろん、死んだ人は、補償を出していますけど、帰ってこないということで、そういう絶対的な損失があるんですけど、経済的な損失という意味で六百億円以上掛かっています。やっとその汚染された農地の復元が来年ぐらいに終わります。
結局ほぼ四十年ぐらい掛かって、最近、三井金属の神岡の社長は朝日新聞に「私の視点」で書いていましたけど、結局四十年掛かって解決したと。そして、住民と企業が信頼関係ができたということで、結局、百億円の公害防止投資を事件が起こる前にやっておけば六百億円の被害は起こらなかったわけです。
結局、公害を出せば、後で非常に社会的コストも企業も負担が重くなるということで、やはり事前にそういう環境債務を計上して対処していくことが今後大事になるんじゃないかと思っております。
○市田忠義君 日本共産党の市田です。
畑参考人にお聞きいたします。
陳述の中でもお述べになりましたが、畑参考人は、リスクゼロ型の掘削除去等の土壌浄化対策、これを排して盛土や封じ込めなどの安易な対策の推奨に今度の法改正がなりかねないと、そう指摘をされています。
私も、今回の改正案で掘削除去の偏重ということが強調されて、現行の指定区域を要措置区域と要届出区域に分類をして、知事が技術的基準に基づいて指示する制度を新たに盛り込んでいると、これが掘削除去の抑制につながるのではないかという懸念をしております。
私事ですが、私は築地に四年前に住んでいまして、今、豊洲に住むという皮肉な、豊洲への移転には私は反対でありますけれども。
畑参考人は、東京ガスの豊洲工場跡地問題あるいは大阪アメニティパークなど多くの土壌・地下水汚染事例にかかわってこられたわけですが、先ほどもお述べになりましたけれども、このリスクゼロ型の掘削除去を抑制して覆土や封じ込めなどのリスク管理型を普及するということについて改めてもう少し詳しくお伺いしたいのと、若干他の参考人の方からも出されたことなんですが、掘削除去というのはかえって汚染地域が広がって汚染の拡大につながるのではないかという考え方についてどうお考えかと。
コスト問題はよく分かりました。中長期的に見れば、中途半端な処理はかえってお金が掛かるというのはよく分かりましたが、今の点について御意見をお伺いしたいと思います。
○参考人(畑明郎君)
確かに、今回の形質変更届管理区域、それから要措置区域ということで、従来の指定区域を二種類に分けて、結局対策を緩める。そして、掘削除去をできるだけやらさないという方向になるおそれは十分あると思っております。
それで、リスク管理という、これは言葉はいいんですけれども、元々この環境リスク論というのはどこから来たかといいますと、アメリカから来たものでして、これBSE問題が一番典型なんですけれども、いわゆる全頭検査なんか要らない、百万人に一人しかBSEにならないんだ、全頭検査のコストは無駄だと。
要は、アメリカの場合はリスクとベネフィットを比較してベネフィットの方が大きければリスクはある程度我慢すると。みんな飛行機とか自動車は交通事故の可能性があるけれども乗るでしょう、ベネフィットがあるから乗るでしょう、環境も一緒ですという形で、こういうことを中西準子なんかは言っているんですけれども、経産省もそういうスタンスなんですけれども、これは僕は全く間違っていると思います。
基本的には、僕はやっぱりEUが取っている予防原則、これは朝日新聞の知恵蔵に環境リスク論とEUの予防原則を比較して書いたことがあるんですけれども、やはり、今EUが進めているRoHS規制とかREACH規制という化学物質の規制は、言わばカドミウムとか水銀とか危ないものはもう製品に入れていかない、工業製品に入らなければできた廃棄物、廃製品も危ないものが入っていないということです。
鉛とか先ほどのカドミウム、水銀など、基本的には六物質に対してはもうやれている。日本のメーカーもEUに輸出はそれができている。自動車とか電気製品を輸出していますから、対応できるんです。
更にもっと、三万種類というすべての工業製品、化学物質に対して規制を掛けようとすると、従来は医薬品と同じように、医薬品だけが安全を証明しなければ販売できなかったんですけれども、すべての工業製品についてメーカーが安全を証明する義務を持たせるという、そういうREACH規制は今もうヨーロッパで始まっています。順次強化されていきますけれども。そういう動きがあります。
それから、やっぱりリスク管理というのは問題ありますし、本当にリスク管理できないんですよね。土壌は確かに人が動かさなければ動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますから、これはどこへ行くか分からないということで、何か法案にもちょっとありましたように、海辺の埋立地はいいんだと、汚染されていても。これはもう論外でして、やっぱり廃棄物処分場は山の中に造るか海に埋めているかどっちかなんですけれども、山の場合はもちろん排水は河川の上流に入ってきますし、海の場合もやはり、大阪湾のフェニックスとかありますけれども、東京湾の埋め立てていますけれども、やはり海の汚染を起こします。
完全にその汚染水を海に流さないことはできません。今、遮水していますけれども、あれは堤防だけ遮水していまして底は抜けていますので、必ず汚染が海に広がります。それで魚の汚染も起こりますし、そういう意味で問題があるということです。
それと、確かに掘削除去した土地をどう処理するかというのはもちろん問題なんですけれども、僕のかかわった京都府の日本最大のクレー射撃場、これは麻生首相が好きらしいんですけれども、要するに鉛の散弾、これを撃つんですよ。それで皿を割るらしいんですけれども。当然鉛の散弾がそこへ散らばって、クレー射撃場の中が鉛で土が全部汚染されちゃったんです。
その土、今京都府立の施設なんですけれども、京都府は十億円以上掛けて全部、秋田県の小坂にあるんですけれども、土壌処理施設で土をきれいにしてまた戻す、そういうことをちゃんとやっているんです。
そういう意味で、それは搬出土壌の処理の仕方、適正な処理をやっぱりどう担保するかという問題でして、これは産廃と一緒でして、ただ今の現状からいくともちろん産廃と同じように汚染土壌がどこへ行っているか分からぬという問題は起こり得ると思いますので、それは十分注意しながらやっていくしかないと思っております。ただ、技術的にはできると思います。
○参考人(畑明郎君)
だから、今回のもちろん一定規模以上の、多分三千平米ぐらいになると聞いておりますけれども、それはもちろん改善、今の法律の、ざる法のざるを少し目を埋める、目を小さくするということにはなると思いますけれども、完全にざるは目が埋まった状態ではないと思っております。
やはり法施行前の有害物質を扱っていた工場、事業場、これは水質汚濁防止法の特定施設以外にもいっぱい出ていますので、やっぱり有害物質を例えば運搬とか保管したところでも汚染は起こっていますので、それから交通機関とかそういうところなんかでも起こっていますので、やっぱり過去のこれは負の遺産だと。製造業の当初負の遺産という言葉が言われたんですけれども、土壌汚染は。過去の負の遺産をいつかの時点で一掃するためには、きちっとまずはやっぱり調査をすべきであると。
もちろん一〇〇%の工場が全部汚染されているとは僕は言いませんし、多分半分ぐらいだろうという土環センターの推定なんかもありますけれども、やっぱりやってみないと分かりませんから、調査はまずちゃんとすべきである。
これはカドミウム汚染米と一緒でして、ついちょっと前、一九九八年ぐらいに、五十ヘクタール単位にワンポイントでじゅうたん的に米を全部調査したら、またいっぱい準汚染米が出てきたという問題がありました。そういう意味で、やっぱり危ない可能性のある工場、事業場については調査を法的に義務付けてしていくべきであると。
あと、対策はどうするかというのは、やっぱりケース・バイ・ケースになると思いますけれども。
○参考人(畑明郎君)
私は元々の出身が京大の工学部の金属でして、それでずっと金属にこだわってやっているんですけど、金属というのは、確かに人間生活とかいろんな経済に役立っているんですけど、プラス面とマイナス面があって、金なんかは全く毒性がないんですけど、金以外の金属はほとんど何らかの毒性はあります。鉄なんかもたくさん取ったらやっぱり問題なんですけど。
確かに、それで必須金属で見ましても、多過ぎても少な過ぎても駄目なんですね。これは、生物は人間も含めて海から生まれた関係で海の中のやっぱり金属の濃度というのが影響しているんですけど、そういう意味で、例えばカドミウムとか水銀とか鉛とかは元々生物とか人間が利用しなかったんです。カルシウムとか鉄とか銅とか、こういうものは生物が利用したのでこれは必須金属になっているんですけど、全く利用しない不要な金属というのがあるんです。
そういうものの典型的なものが水銀であり、カドミウムであり、鉛とか六価クロムとか、そういう非常に有害な重金属なんです。そういうものはやっぱり基本的に、水銀は水俣病を起こしましたし、カドミウムはイタイイタイ病を起こしたと。鉛はもう古来からある毒物なんですけどね。これはもうギリシャ・ローマ時代からいろいろ毒ありますし、砒素なんかもそうですけど。
そういう明らかに人体に有害と分かっている金属についてはできるだけ使っていかないようにしようと、特に工業製品に使っていかないと。例えば、水銀なんかかて、昔はいろいろ、おしろいとかそれから不老長寿の薬とか、多分早く死んだと思うんですけど、そういうものに使われていたぐらいなんですけど。
それらは、明らかにやっぱり有害なものはできるだけ減らしていこうという意味で、僕の書いた本にはいろいろ書いてあるんですけど、やっぱりEUは、ヨーロッパが進めているこういう、元々これは北欧とかスウェーデンの方から始まったんですけど、有害な金属をやっぱり規制していく、工業製品には使っていかないと。そうすると、やっぱり安全な工業製品なので、後、環境汚染も少ないし、廃棄物についても処理、リサイクルしやすくなる。根本的にはそれやらないと。
それで、金属というのは基本的にはなくならない、地球上からなくならないんです。量は常に一定なんです。全部地下資源にあった分ですから、鉄はさびて酸化鉄になりますけど、鉄そのものの量は、地球上の存在量は変わらないです。隕鉄が降ってきて、その分は鉄が増えたかも分からないですけど。そういう意味で、絶対、金属はどこに行っても形変えるだけで、なくならないんですよ。
だから、有害な金属というのは、一回使うとどこかに行っちゃうんです。例えば、水銀でも今、石炭火力発電、石炭の中、少し水銀入っているんですけど、豊洲も石炭からガス造っていましたので水銀汚染あるんですけどね。そういうのは、火力発電は飛んでいるんですよ。アメリカなんかでは一番多いんですよ。中国からも今、水銀が飛んでいるという話もありますし。
そういう意味で、やっぱり危ないものが入っているものはできるだけ削減しよう、減らしていこうと。一遍にゼロにはできませんから。そういう動きというのはヨーロッパを中心に今始まっていますので、やっぱり日本も余りアメリカに追従するんじゃなくて、さっきのリスク論ですね、リスクとベネフィットを比較して、少々のリスクは我慢しろというんじゃなくて、やっぱり予防原則というか、安全なものにしていく、すべての消費するものとか物を、物資をですね。これは食べ物も含めてだと思いますけどね。
例えば農薬なんかも、結構昔は米にも水銀の農薬とか、それから今でも果樹、リンゴとかああいうものは砒素、鉛系の農薬なんかも使われていましたし、シロアリの駆除剤はあの和歌山のカレー事件で砒素が、亜砒酸が使われていましたし、そういうのがまだ使われているんですよね。そういうものをやっぱりどんどん減らしていくか代替のものに替えていく。
例えばカドミウムについては、昔はニッカド電池、まあ今も使われているんですけど、カドミウムはやっぱり問題があるということでだんだんリチウムイオン電池に切り替わっていっていますし、そういう代替のものがあるものについては替えていく。
ただ、自動車の鉛バッテリーは今代替はないんですよね。だから、リチウムイオン電池で自動車搭載型というのはまだ十分実用化されていませんので、そうなれば鉛バッテリーも使わなくて済むというようなことになると思います。
以上です。
○参考人(畑明郎君)
一番いい例はイタイイタイ病だと思うんですけど、先ほども少し紹介しましたけど。
僕は、だから、三井金属については評価しているんですけど。結局、カドミウムの排出量をほぼ四十年間で十分の一以下にしまして、神通川のカドミウムの水質は鉱山の上流も下流もほぼ一緒になったと。
もちろん、ゼロエミッション、ゼロ排出にはならないですね。ゼロにはできないんですけど、少しは出るんですけど。それで、ほぼ無視できるぐらいの濃度になって、自然界レベルになって神通川は清流に戻って、下流の農地も復元田ということで、千ヘクタールぐらい復元して、数百億円の費用が掛かったんですけど、来年終わると。また汚染物質流したらまた再汚染されますから、これも一種の未然防止だと思うんですけど。
それで、三井金属つぶれたかといいますと、決してつぶれていませんね。今、三井金属は先ほど言いました鉛の、自動車のバッテリーの日本最大のリサイクル工場になっているんです、神岡鉱山が。今、神岡鉱山は、鉱石は掘っていませんけど、自動車のバッテリーを回収して、それをまた鉛にして、自動車のバッテリーは非常にシンプルな製品でして、プラスチックの箱に鉛の電極が入っているだけです。
あと硫酸が入っていまして、まあ硫酸は処理したらいいので、プラスチックと鉛はまた再利用できるんです。あとそれ以外にも三井金属は、皆さん持っている携帯電話の中の銅の薄い箔というんですけれども、回路に使うんですけれども、これの世界トップシェアなんですよ。最近ちょっと何か経営苦しいようですけれども、それでも倒産はしていないし、神岡鉱山も操業を続けながらちゃんとそれなりの利益を出して、経済と環境の両立というのができたわけですね。
それで、この前、朝日新聞にも神岡の、まあ三井の取締役ですけれども、神岡の社長は「私の視点」に、今四十年たって成功したと、対策は。
これは、参議院の議員やられた近藤忠孝イタイイタイ病の弁護団長がNHKの「その時歴史が動いた」にも出ておられましたけれども、弁護団も被害者も企業を評価しているんですね、今。一応企業、経済活動と、上流の神岡鉱山は操業を続けています、工場。鉛、亜鉛造っているんですけれども。しかし、それで下流の農業も両立するということで、やっぱり経済と環境の両立はやればできるんだと。
アジアの問題ですけれども、一応このアジアの土壌汚染で私、最近、韓国とか台湾とか中国の調査やっているんですけれども、特に中国は皆さん御存じのようにひどい状況でして、僕は主に南の方の広東省とか湖南省の鉱山を見に行ったんですけれども、ほとんど排水は垂れ流し状態です。
もう鉄分を、真っ赤な水がそのまま垂れ流されて、谷間は全部泥の海になっていると。下流にがんの村が幾つかできていると。がんの原因もよく分からないんですよね、砒素なのか。多分、砒素でがんになっていると僕は思うんですけれども。あと、カドミウムによってイタイイタイ病みたいな患者も出ていまして。
そこの省の研究所の人がいろいろ調べていまして、その人に調査、案内してもらって、うちの中国の留学生がガイドしてくれたんですけれどもね。それで、日本にも一応中国の研究者を呼びまして、それで日本の富山とかイタイイタイ病の視察もやってもらいまして、これはテレビとか毎日新聞なんかに紹介されたんですけれども。
それで、復元の現場なんかも見せたんですけれども、それをそのまま中国に持っていくのは無理ですね。中国にそんなお金がないとか。やはり、日本の経験を生かしてほしいんですけれども、このままいくと中国は環境よりも経済成長優先でいっていますから、何か行くところまで行かないと反省しないのかなという気はあります。
だから、日本としては、やっぱりできるだけ日本の経験を知らせて、こういう解決の仕方をしたんだということでそれを紹介して、それを中国側がどうやって自分でやっていくかという、そのときに技術援助とか経済援助できることはやっぱり日本がやっていくべきだと思っております。
以上です。
○荒井広幸君 ありがとうございました。
○川田龍平君 川田龍平です。
土壌汚染対策法を始め環境関係法は市町村の役割が重要だと考えていますが、現実に地域で土壌汚染の問題が生じた場合に市区町村が住民への汚染状況の説明や緊急的な対応を行うことになると思いますが、環境省と都道府県、それから市区町村の相互に補完的な体制を整える必要があるかどうか、その点でこの法律が十分かどうかということ、あるいは課題があると考えているかどうかを参考人にお聞きしたいと思います。各参考人、お願いします。
○参考人(畑明郎君)
難しい問題なんですけれども、一応二つの事例で紹介したいと思いますけれども。
一つは、滋賀県の栗東の産廃問題ですけれども。栗東市は住民も含めて、僕はほとんど行政からは委員に呼ばれないんですけれども、珍しく栗東市の調査委員には住民推薦で入っていまして、それで栗東市としていろんな対策案の意見を出しているんですけれども。
それに対して滋賀県は、今、嘉田知事なんですけれども、嘉田知事は有名なんですけれども、新幹線の駅は止めたんですけれども、それからダムもある程度止めようとしているんですけれども、この産廃問題についてはからっきし駄目でして、今、栗東市とか周辺の住民の反発を食らっていまして、要は住民はやっぱり全量撤去を要求しているんですよね。確かに僕らも全量撤去が一番望ましいんですけれども、コスト的に二百数十億掛かるので無理なので。
ただ、県が考えている案は、要するに遮水壁で、ソイルセメントの遮水壁で囲って水をくみ上げて処理して産廃を残そうという、そういう案で四十五億円なんですけれどもね。僕らはそれよりも安い方法で効果的な対策ができますということで、底の粘土層が破壊されているんですけれども、その粘土層の修復と、明らかにドラム缶が三千本以上入っているのが分かっているので、そういう明らかに有害なものはやっぱり全部掘削して掘り起こす。
そういう対策は二十億円ぐらいで済むんですよね。そういう提案を栗東市として、その委員会として提案しているんですけれども、県の方はそれをつぶしに来ていまして、県の対策案を強引にやろうとしたんですけれども、結局は、周辺の住民の同意が得られない、自治会の同意は得られないし、七つの自治会のうち一つしか同意が得られなかったし、議会でも、多分これは自民党と共産党が反対してちょっと通らない可能性が強いので、結局、県案についてはちょっと棚上げになっているんですけれども。
そのときに環境省が果たした役割は非常に悪い役割をやっていまして、要は、環境省がどうも全量撤去をやるなと、現地封じ込めやれと。これは土壌汚染対策法と同じスタンスでして、土壌汚染対策法も掘削除去をやめろと、できるだけ現地封じ込めとか土かぶせて終わりにしろと、それと同じことがやられていますね。
これは、四日市の日本最大の不法投棄、百六十万、百七十万立方メートルが不法で、全部足すと三百万立方メートル、巨大なごみの山ができているんですけれども。そのときも、当初、県は不法投棄の部分については全量撤去をしますという案を出したんですけれども、それに対して環境省は、聞くところによると、環境省が圧力を掛けて、結局むちゃくちゃひどい対策なんですけれども、土かぶせて雨水だけ処理する、それで終わりにしようという。
岐阜の、あと椿洞の産廃の不法投棄事件でも、これは市長が当初、全量撤去をやりますということの方針を打ち出していたんですけれども、環境省がいろいろ圧力を掛けて一部撤去で百億円という形で決着ということで、そういう意味でやっぱり今、県とか環境省が市町村に対して果たしている役割というのは決して余り好ましくないという状況だと思っております。
○川田龍平君 ありがとうございます。
岡山市の小鳥が丘団地では、平成十六年に岡山市の水道局による水道管入替えの工事のときに土壌汚染が発見されて、これまで揮発性の有機化合物であるトリクロロエチレンが最大で環境基準の二十七倍、ベンゼンが二十六倍検出されるほどの状況にあると。
このため、窓を閉めていても異臭によって眠れない人であったりとか、頭痛や鼻炎などに悩まされる人であったり、中には住宅ローンが残っているにもかかわらず引っ越しを余儀なくされた人もいると聞いているんですが。
この土壌からの揮発経由による摂取、また住宅地における土壌汚染の場合というのがどうなのかという、長期的に濃度が高くない水準の暴露環境の中での暮らし、健康被害を受ける場合も考えられますが、こうした低濃度の長期暴露による健康被害について、参考人の意見を、答えられる方に答えていただきたいと思うんですが。
○参考人(畑明郎君)
これは私の資料にも書いていますように、私も三回ほど現地に行きまして、住民にも頼まれまして、それで今裁判にもなっております。
それで、この団地ってちっちゃい四十戸足らずの団地なんですけれども、団地の入口というか、道に入ると、川田議員も行かれたんですかね、もうぷうんと変な油臭いにおいがするんですよ。それで、二十四時間それを吸っていまして、多分外出した方が気分がいい、家にいると気分が悪くなると。実際に何かいろいろ発疹とかできものができたりとか。
台所の下に物入れがあるんですけれども、その床がコンクリートを張っていないところが何か噴火口みたいになっていまして、ガスが噴き出してきているんですね、メタンガスとかいろんなガスが。それから、庭の土がぶわぶわになっているんです。非常に軟らかくなっているんです。下から噴き出してきて、一部黒っぽい油そのものが出てきて、十センチ掘りますともう真っ黒けの油まみれの土なんですよ。これは元々何か廃油のリサイクル業者でして、そのかすをまた豊島に持っていったというんです。豊島の産廃業者と何かセットだったらしいんですけれども。
そういうところで健康被害がある、実際に健康被害が起こって裁判を起こしているんですけれども、全く行政の方は、もう岡山市も県も取り合おうとしないと。基準もないと。土壌汚染の大気の基準はないんですよね。土壌の溶出量とか含有量しかない、地下水の基準しかありませんからね。そういう意味でやっぱり裁判に訴えられない、裁判やってもこれは勝てるかどうか分からないと。
もう日常的にずっと、それで、外へ引っ越したいけれども、その家はもう銀行の担保価値ゼロなんですよ。全然お金も貸してくれない、売れない、その家ももういろいろマスコミに出ていますから。そういう悲惨な状況になっているところがあります。だから、実際に人が住んでいるところで日常的にVOC揮発していきますから、そういう大変なところの問題が起こったところがあるんですけれども、それに今の土壌汚染対策法は全く役に立たないという意味で、大気の基準なんかも設定要ると思います。
ただ、さっきの豊洲の問題でも、これ、ベンゼン、シアン、水銀は蒸発するんですよね、常温でも。それの基準はないという、やっぱりそういう問題はあると思います。大気汚染防止法で少し大気の環境基準はあるものはあるんですけれどもね。土壌汚染についてはないということで、問題あると思っています。
以上です。
○川田龍平君 ありがとうございます。
それから、今、汚染原因者の分社化を内容とする、水俣病についてなんですけれども、分社化を内容とするこの与党法案というのは今国会に提出されているんですが、汚染者負担の原則が今度薄くなる傾向にあるという印象を持っていますが、この土壌汚染法とこの汚染者負担の原則についての参考人の御意見を伺いたいと思います。これも答えられる方で結構です。
○参考人(畑明郎君)
だから、この汚染者負担原則ですね、基本的には従来の公害法はそれで貫かれているんですけれども、特に土壌汚染については、農用地の土壌汚染防止法はイタイイタイ病を契機として制定されたんですけど、これは基本的には汚染原因者負担です。だから、神岡鉱山、三井金属が土壌復元費用を、これは国の法律があって少し減額されていますけど、基本的には企業負担、人体被害の補償に農業被害の補償すべて、だから五百億円近い金額を企業は支払っているんです。
それが水俣病の場合、僕はチッソは非常にけしからぬと思うんですけど、三井金属はやっぱり、財閥系企業とそうでない企業の違いか、世間体があるのか知らないですけど、やっぱりきちっと三井金属は、三井財閥の一員だったし、対応を取って原因者負担を貫いているし。
この土壌汚染対策法が元々できたときに、やっぱりその汚染者負担原則は全く貫かれない、土地所有者責任主義と言われていましたけどね。それで、汚染原因者がオーケーしたら所有者が請求できますよと言っていますけど、普通はオーケーしないです。汚染原因者イコール土地所有者だったら問題ないんですけど、汚染原因者は必ず逃げますから。
それをまた証明しようとするとやっぱり裁判しかないとか、そういういっぱい、カネボウでもこれ裁判起こっているんですよ、企業同士が裁判やっているという。
やっぱりそういう意味で、土壌汚染対策法はPPPは貫かれていないということで問題はあると思っています。
本日はこれにて散会いたします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/171/0065/17104140065005a.html
2009年11月19日
汚染土壌処理業の許可の申請の手続について
環水大土発第091104003号
平成2 1 年1 1 月4 日
都道府県・政令市土壌環境保全担当部局長あて
環境省水・大気環境局土壌環境課長
汚染土壌処理業の許可の申請の手続について
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21 年法律第23 号。以下「改正法」とい
う。)により創設された汚染土壌処理業の許可の申請は、改正法附則第2条の規定に基づ
き、改正法の施行の前においても、改正法第22 条第2項の規定の例により行うことがで
きることとされているところ、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定め
る政令(平成21 年政令第245 号)により、附則第2条の規定の施行日は、平成21 年10
月23 日とされたところである。
また、当該手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及
び図面のほか、汚染土壌処理業の許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(以下「省令」という。)を、平成21
年10 月22 日に制定し、公布したところである。
改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「法」という。)の体系的な解説は、後日、
施行通知により示す予定であるが、省令の公布に併せ、申請書記載事項並びに添付書類
及び図面について申請者並びに都道府県及び政令市が参考とすべき事項を下記のとおり
まとめたので、貴職におかれては、これを参照して汚染土壌処理業の許可の申請の手続
に対応されたい。
なお、省令に規定するもののほか、法第4章第2節の規定を実施するために必要な環
境省令及び環境大臣告示については、追って整備することとしており、それまでの間に
申請があった場合は申請書並びに添付書類及び図面に記載される事項のうち当該環境省
令及び環境大臣告示によりその内容が確定する事項については、追加して記載し、又は
添付すれば足りるものとして、取り扱われたい。
記
1 申請書の様式及び記載事項
申請書の様式は、省令の別記に示したとおりであり、その記載事項欄には、以下の内
容を記載させること。
? 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称(省令第3条第1号)
「○○株式会社□□工場」等具体的に記載させること。
? 申請者の事務所の所在地(同)
申請者の事務所は、汚染土壌処理業の許可がされた後は、法第54 条第4項により
都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成14 年政令第336 号)第8条に規定する
市の長を含む。以下同じ。)の立入検査の対象となるため、すべての事務所の所在地
及び連絡先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の設置の場所(法第22 条第2項第2号)
汚染土壌処理施設に係る事業場の所在地及び連絡先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の種類(法第22 条第2項第3号)
省令第1条各号に掲げる種類のいずれかを記載させること。なお、同一の敷地内
において、汚染土壌処理施設を構成する設備のうちに、浄化等、セメント製造、埋
立て及び分別等のうち異なる方法を採用する設備がある場合には、全体として一の
汚染土壌処理施設と解し、申請行為は一回で足りるが、当該採用する方法に応じた
汚染土壌処理施設の種類を記載させること。
さらに浄化等処理施設にあっては、浄化、溶融又は不溶化の別を括弧書で併記さ
せること。
? 汚染土壌処理施設の構造(同)
汚染土壌処理施設の構造を記載させること。構造の例としては、材質、屋根の有
無及び階数が想定されること。
? 汚染土壌処理施設の処理能力(同)
汚染土壌処理施設(埋立処理施設を除く。)の1時間当たりの処理量及び稼働時間
並びにこれらを乗じて得た1日当たりの処理量を記載させること。
埋立処理施設にあっては、埋立地の面積及び埋立容量を記載させること。
? 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(法
第22 条第2項第4号)
汚染土壌処理施設が処理することのできる汚染土壌の特定有害物質の種類を記載
させるとともに、処理することの出来る汚染土壌の濃度の上限値を定めている場合
には当該上限値を記載させること。
? 汚染土壌の処理の方法(省令第3条第3号)
汚染土壌の処理の方法として、熱分解方式、加熱・揮発方式、洗浄方式、化学分
解方式等を記載させること。
また、汚染土壌の処理の一連の作業の手順及び内容を記載させること。ここにい
う「汚染土壌の処理の一連の作業」は、汚染土壌の受入れから、保管、処理までを
意味するが、処理された汚染土壌であっても土壌汚染対策法施行規則(平成14 年環
境省令第29 号)第18 条第1項又は第2項の基準に適合しない場合における当該汚
染土壌を保管する過程までを含むものであること。また、セメント製造施設にあっ
ては、製造されたセメントが製品として出荷するに足りる品質を有することが確認
されるまでの過程を記載させること。
「一連の作業の手順及び内容」は具体的に記載させることを要するが、このうち
「一連の作業の内容」の記載内容の例としては、受入れについては当該受入れを行
う場所、熱分解を行う場合には分解温度及び揮発温度並びに汚染土壌の冷却方法、
洗浄を行う場合には分級、沈殿、ろ過等濃縮の方法や使用する薬剤の種類、化学分
解を行う場合には使用する薬剤の種類や添加の方法等が想定されること。
併せて、浄化等処理施設にあっては、本欄に記載した処理の方法により、?の欄
に記載した汚染土壌を処理することが可能であることを証明する実験の方法及び結
果を記載させること。
? セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法(省令第3条第4号)
以下の内容を記載させること。
イ製造するセメントの製品規格と製造方法
ロ製造するセメントの品質管理の方法
ハ製造されたセメントに含まれる特定有害物質の量の測定方法並びに当該量の上
限値の目安及びその上限の目安の設定根拠
? 保管設備の場所及び容量(省令第3条第5号)
保管設備ごとに場所と容量を記載させること。
なお、保管設備の場所は、省令第2条第2項第2号の添付図面により明らかにさ
せること。
? 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地、再処理汚染土壌処理施設の許可番号、種類及び処理能力(省令第3条第7号)
上記に準じて記載させること。
2 申請書添付書類及び図面
汚染土壌処理業の許可の申請書に添付しなければならない書類及び図面については、
以下によること。
? 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類(省令第2条第2項第1号)
以下の事項を記載させた書類を添付させること。
イ汚染土壌処理施設を稼働させる時間、汚染土壌処理施設の休止日、汚染土壌の
処理の事業を行うための組織及び当該事業に従事する従業員数
ロ汚染土壌処理施設の維持管理(省令第5条第22 号の点検及び機能検査を含む。)
の体制及び計画
? 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設
計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明
らかにする書類及び図面(省令第2条第2項第3号)
汚染土壌処理施設を構成する設備について、当該設備ごとに、平面図、立面図、
断面図、構造図及び設計計算書を添付させること。
なお、設計計算書は、汚染土壌処理施設が、自重、積載荷重その他の加重、地震
及び温度変化に対して構造耐力上安全であることを証明するに足りる内容を備える
必要があること。
? 汚染土壌の処理工程図(省令第2条第2項第4号)
汚染土壌の処理の一連の作業の手順をフロー図により示させること。ここにいう
「汚染土壌の処理の一連の作業」とは、1?に準ずること。
? 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、
当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類(省令第2条第5号)
汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地の登記事項証明書及び公図の写しを添付さ
せること。所有権を有しない場合には、当該敷地について申請者のために賃借権が
設定されたことを証する書類及び公図の写しを添付させること。
? 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(省令第2条第2項第7号)
以下の書類を添付させること。
イ汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有
する者(省令第4条第2号イ)の氏名及び役職並びに当該者が当該業務を統括管
理する権限を有することを確認することのできる管理体制系統図
ロ汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及
び技能を有する者(省令第4条第2号ロ)に係る次の書類
(1) 汚染土壌処理施設に配置されていることを確認することのできる書類
(2) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について3年以上の実務経験を有す
ることを証明する書類
(3) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有することを証明
する書類として次に掲げる書類
(イ) 大気の汚染に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類と
して次に掲げる書類のうちいずれかの書類
(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・大気管理)
に合格したことを証する証書(技術士法施行規則(昭和59 年総理府令第25
号)様式第4)の写し
(?) 大気関係第一種公害防止管理者試験又は大気関係第二種公害防止管理
者試験の合格証書(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施
行規則(昭和46 年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第3号)
様式第5)の写し
(?) 大気関係第一種公害防止管理者又は大気関係第二種公害防止管理者の
資格を得るための講習の修了証書(特定工場における公害防止組織の整備
に関する法律施行規則様式第7)の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46 年法律第
107 号)第8条の2第1項の指定試験機関(平成21 年10 月29 日現在、社
団法人産業環境管理協会)が発行する公害防止管理者等国家試験試験結果
通知書の写し(大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の
科目に合格していることが確認できるものであること)
(?) 省令第4条第2号ロ(イ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ロ) 水質の汚濁に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類とし
て次に掲げる書類のうちいずれかの書類
(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・水質管理)に
合格したことを証する証書の写し
(?) 水質関係第一種公害防止管理者試験又は水質関係第二種公害防止管理者
試験の合格証書の写し
(?) 水質関係第一種公害防止管理者又は水質関係第二種公害防止管理者の資
格を得るための講習の修了証書の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(水質概論及び水質
有害物質特論の科目に合格していることが確認できるものであること)
(?) 省令第4条第2号ロ(ロ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平
成11 年法律第105 号)第2条第1項のダイオキシン類をいう。)を生ずる可能
性のある汚染土壌処理施設にあっては、次のいずれかの書類
(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者試験の合格証書の写し
(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者の資格を得るための講習の修了証書の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(ダイオキシン類概
論及びダイオキシン類特論の科目に合格していることが確認できるものであ
ること)
? 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載
した書類(省令第2条第2項第8号)
汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額については、当該事業の開始及
び継続に必要となる一切の資金の総額を記載させること。具体的には、資本金の額
のほか、当該事業の用に供する汚染土壌処理施設の整備に要する費用、損害賠償保
険の保険料の額等が想定される。
汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の調達方法については、資本金の調達
方法、借入先、借入残高、年間返済額、返済期限、利率等資金の調達に関する一切
の事項を記載させること。利益をもって資金に充てるものについては、その見込額
を記載させること。
? 申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
る書面(省令第2条第2項第13 号)
申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
るため、その旨の誓約書を作成させ、申請者の氏名又は名称及び住所並びに申請者
が法人である場合にはその代表者の氏名を記名し、押印させた上で、添付させるこ
と。なお、申請者が法人である場合には、法第22 条第3項第2号ハのその事業を行
う役員についても、同旨の誓約書を作成し、添付させること。これらの誓約書を作
成する場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
? 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに
汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排
出水に係る用水の系統を説明する書類(省令第2条第2項第15 号)
汚水の処理の方法を示したフロー図及び設置する汚水の処理設備の構造及び能力
を記載した書類並びに排出水に係る用水及び排出水の経路図を添付させること。
? 排水口における排出水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第16号)
排出水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第17 号)
地下水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透
を防止する方法を記載した書類(省令第2条第2項第18 号)
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散等及び地下への浸透を防止するための当該汚染土壌処理施設の
構造並びにそのために設けられた設備の構造及び能力を記載させること。
また、汚染土壌の搬入及び搬出時以外の閉扉等施設管理により当該防止を図る場
合には、当該施設管理の方法を記載した書類を添付させること。
さらに、地下浸透防止措置(省令第4条第1号リ)が講じられている汚染土壌処
理施設にあっては、当該地下浸透防止措置が同号リの環境大臣が定める措置に該当
することを証明する書類を添付させること。
? 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、
排出口から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有
害物質の量の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第19 号)
発生してから排出口から大気中に排出されるまでの大気有害物質の排出経路、大
気有害物質の処理設備の構造、能力及び設置場所、大気有害物質の処理フロー図、
大気中に排出される大気有害物質の量の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及
び時間を記載した書類を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 法第27 条第1項に規定する措置(以下「廃止措置」という。)に要する費用の見
積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面(省令
第2条第2項第20 号)
法第27 条第1項の環境省令で定める廃止措置の内容に応じ、それぞれの廃止措置
に要する費用の見積額及びその算定根拠並びに当該見積額の総計の額の調達方法及
び当該調達方法が実現可能性のあるものであることを説明する書類を添付させること。
この記載に当たっては、?に準じてできる限り詳細に記載させること。
? 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者
がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況
の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項
又は第2項の基準に適合しないときの法第14 条第1項の申請を行うことについての
当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
(省令第2条第2項21 号)
廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷
地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項又は第2項の基準に適
合しないときは、汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地にいる申請者以外の所有者、
管理者又は占有者が法第14 条第1項の申請を行うことについて同意する旨の書類の
写しを添付させること。当該書類には、当該所有者、管理者又は占有者に記名し、
押印させること。この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
? 再処理汚染土壌処理施設について法第22 条第1項の許可を受けた者の当該処理を
受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書
類(省令第2条第2項22 号)
当該処理を受託することについての再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌処理
業者の同意書及び当該再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌の処理の事業の許可
証の写しを添付させること。当該同意書には、当該者に記名し、押印させること。
この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
なお、平成22 年3月31 日までに汚染土壌処理業の許可の申請をする場合には、
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受けることはないことから、再処理汚染土壌
処理施設に処理を委託することはないものとして、当該許可の申請を行わせ、当該
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受け次第、その旨の変更の届出(法第23 条第
3項)をさせること。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
平成2 1 年1 1 月4 日
都道府県・政令市土壌環境保全担当部局長あて
環境省水・大気環境局土壌環境課長
汚染土壌処理業の許可の申請の手続について
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21 年法律第23 号。以下「改正法」とい
う。)により創設された汚染土壌処理業の許可の申請は、改正法附則第2条の規定に基づ
き、改正法の施行の前においても、改正法第22 条第2項の規定の例により行うことがで
きることとされているところ、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定め
る政令(平成21 年政令第245 号)により、附則第2条の規定の施行日は、平成21 年10
月23 日とされたところである。
また、当該手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及
び図面のほか、汚染土壌処理業の許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(以下「省令」という。)を、平成21
年10 月22 日に制定し、公布したところである。
改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「法」という。)の体系的な解説は、後日、
施行通知により示す予定であるが、省令の公布に併せ、申請書記載事項並びに添付書類
及び図面について申請者並びに都道府県及び政令市が参考とすべき事項を下記のとおり
まとめたので、貴職におかれては、これを参照して汚染土壌処理業の許可の申請の手続
に対応されたい。
なお、省令に規定するもののほか、法第4章第2節の規定を実施するために必要な環
境省令及び環境大臣告示については、追って整備することとしており、それまでの間に
申請があった場合は申請書並びに添付書類及び図面に記載される事項のうち当該環境省
令及び環境大臣告示によりその内容が確定する事項については、追加して記載し、又は
添付すれば足りるものとして、取り扱われたい。
記
1 申請書の様式及び記載事項
申請書の様式は、省令の別記に示したとおりであり、その記載事項欄には、以下の内
容を記載させること。
? 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称(省令第3条第1号)
「○○株式会社□□工場」等具体的に記載させること。
? 申請者の事務所の所在地(同)
申請者の事務所は、汚染土壌処理業の許可がされた後は、法第54 条第4項により
都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成14 年政令第336 号)第8条に規定する
市の長を含む。以下同じ。)の立入検査の対象となるため、すべての事務所の所在地
及び連絡先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の設置の場所(法第22 条第2項第2号)
汚染土壌処理施設に係る事業場の所在地及び連絡先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の種類(法第22 条第2項第3号)
省令第1条各号に掲げる種類のいずれかを記載させること。なお、同一の敷地内
において、汚染土壌処理施設を構成する設備のうちに、浄化等、セメント製造、埋
立て及び分別等のうち異なる方法を採用する設備がある場合には、全体として一の
汚染土壌処理施設と解し、申請行為は一回で足りるが、当該採用する方法に応じた
汚染土壌処理施設の種類を記載させること。
さらに浄化等処理施設にあっては、浄化、溶融又は不溶化の別を括弧書で併記さ
せること。
? 汚染土壌処理施設の構造(同)
汚染土壌処理施設の構造を記載させること。構造の例としては、材質、屋根の有
無及び階数が想定されること。
? 汚染土壌処理施設の処理能力(同)
汚染土壌処理施設(埋立処理施設を除く。)の1時間当たりの処理量及び稼働時間
並びにこれらを乗じて得た1日当たりの処理量を記載させること。
埋立処理施設にあっては、埋立地の面積及び埋立容量を記載させること。
? 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(法
第22 条第2項第4号)
汚染土壌処理施設が処理することのできる汚染土壌の特定有害物質の種類を記載
させるとともに、処理することの出来る汚染土壌の濃度の上限値を定めている場合
には当該上限値を記載させること。
? 汚染土壌の処理の方法(省令第3条第3号)
汚染土壌の処理の方法として、熱分解方式、加熱・揮発方式、洗浄方式、化学分
解方式等を記載させること。
また、汚染土壌の処理の一連の作業の手順及び内容を記載させること。ここにい
う「汚染土壌の処理の一連の作業」は、汚染土壌の受入れから、保管、処理までを
意味するが、処理された汚染土壌であっても土壌汚染対策法施行規則(平成14 年環
境省令第29 号)第18 条第1項又は第2項の基準に適合しない場合における当該汚
染土壌を保管する過程までを含むものであること。また、セメント製造施設にあっ
ては、製造されたセメントが製品として出荷するに足りる品質を有することが確認
されるまでの過程を記載させること。
「一連の作業の手順及び内容」は具体的に記載させることを要するが、このうち
「一連の作業の内容」の記載内容の例としては、受入れについては当該受入れを行
う場所、熱分解を行う場合には分解温度及び揮発温度並びに汚染土壌の冷却方法、
洗浄を行う場合には分級、沈殿、ろ過等濃縮の方法や使用する薬剤の種類、化学分
解を行う場合には使用する薬剤の種類や添加の方法等が想定されること。
併せて、浄化等処理施設にあっては、本欄に記載した処理の方法により、?の欄
に記載した汚染土壌を処理することが可能であることを証明する実験の方法及び結
果を記載させること。
? セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法(省令第3条第4号)
以下の内容を記載させること。
イ製造するセメントの製品規格と製造方法
ロ製造するセメントの品質管理の方法
ハ製造されたセメントに含まれる特定有害物質の量の測定方法並びに当該量の上
限値の目安及びその上限の目安の設定根拠
? 保管設備の場所及び容量(省令第3条第5号)
保管設備ごとに場所と容量を記載させること。
なお、保管設備の場所は、省令第2条第2項第2号の添付図面により明らかにさ
せること。
? 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地、再処理汚染土壌処理施設の許可番号、種類及び処理能力(省令第3条第7号)
上記に準じて記載させること。
2 申請書添付書類及び図面
汚染土壌処理業の許可の申請書に添付しなければならない書類及び図面については、
以下によること。
? 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類(省令第2条第2項第1号)
以下の事項を記載させた書類を添付させること。
イ汚染土壌処理施設を稼働させる時間、汚染土壌処理施設の休止日、汚染土壌の
処理の事業を行うための組織及び当該事業に従事する従業員数
ロ汚染土壌処理施設の維持管理(省令第5条第22 号の点検及び機能検査を含む。)
の体制及び計画
? 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設
計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明
らかにする書類及び図面(省令第2条第2項第3号)
汚染土壌処理施設を構成する設備について、当該設備ごとに、平面図、立面図、
断面図、構造図及び設計計算書を添付させること。
なお、設計計算書は、汚染土壌処理施設が、自重、積載荷重その他の加重、地震
及び温度変化に対して構造耐力上安全であることを証明するに足りる内容を備える
必要があること。
? 汚染土壌の処理工程図(省令第2条第2項第4号)
汚染土壌の処理の一連の作業の手順をフロー図により示させること。ここにいう
「汚染土壌の処理の一連の作業」とは、1?に準ずること。
? 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、
当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類(省令第2条第5号)
汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地の登記事項証明書及び公図の写しを添付さ
せること。所有権を有しない場合には、当該敷地について申請者のために賃借権が
設定されたことを証する書類及び公図の写しを添付させること。
? 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(省令第2条第2項第7号)
以下の書類を添付させること。
イ汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有
する者(省令第4条第2号イ)の氏名及び役職並びに当該者が当該業務を統括管
理する権限を有することを確認することのできる管理体制系統図
ロ汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及
び技能を有する者(省令第4条第2号ロ)に係る次の書類
(1) 汚染土壌処理施設に配置されていることを確認することのできる書類
(2) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について3年以上の実務経験を有す
ることを証明する書類
(3) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有することを証明
する書類として次に掲げる書類
(イ) 大気の汚染に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類と
して次に掲げる書類のうちいずれかの書類
(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・大気管理)
に合格したことを証する証書(技術士法施行規則(昭和59 年総理府令第25
号)様式第4)の写し
(?) 大気関係第一種公害防止管理者試験又は大気関係第二種公害防止管理
者試験の合格証書(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施
行規則(昭和46 年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第3号)
様式第5)の写し
(?) 大気関係第一種公害防止管理者又は大気関係第二種公害防止管理者の
資格を得るための講習の修了証書(特定工場における公害防止組織の整備
に関する法律施行規則様式第7)の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46 年法律第
107 号)第8条の2第1項の指定試験機関(平成21 年10 月29 日現在、社
団法人産業環境管理協会)が発行する公害防止管理者等国家試験試験結果
通知書の写し(大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の
科目に合格していることが確認できるものであること)
(?) 省令第4条第2号ロ(イ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ロ) 水質の汚濁に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類とし
て次に掲げる書類のうちいずれかの書類
(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・水質管理)に
合格したことを証する証書の写し
(?) 水質関係第一種公害防止管理者試験又は水質関係第二種公害防止管理者
試験の合格証書の写し
(?) 水質関係第一種公害防止管理者又は水質関係第二種公害防止管理者の資
格を得るための講習の修了証書の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(水質概論及び水質
有害物質特論の科目に合格していることが確認できるものであること)
(?) 省令第4条第2号ロ(ロ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平
成11 年法律第105 号)第2条第1項のダイオキシン類をいう。)を生ずる可能
性のある汚染土壌処理施設にあっては、次のいずれかの書類
(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者試験の合格証書の写し
(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者の資格を得るための講習の修了証書の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(ダイオキシン類概
論及びダイオキシン類特論の科目に合格していることが確認できるものであ
ること)
? 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載
した書類(省令第2条第2項第8号)
汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額については、当該事業の開始及
び継続に必要となる一切の資金の総額を記載させること。具体的には、資本金の額
のほか、当該事業の用に供する汚染土壌処理施設の整備に要する費用、損害賠償保
険の保険料の額等が想定される。
汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の調達方法については、資本金の調達
方法、借入先、借入残高、年間返済額、返済期限、利率等資金の調達に関する一切
の事項を記載させること。利益をもって資金に充てるものについては、その見込額
を記載させること。
? 申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
る書面(省令第2条第2項第13 号)
申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
るため、その旨の誓約書を作成させ、申請者の氏名又は名称及び住所並びに申請者
が法人である場合にはその代表者の氏名を記名し、押印させた上で、添付させるこ
と。なお、申請者が法人である場合には、法第22 条第3項第2号ハのその事業を行
う役員についても、同旨の誓約書を作成し、添付させること。これらの誓約書を作
成する場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
? 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに
汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排
出水に係る用水の系統を説明する書類(省令第2条第2項第15 号)
汚水の処理の方法を示したフロー図及び設置する汚水の処理設備の構造及び能力
を記載した書類並びに排出水に係る用水及び排出水の経路図を添付させること。
? 排水口における排出水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第16号)
排出水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第17 号)
地下水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透
を防止する方法を記載した書類(省令第2条第2項第18 号)
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散等及び地下への浸透を防止するための当該汚染土壌処理施設の
構造並びにそのために設けられた設備の構造及び能力を記載させること。
また、汚染土壌の搬入及び搬出時以外の閉扉等施設管理により当該防止を図る場
合には、当該施設管理の方法を記載した書類を添付させること。
さらに、地下浸透防止措置(省令第4条第1号リ)が講じられている汚染土壌処
理施設にあっては、当該地下浸透防止措置が同号リの環境大臣が定める措置に該当
することを証明する書類を添付させること。
? 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、
排出口から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有
害物質の量の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第19 号)
発生してから排出口から大気中に排出されるまでの大気有害物質の排出経路、大
気有害物質の処理設備の構造、能力及び設置場所、大気有害物質の処理フロー図、
大気中に排出される大気有害物質の量の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及
び時間を記載した書類を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 法第27 条第1項に規定する措置(以下「廃止措置」という。)に要する費用の見
積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面(省令
第2条第2項第20 号)
法第27 条第1項の環境省令で定める廃止措置の内容に応じ、それぞれの廃止措置
に要する費用の見積額及びその算定根拠並びに当該見積額の総計の額の調達方法及
び当該調達方法が実現可能性のあるものであることを説明する書類を添付させること。
この記載に当たっては、?に準じてできる限り詳細に記載させること。
? 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者
がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況
の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項
又は第2項の基準に適合しないときの法第14 条第1項の申請を行うことについての
当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
(省令第2条第2項21 号)
廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷
地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項又は第2項の基準に適
合しないときは、汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地にいる申請者以外の所有者、
管理者又は占有者が法第14 条第1項の申請を行うことについて同意する旨の書類の
写しを添付させること。当該書類には、当該所有者、管理者又は占有者に記名し、
押印させること。この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
? 再処理汚染土壌処理施設について法第22 条第1項の許可を受けた者の当該処理を
受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書
類(省令第2条第2項22 号)
当該処理を受託することについての再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌処理
業者の同意書及び当該再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌の処理の事業の許可
証の写しを添付させること。当該同意書には、当該者に記名し、押印させること。
この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
なお、平成22 年3月31 日までに汚染土壌処理業の許可の申請をする場合には、
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受けることはないことから、再処理汚染土壌
処理施設に処理を委託することはないものとして、当該許可の申請を行わせ、当該
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受け次第、その旨の変更の届出(法第23 条第
3項)をさせること。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
2009年11月19日
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
(平成二十一年十月二十二日環境省令第十号)
(汚染土壌処理施設の種類)
第一条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 浄化等処理施設 汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号。以下「規則」という。)第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二 セメント製造施設 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三 埋立処理施設 汚染土壌の埋立てを行うための施設
四 分別等処理施設 汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設
(汚染土壌処理業の許可の申請)
第二条 法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 汚染土壌の処理工程図
五 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六 埋立処理施設にあっては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う場合における当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
七 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
九 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十三 申請者が法第二十二条第三項第二号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
十四 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十五 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十六 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第四条第一号ト、第五条第十三号において同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。第四条第一号チ及び第五条第十四号において同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十七 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類
十八 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
十九 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(次条第二号において「令」という。)第一条第七号、第十一号、第十二号、第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロ(2)(ハ)において同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十 法第二十七条第一項に規定する措置(次号及び第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面
二十一 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しないときの法第十四条第一項の申請を行うことについての当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
二十二 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合における当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該処理を受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書類
3 法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第七号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。
第三条 法第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
二 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
三 汚染土壌の処理の方法
四 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
五 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
六 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の氏名及び住所
七 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
イ 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
(汚染土壌処理業の許可の基準)
第四条 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に関する基準
イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体、汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
ト 排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第十三号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
(イ) 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(ロ) ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(2) ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備
チ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における排出水の水質を下水道法施行令 第九条の四第一項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第十二条の二第三項の規定により同令第九条の五第一項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第十四号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
(2) 下水道法施行令第九条の四第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第十四号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備
リ 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第十五号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヌ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっ ては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、(6)に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
(1) カドミウム及びその化合物 一・〇ミリグラム
(2) 塩素 三十ミリグラム
(3) 塩化水素 七百ミリグラム
(4) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 十ミリグラム
(5) 鉛及びその化合物 二十ミリグラム
(6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
二 申請者の能力に関する基準
イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
(1) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者
(2) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止 するための知識を有する者として次に掲げる者
(イ) 大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(?) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者
(?) (?)から(?)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ロ) 水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(?) 技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
(?) (?)から(?)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
(汚染土壌の処理に関する基準)
第五条 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
三 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
四 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第五条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第十八条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第二十四条第一項第一号に規定する第二溶出量基準をいう。第八号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
五 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
六 浄化等処理施設にあっては、申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
七 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
八 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。
九 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
十 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
十一 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十二 汚水を地下に浸透させてはならないこと。
十三 排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第一号ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
十四 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
十五 汚染土壌処理施設が設置されている場所にある地下水の下流側の当該汚染土壌処理施設の周縁において、三月に一回以上地下水を採取し、当該地下水の水質を規則第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第六条第一項に規定する地下水基準をいう。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
十六 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ 前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が、排出口において、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超える大気有害物質を排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、大気有害物質(前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質を除く。)の量を一年に一回以上、同号ヌの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
十七 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、法第十六条第一項の環境省令で定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合しているものを搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
十八 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
十九 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者にあっては、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、当該処理を終了したときは、法第二十条第四項の規定の例により、当該処理を委託した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
二十 前号の処理を委託した汚染土壌処理業者にあっては、同号の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者にその写しを送付しなければならないこと。
二十一 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二十二 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
二十三 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第三条 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
2 改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
(平成二十一年十月二十二日環境省令第十号)
(汚染土壌処理施設の種類)
第一条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 浄化等処理施設 汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号。以下「規則」という。)第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二 セメント製造施設 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三 埋立処理施設 汚染土壌の埋立てを行うための施設
四 分別等処理施設 汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設
(汚染土壌処理業の許可の申請)
第二条 法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 汚染土壌の処理工程図
五 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六 埋立処理施設にあっては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う場合における当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
七 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
九 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十三 申請者が法第二十二条第三項第二号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
十四 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十五 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十六 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第四条第一号ト、第五条第十三号において同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。第四条第一号チ及び第五条第十四号において同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十七 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類
十八 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
十九 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(次条第二号において「令」という。)第一条第七号、第十一号、第十二号、第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロ(2)(ハ)において同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十 法第二十七条第一項に規定する措置(次号及び第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面
二十一 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しないときの法第十四条第一項の申請を行うことについての当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
二十二 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合における当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該処理を受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書類
3 法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第七号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。
第三条 法第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
二 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
三 汚染土壌の処理の方法
四 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
五 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
六 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の氏名及び住所
七 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
イ 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
(汚染土壌処理業の許可の基準)
第四条 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に関する基準
イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体、汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
ト 排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第十三号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
(イ) 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(ロ) ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(2) ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備
チ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における排出水の水質を下水道法施行令 第九条の四第一項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第十二条の二第三項の規定により同令第九条の五第一項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第十四号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
(2) 下水道法施行令第九条の四第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第十四号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備
リ 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第十五号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヌ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっ ては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、(6)に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
(1) カドミウム及びその化合物 一・〇ミリグラム
(2) 塩素 三十ミリグラム
(3) 塩化水素 七百ミリグラム
(4) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 十ミリグラム
(5) 鉛及びその化合物 二十ミリグラム
(6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
二 申請者の能力に関する基準
イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
(1) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者
(2) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止 するための知識を有する者として次に掲げる者
(イ) 大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(?) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者
(?) (?)から(?)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ロ) 水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(?) 技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
(?) (?)から(?)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
(汚染土壌の処理に関する基準)
第五条 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
三 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
四 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第五条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第十八条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第二十四条第一項第一号に規定する第二溶出量基準をいう。第八号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
五 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
六 浄化等処理施設にあっては、申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
七 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
八 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。
九 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
十 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
十一 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十二 汚水を地下に浸透させてはならないこと。
十三 排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第一号ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
十四 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
十五 汚染土壌処理施設が設置されている場所にある地下水の下流側の当該汚染土壌処理施設の周縁において、三月に一回以上地下水を採取し、当該地下水の水質を規則第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第六条第一項に規定する地下水基準をいう。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
十六 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ 前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が、排出口において、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超える大気有害物質を排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、大気有害物質(前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質を除く。)の量を一年に一回以上、同号ヌの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
十七 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、法第十六条第一項の環境省令で定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合しているものを搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
十八 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
十九 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者にあっては、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、当該処理を終了したときは、法第二十条第四項の規定の例により、当該処理を委託した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
二十 前号の処理を委託した汚染土壌処理業者にあっては、同号の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者にその写しを送付しなければならないこと。
二十一 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二十二 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
二十三 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第三条 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
2 改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
2009年11月19日
改正後の土壌汚染対策法
土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域(第六条―第十条)
第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
第三節 雑則(第十四条・第十五条)
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りではない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域
(要措置区域の指定等)
第六条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(汚染の除去等の措置)
第七条 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもの(以下「指示措置等」という。)を講じなければならない。
4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公示しなければならない。
6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。
ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(適用除外)
第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
第二節 形質変更時要届出区域
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(適用除外)
第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第三節 雑則
(指定の申請)
第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(台帳)
第十五条 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(運搬に関する基準)
第十七条 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(措置命令)
第十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(管理票)
第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。
3 汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第二節 汚染土壌処理業
(汚染土壌処理業)
第二十二条 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 汚染土壌処理施設の設置の場所
三 汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
四 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
五 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 法人であって、その事業を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
4 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
6 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
7 汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。
8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
9 汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の許可等)
第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前条第三項の規定は、前項の許可について準用する。
3 汚染土壌処理業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(改善命令)
第二十四条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第二十二条第六項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第二十五条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十二条第三項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。
二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。
(名義貸しの禁止)
第二十六条 汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。
(許可の取消し等の場合の措置義務)
第二十七条 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第二十五条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(環境省令への委任)
第二十八条 この節に定めるもののほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第五章 指定調査機関
(指定の申請)
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三十二条 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
第三十三条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの(次条において「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第三十七条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第四十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第三条第一項の指定をしたとき。
二 第三十二条第一項の規定により第三条第一項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。
三 第三十五条(同条の環境省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は第四十条の規定による届出を受けたとき。
第六章 指定支援法人
(指定)
第四十四条 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、支援業務を行う者として指定することができる。
2 前項の指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(業務)
第四十五条 指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 要措置区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
二 次に掲げる事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
イ 土壌汚染状況調査
ロ 要措置区域等内の土地における汚染の除去等の措置
ハ 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更
三 前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行う
(基金)
第四十六条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(次条において単に「基金」という。)を設け、同条の規定により交付を受けた補助金と支援業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
(基金への補助金)
第四十七条 政府は、予算の範囲内において、指定支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
(事業計画等)
第四十八条 指定支援法人は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援法人は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第四十九条 指定支援法人は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(秘密保持義務)
第五十条 指定支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十五条第一号若しくは第二号に掲げる業務又は同条第四号に掲げる業務(同条第一号又は第二号に掲げる業務に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監督命令)
第五十一条 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第五十二条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。
一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 不正の手段により第四十四条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第五十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第四十四条第一項の指定をしたとき。
二 第四十四条第二項の規定による届出を受けたとき。
三 前条の規定により第四十四条第一項の指定を取り消したとき。
第七章 雑則
(報告及び検査)
第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第五十六条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第五十七条 環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第三条第一項ただし書の確認に関する事務
二 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条第二項の命令に関する事務
三 第三条第五項の確認の取消しに関する事務
四 第五条第二項の調査に関する事務
五 第六条第一項の指定に関する事務
六 第六条第二項の公示に関する事務
七 第六条第四項の指定の解除に関する事務
八 第七条第一項の指示に関する事務
九 第七条第五項の指示措置に関する事務
十 前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
(経過措置)
第六十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第六十三条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 第三条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十条から第十二条まで及び第十五条の規定の例により行うことができる。
2 第二十条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第三条 第三条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第三条 新法第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過する日以後に土地の形質の変更(同項に規定する土地の形質の変更をいう。附則第八条において同じ。)に着手する者について適用する。
(指定区域の指定に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている土地の区域は、新法第十一条第一項の規定により指定された同条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなす。
(指定区域台帳に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する旧法第六条第一項の規定による指定区域の台帳は、新法第十五条第一項の規定による形質変更時要届出区域の台帳とみなす。
(措置命令に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした旧法第七条第一項又は第二項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による命令を受けた者に係る旧法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第八条 施行日以後の日に附則第四条の規定により新法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧法第九条第一項の規定による届出をした者は、新法第十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)
第九条 新法第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。
(指定調査機関の指定に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
(変更の届出に関する経過措置)
第十一条 新法第三十五条の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする指定調査機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。
(適合命令に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前に旧法第十六条の規定によりした命令は、新法第三十九条の規定によりした命令とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域(第六条―第十条)
第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
第三節 雑則(第十四条・第十五条)
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りではない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域
(要措置区域の指定等)
第六条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(汚染の除去等の措置)
第七条 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもの(以下「指示措置等」という。)を講じなければならない。
4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公示しなければならない。
6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。
ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(適用除外)
第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
第二節 形質変更時要届出区域
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(適用除外)
第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第三節 雑則
(指定の申請)
第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(台帳)
第十五条 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(運搬に関する基準)
第十七条 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(措置命令)
第十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(管理票)
第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。
3 汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第二節 汚染土壌処理業
(汚染土壌処理業)
第二十二条 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 汚染土壌処理施設の設置の場所
三 汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
四 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
五 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 法人であって、その事業を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
4 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
6 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
7 汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。
8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
9 汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の許可等)
第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前条第三項の規定は、前項の許可について準用する。
3 汚染土壌処理業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(改善命令)
第二十四条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第二十二条第六項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第二十五条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十二条第三項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。
二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。
(名義貸しの禁止)
第二十六条 汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。
(許可の取消し等の場合の措置義務)
第二十七条 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第二十五条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(環境省令への委任)
第二十八条 この節に定めるもののほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第五章 指定調査機関
(指定の申請)
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三十二条 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
第三十三条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの(次条において「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第三十七条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第四十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第三条第一項の指定をしたとき。
二 第三十二条第一項の規定により第三条第一項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。
三 第三十五条(同条の環境省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は第四十条の規定による届出を受けたとき。
第六章 指定支援法人
(指定)
第四十四条 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、支援業務を行う者として指定することができる。
2 前項の指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(業務)
第四十五条 指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 要措置区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
二 次に掲げる事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
イ 土壌汚染状況調査
ロ 要措置区域等内の土地における汚染の除去等の措置
ハ 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更
三 前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行う
(基金)
第四十六条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(次条において単に「基金」という。)を設け、同条の規定により交付を受けた補助金と支援業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
(基金への補助金)
第四十七条 政府は、予算の範囲内において、指定支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
(事業計画等)
第四十八条 指定支援法人は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援法人は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第四十九条 指定支援法人は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(秘密保持義務)
第五十条 指定支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十五条第一号若しくは第二号に掲げる業務又は同条第四号に掲げる業務(同条第一号又は第二号に掲げる業務に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監督命令)
第五十一条 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第五十二条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。
一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 不正の手段により第四十四条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第五十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第四十四条第一項の指定をしたとき。
二 第四十四条第二項の規定による届出を受けたとき。
三 前条の規定により第四十四条第一項の指定を取り消したとき。
第七章 雑則
(報告及び検査)
第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第五十六条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第五十七条 環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第三条第一項ただし書の確認に関する事務
二 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条第二項の命令に関する事務
三 第三条第五項の確認の取消しに関する事務
四 第五条第二項の調査に関する事務
五 第六条第一項の指定に関する事務
六 第六条第二項の公示に関する事務
七 第六条第四項の指定の解除に関する事務
八 第七条第一項の指示に関する事務
九 第七条第五項の指示措置に関する事務
十 前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
(経過措置)
第六十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第六十三条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 第三条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十条から第十二条まで及び第十五条の規定の例により行うことができる。
2 第二十条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第三条 第三条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第三条 新法第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過する日以後に土地の形質の変更(同項に規定する土地の形質の変更をいう。附則第八条において同じ。)に着手する者について適用する。
(指定区域の指定に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている土地の区域は、新法第十一条第一項の規定により指定された同条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなす。
(指定区域台帳に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する旧法第六条第一項の規定による指定区域の台帳は、新法第十五条第一項の規定による形質変更時要届出区域の台帳とみなす。
(措置命令に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした旧法第七条第一項又は第二項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による命令を受けた者に係る旧法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第八条 施行日以後の日に附則第四条の規定により新法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧法第九条第一項の規定による届出をした者は、新法第十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)
第九条 新法第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。
(指定調査機関の指定に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
(変更の届出に関する経過措置)
第十一条 新法第三十五条の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする指定調査機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。
(適合命令に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前に旧法第十六条の規定によりした命令は、新法第三十九条の規定によりした命令とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
2009年11月19日
改正土壌汚染対策法の解説
改正土壌汚染対策法の解説
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(第171回国会内閣提出第59号)については、衆議院においてその一部が修正された上で、4月17日、参議院において可決され、成立したところであり、4月24日、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)として公布され、平成22年4月1日に施行の予定である(平成21年政令第245号)。
本稿では、法案提出の契機となった土壌汚染対策の現状と課題について触れた上で、本法による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)について説明する。
なお、新法の条文、新旧対照表等は、環境省ホームページ* に掲載されているので、御参照いただきたい。
1 現状と課題
昨年12月、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、「今後の土壌汚染対策の在り方について」の答申がなされ、この中で、土壌汚染対策の現状と課題として、
? 法に基づかない自主的な調査による土壌汚染の発見が増加しており、このような土壌汚染地については、情報が開示され、適切かつ確実に管理・対策を進めることが必要
? 最近の土壌汚染対策としては、健康被害のおそれの有無にかかわらず掘削除去が選択されることが多いが、掘削除去は汚染の拡散のリスクを伴うものであることから、汚染の程度等に応じて必要な対策の基準を明確化し、指定区域を健康被害のおそれの有無に応じて分類することが必要
? 汚染土壌の不適正処理の事例が発見されており、汚染土壌の適正処理の確保が必要
との指摘を受けたところである。
環境省は、これを踏まえて土壌汚染対策法を改正することとし、そのための法案を国会に提出した。
2 新法の概要
以下、新法について、主要な条項を解説する。条項については、特に断りがない限り、新法の条項である。
(1)土壌汚染状況調査
? 第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法の変更時の届出義務
第3条第1項ただし書の確認の制度は、土地の利用の方法からみて健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けた場合に同項の土壌汚染状況調査・報告義務を免れることとするものである。しかしながら、当該確認を受けた土地の利用の方法が変更されることにより、当該土地の所有者や従業員以外の者が立ち入ることが可能となり、健康被害が生じるおそれがある場合もあり得る。
このため、当該確認を受けた土地の所有者等に対し、当該土地の利用の方法を変更する前に、変更後の土地の利用の方法を届け出させるとともに(第3条第4項)、都道府県知事は、変更後の土地の利用の方法からみて健康被害が生ずるおそれがないと認められない場合には、当該確認を取り消すこととした(同条第5項)。この取消しにより、当該土地の所有者等は、改めて同条第1項の調査・報告義務を負うこととなる。
? 土壌汚染のおそれがある土地の形質が変更される場合の調査命令
土地の形質の変更は、それが行われる土地に土壌汚染が存在する場合には、掘削工事に伴う汚染土壌の飛散、汚染土壌が帯水層に接することによる地下水汚染の発生をもたらし得るものであるし、掘削された汚染土壌が搬出されて埋立材に利用されることがあるなど、汚染の拡散のリスクを伴うものである。一方、現行法においては、指定区域外における土地の形質の変更について、何ら規制がない。
このため、土地の形質の変更(当該変更に係る部分の面積が環境省令で定める規模以上のものに限る。)をしようとする者は、当該形質の変更に着手する日の30日前までに、当該形質の変更の場所、着手予定日等を都道府県知事に届け出なければならないこととし(第4条第1項。ただし、後述する形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。第13条)、都道府県知事は、当該届出を受けた場合において、その土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、その土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査・報告を命ずることとした(第4条第2項)。
なお、「土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準」としては、
?有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地、
?特定有害物質が土壌に漏洩した土地、
?法に基づかない自主的な調査により汚染が確認されている土地、等を想定している。
(2)区域の指定等
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれの有無にかかわらず一定の基準を超過する土壌汚染地を一律に指定区域に指定する現行制度の下においては、指定区域は健康被害が生ずるおそれがあり、危険な区域であるという安全サイドに立った判断が行われることにより、必ずしも汚染の除去等の措置を講ずる必要のない区域においても、掘削除去が行われることが多い。しかし、掘削除去は、大量の汚染土壌の搬出を伴うため、環境リスクの観点から望ましいものではない。
このため、一定の基準を超過する土壌汚染が存在する土地を、健康被害が生ずるおそれの有無に応じて分類して指定するとともに、健康被害が生ずるおそれのある区域については、都道府県知事が健康被害の防止の観点から最低限必要な措置を明示することとした。
? 要措置区域
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、かつ、当該土地に人の立入りがあったり、当該土地又はその周辺の土地において地下水が飲用に供されている等、当該汚染により健康被害が生ずるおそれがある場合には、当該土地の区域を、要措置区域として指定することとした(第6条第1項)。都道府県知事は、要措置区域の指定をした場合には、当該土地の所有者等又は汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとし(第7条第1項)、この指示をするときは、講ずべき措置及びその理由等を示さなければならないこととした(同条第2項)。
この指示を受けた者は、指示された汚染の除去等の措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置を講ずる義務を負い(同条第3項)、都道府県知事は、この義務の不履行があれば、履行すべきことを命ずることができることとした(同条第4項)。
要措置区域内においては、都道府県知事から指示を受けた者が行う汚染の除去等の措置に伴うもの等を除き、土地の形質の変更を禁止することとした(第9条)。
? 形質変更時要届出区域
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないが、当該汚染により健康被害が生ずるおそれがない場合には、当該土地の区域を、形質変更時要届出区域として指定することとした(第11条第1項)。形質変更時要届出区域内については、土地の形質の変更を行うことによる新たな環境リスクの発生を防止するため、現行法第9条と同様に、土地の形質の変更時の届出等を義務付けることとした(第12条)。
(3) 指定の申請
現在では、土地取引等の際に広く自主的な調査が行われ、土壌汚染が発見されているが、このような法に基づかない調査により発見された土壌汚染地は、指定区域に指定されることはなく、法の規制の下で管理がなされていなかった。
このため、土地の所有者等は、自主的に土壌の汚染の状況について調査した結果、一定の基準を超過する土壌汚染が存在すると思料するときは、都道府県知事に対し、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定することを申請することができることとした(第14条第1項)。都道府県知事は、当該申請に係る調査が公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該自主的な調査を法に基づく調査とみなし、当該調査の結果に基づき、当該土地の区域を要措置区域等に指定することができることとした(同条第3項)。
(4) 汚染土壌の搬出等に関する規制
? 汚染土壌の搬出時の届出
要措置区域等内の土地の土壌(環境省令で定める方法により調査した結果、汚染状態が(2)?の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、都道府県知事に、当該搬出に着手する日の14日前までに、当該汚染土壌の汚染状態、体積、運搬の方法、当該汚染土壌を処理する施設の所在地等を届け出なければならないこととした(第16条第1項)。都道府県知事は、届出の内容が?に違反していると認めるときは、計画の変更を命ずることができることとした(同条第4項)。なお、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合や汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合には、届出の対象外とするが(同条第1項ただし書)、前者については事後届出が必要であることとした(同条第3項)。
? 搬出汚染土壌の運搬及び処理
搬出した汚染土壌を要措置区域等外において運搬する者は、環境省令で定める基準に従って運搬しなければならないこととした(第17条)。
また、汚染土壌を搬出する者は、自らが?の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)であって当該汚染土壌を自ら処理する場合等を除き、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないこととした(第18条第1項)。
? 措置命令
都道府県知事は、汚染土壌を運搬した者が?に違反した場合、又は汚染土壌を要措置区域等外へ搬出した者が?に違反した場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を命ずることができることとした(第19条)。
? 管理票
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者がその汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、当該者は、管理票を用いて、当該汚染土壌が適正に運搬、処理されたことを確認しなければならないこととした(第20条)。また、虚偽の管理票が交付されること等により、汚染土壌の運搬及び処理の確認に支障が生じることとなることから、虚偽の管理票の交付等を禁止することとした(第21条)。
? 汚染土壌処理業
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないこととした(第22条第1項)。また、汚染土壌の処理が確実に行われることを担保するため、都道府県知事は、
1) 汚染土壌処理施設及び申請者の能力が、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること
2) この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること等の欠格事由に該当しないこと
に適合しているときでなければ、許可してはならないこととした(同条第3項)。汚染土壌処理業の許可については、5年間の有効期間を設け、更新を受けなければ失効することとした(同条第4項)。
さらに、汚染土壌処理業者は、環境省令で定める基準に従って汚染土壌の処理を行い(同条第6項)、汚染土壌処理施設に汚染土壌の処理に関する記録を備え置き、利害関係者に閲覧させ(同条第8項)、汚染土壌処理施設における事故が発生したときにその旨を届け出る(同条第9項)義務を負うこととした。
また、都道府県知事は、汚染土壌処理業者により処理基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした(第24条)。都道府県知事は、汚染土壌処理業者が1)又は2)に適合しなくなったとき等に該当する場合には、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができることとした(第25条)。
また、汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は当該事業の許可が取り消された汚染土壌処理業者は、汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならないこととし(第27条第1項)、都道府県知事は、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該施設を事業の用に供した者に対し、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした(同条第2項)。
なお、汚染土壌処理業の許可の申請手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及び図面のほか、当該許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等について定めた、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(平成21年環境省令第10号)が平成21年10月22日に制定・公布されたので、こちらも併せて御参照いただきたい* 。
(5) 指定調査機関
? 指定の更新
指定調査機関の指定に5年間の有効期間を設け、更新を受けなければ失効することとした(第32条第1項)。環境大臣は、この更新の際に、指定調査機関が経理的基礎及び技術的能力を有するか否か等を確認し、基準に適合していると認められない指定調査機関は、更新を受けられないこととした(同条第2項により準用される第31条)。
? 技術管理者の設置
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等に精通した技術者として環境省令で定める基準に適合するものを技術管理者として選任し、土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督を技術管理者にさせなければならないこととした(第33条及び第34条)。また、指定調査機関が技術管理者の選任義務に違反した場合には、環境大臣は、その指定を取り消すことができることとした(第42条第2号)。
(6) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めることとした(第61条第1項)。この規定により、土壌汚染の状況に関する調査や講じられた汚染の除去等の措置(いずれも法に基づくものであると否とを問わない。)に関する情報等が収集されることになり、第4条第2項や第5条第1項の命令が適切に行われること等が期待される。
また、都道府県知事は、公園等の公共施設や学校、卸売市場等の公益的施設等を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地の土壌汚染のおそれの有無を把握させるよう努めることとした(同条第2項)。
(7) 施行期日、経過措置
? 施行期日
本法は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行するが(附則第1条本文)、汚染土壌処理業の許可を受けようとする者は、本法の施行前においても、第22条第2項に準じてその申請を行うことができることとし、この規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされた(附則第1条ただし書、附則第2条)。
これらの施行期日については、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成21年政令第245号)により、それぞれ、平成22年4月1日及び平成21年10月23日と定められた。
? 経過措置
現行法の指定区域は、本法施行後、形質変更時要届出区域とみなし(附則第4条)、現行法の指定区域台帳は、形質変更時要届出区域の台帳とみなすこととした(附則第5条)。現行法の指定調査機関は、本法施行日に、新法第3条第1項の指定を受けたものとみなすこととした(附則第10条)。
以上が新法の概要である。環境省としては、引き続き、省令の改正等所要の準備を行い、新法の円滑な施行を図っていくこととしている。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(第171回国会内閣提出第59号)については、衆議院においてその一部が修正された上で、4月17日、参議院において可決され、成立したところであり、4月24日、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)として公布され、平成22年4月1日に施行の予定である(平成21年政令第245号)。
本稿では、法案提出の契機となった土壌汚染対策の現状と課題について触れた上で、本法による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)について説明する。
なお、新法の条文、新旧対照表等は、環境省ホームページ* に掲載されているので、御参照いただきたい。
1 現状と課題
昨年12月、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、「今後の土壌汚染対策の在り方について」の答申がなされ、この中で、土壌汚染対策の現状と課題として、
? 法に基づかない自主的な調査による土壌汚染の発見が増加しており、このような土壌汚染地については、情報が開示され、適切かつ確実に管理・対策を進めることが必要
? 最近の土壌汚染対策としては、健康被害のおそれの有無にかかわらず掘削除去が選択されることが多いが、掘削除去は汚染の拡散のリスクを伴うものであることから、汚染の程度等に応じて必要な対策の基準を明確化し、指定区域を健康被害のおそれの有無に応じて分類することが必要
? 汚染土壌の不適正処理の事例が発見されており、汚染土壌の適正処理の確保が必要
との指摘を受けたところである。
環境省は、これを踏まえて土壌汚染対策法を改正することとし、そのための法案を国会に提出した。
2 新法の概要
以下、新法について、主要な条項を解説する。条項については、特に断りがない限り、新法の条項である。
(1)土壌汚染状況調査
? 第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法の変更時の届出義務
第3条第1項ただし書の確認の制度は、土地の利用の方法からみて健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けた場合に同項の土壌汚染状況調査・報告義務を免れることとするものである。しかしながら、当該確認を受けた土地の利用の方法が変更されることにより、当該土地の所有者や従業員以外の者が立ち入ることが可能となり、健康被害が生じるおそれがある場合もあり得る。
このため、当該確認を受けた土地の所有者等に対し、当該土地の利用の方法を変更する前に、変更後の土地の利用の方法を届け出させるとともに(第3条第4項)、都道府県知事は、変更後の土地の利用の方法からみて健康被害が生ずるおそれがないと認められない場合には、当該確認を取り消すこととした(同条第5項)。この取消しにより、当該土地の所有者等は、改めて同条第1項の調査・報告義務を負うこととなる。
? 土壌汚染のおそれがある土地の形質が変更される場合の調査命令
土地の形質の変更は、それが行われる土地に土壌汚染が存在する場合には、掘削工事に伴う汚染土壌の飛散、汚染土壌が帯水層に接することによる地下水汚染の発生をもたらし得るものであるし、掘削された汚染土壌が搬出されて埋立材に利用されることがあるなど、汚染の拡散のリスクを伴うものである。一方、現行法においては、指定区域外における土地の形質の変更について、何ら規制がない。
このため、土地の形質の変更(当該変更に係る部分の面積が環境省令で定める規模以上のものに限る。)をしようとする者は、当該形質の変更に着手する日の30日前までに、当該形質の変更の場所、着手予定日等を都道府県知事に届け出なければならないこととし(第4条第1項。ただし、後述する形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。第13条)、都道府県知事は、当該届出を受けた場合において、その土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、その土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査・報告を命ずることとした(第4条第2項)。
なお、「土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準」としては、
?有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地、
?特定有害物質が土壌に漏洩した土地、
?法に基づかない自主的な調査により汚染が確認されている土地、等を想定している。
(2)区域の指定等
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれの有無にかかわらず一定の基準を超過する土壌汚染地を一律に指定区域に指定する現行制度の下においては、指定区域は健康被害が生ずるおそれがあり、危険な区域であるという安全サイドに立った判断が行われることにより、必ずしも汚染の除去等の措置を講ずる必要のない区域においても、掘削除去が行われることが多い。しかし、掘削除去は、大量の汚染土壌の搬出を伴うため、環境リスクの観点から望ましいものではない。
このため、一定の基準を超過する土壌汚染が存在する土地を、健康被害が生ずるおそれの有無に応じて分類して指定するとともに、健康被害が生ずるおそれのある区域については、都道府県知事が健康被害の防止の観点から最低限必要な措置を明示することとした。
? 要措置区域
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、かつ、当該土地に人の立入りがあったり、当該土地又はその周辺の土地において地下水が飲用に供されている等、当該汚染により健康被害が生ずるおそれがある場合には、当該土地の区域を、要措置区域として指定することとした(第6条第1項)。都道府県知事は、要措置区域の指定をした場合には、当該土地の所有者等又は汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとし(第7条第1項)、この指示をするときは、講ずべき措置及びその理由等を示さなければならないこととした(同条第2項)。
この指示を受けた者は、指示された汚染の除去等の措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置を講ずる義務を負い(同条第3項)、都道府県知事は、この義務の不履行があれば、履行すべきことを命ずることができることとした(同条第4項)。
要措置区域内においては、都道府県知事から指示を受けた者が行う汚染の除去等の措置に伴うもの等を除き、土地の形質の変更を禁止することとした(第9条)。
? 形質変更時要届出区域
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないが、当該汚染により健康被害が生ずるおそれがない場合には、当該土地の区域を、形質変更時要届出区域として指定することとした(第11条第1項)。形質変更時要届出区域内については、土地の形質の変更を行うことによる新たな環境リスクの発生を防止するため、現行法第9条と同様に、土地の形質の変更時の届出等を義務付けることとした(第12条)。
(3) 指定の申請
現在では、土地取引等の際に広く自主的な調査が行われ、土壌汚染が発見されているが、このような法に基づかない調査により発見された土壌汚染地は、指定区域に指定されることはなく、法の規制の下で管理がなされていなかった。
このため、土地の所有者等は、自主的に土壌の汚染の状況について調査した結果、一定の基準を超過する土壌汚染が存在すると思料するときは、都道府県知事に対し、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定することを申請することができることとした(第14条第1項)。都道府県知事は、当該申請に係る調査が公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該自主的な調査を法に基づく調査とみなし、当該調査の結果に基づき、当該土地の区域を要措置区域等に指定することができることとした(同条第3項)。
(4) 汚染土壌の搬出等に関する規制
? 汚染土壌の搬出時の届出
要措置区域等内の土地の土壌(環境省令で定める方法により調査した結果、汚染状態が(2)?の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、都道府県知事に、当該搬出に着手する日の14日前までに、当該汚染土壌の汚染状態、体積、運搬の方法、当該汚染土壌を処理する施設の所在地等を届け出なければならないこととした(第16条第1項)。都道府県知事は、届出の内容が?に違反していると認めるときは、計画の変更を命ずることができることとした(同条第4項)。なお、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合や汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合には、届出の対象外とするが(同条第1項ただし書)、前者については事後届出が必要であることとした(同条第3項)。
? 搬出汚染土壌の運搬及び処理
搬出した汚染土壌を要措置区域等外において運搬する者は、環境省令で定める基準に従って運搬しなければならないこととした(第17条)。
また、汚染土壌を搬出する者は、自らが?の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)であって当該汚染土壌を自ら処理する場合等を除き、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないこととした(第18条第1項)。
? 措置命令
都道府県知事は、汚染土壌を運搬した者が?に違反した場合、又は汚染土壌を要措置区域等外へ搬出した者が?に違反した場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を命ずることができることとした(第19条)。
? 管理票
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者がその汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、当該者は、管理票を用いて、当該汚染土壌が適正に運搬、処理されたことを確認しなければならないこととした(第20条)。また、虚偽の管理票が交付されること等により、汚染土壌の運搬及び処理の確認に支障が生じることとなることから、虚偽の管理票の交付等を禁止することとした(第21条)。
? 汚染土壌処理業
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないこととした(第22条第1項)。また、汚染土壌の処理が確実に行われることを担保するため、都道府県知事は、
1) 汚染土壌処理施設及び申請者の能力が、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること
2) この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること等の欠格事由に該当しないこと
に適合しているときでなければ、許可してはならないこととした(同条第3項)。汚染土壌処理業の許可については、5年間の有効期間を設け、更新を受けなければ失効することとした(同条第4項)。
さらに、汚染土壌処理業者は、環境省令で定める基準に従って汚染土壌の処理を行い(同条第6項)、汚染土壌処理施設に汚染土壌の処理に関する記録を備え置き、利害関係者に閲覧させ(同条第8項)、汚染土壌処理施設における事故が発生したときにその旨を届け出る(同条第9項)義務を負うこととした。
また、都道府県知事は、汚染土壌処理業者により処理基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした(第24条)。都道府県知事は、汚染土壌処理業者が1)又は2)に適合しなくなったとき等に該当する場合には、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができることとした(第25条)。
また、汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は当該事業の許可が取り消された汚染土壌処理業者は、汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならないこととし(第27条第1項)、都道府県知事は、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該施設を事業の用に供した者に対し、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした(同条第2項)。
なお、汚染土壌処理業の許可の申請手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及び図面のほか、当該許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等について定めた、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(平成21年環境省令第10号)が平成21年10月22日に制定・公布されたので、こちらも併せて御参照いただきたい* 。
(5) 指定調査機関
? 指定の更新
指定調査機関の指定に5年間の有効期間を設け、更新を受けなければ失効することとした(第32条第1項)。環境大臣は、この更新の際に、指定調査機関が経理的基礎及び技術的能力を有するか否か等を確認し、基準に適合していると認められない指定調査機関は、更新を受けられないこととした(同条第2項により準用される第31条)。
? 技術管理者の設置
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等に精通した技術者として環境省令で定める基準に適合するものを技術管理者として選任し、土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督を技術管理者にさせなければならないこととした(第33条及び第34条)。また、指定調査機関が技術管理者の選任義務に違反した場合には、環境大臣は、その指定を取り消すことができることとした(第42条第2号)。
(6) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めることとした(第61条第1項)。この規定により、土壌汚染の状況に関する調査や講じられた汚染の除去等の措置(いずれも法に基づくものであると否とを問わない。)に関する情報等が収集されることになり、第4条第2項や第5条第1項の命令が適切に行われること等が期待される。
また、都道府県知事は、公園等の公共施設や学校、卸売市場等の公益的施設等を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地の土壌汚染のおそれの有無を把握させるよう努めることとした(同条第2項)。
(7) 施行期日、経過措置
? 施行期日
本法は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行するが(附則第1条本文)、汚染土壌処理業の許可を受けようとする者は、本法の施行前においても、第22条第2項に準じてその申請を行うことができることとし、この規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされた(附則第1条ただし書、附則第2条)。
これらの施行期日については、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成21年政令第245号)により、それぞれ、平成22年4月1日及び平成21年10月23日と定められた。
? 経過措置
現行法の指定区域は、本法施行後、形質変更時要届出区域とみなし(附則第4条)、現行法の指定区域台帳は、形質変更時要届出区域の台帳とみなすこととした(附則第5条)。現行法の指定調査機関は、本法施行日に、新法第3条第1項の指定を受けたものとみなすこととした(附則第10条)。
以上が新法の概要である。環境省としては、引き続き、省令の改正等所要の準備を行い、新法の円滑な施行を図っていくこととしている。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
2009年11月01日
土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内


「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html

追伸
10以上の近畿の地方自治体の土壌汚染ご担当者が参加を予定されています。
環境省や近畿環境地方事務所から複数名の参加を予定されています。
改正土壌汚染対策法や土壌汚染行政のありかたを考える良い機会だと思いますので、是非ご参加いただきますようご案内いたします。

各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html


2009年10月22日
(工事中)汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
1.汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令の概要
(1)制定の趣旨
改正法附則第2条(汚染土壌処理業の許可の申請の手続に係る規定)については、本年10月23日までの政令で定める日から施行するとされているところ。土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令により、同条の施行日が本年10月23日とされたことに伴い、当該許可申請に必要となる手続の細目のほか、当該許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める必要があることから、そのための省令の制定を行うもの。
(2)省令の内容
[1] 汚染土壌処理施設の種類(第1条関係)
改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第22条第2項第3号において、汚染土壌処理施設の種類が申請書の記載事項として定められていることから、汚染土壌処理施設について、当該汚染土壌処理施設における汚染土壌の処理方法に応じて類型化を行い、それぞれについて定義を定めることとする。
[2] 汚染土壌処理業の許可の申請の手続(第2条及び第3条関係)
汚染土壌処理業の許可の申請の手続に必要な申請書の様式、当該申請書の添付書類及び図面並びに新法第22条第2項第1号から第4号までに規定する事項以外の当該申請書の記載事項について定めることとする。
[3] 汚染土壌処理業の許可の基準(第4条関係)
都道府県知事が[2]の申請に応じて汚染土壌処理業の許可を与える際の基準について、汚染土壌処理施設に係るものと申請者の能力に係るものに分けて定めることとする。 [4]汚染土壌の処理に関する基準(第5条関係)
汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理を行うに当たっての基準について定めることとする。 (3)施行
改正法の施行の日(平成22年4月1日)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11694
○環境省令第十号
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
(汚染土壌処理施設の種類)第一条
(汚染土壌処理業の許可の申請)第二条
(汚染土壌処理業の許可の基準)第四条
(汚染土壌の処理に関する基準)第五条
(施行期日)附則
○環境省令第十号
土壌汚染対策法 第二十二条第二項、第三項第一号及び第六項並びに第二十八条の規定に基づき、並びに第二十二条第一項の規定を実施するため、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令を次のように定める。
平成二十一年十月二十二日環境大臣小沢鋭仁
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令

(汚染土壌処理施設の種類)
第一条 土壌汚染対策法 第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 浄化等処理施設汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(以下「規則」という。)第十八条第一項及び
第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二 セメント製造施設汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三 埋立処理施設汚染土壌の埋立てを行うための施設
四 分別等処理施設汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設
(汚染土壌処理業の許可の申請)
第二条 法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 汚染土壌の処理工程図
五 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六 埋立処理施設にあっては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う場合における当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
七 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
九 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十三 申請者が法第二十二条第三項第二号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
十四 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十五 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十六 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第四条第一号ト、第五条第十三号において同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法 第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。第四条第一号チ及び第五条第十四号において同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十七 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類
十八 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
十九 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヌからまでに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。次条第二号において「令」という。)第一条第七号、第十一号、第十二号、第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十 法第二十七条第一項に規定する措置(次号及び第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面
二十一 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しないときの法第十四条第一項の申請を行うことについての当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
二十二 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合における当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該処理を受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書類
3 法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第七号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。
第三条 法第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
二 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
三 汚染土壌の処理の方法
四 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
五 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
六 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の氏名及び住所
七 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
イ 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力

(汚染土壌処理業の許可の基準)
第四条 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に関する基準
イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体、汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
ト 排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第十三号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備及びに掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備?
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(
ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
チ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。排水口における排出水の水質を下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第十二条の二第三項の規定により同令第九条の五第一項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第十四号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
下水道法施行令第九条の四第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第十四号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備
リ 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第十五号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヌ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次のからまでに掲げる大気有害物質の量が当該からまでに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び
環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、、、及びに掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
カドミウム及びその化合物一・〇ミリグラム
塩素三十ミリグラム
塩化水素七百ミリグラム
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素十ミリグラム
鉛及びその化合物二十ミリグラム
窒素酸化物二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄
化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
二 申請者の能力に関する基準
イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者
(1)汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有する者として次に掲げる者
(2)大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
・技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る。)
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者からまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
からまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
(汚染土壌の処理に関する基準)
第五条 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
三 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
四 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第五条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第十八条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第二十四条第一項第一号に規定する第二溶出量基準をいう。第八号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
五 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国
民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
六 浄化等処理施設にあっては、申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
七 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
八 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。
九 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
十 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
十一 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十二 汚水を地下に浸透させてはならないこと。
十三 排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第一号ト及びに掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
?
十四 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
十五 汚染土壌処理施設が設置されている場所にある地下水の下流側の当該汚染土壌処理施設の周縁において、三月に一回以上地下水を採取し、当該地下水の水質を規則第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第六条第一項に規定する地下水基準をいう。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
十六 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ 前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質の量が、排出口において、温度が零度であって、
?
圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該からまでに掲げる許容限度を超える大気有害物質を排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、大気有害物質(前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質を除く。)の量を一年に一回以上、同号ヌの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
十七 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、法第十六条第一項の環境省令で定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合しているものを搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
十八 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
十九 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者にあっては、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、当該処理を終了したときは、法第二十条第四項の規定の例により、当該処理を委託した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
二十 前号の処理を委託した汚染土壌処理業者にあっては、同号の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者にその写しを送付しなければならないこと。
二十一 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二十二 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
二十三 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第三条 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定
(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
2 改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14432&hou_id=11694



(1)制定の趣旨
改正法附則第2条(汚染土壌処理業の許可の申請の手続に係る規定)については、本年10月23日までの政令で定める日から施行するとされているところ。土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令により、同条の施行日が本年10月23日とされたことに伴い、当該許可申請に必要となる手続の細目のほか、当該許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める必要があることから、そのための省令の制定を行うもの。
(2)省令の内容
[1] 汚染土壌処理施設の種類(第1条関係)
改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第22条第2項第3号において、汚染土壌処理施設の種類が申請書の記載事項として定められていることから、汚染土壌処理施設について、当該汚染土壌処理施設における汚染土壌の処理方法に応じて類型化を行い、それぞれについて定義を定めることとする。
[2] 汚染土壌処理業の許可の申請の手続(第2条及び第3条関係)
汚染土壌処理業の許可の申請の手続に必要な申請書の様式、当該申請書の添付書類及び図面並びに新法第22条第2項第1号から第4号までに規定する事項以外の当該申請書の記載事項について定めることとする。
[3] 汚染土壌処理業の許可の基準(第4条関係)
都道府県知事が[2]の申請に応じて汚染土壌処理業の許可を与える際の基準について、汚染土壌処理施設に係るものと申請者の能力に係るものに分けて定めることとする。 [4]汚染土壌の処理に関する基準(第5条関係)
汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理を行うに当たっての基準について定めることとする。 (3)施行
改正法の施行の日(平成22年4月1日)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11694
○環境省令第十号
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
(汚染土壌処理施設の種類)第一条
(汚染土壌処理業の許可の申請)第二条
(汚染土壌処理業の許可の基準)第四条
(汚染土壌の処理に関する基準)第五条
(施行期日)附則
○環境省令第十号
土壌汚染対策法 第二十二条第二項、第三項第一号及び第六項並びに第二十八条の規定に基づき、並びに第二十二条第一項の規定を実施するため、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令を次のように定める。
平成二十一年十月二十二日環境大臣小沢鋭仁
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令

(汚染土壌処理施設の種類)
第一条 土壌汚染対策法 第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 浄化等処理施設汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(以下「規則」という。)第十八条第一項及び
第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二 セメント製造施設汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三 埋立処理施設汚染土壌の埋立てを行うための施設
四 分別等処理施設汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設
(汚染土壌処理業の許可の申請)
第二条 法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 汚染土壌の処理工程図
五 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六 埋立処理施設にあっては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う場合における当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
七 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
九 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十三 申請者が法第二十二条第三項第二号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
十四 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十五 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十六 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第四条第一号ト、第五条第十三号において同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法 第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。第四条第一号チ及び第五条第十四号において同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十七 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類
十八 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
十九 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヌからまでに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。次条第二号において「令」という。)第一条第七号、第十一号、第十二号、第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十 法第二十七条第一項に規定する措置(次号及び第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面
二十一 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しないときの法第十四条第一項の申請を行うことについての当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
二十二 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合における当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該処理を受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書類
3 法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第七号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。
第三条 法第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
二 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
三 汚染土壌の処理の方法
四 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
五 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
六 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の氏名及び住所
七 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
イ 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力

(汚染土壌処理業の許可の基準)
第四条 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に関する基準
イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体、汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
ト 排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第十三号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備及びに掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備?
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(
ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
チ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。排水口における排出水の水質を下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第十二条の二第三項の規定により同令第九条の五第一項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第十四号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
下水道法施行令第九条の四第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第十四号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備
リ 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第十五号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヌ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次のからまでに掲げる大気有害物質の量が当該からまでに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び
環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、、、及びに掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
カドミウム及びその化合物一・〇ミリグラム
塩素三十ミリグラム
塩化水素七百ミリグラム
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素十ミリグラム
鉛及びその化合物二十ミリグラム
窒素酸化物二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄
化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
二 申請者の能力に関する基準
イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者
(1)汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有する者として次に掲げる者
(2)大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
・技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る。)
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者からまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
からまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
(汚染土壌の処理に関する基準)
第五条 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
三 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
四 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第五条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第十八条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第二十四条第一項第一号に規定する第二溶出量基準をいう。第八号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
五 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国
民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
六 浄化等処理施設にあっては、申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
七 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
八 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。
九 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
十 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
十一 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十二 汚水を地下に浸透させてはならないこと。
十三 排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第一号ト及びに掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
?
十四 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
十五 汚染土壌処理施設が設置されている場所にある地下水の下流側の当該汚染土壌処理施設の周縁において、三月に一回以上地下水を採取し、当該地下水の水質を規則第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第六条第一項に規定する地下水基準をいう。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
十六 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ 前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質の量が、排出口において、温度が零度であって、
?
圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該からまでに掲げる許容限度を超える大気有害物質を排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、大気有害物質(前条第一号ヌからまでに掲げる大気有害物質を除く。)の量を一年に一回以上、同号ヌの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
十七 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、法第十六条第一項の環境省令で定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合しているものを搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
十八 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
十九 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者にあっては、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、当該処理を終了したときは、法第二十条第四項の規定の例により、当該処理を委託した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
二十 前号の処理を委託した汚染土壌処理業者にあっては、同号の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者にその写しを送付しなければならないこと。
二十一 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二十二 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
二十三 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第三条 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定
(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
2 改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14432&hou_id=11694



2009年10月20日
「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内

「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html


各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html

2009年10月18日
「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内

「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html


各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html

2009年10月17日
改正土壌汚染対策法 第八章 罰則 の対象条項

第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第三条 第三項
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。

3 知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
第四条第二項
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
第五条第一項
第五条 知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
第七条第四項
第七条 知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の措置
(以下「指示措置」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもの(以下「指示措置等」という。)を講じなければならない。
4 知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
第十二条第四項
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
4 知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
第十六条 第四項
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
第十九条
第十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
第二十四条
第二十四条 知事は、汚染土壌処理業者により第二十二条第六項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第二十五条
第二十五条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十二条第三項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。
二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。
第二十七条第二項
第二十七条 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第二十五条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、前項に規定する汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
二 第九条の規定に違反した者
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
第二十二条 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
第二十二条 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければならない。
第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第二十六条 汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
一 下記の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三条第四項
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設であって、同条第二項第一号に規定する物質に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けたときは、この限りでない。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
第四条第一項
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を知事に届け出なければならない。
第十二条第一項
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を知事に届け出なければならない。
第十六条第一項若しくは第二項
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
第二十三条第三項若しくは第四項
第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 汚染土壌処理業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
第十七条 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
第十八条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
3 汚染土壌の運搬を受託した者は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
4 汚染土壌の処理を受託した者は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
3 ・・・・
この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したときは当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
第二十一条 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第二十一条 (虚偽の管理票の交付等の禁止)
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
第二十二条 汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければならない。
8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
二 第五十条の規定に違反した者
指定支援法人
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第五十四条 環境大臣又は知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
3 知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第十二条第二項若しくは第三項第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第十六条第三項
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。
第二十条第六項
第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
3 汚染土壌の運搬を受託した者は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理を受託した者は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を知事に届け出なければならない。
第四十条
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
2009年10月17日
不確定版!改正土壌汚染対策法の施行に係る政省令事項素案

改正土壌汚染対策法の施行に係る政省令事項素案
※以下「法」とは、改正法による改正後の土壌汚染対策法をいい、「現行令」とは、現行の土壌汚染対策法施行令をいい、「現行規則」とは、現行の土壌汚染対策法施行規則をいう。
※以下において使用する用語は、土壌汚染対策法において使用する用語の例による。
※内容の変更を伴う改正を行わない項目については、記載していない(法改正に伴う用語の整理や、条ずれ対応等技術的修正は、別途行うものとする。)。
1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査(法第3条関係)
2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条関係)
3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査(法第5条関係)
4.要措置区域の指定等(法第6条関係)
5.汚染の除去等の措置等(法第7条関係)
6.要措置区域内における土地の形質の変更の禁止(法第9条関係)
7.形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令(法第12条関係)
8.指定の申請(法第14条関係)
9.台帳(法第15条関係)
10.汚染土壌の搬出時の届出等(法第16条関係)
11.運搬に関する基準(法第17条関係)
12.管理票(法第20条関係)
13.汚染土壌処理業の許可の申請に関する規定の新設(法第22条関係)
14.汚染土壌処理業による汚染土壌の処理の基準(法第22条第6項関係)
15.汚染土壌処理業による汚染土壌の処理に関する記録及び閲覧(法第22条第8項関係)
16.汚染土壌処理業による変更の許可等(法第23条関係)
17.許可の取消し等の場合の措置義務(法第27条第1項関係)
18.許可証の交付等(法第28条関係)
19.指定調査機関の指定(法第29条関係)
20.指定の基準(法第31条関係)
21.技術管理者(法第33条関係)
22.変更の届出(法第35条関係)
23.業務規程の届出(法第37条関係)
24.帳簿の備付け等(法第38条関係)
25.手数料の納付
26.土壌汚染対策基金(法第45条関係)
27.その他
1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査(法第3条関係)

(1)報告期限(法第3条第1項関係)
法第3条第5項の規定により法第3条第1項ただし書の確認を取り消された場合に係る土壌汚染状況調査の結果の報告期限は、(6)の通知を受けた日から120日以内とする。
(2)土壌汚染状況調査の結果の報告(法第3条第1項本文関係)
法第3条第1項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を提出して行うものとする。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
?使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日
?使用が廃止された有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質その他土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)において土壌の汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準(以下「濃度基準」という。)に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
?土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項
?土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
?土壌汚染状況調査に従事した者の監督をした技術管理者の氏名及び技術管理者証番号
(3)土壌汚染状況調査の方法(法第3条第1項本文関係)
法第3条第1項本文の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
?調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(現行規則第3条関係)以下のとおり改正する。
?調査試料採取等の対象とする特定有害物質の種類の確定
調査実施者は、?により把握した情報により、当該調査対象地において土壌の汚染状態が濃度基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類について、試料採取等の対象とするものとする。ただし、次のイ、ロ又はハの場合には、当該イ、
ロ又はハに定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質について、試料採取等の対象としないことができる。
イ ?の規定により都道府県知事から通知を受けた場合当該通知に係る特定有害物質の種類
ロ 法第4条第2項又は法第5条第1項の命令を受けて土壌汚染状況調査を行う場合これらの命令に係る書面に記載された特定有害物質の種類
ハ 申請に係る調査(法第14条第2項の申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合法第14条第1項の申請をしようとする土地の所有者等が当該申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類
?調査対象地において土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類の通知
都道府県知事は、調査実施者が法第3条第1項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、当該調査対象地において土壌の汚染状態が濃度基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して30日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
?試料採取等を行う区域の分類(現行規則第3条第2項関係)
調査実施者は、?により把握した情報により、調査対象地を特定有害物質の種類ごとに、?)汚染が存在するおそれがないと認められる土地、?)汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地、又は?)それ以外の土地に分類するものとする。
?試料採取等の実施(現行規則第5条関係)
土壌ガス調査に係る測定の対象とする特定有害物質の種類は、当該調査対象地において土壌の汚染状態が濃度基準に適合していないおそれがある第一種特定有害物質の種類及びその分解生成物とする。
土壌ガス調査を省略してボーリング調査を実施することができるものとする。土壌溶出量調査及び土壌含有量調査に係る試料採取深度及び混合方法(現行規則第5条第3項第1号及び第2号)を、次のとおり改正する。
イ 試料採取地点の表層の土壌(地表から深さ5センチメートル?までの土壌をいう。以下同じ。)及び深さ5センチメートル?から50センチメートル?までの土壌を採取すること。
ただし、汚染のおそれが生じた際の地表が、試料採取等を行う際の地表の下にあることが明らかである場合*4には、汚染のおそれが生じた際の地表を基準とした深さ50?センチメートルまでの土壌を採取すること。
また、配管が地下にある場合等汚染の発生源が地下にある場合は、当該汚染の発生源がある深度を基準とした深さ50cmセンチメートルまでの土壌を採取すること。
ロ イにより採取された表層の土壌と、深さ5センチメートル5?から50センチメートル?までの土壌とを、同じ重量混合すること。ただし、イただし書の規定により土壌を採取した場合にあっては、当該採取した土壌を混合すること。
?土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定(現行規則第7条関係)
ボーリング調査に係る試料採取等の方法を、次のとおり改正する。
当該地点において、表層の土壌、深さ50?センチメートルの土壌及び深さ1メートルmから10mメートルまでの1メートルごとの土壌(深さ10mメートル以内に帯水層の底面がある場合にあっては、当該底面より深い位置にあるものを除く。)の
採取を行うこと。
?試料採取等の省略(現行規則第10条関係)
調査実施者は、土壌汚染のおそれの把握、試料採取等の対象とする特定有害物質の種類の確定、試料採取等を行う区域の分類及び試料採取等を行わないことができるものとし、この場合においては、調査対象地の区域を、全特定有害物質の種類について土壌含有量及び第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなすものとする。
また、調査実施者は、?の規定により試料採取等の対象とする特定有害物質の種類の確定を行った結果、ある特定有害物質の種類について調査対象地の土壌の汚染状態が濃度基準に適合していないおそれがあると認めるときは、その後の区域の分類及び試料採取等を行わないことができるものとし、この場合においては、調査対象地の区域を、当該特定有害物質の種類について土壌含有量基準及び第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなすものとする。
さらに、調査実施者は、?の規定による区域の分類を行った結果、ある特定有害物質の種類について調査対象地の全部又は一部が??又は?の土地に分類されると認めるときは、その後の試料採取等を行わないことができるものとし、この場合に
おいては、調査対象地の区域(すべての区域が??の土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該特定有害物質の種類について土壌含有量基準及び第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなすものとする。
また、現行規則第10条の規定に基づき試料採取等を省略した場合においても、調査対象地の区域(現行規則第10条第2項に規定する単位区画の区域を除く。)を、当該特定有害物質の種類について土壌含有量基準及び第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなすものとする。
(4)都道府県知事の確認(法第3条第1項ただし書関係)
?確認の要件(現行規則第12条第2項関係)
鉱山に係る要件については、下記のとおり改正する。
鉱山保安法 第2条第2項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地であった土地若しくは同法第39条第1項の命令に基づき土壌汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされている鉱山の敷地であった土地であること。
?確認証の交付
知事は、法第3条第1項ただし書の確認をしたときは、当該確認を受けた土地の所有者等に対し確認証を交付するものとする。
確認証の交付を受けた土地の所有者等は、当該確認証の記載事項に変更を生じたときは、知事に届け出て、確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならないものとする。
また、当該確認証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、知事に確認証の再交付を申請することができるものとする。
(5)法第3条第1項ただし書の確認を受けた者が土地の利用の方法を変更しようとするときの届出(法第3条第4項関係)
法第3条第4項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所在地及び当該確認を受けた年月日
?利用の方法を変更しようとする土地の範囲
?当該変更後の土地の利用の方法
(6)確認の取消しの通知(法第3条第5項関係)
知事は、法第3条第5項の規定により法第3条第1項ただし書の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該土地の所有者等に通知するものとする。
2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条関係)
(1)届出義務の対象となる形質変更の規模(法第4条第1項関係)
法第4条第1項の環境省令で定める規模は、3,000平方メートル?とする。
(2)大規模な土地の形質の変更の届出(法第4条第1項関係)
法第4条第1項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?土地の形質の変更の場所
?土地の形質の変更の着手予定日
?土地の形質の変更を行おうとする範囲
?土地の形質の変更の対象となる土地の面積
届出を行う者が形質の変更を行う土地の所有者等でない場合には、工事請負契約書その他当該土地の所有者等が当該形質の変更を行うことに同意していることを証する書面を、当該届出書に添付するものとする。
(3)届出事項(法第4条第1項関係)
法第4条第1項の環境省令で定める事項は、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、土地の形質の変更を行おうとする範囲及び土地の形質の変更の対象となる土地の面積とする。
(4)届出の例外となる行為(法第4条第1項第1号関係)
法第4条第1項第1号の環境省令で定めるものは、次のいずれかに該当する行為とする。
?次のいずれにも該当しない行為
イ 土壌の敷地外への搬出を伴うこと。
ロ 土地の形質の変更に伴い敷地外への土壌の流出が生ずること。
ハ 土地の形質の変更を行う部分の深さが50センチメートル?以上であること。
?次に掲げる行為であって土壌の敷地外への搬出を伴わないもの
イ 農作業農業を営むために通常行われる行為
ロ 林業の用に供する作業路網の整備
?鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地であった土地において行われる形質の変更
(5)調査命令の対象となる土地の基準(法第4条第2項関係)
法第4条第2項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
?特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、漏洩し、又は地下に浸透した土地であること。
?特定有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
?特定有害物質が保管され、若しくは貯蔵されており、又はされていた土地(特定有害物質を含む液体が地下に浸透することを防止するための措置であって環境大臣が定める基準に適合するものが講じられていたと認められる土地を除く。)であること。
?土壌の特定有害物質による汚染状態が濃度基準に適合しないことが明らかである土地であること。
?その他?から?までと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認める土地であること。
(6)調査命令の手続(法第4条第2項関係)
法第4条第2項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
?調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類
?報告を行うべき期限
3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査(法第5条関係)
(1)調査命令の対象となる土地の基準(法第5条第1項、現行令第3条、現行規則第17条関係)
法第5条第1項の政令で定める基準は、現行令第3条に規定されているが、このうちのとおりとするが、現行令第3条第1号ロ及びハの「基準に適合しないおそれがある」の部分は、法第4条第2項の「汚染されているおそれがあるものとして環境省令
で定める基準に該当する」と整合するよう改正する。ことと解釈することとし、その旨を何らかの形で明確化する。
また、都道府県又は政令市が行う飲用井戸の調査(既存資料による飲用井戸の有無の確認や、回覧板等による飲用井戸の存在の申告依頼)の結果飲用井戸の存在が確認されず、かつ、上水道の飲用が可能である区域については、地下水の利用状況に係る環境省令で定める要件(現行規則第17条第1号から第3号まで)に該当しないものとみなす。
現行規則第17条第4号については、現行どおりとする。
さらに、鉱山に係る要件(現行令第3条第2号ロ)については、下記のとおり改正する。
鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地であった土地であること。
(2)命令手続(法第5条第1項、現行令第4条関係)
法第5条第1項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
?調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類
?報告を行うべき期限
4.要措置区域の指定等(法第6条関係)
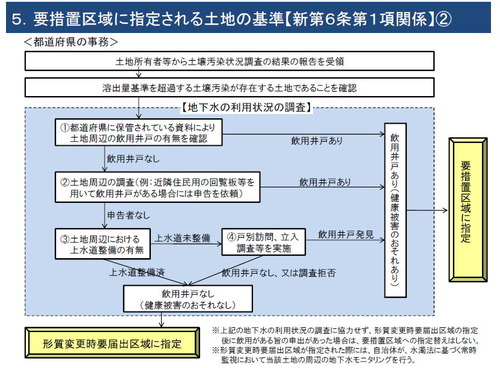
(1)指定の要件(法第6条第1項、現行令第5条、現行規則第17条及び第18条関係)
?法第6条第1項第1号の濃度基準については、現行規則第18条のとおりとする。
?法第6条第1項第2号の政令で定める基準(健康被害のおそれの基準)の規定ぶりについては、現行令第5条のとおりとするが、都道府県又は政令市が行う飲用井戸の調査(既存資料による飲用井戸の有無の確認や、回覧板等による飲用井戸の存在の申告依頼)の結果飲用井戸の存在が確認されず、かつ、上水道の飲用が可能である区域については、地下水の利用状況に係る環境省令で定める要件(現行規則第17条第1号から第3号まで)に該当しないものとみなす。現行規則第17条第4号については、現行どおりとする。
(2)指定の公示(法第6条第2項、現行規則第19条関係)
要措置区域の指定の公示の際の公示事項として、当該要措置区域において講ずべき
指示措置を追加するものとする。
(3)解除の公示(法第6条第5項関係)
要措置区域の解除の公示の際の公示事項として、当該要措置区域において講じられた指示措置等を追加するものとする。
5.汚染の除去等の措置等(法第7条関係)

(1)土地の所有者等への指示(法第7条第1項本文関係)
法第7条第1項本文の指示は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
?汚染の除去等の措置を講ずべき土地の範囲
?当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
?汚染の除去等の措置を講ずべき期限
(2)汚染原因者への指示(法第7条第1項ただし書関係)?汚染原因者
法第7条第1項ただし書に規定する指示は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合
は、この限りでない。(現行規則第21条を踏襲)
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6六条の2二第2二項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第2二条第2二項に規定する一般廃棄物の埋立処分
ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二12 条第1一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二12 条の2二第1一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第2二条第4四項に規定する産業廃棄物の埋立処分
ハ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10 十条第2二項第4四号に規定する基準に従ってする同法第3三条第6六号に規定する廃棄物の排出
?2二以上の汚染原因者に指示する場合
法第7条第1項ただし書に規定する指示は、2二以上の者に対して行う場合には、当該2二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度*6に応じて講ずべき汚染の除去等の措置の内容を定めて行うものとする。
(3)指示措置の種類
(1)?の当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置は、表1の左欄に掲げる土地の汚染の状況に応じ、それぞれ中欄に掲げる汚染の除去等の措置とする。
【表1】
略
(4)都道府県知事の指示の際に示さなければならない事項(法第7条第2項関係)
法第7条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
?汚染の除去等の措置を講ずべき土地の範囲
?汚染の除去等の措置を講ずべき期限
(5)指示措置と同等の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置(法第7条第3項関係)
法第7条第3項の環境省令で定める汚染の除去等の措置は、表1の左欄に掲げる土地の汚染の状況に応じ、それぞれ右欄に掲げる汚染の除去等の措置とする。
(6)命令手続(法第7条第4項関係)
法第7条第4項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
(7)指示措置等に関する技術的基準(法第7条第6項関係)
地下水の水質の測定、土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、土壌入換え、盛土、舗装及び立入禁止の実施の方法について、【表2】のとおり改正する(用語の整理等技術的修正は別途行う。)。
また、地下水汚染の拡大の防止の実施の方法について、?のとおり規定する。
【表2】
汚染の除去等の措置の種類汚染の除去等の措置の実施の方法
?地下水の水質の測定イ当該要措置区域において土壌汚染に起因する地下水
汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、
当初1は4四回以上、 2年目から10年目までは1一年に1一回以上、11 十一年目以降は2年に1回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。(現行規則どおり)
ロ イにより測定した結果を都道府県知事に報告すること。
?土壌汚染の除去1 汚染土壌の掘削による除去
(ニを削除)
2 原位置での浄化による除去
現行規則どおりとする。
?原位置封じ込めロ第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更するか、又は土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により汚染土壌から特定有害物質を除去して第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
チ ハの構造物により埋め戻された場所の内部囲まれた範囲に一以上の観測井を設け、トの確認がなされるま
での間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
?遮水工封じ込めロ第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更するか、又は土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により汚染土壌から特定有害物質を除去して第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
チ ハにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、トの確認がなされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
?原位置不溶化現行規則どおりとする。
?不溶化埋め戻し現行規則どおりとする。
?遮断工封じ込めリニにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、チの確認がなされるまでの間、雨水、地下水
その他の水の浸入がないことを確認すること。
?地下水汚染の拡大の防止1 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該要措置区域がある土地内の、地下水汚染の拡大を的確に防止することができると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。
ロ イにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を抽出し、又は分解除去しすることにより、当該地下水に含まれる特定有害物質を水濁法水質汚濁防止法又は下水道法の排水基準に適合させて、公共用水域又は下水道に排水すること。
ハ 当該要措置区域がある土地であって、地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲に、当該要措置区域を取り囲むように観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を測定し、地下水汚染が当該要措置区域がある土地外に拡大していないことを確認すること。
ただし、隣り合う観測井の間の距離は、30メートルmを超えてはならない。
ニ ハにより測定した結果を都道府県知事に報告すること。
2 透過性地下水反応壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該要措置区域がある土地内の、地下水汚染の拡大を的確に防止することができると認められる地点に透過性地下水反応壁を設置すること。
ロ 当該要措置区域がある土地であって、地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲に、当該要措置区域を取り囲むように観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を測定し、地下水汚染が当該要措置区域がある土地外に拡大していないことを確認すること。
ただし、隣り合う観測井の間の距離は、30メートルmを超えてはならない。
ハ ロにより測定した結果を都道府県知事に報告すること。
?土壌入換替え1 要措置区域外土壌入換替え
(ニを削除。)
2 要措置区域内土壌入換替え
現行規則どおりとする。
?盛土現行規則どおりとする。
*12 塩分濃度が一定以上であること。
*13 地下水の流動の状況等からみて当該土地のうち最も地下水が浅い位置にあると考えられる地点において、一定の深度まで観測用井戸を掘り、当該深度に一年間継続して地下水が存在しないことを確認する。この観測用井戸の設置のためのボーリングについては、形質の変更にあたらない(すなわち、禁止行為に該当しない)ことを通知で明確化する。
?舗装現行規則どおりとする。
?立入禁止現行規則どおりとする。

6.要措置区域内における土地の形質の変更の禁止(法第9条関係)
(1)要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為(法第9条第2号関係)
法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する行為とする。
?次のいずれにも該当しない行為
イ 指示措置等を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
ロ 土地の形質の変更を行う部分の面積の合計が10平方メートル?以上であり、かつ当該部分の深さが50センチメートル?以上(一定の深さまで帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして環境大臣が定める要件*12に該当するものを除く。ハ並びに7(1)?及び?において以下同じ。)が存在しないこと*13について、都道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより1メートルm浅い深さ以上)であること。
ハ 土地の形質の変更を行う部分の深さが3メートルm以上(一定の深さまで帯水層が存在しないことについて、都道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより1メートルm浅い深さ以上)であること。
? 指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更であって、当該変更に伴い当該要措置区域の土壌汚染の拡散がを生じさせないものとして環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの
? 地下水モニタリング(指示措置等の一工程としての地下水モニタリングを含む。)又は地下水汚染の拡大の防止が実施されている要措置区域内で行われる土地の形質の変更であって、汚染の拡散を生じさせないものとして環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの
(2)帯水層の深度に係る都道府県知事の確認
?確認の手続
(1)?ロ及びハの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならないものとする。
イ氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ要措置区域のある土地の所在地
ハ土地のうち最も地下水が浅い位置にあると考えられる地点及びその根拠
ニ観測用井戸の深度
ホ地下水の測定結果
?確認証の交付
知事は、(1)?ロ及びハの確認をしたときは、当該確認を受けた土地の所有者等に対し確認証を交付するものとする。
確認証の交付を受けた土地の所有者等は、当該確認証の記載事項に変更を生じたときは、知事に届け出て、確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならないものとする。また、当該確認証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、知事に確認証の再交付を申請することができるものとする。
?確認の取消し
知事は、(1)?ロ及びハの確認を受けた土地が、当該確認に係る深さまで帯水層が存在しない状態であると認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(3)指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更等に係る都道府県知事の確認?確認の手続
(1)?又は?の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならないものとする。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ 要措置区域のある土地の所在地
ハ 指示措置等及びそれと一体として行われる確認を受けようとする行為に係る設計図書、工事計画書及び工事工程表
?確認証の交付
知事は、(1)?又は?の確認をしたときは、当該確認を受けた土地の所有者等に対し確認証を交付するものとする。
確認証の交付を受けた土地の所有者等は、当該確認証の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事に届け出て、確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならないものとする。また、当該確認証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、
都道府県知事に確認証の再交付を申請することができるものとする。
7.形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令(法第12条関係)
(1)届出の適用除外となる行為(法第12条第1項第1号関係)
法第12条第1項第1号の環境省令で定めるものは、次のいずれにも該当しない行為とする。
?指示措置等を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
?土地の形質の変更を行う部分の面積の合計が10平方メートル?以上であり、かつ当該部分の深さが50センチメートル?以上(一定の深さまで帯水層が存在しないことについて、都道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより1メートル
m浅い深さ以上)であること。
?土地の形質の変更を行う部分の深さが3メートルm以上(一定の深さまで帯水層が存在しないことについて、都道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより1メートルm浅い深さ以上)であること。
(2)帯水層の深度に係る都道府県知事の確認(6(2)と同様。)
(3)計画変更命令の要件(法第12条第4項関係)
法第12条第4項の環境省令で定める基準については、現行規則第36条第1号から第3号までの要件は現行どおりとし、同条第4号の要件はを削除する。
8.指定の申請(法第14条関係)
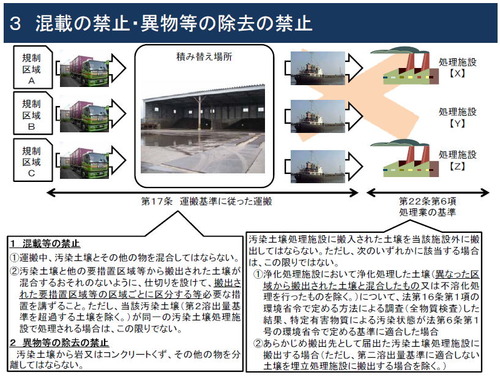

(1)申請手続?法第14条第1項の申請は、所定の様式第○により行うものとする。(様式省略)
?法第14条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ 申請に係る土地の所在地及び申請に係る土地の範囲
ハ 申請に係る調査において調査の対象とした特定有害物質の種類
ニ 申請に係る調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び年月日時、
当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量証明事業者の氏名又は名称その他の申請に係る調査の結果に関する事項
ホ 申請に係る調査を行った者の氏名又は名称
?法第14条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
イ 申請に係る土地の周辺の地図
ロ 申請に係る土地の範囲を表した図面
ハ 申請に係る調査の結果報告書
ニ 申請に係る土地の登記簿の謄本
ホ 申請に係る土地に申請に係る所有者等以外の所有者等がいる場合にあっては、当該所有者等全員の合意書
ヘ 申請者が申請に係る土地の管理者又は占有者である場合にあっては、その旨を証する書類
(2)身分証等
法第14条第4項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
9.台帳(法第15条関係)

(1)帳簿及び図面の区別
要措置区域に係る帳簿及び図面と、形質変更時要届出区域に係る帳簿及び図面は、区別して保管しなければならない。
(2)台帳の記載事項の追加
台帳の記載事項として、次の事項を追加するものとする。
?地歴調査又は試料採取調査を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された要措置区域又は形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び省略の理由
?地下水汚染の有無
?既に汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨
(3)消除
台帳の消除に係る規定(現行規則第20条第7項)を、下記のとおり改正する。
要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定が解除された場合には、知事は、当該区域に係る帳簿及び図面を台帳から消除しなければならない。*
*14 消除した情報は、第61 条第1項の規定に基づき収集される。
*15 現行規則第4条第1項ただし書及び同条第2項と同様、区分線の回転等は認める。
10.汚染土壌の搬出時の届出等(法第16条関係)
(1)搬出汚染土壌の調査方法(法第16条第1項関係)
法第16条第1項の環境省令で定める方法は、次のいずれかのとおりとする。
?要措置区域等外へ搬出する土壌を掘削する前に調査する方法
イ 土壌を掘削する土地の範囲を、起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線及びこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により区画する*15。
ロ イにより区画された土地全てについて、当該区画の中心におけるボーリングにより深さ1メートルmから土壌を掘削する深さまでの1メートルmごとの土壌を採取する。
ハ ロにより採取された土壌について、全ての特定有害物質に係る土壌溶出量及び第二種特定有害物質に係る土壌含有量を測定する。
?要措置区域等外へ搬出する土壌を掘削した後に調査する方法
イ 掘削した土壌を、100立方メートルm3以下ごとに区分する。
ロ イにより区分された土壌それぞれについて、当該土壌の任意の5地点から土壌を採取する。
ハ ロにより採取された5つの土壌のうち任意の1つについて、第一種特定有害物質に係る土壌溶出量を測定する。
ニ ロにより採取された5つの土壌を、同じ重量混合する。
ホ ニにより混合された土壌について、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌溶出量及び第二種特定有害物質に係る土壌含有量を測定する。
(2)都道府県知事の認定手続(法第16条第1項関係)
法第16条第1項の都道府県知事の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?当該要措置区域等の所在地
?土壌の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量証明事業者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
?調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
?調査に従事した者の監督をした技術管理者の氏名及び技術管理者証番号
(3)汚染土壌の搬出時の届出の手続(法第16条第1項関係)
法第16条第1項の届出は、同項第1号から第6号までに規定された事項及び(4)を記載することとした様式の届出書に必要事項を記載し、これに、次の書類及び図面を添付して届け出なければならないこととする。
?搬出しさせようとする汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)の図面
?汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類(汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合にあっては、当該汚染土壌の処理に関する計画)
?汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に係る汚染土壌処理業の許可証の写し
?汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下「自動車等」という。)及び保管設備の構造を記した書類
?当該搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票
?届出を行う都道府県知事の管轄する区域以外に所在する汚染土壌処理施設で処理又は積替えのために一時的に保管施設を使用する場合には、当該汚染土壌処理施設又は保管施設の所在地を管轄する都道府県知事が交付した確認証
(4)汚染土壌の搬出時の届出書の記載事項(法第16条第1項第7号関係)
法第16条第1項第7号の届出書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?汚染土壌の搬出を行う要措置区域等の所在地
?汚染土壌の搬出、運搬及び処理の完了予定日
?汚染土壌の運搬の用に供する自動車等及び保管設備の所有者の氏名又は名称及び連絡先
?搬出の際、当該運搬を容易にするため、当該汚染土壌がある要措置区域等と一筆の土地であって、当該要措置区域等と隣接する土地に設置された機器(汚染土壌及び汚染土壌に含有される特定有害物質又は水が漏洩又は飛散することが防止できる機器に限る。)の中で汚染土壌の含水比の調整を行う場合には、当該行為を行う旨並びに当該行為を行う機器の構造及び設置場所
(5)変更の届出(法第16条第2項関係)
(3)の届出に係る事項の変更の届出は、変更事項を記載した届出書の様式に必要
事項を記載し、これに、(3)に掲げる書類を添付して行わなければしなければならないこととする。
(6)非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした者の届出(法第16条第3項)
法第16条第3項の届出は、?に掲げる事項を記載した届出書の様式に必要事項を記載し、これに、?に掲げる書類及び図面を添付して行わなければ申請しなければならないこととする。
?記載事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ 汚染土壌の搬出を行った要措置区域等の所在地
ハ 搬出したさせた汚染土壌の体積
ニ 汚染土壌の搬出先
ホ 汚染土壌の搬出の着手日
へ 汚染土壌の搬出の完了日
ト 搬出したされた汚染土壌の処理及び処理するための運搬に関する計画
?添付書類
イ 搬出された汚染土壌の現状及び搬出した場所の状況を示す図面及び写真
ロ 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類(汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合にあっては、当該汚染土壌の処理に関する計画)
ハ 汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に係る汚染土壌処理業の許可証の写し
ニ 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等及び保管設備の構造を記した書類
ホ 当該搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票
ヘ 届出を行う都道府県知事の管轄する区域以外に所在する汚染土壌処理施設で処理又は積替えのために一時的に保管施設を使用する場合には、当該汚染土壌処理施設又は保管施設の所在地を管轄する都道府県知事が交付した確認証
11.運搬に関する基準(法第17条関係)
汚染土壌の運搬に関する基準は、次のとおりとする。
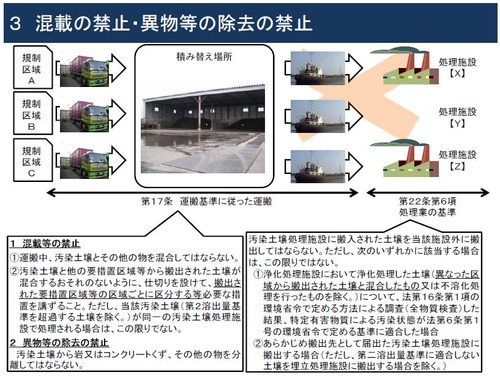
(1)法第16条第1項又は第2項の規定により、届け出た内容に従ってた運搬すること。
?法第16条第1項又は第2項の規定により、提出した届出書に記載された場所(試験研究のために運搬する場合には、当該試験研究を行う施設であって、当該汚染土壌又は特定有害物質の拡散防止措置が講じられている施設又は汚染土壌処理施設)以外の場所で汚染土壌を卸(積替えを含む。)してはならないこと(積替えのために卸すことも禁止)。
?法第16条第1項又は第2項の規定により、提出した届出書に記載された者(試験研究のため運搬する場合には、当該試験研究を行う者又は汚染土壌処理業者)以外に汚染土壌を引き渡してはならないこと。
(2)管理票に関する遵守事項?管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、当該管理票に運搬の用に供した自動車等の識別番号及びその運転者の氏名を記載しなければならない。
?管理票の交付又は回付を受けた者は、汚染土壌を引き渡すときは、交付又は回付を受けた管理票に汚染土壌を引き渡した日時を記載し、汚染土壌を引き渡した相手に対して汚染土壌を引き渡すとともに、管理票を回付しなければならない。
?管理票の交付又は回付を受けた者は、汚染土壌を運搬するときは、当該運搬を行う自動車等に管理票を搭載しなければならない。
?管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票の提示を求められた場合には、正当な理由がない限りこれに応じなければならない。
(3)運搬に伴う汚染の拡散防止措置等
?汚染土壌の転落、飛散、及び流失並びに特定有害物質の揮散、流出、及び地下浸透を防ぐため必要な措置を講ずること。
?運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
?運搬車及び運搬容器は、汚染土壌の転落、飛散、及び流失並びに特定有害物質の揮散及び流出のおそれのないものであること。
?運搬する汚染土壌が転落し、飛散し、若しくは流失し、又は当該運搬の際に生じた汚水若しくはガスが飛散し、流出し、地下に浸透し、又は揮散したときは、直ちに、当該運搬を中止し、自動車等又は保管設備の点検を行うとともに、転落した汚染土壌の回収その他環境の保全に必要な措置を講じなければならない。
(4)表示義務
汚染土壌を運搬するときは、当該運搬の用に供する自動車等の両側面に汚染土壌を運搬している旨を見やすいように表示すること。
(5)混載等の禁止
?運搬中、汚染土壌とその他の物を混合してはならない。
?汚染土壌と他の要措置区域等から搬出された土壌が混合するおそれのないように、仕切りを設けて、搬出された要措置区域等の区域ごとに区分する等必要な措置を講ずること。ただし、当該汚染土壌が同一の汚染土壌処理施設で処理される場合(混載された汚染土壌が当該処理を行う汚染土壌処理施設の事業計画に適合する場合に限る。)は、この限りでない。
?汚染土壌から岩又はコンクリートくずその他の物を分離してはならない。
(6)汚染土壌の積替え及び保管?汚染土壌の積替えを行う場合を除き、汚染土壌を保管してはならない。
?汚染土壌の積替えのため、一時的に汚染土壌を保管する場合には、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ保管する汚染土壌、特定有害物質、又は保管の際に生じた汚水(雨水によるものを含む。)の流失を防止するため、周囲に囲い(積替え及び保管する汚染土壌の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ見やすい箇所に次に掲げるところによる掲示板が設けられていること。
(イ)掲示板の大きさが、縦及び横それぞれ六十60 センチメートル以上であること。
(ロ)汚染土壌の保管のための場所である旨及び保管の場所の管理者の氏名又は名称並びに連絡先が表示されていること。
ハ 汚染土壌を保管する施設の壁面及び床面は、特定有害物質及び特定有害物質を含有する液体が浸透しない構造を有していること。
ニ 汚染土壌の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共用水域の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、当該汚水を水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準に適合するように処理してから排水すること。
?汚染土壌及び特定有害物質の飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
?屋内において汚染土壌を保管し、かつ、排気を行う場合にあっては、当該排出されるガスによる人の健康被害を防止するために必要な設備を設けるとともに、人の健康被害を生じさせないように処理してから排気すること。
(7)汚染土壌の飛散を防止するため、汚染土壌の荷卸し下ろしその他移動を行うときは、
次の各号のいずれかに該当すること。
?粉じんが飛散しにくい構造の施設設備内において行うこと。
?散水施設によって散水が行われていること。((6)?イ、ハ及びニの措置が講じられている場所に限る。)
?防じんカバーで覆われていること。
?薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
?フード及び集じん機が設置されていること。
?前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(8)汚染土壌を搬出する者から汚染土壌の運搬を受託した者は、
当該汚染土壌の運搬を他人に委託してはならない。
(9)汚染土壌を搬出する者から汚染土壌の運搬を受託した者は、
当該汚染土壌の運搬を委託した者に対して、他人の自動車等又は保管設備を当該汚染土壌の運搬の用に供する場合は、当該運搬の用に供する自動車等又は保管設備の管理者の氏名又は名称を明らかにしなければならない。
(10)汚染土壌の当該汚染土壌の処理が行われる施設への運搬は、
措置実施区域等から搬出された日から90日以内に行われなければならない。
12.管理票(法第20条関係)
(1)法第20条第1項の管理票を交付するときは、
下記の方法により行わ交付しなければならないこととする。
?管理票の様式は、別添の通り所定の様式とする。
?法第20条第1項の管理票を交付するときは、法第16条の第1項の届出のときに都道府県知事に提出した管理票を交付しなければならない。
?複数の者に運搬を委託する場合には、運搬の委託を行う者に対して汚染土壌の引き渡しとともに、管理票を回付することをも委託しなければならない。
?管理票は、運搬の用に供する自動車等ごとに交付しなければならない。
(2)法第20条第1項の管理票に記載すべき事項は、
次の事項とする。
?搬出者の氏名(法人の場合には、担当者の氏名を並記)、住所及び連絡先
?搬出する土壌の重量
?管理票の交付年月日及び交付番号
?要措置区域等の所在地
?積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の名称及び所在地
?処理の委託を行った場合には、当該処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び所在地
(3)法第20条第3項の汚染土壌の運搬を受託した者が管理票に記載すべき事項は、
受託した汚染土壌の運搬の用に供した自動車等の番号、当該自動車等の運転手の氏名及び汚染土壌を引き渡した日時とする。
(4)法第20条第3項の汚染土壌の運搬を受託した者が当該管理票を交付した者に対して当該管理票の写しを送付すべき期間は、
当該管理票に係る汚染土壌を受領した日から30日以内とする。
(5)法第20条第4項の汚染土壌の処理を受託した者が管理票に記載すべき事項は、
受託した汚染土壌を受領した者の氏名並びに処理方法及び処理年月日とする。
(6)法第20条第4項の汚染土壌の処理を受託した者が当該管理票を交付した者に対して当該管理票の写しを送付すべき期間は、
当該管理票に係る汚染土壌を受領した日から30日以内(汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設が休止していた期間を除く。)とする。
(7)法第20条第5項の管理票交付者が送付を受けた管理票の写しを保存する期間は、
5年間とする。
(8)法第20条第6項の管理票交付者が交付した管理票の写しの送付を受けない期間は、90日間とする。
(9)法第20条第7項の運搬受託者が管理票の写しを保存する期間は、
5年間とする。
(10)法第20条第8項の処理受託者が管理票の写しを保存する期間は、
5年間とする。
13.汚染土壌処理業の許可の申請に関する規定の新設(法第22条関係)
(1)汚染土壌処理業の許可の申請書の記載事項(法第22条第2項関係)
法第22条第2項第5号の許可の申請書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
?法第22条第2項第3号の汚染土壌処理施設の種類については、次のいずれかを記載すること。
イ 浄化処理施設
加熱、洗浄、化学処理、生物処理、特定有害物質の抽出その他の方法により汚染土壌に含まれる特定有害物質を除去又は汚染土壌を溶融し固形化若しくは汚染土壌に薬剤を注入混合することにより特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更するすることを抑制する処理(以下「不溶化処理」)を行う施設
ロ セメント等製造施設
汚染土壌をセメント等製品の原材料として利用し、セメント等を製造する施設
ハ 埋立処理施設
汚染土壌を埋立処分する施設
ニ 分別等処理施設
イからハまでの処理を行うために、汚染土壌に混入しているコンクリートくず、岩等の除去、汚染土壌の含水比の調整を行う施設
?土壌汚染土壌処理施設を設置する敷地の面積
?廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処分業若しくは特別管理産業廃棄物処分業、又は産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
?汚染土壌を保管する設備を設ける場合には、保管設備の容量
?当該汚染土壌処理施設で処理した土壌を搬出する場合の搬出先となる汚染土壌処理施設
(2)汚染土壌処理業の許可の申請手続(法第22条第1項関係)
法第22条第1項の許可の申請は、同条第2項に規定された事項及び(1)の事項を記載できる様式の申請書に必要事項を記載し、これに、次の書類及び図面を添付して行わ申請しなければらならないこととする。
?事業計画等について
イ 事業計画(施設の保守管理を含む。)の概要を記載した書類
ロ 汚染土壌の処理工程図
ハ 浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生するガスを大気中に排出する場合には、14(4)?に規定する排出されるガスの測定方法を記した書類
ニ 汚染土壌処理施設の周辺の地下水の水質の汚濁の状況の把握方法を記した書類
ホ セメント等製造施設を使用して汚染土壌を処理する場合には、製造されるセメント等の品質の管理の方法を記載した書類
ヘ 汚染土壌の飛散及び粉じんの管理方法を記載した書類
ト 排出水の汚染状態の測定方法を記載した書類
チ 分別等処理施設又は浄化処理施設については、当該施設における処理後の土壌の処理方法を記載した書類及び再処理を行う汚染土壌処理施設の設置者の引き受け承諾書
?人的能力に関するもの
イ 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
ロ 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ホ 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ヘ 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ト 申請者が法第22条第3項第2号イ又はロに該当しない者であることを誓約する書面
チ 申請者が法人である場合には、法第22条第3項第2号ハに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
リ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100 百分の5五以上の株式を有する株主又は出資の額の100 百分の5五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人
に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヌ 法第27 条に規定する許可の取消し等の場合の措置に要する費用の見積額を記した書面及び当該見積額の支払いが可能であることを示す書面
?施設の構造等に関するもの
イ 汚染土壌処理施設(汚染土壌を保管する設備を含む。以下同じ。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図
ロ 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
ハ 申請者がイに掲げる施設を設置する土地の所有者でない場合には、法第27条に規定する許可の取消し等の場合の措置として行う土壌汚染の調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しない場合には、法第14 条に基づく申請を行うことについての当該土地の所有者全員の合意書
ニ 公有水面埋立法第2二条第1一項の免許又は同法第42 四十二条第1一項の承認を受けて埋立てをする場合には、当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
ホ 汚水等の処理の方法及び排出水に係る用水及び排出される水の系統を示した書類
ヘ 浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生するガスの排出方法及び処理方法、並びに当該処理に係る操業の系統概要を示した書類
ト 排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所を示した図面
(3)汚染土壌処理施設の能力(法第22条第3項第1号関係)
汚染土壌の処理を適確に、かつ、継続して行うに足りる汚染土壌処理施設の能力の基準は、次のとおりとする。
?汚染土壌処理施設から排出される水を公共用水域又は下水道に排出する場合には、
排出される水の汚染状態が当該汚染土壌処理施設の排水口において、水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準に適合する排出水を排出するために必要な排水処理施設及び当該排出水の汚染状態を測定する施設が設けられていること。
?浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生するガスを大気中に排出する場合には、
当該ガスが当該施設の排出口において、大気汚染防止法の規定及び14(4)?に適合するガスを排出するために必要な構造並びに大気汚染防止法において測定が義務付けられているガス及び14(4)?に規定する排出されるガスを測定することができる構造を有していること。
?浄化処理施設、セメント等製造施設、分別等処理施設又は埋立処理施設(保管設備を含む。)が設置される床又は地盤面は、特定有害物質及び特定有害物質が溶出又は混入した液体が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
?汚染土壌の埋立の用に供する設備の壁面及び床面は、特定有害物質及び特定有害物質が溶出又は混入した液体が浸透しない構造を有していること。
?受け入れた汚染土壌並びに特定有害物質及び特定有害物質が溶出又は混入した液体が当該施設外への流出失を防止するための堰堤その他の設備を有していること。
?地下水の水質の汚濁の状況を監視できる施設を有すること。ただし、地下浸透の防止措置として環境大臣が定める措置を講じていると都道府県知事が確認した場合を除く。
?著しい騒音、振動又は悪臭を発生し、周辺の環境を損なわないものであること。
?浄化処理施設を用いて行う場合には、当該施設において受け入れた汚染土壌の処理を行ったとき、法第16条第1項に規定する方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合することができる施設を有すること。
(4)汚染土壌処理業の申請者の能力(法第22条第3項第1号関係)
汚染土壌の処理を適確に、かつ、継続して行うに足りる汚染土壌処理業の申請者の能力の基準は、次のとおりとする。(※未成年者、成年被後見人及び被保佐人は、下記の能力を有さないと解する。)
?汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。(※事業計画に管理者がいない場合、施設の定期点検がない場合には、能力がないものと解する。)
?汚染土壌の処理を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
?法第27条に規定する許可の取り消し等の場合の措置義務を行うに足りる経理的基礎を有すること。(※ 保管設備の容量に相当する汚染土壌を処理する場合に必要となる費用及び当該施設の敷地について土壌汚染状況調査を実施する場合に必要となる費用、2年間以上の地下水にモニタリングを行うために必要となる費用の合計額以上の財産を有していること。)
14.汚染土壌処理業による汚染土壌の処理の基準(法第22条第6項関係)
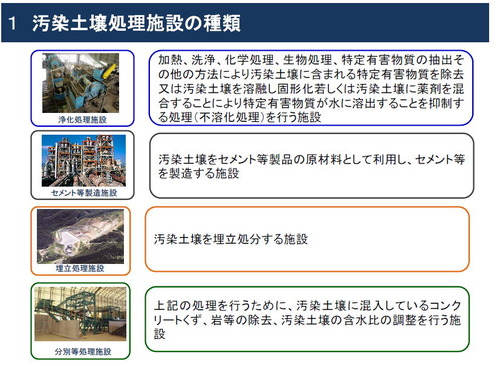
汚染土壌処理業者が行う汚染土壌の処理の基準は、次のとおりとする。
(1)提出した事業計画に従った汚染土壌の処理を行わなければならない。
(2)汚染土壌の処理に関し、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、騒音規制法、
振動規制法、悪臭防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律その他生活環境の保全に関する法令及び条例を遵守しなければならない。

(3)汚染土壌の処理に伴って発生する汚水の適正な処理及び地下浸透防止
?汚染土壌処理施設から排出される水を公共用水域又は下水道に排出する場合には排出水の汚染状態が当該汚染土壌処理施設の排水口において、水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
?汚染土壌処理施設から排出される水を公共用水域又は下水道に排出する場合には、水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準に定められた事項について、同法に基づき環境大臣が定める方法により、毎月、当該排出水の汚染状態を測定しなければならない。
?汚染土壌処理施設から排出される汚水又は廃液を地下に浸透させてはならない。
?汚染土壌処理施設の地下水の下流域の地下水の水質を3月(※6月との意見もあり。)ごとに測定しなければならない。ただし、測定した地下水の汚染状態が、地下水の水質汚濁に係る環境基準に適合していることが1年間確認された場合にあっては1年ごとに測定すれば足りることとする。埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって、地下浸透の防止措置として環境大臣が定める措置を講じていると都道府県知事が確認した場合を除く。
??の規定にかかわらず、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって、地下浸透の防止措置として環境大臣が定める措置を講じていると都道府県知事が確認した場合は、測定することを要しない。
(4)汚染土壌及び汚染土壌の処理に伴って発生するガスの適正な処理
?浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生するガスを大気中に排出する場合には、当該ガスが当該施設の排出口において、大気汚染防止法第2条第1項第3号に規定する有害物質について、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス1一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合しないガスを排出してはならない。
イ カドミウム及びその化合物一・〇1.0 ミリグラム
ロ 塩素30 三〇ミリグラム
ハ 塩化水素七〇〇700 ミリグラム
ニ 弗素、弗化水素及び弗化珪素10 一〇ミリグラム
ホ 鉛及びその化合物20 二〇ミリグラム
ヘ 窒素酸化物二五〇250 立方センチメートル(ただし、排出ガス量が10万立方メートル未満の場合には、三五〇350 立方センチメートル)
※大気汚染防止法の附則において経過措置がおかれている場合は、その例による。
?浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生する気体を大気中に排出する場合には、排出口から大気中に排出される?に掲げる有害物質及び次に掲げる物質の濃度を23月ごと(※1年に1回以上との意見もあり。)(?及び次に掲げる物質?に規定する基準に適合していることが確認されたを除去する設備を有している場合等には、1年ごと)に、次に掲げる物質の濃度を1年ごとに、それぞれ測定しなければならない。
イ 一・二1,2 ―ジクロロエタン
ロ ジクロロメタン
ハ テトラクロロエチレン
ニ トリクロロエチレン
ホ ベンゼン
ヘ 水銀
ト ポリ塩化ビフェニル
チ ダイオキシン類
?法第6条第1項第1号に規定する環境省令で定める基準のうち第1一種特定有害物質の基準に適合しない土壌を処理する場合は、当該汚染土壌に含まれる第1一種特定有害物質の大気への揮発を防止するために必要な措置を講じなければならない。
?汚染土壌の保管、処理、又は荷卸し下ろしその他土壌の移動を行うときは、汚染土壌の飛散を防止するため、次の各号のいずれかに該当すること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において行うこと。
ロ 散水施設によって散水が行われていること(11(6)?イ、ハ及びニの措置が講じられている場所に限る。)。
ハ 防じんカバーで覆われていること。
ニ 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
ホ フード及び集じん機が設置されていること。
ヘ 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(5)搬入された汚染土壌等の管理
?汚染土壌処理施設に搬入された土壌を当該施設外に搬出してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
イ 浄化処理施設において浄化処理した土壌(異なった区域から搬出された土壌と混合したもの又は不溶化処理を行ったものを除く。)について、法第16条第1項の環境省令で定める方法による調査(全特定有害物質検査)をした結果、特定有害物質による汚染状態が法第6条第1号の環境省令で定める基準に適合したものを搬出する場合
ロ あらかじめ搬出先として届け出た汚染土壌処理施設に搬出する場合(ただし、第二溶出量基準に適合しない土壌を埋立処理施設に搬出する場合を除く。)
?処理した土壌を他の汚染土壌処理施設において再処理するため、その土壌の運搬を他人に委託する場合には、当該委託に係る土壌の引き渡しと同時に当該土壌の運搬を受託した者に対し、12に準じて管理票を交付しなければならない。
?分別等処理施設又は浄化処理施設から搬出された土壌の引渡しを受けた汚染土壌処理業者は、当該汚染土壌とともに12に準じて管理票を受領し、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、その写しを搬出した施設の汚染土壌処理業者に対して送付しなければならない。
? ?の管理票の写しを受領した汚染土壌処理業者は、その写しを当該汚染土壌の搬出を行った者に送付しなければならない。
?汚染土壌処理施設に搬入された土壌から分離した物は、廃棄物処理法その他の法令に従い処理(廃棄物は、廃棄物処理法に基づいた処理)しなければならない。
ただし、汚泥については、土壌として取り扱わなければならない。
?セメント等製造施設を使用して汚染土壌を処理する場合には、13(2)?に記載された方法により、セメント等の品質の管理をしなければならない。
?セメント等製造施設で製造された製品は、当該製品としての品質基準を遵守しなければならない。
?引渡しを受けた汚染土壌を13(2)?の規定に基づき提出した書類に記載された保管設備以外で保管してはならない。
?第二2溶出量基準(海面埋立地にあっては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第1条第2項及び第3項の基準第10条第2項第4号に規定する排出方法に関する基準とする。))を超過した土壌を埋立処理施設に搬入してはならない。
?分別等処理施設において、第二2溶出量基準を超過する汚染土壌を処理する場合には、他の区域から搬出された土壌と混合してはならない。
(6)汚染土壌処理業者は、
汚染土壌処理施設の見やすい場所に許可番号、許可を受けた者の氏名又は名称、汚染土壌処理施設の設置場所、汚染土壌処理施設の種類及び、処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(種類及び含有量基準超過、溶出量基準超過又は第2溶出量基準超過の別)を表示しなければならない。
(7)当該汚染土壌処理施設において 処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくはガスが飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、当該施設の操業を停止し、施設の点検を行うとともに、飛散等した汚染土壌等の回収その他環境の保全に必要な措置を講じなければならない。
15.汚染土壌処理業による汚染土壌の処理に関する記録及び閲覧(法第22条第8項関係)
(1)法第22条第8項に規定する汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理に関する記録の方法は、(2)の事項を記載することのできる様式に記録し、その記録を5年間保存することものとする。
(2)法第22条第8項に規定する汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理に関しする記録すべき事項は、
次の事項とする。
?受け入れた土壌の量及び汚染の状況、受け入れ年月日、処理を委託した者の氏名、処分した日(※管理票により保存することも可。)
?公共用水域又は下水道に排出した排出水の汚染状況を測定した日時及びその結果
?汚染土壌処理施設の地下水の水質の汚濁の状況を測定した日時及びその結果
?大気汚染防止法において測定が義務付けられているガス及び14(4)?に規定する排出されるガスを測定した日時及びその結果
?14(5)?イの規定に基づき、法第16条第1項の環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が法第6条第1号の環境省令で定める基準に適合した土壌を搬出する場合には、当該土壌が要措置区域等から搬出され、処理が行われるまでの経緯、14(5)?イの規定に基づき実施した調査の実施日時、実施者、実施方法及び調査の結果、並びに搬出日時、搬出先及び搬出量
?汚染土壌処理施設から搬出した物(?の土壌を除く。)の搬出日時、搬出先及び搬出量(土壌を搬出した場合には、当該土壌を搬出する際に交付した管理票及び搬出先となった汚染土壌処理施設から送付された管理票)
16.汚染土壌処理業による変更の許可等(法第23条関係)
(1)汚染土壌処理業の変更の許可の申請手続(法第23条第1項)
法第23条第1項の変更の許可の申請は、申請者の氏名及び住所、汚染土壌処理業の許可を受けた者の氏名(法人の場合は、法人名)及び許可番号、変更すべき事項を記載した申請書に、変更事項に係る法第22条第2項の規定に基づき都道府県知事に提出した書類又は図面を添付して行わ申請しなければならないこととする。
(2)許可を要しない汚染土壌処理施設の軽微な変更(法第23条第1項)
法第22条第2項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第23条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。)に係る変更であってあつて、当該変更によってよつて当該処理能力が10 十パーセント未満減少されるに至るもの
(3)届出を要する汚染土壌処理業の変更の手続(法第23条第3項)
法第23条第3項の変更の届出は、申請者の氏名又は名称及び住所、汚染土壌処理業の許可を受けた者の氏名又は名称(法人の場合は、法人名)及び許可番号、変更すべき事項を記載した届出書に、変更事項に係る法第22条第2項の規定に基づき都道府県知事に提出した書類又は図面を添付して行わなければ申請しなければならないこととする。
(4)変更の届出を要する事項
法第22条第2項第5号に規定する事項又は法第27条に規定する許可の取消し等の場合の措置義務を行うに足りる経理的基礎に変更があったときは、都道府県知事に届け出なければならないこととする。
(5)汚染土壌処理業の休止等の手続(法第23条第4項)
法第23条第4項の休止等の届出は、申請者の氏名又は名称及び住所、汚染土壌処理業の許可を受けた者の氏名又は名称及び許可番号、変更すべき事項、休止又は廃止の理由、休止、廃止又は再開の予定日、保管中の汚染土壌がある場合には、その処理方法を記載した届出書を提出しなければならないこととする。
17.許可の取消し等の場合の措置義務(法第27条第1項関係)
法第27条第1項に規定する汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は許可を取り消された汚染土壌処理業者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
(1)処理の事業を廃止し、又は許可を取り消されたとき、
現に汚染土壌が汚染土壌処理施設内に残存している場合は、他の汚染土壌処理業者に処理を委託すること。
(2)地下水の汚染状況を測定し、地下水汚染が生じていない状況が2二年間継続することを確認すること。ただし、要措置区域等に指定された場合又は地下水の汚染状況を測定した結果、地下水の汚染が無いことが確認され、かつ、(4)の調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合していることが判明した場合は、地下水の汚染状況の測定を中止することができる。
(3)埋立処理施設については、
汚染土壌を埋め立てた場所を遮水シート及び厚さ50センチメートル以上の土(廃棄物処理施設の許可を得て、廃棄物処理を行っている施設において、排水処理施設が稼働している場合には、厚さ50 センチメートル以上の土)、厚さ10 センチメートル以上のコンクリート又は厚さが3センチメートル以上のアスファルトその他当該汚染土壌を埋め立てた場所への水の浸透を防
止することができるものにより覆い、この覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
(4)土壌汚染の調査を実施し、
その結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認める場合には、法第14条の申請を行うために必要な措置及び当該申請を行うこと。
(5)汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は許可を取り消された日から30日以内に
前各号の措置を行い、その結果を都道府県知事に報告すること。
18.許可証の交付等(法第28条関係)
知事は、汚染土壌処理業の許可をしたときは、汚染土壌処理業者に対し、許可番号、許可を受けた者の氏名又は名称、汚染土壌処理施設の設置場所、汚染土壌処理施設の種類及び、処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態を記載した許
可証を交付することとし、許可を受けた者の申請に基づき、その記載事項に変更が生じた場合には、その書換えを、許可を受けた者が許可証を毀損又は忘失した場合には、再交付をそれぞれ行うこととする。
【参考事項】要措置区域等から掘削された汚泥については、汚染土壌として取り扱うこととする。
19.指定調査機関の指定(法第29条関係)

(1)指定の申請
指定を受けようとする者は、所定の様式による申請書を環境大臣に提出することとし、申請書には、添付書類を添付することとする。
○申請書記載事項
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・土壌汚染状況調査等を行おうとする事業所の名称及び所在地
・土壌汚染状況調査等を行おうとする都道府県
○添付書類
・申請者が法第30条各号の規定に該当しないことを説明した書類(誓約書)
・定款又は寄付行為及び登記事項証明書
・申請の日に属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書
・規則第2条第1項第2号に規定する土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していることを証する書類
・技術管理者として設置される者の氏名及び技術管理者証番号を示した書類
・事業所ごとの技術管理者の設置状況を示した書類
・申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴、法人の種類に応じた構成員の氏名並びに構成員の構成割合
・新法第31条第2号及び第3号に適合することを説明した書類
(2)指定証の交付
環境大臣は、法第3条第1項の指定をしたときは、所定の様式による指定証を交付する。
○指定証の記載事項
・指定された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・指定年月日
・指定番号
・指定の有効期限
(3)指定証の書換え、再交付及び返納
?指定調査機関は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に指定証を添えて、環境大臣に提出し、その書換えを受けることとする。
?指定調査機関は、指定証を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に指定証の再交付を申請することができることとする。
?指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したとき、又は指定を取り消されたときは、遅滞なく、指定証を環境大臣に返納することとする。
20.指定の基準(法第31条関係)
法第31条第1号の環境省令で定める基準であって、技術的能力に係るものは、次のいずれにも該当することとする。
・技術管理者証の交付を受けた者を置いていること。
・前号に掲げる者を土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に当たらせることとしていること。
・前号の監督の業務を行うことにより土壌汚染状況調査等が適確かつ円滑に遂行されるよう、第1号に掲げる者が適切に配置されていること。
21.技術管理者(法第33条関係)
(1)技術管理者の基準
法第33条の環境省令で定める基準は、次のいずれにも該当するものであることとする。
?技術管理者試験に合格したこと。
?次のいずれかに該当すること。
イ 土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者
ロ 地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
ハ 土壌の汚染の状況の調査に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
?次のいずれにも該当しないこと。
イ 法又法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 法第42条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(2)技術管理者試験?試験の施行及び公告
環境大臣は、技術管理者試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、公示することとする。
※試験は、地方環境事務所の管轄区域ごとに会場を設け、年1回、一斉に行うこととし、第1回試験は、平成22年度中に実施することとする。
?試験の内容
土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査等の業務を「適確かつ円滑に遂行する」ための能力として、法の正確な理解や法に基づく調査方法についての知識の有無を問うものに加え、地質学や化学に対する理解や、汚染をより確実に発見するた
めに必要な現場経験から培われる知識の有無を問うものとする。
その他、環境問題全般に関する基礎知識も併せて確認することとする。
?受験の申請
技術管理者試験を受けようとする者は、所定の様式による受験申請書に写真を添えて、これを環境大臣に提出することとする。
○申請書記載事項
・氏名、生年月日
・住所
○添付書類
・写真
?合格証書の交付、再交付及び返納
イ 環境大臣は、技術管理者試験に合格した者に所定の様式の合格証書を交付することとする。
ロ 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができることとする。
ハ 技術管理者試験に関して不正の行為により、試験を無効とされた者は、合格証書を直ちに環境大臣に返納しなければならない。
(3)技術管理者証
?技術管理者証の交付
イ 技術管理者証は、法第33 33条の環境省令で定める基準に適合する者に対し、環境大臣が交付する。ただし、技術管理者証の交付の申請は、申請者が技術管理者試験を受けた日から3年以内に行わなければならないこととする。
ロ 技術管理者証の有効期間は、5年とする。
ハ 技術管理者証の様式は、所定の様式とする。
ニ 技術管理者証の交付を受けようとする者は、所定の様式による申請書を環境大臣に提出することとし、申請書には、添付書類を添付することとする。
○申請書記載事項
・氏名、住所及び本籍
・合格証書番号
○添付書類
・戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面
・技術管理者試験の合格証書
・(1)?イ、ロ又はハのいずれかに該当することを証する書類
・(1)?イ及びロのいずれにも該当しないことを説明した書類(誓約書)
?技術管理者証の書換え、再交付及び返納
イ技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に技術管理者証を添えて、環境大臣に提出し、その書換えを受けることとする。
ロ 技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができることとする。
ハ 技術管理者証の交付を受けている者が、土壌汚染状況調査等に関し不正の行為を行ったと認めるとき、又は技術管理者証の有効期限に至ったときは、5日以内に、当該技術管理者証を環境大臣に返納しなければならないこととする。
ニ 技術管理者証の交付を受けている者が死亡したときは、その届出義務者は、1月以内に、環境大臣に当該技術管理者証を返納しなければならないこととする。
?技術管理者証の更新
イ 技術管理者証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該技術管理者証の有効期間が満了する日までの間に、講習を受け、所定の様式による申請書に当該講習の受講を証する書類を添えて、これを環境大臣に提出することとする。
ロ 技術管理者証の更新は、更新申請者が現に有する技術管理者証と引換えに新たな技術管理者証を交付して行うものとする。
(4)経過措置
旧法における土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条第2項各号のいずれかに該当する者は、第3回技術管理者試験の合格者が決定されるまでの間、(1)の技術管理者の基準のうち?を適用しないこととし、同基準の?を満たすことにより、環境大臣に対し、技術管理者証の交付を申請することができることとする。
なお、当該交付の申請を行おうとする者は、改正省令の施行前においても、(3)?の規定の例により、その申請を行うことができることとする。
22.変更の届出(法第35条関係)
法第35条の届出は、所定の様式による届出書を提出して行うものとする。
○届出義務の対象となる事項
・事業所の名称又は所在地
・指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・技術管理者として設置される者の氏名及び技術管理者証番号
・事業所ごとの技術管理者の設置状況
・土壌汚染状況調査等を行おうとする都道府県
・法人である場合は、役員の氏名、法人の種類に応じた構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成員の構成割合
23.業務規程の届出(法第37条関係)

法第37条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
○業務規程記載事項
・土壌汚染状況調査等を行う事業所の所在地
・土壌汚染状況調査等の結果の通知及び保存に関する事項
・技術管理者の配置に関する事項
・土壌汚染状況調査等を行おうとする都道府県
・法第31条第2号の基準(役員等の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼさないこと)に適合するために遵守すべき事項
・法第31条第3号の基準(調査が不公正にならないための実施体制に関すること)に適合するために遵守すべき事項
・業務実施手順に係る事項
・品質管理のための方針及び組織に係る事項
・人材育成に係る事項

24.帳簿の備付け等(法第38条関係)
(1)帳簿の記載事項
法第38条の土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
・土壌汚染状況調査等の業務の発注者の氏名又は名称及び住所
・土壌汚染状況調査等の方法、結果及び報告期日
・土壌汚染状況調査等について監督を行った技術管理者の氏名及び技術管理者証番号
・技術管理者の監督の状況の記録
(2)帳簿の保存期間
法第38条に規定する帳簿は、当該調査の結果を都道府県知事に報告した日から10年間保存することとする。
25.手数料の納付
次に掲げる者は、手数料を納付しなければならないこととする。
・指定調査機関の指定を受けようとする者
・指定調査機関の指定の更新を受けようとする者
・指定証の書換え又は再交付を受けようとする者
・技術管理者試験を受けようとする者
・技術管理者証の交付を受けようとする者
・技術管理者証の更新、書換え又は再交付を受けようとする者
26.土壌汚染対策基金(法第45条関係)
現在、土壌汚染対策基金による助成金の対象となっている「現行法第7条第1項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた土地の所有者等」は、法改正後においては、「要措置区域内の土地の所有者等であって、法第7条第1項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべき旨の都道府県知事の指示を受けたもの」に該当することから、現行令第8条第1項の助成金の交付対象の要件について、上記のとおり技術的置き換えを行う。
27.その他
宅地建物取引業法施行令に基づく重要事項説明に係る説明事項について、改正を行う。


2009年10月17日
画像入り 改正土壌汚染対策法

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域(第六条―第十条)
第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
第三節 雑則(第十四条・第十五条)
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
附則

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りではない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条 知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。
この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域
(要措置区域の指定等)

第六条 知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(汚染の除去等の措置)

第七条 知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の措置
(以下「指示措置」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもの(以下「指示措置等」という。)を講じなければならない。
4 知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5 知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公示しなければならない。
6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。
ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(適用除外)
第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
第二節 形質変更時要届出区域
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(適用除外)
第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第三節 雑則
(指定の申請)

第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。
この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(台帳)

第十五条 知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(運搬に関する基準)
第十七条 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(措置命令)
第十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(管理票)

第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。
3 汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を知事に届け出なければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第二節 汚染土壌処理業
(汚染土壌処理業)
第二十二条 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二汚染土壌処理施設の設置の場所
三汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
四汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
五その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
ることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ法人であって、その事業を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
4 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
6 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
7 汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。
8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
9 汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(変更の許可等)
第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前条第三項の規定は、前項の許可について準用する。
3 汚染土壌処理業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(改善命令)
第二十四条 知事は、汚染土壌処理業者により第二十二条第六項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第二十五条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十二条第三項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。
二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。
(名義貸しの禁止)
第二十六条 汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。
(許可の取消し等の場合の措置義務)
第二十七条 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第二十五条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、前項に規定する汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(環境省令への委任)
第二十八条 この節に定めるもののほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。
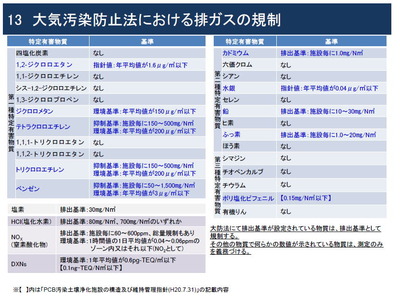

第五章 指定調査機関
(指定の申請)
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三十二条 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
第三十三条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの(次条において「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
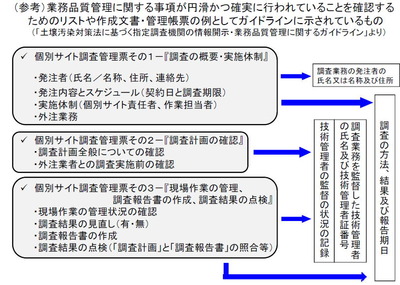
(変更の届出)
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌
汚染状況調査等を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第三十七条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第四十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第三条第一項の指定をしたとき。
二 第三十二条第一項の規定により第三条第一項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。
三 第三十五条(同条の環境省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は第四十条の規定による届出を受けたとき。
第六章 指定支援法人
略
第七章 雑則
(報告及び検査)
第五十四条 環境大臣又は知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第五十五条 知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第五十六条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第五十七条 環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第三条第一項ただし書の確認に関する事務
二 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条第二項の命令に関する事務
三 第三条第五項の確認の取消しに関する事務
四 第五条第二項の調査に関する事務
五 第六条第一項の指定に関する事務
六 第六条第二項の公示に関する事務
七 第六条第四項の指定の解除に関する事務
八 第七条第一項の指示に関する事務
九 第七条第五項の指示措置に関する事務
十 前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条 知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2 知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
(経過措置)
第六十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第六十三条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条第三条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十条から第十二条まで及び第十五条の規定の例により行うことができる。
2 第二十条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項
及び同条第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第三条 第三条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第三条 新法第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過する日以後に土地の形質の変更(同項に規定する土地の形質の変更をいう。附則第八条において同じ。)に着手する者について適用する。
(指定区域の指定に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている土地の区域は、新法第十一条第一項の規定により指定された同条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなす。
(指定区域台帳に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する旧法第六条第一項の規定による指定区域の台帳は、新法第十五条第一項の規定による形質変更時要届出区域の台帳とみなす。
(措置命令に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした旧法第七条第一項又は第二項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による命令を受けた者に係る旧法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第八条 施行日以後の日に附則第四条の規定により新法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧法第九条第一項の規定による届出をした者は、新法第十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)
第九条 新法第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。
(指定調査機関の指定に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
(変更の届出に関する経過措置)
第十一条 新法第三十五条の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする指定調査機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。
(適合命令に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前に旧法第十六条の規定によりした命令は、新法第三十九条の規定によりした命令とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
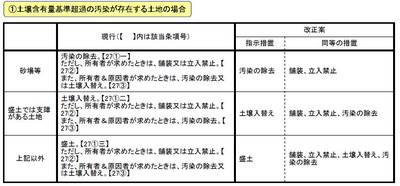
2009年10月15日
ATC「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」
「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」
今年4月に「改正土壌汚染対策法」が国会を通過し、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■
平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
ビオトーププラザ(おおさかATCグリーンエコプラザ内)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方環境事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■参加対象者■
・地方自治体の土壌汚染対策法担当者および大阪ATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会会員等
・今回は会の性格上一般の方は参加できません。一般の方で入場希望の方はご入会手続きが必要です。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■案内状■
申込書等
http://beauty.geocities.jp/atcmdk/091119ws_zitikati_ikenkoukankai.doc
今年4月に「改正土壌汚染対策法」が国会を通過し、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■
平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
ビオトーププラザ(おおさかATCグリーンエコプラザ内)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方環境事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■参加対象者■
・地方自治体の土壌汚染対策法担当者および大阪ATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会会員等
・今回は会の性格上一般の方は参加できません。一般の方で入場希望の方はご入会手続きが必要です。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■案内状■
申込書等
http://beauty.geocities.jp/atcmdk/091119ws_zitikati_ikenkoukankai.doc
2009年07月19日
中小企業に関する土壌汚染における土壌制度小委員会の議論

中小企業の土壌汚染に対する土壌制度小委員会の議論
(市川専門委員)
中小企業の立場から一言申し上げたいと思います。
既に報告書の中でも、中小企業者に対する支援ということがうたわれているところでございますが、自主的な調査をしたような場合に、仮に汚染が見つかったという場合に、どのような措置が要求され、どの程度資金が要るかと。
あるいはその資金、かかった費用についてどのような支援が国の方からなされるのかというあたりについては、ぜひ今後の検討ということになると思います。
予算要求の手続もございますので、直ちにというわけには行かないということは理解をいたしておりますが、中小企業者に対する支援、なかんずくどういう場合にどの程度の国の支援が得られるのかというのが、環境対策要員のいないような小規模な中小企業者にもわかりやすい形でもって示されるということが必要だというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
それから2点目は、国民の正しい理解ということが必要であるというふうに、これもまたこれまで当小委員会におきましても指摘をさせていただいているところでございますが、リスクに応じた対策ということで、必ずしも掘削除去のような費用のかかる対策でなくてもいいんだと、環境省の方からもそういう趣旨のご説明をいただいておりますが、これについての国民の正しい理解というものは必要だというふうに考えておりますので、ぜひそうした考え方の普及啓発ということに引き続き努めていただければというふうに考えております。
それから3点目は、若干その省令改正ということにかかわってくるわけでございますが、形質変更時要届出区域に指定されたような場合にあっても、先ほど鈴木委員からもご指摘ございましたんですが、日常の経済的活動がこれによって大幅に制限されるというようなことは、ぜひ避けていただきたいというふうに考えております。
条文でいいますと12条の第1号のところで通常の管理行為とか軽易な行為、その他の行為であって環境省令で定めるものについては除外をすると、こういうことで、既に現行の省令においてもある程度の小さな面積、浅いようなものについては除外をされておりますが、現行の省令で示しているところで日常の経済活動が阻害されないのかどうか、その点について若干不安視する向きもございます。
この先ほどの資料のでは、ここのところは検討事項として挙がっていないんですけれども、そうした現行の省令についても、もう少し幅広く検討していただいた方がいいのかなという感じを持っております。よろしくお願いをいたします。
(松本委員長)
ありがとうございました。市川専門委員の方からは中小企業の立場に立って、この法改正が適切に、しかも負担のかからないような、そういう正しい認識というのを国民に植えつけてほしいという、強いご要望がございました。ただいまの市川委員からのご発言に対して、事務局から何かございますか。
(笠井土壌環境課長)
まず不必要な対策をやらなければいけないような場合は、かなり少なくなるんじゃないかということを思っております。その上でどういう場合にどの程度のことが必要になってくるのかというのは、インセンティブ的なものも含めてどういうことができるかというのは、予算要求に向けてまた考えていかなければいけない課題だと思っておりますので、ご相談させていただきたいと思います。
国民の正しい理解というところは、まさにこの届出区域というのができるというところが一つの売りでして、制度を変えることで分からせるというのが、今回の改正の一つの柱だと思っております。
12条のことを言われましたけれど、別に経済活動を制約しないために決めているわけではなくて、ここはリスクが少ないものは除こうと、そういう考え方でやっておりますので、リスクのあるものはある、ないものはないと、そういう考え方で見直す必要があるかどうかということを見るのかなと思っております。
http://www.env.go.jp/council/10dojo/y105-10a.html

土壌汚染対策に対する各種支援措置
土壌汚染対策に関する利子助成制度、固定資産税の特例措置、土壌汚染対策基金による助成制度について紹介しています。
利子助成事業について(リンク:財団法人日本環境協会)
http://www.jeas.or.jp/activ/soil_02.html
土壌汚染対策に対する税制特例制度について (PDF版 19KB)
http://www.env.go.jp/water/dojo/zeisei.html
土壌汚染対策に対する助成制度について
http://www.env.go.jp/water/dojo/kikin_josei.html
http://www.env.go.jp/water/dojo/support.html
土壌汚染 中小企業 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4ADBF_jaJP302JP303&q=%E5%9C%9F%E5%A3%8C%E6%B1%9A%E6%9F%93+%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD&lr=
土壌汚染 支援 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_jaJP302JP303&q=%e5%9c%9f%e5%a3%8c%e6%b1%9a%e6%9f%93%e3%80%80%e6%94%af%e6%8f%b4