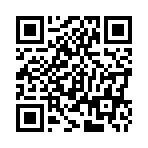2011年02月06日
岡山両備土壌汚染一戸建住宅事件
原告・被告の最終準備書面抜粋です。詳しくは転載元を確認願います。
<提出された準備書面内訳>
2010年12月21日岡山地方裁判所で住民訴訟第一次(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
最終準備書面
平成22年12月13日
岡山地方裁判所 御中
被告訴訟代理人
弁護士 菊池捷男
弁護士 首藤和司
弁護士 財津唯行
第1 争点
1 争いがないと思える事実
① 本件土地、つまり小鳥が丘団地と通称されている一帯の土地は、かつて旭油化工業株式会社が工場敷地として使用していたのを、被告が買い受けて、宅地として造成・分譲したこと、
② 平成16年7月に、本件土地の所定の場所で、岡山市が水道管の入れ替え工事をした際、油分(以下「本件油分」という。)のある黒い土が出てきたこと、本件油分の中には、土壌汚染対策法でいう特定有害物質が存在すること、その存在する特定有害物質の中には、同法でいう土壌含有量基準や土壌溶出量基準を超えるもの(以下「本件基準超過物質」という。)があること、
③ それまでの間、継続して、本件土地には、通常の人に感知できるほどの臭気(以下「本件臭気」という。)があったこと、
④
(第1 争点)
2 本件訴訟物と請求原因事実
(1)本件訴訟の訴訟物は、民法709又は715条による不法行為に基づく損害賠償請求権である。
(2)その請求原因事実は、
① 被告は、本件土地を宅地に造成・分譲する際、「不法行為」をした(原告の主張では、時期、内容が特定できているとは言い難いので、便宜上この表現にする。)
② 本件土地には、当初から、臭気が発生している。
③ 平成16年に至って本件油分が出現し、その中には特定有害物質と本件基準超過物質があった。
④ 本件油分及び特定有害物質と本件基準超過物質は、本件土地全域に存在する。
⑤ 本件土地内の宅地が無価値化し、原告らが健康被害を受けた。
⑥ 被告が①の時点で②ないし⑤の事実を予見することは可能であった。
⑦ 被告の「不法行為」と②ないし⑤の事実との間には相当因果関係がある。
というものであろうと思われる。
3 被告が争点にするもの
2の(2)に対する被告の認否
① 否認
② 認める。
③ 認める。
④ 否認。
⑤ 否認。
⑥ 否認。
被告が①の時点で③及び④の事実を予見することは全く不可能であった。
⑦ 否認する。
本件臭気は、旭油化時代から存在し、被告が宅地造成・分譲した後は、その程度は急激に減衰
本件油分は、旭油化時代の「何か」が原因の1つになっている可能性はある
本件基準超過物質も、旭油化時代の「物」がそのまま残っている可能性は否定できない
第2 本件基準超過物質について
1 土壌汚染対策法上の「特定有害物質」と同法が予定しているリスク
原告は、本件土地に、平成14年に成立した土壌汚染対策法第2条1項の特定有害物質が存在すること、及び、その一部については、土壌含有量基準や土壌溶出量基準を超えていることを、被告の責任である・・・・・
2 土壌含有量基準及び土壌溶出量基準
3 本件土壌から検出された物質と上記土壌含有量基準、土壌溶出量基準との関係
特定有害物質は、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第2種特定有害物質(重金属等)、第3種特定有害物質(農薬等)があるところ、本件では、第1・2種特定有害物質は存在する。
そして、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)に関し、本件土壌から検出されたのは、トリクロロエチレン、ベンゼン、シス―1,2―ジクロロエチレン、であり、
また、第2種特定有害物質(重金属等)に関し、本件土壌から検出されたのは、ヒ素及びその化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物(シアン化合物、鉛及びその化合物は原告提出の甲4号証で認められる・・・)である 、これらの物質については、 、土壌溶出量基準即ち「地下水等の摂取によるリスクに係る基準」のみが問題となる 。
しかも、第2種特定有害物質のうち、ヒ素については、自然由来の可能性が高いものであり、 。
以上を整理すると、本件においては、第1種特定有害物質のうち、トリクロロエチレン、ベンゼン、シス―1,2―ジクロロエチレン、第2種特定有害物質のうち、シアン化合物、鉛及びその化合物について、いずれも土壌溶出量基準即ち「地下水等の摂取によるリスクに係る基準」のみが問題となるものである。
4 特定有害物質の存在がその土地を無価値化し、住民に健康被害を与えるか?
5 本件基準超過物質の内容と広がり
乙1号証は、ボーリング調査でその存在が明らかになったベンゼン、トリクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、ヒ素含有量、ヒ素溶出量及び特定有害物質ではない本件油分を調査・分析した結果の報告書である。対象となった34箇所の表層土壌調査の結果、ベンゼンは8箇所、トリクロロエチレンは1箇所、シス―1,2―ジクロロエチレンは2箇所、ヒ素(溶出量)は5箇所で基準値を超えて・・・本件基準超過物質が本件土地全体に広がって・・・・
甲第4号証は、原告岩野敏幸の自宅での土壌調査結果の報告書であるが、これによれば同原告の自宅敷地には、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物の溶出量値が指定基準(土壌溶出量基準)を超えて存在していることを窺わせる。しかし、これらの基準超過物質も、それらが含まれた地下水を飲まない限り、原告らに何の被害も与えることはないのである。
しかもシアン化合物については
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/51593891.html
<提出された準備書面内訳>
2010年12月21日岡山地方裁判所で住民訴訟第一次(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
最終準備書面
平成22年12月13日
岡山地方裁判所 御中
被告訴訟代理人
弁護士 菊池捷男
弁護士 首藤和司
弁護士 財津唯行
第1 争点
1 争いがないと思える事実
① 本件土地、つまり小鳥が丘団地と通称されている一帯の土地は、かつて旭油化工業株式会社が工場敷地として使用していたのを、被告が買い受けて、宅地として造成・分譲したこと、
② 平成16年7月に、本件土地の所定の場所で、岡山市が水道管の入れ替え工事をした際、油分(以下「本件油分」という。)のある黒い土が出てきたこと、本件油分の中には、土壌汚染対策法でいう特定有害物質が存在すること、その存在する特定有害物質の中には、同法でいう土壌含有量基準や土壌溶出量基準を超えるもの(以下「本件基準超過物質」という。)があること、
③ それまでの間、継続して、本件土地には、通常の人に感知できるほどの臭気(以下「本件臭気」という。)があったこと、
④
(第1 争点)
2 本件訴訟物と請求原因事実
(1)本件訴訟の訴訟物は、民法709又は715条による不法行為に基づく損害賠償請求権である。
(2)その請求原因事実は、
① 被告は、本件土地を宅地に造成・分譲する際、「不法行為」をした(原告の主張では、時期、内容が特定できているとは言い難いので、便宜上この表現にする。)
② 本件土地には、当初から、臭気が発生している。
③ 平成16年に至って本件油分が出現し、その中には特定有害物質と本件基準超過物質があった。
④ 本件油分及び特定有害物質と本件基準超過物質は、本件土地全域に存在する。
⑤ 本件土地内の宅地が無価値化し、原告らが健康被害を受けた。
⑥ 被告が①の時点で②ないし⑤の事実を予見することは可能であった。
⑦ 被告の「不法行為」と②ないし⑤の事実との間には相当因果関係がある。
というものであろうと思われる。
3 被告が争点にするもの
2の(2)に対する被告の認否
① 否認
② 認める。
③ 認める。
④ 否認。
⑤ 否認。
⑥ 否認。
被告が①の時点で③及び④の事実を予見することは全く不可能であった。
⑦ 否認する。
本件臭気は、旭油化時代から存在し、被告が宅地造成・分譲した後は、その程度は急激に減衰
本件油分は、旭油化時代の「何か」が原因の1つになっている可能性はある
本件基準超過物質も、旭油化時代の「物」がそのまま残っている可能性は否定できない
第2 本件基準超過物質について
1 土壌汚染対策法上の「特定有害物質」と同法が予定しているリスク
原告は、本件土地に、平成14年に成立した土壌汚染対策法第2条1項の特定有害物質が存在すること、及び、その一部については、土壌含有量基準や土壌溶出量基準を超えていることを、被告の責任である・・・・・
2 土壌含有量基準及び土壌溶出量基準
3 本件土壌から検出された物質と上記土壌含有量基準、土壌溶出量基準との関係
特定有害物質は、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第2種特定有害物質(重金属等)、第3種特定有害物質(農薬等)があるところ、本件では、第1・2種特定有害物質は存在する。
そして、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)に関し、本件土壌から検出されたのは、トリクロロエチレン、ベンゼン、シス―1,2―ジクロロエチレン、であり、
また、第2種特定有害物質(重金属等)に関し、本件土壌から検出されたのは、ヒ素及びその化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物(シアン化合物、鉛及びその化合物は原告提出の甲4号証で認められる・・・)である 、これらの物質については、 、土壌溶出量基準即ち「地下水等の摂取によるリスクに係る基準」のみが問題となる 。
しかも、第2種特定有害物質のうち、ヒ素については、自然由来の可能性が高いものであり、 。
以上を整理すると、本件においては、第1種特定有害物質のうち、トリクロロエチレン、ベンゼン、シス―1,2―ジクロロエチレン、第2種特定有害物質のうち、シアン化合物、鉛及びその化合物について、いずれも土壌溶出量基準即ち「地下水等の摂取によるリスクに係る基準」のみが問題となるものである。
4 特定有害物質の存在がその土地を無価値化し、住民に健康被害を与えるか?
5 本件基準超過物質の内容と広がり
乙1号証は、ボーリング調査でその存在が明らかになったベンゼン、トリクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、ヒ素含有量、ヒ素溶出量及び特定有害物質ではない本件油分を調査・分析した結果の報告書である。対象となった34箇所の表層土壌調査の結果、ベンゼンは8箇所、トリクロロエチレンは1箇所、シス―1,2―ジクロロエチレンは2箇所、ヒ素(溶出量)は5箇所で基準値を超えて・・・本件基準超過物質が本件土地全体に広がって・・・・
甲第4号証は、原告岩野敏幸の自宅での土壌調査結果の報告書であるが、これによれば同原告の自宅敷地には、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物の溶出量値が指定基準(土壌溶出量基準)を超えて存在していることを窺わせる。しかし、これらの基準超過物質も、それらが含まれた地下水を飲まない限り、原告らに何の被害も与えることはないのである。
しかもシアン化合物については
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/51593891.html