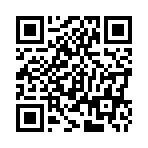2011年09月03日
放射能土壌汚染セミナー後記(平成23年8月21日)
放射能土壌汚染セミナーは、多数の参加を得て盛会裏に終了いたしました。
東日本大震災で福島原子力発電所の事故により放射能土壌汚染が生じており、速やかな除染やリスク管理を行うことが急務となっています。
そこで、放射能土壌汚染調査を実際に福島県等で実施し放射能土壌汚染調査のとりまとめにご活躍されている大阪大学核物理研究センターの藤原守先生や、土壌・水環境における放射性物質の分布や環境修復に詳しい京都大学 原子炉実験所の藤川陽子先生、さらにヒロシマ原爆やチェルノブイリの被害で研究された広島大学の星正治先生をお招きしてセミナーを開催します。
土壌汚染の専門家や多くの人たちが、放射能の知識正しく理解し、福島原発周辺の放射能土壌汚染の現状・課題を学び、一刻も早い放射能土壌汚染対策を目指します。
<日時>
2011年8月21日(日) 13時30分~17時00分
<会 場>
大阪大学中之島センター
・10階ホールおよび7階セミナー室
(京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約5分)
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
<プログラム>
開会 13時30分
開会挨拶 放射能土壌汚染セミナー実行委員会
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 教授 理学博士 星正治 氏
質疑応答
セミナーまとめ 星正治 氏
閉会挨拶 放射能土壌汚染セミナー実行委員会
閉会 17時15分
<定員>
計300名
<聴講料>
1000円
<問い合わせ>
大阪水・土壌汚染研究会
案内チラシは↓
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/20110821_housyanou_dozyouosen.doc
<主催>
放射能土壌汚染セミナー実行委員会
大阪 水・土壌汚染研究会
(「大阪水・土壌汚染研究会」は、「おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会」とは、別の組織です。)
<後援>
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィース)、(財)地域地盤環境研究所 NPO石膏ボードリサイクル推進ネットワーク (社)大阪技術振興協会、建設資源リサイクル研究会、(財)災害科学研究所 ジオテク研究会(財)地域地盤環境研究所、 他
<広報協力>
大阪府環境農林水産総合研究所、(財))大阪科学技術センター、公害防止管理者協会、
環境省近畿環境地方事務所、(財)日本環境協会 環境カウンセラー全国事務局、
建設副産物リサイクル広報推進会議事務局((財)先端建設技術センター)、いさぼうネット
大阪府立公衆衛生研究所、環境人材の(株)グレイス、日経エコロジー、ECO JAPAN
福井原子力センターあっとほうむ、エル・パークおおい おおいり館、大阪科学技術センター
環境ビジネスサイト(株)船井総研、読売新聞、環境新聞
公徳心あふれるブロガーの皆様など
<資料提供協力>
福島県大阪事務所、広島平和資料館、(財)環境科学技術研究所(六ヶ所村)、電気事業連合会、
原子力発電所整備機構、Land-Eco土壌第三者評価委員会、福井県安全環境部原子力安全対策課
もんじゅエムシースケアー、 順不同
<講師プロフィール>
SQALF~大阪大学21世紀懐徳堂東日本大震災プロジェクト
メールで東日本大震災へのご質問、および「防災・復興」関連テーマを扱う「第43回21世紀懐徳堂講座」に期待することについてのご意見をお受けします。
セミナーの最後で下記の検討を行うのはいかがでしょうか?
・放射能土壌汚染ビジネス交流会の創設
・放射能土壌汚染セミナーの東京開催(阪神淡路大震災記念日の頃or今秋)
震災復興支援「放射能土壌汚染セミナー」
~震災のいまとこれから・私たちに何ができるのか~
は、多くの方々のご支援やご協力を頂き無事終了いたしました。
お世話になった方々にお礼申し上げます。
このセミナーの準備を通して、多くの方々の支援や親切をお受けし、ここまで準備ができたことに、お礼申し上げます。
早期に、放射能土壌汚染対策の実施を図り、特に子供たちを含む国民の健康が保護されますよう切に希望します。
開会挨拶
放射能土壌汚染セミナー実行委員長(大阪水・土壌汚染研究部会事務局長)

皆様こんにちは
ただいまご紹介を頂きました 放射能土壌汚染セミナー実行委員会でございます。本日は、非常に暑い中、当セミナーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。
また、講師の先生方は、福島やカザフスタンの放射能汚染問題などの対応に非常にお忙しい中、ご講演を快諾して頂きまことにありがとうございました。
ご来場の方々には、東京方面や、新潟、北海道や九州のご遠方からもお越し頂き誠にありがとうございます。
まず、今回の東日本大震災で犠牲になられた2万人を超える方々のご冥福をお祈りいたしますと共に、被災された多くの方々に心からお見舞い申しあげます。
また、現在も福島の原子力発電所対応や放射能汚染対策に従事されている皆様に心から敬意を表します。
さて、私共の実行委員会の紹介ですが、以前より大阪南港で水・土壌汚染について勉強していたメンバーが実行委員となり本日のセミナーの準備をさせていただきました。
セミナーの運営は素人ですので、行き届かぬことが多々あろうかとは存じますが、何卒ご容赦賜りますようお願いいたします。
本日のセミナー開催にあたり、多くの方々から激励や協力を受け、セミナー広報の協力や資料提供等のご支援を頂きましたことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。
この放射能土壌汚染セミナーの準備を多くの方々からの励ましや支援を受けて進めさせていただき、感じましたことは、「まさに、社会が求めている話題であり、福島の放射能土壌汚染問題を是非多くの方とに考え、一刻も早く、放射能リスク低減に向けた除染や放射能土壌汚染対策を実現する必要がある」
ということでございます 。
福島県から国へ「東日本大震災からの復旧・復興に関する要望」が7月に出されていますが、その78項目の内、約半数が放射能に関係するものでございます。
放射能のモニタリング、除染、廃棄物対策、放射線医療や放射能等に関する拠点整備を要望されておられます。
この地元の要望をいかに、速やかに、有効に実施すべきが求められています。
その中でも特に、「身近な生活空間における放射線量低減対策」を早急に進めるべきであり、とりわけ「こども達が受ける放射線量の低減」が重要だと考えます。
本日のセミナーが、一刻も早く放射能土壌汚染対策を促進し、子供たちの放射能による健康被害を予防するのは勿論、学校や社会で明日の福島未来の日本をさせる人に健やかに成長することや、一日も早い被災地復興の一助となることを願いまして開会のあいさつとさせていただきます。
本日はよろしくお願いいたします。
山田様(プロフィール)から
http://www7b.biglobe.ne.jp/toshisyun/profile/profile.htm
放射能土壌汚染セミナーの概要を作成していただきました
http://www7b.biglobe.ne.jp/toshisyun/news/N34kankyoureprort.pdf
PDFが山田さんの記事です。

講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏



放射性壊変:
α壊変:ヘリウムの原子核が放出される
β壊変:電子(陽電子)が放出される
γ壊変:ガンマ線が放出される。
放射性核種(放射能)からベータ線、ガンマ線(放射線)を放出して安定な核種へ変わる
放射性物質(放射能)を測る単位
1ベクレル(1 Bq) = 毎秒1壊変
千倍をk(キロ)、百万倍をM(メガ)、10億倍をG(ギガ)をつけて kBq、MBq、GBqとあらわす。
放射線を測る単位
知りたいのは放射線の影響である
放射線の流れはエネルギーの流れと考えてよい
エネルギーの単位が基礎となる
誰もが浴びる自然放射線
1年間に日本人は2.4 mSvの放射線を毎年浴びている。
2.4 mSv÷365日 =6.6μSv
大地に含まれる放射性同位元素の量(Bq/kg)
種類 一般の土壌・岩石 花崗岩
カリウム40 100~700 500~1600
ウラン238 10~50 20~200
トリウム232 7~50 20~200
国連科学委員会資料
年間にどのくらい被ばくする?
(1)宇宙飛行士 約360 mSv/年
(2)原発従事者等 50 mSv/年以下に管理すること
(3)パイロット 約 1 mSv/年(+2.4 mSv/年)
(4)一般の人 約 2.4 mSv/年
(5)胸部エックス線写真 約0.3 mSv/年
体内の放射能
カリウム40(天然存在比0.012%):4000Bq(毎秒4000個)
炭素14(天然存存在比0.00000000012%):2500Bq(毎秒2500個)
食物などによる放射線の量は年間0.29ミリシーベルト、ラドンなどによる放射線の量は1.26ミリシーベルト
私達の日常生活の中にも放射線を利用した多くの製品があります。例えば蛍光灯のグロー放電管、夜光時計、煙感知器やカメラの内臓ストロボなどに放射線が使われています。
蛍光灯のグロー放電管の中には放射線を出す放射性同位元素プロメシウム147が入っています。このプロメシウム147から出るベータ線の電離作用により、スイッチを入れるとすぐに放電が起こり、蛍光灯が素早く点灯します。 夜光時計の文字盤や針にもプロメシウム147が塗られており、それから出るベータ線により発光します。
影響の種類
確定的影響:しきい線量あり、線量増加で症状が悪化
確率的影響:しきい線量なし、線量増加で発生確率の増加
影響の例
確定的影響:白内障、脱毛、不妊など
確率的影響:ガン、遺伝的影響(すぐに影響は出ない)
つまり、確定的影響がなければ、直ちに健康への影響はない。
しかし、ガンや遺伝的影響のリスクを知らないと判断できない。
1Gyと1Svは同じと考えてよい
確率的影響は、ガン及び遺伝的影響であり、細胞の中のDNAの損傷が原因となっている
細胞レベルの影響
放射線感受性は、
1)分裂の頻度の高いもの、
2)将来行う分裂数の多いもの、
3)形態・機能の未分化なものほど高い。
ガン・遺伝的影響のリスク
表略
これらの値は広島、長崎の原爆被爆者の追跡調査から得られたデータがもとになっている。
一般人の放射線のリスク(年当たり1mSv)
がんになる確率:5.5×10-5
遺伝的影響: 2×10-6
死亡率から見たリスク(年当たり)
がん: 2.7×10-3
心臓病など: 1.4×10-3
脳梗塞など: 1.1×10-3
肺炎など: 1.3×10-3
老衰: 2.1×10-4
不慮の事故 3.2×10-4
交通事故: 7.9×10-5
転倒・転落:5.3×10-5
溺死など: 4.9×10-5
窒息など: 7.4×10-5
自殺: 2.4×10-4
他殺: 5.0×10-6
一般人に対する放射線のリスクは安全とされる範囲内となっている。
放射線のリスク(1Svあたり)
がんになる確率:5.5×10-2
遺伝的影響: 2×10-3
一般人は1mSv/年とされているので
リスクは(年当たり)
がんになる確率:5.5×10-5
遺伝的影響: 2×10-6
放射線のリスクとたばこのリスクの比較
ガン全体
ガン全体にたいする放射線のリスク:1Svあたり5%(5×10-2 Sv-1)
ガン全体のリスク:10万人当たりの年死亡率257人(2.7×10-3)
たばこによる相対危険度~1.6(非喫煙者を1としたときの危険度)たばこの寄与は0.6となる。
たばこのリスクに対する寄与:2.7×10-3×0.6 = 1.6×10-3
放射線に換算:1.6×10-3/(5×10-2 Sv-1)= 0.032Sv = 32mSv/年
肺がん
肺ガンにたいする放射線のリスク:1Svあたり1%(1×10-2 Sv-1)で肺に対する組織荷重係数は0.12なので、1Svのうち0.12Svが肺に寄与すると考て、リスクは0.083 Sv-1となる。
肺ガン全体のリスク(男):10万人当たりの年死亡率44人(4.4×10-4)
たばこによる相対危険度 1-4本 5-14本 15-24本 25-34本
相対危険度 2.5 3.3 5.4 7.1
たばこの寄与 1.5 2.3 4.4 6.1
リスクに対する寄与 6.6×10-4 1.0×10-3 1.9×10-3 2.7×10-3
放射線に換算 8mSv/年 12mSv/年 23mSv/年 33mSv/年
放射線:ICRPのデータ、死亡率等は厚労省データ
1983年にCo-60(半減期5.27年)が混入した鉄筋でビルが建てられた。最初の年は1100人が500ミリシーベルトも被ばく。
Wikipedia
ホルミシス効果とは、生物に対して通常有害な作用を示すものが、微量であれば逆に良い作用を示す生理的刺激作用のこと。ホルミシスとは、ギリシャ語のホルメに由来する。このホルメはホルモンの語源でもある。意味は、「刺激する」である。特に自然放射線の人体への健康効果を指す場合は、放射線ホルミシス効果、また放射線ホルミシス学説ともいう。ホルメシスとも表記される。
環境放射線の積極的な利用としての放射能泉
自然放射線または環境放射線の積極的な利用は、放射能泉であるラドン温泉やラジウム温泉で行われてきた。ラドン222の濃度が74ベクレル/リットル以上がラドン温泉であり、ラジウムが1億分の1グラム/リットル以上含まれるのがラジウム温泉である。
ヨーロッパのオーストリアでは、インスブルック大学医学部が、1950年代からザルツブルク大学理学部と共同研究を行い、ヨーロッパアルプス山脈の中にあるバートガシュタインのラドン坑道を活用して、年間 約 10,000 人の強直性脊椎炎(ベヒテレフ病)、リウマチ性慢性多発性関節炎、変形性関節症、喘息、アトピー性皮膚炎などの患者に対してラドン吸入療法を行っている。ここでの空気中ラドン222濃度は110ベクレル/リットル以上で放射能療養坑道と呼ばれている。
オーストリアや日本、ロシアなどではこの放射線ホルミシス理論を根拠に、ラドン温泉(ラジウム温泉)の効用がうたわれ、療養のために活用されるラドン温泉やラドン洞窟が存在する。
線量限度(国際放射線防護委員会の勧告)医療被ばくは含まない
職業被ばく 公衆被ばく
実効線量 100mSv/5年 1mSv/年
但し、50mSv/年を
超えない
等価線量
目の水晶体 150mSv/年 15mSv/年
皮膚 500mSv/年 50mSv/年
手および足 500mSv/年
日本の法令には公衆被ばくの規定はない。ただし、放射線事業所の境界を1mSv/年と定めている。
飲食物摂取制限
・原子力施設等で事故が起き、敷地外の一般公衆が過度の被ばくをする恐れのある場合、考慮するべき重要な
核種は、131I、137Cs、90Srなどである。
摂取制限値の飲食物を1年間摂取しつづけた時のリスク
137Csは筋肉にとどまり、全身に被ばく線量を与える。
初年度 5mSv が摂取制限となる。
摂取制限値の飲食物を1年間摂取しつづけた時のリスクは、1mSv/年で5.5×10-5なので、2.8×10-4/年である。
これは不慮の事故のリスク3.2×10-4/年と同じ程度である
飲食物に含まれる放射能の摂取限度は、5 mSvを制限値にしているので、この10倍の物を1年間飲食しても、50 mSv/年であり、ガンのリスクは0.25%となる。
放射線の影響のない場合のガンのリスクが30%程度であることを考えると、大きな影響とは言えない。
離れた地域で放射線レベルが上がっていることについて
福島原発事故直後、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、静岡の1都7県で計測された放射線レベルでは最大で、毎時1μSvと報告された。
放射線のレベルが通常の10倍あるいは100倍というと大変、高い線量のように感じられる。実際には健康に影響のないレベルである。
この放射線レベルで1 年間生活した場合、1年は8760時間だから、8.8mSvで、CT検査1回分の線量で健康に影響のないレベル
すべての場所で4-5cmの深さで、ほぼ100%の放射能が含まれる。
分布はほぼ指数関数である。I∙exp(-λ∙d)
d:表面からの深さ
10分の1減衰距離(L1/10)は18-48 mm
4月に取ったサンプルと比べればL1/10は少し伸びているように見えるが、場所の違いのファクターが大きいかもしれない
これから
子供たちに未来を託せる環境をつくる。
そのためには?
個々の住居の放射能被曝低減
・屋根などに付着しているセシウムなど放射性物質を洗い流す。
・古い葉の除去や雨樋を掃除し、雨樋の下の地面など、家屋周辺の土壌5cm程度を撤去する。
・家屋周辺を15cm程度の厚さのコンクリート壁で囲う。セシウムからのガンマ線は15cm程度のコンクリートで10分の1以下に減少する。(セシウムからの660 keVガンマ線は空気中100mを飛んでやっと40%に減少、200m飛んでも16%しか減少しない。現在報告されている空間線量は、空気中に漂うっている放射性物質のものからでなくて、地表から放出されたガンマ線を測定した結果です。)
・丁寧な対策で生活物資さえ安定に供給されれば、放射線被爆の問題が無く生活だけは続けて行けるでしょう。
●講 師 藤原 守 大阪大学 核物理研究センター 准教授
略歴
大阪大学 理学部 物理学科 卒業
大阪大学 理学研究科 物理学専攻 修士 修了
大阪大学助手を経て助教授
日本原子力研究所先端基礎研究センター(グループリーダー)
研究内容
放射線検出器、レーザー電子光によるクォーク核物理、原子核の巨大共鳴、
磁気スペクトロメーター、原子核構造 など
学会活動
アメリカ物理学会、 日本物理学会 、日本放射光学会http://www.jssrr.jp/
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspI/RX0011D.asp?UNO=12453
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏



わが国の土壌の特性と放射性セシウムの挙動
わが国の土壌は概して、放射性セシウムを吸着しやすい。
一方、諸外国にはセシウム低吸着性の土壌もある。典型例は酸性ポドソル、泥炭等である。このような土壌は土壌生成論的には、日本の本州地域ではどちらかおいうと稀である(一部の高地等には存在する)。これらの土壌でセシウムが吸着しにくい要因としては、pHや土壌の荷電特性、土壌鉱物組成、比表面積、溶解性の有機物量等の特性が関与している。
なお、セシウムは安定同位体としても存在し、土壌水中のその濃度が高ければ同じ土壌でも放射性セシウムの吸着力は低下するが、筆者の経験では、日本の土壌水中の安定同位体のセシウム濃度は低い。仮に土壌の放射性セシウム吸着特性を実験的に検討するときに、安定同位体のセシウムを自然界における以上の量、加えてしまうと、キャリアフリー(無担体)の放射性セシウムで実験するのとまったく異なる結果となるので注意が必要である。

●講 師 藤川 陽子 京都大学 原子炉実験所 准教授
略歴
京都大学大学院工学研究科 衛生工学専攻 修了
京都大学原子炉実験所、助手を経て、助教授、職制変更後、准教授。
専門
環境工学、放射性廃棄物地層処分の安全評価、
放射能・各種重金属・有機汚染物質の土壌圏・水圏における動態、
汚染環境修復技術
学会活動
保健物理学会、土木学会、水環境学会、環境技術学会、原子力学会など。
放射性廃棄物の地中処分に関連して、地水圏中の放射能等の地質媒体への吸着特性解明のための基礎実験、移行モデル構築とモデルの解法の検討、自然環境中の極微量のウラン・プルトニウム・水銀等の移行・分布挙動の調査をおこなっています。
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901065603176505
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 教授 理学博士 星正治 氏



土壌汚染の性質
1.今後問題になる放射能は、半減期30年のセシウム-137である。
2.セシウム-137は土壌に付着すると堅く結びついて何十年もそのままである。
3.そのため、グラウンドや庭など表層土壌に良く付着する。
4.また、木の葉などには強く付着する。同様に稲わらや腐葉土にも良く付着する。
5.道路ではアスファルトではなく、路肩に放射能が多い。雨水などが流れてセシウムが路肩に吸着する。
6.側溝の土壌や雨樋の下など水の流れる場所にも集積する。
7.セシウムの性質を見極め、多量に集積している場所を知る。そこが土壌か植物の葉か、腐葉土かなのかなど材質を区別して除染に当たる。
8.植物などは焼却する。セシウムが蒸散しないよう、一定の温度以下で焼却する。必要に応じて、除染のための排煙装置なども考案する。
土壌汚染の除去
1.福島の放射能汚染は表層から1-3cmまでに沈着している。従って表層から5cm位を剥がす除去すると有効である。
2.1/2から1/10くらいまで表面線量が低下できるとの調査がある。
3.汚染していない土壌を、除去後表層にかぶせると更に安全となる。
4.セシウムは土壌に付着すると数十年たっても離れないので、保管する際、他に移行しにくい性質を持つ。
5.最終的には、処理した土壌は、ゴミの最終処分場を作りそこに搬入し,保管する。
6.焼却灰も同様である。
7.最終処分場がすぐにできない場合は、土嚢袋などに入れ、グランドのコーナーに埋設する。後で取り出して最終処分場に移動する。
8.チェルノブイリではコーナーに山にして積み上げていた。これも有効である。
9.汚染の除去における、基準値の確定が必要である。どのレベルで除去し、どのレベルで最終処分場に持ち込むか、また更に大きい高レベルの土壌をどう処理するかなど。
10.これらは、ボランティアで可能な範囲を超え、学術的な調査と、それをトータルで実行できる事業者が必要となる。
11.汚染やそれに伴う被ばくは進行中であり、早急な対処が必要である。
今後の調査の必要性と内容について
1 . 地表の表面汚染調査
a) 広域汚染地図の作成
b)土壌のサンプリング
c)汚染地域での食品の採取
d) 土壌測定
I-131、Cs-134,Cs-137 からのガンマ線量を測定する。
2 . 住民の被ばく線量調査
住民の被ばく線量について、以下の項目のような調査を行う。
1. 専門家チームを組んでポータブルまたは全身カウンターで計測する。甲状腺についてはI-131 (ヨウ素)を測定し、Cs-137 については全身カウンターで腹部を測定する。
2.特に、子供や妊婦が測定の対象となる。
3. I-131 の測定は特に重要で、10 半減期以内に行う。その観点から6 月15 日までに至急に測定を行う必要がある。
放射線防護の原則
・不必要な放射線被ばくは避ける(行為の正当化)
・被ばくする線量,被ばくする人の数をできるだけ少なくする(放射線防護の最適化)
・1人ひとりの個人の線量は,法令などに定められた上限値を超えないようにする(線量の制限)
質疑応答
たくさんのご質問をありがとうございました。全ての質問票に講師の方からお答えいただきました。
●講 師 星正治
広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線影響評価研究部門 線量測定・評価研究分野 教授 理学博士
履歴
大阪大学理学部 物理学学科、同大学院 理学研究科 物理学専攻出身
大分工業大学講師、
広島大学原爆放射能医学研究所助手、助教授を経て
1994より現職である広島大学原爆放射線医学研究所教授、現在に至る。
社会活動等
原子力委員会委員
原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員会
放射線被曝者医療国際協力推進協議会
科学技術・学術審議会(研究計画・評価分科会)
国連科学委員会国内対応委員会
日本学術振興会科学研究費委員会
JICAセミパラチンスク地域医療改善計画国内支援委員会
中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター詰問委員、他。
受賞等
カザフスタン共和国の人々の健康維持管理への貢献に関する特別賞 (2004/01)
第12回国際放射線影響学会賞 (2003/08)
カザフスタン共和国の人々への保健システムへの貢献に関する特別賞(1999/10)
学会活動
日本医学物理学会、日本医学放射線学会、日本医学放射線学会医療用標準線量研究会、
日本医学放射線物理学会、日本原子力学会、日本放射線影響学会、日本放射線技術学会

放射能土壌汚染セミナーまとめ
寺川さんの開会の挨拶でいいんじゃないですか!
広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 理学博士 星正治 教授
平成23年8月21日 17時15分 大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホールにて
閉会挨拶
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 事務局長 姜(カン)永根

質問:福島原発周辺はいつになれば安全(入ってもよい)となるのでしょうか?
答: 福島原発周辺の放射能レベルは距離によって、また地形によって違います。
藤原 守 放射能土壌汚染セミナー講師
3月の福島第一原子力発電所事故では水素爆発のために原子炉中の放射性物質(主にヨーソ131(131I:半減期8日), セシウム(134Cs:半減期2年, 137Cs:半減期30年)が大気に飛散し、それが、雨や雪が降ることによって地上に降り注ぎました。
気象条件の違いで初めは北部の方向に風によって運ばれ、飯舘村などに多くの放射性物質が地上に降下しました。その後、この風向きは太平洋側に向かい、その後、南に方向を変えました。その時々の、雨や雪の降り方で地上に降った放射性物質の降り方が違うのです。ヨーソとセシウムは水への溶融度の違いによって土壌放射性物質の降下の仕方が違うという事が、はっきりしています。
また、20km圏外の飯舘村の放射能レベルが高く、20km圏内のすぐ近くの川内村などの放射能は1 mSv/hレベルで普通に生活しても全く大丈夫なようです。文部科学省プログラムをリードした形で大阪大学は、こういった放射性物質汚染度マップの作成に大きく貢献しています。
ヨーソ131の半減期は8日です。この放射能は80日も経てば1000分の1になり160日(約半年)も過ぎれば百万分の1に減少します。しかしセシウム137の半減期は30年ですから、30年経っても半分ということになり降下した放射能はなかなか減少しません。降下した放射能は、土壌表面にくっつき雨が降っても5cmも浸透していない事もわかっています。
屋根に降った放射性物質は、太陽に照らされ雨に流され雨樋に集まります。雨樋の下の地面の放射能レベルが高いのはこのためです。また、道路のアスファルトの上に降ったものは雨に流され側溝に集まります。側溝に集まった土砂は、大量の雨が降る梅雨後に川に流され河川の汚染ということになります。樹木の葉っぱにも放射性物質がくっついています。
秋になって、木の葉が舞い落ちる季節には、やはり放射性物質の拡散が起こります。
夏の日照りに照らされ、表面の土壌がホコリとなって風に舞いあげられる季節にも放射性物質の拡散が起こります。
しかし、一般的に言って、土壌や大気の循環によるこれらの拡散過程は非常にゆっくりしたものです。
したがって一般的に云えば、30年経っても放射能レベルの減らない高放射線領域に、何も対策を講じないで、そのまま住めるようになるという状況は考えられません。
個々の住居に対しての放射能被曝を低減する方策としては、簡単です。
1.屋根などに付着しているセシウムなどの放射性物質を洗い流す。
2.雨樋を掃除し、雨樋の下の地面など、家屋周辺の土壌5cm程度を撤去する。
3.家屋周辺を15cm程度の厚さのコンクリート壁で囲う。
セシウムからのガンマ線は15cm程度のコンクリートで10分の1以下に減少するので、家屋周辺からの放射線被爆を減少できる。(セシウムからの660 keVガンマ線は空気中100mを飛んでやっと40%に減少、200m飛んでも16%しか減少しない。現在報告されている空間線量は、空気中に漂うっている放射性物質のものからでなくて、地表から放出されたガンマ線を測定した結果です。)
などの丁寧な対策で生活物資さえ安定に供給されれば、放射線被爆の問題が無く生活だけは続けて行けるでしょう。
しかし、はたして、福島原発周辺の個別の少数の人々にとってのこういった特殊な対策が十分な対策として成り立つかが問題です。福島第一原子力発電所廃炉には数十年の長い年月を要します。
この長い60年間に、原子炉を雇用のよりどころとしてきた多数の人々の生活再建をどのようにしていくかを考えない限り「原子炉周辺にはいつ入れるのか?」という問いには答えた事にはなりません。経済的に雇用を創出し、子供たちが明るい未来を考える事の出来る文化的社会創出を考えて行くことが必要です。
私たちが招いた危機をしっかり見つめ、この危機を克服しチャンスにかえることが出来るかを考えること。これが重要です。さもなければ、福島原発周辺は、文明に見捨てられた廃墟となるでしょう。このような文明の廃墟は世界中にあります。
一人の科学者の私案として、参考意見を述べさせていただくならば、福島原発周辺の産業、社会復興で必要なのは以下に述べるような「長い道程」の大規模改造を行う事ではないでしょうか?
放射能レベルを下げるためには、土壌を掘り下げ、天地返しをする以外には無いでしょう。しかし、これを個別な小さな個別地域で行っても、経済効果は少ないので、大規模に行う。これらは、
1. 放射線レベルの高い周辺地域20 kmx40km領域の山谷を削り、埋め立てることによって広大な平地を作りだす。オランダでは長い年月をかけて広大な土地を開拓してきた歴史がある。オランダの例を見るならば、20kmx40kmはそれほど広大な土地ではない。土木産業によって巨大な雇用が生まれる。また、放射能レベルの低減も出来る。
2. 太陽パネルを敷き詰め、新たなエネルギー産業を創出し、雇用を確保する。東大の試算によれば、日本のエネルギー重要を賄うには一万平方kmに太陽パネルを設置する必要があるとのこと。福島原発周辺の20 km x 40 kmに敷きつめても800平方kmであり、10%程度である。また、電気エネルギーを電気分解して蓄えておく蓄電施設や水素燃料施設も必要となる。
3. 高等教育機関の設立、自然再生エネルギーや放射線に関しての研究機関、病院の設置。
4. 大規模工業団地の設立。
5. 港湾、飛行場など、物資輸送のハブ施設の設立
6. 人々が集まるようになればアミューズメント施設や商店街なども出来る。
7. 金融マネージメントセンター、ITセンターの設立
となろう。
もちろん、水の放射能汚染などの問題はある。しかし、これは、現状でも早晩問題視され、しかも、解決が難しい問題である。必要総費用は100兆円以上の巨大プロジェクトになり、未解決の問題は多くあるが、長期間にわたる科学的検討と着実な施策立案によって福島の再生が可能となるでしょう。
また、個別の人々の問題はしっかりとした科学的対応で解決して行くことも極めて重要です。
福島にゆかりのある高村光太朗の詩「道程」はこのように歌っている「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出きるる。ああ、自然よ。父よ。僕を一人立ちさせた広大な父よ。僕から目を離さないで守る事をせよ。常に父の気魄を僕に充たせよ。この遠い道程のため。この遠い道程のため。」
長い希望への闘いの道程を一歩進み出すかどうかは、日本の我々の選択肢の一つでしょう。
放射能土壌汚染セミナーアンケート結果集計表
平成23年8月21日に大阪大学中之島センターで開催
主催:放射能土壌汚染実行委員会(大阪水・土壌汚染研究会)
1.どの講演内容に興味を持ちましたか?複数回答可
講演1 講演2 講演3 その他
50 47 69 デモが良かった
2.あなたの疑問に対し、どの講演内容が回答に近かったですか?複数回答有り
全回答数: 81
講演1 講演2 講演3 その他
22 24 47 0
属性の内訳は下記の通り
回答性別(枚) 男性 64 女性 9 未回答 8
回答年齢(枚) 20未満 0 20代 2(1) 30代 7(2)
※()内女性 40代 11(2) 50代 21 60代以上 30(4)
3.セミナー運営に対する意見 注:(数)は同様な意見数
3.1肯定的な意見
" ・興味深く聞かせて頂き有難う御座いました。運営方法は、大変良かった、放射線の事が理解できた。
有効な内容を3人の講師が判り易く説明頂きました。タイムリーで安価な良いセミナー。 (11)"
・質問に対し丁寧な回答、有難う御座いました。質疑応答が良かった。(2)
・放射能について正しい知識を学ぶ機会として有益でした
・内容はいずれも面白く、”5cm”の重要性が非常によく理解できました
・専門が土木なので、シーベルトやベクレル等の基礎知識が役に立ちそう
・パネルディスカッションを組むと盛り上がると思う
・放射能について正しい知識を学ぶ機会として有益でした
・今後とも続けて下さい、今後の汚染土壌マップ等
・言いにくいことも説明あり良かった
・星先生の写真やデータが判り易かった
・手作り感と一体感が有ってよかった。
3.2改善意見
・時間が短すぎる。講演時間をもっと長く欲しい。(4)
・土壌汚染の課題と対策についてもっと突っ込んで欲しかった
・放射能汚染土壌に関する内容が少ない
・放射能汚染の基礎的な説明が大半で震災復興の話が不足していました
・内容の重複がある
・藤川先生のパワーポイントをじっくり見たかった
・ストロンチウム90の説明を入れて欲しい
・レーザーポインターが7Fで見れなかったのが残念でした
・汚染土壌に対する対応策が少なく、一般の放射線説明が中心だった
・受講料を無料にしてほしい
・講演者の語尾が聞き取りにくい。マイクのチェックが必要
・タイムマネジメントをしっかり御願いしたい
・専門的内容で分かりにくかった
・質問票記入、忙しいです
3.3今後の期待
・放射線被ばくに関して、ICRPかECRPのどちらが信頼に値するか。後者はカルト。
・次のセミナーは関東地区でも会場を確保して頂くと有りがたいです
・放射線を止めるセミナーを実行して欲しい
・放射能に関する国民教育、電力会社の体質の公開
・今後、セミナー実行委員会として国等へ働き掛けていくのか?
・現場の今を聞きたい
3.4その他意見
・放射線被ばくに関して、ICRPかECRPのどちらが信頼に値するか。後者はカルト。
4.今後のセミナーで取り上げて欲しいテーマ
4.1土壌汚染関係事業者向け
" ・土壌等の除去の詳細方法。どのような事業者や団体が除染を進めているか等。
土壌汚染の実施可能な処理方法。企業向けとして具体的な除染について。
具体的な除染方法について行政・ゼネコンの意見。(13)"
・今回のテーマについて、更に追及して欲しい。同じテーマでも継時的に見てみたいです。(3)
・医学的知見のセミナー(内部被ばく)。人体への影響について。(3)
・放射能のその時点での循環等の拡散状態やその危険度合い
・ファイトレメデェーションが現在どれくらい使われているか
・ファイトレメデェーションと放射能汚染土壌
・今後の調査について汚染結果動向をセミナーで報告して欲しい
・実際に除染に携わった事例等について講演して欲しい
・土対法と放射能汚染、現状のままで良いのか?環境省
・土壌汚染の技術的セミナー
・環境修復に関する事例紹介
・土壌の自然由来放射線やビキニ環礁、チェルノブイリの管理状況とデータ公開
・瓦礫の処分に関する法律
・リスクマネージメント的なセミナー
・放射能汚染された水の流れと影響
・汚染のしきい値(安全)の考え方を明らかにするセミナー
・異分野情報や農耕地汚染問題も取り上げて欲しい
・医学的知見のセミナー(内部被ばく)。人体への影響について。(3)
・体調異変の集計結果
4.2消費者・市民向け
" ・消費者として、農産物への影響を取り上げて欲しい。
水質汚染、大洋魚汚染も知りたい。食品に関するセミナー。
海洋の汚染状況と今後の広がり方、海洋の除染方法、海産物への影響。(5)"
・現地の住民に役立つ内容や具体的なアクションに移した報告を伺いたい。
・放射線測定法を知りたい。
・汚染土処理の方法や処理土の受入れの有無を判断するのは「住民」OR「行政」?
・環境省の方策?「情報開示・意思決定とスキームの構築」が社会にとって重要性が増していると考えます。
" ・結局、放出された放射線は我々が受け入れるしかない。
ただ、一連の対応を見ていると国の機関が発する規制基準を信頼できない。
これから、どのように信頼回復をさせていくのかリスクマネージメントについて取り上げて欲しい"
・市民に分かりやすい講師を呼び、無料で放射線の事を知らない人にセミナーを開催して欲しい
4.3原子力利用
" ・原発の安全性確保の仕組み。
放射能廃棄物処理対策と再生燃料や高速増殖炉の安全性。エネルギー問題。(7)"
・中国や韓国での原発開発や核廃棄物処理に伴う、事故想定時の日本のリスク
・一般的な工業製品の放射線量の測定の実際について基準・規制値、測定実績等
・中性子線は本当に大丈夫か?報道がまびきされているのでは?
・現地の現状を発表する国のフィルターを通らない情報セミナー
・政府の対応や電力会社、保安院の説明に対する正当性評価セミナー
・将来におけるエネルギーの枯渇にどう対処するか
4.4その他
・「放射性物質関連テーマ」を少し時間を掛けて、その2として取り上げて欲しい
・継続的なセミナー開催を期待します。
多数のご来場やアンケートに協力ありがとうございました。
2011年9月2日 大阪水・土壌汚染研究会一同
お問合せ メール:atcmdk@yahoo.co.jp (寺川隆彦)

放射能土壌汚染に関する技術やビジネスマッチング情報を募集します。
http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/5906315.html
<関係ありませんが動画の参考リンク>
【動画】 放射能汚染調査から見た福島とチェルノブイリ(今中哲二)
http://www.youtube.com/watch?v=9U1FKpWiVmg&feature=related
東日本大震災で福島原子力発電所の事故により放射能土壌汚染が生じており、速やかな除染やリスク管理を行うことが急務となっています。
そこで、放射能土壌汚染調査を実際に福島県等で実施し放射能土壌汚染調査のとりまとめにご活躍されている大阪大学核物理研究センターの藤原守先生や、土壌・水環境における放射性物質の分布や環境修復に詳しい京都大学 原子炉実験所の藤川陽子先生、さらにヒロシマ原爆やチェルノブイリの被害で研究された広島大学の星正治先生をお招きしてセミナーを開催します。
土壌汚染の専門家や多くの人たちが、放射能の知識正しく理解し、福島原発周辺の放射能土壌汚染の現状・課題を学び、一刻も早い放射能土壌汚染対策を目指します。
<日時>
2011年8月21日(日) 13時30分~17時00分
<会 場>
大阪大学中之島センター
・10階ホールおよび7階セミナー室
(京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約5分)
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
<プログラム>
開会 13時30分
開会挨拶 放射能土壌汚染セミナー実行委員会
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 教授 理学博士 星正治 氏
質疑応答
セミナーまとめ 星正治 氏
閉会挨拶 放射能土壌汚染セミナー実行委員会
閉会 17時15分
<定員>
計300名
<聴講料>
1000円
<問い合わせ>
大阪水・土壌汚染研究会
案内チラシは↓
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/20110821_housyanou_dozyouosen.doc
<主催>
放射能土壌汚染セミナー実行委員会
大阪 水・土壌汚染研究会
(「大阪水・土壌汚染研究会」は、「おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会」とは、別の組織です。)
<後援>
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィース)、(財)地域地盤環境研究所 NPO石膏ボードリサイクル推進ネットワーク (社)大阪技術振興協会、建設資源リサイクル研究会、(財)災害科学研究所 ジオテク研究会(財)地域地盤環境研究所、 他
<広報協力>
大阪府環境農林水産総合研究所、(財))大阪科学技術センター、公害防止管理者協会、
環境省近畿環境地方事務所、(財)日本環境協会 環境カウンセラー全国事務局、
建設副産物リサイクル広報推進会議事務局((財)先端建設技術センター)、いさぼうネット
大阪府立公衆衛生研究所、環境人材の(株)グレイス、日経エコロジー、ECO JAPAN
福井原子力センターあっとほうむ、エル・パークおおい おおいり館、大阪科学技術センター
環境ビジネスサイト(株)船井総研、読売新聞、環境新聞
公徳心あふれるブロガーの皆様など
<資料提供協力>
福島県大阪事務所、広島平和資料館、(財)環境科学技術研究所(六ヶ所村)、電気事業連合会、
原子力発電所整備機構、Land-Eco土壌第三者評価委員会、福井県安全環境部原子力安全対策課
もんじゅエムシースケアー、 順不同
<講師プロフィール>
SQALF~大阪大学21世紀懐徳堂東日本大震災プロジェクト
メールで東日本大震災へのご質問、および「防災・復興」関連テーマを扱う「第43回21世紀懐徳堂講座」に期待することについてのご意見をお受けします。
セミナーの最後で下記の検討を行うのはいかがでしょうか?
・放射能土壌汚染ビジネス交流会の創設
・放射能土壌汚染セミナーの東京開催(阪神淡路大震災記念日の頃or今秋)
震災復興支援「放射能土壌汚染セミナー」
~震災のいまとこれから・私たちに何ができるのか~
は、多くの方々のご支援やご協力を頂き無事終了いたしました。
お世話になった方々にお礼申し上げます。
このセミナーの準備を通して、多くの方々の支援や親切をお受けし、ここまで準備ができたことに、お礼申し上げます。
早期に、放射能土壌汚染対策の実施を図り、特に子供たちを含む国民の健康が保護されますよう切に希望します。
開会挨拶
放射能土壌汚染セミナー実行委員長(大阪水・土壌汚染研究部会事務局長)

皆様こんにちは
ただいまご紹介を頂きました 放射能土壌汚染セミナー実行委員会でございます。本日は、非常に暑い中、当セミナーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。
また、講師の先生方は、福島やカザフスタンの放射能汚染問題などの対応に非常にお忙しい中、ご講演を快諾して頂きまことにありがとうございました。
ご来場の方々には、東京方面や、新潟、北海道や九州のご遠方からもお越し頂き誠にありがとうございます。
まず、今回の東日本大震災で犠牲になられた2万人を超える方々のご冥福をお祈りいたしますと共に、被災された多くの方々に心からお見舞い申しあげます。
また、現在も福島の原子力発電所対応や放射能汚染対策に従事されている皆様に心から敬意を表します。
さて、私共の実行委員会の紹介ですが、以前より大阪南港で水・土壌汚染について勉強していたメンバーが実行委員となり本日のセミナーの準備をさせていただきました。
セミナーの運営は素人ですので、行き届かぬことが多々あろうかとは存じますが、何卒ご容赦賜りますようお願いいたします。
本日のセミナー開催にあたり、多くの方々から激励や協力を受け、セミナー広報の協力や資料提供等のご支援を頂きましたことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。
この放射能土壌汚染セミナーの準備を多くの方々からの励ましや支援を受けて進めさせていただき、感じましたことは、「まさに、社会が求めている話題であり、福島の放射能土壌汚染問題を是非多くの方とに考え、一刻も早く、放射能リスク低減に向けた除染や放射能土壌汚染対策を実現する必要がある」
ということでございます 。
福島県から国へ「東日本大震災からの復旧・復興に関する要望」が7月に出されていますが、その78項目の内、約半数が放射能に関係するものでございます。
放射能のモニタリング、除染、廃棄物対策、放射線医療や放射能等に関する拠点整備を要望されておられます。
この地元の要望をいかに、速やかに、有効に実施すべきが求められています。
その中でも特に、「身近な生活空間における放射線量低減対策」を早急に進めるべきであり、とりわけ「こども達が受ける放射線量の低減」が重要だと考えます。
本日のセミナーが、一刻も早く放射能土壌汚染対策を促進し、子供たちの放射能による健康被害を予防するのは勿論、学校や社会で明日の福島未来の日本をさせる人に健やかに成長することや、一日も早い被災地復興の一助となることを願いまして開会のあいさつとさせていただきます。
本日はよろしくお願いいたします。
山田様(プロフィール)から
http://www7b.biglobe.ne.jp/toshisyun/profile/profile.htm
放射能土壌汚染セミナーの概要を作成していただきました
http://www7b.biglobe.ne.jp/toshisyun/news/N34kankyoureprort.pdf
PDFが山田さんの記事です。

講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏


放射性壊変:
α壊変:ヘリウムの原子核が放出される
β壊変:電子(陽電子)が放出される
γ壊変:ガンマ線が放出される。
放射性核種(放射能)からベータ線、ガンマ線(放射線)を放出して安定な核種へ変わる
放射性物質(放射能)を測る単位
1ベクレル(1 Bq) = 毎秒1壊変
千倍をk(キロ)、百万倍をM(メガ)、10億倍をG(ギガ)をつけて kBq、MBq、GBqとあらわす。
放射線を測る単位
知りたいのは放射線の影響である
放射線の流れはエネルギーの流れと考えてよい
エネルギーの単位が基礎となる
誰もが浴びる自然放射線
1年間に日本人は2.4 mSvの放射線を毎年浴びている。
2.4 mSv÷365日 =6.6μSv
大地に含まれる放射性同位元素の量(Bq/kg)
種類 一般の土壌・岩石 花崗岩
カリウム40 100~700 500~1600
ウラン238 10~50 20~200
トリウム232 7~50 20~200
国連科学委員会資料
年間にどのくらい被ばくする?
(1)宇宙飛行士 約360 mSv/年
(2)原発従事者等 50 mSv/年以下に管理すること
(3)パイロット 約 1 mSv/年(+2.4 mSv/年)
(4)一般の人 約 2.4 mSv/年
(5)胸部エックス線写真 約0.3 mSv/年
体内の放射能
カリウム40(天然存在比0.012%):4000Bq(毎秒4000個)
炭素14(天然存存在比0.00000000012%):2500Bq(毎秒2500個)
食物などによる放射線の量は年間0.29ミリシーベルト、ラドンなどによる放射線の量は1.26ミリシーベルト
私達の日常生活の中にも放射線を利用した多くの製品があります。例えば蛍光灯のグロー放電管、夜光時計、煙感知器やカメラの内臓ストロボなどに放射線が使われています。
蛍光灯のグロー放電管の中には放射線を出す放射性同位元素プロメシウム147が入っています。このプロメシウム147から出るベータ線の電離作用により、スイッチを入れるとすぐに放電が起こり、蛍光灯が素早く点灯します。 夜光時計の文字盤や針にもプロメシウム147が塗られており、それから出るベータ線により発光します。
影響の種類
確定的影響:しきい線量あり、線量増加で症状が悪化
確率的影響:しきい線量なし、線量増加で発生確率の増加
影響の例
確定的影響:白内障、脱毛、不妊など
確率的影響:ガン、遺伝的影響(すぐに影響は出ない)
つまり、確定的影響がなければ、直ちに健康への影響はない。
しかし、ガンや遺伝的影響のリスクを知らないと判断できない。
1Gyと1Svは同じと考えてよい
確率的影響は、ガン及び遺伝的影響であり、細胞の中のDNAの損傷が原因となっている
細胞レベルの影響
放射線感受性は、
1)分裂の頻度の高いもの、
2)将来行う分裂数の多いもの、
3)形態・機能の未分化なものほど高い。
ガン・遺伝的影響のリスク
表略
これらの値は広島、長崎の原爆被爆者の追跡調査から得られたデータがもとになっている。
一般人の放射線のリスク(年当たり1mSv)
がんになる確率:5.5×10-5
遺伝的影響: 2×10-6
死亡率から見たリスク(年当たり)
がん: 2.7×10-3
心臓病など: 1.4×10-3
脳梗塞など: 1.1×10-3
肺炎など: 1.3×10-3
老衰: 2.1×10-4
不慮の事故 3.2×10-4
交通事故: 7.9×10-5
転倒・転落:5.3×10-5
溺死など: 4.9×10-5
窒息など: 7.4×10-5
自殺: 2.4×10-4
他殺: 5.0×10-6
一般人に対する放射線のリスクは安全とされる範囲内となっている。
放射線のリスク(1Svあたり)
がんになる確率:5.5×10-2
遺伝的影響: 2×10-3
一般人は1mSv/年とされているので
リスクは(年当たり)
がんになる確率:5.5×10-5
遺伝的影響: 2×10-6
放射線のリスクとたばこのリスクの比較
ガン全体
ガン全体にたいする放射線のリスク:1Svあたり5%(5×10-2 Sv-1)
ガン全体のリスク:10万人当たりの年死亡率257人(2.7×10-3)
たばこによる相対危険度~1.6(非喫煙者を1としたときの危険度)たばこの寄与は0.6となる。
たばこのリスクに対する寄与:2.7×10-3×0.6 = 1.6×10-3
放射線に換算:1.6×10-3/(5×10-2 Sv-1)= 0.032Sv = 32mSv/年
肺がん
肺ガンにたいする放射線のリスク:1Svあたり1%(1×10-2 Sv-1)で肺に対する組織荷重係数は0.12なので、1Svのうち0.12Svが肺に寄与すると考て、リスクは0.083 Sv-1となる。
肺ガン全体のリスク(男):10万人当たりの年死亡率44人(4.4×10-4)
たばこによる相対危険度 1-4本 5-14本 15-24本 25-34本
相対危険度 2.5 3.3 5.4 7.1
たばこの寄与 1.5 2.3 4.4 6.1
リスクに対する寄与 6.6×10-4 1.0×10-3 1.9×10-3 2.7×10-3
放射線に換算 8mSv/年 12mSv/年 23mSv/年 33mSv/年
放射線:ICRPのデータ、死亡率等は厚労省データ
1983年にCo-60(半減期5.27年)が混入した鉄筋でビルが建てられた。最初の年は1100人が500ミリシーベルトも被ばく。
Wikipedia
ホルミシス効果とは、生物に対して通常有害な作用を示すものが、微量であれば逆に良い作用を示す生理的刺激作用のこと。ホルミシスとは、ギリシャ語のホルメに由来する。このホルメはホルモンの語源でもある。意味は、「刺激する」である。特に自然放射線の人体への健康効果を指す場合は、放射線ホルミシス効果、また放射線ホルミシス学説ともいう。ホルメシスとも表記される。
環境放射線の積極的な利用としての放射能泉
自然放射線または環境放射線の積極的な利用は、放射能泉であるラドン温泉やラジウム温泉で行われてきた。ラドン222の濃度が74ベクレル/リットル以上がラドン温泉であり、ラジウムが1億分の1グラム/リットル以上含まれるのがラジウム温泉である。
ヨーロッパのオーストリアでは、インスブルック大学医学部が、1950年代からザルツブルク大学理学部と共同研究を行い、ヨーロッパアルプス山脈の中にあるバートガシュタインのラドン坑道を活用して、年間 約 10,000 人の強直性脊椎炎(ベヒテレフ病)、リウマチ性慢性多発性関節炎、変形性関節症、喘息、アトピー性皮膚炎などの患者に対してラドン吸入療法を行っている。ここでの空気中ラドン222濃度は110ベクレル/リットル以上で放射能療養坑道と呼ばれている。
オーストリアや日本、ロシアなどではこの放射線ホルミシス理論を根拠に、ラドン温泉(ラジウム温泉)の効用がうたわれ、療養のために活用されるラドン温泉やラドン洞窟が存在する。
線量限度(国際放射線防護委員会の勧告)医療被ばくは含まない
職業被ばく 公衆被ばく
実効線量 100mSv/5年 1mSv/年
但し、50mSv/年を
超えない
等価線量
目の水晶体 150mSv/年 15mSv/年
皮膚 500mSv/年 50mSv/年
手および足 500mSv/年
日本の法令には公衆被ばくの規定はない。ただし、放射線事業所の境界を1mSv/年と定めている。
飲食物摂取制限
・原子力施設等で事故が起き、敷地外の一般公衆が過度の被ばくをする恐れのある場合、考慮するべき重要な
核種は、131I、137Cs、90Srなどである。
摂取制限値の飲食物を1年間摂取しつづけた時のリスク
137Csは筋肉にとどまり、全身に被ばく線量を与える。
初年度 5mSv が摂取制限となる。
摂取制限値の飲食物を1年間摂取しつづけた時のリスクは、1mSv/年で5.5×10-5なので、2.8×10-4/年である。
これは不慮の事故のリスク3.2×10-4/年と同じ程度である
飲食物に含まれる放射能の摂取限度は、5 mSvを制限値にしているので、この10倍の物を1年間飲食しても、50 mSv/年であり、ガンのリスクは0.25%となる。
放射線の影響のない場合のガンのリスクが30%程度であることを考えると、大きな影響とは言えない。
離れた地域で放射線レベルが上がっていることについて
福島原発事故直後、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、静岡の1都7県で計測された放射線レベルでは最大で、毎時1μSvと報告された。
放射線のレベルが通常の10倍あるいは100倍というと大変、高い線量のように感じられる。実際には健康に影響のないレベルである。
この放射線レベルで1 年間生活した場合、1年は8760時間だから、8.8mSvで、CT検査1回分の線量で健康に影響のないレベル
すべての場所で4-5cmの深さで、ほぼ100%の放射能が含まれる。
分布はほぼ指数関数である。I∙exp(-λ∙d)
d:表面からの深さ
10分の1減衰距離(L1/10)は18-48 mm
4月に取ったサンプルと比べればL1/10は少し伸びているように見えるが、場所の違いのファクターが大きいかもしれない
これから
子供たちに未来を託せる環境をつくる。
そのためには?
個々の住居の放射能被曝低減
・屋根などに付着しているセシウムなど放射性物質を洗い流す。
・古い葉の除去や雨樋を掃除し、雨樋の下の地面など、家屋周辺の土壌5cm程度を撤去する。
・家屋周辺を15cm程度の厚さのコンクリート壁で囲う。セシウムからのガンマ線は15cm程度のコンクリートで10分の1以下に減少する。(セシウムからの660 keVガンマ線は空気中100mを飛んでやっと40%に減少、200m飛んでも16%しか減少しない。現在報告されている空間線量は、空気中に漂うっている放射性物質のものからでなくて、地表から放出されたガンマ線を測定した結果です。)
・丁寧な対策で生活物資さえ安定に供給されれば、放射線被爆の問題が無く生活だけは続けて行けるでしょう。
●講 師 藤原 守 大阪大学 核物理研究センター 准教授
略歴
大阪大学 理学部 物理学科 卒業
大阪大学 理学研究科 物理学専攻 修士 修了
大阪大学助手を経て助教授
日本原子力研究所先端基礎研究センター(グループリーダー)
研究内容
放射線検出器、レーザー電子光によるクォーク核物理、原子核の巨大共鳴、
磁気スペクトロメーター、原子核構造 など
学会活動
アメリカ物理学会、 日本物理学会 、日本放射光学会http://www.jssrr.jp/
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspI/RX0011D.asp?UNO=12453
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏


わが国の土壌の特性と放射性セシウムの挙動
わが国の土壌は概して、放射性セシウムを吸着しやすい。
一方、諸外国にはセシウム低吸着性の土壌もある。典型例は酸性ポドソル、泥炭等である。このような土壌は土壌生成論的には、日本の本州地域ではどちらかおいうと稀である(一部の高地等には存在する)。これらの土壌でセシウムが吸着しにくい要因としては、pHや土壌の荷電特性、土壌鉱物組成、比表面積、溶解性の有機物量等の特性が関与している。
なお、セシウムは安定同位体としても存在し、土壌水中のその濃度が高ければ同じ土壌でも放射性セシウムの吸着力は低下するが、筆者の経験では、日本の土壌水中の安定同位体のセシウム濃度は低い。仮に土壌の放射性セシウム吸着特性を実験的に検討するときに、安定同位体のセシウムを自然界における以上の量、加えてしまうと、キャリアフリー(無担体)の放射性セシウムで実験するのとまったく異なる結果となるので注意が必要である。
●講 師 藤川 陽子 京都大学 原子炉実験所 准教授
略歴
京都大学大学院工学研究科 衛生工学専攻 修了
京都大学原子炉実験所、助手を経て、助教授、職制変更後、准教授。
専門
環境工学、放射性廃棄物地層処分の安全評価、
放射能・各種重金属・有機汚染物質の土壌圏・水圏における動態、
汚染環境修復技術
学会活動
保健物理学会、土木学会、水環境学会、環境技術学会、原子力学会など。
放射性廃棄物の地中処分に関連して、地水圏中の放射能等の地質媒体への吸着特性解明のための基礎実験、移行モデル構築とモデルの解法の検討、自然環境中の極微量のウラン・プルトニウム・水銀等の移行・分布挙動の調査をおこなっています。
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901065603176505
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 教授 理学博士 星正治 氏


土壌汚染の性質
1.今後問題になる放射能は、半減期30年のセシウム-137である。
2.セシウム-137は土壌に付着すると堅く結びついて何十年もそのままである。
3.そのため、グラウンドや庭など表層土壌に良く付着する。
4.また、木の葉などには強く付着する。同様に稲わらや腐葉土にも良く付着する。
5.道路ではアスファルトではなく、路肩に放射能が多い。雨水などが流れてセシウムが路肩に吸着する。
6.側溝の土壌や雨樋の下など水の流れる場所にも集積する。
7.セシウムの性質を見極め、多量に集積している場所を知る。そこが土壌か植物の葉か、腐葉土かなのかなど材質を区別して除染に当たる。
8.植物などは焼却する。セシウムが蒸散しないよう、一定の温度以下で焼却する。必要に応じて、除染のための排煙装置なども考案する。
土壌汚染の除去
1.福島の放射能汚染は表層から1-3cmまでに沈着している。従って表層から5cm位を剥がす除去すると有効である。
2.1/2から1/10くらいまで表面線量が低下できるとの調査がある。
3.汚染していない土壌を、除去後表層にかぶせると更に安全となる。
4.セシウムは土壌に付着すると数十年たっても離れないので、保管する際、他に移行しにくい性質を持つ。
5.最終的には、処理した土壌は、ゴミの最終処分場を作りそこに搬入し,保管する。
6.焼却灰も同様である。
7.最終処分場がすぐにできない場合は、土嚢袋などに入れ、グランドのコーナーに埋設する。後で取り出して最終処分場に移動する。
8.チェルノブイリではコーナーに山にして積み上げていた。これも有効である。
9.汚染の除去における、基準値の確定が必要である。どのレベルで除去し、どのレベルで最終処分場に持ち込むか、また更に大きい高レベルの土壌をどう処理するかなど。
10.これらは、ボランティアで可能な範囲を超え、学術的な調査と、それをトータルで実行できる事業者が必要となる。
11.汚染やそれに伴う被ばくは進行中であり、早急な対処が必要である。
今後の調査の必要性と内容について
1 . 地表の表面汚染調査
a) 広域汚染地図の作成
b)土壌のサンプリング
c)汚染地域での食品の採取
d) 土壌測定
I-131、Cs-134,Cs-137 からのガンマ線量を測定する。
2 . 住民の被ばく線量調査
住民の被ばく線量について、以下の項目のような調査を行う。
1. 専門家チームを組んでポータブルまたは全身カウンターで計測する。甲状腺についてはI-131 (ヨウ素)を測定し、Cs-137 については全身カウンターで腹部を測定する。
2.特に、子供や妊婦が測定の対象となる。
3. I-131 の測定は特に重要で、10 半減期以内に行う。その観点から6 月15 日までに至急に測定を行う必要がある。
放射線防護の原則
・不必要な放射線被ばくは避ける(行為の正当化)
・被ばくする線量,被ばくする人の数をできるだけ少なくする(放射線防護の最適化)
・1人ひとりの個人の線量は,法令などに定められた上限値を超えないようにする(線量の制限)
質疑応答
たくさんのご質問をありがとうございました。全ての質問票に講師の方からお答えいただきました。
●講 師 星正治
広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線影響評価研究部門 線量測定・評価研究分野 教授 理学博士
履歴
大阪大学理学部 物理学学科、同大学院 理学研究科 物理学専攻出身
大分工業大学講師、
広島大学原爆放射能医学研究所助手、助教授を経て
1994より現職である広島大学原爆放射線医学研究所教授、現在に至る。
社会活動等
原子力委員会委員
原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員会
放射線被曝者医療国際協力推進協議会
科学技術・学術審議会(研究計画・評価分科会)
国連科学委員会国内対応委員会
日本学術振興会科学研究費委員会
JICAセミパラチンスク地域医療改善計画国内支援委員会
中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター詰問委員、他。
受賞等
カザフスタン共和国の人々の健康維持管理への貢献に関する特別賞 (2004/01)
第12回国際放射線影響学会賞 (2003/08)
カザフスタン共和国の人々への保健システムへの貢献に関する特別賞(1999/10)
学会活動
日本医学物理学会、日本医学放射線学会、日本医学放射線学会医療用標準線量研究会、
日本医学放射線物理学会、日本原子力学会、日本放射線影響学会、日本放射線技術学会
放射能土壌汚染セミナーまとめ
寺川さんの開会の挨拶でいいんじゃないですか!
広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 理学博士 星正治 教授
平成23年8月21日 17時15分 大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホールにて
閉会挨拶
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 事務局長 姜(カン)永根
質問:福島原発周辺はいつになれば安全(入ってもよい)となるのでしょうか?
答: 福島原発周辺の放射能レベルは距離によって、また地形によって違います。
藤原 守 放射能土壌汚染セミナー講師
3月の福島第一原子力発電所事故では水素爆発のために原子炉中の放射性物質(主にヨーソ131(131I:半減期8日), セシウム(134Cs:半減期2年, 137Cs:半減期30年)が大気に飛散し、それが、雨や雪が降ることによって地上に降り注ぎました。
気象条件の違いで初めは北部の方向に風によって運ばれ、飯舘村などに多くの放射性物質が地上に降下しました。その後、この風向きは太平洋側に向かい、その後、南に方向を変えました。その時々の、雨や雪の降り方で地上に降った放射性物質の降り方が違うのです。ヨーソとセシウムは水への溶融度の違いによって土壌放射性物質の降下の仕方が違うという事が、はっきりしています。
また、20km圏外の飯舘村の放射能レベルが高く、20km圏内のすぐ近くの川内村などの放射能は1 mSv/hレベルで普通に生活しても全く大丈夫なようです。文部科学省プログラムをリードした形で大阪大学は、こういった放射性物質汚染度マップの作成に大きく貢献しています。
ヨーソ131の半減期は8日です。この放射能は80日も経てば1000分の1になり160日(約半年)も過ぎれば百万分の1に減少します。しかしセシウム137の半減期は30年ですから、30年経っても半分ということになり降下した放射能はなかなか減少しません。降下した放射能は、土壌表面にくっつき雨が降っても5cmも浸透していない事もわかっています。
屋根に降った放射性物質は、太陽に照らされ雨に流され雨樋に集まります。雨樋の下の地面の放射能レベルが高いのはこのためです。また、道路のアスファルトの上に降ったものは雨に流され側溝に集まります。側溝に集まった土砂は、大量の雨が降る梅雨後に川に流され河川の汚染ということになります。樹木の葉っぱにも放射性物質がくっついています。
秋になって、木の葉が舞い落ちる季節には、やはり放射性物質の拡散が起こります。
夏の日照りに照らされ、表面の土壌がホコリとなって風に舞いあげられる季節にも放射性物質の拡散が起こります。
しかし、一般的に言って、土壌や大気の循環によるこれらの拡散過程は非常にゆっくりしたものです。
したがって一般的に云えば、30年経っても放射能レベルの減らない高放射線領域に、何も対策を講じないで、そのまま住めるようになるという状況は考えられません。
個々の住居に対しての放射能被曝を低減する方策としては、簡単です。
1.屋根などに付着しているセシウムなどの放射性物質を洗い流す。
2.雨樋を掃除し、雨樋の下の地面など、家屋周辺の土壌5cm程度を撤去する。
3.家屋周辺を15cm程度の厚さのコンクリート壁で囲う。
セシウムからのガンマ線は15cm程度のコンクリートで10分の1以下に減少するので、家屋周辺からの放射線被爆を減少できる。(セシウムからの660 keVガンマ線は空気中100mを飛んでやっと40%に減少、200m飛んでも16%しか減少しない。現在報告されている空間線量は、空気中に漂うっている放射性物質のものからでなくて、地表から放出されたガンマ線を測定した結果です。)
などの丁寧な対策で生活物資さえ安定に供給されれば、放射線被爆の問題が無く生活だけは続けて行けるでしょう。
しかし、はたして、福島原発周辺の個別の少数の人々にとってのこういった特殊な対策が十分な対策として成り立つかが問題です。福島第一原子力発電所廃炉には数十年の長い年月を要します。
この長い60年間に、原子炉を雇用のよりどころとしてきた多数の人々の生活再建をどのようにしていくかを考えない限り「原子炉周辺にはいつ入れるのか?」という問いには答えた事にはなりません。経済的に雇用を創出し、子供たちが明るい未来を考える事の出来る文化的社会創出を考えて行くことが必要です。
私たちが招いた危機をしっかり見つめ、この危機を克服しチャンスにかえることが出来るかを考えること。これが重要です。さもなければ、福島原発周辺は、文明に見捨てられた廃墟となるでしょう。このような文明の廃墟は世界中にあります。
一人の科学者の私案として、参考意見を述べさせていただくならば、福島原発周辺の産業、社会復興で必要なのは以下に述べるような「長い道程」の大規模改造を行う事ではないでしょうか?
放射能レベルを下げるためには、土壌を掘り下げ、天地返しをする以外には無いでしょう。しかし、これを個別な小さな個別地域で行っても、経済効果は少ないので、大規模に行う。これらは、
1. 放射線レベルの高い周辺地域20 kmx40km領域の山谷を削り、埋め立てることによって広大な平地を作りだす。オランダでは長い年月をかけて広大な土地を開拓してきた歴史がある。オランダの例を見るならば、20kmx40kmはそれほど広大な土地ではない。土木産業によって巨大な雇用が生まれる。また、放射能レベルの低減も出来る。
2. 太陽パネルを敷き詰め、新たなエネルギー産業を創出し、雇用を確保する。東大の試算によれば、日本のエネルギー重要を賄うには一万平方kmに太陽パネルを設置する必要があるとのこと。福島原発周辺の20 km x 40 kmに敷きつめても800平方kmであり、10%程度である。また、電気エネルギーを電気分解して蓄えておく蓄電施設や水素燃料施設も必要となる。
3. 高等教育機関の設立、自然再生エネルギーや放射線に関しての研究機関、病院の設置。
4. 大規模工業団地の設立。
5. 港湾、飛行場など、物資輸送のハブ施設の設立
6. 人々が集まるようになればアミューズメント施設や商店街なども出来る。
7. 金融マネージメントセンター、ITセンターの設立
となろう。
もちろん、水の放射能汚染などの問題はある。しかし、これは、現状でも早晩問題視され、しかも、解決が難しい問題である。必要総費用は100兆円以上の巨大プロジェクトになり、未解決の問題は多くあるが、長期間にわたる科学的検討と着実な施策立案によって福島の再生が可能となるでしょう。
また、個別の人々の問題はしっかりとした科学的対応で解決して行くことも極めて重要です。
福島にゆかりのある高村光太朗の詩「道程」はこのように歌っている「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出きるる。ああ、自然よ。父よ。僕を一人立ちさせた広大な父よ。僕から目を離さないで守る事をせよ。常に父の気魄を僕に充たせよ。この遠い道程のため。この遠い道程のため。」
長い希望への闘いの道程を一歩進み出すかどうかは、日本の我々の選択肢の一つでしょう。
放射能土壌汚染セミナーアンケート結果集計表
平成23年8月21日に大阪大学中之島センターで開催
主催:放射能土壌汚染実行委員会(大阪水・土壌汚染研究会)
1.どの講演内容に興味を持ちましたか?複数回答可
講演1 講演2 講演3 その他
50 47 69 デモが良かった
2.あなたの疑問に対し、どの講演内容が回答に近かったですか?複数回答有り
全回答数: 81
講演1 講演2 講演3 その他
22 24 47 0
属性の内訳は下記の通り
回答性別(枚) 男性 64 女性 9 未回答 8
回答年齢(枚) 20未満 0 20代 2(1) 30代 7(2)
※()内女性 40代 11(2) 50代 21 60代以上 30(4)
3.セミナー運営に対する意見 注:(数)は同様な意見数
3.1肯定的な意見
" ・興味深く聞かせて頂き有難う御座いました。運営方法は、大変良かった、放射線の事が理解できた。
有効な内容を3人の講師が判り易く説明頂きました。タイムリーで安価な良いセミナー。 (11)"
・質問に対し丁寧な回答、有難う御座いました。質疑応答が良かった。(2)
・放射能について正しい知識を学ぶ機会として有益でした
・内容はいずれも面白く、”5cm”の重要性が非常によく理解できました
・専門が土木なので、シーベルトやベクレル等の基礎知識が役に立ちそう
・パネルディスカッションを組むと盛り上がると思う
・放射能について正しい知識を学ぶ機会として有益でした
・今後とも続けて下さい、今後の汚染土壌マップ等
・言いにくいことも説明あり良かった
・星先生の写真やデータが判り易かった
・手作り感と一体感が有ってよかった。
3.2改善意見
・時間が短すぎる。講演時間をもっと長く欲しい。(4)
・土壌汚染の課題と対策についてもっと突っ込んで欲しかった
・放射能汚染土壌に関する内容が少ない
・放射能汚染の基礎的な説明が大半で震災復興の話が不足していました
・内容の重複がある
・藤川先生のパワーポイントをじっくり見たかった
・ストロンチウム90の説明を入れて欲しい
・レーザーポインターが7Fで見れなかったのが残念でした
・汚染土壌に対する対応策が少なく、一般の放射線説明が中心だった
・受講料を無料にしてほしい
・講演者の語尾が聞き取りにくい。マイクのチェックが必要
・タイムマネジメントをしっかり御願いしたい
・専門的内容で分かりにくかった
・質問票記入、忙しいです
3.3今後の期待
・放射線被ばくに関して、ICRPかECRPのどちらが信頼に値するか。後者はカルト。
・次のセミナーは関東地区でも会場を確保して頂くと有りがたいです
・放射線を止めるセミナーを実行して欲しい
・放射能に関する国民教育、電力会社の体質の公開
・今後、セミナー実行委員会として国等へ働き掛けていくのか?
・現場の今を聞きたい
3.4その他意見
・放射線被ばくに関して、ICRPかECRPのどちらが信頼に値するか。後者はカルト。
4.今後のセミナーで取り上げて欲しいテーマ
4.1土壌汚染関係事業者向け
" ・土壌等の除去の詳細方法。どのような事業者や団体が除染を進めているか等。
土壌汚染の実施可能な処理方法。企業向けとして具体的な除染について。
具体的な除染方法について行政・ゼネコンの意見。(13)"
・今回のテーマについて、更に追及して欲しい。同じテーマでも継時的に見てみたいです。(3)
・医学的知見のセミナー(内部被ばく)。人体への影響について。(3)
・放射能のその時点での循環等の拡散状態やその危険度合い
・ファイトレメデェーションが現在どれくらい使われているか
・ファイトレメデェーションと放射能汚染土壌
・今後の調査について汚染結果動向をセミナーで報告して欲しい
・実際に除染に携わった事例等について講演して欲しい
・土対法と放射能汚染、現状のままで良いのか?環境省
・土壌汚染の技術的セミナー
・環境修復に関する事例紹介
・土壌の自然由来放射線やビキニ環礁、チェルノブイリの管理状況とデータ公開
・瓦礫の処分に関する法律
・リスクマネージメント的なセミナー
・放射能汚染された水の流れと影響
・汚染のしきい値(安全)の考え方を明らかにするセミナー
・異分野情報や農耕地汚染問題も取り上げて欲しい
・医学的知見のセミナー(内部被ばく)。人体への影響について。(3)
・体調異変の集計結果
4.2消費者・市民向け
" ・消費者として、農産物への影響を取り上げて欲しい。
水質汚染、大洋魚汚染も知りたい。食品に関するセミナー。
海洋の汚染状況と今後の広がり方、海洋の除染方法、海産物への影響。(5)"
・現地の住民に役立つ内容や具体的なアクションに移した報告を伺いたい。
・放射線測定法を知りたい。
・汚染土処理の方法や処理土の受入れの有無を判断するのは「住民」OR「行政」?
・環境省の方策?「情報開示・意思決定とスキームの構築」が社会にとって重要性が増していると考えます。
" ・結局、放出された放射線は我々が受け入れるしかない。
ただ、一連の対応を見ていると国の機関が発する規制基準を信頼できない。
これから、どのように信頼回復をさせていくのかリスクマネージメントについて取り上げて欲しい"
・市民に分かりやすい講師を呼び、無料で放射線の事を知らない人にセミナーを開催して欲しい
4.3原子力利用
" ・原発の安全性確保の仕組み。
放射能廃棄物処理対策と再生燃料や高速増殖炉の安全性。エネルギー問題。(7)"
・中国や韓国での原発開発や核廃棄物処理に伴う、事故想定時の日本のリスク
・一般的な工業製品の放射線量の測定の実際について基準・規制値、測定実績等
・中性子線は本当に大丈夫か?報道がまびきされているのでは?
・現地の現状を発表する国のフィルターを通らない情報セミナー
・政府の対応や電力会社、保安院の説明に対する正当性評価セミナー
・将来におけるエネルギーの枯渇にどう対処するか
4.4その他
・「放射性物質関連テーマ」を少し時間を掛けて、その2として取り上げて欲しい
・継続的なセミナー開催を期待します。
多数のご来場やアンケートに協力ありがとうございました。
2011年9月2日 大阪水・土壌汚染研究会一同
お問合せ メール:atcmdk@yahoo.co.jp (寺川隆彦)

放射能土壌汚染に関する技術やビジネスマッチング情報を募集します。
http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/5906315.html
<関係ありませんが動画の参考リンク>
【動画】 放射能汚染調査から見た福島とチェルノブイリ(今中哲二)
http://www.youtube.com/watch?v=9U1FKpWiVmg&feature=related
2011年08月28日
大阪水・土壌汚染研究会の紹介
大阪 水・土壌汚染研究会
大阪水・土壌汚染研究会は2010年5月19日に大阪南港のATCで設立しました。
(「大阪水・土壌汚染研究会」は、「おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会水・土壌汚染研究部会」とは別の組織です。)
大阪水土壌汚染研究会規約草案
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/osakwsp_kiyaku.doc
<分科会>
・放射能土壌汚染分科会
・原子力発電研究部会
・エネルギー研究部会
・汚染土地取引分科会
・底質汚染分科会
・循環型社会ビジネス分科会
・東アジア環境ビジネス・歴史分科会
・生物多様性分科会
・リスクマネジメント分科会
<組織>
会長代行
奥村勝(技術士 環境部門)
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 副事務局長
事務局長
(環境カウンセラー)
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 実行委員長
幹事
姜
鈴木
久保田
藤原
会員募集中
<会員の取得資格>
・環境カウンセラー
・技術士(環境部門・建設部門)
・技術士(総合技術監理部門)
・測量士
・一級土木施工管理技士
・宅地建物取引主任者
・測量士
・土壌汚染調査技術管理者
・公害防止管理者
・環境計量士
・放射能関係資格
・危険物取扱主任
・マイコン認定
・土壌環境監理士
・リスクマネジヤー
・土壌環境リスク管理者
協力団体募集中
<活動対象キーワード>
・震災復興
・放射能土壌汚染
・放射能汚染廃棄物
・水俣の土壌地下水汚染
・山口県周南市(徳山)水銀汚染底質
・岡山市小鳥が丘団地(両備)
・桃花台ニュータウン地盤沈下と土壌地下水汚染
・神栖ヒ素汚染
・日本海、東シナ海、南シナ海の環境汚染
・底質汚染(大阪湾カブトガニ復元プロジェクト)
・東アジアの環境ビジネスと歴史共通認識
・リスクマネジメント
・電気の安定・安全・安心
・環境資格受験指導(サークル)
メーリングリストできました↓
http://groups.yahoo.co.jp/group/osakawsp/
活動経過
2011年5月 設立
2011年5月 都城市地下水汚染踏査
2011年5月 2010年宮崎口蹄疫原因調査(埋殺地、牧場、畜産試験場、県庁)
2011年5月 日向古代歴史学習(西田原古墳群、宮崎歴史博物館など)
2011年6月 周南市徳山水銀埋立場所調査
2011年6月 鞆の浦朝鮮通信使学習
2011年6月 カブトガニ博物館館見学
2011年6月 熊本県地下水保全見学
2011年6月 広島原爆資料館見学
2011年7月 福井県、もんじゅ、大飯原発見学
2011年6月 広島原爆資料館・平和イベント参加
2011年8月 大阪大学中之島センター「放射能土壌汚染セミナー」主催
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター 理学博士 藤原 守 准教授
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門 工学博士 藤川 陽子 准教授
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所 放射線影響評価研究部門 理学博士 星正治 教授
2011年9月 大阪市立環境学習センター(生き生き地球館)
セミナー「原子放射線は、人の健康や環境にどのような影響があるか」
(講師 京都大学 原子炉実験所 藤川陽子 准教授)
放射能教育パンフレット手配の協力
2011年9月 島根県立古代出雲歴史博物館 環日本海歴史学習 島根原発見学
2011年9月 壱岐アジアの歴史学習(原の辻ガイダンス、一岐国博物館、安国寺)
2011年9月 玄海原発見学
2011年9月 長崎県鷹島アジア歴史学習(松浦町立鷹島歴史資料館他)
2011年10月 大阪大学21 世紀懐徳堂講座「ここから拓く未来」
福島第一原子力発電所から出た放射性物質の分布 講座
核物理研究センター 准教授 藤原 守 大阪大学中之島センター
において放射線物質関連資料提供協力
2011年10月 Land-Eco 土壌第三者評価委員会セミナー「自然災害・自然由来による土壌汚染を考える」
会場:おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトーププラザ
講演:「『建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル』について」 京都大学 名誉教授土壌第三者評価委員会 名誉委員長 嘉門 雅史 氏
講演:「土壌汚染と放射性セシウム」京都大学 原子炉実験所 准教授 土壌第三者評価委員 評価員 藤川 陽子 氏
において放射線物質関連資料提供協力
2011年11月 八町原地熱発電所見学、竹田市・大分市歴史資料館見学
2011年11月 水俣グリーンニューディール
土壌汚染調査基金募集中
大阪水・土壌汚染研究会は2010年5月19日に大阪南港のATCで設立しました。
(「大阪水・土壌汚染研究会」は、「おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会水・土壌汚染研究部会」とは別の組織です。)
大阪水土壌汚染研究会規約草案
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/osakwsp_kiyaku.doc
<分科会>
・放射能土壌汚染分科会
・原子力発電研究部会
・エネルギー研究部会
・汚染土地取引分科会
・底質汚染分科会
・循環型社会ビジネス分科会
・東アジア環境ビジネス・歴史分科会
・生物多様性分科会
・リスクマネジメント分科会
<組織>
会長代行
奥村勝(技術士 環境部門)
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 副事務局長
事務局長
(環境カウンセラー)
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 実行委員長
幹事
姜
鈴木
久保田
藤原
会員募集中
<会員の取得資格>
・環境カウンセラー
・技術士(環境部門・建設部門)
・技術士(総合技術監理部門)
・測量士
・一級土木施工管理技士
・宅地建物取引主任者
・測量士
・土壌汚染調査技術管理者
・公害防止管理者
・環境計量士
・放射能関係資格
・危険物取扱主任
・マイコン認定
・土壌環境監理士
・リスクマネジヤー
・土壌環境リスク管理者
協力団体募集中
<活動対象キーワード>
・震災復興
・放射能土壌汚染
・放射能汚染廃棄物
・水俣の土壌地下水汚染
・山口県周南市(徳山)水銀汚染底質
・岡山市小鳥が丘団地(両備)
・桃花台ニュータウン地盤沈下と土壌地下水汚染
・神栖ヒ素汚染
・日本海、東シナ海、南シナ海の環境汚染
・底質汚染(大阪湾カブトガニ復元プロジェクト)
・東アジアの環境ビジネスと歴史共通認識
・リスクマネジメント
・電気の安定・安全・安心
・環境資格受験指導(サークル)
メーリングリストできました↓
http://groups.yahoo.co.jp/group/osakawsp/
活動経過
2011年5月 設立
2011年5月 都城市地下水汚染踏査
2011年5月 2010年宮崎口蹄疫原因調査(埋殺地、牧場、畜産試験場、県庁)
2011年5月 日向古代歴史学習(西田原古墳群、宮崎歴史博物館など)
2011年6月 周南市徳山水銀埋立場所調査
2011年6月 鞆の浦朝鮮通信使学習
2011年6月 カブトガニ博物館館見学
2011年6月 熊本県地下水保全見学
2011年6月 広島原爆資料館見学
2011年7月 福井県、もんじゅ、大飯原発見学
2011年6月 広島原爆資料館・平和イベント参加
2011年8月 大阪大学中之島センター「放射能土壌汚染セミナー」主催
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター 理学博士 藤原 守 准教授
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門 工学博士 藤川 陽子 准教授
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所 放射線影響評価研究部門 理学博士 星正治 教授
2011年9月 大阪市立環境学習センター(生き生き地球館)
セミナー「原子放射線は、人の健康や環境にどのような影響があるか」
(講師 京都大学 原子炉実験所 藤川陽子 准教授)
放射能教育パンフレット手配の協力
2011年9月 島根県立古代出雲歴史博物館 環日本海歴史学習 島根原発見学
2011年9月 壱岐アジアの歴史学習(原の辻ガイダンス、一岐国博物館、安国寺)
2011年9月 玄海原発見学
2011年9月 長崎県鷹島アジア歴史学習(松浦町立鷹島歴史資料館他)
2011年10月 大阪大学21 世紀懐徳堂講座「ここから拓く未来」
福島第一原子力発電所から出た放射性物質の分布 講座
核物理研究センター 准教授 藤原 守 大阪大学中之島センター
において放射線物質関連資料提供協力
2011年10月 Land-Eco 土壌第三者評価委員会セミナー「自然災害・自然由来による土壌汚染を考える」
会場:おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトーププラザ
講演:「『建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル』について」 京都大学 名誉教授土壌第三者評価委員会 名誉委員長 嘉門 雅史 氏
講演:「土壌汚染と放射性セシウム」京都大学 原子炉実験所 准教授 土壌第三者評価委員 評価員 藤川 陽子 氏
において放射線物質関連資料提供協力
2011年11月 八町原地熱発電所見学、竹田市・大分市歴史資料館見学
2011年11月 水俣グリーンニューディール
土壌汚染調査基金募集中