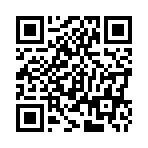2009年12月12日
ISO9000
ISO 9000は、国際標準化機構による品質マネジメントシステム関係の国際規格群。1994年版から2000年版への改正によって、それまでの「製品品質を保証するための規格」から、「品質保証を含んだ、顧客満足の向上を目指すための規格」へと位置付けが変わっている。
目次
1 改定履歴
2 規格要求事項
2.1 JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
3 ISO 9001:2008(2008年改訂版)
4 課題
5 関連項目
改定履
1987年にISO 9000の規格が制定されてから、1994年と2000年さらに2008年にそれぞれ規格改定が行われた。
ISO 9000:1987
ISO 9000:1994 「94年版」と呼ばれる。
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000 「2000年版」と呼ばれる(ISO 9001)。
「2000年版」と呼ばれる規格
ISO 9000:2005 品質マネジメントシステム―基本及び用語
ISO 9001:2000 品質マネジメントシステム―要求事項
国内での批准翻訳的な規格は、JIS Q 9000:2006 / JIS Q 9001:2000などがある。
2008年版の改正は主に要求事項の明確化とISO 14001 との整合性の向上を目的として行われた。
規格要求事項
ISO 9001(品質マネジメントシステム―要求事項)の目次の一部を下に示す。
4. 品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
4.2 文書化に関する要求事項
5. 経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
5.2 顧客重視
5.3 品質方針
5.4 計画
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.6 マネジメントレビュー
6. 資源の運用管理
6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.3 インフラストラクチャー
6.4 作業環境
7. 製品実現
7.1 製品実現の計画
7.2 顧客関連のプロセス
7.3 設計・開発
7.4 購買
7.5 製造及びサービス提供
7.6 監視機器及び測定機器の管理
8. 測定、分析及び改善
8.1 一般
8.2 監視及び測定
8.3 不適合製品の管理
8.4 データの分析
8.5 改善
JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1 品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2 “アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3 アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
ISO 9001:2008(2008年改訂版) [編集]
ISO(国際標準化機構)が、規格の内容の明確化等を目的に平成20年11月15日付けでISO 9001 の改正版を発行したことによって、経済産業省は平成20 年12月20日付けで、JIS Q 9001(品質マネジメントシステム規格)を改正した。今回の改正は、JIS Q 9001 の規格の内容の明確化等を目的とするものであり、組織に要求される事項を追加・変更するものでない。主な改正点は以下のとおり。
(1)規格要求事項の明確化
品質マネジメントシステム:一般要求事項【4.1】アウトソースしたプロセスの管理について、本文の中に“組織は「管理の方式及び程度」を定めなければならない”とするとともに、注記に、「管理の方式及び程度」は以下の3 つの要因により影響されうると説明を追加した。
・アウトソースしたプロセスの適合製品を供給するという組織の能力への影響の可能性
・アウトソースしたプロセスの管理への組織の関与の度合い
・購買管理を遂行する組織の能力
改善:是正処置【8.5.2】及び予防処置【8.5.3】現行版の本文にある“是正処置において実施した活動のレビュー”を、“とった是正処置の有効性のレビュー”と修文することで、ここにおけるレビューとは「実施した是正処置の結果の確認を含む」ことであることを明確にした。
(2)JIS Q 14001 との整合性の向上
記録の管理に関する要求事項【4.2.4】について、JIS Q 14001 との記述順序を揃えることで整合性を向上させた。
■ 品質マネジメントシステム−要求事項 ■
Quality management systems - Requirements
-------------------------------------------------------------------
序文
0.1一般
この規格は、2000年に発行されたISO 9001 (Quality management systems-Requirements)を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
"参考"と記載されている情報は、関連する要求事項の内容を理解するための、又は明確にするための手引である。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は、原国際規格にはない事項である。
これまでにJIS Z 9902(品質システム−製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル)及びJIS Z 9903(品質システム−最終検査・試験における品質保証モデル)を使ってきた組織は、この規格の1.2の記述に従って、規格の要求事項の一部を除外することによって、この規格を使うことができる。
この規格の表題は変更され、もはや品質保証という言葉を含んではいない。このことは、この規格で規定された品質マネジメントシステム要求事項は、製品の品質保証に加えて、顧客満足の向上をも目指そうとしていることを反映している。
この規格の附属書A及び附属書Bは、単に参考情報である。
品質マネジメントシステムを採用することは、組織による戦略上の決定とすべきである。組織における品質マネジメントシステムの設計及び実現は、変化するニーズ、固有の目標、提供する製品、用いられているプロセス、組織の規模及び構造によって影響を受ける。品質マネジメントシステムの構造の均一化又は文書の画一化が、この規格の意図ではない。
この規格が規定する品質マネジメントシステムについての要求事項は、製品に対する要求事項を補完するものである。
この規格は、顧客要求事項、規制要求事項及び組織固有の要求事項を満たす組織の能力を、組織自身が内部で評価するためにも、審査登録機関を含む外部機関が評価するためにも使用することができる。
この規格は、JIS Q 9000(品質マネジメントシステム−基本及び用語)及びJIS Q 9004(品質マネジメントシステム−パフォーマンス改善の指針)に記載されている品質マネジメントの原則を考慮に入れて作成した。
0.2プロセスアプローチ
この規格は、顧客要求事項を満たすことによって顧客満足を向上させるために、品質マネジメントシステムを構築し、実施し、その品質マネジメントシステムの有効性を改善する際にプロセスアプローチを採用することを奨励している。
組織が効果的に機能するためには、数多くの関連し合う活動を明確にし、運営管理する必要がある。インプットをアウトプットに変換することを可能にするために資源を使って運営管理される活動は、プロセスとみなすことができる。一つのプロセスのアウトプットは、多くの場合、次のプロセスヘの直接のインプットとなる。
組織内において、プロセスを明確にし、その相互関係を把握し、運営管理することとあわせて、一連のプロセスをシステムとして適用することを、"プロセスアプローチ"と呼ぶ。
プロセスアプローチの利点の一つは、プロセスの組合せ及びそれらの相互関係とともに、システムにおける個別のプロセス間のつながりについても、システムとして運用している間に管理できることである。
品質マネジメントシステムで、このアプローチを使用するときには、次の事項の重要性が強調される。
a) 要求事項を理解し、満足させる
b) 付加価値の点でプロセスを考慮する必要性
c) プロセスの実施状況及び有効性の成果を得る
d) 客観的な測定結果に基づくプロセスの継続的改善
図1に示すプロセスを基礎とした品質マネジメントシステムのモデルは、4.〜8.に記述したプロセスのつながりを表したものである。この図は、インプットとしての要求事項を決定するうえで顧客が重要な役割を担っていることを示している。顧客満足の監視においては、組織が顧客要求事項を満たしているか否かに関する顧客の受けとめ方についての情報を評価することが必要となる。図1に示すモデルはこの規格のすべての要求事項を網羅しているが、詳細なレベルでのプロセスを示すものではない。
参考
"Plan-Do-Check-Act"(PDCA)として知られる方法論は、あらゆるプロセスに適用できる。PDCAを簡潔に説明すると次のようになる。
Plan: 顧客要求事項及び組織の方針に沿った結果を出すために、必要な目標及びプロセスを設定する。
Do: それらのプロセスを実行する。
Check: 方針、目標、製品要求事項に照らしてプロセス及び製品を監視し、測定し、その結果を報告する。
Act: プロセスの実施状況を継続的に改善するための処置をとる。
-------------------------------------------------------------------
1.適用範囲
1.1一般
この規格は、次の二つの事項に該当する組織に対して、品質マネジメントシステムに関する要求事項を規定するものである。
a) 顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品を一貫して提供する能力をもつことを実証する必要がある場合。
b) 品質マネジメントシステムの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用、並びに顧客要求事項及び適用される規制要求事項への適合の保証を通して、顧客満足の向上を目指す場合。
参考
この規格では、"製品"という用語は、顧客向けに意図された製品又は顧客が要求した製品に限られて使われる。
備考
この規格の対応国際規格を次に示す。
なお、対応の程度を表す記号は、ISO/IEC Guide21に基づき、IDT(一致している)、MOD(修正している)、NEQ(同等でない)とする。
ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements (IDT)
1.2適用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業種及び形態、規模、並びに提供する製品を問わず、あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織やその製品の性質によって、この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には、その要求事項の除外を考慮してもよい。
このような除外を行う場合、除外できる要求事項は7.に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが、顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力、又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば、この規格への適合の宣言は受け入れられない。
-------------------------------------------------------------------
2.引用規格
次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版・追補には適用しない。
JIS Q 9000:2000 品質マネジメントシステム−基本及び用語
備考
ISO 9000:2000、Quality management systems - Fundamentals and vocabulary がこの規格と一致している。
-------------------------------------------------------------------
3.定義
この規格には、JIS Q 9000に規定されている定義を適用する。
この規格では、製品の取引における当事者の名称を次のように変更した。
供給者 → 組織 → 顧客
これまで使われていた"供給者"は"組織"に置き換えられる。"組織"とは、この規格が適用される単位を示す。
同様に、"下請負契約者"は"供給者"に置き換える。
この規格の全体にわたって、"製品"という用語が使われた場合には、"サービス"のこともあわせて意味する。
-------------------------------------------------------------------
4.品質マネジメントシステム
4.1一般要求事項
組織は、この規格の要求事項に従って、品質マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、かつ、維持すること。また、その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善すること。
組織は、次の事項を実施すること。
a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする (1.2参照)。
b) これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d) これらのプロセスの運用及び監視の支援をするために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e) これらのプロセスを監視、測定及び分析する。
f) これらのプロセスについて、計画どおりの結果が得られるように、かつ、継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
組織は、これらのプロセスを、この規格の要求事項に従って運営管理すること。
要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には、組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にすること。アウトソースしたプロセスの管理について、組織の品質マネジメントシステムの中で明確にすること。
参考
1.品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには、運営管理活動、資源の提供、製品実現及び測定にかかわるプロセスが含まれる。
2.ここでいう、"アウトソース"とは、あるプロセス及びその管理を外部委託することである。"アウトソースしたプロセスに関して管理を確実にする"とは、外部委託したプロセスが正しく管理されていることを確実にすることである。
4.2文書化に関する要求事項
4.2.1一般
品質マネジメントシステムの文書には、次の事項を含めること。
a) 文書化した、品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c) この規格が要求する"文書化された手順"
d) 組織内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、組織が必要と判断した文書
e) この規格が要求する記録 (4.2.4参照)
参考
1.この規格で"文書化された手順"という用語を使う場合には、その手順が確立され、文書化され、実施され、かつ、維持されていることを意味する。
2.品質マネジメントシステムの文書化の程度は、次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
3.文書の様式及び媒体の種類はどのようなものでもよい。
4.2.2品質マニュアル
組織は、次の事項を含む品質マニュアルを作成し、維持すること。
a) 品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には、その詳細と正当とする理由 (1.2参照)。
b) 品質マネジメントシステムについて確立された"文書化された手順"又はそれらを参照できる情報
c) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3文書管理
品質マネジメントシステムで必要とされる文書は管理すること。ただし、記録は文書の一種ではあるが、4.2.4に規定する要求事項に従って管理すること。
次の活動に必要な管理を規定する"文書化された手順"を確立すること。
a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書を承認する。
b) 文書をレビューする。また、必要に応じて更新し、再承認する。
c) 文書の変更の識別及び現在の改訂版の識別を確実にする。
d) 該当する文書の適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e) 文書が読みやすく、容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f) どれが外部で作成された文書であるかを明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場合には、適切な識別をする。
4.2.4記録の管理
記録は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために、作成し、維持すること。記録は、読みやすく、容易に識別可能で、検索可能であること。記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために、"文書化された手順"を確立すること。
-------------------------------------------------------------------
5.経営者の責任
5.1経営者のコミットメント
トップマネジメントは、品質マネジメントシステムの構築及び実施、並びにその有効性を継続的に改善することに対するコミットメントの証拠を次の事項によって示すこと。
a) 法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして、顧客要求事項を満たすことの重要性を組織内に周知する。
b)品質方針を設定する。
c)品質目標が設定されることを確実にする。
d) マネジメントレビューを実施する。
e)資源が使用できることを確実にする。
5.2顧客重視
顧客満足の向上を目指して、トップマネジメントは、顧客要求事項が決定され、満たされていることを確実にすること (7.2.1及び8.2.1参照)。
5.3品質方針
トップマネジメントは、品質方針について次の事項を確実にすること。
a) 組織の目的に対して適切である。
b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミットメントを含む。
c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。
d) 組織全体に伝達され、理解される。
e) 適切性の持続のためにレビューする。
5.4計画
5.4.1品質目標
トップマネジメントは、組織内のそれぞれの部門及び階層で品質目標が設定されていることを確実にすること。その品質目標には、製品要求事項 [7.1.a)参照] を満たすために必要なものがあれば含めること。品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針との整合性がとれていること。
5.4.2品質マネジメントシステムの計画
トップマネジメントは、次の事項を確実にすること。
a) 品質目標及び4.1に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシステムの計画が策定される。
b) 品質マネジメントシステムの変更が計画され、実施される場合には、品質マネジメントシステムが"完全に整っている状態"(integrity)を維持している。
5.5責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1責任及び権限
トップマネジメントは、責任及び権限が定められ、組織全体に周知されていることを確実にすること。
5.5.2管理責任者
トップマネジメントは、管理層の中から管理責任者を任命すること。管理責任者は与えられている他の責任とかかわりなく次に示す責任及び権限をもつこと。
a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。
b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無についてトップマネジメントに報告する。
c) 組織全体にわたって、顧客要求事項に対する認識を高めることを確実にする。
参考
1.管理責任者の責任には、品質マネジメントシステムに関する事項について外部と連絡をとることも含めることができる。
2.管理責任者は、上記の責任及び権限を持つ限り、一人である必要はない。
5.5.3内部コミュニケーション
トップマネジメントは、組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にすること。また、品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にすること。
5.6マネジメントレビュー
5.6.1一般
トップマネジメントは、組織の品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ、有効であることを確実にするために、あらかじめ定められた間隔で品質マネジメントシステムをレビューすること。このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価、品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行うこと。
マネジメントレビューの結果の記録は維持すること (4.24参照)。
5.6.2マネジメントレビューヘのインプット
マネジメントレビューへのインプットには次の情報を含むこと。
a) 監査の結果
b) 顧客からのフィードバック
c) プロセスの実施状況及び製品の適合性
d) 予防処置及び是正処置の状況
e) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
f) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
g) 改善のための提案
5.6.3マネジメントレビューからのアウトプット
マネジメントレビューからのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置を含むこと。
a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b) 顧客要求事項への適合に必要な製品の改善
c) 資源の必要性
-------------------------------------------------------------------
6.資源の運用管理
6.1資源の提供
組織は、次の事項に必要な資源を明確にし、提供すること。
a) 品質マネジメントシステムを実施し、維持する。また、その有効性を継続的に改善する。
b) 顧客満足を、顧客要求事項を満たすことによって向上する。
6.2人的資源
6.2.1一般
製品品質に影響がある仕事に従事する要員は、関連する教育、訓練、技能及び経験を判断の根拠として力量があること。
6.2.2力量、認識及び教育・訓練
組織は、次の事項を実施すること。
a) 製品品質に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量を明確にする。
b) 必要な力量がもてるように教育・訓練し、又は他の処置をとる。
c) 教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。
d) 組織の要員が、自らの活動のもつ意味と重要性を認識し、品質目標の達成に向けて自らどのように貢献できるかを認識することを確実にする。
e) 教育、訓練、技能及び経験について該当する記録を維持する (4.2.4参照)。
6.3インフラストラクチャー
組織は、製品要求事項への適合を達成するうえで必要とされるインフラストラクチャーを明確にし、提供し、かつ、維持すること。インフラストラクチャーには次のようなものがある。
a) 建物、作業場所及び関連するユーティリティー(電気、ガス、水など)
b) 設備(ハードウェアとソフトウェアとを含む。)
c) 支援業務(輸送、通信など)
参考
インフラストラクチャーとは、"<組織>組織の運営のために必要な一連の施設、設備及びサービスに関するシステム"を指す(JIS Q 9000の3.3.3参照)。
6.4作業環境
組織は、製品要求事項への適合を達成するために必要な作業環境を明確にし、運営管理すること。
-------------------------------------------------------------------
7.製品実現
7.1製品実現の計画
組織は、製品実現のために必要なプロセスを計画して、構築すること。製品実現の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合性がとれていること(4.1参照)。
製品実現の計画に当たっては、組織は次の事項について該当するものを明確にすること。
a) 製品に対する品質目標及び要求事項
b) 製品に特有な、プロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の必要性
c) その製品のための検証、妥当性確認、監視、検査及び試験活動、並びに製品合否判定基準
d) 製品実現のプロセス及びその結果としての製品が要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録(4.2.4参照)
この計画のアウトプットは、組織の計画の実行に適した様式であること。
参考
1.特定の製品、プロジェクト又は契約に適用される品質マネジメントシステムのプロセス(製品実現のプロセスを含む。)及び資源を規定する文書を品質計画書と呼ぶことがある。
2.組織は、製品実現のプロセスの構築に当たって7.3に規定する要求事項を適用してもよい。
7.2顧客関連のプロセス
7.2.1製品に関連する要求事項の明確化
組織は、次の事項を明確にすること。
a)顧客が規定した要求事項。これには引渡し及び引渡し後の活動に関する要求事項を含む。
b) 顧客が明示してはいないが、指定された用途又は意図された用途が既知である場合、それらの用途に応じた要求事項
c) 製品に関連する法令・規制要求事項
d) 組織が必要と判断する追加要求事項
7.2.2製品に関連する要求事項のレビュー
組織は、製品に関連する要求事項をレビューすること。このレビューは、組織が顧客に製品を提供することについてのコミットメント(例 提案書の提出、契約又は注文の受諾、契約又は注文への変更の受諾)をする前に実施すること。レビューでは次の事項を確実にすること。
a) 製品要求事項が定められている。
b) 契約又は注文の要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、それについて解決されている。
c) 組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。
このレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持すること(4.2.4参照)。
顧客がその要求事項を書面で示さない場合には、組織は顧客要求事項を受諾する前に確認すること。
製品要求事項が変更された場合には、組織は、関連する文書を修正すること。また、変更後の要求事項が関連する要員に理解されていることを確実にすること。
参考
インターネット販売などの状況では、個別の注文に対する正式なレビューの実施は非現実的である。このような場合のレビューでは、カタログや宣伝広告資料などの関連する製品情報をその対象とすることもできる。
7.2.3顧客とのコミュニケーション
組織は、次の事項に関して顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を明確にし、実施すること。
a) 製品情報
b) 引き合い、契約若しくは注文、又はそれらの変更
c) 苦情を含む顧客からのフィードバック
7.3設計・開発
7.3.1設計・開発の計画
組織は、製品の設計・開発の計画を策定し、管理すること。
設計・開発の計画において、組織は次の事項を明確にすること。
a) 設計・開発の段階
b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認
c) 設計・開発に関する責任及び権限
組織は、効果的なコミュニケーションと責任の明確な割当てとを確実にするために、設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理すること。
設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適宜更新すること。
7.3.2設計・開発へのインプット
製品要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を維持すること(4.2.4参照)。インプットには次の事項を含めること。
a) 機能及び性能に関する要求事項
b) 適用される法令・規制要求事項
c) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報
d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項
これらのインプットについては、その適切性をレビューすること。要求事項は、漏れがなく、あいまい(曖昧)ではなく、かつ、相反することがないこと。
7.3.3設計・開発からのアウトプット
設計・開発からのアウトプットは、設計・開発へのインプットと対比した検証ができるような様式で提示されること。また、次の段階に進める前に、承認を受けること。
設計・開発からのアウトプットは次の状態であること。
a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
b) 購買、製造及びサービス提供に対して適切な情報を提供する。
c) 製品の合否判定基準を含むか又はそれを参照している。
d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性を明確にする。
7.3.4設計・開発のレビュー
設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、計画されたとおりに(7.3.1参照)体系的なレビューを行うこと。
a) 設計・開発の結果が要求事項を満たせるかどうかを評価する。
b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。
レビューへの参加者として、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門の代表が含まれていること。このレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
7.3.5設計・開発の検証
設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために、計画されたとおりに(7.3.1参照)検証を実施すること。この検証の結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
7.3.6設計・開発の妥当性確認
結果として得られる製品が、指定された用途又は意図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画した方法(7.3.1参照)に従って、設計・開発の妥当性確認を実施すること。実行可能な場合にはいつでも、製品の引渡し又は提供の前に、妥当性確認を完了すること。妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
7.3.7設計・開発の変更管理
設計・開発の変更を明確にし、記録を維持すること。変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適宜行い、その変更を実施する前に承認すること。設計・開発の変更のレビューには、その変更が、製品を構成する要素及び既に引き渡されている製品に及ぼす影響の評価を含めること。
変更のレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
参考
"変更のレビュー"とは、変更に対して適宜行われたレビュー、検証及び妥当性確認のことである。
7.4購買
7.4.1購買プロセス
組織は、規定された購買要求事項に、購買製品が適合することを確実にすること。供給者及び購買した製品に対する管理の方式と程度は、購買製品が、その後の製品実現のプロセス又は最終製品に及ぼす影響に応じて定めること。
組織は、供給者が組織の要求事項に従って製品を供給する能力を判断の根拠として、供給者を評価し、選定すること。選定、評価及び再評価の基準を定めること。評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
7.4.2購買情報
購買情報では購買製品に関する情報を明確にし、必要な場合には、次の事項のうち該当する事項を含めること。
a) 製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項
b) 要員の適格性確認に関する要求事項
c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項
組織は、供給者に伝達する前に、規定した購買要求事項が妥当であることを確実にすること。
7.4.3購買製品の検証
組織は、購買製品が、規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために、必要な検査又はその他の活動を定めて、実施すること。
組織又はその顧客が、供給者先で検証を実施することにした場合には、組織は、その検証の要領及び購買製品のリリース(出荷許可)の方法を購買情報の中に明確にすること。
7.5製造及びサービス提供
7.5.1製造及びサービス提供の管理
組織は、製造及びサービス提供を計画し、管理された状態で実行すること。管理された状態には、該当する次の状態を含むこと。
a)製品の特性を述べた情報が利用できる。
b) 必要に応じて、作業手順が利用できる。
c) 適切な設備を使用している。
d)監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。
e) 規定された監視及び測定が実施されている。
f)リリース(次工程への引渡し)、顧客への引渡し及び引渡し後の活動が規定されたとおりに実施されている。
7.5.2製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
製造及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、組織は、その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行うこと。これらのプロセスには、製品が使用され、又はサービスが提供されてからでしか不具合が顕在化しないようなプロセスが含まれる。
妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証すること。
組織は、これらのプロセスについて、次の事項のうち適用できるものを含んだ手続きを確立すること。
a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準
b) 設備の承認及び要員の適格性確認
c) 所定の方法及び手順の適用
d) 記録に関する要求事項(4.2.4参照)
e) 妥当性の再確認
7.5.3識別及びトレーサビリティ
必要な場合には、組織は、製品実現の全過程において適切な手段で製品を識別すること。
組織は、監視及び測定の要求事項に関連して、製品の状態を識別すること。
トレーサビリティが要求事項となっている場合には、組織は、製品について固有の識別を管理し、記録すること(4.2.4参照)。
参考 ある産業分野では、構成管理が識別及びトレーサビリティを維持する手段である。
7.5.4顧客の所有物
組織は、顧客の所有物について、それが組織の管理下にある間、又は組織がそれを使用している間は、注意を払うこと。組織は、使用するため又は製品に組み込むために提供された顧客の所有物の識別、検証及び保護・防護を実施すること。顧客の所有物を紛失、損傷した場合又は使用には適さないとわかった場合には、顧客に報告し、記録を維持すること(4.2.4参照)。
参考
顧客の所有物には知的所有権も含まれる。
7.5.5製品の保存
組織は、内部処理から指定納入先への引渡しまでの間、製品を適合した状態のまま保存すること。この保存には、識別、取扱い、包装、保管及び保護を含めること。保存は、製品を構成する要素にも適用すること。
参考
内部処理とは、組織が運営管理している製品実現のプロセスにおける活動をいう。
7.6監視機器及び測定機器の管理
定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は、実施すべき監視及び測定を明確にすること。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にすること(7.2.1参照)。
組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立すること。
測定値の正当性が保証されなければならない場合には、測定機器に関し、次の事項を満たすこと。
a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録する。
b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。
c) 校正の状態が明確にできる識別をする。
d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
e) 取扱い、保守、保管において、損傷及び劣化しないように保護する。
さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、組織は、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。組織は、その機器及び影響を受けた製品に対して、適切な処置をとること。校正及び検証の結果の記録を維持すること(4.2.4参照)。
規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。この確認は、最初に使用するのに先立って実施すること。また、必要に応じて再確認すること。
参考
ISO 10012-1 (Quality assurance requirements for measuring equipment - Part1:Metrological confirmation system for measuring equipment) 及びISO 10012-2 (Quality assurance for measuring equipment - Part2: Guidelines for control of measurement processes)を参照。
http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/ms/iso9000/q9001-requirements.htm
2009年12月12日
土壌汚染ISO14015用地及び組織の環境アセスメント
3−1 用地及び組織の環境アセスメント
Environmental assessment of sites and organizations(EASO):ISO14015
環境マネジメント規格である用地及び組織の環境アセスメント(EASO)は、2001年11月に国際規格(IS)され、現在、日本工業規格(JIS)化の準備が進んでいる。
この規格は、1993年国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント専門委員会(TC207)、環境監査部会(SC2)において新業務項目が提案され、1997年の開発決定から4年間をかけて国際規格化されたものである。
EASOの規格の構成は、次の内容であり本項では、規格原文の表示番号で順を追って紹介する。
0 序文
1 適用範囲
2 用語及び定義
3 役割及び責任
4 アセスメント手順
5 報告
0 序文
組織は、自らの用地及び活動にかかわる環境事項又は起こり得る取得に伴う環境事項を理解することに一層関心を寄せつつある。これらの事項とそれらに関連する事業への影響は、用地及び組織の環境アセスメント(EASO)によって査定することができる。このようなアセスメントは、操業中でも、また、資産取得又は資産分割時においても実施されるし、しばしばデューディリジェンス(Due Diligence)と言われる、より広範な事業評価プロセスの一部として実施されることもある。
この国際規格は、EASOを実施する方法についての指針を提供する.また、この国際規格は、環境アセスメント実施のために、使用する用語の整合を図り、体系化され首尾一貫した、透明性の高い、かつ、客観的なアプローチの基礎を提供する。さらに、この国際規格は、中小企業を含む世界中のあらゆる場所で活動している組織が使用することができる。この国際規格は、適用の方法に柔軟性があり、第三者を雇用する必要性がある場合とそうでない場合があるが自己アセスメントのためにも、また、外部アセスメントにも使用することができる.この国際規格の利用者は、産業界や、過去、現在そしておそらくは将来における特定用地の使用者や、産業界や用地に財務的利害を有する組織(例えば、銀行、保険会社、投資家、土地所有者〉であると期待される。この国際規格は、責任と義務の移譲が行われるときに利用されるであろう。
EASOにおいて使用される情報は、環境マネジメントシステム監査、遵法監査、環境影響アセスメント、環境パフォーマンス評価又は用地調査を含む情報源から入手される。これらのアセスメント又は調査の一部は、他の関連規格(例えば、lSO14001、lS014011又はlSO14031)を使用して、実行されていたかもしれない。
既存の情報と新たに得られた情報の両方を評価するプロセスを通じて、EASOは、環境側面及び環境事項にかかわる事業への影響について結論を導き出そうとするものである。
EASOの結論は客観的情報に基く必要がある。妥当性確認がなされた情報がない場合には、利用可能な環境情報を評価し結論を導き出す際に、EASO評価者には専門的判断を下すことが求められることがある。
この国際規格は、実地探査又は用地浄化の指針を提供するものではない。しかしながら、依頼者から要求があった場合には、それらは他の規格又は手順に従って実施されることとなろう。
1 適用範囲
この国際規格は、環境側面及び環境事項を明確化し、必要に応じて事業へのそれらの影響を決定する指針を提供する。
この国際規格は、アセスメントに関係する当事者(依頼者、評価者及び被評価側の代表者)の役割と責任、及び評価プロセスの諸段階(計画作成、情報収集及び妥当性確認、評価及び報告作成)を規定する.EASOを実施するプロセスを図(3−1−1)に示す。
この国際規格は、次に示すような環境アセスメントの実施方法についての指針を提供するものではない。
a) 初期環境レビュー
b) 環境監査(環境マネジメントシステム及び遵法監査を含む)
c) 環境影響アセスメント、又は
d) 環境パフォーマンス評価
実地探査又は及び用地浄化は、この国際規格の適用範囲外である。同様に、これらを遂行するか否かを決定することも適用範囲外である。
この国際規格は、認証又は審査登録目的の仕様規格として使用したり、又は環境マネジメントシステム要求事項の確立を意図したものではない。
この国際規格を利用しても、依頼者や被評価側に他の規格や法規が課せられることにはならない。
図(3−1−1)用地及び組織の環境アセスメントを実施するプロセス

備考 括弧内の数字はこの国際規格の章節を参照している。破線はこの国際規格に記述されているよう
に(3.2 備考参照)被評価側はEASOに必ずしもかかわらないことがあることをしめす。
2 用語及び定義
この国際規格では、次に示す定義を適用する。
(本項では、ISO14001等の他の規格に定義があるものは除いている。)
2.1 被評価側
アセスメントを受ける用地又は組織
2.2 評価者
十分な能力を有し、所定のアセスメントを実施するため、又はそれに参画するために指名された者
備考 評価者は.アセスメントを行う組繊の内部又は外部の人間であってもよい.また、すべての関連項目に適切に対処することを確実にするために、例えば、特殊な専門領域を必要とする場合には、複数の評価者を必要とすることがある.
2.3 事業への影響
明確化し、評価された環境事項の現実の又は起こり得る影響(財務的又はそれ以外、好ましい又は好ましくない、定性的又は定量的)
2.4 依頼者
アセスメントを委託する組織
例 依頼者は用地の所有者、被評価側、又はその他の者であってよい。
2.7 用地及び組織の環境アセスメント(EASO)
過去、現在、及び予測可能な将来の活動の結果である用地や組織にかかわる環境側面を客観的に明確にし、環境事項を明確にし、その事業への影響を決定するプロセス
備考 事業への影響を決定することは任意であり、依頼者の裁量による。
2.9 環境事項
環境側面に関する妥当性確認が行われた情報が、選択された基準から外れ、かつ、責任又は便益、被評価側又は依頼者例の社会的イメージに対する影響、若しくはその他の費用をもたらす可能性のある事項
2.11 実地探査
機器を使用し、物理的干渉を必要とする場合もある試料採取及び試験
2.13 被評価側の代表者
被評価側を代表する権限を有する者
2.14 用地
地理学上の境界が定められ、そこにおいて組織の管理下での活動が実行できるとされた立地
備考 地理学上の境界は、地上又は水中にあり、天然又は人工いずれの表面構造物の上又は下を含む。
2.15 妥当性確認
アセスメントの目的に照らして、収集したされた情報が正確であり信頼性が高く、十分かつ適切であることを、評価者が決定するプロセス
3 役割及び責任
3.1 依頼者
依頼者の活動には、次に示す各項を含むとよい。
a) アセスメントの必要性を決定する
b) アセスメントの目的を明確にする
c) もし必要とするなら評価者と協議してアセスメントの範囲と基準を決定する
d) 評価者を選任する
e) 評価者に指示を与える
f) アセスメント(計画作成、情報収集及び妥当性確認、評価及び報告作成)のどの部分が評価者によって実施され、どの部分が依頼者の責任であるのかを決定する:この場合、他の専門家を特定し、組み入れることを要求してもよい
g) もし必要とするなら、優先順位の高いアセスメント分野を特定して決定する
h) もし必要があるなら、被評価側の代表者に接触し、全面的な協力を得てプロセスを開始する
i) アセスメント計画を承認する
j) アセスメントを実行するのにふさわしい権限と資源を提供する
k) アセスメントを実行するのに必要な情報を評価者に提供する
l) 評価者からのアセスメント結果を受領し、配布先を決定する
依頼者は、第三者に対するアセスメント結果を開示する場合、事前に、被評価側の代表者に通知するかどうかを決定することが望ましい。
備考 依頼者、評価者及び被評価側の代表者が、同一組織体であってもよい。
3.2 被評価側の代表者
被評価側の代表者の役割と責任には次の事項を含むとよい。
a)アセスメントの目的に合せて関連区域への立ち入りを認め、情報を提供する
b) アセスメントプロセスについて関連の従業員や他の関係者に通知する
c) 面接調査対象者を用意する、又は、用意するのを支援する
d)要請があれば、アセスメントプロセスを支援する要員を提供する、及び、
e)評価者のために安全な作業環境を提供する
依頼者の裁量によって、被評価側の代表者はアセスメントの範囲とアセスメント計画の決定に参画し、また、当該アセスメントの結果を受領してもよい。
被評価側の代表者への告知なしにアセスメントが行なわれる場合、又は、用地及び/又は組織の責任者を特定できない場合、被評価側の代表者の役割は適用されない。
3.3 評価者
評価者と監査者との役割と責任は見方によっては異なっている。監査者は定めた基準に対して既存の情報を検証するのに対して、評価者は更に新たな情報を収集し、事業への影響を決定するために情報を評価することがしばしば要求される。
用地及び組織の環境アセスメントを実施するに際して、評価者は、類似の状況においてすべての評価者に期待される勤勉さ、知識、技能及び判断を行使する必要がある。評価者は、思慮分別を働かせ、また、法律又は他の規則によって別段の行動が求められる場合を除いて、機密を保持することが望ましい。
評価者又は複数の評価者が関与する場合はそのチームリーダーの責任と活動には、次に示す事項を含むとよい。
a) 要請があれば依頼者を支援して、アセスメントの目的、範囲(優先的アセスメント分野の明確化及び決定を含む)、基準を決定する
b) 報告作成の方法及び書式を依頼者と取り決める
c) アセスメント計画を立案し、依頼者の承認、及び、もし必要とするなら被評価側の代表者の承認を得る
d) チェックリストや手順書のような作業文書を作成し、維持する
e) アセスメントの目的に合致する必要な技能が利用可能であるようにし、また、もし必要とするならアセスメントチームを編成する
f) アセスメントチームについて依頼者の承認を得る
g) 初期情報を得る
h) アセスメントの各部を実行するに当たり、アセスメントチームのメンバーに作業を割り当てる
i) アセスメントの計画に沿って情報を収集し、その妥当性確認をする
j) 環境事項を明確にし、評価する
k) 依頼者からの要請があれば、事業への影響を決定する
l) 依頼者からの要請があれば、依頼者への報告書を作成し、それを依頼者に提供する
この国際規格は評価者の能力及び資格要件に関する指針を提供するものではない。しかしながら、環境アセスメントを実施遂行するには次に示す事項を充足することが要請される。
− 十分な教育
− 十分な訓練
− 十分な関連する業務経験
同様に、次に示す知識及び能力
− 関連法律、規則及び関連の文書
− 環境科学及び技術
− 経済及び関連の事業分野
− (商業的)活動に関する運転の技術的及び環境的側面
− 設備運転
− アセスメント技術
4.アセスメント手順
4.1 一般
アセスメントプロセスには、アセスメントの計画作成、情報の収集及び妥当性確認、情報の評価、並びにアセスメントの報告作成を含む。
このプロセスには、依頼者から特に要請された場合には、事業機会の確認を含めてもよい。
4.2 計画作成
4.2.1 一般
一度、アセスメントを実行することが合意されたら計画を作成するのがよい。計画にはアセスメントの目的、範囲及び基準を定め、合意すること、並びに、アセスメント計画を作成することが含まれる。
4.2.2 アセスメントの目的
アセスメントは、依頼者によって定められた目的を考慮する必要がある。EASOの目的には、次のようなものを含めてもよい。
−用地及び/又は組織に関連する環境側面及び環境事項についての情報を明確にし、収集し、評価すること、並びに、要望がある場合には、
−用地及び/又は組織に関連する環境事項の事業への影響を決定すること
4.2.3 アセスメントの範囲
アセスメントの範囲は、アセスメントの境界と焦点を定めるものである。依頼者の裁量によって、この範囲には事業への影響の決定を含めても、また含めなくともよい。
アセスメントの範囲を決める際には、次の各項を考慮するとよい。
− アセスメントの対象となる環境側面の種類
− 他の用地や組織が被評価側に及ばす可能性のある環境影響
− 被評価側の物理的境界(例えば、用地、用地の一部)
− 該当する場合は、隣接及び近隣の用地
− 請負契約者、供給者、組織(例えは、敷地外の廃棄物処理組織)及び個人並びに前の占有者との関係や、これらにかかわる活動などの組織面の境界
− 対象となる期間(例えば、過去、現在及び/又は将来)
−被評価側及び/又は依頼者の活動(例えば、現行事業の継続、変更・拡張・解体・撤廃・改造の諸計画)に関する期間
−基準(4.2.4参照)の作成に関する期間
− もし、該当する場合は、事業への影響費用の限度額
この範囲は、アセスメントに含まれる関連用地や組織を定め、限定してもよい.依頼者の裁量によって、アセスメントが開始された後でもアセスメントの範囲を修正してもよい.そのような変更は記録し、関係者に連絡することが望ましい。
依頼者は、定められたアセスメントの範囲内で、アセスメント中に優先的に扱われる事項を明確にしてもよい.優先事項は、アセスメントを計画している間に利用可能な情報をもとに確定されることが多い。優先事項の明確化を行っても、評価者がアセスメント中に範囲全体を考慮するという義務を免除するものではない。
4.2.4 アセスメント基準
収集した情報を評価する基準を明確にすることが望ましい。基準には次の事項を含めるとよいが、これに限定されるものではない。
−現在適用されまた、合理的に予見される、法律上の要求事項(例えば、同意、許可、環境法、規則、規制方針)
−その他依頼者が定めた環境関連要求事項(例えば、組織の方針及び手順、特定の環境条件、マネジメント慣習、システム及びパフォーマンスの要求事項、業界並びにその業種に適用される慣習や綱領)
−利害関係のある第三者(例えば、保険会社、金融機関〉の要求事項、要請事項又は潜在的な要請事項
−技術的配慮事項
4.2.5 アセスメント計画
該当する場合、アセスメント計画には、次の事項を含めるとよい。
− アセスメントの目的及び範囲
− 依頼者、被評価側の代表者及び評価者を特定する情報
− アセスメント基準
− 優先的アセスメント領域
− 役割及び責任
− アセスメント及び関連報告書の使用言語
− 日程及び期間を含むアセスメントスケジュール
− 必要な資源(例えば、人員、予算、技術)
− 使用するアセスメント手順の概略
− 使用する備考文書、チェックリスト及び手順書並びに作業文書の要約
− 報告要求事項
− 秘密保持についての要求事項
アセスメントに影響するかもしれない制約事項を、アセスメント計画の中で特定してもよい。想定される制約事項には次のものがある。
− アセスメントに利用可能な時間
− アセスメントに利用可能な資源
− 関連地域への立ち入り
− 利用可能な情報
− 関係者との相互連絡又は関連文書の入手
依頼者は、アセスメント計画を検討し、承認することが望ましい。この計画は、もし必要であるなら、被評価側の代表者に通知することが望ましい。
4.3 情報収集及び妥当性確認
4.3.1 一般
アセスメントは、既存文書や記録の検討(用地視察の前及び用地視察中の両方)、活動や物理的状態の観察、そして、面接調査を通じて収集され妥当性確認がなされた環境側面についての情報をもとに行われる。−以下略−
アセスメントに必要とされ得る情報の種類を実践の手引き?に例示する。
実践の手引き? EASOにおいて考慮対称なり得る情報例
− 立地
− 物理的特性(例えば、水文地質学)
− 評価対象地、隣接地及び近隣地 − 用地利用
− 施設、工程及び操業
− 用地の浸食され易さ
− 原材料、副生成物及び製品(有害物を含む)
− 資材の保管及び取扱い
− 大気、水系、土壌への排出及び放出
− 廃棄物の保管、取扱い、処分
− 防災・消火、漏洩防止及びその他の緊急事態対処計画
− 暴風洪水
− 労働及び公衆の安全衛生
− 法的要求事項、組織内及びその他の要求事項、不遵守及び不適合
− 部外者との関係
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また、
他の事項が適用される場合もある。
4.3.2 既存文書及び記録の検査
評価者は、これまでの調査活動と不必要に重複することなく、用地及び/又は組織についての充分な理解を得て、文書及び記録を収集し検討することが望ましい。考慮しうる文書及び記録の例を実践の手引き?に示す。−以下略−
実践の手引き? EASOにおいて考慮されうる文書及び情報源
文 書 情 報 源
− 地図、計画書、写真
− 過去の履歴
− 地質学/水文地質学上の記録
− 地質工学に関する記録
− 出荷記録/取扱い記録
− 安全データ・シート(MSDS:物質安全性データシート)
− 作業指示書
− モニタリング手順及び結果
− 工程に関する文書(例えば、物質収支)
− 保全記録
− 在庫目録
外部
− 政府機関(国、地方規制当局、計画部局)
− 保管文書
− 公益団体
− 商業出版物
−業界行動綱領
−緊急サービス− 保険会社
内部
− 環境、保健衛生、安全部門
− 公式登記・記録(例えば、埋立て、汚染地)
− 緊急対処及びその他対応計画
− 保健衛生、安全及び環境に関する訓練記録
− 事故記録
− 許可書/免許証/通知書
− 組織図(業務と責任)
− 監査及びその他報告書
− 不遵守及び不適合記録
− 苦情
− 組織の方針、計画、マネジメントシステム
− 保険上の要求事項
− 供給業者他の部外者との契約
− その他の訓練記録
− 生産技術部門
− 製造部門
− 購買部門
− 研究開発部門
− 資産管理部門
− 施設管理部門
− 教育・訓練部門
− 法務部門
− 財務会計部門
− 広報部門
− 人事部門
− 医務部門
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また他の事項が適用される場合もある
4.3.3 活動及び物理的状態の観察
評価者は、過去の活動及び操業による用地又は組織の物理的状態に関する情報を観察し、記録することが望ましい。観察対象となりうる用地内外の要素についての例を、実践の手引き?に示す。−以下略−
実践の手引き? EASOにおいて観察されうる要素の例
活動
− 廃棄物管理
− 資材及び製品の取扱い
− 工程の管理
− 排水の管理
− 大気排出管理
− 水系への排出
− 用地利用
物理的条件
− 排水処理設備及び下水システム
− 冷暖房システム
− 配管及び通気孔
− 格納容器.排水路、及び排水だめ
− 貯蔵容器/タンク
− 公益事業体からの供給
− 騒音、光、振動又は熱
− 臭気、塵埃、煤煙、微小粒子
− 地表水及び用地の地形
− 用地の周辺及び隣接地並びに組織
− 土壌及び地下水の状態
− 着色した又は変色した表面
− 影響を受けている動植物
− 理立て
− 建物、工場及び装置類
− 資材の保管
− 有害な資材、製品、物質
− 防火設備及び緊急事態対処設備
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また他の事項が適用される場合もある。
4.3.4 面接調査−省略−
4.4 評価
4.4.1 一般
妥当性がなされた環境側面に関する情報は、評価プロセスにインプットされる資料となる。このプロセスは、図(3−1−2)に示すように、環境事項の明確化と事業への影響の決定という二段階から成る。これら二つの段階は、依頼者の裁量によって、別々の主体が実施してもよく、これは、特に依頼者が事業の影響を決定するために、他の専門技能(例えば、技術的、法律的や財務的)を必要とする場合が該当する。
図(3−1−2)評価プロセス

備考 括弧内の数字はこの国際規格の項目番号を参照している。破線は、この国際規格に記述されているように、事業への影響を決定することがEASOの必須の部分ではないことを示す。
4.4.2 環境事項の明確化
環境事項を明確にするために、環境側面に関する妥当性確認が行われた情報を、選定した基準と比較する.妥当性確認がなされた情報が、選定した基準から外れている場合に環境事項が明確になり、次のような結果を導く場合がある。
− 組繊にとっての責任又は便益
− 被評価側又は依頼者の社会的イメージヘの影響
− その他の費用
事業からみて、関連が肴薄である事項も環境上は関連があるかも知れないし、その逆もあり得る。
この段階を経た結果、依頼者に関連する環境事項が明確にされる。
4.4.3 事業への影響の決定
事業への影響の決定は、これがアセスメントの目的及び範囲に含まれている場合にのみ実施される。
事業への影響は、明確化され評価された環境事項の実際の又は潜在的な影響(財務的とそれ以外、好ましい又は好ましくない、定性的又は定量的)である。
この評価には.一般にEASOの目的にかかわる環境事項の及ぼす影響について判断が含まれる。この段階で、事業への影響に対処するための費用が見積られ被評価側又は依頼者の社会的イメージに対する影響についても明確にされ、評価される。
この判断に当たっては、次の事項が考慮される。
− 緩和措置又は是正、回避又は防止する対策が実際にもたらす若しくはもたらすかもしれない結果
− 環境損害
− 例えば、法律及び他の関連要求事項の現在並びに予想される変更に対する不遵守の結果生ずる現在又は将来の(公法上及び私法上の)責任
− 被評価側及び/又は依頼者の社会的イメージヘの打撃
− 依頼者若しくは被評価側の企業方針又は他の依頼者が定めた要求事項に対する不適合
− 上記の措置又は対策をとる場合の見積り額
− 技術開発
− 諸々の費用支出をしなければならない期間(例えば、執行措置又は新しい法律の制定の可能性に関連した期間)
情報が十分でないため結論が限定される場合は、それを表明する必要があり、また、いかなる見解もそれに応じて性格付けすることが望ましい。
評価プロセスのこの部分の結果として、事業への影響のリストが作成され、適当な場合には定量化される。
5 報告作成
5.2報告内容
評価者は報告書の内容に対して責任を有し、依頼者が認定事実の重要性を理解できるように工夫した方法で情報を提供することが望ましい。これを行うために、評価者は事実と意見を区別し、認定事実の根拠を明確に特定し、また、認定事実に関する相対的不確実性を指摘することが望ましい。
次に示す情報を依頼者に報告することが望ましい。
− 評価した用地及び/又は組織を特定する情報
− 評価者及び報告書作成者の氏名
− アセスメントの目的、範囲及び基準
− アセスメントの日時及び期間
− 利用可能な情報の制約事項及びそれらのアセスメントに対する影響
− 制約事項、除外事項、修正事項及び合意したアセスメントの範囲からの逸脱
− アセスメントの間に収集した情報の要約及びアセスメントの結果
依頼者と評価者の問の合意に従って、次に示す情報も依頼者に報告してもよい。
− 依頼者の氏名
− 被評価側代表者の氏名
− アセスメントチームのメンバーを特定する情報
− アセスメントスケジュール
− 使用したアセスメント手順の要約
− 使用した備考文書、チェックリスト及び手順書並びにその他作業文書の要約
− 評価方法、及び評価の根拠
− 評価者によって実施されたのであれば、その評価の結果
− 想定される次の段階に関する推奨事項
− 秘密保持に関する要求事項
− 結論
EASO報告書の目次の例を実践の手引き?に示す。
アセスメントの範囲で明示されている場合は、報告書に記述された認定事実を補強し、後日又は他の関係者によってアセスメントの再評価ができるように、備考文献や重要な情報を含む十分な文書類を、報告書に入れておくことが望ましい。評価者は、制約が存在する見解について性格付けをすることが望ましい。例えば情報が不十分な場合がそれに該当する。
5.2 報告書様式
依頼者の優先事項についての意向又はその他の取り決めによって、口頭による報告のみが求められることがある。それ以外の場合には、報告は文書によって行うことが望ましい。
実践の手引き? EASO報告書の目次例
a)要約
b) 序文
一 依頼者の氏名
一 被評価用地又は組織
一 被評価側の代表者の氏名
一 評価者の氏名
− アセスメントの日時及び期間
c)目的及び範囲
一 依頼者の指示事項
一 用地及び組織の境界
d)アセスメント基準
e)アセスメントプロセス
f) 情報
一 情報源
一 制約事項及びその予想される影響
一 要約
g) 結論
一 環境事項
一 事業への影響
付録
5.3 報告書の配布
報告書は依頼者の専有財産である。したがって、評価者及び報告書受領者は秘密保持を尊重し、適切な防護措置を取ることが望ましい。報告書の配布は、依頼者の裁量によるものであり、その中には、被評価側に報告書の写しを提供することを含めてもよい。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/004/attached/attach_4328_7.pdf
Environmental assessment of sites and organizations(EASO):ISO14015
環境マネジメント規格である用地及び組織の環境アセスメント(EASO)は、2001年11月に国際規格(IS)され、現在、日本工業規格(JIS)化の準備が進んでいる。
この規格は、1993年国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント専門委員会(TC207)、環境監査部会(SC2)において新業務項目が提案され、1997年の開発決定から4年間をかけて国際規格化されたものである。
EASOの規格の構成は、次の内容であり本項では、規格原文の表示番号で順を追って紹介する。
0 序文
1 適用範囲
2 用語及び定義
3 役割及び責任
4 アセスメント手順
5 報告
0 序文
組織は、自らの用地及び活動にかかわる環境事項又は起こり得る取得に伴う環境事項を理解することに一層関心を寄せつつある。これらの事項とそれらに関連する事業への影響は、用地及び組織の環境アセスメント(EASO)によって査定することができる。このようなアセスメントは、操業中でも、また、資産取得又は資産分割時においても実施されるし、しばしばデューディリジェンス(Due Diligence)と言われる、より広範な事業評価プロセスの一部として実施されることもある。
この国際規格は、EASOを実施する方法についての指針を提供する.また、この国際規格は、環境アセスメント実施のために、使用する用語の整合を図り、体系化され首尾一貫した、透明性の高い、かつ、客観的なアプローチの基礎を提供する。さらに、この国際規格は、中小企業を含む世界中のあらゆる場所で活動している組織が使用することができる。この国際規格は、適用の方法に柔軟性があり、第三者を雇用する必要性がある場合とそうでない場合があるが自己アセスメントのためにも、また、外部アセスメントにも使用することができる.この国際規格の利用者は、産業界や、過去、現在そしておそらくは将来における特定用地の使用者や、産業界や用地に財務的利害を有する組織(例えば、銀行、保険会社、投資家、土地所有者〉であると期待される。この国際規格は、責任と義務の移譲が行われるときに利用されるであろう。
EASOにおいて使用される情報は、環境マネジメントシステム監査、遵法監査、環境影響アセスメント、環境パフォーマンス評価又は用地調査を含む情報源から入手される。これらのアセスメント又は調査の一部は、他の関連規格(例えば、lSO14001、lS014011又はlSO14031)を使用して、実行されていたかもしれない。
既存の情報と新たに得られた情報の両方を評価するプロセスを通じて、EASOは、環境側面及び環境事項にかかわる事業への影響について結論を導き出そうとするものである。
EASOの結論は客観的情報に基く必要がある。妥当性確認がなされた情報がない場合には、利用可能な環境情報を評価し結論を導き出す際に、EASO評価者には専門的判断を下すことが求められることがある。
この国際規格は、実地探査又は用地浄化の指針を提供するものではない。しかしながら、依頼者から要求があった場合には、それらは他の規格又は手順に従って実施されることとなろう。
1 適用範囲
この国際規格は、環境側面及び環境事項を明確化し、必要に応じて事業へのそれらの影響を決定する指針を提供する。
この国際規格は、アセスメントに関係する当事者(依頼者、評価者及び被評価側の代表者)の役割と責任、及び評価プロセスの諸段階(計画作成、情報収集及び妥当性確認、評価及び報告作成)を規定する.EASOを実施するプロセスを図(3−1−1)に示す。
この国際規格は、次に示すような環境アセスメントの実施方法についての指針を提供するものではない。
a) 初期環境レビュー
b) 環境監査(環境マネジメントシステム及び遵法監査を含む)
c) 環境影響アセスメント、又は
d) 環境パフォーマンス評価
実地探査又は及び用地浄化は、この国際規格の適用範囲外である。同様に、これらを遂行するか否かを決定することも適用範囲外である。
この国際規格は、認証又は審査登録目的の仕様規格として使用したり、又は環境マネジメントシステム要求事項の確立を意図したものではない。
この国際規格を利用しても、依頼者や被評価側に他の規格や法規が課せられることにはならない。
図(3−1−1)用地及び組織の環境アセスメントを実施するプロセス

備考 括弧内の数字はこの国際規格の章節を参照している。破線はこの国際規格に記述されているよう
に(3.2 備考参照)被評価側はEASOに必ずしもかかわらないことがあることをしめす。
2 用語及び定義
この国際規格では、次に示す定義を適用する。
(本項では、ISO14001等の他の規格に定義があるものは除いている。)
2.1 被評価側
アセスメントを受ける用地又は組織
2.2 評価者
十分な能力を有し、所定のアセスメントを実施するため、又はそれに参画するために指名された者
備考 評価者は.アセスメントを行う組繊の内部又は外部の人間であってもよい.また、すべての関連項目に適切に対処することを確実にするために、例えば、特殊な専門領域を必要とする場合には、複数の評価者を必要とすることがある.
2.3 事業への影響
明確化し、評価された環境事項の現実の又は起こり得る影響(財務的又はそれ以外、好ましい又は好ましくない、定性的又は定量的)
2.4 依頼者
アセスメントを委託する組織
例 依頼者は用地の所有者、被評価側、又はその他の者であってよい。
2.7 用地及び組織の環境アセスメント(EASO)
過去、現在、及び予測可能な将来の活動の結果である用地や組織にかかわる環境側面を客観的に明確にし、環境事項を明確にし、その事業への影響を決定するプロセス
備考 事業への影響を決定することは任意であり、依頼者の裁量による。
2.9 環境事項
環境側面に関する妥当性確認が行われた情報が、選択された基準から外れ、かつ、責任又は便益、被評価側又は依頼者例の社会的イメージに対する影響、若しくはその他の費用をもたらす可能性のある事項
2.11 実地探査
機器を使用し、物理的干渉を必要とする場合もある試料採取及び試験
2.13 被評価側の代表者
被評価側を代表する権限を有する者
2.14 用地
地理学上の境界が定められ、そこにおいて組織の管理下での活動が実行できるとされた立地
備考 地理学上の境界は、地上又は水中にあり、天然又は人工いずれの表面構造物の上又は下を含む。
2.15 妥当性確認
アセスメントの目的に照らして、収集したされた情報が正確であり信頼性が高く、十分かつ適切であることを、評価者が決定するプロセス
3 役割及び責任
3.1 依頼者
依頼者の活動には、次に示す各項を含むとよい。
a) アセスメントの必要性を決定する
b) アセスメントの目的を明確にする
c) もし必要とするなら評価者と協議してアセスメントの範囲と基準を決定する
d) 評価者を選任する
e) 評価者に指示を与える
f) アセスメント(計画作成、情報収集及び妥当性確認、評価及び報告作成)のどの部分が評価者によって実施され、どの部分が依頼者の責任であるのかを決定する:この場合、他の専門家を特定し、組み入れることを要求してもよい
g) もし必要とするなら、優先順位の高いアセスメント分野を特定して決定する
h) もし必要があるなら、被評価側の代表者に接触し、全面的な協力を得てプロセスを開始する
i) アセスメント計画を承認する
j) アセスメントを実行するのにふさわしい権限と資源を提供する
k) アセスメントを実行するのに必要な情報を評価者に提供する
l) 評価者からのアセスメント結果を受領し、配布先を決定する
依頼者は、第三者に対するアセスメント結果を開示する場合、事前に、被評価側の代表者に通知するかどうかを決定することが望ましい。
備考 依頼者、評価者及び被評価側の代表者が、同一組織体であってもよい。
3.2 被評価側の代表者
被評価側の代表者の役割と責任には次の事項を含むとよい。
a)アセスメントの目的に合せて関連区域への立ち入りを認め、情報を提供する
b) アセスメントプロセスについて関連の従業員や他の関係者に通知する
c) 面接調査対象者を用意する、又は、用意するのを支援する
d)要請があれば、アセスメントプロセスを支援する要員を提供する、及び、
e)評価者のために安全な作業環境を提供する
依頼者の裁量によって、被評価側の代表者はアセスメントの範囲とアセスメント計画の決定に参画し、また、当該アセスメントの結果を受領してもよい。
被評価側の代表者への告知なしにアセスメントが行なわれる場合、又は、用地及び/又は組織の責任者を特定できない場合、被評価側の代表者の役割は適用されない。
3.3 評価者
評価者と監査者との役割と責任は見方によっては異なっている。監査者は定めた基準に対して既存の情報を検証するのに対して、評価者は更に新たな情報を収集し、事業への影響を決定するために情報を評価することがしばしば要求される。
用地及び組織の環境アセスメントを実施するに際して、評価者は、類似の状況においてすべての評価者に期待される勤勉さ、知識、技能及び判断を行使する必要がある。評価者は、思慮分別を働かせ、また、法律又は他の規則によって別段の行動が求められる場合を除いて、機密を保持することが望ましい。
評価者又は複数の評価者が関与する場合はそのチームリーダーの責任と活動には、次に示す事項を含むとよい。
a) 要請があれば依頼者を支援して、アセスメントの目的、範囲(優先的アセスメント分野の明確化及び決定を含む)、基準を決定する
b) 報告作成の方法及び書式を依頼者と取り決める
c) アセスメント計画を立案し、依頼者の承認、及び、もし必要とするなら被評価側の代表者の承認を得る
d) チェックリストや手順書のような作業文書を作成し、維持する
e) アセスメントの目的に合致する必要な技能が利用可能であるようにし、また、もし必要とするならアセスメントチームを編成する
f) アセスメントチームについて依頼者の承認を得る
g) 初期情報を得る
h) アセスメントの各部を実行するに当たり、アセスメントチームのメンバーに作業を割り当てる
i) アセスメントの計画に沿って情報を収集し、その妥当性確認をする
j) 環境事項を明確にし、評価する
k) 依頼者からの要請があれば、事業への影響を決定する
l) 依頼者からの要請があれば、依頼者への報告書を作成し、それを依頼者に提供する
この国際規格は評価者の能力及び資格要件に関する指針を提供するものではない。しかしながら、環境アセスメントを実施遂行するには次に示す事項を充足することが要請される。
− 十分な教育
− 十分な訓練
− 十分な関連する業務経験
同様に、次に示す知識及び能力
− 関連法律、規則及び関連の文書
− 環境科学及び技術
− 経済及び関連の事業分野
− (商業的)活動に関する運転の技術的及び環境的側面
− 設備運転
− アセスメント技術
4.アセスメント手順
4.1 一般
アセスメントプロセスには、アセスメントの計画作成、情報の収集及び妥当性確認、情報の評価、並びにアセスメントの報告作成を含む。
このプロセスには、依頼者から特に要請された場合には、事業機会の確認を含めてもよい。
4.2 計画作成
4.2.1 一般
一度、アセスメントを実行することが合意されたら計画を作成するのがよい。計画にはアセスメントの目的、範囲及び基準を定め、合意すること、並びに、アセスメント計画を作成することが含まれる。
4.2.2 アセスメントの目的
アセスメントは、依頼者によって定められた目的を考慮する必要がある。EASOの目的には、次のようなものを含めてもよい。
−用地及び/又は組織に関連する環境側面及び環境事項についての情報を明確にし、収集し、評価すること、並びに、要望がある場合には、
−用地及び/又は組織に関連する環境事項の事業への影響を決定すること
4.2.3 アセスメントの範囲
アセスメントの範囲は、アセスメントの境界と焦点を定めるものである。依頼者の裁量によって、この範囲には事業への影響の決定を含めても、また含めなくともよい。
アセスメントの範囲を決める際には、次の各項を考慮するとよい。
− アセスメントの対象となる環境側面の種類
− 他の用地や組織が被評価側に及ばす可能性のある環境影響
− 被評価側の物理的境界(例えば、用地、用地の一部)
− 該当する場合は、隣接及び近隣の用地
− 請負契約者、供給者、組織(例えは、敷地外の廃棄物処理組織)及び個人並びに前の占有者との関係や、これらにかかわる活動などの組織面の境界
− 対象となる期間(例えば、過去、現在及び/又は将来)
−被評価側及び/又は依頼者の活動(例えば、現行事業の継続、変更・拡張・解体・撤廃・改造の諸計画)に関する期間
−基準(4.2.4参照)の作成に関する期間
− もし、該当する場合は、事業への影響費用の限度額
この範囲は、アセスメントに含まれる関連用地や組織を定め、限定してもよい.依頼者の裁量によって、アセスメントが開始された後でもアセスメントの範囲を修正してもよい.そのような変更は記録し、関係者に連絡することが望ましい。
依頼者は、定められたアセスメントの範囲内で、アセスメント中に優先的に扱われる事項を明確にしてもよい.優先事項は、アセスメントを計画している間に利用可能な情報をもとに確定されることが多い。優先事項の明確化を行っても、評価者がアセスメント中に範囲全体を考慮するという義務を免除するものではない。
4.2.4 アセスメント基準
収集した情報を評価する基準を明確にすることが望ましい。基準には次の事項を含めるとよいが、これに限定されるものではない。
−現在適用されまた、合理的に予見される、法律上の要求事項(例えば、同意、許可、環境法、規則、規制方針)
−その他依頼者が定めた環境関連要求事項(例えば、組織の方針及び手順、特定の環境条件、マネジメント慣習、システム及びパフォーマンスの要求事項、業界並びにその業種に適用される慣習や綱領)
−利害関係のある第三者(例えば、保険会社、金融機関〉の要求事項、要請事項又は潜在的な要請事項
−技術的配慮事項
4.2.5 アセスメント計画
該当する場合、アセスメント計画には、次の事項を含めるとよい。
− アセスメントの目的及び範囲
− 依頼者、被評価側の代表者及び評価者を特定する情報
− アセスメント基準
− 優先的アセスメント領域
− 役割及び責任
− アセスメント及び関連報告書の使用言語
− 日程及び期間を含むアセスメントスケジュール
− 必要な資源(例えば、人員、予算、技術)
− 使用するアセスメント手順の概略
− 使用する備考文書、チェックリスト及び手順書並びに作業文書の要約
− 報告要求事項
− 秘密保持についての要求事項
アセスメントに影響するかもしれない制約事項を、アセスメント計画の中で特定してもよい。想定される制約事項には次のものがある。
− アセスメントに利用可能な時間
− アセスメントに利用可能な資源
− 関連地域への立ち入り
− 利用可能な情報
− 関係者との相互連絡又は関連文書の入手
依頼者は、アセスメント計画を検討し、承認することが望ましい。この計画は、もし必要であるなら、被評価側の代表者に通知することが望ましい。
4.3 情報収集及び妥当性確認
4.3.1 一般
アセスメントは、既存文書や記録の検討(用地視察の前及び用地視察中の両方)、活動や物理的状態の観察、そして、面接調査を通じて収集され妥当性確認がなされた環境側面についての情報をもとに行われる。−以下略−
アセスメントに必要とされ得る情報の種類を実践の手引き?に例示する。
実践の手引き? EASOにおいて考慮対称なり得る情報例
− 立地
− 物理的特性(例えば、水文地質学)
− 評価対象地、隣接地及び近隣地 − 用地利用
− 施設、工程及び操業
− 用地の浸食され易さ
− 原材料、副生成物及び製品(有害物を含む)
− 資材の保管及び取扱い
− 大気、水系、土壌への排出及び放出
− 廃棄物の保管、取扱い、処分
− 防災・消火、漏洩防止及びその他の緊急事態対処計画
− 暴風洪水
− 労働及び公衆の安全衛生
− 法的要求事項、組織内及びその他の要求事項、不遵守及び不適合
− 部外者との関係
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また、
他の事項が適用される場合もある。
4.3.2 既存文書及び記録の検査
評価者は、これまでの調査活動と不必要に重複することなく、用地及び/又は組織についての充分な理解を得て、文書及び記録を収集し検討することが望ましい。考慮しうる文書及び記録の例を実践の手引き?に示す。−以下略−
実践の手引き? EASOにおいて考慮されうる文書及び情報源
文 書 情 報 源
− 地図、計画書、写真
− 過去の履歴
− 地質学/水文地質学上の記録
− 地質工学に関する記録
− 出荷記録/取扱い記録
− 安全データ・シート(MSDS:物質安全性データシート)
− 作業指示書
− モニタリング手順及び結果
− 工程に関する文書(例えば、物質収支)
− 保全記録
− 在庫目録
外部
− 政府機関(国、地方規制当局、計画部局)
− 保管文書
− 公益団体
− 商業出版物
−業界行動綱領
−緊急サービス− 保険会社
内部
− 環境、保健衛生、安全部門
− 公式登記・記録(例えば、埋立て、汚染地)
− 緊急対処及びその他対応計画
− 保健衛生、安全及び環境に関する訓練記録
− 事故記録
− 許可書/免許証/通知書
− 組織図(業務と責任)
− 監査及びその他報告書
− 不遵守及び不適合記録
− 苦情
− 組織の方針、計画、マネジメントシステム
− 保険上の要求事項
− 供給業者他の部外者との契約
− その他の訓練記録
− 生産技術部門
− 製造部門
− 購買部門
− 研究開発部門
− 資産管理部門
− 施設管理部門
− 教育・訓練部門
− 法務部門
− 財務会計部門
− 広報部門
− 人事部門
− 医務部門
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また他の事項が適用される場合もある
4.3.3 活動及び物理的状態の観察
評価者は、過去の活動及び操業による用地又は組織の物理的状態に関する情報を観察し、記録することが望ましい。観察対象となりうる用地内外の要素についての例を、実践の手引き?に示す。−以下略−
実践の手引き? EASOにおいて観察されうる要素の例
活動
− 廃棄物管理
− 資材及び製品の取扱い
− 工程の管理
− 排水の管理
− 大気排出管理
− 水系への排出
− 用地利用
物理的条件
− 排水処理設備及び下水システム
− 冷暖房システム
− 配管及び通気孔
− 格納容器.排水路、及び排水だめ
− 貯蔵容器/タンク
− 公益事業体からの供給
− 騒音、光、振動又は熱
− 臭気、塵埃、煤煙、微小粒子
− 地表水及び用地の地形
− 用地の周辺及び隣接地並びに組織
− 土壌及び地下水の状態
− 着色した又は変色した表面
− 影響を受けている動植物
− 理立て
− 建物、工場及び装置類
− 資材の保管
− 有害な資材、製品、物質
− 防火設備及び緊急事態対処設備
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また他の事項が適用される場合もある。
4.3.4 面接調査−省略−
4.4 評価
4.4.1 一般
妥当性がなされた環境側面に関する情報は、評価プロセスにインプットされる資料となる。このプロセスは、図(3−1−2)に示すように、環境事項の明確化と事業への影響の決定という二段階から成る。これら二つの段階は、依頼者の裁量によって、別々の主体が実施してもよく、これは、特に依頼者が事業の影響を決定するために、他の専門技能(例えば、技術的、法律的や財務的)を必要とする場合が該当する。
図(3−1−2)評価プロセス

備考 括弧内の数字はこの国際規格の項目番号を参照している。破線は、この国際規格に記述されているように、事業への影響を決定することがEASOの必須の部分ではないことを示す。
4.4.2 環境事項の明確化
環境事項を明確にするために、環境側面に関する妥当性確認が行われた情報を、選定した基準と比較する.妥当性確認がなされた情報が、選定した基準から外れている場合に環境事項が明確になり、次のような結果を導く場合がある。
− 組繊にとっての責任又は便益
− 被評価側又は依頼者の社会的イメージヘの影響
− その他の費用
事業からみて、関連が肴薄である事項も環境上は関連があるかも知れないし、その逆もあり得る。
この段階を経た結果、依頼者に関連する環境事項が明確にされる。
4.4.3 事業への影響の決定
事業への影響の決定は、これがアセスメントの目的及び範囲に含まれている場合にのみ実施される。
事業への影響は、明確化され評価された環境事項の実際の又は潜在的な影響(財務的とそれ以外、好ましい又は好ましくない、定性的又は定量的)である。
この評価には.一般にEASOの目的にかかわる環境事項の及ぼす影響について判断が含まれる。この段階で、事業への影響に対処するための費用が見積られ被評価側又は依頼者の社会的イメージに対する影響についても明確にされ、評価される。
この判断に当たっては、次の事項が考慮される。
− 緩和措置又は是正、回避又は防止する対策が実際にもたらす若しくはもたらすかもしれない結果
− 環境損害
− 例えば、法律及び他の関連要求事項の現在並びに予想される変更に対する不遵守の結果生ずる現在又は将来の(公法上及び私法上の)責任
− 被評価側及び/又は依頼者の社会的イメージヘの打撃
− 依頼者若しくは被評価側の企業方針又は他の依頼者が定めた要求事項に対する不適合
− 上記の措置又は対策をとる場合の見積り額
− 技術開発
− 諸々の費用支出をしなければならない期間(例えば、執行措置又は新しい法律の制定の可能性に関連した期間)
情報が十分でないため結論が限定される場合は、それを表明する必要があり、また、いかなる見解もそれに応じて性格付けすることが望ましい。
評価プロセスのこの部分の結果として、事業への影響のリストが作成され、適当な場合には定量化される。
5 報告作成
5.2報告内容
評価者は報告書の内容に対して責任を有し、依頼者が認定事実の重要性を理解できるように工夫した方法で情報を提供することが望ましい。これを行うために、評価者は事実と意見を区別し、認定事実の根拠を明確に特定し、また、認定事実に関する相対的不確実性を指摘することが望ましい。
次に示す情報を依頼者に報告することが望ましい。
− 評価した用地及び/又は組織を特定する情報
− 評価者及び報告書作成者の氏名
− アセスメントの目的、範囲及び基準
− アセスメントの日時及び期間
− 利用可能な情報の制約事項及びそれらのアセスメントに対する影響
− 制約事項、除外事項、修正事項及び合意したアセスメントの範囲からの逸脱
− アセスメントの間に収集した情報の要約及びアセスメントの結果
依頼者と評価者の問の合意に従って、次に示す情報も依頼者に報告してもよい。
− 依頼者の氏名
− 被評価側代表者の氏名
− アセスメントチームのメンバーを特定する情報
− アセスメントスケジュール
− 使用したアセスメント手順の要約
− 使用した備考文書、チェックリスト及び手順書並びにその他作業文書の要約
− 評価方法、及び評価の根拠
− 評価者によって実施されたのであれば、その評価の結果
− 想定される次の段階に関する推奨事項
− 秘密保持に関する要求事項
− 結論
EASO報告書の目次の例を実践の手引き?に示す。
アセスメントの範囲で明示されている場合は、報告書に記述された認定事実を補強し、後日又は他の関係者によってアセスメントの再評価ができるように、備考文献や重要な情報を含む十分な文書類を、報告書に入れておくことが望ましい。評価者は、制約が存在する見解について性格付けをすることが望ましい。例えば情報が不十分な場合がそれに該当する。
5.2 報告書様式
依頼者の優先事項についての意向又はその他の取り決めによって、口頭による報告のみが求められることがある。それ以外の場合には、報告は文書によって行うことが望ましい。
実践の手引き? EASO報告書の目次例
a)要約
b) 序文
一 依頼者の氏名
一 被評価用地又は組織
一 被評価側の代表者の氏名
一 評価者の氏名
− アセスメントの日時及び期間
c)目的及び範囲
一 依頼者の指示事項
一 用地及び組織の境界
d)アセスメント基準
e)アセスメントプロセス
f) 情報
一 情報源
一 制約事項及びその予想される影響
一 要約
g) 結論
一 環境事項
一 事業への影響
付録
5.3 報告書の配布
報告書は依頼者の専有財産である。したがって、評価者及び報告書受領者は秘密保持を尊重し、適切な防護措置を取ることが望ましい。報告書の配布は、依頼者の裁量によるものであり、その中には、被評価側に報告書の写しを提供することを含めてもよい。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/004/attached/attach_4328_7.pdf
2009年12月12日
ISO14000 規格
ISO 14001 環境マネジメントシステム要求事項
4.1 一般要求事
4.2 環境方針
4.3 計画
4.3.1 環境側面
4.3.2 法的及びその他の要求事項
4.3.3 目的、目標及び実施計画
4.4 実施及び運用
4.4.1 資源、役割、責任及び権限
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
4.4.3 コミュニケーション
4.4.4 文書類
4.4.5 文書管理
4.4.6 運用管理
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
4.5 点検
4.5.1 監視及び測定
4.5.2 順守評価
4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置
4.5.4 記録の管理
4.5.5 内部監査
4.6 マネジメントレビュー
http://www.jisc.go.jp/mss/ems-14001.html
--------------------------------------------------------------------------------
4.1一般要求事項
・ 組織は環境マネジメントシステムを確立し維持しなければならない。その要求事項は、この4.全体で述べる。
--------------------------------------------------------------------------------
4.2 環 境 方 針
・ 最高経営層は組織の環境方針を定め、その方針について次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の活動、製品又はサービスの性質、規模及び環境影響に対して適切である。
b)継続的改善及び汚染の予防の関する約束を含む。
c)関連する環境法規、及び組織が同意する他の要求事項を遵守する約束を含む。
d)環境目的及び目標を設定し、見直しの枠組みを与える。
e)文書化され、実行され、維持されかつ全従業員に周知される。
f)一般の人が入手可能である。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3 計 画
4.3.1 環境側面
・ 組織は著しい環境影響を持つか、又は持ちうる環境側面を決定するために、・ 組織が管理でき、かつ影響を生じると思われる活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は環境目的設定に際して、この著しい影響に関連する側面を確実に配慮しなければならない。
・ 組織はこの情報を常に最新のものとしなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 法的及びその他の要求事項
・ 組織は、その活動、製品またはサービスの環境側面に適用可能な法的要求事項及び組織は同意するその他の要求事項を特定し参照できるような手順を確立し維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.3 目的、目標
・ 組織は組織内の関連する各部門、各階層で文書化された環境目的、及び目標を設定し維持しなければならない。
・ その目的を設定し見直しをするときに、組織は法的及びその他の要求事項、著しい環境側面、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解に配慮しなければならない。
・ 目的、及び目標は汚染予防に関する約束を含め、環境方針と整合させなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.4 環境マネジメントプログラム
・ 組織はその目的及び目標を達成するためにプログラムを策定し維持しなければならない。
・プログラムには次の事項を含まなければならない。
a)組織の関係する、各部門、各階層における、目的、目標を達成するための責任の明示。
b)目的及び、目標を達成するための手段、及び日程
・ プロジェクトが新規開発及び新規若しくは変更された活動、製品又はサービスに関する場合には環境マネジメントが、そのようなプロジェクトにも確実に適用されるようにプログラムの該当部分を改訂しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4実施及び運用
4.4.1体制及び責任
・ 効果的な環境マネジメントを実施するために、役割、責任及び権限を定め文書化し、かつ伝達しなければならない。
・ 経営層は、環境マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な資源を用意しなければならない。
・ 資源には人的資源及び専門的な技能、技術並びに資金を含む。
・ 組織の最高経営層は、特定の管理責任者(複数も可)を指名しなければならない、かつ、その責任者は次に示す役割、責任及び権限を、他の責任とは関わりなく与えられていなければならない。
a)この規格に従って環境マネジメントシステムの要求事項が確立され、実施され、かつ維持されることを確実にすること。
b)見直しのため及び環境マネジメントの改善の基礎として、最高経営層に環境マネジメントシステムの実績を報告すること。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.2訓練、自覚、及び能力
・ 組織は訓練のニーズを明確にしなければならない。
・ 組織は環境に著しい影響を生じる可能性のある作業を行なうすべての要員が適切な訓練を受けることを要求しなければならない。
・ 組織は関連する各部門、及び各階層において、その従業員又は構成員に次の事項を自覚させる手順を確立し維持しなければならない。
a)環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性
b)作業活動による顕在、又は潜在の著しい環境影響及び各人の作業環境上の利点
c)環境方針及び手順との適合、並びに緊急事態への準備及び対応の要求事項を含む環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任
d)予想された運用手順から逸脱した際に予想される結果。
・ 著しい環境影響の原因となりうる作業を行なう要員は適切な教育訓練及び/又は経験に基づく能力を持たなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.3コミュニケーション
・ 組織は環境側面及び環境マネジメントシステムに関して次の手順を確立しなければならない。
a)組織の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション。
b)外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受け付け、文書化し、及び対応すること。
・ 組織は著しい環境側面について外部コミュニケーションのためのプロセスを検討し、 その決定を記録しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.4環境マネジメントシステム文書化
・ 組織は紙面又は電子形式で次に示すことのために情報を確立し維持しなければならない。
a)マネジメントシステムの核となる要素及びその相互作用を記述。
b)関連する文書の所在を示す。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.5文書管理
・ 組織は次のことを確立するために、この規格が要求するすべての文書を管理する手順を確立し、維持しなければならない。
a)文書の所在が分かること
b)文書が定期的にレビューされ、必要に応じて改訂され、かつ所定の責任者によって妥当性が承認されること。
c)環境マネジメントシステムが効果的に機能するために不可欠な業務が行なわれている、 すべての場所で、関連文書の最新版が利用できること。
d)廃止文書は、すべて発行部署及び使用部署から速やかに撤去されること。そうでなければ意図されない使用がないように保証すること
e)法律上及び/又は情報保存の目的で保管される、あらゆる廃止文書は適切に識別される。
・ 文書は読みやすく、日付が(改訂の日付とともに)あって容易に識別でき、順序良く維持されて 指定の期間保持されなければならない。
・ 種々のタイプの文章の作成及び改訂に関する手順と責任を確立し、維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.6運用管理
・ 組織はその方針、目的及び目標に沿って特定された著しい環境側面に関連する、 運用及び活動を特定しなければならない。
・ 組織はメンテナンスを含む、これらの活動を次に示すことにより特定の条件の下で確実に実行されるよう計画しなければならない。
a)その手順がないと、環境方針並びに目的及び目標から逸脱するかもしれない状況に適用する文書化した手順を確立して維持すること。
b)その手順には運用基準を明記すること。
c)組織が用いる物品、サービスの特定可能な著しい環境側面に関する手順を確立し及び維持すること並びに供給者及び請負者に関連手順及び要求事項を伝達すること。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.7緊急事態への準備及び対応
・ 組織は事故及び緊急事態について、可能性を特定し対応するための並びにそれらに伴なうかもしれない環境影響を予防して緩和するための手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は必要に応じて、特に事故又は緊急事態への準備及び対応の手順をレビューし改訂しなければならない。
・ 組織は、また実行可能な場合にはそのような手順を定期的にテストしなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5点検及び是正
4.5.1監視及び測定
・ 組織は環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するために、文書化した手順を確立し、維持しなければならない。
・ これには、パフォーマンス、関連の運用管理、並びに組織の環境目的、目標との適合を追跡するための情報を記録することを含まなければならない。
・ 監視機器は校(較)正され維持されなければならず、かつプロセスの記録は組織の手順に従って保持されなければならない。
・ 組織は関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.2不適合並び是正及び予防処置
・ 組織は不適合を取り扱い調査し、それによって生じるあらゆる影響を緩和する処置をとり、並びに是正及び予防処置に着手して完了する責任と権限を定めた手順を確立して維持しなければならない。
・ 顕在、及び潜在する不適合の原因を除去するために取られる、あらゆる是正処置又は予防処置は問題の大きさに対応し、かつ生じた環境影響に釣り合わなければならない。
・ 組織は是正及び予防処置に伴なう文書化した手順のあらゆる変更を実施に移し、記録しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.3記録
・ 組織は環境記録の識別、維持及び廃棄のための手順を確立し、維持しなければならない。
・ この記録は、訓練記録、並びに監査及び見直し結果を含まなければならない。
・ 環境記録は読みやすく識別可能であり、かつ関連した活動、製品又はサービスに対して追跡可能でなければならない。
・ 環境記録は容易に検索でき、かつ損傷、劣化または紛失を防ぐような方法で保管され、維持されなければならない。
・ 保管期間が定められ記録されなければならない。
・ 記録はシステム及び組織に応じて、この規格の要求事項への適合を示すために維持されなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.4環境マネジメントシステム監査
・ 組織は次のことを行なうために、実施すべき定期的環境マネジメントシステム監査のプログラム(複数も可)及び手順を確立し維持しなければならない。
a)環境マネジメントシステムが
1)この規格の要求事項を含めて、環境マネジメントのために計画された取り決めに合致しているか、
2)適切に実施され維持されているか、
否かを決定する。
b)監査の結果に関する情報を経営層に提供する。
・ 組織の監査プログラムはあらゆるスケジュールを含めて当該活動の環境上の重要性、及び前回監査の結果に基づいていなければならない。
・ 包括的なものとするために、監査手順は監査の範囲、頻度及び方法を、監査を実施し及び結果を報告するための責任及び要求事項とともに含まなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.6経営層による見直し
・ 組織の最高経営層は、環境マネジメントシステムが継続的する適切性、妥当性、かつ有効性を確実にするために、自ら定めた間隔で環境マネジメントシステムを見直さなければならない。
・ 経営層による見直しプロセスでは、経営層がこの評価を実施できるように、必要な情報が確実に収集されなければならない。
・ この見直しは文書化されなければならない。
・ 経営層による見直しは環境マネジメントシステム監査の結果、変化している周囲の状況、及び継続的改善への約束に照らして、方針、目的、及び環境マネジメントシステムのその他の要素の変更の必要性に言及しなければならない。
http://qpon.quu.cc/toyota/14000.htm
ISO 14000は、国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格(IS)の総称。ISO 14000及び環境ISOと称呼する時は、主として要求事項であるISO 14001のことを指す。
ISO 14000シリーズは、1992年の地球サミットをきっかけとして規格策定が始まり、1996年より発行が開始された。 (厳密に言うと、地球サミット前に創設されたBCSD(持続可能な開発のための産業人会議)がISO(国際標準化機構)に対して、環境についての国際標準化に取り組むよう要請を行った。)
概要
ISO 14000ファミリーが支援する環境マネジメントシステム(EMS: Environmental Management Systems)の構築を要求した規格がISO 14001である。
組織(企業、各種団体など)の活動・製品及びサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善するためのシステムを構築し、そのシステムを継続的に改善していくPDCAサイクルを構築することが要求されている。この中で、有害な環境影響(環境への負荷)の低減及び有益な環境影響の増大、組織の経営改善、環境経営が期待される。ただし、環境パフォーマンスの評価に関する具体的な取決めはなく、組織は自主的にできる範囲で評価を行うことになる。
ISO 14001は、1996年9月に制定され、その後、2004年11月に規定の明確化とISO 9001との両立性という原則により規格改定が行われた。 ISO 14001は環境マネジメントシステムの満たすべき必須事項を定めている。関連規格であるISO 14004は、ISO 14001の適用にあたって組織がいかに環境マネジメントシステムを構築するか広義で詳細な事項が示された手引きであり、拘束力はない。日本国内ではこれらに対応し、日本工業規格 JIS Q 14001, JIS Q 14004が制定され、規格群中の他の規格もJIS化が行われている。
近年では、環境マネジメントシステムの適用範囲の拡大が見られ、企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)を評価する際の基準に利用されることがあり、社会的責任投資(SRI: Socially Responsible Investment)にも関連している[1]。 また、組織内外の双方向コミュニケーションによる環境コミュニケーションが促進され、その情報は重要な企業情報として位置づけられる動向がある。
審査登録制度
組織がISO14001に基づき環境マネジメントシステムを構築したことを社会へ伝えるには自己宣言、そして外部機関による評価が可能である。このうち、外部機関である審査登録機関が第三者として審査登録制度に基づき組織を審査し適合している場合は、登録し公に証明され、登録証書が発行される。これがISO14001の認証(審査登録)である。有効期間は審査登録機関により異なるが、概ね登録日から3年間である。なお、このようにマネジメントシステムが規格に適合しているかを審査し登録する場合には「審査登録」または「認証」という用語を使用し、後述の審査登録機関・審査員評価登録機関・審査員研修機関に対して用いる「認定」という用語とは区別する。
国際標準化機構内の政策開発委員会のひとつである適合性評価委員会(CASCO)が作成した規格(ISO/IEC 17011)に適合した「認定機関」が、適合性評価機関、すなわち「審査登録機関(認証機関)」、審査員の資格を与える「審査員評価登録機関」、審査員になるための研修を行う「審査員研修機関」の審査・認定・登録を統括する。なお、認定機関は他の認定機関と相互承認することにより適合性を保っている。日本での唯一の認定機関は日本適合性認定協会(JAB)であり、海外の認定機関と相互承認している。
日本では、品質管理の国際規格である初期のISO 9000シリーズを不要とした国際的な背景もあり、環境問題に関して積極的な取組みが行われ、ISO 14001認証取得した組織数は群を抜いて世界最多国である[4]。 従って日本は審査登録機関の市場として、海外の認定機関より認定された審査登録機関(認証機関)による進出が多く、国際通商、要求事項の翻訳解釈、各国の法的要求事項等のメリット及びデメリットが数多く挙げられる。組織はお墨付き(審査登録または認証)の必要性がある場合、対象となる項目範囲、登録の範囲を決め、さらに審査登録機関の選択が求められる。
大手企業との商取引においては認証の取得を要求される事もよく見られ、中小企業などでも取引先や親会社から求められて取得する例は珍しくなかった。企業以外でも、地方自治体など企業以外の組織が認証を受ける例も多くなり、イメージアップを企図したNPOや宗教法人などが取得する事も見られる。認証取得していることが必ずしも適切な環境マネジメントシステムを構築しているとは限らないため、取引先等の利害関係者の評価方法も重要視される。ISOのシステムを構築したことを情報公開による自己適合宣言、客先等の利害関係者の評価も可能ではある。
ISO 14000ファミリー
ISO 14001:2004 環境マネジメントシステム(EMS)−要求事項及び利用の手引き
ISO 14004:2004 環境マネジメントシステム−原則、システム及び支援技法の一般指針
ISO14005 環境マネジメントシステム−段階的適用のガイド(WD3段階) 2009年発行予定
ISO 14015 環境マネジメント−用地及び組織の環境アセスメント(EASC)。土壌汚染に関する規格。
ISO 14020シリーズ 環境ラベル(EL)
ISO14020:2000 環境ラベル及び宣言‐一般原則
ISO14021:1999 環境ラベル及び宣言-自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示)
ISO14024:1999 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境ラベル表示-原則及び手続
ISO14025 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境宣言-原則と枠組み
TR14025:2000 環境ラベル及び宣言-タイプ? 環境宣言
ISO 14030シリーズ 環境パフォーマンス評価(EPE)
ISO14031:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価-指針
ISO/TR14032:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価 実施例
ISO 14040シリーズ ライフサイクルアセスメント(LCA)
ISO14040 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-原則及び枠組み
ISO14044 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-要求事項及び指針
TS14048 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-データ記述書式
TR14047:2003 環境マネジメント-ライフサイクル影響評価-ISO14042に関する適用事例
ISO 14050 環境マネジメント用語
ISO/TR 14062 環境適合設計 - 2008年1月現在、技術報告書(Technical Report)の情報提供文書として発行、JIS化はされている。
ISO 14063 環境コミュニケーション
ISO 14064-1 温室効果ガス - 第1部:組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-2 温室効果ガス - 第2部:プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量削減又は吸収量増大の定量化、* 監視及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-3 温室効果ガス - 第3部:温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証のための手引
ISO 14065 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する認定又はその他の承認において使用される有効化確認及び検証を行う機関に対する要求事項
ISO 14066 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証を行う者の力量に関する要求事項
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO 19011 品質及び環境マネジメントシステム監査のための指針
ISO Guide64:1997 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメントシステムに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成8年11月26日 環境庁告示78号
国際標準化機構(ISO)は、平成8年9月に
ISO14001(環境マネジメントシステム―仕様及び利用の手引)及び
ISO14004(環境マネジメントシステム―原則、システム及び支援技法の一般指針)を、同年十月に
ISO14010(環境監査の指針―一般原則)、
ISO10411(環境監査の指針―監査手順―環境マネジメントシステムの監査)及び
ISO14012(環境監査の指針―環境監査員のための資格基準)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境マネジメントシステムに関する国際的基準であり、環境基本計画 第三部第三章第一節において、事業者が環境管理を自主的に進める上でその検討状況を踏まえることとされたものである。
なお、これらの国際規格の技術的内容及び規格票の様式は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成8年10月にそれぞれ日本工業規格Q14001、日本工業規格Q14004、日本工業規格Q14010、日本工業規格Q14011及び日本工業規格Q14012として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000067
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント―ライフサイクルアセスメントに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成9年12月11日 環境庁告示85号
国際標準化機構(ISO)は、平成九年六月十五日に
ISO14040(環境マネジメント―ライフサイクルアセスメント―原則及び枠組み)を発行した。
この国際規格は、製品等の原材料の採取から製造、使用及び処分に至る生涯を通しての環境影響を調査する技法であるライフサイクルアセスメントのうち、その調査の実施及び報告の作成にかかわる原則並びに枠組みの部分に関する国際基準である。環境基本計画第三部第三章第一節3では、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、この国際規格は、これに資するものである。
また、この国際規格は、国、地方公共団体、国民等の各主体の自主的積極的な環境保全活動の促進にも資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成9年11月に日本工業規格Q14040として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000068
国際標準化機構(ISO)の環境ラべル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行されたので告示する公布日:平成12年9月22日 環境庁告示63号
国際標準化機構(ISO)の環境ラベル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行された件
国際標準化機構(ISO)は、平成10年8月1日に
ISO14020(環境ラベル及び宣言―一般原則)を、平成11年9月に
ISO14021(環境ラベル及び宣言―自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示))を、同年4月に
ISO14024(環境ラベル及び宣言―タイプ?環境ラべル表示―原則及び手続)を、平成12年3月に
ISO/TR(技術報告書)14025(環境ラベル―タイプ?環境宣言)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格及び技術報告書は、あらゆる種類の製品及びサービスに適用できる環境ラベル及び宣言に関するものである。また、環境基本計画第三部第三章第一節において、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、これらの国際規格及び技術報告書は、これに資するものである。
なお、これらの国際規格及び技術報告書の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、それぞれ平成10年7月に日本工業規格Q14020、平成12年8月に日本工業規格Q14021及び日本工業規格Q14024として制定され、また、平成12年8月に標準情報Q0003として公表されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000070
国際標準化機構(ISO)の環境パフォーマンス評価に関する国際規格が発行されたので告示する 公布日:平成13年2月19日 環境省告示7号
国際標準化機構(ISO)は、平成11年11月にISO14031(環境マネジメント―環境パフォーマンス評価―指針)を発行した。
この国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境パフォーマンス評価の設計及び使用に関する指針である。また、環境基本計画 第三部第二章第三節2(2)イにおいて、「環境に配慮した事業活動の成果について適切に評価するため、環境パフォーマンス評価(中略)について調査研究を進め、その普及を図ります。」とされており、この国際規格は、これに資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成12年10月に日本工業規格Q14031として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000071
http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/46712922.html
4.1 一般要求事
4.2 環境方針
4.3 計画
4.3.1 環境側面
4.3.2 法的及びその他の要求事項
4.3.3 目的、目標及び実施計画
4.4 実施及び運用
4.4.1 資源、役割、責任及び権限
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
4.4.3 コミュニケーション
4.4.4 文書類
4.4.5 文書管理
4.4.6 運用管理
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
4.5 点検
4.5.1 監視及び測定
4.5.2 順守評価
4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置
4.5.4 記録の管理
4.5.5 内部監査
4.6 マネジメントレビュー
http://www.jisc.go.jp/mss/ems-14001.html
--------------------------------------------------------------------------------
4.1一般要求事項
・ 組織は環境マネジメントシステムを確立し維持しなければならない。その要求事項は、この4.全体で述べる。
--------------------------------------------------------------------------------
4.2 環 境 方 針
・ 最高経営層は組織の環境方針を定め、その方針について次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の活動、製品又はサービスの性質、規模及び環境影響に対して適切である。
b)継続的改善及び汚染の予防の関する約束を含む。
c)関連する環境法規、及び組織が同意する他の要求事項を遵守する約束を含む。
d)環境目的及び目標を設定し、見直しの枠組みを与える。
e)文書化され、実行され、維持されかつ全従業員に周知される。
f)一般の人が入手可能である。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3 計 画
4.3.1 環境側面
・ 組織は著しい環境影響を持つか、又は持ちうる環境側面を決定するために、・ 組織が管理でき、かつ影響を生じると思われる活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は環境目的設定に際して、この著しい影響に関連する側面を確実に配慮しなければならない。
・ 組織はこの情報を常に最新のものとしなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 法的及びその他の要求事項
・ 組織は、その活動、製品またはサービスの環境側面に適用可能な法的要求事項及び組織は同意するその他の要求事項を特定し参照できるような手順を確立し維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.3 目的、目標
・ 組織は組織内の関連する各部門、各階層で文書化された環境目的、及び目標を設定し維持しなければならない。
・ その目的を設定し見直しをするときに、組織は法的及びその他の要求事項、著しい環境側面、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解に配慮しなければならない。
・ 目的、及び目標は汚染予防に関する約束を含め、環境方針と整合させなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.4 環境マネジメントプログラム
・ 組織はその目的及び目標を達成するためにプログラムを策定し維持しなければならない。
・プログラムには次の事項を含まなければならない。
a)組織の関係する、各部門、各階層における、目的、目標を達成するための責任の明示。
b)目的及び、目標を達成するための手段、及び日程
・ プロジェクトが新規開発及び新規若しくは変更された活動、製品又はサービスに関する場合には環境マネジメントが、そのようなプロジェクトにも確実に適用されるようにプログラムの該当部分を改訂しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4実施及び運用
4.4.1体制及び責任
・ 効果的な環境マネジメントを実施するために、役割、責任及び権限を定め文書化し、かつ伝達しなければならない。
・ 経営層は、環境マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な資源を用意しなければならない。
・ 資源には人的資源及び専門的な技能、技術並びに資金を含む。
・ 組織の最高経営層は、特定の管理責任者(複数も可)を指名しなければならない、かつ、その責任者は次に示す役割、責任及び権限を、他の責任とは関わりなく与えられていなければならない。
a)この規格に従って環境マネジメントシステムの要求事項が確立され、実施され、かつ維持されることを確実にすること。
b)見直しのため及び環境マネジメントの改善の基礎として、最高経営層に環境マネジメントシステムの実績を報告すること。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.2訓練、自覚、及び能力
・ 組織は訓練のニーズを明確にしなければならない。
・ 組織は環境に著しい影響を生じる可能性のある作業を行なうすべての要員が適切な訓練を受けることを要求しなければならない。
・ 組織は関連する各部門、及び各階層において、その従業員又は構成員に次の事項を自覚させる手順を確立し維持しなければならない。
a)環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性
b)作業活動による顕在、又は潜在の著しい環境影響及び各人の作業環境上の利点
c)環境方針及び手順との適合、並びに緊急事態への準備及び対応の要求事項を含む環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任
d)予想された運用手順から逸脱した際に予想される結果。
・ 著しい環境影響の原因となりうる作業を行なう要員は適切な教育訓練及び/又は経験に基づく能力を持たなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.3コミュニケーション
・ 組織は環境側面及び環境マネジメントシステムに関して次の手順を確立しなければならない。
a)組織の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション。
b)外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受け付け、文書化し、及び対応すること。
・ 組織は著しい環境側面について外部コミュニケーションのためのプロセスを検討し、 その決定を記録しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.4環境マネジメントシステム文書化
・ 組織は紙面又は電子形式で次に示すことのために情報を確立し維持しなければならない。
a)マネジメントシステムの核となる要素及びその相互作用を記述。
b)関連する文書の所在を示す。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.5文書管理
・ 組織は次のことを確立するために、この規格が要求するすべての文書を管理する手順を確立し、維持しなければならない。
a)文書の所在が分かること
b)文書が定期的にレビューされ、必要に応じて改訂され、かつ所定の責任者によって妥当性が承認されること。
c)環境マネジメントシステムが効果的に機能するために不可欠な業務が行なわれている、 すべての場所で、関連文書の最新版が利用できること。
d)廃止文書は、すべて発行部署及び使用部署から速やかに撤去されること。そうでなければ意図されない使用がないように保証すること
e)法律上及び/又は情報保存の目的で保管される、あらゆる廃止文書は適切に識別される。
・ 文書は読みやすく、日付が(改訂の日付とともに)あって容易に識別でき、順序良く維持されて 指定の期間保持されなければならない。
・ 種々のタイプの文章の作成及び改訂に関する手順と責任を確立し、維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.6運用管理
・ 組織はその方針、目的及び目標に沿って特定された著しい環境側面に関連する、 運用及び活動を特定しなければならない。
・ 組織はメンテナンスを含む、これらの活動を次に示すことにより特定の条件の下で確実に実行されるよう計画しなければならない。
a)その手順がないと、環境方針並びに目的及び目標から逸脱するかもしれない状況に適用する文書化した手順を確立して維持すること。
b)その手順には運用基準を明記すること。
c)組織が用いる物品、サービスの特定可能な著しい環境側面に関する手順を確立し及び維持すること並びに供給者及び請負者に関連手順及び要求事項を伝達すること。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.7緊急事態への準備及び対応
・ 組織は事故及び緊急事態について、可能性を特定し対応するための並びにそれらに伴なうかもしれない環境影響を予防して緩和するための手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は必要に応じて、特に事故又は緊急事態への準備及び対応の手順をレビューし改訂しなければならない。
・ 組織は、また実行可能な場合にはそのような手順を定期的にテストしなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5点検及び是正
4.5.1監視及び測定
・ 組織は環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するために、文書化した手順を確立し、維持しなければならない。
・ これには、パフォーマンス、関連の運用管理、並びに組織の環境目的、目標との適合を追跡するための情報を記録することを含まなければならない。
・ 監視機器は校(較)正され維持されなければならず、かつプロセスの記録は組織の手順に従って保持されなければならない。
・ 組織は関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.2不適合並び是正及び予防処置
・ 組織は不適合を取り扱い調査し、それによって生じるあらゆる影響を緩和する処置をとり、並びに是正及び予防処置に着手して完了する責任と権限を定めた手順を確立して維持しなければならない。
・ 顕在、及び潜在する不適合の原因を除去するために取られる、あらゆる是正処置又は予防処置は問題の大きさに対応し、かつ生じた環境影響に釣り合わなければならない。
・ 組織は是正及び予防処置に伴なう文書化した手順のあらゆる変更を実施に移し、記録しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.3記録
・ 組織は環境記録の識別、維持及び廃棄のための手順を確立し、維持しなければならない。
・ この記録は、訓練記録、並びに監査及び見直し結果を含まなければならない。
・ 環境記録は読みやすく識別可能であり、かつ関連した活動、製品又はサービスに対して追跡可能でなければならない。
・ 環境記録は容易に検索でき、かつ損傷、劣化または紛失を防ぐような方法で保管され、維持されなければならない。
・ 保管期間が定められ記録されなければならない。
・ 記録はシステム及び組織に応じて、この規格の要求事項への適合を示すために維持されなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.4環境マネジメントシステム監査
・ 組織は次のことを行なうために、実施すべき定期的環境マネジメントシステム監査のプログラム(複数も可)及び手順を確立し維持しなければならない。
a)環境マネジメントシステムが
1)この規格の要求事項を含めて、環境マネジメントのために計画された取り決めに合致しているか、
2)適切に実施され維持されているか、
否かを決定する。
b)監査の結果に関する情報を経営層に提供する。
・ 組織の監査プログラムはあらゆるスケジュールを含めて当該活動の環境上の重要性、及び前回監査の結果に基づいていなければならない。
・ 包括的なものとするために、監査手順は監査の範囲、頻度及び方法を、監査を実施し及び結果を報告するための責任及び要求事項とともに含まなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.6経営層による見直し
・ 組織の最高経営層は、環境マネジメントシステムが継続的する適切性、妥当性、かつ有効性を確実にするために、自ら定めた間隔で環境マネジメントシステムを見直さなければならない。
・ 経営層による見直しプロセスでは、経営層がこの評価を実施できるように、必要な情報が確実に収集されなければならない。
・ この見直しは文書化されなければならない。
・ 経営層による見直しは環境マネジメントシステム監査の結果、変化している周囲の状況、及び継続的改善への約束に照らして、方針、目的、及び環境マネジメントシステムのその他の要素の変更の必要性に言及しなければならない。
http://qpon.quu.cc/toyota/14000.htm
ISO 14000は、国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格(IS)の総称。ISO 14000及び環境ISOと称呼する時は、主として要求事項であるISO 14001のことを指す。
ISO 14000シリーズは、1992年の地球サミットをきっかけとして規格策定が始まり、1996年より発行が開始された。 (厳密に言うと、地球サミット前に創設されたBCSD(持続可能な開発のための産業人会議)がISO(国際標準化機構)に対して、環境についての国際標準化に取り組むよう要請を行った。)
概要
ISO 14000ファミリーが支援する環境マネジメントシステム(EMS: Environmental Management Systems)の構築を要求した規格がISO 14001である。
組織(企業、各種団体など)の活動・製品及びサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善するためのシステムを構築し、そのシステムを継続的に改善していくPDCAサイクルを構築することが要求されている。この中で、有害な環境影響(環境への負荷)の低減及び有益な環境影響の増大、組織の経営改善、環境経営が期待される。ただし、環境パフォーマンスの評価に関する具体的な取決めはなく、組織は自主的にできる範囲で評価を行うことになる。
ISO 14001は、1996年9月に制定され、その後、2004年11月に規定の明確化とISO 9001との両立性という原則により規格改定が行われた。 ISO 14001は環境マネジメントシステムの満たすべき必須事項を定めている。関連規格であるISO 14004は、ISO 14001の適用にあたって組織がいかに環境マネジメントシステムを構築するか広義で詳細な事項が示された手引きであり、拘束力はない。日本国内ではこれらに対応し、日本工業規格 JIS Q 14001, JIS Q 14004が制定され、規格群中の他の規格もJIS化が行われている。
近年では、環境マネジメントシステムの適用範囲の拡大が見られ、企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)を評価する際の基準に利用されることがあり、社会的責任投資(SRI: Socially Responsible Investment)にも関連している[1]。 また、組織内外の双方向コミュニケーションによる環境コミュニケーションが促進され、その情報は重要な企業情報として位置づけられる動向がある。
審査登録制度
組織がISO14001に基づき環境マネジメントシステムを構築したことを社会へ伝えるには自己宣言、そして外部機関による評価が可能である。このうち、外部機関である審査登録機関が第三者として審査登録制度に基づき組織を審査し適合している場合は、登録し公に証明され、登録証書が発行される。これがISO14001の認証(審査登録)である。有効期間は審査登録機関により異なるが、概ね登録日から3年間である。なお、このようにマネジメントシステムが規格に適合しているかを審査し登録する場合には「審査登録」または「認証」という用語を使用し、後述の審査登録機関・審査員評価登録機関・審査員研修機関に対して用いる「認定」という用語とは区別する。
国際標準化機構内の政策開発委員会のひとつである適合性評価委員会(CASCO)が作成した規格(ISO/IEC 17011)に適合した「認定機関」が、適合性評価機関、すなわち「審査登録機関(認証機関)」、審査員の資格を与える「審査員評価登録機関」、審査員になるための研修を行う「審査員研修機関」の審査・認定・登録を統括する。なお、認定機関は他の認定機関と相互承認することにより適合性を保っている。日本での唯一の認定機関は日本適合性認定協会(JAB)であり、海外の認定機関と相互承認している。
日本では、品質管理の国際規格である初期のISO 9000シリーズを不要とした国際的な背景もあり、環境問題に関して積極的な取組みが行われ、ISO 14001認証取得した組織数は群を抜いて世界最多国である[4]。 従って日本は審査登録機関の市場として、海外の認定機関より認定された審査登録機関(認証機関)による進出が多く、国際通商、要求事項の翻訳解釈、各国の法的要求事項等のメリット及びデメリットが数多く挙げられる。組織はお墨付き(審査登録または認証)の必要性がある場合、対象となる項目範囲、登録の範囲を決め、さらに審査登録機関の選択が求められる。
大手企業との商取引においては認証の取得を要求される事もよく見られ、中小企業などでも取引先や親会社から求められて取得する例は珍しくなかった。企業以外でも、地方自治体など企業以外の組織が認証を受ける例も多くなり、イメージアップを企図したNPOや宗教法人などが取得する事も見られる。認証取得していることが必ずしも適切な環境マネジメントシステムを構築しているとは限らないため、取引先等の利害関係者の評価方法も重要視される。ISOのシステムを構築したことを情報公開による自己適合宣言、客先等の利害関係者の評価も可能ではある。
ISO 14000ファミリー
ISO 14001:2004 環境マネジメントシステム(EMS)−要求事項及び利用の手引き
ISO 14004:2004 環境マネジメントシステム−原則、システム及び支援技法の一般指針
ISO14005 環境マネジメントシステム−段階的適用のガイド(WD3段階) 2009年発行予定
ISO 14015 環境マネジメント−用地及び組織の環境アセスメント(EASC)。土壌汚染に関する規格。
ISO 14020シリーズ 環境ラベル(EL)
ISO14020:2000 環境ラベル及び宣言‐一般原則
ISO14021:1999 環境ラベル及び宣言-自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示)
ISO14024:1999 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境ラベル表示-原則及び手続
ISO14025 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境宣言-原則と枠組み
TR14025:2000 環境ラベル及び宣言-タイプ? 環境宣言
ISO 14030シリーズ 環境パフォーマンス評価(EPE)
ISO14031:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価-指針
ISO/TR14032:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価 実施例
ISO 14040シリーズ ライフサイクルアセスメント(LCA)
ISO14040 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-原則及び枠組み
ISO14044 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-要求事項及び指針
TS14048 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-データ記述書式
TR14047:2003 環境マネジメント-ライフサイクル影響評価-ISO14042に関する適用事例
ISO 14050 環境マネジメント用語
ISO/TR 14062 環境適合設計 - 2008年1月現在、技術報告書(Technical Report)の情報提供文書として発行、JIS化はされている。
ISO 14063 環境コミュニケーション
ISO 14064-1 温室効果ガス - 第1部:組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-2 温室効果ガス - 第2部:プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量削減又は吸収量増大の定量化、* 監視及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-3 温室効果ガス - 第3部:温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証のための手引
ISO 14065 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する認定又はその他の承認において使用される有効化確認及び検証を行う機関に対する要求事項
ISO 14066 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証を行う者の力量に関する要求事項
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO 19011 品質及び環境マネジメントシステム監査のための指針
ISO Guide64:1997 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメントシステムに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成8年11月26日 環境庁告示78号
国際標準化機構(ISO)は、平成8年9月に
ISO14001(環境マネジメントシステム―仕様及び利用の手引)及び
ISO14004(環境マネジメントシステム―原則、システム及び支援技法の一般指針)を、同年十月に
ISO14010(環境監査の指針―一般原則)、
ISO10411(環境監査の指針―監査手順―環境マネジメントシステムの監査)及び
ISO14012(環境監査の指針―環境監査員のための資格基準)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境マネジメントシステムに関する国際的基準であり、環境基本計画 第三部第三章第一節において、事業者が環境管理を自主的に進める上でその検討状況を踏まえることとされたものである。
なお、これらの国際規格の技術的内容及び規格票の様式は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成8年10月にそれぞれ日本工業規格Q14001、日本工業規格Q14004、日本工業規格Q14010、日本工業規格Q14011及び日本工業規格Q14012として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000067
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント―ライフサイクルアセスメントに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成9年12月11日 環境庁告示85号
国際標準化機構(ISO)は、平成九年六月十五日に
ISO14040(環境マネジメント―ライフサイクルアセスメント―原則及び枠組み)を発行した。
この国際規格は、製品等の原材料の採取から製造、使用及び処分に至る生涯を通しての環境影響を調査する技法であるライフサイクルアセスメントのうち、その調査の実施及び報告の作成にかかわる原則並びに枠組みの部分に関する国際基準である。環境基本計画第三部第三章第一節3では、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、この国際規格は、これに資するものである。
また、この国際規格は、国、地方公共団体、国民等の各主体の自主的積極的な環境保全活動の促進にも資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成9年11月に日本工業規格Q14040として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000068
国際標準化機構(ISO)の環境ラべル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行されたので告示する公布日:平成12年9月22日 環境庁告示63号
国際標準化機構(ISO)の環境ラベル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行された件
国際標準化機構(ISO)は、平成10年8月1日に
ISO14020(環境ラベル及び宣言―一般原則)を、平成11年9月に
ISO14021(環境ラベル及び宣言―自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示))を、同年4月に
ISO14024(環境ラベル及び宣言―タイプ?環境ラべル表示―原則及び手続)を、平成12年3月に
ISO/TR(技術報告書)14025(環境ラベル―タイプ?環境宣言)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格及び技術報告書は、あらゆる種類の製品及びサービスに適用できる環境ラベル及び宣言に関するものである。また、環境基本計画第三部第三章第一節において、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、これらの国際規格及び技術報告書は、これに資するものである。
なお、これらの国際規格及び技術報告書の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、それぞれ平成10年7月に日本工業規格Q14020、平成12年8月に日本工業規格Q14021及び日本工業規格Q14024として制定され、また、平成12年8月に標準情報Q0003として公表されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000070
国際標準化機構(ISO)の環境パフォーマンス評価に関する国際規格が発行されたので告示する 公布日:平成13年2月19日 環境省告示7号
国際標準化機構(ISO)は、平成11年11月にISO14031(環境マネジメント―環境パフォーマンス評価―指針)を発行した。
この国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境パフォーマンス評価の設計及び使用に関する指針である。また、環境基本計画 第三部第二章第三節2(2)イにおいて、「環境に配慮した事業活動の成果について適切に評価するため、環境パフォーマンス評価(中略)について調査研究を進め、その普及を図ります。」とされており、この国際規格は、これに資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成12年10月に日本工業規格Q14031として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000071
http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/46712922.html
2009年10月27日
ISO 9000って???
--------------------------------------------------------------------------------
ISO 9000
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ISO 9000:2000
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000
ISO 9000(広義)、規格群「ISO 9000シリーズ」を省略して「ISO 9000s」と表記。
ISO 9000は、国際標準化機構による品質マネジメントシステム関係の国際規格群。1994年版から2000年版への改正によって、それまでの「製品品質を保証するための規格」から、「品質保証を含んだ、顧客満足の向上を目指すための規格」へと位置付けが変わっている。さらに2008年版では・・・
目次
1 改定履歴
2 規格要求事項
2.1 JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
3 ISO 9001:2008(2008年改訂版)
4 課題
5 関連項目
改定履歴
1987年にISO 9000の規格が制定されてから、1994年と2000年さらに2008年にそれぞれ規格改定が行われた。
ISO 9000:1987
ISO 9000:1994 「94年版」と呼ばれる。
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000 「2000年版」と呼ばれる(ISO 9001)。
「2000年版」と呼ばれる規格
ISO 9000:2005 品質マネジメントシステム―基本及び用語
ISO 9001:2000 品質マネジメントシステム―要求事項
国内での批准翻訳的な規格は、JIS Q 9000:2006 / JIS Q 9001:2000などがある。
2008年版の改正は主に要求事項の明確化とISO 14001 との整合性の向上を目的として行われた。
規格要求事項
ISO 9001(品質マネジメントシステム―要求事項)の目次の一部を下に示す。
JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
JISQ9001:2008(ISO9001:2008)規格解釈
目 次
1.2 適用
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
4.2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一般
4.2.2 品質マニュアル
4.2.3 文書管理
4.2.4 記録の管理
5.経営者の責任5.1 経営者のコミットメント
5.2 顧客重視
5.3 品質方針
5.4 計画
5.4.1 品質目標
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
5.5.2 管理責任者
5.5.3 内部コミュニケーション
5.6 マネジメントレビュー
5.6.1 一般
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
5.6.2 マネジメントレビューからのアウトプット
6.資源の運営管理6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.2.1 一般
6.2.2 力量、教育・訓練及び認識
6.3 インフラストラクチャー
6.4 作業環境
7.製品実現7.1 製品実現の計画
7.2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
7.3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
7.3.2 設計・開発へのインプット
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
7.3.4 設計・開発のレビュー
7.3.5 設計・開発の検証
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
7.3.7 設計・開発の変更管理
7.4 購買
7.4.1 購買プロセス
7.4.2 購買情報
7.4.3 購買製品の検証
7.5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
7.5.4 顧客の所有物
7.5.5 製品の保存
7.6 監視機器及び測定機器の管理
8. 測定、分析及び改善
8.1 一般
8.2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
8.2.2 内部監査
8.2.3 プロセスの監視及び測定
8.2.4 製品の監視及び測定
8.3 不適合製品の管理
8.4 データの分析
8.5 改善
8.5.1 継続的改善
8.5.2 是正処置
8.5.3 予防処置
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
第1章 ISO 9000 規格の解説
第1節 ISO9000規格とは
1 ISO9000規格の成立ち
(1) ISOについて
国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)は1947年に設立された民間の非営利組織で本部はスイスのジュネーブにあります。ISOという略称の由来はギリシャ語の「相等しい」「同一の」を意味する“ISOS”から来ているとも言われています。
ISOは、製品やサービスにおける科学技術や経済活動などの国際標準規格を制定する機関です。日本からは日本工業標準調査会(JISC)が参加しています。
日本のISOの窓口は、経済産業省産業技術環境局です。また、ISO規格の入手等に関する問い合わせ窓口は(財)日本規格協会となっています。
1976年 : ISOに関する委員会TC176が設置され、規格作成の活動が開始。
1987年 : ISO9000、9001〜9003、9004制定
1994年 : ISO9000s1994年版発行(JIS Z 9900s:1994発行)
1998年 :(JIS Z 9900s:1998発行)
2000年12月: ISO9000s:2000発行(JIS Q 9000s:2000発行)
(3) 日本の動き
1991年10月にISO9000規格の翻訳規格として、JIS Z 9900規格が発行されました。1993年11月には、JIS Z 9900(ISO9000)規格の審査登録制度の体制確立と、この制度の整備普及を促進するため、経済団体連合会を構成する産業界が約1年の審議検討を行い、自ら基金を拠出し、(財)日本品質システム審査登録認定協会(JAB:現(財)日本適合性認定協会 http://www.jab.or.jp/)を設立しました。
【品質マネジメントの8原則】
a)顧客重視
組織はその顧客に依存しており、そのために、現在及び将来の顧客ニーズを理解し、顧客要求事項を満たし、顧客の期待を越えるように努力すべきである。
b)リーダーシップ
リーダーは、組織の目的及び方向を一致させる。リーダーは、人々が組織の目標を達することに十分に参画できる内部環境を創りだし、維持すべきである。
c)人々の参画
すべての階層の人々は組織にとって根本的要素であり、その全面的な参画によって、組織の便益のためにその能力を活用することが可能となる。
d)プロセスアプローチ
活動及び関連する資源が一つのプロセスとして運営管理されるとき、望まれる結果がより効率よく達成される。
e)マネジメントへのシステムアプローチ
相互の関連するプロセスを一つのシステムとして、明確にし、理解し、運営管理することが組織の目標を効果的で効率よく達成することに寄与する。
f)継続的改善
組織の総合的パフォーマンスの継続的改善を組織の永遠の目標とすべきである。
g)意思決定への事実に基づくアプローチ
効果的な意思決定は、データ及び情報の分析に基づいている。
h)供給者との互恵関係
組織及びその供給者は独立しており、両者の互恵関係は両者の価値創造能力を高める。
(JIS Q 9004 4. 3より)
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/iso/files/iso.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。 組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善に
かかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
ISO 9001:2008(2008年改訂版)
ISO(国際標準化機構)が、規格の内容の明確化等を目的に平成20年11月15日付けでISO 9001 の改正版を発行したことによって、経済産業省は平成20 年12月20日付けで、JIS Q 9001(品質マネジメントシステム規格)を改正した。今回の改正は、JIS Q 9001 の規格の内容の明確化等を目的とするものであり、組織に要求される事項を追加・変更するものでない。主な改正点は以下のとおり。
(1)規格要求事項の明確化
品質マネジメントシステム:一般要求事項【4.1】アウトソースしたプロセスの管理について、本文の中に“組織は「管理の方式及び程度」を定めなければならない”とするとともに、注記に、「管理の方式及び程度」は以下の3 つの要因により影響されうると説明を追加した。
・アウトソースしたプロセスの適合製品を供給するという組織の能力への影響の可能性
・アウトソースしたプロセスの管理への組織の関与の度合い
・購買管理を遂行する組織の能力
改善:是正処置【8.5.2】及び予防処置【8.5.3】現行版の本文にある“是正処置において実施した活動のレビュー”を、“とった是正処置の有効性のレビュー”と修文することで、ここにおけるレビューとは「実施した是正処置の結果の確認を含む」ことであることを明確にした。
(2)JIS Q 14001 との整合性の向上
記録の管理に関する要求事項【4.2.4】について、JIS Q 14001 との記述順序を揃えることで整合性を向上させた。
課題
ISO 9000シリーズは品質管理を管理する規格であり、品質管理そのものと混同すると形骸化が発生するなどの課題がある。第二次世界大戦後に敗戦国から世界に冠たるものづくり大国になった日本国の品質管理手法と同一視するには無理がある。
関連項目
国際標準化機構
ISO 9004:2000 - 品質マネジメントシステム-パフォーマンス改善の指針
ISO 19011 - 内部監査の規格
ISO 10006 - 品質管理-プロジェクト管理における品質の指針
ISO 14000 - 環境マネジメントシステムの国際規格(IS)
ISO 13485 - 医療機器の規制目的の品質マネジメントシステム
ISO/TS 16949 - 自動車の品質マネジメントシステム
品質管理
プロセスアプローチ
Quality Management System(英語)
ISO
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
4. 2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一般
(1)品質マネジメントシステムの文書には,次の事項を含めなければならない。
a)文書化した,品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c)この規格が要求する“文書化された手順”及び記録
d)組織内のプロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実に実施するために,組織が必要と決定した記録を含む文書
注記1
この規格で“文書化された手順”という用語を使う場合には,その手順が確立され,文書化され,実施され,維持されていることを意味する。一つの文書で,一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。“文書化された手順”の要求事項は,複数の文書で対応してもよい。
注記2
品質マネジメントシステムの文書化の程度は,次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
注記3
文書の様式及び媒体の種類は,どのようなものでもよい。
4.2.2 品質マニュアル
(1)組織は,次の事項を含む品質マニュアルを作成し,維持しなければならない。
a)品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には,除外の詳細,及び除外を正当とする理由。(1.2 参照)
b)品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報
c)品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3 文書管理
(1)品質マネジメントシステムで必要とされる文書は,管理しなければならない。ただし,記録は文書の一種ではあるが,4.2.4 に規定する要求事項に従って管理しなければならない。
(2)次の事項に必要な管理を規定するために,文書化された手順”を確立しなければならない。
a)発行前に,適切かどうかの観点から文書を承認する。
b)文書をレビューする。また,必要に応じて更新し,再承認する。
c)文書の変更の識別及び現在有効な版の識別を確実にする。
d)該当する文書の適切な版が,必要なときに,必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e)文書は,読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f)品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし,その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また,これらを何らかの目的で保持する場合には,適切な識別をする。
4.2.4 記録の管理
(1)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成された記録を,管理しなければならない。
(2)組織は,記録の識別,保管,保護,検索,保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)記録は,読みやすく,容易に識別可能かつ検索可能でなければならない。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
4. 2 文書化に関する要求事項4.2.1 一般
(1)品質マネジメントシステムの文書には,次の事項を含めなければならない。
a)文書化した,品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c)この規格が要求する“文書化された手順”及び記録
d)組織内のプロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実に実施するために,組織が必要と決定した記録を含む文書
注記1
この規格で“文書化された手順”という用語を使う場合には,その手順が確立され,文書化され,実施され,維持されていることを意味する。一つの文書で,一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。“文書化された手順”の要求事項は,複数の文書で対応してもよい。
注記2
品質マネジメントシステムの文書化の程度は,次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
注記3
文書の様式及び媒体の種類は,どのようなものでもよい。
4.2.2 品質マニュアル
(1)組織は,次の事項を含む品質マニュアルを作成し,維持しなければならない。
a)品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には,除外の詳細,及び除外を正当とする理由。(1.2 参照)
b)品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報
c)品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3 文書管理
(1)品質マネジメントシステムで必要とされる文書は,管理しなければならない。ただし,記録は文書の一種ではあるが,4.2.4 に規定する要求事項に従って管理しなければならない。
(2)次の事項に必要な管理を規定するために,文書化された手順”を確立しなければならない。
a)発行前に,適切かどうかの観点から文書を承認する。
b)文書をレビューする。また,必要に応じて更新し,再承認する。
c)文書の変更の識別及び現在有効な版の識別を確実にする。
d)該当する文書の適切な版が,必要なときに,必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e)文書は,読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f)品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし,その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また,これらを何らかの目的で保持する場合には,適切な識別をする。
4.2.4 記録の管理
(1)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成された記録を,管理しなければならない。
(2)組織は,記録の識別,保管,保護,検索,保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)記録は,読みやすく,容易に識別可能かつ検索可能でなければならない。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
5.経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
(1)トップマネジメントは,品質マネジメントシステムの構築及び実施,並びにその有効性を継続的に改善することに対するコミットメントの証拠を,次の事項によって示さなければならない。
a)法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして,顧客要求事項を満たすことの重要性を組織内に周知する。
b)品質方針を設定する。
c)品質目標が設定されることを確実にする。
d)マネジメントレビューを実施する。
e)資源が使用できることを確実にする。
5.2 顧客重視
(1)顧客満足の向上を目指して,トップマネジメントは,顧客要求事項が決定され,満たされていることを確実にしなければならない(7.2.1 及び8.2.1 参照)。
5.3 品質方針
(1)トップマネジメントは,品質方針について,次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の目的に対して適切である。
b)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミットメントを含む。
c)品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。
d)組織全体に伝達され,理解される。
e)適切性の持続のためにレビューされる。
5. 4 計画
5.4.1 品質目標
(1)トップマネジメントは,組織内のしかるべき部門及び階層で,品質目標が設定されていることを確実にしなければならない。
(2)その品質目標には,製品要求事項を満たすために必要なものを含む品質目標[7.1.a]参照]が設定されていることを確実にしなければならない。
(3)品質目標は,その達成度が判定可能で,品質方針との整合がとれていなければならない。
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
(1)トップマネジメントは,次の事項を確実にしなければならない。
a)品質目標に加えて,4.1 に規定する要求事項を満たすために,品質マネジメントシステムの計画を策定する。
b)品質マネジメントシステムの変更を計画し,実施する場合には,品質マネジメントシステムを“完全に整っている状態”(integrity)に維持する。
5. 5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
(1)トップマネジメントは,責任及び権限が定められ,組織全体に周知されていることを確実にしなければならない。
5.5.2 管理責任者
(1)トップマネジメントは,組織の管理層の中から管理責任者を任命しなければならない。
(2)管理責任者は,与えられている他の責任とかかわりなく,次に示す責任及び権限をもたなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立,実施及び維持を確実にする。
b)品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について,トップマネジメントに報告する。
c)組織全体にわたって,顧客要求事項に対する認識を高めることを確実にする。
注記1
管理青任者の責任には,品質マネジメントシステムに関する事項について外部と連絡をとることも含めることができる。
注記2
管理責任者は,上記の責任及び権限をもつ限り,一人である必要はない。
5.5.3 内部コミュニケーション
(1)トップマネジメントは,組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にしなければならない。
(2)また,品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にしなければならない。
5. 6 マネジメントレビュー5.6.1 一般
(1)トップマネジメントは,組織の品質マネジメントシステムが,引き続き,適切,妥当かつ有効であることを確実にするために,あらかじめ定められた間隔で品質マネジメントシステムをレビューしなければならない。
(2)このレビューでは,品質マネジメントシステムの改善の機会の評価,並びに品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行わなければならない。
(3)マネジメントレビューの結果の記録は,維持しなければならない。(4.2.4 参照)。
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
(1)マネジメントレビューへのインプットには,次の情報を含めなければならない。
a)監査の結果
b)顧客からのフィードバック
c)プロセスの成果を含む実施状況及び製品の適合性
d)予防処置及び是正処置の状況
e)前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
f)品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
g)改善のための提案
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
(1)マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項に関する決定及び処置すべてを含めなければならない。
a)品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b)顧客要求事項にかかわる,製品の改善
c)資源の必要性
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
(1)マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項に関する決定及び処置すべてを含めなければならない。
a)品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b)顧客要求事項にかかわる,製品の改善
c)資源の必要性
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
6.資源の運営管理
6.1 資源の提供
(1)組織は,次の事項に必要な資源を明確にし,提供しなければならない。
a)品質マネジメントシステムを実施し,維持する。また,その有効性を継続的に改善する。
b)顧客満足を、顧客要求事項を満たすことによって向上する。
6. 2 人的資源6.2.1 一般
(1)製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員は,適切な教育,訓練,技能及び経験を判断の根拠として力量がなければならない。
注記
製品要求事項への適合は,品質マネジメントシステム内の作業に従事する要員によって,直接的に又は間接的に影響を受ける可能性がある。
6.2.2 力量,認識及び教育・訓練
(1)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量を明確にする。
b)該当する場合には(必要な力量が不足している場合には),その必要な力量に到達することができるように教育・訓練を行うか,又は他の処置をとる。
c)教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。
d)組織の要員が,自らの活動のもつ意味及び重要性を認識し,品質目標の達成に向けて自らがどのように貢献できるかを認識することを確実にする。
e)教育,訓練,技能及び経験について該当する記録を維持する(4.2.4 参照)。
6.3 インフラストラクチャー
(1)組織は,製品要求事項への適合を達成するうえで必要とされるインフラストラクチャーを明確にし,提供し,維持しなければならない。インフラストラクチャーとしては,次のようなものが該当する場合がある。
a)建物,作業場所及び関連するユーティリティー(例えば,電気,ガス又は水)
b)設備(ハードウェア及びソフトウェア)
c)支援体制(例えば,輸送,通信又は情報システム)
6.4 作業環境
(1)組織は,製品要求事項への適合を達成するために必要な作業環境を明確にし,運営管理しなければならない。
注記
“作業環境”という用語は,物理的,環境的及びその他の要因を含む(例えば,騒音,気温,湿度,照明又は天候),作業が行われる状態と関連している。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
7.製品実現
7.1 製品実現の計画
(1)組織は,製品実現のために必要なプロセスを計画し,構築しなければならない。
(2)製品実現の計画は,品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合がとれていなければならない(4.1 参照)。
(3)組織は,製品実現の計画に当たって,次の各事項について適切に明確化しなければならない。
a)製品に対する品質目標及び要求事項
b)製品に特有な,プロセス及び文書の確立の必要性,並びに資源の提供の必要性
c)その製品のための検証,妥当性確認,監視,測定,検査及び試験活動,並びに製品合否判定基準
d)製品実現のプロセス及びその結果としての製品が,要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録(4.2.4 参照)
(4)この計画のアウトプットは,組織の運営方法に適した形式でなければならない。
注記1
特定の製品,プロジェクト又は契約に適用される品質マネジメントシステムのプロセス(製品実現のプロセスを含む。)及び資源を規定する文書を,品質計画書と呼ぶことがある。
注記2
組織は,製品実現のプロセスの構築に当たって,7.3 に規定する要求事項を適用してもよい。
7. 2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化
(1)組織は,次の事項を明確にしなければならない。
a)顧客が規定した要求事項。これには引渡し及び引渡し後の活動に関する要求事項を含む。
b)顧客が明示してはいないが,指定された用途又は意図された用途が既知である場合,それらの用途に応じた要求事項
c)製品に適用される法令・規制要求事項
d)組織が必要と判断する追加要求事項すべて
注記
引渡し後の活動には,例えば,保証に関する取決め,メンテナンスサービスのような契約義務,及びリサイクル又は最終廃棄のような補助的サービスのもとでの活動を含む。
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
(1)組織は,製品に関連する要求事項をレビューしなければならない。
(2)このレビューは,組織が顧客に製品を提供することに対するコミットメント(例:提案書の提出,契約又は注文の受諾,契約又は注文への変更の受諾)をする前に実施しなければならない。
(3)レビューでは,次の事項を確実にしなければならない。
a)製品要求事項が定められている。
b)契約又は注文の要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には,それについて解決されている。
c)組織が,定められた要求事項を満たす能力をもっている。
(4)このレビューの結果の記録,及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
(5)顧客がその要求事項を書面で示さない場合には,組織は顧客要求事項を受諾する前に確認しなければならない。
(6)製品要求事項が変更された場合には,組織は,関連する文書を修正しなければならない。
(7)また,変更後の要求事項が,関連する要員に理解されていることを確実にしなければならない。
注記
インターネット販売などでは,個別の注文に対する正式なレビューの実施は非現実的である。このような場合のレビューでは,カタログ又は宣伝広告資料のような関連する製品情報をその対象とすることもできる。
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
(1)組織は,次の事項に関して顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を明確にし,実施しなければならない。
a)製品情報
b)引き合い,契約若しくは注文,又はそれらの変更
c)苦情を含む顧客からのフィードバック
7. 3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
(1)組織は,製品の設計・開発の計画を策定し,管理しなければならない。
(2)設計・開発の計画において,組織は,次の事項を明確にしなければならない。
a)設計・開発の段階
b)設計・開発の各段階に適したレビュー,検証及び妥当性確認
c)設計・開発に関する責任及び権限
(3)組織は,効果的なコミュニケーション及び責任の明確な割当てを確実にするために,設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理しなければならない。
(4)設計・開発の進行に応じて,策定した計画を適切に更新しなければならない。
注記
設計・開発のレビュー,検証及び妥当性確認は,異なった目的を持っている。それらは,製品及び組織に適するように,個々に又はどのような組み合わせでも,実施し,記録することができる。
7.3.2 設計・開発へのインプット
(1)製品要求事項に関連するインプットを明確にし,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。インプットには,次の事項を含めなければならない。
a)機能及び性能に関する要求事項
b)適用される法令・規制要求事項
c)適用可能な場合には,以前の類似した設計から得られた情報
d)設計・開発に不可欠なその他の要求事項
(2)製品要求事項に関連するインプットについては,その適切性をレビューしなければならない。要求事項は,漏れがなく,あいまい(曖昧)でなく,相反することがあってはならない。
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
(1)設計・開発からのアウトプットは,設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式でなければならない。
(2)また,リリースの前に,承認を受けなければならない。
(3)設計・開発からのアウトプットは,次の状態でなければならない。
a)設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
b)購買,製造及びサービス提供に対して適切な情報を提供する。
c)製品の合否判定基準を含むか,又はそれを参照している。
d)安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性を明確にする。
注記
製造及びサービス提供に対する情報には,製品の保存に関する詳細を含めることができる。
7.3.4 設計・開発のレビュー
(1)設計・開発の適切な段階において,次の事項を目的として,計画されたとおりに(7.3.1 参照)体系的なレビューを行わなければならない。
a)設計・開発の結果が要求事項を満たせるかどうかを評価する。
b)問題を明確にし,必要な処置を提案する。
(2)レビューへの参加者には,レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表する者が含まれていなければならない。
(3)このレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない。(4.2.4 参照)
7.3.5 設計・開発の検証
(1)設計・開発からのアウトプットが,設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために,計画されたとおりに(7.3.1参照)検証を実施しなければならない。
(2)この検証の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない。(4.2.4 参照)
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
(1)結果として得られる製品が,指定された用途又は意図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするために,計画した方法(7.3.1 参照)に従って,設計・開発の妥当性確認を実施しなければならない。
(2)実行可能な湯合にはいつでも,製品の引渡し又は提供の前に,妥当性確認を完了しなければならない。
(3)妥当性確認の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
7.3.7 設計・開発の変更管理
(1)設計・開発の変更を明確にし,記録を維持しなければならない。
(2)変更に対して,レビュー,検証及び妥当性確認を適切に行い,その変更を実施する前に承認しなければならない。
(3)設計・開発の変更のレビューには,その変更が,製品を構成する要素及び既に引き渡されている製品に及ぼす影響の評価を含めなければならない。
(4)変更のレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
注記
“変更のレビュー”とは,変更に対して適切に行われたレビュー,検証及び妥当性確認のことである。
7. 4 購買
7.4.1 購買プロセス
(1)組織は,規定された購買要求事項に,購買製品が適合することを確実にしなければならない。
(2)供給者及び購買した製品に対する管理の方式及び程度は,購買製品が,その後の製品実現のプロセス又は最終製品に及ぼす影響に応じて定めなければならない。
(3)組織は,供給者が組織の要求事項に従って製品を供給する能力を判断の根拠として,供給者を評価し,選定しなければならない。選定,評価及び再評価の基準を定めなければならない。
(4)評価の結果の記録,及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
7.4.2 購買情報
(1)購買情報では購買製品に関する情報を明確にし,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。
a)製品,手順,プロセス及び設備の承認に関する要求事項
b)要員の適格性確認に関する要求事項
c)品質マネジメントシステムに関する要求事項
(2)組織は,供給者に伝達する前に,規定した購買要求事項が妥当であることを確実にしなければならない。
7.4.3 購買製品の検証
(1)組織は,購買製品が,規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために,必要な検査又はその他の活動を定めて,実施しなければならない。
(2)組織又はその顧客が,供給者先で検証を実施することにした場合には,組織は,その検証の要領及び購買製品のリリースの方法を購買情報の中で明確にしなければならない。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
7. 5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
(1)組織は,製造及びサービス提供を計画し,管理された状態で実行しなければならない。
(2)管理された状態には,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。
a)製品の特性を述べた情報が利用できる。
b)必要に応じて,作業手順が利用できる。
c)適切な設備を使用している。
d)監視機器及び測定機器が利用でき,使用している。
e)監視及び測定が実施されている。
f)製品のリリース,顧客への引渡し及び引渡し後の活動が実施されている。
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
(1)製造及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットが,それ以降の監視又は測定で検証することが不可能で,その結果,製品が使用され,又はサービスが提供された後でしか不具合が顕在化しない場合には,組織は,その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行わなければならない。
(2)妥当性確認によって,これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証しなければならない。
(3)組織は,これらのプロセスについて,次の事項のうち該当するものを含んだ手続を確立しなければならない。
a)プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準
b)設備の承認及び要員の適格性確認
c)所定の方法及び手順の適用
d)記録に関する要求事項(4. 2. 4 参照)
e)妥当性の再確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
(1)必要な場合には,組織は,製品実現の全過程において適切な手段で製品を識別しなければならない。
(2)組織は,製品実現の全過程において,監視及び測定の要求事項に関連して,製品の状態を識別しなければならない。
(3)トレーサビリティが要求事項となっている場合には,組織は,製品について一意の識別を管理し,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
注記
ある産業分野では,構成管理(configuration management)が識別及びトレーサビリティを維持する手段である。
7.5.4 顧客の所有物
(1)組織は,顧客の所有物について,それが組織の管理下にある間,又は組織がそれを使用している間は,注意を払わなければならない。
(2)組織は,使用するため又は製品に組み込むために提供された顧客の所有物の識別,検証及び保護・防護を実施しなければならない。
(3)顧客の所有物を紛失若しくは損傷した場合又は使用には適さないとわかった場合には,組織は,顧客に報告し,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。注記 顧客の所有物には,知的財産及び個人情報を含めることができる。
7.5.5 製品の保存
(1)組織は,内部処理から指定納入先への引渡しまでの間,要求事項への適合を維持するように製品を保存しなければならない。
(2)この保存には,該当する場合,識別,取扱い,包装,保管及び保護を含めなければならない。保存は,製品を構成する要素にも適用しなければならない。
注記 内部処理とは,組織が運営管理している製品実現のプロセスにおける活動をいう。
7.6 監視機器及び測定機器の管理
(1)定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために,組織は,実施すべき監視及び測定を明確にしなければならない。また,そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にしなければならない。
(2)組織は,監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立しなければならない。
(3)測定値の正当性が保証されなければならない場合には,測定機器に関し,次の事項を満たさなければならない。
a)定められた間隔又は使用前に,国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証,又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には,校正又は検証に用いた基準を記録する(4.2.4 参照)。
b)機器の調整をする,又は必要に応じて再調整する。
c)校正の状態を明確にするために識別を行う。
d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
e)取扱い,保守及び保管において,損傷及び劣化しないように保護する。
(4)さらに,測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には,組織は,その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し,記録しなければならない。
(5)組織は,その機器,及び影響を受けた製品すべてに対して,適切な処置をとらなければならない。校正及び検証の結果の記録を維持しなければならない(4.2.4参照)。
(6)規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には,そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認しなければならない。
(7)この確認は,最初に使用するのに先立って実施しなければならない。
(8)また,必要に応じて再確認しなければならない。
注記
意図した用途を満たすコンピュータソフトウェアの能力の確認には,通常,その使用の適切性を維持するための検証及び構成管理も含まれる。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
8.測定、分析及び改善
8.1 一般
(1)組織は,次の事項のために必要となる監視,測定,分析及び改善のプロセスを計画し,実施しなければならない。
a)製品要求事項への適合性を実証する。
b)品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。
c)品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。
(2)これには,統計的手法を含め,適用可能な方法,及びその使用の程度を決定することを含めなければならない。
8. 2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
(1)組織は,品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして,顧客要求事項を満足しているかどうかに関して顧客がどのように受けとめているかについての情報を監視しなければならない。
(2)この情報の入手及び使用の方法を定めなければならない。
注記
顧客がどのように受け止めているかの監視には,顧客満足度調査,提供された製品の品質に関する顧客からのデータ,ユーザ意見調査,失注分析,顧客からの賛辞,補償請求,ディーラ報告などの情報源から得たインプットを含めることができる。
8.2.2 内部監査
(1)組織は,品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明確にするために,あらかじめ定められた間隔で内部監査を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムが,個別製品の実現の計画(7.1 参照)に適合しているか,この規格の要求事項に適合しているか,及び組織が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合しているか。
b)品質マネジメントシステムが効果的に実施され,維持されているか。
(2)組織は,監査の対象となるプロセス及び領域の状態及び重要性,並びにこれまでの監査結果を考慮して,監査プログラムを策定しなければならない。
(3)監査の基準,範囲,頻度及び方法を規定しなければならない。
(4)監査員の選定及び監査の実施においては,監査プロセスの客観性及び公平性を確保しなければならない。
(5)監査員は自らの仕事は監査してはならない。
(6)監査の計画及び実施,記録の作成及び結果の報告に関する責任,並びに要求事項を規定するために“文書化された手順”を確立しなければならない。監査及びその結果の記録は,維持しなければならない(4.2.4 参照)。
(7)監査された領域に責任をもつ管理者は,検出された不適合及びその原因を除去するために遅滞なく,必要な修正及び是正処置すべてがとられることを確実にしなければならない。
(8)フォローアップには,とられた処置の検証及び検証結果の報告を含めなければならない(8.5.2 参照)。
注記 JIS Q 19011 参照。
8.2.3 プロセスの監視及び測定
(1)組織は,品質マネジメントシステムのプロセスの監視,及び適用可能な場合に行う測定には,適切な方法を適用しなければならない。
(2)これらの方法は,プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するものでなければならない。
(3)計画どおりの結果が達成できない場合には,適切に,修正及び是正処置をとらなければならない。
注記
適切な方法を決定するとき,組織は,製品要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性への影響に応じて,個々のプロセスに対する適切な監視又は測定の方式及び程度を考慮することを推奨する。
8.2.4 製品の監視及び測定
(1)組織は,製品要求事項が満たされていることを検証するために,製品の特性を監視し,測定しなければならない。
(2)監視及び測定は,個別製品の実現の計画(7.1 参照)に従って,製品実現の適切な段階で実施すしなければならない。
(3)合否判定基準への適合の証拠を維持しなければならない。
(4)顧客への引渡しのための製品のリリースを正式に許可した人を,記録しておかなければならない(4.2.4 参照)。
(5)個別製品の実現の計画(7.1 参照)で決めたことが問題なく完了するまでは,顧客への製品のリリース及びサービスの提供は行ってはならない。ただし,当該の権限をもつ者が承認したとき,及び該当する場合に顧客が承認したときは,この限りではない。
8.3 不適合製品の管理
(1)組織は,製品要求事項に適合しない製品が誤って使用されたり,又は引き渡されることを防ぐために,それらを識別し,管理することを確実にしなければならない。
(2)不適合製品の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)該当する場合には,組織は,次の一つ又はそれ以上の方法で,不適合製品を処理しなければならない。
a)発見された不適合を除去するための処置をとる。
b)当該の権限をもつ者,及び該当する場合に顧客が,特別採用によって,その使用,リリース,又は合格と判定することを正式に許可する。
c)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。
d)引渡し後又は使用開始後に不適合製品が検出された場合には,その不適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。
注記
“c)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる”とは“廃棄すること”を含む。
(4)不適合製品に修正を施した場合には,要求事項への適合を実証するための再検証を行わなければならない。
(5)不適合の性質の記録,及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
8.4 データの分析
(1)組織は,品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため,また,品質マネジメントシステムの継続的な改善の可能性を評価するために適切なデータを明確にし,それらのデータを収集し,分析しなければならない。
(2)この中には,監視及び測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の該当する情報源からのデータを含めなければならない。
(3)データの分析によって,次の事項に関連する情報を提供しなければならない。
a)顧客満足(8.2.1 参照)
b)製品要求事項への適合(8.2.4 参照)
c)予防処置の機会を得ることを含む,プロセス及び製品の,特性及び傾向(8.2.3及び8.2.4 参照)
d)供給者(7.4 参照)
8. 5 改善
8.5.1 継続的改善(1)組織は,品質方針,品質目標,監査結果,データの分析,是正処置,予防処置及びマネジメントレビューを通じて,品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
8.5.2 是正処置
(1)組織は,再発防止のため,不適合の原因を除去する処置をとらなければならない。
(2)是正処置は,検出された不適合のもつ影響に応じたものでなければならない。
(3)次の事項に関する要求事項を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
a)不適合(顧客からの苦情を含む)の内容確認
b)不適合の原因の特定
c)不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価
d)必要な処置の決定及び実施
e)とった処置の結果の記録(4. 2. 4 参照)
f)とった是正処置の有効性のレビュー
注記
f)における“とった是正処置”とは,a)〜e)のことである。
8.5.3 予防処置
(1)組織は,起こり得る不適合が発生することを防止するために,その原因を除去する処置を決めなければならない。
(2)予防処置は,起こり得る問題の影響に応じたものでなければならない。
(3)次の事項に関する要求事項を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
a)起こり得る不適合及びその原因の特定
b)不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価
c)必要な処置の決定及び実施
d)とった処置の結果の記録(4.2.4 参照)
e)とった予防処置の有効性のレビュー
注記 e)における“とった予防処置”とは,a)〜d)のことである。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
ISO 9000
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ISO 9000:2000
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000
ISO 9000(広義)、規格群「ISO 9000シリーズ」を省略して「ISO 9000s」と表記。
ISO 9000は、国際標準化機構による品質マネジメントシステム関係の国際規格群。1994年版から2000年版への改正によって、それまでの「製品品質を保証するための規格」から、「品質保証を含んだ、顧客満足の向上を目指すための規格」へと位置付けが変わっている。さらに2008年版では・・・
目次
1 改定履歴
2 規格要求事項
2.1 JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
3 ISO 9001:2008(2008年改訂版)
4 課題
5 関連項目
改定履歴
1987年にISO 9000の規格が制定されてから、1994年と2000年さらに2008年にそれぞれ規格改定が行われた。
ISO 9000:1987
ISO 9000:1994 「94年版」と呼ばれる。
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000 「2000年版」と呼ばれる(ISO 9001)。
「2000年版」と呼ばれる規格
ISO 9000:2005 品質マネジメントシステム―基本及び用語
ISO 9001:2000 品質マネジメントシステム―要求事項
国内での批准翻訳的な規格は、JIS Q 9000:2006 / JIS Q 9001:2000などがある。
2008年版の改正は主に要求事項の明確化とISO 14001 との整合性の向上を目的として行われた。
規格要求事項
ISO 9001(品質マネジメントシステム―要求事項)の目次の一部を下に示す。
JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
JISQ9001:2008(ISO9001:2008)規格解釈
目 次
1.2 適用
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
4.2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一般
4.2.2 品質マニュアル
4.2.3 文書管理
4.2.4 記録の管理
5.経営者の責任5.1 経営者のコミットメント
5.2 顧客重視
5.3 品質方針
5.4 計画
5.4.1 品質目標
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
5.5.2 管理責任者
5.5.3 内部コミュニケーション
5.6 マネジメントレビュー
5.6.1 一般
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
5.6.2 マネジメントレビューからのアウトプット
6.資源の運営管理6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.2.1 一般
6.2.2 力量、教育・訓練及び認識
6.3 インフラストラクチャー
6.4 作業環境
7.製品実現7.1 製品実現の計画
7.2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
7.3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
7.3.2 設計・開発へのインプット
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
7.3.4 設計・開発のレビュー
7.3.5 設計・開発の検証
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
7.3.7 設計・開発の変更管理
7.4 購買
7.4.1 購買プロセス
7.4.2 購買情報
7.4.3 購買製品の検証
7.5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
7.5.4 顧客の所有物
7.5.5 製品の保存
7.6 監視機器及び測定機器の管理
8. 測定、分析及び改善
8.1 一般
8.2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
8.2.2 内部監査
8.2.3 プロセスの監視及び測定
8.2.4 製品の監視及び測定
8.3 不適合製品の管理
8.4 データの分析
8.5 改善
8.5.1 継続的改善
8.5.2 是正処置
8.5.3 予防処置
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
第1章 ISO 9000 規格の解説
第1節 ISO9000規格とは
1 ISO9000規格の成立ち
(1) ISOについて
国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)は1947年に設立された民間の非営利組織で本部はスイスのジュネーブにあります。ISOという略称の由来はギリシャ語の「相等しい」「同一の」を意味する“ISOS”から来ているとも言われています。
ISOは、製品やサービスにおける科学技術や経済活動などの国際標準規格を制定する機関です。日本からは日本工業標準調査会(JISC)が参加しています。
日本のISOの窓口は、経済産業省産業技術環境局です。また、ISO規格の入手等に関する問い合わせ窓口は(財)日本規格協会となっています。
1976年 : ISOに関する委員会TC176が設置され、規格作成の活動が開始。
1987年 : ISO9000、9001〜9003、9004制定
1994年 : ISO9000s1994年版発行(JIS Z 9900s:1994発行)
1998年 :(JIS Z 9900s:1998発行)
2000年12月: ISO9000s:2000発行(JIS Q 9000s:2000発行)
(3) 日本の動き
1991年10月にISO9000規格の翻訳規格として、JIS Z 9900規格が発行されました。1993年11月には、JIS Z 9900(ISO9000)規格の審査登録制度の体制確立と、この制度の整備普及を促進するため、経済団体連合会を構成する産業界が約1年の審議検討を行い、自ら基金を拠出し、(財)日本品質システム審査登録認定協会(JAB:現(財)日本適合性認定協会 http://www.jab.or.jp/)を設立しました。
【品質マネジメントの8原則】
a)顧客重視
組織はその顧客に依存しており、そのために、現在及び将来の顧客ニーズを理解し、顧客要求事項を満たし、顧客の期待を越えるように努力すべきである。
b)リーダーシップ
リーダーは、組織の目的及び方向を一致させる。リーダーは、人々が組織の目標を達することに十分に参画できる内部環境を創りだし、維持すべきである。
c)人々の参画
すべての階層の人々は組織にとって根本的要素であり、その全面的な参画によって、組織の便益のためにその能力を活用することが可能となる。
d)プロセスアプローチ
活動及び関連する資源が一つのプロセスとして運営管理されるとき、望まれる結果がより効率よく達成される。
e)マネジメントへのシステムアプローチ
相互の関連するプロセスを一つのシステムとして、明確にし、理解し、運営管理することが組織の目標を効果的で効率よく達成することに寄与する。
f)継続的改善
組織の総合的パフォーマンスの継続的改善を組織の永遠の目標とすべきである。
g)意思決定への事実に基づくアプローチ
効果的な意思決定は、データ及び情報の分析に基づいている。
h)供給者との互恵関係
組織及びその供給者は独立しており、両者の互恵関係は両者の価値創造能力を高める。
(JIS Q 9004 4. 3より)
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/iso/files/iso.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。 組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善に
かかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
ISO 9001:2008(2008年改訂版)
ISO(国際標準化機構)が、規格の内容の明確化等を目的に平成20年11月15日付けでISO 9001 の改正版を発行したことによって、経済産業省は平成20 年12月20日付けで、JIS Q 9001(品質マネジメントシステム規格)を改正した。今回の改正は、JIS Q 9001 の規格の内容の明確化等を目的とするものであり、組織に要求される事項を追加・変更するものでない。主な改正点は以下のとおり。
(1)規格要求事項の明確化
品質マネジメントシステム:一般要求事項【4.1】アウトソースしたプロセスの管理について、本文の中に“組織は「管理の方式及び程度」を定めなければならない”とするとともに、注記に、「管理の方式及び程度」は以下の3 つの要因により影響されうると説明を追加した。
・アウトソースしたプロセスの適合製品を供給するという組織の能力への影響の可能性
・アウトソースしたプロセスの管理への組織の関与の度合い
・購買管理を遂行する組織の能力
改善:是正処置【8.5.2】及び予防処置【8.5.3】現行版の本文にある“是正処置において実施した活動のレビュー”を、“とった是正処置の有効性のレビュー”と修文することで、ここにおけるレビューとは「実施した是正処置の結果の確認を含む」ことであることを明確にした。
(2)JIS Q 14001 との整合性の向上
記録の管理に関する要求事項【4.2.4】について、JIS Q 14001 との記述順序を揃えることで整合性を向上させた。
課題
ISO 9000シリーズは品質管理を管理する規格であり、品質管理そのものと混同すると形骸化が発生するなどの課題がある。第二次世界大戦後に敗戦国から世界に冠たるものづくり大国になった日本国の品質管理手法と同一視するには無理がある。
関連項目
国際標準化機構
ISO 9004:2000 - 品質マネジメントシステム-パフォーマンス改善の指針
ISO 19011 - 内部監査の規格
ISO 10006 - 品質管理-プロジェクト管理における品質の指針
ISO 14000 - 環境マネジメントシステムの国際規格(IS)
ISO 13485 - 医療機器の規制目的の品質マネジメントシステム
ISO/TS 16949 - 自動車の品質マネジメントシステム
品質管理
プロセスアプローチ
Quality Management System(英語)
ISO
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
4. 2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一般
(1)品質マネジメントシステムの文書には,次の事項を含めなければならない。
a)文書化した,品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c)この規格が要求する“文書化された手順”及び記録
d)組織内のプロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実に実施するために,組織が必要と決定した記録を含む文書
注記1
この規格で“文書化された手順”という用語を使う場合には,その手順が確立され,文書化され,実施され,維持されていることを意味する。一つの文書で,一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。“文書化された手順”の要求事項は,複数の文書で対応してもよい。
注記2
品質マネジメントシステムの文書化の程度は,次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
注記3
文書の様式及び媒体の種類は,どのようなものでもよい。
4.2.2 品質マニュアル
(1)組織は,次の事項を含む品質マニュアルを作成し,維持しなければならない。
a)品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には,除外の詳細,及び除外を正当とする理由。(1.2 参照)
b)品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報
c)品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3 文書管理
(1)品質マネジメントシステムで必要とされる文書は,管理しなければならない。ただし,記録は文書の一種ではあるが,4.2.4 に規定する要求事項に従って管理しなければならない。
(2)次の事項に必要な管理を規定するために,文書化された手順”を確立しなければならない。
a)発行前に,適切かどうかの観点から文書を承認する。
b)文書をレビューする。また,必要に応じて更新し,再承認する。
c)文書の変更の識別及び現在有効な版の識別を確実にする。
d)該当する文書の適切な版が,必要なときに,必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e)文書は,読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f)品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし,その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また,これらを何らかの目的で保持する場合には,適切な識別をする。
4.2.4 記録の管理
(1)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成された記録を,管理しなければならない。
(2)組織は,記録の識別,保管,保護,検索,保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)記録は,読みやすく,容易に識別可能かつ検索可能でなければならない。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1
品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2
“アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3
アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
4. 2 文書化に関する要求事項4.2.1 一般
(1)品質マネジメントシステムの文書には,次の事項を含めなければならない。
a)文書化した,品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c)この規格が要求する“文書化された手順”及び記録
d)組織内のプロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実に実施するために,組織が必要と決定した記録を含む文書
注記1
この規格で“文書化された手順”という用語を使う場合には,その手順が確立され,文書化され,実施され,維持されていることを意味する。一つの文書で,一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。“文書化された手順”の要求事項は,複数の文書で対応してもよい。
注記2
品質マネジメントシステムの文書化の程度は,次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
注記3
文書の様式及び媒体の種類は,どのようなものでもよい。
4.2.2 品質マニュアル
(1)組織は,次の事項を含む品質マニュアルを作成し,維持しなければならない。
a)品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には,除外の詳細,及び除外を正当とする理由。(1.2 参照)
b)品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報
c)品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3 文書管理
(1)品質マネジメントシステムで必要とされる文書は,管理しなければならない。ただし,記録は文書の一種ではあるが,4.2.4 に規定する要求事項に従って管理しなければならない。
(2)次の事項に必要な管理を規定するために,文書化された手順”を確立しなければならない。
a)発行前に,適切かどうかの観点から文書を承認する。
b)文書をレビューする。また,必要に応じて更新し,再承認する。
c)文書の変更の識別及び現在有効な版の識別を確実にする。
d)該当する文書の適切な版が,必要なときに,必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e)文書は,読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f)品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし,その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また,これらを何らかの目的で保持する場合には,適切な識別をする。
4.2.4 記録の管理
(1)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成された記録を,管理しなければならない。
(2)組織は,記録の識別,保管,保護,検索,保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)記録は,読みやすく,容易に識別可能かつ検索可能でなければならない。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
5.経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
(1)トップマネジメントは,品質マネジメントシステムの構築及び実施,並びにその有効性を継続的に改善することに対するコミットメントの証拠を,次の事項によって示さなければならない。
a)法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして,顧客要求事項を満たすことの重要性を組織内に周知する。
b)品質方針を設定する。
c)品質目標が設定されることを確実にする。
d)マネジメントレビューを実施する。
e)資源が使用できることを確実にする。
5.2 顧客重視
(1)顧客満足の向上を目指して,トップマネジメントは,顧客要求事項が決定され,満たされていることを確実にしなければならない(7.2.1 及び8.2.1 参照)。
5.3 品質方針
(1)トップマネジメントは,品質方針について,次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の目的に対して適切である。
b)要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミットメントを含む。
c)品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。
d)組織全体に伝達され,理解される。
e)適切性の持続のためにレビューされる。
5. 4 計画
5.4.1 品質目標
(1)トップマネジメントは,組織内のしかるべき部門及び階層で,品質目標が設定されていることを確実にしなければならない。
(2)その品質目標には,製品要求事項を満たすために必要なものを含む品質目標[7.1.a]参照]が設定されていることを確実にしなければならない。
(3)品質目標は,その達成度が判定可能で,品質方針との整合がとれていなければならない。
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
(1)トップマネジメントは,次の事項を確実にしなければならない。
a)品質目標に加えて,4.1 に規定する要求事項を満たすために,品質マネジメントシステムの計画を策定する。
b)品質マネジメントシステムの変更を計画し,実施する場合には,品質マネジメントシステムを“完全に整っている状態”(integrity)に維持する。
5. 5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
(1)トップマネジメントは,責任及び権限が定められ,組織全体に周知されていることを確実にしなければならない。
5.5.2 管理責任者
(1)トップマネジメントは,組織の管理層の中から管理責任者を任命しなければならない。
(2)管理責任者は,与えられている他の責任とかかわりなく,次に示す責任及び権限をもたなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立,実施及び維持を確実にする。
b)品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について,トップマネジメントに報告する。
c)組織全体にわたって,顧客要求事項に対する認識を高めることを確実にする。
注記1
管理青任者の責任には,品質マネジメントシステムに関する事項について外部と連絡をとることも含めることができる。
注記2
管理責任者は,上記の責任及び権限をもつ限り,一人である必要はない。
5.5.3 内部コミュニケーション
(1)トップマネジメントは,組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にしなければならない。
(2)また,品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にしなければならない。
5. 6 マネジメントレビュー5.6.1 一般
(1)トップマネジメントは,組織の品質マネジメントシステムが,引き続き,適切,妥当かつ有効であることを確実にするために,あらかじめ定められた間隔で品質マネジメントシステムをレビューしなければならない。
(2)このレビューでは,品質マネジメントシステムの改善の機会の評価,並びに品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行わなければならない。
(3)マネジメントレビューの結果の記録は,維持しなければならない。(4.2.4 参照)。
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
(1)マネジメントレビューへのインプットには,次の情報を含めなければならない。
a)監査の結果
b)顧客からのフィードバック
c)プロセスの成果を含む実施状況及び製品の適合性
d)予防処置及び是正処置の状況
e)前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
f)品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
g)改善のための提案
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
(1)マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項に関する決定及び処置すべてを含めなければならない。
a)品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b)顧客要求事項にかかわる,製品の改善
c)資源の必要性
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
(1)マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項に関する決定及び処置すべてを含めなければならない。
a)品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b)顧客要求事項にかかわる,製品の改善
c)資源の必要性
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
6.資源の運営管理
6.1 資源の提供
(1)組織は,次の事項に必要な資源を明確にし,提供しなければならない。
a)品質マネジメントシステムを実施し,維持する。また,その有効性を継続的に改善する。
b)顧客満足を、顧客要求事項を満たすことによって向上する。
6. 2 人的資源6.2.1 一般
(1)製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員は,適切な教育,訓練,技能及び経験を判断の根拠として力量がなければならない。
注記
製品要求事項への適合は,品質マネジメントシステム内の作業に従事する要員によって,直接的に又は間接的に影響を受ける可能性がある。
6.2.2 力量,認識及び教育・訓練
(1)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量を明確にする。
b)該当する場合には(必要な力量が不足している場合には),その必要な力量に到達することができるように教育・訓練を行うか,又は他の処置をとる。
c)教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。
d)組織の要員が,自らの活動のもつ意味及び重要性を認識し,品質目標の達成に向けて自らがどのように貢献できるかを認識することを確実にする。
e)教育,訓練,技能及び経験について該当する記録を維持する(4.2.4 参照)。
6.3 インフラストラクチャー
(1)組織は,製品要求事項への適合を達成するうえで必要とされるインフラストラクチャーを明確にし,提供し,維持しなければならない。インフラストラクチャーとしては,次のようなものが該当する場合がある。
a)建物,作業場所及び関連するユーティリティー(例えば,電気,ガス又は水)
b)設備(ハードウェア及びソフトウェア)
c)支援体制(例えば,輸送,通信又は情報システム)
6.4 作業環境
(1)組織は,製品要求事項への適合を達成するために必要な作業環境を明確にし,運営管理しなければならない。
注記
“作業環境”という用語は,物理的,環境的及びその他の要因を含む(例えば,騒音,気温,湿度,照明又は天候),作業が行われる状態と関連している。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
7.製品実現
7.1 製品実現の計画
(1)組織は,製品実現のために必要なプロセスを計画し,構築しなければならない。
(2)製品実現の計画は,品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合がとれていなければならない(4.1 参照)。
(3)組織は,製品実現の計画に当たって,次の各事項について適切に明確化しなければならない。
a)製品に対する品質目標及び要求事項
b)製品に特有な,プロセス及び文書の確立の必要性,並びに資源の提供の必要性
c)その製品のための検証,妥当性確認,監視,測定,検査及び試験活動,並びに製品合否判定基準
d)製品実現のプロセス及びその結果としての製品が,要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録(4.2.4 参照)
(4)この計画のアウトプットは,組織の運営方法に適した形式でなければならない。
注記1
特定の製品,プロジェクト又は契約に適用される品質マネジメントシステムのプロセス(製品実現のプロセスを含む。)及び資源を規定する文書を,品質計画書と呼ぶことがある。
注記2
組織は,製品実現のプロセスの構築に当たって,7.3 に規定する要求事項を適用してもよい。
7. 2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化
(1)組織は,次の事項を明確にしなければならない。
a)顧客が規定した要求事項。これには引渡し及び引渡し後の活動に関する要求事項を含む。
b)顧客が明示してはいないが,指定された用途又は意図された用途が既知である場合,それらの用途に応じた要求事項
c)製品に適用される法令・規制要求事項
d)組織が必要と判断する追加要求事項すべて
注記
引渡し後の活動には,例えば,保証に関する取決め,メンテナンスサービスのような契約義務,及びリサイクル又は最終廃棄のような補助的サービスのもとでの活動を含む。
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
(1)組織は,製品に関連する要求事項をレビューしなければならない。
(2)このレビューは,組織が顧客に製品を提供することに対するコミットメント(例:提案書の提出,契約又は注文の受諾,契約又は注文への変更の受諾)をする前に実施しなければならない。
(3)レビューでは,次の事項を確実にしなければならない。
a)製品要求事項が定められている。
b)契約又は注文の要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には,それについて解決されている。
c)組織が,定められた要求事項を満たす能力をもっている。
(4)このレビューの結果の記録,及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
(5)顧客がその要求事項を書面で示さない場合には,組織は顧客要求事項を受諾する前に確認しなければならない。
(6)製品要求事項が変更された場合には,組織は,関連する文書を修正しなければならない。
(7)また,変更後の要求事項が,関連する要員に理解されていることを確実にしなければならない。
注記
インターネット販売などでは,個別の注文に対する正式なレビューの実施は非現実的である。このような場合のレビューでは,カタログ又は宣伝広告資料のような関連する製品情報をその対象とすることもできる。
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
(1)組織は,次の事項に関して顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を明確にし,実施しなければならない。
a)製品情報
b)引き合い,契約若しくは注文,又はそれらの変更
c)苦情を含む顧客からのフィードバック
7. 3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
(1)組織は,製品の設計・開発の計画を策定し,管理しなければならない。
(2)設計・開発の計画において,組織は,次の事項を明確にしなければならない。
a)設計・開発の段階
b)設計・開発の各段階に適したレビュー,検証及び妥当性確認
c)設計・開発に関する責任及び権限
(3)組織は,効果的なコミュニケーション及び責任の明確な割当てを確実にするために,設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理しなければならない。
(4)設計・開発の進行に応じて,策定した計画を適切に更新しなければならない。
注記
設計・開発のレビュー,検証及び妥当性確認は,異なった目的を持っている。それらは,製品及び組織に適するように,個々に又はどのような組み合わせでも,実施し,記録することができる。
7.3.2 設計・開発へのインプット
(1)製品要求事項に関連するインプットを明確にし,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。インプットには,次の事項を含めなければならない。
a)機能及び性能に関する要求事項
b)適用される法令・規制要求事項
c)適用可能な場合には,以前の類似した設計から得られた情報
d)設計・開発に不可欠なその他の要求事項
(2)製品要求事項に関連するインプットについては,その適切性をレビューしなければならない。要求事項は,漏れがなく,あいまい(曖昧)でなく,相反することがあってはならない。
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
(1)設計・開発からのアウトプットは,設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式でなければならない。
(2)また,リリースの前に,承認を受けなければならない。
(3)設計・開発からのアウトプットは,次の状態でなければならない。
a)設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
b)購買,製造及びサービス提供に対して適切な情報を提供する。
c)製品の合否判定基準を含むか,又はそれを参照している。
d)安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性を明確にする。
注記
製造及びサービス提供に対する情報には,製品の保存に関する詳細を含めることができる。
7.3.4 設計・開発のレビュー
(1)設計・開発の適切な段階において,次の事項を目的として,計画されたとおりに(7.3.1 参照)体系的なレビューを行わなければならない。
a)設計・開発の結果が要求事項を満たせるかどうかを評価する。
b)問題を明確にし,必要な処置を提案する。
(2)レビューへの参加者には,レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表する者が含まれていなければならない。
(3)このレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない。(4.2.4 参照)
7.3.5 設計・開発の検証
(1)設計・開発からのアウトプットが,設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために,計画されたとおりに(7.3.1参照)検証を実施しなければならない。
(2)この検証の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない。(4.2.4 参照)
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
(1)結果として得られる製品が,指定された用途又は意図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするために,計画した方法(7.3.1 参照)に従って,設計・開発の妥当性確認を実施しなければならない。
(2)実行可能な湯合にはいつでも,製品の引渡し又は提供の前に,妥当性確認を完了しなければならない。
(3)妥当性確認の結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
7.3.7 設計・開発の変更管理
(1)設計・開発の変更を明確にし,記録を維持しなければならない。
(2)変更に対して,レビュー,検証及び妥当性確認を適切に行い,その変更を実施する前に承認しなければならない。
(3)設計・開発の変更のレビューには,その変更が,製品を構成する要素及び既に引き渡されている製品に及ぼす影響の評価を含めなければならない。
(4)変更のレビューの結果の記録,及び必要な処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
注記
“変更のレビュー”とは,変更に対して適切に行われたレビュー,検証及び妥当性確認のことである。
7. 4 購買
7.4.1 購買プロセス
(1)組織は,規定された購買要求事項に,購買製品が適合することを確実にしなければならない。
(2)供給者及び購買した製品に対する管理の方式及び程度は,購買製品が,その後の製品実現のプロセス又は最終製品に及ぼす影響に応じて定めなければならない。
(3)組織は,供給者が組織の要求事項に従って製品を供給する能力を判断の根拠として,供給者を評価し,選定しなければならない。選定,評価及び再評価の基準を定めなければならない。
(4)評価の結果の記録,及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
7.4.2 購買情報
(1)購買情報では購買製品に関する情報を明確にし,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。
a)製品,手順,プロセス及び設備の承認に関する要求事項
b)要員の適格性確認に関する要求事項
c)品質マネジメントシステムに関する要求事項
(2)組織は,供給者に伝達する前に,規定した購買要求事項が妥当であることを確実にしなければならない。
7.4.3 購買製品の検証
(1)組織は,購買製品が,規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために,必要な検査又はその他の活動を定めて,実施しなければならない。
(2)組織又はその顧客が,供給者先で検証を実施することにした場合には,組織は,その検証の要領及び購買製品のリリースの方法を購買情報の中で明確にしなければならない。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
7. 5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
(1)組織は,製造及びサービス提供を計画し,管理された状態で実行しなければならない。
(2)管理された状態には,次の事項のうち該当するものを含めなければならない。
a)製品の特性を述べた情報が利用できる。
b)必要に応じて,作業手順が利用できる。
c)適切な設備を使用している。
d)監視機器及び測定機器が利用でき,使用している。
e)監視及び測定が実施されている。
f)製品のリリース,顧客への引渡し及び引渡し後の活動が実施されている。
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
(1)製造及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットが,それ以降の監視又は測定で検証することが不可能で,その結果,製品が使用され,又はサービスが提供された後でしか不具合が顕在化しない場合には,組織は,その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行わなければならない。
(2)妥当性確認によって,これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証しなければならない。
(3)組織は,これらのプロセスについて,次の事項のうち該当するものを含んだ手続を確立しなければならない。
a)プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準
b)設備の承認及び要員の適格性確認
c)所定の方法及び手順の適用
d)記録に関する要求事項(4. 2. 4 参照)
e)妥当性の再確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
(1)必要な場合には,組織は,製品実現の全過程において適切な手段で製品を識別しなければならない。
(2)組織は,製品実現の全過程において,監視及び測定の要求事項に関連して,製品の状態を識別しなければならない。
(3)トレーサビリティが要求事項となっている場合には,組織は,製品について一意の識別を管理し,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
注記
ある産業分野では,構成管理(configuration management)が識別及びトレーサビリティを維持する手段である。
7.5.4 顧客の所有物
(1)組織は,顧客の所有物について,それが組織の管理下にある間,又は組織がそれを使用している間は,注意を払わなければならない。
(2)組織は,使用するため又は製品に組み込むために提供された顧客の所有物の識別,検証及び保護・防護を実施しなければならない。
(3)顧客の所有物を紛失若しくは損傷した場合又は使用には適さないとわかった場合には,組織は,顧客に報告し,記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。注記 顧客の所有物には,知的財産及び個人情報を含めることができる。
7.5.5 製品の保存
(1)組織は,内部処理から指定納入先への引渡しまでの間,要求事項への適合を維持するように製品を保存しなければならない。
(2)この保存には,該当する場合,識別,取扱い,包装,保管及び保護を含めなければならない。保存は,製品を構成する要素にも適用しなければならない。
注記 内部処理とは,組織が運営管理している製品実現のプロセスにおける活動をいう。
7.6 監視機器及び測定機器の管理
(1)定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために,組織は,実施すべき監視及び測定を明確にしなければならない。また,そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にしなければならない。
(2)組織は,監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立しなければならない。
(3)測定値の正当性が保証されなければならない場合には,測定機器に関し,次の事項を満たさなければならない。
a)定められた間隔又は使用前に,国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証,又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には,校正又は検証に用いた基準を記録する(4.2.4 参照)。
b)機器の調整をする,又は必要に応じて再調整する。
c)校正の状態を明確にするために識別を行う。
d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
e)取扱い,保守及び保管において,損傷及び劣化しないように保護する。
(4)さらに,測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には,組織は,その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し,記録しなければならない。
(5)組織は,その機器,及び影響を受けた製品すべてに対して,適切な処置をとらなければならない。校正及び検証の結果の記録を維持しなければならない(4.2.4参照)。
(6)規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には,そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認しなければならない。
(7)この確認は,最初に使用するのに先立って実施しなければならない。
(8)また,必要に応じて再確認しなければならない。
注記
意図した用途を満たすコンピュータソフトウェアの能力の確認には,通常,その使用の適切性を維持するための検証及び構成管理も含まれる。
ttps://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf
8.測定、分析及び改善
8.1 一般
(1)組織は,次の事項のために必要となる監視,測定,分析及び改善のプロセスを計画し,実施しなければならない。
a)製品要求事項への適合性を実証する。
b)品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。
c)品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。
(2)これには,統計的手法を含め,適用可能な方法,及びその使用の程度を決定することを含めなければならない。
8. 2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
(1)組織は,品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして,顧客要求事項を満足しているかどうかに関して顧客がどのように受けとめているかについての情報を監視しなければならない。
(2)この情報の入手及び使用の方法を定めなければならない。
注記
顧客がどのように受け止めているかの監視には,顧客満足度調査,提供された製品の品質に関する顧客からのデータ,ユーザ意見調査,失注分析,顧客からの賛辞,補償請求,ディーラ報告などの情報源から得たインプットを含めることができる。
8.2.2 内部監査
(1)組織は,品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明確にするために,あらかじめ定められた間隔で内部監査を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムが,個別製品の実現の計画(7.1 参照)に適合しているか,この規格の要求事項に適合しているか,及び組織が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合しているか。
b)品質マネジメントシステムが効果的に実施され,維持されているか。
(2)組織は,監査の対象となるプロセス及び領域の状態及び重要性,並びにこれまでの監査結果を考慮して,監査プログラムを策定しなければならない。
(3)監査の基準,範囲,頻度及び方法を規定しなければならない。
(4)監査員の選定及び監査の実施においては,監査プロセスの客観性及び公平性を確保しなければならない。
(5)監査員は自らの仕事は監査してはならない。
(6)監査の計画及び実施,記録の作成及び結果の報告に関する責任,並びに要求事項を規定するために“文書化された手順”を確立しなければならない。監査及びその結果の記録は,維持しなければならない(4.2.4 参照)。
(7)監査された領域に責任をもつ管理者は,検出された不適合及びその原因を除去するために遅滞なく,必要な修正及び是正処置すべてがとられることを確実にしなければならない。
(8)フォローアップには,とられた処置の検証及び検証結果の報告を含めなければならない(8.5.2 参照)。
注記 JIS Q 19011 参照。
8.2.3 プロセスの監視及び測定
(1)組織は,品質マネジメントシステムのプロセスの監視,及び適用可能な場合に行う測定には,適切な方法を適用しなければならない。
(2)これらの方法は,プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するものでなければならない。
(3)計画どおりの結果が達成できない場合には,適切に,修正及び是正処置をとらなければならない。
注記
適切な方法を決定するとき,組織は,製品要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性への影響に応じて,個々のプロセスに対する適切な監視又は測定の方式及び程度を考慮することを推奨する。
8.2.4 製品の監視及び測定
(1)組織は,製品要求事項が満たされていることを検証するために,製品の特性を監視し,測定しなければならない。
(2)監視及び測定は,個別製品の実現の計画(7.1 参照)に従って,製品実現の適切な段階で実施すしなければならない。
(3)合否判定基準への適合の証拠を維持しなければならない。
(4)顧客への引渡しのための製品のリリースを正式に許可した人を,記録しておかなければならない(4.2.4 参照)。
(5)個別製品の実現の計画(7.1 参照)で決めたことが問題なく完了するまでは,顧客への製品のリリース及びサービスの提供は行ってはならない。ただし,当該の権限をもつ者が承認したとき,及び該当する場合に顧客が承認したときは,この限りではない。
8.3 不適合製品の管理
(1)組織は,製品要求事項に適合しない製品が誤って使用されたり,又は引き渡されることを防ぐために,それらを識別し,管理することを確実にしなければならない。
(2)不適合製品の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
(3)該当する場合には,組織は,次の一つ又はそれ以上の方法で,不適合製品を処理しなければならない。
a)発見された不適合を除去するための処置をとる。
b)当該の権限をもつ者,及び該当する場合に顧客が,特別採用によって,その使用,リリース,又は合格と判定することを正式に許可する。
c)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。
d)引渡し後又は使用開始後に不適合製品が検出された場合には,その不適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。
注記
“c)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる”とは“廃棄すること”を含む。
(4)不適合製品に修正を施した場合には,要求事項への適合を実証するための再検証を行わなければならない。
(5)不適合の性質の記録,及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。
8.4 データの分析
(1)組織は,品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため,また,品質マネジメントシステムの継続的な改善の可能性を評価するために適切なデータを明確にし,それらのデータを収集し,分析しなければならない。
(2)この中には,監視及び測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の該当する情報源からのデータを含めなければならない。
(3)データの分析によって,次の事項に関連する情報を提供しなければならない。
a)顧客満足(8.2.1 参照)
b)製品要求事項への適合(8.2.4 参照)
c)予防処置の機会を得ることを含む,プロセス及び製品の,特性及び傾向(8.2.3及び8.2.4 参照)
d)供給者(7.4 参照)
8. 5 改善
8.5.1 継続的改善(1)組織は,品質方針,品質目標,監査結果,データの分析,是正処置,予防処置及びマネジメントレビューを通じて,品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
8.5.2 是正処置
(1)組織は,再発防止のため,不適合の原因を除去する処置をとらなければならない。
(2)是正処置は,検出された不適合のもつ影響に応じたものでなければならない。
(3)次の事項に関する要求事項を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
a)不適合(顧客からの苦情を含む)の内容確認
b)不適合の原因の特定
c)不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価
d)必要な処置の決定及び実施
e)とった処置の結果の記録(4. 2. 4 参照)
f)とった是正処置の有効性のレビュー
注記
f)における“とった是正処置”とは,a)〜e)のことである。
8.5.3 予防処置
(1)組織は,起こり得る不適合が発生することを防止するために,その原因を除去する処置を決めなければならない。
(2)予防処置は,起こり得る問題の影響に応じたものでなければならない。
(3)次の事項に関する要求事項を規定するために,“文書化された手順”を確立しなければならない。
a)起こり得る不適合及びその原因の特定
b)不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価
c)必要な処置の決定及び実施
d)とった処置の結果の記録(4.2.4 参照)
e)とった予防処置の有効性のレビュー
注記 e)における“とった予防処置”とは,a)〜d)のことである。
https://www.jma.or.jp/JMAQA/contents/data/qa403_04.pdf