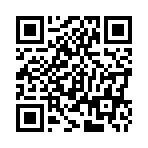2009年12月30日
海洋・沿岸域政策大綱 洋産業振興
急がれるわが国の海洋政策と海洋産業振興
―海洋産業を支える海洋情報インフラとは―
国土交通省海洋・沿岸域政策大綱 平成18年6月
目次
?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識
?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題
1.国際的な動向と課題
2.海洋及び沿岸域の現状と課題
?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進
1.海上における安全を確保する
2.国土の保全と防災対策を推進する
3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する
4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す
5.海洋・沿岸域の利用を推進する
6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する
7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する
8.国際社会との協調及び協力関係を確立する
9.施策を推進するに当たっての基本的考え方
?.施策の推進体制
?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識
我が国は、四方を海に囲まれた「海洋国家」であるとともに、典型的な「島嶼国」EEZ でもある。領海及び排他的経済水域( )の面積は国土面積の約12 倍にあたる約447万km2(うち領海は43 万km2)、海岸線の延長は約35,000km にも達する。日本人は、はるか昔から人や文化の往来、物の輸送、産業、生活等の分野において、海と深く関わってきた。
毎年7月の第3月曜日は、海の恩恵に感謝するとともに海洋国家、日本の繁栄を願う国民の祝日「海の日」と定められているが、そのことは、我が国が海洋とのつながりが特に深い国であることを示すものである。
一方、我が国の海洋・沿岸域を巡っては、海上交通の安全の確保、不審船、密輸・密航等の保安対策の強化、海上災害の防止、海洋汚染の防止、海岸等における防災対策の強化、海洋資源の開発の推進、海上輸送の安定化・活性化といった課題や、沿岸域や閉鎖性水域を中心とした、海岸侵食や砂浜等の消失、埋立等による藻場や干潟の減少、漂流・漂着ゴミの増大や減らない放置艇、赤潮や青潮の発生といった問題が山積している。
他方、国連海洋法条約(1994 年発効)及びリオ地球サミット(1992 年)以来、アジアを含む世界の各国では、「海洋・沿岸域の総合管理」、「持続可能な開発」といった考え方を背景に、海洋・沿岸域に関する様々な施策を総合的に実施するための制度的枠組みを整えて、海洋政策に積極的に取り組むとともに、そうした制度体系を有する国々が連携、協働する流れが強まっている。
このような状況を踏まえ、近年、海洋・沿岸域に関する法制の強化が図られており、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の制定や、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の改正等とともに、「国土形成計画法」において、国土の形成を推進するための総合的かつ基本的な計画である国土形成計画の計画事項として「海域の利用及び保全」が明記され、海洋を貴重な国土空間として位置付けることとしたところである。
海洋・沿岸域を巡る様々な問題や課題は、それぞれが独立で存在するのではなく、相互に関係がある場合が多いことから、こうした問題や課題に取り組むためには、関連する施策を総合的に進めていくことが必要である。
このような観点から、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、海洋・沿岸域に関する施策を総合的に推進していくべく、2004 年9 月に、省内に関係部局の長を構成員とする「国土交通省海洋・沿岸域政策連絡会議」を設置し、海洋・沿岸域政策のあり方について検討を重ね、今回、「国土交通省海洋・沿岸域政策大綱」をまとめた。
国土交通省としては、今後、この大綱に基づき諸般の施策の総合的な推進を図る。
?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題
海洋とは一般には広々とした海を意味するが、この大綱においては、我が国の主権が及ぶ領海(内水を含む)並びに。主権的権利及び管轄権を有する排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚を海洋としている。
我が国は、太平洋の最北西部に位置し、オホーツク海、日本海及び東シナ海という3 つの半閉鎖海と太平洋に囲まれた弧状列島によって構成され、我が国の主権並びに主権的権利及び管轄権が及ぶ水域の面積は447 万km2(領海の43 万km2を含む。)と世界で第6位ともいわれる広さとなっている。また、離島が北方から南方まで広範囲にわたって6,847 島も分布しており、我が国の領土、領海、排他的経済水域等の保全、自然環境の保全等に重要な役割を担っている。
また、この大綱では、海岸線を挟む陸域及び海域(主に内水及び領海を念頭。)の総体を沿岸域としている(なお、この大綱では、海洋と沿岸域を総称して「海洋・沿岸域」としている。)。沿岸域は、水圏、地圏及び気圏の交わる空間であり、洪水、高潮、津波等の自然の脅威にさらされるとともに、自然の微妙なバランスの下、優れた景観や多様で豊かな生態系が形成される等貴重な資源と言える一方、産業、交通、物流、観光、レクリエーション等の様々な利用の要請が輻輳していると言える。
海洋・沿岸域については、未知の分野も多く、基礎となるデータや知見等が十分ではないと言われていることから、今後、更に調査や研究を継続的に進め、それを施策に反映させていくことが重要である。
1.国際的な動向と課題
(1) 各国の取組
1992 年の地球サミット(ブラジル、リオデジャネイロ)でのアジェンダ21 の採択と1994 年の国連海洋法条約の発効以降、アジアを含む世界各国では、海洋の持続可能な開発の推進の動きが進む一方、排他的経済水域や大陸棚等の海洋における自国の権益の確保のため、「海洋の囲い込み」という考え方が広まっており、これらが相まって、総合的な海洋政策の策定等の取組が積極的に進められている。
米国においては、2000 年に海洋法2000 を制定し、同法に基づき海洋政策審議会を設立している。2004 年には、同審議会において報告書「21 世紀の海洋の青写真」を策定し、議会及び大統領に提出した。同報告書は、持続可能性や生態系に基づく管理等を原則とし、政府の海洋管理体制の改善や、研究、観測及び教育の強化等広範にわたり、212 項目の具体的な勧告を行うものである。
これを受け、同年、具体的に実行するための行動計画として、「米国海洋行動計画」を策定した。
一方、沿岸域においては、沿岸域管理法(1972 年)に基づき、沿岸域に接する州が沿岸域管理計画を作成した場合、連邦政府がその推進を支援することとしている。
アジアにおいても中国、韓国が総合的な海洋政策の策定及び実施に力を入れている。中国では「中国海洋アジェンダ、21」(1996 年)を制定し、海洋資源の合理的かつ持続的な利用、海洋経済の一層の発展を促進すること目指している。
2002年には海域使用管理法を制定し、海域の国有を前提として、ゾーニング制度の導入、海域使用権の創設と競争入札制の導入、海域使用料の徴収等について規定し、持続可能な開発と海域管理を推進している。韓国では、先進海洋大国の実現を目指し、沿岸域管理、海洋環境保護、水産等を所掌する海洋水産部を設置し、海洋基本戦略「海洋コリア21」(2000 年)を策定しているほか、海洋水産発展基本法(2002 年)や沿岸域管理法(1999 年)を制定し、海洋管理に関する諸施策を進めている。
以上のほか、東アジア諸国においては、タイが「タイ国家海洋政策」を2003年に策定したほか、インドネシアが沿岸域管理法を、また、マレーシアが国の沿岸域管理政策を、それぞれ策定中である。また、他の地域でも、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、南アフリカ等多くの国が同様の取組みを行っている。(表参照)
(2) 海洋秩序の維持
2001 年の同時多発テロを受け、2003 年5 月、米国からPSI(大量破壊兵器、ミサイル及びその関連物質の拡散に対する安全保障構想) が提案された。現在、日1)本をはじめ60 カ国以上がPSI 活動を支持しており、参加国が共同して取り得るこれらの移転及び輸送の阻止のための海上訓練を合同で行う等多国間連携が行われている。
2005 年10 月にはSUA 条約(海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約) が改正され、犯罪に関与している疑いのある他国籍船舶への公海上2)での乗船や捜索が可能になるなど、ますます国際機関によるテロ防止対策も進んでいる。
また、東南アジア周辺海域における海賊等の多国間にまたがる海上犯罪等については、現在、各国が連携、協力し、これに取り組んでいるが、全ての沿岸国海上法執行機関が、組織、勢力、技術等の面で充分な状況にあるとは言えないため、我が
国からの支援が強く求められている。
一方、近隣諸国の海洋政策上の戦略が我が国周辺海域で競合し、日本海、東シナ海等多くの海域で排他的経済水域の境界が未だ画定していない。
その他にも東シナ海における日中地理的中間線付近における資源開発問題や中国人活動家による尖閣諸島における領有権主張活動、日本海においては竹島問題など我が国の海洋権益を脅かす問題が山積しており、これらに対する厳正かつ適切な対応が求められている。
2.海洋及び沿岸域の現状と課題
(1) 海上交通
? 貨物輸送
エネルギーの93 %(2004 年)及び食料の60 %(2004 年)を海外に依存する我が国においては、輸出入取扱貨物量の99 %以上(2004 年、重量ベース)を海上輸送に依存し、工業製品の輸出や食料及び資源の輸入等の貿易が我が国の経済及び国民生活を支えており、海上輸送は我が国の共通利益となる「物流生命線」であると言える。
全国の津々浦々に1,070 の港湾が配置され、港湾で取扱われている貨物量は、外貿は12 億トン強で、内貿は19 億トン強(2004 年、フレートトン)となっている。
外航海運についてみると、我が国の海上貿易量の世界に占めるシェアは15.7 %(2003 年)であり、中国、アメリカ合衆国に次いで世界第3 位となっている。
外航海運は、各国の経済情勢、さらにはテロや紛争等による影響を受けやすく、安定的な輸送の確保が課題となっている。
また、内航海運は、国内貨物輸送のうち約39 %(2003 年度、トンキロベース)を担っており、我が国の経済や国民生活を支える鉄鋼、石油等の産業物資については、その約8 割を輸送している。営業用トラックと比較してエネルギー効率のよい輸送であり、環境面で優れている一方で、供給面での機動性を欠くため、市況変動による輸送需要の変動に対応しにくく、船腹需給ギャップが生じやすい構造となっている。
? 旅客輸送
旅客輸送は、外航定期航路が15 航路で約45 万6 千人(2004 年、日本人のみ、対前年35.9 %増)、内航旅客が1574 航路で約1 億90 万人(2004 年、対前年6.0 %減)となっている。内航旅客のうち離島航路については、島外との連絡について私的交通の利用が容易でない離島住民の足として必要不可欠であるため、約3 割を公営及び第三セクターが運営しているが、経営状況は厳しく、航路の維持及び改善が課題となっている。
(2) 海上の安全及び海洋汚染
? 海難事故
我が国周辺海域において、救助を必要とする海難に遭遇した船舶(要救助船舶)の隻数は、2001 年から2005 年までの年平均で2,086 隻(死者及び行方不明者167 人)であり、それ以前の5 年間の年平均1,877 隻(同170 人)と比べ11 %増加しているものの、死者及び行方不明者数は約2 %減少している。
また、死者及び行方不明者のうち、約54 %が漁船、約18 %がプレジャーボート及び遊漁船によるものである。これら国民の人命、財産にかかる海難事故への対応として、海難防止のための諸施策を推進するとともに、沿岸海域におけるより迅速かつ的確な人命救助体制の充実強化を進めていくことが重要である。
特に、近年、40 ノット程度の高速で運航する超高速船(ジェットフォイル等)が航行中に障害物と衝突したとみられる事故が多発しており、多数の負傷者を出すケースもあることから、超高速船の安全運航の確保に係る方策の検討が喫緊の課題となっている。
? 海洋汚染及び海上災害
2005 年、海上保安庁は、海上における油、廃棄物、赤潮、青潮等の海洋汚染の発生を360 件確認している。また同庁が防除措置を実施した油排出事故は116 件あり、そのうち影響の大きいタンカーは8 件であった。また船舶火災が118 件発生したが、そのうち約66 %が漁船である。
また、港湾局では、海域環境を整備する日常の業務として、清掃兼油回収船により、日々、漂流3)油、流木、漂流ゴミ等を回収しており、その量は年間約8,000m3(2003 年から2005 年の平均)にのぼる。このような海洋汚染や海上災害の未然防止及び対処能力をより向上させることが必要である。
? 海上テロ及び海賊対策
2001 年9 月に発生した米国同時多発テロ事件発生以後、2002 年10 月には、イエメン沖においてフランス籍タンカー爆破事件が発生する等海上においてもテロが続発している。幸いにして我が国では発生していないものの、依然として我が国を巡るテロ情勢は予断を許さない状況である。
今後とも海上におけるテロの未然防止及び海上における公共の安全と治安維持に万全を期すため、国内外の関係機関と連携し、水際での間隙のない体制を構築、強化することが必要である。
また、2005 年の全世界における海賊事件の発生件数は276 件、そのうち東南アジアにおける発生件数は122 件となっている。これらは減少傾向にあるものの、2005 年3 月に発生した日本籍船舶「韋駄天(いだてん)」が襲撃された事件など、依然として誘拐等の凶悪な海賊事案が発生していることから、引き続き国内外の関係機関との連携や協力関係の強化が必要である。
? 海上犯罪
2005 年の海上保安庁による海上犯罪の送致件数は、6,256 件であり、2004年と比べ、1,395 件の増加となっている。その中でも、暴力団や悪質業者が関与する等組織的かつ広域的な海上環境事犯、我が国の水産資源を枯渇させ、地域経済にも大きな打撃を与えかねない組織的な密漁事犯や外国漁船による不法操業事犯の件数が増加している。
また、我が国周辺海域では、麻薬、覚せい剤等の密輸事犯や不法入国事犯等の国際的な組織犯罪も依然として後を絶たず、ますます悪質かつ巧妙化している。
これら海上犯罪を阻止するために、監視取締り体制の強化を図るとともに、国内外の関係機関との連携強化や各種対策に取り組むなど、海上犯罪対策の徹底を図る必要がある。
(3) 港湾及び航路
周囲を海に囲まれ、臨海部に人口、資産等が集積する我が国において、港湾及び航路は、物流や人流を支え、国民生活の向上や産業活動の発展に大きな役割を果たしている。国際社会と我が国の緊密な関わりの中で、我が国の経済安全保障を実現するためには、より一層の海上輸送の機能強化、安全確保を図ることが極めて重要である。
我が国港湾においては、引き続き物流改革を推進していくとともに、国際海上コンテナ輸送量の増大や船舶の大型化等に適切に対応しつつ、現在進めているスーパー中枢港湾プロジェクトにおいて、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現に向けた港湾整備を図ることや、関係機関と連携、協力した水際対策等危機管理体制の強化を行うこと等が喫緊の課題となっている。
国際海上輸送及び国内海上輸送を担う一連の航路において、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、関門海峡等では、航路や船舶航行が輻輳した湾口部や海峡部等が存在し、海上輸送の要衝、隘路となっている。このような場所で海難事故が発生すれば、長期にわたり航路が閉鎖する可能性が高く、その影響は我が国全体の国民生活や経済産業活動に重大なものとなる。
このため、我が国の経済安全保障を実現するため、船舶の航行水域管理のあり方や国と地方の役割分担について検討
を進める必要がある。
(4) 海洋に関するレクリエーション
海洋に関するレクリエーションには、プレジャーボート(モーターボート、水上オートバイ、ヨット等)、サーフィン、ダイビング、釣り等の「スポーツ型」、海水浴、潮干狩り、水族館等の「リゾート型」のほか、客船等によるクルーズ等がある。
これらの参加人口は、2003 年で海水浴1,890 万人(1995 年:3,000 万人)、釣り1,470 万人(同1,850 万人)、潮干狩り224 万人(同461 万人)、モーターボート及びヨット100 万人(同110 万人)であり、いずれも減少傾向にある。
また、プレジャーボートの保有隻数は、1995 年度の39.8 万隻(モーターボート30.0 万隻、水上オートバイ8.5 万隻、ヨット1.3 万隻)から増加し、1999 年度には43.8 万隻(同32.2 万、10.3 万、1.3 万隻)となったが、これをピークに減少し、2004年度は36.5 万隻(同26.8 万、8.5 万、1.2 万隻)となっている。また、小型船舶操縦士免許保有者数は、2005 年度末で303 万(1995 年度:226 万人)と年々増加している。
一方で、放置艇及び沈廃船の隻数は年で万隻( 年: 8万隻、河川区域含む。)にものぼっており、船舶航行や漁業活動への支障、流水の阻害、津波及び高潮時における艇の流出による被害、景観悪化等の問題が顕在化している。
(5) 鉱物及びエネルギー資源
我が国の領海、排他的経済水域及び大陸棚の海底や海底下には、鉱物資源や、石油、天然ガス、メタンハイドレートといったエネルギー資源の多量の埋蔵が確認されている。また、風力発電や海洋温度差発電といった新エネルギーの可能性も広が
っており、これらの開発及び利用の推進が、将来の我が国の経済活動にとって重要になっているとの指摘がなされている。
(6) 海岸
? 海岸の概要
島国であり、入り組んだ海岸地形をもつ我が国は、約35,000km もの海岸線を有しており、海岸の重要性は特に大きいものがある。
海岸は、自然海岸、半自然海岸及び人工海岸に分類されるが、1960 年当時、8割を占めた自然海岸が、現在は53 %にまで減少しており、半自然海岸が13 %、人工海岸が34 %となっている。
? 海岸侵食
海岸の砂浜は、河川における砂利採取、河川横断工作物の設置等による土砂供給量の減少及び各種構造物の設置等による沿岸方向土砂の流れの変化など、様々な要因により、全国各地で侵食が生じている。また、海砂利採取による侵食も懸念されている。近年は海岸侵食が早いペースで進行(1908 〜 1978 年:72ha/年→ 1978 〜 1992 年:160ha/年)しており、砂浜の減少が、利用空間の減少とともに海岸の景観や生態系を大きく変化させている。
? 災害と防災対策
我が国は、台風の常襲地帯にあり高潮が頻発し(2004 年:27 回)、地震多発地帯で津波の来襲も多い(2004 年:4 回)など、厳しい地理的、自然条件下にある。
また、海岸侵食も全国的に顕在化してきており、放置すれば貴重な国土が失われることから、その保全は極めて重要である。この他、地球温暖化により、今後100年間で海面が9 〜 88cm 上昇するとの予測もある(IPCC(気候変動に関する政府間パネル)による。)。
一方、防災対策としての海岸保全施設は、2004 年度末時点で要保全海岸延長の62 %に設置されているが、このうち約18 %が想定津波高より低く、また、約30 %が想定津波高との比較調査が行われていないほか、施設の老朽化も進んでいる。
? 海岸漂着ゴミ
海岸漂着ゴミは恒常的に発生しているため、景観の悪化や生態系への影響等が生じている。発生起源としては、海域から漂着したもの、河川から流出したもの及び陸域から持ち込まれたもの等であり、近年では海外からと思われる漂着ゴミも日本海側の海岸を中心に確認されている。今後、海岸漂着ゴミへの対応を強化するとともに、関係諸国とも協調、連携した取組を推進することが課題となっている。
(7) 沿岸域の利用状況
現在、国土面積の約3割を占める沿岸に位置する市町村には、総人口の約5割が集中しており、特に東京湾、伊勢湾、大阪湾の沿岸は、全国平均の約10倍もの人口密度となっている。
これらの三大湾と瀬戸内海は、海上交通、工業、物流、エネルギー、港湾、商業、水産業、レクリエーション、観光等で稠密に利用されている。産業の面でも沿岸に位置する市町村の工業製品出荷額は全国の約5割、商業年間販売額は全国の約6割を占める状況となっている。
近年まで、臨海部に集積する重厚長大型産業の移転、縮小等により産業の空洞化が進んでいたが、景気の回復、海外進出企業の国内回帰、物流の高度化等により、臨海部への企業進出が進み出しつつある。
(8) 沿岸域の環境
? 沿岸域に関する水質
我が国では、陸域からの汚濁負荷削減、海域における自然環境の再生や創出等を行い、海域の水質の改善に取り組んできた結果、COD の環境基準の達成率が2004 年で75.5%となっている。
しかし、内湾、内海等の閉鎖性水域では依然として達成率が低くなっており(東京湾63.2 %、伊勢湾50.0 %、瀬戸内海67.3 %)、赤潮や青潮の発生等も見られる(2003 年で東京湾59 件、伊勢湾60 件、瀬戸内海106 件の赤潮が発生)。
? 沿岸域に関する生態系
日本の海洋・沿岸域は、海流の特徴や南北に長い列島の影響により、多様な環境が形成され、同緯度の地中海や北米西岸に比べ豊富な生物相が形成されている(例:海産魚類約3,100 種、藻類約5,500 種)。しかしながら、浅海域では埋立等により藻場や干潟が減少(例:1945 〜 1994 年に4 割の干潟が減少)しているほか、琉球諸島等で海水温の上昇等によるサンゴ礁への影響が懸念されている。
河川及び海洋・沿岸域は、多くの生態系が重なり合って形成されており、特に川と海の接点である汽水域は、沿岸域の中でもすぐれた貴重な生態的価値を有している。
このため、アサリの稚貝やサンゴの幼生の移動等を踏まえた広域的な取組が必要であること、東京湾等の閉鎖性海域を一体として保全することが必要であること、関係者が情報を共有するとともに、科学的な解明を着実に推進し、実現可能な改善策を漸進的に実行する必要があること等が指摘されている。
(9) 沿岸域の総合的な管理
沿岸域に関する課題を解決するためには、沿岸域を自然の系として適切にとらえ、沿岸域の総合的な管理計画を策定し、各種事業、施策、利用等を総合的、計画的に推進することが重要であるとの考え方から、2000年に関係17省庁が「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」を策定し、これに基づきケーススタディ等を行ってきたが、全国的には進んでいないのが現実となっており、このような沿岸域の総合管理の推進をいかに図るかが課題となっている。
?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進
以上のような我が国の海洋・沿岸域を巡る現状及び課題を踏まえると、我が国として海洋・沿岸域に関する施策を総合的かつ戦略的に実施する必要がある。
このような中で、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、以下に掲げる施策を推進していくこととする。
1.海上における安全を確保する
? 海上交通の安全を確保する
海上輸送量の増大や船舶の大型化に対応した安全に航行できる船舶航行水域の確保、航行支援システムの構築、航路標識等の整備、海難事故の分析等を推進するとともに、安全上問題のある条約不適合船(サブスタンダード船)を排除するための措置を行い、海上交通の安全を確保する。
また、ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、事後チェック機能の強化等を図る。
○ 船舶の安全な航行を支援するため、航海用海図の作成や更新、電子海図の整備と普及、航路標識の高機能化、沿岸域情報提供システムの拡充、地震や津波に関する情報の迅速な提供等を推進するとともに、(船舶自動識別装置) AIS を活用した次世代型航行支援システムの構築、航空レーザー等を用いた浅海域の情報の整備、海洋短波レーダー網、(全地球測位システム)波浪計等も活用したGPS的確な漂流予測、航行ルートの選定等を推進。また、衝突回避に必要な他船舶の動向等を的確に表示するINT-NAV(先進安全航行支援システム) の調査研究を推進。
○ 船舶が安全に航行できる環境を確保するため、大型船舶に対応した航路水深の確保、障害物の除去、防波堤の配置等を図るとともに、開発保全航路の指定範囲の拡大や開発保全航路と港湾の間の水域の措置等を行い、これを促進。また、荒天
時に船舶が避難できる避難港の整備を図るとともに、無害通航の外国船舶が我が国の領海内において安全に航行できるよう可航水域を確保。
○ サブスタンダード船の排除等を推進するため、IMO(国際海事機関)加盟国監査を促進するとともにPSC ポートステートコントロールを的確に実施
○ ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、運航労務監理官による監査等の事後チェックの強化を図るとともに、ILO(国際労働機関)海事労働条約の批准に取り組む。
○ 船舶の大型化等が進展する中、海上交通の一層の安全を確保するため、水先人に係る等級別免許制の導入や免許更新要件の見直し等の水先制度改革を実施。
○ 海難事故の再発防止を図るため、海難の調査及び分析に基づく、積極的な勧告や提言を実施。
? 海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する
テロ関連情報の調査、分析体制の整備、海上及び港湾における警備体制を強化するとともに、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施し海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する。
○ 海賊及び海上テロを含む海上における不法行為対策について、アジア海上セキュリティ・イニシアティブ( ) 等に基2004 AMARSECTIVE2004 づき、関係国海上保安機関に対し海上犯罪取締り能力向上のための支援を実施。
○ 国際航海船舶及び国際埠頭施設の保安措置が適確に行われるよう、実施状況の確認や人材育成等を図り、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施するとともに、船舶接岸情報の活用、港湾施設への出入管理の高度化、内航も含めた旅客ターミナルの保安施設整備等を進め、船舶及び港湾の保安対策を強化。
○ 国が港湾施設管理者や税関等の関係機関と協働体制をとり、港湾の利用船舶に関する情報を収集して分析し、問題船等が明らかになった場合、警察機関への通報や港湾施設管理者に警戒指示を行う体制を整備。
○ 臨海部の原子力発電所、石油備蓄基地、米軍施設等の重要施設に対する警備やテロ情報調査体制を強化。
? 事故及び災害等対応の体制を強化する
船舶の衝突や乗揚事故による油の排出、有害液体物質や危険物の流出、火災等の船舶の事故による災害、原子力発電所等のエネルギー施設の事故による災害、台風や津波等の自然現象による災害等の多様な事故及び災害に迅速かつ的確に対応するとともに、地震等に伴う経済的損失の低減を図るため海上からの輸送を確保する体制を強化する。
○ ヘリコプターの機動性、高速性等を活用した機動救難体制の充実強化に努めるほか、特殊な海難への対応体制の強化、救急救命士の養成、洋上救急体制の充実等により救急救命体制を強化。
○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制や臨海部の施設の安全監督体制を一層強化するとともに、OPRC-HNS 議定書(2000 年の危険物質及び有害物による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議定書) に対応した体20)制を確立。
○ 大規模災害対応として、物流と人流の両面における海上−港湾−陸上を結ぶ輸送を確保する広域的な連携、協働体制を確立。
? 海上保安業務体制の充実を図る
海上における総合的な安全及び法秩序を確保するため、海上においてその実態を把握、監視し、直接施策を実施する海上保安業務体制の充実を図る。
○ 巡視船艇、航空機の老朽化や旧式化による業務上の支障の早期解消を図るとともに、海洋権益の保全、沿岸水域の警戒監視体制の構築、大規模災害等に対する救助体制の強化等の新たな業務課題に対応するため、老朽巡視船艇、航空機等の
緊急かつ計画的な代替整備を推進。
○ 携帯電話からの118 番通報による位置情報、コスパス・サーサット捜索救助衛星システムによる遭難警報、船舶に搭載された等から得られる我が国周 ?AIS辺海域の船舶動静情報等を、海上保安庁が保有する各種の情報と横断的に照合で
きるシステムを構築し、救難即応体制、海難防止対策等を向上。
2.国土の保全と防災対策を推進する
? 国民の生命や財産を保護する
安全性の確保が不十分な地域において引き続き防災や減災に取り組む。その際には、施設の耐震化、津波や高潮の予測をより正確かつ迅速に分かりやすく伝達する仕組みや、土地利用施策等の多様な対策を含めた総合的な取組を行う。
○ 海岸保全施設の重点緊急点検結果を受けた、壊滅的な被害が生じるおそれがある海岸における被害防止対策をはじめ、水門の自動化や遠隔操作化、堤防護岸の破堤防止、ハザードマップ作成支援等ハードとソフトが一体となった総合的な津波、高潮(ゼロメートル地帯)対策を推進。
○ 東海・東南海・南海地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による津波被害が想定される沿岸域やゼロメートル地帯における耐震性が十分でない海岸保全施設(堤防、護岸等)の耐震対策を推進。
○ 海岸ごとに潮位、波高、打ち上げ高等を的確かつきめ細かに予測する高潮情報システムの構築、津波警報の一層の迅速化及び精度向上、津波、高潮、高波に関する情報提供の充実や共有化を推進し、防災機関等での情報共有の高度化を推進。
○ 地震発生の予知に寄与する海底地殻変動観測や活断層の調査を実施するとともに、大規模地震に伴う津波の挙動を明らかにするため、津波シミュレーションを実施。また、海域火山活動の監視を行い、船舶航行や漁業活動等に関する災害の防止
を推進。
○ 津波時の放置プレジャーボートの陸への乗り上げ等の防止として、一般海域を含めた係留施設の台帳管理の徹底、係留施設の指定等を実施。
○ 大規模地震発生時の避難者や緊急物資の円滑な輸送の確保に資する港湾施設の耐震化とともに、海岸保全施設の耐震性を短時間かつ低コストで判定可能な「チャート式耐震診断システム」の開発を推進。
○ 地震や津波等の災害時における、海上からの住民の避難や物資輸送等を支援するため、沿岸域における防災情報図の整備を推進。
○ 東京湾及び大阪湾臨海部等において、基幹的広域防災拠点を整備するとともに「道の駅」の防災拠点化を推進。
○ 減災対策として、道路利用者への情報提供、避難路の整備及び救援活動や物資輸送を行う上で重要な役割を果たす緊急輸送道路の確保のため、道路橋の耐震補強や高規格幹線道路ネットワークを整備。さらに、被災を受けた道路について、障害物の除去や応急復旧等の迅速な啓開を実施。
○ 津波被害リスクのある地域において、生命や財産を守るため、津波防護機能を持ち合わせた防波堤の整備を推進。
○ 災害体験の継承、防災知識の蓄積や普及に必要な分かりやすい教材の作成、これらを多くの住民に分かりやすく伝えられる人材の育成、緊急時に備えた体制の構築と防災訓練を推進。
○ 海岸侵食や津波、高潮に対する沿岸域の安全性の低下を防止、軽減するため、関係者間の連携等の仕組みを構築。
? 国土を保全し、領海及び排他的経済水域等の海洋権益を確保する
海岸侵食等の対策を行うことや、外洋域における離島の交通、情報通信やエネルギー供給等に係る基盤の確保等に関する取組により、国境離島をはじめ、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の基線となる国土の保全を図るとともに、日本周辺海域についての適正な海図の作成のための調査や大陸棚の限界画定のための調査、的確な監視警戒等を行い、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の海洋権益の確保を図る。
○ 離島、奄美群島及び小笠原諸島において、交通基盤、産業基盤、生活環境、防災及び国土保全に係る施設等の整備や離島航路の維持及び改善に対する助成、産業や観光の振興、国内外との交流の促進、人材育成の支援等ソフトとハードを一体的に実施する総合的な施策を推進。
○ 我が国の領海及び排他的経済水域等を確保する上で、重要な拠点である国境離島に対して、万全な国土保全を推進するとともに、海象観測の実施等その活用を推進。
○ 大陸棚の限界画定のための調査等の推進や、国境離島の位置情報基盤の整備を推進。また、侵食対策等の海岸の適切な維持及び管理に資する低潮線の調査を実施。
○ 排他的経済水域が画定していない日本海、東シナ海等における海底地形や地質等の情報基盤を整備し、適正な海図の作成を推進。
○ 東シナ海等において顕在化している我が国の海洋権益に関する問題への対応として、機動力や監視能力等に優れた巡視船、航空機等を整備し、厳正かつ的確な監視警戒を実施。
○ 外国漁船による不法操業に対して、特に外国漁船が多数操業している日本海、東シナ海への巡視船艇や航空機の配備等により、効果的かつ厳正な取締りを実施。
3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する
? 海洋・沿岸域のモニター体制を強化する
継続的に海流、海水中の汚染物質、海底地盤の状況、気象、漂流・漂着ゴミ等に関する基礎データの整理、提供体制の強化等を実施し、海洋・沿岸域環境のモニター体制を強化する。
○ 国土交通省における海洋や沿岸域に関する各種情報の収集、整理、提供体制の強化を図るとともに、海域環境の順応的管理に資する波浪、潮位、水深、水質、底質等の効率的なモニタリングを行うことで、海洋や沿岸域のモニター体制を強化。
○ 地球環境に関連した海洋現象を総合的に診断し、「海洋の健康診断表」として提供。
○ 海岸を活動の場としている市民、NPO との協働により、海岸環境に関する情報の広範かつ継続的なモニタリング体制を構築。
○ 排他的経済水域や大陸棚から沿岸域までの海岸線、低潮線、海底地形、地質等の情報基盤を整備。
? 海洋汚染等に対する的確な対応を推進する
大規模油流出、漂流ゴミ、放置座礁船、流出流木及び大型構造物の漂流等が、環境や安全上の支障をきたす等の問題に対し、未然防止対策の推進及び漂着前後それぞれにおける積極的な防除の仕組みの構築等を図る。
○ 油や有害危険物質の流出、放置座礁船等による海洋・沿岸域の汚染に適切に対処するため、領海を越え、場合によっては公海上であっても大型油回収船、巡視船等を迅速に派遣する等国境を越境する海洋汚染について、積極的な防除の取組を推進するための体制等の強化や、保険や基金による被害者保護への的確な取組を実施。
○ 油流出事故が発生した際に迅速かつ的確な油防除措置等の実施に資するため、適切な漂流予測を実施するとともに、沿岸海域の自然的、社会的情報等をデータベース化した沿岸海域環境保全情報の整備を推進。
○ 漂流・漂着ゴミについて、関係省庁と連携して、その処理(回収、処分)、発生源対策を推進。
○ 海洋環境保全講習会や訪船指導等により、漁業者、海事関係者に対して海洋汚染の防止のための指導及び啓発を実施。
? 脆弱な海域の保護及び保全を推進する
船舶からの汚染を防止する必要性が高い海域を、海上輸送を確保しつつ、保護及び保全する。
○ 生態学的又は科学的理由により船舶からの汚染を防止する必要性の高い海域に対し、海上輸送を確保しつつ、これを未然に防止するための措置を導入。
4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す
? 海洋・沿岸域の自然環境を回復させる
埋め立て、沿岸構造物の設置、海岸の消失等により失われた自然環境の回復を図るため、干潟や藻場、サンゴ礁、湿地等の保全と再生、修復を図る。また、ヘドロ、ごみ、ダイオキシン等の有害物質等の堆積、埋立用材及び骨材の採取による深掘等により、元の生態系が失われた海底環境について底質環境を改善する。
○ 流砂系及び漂砂系の連続性を確保し、流入土砂による航路埋没、海岸侵食等の課題に対処するため、関係機関が協働して流砂系及び漂砂系における総合土砂管理を推進する体制を構築。
○ 埋立造成地、工場等からの土地利用転換地、廃棄物の埋立処分地等における緑地、湿地、干潟等の自然空間の再生や創出、砂浜、藻場、サンゴ礁等の回復、底質環境の改善等による自然環境の再生を推進。
○ 珊瑚付着型のブロックや干潟の再生に関する技術開発を推進し、港湾整備等への反映を推進。
○ ダイオキシン類等の有害化学物質による底質汚染の対策を推進。
○ 青潮等の原因とされる深掘跡の効率的な埋め戻し等を実施するため、浚渫土砂等の需給や品質を調整するシステムを構築。
? 海洋・沿岸域の自然環境及び景観の維持及び保全を図る
自然海岸や砂浜、干潟等の生態系への影響を最小化するため、十分な事前環境調査等を行い、沿岸域構造物と環境及び景観との調和を図る。また、多くの海岸で見られる漂着ゴミや放置されている船舶等を処理することや、船舶からの排出ガスの削減等により、自然環境及び景観の維持、保全を図る。
○ 人工海岸の整備、構造物の設置等に際して、環境との調和を一層重視し、石積堤や緩傾斜護岸等自然と共生する取組を実施。
○ 沿岸域にゴミが異常に漂流、漂着し、これを放置することにより船舶航行への支障、海岸保全施設の機能阻害、海岸環境の悪化等が生じているため、実効的な対策を推進。
○ 廃船(繊維強化プラスティック製廃船)の環境に優FRP しい処理と、FRP 廃27)船の不法投棄、放置艇の沈廃船化等の問題に対処するため、FRP 廃船のリサイクルシステムの普及を推進。
○ 海域への廃棄物不法投棄、汚水の不法排出等の海上環境事犯に対し、関係機関と悪質事業者等に係る情報共有体制を構築し、監視取締体制を効率化するとともに強化。
○ 船舶に石油類等を積み出す際に放出されるVOC(揮発性有機化合物質) 対策を実行していくため、放出規制港湾の指定や港湾における排出ガス処理施設の整備を促進。
○ 港湾に係留中の船舶に陸上側施設から電力を供給することで、船舶のアイドリングストップを推進。
○ 沿岸部における魅力ある空間の整備を推進、支援するため、海岸景観形成ガイドラインを踏まえた防災や利用と調和した良好な海岸景観形成を推進するとともに、景観計画の策定等景観法の制度活用について地方公共団体への助言を実施。
? 水質の保全及び回復を図る
下水道の整備及び河川の直接浄化による陸域からの汚濁負荷の削減並びに水質浄化能力を有する干潟や藻場の保全、再生等を行うことにより、依然として閉鎖性水域において、赤潮や青潮が発生している状況を改善する等水質の保全及び回復を図る。
○ 水質改善が進まない三大湾等の閉鎖性海域を中心に、「全国海の再生プロジェクト」として「海の再生」に向けた各種施策、海底の汚泥除去や覆砂による溶出抑制等の海洋・沿岸域の水質改善対策、合流式下水道の改善や高度処理の推進、河川浄
化対策、環境モニタリングを、一層、総合的かつ効果的に推進。
○ 東京湾、大阪湾以外の閉鎖性海域についても、順次再生行動計画の策定に向けた取組を推進。
5.海洋・沿岸域の利用を推進する
? 海上輸送の安定化・活性化を図る
外航海運について、適切な競争環境の確保等により、高質かつ効率的な輸送サービスを安定的に提供できる体制を整える。また、内航海運の経営基盤の強化等により、新造船舶への適切な代替を推進し、内航海運の活性化を図る。
○ 我が国商船隊による安定輸送を確保するための方策の充実・強化。
○ 経済効率、環境、安全等の課題を解決する新技術の開発と実用化を支援する枠組みを創設するとともに、環境問題への対応等社会的要請に応えることのできるスーパーエコシップの普及を促進。
○ 中小零細の多い内航海運事業者のグループ化、協業化を促進し、経営基盤を強化。
? 海洋・沿岸域の経済活動を活性化させる
貿易構造や荷役形態の変化に伴う陳腐化した施設や水際線を有する付加価値の高い低未利用地について、物流拠点や国際競争産業等の立地を推進する等有効利用すること等により、沿岸域の経済活動の活性化を図る。
○ 沿岸域の低未利用地に物流や国際競争産業等新しい機能立地を促し、それに併せて拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路の重点的な整備や、高度成長期時代の老朽化した運河や水路、護岸、防災・減災施設等のリニューアルを推進。
○ 「みなとオアシス」のような交流の場の形成を支援し、多目的拠点としての活用を推進。
○ 沿岸域における公共水域や港湾施設等既存ストックの適正かつ安全な活用促進に資する地域の取組に対し、フィージビリティの調査や規制等との調整等を実施し、これを支援。
? 海洋・沿岸域の新たな利用を推進する
新規航路の開拓、メガフロート等を活用した洋上発電や大陸棚海洋資源開発基地及び中小ガス田の活用を可能とする新たな輸送システムの構築等海洋の新たな利用を、技術の開発動向を踏まえ推進する。
○ 「リサイクルポート」の形成により、海上輸送による効率的な静脈物流ネットワークを構築し、循環資源の広域的な流動を促進。
○ 環境負荷の少ない内航海運による輸送への転換を促進するとともに、沿岸域ネットワーク、島や海の魅力を気軽に楽しむことができる国内旅客航路を活性化。
○ 拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路を重点的に整備。
○ 中小ガス田の活用が可能となるよう、NGH(天然ガスハイドレート)輸送船を活用した新たな輸送システムを構築。
○ 海洋における風力、海洋温度差等による発電といった新エネルギーの活用に向けた洋上発電プラットフォームや大陸棚海洋資源開発基地として、メガフロートの活用を推進。
? 海洋・沿岸域の利用に関する技術の開発等を推進する
環境修復や侵食防護、高潮や津波への対策、耐震性診断、低環境負荷の船舶等の技術の開発、実用化及び普及を推進するとともに、気象、海象、水路状況等の海洋情報の活用を推進し、海上輸送の高度化等を図る。
○ 経済的で環境にやさしい船舶であるスーパーエコシップ等新技術を活用した船舶、船舶からの排出ガスに含まれる硫黄酸化物を大幅に低減するACF(活性炭素繊維) を活用した舶用高機能排煙処理システム、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出を同時に削減する超臨界水を活用した舶用ディーゼル燃焼機関等の研究開発、実用化及び普及を推進。
○ 海上におけるインターネットやTV 電話、電子メール等の通信利用環境を改善する高速大容量の船陸間双方向通信を実現するため、海上ブロードバンドの有望な活用方策の検討、実現に向けて必要な取組の提案を実施。
○ GPS 波浪計、陸上GPS 基準局、船舶AIS 及び海洋短波レーダー等の情報のマッチングにより、船舶に対する各種航行支援情報のリアルタイムの発信を推進。
○ 環境モニタリング結果を活用しつつ、珊瑚付着型のブロックや干潟の再生等に関する技術の向上のための研究開発を持続的に実施。
○ 日本海洋データセンターが収集、管理し提供している各種海洋データを関係機関との連携により充実させ、海洋・沿岸域の基盤情報の整備を推進。
? 海洋・沿岸域の利用を支える船舶や船員を確保する
海上輸送の高度化に対応した船舶や船員を確保するため、造船技能者や優良な船員の育成を行う。
○ 海洋・沿岸域の安全確保、環境保全に資する船舶の供給を支える造船業を振興。また、造船業における技能者の世代交代に対応する造船に関する「匠」の技の円滑な伝承を推進。
○ 船員教育機関における船員養成やBRM 研修を始めとする実践的な技能の教授並びに各種の船員雇用施策により、優良な船員の確保及び育成を促進。
? 海洋・沿岸域の多様な利用を調和させる
沿岸域の利用の輻輳等を解消するため、一般と産業関連等との利用調整、国土保全と経済活動との利用調整を行い、相互に調和がとれるようにする。
○ 沿岸域の環境と産業、観光、レクリエーション等の利用との調整を図り、持続的な沿岸域の利用と保全を図るため、沿岸域の利用と保全に関する施策を国と地方及び利用者、NPO 等の適切な役割分担、相互の連携、協力、協働により、より一層
着実に実施。
○ 沿岸の大都市から排出される廃棄物最終残渣や災害時に発生する廃棄物の適切処分について、最終処分場の広域融通を推進。
6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する
? 人と海のふれあいを取り戻し、海辺のにぎわいを創出する
臨海部における親水空間の確保やアクセスの改善、プレジャーボート等による海洋スポーツやクルーズの活性化等ハード、ソフト両面において人と海のふれあいを取り戻すことにより、海辺のにぎわいを創出し、地域の活性化等に寄与する。
○ 臨海部の水辺空間が市民の親水空間、人と海の触れ合う場となるよう、臨海部の都市公園、港湾緑地、海岸等の整備を推進。
○ 水域を活用したプロムナードやビジター桟橋、水域にアクセスできる斜路や階段護岸等施設の一部として水域を効果的に取り込んだ港湾緑地の整備を行い、海辺のにぎわいを創出。
○ 港湾の資産を地域の視点から再評価するとともに、地域の産業、海に開かれた特性等港湾の資産を最大限に活用し、地元等の市民団体、地NPO 元市町村、港湾管理者、地元企業等の連携による港湾のにぎわいの創出を推進。
○ マリーナ及びフィッシャリーナ等を活用し、プレジャーボート等によるクルーズ、海洋スポーツ等のマリンレジャーの拠点や地域観光情報等の提供を行う「海の駅」の設置を地域と連携して支援し、ネットワーク化を推進。
○ 海洋におけるレクリエーションが安全かつ安心に楽しめる環境を整備するため、沿岸域の流況情報等の整備及び提供を推進。
? 海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る
海との共生について積極的な関心や協力を喚起するため、海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る。
○ 海洋・沿岸域教育に係る普及啓発活動や指導者育成、NPO 等活動団体のネットワーク化、ホームページの作成等の取組を更に拡充し、利用者からのアクセスしやすさの向上や団体同士の連携と協働をより一層促進。また、関連する基礎知識の体
系化や普及啓発の取組を推進。
7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する
海洋・沿岸域に関する施策を総合的、戦略的に実施するため、国家戦略的な視点を踏まえつつ、海洋・沿岸域の総合的管理について、国の施策の基本方向を定立するとともに、各地域において、関係者の共通認識の醸成を図り、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働による計画策定等の取組を着実に推進する。
○ 国の各種基本的な政策等との整合を図りつつ、沿岸域の安全の確保、多面的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自立的な地域の形成を図るため、関係者の共通認識の醸成を図りつつ、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働により、各地域の特性に応じて沿岸域圏の総合的な管理計画を策定するなど、各種事業、施策、利用等を総合的、戦略的に推進する。
8.国際社会との協調及び協力関係を確立する
海洋・沿岸域の安全確保や環境保全等を図るため、IMO等の国際機関の枠組みや、PSIをはじめ各種会合や訓練等海の安全や環境保全に係る国際的な取組に積極的に参画するとともに、SUA条約の改正等に伴う国内の体制の整備や、国土の水没問題等に苦慮している島嶼国への支援、国際的な沿岸防災対策への支援、日ASEAN交通連携プロジェクトの推進、ODAの活用等により、国際社会との協調及び協力関係を確立する。また、東南アジア諸国に対する海上保安機関の設立支援、海上犯罪取締能力や捜索救助技術等高度な技術や知識の移転等により、マラッカ・シンガポール海峡等を含む東南アジア海域の海上保安能力の全体的な向上を図る。
○ マラッカ・シンガポール海峡等日ASEAN 地域における海の安全や環境保全等のため、日ASEAN 海事セキュリティプログラムやOSPAR 計画等を推進。
○ 東南アジア周辺海域の海上の秩序を確保し、これを通じて我が国の海上交通の安全を確保すべく、フィリピン、インドネシア、マレーシア等へ専門家を派遣し、海上保安機関の設立支援や、東南アジア諸国への技術や知識の移転等を実施。
○ 海上阻止訓練に海上保安庁巡視船を参加させるなど、PSI の活動に積極的に参画。
○ 平成17 年10 月に採択されたSUA 条約の改正について、関係省庁の一員として批准に向けた国内体制の整備を推進。
○ PEMSEA(東アジア海域環境管理パートナーシップ) やNOWPAP(北西太平洋地域海行動計画) 等の取組に積極的に参画し、我が国の取組を東アジアに発信するとともに、日本海、黄海等の海洋環境の保全に積極的に取り組む。また、海洋汚染防止に関する取組について日仏協力会議を開催し、技術的、組織的な協力等を推進。
○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制を一層強化するとともに、OPRC − HNS 議定書に対応した体制を確立。
○ シップリサイクル(船舶の解撤)や目標指向の新造船構造基準、次世代航海システム等に関するにおける検討を積極的にリード。
○ IMO やMAIIF(国際海難調査官会議) における、国際的海難についての調査協力体制推進の議論に積極的に参加。
○ ODA を通じた海洋・沿岸域に関する国際協力を推進。
○ 国土の水没問題等に苦慮している島嶼国に対し、国土保全の手法等について情報提供等の支援を実施。
○ 北西太平洋域の各国に津波情報の提供を実施するとともに、インド洋の沿岸国に対しインド洋における津波警戒システムの構築支援及び暫定的な津波監視情報の提供を実施。
○ 船舶、ブイ、フロート等の海洋観測データを準リアルタイムで国際的に収集し、地球環境に関連する海洋の情報を作成して国内外の行政機関や研究機関へ提供。
9.施策を推進するに当たっての基本的考え方
海洋・沿岸域に関する施策については、国土交通省として以下の基本的考え方を十分踏まえ、推進していくこととする。
? 総合的、戦略的な取組
海洋・沿岸域に関する問題は、それぞれ個別に存在するのではなく、相互に関係するものが多く、また、例えば海岸侵食対策のように山地や河川から海岸に土砂を適正に供給する総合的な土砂管理が必要であるなど、陸域、河川等との関係で生じているものもある。
さらに、安全の確保や国土の保全のように中長期的な視点に立って施策を組み合わせて実施することが効果的なものもあることから、関係機関が連携し、関係する施策を総合的、戦略的に実施する。
? 国際的な視野に立った取組
我が国はすべての国境を海域で画し、海上における安全、離島管理、資源やエネルギーの利用及び開発、地球規模の環境問題等海洋に関する課題の中には、国際的な性格を帯び、その解決に当たって国際的な協力が不可欠であるものもあるため、国際的な視野に立った取組を進める。
また、海洋・沿岸域政策に関する幅広い分野に精通し、かつ、国際的枠組みに参加し、我が国の意見を発信していくことができるような人材の育成を図る。
? 国と地方の役割分担、連携及び協働
海洋・沿岸域に関する問題は多岐にわたり、地域的な問題として単独の市町村が取り組むべき問題から、複数の都府県にわたる広域の連携が必要な問題、排他的経済水域及び大陸棚における問題や国際競争力の根幹を担う海上輸送の確保のように国が取り組むことが必要な問題があることから、今後は、国際動向に応じた国の立場を踏まえ、国と地方、また、地域間の役割分担を明確にするとともに、重層的な取組が必要な分野について、連携、協働して取り組んでいく。
? コンセンサスの状況に応じた取組
海洋・沿岸域に関する問題については、多様な価値観が存在し、また、利害関係が複雑であることが多いことから、地方公共団体、漁業者、産業界、海運事業者、海洋レジャー関係者、各公物管理者、地域住民、環境保護団体その他のNPO等多くの関係者の間の情報共有や共通認識の醸成を図り、そのコンセンサスの形成状況に応じて、取組を進める。また、取組に当たっては、関係者の連携、協働の下、試行的に良好な環境を形成することによって理解と協力を得る等の方策も進める。
? 持続的な取組
海洋・沿岸域に関する問題の多く、例えば、干潟や藻場の回復といったことは、長期にわたる取組が必要であるとともに科学的、技術的に解明されていないものもあることから、持続的な取組を着実に推進していく。
? 先行的な取組
良好な環境はいったん損なわれると回復が困難となる場合が多いことから、海洋・沿岸域の海洋環境や自然環境を守るために、損なわれる前に環境のモニタリングや科学的、技術的な分析評価を十分に実施する等の先行的措置を講じる。
? 多様な主体の参画促進
沿岸域における問題については、現在でも地域住民やNPO が参画し、取組を行っているところであるが、特に環境の保全や、海を活用した地域づくり等を中心として、引き続き地域住民、NPO の力に期待するところは大きく、一層の参画を促す。
? 効率的、効果的な施策の実施
国及び地方公共団体とも要員や財源の確保が厳しい中、不断の組織体制の見直し等と併せて、事前の施策効果を見極め、担当部局間の連携、メリハリのある施策の展開、重点施策への要員の集中、民間やNPO との協働等により、効率的かつ効果的に施策を実施する。
本大綱にまとめた施策のうち、法制の整備が必要なものについては、海洋政策を巡る諸状況を踏まえつつ、その整備に向けて検討を進めることとする。
また、本大綱にまとめた施策のうち国土計画上重要な事項については、国土形成計画(全国計画及び広域地方計画)の案において、関係府省とも調整の上、位置付けを図るものとする。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010621_2/02.pdf
―海洋産業を支える海洋情報インフラとは―
国土交通省海洋・沿岸域政策大綱 平成18年6月
目次
?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識
?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題
1.国際的な動向と課題
2.海洋及び沿岸域の現状と課題
?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進
1.海上における安全を確保する
2.国土の保全と防災対策を推進する
3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する
4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す
5.海洋・沿岸域の利用を推進する
6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する
7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する
8.国際社会との協調及び協力関係を確立する
9.施策を推進するに当たっての基本的考え方
?.施策の推進体制
?.海洋・沿岸域政策に関する基本認識
我が国は、四方を海に囲まれた「海洋国家」であるとともに、典型的な「島嶼国」EEZ でもある。領海及び排他的経済水域( )の面積は国土面積の約12 倍にあたる約447万km2(うち領海は43 万km2)、海岸線の延長は約35,000km にも達する。日本人は、はるか昔から人や文化の往来、物の輸送、産業、生活等の分野において、海と深く関わってきた。
毎年7月の第3月曜日は、海の恩恵に感謝するとともに海洋国家、日本の繁栄を願う国民の祝日「海の日」と定められているが、そのことは、我が国が海洋とのつながりが特に深い国であることを示すものである。
一方、我が国の海洋・沿岸域を巡っては、海上交通の安全の確保、不審船、密輸・密航等の保安対策の強化、海上災害の防止、海洋汚染の防止、海岸等における防災対策の強化、海洋資源の開発の推進、海上輸送の安定化・活性化といった課題や、沿岸域や閉鎖性水域を中心とした、海岸侵食や砂浜等の消失、埋立等による藻場や干潟の減少、漂流・漂着ゴミの増大や減らない放置艇、赤潮や青潮の発生といった問題が山積している。
他方、国連海洋法条約(1994 年発効)及びリオ地球サミット(1992 年)以来、アジアを含む世界の各国では、「海洋・沿岸域の総合管理」、「持続可能な開発」といった考え方を背景に、海洋・沿岸域に関する様々な施策を総合的に実施するための制度的枠組みを整えて、海洋政策に積極的に取り組むとともに、そうした制度体系を有する国々が連携、協働する流れが強まっている。
このような状況を踏まえ、近年、海洋・沿岸域に関する法制の強化が図られており、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の制定や、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の改正等とともに、「国土形成計画法」において、国土の形成を推進するための総合的かつ基本的な計画である国土形成計画の計画事項として「海域の利用及び保全」が明記され、海洋を貴重な国土空間として位置付けることとしたところである。
海洋・沿岸域を巡る様々な問題や課題は、それぞれが独立で存在するのではなく、相互に関係がある場合が多いことから、こうした問題や課題に取り組むためには、関連する施策を総合的に進めていくことが必要である。
このような観点から、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、海洋・沿岸域に関する施策を総合的に推進していくべく、2004 年9 月に、省内に関係部局の長を構成員とする「国土交通省海洋・沿岸域政策連絡会議」を設置し、海洋・沿岸域政策のあり方について検討を重ね、今回、「国土交通省海洋・沿岸域政策大綱」をまとめた。
国土交通省としては、今後、この大綱に基づき諸般の施策の総合的な推進を図る。
?.我が国の海洋・沿岸域を巡る現状と課題
海洋とは一般には広々とした海を意味するが、この大綱においては、我が国の主権が及ぶ領海(内水を含む)並びに。主権的権利及び管轄権を有する排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚を海洋としている。
我が国は、太平洋の最北西部に位置し、オホーツク海、日本海及び東シナ海という3 つの半閉鎖海と太平洋に囲まれた弧状列島によって構成され、我が国の主権並びに主権的権利及び管轄権が及ぶ水域の面積は447 万km2(領海の43 万km2を含む。)と世界で第6位ともいわれる広さとなっている。また、離島が北方から南方まで広範囲にわたって6,847 島も分布しており、我が国の領土、領海、排他的経済水域等の保全、自然環境の保全等に重要な役割を担っている。
また、この大綱では、海岸線を挟む陸域及び海域(主に内水及び領海を念頭。)の総体を沿岸域としている(なお、この大綱では、海洋と沿岸域を総称して「海洋・沿岸域」としている。)。沿岸域は、水圏、地圏及び気圏の交わる空間であり、洪水、高潮、津波等の自然の脅威にさらされるとともに、自然の微妙なバランスの下、優れた景観や多様で豊かな生態系が形成される等貴重な資源と言える一方、産業、交通、物流、観光、レクリエーション等の様々な利用の要請が輻輳していると言える。
海洋・沿岸域については、未知の分野も多く、基礎となるデータや知見等が十分ではないと言われていることから、今後、更に調査や研究を継続的に進め、それを施策に反映させていくことが重要である。
1.国際的な動向と課題
(1) 各国の取組
1992 年の地球サミット(ブラジル、リオデジャネイロ)でのアジェンダ21 の採択と1994 年の国連海洋法条約の発効以降、アジアを含む世界各国では、海洋の持続可能な開発の推進の動きが進む一方、排他的経済水域や大陸棚等の海洋における自国の権益の確保のため、「海洋の囲い込み」という考え方が広まっており、これらが相まって、総合的な海洋政策の策定等の取組が積極的に進められている。
米国においては、2000 年に海洋法2000 を制定し、同法に基づき海洋政策審議会を設立している。2004 年には、同審議会において報告書「21 世紀の海洋の青写真」を策定し、議会及び大統領に提出した。同報告書は、持続可能性や生態系に基づく管理等を原則とし、政府の海洋管理体制の改善や、研究、観測及び教育の強化等広範にわたり、212 項目の具体的な勧告を行うものである。
これを受け、同年、具体的に実行するための行動計画として、「米国海洋行動計画」を策定した。
一方、沿岸域においては、沿岸域管理法(1972 年)に基づき、沿岸域に接する州が沿岸域管理計画を作成した場合、連邦政府がその推進を支援することとしている。
アジアにおいても中国、韓国が総合的な海洋政策の策定及び実施に力を入れている。中国では「中国海洋アジェンダ、21」(1996 年)を制定し、海洋資源の合理的かつ持続的な利用、海洋経済の一層の発展を促進すること目指している。
2002年には海域使用管理法を制定し、海域の国有を前提として、ゾーニング制度の導入、海域使用権の創設と競争入札制の導入、海域使用料の徴収等について規定し、持続可能な開発と海域管理を推進している。韓国では、先進海洋大国の実現を目指し、沿岸域管理、海洋環境保護、水産等を所掌する海洋水産部を設置し、海洋基本戦略「海洋コリア21」(2000 年)を策定しているほか、海洋水産発展基本法(2002 年)や沿岸域管理法(1999 年)を制定し、海洋管理に関する諸施策を進めている。
以上のほか、東アジア諸国においては、タイが「タイ国家海洋政策」を2003年に策定したほか、インドネシアが沿岸域管理法を、また、マレーシアが国の沿岸域管理政策を、それぞれ策定中である。また、他の地域でも、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、南アフリカ等多くの国が同様の取組みを行っている。(表参照)
(2) 海洋秩序の維持
2001 年の同時多発テロを受け、2003 年5 月、米国からPSI(大量破壊兵器、ミサイル及びその関連物質の拡散に対する安全保障構想) が提案された。現在、日1)本をはじめ60 カ国以上がPSI 活動を支持しており、参加国が共同して取り得るこれらの移転及び輸送の阻止のための海上訓練を合同で行う等多国間連携が行われている。
2005 年10 月にはSUA 条約(海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約) が改正され、犯罪に関与している疑いのある他国籍船舶への公海上2)での乗船や捜索が可能になるなど、ますます国際機関によるテロ防止対策も進んでいる。
また、東南アジア周辺海域における海賊等の多国間にまたがる海上犯罪等については、現在、各国が連携、協力し、これに取り組んでいるが、全ての沿岸国海上法執行機関が、組織、勢力、技術等の面で充分な状況にあるとは言えないため、我が
国からの支援が強く求められている。
一方、近隣諸国の海洋政策上の戦略が我が国周辺海域で競合し、日本海、東シナ海等多くの海域で排他的経済水域の境界が未だ画定していない。
その他にも東シナ海における日中地理的中間線付近における資源開発問題や中国人活動家による尖閣諸島における領有権主張活動、日本海においては竹島問題など我が国の海洋権益を脅かす問題が山積しており、これらに対する厳正かつ適切な対応が求められている。
2.海洋及び沿岸域の現状と課題
(1) 海上交通
? 貨物輸送
エネルギーの93 %(2004 年)及び食料の60 %(2004 年)を海外に依存する我が国においては、輸出入取扱貨物量の99 %以上(2004 年、重量ベース)を海上輸送に依存し、工業製品の輸出や食料及び資源の輸入等の貿易が我が国の経済及び国民生活を支えており、海上輸送は我が国の共通利益となる「物流生命線」であると言える。
全国の津々浦々に1,070 の港湾が配置され、港湾で取扱われている貨物量は、外貿は12 億トン強で、内貿は19 億トン強(2004 年、フレートトン)となっている。
外航海運についてみると、我が国の海上貿易量の世界に占めるシェアは15.7 %(2003 年)であり、中国、アメリカ合衆国に次いで世界第3 位となっている。
外航海運は、各国の経済情勢、さらにはテロや紛争等による影響を受けやすく、安定的な輸送の確保が課題となっている。
また、内航海運は、国内貨物輸送のうち約39 %(2003 年度、トンキロベース)を担っており、我が国の経済や国民生活を支える鉄鋼、石油等の産業物資については、その約8 割を輸送している。営業用トラックと比較してエネルギー効率のよい輸送であり、環境面で優れている一方で、供給面での機動性を欠くため、市況変動による輸送需要の変動に対応しにくく、船腹需給ギャップが生じやすい構造となっている。
? 旅客輸送
旅客輸送は、外航定期航路が15 航路で約45 万6 千人(2004 年、日本人のみ、対前年35.9 %増)、内航旅客が1574 航路で約1 億90 万人(2004 年、対前年6.0 %減)となっている。内航旅客のうち離島航路については、島外との連絡について私的交通の利用が容易でない離島住民の足として必要不可欠であるため、約3 割を公営及び第三セクターが運営しているが、経営状況は厳しく、航路の維持及び改善が課題となっている。
(2) 海上の安全及び海洋汚染
? 海難事故
我が国周辺海域において、救助を必要とする海難に遭遇した船舶(要救助船舶)の隻数は、2001 年から2005 年までの年平均で2,086 隻(死者及び行方不明者167 人)であり、それ以前の5 年間の年平均1,877 隻(同170 人)と比べ11 %増加しているものの、死者及び行方不明者数は約2 %減少している。
また、死者及び行方不明者のうち、約54 %が漁船、約18 %がプレジャーボート及び遊漁船によるものである。これら国民の人命、財産にかかる海難事故への対応として、海難防止のための諸施策を推進するとともに、沿岸海域におけるより迅速かつ的確な人命救助体制の充実強化を進めていくことが重要である。
特に、近年、40 ノット程度の高速で運航する超高速船(ジェットフォイル等)が航行中に障害物と衝突したとみられる事故が多発しており、多数の負傷者を出すケースもあることから、超高速船の安全運航の確保に係る方策の検討が喫緊の課題となっている。
? 海洋汚染及び海上災害
2005 年、海上保安庁は、海上における油、廃棄物、赤潮、青潮等の海洋汚染の発生を360 件確認している。また同庁が防除措置を実施した油排出事故は116 件あり、そのうち影響の大きいタンカーは8 件であった。また船舶火災が118 件発生したが、そのうち約66 %が漁船である。
また、港湾局では、海域環境を整備する日常の業務として、清掃兼油回収船により、日々、漂流3)油、流木、漂流ゴミ等を回収しており、その量は年間約8,000m3(2003 年から2005 年の平均)にのぼる。このような海洋汚染や海上災害の未然防止及び対処能力をより向上させることが必要である。
? 海上テロ及び海賊対策
2001 年9 月に発生した米国同時多発テロ事件発生以後、2002 年10 月には、イエメン沖においてフランス籍タンカー爆破事件が発生する等海上においてもテロが続発している。幸いにして我が国では発生していないものの、依然として我が国を巡るテロ情勢は予断を許さない状況である。
今後とも海上におけるテロの未然防止及び海上における公共の安全と治安維持に万全を期すため、国内外の関係機関と連携し、水際での間隙のない体制を構築、強化することが必要である。
また、2005 年の全世界における海賊事件の発生件数は276 件、そのうち東南アジアにおける発生件数は122 件となっている。これらは減少傾向にあるものの、2005 年3 月に発生した日本籍船舶「韋駄天(いだてん)」が襲撃された事件など、依然として誘拐等の凶悪な海賊事案が発生していることから、引き続き国内外の関係機関との連携や協力関係の強化が必要である。
? 海上犯罪
2005 年の海上保安庁による海上犯罪の送致件数は、6,256 件であり、2004年と比べ、1,395 件の増加となっている。その中でも、暴力団や悪質業者が関与する等組織的かつ広域的な海上環境事犯、我が国の水産資源を枯渇させ、地域経済にも大きな打撃を与えかねない組織的な密漁事犯や外国漁船による不法操業事犯の件数が増加している。
また、我が国周辺海域では、麻薬、覚せい剤等の密輸事犯や不法入国事犯等の国際的な組織犯罪も依然として後を絶たず、ますます悪質かつ巧妙化している。
これら海上犯罪を阻止するために、監視取締り体制の強化を図るとともに、国内外の関係機関との連携強化や各種対策に取り組むなど、海上犯罪対策の徹底を図る必要がある。
(3) 港湾及び航路
周囲を海に囲まれ、臨海部に人口、資産等が集積する我が国において、港湾及び航路は、物流や人流を支え、国民生活の向上や産業活動の発展に大きな役割を果たしている。国際社会と我が国の緊密な関わりの中で、我が国の経済安全保障を実現するためには、より一層の海上輸送の機能強化、安全確保を図ることが極めて重要である。
我が国港湾においては、引き続き物流改革を推進していくとともに、国際海上コンテナ輸送量の増大や船舶の大型化等に適切に対応しつつ、現在進めているスーパー中枢港湾プロジェクトにおいて、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現に向けた港湾整備を図ることや、関係機関と連携、協力した水際対策等危機管理体制の強化を行うこと等が喫緊の課題となっている。
国際海上輸送及び国内海上輸送を担う一連の航路において、特に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、関門海峡等では、航路や船舶航行が輻輳した湾口部や海峡部等が存在し、海上輸送の要衝、隘路となっている。このような場所で海難事故が発生すれば、長期にわたり航路が閉鎖する可能性が高く、その影響は我が国全体の国民生活や経済産業活動に重大なものとなる。
このため、我が国の経済安全保障を実現するため、船舶の航行水域管理のあり方や国と地方の役割分担について検討
を進める必要がある。
(4) 海洋に関するレクリエーション
海洋に関するレクリエーションには、プレジャーボート(モーターボート、水上オートバイ、ヨット等)、サーフィン、ダイビング、釣り等の「スポーツ型」、海水浴、潮干狩り、水族館等の「リゾート型」のほか、客船等によるクルーズ等がある。
これらの参加人口は、2003 年で海水浴1,890 万人(1995 年:3,000 万人)、釣り1,470 万人(同1,850 万人)、潮干狩り224 万人(同461 万人)、モーターボート及びヨット100 万人(同110 万人)であり、いずれも減少傾向にある。
また、プレジャーボートの保有隻数は、1995 年度の39.8 万隻(モーターボート30.0 万隻、水上オートバイ8.5 万隻、ヨット1.3 万隻)から増加し、1999 年度には43.8 万隻(同32.2 万、10.3 万、1.3 万隻)となったが、これをピークに減少し、2004年度は36.5 万隻(同26.8 万、8.5 万、1.2 万隻)となっている。また、小型船舶操縦士免許保有者数は、2005 年度末で303 万(1995 年度:226 万人)と年々増加している。
一方で、放置艇及び沈廃船の隻数は年で万隻( 年: 8万隻、河川区域含む。)にものぼっており、船舶航行や漁業活動への支障、流水の阻害、津波及び高潮時における艇の流出による被害、景観悪化等の問題が顕在化している。
(5) 鉱物及びエネルギー資源
我が国の領海、排他的経済水域及び大陸棚の海底や海底下には、鉱物資源や、石油、天然ガス、メタンハイドレートといったエネルギー資源の多量の埋蔵が確認されている。また、風力発電や海洋温度差発電といった新エネルギーの可能性も広が
っており、これらの開発及び利用の推進が、将来の我が国の経済活動にとって重要になっているとの指摘がなされている。
(6) 海岸
? 海岸の概要
島国であり、入り組んだ海岸地形をもつ我が国は、約35,000km もの海岸線を有しており、海岸の重要性は特に大きいものがある。
海岸は、自然海岸、半自然海岸及び人工海岸に分類されるが、1960 年当時、8割を占めた自然海岸が、現在は53 %にまで減少しており、半自然海岸が13 %、人工海岸が34 %となっている。
? 海岸侵食
海岸の砂浜は、河川における砂利採取、河川横断工作物の設置等による土砂供給量の減少及び各種構造物の設置等による沿岸方向土砂の流れの変化など、様々な要因により、全国各地で侵食が生じている。また、海砂利採取による侵食も懸念されている。近年は海岸侵食が早いペースで進行(1908 〜 1978 年:72ha/年→ 1978 〜 1992 年:160ha/年)しており、砂浜の減少が、利用空間の減少とともに海岸の景観や生態系を大きく変化させている。
? 災害と防災対策
我が国は、台風の常襲地帯にあり高潮が頻発し(2004 年:27 回)、地震多発地帯で津波の来襲も多い(2004 年:4 回)など、厳しい地理的、自然条件下にある。
また、海岸侵食も全国的に顕在化してきており、放置すれば貴重な国土が失われることから、その保全は極めて重要である。この他、地球温暖化により、今後100年間で海面が9 〜 88cm 上昇するとの予測もある(IPCC(気候変動に関する政府間パネル)による。)。
一方、防災対策としての海岸保全施設は、2004 年度末時点で要保全海岸延長の62 %に設置されているが、このうち約18 %が想定津波高より低く、また、約30 %が想定津波高との比較調査が行われていないほか、施設の老朽化も進んでいる。
? 海岸漂着ゴミ
海岸漂着ゴミは恒常的に発生しているため、景観の悪化や生態系への影響等が生じている。発生起源としては、海域から漂着したもの、河川から流出したもの及び陸域から持ち込まれたもの等であり、近年では海外からと思われる漂着ゴミも日本海側の海岸を中心に確認されている。今後、海岸漂着ゴミへの対応を強化するとともに、関係諸国とも協調、連携した取組を推進することが課題となっている。
(7) 沿岸域の利用状況
現在、国土面積の約3割を占める沿岸に位置する市町村には、総人口の約5割が集中しており、特に東京湾、伊勢湾、大阪湾の沿岸は、全国平均の約10倍もの人口密度となっている。
これらの三大湾と瀬戸内海は、海上交通、工業、物流、エネルギー、港湾、商業、水産業、レクリエーション、観光等で稠密に利用されている。産業の面でも沿岸に位置する市町村の工業製品出荷額は全国の約5割、商業年間販売額は全国の約6割を占める状況となっている。
近年まで、臨海部に集積する重厚長大型産業の移転、縮小等により産業の空洞化が進んでいたが、景気の回復、海外進出企業の国内回帰、物流の高度化等により、臨海部への企業進出が進み出しつつある。
(8) 沿岸域の環境
? 沿岸域に関する水質
我が国では、陸域からの汚濁負荷削減、海域における自然環境の再生や創出等を行い、海域の水質の改善に取り組んできた結果、COD の環境基準の達成率が2004 年で75.5%となっている。
しかし、内湾、内海等の閉鎖性水域では依然として達成率が低くなっており(東京湾63.2 %、伊勢湾50.0 %、瀬戸内海67.3 %)、赤潮や青潮の発生等も見られる(2003 年で東京湾59 件、伊勢湾60 件、瀬戸内海106 件の赤潮が発生)。
? 沿岸域に関する生態系
日本の海洋・沿岸域は、海流の特徴や南北に長い列島の影響により、多様な環境が形成され、同緯度の地中海や北米西岸に比べ豊富な生物相が形成されている(例:海産魚類約3,100 種、藻類約5,500 種)。しかしながら、浅海域では埋立等により藻場や干潟が減少(例:1945 〜 1994 年に4 割の干潟が減少)しているほか、琉球諸島等で海水温の上昇等によるサンゴ礁への影響が懸念されている。
河川及び海洋・沿岸域は、多くの生態系が重なり合って形成されており、特に川と海の接点である汽水域は、沿岸域の中でもすぐれた貴重な生態的価値を有している。
このため、アサリの稚貝やサンゴの幼生の移動等を踏まえた広域的な取組が必要であること、東京湾等の閉鎖性海域を一体として保全することが必要であること、関係者が情報を共有するとともに、科学的な解明を着実に推進し、実現可能な改善策を漸進的に実行する必要があること等が指摘されている。
(9) 沿岸域の総合的な管理
沿岸域に関する課題を解決するためには、沿岸域を自然の系として適切にとらえ、沿岸域の総合的な管理計画を策定し、各種事業、施策、利用等を総合的、計画的に推進することが重要であるとの考え方から、2000年に関係17省庁が「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」を策定し、これに基づきケーススタディ等を行ってきたが、全国的には進んでいないのが現実となっており、このような沿岸域の総合管理の推進をいかに図るかが課題となっている。
?.海洋・沿岸域に関する施策とその推進
以上のような我が国の海洋・沿岸域を巡る現状及び課題を踏まえると、我が国として海洋・沿岸域に関する施策を総合的かつ戦略的に実施する必要がある。
このような中で、海洋・沿岸域に関する行政分野の多くを所管する国土交通省としては、以下に掲げる施策を推進していくこととする。
1.海上における安全を確保する
? 海上交通の安全を確保する
海上輸送量の増大や船舶の大型化に対応した安全に航行できる船舶航行水域の確保、航行支援システムの構築、航路標識等の整備、海難事故の分析等を推進するとともに、安全上問題のある条約不適合船(サブスタンダード船)を排除するための措置を行い、海上交通の安全を確保する。
また、ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、事後チェック機能の強化等を図る。
○ 船舶の安全な航行を支援するため、航海用海図の作成や更新、電子海図の整備と普及、航路標識の高機能化、沿岸域情報提供システムの拡充、地震や津波に関する情報の迅速な提供等を推進するとともに、(船舶自動識別装置) AIS を活用した次世代型航行支援システムの構築、航空レーザー等を用いた浅海域の情報の整備、海洋短波レーダー網、(全地球測位システム)波浪計等も活用したGPS的確な漂流予測、航行ルートの選定等を推進。また、衝突回避に必要な他船舶の動向等を的確に表示するINT-NAV(先進安全航行支援システム) の調査研究を推進。
○ 船舶が安全に航行できる環境を確保するため、大型船舶に対応した航路水深の確保、障害物の除去、防波堤の配置等を図るとともに、開発保全航路の指定範囲の拡大や開発保全航路と港湾の間の水域の措置等を行い、これを促進。また、荒天
時に船舶が避難できる避難港の整備を図るとともに、無害通航の外国船舶が我が国の領海内において安全に航行できるよう可航水域を確保。
○ サブスタンダード船の排除等を推進するため、IMO(国際海事機関)加盟国監査を促進するとともにPSC ポートステートコントロールを的確に実施
○ ヒューマンエラーによる事故の防止等を推進するため、運航労務監理官による監査等の事後チェックの強化を図るとともに、ILO(国際労働機関)海事労働条約の批准に取り組む。
○ 船舶の大型化等が進展する中、海上交通の一層の安全を確保するため、水先人に係る等級別免許制の導入や免許更新要件の見直し等の水先制度改革を実施。
○ 海難事故の再発防止を図るため、海難の調査及び分析に基づく、積極的な勧告や提言を実施。
? 海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する
テロ関連情報の調査、分析体制の整備、海上及び港湾における警備体制を強化するとともに、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施し海上及び港湾におけるテロ対策等を推進する。
○ 海賊及び海上テロを含む海上における不法行為対策について、アジア海上セキュリティ・イニシアティブ( ) 等に基2004 AMARSECTIVE2004 づき、関係国海上保安機関に対し海上犯罪取締り能力向上のための支援を実施。
○ 国際航海船舶及び国際埠頭施設の保安措置が適確に行われるよう、実施状況の確認や人材育成等を図り、我が国の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施するとともに、船舶接岸情報の活用、港湾施設への出入管理の高度化、内航も含めた旅客ターミナルの保安施設整備等を進め、船舶及び港湾の保安対策を強化。
○ 国が港湾施設管理者や税関等の関係機関と協働体制をとり、港湾の利用船舶に関する情報を収集して分析し、問題船等が明らかになった場合、警察機関への通報や港湾施設管理者に警戒指示を行う体制を整備。
○ 臨海部の原子力発電所、石油備蓄基地、米軍施設等の重要施設に対する警備やテロ情報調査体制を強化。
? 事故及び災害等対応の体制を強化する
船舶の衝突や乗揚事故による油の排出、有害液体物質や危険物の流出、火災等の船舶の事故による災害、原子力発電所等のエネルギー施設の事故による災害、台風や津波等の自然現象による災害等の多様な事故及び災害に迅速かつ的確に対応するとともに、地震等に伴う経済的損失の低減を図るため海上からの輸送を確保する体制を強化する。
○ ヘリコプターの機動性、高速性等を活用した機動救難体制の充実強化に努めるほか、特殊な海難への対応体制の強化、救急救命士の養成、洋上救急体制の充実等により救急救命体制を強化。
○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制や臨海部の施設の安全監督体制を一層強化するとともに、OPRC-HNS 議定書(2000 年の危険物質及び有害物による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議定書) に対応した体20)制を確立。
○ 大規模災害対応として、物流と人流の両面における海上−港湾−陸上を結ぶ輸送を確保する広域的な連携、協働体制を確立。
? 海上保安業務体制の充実を図る
海上における総合的な安全及び法秩序を確保するため、海上においてその実態を把握、監視し、直接施策を実施する海上保安業務体制の充実を図る。
○ 巡視船艇、航空機の老朽化や旧式化による業務上の支障の早期解消を図るとともに、海洋権益の保全、沿岸水域の警戒監視体制の構築、大規模災害等に対する救助体制の強化等の新たな業務課題に対応するため、老朽巡視船艇、航空機等の
緊急かつ計画的な代替整備を推進。
○ 携帯電話からの118 番通報による位置情報、コスパス・サーサット捜索救助衛星システムによる遭難警報、船舶に搭載された等から得られる我が国周 ?AIS辺海域の船舶動静情報等を、海上保安庁が保有する各種の情報と横断的に照合で
きるシステムを構築し、救難即応体制、海難防止対策等を向上。
2.国土の保全と防災対策を推進する
? 国民の生命や財産を保護する
安全性の確保が不十分な地域において引き続き防災や減災に取り組む。その際には、施設の耐震化、津波や高潮の予測をより正確かつ迅速に分かりやすく伝達する仕組みや、土地利用施策等の多様な対策を含めた総合的な取組を行う。
○ 海岸保全施設の重点緊急点検結果を受けた、壊滅的な被害が生じるおそれがある海岸における被害防止対策をはじめ、水門の自動化や遠隔操作化、堤防護岸の破堤防止、ハザードマップ作成支援等ハードとソフトが一体となった総合的な津波、高潮(ゼロメートル地帯)対策を推進。
○ 東海・東南海・南海地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による津波被害が想定される沿岸域やゼロメートル地帯における耐震性が十分でない海岸保全施設(堤防、護岸等)の耐震対策を推進。
○ 海岸ごとに潮位、波高、打ち上げ高等を的確かつきめ細かに予測する高潮情報システムの構築、津波警報の一層の迅速化及び精度向上、津波、高潮、高波に関する情報提供の充実や共有化を推進し、防災機関等での情報共有の高度化を推進。
○ 地震発生の予知に寄与する海底地殻変動観測や活断層の調査を実施するとともに、大規模地震に伴う津波の挙動を明らかにするため、津波シミュレーションを実施。また、海域火山活動の監視を行い、船舶航行や漁業活動等に関する災害の防止
を推進。
○ 津波時の放置プレジャーボートの陸への乗り上げ等の防止として、一般海域を含めた係留施設の台帳管理の徹底、係留施設の指定等を実施。
○ 大規模地震発生時の避難者や緊急物資の円滑な輸送の確保に資する港湾施設の耐震化とともに、海岸保全施設の耐震性を短時間かつ低コストで判定可能な「チャート式耐震診断システム」の開発を推進。
○ 地震や津波等の災害時における、海上からの住民の避難や物資輸送等を支援するため、沿岸域における防災情報図の整備を推進。
○ 東京湾及び大阪湾臨海部等において、基幹的広域防災拠点を整備するとともに「道の駅」の防災拠点化を推進。
○ 減災対策として、道路利用者への情報提供、避難路の整備及び救援活動や物資輸送を行う上で重要な役割を果たす緊急輸送道路の確保のため、道路橋の耐震補強や高規格幹線道路ネットワークを整備。さらに、被災を受けた道路について、障害物の除去や応急復旧等の迅速な啓開を実施。
○ 津波被害リスクのある地域において、生命や財産を守るため、津波防護機能を持ち合わせた防波堤の整備を推進。
○ 災害体験の継承、防災知識の蓄積や普及に必要な分かりやすい教材の作成、これらを多くの住民に分かりやすく伝えられる人材の育成、緊急時に備えた体制の構築と防災訓練を推進。
○ 海岸侵食や津波、高潮に対する沿岸域の安全性の低下を防止、軽減するため、関係者間の連携等の仕組みを構築。
? 国土を保全し、領海及び排他的経済水域等の海洋権益を確保する
海岸侵食等の対策を行うことや、外洋域における離島の交通、情報通信やエネルギー供給等に係る基盤の確保等に関する取組により、国境離島をはじめ、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の基線となる国土の保全を図るとともに、日本周辺海域についての適正な海図の作成のための調査や大陸棚の限界画定のための調査、的確な監視警戒等を行い、領海並びに排他的経済水域及び大陸棚の海洋権益の確保を図る。
○ 離島、奄美群島及び小笠原諸島において、交通基盤、産業基盤、生活環境、防災及び国土保全に係る施設等の整備や離島航路の維持及び改善に対する助成、産業や観光の振興、国内外との交流の促進、人材育成の支援等ソフトとハードを一体的に実施する総合的な施策を推進。
○ 我が国の領海及び排他的経済水域等を確保する上で、重要な拠点である国境離島に対して、万全な国土保全を推進するとともに、海象観測の実施等その活用を推進。
○ 大陸棚の限界画定のための調査等の推進や、国境離島の位置情報基盤の整備を推進。また、侵食対策等の海岸の適切な維持及び管理に資する低潮線の調査を実施。
○ 排他的経済水域が画定していない日本海、東シナ海等における海底地形や地質等の情報基盤を整備し、適正な海図の作成を推進。
○ 東シナ海等において顕在化している我が国の海洋権益に関する問題への対応として、機動力や監視能力等に優れた巡視船、航空機等を整備し、厳正かつ的確な監視警戒を実施。
○ 外国漁船による不法操業に対して、特に外国漁船が多数操業している日本海、東シナ海への巡視船艇や航空機の配備等により、効果的かつ厳正な取締りを実施。
3.海洋・沿岸域環境の保護及び保全を推進する
? 海洋・沿岸域のモニター体制を強化する
継続的に海流、海水中の汚染物質、海底地盤の状況、気象、漂流・漂着ゴミ等に関する基礎データの整理、提供体制の強化等を実施し、海洋・沿岸域環境のモニター体制を強化する。
○ 国土交通省における海洋や沿岸域に関する各種情報の収集、整理、提供体制の強化を図るとともに、海域環境の順応的管理に資する波浪、潮位、水深、水質、底質等の効率的なモニタリングを行うことで、海洋や沿岸域のモニター体制を強化。
○ 地球環境に関連した海洋現象を総合的に診断し、「海洋の健康診断表」として提供。
○ 海岸を活動の場としている市民、NPO との協働により、海岸環境に関する情報の広範かつ継続的なモニタリング体制を構築。
○ 排他的経済水域や大陸棚から沿岸域までの海岸線、低潮線、海底地形、地質等の情報基盤を整備。
? 海洋汚染等に対する的確な対応を推進する
大規模油流出、漂流ゴミ、放置座礁船、流出流木及び大型構造物の漂流等が、環境や安全上の支障をきたす等の問題に対し、未然防止対策の推進及び漂着前後それぞれにおける積極的な防除の仕組みの構築等を図る。
○ 油や有害危険物質の流出、放置座礁船等による海洋・沿岸域の汚染に適切に対処するため、領海を越え、場合によっては公海上であっても大型油回収船、巡視船等を迅速に派遣する等国境を越境する海洋汚染について、積極的な防除の取組を推進するための体制等の強化や、保険や基金による被害者保護への的確な取組を実施。
○ 油流出事故が発生した際に迅速かつ的確な油防除措置等の実施に資するため、適切な漂流予測を実施するとともに、沿岸海域の自然的、社会的情報等をデータベース化した沿岸海域環境保全情報の整備を推進。
○ 漂流・漂着ゴミについて、関係省庁と連携して、その処理(回収、処分)、発生源対策を推進。
○ 海洋環境保全講習会や訪船指導等により、漁業者、海事関係者に対して海洋汚染の防止のための指導及び啓発を実施。
? 脆弱な海域の保護及び保全を推進する
船舶からの汚染を防止する必要性が高い海域を、海上輸送を確保しつつ、保護及び保全する。
○ 生態学的又は科学的理由により船舶からの汚染を防止する必要性の高い海域に対し、海上輸送を確保しつつ、これを未然に防止するための措置を導入。
4.海洋・沿岸域の自然環境や美しい景観を取り戻す
? 海洋・沿岸域の自然環境を回復させる
埋め立て、沿岸構造物の設置、海岸の消失等により失われた自然環境の回復を図るため、干潟や藻場、サンゴ礁、湿地等の保全と再生、修復を図る。また、ヘドロ、ごみ、ダイオキシン等の有害物質等の堆積、埋立用材及び骨材の採取による深掘等により、元の生態系が失われた海底環境について底質環境を改善する。
○ 流砂系及び漂砂系の連続性を確保し、流入土砂による航路埋没、海岸侵食等の課題に対処するため、関係機関が協働して流砂系及び漂砂系における総合土砂管理を推進する体制を構築。
○ 埋立造成地、工場等からの土地利用転換地、廃棄物の埋立処分地等における緑地、湿地、干潟等の自然空間の再生や創出、砂浜、藻場、サンゴ礁等の回復、底質環境の改善等による自然環境の再生を推進。
○ 珊瑚付着型のブロックや干潟の再生に関する技術開発を推進し、港湾整備等への反映を推進。
○ ダイオキシン類等の有害化学物質による底質汚染の対策を推進。
○ 青潮等の原因とされる深掘跡の効率的な埋め戻し等を実施するため、浚渫土砂等の需給や品質を調整するシステムを構築。
? 海洋・沿岸域の自然環境及び景観の維持及び保全を図る
自然海岸や砂浜、干潟等の生態系への影響を最小化するため、十分な事前環境調査等を行い、沿岸域構造物と環境及び景観との調和を図る。また、多くの海岸で見られる漂着ゴミや放置されている船舶等を処理することや、船舶からの排出ガスの削減等により、自然環境及び景観の維持、保全を図る。
○ 人工海岸の整備、構造物の設置等に際して、環境との調和を一層重視し、石積堤や緩傾斜護岸等自然と共生する取組を実施。
○ 沿岸域にゴミが異常に漂流、漂着し、これを放置することにより船舶航行への支障、海岸保全施設の機能阻害、海岸環境の悪化等が生じているため、実効的な対策を推進。
○ 廃船(繊維強化プラスティック製廃船)の環境に優FRP しい処理と、FRP 廃27)船の不法投棄、放置艇の沈廃船化等の問題に対処するため、FRP 廃船のリサイクルシステムの普及を推進。
○ 海域への廃棄物不法投棄、汚水の不法排出等の海上環境事犯に対し、関係機関と悪質事業者等に係る情報共有体制を構築し、監視取締体制を効率化するとともに強化。
○ 船舶に石油類等を積み出す際に放出されるVOC(揮発性有機化合物質) 対策を実行していくため、放出規制港湾の指定や港湾における排出ガス処理施設の整備を促進。
○ 港湾に係留中の船舶に陸上側施設から電力を供給することで、船舶のアイドリングストップを推進。
○ 沿岸部における魅力ある空間の整備を推進、支援するため、海岸景観形成ガイドラインを踏まえた防災や利用と調和した良好な海岸景観形成を推進するとともに、景観計画の策定等景観法の制度活用について地方公共団体への助言を実施。
? 水質の保全及び回復を図る
下水道の整備及び河川の直接浄化による陸域からの汚濁負荷の削減並びに水質浄化能力を有する干潟や藻場の保全、再生等を行うことにより、依然として閉鎖性水域において、赤潮や青潮が発生している状況を改善する等水質の保全及び回復を図る。
○ 水質改善が進まない三大湾等の閉鎖性海域を中心に、「全国海の再生プロジェクト」として「海の再生」に向けた各種施策、海底の汚泥除去や覆砂による溶出抑制等の海洋・沿岸域の水質改善対策、合流式下水道の改善や高度処理の推進、河川浄
化対策、環境モニタリングを、一層、総合的かつ効果的に推進。
○ 東京湾、大阪湾以外の閉鎖性海域についても、順次再生行動計画の策定に向けた取組を推進。
5.海洋・沿岸域の利用を推進する
? 海上輸送の安定化・活性化を図る
外航海運について、適切な競争環境の確保等により、高質かつ効率的な輸送サービスを安定的に提供できる体制を整える。また、内航海運の経営基盤の強化等により、新造船舶への適切な代替を推進し、内航海運の活性化を図る。
○ 我が国商船隊による安定輸送を確保するための方策の充実・強化。
○ 経済効率、環境、安全等の課題を解決する新技術の開発と実用化を支援する枠組みを創設するとともに、環境問題への対応等社会的要請に応えることのできるスーパーエコシップの普及を促進。
○ 中小零細の多い内航海運事業者のグループ化、協業化を促進し、経営基盤を強化。
? 海洋・沿岸域の経済活動を活性化させる
貿易構造や荷役形態の変化に伴う陳腐化した施設や水際線を有する付加価値の高い低未利用地について、物流拠点や国際競争産業等の立地を推進する等有効利用すること等により、沿岸域の経済活動の活性化を図る。
○ 沿岸域の低未利用地に物流や国際競争産業等新しい機能立地を促し、それに併せて拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路の重点的な整備や、高度成長期時代の老朽化した運河や水路、護岸、防災・減災施設等のリニューアルを推進。
○ 「みなとオアシス」のような交流の場の形成を支援し、多目的拠点としての活用を推進。
○ 沿岸域における公共水域や港湾施設等既存ストックの適正かつ安全な活用促進に資する地域の取組に対し、フィージビリティの調査や規制等との調整等を実施し、これを支援。
? 海洋・沿岸域の新たな利用を推進する
新規航路の開拓、メガフロート等を活用した洋上発電や大陸棚海洋資源開発基地及び中小ガス田の活用を可能とする新たな輸送システムの構築等海洋の新たな利用を、技術の開発動向を踏まえ推進する。
○ 「リサイクルポート」の形成により、海上輸送による効率的な静脈物流ネットワークを構築し、循環資源の広域的な流動を促進。
○ 環境負荷の少ない内航海運による輸送への転換を促進するとともに、沿岸域ネットワーク、島や海の魅力を気軽に楽しむことができる国内旅客航路を活性化。
○ 拠点的な港湾から高規格幹線道路等へのアクセス道路を重点的に整備。
○ 中小ガス田の活用が可能となるよう、NGH(天然ガスハイドレート)輸送船を活用した新たな輸送システムを構築。
○ 海洋における風力、海洋温度差等による発電といった新エネルギーの活用に向けた洋上発電プラットフォームや大陸棚海洋資源開発基地として、メガフロートの活用を推進。
? 海洋・沿岸域の利用に関する技術の開発等を推進する
環境修復や侵食防護、高潮や津波への対策、耐震性診断、低環境負荷の船舶等の技術の開発、実用化及び普及を推進するとともに、気象、海象、水路状況等の海洋情報の活用を推進し、海上輸送の高度化等を図る。
○ 経済的で環境にやさしい船舶であるスーパーエコシップ等新技術を活用した船舶、船舶からの排出ガスに含まれる硫黄酸化物を大幅に低減するACF(活性炭素繊維) を活用した舶用高機能排煙処理システム、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出を同時に削減する超臨界水を活用した舶用ディーゼル燃焼機関等の研究開発、実用化及び普及を推進。
○ 海上におけるインターネットやTV 電話、電子メール等の通信利用環境を改善する高速大容量の船陸間双方向通信を実現するため、海上ブロードバンドの有望な活用方策の検討、実現に向けて必要な取組の提案を実施。
○ GPS 波浪計、陸上GPS 基準局、船舶AIS 及び海洋短波レーダー等の情報のマッチングにより、船舶に対する各種航行支援情報のリアルタイムの発信を推進。
○ 環境モニタリング結果を活用しつつ、珊瑚付着型のブロックや干潟の再生等に関する技術の向上のための研究開発を持続的に実施。
○ 日本海洋データセンターが収集、管理し提供している各種海洋データを関係機関との連携により充実させ、海洋・沿岸域の基盤情報の整備を推進。
? 海洋・沿岸域の利用を支える船舶や船員を確保する
海上輸送の高度化に対応した船舶や船員を確保するため、造船技能者や優良な船員の育成を行う。
○ 海洋・沿岸域の安全確保、環境保全に資する船舶の供給を支える造船業を振興。また、造船業における技能者の世代交代に対応する造船に関する「匠」の技の円滑な伝承を推進。
○ 船員教育機関における船員養成やBRM 研修を始めとする実践的な技能の教授並びに各種の船員雇用施策により、優良な船員の確保及び育成を促進。
? 海洋・沿岸域の多様な利用を調和させる
沿岸域の利用の輻輳等を解消するため、一般と産業関連等との利用調整、国土保全と経済活動との利用調整を行い、相互に調和がとれるようにする。
○ 沿岸域の環境と産業、観光、レクリエーション等の利用との調整を図り、持続的な沿岸域の利用と保全を図るため、沿岸域の利用と保全に関する施策を国と地方及び利用者、NPO 等の適切な役割分担、相互の連携、協力、協働により、より一層
着実に実施。
○ 沿岸の大都市から排出される廃棄物最終残渣や災害時に発生する廃棄物の適切処分について、最終処分場の広域融通を推進。
6.海洋・沿岸域への親しみ、理解を増進する
? 人と海のふれあいを取り戻し、海辺のにぎわいを創出する
臨海部における親水空間の確保やアクセスの改善、プレジャーボート等による海洋スポーツやクルーズの活性化等ハード、ソフト両面において人と海のふれあいを取り戻すことにより、海辺のにぎわいを創出し、地域の活性化等に寄与する。
○ 臨海部の水辺空間が市民の親水空間、人と海の触れ合う場となるよう、臨海部の都市公園、港湾緑地、海岸等の整備を推進。
○ 水域を活用したプロムナードやビジター桟橋、水域にアクセスできる斜路や階段護岸等施設の一部として水域を効果的に取り込んだ港湾緑地の整備を行い、海辺のにぎわいを創出。
○ 港湾の資産を地域の視点から再評価するとともに、地域の産業、海に開かれた特性等港湾の資産を最大限に活用し、地元等の市民団体、地NPO 元市町村、港湾管理者、地元企業等の連携による港湾のにぎわいの創出を推進。
○ マリーナ及びフィッシャリーナ等を活用し、プレジャーボート等によるクルーズ、海洋スポーツ等のマリンレジャーの拠点や地域観光情報等の提供を行う「海の駅」の設置を地域と連携して支援し、ネットワーク化を推進。
○ 海洋におけるレクリエーションが安全かつ安心に楽しめる環境を整備するため、沿岸域の流況情報等の整備及び提供を推進。
? 海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る
海との共生について積極的な関心や協力を喚起するため、海洋・沿岸域に関する知識の普及及び理解の向上を図る。
○ 海洋・沿岸域教育に係る普及啓発活動や指導者育成、NPO 等活動団体のネットワーク化、ホームページの作成等の取組を更に拡充し、利用者からのアクセスしやすさの向上や団体同士の連携と協働をより一層促進。また、関連する基礎知識の体
系化や普及啓発の取組を推進。
7.海洋・沿岸域の総合的管理を推進する
海洋・沿岸域に関する施策を総合的、戦略的に実施するため、国家戦略的な視点を踏まえつつ、海洋・沿岸域の総合的管理について、国の施策の基本方向を定立するとともに、各地域において、関係者の共通認識の醸成を図り、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働による計画策定等の取組を着実に推進する。
○ 国の各種基本的な政策等との整合を図りつつ、沿岸域の安全の確保、多面的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自立的な地域の形成を図るため、関係者の共通認識の醸成を図りつつ、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働により、各地域の特性に応じて沿岸域圏の総合的な管理計画を策定するなど、各種事業、施策、利用等を総合的、戦略的に推進する。
8.国際社会との協調及び協力関係を確立する
海洋・沿岸域の安全確保や環境保全等を図るため、IMO等の国際機関の枠組みや、PSIをはじめ各種会合や訓練等海の安全や環境保全に係る国際的な取組に積極的に参画するとともに、SUA条約の改正等に伴う国内の体制の整備や、国土の水没問題等に苦慮している島嶼国への支援、国際的な沿岸防災対策への支援、日ASEAN交通連携プロジェクトの推進、ODAの活用等により、国際社会との協調及び協力関係を確立する。また、東南アジア諸国に対する海上保安機関の設立支援、海上犯罪取締能力や捜索救助技術等高度な技術や知識の移転等により、マラッカ・シンガポール海峡等を含む東南アジア海域の海上保安能力の全体的な向上を図る。
○ マラッカ・シンガポール海峡等日ASEAN 地域における海の安全や環境保全等のため、日ASEAN 海事セキュリティプログラムやOSPAR 計画等を推進。
○ 東南アジア周辺海域の海上の秩序を確保し、これを通じて我が国の海上交通の安全を確保すべく、フィリピン、インドネシア、マレーシア等へ専門家を派遣し、海上保安機関の設立支援や、東南アジア諸国への技術や知識の移転等を実施。
○ 海上阻止訓練に海上保安庁巡視船を参加させるなど、PSI の活動に積極的に参画。
○ 平成17 年10 月に採択されたSUA 条約の改正について、関係省庁の一員として批准に向けた国内体制の整備を推進。
○ PEMSEA(東アジア海域環境管理パートナーシップ) やNOWPAP(北西太平洋地域海行動計画) 等の取組に積極的に参画し、我が国の取組を東アジアに発信するとともに、日本海、黄海等の海洋環境の保全に積極的に取り組む。また、海洋汚染防止に関する取組について日仏協力会議を開催し、技術的、組織的な協力等を推進。
○ 大規模な油や有害危険物質の排出事故等への対応体制を一層強化するとともに、OPRC − HNS 議定書に対応した体制を確立。
○ シップリサイクル(船舶の解撤)や目標指向の新造船構造基準、次世代航海システム等に関するにおける検討を積極的にリード。
○ IMO やMAIIF(国際海難調査官会議) における、国際的海難についての調査協力体制推進の議論に積極的に参加。
○ ODA を通じた海洋・沿岸域に関する国際協力を推進。
○ 国土の水没問題等に苦慮している島嶼国に対し、国土保全の手法等について情報提供等の支援を実施。
○ 北西太平洋域の各国に津波情報の提供を実施するとともに、インド洋の沿岸国に対しインド洋における津波警戒システムの構築支援及び暫定的な津波監視情報の提供を実施。
○ 船舶、ブイ、フロート等の海洋観測データを準リアルタイムで国際的に収集し、地球環境に関連する海洋の情報を作成して国内外の行政機関や研究機関へ提供。
9.施策を推進するに当たっての基本的考え方
海洋・沿岸域に関する施策については、国土交通省として以下の基本的考え方を十分踏まえ、推進していくこととする。
? 総合的、戦略的な取組
海洋・沿岸域に関する問題は、それぞれ個別に存在するのではなく、相互に関係するものが多く、また、例えば海岸侵食対策のように山地や河川から海岸に土砂を適正に供給する総合的な土砂管理が必要であるなど、陸域、河川等との関係で生じているものもある。
さらに、安全の確保や国土の保全のように中長期的な視点に立って施策を組み合わせて実施することが効果的なものもあることから、関係機関が連携し、関係する施策を総合的、戦略的に実施する。
? 国際的な視野に立った取組
我が国はすべての国境を海域で画し、海上における安全、離島管理、資源やエネルギーの利用及び開発、地球規模の環境問題等海洋に関する課題の中には、国際的な性格を帯び、その解決に当たって国際的な協力が不可欠であるものもあるため、国際的な視野に立った取組を進める。
また、海洋・沿岸域政策に関する幅広い分野に精通し、かつ、国際的枠組みに参加し、我が国の意見を発信していくことができるような人材の育成を図る。
? 国と地方の役割分担、連携及び協働
海洋・沿岸域に関する問題は多岐にわたり、地域的な問題として単独の市町村が取り組むべき問題から、複数の都府県にわたる広域の連携が必要な問題、排他的経済水域及び大陸棚における問題や国際競争力の根幹を担う海上輸送の確保のように国が取り組むことが必要な問題があることから、今後は、国際動向に応じた国の立場を踏まえ、国と地方、また、地域間の役割分担を明確にするとともに、重層的な取組が必要な分野について、連携、協働して取り組んでいく。
? コンセンサスの状況に応じた取組
海洋・沿岸域に関する問題については、多様な価値観が存在し、また、利害関係が複雑であることが多いことから、地方公共団体、漁業者、産業界、海運事業者、海洋レジャー関係者、各公物管理者、地域住民、環境保護団体その他のNPO等多くの関係者の間の情報共有や共通認識の醸成を図り、そのコンセンサスの形成状況に応じて、取組を進める。また、取組に当たっては、関係者の連携、協働の下、試行的に良好な環境を形成することによって理解と協力を得る等の方策も進める。
? 持続的な取組
海洋・沿岸域に関する問題の多く、例えば、干潟や藻場の回復といったことは、長期にわたる取組が必要であるとともに科学的、技術的に解明されていないものもあることから、持続的な取組を着実に推進していく。
? 先行的な取組
良好な環境はいったん損なわれると回復が困難となる場合が多いことから、海洋・沿岸域の海洋環境や自然環境を守るために、損なわれる前に環境のモニタリングや科学的、技術的な分析評価を十分に実施する等の先行的措置を講じる。
? 多様な主体の参画促進
沿岸域における問題については、現在でも地域住民やNPO が参画し、取組を行っているところであるが、特に環境の保全や、海を活用した地域づくり等を中心として、引き続き地域住民、NPO の力に期待するところは大きく、一層の参画を促す。
? 効率的、効果的な施策の実施
国及び地方公共団体とも要員や財源の確保が厳しい中、不断の組織体制の見直し等と併せて、事前の施策効果を見極め、担当部局間の連携、メリハリのある施策の展開、重点施策への要員の集中、民間やNPO との協働等により、効率的かつ効果的に施策を実施する。
本大綱にまとめた施策のうち、法制の整備が必要なものについては、海洋政策を巡る諸状況を踏まえつつ、その整備に向けて検討を進めることとする。
また、本大綱にまとめた施策のうち国土計画上重要な事項については、国土形成計画(全国計画及び広域地方計画)の案において、関係府省とも調整の上、位置付けを図るものとする。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010621_2/02.pdf
2009年12月29日
第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会
第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会
1.日時
平成21年3月3日(月)14時00分
2.場所
神戸市中央区下山手通5−1−16パレス神戸2階「大会議室」
3.出席者指名
?出席委員
糠善次/ 川本信義/ 山本正直/ 小田英一
福池昌広/ 高橋昭/ 前田健二/ 宮本憲二
藤本昭夫/ 坂井淳/ 原一郎/ 荒井修亮
以上12名
臨席者
水産庁資源管理部管理課課長木實谷浩史
課長補佐渡邉顕太郎
九州漁業調整事務所次長佐藤愁一
独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所部長岩本明雄
資源管理研究室長永井達樹
研究員片町太輔
中央水産研究所主任研究員石田実
和歌山海区漁業調整委員会事務局長田上伸治
大阪海区漁業調整委員会課長補佐狭間文雄
専門委員小菅弘夫
大阪府環境農林水産部水産課課長補佐亀井誠
兵庫県農政環境部農林水産局水産課資源管理係主査峰浩司
兵庫県農政環境部農林水産局水産課漁政係主査森本利晃
岡山海区漁業調整委員会次長佐藤二郎
広島海区漁業調整委員会専門員山根康幸
山口県農林水産部水産振興課主任岡田浩司
徳島県農林水産部水産課技師西岡智哉
香川海区漁業調整委員会副主幹宮川昌志
香川県農林水産部水産課課長補佐井口政紀
技師益井敏光
愛媛県農林水産部水産局水産課資源管理担当係長加藤利弘
愛媛県農林水産研究所主任研究員河本泉
主任研究員関信一郎
福岡県豊前海区漁業調整委員会事務主査竹馬悦子
大分海区漁業調整委員会事務局長日隈邦夫
大分県農林水産部水産振興課副主幹大塚猛
愛媛新聞社大阪支社編集部長芝充
瀬戸内海漁業調整事務所所長佐藤力生
調整課長馬場幸男
資源課長森春雄
指導課長小林一弘
資源管理計画官平松大介
資源保護管理指導官中奥美津子
調整課許可係長酒井仁
調整課調整係玉城哲平
資源課資源管理係長松本貴弘
資源課資源増殖係長萩原邦夫
資源課漁場整備係正岡克洋
4.議題
1.サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について
2.周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について
3.カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について
4.トラフグ資源管理の検討状況について
5.その他



5.議事の内容
(開会)
(馬場調整課長)
ただいまから第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会を
開催いたします。
それでは前田会長、議事進行をお願いいたします。
(挨拶)
(前田会長)
さて、本日の委員会ではサワラ瀬戸内海系群資源回復計画、周防灘小型機船底びき網漁
業対象種資源回復計画、燧灘カタクチイワシ資源回復計画について平成20年度取組の実
施状況と資源状況についての報告をしていただきまして、また平成21年度の取組などに
ついてご審議いただくことといたしております。
更にはトラフグ資源管理の検討状況、平成21年度予算についてもご報告いただくなど
盛りだくさんの内容となっております。
また、ご案内のとおり委員の皆様におかれましては現在の委員の任期が平成17年10
月1日から4年間、今年の9月末日までが任期となっております。緊急の予定がなければ
本日が最後の委員会になろうかと思います。委員の皆様におかれましては最後まで活発な
ご議論をお願い申し上げます。
(木實谷管理課長)
ご承知のとおり広域漁業調整委員会でございますけれども、都道府県の区域を越えて分
布回遊する資源の適切な管理を目的として設置されまして、国が作成する広域の資源回復
計画を中心としてご審議をいただいているところでございます。
現在、全国で18の広域計画そして46の地先計画が実施されておりまして資源回復の
ための取組が全国的に展開されてきているところでございます。瀬戸内海を管轄いただい
ております本委員会の関係では現在までに3つの広域計画が作成実施されているところで
ございますけれども、皆様方の不断のご努力により資源の回復が更に図られることを期待
しているところでございます。
改めて申し上げるまでもなく水産庁といたしましても、この資源回復計画につきまして
は主要施策の1つでございまして今後とも一層推進していくということにしているところ
でございます。現在取り組んでおります資源回復計画につきましては、徐々に回復が見ら
れ始めている計画もございまして、このような資源については将来的には漁業者がみずか
らの力で管理していくような方向にもっていくというのがこれからの課題ではないかとい
うふうに考えているところでございます。
一方で、漁業経営を取り巻く情勢につきましてはご承知のとおりいまだ予断を許さない
状況にございますけれども、適切な資源管理に取り組み水産資源の維持回復を行っていく
ことは、将来的に活力ある漁業構造の確立にもつながっていくものと考えておりまして、
資源管理を目的として設置されました広域漁業調整委員会の役割は一層期待されるものと
考えているところでございます。
なお、広域漁業調整委員会につきましては委員の皆様の任期が一期4年となっておりま
して、現在第2期目の最終年を迎えているということでございます。平成13年に漁業法
が改正され広域漁業調整委員会制度が設けられ、その中で資源回復計画を中心とした課題
に鋭意ご尽力を賜りました皆様のおかげで、資源回復計画も今や全国的な展開になってい
るところでございます。これまで各委員の皆様方が払ってこられましたご努力に対して重
ねて御礼申し上げますとともに、残されました半年の期間におきましても資源管理、漁業
調整といった課題に対しまして引きつづきご支援、ご協力をお願いする次第でございます。
本日はさわらの資源回復計画を始め、盛りだくさんの議題となっているというふうに承
知しております。皆様の有意義なご審議が行われまして、今後さらに瀬戸内海における資
源管理が推進されますよう祈念いたしまして、簡単ですけれども開会のあいさつとさせて
いただきます。
(資料確認)
(前田会長)
それでは、本日使用いたします資料の確認を行いたいと思います。事務局よろしくお願
いします。
(馬場調整課長)
それでは、お手元にお配りしております資料でございますが、まず議事次第、委員名簿、
出席者名簿それから本日の会議での資料としまして資料1−1から1−3までサワラの資
源回復計画関係の資料。資料2−1から資料2−3まで周防灘小型機船底びき網資源回復
計画の資料。資料3−1から3−3までがカタクチイワシ資源回復計画の資料。資料4ト
ラフグ資源管理に関する主な取組。資料5平成21年度予算関連資料がございます。それ
から参考資料といたしまして瀬戸内海で行っている広域種の資源回復計画等に関します資
料をホッチキスどめで配付しております。ざいます。
(議題1 サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について)
(前田会長)
それでは早速、議題1「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の一部変更について」に入り
ます。
まず始めに20年度の実施状況について事務局より報告していただき、次に瀬戸内海区
水産研究所からサワラの資源状況などについて説明をしていただきます。その後、21年
度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。
それでは本年度の実施状況について事務局から報告をお願いいたします。
(平松資源管理計画官)
瀬戸内海漁業調整事務所資源管理計画官をしております平松でございます。
まず資料1−1を用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。座って説明を
させていただきます。
サワラ資源回復計画の平成20年度の実施状況につきまして、資料1−1の表紙をめく
っていただきますと漁獲努力量削減措置実施状況図1ページがございます。こちらの実施
状況図から資料の5ページまで、種苗放流それから漁場整備等の実施状況につきましては
前回の委員会での報告内容と重複いたしますのでここではご説明を割愛させていただきま
す。
資料の6ページをご覧いただきたいと思います。こちらに平成20年の漁獲量の速報値
を載せてございます。6ページの1番の漁獲量の表の欄外、右側に速報値として括弧書き
で各年の数量を書いているところでございます。こちらの数値につきましては、農林水産
省の統計部が半年ごとに速報値として集計しております数値の平成20年の上半期、下半
期の合計の数字を掲載させていただいております。平成20年につきましては、瀬戸内海
の漁獲量が752トンということで集計をされてございます。これと同じ速報値の平成1
9年の数字を見ていただきますと803トンということで速報値の対前年比が94%、マ
イナス6%ということになってございます。私どもの事務所の方で各府県の担当の方から
漁獲状況を聞き取っております情報を整理いたしますと、やはり同様に数%前年を下回る
というような情報をお聞きしてございます。こちらにつきましては、確定値はもう少し時
間が経ってから出るということでございますが、平成20年は平成19年の漁獲量の確定
値1,081トンを若干下回るのではないかと想像をしているところでございます。
平成20年の漁獲量の統計の数字につきましては以上でございますが、6ページの2番、
下の方ですがこちらの方には当広域漁業調整委員会指示で漁獲量の上限が定められており
ます。はなつぎ網、さわら船曳網、サゴシ巾着網、こちらの漁獲量の報告が各県からござ
いましたので、その数値を掲載させていただいてございます。それぞれ表にございます制
限値以内での操業が実施されたというところでございます。
漁獲量については以上でございますが、次に資料の7ページに岡山県が今年度実施いた
しました試験操業調査の結果、それから8ページから9ページには同じく香川県で実施さ
れました試験操業調査の結果を載せてございます。
まず、7ページの岡山県の調査結果でございますが今年度、昨年の10月に試験操業が
3回実施されてございます。真ん中の2番の試験操業結果のところの平成20年の欄をご
覧ください。3回の試験操業によりましてサゴシが197尾漁獲されております。その下、
1隻あたりのCPUEも65.7ということで、それぞれ平成19年の結果を上回る結果
となってございます。197尾の漁獲されたサゴシのうち、放流魚がどれだけ含まれてい
たかというものにつきまして7ページ一番下の表3に漁獲サゴシのデータと右側に放流さ
れたサワラのデータの結果を載せております。平成20年につきましては、197尾のう
ち放流されたものが1尾ということで混獲率は0.5%という結果になってございます。
昨年、一昨年と比べて混獲率が非常に低い結果というのが今年の特徴でございます。
同様に8ページから9ページの香川県の調査結果も傾向といたしましては、ただいまの
岡山県と同様の傾向となってございまして、まず8ページの2番の漁獲状況の1番下の右
端、平成20年の結果といたしまして3回の試験操業で107尾のサゴシが漁獲され、1
隻あたりの漁獲実数も17.8尾ということでそれぞれ前年を上回っているという結果で
ございます。また9ページに漁獲されたもののうち放流されたサワラがどれだけ含まれて
いたかということで表になってございますが、こちらの平成20年のところをご覧いただ
くと、左側の漁獲サゴシ107に対して放流サワラの尾数が1尾ということで混入率が約
1%という形になってございます。それぞれ傾向といたしましては、先ほどの岡山県と同
様な傾向になっているというところでございます。
このように両県とも試験操業での漁獲は昨年よりも多いということ、それから全体の漁
獲の中に占める放流されたサワラの割合が少ないということ、相対的に見ると全体の天然
のサワラ加入が多いということを示す結果となってございます。ただ、近年では加入が卓
越いたしました平成14年ほどの結果にはなっていないというところがございます。若干
漁獲がいいのではないかというような推定もしておりますが、これらの加入状況につきま
してはまた後ほど瀬戸内海区水産研究所の方からの報告にも触れられますのでそちらに譲
りたいと思います。
岡山県、香川県の両県で実施されております試験操業こちらにつきましては、播磨灘の
休漁期間に実施されるものということで、本委員会指示との関係により事前に委員会へ調
査計画の報告、また結果の報告を行うということにされております。平成21年度につき
ましても今年度と同様に調査が計画されておりまして、資料の10ページ、11ページに
それぞれ来年度の調査計画が提出をされていることをご報告いたします。
それから平成20年度の実施状況、最後になりますが資料の12ページ一番後ろでござ
いますが、TAE管理の実施状況を取りまとめてございます。府県別に数字が書かれてお
ります表の一番右端に全体の合計値といたしまして、設定された努力量が12万3,67
4隻日に対しまして平成20年度のTAE管理期間での操業隻日数が2段目の1万5,9
13隻日となってございます。設定値に対する割合といたしましては13%となっており
まして、こちらの出漁隻日数につきましては平成15年度にこのTAE管理を開始して以
降、最も少ない値ということになってございます。
簡単ではございますが平成20年度、本年度のサワラ計画の実施状況についての説明は
以上でございます。
(前田会長)
ただいまの報告につきまして何かご質問はございませんでしょうか。
それではご質問もないようですので、つづきましてサワラの資源状況につきまして瀬戸
内海区水産研究所の永井室長さんより説明をお願いいたします。
(永井室長)
図は漁獲量の経年推移です。横軸が年、縦軸が千トン単位で示した漁獲量です。青が瀬
戸内海の東部、紀伊水道から備讃瀬戸まで、赤が燧灘から伊予灘、あるいは周防灘までの
西部を示します。漁獲量は一番多いときで6千トンを超えましたが、1986年をピーク
に減ってきました。1998年に香川県、岡山県、兵庫県が自主規制を始めてから、徐々
に漁獲量は回復してきて、2000年からは資源回復計画が行われているところです。
2007年の漁獲量は図では1,108トンと記入しておりますが、先ほどの平松さん
の説明で新しい推定値は1,081トンとなっています。漁獲物の年齢を見ますと昔は3
歳、4歳をとっていたのですが、1980年代に入ってから2歳、3歳、1990年代に
入ると1歳、2歳が中心となり、漁獲物の低年齢化が進んいます。とり方としては悪くな
ってきています。
次に資源量の推移ですが、縦軸に漁獲物の年齢組成を基に資源計算して求めた資源量の
経年推移を示しました。一番多いとき1987年で1万6千トンくらいあったものがずっ
と減ってきて、2007年には2,282トンと1987年の14%に減っています。そ
の後、資源量は少し回復してきましたが、ここ4年ほどやや減少ぎみで推移しています。
一時の悪いときは脱したけれど、やや減りぎみで推移しています。
それから資源量に対してどのくらい漁獲しているかという漁獲割合を赤で示しておりま
すが、一時に比べてその割合が高くなってきており、漁獲圧力が増してきています。
次に親魚量(トン)と加入尾数の関係です。横軸に親の資源量をとりまして、縦軸にそ
の年に生まれて秋に加入したサゴシの資源尾数をとっています。図を見ると、親が多いほ
ど子供も多く加入していることがうかがわれます。両者に直線の関係を当てはめると青い
ラインになります。最近年の1998年以降を切り出してみると右の図ですが、同じブル
ーの直線で示していますが、これは2つの図で同じものです。要するに親が多いと子供も
多い、ただ2002年というのは親がそれほど多くなかった割には加入がよかった、強い
年級が生まれてきた。これに対し2004年は親が多かったけれど、期待したほど子供が
生まれてこなかったわけです。いずれにしても最近はこの直線より少し上に点がくるいい
傾向があるのですが、それが親の増加につながっていない。というのは0歳秋から1歳の
間の魚がまだ小さいうちに漁獲されて、親の増加につながっていないと言えると思います。
先ほど2004年は親が多かった割に子供の生き残りが悪かったということを言いまし
たが、その理由として1つ考えられるのはこの年には御承知のように6月から10月に台
風が10個来襲して史上最高ということがありました。この年サワラの卵が多かったとい
うことがネット調査でわかっておりますが、仔魚が少なかった。小さいうちに海が時化て
魚の生き残りが悪かったのかなと思っています。
それから2006年については、2005年の12月から40年ぶりの低温という厳し
い冬でして、表面の水温がこれは大阪湾の例ですけど例年に比べて5度くらい低かった。
その影響がずっとサワラの産卵期まで持ち越してきまして、サワラの産卵時期は開始が遅
れましたが、逆に低温のため産卵の終わりが細く長く続いたという特徴があります。漁獲
の経過や年齢別の漁獲の状況から見て、2006年は非常に低温で、産卵に影響は受けた
が、結果として細く長くつづいた産卵で2006年の加入はそれほど悪くなかったと理解
しています。
いろいろと環境が不安定な例を示します。図の横軸が1月から12月の平年の水温の平
均値ですが、それに対して2006年とか2007年がどうかと比べました。香川県の1
0メートル水温の平年偏差ですが、海域は幾つかあります。3つほどまとめて言いますと、
特徴として2006年は先ほど言ったように平年を下回る水温がずっと続き、3月に平年
値を少し超える時がありますが、低温の年でした。2007年は逆に平年より非常に暑く
て、一番高い時は平年偏差より2度くらい高い場合も見られました。魚の場合1度水温が
高いと人間で言えば5度とか10度に相当すると言われています。水温がかなり高いとい
うことがサワラの仔稚魚の生産率を低下させていないか、つまり2007年生まれの生き
残りがどうだったかということを考える上で、水温が高かった影響を考えていかないとい
けないと思います。
資源評価のまとめとして、2007年の資源量は2,282トンで1987年に比べて
14%と低位です。それから2007年の資源水準は低位で過去5年の動向は減少、生物
学的に望ましい漁獲の係数であるF30%は、現状の漁獲の係数に比べて41%、つまり
現状の漁獲圧力が望ましい状態に比べて非常に高い。望ましいというのは生物学的にサワ
ラにとって優しいという意味なんです。現状はちょっと漁獲圧力が高いと評価しています。
それから2007年の加入は生き残りが悪かったかもしれないということで少ない恐れが
あると考えています。このように特徴的な年の状況を言いましたが、環境が不安定に推移
することが多いので、加入が環境の影響を受けやすいということが最近続いていると考え
ています。
次は漁獲量の動向を図にしたものですが、2008年の東西別漁獲量、左側の柱が春漁、
右側が秋漁、高さが漁獲量、それから赤が全年を下回っている場合、青が前年を上回って
いる場合を示しています。ですから東部の場合春漁は前年を上回って1.1倍、秋漁は0.
6倍でした。西部の場合は1.0の赤ですから前年をやや下回ったもののほとんど1に近
い、秋は1.8倍と秋が良かったことを示します。
図は春漁、秋漁を府県別に示したものです。瀬戸内海の内の方で春も秋も青のところが
見られますが、外側では秋が青だけれども、なかには例えば徳島県のように前年比秋が0.
6倍というところもあります。兵庫県は春も秋も0.6倍、大阪府は0.2倍、0.4倍
で、大阪湾あるいは播磨灘のあたりはよくなかったことが分かります。
次は4月から7月を春漁と定義しまして、その東西別の割合を示しています。今度は左
側がサワラ銘柄、右側がサゴシ銘柄の漁獲量です。東部では春にサワラは1.1倍、サゴ
シは1.0倍、合計163トンでした。西部ではサワラが1.1倍、サゴシが0.5倍で、
春サゴシが西部で悪かった。次の図は府県別に示したものですが、サワラでは香川、広島
で前年を上回って、大阪、兵庫などで下回った。サゴシでは香川、岡山、広島で前年を上
回り、兵庫、愛媛で下回った。
次に8月から12月を秋漁として示しています。8月から12月には東部のサワラで前
年を下回り0.4倍でした。サゴシは前年を上回り3.0倍でした。西部についてはサワ
ラもサゴシも前年を上回って1.1倍と6.7倍です。この2008年はサゴシの銘柄が
東部で3.0倍、西部で6.7倍と前年比で高い値が得られているのが特徴です。それを
府県別に示したものが次の図ですが、サゴシでは大阪と大分で前年を下回ったほかは大体
前年を上回るところが多かった。
それでは次に2008年の秋の漁獲の動向について説明します。
これは大阪府の資料ですが、南部の標本組合の機船船びき網漁業の漁獲量を示していま
す。一番上はシラスの漁獲量、縦軸がトンで横軸が1月から12月まで。ヒストグラムが
平年で赤が2008年、青が2007年、黒が2006年の直近3年ですが、平年と比べ
て2008年は10月にシラスが割と多かったというのが特徴的です。
カタクチイワシについては8月、9月がピークですが、前2年に比べて2008年はち
ょっと悪かった。
サワラについては2006年、7年に比べてピークが余りはっきりしない。10月が一
応低いピークなんですが、余りよくなかったということになります。カタクチが余りよく
なかったということでサワラもよくなかったのかと思われます。ただ10月にシラスがと
れたというところが目新しいと思います。
サワラの尾叉長組成の方ですが、これも大阪府の資料ですが、流網の尾叉長組成が主で
す。9月から12月まです。一番上は曳網でして、9月に曳網でとれたものは46センチ
程度で例年に比べて魚体がやや小さかった。小さかったので、これが流網にかかってこな
かった。50センチより小さかったということであまり流網にはかかってこず、9月は1
歳魚、同じく10月、11月も大阪では1歳魚主体の漁獲であり、0歳魚、その年生まれ
のサゴシがとれたのは12月に入ってからだった。
2008年生まれのサゴシは多いんだとか、それほどでもないという情報がいろいろあ
るわけですが、これについてちょっと御説明しますと、2008年の秋のサゴシの漁獲は
香川県の資料では東部の引田で、これが2008年の秋のサゴシですが、加入が非常によ
かった2002年、それからそれ以降比較的よかった2005年に比べて、2008年は
2002年ほどではないけれども2005年並みであるという数字となっています。それ
から西の方の香川県の伊吹の資料では2005年に比べてもやや小さい半分以下の数字に
なっております。それから高松中央卸売市場での9月から12月の香川県産のサゴシの入
荷量、取扱量は2005年あるいは2002年並みの数字になっております。先ほど御紹
介があったように試験漁獲では2002年の0.4倍、2005年の0.8倍ですから、
2002年に比べるとやはりそれほど多くないが、その次に比較的よかった2005年と
同じかやや下回る程度じゃないかという数字になっています。
愛媛県のサワラとサゴシの資料を分析しますと、2008年秋のサゴシの豊度、1隻1
日あたりの漁獲尾数あるいはキログラム数、川之江と埴生ではキログラム、西条と河原津
では尾数です。2002年から2008年について色別に示しておりますが、2008年
のCPUEで見ると川之江と埴生では2002年並み、2002年というのは図で黒です。
西条と河原津では2002年を下回る。このように、2008年が2002年ほどではな
いということで、良いという情報と悪いという情報が半ばとなっています。
それから、同じ愛媛県でも伊予灘では、月別の漁獲量で図はないのですが、サゴシにつ
いて数字を整理したものを県からいただいたのですが、2005年の漁獲量を1としまし
て、2006、2007、2008年の漁獲量はそれぞれ1.5倍、2.2倍、1.9倍
となりまして、2005年に比べて2008年のサゴシは2倍近い漁獲量で、サゴシが比
較的とれています。
管理方策への提言として、毎年70万尾の加入がないと資源は持続しない。親の資源は
2歳魚主体で若齢化しておりまして、年齢構成も単純化している。そのために環境が悪く、
再生産において仔稚魚の生残が悪い年があると、資源が大きな打撃を受ける恐れがあると
考えています。ですから、サゴシの漁獲を抑えて親を残して、加入動向を見守ることが重
要です。そして、環境や加入、再生産の不安定さを考慮しますと資源回復計画での取り組
みの強化が望まれると考えております。
それから、次は補足なんですが平成20年度第1回サワラブロック漁業者協議会、9月
24日の会議で各県の漁業者の方々から研究サイドへいろいろ要望が出ました。大きなも
のとしては3つほど出たんですが、それに対して私の方でできる範囲で資料を整理して回
答したので、簡単にご紹介したいと思います。
1番目は地域別の放流効果、放流しているが、地域別に漁獲量への反映がどうなってい
るのか示してほしいということです。2番目はサワラがどうして播磨灘に入ってこないか
説明してほしいということです。これに対して非常に説明は難しい、なかなかいい説明が
できないのですが、後でお見せする図の2や小路・益田両先生の講演要旨を見てください
と説明しました。それから、3番目に海の変化、瀬戸内海の海の変化とか温暖化に関する
情報を提供してほしいということで、これについては後で表1をお見せしますが、東シナ
海とか日本海、瀬戸内海に関しての状況を私の方でまとめさせてもらいました。参考資料
として委員の先生のところには「海洋と生物について瀬戸内海の魚類生産に変化はあった
か」というテーマで私が書いたものをお配りしております。これはブロック漁業者協議会
でもお配りしたものです。
サワラの放流魚については、ご承知のように内部標識として小さい卵とか仔魚の段階で
赤い標識を入れております。ですから成魚あるいはサゴシでも、漁獲して頭の中の耳石を
調べたら放流物か天然物かがわかります。その天然物に対して放流物の割合が何%かを海
域別、それから年齢別、それから年別に放流魚の混入率としてまとめました。御覧になっ
てわかるように0歳のところでは混入率が非常に高いです。ただ年齢が高くなるほど値は
低くなっています。図には播磨灘の兵庫県、播磨灘の岡山県、播磨灘の香川県などでの混
入率の数字がありまして、これに漁獲物の年齢組成を別に持っておりますので、両者をか
けてどのくらい放流魚が漁獲されているかというのを直近の3年について推定して図中に
数字としてあげています。
ここでちょっと分かりにくいんですが、赤い色は瀬戸内海、兵庫県の播磨灘で再捕され
たものですが、西部放流分を示しています。図では厚みをもっていませんので1尾とか2
尾なんですが、西から東に来たものが再捕されています。それから瀬戸内海西部なんです
が、燧灘、香川県沖、愛媛沖、安芸灘、伊予灘での特徴として、安芸灘、伊予灘では混入
率が低い、放流物の再捕がない。それからもう1つの特徴は香川沖でも愛媛沖でも燧灘に
ついては、この緑色は厚みをもっていますので、瀬戸内海東部で放したものが備讃瀬戸を
通って西部の方にかなりきていることを示します。ただ、東に比べると西では混入率はそ
れほど高くはないということが特徴です。いずれにしても地域別、年別、年齢別にこのよ
うな混入率となっており、それが漁獲量にどう反映しているかをブロック漁業者協議会で
お示ししました。
それから、後で読んでもらえばいいんですが広島大学小路先生、京都大学益田先生、こ
ういった先生方の指摘として、瀬戸内海のサワラを増やすにはやはりカタクチイワシをは
じめとするサワラの餌となりうる資源の管理をきちんとしないと本格的な回復はないんじ
ゃないかという指摘がなされています。
それについて同じようなことなんですが、灘別にカタクチシラスの漁獲量とかシラスと
カタクチイワシの漁獲量の比、そういったものを灘別に私の方で整理しています。言いた
いことは、シラスの漁獲量が瀬戸内海東部の方で多いものですから、資源としては安定し
ていてもカタクチイワシの影を見ることがどうしても少なくなる。カタクチイワシがいれ
ば、2004年の春に五色で見られたように、カタクチイワシにサワラがつくというふう
なことがありますので、やはりシラスで先取りしてカタクチイワシの影が薄いと、サワラ
が滞留する機会というのは少なくなってくるのだろうと考えています。ただ、シラスとい
うのは非常に大きな漁業を支え、商業的にも価値が高いですから、そっちの方が重要だと
考える行政の方もいるし、漁業者の方もいるわけで、なかなかその辺が難しいところだと
思います。
あと東シナ海、日本海についてはどういった異常現象が見られるかということで1つだ
け言いますと、サワラの東シナ海系群に見られる漁獲量の北への偏りは1999年以降に
日本海の北区で始まりまして、2000年以降太平洋北区、要するに青森の三沢の方や福
島の方で漁獲がかなりあがってきているという情報があります。もう1つ言えば例えば従
来沖縄の魚であるグルクン、これが沖縄での漁獲量が減って、2005年から長崎とか宮
崎で漁獲量が増えていたのが、2008年には福岡で増えているというふうに魚の分布が
更に北へ上がってきているような傾向があります。以上こういったことを瀬戸内海ブロッ
ク漁業者協議会で報告させていただきました。
以上です。
(前田会長)
どうもありがとうございました。
ただいまの説明によりますと、サワラの資源状況につきましては平成19年の資源水準
は低位で動向は減少傾向にあるとのことです。また親魚資源は2歳魚が主体で若齢化し年
齢構成が単純化しているため、再生産や稚魚の生産が悪いと資源に大きな影響を与える恐
れがあるとのことでございます。このため環境や加入の不安定さを考慮すると資源回復計
画での取組強化が望まれるとのご報告でございました。
何かこのご報告に対して質問等がございませんでしょうか。
それではないようですので次に移ります。平成21年度の取組の審議に移ります。
昨年10月の委員会におきまして、休漁期間の変更に関する検討状況の報告がありまし
た。それによりますと伊予灘関係県で休漁期間変更に関する検討を進め、ブロック漁業者
協議会において意見集約を図り、本日の委員会で計画変更について審議したいとのことで
した。
まず事務局より伊予灘の休漁期間の取り扱いを含めた平成21年度の取組について説明
していただきまして、その後、配付資料には含まれておりませんけれども新たな資源管理
体制の構築に向けた検討を行っているということでございますので、その検討条件につい
て報告していただきます。それでは事務局、よろしくお願いします。
(平松計画官)
では、資料につきましてはサワラ資料の1−3でございます。
まず始めに、先ほど会長の方からもございましたとおり伊予灘の休漁期間の変更に関す
る検討状況、検討結果でございますが、前回の委員会では試験操業ですとか既存の研究デ
ータを基にした行政研究担当者会議の検討結果といたしまして、休漁期間を変更しても現
状より漁獲量が増加する可能性が低いということが考えられる等の報告を行い、またこれ
らの結果を踏まえまして伊予灘の関係県におきまして休漁期間の変更案に対する検討を進
めるとご報告いたしました。それらを2月に開催されますブロック漁業者協議会で持ち寄
り、検討を加えて意見の集約を行うということでその後の取組の方針を説明させていただ
きました。
これにつきまして昨年の10月以降、伊予灘関係県の方で検討が行われてきたわけでご
ざいます。2月にブロック漁業者協議会が開催されましたが、その場で伊予灘の関係県と
いたしまして山口県それから大分県、こちらの漁業者協議会の代表委員の方から県内の協
議状況についてご報告がございました。両県ともこの休漁の期間変更については了解する
ということでございました。これらを受けまして2月10日に開催されましたブロック漁
業者協議会におきましては、この伊予灘の休漁期間を15日間後ろの方へずらすという変
更案について了解が得られたというところでございます。これらを踏まえまして本日、来
年度のサワラ計画の取組案ということでまとめさせていただいてございます。
それでは、資料1−3表紙をめくっていただきまして、1ページの漁獲努力量削減措置
(平成21年度案)という地図のページをご覧ください。
内容につきましては、ただいま申し上げましたとおり伊予灘海域での休漁期間につきま
してサワラ流し網漁業(山口・愛媛・大分)としているところですが、こちらの休漁期間
5月16日から6月15日ということにさせていただいております。これが、本年度5月
1日から5月31日までとしていたところからの変更箇所でございます。
その他の海域につきましては、本年度と全く同様の休漁期間として実施したいと考えて
ございます。また、瀬戸内海全域での流し網の目合い規制10.6センチにつきましても
今年度と同様の内容となってございます。来年度の漁獲努力量削減措置につきましては伊
予灘を変更した形でこのような取組で進めたいと考えてございます。
つづきまして、2ページめくっていただきまして種苗生産・中間育成・受精卵放流の取
組、来年度の実施予定を載せてございます。
同様に3ページには広域漁場整備及び漁場環境保全の来年度の事業の実施予定を取りま
とめてございます。放流それから漁場整備、両方につきましておおむね今年度と同じ内容
の実施予定をしてございます。来年度の漁獲努力量削減措置、種苗放流、漁場整備につき
ましてはただいまご説明申し上げました内容で実施したいと考えてございます。
このうち、休漁期間に係ります漁獲努力量の削減措置につきましては休漁期間変更とい
うことでございますので、資源回復計画本文の変更が必要になってまいります。こちらに
つきまして資料の4ページから8ページにかけまして、サワラ瀬戸内海系群資源回復計画
一部変更案という形で新旧対照表のスタイルで載せております。表の右側が現在の回復計
画の文章、左側が変更案になってございます。資料の4ページ、新旧対照表になる部分で
すが、こちらの一番下のところ、漁獲努力量の削減措置の表にあります伊予灘の部分でご
ざいますが、こちらにつきまして現行の5月1日から5月31日という期間を表の左側の
5月16日から6月15日というふうに変更をさせていただきたいと考えてございます。
また、規制措置の内容の変更はこの点のみですが今回の一部変更に併せまして7ページ
にございます海域の定義の中の灯台名につきまして通称名から正式名称に改めさせていた
だくという措置を1ヶ所させていただきたいと考えてございます。変更箇所はその2ヶ所
でございます。
それから資源回復計画におけます休漁等の措置につきましては、これらの措置を担保す
るための瀬戸内海広域漁業調整委員会指示につきましては資料の9ページから11ページ
に案を載せてございます。
こちらの内容につきましては、11ページをご覧いただきたいんですが先ほどご説明い
たしました伊予灘の休漁期間、こちらにつきまして変更後の休漁期間に対応した内容での
設定を考えてございます。
以上が平成21年度のサワラ資源回復計画の措置案でございます。
それから、これから資料はございませんので口頭での説明をさせていただきたいと思い
ますが、このほかに現在資源管理体制の構築に向けた検討といたしまして2つ行ってござ
います。
1つは資源回復計画の取組の強化に関すること、それから2つ目が平成23年度以降の
放流体制の検討に関してでございます。
まず1つ目の回復計画の取組強化に関しましては、サワラ資源の回復に必要な産卵親魚
の確保につきまして、現在の資源水準から考えますと一律に漁獲量を減らすような取組と
いうものは、少ない漁獲量を更に減らすということになるため実現性が困難と考えてござ
います。従いまして、卓越年級群の発生など例年以上の漁獲が見込まれる場合を想定いた
しまして、あらかじめ未成魚の保護による親魚量のかさ上げについて、これらの方法につ
きまして検討しておくことが重要と考えているところでございます。
また、平成20年級群につきましてはある程度の加入量が期待できるということもござ
いまして、早急にそれらの検討を進める必要があると考えているところでございます。こ
のような考え方によりまして、1つの例といたしまして好漁日、漁獲のいい日が2日連続
すれば3日目を臨時休漁にするという取組を想定いたしまして、それらの取組よってどの
ような効果が発現するか、また実際の漁獲の減少がどの程度かというようなことについて
これらの漁獲増加の取り控え効果というものについて検討をしてございます。現在、各地
域の実情に見合った方法というものにつきまして、各府県、地域での検討を行っていただ
くよう行政研究担当者会議、またブロック漁業者協議会において各府県に要請していると
いう状況でございます。これが1つ目の取組強化に関する検討の状況のご報告でございま
す。
つづきまして2つ目のサワラ種苗放流体制の検討状況という部分でございますが、サワ
ラ資源回復計画におきまして種苗放流は漁獲努力量の抑制との一体的な推進が必要とされ
ているところでございます。現在の種苗放流の体制に当たりましては、水研センターの関
与が大きいところでございますが、その水研センターの取組の根拠となります水研センタ
ーの中期計画というものが平成22年度で終了するということ。また、サワラのような広
域回遊種についての国の関与、栽培、放流に対する国の関与を定めております栽培に関す
る基本方針につきましても、平成21年度で終了するということになってございます。
このような状況から、これらの次の基本方針、次期の水研センターの中期計画に瀬戸内海と
しての要望内容等が反映されるよう今年度1月26日の行政研究担当者会議からこの種苗
放流体制、23年度以降の種苗放流体制のあり方について検討を始めたというところでご
ざいます。まだ、検討を始めたばかりでございますので、その具体的内容について、現時
点でご報告できるまでには至っておりませんが、今後、水産庁の本庁また水研センターの
これらの関係する動きを注視しつつ検討の進捗状況に応じまして、適宜ご報告できればと
考えているところでございます。
以上2点口頭でのご報告になりますが、資源管理体制の構築に向けた検討状況について
ご報告しました。これらを含めました来年度、平成21年度の資源回復措置、サワラ回復
計画の取組案と考えてございます。来年度の取組案につきまして、ご審議よろしくお願い
いたします。
(前田会長)
平成21年度の取組の案につきましては、伊予灘の休漁期間についてこれまでの検討を
踏まえ5月1日から5月31日の休漁期間を5月16日から6月15日までに変更したい
とのことでございました。これに伴いまして、資源回復計画を一部変更し本委員会指示に
つきましても変更後の休漁期間に対応した内容により設定するとともに種苗放流等の取組
については本年度と同様の内容で実施したいとのことでございます。
また、後半の新たな資源管理体制の構築に向けた検討につきましては、資源回復計画の
取組の強化及び種苗放流体制の検討に関して行政研究担当者会議等での検討状況及び今後
の検討の進め方について報告がございました。
なお、紀伊水道外域につきましては、2月24日に開催されました「和歌山・徳島連合
海区漁業調整委員会」におきまして、本委員会指示の案が決議されれば本年度と同様の連
合海区委員会指示に従うことが決議されております。
また、宇和海につきましても3月12日に開催予定の愛媛海区漁業調整委員会において
本年度と同様の海区委員会指示を決議する予定となっております。
これから質疑に入りますけれども、まず始めに平成21年度の取組の案につきまして何
かご質問等がございましたらお願いいたします。
ご意見もございませんようですので、それでは「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平
成21年度取組(案、本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員) 会指示(案)につ
いて」承認したいと考えますがよろしいでしょうか。
それでは委員会として「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平成、21年度取組(案)、
本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員会指示(案)について」承認をいたします。
引きつづきまして、第2点目の新たな資源管理体制の構築に向けた検討が行われている
資源回復計画の取組強化及び種苗放流体制の検討状況についての報告がございましたけれ
ども、これにつきましてご質問等がございませんでしょうか。
(高橋委員)
この問題につきましては、この委員会で擁護するというのがいいのかどうかよくわから
ないままに申し上げたいと思います。
行政の方でも将来的な取組というのを検討なさるというようなことでありましたけれど
も、この資源管理についての取組というのは漁業者自身、我々もある意味ではそうだとは
思うんですけれども、今の取組がやっとこさよちよち歩きの状態なんです。これで計画期
間が終わったからおしまいよというのでは、せっかく取り組んだのがほっぽり出されると
いうような気がしてならない。そういう意味では、やはり行政からも当然そういうご意見
が出るんだと思うんですけれども、これは続けてやっていただかないと、せっかく今まで
取り組んできたのが終わってしまうというような気がしますので、国におかれてもこの問
題についてはどうぞ息の長い取組をお願いしたい。
(前田会長)
今後とも水産庁と言いますか、行政サイドでの取組も今までと同様の指導してほしいと
の要望でございます。
何か事務局の方でございますか。
(平松計画官)
今おっしゃられたのは平成23年度まで今の計画期間、5年延長した第2期の計画期間
がございまして、先ほど放流につきましてはそれ以降の体制についていろいろ関係の長期
計画等の進捗に合わせて検討を進めたいという報告をさせていただいております。
後ほど予算の説明の中で本庁から今後の制度的な話も予定しておりますが、サワラにつ
きましても放流だけでなく全体の取組を今後どうしていくかというのは、当然現在の取組
期間の終わりに向けてしかるべきときに具体的な検討を進めていかないといけないとは認
識してございます。その中で一番いいやり方、どのようにやっていくかということを十分
関係の機関とも検討しながら進めていきたいと考えます。
以上でございます。
(前田会長)
どうもありがとうございました。よろしいですか。
ほかにございませんか。
- 17 -
(荒井委員)
回復計画の取組を強化するということで、今1つのアイデアをご提示されましたけれど
も、2日続けていい漁があれば1日休むと、それも1つのアイデアだと思うんですけれど
も、他の魚種あるいは他の海区でこういった取組をやってうまくいってると、あるいはう
まくいくんじゃないかどうかという事例があればちょっとご紹介していただければと思う
んですけれども。
(前田会長)
ございますか、事務局の方で。
(佐藤所長)
実は私ども資源回復計画を最初に立ち上げたときに、これは白書にも載ってますけれども
太平洋のマサバである程度成果が出たんですけれども、要するに魚を増やすということは
獲り控えをするということです。獲り控えをすると何が起こるかというと、ぎりぎりの経
営をやっているというところで更に取るなと、これを要求していかざるを得ない。ところ
が、うまいことに自然の中でたまにボーナスが出ると言ったら変ですが、実は経営に負担
を与えないで資源を回復する道が時々あるんです。それが実は卓越年級群が出たときに、
そのボーナスをできるだけ手をつけないで貯金しておくと。普通の生活費でぎりぎりして
いる人に魚を取るなというのはこれは非常に難しいんです。特に今年さっきの報告にもあ
りましたように、地域によっては相当漁獲量が減っております。平均ですると前年度より
ちょっとかもしれません。だけど播磨灘のように過去に比べて非常に減ってるところ、さ
らに、中間育成までやっている漁業者にとっては、とてもじゃないですけれども受け入れ
られない。そう見ると資源を回復するには、誰に獲る量を減らしてもらうのか。やっぱり
ある程度取れて生活が維持できる人にそこの負担をしてもらおうじゃないかと。それと、
先ほど言いましたように、もしかすると本年度とか20年度に卓越年級群が発生している
可能性がある。そうすれば過去と同じ獲り方をすればたくさん残せるため、昨年と同程度
に我慢をしようと。そういう発想で実は太平洋のマサバのときも経営の維持をすると同時
に、もう一方のボーナスが出たときに欲というものをいかに抑えるか。そこである一定以
上取れた翌日は確実に休むと、それを連続してやったわけです。その成果として漁獲量は
減らないけれど大きな魚が残って翌年から、収益が上がってきたという1つの事例があり
ます。だから、そういう経営と資源の回復をうまくマッチングするタイミングが今回出て
きたんではないかということで、それに期待しているということになりますので、以上で
ございます。
(前田会長)
ありがとうございます。ほかにございませんか。
それでは、サワラ資源回復計画は種苗放流と資源管理の取組を大きな柱としております。
サワラ資源が減少傾向にある中で今後この取組をどうすべきかは、重要なテーマであると
考えますので事務局におかれましては引きつづき検討を進めるようお願いを申し上げたい
と思います。
なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正
式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部
分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承お願い申し上
げます。
(議題2 周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について)
(前田会長)
それでは、再開いたしたいと思います。
つづきまして、議題2の「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部変更
について」に入らせていただきます。
本計画につきましては、前回の委員会で計画延長の骨子について承認しておりますので、
今回は計画延長を内容とした資源回復計画の一部変更について審議を行うこととなってお
ります。
まず、始めに事務局より平成20年の漁獲状況及び本計画の延長について説明していた
だいたあと、計画の一部変更の案についてご審議いただきたいと思います。それでは事務
局から説明をお願いいたします。
(平松計画官)
それでは、周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画に関しまして、資料は資料
番号の2−1から2−3までが関連の資料でございます。
まず始めに資料2−1に基づきまして漁獲状況のご報告、それから資料2−2と2−3
を用いまして延長計画の内容について続けてご説明をさせていただきます。
資料2−1をご覧ください。平成20年の漁獲状況につきまして、先ほどサワラの漁獲
量でもご報告申し上げました平成20年下半期の速報値が2月に公表されましたので、上
半期の数字と合わせまして平成20年の速報値ということでまとめさせていただいており
ます。
こちらによりますと、平成20年は1,751トンということで19年の速報値1,8
70トンに比べまして約6%減少という結果になってございます。それぞれ周防灘計画の
対象魚種ごとの内訳が資料の2−1の下の魚種別の表に載せているとおりでございます。
この中で前年よりも漁獲量が増えておりますのがクルマエビとガザミでございます。一方、
漁獲量が特に減少が大きいのがシャコでございまして320トンが207トンに減少して
いるということでございます。周防灘につきましては漁法別の漁獲量の集計がちょっと時
間を要するということで、確定値は平成18年までということでございまして表に数字を
記載しているとおりでございます。20年の漁獲状況につきましては簡単でございますが、
以上でございます。
つづきまして、計画延長につきまして考え方のご説明をさせていただいて、計画変更案
についてご審議いただきたいと思っております。
まず計画延長の内容につきまして取組の基本的な方針、内容につきまして資料2−2「周
防灘資源回復計画の延長について」という資料にまとめてございます。こちらの資料1ペ
ージをご覧ください。1番といたしまして資源回復措置の継続の必要性ということで、こ
れまでの骨子等でまとめさせていただいた内容を簡単に整理をさせていただいてございま
す。回復計画に取り組んできておりますが、効果も上がっている部分もございますが、引
きつづき取組の継続というものが重要なポイントになっていると考えてございます。この
ような考え方のもと、計画を延長して進めたいということでございますが、まず1ページ
の2番のところに資源回復の目標といたしまして、実施期間と計画の目標を載せてござい
ます。
まず実施期間につきましては(1)にございますように本計画の実施期間は平成25年
度までとするということで、現在の計画が16年11月に作成されて5年間ということで
すので、21年の11月に5年間期間が満了するということでございますが、これを更に
延長するという考えでございます。前回の委員会で骨子の了解をいただいたときにはここ
は平成23年度までとさせていただいておりましたが、回復計画の実施期間が25年度ま
でこの制度としての実施期間が延びるということで、それにあわせて25年度までの延長
としたいと考えてございます。従いまして来年度、21年度からちょうど5年間の取組に
つきまして第2期の取組というような位置づけで今後2ページ以降に記載してございます
内容を中心に進めてまいりたいと考えてございます。
それから、資源回復の目標につきましては現在の計画の目標でございます平成16年の
漁獲量の水準、数字で言いますと2,123トンということになりますがこちらの維持と
いう目標を引きつづき掲げて取り組んでいきたいと考えているところでございます。
それでは、ページをめくっていただきまして2ページ目以降に実際にどのような取組を
行っていくかということで3番の資源回復のために講じる措置というところ以降に取りま
とめてございます。
まず(1)の漁獲努力量の削減措置につきましては、まず?の小型魚の水揚げ制限、こ
れは現在取り組んでおります制限サイズを引きつづき継続実施すると考えてございます。
2つ目の取組といたしまして、シャワー設備の導入がございますがこちらのところで資
料の中にアンダーラインを引いている部分、こちらがこれまでの取組にプラスした部分、
検討の方向性も含めまして今回の計画延長に当たりましてこのような観点の取組を進めて
いくという部分の追加部分をアンダーラインをしております。シャワー設備の導入でいき
ますと、これまでの再放流魚の生残率の向上というものに加えて、持ち帰り出荷する漁獲
物の鮮度維持というもの、これをシャワー設備の導入の目的の中に位置づけとして追加す
るということで取り組んでいきたいと考えております。
現在、山口県、福岡県、大分県の3県のうち大分、福岡が導入済みということで山口県の方で今、順次導入しているという
ところでございますので、未導入船につきまして先ほど言いました再放流魚の生産率の向
上に加えた、漁獲物の鮮度保持というものを目的に加えまして導入促進を推進していきた
いと考えているところでございます。また鮮度維持ということに関しまして現在、夏場に
機能を発揮します簡易冷却装置の現場での応用試験というものも進められておりますの
で、これらの取組も推進していきたいと考えております。それらを含めて効果的なシャワ
ーの活用方法というものも考えつつ、効果的なシャワーの利用というふうなものを推進し
たいと思っているところでございます。
それから、産卵親魚の保護といたしまして実施しております抱卵ガザミの再放流につき
ましては、現在取り組んでいるとおり継続していくということ、また休漁期間の設定につ
きましてはこちらは海底清掃等の漁場環境改善の取組とあわせて実施するという考えを今
後も継続するということで考えてございます。
?といたしまして、漁具の改良がございます。これはこれまでの取組の中でも進めてま
いりましたが、それら試験研究をより推進することを考えておりまして現在幼稚魚の混獲
防止漁具の性能試験も実施されておりますので、このような取組について実用化に向けた
推進を行ってまいりたいと考えているところでございます。
以上が漁獲努力量の削減措置でございますが、回復計画の2つ目の柱でございます資源
の積極的培養措置ということで、これは主に種苗の放流というものになりますがこちらに
つきまして2ページから3ページに記載しております。この回復計画を進めるに当たって
今年度から事業として立ち上がりました資源管理アドバイザー制度等を活用しつつ、この
3県の連携、協力というものによる放流体制の構築というものを推進していきたいと考え
てございます。特にクルマエビにつきましては、山口、福岡、大分の3県で共同した事業
も実施してございますので、これらの事業の推進というものを図っていきたいと考えてご
ざいます。
3つ目の柱として漁場環境の保全措置ということでございますが、こちらは水産基盤整
備事業等の漁場環境改善の事業について取組を引きつづき行いたいと考えております。
資源回復のための措置といたしましては、以上3本柱の内容でございます。次に資料の
3ページの4番にございます漁業経営安定の取組ということでこちらは今後この資源回復
計画によりまして、資源の回復、漁獲の増大というものを進めていく取組にあわせまして
経営的な観点での検討を並行して実施していく。これは今回新たに盛り込んだ内容でござ
います。
大きな柱としましては2つございまして1つがコストの削減ということでございます。
燃油につきましては昨年度非常に高騰いたしまして、こういうコスト削減、特に燃油の使
用の抑制等の取組というものの重要性が出てきておるわけでございますが、このような観
点での操業コストの低減策ということについて検討するというのが1 つでございます。
2つ目といたしまして先ほどのシャワー設備のところでも申し上げましたが、漁獲物の付
加価値向上、単価アップ等に向けた取組ということについて、各種検討をあわせて実施し
ていきたいと考えているところでございます。これら、資源回復措置の取組プラス漁業経
営安定の取組という観点で来年度以降の取組を進めたいと考えているところでございます。
その他、3ページの中段以降にございます5番の公的担保措置、6番の支援策等につき
ましては従前どおりの体制で進めていきたいと考えているところでございます。
最後、資料は4ページになりますがその他といたしまして、これは今までの回復計画の
中でも取組として進めてきたところでございますが、他漁業への取組の拡大というような
部分につきましては現在、カニ籠漁業のカニ籠目合いの適正化試験というものも実施され
て小さなカニ、ガザミですがこれを漁獲しないようにするための検討ということが進めら
れてございますので、そのような取組をこの関連漁業へのアプローチというようなことで
進めていきたいと、このような取組を推進していきたいと考えてございます。このような
考え方のもと、来年度以降の5ヵ年間の取組を第2期の取組として進めていきたいと考え
てございます。
回復計画につきましては今申し上げましたとおり実施期間の延長ということになります
ので、計画変更が必要になります。そちらにつきましては資料2−3、1 枚資料、裏表印
刷しているものでございます。こちらも新旧対照表によります変更案ということで、表の
右側が現行の計画、左側が変更案ということで整理をしてございます。変更箇所としまし
ては、資料2−3の1ページのちょうど中ほどの行に当たりますが、資源回復目標の中で
実施機関に係る部分、現行では当面の5年間としている部分を平成25年度までの間とい
うふうに改めたいと思っております。また、平成16年の漁獲量が統計の数値が公表され
ておりますので2,123トンという具体的な数字を盛り込むということにしてございます。
変更内容は以上の2点ですが、実施期間につきましては1ページ目の一番下の2行にご
ざいますように、もう1ヶ所実施機関が当面の5年間が平成25年度までの間というふう
に記載されている部分がございます。
変更箇所は以上でございますが、2ページ目にございます海域の定義の基点のところに
つきましても市町村合併に伴う市町村名の修正と、灯台等の名称を正式名称に改めるとい
うことで一部記載内容が変わってございますが、実際の基点そのものにつきましては変更
ございません。表現方法の変更をこの計画変更にあわせて行いたいと考えてございます。
周防灘計画の延長の取組内容・方針、それから資源回復計画の一部変更案につきまして
は、以上でございます。
(前田会長)
計画の延長につきましては実施機関を平成25年度までとし、現在実施している漁獲努
力量の削減措置を継続しつつ漁獲物の鮮度維持等の漁業経営安定の取組に検討を進めてい
るとのことでございました。
それでは、ただいまの説明につきましてご質問がございませんでしょうか。
それでは、ないようですので「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部
変更(案)について」承認したいと思いますがよろしいでしょうか。
ありがとうございました。それでは、委員会といたしまして「周防灘小型機船底びき網
漁業対象種資源回復計画の一部変更(案)について」承認をいたします。
なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正
式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部
分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承をお願い申し
上げます。各関係、各委員におかれましては本計画の適切な実施について、よろしくご指
導お願い申し上げます。
(議題3 カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について)
(前田会長)
「つづきまして議題3のカタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について」
に入ります。
まず、20年度の実施状況と資源状況などについて事務局より報告していただきまして、
引きつづいて21年度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。
また、計画作成後4年が経過し、来年3月で計画期間満了を迎える本計画の評価という
ことで事務局より報告していただきます。それでは、本年度の実施状況などにつきまして
事務局から報告お願いいたします。
(中奥資源保護管理指導官)
瀬戸内海漁業調整事務所、中奥です。よろしくお願いいたします。
それでは着席させていただきましてご説明させていただきます。
では、20年度の取組について資料3−1をご覧ください。対象漁業の許可期間は1ペ
ージの(1)に示すとおりでございます。これに対しまして資源回復措置としましては(2)
にあります休漁期間と(3)にあります定期休漁日を設定し取り組まれました。本年度定
期休漁日につきましては広島県が燃油高騰の要因もあり、従来の木曜日に加えて日曜日も
追加実施されました。20年度の操業実績といたしまして(4)にありますとおり瀬戸内
海機船船びき網につきましては広島県は6月13日から10月10日まで、香川県は6月
10日から9月10日まで、愛媛県は6月10日から9月10まで、愛媛県のいわし機船
船びき網では6月10日から8月17日までとなっております。
次に燧灘のカタクチイワシの資源状況です、2ページをご覧ください。資源状況につき
ましては関係3県の広島県、香川県、愛媛県の水産試験研究担当者の方々により資源解析
が行われた結果です。
(1)は漁獲量の動向です。平成18年までは農林水産統計から、平成19年、20年
は共販量からの推定量をグラフにしました。平成20年の漁獲量はカタクチイワシとシラ
スを合わせて1万4,540トンと前年の108%となっております。
(2)は初期資源尾数の動向です。本計画の目標は回復計画開始当初の資源尾数水準、
これは平成12年から16年の平均で346億尾です。この水準と計画期間終了後に同程
度維持することとしております。その基準である資源尾数は、春季発生群の初期資源尾数
を用いることとしています。グラフはその動向について示しております。平成20年につ
いては水準より若干低い値、340億尾で目標の98%となっております。
(3)は初期資源尾数の漁獲率の動向を示しております。グラフのとおり資源量に対す
る漁獲率は(2)の資源尾数をベースに出しているため、このように高い値となります。
それを踏まえて見てみますと、例年86%前後で推移し平成20年も平年並みの値となっ
ております。
(4)は資源状況の考察です。3県の水産試験研究担当者の資源解析、燧灘のカタクチ
イワシ漁獲量及び瀬戸内海系群カタクチイワシの資源評価結果から判断して、資源水準は
中位、動向は横ばいとの評価が出ております。
次に、脂イワシ調査結果について3ページに取りまとめております。本調査は19年度
から関係3県と瀬戸内水研が協力して調査を開始したものです。19年度の結果報告から
脂質含有量と製品単価の急低下との関連から脂質含有量が2%以上のものを脂イワシと仮
定義したことから、今年度も引きつづき調査を行い図1のように脂質含有量と肥満度の間
に正の相関が見られたことから、脂イワシの判定指標として肥満度が利用できると判定し
ました。図1の脂質含有量2%のときの肥満度は約10であり、肥満度10を脂イワシの
発生警戒値とする結果を得ました。
20年度の取組状況については以上です。
(前田会長)
ただいまの説明によりますと、本年度は広島県の定期休漁日について従来の木曜日に加
えて日曜日も追加して実施されたとのことでございました。また、燧灘のカタクチイワシ
の資源水準は中位、動向は横ばいとのことでございます。ただいまの報告について、何か
ご質問等がございませんでしょうか。
ないようですので、つづきまして平成21年度の取組について事務局から説明をお願い
いたします。
(中奥資源保護管理指導官)
21年度の取組案につきましては、資料3−2をご覧ください。
1ページ目、平成21年度の資源回復措置の取組としまして2と3にあります漁期始め
及び漁期終期の休漁、定期休漁日の設定につきまして従来と同様に継続することとしてお
ります。また、漁期始め及び漁期終期の休漁期間の担保措置としまして本委員会指示を平
成20年度と同様の内容で設定したいと考えております。本委員会指示の対象海域は2ペ
ージの図に示しております。3ページには本委員会指示の案を添付しております。なお、
2月12日に開催されましたカタクチイワシブロック漁業者協議会において21年度取組
案及び本委員会指示案につきましては了解が得られております。また、20年度取組でご
紹介しました脂イワシに関する調査につきましても引きつづき瀬戸内水研と関係3県が協
力して続けることにしております。
21年度の取組案につきましては以上です。よろしくご審議お願いいたします。
(前田会長)
平成21年度は引きつづきまして従来と同様の資源回復措置を実施し、本委員会指示に
つきましても本年度と同様の内容で行いたいとのことでございます。また、脂イワシに関
する調査についても引きつづき行われるとのことでございました。
ただいまの説明に対してご質問等ございませんでしょうか。
、「( それではないようですので平成21年度取組案)及びこれに係る本委員会指示(案)
について」承認したいと考えますがよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声)
(前田会長)
委員会として「平成21年度取組(案)及びこれに係る本委員会指示(案)について」
承認をいたします。
それでは、次に本計画も計画作成から4年が経過し、来年度が最終年度となっておりま
す。こうした状況を踏まえまして、事務局から本計画のこれまでの取組に対する評価につ
いて報告していただきたいと思います。では、事務局よろしくお願いいたします。
(中奥資源保護管理指導官)
4年間の取組状況を評価にまとめておりますので資料3−3をご覧ください。
まず、計画の概要といたしましては1ページの2にあるとおり瀬戸内海海域におけるカ
タクチイワシに対する漁獲圧力は経年的に高い傾向であり、現在の比較的安定した加入状
況が悪化すれば資源悪化や漁獲量減少を招く恐れがあるため、現状の水準を下回らないよ
うに資源量を維持する必要があります。そのために、資源回復の目標としまして5年間の
計画期間後に燧灘のカタクチイワシの資源尾数水準を計画開始前の平成12年から16年
の平均と同程度に維持することを目標にしました。講じている措置は休漁期間の設定と、
定期休漁日の設定となっております。
次の3の計画実施状況ですが、6ページ以降に添付しております図表をご覧いただきな
がらお聞きください。まず、漁獲努力量削減措置の実施状況を6ページの表1と表2にま
とめております。
表1では本計画で定められた休漁期間に加えて自主休漁が取り組まれておりますので、
その内容を整理しております。まず、広島県の瀬戸内海機船船びき網漁業の17年度を例
に説明しますと、表にあります操業開始日とは計画上6月10日から操業できるところを
実際に操業を開始された日が6月13日であり、定められた休漁期間に加えて6月10、
11、12と3日間の自主休漁を実施されたことから(A)の自主、休漁日数3という整
理をしています。同様に操業終漁日では11月30日まで操業できるところを実際は10
月31日で終漁されたということなので、定められた休漁期間に加えて30日の自主休漁
を実施され(B)の自主休漁日数30で、17年度の広島県の合計自主休漁日数は33日
となります。そのほか、表にまとめた以外にも天候や魚の状態で臨時休漁も適宜実施され
ております。
表2では定期休漁日について取りまとめました。平成20年度の広島県は先ほども報告
しましたとおり、燃油高騰の要因もあり木曜日のほか暫定的に日曜日が追加されました。
なお、本計画に定められました休漁期間に対しては本委員会指示が毎年設定されておりま
す。また、平成19年度に愛媛県宮窪町漁協所属のいわし機船船びき網漁業1ヵ統の本計
画参加により、対象海域拡大の一部変更を行いました。5ページの図1が拡大しました対
象海域になっております。
次に、支援事業について7ページ表3にまとめたとおり愛媛県で平成18年度から延べ
54隻日、494万6千円の休漁漁船活用支援事業で漁場監視が実施されております。以
上が漁獲努力量削減措置に関する実施状況です。
次に関連調査としまして、資源評価については関係3県と瀬戸内海区水産研究所が協力
して行っており、8ページの表4にあるとおり卵稚仔調査や表5の脂イワシに関する調査
が実施されております。餌料環境調査、脂質含有量調査、発生要因分析などを行い、基礎
データの収集や肥満度を利用した脂イワシの判定指標の検討など研究が行われておりま
す。
次に資源動向と漁獲量の推移ですが、9ページの図2をご覧ください。燧灘のカタクチ
イワシの資源動向は春季発生群の初期資源尾数について平成5年以降のデータをもとに推
定されております。グラフに示すとおり平成5年以降は減少傾向で、平成8年に138億
尾と最低の水準になりましたが、その後、回復傾向で平成12年以降は300億から40
0億尾の水準を維持しております。
次に漁獲量ですが、10ページの左上の図3をご覧ください。燧灘での近年のシラスを
含む漁獲量は1万1千トンから1万7千トンで推移しており、平成12年から20年の平
均漁獲量は1万4千トン程度となっています。
次に県別に見ますと、図4の広島県では平成15年に3千トンを超えましたが、その後
は1千トン前後で推移し、図5の香川県では平成17年に1万トンを超えましたが、その
後はおおむね7千トンで推移しております。図6の愛媛県では3千トンから5千トンで推
移しております。
また、各県の銘柄別共販量とその割合から漁獲の主体を見てみますと、瀬戸内海機船船
びき網漁業では11ページの図7からご覧ください。上段のグラフが銘柄別の漁獲量、下
段が銘柄別の構成割合になっております。図7の広島県ではチリメンを主体に漁獲してお
り、図8の香川県では中羽を主体に小羽から大羽を漁獲、12ページの図9の愛媛県では
中小羽を主体に小羽から大羽を漁獲、図10のいわし機船船びき漁業ではカエリを主体に
チリメンを漁獲しています。このことから、漁獲対象が広島県はチリメン主体、香川県及
び愛媛県は煮干加工向けのサイズを主体に、いわし機船船びき網漁業においてはカエリ、
小羽を主体にそれぞれ漁獲しているようです。
次に目標達成状況ですが、戻りますが9ページの図2をご覧ください。本計画の資源回
復目標は、5年間の計画期間後に燧灘のカタクチイワシの資源尾数水準を計画開始前の5
年間、平成12年から16年の平均と同程度に維持することとしております。この指標と
して用いる資源尾数は、燧灘の資源評価で算定された初期資源尾数です。図2に引いてお
ります破線は回復目標の指標であります平成12年から16年の平均値である346億尾
を示し、計画開始後の平成17年から折れ線を太線で表しております。達成状況について
はご覧いただいているとおり、平成20年の資源尾数は340億尾で目標である346億
尾の98%であり目標水準で安定しております。
最後に評価と今後の課題としてまとめておりますので、本文4ページをご覧ください。
本計画を4年間実施してきた評価として、現時点でカタクチイワシは産卵親魚量と加入量
の間に明瞭な関係が認められていないため、資源管理措置の効果を定量的に判断すること
はできませんが、初期資源尾数が安定的に確保され漁獲量が一時期の低水準より回復し安
定していることから措置はおおむね妥当であると考えます。また、瀬戸内海区水産研究所
の指導のもと、関係3県の協力で資源評価体制が確立され、またその体制により脂イワシ
の判別法で化学分析を必要としない簡易な肥満度を活用できることが明らかにされたとこ
ろであり、操業方法の改善に寄与することも期待できます。
次に今後の課題ですが、漁獲努力量削減措置は評価で述べましたとおり一定の効果があ
ったと考えますが、今後の資源量の維持、安定を考えますと資源予測の精度を高め資源動
向に即した措置について検討が必要であります。また漁獲動向や脂イワシの発生により製
品価格の年変動が大きいため脂イワシ発生のメカニズム解明に期待されていますが、その
研究成果をいかに現場で活用していくかが重要であります。更に、脂イワシの発生による
価格低下から漁獲金額の向上の取組として、漁獲物の付加価値向上や操業及び加工コスト
の削減などについて検討を行い漁業経営の安定に向けた取組を推進することが重要である
と考えます。以上が本計画の評価ということで、4年間の取組状況を取りまとめ最後に評
価と今後の課題としてまとめました。
本計画の計画期間は来年度末までとなっておりますが、今後の課題にありますように、
燧灘のカタクチイワシに関する資源管理については引きつづき検討していきたいと考えて
おりますので、関係県や漁業者の方々と今後話し合いを深めていく予定としております。
(前田会長)
説明していただきましたけれども、現行の計画の評価を簡単にまとめますと、初期資源
尾数が安定的に確保されたこと及び漁獲量が一時期の低水準より回復し安定しているこ
と、また本計画によりいわし機船船びき網漁業者を加えた体制が整えられたなどの評価を
行うとともに、今後の課題としては資源量の維持、安定に加えて漁業経営の安定に向けた
取組の推進が重要であると以上のような内容であったかと思います。
ただいまの説明につきましてご質問がございましたら。
ご意見等もございませんか。それでは事務局におかれましては今後、関係県、漁業者等
と十分協議をしていただきまして22年度以降の燧灘におけるカタクチイワシの資源管理
について、よろしく検討をお願いいたしたいと思います。
(議題4 トラフグ資源管理の検討状況について(報告))
(前田会長)
つづきまして、議題4「トラフグ資源管理の検討状況について(報告)」につきまして、
事務局より報告していただきたいと思います。
(森資源課長)
瀬戸内海漁業調整事務所で資源課長を担当しております森と申します。
資料4を用いましてトラフグ資源管理の検討状況についてご報告いたします。座ってご
報告させていただきます。
「トラフグ資源管理に関する主な取組」としまして、まず「瀬戸内海関係府県との会議
等」でございます。この中の「関係県との意見交換会」についてでございますが、瀬戸内
海のトラフグ資源管理の検討は、トラフグ資源量が多く重要度が高い愛媛県、山口県、大
分県、広島県の瀬戸内海西部4 県から進めてはどうかとの瀬戸内海区水産研究所担当者
からの助言を受けまして、瀬戸内海西部4 県と意見交換会を開催することにしております。
なお、意見交換を終えた大分県、愛媛県、山口県3県においては今後トラフグの資源管
理につき何らかの対応をしていかざるを得ないとの認識であり、引き続き関係漁業者の意
見等を聞くため浜回りを行う方向で検討中です。
その下、「瀬戸内海区水産研究所との打合せ」につきましては、昨年11月と12月に
2回実施しております。瀬戸内海区水産研究所担当者からは情報提供や助言をいただいて
おります。主なところをご紹介しますと、1つ目はトラフグの資源水準は極めて悪いとい
うこと、2つ目は九州・山口北西海域では既に資源回復計画に取組んでおり、同じ系群を
漁獲している瀬戸内海においても資源管理を進めることが重要であること、3つ目は九州、
山口関係県からは瀬戸内海における資源管理の取組への要望が大きいこと、最後に特に漁
獲量の多い愛媛県、山口県、大分県、広島県の資源管理の取組が重要であることなどです。
次に「九州・山口北西海域関係機関との会議等」でございますが、まず「九州漁業調整
事務所との情報交換」についてですが、昨年の12月、九州漁業調整事務所で実施いたし
ました。九州漁業調整事務所担当者から、九州・山口北西海域のトラフグ資源回復計画の
取組状況等について説明を受けるとともに、今後は更に一層、両事務所が情報交換を密に
していくことを確認しております。
最後に「トラフグWG会議関連」と、一番下の「九州・山口北西海域トラフグ資源回復
計画に係る行政担当者会議」についてですが、九州・山口北西海域においては研究者の会
議であるトラフグWG会議と行政担当者会議が開催されておりますが、九州・山口北西海
域におけるトラフグ資源の状況や資源回復計画の取組状況等を把握するため、これらの会
議には瀬戸内海漁業調整事務所から担当者が出席しております。
平成20年10月21日開催の第17回瀬戸内海広域漁業調整委員会以降の主な取組は
以上のとおりでございます。
引きつづき、他海域の状況も把握しつつ、また関係県のご協力を得つつ、更には関係漁
業者のご意見を踏まえつつ検討を進めてまいりたいと考えております。また検討状況につ
きましては適宜本委員会に報告を行いたいと考えております。
(前田会長)
ただいまの報告につきまして何かご意見、ご質問はございませんか。
それでは、トラフグの資源水準は低位横ばいとの資源評価がなされております。トラフ
グの資源管理につきましては、こうした資源評価を踏まえまして引きつづき検討を進めて
いただくようお願いを申し上げます。
(議題5 平成21年度予算について)
(前田会長)
それではつづきまして、議題5の「平成21年度予算について」に入ります。水産庁管
理課さんより説明がございます、よろしくお願いいたします。
(渡邉管理課課長補佐)
水産庁管理課の渡辺と申します。
私から平成21年度予算につきましてご説明申し上げます。資料の5の1ページをご覧
ください。
21年度予算に関しましては、その前提となる資源回復計画につきまして新たな方向性
が確定をいたしました。先ほど高橋委員からもご発言がありましたけれども、今回この2
1年度予算に関しましては、この資源回復計画の今後の展開についてということを中心に
ご説明を申し上げます。
まずこの1ページ目の一番左側をご覧いただきたいんですが、現行の資源回復計画、今
平成14年から取組の開始をいたしまして現在64計画で実施中、5計画で作成中という
ことでございまして、資源の回復が必要な魚種等を対象に漁獲努力量の削減等を実施して
いくということで取り組んできております。計画開始から時間が大分たってきておりまし
て、中には資源の回復の兆しが見られつつある計画も出てきているところでございまして、
そうしたものについてはこの資料の一番右側にございますけれども、最終的には経営支援
を行わない形で自立的に、漁業者、あと行政、研究者がともに資源管理を行っていくとい
うものが最終的な理想になるわけでございます。とは言っても、いきなり自立といっても
さまざまな課題があります。そうした課題も踏まえまして、水産庁としてはどのような形
で取り組んでいけば最終的に自立というようなものが有効に、効果的に達成できるのかと
いうものを当然考えていかなければならないという課題があると考えております。そうし
たことを踏まえて今回、新たに一番右側の右から1つ戻っていただいたところにポスト資
源回復計画というものがございますけれども、最終的に自立に向けた準備期間ということ
でより効果的な取組というのもどのようなものがあるのかというものを考えながら、これ
までと同様の取組、そしてこれまでと同様の形で支援を行う準備期間として、ポスト資源
回復計画というものを新たに位置づけて推進をしていきたいと考えてございます。
中にポスト資源回復計画のところにも書いてありますけれども、基本的に実施機関は原
則5年間取り組んでいきたいと考えておりまして、繰り返しますけれどもポスト資源回復
計画の下の部分に矢印が出ておりますが、これまでと同様に漁獲努力量の削減措置である
とか種苗放流の積極的な推進、漁場環境の保全措置等に対する支援を引きつづきやってい
きたいと考えております。
また、こうしたことに加えまして、これまで既存の資源回復計画につきましても現在の
ところ平成18年度に着手したものに作成を限るということにしておったわけでございま
すけれども、これまでさまざまな作成に対する要望等もございましたので、そうしたこと
も踏まえまして今後また新たに資源回復計画の作成についても可能にしていくことといた
しましたのであわせてご報告をいたします。
資源回復計画につきましても、努力量の削減措置等に対する支援というものを当然なが
らこれまでと同じように行っていきたいと考えております。
なお、ポスト資源回復計画に移行するに当たってこれまでにやってきた取り組みがどう
だったのか、また今後最終的な自立に向けてどのような取組が有効でかつ取り組み可能な
のかというようなものを当然評価検討していかなければいけませんので、そうしたことを
するために左側の2つ目のところにポスト資源回復計画移行調査というものがございます
けれども、そのための予算というものも今回新たに確保をいたしましたのであわせてご報
告をいたします。
このほか平成21年度予算につきましては、繰り返しますがこれまでと同様に漁業者協
議会の開催であるとか、資源回復計画の普及・啓発の取組、また漁獲努力量の削減、種苗
放流、漁場環境保全といったものに対す支援措置というものも引きつづき確保をいたしま
したので、引きつづきご活用をいただければと思っております。
また、2ページ以降にはそうした各事業のPR判を添付しておりますのでご参照いただ
ければと思います。
以上、簡単ではございますけれども平成21年度予算につきましてご説明を終わります。
以上でございます。
(前田会長)
どうもありがとうございました。
何かご質問といいますか、ございませんでしょうか。
(議題6 その他)
(前田会長)
ございませんか、それでは議題5の「その他」に入りますけれども、せっかくの委員会
でございますので何か取り上げる事項等はございませんでしょうか。
よろしいですか。それでは事務局の方から委員の任期及び次回の委員会の開催予定など
についてご説明お願いいたします。
(馬場調整課長)
瀬戸内海広域漁業調整委員会の現在の委員の任期は平成17年10月1日から4年間、
今年の9月末日までが任期となっており、次回の委員会につきましては緊急開催の必要が
なければ例年どおり10月ごろに開催したいと考えております。
委員につきましては、海区委員の代表については改めて選定していただき、また大臣選
任委員につきましても改めて選任し直した上で開催させていただく予定です。
委員の皆さまには大変お世話になり、まことにありがとうございました。
なお次回の委員会の日時、場所等につきましては改めて事務局より新委員さんに連絡さ
せていただきます。以上でございます。
(閉会)
(前田会長)
ありがとうございました。
馬場課長さんからお話がございましたとおり、今日、出席していただいておりますメン
バーでの委員会はこれで最後になろうかと思います。委員の皆様方、4年間大変ご苦労さ
までございました。この4年間に当委員会で取り上げられましたいろいろな課題に取り組
んでまいりました。そして、その課題に対しましてそれぞれ一定の成果を上げることがで
きました。これ、一重に委員皆様方のご尽力の賜であると感謝を申し上げる次第でござい
ます。
今後とも委員皆様方にはご健勝で、そしてまたそれぞれのお立場、またそれぞれの分野
でご活躍していただくことを心からご祈念申し上げるものでございます。
それでは、これで本日の会を閉じたいと思いますが、各委員さん、また、ご臨席の皆様
には本委員会の開催へのご協力ありがとうございました。
また、議事録署名人の山本委員さん、原委員さんにおかれましては後日議事録が送付さ
れると思いますのでよろしくお願いを申し上げます。
それではこれをもちまして、第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会を閉会いたしたいと
思います。どうもありがとうございました。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/s_kouiki/setouti/pdf/s_18.pdf
1.日時
平成21年3月3日(月)14時00分
2.場所
神戸市中央区下山手通5−1−16パレス神戸2階「大会議室」
3.出席者指名
?出席委員
糠善次/ 川本信義/ 山本正直/ 小田英一
福池昌広/ 高橋昭/ 前田健二/ 宮本憲二
藤本昭夫/ 坂井淳/ 原一郎/ 荒井修亮
以上12名
臨席者
水産庁資源管理部管理課課長木實谷浩史
課長補佐渡邉顕太郎
九州漁業調整事務所次長佐藤愁一
独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所部長岩本明雄
資源管理研究室長永井達樹
研究員片町太輔
中央水産研究所主任研究員石田実
和歌山海区漁業調整委員会事務局長田上伸治
大阪海区漁業調整委員会課長補佐狭間文雄
専門委員小菅弘夫
大阪府環境農林水産部水産課課長補佐亀井誠
兵庫県農政環境部農林水産局水産課資源管理係主査峰浩司
兵庫県農政環境部農林水産局水産課漁政係主査森本利晃
岡山海区漁業調整委員会次長佐藤二郎
広島海区漁業調整委員会専門員山根康幸
山口県農林水産部水産振興課主任岡田浩司
徳島県農林水産部水産課技師西岡智哉
香川海区漁業調整委員会副主幹宮川昌志
香川県農林水産部水産課課長補佐井口政紀
技師益井敏光
愛媛県農林水産部水産局水産課資源管理担当係長加藤利弘
愛媛県農林水産研究所主任研究員河本泉
主任研究員関信一郎
福岡県豊前海区漁業調整委員会事務主査竹馬悦子
大分海区漁業調整委員会事務局長日隈邦夫
大分県農林水産部水産振興課副主幹大塚猛
愛媛新聞社大阪支社編集部長芝充
瀬戸内海漁業調整事務所所長佐藤力生
調整課長馬場幸男
資源課長森春雄
指導課長小林一弘
資源管理計画官平松大介
資源保護管理指導官中奥美津子
調整課許可係長酒井仁
調整課調整係玉城哲平
資源課資源管理係長松本貴弘
資源課資源増殖係長萩原邦夫
資源課漁場整備係正岡克洋
4.議題
1.サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について
2.周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について
3.カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について
4.トラフグ資源管理の検討状況について
5.その他



5.議事の内容
(開会)
(馬場調整課長)
ただいまから第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会を
開催いたします。
それでは前田会長、議事進行をお願いいたします。
(挨拶)
(前田会長)
さて、本日の委員会ではサワラ瀬戸内海系群資源回復計画、周防灘小型機船底びき網漁
業対象種資源回復計画、燧灘カタクチイワシ資源回復計画について平成20年度取組の実
施状況と資源状況についての報告をしていただきまして、また平成21年度の取組などに
ついてご審議いただくことといたしております。
更にはトラフグ資源管理の検討状況、平成21年度予算についてもご報告いただくなど
盛りだくさんの内容となっております。
また、ご案内のとおり委員の皆様におかれましては現在の委員の任期が平成17年10
月1日から4年間、今年の9月末日までが任期となっております。緊急の予定がなければ
本日が最後の委員会になろうかと思います。委員の皆様におかれましては最後まで活発な
ご議論をお願い申し上げます。
(木實谷管理課長)
ご承知のとおり広域漁業調整委員会でございますけれども、都道府県の区域を越えて分
布回遊する資源の適切な管理を目的として設置されまして、国が作成する広域の資源回復
計画を中心としてご審議をいただいているところでございます。
現在、全国で18の広域計画そして46の地先計画が実施されておりまして資源回復の
ための取組が全国的に展開されてきているところでございます。瀬戸内海を管轄いただい
ております本委員会の関係では現在までに3つの広域計画が作成実施されているところで
ございますけれども、皆様方の不断のご努力により資源の回復が更に図られることを期待
しているところでございます。
改めて申し上げるまでもなく水産庁といたしましても、この資源回復計画につきまして
は主要施策の1つでございまして今後とも一層推進していくということにしているところ
でございます。現在取り組んでおります資源回復計画につきましては、徐々に回復が見ら
れ始めている計画もございまして、このような資源については将来的には漁業者がみずか
らの力で管理していくような方向にもっていくというのがこれからの課題ではないかとい
うふうに考えているところでございます。
一方で、漁業経営を取り巻く情勢につきましてはご承知のとおりいまだ予断を許さない
状況にございますけれども、適切な資源管理に取り組み水産資源の維持回復を行っていく
ことは、将来的に活力ある漁業構造の確立にもつながっていくものと考えておりまして、
資源管理を目的として設置されました広域漁業調整委員会の役割は一層期待されるものと
考えているところでございます。
なお、広域漁業調整委員会につきましては委員の皆様の任期が一期4年となっておりま
して、現在第2期目の最終年を迎えているということでございます。平成13年に漁業法
が改正され広域漁業調整委員会制度が設けられ、その中で資源回復計画を中心とした課題
に鋭意ご尽力を賜りました皆様のおかげで、資源回復計画も今や全国的な展開になってい
るところでございます。これまで各委員の皆様方が払ってこられましたご努力に対して重
ねて御礼申し上げますとともに、残されました半年の期間におきましても資源管理、漁業
調整といった課題に対しまして引きつづきご支援、ご協力をお願いする次第でございます。
本日はさわらの資源回復計画を始め、盛りだくさんの議題となっているというふうに承
知しております。皆様の有意義なご審議が行われまして、今後さらに瀬戸内海における資
源管理が推進されますよう祈念いたしまして、簡単ですけれども開会のあいさつとさせて
いただきます。
(資料確認)
(前田会長)
それでは、本日使用いたします資料の確認を行いたいと思います。事務局よろしくお願
いします。
(馬場調整課長)
それでは、お手元にお配りしております資料でございますが、まず議事次第、委員名簿、
出席者名簿それから本日の会議での資料としまして資料1−1から1−3までサワラの資
源回復計画関係の資料。資料2−1から資料2−3まで周防灘小型機船底びき網資源回復
計画の資料。資料3−1から3−3までがカタクチイワシ資源回復計画の資料。資料4ト
ラフグ資源管理に関する主な取組。資料5平成21年度予算関連資料がございます。それ
から参考資料といたしまして瀬戸内海で行っている広域種の資源回復計画等に関します資
料をホッチキスどめで配付しております。ざいます。
(議題1 サワラ瀬戸内海系群資源回復計画について)
(前田会長)
それでは早速、議題1「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の一部変更について」に入り
ます。
まず始めに20年度の実施状況について事務局より報告していただき、次に瀬戸内海区
水産研究所からサワラの資源状況などについて説明をしていただきます。その後、21年
度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。
それでは本年度の実施状況について事務局から報告をお願いいたします。
(平松資源管理計画官)
瀬戸内海漁業調整事務所資源管理計画官をしております平松でございます。
まず資料1−1を用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。座って説明を
させていただきます。
サワラ資源回復計画の平成20年度の実施状況につきまして、資料1−1の表紙をめく
っていただきますと漁獲努力量削減措置実施状況図1ページがございます。こちらの実施
状況図から資料の5ページまで、種苗放流それから漁場整備等の実施状況につきましては
前回の委員会での報告内容と重複いたしますのでここではご説明を割愛させていただきま
す。
資料の6ページをご覧いただきたいと思います。こちらに平成20年の漁獲量の速報値
を載せてございます。6ページの1番の漁獲量の表の欄外、右側に速報値として括弧書き
で各年の数量を書いているところでございます。こちらの数値につきましては、農林水産
省の統計部が半年ごとに速報値として集計しております数値の平成20年の上半期、下半
期の合計の数字を掲載させていただいております。平成20年につきましては、瀬戸内海
の漁獲量が752トンということで集計をされてございます。これと同じ速報値の平成1
9年の数字を見ていただきますと803トンということで速報値の対前年比が94%、マ
イナス6%ということになってございます。私どもの事務所の方で各府県の担当の方から
漁獲状況を聞き取っております情報を整理いたしますと、やはり同様に数%前年を下回る
というような情報をお聞きしてございます。こちらにつきましては、確定値はもう少し時
間が経ってから出るということでございますが、平成20年は平成19年の漁獲量の確定
値1,081トンを若干下回るのではないかと想像をしているところでございます。
平成20年の漁獲量の統計の数字につきましては以上でございますが、6ページの2番、
下の方ですがこちらの方には当広域漁業調整委員会指示で漁獲量の上限が定められており
ます。はなつぎ網、さわら船曳網、サゴシ巾着網、こちらの漁獲量の報告が各県からござ
いましたので、その数値を掲載させていただいてございます。それぞれ表にございます制
限値以内での操業が実施されたというところでございます。
漁獲量については以上でございますが、次に資料の7ページに岡山県が今年度実施いた
しました試験操業調査の結果、それから8ページから9ページには同じく香川県で実施さ
れました試験操業調査の結果を載せてございます。
まず、7ページの岡山県の調査結果でございますが今年度、昨年の10月に試験操業が
3回実施されてございます。真ん中の2番の試験操業結果のところの平成20年の欄をご
覧ください。3回の試験操業によりましてサゴシが197尾漁獲されております。その下、
1隻あたりのCPUEも65.7ということで、それぞれ平成19年の結果を上回る結果
となってございます。197尾の漁獲されたサゴシのうち、放流魚がどれだけ含まれてい
たかというものにつきまして7ページ一番下の表3に漁獲サゴシのデータと右側に放流さ
れたサワラのデータの結果を載せております。平成20年につきましては、197尾のう
ち放流されたものが1尾ということで混獲率は0.5%という結果になってございます。
昨年、一昨年と比べて混獲率が非常に低い結果というのが今年の特徴でございます。
同様に8ページから9ページの香川県の調査結果も傾向といたしましては、ただいまの
岡山県と同様の傾向となってございまして、まず8ページの2番の漁獲状況の1番下の右
端、平成20年の結果といたしまして3回の試験操業で107尾のサゴシが漁獲され、1
隻あたりの漁獲実数も17.8尾ということでそれぞれ前年を上回っているという結果で
ございます。また9ページに漁獲されたもののうち放流されたサワラがどれだけ含まれて
いたかということで表になってございますが、こちらの平成20年のところをご覧いただ
くと、左側の漁獲サゴシ107に対して放流サワラの尾数が1尾ということで混入率が約
1%という形になってございます。それぞれ傾向といたしましては、先ほどの岡山県と同
様な傾向になっているというところでございます。
このように両県とも試験操業での漁獲は昨年よりも多いということ、それから全体の漁
獲の中に占める放流されたサワラの割合が少ないということ、相対的に見ると全体の天然
のサワラ加入が多いということを示す結果となってございます。ただ、近年では加入が卓
越いたしました平成14年ほどの結果にはなっていないというところがございます。若干
漁獲がいいのではないかというような推定もしておりますが、これらの加入状況につきま
してはまた後ほど瀬戸内海区水産研究所の方からの報告にも触れられますのでそちらに譲
りたいと思います。
岡山県、香川県の両県で実施されております試験操業こちらにつきましては、播磨灘の
休漁期間に実施されるものということで、本委員会指示との関係により事前に委員会へ調
査計画の報告、また結果の報告を行うということにされております。平成21年度につき
ましても今年度と同様に調査が計画されておりまして、資料の10ページ、11ページに
それぞれ来年度の調査計画が提出をされていることをご報告いたします。
それから平成20年度の実施状況、最後になりますが資料の12ページ一番後ろでござ
いますが、TAE管理の実施状況を取りまとめてございます。府県別に数字が書かれてお
ります表の一番右端に全体の合計値といたしまして、設定された努力量が12万3,67
4隻日に対しまして平成20年度のTAE管理期間での操業隻日数が2段目の1万5,9
13隻日となってございます。設定値に対する割合といたしましては13%となっており
まして、こちらの出漁隻日数につきましては平成15年度にこのTAE管理を開始して以
降、最も少ない値ということになってございます。
簡単ではございますが平成20年度、本年度のサワラ計画の実施状況についての説明は
以上でございます。
(前田会長)
ただいまの報告につきまして何かご質問はございませんでしょうか。
それではご質問もないようですので、つづきましてサワラの資源状況につきまして瀬戸
内海区水産研究所の永井室長さんより説明をお願いいたします。
(永井室長)
図は漁獲量の経年推移です。横軸が年、縦軸が千トン単位で示した漁獲量です。青が瀬
戸内海の東部、紀伊水道から備讃瀬戸まで、赤が燧灘から伊予灘、あるいは周防灘までの
西部を示します。漁獲量は一番多いときで6千トンを超えましたが、1986年をピーク
に減ってきました。1998年に香川県、岡山県、兵庫県が自主規制を始めてから、徐々
に漁獲量は回復してきて、2000年からは資源回復計画が行われているところです。
2007年の漁獲量は図では1,108トンと記入しておりますが、先ほどの平松さん
の説明で新しい推定値は1,081トンとなっています。漁獲物の年齢を見ますと昔は3
歳、4歳をとっていたのですが、1980年代に入ってから2歳、3歳、1990年代に
入ると1歳、2歳が中心となり、漁獲物の低年齢化が進んいます。とり方としては悪くな
ってきています。
次に資源量の推移ですが、縦軸に漁獲物の年齢組成を基に資源計算して求めた資源量の
経年推移を示しました。一番多いとき1987年で1万6千トンくらいあったものがずっ
と減ってきて、2007年には2,282トンと1987年の14%に減っています。そ
の後、資源量は少し回復してきましたが、ここ4年ほどやや減少ぎみで推移しています。
一時の悪いときは脱したけれど、やや減りぎみで推移しています。
それから資源量に対してどのくらい漁獲しているかという漁獲割合を赤で示しておりま
すが、一時に比べてその割合が高くなってきており、漁獲圧力が増してきています。
次に親魚量(トン)と加入尾数の関係です。横軸に親の資源量をとりまして、縦軸にそ
の年に生まれて秋に加入したサゴシの資源尾数をとっています。図を見ると、親が多いほ
ど子供も多く加入していることがうかがわれます。両者に直線の関係を当てはめると青い
ラインになります。最近年の1998年以降を切り出してみると右の図ですが、同じブル
ーの直線で示していますが、これは2つの図で同じものです。要するに親が多いと子供も
多い、ただ2002年というのは親がそれほど多くなかった割には加入がよかった、強い
年級が生まれてきた。これに対し2004年は親が多かったけれど、期待したほど子供が
生まれてこなかったわけです。いずれにしても最近はこの直線より少し上に点がくるいい
傾向があるのですが、それが親の増加につながっていない。というのは0歳秋から1歳の
間の魚がまだ小さいうちに漁獲されて、親の増加につながっていないと言えると思います。
先ほど2004年は親が多かった割に子供の生き残りが悪かったということを言いまし
たが、その理由として1つ考えられるのはこの年には御承知のように6月から10月に台
風が10個来襲して史上最高ということがありました。この年サワラの卵が多かったとい
うことがネット調査でわかっておりますが、仔魚が少なかった。小さいうちに海が時化て
魚の生き残りが悪かったのかなと思っています。
それから2006年については、2005年の12月から40年ぶりの低温という厳し
い冬でして、表面の水温がこれは大阪湾の例ですけど例年に比べて5度くらい低かった。
その影響がずっとサワラの産卵期まで持ち越してきまして、サワラの産卵時期は開始が遅
れましたが、逆に低温のため産卵の終わりが細く長く続いたという特徴があります。漁獲
の経過や年齢別の漁獲の状況から見て、2006年は非常に低温で、産卵に影響は受けた
が、結果として細く長くつづいた産卵で2006年の加入はそれほど悪くなかったと理解
しています。
いろいろと環境が不安定な例を示します。図の横軸が1月から12月の平年の水温の平
均値ですが、それに対して2006年とか2007年がどうかと比べました。香川県の1
0メートル水温の平年偏差ですが、海域は幾つかあります。3つほどまとめて言いますと、
特徴として2006年は先ほど言ったように平年を下回る水温がずっと続き、3月に平年
値を少し超える時がありますが、低温の年でした。2007年は逆に平年より非常に暑く
て、一番高い時は平年偏差より2度くらい高い場合も見られました。魚の場合1度水温が
高いと人間で言えば5度とか10度に相当すると言われています。水温がかなり高いとい
うことがサワラの仔稚魚の生産率を低下させていないか、つまり2007年生まれの生き
残りがどうだったかということを考える上で、水温が高かった影響を考えていかないとい
けないと思います。
資源評価のまとめとして、2007年の資源量は2,282トンで1987年に比べて
14%と低位です。それから2007年の資源水準は低位で過去5年の動向は減少、生物
学的に望ましい漁獲の係数であるF30%は、現状の漁獲の係数に比べて41%、つまり
現状の漁獲圧力が望ましい状態に比べて非常に高い。望ましいというのは生物学的にサワ
ラにとって優しいという意味なんです。現状はちょっと漁獲圧力が高いと評価しています。
それから2007年の加入は生き残りが悪かったかもしれないということで少ない恐れが
あると考えています。このように特徴的な年の状況を言いましたが、環境が不安定に推移
することが多いので、加入が環境の影響を受けやすいということが最近続いていると考え
ています。
次は漁獲量の動向を図にしたものですが、2008年の東西別漁獲量、左側の柱が春漁、
右側が秋漁、高さが漁獲量、それから赤が全年を下回っている場合、青が前年を上回って
いる場合を示しています。ですから東部の場合春漁は前年を上回って1.1倍、秋漁は0.
6倍でした。西部の場合は1.0の赤ですから前年をやや下回ったもののほとんど1に近
い、秋は1.8倍と秋が良かったことを示します。
図は春漁、秋漁を府県別に示したものです。瀬戸内海の内の方で春も秋も青のところが
見られますが、外側では秋が青だけれども、なかには例えば徳島県のように前年比秋が0.
6倍というところもあります。兵庫県は春も秋も0.6倍、大阪府は0.2倍、0.4倍
で、大阪湾あるいは播磨灘のあたりはよくなかったことが分かります。
次は4月から7月を春漁と定義しまして、その東西別の割合を示しています。今度は左
側がサワラ銘柄、右側がサゴシ銘柄の漁獲量です。東部では春にサワラは1.1倍、サゴ
シは1.0倍、合計163トンでした。西部ではサワラが1.1倍、サゴシが0.5倍で、
春サゴシが西部で悪かった。次の図は府県別に示したものですが、サワラでは香川、広島
で前年を上回って、大阪、兵庫などで下回った。サゴシでは香川、岡山、広島で前年を上
回り、兵庫、愛媛で下回った。
次に8月から12月を秋漁として示しています。8月から12月には東部のサワラで前
年を下回り0.4倍でした。サゴシは前年を上回り3.0倍でした。西部についてはサワ
ラもサゴシも前年を上回って1.1倍と6.7倍です。この2008年はサゴシの銘柄が
東部で3.0倍、西部で6.7倍と前年比で高い値が得られているのが特徴です。それを
府県別に示したものが次の図ですが、サゴシでは大阪と大分で前年を下回ったほかは大体
前年を上回るところが多かった。
それでは次に2008年の秋の漁獲の動向について説明します。
これは大阪府の資料ですが、南部の標本組合の機船船びき網漁業の漁獲量を示していま
す。一番上はシラスの漁獲量、縦軸がトンで横軸が1月から12月まで。ヒストグラムが
平年で赤が2008年、青が2007年、黒が2006年の直近3年ですが、平年と比べ
て2008年は10月にシラスが割と多かったというのが特徴的です。
カタクチイワシについては8月、9月がピークですが、前2年に比べて2008年はち
ょっと悪かった。
サワラについては2006年、7年に比べてピークが余りはっきりしない。10月が一
応低いピークなんですが、余りよくなかったということになります。カタクチが余りよく
なかったということでサワラもよくなかったのかと思われます。ただ10月にシラスがと
れたというところが目新しいと思います。
サワラの尾叉長組成の方ですが、これも大阪府の資料ですが、流網の尾叉長組成が主で
す。9月から12月まです。一番上は曳網でして、9月に曳網でとれたものは46センチ
程度で例年に比べて魚体がやや小さかった。小さかったので、これが流網にかかってこな
かった。50センチより小さかったということであまり流網にはかかってこず、9月は1
歳魚、同じく10月、11月も大阪では1歳魚主体の漁獲であり、0歳魚、その年生まれ
のサゴシがとれたのは12月に入ってからだった。
2008年生まれのサゴシは多いんだとか、それほどでもないという情報がいろいろあ
るわけですが、これについてちょっと御説明しますと、2008年の秋のサゴシの漁獲は
香川県の資料では東部の引田で、これが2008年の秋のサゴシですが、加入が非常によ
かった2002年、それからそれ以降比較的よかった2005年に比べて、2008年は
2002年ほどではないけれども2005年並みであるという数字となっています。それ
から西の方の香川県の伊吹の資料では2005年に比べてもやや小さい半分以下の数字に
なっております。それから高松中央卸売市場での9月から12月の香川県産のサゴシの入
荷量、取扱量は2005年あるいは2002年並みの数字になっております。先ほど御紹
介があったように試験漁獲では2002年の0.4倍、2005年の0.8倍ですから、
2002年に比べるとやはりそれほど多くないが、その次に比較的よかった2005年と
同じかやや下回る程度じゃないかという数字になっています。
愛媛県のサワラとサゴシの資料を分析しますと、2008年秋のサゴシの豊度、1隻1
日あたりの漁獲尾数あるいはキログラム数、川之江と埴生ではキログラム、西条と河原津
では尾数です。2002年から2008年について色別に示しておりますが、2008年
のCPUEで見ると川之江と埴生では2002年並み、2002年というのは図で黒です。
西条と河原津では2002年を下回る。このように、2008年が2002年ほどではな
いということで、良いという情報と悪いという情報が半ばとなっています。
それから、同じ愛媛県でも伊予灘では、月別の漁獲量で図はないのですが、サゴシにつ
いて数字を整理したものを県からいただいたのですが、2005年の漁獲量を1としまし
て、2006、2007、2008年の漁獲量はそれぞれ1.5倍、2.2倍、1.9倍
となりまして、2005年に比べて2008年のサゴシは2倍近い漁獲量で、サゴシが比
較的とれています。
管理方策への提言として、毎年70万尾の加入がないと資源は持続しない。親の資源は
2歳魚主体で若齢化しておりまして、年齢構成も単純化している。そのために環境が悪く、
再生産において仔稚魚の生残が悪い年があると、資源が大きな打撃を受ける恐れがあると
考えています。ですから、サゴシの漁獲を抑えて親を残して、加入動向を見守ることが重
要です。そして、環境や加入、再生産の不安定さを考慮しますと資源回復計画での取り組
みの強化が望まれると考えております。
それから、次は補足なんですが平成20年度第1回サワラブロック漁業者協議会、9月
24日の会議で各県の漁業者の方々から研究サイドへいろいろ要望が出ました。大きなも
のとしては3つほど出たんですが、それに対して私の方でできる範囲で資料を整理して回
答したので、簡単にご紹介したいと思います。
1番目は地域別の放流効果、放流しているが、地域別に漁獲量への反映がどうなってい
るのか示してほしいということです。2番目はサワラがどうして播磨灘に入ってこないか
説明してほしいということです。これに対して非常に説明は難しい、なかなかいい説明が
できないのですが、後でお見せする図の2や小路・益田両先生の講演要旨を見てください
と説明しました。それから、3番目に海の変化、瀬戸内海の海の変化とか温暖化に関する
情報を提供してほしいということで、これについては後で表1をお見せしますが、東シナ
海とか日本海、瀬戸内海に関しての状況を私の方でまとめさせてもらいました。参考資料
として委員の先生のところには「海洋と生物について瀬戸内海の魚類生産に変化はあった
か」というテーマで私が書いたものをお配りしております。これはブロック漁業者協議会
でもお配りしたものです。
サワラの放流魚については、ご承知のように内部標識として小さい卵とか仔魚の段階で
赤い標識を入れております。ですから成魚あるいはサゴシでも、漁獲して頭の中の耳石を
調べたら放流物か天然物かがわかります。その天然物に対して放流物の割合が何%かを海
域別、それから年齢別、それから年別に放流魚の混入率としてまとめました。御覧になっ
てわかるように0歳のところでは混入率が非常に高いです。ただ年齢が高くなるほど値は
低くなっています。図には播磨灘の兵庫県、播磨灘の岡山県、播磨灘の香川県などでの混
入率の数字がありまして、これに漁獲物の年齢組成を別に持っておりますので、両者をか
けてどのくらい放流魚が漁獲されているかというのを直近の3年について推定して図中に
数字としてあげています。
ここでちょっと分かりにくいんですが、赤い色は瀬戸内海、兵庫県の播磨灘で再捕され
たものですが、西部放流分を示しています。図では厚みをもっていませんので1尾とか2
尾なんですが、西から東に来たものが再捕されています。それから瀬戸内海西部なんです
が、燧灘、香川県沖、愛媛沖、安芸灘、伊予灘での特徴として、安芸灘、伊予灘では混入
率が低い、放流物の再捕がない。それからもう1つの特徴は香川沖でも愛媛沖でも燧灘に
ついては、この緑色は厚みをもっていますので、瀬戸内海東部で放したものが備讃瀬戸を
通って西部の方にかなりきていることを示します。ただ、東に比べると西では混入率はそ
れほど高くはないということが特徴です。いずれにしても地域別、年別、年齢別にこのよ
うな混入率となっており、それが漁獲量にどう反映しているかをブロック漁業者協議会で
お示ししました。
それから、後で読んでもらえばいいんですが広島大学小路先生、京都大学益田先生、こ
ういった先生方の指摘として、瀬戸内海のサワラを増やすにはやはりカタクチイワシをは
じめとするサワラの餌となりうる資源の管理をきちんとしないと本格的な回復はないんじ
ゃないかという指摘がなされています。
それについて同じようなことなんですが、灘別にカタクチシラスの漁獲量とかシラスと
カタクチイワシの漁獲量の比、そういったものを灘別に私の方で整理しています。言いた
いことは、シラスの漁獲量が瀬戸内海東部の方で多いものですから、資源としては安定し
ていてもカタクチイワシの影を見ることがどうしても少なくなる。カタクチイワシがいれ
ば、2004年の春に五色で見られたように、カタクチイワシにサワラがつくというふう
なことがありますので、やはりシラスで先取りしてカタクチイワシの影が薄いと、サワラ
が滞留する機会というのは少なくなってくるのだろうと考えています。ただ、シラスとい
うのは非常に大きな漁業を支え、商業的にも価値が高いですから、そっちの方が重要だと
考える行政の方もいるし、漁業者の方もいるわけで、なかなかその辺が難しいところだと
思います。
あと東シナ海、日本海についてはどういった異常現象が見られるかということで1つだ
け言いますと、サワラの東シナ海系群に見られる漁獲量の北への偏りは1999年以降に
日本海の北区で始まりまして、2000年以降太平洋北区、要するに青森の三沢の方や福
島の方で漁獲がかなりあがってきているという情報があります。もう1つ言えば例えば従
来沖縄の魚であるグルクン、これが沖縄での漁獲量が減って、2005年から長崎とか宮
崎で漁獲量が増えていたのが、2008年には福岡で増えているというふうに魚の分布が
更に北へ上がってきているような傾向があります。以上こういったことを瀬戸内海ブロッ
ク漁業者協議会で報告させていただきました。
以上です。
(前田会長)
どうもありがとうございました。
ただいまの説明によりますと、サワラの資源状況につきましては平成19年の資源水準
は低位で動向は減少傾向にあるとのことです。また親魚資源は2歳魚が主体で若齢化し年
齢構成が単純化しているため、再生産や稚魚の生産が悪いと資源に大きな影響を与える恐
れがあるとのことでございます。このため環境や加入の不安定さを考慮すると資源回復計
画での取組強化が望まれるとのご報告でございました。
何かこのご報告に対して質問等がございませんでしょうか。
それではないようですので次に移ります。平成21年度の取組の審議に移ります。
昨年10月の委員会におきまして、休漁期間の変更に関する検討状況の報告がありまし
た。それによりますと伊予灘関係県で休漁期間変更に関する検討を進め、ブロック漁業者
協議会において意見集約を図り、本日の委員会で計画変更について審議したいとのことで
した。
まず事務局より伊予灘の休漁期間の取り扱いを含めた平成21年度の取組について説明
していただきまして、その後、配付資料には含まれておりませんけれども新たな資源管理
体制の構築に向けた検討を行っているということでございますので、その検討条件につい
て報告していただきます。それでは事務局、よろしくお願いします。
(平松計画官)
では、資料につきましてはサワラ資料の1−3でございます。
まず始めに、先ほど会長の方からもございましたとおり伊予灘の休漁期間の変更に関す
る検討状況、検討結果でございますが、前回の委員会では試験操業ですとか既存の研究デ
ータを基にした行政研究担当者会議の検討結果といたしまして、休漁期間を変更しても現
状より漁獲量が増加する可能性が低いということが考えられる等の報告を行い、またこれ
らの結果を踏まえまして伊予灘の関係県におきまして休漁期間の変更案に対する検討を進
めるとご報告いたしました。それらを2月に開催されますブロック漁業者協議会で持ち寄
り、検討を加えて意見の集約を行うということでその後の取組の方針を説明させていただ
きました。
これにつきまして昨年の10月以降、伊予灘関係県の方で検討が行われてきたわけでご
ざいます。2月にブロック漁業者協議会が開催されましたが、その場で伊予灘の関係県と
いたしまして山口県それから大分県、こちらの漁業者協議会の代表委員の方から県内の協
議状況についてご報告がございました。両県ともこの休漁の期間変更については了解する
ということでございました。これらを受けまして2月10日に開催されましたブロック漁
業者協議会におきましては、この伊予灘の休漁期間を15日間後ろの方へずらすという変
更案について了解が得られたというところでございます。これらを踏まえまして本日、来
年度のサワラ計画の取組案ということでまとめさせていただいてございます。
それでは、資料1−3表紙をめくっていただきまして、1ページの漁獲努力量削減措置
(平成21年度案)という地図のページをご覧ください。
内容につきましては、ただいま申し上げましたとおり伊予灘海域での休漁期間につきま
してサワラ流し網漁業(山口・愛媛・大分)としているところですが、こちらの休漁期間
5月16日から6月15日ということにさせていただいております。これが、本年度5月
1日から5月31日までとしていたところからの変更箇所でございます。
その他の海域につきましては、本年度と全く同様の休漁期間として実施したいと考えて
ございます。また、瀬戸内海全域での流し網の目合い規制10.6センチにつきましても
今年度と同様の内容となってございます。来年度の漁獲努力量削減措置につきましては伊
予灘を変更した形でこのような取組で進めたいと考えてございます。
つづきまして、2ページめくっていただきまして種苗生産・中間育成・受精卵放流の取
組、来年度の実施予定を載せてございます。
同様に3ページには広域漁場整備及び漁場環境保全の来年度の事業の実施予定を取りま
とめてございます。放流それから漁場整備、両方につきましておおむね今年度と同じ内容
の実施予定をしてございます。来年度の漁獲努力量削減措置、種苗放流、漁場整備につき
ましてはただいまご説明申し上げました内容で実施したいと考えてございます。
このうち、休漁期間に係ります漁獲努力量の削減措置につきましては休漁期間変更とい
うことでございますので、資源回復計画本文の変更が必要になってまいります。こちらに
つきまして資料の4ページから8ページにかけまして、サワラ瀬戸内海系群資源回復計画
一部変更案という形で新旧対照表のスタイルで載せております。表の右側が現在の回復計
画の文章、左側が変更案になってございます。資料の4ページ、新旧対照表になる部分で
すが、こちらの一番下のところ、漁獲努力量の削減措置の表にあります伊予灘の部分でご
ざいますが、こちらにつきまして現行の5月1日から5月31日という期間を表の左側の
5月16日から6月15日というふうに変更をさせていただきたいと考えてございます。
また、規制措置の内容の変更はこの点のみですが今回の一部変更に併せまして7ページ
にございます海域の定義の中の灯台名につきまして通称名から正式名称に改めさせていた
だくという措置を1ヶ所させていただきたいと考えてございます。変更箇所はその2ヶ所
でございます。
それから資源回復計画におけます休漁等の措置につきましては、これらの措置を担保す
るための瀬戸内海広域漁業調整委員会指示につきましては資料の9ページから11ページ
に案を載せてございます。
こちらの内容につきましては、11ページをご覧いただきたいんですが先ほどご説明い
たしました伊予灘の休漁期間、こちらにつきまして変更後の休漁期間に対応した内容での
設定を考えてございます。
以上が平成21年度のサワラ資源回復計画の措置案でございます。
それから、これから資料はございませんので口頭での説明をさせていただきたいと思い
ますが、このほかに現在資源管理体制の構築に向けた検討といたしまして2つ行ってござ
います。
1つは資源回復計画の取組の強化に関すること、それから2つ目が平成23年度以降の
放流体制の検討に関してでございます。
まず1つ目の回復計画の取組強化に関しましては、サワラ資源の回復に必要な産卵親魚
の確保につきまして、現在の資源水準から考えますと一律に漁獲量を減らすような取組と
いうものは、少ない漁獲量を更に減らすということになるため実現性が困難と考えてござ
います。従いまして、卓越年級群の発生など例年以上の漁獲が見込まれる場合を想定いた
しまして、あらかじめ未成魚の保護による親魚量のかさ上げについて、これらの方法につ
きまして検討しておくことが重要と考えているところでございます。
また、平成20年級群につきましてはある程度の加入量が期待できるということもござ
いまして、早急にそれらの検討を進める必要があると考えているところでございます。こ
のような考え方によりまして、1つの例といたしまして好漁日、漁獲のいい日が2日連続
すれば3日目を臨時休漁にするという取組を想定いたしまして、それらの取組よってどの
ような効果が発現するか、また実際の漁獲の減少がどの程度かというようなことについて
これらの漁獲増加の取り控え効果というものについて検討をしてございます。現在、各地
域の実情に見合った方法というものにつきまして、各府県、地域での検討を行っていただ
くよう行政研究担当者会議、またブロック漁業者協議会において各府県に要請していると
いう状況でございます。これが1つ目の取組強化に関する検討の状況のご報告でございま
す。
つづきまして2つ目のサワラ種苗放流体制の検討状況という部分でございますが、サワ
ラ資源回復計画におきまして種苗放流は漁獲努力量の抑制との一体的な推進が必要とされ
ているところでございます。現在の種苗放流の体制に当たりましては、水研センターの関
与が大きいところでございますが、その水研センターの取組の根拠となります水研センタ
ーの中期計画というものが平成22年度で終了するということ。また、サワラのような広
域回遊種についての国の関与、栽培、放流に対する国の関与を定めております栽培に関す
る基本方針につきましても、平成21年度で終了するということになってございます。
このような状況から、これらの次の基本方針、次期の水研センターの中期計画に瀬戸内海と
しての要望内容等が反映されるよう今年度1月26日の行政研究担当者会議からこの種苗
放流体制、23年度以降の種苗放流体制のあり方について検討を始めたというところでご
ざいます。まだ、検討を始めたばかりでございますので、その具体的内容について、現時
点でご報告できるまでには至っておりませんが、今後、水産庁の本庁また水研センターの
これらの関係する動きを注視しつつ検討の進捗状況に応じまして、適宜ご報告できればと
考えているところでございます。
以上2点口頭でのご報告になりますが、資源管理体制の構築に向けた検討状況について
ご報告しました。これらを含めました来年度、平成21年度の資源回復措置、サワラ回復
計画の取組案と考えてございます。来年度の取組案につきまして、ご審議よろしくお願い
いたします。
(前田会長)
平成21年度の取組の案につきましては、伊予灘の休漁期間についてこれまでの検討を
踏まえ5月1日から5月31日の休漁期間を5月16日から6月15日までに変更したい
とのことでございました。これに伴いまして、資源回復計画を一部変更し本委員会指示に
つきましても変更後の休漁期間に対応した内容により設定するとともに種苗放流等の取組
については本年度と同様の内容で実施したいとのことでございます。
また、後半の新たな資源管理体制の構築に向けた検討につきましては、資源回復計画の
取組の強化及び種苗放流体制の検討に関して行政研究担当者会議等での検討状況及び今後
の検討の進め方について報告がございました。
なお、紀伊水道外域につきましては、2月24日に開催されました「和歌山・徳島連合
海区漁業調整委員会」におきまして、本委員会指示の案が決議されれば本年度と同様の連
合海区委員会指示に従うことが決議されております。
また、宇和海につきましても3月12日に開催予定の愛媛海区漁業調整委員会において
本年度と同様の海区委員会指示を決議する予定となっております。
これから質疑に入りますけれども、まず始めに平成21年度の取組の案につきまして何
かご質問等がございましたらお願いいたします。
ご意見もございませんようですので、それでは「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平
成21年度取組(案、本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員) 会指示(案)につ
いて」承認したいと考えますがよろしいでしょうか。
それでは委員会として「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画の平成、21年度取組(案)、
本計画の一部変更(案)及びこれに係る本委員会指示(案)について」承認をいたします。
引きつづきまして、第2点目の新たな資源管理体制の構築に向けた検討が行われている
資源回復計画の取組強化及び種苗放流体制の検討状況についての報告がございましたけれ
ども、これにつきましてご質問等がございませんでしょうか。
(高橋委員)
この問題につきましては、この委員会で擁護するというのがいいのかどうかよくわから
ないままに申し上げたいと思います。
行政の方でも将来的な取組というのを検討なさるというようなことでありましたけれど
も、この資源管理についての取組というのは漁業者自身、我々もある意味ではそうだとは
思うんですけれども、今の取組がやっとこさよちよち歩きの状態なんです。これで計画期
間が終わったからおしまいよというのでは、せっかく取り組んだのがほっぽり出されると
いうような気がしてならない。そういう意味では、やはり行政からも当然そういうご意見
が出るんだと思うんですけれども、これは続けてやっていただかないと、せっかく今まで
取り組んできたのが終わってしまうというような気がしますので、国におかれてもこの問
題についてはどうぞ息の長い取組をお願いしたい。
(前田会長)
今後とも水産庁と言いますか、行政サイドでの取組も今までと同様の指導してほしいと
の要望でございます。
何か事務局の方でございますか。
(平松計画官)
今おっしゃられたのは平成23年度まで今の計画期間、5年延長した第2期の計画期間
がございまして、先ほど放流につきましてはそれ以降の体制についていろいろ関係の長期
計画等の進捗に合わせて検討を進めたいという報告をさせていただいております。
後ほど予算の説明の中で本庁から今後の制度的な話も予定しておりますが、サワラにつ
きましても放流だけでなく全体の取組を今後どうしていくかというのは、当然現在の取組
期間の終わりに向けてしかるべきときに具体的な検討を進めていかないといけないとは認
識してございます。その中で一番いいやり方、どのようにやっていくかということを十分
関係の機関とも検討しながら進めていきたいと考えます。
以上でございます。
(前田会長)
どうもありがとうございました。よろしいですか。
ほかにございませんか。
- 17 -
(荒井委員)
回復計画の取組を強化するということで、今1つのアイデアをご提示されましたけれど
も、2日続けていい漁があれば1日休むと、それも1つのアイデアだと思うんですけれど
も、他の魚種あるいは他の海区でこういった取組をやってうまくいってると、あるいはう
まくいくんじゃないかどうかという事例があればちょっとご紹介していただければと思う
んですけれども。
(前田会長)
ございますか、事務局の方で。
(佐藤所長)
実は私ども資源回復計画を最初に立ち上げたときに、これは白書にも載ってますけれども
太平洋のマサバである程度成果が出たんですけれども、要するに魚を増やすということは
獲り控えをするということです。獲り控えをすると何が起こるかというと、ぎりぎりの経
営をやっているというところで更に取るなと、これを要求していかざるを得ない。ところ
が、うまいことに自然の中でたまにボーナスが出ると言ったら変ですが、実は経営に負担
を与えないで資源を回復する道が時々あるんです。それが実は卓越年級群が出たときに、
そのボーナスをできるだけ手をつけないで貯金しておくと。普通の生活費でぎりぎりして
いる人に魚を取るなというのはこれは非常に難しいんです。特に今年さっきの報告にもあ
りましたように、地域によっては相当漁獲量が減っております。平均ですると前年度より
ちょっとかもしれません。だけど播磨灘のように過去に比べて非常に減ってるところ、さ
らに、中間育成までやっている漁業者にとっては、とてもじゃないですけれども受け入れ
られない。そう見ると資源を回復するには、誰に獲る量を減らしてもらうのか。やっぱり
ある程度取れて生活が維持できる人にそこの負担をしてもらおうじゃないかと。それと、
先ほど言いましたように、もしかすると本年度とか20年度に卓越年級群が発生している
可能性がある。そうすれば過去と同じ獲り方をすればたくさん残せるため、昨年と同程度
に我慢をしようと。そういう発想で実は太平洋のマサバのときも経営の維持をすると同時
に、もう一方のボーナスが出たときに欲というものをいかに抑えるか。そこである一定以
上取れた翌日は確実に休むと、それを連続してやったわけです。その成果として漁獲量は
減らないけれど大きな魚が残って翌年から、収益が上がってきたという1つの事例があり
ます。だから、そういう経営と資源の回復をうまくマッチングするタイミングが今回出て
きたんではないかということで、それに期待しているということになりますので、以上で
ございます。
(前田会長)
ありがとうございます。ほかにございませんか。
それでは、サワラ資源回復計画は種苗放流と資源管理の取組を大きな柱としております。
サワラ資源が減少傾向にある中で今後この取組をどうすべきかは、重要なテーマであると
考えますので事務局におかれましては引きつづき検討を進めるようお願いを申し上げたい
と思います。
なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正
式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部
分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承お願い申し上
げます。
(議題2 周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画について)
(前田会長)
それでは、再開いたしたいと思います。
つづきまして、議題2の「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部変更
について」に入らせていただきます。
本計画につきましては、前回の委員会で計画延長の骨子について承認しておりますので、
今回は計画延長を内容とした資源回復計画の一部変更について審議を行うこととなってお
ります。
まず、始めに事務局より平成20年の漁獲状況及び本計画の延長について説明していた
だいたあと、計画の一部変更の案についてご審議いただきたいと思います。それでは事務
局から説明をお願いいたします。
(平松計画官)
それでは、周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画に関しまして、資料は資料
番号の2−1から2−3までが関連の資料でございます。
まず始めに資料2−1に基づきまして漁獲状況のご報告、それから資料2−2と2−3
を用いまして延長計画の内容について続けてご説明をさせていただきます。
資料2−1をご覧ください。平成20年の漁獲状況につきまして、先ほどサワラの漁獲
量でもご報告申し上げました平成20年下半期の速報値が2月に公表されましたので、上
半期の数字と合わせまして平成20年の速報値ということでまとめさせていただいており
ます。
こちらによりますと、平成20年は1,751トンということで19年の速報値1,8
70トンに比べまして約6%減少という結果になってございます。それぞれ周防灘計画の
対象魚種ごとの内訳が資料の2−1の下の魚種別の表に載せているとおりでございます。
この中で前年よりも漁獲量が増えておりますのがクルマエビとガザミでございます。一方、
漁獲量が特に減少が大きいのがシャコでございまして320トンが207トンに減少して
いるということでございます。周防灘につきましては漁法別の漁獲量の集計がちょっと時
間を要するということで、確定値は平成18年までということでございまして表に数字を
記載しているとおりでございます。20年の漁獲状況につきましては簡単でございますが、
以上でございます。
つづきまして、計画延長につきまして考え方のご説明をさせていただいて、計画変更案
についてご審議いただきたいと思っております。
まず計画延長の内容につきまして取組の基本的な方針、内容につきまして資料2−2「周
防灘資源回復計画の延長について」という資料にまとめてございます。こちらの資料1ペ
ージをご覧ください。1番といたしまして資源回復措置の継続の必要性ということで、こ
れまでの骨子等でまとめさせていただいた内容を簡単に整理をさせていただいてございま
す。回復計画に取り組んできておりますが、効果も上がっている部分もございますが、引
きつづき取組の継続というものが重要なポイントになっていると考えてございます。この
ような考え方のもと、計画を延長して進めたいということでございますが、まず1ページ
の2番のところに資源回復の目標といたしまして、実施期間と計画の目標を載せてござい
ます。
まず実施期間につきましては(1)にございますように本計画の実施期間は平成25年
度までとするということで、現在の計画が16年11月に作成されて5年間ということで
すので、21年の11月に5年間期間が満了するということでございますが、これを更に
延長するという考えでございます。前回の委員会で骨子の了解をいただいたときにはここ
は平成23年度までとさせていただいておりましたが、回復計画の実施期間が25年度ま
でこの制度としての実施期間が延びるということで、それにあわせて25年度までの延長
としたいと考えてございます。従いまして来年度、21年度からちょうど5年間の取組に
つきまして第2期の取組というような位置づけで今後2ページ以降に記載してございます
内容を中心に進めてまいりたいと考えてございます。
それから、資源回復の目標につきましては現在の計画の目標でございます平成16年の
漁獲量の水準、数字で言いますと2,123トンということになりますがこちらの維持と
いう目標を引きつづき掲げて取り組んでいきたいと考えているところでございます。
それでは、ページをめくっていただきまして2ページ目以降に実際にどのような取組を
行っていくかということで3番の資源回復のために講じる措置というところ以降に取りま
とめてございます。
まず(1)の漁獲努力量の削減措置につきましては、まず?の小型魚の水揚げ制限、こ
れは現在取り組んでおります制限サイズを引きつづき継続実施すると考えてございます。
2つ目の取組といたしまして、シャワー設備の導入がございますがこちらのところで資
料の中にアンダーラインを引いている部分、こちらがこれまでの取組にプラスした部分、
検討の方向性も含めまして今回の計画延長に当たりましてこのような観点の取組を進めて
いくという部分の追加部分をアンダーラインをしております。シャワー設備の導入でいき
ますと、これまでの再放流魚の生残率の向上というものに加えて、持ち帰り出荷する漁獲
物の鮮度維持というもの、これをシャワー設備の導入の目的の中に位置づけとして追加す
るということで取り組んでいきたいと考えております。
現在、山口県、福岡県、大分県の3県のうち大分、福岡が導入済みということで山口県の方で今、順次導入しているという
ところでございますので、未導入船につきまして先ほど言いました再放流魚の生産率の向
上に加えた、漁獲物の鮮度保持というものを目的に加えまして導入促進を推進していきた
いと考えているところでございます。また鮮度維持ということに関しまして現在、夏場に
機能を発揮します簡易冷却装置の現場での応用試験というものも進められておりますの
で、これらの取組も推進していきたいと考えております。それらを含めて効果的なシャワ
ーの活用方法というものも考えつつ、効果的なシャワーの利用というふうなものを推進し
たいと思っているところでございます。
それから、産卵親魚の保護といたしまして実施しております抱卵ガザミの再放流につき
ましては、現在取り組んでいるとおり継続していくということ、また休漁期間の設定につ
きましてはこちらは海底清掃等の漁場環境改善の取組とあわせて実施するという考えを今
後も継続するということで考えてございます。
?といたしまして、漁具の改良がございます。これはこれまでの取組の中でも進めてま
いりましたが、それら試験研究をより推進することを考えておりまして現在幼稚魚の混獲
防止漁具の性能試験も実施されておりますので、このような取組について実用化に向けた
推進を行ってまいりたいと考えているところでございます。
以上が漁獲努力量の削減措置でございますが、回復計画の2つ目の柱でございます資源
の積極的培養措置ということで、これは主に種苗の放流というものになりますがこちらに
つきまして2ページから3ページに記載しております。この回復計画を進めるに当たって
今年度から事業として立ち上がりました資源管理アドバイザー制度等を活用しつつ、この
3県の連携、協力というものによる放流体制の構築というものを推進していきたいと考え
てございます。特にクルマエビにつきましては、山口、福岡、大分の3県で共同した事業
も実施してございますので、これらの事業の推進というものを図っていきたいと考えてご
ざいます。
3つ目の柱として漁場環境の保全措置ということでございますが、こちらは水産基盤整
備事業等の漁場環境改善の事業について取組を引きつづき行いたいと考えております。
資源回復のための措置といたしましては、以上3本柱の内容でございます。次に資料の
3ページの4番にございます漁業経営安定の取組ということでこちらは今後この資源回復
計画によりまして、資源の回復、漁獲の増大というものを進めていく取組にあわせまして
経営的な観点での検討を並行して実施していく。これは今回新たに盛り込んだ内容でござ
います。
大きな柱としましては2つございまして1つがコストの削減ということでございます。
燃油につきましては昨年度非常に高騰いたしまして、こういうコスト削減、特に燃油の使
用の抑制等の取組というものの重要性が出てきておるわけでございますが、このような観
点での操業コストの低減策ということについて検討するというのが1 つでございます。
2つ目といたしまして先ほどのシャワー設備のところでも申し上げましたが、漁獲物の付
加価値向上、単価アップ等に向けた取組ということについて、各種検討をあわせて実施し
ていきたいと考えているところでございます。これら、資源回復措置の取組プラス漁業経
営安定の取組という観点で来年度以降の取組を進めたいと考えているところでございます。
その他、3ページの中段以降にございます5番の公的担保措置、6番の支援策等につき
ましては従前どおりの体制で進めていきたいと考えているところでございます。
最後、資料は4ページになりますがその他といたしまして、これは今までの回復計画の
中でも取組として進めてきたところでございますが、他漁業への取組の拡大というような
部分につきましては現在、カニ籠漁業のカニ籠目合いの適正化試験というものも実施され
て小さなカニ、ガザミですがこれを漁獲しないようにするための検討ということが進めら
れてございますので、そのような取組をこの関連漁業へのアプローチというようなことで
進めていきたいと、このような取組を推進していきたいと考えてございます。このような
考え方のもと、来年度以降の5ヵ年間の取組を第2期の取組として進めていきたいと考え
てございます。
回復計画につきましては今申し上げましたとおり実施期間の延長ということになります
ので、計画変更が必要になります。そちらにつきましては資料2−3、1 枚資料、裏表印
刷しているものでございます。こちらも新旧対照表によります変更案ということで、表の
右側が現行の計画、左側が変更案ということで整理をしてございます。変更箇所としまし
ては、資料2−3の1ページのちょうど中ほどの行に当たりますが、資源回復目標の中で
実施機関に係る部分、現行では当面の5年間としている部分を平成25年度までの間とい
うふうに改めたいと思っております。また、平成16年の漁獲量が統計の数値が公表され
ておりますので2,123トンという具体的な数字を盛り込むということにしてございます。
変更内容は以上の2点ですが、実施期間につきましては1ページ目の一番下の2行にご
ざいますように、もう1ヶ所実施機関が当面の5年間が平成25年度までの間というふう
に記載されている部分がございます。
変更箇所は以上でございますが、2ページ目にございます海域の定義の基点のところに
つきましても市町村合併に伴う市町村名の修正と、灯台等の名称を正式名称に改めるとい
うことで一部記載内容が変わってございますが、実際の基点そのものにつきましては変更
ございません。表現方法の変更をこの計画変更にあわせて行いたいと考えてございます。
周防灘計画の延長の取組内容・方針、それから資源回復計画の一部変更案につきまして
は、以上でございます。
(前田会長)
計画の延長につきましては実施機関を平成25年度までとし、現在実施している漁獲努
力量の削減措置を継続しつつ漁獲物の鮮度維持等の漁業経営安定の取組に検討を進めてい
るとのことでございました。
それでは、ただいまの説明につきましてご質問がございませんでしょうか。
それでは、ないようですので「周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の一部
変更(案)について」承認したいと思いますがよろしいでしょうか。
ありがとうございました。それでは、委員会といたしまして「周防灘小型機船底びき網
漁業対象種資源回復計画の一部変更(案)について」承認をいたします。
なお、本計画の一部変更につきましては今後、国において本委員会等の意見を踏まえ正
式な計画としてまとめ上げることになるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部
分的な修正、文言の訂正等につきましては事務局に一任ということでご了承をお願い申し
上げます。各関係、各委員におかれましては本計画の適切な実施について、よろしくご指
導お願い申し上げます。
(議題3 カタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について)
(前田会長)
「つづきまして議題3のカタクチイワシ瀬戸内海系群(燧灘)資源回復計画について」
に入ります。
まず、20年度の実施状況と資源状況などについて事務局より報告していただきまして、
引きつづいて21年度の取組につきましてご審議いただきたいと思います。
また、計画作成後4年が経過し、来年3月で計画期間満了を迎える本計画の評価という
ことで事務局より報告していただきます。それでは、本年度の実施状況などにつきまして
事務局から報告お願いいたします。
(中奥資源保護管理指導官)
瀬戸内海漁業調整事務所、中奥です。よろしくお願いいたします。
それでは着席させていただきましてご説明させていただきます。
では、20年度の取組について資料3−1をご覧ください。対象漁業の許可期間は1ペ
ージの(1)に示すとおりでございます。これに対しまして資源回復措置としましては(2)
にあります休漁期間と(3)にあります定期休漁日を設定し取り組まれました。本年度定
期休漁日につきましては広島県が燃油高騰の要因もあり、従来の木曜日に加えて日曜日も
追加実施されました。20年度の操業実績といたしまして(4)にありますとおり瀬戸内
海機船船びき網につきましては広島県は6月13日から10月10日まで、香川県は6月
10日から9月10日まで、愛媛県は6月10日から9月10まで、愛媛県のいわし機船
船びき網では6月10日から8月17日までとなっております。
次に燧灘のカタクチイワシの資源状況です、2ページをご覧ください。資源状況につき
ましては関係3県の広島県、香川県、愛媛県の水産試験研究担当者の方々により資源解析
が行われた結果です。
(1)は漁獲量の動向です。平成18年までは農林水産統計から、平成19年、20年
は共販量からの推定量をグラフにしました。平成20年の漁獲量はカタクチイワシとシラ
スを合わせて1万4,540トンと前年の108%となっております。
(2)は初期資源尾数の動向です。本計画の目標は回復計画開始当初の資源尾数水準、
これは平成12年から16年の平均で346億尾です。この水準と計画期間終了後に同程
度維持することとしております。その基準である資源尾数は、春季発生群の初期資源尾数
を用いることとしています。グラフはその動向について示しております。平成20年につ
いては水準より若干低い値、340億尾で目標の98%となっております。
(3)は初期資源尾数の漁獲率の動向を示しております。グラフのとおり資源量に対す
る漁獲率は(2)の資源尾数をベースに出しているため、このように高い値となります。
それを踏まえて見てみますと、例年86%前後で推移し平成20年も平年並みの値となっ
ております。
(4)は資源状況の考察です。3県の水産試験研究担当者の資源解析、燧灘のカタクチ
イワシ漁獲量及び瀬戸内海系群カタクチイワシの資源評価結果から判断して、資源水準は
中位、動向は横ばいとの評価が出ております。
次に、脂イワシ調査結果について3ページに取りまとめております。本調査は19年度
から関係3県と瀬戸内水研が協力して調査を開始したものです。19年度の結果報告から
脂質含有量と製品単価の急低下との関連から脂質含有量が2%以上のものを脂イワシと仮
定義したことから、今年度も引きつづき調査を行い図1のように脂質含有量と肥満度の間
に正の相関が見られたことから、脂イワシの判定指標として肥満度が利用できると判定し
ました。図1の脂質含有量2%のときの肥満度は約10であり、肥満度10を脂イワシの
発生警戒値とする結果を得ました。
20年度の取組状況については以上です。
(前田会長)
ただいまの説明によりますと、本年度は広島県の定期休漁日について従来の木曜日に加
えて日曜日も追加して実施されたとのことでございました。また、燧灘のカタクチイワシ
の資源水準は中位、動向は横ばいとのことでございます。ただいまの報告について、何か
ご質問等がございませんでしょうか。
ないようですので、つづきまして平成21年度の取組について事務局から説明をお願い
いたします。
(中奥資源保護管理指導官)
21年度の取組案につきましては、資料3−2をご覧ください。
1ページ目、平成21年度の資源回復措置の取組としまして2と3にあります漁期始め
及び漁期終期の休漁、定期休漁日の設定につきまして従来と同様に継続することとしてお
ります。また、漁期始め及び漁期終期の休漁期間の担保措置としまして本委員会指示を平
成20年度と同様の内容で設定したいと考えております。本委員会指示の対象海域は2ペ
ージの図に示しております。3ページには本委員会指示の案を添付しております。なお、
2月12日に開催されましたカタクチイワシブロック漁業者協議会において21年度取組
案及び本委員会指示案につきましては了解が得られております。また、20年度取組でご
紹介しました脂イワシに関する調査につきましても引きつづき瀬戸内水研と関係3県が協
力して続けることにしております。
21年度の取組案につきましては以上です。よろしくご審議お願いいたします。
(前田会長)
平成21年度は引きつづきまして従来と同様の資源回復措置を実施し、本委員会指示に
つきましても本年度と同様の内容で行いたいとのことでございます。また、脂イワシに関
する調査についても引きつづき行われるとのことでございました。
ただいまの説明に対してご質問等ございませんでしょうか。
、「( それではないようですので平成21年度取組案)及びこれに係る本委員会指示(案)
について」承認したいと考えますがよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声)
(前田会長)
委員会として「平成21年度取組(案)及びこれに係る本委員会指示(案)について」
承認をいたします。
それでは、次に本計画も計画作成から4年が経過し、来年度が最終年度となっておりま
す。こうした状況を踏まえまして、事務局から本計画のこれまでの取組に対する評価につ
いて報告していただきたいと思います。では、事務局よろしくお願いいたします。
(中奥資源保護管理指導官)
4年間の取組状況を評価にまとめておりますので資料3−3をご覧ください。
まず、計画の概要といたしましては1ページの2にあるとおり瀬戸内海海域におけるカ
タクチイワシに対する漁獲圧力は経年的に高い傾向であり、現在の比較的安定した加入状
況が悪化すれば資源悪化や漁獲量減少を招く恐れがあるため、現状の水準を下回らないよ
うに資源量を維持する必要があります。そのために、資源回復の目標としまして5年間の
計画期間後に燧灘のカタクチイワシの資源尾数水準を計画開始前の平成12年から16年
の平均と同程度に維持することを目標にしました。講じている措置は休漁期間の設定と、
定期休漁日の設定となっております。
次の3の計画実施状況ですが、6ページ以降に添付しております図表をご覧いただきな
がらお聞きください。まず、漁獲努力量削減措置の実施状況を6ページの表1と表2にま
とめております。
表1では本計画で定められた休漁期間に加えて自主休漁が取り組まれておりますので、
その内容を整理しております。まず、広島県の瀬戸内海機船船びき網漁業の17年度を例
に説明しますと、表にあります操業開始日とは計画上6月10日から操業できるところを
実際に操業を開始された日が6月13日であり、定められた休漁期間に加えて6月10、
11、12と3日間の自主休漁を実施されたことから(A)の自主、休漁日数3という整
理をしています。同様に操業終漁日では11月30日まで操業できるところを実際は10
月31日で終漁されたということなので、定められた休漁期間に加えて30日の自主休漁
を実施され(B)の自主休漁日数30で、17年度の広島県の合計自主休漁日数は33日
となります。そのほか、表にまとめた以外にも天候や魚の状態で臨時休漁も適宜実施され
ております。
表2では定期休漁日について取りまとめました。平成20年度の広島県は先ほども報告
しましたとおり、燃油高騰の要因もあり木曜日のほか暫定的に日曜日が追加されました。
なお、本計画に定められました休漁期間に対しては本委員会指示が毎年設定されておりま
す。また、平成19年度に愛媛県宮窪町漁協所属のいわし機船船びき網漁業1ヵ統の本計
画参加により、対象海域拡大の一部変更を行いました。5ページの図1が拡大しました対
象海域になっております。
次に、支援事業について7ページ表3にまとめたとおり愛媛県で平成18年度から延べ
54隻日、494万6千円の休漁漁船活用支援事業で漁場監視が実施されております。以
上が漁獲努力量削減措置に関する実施状況です。
次に関連調査としまして、資源評価については関係3県と瀬戸内海区水産研究所が協力
して行っており、8ページの表4にあるとおり卵稚仔調査や表5の脂イワシに関する調査
が実施されております。餌料環境調査、脂質含有量調査、発生要因分析などを行い、基礎
データの収集や肥満度を利用した脂イワシの判定指標の検討など研究が行われておりま
す。
次に資源動向と漁獲量の推移ですが、9ページの図2をご覧ください。燧灘のカタクチ
イワシの資源動向は春季発生群の初期資源尾数について平成5年以降のデータをもとに推
定されております。グラフに示すとおり平成5年以降は減少傾向で、平成8年に138億
尾と最低の水準になりましたが、その後、回復傾向で平成12年以降は300億から40
0億尾の水準を維持しております。
次に漁獲量ですが、10ページの左上の図3をご覧ください。燧灘での近年のシラスを
含む漁獲量は1万1千トンから1万7千トンで推移しており、平成12年から20年の平
均漁獲量は1万4千トン程度となっています。
次に県別に見ますと、図4の広島県では平成15年に3千トンを超えましたが、その後
は1千トン前後で推移し、図5の香川県では平成17年に1万トンを超えましたが、その
後はおおむね7千トンで推移しております。図6の愛媛県では3千トンから5千トンで推
移しております。
また、各県の銘柄別共販量とその割合から漁獲の主体を見てみますと、瀬戸内海機船船
びき網漁業では11ページの図7からご覧ください。上段のグラフが銘柄別の漁獲量、下
段が銘柄別の構成割合になっております。図7の広島県ではチリメンを主体に漁獲してお
り、図8の香川県では中羽を主体に小羽から大羽を漁獲、12ページの図9の愛媛県では
中小羽を主体に小羽から大羽を漁獲、図10のいわし機船船びき漁業ではカエリを主体に
チリメンを漁獲しています。このことから、漁獲対象が広島県はチリメン主体、香川県及
び愛媛県は煮干加工向けのサイズを主体に、いわし機船船びき網漁業においてはカエリ、
小羽を主体にそれぞれ漁獲しているようです。
次に目標達成状況ですが、戻りますが9ページの図2をご覧ください。本計画の資源回
復目標は、5年間の計画期間後に燧灘のカタクチイワシの資源尾数水準を計画開始前の5
年間、平成12年から16年の平均と同程度に維持することとしております。この指標と
して用いる資源尾数は、燧灘の資源評価で算定された初期資源尾数です。図2に引いてお
ります破線は回復目標の指標であります平成12年から16年の平均値である346億尾
を示し、計画開始後の平成17年から折れ線を太線で表しております。達成状況について
はご覧いただいているとおり、平成20年の資源尾数は340億尾で目標である346億
尾の98%であり目標水準で安定しております。
最後に評価と今後の課題としてまとめておりますので、本文4ページをご覧ください。
本計画を4年間実施してきた評価として、現時点でカタクチイワシは産卵親魚量と加入量
の間に明瞭な関係が認められていないため、資源管理措置の効果を定量的に判断すること
はできませんが、初期資源尾数が安定的に確保され漁獲量が一時期の低水準より回復し安
定していることから措置はおおむね妥当であると考えます。また、瀬戸内海区水産研究所
の指導のもと、関係3県の協力で資源評価体制が確立され、またその体制により脂イワシ
の判別法で化学分析を必要としない簡易な肥満度を活用できることが明らかにされたとこ
ろであり、操業方法の改善に寄与することも期待できます。
次に今後の課題ですが、漁獲努力量削減措置は評価で述べましたとおり一定の効果があ
ったと考えますが、今後の資源量の維持、安定を考えますと資源予測の精度を高め資源動
向に即した措置について検討が必要であります。また漁獲動向や脂イワシの発生により製
品価格の年変動が大きいため脂イワシ発生のメカニズム解明に期待されていますが、その
研究成果をいかに現場で活用していくかが重要であります。更に、脂イワシの発生による
価格低下から漁獲金額の向上の取組として、漁獲物の付加価値向上や操業及び加工コスト
の削減などについて検討を行い漁業経営の安定に向けた取組を推進することが重要である
と考えます。以上が本計画の評価ということで、4年間の取組状況を取りまとめ最後に評
価と今後の課題としてまとめました。
本計画の計画期間は来年度末までとなっておりますが、今後の課題にありますように、
燧灘のカタクチイワシに関する資源管理については引きつづき検討していきたいと考えて
おりますので、関係県や漁業者の方々と今後話し合いを深めていく予定としております。
(前田会長)
説明していただきましたけれども、現行の計画の評価を簡単にまとめますと、初期資源
尾数が安定的に確保されたこと及び漁獲量が一時期の低水準より回復し安定しているこ
と、また本計画によりいわし機船船びき網漁業者を加えた体制が整えられたなどの評価を
行うとともに、今後の課題としては資源量の維持、安定に加えて漁業経営の安定に向けた
取組の推進が重要であると以上のような内容であったかと思います。
ただいまの説明につきましてご質問がございましたら。
ご意見等もございませんか。それでは事務局におかれましては今後、関係県、漁業者等
と十分協議をしていただきまして22年度以降の燧灘におけるカタクチイワシの資源管理
について、よろしく検討をお願いいたしたいと思います。
(議題4 トラフグ資源管理の検討状況について(報告))
(前田会長)
つづきまして、議題4「トラフグ資源管理の検討状況について(報告)」につきまして、
事務局より報告していただきたいと思います。
(森資源課長)
瀬戸内海漁業調整事務所で資源課長を担当しております森と申します。
資料4を用いましてトラフグ資源管理の検討状況についてご報告いたします。座ってご
報告させていただきます。
「トラフグ資源管理に関する主な取組」としまして、まず「瀬戸内海関係府県との会議
等」でございます。この中の「関係県との意見交換会」についてでございますが、瀬戸内
海のトラフグ資源管理の検討は、トラフグ資源量が多く重要度が高い愛媛県、山口県、大
分県、広島県の瀬戸内海西部4 県から進めてはどうかとの瀬戸内海区水産研究所担当者
からの助言を受けまして、瀬戸内海西部4 県と意見交換会を開催することにしております。
なお、意見交換を終えた大分県、愛媛県、山口県3県においては今後トラフグの資源管
理につき何らかの対応をしていかざるを得ないとの認識であり、引き続き関係漁業者の意
見等を聞くため浜回りを行う方向で検討中です。
その下、「瀬戸内海区水産研究所との打合せ」につきましては、昨年11月と12月に
2回実施しております。瀬戸内海区水産研究所担当者からは情報提供や助言をいただいて
おります。主なところをご紹介しますと、1つ目はトラフグの資源水準は極めて悪いとい
うこと、2つ目は九州・山口北西海域では既に資源回復計画に取組んでおり、同じ系群を
漁獲している瀬戸内海においても資源管理を進めることが重要であること、3つ目は九州、
山口関係県からは瀬戸内海における資源管理の取組への要望が大きいこと、最後に特に漁
獲量の多い愛媛県、山口県、大分県、広島県の資源管理の取組が重要であることなどです。
次に「九州・山口北西海域関係機関との会議等」でございますが、まず「九州漁業調整
事務所との情報交換」についてですが、昨年の12月、九州漁業調整事務所で実施いたし
ました。九州漁業調整事務所担当者から、九州・山口北西海域のトラフグ資源回復計画の
取組状況等について説明を受けるとともに、今後は更に一層、両事務所が情報交換を密に
していくことを確認しております。
最後に「トラフグWG会議関連」と、一番下の「九州・山口北西海域トラフグ資源回復
計画に係る行政担当者会議」についてですが、九州・山口北西海域においては研究者の会
議であるトラフグWG会議と行政担当者会議が開催されておりますが、九州・山口北西海
域におけるトラフグ資源の状況や資源回復計画の取組状況等を把握するため、これらの会
議には瀬戸内海漁業調整事務所から担当者が出席しております。
平成20年10月21日開催の第17回瀬戸内海広域漁業調整委員会以降の主な取組は
以上のとおりでございます。
引きつづき、他海域の状況も把握しつつ、また関係県のご協力を得つつ、更には関係漁
業者のご意見を踏まえつつ検討を進めてまいりたいと考えております。また検討状況につ
きましては適宜本委員会に報告を行いたいと考えております。
(前田会長)
ただいまの報告につきまして何かご意見、ご質問はございませんか。
それでは、トラフグの資源水準は低位横ばいとの資源評価がなされております。トラフ
グの資源管理につきましては、こうした資源評価を踏まえまして引きつづき検討を進めて
いただくようお願いを申し上げます。
(議題5 平成21年度予算について)
(前田会長)
それではつづきまして、議題5の「平成21年度予算について」に入ります。水産庁管
理課さんより説明がございます、よろしくお願いいたします。
(渡邉管理課課長補佐)
水産庁管理課の渡辺と申します。
私から平成21年度予算につきましてご説明申し上げます。資料の5の1ページをご覧
ください。
21年度予算に関しましては、その前提となる資源回復計画につきまして新たな方向性
が確定をいたしました。先ほど高橋委員からもご発言がありましたけれども、今回この2
1年度予算に関しましては、この資源回復計画の今後の展開についてということを中心に
ご説明を申し上げます。
まずこの1ページ目の一番左側をご覧いただきたいんですが、現行の資源回復計画、今
平成14年から取組の開始をいたしまして現在64計画で実施中、5計画で作成中という
ことでございまして、資源の回復が必要な魚種等を対象に漁獲努力量の削減等を実施して
いくということで取り組んできております。計画開始から時間が大分たってきておりまし
て、中には資源の回復の兆しが見られつつある計画も出てきているところでございまして、
そうしたものについてはこの資料の一番右側にございますけれども、最終的には経営支援
を行わない形で自立的に、漁業者、あと行政、研究者がともに資源管理を行っていくとい
うものが最終的な理想になるわけでございます。とは言っても、いきなり自立といっても
さまざまな課題があります。そうした課題も踏まえまして、水産庁としてはどのような形
で取り組んでいけば最終的に自立というようなものが有効に、効果的に達成できるのかと
いうものを当然考えていかなければならないという課題があると考えております。そうし
たことを踏まえて今回、新たに一番右側の右から1つ戻っていただいたところにポスト資
源回復計画というものがございますけれども、最終的に自立に向けた準備期間ということ
でより効果的な取組というのもどのようなものがあるのかというものを考えながら、これ
までと同様の取組、そしてこれまでと同様の形で支援を行う準備期間として、ポスト資源
回復計画というものを新たに位置づけて推進をしていきたいと考えてございます。
中にポスト資源回復計画のところにも書いてありますけれども、基本的に実施機関は原
則5年間取り組んでいきたいと考えておりまして、繰り返しますけれどもポスト資源回復
計画の下の部分に矢印が出ておりますが、これまでと同様に漁獲努力量の削減措置である
とか種苗放流の積極的な推進、漁場環境の保全措置等に対する支援を引きつづきやってい
きたいと考えております。
また、こうしたことに加えまして、これまで既存の資源回復計画につきましても現在の
ところ平成18年度に着手したものに作成を限るということにしておったわけでございま
すけれども、これまでさまざまな作成に対する要望等もございましたので、そうしたこと
も踏まえまして今後また新たに資源回復計画の作成についても可能にしていくことといた
しましたのであわせてご報告をいたします。
資源回復計画につきましても、努力量の削減措置等に対する支援というものを当然なが
らこれまでと同じように行っていきたいと考えております。
なお、ポスト資源回復計画に移行するに当たってこれまでにやってきた取り組みがどう
だったのか、また今後最終的な自立に向けてどのような取組が有効でかつ取り組み可能な
のかというようなものを当然評価検討していかなければいけませんので、そうしたことを
するために左側の2つ目のところにポスト資源回復計画移行調査というものがございます
けれども、そのための予算というものも今回新たに確保をいたしましたのであわせてご報
告をいたします。
このほか平成21年度予算につきましては、繰り返しますがこれまでと同様に漁業者協
議会の開催であるとか、資源回復計画の普及・啓発の取組、また漁獲努力量の削減、種苗
放流、漁場環境保全といったものに対す支援措置というものも引きつづき確保をいたしま
したので、引きつづきご活用をいただければと思っております。
また、2ページ以降にはそうした各事業のPR判を添付しておりますのでご参照いただ
ければと思います。
以上、簡単ではございますけれども平成21年度予算につきましてご説明を終わります。
以上でございます。
(前田会長)
どうもありがとうございました。
何かご質問といいますか、ございませんでしょうか。
(議題6 その他)
(前田会長)
ございませんか、それでは議題5の「その他」に入りますけれども、せっかくの委員会
でございますので何か取り上げる事項等はございませんでしょうか。
よろしいですか。それでは事務局の方から委員の任期及び次回の委員会の開催予定など
についてご説明お願いいたします。
(馬場調整課長)
瀬戸内海広域漁業調整委員会の現在の委員の任期は平成17年10月1日から4年間、
今年の9月末日までが任期となっており、次回の委員会につきましては緊急開催の必要が
なければ例年どおり10月ごろに開催したいと考えております。
委員につきましては、海区委員の代表については改めて選定していただき、また大臣選
任委員につきましても改めて選任し直した上で開催させていただく予定です。
委員の皆さまには大変お世話になり、まことにありがとうございました。
なお次回の委員会の日時、場所等につきましては改めて事務局より新委員さんに連絡さ
せていただきます。以上でございます。
(閉会)
(前田会長)
ありがとうございました。
馬場課長さんからお話がございましたとおり、今日、出席していただいておりますメン
バーでの委員会はこれで最後になろうかと思います。委員の皆様方、4年間大変ご苦労さ
までございました。この4年間に当委員会で取り上げられましたいろいろな課題に取り組
んでまいりました。そして、その課題に対しましてそれぞれ一定の成果を上げることがで
きました。これ、一重に委員皆様方のご尽力の賜であると感謝を申し上げる次第でござい
ます。
今後とも委員皆様方にはご健勝で、そしてまたそれぞれのお立場、またそれぞれの分野
でご活躍していただくことを心からご祈念申し上げるものでございます。
それでは、これで本日の会を閉じたいと思いますが、各委員さん、また、ご臨席の皆様
には本委員会の開催へのご協力ありがとうございました。
また、議事録署名人の山本委員さん、原委員さんにおかれましては後日議事録が送付さ
れると思いますのでよろしくお願いを申し上げます。
それではこれをもちまして、第18回瀬戸内海広域漁業調整委員会を閉会いたしたいと
思います。どうもありがとうございました。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/s_kouiki/setouti/pdf/s_18.pdf
2009年12月29日
小鳥が丘団地土壌汚染「現地報告と裁判経過」

2009年12月18日おおさかATCグリーンエコプラザで「土壌汚染の社会的問題」と題するセミナーが開催されました。
そのセミナー資料に一部加筆してを公開します。
なお、裁判内容は一次訴訟(3世帯)について記しています。二次訴訟(約18世帯)についてはあまり触れ居いません。
ATCグリーンエコプラザのセミナールームにおける桃花台及び小鳥が丘等のの住民たち
大阪市立大学特任教授の畑明郎先生と環境カウンセラーの藤原きよみさん
小鳥が丘団地土壌汚染「現地報告と裁判経過」
小鳥が丘団地救済協議会
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
1. 小鳥が丘団地土壌汚染の概要
1.1 はじめに
小鳥が丘団地は岡山市の東部にあり、すぐそばには小鳥の森公園という農林センターのある自然に恵まれた戸数35戸の小さな住宅団地です。
「土壌汚染問題」が発覚して5年以上になりますがその間、宅地販売業者はもちろん岡山県、岡山市、議員、等に何度となく解決を要望してきましたが今もそのままの状態です。
発覚当初は不安・心配ばかりでしたが、関係者の信じられない対応ぶりに段々憤りを覚え、そのエネルギーを支えに、ここまでやってきましたが、最近ではあまりの道理のなさに怒りを通り過ぎて、茶番劇を見ている様な錯覚さえ感じます。

大阪市立大学大学院 畑明郎先生と環境カウンセラーの藤原きよみさん
1.2 汚染発覚
2004年7月(H16)に岡山市水道局から鉛製水道管解消事業の為、団地の水道管を取り替えるとの連絡があり、取り替え工事中に土壌汚染が発覚しました。
刺激臭のある油のような液体がポンプで排水しなければならない程、大量に湧き出しました。
「小鳥が丘団地」が開発された1987年(S62)には、鉛の水道管は鉛公害で国会でも取り上げられ、昭和56年当時使用を止めていたものを何故この団地で使用していたのか、岡山市水道局に公開質問状を出しましたが、水道局からは、団地造成の時に水道工事業者が、小鳥が丘団地の土質が悪いので鉛管を使用したいと要請があり、使用を認めたと回答がありました。
それと、水道管入れ替えで排出した土壌は、持ち出しても処理できないので埋め戻すしかないと言われました。
団地造成当時から土壌汚染は認識されていたのです。
しかし、その土壌が悪いため、あえて腐食に強い鉛水道管を使用したにもかかわらず、鉛管に腐食による穴が明いていました。風呂の配水管が溶けていた住宅もあります。
1.3 汚染の原因
汚染源は直ぐ分かりました。20年ぐらい前までこの土地で操業していた旭油化工業という化学工場の跡地で、操業中は悪臭公害で行政より十数回に渡り行政指導を行ったが改善されませんでした。
当時の関係者に聞くと、主に京阪神地方の工場廃油の処分を引き受け、ドラム缶で集め、この土地に垂れ流ししていたようです。それを十数年に渡り廃棄し続けました。しかも香川県豊島産業廃棄物不法投棄事件と関連がありました。豊島の廃棄物搬入ルートに旭油化工業の名前が資料に載っていました。
悪臭公害の解決策として1982年(S57)に、行政も関与し両備バス?(現両備ホールディングス?)が買い取るという事で操業を停止し、旭油化工業と両備バス?の間で売買契約が成立しました。この工場跡地を両備バス?が宅地開発販売したのが、「小鳥が丘団地」です。
20数年前の事ですから周辺に住んでいて当時の様子を知る人も多く、話を聞くと相当ひどいものだった様です。住宅団地になると聞いて本当に大丈夫なのかと疑問に思った人も居たようです。
旭油化工業は近郊の赤磐郡吉井町(現あかいわ市)に名前を瑞穂産業と変え工場を設置し、当地と同様に廃油を垂れ流して土壌汚染を引き起こした為、吉井町ではこの公害工場を1983年1月に操業わずか3か月で撤退させ跡地を調査し土壌汚染が深刻と判断し土壌入替えを行っています。

1.4 汚染発覚以降の推移
汚染発覚当初、両備バス?は3箇所のボーリング調査や全戸数の庭の表層土調査他の土壌調査を実施し、環境基準値を超える有害物質が検出されましたが、岡山大学の先生を中心とする両備バス設立の委員会(南古都?環境対策検討委員会)の意見書により、住民の健康への影響が直ちに懸念されるものではない、と回答し、その後の調査も住民との話し合いも打ち切り、長く放置された状態が続きました。
両備バス?の対応
・宅地開発当時、土壌汚染の認識はなかったと主張。
・両備バス?が住民に示した話し合いに応じる前提。
?両備バスに法的責任が無い事を認めること。
?両備バスは、これ以上調査はしない。
?住民の意見を統一すること。
?地層のガス抜き工事等改良案は提示したが、費用については両備バスがすべて負担するものではない。
(住民側の負担が基本)
・ガス中毒
2006年6月に住民が倉庫工事のため自宅庭を掘削したところ地下15cm〜40cm部分から黒い刺激臭のする土壌が出てきました。現地確認を両備バス?に連絡をしましたが拒否され、現地はそのままの状態でした。
2006年10月、住民は掘削した自宅庭をそのままにも出来ず、掘削跡の埋め戻しや堆積した土壌を移動中に倒れ、救急車で病院に搬送され治療を受けました。診断書はガス中毒(亜硫酸ガス中毒疑い)です。原因は庭の掘削跡に水が常時溜まっていて、移動中の堆積した黒い土壌と反応して発生したガスを吸い込んだ様です。
・行政開発許可
小鳥が丘団地の開発は3期に分かれていて、最初の第1期は岡山県が宅地開発許可を与え、その後の権限移譲により第2期3期の宅地開発許可は岡山市が与えています。
住民が健康被害を受けたにもかかわらず両備バス?が調査をしないので、開発を許可した行政に土壌調査要望書を提出しましたが、岡山県は現在の担当行政は岡山市だからそちらの方へと言われ、岡山市に行けば最初に土地調査をして開発許可を出したのは岡山県であり岡山市は土地に関与していないし、調査を適用するような法律がないので出来ないとの(たらい回しの)回答でした。
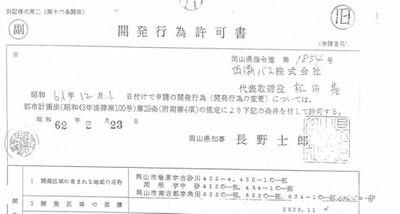
岡山県の開発許可証
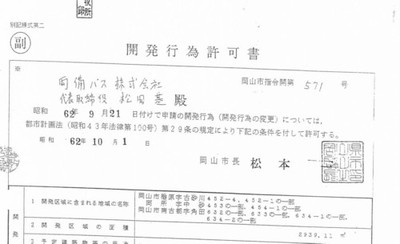
岡山市の開発許可証
・汚染土壌処分方法
このままでは心配なので、住民が自費で自宅庭の表層土を入れ替えようと思い土壌の廃棄場所を指定してもらう為、2006年9月に岡山市を訪ねたところ、「小鳥が丘団地の土壌は汚染指定区域外の土地ではあるが汚染指定地と同等の処分をして下さい」と言われました。
つまり、汚染土壌なので指定機関で調査をし、指定機関が指示する場所でないと捨ててはならないと言うのです。もちろん検査費用や廃棄費用は住民の負担です。
・刑事告訴
この様な健康被害に合う事態になった為、住民2名で、2006年11月に重要事項説明違反で宅地開発販売業者を刑事告訴しましたが、土地購入日(平成5年)からの時効で受理して貰えませんでした。
この件の時効は最大でも3年で、私たちの案件は売買契約から3年と言われましたが、そもそも土壌汚染のような土中に原因のある瑕疵は建物と違って1年や3年で購入者が発見できる方が稀で長期間経った後、何かのきっかけで発覚するのが普通だと思い法律の不備を感じます。
・国土交通省、環境省、法務省
国土交通省、環境省、法務省にも質問状を送りましたが、地元の地方自治体に言ってくださいとしか回答してもらえません。
・寄付依頼
銀行からは、土地建物の担保価値なし、と言われ担保融資も受けられないため、住民による土壌調査を実行出来ずにいましたが、このままでは実態が分からぬまま放置されてしまいます。そこで寄付をお願いし、足らないところは住民で資金を工面し、民間の調査分析会社にガス中毒で倒れた自宅内の表層土壌の調査分析を委託しました。
・住民土壌汚染調査
この分析結果報告書を、大阪市立大学大学院 畑 明郎 先生に見て頂き、ご意見を伺いました。畑 先生から頂いたメールです。
“サンプル数は少ないものの、土壌ガスから発がん性のベンゼンが、土壌溶出量基準を超えるベンゼン、猛毒のシアン、発がん性のある鉛やヒ素が検出されており、危険で有害な土壌であることが証明されたと思います。ベンゼンや鉛は、廃油や廃溶剤などからと考えられますが、シアンやヒ素の原因は不明です。応急対策として、敷地土壌のアスファルトやセメントによる被覆が早急に必要と考えます。恒久対策としては、建物移転・撤去→土壌入れ替え→再建築しかないと思います。”

汚染発覚当初、両備バス?が行った全戸数の表層土調査の時、この家の庭も表層土調査を行っていますが異状なしでした。なぜこれほど違うのか疑問です。
この分析結果報告書は当然、岡山県や岡山市の担当窓口に提出し、猛毒のシアンが検出されましたと相談しましたが、自治体では詳しい調査は出来ないとの事でした。
自治体が公正な調査をして汚染実態を明らかにしなければ、その後の対策は前に進まないと思うのですが、自治体にいくら要望しても民間の問題なので調査する法律がない、と言います。
? 放置された状態でした。
1.5 私たちの懸念する事
小鳥が丘団地土壌汚染で最も深刻な事は住宅地である事です。1日で一番長い時間を過ごすマイホームで安全に生活出来ないのです。
・住民にはアトピー性皮膚炎、鼻炎、頭痛、死亡者にガンが多い等、懸念する事が多い。
・団地内から可燃性ガスが出ていて、地元消防署も確認し、充満すれば爆発の危険性も指摘された。
・夏になると夜中に家庭用ガス漏れ警報器が鳴る家もある。
・一戸建て住宅なのに、庭で家庭菜園しても食べない方がいいと言われた。
・小さな子供が砂遊びすると、注意しても口に入れる事があるので、庭で土いじりさせない様に言われた。
・団地に接する川に油が染み出している。
・解決出来なければ、当事者一代でなく、子や孫の何代にも渡って被害を出し続ける。
・周辺への汚染拡大の危険がある。周辺地域に地下水汚染を疑われる現象があり、心配しています。
私たちは安全安心に生活したいだけなのですが今の状況はそれを許してくれません。
1.6 民事裁判に発展
汚染発覚後、被害者住民35世帯で「小鳥が丘環境対策委員会」を設立し対応してきましたが、両備バスはこれ以上調査しない態度を鮮明にし、公的支援もほとんどないに等しく、こう着状態が続きました。
その中で、機動的に活動して証拠を集めなければ進展が無い、と考える住民が、「小鳥が丘環境対策委員会」を一時脱退、別働隊として2名で証拠集め活動(後に「小鳥が丘団地有志の会」を経て「小鳥が丘団地救済協議会」を立上げ)を始めました。
こうして先行した「小鳥が丘団地救済協議会」3世帯(住民訴訟第一次)と後から続いた「小鳥が丘環境対策委員会」18世帯(住民訴訟第二次)が民事裁判で闘っています。

2.土壌汚染発覚から民事提訴までの過程
2004年7月、岡山市水道局が鉛管解消工事による水道管取替工事を町内会へ連絡。団地開発時期から考えると鉛管が埋没している事に疑問を持った住民岩野氏が岡山市に質問したがあいまいで疑問が残る。
同月29日、水道工事による土壌掘削で土壌汚染が発覚。その時調査した岡山市の分析結果では、土壌から水抽出法で硫酸イオンが1?あたり4000?検出。
2004年8月、小鳥が丘団地35世帯住民で「小鳥が丘環境対策委員会」を設立、住民代表委員7名を選抜し実質的に動いてきた岩野氏が会長になる。岩野氏の知人の羽原弁護士にもアドバイス頂くため協力していただく。
2004年9月、岡山市保険所が健康相談を実施。住民の不安解消を目的に実施したもので、土壌汚染との因果関係を問うものではない。相談に応じた65人の住民うち42人に皮膚炎や鼻炎、頭痛などの気になる症状。
2004年9月、両備バス?が団地内道路3か所のボーリング調査を実施。3本目のボーリングの4〜5m近辺で悪臭のする油のような液体が噴水のように噴き上げ、金属片やボロ切れなどが発見。立ち会いしていた両備バス?不動産部課長が直ぐ連絡し不動産部のトップの方が後から駆け付けた。同月28日、住民集会にて概況調査分析結果報告があり、環境基準値の約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、6倍のシスー1,2−ジクロロエチレンが検出されたと報告。
2004年10月4日、住民は土壌汚染問題だけに付きっきりになる時間はないので住民代表委員7名の任を解き、羽原弁護士を含む2名の弁護士に両備との示談交渉を依頼。今後の窓口は岩野氏と会計担当(藤原)を決める。
2004年10月、両備バス?がボーリング調査で汚染が判明した特定有害物質、ベンゼン・トリクロロエチレン・シスー1,2−ジクロロエチレン・ひ素含有量・ひ素溶出量・及び特定有害物質ではないが油分について、各戸の表層土壌調査34か所を実施。同月23日、調査結果報告があり、指定基準を超えたのは34か所中、ベンゼンが11倍など8か所・トリクロロエチレン1か所・シスー1,2−ジクロロエチレン2か所・ひ素溶出量5か所。住民の多くは両備バス?に無償移転を要請。
2004年10月、両備バス?が岡山大学の先生を中心とした「環境対策検討委員会」(南古都?環境対策検討委員会)(以下、岡大委員会と略す)を同月16日設立。最初住民は公平な第3者機関を設立してくれたと錯覚した。住民が請求しても住民代表者の参加も傍聴も認められない、議事録の開示もなし。
2004年11月、岡山市が油状物質調査。沼川(側)護岸の切れ目から油が流れていると住民が連絡。岡山市からの検査結果報告は、護岸付着物の主な構成物質は植物プランクトン。信じ難いもので、2回もサンプル採取に来るなど違和感。
2004年11月頃、汚染原因者の旭油化工業が立ち退き後に近郊の赤磐郡吉井町(現あかいわ市)に工場を設置し同様に違法操業した為、1983年1月に操業わずか3か月で撤退させた吉井町の公害資料を入手。
2004年12月、両備バス?が隣接地に仮設事務所設置、当分の間毎週土曜日駐在、コミュニケーションを図る為としたが両備バス?不動産部課長が、「調査しないで買うのは住民の責任」と発言。
2004年12月、両備バス?が電気探査を実施。同月27日、調査結果報告で全体に低比抵抗であり1%以上の油分による、又、タンク跡に位置する箇所は油の漏洩を示している。同日、岡大委員会の意見書が提出され「異臭による不快感はあるものの住民の健康への影響がただちに懸念されるものではない」との記述。住民を除外した状態での方針決定は納得できないし、汚染原因となった化学工場の操業実態に対する調査は汚染物質の特定のため極めて重要なのに、この点についての調査はほとんど行われてない。
2005年1月頃、両備バス?が住民宅を戸別訪問。
2005年1月、住民依頼にて江本 匡 氏が意見書。
2005年1月、香川県豊島公害調停選定代表人の一人として活躍された石井とおる県議来訪、「豊島産廃不法投棄事件や土壌汚染問題」を住民に講演。
2005年2月、住民依頼にて中地重晴 氏が意見書。
2005年2月、町内会会長名で岡山市役所に陳情書提出。
2005年3月、市役所上道支所へ要望書提出。両備バス?及び岡大委員会へも要望書提出。
2005年3月、住民代表7名で豊島視察調査。搬入ルートに岡山市旭油化工業の名前あり。
2005年3月、第20回小鳥が丘環境対策委員会(第1回大会)を近くの公民館で開催。関係者に参加要請したが岡山大学委員会は出席せず、岡山大学委員会の「最終意見書・対策提案書」を両備バス?が代読。小鳥が丘環境対策委員会の顧問を引受けて頂いた石井とおる県議が住民の参加を拒否するのは岡大委員会なのか、それとも両備バス?なのかと追及。
2005年4月、住民2名で岡山大学委員会に質問書を提出するため訪問したが、2005年3月で解散したと回答。住民が直接質問する機会も与えられないまま、わずか6カ月で3回の意見書を出し一方的に解散。住民の不信感が一気に高まった。両備バス?はこの意見書をもとに追加調査も住民との話し合いも拒否。
2005年5月、町内会住民による土壌調査(ボーリング調査)。
2005年5月、多数の住民が固定資産評価審査委員会に評価審査申出書提出。同7月に固定資産評価審査委員会は申出を却下。
<進展しない状態が長く続きました>
2005年7月、現状のこう着状態を打開するには、機動的に活動して証拠を集めなければ進展が無い、と考える住民2名(岩野・藤原)が、「小鳥が丘環境対策委員会」を一時脱退、別働隊として2名で証拠集め活動。
2005年7月、岡山市と両備バス?の2者会談で両備が住民との話し合いに応ずる前提条件として、両備に法的責任が無いことを認めること等の条件を提示。同月の岡山市と住民の2者会談で岡山市が伝達。住民は承諾せず。
2005年8月、両備バスが責任を認めようとしない姿勢では話し合いをいくら続けても解決できないと考える別働隊の住民2名が、情報収集・証拠集め・広報・第3者への協力依頼・多くの町内住民に希望を持って立ち上がってもらう基盤を作る事を目的に、「小鳥が丘団地有志の会」結成9名(近隣住民含む)。
(「小鳥が丘団地有志の会」の活動)
2005年9月4日、署名活動、小鳥の森フェスタ、岡山市上道公民館一帯。
2005年9月18日、署名活動、JR東岡山駅、東岡山駅表口・裏口一帯。
2005年9月23日、ジャーナリスト井部正之氏が週刊金曜日で「旭油化の汚染を売った両備バス」と題して土壌汚染と被害の実態を報道。
2005年9月25日、署名活動、JR東岡山駅、東岡山駅表口・裏口一帯。
2005年10月2日、署名活動、平島学区体育大会、昼食時間に各町内会テントを巡回。
2005年10月4日、岡山県河川課に砂川廃川敷地の交換について質問したが現在は岡山市が管轄と回答。10月18日に岡山市河川港湾課を訪ねたが1〜3期開発認可は岡山県で行っているため資料なしと回答したので同日再び岡山県河川課を訪問し後から文書による説明書提出を要望。
2005年10月、岡山市(開発指導課・環境規制課)を訪問面談。
2005年10月〜12月、岡山県(環境政策課・産業廃棄物対策課・建築指導課・河川課)を何度も訪問面談。
2005年10月5日、岡山市長選挙にあたり候補者に質問書提出(高谷、熊代、高井、各候補)。
2005年10月12日、新岡山市長の高谷茂男氏に面談申し込み。直接面談拒否。環境規制課へ回される。
2005年10月19日、小鳥が丘団地近くの中国銀行平島支店に不動産担保ローン相談に行く。後日、担保価値なしと融資を断られる。
2005年10月20日、岡山県産業廃棄物対策課に、1983年(S58年)当時の県の実例集記載の旭油化跡地撤去完了確認の内容開示を要求。
2005年10月22日、署名活動、スーパーマルナカ平島店及びJR東岡山駅、マルナカ入口一帯及び東岡山駅表口・裏口一帯。
2005年10月28日、岡山県産業廃棄物対策課、「旭油化撤退後1983年に県が廃棄物撤去確認調査で有害物質の撤去を確認と新聞報道にあるが事実か」の質問に「目視にて現状を確認、搬出物内容は確認してない」と回答。また10月20日に開示要求した1983年当時の県の実例集は書類保管期限切れのため無いと回答。
2005年10月29日、署名活動、スーパーマルナカ平島店及びJR東岡山駅、マルナカ入口一帯及び東岡山駅表口・裏口一帯。
2005年11月2日、岡山県河川課、砂川廃川敷地の交換について簡単なメモ受領、汚染が激しいと想定される国有河川敷地を懸念なく両備に交換譲渡したのか?河川敷地の公用廃止資料開示請求を行う。
2005年11月5日、署名活動、JR東岡山駅、東岡山駅表口・裏口一帯。
2005年11月12日、署名活動、JR東岡山駅、東岡山駅表口・裏口一帯。
2005年11月20日、署名活動、沢田の柿祭り、岡山市沢田の百間川一帯。
2005年11月頃、小鳥が丘団地内の玄関ポーチと道路の境のコンクリートの割れ目から雨水のアワを伴ってガスが蒸発するのが目視されたので連絡し、西大寺消防署が「可燃性ガスが出ている」ことを確認。

2006年1月16日、岡山県へ(土壌調査等)要望書、提出(1度目)。集まった署名3382名分を添えて。
2006年1月16日、署名活動を住民全体で行おうと呼びかけに対する「小鳥が丘環境対策委員会」(以下、自治会委員会と略す)役員の返事は、法的資格のある人(弁護士等)以外の外部の人間は入れない、環境対策委員会を脱退した者の進め方に妥協する事はない、完全浄化対策工事で無くても徐々に環境改善出来れば良い、風評被害が解消されなくても仕方が無い。このため統一活動は断念しました。
2006年1月23日、岡山県会議員55名に土壌汚染問題請願書提出。
2006年1月24日〜2月、県会議員4名に面談し事情説明と請願。国会議員1名の事務所訪問し事務局長に面談し請願書提出。
2006年2月3日、岡山市水道局へ「小鳥が丘の鉛管使用について」公開質問状提出、「小鳥が丘団地」が開発された昭和62年当時岡山市はすでに鉛管の使用を止めていたのに何故当団地で使用したのか。同月14日、回答書受領、開発当時の給水協議に際し廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから樹脂系のポリエチレン管は変質する恐れがあり鉛管の使用を承認。
2006年2月13日、岡山県への1月16日提出、要望書に対する各課合同の口頭回答。
(産業廃棄物対策課)
岡山市内における環境問題は岡山市が行政権を持っており、県は動くべきでない、
(建築指導課)
Q1,公害企業として何度も行政指導をしても廃油の垂れ流しを改善されなかった旭油化工場跡地を、昭和62年当時、宅地として許可した理由は?
A1,都市計画法に沿い技術基準(住宅に耐える土壌の強度があるか)に合っていれば良く、他の問題(有害物質等)は対象外であり、宅地開発許可は合法である、
Q2,当時、県の環境課でも相当問題になった公害工場の案件に対し土壌汚染の検討もしてない事はおかしいと思うが、情報交換はして無かったのか?
A2,他の課との情報交換連絡はしていない。他法令を参考にする事は位置づけられていない、
Q3,1983年(S58年)当時の「岡山県実例集」に記載している「旭油化跡地撤去完了確認調査資料」を開示請求したい、
A3,当時の経緯調査資料は書類保管期限切れのため処分したので資料は無い、
(河川課)
Q1,汚染が激しいと想定される国有河川敷地を懸念なく民間の両備に交換譲渡したのか?また公文書開示請求により2005年(H17年)11月8日に開示された「一級河川旭川水系砂川の河川敷地の公用廃止(昭和63年12月9日付け岡山県告示第973号)の起案文書」に掲載されている両備の行った「河川法20条の河川工事」とは何の工事か?
A1,「河川法20条の工事」の別紙内訳書は書類保管期限切れのため処分したので内容は分からない、この程度の案件では調査するつもりは無い。
2006年2月24日、近隣町内会長及び学区連合町内会会長に面談。協力依頼。
2006年3月5日、ビラ配布・街頭演説・署名活動、表町商店街、岡山市表町(天満屋)百貨店前通行路一帯。
2006年3月10日、ビラ配布・街頭演説・署名活動、岡山県庁前、岡山県庁前道路一帯。
2006年3月17日、ビラ配布・街頭演説・署名活動、岡山県庁前、岡山県庁前道路一帯。
2006年3月23日、ビラ配布・街頭演説・署名活動、岡山県庁前、岡山県庁前道路一帯。
2006年3月26日、ビラ配布・街頭演説・署名活動、表町商店街、岡山市表町(天満屋)百貨店前通行路一帯。小笠原賢二氏が参加し応援演説。
2006年5月頃、(両備バスと朝油化との)和解調書入手。(両備バス?が1982年に旭油化工業跡地を取得するに当たり有害物質の除去を条件とし、違反したときの損害賠償金額を明記して買収した裁判記録)。
2006年6月5日、岩野邸の倉庫工事で庭を掘削中地下20cmぐらいから黒い土と刺激臭のするガスが出てきたので施工業者は工事を中断し警察と管理会社へ連絡。住民が関係者に連絡し、岡山市・西大寺警察署2名(生活安全課、土壌サンプル持ち帰り)が駆け付ける。なお両備バスと岡山県は連絡するも来ず。瀬戸内海放送テレビ取材あり。
2006年6月7日、読売新聞取材あり。取材中記者は蒸発するガスでむせかえる。
2006年6月8日、販売会社の両備バス?が現地確認に来ないので復旧作業ができず、掘削跡地にビニールシートで覆いをし、杭を打って立入禁止の表示をする。
2006年6月7日〜12日、西大寺警察署・岡山検察庁・岡山市(環境規制課・総務課)・岡山県庁(産業廃棄物対策課・秘書課)・岡山県警に相談。
2006年6月9日、西大寺警察署生活安全課が土壌サンプル追加持ち帰り。最初持ち帰ったサンプルでは足らないとの事。
2006年6月15日、西大寺警察署(相談課・生活安全課)・岡山県警(生活安全課)に被害届(廃棄物不法投棄)について相談。
2006年6月20日、岡山市(秘書課・環境規制課)が現地訪問。
2006年6月24日、大橋光雄氏(廃棄物処分場問題全国ネットワーク事務局長)が来訪。これほどのものが出ながら行政が動かない事には憤慨され、「住民がもっと言わないと」と少し叱りつつも励ましてくれた。
2006年6月、有志の会を解消し、関係機関への要請・陳情等、公害調停・民事裁判に向け「小鳥が丘団地救済協議会」結成。
(「小鳥が丘団地救済協議会」の活動)
2006年7月、「小鳥が丘団地救済協議会」でホームページ開設。
2006年7月13日、環境省中四国地方環境事務所を訪問。説明と相談。
2006年7月26日、岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結について報道。
2006年8月17日〜9月11日、「ホームページ開設のお知らせ」チラシ配布、(県会議員会館・岡山県庁・岡山市・和気町・備前市・赤磐市・瀬戸内市・倉敷市・倉敷議員会館・総社市・総社議員会館・岡山大学宿舎・岡山振興局・岡山東及び西社会保険事務所・瀬戸町・岡山県北方面の各市及び町及び振興局・岡山南方面の各町)、約2900枚。
2006年8月29日、両備グループ代表に両備バス?が開発した小鳥が丘団地住民の庭から黒い土とガスが出て担当者に連絡したが現地確認の対応もない事の改善要請文を期限付きで配達証明郵便で郵送。
2006年8月31日、環境省中四国地方環境事務所より電話にて回答。検討したが難しい、土壌汚染対策法で相手方と話し合うしかないと回答。
2006年9月6日、要請していた土壌調査分析結果について西大寺警察署(生活安全課)より電話回答。犯罪になるようなものは何も出てない。
2006年9月6日、西大寺警察署(生活安全課)を訪問し土壌調査分析結果の資料閲覧を要請。処理法違反を含めて犯罪性はない、犯罪捜査に関する資料は公開できない、土壌の入れ替えは通常の処理をしても警察としてはかまわない(持ち出しOK)、何故住民全体で問題にしないのか、(周辺住民の20年のしがらみがあるんでしょうねと担当者が感想を述べる)。
2006年9月15日、西大寺保険所へ土壌検査依頼に行く、出来ないと言われ、指示された岡山市保険福祉会館2F環境衛生課に行くが、土壌検査は出来ない、他の相談窓口は無いと回答。
2006年9月15日、岡山市(環境保全課)訪問。庭の土を自費で入替えると申出ると、小鳥が丘団地に土壌汚染は有ると初めて発言した。土壌を自由に搬出出来ない旨を文書で指示するよう要請。
2006年9月26日、岡山裁判所で裁判について説明を聞く。
2006年10月5日、汚染土壌の処分方法について岡山市環境保全課から文書を受領。小鳥が丘団地の土壌については、指定区域外の土地ではあるが、指定区域と同等の方法で適正に処分してください。
2006年10月9日、ジャーナリスト井部氏が再度取材に来訪、それに伴い愛知小牧市から丸山氏、木下氏、が現地視察。
2006年10月11日、岡山市水道局を訪問。開発当時の水道鉛管埋没工事状況の詳しい回答書要求。
2006年10月13日、自宅庭掘削跡を埋め戻し中に住民(岩野氏)がガス中毒で倒れ入院。
2006年10月17日、両備バス?代表取締役社長へ申し入れ書を内容証明郵便で出す。
2006年10月27日、岡山弁護士会に無料相談。
2006年10月27日、岡山市(環境保全課)訪問相談。個人所有地は行政では検査できない。岡山大学委員会は委員会意見書でなく、両備意見書だから、両備が代読したものと考える、と回答。
2006年10月30日、両備バス?顧問弁護士6名連盟により、ご連絡と題して返書。団地住民全員を代理するものでないので個人の意見として承る、自宅庭の硫酸ピッチ騒動については土壌の分析結果でそのような事実が判明して無いのであれば即刻止めてください。
2006年11月1日、岡山県警本部へ宅建取引業法違反で両備バス?を告訴。時効のため不受理。

2006年11月2日、岡山県警本部生活環境課を訪問。時効に抵触しない別の項目違反について相談。
2006年11月10日、国土交通大臣へ質問状。

2006年11月10日、河田英正法律事務所を訪問し相談。
2006年11月14日、岡山市(環境保全課)に愛知県小牧市土壌汚染問題で小牧市が土壌調査した事例を研究するよう要請。
2006年11月15日、国交省より電話回答。岡山県に連絡しておくから相談してください。書類を見る限りでは、有害物質の除去を含めて、権利・義務の全てを、両備バスが引き継いだ事になります。汚染原因者と同じ立場になります。
2006年11月16日、国交省の電話回答で岡山県建築指導課訪問し相談。
2006年11月13日〜11月20日、岡山県警本部(生活環境課)・岡山市(環境保全課・秘書課)・岡山県(循環型社会推進課)等を何度も訪問面談。
2006年11月17日、環境大臣へ質問状。
2006年11月24日、法務大臣へ質問状。
2006年11月24日、岡山県建築指導課に、11月16日教示された、申立書(宅地建物取引業免許の適性について(両備バスの行政指導について))を提出。(住宅地図を添えて)
2006年12月1日、環境省から回答書。地域の土壌環境行政を所管する岡山市が対応していると認識、岡山市とよく相談して頂きたい、本件に係る土地の売買に関する両備バスの責任については、民事的に解決されるべき事案と考えております。
2006年12月4日、チラシ配布500枚。
2006年12月7日、法務省から回答書。本件については、個別の具体的事件に関することであり、当省では対応いたしかねる旨。
2006年12月9日、週刊金曜日に小鳥が丘団地土壌汚染問題第2弾が掲載(井部正之氏報道)。
2006年12月22日、TBSテレビ朝ズバ!番組担当者取材来訪。
2006年12月27日、岡山市(秘書広報室)訪問。愛知県小牧市土壌汚染問題で環境保全課が1月中下旬視察で小牧市と折衝中との確認がとれた。
2006年12月28日、岡山市環境保全課審議官他1名が岩野邸で事情聴取。
2007年1月19日、岡山市(環境保全課)小牧市視察実施。
2007年1月24日、岡山県知事へ要望書(2度目)
2007年1月30日、岡山市長へ要望書。
2007年2月1日〜2日、テレビ朝日報道ステーション担当ディレクターが取材下見に来訪。
2007年2月5日、岡山県庁で(循環型社会推進課)から、1月24日に提出した岡山県知事宛て要望書、の回答を口頭で受ける(1度目と同じですと回答)、文書回答を要望する。
2007年2月5日、岡山県備前県民局を訪問。沼川に油が流れている件を相談。
2007年2月6日、岡山県備前県民局2名現地確認。沼川護岸が原因でなく宅地土壌の問題と思われるので住民から岡山市に相談するよう回答。
2007年2月6日、住民が岡山市に道路地下から水の流れる音がする件を連絡。
2007年2月7日、岡山市西大寺支所建設課が道路地下から水の流れる音がする件で視察。普通の道路保全だけでは無いので事情を確認してから連絡する。(土壌汚染の関係もあるので)。
2007年2月7日、岡山市長より回答書。両備バス?が設立した環境対策検討委員会での審議の結果、健康への影響が直ちに懸念されるものではないと判断されていることから、現時点では、市が主導して土壌調査等を実施することは考えておりません。
2007年2月8日、羽原弁護士事務所を訪問し河田弁護士を含め救済協議会住民で協議。時効中断するので公害調停を、まず行なう。自治会委員会からも公害調停の相談を受けていて23日の住民総会で説明依頼を受けているが救済協議会からの相談が先なので一緒にやるのであれば受けるとの羽原弁護士の意向。目的が同じである事、住民不利になる情報を両備に漏らさない事、が合意できれば一緒にやれると伝えた。
2007年2月9日〜12日、テレビ朝日報道ステーション取材。地質学者の楡井久先生やニュースキャスター長野智子氏が訪れ庭先から汚染物質が出た岩野邸庭の地質調査、住民の聞き取り取材、旭油化元関係者や当時の様子を知る周辺住民に聞き取り取材。救済協議会住民はもちろん自治会委員会住民も全面的に協力。
2007年2月13日、岡山県生活環境部(環境管理課・循環型社会推進課)より、2月5日に要望した回答書受領。 岡山県知事あてに提出した要望については岡山市と十分に協議するように。
2007年2月13日、岡山県建築指導課より、2006年11月24日申請の申立書、の回答書受領。違反行為等が行われてから長期間を経過した後の行政処分は行政の裁量の範囲を超え、裁量権濫用にあたるおそれがあることなどの観点から行政処分を行うことが困難。
2007年2月19日、当初から相談している羽原弁護士から、テレビ朝日報道ステーション取材ディレクター2名が、経緯と今後の予定、につき取材があるので同席を依頼される。ディレクターから、平等を期すため来週は相手方の両備バス?の取材をすると知らされる。
2007年2月21日、テレビ朝日報道ステーション取材放映中止。ディレクターから突然の言葉。地質調査の分析結果報告だけでもと要請するが上司と相談してみると保留していたがその後連絡が取れなくなり、羽原弁護士から問い合わせすると開示できない旨回答。
2007年2月26日、岡山市に公文書開示請求、1月18日環境保全課小牧市視察に関する一切の文書。2007年3月9日、開示。
2007年3月4日、小笠原賢二氏の市会議員選挙事務所開き参加。小鳥が丘団地土壌汚染問題についてスピーチ。
2007年3月6日、自治労岡山県本部で委員長と面談。協力要請。
2007年3月10日、環瀬戸内海会議事務局長、松本宣嵩氏現地視察。
2007年3月13日、岡山地方法務局内人権相談事務所を訪問相談。
質問:土壌汚染の分譲住宅地を知らずに購入して、健康被害に遭い宅地建物の価値も無くなったのに、連絡しても放置されたことは人権侵害だと思う。回答:司法手続きの検討しかないと思う。岡山市には相談があった事は連絡しておきます。
2007年3月13日、岩野邸庭の土壌調査を依頼していた倉敷市水島の民間土壌分析会社が3月26日実施で土壌調査を受託。
2007年3月15日、倉敷市水島の民間土壌分析会社が土壌調査を辞退。
2007年3月20日、小鳥が丘団地救済協議会の郵便振替口座開設申し込み。
2007年4月、小鳥が丘環境対策委員会(自治会委員会)に連携を申入れたが方針が違う事を理由に断られる。 (自治会委員会の方針)― この地に永遠に住み続けるために、安全かつ安心して住める町にしたい、そのため10年〜20年かけても地道に活動する。 (救済協議会の方針)― 健康を犠牲にしてまで住み続ける事にこだわるべきでない、まず先に住民移転を要請し実現した後で土壌改良を目指す方が解決しやすい。
2007年4月4日、兵庫県姫路市?ニッテクリサーチに土壌調査を発注。倉敷市水島の民間土壌分析会社が辞退した教訓に学び調査目的を変更した。
2007年4月7日、河田英正弁護士が「小鳥が丘団地」現地視察。ガスの蒸発臭や油の滲み出し等を確認。河田弁護士の弁「弁護士は現地に行って困っている状態を見ないと力が湧いてこないのですよ!」。
2007年4月9日、兵庫県姫路市?ニッテクリサーチが岩野邸土壌調査実施。
2007年4月15日、大阪市立大学の畑 明郎 教授が現地視察。
2007年4月15日、自治会委員会の役員会に合同公害調停を申入れたが不承知なので一緒に出来ない旨、羽原弁護士に連絡。
2007年4月15日、河田弁護士に救済協議会だけで公害調停申請依頼。河田弁護士は団地住民全体でやらないと有志での公害調停は意味が無い、民事裁判しか無いと回答。民事裁判は救済協議会メンバーで協議してないので依頼を保留する。
2007年4月20日、地元岡山県の片山虎之助議員へ公開質問状送付。回答なし。
2007年4月27日、?ニッテクリサーチが岩野邸土壌調査結果報告書を持参。
2007年4月28日、岩野邸土壌調査結果報告書を畑 明郎 教授に郵送。意見を伺う。
2007年4月30日、岩野邸土壌調査結果報告書についての畑 明郎教授の意見がメールで来る。(内容は、前掲 「1. 土壌汚染の概要 住民土壌汚染調査」に掲載)。
2007年5月12日、岡山シティーホテル桑田町で記者会見し畑明郎教授が「住民による土壌調査結果」を報告。
2007年5月14日、岡山県循環型社会推進課及び岡山市環境保全課に岩野邸土壌調査結果報告を提出し相談する。
2007年5月、複数の有識者から、私たちが集めた資料があれば十分裁判になるとアドバイスがある。
2007年5月21日、「小鳥が丘団地救済協議会」メンバーに民事裁判提訴の最終確認。
2007年5月26日、読売新聞大阪本社記者から電話取材。
2007年6月、小鳥が丘団地救済協議会のうち3世帯が民事訴訟を決意。
(「小鳥が丘団地町内会」の動き)
2006年6月25日、小鳥が丘団地町内会臨時総会で1班〜3班と4班〜5班に分割を承認(4班〜5班は別の会社が開発し完成後に小鳥が丘団地町内会に18世帯が加入、宅地の履歴が違う事から町内会全体の共通問題でない事が理由)。翌年4月の新年度から小鳥が丘団地町内会は35世帯となる。
(「小鳥が丘環境対策委員会(自治会委員会)」の活動)
2007年7月10日、小鳥が丘住民23人、岡山県公害審査会に公害調停を申請(相手方は旧両備バスと岡山市)。
3.裁判経過及びその時期の特記事項
2007年6月11日、河田弁護士に救済協議会3名で民事訴訟を依頼。
2007年6月11日、岩野邸で22時頃、家庭用ガス漏れ警報器が鳴る。プロパンガスの漏れではない。
2007年6月13日、西大寺消防署上道出張所、岩野邸ガス警報器作動した件で調査。
2007年6月16日〜17日、環瀬戸内海会議第18回総会(会場は瀬戸内市牛窓町前島)に参加し、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題を報告。
2007年6月22日、岩野邸で21時頃、再び家庭用ガス漏れ警報器が鳴り西大寺消防署上道出張所に通報。消防車が駆け付ける。
2007年6月23日、両備グループ監査室 設立
設置場所 旧両備バス本社:岡山市錦町7-23
組織および就任者
監査室長 佐藤允彦 ?中国バス専務取締役 兼務 監査室主任監査役 窪田新治、
監査室主任監査役 桑原彰一郎 監査室分析統括監査役 福間和興
2007年7月3日、岩野邸で18時40分頃、今夏3度目の家庭用ガス漏れ警報器が鳴り西大寺消防署上道出張所に通報。消防車で駆け付けるが、消防署では危険な時に駆け付けるしか出来ないと説明。
2007年7月7日、週刊プレイボーイのルポライターが現地取材。
2007年7月11日、岩野邸で20時頃、今夏4度目の家庭用ガス漏れ警報器が鳴る。窓を開け扇風機を回して換気し自己防衛する。通報せず。
2007年7月13日、河田弁護士が住民3名の代理人として両備ホールディングス株式会社(旧両備バス?)へ通知・催告書を郵送(提訴までの準備期間がいるので時効を6か月間延長)。
2007年7月19日、午前に不動産取引会社代表が現地視察。午後は鬼木のぞみ市会議員現地視察。
2007年7月28日、両備ホールディングス株式会社より回答書。法廷で全面的に争う。
2007年7月28日、技術士(建設)の方が現地視察。
2007年7月31日、週刊プレイボーイに「産廃に沈む住宅地」と題して小鳥が丘団地土壌汚染問題が掲載される。
2007年8月23日、おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会、水・土壌汚染対策研究部会第22回セミナーに参加。小鳥が丘団地に来られた、畑 教授、楡井教授が講演。
2007年8月31日、小鳥が丘団地救済協議会メンバーのうち3世帯が岡山地方裁判所へ民事提訴(住民訴訟第一次)。
2007年10月5日、みずしま財団塩飽氏・東京経済大学の磯野教授が現地視察。
2007年10月5日、技術士(環境)の方が現地視察。

2007年8月23日 おおさかATCグリーンエコプラザでOAP等の土壌汚染問題等についてのセミナーに住民が参加し、小鳥が丘土壌汚染の状況を説明する。

2007年10月28日、(住民訴訟第一次)住民と支援者でフォーラムを上道公民館で開催。
畑 教授が基調講演、現地報告として愛知県小牧市の丸山氏と小鳥が丘団地救済協議会が汚染問題を報告、総合司会に石井とおる氏で進行。小鳥が丘住民や関係者に参加を呼びかけ、民事訴訟の経緯と被害当事者住民が積極的に立ち上がるよう呼びかけ。

おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染会員(技術士 環境カウンセラー 土壌環境監理士等)が小鳥が丘団地の土壌汚染現場を確認すると共にフォーラムに参加する。

2007年10月、自治会委員会の小鳥が丘住民23人、公害調停打ち切り。
2007年10月 おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会で取り上げられる。
2007年11月13日、岡山地方裁判所、初回口頭弁論(住民訴訟第一次)。
2007年11月、自治会委員会の小鳥が丘住民23人から依頼された弁護士から証拠資料の提供要請あり。了解する。
2007年12月11日、住民訴訟第一次(3世帯)、第2回口頭弁論。
2007年12月27日、自治会委員会の小鳥が丘住民23人で住民訴訟第二次(18世帯)、民事提訴。
2008年1月13日、毎日新聞記者2名が現地視察。
2008年1月23日、財団法人PHD協会及びその研修生が現地視察。
2008年1月29日、住民訴訟第一次(3世帯)、第3回口頭弁論。
(裁判長)
住民訴訟第二次(18世帯)の初回口頭弁論が3月4日にあるので次回口頭弁論は其の後にしたい、被告の資料は同じものは資料番号を同じにしてもらいたい。被告答弁は同じでしょう?裁判は個々に並行して行う。
(被告弁護士)
違う個所もあるのでその答弁は別にして同じ答弁の箇所は番号を揃える。
2008年1月、岩野氏転居。
2008年2月12日、?環境新聞社・?エイチテック が現地視察。
2008年3月4日、住民訴訟第二次(18世帯)、初回口頭弁論。裁判所は第一次訴訟と並行して個々に行う日程を組んだため以降の第二次訴訟の口頭弁論期日は不確実につき省略。
2008年3月6日、若井たつこ市会議員が岡山市議会で小鳥が丘団地土壌汚染問題を質問。(土壌汚染地域の税減免措置について)
2008年3月11日、住民訴訟第一次(3世帯)、第4回口頭弁論。
(裁判長)
訴訟第二次(18世帯)で現地視察することになっているので一緒に立ち会いませんか
(河田弁護士)
土壌掘削調査等を実施しながら現地立ち会いでないと効果的でないのでは?。
2008年4月4日、住民訴訟第一次(3世帯)、第5回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
(裁判長)
調査不足ではないかと思う。
2008年5月19日、住民訴訟第一次(3世帯)、第6回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
(裁判長)
5月30日に行う現地視察で訴訟第二次(18世帯)は学者の中地氏が立ち会うことになっている。
(河田弁護士)
こちらも 畑 教授の立ち会いを予定している、機械で2か所掘削し、より効果的になるよう予定している。
2008年5月30日、岡山地方裁判所が、小鳥が丘団地現地視察(13:30〜15:30)。
裁判官、原告住民および弁護士や学者、被告弁護士が、多くのマスコミや関係者の見守るなか、小鳥が丘団地内を見て回る。住民訴訟第一次(3世帯)は庭と駐車場をユンボで2箇所掘削、住民訴訟第二次(18世帯)は庭を住民が削岩機で3箇所と地盤沈下で下がった塀や、油や石灰と思われる液体が滲み出ている擁癖や、玄関前側溝から可燃性ガスの泡が吹き出している箇所を住民が説明した。

(写真は「土壌汚染問題裁判・公開調査 投稿者: 竹永みつえ」から拝借しました。謹んでお礼申し上げます。)
http://okjcp.jp/t/?p=1837
2008年7月9日、住民訴訟第一次(3世帯)、第7回口頭弁論準備手続き(進行協議) 。
5月30日の現地視察DVD添付の準備書面提出。
(裁判長)
岡大検討委員会の会議録原本の提出を要求中、被告側は拒否。
2008年8月12日、ジャーナリスト山本節子氏が現地視察。
2008年8月30日、滋賀大学学生が研修で現地視察。
2008年9月22日、東京経済大学の磯野弥生教授・一橋大学の山下英俊 準教授が現地視察。
2008年9月29日、住民訴訟第一次(3世帯)、第8回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
(裁判長)
被告はこれ以上調査はしないとのことなので、原告側で調査といっても費用負担は難しいと思うので裁判所から的を絞った調査提案をしようと思う。
(河田弁護士)
原告側は畑教授の意見書を提出する方向で検討する無論原告費用負担で。
(裁判長)
それは助かります。
2008年10月24日、(3世帯)住民、代理人弁護士と供に大阪市立大学研究室に畑 明郎教授を訪問して原告・被告の調査資料を提出、検討を約束。
2008年11月10日、(3世帯)住民、畑 明郎教授より「岡山市小鳥が丘団地土壌汚染裁判資料コメント」と題して意見書受領。
2008年11月17日、住民訴訟第一次(3世帯)、第9回口頭弁論準備手続き(進行協議)。畑 明郎教授の意見書を提出。 住民訴訟第二次(18世帯)は学者の調査方法意見書を提出する方向で準備していると説明あり。土壌改良の為の土壌調査は詳細な調査が必要なので費用は高額になると思われ実現できるのか推移を待つ事になりました。
2009年1月14日、雑誌エコロジーの依頼で井部氏現地取材。

2009年1月30日、住民訴訟第一次(3世帯)、第10回口頭弁論準備手続き予定延期。 これは住民訴訟第二次(18世帯)が現地調査の概要を提示することになっていましたが、その費用が高額になり、とうていその費用負担ができないことが判明してそのやり方を再提示することになったようです。さらに調査を簡略化して効果的な結果が得られる方法(調査箇所を減らすなど)を検討し、これについて被告側の対応をみることになったとのことです。
2009年4月4日、近畿弁護士会連合会及び大阪弁護士会の弁護士6名で現地視察
2009年4月6日、住民訴訟第一次(3世帯)、第10回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
大掛かりな調査は費用の面で出来ないが、訴訟第一次(3世帯)で出来る団地内の土壌調査を原告負担で実施し損害立証していくと答弁した。
訴訟第二次(18世帯)の土壌調査は、住民が費用負担に耐えられるか又被告両備に折半負担を提案予定だが両備が責任を認めていない現状や全面的に争う姿勢から、この方法では展望が開けない(期待が持てない)と判断し、訴訟第一次(3世帯)単独でまず損害賠償で勝利する方向に方針転換しました。
2009年6月10日、住民訴訟第一次(3世帯)、第11回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
訴訟第一次(3世帯)で出来る団地内の土壌調査を近く実施予定なので調査結果は次回口頭弁論までに提出したい。
2009年6月13日、訴訟第一次(3世帯)は環境総合研究所に現地地質調査分析を依頼し職員を現地に派遣してもらい住民による調査サンプル採取を行う。(モニター井戸水質3か所、原告敷地駐車場土壌1か所、沼川護岸擁護壁付着物1か所、合計5か所)。
2009年7月9日、環境総合研究所から調査分析報告書が送られてくる。護岸の付着物もはっきりと油分が検出されていた。いずれも汚染の程度は著しいものとなっていたので早速、調査報告書は証拠として裁判所に提出。
2009年7月9日、ジン・ネット(日本テレビ系)取材のため現地視察。
2009年9月1日、住民訴訟第一次(3世帯)、第12回口頭弁論準備手続き(進行協議)。 損害賠償結審に向け最終答弁書を提出する旨申し入れした。
2009年9月5日、(3世帯)訴訟の住人藤原氏転居。
2009年10月20日、住民訴訟第一次(3世帯)、第13回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
原告住民3名の陳述書は提出済み。裁判長から結審に向け確認があり次回は原告本人尋問および被告反対尋問が予定された。
2009年12月8日、住民訴訟第一次(3世帯)、第14回口頭弁論。 原告本人尋問実施。3名合計で実質尋問時間が3時間。
次回は被告が住宅の価値はあると主張する根拠として小鳥が丘団地内の競売物件の資料を提出する事になり2010年1月19日に進行協議を設定。
2009年12月18日、おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会、水・土壌汚染対策研究部会第35回セミナーで、小鳥が丘団地救済協議会が「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」と題して講演。

(写真はATCで質疑応答の司会をする畑明郎先生と土壌汚染タレントの藤原きよみさん、後ろは新名康幸事務局長です。)
2009年12月 100周年記念9トンの餅つき大会 両備グループ 代表 小嶋光信

●岡山市の土壌・地下水汚染対策について
岡山県環境への負荷の低減に関する条例について
平成14年4月1日に『岡山県環境への負荷の低減に関する条例』が施行されました。(一部の規定は平成14年10月1日から施行)有害物質取扱事業場の設置者は、当該事業場の敷地内で土壌又は地下水汚染を自主な調査により発見したときは、速やかな届出が義務づけられました。
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1
岡山市環境局環境保全課 水質係
TEL 086-803-1281
FAX 086-803-1737
E-mail kankyouhozen@city.okayama.jp
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyoukisei/dojou-tikasuiosen/dojyou-tikasuiosen.html
●参考リンク
国会と藤原きよみ(環境カウンセラー)岡山市の小鳥が丘団地Vs両備の土壌汚染事件の議論
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/49372319.html
藤原きよみの海が好き!釣りが好き!地球が大好き!ブログ
ATCグリーンエコプラザです☆
http://kiyomi.blog.eonet.jp/kiyomi/2009/12/post-9295.html
岡山で両備が販売した小鳥が丘団地の土地・地下水汚染事件の経緯
http://beauty.geocities.jp/oecacasa/kotorigaokanorekisi.htm

写真はおおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会の土壌汚染相談窓口の土壌汚染タレントの藤原きよみさん(環境省登録:環境カウンセラー)です。
この資料は岡山市両備小鳥が丘団地土壌汚染事件一次訴訟原告団の資料に基づいており、事実内容を保障するものではありません。また、損害等について一切の責任を負うものではありません。
事実と異なる表現等のご意見がありましたら、下のコメント欄にご記入願います。
2009年12月27日
第171回国会 環境委員会 畑明郎先生の発言
第171回国会 環境委員会 第5号
平成二十一年四月十四日(火曜日)
大阪市立大学大学院特任教授日本環境学会会長 畑 明郎君
本日の会議に付した案件
○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付)
○委員長(有村治子君)
ただいまから環境委員会を開会いたします。
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○参考人(畑明郎君)
大阪市立大学の畑と申します。
資料としましては、昨年十一月に日弁連の機関誌の「自由と正義」という雑誌があるんですけれども、それに土壌汚染対策法の特集がありまして、それの巻頭論文を付けております。二番目には大塚先生も書かれていますので、また参考にしていただければと思います。
元々、私は七年前にここに、法律できるときの、制定のときの参考人で、大野参考人と私とあと二人の方だったんですけれども。そのときに、ちょうど五月だったんですけれども、四月ですから今、似た時期ですけれども、非常に問題はいっぱいあるということで、当時は一応民主党の福山議員の紹介でこれ参加したわけですけれども、十五項目ぐらい問題あるということで、中でも大きな問題点は、二番目の、この法律はやっぱり土壌汚染の事後対策法である、未然防止法ではないということです。
それから、地下水の汚染の防止の観点がほとんどないと。土は人間が動かさないと動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますので、そこの防止の対策がこの法律では非常に問題があると。
それから、五番目の三条の調査対象ですね、これが一番問題なんですけれども、いわゆる水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止時、それも法律施行後の廃止時、さらに宅地等への転用する場合だけ、そういう形で非常に法対象を狭くしていると。それから、それ以外にも金属鉱山・製錬所、廃棄物処分場の跡地周辺、軍事基地等を対象外にしていることです。
それから七番目が、調査、対策を原則として汚染原因者でなく土地所有者等に義務付けている点です。
それから十番目が、対策は原則として覆土、つまり五十センチ以上の盛土でよしとする、土壌の浄化は特別な場合だと。これは保育園とか幼稚園とかそういう場合だけだという感じになっておりまして、この法律制定時から非常に問題があったと思っております。
とても土壌汚染問題の根本的解決につながる法律とは言えませんし、そればかりか、土壌汚染を覆土で隠ぺいし、言わば臭い物にふたをする、後世に負の遺産を残すことを合法化するざる法ではないかということで批判したわけです。
やはり法施行後五年、今六年ですけれども、たった現在、そのざる法性はますます明らかになったのではないかと思っております。
二番目のは、もう御存じのように、先ほど言われましたように、法対象が非常に、二%しかないとか、廃止工場の八割は調査を逃げている、つまり宅地等に用途を転用しないということで、ブラウンフィールド化している。
それから対策も二%しかないと。それから、四条の調査命令も、発動したのは五件。これは、環境省は課長会議の何か通達出していまして、一キロ以内ぐらいに直接水道の飲み水に使用している場合だけ発令しろ、それ以外発令するなというそういう通達を出しておりまして、結果的に五件しかないと。しかも、それは岩手県とか鳥取県とか、皆さん御存じの特定の知事がおられたときしか、県しか命令を出しておりません。そういうことで、非常に実効性の乏しいざる法となっていると思います。
それで、いわゆるこの法律自身は盛土、舗装等で摂取経路を遮断する対策で十分であると言っているんですけど、リスク管理といっておりますけど、汚染土壌が残っている限り半永久的に管理する必要があるわけですね。
特に問題なのは地下水の問題です。土壌が汚染されていますと、必ずそれに接触している地下水は汚染されます。その地下水は勝手に動きます。ということで、確かに直接都市部では飲み水にしていないんですけど、地下水によって汚染が拡散するという点で、その地下水のくみ上げ処理とか遮水壁で囲むとか幾つかの方法があるんですけど、一〇〇%水をカットすることは技術的には困難です。
幾らお金を掛けても困難です。ということで、こういうリスク管理には非常に問題があるということで、やはりリスクゼロ型の掘削除去の方が結果的には多く採用されているし、その方が私はいいと思っております。
当然それを掘削除去した汚染土壌については適正に処理することは当たり前のことでして、これは技術的に、最近、秋田とか川崎とか幾つかにその汚染土壌をきれいにするプラントもできておりますし、問題はコストですね、お金が掛かりますから。その負担をだれがするかという問題だと思っております。
それから三番目の、大野さんのおられる土環センターの調査によれば、いわゆる製造業だけじゃなくてサービス業も含めて九十三万か所ぐらい汚染地があるんではないかと推定されています。
これの調査費用が二兆円で、浄化費用が十一兆円で、合計十三兆円の土壌浄化ビジネスです。既に二〇〇七年でほぼ二千億円近い、年間二千億円の土壌浄化ビジネスになっております。二〇〇八年はちょっと景気の悪化で初めて落ち込むようですけど、それまではずっと右肩上がりで土壌浄化ビジネスの業界は成長しております。
それと、あと汚染地ですけど、基本的には東京、関東、近畿、中部の三大都市圏のいわゆるオールドエコノミーというか、そういう重化学工業の工場地帯のところに多いということです。
それから四番目は、私自身いろんな事件にかかわっているんですけど、基本的には市民、住民の依頼によってやってきたものが二十件以上あります。その中で法対象になったものは、この二十件のうちわずか三件です。
大阪のカネボウの中研の跡地、神戸の日本テルペン化学、川西の中央北地区、これは皮なめし工場です。ということで、大半が法施行前に廃止された工場、事業場や廃棄物処分場周辺の跡地です。ということで、法施行前に廃止された工場跡地、特に有害物質を取り扱っていた事業場をやっぱり法対象にする必要があるし、ドイツなんかでは廃棄物処分場の跡地周辺も法対象にしております。
あと、先ほど出ましたように、私はこの二番目の、?の大阪アメニティパークの、OAPの事件にかなり三年間ぐらいずっと住民に頼まれてかかわったんですけど、このときには土壌汚染対策法は全く役に立たなかったです。宅建業法でやっと三菱は対策とか調査をやったということになったわけですね。
それからあと、七番目以降、そこに滋賀県の例がありまして、私、滋賀県に住んでおりまして、有村委員長も滋賀県出身だそうなんですけど、守山、野洲とか信楽では、これは水道の飲み水の汚染が起こりました。
それから、住友大阪セメント、セメント工場もいろいろ問題あるんですけど、それから、今、滋賀県の知事が栗東の新幹線の駅止めましたけど、この産廃処分場の問題がもう一つありまして、そういう周辺で地下水汚染、土壌汚染が起こっております。
それから、このテルペン化学で、神戸の、非常に印象的だったんですけど、法対象になっているんですけど、法施行時に稼働していた施設では使っていた薬品だけの元素を、有害な元素を対象にしていまして、過去にあった施設の有害物質についてはこれは法対象にならないんだという解釈を神戸市、環境省がしておりまして、それは何かの間違いじゃないかと思ったんですけど、あくまで自主的調査だと。非常に法律自身を狭く運用していると。
いわゆるこういう土壌汚染というのは、一回汚染されますと十年、二十年、三十年、数十年間は蓄積します。そういう意味で、過去の汚染も考慮して調査、対策しないと意味がないと思うんですけど、非常に法律の運用が狭くなっている問題があると思っております。
それから、ここには書いていませんけど、武田薬品の神奈川の湘南工場の最近例知ったんですけど、これは工場の廃止は最近なんですけど、施設が法施行前に廃止されていた、だから法対象にならないと。神奈川県の条例でやっと対象になったという事例がございます。
あと、四日市の例のフェロシルト事件とか産廃処分場の問題とか、あと岐阜とかです。僕自身は、ずっとイタイイタイ病を起こした三井金属の神岡鉱山の排水・土壌汚染対策を四十年近くやっておりますけど、ここは一応今成功しましたけど、工場の下に汚染土壌が残っていまして、約九十トンぐらいカドミウムが残っているんですけど、完全に地下水くむまでに処理するには百年掛かると言われています。
そういう意味で、汚染土壌を残しますと非常に半永久的に処理コストが掛かるということです。結果的には取ってしまった方が安く上がる。これは産廃処分場でも一緒なんですけど、豊島とか青森、岩手のように全量撤去した方が後々ランニングコストというか排水処理とかいろんなリスク管理の費用が結果的には安く上がると思っております。
それから、皆さん御存じの築地市場の問題です。この問題につきまして、一応最近かかわっておりまして、もう御存じなので飛ばしますけど、これは面積的には日本最大の土壌汚染地になりますということで、一千億じゃなくて六百数十億円対策費が掛かる。
それも、二メートル土取って、汚染土壌は下に残ります。汚染地下水は半永久的にくみ上げて処理する、このコストがまた掛かります。そういう対策を東京都がやろうとしています。
今回の法律の件ですけど、僕は基本的にはやっぱりリスクゼロ型の掘削除去の土壌浄化対策の方がいいと思っていますし、盛土、封じ込め等は、こういう安易な対策は問題があると思っています。特に今回の法律はそういう点を、何か掘削除去を排して安易な対策、安上がりな対策を推進、推奨しようとしているということで問題があると思っています。
そういう意味で、東京都の条例とか滋賀県の条例のいわゆる一定規模以上の土地の改変、これは今回の法律には適用されているんですけど、問題はあとは、東京都、あと神奈川県横浜市、川崎市、大阪府等が採用しているんですけど、過去に有害物質を取り扱っていた工場、事業場については条例の対象にするということはやっぱり法律についてもやっていく必要があるんじゃないかと思っています。
それと、滋賀県の条例は、今回、環境省の委員会では全く取り上げられなかったんです。私は滋賀県に今住んでいるんですけど、一応、二〇〇七年に滋賀県の公害防止条例、一部を改正しまして、地下水汚染の未然防止、それから地下水汚染の早期発見と改善、法施行前に廃止された跡地を土壌調査の対象とするというこういう条例を定めて、もう施行しております。
こういうことをやっぱり全国の法律でもやってほしいなということです。やはり条例、要綱の方が進んでいると思いますし、進んだ条例、要綱を参考とした根本的な法改正をやっていただきたいと思っております。
終わりの部分はもう繰り返しになるんですけど、特に強調しますと、やはり法施行前、実際に僕が土壌汚染の問題にかかわっていると、ほとんどは法施行前の工場、事業場の跡地なんです。それも製造業だけじゃなくて、もちろんガソリンスタンドとかそういうサービス業なんかもあります。
そういう法施行前に有害物質を扱っていた工場跡地とか廃棄物処分場の跡地を法対象にする必要があるんじゃないかと思っております。これは日弁連の意見書でも提案されていますし、地方自治体、神奈川県とか先ほどの滋賀県とか東京都とか、条例ではそういうことを定めているところもあります。
それから、やっぱり土壌汚染の未然防止です。こういうことも今回全く入っていませんが、やはり長期的にはこれをやっておかないと、いったん汚染された土は、先ほど大野さん言われましたように、一〇〇%きれいにすることは技術的にはできません、多分幾らお金を掛けても。
そういう意味で、やっぱり汚染しないということが一番大事ですので、未然防止をやっていく必要がある。そのために、やっぱり操業中の工場、事業場についても滋賀県のように井戸を掘って調べる、常時監視するとかそういうことが大事ではないかと思っております。
そういう意味で、確かに今回の法改正は法対象を一定拡大するプラス面あるんですけれども、マイナス面もありまして、特に掘削除去を排するということは問題があるんじゃないかと思っています。
それと、築地市場の移転問題に関連しまして民主党が修正案を出しまして、衆議院で修正案が通ったようですけれども、いわゆる土壌汚染対策法施行以前の廃止工場、事業場であっても、公園、学校、市場等の、これは築地市場を完全に意識しているんですけれども、そういう公共施設等に利用する場合は法対象とするということが通ったことはそれなりに画期的だと思うんですけれども、私としてはやっぱりすべての施行前の有害物質を扱っていた廃止工場、事業場も法対象にすべきではないかと思っています。
そういう意味で、東京都環境条例とか滋賀県の条例とか、あと川崎市、横浜市、大阪府等の進んだ条例、要綱を参考にした抜本的な法改正を今後やっていただきたいと思っております。
あと、新聞記事を幾つか、朝日新聞とか、それから公明党さんの聖教新聞も頼まれまして、最近、三月に。これ百万か所ぐらい汚染用地がある、築地市場のことも書いてくれよということで少し写真とちょっとコメントが入っております。
それと、社民党の社会新報とか、赤旗とか東京新聞とか、あと毎日新聞とか朝日新聞等にも書いておりますし、あと、最後にちょっとありますように、中国の土壌汚染問題、最近中国は恐らく空気も水も土も食べ物も汚染されていまして、非常に問題がありまして、最近中国の土壌汚染のこともやっておりますので、また参考にしていただければと思っております。
○参考人(畑明郎君)
まず、附則三条につきましては、これはもう築地市場の移転問題で衆議院の川内議員なんかと私一緒にやっているんですけど、やはり法施行前の廃止工場、事業場をその法対象にしないという附則三条は取っ払うべきだと私は思っております。
それから、二番目の一定規模の問題ですけど、これはこれでそれなりに評価できるんですけど、ただ、規模だけでやっていいのかという問題があると思います。例えば、水質汚濁防止法の排水基準の適用の仕方なんですけど、有害物質を扱っている場合は排水量に関係ありません。
普通は排水量一日五十トン以上という場合に排水基準を掛けるんですけど、僕は以前京都市の公害の局におりましたけど、そのときには、有害物質を扱っている、それが出る、排水に出るところは排水量に関係なしに排水基準の規制を掛けております。
そういう意味で、やっぱり有害物質を扱っている工場、事業場については、規模についてはむしろ取っ払うべきだと私は思っております。
それから、民主党案の今回の、公共施設等に転用する場合に調査を義務付ける、これはこれでそれなりの意義は、築地市場の移転問題を法対象にするという意味で意義はあると思うんですけど、ただ、これだけではまだ問題があると思っています。
やはりさっき、何度も言うんですけど、過去に有害物質を扱っていた工場、事業場は基本的には汚染している可能性が強いですので、僕もいろいろ、大阪のUSJも住金の跡地なんですけど、あの場合なんかはほとんど工場の敷地内に産廃を埋めていたんです、それも大量に七十万トンという。それが今ジュラシック・パークという恐竜のパークになっているんですけど。
それで、過去に工場、事業場が工場敷地内に産廃を埋めたりとか、それから別に故意でなくても非意図的に液が漏れてしまった、それで床から、それから排水、例えばあとは排水溝です。必ず排水パイプというのは、時間がたちますと穴が空きます。だから、穴が空いて、そこから廃液が漏れてしまって汚染してしまう。
これは大学なんかでもそういう例はありますし、先ほどのカネボウの中央研究所なんかはほとんどその下水管の途中で液が漏れてしまって土壌汚染してしまったという例がありますので、そういう意味で、やっぱりその有害物質を扱っていた工場、事業場については汚染の危険が強いということで調査を義務付けるべきだと思っております。
○参考人(畑明郎君)
掘削除去の問題ですけど、いわゆる環境基準の設定の根拠なんですけど、よく行政とか企業は直ちに影響はないとかいう言い方するんですけど、元々環境基準等はどういう形で設定されたかといいますと、やはりイタイイタイ病とか水俣病のように非常に低濃度の有害物質を長期間暴露することによって被害が起こるわけです。そういう意味で、じわじわと来るものですから、目に見えてすぐ人が倒れるとかそういう急性中毒ではないんです。
そこを逆手に取って、影響はすぐないとか、出ていないとか、直ちに健康に影響はないという形ですぐ行政は逃げる場合が多いんですけど、やはり長期的な影響を考える必要があるということで、土壌の汚染とか地下水の汚染を残すということはやっぱり将来いろいろな問題が起こる可能性があるということで、掘削除去の方がいいと思いますし、それから費用対効果ですけど、これは時間スケールを考慮しないと駄目だと思うんですね。
例えば岩手県の例ですけど、旧松尾鉱山という硫黄鉱山があるんですけど、これ岩手県の方は御存じなんですけど、日本で一番大きい鉱山がありまして、いまだに酸性の水が出てくるんです。北上川を汚染するということで、非常にでっかい排水処理設備が造られています。これ半永久的に稼働しています。それを国とか岩手県は税金でやっているわけです。
そういうコストは莫大なコストになります。そういう意味で、青森・岩手県境の不法投棄のときに、当時の増田知事が、やはり長期的に見ると全量撤去した方が安上がりであると、この松尾鉱山の例を考慮して岩手県はそういう判断を取ったと聞いております。
そういう意味で、本当に、当面はそれは掘削除去はコストは掛かりますけど、長期的に見ると、そういう維持管理コストを考えるとそんなに高いものではないという場合もあるということです。
それから、覆土の問題ですけど、これは用途を非常に限定されます。例えば、通常、ビルなんかを建てる場合は基礎工事をやるわけです、くいを打ったりとかですね。下をかき混ぜますから、そういう工事をしたら、下に汚染土壌が残っているとその汚染土壌の対策も要りますし、五十センチぐらい覆土しても、これは豊洲の例ですけど、あそこは地下水位がほとんどゼロメートルのときがあるんですけど、土を多少上へ入れても、地下水が上昇してきて雨水と地下水が混ざり合ってまたその入れたきれいな土が再汚染される危険性が高いんです。
OAPでもこれは実際に起こったんですけれども、五年ぐらいでもう起こっちゃったんです。ということで、その五十センチぐらいの覆土では将来的には安全な対策にならないし、地下は触れなくなると、地下の倉庫とか地下の構造物を造れなくなる、造りにくくなるという問題はあります。
OAPにつきましてはどうするかといいますと、五十年後建て替えるときにやりますということで三菱は説明している。当面は、二メートル土入れ替えて、地下水はくみ上げて今延々と処理しているんです、コストを掛けて。取りあえずそういう、これは暫定的な対策だと私は思っております。恒久対策はやはりきれいにするということが大事じゃないかと思います。
○参考人(畑明郎君)
今、大塚先生言われましたように、これは廃棄物の問題と一緒でして、廃棄物処理法上いろんなマニフェストとかやっておりますけど、やはり不法投棄はなくなっておりませんし、僕自身も滋賀県の栗東とか四日市の日本最大の不法投棄の大矢知の問題にもかかわっているんですけど、これ同じことが起こり得ると思います。法律で幾ら汚染土壌のマニフェストを定めてフォローしたとしても、やはり限界はあると思います。
そういう意味で、やはりもう少し排出者責任をどう担保していくかという、これは廃棄物も一緒ですけど、取っていく必要あると思います。
これは残土についても一緒でして、残土も結構怪しいものがありまして、僕は汚染土壌も残土も廃棄物扱いというか、廃棄物処理法の対象にすべきだと思います。そういう意味で、もちろん廃棄物処理法ももっと強化しないと駄目なんですけど、強化した上で汚染土壌と残土等を管理していく。
最近でも残土に関連して、石原産業のフェロシルト事件というのがありましたけど、こういうことはついこの間も起こったばかりですよね。あれ、フェロシルトの回収に五百億円掛かるんですよ、これ石原産業が負担して、三年間赤字決算なんです。やっぱりいったんそういう不法投棄しますと非常にコストが掛かるという問題はありますので、この辺は、せっかく法律作ったんですから、きちっとそれは運用というか施行していってほしいなと思っております。
○参考人(畑明郎君)
これは日経新聞等でも拝見しましたけど、この環境債務ということをこういう企業の会計の中に入れていくことについては大賛成ですし、ストック型汚染と僕らは言っているんですけど、土壌汚染と産業廃棄物の問題というのがやっぱり現在はかなり先送りされていると。
言わば臭いものにふたをしてわざと調査しないとか、調査してもできるだけ安価な対策で終わらせて、将来世代にやっぱり負の遺産を送っているところがあると思いますので、やっぱり早めにそういう資産計上していくことはいいことだと思っていますし、非常に面白いのは、上場企業で一番環境債務たくさん計上しているのはOAP事件を起こした三菱マテリアルです。
それと、僕はイタイイタイ病のことをずっとやっているんですけど、結局、イタイイタイ病の場合、公害を出せば結果的に高く付いた例なんですけど、ほぼ掛かった費用が六百億円以上掛かっております。もちろん、死んだ人は、補償を出していますけど、帰ってこないということで、そういう絶対的な損失があるんですけど、経済的な損失という意味で六百億円以上掛かっています。やっとその汚染された農地の復元が来年ぐらいに終わります。
結局ほぼ四十年ぐらい掛かって、最近、三井金属の神岡の社長は朝日新聞に「私の視点」で書いていましたけど、結局四十年掛かって解決したと。そして、住民と企業が信頼関係ができたということで、結局、百億円の公害防止投資を事件が起こる前にやっておけば六百億円の被害は起こらなかったわけです。
結局、公害を出せば、後で非常に社会的コストも企業も負担が重くなるということで、やはり事前にそういう環境債務を計上して対処していくことが今後大事になるんじゃないかと思っております。
○市田忠義君 日本共産党の市田です。
畑参考人にお聞きいたします。
陳述の中でもお述べになりましたが、畑参考人は、リスクゼロ型の掘削除去等の土壌浄化対策、これを排して盛土や封じ込めなどの安易な対策の推奨に今度の法改正がなりかねないと、そう指摘をされています。
私も、今回の改正案で掘削除去の偏重ということが強調されて、現行の指定区域を要措置区域と要届出区域に分類をして、知事が技術的基準に基づいて指示する制度を新たに盛り込んでいると、これが掘削除去の抑制につながるのではないかという懸念をしております。
私事ですが、私は築地に四年前に住んでいまして、今、豊洲に住むという皮肉な、豊洲への移転には私は反対でありますけれども。
畑参考人は、東京ガスの豊洲工場跡地問題あるいは大阪アメニティパークなど多くの土壌・地下水汚染事例にかかわってこられたわけですが、先ほどもお述べになりましたけれども、このリスクゼロ型の掘削除去を抑制して覆土や封じ込めなどのリスク管理型を普及するということについて改めてもう少し詳しくお伺いしたいのと、若干他の参考人の方からも出されたことなんですが、掘削除去というのはかえって汚染地域が広がって汚染の拡大につながるのではないかという考え方についてどうお考えかと。
コスト問題はよく分かりました。中長期的に見れば、中途半端な処理はかえってお金が掛かるというのはよく分かりましたが、今の点について御意見をお伺いしたいと思います。
○参考人(畑明郎君)
確かに、今回の形質変更届管理区域、それから要措置区域ということで、従来の指定区域を二種類に分けて、結局対策を緩める。そして、掘削除去をできるだけやらさないという方向になるおそれは十分あると思っております。
それで、リスク管理という、これは言葉はいいんですけれども、元々この環境リスク論というのはどこから来たかといいますと、アメリカから来たものでして、これBSE問題が一番典型なんですけれども、いわゆる全頭検査なんか要らない、百万人に一人しかBSEにならないんだ、全頭検査のコストは無駄だと。
要は、アメリカの場合はリスクとベネフィットを比較してベネフィットの方が大きければリスクはある程度我慢すると。みんな飛行機とか自動車は交通事故の可能性があるけれども乗るでしょう、ベネフィットがあるから乗るでしょう、環境も一緒ですという形で、こういうことを中西準子なんかは言っているんですけれども、経産省もそういうスタンスなんですけれども、これは僕は全く間違っていると思います。
基本的には、僕はやっぱりEUが取っている予防原則、これは朝日新聞の知恵蔵に環境リスク論とEUの予防原則を比較して書いたことがあるんですけれども、やはり、今EUが進めているRoHS規制とかREACH規制という化学物質の規制は、言わばカドミウムとか水銀とか危ないものはもう製品に入れていかない、工業製品に入らなければできた廃棄物、廃製品も危ないものが入っていないということです。
鉛とか先ほどのカドミウム、水銀など、基本的には六物質に対してはもうやれている。日本のメーカーもEUに輸出はそれができている。自動車とか電気製品を輸出していますから、対応できるんです。
更にもっと、三万種類というすべての工業製品、化学物質に対して規制を掛けようとすると、従来は医薬品と同じように、医薬品だけが安全を証明しなければ販売できなかったんですけれども、すべての工業製品についてメーカーが安全を証明する義務を持たせるという、そういうREACH規制は今もうヨーロッパで始まっています。順次強化されていきますけれども。そういう動きがあります。
それから、やっぱりリスク管理というのは問題ありますし、本当にリスク管理できないんですよね。土壌は確かに人が動かさなければ動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますから、これはどこへ行くか分からないということで、何か法案にもちょっとありましたように、海辺の埋立地はいいんだと、汚染されていても。これはもう論外でして、やっぱり廃棄物処分場は山の中に造るか海に埋めているかどっちかなんですけれども、山の場合はもちろん排水は河川の上流に入ってきますし、海の場合もやはり、大阪湾のフェニックスとかありますけれども、東京湾の埋め立てていますけれども、やはり海の汚染を起こします。
完全にその汚染水を海に流さないことはできません。今、遮水していますけれども、あれは堤防だけ遮水していまして底は抜けていますので、必ず汚染が海に広がります。それで魚の汚染も起こりますし、そういう意味で問題があるということです。
それと、確かに掘削除去した土地をどう処理するかというのはもちろん問題なんですけれども、僕のかかわった京都府の日本最大のクレー射撃場、これは麻生首相が好きらしいんですけれども、要するに鉛の散弾、これを撃つんですよ。それで皿を割るらしいんですけれども。当然鉛の散弾がそこへ散らばって、クレー射撃場の中が鉛で土が全部汚染されちゃったんです。
その土、今京都府立の施設なんですけれども、京都府は十億円以上掛けて全部、秋田県の小坂にあるんですけれども、土壌処理施設で土をきれいにしてまた戻す、そういうことをちゃんとやっているんです。
そういう意味で、それは搬出土壌の処理の仕方、適正な処理をやっぱりどう担保するかという問題でして、これは産廃と一緒でして、ただ今の現状からいくともちろん産廃と同じように汚染土壌がどこへ行っているか分からぬという問題は起こり得ると思いますので、それは十分注意しながらやっていくしかないと思っております。ただ、技術的にはできると思います。
○参考人(畑明郎君)
だから、今回のもちろん一定規模以上の、多分三千平米ぐらいになると聞いておりますけれども、それはもちろん改善、今の法律の、ざる法のざるを少し目を埋める、目を小さくするということにはなると思いますけれども、完全にざるは目が埋まった状態ではないと思っております。
やはり法施行前の有害物質を扱っていた工場、事業場、これは水質汚濁防止法の特定施設以外にもいっぱい出ていますので、やっぱり有害物質を例えば運搬とか保管したところでも汚染は起こっていますので、それから交通機関とかそういうところなんかでも起こっていますので、やっぱり過去のこれは負の遺産だと。製造業の当初負の遺産という言葉が言われたんですけれども、土壌汚染は。過去の負の遺産をいつかの時点で一掃するためには、きちっとまずはやっぱり調査をすべきであると。
もちろん一〇〇%の工場が全部汚染されているとは僕は言いませんし、多分半分ぐらいだろうという土環センターの推定なんかもありますけれども、やっぱりやってみないと分かりませんから、調査はまずちゃんとすべきである。
これはカドミウム汚染米と一緒でして、ついちょっと前、一九九八年ぐらいに、五十ヘクタール単位にワンポイントでじゅうたん的に米を全部調査したら、またいっぱい準汚染米が出てきたという問題がありました。そういう意味で、やっぱり危ない可能性のある工場、事業場については調査を法的に義務付けてしていくべきであると。
あと、対策はどうするかというのは、やっぱりケース・バイ・ケースになると思いますけれども。
○参考人(畑明郎君)
私は元々の出身が京大の工学部の金属でして、それでずっと金属にこだわってやっているんですけど、金属というのは、確かに人間生活とかいろんな経済に役立っているんですけど、プラス面とマイナス面があって、金なんかは全く毒性がないんですけど、金以外の金属はほとんど何らかの毒性はあります。鉄なんかもたくさん取ったらやっぱり問題なんですけど。
確かに、それで必須金属で見ましても、多過ぎても少な過ぎても駄目なんですね。これは、生物は人間も含めて海から生まれた関係で海の中のやっぱり金属の濃度というのが影響しているんですけど、そういう意味で、例えばカドミウムとか水銀とか鉛とかは元々生物とか人間が利用しなかったんです。カルシウムとか鉄とか銅とか、こういうものは生物が利用したのでこれは必須金属になっているんですけど、全く利用しない不要な金属というのがあるんです。
そういうものの典型的なものが水銀であり、カドミウムであり、鉛とか六価クロムとか、そういう非常に有害な重金属なんです。そういうものはやっぱり基本的に、水銀は水俣病を起こしましたし、カドミウムはイタイイタイ病を起こしたと。鉛はもう古来からある毒物なんですけどね。これはもうギリシャ・ローマ時代からいろいろ毒ありますし、砒素なんかもそうですけど。
そういう明らかに人体に有害と分かっている金属についてはできるだけ使っていかないようにしようと、特に工業製品に使っていかないと。例えば、水銀なんかかて、昔はいろいろ、おしろいとかそれから不老長寿の薬とか、多分早く死んだと思うんですけど、そういうものに使われていたぐらいなんですけど。
それらは、明らかにやっぱり有害なものはできるだけ減らしていこうという意味で、僕の書いた本にはいろいろ書いてあるんですけど、やっぱりEUは、ヨーロッパが進めているこういう、元々これは北欧とかスウェーデンの方から始まったんですけど、有害な金属をやっぱり規制していく、工業製品には使っていかないと。そうすると、やっぱり安全な工業製品なので、後、環境汚染も少ないし、廃棄物についても処理、リサイクルしやすくなる。根本的にはそれやらないと。
それで、金属というのは基本的にはなくならない、地球上からなくならないんです。量は常に一定なんです。全部地下資源にあった分ですから、鉄はさびて酸化鉄になりますけど、鉄そのものの量は、地球上の存在量は変わらないです。隕鉄が降ってきて、その分は鉄が増えたかも分からないですけど。そういう意味で、絶対、金属はどこに行っても形変えるだけで、なくならないんですよ。
だから、有害な金属というのは、一回使うとどこかに行っちゃうんです。例えば、水銀でも今、石炭火力発電、石炭の中、少し水銀入っているんですけど、豊洲も石炭からガス造っていましたので水銀汚染あるんですけどね。そういうのは、火力発電は飛んでいるんですよ。アメリカなんかでは一番多いんですよ。中国からも今、水銀が飛んでいるという話もありますし。
そういう意味で、やっぱり危ないものが入っているものはできるだけ削減しよう、減らしていこうと。一遍にゼロにはできませんから。そういう動きというのはヨーロッパを中心に今始まっていますので、やっぱり日本も余りアメリカに追従するんじゃなくて、さっきのリスク論ですね、リスクとベネフィットを比較して、少々のリスクは我慢しろというんじゃなくて、やっぱり予防原則というか、安全なものにしていく、すべての消費するものとか物を、物資をですね。これは食べ物も含めてだと思いますけどね。
例えば農薬なんかも、結構昔は米にも水銀の農薬とか、それから今でも果樹、リンゴとかああいうものは砒素、鉛系の農薬なんかも使われていましたし、シロアリの駆除剤はあの和歌山のカレー事件で砒素が、亜砒酸が使われていましたし、そういうのがまだ使われているんですよね。そういうものをやっぱりどんどん減らしていくか代替のものに替えていく。
例えばカドミウムについては、昔はニッカド電池、まあ今も使われているんですけど、カドミウムはやっぱり問題があるということでだんだんリチウムイオン電池に切り替わっていっていますし、そういう代替のものがあるものについては替えていく。
ただ、自動車の鉛バッテリーは今代替はないんですよね。だから、リチウムイオン電池で自動車搭載型というのはまだ十分実用化されていませんので、そうなれば鉛バッテリーも使わなくて済むというようなことになると思います。
以上です。
○参考人(畑明郎君)
一番いい例はイタイイタイ病だと思うんですけど、先ほども少し紹介しましたけど。
僕は、だから、三井金属については評価しているんですけど。結局、カドミウムの排出量をほぼ四十年間で十分の一以下にしまして、神通川のカドミウムの水質は鉱山の上流も下流もほぼ一緒になったと。
もちろん、ゼロエミッション、ゼロ排出にはならないですね。ゼロにはできないんですけど、少しは出るんですけど。それで、ほぼ無視できるぐらいの濃度になって、自然界レベルになって神通川は清流に戻って、下流の農地も復元田ということで、千ヘクタールぐらい復元して、数百億円の費用が掛かったんですけど、来年終わると。また汚染物質流したらまた再汚染されますから、これも一種の未然防止だと思うんですけど。
それで、三井金属つぶれたかといいますと、決してつぶれていませんね。今、三井金属は先ほど言いました鉛の、自動車のバッテリーの日本最大のリサイクル工場になっているんです、神岡鉱山が。今、神岡鉱山は、鉱石は掘っていませんけど、自動車のバッテリーを回収して、それをまた鉛にして、自動車のバッテリーは非常にシンプルな製品でして、プラスチックの箱に鉛の電極が入っているだけです。
あと硫酸が入っていまして、まあ硫酸は処理したらいいので、プラスチックと鉛はまた再利用できるんです。あとそれ以外にも三井金属は、皆さん持っている携帯電話の中の銅の薄い箔というんですけれども、回路に使うんですけれども、これの世界トップシェアなんですよ。最近ちょっと何か経営苦しいようですけれども、それでも倒産はしていないし、神岡鉱山も操業を続けながらちゃんとそれなりの利益を出して、経済と環境の両立というのができたわけですね。
それで、この前、朝日新聞にも神岡の、まあ三井の取締役ですけれども、神岡の社長は「私の視点」に、今四十年たって成功したと、対策は。
これは、参議院の議員やられた近藤忠孝イタイイタイ病の弁護団長がNHKの「その時歴史が動いた」にも出ておられましたけれども、弁護団も被害者も企業を評価しているんですね、今。一応企業、経済活動と、上流の神岡鉱山は操業を続けています、工場。鉛、亜鉛造っているんですけれども。しかし、それで下流の農業も両立するということで、やっぱり経済と環境の両立はやればできるんだと。
アジアの問題ですけれども、一応このアジアの土壌汚染で私、最近、韓国とか台湾とか中国の調査やっているんですけれども、特に中国は皆さん御存じのようにひどい状況でして、僕は主に南の方の広東省とか湖南省の鉱山を見に行ったんですけれども、ほとんど排水は垂れ流し状態です。
もう鉄分を、真っ赤な水がそのまま垂れ流されて、谷間は全部泥の海になっていると。下流にがんの村が幾つかできていると。がんの原因もよく分からないんですよね、砒素なのか。多分、砒素でがんになっていると僕は思うんですけれども。あと、カドミウムによってイタイイタイ病みたいな患者も出ていまして。
そこの省の研究所の人がいろいろ調べていまして、その人に調査、案内してもらって、うちの中国の留学生がガイドしてくれたんですけれどもね。それで、日本にも一応中国の研究者を呼びまして、それで日本の富山とかイタイイタイ病の視察もやってもらいまして、これはテレビとか毎日新聞なんかに紹介されたんですけれども。
それで、復元の現場なんかも見せたんですけれども、それをそのまま中国に持っていくのは無理ですね。中国にそんなお金がないとか。やはり、日本の経験を生かしてほしいんですけれども、このままいくと中国は環境よりも経済成長優先でいっていますから、何か行くところまで行かないと反省しないのかなという気はあります。
だから、日本としては、やっぱりできるだけ日本の経験を知らせて、こういう解決の仕方をしたんだということでそれを紹介して、それを中国側がどうやって自分でやっていくかという、そのときに技術援助とか経済援助できることはやっぱり日本がやっていくべきだと思っております。
以上です。
○荒井広幸君 ありがとうございました。
○川田龍平君 川田龍平です。
土壌汚染対策法を始め環境関係法は市町村の役割が重要だと考えていますが、現実に地域で土壌汚染の問題が生じた場合に市区町村が住民への汚染状況の説明や緊急的な対応を行うことになると思いますが、環境省と都道府県、それから市区町村の相互に補完的な体制を整える必要があるかどうか、その点でこの法律が十分かどうかということ、あるいは課題があると考えているかどうかを参考人にお聞きしたいと思います。各参考人、お願いします。
○参考人(畑明郎君)
難しい問題なんですけれども、一応二つの事例で紹介したいと思いますけれども。
一つは、滋賀県の栗東の産廃問題ですけれども。栗東市は住民も含めて、僕はほとんど行政からは委員に呼ばれないんですけれども、珍しく栗東市の調査委員には住民推薦で入っていまして、それで栗東市としていろんな対策案の意見を出しているんですけれども。
それに対して滋賀県は、今、嘉田知事なんですけれども、嘉田知事は有名なんですけれども、新幹線の駅は止めたんですけれども、それからダムもある程度止めようとしているんですけれども、この産廃問題についてはからっきし駄目でして、今、栗東市とか周辺の住民の反発を食らっていまして、要は住民はやっぱり全量撤去を要求しているんですよね。確かに僕らも全量撤去が一番望ましいんですけれども、コスト的に二百数十億掛かるので無理なので。
ただ、県が考えている案は、要するに遮水壁で、ソイルセメントの遮水壁で囲って水をくみ上げて処理して産廃を残そうという、そういう案で四十五億円なんですけれどもね。僕らはそれよりも安い方法で効果的な対策ができますということで、底の粘土層が破壊されているんですけれども、その粘土層の修復と、明らかにドラム缶が三千本以上入っているのが分かっているので、そういう明らかに有害なものはやっぱり全部掘削して掘り起こす。
そういう対策は二十億円ぐらいで済むんですよね。そういう提案を栗東市として、その委員会として提案しているんですけれども、県の方はそれをつぶしに来ていまして、県の対策案を強引にやろうとしたんですけれども、結局は、周辺の住民の同意が得られない、自治会の同意は得られないし、七つの自治会のうち一つしか同意が得られなかったし、議会でも、多分これは自民党と共産党が反対してちょっと通らない可能性が強いので、結局、県案についてはちょっと棚上げになっているんですけれども。
そのときに環境省が果たした役割は非常に悪い役割をやっていまして、要は、環境省がどうも全量撤去をやるなと、現地封じ込めやれと。これは土壌汚染対策法と同じスタンスでして、土壌汚染対策法も掘削除去をやめろと、できるだけ現地封じ込めとか土かぶせて終わりにしろと、それと同じことがやられていますね。
これは、四日市の日本最大の不法投棄、百六十万、百七十万立方メートルが不法で、全部足すと三百万立方メートル、巨大なごみの山ができているんですけれども。そのときも、当初、県は不法投棄の部分については全量撤去をしますという案を出したんですけれども、それに対して環境省は、聞くところによると、環境省が圧力を掛けて、結局むちゃくちゃひどい対策なんですけれども、土かぶせて雨水だけ処理する、それで終わりにしようという。
岐阜の、あと椿洞の産廃の不法投棄事件でも、これは市長が当初、全量撤去をやりますということの方針を打ち出していたんですけれども、環境省がいろいろ圧力を掛けて一部撤去で百億円という形で決着ということで、そういう意味でやっぱり今、県とか環境省が市町村に対して果たしている役割というのは決して余り好ましくないという状況だと思っております。
○川田龍平君 ありがとうございます。
岡山市の小鳥が丘団地では、平成十六年に岡山市の水道局による水道管入替えの工事のときに土壌汚染が発見されて、これまで揮発性の有機化合物であるトリクロロエチレンが最大で環境基準の二十七倍、ベンゼンが二十六倍検出されるほどの状況にあると。
このため、窓を閉めていても異臭によって眠れない人であったりとか、頭痛や鼻炎などに悩まされる人であったり、中には住宅ローンが残っているにもかかわらず引っ越しを余儀なくされた人もいると聞いているんですが。
この土壌からの揮発経由による摂取、また住宅地における土壌汚染の場合というのがどうなのかという、長期的に濃度が高くない水準の暴露環境の中での暮らし、健康被害を受ける場合も考えられますが、こうした低濃度の長期暴露による健康被害について、参考人の意見を、答えられる方に答えていただきたいと思うんですが。
○参考人(畑明郎君)
これは私の資料にも書いていますように、私も三回ほど現地に行きまして、住民にも頼まれまして、それで今裁判にもなっております。
それで、この団地ってちっちゃい四十戸足らずの団地なんですけれども、団地の入口というか、道に入ると、川田議員も行かれたんですかね、もうぷうんと変な油臭いにおいがするんですよ。それで、二十四時間それを吸っていまして、多分外出した方が気分がいい、家にいると気分が悪くなると。実際に何かいろいろ発疹とかできものができたりとか。
台所の下に物入れがあるんですけれども、その床がコンクリートを張っていないところが何か噴火口みたいになっていまして、ガスが噴き出してきているんですね、メタンガスとかいろんなガスが。それから、庭の土がぶわぶわになっているんです。非常に軟らかくなっているんです。下から噴き出してきて、一部黒っぽい油そのものが出てきて、十センチ掘りますともう真っ黒けの油まみれの土なんですよ。これは元々何か廃油のリサイクル業者でして、そのかすをまた豊島に持っていったというんです。豊島の産廃業者と何かセットだったらしいんですけれども。
そういうところで健康被害がある、実際に健康被害が起こって裁判を起こしているんですけれども、全く行政の方は、もう岡山市も県も取り合おうとしないと。基準もないと。土壌汚染の大気の基準はないんですよね。土壌の溶出量とか含有量しかない、地下水の基準しかありませんからね。そういう意味でやっぱり裁判に訴えられない、裁判やってもこれは勝てるかどうか分からないと。
もう日常的にずっと、それで、外へ引っ越したいけれども、その家はもう銀行の担保価値ゼロなんですよ。全然お金も貸してくれない、売れない、その家ももういろいろマスコミに出ていますから。そういう悲惨な状況になっているところがあります。だから、実際に人が住んでいるところで日常的にVOC揮発していきますから、そういう大変なところの問題が起こったところがあるんですけれども、それに今の土壌汚染対策法は全く役に立たないという意味で、大気の基準なんかも設定要ると思います。
ただ、さっきの豊洲の問題でも、これ、ベンゼン、シアン、水銀は蒸発するんですよね、常温でも。それの基準はないという、やっぱりそういう問題はあると思います。大気汚染防止法で少し大気の環境基準はあるものはあるんですけれどもね。土壌汚染についてはないということで、問題あると思っています。
以上です。
○川田龍平君 ありがとうございます。
それから、今、汚染原因者の分社化を内容とする、水俣病についてなんですけれども、分社化を内容とするこの与党法案というのは今国会に提出されているんですが、汚染者負担の原則が今度薄くなる傾向にあるという印象を持っていますが、この土壌汚染法とこの汚染者負担の原則についての参考人の御意見を伺いたいと思います。これも答えられる方で結構です。
○参考人(畑明郎君)
だから、この汚染者負担原則ですね、基本的には従来の公害法はそれで貫かれているんですけれども、特に土壌汚染については、農用地の土壌汚染防止法はイタイイタイ病を契機として制定されたんですけど、これは基本的には汚染原因者負担です。だから、神岡鉱山、三井金属が土壌復元費用を、これは国の法律があって少し減額されていますけど、基本的には企業負担、人体被害の補償に農業被害の補償すべて、だから五百億円近い金額を企業は支払っているんです。
それが水俣病の場合、僕はチッソは非常にけしからぬと思うんですけど、三井金属はやっぱり、財閥系企業とそうでない企業の違いか、世間体があるのか知らないですけど、やっぱりきちっと三井金属は、三井財閥の一員だったし、対応を取って原因者負担を貫いているし。
この土壌汚染対策法が元々できたときに、やっぱりその汚染者負担原則は全く貫かれない、土地所有者責任主義と言われていましたけどね。それで、汚染原因者がオーケーしたら所有者が請求できますよと言っていますけど、普通はオーケーしないです。汚染原因者イコール土地所有者だったら問題ないんですけど、汚染原因者は必ず逃げますから。
それをまた証明しようとするとやっぱり裁判しかないとか、そういういっぱい、カネボウでもこれ裁判起こっているんですよ、企業同士が裁判やっているという。
やっぱりそういう意味で、土壌汚染対策法はPPPは貫かれていないということで問題はあると思っています。
本日はこれにて散会いたします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/171/0065/17104140065005a.html
平成二十一年四月十四日(火曜日)
大阪市立大学大学院特任教授日本環境学会会長 畑 明郎君
本日の会議に付した案件
○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付)
○委員長(有村治子君)
ただいまから環境委員会を開会いたします。
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○参考人(畑明郎君)
大阪市立大学の畑と申します。
資料としましては、昨年十一月に日弁連の機関誌の「自由と正義」という雑誌があるんですけれども、それに土壌汚染対策法の特集がありまして、それの巻頭論文を付けております。二番目には大塚先生も書かれていますので、また参考にしていただければと思います。
元々、私は七年前にここに、法律できるときの、制定のときの参考人で、大野参考人と私とあと二人の方だったんですけれども。そのときに、ちょうど五月だったんですけれども、四月ですから今、似た時期ですけれども、非常に問題はいっぱいあるということで、当時は一応民主党の福山議員の紹介でこれ参加したわけですけれども、十五項目ぐらい問題あるということで、中でも大きな問題点は、二番目の、この法律はやっぱり土壌汚染の事後対策法である、未然防止法ではないということです。
それから、地下水の汚染の防止の観点がほとんどないと。土は人間が動かさないと動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますので、そこの防止の対策がこの法律では非常に問題があると。
それから、五番目の三条の調査対象ですね、これが一番問題なんですけれども、いわゆる水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止時、それも法律施行後の廃止時、さらに宅地等への転用する場合だけ、そういう形で非常に法対象を狭くしていると。それから、それ以外にも金属鉱山・製錬所、廃棄物処分場の跡地周辺、軍事基地等を対象外にしていることです。
それから七番目が、調査、対策を原則として汚染原因者でなく土地所有者等に義務付けている点です。
それから十番目が、対策は原則として覆土、つまり五十センチ以上の盛土でよしとする、土壌の浄化は特別な場合だと。これは保育園とか幼稚園とかそういう場合だけだという感じになっておりまして、この法律制定時から非常に問題があったと思っております。
とても土壌汚染問題の根本的解決につながる法律とは言えませんし、そればかりか、土壌汚染を覆土で隠ぺいし、言わば臭い物にふたをする、後世に負の遺産を残すことを合法化するざる法ではないかということで批判したわけです。
やはり法施行後五年、今六年ですけれども、たった現在、そのざる法性はますます明らかになったのではないかと思っております。
二番目のは、もう御存じのように、先ほど言われましたように、法対象が非常に、二%しかないとか、廃止工場の八割は調査を逃げている、つまり宅地等に用途を転用しないということで、ブラウンフィールド化している。
それから対策も二%しかないと。それから、四条の調査命令も、発動したのは五件。これは、環境省は課長会議の何か通達出していまして、一キロ以内ぐらいに直接水道の飲み水に使用している場合だけ発令しろ、それ以外発令するなというそういう通達を出しておりまして、結果的に五件しかないと。しかも、それは岩手県とか鳥取県とか、皆さん御存じの特定の知事がおられたときしか、県しか命令を出しておりません。そういうことで、非常に実効性の乏しいざる法となっていると思います。
それで、いわゆるこの法律自身は盛土、舗装等で摂取経路を遮断する対策で十分であると言っているんですけど、リスク管理といっておりますけど、汚染土壌が残っている限り半永久的に管理する必要があるわけですね。
特に問題なのは地下水の問題です。土壌が汚染されていますと、必ずそれに接触している地下水は汚染されます。その地下水は勝手に動きます。ということで、確かに直接都市部では飲み水にしていないんですけど、地下水によって汚染が拡散するという点で、その地下水のくみ上げ処理とか遮水壁で囲むとか幾つかの方法があるんですけど、一〇〇%水をカットすることは技術的には困難です。
幾らお金を掛けても困難です。ということで、こういうリスク管理には非常に問題があるということで、やはりリスクゼロ型の掘削除去の方が結果的には多く採用されているし、その方が私はいいと思っております。
当然それを掘削除去した汚染土壌については適正に処理することは当たり前のことでして、これは技術的に、最近、秋田とか川崎とか幾つかにその汚染土壌をきれいにするプラントもできておりますし、問題はコストですね、お金が掛かりますから。その負担をだれがするかという問題だと思っております。
それから三番目の、大野さんのおられる土環センターの調査によれば、いわゆる製造業だけじゃなくてサービス業も含めて九十三万か所ぐらい汚染地があるんではないかと推定されています。
これの調査費用が二兆円で、浄化費用が十一兆円で、合計十三兆円の土壌浄化ビジネスです。既に二〇〇七年でほぼ二千億円近い、年間二千億円の土壌浄化ビジネスになっております。二〇〇八年はちょっと景気の悪化で初めて落ち込むようですけど、それまではずっと右肩上がりで土壌浄化ビジネスの業界は成長しております。
それと、あと汚染地ですけど、基本的には東京、関東、近畿、中部の三大都市圏のいわゆるオールドエコノミーというか、そういう重化学工業の工場地帯のところに多いということです。
それから四番目は、私自身いろんな事件にかかわっているんですけど、基本的には市民、住民の依頼によってやってきたものが二十件以上あります。その中で法対象になったものは、この二十件のうちわずか三件です。
大阪のカネボウの中研の跡地、神戸の日本テルペン化学、川西の中央北地区、これは皮なめし工場です。ということで、大半が法施行前に廃止された工場、事業場や廃棄物処分場周辺の跡地です。ということで、法施行前に廃止された工場跡地、特に有害物質を取り扱っていた事業場をやっぱり法対象にする必要があるし、ドイツなんかでは廃棄物処分場の跡地周辺も法対象にしております。
あと、先ほど出ましたように、私はこの二番目の、?の大阪アメニティパークの、OAPの事件にかなり三年間ぐらいずっと住民に頼まれてかかわったんですけど、このときには土壌汚染対策法は全く役に立たなかったです。宅建業法でやっと三菱は対策とか調査をやったということになったわけですね。
それからあと、七番目以降、そこに滋賀県の例がありまして、私、滋賀県に住んでおりまして、有村委員長も滋賀県出身だそうなんですけど、守山、野洲とか信楽では、これは水道の飲み水の汚染が起こりました。
それから、住友大阪セメント、セメント工場もいろいろ問題あるんですけど、それから、今、滋賀県の知事が栗東の新幹線の駅止めましたけど、この産廃処分場の問題がもう一つありまして、そういう周辺で地下水汚染、土壌汚染が起こっております。
それから、このテルペン化学で、神戸の、非常に印象的だったんですけど、法対象になっているんですけど、法施行時に稼働していた施設では使っていた薬品だけの元素を、有害な元素を対象にしていまして、過去にあった施設の有害物質についてはこれは法対象にならないんだという解釈を神戸市、環境省がしておりまして、それは何かの間違いじゃないかと思ったんですけど、あくまで自主的調査だと。非常に法律自身を狭く運用していると。
いわゆるこういう土壌汚染というのは、一回汚染されますと十年、二十年、三十年、数十年間は蓄積します。そういう意味で、過去の汚染も考慮して調査、対策しないと意味がないと思うんですけど、非常に法律の運用が狭くなっている問題があると思っております。
それから、ここには書いていませんけど、武田薬品の神奈川の湘南工場の最近例知ったんですけど、これは工場の廃止は最近なんですけど、施設が法施行前に廃止されていた、だから法対象にならないと。神奈川県の条例でやっと対象になったという事例がございます。
あと、四日市の例のフェロシルト事件とか産廃処分場の問題とか、あと岐阜とかです。僕自身は、ずっとイタイイタイ病を起こした三井金属の神岡鉱山の排水・土壌汚染対策を四十年近くやっておりますけど、ここは一応今成功しましたけど、工場の下に汚染土壌が残っていまして、約九十トンぐらいカドミウムが残っているんですけど、完全に地下水くむまでに処理するには百年掛かると言われています。
そういう意味で、汚染土壌を残しますと非常に半永久的に処理コストが掛かるということです。結果的には取ってしまった方が安く上がる。これは産廃処分場でも一緒なんですけど、豊島とか青森、岩手のように全量撤去した方が後々ランニングコストというか排水処理とかいろんなリスク管理の費用が結果的には安く上がると思っております。
それから、皆さん御存じの築地市場の問題です。この問題につきまして、一応最近かかわっておりまして、もう御存じなので飛ばしますけど、これは面積的には日本最大の土壌汚染地になりますということで、一千億じゃなくて六百数十億円対策費が掛かる。
それも、二メートル土取って、汚染土壌は下に残ります。汚染地下水は半永久的にくみ上げて処理する、このコストがまた掛かります。そういう対策を東京都がやろうとしています。
今回の法律の件ですけど、僕は基本的にはやっぱりリスクゼロ型の掘削除去の土壌浄化対策の方がいいと思っていますし、盛土、封じ込め等は、こういう安易な対策は問題があると思っています。特に今回の法律はそういう点を、何か掘削除去を排して安易な対策、安上がりな対策を推進、推奨しようとしているということで問題があると思っています。
そういう意味で、東京都の条例とか滋賀県の条例のいわゆる一定規模以上の土地の改変、これは今回の法律には適用されているんですけど、問題はあとは、東京都、あと神奈川県横浜市、川崎市、大阪府等が採用しているんですけど、過去に有害物質を取り扱っていた工場、事業場については条例の対象にするということはやっぱり法律についてもやっていく必要があるんじゃないかと思っています。
それと、滋賀県の条例は、今回、環境省の委員会では全く取り上げられなかったんです。私は滋賀県に今住んでいるんですけど、一応、二〇〇七年に滋賀県の公害防止条例、一部を改正しまして、地下水汚染の未然防止、それから地下水汚染の早期発見と改善、法施行前に廃止された跡地を土壌調査の対象とするというこういう条例を定めて、もう施行しております。
こういうことをやっぱり全国の法律でもやってほしいなということです。やはり条例、要綱の方が進んでいると思いますし、進んだ条例、要綱を参考とした根本的な法改正をやっていただきたいと思っております。
終わりの部分はもう繰り返しになるんですけど、特に強調しますと、やはり法施行前、実際に僕が土壌汚染の問題にかかわっていると、ほとんどは法施行前の工場、事業場の跡地なんです。それも製造業だけじゃなくて、もちろんガソリンスタンドとかそういうサービス業なんかもあります。
そういう法施行前に有害物質を扱っていた工場跡地とか廃棄物処分場の跡地を法対象にする必要があるんじゃないかと思っております。これは日弁連の意見書でも提案されていますし、地方自治体、神奈川県とか先ほどの滋賀県とか東京都とか、条例ではそういうことを定めているところもあります。
それから、やっぱり土壌汚染の未然防止です。こういうことも今回全く入っていませんが、やはり長期的にはこれをやっておかないと、いったん汚染された土は、先ほど大野さん言われましたように、一〇〇%きれいにすることは技術的にはできません、多分幾らお金を掛けても。
そういう意味で、やっぱり汚染しないということが一番大事ですので、未然防止をやっていく必要がある。そのために、やっぱり操業中の工場、事業場についても滋賀県のように井戸を掘って調べる、常時監視するとかそういうことが大事ではないかと思っております。
そういう意味で、確かに今回の法改正は法対象を一定拡大するプラス面あるんですけれども、マイナス面もありまして、特に掘削除去を排するということは問題があるんじゃないかと思っています。
それと、築地市場の移転問題に関連しまして民主党が修正案を出しまして、衆議院で修正案が通ったようですけれども、いわゆる土壌汚染対策法施行以前の廃止工場、事業場であっても、公園、学校、市場等の、これは築地市場を完全に意識しているんですけれども、そういう公共施設等に利用する場合は法対象とするということが通ったことはそれなりに画期的だと思うんですけれども、私としてはやっぱりすべての施行前の有害物質を扱っていた廃止工場、事業場も法対象にすべきではないかと思っています。
そういう意味で、東京都環境条例とか滋賀県の条例とか、あと川崎市、横浜市、大阪府等の進んだ条例、要綱を参考にした抜本的な法改正を今後やっていただきたいと思っております。
あと、新聞記事を幾つか、朝日新聞とか、それから公明党さんの聖教新聞も頼まれまして、最近、三月に。これ百万か所ぐらい汚染用地がある、築地市場のことも書いてくれよということで少し写真とちょっとコメントが入っております。
それと、社民党の社会新報とか、赤旗とか東京新聞とか、あと毎日新聞とか朝日新聞等にも書いておりますし、あと、最後にちょっとありますように、中国の土壌汚染問題、最近中国は恐らく空気も水も土も食べ物も汚染されていまして、非常に問題がありまして、最近中国の土壌汚染のこともやっておりますので、また参考にしていただければと思っております。
○参考人(畑明郎君)
まず、附則三条につきましては、これはもう築地市場の移転問題で衆議院の川内議員なんかと私一緒にやっているんですけど、やはり法施行前の廃止工場、事業場をその法対象にしないという附則三条は取っ払うべきだと私は思っております。
それから、二番目の一定規模の問題ですけど、これはこれでそれなりに評価できるんですけど、ただ、規模だけでやっていいのかという問題があると思います。例えば、水質汚濁防止法の排水基準の適用の仕方なんですけど、有害物質を扱っている場合は排水量に関係ありません。
普通は排水量一日五十トン以上という場合に排水基準を掛けるんですけど、僕は以前京都市の公害の局におりましたけど、そのときには、有害物質を扱っている、それが出る、排水に出るところは排水量に関係なしに排水基準の規制を掛けております。
そういう意味で、やっぱり有害物質を扱っている工場、事業場については、規模についてはむしろ取っ払うべきだと私は思っております。
それから、民主党案の今回の、公共施設等に転用する場合に調査を義務付ける、これはこれでそれなりの意義は、築地市場の移転問題を法対象にするという意味で意義はあると思うんですけど、ただ、これだけではまだ問題があると思っています。
やはりさっき、何度も言うんですけど、過去に有害物質を扱っていた工場、事業場は基本的には汚染している可能性が強いですので、僕もいろいろ、大阪のUSJも住金の跡地なんですけど、あの場合なんかはほとんど工場の敷地内に産廃を埋めていたんです、それも大量に七十万トンという。それが今ジュラシック・パークという恐竜のパークになっているんですけど。
それで、過去に工場、事業場が工場敷地内に産廃を埋めたりとか、それから別に故意でなくても非意図的に液が漏れてしまった、それで床から、それから排水、例えばあとは排水溝です。必ず排水パイプというのは、時間がたちますと穴が空きます。だから、穴が空いて、そこから廃液が漏れてしまって汚染してしまう。
これは大学なんかでもそういう例はありますし、先ほどのカネボウの中央研究所なんかはほとんどその下水管の途中で液が漏れてしまって土壌汚染してしまったという例がありますので、そういう意味で、やっぱりその有害物質を扱っていた工場、事業場については汚染の危険が強いということで調査を義務付けるべきだと思っております。
○参考人(畑明郎君)
掘削除去の問題ですけど、いわゆる環境基準の設定の根拠なんですけど、よく行政とか企業は直ちに影響はないとかいう言い方するんですけど、元々環境基準等はどういう形で設定されたかといいますと、やはりイタイイタイ病とか水俣病のように非常に低濃度の有害物質を長期間暴露することによって被害が起こるわけです。そういう意味で、じわじわと来るものですから、目に見えてすぐ人が倒れるとかそういう急性中毒ではないんです。
そこを逆手に取って、影響はすぐないとか、出ていないとか、直ちに健康に影響はないという形ですぐ行政は逃げる場合が多いんですけど、やはり長期的な影響を考える必要があるということで、土壌の汚染とか地下水の汚染を残すということはやっぱり将来いろいろな問題が起こる可能性があるということで、掘削除去の方がいいと思いますし、それから費用対効果ですけど、これは時間スケールを考慮しないと駄目だと思うんですね。
例えば岩手県の例ですけど、旧松尾鉱山という硫黄鉱山があるんですけど、これ岩手県の方は御存じなんですけど、日本で一番大きい鉱山がありまして、いまだに酸性の水が出てくるんです。北上川を汚染するということで、非常にでっかい排水処理設備が造られています。これ半永久的に稼働しています。それを国とか岩手県は税金でやっているわけです。
そういうコストは莫大なコストになります。そういう意味で、青森・岩手県境の不法投棄のときに、当時の増田知事が、やはり長期的に見ると全量撤去した方が安上がりであると、この松尾鉱山の例を考慮して岩手県はそういう判断を取ったと聞いております。
そういう意味で、本当に、当面はそれは掘削除去はコストは掛かりますけど、長期的に見ると、そういう維持管理コストを考えるとそんなに高いものではないという場合もあるということです。
それから、覆土の問題ですけど、これは用途を非常に限定されます。例えば、通常、ビルなんかを建てる場合は基礎工事をやるわけです、くいを打ったりとかですね。下をかき混ぜますから、そういう工事をしたら、下に汚染土壌が残っているとその汚染土壌の対策も要りますし、五十センチぐらい覆土しても、これは豊洲の例ですけど、あそこは地下水位がほとんどゼロメートルのときがあるんですけど、土を多少上へ入れても、地下水が上昇してきて雨水と地下水が混ざり合ってまたその入れたきれいな土が再汚染される危険性が高いんです。
OAPでもこれは実際に起こったんですけれども、五年ぐらいでもう起こっちゃったんです。ということで、その五十センチぐらいの覆土では将来的には安全な対策にならないし、地下は触れなくなると、地下の倉庫とか地下の構造物を造れなくなる、造りにくくなるという問題はあります。
OAPにつきましてはどうするかといいますと、五十年後建て替えるときにやりますということで三菱は説明している。当面は、二メートル土入れ替えて、地下水はくみ上げて今延々と処理しているんです、コストを掛けて。取りあえずそういう、これは暫定的な対策だと私は思っております。恒久対策はやはりきれいにするということが大事じゃないかと思います。
○参考人(畑明郎君)
今、大塚先生言われましたように、これは廃棄物の問題と一緒でして、廃棄物処理法上いろんなマニフェストとかやっておりますけど、やはり不法投棄はなくなっておりませんし、僕自身も滋賀県の栗東とか四日市の日本最大の不法投棄の大矢知の問題にもかかわっているんですけど、これ同じことが起こり得ると思います。法律で幾ら汚染土壌のマニフェストを定めてフォローしたとしても、やはり限界はあると思います。
そういう意味で、やはりもう少し排出者責任をどう担保していくかという、これは廃棄物も一緒ですけど、取っていく必要あると思います。
これは残土についても一緒でして、残土も結構怪しいものがありまして、僕は汚染土壌も残土も廃棄物扱いというか、廃棄物処理法の対象にすべきだと思います。そういう意味で、もちろん廃棄物処理法ももっと強化しないと駄目なんですけど、強化した上で汚染土壌と残土等を管理していく。
最近でも残土に関連して、石原産業のフェロシルト事件というのがありましたけど、こういうことはついこの間も起こったばかりですよね。あれ、フェロシルトの回収に五百億円掛かるんですよ、これ石原産業が負担して、三年間赤字決算なんです。やっぱりいったんそういう不法投棄しますと非常にコストが掛かるという問題はありますので、この辺は、せっかく法律作ったんですから、きちっとそれは運用というか施行していってほしいなと思っております。
○参考人(畑明郎君)
これは日経新聞等でも拝見しましたけど、この環境債務ということをこういう企業の会計の中に入れていくことについては大賛成ですし、ストック型汚染と僕らは言っているんですけど、土壌汚染と産業廃棄物の問題というのがやっぱり現在はかなり先送りされていると。
言わば臭いものにふたをしてわざと調査しないとか、調査してもできるだけ安価な対策で終わらせて、将来世代にやっぱり負の遺産を送っているところがあると思いますので、やっぱり早めにそういう資産計上していくことはいいことだと思っていますし、非常に面白いのは、上場企業で一番環境債務たくさん計上しているのはOAP事件を起こした三菱マテリアルです。
それと、僕はイタイイタイ病のことをずっとやっているんですけど、結局、イタイイタイ病の場合、公害を出せば結果的に高く付いた例なんですけど、ほぼ掛かった費用が六百億円以上掛かっております。もちろん、死んだ人は、補償を出していますけど、帰ってこないということで、そういう絶対的な損失があるんですけど、経済的な損失という意味で六百億円以上掛かっています。やっとその汚染された農地の復元が来年ぐらいに終わります。
結局ほぼ四十年ぐらい掛かって、最近、三井金属の神岡の社長は朝日新聞に「私の視点」で書いていましたけど、結局四十年掛かって解決したと。そして、住民と企業が信頼関係ができたということで、結局、百億円の公害防止投資を事件が起こる前にやっておけば六百億円の被害は起こらなかったわけです。
結局、公害を出せば、後で非常に社会的コストも企業も負担が重くなるということで、やはり事前にそういう環境債務を計上して対処していくことが今後大事になるんじゃないかと思っております。
○市田忠義君 日本共産党の市田です。
畑参考人にお聞きいたします。
陳述の中でもお述べになりましたが、畑参考人は、リスクゼロ型の掘削除去等の土壌浄化対策、これを排して盛土や封じ込めなどの安易な対策の推奨に今度の法改正がなりかねないと、そう指摘をされています。
私も、今回の改正案で掘削除去の偏重ということが強調されて、現行の指定区域を要措置区域と要届出区域に分類をして、知事が技術的基準に基づいて指示する制度を新たに盛り込んでいると、これが掘削除去の抑制につながるのではないかという懸念をしております。
私事ですが、私は築地に四年前に住んでいまして、今、豊洲に住むという皮肉な、豊洲への移転には私は反対でありますけれども。
畑参考人は、東京ガスの豊洲工場跡地問題あるいは大阪アメニティパークなど多くの土壌・地下水汚染事例にかかわってこられたわけですが、先ほどもお述べになりましたけれども、このリスクゼロ型の掘削除去を抑制して覆土や封じ込めなどのリスク管理型を普及するということについて改めてもう少し詳しくお伺いしたいのと、若干他の参考人の方からも出されたことなんですが、掘削除去というのはかえって汚染地域が広がって汚染の拡大につながるのではないかという考え方についてどうお考えかと。
コスト問題はよく分かりました。中長期的に見れば、中途半端な処理はかえってお金が掛かるというのはよく分かりましたが、今の点について御意見をお伺いしたいと思います。
○参考人(畑明郎君)
確かに、今回の形質変更届管理区域、それから要措置区域ということで、従来の指定区域を二種類に分けて、結局対策を緩める。そして、掘削除去をできるだけやらさないという方向になるおそれは十分あると思っております。
それで、リスク管理という、これは言葉はいいんですけれども、元々この環境リスク論というのはどこから来たかといいますと、アメリカから来たものでして、これBSE問題が一番典型なんですけれども、いわゆる全頭検査なんか要らない、百万人に一人しかBSEにならないんだ、全頭検査のコストは無駄だと。
要は、アメリカの場合はリスクとベネフィットを比較してベネフィットの方が大きければリスクはある程度我慢すると。みんな飛行機とか自動車は交通事故の可能性があるけれども乗るでしょう、ベネフィットがあるから乗るでしょう、環境も一緒ですという形で、こういうことを中西準子なんかは言っているんですけれども、経産省もそういうスタンスなんですけれども、これは僕は全く間違っていると思います。
基本的には、僕はやっぱりEUが取っている予防原則、これは朝日新聞の知恵蔵に環境リスク論とEUの予防原則を比較して書いたことがあるんですけれども、やはり、今EUが進めているRoHS規制とかREACH規制という化学物質の規制は、言わばカドミウムとか水銀とか危ないものはもう製品に入れていかない、工業製品に入らなければできた廃棄物、廃製品も危ないものが入っていないということです。
鉛とか先ほどのカドミウム、水銀など、基本的には六物質に対してはもうやれている。日本のメーカーもEUに輸出はそれができている。自動車とか電気製品を輸出していますから、対応できるんです。
更にもっと、三万種類というすべての工業製品、化学物質に対して規制を掛けようとすると、従来は医薬品と同じように、医薬品だけが安全を証明しなければ販売できなかったんですけれども、すべての工業製品についてメーカーが安全を証明する義務を持たせるという、そういうREACH規制は今もうヨーロッパで始まっています。順次強化されていきますけれども。そういう動きがあります。
それから、やっぱりリスク管理というのは問題ありますし、本当にリスク管理できないんですよね。土壌は確かに人が動かさなければ動かないんですけれども、地下水は勝手に動きますから、これはどこへ行くか分からないということで、何か法案にもちょっとありましたように、海辺の埋立地はいいんだと、汚染されていても。これはもう論外でして、やっぱり廃棄物処分場は山の中に造るか海に埋めているかどっちかなんですけれども、山の場合はもちろん排水は河川の上流に入ってきますし、海の場合もやはり、大阪湾のフェニックスとかありますけれども、東京湾の埋め立てていますけれども、やはり海の汚染を起こします。
完全にその汚染水を海に流さないことはできません。今、遮水していますけれども、あれは堤防だけ遮水していまして底は抜けていますので、必ず汚染が海に広がります。それで魚の汚染も起こりますし、そういう意味で問題があるということです。
それと、確かに掘削除去した土地をどう処理するかというのはもちろん問題なんですけれども、僕のかかわった京都府の日本最大のクレー射撃場、これは麻生首相が好きらしいんですけれども、要するに鉛の散弾、これを撃つんですよ。それで皿を割るらしいんですけれども。当然鉛の散弾がそこへ散らばって、クレー射撃場の中が鉛で土が全部汚染されちゃったんです。
その土、今京都府立の施設なんですけれども、京都府は十億円以上掛けて全部、秋田県の小坂にあるんですけれども、土壌処理施設で土をきれいにしてまた戻す、そういうことをちゃんとやっているんです。
そういう意味で、それは搬出土壌の処理の仕方、適正な処理をやっぱりどう担保するかという問題でして、これは産廃と一緒でして、ただ今の現状からいくともちろん産廃と同じように汚染土壌がどこへ行っているか分からぬという問題は起こり得ると思いますので、それは十分注意しながらやっていくしかないと思っております。ただ、技術的にはできると思います。
○参考人(畑明郎君)
だから、今回のもちろん一定規模以上の、多分三千平米ぐらいになると聞いておりますけれども、それはもちろん改善、今の法律の、ざる法のざるを少し目を埋める、目を小さくするということにはなると思いますけれども、完全にざるは目が埋まった状態ではないと思っております。
やはり法施行前の有害物質を扱っていた工場、事業場、これは水質汚濁防止法の特定施設以外にもいっぱい出ていますので、やっぱり有害物質を例えば運搬とか保管したところでも汚染は起こっていますので、それから交通機関とかそういうところなんかでも起こっていますので、やっぱり過去のこれは負の遺産だと。製造業の当初負の遺産という言葉が言われたんですけれども、土壌汚染は。過去の負の遺産をいつかの時点で一掃するためには、きちっとまずはやっぱり調査をすべきであると。
もちろん一〇〇%の工場が全部汚染されているとは僕は言いませんし、多分半分ぐらいだろうという土環センターの推定なんかもありますけれども、やっぱりやってみないと分かりませんから、調査はまずちゃんとすべきである。
これはカドミウム汚染米と一緒でして、ついちょっと前、一九九八年ぐらいに、五十ヘクタール単位にワンポイントでじゅうたん的に米を全部調査したら、またいっぱい準汚染米が出てきたという問題がありました。そういう意味で、やっぱり危ない可能性のある工場、事業場については調査を法的に義務付けてしていくべきであると。
あと、対策はどうするかというのは、やっぱりケース・バイ・ケースになると思いますけれども。
○参考人(畑明郎君)
私は元々の出身が京大の工学部の金属でして、それでずっと金属にこだわってやっているんですけど、金属というのは、確かに人間生活とかいろんな経済に役立っているんですけど、プラス面とマイナス面があって、金なんかは全く毒性がないんですけど、金以外の金属はほとんど何らかの毒性はあります。鉄なんかもたくさん取ったらやっぱり問題なんですけど。
確かに、それで必須金属で見ましても、多過ぎても少な過ぎても駄目なんですね。これは、生物は人間も含めて海から生まれた関係で海の中のやっぱり金属の濃度というのが影響しているんですけど、そういう意味で、例えばカドミウムとか水銀とか鉛とかは元々生物とか人間が利用しなかったんです。カルシウムとか鉄とか銅とか、こういうものは生物が利用したのでこれは必須金属になっているんですけど、全く利用しない不要な金属というのがあるんです。
そういうものの典型的なものが水銀であり、カドミウムであり、鉛とか六価クロムとか、そういう非常に有害な重金属なんです。そういうものはやっぱり基本的に、水銀は水俣病を起こしましたし、カドミウムはイタイイタイ病を起こしたと。鉛はもう古来からある毒物なんですけどね。これはもうギリシャ・ローマ時代からいろいろ毒ありますし、砒素なんかもそうですけど。
そういう明らかに人体に有害と分かっている金属についてはできるだけ使っていかないようにしようと、特に工業製品に使っていかないと。例えば、水銀なんかかて、昔はいろいろ、おしろいとかそれから不老長寿の薬とか、多分早く死んだと思うんですけど、そういうものに使われていたぐらいなんですけど。
それらは、明らかにやっぱり有害なものはできるだけ減らしていこうという意味で、僕の書いた本にはいろいろ書いてあるんですけど、やっぱりEUは、ヨーロッパが進めているこういう、元々これは北欧とかスウェーデンの方から始まったんですけど、有害な金属をやっぱり規制していく、工業製品には使っていかないと。そうすると、やっぱり安全な工業製品なので、後、環境汚染も少ないし、廃棄物についても処理、リサイクルしやすくなる。根本的にはそれやらないと。
それで、金属というのは基本的にはなくならない、地球上からなくならないんです。量は常に一定なんです。全部地下資源にあった分ですから、鉄はさびて酸化鉄になりますけど、鉄そのものの量は、地球上の存在量は変わらないです。隕鉄が降ってきて、その分は鉄が増えたかも分からないですけど。そういう意味で、絶対、金属はどこに行っても形変えるだけで、なくならないんですよ。
だから、有害な金属というのは、一回使うとどこかに行っちゃうんです。例えば、水銀でも今、石炭火力発電、石炭の中、少し水銀入っているんですけど、豊洲も石炭からガス造っていましたので水銀汚染あるんですけどね。そういうのは、火力発電は飛んでいるんですよ。アメリカなんかでは一番多いんですよ。中国からも今、水銀が飛んでいるという話もありますし。
そういう意味で、やっぱり危ないものが入っているものはできるだけ削減しよう、減らしていこうと。一遍にゼロにはできませんから。そういう動きというのはヨーロッパを中心に今始まっていますので、やっぱり日本も余りアメリカに追従するんじゃなくて、さっきのリスク論ですね、リスクとベネフィットを比較して、少々のリスクは我慢しろというんじゃなくて、やっぱり予防原則というか、安全なものにしていく、すべての消費するものとか物を、物資をですね。これは食べ物も含めてだと思いますけどね。
例えば農薬なんかも、結構昔は米にも水銀の農薬とか、それから今でも果樹、リンゴとかああいうものは砒素、鉛系の農薬なんかも使われていましたし、シロアリの駆除剤はあの和歌山のカレー事件で砒素が、亜砒酸が使われていましたし、そういうのがまだ使われているんですよね。そういうものをやっぱりどんどん減らしていくか代替のものに替えていく。
例えばカドミウムについては、昔はニッカド電池、まあ今も使われているんですけど、カドミウムはやっぱり問題があるということでだんだんリチウムイオン電池に切り替わっていっていますし、そういう代替のものがあるものについては替えていく。
ただ、自動車の鉛バッテリーは今代替はないんですよね。だから、リチウムイオン電池で自動車搭載型というのはまだ十分実用化されていませんので、そうなれば鉛バッテリーも使わなくて済むというようなことになると思います。
以上です。
○参考人(畑明郎君)
一番いい例はイタイイタイ病だと思うんですけど、先ほども少し紹介しましたけど。
僕は、だから、三井金属については評価しているんですけど。結局、カドミウムの排出量をほぼ四十年間で十分の一以下にしまして、神通川のカドミウムの水質は鉱山の上流も下流もほぼ一緒になったと。
もちろん、ゼロエミッション、ゼロ排出にはならないですね。ゼロにはできないんですけど、少しは出るんですけど。それで、ほぼ無視できるぐらいの濃度になって、自然界レベルになって神通川は清流に戻って、下流の農地も復元田ということで、千ヘクタールぐらい復元して、数百億円の費用が掛かったんですけど、来年終わると。また汚染物質流したらまた再汚染されますから、これも一種の未然防止だと思うんですけど。
それで、三井金属つぶれたかといいますと、決してつぶれていませんね。今、三井金属は先ほど言いました鉛の、自動車のバッテリーの日本最大のリサイクル工場になっているんです、神岡鉱山が。今、神岡鉱山は、鉱石は掘っていませんけど、自動車のバッテリーを回収して、それをまた鉛にして、自動車のバッテリーは非常にシンプルな製品でして、プラスチックの箱に鉛の電極が入っているだけです。
あと硫酸が入っていまして、まあ硫酸は処理したらいいので、プラスチックと鉛はまた再利用できるんです。あとそれ以外にも三井金属は、皆さん持っている携帯電話の中の銅の薄い箔というんですけれども、回路に使うんですけれども、これの世界トップシェアなんですよ。最近ちょっと何か経営苦しいようですけれども、それでも倒産はしていないし、神岡鉱山も操業を続けながらちゃんとそれなりの利益を出して、経済と環境の両立というのができたわけですね。
それで、この前、朝日新聞にも神岡の、まあ三井の取締役ですけれども、神岡の社長は「私の視点」に、今四十年たって成功したと、対策は。
これは、参議院の議員やられた近藤忠孝イタイイタイ病の弁護団長がNHKの「その時歴史が動いた」にも出ておられましたけれども、弁護団も被害者も企業を評価しているんですね、今。一応企業、経済活動と、上流の神岡鉱山は操業を続けています、工場。鉛、亜鉛造っているんですけれども。しかし、それで下流の農業も両立するということで、やっぱり経済と環境の両立はやればできるんだと。
アジアの問題ですけれども、一応このアジアの土壌汚染で私、最近、韓国とか台湾とか中国の調査やっているんですけれども、特に中国は皆さん御存じのようにひどい状況でして、僕は主に南の方の広東省とか湖南省の鉱山を見に行ったんですけれども、ほとんど排水は垂れ流し状態です。
もう鉄分を、真っ赤な水がそのまま垂れ流されて、谷間は全部泥の海になっていると。下流にがんの村が幾つかできていると。がんの原因もよく分からないんですよね、砒素なのか。多分、砒素でがんになっていると僕は思うんですけれども。あと、カドミウムによってイタイイタイ病みたいな患者も出ていまして。
そこの省の研究所の人がいろいろ調べていまして、その人に調査、案内してもらって、うちの中国の留学生がガイドしてくれたんですけれどもね。それで、日本にも一応中国の研究者を呼びまして、それで日本の富山とかイタイイタイ病の視察もやってもらいまして、これはテレビとか毎日新聞なんかに紹介されたんですけれども。
それで、復元の現場なんかも見せたんですけれども、それをそのまま中国に持っていくのは無理ですね。中国にそんなお金がないとか。やはり、日本の経験を生かしてほしいんですけれども、このままいくと中国は環境よりも経済成長優先でいっていますから、何か行くところまで行かないと反省しないのかなという気はあります。
だから、日本としては、やっぱりできるだけ日本の経験を知らせて、こういう解決の仕方をしたんだということでそれを紹介して、それを中国側がどうやって自分でやっていくかという、そのときに技術援助とか経済援助できることはやっぱり日本がやっていくべきだと思っております。
以上です。
○荒井広幸君 ありがとうございました。
○川田龍平君 川田龍平です。
土壌汚染対策法を始め環境関係法は市町村の役割が重要だと考えていますが、現実に地域で土壌汚染の問題が生じた場合に市区町村が住民への汚染状況の説明や緊急的な対応を行うことになると思いますが、環境省と都道府県、それから市区町村の相互に補完的な体制を整える必要があるかどうか、その点でこの法律が十分かどうかということ、あるいは課題があると考えているかどうかを参考人にお聞きしたいと思います。各参考人、お願いします。
○参考人(畑明郎君)
難しい問題なんですけれども、一応二つの事例で紹介したいと思いますけれども。
一つは、滋賀県の栗東の産廃問題ですけれども。栗東市は住民も含めて、僕はほとんど行政からは委員に呼ばれないんですけれども、珍しく栗東市の調査委員には住民推薦で入っていまして、それで栗東市としていろんな対策案の意見を出しているんですけれども。
それに対して滋賀県は、今、嘉田知事なんですけれども、嘉田知事は有名なんですけれども、新幹線の駅は止めたんですけれども、それからダムもある程度止めようとしているんですけれども、この産廃問題についてはからっきし駄目でして、今、栗東市とか周辺の住民の反発を食らっていまして、要は住民はやっぱり全量撤去を要求しているんですよね。確かに僕らも全量撤去が一番望ましいんですけれども、コスト的に二百数十億掛かるので無理なので。
ただ、県が考えている案は、要するに遮水壁で、ソイルセメントの遮水壁で囲って水をくみ上げて処理して産廃を残そうという、そういう案で四十五億円なんですけれどもね。僕らはそれよりも安い方法で効果的な対策ができますということで、底の粘土層が破壊されているんですけれども、その粘土層の修復と、明らかにドラム缶が三千本以上入っているのが分かっているので、そういう明らかに有害なものはやっぱり全部掘削して掘り起こす。
そういう対策は二十億円ぐらいで済むんですよね。そういう提案を栗東市として、その委員会として提案しているんですけれども、県の方はそれをつぶしに来ていまして、県の対策案を強引にやろうとしたんですけれども、結局は、周辺の住民の同意が得られない、自治会の同意は得られないし、七つの自治会のうち一つしか同意が得られなかったし、議会でも、多分これは自民党と共産党が反対してちょっと通らない可能性が強いので、結局、県案についてはちょっと棚上げになっているんですけれども。
そのときに環境省が果たした役割は非常に悪い役割をやっていまして、要は、環境省がどうも全量撤去をやるなと、現地封じ込めやれと。これは土壌汚染対策法と同じスタンスでして、土壌汚染対策法も掘削除去をやめろと、できるだけ現地封じ込めとか土かぶせて終わりにしろと、それと同じことがやられていますね。
これは、四日市の日本最大の不法投棄、百六十万、百七十万立方メートルが不法で、全部足すと三百万立方メートル、巨大なごみの山ができているんですけれども。そのときも、当初、県は不法投棄の部分については全量撤去をしますという案を出したんですけれども、それに対して環境省は、聞くところによると、環境省が圧力を掛けて、結局むちゃくちゃひどい対策なんですけれども、土かぶせて雨水だけ処理する、それで終わりにしようという。
岐阜の、あと椿洞の産廃の不法投棄事件でも、これは市長が当初、全量撤去をやりますということの方針を打ち出していたんですけれども、環境省がいろいろ圧力を掛けて一部撤去で百億円という形で決着ということで、そういう意味でやっぱり今、県とか環境省が市町村に対して果たしている役割というのは決して余り好ましくないという状況だと思っております。
○川田龍平君 ありがとうございます。
岡山市の小鳥が丘団地では、平成十六年に岡山市の水道局による水道管入替えの工事のときに土壌汚染が発見されて、これまで揮発性の有機化合物であるトリクロロエチレンが最大で環境基準の二十七倍、ベンゼンが二十六倍検出されるほどの状況にあると。
このため、窓を閉めていても異臭によって眠れない人であったりとか、頭痛や鼻炎などに悩まされる人であったり、中には住宅ローンが残っているにもかかわらず引っ越しを余儀なくされた人もいると聞いているんですが。
この土壌からの揮発経由による摂取、また住宅地における土壌汚染の場合というのがどうなのかという、長期的に濃度が高くない水準の暴露環境の中での暮らし、健康被害を受ける場合も考えられますが、こうした低濃度の長期暴露による健康被害について、参考人の意見を、答えられる方に答えていただきたいと思うんですが。
○参考人(畑明郎君)
これは私の資料にも書いていますように、私も三回ほど現地に行きまして、住民にも頼まれまして、それで今裁判にもなっております。
それで、この団地ってちっちゃい四十戸足らずの団地なんですけれども、団地の入口というか、道に入ると、川田議員も行かれたんですかね、もうぷうんと変な油臭いにおいがするんですよ。それで、二十四時間それを吸っていまして、多分外出した方が気分がいい、家にいると気分が悪くなると。実際に何かいろいろ発疹とかできものができたりとか。
台所の下に物入れがあるんですけれども、その床がコンクリートを張っていないところが何か噴火口みたいになっていまして、ガスが噴き出してきているんですね、メタンガスとかいろんなガスが。それから、庭の土がぶわぶわになっているんです。非常に軟らかくなっているんです。下から噴き出してきて、一部黒っぽい油そのものが出てきて、十センチ掘りますともう真っ黒けの油まみれの土なんですよ。これは元々何か廃油のリサイクル業者でして、そのかすをまた豊島に持っていったというんです。豊島の産廃業者と何かセットだったらしいんですけれども。
そういうところで健康被害がある、実際に健康被害が起こって裁判を起こしているんですけれども、全く行政の方は、もう岡山市も県も取り合おうとしないと。基準もないと。土壌汚染の大気の基準はないんですよね。土壌の溶出量とか含有量しかない、地下水の基準しかありませんからね。そういう意味でやっぱり裁判に訴えられない、裁判やってもこれは勝てるかどうか分からないと。
もう日常的にずっと、それで、外へ引っ越したいけれども、その家はもう銀行の担保価値ゼロなんですよ。全然お金も貸してくれない、売れない、その家ももういろいろマスコミに出ていますから。そういう悲惨な状況になっているところがあります。だから、実際に人が住んでいるところで日常的にVOC揮発していきますから、そういう大変なところの問題が起こったところがあるんですけれども、それに今の土壌汚染対策法は全く役に立たないという意味で、大気の基準なんかも設定要ると思います。
ただ、さっきの豊洲の問題でも、これ、ベンゼン、シアン、水銀は蒸発するんですよね、常温でも。それの基準はないという、やっぱりそういう問題はあると思います。大気汚染防止法で少し大気の環境基準はあるものはあるんですけれどもね。土壌汚染についてはないということで、問題あると思っています。
以上です。
○川田龍平君 ありがとうございます。
それから、今、汚染原因者の分社化を内容とする、水俣病についてなんですけれども、分社化を内容とするこの与党法案というのは今国会に提出されているんですが、汚染者負担の原則が今度薄くなる傾向にあるという印象を持っていますが、この土壌汚染法とこの汚染者負担の原則についての参考人の御意見を伺いたいと思います。これも答えられる方で結構です。
○参考人(畑明郎君)
だから、この汚染者負担原則ですね、基本的には従来の公害法はそれで貫かれているんですけれども、特に土壌汚染については、農用地の土壌汚染防止法はイタイイタイ病を契機として制定されたんですけど、これは基本的には汚染原因者負担です。だから、神岡鉱山、三井金属が土壌復元費用を、これは国の法律があって少し減額されていますけど、基本的には企業負担、人体被害の補償に農業被害の補償すべて、だから五百億円近い金額を企業は支払っているんです。
それが水俣病の場合、僕はチッソは非常にけしからぬと思うんですけど、三井金属はやっぱり、財閥系企業とそうでない企業の違いか、世間体があるのか知らないですけど、やっぱりきちっと三井金属は、三井財閥の一員だったし、対応を取って原因者負担を貫いているし。
この土壌汚染対策法が元々できたときに、やっぱりその汚染者負担原則は全く貫かれない、土地所有者責任主義と言われていましたけどね。それで、汚染原因者がオーケーしたら所有者が請求できますよと言っていますけど、普通はオーケーしないです。汚染原因者イコール土地所有者だったら問題ないんですけど、汚染原因者は必ず逃げますから。
それをまた証明しようとするとやっぱり裁判しかないとか、そういういっぱい、カネボウでもこれ裁判起こっているんですよ、企業同士が裁判やっているという。
やっぱりそういう意味で、土壌汚染対策法はPPPは貫かれていないということで問題はあると思っています。
本日はこれにて散会いたします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/171/0065/17104140065005a.html
2009年12月27日
平成21 年2月20 日大阪市底質対策等技術検討会
大阪市底質対策等技術検討会会議要旨
1 日 時 平成21 年2月20 日(金) 午後1時30 分〜午後2時50 分
2 場 所 環境局第11〜13 会議室(WTCコスモタワービル36 階)
3 出席者
(委 員)
大阪大学名誉教授 村岡 浩爾
大阪人間科学大学人間科学部教授 福永 勲
摂南大学薬学部准教授 上野 仁
京都大学原子炉実験所准教授 藤川 陽子
(事務局)
大阪市環境局・港湾局・建設局
(オブザーバ)
大阪府都市整備部河川室、大阪府環境農林水産部環境管理室、
大阪府環境農林水産総合研究所、大阪市立環境科学研究所水環境担当
4 議 題
(1) 委員長の選出
(2) 報告案件
? 平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
? 大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策について
? 大阪市管理河川(道頓堀川等)における底質浄化対策について
5 議事要旨
(1) 委員長の選出について
要綱の規定に基づき、委員の互選により村岡委員が委員長として選出された。また、村岡委員長の指名により、福永委員が委員長の職務代行を行うこととなった。
(2) 平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
事務局(環境局)から、大阪市域における平成15〜19 年度までの5年間の水質・底質に係るダイオキシン類濃度測定結果及び水質に係る代表的な汚濁指標であるBOD やCOD の汚濁状況について報告を行った。
(3) 大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策について
事務局(港湾局)から、平成18 年度から着手している大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策に伴う環境対策の概要(浚渫場所周辺における事前・日常的な水質環境監視や処分地(夢洲)及びその周辺おける水質環境調査結果など)の報告を行うとともに、平成19 年度に着手した港区尻無川(水門上流)堤防工事における環境対策の概要(工事場所周辺における事前・日常的な水質環境監視や固化処理による封じ込め効果を確認するための水質調査の実施結果など)について報告を行った。
(4) 大阪市管理河川(道頓堀川等)における底質浄化対策について
事務局(建設局)から、道頓堀川水辺整備事業のうち、湊町右岸工区における遊歩道の設置に係る工事概要、浚渫土の処理、工事中の環境監視結果などについて報告を行った。
【結果】
(2)〜(4)について、事務局からの報告内容について、各委員からご理解をいただいたが、底質ダイオキシン類溶出量の測定値の評価に関して、「底質ダイオキシン類に関する分析手法を含めた統一的な取り扱いの確立に向け、今後、府市等関係機関が連携すること」などが要望として出された。
6 会議資料:
(1)資料1 :平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
(2)資料2 :大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策及び港区尻無川(水門上流)堤防工事における環境対策について
(3)資料3 :大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策について
(4)参考資料:大阪市底質対策等技術検討会開催要綱
7 問い合わせ先
大阪市環境局環境保全部土壌水質担当
Tel:06-6615-7984、FAX:06-6615-7949、E-mail:ja0040@city.osaka.lg.jp
大阪市底質対策等技術検討会会議録
発言者(事務局及びオブザーバ)
・環境局環境保全部長 西山健一郎
・環境局環境保全部土壌水質担当課長 大石 一裕
・環境局環境保全部土壌水質担当課長代理 前田 和男
・環境局環境保全部環境情報担当課長代理 黒木 隆司
・環境局環境保全部担当係長 宮本 敏之(司会者)
・港湾局計画整備部環境保全担当課長代理 有門 貴
・建設局下水道河川部河川担当課長代理 三村 経雄
・大阪市立環境科学研究所水環境担当研究主任 先山 孝則
議事内容:次のとおり
西山環境保全部長
さて、大阪市では、これまで「大阪市底質対策技術検討会」におきまして、市内の河川並びに海域における底質汚染などに関しまして、その汚染要因や浄化対策につきまして検討するとともに、市域内における土壌汚染、また、地下水汚染に係ります調査・対策に関しましては、別途「大阪市土壌汚染対策専門委員会」を設置させていただき、学識者の先生方より検討をいただいたところでございます。
今般、大阪市では、これらの2つの委員会をより総合的に運用いたしまして、大阪市域内の公共用水域に係ります有害な底質、また、市域内の土壌汚染・地下水汚染など、水環境分野と地盤環境の分野の対策を一体的に推進いたしますため、平成20 年7月に底質の委員会に土壌の委員会を整理・統合させていただいたところでございます。
本日は、これまで「底質対策技術検討会」でご検討いただきました大阪港湾区域並びに本市の管理河川におけます底質浄化対策の進捗の状況、また、環境監視の結果などにつきまして、ご検討いただきたいと考えてございます。
本市といたしましては、今後とも、良好な都市環境を確保するとともに、水環境、また、地盤環境をはじめ、各種の環境施策をより一層、推進していく所存でございますので、委員の先生方におかれましては、引き続き、お力添えを賜りますようお願い申しあげまして、簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。
大阪市では、これまで「大阪市底質対策技術検討会」におきまして、底質汚染問題について、また、「大阪市土壌汚染対策専門委員会」では、土壌汚染や地下水汚染問題について、それぞれ検討を行ってまいりましたが、今後の環境施策を円滑に推進していくために、この2つの委員会を統合いたしまして、参考資料に示しますとおり、要綱改訂を行ってきたところです。
本検討会の委員につきましては、村岡先生、福永先生には再任させていただきますとともに、新たに上野先生、藤川先生には委員にご就任いただき、検討を進めていくこととなりました。
村岡委員長
委員の先生方から、ご賛同を得ましたので、この検討会の委員長を務めさせていただきます。
この検討会は、先ほど西山部長からも、ご説明ありましたように、これまでの2つの委員会を統合した新たな委員会となっています。これまで扱ってきました内容は、底質汚染、土壌汚染、地下水汚染であります。これらの内容については、相互に関係する場合もあり、独立して考えなければならない場合もあります。
この3つの汚染は、対策という面から扱っていく拠り所となる法律は3つとも別であります。ということで、これを行政サイドから扱われるにしても、環境局、港湾局、建設局と3つに分かれているわけです。
今回、統合的に検討するということになりまして、ある意味では、行政の縦割りを除いた総合的な検討ができる場であるということで、好ましい形になってきたのではないかと思います。
委員の先生方にも、それぞれご専門があるわけですが、この際、ご自分の専門以外に関連することが多いでしょうから、そういったところから広く総合的にご議論いただくことが望ましいと思いますので、その点、ご協力の方よろしくお願いいたします。
それでは、早速、議事に入りますが、本日の議題は、報告案件だけ3つあるようでございます。
まず、第1の議案ですけれども、「平成19 年度 ダイオキシン類環境調査結果」についてでございます。
事務局(環境局前田課長代理)
お手元の資料1に基づきまして、「平成19 年度ダイオキシン類調査結果」について、ご説明させていただきます。平成19 年度のダイオキシン類の水質・底質調査地点及び環境基準の適合状況を表しております。大阪市の地図上に、水質・底質のダイオキシン類の調査地点と環境基準の適合・不適合を示しております。各地点ごとに円がありますが、円の上半分が赤い場合は水質の環境基準不適合を、下半分が赤い場合は、底質の環境基準が不適合を、全体が赤い場合は、水質・底質両方とも環境基準不適合であることを表しております。
平成19 年度、水質につきましては、古川の徳栄橋、神崎川の小松橋、東横堀川の本町橋の3箇所で環境基準不適合となっております。
事務局(環境局前田課長代理)
また、底質につきましては、古川の徳栄橋、六軒家川の春日出橋、住吉川の住之江大橋下流1,100mの地点で環境基準不適合となっております。
こちらの表−1でございますが、水質のダイオキシン類濃度の経年変化を示しております。経年変化としましては、平成15 年度から19年度までのデータで示しております。
環境基準を超える又は高めのデータが出ている地点につきましては、調査回数を多く設定するというように、年度・地点により、調査回数が異なっております。複数回、測定を行う地点につきましては、データを範囲で示しております。
青色の網掛けをしており、下線を引いておりますのは、環境基準値1pg-TEQ/L を超えたところです。道頓堀川の大黒橋、古川の徳栄橋、東横堀川の本町橋、寝屋川の今津橋、京橋、神崎川の小松橋において、環境基準不適合となる傾向にあります。
資料の3枚目をご覧いただきたいのですが、こちらの方は、底質のダイオキシン類濃度の経年変化を示したものでございます。水質と同様に、平成15 年度から19 年度までのデータでお示ししております。
水質と同様、網をかけて下線を引いておりますところが、環境基準値150pg-TEQ/g を超えたところであります。道頓堀川の大黒橋、古川の徳栄橋の他、木津川、神崎川の河口部において、環境基準が不適合となる傾向が続いております。
ダイオキシン類の汚染要因でありますが、大阪府、大阪市で設置しております「河川及び港湾の底質浄化対策検討委員会」において検討されておりまして、大阪府及び大阪市の河川及び港湾におけるダイオキシン類の汚染は、主にPCB 製剤、並びに農薬、燃焼由来の要因が複合したものであり、個々の発生源の影響を特定することは困難であると結論づけられております。
底質浄化対策についてですが、まず、本市管理河川についてご説明させていただきますと、道頓堀川、東横堀川につきましては、既存の測定結果におきまして、すでに底質ダイオキシン類の環境基準の超過が判明しておりますので、大阪市建設局が詳細調査を行い、ダイオキシン類による底質汚染を確認しております。底質浄化対策につきましては、平成19 年度に同局が両河川の一部の区間で浚渫による浄化対策を実施しております。
港湾区域につきましては、同じく既存の測定結果におきまして、既に底質ダイオキシン類の環境基準の超過が判明しておりますので、大阪市港湾局が平成15 年度から17 年度にかけまして、正蓮寺川、尻無川、木津川、木津川運河等の大阪港湾区域の河川、港湾重複7区域におきまして、底質ダイオキシン類の汚染範囲等の調査を行っております。
事務局
(環境局前田課長代理)
底質浄化対策につきましては、平成18 年度から、木津川運河の一部区域、大正内港の一部区域で、同局が浚渫による浄化対策に着手しているところでございます。
さらに、大阪市以外の管理河川につきましては、神崎川、古川におきまして検討がなされているところでありますが、神崎川につきましては、大阪府におきまして、本川で平成18 年度以降、浚渫と覆砂による底質対策が行われているところでございます。
また、神崎川上流の水路で高濃度の底質ダイオキシン類が検出されているということで、大阪府の方で汚染底質の除去及び底質除去後の環境モニタリングが実施されております。
特に、古川につきましては、大阪府と大阪市が連携いたしまして、ダイオキシン類による底質汚染原因究明のための追跡調査を行い、上流に環境基準を超える底質があることが判明いたしました。その後、古川の河川管理者である大阪府の方で、詳細調査が行われ、上流域の水路に高濃度の底質があることが判明いたしました。そのため、大阪府では優先順位を上げて、古川の浄化対策に取り組むこととし、平成20 年度中にも、一部の区間で浚渫による浄化対策に着手されるものと聞いております。
最後に、水質の汚濁状況についてですが、資料3枚目のペーパーをめくっていただきまして、裏面をご覧ください。
こちらは、平成19 年度の大阪市内の水質調査地点と河川のBOD 及び海域のCOD の汚濁状況を示しております。先ほどのダイオキシン類の調査結果と同様、大阪市の地図に水質の調査地点とBOD,COD の測定結果を示しています。
円の横に数字がございますが、上段が年平均値、下段が環境基準の評価を行うための75%値であります。円の大きさが、地点により異なっておりますが、大きさは年平均値の数値に比例しておりまして、円内にメッシュがあるところは、環境基準を超過していることを示しています。
平成19 年度の調査結果では、寝屋川の今津橋、古川の徳栄橋、平野川の安泰橋等寝屋川水系の6地点で環境基準を超過しております。
最後の資料の4枚目でございますが、河川BOD 及び海域COD の環境基準の評価を行うための75%値につきまして、平成15 年度から19年度までの経年変化を示しております。表中の1から38 番までが河川域でありBOD の測定値を示しています。39 から50 番までが海域ということでCOD の測定値となっています。
神崎川、大和川におきましても、環境基準の不適合はみられますけでれども、改善傾向にあることがうかがわれます。これに対しまして、寝屋川、平野川等の寝屋川水域の各地点では、引き続き、環境基準不適合の状況が続いていることがうかがわれます。
寝屋川、平野川等の河川の水質につきましては、上流域の影響を受けやすいことから、流域の自治体や河川管理者等との連携した取組が重要であると考えまして、生活排水対策や底質対策等につきまして、大阪府や寝屋川流域の市等で構成いたします「寝屋川流域協議会」等の関係機関と連携を図っていく所存であります。
以上で、ご説明を終わらせていただきます。
村岡委員長
ただいまのご説明に関しまして、何かご質問やご意見等はありますでしょうか?
福永委員
全体の評価として、特に、この数字をどうみるかということですが、底質においては変動幅が大きく、サンプリングのばらつきが考えられるのですが、サンプルのばらつきの範囲内で、特に例年と異なるような異常な値は見られなかったと評価していいでしょうか?
事務局(環境局前田課長代理)
先生のおっしゃるとおり、例年の変動の範囲内で収まっているものと考えております。地点によりましては、環境基準近傍のところもありますので、環境基準を超えたり、下回ったりということもございますが、概ね、例年の変動の範囲内で、データが推移しているものと考えております。
村岡委員長
他に、何かありますでしょうか?
藤川委員
底質ダイオキシンと水質ダイオキシンの濃度を比較していたのですが、16、18、20 番の3地点ですが、底質の濃度と水質の濃度の比率が著しく他の地点と異なりまして、底質濃度が低いにもかかわらず、水質中の濃度が高く出ていますが、これは何か理由があるのでしょうか?
もしかすると、水質と底質の採取ポイントが異なっているのでしょうか?
事務局(環境局黒木課長代理)
サンプリング地点において、底質が実際に採れない地点については、場所を移動して採取している関係がございます。16 番の本町橋でございますが、底質は平野橋で、20 番の小松橋では、底質は江口橋でサンプリングしております。
ということで、水質とは調査地点が異なっております。
藤川委員
18 番については、どうでしょうか?
事務局(環境局黒木課長代理)
18 番につきましては、水質も底質も今津橋でサンプリングしております。
藤川委員
普通、底質の場合は、ダイオキシンを濃縮すると思うのですが、通常の河川の状況であれば、底質からの微量の脱着か巻き上げで水質に反映されると思いますので、例えば他の地点は、底質と水質の比率ですが、水が1なら底質が200 くらいになっていますが、この3地点中2地点は同じ場所で採られているのに、水質濃度と底質濃度の状況が異なるということは、どこか異なるところに汚染源があるのか又は底質の採取状況に問題があるのか、又は分析上、何かがあるのかなと思います。
これについては、安全がどうこうというよりは、やはり、そういう傾向があるのであれば把握しておかれた方が、今後の対策のためにもいいのではないかと思います。
村岡委員長
今の問題は、要するに同じ地点における水質と底質の濃度の関係で、それが関連する現象として起こっているのか或いは、そうではないのかということですよね。
水の場合は、おそらく一過性で流れていってしまうと思いますので、必ずしも、そこの底質が溶出してきて、ダイオキシンの水質が悪くなるということは、ちょっと考えにくいケースもあると思います。
しかしながら、これだけ地点で差があるということは、何か他に原因があるのではないかということだと思うので、その点に注目されておく必要があるのではないかと思われます。
もう1つは、何年も汚染が長引いている地点があるわけですが、そうしますと、こういったことについては、当然、その汚染源がどこかという汚染源の特定についても、これまで調査されてきたはずだと思いますが、…
その汚染源を特定する作業の結果としては、原因不明ということですか?
事務局(環境局大石課長)
大阪市としましては、原因不明と考えております。
村岡委員長
水質についてもですか?
事務局(環境局大石課長)
そうです。
村岡委員長
BODについてもですか?
事務局(環境局大石課長)
BODにつきましては、本日、大阪府さんも来られているわけですが、大阪府さんと連携協力しながら、いろいろ調査もしておりますし、また、対策についても、上流域の自治体の方にも、ご要望させていただいております。
市内河川は、長期的には改善傾向にあると思っておりますが、まだ、6箇所ほど寝屋川流域で環境基準を超えているところがございますので、今後とも、連携を密にしながら、対策に努めてまいりたいと考えております。
村岡委員長
水質の方は、流れていってしまいますのでともかく、底質の問題が長引いているということは、そこの底質を除去する以外に、対策はないと断言していいのですか?
事務局(環境局大石課長)
私どもとしましては、特に寝屋川のところで、水質なり底質が市域内で環境基準を超えているということで、先ほど前田の方から説明しましたように、大阪府さんと連携しながら追跡調査を実施してきて、結果として、ご案内のとおり門真の第8水路で、高濃度のダイオキシン類を含む底質が溜まっていることがわかってまいりました。
それで、門真第八水路につきましては、門真市の方で、今年度、詳細調査をやられて、対策をどうしていくかを決められるというふうに聞いております。
古川本川の方では、大阪府河川室さんの方で、今年度、一部浚渫されると聞いております。
我々としては、その結果を期待しているところですが、今後ともモニタリング等を適宜行いまして、対策の効果を把握してまいりたいと考えております。
村岡委員長
他にございませんか?
福永委員
藤川先生の意見に対する私なりの考えなのですが、16、17、18 番の数値が低いのは、川でwet な底質が採れずに砂質的な底質が採れた場合は、数値としては小さなものとなるのではないか?だから、サンプリング場所の橋のたもとに泥がたまらず、砂混じりのサンプリングでは、このような結果になるのではないかと私は思っております。
村岡委員長
ただいまの福永先生の意見につきまして、何かございますか?他にご意見がないようですので、市の方でも、これらの貴重なご意見を参考にして、今後の検討の中に採り入れていただきたいと思います。
それでは、次の議題に移ります。
次も報告事項ですが、「大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策」について、ご説明をお願いします。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料2を用いまして、大阪港湾区域におけます底質浄化対策及び港区尻無川堤防工事におけます環境対策につきまして、ご説明させていただきます。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料2の表紙をめくっていただきますと地図がございますが、今回説明させていただきます右下の方の赤い丸印2つが、平成18 年度から行っております大阪港湾区域の底質ダイオキシン類浄化対策の工事箇所でございます。その右上の方に青い丸印がありますが、これが19 年度から20 年度にかけて対策を行いました尻無川の工事箇所でございます。
図面をめくっていただきますと、1頁から12 頁までが、大阪港湾区域における底質ダイオキシン類浄化対策に伴う環境対策についてということで、平成18 年度から行っているものでございます。
また、この対策は、平成18 年3月に策定いたしました「大阪港湾区域におけます底質ダイオキシン類浄化対策方針」に基づいて実施しておりますもので、対策方針自体を参考資料として10 頁から12 頁に添付しております。
平成18 年度の浄化対策の概要ですが、実施場所は、木津川運河の一部区域及び大正内港の一部区域です。
対策土量は、それぞれ100m3、50m3 となっております。 ????
対象としました底質は、1000pg-TEQ/g から3000pg-TEQ/g の範囲で、いわゆる中濃度レベルでございます。浚渫除去しました底質を近傍の管理型処分地であります夢洲1区まで運搬しまして、そこで袋詰脱水処理を行いまして、同じく夢洲1区に処分したというものです。
環境対策でございますが、大阪府・市の河川及び港湾の底質ダイオキシン類対策検討委員会の「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル(案)」等に準拠いたしまして、次の3項目の対策を行っております。
1.浚渫場所における防止枠及び防止膜による汚濁防止対策
2.工事施工へのフィードバック等を実施するため、浚渫場所周辺における事前調査及び日常的な水質環境監視の実施
3.浚渫土砂処分地であります夢洲における水質環境調査の実施でございます。浚渫場所に関わります水質環境監視調査でございますが、調査地点としましては、工事箇所の上流側、下流側それぞれに放流箇所に近い順に補助監視点、基準監視点を、一番遠いところにバックグランド点を設置してございます。
調査地点は、次頁の図2に示すとおりです。それぞれの調査地点を設定し、浚渫工事の実施にあたりましては、水質環境監視調査を実施いたしました。
調査内容は、4頁の表2に示すとおりでありまして、日々の工事の監視に用います濁度は、基本監視点におきまして、深度方向に水深50cm から1m間隔の各層で測定いたしました。最下層は底面から1mの深さのところでございます。ダイオキシン類や生活環境項目などの採水測定は、それぞれの基本監視点で水深約2割程度の深さで行いました。
また、バックグランド点の濁りの測定も、同じく水深の2割程度の深さで行いました。
事務局(港湾局有門課長代理)
工事前に、現地で実施いたしました事前調査結果を基に、濁度等の日々の工事の環境監視基準を設定いたしました。その内容が、4頁にございます表2に示すとおりでございます。
濁度等の環境監視基準の設定は、事前調査データが少なかったこと等、精度的なことを勘案いたしまして、事前の水質調査結果のダイオキシン類濃度と濁度の平均値を利用いたしまして、比例的に監視基準を設定したということでございます。
工事中の水質環境監視調査結果につきましては、5頁の表3のとおりでございます。表3-1 は、木津川運河の濁度の監視結果で週平均値を記載しております。
次の頁の表3-2 が、大正内港の濁度の監視結果で、同じく週平均値を記載しております。その下の表3-3 がダイオキシン類等の採水分析結果です。採水は、水深の約2割程度の深さで行っております。
結果といたしましては、異常なにごりや油膜の発生もなく、全ての地点で、水質環境監視基準(週平均値)において適合している状況でございました。ただ、濁度につきましては、補助監視点で超過した地点もございますが、同時期の基準監視点では適合しておりますので、問題はないものと考えております。
資料の7頁でございます。浚渫した底質は、夢洲1区で袋詰脱水した後、夢洲1区の管理型処分場において処分いたしました。処分先の夢洲及びその周辺の水質環境調査を行っておりますが、脱水した排出水については水質調査を実施し、ダイオキシン類に係る排水監視基準に適合していることを確認したうえで、夢洲1区のとなりにあります夢洲3区へ放流いたしました。
写真等につきましては、12頁以降に掲載しております。夢洲3区への放流水の調査結果につきま
しては、表4のとおり基準に適合しております。
この排出水は、夢洲3区からその南側にございます2区を経由いたしまして、2区の余水吐から海域に放流してございます。その際の水質調査結果は、7頁の表5のとおり排水基準に適合している状況でございます。
以上が、平成18 年度に行いました内容でございまして、平成19年度は夢洲1区側における作業を行ってございまして、平成20 年度は、現在、浄化対策工事を実施しておりまして、同様の環境対策を行っているところでございます。実際の実施場所は2箇所ありまして、18 年度と同様に、木津川運河に引き続き大正内港においても実施しておりますが、大正内港につきましては、18 年度の地点とは異なる場所で行っております。
対象としておりますダイオキシン類の濃度は、150〜1000 pg-TEQ/gといういわゆる低濃度及び1000〜3000pg-TEQ/g までのいわゆる中濃度を対象としております。
以上が、大阪港湾区域における底質浄化対策の実施結果でございます。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料の13 頁でございますが、尻無川右岸の堤防工事における環境対策について説明させていただきます。この工事は、堤防におけます耐震補強工事を行っているものですが、本工事区域内に、ダイオキシン類及びPCB の環境基準を超過した底質が確認されましたことから、工事に際しての環境対策を行ったものです。
平成19 年度から20 年度にかけて実施いたしました。次の頁ですが、対策土量としましては、約1700m3 でございます。ダイオキシン類の濃度は、160〜970pg-TEQ/g ということで、いわゆる低濃度といわれるものです。
PCB につきましては17〜37mg/kg ということでございます。対策方法といたしましては、底質を現地でセメントを加えることに
より固化処理を行い、原位置で矢板内に封じ込めを行うというものでございます。
環境対策につきましては、先ほど説明いたしました水質の浄化対策のものとほぼ同様でございます。調査内容につきましては、15 頁の表1のとおりでございます。
また、水質環境監視調査地点等につきましても、16 頁にございます図2のとおりでございます。
現地で事前に行いました環境調査結果を用いまして、濁度とダイオキシン類濃度との相関から17 頁の表2に示しております濁度等の水質環境監視基準を設定してございます。相関図を下につけているところです。
工事中の水質環境監視結果につきましては、18 頁の表3に示すとおりでございます。表3-1 は、濁度の監視結果でございます。本文にも記載させていただいておりますが、5月から6月の梅雨の時期には河川上流からの濁水の流入による影響から濃度が高くなる傾向が見られ、一部の個別測定値が超過いたしましたが、週平均値を超過することはありませんでした。
また、採水分析結果といたしましては、SS が1回基準値を超過してございますが、工事施工箇所からみて、流れの上流側でございまして、下流側におきましては基準値以下でございましたので、工事以外の影響によるものと考えてございます。また、DO につきましても、1回基準値を下回っておりますが、一般的に夏場に低くなる傾向がございますので、一時的に数値が低下したのではないかと考えております。
同日において、工事施行箇所の上流側、下流側ともに基準値を下回っていることから、工事の影響ではないものと考えております。
また、表3-2 は採水分析結果を示しておりまして、採水箇所は水深の約2割程度の深さで行っております。20 頁ですが、この工事の場合、原位置で底質にセメントを加えて固化処理を行うということでございますので、この固化処理効果の確認というものを実施しております。事前に配合試験を行いました。
その結果が表4でございます。この結果を基に、固化剤でありますセメントをどれだけ加えるかという混入量を決定いたしました。
事務局(港湾局有門課長代理)
また、実際に、現地で固化処理を行いました底質につきましても、溶出試験を行っております。その結果が表5及び表6でございます。
表5は、六価クロムについて、表4の結果を受け、決めました添加量を底質に加えまして、大丈夫かどうかをみるために行ったものであります。実際の現地における固化物の溶出試験結果は、表5及び表6のとおり基準値以下の内容となってございます。
合わせまして、当委員会の前身でございます委員会におけるご指摘を踏まえまして、溶出試験につきましては、水銀、六価クロムについても行っているところでございます。
表7につきましては、事後の水質調査の概要を記載しておりますが、工事完了が1月ということもございまして、採水は2月に実施しておりますので、現在、分析中でございます。3月中旬には結果が判明するものと思われます。
最後に、尻無川右岸の堤防工事に関する写真を最後の頁に掲載しております。以上が、港湾局からの報告でございます。
村岡委員長
先ほど同様に、何かご質問等はありませんでしょうか?
村岡委員長
17 頁の相関図ですが、いつ頃、どの場所のデータでしょうか?
事務局(港湾局有門課長代理)
実際の対策工事は、春から行っているわけですが、事前調査につきましては、前の年の秋(9月〜10 月頃)のデータでございます。
村岡委員長
現実に、濁度との相関において、監視するということも必要になってくるでしょうから、相関をとるものについては、今後もデータを蓄積される方がいいのでは…と思います。
他に何かございませんか?よろしいでしょうか?ありがとうございました。それでは、この件についても、ご理解いただいたということで、次の3つめですが、大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策について、ご説明いただきたいと思います。
事務局(建設局三村課長代理)
資料3の大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策についてでございますが、工事名としましては、「道頓堀川水辺整備その他工事(湊町右岸工区)」に関わります浄化対策ということでございます。本件につきましては、本会議の前回に開かれました平成19 年9月に、ご報告させていただいた状況を審議していただいたという工事でございます。
1頁は、工事概要ですが、道頓堀川の水辺整備ということで、ミナミを東西に流れます道頓堀川に遊歩道を設置していくという事業でございます。1-1 の構造ですが、位置的には下の図にありますように四ツ橋筋のすぐ西側の北沿いです。住所でいいますと、西区南堀江というところでございます。
延長としましては約130mほどあり、遊歩道を建設するのですが、河川の中に新しい護岸を作って、河川の中を埋め立てる形式となっております。
遊歩道の幅は、大体9〜13mとなっておりまして、河川内に鋼矢板又は鋼管矢板を打設してまいります。
今回の対象となります土量は、約4000m3 となっております。これにつきましては、ヘドロ層を除去した後に、底質の入れ替えを行っていきます。
下に、図-1 として地図が出ております。1頁めくっていただきまして、2頁でございます。若干小さくて見づらくて申し訳ありませんが、左側が施行する前の現況図でございまして、護岸即ち大きなコンクリートの壁でございますが、その前に鋼矢板の護岸があります。右側の方は計画となっておりますが、大きな護岸であるコンクリート上部を撤去いたしまして、川の中に鋼矢板
を立てますが、幅は狭いところでは9mから13mほどございます。
次の3頁のところには、非常に見づらいですが、平面図が載っておりますが、図のように矢板、鋼矢板を打っている状況でございます。
次の4頁に出ておりますのが、前回の平成19 年9月のときに、ご報告させていただきましたこの工事現場における底質の状況でございます。
?の概略調査ということで、含有量と溶出量それぞれ2地点で測定した結果を示しております。含有量につきましては、220、230pg-TEQ/gということで環境基準を超えています。また、溶出量につきましても、いわゆる海洋汚染防止法の基準をオーバーしております。この概略調査といいますのは、工事現場内の概ね真ん中に位置する2地点を選んで、その表層の土をとりましたが、次の?の詳細調査では、平面的に8地点を選びまして、それぞれについて鉛直方向についても、ヘドロ層50cm おきに砂層のところまで、溶出及び含有量について、再度詳細に調査いたしました。
その結果でございますが、ダイオキシン類の含有につきましては、概略調査とさほど変わらない数字であり、最高で470 という数字が出ております。
事務局(建設局三村課長代理)
それから、ダイオキシン類の溶出ですが、概略調査の時には、44や21 pg-TEQ/L でございましたが、全て10 未満となっている状況でございます。
その他に、一部の箇所では溶出ですが、総水銀や鉛について、若干基準を超えるものが出ております。6頁ですが、図が小さくて恐縮ですが、真ん中に赤い点が2つございます。これは、一番最初に行いました概略調査の地点でございます。
それから、黒い点が8地点ありますが、これが概略調査の土を採った箇所でございます。
我々といたしましては、概略調査の時に出てまいりました溶出量が、通常時の数値よりも若干大きいということもございまして、前回の会議の時に、おはかりさせていただきましたが、一番最初の概略調査の地図周辺の4スミを囲むように、再度調査をしたということで、7頁に平面的な位置が出ております。
概略調査の赤い点のまわり4スミを、再度調査させていただくということと、念のために、その他に3点の合計11 地点、検体数としては16 検体となると思いますが、鉛直方向にも調査させていただきました。その結果が8頁にございます。
8頁には、ダイオキシンの含有あるいは溶出について記載しておりますが、含有量といたしましては、前回または前々回に調査いたしましたような数値でございまして、今回の場合には最高で330 pg-TEQ/gというような数字が出ております。溶出量につきましては、海洋汚染防止法基準、これは埋立が可能かどうかの基準ですが、10 未満の数字ばかりでございまして、最高で6.5 というような数字となっております。
これによりまして、北港に埋立処分する土は約2,800m3、溶出量を再チェックした形で、鉛、水銀というものが混ざっているということで、海洋投棄できないという土量はセメント原料として、セメント工場に運搬しましたのが、1,200m3 というような形で確定させていただきました。
9頁でございますが、工事中の環境監視ということで、前回の会議の時に、事前の水質調査の結果を報告させていただいております。10頁には水質環境基準ということで、その下側に出てまいりますが、pH,BOD,SS,DO、濁度が記載されております。この中で、濁度でございますが、濁度の週平均値は10.0 度、個別測定値は22.3 度で、事前の水質調査結果から設定されております。週平均値の10.0 度でございますが、事前の水質調査結果の段階でダイオキシン類の水質が3.6pg-TEQ/L ということでございまして、この10.0 度という数値につきましては、事前の水質調査結果に関して、現状より悪化させないという形の監視基準としております。
11 頁については、監視状況の結果を掲載しております。11 頁は、濁度の測定結果でございます。これは、週平均値の数字
を載せさせていただいておりまして、その下に個々の数字の最大・最小値を記載しております。
事務局(建設局三村課長代理)
個々の数値及び週平均値につきましても、環境監視基準値を上回るところはございませんでした。pH,BOD,SS,DO等の生活環境項目の測定でございますが、DO とBOD につきましては、一部の期間で監視基準を上回るあるいは下回るようなところが出てまいりまして、その期間につきましては、DO の場合は、矢板の打設や鋼管矢板の打設という時期でありまして、若干、矢板の打設速度を遅らせるというかゆっくりさせるというようなことで対応しました。
BOD の場合は、埋め立ての時、土を締切内に入れる時の状況でございますが、この時につきましても、若干、土砂の掘削あるいは投入に係るスピードを落とさせていただいたということでございます。
今回の工事につきましては、以上のような結果となっています。
村岡委員長
ご質問やご意見がありましたら、お願いします。
上野委員
ダイオキシン類の溶出量ですが、2回目の測定時点でも、若干、まだ数値が高いような気がするのですが、浚渫土中の特徴としては何かあるのでしょうか?あるいは溶出液が、若干濁っているとかはあるのでしょうか?
オブザーバ
(大阪市立環境科学研究所先山主任)
私は、本データを事前に見せていただきましたので、その印象からご説明させていただきます。先生がおっしゃるように、底質の2回目の測定データにつきましても、若干高いかなという気がしますが、まず、1回目の方が非常に高いということで、溶出量が多くなるような状況にあった泥なのかどうかということをみる指標がないかというご相談で、事前に見せていただきました。
しかし、その時点では、そのことを判断するようなデータの採取がなされていないということで、すでに、この時の泥が存在しない段階では、その判断はできませんでした。
2回目のデータにつきましては、平均の粒子径などは若干、データとしてとられていましたので、それを見せていただきまた。そうすると、この底質は、ダイオキシンも高いですけれども、かなりヘドロ化しているということで、平均粒子径が0.05mm を下回るようなものもたくさんありまして、非常に微粒子の底質が多いという状況がうかがえると思います。
ですから、ろ過操作等のバラツキというものが、結構、大きく効いてくるのではないかという判断を私はいたしました。
村岡委員長
このろ過操作というのは、現在のところ、どのような基準でやっておられるのですか?
オブザーバ
(大阪市立環境科学研究所先山主任)
ろ過操作につきましては、海洋汚染防止法で、ご存知のように孔径という表現がなされているわけですが、前回の委員会でも若干、説明させていただいたのですが、私が調べたところによりますと、市販品ではガラス繊維ろ紙で、仕様上、そのような表現がなされているものは存在しません。
現実には、様々なメーカーにより表現方法が異なるということで、その孔径に値するそれぞれの表現が、どの程度かとい
うことは、メーカーによってばらついております。
それを使用するときに、孔径と置き換えて読むのか、それよりも孔径の方が小さいということで、1μmよりも小さなものを使用するかということで、かなりろ過操作にバラツキが出る可能性があります。
しかし、公式には孔径という表現がされておりますので、孔径をどのように分析する側が解釈するかということで、結果に大きな違いが出ているのではないかと思います。具体的には、孔径と同じような意味で使われているメーカーさんのものでしたら、粒子保持能という表現があり、ろ過の初期段階でその粒子径以上のものが98%以上止められるという表現をされているところもあります。
もう一方では、保留粒子径ということで、「1μmのものを止めようとしますと、さらにその半分くらいの0.4〜0.6μmのものを使わないとダメですよ。」ということがカタログ上では示されていますので、その辺、混同して使用している可能性があるのかなと思います。
ですので、どのようなものを使うかということは、いずれ公式の委員会の場で承認を得て、標準的な操作の仕方というのを用いないと、なかなか説明がつかないデータが出てくる可能性があると考えられます。
村岡委員長
何か関連して、ご意見ありませんでしょうか?
福永委員
後で、この件に関して、お願いしようかなと思っていたのですが、前回の委員会でも、かなり問題になって、結局ばらついたデータが出てきて、議論に困るというようなことが多いと思うのですけれども、環境科学研究所さんの方で、大阪府さんとも調整していただきながら、誰が行っても同じ答えが出るというふうなフロー、いわば、今法令的には定められているんですけれども、必ずしも十分ではないので、人によって異なった答えが出るということですから、この委員会にデータとして出すという時には必ずこの方法で行えば、間違いない安定した数値が出るというフローを考えていただければ、この委員会としてはありがたいのではないかと思いますので、お願いしたいと思います。
事務局(環境局大石課長)
福永先生のご指摘の点ですが、先般、環境省の方から底質の調査方法に関わりまして、アンケート調査がまいりました。その時に、私どもの回答の中に、分析に用いるろ紙の規格をはっきりと明記してほしいということをお返ししております。いずれにいたしましても、前回以降、村岡先生にもご指摘をいただきながら、府市で、きちんと統一的な取り扱いを決めるようにというご指摘もありましたので、今後、大阪府の底質委員会の事務局とも調整をしながら、また、本市環境科学研究所、大阪府環境農林水産総合研究所とも、ご相談しながら、統一的な取り扱いができるかどうかも含めまして検討を進めてまいりたいと考えております。
村岡委員長
その点につきましては、ぜひスタンダードな測定値をもとに議論ができるように進めてほしいと思います。
藤川委員
濁度とダイオキシンの関係を0.1pg-TEQ/L だというのが、先ほどの回帰分析の結果ですけれども、今回の方では、濁度との関係を3.6pg-TEQ/L というふうにおっしゃっていただいたのですが、濁度1が0.1 なのか0.36 なのかというので、そういうデータは蓄積していただくのは、妥当だと思うのですが、ただ、この時の濁度10 で3.6pg-TEQ/L とおっしゃった時のろ過方法は、どのようなものだったのかを教えていただきたいのが第1点です。
もう1つは、ダイオキシン類については溶出量と含有量を両方測ると思いますが、普通、ダイオキシン類は溶出量は低いでしょうから、例えば、この溶出量と含有量の比が含有量5に対して溶出量が1というデータが出た時点で、直ちに環境科学研究所さんから、現場の方にご相談いただくなり、再分析に回すなりの対応をしていただくと早いと思うのです。
だから、そういうことを現場で徹底していただいたらどうかなというのが第2点です。
不自然なデータが出れば、すぐに追加のサンプリングはもちろんですけれども、再分析ということも考えられると思います。
事務局(建設局三村課長代理)
事前の水質調査を行った時には、2回目の詳細調査と同じ方法で行っております。一番最初の概略調査あるいは次の詳細調査、それから事前の水質調査という段階を経まして、事前の水質調査と詳細調査はほぼ同じような時期になっておりますが、一番最初の概略調査と次の詳細調査と次の詳細調査あるいは事前水質調査とは若干、違うような形であると聞いております。
私どもは、工事を発注してから、水質調査あるいは底質調査を行っておりますので、これからはちょっと考え直さなくてはいけないのですが、当時の工事期間中にそういうふうな状況が出てまいりますので、結果が出るまで少なくとも1カ月、2カ月ほどかかりますので、若干、その辺のところが、我々としては考え直さなくてはならないところではあると思います。
事務局(環境局大石課長)
2点目のご指摘でございますが、我々といたしましては、これからもデータの蓄積につきましては、統一的に、今後も進めていきたいと考えております。
また、検討会の事務局を、大阪市的にも港湾局、環境局、建設局、オブザーバとして環境科学研究所さんにも入っていただいておりますので、うまく機能させていきながら連絡体制をとっていきたいと考えております。
村岡委員長
今の問題は、すぐに解決できるものとは思えないですし、その時、その時に判断しないといけない大変難しい問題ですが、是非ともいい値が出るように、「正しい値が出て、正しい判断ができるように」努力をしてくださいということですから、その辺のところをよろしくお願いいたします。
他にございますか?
それでは、ご意見がないようでございますので、本日の議題である3つの報告について、委員の先生方、いろいろご指摘いただきましたので、これで全て終わったというわけではありませんが、ともかく、この報告の中身について、十分確認できたということにさせていただきます。
合わせまして、これに基づいて、また、作業が進められると思いますので、ぜひ、それが円滑に、いい効果が上げられますようにお願いしたいと思います。
それでは、以上をもちまして、議事を終わりたいと思います。後、進行を事務局にお願いします。
大阪市底質対策等技術検討会
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000019399.html
1 日 時 平成21 年2月20 日(金) 午後1時30 分〜午後2時50 分
2 場 所 環境局第11〜13 会議室(WTCコスモタワービル36 階)
3 出席者
(委 員)
大阪大学名誉教授 村岡 浩爾
大阪人間科学大学人間科学部教授 福永 勲
摂南大学薬学部准教授 上野 仁
京都大学原子炉実験所准教授 藤川 陽子
(事務局)
大阪市環境局・港湾局・建設局
(オブザーバ)
大阪府都市整備部河川室、大阪府環境農林水産部環境管理室、
大阪府環境農林水産総合研究所、大阪市立環境科学研究所水環境担当
4 議 題
(1) 委員長の選出
(2) 報告案件
? 平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
? 大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策について
? 大阪市管理河川(道頓堀川等)における底質浄化対策について
5 議事要旨
(1) 委員長の選出について
要綱の規定に基づき、委員の互選により村岡委員が委員長として選出された。また、村岡委員長の指名により、福永委員が委員長の職務代行を行うこととなった。
(2) 平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
事務局(環境局)から、大阪市域における平成15〜19 年度までの5年間の水質・底質に係るダイオキシン類濃度測定結果及び水質に係る代表的な汚濁指標であるBOD やCOD の汚濁状況について報告を行った。
(3) 大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策について
事務局(港湾局)から、平成18 年度から着手している大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策に伴う環境対策の概要(浚渫場所周辺における事前・日常的な水質環境監視や処分地(夢洲)及びその周辺おける水質環境調査結果など)の報告を行うとともに、平成19 年度に着手した港区尻無川(水門上流)堤防工事における環境対策の概要(工事場所周辺における事前・日常的な水質環境監視や固化処理による封じ込め効果を確認するための水質調査の実施結果など)について報告を行った。
(4) 大阪市管理河川(道頓堀川等)における底質浄化対策について
事務局(建設局)から、道頓堀川水辺整備事業のうち、湊町右岸工区における遊歩道の設置に係る工事概要、浚渫土の処理、工事中の環境監視結果などについて報告を行った。
【結果】
(2)〜(4)について、事務局からの報告内容について、各委員からご理解をいただいたが、底質ダイオキシン類溶出量の測定値の評価に関して、「底質ダイオキシン類に関する分析手法を含めた統一的な取り扱いの確立に向け、今後、府市等関係機関が連携すること」などが要望として出された。
6 会議資料:
(1)資料1 :平成19 年度ダイオキシン類環境調査結果について
(2)資料2 :大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策及び港区尻無川(水門上流)堤防工事における環境対策について
(3)資料3 :大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策について
(4)参考資料:大阪市底質対策等技術検討会開催要綱
7 問い合わせ先
大阪市環境局環境保全部土壌水質担当
Tel:06-6615-7984、FAX:06-6615-7949、E-mail:ja0040@city.osaka.lg.jp
大阪市底質対策等技術検討会会議録
発言者(事務局及びオブザーバ)
・環境局環境保全部長 西山健一郎
・環境局環境保全部土壌水質担当課長 大石 一裕
・環境局環境保全部土壌水質担当課長代理 前田 和男
・環境局環境保全部環境情報担当課長代理 黒木 隆司
・環境局環境保全部担当係長 宮本 敏之(司会者)
・港湾局計画整備部環境保全担当課長代理 有門 貴
・建設局下水道河川部河川担当課長代理 三村 経雄
・大阪市立環境科学研究所水環境担当研究主任 先山 孝則
議事内容:次のとおり
西山環境保全部長
さて、大阪市では、これまで「大阪市底質対策技術検討会」におきまして、市内の河川並びに海域における底質汚染などに関しまして、その汚染要因や浄化対策につきまして検討するとともに、市域内における土壌汚染、また、地下水汚染に係ります調査・対策に関しましては、別途「大阪市土壌汚染対策専門委員会」を設置させていただき、学識者の先生方より検討をいただいたところでございます。
今般、大阪市では、これらの2つの委員会をより総合的に運用いたしまして、大阪市域内の公共用水域に係ります有害な底質、また、市域内の土壌汚染・地下水汚染など、水環境分野と地盤環境の分野の対策を一体的に推進いたしますため、平成20 年7月に底質の委員会に土壌の委員会を整理・統合させていただいたところでございます。
本日は、これまで「底質対策技術検討会」でご検討いただきました大阪港湾区域並びに本市の管理河川におけます底質浄化対策の進捗の状況、また、環境監視の結果などにつきまして、ご検討いただきたいと考えてございます。
本市といたしましては、今後とも、良好な都市環境を確保するとともに、水環境、また、地盤環境をはじめ、各種の環境施策をより一層、推進していく所存でございますので、委員の先生方におかれましては、引き続き、お力添えを賜りますようお願い申しあげまして、簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。
大阪市では、これまで「大阪市底質対策技術検討会」におきまして、底質汚染問題について、また、「大阪市土壌汚染対策専門委員会」では、土壌汚染や地下水汚染問題について、それぞれ検討を行ってまいりましたが、今後の環境施策を円滑に推進していくために、この2つの委員会を統合いたしまして、参考資料に示しますとおり、要綱改訂を行ってきたところです。
本検討会の委員につきましては、村岡先生、福永先生には再任させていただきますとともに、新たに上野先生、藤川先生には委員にご就任いただき、検討を進めていくこととなりました。
村岡委員長
委員の先生方から、ご賛同を得ましたので、この検討会の委員長を務めさせていただきます。
この検討会は、先ほど西山部長からも、ご説明ありましたように、これまでの2つの委員会を統合した新たな委員会となっています。これまで扱ってきました内容は、底質汚染、土壌汚染、地下水汚染であります。これらの内容については、相互に関係する場合もあり、独立して考えなければならない場合もあります。
この3つの汚染は、対策という面から扱っていく拠り所となる法律は3つとも別であります。ということで、これを行政サイドから扱われるにしても、環境局、港湾局、建設局と3つに分かれているわけです。
今回、統合的に検討するということになりまして、ある意味では、行政の縦割りを除いた総合的な検討ができる場であるということで、好ましい形になってきたのではないかと思います。
委員の先生方にも、それぞれご専門があるわけですが、この際、ご自分の専門以外に関連することが多いでしょうから、そういったところから広く総合的にご議論いただくことが望ましいと思いますので、その点、ご協力の方よろしくお願いいたします。
それでは、早速、議事に入りますが、本日の議題は、報告案件だけ3つあるようでございます。
まず、第1の議案ですけれども、「平成19 年度 ダイオキシン類環境調査結果」についてでございます。
事務局(環境局前田課長代理)
お手元の資料1に基づきまして、「平成19 年度ダイオキシン類調査結果」について、ご説明させていただきます。平成19 年度のダイオキシン類の水質・底質調査地点及び環境基準の適合状況を表しております。大阪市の地図上に、水質・底質のダイオキシン類の調査地点と環境基準の適合・不適合を示しております。各地点ごとに円がありますが、円の上半分が赤い場合は水質の環境基準不適合を、下半分が赤い場合は、底質の環境基準が不適合を、全体が赤い場合は、水質・底質両方とも環境基準不適合であることを表しております。
平成19 年度、水質につきましては、古川の徳栄橋、神崎川の小松橋、東横堀川の本町橋の3箇所で環境基準不適合となっております。
事務局(環境局前田課長代理)
また、底質につきましては、古川の徳栄橋、六軒家川の春日出橋、住吉川の住之江大橋下流1,100mの地点で環境基準不適合となっております。
こちらの表−1でございますが、水質のダイオキシン類濃度の経年変化を示しております。経年変化としましては、平成15 年度から19年度までのデータで示しております。
環境基準を超える又は高めのデータが出ている地点につきましては、調査回数を多く設定するというように、年度・地点により、調査回数が異なっております。複数回、測定を行う地点につきましては、データを範囲で示しております。
青色の網掛けをしており、下線を引いておりますのは、環境基準値1pg-TEQ/L を超えたところです。道頓堀川の大黒橋、古川の徳栄橋、東横堀川の本町橋、寝屋川の今津橋、京橋、神崎川の小松橋において、環境基準不適合となる傾向にあります。
資料の3枚目をご覧いただきたいのですが、こちらの方は、底質のダイオキシン類濃度の経年変化を示したものでございます。水質と同様に、平成15 年度から19 年度までのデータでお示ししております。
水質と同様、網をかけて下線を引いておりますところが、環境基準値150pg-TEQ/g を超えたところであります。道頓堀川の大黒橋、古川の徳栄橋の他、木津川、神崎川の河口部において、環境基準が不適合となる傾向が続いております。
ダイオキシン類の汚染要因でありますが、大阪府、大阪市で設置しております「河川及び港湾の底質浄化対策検討委員会」において検討されておりまして、大阪府及び大阪市の河川及び港湾におけるダイオキシン類の汚染は、主にPCB 製剤、並びに農薬、燃焼由来の要因が複合したものであり、個々の発生源の影響を特定することは困難であると結論づけられております。
底質浄化対策についてですが、まず、本市管理河川についてご説明させていただきますと、道頓堀川、東横堀川につきましては、既存の測定結果におきまして、すでに底質ダイオキシン類の環境基準の超過が判明しておりますので、大阪市建設局が詳細調査を行い、ダイオキシン類による底質汚染を確認しております。底質浄化対策につきましては、平成19 年度に同局が両河川の一部の区間で浚渫による浄化対策を実施しております。
港湾区域につきましては、同じく既存の測定結果におきまして、既に底質ダイオキシン類の環境基準の超過が判明しておりますので、大阪市港湾局が平成15 年度から17 年度にかけまして、正蓮寺川、尻無川、木津川、木津川運河等の大阪港湾区域の河川、港湾重複7区域におきまして、底質ダイオキシン類の汚染範囲等の調査を行っております。
事務局
(環境局前田課長代理)
底質浄化対策につきましては、平成18 年度から、木津川運河の一部区域、大正内港の一部区域で、同局が浚渫による浄化対策に着手しているところでございます。
さらに、大阪市以外の管理河川につきましては、神崎川、古川におきまして検討がなされているところでありますが、神崎川につきましては、大阪府におきまして、本川で平成18 年度以降、浚渫と覆砂による底質対策が行われているところでございます。
また、神崎川上流の水路で高濃度の底質ダイオキシン類が検出されているということで、大阪府の方で汚染底質の除去及び底質除去後の環境モニタリングが実施されております。
特に、古川につきましては、大阪府と大阪市が連携いたしまして、ダイオキシン類による底質汚染原因究明のための追跡調査を行い、上流に環境基準を超える底質があることが判明いたしました。その後、古川の河川管理者である大阪府の方で、詳細調査が行われ、上流域の水路に高濃度の底質があることが判明いたしました。そのため、大阪府では優先順位を上げて、古川の浄化対策に取り組むこととし、平成20 年度中にも、一部の区間で浚渫による浄化対策に着手されるものと聞いております。
最後に、水質の汚濁状況についてですが、資料3枚目のペーパーをめくっていただきまして、裏面をご覧ください。
こちらは、平成19 年度の大阪市内の水質調査地点と河川のBOD 及び海域のCOD の汚濁状況を示しております。先ほどのダイオキシン類の調査結果と同様、大阪市の地図に水質の調査地点とBOD,COD の測定結果を示しています。
円の横に数字がございますが、上段が年平均値、下段が環境基準の評価を行うための75%値であります。円の大きさが、地点により異なっておりますが、大きさは年平均値の数値に比例しておりまして、円内にメッシュがあるところは、環境基準を超過していることを示しています。
平成19 年度の調査結果では、寝屋川の今津橋、古川の徳栄橋、平野川の安泰橋等寝屋川水系の6地点で環境基準を超過しております。
最後の資料の4枚目でございますが、河川BOD 及び海域COD の環境基準の評価を行うための75%値につきまして、平成15 年度から19年度までの経年変化を示しております。表中の1から38 番までが河川域でありBOD の測定値を示しています。39 から50 番までが海域ということでCOD の測定値となっています。
神崎川、大和川におきましても、環境基準の不適合はみられますけでれども、改善傾向にあることがうかがわれます。これに対しまして、寝屋川、平野川等の寝屋川水域の各地点では、引き続き、環境基準不適合の状況が続いていることがうかがわれます。
寝屋川、平野川等の河川の水質につきましては、上流域の影響を受けやすいことから、流域の自治体や河川管理者等との連携した取組が重要であると考えまして、生活排水対策や底質対策等につきまして、大阪府や寝屋川流域の市等で構成いたします「寝屋川流域協議会」等の関係機関と連携を図っていく所存であります。
以上で、ご説明を終わらせていただきます。
村岡委員長
ただいまのご説明に関しまして、何かご質問やご意見等はありますでしょうか?
福永委員
全体の評価として、特に、この数字をどうみるかということですが、底質においては変動幅が大きく、サンプリングのばらつきが考えられるのですが、サンプルのばらつきの範囲内で、特に例年と異なるような異常な値は見られなかったと評価していいでしょうか?
事務局(環境局前田課長代理)
先生のおっしゃるとおり、例年の変動の範囲内で収まっているものと考えております。地点によりましては、環境基準近傍のところもありますので、環境基準を超えたり、下回ったりということもございますが、概ね、例年の変動の範囲内で、データが推移しているものと考えております。
村岡委員長
他に、何かありますでしょうか?
藤川委員
底質ダイオキシンと水質ダイオキシンの濃度を比較していたのですが、16、18、20 番の3地点ですが、底質の濃度と水質の濃度の比率が著しく他の地点と異なりまして、底質濃度が低いにもかかわらず、水質中の濃度が高く出ていますが、これは何か理由があるのでしょうか?
もしかすると、水質と底質の採取ポイントが異なっているのでしょうか?
事務局(環境局黒木課長代理)
サンプリング地点において、底質が実際に採れない地点については、場所を移動して採取している関係がございます。16 番の本町橋でございますが、底質は平野橋で、20 番の小松橋では、底質は江口橋でサンプリングしております。
ということで、水質とは調査地点が異なっております。
藤川委員
18 番については、どうでしょうか?
事務局(環境局黒木課長代理)
18 番につきましては、水質も底質も今津橋でサンプリングしております。
藤川委員
普通、底質の場合は、ダイオキシンを濃縮すると思うのですが、通常の河川の状況であれば、底質からの微量の脱着か巻き上げで水質に反映されると思いますので、例えば他の地点は、底質と水質の比率ですが、水が1なら底質が200 くらいになっていますが、この3地点中2地点は同じ場所で採られているのに、水質濃度と底質濃度の状況が異なるということは、どこか異なるところに汚染源があるのか又は底質の採取状況に問題があるのか、又は分析上、何かがあるのかなと思います。
これについては、安全がどうこうというよりは、やはり、そういう傾向があるのであれば把握しておかれた方が、今後の対策のためにもいいのではないかと思います。
村岡委員長
今の問題は、要するに同じ地点における水質と底質の濃度の関係で、それが関連する現象として起こっているのか或いは、そうではないのかということですよね。
水の場合は、おそらく一過性で流れていってしまうと思いますので、必ずしも、そこの底質が溶出してきて、ダイオキシンの水質が悪くなるということは、ちょっと考えにくいケースもあると思います。
しかしながら、これだけ地点で差があるということは、何か他に原因があるのではないかということだと思うので、その点に注目されておく必要があるのではないかと思われます。
もう1つは、何年も汚染が長引いている地点があるわけですが、そうしますと、こういったことについては、当然、その汚染源がどこかという汚染源の特定についても、これまで調査されてきたはずだと思いますが、…
その汚染源を特定する作業の結果としては、原因不明ということですか?
事務局(環境局大石課長)
大阪市としましては、原因不明と考えております。
村岡委員長
水質についてもですか?
事務局(環境局大石課長)
そうです。
村岡委員長
BODについてもですか?
事務局(環境局大石課長)
BODにつきましては、本日、大阪府さんも来られているわけですが、大阪府さんと連携協力しながら、いろいろ調査もしておりますし、また、対策についても、上流域の自治体の方にも、ご要望させていただいております。
市内河川は、長期的には改善傾向にあると思っておりますが、まだ、6箇所ほど寝屋川流域で環境基準を超えているところがございますので、今後とも、連携を密にしながら、対策に努めてまいりたいと考えております。
村岡委員長
水質の方は、流れていってしまいますのでともかく、底質の問題が長引いているということは、そこの底質を除去する以外に、対策はないと断言していいのですか?
事務局(環境局大石課長)
私どもとしましては、特に寝屋川のところで、水質なり底質が市域内で環境基準を超えているということで、先ほど前田の方から説明しましたように、大阪府さんと連携しながら追跡調査を実施してきて、結果として、ご案内のとおり門真の第8水路で、高濃度のダイオキシン類を含む底質が溜まっていることがわかってまいりました。
それで、門真第八水路につきましては、門真市の方で、今年度、詳細調査をやられて、対策をどうしていくかを決められるというふうに聞いております。
古川本川の方では、大阪府河川室さんの方で、今年度、一部浚渫されると聞いております。
我々としては、その結果を期待しているところですが、今後ともモニタリング等を適宜行いまして、対策の効果を把握してまいりたいと考えております。
村岡委員長
他にございませんか?
福永委員
藤川先生の意見に対する私なりの考えなのですが、16、17、18 番の数値が低いのは、川でwet な底質が採れずに砂質的な底質が採れた場合は、数値としては小さなものとなるのではないか?だから、サンプリング場所の橋のたもとに泥がたまらず、砂混じりのサンプリングでは、このような結果になるのではないかと私は思っております。
村岡委員長
ただいまの福永先生の意見につきまして、何かございますか?他にご意見がないようですので、市の方でも、これらの貴重なご意見を参考にして、今後の検討の中に採り入れていただきたいと思います。
それでは、次の議題に移ります。
次も報告事項ですが、「大阪港湾区域(木津川運河等)における底質浄化対策」について、ご説明をお願いします。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料2を用いまして、大阪港湾区域におけます底質浄化対策及び港区尻無川堤防工事におけます環境対策につきまして、ご説明させていただきます。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料2の表紙をめくっていただきますと地図がございますが、今回説明させていただきます右下の方の赤い丸印2つが、平成18 年度から行っております大阪港湾区域の底質ダイオキシン類浄化対策の工事箇所でございます。その右上の方に青い丸印がありますが、これが19 年度から20 年度にかけて対策を行いました尻無川の工事箇所でございます。
図面をめくっていただきますと、1頁から12 頁までが、大阪港湾区域における底質ダイオキシン類浄化対策に伴う環境対策についてということで、平成18 年度から行っているものでございます。
また、この対策は、平成18 年3月に策定いたしました「大阪港湾区域におけます底質ダイオキシン類浄化対策方針」に基づいて実施しておりますもので、対策方針自体を参考資料として10 頁から12 頁に添付しております。
平成18 年度の浄化対策の概要ですが、実施場所は、木津川運河の一部区域及び大正内港の一部区域です。
対策土量は、それぞれ100m3、50m3 となっております。 ????
対象としました底質は、1000pg-TEQ/g から3000pg-TEQ/g の範囲で、いわゆる中濃度レベルでございます。浚渫除去しました底質を近傍の管理型処分地であります夢洲1区まで運搬しまして、そこで袋詰脱水処理を行いまして、同じく夢洲1区に処分したというものです。
環境対策でございますが、大阪府・市の河川及び港湾の底質ダイオキシン類対策検討委員会の「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル(案)」等に準拠いたしまして、次の3項目の対策を行っております。
1.浚渫場所における防止枠及び防止膜による汚濁防止対策
2.工事施工へのフィードバック等を実施するため、浚渫場所周辺における事前調査及び日常的な水質環境監視の実施
3.浚渫土砂処分地であります夢洲における水質環境調査の実施でございます。浚渫場所に関わります水質環境監視調査でございますが、調査地点としましては、工事箇所の上流側、下流側それぞれに放流箇所に近い順に補助監視点、基準監視点を、一番遠いところにバックグランド点を設置してございます。
調査地点は、次頁の図2に示すとおりです。それぞれの調査地点を設定し、浚渫工事の実施にあたりましては、水質環境監視調査を実施いたしました。
調査内容は、4頁の表2に示すとおりでありまして、日々の工事の監視に用います濁度は、基本監視点におきまして、深度方向に水深50cm から1m間隔の各層で測定いたしました。最下層は底面から1mの深さのところでございます。ダイオキシン類や生活環境項目などの採水測定は、それぞれの基本監視点で水深約2割程度の深さで行いました。
また、バックグランド点の濁りの測定も、同じく水深の2割程度の深さで行いました。
事務局(港湾局有門課長代理)
工事前に、現地で実施いたしました事前調査結果を基に、濁度等の日々の工事の環境監視基準を設定いたしました。その内容が、4頁にございます表2に示すとおりでございます。
濁度等の環境監視基準の設定は、事前調査データが少なかったこと等、精度的なことを勘案いたしまして、事前の水質調査結果のダイオキシン類濃度と濁度の平均値を利用いたしまして、比例的に監視基準を設定したということでございます。
工事中の水質環境監視調査結果につきましては、5頁の表3のとおりでございます。表3-1 は、木津川運河の濁度の監視結果で週平均値を記載しております。
次の頁の表3-2 が、大正内港の濁度の監視結果で、同じく週平均値を記載しております。その下の表3-3 がダイオキシン類等の採水分析結果です。採水は、水深の約2割程度の深さで行っております。
結果といたしましては、異常なにごりや油膜の発生もなく、全ての地点で、水質環境監視基準(週平均値)において適合している状況でございました。ただ、濁度につきましては、補助監視点で超過した地点もございますが、同時期の基準監視点では適合しておりますので、問題はないものと考えております。
資料の7頁でございます。浚渫した底質は、夢洲1区で袋詰脱水した後、夢洲1区の管理型処分場において処分いたしました。処分先の夢洲及びその周辺の水質環境調査を行っておりますが、脱水した排出水については水質調査を実施し、ダイオキシン類に係る排水監視基準に適合していることを確認したうえで、夢洲1区のとなりにあります夢洲3区へ放流いたしました。
写真等につきましては、12頁以降に掲載しております。夢洲3区への放流水の調査結果につきま
しては、表4のとおり基準に適合しております。
この排出水は、夢洲3区からその南側にございます2区を経由いたしまして、2区の余水吐から海域に放流してございます。その際の水質調査結果は、7頁の表5のとおり排水基準に適合している状況でございます。
以上が、平成18 年度に行いました内容でございまして、平成19年度は夢洲1区側における作業を行ってございまして、平成20 年度は、現在、浄化対策工事を実施しておりまして、同様の環境対策を行っているところでございます。実際の実施場所は2箇所ありまして、18 年度と同様に、木津川運河に引き続き大正内港においても実施しておりますが、大正内港につきましては、18 年度の地点とは異なる場所で行っております。
対象としておりますダイオキシン類の濃度は、150〜1000 pg-TEQ/gといういわゆる低濃度及び1000〜3000pg-TEQ/g までのいわゆる中濃度を対象としております。
以上が、大阪港湾区域における底質浄化対策の実施結果でございます。
事務局(港湾局有門課長代理)
資料の13 頁でございますが、尻無川右岸の堤防工事における環境対策について説明させていただきます。この工事は、堤防におけます耐震補強工事を行っているものですが、本工事区域内に、ダイオキシン類及びPCB の環境基準を超過した底質が確認されましたことから、工事に際しての環境対策を行ったものです。
平成19 年度から20 年度にかけて実施いたしました。次の頁ですが、対策土量としましては、約1700m3 でございます。ダイオキシン類の濃度は、160〜970pg-TEQ/g ということで、いわゆる低濃度といわれるものです。
PCB につきましては17〜37mg/kg ということでございます。対策方法といたしましては、底質を現地でセメントを加えることに
より固化処理を行い、原位置で矢板内に封じ込めを行うというものでございます。
環境対策につきましては、先ほど説明いたしました水質の浄化対策のものとほぼ同様でございます。調査内容につきましては、15 頁の表1のとおりでございます。
また、水質環境監視調査地点等につきましても、16 頁にございます図2のとおりでございます。
現地で事前に行いました環境調査結果を用いまして、濁度とダイオキシン類濃度との相関から17 頁の表2に示しております濁度等の水質環境監視基準を設定してございます。相関図を下につけているところです。
工事中の水質環境監視結果につきましては、18 頁の表3に示すとおりでございます。表3-1 は、濁度の監視結果でございます。本文にも記載させていただいておりますが、5月から6月の梅雨の時期には河川上流からの濁水の流入による影響から濃度が高くなる傾向が見られ、一部の個別測定値が超過いたしましたが、週平均値を超過することはありませんでした。
また、採水分析結果といたしましては、SS が1回基準値を超過してございますが、工事施工箇所からみて、流れの上流側でございまして、下流側におきましては基準値以下でございましたので、工事以外の影響によるものと考えてございます。また、DO につきましても、1回基準値を下回っておりますが、一般的に夏場に低くなる傾向がございますので、一時的に数値が低下したのではないかと考えております。
同日において、工事施行箇所の上流側、下流側ともに基準値を下回っていることから、工事の影響ではないものと考えております。
また、表3-2 は採水分析結果を示しておりまして、採水箇所は水深の約2割程度の深さで行っております。20 頁ですが、この工事の場合、原位置で底質にセメントを加えて固化処理を行うということでございますので、この固化処理効果の確認というものを実施しております。事前に配合試験を行いました。
その結果が表4でございます。この結果を基に、固化剤でありますセメントをどれだけ加えるかという混入量を決定いたしました。
事務局(港湾局有門課長代理)
また、実際に、現地で固化処理を行いました底質につきましても、溶出試験を行っております。その結果が表5及び表6でございます。
表5は、六価クロムについて、表4の結果を受け、決めました添加量を底質に加えまして、大丈夫かどうかをみるために行ったものであります。実際の現地における固化物の溶出試験結果は、表5及び表6のとおり基準値以下の内容となってございます。
合わせまして、当委員会の前身でございます委員会におけるご指摘を踏まえまして、溶出試験につきましては、水銀、六価クロムについても行っているところでございます。
表7につきましては、事後の水質調査の概要を記載しておりますが、工事完了が1月ということもございまして、採水は2月に実施しておりますので、現在、分析中でございます。3月中旬には結果が判明するものと思われます。
最後に、尻無川右岸の堤防工事に関する写真を最後の頁に掲載しております。以上が、港湾局からの報告でございます。
村岡委員長
先ほど同様に、何かご質問等はありませんでしょうか?
村岡委員長
17 頁の相関図ですが、いつ頃、どの場所のデータでしょうか?
事務局(港湾局有門課長代理)
実際の対策工事は、春から行っているわけですが、事前調査につきましては、前の年の秋(9月〜10 月頃)のデータでございます。
村岡委員長
現実に、濁度との相関において、監視するということも必要になってくるでしょうから、相関をとるものについては、今後もデータを蓄積される方がいいのでは…と思います。
他に何かございませんか?よろしいでしょうか?ありがとうございました。それでは、この件についても、ご理解いただいたということで、次の3つめですが、大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策について、ご説明いただきたいと思います。
事務局(建設局三村課長代理)
資料3の大阪市管理河川(道頓堀川)における底質浄化対策についてでございますが、工事名としましては、「道頓堀川水辺整備その他工事(湊町右岸工区)」に関わります浄化対策ということでございます。本件につきましては、本会議の前回に開かれました平成19 年9月に、ご報告させていただいた状況を審議していただいたという工事でございます。
1頁は、工事概要ですが、道頓堀川の水辺整備ということで、ミナミを東西に流れます道頓堀川に遊歩道を設置していくという事業でございます。1-1 の構造ですが、位置的には下の図にありますように四ツ橋筋のすぐ西側の北沿いです。住所でいいますと、西区南堀江というところでございます。
延長としましては約130mほどあり、遊歩道を建設するのですが、河川の中に新しい護岸を作って、河川の中を埋め立てる形式となっております。
遊歩道の幅は、大体9〜13mとなっておりまして、河川内に鋼矢板又は鋼管矢板を打設してまいります。
今回の対象となります土量は、約4000m3 となっております。これにつきましては、ヘドロ層を除去した後に、底質の入れ替えを行っていきます。
下に、図-1 として地図が出ております。1頁めくっていただきまして、2頁でございます。若干小さくて見づらくて申し訳ありませんが、左側が施行する前の現況図でございまして、護岸即ち大きなコンクリートの壁でございますが、その前に鋼矢板の護岸があります。右側の方は計画となっておりますが、大きな護岸であるコンクリート上部を撤去いたしまして、川の中に鋼矢板
を立てますが、幅は狭いところでは9mから13mほどございます。
次の3頁のところには、非常に見づらいですが、平面図が載っておりますが、図のように矢板、鋼矢板を打っている状況でございます。
次の4頁に出ておりますのが、前回の平成19 年9月のときに、ご報告させていただきましたこの工事現場における底質の状況でございます。
?の概略調査ということで、含有量と溶出量それぞれ2地点で測定した結果を示しております。含有量につきましては、220、230pg-TEQ/gということで環境基準を超えています。また、溶出量につきましても、いわゆる海洋汚染防止法の基準をオーバーしております。この概略調査といいますのは、工事現場内の概ね真ん中に位置する2地点を選んで、その表層の土をとりましたが、次の?の詳細調査では、平面的に8地点を選びまして、それぞれについて鉛直方向についても、ヘドロ層50cm おきに砂層のところまで、溶出及び含有量について、再度詳細に調査いたしました。
その結果でございますが、ダイオキシン類の含有につきましては、概略調査とさほど変わらない数字であり、最高で470 という数字が出ております。
事務局(建設局三村課長代理)
それから、ダイオキシン類の溶出ですが、概略調査の時には、44や21 pg-TEQ/L でございましたが、全て10 未満となっている状況でございます。
その他に、一部の箇所では溶出ですが、総水銀や鉛について、若干基準を超えるものが出ております。6頁ですが、図が小さくて恐縮ですが、真ん中に赤い点が2つございます。これは、一番最初に行いました概略調査の地点でございます。
それから、黒い点が8地点ありますが、これが概略調査の土を採った箇所でございます。
我々といたしましては、概略調査の時に出てまいりました溶出量が、通常時の数値よりも若干大きいということもございまして、前回の会議の時に、おはかりさせていただきましたが、一番最初の概略調査の地図周辺の4スミを囲むように、再度調査をしたということで、7頁に平面的な位置が出ております。
概略調査の赤い点のまわり4スミを、再度調査させていただくということと、念のために、その他に3点の合計11 地点、検体数としては16 検体となると思いますが、鉛直方向にも調査させていただきました。その結果が8頁にございます。
8頁には、ダイオキシンの含有あるいは溶出について記載しておりますが、含有量といたしましては、前回または前々回に調査いたしましたような数値でございまして、今回の場合には最高で330 pg-TEQ/gというような数字が出ております。溶出量につきましては、海洋汚染防止法基準、これは埋立が可能かどうかの基準ですが、10 未満の数字ばかりでございまして、最高で6.5 というような数字となっております。
これによりまして、北港に埋立処分する土は約2,800m3、溶出量を再チェックした形で、鉛、水銀というものが混ざっているということで、海洋投棄できないという土量はセメント原料として、セメント工場に運搬しましたのが、1,200m3 というような形で確定させていただきました。
9頁でございますが、工事中の環境監視ということで、前回の会議の時に、事前の水質調査の結果を報告させていただいております。10頁には水質環境基準ということで、その下側に出てまいりますが、pH,BOD,SS,DO、濁度が記載されております。この中で、濁度でございますが、濁度の週平均値は10.0 度、個別測定値は22.3 度で、事前の水質調査結果から設定されております。週平均値の10.0 度でございますが、事前の水質調査結果の段階でダイオキシン類の水質が3.6pg-TEQ/L ということでございまして、この10.0 度という数値につきましては、事前の水質調査結果に関して、現状より悪化させないという形の監視基準としております。
11 頁については、監視状況の結果を掲載しております。11 頁は、濁度の測定結果でございます。これは、週平均値の数字
を載せさせていただいておりまして、その下に個々の数字の最大・最小値を記載しております。
事務局(建設局三村課長代理)
個々の数値及び週平均値につきましても、環境監視基準値を上回るところはございませんでした。pH,BOD,SS,DO等の生活環境項目の測定でございますが、DO とBOD につきましては、一部の期間で監視基準を上回るあるいは下回るようなところが出てまいりまして、その期間につきましては、DO の場合は、矢板の打設や鋼管矢板の打設という時期でありまして、若干、矢板の打設速度を遅らせるというかゆっくりさせるというようなことで対応しました。
BOD の場合は、埋め立ての時、土を締切内に入れる時の状況でございますが、この時につきましても、若干、土砂の掘削あるいは投入に係るスピードを落とさせていただいたということでございます。
今回の工事につきましては、以上のような結果となっています。
村岡委員長
ご質問やご意見がありましたら、お願いします。
上野委員
ダイオキシン類の溶出量ですが、2回目の測定時点でも、若干、まだ数値が高いような気がするのですが、浚渫土中の特徴としては何かあるのでしょうか?あるいは溶出液が、若干濁っているとかはあるのでしょうか?
オブザーバ
(大阪市立環境科学研究所先山主任)
私は、本データを事前に見せていただきましたので、その印象からご説明させていただきます。先生がおっしゃるように、底質の2回目の測定データにつきましても、若干高いかなという気がしますが、まず、1回目の方が非常に高いということで、溶出量が多くなるような状況にあった泥なのかどうかということをみる指標がないかというご相談で、事前に見せていただきました。
しかし、その時点では、そのことを判断するようなデータの採取がなされていないということで、すでに、この時の泥が存在しない段階では、その判断はできませんでした。
2回目のデータにつきましては、平均の粒子径などは若干、データとしてとられていましたので、それを見せていただきまた。そうすると、この底質は、ダイオキシンも高いですけれども、かなりヘドロ化しているということで、平均粒子径が0.05mm を下回るようなものもたくさんありまして、非常に微粒子の底質が多いという状況がうかがえると思います。
ですから、ろ過操作等のバラツキというものが、結構、大きく効いてくるのではないかという判断を私はいたしました。
村岡委員長
このろ過操作というのは、現在のところ、どのような基準でやっておられるのですか?
オブザーバ
(大阪市立環境科学研究所先山主任)
ろ過操作につきましては、海洋汚染防止法で、ご存知のように孔径という表現がなされているわけですが、前回の委員会でも若干、説明させていただいたのですが、私が調べたところによりますと、市販品ではガラス繊維ろ紙で、仕様上、そのような表現がなされているものは存在しません。
現実には、様々なメーカーにより表現方法が異なるということで、その孔径に値するそれぞれの表現が、どの程度かとい
うことは、メーカーによってばらついております。
それを使用するときに、孔径と置き換えて読むのか、それよりも孔径の方が小さいということで、1μmよりも小さなものを使用するかということで、かなりろ過操作にバラツキが出る可能性があります。
しかし、公式には孔径という表現がされておりますので、孔径をどのように分析する側が解釈するかということで、結果に大きな違いが出ているのではないかと思います。具体的には、孔径と同じような意味で使われているメーカーさんのものでしたら、粒子保持能という表現があり、ろ過の初期段階でその粒子径以上のものが98%以上止められるという表現をされているところもあります。
もう一方では、保留粒子径ということで、「1μmのものを止めようとしますと、さらにその半分くらいの0.4〜0.6μmのものを使わないとダメですよ。」ということがカタログ上では示されていますので、その辺、混同して使用している可能性があるのかなと思います。
ですので、どのようなものを使うかということは、いずれ公式の委員会の場で承認を得て、標準的な操作の仕方というのを用いないと、なかなか説明がつかないデータが出てくる可能性があると考えられます。
村岡委員長
何か関連して、ご意見ありませんでしょうか?
福永委員
後で、この件に関して、お願いしようかなと思っていたのですが、前回の委員会でも、かなり問題になって、結局ばらついたデータが出てきて、議論に困るというようなことが多いと思うのですけれども、環境科学研究所さんの方で、大阪府さんとも調整していただきながら、誰が行っても同じ答えが出るというふうなフロー、いわば、今法令的には定められているんですけれども、必ずしも十分ではないので、人によって異なった答えが出るということですから、この委員会にデータとして出すという時には必ずこの方法で行えば、間違いない安定した数値が出るというフローを考えていただければ、この委員会としてはありがたいのではないかと思いますので、お願いしたいと思います。
事務局(環境局大石課長)
福永先生のご指摘の点ですが、先般、環境省の方から底質の調査方法に関わりまして、アンケート調査がまいりました。その時に、私どもの回答の中に、分析に用いるろ紙の規格をはっきりと明記してほしいということをお返ししております。いずれにいたしましても、前回以降、村岡先生にもご指摘をいただきながら、府市で、きちんと統一的な取り扱いを決めるようにというご指摘もありましたので、今後、大阪府の底質委員会の事務局とも調整をしながら、また、本市環境科学研究所、大阪府環境農林水産総合研究所とも、ご相談しながら、統一的な取り扱いができるかどうかも含めまして検討を進めてまいりたいと考えております。
村岡委員長
その点につきましては、ぜひスタンダードな測定値をもとに議論ができるように進めてほしいと思います。
藤川委員
濁度とダイオキシンの関係を0.1pg-TEQ/L だというのが、先ほどの回帰分析の結果ですけれども、今回の方では、濁度との関係を3.6pg-TEQ/L というふうにおっしゃっていただいたのですが、濁度1が0.1 なのか0.36 なのかというので、そういうデータは蓄積していただくのは、妥当だと思うのですが、ただ、この時の濁度10 で3.6pg-TEQ/L とおっしゃった時のろ過方法は、どのようなものだったのかを教えていただきたいのが第1点です。
もう1つは、ダイオキシン類については溶出量と含有量を両方測ると思いますが、普通、ダイオキシン類は溶出量は低いでしょうから、例えば、この溶出量と含有量の比が含有量5に対して溶出量が1というデータが出た時点で、直ちに環境科学研究所さんから、現場の方にご相談いただくなり、再分析に回すなりの対応をしていただくと早いと思うのです。
だから、そういうことを現場で徹底していただいたらどうかなというのが第2点です。
不自然なデータが出れば、すぐに追加のサンプリングはもちろんですけれども、再分析ということも考えられると思います。
事務局(建設局三村課長代理)
事前の水質調査を行った時には、2回目の詳細調査と同じ方法で行っております。一番最初の概略調査あるいは次の詳細調査、それから事前の水質調査という段階を経まして、事前の水質調査と詳細調査はほぼ同じような時期になっておりますが、一番最初の概略調査と次の詳細調査と次の詳細調査あるいは事前水質調査とは若干、違うような形であると聞いております。
私どもは、工事を発注してから、水質調査あるいは底質調査を行っておりますので、これからはちょっと考え直さなくてはいけないのですが、当時の工事期間中にそういうふうな状況が出てまいりますので、結果が出るまで少なくとも1カ月、2カ月ほどかかりますので、若干、その辺のところが、我々としては考え直さなくてはならないところではあると思います。
事務局(環境局大石課長)
2点目のご指摘でございますが、我々といたしましては、これからもデータの蓄積につきましては、統一的に、今後も進めていきたいと考えております。
また、検討会の事務局を、大阪市的にも港湾局、環境局、建設局、オブザーバとして環境科学研究所さんにも入っていただいておりますので、うまく機能させていきながら連絡体制をとっていきたいと考えております。
村岡委員長
今の問題は、すぐに解決できるものとは思えないですし、その時、その時に判断しないといけない大変難しい問題ですが、是非ともいい値が出るように、「正しい値が出て、正しい判断ができるように」努力をしてくださいということですから、その辺のところをよろしくお願いいたします。
他にございますか?
それでは、ご意見がないようでございますので、本日の議題である3つの報告について、委員の先生方、いろいろご指摘いただきましたので、これで全て終わったというわけではありませんが、ともかく、この報告の中身について、十分確認できたということにさせていただきます。
合わせまして、これに基づいて、また、作業が進められると思いますので、ぜひ、それが円滑に、いい効果が上げられますようにお願いしたいと思います。
それでは、以上をもちまして、議事を終わりたいと思います。後、進行を事務局にお願いします。
大阪市底質対策等技術検討会
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000019399.html
2009年12月22日
岡山の環境裁判例
処分取消請求控訴事件(岡山県岡山市)
○ 土地の埋立てに使用された係争物が産業廃棄物ではないとして市がなした事業停止処分等が取り消された事例
広島高裁 平成16年7月22日判決
事件番号 平成14年(行コ)第16号
事件名 処分取消請求控訴事件
結果 原判決変更
原審 岡山地裁平成12年(行ウ)第24号
出典 最高裁判所ホームページ
【判示要旨】
土地の埋め立てに使用された本件係争物が,産業廃棄物であるか否かが争点となった事案について,本件係争物が産業廃棄物であるとは認められないとして,被控訴人の控訴人らに対する本件行政処分の取消しを命じた事例
【判決文】(抜粋)
第1 主文
1 原判決主文第2項を次のとおり変更する。
(1) 控訴人らの下記(2)及び(3)の各処分無効確認請求をいずれも棄却する。
(2) 被控訴人が,控訴人エヌエス日進株式会社に対して,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成12年法律第105号による改正前のもの)14条の3第1号及び14条の6に基づき平成12年12月19日付け岡山市指令産廃第544号により行った平成13年1月10日から同月19日までの事業停止処分は,これを取り消す。
(3) 被控訴人が,控訴人有限会社津下建材に対して,同法12条1項及び19条の3に基づき平成12年12月19日付け岡山市指令産廃第545号により行った岡山市ab番c地内及びその周辺への汚泥の搬入中止及びその撤去を命じる処分は,これを取り消す。
2 控訴人エヌエス日進株式会社のその余の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,1,2審を通じて,控訴人エヌエス日進株式会社と被控訴人との間ではこれを2分し,その1を控訴人エヌエス日進株式会社の負担とし,その余を被控訴人の負担とし,控訴人有限会社津下建材と被控訴人との間では全部被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,本件係争物が産業廃棄物に該当するとして被控訴人が控訴人らに対してした各処分(以下「本件各処分」という。)等について,本件係争物は改良土であって産業廃棄物ではない等と主張する控訴人らが,主位的に本件各処分等の無効確認を,予備的にその取消を求めた事案である。
2 争いのない事実及び証拠上容易に認定できる事実
(1) 当事者等
ア エヌエス日進は,昭和52年2月12日に設立され,産業廃棄物収集運搬業(被控訴人平成9年5月28日付け更新許可。乙4の1),産業廃棄物処分業(被控訴人平成9年5月28日付け更新許可。乙4の2)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(被控訴人平成11年3月2日付け更新許可。乙4の3)の各許可を受け,産業廃棄物処理を主な業務とする株式会社である。
イ 津下建材は,産業廃棄物収集運搬業(被控訴人平成10年12月20日付け更新許可)の許可を受け,これを業として行っている有限会社であり,収集運搬車両として,登録番号岡山11こ3145及び岡山11こ3148を含め合計7台のダンプを利用することを被控訴人に届けている(乙8,11,12)。
ウ 訴外株式会社未来(以下「訴外未来」という。)は,重機数台を所有し,土木工事を業として行っている株式会社であり,その代表者は訴外A(以下「訴外A」という。)であるが,同人は,津下建材代表者の夫である(乙11)。
エ 岡山市環境事業局業務部産業廃棄物対策課(平成13年4月1日付け機構改革により現在は岡山市環境局保全部産業廃棄物対策課である。以下「産廃課」という。)は,廃棄物処理法2条4項に定める産業廃棄物の処理等に関する事務を地方自治法2条10項に定める法定受託業務として執行するために設置された被控訴人の組織である。
(2) 本件各処分等に至る経緯
ア 産廃課職員は,平成12年8月24日,エヌエス日進のd事業場に対する立入調査を行った。d事業場には,汚泥の天日乾燥・混練固化施設(以下「ピット」という。),破砕施設などの産業廃棄物中間処理施設に加え,ピットで乾燥固化されたものを原材料として改良土を製造するための施設(以下「改良土プラント」という。)があった。
イ 同年9月11日及び同月14日,灰色の有体物(以下「本件係争物」という。)が,訴外未来所有の10トンダンプにより,d事業場から岡山市a地内の土地(以下「本件土地」という。)に運搬され,本件土地に本件係争物が降ろされた。
ウ 産廃課職員は,同月14日午後5時30分ころ,本件土地への立入調査を実施し,本件係争物を採取して持ち帰った。
エ B(以下「B」という。)は,同月21日午後1時31分ころ,訴外未来所有の10トンダンプに本件係争物を積載してd事業場を出発し,同日午後1時50分ころ,本件土地に到着し,本件土地に本件係争物を降ろした。そこで,産廃課職員が,Bに事情聴取したところ,Bは以下のとおり答えた。また,産廃課職員は,同日,本件係争物を採取して持ち帰った。
(ア) 訴外未来の代表者である訴外Aの指示により,平成12年5月若しくは同年6月ころから,エヌエス日進より改良土として購入したものをd事業場からダンプで本件土地へ搬入し,埋立に使用していた。
(イ) 搬入量は,10トンダンプで1日あたり少ないときは7車分,多いときは50車分である。
オ 産廃課職員は,同日,訴外Aに事情聴取を行い,その際,同人は以下のとおり答えた。そして,被控訴人は,同月22日,訴外Aから,関係書類の提出を受けた。
(ア) 平成12年6月,本件土地のうち,岡山市ae番f及び同所b番cの各土地を重機置場にする目的で,エヌエス日進の代表者であるC(以下「C」という。)から購入した。
(イ) 埋立に利用していた材料は,エヌエス日進から改良土として購入したものである。その価格は,10トンあたり,当初2000円であったが,平成12年5月からは3500円に値上がりした。
カ 産廃課職員は,同日,Cにも来庁するよう求めたが,Cは出張中のため,エヌエス日進の営業課長であるD(以下「D」という。)が訪れ,事情聴取に応じた。
キ 被控訴人は,同月22日付け書面をもって,Cの来庁を求めたところ,同月26日,同人はDとともに訪れ,以下のとおり述べた。
(ア) エヌエス日進が,平成12年4月から7月までの間に受け入れた汚泥の大半は,大本・アイサワ・蜂谷共同企業体(以下「訴外共同企業体」という。)がシールド工事を請け負っている岡山市g町作業所から排出されたものである。
(イ) 訴外共同企業体からの受託開始は,平成10年12月ころであるが,本格的な受入は,平成12年5月以降で,同年4月から8月末までの処分委託実績は,10トンダンプで576車分である。
ク 被控訴人は,同年10月17日付けで,エヌエス日進に対し,以下のとおり,予定している不利益処分,不利益処分の事実となる原因等を記載した弁明の機会付与通知書を送付した(甲23)。
(ア) 予定している不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(予定している不利益処分の内容)
? 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部停止10日間
? 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止10日間
(根拠となる法令の条項)
? 廃棄物処理法14条の3第1号
? 廃棄物処理法14条の6
(イ) 不利益処分の原因となる事実
平成12年6月上旬から同年9月21日までの間,産業廃棄物中間処理業務に伴って生じた産業廃棄物である汚泥(セメント等により固化したもの)の収集運搬を訴外未来こと津下建材に委託する際,書面による委託契約を行わなかった。
(ウ) 弁明の機会の付与の方式 弁明書の提出
(エ) 弁明書の提出期限 平成12年10月30日
ケ 被控訴人は,同年10月17日付けで,津下建材及び訴外未来に対し,以下のとおり予定している不利益処分,不利益処分の原因となる事実(本件係争物が産業廃棄物であること)等を記載した弁明の機会付与通知書を送付した。
(ア) 予定している不利益処分の内容
? 岡山市ab番c地内及びその周辺への汚泥(セメント等により固化したものを含む)の搬入を中止すること。
? 岡山市ab番c地内及びその周辺に放棄している汚泥(セメント等により固化したもの)を平成13年4月10日までに適正な処分を行うことができる場所へ撤去すること。
(イ) 弁明の機会の付与の方式 弁明書の提出
(ウ) 弁明書の提出期限 平成12年10月30日
コ エヌエス日進,津下建材及び訴外未来ら代理人であった菊池捷男弁護士(以下「菊池弁護士」という。)らは,同月26日,被控訴人に,弁明書と題する書面を提出し,本件係争物は有価物(第3種,第4種改良土建設資材)であるから産業廃棄物ではないと主張し,被控訴人が本件係争物を産業廃棄物であると断定した根拠についてその争点の明確化を求めた(乙27)。
サ これを受けて,被控訴人は,同年11月27日付けで,菊池弁護士に対し,以下の内容を記載した弁明の機会の付与通知書(補充)を送付し,菊池弁護士の元に同月28日到着した(甲24の(1),(2))。
(ア) 不利益処分の原因となる事実の補充部分(産業廃棄物である汚泥と認定した理由)
以下の事実等を総合的に勘案した結果,本件係争物は「廃棄物」すなわち「不要物」に該当する。
? 本件係争物は,造成地への搬入直後も泥状を呈し,天日乾燥しなければ,埋め立てることができないことなどから中間処理が不完全である。
? 本件係争物は,中間処理過程においてセメント等を添加している上,中間処理後の粒状も均一でなく,岡山県や岡山市における「改良土」の基準にも該当しない。
? 排出者(工事請負業者)は,汚泥をセメント固化等したのち「建設汚泥(産業廃棄物)」として排出し,エヌエス日進に処理委託している。
? セメント固化後に排出の建設汚泥については,通常,同業者は「改良土として製造できない。」等との理由から,全量管理型最終処分場に処理委託している。
? セメント固化後に排出の建設汚泥を「改良土」に製造・販売している業者は,岡山市内においては他に見当たらない。
? リサイクルを推進している岡山市でさえ,セメント添加による「改良土」は,業者から一切購入していない。
? 同業者に比べ,本件係争物の売買価格がかなり安価である。
? エヌエス日進における「改良土」の販売先は,本年5月以降訴外未来こと津下建材のみである。
(イ) 補充部分についての弁明の機会の付与の方式 弁明書の提出
(ウ) 弁明書の提出期限 平成12年12月11日
シ これに対し,菊池弁護士らは,同年12月1日までに,被控訴人に,弁明書(補充)を提出し,反論した(乙54)。
ス そして,菊池弁護士らは,同月5日付けの証拠開示請求書と題する書面を被控訴人に提出し,上記サ(ア)の根拠となった証拠の開示を求めた(甲25)。
セ さらに,菊池弁護士らは,同月13日付けの弁明の機会の付与と証拠開示の請求と題する書面を送付し,被控訴人に同月14日に到着した(甲26の(1),(2))。
ソ しかし,被控訴人は,エヌエス日進らからの上記ス及びセの求めに応ずることなく,同月19日,エヌエス日進及び津下建材に対し,以下の内容の本件各処分をした。
(ア) エヌエス日進に対するもの(乙29。岡山市指令産廃第544号。以下「本件事業停止処分」という。)
産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可に係る事業全部の平成13年1月10日から同月19日までの10日間の事業停止
(イ) 津下建材に対するもの(乙30。岡山市指令産廃第545号。以下「本件中止撤去命令処分」という。)
? 岡山市ab番c地内及びその周辺への汚泥(セメント等により固化したものを含む)の搬入を中止すること。
? 岡山市ab番c地内及びその周辺に放棄している汚泥(セメント等により固化したもの)を平成13年4月10日までに適正な処分を行うことができる場所へ撤去すること。
タ また,被控訴人は,エヌエス日進に対し,平成12年12月19日,産業廃棄物処理業に係る許可証の返納を求める通知をした(乙67。岡山市指令産廃第546号。以下「本件許可証返納通知」といい,本件各処分と併せて述べる場合には「本件各処分等」という。)
3 争点
(1) 本件事業停止処分に係るエヌエス日進の訴えの適法性
(略)
(2) 本件許可証返納通知に係るエヌエス日進の訴えの適法性
(略)
(3) 本件係争物の特定性等
(略)
(4) 本件係争物の産業廃棄物該当性
(略)
(5) 本件各処分等に係る行政手続の違法性
(略)
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件事業停止処分に係るエヌエス日進の訴えの適法性)について
(1) 被控訴人は,本件事業停止処分に係るエヌエス日進の訴えは,本件事業停止期間の経過により,訴えの利益が既に消滅していると主張する。
(2) 行政処分についての取消訴訟あるいは無効確認訴訟は,当該処分の効果が期間の経過等により消滅した場合においても,なお処分の取消しあるいは無効確認をしなければ回復できないような法律上の利益を有する者に限りこれを提起することができる(行政事件訴訟法9条,36条)。したがって,事業停止処分のように,行政処分が一定の期間内に限り,国民の権利利益を制約するものである場合,すわなち,処分に期間が付されている場合,期間経過後においては,処分がされたことを理由として法律上の不利益を受けるおそれがあるのでなければ,その取消し等を求める訴えの利益は消滅する。
(3) 本件の場合に本件事業停止期間が経過していることは明らかであるから,なお,エヌエス日進において,法律上の不利益を受けるおそれがあると認められるかが問題となる。
ア 廃棄物処理法14条2項,5項及び同法14条の4第2項は,産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業について,5年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う旨規定しており,その更新許可にあっては,許可に準じる審査基準が適用されるが,同法14条3項等により適用される同法7条3項4号ホは「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」には許可をしてはならない旨規定している。
イ この規定について,被控訴人は,申請者の資質及び社会的信用の面から適切な業務運営が初めから期待できないことが明らかな者をいい,エヌエス日進のように比較的短期間の事業停止処分を受けた者は,上記規定に該当するとされることはあり得ないと主張する。しかし,上記規定には被控訴人主張のような限定は付されておらず,エヌエス日進が,将来産業廃棄物収集運搬業等の許可の更新を申請した場合,本件事業停止処分の存在がエヌエス日進にとって不利益な事由として考慮されるおそれがあるといわざるを得ない。
(4) 以上によれば,本件事業停止処分に係るエヌエス日進の訴えには訴えの利益があると認められるから,当該訴えは適法である。被控訴人の上記主張は採用できない。
2 争点(2)(本件許可証返納通知に係るエヌエス日進の訴えの適法性)について
(1) 被控訴人は,本件許可証返納通知は,これによってエヌエス日進に法律上の作為義務が発生するものではなく,また,これに従わなかったとしても,そのこと自体で不利益を受ける訳ではないから,取消訴訟等の対象となる処分には該当せず,本件許可証返納通知に係るエヌエス日進の訴えは不適法であると主張する。
(2) 取消訴訟等の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁)。
(3) そこで,本件許可証返納通知について検討するに,本件細則(乙34)は,許可証を返納しなければならない場合として業務停止処分が為された場合を規定しているのみであって,本件細則に基づく本件許可証返納通知には,これを強制する手続等に関する規定はない。したがって,本件許可証返納通知は,取消訴訟等の対象となる処分には該当しないというべきである。これに対し,エヌエス日進は,許可証を返納した結果,廃棄物の処理委託契約を一切締結できなくなるという極めて重大な影響を受けると主張するが,これは事業停止処分の結果であって,許可証の返納によるものではないから,エヌエス日進の上記主張は採用できない。
(4) 以上によれば,被控訴人の上記主張は理由がある。したがって,本件許可証返納通知に係るエヌエス日進の訴えは不適法である。
3 争点(3)(本件係争物の特定性)について
(1) 控訴人らは,本件各処分の対象となる本件係争物の特定が不十分又は対象物が不存在もしくは誤認の瑕疵があると主張する。
(2) 本件事業停止処分における不利益処分の原因となる事実は「平成12年6月上旬から同年9月21日までの間,産業廃棄物中間処理業務に伴って生じた産業廃棄物である汚泥(セメント等により固化したもの)の収集運搬を訴外未来こと津下建材に委託する際,書面による委託契約を行わなかった。」というものであり,本件中止撤去命令処分の内容は「岡山市ab番c地内及びその周辺への汚泥(セメント等により固化したものを含む)の搬入を中止すること。岡山市ab番c地内及びその周辺に放棄している汚泥(セメント等により固化したもの)を平成13年4月10日までに適正な処分を行うことができる場所へ撤去すること。」である。
本件各処分に至る経緯は,前記第2の2(2)で認定したとおりであり,平成12年9月の事情聴取の時点から,本件係争物について,被控訴人は産業廃棄物である汚泥であると主張し,控訴人らは,改良土であって,産業廃棄物ではないと主張し,控訴人らは,被控訴人が本件係争物を産業廃棄物であると断定した根拠についてその争点の明確化等を求めていたことが認められる。控訴人らは,対象の特定性(その性状,搬入期間,搬入量)において不十分であるばかりでなく,エヌエス日進が製造した改良土を本件土地に搬入を開始したのは,平成12年8月中旬以降であると主張する。
しかし,本件においては,上記のとおり,本件係争物の産業廃棄物該当性については争いがあるところ,本件各処分の対象となる本件係争物が何を意味するのかということについては控訴人らと被控訴人との間に事実上争いはないと認められる上,本件の場合には,搬入期間及び搬入量が本件係争物の特定に不可欠なものであるとまではいうことはできないから,本件係争物の特定性を欠くものとは認められない。
(3) 以上によれば,控訴人らの上記主張は採用できない。
4 争点(4)(本件係争物の産業廃棄物性)について
(1) 産業廃棄物の定義
ア 廃棄物処理法は,2条1項において,「『廃棄物』とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のものをいう。」と定義しているが,この規定は,一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示したものであり,廃棄物とは,占有者が自ら利用し,又は他人に有償で売却することができないために不要となったものをいい,これらに該当するか否かは占有者の意思,その性状等を総合的に勘案して定めるべきものと解される。
したがって,当該物について,占有者が主観的に他人に有償で売却することができると判断しただけであって,客観的には他人に有償で売却することができないものは,廃棄物に該当するといわざるを得ない。
イ また,廃棄物処理法は,同条4項1号において,「『産業廃棄物』とは,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。」と定義している。そして,同法施行令2条は,上記政令で定める廃棄物について,紙くず等12種類のものを規定するほか,13号において「燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類又は前各号に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって,これらの産業廃棄物に該当しないもの」と規定している。
ウ 以上によれば,ある産業廃棄物を再利用のために処理をし,他人に有償で売却することができる状態となった場合には,当該産業廃棄物は,その産業廃棄物該当性を失うものと解される。したがって,ある産業廃棄物に何らかの処理がなされても,未だ他人に有償で売却することができる状態に至っていない場合には,その産業廃棄物該当性は失われないものと解される。
(2) 産業廃棄物該当性についての主張立証責任
ア 国民の自由を制限し,国民に義務を課する行政処分の取消しを求める訴訟においては,行政庁がその適法であることの主張立証責任を負担すると解すべきであるところ,エヌエス日進のd事業場に搬入された時点では産業廃棄物である汚泥であったことについては当事者間に争いがない本件の場合,本件係争物が産業廃棄物である汚泥に再利用のための処理をし,他人に有償で売却することができる状態となったことについて,控訴人らが主張立証責任を負担するのか,本件係争物がその産業廃棄物該当性を失っていないことについて被控訴人が主張立証責任を負担するのかが問題となる。
イ そこで検討するに,上記(1)で述べたところによれば,確かに,本件係争物が汚泥の状態にないということだけでは,その産業廃棄物該当性は否定されないものの,被控訴人は,本件事業停止処分にあたっては,エヌエス日進が平成12年6月上旬から同年9月21日までの間,産業廃棄物である本件係争物の収集運搬を津下建材に委託する際,書面による委託契約を行わなかったことを不利益処分の原因となる事実としている以上,上記の期間において,本件係争物が汚泥であったということ又は本件係争物はこれを他人に有償で売却することができないものであったということについて,被控訴人がその主張立証をする責任を負うといわなければならない。また,被控訴人は,本件中止撤去命令処分にあたっては,津下建材が同命令時に産業廃棄物である本件係争物を本件土地に放棄していたことを不利益処分の原因となる事実としたものであるから,同様に,同命令時において,本件係争物が汚泥であったということ又は本件係争物はこれを他人に有償で売却することができないものであったということについて,被控訴人がその主張立証をする責任を負うといわなければならない。
(3) 本件係争物の産業廃棄物該当性の有無
ア まず,被控訴人は,本件係争物は産業廃棄物である汚泥であると主張するので,この点について検討する。
(ア) 汚泥とは,工場排水等の処理後に残るでい状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであって,有機性及び無機性のものをすべて含むとされているところ,旧厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室作成の建設廃棄物処理指針(平成11年3月。甲30,乙33。以下「本件指針」という。)によれば,「建設汚泥の取扱い」として,以下のとおり記載されていた。
? 地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち,含水率が高く粒子が微細な泥状のものは,無機性汚泥として取り扱う。また,粒子が直径74ミクロンを超える粒子をおおむね95%以上含む掘削物にあっては,容易に水分を除去できるので,ずり分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって,かつ,生活環境の保全上支障のないものは土砂として扱うことができる。
? 泥状の状態とは,標準仕様ダンプトラックに山積みができず,また,その上を人が歩けない状態をいい,この状態を土の強度を示す指標でいえば,コーン指数がおおむね200kN/?以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/?以下である。
? しかし,掘削物を標準仕様ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっても,運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので,これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要がある。なお,地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり,土砂は廃棄物処理法の対象外である。
? この土砂か汚泥かの判断は,掘削工事に伴って排出される時点で行うものとする。掘削工事から排出されるとは,水を利用し,地山を掘削する工法においては,発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを,掘削工事としてとらえ,この一体となるシステムから排出される時点で判断することとなる。
(イ) 本件の場合,本件係争物がエヌエス日進のd事業場に搬入された時点で,産業廃棄物である汚泥であったことについては,当事者間に争いがない。しかし,本件各処分においてその産業廃棄物該当性が問題とされる時点は,本件事業停止処分については平成12年6月上旬から同年9月21日までの間であり,本件中止撤去命令処分についてはその処分時である同年12月19日の時点であるから,その各時点で本件係争物が産業廃棄物である汚泥と認められるかを検討しなければならない。
(ウ) この点について,被控訴人は,本件土地へのダンプアウトされた直後の本件係争物について目視,歩行実験した結果及び関係者からの事情聴取(乙11,13,14,49,51,52,証人F,同〔いずれも原審〕)から,本件係争物は,本件土地への搬入時点で泥状を呈しており,本件土地に人工的に掘った穴で天日乾燥して固めた後でなければ埋め立てることができないほどの流動性を有しており,平成12年9月21日に歩行実験を行ったところ,同実験を実施した産廃課職員F(以下「F」という。)は,くるぶしのあたりまで埋まり,歩行困難な状態であったと報告していること等から,本件係争物は産業廃棄物である汚泥であると主張している。
(エ) 証拠(乙11及び13添付の各写真,甲32〜35,39,154,155,証人B)によれば,平成12年9月21日に本件土地へダンプアウトされた直後の本件係争物は,エヌエス日進のd事業場でB運転のダンプに積載され,山道を約20分程度要して運搬されたにもかかわらず,約45度の安息角をもって堆積しており,ダンプの荷台にも粘土状あるいは液状の物体の付着は認められないこと,同月14日の本件係争物もほぼ同様な状態であったことが認められる。
これらの事実及び前記(ア)の本件指針からすると,本件係争物は産業廃棄物である汚泥であるとは認められないというべきである。なお,本件指針によれば,土質を示すコーン指数も汚泥かどうかを判断する基準の一つとされているところ,産廃課職員は,同月14日及び21日の立入検査の際,本件係争物を採取したが,これらについて,コーン指数についての検査が行われていない(当事者間に争いがない)ため,本件の場合,コーン指数の点から本件係争物の性状を判断することはできない。
さらに,被控訴人は,泥状物堆積実験を行い,その報告書等(乙81〜83)を提出するが,上記実験に用いられた建設発生土は,その性状,そのダンプアウト中の状態等からして,本件係争物とはその性状を著しく異にするものといわざるを得ないから,上記実験結果によっても,上記結論は左右されない。
(オ) したがって,被控訴人の本件係争物が産業廃棄物である汚泥である旨の上記主張は採用できない。
イ 次に,被控訴人は,本件係争物は建設汚泥として排出された後他人に有償で売却できるものとして再生されたものではない旨主張し,その根拠をあげるので,この点について検討する。
(ア) 被控訴人は,本件の場合,エヌエス日進は,訴外未来に10トンあたり3500円で売却した本件係争物を10トンあたり4750円の運搬賃等を支払って納品しており,控訴人らは,有償での売却を仮装している旨主張し,この点について,弁明書(乙27)添付の訴外未来作成の請求書等から明らかとなったその取引関係から認められるものであって,Cから訴外Aに売却されて所有権移転登記もなされた土地についてCを債務者とする根抵当権設定登記が抹消されないでいたこと(乙44の(3),(4)),埋め立てられた本件土地の全部が訴外Aの土地ではないこと(乙43の(2),44の(5)),本件土地の排水施設をCが管理していること(乙45)などは,これを裏付けるものであると主張する。
しかし,上記根抵当権設定登記は旧岡山市民信用金庫を根抵当権者とするものであるが,同信用金庫が破綻したことは当裁判所に顕著であり,また,平成14年2月には同登記は抹消されている(甲118,119)のであるから,平成12年の時点において,控訴人らが主張するとおり,同根抵当権は被担保債権も存在しない実体のないものであった可能性は十分にあるものということができる。そして,被控訴人が主張するその他の点を考慮しても,Cと訴外Aが通常のビジネス上の交際を超えて本件係争物の有償譲渡を共謀して仮装するような関係にあったとは認められない。そもそも,被控訴人が主張する上記仮装の根拠は,控訴人ら代理人が被控訴人に提出した弁明書(乙27)に添付された資料であるところ,そこに有償譲渡仮装の証拠資料を誤って混入させてしまうというような事態は想定し難い。これに対して,控訴人らは,上記請求書中の「土工 上高田 8H−3人」(乙27の73頁)等は,本件土地の100メートル南に所在するエヌエス日進の分別場所の工事代金であり,「11t常用 d 8H−2台」(乙27の74頁)等は,dでダンプをチャーターした代金であり,本件係争物のdから本件土地への運搬賃ではないと主張し,Cも,原審において,この主張に沿う供述をしている。そして,控訴人らが主張する分別場所が存在し,その土地の所有者がCであることは,証拠(乙38の(3),43の(2))上これを認めることができ,また,上記請求書中には,「k」という記載もなされており,これはエヌエス日進における営業所の一つであると認められる(Cの原審供述)。
被控訴人は,エヌエス日進が訴外未来に対し,10トンあたり3500円という極めて安価であるいは原価割れで本件係争物を販売しているとも主張するが,証拠(乙25,甲94)によれば,エヌエス日進は,訴外共同企業体から汚泥の処理を委託され,その委託代金として,ダンプ1台あたり1万8000円を受領しており,石灰代,人件費等の製造費用を差し引いても,10トンあたり3500円で販売すると,1立米あたり約1000円程度の利益を得ることができることが認められる。
これらの点を総合考慮すると,本件の場合,上記請求書中のエヌエス日進の訴外未来に対する支払が本件係争物の本件土地への運搬賃等であると断定することまではできないといわざるを得ない。
(イ) さらに,被控訴人は,
?改良土は,通常茶色で粒状が均一で小さくさらさらしているはずなのに,本件係争物は,灰色で粒径が40?以上の粒土が混在している,
?本件係争物はpH値が12で,植物の生育に適さない,
?本件係争物のようにセメント添加により粘土状の状態で排出された汚泥は,改良土として加工できない,
?本件係争物が建設汚泥リサイクル指針に定める第3種又は第4種改良土に該当するとしても,岡山県や岡山市の基準には適合しない等公共団体への売却はできず,民間は改良土を利用しないのが通常であるから,その商品価値はなく,商品価値があったとしても,その市場性も極めて狭いものであるから,当然に有価物にはならない,
?平成12年8月24日のエヌエス日進のd事業場への立入検査の際,原料となるべき建設発生土等は全く保管されていなかったし,その際,E工場長は委託処理について述べたが,訴外事業団に対する調査の結果,その発言が虚偽であったことが判明した,
?控訴人らの主張によっても,行方不明の改良土が多く存在する,
?エヌエス日進は,訴外共同企業体には,改良土として道路中央分離帯の工事に使用すると説明していた,などと主張する。
しかしながら,このうち,?ないし?については,証拠(甲154〜158)によれば,京都大学大学院地球環境学堂のH教授は,根拠として十分でない,あるいは誤った見解であるとの意見を述べていること等が認められ,被控訴人の主張は一つの見解にしか過ぎないといわざるを得ないし,pH値については,当初産廃課職員において,問題とされていなかったことが認められる(原審証人Iの供述)。
?については,建設汚泥を材料としてセメント系固化剤を使用して改良土を製造する方法は,一般に行われているものであり(甲65,101),また,?のうち,建設発生土等の保管の点については,控訴人らは,これを否認しているところ,原審証人の供述によれば,同日の立入検査時に直接確認した調査員はおらず,帰りの車の中で話が出たものに過ぎないというのであるから,これを直ちに採用することはできない。?の点については,控訴人らは被控訴人とは異なる計算をしており,これが全く根拠のないものとは認められない。?のE工場長の発言については,控訴人らはこれを否認し,これに沿ったE工場長の陳述書(甲37)を提出しており,また,?については,産廃課職員作成の報告書(乙25)においても「道路の中央分離帯等に使用する」と記載されており,道路の中央分離帯工事のみに使用するとはされていないことからして,これらを直ちに採用することはできない。
(ウ) 一方,証拠(甲161)によれば,本件係争物には,控訴人らが主張するとおり,石灰が添加されていたことが認められるのであって,このことは本件係争物がエヌエス日進d事業場に設置されている改良土プラントで処理されたことを裏付けるものである上,本件係争物によって埋立られた本件土地が3年以上経った時点においても,当初の形状を保持していること(争いがない)は,本件係争物が控訴人ら主張の締め固めの効果を持つことを裏付けるものである。さらに,エヌエス日進は,建設汚泥を材料とした改良土について,他にも販売実績を有している(甲21,67ないし70等。枝番を含む。)
(エ) 以上検討した結果によれば,本件の場合,被控訴人が,本件係争物の売買が仮装ではないかと疑念を持つに至ったことにその根拠が全くなかったとまではいえないものの,本件係争物が有価物ではなく,訴外未来を含む控訴人らの間で売買が仮装されたと断定することはできないといわざるを得ない。したがって,本件係争物については,有価物として再生されていない産業廃棄物であるとも認めることはできない。被控訴人のその他の主張,立証によっても,以上の認定,判断を覆すには足りない。
5 争点(5)(本件各処分に係る行政手続の違法性)について
上記4によれば,本件各処分は,産業廃棄物とは認められない本件係争物を産業廃棄物として行われたものであるから,違法なものであるといわざるを得ないが,その瑕疵の程度は,前記第2の2(2)で認定した本件各処分に至る経緯及び上記4によれば,明白なものであるとは認め難いというべきであるから,本件各処分の取消事由となるに止まり,無効事由とはならないといわざるを得ない。
控訴人らは,本件各処分の無効確認を主位的請求とし,前記第2の3(5)のアにおいて,本件各処分に係る行政手続の違法性についての主張をしている。しかし,仮に,本件各処分に係る行政手続に控訴人ら主張の違法性があると認められるとしても,その違法は本件各処分の取消事由とはなるものの,無効事由とはならないと解されるから,上記のとおり既に取消事由があることが認められる本件の場合には,争点(5)についてさらに判断を加える必要はないといわざるを得ない。
6 以上によれば,控訴人らの本件各請求は,本件各処分の無効確認を求める主位的請求は理由がないからこれを棄却すべきであるが,本件各処分の取消を求める予備的請求は理由があるからこれを認容し,エヌエス日進の本件許可証返納通知の無効確認等を求める訴えは不適法であるから却下すべきである。
第4 結論
よって,結論を異にする原判決を変更し,仮執行宣言については相当でないからこれを付さないこととし,主文のとおり判決する。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei61.htm
○ 土地の埋立てに使用された係争物が産業廃棄物ではないとして市がなした事業停止処分等が取り消された事例
広島高裁 平成16年7月22日判決
事件番号 平成14年(行コ)第16号
事件名 処分取消請求控訴事件
結果 原判決変更
原審 岡山地裁平成12年(行ウ)第24号
出典 最高裁判所ホームページ
【判示要旨】
土地の埋め立てに使用された本件係争物が,産業廃棄物であるか否かが争点となった事案について,本件係争物が産業廃棄物であるとは認められないとして,被控訴人の控訴人らに対する本件行政処分の取消しを命じた事例
【判決文】(抜粋)
第1 主文
1 原判決主文第2項を次のとおり変更する。
(1) 控訴人らの下記(2)及び(3)の各処分無効確認請求をいずれも棄却する。
(2) 被控訴人が,控訴人エヌエス日進株式会社に対して,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成12年法律第105号による改正前のもの)14条の3第1号及び14条の6に基づき平成12年12月19日付け岡山市指令産廃第544号により行った平成13年1月10日から同月19日までの事業停止処分は,これを取り消す。
(3) 被控訴人が,控訴人有限会社津下建材に対して,同法12条1項及び19条の3に基づき平成12年12月19日付け岡山市指令産廃第545号により行った岡山市ab番c地内及びその周辺への汚泥の搬入中止及びその撤去を命じる処分は,これを取り消す。
2 控訴人エヌエス日進株式会社のその余の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,1,2審を通じて,控訴人エヌエス日進株式会社と被控訴人との間ではこれを2分し,その1を控訴人エヌエス日進株式会社の負担とし,その余を被控訴人の負担とし,控訴人有限会社津下建材と被控訴人との間では全部被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,本件係争物が産業廃棄物に該当するとして被控訴人が控訴人らに対してした各処分(以下「本件各処分」という。)等について,本件係争物は改良土であって産業廃棄物ではない等と主張する控訴人らが,主位的に本件各処分等の無効確認を,予備的にその取消を求めた事案である。
2 争いのない事実及び証拠上容易に認定できる事実
(1) 当事者等
ア エヌエス日進は,昭和52年2月12日に設立され,産業廃棄物収集運搬業(被控訴人平成9年5月28日付け更新許可。乙4の1),産業廃棄物処分業(被控訴人平成9年5月28日付け更新許可。乙4の2)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(被控訴人平成11年3月2日付け更新許可。乙4の3)の各許可を受け,産業廃棄物処理を主な業務とする株式会社である。
イ 津下建材は,産業廃棄物収集運搬業(被控訴人平成10年12月20日付け更新許可)の許可を受け,これを業として行っている有限会社であり,収集運搬車両として,登録番号岡山11こ3145及び岡山11こ3148を含め合計7台のダンプを利用することを被控訴人に届けている(乙8,11,12)。
ウ 訴外株式会社未来(以下「訴外未来」という。)は,重機数台を所有し,土木工事を業として行っている株式会社であり,その代表者は訴外A(以下「訴外A」という。)であるが,同人は,津下建材代表者の夫である(乙11)。
エ 岡山市環境事業局業務部産業廃棄物対策課(平成13年4月1日付け機構改革により現在は岡山市環境局保全部産業廃棄物対策課である。以下「産廃課」という。)は,廃棄物処理法2条4項に定める産業廃棄物の処理等に関する事務を地方自治法2条10項に定める法定受託業務として執行するために設置された被控訴人の組織である。
(2) 本件各処分等に至る経緯
ア 産廃課職員は,平成12年8月24日,エヌエス日進のd事業場に対する立入調査を行った。d事業場には,汚泥の天日乾燥・混練固化施設(以下「ピット」という。),破砕施設などの産業廃棄物中間処理施設に加え,ピットで乾燥固化されたものを原材料として改良土を製造するための施設(以下「改良土プラント」という。)があった。
イ 同年9月11日及び同月14日,灰色の有体物(以下「本件係争物」という。)が,訴外未来所有の10トンダンプにより,d事業場から岡山市a地内の土地(以下「本件土地」という。)に運搬され,本件土地に本件係争物が降ろされた。
ウ 産廃課職員は,同月14日午後5時30分ころ,本件土地への立入調査を実施し,本件係争物を採取して持ち帰った。
エ B(以下「B」という。)は,同月21日午後1時31分ころ,訴外未来所有の10トンダンプに本件係争物を積載してd事業場を出発し,同日午後1時50分ころ,本件土地に到着し,本件土地に本件係争物を降ろした。そこで,産廃課職員が,Bに事情聴取したところ,Bは以下のとおり答えた。また,産廃課職員は,同日,本件係争物を採取して持ち帰った。
(ア) 訴外未来の代表者である訴外Aの指示により,平成12年5月若しくは同年6月ころから,エヌエス日進より改良土として購入したものをd事業場からダンプで本件土地へ搬入し,埋立に使用していた。
(イ) 搬入量は,10トンダンプで1日あたり少ないときは7車分,多いときは50車分である。
オ 産廃課職員は,同日,訴外Aに事情聴取を行い,その際,同人は以下のとおり答えた。そして,被控訴人は,同月22日,訴外Aから,関係書類の提出を受けた。
(ア) 平成12年6月,本件土地のうち,岡山市ae番f及び同所b番cの各土地を重機置場にする目的で,エヌエス日進の代表者であるC(以下「C」という。)から購入した。
(イ) 埋立に利用していた材料は,エヌエス日進から改良土として購入したものである。その価格は,10トンあたり,当初2000円であったが,平成12年5月からは3500円に値上がりした。
カ 産廃課職員は,同日,Cにも来庁するよう求めたが,Cは出張中のため,エヌエス日進の営業課長であるD(以下「D」という。)が訪れ,事情聴取に応じた。
キ 被控訴人は,同月22日付け書面をもって,Cの来庁を求めたところ,同月26日,同人はDとともに訪れ,以下のとおり述べた。
(ア) エヌエス日進が,平成12年4月から7月までの間に受け入れた汚泥の大半は,大本・アイサワ・蜂谷共同企業体(以下「訴外共同企業体」という。)がシールド工事を請け負っている岡山市g町作業所から排出されたものである。
(イ) 訴外共同企業体からの受託開始は,平成10年12月ころであるが,本格的な受入は,平成12年5月以降で,同年4月から8月末までの処分委託実績は,10トンダンプで576車分である。
ク 被控訴人は,同年10月17日付けで,エヌエス日進に対し,以下のとおり,予定している不利益処分,不利益処分の事実となる原因等を記載した弁明の機会付与通知書を送付した(甲23)。
(ア) 予定している不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(予定している不利益処分の内容)
? 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部停止10日間
? 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止10日間
(根拠となる法令の条項)
? 廃棄物処理法14条の3第1号
? 廃棄物処理法14条の6
(イ) 不利益処分の原因となる事実
平成12年6月上旬から同年9月21日までの間,産業廃棄物中間処理業務に伴って生じた産業廃棄物である汚泥(セメント等により固化したもの)の収集運搬を訴外未来こと津下建材に委託する際,書面による委託契約を行わなかった。
(ウ) 弁明の機会の付与の方式 弁明書の提出
(エ) 弁明書の提出期限 平成12年10月30日
ケ 被控訴人は,同年10月17日付けで,津下建材及び訴外未来に対し,以下のとおり予定している不利益処分,不利益処分の原因となる事実(本件係争物が産業廃棄物であること)等を記載した弁明の機会付与通知書を送付した。
(ア) 予定している不利益処分の内容
? 岡山市ab番c地内及びその周辺への汚泥(セメント等により固化したものを含む)の搬入を中止すること。
? 岡山市ab番c地内及びその周辺に放棄している汚泥(セメント等により固化したもの)を平成13年4月10日までに適正な処分を行うことができる場所へ撤去すること。
(イ) 弁明の機会の付与の方式 弁明書の提出
(ウ) 弁明書の提出期限 平成12年10月30日
コ エヌエス日進,津下建材及び訴外未来ら代理人であった菊池捷男弁護士(以下「菊池弁護士」という。)らは,同月26日,被控訴人に,弁明書と題する書面を提出し,本件係争物は有価物(第3種,第4種改良土建設資材)であるから産業廃棄物ではないと主張し,被控訴人が本件係争物を産業廃棄物であると断定した根拠についてその争点の明確化を求めた(乙27)。
サ これを受けて,被控訴人は,同年11月27日付けで,菊池弁護士に対し,以下の内容を記載した弁明の機会の付与通知書(補充)を送付し,菊池弁護士の元に同月28日到着した(甲24の(1),(2))。
(ア) 不利益処分の原因となる事実の補充部分(産業廃棄物である汚泥と認定した理由)
以下の事実等を総合的に勘案した結果,本件係争物は「廃棄物」すなわち「不要物」に該当する。
? 本件係争物は,造成地への搬入直後も泥状を呈し,天日乾燥しなければ,埋め立てることができないことなどから中間処理が不完全である。
? 本件係争物は,中間処理過程においてセメント等を添加している上,中間処理後の粒状も均一でなく,岡山県や岡山市における「改良土」の基準にも該当しない。
? 排出者(工事請負業者)は,汚泥をセメント固化等したのち「建設汚泥(産業廃棄物)」として排出し,エヌエス日進に処理委託している。
? セメント固化後に排出の建設汚泥については,通常,同業者は「改良土として製造できない。」等との理由から,全量管理型最終処分場に処理委託している。
? セメント固化後に排出の建設汚泥を「改良土」に製造・販売している業者は,岡山市内においては他に見当たらない。
? リサイクルを推進している岡山市でさえ,セメント添加による「改良土」は,業者から一切購入していない。
? 同業者に比べ,本件係争物の売買価格がかなり安価である。
? エヌエス日進における「改良土」の販売先は,本年5月以降訴外未来こと津下建材のみである。
(イ) 補充部分についての弁明の機会の付与の方式 弁明書の提出
(ウ) 弁明書の提出期限 平成12年12月11日
シ これに対し,菊池弁護士らは,同年12月1日までに,被控訴人に,弁明書(補充)を提出し,反論した(乙54)。
ス そして,菊池弁護士らは,同月5日付けの証拠開示請求書と題する書面を被控訴人に提出し,上記サ(ア)の根拠となった証拠の開示を求めた(甲25)。
セ さらに,菊池弁護士らは,同月13日付けの弁明の機会の付与と証拠開示の請求と題する書面を送付し,被控訴人に同月14日に到着した(甲26の(1),(2))。
ソ しかし,被控訴人は,エヌエス日進らからの上記ス及びセの求めに応ずることなく,同月19日,エヌエス日進及び津下建材に対し,以下の内容の本件各処分をした。
(ア) エヌエス日進に対するもの(乙29。岡山市指令産廃第544号。以下「本件事業停止処分」という。)
産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可に係る事業全部の平成13年1月10日から同月19日までの10日間の事業停止
(イ) 津下建材に対するもの(乙30。岡山市指令産廃第545号。以下「本件中止撤去命令処分」という。)
? 岡山市ab番c地内及びその周辺への汚泥(セメント等により固化したものを含む)の搬入を中止すること。
? 岡山市ab番c地内及びその周辺に放棄している汚泥(セメント等により固化したもの)を平成13年4月10日までに適正な処分を行うことができる場所へ撤去すること。
タ また,被控訴人は,エヌエス日進に対し,平成12年12月19日,産業廃棄物処理業に係る許可証の返納を求める通知をした(乙67。岡山市指令産廃第546号。以下「本件許可証返納通知」といい,本件各処分と併せて述べる場合には「本件各処分等」という。)
3 争点
(1) 本件事業停止処分に係るエヌエス日進の訴えの適法性
(略)
(2) 本件許可証返納通知に係るエヌエス日進の訴えの適法性
(略)
(3) 本件係争物の特定性等
(略)
(4) 本件係争物の産業廃棄物該当性
(略)
(5) 本件各処分等に係る行政手続の違法性
(略)
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件事業停止処分に係るエヌエス日進の訴えの適法性)について
(1) 被控訴人は,本件事業停止処分に係るエヌエス日進の訴えは,本件事業停止期間の経過により,訴えの利益が既に消滅していると主張する。
(2) 行政処分についての取消訴訟あるいは無効確認訴訟は,当該処分の効果が期間の経過等により消滅した場合においても,なお処分の取消しあるいは無効確認をしなければ回復できないような法律上の利益を有する者に限りこれを提起することができる(行政事件訴訟法9条,36条)。したがって,事業停止処分のように,行政処分が一定の期間内に限り,国民の権利利益を制約するものである場合,すわなち,処分に期間が付されている場合,期間経過後においては,処分がされたことを理由として法律上の不利益を受けるおそれがあるのでなければ,その取消し等を求める訴えの利益は消滅する。
(3) 本件の場合に本件事業停止期間が経過していることは明らかであるから,なお,エヌエス日進において,法律上の不利益を受けるおそれがあると認められるかが問題となる。
ア 廃棄物処理法14条2項,5項及び同法14条の4第2項は,産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業について,5年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う旨規定しており,その更新許可にあっては,許可に準じる審査基準が適用されるが,同法14条3項等により適用される同法7条3項4号ホは「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」には許可をしてはならない旨規定している。
イ この規定について,被控訴人は,申請者の資質及び社会的信用の面から適切な業務運営が初めから期待できないことが明らかな者をいい,エヌエス日進のように比較的短期間の事業停止処分を受けた者は,上記規定に該当するとされることはあり得ないと主張する。しかし,上記規定には被控訴人主張のような限定は付されておらず,エヌエス日進が,将来産業廃棄物収集運搬業等の許可の更新を申請した場合,本件事業停止処分の存在がエヌエス日進にとって不利益な事由として考慮されるおそれがあるといわざるを得ない。
(4) 以上によれば,本件事業停止処分に係るエヌエス日進の訴えには訴えの利益があると認められるから,当該訴えは適法である。被控訴人の上記主張は採用できない。
2 争点(2)(本件許可証返納通知に係るエヌエス日進の訴えの適法性)について
(1) 被控訴人は,本件許可証返納通知は,これによってエヌエス日進に法律上の作為義務が発生するものではなく,また,これに従わなかったとしても,そのこと自体で不利益を受ける訳ではないから,取消訴訟等の対象となる処分には該当せず,本件許可証返納通知に係るエヌエス日進の訴えは不適法であると主張する。
(2) 取消訴訟等の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁)。
(3) そこで,本件許可証返納通知について検討するに,本件細則(乙34)は,許可証を返納しなければならない場合として業務停止処分が為された場合を規定しているのみであって,本件細則に基づく本件許可証返納通知には,これを強制する手続等に関する規定はない。したがって,本件許可証返納通知は,取消訴訟等の対象となる処分には該当しないというべきである。これに対し,エヌエス日進は,許可証を返納した結果,廃棄物の処理委託契約を一切締結できなくなるという極めて重大な影響を受けると主張するが,これは事業停止処分の結果であって,許可証の返納によるものではないから,エヌエス日進の上記主張は採用できない。
(4) 以上によれば,被控訴人の上記主張は理由がある。したがって,本件許可証返納通知に係るエヌエス日進の訴えは不適法である。
3 争点(3)(本件係争物の特定性)について
(1) 控訴人らは,本件各処分の対象となる本件係争物の特定が不十分又は対象物が不存在もしくは誤認の瑕疵があると主張する。
(2) 本件事業停止処分における不利益処分の原因となる事実は「平成12年6月上旬から同年9月21日までの間,産業廃棄物中間処理業務に伴って生じた産業廃棄物である汚泥(セメント等により固化したもの)の収集運搬を訴外未来こと津下建材に委託する際,書面による委託契約を行わなかった。」というものであり,本件中止撤去命令処分の内容は「岡山市ab番c地内及びその周辺への汚泥(セメント等により固化したものを含む)の搬入を中止すること。岡山市ab番c地内及びその周辺に放棄している汚泥(セメント等により固化したもの)を平成13年4月10日までに適正な処分を行うことができる場所へ撤去すること。」である。
本件各処分に至る経緯は,前記第2の2(2)で認定したとおりであり,平成12年9月の事情聴取の時点から,本件係争物について,被控訴人は産業廃棄物である汚泥であると主張し,控訴人らは,改良土であって,産業廃棄物ではないと主張し,控訴人らは,被控訴人が本件係争物を産業廃棄物であると断定した根拠についてその争点の明確化等を求めていたことが認められる。控訴人らは,対象の特定性(その性状,搬入期間,搬入量)において不十分であるばかりでなく,エヌエス日進が製造した改良土を本件土地に搬入を開始したのは,平成12年8月中旬以降であると主張する。
しかし,本件においては,上記のとおり,本件係争物の産業廃棄物該当性については争いがあるところ,本件各処分の対象となる本件係争物が何を意味するのかということについては控訴人らと被控訴人との間に事実上争いはないと認められる上,本件の場合には,搬入期間及び搬入量が本件係争物の特定に不可欠なものであるとまではいうことはできないから,本件係争物の特定性を欠くものとは認められない。
(3) 以上によれば,控訴人らの上記主張は採用できない。
4 争点(4)(本件係争物の産業廃棄物性)について
(1) 産業廃棄物の定義
ア 廃棄物処理法は,2条1項において,「『廃棄物』とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のものをいう。」と定義しているが,この規定は,一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示したものであり,廃棄物とは,占有者が自ら利用し,又は他人に有償で売却することができないために不要となったものをいい,これらに該当するか否かは占有者の意思,その性状等を総合的に勘案して定めるべきものと解される。
したがって,当該物について,占有者が主観的に他人に有償で売却することができると判断しただけであって,客観的には他人に有償で売却することができないものは,廃棄物に該当するといわざるを得ない。
イ また,廃棄物処理法は,同条4項1号において,「『産業廃棄物』とは,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。」と定義している。そして,同法施行令2条は,上記政令で定める廃棄物について,紙くず等12種類のものを規定するほか,13号において「燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類又は前各号に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって,これらの産業廃棄物に該当しないもの」と規定している。
ウ 以上によれば,ある産業廃棄物を再利用のために処理をし,他人に有償で売却することができる状態となった場合には,当該産業廃棄物は,その産業廃棄物該当性を失うものと解される。したがって,ある産業廃棄物に何らかの処理がなされても,未だ他人に有償で売却することができる状態に至っていない場合には,その産業廃棄物該当性は失われないものと解される。
(2) 産業廃棄物該当性についての主張立証責任
ア 国民の自由を制限し,国民に義務を課する行政処分の取消しを求める訴訟においては,行政庁がその適法であることの主張立証責任を負担すると解すべきであるところ,エヌエス日進のd事業場に搬入された時点では産業廃棄物である汚泥であったことについては当事者間に争いがない本件の場合,本件係争物が産業廃棄物である汚泥に再利用のための処理をし,他人に有償で売却することができる状態となったことについて,控訴人らが主張立証責任を負担するのか,本件係争物がその産業廃棄物該当性を失っていないことについて被控訴人が主張立証責任を負担するのかが問題となる。
イ そこで検討するに,上記(1)で述べたところによれば,確かに,本件係争物が汚泥の状態にないということだけでは,その産業廃棄物該当性は否定されないものの,被控訴人は,本件事業停止処分にあたっては,エヌエス日進が平成12年6月上旬から同年9月21日までの間,産業廃棄物である本件係争物の収集運搬を津下建材に委託する際,書面による委託契約を行わなかったことを不利益処分の原因となる事実としている以上,上記の期間において,本件係争物が汚泥であったということ又は本件係争物はこれを他人に有償で売却することができないものであったということについて,被控訴人がその主張立証をする責任を負うといわなければならない。また,被控訴人は,本件中止撤去命令処分にあたっては,津下建材が同命令時に産業廃棄物である本件係争物を本件土地に放棄していたことを不利益処分の原因となる事実としたものであるから,同様に,同命令時において,本件係争物が汚泥であったということ又は本件係争物はこれを他人に有償で売却することができないものであったということについて,被控訴人がその主張立証をする責任を負うといわなければならない。
(3) 本件係争物の産業廃棄物該当性の有無
ア まず,被控訴人は,本件係争物は産業廃棄物である汚泥であると主張するので,この点について検討する。
(ア) 汚泥とは,工場排水等の処理後に残るでい状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであって,有機性及び無機性のものをすべて含むとされているところ,旧厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室作成の建設廃棄物処理指針(平成11年3月。甲30,乙33。以下「本件指針」という。)によれば,「建設汚泥の取扱い」として,以下のとおり記載されていた。
? 地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち,含水率が高く粒子が微細な泥状のものは,無機性汚泥として取り扱う。また,粒子が直径74ミクロンを超える粒子をおおむね95%以上含む掘削物にあっては,容易に水分を除去できるので,ずり分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって,かつ,生活環境の保全上支障のないものは土砂として扱うことができる。
? 泥状の状態とは,標準仕様ダンプトラックに山積みができず,また,その上を人が歩けない状態をいい,この状態を土の強度を示す指標でいえば,コーン指数がおおむね200kN/?以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/?以下である。
? しかし,掘削物を標準仕様ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっても,運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので,これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要がある。なお,地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり,土砂は廃棄物処理法の対象外である。
? この土砂か汚泥かの判断は,掘削工事に伴って排出される時点で行うものとする。掘削工事から排出されるとは,水を利用し,地山を掘削する工法においては,発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを,掘削工事としてとらえ,この一体となるシステムから排出される時点で判断することとなる。
(イ) 本件の場合,本件係争物がエヌエス日進のd事業場に搬入された時点で,産業廃棄物である汚泥であったことについては,当事者間に争いがない。しかし,本件各処分においてその産業廃棄物該当性が問題とされる時点は,本件事業停止処分については平成12年6月上旬から同年9月21日までの間であり,本件中止撤去命令処分についてはその処分時である同年12月19日の時点であるから,その各時点で本件係争物が産業廃棄物である汚泥と認められるかを検討しなければならない。
(ウ) この点について,被控訴人は,本件土地へのダンプアウトされた直後の本件係争物について目視,歩行実験した結果及び関係者からの事情聴取(乙11,13,14,49,51,52,証人F,同〔いずれも原審〕)から,本件係争物は,本件土地への搬入時点で泥状を呈しており,本件土地に人工的に掘った穴で天日乾燥して固めた後でなければ埋め立てることができないほどの流動性を有しており,平成12年9月21日に歩行実験を行ったところ,同実験を実施した産廃課職員F(以下「F」という。)は,くるぶしのあたりまで埋まり,歩行困難な状態であったと報告していること等から,本件係争物は産業廃棄物である汚泥であると主張している。
(エ) 証拠(乙11及び13添付の各写真,甲32〜35,39,154,155,証人B)によれば,平成12年9月21日に本件土地へダンプアウトされた直後の本件係争物は,エヌエス日進のd事業場でB運転のダンプに積載され,山道を約20分程度要して運搬されたにもかかわらず,約45度の安息角をもって堆積しており,ダンプの荷台にも粘土状あるいは液状の物体の付着は認められないこと,同月14日の本件係争物もほぼ同様な状態であったことが認められる。
これらの事実及び前記(ア)の本件指針からすると,本件係争物は産業廃棄物である汚泥であるとは認められないというべきである。なお,本件指針によれば,土質を示すコーン指数も汚泥かどうかを判断する基準の一つとされているところ,産廃課職員は,同月14日及び21日の立入検査の際,本件係争物を採取したが,これらについて,コーン指数についての検査が行われていない(当事者間に争いがない)ため,本件の場合,コーン指数の点から本件係争物の性状を判断することはできない。
さらに,被控訴人は,泥状物堆積実験を行い,その報告書等(乙81〜83)を提出するが,上記実験に用いられた建設発生土は,その性状,そのダンプアウト中の状態等からして,本件係争物とはその性状を著しく異にするものといわざるを得ないから,上記実験結果によっても,上記結論は左右されない。
(オ) したがって,被控訴人の本件係争物が産業廃棄物である汚泥である旨の上記主張は採用できない。
イ 次に,被控訴人は,本件係争物は建設汚泥として排出された後他人に有償で売却できるものとして再生されたものではない旨主張し,その根拠をあげるので,この点について検討する。
(ア) 被控訴人は,本件の場合,エヌエス日進は,訴外未来に10トンあたり3500円で売却した本件係争物を10トンあたり4750円の運搬賃等を支払って納品しており,控訴人らは,有償での売却を仮装している旨主張し,この点について,弁明書(乙27)添付の訴外未来作成の請求書等から明らかとなったその取引関係から認められるものであって,Cから訴外Aに売却されて所有権移転登記もなされた土地についてCを債務者とする根抵当権設定登記が抹消されないでいたこと(乙44の(3),(4)),埋め立てられた本件土地の全部が訴外Aの土地ではないこと(乙43の(2),44の(5)),本件土地の排水施設をCが管理していること(乙45)などは,これを裏付けるものであると主張する。
しかし,上記根抵当権設定登記は旧岡山市民信用金庫を根抵当権者とするものであるが,同信用金庫が破綻したことは当裁判所に顕著であり,また,平成14年2月には同登記は抹消されている(甲118,119)のであるから,平成12年の時点において,控訴人らが主張するとおり,同根抵当権は被担保債権も存在しない実体のないものであった可能性は十分にあるものということができる。そして,被控訴人が主張するその他の点を考慮しても,Cと訴外Aが通常のビジネス上の交際を超えて本件係争物の有償譲渡を共謀して仮装するような関係にあったとは認められない。そもそも,被控訴人が主張する上記仮装の根拠は,控訴人ら代理人が被控訴人に提出した弁明書(乙27)に添付された資料であるところ,そこに有償譲渡仮装の証拠資料を誤って混入させてしまうというような事態は想定し難い。これに対して,控訴人らは,上記請求書中の「土工 上高田 8H−3人」(乙27の73頁)等は,本件土地の100メートル南に所在するエヌエス日進の分別場所の工事代金であり,「11t常用 d 8H−2台」(乙27の74頁)等は,dでダンプをチャーターした代金であり,本件係争物のdから本件土地への運搬賃ではないと主張し,Cも,原審において,この主張に沿う供述をしている。そして,控訴人らが主張する分別場所が存在し,その土地の所有者がCであることは,証拠(乙38の(3),43の(2))上これを認めることができ,また,上記請求書中には,「k」という記載もなされており,これはエヌエス日進における営業所の一つであると認められる(Cの原審供述)。
被控訴人は,エヌエス日進が訴外未来に対し,10トンあたり3500円という極めて安価であるいは原価割れで本件係争物を販売しているとも主張するが,証拠(乙25,甲94)によれば,エヌエス日進は,訴外共同企業体から汚泥の処理を委託され,その委託代金として,ダンプ1台あたり1万8000円を受領しており,石灰代,人件費等の製造費用を差し引いても,10トンあたり3500円で販売すると,1立米あたり約1000円程度の利益を得ることができることが認められる。
これらの点を総合考慮すると,本件の場合,上記請求書中のエヌエス日進の訴外未来に対する支払が本件係争物の本件土地への運搬賃等であると断定することまではできないといわざるを得ない。
(イ) さらに,被控訴人は,
?改良土は,通常茶色で粒状が均一で小さくさらさらしているはずなのに,本件係争物は,灰色で粒径が40?以上の粒土が混在している,
?本件係争物はpH値が12で,植物の生育に適さない,
?本件係争物のようにセメント添加により粘土状の状態で排出された汚泥は,改良土として加工できない,
?本件係争物が建設汚泥リサイクル指針に定める第3種又は第4種改良土に該当するとしても,岡山県や岡山市の基準には適合しない等公共団体への売却はできず,民間は改良土を利用しないのが通常であるから,その商品価値はなく,商品価値があったとしても,その市場性も極めて狭いものであるから,当然に有価物にはならない,
?平成12年8月24日のエヌエス日進のd事業場への立入検査の際,原料となるべき建設発生土等は全く保管されていなかったし,その際,E工場長は委託処理について述べたが,訴外事業団に対する調査の結果,その発言が虚偽であったことが判明した,
?控訴人らの主張によっても,行方不明の改良土が多く存在する,
?エヌエス日進は,訴外共同企業体には,改良土として道路中央分離帯の工事に使用すると説明していた,などと主張する。
しかしながら,このうち,?ないし?については,証拠(甲154〜158)によれば,京都大学大学院地球環境学堂のH教授は,根拠として十分でない,あるいは誤った見解であるとの意見を述べていること等が認められ,被控訴人の主張は一つの見解にしか過ぎないといわざるを得ないし,pH値については,当初産廃課職員において,問題とされていなかったことが認められる(原審証人Iの供述)。
?については,建設汚泥を材料としてセメント系固化剤を使用して改良土を製造する方法は,一般に行われているものであり(甲65,101),また,?のうち,建設発生土等の保管の点については,控訴人らは,これを否認しているところ,原審証人の供述によれば,同日の立入検査時に直接確認した調査員はおらず,帰りの車の中で話が出たものに過ぎないというのであるから,これを直ちに採用することはできない。?の点については,控訴人らは被控訴人とは異なる計算をしており,これが全く根拠のないものとは認められない。?のE工場長の発言については,控訴人らはこれを否認し,これに沿ったE工場長の陳述書(甲37)を提出しており,また,?については,産廃課職員作成の報告書(乙25)においても「道路の中央分離帯等に使用する」と記載されており,道路の中央分離帯工事のみに使用するとはされていないことからして,これらを直ちに採用することはできない。
(ウ) 一方,証拠(甲161)によれば,本件係争物には,控訴人らが主張するとおり,石灰が添加されていたことが認められるのであって,このことは本件係争物がエヌエス日進d事業場に設置されている改良土プラントで処理されたことを裏付けるものである上,本件係争物によって埋立られた本件土地が3年以上経った時点においても,当初の形状を保持していること(争いがない)は,本件係争物が控訴人ら主張の締め固めの効果を持つことを裏付けるものである。さらに,エヌエス日進は,建設汚泥を材料とした改良土について,他にも販売実績を有している(甲21,67ないし70等。枝番を含む。)
(エ) 以上検討した結果によれば,本件の場合,被控訴人が,本件係争物の売買が仮装ではないかと疑念を持つに至ったことにその根拠が全くなかったとまではいえないものの,本件係争物が有価物ではなく,訴外未来を含む控訴人らの間で売買が仮装されたと断定することはできないといわざるを得ない。したがって,本件係争物については,有価物として再生されていない産業廃棄物であるとも認めることはできない。被控訴人のその他の主張,立証によっても,以上の認定,判断を覆すには足りない。
5 争点(5)(本件各処分に係る行政手続の違法性)について
上記4によれば,本件各処分は,産業廃棄物とは認められない本件係争物を産業廃棄物として行われたものであるから,違法なものであるといわざるを得ないが,その瑕疵の程度は,前記第2の2(2)で認定した本件各処分に至る経緯及び上記4によれば,明白なものであるとは認め難いというべきであるから,本件各処分の取消事由となるに止まり,無効事由とはならないといわざるを得ない。
控訴人らは,本件各処分の無効確認を主位的請求とし,前記第2の3(5)のアにおいて,本件各処分に係る行政手続の違法性についての主張をしている。しかし,仮に,本件各処分に係る行政手続に控訴人ら主張の違法性があると認められるとしても,その違法は本件各処分の取消事由とはなるものの,無効事由とはならないと解されるから,上記のとおり既に取消事由があることが認められる本件の場合には,争点(5)についてさらに判断を加える必要はないといわざるを得ない。
6 以上によれば,控訴人らの本件各請求は,本件各処分の無効確認を求める主位的請求は理由がないからこれを棄却すべきであるが,本件各処分の取消を求める予備的請求は理由があるからこれを認容し,エヌエス日進の本件許可証返納通知の無効確認等を求める訴えは不適法であるから却下すべきである。
第4 結論
よって,結論を異にする原判決を変更し,仮執行宣言については相当でないからこれを付さないこととし,主文のとおり判決する。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei61.htm
2009年12月19日
ATC「わが国の土壌汚染リスク評価の在り方」セミナー

■ATCグリーンエコプラザ「わが国の土壌汚染リスク評価の在り方」セミナー■
〜地圏環境リスク評価システム〜
改正土壌汚染対策法の施行を控え、土壌・地下水汚染のリスクを適切に評価することがますます重要になってきています。
そこで、今回は、土壌・地下水汚染におけるリスク評価について、産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門地圏環境評価研究グループ長 駒井武氏に、土壌汚染の健康リスクを個々の現場ごとに定量化できる地圏環境リスク評価システム(GERAS)についてご紹介していただいただきます。
さらに、和歌山大学准教授の江種伸之氏に「我が国のリスク評価のあり方について」ご講演いただきます。
土壌・地下水汚染に関わるリスク評価について考える良い機会になるかと思いますので、奮ってお申し込みください。
■開催日時■
2010年1月21日(木) 14:00〜17:00
■プログラム■
講演1:リスク評価ソフト「GERAS」について
講 師:(独)産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 地圏環境評価研究グループ長 駒井 武 氏
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2009/pr20090930/
pr20090930.html
講演2:我が国のリスク評価について(仮題)
講 師:和歌山大学 システム工学部 環境システム学科 教授 江種 伸之 氏
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51094124.html
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://atcwsr.earthblog.jp/
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html
■受講料■
1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)
■会 場■
おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■定 員■
100名
■申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp
http://www.e-being.jp/work/concierge.htm
■交 流 会■
セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(2000 円/人) http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html
詳しくはブログで
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51081857.html
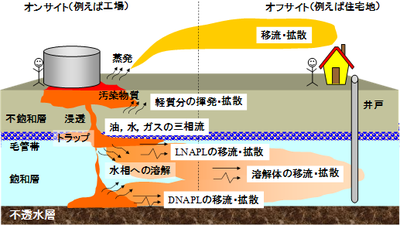
2009年12月15日
ATCセミナー地域環境と福祉とエコビジネスへの展開
おおさかATCグリーンエコプラザ 環境ビジネスセミナー
地域における環境と福祉の統合モデルの実践とエコビジネスへの展開
社会の高齢化、障害者への対応、雇用問題等の社会問題が増える現在、高福祉化社会の構築・実現が望まれてい
ます。
また、一方では急激に進む気候変動・地球温暖化や自然環境破壊・生物多様性の減少等の環境問題が大きくクロ
ーズアップされています。
これからの持続可能な豊かな暮らし社会をつくるためには、環境保全と福祉の充実を統合した考え方に基づいて、地域社会の街づくりや教育・啓発活動を実践することが重要です。
言い換えればこれからの21世紀は「福祉と環境との融合」を目指す時代と捉える必要があります。
そこで今回のセミナーでは、前環境省事務次官で環境福祉学会副会長の炭谷茂様に環境福祉学の理論と実践について基調講演をして頂き、その後に、地域社会で具体的に環境と福祉の統合事業の実践活動をしている徳島市のNPO法人太陽と緑の会様と米子市のNPO法人エコパートナーとっとり様から、先導的な活動内容とその成果・課題等の学習を行います。
開催日時
平成22年1月29日(金)13:30〜17:00
内容
基調講演「環境福祉学とは何か〜まちづくり、企業活動等への活用〜」
講師:環境福祉学会副会長、恩賜財団済生会理事長
(元環境省事務次官) 炭谷茂氏
講演1 「環境保全と障害者福祉を融合した社会貢献事業」
講師:NPO法人太陽と緑の会代表理事杉浦良氏
講演2 「障害者施設と連携した環境改善活動」
講師:NPO法人エコパートナーとっとり理事長大野木昭夫氏
(サンイン技術コンサルタント株式会社代表取締役社長)
主催おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)
協力ATCエイジレスセンター
受講料
無料
会場
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」
定員
100 名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までFAX またはE-mail でお送りします。)
お申し込み
おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで
〈事務局〉〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ「環境と福祉の統合モデル」セミナー(1 月29 日)係TEL:06-6615-5688
お申し込みはE−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください
http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100129.pdf
E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890
http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100129.pdf
地域における環境と福祉の統合モデルの実践とエコビジネスへの展開
社会の高齢化、障害者への対応、雇用問題等の社会問題が増える現在、高福祉化社会の構築・実現が望まれてい
ます。
また、一方では急激に進む気候変動・地球温暖化や自然環境破壊・生物多様性の減少等の環境問題が大きくクロ
ーズアップされています。
これからの持続可能な豊かな暮らし社会をつくるためには、環境保全と福祉の充実を統合した考え方に基づいて、地域社会の街づくりや教育・啓発活動を実践することが重要です。
言い換えればこれからの21世紀は「福祉と環境との融合」を目指す時代と捉える必要があります。
そこで今回のセミナーでは、前環境省事務次官で環境福祉学会副会長の炭谷茂様に環境福祉学の理論と実践について基調講演をして頂き、その後に、地域社会で具体的に環境と福祉の統合事業の実践活動をしている徳島市のNPO法人太陽と緑の会様と米子市のNPO法人エコパートナーとっとり様から、先導的な活動内容とその成果・課題等の学習を行います。
開催日時
平成22年1月29日(金)13:30〜17:00
内容
基調講演「環境福祉学とは何か〜まちづくり、企業活動等への活用〜」
講師:環境福祉学会副会長、恩賜財団済生会理事長
(元環境省事務次官) 炭谷茂氏
講演1 「環境保全と障害者福祉を融合した社会貢献事業」
講師:NPO法人太陽と緑の会代表理事杉浦良氏
講演2 「障害者施設と連携した環境改善活動」
講師:NPO法人エコパートナーとっとり理事長大野木昭夫氏
(サンイン技術コンサルタント株式会社代表取締役社長)
主催おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)
協力ATCエイジレスセンター
受講料
無料
会場
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」
定員
100 名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までFAX またはE-mail でお送りします。)
お申し込み
おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで
〈事務局〉〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ「環境と福祉の統合モデル」セミナー(1 月29 日)係TEL:06-6615-5688
お申し込みはE−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください
http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100129.pdf
E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890
http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100129.pdf
2009年12月15日
ATC「自然環境復元と生物多様性」セミナー

おおさかATCグリーンエコプラザ循環型社会形成推進セミナー
2010年10月に名古屋市で開かれる生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に向けて自然環境復元と
生物多様性保全への関心が高まっている。
生物多様性減少の要因は、人間のさまざまな活動によってもたらされるものであり、人口増加、森林破壊、さまざまな汚染、および地球温暖化による顕著な気候変動等があるが、これらが累積しながら生物多様性維持に大きな打撃を与えている。そこで今回のセミナーでは「関西における自然環境復元と生物多様性保全」に焦点を当て、20年前からこの問題に取り組み、活動を展開しているNPO法人自然環境復元協会と再生医の会・関西の協力を得て本セミナーを開催しますのでご案内いたします。
開催日時
平成22年1月26日(火) 13:30〜17:00
基調講演
「自然環境復元と生物多様性について」
講師:富士常葉大学教授、静岡大学名誉教授、自然環境復元協会理事長 杉山恵一氏
講演1 「滋賀県の山門(やまかど)水源の森における生物多様性の維持と復元の取り組みの成果と課題
〜湿地を含む里山管理の手探りの挑戦10年間、やっと明かりが見えてきた〜」
講師:山門水源の森連絡協議会会長、山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会理事
環境再生医の会・関西会長 村上宣雄氏
講演2 「国営明石海峡公園神戸地区の生物多様性と市民参画による復元・保全活動
〜市民の手でどこまでできる森・棚田・農耕地・草地の再生と管理〜」
講師:あいな里山公園ビオパーク代表グローバル環境文化研究所 代表 赤尾整志氏
講演3 「外来生物が身近な自然環境を侵している
〜大川(旧淀川)での調査漁を通して気づかされたこと〜」
講師:NPO法人関西ナショナル・トラスト協会常任理事、グローバル環境文化研究所会員、
日本環境教育学会 関西支部世話人 岡村悦治氏
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)
協力
自然環境復元協会、環境再生医の会・関西
受講料
無料
会場
アジア太平洋トレードセンターー(ATC)ITM棟、
おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」
定員
100 名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までFAX またはE-mail でお送りします。)
お申し込み
おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで
〈事務局〉〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ「自然環境保全」セミナー(1 月26 日)係TEL:06-6615-5688
お申し込みはE−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください
E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890
http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100126.pdf
2009年12月12日
ISO9000
ISO 9000は、国際標準化機構による品質マネジメントシステム関係の国際規格群。1994年版から2000年版への改正によって、それまでの「製品品質を保証するための規格」から、「品質保証を含んだ、顧客満足の向上を目指すための規格」へと位置付けが変わっている。
目次
1 改定履歴
2 規格要求事項
2.1 JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
3 ISO 9001:2008(2008年改訂版)
4 課題
5 関連項目
改定履
1987年にISO 9000の規格が制定されてから、1994年と2000年さらに2008年にそれぞれ規格改定が行われた。
ISO 9000:1987
ISO 9000:1994 「94年版」と呼ばれる。
ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000 「2000年版」と呼ばれる(ISO 9001)。
「2000年版」と呼ばれる規格
ISO 9000:2005 品質マネジメントシステム―基本及び用語
ISO 9001:2000 品質マネジメントシステム―要求事項
国内での批准翻訳的な規格は、JIS Q 9000:2006 / JIS Q 9001:2000などがある。
2008年版の改正は主に要求事項の明確化とISO 14001 との整合性の向上を目的として行われた。
規格要求事項
ISO 9001(品質マネジメントシステム―要求事項)の目次の一部を下に示す。
4. 品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
4.2 文書化に関する要求事項
5. 経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
5.2 顧客重視
5.3 品質方針
5.4 計画
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.6 マネジメントレビュー
6. 資源の運用管理
6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.3 インフラストラクチャー
6.4 作業環境
7. 製品実現
7.1 製品実現の計画
7.2 顧客関連のプロセス
7.3 設計・開発
7.4 購買
7.5 製造及びサービス提供
7.6 監視機器及び測定機器の管理
8. 測定、分析及び改善
8.1 一般
8.2 監視及び測定
8.3 不適合製品の管理
8.4 データの分析
8.5 改善
JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008)規格要求事項
1.2 適 用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業務及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求事項の除外を考慮することができる。
このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7 に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない。
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
(1)組織は,この規格の要求事項に従って,品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持しなければならない。
(2)また,その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善しなければならない。
(3)組織は,次の事項を実施しなければならない。
a)品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。(1.2 参照)
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c)これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d)これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e)これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析する。
f)これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
(4)組織は,これらのプロセスを,この規格の要求事項に従って運営管理しなければならない。
(5)要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には,組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にしなければならない。
(6)これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,組織の品質マネジメントシステムの中で定めなければならない。
注記1 品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには,運営管理活動,資源の提供,製品実現,測定,分析及び改善にかかわるプロセスが含まれる。
注記2 “アウトソースしたプロセス”とは,組織の品質マネジメントシステムにとって必要であり,その組織が外部に実施させることにしたプロセスである。
注記3 アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしたとしても,すべての顧客要求事項及び法令・規制要求事項への適合に対する組織の責任が免除されるものではない。アウトソースしたプロセスに適用される管理の方式及び程度は,次のような要因によって影響され得る。
a)要求事項に適合する製品を提供するために必要な組織の能力に対する,アウトソースしたプロセスの影響の可能性
b)そのプロセスの管理への関与の度合い
c)7.4 の適用において必要な管理を遂行する能力
ISO 9001:2008(2008年改訂版) [編集]
ISO(国際標準化機構)が、規格の内容の明確化等を目的に平成20年11月15日付けでISO 9001 の改正版を発行したことによって、経済産業省は平成20 年12月20日付けで、JIS Q 9001(品質マネジメントシステム規格)を改正した。今回の改正は、JIS Q 9001 の規格の内容の明確化等を目的とするものであり、組織に要求される事項を追加・変更するものでない。主な改正点は以下のとおり。
(1)規格要求事項の明確化
品質マネジメントシステム:一般要求事項【4.1】アウトソースしたプロセスの管理について、本文の中に“組織は「管理の方式及び程度」を定めなければならない”とするとともに、注記に、「管理の方式及び程度」は以下の3 つの要因により影響されうると説明を追加した。
・アウトソースしたプロセスの適合製品を供給するという組織の能力への影響の可能性
・アウトソースしたプロセスの管理への組織の関与の度合い
・購買管理を遂行する組織の能力
改善:是正処置【8.5.2】及び予防処置【8.5.3】現行版の本文にある“是正処置において実施した活動のレビュー”を、“とった是正処置の有効性のレビュー”と修文することで、ここにおけるレビューとは「実施した是正処置の結果の確認を含む」ことであることを明確にした。
(2)JIS Q 14001 との整合性の向上
記録の管理に関する要求事項【4.2.4】について、JIS Q 14001 との記述順序を揃えることで整合性を向上させた。
■ 品質マネジメントシステム−要求事項 ■
Quality management systems - Requirements
-------------------------------------------------------------------
序文
0.1一般
この規格は、2000年に発行されたISO 9001 (Quality management systems-Requirements)を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
"参考"と記載されている情報は、関連する要求事項の内容を理解するための、又は明確にするための手引である。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は、原国際規格にはない事項である。
これまでにJIS Z 9902(品質システム−製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル)及びJIS Z 9903(品質システム−最終検査・試験における品質保証モデル)を使ってきた組織は、この規格の1.2の記述に従って、規格の要求事項の一部を除外することによって、この規格を使うことができる。
この規格の表題は変更され、もはや品質保証という言葉を含んではいない。このことは、この規格で規定された品質マネジメントシステム要求事項は、製品の品質保証に加えて、顧客満足の向上をも目指そうとしていることを反映している。
この規格の附属書A及び附属書Bは、単に参考情報である。
品質マネジメントシステムを採用することは、組織による戦略上の決定とすべきである。組織における品質マネジメントシステムの設計及び実現は、変化するニーズ、固有の目標、提供する製品、用いられているプロセス、組織の規模及び構造によって影響を受ける。品質マネジメントシステムの構造の均一化又は文書の画一化が、この規格の意図ではない。
この規格が規定する品質マネジメントシステムについての要求事項は、製品に対する要求事項を補完するものである。
この規格は、顧客要求事項、規制要求事項及び組織固有の要求事項を満たす組織の能力を、組織自身が内部で評価するためにも、審査登録機関を含む外部機関が評価するためにも使用することができる。
この規格は、JIS Q 9000(品質マネジメントシステム−基本及び用語)及びJIS Q 9004(品質マネジメントシステム−パフォーマンス改善の指針)に記載されている品質マネジメントの原則を考慮に入れて作成した。
0.2プロセスアプローチ
この規格は、顧客要求事項を満たすことによって顧客満足を向上させるために、品質マネジメントシステムを構築し、実施し、その品質マネジメントシステムの有効性を改善する際にプロセスアプローチを採用することを奨励している。
組織が効果的に機能するためには、数多くの関連し合う活動を明確にし、運営管理する必要がある。インプットをアウトプットに変換することを可能にするために資源を使って運営管理される活動は、プロセスとみなすことができる。一つのプロセスのアウトプットは、多くの場合、次のプロセスヘの直接のインプットとなる。
組織内において、プロセスを明確にし、その相互関係を把握し、運営管理することとあわせて、一連のプロセスをシステムとして適用することを、"プロセスアプローチ"と呼ぶ。
プロセスアプローチの利点の一つは、プロセスの組合せ及びそれらの相互関係とともに、システムにおける個別のプロセス間のつながりについても、システムとして運用している間に管理できることである。
品質マネジメントシステムで、このアプローチを使用するときには、次の事項の重要性が強調される。
a) 要求事項を理解し、満足させる
b) 付加価値の点でプロセスを考慮する必要性
c) プロセスの実施状況及び有効性の成果を得る
d) 客観的な測定結果に基づくプロセスの継続的改善
図1に示すプロセスを基礎とした品質マネジメントシステムのモデルは、4.〜8.に記述したプロセスのつながりを表したものである。この図は、インプットとしての要求事項を決定するうえで顧客が重要な役割を担っていることを示している。顧客満足の監視においては、組織が顧客要求事項を満たしているか否かに関する顧客の受けとめ方についての情報を評価することが必要となる。図1に示すモデルはこの規格のすべての要求事項を網羅しているが、詳細なレベルでのプロセスを示すものではない。
参考
"Plan-Do-Check-Act"(PDCA)として知られる方法論は、あらゆるプロセスに適用できる。PDCAを簡潔に説明すると次のようになる。
Plan: 顧客要求事項及び組織の方針に沿った結果を出すために、必要な目標及びプロセスを設定する。
Do: それらのプロセスを実行する。
Check: 方針、目標、製品要求事項に照らしてプロセス及び製品を監視し、測定し、その結果を報告する。
Act: プロセスの実施状況を継続的に改善するための処置をとる。
-------------------------------------------------------------------
1.適用範囲
1.1一般
この規格は、次の二つの事項に該当する組織に対して、品質マネジメントシステムに関する要求事項を規定するものである。
a) 顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品を一貫して提供する能力をもつことを実証する必要がある場合。
b) 品質マネジメントシステムの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用、並びに顧客要求事項及び適用される規制要求事項への適合の保証を通して、顧客満足の向上を目指す場合。
参考
この規格では、"製品"という用語は、顧客向けに意図された製品又は顧客が要求した製品に限られて使われる。
備考
この規格の対応国際規格を次に示す。
なお、対応の程度を表す記号は、ISO/IEC Guide21に基づき、IDT(一致している)、MOD(修正している)、NEQ(同等でない)とする。
ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements (IDT)
1.2適用
この規格の要求事項ははん(汎)用性があり、業種及び形態、規模、並びに提供する製品を問わず、あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織やその製品の性質によって、この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には、その要求事項の除外を考慮してもよい。
このような除外を行う場合、除外できる要求事項は7.に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが、顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力、又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば、この規格への適合の宣言は受け入れられない。
-------------------------------------------------------------------
2.引用規格
次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版・追補には適用しない。
JIS Q 9000:2000 品質マネジメントシステム−基本及び用語
備考
ISO 9000:2000、Quality management systems - Fundamentals and vocabulary がこの規格と一致している。
-------------------------------------------------------------------
3.定義
この規格には、JIS Q 9000に規定されている定義を適用する。
この規格では、製品の取引における当事者の名称を次のように変更した。
供給者 → 組織 → 顧客
これまで使われていた"供給者"は"組織"に置き換えられる。"組織"とは、この規格が適用される単位を示す。
同様に、"下請負契約者"は"供給者"に置き換える。
この規格の全体にわたって、"製品"という用語が使われた場合には、"サービス"のこともあわせて意味する。
-------------------------------------------------------------------
4.品質マネジメントシステム
4.1一般要求事項
組織は、この規格の要求事項に従って、品質マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、かつ、維持すること。また、その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善すること。
組織は、次の事項を実施すること。
a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする (1.2参照)。
b) これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。
c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。
d) これらのプロセスの運用及び監視の支援をするために必要な資源及び情報を利用できることを確実にする。
e) これらのプロセスを監視、測定及び分析する。
f) これらのプロセスについて、計画どおりの結果が得られるように、かつ、継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
組織は、これらのプロセスを、この規格の要求事項に従って運営管理すること。
要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には、組織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にすること。アウトソースしたプロセスの管理について、組織の品質マネジメントシステムの中で明確にすること。
参考
1.品質マネジメントシステムに必要となるプロセスには、運営管理活動、資源の提供、製品実現及び測定にかかわるプロセスが含まれる。
2.ここでいう、"アウトソース"とは、あるプロセス及びその管理を外部委託することである。"アウトソースしたプロセスに関して管理を確実にする"とは、外部委託したプロセスが正しく管理されていることを確実にすることである。
4.2文書化に関する要求事項
4.2.1一般
品質マネジメントシステムの文書には、次の事項を含めること。
a) 文書化した、品質方針及び品質目標の表明
b)品質マニュアル
c) この規格が要求する"文書化された手順"
d) 組織内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、組織が必要と判断した文書
e) この規格が要求する記録 (4.2.4参照)
参考
1.この規格で"文書化された手順"という用語を使う場合には、その手順が確立され、文書化され、実施され、かつ、維持されていることを意味する。
2.品質マネジメントシステムの文書化の程度は、次の理由から組織によって異なることがある。
a)組織の規模及び活動の種類
b)プロセス及びそれらの相互関係の複雑さ
c)要員の力量
3.文書の様式及び媒体の種類はどのようなものでもよい。
4.2.2品質マニュアル
組織は、次の事項を含む品質マニュアルを作成し、維持すること。
a) 品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には、その詳細と正当とする理由 (1.2参照)。
b) 品質マネジメントシステムについて確立された"文書化された手順"又はそれらを参照できる情報
c) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述
4.2.3文書管理
品質マネジメントシステムで必要とされる文書は管理すること。ただし、記録は文書の一種ではあるが、4.2.4に規定する要求事項に従って管理すること。
次の活動に必要な管理を規定する"文書化された手順"を確立すること。
a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書を承認する。
b) 文書をレビューする。また、必要に応じて更新し、再承認する。
c) 文書の変更の識別及び現在の改訂版の識別を確実にする。
d) 該当する文書の適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e) 文書が読みやすく、容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f) どれが外部で作成された文書であるかを明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場合には、適切な識別をする。
4.2.4記録の管理
記録は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために、作成し、維持すること。記録は、読みやすく、容易に識別可能で、検索可能であること。記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定するために、"文書化された手順"を確立すること。
-------------------------------------------------------------------
5.経営者の責任
5.1経営者のコミットメント
トップマネジメントは、品質マネジメントシステムの構築及び実施、並びにその有効性を継続的に改善することに対するコミットメントの証拠を次の事項によって示すこと。
a) 法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして、顧客要求事項を満たすことの重要性を組織内に周知する。
b)品質方針を設定する。
c)品質目標が設定されることを確実にする。
d) マネジメントレビューを実施する。
e)資源が使用できることを確実にする。
5.2顧客重視
顧客満足の向上を目指して、トップマネジメントは、顧客要求事項が決定され、満たされていることを確実にすること (7.2.1及び8.2.1参照)。
5.3品質方針
トップマネジメントは、品質方針について次の事項を確実にすること。
a) 組織の目的に対して適切である。
b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミットメントを含む。
c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。
d) 組織全体に伝達され、理解される。
e) 適切性の持続のためにレビューする。
5.4計画
5.4.1品質目標
トップマネジメントは、組織内のそれぞれの部門及び階層で品質目標が設定されていることを確実にすること。その品質目標には、製品要求事項 [7.1.a)参照] を満たすために必要なものがあれば含めること。品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針との整合性がとれていること。
5.4.2品質マネジメントシステムの計画
トップマネジメントは、次の事項を確実にすること。
a) 品質目標及び4.1に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシステムの計画が策定される。
b) 品質マネジメントシステムの変更が計画され、実施される場合には、品質マネジメントシステムが"完全に整っている状態"(integrity)を維持している。
5.5責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1責任及び権限
トップマネジメントは、責任及び権限が定められ、組織全体に周知されていることを確実にすること。
5.5.2管理責任者
トップマネジメントは、管理層の中から管理責任者を任命すること。管理責任者は与えられている他の責任とかかわりなく次に示す責任及び権限をもつこと。
a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。
b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無についてトップマネジメントに報告する。
c) 組織全体にわたって、顧客要求事項に対する認識を高めることを確実にする。
参考
1.管理責任者の責任には、品質マネジメントシステムに関する事項について外部と連絡をとることも含めることができる。
2.管理責任者は、上記の責任及び権限を持つ限り、一人である必要はない。
5.5.3内部コミュニケーション
トップマネジメントは、組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にすること。また、品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にすること。
5.6マネジメントレビュー
5.6.1一般
トップマネジメントは、組織の品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ、有効であることを確実にするために、あらかじめ定められた間隔で品質マネジメントシステムをレビューすること。このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価、品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行うこと。
マネジメントレビューの結果の記録は維持すること (4.24参照)。
5.6.2マネジメントレビューヘのインプット
マネジメントレビューへのインプットには次の情報を含むこと。
a) 監査の結果
b) 顧客からのフィードバック
c) プロセスの実施状況及び製品の適合性
d) 予防処置及び是正処置の状況
e) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
f) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
g) 改善のための提案
5.6.3マネジメントレビューからのアウトプット
マネジメントレビューからのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置を含むこと。
a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b) 顧客要求事項への適合に必要な製品の改善
c) 資源の必要性
-------------------------------------------------------------------
6.資源の運用管理
6.1資源の提供
組織は、次の事項に必要な資源を明確にし、提供すること。
a) 品質マネジメントシステムを実施し、維持する。また、その有効性を継続的に改善する。
b) 顧客満足を、顧客要求事項を満たすことによって向上する。
6.2人的資源
6.2.1一般
製品品質に影響がある仕事に従事する要員は、関連する教育、訓練、技能及び経験を判断の根拠として力量があること。
6.2.2力量、認識及び教育・訓練
組織は、次の事項を実施すること。
a) 製品品質に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量を明確にする。
b) 必要な力量がもてるように教育・訓練し、又は他の処置をとる。
c) 教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。
d) 組織の要員が、自らの活動のもつ意味と重要性を認識し、品質目標の達成に向けて自らどのように貢献できるかを認識することを確実にする。
e) 教育、訓練、技能及び経験について該当する記録を維持する (4.2.4参照)。
6.3インフラストラクチャー
組織は、製品要求事項への適合を達成するうえで必要とされるインフラストラクチャーを明確にし、提供し、かつ、維持すること。インフラストラクチャーには次のようなものがある。
a) 建物、作業場所及び関連するユーティリティー(電気、ガス、水など)
b) 設備(ハードウェアとソフトウェアとを含む。)
c) 支援業務(輸送、通信など)
参考
インフラストラクチャーとは、"<組織>組織の運営のために必要な一連の施設、設備及びサービスに関するシステム"を指す(JIS Q 9000の3.3.3参照)。
6.4作業環境
組織は、製品要求事項への適合を達成するために必要な作業環境を明確にし、運営管理すること。
-------------------------------------------------------------------
7.製品実現
7.1製品実現の計画
組織は、製品実現のために必要なプロセスを計画して、構築すること。製品実現の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合性がとれていること(4.1参照)。
製品実現の計画に当たっては、組織は次の事項について該当するものを明確にすること。
a) 製品に対する品質目標及び要求事項
b) 製品に特有な、プロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の必要性
c) その製品のための検証、妥当性確認、監視、検査及び試験活動、並びに製品合否判定基準
d) 製品実現のプロセス及びその結果としての製品が要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録(4.2.4参照)
この計画のアウトプットは、組織の計画の実行に適した様式であること。
参考
1.特定の製品、プロジェクト又は契約に適用される品質マネジメントシステムのプロセス(製品実現のプロセスを含む。)及び資源を規定する文書を品質計画書と呼ぶことがある。
2.組織は、製品実現のプロセスの構築に当たって7.3に規定する要求事項を適用してもよい。
7.2顧客関連のプロセス
7.2.1製品に関連する要求事項の明確化
組織は、次の事項を明確にすること。
a)顧客が規定した要求事項。これには引渡し及び引渡し後の活動に関する要求事項を含む。
b) 顧客が明示してはいないが、指定された用途又は意図された用途が既知である場合、それらの用途に応じた要求事項
c) 製品に関連する法令・規制要求事項
d) 組織が必要と判断する追加要求事項
7.2.2製品に関連する要求事項のレビュー
組織は、製品に関連する要求事項をレビューすること。このレビューは、組織が顧客に製品を提供することについてのコミットメント(例 提案書の提出、契約又は注文の受諾、契約又は注文への変更の受諾)をする前に実施すること。レビューでは次の事項を確実にすること。
a) 製品要求事項が定められている。
b) 契約又は注文の要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、それについて解決されている。
c) 組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。
このレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持すること(4.2.4参照)。
顧客がその要求事項を書面で示さない場合には、組織は顧客要求事項を受諾する前に確認すること。
製品要求事項が変更された場合には、組織は、関連する文書を修正すること。また、変更後の要求事項が関連する要員に理解されていることを確実にすること。
参考
インターネット販売などの状況では、個別の注文に対する正式なレビューの実施は非現実的である。このような場合のレビューでは、カタログや宣伝広告資料などの関連する製品情報をその対象とすることもできる。
7.2.3顧客とのコミュニケーション
組織は、次の事項に関して顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を明確にし、実施すること。
a) 製品情報
b) 引き合い、契約若しくは注文、又はそれらの変更
c) 苦情を含む顧客からのフィードバック
7.3設計・開発
7.3.1設計・開発の計画
組織は、製品の設計・開発の計画を策定し、管理すること。
設計・開発の計画において、組織は次の事項を明確にすること。
a) 設計・開発の段階
b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認
c) 設計・開発に関する責任及び権限
組織は、効果的なコミュニケーションと責任の明確な割当てとを確実にするために、設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理すること。
設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適宜更新すること。
7.3.2設計・開発へのインプット
製品要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を維持すること(4.2.4参照)。インプットには次の事項を含めること。
a) 機能及び性能に関する要求事項
b) 適用される法令・規制要求事項
c) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報
d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項
これらのインプットについては、その適切性をレビューすること。要求事項は、漏れがなく、あいまい(曖昧)ではなく、かつ、相反することがないこと。
7.3.3設計・開発からのアウトプット
設計・開発からのアウトプットは、設計・開発へのインプットと対比した検証ができるような様式で提示されること。また、次の段階に進める前に、承認を受けること。
設計・開発からのアウトプットは次の状態であること。
a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
b) 購買、製造及びサービス提供に対して適切な情報を提供する。
c) 製品の合否判定基準を含むか又はそれを参照している。
d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性を明確にする。
7.3.4設計・開発のレビュー
設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、計画されたとおりに(7.3.1参照)体系的なレビューを行うこと。
a) 設計・開発の結果が要求事項を満たせるかどうかを評価する。
b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。
レビューへの参加者として、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門の代表が含まれていること。このレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
7.3.5設計・開発の検証
設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために、計画されたとおりに(7.3.1参照)検証を実施すること。この検証の結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
7.3.6設計・開発の妥当性確認
結果として得られる製品が、指定された用途又は意図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画した方法(7.3.1参照)に従って、設計・開発の妥当性確認を実施すること。実行可能な場合にはいつでも、製品の引渡し又は提供の前に、妥当性確認を完了すること。妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
7.3.7設計・開発の変更管理
設計・開発の変更を明確にし、記録を維持すること。変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適宜行い、その変更を実施する前に承認すること。設計・開発の変更のレビューには、その変更が、製品を構成する要素及び既に引き渡されている製品に及ぼす影響の評価を含めること。
変更のレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
参考
"変更のレビュー"とは、変更に対して適宜行われたレビュー、検証及び妥当性確認のことである。
7.4購買
7.4.1購買プロセス
組織は、規定された購買要求事項に、購買製品が適合することを確実にすること。供給者及び購買した製品に対する管理の方式と程度は、購買製品が、その後の製品実現のプロセス又は最終製品に及ぼす影響に応じて定めること。
組織は、供給者が組織の要求事項に従って製品を供給する能力を判断の根拠として、供給者を評価し、選定すること。選定、評価及び再評価の基準を定めること。評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持すること(4.2.4参照)。
7.4.2購買情報
購買情報では購買製品に関する情報を明確にし、必要な場合には、次の事項のうち該当する事項を含めること。
a) 製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項
b) 要員の適格性確認に関する要求事項
c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項
組織は、供給者に伝達する前に、規定した購買要求事項が妥当であることを確実にすること。
7.4.3購買製品の検証
組織は、購買製品が、規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために、必要な検査又はその他の活動を定めて、実施すること。
組織又はその顧客が、供給者先で検証を実施することにした場合には、組織は、その検証の要領及び購買製品のリリース(出荷許可)の方法を購買情報の中に明確にすること。
7.5製造及びサービス提供
7.5.1製造及びサービス提供の管理
組織は、製造及びサービス提供を計画し、管理された状態で実行すること。管理された状態には、該当する次の状態を含むこと。
a)製品の特性を述べた情報が利用できる。
b) 必要に応じて、作業手順が利用できる。
c) 適切な設備を使用している。
d)監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。
e) 規定された監視及び測定が実施されている。
f)リリース(次工程への引渡し)、顧客への引渡し及び引渡し後の活動が規定されたとおりに実施されている。
7.5.2製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
製造及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、組織は、その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行うこと。これらのプロセスには、製品が使用され、又はサービスが提供されてからでしか不具合が顕在化しないようなプロセスが含まれる。
妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証すること。
組織は、これらのプロセスについて、次の事項のうち適用できるものを含んだ手続きを確立すること。
a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準
b) 設備の承認及び要員の適格性確認
c) 所定の方法及び手順の適用
d) 記録に関する要求事項(4.2.4参照)
e) 妥当性の再確認
7.5.3識別及びトレーサビリティ
必要な場合には、組織は、製品実現の全過程において適切な手段で製品を識別すること。
組織は、監視及び測定の要求事項に関連して、製品の状態を識別すること。
トレーサビリティが要求事項となっている場合には、組織は、製品について固有の識別を管理し、記録すること(4.2.4参照)。
参考 ある産業分野では、構成管理が識別及びトレーサビリティを維持する手段である。
7.5.4顧客の所有物
組織は、顧客の所有物について、それが組織の管理下にある間、又は組織がそれを使用している間は、注意を払うこと。組織は、使用するため又は製品に組み込むために提供された顧客の所有物の識別、検証及び保護・防護を実施すること。顧客の所有物を紛失、損傷した場合又は使用には適さないとわかった場合には、顧客に報告し、記録を維持すること(4.2.4参照)。
参考
顧客の所有物には知的所有権も含まれる。
7.5.5製品の保存
組織は、内部処理から指定納入先への引渡しまでの間、製品を適合した状態のまま保存すること。この保存には、識別、取扱い、包装、保管及び保護を含めること。保存は、製品を構成する要素にも適用すること。
参考
内部処理とは、組織が運営管理している製品実現のプロセスにおける活動をいう。
7.6監視機器及び測定機器の管理
定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は、実施すべき監視及び測定を明確にすること。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にすること(7.2.1参照)。
組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立すること。
測定値の正当性が保証されなければならない場合には、測定機器に関し、次の事項を満たすこと。
a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録する。
b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。
c) 校正の状態が明確にできる識別をする。
d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
e) 取扱い、保守、保管において、損傷及び劣化しないように保護する。
さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、組織は、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。組織は、その機器及び影響を受けた製品に対して、適切な処置をとること。校正及び検証の結果の記録を維持すること(4.2.4参照)。
規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。この確認は、最初に使用するのに先立って実施すること。また、必要に応じて再確認すること。
参考
ISO 10012-1 (Quality assurance requirements for measuring equipment - Part1:Metrological confirmation system for measuring equipment) 及びISO 10012-2 (Quality assurance for measuring equipment - Part2: Guidelines for control of measurement processes)を参照。
http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/ms/iso9000/q9001-requirements.htm
2009年12月12日
土壌汚染ISO14015用地及び組織の環境アセスメント
3−1 用地及び組織の環境アセスメント
Environmental assessment of sites and organizations(EASO):ISO14015
環境マネジメント規格である用地及び組織の環境アセスメント(EASO)は、2001年11月に国際規格(IS)され、現在、日本工業規格(JIS)化の準備が進んでいる。
この規格は、1993年国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント専門委員会(TC207)、環境監査部会(SC2)において新業務項目が提案され、1997年の開発決定から4年間をかけて国際規格化されたものである。
EASOの規格の構成は、次の内容であり本項では、規格原文の表示番号で順を追って紹介する。
0 序文
1 適用範囲
2 用語及び定義
3 役割及び責任
4 アセスメント手順
5 報告
0 序文
組織は、自らの用地及び活動にかかわる環境事項又は起こり得る取得に伴う環境事項を理解することに一層関心を寄せつつある。これらの事項とそれらに関連する事業への影響は、用地及び組織の環境アセスメント(EASO)によって査定することができる。このようなアセスメントは、操業中でも、また、資産取得又は資産分割時においても実施されるし、しばしばデューディリジェンス(Due Diligence)と言われる、より広範な事業評価プロセスの一部として実施されることもある。
この国際規格は、EASOを実施する方法についての指針を提供する.また、この国際規格は、環境アセスメント実施のために、使用する用語の整合を図り、体系化され首尾一貫した、透明性の高い、かつ、客観的なアプローチの基礎を提供する。さらに、この国際規格は、中小企業を含む世界中のあらゆる場所で活動している組織が使用することができる。この国際規格は、適用の方法に柔軟性があり、第三者を雇用する必要性がある場合とそうでない場合があるが自己アセスメントのためにも、また、外部アセスメントにも使用することができる.この国際規格の利用者は、産業界や、過去、現在そしておそらくは将来における特定用地の使用者や、産業界や用地に財務的利害を有する組織(例えば、銀行、保険会社、投資家、土地所有者〉であると期待される。この国際規格は、責任と義務の移譲が行われるときに利用されるであろう。
EASOにおいて使用される情報は、環境マネジメントシステム監査、遵法監査、環境影響アセスメント、環境パフォーマンス評価又は用地調査を含む情報源から入手される。これらのアセスメント又は調査の一部は、他の関連規格(例えば、lSO14001、lS014011又はlSO14031)を使用して、実行されていたかもしれない。
既存の情報と新たに得られた情報の両方を評価するプロセスを通じて、EASOは、環境側面及び環境事項にかかわる事業への影響について結論を導き出そうとするものである。
EASOの結論は客観的情報に基く必要がある。妥当性確認がなされた情報がない場合には、利用可能な環境情報を評価し結論を導き出す際に、EASO評価者には専門的判断を下すことが求められることがある。
この国際規格は、実地探査又は用地浄化の指針を提供するものではない。しかしながら、依頼者から要求があった場合には、それらは他の規格又は手順に従って実施されることとなろう。
1 適用範囲
この国際規格は、環境側面及び環境事項を明確化し、必要に応じて事業へのそれらの影響を決定する指針を提供する。
この国際規格は、アセスメントに関係する当事者(依頼者、評価者及び被評価側の代表者)の役割と責任、及び評価プロセスの諸段階(計画作成、情報収集及び妥当性確認、評価及び報告作成)を規定する.EASOを実施するプロセスを図(3−1−1)に示す。
この国際規格は、次に示すような環境アセスメントの実施方法についての指針を提供するものではない。
a) 初期環境レビュー
b) 環境監査(環境マネジメントシステム及び遵法監査を含む)
c) 環境影響アセスメント、又は
d) 環境パフォーマンス評価
実地探査又は及び用地浄化は、この国際規格の適用範囲外である。同様に、これらを遂行するか否かを決定することも適用範囲外である。
この国際規格は、認証又は審査登録目的の仕様規格として使用したり、又は環境マネジメントシステム要求事項の確立を意図したものではない。
この国際規格を利用しても、依頼者や被評価側に他の規格や法規が課せられることにはならない。
図(3−1−1)用地及び組織の環境アセスメントを実施するプロセス

備考 括弧内の数字はこの国際規格の章節を参照している。破線はこの国際規格に記述されているよう
に(3.2 備考参照)被評価側はEASOに必ずしもかかわらないことがあることをしめす。
2 用語及び定義
この国際規格では、次に示す定義を適用する。
(本項では、ISO14001等の他の規格に定義があるものは除いている。)
2.1 被評価側
アセスメントを受ける用地又は組織
2.2 評価者
十分な能力を有し、所定のアセスメントを実施するため、又はそれに参画するために指名された者
備考 評価者は.アセスメントを行う組繊の内部又は外部の人間であってもよい.また、すべての関連項目に適切に対処することを確実にするために、例えば、特殊な専門領域を必要とする場合には、複数の評価者を必要とすることがある.
2.3 事業への影響
明確化し、評価された環境事項の現実の又は起こり得る影響(財務的又はそれ以外、好ましい又は好ましくない、定性的又は定量的)
2.4 依頼者
アセスメントを委託する組織
例 依頼者は用地の所有者、被評価側、又はその他の者であってよい。
2.7 用地及び組織の環境アセスメント(EASO)
過去、現在、及び予測可能な将来の活動の結果である用地や組織にかかわる環境側面を客観的に明確にし、環境事項を明確にし、その事業への影響を決定するプロセス
備考 事業への影響を決定することは任意であり、依頼者の裁量による。
2.9 環境事項
環境側面に関する妥当性確認が行われた情報が、選択された基準から外れ、かつ、責任又は便益、被評価側又は依頼者例の社会的イメージに対する影響、若しくはその他の費用をもたらす可能性のある事項
2.11 実地探査
機器を使用し、物理的干渉を必要とする場合もある試料採取及び試験
2.13 被評価側の代表者
被評価側を代表する権限を有する者
2.14 用地
地理学上の境界が定められ、そこにおいて組織の管理下での活動が実行できるとされた立地
備考 地理学上の境界は、地上又は水中にあり、天然又は人工いずれの表面構造物の上又は下を含む。
2.15 妥当性確認
アセスメントの目的に照らして、収集したされた情報が正確であり信頼性が高く、十分かつ適切であることを、評価者が決定するプロセス
3 役割及び責任
3.1 依頼者
依頼者の活動には、次に示す各項を含むとよい。
a) アセスメントの必要性を決定する
b) アセスメントの目的を明確にする
c) もし必要とするなら評価者と協議してアセスメントの範囲と基準を決定する
d) 評価者を選任する
e) 評価者に指示を与える
f) アセスメント(計画作成、情報収集及び妥当性確認、評価及び報告作成)のどの部分が評価者によって実施され、どの部分が依頼者の責任であるのかを決定する:この場合、他の専門家を特定し、組み入れることを要求してもよい
g) もし必要とするなら、優先順位の高いアセスメント分野を特定して決定する
h) もし必要があるなら、被評価側の代表者に接触し、全面的な協力を得てプロセスを開始する
i) アセスメント計画を承認する
j) アセスメントを実行するのにふさわしい権限と資源を提供する
k) アセスメントを実行するのに必要な情報を評価者に提供する
l) 評価者からのアセスメント結果を受領し、配布先を決定する
依頼者は、第三者に対するアセスメント結果を開示する場合、事前に、被評価側の代表者に通知するかどうかを決定することが望ましい。
備考 依頼者、評価者及び被評価側の代表者が、同一組織体であってもよい。
3.2 被評価側の代表者
被評価側の代表者の役割と責任には次の事項を含むとよい。
a)アセスメントの目的に合せて関連区域への立ち入りを認め、情報を提供する
b) アセスメントプロセスについて関連の従業員や他の関係者に通知する
c) 面接調査対象者を用意する、又は、用意するのを支援する
d)要請があれば、アセスメントプロセスを支援する要員を提供する、及び、
e)評価者のために安全な作業環境を提供する
依頼者の裁量によって、被評価側の代表者はアセスメントの範囲とアセスメント計画の決定に参画し、また、当該アセスメントの結果を受領してもよい。
被評価側の代表者への告知なしにアセスメントが行なわれる場合、又は、用地及び/又は組織の責任者を特定できない場合、被評価側の代表者の役割は適用されない。
3.3 評価者
評価者と監査者との役割と責任は見方によっては異なっている。監査者は定めた基準に対して既存の情報を検証するのに対して、評価者は更に新たな情報を収集し、事業への影響を決定するために情報を評価することがしばしば要求される。
用地及び組織の環境アセスメントを実施するに際して、評価者は、類似の状況においてすべての評価者に期待される勤勉さ、知識、技能及び判断を行使する必要がある。評価者は、思慮分別を働かせ、また、法律又は他の規則によって別段の行動が求められる場合を除いて、機密を保持することが望ましい。
評価者又は複数の評価者が関与する場合はそのチームリーダーの責任と活動には、次に示す事項を含むとよい。
a) 要請があれば依頼者を支援して、アセスメントの目的、範囲(優先的アセスメント分野の明確化及び決定を含む)、基準を決定する
b) 報告作成の方法及び書式を依頼者と取り決める
c) アセスメント計画を立案し、依頼者の承認、及び、もし必要とするなら被評価側の代表者の承認を得る
d) チェックリストや手順書のような作業文書を作成し、維持する
e) アセスメントの目的に合致する必要な技能が利用可能であるようにし、また、もし必要とするならアセスメントチームを編成する
f) アセスメントチームについて依頼者の承認を得る
g) 初期情報を得る
h) アセスメントの各部を実行するに当たり、アセスメントチームのメンバーに作業を割り当てる
i) アセスメントの計画に沿って情報を収集し、その妥当性確認をする
j) 環境事項を明確にし、評価する
k) 依頼者からの要請があれば、事業への影響を決定する
l) 依頼者からの要請があれば、依頼者への報告書を作成し、それを依頼者に提供する
この国際規格は評価者の能力及び資格要件に関する指針を提供するものではない。しかしながら、環境アセスメントを実施遂行するには次に示す事項を充足することが要請される。
− 十分な教育
− 十分な訓練
− 十分な関連する業務経験
同様に、次に示す知識及び能力
− 関連法律、規則及び関連の文書
− 環境科学及び技術
− 経済及び関連の事業分野
− (商業的)活動に関する運転の技術的及び環境的側面
− 設備運転
− アセスメント技術
4.アセスメント手順
4.1 一般
アセスメントプロセスには、アセスメントの計画作成、情報の収集及び妥当性確認、情報の評価、並びにアセスメントの報告作成を含む。
このプロセスには、依頼者から特に要請された場合には、事業機会の確認を含めてもよい。
4.2 計画作成
4.2.1 一般
一度、アセスメントを実行することが合意されたら計画を作成するのがよい。計画にはアセスメントの目的、範囲及び基準を定め、合意すること、並びに、アセスメント計画を作成することが含まれる。
4.2.2 アセスメントの目的
アセスメントは、依頼者によって定められた目的を考慮する必要がある。EASOの目的には、次のようなものを含めてもよい。
−用地及び/又は組織に関連する環境側面及び環境事項についての情報を明確にし、収集し、評価すること、並びに、要望がある場合には、
−用地及び/又は組織に関連する環境事項の事業への影響を決定すること
4.2.3 アセスメントの範囲
アセスメントの範囲は、アセスメントの境界と焦点を定めるものである。依頼者の裁量によって、この範囲には事業への影響の決定を含めても、また含めなくともよい。
アセスメントの範囲を決める際には、次の各項を考慮するとよい。
− アセスメントの対象となる環境側面の種類
− 他の用地や組織が被評価側に及ばす可能性のある環境影響
− 被評価側の物理的境界(例えば、用地、用地の一部)
− 該当する場合は、隣接及び近隣の用地
− 請負契約者、供給者、組織(例えは、敷地外の廃棄物処理組織)及び個人並びに前の占有者との関係や、これらにかかわる活動などの組織面の境界
− 対象となる期間(例えば、過去、現在及び/又は将来)
−被評価側及び/又は依頼者の活動(例えば、現行事業の継続、変更・拡張・解体・撤廃・改造の諸計画)に関する期間
−基準(4.2.4参照)の作成に関する期間
− もし、該当する場合は、事業への影響費用の限度額
この範囲は、アセスメントに含まれる関連用地や組織を定め、限定してもよい.依頼者の裁量によって、アセスメントが開始された後でもアセスメントの範囲を修正してもよい.そのような変更は記録し、関係者に連絡することが望ましい。
依頼者は、定められたアセスメントの範囲内で、アセスメント中に優先的に扱われる事項を明確にしてもよい.優先事項は、アセスメントを計画している間に利用可能な情報をもとに確定されることが多い。優先事項の明確化を行っても、評価者がアセスメント中に範囲全体を考慮するという義務を免除するものではない。
4.2.4 アセスメント基準
収集した情報を評価する基準を明確にすることが望ましい。基準には次の事項を含めるとよいが、これに限定されるものではない。
−現在適用されまた、合理的に予見される、法律上の要求事項(例えば、同意、許可、環境法、規則、規制方針)
−その他依頼者が定めた環境関連要求事項(例えば、組織の方針及び手順、特定の環境条件、マネジメント慣習、システム及びパフォーマンスの要求事項、業界並びにその業種に適用される慣習や綱領)
−利害関係のある第三者(例えば、保険会社、金融機関〉の要求事項、要請事項又は潜在的な要請事項
−技術的配慮事項
4.2.5 アセスメント計画
該当する場合、アセスメント計画には、次の事項を含めるとよい。
− アセスメントの目的及び範囲
− 依頼者、被評価側の代表者及び評価者を特定する情報
− アセスメント基準
− 優先的アセスメント領域
− 役割及び責任
− アセスメント及び関連報告書の使用言語
− 日程及び期間を含むアセスメントスケジュール
− 必要な資源(例えば、人員、予算、技術)
− 使用するアセスメント手順の概略
− 使用する備考文書、チェックリスト及び手順書並びに作業文書の要約
− 報告要求事項
− 秘密保持についての要求事項
アセスメントに影響するかもしれない制約事項を、アセスメント計画の中で特定してもよい。想定される制約事項には次のものがある。
− アセスメントに利用可能な時間
− アセスメントに利用可能な資源
− 関連地域への立ち入り
− 利用可能な情報
− 関係者との相互連絡又は関連文書の入手
依頼者は、アセスメント計画を検討し、承認することが望ましい。この計画は、もし必要であるなら、被評価側の代表者に通知することが望ましい。
4.3 情報収集及び妥当性確認
4.3.1 一般
アセスメントは、既存文書や記録の検討(用地視察の前及び用地視察中の両方)、活動や物理的状態の観察、そして、面接調査を通じて収集され妥当性確認がなされた環境側面についての情報をもとに行われる。−以下略−
アセスメントに必要とされ得る情報の種類を実践の手引き?に例示する。
実践の手引き? EASOにおいて考慮対称なり得る情報例
− 立地
− 物理的特性(例えば、水文地質学)
− 評価対象地、隣接地及び近隣地 − 用地利用
− 施設、工程及び操業
− 用地の浸食され易さ
− 原材料、副生成物及び製品(有害物を含む)
− 資材の保管及び取扱い
− 大気、水系、土壌への排出及び放出
− 廃棄物の保管、取扱い、処分
− 防災・消火、漏洩防止及びその他の緊急事態対処計画
− 暴風洪水
− 労働及び公衆の安全衛生
− 法的要求事項、組織内及びその他の要求事項、不遵守及び不適合
− 部外者との関係
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また、
他の事項が適用される場合もある。
4.3.2 既存文書及び記録の検査
評価者は、これまでの調査活動と不必要に重複することなく、用地及び/又は組織についての充分な理解を得て、文書及び記録を収集し検討することが望ましい。考慮しうる文書及び記録の例を実践の手引き?に示す。−以下略−
実践の手引き? EASOにおいて考慮されうる文書及び情報源
文 書 情 報 源
− 地図、計画書、写真
− 過去の履歴
− 地質学/水文地質学上の記録
− 地質工学に関する記録
− 出荷記録/取扱い記録
− 安全データ・シート(MSDS:物質安全性データシート)
− 作業指示書
− モニタリング手順及び結果
− 工程に関する文書(例えば、物質収支)
− 保全記録
− 在庫目録
外部
− 政府機関(国、地方規制当局、計画部局)
− 保管文書
− 公益団体
− 商業出版物
−業界行動綱領
−緊急サービス− 保険会社
内部
− 環境、保健衛生、安全部門
− 公式登記・記録(例えば、埋立て、汚染地)
− 緊急対処及びその他対応計画
− 保健衛生、安全及び環境に関する訓練記録
− 事故記録
− 許可書/免許証/通知書
− 組織図(業務と責任)
− 監査及びその他報告書
− 不遵守及び不適合記録
− 苦情
− 組織の方針、計画、マネジメントシステム
− 保険上の要求事項
− 供給業者他の部外者との契約
− その他の訓練記録
− 生産技術部門
− 製造部門
− 購買部門
− 研究開発部門
− 資産管理部門
− 施設管理部門
− 教育・訓練部門
− 法務部門
− 財務会計部門
− 広報部門
− 人事部門
− 医務部門
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また他の事項が適用される場合もある
4.3.3 活動及び物理的状態の観察
評価者は、過去の活動及び操業による用地又は組織の物理的状態に関する情報を観察し、記録することが望ましい。観察対象となりうる用地内外の要素についての例を、実践の手引き?に示す。−以下略−
実践の手引き? EASOにおいて観察されうる要素の例
活動
− 廃棄物管理
− 資材及び製品の取扱い
− 工程の管理
− 排水の管理
− 大気排出管理
− 水系への排出
− 用地利用
物理的条件
− 排水処理設備及び下水システム
− 冷暖房システム
− 配管及び通気孔
− 格納容器.排水路、及び排水だめ
− 貯蔵容器/タンク
− 公益事業体からの供給
− 騒音、光、振動又は熱
− 臭気、塵埃、煤煙、微小粒子
− 地表水及び用地の地形
− 用地の周辺及び隣接地並びに組織
− 土壌及び地下水の状態
− 着色した又は変色した表面
− 影響を受けている動植物
− 理立て
− 建物、工場及び装置類
− 資材の保管
− 有害な資材、製品、物質
− 防火設備及び緊急事態対処設備
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また他の事項が適用される場合もある。
4.3.4 面接調査−省略−
4.4 評価
4.4.1 一般
妥当性がなされた環境側面に関する情報は、評価プロセスにインプットされる資料となる。このプロセスは、図(3−1−2)に示すように、環境事項の明確化と事業への影響の決定という二段階から成る。これら二つの段階は、依頼者の裁量によって、別々の主体が実施してもよく、これは、特に依頼者が事業の影響を決定するために、他の専門技能(例えば、技術的、法律的や財務的)を必要とする場合が該当する。
図(3−1−2)評価プロセス

備考 括弧内の数字はこの国際規格の項目番号を参照している。破線は、この国際規格に記述されているように、事業への影響を決定することがEASOの必須の部分ではないことを示す。
4.4.2 環境事項の明確化
環境事項を明確にするために、環境側面に関する妥当性確認が行われた情報を、選定した基準と比較する.妥当性確認がなされた情報が、選定した基準から外れている場合に環境事項が明確になり、次のような結果を導く場合がある。
− 組繊にとっての責任又は便益
− 被評価側又は依頼者の社会的イメージヘの影響
− その他の費用
事業からみて、関連が肴薄である事項も環境上は関連があるかも知れないし、その逆もあり得る。
この段階を経た結果、依頼者に関連する環境事項が明確にされる。
4.4.3 事業への影響の決定
事業への影響の決定は、これがアセスメントの目的及び範囲に含まれている場合にのみ実施される。
事業への影響は、明確化され評価された環境事項の実際の又は潜在的な影響(財務的とそれ以外、好ましい又は好ましくない、定性的又は定量的)である。
この評価には.一般にEASOの目的にかかわる環境事項の及ぼす影響について判断が含まれる。この段階で、事業への影響に対処するための費用が見積られ被評価側又は依頼者の社会的イメージに対する影響についても明確にされ、評価される。
この判断に当たっては、次の事項が考慮される。
− 緩和措置又は是正、回避又は防止する対策が実際にもたらす若しくはもたらすかもしれない結果
− 環境損害
− 例えば、法律及び他の関連要求事項の現在並びに予想される変更に対する不遵守の結果生ずる現在又は将来の(公法上及び私法上の)責任
− 被評価側及び/又は依頼者の社会的イメージヘの打撃
− 依頼者若しくは被評価側の企業方針又は他の依頼者が定めた要求事項に対する不適合
− 上記の措置又は対策をとる場合の見積り額
− 技術開発
− 諸々の費用支出をしなければならない期間(例えば、執行措置又は新しい法律の制定の可能性に関連した期間)
情報が十分でないため結論が限定される場合は、それを表明する必要があり、また、いかなる見解もそれに応じて性格付けすることが望ましい。
評価プロセスのこの部分の結果として、事業への影響のリストが作成され、適当な場合には定量化される。
5 報告作成
5.2報告内容
評価者は報告書の内容に対して責任を有し、依頼者が認定事実の重要性を理解できるように工夫した方法で情報を提供することが望ましい。これを行うために、評価者は事実と意見を区別し、認定事実の根拠を明確に特定し、また、認定事実に関する相対的不確実性を指摘することが望ましい。
次に示す情報を依頼者に報告することが望ましい。
− 評価した用地及び/又は組織を特定する情報
− 評価者及び報告書作成者の氏名
− アセスメントの目的、範囲及び基準
− アセスメントの日時及び期間
− 利用可能な情報の制約事項及びそれらのアセスメントに対する影響
− 制約事項、除外事項、修正事項及び合意したアセスメントの範囲からの逸脱
− アセスメントの間に収集した情報の要約及びアセスメントの結果
依頼者と評価者の問の合意に従って、次に示す情報も依頼者に報告してもよい。
− 依頼者の氏名
− 被評価側代表者の氏名
− アセスメントチームのメンバーを特定する情報
− アセスメントスケジュール
− 使用したアセスメント手順の要約
− 使用した備考文書、チェックリスト及び手順書並びにその他作業文書の要約
− 評価方法、及び評価の根拠
− 評価者によって実施されたのであれば、その評価の結果
− 想定される次の段階に関する推奨事項
− 秘密保持に関する要求事項
− 結論
EASO報告書の目次の例を実践の手引き?に示す。
アセスメントの範囲で明示されている場合は、報告書に記述された認定事実を補強し、後日又は他の関係者によってアセスメントの再評価ができるように、備考文献や重要な情報を含む十分な文書類を、報告書に入れておくことが望ましい。評価者は、制約が存在する見解について性格付けをすることが望ましい。例えば情報が不十分な場合がそれに該当する。
5.2 報告書様式
依頼者の優先事項についての意向又はその他の取り決めによって、口頭による報告のみが求められることがある。それ以外の場合には、報告は文書によって行うことが望ましい。
実践の手引き? EASO報告書の目次例
a)要約
b) 序文
一 依頼者の氏名
一 被評価用地又は組織
一 被評価側の代表者の氏名
一 評価者の氏名
− アセスメントの日時及び期間
c)目的及び範囲
一 依頼者の指示事項
一 用地及び組織の境界
d)アセスメント基準
e)アセスメントプロセス
f) 情報
一 情報源
一 制約事項及びその予想される影響
一 要約
g) 結論
一 環境事項
一 事業への影響
付録
5.3 報告書の配布
報告書は依頼者の専有財産である。したがって、評価者及び報告書受領者は秘密保持を尊重し、適切な防護措置を取ることが望ましい。報告書の配布は、依頼者の裁量によるものであり、その中には、被評価側に報告書の写しを提供することを含めてもよい。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/004/attached/attach_4328_7.pdf
Environmental assessment of sites and organizations(EASO):ISO14015
環境マネジメント規格である用地及び組織の環境アセスメント(EASO)は、2001年11月に国際規格(IS)され、現在、日本工業規格(JIS)化の準備が進んでいる。
この規格は、1993年国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント専門委員会(TC207)、環境監査部会(SC2)において新業務項目が提案され、1997年の開発決定から4年間をかけて国際規格化されたものである。
EASOの規格の構成は、次の内容であり本項では、規格原文の表示番号で順を追って紹介する。
0 序文
1 適用範囲
2 用語及び定義
3 役割及び責任
4 アセスメント手順
5 報告
0 序文
組織は、自らの用地及び活動にかかわる環境事項又は起こり得る取得に伴う環境事項を理解することに一層関心を寄せつつある。これらの事項とそれらに関連する事業への影響は、用地及び組織の環境アセスメント(EASO)によって査定することができる。このようなアセスメントは、操業中でも、また、資産取得又は資産分割時においても実施されるし、しばしばデューディリジェンス(Due Diligence)と言われる、より広範な事業評価プロセスの一部として実施されることもある。
この国際規格は、EASOを実施する方法についての指針を提供する.また、この国際規格は、環境アセスメント実施のために、使用する用語の整合を図り、体系化され首尾一貫した、透明性の高い、かつ、客観的なアプローチの基礎を提供する。さらに、この国際規格は、中小企業を含む世界中のあらゆる場所で活動している組織が使用することができる。この国際規格は、適用の方法に柔軟性があり、第三者を雇用する必要性がある場合とそうでない場合があるが自己アセスメントのためにも、また、外部アセスメントにも使用することができる.この国際規格の利用者は、産業界や、過去、現在そしておそらくは将来における特定用地の使用者や、産業界や用地に財務的利害を有する組織(例えば、銀行、保険会社、投資家、土地所有者〉であると期待される。この国際規格は、責任と義務の移譲が行われるときに利用されるであろう。
EASOにおいて使用される情報は、環境マネジメントシステム監査、遵法監査、環境影響アセスメント、環境パフォーマンス評価又は用地調査を含む情報源から入手される。これらのアセスメント又は調査の一部は、他の関連規格(例えば、lSO14001、lS014011又はlSO14031)を使用して、実行されていたかもしれない。
既存の情報と新たに得られた情報の両方を評価するプロセスを通じて、EASOは、環境側面及び環境事項にかかわる事業への影響について結論を導き出そうとするものである。
EASOの結論は客観的情報に基く必要がある。妥当性確認がなされた情報がない場合には、利用可能な環境情報を評価し結論を導き出す際に、EASO評価者には専門的判断を下すことが求められることがある。
この国際規格は、実地探査又は用地浄化の指針を提供するものではない。しかしながら、依頼者から要求があった場合には、それらは他の規格又は手順に従って実施されることとなろう。
1 適用範囲
この国際規格は、環境側面及び環境事項を明確化し、必要に応じて事業へのそれらの影響を決定する指針を提供する。
この国際規格は、アセスメントに関係する当事者(依頼者、評価者及び被評価側の代表者)の役割と責任、及び評価プロセスの諸段階(計画作成、情報収集及び妥当性確認、評価及び報告作成)を規定する.EASOを実施するプロセスを図(3−1−1)に示す。
この国際規格は、次に示すような環境アセスメントの実施方法についての指針を提供するものではない。
a) 初期環境レビュー
b) 環境監査(環境マネジメントシステム及び遵法監査を含む)
c) 環境影響アセスメント、又は
d) 環境パフォーマンス評価
実地探査又は及び用地浄化は、この国際規格の適用範囲外である。同様に、これらを遂行するか否かを決定することも適用範囲外である。
この国際規格は、認証又は審査登録目的の仕様規格として使用したり、又は環境マネジメントシステム要求事項の確立を意図したものではない。
この国際規格を利用しても、依頼者や被評価側に他の規格や法規が課せられることにはならない。
図(3−1−1)用地及び組織の環境アセスメントを実施するプロセス

備考 括弧内の数字はこの国際規格の章節を参照している。破線はこの国際規格に記述されているよう
に(3.2 備考参照)被評価側はEASOに必ずしもかかわらないことがあることをしめす。
2 用語及び定義
この国際規格では、次に示す定義を適用する。
(本項では、ISO14001等の他の規格に定義があるものは除いている。)
2.1 被評価側
アセスメントを受ける用地又は組織
2.2 評価者
十分な能力を有し、所定のアセスメントを実施するため、又はそれに参画するために指名された者
備考 評価者は.アセスメントを行う組繊の内部又は外部の人間であってもよい.また、すべての関連項目に適切に対処することを確実にするために、例えば、特殊な専門領域を必要とする場合には、複数の評価者を必要とすることがある.
2.3 事業への影響
明確化し、評価された環境事項の現実の又は起こり得る影響(財務的又はそれ以外、好ましい又は好ましくない、定性的又は定量的)
2.4 依頼者
アセスメントを委託する組織
例 依頼者は用地の所有者、被評価側、又はその他の者であってよい。
2.7 用地及び組織の環境アセスメント(EASO)
過去、現在、及び予測可能な将来の活動の結果である用地や組織にかかわる環境側面を客観的に明確にし、環境事項を明確にし、その事業への影響を決定するプロセス
備考 事業への影響を決定することは任意であり、依頼者の裁量による。
2.9 環境事項
環境側面に関する妥当性確認が行われた情報が、選択された基準から外れ、かつ、責任又は便益、被評価側又は依頼者例の社会的イメージに対する影響、若しくはその他の費用をもたらす可能性のある事項
2.11 実地探査
機器を使用し、物理的干渉を必要とする場合もある試料採取及び試験
2.13 被評価側の代表者
被評価側を代表する権限を有する者
2.14 用地
地理学上の境界が定められ、そこにおいて組織の管理下での活動が実行できるとされた立地
備考 地理学上の境界は、地上又は水中にあり、天然又は人工いずれの表面構造物の上又は下を含む。
2.15 妥当性確認
アセスメントの目的に照らして、収集したされた情報が正確であり信頼性が高く、十分かつ適切であることを、評価者が決定するプロセス
3 役割及び責任
3.1 依頼者
依頼者の活動には、次に示す各項を含むとよい。
a) アセスメントの必要性を決定する
b) アセスメントの目的を明確にする
c) もし必要とするなら評価者と協議してアセスメントの範囲と基準を決定する
d) 評価者を選任する
e) 評価者に指示を与える
f) アセスメント(計画作成、情報収集及び妥当性確認、評価及び報告作成)のどの部分が評価者によって実施され、どの部分が依頼者の責任であるのかを決定する:この場合、他の専門家を特定し、組み入れることを要求してもよい
g) もし必要とするなら、優先順位の高いアセスメント分野を特定して決定する
h) もし必要があるなら、被評価側の代表者に接触し、全面的な協力を得てプロセスを開始する
i) アセスメント計画を承認する
j) アセスメントを実行するのにふさわしい権限と資源を提供する
k) アセスメントを実行するのに必要な情報を評価者に提供する
l) 評価者からのアセスメント結果を受領し、配布先を決定する
依頼者は、第三者に対するアセスメント結果を開示する場合、事前に、被評価側の代表者に通知するかどうかを決定することが望ましい。
備考 依頼者、評価者及び被評価側の代表者が、同一組織体であってもよい。
3.2 被評価側の代表者
被評価側の代表者の役割と責任には次の事項を含むとよい。
a)アセスメントの目的に合せて関連区域への立ち入りを認め、情報を提供する
b) アセスメントプロセスについて関連の従業員や他の関係者に通知する
c) 面接調査対象者を用意する、又は、用意するのを支援する
d)要請があれば、アセスメントプロセスを支援する要員を提供する、及び、
e)評価者のために安全な作業環境を提供する
依頼者の裁量によって、被評価側の代表者はアセスメントの範囲とアセスメント計画の決定に参画し、また、当該アセスメントの結果を受領してもよい。
被評価側の代表者への告知なしにアセスメントが行なわれる場合、又は、用地及び/又は組織の責任者を特定できない場合、被評価側の代表者の役割は適用されない。
3.3 評価者
評価者と監査者との役割と責任は見方によっては異なっている。監査者は定めた基準に対して既存の情報を検証するのに対して、評価者は更に新たな情報を収集し、事業への影響を決定するために情報を評価することがしばしば要求される。
用地及び組織の環境アセスメントを実施するに際して、評価者は、類似の状況においてすべての評価者に期待される勤勉さ、知識、技能及び判断を行使する必要がある。評価者は、思慮分別を働かせ、また、法律又は他の規則によって別段の行動が求められる場合を除いて、機密を保持することが望ましい。
評価者又は複数の評価者が関与する場合はそのチームリーダーの責任と活動には、次に示す事項を含むとよい。
a) 要請があれば依頼者を支援して、アセスメントの目的、範囲(優先的アセスメント分野の明確化及び決定を含む)、基準を決定する
b) 報告作成の方法及び書式を依頼者と取り決める
c) アセスメント計画を立案し、依頼者の承認、及び、もし必要とするなら被評価側の代表者の承認を得る
d) チェックリストや手順書のような作業文書を作成し、維持する
e) アセスメントの目的に合致する必要な技能が利用可能であるようにし、また、もし必要とするならアセスメントチームを編成する
f) アセスメントチームについて依頼者の承認を得る
g) 初期情報を得る
h) アセスメントの各部を実行するに当たり、アセスメントチームのメンバーに作業を割り当てる
i) アセスメントの計画に沿って情報を収集し、その妥当性確認をする
j) 環境事項を明確にし、評価する
k) 依頼者からの要請があれば、事業への影響を決定する
l) 依頼者からの要請があれば、依頼者への報告書を作成し、それを依頼者に提供する
この国際規格は評価者の能力及び資格要件に関する指針を提供するものではない。しかしながら、環境アセスメントを実施遂行するには次に示す事項を充足することが要請される。
− 十分な教育
− 十分な訓練
− 十分な関連する業務経験
同様に、次に示す知識及び能力
− 関連法律、規則及び関連の文書
− 環境科学及び技術
− 経済及び関連の事業分野
− (商業的)活動に関する運転の技術的及び環境的側面
− 設備運転
− アセスメント技術
4.アセスメント手順
4.1 一般
アセスメントプロセスには、アセスメントの計画作成、情報の収集及び妥当性確認、情報の評価、並びにアセスメントの報告作成を含む。
このプロセスには、依頼者から特に要請された場合には、事業機会の確認を含めてもよい。
4.2 計画作成
4.2.1 一般
一度、アセスメントを実行することが合意されたら計画を作成するのがよい。計画にはアセスメントの目的、範囲及び基準を定め、合意すること、並びに、アセスメント計画を作成することが含まれる。
4.2.2 アセスメントの目的
アセスメントは、依頼者によって定められた目的を考慮する必要がある。EASOの目的には、次のようなものを含めてもよい。
−用地及び/又は組織に関連する環境側面及び環境事項についての情報を明確にし、収集し、評価すること、並びに、要望がある場合には、
−用地及び/又は組織に関連する環境事項の事業への影響を決定すること
4.2.3 アセスメントの範囲
アセスメントの範囲は、アセスメントの境界と焦点を定めるものである。依頼者の裁量によって、この範囲には事業への影響の決定を含めても、また含めなくともよい。
アセスメントの範囲を決める際には、次の各項を考慮するとよい。
− アセスメントの対象となる環境側面の種類
− 他の用地や組織が被評価側に及ばす可能性のある環境影響
− 被評価側の物理的境界(例えば、用地、用地の一部)
− 該当する場合は、隣接及び近隣の用地
− 請負契約者、供給者、組織(例えは、敷地外の廃棄物処理組織)及び個人並びに前の占有者との関係や、これらにかかわる活動などの組織面の境界
− 対象となる期間(例えば、過去、現在及び/又は将来)
−被評価側及び/又は依頼者の活動(例えば、現行事業の継続、変更・拡張・解体・撤廃・改造の諸計画)に関する期間
−基準(4.2.4参照)の作成に関する期間
− もし、該当する場合は、事業への影響費用の限度額
この範囲は、アセスメントに含まれる関連用地や組織を定め、限定してもよい.依頼者の裁量によって、アセスメントが開始された後でもアセスメントの範囲を修正してもよい.そのような変更は記録し、関係者に連絡することが望ましい。
依頼者は、定められたアセスメントの範囲内で、アセスメント中に優先的に扱われる事項を明確にしてもよい.優先事項は、アセスメントを計画している間に利用可能な情報をもとに確定されることが多い。優先事項の明確化を行っても、評価者がアセスメント中に範囲全体を考慮するという義務を免除するものではない。
4.2.4 アセスメント基準
収集した情報を評価する基準を明確にすることが望ましい。基準には次の事項を含めるとよいが、これに限定されるものではない。
−現在適用されまた、合理的に予見される、法律上の要求事項(例えば、同意、許可、環境法、規則、規制方針)
−その他依頼者が定めた環境関連要求事項(例えば、組織の方針及び手順、特定の環境条件、マネジメント慣習、システム及びパフォーマンスの要求事項、業界並びにその業種に適用される慣習や綱領)
−利害関係のある第三者(例えば、保険会社、金融機関〉の要求事項、要請事項又は潜在的な要請事項
−技術的配慮事項
4.2.5 アセスメント計画
該当する場合、アセスメント計画には、次の事項を含めるとよい。
− アセスメントの目的及び範囲
− 依頼者、被評価側の代表者及び評価者を特定する情報
− アセスメント基準
− 優先的アセスメント領域
− 役割及び責任
− アセスメント及び関連報告書の使用言語
− 日程及び期間を含むアセスメントスケジュール
− 必要な資源(例えば、人員、予算、技術)
− 使用するアセスメント手順の概略
− 使用する備考文書、チェックリスト及び手順書並びに作業文書の要約
− 報告要求事項
− 秘密保持についての要求事項
アセスメントに影響するかもしれない制約事項を、アセスメント計画の中で特定してもよい。想定される制約事項には次のものがある。
− アセスメントに利用可能な時間
− アセスメントに利用可能な資源
− 関連地域への立ち入り
− 利用可能な情報
− 関係者との相互連絡又は関連文書の入手
依頼者は、アセスメント計画を検討し、承認することが望ましい。この計画は、もし必要であるなら、被評価側の代表者に通知することが望ましい。
4.3 情報収集及び妥当性確認
4.3.1 一般
アセスメントは、既存文書や記録の検討(用地視察の前及び用地視察中の両方)、活動や物理的状態の観察、そして、面接調査を通じて収集され妥当性確認がなされた環境側面についての情報をもとに行われる。−以下略−
アセスメントに必要とされ得る情報の種類を実践の手引き?に例示する。
実践の手引き? EASOにおいて考慮対称なり得る情報例
− 立地
− 物理的特性(例えば、水文地質学)
− 評価対象地、隣接地及び近隣地 − 用地利用
− 施設、工程及び操業
− 用地の浸食され易さ
− 原材料、副生成物及び製品(有害物を含む)
− 資材の保管及び取扱い
− 大気、水系、土壌への排出及び放出
− 廃棄物の保管、取扱い、処分
− 防災・消火、漏洩防止及びその他の緊急事態対処計画
− 暴風洪水
− 労働及び公衆の安全衛生
− 法的要求事項、組織内及びその他の要求事項、不遵守及び不適合
− 部外者との関係
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また、
他の事項が適用される場合もある。
4.3.2 既存文書及び記録の検査
評価者は、これまでの調査活動と不必要に重複することなく、用地及び/又は組織についての充分な理解を得て、文書及び記録を収集し検討することが望ましい。考慮しうる文書及び記録の例を実践の手引き?に示す。−以下略−
実践の手引き? EASOにおいて考慮されうる文書及び情報源
文 書 情 報 源
− 地図、計画書、写真
− 過去の履歴
− 地質学/水文地質学上の記録
− 地質工学に関する記録
− 出荷記録/取扱い記録
− 安全データ・シート(MSDS:物質安全性データシート)
− 作業指示書
− モニタリング手順及び結果
− 工程に関する文書(例えば、物質収支)
− 保全記録
− 在庫目録
外部
− 政府機関(国、地方規制当局、計画部局)
− 保管文書
− 公益団体
− 商業出版物
−業界行動綱領
−緊急サービス− 保険会社
内部
− 環境、保健衛生、安全部門
− 公式登記・記録(例えば、埋立て、汚染地)
− 緊急対処及びその他対応計画
− 保健衛生、安全及び環境に関する訓練記録
− 事故記録
− 許可書/免許証/通知書
− 組織図(業務と責任)
− 監査及びその他報告書
− 不遵守及び不適合記録
− 苦情
− 組織の方針、計画、マネジメントシステム
− 保険上の要求事項
− 供給業者他の部外者との契約
− その他の訓練記録
− 生産技術部門
− 製造部門
− 購買部門
− 研究開発部門
− 資産管理部門
− 施設管理部門
− 教育・訓練部門
− 法務部門
− 財務会計部門
− 広報部門
− 人事部門
− 医務部門
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また他の事項が適用される場合もある
4.3.3 活動及び物理的状態の観察
評価者は、過去の活動及び操業による用地又は組織の物理的状態に関する情報を観察し、記録することが望ましい。観察対象となりうる用地内外の要素についての例を、実践の手引き?に示す。−以下略−
実践の手引き? EASOにおいて観察されうる要素の例
活動
− 廃棄物管理
− 資材及び製品の取扱い
− 工程の管理
− 排水の管理
− 大気排出管理
− 水系への排出
− 用地利用
物理的条件
− 排水処理設備及び下水システム
− 冷暖房システム
− 配管及び通気孔
− 格納容器.排水路、及び排水だめ
− 貯蔵容器/タンク
− 公益事業体からの供給
− 騒音、光、振動又は熱
− 臭気、塵埃、煤煙、微小粒子
− 地表水及び用地の地形
− 用地の周辺及び隣接地並びに組織
− 土壌及び地下水の状態
− 着色した又は変色した表面
− 影響を受けている動植物
− 理立て
− 建物、工場及び装置類
− 資材の保管
− 有害な資材、製品、物質
− 防火設備及び緊急事態対処設備
これらすべてが、あらゆる用地や組織において考慮されるわけではなく、また他の事項が適用される場合もある。
4.3.4 面接調査−省略−
4.4 評価
4.4.1 一般
妥当性がなされた環境側面に関する情報は、評価プロセスにインプットされる資料となる。このプロセスは、図(3−1−2)に示すように、環境事項の明確化と事業への影響の決定という二段階から成る。これら二つの段階は、依頼者の裁量によって、別々の主体が実施してもよく、これは、特に依頼者が事業の影響を決定するために、他の専門技能(例えば、技術的、法律的や財務的)を必要とする場合が該当する。
図(3−1−2)評価プロセス

備考 括弧内の数字はこの国際規格の項目番号を参照している。破線は、この国際規格に記述されているように、事業への影響を決定することがEASOの必須の部分ではないことを示す。
4.4.2 環境事項の明確化
環境事項を明確にするために、環境側面に関する妥当性確認が行われた情報を、選定した基準と比較する.妥当性確認がなされた情報が、選定した基準から外れている場合に環境事項が明確になり、次のような結果を導く場合がある。
− 組繊にとっての責任又は便益
− 被評価側又は依頼者の社会的イメージヘの影響
− その他の費用
事業からみて、関連が肴薄である事項も環境上は関連があるかも知れないし、その逆もあり得る。
この段階を経た結果、依頼者に関連する環境事項が明確にされる。
4.4.3 事業への影響の決定
事業への影響の決定は、これがアセスメントの目的及び範囲に含まれている場合にのみ実施される。
事業への影響は、明確化され評価された環境事項の実際の又は潜在的な影響(財務的とそれ以外、好ましい又は好ましくない、定性的又は定量的)である。
この評価には.一般にEASOの目的にかかわる環境事項の及ぼす影響について判断が含まれる。この段階で、事業への影響に対処するための費用が見積られ被評価側又は依頼者の社会的イメージに対する影響についても明確にされ、評価される。
この判断に当たっては、次の事項が考慮される。
− 緩和措置又は是正、回避又は防止する対策が実際にもたらす若しくはもたらすかもしれない結果
− 環境損害
− 例えば、法律及び他の関連要求事項の現在並びに予想される変更に対する不遵守の結果生ずる現在又は将来の(公法上及び私法上の)責任
− 被評価側及び/又は依頼者の社会的イメージヘの打撃
− 依頼者若しくは被評価側の企業方針又は他の依頼者が定めた要求事項に対する不適合
− 上記の措置又は対策をとる場合の見積り額
− 技術開発
− 諸々の費用支出をしなければならない期間(例えば、執行措置又は新しい法律の制定の可能性に関連した期間)
情報が十分でないため結論が限定される場合は、それを表明する必要があり、また、いかなる見解もそれに応じて性格付けすることが望ましい。
評価プロセスのこの部分の結果として、事業への影響のリストが作成され、適当な場合には定量化される。
5 報告作成
5.2報告内容
評価者は報告書の内容に対して責任を有し、依頼者が認定事実の重要性を理解できるように工夫した方法で情報を提供することが望ましい。これを行うために、評価者は事実と意見を区別し、認定事実の根拠を明確に特定し、また、認定事実に関する相対的不確実性を指摘することが望ましい。
次に示す情報を依頼者に報告することが望ましい。
− 評価した用地及び/又は組織を特定する情報
− 評価者及び報告書作成者の氏名
− アセスメントの目的、範囲及び基準
− アセスメントの日時及び期間
− 利用可能な情報の制約事項及びそれらのアセスメントに対する影響
− 制約事項、除外事項、修正事項及び合意したアセスメントの範囲からの逸脱
− アセスメントの間に収集した情報の要約及びアセスメントの結果
依頼者と評価者の問の合意に従って、次に示す情報も依頼者に報告してもよい。
− 依頼者の氏名
− 被評価側代表者の氏名
− アセスメントチームのメンバーを特定する情報
− アセスメントスケジュール
− 使用したアセスメント手順の要約
− 使用した備考文書、チェックリスト及び手順書並びにその他作業文書の要約
− 評価方法、及び評価の根拠
− 評価者によって実施されたのであれば、その評価の結果
− 想定される次の段階に関する推奨事項
− 秘密保持に関する要求事項
− 結論
EASO報告書の目次の例を実践の手引き?に示す。
アセスメントの範囲で明示されている場合は、報告書に記述された認定事実を補強し、後日又は他の関係者によってアセスメントの再評価ができるように、備考文献や重要な情報を含む十分な文書類を、報告書に入れておくことが望ましい。評価者は、制約が存在する見解について性格付けをすることが望ましい。例えば情報が不十分な場合がそれに該当する。
5.2 報告書様式
依頼者の優先事項についての意向又はその他の取り決めによって、口頭による報告のみが求められることがある。それ以外の場合には、報告は文書によって行うことが望ましい。
実践の手引き? EASO報告書の目次例
a)要約
b) 序文
一 依頼者の氏名
一 被評価用地又は組織
一 被評価側の代表者の氏名
一 評価者の氏名
− アセスメントの日時及び期間
c)目的及び範囲
一 依頼者の指示事項
一 用地及び組織の境界
d)アセスメント基準
e)アセスメントプロセス
f) 情報
一 情報源
一 制約事項及びその予想される影響
一 要約
g) 結論
一 環境事項
一 事業への影響
付録
5.3 報告書の配布
報告書は依頼者の専有財産である。したがって、評価者及び報告書受領者は秘密保持を尊重し、適切な防護措置を取ることが望ましい。報告書の配布は、依頼者の裁量によるものであり、その中には、被評価側に報告書の写しを提供することを含めてもよい。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/004/attached/attach_4328_7.pdf
2009年12月12日
ISO14000 規格
ISO 14001 環境マネジメントシステム要求事項
4.1 一般要求事
4.2 環境方針
4.3 計画
4.3.1 環境側面
4.3.2 法的及びその他の要求事項
4.3.3 目的、目標及び実施計画
4.4 実施及び運用
4.4.1 資源、役割、責任及び権限
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
4.4.3 コミュニケーション
4.4.4 文書類
4.4.5 文書管理
4.4.6 運用管理
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
4.5 点検
4.5.1 監視及び測定
4.5.2 順守評価
4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置
4.5.4 記録の管理
4.5.5 内部監査
4.6 マネジメントレビュー
http://www.jisc.go.jp/mss/ems-14001.html
--------------------------------------------------------------------------------
4.1一般要求事項
・ 組織は環境マネジメントシステムを確立し維持しなければならない。その要求事項は、この4.全体で述べる。
--------------------------------------------------------------------------------
4.2 環 境 方 針
・ 最高経営層は組織の環境方針を定め、その方針について次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の活動、製品又はサービスの性質、規模及び環境影響に対して適切である。
b)継続的改善及び汚染の予防の関する約束を含む。
c)関連する環境法規、及び組織が同意する他の要求事項を遵守する約束を含む。
d)環境目的及び目標を設定し、見直しの枠組みを与える。
e)文書化され、実行され、維持されかつ全従業員に周知される。
f)一般の人が入手可能である。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3 計 画
4.3.1 環境側面
・ 組織は著しい環境影響を持つか、又は持ちうる環境側面を決定するために、・ 組織が管理でき、かつ影響を生じると思われる活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は環境目的設定に際して、この著しい影響に関連する側面を確実に配慮しなければならない。
・ 組織はこの情報を常に最新のものとしなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 法的及びその他の要求事項
・ 組織は、その活動、製品またはサービスの環境側面に適用可能な法的要求事項及び組織は同意するその他の要求事項を特定し参照できるような手順を確立し維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.3 目的、目標
・ 組織は組織内の関連する各部門、各階層で文書化された環境目的、及び目標を設定し維持しなければならない。
・ その目的を設定し見直しをするときに、組織は法的及びその他の要求事項、著しい環境側面、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解に配慮しなければならない。
・ 目的、及び目標は汚染予防に関する約束を含め、環境方針と整合させなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.4 環境マネジメントプログラム
・ 組織はその目的及び目標を達成するためにプログラムを策定し維持しなければならない。
・プログラムには次の事項を含まなければならない。
a)組織の関係する、各部門、各階層における、目的、目標を達成するための責任の明示。
b)目的及び、目標を達成するための手段、及び日程
・ プロジェクトが新規開発及び新規若しくは変更された活動、製品又はサービスに関する場合には環境マネジメントが、そのようなプロジェクトにも確実に適用されるようにプログラムの該当部分を改訂しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4実施及び運用
4.4.1体制及び責任
・ 効果的な環境マネジメントを実施するために、役割、責任及び権限を定め文書化し、かつ伝達しなければならない。
・ 経営層は、環境マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な資源を用意しなければならない。
・ 資源には人的資源及び専門的な技能、技術並びに資金を含む。
・ 組織の最高経営層は、特定の管理責任者(複数も可)を指名しなければならない、かつ、その責任者は次に示す役割、責任及び権限を、他の責任とは関わりなく与えられていなければならない。
a)この規格に従って環境マネジメントシステムの要求事項が確立され、実施され、かつ維持されることを確実にすること。
b)見直しのため及び環境マネジメントの改善の基礎として、最高経営層に環境マネジメントシステムの実績を報告すること。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.2訓練、自覚、及び能力
・ 組織は訓練のニーズを明確にしなければならない。
・ 組織は環境に著しい影響を生じる可能性のある作業を行なうすべての要員が適切な訓練を受けることを要求しなければならない。
・ 組織は関連する各部門、及び各階層において、その従業員又は構成員に次の事項を自覚させる手順を確立し維持しなければならない。
a)環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性
b)作業活動による顕在、又は潜在の著しい環境影響及び各人の作業環境上の利点
c)環境方針及び手順との適合、並びに緊急事態への準備及び対応の要求事項を含む環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任
d)予想された運用手順から逸脱した際に予想される結果。
・ 著しい環境影響の原因となりうる作業を行なう要員は適切な教育訓練及び/又は経験に基づく能力を持たなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.3コミュニケーション
・ 組織は環境側面及び環境マネジメントシステムに関して次の手順を確立しなければならない。
a)組織の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション。
b)外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受け付け、文書化し、及び対応すること。
・ 組織は著しい環境側面について外部コミュニケーションのためのプロセスを検討し、 その決定を記録しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.4環境マネジメントシステム文書化
・ 組織は紙面又は電子形式で次に示すことのために情報を確立し維持しなければならない。
a)マネジメントシステムの核となる要素及びその相互作用を記述。
b)関連する文書の所在を示す。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.5文書管理
・ 組織は次のことを確立するために、この規格が要求するすべての文書を管理する手順を確立し、維持しなければならない。
a)文書の所在が分かること
b)文書が定期的にレビューされ、必要に応じて改訂され、かつ所定の責任者によって妥当性が承認されること。
c)環境マネジメントシステムが効果的に機能するために不可欠な業務が行なわれている、 すべての場所で、関連文書の最新版が利用できること。
d)廃止文書は、すべて発行部署及び使用部署から速やかに撤去されること。そうでなければ意図されない使用がないように保証すること
e)法律上及び/又は情報保存の目的で保管される、あらゆる廃止文書は適切に識別される。
・ 文書は読みやすく、日付が(改訂の日付とともに)あって容易に識別でき、順序良く維持されて 指定の期間保持されなければならない。
・ 種々のタイプの文章の作成及び改訂に関する手順と責任を確立し、維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.6運用管理
・ 組織はその方針、目的及び目標に沿って特定された著しい環境側面に関連する、 運用及び活動を特定しなければならない。
・ 組織はメンテナンスを含む、これらの活動を次に示すことにより特定の条件の下で確実に実行されるよう計画しなければならない。
a)その手順がないと、環境方針並びに目的及び目標から逸脱するかもしれない状況に適用する文書化した手順を確立して維持すること。
b)その手順には運用基準を明記すること。
c)組織が用いる物品、サービスの特定可能な著しい環境側面に関する手順を確立し及び維持すること並びに供給者及び請負者に関連手順及び要求事項を伝達すること。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.7緊急事態への準備及び対応
・ 組織は事故及び緊急事態について、可能性を特定し対応するための並びにそれらに伴なうかもしれない環境影響を予防して緩和するための手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は必要に応じて、特に事故又は緊急事態への準備及び対応の手順をレビューし改訂しなければならない。
・ 組織は、また実行可能な場合にはそのような手順を定期的にテストしなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5点検及び是正
4.5.1監視及び測定
・ 組織は環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するために、文書化した手順を確立し、維持しなければならない。
・ これには、パフォーマンス、関連の運用管理、並びに組織の環境目的、目標との適合を追跡するための情報を記録することを含まなければならない。
・ 監視機器は校(較)正され維持されなければならず、かつプロセスの記録は組織の手順に従って保持されなければならない。
・ 組織は関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.2不適合並び是正及び予防処置
・ 組織は不適合を取り扱い調査し、それによって生じるあらゆる影響を緩和する処置をとり、並びに是正及び予防処置に着手して完了する責任と権限を定めた手順を確立して維持しなければならない。
・ 顕在、及び潜在する不適合の原因を除去するために取られる、あらゆる是正処置又は予防処置は問題の大きさに対応し、かつ生じた環境影響に釣り合わなければならない。
・ 組織は是正及び予防処置に伴なう文書化した手順のあらゆる変更を実施に移し、記録しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.3記録
・ 組織は環境記録の識別、維持及び廃棄のための手順を確立し、維持しなければならない。
・ この記録は、訓練記録、並びに監査及び見直し結果を含まなければならない。
・ 環境記録は読みやすく識別可能であり、かつ関連した活動、製品又はサービスに対して追跡可能でなければならない。
・ 環境記録は容易に検索でき、かつ損傷、劣化または紛失を防ぐような方法で保管され、維持されなければならない。
・ 保管期間が定められ記録されなければならない。
・ 記録はシステム及び組織に応じて、この規格の要求事項への適合を示すために維持されなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.4環境マネジメントシステム監査
・ 組織は次のことを行なうために、実施すべき定期的環境マネジメントシステム監査のプログラム(複数も可)及び手順を確立し維持しなければならない。
a)環境マネジメントシステムが
1)この規格の要求事項を含めて、環境マネジメントのために計画された取り決めに合致しているか、
2)適切に実施され維持されているか、
否かを決定する。
b)監査の結果に関する情報を経営層に提供する。
・ 組織の監査プログラムはあらゆるスケジュールを含めて当該活動の環境上の重要性、及び前回監査の結果に基づいていなければならない。
・ 包括的なものとするために、監査手順は監査の範囲、頻度及び方法を、監査を実施し及び結果を報告するための責任及び要求事項とともに含まなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.6経営層による見直し
・ 組織の最高経営層は、環境マネジメントシステムが継続的する適切性、妥当性、かつ有効性を確実にするために、自ら定めた間隔で環境マネジメントシステムを見直さなければならない。
・ 経営層による見直しプロセスでは、経営層がこの評価を実施できるように、必要な情報が確実に収集されなければならない。
・ この見直しは文書化されなければならない。
・ 経営層による見直しは環境マネジメントシステム監査の結果、変化している周囲の状況、及び継続的改善への約束に照らして、方針、目的、及び環境マネジメントシステムのその他の要素の変更の必要性に言及しなければならない。
http://qpon.quu.cc/toyota/14000.htm
ISO 14000は、国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格(IS)の総称。ISO 14000及び環境ISOと称呼する時は、主として要求事項であるISO 14001のことを指す。
ISO 14000シリーズは、1992年の地球サミットをきっかけとして規格策定が始まり、1996年より発行が開始された。 (厳密に言うと、地球サミット前に創設されたBCSD(持続可能な開発のための産業人会議)がISO(国際標準化機構)に対して、環境についての国際標準化に取り組むよう要請を行った。)
概要
ISO 14000ファミリーが支援する環境マネジメントシステム(EMS: Environmental Management Systems)の構築を要求した規格がISO 14001である。
組織(企業、各種団体など)の活動・製品及びサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善するためのシステムを構築し、そのシステムを継続的に改善していくPDCAサイクルを構築することが要求されている。この中で、有害な環境影響(環境への負荷)の低減及び有益な環境影響の増大、組織の経営改善、環境経営が期待される。ただし、環境パフォーマンスの評価に関する具体的な取決めはなく、組織は自主的にできる範囲で評価を行うことになる。
ISO 14001は、1996年9月に制定され、その後、2004年11月に規定の明確化とISO 9001との両立性という原則により規格改定が行われた。 ISO 14001は環境マネジメントシステムの満たすべき必須事項を定めている。関連規格であるISO 14004は、ISO 14001の適用にあたって組織がいかに環境マネジメントシステムを構築するか広義で詳細な事項が示された手引きであり、拘束力はない。日本国内ではこれらに対応し、日本工業規格 JIS Q 14001, JIS Q 14004が制定され、規格群中の他の規格もJIS化が行われている。
近年では、環境マネジメントシステムの適用範囲の拡大が見られ、企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)を評価する際の基準に利用されることがあり、社会的責任投資(SRI: Socially Responsible Investment)にも関連している[1]。 また、組織内外の双方向コミュニケーションによる環境コミュニケーションが促進され、その情報は重要な企業情報として位置づけられる動向がある。
審査登録制度
組織がISO14001に基づき環境マネジメントシステムを構築したことを社会へ伝えるには自己宣言、そして外部機関による評価が可能である。このうち、外部機関である審査登録機関が第三者として審査登録制度に基づき組織を審査し適合している場合は、登録し公に証明され、登録証書が発行される。これがISO14001の認証(審査登録)である。有効期間は審査登録機関により異なるが、概ね登録日から3年間である。なお、このようにマネジメントシステムが規格に適合しているかを審査し登録する場合には「審査登録」または「認証」という用語を使用し、後述の審査登録機関・審査員評価登録機関・審査員研修機関に対して用いる「認定」という用語とは区別する。
国際標準化機構内の政策開発委員会のひとつである適合性評価委員会(CASCO)が作成した規格(ISO/IEC 17011)に適合した「認定機関」が、適合性評価機関、すなわち「審査登録機関(認証機関)」、審査員の資格を与える「審査員評価登録機関」、審査員になるための研修を行う「審査員研修機関」の審査・認定・登録を統括する。なお、認定機関は他の認定機関と相互承認することにより適合性を保っている。日本での唯一の認定機関は日本適合性認定協会(JAB)であり、海外の認定機関と相互承認している。
日本では、品質管理の国際規格である初期のISO 9000シリーズを不要とした国際的な背景もあり、環境問題に関して積極的な取組みが行われ、ISO 14001認証取得した組織数は群を抜いて世界最多国である[4]。 従って日本は審査登録機関の市場として、海外の認定機関より認定された審査登録機関(認証機関)による進出が多く、国際通商、要求事項の翻訳解釈、各国の法的要求事項等のメリット及びデメリットが数多く挙げられる。組織はお墨付き(審査登録または認証)の必要性がある場合、対象となる項目範囲、登録の範囲を決め、さらに審査登録機関の選択が求められる。
大手企業との商取引においては認証の取得を要求される事もよく見られ、中小企業などでも取引先や親会社から求められて取得する例は珍しくなかった。企業以外でも、地方自治体など企業以外の組織が認証を受ける例も多くなり、イメージアップを企図したNPOや宗教法人などが取得する事も見られる。認証取得していることが必ずしも適切な環境マネジメントシステムを構築しているとは限らないため、取引先等の利害関係者の評価方法も重要視される。ISOのシステムを構築したことを情報公開による自己適合宣言、客先等の利害関係者の評価も可能ではある。
ISO 14000ファミリー
ISO 14001:2004 環境マネジメントシステム(EMS)−要求事項及び利用の手引き
ISO 14004:2004 環境マネジメントシステム−原則、システム及び支援技法の一般指針
ISO14005 環境マネジメントシステム−段階的適用のガイド(WD3段階) 2009年発行予定
ISO 14015 環境マネジメント−用地及び組織の環境アセスメント(EASC)。土壌汚染に関する規格。
ISO 14020シリーズ 環境ラベル(EL)
ISO14020:2000 環境ラベル及び宣言‐一般原則
ISO14021:1999 環境ラベル及び宣言-自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示)
ISO14024:1999 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境ラベル表示-原則及び手続
ISO14025 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境宣言-原則と枠組み
TR14025:2000 環境ラベル及び宣言-タイプ? 環境宣言
ISO 14030シリーズ 環境パフォーマンス評価(EPE)
ISO14031:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価-指針
ISO/TR14032:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価 実施例
ISO 14040シリーズ ライフサイクルアセスメント(LCA)
ISO14040 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-原則及び枠組み
ISO14044 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-要求事項及び指針
TS14048 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-データ記述書式
TR14047:2003 環境マネジメント-ライフサイクル影響評価-ISO14042に関する適用事例
ISO 14050 環境マネジメント用語
ISO/TR 14062 環境適合設計 - 2008年1月現在、技術報告書(Technical Report)の情報提供文書として発行、JIS化はされている。
ISO 14063 環境コミュニケーション
ISO 14064-1 温室効果ガス - 第1部:組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-2 温室効果ガス - 第2部:プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量削減又は吸収量増大の定量化、* 監視及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-3 温室効果ガス - 第3部:温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証のための手引
ISO 14065 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する認定又はその他の承認において使用される有効化確認及び検証を行う機関に対する要求事項
ISO 14066 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証を行う者の力量に関する要求事項
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO 19011 品質及び環境マネジメントシステム監査のための指針
ISO Guide64:1997 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメントシステムに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成8年11月26日 環境庁告示78号
国際標準化機構(ISO)は、平成8年9月に
ISO14001(環境マネジメントシステム―仕様及び利用の手引)及び
ISO14004(環境マネジメントシステム―原則、システム及び支援技法の一般指針)を、同年十月に
ISO14010(環境監査の指針―一般原則)、
ISO10411(環境監査の指針―監査手順―環境マネジメントシステムの監査)及び
ISO14012(環境監査の指針―環境監査員のための資格基準)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境マネジメントシステムに関する国際的基準であり、環境基本計画 第三部第三章第一節において、事業者が環境管理を自主的に進める上でその検討状況を踏まえることとされたものである。
なお、これらの国際規格の技術的内容及び規格票の様式は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成8年10月にそれぞれ日本工業規格Q14001、日本工業規格Q14004、日本工業規格Q14010、日本工業規格Q14011及び日本工業規格Q14012として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000067
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント―ライフサイクルアセスメントに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成9年12月11日 環境庁告示85号
国際標準化機構(ISO)は、平成九年六月十五日に
ISO14040(環境マネジメント―ライフサイクルアセスメント―原則及び枠組み)を発行した。
この国際規格は、製品等の原材料の採取から製造、使用及び処分に至る生涯を通しての環境影響を調査する技法であるライフサイクルアセスメントのうち、その調査の実施及び報告の作成にかかわる原則並びに枠組みの部分に関する国際基準である。環境基本計画第三部第三章第一節3では、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、この国際規格は、これに資するものである。
また、この国際規格は、国、地方公共団体、国民等の各主体の自主的積極的な環境保全活動の促進にも資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成9年11月に日本工業規格Q14040として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000068
国際標準化機構(ISO)の環境ラべル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行されたので告示する公布日:平成12年9月22日 環境庁告示63号
国際標準化機構(ISO)の環境ラベル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行された件
国際標準化機構(ISO)は、平成10年8月1日に
ISO14020(環境ラベル及び宣言―一般原則)を、平成11年9月に
ISO14021(環境ラベル及び宣言―自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示))を、同年4月に
ISO14024(環境ラベル及び宣言―タイプ?環境ラべル表示―原則及び手続)を、平成12年3月に
ISO/TR(技術報告書)14025(環境ラベル―タイプ?環境宣言)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格及び技術報告書は、あらゆる種類の製品及びサービスに適用できる環境ラベル及び宣言に関するものである。また、環境基本計画第三部第三章第一節において、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、これらの国際規格及び技術報告書は、これに資するものである。
なお、これらの国際規格及び技術報告書の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、それぞれ平成10年7月に日本工業規格Q14020、平成12年8月に日本工業規格Q14021及び日本工業規格Q14024として制定され、また、平成12年8月に標準情報Q0003として公表されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000070
国際標準化機構(ISO)の環境パフォーマンス評価に関する国際規格が発行されたので告示する 公布日:平成13年2月19日 環境省告示7号
国際標準化機構(ISO)は、平成11年11月にISO14031(環境マネジメント―環境パフォーマンス評価―指針)を発行した。
この国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境パフォーマンス評価の設計及び使用に関する指針である。また、環境基本計画 第三部第二章第三節2(2)イにおいて、「環境に配慮した事業活動の成果について適切に評価するため、環境パフォーマンス評価(中略)について調査研究を進め、その普及を図ります。」とされており、この国際規格は、これに資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成12年10月に日本工業規格Q14031として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000071
http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/46712922.html
4.1 一般要求事
4.2 環境方針
4.3 計画
4.3.1 環境側面
4.3.2 法的及びその他の要求事項
4.3.3 目的、目標及び実施計画
4.4 実施及び運用
4.4.1 資源、役割、責任及び権限
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
4.4.3 コミュニケーション
4.4.4 文書類
4.4.5 文書管理
4.4.6 運用管理
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
4.5 点検
4.5.1 監視及び測定
4.5.2 順守評価
4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置
4.5.4 記録の管理
4.5.5 内部監査
4.6 マネジメントレビュー
http://www.jisc.go.jp/mss/ems-14001.html
--------------------------------------------------------------------------------
4.1一般要求事項
・ 組織は環境マネジメントシステムを確立し維持しなければならない。その要求事項は、この4.全体で述べる。
--------------------------------------------------------------------------------
4.2 環 境 方 針
・ 最高経営層は組織の環境方針を定め、その方針について次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の活動、製品又はサービスの性質、規模及び環境影響に対して適切である。
b)継続的改善及び汚染の予防の関する約束を含む。
c)関連する環境法規、及び組織が同意する他の要求事項を遵守する約束を含む。
d)環境目的及び目標を設定し、見直しの枠組みを与える。
e)文書化され、実行され、維持されかつ全従業員に周知される。
f)一般の人が入手可能である。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3 計 画
4.3.1 環境側面
・ 組織は著しい環境影響を持つか、又は持ちうる環境側面を決定するために、・ 組織が管理でき、かつ影響を生じると思われる活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は環境目的設定に際して、この著しい影響に関連する側面を確実に配慮しなければならない。
・ 組織はこの情報を常に最新のものとしなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 法的及びその他の要求事項
・ 組織は、その活動、製品またはサービスの環境側面に適用可能な法的要求事項及び組織は同意するその他の要求事項を特定し参照できるような手順を確立し維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.3 目的、目標
・ 組織は組織内の関連する各部門、各階層で文書化された環境目的、及び目標を設定し維持しなければならない。
・ その目的を設定し見直しをするときに、組織は法的及びその他の要求事項、著しい環境側面、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解に配慮しなければならない。
・ 目的、及び目標は汚染予防に関する約束を含め、環境方針と整合させなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.3.4 環境マネジメントプログラム
・ 組織はその目的及び目標を達成するためにプログラムを策定し維持しなければならない。
・プログラムには次の事項を含まなければならない。
a)組織の関係する、各部門、各階層における、目的、目標を達成するための責任の明示。
b)目的及び、目標を達成するための手段、及び日程
・ プロジェクトが新規開発及び新規若しくは変更された活動、製品又はサービスに関する場合には環境マネジメントが、そのようなプロジェクトにも確実に適用されるようにプログラムの該当部分を改訂しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4実施及び運用
4.4.1体制及び責任
・ 効果的な環境マネジメントを実施するために、役割、責任及び権限を定め文書化し、かつ伝達しなければならない。
・ 経営層は、環境マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な資源を用意しなければならない。
・ 資源には人的資源及び専門的な技能、技術並びに資金を含む。
・ 組織の最高経営層は、特定の管理責任者(複数も可)を指名しなければならない、かつ、その責任者は次に示す役割、責任及び権限を、他の責任とは関わりなく与えられていなければならない。
a)この規格に従って環境マネジメントシステムの要求事項が確立され、実施され、かつ維持されることを確実にすること。
b)見直しのため及び環境マネジメントの改善の基礎として、最高経営層に環境マネジメントシステムの実績を報告すること。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.2訓練、自覚、及び能力
・ 組織は訓練のニーズを明確にしなければならない。
・ 組織は環境に著しい影響を生じる可能性のある作業を行なうすべての要員が適切な訓練を受けることを要求しなければならない。
・ 組織は関連する各部門、及び各階層において、その従業員又は構成員に次の事項を自覚させる手順を確立し維持しなければならない。
a)環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性
b)作業活動による顕在、又は潜在の著しい環境影響及び各人の作業環境上の利点
c)環境方針及び手順との適合、並びに緊急事態への準備及び対応の要求事項を含む環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任
d)予想された運用手順から逸脱した際に予想される結果。
・ 著しい環境影響の原因となりうる作業を行なう要員は適切な教育訓練及び/又は経験に基づく能力を持たなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.3コミュニケーション
・ 組織は環境側面及び環境マネジメントシステムに関して次の手順を確立しなければならない。
a)組織の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション。
b)外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受け付け、文書化し、及び対応すること。
・ 組織は著しい環境側面について外部コミュニケーションのためのプロセスを検討し、 その決定を記録しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.4環境マネジメントシステム文書化
・ 組織は紙面又は電子形式で次に示すことのために情報を確立し維持しなければならない。
a)マネジメントシステムの核となる要素及びその相互作用を記述。
b)関連する文書の所在を示す。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.5文書管理
・ 組織は次のことを確立するために、この規格が要求するすべての文書を管理する手順を確立し、維持しなければならない。
a)文書の所在が分かること
b)文書が定期的にレビューされ、必要に応じて改訂され、かつ所定の責任者によって妥当性が承認されること。
c)環境マネジメントシステムが効果的に機能するために不可欠な業務が行なわれている、 すべての場所で、関連文書の最新版が利用できること。
d)廃止文書は、すべて発行部署及び使用部署から速やかに撤去されること。そうでなければ意図されない使用がないように保証すること
e)法律上及び/又は情報保存の目的で保管される、あらゆる廃止文書は適切に識別される。
・ 文書は読みやすく、日付が(改訂の日付とともに)あって容易に識別でき、順序良く維持されて 指定の期間保持されなければならない。
・ 種々のタイプの文章の作成及び改訂に関する手順と責任を確立し、維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.6運用管理
・ 組織はその方針、目的及び目標に沿って特定された著しい環境側面に関連する、 運用及び活動を特定しなければならない。
・ 組織はメンテナンスを含む、これらの活動を次に示すことにより特定の条件の下で確実に実行されるよう計画しなければならない。
a)その手順がないと、環境方針並びに目的及び目標から逸脱するかもしれない状況に適用する文書化した手順を確立して維持すること。
b)その手順には運用基準を明記すること。
c)組織が用いる物品、サービスの特定可能な著しい環境側面に関する手順を確立し及び維持すること並びに供給者及び請負者に関連手順及び要求事項を伝達すること。
--------------------------------------------------------------------------------
4.4.7緊急事態への準備及び対応
・ 組織は事故及び緊急事態について、可能性を特定し対応するための並びにそれらに伴なうかもしれない環境影響を予防して緩和するための手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は必要に応じて、特に事故又は緊急事態への準備及び対応の手順をレビューし改訂しなければならない。
・ 組織は、また実行可能な場合にはそのような手順を定期的にテストしなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5点検及び是正
4.5.1監視及び測定
・ 組織は環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するために、文書化した手順を確立し、維持しなければならない。
・ これには、パフォーマンス、関連の運用管理、並びに組織の環境目的、目標との適合を追跡するための情報を記録することを含まなければならない。
・ 監視機器は校(較)正され維持されなければならず、かつプロセスの記録は組織の手順に従って保持されなければならない。
・ 組織は関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し維持しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.2不適合並び是正及び予防処置
・ 組織は不適合を取り扱い調査し、それによって生じるあらゆる影響を緩和する処置をとり、並びに是正及び予防処置に着手して完了する責任と権限を定めた手順を確立して維持しなければならない。
・ 顕在、及び潜在する不適合の原因を除去するために取られる、あらゆる是正処置又は予防処置は問題の大きさに対応し、かつ生じた環境影響に釣り合わなければならない。
・ 組織は是正及び予防処置に伴なう文書化した手順のあらゆる変更を実施に移し、記録しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.3記録
・ 組織は環境記録の識別、維持及び廃棄のための手順を確立し、維持しなければならない。
・ この記録は、訓練記録、並びに監査及び見直し結果を含まなければならない。
・ 環境記録は読みやすく識別可能であり、かつ関連した活動、製品又はサービスに対して追跡可能でなければならない。
・ 環境記録は容易に検索でき、かつ損傷、劣化または紛失を防ぐような方法で保管され、維持されなければならない。
・ 保管期間が定められ記録されなければならない。
・ 記録はシステム及び組織に応じて、この規格の要求事項への適合を示すために維持されなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.5.4環境マネジメントシステム監査
・ 組織は次のことを行なうために、実施すべき定期的環境マネジメントシステム監査のプログラム(複数も可)及び手順を確立し維持しなければならない。
a)環境マネジメントシステムが
1)この規格の要求事項を含めて、環境マネジメントのために計画された取り決めに合致しているか、
2)適切に実施され維持されているか、
否かを決定する。
b)監査の結果に関する情報を経営層に提供する。
・ 組織の監査プログラムはあらゆるスケジュールを含めて当該活動の環境上の重要性、及び前回監査の結果に基づいていなければならない。
・ 包括的なものとするために、監査手順は監査の範囲、頻度及び方法を、監査を実施し及び結果を報告するための責任及び要求事項とともに含まなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
4.6経営層による見直し
・ 組織の最高経営層は、環境マネジメントシステムが継続的する適切性、妥当性、かつ有効性を確実にするために、自ら定めた間隔で環境マネジメントシステムを見直さなければならない。
・ 経営層による見直しプロセスでは、経営層がこの評価を実施できるように、必要な情報が確実に収集されなければならない。
・ この見直しは文書化されなければならない。
・ 経営層による見直しは環境マネジメントシステム監査の結果、変化している周囲の状況、及び継続的改善への約束に照らして、方針、目的、及び環境マネジメントシステムのその他の要素の変更の必要性に言及しなければならない。
http://qpon.quu.cc/toyota/14000.htm
ISO 14000は、国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格(IS)の総称。ISO 14000及び環境ISOと称呼する時は、主として要求事項であるISO 14001のことを指す。
ISO 14000シリーズは、1992年の地球サミットをきっかけとして規格策定が始まり、1996年より発行が開始された。 (厳密に言うと、地球サミット前に創設されたBCSD(持続可能な開発のための産業人会議)がISO(国際標準化機構)に対して、環境についての国際標準化に取り組むよう要請を行った。)
概要
ISO 14000ファミリーが支援する環境マネジメントシステム(EMS: Environmental Management Systems)の構築を要求した規格がISO 14001である。
組織(企業、各種団体など)の活動・製品及びサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善するためのシステムを構築し、そのシステムを継続的に改善していくPDCAサイクルを構築することが要求されている。この中で、有害な環境影響(環境への負荷)の低減及び有益な環境影響の増大、組織の経営改善、環境経営が期待される。ただし、環境パフォーマンスの評価に関する具体的な取決めはなく、組織は自主的にできる範囲で評価を行うことになる。
ISO 14001は、1996年9月に制定され、その後、2004年11月に規定の明確化とISO 9001との両立性という原則により規格改定が行われた。 ISO 14001は環境マネジメントシステムの満たすべき必須事項を定めている。関連規格であるISO 14004は、ISO 14001の適用にあたって組織がいかに環境マネジメントシステムを構築するか広義で詳細な事項が示された手引きであり、拘束力はない。日本国内ではこれらに対応し、日本工業規格 JIS Q 14001, JIS Q 14004が制定され、規格群中の他の規格もJIS化が行われている。
近年では、環境マネジメントシステムの適用範囲の拡大が見られ、企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)を評価する際の基準に利用されることがあり、社会的責任投資(SRI: Socially Responsible Investment)にも関連している[1]。 また、組織内外の双方向コミュニケーションによる環境コミュニケーションが促進され、その情報は重要な企業情報として位置づけられる動向がある。
審査登録制度
組織がISO14001に基づき環境マネジメントシステムを構築したことを社会へ伝えるには自己宣言、そして外部機関による評価が可能である。このうち、外部機関である審査登録機関が第三者として審査登録制度に基づき組織を審査し適合している場合は、登録し公に証明され、登録証書が発行される。これがISO14001の認証(審査登録)である。有効期間は審査登録機関により異なるが、概ね登録日から3年間である。なお、このようにマネジメントシステムが規格に適合しているかを審査し登録する場合には「審査登録」または「認証」という用語を使用し、後述の審査登録機関・審査員評価登録機関・審査員研修機関に対して用いる「認定」という用語とは区別する。
国際標準化機構内の政策開発委員会のひとつである適合性評価委員会(CASCO)が作成した規格(ISO/IEC 17011)に適合した「認定機関」が、適合性評価機関、すなわち「審査登録機関(認証機関)」、審査員の資格を与える「審査員評価登録機関」、審査員になるための研修を行う「審査員研修機関」の審査・認定・登録を統括する。なお、認定機関は他の認定機関と相互承認することにより適合性を保っている。日本での唯一の認定機関は日本適合性認定協会(JAB)であり、海外の認定機関と相互承認している。
日本では、品質管理の国際規格である初期のISO 9000シリーズを不要とした国際的な背景もあり、環境問題に関して積極的な取組みが行われ、ISO 14001認証取得した組織数は群を抜いて世界最多国である[4]。 従って日本は審査登録機関の市場として、海外の認定機関より認定された審査登録機関(認証機関)による進出が多く、国際通商、要求事項の翻訳解釈、各国の法的要求事項等のメリット及びデメリットが数多く挙げられる。組織はお墨付き(審査登録または認証)の必要性がある場合、対象となる項目範囲、登録の範囲を決め、さらに審査登録機関の選択が求められる。
大手企業との商取引においては認証の取得を要求される事もよく見られ、中小企業などでも取引先や親会社から求められて取得する例は珍しくなかった。企業以外でも、地方自治体など企業以外の組織が認証を受ける例も多くなり、イメージアップを企図したNPOや宗教法人などが取得する事も見られる。認証取得していることが必ずしも適切な環境マネジメントシステムを構築しているとは限らないため、取引先等の利害関係者の評価方法も重要視される。ISOのシステムを構築したことを情報公開による自己適合宣言、客先等の利害関係者の評価も可能ではある。
ISO 14000ファミリー
ISO 14001:2004 環境マネジメントシステム(EMS)−要求事項及び利用の手引き
ISO 14004:2004 環境マネジメントシステム−原則、システム及び支援技法の一般指針
ISO14005 環境マネジメントシステム−段階的適用のガイド(WD3段階) 2009年発行予定
ISO 14015 環境マネジメント−用地及び組織の環境アセスメント(EASC)。土壌汚染に関する規格。
ISO 14020シリーズ 環境ラベル(EL)
ISO14020:2000 環境ラベル及び宣言‐一般原則
ISO14021:1999 環境ラベル及び宣言-自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示)
ISO14024:1999 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境ラベル表示-原則及び手続
ISO14025 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境宣言-原則と枠組み
TR14025:2000 環境ラベル及び宣言-タイプ? 環境宣言
ISO 14030シリーズ 環境パフォーマンス評価(EPE)
ISO14031:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価-指針
ISO/TR14032:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価 実施例
ISO 14040シリーズ ライフサイクルアセスメント(LCA)
ISO14040 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-原則及び枠組み
ISO14044 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-要求事項及び指針
TS14048 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-データ記述書式
TR14047:2003 環境マネジメント-ライフサイクル影響評価-ISO14042に関する適用事例
ISO 14050 環境マネジメント用語
ISO/TR 14062 環境適合設計 - 2008年1月現在、技術報告書(Technical Report)の情報提供文書として発行、JIS化はされている。
ISO 14063 環境コミュニケーション
ISO 14064-1 温室効果ガス - 第1部:組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-2 温室効果ガス - 第2部:プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量削減又は吸収量増大の定量化、* 監視及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-3 温室効果ガス - 第3部:温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証のための手引
ISO 14065 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する認定又はその他の承認において使用される有効化確認及び検証を行う機関に対する要求事項
ISO 14066 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証を行う者の力量に関する要求事項
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO 19011 品質及び環境マネジメントシステム監査のための指針
ISO Guide64:1997 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメントシステムに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成8年11月26日 環境庁告示78号
国際標準化機構(ISO)は、平成8年9月に
ISO14001(環境マネジメントシステム―仕様及び利用の手引)及び
ISO14004(環境マネジメントシステム―原則、システム及び支援技法の一般指針)を、同年十月に
ISO14010(環境監査の指針―一般原則)、
ISO10411(環境監査の指針―監査手順―環境マネジメントシステムの監査)及び
ISO14012(環境監査の指針―環境監査員のための資格基準)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境マネジメントシステムに関する国際的基準であり、環境基本計画 第三部第三章第一節において、事業者が環境管理を自主的に進める上でその検討状況を踏まえることとされたものである。
なお、これらの国際規格の技術的内容及び規格票の様式は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成8年10月にそれぞれ日本工業規格Q14001、日本工業規格Q14004、日本工業規格Q14010、日本工業規格Q14011及び日本工業規格Q14012として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000067
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント―ライフサイクルアセスメントに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成9年12月11日 環境庁告示85号
国際標準化機構(ISO)は、平成九年六月十五日に
ISO14040(環境マネジメント―ライフサイクルアセスメント―原則及び枠組み)を発行した。
この国際規格は、製品等の原材料の採取から製造、使用及び処分に至る生涯を通しての環境影響を調査する技法であるライフサイクルアセスメントのうち、その調査の実施及び報告の作成にかかわる原則並びに枠組みの部分に関する国際基準である。環境基本計画第三部第三章第一節3では、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、この国際規格は、これに資するものである。
また、この国際規格は、国、地方公共団体、国民等の各主体の自主的積極的な環境保全活動の促進にも資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成9年11月に日本工業規格Q14040として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000068
国際標準化機構(ISO)の環境ラべル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行されたので告示する公布日:平成12年9月22日 環境庁告示63号
国際標準化機構(ISO)の環境ラベル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行された件
国際標準化機構(ISO)は、平成10年8月1日に
ISO14020(環境ラベル及び宣言―一般原則)を、平成11年9月に
ISO14021(環境ラベル及び宣言―自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示))を、同年4月に
ISO14024(環境ラベル及び宣言―タイプ?環境ラべル表示―原則及び手続)を、平成12年3月に
ISO/TR(技術報告書)14025(環境ラベル―タイプ?環境宣言)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格及び技術報告書は、あらゆる種類の製品及びサービスに適用できる環境ラベル及び宣言に関するものである。また、環境基本計画第三部第三章第一節において、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、これらの国際規格及び技術報告書は、これに資するものである。
なお、これらの国際規格及び技術報告書の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、それぞれ平成10年7月に日本工業規格Q14020、平成12年8月に日本工業規格Q14021及び日本工業規格Q14024として制定され、また、平成12年8月に標準情報Q0003として公表されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000070
国際標準化機構(ISO)の環境パフォーマンス評価に関する国際規格が発行されたので告示する 公布日:平成13年2月19日 環境省告示7号
国際標準化機構(ISO)は、平成11年11月にISO14031(環境マネジメント―環境パフォーマンス評価―指針)を発行した。
この国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境パフォーマンス評価の設計及び使用に関する指針である。また、環境基本計画 第三部第二章第三節2(2)イにおいて、「環境に配慮した事業活動の成果について適切に評価するため、環境パフォーマンス評価(中略)について調査研究を進め、その普及を図ります。」とされており、この国際規格は、これに資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成12年10月に日本工業規格Q14031として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000071
http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/46712922.html
2009年12月12日
環境報告書ガイドライン TEX F
環境報告ガイドライン〜持続可能な社会をめざして〜(2007年版)
平成19 年6 月
目 次
(はじめに)
序章 ガイドラインの改訂にあたって
1.ガイドラインの目的と内容
2.ガイドラインの対象
3.創意工夫の勧め 〜特色ある環境報告を〜
4.既存ガイドライン等との関係
第1章 環境報告書とは何か
1.環境報告書の定義と環境報告ガイドライン
2.環境報告書の基本的機能
3.環境報告書における環境報告の一般的報告原則
4.環境報告書の基本的要件
5.環境報告書の活用にあたっての留意点
6.環境報告書の内容及び信頼性を向上させるための作成過程における方策
第2章 環境報告の記載項目の枠組み
1.環境報告の全体構成
第3章 環境報告における個別の情報・指標
1.基本的項目(BI)
BI-1:経営責任者の緒言
BI-2:報告にあたっての基本的要件
BI-2-1:報告の対象組織・期間・分野
BI-2-2:報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況
BI-3:事業の概況(経営指標を含む)
BI-4:環境報告の概要
BI-4-1:主要な指標等の一覧
BI-4-2:事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括
BI-5:事業活動のマテリアルバランス(インプット、内部循環、アウトプット)
2.「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す情報・指標(MPI)
MP-1:環境マネジメントの状況
MP-1-1:事業活動における環境配慮の方針
MP-1-2:環境マネジメントシステムの状況
MP-2:環境に関する規制の遵守状況
MP-3:環境会計情報
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
MP-5:サプライチェーンマネジメント等の状況
MP-6:グリーン購入・調達の状況
MP-7:環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
MP-9:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
MP-10:環境コミュニケーションの状況
MP-11:環境に関する社会貢献活動の状況
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
3.「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標
(OPI)
OP-1:総エネルギー投入量及びその低減対策
OP-2:総物質投入量及びその低減対策
OP-3:水資源投入量及びその低減対策
OP-4:事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
OP-5:総製品生産量又は総商品販売量
OP-6:温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP-7:大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
OP-8:化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP-9:廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
OP-10:総排水量等及びその低減対策
4.「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標(EEI)
第4章 「社会的取組の状況」を表す情報・指標
第5章 環境報告の充実に向けた今後の課題
「環境報告書の記載事項等に関する告示」と本ガイドライン及び「環境報告書ガイドライン(2003年度版)」との比較
【参考資料】
2.用語解説
3.Q&A
4.環境効率指標の事例
5.指標の一般的な計算例
6.国内外の研究機関等及び諸外国における研究成果
(はじめに)
今日、地球温暖化問題をはじめ、エネルギー資源、水資源、天然資源の枯渇や生物多様性の喪失等さまざまな地球環境問題が深刻化しています。また、地球規模での人口増加や経済規模の拡大と人間活動の一層のグローバル化が進む中で、人類の生存基盤に関する課題が生じており、人間社会の持続性にも大きな影響が及ぶ可能性が指摘されています。
このような中、平成18 年4 月には「第三次環境基本計画*」が閣議決定され、今後の環境政策の方向性として、「環境的側面・経済的側面・社会的側面の統合的な向上」が打ち出されました。
これまで環境省では、平成16 年3 月に「環境報告書ガイドライン(2003 年度版)」を策定する等、さまざまな形で環境報告書の普及促進を図ってきました。この結果、平成17 年度「環境にやさしい企業行動調査」1によると、環境報告書を作成・公表
する事業者数は着実に増加しつつあり、933 社が環境報告書を発行しています。
今後、事業者においてはさらなる取組が期待されます。
また、「環境情報の提供の促進等による特定事業者*等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16 年法律第77 号:環境配慮促進法、平成17 年4 月施行)により、特定事業者が環境報告書を作成・公表しています。
我が国における事業者の活動もグローバル化が進み、同時に環境への影響も複雑になっており、これまでのような規制対応を中心にした環境保全だけでなく、環境への配慮を企業経営に統合する「環境経営」という考え方に基づく取組が求められています。
このような中、事業者が自らの事業活動における環境配慮の取組状況に関して積極的に情報を公開し、社会からの評価を受け、経営に反映していくための、社会的説明責任や環境コミュニケーションの重要性が認識されつつあり、環境報告書の役割が大きくなってきています。
一方、消費や投融資を行う者にも環境に配慮した行動が期待されています。その判断を行う際にも環境報告書は事業者の環境配慮の取組状況に関する有用な情報を提供するものとして活用することができます。特に、金融機関をはじめ、企業や
個人投資家が投融資の意思決定を行う際の企業評価ツールとして環境報告書が有用であると考えられます。
また、昨今、国内外において、企業の社会的責任*(CSR:Corporate Social Responsibility )への関心が高まり、さらに、グローバル・リポーティング・イニシアチブ*(GRI:Global Reporting Initiative)による新たなガイドラインの公表等、国内外での取組が進展しています。
このような動きを背景に、世界の中で日本が果たすべき役割も期待されています。
こうした状況を踏まえ、環境報告書の作成者、利用者、有識者等からなる「環境報告書ガイドライン改訂検討会」とともに、その下に事業者の環境パフォーマンス指標等に関する個別の案件について詳細に検討するための「環境パフォーマンス指標ガイドライン改訂ワーキンググループ」を設置しました。それぞれにおいて5 回、4 回の検討を行い、環境省において「環境報告ガイドライン2007 年版」を取りまとめました。
改訂にあたっては、「環境報告書ガイドライン(2003年度版)」策定後の国内外の動向を踏まえ、環境報告書ガイドラインの位置づけを見直し、「事業者の環境パフォーマンス指標ガイドライン(2002年度版)」との統合を図る等、必要な見直しを行いました。
また、社会や経済分野まで記載した「サステナビリティ(持続可能性)報告書」や「社会・環境報告書」、企業の社会的責任(CSR)に基づく取組の成果を公表する「CSR報告書」等、環境報告書の名称や報告の内容が多様化していることから、環境報告書で定期的に環境報告を記載する際の指針を示すものとして、「環境報告ガイドライン」と名称を改めました。
今回の環境報告ガイドライン改訂のポイントは、次のとおりです。
?主要な指標等の一覧の導入
?環境報告の信頼性向上に向けた方策の推奨
?ステークホルダー(利害関係者)の視点をより重視した環境報告の推奨
?金融のグリーン化の促進(環境に配慮した投融資の促進)
?生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の促進
なお、「環境報告書の記載事項等の手引き」、「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」等の関連する手引書を環境報告ガイドラインの付属書として扱うことと致しました。
序章 ガイドラインの改訂にあたって
昨今、社会や経済分野まで記載したサステナビリティレポートや社会・環境報告書が発行されています。環境配慮促進法では、これらの名称や環境以外の分野に関する情報の記載の有無、報告を発信する媒体を問わず事業者が自らの事業活動に伴
う環境配慮の状況について定期的に公表しているものを「環境報告書」と定義しています。
今回の改訂では、環境報告書の名称や報告の内容が多様化したことに鑑み、本ガイドラインの位置づけを環境報告書で定期的に環境情報の報告を行う際のあり方を示す指針としました。そのため、「環境報告書」という名称以外の環境報告書作成の際にも利用可能であることを明確に示す「環境報告ガイドライン」と名称を改めました。
1.ガイドラインの目的と内容
このガイドラインでは、環境報告書で事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の状況について定期的に公表することを「環境報告」と呼びます。このガイドラインは、初めて環境報告書を作成し環境報告を行おうと考えている事業者の方々はもとより、既に環境報告を行っている事業者の方々にも、「環境経営」を行う上でより充実した実務的な手引きとなるよう作成したものです。
そのため、環境報告に係る国内外の最新の動向を踏まえ、その望ましいと思われる方向及び内容を取りまとめました。
環境報告を行う際には、第1章の環境報告書の定義、基本的機能及び原則等を参考にして、その作成に取り組んでいただき、さらには環境報告として記載することが必要と考えられる項目等を取りまとめている第2章、第3章を参考に、その項目や内容を検討していただきたいと思います。
第2章の「環境報告の記載項目の枠組み」では、環境報告書に記載する環境報告の内容として5分野29項目(第4章「社会的取組の状況」を含む)を説明し、第3章「環境報告における個別の情報・指標」では環境報告の項目毎に、次の2種類の情
報・指標を列挙しました。
(1)記載する情報・指標
全ての事業者に共通して重要性があると考えられる環境情報・指標
(2)記載することが期待される情報・指標
環境報告書の基本的機能を踏まえ、持続可能な社会の構築に向けて、必要に応じて、記載することが期待される情報・指標
また、第4章「社会的取組の状況」に社会面の報告のための情報・指標を記載しました。さらに第5章では、環境報告の充実に向けた今後の課題を記載しています。
このガイドラインでは、環境報告書に記載する環境報告の情報・指標を示すとともに、それぞれの項目や情報・指標について、具体的な例示やその環境上の課題や意義、指標算定にあたっての留意点の解説もしていますので、ステークホルダーが、環境報告を読んだり、分析したりする上での手引きとして活用していただくことも期待しています。
しかし、本ガイドラインで取り上げた項目及び情報・指標は限定列挙的に規定したものではなく、現時点での検討結果を取りまとめたものです。ステークホルダーの関心が高いもの等については、環境保全上の支障が生じることについて必ずしも科学的に十分には証明されていないものも含め、当該事業者自身が重要性の判断を行い、本ガイドラインでは取り上げていない項目や内容であっても積極的に記載していくことが必要です。
2.ガイドラインの対象
現在、我が国においては、環境報告書を作成・発行する事業者等は増加しつつあるものの、事業者全体に占める割合は少ないと推定されます。まずは、資金及び人材が比較的豊富である事業者を中心とした自主的かつ積極的な取組が必要ですが、将来的には、全ての事業者が作成・公表していくことが望まれます。
「循環型社会形成推進基本計画(平成15年3月閣議決定)」においては、取組目標の一つとして、上場企業の約50%及び従業員500人以上の非上場企業の約30%が環境報告書を公表することを掲げています。また、「環境配慮促進法」においても、
大企業者は環境報告書の公表や環境配慮等の状況の公表に努めることと規定しています。
このガイドラインは、環境報告書で環境報告を行う全ての事業者を対象としていますが、特に上場企業や従業員500人以上の非上場企業等の大規模事業者にあっては、このガイドラインに示した項目や情報を盛り込んだ、できるだけ質の高い環境報告
を行うことが期待されます。また、環境報告書の作成を始めたばかりの事業者や、中小事業者(工場等のサイト単位を含む)にあっては、このガイドラインを参考に、可能なところから段階的に取り組むことが望まれます。
一方、環境配慮促進法の中で環境報告書の公表が義務づけられている特定事業者については、このガイドライン及び、「環境報告書の記載事項等の手引き」を参照しつつ、「環境報告書の記載事項等に関する告示」に示された「環境報告書の記載
事項等」を網羅した環境報告書を作成することが期待されます。
なお、環境省では別途、中小事業者が、比較的容易に環境経営システムの構築及び運用、事業活動における環境配慮の取組の実施及び環境報告書の作成ができるよう「エコアクション21」(環境経営システム・環境活動レポートガイドライン‐2004年版‐)を策定しています。この「エコアクション21」に規定する「環境活動レポート」の要件を満たして作成・公表されたものは、環境報告書の範疇に含まれます。
平成16年度より財団法人 地球環境戦略研究機関で認証・登録制度を実施しており、この制度では認証・登録を受けた事業者名及び環境活動レポートを公表しています。
3.創意工夫の勧め〜特色ある環境報告を〜
環境報告書は、事業者が社会に対して自らの事業活動に伴い発生した環境負荷についての説明責任を果たし、ステークホルダーの意思決定に有用な情報を提供するものであり、環境コミュニケーションの重要なツールとして社会的に記載すべき項
目や内容があると考えられます。
しかしその一方で、環境報告書は、環境報告書を活用したステークホルダーとのコミュニケーションのあり方を考慮に入れつつ、事業者の経営方針や考え方、風土や特徴を反映させて作成されるべきものです。その点では環境報告を行う項目や記
載情報、さらには紙媒体だけでなくインターネット等の活用も含めた公表の方法等について、各事業者の「創意工夫」が求められます。
事業者には、このガイドラインを踏まえた上で、各事業者の特色が反映された環境報告書を作成・公表することを期待しています。
このガイドラインの普及状況を確認し、内容の継続的改善を図っていくため、このガイドラインに準拠して環境報告書を作成した場合には、環境報告書にその旨を明記することを希望しています。本ガイドラインが環境報告書に記載する環境に関する項目として掲げている5分野29項目全てを記載している場合、もしくは記載しない項目については、その理由を記載している場合は準拠しているとみなします。
また、記載した内容と本ガイドラインが示す29項目との関わりを何らかの形で明示することが期待されます。
4.既存ガイドライン等との関係
環境報告書の内容に関するガイドラインや手引きとして次のものがあります。
○「環境報告書の記載事項等の手引き」(平成17 年12 月)
環境報告書の普及により、環境に配慮した事業活動の促進を図るため、平成16 年5月に、環境配慮促進法が成立しました。この中で、環境報告書を作成・公表する義務のある一定の要件を満たした特定事業者においては、「告示」に定めた環境報告書に記載すべき項目や記録の方法(以下、「記載事項等」)に従って作成・公表するように努めることとされています(法第9 条第2 項)。
この手引きは、「記載事項等」を詳細に、かつ分かりやすく解説するために作成したもので、特定事業者を主な対象としていま
すが、環境報告書の作成・公表を始めたばかりの事業者の方々にも活用していただきたいと考えています。しました。
「環境報告書の記載事項等の手引き」:
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
○「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」(平成18 年3 月)
この手引は環境報告書の信頼性を高めるために事業者自らがその評価を行う場合の自己評価の考え方、実施手順から結果の公表までを説明したもので、一つの手法を示し、全ての団体・事業者を対象としています。
「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」:
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
※「環境パフォーマンス指標ガイドライン」
「環境パフォーマンス指標ガイドライン2002 年度版」における環境パフォーマンスの考え方や算定方法については、最新の状況を加味した上で、本環境報告ガイドラインに統合しました。
「環境パフォーマンス指標ガイドライン2002 年度版」では、ほぼ全ての事業者に共通し、環境政策上も重要と考えられる指標を[コア指標]として集約・整理し、それ以外の指標については[サブ指標]としていました。環境パフォーマンス指標ガイドライン2002 年度版の[コア指標]及び[その他のサブ指標]は本ガイドラインの『第3章 3.「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標』の記載項目に該当します。
[サブ指標]は主に『第3章 2.「環境マネジメント等、環境経営に関する状況」を表す情報・指標』に含まれています。
このほか、環境報告に関するガイドラインとしては、経済産業省の「ステークホルダー重視による環境レポーティングガイドライン2001」、グローバル・リポーティング・イニシアチブ(GRI)の「サステナビリティ・リポーティング・ガイドラインG3(2006 年版)」等、複数存在しています。参考資料の6.【国内外の研究機関等及び諸外国における研究成果】も参照して、よりよい環境報告を行うことが期待されます。
また、環境報告に関連の深い、事業者等の環境マネジメントや情報提供に関するガイドライン等としては次のようなものがあります。
○「環境会計ガイドライン2005 年版」(平成17 年2 月)
環境会計とは、「企業等が、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的(貨幣単位又は物量単位)に測定し伝達する仕組み」です。
環境会計情報は、環境報告書を通じて環境保全への取組姿勢や具体的な対応等と併せて公表することによって、事業者等の環境保全への取組をステークホルダーに伝達するために有効です。これを公表することは事業者等の社会的信頼を高め、社会的評価を確立していくことにつながります。
すなわち、外部の消費者、投資家、地域住民等に対して説明責任を果たすと同時に、環境保全の観点も含めた、より適切な事業者評価に結びつく役割が期待されます。
「環境会計ガイドライン 2005 年版」
http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html
○エコアクション21
エコアクション21 は、中小企業向けに取り組み易く取りまとめられた環境経営システム及び環境活動レポートのガイドライン等より構成されているとともに、環境経営システムの中の環境負荷の把握及び環境目標の設定において、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量及び総排水量の把握と目標設定を求めています。
この事業者の取組を「エコアクション21 審査人」が審査し、財団法人地球環境戦略研究機関 持続性センター(エコアクション21 中央事務局)が認証し、登録します。なお、環境活動レポートの要件は、環境方針、環境目標とその実績、主要な環境活動計画の内容、環境活動の取組結果の評価、環境関連法規への違反、訴訟等の有無の記載と、このレポートを事業所において備え付け一般の閲覧を可能にし、エコアクション21 中央事務局に送付することです(中央事務局が取組事業者名及び環境活動レポートを公表する)。
財団法人 地球環境戦略研究機関 持続性センター
http://www.ea21.jp/
○ISO14001
ISO14001(JIS Q 14001)(環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引)は、いわゆるPDCA サイクルによる環境マネジメントシステムを構築・運用することにより、システムの継続的改善を図ることを基本としています。継続的改善とは、「組
織の環境方針に沿って全体的な環境パフォーマンスの改善を達成するための環境マネジメントシステムを向上させるプロセス」と定義されています。
ここでは、組織は内部及び外部のコミュニケーションの手順を確立することが求められています。外部とのコミュニケーションを検討するときには、すべての利害関係者の見解及び情報ニーズを考慮することとしており、その方法として、年次報告書、ニュースレター、インターネット及び地域での会合等が挙げられています。
なお、本環境報告ガイドラインは、環境マネジメントシステムの適合要件や審査登録の基準に変更を加えるものではありません。
○ISO14063
ISO14063(JIS Q14063)(環境マネジメント−環境コミュニケーション−指針及びその事例)は、環境コミュニケーションの規格です。環境コミュニケーションは、「環境に関する課題、側面及びパフォーマンスについて理解の共有を促進するために、情報を提供及び入手し、並びに内部及び外部の利害関係者2の対話にかかわる、組織が実行するプロセス」と定義されています。
環境コミュニケーションは、持続可能な社会の構築に向けて、利害関係者間のパートナーシップを確立するために、環境負荷や環境保全活動等に関する情報を提供し、利害関係者の意見を聞き、討議することにより、互いの理解と納得を深めていくこと
といえます。なお、環境コミュニケーションは環境報告よりも広範なもので、環境報告書は環境コミュニケーションのツールの一つです。
利害関係者:ここでは「利害関係者」をステークホルダーと同義で使用しています。
体制整備
【既存のガイドライン等との関係】
*「環境報告書の記載事項等の手引き」、*「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」については本環境報告ガイドラインの改訂に伴い、整合性を図るための改訂を順次実施します。
第1章 環境報告書とは何か
1.環境報告書の定義と環境報告ガイドライン
環境報告書とは、その名称や環境以外の分野に関する情報の記載の有無並びに公表媒体に関わらず、事業者が事業活動における環境負荷及び環境配慮等の取組状況に関する説明責任を果たし、ステークホルダーの判断に影響を与える有用な情報を提供するとともに、環境コミュニケーションを促進するためのものです。
この環境報告ガイドラインは、環境報告書で社会に対して事業活動における環境配慮の方針、目標を明らかにし、取組内容・実績及びそのための組織体制・システム等、自らの事業活動に伴う環境負荷の状況及び事業活動における環境配慮の取組
状況を取りまとめ、広く社会に対して定期的に公表・報告する際に参考とするためのものです。
環境報告書を作成するにあたっては、このガイドラインに記載した一般的報告原則に則り、総合的体系的に記述する必要があります。
解説:環境報告書の名称
現在発行されている「環境報告書」の名称は、社会や経済分野まで記載した「サステナビリティ(持続可能性)報告書」や「社会・環境報告書」、企業の社会的責任(CSR)に基づく取組の成果を公表する「CSR報告書」等、その内容や作成趣旨によりさまざまです。本ガイドラインでは、事業者が自らの事業活動に伴う環境負荷の状況及び事業活動における環境配慮の取組状況を総合的・体系的に取りまとめ、定期的に公表・報告するものを総称して環境報告書として呼びます。したがって、企業の社会的責任や持続可能性に関する情報を含む場合であっても、本ガイドラインで言うところの「環境報告書」とみなします。
事業者は事業活動における環境負荷を低減する活動や環境の保全への取組の状況を記載した環境報告書を定期的に作成し公表することが期待されます。
解説:環境報告書の公表媒体
現在発行されている環境報告書の媒体には、冊子・印刷物、インターネット(URL)での公開、CD 等さまざまなものがありますが、媒体は何であれ、その内容が本ガイドラインの定義に合致し、事業者が自らの事業活動に伴う環境負荷の状況及び事業活動における環境配慮の取組状況を総合的に取りまとめ、公表するものを総称して環境報告書と呼びます。
解説:環境報告の定期的公表・報告
基本的には事業者の事業年度または営業年度に合わせ、少なくとも毎年(度)一回、作成・公表することが望まれます。例えば、環境報告書は会計年度終了時や株主総会等、ステークホルダーへの情報提供にふさわしい時期に作成・公表すること
が考えられます。インターネットを活用する場合等、公表媒体によっては、その開示内容に応じて公表頻度を多くすることも有効です。
2.環境報告書の基本的機能
環境報告書には、事業者と社会とのコミュニケーションツールとしての外部(社会的)機能と、事業者自身の事業活動における環境配慮等の取組を促進させる内部機能の二つの基本的機能があります。これらにより、事業者の自主的な事業活動に
おける環境配慮等の取組が推進されます。
外部機能には、次の三つの機能があります。
?事業者の社会に対する説明責任に基づく情報開示機能
?ステークホルダーの判断に影響を与える有用な情報を提供するための機能
?事業者の社会とのプレッジ・アンド・レビュー(誓約と評価)による環境活動等の推進機能
内部機能には、次の二つがあります。
?自らの環境配慮等の取組に関する方針・目標・行動計画等の策定・見直しのための機能
?経営者や従業員の意識付け、行動促進のための機能
環境報告書で環境報告を行う際には、これらの機能を適切に果たすよう留意することが必要です。
解説:事業者と社会とのコミュニケーションツールとしての外部機能
環境報告書は、「事業者が、社会に対して開いた窓であり、コミュニケーションの重要なツールである」と言えます。ステークホルダーはその窓を通して、その事業者が環境問題等についてどのように考え、どう対応しようとしているのかを知ることができます。
また、事業者はその窓を通して、ステークホルダーが事業者に何を求め、どう感じているのかを知ることができます。
解説:社会に対する説明責任に基づく情報開示機能
社会経済活動の主要な部分を占める事業者は、その事業活動を通じて大きな環境負荷を発生させています。そのため公共財ないし全生命共有の財産である「環境」について、さらには深刻化する環境問題に対して、どのような環境負荷を発生させ、
これをどのように低減しようとしているのか、どのような環境配慮の取組を行っているのか等を、公表・説明する責任があり、その手段として環境報告書で環境報告を行うことは最も重要な地位を占めるものです。
解説:ステークホルダーの判断に影響を与える有用な情報を提供する機能
ステークホルダーの製品やサービスの選択、投融資先等の選択等にあたっては、各種の製品情報や経営情報の開示が必要不可欠であり、その際に環境面やリスク管理等に関する情報が重要な判断材料になると考えられます。事業者はそのような意思決定の判断材料となる有用な情報を提供することが求められています。
そして、さまざまなステークホルダーが、環境報告書で環境報告を行うことの有無を含む事業者の環境配慮に関する情報を、事業者や製品・サービス選択の判断材料とするようになりつつあります。さらに、環境等に対する配慮の状況から事業者の格付を行う評価機関や、投融資や取引の意思決定を行う事業者が増加しています。
このように環境配慮への積極的な取組を進めた事業者が正当に評価され、いわば市場原理の中で公正かつ効果的にそのような取組が今後ますます進展することが期待されます。
特に、製品・サービス市場における情報媒体としては環境ラベルが主たる役割を果たし得るのに対して、資本市場や雇用市場における情報媒体として、環境報告書が重要な役割を果たすものであり、こうした効果は、CSR ファンドやエコファンド等の社会的責任投資*(SRI:Socially Responsible Investment)の普及が進む中で、次第に現実のものとなりつつあります。
近年、欧米において、公的年金等の資金の運用先や個人投資家も含めて「積極的に環境配慮に取り組む企業」に優先的に投資を行おうとする動きがあります。国内においても社会的責任投資(SRI)の取組が普及しつつあり、このような中で、我が国の事業者が環境報告書を作成・公表し、自らの事業活動における環境配慮の取組状況についての情報を公開していくことは、グリーン投資、グリーンマネーの拡大につながり、持続可能な社会の構築に向けた環境と経済の統合的向上に資するものと考えられます。
また、グリーン購入・調達が進展するとともに、取引先の選定等に際して事業者の環境や社会に対する配慮への取組状況についての情報を求められることが多くなってきており、環境報告書はその際の説明資料としても使用できます。
解説:事業者の社会とのプレッジ・アンド・レビュー(誓約と評価)による環境活動等の推進のための機能
事業者が社会に対して事業活動における環境配慮等の取組に関する方針や目標を誓約し公表することにより、社会がその状況を評価するいわゆるプレッジ・アンド・レビューの効果が働き、取組がより着実に進められることが期待されます。
また、環境報告の実施にあたって、外部の目や同業他社との比較を意識し、より前向きに取組を行っていくことは、環境保全に向けて社会全体の取組が進展することにつながると考えられます。
さらに、幅広いステークホルダーの間で環境コミュニケーションが進むことにより、社会全体の環境意識が向上するとともに、各主体の取組の状況と課題についての認識が深まれば、それぞれの役割に応じたパートナーシップの下で社会全体での
取組のレベルアップに役立つことが期待されます。
解説:事業者自身の環境配慮等の取組に関する方針・目標・行動計画等の策定・見直しの機能
環境負荷の実態や事業活動における環境配慮の取組状況を外部に報告することにより、事業者自身が報告の内容を充実させるため、事業活動における環境配慮の取組の内容やレベルを自主的に高める効果があるとともに、社内的に環境情報の収集システムが整備され、事業者自身の環境配慮の取組に関する方針、目標、行動計画等を見直し、新たに策定する契機になります。
解説:経営者や従業員の意識付け、行動促進のための機能
自らの取組内容を従業員に理解してもらい、その環境意識を高めるために、環境報告書は従業員の教育・研修のツールとしても活用でき、さらには自らの事業活動における環境配慮等の取組状況を知るとともに、それらの取組を行うことにより従
業員自身が、自社に誇りを持つことにつながります。
また、環境報告書に経営者の緒言等を記載することにより、経営者自身の意識付けも期待できます。
3.環境報告書における環境報告の一般的報告原則
環境報告書は、事業者の説明責任の観点及びステークホルダーの意思決定に有用な情報を提供する観点から、環境コミュニケーションのツールとして作成・公表されるものであり、以下に示す4つの一般的報告原則は、環境報告書の基本的機能を
満たすために必要不可欠なものです。
これらの一般的報告原則に合致しない場合は、環境報告書に期待される機能を果たすことができません。ここでは、環境報告書で環境報告を行う際の“一般的報告原則”について解説します。
? 目的適合性
環境報告においては、事業者の事業活動に伴う環境等への影響の状況及び事業活動における環境等への配慮の取組状況に関する、ステークホルダーの判断に影響を与える重要な情報が、適切な時期に提供される必要があります。
解説:目的適合性のための重要性と適時性
作成・公表される環境報告書は、ステークホルダーがその事業者及びその環境報告書に対して、どのようなことを期待して、どのような情報を求めているかを、十分に考慮することが必要です。
そのためには、ステークホルダーが誰なのかをあらかじめ特定し、それらのステークホルダーとの対話の過程を通じて、彼らの期待やニーズを理解することが有効になります。環境報告書はそのようなステークホルダーの期待やニーズに適合し、重要性のある情報が適切に記載されていることが望まれます。
なお、情報に重要性があるかどうかについては、ステークホルダーとの関与結果等を参考にして、ステークホルダーの意思決定や判断に影響を与える大きさから決定することになります。本ガイドラインで示した29項目の環境報告書の記載事項
(各項目における「(1)記載する情報・指標」)は、すべての事業者に共通して重要性があると考えられる情報ですが、それぞれの事業者の判断にもとづいて記載しない事項がある場合には、その理由を説明すること、また、29項目以外にも事業内容やステークホルダーとの関係等から重要な事項が存在する場合は、その事項を開示することが必要です。
さらに、環境情報が有用であるためには、ステークホルダーに対して適切な時期に提供される必要があります。また、当該事業者の、環境報告書対象期間中の事業活動における環境配慮の取組状況、あるいは環境に関する事故、さらには事業活動
における環境配慮の取組に関する方針・目標の策定・改訂等について、公表時期を適切に判断して公表されるようにすることが重要です。環境に関わる重要な後発事象についても記載することが期待されます
(参考:4.報告にあたっての基本的要件?対象期間)。
? 信頼性
環境報告は、信頼できる情報を提供するために、重要な情報の網羅性、正確性、中立性、検証可能性を確保しなければなりません。
解説:信頼性確保のための重要な情報の網羅性、正確性、中立性、検証可能性
作成・公表した環境報告書が、多くのステークホルダーに受け入れられ、有用なツールとして活用されるためには、事業者が環境報告書の信頼性を高める努力をしていくことが必要です。
環境報告書の信頼性が確保されるためには、事業活動に伴う環境的・経済的・社会的影響及び事業活動における環境・経済・社会配慮の取組状況を忠実に表現する上で重要な情報が確実に網羅されている必要があります。また、記載された情報が正確かつ伝えようとする内容が間違いなく伝わるように必要な情報が含まれていることが必要です。
特に、重要な情報ほど、正確で誤解を与えない詳細な情報を提供する必要があります。さらに、提供される情報は中立かつ検証可能であることが必要です。
環境報告の信頼性を高める手段としては、チェックリストやプロセスを示しつつ自己評価を実施することや監査役の監査の過程で環境情報の正確性を確認する等組織内部で実施する方法や、独立した第三者の審査を受けたり意見を聞いたりする等組織外の主体の関与を得る方法、本ガイドライン等への準拠を示す方法があります。
そして複数の方法を組み合わせることにより、信頼性をさらに高める方法を選択し、できる範囲でより適切に進めることが望まれます。
加えて、環境報告として記載された環境情報については、客観的な立場から検証可能であることが必要です。検証可能であるということは、第一に、環境報告として記載された情報のそれぞれについて、算定方法や集計範囲等が明記されており、検証可能な形で表示されているということです。第二には、環境報告として記載された情報のそれぞれについて、根拠資料が存在するとともに、その集計システム等が構築されており、情報の信頼性を第三者が確認する手段があるということです。
? 理解容易性
環境報告は、ステークホルダーの誤解を招かないように、必要な情報を理解容易な表現で明瞭に提供することが望まれます。
解説:理解容易な表現
公表された環境報告書の読み手(ステークホルダー)は多種多様であり、環境報告を行う際には、わかりやすく、かつ誤解のないように配慮することが重要です。
記載された情報が理解容易であるためには、できる限り簡潔な表現が求められますが、内容が複雑であっても必要な情報は適切に提供される必要があります。
例えば、不確実性を伴う情報を提供する場合には、不確実な性質、対象範囲、判断根拠等を明記することが必要です。併せて過去数年における経年変化を示すことも理解を深める上では重要です。
また、特定の情報を提供する場合には、全体に占める割合が容易に判読できるように、取組内容を列挙するだけでなく、その取組が全体の中でどの程度の割合を占めているのかを記載することが望まれます。
さらに、公表されている環境報告の中には、自社の取組内容のみを定性的に記載し、数値データ(実績や目標)や自らの環境負荷の実態についてほとんど記載していないものがあります。事実を正確に伝える上で、数値の記載は極めて重要であり、可能な限り実数値を記載することが望まれます。
その上で、環境報告書はコミュニケーションツールとして、見やすい、わかりやすい、読みやすいものであるとともに、読み手が「読んでみたい」と興味を抱くような表現の工夫も大切です。
そのためには、
・簡潔な文章と文体を心がける
・文章に加え、グラフや写真等を交えて表現する
・記載した取組や数値等の意味を適切に説明すること
等が望まれます。
なお、業界や社内だけで通用するような言い回しや表現、用語は可能な限り避けるべきであり、場合により注釈等を付すことが望まれます。
? 比較容易性
環境報告は、事業活動の各期間を通じて比較可能であり、かつ異なる事業者間を通じても一定の範囲で比較の基礎となる情報を提供することが望まれます。
解説:比較の基礎となる情報
まず第一に、記載された情報は、単年度のものだけでなく、当該事業者における経年の変化が比較できるよう記載することが望まれます。なお、前年と比較して著しい数値の増減等があった場合は、その理由や説明を記載することが期待されます。
第二に、事業者の事業特性や業態によって環境負荷の状況は異なると考えられますが、同一業種の事業者間、さらには業種の異なる事業者間での比較が容易であるよう記載されていることも望まれます。例えば、業界平均値等の比較のベースとな
る数値を、自社の数値に併記する等の工夫も有効です。
なお、他事業者や業界平均等と比較して環境パフォーマンスに著しい差異が見られる場合は、その理由や説明を記載することが期待されます。
環境報告が比較容易となれば、ステークホルダーが環境配慮に積極的な事業者を選択する際の有用なツールとして活用されることが期待されます。
記載するデータの根拠や収集方法、測定・算定方法等を明記すること、本ガイドラインを含め社会的に合意された環境報告のためのガイドラインに準拠して環境報告を実施すること、業界等で合意した共通の手法で環境パフォーマンスに関する情報を測定すること等は、環境報告の信頼性を高めるとともに、事業者間の比較容易性をも高めることにつながります。
算定方法や算定に用いた係数は継続的に使用することが原則です。しかし、算定方法や係数を変更する場合は合理的な理由が必要であり、変更した場合には、その旨、その理由、変更したことによる影響について記載が必要です。
4.環境報告書の基本的要件
? 対象組織の明確化
環境報告書で対象とする組織の範囲(バウンダリー)を明示することが必要です。
解説
報告対象組織の決定にあたっては、事業活動に伴う環境負荷の状況及び環境配慮への取組状況を考慮することが必要です。
多くの事業者は、その事業活動を、一法人のみで行っているのではなく、国内外の子会社等へ生産移転や運送委託等をしています。したがって、当該事業者の環境パフォーマンスについて実状にあった形で正確かつ公正に評価するためには、生産移転先等の関係事業者も含めた組織の活動全体をカバーすることが期待されます。このため、財務会計の集計範囲に準じて、連結決算対象組織全体を把握することが基本となります。
ただし、データ集計に要する負担や他者との比較評価の行いやすさ等を勘案して、環境負荷の低減に関して直接的に経営のコントロールが可能である範囲を踏まえて境界を定め、その境界を明確に示し、その境界を定めた理由を明らかにすることが必要です。
また、会社概要は単独決算のデータ、環境パフォーマンスは主要事業所のみのデータ、事業活動における環境配慮の取組状況の記述は海外の事業所や子会社での取組も含むといった具合に、その内容によって対象組織の範囲(バウンダリー)が異なる場合は、まず環境報告の対象とすべき連結決算対象組織全体を明確にし、それぞれの項目において対象組織を明記するとともに、対象組織に加えた理由、あるいは除いた理由を記載することが必要です。
さらに、前回の環境報告書と当該年度等の環境報告書の対象組織が異なる場合は、その状況についても記載し、経年での比較容易性に配慮することが望まれます。
報告対象組織の記載にあたっては、組織全体の概要を理解できる図等を用いるとともに、全体の経営戦略や各組織の位置付け等についてもある程度説明する等の工夫を行うと、対象組織についての理解を得る手助けになると考えられます。
【求められる環境配慮の範囲の拡大】
製品を提供する事業者を例にとると、下図に示した連結決算対象組織の境界を超えて、サプライチェーン*を含めたライフサイクル全般にわたり、可能な限り環境負荷の全体像を把握していく努力をすることが望まれます。
? 対象期間の明確化
環境報告書で対象とする期間を明示することが必要です。
解説
環境報告書の対象期間は、会社概要や財務情報と環境パフォーマンス情報等、環境報告書に記載された各種データの対象期間を可能な限り統一し、もし内容により異なる場合には、その点を明記することが必要です。
また、公表された事業活動における環境配慮の取組実施期間あるいは環境負荷のデータ収集期間が、環境報告の対象期間と一致していることが必要です。
しかし、取組の全てが一定期間内で終了するわけではないこと、過去に行った取組であっても現在まで継続して効果を発揮している場合があること等により、当該年度の取組のみの記載では事業者の取組全体を適切に紹介できない場合があります。その場合には理由等を明記して、過去の取組等を記載することが望まれます。
環境配慮の取組について、少なくとも事業年度又は営業年度ごとに環境報告を行い、次回の公表予定について記載することが必要です。
なお、報告対象期間の終了後であっても、環境報告を公表するまでの間に、ステークホルダーの判断に影響を及ぼす重大な事件・事故あるいは翌年度の環境パフォーマンスに影響を及ぼす重要な後発事象が生じた場合には、環境報告書に記載することが期待されます。
? 対象分野の明確化
環境報告書で対象とする内容の分野を明示することが必要です。
解説
環境報告書を作成する事業者は、当該環境報告書にてどの分野を報告しているのか(環境報告だけなのか、あるいは社会的取組も含むのかどうか等)を明確に示す必要があります。
現代社会においては、環境的側面、経済的側面、社会的側面が複雑に係わっており、環境負荷を低減し持続可能な社会を築いていくためには、社会経済システムに環境への配慮が織り込まれている必要があります。 環境的側面から持続可能であるためには、社会、経済の側面についても健全で持続的でなければなりません。
近年、欧米に限らず我が国においても、環境分野だけでなく社会的分野、経済的分野等についても報告の対象分野として拡大する事業者が増加しており、これを「サステナビリティ(持続可能性)報告」あるいは「社会・環境報告書」、「CSR 報告書」
として普及していこうという動きが強まっています。
社会的分野とは、環境面での社会貢献取組ではなく、労働安全衛生、雇用、人権、地域及び社会に対する貢献、企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引、個人情報保護、広範な消費者保護及び製品安全等のことです(参照:第4章)。また、経済的分野とは、売上高や利益の状況、資産、投融資額、賃金、労働生産性、雇用創出効果
等のことです。
社会的分野及び経済的分野に関しては、環境分野とは異なり、どのような項目や内容を、どのように取り扱うか等について、まだ社会的合意が成立しているとはいえないというのが現状であり、今後、さまざまな検討が積み重ねられ実務の成熟を待つ必要があります。また、社会的取組の状況については、組織の社会的責任の観点から、ISO(国際標準化機構)が規格の開発を開始する等進展しており、これらの国内外の動向にも留意していく必要があります。
ISO26000 の「組織の社会的責任指針(案)」では、組織の社会的責任をめぐる課題として、環境の他、人権、労働慣行、組織統治、公正な事業活動、コミュニティ参画及び社会開発、消費者課題が掲げられています。
本ガイドラインの第4章「社会的取組の状況」に関する情報・指標を参考にしつつ、報告の対象分野を拡大していくことが期待されます。
5.環境報告書の活用にあたっての留意点
(1)ステークホルダーとの関わり
?ステークホルダーとは
ステークホルダーとは事業者等の環境への取組を含む事業活動に対して、直接的または間接的に利害関係がある組織や人物をいいます。事業者の利害関係者には、消費者、投資家、取引先、従業員、地域住民、行政組織等が考えられます。
環境報告書には、ステークホルダーが行うさまざまな意思決定や判断に必要な情報を適切に記載することが期待されます。
?重要な項目の考え方
環境報告書は、事業者が社会との間で行うコミュニケーションの重要なツールであり、その読み手にはさまざまなステークホルダーが考えられます。環境報告書に求められる情報の内容や質は、ターゲットとするステークホルダーにより異なってきます。
環境報告書のステークホルダーが必要としている情報を的確に抽出するには、ステークホルダーとの協議を行なったり、関与(エンゲージメント)3を促進する等が考えられます。
?環境報告書の対象となるステークホルダー
環境報告書の対象となるステークホルダーには、顧客(消費者を含む)や生活者、株主や金融機関、投資家、取引先、従業員及びその家族、学識経験者や環境NGO、消費者団体、学生、さらには地域住民や行政とさまざまな主体が考えられます。環境報告は、このようなステークホルダーに自社の環境配慮への取組を効率的かつ効果的に説明することができます。
一方、環境報告書によって、ステークホルダーの環境意識等が向上することや、環境保全への活動が促されることも期待できます。また、環境報告書は、外部のステークホルダーに向けてのみ作成されているのではなく、その事業者の経営陣をはじめとする役員、従業員やその家族等も重要な環境報告書の読み手であると言えます。
いずれにしろ、主としてどのような読み手やステークホルダーを想定して環境報告書を作成するのか、あるいは全ての主体を対象とした環境報告書を作成するのか等を十分に検討することが大切です。本ガイドラインは一般的に想定される主な読み手の全てを念頭において編集しましたが、以下に主な読み手について説明します(ただし、順不同)。
○顧客(消費者を含む)
環境問題の深刻化や顕在化に伴い、顧客(消費者を含む)等の環境等に対する意識は ステークホルダーの「関与(エンゲージメント)とは、組織がステークホルダーを理解し、彼らを組織の活動および意思決定過程に関与させるすべての努力を包含する包括的な用語です。
ステークホルダーへの情報伝達や相談(Consultation)、対話(Dialogue)、協働(Partnership)等の相互的で意欲的な協力関係をいいます。
高まりつつあり、これまでの価格や品質に加え、環境配慮等の側面が製品やサービスを選択する際の判断材料の一つになってきています。
○株主、金融機関、投資家
株主や金融機関、投資家は、従来に増して環境報告の対象となる重要なステークホルダーとなりつつあります。欧米のみならず我が国においても、事業者の事業活動への環境配慮等の取組状況は、投資や融資の際の判断材料の一つとして考えられています。
具体的には、社会的責任投資(SRI)等に見られるように環境問題等に熱心に取り組んでいる事業者を支援していきたいという考えや、環境問題等への対応の有無をリスクや機会と捉え、その取組如何が事業者の今後の業績を左右するという考えが広がりつつあります。
これらのステークホルダーは、事業活動における環境配慮の取組状況や環境に関する規制遵守状況等に強い関心を持っていると考えられます。
○取引先(購入・調達の依頼先や発注の相手先等)
納入先や発注者等による環境に配慮したサプライチェーンマネジメントの一環として、環境問題に適正に取り組むことを取引(入札や発注等)の条件の一つとする動きが強まってきています。
納入先や発注者等の取引の相手先に対する、環境問題に係る取引先の関心事としては、環境マネジメントの状況、化学物質の使用、管理の状況等が考えられます。
○従業員及びその家族
有能な従業員を雇用するとともに、従業員の志気を向上させ、自らの事業者に対する誇りを養うためには、環境方針や自らの事業活動への環境配慮の取組に関する姿勢を示し、従業員やその家族から理解を得ることが重要になります。また、従業員への教育・研修のツールとして、環境報告書を活用することも考えられます。
○学識経験者、環境NGO、消費者団体
これらの団体等は環境問題等に関するオピニオンリーダーとして、あるいは専門的な立場から、事業者の事業活動への環境配慮等の取組状況を評価し、一般にわかりやすく伝えるインタープリター(通訳者)の役割を果たしており、一般の消費者やマスコミに強い影響力を持っています。
これらのステークホルダーに対しては環境配慮の取組状況や事業活動に伴う環境負荷の状況等、経年変化を示すことや、業界内での比較が容易な形で示すことが重要です。
○学生等
近年、環境に関する学部や学科、講座を有する大学が増えてきており、環境問題に取り組む学生サークルも数多く存在し、活発に活動しています。これらの場で活動する学生等から事業活動における環境配慮等の取組について高い評価を得ることは、将来の顧客の獲得や有能な従業員の採用等に大きな影響を及ぼすものと考えられます。
○地域住民
地域住民は、工場等においてどのような環境保全への取組が行われているか、特に公害防止の対策や環境事故の未然防止対策等がどのように行われているかについて、関心を持っています。特に事業所単位のサイト環境レポートについては地域住民を意識して重要性の判断を行うことが望まれます。
○行政
行政は、所管地域内の環境負荷の状況などを把握する必要があり、事業者は環境規制に従って環境報告を行うことが必要です。地方公共団体においても、地域の環境基本計画や地球温暖化対策行動計画等の中で、地域の事業者を計画の主要な対象として事業者の自主的な取組を通じた環境報告を促進し、その事業活動における環境負荷の低減を図ろうとする動きがあります。また、グリーン購入の進展と共に、入札参加や事業発注の条件の一つとして、環境マネジメントシステム(ISO14001 やエコアクション21等)の認証取得や環境報告書の作成・公表等を求める事例も増えています。
(2)環境報告書の活用
?公表媒体について
環境報告書の公表にあたっては、事業者を取り巻くステークホルダーとのコミュニケーションを深め、より多くのステークホルダーが活用する機会を作ることが大切です。また、環境報告書の情報がインターネットやマスメディア等のさまざまな媒体により、広く提供されることが期待されます。
そこで定期的な環境報告書の発行に加えて、より高い頻度で開示することが適切で重要な環境パフォーマンス情報や環境配慮の取組について、インターネット等を活用した追加的な情報発信をすることも有効であり、報告書の質を落とさずに複数の公表媒体の効果的かつ相互に連携した利用が期待されます。
インターネットは読み手が手軽に情報を入手できる手段として、また、情報を容易に最新の状態に更新することが可能であるという特徴を活かし、時宜にかなった情報を提供することができます。環境活動情報を冊子による環境報告書に記載するだけではなく、環境報告書とインターネットを併用する等の工夫をする等、読み手にとって必要な情報をタイムリーに提供することが期待されます。例えば、「環境報告の概要(BI-4)」にある「主要な指標等の一覧(BI-4-1)」等、環境報告書の主要な情報の公表や、詳細なデータをインターネット上で公表することも考えられます。
ただし、インターネットを併用する場合は、掲載している情報がどの時期の情報であるかを明記し、冊子の情報との違いが分かるように工夫することや、関連した情報を掲載したインターネットのURLを冊子に示す等、冊子の情報との関係を明確
にすることが必要です。また、過去の情報についても参照できるようにしておくことが期待されます。
事業者の環境に関する活動が活発になるに従って、公表する環境配慮等の情報が増加する傾向にあります。より多くのステークホルダーに、より簡潔に環境報告書の内容を伝えたい場合には、環境報告書の要点のみを分かりやすくまとめた、いわ
ゆるダイジェスト版等を別途作成し、広く配布する方法もあります。
また、事業所を立地して活動している地域の情報に特化した地域版の環境報告書(環境サイトレポート)も地域とのコミュニケーションにおいて有効と考えられます。環境サイトレポート等については、地域住民等が必要とする水資源投入量、大気汚染や生活環境に係る負荷量、化学物質の排出量、総排水量等の地域性の高い環境パフォーマンスに関する情報や地域での活動に関する情報等に重点を置いて、簡潔に取りまとめることが望まれます。
どのような方法で環境報告書を公表するかは、想定される環境報告書の利用者の利便性や理解容易性を考慮し、事業者が自ら有効と判断した媒体、表現手段、作成方法を選択する必要があります。
なお、環境に関する重要な事象が起きた場合には、関連する情報を速やかにインターネット等で公表することが期待されます。
?トピックス・特集について
事業者の環境配慮等の活動の中で、社会的に注目を集めている特定の事象や活動(自社に不利な情報を含む)、ステークホルダーとの関係から重要と判断される情報について、トピックスや特集のページを設けて環境報告書に掲載する等、読み手
の関心に応える工夫をすることが期待されます。
また、必要に応じて、特集に記載することにした背景についても読み手に説明することや図表や写真等を活用し、わかりやすく説明することが望まれます。
ただし、トピックス・特集をもって体系的な情報の代わりとすることはできません。トピックスや特集にスペースを割きすぎることによって、必要な情報が十分に提供されないことのないように配慮する必要もあります。
6.環境報告書の内容及び信頼性を向上させるための作成過程における方策
環境報告書を作成する過程では、環境報告書の内容をより良いものとし、「信頼性」を高める(すなわち重要な情報の網羅性、正確性、中立性、検証可能性の観点からより適切なものとする)ための努力が求められます。そのためには、まず、事業者自らが報告書の内容について評価するとともに、報告書の基礎となる情報を正確なものとするよう努力が必要です。
また、環境報告書の作成過程にステークホルダーが参画する、できあがった環境報告書についての意見をステークホルダーに求め意見書を添付する、中立的な第三者の審査を受ける等、組織外の主体が関わることで、事業者自身が見落としていた論点が明らかになり、報告書の内容が向上し、信頼性がさらに高まることも期待されます。
これらはいずれも重要な取組ですが、ステークホルダーとの関わり方や第三者からの外部審査の必要性、さらに事業者の経営資源の状況や環境報告書の作成の成熟度に応じて、また、必要に応じて組み合わせて取り組むことが期待されます。
事業者自らが実施する信頼性を向上させる方策の例は、次の通りです。
?自己評価の実施
自己評価は、環境報告書の信頼性についてチェックリストを用いつつ事業者自身がレビューするもので、自己評価を行った場合にその手法・過程・結果等を公表するものです。
環境省では、「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」を作成していますので、この手引きが活用されることを期待します。
「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」:
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
?内部管理の徹底
これは、事業者内部の環境マネジメントシステム(ISO14001 やエコアクション21 等)を徹底し、内部監査等を厳格に行う取組であり、事業者自身が情報の比較容易性や信頼性を確認するものです。内部監査を実施する過程で、環境報告書で公表する数値データの把握・集計・評価・公表の仕方や、外部コミュニケーションにおける環境報告書の活用状況及びステークホルダーとのコミュニケーションの状況についても確認することが期待されます。
?内部監査基準や環境報告書作成の基準等の公開
これは、事業者自身が、その内部監査の基準や環境報告書作成の基準等を公開する取組であり、特に環境報告書の作成の基準が明らかにされれば、外部の第三者がそれに基づいてレビューを行うことも可能となります。
?社内監査制度等の活用
これは、社内で環境報告書を作成した部門以外の社内組織等、例えば役員や監査担当部署、監査役や社外取締役等が客観的な視点をもって、環境報告書を検証するものです。
事業者以外の第三者が実施する信頼性を向上させる方策の例は、次の通りです。
?双方向コミュニケーション手法の組込
これは、環境報告書の記載情報や環境保全への取組について、事業者がステークホルダーからの質問や意見に回答するだけでなく、両者が相互に意見を交換する仕組みを作ったり場を設けたりする取組です。事業者とステークホルダー等による座
談会や説明会を開催し、その概要を環境報告書に掲載する事例もあります。
?第三者による意見
これは、環境報告書を作成する事業者以外の主体(第三者)が、環境報告書の記載情報について評価や勧告等の意見を表明したり、環境報告書の背景にある事業者の取組に対して意見を表明するものです。なお、意見を表明する第三者の選択基準
やその第三者の作成段階における関与の状況等、第三者意見表明の手続の概要を記載するとともに、第三者の意見に対して、事業者側が今後どうしていくのかについてコミットメントすることが望まれます。
?第三者による審査
これは、環境報告書を作成する事業者以外の第三者(監査法人等の審査機関)が、環境報告書の記載情報やその背景にある取組内容の結果(環境パフォーマンス指標)について、適切な作成基準に従って作成されているかどうかを審査し、それらの正確性を中心とする審査の結論を表明するものです。その際は、事業者が本ガイドラインや他のガイドライン等から適切なものを選択し、あるいは自ら定めた作成基準に従って環境報告書を作成し、その作成基準を審査機関が判断規準(クライテリア)
として審査を行います。
?NGO・NPO 等との連携による環境報告書の作成
環境報告書の企画、作成の過程にNGO・NPO のスタッフ、学生、一般消費者等が直接関わり、事業者との一種の共同作業により環境報告書を作成する取組であり、連携の方法には単に意見交換を行うものから、記載情報のチェックを行うものまで、
さまざまな内容があります。
また、参考資料の7.【チェックリスト】等を用いて本ガイドラインへの準拠の状況を示すことも信頼性の向上に資すると考えられます。
上記のような環境報告書の内容及び信頼性を向上させる取組と合わせて、それらの取組の結果や意見等に対応した状況についても、環境報告書に記載することが期待されます。
第2章 環境報告の記載項目の枠組み
1.環境報告の全体構成
環境報告には「環境報告として記載すべきと考えられる項目」があります。これは、環境報告により社会的説明責任を果たすとともに、ステークホルダーの意思決定に有用な情報を提供するため、さらには環境報告が環境コミュニケーションのツールとして機能するために不可欠な項目であり、現在発行されている多くの環境報告書等で網羅されている項目です。環境報告として記載する情報・指標は、次の5つの分野に分類されます(第3章を参照)。
(1)基本的項目
(2)環境マネジメント等の環境経営に関する状況
(3) 事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況
(4)環境配慮と経営との関連状況
(5)社会的取組の状況
上記の各分野の中で環境報告として記載する項目は、以下のとおりです。
(1)基本的項目(BI, Basic Information)
経営責任者の緒言、報告にあたっての基本的要件(報告範囲の環境負荷の捕捉
状況を含む)、経営指標を含む事業概要及び主要な指標等の一覧等で、事業者が
環境に係る説明責任を果たすとともに、ステークホルダーの意思決定に有用な情
報を提供し、社会との環境コミュニケーションを図りパートナーシップを構築し
ていく上での基礎的な内容です。
なお、経営責任者の緒言は、単なる挨拶ではなく、事業活動における環境配慮
の取組状況に関する総括と社会に対しての誓約となっていることが必要です。ま
た、事業者の事業活動に伴う環境負荷の状況と事業活動における環境配慮の取組
の全体像を説明します。目標、計画、実績等については、環境負荷の状況も含め
て一覧表等に取りまとめることが望まれます。
基本的項目として記載する項目は、以下の5項目です。
BI-1:経営責任者の緒言
BI-2:報告にあたっての基本的要件
BI-2-1:報告の対象組織・期間・分野
BI-2-2:報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況
BI-3:事業の概況(経営指標を含む)
BI-4:環境報告の概要
BI-4-1:主要な指標等の一覧
BI-4-2:事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括
BI-5:事業活動のマテリアルバランス(インプット、内部循環、アウトプット)
(2)「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す情報・指標(環境マネジメント指標:MPI, Management Performance Indicators)
事業者の環境経営における環境配慮の取組について、その方針、目標、計画及
び実績について説明します。
また、事業者の組織的な環境マネジメント全般の状況についてまとめて説明す
るパートでもあり、環境マネジメントシステム、環境に関する規制遵守の状況、
環境会計情報、環境に配慮した投融資、環境に配慮したサプライチェーンマネジメ
ント、環境に配慮した新技術等の研究開発状況、生物多様性への対応、環境コミ
ュニケーションの状況等、さらに、環境負荷低減に資する製品・サービスの状況(無
形のサービス・役務を含む)についても記載します。
環境マネジメント指標として記載する項目は、以下の12項目です。
MP-1:環境マネジメントの状況
MP-1-1:事業活動における環境配慮の方針
MP-1-2:環境マネジメントシステムの状況
MP-2:環境に関する規制の遵守状況
MP-3:環境会計情報
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
MP-5:サプライチェーンマネジメント等の状況
MP-6:グリーン購入・調達の状況
MP-7:環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
MP-9:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
MP-10:環境コミュニケーションの状況
MP-11:環境に関する社会貢献活動の状況
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
(3)「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標(オペレーション指標:OPI, Operational Performance Indicators)
事業活動全体における物質やエネルギー等のインプット、アウトプットを把握
するマテリアルバランス*の考え方に基づき事業活動の環境負荷を捉えます。
事業者が自らの事業活動において環境負荷の低減に向けて取り組んでいる方
針、目標、計画、環境パフォーマンスの状況及びその実績等を中心に記載します。
また、環境負荷削減の観点から、環境配慮の状況を明らかにしていくことが重要
で、その内訳についても記載することが期待されます。また、製品・サービスの
ライフサイクルでの環境負荷低減等、事業活動の上流・下流部分での取組や実績
についても記載することが望まれます。
オペレーション指標として記載する項目は、以下の10項目です。
(インプット)
OP-1:総エネルギー投入量及びその低減対策
OP-2:総物質投入量及びその低減対策
OP-3:水資源投入量及びその低減対策
(内部循環)
OP-4:事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
(アウトプット)
(製品)
OP-5:総製品生産量又は総商品販売量
(排出物・放出物)
OP-6:温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP-7:大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
OP-8:化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP-9:廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
OP-10:総排水量等及びその低減対策
(4)「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標(環境効率指標:EEI, Eco-Efficiency Indicators)
環境負荷はその総量を削減することが事業者に求められています。一方、事業経営
の観点から、経済効率性の高い環境への取組が求められています。そのため、事業者
の環境パフォーマンスや環境への取組を把握・評価する場合には、環境負荷の総量を
示す指標だけでなく、事業者の生み出す経済価値を反映しながらその環境への取組の
効率性を表す指標(以下、「環境効率指標」)を把握・管理することが重要になります。
本ガイドラインでは、第三次環境基本計画の「総合的環境指標*」も参考にして、
代表的な事例を紹介します。
(注)
上記4分野のうち、(2)環境マネジメント指標(MPI)、(3)オペレーション
指標(OPI)及び(4)環境効率指標(EEI)の3分野の情報・指標を合わせて、「環
境パフォーマンス指標(EPI, Environmental Performance Indicators)」と称するこ
とにします。
(5)「社会的取組の状況」を表す情報・指標(第4章)(社会パフォーマンス指標:SPI, Social Performance Indicators)
近年、環境報告書の記載内容を広げ、社会・環境(CSR)報告書等として、事
業者の社会的側面についても情報開示、報告する取組が広がりつつあります。し
かし、社会的側面の記載項目については、まだ社会的合意が成立しているとはい
えない段階にあるといえます。本ガイドラインでは、我が国の既発行の社会・環
境(CSR)報告書等から代表的情報・指標等を取り上げるとともに、法律等にお
いて開示が求められている情報、及び今後記載が重要になると考えられる情報を
取りまとめました。
? 労働安全衛生に関する情報・指標
? 雇用に関する情報・指標
? 人権に関する情報・指標
? 地域及び社会に対する貢献に関する情報・指標
? 企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引に関する情報・指標
? 個人情報保護に関する情報・指標
? 広範な消費者保護及び製品安全に関する情報・指標
? 企業の社会的側面に関する経済的情報・指標
? その他の社会的項目に関する情報・指標
第3章 環境報告における個別の情報・指標
前章では環境報告の全体構成(5分野)並びにその概要を述べましたが、本章では
環境報告における基本的項目(BI)と環境パフォーマンス指標(EPI)に関連する各
分野について、記載する個別の情報・指標の要点を説明します。社会パフォーマンス
指標(SPI)に関しては、第4章にて説明します。
【環境報告における情報・指標の分類】
(1) 本章では、環境報告において全ての事業者に共通して重要性があると考えられる
記載すべき項目は「(1)記載する情報・指標」として「ア.〜」「イ.〜」「ウ.〜」・・・
で表記しています。また、環境報告書の基本的機能を踏まえ、持続可能な社会の
構築に向けて必要に応じて記載することが望ましい推奨項目は「(2)記載するこ
とが期待される情報・指標」として「?〜」で表記しています。
(2) 「(1)記載する情報・指標」及び「(2)記載することが期待される情報・指標」の
それぞれにおける例示項目を「・〜」で表記しています。
(注)
? 情報・指標の記載にあたっては、必要に応じて国内・海外に分けて記載することが望まれます。
? 算定式や単位は一般的なものを記載していますが、実務上で用いられている算定式
や単位で記載することができます。また、算定に用いた算定式や係数等を記載する
ことが必要です。
? 本ガイドラインは環境報告の項目立て及び各項目の情報・指標の記載の仕方や順番
を規定するものではありません。記載する情報・指標の内容が重複する場合は、項
目毎に記載する必要はなく、まとめて記載することができます。
? 環境報告にあたっては、第3章の全ての項目の情報を記載することが望まれますが、
環境への影響が無い、もしくは非常に小さいと判断される項目等については、記載
しない理由を明記します。(参照:参考資料の3.【Q&A】)
? 環境報告書には第3章の環境報告の項目と第4章の社会的取組の状況をあわせて5
分野29項目全てを記載することが期待されます。
1.基本的項目(BI)
環境報告書に記載する環境報告の「基本的項目」(BI)は以下の5 項目です。本節で
は、それぞれの基本的な考え方や記載する具体的な情報・指標等について解説します。
(基本的項目:BI)
BI-1:経営責任者の緒言
BI-2:報告にあたっての基本的要件
BI-2-1:報告の対象組織・期間・分野
BI-2-2:報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況
BI-3:事業の概況(経営指標を含む)
BI-4:環境報告の概要
BI-4-1:主要な指標等の一覧
BI-4-2:事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括
BI-5:事業活動のマテリアルバランス(インプット、内部循環、アウトプット)
BI-1:経営責任者の緒言
経営責任者の緒言は、環境報告書の巻頭に記載され、経営責任者のコミットメント
(誓約)に加えて、事業者自身の環境経営の方針、取組の現状、将来の目標等が現状
や実績を踏まえて総括的に盛り込まれたものであり、極めて重要なものです。
さらに、総括やコミットメント(誓約)の内容は、自らの業種、規模、事業特性等
に応じた適切かつ具体的なものである必要があり、単なる一般論を述べるだけでは不
十分です。
なお、「社会的取組の状況」についても併せて報告する場合、企業の社会的責任全
体に関するコミットメントを行うことが必要です。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境経営の方針
イ.環境問題の現状、事業活動における環境配慮の取組の必要性及び持続可能な社
会のあり方についての認識
ウ.自らの業種、規模、事業特性あるいは海外展開等に応じた事業活動における環
境配慮の方針、戦略及び事業活動に伴う環境負荷の状況(重大な環境側面)と
その低減に向けた取組の内容、実績及び目標等の総括
エ.これらの取組に関して、確実に実施し、目標等を明示した期限までに達成し、
その結果及び内容を公表すること、についての社会へのコミットメント
オ.経営責任者等の署名
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 持続可能な社会の実現に貢献するための経営方針、目標等(社会的取組に関するものも含む)
? 環境報告の記載内容について、事業活動に伴う重大な環境負荷及びその削減の目標・取組等を漏れなく記載し、正確であることの記載
? 環境変化が及ぼす事業への影響
? 報告範囲に関する経営責任者の考え方や方針
? 報告内容の信頼性確保に関する経営責任者の考え方や取組の方針
? 環境報告の外部審査を受審した場合は、その旨
(3) 解説
経営責任者の緒言は、経営責任者もしくは代表権のある環境担当役員の環境報告
にあたっての概括的なステートメントとして記載されるものです。そのため、細か
な点を詳しく述べるのではなく、経営責任者の「環境経営」に対する考え方が、経
営責任者自身の言葉で率直に語られるとともに、その実行を社会に対してコミット
メント(誓約)を行うことが必要です。
環境報告にあたっては
・自らの業種、規模、事業特性あるいは海外展開等を踏まえる
・事業活動における環境配慮の方針、事業活動に伴う環境負荷の状況、事業活動
における環境配慮の取組内容、実績及び目標等を明確かつ簡潔に総括する
・これらの取組を確実に実施し、目標等を明示した期限までに達成することを誓約する(コミットメント)
こと等に配慮することが望まれます。
さらに可能であれば、環境報告の内容について、事業活動に伴う重大な環境負荷
及びその削減の目標や取組等を漏れなく記載し、正確であることを記すこと、環境
情報を積極的に開示し、ステークホルダーとの環境コミュニケーションを積極的に
図っていくこと等を表明することも望まれます。また、報告範囲の概要や報告内容の
信頼性の確保等にも言及することが望まれます。
これは、事業の実態を踏まえた適切かつ正確な環境報告のための環境報告書を作
成・公表して、社会的説明責任を果たし、ステークホルダーに意思決定のための情
報を提供することは、経営責任者の重要な責務の一つであり、経営責任者自身が環
境報告書の記載内容に責任を持つことが必要であると考えられるからです。
BI-2:報告にあたっての基本的要件
BI-2-1:報告の対象組織・期間・分野
環境報告書による環境報告の公表にあたっての基本的要件である、対象組織、対象
期間、対象分野、準拠あるいは参考にした環境報告等に関する基準又はガイドライン
等について具体的に記載します。
併せて、環境報告を環境コミュニケーションツールとするために必要な、作成部署
の明確化や連絡先の明示等の他、意見や質問等を受付ける方法等を工夫することが必
要です。
(1) 記載する情報・指標
ア.報告対象組織(過去に環境報告書を発行している場合は、直近の報告書における報告対象組織からの変化や経緯等についても記載する。)
イ.報告対象期間、発行日及び次回発行予定(なお、過去に環境報告書を発行している場合は、直近の報告書の発行日も記載する。)
ウ.報告対象分野(環境的側面・社会的側面・経済的側面等)
エ.準拠あるいは参考にした環境報告等に関する基準又はガイドライン等(業種毎のものを含む。)
オ.作成部署及び連絡先
カ.ウェブサイトのURL
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? ステークホルダーからの意見や質問を受付け、質問等に答える旨の記述等、何らかのフィードバックの手段
? 主な関連公表資料の一覧(会社案内、有価証券報告書、ISO14001及びエコア
クション21等の認証取得事業者はその環境方針及び著しい環境側面に関する
コミュニケーション資料、環境パンフレット、技術パンフレット等の主な関連
資料の一覧、その概要や入手方法)
(3) 解説
報告にあたっての基本的要件である対象組織・期間・分野の記載は、特定のわか
りやすい場所に記載することが求められます。
なお、報告対象組織の記載において、連結決算対象組織の一部を報告対象とする
場合は、連結決算対象組織との異同について会社名を挙げて記すことが望まれます。
記載する項目によって対象組織の範囲が異なる場合は、対象組織を明確に記載す
ることが望まれます。
特に、海外での事業については、国内の活動の報告と区別して記載することが期待されます。
環境報告書をインターネットにおいて公表している場合は、そのインターネット
のURLを記載します。さらに、冊子やインターネット以外の媒体(CD-ROM等)で発
行している場合は、その内容と入手方法を記載します。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 報告対象組織については、工場・事業所・子会社等の範囲、海外事業所の範囲、
連結決算対象組織との異同を示すべきです。なお、全体を対象としていない場
合で対象を拡大する予定がある場合は、そのスケジュール等を記載します。ま
た、記載項目等により範囲が異なる場合は、項目毎の範囲を記載します。
(ii) 環境報告に当たり準拠あるいは参考にした基準又はガイドライン等と実際に報
告した内容や項目との比較表等があれば、読み手にはわかり易くなります。
(iii) 連絡先には、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等も記載します。
BI-2-2:報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況
環境報告で対象とする組織の範囲(バウンダリー)は、原則として連結決算対象組
織全体であることが期待されますが、報告対象組織の範囲を限定している場合には、
その報告対象組織における環境負荷が連結決算対象組織全体における環境負荷の内ど
の程度を捕捉しているかを記載します。
その際、報告対象組織及びその環境負荷が事業全体の環境負荷の内どの程度を占め
ているかを読み手に伝えるために、事業者が独自に工夫してその捕捉状況を記載しま
す。さらに報告対象組織の範囲を限定した考え方や計算根拠等を明示する必要があり
ます。
(1) 記載する情報・指標
ア.報告対象組織の環境負荷が事業全体(連結決算対象組織全体)の環境負荷に占める割合(「環境負荷の捕捉率」等による状況)
ただし、環境負荷の捕捉率が正確に把握できない場合は、捕捉対象の環境負荷が
連結決算対象組織全体における環境負荷に占めるおおよその割合を記載し、順次、
精度を向上させていくことが望まれます。
環境負荷の捕捉率を示す指標としては、例えば、次のような情報や指標が考え
られます。
・ 連結決算対象組織全体の温室効果ガス排出量に対する報告対象組織の温室効
果ガス排出量の割合(エネルギー使用量や事業内容によっては、電力消費量
等把握の容易なもので代替することも考えられる。)
・ 連結決算対象組織全体の資源投入量に対する報告対象組織の資源投入量の割合
・ その他、事業内容に応じ、代表的な環境負荷に関する環境負荷の捕捉率
・ 上記以外に、事業者独自の創意工夫による事業全体に対する環境負荷の捕捉率
上記の指標について、十分な情報が得られない場合、次のような指標を補足的
に、必要に応じて組み合わせる必要があります。なお、これらの指標については、
当該指標を用いた考え方を示すことが期待され、採用したこれらの指標によって、
おおよその環境負荷の捕捉状況が明らかになることを説明する必要があります。
・連結決算対象組織全体の売上高に対する報告対象組織の売上高の割合
・連結決算対象組織全体の従業員数に対する報告対象組織の従業員数の割合
・上記以外に、事業者独自の創意工夫による指標
(2) 解説
報告対象組織の「環境負荷の捕捉率」とは、報告対象組織の事業活動に伴う環境
負荷が事業全体の環境負荷に占める割合を示す指標です。事業者の財務上の報告範囲
は連結決算対象組織が基本となっていることから、「環境経営」の報告である環境報告
の範囲も、原則としては連結決算対象組織の全てを報告範囲とし、その環境負荷を記
載することが期待されます。
しかし、報告対象組織の範囲を決定する際に、連結決算対象組織の特
定の範囲で環境負荷の大半が捕捉出来る場合には、その範囲を報告対象としても大き
な問題は発生しないと考えられます。また、限られた組織から報告を始め、徐々に対
象組織を広げることも考えられます。そこで、実際に報告対象となった組織の環境負
荷の捕捉率を示す必要があります。
しかしながら現状では、多くの環境報告書では、事業者の報告範囲の環境負荷が連
結決算対象組織全体の中でどれ位捕捉されているかが曖昧です。このことは事業者自
身にとってもステークホルダーにとっても、その判断や意思決定を誤らせる可能性が
あり、環境負荷の捕捉状況は「環境経営」における最も基本的かつ重要な事項と考え
られます。
特に、海外で事業展開する日本企業が増加している現状に鑑み、国内だけでなく海外
を含めた自らの環境負荷の全体像を正確に把握・管理するために、効率的・効果的な環
境負荷の計測・収集システムを構築することが強く期待されます。
連結決算対象組織の環境負荷の把握については、出資比率で計算する方法もあります
が、出資比率とは関係なく100%として把握する方法を原則とします。出資比率で計算
する方法を採用した場合には、その旨を明記することが必要です。
BI-3:事業の概況(経営指標を含む)
報告者がどのような事業者で、どのような事業活動をし、その規模等はどの程度な
のかをわかりやすく説明することが必要です。事業の概況が適切に記載されていなけ
れば、その事業者の事業特性等に応じたどのような環境負荷があるのか、事業活動に
おいて環境配慮の取組がどのように重要なのかわかりません。
したがって、事業の具体的内容、主要な製品やサービスの内容、財務データを含む
経営指標値等をわかりやすく、具体的に記載します。特に報告の対象組織については、
前回の報告からの変化や経緯等についても記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.主たる事業の種類(業種・業態)
イ.主要な製品・サービスの内容(事業分野等)
ウ.売上高又は生産額(連結決算対象組織全体及び報告事業者単独、報告対象組織)
エ.従業員数(連結決算対象組織全体及び報告事業者単独、報告対象組織)
オ.その他の経営関連情報(総資産、売上総利益、営業利益、経常利益、純損益、付加価値額等)
カ.報告対象期間中に発生した組織構造、株主構成、製品・サービス等の重大な変
化の状況(合併、分社化、子会社や事業部門の売却、新規事業分野への進出、
工場等の建設等により環境負荷に大きな変化があった場合)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 主たる事業活動の範囲、工場・事業所数、本社・主要な工場・事業場の所在地及びそれぞれの生産品目
? 全体的な経営方針等(可能な範囲で、今後の海外での事業展開を含む)
? 事業者の沿革及び事業活動における環境配慮の取組の歴史等の概要
? 対象市場や顧客の種類(小売、卸売り、政府等)
(3) 解説
経営指標を含む事業の概況について記載する項目です。製品・サービスの生産・
販売額(売上高)、従業員数等の重要な経営指標は、環境負荷単位当たりの製品・
サービス価値(環境効率(Eco-Efficiency))、製品・サービス価値単位当たりの環
境負荷(環境負荷集約度)等を算出する際の基礎データとして必要不可欠な情報で
す。これらの情報については、後述する環境パフォーマンス指標(EPI)のひとつと
して環境効率指標(EEI)にて詳しく述べることにします。なお、経営指標につい
て、業界等で概ね合意された指標がある場合は、それを記載することが望まれます。
また、事業の概況の記載にあたって、主たる事業の種類(業種業態)及び主たる
事業活動の範囲(活動拠点)について、事業活動に伴う環境負荷や事業活動におけ
る環境配慮の取組状況との関連を含めて具体的に、かつ、わかりやすく記載するこ
とが望まれます。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 売上高、生産額あるいは従業員数については、少なくとも過去5 年間程度を記載します。
(ii) 事業者の生産品目の記載にあたっては、主要な原材料の採掘、調達、営業や販
売活動を行っている地域について、日本国内だけか、海外も含むのか、特定地
域のみか等を考慮します。
BI-4:環境報告の概要 BI-4-1:主要な指標等の一覧
事業の概況(BI-3参照)、環境に関する規制の遵守状況(MP-2参照)、温室効果ガ
スの排出量(OP-6参照)、廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量(OP-9参照)及び事
業活動にとって重要と考えられる項目について、サマリーとしてまとめ、見開き程度
の内容で、図表を活用してわかりやすく、簡潔に記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア. 事業の概況(会社名、売上高、総資産等)(過去5年程度、BI-3参照)
イ. 環境に関する規制の遵守状況(MP-2参照)
ウ. 主要な環境パフォーマンス等の推移(過去5年程度)
・総エネルギー投入量(OP-1参照)
・総物質投入量(OP-2参照)
・水資源投入量(OP-3参照)
・総製品生産量又は総商品販売量(OP-5参照)
・温室効果ガスの排出量(OP-6参照)
・化学物質の排出量、移動量(OP-8参照)
・廃棄物等総排出量及び廃棄物最終処分量(OP-9参照)
・総排水量等(OP-10参照)
・環境効率指標(EEI参照)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境に関する特記事項等(環境機器の導入等の環境負荷の低減対策、土壌汚染の発覚等の当年度の特記すべき取組や成果等)
? 報告対象組織
(3) 解説
事業特性に応じた環境負荷の発生ないし抑制・削減の状況が一目で理解できるよ
うな概要を記載することが望まれます。その上で、環境規制の遵守状況や温室効果
ガス、廃棄物等の排出量、さらに事業特性からみて重要と考えられる項目を要約する
形でコンパクトにまとめることが望まれます。
「主要な指標等の一覧」は、事業者における重要な環境負荷の推移を時系列に比
較するのに有効です。ただし、重要な環境負荷の判断については、業種特性や事業
規模等による違いがあり事業者間の比較は容易でないことが想定されますし、ステ
ークホルダーによっても判断基準が異なることも想定されます。環境報告書の読み
手が事業者間の比較をする場合は、それぞれの指標が持つ特性や限界等に十分留意
することが必要です。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 表記方法としては、一覧表やグラフを用いてわかりやすく表記することが期待
されます。参考資料に表記方法の例を記載しています。
BI-4-2:事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括
事業活動における環境配慮の方針に対応した、長期目標及びその推移、当期及び
次期報告対象期間の目標、それぞれの目標に対応した計画、報告対象期間の環境負
荷の実績及び推移、その低減のための取組の状況、取組結果の評価分析や改善策等
を、基準とした期のデータとともに、全体を一覧表形式で記載します。
また、必要に応じて環境報告全体の概要を記載すると、よりわかりやすくなります。
(1) 記載する情報・指標
ア.事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績、改善策等の総括
例えば、次のような情報や指標を用いて「総括」を示すことが考えられます。
・環境負荷の実績及び推移
・環境負荷の実績及び推移に関する分析・検討内容
・事業活動における環境配慮の取組に関する中長期目標及びその推移、当期及び次期対象期間の目標
・中長期目標については、制定時期、基準とした時期、対象期間及び目標時期
・目標の対象期間末までの達成状況
・事業活動における環境配慮の取組に関する中長期目標、当期及び次期対象期間
の目標に対応した計画、報告対象期間の環境負荷の実績、事業活動における環
境配慮の取組結果等に対する評価及び改善策
・基準とした時期のデータ
・環境報告全体の概要及びそれぞれの内容の対応ページ
・事業内容、製品・サービスの特性に応じた事業活動における環境配慮の取組の課題
・報告対象期間における特徴的な取組
・前回の報告時と比べて追加・改善した取組等
(2) 解説
環境報告全体の概要を記載するとともに、当該事業者の事業活動と環境問題への関
わりがどのような状態にあるのか、さらに、どのような課題があり、どのように改善
するのか等について図表等を用いて表現することは、読み手の理解を助けるために望
ましいと考えられます。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 環境負荷の実績とは、主要な環境パフォーマンス指標の総エネルギー投入量、総
物質投入量、水資源投入量、事業エリア内で循環的利用を行う物質量、温室効果
ガス排出量、大気汚染、生活環境に係る環境負荷量、化学物質排出量及び移動量、
総製品生産量又は総商品販売量、廃棄物等総排出量及び廃棄物最終処分量、総排
水量の報告期間における集計値をいいます(後述のOPI を参照)。これらについ
ては、ステークホルダーが適正な判断を行うことができるように主要な環境パフ
ォーマンス指標に関する分析・検討内容、例えば環境パフォーマンス指標の著し
い改善又は悪化の要因についての分析、環境パフォーマンス指標に重要な影響を
与える可能性のある新技術や新設備の導入に係る情報等を具体的に、かつ、わか
りやすく記載することが求められます。さらに将来に関する事項を記載する場合
には、当該事項は環境報告書発行日現在において判断したものである旨を記載し
ます。
(ii) 事業活動における環境配慮の方針を踏まえた中長期の目標(事業活動における環
境配慮の取組の到達点)と、当期(報告対象期間)及び次期報告対象期間の目標、
目標の達成状況や改善すべき課題等を記載します。目標は、単なる努力目標では
なく、実際に達成すべき目標であり、可能な限り具体的、定量的かつ測定可能な
ものを記載するとともに、目標の達成状況に関する分析・検討内容、例えば、主
要な目標を達成できないと判断した場合の経緯と要因についての分析、今後の取
組方針や新たな目標に係る情報等を具体的に、かつ、わかりやすく記載すること
が求められます。
(iii) これらの目標は、事業活動のライフサイクル全体を踏まえ、事業エリア内のものだ
けでなく、原材料・部材の購入、輸送、製品・サービスの使用・廃棄等の事業活
動の上・下流までを対象とすることが望まれます。目標の設定にあたっては、循
環型社会形成推進基本計画に掲げられている目標(例えば資源生産性、循環利用
率等)等を踏まえて、それぞれの事業者が目標を設定することが期待されます。
(iv) さらに、目標に対応した計画の概要、報告対象期間の環境負荷の実績及びその評
価と改善策、負荷低減のための取組の状況、環境会計情報(事業活動における環
境配慮の取組に要したコスト(環境保全コスト)及び経済的効果等)等の総括デ
ータも併せて記載します。その際、これら全体を一覧表形式等で記載すると、よ
りわかりやすくなります。
(v) 取組の進捗状況を明らかにするため、基準とした期(暦年又は年度等)の環境負
荷の実績等も記載することが望まれます。
(vi) 一方、環境報告の記載項目は多岐にわたるため、当該事業者の事業活動と環境問
題への関わりがどのようにあり、これに対してどのような事業活動における環境
配慮の取組を行っているのかを理解することが難しくなる場合もあります。また、
前回の環境報告と比較して、当該環境報告の対象期間において、どのような特徴
的な取組があり、どのような成果が上がったのかをわかりやすく示すことも望ま
れます。
BI-5:事業活動のマテリアルバランス(インプット、内部循環、アウトプット)
外部のステークホルダーが、事業者の全体的な状況を適切に把握するためには、
事業者が自らの事業活動に対して、全体としてどの程度の資源・エネルギーを投
入し(事業活動へのインプット)、どの程度の環境負荷物質(廃棄物を含む)等
を排出し、どの程度の製品を生産・販売したのか(事業活動からのアウトプット)
を、マテリアルバランスの観点から整理し、公表することが望まれます。併せて、
事業エリア内における循環的資源利用量(エネルギー、廃棄物、水資源等)も記
載します。
なお、このマテリアルバランスは事業者の製造業的活動と非製造業的活動のい
ずれも対象としますが、アウトプットについては有形の製品と放出物・廃棄物の
みを表現するものとします。無形のアウトプットであるサービスや役務等は、別
途環境負荷低減に資する製品・サービスの状況(MP-12)にて記載することとします。
(1) 記載する情報・指標
ア.事業活動に伴う環境負荷の全体像
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境負荷の全体像等に、可能な場合は環境に配慮したサプライチェーンマネジ
メントや製品等のライフサイクル全体を踏まえた環境負荷を付け加える。
(3) 解説
マテリアルバランスの整理、把握にあたっては、原則としてここに示す10 種類のオ
ペレーション指標(OPI)により、事業活動に伴うマテリアルバランスを、実績値が
記載された図等でわかりやすく示すことが求められます。
さらに、事業活動に対する直接的なインプット・アウトプットだけでなく、事業エ
リア内における循環的資源利用量(エネルギー、廃棄物、水資源等)を把握・管理
することが重要です。加えて、原材料の採取段階や、他の事業者から購入する原材料・
部品等の生産段階等で発生する環境負荷、製品の使用・消費・廃棄段階で発生する環
境負荷についても、ライフサイクル全体を踏まえて把握・評価することが重要です。
また、このような事業活動のマテリアルバランスや製品等のライフサイクル全体の
環境負荷を適切に整理、把握することは、事業者自身の事業活動における環境配慮の
取組を効果的・効率的に推進するため、さらには社会全体で地球温暖化対策を推進す
るとともに、物質循環を確保し、持続可能な循環型社会を形成していくためにも必要
であると考えられます。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 事業活動への資源等に関するインプットの状況、事業活動からの製品及び商品
等の提供又は廃棄物等の排出に関するアウトプットの状況、並びに事業エリア
内におけるエネルギー、廃棄物、水資源等の循環的な利用に関する状況等について可能な限り図表等を活用して、わかり
やすく、かつ、簡潔に記載します。
(ii) マテリアルバランスの考え方は第2章(3)「事業活動に伴う環境負荷及びその低
減に向けた取組の状況」を表す情報・指標の表「マテリアルバランス」を参照し
てください。
【指標算定にあたっての留意点<インプットの考え方>】
インプットの投入量は、事業エリア内への投入量として、購入量が想定されます。
在庫(ストック)のない、電力、ガスは、投入量(=購入量=使用量)となりますが、
燃料油や総物質、水資源等の在庫(ストック)がある場合は購入量と使用量が異なり
ます。在庫(ストック)がある場合、消費に伴うアウトプットの環境負荷物質と対応
する投入量としては、期首在庫量と期末在庫量を考慮した使用量(=期首在庫量+購
入量−期末在庫量)になります。したがって、在庫(ストック)がある場合の投入量
は、使用量(払出量)を記載することが望まれます。ただし、期首在庫量と期末在庫
量との差異が僅少の場合には、投入量=購入量としても構いません。
2.「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す情報・指標(MPI)
環境報告書に記載する「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す環境
報告の情報・指標(環境マネジメント指標:MPI)は以下の12 項目です。本節では、
それぞれの基本的な考え方や記載が望まれる具体的な情報・指標等について解説します。
(環境マネジメント指標:MPI)
MP-1:環境マネジメントの状況
MP-1-1:事業活動における環境配慮の方針
MP-1-2:環境マネジメントシステムの状況
MP-2:環境に関する規制の遵守状況
MP-3:環境会計情報
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
MP-5:サプライチェーンマネジメント等の状況
MP-6:グリーン購入・調達の状況
MP-7:環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
MP-9:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
MP-10:環境コミュニケーションの状況
MP-11:環境に関する社会貢献活動の状況
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
MP-1:環境マネジメントの状況 MP-1-1:事業活動における環境配慮の方針
事業活動における環境配慮の取組を行うにあたって、事業活動における環境配慮
の方針(事業活動における環境配慮の取組に関する基本的方針や考え方)を適切に
定め、記載します。
事業活動における環境配慮の方針は、自らの事業活動に対応した具体的な内容
で、経営責任者の緒言との整合が図られていることが望まれます。
(1) 記載する情報・指標
ア.事業活動における環境配慮の方針
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境配慮の方針の制定時期、制定方法、全体的な経営方針等との整合性及び位置付け、コーポレート・ガバナンスとの関連
? 事業活動における環境配慮の方針が意図する具体的内容、将来ビジョン、制定した背景等に関するわかりやすい説明
? 同意する(遵守する)環境に関する憲章、協定等の名称と内容
(3) 解説
事業活動における環境配慮の方針を記載するだけでなく、その説明資料として、事
業特性等に応じて、どのような環境負荷があり、どのような事業活動における環境配
慮の取組が必要か等、事業活動における環境配慮の方針を策定した背景や理由を記載
していることも重要です。
また、事業活動における環境配慮の方針は、事業活動のライフサイクル全体を踏まえ、
事業エリア内のものだけでなく、原材料・部材の購入、輸送、製品・サービスの使用・
廃棄等の事業活動の上・下流までを対象とすることが必要です。
さらに、事業活動における環境配慮の方針は、我が国の環境基本計画及び循環型社
会形成推進基本計画等を踏まえて作成することが期待されます。
なお、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001 及びエコアクション21 に
おいても、環境マネジメントシステムの構築に当たり、環境方針を策定することが求
められていますが、環境報告書の対象組織と認証取得の対象組織が同一の場合は、こ
れらの環境方針と本ガイドラインの事業活動における環境配慮の方針は同じものであ
ると考えられます。
【情報記載にあたっての留意点】
環境配慮の方針については、事業内容や製品・サービスの特性や規模、また事業活
動に伴う重要な環境負荷等に対応した適切なものであることが必要です。
MP-1-2:環境マネジメントシステムの状況
環境マネジメントシステム(EMS)の構築状況、環境マネジメントの組織体制、
環境マネジメント手法の概要、ISO14001 やエコアクション21 等の認証取得状況、
従業員教育、環境監査*等の状況等を記載します。
また、今後のEMS の導入・構築の拡張計画や検討状況についても記載が望まれ
ます。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境マネジメントシステムの状況
例えば、次のような情報や指標を用いて記載することが考えられます。
・全社的な環境マネジメントシステムの構築、運用状況及びその評価とそれを踏
まえた今後の方向性(システム及びPDCAサイクルの説明を含む)
・全社的な環境マネジメントの組織体制の状況(環境管理に対する内部統制シス
テムの整備状況、それぞれの責任、権限、組織の説明を含む)及びその組織体制図
・環境に関するリスク管理体制の整備状況
・環境マネジメントシステム構築事業所の数、割合、並びに今後のEMSの導入・
構築の拡張計画や検討状況
・ISO14001やエコアクション21等の外部認証(自己適合宣言がある場合には、
その旨を記載する)を取得している場合には、取得している事業所等の数、割
合(全従業員数に対する認証取得事業所等の従業員の割合等)、認証取得時期
・環境保全に関する従業員教育、訓練の実施状況(研修実施回数、教育等を受け
た従業員の数、割合、従業員1人当たりの年間平均教育時間数等)
・想定される環境に関する緊急事態の内容と緊急時対応の状況
・環境影響の監視、測定の実施状況
・環境マネジメントシステムの監査の基準、実施状況(内部監査・外部審査の回
数)、監査結果及びその対応方法等
・環境マネジメントシステムの全体像を示すフロー図
・事業活動における環境配慮の取組成果の従業員等の業績評価への反映
・社内での表彰制度等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? SRIインデックスへの組み入れ状況や環境経営度ランキング等の各種表彰・評価の状況
(3) 解説
事業者が自らの環境パフォーマンスを向上させていくためには、その基盤とも言う
べき環境マネジメントシステム(EMS)を適切に構築し運用しなければなりません。
この環境マネジメントシステムがどのように構築され、どのように運用されているか
は、環境報告として環境報告書に記載すべき重要な情報です。また、今後のEMS の
導入・構築の拡張計画や検討状況は報告範囲や環境負荷データの収集範囲とも関係
するため記載することが望まれます。
なお、環境マネジメントシステムの構築・運用状況は、それぞれの事業者の形態
や規模等により異なると考えられますが、それぞれの特性に応じて具体的に記載す
ることが望まれます。
MP-2:環境に関する規制の遵守状況
環境に関する規制の遵守状況、違反、罰金、事故、苦情等の状況、並びにそれら
への対応・改善状況を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境に関する規制の遵守状況
例えば、次のような情報や指標を記載することが考えられます。
・事業活動との関係が強い重要な法規制等を遵守していることの確認方法とその結果(定期又は不定期の内部チェック体制の内容)
・少なくとも過去3年以内の重要な法規制等の違反の有無(重要な法規制違反、
基準超過等につき規制当局から指導、勧告、命令、処分を受けた場合には、そ
の内容、改善の現状、再発防止に向けた取組の状況、そうした事項がない場合
には、それを確認する方策や仕組みとともにその旨を記載)
・環境に関する罰金、過料等の金額及び件数
・環境関連の訴訟を行っている又は受けている場合は、その内容及び対応状況
・環境に関する苦情やステークホルダーからの要求等の内容及び件数(騒音及び
振動、悪臭等に対する苦情等の状況を含む)
・上記のような法令や協定違反、事故、事件、苦情等があった場合、それらへの
具体的な対応状況・改善方策等(経営レベルを含む)
・環境規制を上回る自主基準等を設定している場合は、その方針等
・環境ラベル、環境広告、製品環境情報等における違反表示、誤表示等の状況
(2) 解説
事業者が事業活動における環境配慮の取組を行い、社会の信頼を勝ち得ていくため
には、環境コミュニケーション等を積極的に行っていくと同時に、環境に関する法令、
条例、協定等の規制や約束事項を遵守し、また、自社に不利な情報も含めて、その情
報を適切に開示していく必要があります。特に、さまざまな法令等の遵守状況や、違
反や事故、苦情等の情報は環境報告として環境報告書に記載すべき重要な情報であり、
社会からの信頼を得ていくためにも必要です。
さらに、上記のような法令や協定違反、事故、事件、苦情等が実際にあった場合、
それらへの具体的な対応状況・改善方策等(経営レベルを含む)を記載することが望まれます。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 特有の法的規制、取引慣行、経営方針及び重要な訴訟事件等の発生等、ステーク
ホルダーの判断や見解に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、具体的にわかり
やすく、中立的な記述を行うことが必要です。そのような事実がない場合には、
その旨を記載しますが、単に事実がないというだけではなく、それを確認する組
織的な方策や仕組みとともに記載することが望まれます。
(ii) 実務上の留意点として、環境計量証明事業者に測定を依頼し、規制値オーバーと
なった場合、通常再測定を依頼します。その結果、規制値内となった場合、1度
目の計量証明書の発行を依頼しない事例があります。環境計量証明事業者が、合
理的であると認めない限り、計量証明書の発行を受け、監督官庁への連絡等規制
値違反としての対応が必要です。なお、環境に関する規制を遵守するために、今
後は公害防止等に係る測定実施や測定結果あるいは計量証明書の管理に関し、内
部統制や内部監査の体制が整備され、適正に運用されることが望まれます。
MP-3:環境会計情報
環境省「環境会計ガイドライン(2005 年版)」に示された考え方を参考にして、
事業活動における環境保全コストと、その活動により得られた環境保全効果及び環
境保全対策に伴う経済効果を総括的に記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境保全コスト*
イ.環境保全効果*
ウ.環境保全対策に伴う経済効果*
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 企業の内部管理に活用した環境管理会計*に関する情報
(3) 解説
事業者が事業活動における環境配慮の取組を行っていく上で、環境保全コストを
管理し、環境保全対策の費用対効果を分析することにより、適切な経営判断を通じ
て効率的かつ効果的な事業活動における環境配慮の取組を推進することが必要です。
また、環境会計情報やその導入目的・利用方法等を公表することは、ステークホル
ダーが事業者の事業活動における環境配慮の取組状況をバランスよく理解し、評価
するための有効な手段となります。
こうした意味で、環境会計が多くの事業者によって導入されるとともに、集計さ
れた定量的な情報が、わかりやすく総括的に整理されて環境報告書に適切に記載さ
れ、公表されることが望まれます。
公表にあたっては、「環境会計ガイドライン(2005年版)」に示す公表用フォー
マット等を用いることにより、環境会計情報を総括的に開示することができます。
また、マテリアルフローコスト会計や環境に配慮した設備投資等の内部管理のた
めの環境管理会計に関する説明を記載することや、環境会計情報と後述する環境効
率指標を統合して開示することも有効です。
(参考)環境会計ガイドライン2005 年版
http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html
経済産業省「環境管理会計手法ワークブック」
http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/sonota/policy1-01.html
【情報記載にあたっての留意点】
環境保全コストは、事業者内での環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、影響の除
去、発生した被害の回復又はこれらに資する取組のための投資額及び費用額であり、
ここでいう投資額は事業者内における投資のことです。「MP-4 環境に配慮した投融資」
での投融資は、他の事業者等への出資や株式の購入やプロジェクトへの投融資等を指
します。
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
環境配慮促進法(第4条)では、金融機関だけでなく全ての事業者に対して投資そ
の他の行為をするにあたっては、環境情報を勘案して行うように努めることを定めて
います。
また、製品・サービスの市場だけでなく、金融市場においても環境配慮が評価され
ることが期待されます。
そのため、金融機関には本業の中で環境配慮が求められますし、それ以外の企業に
おいても、年金基金の運用等を行う際に、通常の事業活動における投資・融資とは異
なる一般的な投資家として、環境に配慮した有価証券投資やその他の投融資を行うこ
とが期待されます。
そこで、環境報告として環境に配慮した資金の流れの状況について記載します。併
せて、排出量取引等の新しい投資・融資活動についても、取組の状況を示すことが期
待されます。
(1) 記載する情報・指標
ア.投資・融資にあたっての環境配慮の方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
(投融資を実施する場合)
? 環境保全に資する事業やそのような事業を行う企業に対する投融資の状況
? 環境への配慮状況を評価しつつ行う事業や企業に対する投融資の状況
? カーボンファンド*等への投資の状況
? 外部の環境インデックスを使用した投資の状況
(投融資を受ける場合)
? 金融機関等から受けた環境関連の投資や融資の状況
(その他)
? 資金運用や企業年金におけるSRI運用額
(注)金融機関の環境に配慮した融資あるいは投資ファンド等の金融商品は、後述する
「MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況」にも該当します。
(3) 解説
環境と経済を統合的に向上させる観点から、金融市場においても環境の価値が積極
的に評価されることが期待されます。そのためには、まず金融機関において、環境保
全に資する事業や環境に配慮した企業活動等の評価に基づいて投資・融資を行うこと
が望まれます。
金融機関以外の事業者についても、その保有する資金の運用にあたっては環境に配
慮して行動することが期待されます。特に、取引先や買収対象企業等他の主体に対し
て投資・融資を行うに際しては、相手先の環境情報を勘案して行うことが環境配慮促
進法において求められています。
また、年金基金等の事業に直接関連しない資金については、年金基金等は国内外に
おいて資本市場の大きな部分を占める機関投資家として中長期的な投資・融資を行っ
ていることから、環境に配慮した投資・融資を行うことが強く期待されます。
環境に配慮した直接金融には、例えば環境に配慮した企業に直接投資を行うSRI や
環境に配慮したプロジェクトに投資するグリーンファンド等があります。さらに、今
後、環境保全に資する事業活動に対して投資を行うことも期待されます。一方、間接
金融である融資についても、例えば
?土壌の汚染状況、回復見込み等を担保価値の評価に組み込むことによって、汚染土壌の回復を図るような事業を優遇する融資、
?環境配慮について金利等のインセンティブがついているような融資商品、
?開発行為に際して一定の環境配慮が求められるような事業への融資、
?環境負荷の低減そのもの
につながる環境ビジネスを促進するような事業への融資があります。
一部の銀行等の金融機関では、環境負荷の低減に資する事業への融資額及びその事
業を通して排出される温室効果ガスの低減効果量を公表する動きがあります。このよ
うな環境に配慮した事業や企業へ投融資の状況について、金融機関等が積極的に情報
公開していくことが期待されます。(参照:MP-12)
【情報記載にあたっての留意点】
自らの事業における環境配慮型の設備投資額は、「MP-3:環境会計情報」の構成要
素である環境保全コストの中の「投資」に相当します。(参照:MP-3)
MP-5:サプライチェーンマネジメント等の状況
取引先に対して、事業活動における環境配慮の取組に関し、どのような要求や依
頼をしているのか、それをどのようにマネジメントしているのか等、環境等に配慮
したサプライチェーンマネジメントの状況は、環境報告として環境報告書に記載す
べき重要な情報です。
ここでは環境等に配慮したサプライチェーンマネジメントに関する概要を記載
します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境等に配慮したサプライチェーンマネジメントの方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 調達量全体に対する環境等に配慮した調達量の割合
? 川上から川下への化学物質有害性情報や原材料採取の場所、採取時の環境配慮
等の環境情報の伝達方針及び取組状況
(3) 解説
事業活動における環境配慮の取組は、自らの直接的な事業活動の範囲だけにとど
まるものではなく、原材料の調達、部品・部材の調達、製品等の購入、輸送、廃棄
物処理等、さまざまな取引先をも視野に入れる必要があります。このような幅広い
取引先と協働して、サプライチェーンのグリーン化を推進していくことが求められ
ています。
また、ISO14001及びエコアクション21等の認証登録制度をサプライチェーンマネ
ジメントにおいて活用していくことも有効な方策であると考えられます。
最近では、海外からの素材・部品等の調達あるいは海外現地での操業を背景とし
て、環境だけでなくフェアトレード*やCSR調達等社会面への視点も広がってきてお
り、社会性からもサプライチェーンマネジメントを考えていくことが期待されてい
ます。
【情報記載にあたっての留意点】
環境に配慮したサプライチェーンマネジメントの状況は、それぞれの事業者の形
態や規模等により異なると考えられますが、それぞれの特性に応じた状況を具体的
に記載することが望まれます。
MP-6:グリーン購入・調達の状況
環境への負荷を極力少なくし、資源・エネルギーの循環的利用を促進していくた
めには、自らの事業エリア内における取組のみならず、原材料、部品、製品、サー
ビス(以下、製品・サービス等という。)の購入先、いわゆる事業エリアの上流側
での取組を積極的に働きかけていくことが必要であり、そのための重要な手法とし
て、環境負荷低減に資する製品・サービス等*の優先的購入(グリーン購入・調達)
があります。
このグリーン購入・調達がどのように行われ、どの程度の成果を上げているか、
さらに今後の目標や拡張計画を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.グリーン購入・調達の基本方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境負荷低減に資する製品・サービス等の購入・調達量、額、品目数等(MP-12:
環境負荷低減に資する製品・サービスの状況、参照)
? 購入・調達全体に対する環境負荷低減に資する製品・サービス等の購入・調達の割合
? 購入・調達先に対する環境配慮に関する要請の状況
(3) 解説
業種、事業規模等によって購入・調達する製品・サービス等は千差万別であるため、
それぞれの製品・サービス等の特性に応じたグリーン購入・調達の状況(グリーン購
入の購入全体に占める割合を含む)を具体的に記載することが望まれます。例えば、
以下のような事例が考えられます。
? 古紙や合法性の確認がとれた木材(森林認証*材等)を使用した紙
? 再生材使用や詰替型等の事務用品
? 省エネ性能の高い事務機器
? 低公害車*
? 再生材を使用した原材料等
等
(参考)グリーン購入ネットワーク
http://www.gpn.jp/
MP-7:環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況
環境に配慮した生産技術、工法等に関する研究開発の状況、製品・サービスの環
境適合設計*(DfE:Design for Environment)等の研究開発の状況、環境に配慮
した販売、営業方法の工夫、ビジネスモデル等を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境に配慮した生産技術、工法、DfE等の研究開発に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほかに、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? LCA(ライフサイクルアセスメント)手法を用いた研究開発の状況
? 環境に配慮した販売、営業方法の工夫、ビジネスモデル等
? 環境適合設計(DfE)等の研究開発に充当した研究開発資金
(3) 解説
事業活動における環境配慮の取組を行っていくためには、環境に配慮した生産方法
や工法、環境に配慮した製品・サービスの開発・設計(環境適合設計(DfE))等の研
究開発、環境に配慮した販売、営業方法の工夫、さらには環境配慮型のビジネスモデ
ルの開発等に積極的に取り組んでいくことが必要です。これらの研究開発が、将来の
環境パフォーマンスの向上、さらには自社のエコビジネスの進展等につながっていく
と考えられます。
この事業活動における環境配慮の取組に関する研究開発がどのように行われ、どの
程度成果を上げているかは、環境報告として環境報告書に記載すべき重要な情報です。
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
輸送に係るエネルギー起源二酸化炭素(CO2)やNOx・PM の排出量と、原材料
等を購入先から搬入するためや、製品・サービス、廃棄物等を搬出するための輸送
又は旅客の輸送に伴う環境負荷の状況及びその低減対策を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境に配慮した輸送に関する方針、目標、計画等
イ.総輸送量及びその低減対策に関する取組状況、実績等
ウ.輸送に伴うエネルギー起源CO2排出量及びその低減対策に関する取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 大都市圏におけるNOx・PM法の取組状況
? 輸送に伴う梱包材等の再利用量(率)と廃棄量
(3) 解説
我が国における2005年度のCO2排出量(速報値)は12億9,700万トン-CO2(1990
年度比13.3%増)ですが、運輸部門からの排出量は2億5,700万トン-CO2(同18.1%
増)となっており、全体の排出量の19.8%を占めています。また、自動車輸送の増
加及び集中に伴い、NOx・PMを起因とする都市部の大気汚染は改善が求められてい
ます。この輸送に伴うCO2及び大気汚染物質の排出を削減していくためには、鉄道・
船舶輸送への切り替え等のモーダルシフトの推進や、集配拠点の再編、渋滞等を勘
案した輸送効率の高いルートの選択、共同輸配送や帰り荷確保等の輸送効率の向上
とともに、輸送量そのものを極力削減していくことが必要です。
事業者は自らの部品や製品を運ぶ場合には、自家用トラックを使うか、運送業者
の営業用トラックを使うことになりますが、いずれにしても事業者の責務として温
室効果ガスやNOx・PMの排出あるいは輸送用梱包材等の廃棄物発生を抑制・低減す
るべく努力しなければなりません。
平成18年4月から施行された改正省エネ法では、一定規模以上の貨物輸送事業者、
旅客輸送事業者、荷主に省エネルギー計画策定とエネルギー使用量報告が義務付け
られました。輸送活動に携わるそれぞれの主体に、エネルギー資源の有効利用を図
るとともに、輸送に伴うエネルギー起源CO2の発生をより一層抑制することが求めら
れています。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 環境に配慮した輸送としては、総輸送量と輸送に伴うエネルギー起源CO2 の排出
量が主要な指標となります。総輸送量は、自社輸送及び製品・サービスに伴う外
注分(委託等)の輸送について、その輸送手段ごと(自動車、船舶、鉄道、航空
機等)に合算し、トンキロ(t×km)又は人キロ(人×km)単位で記載します。
(ii) 輸送に伴うエネルギー起源CO2 の排出量は、「地球温暖化対策推進法施行令」の規
定に基づき、燃料の使用量を把握し、排出係数を用いて算定し、t-CO2 単位で記
載します。
(iii) 事業者の製品・サービスに伴う輸送の外注分(委託分)については、その正確な
把握、算定が困難ですが、可能な限りこれを把握することが望まれます。ただし、
把握が難しい場合は、主要な製品についてのみ算定する、一定のシミュレーショ
ンモデル等により推計すること等もできますが、その根拠を明示する必要があり
ます。
(iv) 原材料、燃料等の購入に伴う輸送については、専用又はチャーター等の輸送手段
により、また、他の一般貨物等と混載されないで納入される場合は、これを別途
記載することが望まれます。さらに、自社輸送と外注分の別、輸送手段毎の内訳
等を公表することが望まれます。
(v) 共同輸配送や帰り荷確保等による輸送効率(単位:%)、すなわち
[輸送トンキロ(t×km)]/[能力トンキロ(t×km)]又は
[輸送人キロ(人×km)]/[能力人キロ(人×km)]
の向上も、CO2 や大気汚染物質の排出削減に資するものであり、併せて把握・公
表することが望まれます。
(vi) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
MP-9:生物多様性*の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
生物多様性条約*(日本は平成5 年締結)と新・生物多様性国家戦略*(平成14 年決
定)の精神に鑑み、生態系の保全、生物種の絶滅の防止と回復、生物資源の持続可能
な利用を達成するための方針、目標、実績等を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.生物多様性の保全に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
例えば、次のような情報や指標を用いて記載することが考えられます。
・ 事業活動に伴う生態系や野生生物への主要な影響とその評価(海外の生物多
様性の豊かな地域における開発を含む)
・ 原材料調達における生態系や野生生物への主要な影響とその評価(影響が大
きい業種の場合には、そのプロセスにおける影響も含む)
・ 事業活動によって発生し得る生物多様性への影響を回避ないしは軽減するための取組
・ 所有、賃借、あるいは管理する土地及び隣接地域における生物多様性の保全に関する情報
・ 生物多様性が豊か、あるいは保護する価値が高い地域4に所有、賃借、管理し
ている土地がある場合は、その面積と保全状況等
・ 生態系の保全・再生のために積極的に行うプログラム及び目標(生物多様性
が豊か、あるいは保護する価値が高い土地の買い上げや寄付等による保全活動を含む)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 生産あるいは原材料調達の過程において生物多様性へ与える影響を軽減し、生
物資源の持続可能な利用のための配慮がなされた製品やサービスと、それが全
製品及び全サービスに占める割合
? (社)日本農林規格協会による有機農産物や栽培期間中に化学合成農薬を使用
していない、あるいは節減して栽培した農産物の利用方針や取組状況等
? 所有、賃借、あるいは管理する土地及び隣接地域に生息・生育する生物種に関
する情報(特に、絶滅が危惧される生物種*及びその地域に固有な生物種につ
いての情報)
? 事業活動に起因する生息・生育地の改変内容、及び生息・生育地を保護または
復元した割合
? 山地、農地、市街地等における遊休地を生物多様性の保全のために再び自然を修復した面積
? 計画中の事業や、開発の過程における生物多様性や生態系への影響の評価と対
策(回避、軽減)の実績
? 保護地域あるいは脆弱な生態系からなる地域とその周辺において計画中の事
業、及びその事業が生物多様性と生態系に与える影響
(3) 解説
開発や原料調達をはじめ、事業活動は直接的、間接的に生物多様性に大きな影響を
与えています。生物多様性及びその重要な構成要素の一つである生態系は、生物・遺
伝資源の源泉としての利用価値や、物質循環、気象の調節、文化の源泉等の生態系サ
ービスをもたらしており、私たち人類の生活と事業活動が大きく依存しているものです。
過剰な利用や開発等による生態系の破壊は、私たち人類の生活や事業活動を持続
不可能にする可能性があるため、十分な配慮を払うことが必要です。
その一方で、生物多様性への配慮を経営システムの中に統合することは、長期的な
観点から、リスクの低減や持続可能な企業経営の安定化にも資するものであることを
認識する必要があります。
具体的には、生物多様性に影響を与えている以下のような主要な原因について、組
織の影響が及び得る事業エリア及び、その上流・下流のサプライチェーンを含めた、
より広い範囲で配慮することが望まれます。
? 過度の捕獲・採集等生物多様性に影響を与える方法で生産された原料の利用
? 生息・生育域の開発(事業所や施設の設置等)や活動(レジャー等)
? 外来生物の移入(原材料等にする生物の野生化、無計画な緑化、寄生虫・病気等)
? 遺伝子組み換え生物の移入
? 生息・生育環境の変化(化学物質や肥料等による汚染等)
また、生物多様性や生態系の保全・持続可能な利用を確保するためには、専門的な
知見が不可欠であることから、研究者や専門性の高いNGO・NPO 等、社外の専門家
との連携や、IUCN(国際自然保護連合)の「ビジネスと生物多様性:共に活動する
ためのハンドブック」(日本語版は生物多様性JAPAN 発行)等の企業向けのガイダン
スの活用等も有効と考えられます。
最近では、生物資源の持続可能な利用のために水産エコラベル*等の認証制度に取り
組む事例も増えてきています。
【情報記載にあたっての留意点】
原材料調達において、生物多様性への影響を把握することが困難な場合もあります
が、サプライチェーンマネジメントやグリーン購入・調達の観点からも、自らの購入・
調達の方針を明確にしていくことが期待されます。
MP-10:環境コミュニケーションの状況
環境コミュニケーションの取組がどのように行われ、どの程度成果を上げている
かは、環境報告として環境報告書に記載すべき重要な情報です。ここでは環境報告
書、環境ラベル*等による環境情報開示及びステークホルダーとの環境コミュニケ
ーションの実施状況等を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境コミュニケーションに関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境報告書、環境ラベル等による環境情報開示の状況
? 主要なステークホルダーとの環境コミュニケーション等の状況(例えば調査の
実施、地域住民との懇談会、定期的な訪問や報告、取引先との懇談会、ステー
クホルダー・ダイアログ、ニュースレター、ステークホルダーからの問い合わ
せへの対応等によるコミュニケーションの状況と種別ごとの回数)
? 環境報告書又はサイト単位の環境レポートを発行している事業所の状況
? 環境関連展示会等への出展の状況
? 環境関連広告・宣伝の方針及び状況
? 広告・宣伝の方法や媒体等に関する環境配慮の状況
(3) 解説
事業者が事業活動における環境配慮の取組を行うことにより、社会の信頼を勝ち
得ていくためには、社会的説明責任及びステークホルダーに有用な情報を提供する
必要性等の観点から、自ら環境に関する情報を開示し、積極的に環境コミュニケー
ションを図っていく必要があります。特に、環境報告書の作成・公表の取組や、環
境ラベルや環境広告等により、環境に関する情報を積極的にステークホルダー等に
伝えていく取組は、事業者が当然果たすべき責務の一つであると言えます。
ISO では、環境ラベルに関する規格ISO14020 シリーズで環境ラベルの一般原則と
環境ラベルの3 つのタイプを規格基準化しています。これらを参照して取り組むこと
が期待されます。
また、ISO 規格にはISO14063「環境コミュニケーション−指針及びその事例」があ
り、さまざまな環境コミュニケーションの手段が規格化されています。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 環境コミュニケーションに関する環境配慮の状況は、委託先に外注している印刷
物等(広告宣伝物を含む)も含めて記載することが期待されます。
(ii) ステークホルダーからの問い合せの状況やその対応内容等についても記載す
ることが期待されます。また、環境コミュニケーションの実績だけでなく、
これを実施した効果や、それらをどのように活用しているかを記載すること
も望まれます。
なお、環境報告書、環境ラベル等による環境情報の開示状況及びステークホ
ルダーとの環境コミュニケーション及びパートナーシップの実施状況は、それ
ぞれの業種や規模等により異なると考えられますが、それぞれの特性に応じた
環境コミュニケーション等の状況を具体的に記載することが望まれます。
実務上の留意点としては、環境ラベルを使用する際には消費者に誤認を与え
ない正確な表示を行うことが重要です。
MP-11:環境に関する社会貢献活動の状況
環境保全に関して、事業者が自ら実施する取組、従業員がボランタリーに実施す
る取組等の社会貢献活動の状況を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境に関する社会貢献活動の方針、目標、計画、取組状況、実績等
例えば、次のような情報や指標を用いて記載することが考えられます。
・ 従業員の有給ボランティア活動の状況及び延べ参加人数
・ 加盟又は支援する環境保全に関する団体(NPO、業界団体等)
・ 環境保全を進めるNPO、業界団体への支援状況、支援額、物資援助額等
・ 地域社会に提供された環境教育プログラムの状況
・ 地域社会と協力して実施した環境・社会的活動の状況
・ ステークホルダーと協力して実施した、上記以外の活動の状況
・ 環境保全活動に関する表彰の状況
・ 緑化、植林、自然修復等の状況
・ 自社で関与している財団等の助成実績等
(2) 解説
事業者が事業活動における環境配慮の取組を行うと同時に、他のさまざまなセク
ターと協働し、パートナーシップを築きながら、持続可能な循環型社会の構築に取
り組んでいくことが望まれます。その具体的な活動の一つとして、事業者や従業員
が自ら行う環境社会貢献活動、環境NPOへの支援、業界団体等での取組等があり、
このような社会貢献活動を積極的、自主的に行っていくことが必要です。
この環境に関する社会貢献活動をどのように実施しているかは、環境報告書に記
載することが望まれる重要な情報です。
【情報記載にあたっての留意点】
環境に関する社会貢献活動の状況は、事業者の業種や規模、あるいはそれぞれの
考え方等により異なると考えられますが、各事業者の特性に応じた社会貢献活動の
状況を具体的に記載することが望まれます。
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
事業者が自ら生産・販売する製品・サービス等に伴う環境負荷を削減していくこと
は、事業者にとって最も重要な使命の一つであり、持続可能な環境保全型社会、循環
型社会を構築していく上で必要不可欠な取組であると言えます。
したがって、環境負荷低減に資する製品・サービス(無形の機能・役務を含む)等
の生産・販売に積極的に取り組んでいる状況を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境負荷低減に資する製品・サービス等に対する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.容器包装リサイクル法、家電リサイクル法及び自動車リサイクル法等に基づく再商品化の状況
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境負荷低減に資する製品・サービス等(環境ラベル認定等製品*等)の生産
量又は販売量及び全体に占める割合、それによる環境保全効果の状況
? 省エネルギー基準適合製品*の数
? 解体、リサイクル、再使用又は省資源に配慮した設計がされた製品数
? 主要製品のライフサイクル全体からの環境負荷の分析評価(LCA)の結果
? 製品群毎のエネルギー消費効率
? 製品の使用に伴う二酸化炭素(CO2)排出総量(当年度出荷製品全体の推計及び主要製品のCO2排出係数)
? 温室効果ガスの削減に資する製品・サービスの販売量及び期待される温室効果ガスの削減量
? 教育研究機関における環境教育、環境研究の状況
? 静脈物流・流通の状況(廃棄物の輸送等)
? 金融関連機関における環境関連金融の状況(環境保全事業融資・信託、エコファンド、環境賠償責任保険等)
? サービサイジング*の取組状況
? 小売業等における環境に配慮した商品の販売や包装削減対策(マイバックの推進活動)等
? 旅行業・ホテル業等におけるエコツーリズム*、エコホテルの取組の状況等
(3) 解説
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の規定による対象機器、使用済
自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)、 容器包装に係る分別収集
及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)等においては、自らが
生産・販売した製品等のリサイクル等が求められており、いわゆる拡大生産者責任への
対応が必要となってきています。これらのリサイクル法への取組状況や該当するその他
のリサイクル法に基づく取組の状況についても記載することが期待されます。
他方、事業者自身の環境経営、特にエコビジネスの推進という観点からも、製品・サ
ービス等の環境負荷低減は必須の取組であると言えます。事業者が生産・販売する環境
負荷低減に資する製品・サービス等の種類は多岐に渡り、その状況はそれぞれの業種、
規模等により異なると考えられますが、それぞれの特性に応じた取組状況をOP-5の総
製品生産量又は総商品販売量に対する割合や、それによる環境保全効果(推計を含む)
の概要等を具体的に記載することが望まれます。
さまざまな環境負荷を大幅に低減するためには、素材・部品・製品等の製造段階での
取組だけでは不十分であり、その上流側(企画・開発、設計、調達等の段階)や下流側
(輸送、販売、使用・利用、あるいは廃棄・回収等の段階)を含めた、あらゆる製品・
サービス等のライフサイクルにおける環境負荷低減の取組が必要です。これを事業者か
らみると、提供する製品・サービス等の環境負荷を低減することが市場から求められて
いるわけで、商品市場のグリーン化ということができます。
これは多様な領域・分野において環境ビジネスが可能なことを物語っていますが、近
年では汚染を防止する装置や設備、製品以外のさまざまな技術・ソフト・サービス系の
環境ビジネスが隆盛を見せています。
これらは全般的に新しい環境ビジネスであり、環境ISOの導入や環境報告書の作成支援、環境会計のコンサルティングや環境情報サービス、環境格付等が挙げられます。温室効果ガスの排出量検証や京都メカニズムの活用に
よる排出量取引あるいはCDMの有効化審査等も温室効果ガス削減費用を社会全体で最
小化するためのサービスです。
また、廃棄物の広域輸送や有害物回収事業等の“静脈物流”、詰替え・量り売りや中
古品再生販売、家電修理等や環境装置リースや家電レンタル等のサービサイジングの取
組も、直接・間接を問わず循環型社会形成に貢献するものです。さらにエコツーリズム
は人々の環境意識の向上に資するものですし、学校法人等の環境教育は環境意識の高い
人材を育成するものです。このように環境配慮型のサービス・役務等のビジネスモデル
には際限がないと言っても過言ではありません。
国等においては、グリーン購入法により、環境に配慮した物品やサービス等を優先
的に購入・調達してきました。さらに、環境配慮契約法が2007 年5月に成立し、国
等が電気を購入したり、庁舎を建設したりする際の契約についても、温室効果ガス等
の排出の削減への配慮が求められることとなりました。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 事業者の製品・サービス等に係る環境負荷の低減に資する取組について記載しま
す。リサイクルへの取組の他、環境ビジネスの推進等、本業についても、記載す
ることが期待されます。
(ii) 金融機関等による環境配慮型の金融商品としては、損害保険会社による土壌汚染
に対する環境賠償責任保険、銀行の環境に配慮した行動を取る企業に対する金利
優遇や環境保全事業に対する金利優遇、エコファンド(環境にも配慮した投資信
託)等があります。これらの金額を指標とすることが考えられます。
(iii) 銀行、証券、保険等の金融機関、流通・小売業、運送業、商社等においては、直
接的な生産活動を行っていない場合が多いことから、自らのサービスに係る環境
配慮の取組について、その業種特性に応じた記述の工夫が求められます。例えば、
金融機関等においては、投融資にあたっての環境配慮について記載することが望
まれます。最近では、環境関連融資を通じて融資先の事業者が実際に達成した環
境負荷削減の効果を定量的に評価する金融機関も見受けられます。
(iv) 環境ラベル認定等製品については、環境ラベルのタイプ・種類を明確にし、該
当する製品の重量又は個数、面積、容積等で把握します。
(v) 容器包装リサイクル法の再商品化義務量は、対象となる容器包装の製造量及び
利用量を集計します。
3.「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標(OPI)
環境報告に記載する「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」
を表す環境報告の情報・指標(オペレーション指標:OPI)は以下の10 項目です。
本節では、それぞれの基本的な考え方や記載が望まれる具体的な情報・指標等につい
て解説します。
(オペレーション指標:OPI)
【インプット】
OP-1:総エネルギー投入量及びその低減対策
OP-2:総物質投入量及びその低減対策
OP-3:水資源投入量及びその低減対策
【内部循環】
OP-4:事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
【アウトプット】
(製品・商品)
OP-5:総製品生産量又は総商品販売量
(排出物・放出物)
OP-6:温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP-7:大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
OP-8:化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP-9:廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
OP-10:総排水量等及びその低減対策
(注)
地域への影響が大きいと考えられるOP-3(水資源投入量)、OP-7(大気汚染、生
活環境に係る負荷量)、OP-8(化学物質の排出量、移動量)、OP-10(総排水量)
等の項目については個別事業所毎の数値を公表することが期待されます。
OP-1:総エネルギー投入量及びその低減対策
石油、天然ガス、石炭等の化石燃料の使用に伴い、地球温暖化の原因となる二
酸化炭素(CO2)が排出されます。このため総エネルギー投入量及び内訳と、その
低減対策、さらにエネルギー生産性及び事業エリア内で事業者が自ら行った自家
発電量等を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.総エネルギー投入量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.総エネルギー投入量(ジュール)
ウ.総エネルギー投入量の内訳(種類別使用量)(ジュール)
・購入電力(購入した新エネルギー*を除く)
・化石燃料(石油、天然ガス、LPG、石炭等)
・新エネルギー(再生可能エネルギー*、リサイクルエネルギー、従来型エネルギーの新利用形態)
・その他(購入熱等)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 熱循環型の自家発電の状況及びその拡大策と将来計画・目標
? エネルギー自給量・回収量のエネルギー源別内訳(ジュール又はその他の単位)
・化石燃料
・新エネルギー
・コージェネレーション
・その他
? エネルギー生産性、エネルギー利用効率及びその向上対策
(3) 解説
我が国では、化石燃料の使用によるCO2 の排出量が、CO2 排出量全体の約9割を
占めています。地球温暖化の防止に向けては、総エネルギー投入量を削減するとと
もに、太陽光発電、風力発電、バイオマスエネルギー等を含む新エネルギーの一層
の導入を促進する等、よりCO2 排出の少ないエネルギーへの転換が必要になっています。
このため、総エネルギー投入量を把握・管理することとします。併せて、環境配慮
分を含む投入エネルギーの内訳を把握することも重要です。
また、最近では事業所内で使用するエネルギー源として事業所内の余剰エネルギ
ーないし回収せずに放出していた熱源を有効利用する動きが顕著となってきていま
す。事業所内でさまざまな未利用のエネルギー源を用いて自家発電を行い、自ら利
用すると同時に電力会社へ売電するところも出てきています。このように外部から
の買電とは別に、自家発電等もエネルギー使用量の低減につながることが期待されます。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 総エネルギー投入量は、電気及び各燃料等の使用量をそれぞれ把握し、「エネルギ
ーの使用の合理化に関する法律施行規則 別表第1、別表第2、別表第3」に定め
られた熱量換算係数により算出します。「エネルギー源別発熱量表」において定め
のない新エネルギー等の算出にあたっては、換算係数の出典を記載します。
(ii) 購入電力量(kWh)を発熱量(J)に換算する場合の換算係数は、「エネルギーの使用
の合理化に関する法律施行規則 別表第3」に基づき、昼間の電気については
9.97MJ/kWh、夜間の電気については9.28MJ/kWh を用いることとします。
なお、「昼間」とは、午前8時から午後10時までをいい、「夜間」とは、午後10
時から翌日の午前8時までをいいます(「エネルギーの使用の合理化に関する法律
施行規則 別表第3 備考2」)。 なお、昼間・夜間の区別ができない場合は、すべ
ての電気使用量を昼間として算定します(資源エネルギー庁「エネルギーの使用の
合理化に関する法律第15条に基づく定期報告書記入要領(平成18年4月)」)。
(iii) 総エネルギー投入量と併せて、電気及び燃料等の使用量の内訳も把握することが
望まれます。
(iv) 総エネルギー投入量には、直接行う輸送等に係る燃料消費量は含めますが、外部
に委託した製品等の輸送に伴う燃料消費量は別に把握することとして、含めません。
(v) 製品の製造において原材料等として投入される石油、石炭等は、総物質投入量と
して把握します。
(vi) 投入したエネルギー量の内訳については、それぞれのエネルギー源に応じた適切
な単位で把握しても構いません。
(vii) 購入した新エネルギー(風力発電による電力等)は、購入電力には含めず、新エ
ネルギーの内数として把握します。
(viii)余剰電力の売電量については、購入電力量と相殺することができます。又は、そ
の発電のために要した化石燃料の量を算出し、化石燃料投入量から差し引くこと
もできます。ただし、発電のために要した燃料が購入電力の発電のために要した
燃料と異なる場合には、購入電力と相殺せず、別途把握し併記することが望まれます。
(ix)参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-2:総物質投入量及びその低減対策
自然界からの資源(天然資源)の採取量は年々増加しており、この資源を、枯
渇性のものから再生可能なものへと質の転換を図りつつ、枯渇性天然資源の消費
を抑制するとともに、使用済みの資源の循環的な利用*(再使用*、再生利用*、熱
回収*)を進めながら、総物質投入量*を低減することが、持続可能な社会の形成
の観点から必要になります。
このため、総物質投入量及び内訳とその低減対策、さらに資源生産性及び循環
利用率を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.総物質投入量(又は主要な原材料等の購入量、容器包装材を含む)の低減対策
及び再生可能資源や循環資源の有効利用に関する方針、目標、計画、取組状況、
実績等
イ.総物質投入量(又は主要な原材料等の購入量、容器包装材を含む)(トン)
ウ.総物質投入量の内訳(トン)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 資源生産性及びその向上対策
? 循環利用率、循環利用率の向上対策
? 製品・商品以外の消耗品等として消費する資源(容器包装のための資材を除く)の量
? 自ら所有する資本財として設備投資等に投入する資源の量
? 請け負った土木・建築工事等に投入する資源の量
? 製品群毎の再使用・再生利用可能部分の比率
? 使用済み製品、容器・包装の回収量
? 回収した使用済み製品、容器・包装の再使用量、再生利用量、熱回収量及び各々の率
(3) 解説
自然界からの資源(天然資源)の採取量は年々増加しています。わが国の平成16
年度(2004 年度)の社会経済活動に伴う総物質投入量は19.4 億トンに及びます。
そのうち天然資源採取量は17.0 億トンですが、再生利用されている資源は2.5 億ト
ンであり、総物質投入量の1 割超です。
総物質投入量は、その内訳として天然資源の消費を抑制しつつ、循環資源を有効
に利用していくことが必要な指標であることから、資源の種類の内訳、資源投入時
の状態の内訳、天然資源、循環資源等の投入量等も把握することが望まれます。天
然資源については、枯渇性のものから更新性のものへの転換を図りつつ、枯渇性天
然資源の消費の抑制を図りつつ、総物質投入量を削減することが必要です。
また、「循環型社会形成推進基本計画」においては、持続可能な生産・消費形態
への転換を目指して、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るため、天然資源の投入から廃棄に至るまでの社会における物の流れを見渡し、そ
の流れを適正なものに変えていくことで、経済的な豊かさを保ちつつも環境への負
荷を低減する目標を設定しています。そして物質フロー目標として、資源生産性、
循環利用率及び最終処分量の3つを掲げており、これらの目標は、各事業者の取組
においても、最大限尊重されるべきものであると言えます。
なお、事業者として事業活動における環境配慮の取組についての方針を検討する
にあたっては、LCA 的アプローチが求められるようになってきています。アウトプ
ットだけでなく、インプットの段階から内訳を含めて全体的に把握することが重要
となります。
総物質投入量は、投入資源の管理、排出物の発生抑制の観点から将来重要になる指
標と考えられます。事業の内容によっては集計が極めて困難ではありますが、算定可
能な資源についての投入量を把握するところから段階的に取組を進めるとともに、業
態又は企業にとって適切な算定方法の開発に取り組むことが期待されます。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 総物質投入量は、エネルギー及び水を除く資源で、事業活動に直接投入された物
質の合計、主な種類の内訳、資源投入時の状態の内訳、天然資源の投入量、主要
な原材料等及び製品・商品の購入・仕入量をトン単位で把握します。
(ii) 記載単位は、内訳については、重量(単位はトン)以外の単位で管理することが
適切な場合には、実務上用いられている単位によることができます。
(iii) 総物質投入量の主な種類の内訳には、金属、プラスチック、ゴム等の資源の種類
別の量及び割合を可能な限り記載します。主要な原材料等及び商品のみを記載す
る場合は、対象外とした原材料等又は製品・商品(容器包装を含む)の主な内容、
対象とした主要な原材料等又は製品・商品の購入・仕入金額に対する総購入・仕
入高に占める割合を記載します。以下に分類の例を示しますが、事業者の実情に
合わせて、合理的な分類を選択して記載することが期待されます。
<資源の種類別投入量の内訳>
○資源の種類(トン又はその他の単位)
? 金属(鉄、アルミニウム、銅、鉛等)
? プラスチック
? ゴム
? ガラス
? 木材
? 紙
? 農産物 等
○投入時の状態(トン又はその他の単位)
? 部品、半製品、製品、商品
? 原材料
? 補助材料
? 容器包装材
○その他の指標(トン又はその他の単位)
? 枯渇性天然資源(化石資源、希少鉱物等)
? 循環資源
? 更新性天然資源(適切に管理された農林水産物等)
? 化学物質(PRTR 対象物質等)
(iv) 資源生産性は総売上高を総物質投入量で除して算出します。
(v) 総物質投入量には、購入・仕入以外の消耗品等として消費する資源(容器包装の
ための資材を除く)の量、資本財として設備投資等に投入される資源の量、事業
者の内部で循環的な利用が行なわれている物質を含めません。ただし、総物質投
入量とは別に記載することができます。
(vi) 部品・半製品・製品については、それを構成する資源の種類を把握することが望
まれます。それが困難な場合には、総重量で集計する方法もあります。
(vii) 総物質投入量を把握するのが困難な場合には、総製品生産量又は総商品販売量と
廃棄物等総発生量を足し合わせて算出する方法もあります。
(viii) グリーン調達については、事業者が製品・サービス等を提供するために購入した
材料のうち、環境配慮型であると自らが判断した物の投入量を把握します。ただ
し、その判断基準を明らかにすることが必要です。自家消費の分は、グリーン購
入(環境配慮型製品・サービス等の購入量等)として、別途把握することとしま
す(参照:MP-6)。
(ix) 循環利用率は、循環利用量を総物質投入量で除して算出します。
(x) 回収量は、他社の製品及び商品並びに容器包装の回収を含めて、原則としてトン
単位で記載します。ただし、実務上用いられているその他の単位で記載すること
ができます。
(xi) 返品された製品については、OP-5 で区分して把握します。
OP-3:水資源投入量及びその低減対策
水資源は人間を含めた生物の生存に不可欠な要素であり、社会経済システムの
存立基盤でもあります。
このため、水資源投入量及び内訳と、その低減対策を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.水資源投入量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.水資源投入量(?)
ウ.水資源投入量内訳(?)
・上水
・工業用水
・地下水
・海水
・河川水
・雨水 等
(2) 解説
地球上に存在する水資源のうち淡水は約2.5%ですが、飲料、生活用水、生産活
動に利用可能な河川、湖沼、地下水等は約0.8%に過ぎません。水の循環利用と希
少な水資源利用の効率化を進めることが課題となっています。
このため、水資源投入量を把握・管理することとします。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 水資源投入量には、事業所内で循環的に利用している量は含めません。別途「循
環的利用を行っている物質量等(OP-4)」として把握することとします。ただし、
水資源の希少性から事業者内部での循環的利用量の把握は極めて重要です。
(ii) 水資源投入量と併せて、水源ごとの投入量も把握することが望まれます。
(iii) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-4:事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
事業エリア外からの総物質投入量とは別に、事業エリア内で事業者が自ら実施
する循環的利用型の物質量等を記載します。また、我が国では水資源の枯渇の実
感は乏しいものの、世界的には特定の途上国や砂漠地帯を中心に水資源の枯渇が
危惧されています。そこで、事業所内における上水の循環的再利用の普及や中水・
雨水の利用が強く求められています。
(1) 記載する情報・指標
ア.事業エリア内における物質(水資源を含む)等の循環的利用に関する方針、目
標、計画、取組状況、実績等
イ.事業エリア内における循環的に利用された物質量(トン)
ウ.事業エリア内における循環的利用型の物質の種類と物質量の内訳(トン)
エ.事業エリア内での水の循環的利用量(立方メートル)及びその増大対策
オ.水の循環的利用量(立方メートル)の内訳
・水のリサイクル量(原則として、冷却水は含まない)
・中水*の利用
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 事業エリア内で再使用された資源の量
? 事業エリア内で再生利用された資源の量
? 事業エリア内で熱回収された資源の量
(3) 解説
循環資源の投入量を増大させ、循環資源利用率を高めていくことは、循環型社会形
成推進基本計画の中でも強調されているように、天然資源の消費を抑制し、持続可能
な循環型社会の構築を図っていく上で、極めて重要です。
天然資源については、枯渇性天然資源の消費を抑制するとともに、使用済みの資源
の循環的な利用(再使用、再生利用、熱回収)を進めることが、持続可能な社会形成
の観点から必要になります。
また、水資源についても、希少な水資源の利用の効率化を進めることが課題となっ
ています。そこで効率の良い水資源の利用が求められますが、事業所外からの投入
水資源量を削減するだけでなく、事業所内での水資源の循環利用率を高めていくこと
は、持続可能な循環型社会の構築を図っていく上でも極めて重要です。とりわけ、最近
では一度使用した上水を事業所内で処理して循環利用する中水の利用が普及しつつあ
ります。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 循環的利用を行っている物質の種類別内訳は、OP-2:総物質投入量とOP-9:廃
棄物等総排出物、廃棄物最終処分量の【指標算定にあたっての留意点】を参照し
てください。
(ii) 製紙業等において再利用する“黒液”の量は含まれます。
(iii) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-5:総製品生産量又は総商品販売量
総製品生産量又は総商品販売量は、マテリアルバランスの観点から、アウトプ
ットを構成する指標として重要です。この指標は、総エネルギー投入量、水資源
投入量、温室効果ガス排出量、化学物質排出量、廃棄物等排出量、総排水量の環
境への負荷を評価する際にも必要な指標です。
このため、総製品生産量又は総商品販売量、容器包装使用量に関する情報を記
載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.総製品生産量又は総商品販売量
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 容器包装使用量
(3) 解説
社会全体での環境負荷の低減や循環型社会の形成の観点から、使用の段階でエネ
ルギー消費量や廃棄物の発生量が少なく、使用後に循環利用が可能な製品の生産量
又は販売量の増大が期待されています。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 総製品生産量又は総商品販売量は、いずれを把握しても良いものとします。総商
品販売量は主要な製品及び商品の販売量の合計をトン単位で記載します。
(ii) 主要な製品及び商品の販売量のみを記載する場合、対象外とした製品及び商品の
主な内容、対象とした主要な製品及び商品の売上高が総売上高に占める割合を記
載します。
(iii) 期首と期末の原料・半製品・製品の重量に大きな差異がある場合は、総物質投入
量とのマテリアルバランスを考慮する上で、期首と期末の在庫増減重量を記載す
ることが望まれます。
OP-6:温室効果ガス*の排出量及びその低減対策
地球温暖化が進行すると、海面上昇による水害、農産物生産量の減少、伝染病の
伝染範囲の拡大、生息環境の変化による一部野生生物の絶滅等、深刻な影響が生じ
るおそれがあります。それゆえ、大気中の温室効果ガスの安定(地球温暖化防止)と
いう気候変動枠組条約の究極目的を達成するために、その第3回締約国会議で京都議
定書(2005 年2 月16 日発効)が採択されました。京都議定書の数値目標を達成する
ために、事業者として温室効果ガスの排出削減活動を主体的に行う必要があります。
このため、温室効果ガス排出量(トン-CO2 換算)、すなわち京都議定書対象6物
質のそれぞれの排出量及び排出活動源別の内訳と、その低減の基本方針と対策を記
載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.温室効果ガス等排出量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.温室効果ガス(京都議定書6物質)の総排出量(国内・海外別の内訳)(トン-CO2換算)
ウ.温室効果ガス(京都議定書6物質)の種類別排出量の内訳(トン-CO2換算)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 温室効果ガス(京都議定書6物質)の排出活動源別排出量の内訳(事業所別、事業者別)(トン-CO2換算)
? 京都メカニズム*を活用している場合には、その内容、削減量(クレジット量)
? 自主参加型国内排出量取引制度に参加している場合には、その内容と削減量
? 温室効果ガス排出量の算定を担保する仕組み(第三者検証、ISO14064(温室効果ガス排出・削減量の算定・報告・検証に関する規格)等)を利用した場合には、その内容と削減量
? 購入電力の排出係数の推移・見通し
(3) 解説
地球温暖化は、二酸化炭素(CO2)やメタン等の温室効果を有するガスが人間活動
の拡大に伴って大気中に大量に排出され、その大気中濃度の上昇に伴い地球全体と
しての平均気温が上昇する現象です。
この大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的として「気候変動枠組条
約」が、1992年に署名開始(日本は1992年署名)、1994年に発効しています。この気
候変動枠組条約の目的を達成するために、1997年に京都でCOP3(気候変動枠組条約第
3回締約国会議)が開催され、そこで採択された取り決めが「京都議定書」(日本は20
02年6月4日批准)です。これは、先進国等に対し温室効果ガスを第1約束期間(2008
年〜2012年)に1990年を基準年として一定数値(日本は6%)削減することを義務づけ
ています。ロシアの批准により発効要件が満たされ、2005年2月16日に発効し、我が国
も京都議定書の目標を達成することが義務づけられました。この削減目標を達成するた
めに、京都メカニズム等が導入されています。
特にCO2は、我が国の温室効果ガス排出量全体の約9割という最も大きな割合で
地球温暖化に寄与しており、石炭・石油等の化石燃料の燃焼により大量に排出され
ています。
温室効果ガス排出量は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の合計、主な内訳
を二酸化炭素量に換算しトン(以下「トン-CO2換算」という。)単位で記載します。
ただし、CO2以外の温室効果ガスの排出量が僅少である場合には、CO2排出量のみを
記載することができます。
温室効果ガス排出量の主な内訳には、温室効果ガスの種類別の内訳及び集計対象
とした排出活動の内訳を可能な限り記載します。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温暖化対策推進法)に基づき、
平成18年4月1日から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの
温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。報告の
対象となる温室効果ガスは、エネルギー起源CO2及び非エネルギー起源CO2、メ
タン、一酸化二窒素、代替フロン等3ガス(HFC:ハイドロフルオロカーボン、
PFC:パーフルオロカーボン、SF6:六ふっ化硫黄)です。
(ii) 温室効果ガス排出量の算定方法の詳細については、環境省の「温室効果ガス排出量
算定・報告マニュアル」(2006年11月公表)を参照してください。
(参考)環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」
http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual/index.html
(iii) 温室効果ガスの排出削減のための個別対策の導入による削減効果を評価する方法
については、対策の種類によってさまざまな考え方がありますが、個々の対策の実
態に即した合理的な方法により評価する必要があります。例えば、対策前の排出量
と対策後の排出量の差を求める方法の他、対策によって削減効果が見込まれる期間
に影響を受ける電源が想定できる場合には当該電源の排出係数を電気の削減量に
乗じて算定する方法等があります。
(iv) 温室効果ガスの削減量について環境報告書に記載する際には、算定に用いた式と排
出係数を併せて記載し、算定根拠を明らかにすることが必要です。
(v) 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」による報告義務があ
る特定排出者が、エネルギー起源CO2の排出量を報告している場合は、温暖化対
策推進法に基づく報告とみなされます。ただし、その場合でも、エネルギー起源
CO2 以外のガスについて報告の対象となっている場合には、温暖化対策推進法
に基づく報告・公表が必要です。
(vi) 海外における排出分について、当該国において排出係数が定められている場合に
は、それに基づき算定します。
(vii) HFC については、OP-8 化学物質の排出量(フロン類)としても把握します。
(viii) 京都メカニズムを活用したCO2 排出削減量については、事業者の直接の排出抑
制ではないことから、別途把握することとします。
(ix) 温室効果ガスの排出活動源別の排出量の内訳についても、以下のような項目を記
載することが期待されます。
・ 事業エリア内でのエネルギー消費
・ 輸送に伴う燃料使用
・ 廃棄物処理
・ 工業プロセス
・ その他
(x) 総エネルギー投入量が購入電力のみの場合は、エネルギー起源CO2 の排出量と合
わせて記載することができます。
(xi) 電力由来の温室効果ガスの排出量を算出する際に、対象年度の電力のCO2 排出係
数が電力会社から公表されていない場合は、直近の公表数値を活用します。その
場合は、次年度以降の複数期間を同時に報告する際に、新たに公表されたCO2 排
出係数を用いて、対応する年度に関して改めて排出量を算出するという考え方が
あります。
(xii) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-7:大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
排出規制項目の遵守状況を始めとして、大気汚染物質の排出の状況及びその防止
の取組について記載します。さらに、騒音、振動、悪臭の発生の状況並びにその低
減対策についても記載します。また、ヒートアイランド現象の緩和等による都市の
熱環境改善の取組についても記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)排出量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.大気汚染防止法に基づく硫黄酸化物(SOx)排出量(トン)、窒素酸化物(N
Ox)排出量(トン)、揮発性有機化合物(VOC)排出量(トン)
ウ.騒音規制法に基づく騒音等の状況(デシベル)及びその低減対策
エ.振動規制法に基づく振動等の状況(デシベル)及びその低減対策
オ.悪臭防止法に基づく悪臭等の状況(特定悪臭物質濃度または臭気指数)及びその低減対策
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 屋上、壁面及び敷地内の緑化や高反射性塗装、保水性舗装等、都市表面被覆の改善につながる建物、構造物への環境対策の状況
? 地中熱や河川水等を活用した空調排熱等、大気中への人工排熱の排出削減につながる建物等への環境対策の状況
(3) 解説
一酸化窒素や二酸化窒素等の窒素酸化物(NOx)は、主に物の燃焼に伴って発生し、
その主な発生源は工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。(移動発生
源についてはMP-8 を参照してください)NOx 及び揮発性有機化合物(VOC)は光化
学オキシダント、浮遊粒子状物質(SPM)、酸性雨の原因物質となります。
騒音・振動は、その発生源の周辺地域に限定的に存在する物理現象ですが、人の活
動する範囲で広く存在するため、工場・事業場、建設作業や自動車、航空機、鉄道等
の交通による騒音・振動が及ぼす影響から生活環境を保全することは大きな課題とな
っています。
騒音の苦情件数はここ数年増加していますが、発生源別にみると、工場・事業場に
係る苦情の割合が3 割以上、建設作業に係る苦情の割合が3 割弱を占めています。近
年では、低周波音も大きな問題となっています。また、振動の苦情件数を発生源別に
みると、建設作業振動に対する件数が最も多く、工場・事業場振動に係る件数がそれ
に次いでおり、苦情原因として依然大きな割合を占めています。
悪臭の苦情件数は昭和47 年をピークに減少傾向にありましたが、ここ数年は増加傾
向にあります。発生源別にみると、畜産農業や製造工場等、かつて問題となっていた
業種に係る苦情は横ばいで推移していますが、近年、サービス業等に係る苦情が増加
する傾向にあります。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 騒音、振動、悪臭については都道府県知事により指定された地域の場合に該当します。
(ii) SOx、NOx ならびにVOC については、参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-8:化学物質*の排出量、移動量及びその低減対策
わが国では現在、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質
審査規制法)」、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「PCB廃棄物適正
処理特別法」、「ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン法)」等により、
それぞれの法律で指定された化学物質の製造、輸入、使用、処分方法、排出量等
が規制されています。また、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)」では、上記の規制
対象物質を含む幅広い化学物質について、環境への排出量及び廃棄物としての移
動量等の把握・届出(PRTR制度*)、化学物質等安全データシート(MSDS)の
提供が義務付けられ、化学物質の管理とリスクコミュニケーションの推進が責務
とされています。
これらの法律の適用を受ける化学物質は勿論のこと、事業者が自主的に管理の
対象としている化学物質についても、化学物質ごとにそれぞれの排出量、移動量
と、その管理状況を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.化学物質の管理方針及び管理状況
イ.化学物質の排出量、移動量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
ウ.より安全な化学物質への代替措置の取組状況、実績等
エ. 化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制度の対象物質の排出量、移動量(トン)
オ.大気汚染防止法に基づく有害大気汚染物質のうち指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)の排出濃度
カ.土壌・地下水汚染状況
キ.ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類による汚染状況
ク.水質汚濁防止法に基づく排出水及び特定地下浸透水中の有害物質の濃度
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 化学物質の製造・輸入量、取扱量、平均保管量、最大保管量(トン)、用途等
? 化学物質に関するリスクコミュニケーションの状況(説明会の開催回数等)
? 「Japanチャレンジプログラム*」の対象物質の取扱状況及び安全性情報収集状況
? 取り扱っている化学物質の安全性情報の収集、リスク評価の実施(物質名、物質数等)
? 川上(化学物質製造事業者等)から川下への化学物質有害性情報に係る伝達の方針及び取組状況
? 川下から川上への化学物質の用途情報に係る伝達の方針及び取組状況
(3) 解説
現代社会では、多種多様な化学物質が大量に製造されさまざまな場面で幅広く利
用されています。また、ダイオキシン類等のように、非意図的に生成される化学物
質もあります。化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な
管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を
及ぼすおそれがあるものがあります。
事業活動に対する信頼性を高めるとともに、化学物質管理に対する姿勢・努力に
対する社会的評価が可能となるよう、事業者は、説明会の開催等を通じてリスクコ
ミュニケーションを行うことが重要であり、個々のPRTR対象物質について排出量及
び移動量を公表し、その中で重点的に取り組んでいる対策についても説明すること
が望まれます。
欧州では、家電・電子機器に含まれる特定有害物質の使用が禁止(RoHS指令)され
るとともに、化学物質の総合的な登録・評価・許可・制限の制度(REACH)が始まる
等、国内外で有害物質に関する規制が厳しくなってきています。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 化学物質に関する情報を記載する際には、取扱量や購入量が多いもの、あるい
は危険性が高い等、ステークホルダーへの影響が大きいと考えられる化学物質
のみについて、物質毎に排出量、移動量等を区別して記載します。さらに平均
保管量、最大保管量についても記載することが期待されます。
(ii) PRTR 対象物質の排出量及び移動量の把握方法には次の5つの方法があります。
? 物質収支を用いる方法
? 排出係数を用いる方法
? 実測値を用いる方法
? 物性値を用いる方法
? その他の方法
(iii) PRTR 対象物質の算定方法の詳細については、経済産業省・環境省の「PRTR 排
出量等算出マニュアル」(2004 年1 月最終改訂)を参照してください。
(iv) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回
収・破壊法)で対象としているフロン類については、排出量(漏洩量を含む)、回
収量(フロン回収・破壊法に基づき回収業者に引き渡した量)、破壊量(フロン回
収・破壊法に基づき破壊業者に引き渡された量。回収量の内数)についても、可
能な限り把握します。なお、排出量についてはCFC、HCFC はPRTR 対象物質
として、HFC は温室効果ガスとしても把握します。
(v) その他の化学物質の排出量及び法律に規定された物質ごとの排出量を把握するこ
とが求められます。
(vi) 土壌汚染・地下水汚染の状況については、土壌汚染対策法に基づく調査や自主的
に実施した調査の状況について記載することが期待されます。
(vii) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-9:廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
我が国の廃棄物量は、1960年代以降増加を続け、1990年代に入り高水準のまま
ほぼ横ばいで推移しています。近年最終処分場の残余容量が逼迫する一方、処分
にかかる費用の高騰、不法投棄といった問題が引き起こされています。そこで、
廃棄物等*の発生の抑制、循環利用、適正処分が急務となっています。
このため、廃棄物等排出量及び廃棄物*の処理方法の内訳、さらには廃棄物の処
理方法の中でも、最終処分場の不足及び不法投棄の問題を鑑み廃棄物最終処分量
及びその低減対策を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.廃棄物等の発生抑制、削減、リサイクル対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.廃棄物の総排出量(トン)
ウ.廃棄物最終処分量(トン)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 拡大生産者責任に対する対応
? 廃棄物等の処理方法の内訳
? 廃棄物等総排出量の主な内訳(有価物を含む)
? 廃棄物最終処分量の内訳
・直接埋立処分される産業廃棄物量(マニフェスト*で把握する最終処分量)
・産業廃棄物*で埋立処分が予想される中間処理後残渣量及び再資源化に伴う残滓量
・一般廃棄物*で埋立処分される量と中間処理・再資源化後埋立が予想される量
・自社の最終処分場に埋立処分した廃棄物量
? 発注者として建設廃棄物の削減・再資源化等に対する対応
? マニフェスト交付枚数及び電子マニフェスト利用状況
(3) 解説
環境基本計画及び循環型社会形成推進基本法にも示されている通り、廃棄物・リ
サイクル対策は、第一に廃棄物等の発生抑制(リデュース)、第二に使用済製品、
部品の再使用(リユース)、第三に回収されたものを原材料として利用する再生利
用(マテリアルリサイクル)、第四に熱回収(サーマルリサイクル)を行い、それ
でもやむを得ず廃棄物となるものについては、適正な処分を行うという優先順位を
念頭に置くこととされています(ただし、廃棄物以外の環境負荷とトレードオフと
なる可能性があることから、この順によらない場合もあります)。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 廃棄物等総排出量は、事業活動に伴い発生した廃棄物等の排出量の合計、主な
内訳をトン単位で記載します。廃棄物等総排出量は、事業者がその敷地外(管
理外)に、排出・搬出したもの(製品・サービス等の提供に伴い出荷したものを
除く。)及び敷地内で埋め立てたものの重量をすべて合計して算出します。
(ii) 廃棄物の廃棄物等総排出量の主な内訳には、一般廃棄物(そのうちの特別管理
一般廃棄物)、産業廃棄物(そのうちの特別管理産業廃棄物*)の別を記載しま
す。なお、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物については、ステークホ
ルダーの判断に影響を与える可能性がある場合には、その内容、事業活動との
関連による主な発生要因、処分状況を記載します。
(iii) 廃棄物最終処分量は、廃棄物等の埋立処分量及び埋立が予想される中間処理・
再資源化後の残渣や残滓を含み、内訳をトン単位で可能な限り記載します。た
だし、一般廃棄物の排出量が僅少である場合には、産業廃棄物管理票により集
計した産業廃棄物の埋立処分量と中間処理・再資源化後の残渣や残滓量のみを
記載することができます。
(iv) 廃棄物最終処分量の内訳では、自社の最終処分場に最終処分(埋立等)された自
社の廃棄物の重量を合計して算出します。
(v) 廃棄物最終処分量には、埋立処分が予想される再利用、再生利用、熱回収及び単
純焼却*の際の残渣や残滓も含まれますが、直接最終処分される量とは区別して
把握、開示します。残渣や残滓の量を把握できなかった場合は、その旨を明らか
にする必要があります。
(vi) 廃棄物等の処理方法の内訳について、バイオマス発電施設への搬入等、最終処
分の埋立て量や焼却量を軽減する取組の状況等についても記載します。
(vii) 廃棄物等の処理方法の内訳には、再使用される循環資源の量、再生利用される
循環資源の量、熱回収される循環資源の量、熱回収を伴わない単純焼却される
廃棄物の量があります。
(viii) 循環的な利用量には、事業者の敷地内で循環的な利用がなされている物質は含
めません。事業者の敷地内で再使用、再生利用される循環資源については、
「OP-4:循環的利用を行っている物質等」に記載します。
(ix) 再使用、再生利用される循環資源は、事業者がその敷地外(管理外)に、排出・
搬出した循環資源のうち再使用・再生利用したものの重量を合計して算出します。
(x) 工場・事業場の施設や設備等の建て替え、廃棄等に伴う建設廃材は、生産財、資
本財としての性格を有するため、建て替えや廃棄等を行う年度に突出して排出量
が増えるといった変動要因が多いことから、廃棄物総排出量に含めず、分けて把
握し、その総発生量の注記が望まれます。
(xi) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-10:総排水量等及びその低減対策
事業所からの排水や一般家庭からの生活排水による水質汚染は、人の健康への
被害を与え、また魚介類等生態系、水道水質等の生活環境へ影響を及ぼしてきま
した。公共用水域への有機汚濁物質等による汚染に関しては、環境基準が未達成
の水域が存在します。
このため総排水量、排出先ごとの排水量と水質及びその低減対策を記載しま
す。
(1) 記載する情報・指標
ア.総排水量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.総排水量(立方メートル)
ウ.水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく排水規制項目(健
康項目*、生活環境項目*、ダイオキシン類)の排出濃度(平均値、最大値)並
びに水質汚濁防止法等の総量規制対象項目で示した汚濁負荷量、並びにその低
減対策
エ.排出先別排水量の内訳(立方メートル)
・河川
・湖沼
・海域
・下水道等
(2) 記載することが期待される情報・指標
? 海や河川湖沼等の水利用(主に熱交換として)における温排水・冷排水の利用量及び平均温度差
(3) 解説
水は、雨となって地上に降り、森林や土壌を経て、地下水として保水され又は河
川を通って海に注ぎ、蒸発して再び雨になるという循環過程の中にあります。健全
な水循環の確保及び水質の維持のために、水利用に伴う環境への負荷を管理するこ
とが必要です。水質の汚濁については、人の健康を保護し、及び生活環境を保全す
る上でそれぞれ維持することが望ましい基準として、環境基準が設定されています。
環境基準の達成や、水質汚染の未然防止を目的として、水質汚濁防止法に基づき、
工場及び事業場からの排水について、健康項目27 項目、生活環境項目15 項目の排
水基準が定められています。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 総排水量は、事業活動に伴い発生した排水量の合計、主な内訳を立方メートル
単位で記載します。総排水量の主な内訳には、河川、湖沼、海域、下水道等の
排出先別に記載します。
(ii) 水資源投入量には、製造過程に使用されなかった場合も含め、外部から供給された水
量すべてを含むことが期待されます。例えば、純水製造時にR/O 膜からオーバーフロ
ーし、実際に工程に投入されずに排水される水量も水資源投入量に算入します。
(iii) 排水規制項目の排出濃度のうち、健康項目及び生活環境項目(pH、大腸菌群数
以外)についてはリットル当たりミリグラム(mg/?)単位で、ダイオキシン類につ
いてはリットル当たりピコグラム(pg-TEQ/?)単位で記載します。
(iv) 排水量を流量計等のメーターによって測定していない場合は、排水量を合理的な方法
で算定します。この場合は、開示している排水量が実測に基づく数値ではない旨及び
排水量の算定方法を注記することとします。
(v) 総量規制対象地域から排出される排水の汚濁負荷量については、トン単位で記
載します。
(vi) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
4.「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標(EEI)
(環境効率指標:EEI)
(1) 記載する情報・指標
ア.事業によって創出される付加価値等の経済的な価値と、事業に伴う環境負荷(影響)の関係
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境効率*の改善状況
(3) 解説
事業にあたっては、できるだけ少ない環境負荷で事業活動を行うことが期待されま
す。そのような全体的な状況を示すものとして、事業全体の環境効率を示す環境効率
指標があります。本来であれば、事業に関わるすべての環境負荷と事業の活動成果を
表す経営指標(付加価値や売上高等)との関係を示すことが望まれます。しかし、少
なくとも現在、複数の環境負荷を一つに統合する算定方法についてはいくつかの手法
や理論が存在し、ガイドラインとして特定の手法を推奨するには時期尚早の段階にあ
ります。一方、複数の環境負荷を統合せずに、事業活動に伴う特定の環境負荷につい
て、環境保全コスト一単位当たりの値や付加価値等との比較についての環境効率を算
出する方法もあります。
ただし、事業者にとっては本来は購入や調達を含むサプライチェーンや使用・廃棄
の段階も含めた環境効率性を高めることが目標となるべきであり、それらに関する環
境負荷の把握が可能である場合は、できるだけ範囲を広げて環境効率性を示すことが
期待されます。
また、環境負荷の内容についても、できるだけ幅広いもので示していくことも望ま
れます。環境効率を示す指標の分子・分母にはさまざまな要素と組み合せがあり、業
種や事業特性に応じた要素を適切に選定することが必要です。また、いくつかの指標
を組み合わせて用いることによって、より幅広い情報を提供することも考えられます。
なお、環境効率の定義や測定の形態は業種により異なることがあり、事業内容の異な
る事業者間について比較する場合には注意が必要です。
さらに、環境効率や全体的な環境負荷総量(異なる種類の環境負荷の量を何らかの
係数により統合した単一の指標で表すもの)に関する改善状況について、中長期の目
標と関連させて示すことも期待されます。
(4) 代表的な環境効率指標の事例
環境効率については、個別の環境負荷を対象とする環境効率指標と、複数の環境負
荷(環境影響)を統合した値を対象とする環境効率指標があります。前者には売上高
CO2 原単位や生産高廃棄物原単位等があり、後者には各事業者による独自の手法だけ
でなく、「LIME(被害算定型環境影響評価手法)」や「JEPIX(環境政策優先度指数)」等
の民間研究機関が開発した手法があります。特に、後者の環境効率指標を用いる場合
は、統合に用いる係数はさまざまな推定条件や前提条件に基づいて算定されているこ
とを十分に理解することが必要です。それゆえ、環境報告においては環境効率指標の
考え方とともに算定式を明記し、ステークホルダーに指標の持つ意味を正確に伝える
工夫が求められます。また、事業者間の比較を行う際には、環境効率指標が持つ特性
や限界等に十分留意する必要があります。
環境効率指標に採用する分子・分母にはさまざまな指標が可能ですが、代表的な環
境効率指標には以下のようなものが考えられます。ここで示すもの以外にも、事業者
等において考案されている多様な環境効率指標を参考資料に例示しています。(参照:
【指標算出にあたっての留意点】
(i) 環境効率指標の計算にあたっては、分子(経済価値)と分母(環境負荷)の数値
のバウンダリー(集計範囲)を一致させることが必要です。
(ii) 分母(環境負荷)に採用する数値(CO2 排出量や廃棄物最終処分量等)は、相対
値ではなく総量で表示することが必要です。
(iii) 環境効率指標は事業者の環境経営の取組や努力を如実に反映するものですが、そ
れはあくまでも相対値であるため、読み手に誤解を与えないように、総量も併記
する必要があります。
(iv) 環境効率指標の開示は経年変化が明確に分かるように記載する必要があります。
それは事業者の取組の成果や課題を分析することにも役に立つものです。
第4章 「社会的取組の状況」を表す情報・指標
1.環境報告書に記載する情報・指標の考え方
近年、我が国で発行される広い意味での環境報告書の内、62.7%が環境保全の取組
だけでなく社会的取組の状況についても記載しているとの調査結果5があります。また、
その名称も「CSR 報告書」「環境・社会報告書」「サステナビリティ報告書」等、社会
性を含むものが多く見られるようになっています。これは、環境問題と社会問題への
取組が、企業の社会的責任を果たす上でいずれも重要な課題であることから、併せて
報告を行っているものと考えられます。
平成18 年4 月に閣議決定された第三次環境基本計画においても、環境政策の基本的
方向の一つ目として、「環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合的向上」が掲げら
れています。事業者という経済的な主体が、事業活動の環境的側面や社会的側面を経
営方針に組み込み、その取組状況を開示することは、持続可能な社会の実現のために
望ましいと考えられます。
このような観点から、本章では、既存の環境報告書に多く記載されている項目や、
さまざまなガイドライン等に示されている項目を踏まえて、「社会的取組の状況」を表
す情報・指標を示します。
特に、地域コミュニティの活力は、環境的側面と社会的側面の両方にとって重要な
課題です。事業者として地域コミュニティとどのような関係を築くのかを考えるに当
たっては、この両方の側面を併せて検討していくことが望ましいといえます。このよ
うな地域コミュニティとの関係について、アメリカにおいては企業の社会的責任とし
て重視されています。他方、ヨーロッパにおける企業の社会的責任の議論では、域内
の雇用確保や人材育成等の問題に大きな関心が払われています。
いずれにしても、社会的取組の内容については、社会的な重要性やそれぞれの事業
者が置かれている状況によって重視すべき課題が大きく異なります。したがって、以
下に記載する項目はあくまでも例であり、これ以外の項目も含め、各事業者が必要と
考える社会的課題の解決に向けた取組について記載していくことが求められます。
社会的取組についての記載内容を検討する際には、環境保全に係る項目と同様にス
テークホルダーとの関係が重要であり、当該地域固有の文化的・歴史的背景に鑑み、
さまざまなステークホルダーと意見交換を行いながら、自らにとって特に課題となる
項目を中心に記載することが望まれます。
なお、現在、政府や民間団体においても、企業の社会的責任に関し、さまざまな調
査研究が報告されており、現在も検討が行われているものもあります。社会的取組の
状況について記載する際は、それらも参考にしつつ、適切な情報を提供することが望
まれます。
2.「社会的取組の状況」を表す情報・指標(SPI)
(1) 記載することが期待される情報・指標
「社会的取組の状況」を記載する場合、社会的取組への方針、目標、計画等を記
述することが期待されます。また、例えば、次のような情報や指標について、ステ
ークホルダーとの協議を行う等、選定手順を工夫しつつ、社会的な重要性も踏まえ、
適切な情報や指標を選択して記載することが期待されます。さらに、事業活動全体
として社会的な価値の創造にどの程度寄与できたか、取りまとめて示すことも考え
られます。
?労働安全衛生に関する情報・指標
・労働安全衛生に関する方針、計画、取組
・労働災害発生頻度、労働災害件数
・従業員の健康管理に関する方針、取組
・度数率、強度率、労働損失日数
・健康/安全に係る支出額、一人あたり支出額
・労働安全衛生マネジメントシステム指針への対応
・労働安全衛生委員会の議事内容と従業員への周知
※危険性・有害性等の調査等に関する指針への対応
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-5-1-0.htm
※ 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-19/hor1-19-1-1-0.htm
※ 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-21/hor1-21-1-1-0.htm
※ 労働安全衛生マネジメントシステム指針
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-58-1-0.htm
?雇用に関する情報・指標
・雇用に関する方針、計画、取組
・労働力の内訳
・賃金等の状況
・従業員の公正採用選考の状況
・人事評価制度の状況
・教育研修制度の状況
・男女雇用機会均等法に係る情報
・障害者の雇用方針及び取組状況、障害者の雇用の促進等に関する法律による障害者の雇用状況
・外国人の雇用方針及び雇用状況
・福利厚生の状況
・労使関係の状況
・職場環境改善の取組状況
※ 女性労働者の能力発揮促進のための企業の自主的取組に関するガイドライン
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-35.htm
※ 職場におけるエイズ問題に関するガイドライン
http://api-net.jfap.or.jp/mhw/document/doc_02_29.htm
※ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-2.pdf
?人権に関する情報・指標
・人権に関する方針、計画、取組
・差別対策の取組状況
・児童労働、強制・義務労働防止の取組状況(サプライチェーンを含むこれらに関する撤廃プログラムの状況等)
・人権に関する従業員への教育研修
?地域及び社会に対する貢献に関する情報・指標
・地域文化やコミュニティの尊重、保護等に係る方針、計画、取組(特に事業活動に係る国内外の地域)
・発展途上国等における社会的な取組
・フェアトレード、CSR調達の状況
・地域の教育・研修への協力、支援の状況
・環境以外の社会貢献に係る方針、計画、取組
・NPO、業界団体等への支援状況、支援額、物資援助額等
?企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引に関する情報・指標
・企業統治・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引に係る方針、体制、計画、取組
・環境関連以外の法律等の違反、行政機関からの指導・勧告・命令・処分等の内容及び件数
・環境関連以外の訴訟を行っている又は受けている場合は、その全ての内容及び対応状況
・行動規範策定の状況
・独占禁止法遵守等の公正取引の取組状況
・公益通報者保護に係る方針、計画、取組
?個人情報保護に関する情報・指標
・個人情報保護に係る方針、計画、取組
?広範な消費者保護及び製品安全に関する情報・指標
・消費者保護、製品安全及び品質に係る方針、計画、取組
・製品・サービスの設計・製造・販売(提供)・使用・廃棄の過程を通じて、顧客の安全・衛生を確保する取り組みの方針・取組
・主要な製品・サービスの安全基準適合性を認証・検証する機関及び必要に応じて認証・検証手続きの記載と安全基準適合性の数値目標と達成状況
・顧客への宣伝・販売に関する法令・自主規制基準等を遵守する社内体制
・PL法対策、特に製品設計、製造及び表示における安全対策
・販売後の点検、修理等のアフターサービスプログラム
・消費者クレーム窓口の設置及びその処理状況(消費者基本法による製品等の苦
情処理窓口の設置及びその処理の状況、消費生活用製品安全法による製品に関
する被害発生の報告の状況)
・景品法による製品等の品質表示・説明に関する根拠資料の開示の状況
・製品等のリコール及び回収等の状況
・消費者契約法、消費者基本法、金融商品取引法、特定商取引法遵守に関する販
売並びに消費者契約の契約条項等の適正化プログラム及びその遵守状況
?企業の社会的側面に関する経済的情報・指標
・ステークホルダー別の企業価値(付加価値)の配分
・環境関連分野以外の寄付や献金の相手先及び金額
・適正な納税負担の状況
?その他の社会的項目に関する情報・指標
・動物実験を実施する際の方針、計画、取組
・知的財産の尊重、保全
・武器及び軍事転用可能な製品・商品の取扱・開発・製造・販売に関する方針、計画、取組
・受賞歴
(2)解説
社会的側面に関する情報として、どのような情報を記載することが望ましいかに
ついては、さまざまな意見があります。
例えば、OECD(経済協力開発機構)の「多国籍企業ガイドライン」(最新版は2000
年6月改訂)は、多国籍企業による貿易・投資の自由化、経済のグローバル化に対する
市民社会からの懸念に応えるための行動規範として策定されましたが、その内容は序文
に加えて10章(定義と原則、一般方針、情報開示、雇用及び労使関係、環境問題、贈賄
の防止、消費者利益、科学及び技術、公正な競争、課税)からなります。
また、GRIガイドライン第3版では、社会的パフォーマンス指標の項目として、労
働慣行とディーセント・ワーク(公正な労働条件)、人権、社会、製品責任の4種
類を挙げています。
社会的側面は、地域、国、地球等の持続可能性、各レベルのステークホルダーへ
の影響、事業者に求められる社会的責任を考慮して検討されるべきものです。この
ガイドラインでは、記載することが期待される情報・指標を、労働安全衛生、雇用、
人権、地域及び社会に対する貢献、企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫
理・コンプライアンス及び公正取引、個人情報保護、広範な消費者保護及び製品安
全、企業の社会的側面に関する経済的情報・指標、その他の社会的項目の9種類に分
類しましたが、これらは現在、社会的な関心が高いと思われるもの、法律等による
規制等があるものです。
社会的側面の情報・指標は、それぞれの業種や規模等により異なると考えられま
すが、本ガイドラインを参考に、それぞれの状況に応じた項目を具体的に記載する
ことが望まれます。
第5章 環境報告の充実に向けた今後の課題
1.ステークホルダーとの協働による質の高い環境報告を
環境問題が多岐にわたり、かつ事業活動の範囲が広がるに従い、事業者は環境報
告の内容について、事業内容等を踏まえて、適切なものとなるように工夫する必要
があります。ただし、どのような課題に焦点を当てるか等について、必ずしも客観
的に明らかではない場合も多くみられます。このようなことを踏まえると、今後は、
さまざまなステークホルダーと意見交換を行いながら環境報告を行っていく必要性
が高くなってくると考えられます。
そのような必要性を踏まえ、環境報告書の作成過程において、ステークホルダー
等と必要な意見交換が適切に行われ、次年度の環境報告に反映される仕組みの開発
に、関係者全体で努めていく必要があります。
また、ステークホルダーには、環境報告に積極的に協力・関与することが期待さ
れ、関係者全体で質の高い環境報告の普及啓発に努めていく必要があります。
2.環境報告の活用方策について
事業者は積極的に環境報告書による環境報告を行っていくことが求められてい
ます。一方、環境報告書がステークホルダーエンゲージメントのツールとしての役割
を高め、事業者の環境配慮の取組を説明する場で幅広く活用されることが期待されま
す。
環境報告の活用方策としては、まず、事業者内部において十分に活用されることが
期待されます。環境経営を進めるためには、経営者が率先して必要かつ十分なコミッ
トメントを記載するとともに、環境報告の内容を十分に把握し、従業員に浸透させる
措置をとる必要があります。また、従業員についても、環境報告の内容を把握し、環
境配慮に努めることが望まれます。
株主等の出資者や地域住民、マスコミ、関係するNPO 等といった外部のステーク
ホルダーに対して、説明会や記者会見、意見交換会等を行い、環境配慮の取組状況や
環境経営の方針について説明する機会を設けて活用するようなことも期待されます。
その際には、できるだけステークホルダーとの意思疎通を行い、ステークホルダーが
十分な知見を得ることができるとともに、事業者としてステークホルダーの意見を経
営に反映させていくことができるようにすることも望まれます。
また、環境報告は投融資や企業評価の際に活用される機会も増えてくることが期待
され、できるだけわかりやすく合理的に環境配慮の状況の全体像を伝えるための方法
についても、金融関連の評価機関等も関与し、関係者全体で開発していく必要があり
ます。
その他、今後、環境報告がさまざまな場面で十分に活用されるよう、環境報告の関
係者が活用方策の開発等に努めていく必要があると考えられます。
3.社会的取組の状況について
昨今、CSR 報告書や社会・環境報告書等、環境報告書の中で社会的取組の状況につ
いて公表する事業者が増えてきており、社会的取組についての情報や指標を示したガ
イドラインが求められています。環境問題は社会的状況との関連が強いことから、事
業者が「社会的取組の状況」についても自主的に開示していく方向は好ましく推奨し
ていきたいと考えていますので、本ガイドラインでは記載が望ましいと考えられる情
報・指標を例示しました。
社会的側面の情報・指標については、他省庁やさまざまな国際機関、NPO 等でも検
討が行われていますが、現在は研究の途上にあります。今後は、それらの研究成果を
踏まえて、できるだけ幅広い関係者の参画の下に、企業の社会的責任に関する報告全
体と環境報告の在り方について検討していく必要があります。
一方、社会的取組の情報を重視し、環境経営や環境パフォーマンスに関する情報を
十分に記載していない環境報告書も見受けられます。地球環境問題の深刻化の中で、
持続的社会の創造の基盤となる環境配慮の取組について、事業者が積極的かつ自主的
に情報開示をしていくことは、これまで以上に重要となってきています。それゆえ事
業者においては、環境配慮の取組状況を本ガイドラインに準拠し適切に情報開示して
いくことが強く期待されます。
【参考資料】
1.BI-4-1:主要な指標等の一覧(掲載する際の例)
2.用語解説
3.Q&A
4.環境効率指標の事例
5.指標の一般的な計算例
6.国内外の研究機関等及び諸外国における研究成果
7.チェックリスト
2.【用語解説】
(注)出典明記のないものは、環境省にて定義ない
し解説されていることを示す。また、各項目
の( )内の数字は本文の記載頁を示す。
はじめに
(ア) 第三次環境基本計画
環境基本計画は、環境基本法第15 条に基づき、政府全体の環境の保全に関する総合的かつ長期
的な施策の大綱を定めるもの。環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議決定
を経て告示される。
第三次環境基本計画は、平成18 年4 月7 日に閣議決定された。今後の環境政策の展開の方向と
して、環境と経済の好循環に加えて、社会的な側面も一体的な向上を目指す「環境的側面、経済的
側面、社会的側面の統合的な向上」等を提示している。今後展開する取組として「市場において環
境の価値が積極的に評価される仕組みづくり」「環境保全の人づくり・地域づくりの推進」等を
決定している。計画の効果的な推進のための枠組みとして、計画の進捗状況を具体的な数値で明ら
かにするため、重点分野での具体的な指標・目標、総合的な環境指標を設定している。
(イ) 特定事業者
環境配慮促進法第2 条第4項の規定に基づき、特別の法律によって設立された法人であって、そ
の事業の運営のために必要な経費に関する国の交付金又は補助金の交付の状況その他からみた
その事業の国の事務又は事業との関連性の程度、協同組織であるかどうかその他のその組織の態
様、その事業活動に伴う環境への負荷の程度、その事業活動の規模その他の事情を勘案して政令
で定めるもの。
(ウ) 企業の社会的責任(CSR)Corporate Social Responsibility。
企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホルダー(利害関
係者)全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え方であり、法令等の遵守、環境保護、人権
擁護、消費者保護等の社会的側面にも責任を有するという考え方。
(エ) グローバル・リポーティング・イニシアチブ(GRI)
国際的なサステナビリティ・レポーティングのガイドライン作りを使命とするオランダに本部
を置くNGO で国連環境計画(UNEP)の公認協力関である。
(ア) ステークホルダー
一般に利害関係者と訳され、企業等の環境への取組を含む事業活動に対して、直接的または間接
的に利害関係がある組織や個人をいう。企業の利害関係者としては、顧客・消費者、株主・投資家、
取引先、従業員、NPO、地域住民、行政組織等をいう。
第1章 環境報告書とは何か
2.環境報告書の基本的機能
「社会的責任投資」(SRI)Socially Responsible Investment。
確定した国際的な定義はないが、狭義では「企業への株式投資の際に、財務的分析に加えて、企業の環境対
応や社会的活動等の評価、つまり企業の社会的責任の評価を加味して投資先企業を決定する投資
手法」の意。広義では「社会性に配慮したお金の流れとその流れをつくる投融資行動」とされ、
?スクリーン運用(対象銘柄の環境・社会的側面を評価した株・債券への投資)のほかに、
?株主行動(株主の立場から、経営陣との対話や議決権行使、株主議案の提出等を通じて企業に社会的な行
動をとるよう働きかけるもの)や、
?コミュニティ投資(上記の二つが主に大企業を対象としているのに対して、主として地域の貧困層の経済的支
援のための投融資)がある。
「後発事象」
会計用語で、決算日後に発生し、次期以降の財政状態や経営成績に影響を及ぼす事象を後発事
象という。環境報告書では、基準日の翌日から環境報告書の発行日までに、重要な法規制等の違反
の判明、重要な訴訟事件等の発生又は決着、その他ステークホルダーの判断に影響を及ぼす可能
性のある重要な事実が発生した場合には、その内容、今後の見通し等を重要な後発事象として、記
載することが期待される。
「サプライチェーン」
企業における原料の調達から最終消費者に届けるまでの供給活動(調達・開発・生産・輸送・
保管・販売)における全プロセスの繋がり。事業者が他の事業者から原材料や部品等を調達する
際に、製品の価格や品質に加えて環境配慮型の製品やサービスを優先的に選択するというサプラ
イチェーンの環境配慮が進むことで、産業全体の環境配慮を進める効果が期待されている。
第2章 環境報告の記載項目の枠組み
「マテリアルバランス」
事業活動に投入された資源・エネルギー量(インプット)と、製造された製品・サービスの生産・
販売量、廃棄物・温室効果ガス・排水・化学物質等の環境負荷発生量(アウトプット)を、分かり
やすくまとめたものである。
「総合的環境指標」
環境基本計画では「環境の状況、取組の状況等を総体的に表す指標」と定義されており、環境基
本計画の進捗状況についての全体的な傾向を明らかにし、環境基本計画の実効性の確保に資する
ために活用するという方向性が示されている。
「環境監査」
特定される環境にかかわる活動、出来事、状況、マネジメントシステム又はこれらの事項に関す
る情報が監査基準に適合しているかどうかを決定するために監査証拠を客観的に入手し評価し、
かつ、このプロセスの結果を依頼者に伝達する、体系的で文書化された検証プロセス。
「環境保全コスト」
環境会計の構成要素の1つ。環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、影響の除去、発生した被害
の回復又はこれらに資する取組のための投資額及び費用額とし、貨幣単位で測定する。
「環境保全効果」
環境会計の構成要素の1つ。環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、影響の除去、発生した被害
の回復又はこれらに資する取組による効果とし、物量単位で測定する。
「環境保全対策に伴う経済効果」
環境会計の構成要素の1つ。環境保全対策を進めた結果、企業等の利益に貢献した効果とし、貨
幣単位で測定する。
環境保全対策に伴う経済効果は、その根拠の確実さの程度によって、実質的効果と推定的効果と
に分けることとし、実質的効果は確実な根拠に基づいて算定される経済効果を、推定的効果は仮定
的な計算に基づいて推計される経済効果をさす。
「環境管理会計」
環境会計は、企業外部へ情報開示を行う外部環境会計(external environmental accounting)
と、企業内部の経営管理に資する内部環境会計(internal environmental accounting)に大別
され、この内部環境会計を環境管理会計(environmental management accounting: EMA)
と呼ぶことが、近年、欧米では定着しつつある。
資材原材料利用の効率性を高め、環境への影響とリスクを緩和し、環境保全コストを削減すること
を目的として、財務会計と原価計算(管理会計)からデータを取り入れるための複合的なアプロ
ーチ。民間企業または公共企業体を対象としたものであり、国家は対象としない。また物量情報だ
けでなく貨幣情報も含む。
「カーボンファンド」
クリーン開発メカニズム( CDM : CleanDevelopment Mechanism)や共同実施(JI:Joint
Implementation)のような温室効果ガスの排出削減プロジェクトの実施には、事業運営上のさまざ
まなリスクが伴う。こうしたリスクを回避するため、複数の企業が出資者となり、単独では持つこ
とが困難な情報収集力・資金力・リスク軽減能力を駆使するとともに、ファンドという形態を活用
して多様なプロジェクトをポートフォリオに取り入れることにより、単独企業での取得に比して
低リスクで安く安定的に排出権を獲得する仕組み。排出権買取ファンドとも呼ぶ。
「フェアトレード」
フェアトレードとは公正取引の意であるが、とりわけ、経済的・社会的に立場の弱い生産者に配
慮した貿易・取引を指す場合が多い。主に発展途上国の農産物や手工芸品などの生産者は、国際的
な商品価格の変動にさらされ、収入が不安定になることも少なくない。また、生産に必要な物資や
資金を買い手から前借りする場合などもあり、買い手の値下げ圧力のために不当な対価しか得ら
れないこともある。
こうした構造的な問題に対し、国際市場価格よりも高めに設定した価格で長期にわたって継続
的に直接取引することにより、生産者の生活と人権を保護し自立を支援する社会運動がフェアト
レードである。搾取的な取引は、人道面だけでなく土地や森林など環境面の負荷につながるほか、
商品の品質にも影響が出ることもあり、フェアトレードは経済・社会・環境面でバランスのとれた
持続可能な発展のための社会的措置であると認識されている。各種商品についてのフェアトレー
ドの国際規格も定められている。
「環境負荷低減に資する製品・サービス等」
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第2条第1項に定
める「環境物品等」を指す。具体的には以下のとおり。
・環境負荷低減に資する原材料又は部品(再生資源、再生部品等)
・環境負荷低減に資する製品(再生資源・再生部品を用いた製品、環境汚染物質の使用を削減した製品、エネルギー消費量の少ない製品、再使用・再生利用が可能な製品等)
・環境負荷低減に資するサービス(低公害車を用いた運送サービス等)
「森林認証」
森林認証は、独立した第三者機関が一定の基準等を基に、適切な森林経営や持続可能な森林経営
が行われている森林又は経営組織等を認証し、それらの森林から生産された木材・木材製品へラベ
ルを貼り付けることにより、消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する取組
である。森林認証の例としては、世界的規模のFSC(森林管理協議会)や我が国独自の制度であ
るSGEC(緑の循環認証会議)による認証がある。
「低公害車」
既存のガソリン自動車やディーゼル自動車に比べ、窒素酸化物や二酸化炭素等の排出量の少な
い自動車。経済産業省・国土交通省・環境省で策定した「低公害車開発普及アクションプラン」で
は電気自動車、圧縮天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び低燃費かつ低排
出ガス認定車の5 種が実用段階にある低公害車として挙げられている。これ以外にも、環境負荷
の削減を意図した自動車としてLPG 車、希薄燃焼エンジン車、ソーラー自動車、水素自動車、燃料
電池自動車、エタノール自動車、バイオディーゼル自動車等多種多様なものが挙げられる。
「環境適合設計(DfE)」
DfE は「Design for Environment」の略。環境への負荷がより少ないもの作りを進めることで、
「ものやサービスがライフサイクルを通じて与える環境への負荷を可能な限り低減させるため
のプロセス」であり、環境調和型製品の設計方法を意味する。環境配慮設計やエコデザインとも呼
ばれる。DFE と表記される場合もあるが、ISO ではDfE としており、JIS では「環境適合設計」とし
ている。
DfX は、"X"の部分に製品競争力を高めるための何らかの視点をおいた製品設計・開発手法
の総称であり、設計以外の段階、つまり製造、配送、使用、保全、廃棄等の段階における任意のパ
フォーマンスを向上させるメカニズムを設計段階において製品に実装する作業のことをいう。
「生物多様性」
生物多様性は遺伝子、種、生態系の3つのレベルでとらえられることが多い。すなわち、自然生
態系を構成する動物、植物、微生物等地球上の豊かな生物種の多様性とその遺伝子の多様性、そし
て地域ごとのさまざまな生態系の多様性をも意味する包括的な概念である。地球の生態系の中で
は生物が刻一刻と生まれ、死に、エネルギーが流れ、水や物質が循環しており、生物多様性はこう
した自然界の動きを形づくっている。
「生物多様性条約」
正式名称は「生物の多様性に関する条約」。1992年に採択され、同年リオ・デ・ジャネイロ(ブラ
ジル)で開催された国連環境開発会議(地球サミット)で署名が開始され、翌1993 年に発効した。
生物多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正な配分
を目的としている。国連の国際生物多様性年である2010 年に開催される第10 回締約国会議を名古
屋に招致することが、政府により決定されている。
「生物多様性国家戦略」
生物多様性条約第6 条に規定されている生物多様性の保全と持続的利用のための国家的戦略
あるいは計画のことで、締約国はその状況と能力に応じて作成することとされている。この戦略で
は、生物多様性の保全、持続可能な利用、普及啓発に関する措置、研究の推進、国際協力等多方面
にわたる施策・計画が定められ、関連する部門での生物多様性保全、持続可能な利用への取組も求
められる。
日本では、1995 年10 月に、政府の生物多様性保全の取組指針として「地球環境保全に関する関
係閣僚会議」で「生物多様性国家戦略」を決定し、2002 年3 月には、「新・生物多様性国家戦略」を
決定した。
「絶滅が危惧される種」
国内では、環境省や都道府県発行のレッドデータブックに記載されている動植物種全般に対し、
準絶滅危惧種等も含めて「絶滅が危惧される種」と呼ぶ。国際的には国際自然保護連合(IUCN)の
レッドデータブックに記載された種。
「水産エコラベル」
水産エコラベルに関わるガイドラインとして、2005 年にFAO(国連食糧農業機関)が採択した「海
面漁業により漁獲された魚及び水産物のエコラベリングのためのガイドライン」があり、第三者
機関が生産者の取組を審査しその適正性を証明する仕組みを定めている。
世界的規模の取組としては、国際的な第三者機関であり非営利団体であるMSC(海洋管理協議
会)の認証があり、持続可能な漁業であることを漁業に対して審査する「漁業認証」と、商品の加
工流通過程の管理が適正であることを審査する「CoC 認証」で構成されている。
「環境ラベル」
製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、
(1)「エコマーク」等第三者が一定の基準に基づいて環境保全に資する製品を認定するもの、
(2)事業者が自らの製品の環境情報を自己主張するもの、
(3)ライフサイクルアセスメント(LCA)を基礎に製品の環境情報を定量的に表示するもの等がある。
「環境ラベル認定等製品」
環境ラベル認定等製品には特に定まった定義はない。事業者が、環境負荷低減に資する製品・
サービス等と評価するものを対象とする。たとえば、グリーン購入法第2 条第1 項に定める「環境
物品等」やエコマーク等の環境ラベル認定商品等が挙げられる。
「省エネルギー基準適合製品」
大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であってその
性能の向上を図ることが特に必要なものとして施行令で指定された機器(特定機器)については、
特定機器ごとに、その性能の向上に関し製造事業者等の判断の基準となるべき事項(省エネルギー
基準)が定められている(省エネルギー法18 条、施行令7 条)。この省エネルギー基準に適合して
いる製品のことをいう。
「サービサイジング」
これまで製品として販売していたものをサービス化して提供することを意味する用語である。
本質的にモノの価値はその機能にあり、また環境負荷からみても物を所有するとメンテナンス
や廃棄・最終処分について事業者自らが直接に責任を負うことになる。外部の専門業者からリース
やレンタルといった形態で「機能」の提供を受けることにより、事業者自身の環境負荷を低減する
ことができる。
この用語は、主に米国を中心に使用されており、欧州では、同じ概念を表す用語として、PSS
(Product service systems:製品サービスシステム)を使用している。PSS は「使用者のニーズ
を充たすように製品とサービスを結合して市場に提供されるセット(システム)」と定義されて
いる。
「エコツーリズム」
自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴
史文化の保全に責任を持つ観光のありかた。自然環境等の資源を損なうことなく、自然を対象とす
る観光をおこして地域の振興を図ろうという考え方である。
「新エネルギー」
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネルギー法)」において、「新エネルギー
利用等」として規定された、技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及
が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なものをいう。
具体的には、大きく3 つに分かれる。再生可能エネルギー(風力発電、太陽光発電、太陽熱利用
等。ただし水力発電は除く)、リサイクルエネルギー(廃棄物発電、廃棄物熱利用など)、従来型
エネルギーの新利用形態(燃料電池、天然ガスコージェネレーション等)。本ガイドラインにおい
ては、グリーン電力証書による購入電力も新エネルギーに含むことにする。
「再生可能エネルギー」
化石燃料や鉱物などのような短期間で再生できない枯渇性資源によらないエネルギー。具体的
には、風力、太陽光、水力、バイオマス、海洋、地熱等を指す。
「循環的な利用」
循環的な利用とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう(循環型社会形成推進基本法)。
「再使用」
(1)循環資源(廃棄物等のうち有用なものをいう)を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む)、
(2)循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること(循環型社会形成推進基本法2 条5項)。
「再生利用」
循環資源の全部又は一部を原材料として利用すること(循環型社会形成推進基本法)。
「熱回収」
循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のある
ものを、熱を得ることに利用することをいう(循環型社会形成推進基本法2 条7 項)。例えば、廃
棄物の焼却によって生じる実熱を冷暖房や温水等の熱源として利用すること。
「総物質投入量」
総物質投入量は、製品・サービス等の原材料等として事業活動に直接投入される物質をいう。た
だし、事業者内部で循環的に利用(再使用、再生利用、熱回収)している物質は含めない。
「中水」
中水とは上水と下水の中間に位置付けられる水の用途で、水をリサイクルして限定した用途に
利用するもの。上水の使用量が増加し水源不足が都市の深刻な問題となっていることや上下水コ
スト低減の面から、水資源の節減を図る中水が近年注目を集めつつある。
「温室効果ガス」
大気中の二酸化炭素やメタン等のガスは太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きが
ある。これらのガスを温室効果ガスという。温室効果ガスのうち、京都議定書における削減約束の
対象物質は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC 類、PFC 類、六ふっ化硫黄の6 種類。
「京都メカニズム」
温室効果ガスの削減を国際的に連携して確実に進めるための仕組みとして京都議定書で定め
たもので、「クリーン開発メカニズム(CDM)」「共同実施(JI)」「排出量取引(ET)」の3つからなる。
国家間で投資や取引といった市場メカニズムを活用する点が特徴。なお、先進国が植林等により
二酸化炭素を吸収・固定する「吸収源活動」も認められている。
「化学物質」
本ガイドラインでは、「大気汚染防止法」、「PCB廃棄物適正処理特別法」、「ダイオキシン法」、「化
学物質審査規制法」、「化学物質排出把握管理促進法」等の法令の適用を受ける化学物質及び事業者
が自主的に管理対象とする化学物質が該当する。
「PRTR 制度」Pollutant Release and Transfer Register(化学物質排出移動量届出制度)。
人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれて
事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、国に報告を行い、国は事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、対象化学物質の環境への排出量等を把握、集計し、公表する仕組みをいう。
日本では平成11 年、「化学物質排出把握管理促進法」により制度化された。
「Japan チャレンジプログラム」
官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム。産業界と国が連携して、既存化学物質
の安全性情報の収集を加速化し、化学物質の安全性について広く国民に情報発信することを目的
に、平成17 年6 月より開始したプログラム。
「廃棄物等」
廃棄物及び一度使用され、もしくは使用されずに収集され、もしくは廃棄された物品(現に使用
されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理もしくは販売、エネルギーの供給、土木建築
に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(廃棄物並びに放射
性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう(循環型社会形成推進基本法2 条2 項)。
「廃棄物」
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は
不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を
いう(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2 条)。
「マニフェスト」
産業廃棄物管理表。排出事業者が産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託する際に産業廃棄物の
名称・数量等を記入して、廃棄物の流れを自ら把握・管理する為の帳票。産業廃棄物の排出事業者
にはこのマニフェストを使って廃棄物の流れを管理し、適正な処理を確保することが義務づけら
れている。また、家電リサイクル法や自動車リサイクル法でも採用されている。
「産業廃棄物」
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック
類その他政令(廃棄物処理法施行令第2 条)で定める廃棄物をいう(廃棄物処理法第2 条第4 項)。
「一般廃棄物」
産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ごみ」
は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活
に伴って生じた「家庭ごみ」に分類される。
「特別管理産業廃棄物」
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有するものとして施行令で定めるもの。具体的には、引火性廃油、強酸、強
アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB 汚染物、廃石綿、重金属を含む
ばいじん、汚泥等)(廃棄物処理法2 条5 項、施行令2 条の4)。
「単純焼却」
単純焼却とは、熱回収を伴わずに単に焼却することをいう。
「健康項目及び生活環境項目」
水質汚濁防止法に基づき工場及び事業場からの排水に対して定められる排水基準項目。人の健
康保護の観点から健康項目としてカドミウム、シアン等27 項目、生活環境保全の観点から水の汚
染状態を示す生活環境項目としてpH、BOD 等15項目に関する基準が定められている。
「環境効率」
環境効率という概念は、1992 年にWBCSD(持続可能な発展のための世界経済人会議)により提唱
されたもので、〔製品もしくはサービスの価値/環境影響〕で表わされる。資源の効率的活用を通
じ、環境影響や環境負荷の低減を目指すための指標である。
環境負荷量1 単位当たりの付加価値や売上高等の値が用いられることが多い。分子・分母が形
式上逆になる「原単位」についても、ここでは環境効率指標の中に含めている。環境効率にはコー
ポレートレベルだけでなく、製品や事業所等のセグメントレベルのものもある。
なお、資源生産性の向上と環境負荷の軽減を図り、持続可能な社会の実現を目標とする「ファク
ター」という概念がある。これは、基準となる環境効率を分母とし、目標とすべき環境効率や評価
すべき環境効率を分子とするもので、環境効率が何倍上昇したのかを示す指標である。地球規模で
の持続可能な発展のため、ファクター4 やファクター10 等が提唱されている。
3.【Q&A】
序章 ガイドラインの改訂に当たって
問:当社は中小企業で、エコアクション21 にも取り組んでいないのですが、その場合は本ガイドライ
ンとエコアクション21 の第5 章「環境活動レポートガイドライン」のどちらを利用したほうがいい
のでしょうか?
答:どちらを用いても構いません。ただし、本ガイドラインは、主に大規模事業者等を対象として作
成しており、初めて作成する企業や中小企業の場合「環境活動レポートガイドライン」の方が
比較的に平易で、取り組み易いといえるでしょう。
問:このガイドラインには「準拠」しなければいけないのでしょうか?
答:準拠が望まれますが、義務ではありません。ただし、本ガイドラインや他の資料を参考に業種
や業態、ステークホルダーとの関係から適切な環境報告を作成することが期待されます。
第1 章 環境報告書とは何か
4.環境報告書の基本的要件
問:報告対象範囲と環境等に配慮したサプライチェーンマネジメントの範囲とは異なるという理解でいいのでしょうか?
答:はい、異なります。本ガイドラインでは報告対象範囲は連結決算対象組織とすることを基本と
しています。ただし、報告対象範囲外ではあっても、サプライチェーンの環境面のマネジメント
の状況について積極的に把握を行い、その状況を記載することが期待されます。
第3 章 環境報告における個別の情報・指標
問:「(1)記載する情報・指標」と、「(2)記載することが期待される情報・指標」の違いは何ですか?
答:本ガイドラインでは、環境報告において記載すべき項目である「(1)記載する情報・指標」と、記
載することが望ましい推奨項目である「(2)記載することが期待される情報・指標」の2 段階に分
けています。前者は、「方針、目標、計画、取組状況、実績」、「法規制で義務があるもの」、
「既存の環境報告書で記載が定着している情報・指標」等の基本的項目です。そして、後者
は環境経営の取組内容をより具体的に伝えるために記載することが望ましい情報や指標です。
ただし、本ガイドラインは環境報告として記載する標準的な項目を示したものであり、記載項
目を強制あるいは制限するものではありません。したがって、本ガイドラインに示した項目の他
にも、ステークホルダーの関心の高い情報等、事業者の判断で重要と考えられる情報や指標
を記載することが望まれます。
問:「情報・指標を記載しない理由を明記」とありますが、どのように書けばいいのでしょうか?
答:本ガイドラインにある情報・指標を記載しない理由としては、例えば下記の記載例が考えられ
ます。それぞれの情報・指標を記載する頁に書く方法もありますし、あるいは、本ガイドライン
の情報・指標項目と報告書記載頁の対照表を設け、その表中にまとめて書く方法もあります。
・事業活動に関連しない項目がある場合の例
「M株式会社では、資材等の輸送はほとんど行っていないため、本項目は環境報告書には
記載しません。なお、今後なんらかの外部の輸送事業者への委託等を行った際に、その環
境影響の種類や程度について検討し、重要な環境負荷が生じると考えられる場合には、本
項目を記載します。」
・データ把握の途上にあり、公表できない場合の例(その場合、公表する予定を記載する)
「S 株式会社では、△△事業所の移転に伴い、同事業所の環境負荷の状況について調査
の途上であり、本項目は本年度の環境報告書には記載しません。翌年度より、必要と判断
される同事業所の環境負荷の状況について、環境報告書に記載する予定です。」
問:経営指標は、有価証券報告書やアニュアルレポートでもより詳細に報告していますが、その旨を記載しておいた方がいいでしょうか?
答:はい、そうです。報告媒体ごとの使い分けや報告内容の切り分けについて、わかりやすく示すことも望まれます。
問:環境パフォーマンス指標(EPI)のダイジェストを、ここでは一覧にして示すよう求めています。
BI-4-2「事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括」やBI-5
「事業活動のマテリアルバランス」でも環境パフォーマンス指標の記載を求めています。重複す
るのではないでしょうか?
答:「主要な指標等の一覧」は事業者の環境負荷の推移を一覧するためのものです。一覧できる
ことで、ステークホルダーに理解しやすい情報となります。このような一覧があることで経年比
較をし易くなりますし、もちろん報告範囲等の違いもあり一律にはできませんが、他社比較もあ
る程度は可能になります。
BI-4-2 は発行した年度の環境報告書全体の概要です。BI-5 も発行した年度の環境負荷
の状況をまとめて報告する項目です。マテリアルバランスの記載方法は各社各様であるため、
別途、記載した方がステークホルダーには理解しやすくなります。なお、BI-4-1 とBI-4-2 や
BI-5 の重複する部分については、BI-4-1 と合わせて記載することもできます。
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
問:当社は事業会社で、金融機関ではありません。環境に配慮した投融資といっても具体的なイメ
ージがわかないのですが、報告する必要があるのでしょうか?
答:はい、必要です。事業会社でも、投資や融資を行っているケースは少なくありません。例えば、
供給業者等の取引先や事業に対する融資や投資において環境配慮を行っていれば、その
状況について記載します。また、各種の事業資金運用や従業員の年金運用にSRI を勧めるこ
とや、自社の資産運用の際に環境に配慮した運用先を選定することも含まれます。
問:環境に配慮した投融資には様々なものがあり、わかりにくい印象を持っています。金融機関の
場合と事業会社の場合について、それぞれ具体的な例を説明していただけませんか?
答:以下に、環境に配慮した投融資の例をいくつかの視点から示します。
【金融機関の例】
企業(コーポレート)単位 事業(プロジェクト)単位投資
(直接金融)
■SRI(うち、主にスクリーン運用と株主行動)
■グリーンファンド(1)等への投資(風力発電プロジェクトの証券購入、自治体の環境保全事業の債券購入等)融資
(間接金融)
■担保等の環境リスク評価(主に不動産の土壌汚染の有無の調査)
■環境面のインセンティブ融資(環境配慮をしている組織には金利を優遇するいわゆる「環境配慮型融資」等)
■プロジェクトファイナンス(2)における環境面の配慮とスクリーニング(赤道原則(3)やJBIC ガイドライン(4)の採用等)
■環境負荷を直接削減するプロジェクトへの融資(太陽光発電パネルの設置費用融資や、風力発電事業へのプロジェクトファイナンス等)
【事業会社の例】
投融資
■供給業者等の取引先やそれ以外の事業者に対する投融資において、融資や投資を実施する際に、環境配慮の状況を加味し、スクリーニング等を行い、実施後も管理・指導を行う。
運用
■預金先や取引する金融機関を、環境配慮状況によって選定する。
■企業年金や内部留保の運用を、SRI 等にて行う。
(1)グリーンファンド:自然エネルギーの普及を目的とする基金の総称。
(2)プロジェクトファイナンス:融資先企業の債務保証を必要とせず、融資の利払い及び返済の原資をプロジェクトか
ら生み出される収益に限定し、担保をプロジェクトの資産・権利に依存する資金調達手法。
(3)赤道原則:大規模なプロジェクトファイナンス案件において、環境・社会面のリスクを判断・評価及び管理するた
めの民間金融機関の自主的な基準。10 原則からなり、環境影響の大きなプロジェクトの場合、環境アセスメント
レポートや環境緩和計画の策定・公開が必要になる。2006 年7 月に改訂。
(4) JBIC ガイドライン:国際協力銀行(JBIC)による、国際金融等業務と海外経済協力業務の2つの環境配慮のため
のガイドラインを統合した「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」。2003 年10 月1日より施行。
MP-6:グリーン購入・調達の状況
問:環境に配慮したサプライチェーンマネジメントとグリーン購入・調達は同じもののように見えます
が、具体的には何が異なるのですか?
答:サプライチェーンマネジメントは、上流の原料調達や製品・サービスの供給業者だけでなく、
下流の流通業者や最終消費者等に対する環境配慮への取組の促進も含む概念です。一方、
グリーン購入・調達は、製品やサービスを購入・調達する際に、価格や品質、納期に加えて環
境への負荷ができるだけ少ないものを考慮して優先的に採用することであり、基本的には上
流の供給業者等を対象とします。環境に配慮したサプライチェーンマネジメントの方が、グリー
ン購入・調達より意味が広いといえます。
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
問:当社は物流会社ではありませんし、自社製品の輸送は全て外部委託しているので、直接的に
は輸送に係る環境負荷がないのですが、輸送について記載する必要があるのでしょうか?
答:はい、必要です。改正省エネ法では、一定以上の輸送を委託する事業者にも、荷主の責任と
して輸送に伴うCO2 排出量等のパフォーマンス報告を求めています。そのため、輸送の委託
先が連結決算対象組織外であっても、この件に関しては報告が望まれます。
MP-9:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
問:なぜ生物多様性の保全が必要なのでしょうか?
答:人間を含めてすべての生き物は、多様な生物と大気、水、土壌等の要素から構成される生態
系という、一つの系の中で相互に深く関わりを持ち、物質循環や食物網等の様々な鎖でつな
がりあって生きています。人間生存の基盤である環境は、こうした生物の多様性と自然の物質
循環を基礎とする生態系が健全に維持されることにより成り立っています。また、多様な生物
が生存している生態系は、気候変動等の環境変化に対してより安定しているといえます。
生物多様性は、食料や薬品等の生物資源の供給源としても重要です。動植物や微生物か
ら医薬品として用いることのできる物質を発見することもありますし、原材料の調達を生物資源
に大きく依存している事業者も多くあります。また、生態系が物質循環や気象の調節に大きな
役割を果たす等、人間や生物が生存していく上で不可欠な生存基盤としても重要であること
がわかっています。言い換えれば、人類の生存のために、また、長期的なリスクの軽減、事業
者の持続的な経営のためにも、生物多様性の保全が必要です。
問:生物多様性はある特定の事業者の問題であり、一般の多くの事業者には関係がないのではないでしょうか?
答:いいえ、影響の直接的関係はなくても、間接的に影響を与えているケースは少なくありません。
生息域の開発、外来生物の移入、環境の変化等は生物多様性を減少させる主要な原因です
が、多くの産業は原料調達や事業所の設置等を通じてこうした原因を作り出しており、直接的
ないしサプライチェーン等を通じて間接的に生物多様性に様々な影響を与えています。
また、生物多様性は人間の生存基盤を提供しているという意味でも、企業の活動や消費者
の消費行動と密接な関係があります。生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用には、
消費者を含めた経済活動に関与している全ての関係者の取組が必要です。
問:生物多様性について、既存の環境報告書にはどのような記載事例がありますか?
答:下記のような内容を報告している例があります。
【欧州オイルメジャー】
・ エネルギー会社として初めて「生物多様性基準」を採用したこと。また、企業として唯一、UNESCO(国連教育科学文化機関)が認定している世界遺産地域で事業を展開しないことを表明していること。
・ IUCN(国際自然保護連合)による保護地域のカテゴリー?〜?のうち、?〜?の場所については、自社の影響の最小化に努めるとともに、該当地域での活動を逐次報告していること。
・ 100 以上の自然科学保護機関と協力しており、UNESCO の世界遺産地域の管理にも自社の業務技術を活用する試験プログラムを実施していること。
【国内大手建設会社】
・ 生態系の保全を環境面の重点4 分野の一つと位置づけ、「生態系保全行動指針」を策定し
て環境マネジメントに組み込んでいること。
・ 今後は、建設現場の環境管理計画に生態系保全についての確認事項を組み込むこと。
・ 生態系保全行動指針に基づいた、三事例の報告。
-分譲住宅敷地内の調節池を多様な生物が生育できるように工夫
-建設予定地に生息するある生物種が建設後も棲めるよう配慮
-生物多様性の保全に寄与する可能性のある資格の従業員による取得の支援
【国内電機メーカー】
・ NGO のコンサベーション・インターナショナルとともに生態系保全面において協働することと
し、生態系保全についての認識、保全に取り組む理由、活動の方針等。
・ その協働から世界で9 つの保全プログラムを行っていること、及びそうしたプログラムを行う際
の選定基準。
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
問:当社は、製造業ではありませんが、環境負荷低減に貢献できるサービスを展開しています。そ
れについても記載していいのですか?
答:本ガイドラインはあらゆる業種を対象に作成しており、本指標も全ての業種に当てはまります。
リサイクルの取組や環境ビジネス、環境に配慮した製品・サービスの取扱等、環境負荷を低減
する取組について、できるだけ具体的な内容の記載が望まれます。
OP-6:温室効果ガスの排出量及びその低減対策
問:自社で京都メカニズムを利用しているのですが、パフォーマンス報告としてはどのように記載す
ればいいのでしょうか?
答:温暖化対策推進法において、京都メカニズムによるクレジットについては、排出量の報告と併
せてあくまでも任意にその購入量等の情報を提供できることとしています。また、排出量から
購入分を控除できるような扱いとはしていません。
なお、京都メカニズムについては下記のウェブサイトで、より詳しい情報が得られますので
参照ください。
環境省 京都メカニズム情報コーナー:
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/index.html
京都メカニズム情報プラットフォーム:
http://www.kyomecha.org/
EEI:環境効率指標
問:環境効率指標については、各社各様の指標を作成しており、まだ一般的には定式化されてい
ないと理解しています。【指標算出に当たっての留意点】を踏まえて、自社の経営戦略に応じ
て独自に作成してよい、ということでしょうか?
答:はい、そうです。現状では各事業者の創意工夫に任されていますが、何らかの環境効率指標
を作成・公表することが期待されます。作成に当たっては、できるだけ事業経営の要因に左右
されない指標が望ましいといえます。それゆえ、生産高、売上高、付加価値等は環境負荷や
環境影響との相関を測るのに比較的適していますが、利益の場合は環境経営以外の様々な
要因の影響を受けるため環境効率指標に用いることはあまり望ましくありません。
なお、環境効率指標を算定する際には、個別の環境負荷を用いる場合と複数の環境負荷
ないし環境影響を統合する場合がありますが、詳細は次項4.【環境効率指標の事例】を参照
ください。
●LIME(被害算定型環境影響評価手法)について
http://unit.aist.go.jp/lca-center/ci/activity/project/lime/index.html
●JEPIX(日本における環境政策優先度指数)について
JEPIX 報告書は、以下のウェブサイトから無償で入手できます。
http://www.jepix.org/request.php
また、JEPIX の簡易算出シート(エクセルシート)が開発され、以下のウェブサイトから無償で入手できます。
国際基督教大学(ICU)
http://subsite.icu.ac.jp/coe/download/download.html
http://www.kpmg.or.jp/profile/azsus/jepix.html
(注1)(社)産業環境管理協会に事務局をおく「日本環境効率フォーラム」では、
http://www.jemai.or.jp/CACHE/eco-efficiency_index.cfm
なお、算出にあたり、いくつかの考え方がありますので、インターネット上に掲載している事業者
等のURL を参考に示します。
○環境省中央環境審議会 地球環境部会「目標達成シナリオ小委員会」中間取りまとめ(平成13年6 月)
http://www.env.go.jp/council/06earth/r062-01/index.html
電気の使用に係る対策の温室効果ガス削減量を、電気の削減量(kWh)に全電源平均排出係数(0.36kg-CO2/kWh)と火力平均排出係数(0.69kg-CO2/kWh)をそれぞれ乗じたものを併記しています。
○独立行政法人 新エネルギー産業技術総合開発機構(既存のエネルギー使用との比較による削減効果)
http://www.nedo.go.jp/nedata/17fy/12/h/0012h001.html
燃料電池導入の場合のCO2 排出削減量を、LNG 火力平均CO2発生量を用いて算出した結果を示しています。
○電気事業連合会:
http://www.fepc.or.jp/index.html
(電気事業における環境行動計画)
http://www.fepc.or.jp/env/report2006/
CO2 排出原単位の増減の要因分析や1990 年度、2003 年度、2004 年度、2005 年度のCO2 排出実績と2010 年度の見通しが出ています。
http://www.fepc.or.jp/thumbnail/env-report2006/warming01.html
○石油連盟 暮らしと石油の情報館:
http://sys.paj.gr.jp/
(石油コージェネレーションの環境特性)
http://sys.paj.gr.jp/cogeneration/environment01_2.html
石油コージェネレーションを導入して一般電気事業者からの購入電力を削減する場合の評価として、火力平均係数を用いる手法を示しています。
○社団法人日本ガス協会:
http://www.gas.or.jp/default.html
(II 説明資料/3.地球温暖化対策)
http://www.gas.or.jp/kankyo/02_03.html
ガス事業の自主行動計画における目標、CO2 排出実績及び見通し、実績の評価、目標を達成するために実施した取組、CO2 排出減少の寄与量(要因分析)を示しています。
○東京電力株式会社:
http://www.tepco.co.jp/index-j.html
(全電源平均係数と火力平均係数)
http://www.tepco.co.jp/eco/kurashi/shiryou/shi-005a-j.html
省電力によるCO2 削減量を計算するときに、全電源平均のCO2 排出係数を使って求める手法
を示しています。
○東京ガス株式会社:http://www.tokyo-gas.co.jp/company.html(CO2 排出原単位の考え方)
http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/report/environment/warming/01.html
詳細は、「PRTR 排出量等算出マニュアル」を参考にしてください。
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/calc.html
ある製品の全国出荷量(t/年) ある製品のVOC 含有率(%)
【水質汚濁負荷量】
■水質汚濁負荷量の算定式
COD に係る汚濁負荷量(t)
=特定排出水のCOD(mg/?)×年間の特定排出水量(m3)×10-6
窒素含有量に係る汚濁負荷量(t)
=特定排出水の窒素含有量(mg/?)×年間の特定排出水量(m3)×10-6
りんに係る汚濁負荷量(t)
=特定排出水のりん含有量(mg/?)×年間の特定排出水量(m3)×10-6
(注1)複数の排出口から排水している場合は、各々の排出口ごとに汚濁負荷量を算定し、それらを
合計します。
(注2)水質汚濁防止法上の総量規制の対象でない事業者については、年間の特定排出水量(m3)を総排水量とし、特定排出水のCOD、窒素含有量、りん含有量は排出水中のそれぞれを指します。
(注 3)総量規制項目以外の健康項目、生活環境項目、ダイオキシン類等について、汚濁負荷量を算定する時は、上記COD の算定式と同様です。
(注4)下水道への排出の場合は、汚濁負荷量を算定しても、公共水域への排出量との合算は、通常行いません。
(参考資料)
「化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和54 年5 月16 日環境省告示第38 号)」、
「窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成13 年12 月13 日環境省告示第77 号)」、
「りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成13 年12 月13 日環境省告示第78 号)」
6.【国内外の研究機関等及び諸外国における研究成果】
諸外国等における環境報告書に関する情報入手先の抜粋を記載します。リンク先のURL は、平成19 年6 月時点のものです。
○事業者の環境報告書へのリンク
・環境省環境報告書データベース
http://www.kankyohokoku.jp(構築中)
・エコアクション21 認証・登録事業者リスト(環境活動レポート)
http://www.ea21.jp/list/ninsho_list.php
・環境報告書プラザ(経済産業省)
http://www.ecosearch.jp/kankyoplz/top.html
・サステナビリティ・コミョニケーション・ネットワーク(NSC)
http://www.gef.or.jp/nsc/
○環境報告書に関する研究・事例等(報告書ガイドライン)
・環境報告書の記載事項等の手引き
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
・環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
・経済産業省「ステークホルダー重視による環境レポーティングガイドライン2001」
http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/reports/report01/guideline2001-0.pdf
・GRI サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006
http://www.globalreporting.org/
(民間調査研究機関)
・AccountAbility(アカウンタビリティ社)
http://www.accountability.org.uk
・ACCA (Association of Chartered Certified Accountants 英国勅許公認会計士協会)
http://www.acca.co.uk/
・Ceres(セリーズ)
http://www.ceres.org/
・EMAS(Eco-Management Audit Scheme 環境管理・環境監査スキーム )
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
・NRTT(環境と経済に関するカナダ円卓会議)
http://www.nrtee-trnee.ca/
・WBCSD(持続可能な発展のための世界経済人会議)
http://www.wbcsd.org/
・WRI(世界資源研究所)
http://www.wri.org/
・日本環境情報審査協会
http://www.j-aoei.org/
○CSR に関する研究・事例等
・内閣府「企業における消費者対応部門及び自主行動基準に関する実態調査報告」
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/kohyo/index.html
・厚生労働省「労働におけるCSR のあり方に関する研究会」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0625-8.html
・経済産業省「企業の社会的責任(CSR)に関する懇談会中間報告書」
http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/press/0005570/index.html
・国土交通省「CSR の見地からのグリーン物流推進企業マニュアル」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/15/150427_.html
・(独)国際協力機構「環境社会配慮ガイドライン」
http://www.jica.go.jp/environment/guideline/index.html
・国際協力銀行「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」
http://www.jbic.go.jp/japanese/environ/guide/kankyou/index.php
・日本公認会計士協会
「経営研究調査会研究報告第28 号「企業価値向上に関するKPI を中心としたCSR 非財務情報項目に関する提言」について」
http://db.jicpa.or.jp/visitor/search_detail.php?id=64
「経営研究調査会研究報告第26 号「CSR マネジメント及び情報開示並びに保証業務の基本的考え方について」について」
http://db.jicpa.or.jp/visitor/search_detail.php?id=66
・OECD 多国籍企業ガイドライン(OECD Multinational Enterprise Guidelines)
・グローバル・コンパクト(United Nations Global Compact)
・日本経済団体連合会「企業行動憲章」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/cgcb/charter.html
○SRI に関する研究・事例等
・環境省「環境と金融に関する懇談会」報告書
http://www.env.go.jp/policy/kinyu/rep_h1807/index.html
(民間評価機関)
・Carbon Disclosure Project :CDP
http://www.cdproject.net/
・Ethibel (ベルギー)
http://www.ethibel.org/subs_e/2_label/sub2_2.html
・Oekom Research(ドイツ)
http://www.oekom-research.de/ag/english/index_research.htm
・EIRIS (イギリス)
http://www.eiris.org/index.htm
・SAM (スイス)
http://www.sam-group.com
・KLD (アメリカ)
http://www.kld.com
・INNOVEST (アメリカ)
http://www.innovestgroup.com
・Dow Jones Sustainability Index(アメリカ)
http://www.sustainability-index.com/
・FTSE4Good (イギリス)
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
○環境会計に関する研究・事例等
・環境省「環境会計ガイドライン 2005 年版」
http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html
・経済産業省「環境管理会計手法ワークブック」、「マテリアルフローコスト会計」
http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/sonota/policy1-01.html
○環境効率に関する研究・事例等
・経済産業省「環境効率」
http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/sonota/policy1-04.html
・日本環境効率フォーラム
http://www.jemai.or.jp/CACHE/eco-efficiency_details_grunge184.cfm
・NSC 環境部会「2005・2006 年度活動報告」(環境経営指標研究)
http://www.gef.or.jp/nsc/
○環境情報に関する研究・事例等
・国立環境研究所「地球環境研究支援データベース」
http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/db/dbhome.html
・国立環境研究所 環境情報案内・交流サイト「EIC ネット」
http://www.eic.or.jp/
平成19 年6 月
目 次
(はじめに)
序章 ガイドラインの改訂にあたって
1.ガイドラインの目的と内容
2.ガイドラインの対象
3.創意工夫の勧め 〜特色ある環境報告を〜
4.既存ガイドライン等との関係
第1章 環境報告書とは何か
1.環境報告書の定義と環境報告ガイドライン
2.環境報告書の基本的機能
3.環境報告書における環境報告の一般的報告原則
4.環境報告書の基本的要件
5.環境報告書の活用にあたっての留意点
6.環境報告書の内容及び信頼性を向上させるための作成過程における方策
第2章 環境報告の記載項目の枠組み
1.環境報告の全体構成
第3章 環境報告における個別の情報・指標
1.基本的項目(BI)
BI-1:経営責任者の緒言
BI-2:報告にあたっての基本的要件
BI-2-1:報告の対象組織・期間・分野
BI-2-2:報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況
BI-3:事業の概況(経営指標を含む)
BI-4:環境報告の概要
BI-4-1:主要な指標等の一覧
BI-4-2:事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括
BI-5:事業活動のマテリアルバランス(インプット、内部循環、アウトプット)
2.「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す情報・指標(MPI)
MP-1:環境マネジメントの状況
MP-1-1:事業活動における環境配慮の方針
MP-1-2:環境マネジメントシステムの状況
MP-2:環境に関する規制の遵守状況
MP-3:環境会計情報
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
MP-5:サプライチェーンマネジメント等の状況
MP-6:グリーン購入・調達の状況
MP-7:環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
MP-9:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
MP-10:環境コミュニケーションの状況
MP-11:環境に関する社会貢献活動の状況
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
3.「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標
(OPI)
OP-1:総エネルギー投入量及びその低減対策
OP-2:総物質投入量及びその低減対策
OP-3:水資源投入量及びその低減対策
OP-4:事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
OP-5:総製品生産量又は総商品販売量
OP-6:温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP-7:大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
OP-8:化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP-9:廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
OP-10:総排水量等及びその低減対策
4.「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標(EEI)
第4章 「社会的取組の状況」を表す情報・指標
第5章 環境報告の充実に向けた今後の課題
「環境報告書の記載事項等に関する告示」と本ガイドライン及び「環境報告書ガイドライン(2003年度版)」との比較
【参考資料】
2.用語解説
3.Q&A
4.環境効率指標の事例
5.指標の一般的な計算例
6.国内外の研究機関等及び諸外国における研究成果
(はじめに)
今日、地球温暖化問題をはじめ、エネルギー資源、水資源、天然資源の枯渇や生物多様性の喪失等さまざまな地球環境問題が深刻化しています。また、地球規模での人口増加や経済規模の拡大と人間活動の一層のグローバル化が進む中で、人類の生存基盤に関する課題が生じており、人間社会の持続性にも大きな影響が及ぶ可能性が指摘されています。
このような中、平成18 年4 月には「第三次環境基本計画*」が閣議決定され、今後の環境政策の方向性として、「環境的側面・経済的側面・社会的側面の統合的な向上」が打ち出されました。
これまで環境省では、平成16 年3 月に「環境報告書ガイドライン(2003 年度版)」を策定する等、さまざまな形で環境報告書の普及促進を図ってきました。この結果、平成17 年度「環境にやさしい企業行動調査」1によると、環境報告書を作成・公表
する事業者数は着実に増加しつつあり、933 社が環境報告書を発行しています。
今後、事業者においてはさらなる取組が期待されます。
また、「環境情報の提供の促進等による特定事業者*等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16 年法律第77 号:環境配慮促進法、平成17 年4 月施行)により、特定事業者が環境報告書を作成・公表しています。
我が国における事業者の活動もグローバル化が進み、同時に環境への影響も複雑になっており、これまでのような規制対応を中心にした環境保全だけでなく、環境への配慮を企業経営に統合する「環境経営」という考え方に基づく取組が求められています。
このような中、事業者が自らの事業活動における環境配慮の取組状況に関して積極的に情報を公開し、社会からの評価を受け、経営に反映していくための、社会的説明責任や環境コミュニケーションの重要性が認識されつつあり、環境報告書の役割が大きくなってきています。
一方、消費や投融資を行う者にも環境に配慮した行動が期待されています。その判断を行う際にも環境報告書は事業者の環境配慮の取組状況に関する有用な情報を提供するものとして活用することができます。特に、金融機関をはじめ、企業や
個人投資家が投融資の意思決定を行う際の企業評価ツールとして環境報告書が有用であると考えられます。
また、昨今、国内外において、企業の社会的責任*(CSR:Corporate Social Responsibility )への関心が高まり、さらに、グローバル・リポーティング・イニシアチブ*(GRI:Global Reporting Initiative)による新たなガイドラインの公表等、国内外での取組が進展しています。
このような動きを背景に、世界の中で日本が果たすべき役割も期待されています。
こうした状況を踏まえ、環境報告書の作成者、利用者、有識者等からなる「環境報告書ガイドライン改訂検討会」とともに、その下に事業者の環境パフォーマンス指標等に関する個別の案件について詳細に検討するための「環境パフォーマンス指標ガイドライン改訂ワーキンググループ」を設置しました。それぞれにおいて5 回、4 回の検討を行い、環境省において「環境報告ガイドライン2007 年版」を取りまとめました。
改訂にあたっては、「環境報告書ガイドライン(2003年度版)」策定後の国内外の動向を踏まえ、環境報告書ガイドラインの位置づけを見直し、「事業者の環境パフォーマンス指標ガイドライン(2002年度版)」との統合を図る等、必要な見直しを行いました。
また、社会や経済分野まで記載した「サステナビリティ(持続可能性)報告書」や「社会・環境報告書」、企業の社会的責任(CSR)に基づく取組の成果を公表する「CSR報告書」等、環境報告書の名称や報告の内容が多様化していることから、環境報告書で定期的に環境報告を記載する際の指針を示すものとして、「環境報告ガイドライン」と名称を改めました。
今回の環境報告ガイドライン改訂のポイントは、次のとおりです。
?主要な指標等の一覧の導入
?環境報告の信頼性向上に向けた方策の推奨
?ステークホルダー(利害関係者)の視点をより重視した環境報告の推奨
?金融のグリーン化の促進(環境に配慮した投融資の促進)
?生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の促進
なお、「環境報告書の記載事項等の手引き」、「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」等の関連する手引書を環境報告ガイドラインの付属書として扱うことと致しました。
序章 ガイドラインの改訂にあたって
昨今、社会や経済分野まで記載したサステナビリティレポートや社会・環境報告書が発行されています。環境配慮促進法では、これらの名称や環境以外の分野に関する情報の記載の有無、報告を発信する媒体を問わず事業者が自らの事業活動に伴
う環境配慮の状況について定期的に公表しているものを「環境報告書」と定義しています。
今回の改訂では、環境報告書の名称や報告の内容が多様化したことに鑑み、本ガイドラインの位置づけを環境報告書で定期的に環境情報の報告を行う際のあり方を示す指針としました。そのため、「環境報告書」という名称以外の環境報告書作成の際にも利用可能であることを明確に示す「環境報告ガイドライン」と名称を改めました。
1.ガイドラインの目的と内容
このガイドラインでは、環境報告書で事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の状況について定期的に公表することを「環境報告」と呼びます。このガイドラインは、初めて環境報告書を作成し環境報告を行おうと考えている事業者の方々はもとより、既に環境報告を行っている事業者の方々にも、「環境経営」を行う上でより充実した実務的な手引きとなるよう作成したものです。
そのため、環境報告に係る国内外の最新の動向を踏まえ、その望ましいと思われる方向及び内容を取りまとめました。
環境報告を行う際には、第1章の環境報告書の定義、基本的機能及び原則等を参考にして、その作成に取り組んでいただき、さらには環境報告として記載することが必要と考えられる項目等を取りまとめている第2章、第3章を参考に、その項目や内容を検討していただきたいと思います。
第2章の「環境報告の記載項目の枠組み」では、環境報告書に記載する環境報告の内容として5分野29項目(第4章「社会的取組の状況」を含む)を説明し、第3章「環境報告における個別の情報・指標」では環境報告の項目毎に、次の2種類の情
報・指標を列挙しました。
(1)記載する情報・指標
全ての事業者に共通して重要性があると考えられる環境情報・指標
(2)記載することが期待される情報・指標
環境報告書の基本的機能を踏まえ、持続可能な社会の構築に向けて、必要に応じて、記載することが期待される情報・指標
また、第4章「社会的取組の状況」に社会面の報告のための情報・指標を記載しました。さらに第5章では、環境報告の充実に向けた今後の課題を記載しています。
このガイドラインでは、環境報告書に記載する環境報告の情報・指標を示すとともに、それぞれの項目や情報・指標について、具体的な例示やその環境上の課題や意義、指標算定にあたっての留意点の解説もしていますので、ステークホルダーが、環境報告を読んだり、分析したりする上での手引きとして活用していただくことも期待しています。
しかし、本ガイドラインで取り上げた項目及び情報・指標は限定列挙的に規定したものではなく、現時点での検討結果を取りまとめたものです。ステークホルダーの関心が高いもの等については、環境保全上の支障が生じることについて必ずしも科学的に十分には証明されていないものも含め、当該事業者自身が重要性の判断を行い、本ガイドラインでは取り上げていない項目や内容であっても積極的に記載していくことが必要です。
2.ガイドラインの対象
現在、我が国においては、環境報告書を作成・発行する事業者等は増加しつつあるものの、事業者全体に占める割合は少ないと推定されます。まずは、資金及び人材が比較的豊富である事業者を中心とした自主的かつ積極的な取組が必要ですが、将来的には、全ての事業者が作成・公表していくことが望まれます。
「循環型社会形成推進基本計画(平成15年3月閣議決定)」においては、取組目標の一つとして、上場企業の約50%及び従業員500人以上の非上場企業の約30%が環境報告書を公表することを掲げています。また、「環境配慮促進法」においても、
大企業者は環境報告書の公表や環境配慮等の状況の公表に努めることと規定しています。
このガイドラインは、環境報告書で環境報告を行う全ての事業者を対象としていますが、特に上場企業や従業員500人以上の非上場企業等の大規模事業者にあっては、このガイドラインに示した項目や情報を盛り込んだ、できるだけ質の高い環境報告
を行うことが期待されます。また、環境報告書の作成を始めたばかりの事業者や、中小事業者(工場等のサイト単位を含む)にあっては、このガイドラインを参考に、可能なところから段階的に取り組むことが望まれます。
一方、環境配慮促進法の中で環境報告書の公表が義務づけられている特定事業者については、このガイドライン及び、「環境報告書の記載事項等の手引き」を参照しつつ、「環境報告書の記載事項等に関する告示」に示された「環境報告書の記載
事項等」を網羅した環境報告書を作成することが期待されます。
なお、環境省では別途、中小事業者が、比較的容易に環境経営システムの構築及び運用、事業活動における環境配慮の取組の実施及び環境報告書の作成ができるよう「エコアクション21」(環境経営システム・環境活動レポートガイドライン‐2004年版‐)を策定しています。この「エコアクション21」に規定する「環境活動レポート」の要件を満たして作成・公表されたものは、環境報告書の範疇に含まれます。
平成16年度より財団法人 地球環境戦略研究機関で認証・登録制度を実施しており、この制度では認証・登録を受けた事業者名及び環境活動レポートを公表しています。
3.創意工夫の勧め〜特色ある環境報告を〜
環境報告書は、事業者が社会に対して自らの事業活動に伴い発生した環境負荷についての説明責任を果たし、ステークホルダーの意思決定に有用な情報を提供するものであり、環境コミュニケーションの重要なツールとして社会的に記載すべき項
目や内容があると考えられます。
しかしその一方で、環境報告書は、環境報告書を活用したステークホルダーとのコミュニケーションのあり方を考慮に入れつつ、事業者の経営方針や考え方、風土や特徴を反映させて作成されるべきものです。その点では環境報告を行う項目や記
載情報、さらには紙媒体だけでなくインターネット等の活用も含めた公表の方法等について、各事業者の「創意工夫」が求められます。
事業者には、このガイドラインを踏まえた上で、各事業者の特色が反映された環境報告書を作成・公表することを期待しています。
このガイドラインの普及状況を確認し、内容の継続的改善を図っていくため、このガイドラインに準拠して環境報告書を作成した場合には、環境報告書にその旨を明記することを希望しています。本ガイドラインが環境報告書に記載する環境に関する項目として掲げている5分野29項目全てを記載している場合、もしくは記載しない項目については、その理由を記載している場合は準拠しているとみなします。
また、記載した内容と本ガイドラインが示す29項目との関わりを何らかの形で明示することが期待されます。
4.既存ガイドライン等との関係
環境報告書の内容に関するガイドラインや手引きとして次のものがあります。
○「環境報告書の記載事項等の手引き」(平成17 年12 月)
環境報告書の普及により、環境に配慮した事業活動の促進を図るため、平成16 年5月に、環境配慮促進法が成立しました。この中で、環境報告書を作成・公表する義務のある一定の要件を満たした特定事業者においては、「告示」に定めた環境報告書に記載すべき項目や記録の方法(以下、「記載事項等」)に従って作成・公表するように努めることとされています(法第9 条第2 項)。
この手引きは、「記載事項等」を詳細に、かつ分かりやすく解説するために作成したもので、特定事業者を主な対象としていま
すが、環境報告書の作成・公表を始めたばかりの事業者の方々にも活用していただきたいと考えています。しました。
「環境報告書の記載事項等の手引き」:
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
○「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」(平成18 年3 月)
この手引は環境報告書の信頼性を高めるために事業者自らがその評価を行う場合の自己評価の考え方、実施手順から結果の公表までを説明したもので、一つの手法を示し、全ての団体・事業者を対象としています。
「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」:
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
※「環境パフォーマンス指標ガイドライン」
「環境パフォーマンス指標ガイドライン2002 年度版」における環境パフォーマンスの考え方や算定方法については、最新の状況を加味した上で、本環境報告ガイドラインに統合しました。
「環境パフォーマンス指標ガイドライン2002 年度版」では、ほぼ全ての事業者に共通し、環境政策上も重要と考えられる指標を[コア指標]として集約・整理し、それ以外の指標については[サブ指標]としていました。環境パフォーマンス指標ガイドライン2002 年度版の[コア指標]及び[その他のサブ指標]は本ガイドラインの『第3章 3.「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標』の記載項目に該当します。
[サブ指標]は主に『第3章 2.「環境マネジメント等、環境経営に関する状況」を表す情報・指標』に含まれています。
このほか、環境報告に関するガイドラインとしては、経済産業省の「ステークホルダー重視による環境レポーティングガイドライン2001」、グローバル・リポーティング・イニシアチブ(GRI)の「サステナビリティ・リポーティング・ガイドラインG3(2006 年版)」等、複数存在しています。参考資料の6.【国内外の研究機関等及び諸外国における研究成果】も参照して、よりよい環境報告を行うことが期待されます。
また、環境報告に関連の深い、事業者等の環境マネジメントや情報提供に関するガイドライン等としては次のようなものがあります。
○「環境会計ガイドライン2005 年版」(平成17 年2 月)
環境会計とは、「企業等が、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的(貨幣単位又は物量単位)に測定し伝達する仕組み」です。
環境会計情報は、環境報告書を通じて環境保全への取組姿勢や具体的な対応等と併せて公表することによって、事業者等の環境保全への取組をステークホルダーに伝達するために有効です。これを公表することは事業者等の社会的信頼を高め、社会的評価を確立していくことにつながります。
すなわち、外部の消費者、投資家、地域住民等に対して説明責任を果たすと同時に、環境保全の観点も含めた、より適切な事業者評価に結びつく役割が期待されます。
「環境会計ガイドライン 2005 年版」
http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html
○エコアクション21
エコアクション21 は、中小企業向けに取り組み易く取りまとめられた環境経営システム及び環境活動レポートのガイドライン等より構成されているとともに、環境経営システムの中の環境負荷の把握及び環境目標の設定において、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量及び総排水量の把握と目標設定を求めています。
この事業者の取組を「エコアクション21 審査人」が審査し、財団法人地球環境戦略研究機関 持続性センター(エコアクション21 中央事務局)が認証し、登録します。なお、環境活動レポートの要件は、環境方針、環境目標とその実績、主要な環境活動計画の内容、環境活動の取組結果の評価、環境関連法規への違反、訴訟等の有無の記載と、このレポートを事業所において備え付け一般の閲覧を可能にし、エコアクション21 中央事務局に送付することです(中央事務局が取組事業者名及び環境活動レポートを公表する)。
財団法人 地球環境戦略研究機関 持続性センター
http://www.ea21.jp/
○ISO14001
ISO14001(JIS Q 14001)(環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引)は、いわゆるPDCA サイクルによる環境マネジメントシステムを構築・運用することにより、システムの継続的改善を図ることを基本としています。継続的改善とは、「組
織の環境方針に沿って全体的な環境パフォーマンスの改善を達成するための環境マネジメントシステムを向上させるプロセス」と定義されています。
ここでは、組織は内部及び外部のコミュニケーションの手順を確立することが求められています。外部とのコミュニケーションを検討するときには、すべての利害関係者の見解及び情報ニーズを考慮することとしており、その方法として、年次報告書、ニュースレター、インターネット及び地域での会合等が挙げられています。
なお、本環境報告ガイドラインは、環境マネジメントシステムの適合要件や審査登録の基準に変更を加えるものではありません。
○ISO14063
ISO14063(JIS Q14063)(環境マネジメント−環境コミュニケーション−指針及びその事例)は、環境コミュニケーションの規格です。環境コミュニケーションは、「環境に関する課題、側面及びパフォーマンスについて理解の共有を促進するために、情報を提供及び入手し、並びに内部及び外部の利害関係者2の対話にかかわる、組織が実行するプロセス」と定義されています。
環境コミュニケーションは、持続可能な社会の構築に向けて、利害関係者間のパートナーシップを確立するために、環境負荷や環境保全活動等に関する情報を提供し、利害関係者の意見を聞き、討議することにより、互いの理解と納得を深めていくこと
といえます。なお、環境コミュニケーションは環境報告よりも広範なもので、環境報告書は環境コミュニケーションのツールの一つです。
利害関係者:ここでは「利害関係者」をステークホルダーと同義で使用しています。
体制整備
【既存のガイドライン等との関係】
*「環境報告書の記載事項等の手引き」、*「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」については本環境報告ガイドラインの改訂に伴い、整合性を図るための改訂を順次実施します。
第1章 環境報告書とは何か
1.環境報告書の定義と環境報告ガイドライン
環境報告書とは、その名称や環境以外の分野に関する情報の記載の有無並びに公表媒体に関わらず、事業者が事業活動における環境負荷及び環境配慮等の取組状況に関する説明責任を果たし、ステークホルダーの判断に影響を与える有用な情報を提供するとともに、環境コミュニケーションを促進するためのものです。
この環境報告ガイドラインは、環境報告書で社会に対して事業活動における環境配慮の方針、目標を明らかにし、取組内容・実績及びそのための組織体制・システム等、自らの事業活動に伴う環境負荷の状況及び事業活動における環境配慮の取組
状況を取りまとめ、広く社会に対して定期的に公表・報告する際に参考とするためのものです。
環境報告書を作成するにあたっては、このガイドラインに記載した一般的報告原則に則り、総合的体系的に記述する必要があります。
解説:環境報告書の名称
現在発行されている「環境報告書」の名称は、社会や経済分野まで記載した「サステナビリティ(持続可能性)報告書」や「社会・環境報告書」、企業の社会的責任(CSR)に基づく取組の成果を公表する「CSR報告書」等、その内容や作成趣旨によりさまざまです。本ガイドラインでは、事業者が自らの事業活動に伴う環境負荷の状況及び事業活動における環境配慮の取組状況を総合的・体系的に取りまとめ、定期的に公表・報告するものを総称して環境報告書として呼びます。したがって、企業の社会的責任や持続可能性に関する情報を含む場合であっても、本ガイドラインで言うところの「環境報告書」とみなします。
事業者は事業活動における環境負荷を低減する活動や環境の保全への取組の状況を記載した環境報告書を定期的に作成し公表することが期待されます。
解説:環境報告書の公表媒体
現在発行されている環境報告書の媒体には、冊子・印刷物、インターネット(URL)での公開、CD 等さまざまなものがありますが、媒体は何であれ、その内容が本ガイドラインの定義に合致し、事業者が自らの事業活動に伴う環境負荷の状況及び事業活動における環境配慮の取組状況を総合的に取りまとめ、公表するものを総称して環境報告書と呼びます。
解説:環境報告の定期的公表・報告
基本的には事業者の事業年度または営業年度に合わせ、少なくとも毎年(度)一回、作成・公表することが望まれます。例えば、環境報告書は会計年度終了時や株主総会等、ステークホルダーへの情報提供にふさわしい時期に作成・公表すること
が考えられます。インターネットを活用する場合等、公表媒体によっては、その開示内容に応じて公表頻度を多くすることも有効です。
2.環境報告書の基本的機能
環境報告書には、事業者と社会とのコミュニケーションツールとしての外部(社会的)機能と、事業者自身の事業活動における環境配慮等の取組を促進させる内部機能の二つの基本的機能があります。これらにより、事業者の自主的な事業活動に
おける環境配慮等の取組が推進されます。
外部機能には、次の三つの機能があります。
?事業者の社会に対する説明責任に基づく情報開示機能
?ステークホルダーの判断に影響を与える有用な情報を提供するための機能
?事業者の社会とのプレッジ・アンド・レビュー(誓約と評価)による環境活動等の推進機能
内部機能には、次の二つがあります。
?自らの環境配慮等の取組に関する方針・目標・行動計画等の策定・見直しのための機能
?経営者や従業員の意識付け、行動促進のための機能
環境報告書で環境報告を行う際には、これらの機能を適切に果たすよう留意することが必要です。
解説:事業者と社会とのコミュニケーションツールとしての外部機能
環境報告書は、「事業者が、社会に対して開いた窓であり、コミュニケーションの重要なツールである」と言えます。ステークホルダーはその窓を通して、その事業者が環境問題等についてどのように考え、どう対応しようとしているのかを知ることができます。
また、事業者はその窓を通して、ステークホルダーが事業者に何を求め、どう感じているのかを知ることができます。
解説:社会に対する説明責任に基づく情報開示機能
社会経済活動の主要な部分を占める事業者は、その事業活動を通じて大きな環境負荷を発生させています。そのため公共財ないし全生命共有の財産である「環境」について、さらには深刻化する環境問題に対して、どのような環境負荷を発生させ、
これをどのように低減しようとしているのか、どのような環境配慮の取組を行っているのか等を、公表・説明する責任があり、その手段として環境報告書で環境報告を行うことは最も重要な地位を占めるものです。
解説:ステークホルダーの判断に影響を与える有用な情報を提供する機能
ステークホルダーの製品やサービスの選択、投融資先等の選択等にあたっては、各種の製品情報や経営情報の開示が必要不可欠であり、その際に環境面やリスク管理等に関する情報が重要な判断材料になると考えられます。事業者はそのような意思決定の判断材料となる有用な情報を提供することが求められています。
そして、さまざまなステークホルダーが、環境報告書で環境報告を行うことの有無を含む事業者の環境配慮に関する情報を、事業者や製品・サービス選択の判断材料とするようになりつつあります。さらに、環境等に対する配慮の状況から事業者の格付を行う評価機関や、投融資や取引の意思決定を行う事業者が増加しています。
このように環境配慮への積極的な取組を進めた事業者が正当に評価され、いわば市場原理の中で公正かつ効果的にそのような取組が今後ますます進展することが期待されます。
特に、製品・サービス市場における情報媒体としては環境ラベルが主たる役割を果たし得るのに対して、資本市場や雇用市場における情報媒体として、環境報告書が重要な役割を果たすものであり、こうした効果は、CSR ファンドやエコファンド等の社会的責任投資*(SRI:Socially Responsible Investment)の普及が進む中で、次第に現実のものとなりつつあります。
近年、欧米において、公的年金等の資金の運用先や個人投資家も含めて「積極的に環境配慮に取り組む企業」に優先的に投資を行おうとする動きがあります。国内においても社会的責任投資(SRI)の取組が普及しつつあり、このような中で、我が国の事業者が環境報告書を作成・公表し、自らの事業活動における環境配慮の取組状況についての情報を公開していくことは、グリーン投資、グリーンマネーの拡大につながり、持続可能な社会の構築に向けた環境と経済の統合的向上に資するものと考えられます。
また、グリーン購入・調達が進展するとともに、取引先の選定等に際して事業者の環境や社会に対する配慮への取組状況についての情報を求められることが多くなってきており、環境報告書はその際の説明資料としても使用できます。
解説:事業者の社会とのプレッジ・アンド・レビュー(誓約と評価)による環境活動等の推進のための機能
事業者が社会に対して事業活動における環境配慮等の取組に関する方針や目標を誓約し公表することにより、社会がその状況を評価するいわゆるプレッジ・アンド・レビューの効果が働き、取組がより着実に進められることが期待されます。
また、環境報告の実施にあたって、外部の目や同業他社との比較を意識し、より前向きに取組を行っていくことは、環境保全に向けて社会全体の取組が進展することにつながると考えられます。
さらに、幅広いステークホルダーの間で環境コミュニケーションが進むことにより、社会全体の環境意識が向上するとともに、各主体の取組の状況と課題についての認識が深まれば、それぞれの役割に応じたパートナーシップの下で社会全体での
取組のレベルアップに役立つことが期待されます。
解説:事業者自身の環境配慮等の取組に関する方針・目標・行動計画等の策定・見直しの機能
環境負荷の実態や事業活動における環境配慮の取組状況を外部に報告することにより、事業者自身が報告の内容を充実させるため、事業活動における環境配慮の取組の内容やレベルを自主的に高める効果があるとともに、社内的に環境情報の収集システムが整備され、事業者自身の環境配慮の取組に関する方針、目標、行動計画等を見直し、新たに策定する契機になります。
解説:経営者や従業員の意識付け、行動促進のための機能
自らの取組内容を従業員に理解してもらい、その環境意識を高めるために、環境報告書は従業員の教育・研修のツールとしても活用でき、さらには自らの事業活動における環境配慮等の取組状況を知るとともに、それらの取組を行うことにより従
業員自身が、自社に誇りを持つことにつながります。
また、環境報告書に経営者の緒言等を記載することにより、経営者自身の意識付けも期待できます。
3.環境報告書における環境報告の一般的報告原則
環境報告書は、事業者の説明責任の観点及びステークホルダーの意思決定に有用な情報を提供する観点から、環境コミュニケーションのツールとして作成・公表されるものであり、以下に示す4つの一般的報告原則は、環境報告書の基本的機能を
満たすために必要不可欠なものです。
これらの一般的報告原則に合致しない場合は、環境報告書に期待される機能を果たすことができません。ここでは、環境報告書で環境報告を行う際の“一般的報告原則”について解説します。
? 目的適合性
環境報告においては、事業者の事業活動に伴う環境等への影響の状況及び事業活動における環境等への配慮の取組状況に関する、ステークホルダーの判断に影響を与える重要な情報が、適切な時期に提供される必要があります。
解説:目的適合性のための重要性と適時性
作成・公表される環境報告書は、ステークホルダーがその事業者及びその環境報告書に対して、どのようなことを期待して、どのような情報を求めているかを、十分に考慮することが必要です。
そのためには、ステークホルダーが誰なのかをあらかじめ特定し、それらのステークホルダーとの対話の過程を通じて、彼らの期待やニーズを理解することが有効になります。環境報告書はそのようなステークホルダーの期待やニーズに適合し、重要性のある情報が適切に記載されていることが望まれます。
なお、情報に重要性があるかどうかについては、ステークホルダーとの関与結果等を参考にして、ステークホルダーの意思決定や判断に影響を与える大きさから決定することになります。本ガイドラインで示した29項目の環境報告書の記載事項
(各項目における「(1)記載する情報・指標」)は、すべての事業者に共通して重要性があると考えられる情報ですが、それぞれの事業者の判断にもとづいて記載しない事項がある場合には、その理由を説明すること、また、29項目以外にも事業内容やステークホルダーとの関係等から重要な事項が存在する場合は、その事項を開示することが必要です。
さらに、環境情報が有用であるためには、ステークホルダーに対して適切な時期に提供される必要があります。また、当該事業者の、環境報告書対象期間中の事業活動における環境配慮の取組状況、あるいは環境に関する事故、さらには事業活動
における環境配慮の取組に関する方針・目標の策定・改訂等について、公表時期を適切に判断して公表されるようにすることが重要です。環境に関わる重要な後発事象についても記載することが期待されます
(参考:4.報告にあたっての基本的要件?対象期間)。
? 信頼性
環境報告は、信頼できる情報を提供するために、重要な情報の網羅性、正確性、中立性、検証可能性を確保しなければなりません。
解説:信頼性確保のための重要な情報の網羅性、正確性、中立性、検証可能性
作成・公表した環境報告書が、多くのステークホルダーに受け入れられ、有用なツールとして活用されるためには、事業者が環境報告書の信頼性を高める努力をしていくことが必要です。
環境報告書の信頼性が確保されるためには、事業活動に伴う環境的・経済的・社会的影響及び事業活動における環境・経済・社会配慮の取組状況を忠実に表現する上で重要な情報が確実に網羅されている必要があります。また、記載された情報が正確かつ伝えようとする内容が間違いなく伝わるように必要な情報が含まれていることが必要です。
特に、重要な情報ほど、正確で誤解を与えない詳細な情報を提供する必要があります。さらに、提供される情報は中立かつ検証可能であることが必要です。
環境報告の信頼性を高める手段としては、チェックリストやプロセスを示しつつ自己評価を実施することや監査役の監査の過程で環境情報の正確性を確認する等組織内部で実施する方法や、独立した第三者の審査を受けたり意見を聞いたりする等組織外の主体の関与を得る方法、本ガイドライン等への準拠を示す方法があります。
そして複数の方法を組み合わせることにより、信頼性をさらに高める方法を選択し、できる範囲でより適切に進めることが望まれます。
加えて、環境報告として記載された環境情報については、客観的な立場から検証可能であることが必要です。検証可能であるということは、第一に、環境報告として記載された情報のそれぞれについて、算定方法や集計範囲等が明記されており、検証可能な形で表示されているということです。第二には、環境報告として記載された情報のそれぞれについて、根拠資料が存在するとともに、その集計システム等が構築されており、情報の信頼性を第三者が確認する手段があるということです。
? 理解容易性
環境報告は、ステークホルダーの誤解を招かないように、必要な情報を理解容易な表現で明瞭に提供することが望まれます。
解説:理解容易な表現
公表された環境報告書の読み手(ステークホルダー)は多種多様であり、環境報告を行う際には、わかりやすく、かつ誤解のないように配慮することが重要です。
記載された情報が理解容易であるためには、できる限り簡潔な表現が求められますが、内容が複雑であっても必要な情報は適切に提供される必要があります。
例えば、不確実性を伴う情報を提供する場合には、不確実な性質、対象範囲、判断根拠等を明記することが必要です。併せて過去数年における経年変化を示すことも理解を深める上では重要です。
また、特定の情報を提供する場合には、全体に占める割合が容易に判読できるように、取組内容を列挙するだけでなく、その取組が全体の中でどの程度の割合を占めているのかを記載することが望まれます。
さらに、公表されている環境報告の中には、自社の取組内容のみを定性的に記載し、数値データ(実績や目標)や自らの環境負荷の実態についてほとんど記載していないものがあります。事実を正確に伝える上で、数値の記載は極めて重要であり、可能な限り実数値を記載することが望まれます。
その上で、環境報告書はコミュニケーションツールとして、見やすい、わかりやすい、読みやすいものであるとともに、読み手が「読んでみたい」と興味を抱くような表現の工夫も大切です。
そのためには、
・簡潔な文章と文体を心がける
・文章に加え、グラフや写真等を交えて表現する
・記載した取組や数値等の意味を適切に説明すること
等が望まれます。
なお、業界や社内だけで通用するような言い回しや表現、用語は可能な限り避けるべきであり、場合により注釈等を付すことが望まれます。
? 比較容易性
環境報告は、事業活動の各期間を通じて比較可能であり、かつ異なる事業者間を通じても一定の範囲で比較の基礎となる情報を提供することが望まれます。
解説:比較の基礎となる情報
まず第一に、記載された情報は、単年度のものだけでなく、当該事業者における経年の変化が比較できるよう記載することが望まれます。なお、前年と比較して著しい数値の増減等があった場合は、その理由や説明を記載することが期待されます。
第二に、事業者の事業特性や業態によって環境負荷の状況は異なると考えられますが、同一業種の事業者間、さらには業種の異なる事業者間での比較が容易であるよう記載されていることも望まれます。例えば、業界平均値等の比較のベースとな
る数値を、自社の数値に併記する等の工夫も有効です。
なお、他事業者や業界平均等と比較して環境パフォーマンスに著しい差異が見られる場合は、その理由や説明を記載することが期待されます。
環境報告が比較容易となれば、ステークホルダーが環境配慮に積極的な事業者を選択する際の有用なツールとして活用されることが期待されます。
記載するデータの根拠や収集方法、測定・算定方法等を明記すること、本ガイドラインを含め社会的に合意された環境報告のためのガイドラインに準拠して環境報告を実施すること、業界等で合意した共通の手法で環境パフォーマンスに関する情報を測定すること等は、環境報告の信頼性を高めるとともに、事業者間の比較容易性をも高めることにつながります。
算定方法や算定に用いた係数は継続的に使用することが原則です。しかし、算定方法や係数を変更する場合は合理的な理由が必要であり、変更した場合には、その旨、その理由、変更したことによる影響について記載が必要です。
4.環境報告書の基本的要件
? 対象組織の明確化
環境報告書で対象とする組織の範囲(バウンダリー)を明示することが必要です。
解説
報告対象組織の決定にあたっては、事業活動に伴う環境負荷の状況及び環境配慮への取組状況を考慮することが必要です。
多くの事業者は、その事業活動を、一法人のみで行っているのではなく、国内外の子会社等へ生産移転や運送委託等をしています。したがって、当該事業者の環境パフォーマンスについて実状にあった形で正確かつ公正に評価するためには、生産移転先等の関係事業者も含めた組織の活動全体をカバーすることが期待されます。このため、財務会計の集計範囲に準じて、連結決算対象組織全体を把握することが基本となります。
ただし、データ集計に要する負担や他者との比較評価の行いやすさ等を勘案して、環境負荷の低減に関して直接的に経営のコントロールが可能である範囲を踏まえて境界を定め、その境界を明確に示し、その境界を定めた理由を明らかにすることが必要です。
また、会社概要は単独決算のデータ、環境パフォーマンスは主要事業所のみのデータ、事業活動における環境配慮の取組状況の記述は海外の事業所や子会社での取組も含むといった具合に、その内容によって対象組織の範囲(バウンダリー)が異なる場合は、まず環境報告の対象とすべき連結決算対象組織全体を明確にし、それぞれの項目において対象組織を明記するとともに、対象組織に加えた理由、あるいは除いた理由を記載することが必要です。
さらに、前回の環境報告書と当該年度等の環境報告書の対象組織が異なる場合は、その状況についても記載し、経年での比較容易性に配慮することが望まれます。
報告対象組織の記載にあたっては、組織全体の概要を理解できる図等を用いるとともに、全体の経営戦略や各組織の位置付け等についてもある程度説明する等の工夫を行うと、対象組織についての理解を得る手助けになると考えられます。
【求められる環境配慮の範囲の拡大】
製品を提供する事業者を例にとると、下図に示した連結決算対象組織の境界を超えて、サプライチェーン*を含めたライフサイクル全般にわたり、可能な限り環境負荷の全体像を把握していく努力をすることが望まれます。
? 対象期間の明確化
環境報告書で対象とする期間を明示することが必要です。
解説
環境報告書の対象期間は、会社概要や財務情報と環境パフォーマンス情報等、環境報告書に記載された各種データの対象期間を可能な限り統一し、もし内容により異なる場合には、その点を明記することが必要です。
また、公表された事業活動における環境配慮の取組実施期間あるいは環境負荷のデータ収集期間が、環境報告の対象期間と一致していることが必要です。
しかし、取組の全てが一定期間内で終了するわけではないこと、過去に行った取組であっても現在まで継続して効果を発揮している場合があること等により、当該年度の取組のみの記載では事業者の取組全体を適切に紹介できない場合があります。その場合には理由等を明記して、過去の取組等を記載することが望まれます。
環境配慮の取組について、少なくとも事業年度又は営業年度ごとに環境報告を行い、次回の公表予定について記載することが必要です。
なお、報告対象期間の終了後であっても、環境報告を公表するまでの間に、ステークホルダーの判断に影響を及ぼす重大な事件・事故あるいは翌年度の環境パフォーマンスに影響を及ぼす重要な後発事象が生じた場合には、環境報告書に記載することが期待されます。
? 対象分野の明確化
環境報告書で対象とする内容の分野を明示することが必要です。
解説
環境報告書を作成する事業者は、当該環境報告書にてどの分野を報告しているのか(環境報告だけなのか、あるいは社会的取組も含むのかどうか等)を明確に示す必要があります。
現代社会においては、環境的側面、経済的側面、社会的側面が複雑に係わっており、環境負荷を低減し持続可能な社会を築いていくためには、社会経済システムに環境への配慮が織り込まれている必要があります。 環境的側面から持続可能であるためには、社会、経済の側面についても健全で持続的でなければなりません。
近年、欧米に限らず我が国においても、環境分野だけでなく社会的分野、経済的分野等についても報告の対象分野として拡大する事業者が増加しており、これを「サステナビリティ(持続可能性)報告」あるいは「社会・環境報告書」、「CSR 報告書」
として普及していこうという動きが強まっています。
社会的分野とは、環境面での社会貢献取組ではなく、労働安全衛生、雇用、人権、地域及び社会に対する貢献、企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引、個人情報保護、広範な消費者保護及び製品安全等のことです(参照:第4章)。また、経済的分野とは、売上高や利益の状況、資産、投融資額、賃金、労働生産性、雇用創出効果
等のことです。
社会的分野及び経済的分野に関しては、環境分野とは異なり、どのような項目や内容を、どのように取り扱うか等について、まだ社会的合意が成立しているとはいえないというのが現状であり、今後、さまざまな検討が積み重ねられ実務の成熟を待つ必要があります。また、社会的取組の状況については、組織の社会的責任の観点から、ISO(国際標準化機構)が規格の開発を開始する等進展しており、これらの国内外の動向にも留意していく必要があります。
ISO26000 の「組織の社会的責任指針(案)」では、組織の社会的責任をめぐる課題として、環境の他、人権、労働慣行、組織統治、公正な事業活動、コミュニティ参画及び社会開発、消費者課題が掲げられています。
本ガイドラインの第4章「社会的取組の状況」に関する情報・指標を参考にしつつ、報告の対象分野を拡大していくことが期待されます。
5.環境報告書の活用にあたっての留意点
(1)ステークホルダーとの関わり
?ステークホルダーとは
ステークホルダーとは事業者等の環境への取組を含む事業活動に対して、直接的または間接的に利害関係がある組織や人物をいいます。事業者の利害関係者には、消費者、投資家、取引先、従業員、地域住民、行政組織等が考えられます。
環境報告書には、ステークホルダーが行うさまざまな意思決定や判断に必要な情報を適切に記載することが期待されます。
?重要な項目の考え方
環境報告書は、事業者が社会との間で行うコミュニケーションの重要なツールであり、その読み手にはさまざまなステークホルダーが考えられます。環境報告書に求められる情報の内容や質は、ターゲットとするステークホルダーにより異なってきます。
環境報告書のステークホルダーが必要としている情報を的確に抽出するには、ステークホルダーとの協議を行なったり、関与(エンゲージメント)3を促進する等が考えられます。
?環境報告書の対象となるステークホルダー
環境報告書の対象となるステークホルダーには、顧客(消費者を含む)や生活者、株主や金融機関、投資家、取引先、従業員及びその家族、学識経験者や環境NGO、消費者団体、学生、さらには地域住民や行政とさまざまな主体が考えられます。環境報告は、このようなステークホルダーに自社の環境配慮への取組を効率的かつ効果的に説明することができます。
一方、環境報告書によって、ステークホルダーの環境意識等が向上することや、環境保全への活動が促されることも期待できます。また、環境報告書は、外部のステークホルダーに向けてのみ作成されているのではなく、その事業者の経営陣をはじめとする役員、従業員やその家族等も重要な環境報告書の読み手であると言えます。
いずれにしろ、主としてどのような読み手やステークホルダーを想定して環境報告書を作成するのか、あるいは全ての主体を対象とした環境報告書を作成するのか等を十分に検討することが大切です。本ガイドラインは一般的に想定される主な読み手の全てを念頭において編集しましたが、以下に主な読み手について説明します(ただし、順不同)。
○顧客(消費者を含む)
環境問題の深刻化や顕在化に伴い、顧客(消費者を含む)等の環境等に対する意識は ステークホルダーの「関与(エンゲージメント)とは、組織がステークホルダーを理解し、彼らを組織の活動および意思決定過程に関与させるすべての努力を包含する包括的な用語です。
ステークホルダーへの情報伝達や相談(Consultation)、対話(Dialogue)、協働(Partnership)等の相互的で意欲的な協力関係をいいます。
高まりつつあり、これまでの価格や品質に加え、環境配慮等の側面が製品やサービスを選択する際の判断材料の一つになってきています。
○株主、金融機関、投資家
株主や金融機関、投資家は、従来に増して環境報告の対象となる重要なステークホルダーとなりつつあります。欧米のみならず我が国においても、事業者の事業活動への環境配慮等の取組状況は、投資や融資の際の判断材料の一つとして考えられています。
具体的には、社会的責任投資(SRI)等に見られるように環境問題等に熱心に取り組んでいる事業者を支援していきたいという考えや、環境問題等への対応の有無をリスクや機会と捉え、その取組如何が事業者の今後の業績を左右するという考えが広がりつつあります。
これらのステークホルダーは、事業活動における環境配慮の取組状況や環境に関する規制遵守状況等に強い関心を持っていると考えられます。
○取引先(購入・調達の依頼先や発注の相手先等)
納入先や発注者等による環境に配慮したサプライチェーンマネジメントの一環として、環境問題に適正に取り組むことを取引(入札や発注等)の条件の一つとする動きが強まってきています。
納入先や発注者等の取引の相手先に対する、環境問題に係る取引先の関心事としては、環境マネジメントの状況、化学物質の使用、管理の状況等が考えられます。
○従業員及びその家族
有能な従業員を雇用するとともに、従業員の志気を向上させ、自らの事業者に対する誇りを養うためには、環境方針や自らの事業活動への環境配慮の取組に関する姿勢を示し、従業員やその家族から理解を得ることが重要になります。また、従業員への教育・研修のツールとして、環境報告書を活用することも考えられます。
○学識経験者、環境NGO、消費者団体
これらの団体等は環境問題等に関するオピニオンリーダーとして、あるいは専門的な立場から、事業者の事業活動への環境配慮等の取組状況を評価し、一般にわかりやすく伝えるインタープリター(通訳者)の役割を果たしており、一般の消費者やマスコミに強い影響力を持っています。
これらのステークホルダーに対しては環境配慮の取組状況や事業活動に伴う環境負荷の状況等、経年変化を示すことや、業界内での比較が容易な形で示すことが重要です。
○学生等
近年、環境に関する学部や学科、講座を有する大学が増えてきており、環境問題に取り組む学生サークルも数多く存在し、活発に活動しています。これらの場で活動する学生等から事業活動における環境配慮等の取組について高い評価を得ることは、将来の顧客の獲得や有能な従業員の採用等に大きな影響を及ぼすものと考えられます。
○地域住民
地域住民は、工場等においてどのような環境保全への取組が行われているか、特に公害防止の対策や環境事故の未然防止対策等がどのように行われているかについて、関心を持っています。特に事業所単位のサイト環境レポートについては地域住民を意識して重要性の判断を行うことが望まれます。
○行政
行政は、所管地域内の環境負荷の状況などを把握する必要があり、事業者は環境規制に従って環境報告を行うことが必要です。地方公共団体においても、地域の環境基本計画や地球温暖化対策行動計画等の中で、地域の事業者を計画の主要な対象として事業者の自主的な取組を通じた環境報告を促進し、その事業活動における環境負荷の低減を図ろうとする動きがあります。また、グリーン購入の進展と共に、入札参加や事業発注の条件の一つとして、環境マネジメントシステム(ISO14001 やエコアクション21等)の認証取得や環境報告書の作成・公表等を求める事例も増えています。
(2)環境報告書の活用
?公表媒体について
環境報告書の公表にあたっては、事業者を取り巻くステークホルダーとのコミュニケーションを深め、より多くのステークホルダーが活用する機会を作ることが大切です。また、環境報告書の情報がインターネットやマスメディア等のさまざまな媒体により、広く提供されることが期待されます。
そこで定期的な環境報告書の発行に加えて、より高い頻度で開示することが適切で重要な環境パフォーマンス情報や環境配慮の取組について、インターネット等を活用した追加的な情報発信をすることも有効であり、報告書の質を落とさずに複数の公表媒体の効果的かつ相互に連携した利用が期待されます。
インターネットは読み手が手軽に情報を入手できる手段として、また、情報を容易に最新の状態に更新することが可能であるという特徴を活かし、時宜にかなった情報を提供することができます。環境活動情報を冊子による環境報告書に記載するだけではなく、環境報告書とインターネットを併用する等の工夫をする等、読み手にとって必要な情報をタイムリーに提供することが期待されます。例えば、「環境報告の概要(BI-4)」にある「主要な指標等の一覧(BI-4-1)」等、環境報告書の主要な情報の公表や、詳細なデータをインターネット上で公表することも考えられます。
ただし、インターネットを併用する場合は、掲載している情報がどの時期の情報であるかを明記し、冊子の情報との違いが分かるように工夫することや、関連した情報を掲載したインターネットのURLを冊子に示す等、冊子の情報との関係を明確
にすることが必要です。また、過去の情報についても参照できるようにしておくことが期待されます。
事業者の環境に関する活動が活発になるに従って、公表する環境配慮等の情報が増加する傾向にあります。より多くのステークホルダーに、より簡潔に環境報告書の内容を伝えたい場合には、環境報告書の要点のみを分かりやすくまとめた、いわ
ゆるダイジェスト版等を別途作成し、広く配布する方法もあります。
また、事業所を立地して活動している地域の情報に特化した地域版の環境報告書(環境サイトレポート)も地域とのコミュニケーションにおいて有効と考えられます。環境サイトレポート等については、地域住民等が必要とする水資源投入量、大気汚染や生活環境に係る負荷量、化学物質の排出量、総排水量等の地域性の高い環境パフォーマンスに関する情報や地域での活動に関する情報等に重点を置いて、簡潔に取りまとめることが望まれます。
どのような方法で環境報告書を公表するかは、想定される環境報告書の利用者の利便性や理解容易性を考慮し、事業者が自ら有効と判断した媒体、表現手段、作成方法を選択する必要があります。
なお、環境に関する重要な事象が起きた場合には、関連する情報を速やかにインターネット等で公表することが期待されます。
?トピックス・特集について
事業者の環境配慮等の活動の中で、社会的に注目を集めている特定の事象や活動(自社に不利な情報を含む)、ステークホルダーとの関係から重要と判断される情報について、トピックスや特集のページを設けて環境報告書に掲載する等、読み手
の関心に応える工夫をすることが期待されます。
また、必要に応じて、特集に記載することにした背景についても読み手に説明することや図表や写真等を活用し、わかりやすく説明することが望まれます。
ただし、トピックス・特集をもって体系的な情報の代わりとすることはできません。トピックスや特集にスペースを割きすぎることによって、必要な情報が十分に提供されないことのないように配慮する必要もあります。
6.環境報告書の内容及び信頼性を向上させるための作成過程における方策
環境報告書を作成する過程では、環境報告書の内容をより良いものとし、「信頼性」を高める(すなわち重要な情報の網羅性、正確性、中立性、検証可能性の観点からより適切なものとする)ための努力が求められます。そのためには、まず、事業者自らが報告書の内容について評価するとともに、報告書の基礎となる情報を正確なものとするよう努力が必要です。
また、環境報告書の作成過程にステークホルダーが参画する、できあがった環境報告書についての意見をステークホルダーに求め意見書を添付する、中立的な第三者の審査を受ける等、組織外の主体が関わることで、事業者自身が見落としていた論点が明らかになり、報告書の内容が向上し、信頼性がさらに高まることも期待されます。
これらはいずれも重要な取組ですが、ステークホルダーとの関わり方や第三者からの外部審査の必要性、さらに事業者の経営資源の状況や環境報告書の作成の成熟度に応じて、また、必要に応じて組み合わせて取り組むことが期待されます。
事業者自らが実施する信頼性を向上させる方策の例は、次の通りです。
?自己評価の実施
自己評価は、環境報告書の信頼性についてチェックリストを用いつつ事業者自身がレビューするもので、自己評価を行った場合にその手法・過程・結果等を公表するものです。
環境省では、「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」を作成していますので、この手引きが活用されることを期待します。
「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)」:
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
?内部管理の徹底
これは、事業者内部の環境マネジメントシステム(ISO14001 やエコアクション21 等)を徹底し、内部監査等を厳格に行う取組であり、事業者自身が情報の比較容易性や信頼性を確認するものです。内部監査を実施する過程で、環境報告書で公表する数値データの把握・集計・評価・公表の仕方や、外部コミュニケーションにおける環境報告書の活用状況及びステークホルダーとのコミュニケーションの状況についても確認することが期待されます。
?内部監査基準や環境報告書作成の基準等の公開
これは、事業者自身が、その内部監査の基準や環境報告書作成の基準等を公開する取組であり、特に環境報告書の作成の基準が明らかにされれば、外部の第三者がそれに基づいてレビューを行うことも可能となります。
?社内監査制度等の活用
これは、社内で環境報告書を作成した部門以外の社内組織等、例えば役員や監査担当部署、監査役や社外取締役等が客観的な視点をもって、環境報告書を検証するものです。
事業者以外の第三者が実施する信頼性を向上させる方策の例は、次の通りです。
?双方向コミュニケーション手法の組込
これは、環境報告書の記載情報や環境保全への取組について、事業者がステークホルダーからの質問や意見に回答するだけでなく、両者が相互に意見を交換する仕組みを作ったり場を設けたりする取組です。事業者とステークホルダー等による座
談会や説明会を開催し、その概要を環境報告書に掲載する事例もあります。
?第三者による意見
これは、環境報告書を作成する事業者以外の主体(第三者)が、環境報告書の記載情報について評価や勧告等の意見を表明したり、環境報告書の背景にある事業者の取組に対して意見を表明するものです。なお、意見を表明する第三者の選択基準
やその第三者の作成段階における関与の状況等、第三者意見表明の手続の概要を記載するとともに、第三者の意見に対して、事業者側が今後どうしていくのかについてコミットメントすることが望まれます。
?第三者による審査
これは、環境報告書を作成する事業者以外の第三者(監査法人等の審査機関)が、環境報告書の記載情報やその背景にある取組内容の結果(環境パフォーマンス指標)について、適切な作成基準に従って作成されているかどうかを審査し、それらの正確性を中心とする審査の結論を表明するものです。その際は、事業者が本ガイドラインや他のガイドライン等から適切なものを選択し、あるいは自ら定めた作成基準に従って環境報告書を作成し、その作成基準を審査機関が判断規準(クライテリア)
として審査を行います。
?NGO・NPO 等との連携による環境報告書の作成
環境報告書の企画、作成の過程にNGO・NPO のスタッフ、学生、一般消費者等が直接関わり、事業者との一種の共同作業により環境報告書を作成する取組であり、連携の方法には単に意見交換を行うものから、記載情報のチェックを行うものまで、
さまざまな内容があります。
また、参考資料の7.【チェックリスト】等を用いて本ガイドラインへの準拠の状況を示すことも信頼性の向上に資すると考えられます。
上記のような環境報告書の内容及び信頼性を向上させる取組と合わせて、それらの取組の結果や意見等に対応した状況についても、環境報告書に記載することが期待されます。
第2章 環境報告の記載項目の枠組み
1.環境報告の全体構成
環境報告には「環境報告として記載すべきと考えられる項目」があります。これは、環境報告により社会的説明責任を果たすとともに、ステークホルダーの意思決定に有用な情報を提供するため、さらには環境報告が環境コミュニケーションのツールとして機能するために不可欠な項目であり、現在発行されている多くの環境報告書等で網羅されている項目です。環境報告として記載する情報・指標は、次の5つの分野に分類されます(第3章を参照)。
(1)基本的項目
(2)環境マネジメント等の環境経営に関する状況
(3) 事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況
(4)環境配慮と経営との関連状況
(5)社会的取組の状況
上記の各分野の中で環境報告として記載する項目は、以下のとおりです。
(1)基本的項目(BI, Basic Information)
経営責任者の緒言、報告にあたっての基本的要件(報告範囲の環境負荷の捕捉
状況を含む)、経営指標を含む事業概要及び主要な指標等の一覧等で、事業者が
環境に係る説明責任を果たすとともに、ステークホルダーの意思決定に有用な情
報を提供し、社会との環境コミュニケーションを図りパートナーシップを構築し
ていく上での基礎的な内容です。
なお、経営責任者の緒言は、単なる挨拶ではなく、事業活動における環境配慮
の取組状況に関する総括と社会に対しての誓約となっていることが必要です。ま
た、事業者の事業活動に伴う環境負荷の状況と事業活動における環境配慮の取組
の全体像を説明します。目標、計画、実績等については、環境負荷の状況も含め
て一覧表等に取りまとめることが望まれます。
基本的項目として記載する項目は、以下の5項目です。
BI-1:経営責任者の緒言
BI-2:報告にあたっての基本的要件
BI-2-1:報告の対象組織・期間・分野
BI-2-2:報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況
BI-3:事業の概況(経営指標を含む)
BI-4:環境報告の概要
BI-4-1:主要な指標等の一覧
BI-4-2:事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括
BI-5:事業活動のマテリアルバランス(インプット、内部循環、アウトプット)
(2)「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す情報・指標(環境マネジメント指標:MPI, Management Performance Indicators)
事業者の環境経営における環境配慮の取組について、その方針、目標、計画及
び実績について説明します。
また、事業者の組織的な環境マネジメント全般の状況についてまとめて説明す
るパートでもあり、環境マネジメントシステム、環境に関する規制遵守の状況、
環境会計情報、環境に配慮した投融資、環境に配慮したサプライチェーンマネジメ
ント、環境に配慮した新技術等の研究開発状況、生物多様性への対応、環境コミ
ュニケーションの状況等、さらに、環境負荷低減に資する製品・サービスの状況(無
形のサービス・役務を含む)についても記載します。
環境マネジメント指標として記載する項目は、以下の12項目です。
MP-1:環境マネジメントの状況
MP-1-1:事業活動における環境配慮の方針
MP-1-2:環境マネジメントシステムの状況
MP-2:環境に関する規制の遵守状況
MP-3:環境会計情報
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
MP-5:サプライチェーンマネジメント等の状況
MP-6:グリーン購入・調達の状況
MP-7:環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
MP-9:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
MP-10:環境コミュニケーションの状況
MP-11:環境に関する社会貢献活動の状況
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
(3)「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標(オペレーション指標:OPI, Operational Performance Indicators)
事業活動全体における物質やエネルギー等のインプット、アウトプットを把握
するマテリアルバランス*の考え方に基づき事業活動の環境負荷を捉えます。
事業者が自らの事業活動において環境負荷の低減に向けて取り組んでいる方
針、目標、計画、環境パフォーマンスの状況及びその実績等を中心に記載します。
また、環境負荷削減の観点から、環境配慮の状況を明らかにしていくことが重要
で、その内訳についても記載することが期待されます。また、製品・サービスの
ライフサイクルでの環境負荷低減等、事業活動の上流・下流部分での取組や実績
についても記載することが望まれます。
オペレーション指標として記載する項目は、以下の10項目です。
(インプット)
OP-1:総エネルギー投入量及びその低減対策
OP-2:総物質投入量及びその低減対策
OP-3:水資源投入量及びその低減対策
(内部循環)
OP-4:事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
(アウトプット)
(製品)
OP-5:総製品生産量又は総商品販売量
(排出物・放出物)
OP-6:温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP-7:大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
OP-8:化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP-9:廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
OP-10:総排水量等及びその低減対策
(4)「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標(環境効率指標:EEI, Eco-Efficiency Indicators)
環境負荷はその総量を削減することが事業者に求められています。一方、事業経営
の観点から、経済効率性の高い環境への取組が求められています。そのため、事業者
の環境パフォーマンスや環境への取組を把握・評価する場合には、環境負荷の総量を
示す指標だけでなく、事業者の生み出す経済価値を反映しながらその環境への取組の
効率性を表す指標(以下、「環境効率指標」)を把握・管理することが重要になります。
本ガイドラインでは、第三次環境基本計画の「総合的環境指標*」も参考にして、
代表的な事例を紹介します。
(注)
上記4分野のうち、(2)環境マネジメント指標(MPI)、(3)オペレーション
指標(OPI)及び(4)環境効率指標(EEI)の3分野の情報・指標を合わせて、「環
境パフォーマンス指標(EPI, Environmental Performance Indicators)」と称するこ
とにします。
(5)「社会的取組の状況」を表す情報・指標(第4章)(社会パフォーマンス指標:SPI, Social Performance Indicators)
近年、環境報告書の記載内容を広げ、社会・環境(CSR)報告書等として、事
業者の社会的側面についても情報開示、報告する取組が広がりつつあります。し
かし、社会的側面の記載項目については、まだ社会的合意が成立しているとはい
えない段階にあるといえます。本ガイドラインでは、我が国の既発行の社会・環
境(CSR)報告書等から代表的情報・指標等を取り上げるとともに、法律等にお
いて開示が求められている情報、及び今後記載が重要になると考えられる情報を
取りまとめました。
? 労働安全衛生に関する情報・指標
? 雇用に関する情報・指標
? 人権に関する情報・指標
? 地域及び社会に対する貢献に関する情報・指標
? 企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引に関する情報・指標
? 個人情報保護に関する情報・指標
? 広範な消費者保護及び製品安全に関する情報・指標
? 企業の社会的側面に関する経済的情報・指標
? その他の社会的項目に関する情報・指標
第3章 環境報告における個別の情報・指標
前章では環境報告の全体構成(5分野)並びにその概要を述べましたが、本章では
環境報告における基本的項目(BI)と環境パフォーマンス指標(EPI)に関連する各
分野について、記載する個別の情報・指標の要点を説明します。社会パフォーマンス
指標(SPI)に関しては、第4章にて説明します。
【環境報告における情報・指標の分類】
(1) 本章では、環境報告において全ての事業者に共通して重要性があると考えられる
記載すべき項目は「(1)記載する情報・指標」として「ア.〜」「イ.〜」「ウ.〜」・・・
で表記しています。また、環境報告書の基本的機能を踏まえ、持続可能な社会の
構築に向けて必要に応じて記載することが望ましい推奨項目は「(2)記載するこ
とが期待される情報・指標」として「?〜」で表記しています。
(2) 「(1)記載する情報・指標」及び「(2)記載することが期待される情報・指標」の
それぞれにおける例示項目を「・〜」で表記しています。
(注)
? 情報・指標の記載にあたっては、必要に応じて国内・海外に分けて記載することが望まれます。
? 算定式や単位は一般的なものを記載していますが、実務上で用いられている算定式
や単位で記載することができます。また、算定に用いた算定式や係数等を記載する
ことが必要です。
? 本ガイドラインは環境報告の項目立て及び各項目の情報・指標の記載の仕方や順番
を規定するものではありません。記載する情報・指標の内容が重複する場合は、項
目毎に記載する必要はなく、まとめて記載することができます。
? 環境報告にあたっては、第3章の全ての項目の情報を記載することが望まれますが、
環境への影響が無い、もしくは非常に小さいと判断される項目等については、記載
しない理由を明記します。(参照:参考資料の3.【Q&A】)
? 環境報告書には第3章の環境報告の項目と第4章の社会的取組の状況をあわせて5
分野29項目全てを記載することが期待されます。
1.基本的項目(BI)
環境報告書に記載する環境報告の「基本的項目」(BI)は以下の5 項目です。本節で
は、それぞれの基本的な考え方や記載する具体的な情報・指標等について解説します。
(基本的項目:BI)
BI-1:経営責任者の緒言
BI-2:報告にあたっての基本的要件
BI-2-1:報告の対象組織・期間・分野
BI-2-2:報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況
BI-3:事業の概況(経営指標を含む)
BI-4:環境報告の概要
BI-4-1:主要な指標等の一覧
BI-4-2:事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括
BI-5:事業活動のマテリアルバランス(インプット、内部循環、アウトプット)
BI-1:経営責任者の緒言
経営責任者の緒言は、環境報告書の巻頭に記載され、経営責任者のコミットメント
(誓約)に加えて、事業者自身の環境経営の方針、取組の現状、将来の目標等が現状
や実績を踏まえて総括的に盛り込まれたものであり、極めて重要なものです。
さらに、総括やコミットメント(誓約)の内容は、自らの業種、規模、事業特性等
に応じた適切かつ具体的なものである必要があり、単なる一般論を述べるだけでは不
十分です。
なお、「社会的取組の状況」についても併せて報告する場合、企業の社会的責任全
体に関するコミットメントを行うことが必要です。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境経営の方針
イ.環境問題の現状、事業活動における環境配慮の取組の必要性及び持続可能な社
会のあり方についての認識
ウ.自らの業種、規模、事業特性あるいは海外展開等に応じた事業活動における環
境配慮の方針、戦略及び事業活動に伴う環境負荷の状況(重大な環境側面)と
その低減に向けた取組の内容、実績及び目標等の総括
エ.これらの取組に関して、確実に実施し、目標等を明示した期限までに達成し、
その結果及び内容を公表すること、についての社会へのコミットメント
オ.経営責任者等の署名
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 持続可能な社会の実現に貢献するための経営方針、目標等(社会的取組に関するものも含む)
? 環境報告の記載内容について、事業活動に伴う重大な環境負荷及びその削減の目標・取組等を漏れなく記載し、正確であることの記載
? 環境変化が及ぼす事業への影響
? 報告範囲に関する経営責任者の考え方や方針
? 報告内容の信頼性確保に関する経営責任者の考え方や取組の方針
? 環境報告の外部審査を受審した場合は、その旨
(3) 解説
経営責任者の緒言は、経営責任者もしくは代表権のある環境担当役員の環境報告
にあたっての概括的なステートメントとして記載されるものです。そのため、細か
な点を詳しく述べるのではなく、経営責任者の「環境経営」に対する考え方が、経
営責任者自身の言葉で率直に語られるとともに、その実行を社会に対してコミット
メント(誓約)を行うことが必要です。
環境報告にあたっては
・自らの業種、規模、事業特性あるいは海外展開等を踏まえる
・事業活動における環境配慮の方針、事業活動に伴う環境負荷の状況、事業活動
における環境配慮の取組内容、実績及び目標等を明確かつ簡潔に総括する
・これらの取組を確実に実施し、目標等を明示した期限までに達成することを誓約する(コミットメント)
こと等に配慮することが望まれます。
さらに可能であれば、環境報告の内容について、事業活動に伴う重大な環境負荷
及びその削減の目標や取組等を漏れなく記載し、正確であることを記すこと、環境
情報を積極的に開示し、ステークホルダーとの環境コミュニケーションを積極的に
図っていくこと等を表明することも望まれます。また、報告範囲の概要や報告内容の
信頼性の確保等にも言及することが望まれます。
これは、事業の実態を踏まえた適切かつ正確な環境報告のための環境報告書を作
成・公表して、社会的説明責任を果たし、ステークホルダーに意思決定のための情
報を提供することは、経営責任者の重要な責務の一つであり、経営責任者自身が環
境報告書の記載内容に責任を持つことが必要であると考えられるからです。
BI-2:報告にあたっての基本的要件
BI-2-1:報告の対象組織・期間・分野
環境報告書による環境報告の公表にあたっての基本的要件である、対象組織、対象
期間、対象分野、準拠あるいは参考にした環境報告等に関する基準又はガイドライン
等について具体的に記載します。
併せて、環境報告を環境コミュニケーションツールとするために必要な、作成部署
の明確化や連絡先の明示等の他、意見や質問等を受付ける方法等を工夫することが必
要です。
(1) 記載する情報・指標
ア.報告対象組織(過去に環境報告書を発行している場合は、直近の報告書における報告対象組織からの変化や経緯等についても記載する。)
イ.報告対象期間、発行日及び次回発行予定(なお、過去に環境報告書を発行している場合は、直近の報告書の発行日も記載する。)
ウ.報告対象分野(環境的側面・社会的側面・経済的側面等)
エ.準拠あるいは参考にした環境報告等に関する基準又はガイドライン等(業種毎のものを含む。)
オ.作成部署及び連絡先
カ.ウェブサイトのURL
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? ステークホルダーからの意見や質問を受付け、質問等に答える旨の記述等、何らかのフィードバックの手段
? 主な関連公表資料の一覧(会社案内、有価証券報告書、ISO14001及びエコア
クション21等の認証取得事業者はその環境方針及び著しい環境側面に関する
コミュニケーション資料、環境パンフレット、技術パンフレット等の主な関連
資料の一覧、その概要や入手方法)
(3) 解説
報告にあたっての基本的要件である対象組織・期間・分野の記載は、特定のわか
りやすい場所に記載することが求められます。
なお、報告対象組織の記載において、連結決算対象組織の一部を報告対象とする
場合は、連結決算対象組織との異同について会社名を挙げて記すことが望まれます。
記載する項目によって対象組織の範囲が異なる場合は、対象組織を明確に記載す
ることが望まれます。
特に、海外での事業については、国内の活動の報告と区別して記載することが期待されます。
環境報告書をインターネットにおいて公表している場合は、そのインターネット
のURLを記載します。さらに、冊子やインターネット以外の媒体(CD-ROM等)で発
行している場合は、その内容と入手方法を記載します。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 報告対象組織については、工場・事業所・子会社等の範囲、海外事業所の範囲、
連結決算対象組織との異同を示すべきです。なお、全体を対象としていない場
合で対象を拡大する予定がある場合は、そのスケジュール等を記載します。ま
た、記載項目等により範囲が異なる場合は、項目毎の範囲を記載します。
(ii) 環境報告に当たり準拠あるいは参考にした基準又はガイドライン等と実際に報
告した内容や項目との比較表等があれば、読み手にはわかり易くなります。
(iii) 連絡先には、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等も記載します。
BI-2-2:報告対象組織の範囲と環境負荷の捕捉状況
環境報告で対象とする組織の範囲(バウンダリー)は、原則として連結決算対象組
織全体であることが期待されますが、報告対象組織の範囲を限定している場合には、
その報告対象組織における環境負荷が連結決算対象組織全体における環境負荷の内ど
の程度を捕捉しているかを記載します。
その際、報告対象組織及びその環境負荷が事業全体の環境負荷の内どの程度を占め
ているかを読み手に伝えるために、事業者が独自に工夫してその捕捉状況を記載しま
す。さらに報告対象組織の範囲を限定した考え方や計算根拠等を明示する必要があり
ます。
(1) 記載する情報・指標
ア.報告対象組織の環境負荷が事業全体(連結決算対象組織全体)の環境負荷に占める割合(「環境負荷の捕捉率」等による状況)
ただし、環境負荷の捕捉率が正確に把握できない場合は、捕捉対象の環境負荷が
連結決算対象組織全体における環境負荷に占めるおおよその割合を記載し、順次、
精度を向上させていくことが望まれます。
環境負荷の捕捉率を示す指標としては、例えば、次のような情報や指標が考え
られます。
・ 連結決算対象組織全体の温室効果ガス排出量に対する報告対象組織の温室効
果ガス排出量の割合(エネルギー使用量や事業内容によっては、電力消費量
等把握の容易なもので代替することも考えられる。)
・ 連結決算対象組織全体の資源投入量に対する報告対象組織の資源投入量の割合
・ その他、事業内容に応じ、代表的な環境負荷に関する環境負荷の捕捉率
・ 上記以外に、事業者独自の創意工夫による事業全体に対する環境負荷の捕捉率
上記の指標について、十分な情報が得られない場合、次のような指標を補足的
に、必要に応じて組み合わせる必要があります。なお、これらの指標については、
当該指標を用いた考え方を示すことが期待され、採用したこれらの指標によって、
おおよその環境負荷の捕捉状況が明らかになることを説明する必要があります。
・連結決算対象組織全体の売上高に対する報告対象組織の売上高の割合
・連結決算対象組織全体の従業員数に対する報告対象組織の従業員数の割合
・上記以外に、事業者独自の創意工夫による指標
(2) 解説
報告対象組織の「環境負荷の捕捉率」とは、報告対象組織の事業活動に伴う環境
負荷が事業全体の環境負荷に占める割合を示す指標です。事業者の財務上の報告範囲
は連結決算対象組織が基本となっていることから、「環境経営」の報告である環境報告
の範囲も、原則としては連結決算対象組織の全てを報告範囲とし、その環境負荷を記
載することが期待されます。
しかし、報告対象組織の範囲を決定する際に、連結決算対象組織の特
定の範囲で環境負荷の大半が捕捉出来る場合には、その範囲を報告対象としても大き
な問題は発生しないと考えられます。また、限られた組織から報告を始め、徐々に対
象組織を広げることも考えられます。そこで、実際に報告対象となった組織の環境負
荷の捕捉率を示す必要があります。
しかしながら現状では、多くの環境報告書では、事業者の報告範囲の環境負荷が連
結決算対象組織全体の中でどれ位捕捉されているかが曖昧です。このことは事業者自
身にとってもステークホルダーにとっても、その判断や意思決定を誤らせる可能性が
あり、環境負荷の捕捉状況は「環境経営」における最も基本的かつ重要な事項と考え
られます。
特に、海外で事業展開する日本企業が増加している現状に鑑み、国内だけでなく海外
を含めた自らの環境負荷の全体像を正確に把握・管理するために、効率的・効果的な環
境負荷の計測・収集システムを構築することが強く期待されます。
連結決算対象組織の環境負荷の把握については、出資比率で計算する方法もあります
が、出資比率とは関係なく100%として把握する方法を原則とします。出資比率で計算
する方法を採用した場合には、その旨を明記することが必要です。
BI-3:事業の概況(経営指標を含む)
報告者がどのような事業者で、どのような事業活動をし、その規模等はどの程度な
のかをわかりやすく説明することが必要です。事業の概況が適切に記載されていなけ
れば、その事業者の事業特性等に応じたどのような環境負荷があるのか、事業活動に
おいて環境配慮の取組がどのように重要なのかわかりません。
したがって、事業の具体的内容、主要な製品やサービスの内容、財務データを含む
経営指標値等をわかりやすく、具体的に記載します。特に報告の対象組織については、
前回の報告からの変化や経緯等についても記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.主たる事業の種類(業種・業態)
イ.主要な製品・サービスの内容(事業分野等)
ウ.売上高又は生産額(連結決算対象組織全体及び報告事業者単独、報告対象組織)
エ.従業員数(連結決算対象組織全体及び報告事業者単独、報告対象組織)
オ.その他の経営関連情報(総資産、売上総利益、営業利益、経常利益、純損益、付加価値額等)
カ.報告対象期間中に発生した組織構造、株主構成、製品・サービス等の重大な変
化の状況(合併、分社化、子会社や事業部門の売却、新規事業分野への進出、
工場等の建設等により環境負荷に大きな変化があった場合)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 主たる事業活動の範囲、工場・事業所数、本社・主要な工場・事業場の所在地及びそれぞれの生産品目
? 全体的な経営方針等(可能な範囲で、今後の海外での事業展開を含む)
? 事業者の沿革及び事業活動における環境配慮の取組の歴史等の概要
? 対象市場や顧客の種類(小売、卸売り、政府等)
(3) 解説
経営指標を含む事業の概況について記載する項目です。製品・サービスの生産・
販売額(売上高)、従業員数等の重要な経営指標は、環境負荷単位当たりの製品・
サービス価値(環境効率(Eco-Efficiency))、製品・サービス価値単位当たりの環
境負荷(環境負荷集約度)等を算出する際の基礎データとして必要不可欠な情報で
す。これらの情報については、後述する環境パフォーマンス指標(EPI)のひとつと
して環境効率指標(EEI)にて詳しく述べることにします。なお、経営指標につい
て、業界等で概ね合意された指標がある場合は、それを記載することが望まれます。
また、事業の概況の記載にあたって、主たる事業の種類(業種業態)及び主たる
事業活動の範囲(活動拠点)について、事業活動に伴う環境負荷や事業活動におけ
る環境配慮の取組状況との関連を含めて具体的に、かつ、わかりやすく記載するこ
とが望まれます。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 売上高、生産額あるいは従業員数については、少なくとも過去5 年間程度を記載します。
(ii) 事業者の生産品目の記載にあたっては、主要な原材料の採掘、調達、営業や販
売活動を行っている地域について、日本国内だけか、海外も含むのか、特定地
域のみか等を考慮します。
BI-4:環境報告の概要 BI-4-1:主要な指標等の一覧
事業の概況(BI-3参照)、環境に関する規制の遵守状況(MP-2参照)、温室効果ガ
スの排出量(OP-6参照)、廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量(OP-9参照)及び事
業活動にとって重要と考えられる項目について、サマリーとしてまとめ、見開き程度
の内容で、図表を活用してわかりやすく、簡潔に記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア. 事業の概況(会社名、売上高、総資産等)(過去5年程度、BI-3参照)
イ. 環境に関する規制の遵守状況(MP-2参照)
ウ. 主要な環境パフォーマンス等の推移(過去5年程度)
・総エネルギー投入量(OP-1参照)
・総物質投入量(OP-2参照)
・水資源投入量(OP-3参照)
・総製品生産量又は総商品販売量(OP-5参照)
・温室効果ガスの排出量(OP-6参照)
・化学物質の排出量、移動量(OP-8参照)
・廃棄物等総排出量及び廃棄物最終処分量(OP-9参照)
・総排水量等(OP-10参照)
・環境効率指標(EEI参照)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境に関する特記事項等(環境機器の導入等の環境負荷の低減対策、土壌汚染の発覚等の当年度の特記すべき取組や成果等)
? 報告対象組織
(3) 解説
事業特性に応じた環境負荷の発生ないし抑制・削減の状況が一目で理解できるよ
うな概要を記載することが望まれます。その上で、環境規制の遵守状況や温室効果
ガス、廃棄物等の排出量、さらに事業特性からみて重要と考えられる項目を要約する
形でコンパクトにまとめることが望まれます。
「主要な指標等の一覧」は、事業者における重要な環境負荷の推移を時系列に比
較するのに有効です。ただし、重要な環境負荷の判断については、業種特性や事業
規模等による違いがあり事業者間の比較は容易でないことが想定されますし、ステ
ークホルダーによっても判断基準が異なることも想定されます。環境報告書の読み
手が事業者間の比較をする場合は、それぞれの指標が持つ特性や限界等に十分留意
することが必要です。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 表記方法としては、一覧表やグラフを用いてわかりやすく表記することが期待
されます。参考資料に表記方法の例を記載しています。
BI-4-2:事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括
事業活動における環境配慮の方針に対応した、長期目標及びその推移、当期及び
次期報告対象期間の目標、それぞれの目標に対応した計画、報告対象期間の環境負
荷の実績及び推移、その低減のための取組の状況、取組結果の評価分析や改善策等
を、基準とした期のデータとともに、全体を一覧表形式で記載します。
また、必要に応じて環境報告全体の概要を記載すると、よりわかりやすくなります。
(1) 記載する情報・指標
ア.事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績、改善策等の総括
例えば、次のような情報や指標を用いて「総括」を示すことが考えられます。
・環境負荷の実績及び推移
・環境負荷の実績及び推移に関する分析・検討内容
・事業活動における環境配慮の取組に関する中長期目標及びその推移、当期及び次期対象期間の目標
・中長期目標については、制定時期、基準とした時期、対象期間及び目標時期
・目標の対象期間末までの達成状況
・事業活動における環境配慮の取組に関する中長期目標、当期及び次期対象期間
の目標に対応した計画、報告対象期間の環境負荷の実績、事業活動における環
境配慮の取組結果等に対する評価及び改善策
・基準とした時期のデータ
・環境報告全体の概要及びそれぞれの内容の対応ページ
・事業内容、製品・サービスの特性に応じた事業活動における環境配慮の取組の課題
・報告対象期間における特徴的な取組
・前回の報告時と比べて追加・改善した取組等
(2) 解説
環境報告全体の概要を記載するとともに、当該事業者の事業活動と環境問題への関
わりがどのような状態にあるのか、さらに、どのような課題があり、どのように改善
するのか等について図表等を用いて表現することは、読み手の理解を助けるために望
ましいと考えられます。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 環境負荷の実績とは、主要な環境パフォーマンス指標の総エネルギー投入量、総
物質投入量、水資源投入量、事業エリア内で循環的利用を行う物質量、温室効果
ガス排出量、大気汚染、生活環境に係る環境負荷量、化学物質排出量及び移動量、
総製品生産量又は総商品販売量、廃棄物等総排出量及び廃棄物最終処分量、総排
水量の報告期間における集計値をいいます(後述のOPI を参照)。これらについ
ては、ステークホルダーが適正な判断を行うことができるように主要な環境パフ
ォーマンス指標に関する分析・検討内容、例えば環境パフォーマンス指標の著し
い改善又は悪化の要因についての分析、環境パフォーマンス指標に重要な影響を
与える可能性のある新技術や新設備の導入に係る情報等を具体的に、かつ、わか
りやすく記載することが求められます。さらに将来に関する事項を記載する場合
には、当該事項は環境報告書発行日現在において判断したものである旨を記載し
ます。
(ii) 事業活動における環境配慮の方針を踏まえた中長期の目標(事業活動における環
境配慮の取組の到達点)と、当期(報告対象期間)及び次期報告対象期間の目標、
目標の達成状況や改善すべき課題等を記載します。目標は、単なる努力目標では
なく、実際に達成すべき目標であり、可能な限り具体的、定量的かつ測定可能な
ものを記載するとともに、目標の達成状況に関する分析・検討内容、例えば、主
要な目標を達成できないと判断した場合の経緯と要因についての分析、今後の取
組方針や新たな目標に係る情報等を具体的に、かつ、わかりやすく記載すること
が求められます。
(iii) これらの目標は、事業活動のライフサイクル全体を踏まえ、事業エリア内のものだ
けでなく、原材料・部材の購入、輸送、製品・サービスの使用・廃棄等の事業活
動の上・下流までを対象とすることが望まれます。目標の設定にあたっては、循
環型社会形成推進基本計画に掲げられている目標(例えば資源生産性、循環利用
率等)等を踏まえて、それぞれの事業者が目標を設定することが期待されます。
(iv) さらに、目標に対応した計画の概要、報告対象期間の環境負荷の実績及びその評
価と改善策、負荷低減のための取組の状況、環境会計情報(事業活動における環
境配慮の取組に要したコスト(環境保全コスト)及び経済的効果等)等の総括デ
ータも併せて記載します。その際、これら全体を一覧表形式等で記載すると、よ
りわかりやすくなります。
(v) 取組の進捗状況を明らかにするため、基準とした期(暦年又は年度等)の環境負
荷の実績等も記載することが望まれます。
(vi) 一方、環境報告の記載項目は多岐にわたるため、当該事業者の事業活動と環境問
題への関わりがどのようにあり、これに対してどのような事業活動における環境
配慮の取組を行っているのかを理解することが難しくなる場合もあります。また、
前回の環境報告と比較して、当該環境報告の対象期間において、どのような特徴
的な取組があり、どのような成果が上がったのかをわかりやすく示すことも望ま
れます。
BI-5:事業活動のマテリアルバランス(インプット、内部循環、アウトプット)
外部のステークホルダーが、事業者の全体的な状況を適切に把握するためには、
事業者が自らの事業活動に対して、全体としてどの程度の資源・エネルギーを投
入し(事業活動へのインプット)、どの程度の環境負荷物質(廃棄物を含む)等
を排出し、どの程度の製品を生産・販売したのか(事業活動からのアウトプット)
を、マテリアルバランスの観点から整理し、公表することが望まれます。併せて、
事業エリア内における循環的資源利用量(エネルギー、廃棄物、水資源等)も記
載します。
なお、このマテリアルバランスは事業者の製造業的活動と非製造業的活動のい
ずれも対象としますが、アウトプットについては有形の製品と放出物・廃棄物の
みを表現するものとします。無形のアウトプットであるサービスや役務等は、別
途環境負荷低減に資する製品・サービスの状況(MP-12)にて記載することとします。
(1) 記載する情報・指標
ア.事業活動に伴う環境負荷の全体像
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境負荷の全体像等に、可能な場合は環境に配慮したサプライチェーンマネジ
メントや製品等のライフサイクル全体を踏まえた環境負荷を付け加える。
(3) 解説
マテリアルバランスの整理、把握にあたっては、原則としてここに示す10 種類のオ
ペレーション指標(OPI)により、事業活動に伴うマテリアルバランスを、実績値が
記載された図等でわかりやすく示すことが求められます。
さらに、事業活動に対する直接的なインプット・アウトプットだけでなく、事業エ
リア内における循環的資源利用量(エネルギー、廃棄物、水資源等)を把握・管理
することが重要です。加えて、原材料の採取段階や、他の事業者から購入する原材料・
部品等の生産段階等で発生する環境負荷、製品の使用・消費・廃棄段階で発生する環
境負荷についても、ライフサイクル全体を踏まえて把握・評価することが重要です。
また、このような事業活動のマテリアルバランスや製品等のライフサイクル全体の
環境負荷を適切に整理、把握することは、事業者自身の事業活動における環境配慮の
取組を効果的・効率的に推進するため、さらには社会全体で地球温暖化対策を推進す
るとともに、物質循環を確保し、持続可能な循環型社会を形成していくためにも必要
であると考えられます。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 事業活動への資源等に関するインプットの状況、事業活動からの製品及び商品
等の提供又は廃棄物等の排出に関するアウトプットの状況、並びに事業エリア
内におけるエネルギー、廃棄物、水資源等の循環的な利用に関する状況等について可能な限り図表等を活用して、わかり
やすく、かつ、簡潔に記載します。
(ii) マテリアルバランスの考え方は第2章(3)「事業活動に伴う環境負荷及びその低
減に向けた取組の状況」を表す情報・指標の表「マテリアルバランス」を参照し
てください。
【指標算定にあたっての留意点<インプットの考え方>】
インプットの投入量は、事業エリア内への投入量として、購入量が想定されます。
在庫(ストック)のない、電力、ガスは、投入量(=購入量=使用量)となりますが、
燃料油や総物質、水資源等の在庫(ストック)がある場合は購入量と使用量が異なり
ます。在庫(ストック)がある場合、消費に伴うアウトプットの環境負荷物質と対応
する投入量としては、期首在庫量と期末在庫量を考慮した使用量(=期首在庫量+購
入量−期末在庫量)になります。したがって、在庫(ストック)がある場合の投入量
は、使用量(払出量)を記載することが望まれます。ただし、期首在庫量と期末在庫
量との差異が僅少の場合には、投入量=購入量としても構いません。
2.「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す情報・指標(MPI)
環境報告書に記載する「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す環境
報告の情報・指標(環境マネジメント指標:MPI)は以下の12 項目です。本節では、
それぞれの基本的な考え方や記載が望まれる具体的な情報・指標等について解説します。
(環境マネジメント指標:MPI)
MP-1:環境マネジメントの状況
MP-1-1:事業活動における環境配慮の方針
MP-1-2:環境マネジメントシステムの状況
MP-2:環境に関する規制の遵守状況
MP-3:環境会計情報
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
MP-5:サプライチェーンマネジメント等の状況
MP-6:グリーン購入・調達の状況
MP-7:環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
MP-9:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
MP-10:環境コミュニケーションの状況
MP-11:環境に関する社会貢献活動の状況
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
MP-1:環境マネジメントの状況 MP-1-1:事業活動における環境配慮の方針
事業活動における環境配慮の取組を行うにあたって、事業活動における環境配慮
の方針(事業活動における環境配慮の取組に関する基本的方針や考え方)を適切に
定め、記載します。
事業活動における環境配慮の方針は、自らの事業活動に対応した具体的な内容
で、経営責任者の緒言との整合が図られていることが望まれます。
(1) 記載する情報・指標
ア.事業活動における環境配慮の方針
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境配慮の方針の制定時期、制定方法、全体的な経営方針等との整合性及び位置付け、コーポレート・ガバナンスとの関連
? 事業活動における環境配慮の方針が意図する具体的内容、将来ビジョン、制定した背景等に関するわかりやすい説明
? 同意する(遵守する)環境に関する憲章、協定等の名称と内容
(3) 解説
事業活動における環境配慮の方針を記載するだけでなく、その説明資料として、事
業特性等に応じて、どのような環境負荷があり、どのような事業活動における環境配
慮の取組が必要か等、事業活動における環境配慮の方針を策定した背景や理由を記載
していることも重要です。
また、事業活動における環境配慮の方針は、事業活動のライフサイクル全体を踏まえ、
事業エリア内のものだけでなく、原材料・部材の購入、輸送、製品・サービスの使用・
廃棄等の事業活動の上・下流までを対象とすることが必要です。
さらに、事業活動における環境配慮の方針は、我が国の環境基本計画及び循環型社
会形成推進基本計画等を踏まえて作成することが期待されます。
なお、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001 及びエコアクション21 に
おいても、環境マネジメントシステムの構築に当たり、環境方針を策定することが求
められていますが、環境報告書の対象組織と認証取得の対象組織が同一の場合は、こ
れらの環境方針と本ガイドラインの事業活動における環境配慮の方針は同じものであ
ると考えられます。
【情報記載にあたっての留意点】
環境配慮の方針については、事業内容や製品・サービスの特性や規模、また事業活
動に伴う重要な環境負荷等に対応した適切なものであることが必要です。
MP-1-2:環境マネジメントシステムの状況
環境マネジメントシステム(EMS)の構築状況、環境マネジメントの組織体制、
環境マネジメント手法の概要、ISO14001 やエコアクション21 等の認証取得状況、
従業員教育、環境監査*等の状況等を記載します。
また、今後のEMS の導入・構築の拡張計画や検討状況についても記載が望まれ
ます。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境マネジメントシステムの状況
例えば、次のような情報や指標を用いて記載することが考えられます。
・全社的な環境マネジメントシステムの構築、運用状況及びその評価とそれを踏
まえた今後の方向性(システム及びPDCAサイクルの説明を含む)
・全社的な環境マネジメントの組織体制の状況(環境管理に対する内部統制シス
テムの整備状況、それぞれの責任、権限、組織の説明を含む)及びその組織体制図
・環境に関するリスク管理体制の整備状況
・環境マネジメントシステム構築事業所の数、割合、並びに今後のEMSの導入・
構築の拡張計画や検討状況
・ISO14001やエコアクション21等の外部認証(自己適合宣言がある場合には、
その旨を記載する)を取得している場合には、取得している事業所等の数、割
合(全従業員数に対する認証取得事業所等の従業員の割合等)、認証取得時期
・環境保全に関する従業員教育、訓練の実施状況(研修実施回数、教育等を受け
た従業員の数、割合、従業員1人当たりの年間平均教育時間数等)
・想定される環境に関する緊急事態の内容と緊急時対応の状況
・環境影響の監視、測定の実施状況
・環境マネジメントシステムの監査の基準、実施状況(内部監査・外部審査の回
数)、監査結果及びその対応方法等
・環境マネジメントシステムの全体像を示すフロー図
・事業活動における環境配慮の取組成果の従業員等の業績評価への反映
・社内での表彰制度等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? SRIインデックスへの組み入れ状況や環境経営度ランキング等の各種表彰・評価の状況
(3) 解説
事業者が自らの環境パフォーマンスを向上させていくためには、その基盤とも言う
べき環境マネジメントシステム(EMS)を適切に構築し運用しなければなりません。
この環境マネジメントシステムがどのように構築され、どのように運用されているか
は、環境報告として環境報告書に記載すべき重要な情報です。また、今後のEMS の
導入・構築の拡張計画や検討状況は報告範囲や環境負荷データの収集範囲とも関係
するため記載することが望まれます。
なお、環境マネジメントシステムの構築・運用状況は、それぞれの事業者の形態
や規模等により異なると考えられますが、それぞれの特性に応じて具体的に記載す
ることが望まれます。
MP-2:環境に関する規制の遵守状況
環境に関する規制の遵守状況、違反、罰金、事故、苦情等の状況、並びにそれら
への対応・改善状況を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境に関する規制の遵守状況
例えば、次のような情報や指標を記載することが考えられます。
・事業活動との関係が強い重要な法規制等を遵守していることの確認方法とその結果(定期又は不定期の内部チェック体制の内容)
・少なくとも過去3年以内の重要な法規制等の違反の有無(重要な法規制違反、
基準超過等につき規制当局から指導、勧告、命令、処分を受けた場合には、そ
の内容、改善の現状、再発防止に向けた取組の状況、そうした事項がない場合
には、それを確認する方策や仕組みとともにその旨を記載)
・環境に関する罰金、過料等の金額及び件数
・環境関連の訴訟を行っている又は受けている場合は、その内容及び対応状況
・環境に関する苦情やステークホルダーからの要求等の内容及び件数(騒音及び
振動、悪臭等に対する苦情等の状況を含む)
・上記のような法令や協定違反、事故、事件、苦情等があった場合、それらへの
具体的な対応状況・改善方策等(経営レベルを含む)
・環境規制を上回る自主基準等を設定している場合は、その方針等
・環境ラベル、環境広告、製品環境情報等における違反表示、誤表示等の状況
(2) 解説
事業者が事業活動における環境配慮の取組を行い、社会の信頼を勝ち得ていくため
には、環境コミュニケーション等を積極的に行っていくと同時に、環境に関する法令、
条例、協定等の規制や約束事項を遵守し、また、自社に不利な情報も含めて、その情
報を適切に開示していく必要があります。特に、さまざまな法令等の遵守状況や、違
反や事故、苦情等の情報は環境報告として環境報告書に記載すべき重要な情報であり、
社会からの信頼を得ていくためにも必要です。
さらに、上記のような法令や協定違反、事故、事件、苦情等が実際にあった場合、
それらへの具体的な対応状況・改善方策等(経営レベルを含む)を記載することが望まれます。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 特有の法的規制、取引慣行、経営方針及び重要な訴訟事件等の発生等、ステーク
ホルダーの判断や見解に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、具体的にわかり
やすく、中立的な記述を行うことが必要です。そのような事実がない場合には、
その旨を記載しますが、単に事実がないというだけではなく、それを確認する組
織的な方策や仕組みとともに記載することが望まれます。
(ii) 実務上の留意点として、環境計量証明事業者に測定を依頼し、規制値オーバーと
なった場合、通常再測定を依頼します。その結果、規制値内となった場合、1度
目の計量証明書の発行を依頼しない事例があります。環境計量証明事業者が、合
理的であると認めない限り、計量証明書の発行を受け、監督官庁への連絡等規制
値違反としての対応が必要です。なお、環境に関する規制を遵守するために、今
後は公害防止等に係る測定実施や測定結果あるいは計量証明書の管理に関し、内
部統制や内部監査の体制が整備され、適正に運用されることが望まれます。
MP-3:環境会計情報
環境省「環境会計ガイドライン(2005 年版)」に示された考え方を参考にして、
事業活動における環境保全コストと、その活動により得られた環境保全効果及び環
境保全対策に伴う経済効果を総括的に記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境保全コスト*
イ.環境保全効果*
ウ.環境保全対策に伴う経済効果*
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 企業の内部管理に活用した環境管理会計*に関する情報
(3) 解説
事業者が事業活動における環境配慮の取組を行っていく上で、環境保全コストを
管理し、環境保全対策の費用対効果を分析することにより、適切な経営判断を通じ
て効率的かつ効果的な事業活動における環境配慮の取組を推進することが必要です。
また、環境会計情報やその導入目的・利用方法等を公表することは、ステークホル
ダーが事業者の事業活動における環境配慮の取組状況をバランスよく理解し、評価
するための有効な手段となります。
こうした意味で、環境会計が多くの事業者によって導入されるとともに、集計さ
れた定量的な情報が、わかりやすく総括的に整理されて環境報告書に適切に記載さ
れ、公表されることが望まれます。
公表にあたっては、「環境会計ガイドライン(2005年版)」に示す公表用フォー
マット等を用いることにより、環境会計情報を総括的に開示することができます。
また、マテリアルフローコスト会計や環境に配慮した設備投資等の内部管理のた
めの環境管理会計に関する説明を記載することや、環境会計情報と後述する環境効
率指標を統合して開示することも有効です。
(参考)環境会計ガイドライン2005 年版
http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html
経済産業省「環境管理会計手法ワークブック」
http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/sonota/policy1-01.html
【情報記載にあたっての留意点】
環境保全コストは、事業者内での環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、影響の除
去、発生した被害の回復又はこれらに資する取組のための投資額及び費用額であり、
ここでいう投資額は事業者内における投資のことです。「MP-4 環境に配慮した投融資」
での投融資は、他の事業者等への出資や株式の購入やプロジェクトへの投融資等を指
します。
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
環境配慮促進法(第4条)では、金融機関だけでなく全ての事業者に対して投資そ
の他の行為をするにあたっては、環境情報を勘案して行うように努めることを定めて
います。
また、製品・サービスの市場だけでなく、金融市場においても環境配慮が評価され
ることが期待されます。
そのため、金融機関には本業の中で環境配慮が求められますし、それ以外の企業に
おいても、年金基金の運用等を行う際に、通常の事業活動における投資・融資とは異
なる一般的な投資家として、環境に配慮した有価証券投資やその他の投融資を行うこ
とが期待されます。
そこで、環境報告として環境に配慮した資金の流れの状況について記載します。併
せて、排出量取引等の新しい投資・融資活動についても、取組の状況を示すことが期
待されます。
(1) 記載する情報・指標
ア.投資・融資にあたっての環境配慮の方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
(投融資を実施する場合)
? 環境保全に資する事業やそのような事業を行う企業に対する投融資の状況
? 環境への配慮状況を評価しつつ行う事業や企業に対する投融資の状況
? カーボンファンド*等への投資の状況
? 外部の環境インデックスを使用した投資の状況
(投融資を受ける場合)
? 金融機関等から受けた環境関連の投資や融資の状況
(その他)
? 資金運用や企業年金におけるSRI運用額
(注)金融機関の環境に配慮した融資あるいは投資ファンド等の金融商品は、後述する
「MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況」にも該当します。
(3) 解説
環境と経済を統合的に向上させる観点から、金融市場においても環境の価値が積極
的に評価されることが期待されます。そのためには、まず金融機関において、環境保
全に資する事業や環境に配慮した企業活動等の評価に基づいて投資・融資を行うこと
が望まれます。
金融機関以外の事業者についても、その保有する資金の運用にあたっては環境に配
慮して行動することが期待されます。特に、取引先や買収対象企業等他の主体に対し
て投資・融資を行うに際しては、相手先の環境情報を勘案して行うことが環境配慮促
進法において求められています。
また、年金基金等の事業に直接関連しない資金については、年金基金等は国内外に
おいて資本市場の大きな部分を占める機関投資家として中長期的な投資・融資を行っ
ていることから、環境に配慮した投資・融資を行うことが強く期待されます。
環境に配慮した直接金融には、例えば環境に配慮した企業に直接投資を行うSRI や
環境に配慮したプロジェクトに投資するグリーンファンド等があります。さらに、今
後、環境保全に資する事業活動に対して投資を行うことも期待されます。一方、間接
金融である融資についても、例えば
?土壌の汚染状況、回復見込み等を担保価値の評価に組み込むことによって、汚染土壌の回復を図るような事業を優遇する融資、
?環境配慮について金利等のインセンティブがついているような融資商品、
?開発行為に際して一定の環境配慮が求められるような事業への融資、
?環境負荷の低減そのもの
につながる環境ビジネスを促進するような事業への融資があります。
一部の銀行等の金融機関では、環境負荷の低減に資する事業への融資額及びその事
業を通して排出される温室効果ガスの低減効果量を公表する動きがあります。このよ
うな環境に配慮した事業や企業へ投融資の状況について、金融機関等が積極的に情報
公開していくことが期待されます。(参照:MP-12)
【情報記載にあたっての留意点】
自らの事業における環境配慮型の設備投資額は、「MP-3:環境会計情報」の構成要
素である環境保全コストの中の「投資」に相当します。(参照:MP-3)
MP-5:サプライチェーンマネジメント等の状況
取引先に対して、事業活動における環境配慮の取組に関し、どのような要求や依
頼をしているのか、それをどのようにマネジメントしているのか等、環境等に配慮
したサプライチェーンマネジメントの状況は、環境報告として環境報告書に記載す
べき重要な情報です。
ここでは環境等に配慮したサプライチェーンマネジメントに関する概要を記載
します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境等に配慮したサプライチェーンマネジメントの方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 調達量全体に対する環境等に配慮した調達量の割合
? 川上から川下への化学物質有害性情報や原材料採取の場所、採取時の環境配慮
等の環境情報の伝達方針及び取組状況
(3) 解説
事業活動における環境配慮の取組は、自らの直接的な事業活動の範囲だけにとど
まるものではなく、原材料の調達、部品・部材の調達、製品等の購入、輸送、廃棄
物処理等、さまざまな取引先をも視野に入れる必要があります。このような幅広い
取引先と協働して、サプライチェーンのグリーン化を推進していくことが求められ
ています。
また、ISO14001及びエコアクション21等の認証登録制度をサプライチェーンマネ
ジメントにおいて活用していくことも有効な方策であると考えられます。
最近では、海外からの素材・部品等の調達あるいは海外現地での操業を背景とし
て、環境だけでなくフェアトレード*やCSR調達等社会面への視点も広がってきてお
り、社会性からもサプライチェーンマネジメントを考えていくことが期待されてい
ます。
【情報記載にあたっての留意点】
環境に配慮したサプライチェーンマネジメントの状況は、それぞれの事業者の形
態や規模等により異なると考えられますが、それぞれの特性に応じた状況を具体的
に記載することが望まれます。
MP-6:グリーン購入・調達の状況
環境への負荷を極力少なくし、資源・エネルギーの循環的利用を促進していくた
めには、自らの事業エリア内における取組のみならず、原材料、部品、製品、サー
ビス(以下、製品・サービス等という。)の購入先、いわゆる事業エリアの上流側
での取組を積極的に働きかけていくことが必要であり、そのための重要な手法とし
て、環境負荷低減に資する製品・サービス等*の優先的購入(グリーン購入・調達)
があります。
このグリーン購入・調達がどのように行われ、どの程度の成果を上げているか、
さらに今後の目標や拡張計画を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.グリーン購入・調達の基本方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境負荷低減に資する製品・サービス等の購入・調達量、額、品目数等(MP-12:
環境負荷低減に資する製品・サービスの状況、参照)
? 購入・調達全体に対する環境負荷低減に資する製品・サービス等の購入・調達の割合
? 購入・調達先に対する環境配慮に関する要請の状況
(3) 解説
業種、事業規模等によって購入・調達する製品・サービス等は千差万別であるため、
それぞれの製品・サービス等の特性に応じたグリーン購入・調達の状況(グリーン購
入の購入全体に占める割合を含む)を具体的に記載することが望まれます。例えば、
以下のような事例が考えられます。
? 古紙や合法性の確認がとれた木材(森林認証*材等)を使用した紙
? 再生材使用や詰替型等の事務用品
? 省エネ性能の高い事務機器
? 低公害車*
? 再生材を使用した原材料等
等
(参考)グリーン購入ネットワーク
http://www.gpn.jp/
MP-7:環境に配慮した新技術、DfE 等の研究開発の状況
環境に配慮した生産技術、工法等に関する研究開発の状況、製品・サービスの環
境適合設計*(DfE:Design for Environment)等の研究開発の状況、環境に配慮
した販売、営業方法の工夫、ビジネスモデル等を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境に配慮した生産技術、工法、DfE等の研究開発に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほかに、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? LCA(ライフサイクルアセスメント)手法を用いた研究開発の状況
? 環境に配慮した販売、営業方法の工夫、ビジネスモデル等
? 環境適合設計(DfE)等の研究開発に充当した研究開発資金
(3) 解説
事業活動における環境配慮の取組を行っていくためには、環境に配慮した生産方法
や工法、環境に配慮した製品・サービスの開発・設計(環境適合設計(DfE))等の研
究開発、環境に配慮した販売、営業方法の工夫、さらには環境配慮型のビジネスモデ
ルの開発等に積極的に取り組んでいくことが必要です。これらの研究開発が、将来の
環境パフォーマンスの向上、さらには自社のエコビジネスの進展等につながっていく
と考えられます。
この事業活動における環境配慮の取組に関する研究開発がどのように行われ、どの
程度成果を上げているかは、環境報告として環境報告書に記載すべき重要な情報です。
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
輸送に係るエネルギー起源二酸化炭素(CO2)やNOx・PM の排出量と、原材料
等を購入先から搬入するためや、製品・サービス、廃棄物等を搬出するための輸送
又は旅客の輸送に伴う環境負荷の状況及びその低減対策を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境に配慮した輸送に関する方針、目標、計画等
イ.総輸送量及びその低減対策に関する取組状況、実績等
ウ.輸送に伴うエネルギー起源CO2排出量及びその低減対策に関する取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 大都市圏におけるNOx・PM法の取組状況
? 輸送に伴う梱包材等の再利用量(率)と廃棄量
(3) 解説
我が国における2005年度のCO2排出量(速報値)は12億9,700万トン-CO2(1990
年度比13.3%増)ですが、運輸部門からの排出量は2億5,700万トン-CO2(同18.1%
増)となっており、全体の排出量の19.8%を占めています。また、自動車輸送の増
加及び集中に伴い、NOx・PMを起因とする都市部の大気汚染は改善が求められてい
ます。この輸送に伴うCO2及び大気汚染物質の排出を削減していくためには、鉄道・
船舶輸送への切り替え等のモーダルシフトの推進や、集配拠点の再編、渋滞等を勘
案した輸送効率の高いルートの選択、共同輸配送や帰り荷確保等の輸送効率の向上
とともに、輸送量そのものを極力削減していくことが必要です。
事業者は自らの部品や製品を運ぶ場合には、自家用トラックを使うか、運送業者
の営業用トラックを使うことになりますが、いずれにしても事業者の責務として温
室効果ガスやNOx・PMの排出あるいは輸送用梱包材等の廃棄物発生を抑制・低減す
るべく努力しなければなりません。
平成18年4月から施行された改正省エネ法では、一定規模以上の貨物輸送事業者、
旅客輸送事業者、荷主に省エネルギー計画策定とエネルギー使用量報告が義務付け
られました。輸送活動に携わるそれぞれの主体に、エネルギー資源の有効利用を図
るとともに、輸送に伴うエネルギー起源CO2の発生をより一層抑制することが求めら
れています。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 環境に配慮した輸送としては、総輸送量と輸送に伴うエネルギー起源CO2 の排出
量が主要な指標となります。総輸送量は、自社輸送及び製品・サービスに伴う外
注分(委託等)の輸送について、その輸送手段ごと(自動車、船舶、鉄道、航空
機等)に合算し、トンキロ(t×km)又は人キロ(人×km)単位で記載します。
(ii) 輸送に伴うエネルギー起源CO2 の排出量は、「地球温暖化対策推進法施行令」の規
定に基づき、燃料の使用量を把握し、排出係数を用いて算定し、t-CO2 単位で記
載します。
(iii) 事業者の製品・サービスに伴う輸送の外注分(委託分)については、その正確な
把握、算定が困難ですが、可能な限りこれを把握することが望まれます。ただし、
把握が難しい場合は、主要な製品についてのみ算定する、一定のシミュレーショ
ンモデル等により推計すること等もできますが、その根拠を明示する必要があり
ます。
(iv) 原材料、燃料等の購入に伴う輸送については、専用又はチャーター等の輸送手段
により、また、他の一般貨物等と混載されないで納入される場合は、これを別途
記載することが望まれます。さらに、自社輸送と外注分の別、輸送手段毎の内訳
等を公表することが望まれます。
(v) 共同輸配送や帰り荷確保等による輸送効率(単位:%)、すなわち
[輸送トンキロ(t×km)]/[能力トンキロ(t×km)]又は
[輸送人キロ(人×km)]/[能力人キロ(人×km)]
の向上も、CO2 や大気汚染物質の排出削減に資するものであり、併せて把握・公
表することが望まれます。
(vi) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
MP-9:生物多様性*の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
生物多様性条約*(日本は平成5 年締結)と新・生物多様性国家戦略*(平成14 年決
定)の精神に鑑み、生態系の保全、生物種の絶滅の防止と回復、生物資源の持続可能
な利用を達成するための方針、目標、実績等を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.生物多様性の保全に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
例えば、次のような情報や指標を用いて記載することが考えられます。
・ 事業活動に伴う生態系や野生生物への主要な影響とその評価(海外の生物多
様性の豊かな地域における開発を含む)
・ 原材料調達における生態系や野生生物への主要な影響とその評価(影響が大
きい業種の場合には、そのプロセスにおける影響も含む)
・ 事業活動によって発生し得る生物多様性への影響を回避ないしは軽減するための取組
・ 所有、賃借、あるいは管理する土地及び隣接地域における生物多様性の保全に関する情報
・ 生物多様性が豊か、あるいは保護する価値が高い地域4に所有、賃借、管理し
ている土地がある場合は、その面積と保全状況等
・ 生態系の保全・再生のために積極的に行うプログラム及び目標(生物多様性
が豊か、あるいは保護する価値が高い土地の買い上げや寄付等による保全活動を含む)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 生産あるいは原材料調達の過程において生物多様性へ与える影響を軽減し、生
物資源の持続可能な利用のための配慮がなされた製品やサービスと、それが全
製品及び全サービスに占める割合
? (社)日本農林規格協会による有機農産物や栽培期間中に化学合成農薬を使用
していない、あるいは節減して栽培した農産物の利用方針や取組状況等
? 所有、賃借、あるいは管理する土地及び隣接地域に生息・生育する生物種に関
する情報(特に、絶滅が危惧される生物種*及びその地域に固有な生物種につ
いての情報)
? 事業活動に起因する生息・生育地の改変内容、及び生息・生育地を保護または
復元した割合
? 山地、農地、市街地等における遊休地を生物多様性の保全のために再び自然を修復した面積
? 計画中の事業や、開発の過程における生物多様性や生態系への影響の評価と対
策(回避、軽減)の実績
? 保護地域あるいは脆弱な生態系からなる地域とその周辺において計画中の事
業、及びその事業が生物多様性と生態系に与える影響
(3) 解説
開発や原料調達をはじめ、事業活動は直接的、間接的に生物多様性に大きな影響を
与えています。生物多様性及びその重要な構成要素の一つである生態系は、生物・遺
伝資源の源泉としての利用価値や、物質循環、気象の調節、文化の源泉等の生態系サ
ービスをもたらしており、私たち人類の生活と事業活動が大きく依存しているものです。
過剰な利用や開発等による生態系の破壊は、私たち人類の生活や事業活動を持続
不可能にする可能性があるため、十分な配慮を払うことが必要です。
その一方で、生物多様性への配慮を経営システムの中に統合することは、長期的な
観点から、リスクの低減や持続可能な企業経営の安定化にも資するものであることを
認識する必要があります。
具体的には、生物多様性に影響を与えている以下のような主要な原因について、組
織の影響が及び得る事業エリア及び、その上流・下流のサプライチェーンを含めた、
より広い範囲で配慮することが望まれます。
? 過度の捕獲・採集等生物多様性に影響を与える方法で生産された原料の利用
? 生息・生育域の開発(事業所や施設の設置等)や活動(レジャー等)
? 外来生物の移入(原材料等にする生物の野生化、無計画な緑化、寄生虫・病気等)
? 遺伝子組み換え生物の移入
? 生息・生育環境の変化(化学物質や肥料等による汚染等)
また、生物多様性や生態系の保全・持続可能な利用を確保するためには、専門的な
知見が不可欠であることから、研究者や専門性の高いNGO・NPO 等、社外の専門家
との連携や、IUCN(国際自然保護連合)の「ビジネスと生物多様性:共に活動する
ためのハンドブック」(日本語版は生物多様性JAPAN 発行)等の企業向けのガイダン
スの活用等も有効と考えられます。
最近では、生物資源の持続可能な利用のために水産エコラベル*等の認証制度に取り
組む事例も増えてきています。
【情報記載にあたっての留意点】
原材料調達において、生物多様性への影響を把握することが困難な場合もあります
が、サプライチェーンマネジメントやグリーン購入・調達の観点からも、自らの購入・
調達の方針を明確にしていくことが期待されます。
MP-10:環境コミュニケーションの状況
環境コミュニケーションの取組がどのように行われ、どの程度成果を上げている
かは、環境報告として環境報告書に記載すべき重要な情報です。ここでは環境報告
書、環境ラベル*等による環境情報開示及びステークホルダーとの環境コミュニケ
ーションの実施状況等を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境コミュニケーションに関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境報告書、環境ラベル等による環境情報開示の状況
? 主要なステークホルダーとの環境コミュニケーション等の状況(例えば調査の
実施、地域住民との懇談会、定期的な訪問や報告、取引先との懇談会、ステー
クホルダー・ダイアログ、ニュースレター、ステークホルダーからの問い合わ
せへの対応等によるコミュニケーションの状況と種別ごとの回数)
? 環境報告書又はサイト単位の環境レポートを発行している事業所の状況
? 環境関連展示会等への出展の状況
? 環境関連広告・宣伝の方針及び状況
? 広告・宣伝の方法や媒体等に関する環境配慮の状況
(3) 解説
事業者が事業活動における環境配慮の取組を行うことにより、社会の信頼を勝ち
得ていくためには、社会的説明責任及びステークホルダーに有用な情報を提供する
必要性等の観点から、自ら環境に関する情報を開示し、積極的に環境コミュニケー
ションを図っていく必要があります。特に、環境報告書の作成・公表の取組や、環
境ラベルや環境広告等により、環境に関する情報を積極的にステークホルダー等に
伝えていく取組は、事業者が当然果たすべき責務の一つであると言えます。
ISO では、環境ラベルに関する規格ISO14020 シリーズで環境ラベルの一般原則と
環境ラベルの3 つのタイプを規格基準化しています。これらを参照して取り組むこと
が期待されます。
また、ISO 規格にはISO14063「環境コミュニケーション−指針及びその事例」があ
り、さまざまな環境コミュニケーションの手段が規格化されています。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 環境コミュニケーションに関する環境配慮の状況は、委託先に外注している印刷
物等(広告宣伝物を含む)も含めて記載することが期待されます。
(ii) ステークホルダーからの問い合せの状況やその対応内容等についても記載す
ることが期待されます。また、環境コミュニケーションの実績だけでなく、
これを実施した効果や、それらをどのように活用しているかを記載すること
も望まれます。
なお、環境報告書、環境ラベル等による環境情報の開示状況及びステークホ
ルダーとの環境コミュニケーション及びパートナーシップの実施状況は、それ
ぞれの業種や規模等により異なると考えられますが、それぞれの特性に応じた
環境コミュニケーション等の状況を具体的に記載することが望まれます。
実務上の留意点としては、環境ラベルを使用する際には消費者に誤認を与え
ない正確な表示を行うことが重要です。
MP-11:環境に関する社会貢献活動の状況
環境保全に関して、事業者が自ら実施する取組、従業員がボランタリーに実施す
る取組等の社会貢献活動の状況を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境に関する社会貢献活動の方針、目標、計画、取組状況、実績等
例えば、次のような情報や指標を用いて記載することが考えられます。
・ 従業員の有給ボランティア活動の状況及び延べ参加人数
・ 加盟又は支援する環境保全に関する団体(NPO、業界団体等)
・ 環境保全を進めるNPO、業界団体への支援状況、支援額、物資援助額等
・ 地域社会に提供された環境教育プログラムの状況
・ 地域社会と協力して実施した環境・社会的活動の状況
・ ステークホルダーと協力して実施した、上記以外の活動の状況
・ 環境保全活動に関する表彰の状況
・ 緑化、植林、自然修復等の状況
・ 自社で関与している財団等の助成実績等
(2) 解説
事業者が事業活動における環境配慮の取組を行うと同時に、他のさまざまなセク
ターと協働し、パートナーシップを築きながら、持続可能な循環型社会の構築に取
り組んでいくことが望まれます。その具体的な活動の一つとして、事業者や従業員
が自ら行う環境社会貢献活動、環境NPOへの支援、業界団体等での取組等があり、
このような社会貢献活動を積極的、自主的に行っていくことが必要です。
この環境に関する社会貢献活動をどのように実施しているかは、環境報告書に記
載することが望まれる重要な情報です。
【情報記載にあたっての留意点】
環境に関する社会貢献活動の状況は、事業者の業種や規模、あるいはそれぞれの
考え方等により異なると考えられますが、各事業者の特性に応じた社会貢献活動の
状況を具体的に記載することが望まれます。
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
事業者が自ら生産・販売する製品・サービス等に伴う環境負荷を削減していくこと
は、事業者にとって最も重要な使命の一つであり、持続可能な環境保全型社会、循環
型社会を構築していく上で必要不可欠な取組であると言えます。
したがって、環境負荷低減に資する製品・サービス(無形の機能・役務を含む)等
の生産・販売に積極的に取り組んでいる状況を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.環境負荷低減に資する製品・サービス等に対する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.容器包装リサイクル法、家電リサイクル法及び自動車リサイクル法等に基づく再商品化の状況
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境負荷低減に資する製品・サービス等(環境ラベル認定等製品*等)の生産
量又は販売量及び全体に占める割合、それによる環境保全効果の状況
? 省エネルギー基準適合製品*の数
? 解体、リサイクル、再使用又は省資源に配慮した設計がされた製品数
? 主要製品のライフサイクル全体からの環境負荷の分析評価(LCA)の結果
? 製品群毎のエネルギー消費効率
? 製品の使用に伴う二酸化炭素(CO2)排出総量(当年度出荷製品全体の推計及び主要製品のCO2排出係数)
? 温室効果ガスの削減に資する製品・サービスの販売量及び期待される温室効果ガスの削減量
? 教育研究機関における環境教育、環境研究の状況
? 静脈物流・流通の状況(廃棄物の輸送等)
? 金融関連機関における環境関連金融の状況(環境保全事業融資・信託、エコファンド、環境賠償責任保険等)
? サービサイジング*の取組状況
? 小売業等における環境に配慮した商品の販売や包装削減対策(マイバックの推進活動)等
? 旅行業・ホテル業等におけるエコツーリズム*、エコホテルの取組の状況等
(3) 解説
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の規定による対象機器、使用済
自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)、 容器包装に係る分別収集
及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)等においては、自らが
生産・販売した製品等のリサイクル等が求められており、いわゆる拡大生産者責任への
対応が必要となってきています。これらのリサイクル法への取組状況や該当するその他
のリサイクル法に基づく取組の状況についても記載することが期待されます。
他方、事業者自身の環境経営、特にエコビジネスの推進という観点からも、製品・サ
ービス等の環境負荷低減は必須の取組であると言えます。事業者が生産・販売する環境
負荷低減に資する製品・サービス等の種類は多岐に渡り、その状況はそれぞれの業種、
規模等により異なると考えられますが、それぞれの特性に応じた取組状況をOP-5の総
製品生産量又は総商品販売量に対する割合や、それによる環境保全効果(推計を含む)
の概要等を具体的に記載することが望まれます。
さまざまな環境負荷を大幅に低減するためには、素材・部品・製品等の製造段階での
取組だけでは不十分であり、その上流側(企画・開発、設計、調達等の段階)や下流側
(輸送、販売、使用・利用、あるいは廃棄・回収等の段階)を含めた、あらゆる製品・
サービス等のライフサイクルにおける環境負荷低減の取組が必要です。これを事業者か
らみると、提供する製品・サービス等の環境負荷を低減することが市場から求められて
いるわけで、商品市場のグリーン化ということができます。
これは多様な領域・分野において環境ビジネスが可能なことを物語っていますが、近
年では汚染を防止する装置や設備、製品以外のさまざまな技術・ソフト・サービス系の
環境ビジネスが隆盛を見せています。
これらは全般的に新しい環境ビジネスであり、環境ISOの導入や環境報告書の作成支援、環境会計のコンサルティングや環境情報サービス、環境格付等が挙げられます。温室効果ガスの排出量検証や京都メカニズムの活用に
よる排出量取引あるいはCDMの有効化審査等も温室効果ガス削減費用を社会全体で最
小化するためのサービスです。
また、廃棄物の広域輸送や有害物回収事業等の“静脈物流”、詰替え・量り売りや中
古品再生販売、家電修理等や環境装置リースや家電レンタル等のサービサイジングの取
組も、直接・間接を問わず循環型社会形成に貢献するものです。さらにエコツーリズム
は人々の環境意識の向上に資するものですし、学校法人等の環境教育は環境意識の高い
人材を育成するものです。このように環境配慮型のサービス・役務等のビジネスモデル
には際限がないと言っても過言ではありません。
国等においては、グリーン購入法により、環境に配慮した物品やサービス等を優先
的に購入・調達してきました。さらに、環境配慮契約法が2007 年5月に成立し、国
等が電気を購入したり、庁舎を建設したりする際の契約についても、温室効果ガス等
の排出の削減への配慮が求められることとなりました。
【情報記載にあたっての留意点】
(i) 事業者の製品・サービス等に係る環境負荷の低減に資する取組について記載しま
す。リサイクルへの取組の他、環境ビジネスの推進等、本業についても、記載す
ることが期待されます。
(ii) 金融機関等による環境配慮型の金融商品としては、損害保険会社による土壌汚染
に対する環境賠償責任保険、銀行の環境に配慮した行動を取る企業に対する金利
優遇や環境保全事業に対する金利優遇、エコファンド(環境にも配慮した投資信
託)等があります。これらの金額を指標とすることが考えられます。
(iii) 銀行、証券、保険等の金融機関、流通・小売業、運送業、商社等においては、直
接的な生産活動を行っていない場合が多いことから、自らのサービスに係る環境
配慮の取組について、その業種特性に応じた記述の工夫が求められます。例えば、
金融機関等においては、投融資にあたっての環境配慮について記載することが望
まれます。最近では、環境関連融資を通じて融資先の事業者が実際に達成した環
境負荷削減の効果を定量的に評価する金融機関も見受けられます。
(iv) 環境ラベル認定等製品については、環境ラベルのタイプ・種類を明確にし、該
当する製品の重量又は個数、面積、容積等で把握します。
(v) 容器包装リサイクル法の再商品化義務量は、対象となる容器包装の製造量及び
利用量を集計します。
3.「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標(OPI)
環境報告に記載する「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」
を表す環境報告の情報・指標(オペレーション指標:OPI)は以下の10 項目です。
本節では、それぞれの基本的な考え方や記載が望まれる具体的な情報・指標等につい
て解説します。
(オペレーション指標:OPI)
【インプット】
OP-1:総エネルギー投入量及びその低減対策
OP-2:総物質投入量及びその低減対策
OP-3:水資源投入量及びその低減対策
【内部循環】
OP-4:事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
【アウトプット】
(製品・商品)
OP-5:総製品生産量又は総商品販売量
(排出物・放出物)
OP-6:温室効果ガスの排出量及びその低減対策
OP-7:大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
OP-8:化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
OP-9:廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
OP-10:総排水量等及びその低減対策
(注)
地域への影響が大きいと考えられるOP-3(水資源投入量)、OP-7(大気汚染、生
活環境に係る負荷量)、OP-8(化学物質の排出量、移動量)、OP-10(総排水量)
等の項目については個別事業所毎の数値を公表することが期待されます。
OP-1:総エネルギー投入量及びその低減対策
石油、天然ガス、石炭等の化石燃料の使用に伴い、地球温暖化の原因となる二
酸化炭素(CO2)が排出されます。このため総エネルギー投入量及び内訳と、その
低減対策、さらにエネルギー生産性及び事業エリア内で事業者が自ら行った自家
発電量等を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.総エネルギー投入量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.総エネルギー投入量(ジュール)
ウ.総エネルギー投入量の内訳(種類別使用量)(ジュール)
・購入電力(購入した新エネルギー*を除く)
・化石燃料(石油、天然ガス、LPG、石炭等)
・新エネルギー(再生可能エネルギー*、リサイクルエネルギー、従来型エネルギーの新利用形態)
・その他(購入熱等)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 熱循環型の自家発電の状況及びその拡大策と将来計画・目標
? エネルギー自給量・回収量のエネルギー源別内訳(ジュール又はその他の単位)
・化石燃料
・新エネルギー
・コージェネレーション
・その他
? エネルギー生産性、エネルギー利用効率及びその向上対策
(3) 解説
我が国では、化石燃料の使用によるCO2 の排出量が、CO2 排出量全体の約9割を
占めています。地球温暖化の防止に向けては、総エネルギー投入量を削減するとと
もに、太陽光発電、風力発電、バイオマスエネルギー等を含む新エネルギーの一層
の導入を促進する等、よりCO2 排出の少ないエネルギーへの転換が必要になっています。
このため、総エネルギー投入量を把握・管理することとします。併せて、環境配慮
分を含む投入エネルギーの内訳を把握することも重要です。
また、最近では事業所内で使用するエネルギー源として事業所内の余剰エネルギ
ーないし回収せずに放出していた熱源を有効利用する動きが顕著となってきていま
す。事業所内でさまざまな未利用のエネルギー源を用いて自家発電を行い、自ら利
用すると同時に電力会社へ売電するところも出てきています。このように外部から
の買電とは別に、自家発電等もエネルギー使用量の低減につながることが期待されます。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 総エネルギー投入量は、電気及び各燃料等の使用量をそれぞれ把握し、「エネルギ
ーの使用の合理化に関する法律施行規則 別表第1、別表第2、別表第3」に定め
られた熱量換算係数により算出します。「エネルギー源別発熱量表」において定め
のない新エネルギー等の算出にあたっては、換算係数の出典を記載します。
(ii) 購入電力量(kWh)を発熱量(J)に換算する場合の換算係数は、「エネルギーの使用
の合理化に関する法律施行規則 別表第3」に基づき、昼間の電気については
9.97MJ/kWh、夜間の電気については9.28MJ/kWh を用いることとします。
なお、「昼間」とは、午前8時から午後10時までをいい、「夜間」とは、午後10
時から翌日の午前8時までをいいます(「エネルギーの使用の合理化に関する法律
施行規則 別表第3 備考2」)。 なお、昼間・夜間の区別ができない場合は、すべ
ての電気使用量を昼間として算定します(資源エネルギー庁「エネルギーの使用の
合理化に関する法律第15条に基づく定期報告書記入要領(平成18年4月)」)。
(iii) 総エネルギー投入量と併せて、電気及び燃料等の使用量の内訳も把握することが
望まれます。
(iv) 総エネルギー投入量には、直接行う輸送等に係る燃料消費量は含めますが、外部
に委託した製品等の輸送に伴う燃料消費量は別に把握することとして、含めません。
(v) 製品の製造において原材料等として投入される石油、石炭等は、総物質投入量と
して把握します。
(vi) 投入したエネルギー量の内訳については、それぞれのエネルギー源に応じた適切
な単位で把握しても構いません。
(vii) 購入した新エネルギー(風力発電による電力等)は、購入電力には含めず、新エ
ネルギーの内数として把握します。
(viii)余剰電力の売電量については、購入電力量と相殺することができます。又は、そ
の発電のために要した化石燃料の量を算出し、化石燃料投入量から差し引くこと
もできます。ただし、発電のために要した燃料が購入電力の発電のために要した
燃料と異なる場合には、購入電力と相殺せず、別途把握し併記することが望まれます。
(ix)参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-2:総物質投入量及びその低減対策
自然界からの資源(天然資源)の採取量は年々増加しており、この資源を、枯
渇性のものから再生可能なものへと質の転換を図りつつ、枯渇性天然資源の消費
を抑制するとともに、使用済みの資源の循環的な利用*(再使用*、再生利用*、熱
回収*)を進めながら、総物質投入量*を低減することが、持続可能な社会の形成
の観点から必要になります。
このため、総物質投入量及び内訳とその低減対策、さらに資源生産性及び循環
利用率を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.総物質投入量(又は主要な原材料等の購入量、容器包装材を含む)の低減対策
及び再生可能資源や循環資源の有効利用に関する方針、目標、計画、取組状況、
実績等
イ.総物質投入量(又は主要な原材料等の購入量、容器包装材を含む)(トン)
ウ.総物質投入量の内訳(トン)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 資源生産性及びその向上対策
? 循環利用率、循環利用率の向上対策
? 製品・商品以外の消耗品等として消費する資源(容器包装のための資材を除く)の量
? 自ら所有する資本財として設備投資等に投入する資源の量
? 請け負った土木・建築工事等に投入する資源の量
? 製品群毎の再使用・再生利用可能部分の比率
? 使用済み製品、容器・包装の回収量
? 回収した使用済み製品、容器・包装の再使用量、再生利用量、熱回収量及び各々の率
(3) 解説
自然界からの資源(天然資源)の採取量は年々増加しています。わが国の平成16
年度(2004 年度)の社会経済活動に伴う総物質投入量は19.4 億トンに及びます。
そのうち天然資源採取量は17.0 億トンですが、再生利用されている資源は2.5 億ト
ンであり、総物質投入量の1 割超です。
総物質投入量は、その内訳として天然資源の消費を抑制しつつ、循環資源を有効
に利用していくことが必要な指標であることから、資源の種類の内訳、資源投入時
の状態の内訳、天然資源、循環資源等の投入量等も把握することが望まれます。天
然資源については、枯渇性のものから更新性のものへの転換を図りつつ、枯渇性天
然資源の消費の抑制を図りつつ、総物質投入量を削減することが必要です。
また、「循環型社会形成推進基本計画」においては、持続可能な生産・消費形態
への転換を目指して、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るため、天然資源の投入から廃棄に至るまでの社会における物の流れを見渡し、そ
の流れを適正なものに変えていくことで、経済的な豊かさを保ちつつも環境への負
荷を低減する目標を設定しています。そして物質フロー目標として、資源生産性、
循環利用率及び最終処分量の3つを掲げており、これらの目標は、各事業者の取組
においても、最大限尊重されるべきものであると言えます。
なお、事業者として事業活動における環境配慮の取組についての方針を検討する
にあたっては、LCA 的アプローチが求められるようになってきています。アウトプ
ットだけでなく、インプットの段階から内訳を含めて全体的に把握することが重要
となります。
総物質投入量は、投入資源の管理、排出物の発生抑制の観点から将来重要になる指
標と考えられます。事業の内容によっては集計が極めて困難ではありますが、算定可
能な資源についての投入量を把握するところから段階的に取組を進めるとともに、業
態又は企業にとって適切な算定方法の開発に取り組むことが期待されます。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 総物質投入量は、エネルギー及び水を除く資源で、事業活動に直接投入された物
質の合計、主な種類の内訳、資源投入時の状態の内訳、天然資源の投入量、主要
な原材料等及び製品・商品の購入・仕入量をトン単位で把握します。
(ii) 記載単位は、内訳については、重量(単位はトン)以外の単位で管理することが
適切な場合には、実務上用いられている単位によることができます。
(iii) 総物質投入量の主な種類の内訳には、金属、プラスチック、ゴム等の資源の種類
別の量及び割合を可能な限り記載します。主要な原材料等及び商品のみを記載す
る場合は、対象外とした原材料等又は製品・商品(容器包装を含む)の主な内容、
対象とした主要な原材料等又は製品・商品の購入・仕入金額に対する総購入・仕
入高に占める割合を記載します。以下に分類の例を示しますが、事業者の実情に
合わせて、合理的な分類を選択して記載することが期待されます。
<資源の種類別投入量の内訳>
○資源の種類(トン又はその他の単位)
? 金属(鉄、アルミニウム、銅、鉛等)
? プラスチック
? ゴム
? ガラス
? 木材
? 紙
? 農産物 等
○投入時の状態(トン又はその他の単位)
? 部品、半製品、製品、商品
? 原材料
? 補助材料
? 容器包装材
○その他の指標(トン又はその他の単位)
? 枯渇性天然資源(化石資源、希少鉱物等)
? 循環資源
? 更新性天然資源(適切に管理された農林水産物等)
? 化学物質(PRTR 対象物質等)
(iv) 資源生産性は総売上高を総物質投入量で除して算出します。
(v) 総物質投入量には、購入・仕入以外の消耗品等として消費する資源(容器包装の
ための資材を除く)の量、資本財として設備投資等に投入される資源の量、事業
者の内部で循環的な利用が行なわれている物質を含めません。ただし、総物質投
入量とは別に記載することができます。
(vi) 部品・半製品・製品については、それを構成する資源の種類を把握することが望
まれます。それが困難な場合には、総重量で集計する方法もあります。
(vii) 総物質投入量を把握するのが困難な場合には、総製品生産量又は総商品販売量と
廃棄物等総発生量を足し合わせて算出する方法もあります。
(viii) グリーン調達については、事業者が製品・サービス等を提供するために購入した
材料のうち、環境配慮型であると自らが判断した物の投入量を把握します。ただ
し、その判断基準を明らかにすることが必要です。自家消費の分は、グリーン購
入(環境配慮型製品・サービス等の購入量等)として、別途把握することとしま
す(参照:MP-6)。
(ix) 循環利用率は、循環利用量を総物質投入量で除して算出します。
(x) 回収量は、他社の製品及び商品並びに容器包装の回収を含めて、原則としてトン
単位で記載します。ただし、実務上用いられているその他の単位で記載すること
ができます。
(xi) 返品された製品については、OP-5 で区分して把握します。
OP-3:水資源投入量及びその低減対策
水資源は人間を含めた生物の生存に不可欠な要素であり、社会経済システムの
存立基盤でもあります。
このため、水資源投入量及び内訳と、その低減対策を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.水資源投入量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.水資源投入量(?)
ウ.水資源投入量内訳(?)
・上水
・工業用水
・地下水
・海水
・河川水
・雨水 等
(2) 解説
地球上に存在する水資源のうち淡水は約2.5%ですが、飲料、生活用水、生産活
動に利用可能な河川、湖沼、地下水等は約0.8%に過ぎません。水の循環利用と希
少な水資源利用の効率化を進めることが課題となっています。
このため、水資源投入量を把握・管理することとします。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 水資源投入量には、事業所内で循環的に利用している量は含めません。別途「循
環的利用を行っている物質量等(OP-4)」として把握することとします。ただし、
水資源の希少性から事業者内部での循環的利用量の把握は極めて重要です。
(ii) 水資源投入量と併せて、水源ごとの投入量も把握することが望まれます。
(iii) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-4:事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等
事業エリア外からの総物質投入量とは別に、事業エリア内で事業者が自ら実施
する循環的利用型の物質量等を記載します。また、我が国では水資源の枯渇の実
感は乏しいものの、世界的には特定の途上国や砂漠地帯を中心に水資源の枯渇が
危惧されています。そこで、事業所内における上水の循環的再利用の普及や中水・
雨水の利用が強く求められています。
(1) 記載する情報・指標
ア.事業エリア内における物質(水資源を含む)等の循環的利用に関する方針、目
標、計画、取組状況、実績等
イ.事業エリア内における循環的に利用された物質量(トン)
ウ.事業エリア内における循環的利用型の物質の種類と物質量の内訳(トン)
エ.事業エリア内での水の循環的利用量(立方メートル)及びその増大対策
オ.水の循環的利用量(立方メートル)の内訳
・水のリサイクル量(原則として、冷却水は含まない)
・中水*の利用
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 事業エリア内で再使用された資源の量
? 事業エリア内で再生利用された資源の量
? 事業エリア内で熱回収された資源の量
(3) 解説
循環資源の投入量を増大させ、循環資源利用率を高めていくことは、循環型社会形
成推進基本計画の中でも強調されているように、天然資源の消費を抑制し、持続可能
な循環型社会の構築を図っていく上で、極めて重要です。
天然資源については、枯渇性天然資源の消費を抑制するとともに、使用済みの資源
の循環的な利用(再使用、再生利用、熱回収)を進めることが、持続可能な社会形成
の観点から必要になります。
また、水資源についても、希少な水資源の利用の効率化を進めることが課題となっ
ています。そこで効率の良い水資源の利用が求められますが、事業所外からの投入
水資源量を削減するだけでなく、事業所内での水資源の循環利用率を高めていくこと
は、持続可能な循環型社会の構築を図っていく上でも極めて重要です。とりわけ、最近
では一度使用した上水を事業所内で処理して循環利用する中水の利用が普及しつつあ
ります。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 循環的利用を行っている物質の種類別内訳は、OP-2:総物質投入量とOP-9:廃
棄物等総排出物、廃棄物最終処分量の【指標算定にあたっての留意点】を参照し
てください。
(ii) 製紙業等において再利用する“黒液”の量は含まれます。
(iii) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-5:総製品生産量又は総商品販売量
総製品生産量又は総商品販売量は、マテリアルバランスの観点から、アウトプ
ットを構成する指標として重要です。この指標は、総エネルギー投入量、水資源
投入量、温室効果ガス排出量、化学物質排出量、廃棄物等排出量、総排水量の環
境への負荷を評価する際にも必要な指標です。
このため、総製品生産量又は総商品販売量、容器包装使用量に関する情報を記
載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.総製品生産量又は総商品販売量
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 容器包装使用量
(3) 解説
社会全体での環境負荷の低減や循環型社会の形成の観点から、使用の段階でエネ
ルギー消費量や廃棄物の発生量が少なく、使用後に循環利用が可能な製品の生産量
又は販売量の増大が期待されています。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 総製品生産量又は総商品販売量は、いずれを把握しても良いものとします。総商
品販売量は主要な製品及び商品の販売量の合計をトン単位で記載します。
(ii) 主要な製品及び商品の販売量のみを記載する場合、対象外とした製品及び商品の
主な内容、対象とした主要な製品及び商品の売上高が総売上高に占める割合を記
載します。
(iii) 期首と期末の原料・半製品・製品の重量に大きな差異がある場合は、総物質投入
量とのマテリアルバランスを考慮する上で、期首と期末の在庫増減重量を記載す
ることが望まれます。
OP-6:温室効果ガス*の排出量及びその低減対策
地球温暖化が進行すると、海面上昇による水害、農産物生産量の減少、伝染病の
伝染範囲の拡大、生息環境の変化による一部野生生物の絶滅等、深刻な影響が生じ
るおそれがあります。それゆえ、大気中の温室効果ガスの安定(地球温暖化防止)と
いう気候変動枠組条約の究極目的を達成するために、その第3回締約国会議で京都議
定書(2005 年2 月16 日発効)が採択されました。京都議定書の数値目標を達成する
ために、事業者として温室効果ガスの排出削減活動を主体的に行う必要があります。
このため、温室効果ガス排出量(トン-CO2 換算)、すなわち京都議定書対象6物
質のそれぞれの排出量及び排出活動源別の内訳と、その低減の基本方針と対策を記
載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.温室効果ガス等排出量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.温室効果ガス(京都議定書6物質)の総排出量(国内・海外別の内訳)(トン-CO2換算)
ウ.温室効果ガス(京都議定書6物質)の種類別排出量の内訳(トン-CO2換算)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 温室効果ガス(京都議定書6物質)の排出活動源別排出量の内訳(事業所別、事業者別)(トン-CO2換算)
? 京都メカニズム*を活用している場合には、その内容、削減量(クレジット量)
? 自主参加型国内排出量取引制度に参加している場合には、その内容と削減量
? 温室効果ガス排出量の算定を担保する仕組み(第三者検証、ISO14064(温室効果ガス排出・削減量の算定・報告・検証に関する規格)等)を利用した場合には、その内容と削減量
? 購入電力の排出係数の推移・見通し
(3) 解説
地球温暖化は、二酸化炭素(CO2)やメタン等の温室効果を有するガスが人間活動
の拡大に伴って大気中に大量に排出され、その大気中濃度の上昇に伴い地球全体と
しての平均気温が上昇する現象です。
この大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的として「気候変動枠組条
約」が、1992年に署名開始(日本は1992年署名)、1994年に発効しています。この気
候変動枠組条約の目的を達成するために、1997年に京都でCOP3(気候変動枠組条約第
3回締約国会議)が開催され、そこで採択された取り決めが「京都議定書」(日本は20
02年6月4日批准)です。これは、先進国等に対し温室効果ガスを第1約束期間(2008
年〜2012年)に1990年を基準年として一定数値(日本は6%)削減することを義務づけ
ています。ロシアの批准により発効要件が満たされ、2005年2月16日に発効し、我が国
も京都議定書の目標を達成することが義務づけられました。この削減目標を達成するた
めに、京都メカニズム等が導入されています。
特にCO2は、我が国の温室効果ガス排出量全体の約9割という最も大きな割合で
地球温暖化に寄与しており、石炭・石油等の化石燃料の燃焼により大量に排出され
ています。
温室効果ガス排出量は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の合計、主な内訳
を二酸化炭素量に換算しトン(以下「トン-CO2換算」という。)単位で記載します。
ただし、CO2以外の温室効果ガスの排出量が僅少である場合には、CO2排出量のみを
記載することができます。
温室効果ガス排出量の主な内訳には、温室効果ガスの種類別の内訳及び集計対象
とした排出活動の内訳を可能な限り記載します。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温暖化対策推進法)に基づき、
平成18年4月1日から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの
温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。報告の
対象となる温室効果ガスは、エネルギー起源CO2及び非エネルギー起源CO2、メ
タン、一酸化二窒素、代替フロン等3ガス(HFC:ハイドロフルオロカーボン、
PFC:パーフルオロカーボン、SF6:六ふっ化硫黄)です。
(ii) 温室効果ガス排出量の算定方法の詳細については、環境省の「温室効果ガス排出量
算定・報告マニュアル」(2006年11月公表)を参照してください。
(参考)環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」
http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual/index.html
(iii) 温室効果ガスの排出削減のための個別対策の導入による削減効果を評価する方法
については、対策の種類によってさまざまな考え方がありますが、個々の対策の実
態に即した合理的な方法により評価する必要があります。例えば、対策前の排出量
と対策後の排出量の差を求める方法の他、対策によって削減効果が見込まれる期間
に影響を受ける電源が想定できる場合には当該電源の排出係数を電気の削減量に
乗じて算定する方法等があります。
(iv) 温室効果ガスの削減量について環境報告書に記載する際には、算定に用いた式と排
出係数を併せて記載し、算定根拠を明らかにすることが必要です。
(v) 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」による報告義務があ
る特定排出者が、エネルギー起源CO2の排出量を報告している場合は、温暖化対
策推進法に基づく報告とみなされます。ただし、その場合でも、エネルギー起源
CO2 以外のガスについて報告の対象となっている場合には、温暖化対策推進法
に基づく報告・公表が必要です。
(vi) 海外における排出分について、当該国において排出係数が定められている場合に
は、それに基づき算定します。
(vii) HFC については、OP-8 化学物質の排出量(フロン類)としても把握します。
(viii) 京都メカニズムを活用したCO2 排出削減量については、事業者の直接の排出抑
制ではないことから、別途把握することとします。
(ix) 温室効果ガスの排出活動源別の排出量の内訳についても、以下のような項目を記
載することが期待されます。
・ 事業エリア内でのエネルギー消費
・ 輸送に伴う燃料使用
・ 廃棄物処理
・ 工業プロセス
・ その他
(x) 総エネルギー投入量が購入電力のみの場合は、エネルギー起源CO2 の排出量と合
わせて記載することができます。
(xi) 電力由来の温室効果ガスの排出量を算出する際に、対象年度の電力のCO2 排出係
数が電力会社から公表されていない場合は、直近の公表数値を活用します。その
場合は、次年度以降の複数期間を同時に報告する際に、新たに公表されたCO2 排
出係数を用いて、対応する年度に関して改めて排出量を算出するという考え方が
あります。
(xii) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-7:大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
排出規制項目の遵守状況を始めとして、大気汚染物質の排出の状況及びその防止
の取組について記載します。さらに、騒音、振動、悪臭の発生の状況並びにその低
減対策についても記載します。また、ヒートアイランド現象の緩和等による都市の
熱環境改善の取組についても記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)排出量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.大気汚染防止法に基づく硫黄酸化物(SOx)排出量(トン)、窒素酸化物(N
Ox)排出量(トン)、揮発性有機化合物(VOC)排出量(トン)
ウ.騒音規制法に基づく騒音等の状況(デシベル)及びその低減対策
エ.振動規制法に基づく振動等の状況(デシベル)及びその低減対策
オ.悪臭防止法に基づく悪臭等の状況(特定悪臭物質濃度または臭気指数)及びその低減対策
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 屋上、壁面及び敷地内の緑化や高反射性塗装、保水性舗装等、都市表面被覆の改善につながる建物、構造物への環境対策の状況
? 地中熱や河川水等を活用した空調排熱等、大気中への人工排熱の排出削減につながる建物等への環境対策の状況
(3) 解説
一酸化窒素や二酸化窒素等の窒素酸化物(NOx)は、主に物の燃焼に伴って発生し、
その主な発生源は工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。(移動発生
源についてはMP-8 を参照してください)NOx 及び揮発性有機化合物(VOC)は光化
学オキシダント、浮遊粒子状物質(SPM)、酸性雨の原因物質となります。
騒音・振動は、その発生源の周辺地域に限定的に存在する物理現象ですが、人の活
動する範囲で広く存在するため、工場・事業場、建設作業や自動車、航空機、鉄道等
の交通による騒音・振動が及ぼす影響から生活環境を保全することは大きな課題とな
っています。
騒音の苦情件数はここ数年増加していますが、発生源別にみると、工場・事業場に
係る苦情の割合が3 割以上、建設作業に係る苦情の割合が3 割弱を占めています。近
年では、低周波音も大きな問題となっています。また、振動の苦情件数を発生源別に
みると、建設作業振動に対する件数が最も多く、工場・事業場振動に係る件数がそれ
に次いでおり、苦情原因として依然大きな割合を占めています。
悪臭の苦情件数は昭和47 年をピークに減少傾向にありましたが、ここ数年は増加傾
向にあります。発生源別にみると、畜産農業や製造工場等、かつて問題となっていた
業種に係る苦情は横ばいで推移していますが、近年、サービス業等に係る苦情が増加
する傾向にあります。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 騒音、振動、悪臭については都道府県知事により指定された地域の場合に該当します。
(ii) SOx、NOx ならびにVOC については、参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-8:化学物質*の排出量、移動量及びその低減対策
わが国では現在、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質
審査規制法)」、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「PCB廃棄物適正
処理特別法」、「ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン法)」等により、
それぞれの法律で指定された化学物質の製造、輸入、使用、処分方法、排出量等
が規制されています。また、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)」では、上記の規制
対象物質を含む幅広い化学物質について、環境への排出量及び廃棄物としての移
動量等の把握・届出(PRTR制度*)、化学物質等安全データシート(MSDS)の
提供が義務付けられ、化学物質の管理とリスクコミュニケーションの推進が責務
とされています。
これらの法律の適用を受ける化学物質は勿論のこと、事業者が自主的に管理の
対象としている化学物質についても、化学物質ごとにそれぞれの排出量、移動量
と、その管理状況を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.化学物質の管理方針及び管理状況
イ.化学物質の排出量、移動量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
ウ.より安全な化学物質への代替措置の取組状況、実績等
エ. 化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制度の対象物質の排出量、移動量(トン)
オ.大気汚染防止法に基づく有害大気汚染物質のうち指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)の排出濃度
カ.土壌・地下水汚染状況
キ.ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類による汚染状況
ク.水質汚濁防止法に基づく排出水及び特定地下浸透水中の有害物質の濃度
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 化学物質の製造・輸入量、取扱量、平均保管量、最大保管量(トン)、用途等
? 化学物質に関するリスクコミュニケーションの状況(説明会の開催回数等)
? 「Japanチャレンジプログラム*」の対象物質の取扱状況及び安全性情報収集状況
? 取り扱っている化学物質の安全性情報の収集、リスク評価の実施(物質名、物質数等)
? 川上(化学物質製造事業者等)から川下への化学物質有害性情報に係る伝達の方針及び取組状況
? 川下から川上への化学物質の用途情報に係る伝達の方針及び取組状況
(3) 解説
現代社会では、多種多様な化学物質が大量に製造されさまざまな場面で幅広く利
用されています。また、ダイオキシン類等のように、非意図的に生成される化学物
質もあります。化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な
管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を
及ぼすおそれがあるものがあります。
事業活動に対する信頼性を高めるとともに、化学物質管理に対する姿勢・努力に
対する社会的評価が可能となるよう、事業者は、説明会の開催等を通じてリスクコ
ミュニケーションを行うことが重要であり、個々のPRTR対象物質について排出量及
び移動量を公表し、その中で重点的に取り組んでいる対策についても説明すること
が望まれます。
欧州では、家電・電子機器に含まれる特定有害物質の使用が禁止(RoHS指令)され
るとともに、化学物質の総合的な登録・評価・許可・制限の制度(REACH)が始まる
等、国内外で有害物質に関する規制が厳しくなってきています。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 化学物質に関する情報を記載する際には、取扱量や購入量が多いもの、あるい
は危険性が高い等、ステークホルダーへの影響が大きいと考えられる化学物質
のみについて、物質毎に排出量、移動量等を区別して記載します。さらに平均
保管量、最大保管量についても記載することが期待されます。
(ii) PRTR 対象物質の排出量及び移動量の把握方法には次の5つの方法があります。
? 物質収支を用いる方法
? 排出係数を用いる方法
? 実測値を用いる方法
? 物性値を用いる方法
? その他の方法
(iii) PRTR 対象物質の算定方法の詳細については、経済産業省・環境省の「PRTR 排
出量等算出マニュアル」(2004 年1 月最終改訂)を参照してください。
(iv) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回
収・破壊法)で対象としているフロン類については、排出量(漏洩量を含む)、回
収量(フロン回収・破壊法に基づき回収業者に引き渡した量)、破壊量(フロン回
収・破壊法に基づき破壊業者に引き渡された量。回収量の内数)についても、可
能な限り把握します。なお、排出量についてはCFC、HCFC はPRTR 対象物質
として、HFC は温室効果ガスとしても把握します。
(v) その他の化学物質の排出量及び法律に規定された物質ごとの排出量を把握するこ
とが求められます。
(vi) 土壌汚染・地下水汚染の状況については、土壌汚染対策法に基づく調査や自主的
に実施した調査の状況について記載することが期待されます。
(vii) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-9:廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
我が国の廃棄物量は、1960年代以降増加を続け、1990年代に入り高水準のまま
ほぼ横ばいで推移しています。近年最終処分場の残余容量が逼迫する一方、処分
にかかる費用の高騰、不法投棄といった問題が引き起こされています。そこで、
廃棄物等*の発生の抑制、循環利用、適正処分が急務となっています。
このため、廃棄物等排出量及び廃棄物*の処理方法の内訳、さらには廃棄物の処
理方法の中でも、最終処分場の不足及び不法投棄の問題を鑑み廃棄物最終処分量
及びその低減対策を記載します。
(1) 記載する情報・指標
ア.廃棄物等の発生抑制、削減、リサイクル対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.廃棄物の総排出量(トン)
ウ.廃棄物最終処分量(トン)
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 拡大生産者責任に対する対応
? 廃棄物等の処理方法の内訳
? 廃棄物等総排出量の主な内訳(有価物を含む)
? 廃棄物最終処分量の内訳
・直接埋立処分される産業廃棄物量(マニフェスト*で把握する最終処分量)
・産業廃棄物*で埋立処分が予想される中間処理後残渣量及び再資源化に伴う残滓量
・一般廃棄物*で埋立処分される量と中間処理・再資源化後埋立が予想される量
・自社の最終処分場に埋立処分した廃棄物量
? 発注者として建設廃棄物の削減・再資源化等に対する対応
? マニフェスト交付枚数及び電子マニフェスト利用状況
(3) 解説
環境基本計画及び循環型社会形成推進基本法にも示されている通り、廃棄物・リ
サイクル対策は、第一に廃棄物等の発生抑制(リデュース)、第二に使用済製品、
部品の再使用(リユース)、第三に回収されたものを原材料として利用する再生利
用(マテリアルリサイクル)、第四に熱回収(サーマルリサイクル)を行い、それ
でもやむを得ず廃棄物となるものについては、適正な処分を行うという優先順位を
念頭に置くこととされています(ただし、廃棄物以外の環境負荷とトレードオフと
なる可能性があることから、この順によらない場合もあります)。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 廃棄物等総排出量は、事業活動に伴い発生した廃棄物等の排出量の合計、主な
内訳をトン単位で記載します。廃棄物等総排出量は、事業者がその敷地外(管
理外)に、排出・搬出したもの(製品・サービス等の提供に伴い出荷したものを
除く。)及び敷地内で埋め立てたものの重量をすべて合計して算出します。
(ii) 廃棄物の廃棄物等総排出量の主な内訳には、一般廃棄物(そのうちの特別管理
一般廃棄物)、産業廃棄物(そのうちの特別管理産業廃棄物*)の別を記載しま
す。なお、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物については、ステークホ
ルダーの判断に影響を与える可能性がある場合には、その内容、事業活動との
関連による主な発生要因、処分状況を記載します。
(iii) 廃棄物最終処分量は、廃棄物等の埋立処分量及び埋立が予想される中間処理・
再資源化後の残渣や残滓を含み、内訳をトン単位で可能な限り記載します。た
だし、一般廃棄物の排出量が僅少である場合には、産業廃棄物管理票により集
計した産業廃棄物の埋立処分量と中間処理・再資源化後の残渣や残滓量のみを
記載することができます。
(iv) 廃棄物最終処分量の内訳では、自社の最終処分場に最終処分(埋立等)された自
社の廃棄物の重量を合計して算出します。
(v) 廃棄物最終処分量には、埋立処分が予想される再利用、再生利用、熱回収及び単
純焼却*の際の残渣や残滓も含まれますが、直接最終処分される量とは区別して
把握、開示します。残渣や残滓の量を把握できなかった場合は、その旨を明らか
にする必要があります。
(vi) 廃棄物等の処理方法の内訳について、バイオマス発電施設への搬入等、最終処
分の埋立て量や焼却量を軽減する取組の状況等についても記載します。
(vii) 廃棄物等の処理方法の内訳には、再使用される循環資源の量、再生利用される
循環資源の量、熱回収される循環資源の量、熱回収を伴わない単純焼却される
廃棄物の量があります。
(viii) 循環的な利用量には、事業者の敷地内で循環的な利用がなされている物質は含
めません。事業者の敷地内で再使用、再生利用される循環資源については、
「OP-4:循環的利用を行っている物質等」に記載します。
(ix) 再使用、再生利用される循環資源は、事業者がその敷地外(管理外)に、排出・
搬出した循環資源のうち再使用・再生利用したものの重量を合計して算出します。
(x) 工場・事業場の施設や設備等の建て替え、廃棄等に伴う建設廃材は、生産財、資
本財としての性格を有するため、建て替えや廃棄等を行う年度に突出して排出量
が増えるといった変動要因が多いことから、廃棄物総排出量に含めず、分けて把
握し、その総発生量の注記が望まれます。
(xi) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
OP-10:総排水量等及びその低減対策
事業所からの排水や一般家庭からの生活排水による水質汚染は、人の健康への
被害を与え、また魚介類等生態系、水道水質等の生活環境へ影響を及ぼしてきま
した。公共用水域への有機汚濁物質等による汚染に関しては、環境基準が未達成
の水域が存在します。
このため総排水量、排出先ごとの排水量と水質及びその低減対策を記載しま
す。
(1) 記載する情報・指標
ア.総排水量の低減対策に関する方針、目標、計画、取組状況、実績等
イ.総排水量(立方メートル)
ウ.水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく排水規制項目(健
康項目*、生活環境項目*、ダイオキシン類)の排出濃度(平均値、最大値)並
びに水質汚濁防止法等の総量規制対象項目で示した汚濁負荷量、並びにその低
減対策
エ.排出先別排水量の内訳(立方メートル)
・河川
・湖沼
・海域
・下水道等
(2) 記載することが期待される情報・指標
? 海や河川湖沼等の水利用(主に熱交換として)における温排水・冷排水の利用量及び平均温度差
(3) 解説
水は、雨となって地上に降り、森林や土壌を経て、地下水として保水され又は河
川を通って海に注ぎ、蒸発して再び雨になるという循環過程の中にあります。健全
な水循環の確保及び水質の維持のために、水利用に伴う環境への負荷を管理するこ
とが必要です。水質の汚濁については、人の健康を保護し、及び生活環境を保全す
る上でそれぞれ維持することが望ましい基準として、環境基準が設定されています。
環境基準の達成や、水質汚染の未然防止を目的として、水質汚濁防止法に基づき、
工場及び事業場からの排水について、健康項目27 項目、生活環境項目15 項目の排
水基準が定められています。
【指標算定にあたっての留意点】
(i) 総排水量は、事業活動に伴い発生した排水量の合計、主な内訳を立方メートル
単位で記載します。総排水量の主な内訳には、河川、湖沼、海域、下水道等の
排出先別に記載します。
(ii) 水資源投入量には、製造過程に使用されなかった場合も含め、外部から供給された水
量すべてを含むことが期待されます。例えば、純水製造時にR/O 膜からオーバーフロ
ーし、実際に工程に投入されずに排水される水量も水資源投入量に算入します。
(iii) 排水規制項目の排出濃度のうち、健康項目及び生活環境項目(pH、大腸菌群数
以外)についてはリットル当たりミリグラム(mg/?)単位で、ダイオキシン類につ
いてはリットル当たりピコグラム(pg-TEQ/?)単位で記載します。
(iv) 排水量を流量計等のメーターによって測定していない場合は、排水量を合理的な方法
で算定します。この場合は、開示している排水量が実測に基づく数値ではない旨及び
排水量の算定方法を注記することとします。
(v) 総量規制対象地域から排出される排水の汚濁負荷量については、トン単位で記
載します。
(vi) 参考資料の5.【指標の一般的な計算例】を参照してください。
4.「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標(EEI)
(環境効率指標:EEI)
(1) 記載する情報・指標
ア.事業によって創出される付加価値等の経済的な価値と、事業に伴う環境負荷(影響)の関係
(2) 記載することが期待される情報・指標
(1)のほか、例えば次のような情報や指標を記載することが期待されます。
? 環境効率*の改善状況
(3) 解説
事業にあたっては、できるだけ少ない環境負荷で事業活動を行うことが期待されま
す。そのような全体的な状況を示すものとして、事業全体の環境効率を示す環境効率
指標があります。本来であれば、事業に関わるすべての環境負荷と事業の活動成果を
表す経営指標(付加価値や売上高等)との関係を示すことが望まれます。しかし、少
なくとも現在、複数の環境負荷を一つに統合する算定方法についてはいくつかの手法
や理論が存在し、ガイドラインとして特定の手法を推奨するには時期尚早の段階にあ
ります。一方、複数の環境負荷を統合せずに、事業活動に伴う特定の環境負荷につい
て、環境保全コスト一単位当たりの値や付加価値等との比較についての環境効率を算
出する方法もあります。
ただし、事業者にとっては本来は購入や調達を含むサプライチェーンや使用・廃棄
の段階も含めた環境効率性を高めることが目標となるべきであり、それらに関する環
境負荷の把握が可能である場合は、できるだけ範囲を広げて環境効率性を示すことが
期待されます。
また、環境負荷の内容についても、できるだけ幅広いもので示していくことも望ま
れます。環境効率を示す指標の分子・分母にはさまざまな要素と組み合せがあり、業
種や事業特性に応じた要素を適切に選定することが必要です。また、いくつかの指標
を組み合わせて用いることによって、より幅広い情報を提供することも考えられます。
なお、環境効率の定義や測定の形態は業種により異なることがあり、事業内容の異な
る事業者間について比較する場合には注意が必要です。
さらに、環境効率や全体的な環境負荷総量(異なる種類の環境負荷の量を何らかの
係数により統合した単一の指標で表すもの)に関する改善状況について、中長期の目
標と関連させて示すことも期待されます。
(4) 代表的な環境効率指標の事例
環境効率については、個別の環境負荷を対象とする環境効率指標と、複数の環境負
荷(環境影響)を統合した値を対象とする環境効率指標があります。前者には売上高
CO2 原単位や生産高廃棄物原単位等があり、後者には各事業者による独自の手法だけ
でなく、「LIME(被害算定型環境影響評価手法)」や「JEPIX(環境政策優先度指数)」等
の民間研究機関が開発した手法があります。特に、後者の環境効率指標を用いる場合
は、統合に用いる係数はさまざまな推定条件や前提条件に基づいて算定されているこ
とを十分に理解することが必要です。それゆえ、環境報告においては環境効率指標の
考え方とともに算定式を明記し、ステークホルダーに指標の持つ意味を正確に伝える
工夫が求められます。また、事業者間の比較を行う際には、環境効率指標が持つ特性
や限界等に十分留意する必要があります。
環境効率指標に採用する分子・分母にはさまざまな指標が可能ですが、代表的な環
境効率指標には以下のようなものが考えられます。ここで示すもの以外にも、事業者
等において考案されている多様な環境効率指標を参考資料に例示しています。(参照:
【指標算出にあたっての留意点】
(i) 環境効率指標の計算にあたっては、分子(経済価値)と分母(環境負荷)の数値
のバウンダリー(集計範囲)を一致させることが必要です。
(ii) 分母(環境負荷)に採用する数値(CO2 排出量や廃棄物最終処分量等)は、相対
値ではなく総量で表示することが必要です。
(iii) 環境効率指標は事業者の環境経営の取組や努力を如実に反映するものですが、そ
れはあくまでも相対値であるため、読み手に誤解を与えないように、総量も併記
する必要があります。
(iv) 環境効率指標の開示は経年変化が明確に分かるように記載する必要があります。
それは事業者の取組の成果や課題を分析することにも役に立つものです。
第4章 「社会的取組の状況」を表す情報・指標
1.環境報告書に記載する情報・指標の考え方
近年、我が国で発行される広い意味での環境報告書の内、62.7%が環境保全の取組
だけでなく社会的取組の状況についても記載しているとの調査結果5があります。また、
その名称も「CSR 報告書」「環境・社会報告書」「サステナビリティ報告書」等、社会
性を含むものが多く見られるようになっています。これは、環境問題と社会問題への
取組が、企業の社会的責任を果たす上でいずれも重要な課題であることから、併せて
報告を行っているものと考えられます。
平成18 年4 月に閣議決定された第三次環境基本計画においても、環境政策の基本的
方向の一つ目として、「環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合的向上」が掲げら
れています。事業者という経済的な主体が、事業活動の環境的側面や社会的側面を経
営方針に組み込み、その取組状況を開示することは、持続可能な社会の実現のために
望ましいと考えられます。
このような観点から、本章では、既存の環境報告書に多く記載されている項目や、
さまざまなガイドライン等に示されている項目を踏まえて、「社会的取組の状況」を表
す情報・指標を示します。
特に、地域コミュニティの活力は、環境的側面と社会的側面の両方にとって重要な
課題です。事業者として地域コミュニティとどのような関係を築くのかを考えるに当
たっては、この両方の側面を併せて検討していくことが望ましいといえます。このよ
うな地域コミュニティとの関係について、アメリカにおいては企業の社会的責任とし
て重視されています。他方、ヨーロッパにおける企業の社会的責任の議論では、域内
の雇用確保や人材育成等の問題に大きな関心が払われています。
いずれにしても、社会的取組の内容については、社会的な重要性やそれぞれの事業
者が置かれている状況によって重視すべき課題が大きく異なります。したがって、以
下に記載する項目はあくまでも例であり、これ以外の項目も含め、各事業者が必要と
考える社会的課題の解決に向けた取組について記載していくことが求められます。
社会的取組についての記載内容を検討する際には、環境保全に係る項目と同様にス
テークホルダーとの関係が重要であり、当該地域固有の文化的・歴史的背景に鑑み、
さまざまなステークホルダーと意見交換を行いながら、自らにとって特に課題となる
項目を中心に記載することが望まれます。
なお、現在、政府や民間団体においても、企業の社会的責任に関し、さまざまな調
査研究が報告されており、現在も検討が行われているものもあります。社会的取組の
状況について記載する際は、それらも参考にしつつ、適切な情報を提供することが望
まれます。
2.「社会的取組の状況」を表す情報・指標(SPI)
(1) 記載することが期待される情報・指標
「社会的取組の状況」を記載する場合、社会的取組への方針、目標、計画等を記
述することが期待されます。また、例えば、次のような情報や指標について、ステ
ークホルダーとの協議を行う等、選定手順を工夫しつつ、社会的な重要性も踏まえ、
適切な情報や指標を選択して記載することが期待されます。さらに、事業活動全体
として社会的な価値の創造にどの程度寄与できたか、取りまとめて示すことも考え
られます。
?労働安全衛生に関する情報・指標
・労働安全衛生に関する方針、計画、取組
・労働災害発生頻度、労働災害件数
・従業員の健康管理に関する方針、取組
・度数率、強度率、労働損失日数
・健康/安全に係る支出額、一人あたり支出額
・労働安全衛生マネジメントシステム指針への対応
・労働安全衛生委員会の議事内容と従業員への周知
※危険性・有害性等の調査等に関する指針への対応
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-5-1-0.htm
※ 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-19/hor1-19-1-1-0.htm
※ 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-21/hor1-21-1-1-0.htm
※ 労働安全衛生マネジメントシステム指針
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-58-1-0.htm
?雇用に関する情報・指標
・雇用に関する方針、計画、取組
・労働力の内訳
・賃金等の状況
・従業員の公正採用選考の状況
・人事評価制度の状況
・教育研修制度の状況
・男女雇用機会均等法に係る情報
・障害者の雇用方針及び取組状況、障害者の雇用の促進等に関する法律による障害者の雇用状況
・外国人の雇用方針及び雇用状況
・福利厚生の状況
・労使関係の状況
・職場環境改善の取組状況
※ 女性労働者の能力発揮促進のための企業の自主的取組に関するガイドライン
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-35.htm
※ 職場におけるエイズ問題に関するガイドライン
http://api-net.jfap.or.jp/mhw/document/doc_02_29.htm
※ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-2.pdf
?人権に関する情報・指標
・人権に関する方針、計画、取組
・差別対策の取組状況
・児童労働、強制・義務労働防止の取組状況(サプライチェーンを含むこれらに関する撤廃プログラムの状況等)
・人権に関する従業員への教育研修
?地域及び社会に対する貢献に関する情報・指標
・地域文化やコミュニティの尊重、保護等に係る方針、計画、取組(特に事業活動に係る国内外の地域)
・発展途上国等における社会的な取組
・フェアトレード、CSR調達の状況
・地域の教育・研修への協力、支援の状況
・環境以外の社会貢献に係る方針、計画、取組
・NPO、業界団体等への支援状況、支援額、物資援助額等
?企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引に関する情報・指標
・企業統治・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引に係る方針、体制、計画、取組
・環境関連以外の法律等の違反、行政機関からの指導・勧告・命令・処分等の内容及び件数
・環境関連以外の訴訟を行っている又は受けている場合は、その全ての内容及び対応状況
・行動規範策定の状況
・独占禁止法遵守等の公正取引の取組状況
・公益通報者保護に係る方針、計画、取組
?個人情報保護に関する情報・指標
・個人情報保護に係る方針、計画、取組
?広範な消費者保護及び製品安全に関する情報・指標
・消費者保護、製品安全及び品質に係る方針、計画、取組
・製品・サービスの設計・製造・販売(提供)・使用・廃棄の過程を通じて、顧客の安全・衛生を確保する取り組みの方針・取組
・主要な製品・サービスの安全基準適合性を認証・検証する機関及び必要に応じて認証・検証手続きの記載と安全基準適合性の数値目標と達成状況
・顧客への宣伝・販売に関する法令・自主規制基準等を遵守する社内体制
・PL法対策、特に製品設計、製造及び表示における安全対策
・販売後の点検、修理等のアフターサービスプログラム
・消費者クレーム窓口の設置及びその処理状況(消費者基本法による製品等の苦
情処理窓口の設置及びその処理の状況、消費生活用製品安全法による製品に関
する被害発生の報告の状況)
・景品法による製品等の品質表示・説明に関する根拠資料の開示の状況
・製品等のリコール及び回収等の状況
・消費者契約法、消費者基本法、金融商品取引法、特定商取引法遵守に関する販
売並びに消費者契約の契約条項等の適正化プログラム及びその遵守状況
?企業の社会的側面に関する経済的情報・指標
・ステークホルダー別の企業価値(付加価値)の配分
・環境関連分野以外の寄付や献金の相手先及び金額
・適正な納税負担の状況
?その他の社会的項目に関する情報・指標
・動物実験を実施する際の方針、計画、取組
・知的財産の尊重、保全
・武器及び軍事転用可能な製品・商品の取扱・開発・製造・販売に関する方針、計画、取組
・受賞歴
(2)解説
社会的側面に関する情報として、どのような情報を記載することが望ましいかに
ついては、さまざまな意見があります。
例えば、OECD(経済協力開発機構)の「多国籍企業ガイドライン」(最新版は2000
年6月改訂)は、多国籍企業による貿易・投資の自由化、経済のグローバル化に対する
市民社会からの懸念に応えるための行動規範として策定されましたが、その内容は序文
に加えて10章(定義と原則、一般方針、情報開示、雇用及び労使関係、環境問題、贈賄
の防止、消費者利益、科学及び技術、公正な競争、課税)からなります。
また、GRIガイドライン第3版では、社会的パフォーマンス指標の項目として、労
働慣行とディーセント・ワーク(公正な労働条件)、人権、社会、製品責任の4種
類を挙げています。
社会的側面は、地域、国、地球等の持続可能性、各レベルのステークホルダーへ
の影響、事業者に求められる社会的責任を考慮して検討されるべきものです。この
ガイドラインでは、記載することが期待される情報・指標を、労働安全衛生、雇用、
人権、地域及び社会に対する貢献、企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫
理・コンプライアンス及び公正取引、個人情報保護、広範な消費者保護及び製品安
全、企業の社会的側面に関する経済的情報・指標、その他の社会的項目の9種類に分
類しましたが、これらは現在、社会的な関心が高いと思われるもの、法律等による
規制等があるものです。
社会的側面の情報・指標は、それぞれの業種や規模等により異なると考えられま
すが、本ガイドラインを参考に、それぞれの状況に応じた項目を具体的に記載する
ことが望まれます。
第5章 環境報告の充実に向けた今後の課題
1.ステークホルダーとの協働による質の高い環境報告を
環境問題が多岐にわたり、かつ事業活動の範囲が広がるに従い、事業者は環境報
告の内容について、事業内容等を踏まえて、適切なものとなるように工夫する必要
があります。ただし、どのような課題に焦点を当てるか等について、必ずしも客観
的に明らかではない場合も多くみられます。このようなことを踏まえると、今後は、
さまざまなステークホルダーと意見交換を行いながら環境報告を行っていく必要性
が高くなってくると考えられます。
そのような必要性を踏まえ、環境報告書の作成過程において、ステークホルダー
等と必要な意見交換が適切に行われ、次年度の環境報告に反映される仕組みの開発
に、関係者全体で努めていく必要があります。
また、ステークホルダーには、環境報告に積極的に協力・関与することが期待さ
れ、関係者全体で質の高い環境報告の普及啓発に努めていく必要があります。
2.環境報告の活用方策について
事業者は積極的に環境報告書による環境報告を行っていくことが求められてい
ます。一方、環境報告書がステークホルダーエンゲージメントのツールとしての役割
を高め、事業者の環境配慮の取組を説明する場で幅広く活用されることが期待されま
す。
環境報告の活用方策としては、まず、事業者内部において十分に活用されることが
期待されます。環境経営を進めるためには、経営者が率先して必要かつ十分なコミッ
トメントを記載するとともに、環境報告の内容を十分に把握し、従業員に浸透させる
措置をとる必要があります。また、従業員についても、環境報告の内容を把握し、環
境配慮に努めることが望まれます。
株主等の出資者や地域住民、マスコミ、関係するNPO 等といった外部のステーク
ホルダーに対して、説明会や記者会見、意見交換会等を行い、環境配慮の取組状況や
環境経営の方針について説明する機会を設けて活用するようなことも期待されます。
その際には、できるだけステークホルダーとの意思疎通を行い、ステークホルダーが
十分な知見を得ることができるとともに、事業者としてステークホルダーの意見を経
営に反映させていくことができるようにすることも望まれます。
また、環境報告は投融資や企業評価の際に活用される機会も増えてくることが期待
され、できるだけわかりやすく合理的に環境配慮の状況の全体像を伝えるための方法
についても、金融関連の評価機関等も関与し、関係者全体で開発していく必要があり
ます。
その他、今後、環境報告がさまざまな場面で十分に活用されるよう、環境報告の関
係者が活用方策の開発等に努めていく必要があると考えられます。
3.社会的取組の状況について
昨今、CSR 報告書や社会・環境報告書等、環境報告書の中で社会的取組の状況につ
いて公表する事業者が増えてきており、社会的取組についての情報や指標を示したガ
イドラインが求められています。環境問題は社会的状況との関連が強いことから、事
業者が「社会的取組の状況」についても自主的に開示していく方向は好ましく推奨し
ていきたいと考えていますので、本ガイドラインでは記載が望ましいと考えられる情
報・指標を例示しました。
社会的側面の情報・指標については、他省庁やさまざまな国際機関、NPO 等でも検
討が行われていますが、現在は研究の途上にあります。今後は、それらの研究成果を
踏まえて、できるだけ幅広い関係者の参画の下に、企業の社会的責任に関する報告全
体と環境報告の在り方について検討していく必要があります。
一方、社会的取組の情報を重視し、環境経営や環境パフォーマンスに関する情報を
十分に記載していない環境報告書も見受けられます。地球環境問題の深刻化の中で、
持続的社会の創造の基盤となる環境配慮の取組について、事業者が積極的かつ自主的
に情報開示をしていくことは、これまで以上に重要となってきています。それゆえ事
業者においては、環境配慮の取組状況を本ガイドラインに準拠し適切に情報開示して
いくことが強く期待されます。
【参考資料】
1.BI-4-1:主要な指標等の一覧(掲載する際の例)
2.用語解説
3.Q&A
4.環境効率指標の事例
5.指標の一般的な計算例
6.国内外の研究機関等及び諸外国における研究成果
7.チェックリスト
2.【用語解説】
(注)出典明記のないものは、環境省にて定義ない
し解説されていることを示す。また、各項目
の( )内の数字は本文の記載頁を示す。
はじめに
(ア) 第三次環境基本計画
環境基本計画は、環境基本法第15 条に基づき、政府全体の環境の保全に関する総合的かつ長期
的な施策の大綱を定めるもの。環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議決定
を経て告示される。
第三次環境基本計画は、平成18 年4 月7 日に閣議決定された。今後の環境政策の展開の方向と
して、環境と経済の好循環に加えて、社会的な側面も一体的な向上を目指す「環境的側面、経済的
側面、社会的側面の統合的な向上」等を提示している。今後展開する取組として「市場において環
境の価値が積極的に評価される仕組みづくり」「環境保全の人づくり・地域づくりの推進」等を
決定している。計画の効果的な推進のための枠組みとして、計画の進捗状況を具体的な数値で明ら
かにするため、重点分野での具体的な指標・目標、総合的な環境指標を設定している。
(イ) 特定事業者
環境配慮促進法第2 条第4項の規定に基づき、特別の法律によって設立された法人であって、そ
の事業の運営のために必要な経費に関する国の交付金又は補助金の交付の状況その他からみた
その事業の国の事務又は事業との関連性の程度、協同組織であるかどうかその他のその組織の態
様、その事業活動に伴う環境への負荷の程度、その事業活動の規模その他の事情を勘案して政令
で定めるもの。
(ウ) 企業の社会的責任(CSR)Corporate Social Responsibility。
企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホルダー(利害関
係者)全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え方であり、法令等の遵守、環境保護、人権
擁護、消費者保護等の社会的側面にも責任を有するという考え方。
(エ) グローバル・リポーティング・イニシアチブ(GRI)
国際的なサステナビリティ・レポーティングのガイドライン作りを使命とするオランダに本部
を置くNGO で国連環境計画(UNEP)の公認協力関である。
(ア) ステークホルダー
一般に利害関係者と訳され、企業等の環境への取組を含む事業活動に対して、直接的または間接
的に利害関係がある組織や個人をいう。企業の利害関係者としては、顧客・消費者、株主・投資家、
取引先、従業員、NPO、地域住民、行政組織等をいう。
第1章 環境報告書とは何か
2.環境報告書の基本的機能
「社会的責任投資」(SRI)Socially Responsible Investment。
確定した国際的な定義はないが、狭義では「企業への株式投資の際に、財務的分析に加えて、企業の環境対
応や社会的活動等の評価、つまり企業の社会的責任の評価を加味して投資先企業を決定する投資
手法」の意。広義では「社会性に配慮したお金の流れとその流れをつくる投融資行動」とされ、
?スクリーン運用(対象銘柄の環境・社会的側面を評価した株・債券への投資)のほかに、
?株主行動(株主の立場から、経営陣との対話や議決権行使、株主議案の提出等を通じて企業に社会的な行
動をとるよう働きかけるもの)や、
?コミュニティ投資(上記の二つが主に大企業を対象としているのに対して、主として地域の貧困層の経済的支
援のための投融資)がある。
「後発事象」
会計用語で、決算日後に発生し、次期以降の財政状態や経営成績に影響を及ぼす事象を後発事
象という。環境報告書では、基準日の翌日から環境報告書の発行日までに、重要な法規制等の違反
の判明、重要な訴訟事件等の発生又は決着、その他ステークホルダーの判断に影響を及ぼす可能
性のある重要な事実が発生した場合には、その内容、今後の見通し等を重要な後発事象として、記
載することが期待される。
「サプライチェーン」
企業における原料の調達から最終消費者に届けるまでの供給活動(調達・開発・生産・輸送・
保管・販売)における全プロセスの繋がり。事業者が他の事業者から原材料や部品等を調達する
際に、製品の価格や品質に加えて環境配慮型の製品やサービスを優先的に選択するというサプラ
イチェーンの環境配慮が進むことで、産業全体の環境配慮を進める効果が期待されている。
第2章 環境報告の記載項目の枠組み
「マテリアルバランス」
事業活動に投入された資源・エネルギー量(インプット)と、製造された製品・サービスの生産・
販売量、廃棄物・温室効果ガス・排水・化学物質等の環境負荷発生量(アウトプット)を、分かり
やすくまとめたものである。
「総合的環境指標」
環境基本計画では「環境の状況、取組の状況等を総体的に表す指標」と定義されており、環境基
本計画の進捗状況についての全体的な傾向を明らかにし、環境基本計画の実効性の確保に資する
ために活用するという方向性が示されている。
「環境監査」
特定される環境にかかわる活動、出来事、状況、マネジメントシステム又はこれらの事項に関す
る情報が監査基準に適合しているかどうかを決定するために監査証拠を客観的に入手し評価し、
かつ、このプロセスの結果を依頼者に伝達する、体系的で文書化された検証プロセス。
「環境保全コスト」
環境会計の構成要素の1つ。環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、影響の除去、発生した被害
の回復又はこれらに資する取組のための投資額及び費用額とし、貨幣単位で測定する。
「環境保全効果」
環境会計の構成要素の1つ。環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、影響の除去、発生した被害
の回復又はこれらに資する取組による効果とし、物量単位で測定する。
「環境保全対策に伴う経済効果」
環境会計の構成要素の1つ。環境保全対策を進めた結果、企業等の利益に貢献した効果とし、貨
幣単位で測定する。
環境保全対策に伴う経済効果は、その根拠の確実さの程度によって、実質的効果と推定的効果と
に分けることとし、実質的効果は確実な根拠に基づいて算定される経済効果を、推定的効果は仮定
的な計算に基づいて推計される経済効果をさす。
「環境管理会計」
環境会計は、企業外部へ情報開示を行う外部環境会計(external environmental accounting)
と、企業内部の経営管理に資する内部環境会計(internal environmental accounting)に大別
され、この内部環境会計を環境管理会計(environmental management accounting: EMA)
と呼ぶことが、近年、欧米では定着しつつある。
資材原材料利用の効率性を高め、環境への影響とリスクを緩和し、環境保全コストを削減すること
を目的として、財務会計と原価計算(管理会計)からデータを取り入れるための複合的なアプロ
ーチ。民間企業または公共企業体を対象としたものであり、国家は対象としない。また物量情報だ
けでなく貨幣情報も含む。
「カーボンファンド」
クリーン開発メカニズム( CDM : CleanDevelopment Mechanism)や共同実施(JI:Joint
Implementation)のような温室効果ガスの排出削減プロジェクトの実施には、事業運営上のさまざ
まなリスクが伴う。こうしたリスクを回避するため、複数の企業が出資者となり、単独では持つこ
とが困難な情報収集力・資金力・リスク軽減能力を駆使するとともに、ファンドという形態を活用
して多様なプロジェクトをポートフォリオに取り入れることにより、単独企業での取得に比して
低リスクで安く安定的に排出権を獲得する仕組み。排出権買取ファンドとも呼ぶ。
「フェアトレード」
フェアトレードとは公正取引の意であるが、とりわけ、経済的・社会的に立場の弱い生産者に配
慮した貿易・取引を指す場合が多い。主に発展途上国の農産物や手工芸品などの生産者は、国際的
な商品価格の変動にさらされ、収入が不安定になることも少なくない。また、生産に必要な物資や
資金を買い手から前借りする場合などもあり、買い手の値下げ圧力のために不当な対価しか得ら
れないこともある。
こうした構造的な問題に対し、国際市場価格よりも高めに設定した価格で長期にわたって継続
的に直接取引することにより、生産者の生活と人権を保護し自立を支援する社会運動がフェアト
レードである。搾取的な取引は、人道面だけでなく土地や森林など環境面の負荷につながるほか、
商品の品質にも影響が出ることもあり、フェアトレードは経済・社会・環境面でバランスのとれた
持続可能な発展のための社会的措置であると認識されている。各種商品についてのフェアトレー
ドの国際規格も定められている。
「環境負荷低減に資する製品・サービス等」
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第2条第1項に定
める「環境物品等」を指す。具体的には以下のとおり。
・環境負荷低減に資する原材料又は部品(再生資源、再生部品等)
・環境負荷低減に資する製品(再生資源・再生部品を用いた製品、環境汚染物質の使用を削減した製品、エネルギー消費量の少ない製品、再使用・再生利用が可能な製品等)
・環境負荷低減に資するサービス(低公害車を用いた運送サービス等)
「森林認証」
森林認証は、独立した第三者機関が一定の基準等を基に、適切な森林経営や持続可能な森林経営
が行われている森林又は経営組織等を認証し、それらの森林から生産された木材・木材製品へラベ
ルを貼り付けることにより、消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する取組
である。森林認証の例としては、世界的規模のFSC(森林管理協議会)や我が国独自の制度であ
るSGEC(緑の循環認証会議)による認証がある。
「低公害車」
既存のガソリン自動車やディーゼル自動車に比べ、窒素酸化物や二酸化炭素等の排出量の少な
い自動車。経済産業省・国土交通省・環境省で策定した「低公害車開発普及アクションプラン」で
は電気自動車、圧縮天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び低燃費かつ低排
出ガス認定車の5 種が実用段階にある低公害車として挙げられている。これ以外にも、環境負荷
の削減を意図した自動車としてLPG 車、希薄燃焼エンジン車、ソーラー自動車、水素自動車、燃料
電池自動車、エタノール自動車、バイオディーゼル自動車等多種多様なものが挙げられる。
「環境適合設計(DfE)」
DfE は「Design for Environment」の略。環境への負荷がより少ないもの作りを進めることで、
「ものやサービスがライフサイクルを通じて与える環境への負荷を可能な限り低減させるため
のプロセス」であり、環境調和型製品の設計方法を意味する。環境配慮設計やエコデザインとも呼
ばれる。DFE と表記される場合もあるが、ISO ではDfE としており、JIS では「環境適合設計」とし
ている。
DfX は、"X"の部分に製品競争力を高めるための何らかの視点をおいた製品設計・開発手法
の総称であり、設計以外の段階、つまり製造、配送、使用、保全、廃棄等の段階における任意のパ
フォーマンスを向上させるメカニズムを設計段階において製品に実装する作業のことをいう。
「生物多様性」
生物多様性は遺伝子、種、生態系の3つのレベルでとらえられることが多い。すなわち、自然生
態系を構成する動物、植物、微生物等地球上の豊かな生物種の多様性とその遺伝子の多様性、そし
て地域ごとのさまざまな生態系の多様性をも意味する包括的な概念である。地球の生態系の中で
は生物が刻一刻と生まれ、死に、エネルギーが流れ、水や物質が循環しており、生物多様性はこう
した自然界の動きを形づくっている。
「生物多様性条約」
正式名称は「生物の多様性に関する条約」。1992年に採択され、同年リオ・デ・ジャネイロ(ブラ
ジル)で開催された国連環境開発会議(地球サミット)で署名が開始され、翌1993 年に発効した。
生物多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正な配分
を目的としている。国連の国際生物多様性年である2010 年に開催される第10 回締約国会議を名古
屋に招致することが、政府により決定されている。
「生物多様性国家戦略」
生物多様性条約第6 条に規定されている生物多様性の保全と持続的利用のための国家的戦略
あるいは計画のことで、締約国はその状況と能力に応じて作成することとされている。この戦略で
は、生物多様性の保全、持続可能な利用、普及啓発に関する措置、研究の推進、国際協力等多方面
にわたる施策・計画が定められ、関連する部門での生物多様性保全、持続可能な利用への取組も求
められる。
日本では、1995 年10 月に、政府の生物多様性保全の取組指針として「地球環境保全に関する関
係閣僚会議」で「生物多様性国家戦略」を決定し、2002 年3 月には、「新・生物多様性国家戦略」を
決定した。
「絶滅が危惧される種」
国内では、環境省や都道府県発行のレッドデータブックに記載されている動植物種全般に対し、
準絶滅危惧種等も含めて「絶滅が危惧される種」と呼ぶ。国際的には国際自然保護連合(IUCN)の
レッドデータブックに記載された種。
「水産エコラベル」
水産エコラベルに関わるガイドラインとして、2005 年にFAO(国連食糧農業機関)が採択した「海
面漁業により漁獲された魚及び水産物のエコラベリングのためのガイドライン」があり、第三者
機関が生産者の取組を審査しその適正性を証明する仕組みを定めている。
世界的規模の取組としては、国際的な第三者機関であり非営利団体であるMSC(海洋管理協議
会)の認証があり、持続可能な漁業であることを漁業に対して審査する「漁業認証」と、商品の加
工流通過程の管理が適正であることを審査する「CoC 認証」で構成されている。
「環境ラベル」
製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、
(1)「エコマーク」等第三者が一定の基準に基づいて環境保全に資する製品を認定するもの、
(2)事業者が自らの製品の環境情報を自己主張するもの、
(3)ライフサイクルアセスメント(LCA)を基礎に製品の環境情報を定量的に表示するもの等がある。
「環境ラベル認定等製品」
環境ラベル認定等製品には特に定まった定義はない。事業者が、環境負荷低減に資する製品・
サービス等と評価するものを対象とする。たとえば、グリーン購入法第2 条第1 項に定める「環境
物品等」やエコマーク等の環境ラベル認定商品等が挙げられる。
「省エネルギー基準適合製品」
大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であってその
性能の向上を図ることが特に必要なものとして施行令で指定された機器(特定機器)については、
特定機器ごとに、その性能の向上に関し製造事業者等の判断の基準となるべき事項(省エネルギー
基準)が定められている(省エネルギー法18 条、施行令7 条)。この省エネルギー基準に適合して
いる製品のことをいう。
「サービサイジング」
これまで製品として販売していたものをサービス化して提供することを意味する用語である。
本質的にモノの価値はその機能にあり、また環境負荷からみても物を所有するとメンテナンス
や廃棄・最終処分について事業者自らが直接に責任を負うことになる。外部の専門業者からリース
やレンタルといった形態で「機能」の提供を受けることにより、事業者自身の環境負荷を低減する
ことができる。
この用語は、主に米国を中心に使用されており、欧州では、同じ概念を表す用語として、PSS
(Product service systems:製品サービスシステム)を使用している。PSS は「使用者のニーズ
を充たすように製品とサービスを結合して市場に提供されるセット(システム)」と定義されて
いる。
「エコツーリズム」
自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴
史文化の保全に責任を持つ観光のありかた。自然環境等の資源を損なうことなく、自然を対象とす
る観光をおこして地域の振興を図ろうという考え方である。
「新エネルギー」
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネルギー法)」において、「新エネルギー
利用等」として規定された、技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及
が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なものをいう。
具体的には、大きく3 つに分かれる。再生可能エネルギー(風力発電、太陽光発電、太陽熱利用
等。ただし水力発電は除く)、リサイクルエネルギー(廃棄物発電、廃棄物熱利用など)、従来型
エネルギーの新利用形態(燃料電池、天然ガスコージェネレーション等)。本ガイドラインにおい
ては、グリーン電力証書による購入電力も新エネルギーに含むことにする。
「再生可能エネルギー」
化石燃料や鉱物などのような短期間で再生できない枯渇性資源によらないエネルギー。具体的
には、風力、太陽光、水力、バイオマス、海洋、地熱等を指す。
「循環的な利用」
循環的な利用とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう(循環型社会形成推進基本法)。
「再使用」
(1)循環資源(廃棄物等のうち有用なものをいう)を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む)、
(2)循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること(循環型社会形成推進基本法2 条5項)。
「再生利用」
循環資源の全部又は一部を原材料として利用すること(循環型社会形成推進基本法)。
「熱回収」
循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のある
ものを、熱を得ることに利用することをいう(循環型社会形成推進基本法2 条7 項)。例えば、廃
棄物の焼却によって生じる実熱を冷暖房や温水等の熱源として利用すること。
「総物質投入量」
総物質投入量は、製品・サービス等の原材料等として事業活動に直接投入される物質をいう。た
だし、事業者内部で循環的に利用(再使用、再生利用、熱回収)している物質は含めない。
「中水」
中水とは上水と下水の中間に位置付けられる水の用途で、水をリサイクルして限定した用途に
利用するもの。上水の使用量が増加し水源不足が都市の深刻な問題となっていることや上下水コ
スト低減の面から、水資源の節減を図る中水が近年注目を集めつつある。
「温室効果ガス」
大気中の二酸化炭素やメタン等のガスは太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きが
ある。これらのガスを温室効果ガスという。温室効果ガスのうち、京都議定書における削減約束の
対象物質は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC 類、PFC 類、六ふっ化硫黄の6 種類。
「京都メカニズム」
温室効果ガスの削減を国際的に連携して確実に進めるための仕組みとして京都議定書で定め
たもので、「クリーン開発メカニズム(CDM)」「共同実施(JI)」「排出量取引(ET)」の3つからなる。
国家間で投資や取引といった市場メカニズムを活用する点が特徴。なお、先進国が植林等により
二酸化炭素を吸収・固定する「吸収源活動」も認められている。
「化学物質」
本ガイドラインでは、「大気汚染防止法」、「PCB廃棄物適正処理特別法」、「ダイオキシン法」、「化
学物質審査規制法」、「化学物質排出把握管理促進法」等の法令の適用を受ける化学物質及び事業者
が自主的に管理対象とする化学物質が該当する。
「PRTR 制度」Pollutant Release and Transfer Register(化学物質排出移動量届出制度)。
人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれて
事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、国に報告を行い、国は事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、対象化学物質の環境への排出量等を把握、集計し、公表する仕組みをいう。
日本では平成11 年、「化学物質排出把握管理促進法」により制度化された。
「Japan チャレンジプログラム」
官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム。産業界と国が連携して、既存化学物質
の安全性情報の収集を加速化し、化学物質の安全性について広く国民に情報発信することを目的
に、平成17 年6 月より開始したプログラム。
「廃棄物等」
廃棄物及び一度使用され、もしくは使用されずに収集され、もしくは廃棄された物品(現に使用
されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理もしくは販売、エネルギーの供給、土木建築
に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(廃棄物並びに放射
性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう(循環型社会形成推進基本法2 条2 項)。
「廃棄物」
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は
不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を
いう(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2 条)。
「マニフェスト」
産業廃棄物管理表。排出事業者が産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託する際に産業廃棄物の
名称・数量等を記入して、廃棄物の流れを自ら把握・管理する為の帳票。産業廃棄物の排出事業者
にはこのマニフェストを使って廃棄物の流れを管理し、適正な処理を確保することが義務づけら
れている。また、家電リサイクル法や自動車リサイクル法でも採用されている。
「産業廃棄物」
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック
類その他政令(廃棄物処理法施行令第2 条)で定める廃棄物をいう(廃棄物処理法第2 条第4 項)。
「一般廃棄物」
産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ごみ」
は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活
に伴って生じた「家庭ごみ」に分類される。
「特別管理産業廃棄物」
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有するものとして施行令で定めるもの。具体的には、引火性廃油、強酸、強
アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB 汚染物、廃石綿、重金属を含む
ばいじん、汚泥等)(廃棄物処理法2 条5 項、施行令2 条の4)。
「単純焼却」
単純焼却とは、熱回収を伴わずに単に焼却することをいう。
「健康項目及び生活環境項目」
水質汚濁防止法に基づき工場及び事業場からの排水に対して定められる排水基準項目。人の健
康保護の観点から健康項目としてカドミウム、シアン等27 項目、生活環境保全の観点から水の汚
染状態を示す生活環境項目としてpH、BOD 等15項目に関する基準が定められている。
「環境効率」
環境効率という概念は、1992 年にWBCSD(持続可能な発展のための世界経済人会議)により提唱
されたもので、〔製品もしくはサービスの価値/環境影響〕で表わされる。資源の効率的活用を通
じ、環境影響や環境負荷の低減を目指すための指標である。
環境負荷量1 単位当たりの付加価値や売上高等の値が用いられることが多い。分子・分母が形
式上逆になる「原単位」についても、ここでは環境効率指標の中に含めている。環境効率にはコー
ポレートレベルだけでなく、製品や事業所等のセグメントレベルのものもある。
なお、資源生産性の向上と環境負荷の軽減を図り、持続可能な社会の実現を目標とする「ファク
ター」という概念がある。これは、基準となる環境効率を分母とし、目標とすべき環境効率や評価
すべき環境効率を分子とするもので、環境効率が何倍上昇したのかを示す指標である。地球規模で
の持続可能な発展のため、ファクター4 やファクター10 等が提唱されている。
3.【Q&A】
序章 ガイドラインの改訂に当たって
問:当社は中小企業で、エコアクション21 にも取り組んでいないのですが、その場合は本ガイドライ
ンとエコアクション21 の第5 章「環境活動レポートガイドライン」のどちらを利用したほうがいい
のでしょうか?
答:どちらを用いても構いません。ただし、本ガイドラインは、主に大規模事業者等を対象として作
成しており、初めて作成する企業や中小企業の場合「環境活動レポートガイドライン」の方が
比較的に平易で、取り組み易いといえるでしょう。
問:このガイドラインには「準拠」しなければいけないのでしょうか?
答:準拠が望まれますが、義務ではありません。ただし、本ガイドラインや他の資料を参考に業種
や業態、ステークホルダーとの関係から適切な環境報告を作成することが期待されます。
第1 章 環境報告書とは何か
4.環境報告書の基本的要件
問:報告対象範囲と環境等に配慮したサプライチェーンマネジメントの範囲とは異なるという理解でいいのでしょうか?
答:はい、異なります。本ガイドラインでは報告対象範囲は連結決算対象組織とすることを基本と
しています。ただし、報告対象範囲外ではあっても、サプライチェーンの環境面のマネジメント
の状況について積極的に把握を行い、その状況を記載することが期待されます。
第3 章 環境報告における個別の情報・指標
問:「(1)記載する情報・指標」と、「(2)記載することが期待される情報・指標」の違いは何ですか?
答:本ガイドラインでは、環境報告において記載すべき項目である「(1)記載する情報・指標」と、記
載することが望ましい推奨項目である「(2)記載することが期待される情報・指標」の2 段階に分
けています。前者は、「方針、目標、計画、取組状況、実績」、「法規制で義務があるもの」、
「既存の環境報告書で記載が定着している情報・指標」等の基本的項目です。そして、後者
は環境経営の取組内容をより具体的に伝えるために記載することが望ましい情報や指標です。
ただし、本ガイドラインは環境報告として記載する標準的な項目を示したものであり、記載項
目を強制あるいは制限するものではありません。したがって、本ガイドラインに示した項目の他
にも、ステークホルダーの関心の高い情報等、事業者の判断で重要と考えられる情報や指標
を記載することが望まれます。
問:「情報・指標を記載しない理由を明記」とありますが、どのように書けばいいのでしょうか?
答:本ガイドラインにある情報・指標を記載しない理由としては、例えば下記の記載例が考えられ
ます。それぞれの情報・指標を記載する頁に書く方法もありますし、あるいは、本ガイドライン
の情報・指標項目と報告書記載頁の対照表を設け、その表中にまとめて書く方法もあります。
・事業活動に関連しない項目がある場合の例
「M株式会社では、資材等の輸送はほとんど行っていないため、本項目は環境報告書には
記載しません。なお、今後なんらかの外部の輸送事業者への委託等を行った際に、その環
境影響の種類や程度について検討し、重要な環境負荷が生じると考えられる場合には、本
項目を記載します。」
・データ把握の途上にあり、公表できない場合の例(その場合、公表する予定を記載する)
「S 株式会社では、△△事業所の移転に伴い、同事業所の環境負荷の状況について調査
の途上であり、本項目は本年度の環境報告書には記載しません。翌年度より、必要と判断
される同事業所の環境負荷の状況について、環境報告書に記載する予定です。」
問:経営指標は、有価証券報告書やアニュアルレポートでもより詳細に報告していますが、その旨を記載しておいた方がいいでしょうか?
答:はい、そうです。報告媒体ごとの使い分けや報告内容の切り分けについて、わかりやすく示すことも望まれます。
問:環境パフォーマンス指標(EPI)のダイジェストを、ここでは一覧にして示すよう求めています。
BI-4-2「事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括」やBI-5
「事業活動のマテリアルバランス」でも環境パフォーマンス指標の記載を求めています。重複す
るのではないでしょうか?
答:「主要な指標等の一覧」は事業者の環境負荷の推移を一覧するためのものです。一覧できる
ことで、ステークホルダーに理解しやすい情報となります。このような一覧があることで経年比
較をし易くなりますし、もちろん報告範囲等の違いもあり一律にはできませんが、他社比較もあ
る程度は可能になります。
BI-4-2 は発行した年度の環境報告書全体の概要です。BI-5 も発行した年度の環境負荷
の状況をまとめて報告する項目です。マテリアルバランスの記載方法は各社各様であるため、
別途、記載した方がステークホルダーには理解しやすくなります。なお、BI-4-1 とBI-4-2 や
BI-5 の重複する部分については、BI-4-1 と合わせて記載することもできます。
MP-4:環境に配慮した投融資の状況
問:当社は事業会社で、金融機関ではありません。環境に配慮した投融資といっても具体的なイメ
ージがわかないのですが、報告する必要があるのでしょうか?
答:はい、必要です。事業会社でも、投資や融資を行っているケースは少なくありません。例えば、
供給業者等の取引先や事業に対する融資や投資において環境配慮を行っていれば、その
状況について記載します。また、各種の事業資金運用や従業員の年金運用にSRI を勧めるこ
とや、自社の資産運用の際に環境に配慮した運用先を選定することも含まれます。
問:環境に配慮した投融資には様々なものがあり、わかりにくい印象を持っています。金融機関の
場合と事業会社の場合について、それぞれ具体的な例を説明していただけませんか?
答:以下に、環境に配慮した投融資の例をいくつかの視点から示します。
【金融機関の例】
企業(コーポレート)単位 事業(プロジェクト)単位投資
(直接金融)
■SRI(うち、主にスクリーン運用と株主行動)
■グリーンファンド(1)等への投資(風力発電プロジェクトの証券購入、自治体の環境保全事業の債券購入等)融資
(間接金融)
■担保等の環境リスク評価(主に不動産の土壌汚染の有無の調査)
■環境面のインセンティブ融資(環境配慮をしている組織には金利を優遇するいわゆる「環境配慮型融資」等)
■プロジェクトファイナンス(2)における環境面の配慮とスクリーニング(赤道原則(3)やJBIC ガイドライン(4)の採用等)
■環境負荷を直接削減するプロジェクトへの融資(太陽光発電パネルの設置費用融資や、風力発電事業へのプロジェクトファイナンス等)
【事業会社の例】
投融資
■供給業者等の取引先やそれ以外の事業者に対する投融資において、融資や投資を実施する際に、環境配慮の状況を加味し、スクリーニング等を行い、実施後も管理・指導を行う。
運用
■預金先や取引する金融機関を、環境配慮状況によって選定する。
■企業年金や内部留保の運用を、SRI 等にて行う。
(1)グリーンファンド:自然エネルギーの普及を目的とする基金の総称。
(2)プロジェクトファイナンス:融資先企業の債務保証を必要とせず、融資の利払い及び返済の原資をプロジェクトか
ら生み出される収益に限定し、担保をプロジェクトの資産・権利に依存する資金調達手法。
(3)赤道原則:大規模なプロジェクトファイナンス案件において、環境・社会面のリスクを判断・評価及び管理するた
めの民間金融機関の自主的な基準。10 原則からなり、環境影響の大きなプロジェクトの場合、環境アセスメント
レポートや環境緩和計画の策定・公開が必要になる。2006 年7 月に改訂。
(4) JBIC ガイドライン:国際協力銀行(JBIC)による、国際金融等業務と海外経済協力業務の2つの環境配慮のため
のガイドラインを統合した「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」。2003 年10 月1日より施行。
MP-6:グリーン購入・調達の状況
問:環境に配慮したサプライチェーンマネジメントとグリーン購入・調達は同じもののように見えます
が、具体的には何が異なるのですか?
答:サプライチェーンマネジメントは、上流の原料調達や製品・サービスの供給業者だけでなく、
下流の流通業者や最終消費者等に対する環境配慮への取組の促進も含む概念です。一方、
グリーン購入・調達は、製品やサービスを購入・調達する際に、価格や品質、納期に加えて環
境への負荷ができるだけ少ないものを考慮して優先的に採用することであり、基本的には上
流の供給業者等を対象とします。環境に配慮したサプライチェーンマネジメントの方が、グリー
ン購入・調達より意味が広いといえます。
MP-8:環境に配慮した輸送に関する状況
問:当社は物流会社ではありませんし、自社製品の輸送は全て外部委託しているので、直接的に
は輸送に係る環境負荷がないのですが、輸送について記載する必要があるのでしょうか?
答:はい、必要です。改正省エネ法では、一定以上の輸送を委託する事業者にも、荷主の責任と
して輸送に伴うCO2 排出量等のパフォーマンス報告を求めています。そのため、輸送の委託
先が連結決算対象組織外であっても、この件に関しては報告が望まれます。
MP-9:生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
問:なぜ生物多様性の保全が必要なのでしょうか?
答:人間を含めてすべての生き物は、多様な生物と大気、水、土壌等の要素から構成される生態
系という、一つの系の中で相互に深く関わりを持ち、物質循環や食物網等の様々な鎖でつな
がりあって生きています。人間生存の基盤である環境は、こうした生物の多様性と自然の物質
循環を基礎とする生態系が健全に維持されることにより成り立っています。また、多様な生物
が生存している生態系は、気候変動等の環境変化に対してより安定しているといえます。
生物多様性は、食料や薬品等の生物資源の供給源としても重要です。動植物や微生物か
ら医薬品として用いることのできる物質を発見することもありますし、原材料の調達を生物資源
に大きく依存している事業者も多くあります。また、生態系が物質循環や気象の調節に大きな
役割を果たす等、人間や生物が生存していく上で不可欠な生存基盤としても重要であること
がわかっています。言い換えれば、人類の生存のために、また、長期的なリスクの軽減、事業
者の持続的な経営のためにも、生物多様性の保全が必要です。
問:生物多様性はある特定の事業者の問題であり、一般の多くの事業者には関係がないのではないでしょうか?
答:いいえ、影響の直接的関係はなくても、間接的に影響を与えているケースは少なくありません。
生息域の開発、外来生物の移入、環境の変化等は生物多様性を減少させる主要な原因です
が、多くの産業は原料調達や事業所の設置等を通じてこうした原因を作り出しており、直接的
ないしサプライチェーン等を通じて間接的に生物多様性に様々な影響を与えています。
また、生物多様性は人間の生存基盤を提供しているという意味でも、企業の活動や消費者
の消費行動と密接な関係があります。生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用には、
消費者を含めた経済活動に関与している全ての関係者の取組が必要です。
問:生物多様性について、既存の環境報告書にはどのような記載事例がありますか?
答:下記のような内容を報告している例があります。
【欧州オイルメジャー】
・ エネルギー会社として初めて「生物多様性基準」を採用したこと。また、企業として唯一、UNESCO(国連教育科学文化機関)が認定している世界遺産地域で事業を展開しないことを表明していること。
・ IUCN(国際自然保護連合)による保護地域のカテゴリー?〜?のうち、?〜?の場所については、自社の影響の最小化に努めるとともに、該当地域での活動を逐次報告していること。
・ 100 以上の自然科学保護機関と協力しており、UNESCO の世界遺産地域の管理にも自社の業務技術を活用する試験プログラムを実施していること。
【国内大手建設会社】
・ 生態系の保全を環境面の重点4 分野の一つと位置づけ、「生態系保全行動指針」を策定し
て環境マネジメントに組み込んでいること。
・ 今後は、建設現場の環境管理計画に生態系保全についての確認事項を組み込むこと。
・ 生態系保全行動指針に基づいた、三事例の報告。
-分譲住宅敷地内の調節池を多様な生物が生育できるように工夫
-建設予定地に生息するある生物種が建設後も棲めるよう配慮
-生物多様性の保全に寄与する可能性のある資格の従業員による取得の支援
【国内電機メーカー】
・ NGO のコンサベーション・インターナショナルとともに生態系保全面において協働することと
し、生態系保全についての認識、保全に取り組む理由、活動の方針等。
・ その協働から世界で9 つの保全プログラムを行っていること、及びそうしたプログラムを行う際
の選定基準。
MP-12:環境負荷低減に資する製品・サービスの状況
問:当社は、製造業ではありませんが、環境負荷低減に貢献できるサービスを展開しています。そ
れについても記載していいのですか?
答:本ガイドラインはあらゆる業種を対象に作成しており、本指標も全ての業種に当てはまります。
リサイクルの取組や環境ビジネス、環境に配慮した製品・サービスの取扱等、環境負荷を低減
する取組について、できるだけ具体的な内容の記載が望まれます。
OP-6:温室効果ガスの排出量及びその低減対策
問:自社で京都メカニズムを利用しているのですが、パフォーマンス報告としてはどのように記載す
ればいいのでしょうか?
答:温暖化対策推進法において、京都メカニズムによるクレジットについては、排出量の報告と併
せてあくまでも任意にその購入量等の情報を提供できることとしています。また、排出量から
購入分を控除できるような扱いとはしていません。
なお、京都メカニズムについては下記のウェブサイトで、より詳しい情報が得られますので
参照ください。
環境省 京都メカニズム情報コーナー:
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/index.html
京都メカニズム情報プラットフォーム:
http://www.kyomecha.org/
EEI:環境効率指標
問:環境効率指標については、各社各様の指標を作成しており、まだ一般的には定式化されてい
ないと理解しています。【指標算出に当たっての留意点】を踏まえて、自社の経営戦略に応じ
て独自に作成してよい、ということでしょうか?
答:はい、そうです。現状では各事業者の創意工夫に任されていますが、何らかの環境効率指標
を作成・公表することが期待されます。作成に当たっては、できるだけ事業経営の要因に左右
されない指標が望ましいといえます。それゆえ、生産高、売上高、付加価値等は環境負荷や
環境影響との相関を測るのに比較的適していますが、利益の場合は環境経営以外の様々な
要因の影響を受けるため環境効率指標に用いることはあまり望ましくありません。
なお、環境効率指標を算定する際には、個別の環境負荷を用いる場合と複数の環境負荷
ないし環境影響を統合する場合がありますが、詳細は次項4.【環境効率指標の事例】を参照
ください。
●LIME(被害算定型環境影響評価手法)について
http://unit.aist.go.jp/lca-center/ci/activity/project/lime/index.html
●JEPIX(日本における環境政策優先度指数)について
JEPIX 報告書は、以下のウェブサイトから無償で入手できます。
http://www.jepix.org/request.php
また、JEPIX の簡易算出シート(エクセルシート)が開発され、以下のウェブサイトから無償で入手できます。
国際基督教大学(ICU)
http://subsite.icu.ac.jp/coe/download/download.html
http://www.kpmg.or.jp/profile/azsus/jepix.html
(注1)(社)産業環境管理協会に事務局をおく「日本環境効率フォーラム」では、
http://www.jemai.or.jp/CACHE/eco-efficiency_index.cfm
なお、算出にあたり、いくつかの考え方がありますので、インターネット上に掲載している事業者
等のURL を参考に示します。
○環境省中央環境審議会 地球環境部会「目標達成シナリオ小委員会」中間取りまとめ(平成13年6 月)
http://www.env.go.jp/council/06earth/r062-01/index.html
電気の使用に係る対策の温室効果ガス削減量を、電気の削減量(kWh)に全電源平均排出係数(0.36kg-CO2/kWh)と火力平均排出係数(0.69kg-CO2/kWh)をそれぞれ乗じたものを併記しています。
○独立行政法人 新エネルギー産業技術総合開発機構(既存のエネルギー使用との比較による削減効果)
http://www.nedo.go.jp/nedata/17fy/12/h/0012h001.html
燃料電池導入の場合のCO2 排出削減量を、LNG 火力平均CO2発生量を用いて算出した結果を示しています。
○電気事業連合会:
http://www.fepc.or.jp/index.html
(電気事業における環境行動計画)
http://www.fepc.or.jp/env/report2006/
CO2 排出原単位の増減の要因分析や1990 年度、2003 年度、2004 年度、2005 年度のCO2 排出実績と2010 年度の見通しが出ています。
http://www.fepc.or.jp/thumbnail/env-report2006/warming01.html
○石油連盟 暮らしと石油の情報館:
http://sys.paj.gr.jp/
(石油コージェネレーションの環境特性)
http://sys.paj.gr.jp/cogeneration/environment01_2.html
石油コージェネレーションを導入して一般電気事業者からの購入電力を削減する場合の評価として、火力平均係数を用いる手法を示しています。
○社団法人日本ガス協会:
http://www.gas.or.jp/default.html
(II 説明資料/3.地球温暖化対策)
http://www.gas.or.jp/kankyo/02_03.html
ガス事業の自主行動計画における目標、CO2 排出実績及び見通し、実績の評価、目標を達成するために実施した取組、CO2 排出減少の寄与量(要因分析)を示しています。
○東京電力株式会社:
http://www.tepco.co.jp/index-j.html
(全電源平均係数と火力平均係数)
http://www.tepco.co.jp/eco/kurashi/shiryou/shi-005a-j.html
省電力によるCO2 削減量を計算するときに、全電源平均のCO2 排出係数を使って求める手法
を示しています。
○東京ガス株式会社:http://www.tokyo-gas.co.jp/company.html(CO2 排出原単位の考え方)
http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/report/environment/warming/01.html
詳細は、「PRTR 排出量等算出マニュアル」を参考にしてください。
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/calc.html
ある製品の全国出荷量(t/年) ある製品のVOC 含有率(%)
【水質汚濁負荷量】
■水質汚濁負荷量の算定式
COD に係る汚濁負荷量(t)
=特定排出水のCOD(mg/?)×年間の特定排出水量(m3)×10-6
窒素含有量に係る汚濁負荷量(t)
=特定排出水の窒素含有量(mg/?)×年間の特定排出水量(m3)×10-6
りんに係る汚濁負荷量(t)
=特定排出水のりん含有量(mg/?)×年間の特定排出水量(m3)×10-6
(注1)複数の排出口から排水している場合は、各々の排出口ごとに汚濁負荷量を算定し、それらを
合計します。
(注2)水質汚濁防止法上の総量規制の対象でない事業者については、年間の特定排出水量(m3)を総排水量とし、特定排出水のCOD、窒素含有量、りん含有量は排出水中のそれぞれを指します。
(注 3)総量規制項目以外の健康項目、生活環境項目、ダイオキシン類等について、汚濁負荷量を算定する時は、上記COD の算定式と同様です。
(注4)下水道への排出の場合は、汚濁負荷量を算定しても、公共水域への排出量との合算は、通常行いません。
(参考資料)
「化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和54 年5 月16 日環境省告示第38 号)」、
「窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成13 年12 月13 日環境省告示第77 号)」、
「りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成13 年12 月13 日環境省告示第78 号)」
6.【国内外の研究機関等及び諸外国における研究成果】
諸外国等における環境報告書に関する情報入手先の抜粋を記載します。リンク先のURL は、平成19 年6 月時点のものです。
○事業者の環境報告書へのリンク
・環境省環境報告書データベース
http://www.kankyohokoku.jp(構築中)
・エコアクション21 認証・登録事業者リスト(環境活動レポート)
http://www.ea21.jp/list/ninsho_list.php
・環境報告書プラザ(経済産業省)
http://www.ecosearch.jp/kankyoplz/top.html
・サステナビリティ・コミョニケーション・ネットワーク(NSC)
http://www.gef.or.jp/nsc/
○環境報告書に関する研究・事例等(報告書ガイドライン)
・環境報告書の記載事項等の手引き
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
・環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き(試行版)
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
・経済産業省「ステークホルダー重視による環境レポーティングガイドライン2001」
http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/reports/report01/guideline2001-0.pdf
・GRI サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006
http://www.globalreporting.org/
(民間調査研究機関)
・AccountAbility(アカウンタビリティ社)
http://www.accountability.org.uk
・ACCA (Association of Chartered Certified Accountants 英国勅許公認会計士協会)
http://www.acca.co.uk/
・Ceres(セリーズ)
http://www.ceres.org/
・EMAS(Eco-Management Audit Scheme 環境管理・環境監査スキーム )
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
・NRTT(環境と経済に関するカナダ円卓会議)
http://www.nrtee-trnee.ca/
・WBCSD(持続可能な発展のための世界経済人会議)
http://www.wbcsd.org/
・WRI(世界資源研究所)
http://www.wri.org/
・日本環境情報審査協会
http://www.j-aoei.org/
○CSR に関する研究・事例等
・内閣府「企業における消費者対応部門及び自主行動基準に関する実態調査報告」
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/kohyo/index.html
・厚生労働省「労働におけるCSR のあり方に関する研究会」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0625-8.html
・経済産業省「企業の社会的責任(CSR)に関する懇談会中間報告書」
http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/press/0005570/index.html
・国土交通省「CSR の見地からのグリーン物流推進企業マニュアル」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/15/150427_.html
・(独)国際協力機構「環境社会配慮ガイドライン」
http://www.jica.go.jp/environment/guideline/index.html
・国際協力銀行「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」
http://www.jbic.go.jp/japanese/environ/guide/kankyou/index.php
・日本公認会計士協会
「経営研究調査会研究報告第28 号「企業価値向上に関するKPI を中心としたCSR 非財務情報項目に関する提言」について」
http://db.jicpa.or.jp/visitor/search_detail.php?id=64
「経営研究調査会研究報告第26 号「CSR マネジメント及び情報開示並びに保証業務の基本的考え方について」について」
http://db.jicpa.or.jp/visitor/search_detail.php?id=66
・OECD 多国籍企業ガイドライン(OECD Multinational Enterprise Guidelines)
・グローバル・コンパクト(United Nations Global Compact)
・日本経済団体連合会「企業行動憲章」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/cgcb/charter.html
○SRI に関する研究・事例等
・環境省「環境と金融に関する懇談会」報告書
http://www.env.go.jp/policy/kinyu/rep_h1807/index.html
(民間評価機関)
・Carbon Disclosure Project :CDP
http://www.cdproject.net/
・Ethibel (ベルギー)
http://www.ethibel.org/subs_e/2_label/sub2_2.html
・Oekom Research(ドイツ)
http://www.oekom-research.de/ag/english/index_research.htm
・EIRIS (イギリス)
http://www.eiris.org/index.htm
・SAM (スイス)
http://www.sam-group.com
・KLD (アメリカ)
http://www.kld.com
・INNOVEST (アメリカ)
http://www.innovestgroup.com
・Dow Jones Sustainability Index(アメリカ)
http://www.sustainability-index.com/
・FTSE4Good (イギリス)
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
○環境会計に関する研究・事例等
・環境省「環境会計ガイドライン 2005 年版」
http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html
・経済産業省「環境管理会計手法ワークブック」、「マテリアルフローコスト会計」
http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/sonota/policy1-01.html
○環境効率に関する研究・事例等
・経済産業省「環境効率」
http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/sonota/policy1-04.html
・日本環境効率フォーラム
http://www.jemai.or.jp/CACHE/eco-efficiency_details_grunge184.cfm
・NSC 環境部会「2005・2006 年度活動報告」(環境経営指標研究)
http://www.gef.or.jp/nsc/
○環境情報に関する研究・事例等
・国立環境研究所「地球環境研究支援データベース」
http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/db/dbhome.html
・国立環境研究所 環境情報案内・交流サイト「EIC ネット」
http://www.eic.or.jp/
2009年12月06日
日本弁護士連合会水俣病被害実態調査 結果報告書
水俣病被害実態調査 結果報告書
2008年10月
日本弁護士連合会
第1 調査の概要
1 調査の目的
2 調査の方法
3 調査の概要
4 調査結果を見る上での注意点
第2 調査分析
1 基本情報について
2 現在の健康被害の内容について
3 居住歴,生活歴等について
4 昭和20年代から昭和40年代まで不知火海の魚介類の摂取状況
5 家族構成・同居していた家族について
6 水俣病関係の認定申請について
7 家族の申請状況について
8 胎児性世代,小児性世代の健康被害について
9 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決後に水俣病認定申請をした方のきっかけ
10 新保険手帳の申請をされた方のきっかけ
11 不知火海沿岸全域の健康調査について
12 水俣病の認定(公健法)基準について
13 今回の調査に関する自由記載
第1 調査の概要
1 調査の目的
日本弁護士連合会は,1977年の人権擁護大会において「公害被害者の救済に関する決議」
を採択し,それ以降,水俣病問題についての調査研究を重ね,被害者の方の即時・完全救済等
を求める決議,具体的方策の提言などを行ってきた。
そして,2007年7月に「与党水俣病問題に関するプロジェクトチーム」が公表した「水
俣病に係る新たな救済策について(中間取りまとめ)」を受け,同年9月14日に「水俣病問
題について抜本的な救済策を求める意見書」を発表した。同意見書では,公健法に基づく救済
策を抜本的に改め,新たに総合的な救済施策を講じるべきであることを提案するとともに,新
たな救済施策の具体的内容として,水俣病認定基準の抜本的改定,水俣病患者に対する十分な
補償,水俣病患者に対する医療面,福祉面に対する恒久対策,国及び熊本県による経済的負担
等の事項を提示した。また,水俣病患者の実効的な救済を図るために,不知火海岸沿岸の健康
調査を早急かつ網羅的に行うべきことを提案した。
その後,与党水俣病問題に関するプロジェクトチームが救済策の実現に向けて検討を重ねて
いるが,依然として公健法に基づく認定基準を堅持する態度を変えておらず,また,一時金の
金額も関西水俣病訴訟最高裁判決の水準額(400万円から800万円)を大幅に下回る金額
(150万円)しか提示していないなど,当連合会が発表している提言からすると未だ不十分
なものにとどまっていると言わざるを得ない。また,国による不知火沿岸の健康調査も未だに
実施されていない。
そこで,当連合会としては,現地を訪れて水俣病患者の被害実態を調査することにより,具
体的なあるべき救済施策を研究し,今後も引き続き国に対して提言をしていく必要があると考
え,九州弁護士会連合会及び熊本県弁護士会の協力を得て,水俣病問題に関する被害実態調査
を実施した。
2 調査の方法
(1)調査対象
水俣病患者団体に実態調査協力の依頼をし,107名から協力を得られた。
(2)調査期間
2008年6月14日から同月15日まで。
(3)調査方法
調査事項書自己記入後,弁護士による個別面接調査。
なお,実態調査に携わった弁護士は,日本弁護士連合会人権擁護委員会委員5名,人権救済
調査室嘱託1名,同公害対策・環境保全委員会委員3名,九州弁護士会連合会人権擁護委員会
委員10名,熊本県弁護士会会員3名の合計22名である。
3 水俣病実態調査の概要
調査結果の概要は以下の通りである。
(1)現在の健康被害の内容について
今回の調査対象者は,実際にはほとんどの者が公健法上の水俣病患者としては認定されてい
ないが,次のとおり,四肢抹消優位の感覚障害,運動失調,視野狭窄のいずれについても異常
を訴えている者が多く存在した。
○感覚の異常である手足のしびれについては,すべての調査対象者が何らかの異常を訴えていた。
○手足の感覚麻痺については,調査対象者107名のうち93名が何らかの異常を訴えていた。
○上下肢の運動症状については,ほとんどの調査対象者が,つまずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいなど何らかの異常を訴えていた。
○視野狭窄については,調査対象者107名のうち93名が何らかの異常を訴えていた。
このデータから,感覚麻痺の有無だけを基準にするだけでは割り切れない患者が多数存在す
ることが窺われ,また,厳密な診察をすれば相当程度の者が水俣病と認定されるのではないか
と推測されるという結果が得られた。
(2)日常生活や仕事への影響について
日常生活上については,すべての調査対象者が何らかの支障を訴えていた。具体的には,足
のこむらがえり,常時疲れやすい,関節が痛い,耳鳴りがひどいなど身体的な症状を訴えてい
たり,茶碗を落として割ったりする,車の運転をしているとき横がまともに見えない,風呂の
湯加減が分からないなどの日常生活上の支障を訴えていた。
仕事面については,漁業に携わっている人が多い関係から,重い船具を持つことができない,
荷物を運ぼうとすると落としてしまう,網の修理が苦手であるなどの支障を訴える者が多かっ
た。そのほか,立ちくらみ,めまいのため仕事がしにくい,目を使う仕事ができない,補助的
な仕事に限定される,脚立など高い所へあがれないなどの支障も観られた。
日常生活や仕事面での差別等については,特にないと回答した者も多く存在したが,様々な
不利益,差別を受けたことがあると回答した者も多かった。具体的には,「大した症状もない
のにお金をもらっている」と悪口を言われる,医療費を支払わないことについて詐病ではない
かと言われる,見合いをしても水俣病の話が出ると相手から断られるなどの差別が見られた。
(3)病院での診察について
ほとんどの調査対象者がこれまで病院にかかったことがあったと回答しているが,水俣病あ
るいは水俣病の疑いとの診断を受けた者は,60代〜70代では約54%であったが,40代
〜50代では約30%にとどまった。治療内容については,保険適用外となるものも少なくな
く,はり,きゅう,マッサージ,電気治療,湿布,漢方治療薬などを利用している者も多く存
在した。
(4)公健法上の水俣病の認定申請について
公健法上の水俣病の認定申請を行っていた者は56名であり,そのうち,平成16年10月
15日の関西水俣病訴訟最高裁判決まで公健法上の水俣病の認定申請を行っていなかった者は
37名であった。認定申請をしていなかった理由については,「自分や家族に差別(結婚,就
職,近所付き合い)などの不利益が生じると思った」「自分が水俣病であることが分からなか
った」などが多く,依然として差別や偏見が根強く残っていること,水俣病に関する情報が十
分に周知徹底されていないことが窺われた。
(5)不知火海沿岸の健康調査について
調査対象者の約82%が不知火海沿岸の健康調査について,国,県の負担で実施すべきであ
ると回答をし,調査対象者の約72%が,今から調査をすれば健康被害の実態は分かると回答
しており,多くの者が実態調査を希望していることが判明した。
(6)認定基準について
調査対象者の約82%が現行の公健法上の水俣病の認定基準は厳しすぎると回答し,約7
6%が現行の基準を変えるべきであると回答していた。多くの者が,被害状況に応じた救済が
なされていないと感じていることが窺われた。
4 調査結果を見る上での注意点
今回の実態調査にあたっては,無作為抽出的に対象者を選出するのではなく,既存の水俣病
患者団体に実態調査協力の依頼をし,各水俣病患者団体において患者を選定してもらっている。
調査対象者数も僅か107名であることから,今回の調査結果が水俣病患者の全体の実態を反
映しているとは限らない。
また,今回の実態調査では,例えば「公健法上の水俣病の認定申請」について自分が申請を
しているか否かが不明であったり,過去の状況について一部記憶が定かでなかったりする事例
も見られた。限られた時間の聞き取り調査であったため,設問の内容によっては,必ずしも統
計的に正しいデータが得られていない可能性があることを付言しておく。そこで,今回の実態
調査においては,正確な数字よりも,患者の状況や特徴についての傾向を把握する趣旨で見て
いただければ幸いである。
なお,質問項目の中には,「いつ頃から症状が出ているのですか。」というような個々の患
者によって状況が異なり,集計が困難なものもある。そのような場合,集計結果を省略させて
頂いている点をご容赦されたい。
また,集計は,弁護士による個別面談を経て修正,加筆された調査事項書を基にしている。
第2 調査分析
以下,調査事項書の質問事項順に集計結果を記載する。
なお,前述のとおり集計が困難な質問項目については,記載を省略している。
1 基本情報について
<調査結果の補足説明>
?の手足のしびれについて
手足のしびれについては調査対象者107名全員が感覚の異常である手足のしびれを訴え
ていたということになる。40代〜50代の胎児性世代,小児性世代の患者と60代〜70
代の患者とでは,その傾向はほとんど変わらなかった。
?つまずきやすい,転びやすい・?細かい作業がしにくいについて
つまずきやすい,転びやすいは下肢運動症状に,?細かい作業がしにくいは上肢運動症状
に該当する。
つまずきやすい,転びやすいは,年代に関わらず,ほとんどの調査対象者が症状の異常を
訴えている。
また,細かい作業がしにくいという症状についても,年代に関わらず,ほとんどの調査対
象者が症状の異常を訴えていた。
なお,つまずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいという症状について,いずれ
もなしと答えている者はおらず,すべての調査対象者が何らかの異常を訴えていた。
<コメント>
?の手足の感覚麻痺について
手足の感覚麻痺については調査対象者107名のうち,93名が何らかの異常を訴えてい
た。そのうち,40代〜50代では,感覚麻痺が「常時」と回答した者よりも「時々」と回
答した者の方が多かったが,60代〜70代では,「常時」と回答した者が「時々」と回答し
た者の2倍となっていた。今回の調査だけでははっきりとしたことは言えないが,40代〜
50代と60代〜70代との間で感覚麻痺について「常時」と「時々」との間に差があると
いうことに関して,一定の有意性が認められる可能性がある。
なお,今回の調査では40代〜50代の患者のうち,感覚麻痺についてなしと答えた者が
4名いた。しかしながら,前述した?のとおり,40代〜50代の調査対象者の全てが,つ
まずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいなどという症状を訴えており,感覚麻痺
はないものの,運動症状に何らかの異常を来している者も相当数存在していると考えられる。
このようなことから,感覚麻痺の有無だけを基準にするだけでは割り切れない症状の患者が
相当数存在することが窺われた。
?の全身の感覚麻痺について
全身の感覚麻痺については調査対象者107名のうち半数近くの者が何らかの異常を訴え
ていた。
但し,例えば手足の先ではなく腕の部分に感覚麻痺を感じた場合に,回答する側からする
と,これが全身性の感覚麻痺なのか,四肢末梢の感覚麻痺なのかは判然としない場合も少な
くなかったようである。全身性か末梢の感覚障害かは厳密に専門の医者の検査によって判断
しないと誤るおそれがあると言えよう。言い換えれば,水俣病の診断基準のうち「感覚障害」
の取り方には十分に注意して行う必要があるということになる。
?視野狭窄について
視野狭窄の何らかの異常を訴えている者の割合は,全部で93名と約87%であり,40
代〜50代でも異常を訴えるのは53名中44名と約83%である。今回の調査では視野狭
窄を訴えている者の割合がかなり高い。これは,調査対象者の選別について比較的重症の患
者が選択されたのではないかと推測される。
○健康被害についての総合的なコメント
前記内容を総合し,40代〜50代の調査対象者で,?感覚障害(感覚麻痺),?運動失調,
?視野狭窄について複数の異常を訴えている人たちがどれくらいいるのかという統計を出し
たところ,次のような結果が得られた。
?の感覚障害については,常時か時々の別はあるものの,全員が手足のしびれを訴えてお
り(?の「手足のしびれ」),また,約87%の人が手足の感覚麻痺を訴えている(?の「手
足の感覚麻痺」)。従って何らかの手足の感覚障害という意味では,全員が異常を訴えている
ということになる。
?の運動失調については,上肢と下肢に若干の違いがあるが,常時,時々を含めて何らか
の運動失調がある者は全員である(?のつまずきやすい,転びやすいが下肢に関する運動失
調。?の細かい作業がしにくいが上肢に関する運動失調)。
?視野狭窄については,40代〜50代の患者の53名のうち44名が常時または時々の
異常を訴えている(?の視野狭窄)。
すなわち,今回の調査対象者については,実際には,ほとんどの者が公健法上の水俣病患
者としては認定されていないが(6項?参照),四肢抹消優位の感覚障害,運動失調,視野狭
窄のいずれについても異常を訴えている者が大多数であることを考えると,厳密な診察をす
れば相当程度の者が水俣病と認定されるのではないかと推測される。
(2)いつ頃から症状が出ているのですか。
症状や回答者によって異なる回答であった。但し,症状の種類を問わず,年齢を重ねるごとに症状が悪化している傾向にあるようであった。
(3)上記の症状による日常生活や仕事への影響についてお聞きします。
? 日常生活においてどのような支障が生じていますか。
今回の調査対象者の全員が,日常生活上の何らの支障を訴えている。以下に,具体例を紹介する。
・足のこむらがえり。
・常時疲れやすい。
・人の支えがないと歩くのが困難。
・関節が痛い。
・手足のしびれ。
・小さい物をうまくつまめない。
・手足のしびれのため,例えば,けがをしてもあまり痛みを感じないので,いつ,どこで怪我をしたのかが分からない。血が出ているのを見て初めて気が付く程度。
・夜よく寝られない。
・カラス曲がりなど日常茶飯事で,ひどいときは30分,40分つりっぱなしの時もある。
・耳鳴りがひどく,人の声が聞こえないので,自分もついつい大声で話してしまう。
・心臓に不整脈がある(ニトロを持っている)。
・茶碗を落として割ったりする。
・1人で布団も干せない。
・箸がうまく使えない。
・言葉がどもり,人に挨拶などができない。
・人間関係が作れない。子ども時代から症状があり友達ができなかった。
・物をつかんでいる感覚がない。
・手がふるえるのでお茶を出すのが嫌。
・味付けが濃すぎたり,薄すぎたりする。
・車の運転をしているとき,横がまともに見えない。
・細かい仕事がつらい(手の震え)。
・脱いだつもりのつっかけが脱げなくて,そのまま上ってしまう。段差に躓いて,転倒し,骨折した。
・一番困るのは眼。手術のしようがないと言われている。新聞は読めない。目薬は1日1本必要。
・風呂に入るとき心臓から下までしか浸かれない。
・風呂の湯加減がわからない。
・怖くて水泳ができない。
・長く座っているのが苦痛。長く座っていると足がしびれて固まって立ち上がれなくなる。あぐらが長時間できない。座敷の食事等がつらく,早く終わってくれないかと思ってしまう。
・忘れてしまって何度も尋ねることがある。
・家の外にはほとんど出ない。テレビも見ない。本も読まない。家では掃除,洗濯をしているが頭が痛かったりだるかったりするので,掃除,洗濯を毎日することはできない。他は何もしていない。
・左右の視力が違い,また,視力も変わってくるため眼鏡が合わない。そのため,頭痛がする。
・何を食べてもおいしくない。等
? 仕事面で何か不都合や被害を受けたりしていますか。
仕事への支障についての訴えのみならず,それによる周囲からの反応について回答するものも見られた。以下に,具体例を紹介する。
・仕事に就いたことがない。
・補助的な仕事に限定される。スーパーのレジの仕事などしかできない。
・目を使う仕事ができない。
・長期間機械を扱うと,調子が悪くなる(腕など)。疲れやすいとは思う。
・指先にとげなどが刺さっていても気づかない。
・仕事中に休むことが多くなった。細かい作業ができないので困ることがある。同じ状態でいられない。重い物を抱えると,つって,しばらく腕をのばせない。
・立ちくらみ,めまいのため仕事がしにくい。県外で仕事しているとき,水俣出身ということがわかると「あなたも泡をふくんじゃないの?」などと言われた。
・パートに出たが,水俣病のことを言われた。私は申請中とは言わず黙っていたが,居づらくなり辞めてしまいまった。農作業も身体が痛く,していない。
・細かい作業が出来ない。文字を書けないのが,一番つらい。
・ひざが曲がらないので座るときは足を投げ出さないといけない。和式トイレが使えない。草むしりができない。
・手に力が入らないので,雑巾が絞れず,仕事の手伝いができなくなった。
・脚立など高い所へ上がれない。
・手が震えてハンダ付けができないときがある。
・手の感覚がないので,痛みを感じない。水俣病報道でよく登場したこともあり,会社から「お前はなぜ自分が水俣病だと言うのか」「お前の血は青いんだろう」「神経が通っていないんだろう」と言われた。
・物忘れ。商品の陳列がうまくできず,時間がかかる。
・高校卒業後,国鉄の試験を受けたが,耳鳴りのために面接,身体検査で落ちた。
・声が聞き取りにくいのですぐに返答できない。電話対応に困る。
・何か言われていることはわかるが,中身がわからないので何度も聞き直す。
・網を引く作業が船の上なので,すぐ転んで青あざができてしまう。手の握力も17〜18kgしかない。
・船の修理の仕事をしている。仕事に関してお客から信用を失いつつある。なくなっているかもしれない。仕事の集中力というか取り組みにむらがある。
・重たい船具(2kg)を持てないことがある。
・海上タクシーの仕事をしているが,荷物を運ぼうとすると落としてしまう。弁償することもあった。
・若い頃から漁業の網の修理が苦手だった。道具に糸が通らない。
・漁は2人でする仕事なので,自分が休めば夫も漁に行けず仕事が出来ない。よって収入減となる。子どもを育てるためには毎日漁に行かねばならない。
・農作業中にハサミ,のこを落とす。
・腰痛や肩こりがひどくなり痛み止めの注射を打つことが多く,通院しながらの農作業で仕事も進まない事も多い。人に代わってもらうことも多い。
・建設関係の仕事をしているが,手足のしびれがあるため測量作業がうまくできないことが多く,他の人から「他の人に代われ」と言われることがある。
・建設関係の仕事なので段差のある足場での作業(上り下り)がきつい。
・靴下工場で細かい作業だったので大変でした。
・手足が自由でないために,作業中に指を切断した。等
? 日常生活や仕事の面で不利益を生じたり,差別を受けたりしたことがありますか。
特にないと回答したものも多く存在したが,様々な不利益,差別を受けたりしたことがあると回答しているものも多かった。具体的な不利益,差別事例についての訴えを紹介する。
・高卒後,大阪で過ごしていたところ,テレビで水俣病のニュースが流れると「あなたの郷里
が映っている」等と言われ恥ずかしかった。夫の母が福岡の病院で手術を受けた。母は医療
手帳を持っていたので医療費がかからないが,看護師は医療手帳を見て,「これ何ですか!」
と驚いた。他の患者は支払をしているのに母だけ払わない扱いを説明するのに大変だった。
・差別についてあるとは思うが「大した症状もないのにお金をもらっている」「お金をほしが
っている」と悪口を言われる。だから自分も友達にもいえない。
・水俣病について活動(ビラ配り)をしていると,通行人の女性から「ニセ患者」と言われた。
・いとこが認定患者で胎児性患者を産んでいるが,差別を受けているのを見てきた。身内に漁
業関係者がいて,迷惑がられた。汽車では水俣で窓を閉めていた。
・自分ではないが,妹が「そんな身体なら家の人も早くいなくなればいいと思う」などと心な
い言葉をかけられた。
・薬剤師から,「認定患者だけが本当の患者だ,薬のありがたみが分かっていない,薬のお金
を払っていない,自分たちが払った税金が使われている」などと言われた。
・医療費を支払わないことについて,詐病ではないかと言われたことがある。「あんた達はよ
かなー,手帳もらえてなー,医療費がただで!」
・子どもが結婚前だったから申請しなかった。差別されるから。それまで手足のしびれはない
と言って隠していた。
・集会場などで声が聞きづらく困る。耳が聞こえないことで「つんぼ」とか言われる。隣家の
人が,結婚が破談になったという話を聞いた。
・お金目当てと言われる。
・水俣病だとお嫁に行けないなどと言われていたし,あえて調べようとは思っていなかった。
今までは,ただの神経痛ではないかと思っていたが,平成16年頃に水俣病のことを知って,
平成7年の政治解決の時もまさか自分が水俣病だとは思わなかった。
・裁判をしているので,「金がほしくてやっている,それくらいは誰でも身体に異常はある」
という悪口を言われる。父が認定されたときもニセ患者と言われた。
・ある人から「指輪など似合わない手だ」と言われた。口をつぐんで通行したり,けがらわし
いなどといわれた。行政からの正確な情報提供がないため。
・自分も見合いをしたが,水俣病の話が出ると,相手が断ってきたりした。結局,水俣病のこ
とをよく知らない外国人の女性と結婚した。
・テレビに出たあと差別を受けた。今の職場もいつ辞めさせられるか分からない。
・実家から送ってくる魚をおすそわけすると,「水俣からきたものだから嫌だ」と言われたこ
とはある。
・今現在はそうでもないが,幼小時期は冷たい目でみられたこともある。島外に出ていて結婚
していた際,県営住宅にいたとき,「笑わない人がきた」とか色々なことをいわれた。
・学校生活のときいじめられた。但し,水俣病との自覚はなく,トロイのが原因でいじめられ
ていると思っていた。
・小学校,中学校のとき悪口を言われた。近所のおばさんに会った際に父,母,妹だけに声を
かけて,自分に声をかけないということもあった。腹も立つし,とても悲しい。今でもそう
である。
・無理な仕事ができなくなった(手先や目を使う仕事ができない)。
・仕事中でもよくころぶことがある。高所のよう壁から足を踏み外して落ちたこともある。そ
のつど,「ボケか」と言われたりして,人からさげすまされているという思いがする。
・表だってはないが,何かを理由にして仕事がどんどん減っている。
・感覚がなく荷物を落としたり壊したりするため,職場の人からすごく言われる。
・仕事ができないことの理由がわかってもらえない。
・チッソの昭和50年度の採用試験を受けたときのこと。筆記試験が終わり,面接試験を受け
ていた時,面接試験の最後の質問で,「チッソが水俣病を起こしたことがよいか悪いか答え
なさい」と言われました。その時に,「それは悪い」と言ったら,面接官が「悪いだな」と
確認し,面接が終わった。結果は不採用だった。
・午前中しか仕事ができない。漁師なので潮加減があるが,夕方までの長時間の仕事ができな
い。
・手に力がなく配送中に店の商品を落とし,ビン類など割って弁償したりしている。
・親が認定されたとたん,縁談が破談になった人が近所にいた(相手は県外の人で,相手の両
親の反対のため)。
・仕事ができないために上司に解雇を申し渡され,職安に行こうとしたこともある。
等
水俣病以外の診断結果としてあげられていたものでは,「手足のしびれ」,「めまい」,「頭痛」,「腰痛」,「関節痛」,「原因不明」,「仕事上の疲労」等の回答があった。
<コメント>
手足のしびれというのは感覚障害の典型的な症状であり,水俣病患者には頭痛や腰痛,関
節痛などを訴える者も多くいる。診察を受けたときに,医師の側に,これらの症状が水俣病
の症状であるという理解がなかった可能性もある。
? いつ頃から病院に通っていますか。
40代〜50代の胎児性世代,小児性世代では子どものころから病院通いをしている人が多い。その一方で,最近になって通院を始めた者もいる。
<コメント>
症状によって発症の時期が異なること,複数の症状を訴える者が大半であるということ等
の事情によるものと思われる。
? どのような治療を受けていますか。
はり,きゅう,マッサージ,電気治療,湿布,漢方治療薬などといった回答が多く見られ
た。
<コメント>
これらの治療方法は保険適用外となることも多く,別途,医療費や医療手当の支給の必要
性が高いものである。
? 病院に通うことでの不都合があれば教えてください。
病院まで遠くて通院に時間がかかる,交通の便が悪いといった病院までのアクセスに関す
る回答や,1人で通院が出来ないという身体面での不都合を訴える回答,交通費や治療費な
どの経済的負担が大きいといった費用面での回答のほか,通院によって仕事に支障が生じる,
仕事を休めないので通院できない,医師の紹介が必要など不便といった回答があった。
<コメント>
未回答にはその年代には出生していなかったり幼児期であったために記憶が定かでなかった
りするものも含まれる。そのため,昭和20年代については未回答の割合が高くなっているも
のの,同年代に魚介類を摂取していないということではない。また,その年代に出生していな
い場合でも,母親が魚介類を摂取していれば胎児性の水銀暴露の問題が生じうる。
汚染地域を離れても家族から魚介類を送られてくることによってその魚介類を多食したとい
う例もあり,汚染地域を離れたことが魚介類の摂食と切り離されるとは一概には言えない。
さらに,地域によっては山間部や汚染地域と離れているような地区に居住していても行商か
ら購入したという例も見られた。
?ほぼ毎日?1週間に1回?1ヶ月に数回?ほとんど食べていない未回答
6 水俣病関係の認定申請について
(1)あなたはこれまで水俣病関係の認定申請をしたことがありますか。
ある 90名
ない 17名
(2)前項で「ある」と答えた方は下記にご回答ください。
? 認定申請(公健法)
水俣病関係の認定申請をしたことがあると回答した90名のうち,56名が公健法上の認
定申請に関しての申請状況を回答した。
結果の内訳は,認定2名,保留12名,棄却16名,申請中(審査中)8名,その他・回
答不明19名であった(1名は2回申請し,1回が棄却,1回が保留)。
? 総合対策医療事業
省略
? 政治解決(平成7年)のときの総合対策医療事業
省略
? 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決まで認定申請(公健法)をしたことがなかった
(公健法上の認定申請に関しての申請状況を回答した対象者について集計)
したことがない 37名
したことがある 19名
(3)平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決まで申請しなかった理由についてお聞きします。
(公健法上の認定申請に関しての申請状況を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴
訟最高裁判決まで認定申請をしたことがなかったと回答した対象者37名について集計。複
数回答可能。)
? 申請しても認定されないと思ったから。…5名
? 自分や家族に差別(結婚,就職,近所付き合い)などの不利益が生じると思ったから。…18名
? 認定申請についてのやり方がわからなかったから。…7名
? 自分が水俣病であることがわからなかったから。…18名
? 自分が水俣病であることを周囲に知られたくなかったから。…7名
? その他…10名
未回答…2名
<コメント>
?の差別などの不利益が生じると思ったとの回答や,?の自分が水俣病であることを周囲に
知られたくなかったという回答からは,依然として水俣病に対する差別や偏見が根強く残って
いることが窺われる。
?の申請しても認定されないと思ったというのは,現行の認定審査基準の審査が厳しすぎて,
殆どの患者が認定されないという基準の不合理性を患者が感じていることを示していると思わ
れる。
?の認定申請についてのやり方が分からなかったというのは,行政からの情報提供が不十分
であるということを示している。また,?の自分が水俣病であることが分からなかったと回答
する者も多かった(約半数)。
なお,その他の理由として,
・有機水銀による健康被害を受けていることは自覚していたが,救済を受けることができる「水
俣病」とは思わなかった。
・祖母から恥ずかしいから申請するなと言われた。近所から水俣病の人と接触するとうつるか
ら行くな等と言われていた。認定されると子どもまで差別されるかもしれないと思った。
・母親にも,歩行障害,手足のふるえ,よだれ(口回りのしびれ)の症状が強くあったが,差
別のおそれ(妹の結婚など)から申請は拒否していた。(母親自身と妹の意向)
・親戚,友人等にチッソの関係者が多いため対人関係の悪化を懸念して見送っていた。
・認定,申請方法などの制度説明は役所からもされたことは全くない。
・申請が出来ることを知らなかった。もう終わったこと,過去のことと思っていた。
・若かったので重く考えてなかった。歳を増すごとに酷くなった。
・他の都道府県に居住していたので関心を持たなかった。
等の回答があった。(但し,集計対象者外の人の回答も含む)
(4)前項で?(自分が水俣病であることがわからなかった)に○をつけた方にお聞きします。
どうして自分が水俣病であると思わなかったのですか。
(公健法上の認定申請に関しての申請情報を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴
訟最高裁判決まで認定申請をしたことがなく,その理由について「自分が水俣病であること
がわからなかったから」を選択した対象者18名について集計。複数回答可能。)
? 手足のしびれなどの感覚障害を感じなかった。…0名
? 生まれたときから手足のしびれなどの感覚障害があり,自分の症状が水俣病であるとは思わなかった。…4名
? いわゆる急性劇症型の人が水俣病であり,自分は水俣病であるとは思わなかった。…18名
? 魚を多食しておらず,水俣病になったとは思わなかった。…1名
? その他…1名
<コメント>
本項の質問の対象者全員(18名)が,?のいわゆる急性劇症型の人が水俣病であり自分が
水俣病であるとは思わなかったとの理由を選択しており,これは,水俣病に対する情報開示が
不十分であったことを示すものと言える。(なお,集計対象者外の人についても,かなりの人
数がこの選択肢を理由にあげており,有効な回答ではないが,「水俣病=急性劇症型」という
とらえ方がかなり根深く浸透していたことが窺われる。)
?の生まれたときから手足のしびれなどの感覚障害があり,自分の症状が水俣病であると思
わなかったとの回答についても,?と同様に水俣病に関する情報提供が十分になされていなか
ったことを推測させるものである。
なお,その他の理由として,
・症状が出てきたのが後からで,明確な診断がなかった。
・平成7年当時,他県にいたので,政治解決を知らなかった。行政からは何も情報提供はなかった。
・診察に行かなかったから,はっきりわからなかった。
・行政から情報提供もなかったので水俣病であるとの認識がなかった。
・他人と比較しないので,分からなかった。
・テレビで見るひどい状態の人だけが水俣病と思っていた。
等の回答があった。(但し,集計対象者外の人の回答も含む)
7 家族の申請状況について
(1)あなたの家族で,これまで水俣病の申請をした方はいますか。
いる 92名
いない 15名
(2)その方はあなたとはどのような関係の人ですか。
省略
(3)申請した結果はどうでしたか。
省略
(4)申請した時期はいつごろですか。
省略
(5)その家族の症状はどのようなものでしたか。
家族の症状についての回答は,手足のしびれやカラス曲がりなどが主であった。
(6)あなたの症状と具体的に違っていたところを述べてください。
省略
8 胎児性世代,小児性世代の健康被害について
(1)胎児性世代,小児性世代の人たち(40代,50代)と60才以上の人たちとの間で,健康被害に違いがあると思いますか。
?はい 20名
?いいえ 12名
?わからない 70名
未回答 5名
(2)そのように考えられる理由について述べて下さい。
省略
(3)手足のしびれなどについて違いがあると思いますか。
?はい 16名
?いいえ 12名
?わからない 67名
未回答 12名
(4)その理由について述べてください。
省略
(5)胎児性世代と小児性世代には何か違いがあると思いますか。
?はい 7名
?いいえ 4名
?わからない 89名
未回答 7名
9 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決後に水俣病認定申請をした方のきっかけ
(公健法上の認定申請に関しての申請情報を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴訟
最高裁判決まで認定申請(公健法)をしたことがなかったと回答した対象者37名について集計。複数回答可能。)
?知人,友人に勧められた 14名
?病院,医師に勧められた 3名
?被害者団体に勧められた 9名
?新聞報道やテレビ等を見て 2名
?家族や親戚に勧められた 11名
?その他 3名
未回答 5名
10 新保険手帳の申請をされた方のきっかけ
?知人,友人に勧められた 18名
?病院,医師に勧められた 2名
?被害者団体に勧められた 7名
?新聞報道やテレビ等を見て 0名
?家族や親戚に勧められた 13名
11 不知火海沿岸全域の健康調査について
(1)国,県の費用負担で調査を実施すべきである。(○をつけてください)
?はい 88名
?いいえ 7名
?どちらでもない 12名
(2)今から調査して健康被害の実態はわかると思いますか。(○をつけてください)
?はい 77名
?いいえ 19名
?どちらでもない 11名
(3)また,その理由について答えてください。
? 調査が必要であると回答した理由
早期解決のために国などによる健康調査の必要性に言及するもの,水俣病が未解決であるに
もかかわらず,一般には「終わったもの」と受けとめられているものに言及するもの等が多く
見られた。
・汚染地域の人たちが水俣病ということで差別されると思い,申請さえもできないでいる人が
まだ多くいる。調査をすれば実態が分かる。
・行政が健康診断のように行えば,多くの人が診断を受けると思う。
・現実に被害があって苦しんでいる人がたくさんいる。家庭訪問も取り入れるべきである。
・まだ水俣病であると気づいていない患者も多い。
・診断基準に納得ができない。症状に応じて判断されていないと思う。
・後から症状が出てきている人もいるので,調査には意味がある。
・感覚障害等が水俣病であるという情報は全く得られず,行政からも情報提供はなされなかった。
・あれだけの水銀を食べさせられていても「偽患者」と言われる。きちんと調査をしてほしい。
?調査を実施すべきであるか,健康被害の実態は分かるか,について「いいえ」あるいは「どちらでもない」と回答した理由
・調べる側のさじ加減次第。良くなるとは思わない。
・調査手法に疑問。
・水俣病であると偽った人がいた。本当に水俣病であることが分かるのか疑わしい。
・健康被害のある人は,既に各自が病院で検査済み。
・今頃,という感じ。遅すぎる。
・チッソ関係の仕事をしている人からは嫌がられることがある。
・今になって調査にお金をかけるのではなく,補償に回して欲しい。
12 水俣病の認定(公健法)基準について
(1)基準についてどのように考えていますか。(○をつけてください)
?きびしすぎる 88名
?妥当である 6名
?どちらでもない 13名
(2)そのように考える理由について述べて下さい。
基準がきびしすぎるとする理由としては,ほとんど申請が認められない,昭和52年より以
前の判断基準にすべきである,とするものが多数を占めた。中には,胎児性,小児性について
もっと解明すべきとするものも見られた。
一方,基準は妥当であるとする理由としては,きちんと検査をすれば自分が水俣病であるこ
とは分かるはず(認定審査会の運用の問題点を指摘する趣旨で述べられている)とするものが
見られた。
(3)基準を改訂すべきであると思いますか。
?きびしすぎる(はい) 81名
?妥当である(いいえ) 5名
?どちらでもない 14名
未回答 7名
(4)そのように考える理由について述べてください。
基準を改訂すべきであるとする理由としては,被害状況に応じ被害者を救済すべきとの趣旨
の回答が多数を占め,その他,関西水俣訴訟最高裁判決に準ずべきとの趣旨の回答も見られた。
一方,基準を改訂する必要はないとする理由としては,きちんと検査をすれば自分が水俣病
であることは分かるはず(認定審査会の運用の問題点を指摘する趣旨で述べられている)とす
るものが見られた。
13 今回の調査に関する自由記載
自由記載欄には患者の様々な思いが綴られていた。その内の一部を紹介することとする。
・水俣病はまだ終わっていない。水俣病患者はまだ救済されていないということを全国の皆さ
んに知っていただきたい。劇症型の水俣病で,軽いのはニセ患者だと思っている人が非常に
多いが,正しく水俣病のことを知ってほしい。水俣病の全面救済を1日も早くしてほしい。
全面救済をするには汚染地区の住民の全部の健康調査をしなければならない。
・平成7年の時に申請していない。ちょうどこのころからしびれを感じ始めた。水俣病の症状
を当時あまり知らなかった。水俣病の申請ができるとは思わなかった。
・もっと掘り下げて調べて欲しい。水俣病は終わったと思っている人が多い。多くの人に水俣
病について知って欲しい。
・子どもの頃から水俣病の症状に苦しめられてきた。私の母も同じ。母が水俣病だったか私に
は分かりませんが,私と同じ症状で苦しめられながら亡くなりました。もし,チッソの水銀
が原因でこうなったのであれば,チッソには責任をとってもらいたい。チッソの利益のため
に,私たちは何も知らずに自分の人生を台無しにされました。それを切りがないはないでし
ょう。最後の1人まで補償するのは当たり前のことです。たとえ,過失であっても,もし私
がチッソの立場だったら責任を取らされていますよ。
・この世に生まれる前から母胎の中で水銀にまみれ,生まれ落ちてすぐから命をつなぐため,
水銀に汚染された母親の母乳を飲まされて,生きなければならなかった赤ん坊。何も知らな
いで,愛しいわが子のために毒の入ったお乳を飲ませた母親。何の疑いも持たないで,無心
にお乳を飲み続けた末に水銀に身体をむしばまれて生きるしかない子どもたちが存在してい
るという現状をちゃんと見て欲しいと思う。50年以上の人生を水銀に苦しめられながら生
きてきて,これからもそれはもっと酷くなって続いていくという現実があることをしっかり
と認めて欲しい。
・汚染のことは聞いていたが,魚屋で売っているものだからと思って食べた。症状の重い人は
長年食べているからで,自分は未だ症状は出ないだろうと思った。申請した人に対する中傷
として,「申請されたとよー,まだ若いかモンのそがんことのあるもんか」という話を聞い
ていた。自分も申請したら同じように言われると思った。嫁ぎ先の両親も否定的だった。当
初は劇症型だけが「水俣病」だと思っていたが,新聞等で感覚障害でも「水俣病」であり,
メチル水銀が原因と報道されているので,そうであれば,自分も水俣病ではないかと思うよ
うになった。
・水俣湾だけの話だと思っていた。獅子島でも水俣患者がいることは平成18年になって始めて知った。悔しい,残念,どうして早く教えてくれなかったのかと。水俣病についての知識はあったが,自分の症状が水俣病だとは思っていなかった。昨年の12月に友人が水俣病の話があるので行くように誘われた。その際に「症状」を聞いた所,自分の症状とあっていることに驚いた。市役所に照会し,患者団体を紹介された。それ以前は関心もなかった。水俣病の患者は特別の人だろうと思っていた。
・胎児性世代についてちゃんと検査してほしい。漁師で毎日魚を食べていて「棄却」では納得できない。現在,手足の多少の麻痺(転びやすい),足のしびれ,カラス曲がりなどで障害も多いのに,まったく認定の外とはおかしい。自分が水俣病でないというのはどう考えてもおかしい。どうしても進展しなければ裁判も考えている。将来が不安。症状はひどくなっている感じがする。
・目に見えない症状をもっている人に対してもしっかり理解してあげるべきだ。苦しんでいる人は多くいる。自分でもよく分からないことが多く,判断できない。
・自分は早いうちから水俣病のおそれありと言われていたが,なかなか認定されなかった。同じ症状のある人でも認定に差があるのはおかしいのではないか。会社は責任を認めて,できる限り救済してもらいたい。
・チッソの対応に不満がある。テレビ等で見聞きするチッソの態度や意見に腹が立つ。
・水俣病の調査は行政がすべきものである。行政がきちんと住民の健康調査を行い,水俣病の全面的な救済をすべきである。
・不知火海沿岸の住民の健康調査を実施して,早くすべての人々を救済してほしい。そうしないと再び何回も裁判等の問題が今後起こってくると思う。
・何回も同じような調査をされている。社会に反映されていないのではないか。
・医者の検診の時は2〜3分見ただけで「ここはどうですか」って聞かれて「えぇ」ていったらそれでおしまい。「ここがおかしい」と言ったら 「そのようなことは言わなくてよい。聞いていることだけ答えろ」と言われた。これが実情。これでは検診とは言えない。
・打ち切られても今後水俣病の人が出てくる可能性が極めて高い。水俣病は年をとって気づくことが多いので。
・水俣病の重さによって,例えば5段階で認定して重さに応じて補償をすべきではないか。オール・オア・ナッシングは不当。裁判をしている高齢者は苦しんでいる。国に対策を望む。
・いろいろな調査が度重なっているので,現実的な救済を早期にしてほしい。チッソにはこの問題から逃げることなく,責任をとって救済に取り組んでほしい。
・基準を考え直してほしい。疫学を重視すべきである。行政から情報がきたことはない。行政の怠慢である。高齢化しており,早く解決してほしい。医師も経験がなく,診断能力がない。
・症状は人によって様々である。検査もそれにマッチしたものにしてほしい。今回の調査が,基準見直し,患者切り捨てでない方向に行くためのきっかけとなることを望む。
・被害者も高齢化しており,早く解決し,救済してほしい。救済が進まないことについて,特にチッソの対応については腹立たしい。調査を進め,救済してほしい。
・現在被害者団体に入り少しずつ水俣病のことについて分かるようになったが,若いときから関係があったとは思いもしなかった。いとこたちがたくさんいて,水俣病であったことは知っていたが,自分も同じ水俣病であることが分かったのがあまりにも遅すぎた。残念でならない。でも,この機会に自分たちが水俣病であることが分かったことは幸いであった。遅くなったとはいえ自分たちがやらなければいけないこと,出来ることは進んで参加し,みんなで協力して頑張りたいと思う。
・今,申請している人たちの中にも1800万円に相当する重い被害者はたくさんいる。150万で一律救済ならば全員救済にしてほしい。程度の差に応じて補償する制度を作るべき。行政側が,税金が高くなったのは水俣病患者が多く出てきたせいだとあちこちで言っている。そのせいで町民が水俣病のせいでと思うようになっている傾向もある。
・このままだと地球が危ない。大変苦労してきた。後がない。
・生きているうちに補償してほしい。それが一番。自分が死んだ後に残される娘のことがとても心配。娘は水俣病が一番ひどかったときに生まれた。
・水俣病は終わりではないので弁護士の方も力を貸して下さい。1人でも多くの人を救済してください。
・日弁連の調査はありがたい。この調査結果を国・県は,重く受け止めて水俣病解決に努めてほしい。
・被害者の相談には乗ってくれた弁護士に頑張ってもらっていることで心強い,一緒に頑張ってほしい。チッソの分社化は被害者にとってマイナスになるのでは。
・聞き取りがあったことで,これまで言いにくかったことをみんなに伝えて,理解してもらえることがよかった。以前より,基準が緩和されているように思える。申請しやすくなっているように思える。
以 上
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/minamata_houkokusyo_000.pdf
2008年10月
日本弁護士連合会
第1 調査の概要
1 調査の目的
2 調査の方法
3 調査の概要
4 調査結果を見る上での注意点
第2 調査分析
1 基本情報について
2 現在の健康被害の内容について
3 居住歴,生活歴等について
4 昭和20年代から昭和40年代まで不知火海の魚介類の摂取状況
5 家族構成・同居していた家族について
6 水俣病関係の認定申請について
7 家族の申請状況について
8 胎児性世代,小児性世代の健康被害について
9 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決後に水俣病認定申請をした方のきっかけ
10 新保険手帳の申請をされた方のきっかけ
11 不知火海沿岸全域の健康調査について
12 水俣病の認定(公健法)基準について
13 今回の調査に関する自由記載
第1 調査の概要
1 調査の目的
日本弁護士連合会は,1977年の人権擁護大会において「公害被害者の救済に関する決議」
を採択し,それ以降,水俣病問題についての調査研究を重ね,被害者の方の即時・完全救済等
を求める決議,具体的方策の提言などを行ってきた。
そして,2007年7月に「与党水俣病問題に関するプロジェクトチーム」が公表した「水
俣病に係る新たな救済策について(中間取りまとめ)」を受け,同年9月14日に「水俣病問
題について抜本的な救済策を求める意見書」を発表した。同意見書では,公健法に基づく救済
策を抜本的に改め,新たに総合的な救済施策を講じるべきであることを提案するとともに,新
たな救済施策の具体的内容として,水俣病認定基準の抜本的改定,水俣病患者に対する十分な
補償,水俣病患者に対する医療面,福祉面に対する恒久対策,国及び熊本県による経済的負担
等の事項を提示した。また,水俣病患者の実効的な救済を図るために,不知火海岸沿岸の健康
調査を早急かつ網羅的に行うべきことを提案した。
その後,与党水俣病問題に関するプロジェクトチームが救済策の実現に向けて検討を重ねて
いるが,依然として公健法に基づく認定基準を堅持する態度を変えておらず,また,一時金の
金額も関西水俣病訴訟最高裁判決の水準額(400万円から800万円)を大幅に下回る金額
(150万円)しか提示していないなど,当連合会が発表している提言からすると未だ不十分
なものにとどまっていると言わざるを得ない。また,国による不知火沿岸の健康調査も未だに
実施されていない。
そこで,当連合会としては,現地を訪れて水俣病患者の被害実態を調査することにより,具
体的なあるべき救済施策を研究し,今後も引き続き国に対して提言をしていく必要があると考
え,九州弁護士会連合会及び熊本県弁護士会の協力を得て,水俣病問題に関する被害実態調査
を実施した。
2 調査の方法
(1)調査対象
水俣病患者団体に実態調査協力の依頼をし,107名から協力を得られた。
(2)調査期間
2008年6月14日から同月15日まで。
(3)調査方法
調査事項書自己記入後,弁護士による個別面接調査。
なお,実態調査に携わった弁護士は,日本弁護士連合会人権擁護委員会委員5名,人権救済
調査室嘱託1名,同公害対策・環境保全委員会委員3名,九州弁護士会連合会人権擁護委員会
委員10名,熊本県弁護士会会員3名の合計22名である。
3 水俣病実態調査の概要
調査結果の概要は以下の通りである。
(1)現在の健康被害の内容について
今回の調査対象者は,実際にはほとんどの者が公健法上の水俣病患者としては認定されてい
ないが,次のとおり,四肢抹消優位の感覚障害,運動失調,視野狭窄のいずれについても異常
を訴えている者が多く存在した。
○感覚の異常である手足のしびれについては,すべての調査対象者が何らかの異常を訴えていた。
○手足の感覚麻痺については,調査対象者107名のうち93名が何らかの異常を訴えていた。
○上下肢の運動症状については,ほとんどの調査対象者が,つまずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいなど何らかの異常を訴えていた。
○視野狭窄については,調査対象者107名のうち93名が何らかの異常を訴えていた。
このデータから,感覚麻痺の有無だけを基準にするだけでは割り切れない患者が多数存在す
ることが窺われ,また,厳密な診察をすれば相当程度の者が水俣病と認定されるのではないか
と推測されるという結果が得られた。
(2)日常生活や仕事への影響について
日常生活上については,すべての調査対象者が何らかの支障を訴えていた。具体的には,足
のこむらがえり,常時疲れやすい,関節が痛い,耳鳴りがひどいなど身体的な症状を訴えてい
たり,茶碗を落として割ったりする,車の運転をしているとき横がまともに見えない,風呂の
湯加減が分からないなどの日常生活上の支障を訴えていた。
仕事面については,漁業に携わっている人が多い関係から,重い船具を持つことができない,
荷物を運ぼうとすると落としてしまう,網の修理が苦手であるなどの支障を訴える者が多かっ
た。そのほか,立ちくらみ,めまいのため仕事がしにくい,目を使う仕事ができない,補助的
な仕事に限定される,脚立など高い所へあがれないなどの支障も観られた。
日常生活や仕事面での差別等については,特にないと回答した者も多く存在したが,様々な
不利益,差別を受けたことがあると回答した者も多かった。具体的には,「大した症状もない
のにお金をもらっている」と悪口を言われる,医療費を支払わないことについて詐病ではない
かと言われる,見合いをしても水俣病の話が出ると相手から断られるなどの差別が見られた。
(3)病院での診察について
ほとんどの調査対象者がこれまで病院にかかったことがあったと回答しているが,水俣病あ
るいは水俣病の疑いとの診断を受けた者は,60代〜70代では約54%であったが,40代
〜50代では約30%にとどまった。治療内容については,保険適用外となるものも少なくな
く,はり,きゅう,マッサージ,電気治療,湿布,漢方治療薬などを利用している者も多く存
在した。
(4)公健法上の水俣病の認定申請について
公健法上の水俣病の認定申請を行っていた者は56名であり,そのうち,平成16年10月
15日の関西水俣病訴訟最高裁判決まで公健法上の水俣病の認定申請を行っていなかった者は
37名であった。認定申請をしていなかった理由については,「自分や家族に差別(結婚,就
職,近所付き合い)などの不利益が生じると思った」「自分が水俣病であることが分からなか
った」などが多く,依然として差別や偏見が根強く残っていること,水俣病に関する情報が十
分に周知徹底されていないことが窺われた。
(5)不知火海沿岸の健康調査について
調査対象者の約82%が不知火海沿岸の健康調査について,国,県の負担で実施すべきであ
ると回答をし,調査対象者の約72%が,今から調査をすれば健康被害の実態は分かると回答
しており,多くの者が実態調査を希望していることが判明した。
(6)認定基準について
調査対象者の約82%が現行の公健法上の水俣病の認定基準は厳しすぎると回答し,約7
6%が現行の基準を変えるべきであると回答していた。多くの者が,被害状況に応じた救済が
なされていないと感じていることが窺われた。
4 調査結果を見る上での注意点
今回の実態調査にあたっては,無作為抽出的に対象者を選出するのではなく,既存の水俣病
患者団体に実態調査協力の依頼をし,各水俣病患者団体において患者を選定してもらっている。
調査対象者数も僅か107名であることから,今回の調査結果が水俣病患者の全体の実態を反
映しているとは限らない。
また,今回の実態調査では,例えば「公健法上の水俣病の認定申請」について自分が申請を
しているか否かが不明であったり,過去の状況について一部記憶が定かでなかったりする事例
も見られた。限られた時間の聞き取り調査であったため,設問の内容によっては,必ずしも統
計的に正しいデータが得られていない可能性があることを付言しておく。そこで,今回の実態
調査においては,正確な数字よりも,患者の状況や特徴についての傾向を把握する趣旨で見て
いただければ幸いである。
なお,質問項目の中には,「いつ頃から症状が出ているのですか。」というような個々の患
者によって状況が異なり,集計が困難なものもある。そのような場合,集計結果を省略させて
頂いている点をご容赦されたい。
また,集計は,弁護士による個別面談を経て修正,加筆された調査事項書を基にしている。
第2 調査分析
以下,調査事項書の質問事項順に集計結果を記載する。
なお,前述のとおり集計が困難な質問項目については,記載を省略している。
1 基本情報について
<調査結果の補足説明>
?の手足のしびれについて
手足のしびれについては調査対象者107名全員が感覚の異常である手足のしびれを訴え
ていたということになる。40代〜50代の胎児性世代,小児性世代の患者と60代〜70
代の患者とでは,その傾向はほとんど変わらなかった。
?つまずきやすい,転びやすい・?細かい作業がしにくいについて
つまずきやすい,転びやすいは下肢運動症状に,?細かい作業がしにくいは上肢運動症状
に該当する。
つまずきやすい,転びやすいは,年代に関わらず,ほとんどの調査対象者が症状の異常を
訴えている。
また,細かい作業がしにくいという症状についても,年代に関わらず,ほとんどの調査対
象者が症状の異常を訴えていた。
なお,つまずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいという症状について,いずれ
もなしと答えている者はおらず,すべての調査対象者が何らかの異常を訴えていた。
<コメント>
?の手足の感覚麻痺について
手足の感覚麻痺については調査対象者107名のうち,93名が何らかの異常を訴えてい
た。そのうち,40代〜50代では,感覚麻痺が「常時」と回答した者よりも「時々」と回
答した者の方が多かったが,60代〜70代では,「常時」と回答した者が「時々」と回答し
た者の2倍となっていた。今回の調査だけでははっきりとしたことは言えないが,40代〜
50代と60代〜70代との間で感覚麻痺について「常時」と「時々」との間に差があると
いうことに関して,一定の有意性が認められる可能性がある。
なお,今回の調査では40代〜50代の患者のうち,感覚麻痺についてなしと答えた者が
4名いた。しかしながら,前述した?のとおり,40代〜50代の調査対象者の全てが,つ
まずきやすい,転びやすい,細かい作業がしにくいなどという症状を訴えており,感覚麻痺
はないものの,運動症状に何らかの異常を来している者も相当数存在していると考えられる。
このようなことから,感覚麻痺の有無だけを基準にするだけでは割り切れない症状の患者が
相当数存在することが窺われた。
?の全身の感覚麻痺について
全身の感覚麻痺については調査対象者107名のうち半数近くの者が何らかの異常を訴え
ていた。
但し,例えば手足の先ではなく腕の部分に感覚麻痺を感じた場合に,回答する側からする
と,これが全身性の感覚麻痺なのか,四肢末梢の感覚麻痺なのかは判然としない場合も少な
くなかったようである。全身性か末梢の感覚障害かは厳密に専門の医者の検査によって判断
しないと誤るおそれがあると言えよう。言い換えれば,水俣病の診断基準のうち「感覚障害」
の取り方には十分に注意して行う必要があるということになる。
?視野狭窄について
視野狭窄の何らかの異常を訴えている者の割合は,全部で93名と約87%であり,40
代〜50代でも異常を訴えるのは53名中44名と約83%である。今回の調査では視野狭
窄を訴えている者の割合がかなり高い。これは,調査対象者の選別について比較的重症の患
者が選択されたのではないかと推測される。
○健康被害についての総合的なコメント
前記内容を総合し,40代〜50代の調査対象者で,?感覚障害(感覚麻痺),?運動失調,
?視野狭窄について複数の異常を訴えている人たちがどれくらいいるのかという統計を出し
たところ,次のような結果が得られた。
?の感覚障害については,常時か時々の別はあるものの,全員が手足のしびれを訴えてお
り(?の「手足のしびれ」),また,約87%の人が手足の感覚麻痺を訴えている(?の「手
足の感覚麻痺」)。従って何らかの手足の感覚障害という意味では,全員が異常を訴えている
ということになる。
?の運動失調については,上肢と下肢に若干の違いがあるが,常時,時々を含めて何らか
の運動失調がある者は全員である(?のつまずきやすい,転びやすいが下肢に関する運動失
調。?の細かい作業がしにくいが上肢に関する運動失調)。
?視野狭窄については,40代〜50代の患者の53名のうち44名が常時または時々の
異常を訴えている(?の視野狭窄)。
すなわち,今回の調査対象者については,実際には,ほとんどの者が公健法上の水俣病患
者としては認定されていないが(6項?参照),四肢抹消優位の感覚障害,運動失調,視野狭
窄のいずれについても異常を訴えている者が大多数であることを考えると,厳密な診察をす
れば相当程度の者が水俣病と認定されるのではないかと推測される。
(2)いつ頃から症状が出ているのですか。
症状や回答者によって異なる回答であった。但し,症状の種類を問わず,年齢を重ねるごとに症状が悪化している傾向にあるようであった。
(3)上記の症状による日常生活や仕事への影響についてお聞きします。
? 日常生活においてどのような支障が生じていますか。
今回の調査対象者の全員が,日常生活上の何らの支障を訴えている。以下に,具体例を紹介する。
・足のこむらがえり。
・常時疲れやすい。
・人の支えがないと歩くのが困難。
・関節が痛い。
・手足のしびれ。
・小さい物をうまくつまめない。
・手足のしびれのため,例えば,けがをしてもあまり痛みを感じないので,いつ,どこで怪我をしたのかが分からない。血が出ているのを見て初めて気が付く程度。
・夜よく寝られない。
・カラス曲がりなど日常茶飯事で,ひどいときは30分,40分つりっぱなしの時もある。
・耳鳴りがひどく,人の声が聞こえないので,自分もついつい大声で話してしまう。
・心臓に不整脈がある(ニトロを持っている)。
・茶碗を落として割ったりする。
・1人で布団も干せない。
・箸がうまく使えない。
・言葉がどもり,人に挨拶などができない。
・人間関係が作れない。子ども時代から症状があり友達ができなかった。
・物をつかんでいる感覚がない。
・手がふるえるのでお茶を出すのが嫌。
・味付けが濃すぎたり,薄すぎたりする。
・車の運転をしているとき,横がまともに見えない。
・細かい仕事がつらい(手の震え)。
・脱いだつもりのつっかけが脱げなくて,そのまま上ってしまう。段差に躓いて,転倒し,骨折した。
・一番困るのは眼。手術のしようがないと言われている。新聞は読めない。目薬は1日1本必要。
・風呂に入るとき心臓から下までしか浸かれない。
・風呂の湯加減がわからない。
・怖くて水泳ができない。
・長く座っているのが苦痛。長く座っていると足がしびれて固まって立ち上がれなくなる。あぐらが長時間できない。座敷の食事等がつらく,早く終わってくれないかと思ってしまう。
・忘れてしまって何度も尋ねることがある。
・家の外にはほとんど出ない。テレビも見ない。本も読まない。家では掃除,洗濯をしているが頭が痛かったりだるかったりするので,掃除,洗濯を毎日することはできない。他は何もしていない。
・左右の視力が違い,また,視力も変わってくるため眼鏡が合わない。そのため,頭痛がする。
・何を食べてもおいしくない。等
? 仕事面で何か不都合や被害を受けたりしていますか。
仕事への支障についての訴えのみならず,それによる周囲からの反応について回答するものも見られた。以下に,具体例を紹介する。
・仕事に就いたことがない。
・補助的な仕事に限定される。スーパーのレジの仕事などしかできない。
・目を使う仕事ができない。
・長期間機械を扱うと,調子が悪くなる(腕など)。疲れやすいとは思う。
・指先にとげなどが刺さっていても気づかない。
・仕事中に休むことが多くなった。細かい作業ができないので困ることがある。同じ状態でいられない。重い物を抱えると,つって,しばらく腕をのばせない。
・立ちくらみ,めまいのため仕事がしにくい。県外で仕事しているとき,水俣出身ということがわかると「あなたも泡をふくんじゃないの?」などと言われた。
・パートに出たが,水俣病のことを言われた。私は申請中とは言わず黙っていたが,居づらくなり辞めてしまいまった。農作業も身体が痛く,していない。
・細かい作業が出来ない。文字を書けないのが,一番つらい。
・ひざが曲がらないので座るときは足を投げ出さないといけない。和式トイレが使えない。草むしりができない。
・手に力が入らないので,雑巾が絞れず,仕事の手伝いができなくなった。
・脚立など高い所へ上がれない。
・手が震えてハンダ付けができないときがある。
・手の感覚がないので,痛みを感じない。水俣病報道でよく登場したこともあり,会社から「お前はなぜ自分が水俣病だと言うのか」「お前の血は青いんだろう」「神経が通っていないんだろう」と言われた。
・物忘れ。商品の陳列がうまくできず,時間がかかる。
・高校卒業後,国鉄の試験を受けたが,耳鳴りのために面接,身体検査で落ちた。
・声が聞き取りにくいのですぐに返答できない。電話対応に困る。
・何か言われていることはわかるが,中身がわからないので何度も聞き直す。
・網を引く作業が船の上なので,すぐ転んで青あざができてしまう。手の握力も17〜18kgしかない。
・船の修理の仕事をしている。仕事に関してお客から信用を失いつつある。なくなっているかもしれない。仕事の集中力というか取り組みにむらがある。
・重たい船具(2kg)を持てないことがある。
・海上タクシーの仕事をしているが,荷物を運ぼうとすると落としてしまう。弁償することもあった。
・若い頃から漁業の網の修理が苦手だった。道具に糸が通らない。
・漁は2人でする仕事なので,自分が休めば夫も漁に行けず仕事が出来ない。よって収入減となる。子どもを育てるためには毎日漁に行かねばならない。
・農作業中にハサミ,のこを落とす。
・腰痛や肩こりがひどくなり痛み止めの注射を打つことが多く,通院しながらの農作業で仕事も進まない事も多い。人に代わってもらうことも多い。
・建設関係の仕事をしているが,手足のしびれがあるため測量作業がうまくできないことが多く,他の人から「他の人に代われ」と言われることがある。
・建設関係の仕事なので段差のある足場での作業(上り下り)がきつい。
・靴下工場で細かい作業だったので大変でした。
・手足が自由でないために,作業中に指を切断した。等
? 日常生活や仕事の面で不利益を生じたり,差別を受けたりしたことがありますか。
特にないと回答したものも多く存在したが,様々な不利益,差別を受けたりしたことがあると回答しているものも多かった。具体的な不利益,差別事例についての訴えを紹介する。
・高卒後,大阪で過ごしていたところ,テレビで水俣病のニュースが流れると「あなたの郷里
が映っている」等と言われ恥ずかしかった。夫の母が福岡の病院で手術を受けた。母は医療
手帳を持っていたので医療費がかからないが,看護師は医療手帳を見て,「これ何ですか!」
と驚いた。他の患者は支払をしているのに母だけ払わない扱いを説明するのに大変だった。
・差別についてあるとは思うが「大した症状もないのにお金をもらっている」「お金をほしが
っている」と悪口を言われる。だから自分も友達にもいえない。
・水俣病について活動(ビラ配り)をしていると,通行人の女性から「ニセ患者」と言われた。
・いとこが認定患者で胎児性患者を産んでいるが,差別を受けているのを見てきた。身内に漁
業関係者がいて,迷惑がられた。汽車では水俣で窓を閉めていた。
・自分ではないが,妹が「そんな身体なら家の人も早くいなくなればいいと思う」などと心な
い言葉をかけられた。
・薬剤師から,「認定患者だけが本当の患者だ,薬のありがたみが分かっていない,薬のお金
を払っていない,自分たちが払った税金が使われている」などと言われた。
・医療費を支払わないことについて,詐病ではないかと言われたことがある。「あんた達はよ
かなー,手帳もらえてなー,医療費がただで!」
・子どもが結婚前だったから申請しなかった。差別されるから。それまで手足のしびれはない
と言って隠していた。
・集会場などで声が聞きづらく困る。耳が聞こえないことで「つんぼ」とか言われる。隣家の
人が,結婚が破談になったという話を聞いた。
・お金目当てと言われる。
・水俣病だとお嫁に行けないなどと言われていたし,あえて調べようとは思っていなかった。
今までは,ただの神経痛ではないかと思っていたが,平成16年頃に水俣病のことを知って,
平成7年の政治解決の時もまさか自分が水俣病だとは思わなかった。
・裁判をしているので,「金がほしくてやっている,それくらいは誰でも身体に異常はある」
という悪口を言われる。父が認定されたときもニセ患者と言われた。
・ある人から「指輪など似合わない手だ」と言われた。口をつぐんで通行したり,けがらわし
いなどといわれた。行政からの正確な情報提供がないため。
・自分も見合いをしたが,水俣病の話が出ると,相手が断ってきたりした。結局,水俣病のこ
とをよく知らない外国人の女性と結婚した。
・テレビに出たあと差別を受けた。今の職場もいつ辞めさせられるか分からない。
・実家から送ってくる魚をおすそわけすると,「水俣からきたものだから嫌だ」と言われたこ
とはある。
・今現在はそうでもないが,幼小時期は冷たい目でみられたこともある。島外に出ていて結婚
していた際,県営住宅にいたとき,「笑わない人がきた」とか色々なことをいわれた。
・学校生活のときいじめられた。但し,水俣病との自覚はなく,トロイのが原因でいじめられ
ていると思っていた。
・小学校,中学校のとき悪口を言われた。近所のおばさんに会った際に父,母,妹だけに声を
かけて,自分に声をかけないということもあった。腹も立つし,とても悲しい。今でもそう
である。
・無理な仕事ができなくなった(手先や目を使う仕事ができない)。
・仕事中でもよくころぶことがある。高所のよう壁から足を踏み外して落ちたこともある。そ
のつど,「ボケか」と言われたりして,人からさげすまされているという思いがする。
・表だってはないが,何かを理由にして仕事がどんどん減っている。
・感覚がなく荷物を落としたり壊したりするため,職場の人からすごく言われる。
・仕事ができないことの理由がわかってもらえない。
・チッソの昭和50年度の採用試験を受けたときのこと。筆記試験が終わり,面接試験を受け
ていた時,面接試験の最後の質問で,「チッソが水俣病を起こしたことがよいか悪いか答え
なさい」と言われました。その時に,「それは悪い」と言ったら,面接官が「悪いだな」と
確認し,面接が終わった。結果は不採用だった。
・午前中しか仕事ができない。漁師なので潮加減があるが,夕方までの長時間の仕事ができな
い。
・手に力がなく配送中に店の商品を落とし,ビン類など割って弁償したりしている。
・親が認定されたとたん,縁談が破談になった人が近所にいた(相手は県外の人で,相手の両
親の反対のため)。
・仕事ができないために上司に解雇を申し渡され,職安に行こうとしたこともある。
等
水俣病以外の診断結果としてあげられていたものでは,「手足のしびれ」,「めまい」,「頭痛」,「腰痛」,「関節痛」,「原因不明」,「仕事上の疲労」等の回答があった。
<コメント>
手足のしびれというのは感覚障害の典型的な症状であり,水俣病患者には頭痛や腰痛,関
節痛などを訴える者も多くいる。診察を受けたときに,医師の側に,これらの症状が水俣病
の症状であるという理解がなかった可能性もある。
? いつ頃から病院に通っていますか。
40代〜50代の胎児性世代,小児性世代では子どものころから病院通いをしている人が多い。その一方で,最近になって通院を始めた者もいる。
<コメント>
症状によって発症の時期が異なること,複数の症状を訴える者が大半であるということ等
の事情によるものと思われる。
? どのような治療を受けていますか。
はり,きゅう,マッサージ,電気治療,湿布,漢方治療薬などといった回答が多く見られ
た。
<コメント>
これらの治療方法は保険適用外となることも多く,別途,医療費や医療手当の支給の必要
性が高いものである。
? 病院に通うことでの不都合があれば教えてください。
病院まで遠くて通院に時間がかかる,交通の便が悪いといった病院までのアクセスに関す
る回答や,1人で通院が出来ないという身体面での不都合を訴える回答,交通費や治療費な
どの経済的負担が大きいといった費用面での回答のほか,通院によって仕事に支障が生じる,
仕事を休めないので通院できない,医師の紹介が必要など不便といった回答があった。
<コメント>
未回答にはその年代には出生していなかったり幼児期であったために記憶が定かでなかった
りするものも含まれる。そのため,昭和20年代については未回答の割合が高くなっているも
のの,同年代に魚介類を摂取していないということではない。また,その年代に出生していな
い場合でも,母親が魚介類を摂取していれば胎児性の水銀暴露の問題が生じうる。
汚染地域を離れても家族から魚介類を送られてくることによってその魚介類を多食したとい
う例もあり,汚染地域を離れたことが魚介類の摂食と切り離されるとは一概には言えない。
さらに,地域によっては山間部や汚染地域と離れているような地区に居住していても行商か
ら購入したという例も見られた。
?ほぼ毎日?1週間に1回?1ヶ月に数回?ほとんど食べていない未回答
6 水俣病関係の認定申請について
(1)あなたはこれまで水俣病関係の認定申請をしたことがありますか。
ある 90名
ない 17名
(2)前項で「ある」と答えた方は下記にご回答ください。
? 認定申請(公健法)
水俣病関係の認定申請をしたことがあると回答した90名のうち,56名が公健法上の認
定申請に関しての申請状況を回答した。
結果の内訳は,認定2名,保留12名,棄却16名,申請中(審査中)8名,その他・回
答不明19名であった(1名は2回申請し,1回が棄却,1回が保留)。
? 総合対策医療事業
省略
? 政治解決(平成7年)のときの総合対策医療事業
省略
? 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決まで認定申請(公健法)をしたことがなかった
(公健法上の認定申請に関しての申請状況を回答した対象者について集計)
したことがない 37名
したことがある 19名
(3)平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決まで申請しなかった理由についてお聞きします。
(公健法上の認定申請に関しての申請状況を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴
訟最高裁判決まで認定申請をしたことがなかったと回答した対象者37名について集計。複
数回答可能。)
? 申請しても認定されないと思ったから。…5名
? 自分や家族に差別(結婚,就職,近所付き合い)などの不利益が生じると思ったから。…18名
? 認定申請についてのやり方がわからなかったから。…7名
? 自分が水俣病であることがわからなかったから。…18名
? 自分が水俣病であることを周囲に知られたくなかったから。…7名
? その他…10名
未回答…2名
<コメント>
?の差別などの不利益が生じると思ったとの回答や,?の自分が水俣病であることを周囲に
知られたくなかったという回答からは,依然として水俣病に対する差別や偏見が根強く残って
いることが窺われる。
?の申請しても認定されないと思ったというのは,現行の認定審査基準の審査が厳しすぎて,
殆どの患者が認定されないという基準の不合理性を患者が感じていることを示していると思わ
れる。
?の認定申請についてのやり方が分からなかったというのは,行政からの情報提供が不十分
であるということを示している。また,?の自分が水俣病であることが分からなかったと回答
する者も多かった(約半数)。
なお,その他の理由として,
・有機水銀による健康被害を受けていることは自覚していたが,救済を受けることができる「水
俣病」とは思わなかった。
・祖母から恥ずかしいから申請するなと言われた。近所から水俣病の人と接触するとうつるか
ら行くな等と言われていた。認定されると子どもまで差別されるかもしれないと思った。
・母親にも,歩行障害,手足のふるえ,よだれ(口回りのしびれ)の症状が強くあったが,差
別のおそれ(妹の結婚など)から申請は拒否していた。(母親自身と妹の意向)
・親戚,友人等にチッソの関係者が多いため対人関係の悪化を懸念して見送っていた。
・認定,申請方法などの制度説明は役所からもされたことは全くない。
・申請が出来ることを知らなかった。もう終わったこと,過去のことと思っていた。
・若かったので重く考えてなかった。歳を増すごとに酷くなった。
・他の都道府県に居住していたので関心を持たなかった。
等の回答があった。(但し,集計対象者外の人の回答も含む)
(4)前項で?(自分が水俣病であることがわからなかった)に○をつけた方にお聞きします。
どうして自分が水俣病であると思わなかったのですか。
(公健法上の認定申請に関しての申請情報を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴
訟最高裁判決まで認定申請をしたことがなく,その理由について「自分が水俣病であること
がわからなかったから」を選択した対象者18名について集計。複数回答可能。)
? 手足のしびれなどの感覚障害を感じなかった。…0名
? 生まれたときから手足のしびれなどの感覚障害があり,自分の症状が水俣病であるとは思わなかった。…4名
? いわゆる急性劇症型の人が水俣病であり,自分は水俣病であるとは思わなかった。…18名
? 魚を多食しておらず,水俣病になったとは思わなかった。…1名
? その他…1名
<コメント>
本項の質問の対象者全員(18名)が,?のいわゆる急性劇症型の人が水俣病であり自分が
水俣病であるとは思わなかったとの理由を選択しており,これは,水俣病に対する情報開示が
不十分であったことを示すものと言える。(なお,集計対象者外の人についても,かなりの人
数がこの選択肢を理由にあげており,有効な回答ではないが,「水俣病=急性劇症型」という
とらえ方がかなり根深く浸透していたことが窺われる。)
?の生まれたときから手足のしびれなどの感覚障害があり,自分の症状が水俣病であると思
わなかったとの回答についても,?と同様に水俣病に関する情報提供が十分になされていなか
ったことを推測させるものである。
なお,その他の理由として,
・症状が出てきたのが後からで,明確な診断がなかった。
・平成7年当時,他県にいたので,政治解決を知らなかった。行政からは何も情報提供はなかった。
・診察に行かなかったから,はっきりわからなかった。
・行政から情報提供もなかったので水俣病であるとの認識がなかった。
・他人と比較しないので,分からなかった。
・テレビで見るひどい状態の人だけが水俣病と思っていた。
等の回答があった。(但し,集計対象者外の人の回答も含む)
7 家族の申請状況について
(1)あなたの家族で,これまで水俣病の申請をした方はいますか。
いる 92名
いない 15名
(2)その方はあなたとはどのような関係の人ですか。
省略
(3)申請した結果はどうでしたか。
省略
(4)申請した時期はいつごろですか。
省略
(5)その家族の症状はどのようなものでしたか。
家族の症状についての回答は,手足のしびれやカラス曲がりなどが主であった。
(6)あなたの症状と具体的に違っていたところを述べてください。
省略
8 胎児性世代,小児性世代の健康被害について
(1)胎児性世代,小児性世代の人たち(40代,50代)と60才以上の人たちとの間で,健康被害に違いがあると思いますか。
?はい 20名
?いいえ 12名
?わからない 70名
未回答 5名
(2)そのように考えられる理由について述べて下さい。
省略
(3)手足のしびれなどについて違いがあると思いますか。
?はい 16名
?いいえ 12名
?わからない 67名
未回答 12名
(4)その理由について述べてください。
省略
(5)胎児性世代と小児性世代には何か違いがあると思いますか。
?はい 7名
?いいえ 4名
?わからない 89名
未回答 7名
9 平成16年10月15日関西水俣病訴訟最高裁判決後に水俣病認定申請をした方のきっかけ
(公健法上の認定申請に関しての申請情報を回答し,平成16年10月15日関西水俣病訴訟
最高裁判決まで認定申請(公健法)をしたことがなかったと回答した対象者37名について集計。複数回答可能。)
?知人,友人に勧められた 14名
?病院,医師に勧められた 3名
?被害者団体に勧められた 9名
?新聞報道やテレビ等を見て 2名
?家族や親戚に勧められた 11名
?その他 3名
未回答 5名
10 新保険手帳の申請をされた方のきっかけ
?知人,友人に勧められた 18名
?病院,医師に勧められた 2名
?被害者団体に勧められた 7名
?新聞報道やテレビ等を見て 0名
?家族や親戚に勧められた 13名
11 不知火海沿岸全域の健康調査について
(1)国,県の費用負担で調査を実施すべきである。(○をつけてください)
?はい 88名
?いいえ 7名
?どちらでもない 12名
(2)今から調査して健康被害の実態はわかると思いますか。(○をつけてください)
?はい 77名
?いいえ 19名
?どちらでもない 11名
(3)また,その理由について答えてください。
? 調査が必要であると回答した理由
早期解決のために国などによる健康調査の必要性に言及するもの,水俣病が未解決であるに
もかかわらず,一般には「終わったもの」と受けとめられているものに言及するもの等が多く
見られた。
・汚染地域の人たちが水俣病ということで差別されると思い,申請さえもできないでいる人が
まだ多くいる。調査をすれば実態が分かる。
・行政が健康診断のように行えば,多くの人が診断を受けると思う。
・現実に被害があって苦しんでいる人がたくさんいる。家庭訪問も取り入れるべきである。
・まだ水俣病であると気づいていない患者も多い。
・診断基準に納得ができない。症状に応じて判断されていないと思う。
・後から症状が出てきている人もいるので,調査には意味がある。
・感覚障害等が水俣病であるという情報は全く得られず,行政からも情報提供はなされなかった。
・あれだけの水銀を食べさせられていても「偽患者」と言われる。きちんと調査をしてほしい。
?調査を実施すべきであるか,健康被害の実態は分かるか,について「いいえ」あるいは「どちらでもない」と回答した理由
・調べる側のさじ加減次第。良くなるとは思わない。
・調査手法に疑問。
・水俣病であると偽った人がいた。本当に水俣病であることが分かるのか疑わしい。
・健康被害のある人は,既に各自が病院で検査済み。
・今頃,という感じ。遅すぎる。
・チッソ関係の仕事をしている人からは嫌がられることがある。
・今になって調査にお金をかけるのではなく,補償に回して欲しい。
12 水俣病の認定(公健法)基準について
(1)基準についてどのように考えていますか。(○をつけてください)
?きびしすぎる 88名
?妥当である 6名
?どちらでもない 13名
(2)そのように考える理由について述べて下さい。
基準がきびしすぎるとする理由としては,ほとんど申請が認められない,昭和52年より以
前の判断基準にすべきである,とするものが多数を占めた。中には,胎児性,小児性について
もっと解明すべきとするものも見られた。
一方,基準は妥当であるとする理由としては,きちんと検査をすれば自分が水俣病であるこ
とは分かるはず(認定審査会の運用の問題点を指摘する趣旨で述べられている)とするものが
見られた。
(3)基準を改訂すべきであると思いますか。
?きびしすぎる(はい) 81名
?妥当である(いいえ) 5名
?どちらでもない 14名
未回答 7名
(4)そのように考える理由について述べてください。
基準を改訂すべきであるとする理由としては,被害状況に応じ被害者を救済すべきとの趣旨
の回答が多数を占め,その他,関西水俣訴訟最高裁判決に準ずべきとの趣旨の回答も見られた。
一方,基準を改訂する必要はないとする理由としては,きちんと検査をすれば自分が水俣病
であることは分かるはず(認定審査会の運用の問題点を指摘する趣旨で述べられている)とす
るものが見られた。
13 今回の調査に関する自由記載
自由記載欄には患者の様々な思いが綴られていた。その内の一部を紹介することとする。
・水俣病はまだ終わっていない。水俣病患者はまだ救済されていないということを全国の皆さ
んに知っていただきたい。劇症型の水俣病で,軽いのはニセ患者だと思っている人が非常に
多いが,正しく水俣病のことを知ってほしい。水俣病の全面救済を1日も早くしてほしい。
全面救済をするには汚染地区の住民の全部の健康調査をしなければならない。
・平成7年の時に申請していない。ちょうどこのころからしびれを感じ始めた。水俣病の症状
を当時あまり知らなかった。水俣病の申請ができるとは思わなかった。
・もっと掘り下げて調べて欲しい。水俣病は終わったと思っている人が多い。多くの人に水俣
病について知って欲しい。
・子どもの頃から水俣病の症状に苦しめられてきた。私の母も同じ。母が水俣病だったか私に
は分かりませんが,私と同じ症状で苦しめられながら亡くなりました。もし,チッソの水銀
が原因でこうなったのであれば,チッソには責任をとってもらいたい。チッソの利益のため
に,私たちは何も知らずに自分の人生を台無しにされました。それを切りがないはないでし
ょう。最後の1人まで補償するのは当たり前のことです。たとえ,過失であっても,もし私
がチッソの立場だったら責任を取らされていますよ。
・この世に生まれる前から母胎の中で水銀にまみれ,生まれ落ちてすぐから命をつなぐため,
水銀に汚染された母親の母乳を飲まされて,生きなければならなかった赤ん坊。何も知らな
いで,愛しいわが子のために毒の入ったお乳を飲ませた母親。何の疑いも持たないで,無心
にお乳を飲み続けた末に水銀に身体をむしばまれて生きるしかない子どもたちが存在してい
るという現状をちゃんと見て欲しいと思う。50年以上の人生を水銀に苦しめられながら生
きてきて,これからもそれはもっと酷くなって続いていくという現実があることをしっかり
と認めて欲しい。
・汚染のことは聞いていたが,魚屋で売っているものだからと思って食べた。症状の重い人は
長年食べているからで,自分は未だ症状は出ないだろうと思った。申請した人に対する中傷
として,「申請されたとよー,まだ若いかモンのそがんことのあるもんか」という話を聞い
ていた。自分も申請したら同じように言われると思った。嫁ぎ先の両親も否定的だった。当
初は劇症型だけが「水俣病」だと思っていたが,新聞等で感覚障害でも「水俣病」であり,
メチル水銀が原因と報道されているので,そうであれば,自分も水俣病ではないかと思うよ
うになった。
・水俣湾だけの話だと思っていた。獅子島でも水俣患者がいることは平成18年になって始めて知った。悔しい,残念,どうして早く教えてくれなかったのかと。水俣病についての知識はあったが,自分の症状が水俣病だとは思っていなかった。昨年の12月に友人が水俣病の話があるので行くように誘われた。その際に「症状」を聞いた所,自分の症状とあっていることに驚いた。市役所に照会し,患者団体を紹介された。それ以前は関心もなかった。水俣病の患者は特別の人だろうと思っていた。
・胎児性世代についてちゃんと検査してほしい。漁師で毎日魚を食べていて「棄却」では納得できない。現在,手足の多少の麻痺(転びやすい),足のしびれ,カラス曲がりなどで障害も多いのに,まったく認定の外とはおかしい。自分が水俣病でないというのはどう考えてもおかしい。どうしても進展しなければ裁判も考えている。将来が不安。症状はひどくなっている感じがする。
・目に見えない症状をもっている人に対してもしっかり理解してあげるべきだ。苦しんでいる人は多くいる。自分でもよく分からないことが多く,判断できない。
・自分は早いうちから水俣病のおそれありと言われていたが,なかなか認定されなかった。同じ症状のある人でも認定に差があるのはおかしいのではないか。会社は責任を認めて,できる限り救済してもらいたい。
・チッソの対応に不満がある。テレビ等で見聞きするチッソの態度や意見に腹が立つ。
・水俣病の調査は行政がすべきものである。行政がきちんと住民の健康調査を行い,水俣病の全面的な救済をすべきである。
・不知火海沿岸の住民の健康調査を実施して,早くすべての人々を救済してほしい。そうしないと再び何回も裁判等の問題が今後起こってくると思う。
・何回も同じような調査をされている。社会に反映されていないのではないか。
・医者の検診の時は2〜3分見ただけで「ここはどうですか」って聞かれて「えぇ」ていったらそれでおしまい。「ここがおかしい」と言ったら 「そのようなことは言わなくてよい。聞いていることだけ答えろ」と言われた。これが実情。これでは検診とは言えない。
・打ち切られても今後水俣病の人が出てくる可能性が極めて高い。水俣病は年をとって気づくことが多いので。
・水俣病の重さによって,例えば5段階で認定して重さに応じて補償をすべきではないか。オール・オア・ナッシングは不当。裁判をしている高齢者は苦しんでいる。国に対策を望む。
・いろいろな調査が度重なっているので,現実的な救済を早期にしてほしい。チッソにはこの問題から逃げることなく,責任をとって救済に取り組んでほしい。
・基準を考え直してほしい。疫学を重視すべきである。行政から情報がきたことはない。行政の怠慢である。高齢化しており,早く解決してほしい。医師も経験がなく,診断能力がない。
・症状は人によって様々である。検査もそれにマッチしたものにしてほしい。今回の調査が,基準見直し,患者切り捨てでない方向に行くためのきっかけとなることを望む。
・被害者も高齢化しており,早く解決し,救済してほしい。救済が進まないことについて,特にチッソの対応については腹立たしい。調査を進め,救済してほしい。
・現在被害者団体に入り少しずつ水俣病のことについて分かるようになったが,若いときから関係があったとは思いもしなかった。いとこたちがたくさんいて,水俣病であったことは知っていたが,自分も同じ水俣病であることが分かったのがあまりにも遅すぎた。残念でならない。でも,この機会に自分たちが水俣病であることが分かったことは幸いであった。遅くなったとはいえ自分たちがやらなければいけないこと,出来ることは進んで参加し,みんなで協力して頑張りたいと思う。
・今,申請している人たちの中にも1800万円に相当する重い被害者はたくさんいる。150万で一律救済ならば全員救済にしてほしい。程度の差に応じて補償する制度を作るべき。行政側が,税金が高くなったのは水俣病患者が多く出てきたせいだとあちこちで言っている。そのせいで町民が水俣病のせいでと思うようになっている傾向もある。
・このままだと地球が危ない。大変苦労してきた。後がない。
・生きているうちに補償してほしい。それが一番。自分が死んだ後に残される娘のことがとても心配。娘は水俣病が一番ひどかったときに生まれた。
・水俣病は終わりではないので弁護士の方も力を貸して下さい。1人でも多くの人を救済してください。
・日弁連の調査はありがたい。この調査結果を国・県は,重く受け止めて水俣病解決に努めてほしい。
・被害者の相談には乗ってくれた弁護士に頑張ってもらっていることで心強い,一緒に頑張ってほしい。チッソの分社化は被害者にとってマイナスになるのでは。
・聞き取りがあったことで,これまで言いにくかったことをみんなに伝えて,理解してもらえることがよかった。以前より,基準が緩和されているように思える。申請しやすくなっているように思える。
以 上
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/minamata_houkokusyo_000.pdf