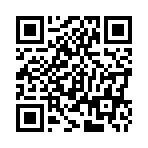2009年11月30日
パナソニック敷地内のPCB入り埋設コンデンサ等掘り起こしと
パナソニック敷地内のPCB入り埋設コンデンサ等掘り起こしと適正処理について
2003年1月31日
松下電器では、当社グループ工場敷地内にPCB入りコンデンサ等が埋設されている実態に対処するため、埋設物の掘り起こしに着手し、適正保管と届出を行ないます。また、PCB入り機器等の無害化処理及び汚染土壌の浄化の研究を促進してまいります。
当社では、2002年4月にPCB入りコンデンサの埋設を公表し、その対策を進めている富山松下電器(株)での対応を契機に、当社グループの拠点のうち、PCBを使用した製品を以前製造していた工場と、PCB入り製品を使用していた工場の調査の徹底を図ってまいりました。その結果、従来から対策を進めていた工場を含む4工場及び1工場跡地でPCB入りコンデンサ等を埋設していることを、グループ本社として把握いたしました。2工場については、埋設によると思われる土壌及び地下水の敷地内汚染の実態がわかりましたが、敷地外への汚染拡散はないと考えております。また、他の2工場については、敷地内汚染は検出されないため、敷地外への汚染拡散はないと考えております。なお、1工場跡地については調査中です。地域住民の皆様、関係の皆様にご心配をお掛けすることを誠に申し訳なく存じます。
調査結果を真摯に受け止めると同時に、PCB埋設物の掘り起こし、敷地外への汚染拡散防止、掘り起こした埋設物の適正保管・届出、及び適正処理について、グループ全体として継続して最善の対策を積極的に行なってまいります。そのために、環境担当役員を委員長とする土壌環境対策委員会を、その傘下に土壌環境対策タスクフォースを2月1日付で発足し、特に無害化処理については以下の2点に取組みます。
PCB使用機器については「PCB特別措置法」に基づいて、2016年7月までに適正処理を行うことを推進します。
PCBにより汚染された土壌の浄化については、浄化技術や施設の確立に合わせて推進します。
1.調査結果について
松下産業機器(株)豊中工場(以下、豊中工場)、松江松下電器(株)松江工場(以下、松江工場)の2工場は、埋設によると思われる土壌及び地下水の敷地内汚染がわかりましたが、現在までの対策と調査結果から敷地外への汚染はないと考えております。
松下電器産業(株)高槻工場(以下、高槻工場)、松下電器産業(株)長岡工場(以下、長岡工場)の2工場は、PCB入り使用済み電気機器(照明用安定器)の埋設が聞き取り調査により推定されます。敷地内の土壌及び地下水からPCBは検出されていません。従って、敷地外への汚染はないと考えております。
塚本工場跡地については現在、調査中です。
以下、その現状を報告いたします。
(注)特定箇所の事前調査データ
各工場の経過と対策については別紙資料(1〜5)をご参照願います。
2.今後の対応と安全対策について
豊中・松江両工場とも遮水工事や揚水浄化等の対策により敷地外への汚染拡散はないと考えておりますが、さらに徹底すべく今後の対応と安全対策については次のように考えております。
今後はPCB特別措置法や土壌汚染対策法等に基づいて、適正保管と届出および適正処理を推進してまいります。
その際、それぞれの工場の所轄官庁である府県や市からご指示やご指導に従って、必要な調査・対策を実施してまいります。
高槻・長岡工場は、掘削・取出しを進め、確認できた段階で、適正保管と届出を致します。なお、周辺環境を考慮して継続してモニタリングを実施します。
塚本工場跡地については、早急に行政にご相談の上、詳細調査の実施を進めます。同時に外部への拡散防止を図るため、「鋼矢板による遮水」と「地下水を敷地内に呼込む揚水浄化」の対策を検討します。
3.地域への対応について
まずは、今回の発表内容につき周辺住民の皆様への説明をご要望に応じて実施したいと考えております。そこでは、当社敷地内での状況とそこに至った経過と原因、合わせて今後の対応計画について、説明させていただきます。
また府県および市とご相談する所存です。
以 上
別 紙 1
豊中工場について
1. 会社概要
会社名 松下産業機器株式会社
代表者 代表取締役社長 大谷昌三
所在地 大阪府豊中市稲津町3丁目1番1号(約40千m2)
資本金 30億円
操業履歴 1957年(昭和32年)豊中工場操業開始
1977年(昭和52年)松下産業機器(株)設立(松下電器産業(株)より分離独立)
事業内容 産業機器、電気機器、医療機械器具等の開発・製造・販売
2. 現 状
PCB入りコンデンサ不良品の埋設並びに土壌及び地下水の調査結果は下表の通りです。
* 環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づく概況調査
(2002年12月実施)
3. 経過と対策
松下産業機器(株)豊中工場において、1957年(昭和32年)10月から1972年(昭和47年)3月までの間、化学的に安定なPCBを絶縁油として使用したコンデンサを製造しておりました。
通商産業省(当時)の通達に基づき、1972年(昭和47年)3月に全面的に使用を中止しましたが、工場排水路から近くの三田池にPCBが流出していることがわかりました。大阪府様・豊中市様のご指導のもと、工場排水路と三田池の汚泥処理工事を実施し、1973年(昭和48年)に弊社敷地内グランド地下にコンクリ−ト槽を設置し、浚渫汚泥等を保管することによりこの件に関する対応は完了しました。
1998年(平成10年)の松下電器グループにおける「塩素系地下水汚染問題」を契機に調査を実施し、同年12月に地下水から浅井戸で最高6.8mg/lのPCBが検出されましたが、過去から継続して観測している3ヶ所の観測井戸(深井戸)では検出されませんでした。土壌からは最高で0.0007mg/l(溶出量値)が検出されました。
この調査結果に基づき、外部への拡散防止を第一に考え、環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」(以下指針という)に基づく環境対策を実施いたしました。その内容は、次のとおりです。
(1) 地下水は、揚水による浄化対策を1999年(平成11年)4月より実施いたしました。これは、揚水した地下水を凝集沈殿法で処理し、更に活性炭処理を行い、環境基準を満たす状態にして下水道へ放流するものです。
(2) 鋼矢板による遮水工事を2000年(平成12年)3月より2002年(平成14年)3月にかけて、敷地内下水道等のインフラ整備および地盤強化対策工事とともに実施いたしました。これは、敷地全周(約836m)に鋼矢板を地下14mの難透水層に打設し、封じ込めるものです。
(3) 敷地内の通路等はアスファルト等による被覆を実施し、飛散ならびに雨水の浸透を防止しました。
以上により、敷地外への汚染拡散はないものと考えております。2002年12月の測定結果からも地下水下流側にある敷地内の鋼矢板の外側で、PCBは検出されておりません。
さらに、先述の環境省指針に基づき、鋼矢板による遮水と揚水浄化を継続してまいります。
一方、この工事に際し、コンデンサ不良品を含むPCB汚染土壌を発見しました。あらためて過去の担当者からの聞き取り調査を実施した結果、これらのコンデンサは、1971年(昭和46年)以前において、不良品等を敷地内に埋設していたものと推測いたしております。
汚染の原因については、これらの埋設されたコンデンサ不良品から土壌に浸透したものや、PCB使用中止以前にPCB使用場所で製造中に漏れたものであると推測いたしております。
発見したコンデンサ不良品等は、分別して専用の保管倉庫に保管し、PCB特別措置法等に基づき大阪府様へ届出を済ませております。同時に掘削した土壌については、敷地内の保管施設へ保管いたしております。
4. 今後の対応について
上記の通り、遮水工事や揚水浄化等の対策により敷地外への汚染拡散はないと考えておりますが、さらに徹底すべく今後の対応と安全対策については次のように考えております。
拡散防止策としての鋼矢板による遮水と揚水浄化は、今後も継続いたします。
埋設されている可能性が高いコンデンサ不良品は、今後順次掘り起こし、PCB特別措置法や土壌汚染対策法等に基づいて適正保管と届出を行い、さらに適正処理を推進してまいります。
その際、大阪府様、豊中市様からのご指示やご指導に従って、必要な調査・対策を実施してまいります。
以 上
別 紙 2
松江工場について
1. 会社概要
会社名 松江松下電器株式会社
代表者 代表取締役社長 大嶋邦雄
所在地 島根県松江市乃木福富町字大所369番地(約35千m2)
操業開始 1966年(昭和41年)7月1日
事業内容 電気・電子機器用電子部品の開発・製造・販売
2. 現 状
埋設物と敷地内の土壌および地下水の調査結果は下表の通りです。
*環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づく概況調査および詳細調査結果
(1) 概況調査
環境省の調査・対策指針に基づき敷地内を30m毎に30地点ボーリング調査を実施。
埋設推定箇所及び元使用場所の3箇所の地下水からPCBを検出しました。(2002年8〜9月実施)
(2) 詳細調査
概況調査及び従業員の聞き取り調査結果を元に、埋設場所の特定と埋設状況確認のため推定個所を中心に、詳細調査を行いました。(2002年12月実施)
3. 経過と対策
松江松下電器(株)松江工場において、1966年(昭和41年)7月の創業開始から1972年(昭和47年)2月の間、化学的に安定なPCBを絶縁油として使用のコンデンサを製造しておりました。
通商産業省(当時)の通達に基づき、1972年2月に全面的に使用を中止いたしましたが、工場排水路から近くの河川および河口付近の宍道湖にPCBが流出していることがわかりました。島根県様、松江市様のご指導のもと、汚染の浄化・流出対策を行い、この件に関する対応は完了しました。
1995年阪神大震災時の液状化問題を契機に液状化防止対策として、1995年10月から1996年12月の間で地質・地下水の調査および対策工事を実施いたしました。その際、PCBについても一部調査した結果、PCBを検出しましたが、地下水下流側敷地境界の地下水では検出されませんでした。この結果より、敷地外にはPCBが拡散していないと判断し、液状化防止と敷地外への汚染の拡散防止の強化を第一に考え、敷地周辺部全域への鋼矢板設置による遮水、および揚水による水位差確保と揚水の浄化対策を実施いたしました。
以上より敷地外汚染の可能性はないと考えます。
4. 今後の対応について
上記の通り、遮水工事や揚水浄化等の対策により敷地外への汚染はないと考えておりますが、さらに徹底すべく今後の対応と安全対策については次のように考えております。
拡散防止策としての鋼矢板による遮水と揚水浄化は、今後も継続いたします。
今後は設備移転・建物の増改築にあわせて順次掘り起こし、PCB特別措置法や土壌汚染対策法等に基づいて適正保管と届出を行い、さらに適正処理を推進してまいります。
その際、島根県様や松江市様から指示や指導に従って、必要な調査・対策を実施してまいります。
以 上
別 紙 3
塚本工場跡地について
1. 会社概要
会社名 松下電器産業株式会社 資産活用センター
代表者 所長 二星正樹
所在地 大阪府門真市大字門真1006番地
塚本工場跡地
北側土地
(元工場、現在:松下リース・クレジット株式会社)
大阪市淀川区田川2丁目8番7号
土地面積 3,948m2
南側土地 (元運動場、現在:月極め駐車場)
大阪市淀川区田川1丁目15番
土地面積 2,664m2
2. 現在までの経過
(1) 土地利用の履歴 [1] 塚本工場跡地・北側土地
1931年 3月 第7工場発足・ラジオ生産開始
1948年11月 コンデンサ生産開始(鉱物油使用コンデンサ)
1952年11月 AF式コンデンサ生産開始(PCB使用コンデンサ)
1957年 9月 コンデンサの生産を豊中へ移転
1958〜1993年 電化グループ電熱器事業部が使用・電熱器等生産
1995年 9月 松下リース・クレジット株式会社に土地を売却〜現在に至る
[2] 塚本工場跡地・南側土地 1955年12月 南側土地購入(グランドとして利用)
1964年 9月 運動場として整備
1996年 2月 月極め駐車場開設(全面アスファルト舗装)〜現在に至る
(2) 問題の発見とその推定原因 [1] 発見の経緯
2002年(平成14年)4月のPCB入りコンデンサの埋設が判明した富山松下電器(株)の対応を契機に、PCBを使用した製品を製造していた工場の調査を進めてまいりました。
その結果、塚本工場跡地において、上記の通り1952年(昭和27年)から1957年(昭和32年)の間、化学的に安定なPCBを絶縁油として使用したコンデンサを製造したことを確認し、さらに調査を進めた結果、昨年11月末南側土地の特定箇所のサンプリングで、PCB入りコンデンサの埋設物の一部と思われるものを含んだ土壌を発見しました。
なお、北側土地(工場跡地)については、現在のところPCB入りコンデンサの埋設物は発見されていませんが、土壌汚染が一部認められました。
[2] 推定原因
南側土地の汚染の原因については、埋設された不良コンデンサから土壌に浸透したものと推測いたします。北側土地の汚染の原因については不明です。今後、詳細調査を実施し解明してまいります。
3. 現状
(1) 土壌及び地下水の調査結果
・南側土地
※1:埋設物は地表から深さ約1.5m〜2.0mの間に点在、平面方向の範囲は特定されておりません。
・北側土地
4. 今後の対応
(1) 基本的な考え方
早急に詳細調査を実施し、大阪市様に相談の上、汚染拡散防止のための緊急対策工事など必要な対策を講じて、周辺住民の皆様の安全確保を第一に取り組む所存です。
以 上
別 紙 4
高槻工場について
1. 会社概要
会社名 松下電器産業株式会社 照明社・ディスプレイデバイス社 高槻工場
代表者 照明社社長 松川昭男
所在地 大阪府高槻市幸町1番1号(約225千m2)
操業開始 1954年(昭和29年)3月
事業内容 照明社…蛍光灯、一般電球、ハロゲン電球などの開発・製造・販売
ディスプレイデバイス社…ブラウン管、PDPなどの開発・製造・販売
2. 現 状
推定される埋設物と敷地内の土壌および地下水の調査結果は下表のとおりです。
*環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づく概況調査および詳細調査結果
3. 経過
・ 2002年4月のPCB入りコンデンサの埋設が判明した富山松下電器(株)の対応を契機に、聞き取り調査を実施した結果、立体駐車場床下部分にPCB入り照明用安定器が埋設されていることが推定できました。
・ 埋設時期は1984年で、推定埋設箇所は、1ヶ所と思われます。
・ 埋設当時の保管としては、飛散・流出・地下浸透のないように配慮して処置したものと考えられます。
・ 昨年より新設監視井戸にて水質分析、該当建物周辺にて土壌及び地下水調査を実施した結果、PCBは検出されませんでした。
4. 今後の対応
・ 高槻工場における埋設状況は安定な状態にあると考えられますが、周辺環境を考慮し、継続して地下水モニタリングを実施します。
・ 上記埋設物につき、今後計画的に掘削・取出しを進め、適正保管と届出を実施し、さらに適正処理を推進してまいります。
・ その際、大阪府様及び高槻市様とご相談の上、速やかに対応させていただく所存です。
以 上
別 紙 5
長岡工場について
1. 会社概要
会社名 松下電器産業株式会社 半導体社 長岡工場
代表者 半導体社社長 古池 進
所在地 京都府長岡京市神足焼町1番地(約60千m2)
操業開始 1968年(昭和43年)8月
事業内容 半導体製品の開発・製造・販売
2. 現 状
推定される埋設物と敷地内の土壌および地下水の調査結果は下表のとおりです。
*環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づく概況調査および詳細調査結果
3. 経過
・ 2002年4月のPCB入りコンデンサーの埋設が判明した富山松下電器(株)の対応を契機に、聞き取り調査を実施した結果、長岡工場敷地内3ヶ所にPCB入り照明用安定器等が、埋設されていることが推定できました。
・ 埋設当時の保管としては飛散・流出・地下浸透のないように配慮して処置したものと考えられます。
・ また、同表のように敷地内の土壌および地下水の調査を実施した結果、PCBは検出されませんでした。
4. 今後の対応
・ 長岡工場における埋設状況は安定な状態にあると考えていますが、周辺環境を考慮し、継続して地下水モニタリングを実施します。
・ 上記埋設物につき、今後計画的に掘削・取出しを進め、適正保管と届出を実施し、さらに適正処理を推進してまいります。
・ その際、京都府様、長岡京市様とご相談の上、速やかに対応させていただく所存です。
2.4 保管(一時保管施設の構造等)
・設置場所:大田区城南島三丁目
・敷地面積:約2,700 平方メートル
・主要構造:建屋は鉄骨テント構造、床はコンクリート構造とし、外部からの浸入水を防止す
るため、周辺地盤より高くする。また、屋根は雨水が浸入しない構造とする。
・保管方法:汚染土壌を密閉容器(ドラム缶)に入れたまま保管
2003年1月31日
松下電器では、当社グループ工場敷地内にPCB入りコンデンサ等が埋設されている実態に対処するため、埋設物の掘り起こしに着手し、適正保管と届出を行ないます。また、PCB入り機器等の無害化処理及び汚染土壌の浄化の研究を促進してまいります。
当社では、2002年4月にPCB入りコンデンサの埋設を公表し、その対策を進めている富山松下電器(株)での対応を契機に、当社グループの拠点のうち、PCBを使用した製品を以前製造していた工場と、PCB入り製品を使用していた工場の調査の徹底を図ってまいりました。その結果、従来から対策を進めていた工場を含む4工場及び1工場跡地でPCB入りコンデンサ等を埋設していることを、グループ本社として把握いたしました。2工場については、埋設によると思われる土壌及び地下水の敷地内汚染の実態がわかりましたが、敷地外への汚染拡散はないと考えております。また、他の2工場については、敷地内汚染は検出されないため、敷地外への汚染拡散はないと考えております。なお、1工場跡地については調査中です。地域住民の皆様、関係の皆様にご心配をお掛けすることを誠に申し訳なく存じます。
調査結果を真摯に受け止めると同時に、PCB埋設物の掘り起こし、敷地外への汚染拡散防止、掘り起こした埋設物の適正保管・届出、及び適正処理について、グループ全体として継続して最善の対策を積極的に行なってまいります。そのために、環境担当役員を委員長とする土壌環境対策委員会を、その傘下に土壌環境対策タスクフォースを2月1日付で発足し、特に無害化処理については以下の2点に取組みます。
PCB使用機器については「PCB特別措置法」に基づいて、2016年7月までに適正処理を行うことを推進します。
PCBにより汚染された土壌の浄化については、浄化技術や施設の確立に合わせて推進します。
1.調査結果について
松下産業機器(株)豊中工場(以下、豊中工場)、松江松下電器(株)松江工場(以下、松江工場)の2工場は、埋設によると思われる土壌及び地下水の敷地内汚染がわかりましたが、現在までの対策と調査結果から敷地外への汚染はないと考えております。
松下電器産業(株)高槻工場(以下、高槻工場)、松下電器産業(株)長岡工場(以下、長岡工場)の2工場は、PCB入り使用済み電気機器(照明用安定器)の埋設が聞き取り調査により推定されます。敷地内の土壌及び地下水からPCBは検出されていません。従って、敷地外への汚染はないと考えております。
塚本工場跡地については現在、調査中です。
以下、その現状を報告いたします。
(注)特定箇所の事前調査データ
各工場の経過と対策については別紙資料(1〜5)をご参照願います。
2.今後の対応と安全対策について
豊中・松江両工場とも遮水工事や揚水浄化等の対策により敷地外への汚染拡散はないと考えておりますが、さらに徹底すべく今後の対応と安全対策については次のように考えております。
今後はPCB特別措置法や土壌汚染対策法等に基づいて、適正保管と届出および適正処理を推進してまいります。
その際、それぞれの工場の所轄官庁である府県や市からご指示やご指導に従って、必要な調査・対策を実施してまいります。
高槻・長岡工場は、掘削・取出しを進め、確認できた段階で、適正保管と届出を致します。なお、周辺環境を考慮して継続してモニタリングを実施します。
塚本工場跡地については、早急に行政にご相談の上、詳細調査の実施を進めます。同時に外部への拡散防止を図るため、「鋼矢板による遮水」と「地下水を敷地内に呼込む揚水浄化」の対策を検討します。
3.地域への対応について
まずは、今回の発表内容につき周辺住民の皆様への説明をご要望に応じて実施したいと考えております。そこでは、当社敷地内での状況とそこに至った経過と原因、合わせて今後の対応計画について、説明させていただきます。
また府県および市とご相談する所存です。
以 上
別 紙 1
豊中工場について
1. 会社概要
会社名 松下産業機器株式会社
代表者 代表取締役社長 大谷昌三
所在地 大阪府豊中市稲津町3丁目1番1号(約40千m2)
資本金 30億円
操業履歴 1957年(昭和32年)豊中工場操業開始
1977年(昭和52年)松下産業機器(株)設立(松下電器産業(株)より分離独立)
事業内容 産業機器、電気機器、医療機械器具等の開発・製造・販売
2. 現 状
PCB入りコンデンサ不良品の埋設並びに土壌及び地下水の調査結果は下表の通りです。
* 環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づく概況調査
(2002年12月実施)
3. 経過と対策
松下産業機器(株)豊中工場において、1957年(昭和32年)10月から1972年(昭和47年)3月までの間、化学的に安定なPCBを絶縁油として使用したコンデンサを製造しておりました。
通商産業省(当時)の通達に基づき、1972年(昭和47年)3月に全面的に使用を中止しましたが、工場排水路から近くの三田池にPCBが流出していることがわかりました。大阪府様・豊中市様のご指導のもと、工場排水路と三田池の汚泥処理工事を実施し、1973年(昭和48年)に弊社敷地内グランド地下にコンクリ−ト槽を設置し、浚渫汚泥等を保管することによりこの件に関する対応は完了しました。
1998年(平成10年)の松下電器グループにおける「塩素系地下水汚染問題」を契機に調査を実施し、同年12月に地下水から浅井戸で最高6.8mg/lのPCBが検出されましたが、過去から継続して観測している3ヶ所の観測井戸(深井戸)では検出されませんでした。土壌からは最高で0.0007mg/l(溶出量値)が検出されました。
この調査結果に基づき、外部への拡散防止を第一に考え、環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」(以下指針という)に基づく環境対策を実施いたしました。その内容は、次のとおりです。
(1) 地下水は、揚水による浄化対策を1999年(平成11年)4月より実施いたしました。これは、揚水した地下水を凝集沈殿法で処理し、更に活性炭処理を行い、環境基準を満たす状態にして下水道へ放流するものです。
(2) 鋼矢板による遮水工事を2000年(平成12年)3月より2002年(平成14年)3月にかけて、敷地内下水道等のインフラ整備および地盤強化対策工事とともに実施いたしました。これは、敷地全周(約836m)に鋼矢板を地下14mの難透水層に打設し、封じ込めるものです。
(3) 敷地内の通路等はアスファルト等による被覆を実施し、飛散ならびに雨水の浸透を防止しました。
以上により、敷地外への汚染拡散はないものと考えております。2002年12月の測定結果からも地下水下流側にある敷地内の鋼矢板の外側で、PCBは検出されておりません。
さらに、先述の環境省指針に基づき、鋼矢板による遮水と揚水浄化を継続してまいります。
一方、この工事に際し、コンデンサ不良品を含むPCB汚染土壌を発見しました。あらためて過去の担当者からの聞き取り調査を実施した結果、これらのコンデンサは、1971年(昭和46年)以前において、不良品等を敷地内に埋設していたものと推測いたしております。
汚染の原因については、これらの埋設されたコンデンサ不良品から土壌に浸透したものや、PCB使用中止以前にPCB使用場所で製造中に漏れたものであると推測いたしております。
発見したコンデンサ不良品等は、分別して専用の保管倉庫に保管し、PCB特別措置法等に基づき大阪府様へ届出を済ませております。同時に掘削した土壌については、敷地内の保管施設へ保管いたしております。
4. 今後の対応について
上記の通り、遮水工事や揚水浄化等の対策により敷地外への汚染拡散はないと考えておりますが、さらに徹底すべく今後の対応と安全対策については次のように考えております。
拡散防止策としての鋼矢板による遮水と揚水浄化は、今後も継続いたします。
埋設されている可能性が高いコンデンサ不良品は、今後順次掘り起こし、PCB特別措置法や土壌汚染対策法等に基づいて適正保管と届出を行い、さらに適正処理を推進してまいります。
その際、大阪府様、豊中市様からのご指示やご指導に従って、必要な調査・対策を実施してまいります。
以 上
別 紙 2
松江工場について
1. 会社概要
会社名 松江松下電器株式会社
代表者 代表取締役社長 大嶋邦雄
所在地 島根県松江市乃木福富町字大所369番地(約35千m2)
操業開始 1966年(昭和41年)7月1日
事業内容 電気・電子機器用電子部品の開発・製造・販売
2. 現 状
埋設物と敷地内の土壌および地下水の調査結果は下表の通りです。
*環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づく概況調査および詳細調査結果
(1) 概況調査
環境省の調査・対策指針に基づき敷地内を30m毎に30地点ボーリング調査を実施。
埋設推定箇所及び元使用場所の3箇所の地下水からPCBを検出しました。(2002年8〜9月実施)
(2) 詳細調査
概況調査及び従業員の聞き取り調査結果を元に、埋設場所の特定と埋設状況確認のため推定個所を中心に、詳細調査を行いました。(2002年12月実施)
3. 経過と対策
松江松下電器(株)松江工場において、1966年(昭和41年)7月の創業開始から1972年(昭和47年)2月の間、化学的に安定なPCBを絶縁油として使用のコンデンサを製造しておりました。
通商産業省(当時)の通達に基づき、1972年2月に全面的に使用を中止いたしましたが、工場排水路から近くの河川および河口付近の宍道湖にPCBが流出していることがわかりました。島根県様、松江市様のご指導のもと、汚染の浄化・流出対策を行い、この件に関する対応は完了しました。
1995年阪神大震災時の液状化問題を契機に液状化防止対策として、1995年10月から1996年12月の間で地質・地下水の調査および対策工事を実施いたしました。その際、PCBについても一部調査した結果、PCBを検出しましたが、地下水下流側敷地境界の地下水では検出されませんでした。この結果より、敷地外にはPCBが拡散していないと判断し、液状化防止と敷地外への汚染の拡散防止の強化を第一に考え、敷地周辺部全域への鋼矢板設置による遮水、および揚水による水位差確保と揚水の浄化対策を実施いたしました。
以上より敷地外汚染の可能性はないと考えます。
4. 今後の対応について
上記の通り、遮水工事や揚水浄化等の対策により敷地外への汚染はないと考えておりますが、さらに徹底すべく今後の対応と安全対策については次のように考えております。
拡散防止策としての鋼矢板による遮水と揚水浄化は、今後も継続いたします。
今後は設備移転・建物の増改築にあわせて順次掘り起こし、PCB特別措置法や土壌汚染対策法等に基づいて適正保管と届出を行い、さらに適正処理を推進してまいります。
その際、島根県様や松江市様から指示や指導に従って、必要な調査・対策を実施してまいります。
以 上
別 紙 3
塚本工場跡地について
1. 会社概要
会社名 松下電器産業株式会社 資産活用センター
代表者 所長 二星正樹
所在地 大阪府門真市大字門真1006番地
塚本工場跡地
北側土地
(元工場、現在:松下リース・クレジット株式会社)
大阪市淀川区田川2丁目8番7号
土地面積 3,948m2
南側土地 (元運動場、現在:月極め駐車場)
大阪市淀川区田川1丁目15番
土地面積 2,664m2
2. 現在までの経過
(1) 土地利用の履歴 [1] 塚本工場跡地・北側土地
1931年 3月 第7工場発足・ラジオ生産開始
1948年11月 コンデンサ生産開始(鉱物油使用コンデンサ)
1952年11月 AF式コンデンサ生産開始(PCB使用コンデンサ)
1957年 9月 コンデンサの生産を豊中へ移転
1958〜1993年 電化グループ電熱器事業部が使用・電熱器等生産
1995年 9月 松下リース・クレジット株式会社に土地を売却〜現在に至る
[2] 塚本工場跡地・南側土地 1955年12月 南側土地購入(グランドとして利用)
1964年 9月 運動場として整備
1996年 2月 月極め駐車場開設(全面アスファルト舗装)〜現在に至る
(2) 問題の発見とその推定原因 [1] 発見の経緯
2002年(平成14年)4月のPCB入りコンデンサの埋設が判明した富山松下電器(株)の対応を契機に、PCBを使用した製品を製造していた工場の調査を進めてまいりました。
その結果、塚本工場跡地において、上記の通り1952年(昭和27年)から1957年(昭和32年)の間、化学的に安定なPCBを絶縁油として使用したコンデンサを製造したことを確認し、さらに調査を進めた結果、昨年11月末南側土地の特定箇所のサンプリングで、PCB入りコンデンサの埋設物の一部と思われるものを含んだ土壌を発見しました。
なお、北側土地(工場跡地)については、現在のところPCB入りコンデンサの埋設物は発見されていませんが、土壌汚染が一部認められました。
[2] 推定原因
南側土地の汚染の原因については、埋設された不良コンデンサから土壌に浸透したものと推測いたします。北側土地の汚染の原因については不明です。今後、詳細調査を実施し解明してまいります。
3. 現状
(1) 土壌及び地下水の調査結果
・南側土地
※1:埋設物は地表から深さ約1.5m〜2.0mの間に点在、平面方向の範囲は特定されておりません。
・北側土地
4. 今後の対応
(1) 基本的な考え方
早急に詳細調査を実施し、大阪市様に相談の上、汚染拡散防止のための緊急対策工事など必要な対策を講じて、周辺住民の皆様の安全確保を第一に取り組む所存です。
以 上
別 紙 4
高槻工場について
1. 会社概要
会社名 松下電器産業株式会社 照明社・ディスプレイデバイス社 高槻工場
代表者 照明社社長 松川昭男
所在地 大阪府高槻市幸町1番1号(約225千m2)
操業開始 1954年(昭和29年)3月
事業内容 照明社…蛍光灯、一般電球、ハロゲン電球などの開発・製造・販売
ディスプレイデバイス社…ブラウン管、PDPなどの開発・製造・販売
2. 現 状
推定される埋設物と敷地内の土壌および地下水の調査結果は下表のとおりです。
*環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づく概況調査および詳細調査結果
3. 経過
・ 2002年4月のPCB入りコンデンサの埋設が判明した富山松下電器(株)の対応を契機に、聞き取り調査を実施した結果、立体駐車場床下部分にPCB入り照明用安定器が埋設されていることが推定できました。
・ 埋設時期は1984年で、推定埋設箇所は、1ヶ所と思われます。
・ 埋設当時の保管としては、飛散・流出・地下浸透のないように配慮して処置したものと考えられます。
・ 昨年より新設監視井戸にて水質分析、該当建物周辺にて土壌及び地下水調査を実施した結果、PCBは検出されませんでした。
4. 今後の対応
・ 高槻工場における埋設状況は安定な状態にあると考えられますが、周辺環境を考慮し、継続して地下水モニタリングを実施します。
・ 上記埋設物につき、今後計画的に掘削・取出しを進め、適正保管と届出を実施し、さらに適正処理を推進してまいります。
・ その際、大阪府様及び高槻市様とご相談の上、速やかに対応させていただく所存です。
以 上
別 紙 5
長岡工場について
1. 会社概要
会社名 松下電器産業株式会社 半導体社 長岡工場
代表者 半導体社社長 古池 進
所在地 京都府長岡京市神足焼町1番地(約60千m2)
操業開始 1968年(昭和43年)8月
事業内容 半導体製品の開発・製造・販売
2. 現 状
推定される埋設物と敷地内の土壌および地下水の調査結果は下表のとおりです。
*環境省の「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づく概況調査および詳細調査結果
3. 経過
・ 2002年4月のPCB入りコンデンサーの埋設が判明した富山松下電器(株)の対応を契機に、聞き取り調査を実施した結果、長岡工場敷地内3ヶ所にPCB入り照明用安定器等が、埋設されていることが推定できました。
・ 埋設当時の保管としては飛散・流出・地下浸透のないように配慮して処置したものと考えられます。
・ また、同表のように敷地内の土壌および地下水の調査を実施した結果、PCBは検出されませんでした。
4. 今後の対応
・ 長岡工場における埋設状況は安定な状態にあると考えていますが、周辺環境を考慮し、継続して地下水モニタリングを実施します。
・ 上記埋設物につき、今後計画的に掘削・取出しを進め、適正保管と届出を実施し、さらに適正処理を推進してまいります。
・ その際、京都府様、長岡京市様とご相談の上、速やかに対応させていただく所存です。
2.4 保管(一時保管施設の構造等)
・設置場所:大田区城南島三丁目
・敷地面積:約2,700 平方メートル
・主要構造:建屋は鉄骨テント構造、床はコンクリート構造とし、外部からの浸入水を防止す
るため、周辺地盤より高くする。また、屋根は雨水が浸入しない構造とする。
・保管方法:汚染土壌を密閉容器(ドラム缶)に入れたまま保管
2009年11月29日
地下水汚染 環境省 発表
地下水汚染
鉛 (23倍)東京都渋谷区上原
六価クロム (54倍)佐賀県鳥栖市原町
砒素 (44倍)兵庫県豊岡市若松
総水銀(36倍)福井県越前市家久
四塩化炭素 (180倍)千葉県千葉市稲毛区長沼町
1,2-ジクロロエタン (19倍)大阪府高槻市唐崎中
1,1-ジクロロエチレン (48倍)千葉県野田市木間ヶ瀬
シス-1,2-ジクロロエチレン (750倍)秋田県由利本荘市大浦
(228倍)新潟県上越市新光町
(158倍)大阪府高槻市桃園町
(120倍)新潟県燕市南
1,1,2-トリクロロエタン (11倍)宮崎県延岡市別府町
トリクロロエチレン(2733倍)秋田県井川町浜井川
(1467倍)福岡県福岡市香椎駅前
(1167倍)秋田県由利本荘市大浦
(400倍)愛知県豊田市神池町
(107倍)千葉県千葉市花見川区作新台4丁目
(103倍)滋賀県草津市矢倉
テトラクロロエチレン(2100倍)兵庫県明石市魚住町
(1100倍)千葉県松戸市紙敷
(430倍)福岡県福岡市香椎駅前
(430倍)福岡県福岡市田島
(190倍)愛知県名古屋市昭和区広見町
(160倍)宮城県栗原市築館萩沢
(160倍)福島県須賀川市小作田
(150倍)兵庫県明石市大久保町
(120倍)福岡県朝倉市屋永
(110倍)岩手県大船渡市下船渡
(110倍)兵庫県明石市大久保町
(110倍)兵庫県加東市高岡
(110倍)山口県岩国市下久原
(110倍)山口県周南市古市
(100倍)北海道旭川市大町
(100倍)滋賀県彦根市城北
ベンゼン (10倍)福井県越前市家久
ふっ素 (18倍)岐阜県御嵩町御嵩
ほう素 (9.9倍)福島県郡山市芳賀
酸性窒素及び亜硝酸性窒素
(12倍)栃木県藤岡町藤岡
(10倍)埼玉県深谷市櫛引
(10倍)神奈川県横浜市南区六ツ川
(8.5倍)茨城県つくば市上里
(8倍)長野県飯島町七久保
(7.2倍)青森県南部町平
(7倍)神奈川県海老名市本郷
(6倍)千葉県船橋市旭町6丁目
(6倍)群馬県館林市成島町
(6倍)茨城県板東市長須
http://www.env.go.jp/water/report/h21-03/full.pdf
鉛 (23倍)東京都渋谷区上原
六価クロム (54倍)佐賀県鳥栖市原町
砒素 (44倍)兵庫県豊岡市若松
総水銀(36倍)福井県越前市家久
四塩化炭素 (180倍)千葉県千葉市稲毛区長沼町
1,2-ジクロロエタン (19倍)大阪府高槻市唐崎中
1,1-ジクロロエチレン (48倍)千葉県野田市木間ヶ瀬
シス-1,2-ジクロロエチレン (750倍)秋田県由利本荘市大浦
(228倍)新潟県上越市新光町
(158倍)大阪府高槻市桃園町
(120倍)新潟県燕市南
1,1,2-トリクロロエタン (11倍)宮崎県延岡市別府町
トリクロロエチレン(2733倍)秋田県井川町浜井川
(1467倍)福岡県福岡市香椎駅前
(1167倍)秋田県由利本荘市大浦
(400倍)愛知県豊田市神池町
(107倍)千葉県千葉市花見川区作新台4丁目
(103倍)滋賀県草津市矢倉
テトラクロロエチレン(2100倍)兵庫県明石市魚住町
(1100倍)千葉県松戸市紙敷
(430倍)福岡県福岡市香椎駅前
(430倍)福岡県福岡市田島
(190倍)愛知県名古屋市昭和区広見町
(160倍)宮城県栗原市築館萩沢
(160倍)福島県須賀川市小作田
(150倍)兵庫県明石市大久保町
(120倍)福岡県朝倉市屋永
(110倍)岩手県大船渡市下船渡
(110倍)兵庫県明石市大久保町
(110倍)兵庫県加東市高岡
(110倍)山口県岩国市下久原
(110倍)山口県周南市古市
(100倍)北海道旭川市大町
(100倍)滋賀県彦根市城北
ベンゼン (10倍)福井県越前市家久
ふっ素 (18倍)岐阜県御嵩町御嵩
ほう素 (9.9倍)福島県郡山市芳賀
酸性窒素及び亜硝酸性窒素
(12倍)栃木県藤岡町藤岡
(10倍)埼玉県深谷市櫛引
(10倍)神奈川県横浜市南区六ツ川
(8.5倍)茨城県つくば市上里
(8倍)長野県飯島町七久保
(7.2倍)青森県南部町平
(7倍)神奈川県海老名市本郷
(6倍)千葉県船橋市旭町6丁目
(6倍)群馬県館林市成島町
(6倍)茨城県板東市長須
http://www.env.go.jp/water/report/h21-03/full.pdf
2009年11月29日
東京都 中央区 豊洲新市場予定地
豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る築地市場移転問題に関する要望
平成21年2月6日に東京都から、「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」の提言及び「豊洲新市場整備方針」等について発表されました。中央区では、これを受けて区長から下記のとおり、東京都知事宛て要望をいたしましたのでお知らせいたします。
平成21年2月26日
東京都知事 石原慎太郎様
中央区長 矢田美英
豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る築地市場移転問題に関する要望について
さて、本区にあります築地市場は、昭和10年2月の開場以来、「都民の台所」として都民の食生活を支えるとともに、全国規模の食材流通に欠かせない拠点であります。また、74年にも及ぶ歴史の中で、場外市場とともに日本の食文化を代表する「築地ブランド」を育んでまいりました。
しかし、平成11年に豊洲への移転整備が打ち出されたことから、本区は、地域住民や市場関係者等の移転整備に伴うさまざまな疑問や不安を受けて東京都に対して繰り返し、質問や申入れなどを行ってまいりました。また、豊洲新市場基本計画が公表されるなど移転計画が具体化する中、仮に市場が移転した場合にあっても、築地市場地区が活気とにぎわいを持ち続けるためにどうあるべきかを、「築地市場地区の活気とにぎわいビジョン」の策定により明らかにしました。
その後、かねてから不安を抱いていた新市場予定地の土壌汚染については、専門家会議が設置されたことから、その調査・検討状況を注視してまいりましたが、詳細調査で基準値を大幅に上回るベンゼンが検出されるなど、憂慮すべき状況が明らかとなったところであります。
さらに、専門家会議の提言を受けて対策をとりまとめるにあたり、具体的な技術・工法の公募が実施され、その評価・検証のため技術会議が設置されたことから、これらの状況の推移を慎重に見守ってきたところであります。こうした経過の中、汚染物質や不透水層に関するデータの一部が遅れて公表されたことは、誠に遺憾であります。
このような状況において、2月6日、技術会議の検討結果を踏まえた土壌汚染対策が発表されました。しかしながら、その内容は高度で専門的なものにもかかわらず、説明が不足しており、何よりも優先されるべき食の安全・安心が実際に確保され、将来にわたって人への健康被害を及ぼす危惧はないのか、技術会議の議事録、データ等の公開も含め、十分な説明がなされなければなりません。また、交通アクセスの問題、場外市場への対応など今後のまちづくりを進める上での課題についても、地域住民や市場関係者の抱く懸念や不安が、未だ完全に払拭されているとは言えないところであります。
つきましては、以下の事項について明確にしていただけるよう要望いたします。
1 土壌汚染の問題
生鮮食品を取り扱う市場においては、科学的見地から食の安全・安心及び人の健康被害の防止の確保が図られることが何よりも重要であり、その取組みについて広く都民に理解され、信頼を得られることが不可欠である。
そのため、高度で専門的な事項にわたる土壌汚染対策の内容について、すべて明らかにし、本区をはじめ市場関係者や広く都民に対し必要な説明を十分に行い、理解を得ること。
2 築地市場用地の扱い
移転方針のもとで売却するとしている築地市場用地について、土地利用計画が明らかとなっていない。そのため、用地の扱いについて地元区として大変懸念されることから、地域の将来像を踏まえた具体的な土地利用計画を都はどのように考えているのか明らかにすること。
また本区と事前に協議を行い、市場関係者、地域住民等の意見を聴くとともに、幅広い議論を通じ英知を集め、都心に残された貴重な用地としてふさわしい活用がなされるよう十分に配慮すること。
3 場外市場の問題
これまで、場外市場は築地市場とともに一体となって「築地ブランド」を守り、育ててきた。「築地ブランド」は、今や、その名が世界にとどろき、日本屈指の観光スポットとなっている。
日本の財産である「築地ブランド」を守り、店舗数が350にのぼる場外市場を活気とにぎわいのあるまちとして発展させていくために、築地市場地区のまちづくりを都はどのように考えているのか明らかにすること。
4 交通アクセス問題
環状第二号線については、これまで豊洲新市場の開場する平成24年度時点で暫定開通、平成27年度までに供用開始するとしていた。しかし、開場時期の延期により、整備スケジュールや築地市場の営業に影響を与えることが考えられる。
そこで、改めて供用開始までのスケジュールについて示し、築地市場の営業に支障をきたさぬよう環状第二号線の整備を図ること。
5 移転までの間の現市場の整備
豊洲新市場の開場時期が延期したことを踏まえ、都民の台所として現在の機能を維持するための現市場の老朽化対策、安全対策、衛生対策等の計画について改めて都はどのように考えているのか明らかにすること。
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseizyoho/tukizisizyo/dojyoosenitennmonndaiyobo/index.html
築地市場再整備問題の経緯東京都中央区の取り組み
昭和57年3月
第22回東京都卸売市場審議会答申「第3次卸売市場整備基本方針」(昭和56年3月)を受けて「第3次東京都卸売市場整備計画」策定(昭和56から65年度)
青果市場:
・大田区及び品川区を中心とする地元消費の機能と築地・神田市場の過密解消を図るため、大井市場(仮称)を建設する。新市場の建設に伴って神田市場を廃止する。
水産市場
・大田区及び品川区を中心とする地元消費の機能と築地市場の過密解消を図るため、大井市場(仮称)を建設し、築地市場及び足立市場と合わせて計3市場を配置する。
6月
中央区議会が都知事・都議会へ「築地市場の大井移転反対の要請行動」を行い、決議書を渡す。
昭和61年1月
東京都首脳部会議において、築地市場の現在地での再整備を決定
3月
第31回東京都卸売市場審議会「第4次卸売市場整備基本方針」を答申「現在地において、立体化(1階部分を水産物部2階部分を青果部とするなど)を行い基幹市場としての機能を維持できるよう再整備の必要がある」
12月
「第4次卸売市場整備基本方針」を受けて、「第4次東京都卸売市場整備計画」策定(昭和61から70年度)
昭和62年4月
東京都と築地市場業界の協議機関として「築地市場再整備協議会(会長:市場長)」が設置される。
昭和63年11月
「築地市場再整備基本計画」策定
平成2年6月
「築地市場再整備基本設計」策定
平成3年1月
仮設工事着工
2月
第38回東京都卸売市場審議会「第5次卸売市場整備基本方針」を答申「築地市場再整備協議会」を「築地市場再整備推進協議会」に改組するなど、組織強化を図る。
11月
「第5次東京都卸売市場整備計画」策定(平成3から12年度)
[築地市場の再整備]現在地で営業しながら再整備を進める。また、可能な限り工期短縮に努める。
平成4年12月
本格工事着工(築地川東支川埋立)
平成5年5月
市場再整備の起工式が行われる。
平成8年4月
第46回東京都卸売市場審議会「第6次卸売市場整備基本方針」を答申「健全な財政計画に基づき、1. 工期の短縮、2. 建設コストの縮減、3. 基幹市場としての機能を維持していくため、流通環境の変化に対応した効率的で使いやすい市場とする視点から見直しを行う必要がある。」
11月
「第6次東京都卸売市場整備計画」策定(平成8から17年度)
[基本計画の変更]
1. 1階水産物部、2階青果部という立体的・一体的配置を改め、それぞれ分けて平面的に整備する。
2. 建築年次の比較的新しい施設は、原則継続使用する。 など
平成9年10月
築地市場再整備推進協議会において新しい計画についての協議を開始
平成10年2月
区長が副知事に面談のうえ「築地市場再整備に関する要望書」を提出(26日)
3月
都議会予算特別委員会において、中央卸売市場長が「全業界から一致して移転について調査、検討の要望があれば、(調査、検討を)行う」と答弁
議長が「築地市場再整備に関する要望書」を提出(31日)
4月
業界6団体が「臨海部に市場をつくることが可能かどうかについて調査・検討を早急かつ具体的に行い、当局の見解をだすよう」要望書を中央卸売市場長へ提出(2日)
5月
中央区議会に「築地市場再整備対策特別委員会」を設置
6月
業界6団体に対し東京都が回答(30日)
1. 移転の可能性を判断するためには、市場業界全体の一致した意思と場外市場関係者並びに関係区の協力が前提となる。
2. 市場業界各団体は一致した意思を明らかにするとともに場外市場関係者並びに関係区等の理解と協力を得るよう努力する必要がある。
3. これらのことを確認できる文書を今年中に提出すること。
中央区「中央区築地市場再整備対策本部」設置(30日)
7月
区長、議長の連名で副知事に面談のうえ築地市場再整備に関し都の考えを質す「築地市場の再整備に関する確認について」を提出(6日)
10月
中央区「築地市場に関するアンケート調査」実施(結果発表は翌年1月)
11月
区長、議長の連名で「築地市場再整備に関する要請」を提出(25日)
12月
市場業界各団体から東京都あて築地市場再整備に関する回答書を提出
1. 東京都中央卸売市場買出人団体連合会:現在地再整備
2. 東京魚市場卸協同組合:現在地再整備
3. 東京都水産物卸売業者協会、東京魚市場買参協同組合、築地市場青果連合事業協会、築地市場関連事業者等協議会の4団体連名:豊洲移転で意思統一
平成11年1月
中央区「築地市場に関するアンケート調査」調査結果を発表
2月
築地市場再整備推進協議会再開
東京都「築地市場整備問題検討会」を設置(8日)
3月
区長、議長の連名で「『築地市場整備問題検討会』に関する要請」を提出(15日)
第50回東京都卸売市場審議会開催(18日)
築地市場再整備推進協議会において改定試案Aを発表
4月
築地市場再整備推進協議会において改定試案B、Cを発表
東京魚市場卸協同組合、新理事長を選任
6月
築地市場再整備推進協議会において改定試案D、Eを発表。東京魚市場卸協同組合、独自案を提示「工期は13年」
7月
築地市場移転推進協議会「豊洲新市場構想」を披露
9月
都知事、築地市場を視察「古い、狭い、そして危ない」(1日)
中央区議会「築地市場の現在地での再整備を求める意見書」を採択(30日)
10月
区長、議長の連名で副知事に面談のうえ「築地市場再整備促進の要望について」を提出(6日)
第51回東京都卸売市場審議会開催(8日)
11月
第28回築地市場再整備推進協議会は移転整備の方向で検討をまとめる(9日)
区長、議長の連名で副知事に面談のうえ「築地市場再整備に関する抗議」を提出(10日)
行政、議会、町会、各種団体により築地市場移転反対運動を展開する「築地市場移転に断固反対する会」設立(29日)
築地市場移転に断固反対する会、移転反対署名運動展開。106,032人の署名が集まる。(29日から12月10日)
12月
築地市場移転に断固反対する会主催による「築地市場移転断固反対総決起大会」開催、中央会館ホールに900人が参加。その後、署名を添え副知事に面談のうえ「築地市場移転に断固反対する陳情」を提出(15日)
平成12年5月
築地市場移転に断固反対する会、総勢27名で副知事と面談のうえ「築地市場再整備に関する申し入れ」を提出(22日)
6月
東京ガスから副知事あて「弊社豊洲用地への築地市場移転に関わる御都のお考えについて(質問)」提出(2日)
第53回東京都卸売市場審議会開催(7日)
10月
中央区「築地市場現在地再整備促進基礎調査(中間報告)」公表「移転の場合は市場離れ6割」(25日)
11月
区長、議長、反対する会代表の連名で東京都議会正副議長、6会派代表者あて「築地市場再整備に関する要望書」提出(7日)
12月
都知事、都議会本会議で代表質問に対し「現在地での再整備はとても困難」と答弁(7日)
中央区「築地市場現在地再整備促進基礎調査」公表(20日)
第54回東京都卸売市場審議会開催、東京都卸売市場整備基本方針案(中間報告)了承。「(築地市場は)早急に、移転整備について検討する必要がある。」(22日)
平成13年1月
東京ガス、自社用地の土壌調査の結果を公表。豊洲は基準値をはるかに超える汚染状況(25日)
2月
東京都と東京ガス間で、用地問題等の本格的協議に入る覚書を締結(21日)
都知事、都議会本会議施政方針表明にて移転候補地は豊洲と言明(21日)
区長、議長の連名で都知事あて「築地市場再整備に関する知事施政方針への抗議」提出(28日)
4月
第55回東京都卸売市場審議会開催、東京都卸売市場整備基本方針を知事あて答申「(築地市場は)早急に豊洲地区を候補地として移転整備に向けた検討を進めるべきである。」(18日)
区長、議長の連名で都知事あて「築地市場再整備に関する要請」提出(19日)
5月
魚市場同友会(東京魚市場卸協同組合有志組織)主催による「築地で出来るぞ市場再整備!築地市場と街づくりについてのシンポジウム」開催(26日)
7月
東京都と東京ガス間で、市場の移転を織り込んだ豊洲のまちづくりを協力して進めることに合意。都知事定例記者会見で発表(6日)
濱渦副知事が区長を訪問。移転について協力を要請するとともに、平成11年11月に中央区が東京都に質していた移転整備に係る"五つの疑問"について回答する。(12日)
8月
築地市場移転に断固反対する会役員会を開催、「築地市場再整備に関する声明」を発表(3日)
9月
有識者及び市場業者による東京都「第1回新市場基本コンセプト懇談会」開催、13年度内に10回開催し市場流通の現状と問題点をまとめ、新市場のコンセプトを作成する予定(10日)
12月
第7次東京都卸売市場整備計画を発表、「現行の計画を改め、築地市場を豊洲地区に移転する」これに対し、区長・議長の連名で「東京都卸売市場整備計画についてのコメント」を発表(25日)
平成14年1月
第56回東京都卸売市場審議会開催、第7次東京都卸売市場整備計画を報告(28日)
2月
東京都「第34回築地市場再整備推進協議会」開催、第7次東京都卸売市場整備計画及び新市場基本コンセプト懇談会の検討状況を報告(15日)
3月
東京都「第35回築地市場再整備推進協議会」開催、協議会を改組し、「新市場建設協議会」の設置を了承(29日)
4月
築地市場移転に断固反対する会役員会を開催、交通アクセスや土壌汚染対策などの進捗状況を監視し、東京都に対し必要な働きかけを行うことを確認(4日)
5月
東京都「第1回新市場建設協議会」開催、新市場基本コンセプト懇談会の検討結果を報告(21日)
6月
東京都「第2回新市場建設協議会」開催、新市場予定地の概要及び基本構想協議の内容・方向性を報告(8日)
9月
東京都「豊洲・晴海開発整備計画再改定(豊洲)案」を発表、「豊洲地区に新市場の整備計画を織り込む」これに対し、区長名で都知事あて「豊洲・晴海開発整備計画の再改定に対する抗議」提出(27日)
10月
東京都「第3回新市場建設協議会」開催、豊洲・晴海開発整備計画再改定(豊洲)案及び新市場建設基本問題検討会の検討状況を報告(1日)
平成15年2月
東京都「第4回新市場建設協議会」開催。新市場づくりの検討結果のまとめについて報告するとともに、新市場建設基本構想起草懇談会を設置(3日)
2月27日から3月20日
東京都「新市場建設基本構想起草懇談会」を4回開催。各団体の意見を基に新市場の基本コンセプトについて検討
3月
東京都「第5回新市場建設協議会」開催。新市場建設基本構想起草懇談会における検討結果を報告し、新市場の基本コンセプト体系案及び新市場建設基本構想の起草について説明(27日)
5月
第57回東京都卸売市場審議会開催。豊洲新市場基本構想を報告(13日)
東京都「第6回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場基本構想を報告(15日)
7月
東京都「第7回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場基本計画策定について報告(8日)
9月
東京都「東京都市計画・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)素案」に対し、区長名で意見書を提出(30日)
中央区議会「東京都市計画区域マスタープラン素案について見直しを求める意見書」採択 (30日)
12月
東京都「第8回新市場建設協議会」開催。流通ゾーンの機能配置に係る検討経過及び今後の検討課題について報告(15日)
平成16年2月
東京都「環状第2号線の一部区間(晴海四丁目から築地五丁目)における道路構造形式を地下構造から平面構造(地上化)へ変更する」これに対し、区長、議長連名で都知事あて申し入れを行う。(19日)
4月
第58回東京都卸売市場審議会開催。豊洲新市場基本計画策定について、現在までの検討経過を報告(14日)
東京都「第9回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場基本計画策定について、現在までの検討経過を報告(15日)
5月
築地市場移転に断固反対する会総会を開催。
「築地市場移転反対の姿勢は変わらないが、万が一東京都が移転を強行した場合に備えて、移転後の築地地区のあり方を主体的に検討していく築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会を設置し、そのビジョンをもって東京都に対し、必要な働きかけを行っていく」ことを議決した。(24日)
7月
東京都「第10回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場基本計画を発表。協議会の了承を得る。(21日)
第59回東京都卸売市場審議会開催。豊洲新市場基本計画を報告(22日)
9月
築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会
5月から9月までの間6回開催
築地市場移転に断固反対する会総会開催
築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会中間まとめについて報告。
今後の会の方向性について次のとおり確認した。
「本年12月の最終報告に向けて、中央区がビジョンの中間まとめをもとに地域への説明にあたると同時に東京都と具体的な交渉に入ることになるので、東京都の対応を含め、具体的な成果が確認されるまでその推移を見守っていく。」(21日)
築地市場の跡地について「築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会中間まとめ」をもとに、中央区及び地元と協議を行うよう区長名で都知事あて要望書を提出(21日)
10月から12月
「築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会中間まとめ」について、各地区のまちづくり協議会をはじめとして、町会、自治会、関係団体等に対する説明会を開催
12月
第7回築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会開催。中間まとめの地域への説明会等での意見を踏まえた「築地市場地区の活気とにぎわいビジョン」と今後の進め方について協議(7日)
築地市場移転に断固反対する会総会開催
中間まとめの地域・関係団体への説明状況について区事務局から報告。さらに、地域や関係団体の意見を踏まえ、ビジョンの最終まとめとして「築地地区の活気とにぎわいビジョン − 世界に誇れる都心のさらなる発展に向けて」を発表し、断固反対する会の了承を得た。
今後の方向性について次のとおり確認した。「今後も引き続き、断固反対する会の意見を聴きながら、築地市場地区を核とした活気とにぎわいのあるまちづくりと、まちとの調和のとれた道路づくりに向けて、このビジョンを踏まえた都と区の真摯な協議への対応状況を注視していく。」(17日)
都知事に対し、築地市場地区や環状第2号線沿線のまちづくりを進めていくにあたっては「築地市場地区の活気とにぎわいビジョン」をもとに、中央区と協議、検討を行うよう区長名で要望書を提出(17日)
平成17年3月
農林水産省「中央卸売市場整備計画」を公表
豊洲新市場が新設市場として位置付けられる。(31日)
4月
第62回東京都卸売市場審議会開催
第8次東京都卸売市場整備基本方針を答申
豊洲新市場を中央卸売市場と位置付け、平成24年開場を目途に整備する方針が示された。(26日)
9月
東京都「第11回新市場建設協議会」開催
豊洲新市場実施計画のまとめ(案)を報告(15日)
11月
第63回東京都卸売市場審議会開催
第8次東京都卸売市場整備計画を報告。築地市場が豊洲地区へ移転し、豊洲新市場を平成24年度開場を目途に整備することとされた。
豊洲新市場実施計画のまとめを報告(22日)
平成18年2月
地元の懸念や不安を解消し、築地市場地区が今後とも活気ある地域として存続していくために、市場移転の前提となる7つの疑問(移転先の土地確保の問題、築地市場用地の扱い、交通アクセス問題、場外市場の問題、移転までの間の現市場の整備、土壌汚染の問題、財源確保の問題)について、都知事に対し再度回答を求めた。(9日)
都知事より、7つの疑問について回答がなされる。(13日)
築地市場移転に断固反対する会総会開催
区事務局から7つの疑問に対する東京都からの回答及び場外市場地区の活性化に向けた取組について、「築地食のまちづくり協議会」会長にから当協議会設立について報告がなされた。
これらの報告を受けて、今後の運動方針について協議が行われ、「築地市場移転に断固反対する会」としての活動を終了し、「新しい築地をつくる会」として市場移転後の活気とにぎわいのあるまちづくりに向けて、目標も新たに再出発することが決議された。(17日)
***********************************
平成18年2月13日
中央区長 矢田 美英 様
東京都知事 石原 慎太郎
築地市場移転について
日頃より、東京都の事業運営にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
さて、東京都は、昨年11月に「第8次東京都卸売市場整備計画」を策定し、築地市場を豊洲地区に移転して、平成24年度を目途に豊洲新市場を開場することといたしました。
豊洲新市場においては、21世紀の生鮮食料品流通の中核を担う拠点として、流通環境の変化に対応できる機能を取り入れるとともに、東京の新しい観光拠点となる千客万来のにぎわいゾーンを創出していきたいと考えております。
築地市場移転にあたっては、関係機関をはじめ広く都民のご意見も伺いながら進めていきたいと考えておりますので、貴区におかれましても、一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、平成18年2月9日付17中企企第95号については、別紙のとおりご説明申し上げます。
別紙
1 移転先の44ヘクタールの土地の確保問題
豊洲新市場予定地の確保状況について
豊洲地区において新市場用地を確保するためには、民間地権者から土地を取得することは不可欠であり、平成14年7月の民間地権者と東京都が締結した「豊洲地区開発整備に係る合意」において、築地市場の豊洲地区への移転について合意を行っている。
豊洲新市場の購入予定用地37.5ヘクタールについては、既に16年度に一部先行取得している。今後は、24年度の市場開場が可能となるよう、土地区画整理事業の進捗に合わせ、保留地や仮換地後の地権者から順次取得していく。
なお、防潮護岸を含んだ総面積は、約44ヘクタールとなる。
2 築地市場用地の扱い
築地市場用地の売却方針のもとでの跡地利用について
築地市場地域は、高い開発ポテンシャルとともに快適な水辺空間や豊かな緑の環境を有している。築地市場用地は、豊洲新市場移転に関わる費用等に充てるため売却するが、跡地利用については、この立地特性を十分活かし、都民全体の貴重な財産として東京のまちづくりに貢献するものとなるよう、今後、慎重に検討していきたい。
3 交通アクセス問題
豊洲地区における市場の発生集中交通への対応及び幹線道路の整備スケジュールについて
豊洲新市場への交通アクセスとして、地区の南北及び東西の骨格となる晴海通り延伸部、環状第二号線及び補助第315号線の整備を着実に進める。
晴海通り延伸部については、平成18年度に全線開通する予定である。環状第二号線については、27年度までに全線開通する予定であるが、豊洲新市場が開場する24年度時点では暫定開通で対応する。なお、晴海から築地までの区間については、16年2月に都市計画変更素案説明会を行っており、19年度の都市計画変更及び事業認可取得に向け、引き続き、都市計画及びアセス手続を進める。補助第315号線のうち、新交通システム「ゆりかもめ」の豊洲延伸(有明〜豊洲間)に係る区間については、17年度末までに開通する。
4 場外市場の問題
豊洲新市場へ移転を希望する場外市場業者への対応及び市場業者の築地市場移転に伴う負担増について
豊洲新市場におけるにぎわいを創出する千客万来施設は、民間事業者のノウハウを活用して整備することとしているが、整備にあたり、豊洲新市場へ移転を希望する場外市場業者の要望も視野に入れ、施設の内容、規模などの検討を行っていく。
豊洲新市場においても、市場業者の健全な経営が確保されることは重要である。市場施設の建設経費や運営費は原則として市場業者の使用料で賄うが、適正な施設規模や効率的な整備・運営手法など様々な角度から事業費の削減に取り組むことにより、市場業者の負担の抑制を図っていく。
5 移転までの間の現市場の整備
築地市場における衛生対策及び防災対策について
豊洲新市場の開場までには相当期間を必要とし、この間も都民の台所としての現在の機能を維持するため、施設の再配置、売場の集約化や低温化など、物流の効率化、衛生対策、耐震改修工事等を行ってきた。
今後も、第8次東京都卸売市場整備計画に基づき、衛生対策、環境対策、老朽化施設の補修又は撤去、交通動線の改善等を行っていく。
6 土壌汚染の問題
豊洲地区における土壌汚染対策について
新市場予定地の土壌汚染については、汚染原因者である東京ガスの責任により処理を行う。
東京ガスは、環境確保条例に定める土壌汚染処理基準の10倍を超える汚染土壌については、すべて処理基準以下となるよう処理をする。また、10倍以下の汚染土壌についても条例で定める土壌汚染対策指針に基づき用地全体を覆土し飛散を防止することとしていることから、安全性に問題はない。特に、市場は生鮮食料品を取り扱うものであり、安全をより一層確実なものとするため、少なくとも盛土後の地盤高から4.5mの深さまではすべて処理基準以下とする。処理基準以下となっているかについては、環境大臣が指定する指定調査機関が調査を行う。
処理が適切に行われているかについては、東京都が確認を行う。これらの処理は、仮換地として地権者に引き渡されるとき又は保留地として処分されるときまでに完了することとしている。その後、中央卸売市場は地権者から土地を取得する。
7 財源確保の問題(市場整備・幹線道路整備)
豊洲新市場建設や幹線道路整備の財源について
豊洲新市場建設の財源については、築地市場跡地の売却費、企業債、国庫補助金等を充てる予定である。
環状第二号線や晴海通り延伸部、補助第315号線等の幹線道路は、公共負担と開発者負担により財源確保に努めながら整備を進める。
***********************************
3月
築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり委員会を開催し、銀座・築地地区分科会および勝どき・豊海・晴海分科会での調査・検討を踏まえ、「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり調査報告書(平成17年度)」を取りまとめた。(1日)
6月
環状第2号線の地下から地上への都市計画変更案について東京都から全員協議会へ説明が行われる。(28日)
8月
東京都より都市計画変更案への意見照会あり。(15日)
9月
東京都「東京都市計画道路環状第2号線建設事業」について「東京都環境影響評価条例」に基づき、都知事(環境局)に環境影響評価書案を提出。(14日)
10月
広く区民等へ都市計画変更案を周知し意見をもらうため、計画案の広告・縦覧を開始する。(11日〜25日)
東京都「第12回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場の施設規模、配置などを取りまとめた基本設計相当が決定された。協議会の了承を得る。(13日)
11月
第64回東京都卸売市場審議会開催。豊洲新市場の整備について、基本設計相当を取りまとめ、PFI手法を導入することを報告(20日)
12月
「築地食のまちづくり協議会」が特定非営利活動法人(NPO法人)に認証され、法人格を取得した。(1日)
平成19年1月
東京都「東京都市計画道路環状第2号線建設事業」について、環境影響評価書案に対して寄せられた都民等の意見に対する見解書を作成し、都知事(環境局)に提出。(19日)
東京都「豊洲新市場建設事業」について「東京都環境影響評価条例」に基づき、東京都知事(環境局)に環境影響評価書案を提出。(25日)
2月
平成19年度「築地食のまちづくり協議会通常総会」開催。(19日)
3月
築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり委員会を開催し、銀座・築地地区分科会および勝どき・豊海・晴海分科会での調査・検討を踏まえ、「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり調査報告書(平成18年度)」を取りまとめた。(27日)
昭和57年3月
第22回東京都卸売市場審議会答申「第3次卸売市場整備基本方針」(昭和56年3月)を受けて「第3次東京都卸売市場整備計画」策定(昭和56から65年度)
青果市場:
・大田区及び品川区を中心とする地元消費の機能と築地・神田市場の過密解消を図るため、大井市場(仮称)を建設する。新市場の建設に伴って神田市場を廃止する。
水産市場
・大田区及び品川区を中心とする地元消費の機能と築地市場の過密解消を図るため、大井市場(仮称)を建設し、築地市場及び足立市場と合わせて計3市場を配置する。
6月
中央区議会が都知事・都議会へ「築地市場の大井移転反対の要請行動」を行い、決議書を渡す。
昭和61年1月
東京都首脳部会議において、築地市場の現在地での再整備を決定
3月
第31回東京都卸売市場審議会「第4次卸売市場整備基本方針」を答申「現在地において、立体化(1階部分を水産物部2階部分を青果部とするなど)を行い基幹市場としての機能を維持できるよう再整備の必要がある」
12月
「第4次卸売市場整備基本方針」を受けて、「第4次東京都卸売市場整備計画」策定(昭和61から70年度)
昭和62年4月
東京都と築地市場業界の協議機関として「築地市場再整備協議会(会長:市場長)」が設置される。
昭和63年11月
「築地市場再整備基本計画」策定
平成2年6月
「築地市場再整備基本設計」策定
平成3年1月
仮設工事着工
2月
第38回東京都卸売市場審議会「第5次卸売市場整備基本方針」を答申「築地市場再整備協議会」を「築地市場再整備推進協議会」に改組するなど、組織強化を図る。
11月
「第5次東京都卸売市場整備計画」策定(平成3から12年度)
[築地市場の再整備]現在地で営業しながら再整備を進める。また、可能な限り工期短縮に努める。
平成4年12月
本格工事着工(築地川東支川埋立)
平成5年5月
市場再整備の起工式が行われる。
平成8年4月
第46回東京都卸売市場審議会「第6次卸売市場整備基本方針」を答申「健全な財政計画に基づき、1. 工期の短縮、2. 建設コストの縮減、3. 基幹市場としての機能を維持していくため、流通環境の変化に対応した効率的で使いやすい市場とする視点から見直しを行う必要がある。」
11月
「第6次東京都卸売市場整備計画」策定(平成8から17年度)
[基本計画の変更]
1. 1階水産物部、2階青果部という立体的・一体的配置を改め、それぞれ分けて平面的に整備する。
2. 建築年次の比較的新しい施設は、原則継続使用する。
など
平成9年10月
築地市場再整備推進協議会において新しい計画についての協議を開始
平成10年2月
区長が副知事に面談のうえ「築地市場再整備に関する要望書」を提出(26日)
3月
都議会予算特別委員会において、中央卸売市場長が「全業界から一致して移転について調査、検討の要望があれば、(調査、検討を)行う」と答弁
議長が「築地市場再整備に関する要望書」を提出(31日)
4月
業界6団体が「臨海部に市場をつくることが可能かどうかについて調査・検討を早急かつ具体的に行い、当局の見解をだすよう」要望書を中央卸売市場長へ提出(2日)
5月
中央区議会に「築地市場再整備対策特別委員会」を設置
6月
業界6団体に対し東京都が回答(30日)
1. 移転の可能性を判断するためには、市場業界全体の一致した意思と場外市場関係者並びに関係区の協力が前提となる。
2. 市場業界各団体は一致した意思を明らかにするとともに場外市場関係者並びに関係区等の理解と協力を得るよう努力する必要がある。
3. これらのことを確認できる文書を今年中に提出すること。
中央区「中央区築地市場再整備対策本部」設置(30日)
7月
区長、議長の連名で副知事に面談のうえ築地市場再整備に関し都の考えを質す「築地市場の再整備に関する確認について」を提出(6日)
10月
中央区「築地市場に関するアンケート調査」実施(結果発表は翌年1月)
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseizyoho/tukizisizyo/tsukijikeiitorikumi19ikou/index.html
平成21年2月6日に東京都から、「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」の提言及び「豊洲新市場整備方針」等について発表されました。中央区では、これを受けて区長から下記のとおり、東京都知事宛て要望をいたしましたのでお知らせいたします。
平成21年2月26日
東京都知事 石原慎太郎様
中央区長 矢田美英
豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る築地市場移転問題に関する要望について
さて、本区にあります築地市場は、昭和10年2月の開場以来、「都民の台所」として都民の食生活を支えるとともに、全国規模の食材流通に欠かせない拠点であります。また、74年にも及ぶ歴史の中で、場外市場とともに日本の食文化を代表する「築地ブランド」を育んでまいりました。
しかし、平成11年に豊洲への移転整備が打ち出されたことから、本区は、地域住民や市場関係者等の移転整備に伴うさまざまな疑問や不安を受けて東京都に対して繰り返し、質問や申入れなどを行ってまいりました。また、豊洲新市場基本計画が公表されるなど移転計画が具体化する中、仮に市場が移転した場合にあっても、築地市場地区が活気とにぎわいを持ち続けるためにどうあるべきかを、「築地市場地区の活気とにぎわいビジョン」の策定により明らかにしました。
その後、かねてから不安を抱いていた新市場予定地の土壌汚染については、専門家会議が設置されたことから、その調査・検討状況を注視してまいりましたが、詳細調査で基準値を大幅に上回るベンゼンが検出されるなど、憂慮すべき状況が明らかとなったところであります。
さらに、専門家会議の提言を受けて対策をとりまとめるにあたり、具体的な技術・工法の公募が実施され、その評価・検証のため技術会議が設置されたことから、これらの状況の推移を慎重に見守ってきたところであります。こうした経過の中、汚染物質や不透水層に関するデータの一部が遅れて公表されたことは、誠に遺憾であります。
このような状況において、2月6日、技術会議の検討結果を踏まえた土壌汚染対策が発表されました。しかしながら、その内容は高度で専門的なものにもかかわらず、説明が不足しており、何よりも優先されるべき食の安全・安心が実際に確保され、将来にわたって人への健康被害を及ぼす危惧はないのか、技術会議の議事録、データ等の公開も含め、十分な説明がなされなければなりません。また、交通アクセスの問題、場外市場への対応など今後のまちづくりを進める上での課題についても、地域住民や市場関係者の抱く懸念や不安が、未だ完全に払拭されているとは言えないところであります。
つきましては、以下の事項について明確にしていただけるよう要望いたします。
1 土壌汚染の問題
生鮮食品を取り扱う市場においては、科学的見地から食の安全・安心及び人の健康被害の防止の確保が図られることが何よりも重要であり、その取組みについて広く都民に理解され、信頼を得られることが不可欠である。
そのため、高度で専門的な事項にわたる土壌汚染対策の内容について、すべて明らかにし、本区をはじめ市場関係者や広く都民に対し必要な説明を十分に行い、理解を得ること。
2 築地市場用地の扱い
移転方針のもとで売却するとしている築地市場用地について、土地利用計画が明らかとなっていない。そのため、用地の扱いについて地元区として大変懸念されることから、地域の将来像を踏まえた具体的な土地利用計画を都はどのように考えているのか明らかにすること。
また本区と事前に協議を行い、市場関係者、地域住民等の意見を聴くとともに、幅広い議論を通じ英知を集め、都心に残された貴重な用地としてふさわしい活用がなされるよう十分に配慮すること。
3 場外市場の問題
これまで、場外市場は築地市場とともに一体となって「築地ブランド」を守り、育ててきた。「築地ブランド」は、今や、その名が世界にとどろき、日本屈指の観光スポットとなっている。
日本の財産である「築地ブランド」を守り、店舗数が350にのぼる場外市場を活気とにぎわいのあるまちとして発展させていくために、築地市場地区のまちづくりを都はどのように考えているのか明らかにすること。
4 交通アクセス問題
環状第二号線については、これまで豊洲新市場の開場する平成24年度時点で暫定開通、平成27年度までに供用開始するとしていた。しかし、開場時期の延期により、整備スケジュールや築地市場の営業に影響を与えることが考えられる。
そこで、改めて供用開始までのスケジュールについて示し、築地市場の営業に支障をきたさぬよう環状第二号線の整備を図ること。
5 移転までの間の現市場の整備
豊洲新市場の開場時期が延期したことを踏まえ、都民の台所として現在の機能を維持するための現市場の老朽化対策、安全対策、衛生対策等の計画について改めて都はどのように考えているのか明らかにすること。
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseizyoho/tukizisizyo/dojyoosenitennmonndaiyobo/index.html
築地市場再整備問題の経緯東京都中央区の取り組み
昭和57年3月
第22回東京都卸売市場審議会答申「第3次卸売市場整備基本方針」(昭和56年3月)を受けて「第3次東京都卸売市場整備計画」策定(昭和56から65年度)
青果市場:
・大田区及び品川区を中心とする地元消費の機能と築地・神田市場の過密解消を図るため、大井市場(仮称)を建設する。新市場の建設に伴って神田市場を廃止する。
水産市場
・大田区及び品川区を中心とする地元消費の機能と築地市場の過密解消を図るため、大井市場(仮称)を建設し、築地市場及び足立市場と合わせて計3市場を配置する。
6月
中央区議会が都知事・都議会へ「築地市場の大井移転反対の要請行動」を行い、決議書を渡す。
昭和61年1月
東京都首脳部会議において、築地市場の現在地での再整備を決定
3月
第31回東京都卸売市場審議会「第4次卸売市場整備基本方針」を答申「現在地において、立体化(1階部分を水産物部2階部分を青果部とするなど)を行い基幹市場としての機能を維持できるよう再整備の必要がある」
12月
「第4次卸売市場整備基本方針」を受けて、「第4次東京都卸売市場整備計画」策定(昭和61から70年度)
昭和62年4月
東京都と築地市場業界の協議機関として「築地市場再整備協議会(会長:市場長)」が設置される。
昭和63年11月
「築地市場再整備基本計画」策定
平成2年6月
「築地市場再整備基本設計」策定
平成3年1月
仮設工事着工
2月
第38回東京都卸売市場審議会「第5次卸売市場整備基本方針」を答申「築地市場再整備協議会」を「築地市場再整備推進協議会」に改組するなど、組織強化を図る。
11月
「第5次東京都卸売市場整備計画」策定(平成3から12年度)
[築地市場の再整備]現在地で営業しながら再整備を進める。また、可能な限り工期短縮に努める。
平成4年12月
本格工事着工(築地川東支川埋立)
平成5年5月
市場再整備の起工式が行われる。
平成8年4月
第46回東京都卸売市場審議会「第6次卸売市場整備基本方針」を答申「健全な財政計画に基づき、1. 工期の短縮、2. 建設コストの縮減、3. 基幹市場としての機能を維持していくため、流通環境の変化に対応した効率的で使いやすい市場とする視点から見直しを行う必要がある。」
11月
「第6次東京都卸売市場整備計画」策定(平成8から17年度)
[基本計画の変更]
1. 1階水産物部、2階青果部という立体的・一体的配置を改め、それぞれ分けて平面的に整備する。
2. 建築年次の比較的新しい施設は、原則継続使用する。 など
平成9年10月
築地市場再整備推進協議会において新しい計画についての協議を開始
平成10年2月
区長が副知事に面談のうえ「築地市場再整備に関する要望書」を提出(26日)
3月
都議会予算特別委員会において、中央卸売市場長が「全業界から一致して移転について調査、検討の要望があれば、(調査、検討を)行う」と答弁
議長が「築地市場再整備に関する要望書」を提出(31日)
4月
業界6団体が「臨海部に市場をつくることが可能かどうかについて調査・検討を早急かつ具体的に行い、当局の見解をだすよう」要望書を中央卸売市場長へ提出(2日)
5月
中央区議会に「築地市場再整備対策特別委員会」を設置
6月
業界6団体に対し東京都が回答(30日)
1. 移転の可能性を判断するためには、市場業界全体の一致した意思と場外市場関係者並びに関係区の協力が前提となる。
2. 市場業界各団体は一致した意思を明らかにするとともに場外市場関係者並びに関係区等の理解と協力を得るよう努力する必要がある。
3. これらのことを確認できる文書を今年中に提出すること。
中央区「中央区築地市場再整備対策本部」設置(30日)
7月
区長、議長の連名で副知事に面談のうえ築地市場再整備に関し都の考えを質す「築地市場の再整備に関する確認について」を提出(6日)
10月
中央区「築地市場に関するアンケート調査」実施(結果発表は翌年1月)
11月
区長、議長の連名で「築地市場再整備に関する要請」を提出(25日)
12月
市場業界各団体から東京都あて築地市場再整備に関する回答書を提出
1. 東京都中央卸売市場買出人団体連合会:現在地再整備
2. 東京魚市場卸協同組合:現在地再整備
3. 東京都水産物卸売業者協会、東京魚市場買参協同組合、築地市場青果連合事業協会、築地市場関連事業者等協議会の4団体連名:豊洲移転で意思統一
平成11年1月
中央区「築地市場に関するアンケート調査」調査結果を発表
2月
築地市場再整備推進協議会再開
東京都「築地市場整備問題検討会」を設置(8日)
3月
区長、議長の連名で「『築地市場整備問題検討会』に関する要請」を提出(15日)
第50回東京都卸売市場審議会開催(18日)
築地市場再整備推進協議会において改定試案Aを発表
4月
築地市場再整備推進協議会において改定試案B、Cを発表
東京魚市場卸協同組合、新理事長を選任
6月
築地市場再整備推進協議会において改定試案D、Eを発表。東京魚市場卸協同組合、独自案を提示「工期は13年」
7月
築地市場移転推進協議会「豊洲新市場構想」を披露
9月
都知事、築地市場を視察「古い、狭い、そして危ない」(1日)
中央区議会「築地市場の現在地での再整備を求める意見書」を採択(30日)
10月
区長、議長の連名で副知事に面談のうえ「築地市場再整備促進の要望について」を提出(6日)
第51回東京都卸売市場審議会開催(8日)
11月
第28回築地市場再整備推進協議会は移転整備の方向で検討をまとめる(9日)
区長、議長の連名で副知事に面談のうえ「築地市場再整備に関する抗議」を提出(10日)
行政、議会、町会、各種団体により築地市場移転反対運動を展開する「築地市場移転に断固反対する会」設立(29日)
築地市場移転に断固反対する会、移転反対署名運動展開。106,032人の署名が集まる。(29日から12月10日)
12月
築地市場移転に断固反対する会主催による「築地市場移転断固反対総決起大会」開催、中央会館ホールに900人が参加。その後、署名を添え副知事に面談のうえ「築地市場移転に断固反対する陳情」を提出(15日)
平成12年5月
築地市場移転に断固反対する会、総勢27名で副知事と面談のうえ「築地市場再整備に関する申し入れ」を提出(22日)
6月
東京ガスから副知事あて「弊社豊洲用地への築地市場移転に関わる御都のお考えについて(質問)」提出(2日)
第53回東京都卸売市場審議会開催(7日)
10月
中央区「築地市場現在地再整備促進基礎調査(中間報告)」公表「移転の場合は市場離れ6割」(25日)
11月
区長、議長、反対する会代表の連名で東京都議会正副議長、6会派代表者あて「築地市場再整備に関する要望書」提出(7日)
12月
都知事、都議会本会議で代表質問に対し「現在地での再整備はとても困難」と答弁(7日)
中央区「築地市場現在地再整備促進基礎調査」公表(20日)
第54回東京都卸売市場審議会開催、東京都卸売市場整備基本方針案(中間報告)了承。「(築地市場は)早急に、移転整備について検討する必要がある。」(22日)
平成13年1月
東京ガス、自社用地の土壌調査の結果を公表。豊洲は基準値をはるかに超える汚染状況(25日)
2月
東京都と東京ガス間で、用地問題等の本格的協議に入る覚書を締結(21日)
都知事、都議会本会議施政方針表明にて移転候補地は豊洲と言明(21日)
区長、議長の連名で都知事あて「築地市場再整備に関する知事施政方針への抗議」提出(28日)
4月
第55回東京都卸売市場審議会開催、東京都卸売市場整備基本方針を知事あて答申「(築地市場は)早急に豊洲地区を候補地として移転整備に向けた検討を進めるべきである。」(18日)
区長、議長の連名で都知事あて「築地市場再整備に関する要請」提出(19日)
5月
魚市場同友会(東京魚市場卸協同組合有志組織)主催による「築地で出来るぞ市場再整備!築地市場と街づくりについてのシンポジウム」開催(26日)
7月
東京都と東京ガス間で、市場の移転を織り込んだ豊洲のまちづくりを協力して進めることに合意。都知事定例記者会見で発表(6日)
濱渦副知事が区長を訪問。移転について協力を要請するとともに、平成11年11月に中央区が東京都に質していた移転整備に係る"五つの疑問"について回答する。(12日)
8月
築地市場移転に断固反対する会役員会を開催、「築地市場再整備に関する声明」を発表(3日)
9月
有識者及び市場業者による東京都「第1回新市場基本コンセプト懇談会」開催、13年度内に10回開催し市場流通の現状と問題点をまとめ、新市場のコンセプトを作成する予定(10日)
12月
第7次東京都卸売市場整備計画を発表、「現行の計画を改め、築地市場を豊洲地区に移転する」これに対し、区長・議長の連名で「東京都卸売市場整備計画についてのコメント」を発表(25日)
平成14年1月
第56回東京都卸売市場審議会開催、第7次東京都卸売市場整備計画を報告(28日)
2月
東京都「第34回築地市場再整備推進協議会」開催、第7次東京都卸売市場整備計画及び新市場基本コンセプト懇談会の検討状況を報告(15日)
3月
東京都「第35回築地市場再整備推進協議会」開催、協議会を改組し、「新市場建設協議会」の設置を了承(29日)
4月
築地市場移転に断固反対する会役員会を開催、交通アクセスや土壌汚染対策などの進捗状況を監視し、東京都に対し必要な働きかけを行うことを確認(4日)
5月
東京都「第1回新市場建設協議会」開催、新市場基本コンセプト懇談会の検討結果を報告(21日)
6月
東京都「第2回新市場建設協議会」開催、新市場予定地の概要及び基本構想協議の内容・方向性を報告(8日)
9月
東京都「豊洲・晴海開発整備計画再改定(豊洲)案」を発表、「豊洲地区に新市場の整備計画を織り込む」これに対し、区長名で都知事あて「豊洲・晴海開発整備計画の再改定に対する抗議」提出(27日)
10月
東京都「第3回新市場建設協議会」開催、豊洲・晴海開発整備計画再改定(豊洲)案及び新市場建設基本問題検討会の検討状況を報告(1日)
平成15年2月
東京都「第4回新市場建設協議会」開催。新市場づくりの検討結果のまとめについて報告するとともに、新市場建設基本構想起草懇談会を設置(3日)
2月27日から3月20日
東京都「新市場建設基本構想起草懇談会」を4回開催。各団体の意見を基に新市場の基本コンセプトについて検討
3月
東京都「第5回新市場建設協議会」開催。新市場建設基本構想起草懇談会における検討結果を報告し、新市場の基本コンセプト体系案及び新市場建設基本構想の起草について説明(27日)
5月
第57回東京都卸売市場審議会開催。豊洲新市場基本構想を報告(13日)
東京都「第6回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場基本構想を報告(15日)
7月
東京都「第7回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場基本計画策定について報告(8日)
9月
東京都「東京都市計画・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)素案」に対し、区長名で意見書を提出(30日)
中央区議会「東京都市計画区域マスタープラン素案について見直しを求める意見書」採択 (30日)
12月
東京都「第8回新市場建設協議会」開催。流通ゾーンの機能配置に係る検討経過及び今後の検討課題について報告(15日)
平成16年2月
東京都「環状第2号線の一部区間(晴海四丁目から築地五丁目)における道路構造形式を地下構造から平面構造(地上化)へ変更する」これに対し、区長、議長連名で都知事あて申し入れを行う。(19日)
4月
第58回東京都卸売市場審議会開催。豊洲新市場基本計画策定について、現在までの検討経過を報告(14日)
東京都「第9回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場基本計画策定について、現在までの検討経過を報告(15日)
5月
築地市場移転に断固反対する会総会を開催。
「築地市場移転反対の姿勢は変わらないが、万が一東京都が移転を強行した場合に備えて、移転後の築地地区のあり方を主体的に検討していく築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会を設置し、そのビジョンをもって東京都に対し、必要な働きかけを行っていく」ことを議決した。(24日)
7月
東京都「第10回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場基本計画を発表。協議会の了承を得る。(21日)
第59回東京都卸売市場審議会開催。豊洲新市場基本計画を報告(22日)
9月
築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会
5月から9月までの間6回開催
築地市場移転に断固反対する会総会開催
築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会中間まとめについて報告。
今後の会の方向性について次のとおり確認した。
「本年12月の最終報告に向けて、中央区がビジョンの中間まとめをもとに地域への説明にあたると同時に東京都と具体的な交渉に入ることになるので、東京都の対応を含め、具体的な成果が確認されるまでその推移を見守っていく。」(21日)
築地市場の跡地について「築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会中間まとめ」をもとに、中央区及び地元と協議を行うよう区長名で都知事あて要望書を提出(21日)
10月から12月
「築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会中間まとめ」について、各地区のまちづくり協議会をはじめとして、町会、自治会、関係団体等に対する説明会を開催
12月
第7回築地市場地区の活気とにぎわいビジョンづくり委員会開催。中間まとめの地域への説明会等での意見を踏まえた「築地市場地区の活気とにぎわいビジョン」と今後の進め方について協議(7日)
築地市場移転に断固反対する会総会開催
中間まとめの地域・関係団体への説明状況について区事務局から報告。さらに、地域や関係団体の意見を踏まえ、ビジョンの最終まとめとして「築地地区の活気とにぎわいビジョン − 世界に誇れる都心のさらなる発展に向けて」を発表し、断固反対する会の了承を得た。
今後の方向性について次のとおり確認した。「今後も引き続き、断固反対する会の意見を聴きながら、築地市場地区を核とした活気とにぎわいのあるまちづくりと、まちとの調和のとれた道路づくりに向けて、このビジョンを踏まえた都と区の真摯な協議への対応状況を注視していく。」(17日)
都知事に対し、築地市場地区や環状第2号線沿線のまちづくりを進めていくにあたっては「築地市場地区の活気とにぎわいビジョン」をもとに、中央区と協議、検討を行うよう区長名で要望書を提出(17日)
平成17年3月
農林水産省「中央卸売市場整備計画」を公表
豊洲新市場が新設市場として位置付けられる。(31日)
4月
第62回東京都卸売市場審議会開催
第8次東京都卸売市場整備基本方針を答申
豊洲新市場を中央卸売市場と位置付け、平成24年開場を目途に整備する方針が示された。(26日)
9月
東京都「第11回新市場建設協議会」開催
豊洲新市場実施計画のまとめ(案)を報告(15日)
11月
第63回東京都卸売市場審議会開催
第8次東京都卸売市場整備計画を報告。築地市場が豊洲地区へ移転し、豊洲新市場を平成24年度開場を目途に整備することとされた。
豊洲新市場実施計画のまとめを報告(22日)
平成18年2月
地元の懸念や不安を解消し、築地市場地区が今後とも活気ある地域として存続していくために、市場移転の前提となる7つの疑問(移転先の土地確保の問題、築地市場用地の扱い、交通アクセス問題、場外市場の問題、移転までの間の現市場の整備、土壌汚染の問題、財源確保の問題)について、都知事に対し再度回答を求めた。(9日)
都知事より、7つの疑問について回答がなされる。(13日)
築地市場移転に断固反対する会総会開催
区事務局から7つの疑問に対する東京都からの回答及び場外市場地区の活性化に向けた取組について、「築地食のまちづくり協議会」会長にから当協議会設立について報告がなされた。
これらの報告を受けて、今後の運動方針について協議が行われ、「築地市場移転に断固反対する会」としての活動を終了し、「新しい築地をつくる会」として市場移転後の活気とにぎわいのあるまちづくりに向けて、目標も新たに再出発することが決議された。(17日)
***********************************
平成18年2月13日
中央区長 矢田 美英 様
東京都知事 石原 慎太郎
築地市場移転について
日頃より、東京都の事業運営にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
さて、東京都は、昨年11月に「第8次東京都卸売市場整備計画」を策定し、築地市場を豊洲地区に移転して、平成24年度を目途に豊洲新市場を開場することといたしました。
豊洲新市場においては、21世紀の生鮮食料品流通の中核を担う拠点として、流通環境の変化に対応できる機能を取り入れるとともに、東京の新しい観光拠点となる千客万来のにぎわいゾーンを創出していきたいと考えております。
築地市場移転にあたっては、関係機関をはじめ広く都民のご意見も伺いながら進めていきたいと考えておりますので、貴区におかれましても、一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、平成18年2月9日付17中企企第95号については、別紙のとおりご説明申し上げます。
別紙
1 移転先の44ヘクタールの土地の確保問題
豊洲新市場予定地の確保状況について
豊洲地区において新市場用地を確保するためには、民間地権者から土地を取得することは不可欠であり、平成14年7月の民間地権者と東京都が締結した「豊洲地区開発整備に係る合意」において、築地市場の豊洲地区への移転について合意を行っている。
豊洲新市場の購入予定用地37.5ヘクタールについては、既に16年度に一部先行取得している。今後は、24年度の市場開場が可能となるよう、土地区画整理事業の進捗に合わせ、保留地や仮換地後の地権者から順次取得していく。
なお、防潮護岸を含んだ総面積は、約44ヘクタールとなる。
2 築地市場用地の扱い
築地市場用地の売却方針のもとでの跡地利用について
築地市場地域は、高い開発ポテンシャルとともに快適な水辺空間や豊かな緑の環境を有している。築地市場用地は、豊洲新市場移転に関わる費用等に充てるため売却するが、跡地利用については、この立地特性を十分活かし、都民全体の貴重な財産として東京のまちづくりに貢献するものとなるよう、今後、慎重に検討していきたい。
3 交通アクセス問題
豊洲地区における市場の発生集中交通への対応及び幹線道路の整備スケジュールについて
豊洲新市場への交通アクセスとして、地区の南北及び東西の骨格となる晴海通り延伸部、環状第二号線及び補助第315号線の整備を着実に進める。
晴海通り延伸部については、平成18年度に全線開通する予定である。環状第二号線については、27年度までに全線開通する予定であるが、豊洲新市場が開場する24年度時点では暫定開通で対応する。なお、晴海から築地までの区間については、16年2月に都市計画変更素案説明会を行っており、19年度の都市計画変更及び事業認可取得に向け、引き続き、都市計画及びアセス手続を進める。補助第315号線のうち、新交通システム「ゆりかもめ」の豊洲延伸(有明〜豊洲間)に係る区間については、17年度末までに開通する。
4 場外市場の問題
豊洲新市場へ移転を希望する場外市場業者への対応及び市場業者の築地市場移転に伴う負担増について
豊洲新市場におけるにぎわいを創出する千客万来施設は、民間事業者のノウハウを活用して整備することとしているが、整備にあたり、豊洲新市場へ移転を希望する場外市場業者の要望も視野に入れ、施設の内容、規模などの検討を行っていく。
豊洲新市場においても、市場業者の健全な経営が確保されることは重要である。市場施設の建設経費や運営費は原則として市場業者の使用料で賄うが、適正な施設規模や効率的な整備・運営手法など様々な角度から事業費の削減に取り組むことにより、市場業者の負担の抑制を図っていく。
5 移転までの間の現市場の整備
築地市場における衛生対策及び防災対策について
豊洲新市場の開場までには相当期間を必要とし、この間も都民の台所としての現在の機能を維持するため、施設の再配置、売場の集約化や低温化など、物流の効率化、衛生対策、耐震改修工事等を行ってきた。
今後も、第8次東京都卸売市場整備計画に基づき、衛生対策、環境対策、老朽化施設の補修又は撤去、交通動線の改善等を行っていく。
6 土壌汚染の問題
豊洲地区における土壌汚染対策について
新市場予定地の土壌汚染については、汚染原因者である東京ガスの責任により処理を行う。
東京ガスは、環境確保条例に定める土壌汚染処理基準の10倍を超える汚染土壌については、すべて処理基準以下となるよう処理をする。また、10倍以下の汚染土壌についても条例で定める土壌汚染対策指針に基づき用地全体を覆土し飛散を防止することとしていることから、安全性に問題はない。特に、市場は生鮮食料品を取り扱うものであり、安全をより一層確実なものとするため、少なくとも盛土後の地盤高から4.5mの深さまではすべて処理基準以下とする。処理基準以下となっているかについては、環境大臣が指定する指定調査機関が調査を行う。
処理が適切に行われているかについては、東京都が確認を行う。これらの処理は、仮換地として地権者に引き渡されるとき又は保留地として処分されるときまでに完了することとしている。その後、中央卸売市場は地権者から土地を取得する。
7 財源確保の問題(市場整備・幹線道路整備)
豊洲新市場建設や幹線道路整備の財源について
豊洲新市場建設の財源については、築地市場跡地の売却費、企業債、国庫補助金等を充てる予定である。
環状第二号線や晴海通り延伸部、補助第315号線等の幹線道路は、公共負担と開発者負担により財源確保に努めながら整備を進める。
***********************************
3月
築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり委員会を開催し、銀座・築地地区分科会および勝どき・豊海・晴海分科会での調査・検討を踏まえ、「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり調査報告書(平成17年度)」を取りまとめた。(1日)
6月
環状第2号線の地下から地上への都市計画変更案について東京都から全員協議会へ説明が行われる。(28日)
8月
東京都より都市計画変更案への意見照会あり。(15日)
9月
東京都「東京都市計画道路環状第2号線建設事業」について「東京都環境影響評価条例」に基づき、都知事(環境局)に環境影響評価書案を提出。(14日)
10月
広く区民等へ都市計画変更案を周知し意見をもらうため、計画案の広告・縦覧を開始する。(11日〜25日)
東京都「第12回新市場建設協議会」開催。豊洲新市場の施設規模、配置などを取りまとめた基本設計相当が決定された。協議会の了承を得る。(13日)
11月
第64回東京都卸売市場審議会開催。豊洲新市場の整備について、基本設計相当を取りまとめ、PFI手法を導入することを報告(20日)
12月
「築地食のまちづくり協議会」が特定非営利活動法人(NPO法人)に認証され、法人格を取得した。(1日)
平成19年1月
東京都「東京都市計画道路環状第2号線建設事業」について、環境影響評価書案に対して寄せられた都民等の意見に対する見解書を作成し、都知事(環境局)に提出。(19日)
東京都「豊洲新市場建設事業」について「東京都環境影響評価条例」に基づき、東京都知事(環境局)に環境影響評価書案を提出。(25日)
2月
平成19年度「築地食のまちづくり協議会通常総会」開催。(19日)
3月
築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり委員会を開催し、銀座・築地地区分科会および勝どき・豊海・晴海分科会での調査・検討を踏まえ、「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり調査報告書(平成18年度)」を取りまとめた。(27日)
昭和57年3月
第22回東京都卸売市場審議会答申「第3次卸売市場整備基本方針」(昭和56年3月)を受けて「第3次東京都卸売市場整備計画」策定(昭和56から65年度)
青果市場:
・大田区及び品川区を中心とする地元消費の機能と築地・神田市場の過密解消を図るため、大井市場(仮称)を建設する。新市場の建設に伴って神田市場を廃止する。
水産市場
・大田区及び品川区を中心とする地元消費の機能と築地市場の過密解消を図るため、大井市場(仮称)を建設し、築地市場及び足立市場と合わせて計3市場を配置する。
6月
中央区議会が都知事・都議会へ「築地市場の大井移転反対の要請行動」を行い、決議書を渡す。
昭和61年1月
東京都首脳部会議において、築地市場の現在地での再整備を決定
3月
第31回東京都卸売市場審議会「第4次卸売市場整備基本方針」を答申「現在地において、立体化(1階部分を水産物部2階部分を青果部とするなど)を行い基幹市場としての機能を維持できるよう再整備の必要がある」
12月
「第4次卸売市場整備基本方針」を受けて、「第4次東京都卸売市場整備計画」策定(昭和61から70年度)
昭和62年4月
東京都と築地市場業界の協議機関として「築地市場再整備協議会(会長:市場長)」が設置される。
昭和63年11月
「築地市場再整備基本計画」策定
平成2年6月
「築地市場再整備基本設計」策定
平成3年1月
仮設工事着工
2月
第38回東京都卸売市場審議会「第5次卸売市場整備基本方針」を答申「築地市場再整備協議会」を「築地市場再整備推進協議会」に改組するなど、組織強化を図る。
11月
「第5次東京都卸売市場整備計画」策定(平成3から12年度)
[築地市場の再整備]現在地で営業しながら再整備を進める。また、可能な限り工期短縮に努める。
平成4年12月
本格工事着工(築地川東支川埋立)
平成5年5月
市場再整備の起工式が行われる。
平成8年4月
第46回東京都卸売市場審議会「第6次卸売市場整備基本方針」を答申「健全な財政計画に基づき、1. 工期の短縮、2. 建設コストの縮減、3. 基幹市場としての機能を維持していくため、流通環境の変化に対応した効率的で使いやすい市場とする視点から見直しを行う必要がある。」
11月
「第6次東京都卸売市場整備計画」策定(平成8から17年度)
[基本計画の変更]
1. 1階水産物部、2階青果部という立体的・一体的配置を改め、それぞれ分けて平面的に整備する。
2. 建築年次の比較的新しい施設は、原則継続使用する。
など
平成9年10月
築地市場再整備推進協議会において新しい計画についての協議を開始
平成10年2月
区長が副知事に面談のうえ「築地市場再整備に関する要望書」を提出(26日)
3月
都議会予算特別委員会において、中央卸売市場長が「全業界から一致して移転について調査、検討の要望があれば、(調査、検討を)行う」と答弁
議長が「築地市場再整備に関する要望書」を提出(31日)
4月
業界6団体が「臨海部に市場をつくることが可能かどうかについて調査・検討を早急かつ具体的に行い、当局の見解をだすよう」要望書を中央卸売市場長へ提出(2日)
5月
中央区議会に「築地市場再整備対策特別委員会」を設置
6月
業界6団体に対し東京都が回答(30日)
1. 移転の可能性を判断するためには、市場業界全体の一致した意思と場外市場関係者並びに関係区の協力が前提となる。
2. 市場業界各団体は一致した意思を明らかにするとともに場外市場関係者並びに関係区等の理解と協力を得るよう努力する必要がある。
3. これらのことを確認できる文書を今年中に提出すること。
中央区「中央区築地市場再整備対策本部」設置(30日)
7月
区長、議長の連名で副知事に面談のうえ築地市場再整備に関し都の考えを質す「築地市場の再整備に関する確認について」を提出(6日)
10月
中央区「築地市場に関するアンケート調査」実施(結果発表は翌年1月)
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseizyoho/tukizisizyo/tsukijikeiitorikumi19ikou/index.html
2009年11月27日
ATCセミナー「地域活性化と多様化するエコツーリズム」
ATCグリーンエコプラザセミナー
「地域活性化と多様化するエコツーリズム」のご案内

環境大臣を議長とした「エコツーリズム推進会議(H15〜H16年)」ではエコツーリズムの概念を「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた」とし、平成19年制定の「エコツーリズム推進法」においては、「自然環境の保全」「観光振興」「環境教育の場としての活用」を基本理念としています。観光客に地域の資源を伝えることで、地域住民も地域を再認識し、様々な活動を通じて地域社会そのものの活性化が生まれています。
今回のセミナーでは、京都嵯峨芸術大学の真板昭夫教授に、エコツーリズムとは何か、その意義、様々な活動、成果等をご紹介して頂いた後、エコツーリズムにおいて顕著なる成果をあげておられる団体・企業に、その活動をご紹介頂いて、エコツーリズムを考えていきます。
日時
平成21年11月27日(金) 13:30〜17:00
内容
基調講演「目からうろこのエコツーリズム」
講師:京都嵯峨芸術大学 芸術学部教授 真板昭夫 氏
(NPO法人日本エコツーリズム協会理事)
講演1 「里地里山の身近な自然と生活文化が宝物〜飯能市エコツーリズム〜」
講師:飯能市環境部エコツーリズム推進室 主査 大野裕司 氏
講演2 「”エコ・エージェント”の存在と未来の可能性について
〜ニュービジネスによる持続可能なエコ実現〜」
講師:有限会社地域観光プロデュースセンター 代表 吉見精二 氏
(NPO法人日本エコツーリズム協会理事)
講演3 「環境教育と自然体験を目的とした様々なツアーの提案」
講師:近畿日本ツーリスト株式会社 関西営業本部 業務課長 松岡一隆 氏
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)
参加費
無 料
会場
アジア太平洋トレードセンターー(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
定員
60名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までFAX またはE-mail でお送りします。)
お申し込み
おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ「エコツーリズム」セミナー(11 月27 日)係TEL:06-6615-5688
E−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください
E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890
チラシ
http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar091127.pdf
エコツーリズム推進法について
平成19年6月20日の参議院本会議において、エコツーリズム推進法が成立しました。

1.成立の背景
最近の身近な環境についての保護意識の高まりや、自然と直接ふれあう体験への欲求の高まりが見られるようになってきています。
このような背景から、これまでのパッケージ・通過型の観光とは異なり、地域の自然環境の保全に配慮しながら、時間をかけて自然とふれあう「エコツーリズム」が推進される事例が見られるようになってきました。
しかし、現在は地域の環境への配慮を欠いた単なる自然体験ツアーがエコツアーと呼ばれたり、観光活動の過剰な利用により自然環境が劣化する事例も見られます。
このような状況を踏まえ、適切なエコツーリズムを推進するための総合的な枠組みを定める法律が制定されました。
2.法律の趣旨
この法律は、地域の自然環境の保全に配慮しつつ、地域の創意工夫を生かした「エコツーリズム」を推進するに当たり、以下の4つの具体的な推進方策を定め、エコツーリズムを通じた自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の推進を図るものです。
(1)政府による基本方針の策定
(2)地域の関係者による推進協議会の設置
(3)地域のエコツーリズム推進方策の策定
(4)地域の自然観光資源の保全
3.今後の取り組み
エコツーリズム推進法は、平成20年4月1日の施行です。(同日、エコツーリズム推進法施行規則公布・施行)
政府は、エコツーリズム推進のための基本方針を作成します。 (平成20年6月6日閣議決定)
市町村が作成した地域ごとの全体構想は、主務大臣の認定を申請することができ、この基本方針に適合するものが認定されます。
国は、全体構想の認定を受けた市町村に対して、広報に努めるなど、地域のエコツーリズム実現に関する施策を推進します。

※主務大臣 環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣
http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/law.html
エコツーリズム推進法
(目的)
第一条 この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めることにより、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「自然観光資源」とは、次に掲げるものをいう。
一 動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源
二 自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源
2 この法律において「エコツーリズム」とは、観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動をいう。
3 この法律において「特定事業者」とは、観光旅行者に対し、自然観光資源についての案内又は助言を業として行う者(そのあっせんを業として行う者を含む。)をいう。
4 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備の設置その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
(基本理念)
第三条 エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されるとともに、実施の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを反映させつつ実施されなければならない。
2 エコツーリズムは、特定事業者が自主的かつ積極的に取り組むとともに、観光の振興に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。
3 エコツーリズムは、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携し、地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。
4 エコツーリズムの実施に当たっては、環境の保全についての国民の理解を深めることの重要性にかんがみ、環境教育の場として活用が図られるよう配慮されなければならない。
(基本方針)
第四条 政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次の事項を定めるものとする。
一 エコツーリズムの推進に関する基本的方向
二 次条第一項に規定するエコツーリズム推進協議会に関する基本的事項
三 次条第二項第一号のエコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項
四 第六条第二項のエコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項
五 生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項
3 環境大臣及び国土交通大臣は、あらかじめ文部科学大臣及び農林水産大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣及び国土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
5 環境大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 基本方針は、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
(エコツーリズム推進協議会)
第五条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者(以下「特定事業者等」という。)並びに関係行政機関及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次の事務を行うものとする。
一 エコツーリズム推進全体構想を作成すること。
二 エコツーリズムの推進に係る連絡調整を行うこと。
3 前項第一号に規定するエコツーリズム推進全体構想(以下「全体構想」という。)には、基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。
一 エコツーリズムを推進する地域
二 エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地
三 エコツーリズムの実施の方法
四 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置(当該協議会に係る市町村の長が第八条第一項の特定自然観光資源の指定をしようとするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置を含む。以下同じ。)
五 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担
六 その他エコツーリズムの推進に必要な事項
4 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
5 前項の規定は、全体構想の変更又は廃止について準用する。
6 特定事業者等は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る協議会が作成すべき全体構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。
7 特定事業者等で協議会の構成員でないものは、市町村に対して書面でその意思を表示することによって、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
9 協議会の構成員は、相協力して、全体構想の実施に努めなければならない。
(全体構想の認定)
第六条 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針に適合するものであること。
二 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
3 主務大臣は、二以上の市町村から共同して第一項の規定による認定の申請があった場合において、自然的経済的社会的条件からみて、当該市町村の区域において一体としてエコツーリズムを推進することが適当であると認めるときは、当該申請に係る全体構想を一体として前項の認定をすることができる。
4 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。
5 市町村は、その組織した協議会が第二項の認定を受けた全体構想を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該変更後の全体構想について主務大臣の認定を受けなければならない。
6 主務大臣は、第二項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた全体構想(以下「認定全体構想」という。)が基本方針に適合しなくなったと認めるとき、又は認定全体構想に従ってエコツーリズムが推進されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
7 第二項及び第四項の規定は第五項の変更の認定について、第四項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(認定全体構想についての周知等)
第七条 主務大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者その他の者に認定全体構想の内容について周知するものとする。
2 国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、認定全体構想を作成した協議会の構成員である特定事業者が当該認定全体構想に基づくエコツーリズムに係る事業を実施するため、法令の規定による許可その他の処分を求めたときは、当該エコツーリズムに係る事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
(特定自然観光資源の指定)
第八条 全体構想について第六条第二項の認定を受けた市町村(第十二条を除き、以下単に「市町村」という。)の長(以下単に「市町村長」という。)は、認定全体構想に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源(風俗慣習その他の無形の観光資源を除く。以下この項において同じ。)であって、保護のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源として指定することができる。ただし、他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源として主務省令で定めるものについては、この限りでない。
2 市町村長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定自然観光資源の所在する区域の土地の所有者等の同意を得なければならない。
3 市町村長は、第一項の指定をするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置の内容を公示しなければならない。
4 市町村長は、第一項の指定をしたときは、当該特定自然観光資源の所在する区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
5 市町村長は、第一項の指定をした場合において、当該特定自然観光資源が同項ただし書の主務省令で定める自然観光資源に該当するに至ったときその他その後の事情の変化によりその指定の必要がなくなり、又はその指定を継続することが適当でなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
6 市町村長は、前項の規定による指定の解除をするときは、その旨を公示しなければならない。
(特定自然観光資源に関する規制)
第九条 特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。
二 観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
三 著しく悪臭を発散させ、音響機器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。
四 前三号に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認定全体構想に従い市町村の条例で定める行為
2 市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内において前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第十条 市町村長は、認定全体構想に従い、第八条第一項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りにつきあらかじめ当該市町村長の承認を受けるべき旨の制限をすることができる。ただし、他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源であって主務省令で定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定による制限がされたときは、同項の承認を受けた者以外の者は、当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ってはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって主務省令で定めるものを行うために立ち入る場合については、この限りでない。
3 第一項の承認は、立ち入ろうとする者の数について、市町村長が定める数の範囲内において行うものとする。
4 市町村の当該職員は、第二項の規定に違反して当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入る者があるときは、当該区域への立入りをやめるよう指示し、又は当該区域から退去するよう指示することができる。
5 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の制限について準用する。この場合において、同条第三項中「その保護のために講ずる措置の内容」とあるのは「立入りを制限する人数及び期間その他必要な事項」と、同条第五項中「同項ただし書の主務省令で定める自然観光資源」とあるのは「第十条第一項ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源」と読み替えるものとする。
6 前条第三項の規定は、第四項の職員について準用する。
(活動状況の公表)
第十一条 主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(活動状況の報告)
第十二条 主務大臣は、市町村に対し、その組織した協議会の活動状況について報告を求めることができる。
(技術的助言)
第十三条 主務大臣は、広域の自然観光資源の保護及び育成に関する活動その他の協議会の活動の促進を図るため、協議会の構成員に対し、必要な技術的助言を行うものとする。
(情報の収集等)
第十四条 主務大臣は、自然観光資源の保護及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。
(広報活動等)
第十五条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。
(財政上の措置等)
第十六条 国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(エコツーリズム推進連絡会議)
第十七条 政府は、環境省、国土交通省、文部科学省、農林水産省その他の関係行政機関の職員をもって構成するエコツーリズム推進連絡会議を設け、エコツーリズムの総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
(主務大臣等)
第十八条 この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。

(罰則)
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者
二 第十条第四項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者
第二十条 第九条第一項第四号の規定に基づく条例には、同条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないでみだりに同号に掲げる行為をした者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
理 由
エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「地域活性化と多様化するエコツーリズム」のご案内

環境大臣を議長とした「エコツーリズム推進会議(H15〜H16年)」ではエコツーリズムの概念を「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた」とし、平成19年制定の「エコツーリズム推進法」においては、「自然環境の保全」「観光振興」「環境教育の場としての活用」を基本理念としています。観光客に地域の資源を伝えることで、地域住民も地域を再認識し、様々な活動を通じて地域社会そのものの活性化が生まれています。
今回のセミナーでは、京都嵯峨芸術大学の真板昭夫教授に、エコツーリズムとは何か、その意義、様々な活動、成果等をご紹介して頂いた後、エコツーリズムにおいて顕著なる成果をあげておられる団体・企業に、その活動をご紹介頂いて、エコツーリズムを考えていきます。
日時
平成21年11月27日(金) 13:30〜17:00
内容
基調講演「目からうろこのエコツーリズム」
講師:京都嵯峨芸術大学 芸術学部教授 真板昭夫 氏
(NPO法人日本エコツーリズム協会理事)
講演1 「里地里山の身近な自然と生活文化が宝物〜飯能市エコツーリズム〜」
講師:飯能市環境部エコツーリズム推進室 主査 大野裕司 氏
講演2 「”エコ・エージェント”の存在と未来の可能性について
〜ニュービジネスによる持続可能なエコ実現〜」
講師:有限会社地域観光プロデュースセンター 代表 吉見精二 氏
(NPO法人日本エコツーリズム協会理事)
講演3 「環境教育と自然体験を目的とした様々なツアーの提案」
講師:近畿日本ツーリスト株式会社 関西営業本部 業務課長 松岡一隆 氏
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)
参加費
無 料
会場
アジア太平洋トレードセンターー(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
定員
60名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までFAX またはE-mail でお送りします。)
お申し込み
おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ「エコツーリズム」セミナー(11 月27 日)係TEL:06-6615-5688
E−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください
E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890
チラシ
http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar091127.pdf
エコツーリズム推進法について
平成19年6月20日の参議院本会議において、エコツーリズム推進法が成立しました。

1.成立の背景
最近の身近な環境についての保護意識の高まりや、自然と直接ふれあう体験への欲求の高まりが見られるようになってきています。
このような背景から、これまでのパッケージ・通過型の観光とは異なり、地域の自然環境の保全に配慮しながら、時間をかけて自然とふれあう「エコツーリズム」が推進される事例が見られるようになってきました。
しかし、現在は地域の環境への配慮を欠いた単なる自然体験ツアーがエコツアーと呼ばれたり、観光活動の過剰な利用により自然環境が劣化する事例も見られます。
このような状況を踏まえ、適切なエコツーリズムを推進するための総合的な枠組みを定める法律が制定されました。
2.法律の趣旨
この法律は、地域の自然環境の保全に配慮しつつ、地域の創意工夫を生かした「エコツーリズム」を推進するに当たり、以下の4つの具体的な推進方策を定め、エコツーリズムを通じた自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の推進を図るものです。
(1)政府による基本方針の策定
(2)地域の関係者による推進協議会の設置
(3)地域のエコツーリズム推進方策の策定
(4)地域の自然観光資源の保全
3.今後の取り組み
エコツーリズム推進法は、平成20年4月1日の施行です。(同日、エコツーリズム推進法施行規則公布・施行)
政府は、エコツーリズム推進のための基本方針を作成します。 (平成20年6月6日閣議決定)
市町村が作成した地域ごとの全体構想は、主務大臣の認定を申請することができ、この基本方針に適合するものが認定されます。
国は、全体構想の認定を受けた市町村に対して、広報に努めるなど、地域のエコツーリズム実現に関する施策を推進します。

※主務大臣 環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣
http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/law.html
エコツーリズム推進法
(目的)
第一条 この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めることにより、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「自然観光資源」とは、次に掲げるものをいう。
一 動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源
二 自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源
2 この法律において「エコツーリズム」とは、観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動をいう。
3 この法律において「特定事業者」とは、観光旅行者に対し、自然観光資源についての案内又は助言を業として行う者(そのあっせんを業として行う者を含む。)をいう。
4 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備の設置その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
(基本理念)
第三条 エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されるとともに、実施の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを反映させつつ実施されなければならない。
2 エコツーリズムは、特定事業者が自主的かつ積極的に取り組むとともに、観光の振興に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。
3 エコツーリズムは、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携し、地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。
4 エコツーリズムの実施に当たっては、環境の保全についての国民の理解を深めることの重要性にかんがみ、環境教育の場として活用が図られるよう配慮されなければならない。
(基本方針)
第四条 政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次の事項を定めるものとする。
一 エコツーリズムの推進に関する基本的方向
二 次条第一項に規定するエコツーリズム推進協議会に関する基本的事項
三 次条第二項第一号のエコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項
四 第六条第二項のエコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項
五 生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項
3 環境大臣及び国土交通大臣は、あらかじめ文部科学大臣及び農林水産大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣及び国土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
5 環境大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 基本方針は、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
(エコツーリズム推進協議会)
第五条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者(以下「特定事業者等」という。)並びに関係行政機関及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次の事務を行うものとする。
一 エコツーリズム推進全体構想を作成すること。
二 エコツーリズムの推進に係る連絡調整を行うこと。
3 前項第一号に規定するエコツーリズム推進全体構想(以下「全体構想」という。)には、基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。
一 エコツーリズムを推進する地域
二 エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地
三 エコツーリズムの実施の方法
四 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置(当該協議会に係る市町村の長が第八条第一項の特定自然観光資源の指定をしようとするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置を含む。以下同じ。)
五 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担
六 その他エコツーリズムの推進に必要な事項
4 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
5 前項の規定は、全体構想の変更又は廃止について準用する。
6 特定事業者等は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る協議会が作成すべき全体構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。
7 特定事業者等で協議会の構成員でないものは、市町村に対して書面でその意思を表示することによって、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
9 協議会の構成員は、相協力して、全体構想の実施に努めなければならない。
(全体構想の認定)
第六条 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針に適合するものであること。
二 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
3 主務大臣は、二以上の市町村から共同して第一項の規定による認定の申請があった場合において、自然的経済的社会的条件からみて、当該市町村の区域において一体としてエコツーリズムを推進することが適当であると認めるときは、当該申請に係る全体構想を一体として前項の認定をすることができる。
4 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。
5 市町村は、その組織した協議会が第二項の認定を受けた全体構想を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該変更後の全体構想について主務大臣の認定を受けなければならない。
6 主務大臣は、第二項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた全体構想(以下「認定全体構想」という。)が基本方針に適合しなくなったと認めるとき、又は認定全体構想に従ってエコツーリズムが推進されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
7 第二項及び第四項の規定は第五項の変更の認定について、第四項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(認定全体構想についての周知等)
第七条 主務大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者その他の者に認定全体構想の内容について周知するものとする。
2 国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、認定全体構想を作成した協議会の構成員である特定事業者が当該認定全体構想に基づくエコツーリズムに係る事業を実施するため、法令の規定による許可その他の処分を求めたときは、当該エコツーリズムに係る事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
(特定自然観光資源の指定)
第八条 全体構想について第六条第二項の認定を受けた市町村(第十二条を除き、以下単に「市町村」という。)の長(以下単に「市町村長」という。)は、認定全体構想に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源(風俗慣習その他の無形の観光資源を除く。以下この項において同じ。)であって、保護のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源として指定することができる。ただし、他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源として主務省令で定めるものについては、この限りでない。
2 市町村長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定自然観光資源の所在する区域の土地の所有者等の同意を得なければならない。
3 市町村長は、第一項の指定をするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置の内容を公示しなければならない。
4 市町村長は、第一項の指定をしたときは、当該特定自然観光資源の所在する区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
5 市町村長は、第一項の指定をした場合において、当該特定自然観光資源が同項ただし書の主務省令で定める自然観光資源に該当するに至ったときその他その後の事情の変化によりその指定の必要がなくなり、又はその指定を継続することが適当でなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
6 市町村長は、前項の規定による指定の解除をするときは、その旨を公示しなければならない。
(特定自然観光資源に関する規制)
第九条 特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。
二 観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
三 著しく悪臭を発散させ、音響機器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。
四 前三号に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認定全体構想に従い市町村の条例で定める行為
2 市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内において前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第十条 市町村長は、認定全体構想に従い、第八条第一項の規定により指定した特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該特定自然観光資源の所在する区域への立入りにつきあらかじめ当該市町村長の承認を受けるべき旨の制限をすることができる。ただし、他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源であって主務省令で定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定による制限がされたときは、同項の承認を受けた者以外の者は、当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ってはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって主務省令で定めるものを行うために立ち入る場合については、この限りでない。
3 第一項の承認は、立ち入ろうとする者の数について、市町村長が定める数の範囲内において行うものとする。
4 市町村の当該職員は、第二項の規定に違反して当該特定自然観光資源の所在する区域に立ち入る者があるときは、当該区域への立入りをやめるよう指示し、又は当該区域から退去するよう指示することができる。
5 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の制限について準用する。この場合において、同条第三項中「その保護のために講ずる措置の内容」とあるのは「立入りを制限する人数及び期間その他必要な事項」と、同条第五項中「同項ただし書の主務省令で定める自然観光資源」とあるのは「第十条第一項ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源」と読み替えるものとする。
6 前条第三項の規定は、第四項の職員について準用する。
(活動状況の公表)
第十一条 主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(活動状況の報告)
第十二条 主務大臣は、市町村に対し、その組織した協議会の活動状況について報告を求めることができる。
(技術的助言)
第十三条 主務大臣は、広域の自然観光資源の保護及び育成に関する活動その他の協議会の活動の促進を図るため、協議会の構成員に対し、必要な技術的助言を行うものとする。
(情報の収集等)
第十四条 主務大臣は、自然観光資源の保護及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。
(広報活動等)
第十五条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。
(財政上の措置等)
第十六条 国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(エコツーリズム推進連絡会議)
第十七条 政府は、環境省、国土交通省、文部科学省、農林水産省その他の関係行政機関の職員をもって構成するエコツーリズム推進連絡会議を設け、エコツーリズムの総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
(主務大臣等)
第十八条 この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。

(罰則)
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者
二 第十条第四項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者
第二十条 第九条第一項第四号の規定に基づく条例には、同条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないでみだりに同号に掲げる行為をした者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
理 由
エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

2009年11月23日
桃花台新聞 土壌と地下水の汚染 転載
桃花台新聞 土壌と地下水の汚染
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その7(愛知県)
桃花台ニュータウン在住の愛知県議会議員・天野まさきさんの公式ブログを見て知ったのですが、09年11月18日(水)に愛知県が、9月末に実施した桃花台ニュータウン内・城山地区と光ヶ丘小学校および大城小学校グランドに埋設されている、産業廃棄物による地下水汚染の調査結果を、公表したそうです。
それによると、相変わらず光ヶ丘および大城両小学校では、環境基準を上回る汚染物質は確認されなかったそうです。しかし城山地区の2ヶ所の井戸では、今まででもっとも高い、最大で環境基準の"8.6倍"の総水銀が検出されたそうです。
最後に感想を少し。
「今年(2009年)になってから、(愛知県が)調査結果をなかなか報じないなぁ・・・」なんて思っていたのですが、調査結果を見てみると、去年(2008年)は全4回行われていますが、今年は2月に行われた調査結果と合わせて、2回しか行われていません。昨年も最終が9月だった事から、おそらく今年はこれ以上調査結果が発表される事はないのではないかと。
この点(調査回数が減らされた事)については、疑問です。「問題ある物質が検出されない」、または「検出されてもその量は安定している」と言うのであれば別ですが、実際検出されていますし、その量は決して安定していません。今回の調査で総水銀が環境基準を上回った2地点(NO.1と2)について言えば、検出される量は回を重ねるごとに増えていますし、前回の調査で検出された「NO.5」については、今回は検出されていません。
このように、調査結果が安定していない状態で検査回数を減らす事は、"問題を未然に防ぐ"(例えばどこかの地点で急激に環境基準を上回る物質の量が増えたり、あるいは別に地点へと移動が認められるするような危険を事前に速やかに察知する)と言う観点から、問題があると思います。
*****************************
桃花台を含む日本の産業廃棄物処理問題について書かれた書籍が発刊(世界思想社)
『土壌・底質汚染と健康被害ラーニング』と言うブログの記事を読んで知ったのですが、桃花台ニュータウンを含む日本の様々な地域で問題となっている産業廃棄物の処分問題について書かれた書籍が、先月(10月)発売されたそうです。
・出版案内:『廃棄物列島・日本−深刻化する廃棄物問題と政策提言−』(土壌・底質汚染と健康被害ラーニング)
・廃棄物列島・日本 ― 深刻化する廃棄物問題と政策提言(世界思想社)・・・出版社の書籍案内ページ。
書籍には桃花台ニュータウンで問題となっている「産業廃棄物の問題」だけでなく、桃花台周辺でも埋設が確認され最近撤去された石原産業の「フェロシルト問題」も取り上げられています。
興味のある方は、読んでみてはいかがでしょう?
ちなみに、この書籍発刊と関係していると思われる講演会が、大阪府大阪市にあるおおさかATCグリーンエコプラザで、12月18日(金)に行われるそうです。
・ATCセミナー 土壌・地下水汚染の社会的問題の事例(案)(EICネット)
この講演会では、桃花台ニュータウンの事例も取り上げられるようです。興味のある方は行ってみてはいかがでしょう?
(・・・と言っても大阪なので、なかなか気軽には行けませんが・・・(^^; )
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その6(愛知県)3月18日(水)、
愛知県が2月6日(金)に城山地区で実施した地下水調査の結果を、発表しました。それによると、5つの観測地点のうち3つから、また環境基準を上回る「総水銀」が検出されたそうです。そのうちの1つからは、これまでで最大の、環境基準"約7.8倍"の総水銀が検出されたそうです。
なお、光ヶ丘小学校と大城小学校の地下水質調査は、過去4回の調査で一度も環境基準を上回る物質が検出されなかった事から、今回は行わなかったそうです。
*****************************
地盤沈下問題の裁判で都市再生機構が敗訴(愛知県)
3年前の2006年に、都市再生機構(別称「UR都市機構」、旧・住宅・都市整備公団)が愛知県に対し「城山5丁目地区で起きた地盤沈下の責任は愛知県にある」として、住民に対し機構側が支払った補償費用や調査費用などを請求する裁判を、名古屋地裁に起こしました。その裁判が、3月26日(木)に結審したそうです。
裁判官は「機構には地盤を十分に調査する責任があった。」として、機構側の訴えを棄却(機構側が敗訴)したそうです。
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その5(愛知県)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、11月11日(火)に愛知県が、9月末に実施した桃花台ニュータウン内・城山地区と光ヶ丘小学校および大城小学校グランドに埋設されている、産業廃棄物による地下水汚染の調査結果を、公表したそうです。
それによると、相変わらず光ヶ丘および大城両小学校では、環境基準を上回る汚染物質は確認されなかったそうです。しかし城山地区の2ヶ所の井戸では、前回を上回る、最大で環境基準の"7.6倍"の総水銀が検出されたそうです。
(※11月12日(水)朝刊 18面)
ただ、前回の調査(6月採取、8月結果発表)と前々回(4月採取、5月結果発表)で環境基準を上回る総水銀が見つかった、城山地区の3地点の内の1地点では、今回は環境基準を上回る汚染物質は、見つからなかったそうです。
*****************************
住民が愛知県と都市再生機構を提訴 - その3(地盤沈下と土壌汚染問題)
去年(2007年)の10月、埋設している産業廃棄物が原因で地盤沈下が起きている城山地区に住む一部住民が、愛知県や都市再生機構を相手取って、損害賠償を求める裁判を起こしましたが、それとは別の住民8世帯12人が、11月10日(月)、同じく愛知県や都市再生機構を相手取って、廃棄物の除去や総額1億2000万円の損害賠償を求める裁判を、名古屋地裁に起こしたそうです。
(※中日新聞 11月11日(火)朝刊 30面)
*****************************
公害調停が決裂(地盤沈下と土壌汚染問題)
今年(2008年)の春から桃花台ニュータウン住民と愛知県、都市再生機構などが参加して行なわれた公害調停での話し合いが決裂したそうです。
・桃花台ニュータウン地盤沈下問題:公害調停が決裂 住民側、民事訴訟の方針(毎日jp)
・桃花台地盤沈下 調停を打ち切り(YOMIURI ONLINE)
また記事によると、今後住民側は「国の公害等調整委員会に対し裁定を求める申請を行うとともに、愛知県と都市再生機構を相手取って新たに民事訴訟を起こす方針」との事。
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その4(愛知県)
8月5日(火)、愛知県が、6月に行った、桃花台ニュータウン内の城山地区と3つの学校グラウンドに埋設している産業廃棄物による地下水汚染を調べた4回目の調査結果を、公表したそうです。
前回(4月)の調査で環境基準を上回る"総水銀"が見つかった城山地区の3地点の地下水で、最大で環境基準の"6.6倍"(前回との比較では最大"約2.4倍")の"総水銀"が検出されたそうです。
(※8月6日(水)朝刊 16面)
また城山地区の3ヶ所の数値が増えた理由について、愛知県庁住宅計画課の担当者は、「丘陵地であり、地下水面が季節によって変動したためではないか」と言っているそうです。
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その3(愛知県)
今年(2008年)の2月に行なわれた地下水調査で環境基準を上回る有害物質が見つかった城山5丁目地区。当初3回目の調査は6月に行なわれる予定でしたが、この結果を受けて4月に前倒しになりました。その調査結果が、5月21日(水)に公開されたそうです。それによると、今回もまた、最大で環境基準の3倍の総水銀が検出されたそうです。
(※中日新聞紙面 5月22日(木)朝刊 18面)
*****************************
署名活動への協力求む!(桃花台ニュータウン区長会)
ずいぶん前から署名活動が行なわれているのを知ってはいたのですが、記事にするのをずっと忘れていました・・・。 (^^;
桃花台ニュータウン区長会が中心となって、愛知県と都市再生機構に対する要望書への署名活動が、現在行なわれています。
・地盤沈下問題(桃花台ニュータウン区長会)
回覧版等で周ってきてご存知の方もいるかもしれませんが、あらためて詳しく書こうと思います。
2者に対して要望している内容は、主に以下の3つです。
・第三者機関を設置し、原因究明と問題解決にあたる事。
・問題が発覚した土地の全ての土壌を撤去し、きちんと賠償する事。
・情報をきちんと開示する事。
署名に使われている用紙は、各地区の区長をやられている方の方に問い合わせれば、たぶん貰えると思います。「実物を見てみたい」と言う方は、あおい交通や名鉄バスの「光ヶ丘2丁目」停留所北側にある掲示板に貼られているので、行って見てみて下さい。
*****************************
土壌から環境基準を大幅に上回るヒ素!(エコーガーデン桃花台)
中日新聞の記事を読んで知ったのですが、昨年(2007年)10月から土壌調査を行なっていた、小牧市古雅3丁目に整備予定の住宅地「エコーガーデン桃花台」の敷地内にある土壌から、環境基準を大幅に上回るヒ素が見つかったそうです。
(※4月5日(土)朝刊 20面)
記事によると、調査結果は、以下のようなものだったそうです。
有害物質が見つかった場所:全121戸の内の7戸の宅地
見つかった有害物質:最高で環境基準の7倍の「ヒ素」、環境基準をやや上回る「フッ素」
汚染されている土の量:約2万m?
汚染された原因:不明
なお、汚染された土壌は以前愛知県住宅公社の人が言っていた通り、全て撤去するそうです。またその分新しい土を持ってきて、掘り出した部分を埋めるそうです。
あと記事にはこの場所に関する歴史も、少し書かれていました。それと私が知っている情報をまとめると、以下のような経緯があるようです。
1970年代頃:元々山林や原野だった土地を愛知県が購入。
(県は1989年頃まで、暫定調整池として利用。)
↓
1999年3月:愛知県住宅供給公社が愛知県から土地を購入。
(土地は主に駐車場として利用される。なお駐車場の管理は、桃花台新交通(※2006年9月頃まで)や(財)桃花台センター(※2007年3月末日まで)が行なっていた。)
↓
2007年4月:エコーガーデン桃花台の整備工事開始
↓
2007年10月:公社が土壌調査を開始
↓
現在に到る
この件に関する感想を、書こうと思います。
エコーガーデンの場合「汚染された土壌を全て撤去する」との事なので、今後健康被害や地盤沈下が起きる可能性は低いと思いますが、・・・
気になるのが、「なぜ汚染されたのか?」と言う点です。なぜなら公社は今のところ「原因は不明」と発表していますが、もしその原因が"調整池の埋め立て"に利用した土にあるとしたら、汚染されている地域が更に広がる可能性があるからです。
書籍『桃花台 まちの記録』によると、過去に桃花台ニュータウン内で調整池だった場所が、実はもう1つあります。それはニュータウン最北部の篠岡3丁目地区です。ちょどWikipediaに公開されている画像に、この2つの地域が調整池だった頃の航空写真があるので、興味のある方は見てみて下さい。
この場所も、長らくずっと空き地のままでした。調整池だった場所はしばらく土地を"寝かせて"地盤を固める必要がある為、このように放置されていたのだとか。
ちなみに去年(2007年)の夏頃から住宅の建設が始められ、今空き地はほとんど残っていません。
元・調整池があった場所が汚染されていたからと言って、必ずしもこの場所の土壌も汚染されているとは言えません。しかし「同じ土が運ばれた」とか、あるいは「同じ業者が埋め立て工事を行なっている」と言う可能性は、十分考えられます。そうなれば必然的に、汚染されている可能性も高くなります。
なので私は、あらためて愛知県庁に強く求めたい!
「すぐにでも、ニュータウン全地区の土壌調査をするべきだ!!」
そもそも「自治体」と言うのは、住民の健康や幸せ、財産を守る為の組織なのではないでしょう?それが住民と争うと言うのは、根本的に間違っていると思います。
それと現在県庁で働いている人は、ニュータウンの整備事業に携わった人ではないかもしれません。なので個人としての責任は、まったくないかもしれません。
しかし県庁で働いている人も、"一個人"として、この問題を考えて欲しい。もし自分が数十年ものローンを組んで購入した住宅の地下に、「産業廃棄物や有害物質が埋まっている」と判かったら、どんな気持ちがするのかという事を。
*****************************
公害調停(地盤沈下と土壌汚染問題)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、3月18日(火)、愛知県庁三の丸庁舎で、桃花台ニュータウン住民が公害紛争処理法に基づき愛知県の公害審議会に申請した、「公害調停」の1回目が行なわれたそうです。
(※3月19日(水)朝刊 18面)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、3月18日(火)、愛知県庁三の丸庁舎で、桃花台ニュータウン住民が公害紛争処理法に基づき愛知県の公害審議会に申請した、「公害調停」の1回目が行なわれたそうです。
(※3月19日(水)朝刊 18面)
*****************************
「公害調停」とは、「公害問題で当事者間の話し合いで解決しない時、行政(都道府県や国)が間に入り調停する事」のようです。
ただ今回は愛知県も"当事者"なので、話し合いには桃花台ニュータウン住民と桃花台ニュータウンの造成を行なった愛知県、そして住宅を販売した旧・住宅都市整備公団(現・都市再生機構)などと、審議会の委員による4者で行なわれたようです。
記事によると、話し合い後の記者会見で住民側が言うには、今回の会合では当事者である3者の主張は、以下のようなものだったそうです。
住民側:地盤沈下の原因をはっきりさせる為、中立公正な立場の機関による土壌調査を要請。
愛知県:調停の打ち切りを要請。
都市再生機構など:「調停には応じられない」、「当社には責任はない」(※恐らく住宅メーカーも含まれているのではないかと思われます。)
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その2(愛知県)
小牧市の公式サイトを見て知ったのですが、2月6日(水)・7日(木)の2日間、産業廃棄物の埋設が発覚している城山地区と光ヶ丘小学校、大城小学校の敷地内で、2回目の地下水調査が行なわれたそうです。その結果が今日(3月7日(金))、愛知県によって発表されたそうです。
それによると、城山地区の1つの観測用の井戸から、環境基準の"3.4倍"にあたる「総水銀」が検出されたそうです。
土壌調査地点を見に行ってきました! - その2(小牧市城山5丁目)
先日再度、小牧市城山5丁目にある土壌調査地点を見に行ってきました。以前は金属の壁で覆われていましたがそれは取り除かれ、その代わりに低い垣根が作られていました。
*****************************
住民が愛知県と都市再生機構を提訴 - その2(地盤沈下と土壌汚染問題)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、今年(2007年)10月に城山地区住民が愛知県と都市再生機構を相手取って起こした損害賠償訴訟の第1回口頭弁論が、12月6日(木)に、名古屋地裁で行なわれたそうです。
(※12月7日(金)朝刊 34面)
記事によると、住民側の主張は、以下の通りです。
住民:
「県は有害物質の存在を知りながら造成した。機構は必要な地盤調査や廃棄物撤去をしないまま分譲した結果、居住環境が損なわれた。」
これに対し愛知県と都市再生機構(UR都市機構)は、以下のように反論し、自分たちの賠償責任を否定したそうです。
愛知県:
「地中に有害物質があるとの認識はなく、造成は適切だった。」
都市再生機構:
「健康への影響はなく、住宅の欠陥はない。」
最後に、この裁判に関する感想を書こうと思います。
愛知県と都市再生機構が上記のような反応を示すのは、当然だと思います。と言うのも、両者は桃花台ニュータウンの地盤沈下と土壌汚染問題に関する別の裁判でも、お互いの責任を争っているからです。
この問題、愛知県・都市再生機構双方ともに責任があると思います。
愛知県の方は土地購入の段階で、この地に産業廃棄物が埋められていた事を知っていた可能性があります。仮に知らなかったとしても、造成工事の段階で、当時の愛知県庁職員が「廃棄物と見られる粘土が、大量に堆積していた事を確認」したと話している(そのため愛知県の「有害物質があるとの認識がない」と言う発言は嘘の可能性があると思います。)以上、少なくとも問題があると思われる土壌の調査・分析を行なうべきだったと思いますし、それらを適切に除去すべきだったと思うからです。
また都市再生機構の方は、住民側の「住宅を建てる前の段階で地盤調査を行なうべきだった」と言う主張が正しいと思うから、彼らにも責任があると思います。
ただ上記でも書きましたが、愛知県と都市再生機構は別の裁判でもこの問題を争っている以上、どうあっても、お互い責任を認めないでしょう。なので住民側は、もう少しこの裁判の行方を見守ってから、愛知県と都市再生機構のどちらか一方(都市再生機構が勝てば愛知県、訴えが否決されれば都市再生機構)を訴えた方が良かったのではないかとも・・・思います。
*****************************
調査に関する感想を書こうと思います。
率直に言って、愛知県の調査は信用できないので、小牧市か、別の第三者機関に調査を依頼するべきだと思います。と言うのも、先日発覚した小牧市大草で地下水が水銀で汚染されていた件に関しても、一度フェロシルトの関係で調査した時は「有害物質が見つからなかった」としているからです。
この件について愛知県にメールで確認をしたところ、「フェロシルトの分析結果からフェロシルト中には水銀が含まれていないことがわかっていたため、水銀については調査していまかった。」との返信がありましたが、果たしてそれが本当なのかどうか・・・。
それに愛知県は、城山5丁目の土壌調査結果を一度は「有害物質は検出されなかった」と言っていますし・・・。
(ちなみに同じ土壌を調査した小牧市の結果では、環境基準を上回る"ヒ素"と"ジクロロメタン"が検出されています。)
・土壌調査の結果公表(愛知県、小牧市)(桃花台新聞)
それと今回の調査方法は、少しおかしいと思います。確かに愛知県の調査では、光ヶ丘小学校と大城小学校では鉛しか見つかっていませんが、城山地区と同じ産業廃棄物が埋設されているのなら、当然"ヒ素"や"総水銀"に関しても行なうべきだと思います。
それこそ場所が小学校だけに、後になって「検出対象から外していたから」では済まされないと思うからです。
あと、上記でも書きましたが、去年(2006年)10月に発表された小牧市の調査では、城山5丁目の土壌から"ジクロロメタン"が検出されています。そのため、この物質も調査対象にして、改めて調査すべきだと思います。
*****************************
住民が愛知県と都市再生機構を提訴(地盤沈下と土壌汚染問題)
10月12日(金)、城山地区の住民が、愛知県と都市再生機構(UR都市機構、旧・都市整備公団)に対し、「適切な地盤調査や廃棄物の撤去をしないまま分譲され、居住環境が損なわれた」として、住宅の購入代金分(総額約9300万円)の損害賠償を求める裁判を起こしたそうです。
(※11月3日(土)朝刊 38面)
最初にこの記事を読んで思ったのが、愛知県側の対応の"まずさ"でした。こと桃花台ニュータウンの地盤沈下と土壌汚染問題に関して、「県独自の調査はしない」と言ったり、埋設されているものが明らかに産業廃棄物だと判かった後でもそれを「黒い土」と表現してみたり・・・。
今回も記事によると、住宅計画課の担当者が「地中の物質は健康への影響がなく、撤去の必要もなかった。造成工事は適正だった」と話しているそうです。
一応付け加えておくと、現在住宅計画課で働いている職員が、撤去しないままの造成を指示した訳ではないでしょう。なので、直接彼らの責任ではないだろうけど、・・・
環境基準を越える有害物質(水銀や鉛、ヒ素など)が見つかっている以上、どう考えても撤去せず住宅地の造成を行なうのはおかしいと思います。確かに現在までは、健康被害が出ていないようですが、今後どうなるのかはまったく解かりません。
それにもし安全だと言うのであれば、住宅計画課の職員の人達に対して言いたいのは、「ではあなた達は、この場所に数千万円のお金を払って住めますか?」と言うことです。
現在地盤沈下と土壌汚染が問題となっている城山5丁目地区には、数千万円払って一戸建て住宅を購入した人が住んでいます。その事をもっと考えて、発言すべきだろうと思います。
一方、都市再生機構の対応ですが、今回の記事によると「係争中でコメントは差し控えたい」と発言しているそうです。上記の愛知県庁職員のコメントと比較すると、(こういう表現が適切かどうか解かりませんが)「非常に大人の対応だなぁ・・・」と思います。
あと今回の裁判で気になったのが、住民側が求めた損害賠償請求額です。総額約9300万円との事ですが、「5人が提訴した」とあるので、そうなると1人辺り約1860万円にしかなりません。
桃花台ニュータウン内の新築一戸建て住宅の購入価格は、だいたい3000万円〜5000万円くらい(ちなみに、そのうちの約100万円は、法律的根拠がまったくない、違法な桃花台線の建設費用分です)。
なので、「さすがにこの額は低すぎるのではないか・・・」と思いました。
ただこの点については、"同じ世帯の住民が複数参加している"とか"法律上請求できる額面の上限が規定されているから"などの理由があるのかもしれませんが・・・果たして?
*****************************
産業廃棄物最終処分場周辺で地下水汚染!(春日井市神屋町〜小牧市大草)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、春日井市神屋町と小牧市大草にまたがる産業廃棄物最終処分場近くの井戸水から、最大で環境基準の5.8倍の水銀が検出されたそうです。
(※10月31日(水)朝刊 20面)
いずれの井戸も飲料用ではなく工業用で、健康被害などは出ていないそうです。
また原因ですが、周辺で水銀の使用が確認されなかったことなどから、調査した愛知県庁と春日井市役所は、「地層・地質に由来するもの」と考えているようです。
この記事を読んで一番最初に感じたのは、記事でも調査結果でもまったく触れられていませんが、この最終処分場のすぐ南側でフェロシルトの埋設が確認されているので、その事との因果関係です。一応他の埋設場所からも水銀が見つかっていないようなので、これは私の考え違いで、まったく関係ないのかもしれません。
ただ気になるのが、その時行なわれた調査結果です。上記の場所でフェロシルトが見つかった以後、愛知県庁と春日井市役所は、周辺地区の土壌や河川、地下水(井戸)などを調査しました。その時の調査結果は、土壌から環境基準の9.6倍の六価クロムが見つかったものの、「周辺河川や井戸などからは、環境基準を上回る有害物質は見つからなかった」となっているからです。
フェロシルトに関する調査で水銀が見つからなかった件について、愛知県庁にメールで問い合わせてみました。すると、「フェロシルトの分析結果からフェロシルト中には水銀が含まれていないことがわかっていたため、水銀については調査していまかった。」との返信がありました。
ただ気になるのが・・・「本当にそうなのか?」と言う事です。と言うのも、桃花台ニュータウン内で起こっている地盤沈下と土壌汚染問題で、愛知県は当初「(問題となっている土地から)環境基準を上回る有害物質は見つからなかった」としていたのですが、小牧市や都市再生機構の調査では、環境基準を上回る有害物質が見つかっていたからです。
その後に行なわれた愛知県の調査では、有害物質が見つかっています。更にこの調査結果では、問題のある土壌がニュータウン内の学校グラウンド地下に埋設されている事も解かっています。そのため今度は「なぜ最初の調査で見つからなかったのか?」、「どうして学校地下に埋設されている事が解かったのか?」と言う疑問が残ります。
果たして、今回の調査もニュータウン内の土壌汚染の調査も、愛知県は本当にちゃんとした調査を行なったのか、・・・。
あと気になるのが、地下水が流れ込む先の太良池や八田川は、農業用水に利用されています。そして小牧市大草地区は米や桃、ぶどうなどの生産が盛んな地域です。そのため、今回の地下水汚染は農業への影響も十分考えられます。
そのため愛知県は、今後この地下水調査を、継続的にしっかりと行なうべきだと思います。ただ愛知県だけでは調査が不安なので、第三者機関にも調査を依頼した方が良いのではないかとも思います。
*****************************
固定資産税の減免措置(小牧市城山5丁目)
共産党の小牧市委員会が発行している広報誌「民報こまき 07年8月号外」を読んで知ったのですが、地盤沈下と土壌汚染の問題が起こっている桃花台ニュータウンの城山地区での固定資産税の減免が、小牧市議会で決定したそうです。
詳しい適用範囲や減免額などは書かれていなかったので判からないのですが、適用範囲はおそらく問題が起こっている城山5丁目になると思われます。
減免措置の詳細について小牧市役所に問い合わせたところ、先日メールで回答がありました。それによると、対象となるのは、やはり「城山5丁目の地盤沈下の被害を受けている住宅」なのだそうです。
また減免される期間は、「平成15年度(2003年度)〜19年度(2007年度)までの5年間」とのこと。なので、おそらく最近決まった事ではなくずいぶん前に決定したか、あるいは過去に遡って行なわれるようです。
なお減免される額は、それぞれ住宅によって傾き具合などが異なるそうで、それぞれの住宅の傾き具合(都市再生機構が調査)を応じて、土地・家屋を合わせて2割から8割の幅で、行なわれるそうです。
この件の詳細に関し共産党の小牧市委員会に問い合わせたところ、固定資産税減免措置は、今年(2007年)6月の市議会で、市側が実施を表明したものなのだそうです。その後8月に、対象者となった都市再生機構が建設した105戸のうち50戸の家庭に対し、市が個別訪問。それぞれの家庭で説明を行なったそうです。
なお、2008年度以降については、「新しいルールで実施予定」との事。
この件に関する記載が、「小牧市議会だより 2月1日号」に掲載されていました。それによると、固定資産税の減免措置が行なわれたのは、48世帯だったそうです。
また現在、都市再生機構が家屋の再調査を行なっているそうで、その結果被害が新たに確認された世帯に対しても、同様の減免措置を行なうそうです。
*****************************
住民が愛知県に公開質問状を提出 - その2(地盤沈下と土壌汚染問題)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、7月6日(金)、桃花台ニュータウン住民が愛知県庁に対し、地盤沈下と土壌汚染問題に関する3回目の公開質問状を提出したそうです。
(※7月7日(土)朝刊 24面)
記事によると、「(愛知県が今年初めに行なった土壌調査の結果について)この発表のみで"安全"とされても、納得できない」とした上で、以下のような質問だったそうです。
*****************************
土壌調査結果に関する住民説明会(城山会館、愛知県)
07年4月29日(日)、城山会館で、愛知県庁による城山地区に住む一部の住民を対象とした土壌調査結果の説明会が、行なわれるそうです。
時間:午後1時 から 午後3時
この件に関する問い合わせ先は、愛知県庁 建設部 建築担当局住宅計画課です。
これまで「住民説明会」と称して行なわれてきたものは、いずれも問題となっている地域住民だけとなっています。しかし実際は、光ヶ丘小学校や大城小学校でも、土壌汚染が確認されています。そのため私は、「これらの学校に通っている生徒やその保護者、ならびに学校周辺地域の住民に対しても、説明会を開催すべきだ」と思います。
また、「城山地区以外の場所でも地盤沈下が起こっている」と言う話を、何回か聞いた事があります。土壌汚染に関しては、「実際自分の家の下にも埋まっているのではないか」と心配している人もいることでしょう。
なので私は、「愛知県は、一部地域住民を対象とした説明会だけでなく、桃花台ニュータウン住民全員を対象とした説明会を開催するべきだ」とも思います。
この説明会に関する記事が、中日新聞の紙面に掲載されていました。
(4月30日(月)朝刊 15面)
記事によると、出席したのは、愛知県側が県庁住宅計画課などの担当者9人、住民側が70人だったそうです。そして事前に戸別に配布された調査結果を、あらためて説明したそうです。
会では「県側がこれまでと同じ主張を繰り返し、住民側とが厳しく追及する」と言ったやりとりが、また行なわれたようです。それと相変わらず、県側は、産業廃棄物を「黒っぽい土」と表現し、住民側ともめたようです。
あと、記事の最後には城山区長の談話として、「疑惑のある土地は県の責任で撤去すべきであり、地域でまとまって裁判に訴えることも考えねばならない」と言う発言が、掲載されていました。
*****************************
壌調査の結果公表 - その3(愛知県)
4月12日(木)、愛知県が、小学校グランドと地盤沈下が問題となっている地域の土壌調査の結果を、公表したそうです。
それによると、今回の調査結果は以下のようなものでした。
調査期間:
2006年12月〜2007年3月
調査対象地域:
例.地域および施設名(調:、黒:、環:)
・調・・・調査対象地域および施設での全調査地点数
・黒・・・調査地点のうち、黒い土が見つかった場所
・環・・・調査地点のうち、環境基準を上回る物質が見つかった場所
・光ヶ丘小学校(調:14、黒:14、環:5)
・光ヶ丘中学校(調:14、黒:4、環:0)
・大城小学校(調:13、黒:4、環:2)
・タウン城山(調:55、黒:21、環:7)
・グリーンテラス城山(調:41、黒:2、環:0)
調査結果:
・全ての調査地域で、黒い土を確認。
・黒い土が見つかった全ての地点で、油分を確認。
・全ての調査地域で、環境基準を超えるダイオキシンは検出されず。
・光ヶ丘中学校とグリーンテラス城山では、環境基準を超える物質は検出されず。
・光ヶ丘小学校と大城小学校では、調査した全27地点のうち7地点から、環境基準の〜2.2倍の鉛が検出。
・タウン城山では、調査した55地点のうち7地点から、環境基準の〜6.9倍の鉛、1.2倍の総水銀、1.5倍のヒ素が検出。
・環境基準を超えた物質が見つかった場所では、黒い土の上に〜2.5メートルの土がある。
この調査結果に対し、愛知県は、環境基準を上回る物質が見つかった場所は土で覆われており、なおかつ地下水を飲料水として利用していないことから、住民に対し「人体への健康への影響はない」と言っているそうです。
また検出された理由は判からないけれど、造成当時は黒い土に匂いも油膜もなく、「造成は適切だった」として、あらためて自らの責任を否定したそうです。
あと今後ですが、「念のため、周辺地域で地下水調査を行うことを検討する」そうです。
*****************************
土壌調査の結果公表 - その2(都市再生機構)
「中日新聞」の紙面と「メ〜テレニュース」の記事を読んで知ったのですが、06年11月26日(日)に「都市再生機構」が、地盤沈下が問題となっている地域住民を対象とした説明会を開き、これまで判かった調査結果を公表したそうです。
(11月27日(月)朝刊 29面)
これら記事によると、調査結果は下記のようなものだったそうです。
・地盤沈下が問題となっている地域の土壌から、「産業廃棄物」の残存が、科学的に確認された。
・産業廃棄物が含まれる土壌から、基準値の170倍の「鉛」を含む5種類の有害物質が検出された。また油分や木片、ガラス片、ビニール袋、繊維のようなもの、地下水ではない「たまり水」なども確認された。
・地盤沈下の原因は、産業廃棄物層とその上部にある覆土層がそれぞれ沈下した事が原因である。「愛知県」が行なった造成工事の際、土を固める作業が不十分な地盤があり、その為覆土層に雨水が浸透し、覆土層が沈下した。その結果産業廃棄物層にかかる荷重が増え、産業廃棄物層も沈下した。
・今後覆土層が沈下する可能性は非常に低く、産業廃棄物層の沈下もほぼ終了している為、今後沈下はほとんど発生しない。
また都市再生機構は今後の対策として、「一軒ごとの建物の傾きを調べ、場合によっては、ジャッキアップ工法で建物や外構の修復工事をする」としたそうです。また修復工事の開始時期については、「愛知県の調査結果と見解の発表後」としたそうです。
これに対し住民側からは、「産廃が残っている以上、いくら宅地地盤の強度があると言っても、対策は不十分」として、「産業排気武具の完全撤去」を求める意見が相次いだそうです。いっぽう都市再生機構はこの点について、「愛知県の調査結果を待ってから検討する」としたそうです。
*****************************
有害物質を含む土壌が埋設された可能性のある学校(大城小学校、光ヶ丘小・中学校)
愛知県による地盤沈下に関する住民説明会で明らかになった、城山5丁目の土壌(小牧市の調査で、環境基準を大きく上回る有害物質が発見された)が造成時に桃花台ニュータウン内の3つの学校グランドに運び込まれた問題について、どの学校なのか「愛知県庁」に問い合わせたところ、グラウンドに運び込まれた学校は、以下の3校なのだそうです。
・大城小学校
・光ヶ丘小学校
・光ヶ丘中学校
なお今のところ、「グラウンドのどの辺りに、どの程度の規模で埋められたのか」と言う点については、まだ判かっていないそうです。その為、この点も含めて今後の調査で明らかにしていくそうです。
*****************************
知県知事、情報開示を明言(地盤沈下と土壌汚染問題)
11月20日(月)の定例記者会見で、神田真秋 愛知県知事が、土壌調査の際に採取する、「地盤沈下」の原因と関係する「地耐力」に関する情報を、住民に開示する事を明言したそうです。
*****************************
地盤沈下に関する住民説明会 - その2(小牧勤労センター、愛知県)
11月19日(日)、「小牧勤労会館(小牧勤労センター)」で、地盤沈下が問題となっている城山5丁目の住民を対象とした、「愛知県庁」による説明会が行なわれたそうです。
新しい情報としては、以下の通りです。
・有害物質を含む土壌を含む造成の際に出た残土を、ニュータウン内の小中学校の内の3校のグランドに埋めた。
・土を運び込んだ小中学校のグランドも、調査範囲に含む。
・今後行なわれる調査は、「地盤沈下」の原因究明とは関係無く、あくまで環境基準の観点から、有害物質の範囲を特定するために行なう。
・新たに始める調査は年内に開始し、来年(2007年)の3月までに結果をまとめる予定。
ちなみに、この件に関する記事は、「中日新聞」の紙面にも掲載されています。
(※11月20日(月)朝刊 14面)
今回の説明会について、私は「やる予定だ」と言う情報は知っていましたが、いつどこでやるのかはまったく知りませんでした。正直その点から、少し違和感を憶えます。実際地盤沈下が起こっている地域や場所は、「桃花台ニュータウン」の一部の地域に過ぎません。しかしニュースなどで「桃花台ニュータウンで地盤沈下が・・・」と報じられている以上、ニュータウン住民全体の問題だとも言えます。その点を考えても、「住民全体に対して説明会を行なうべきだ」と思います。
また今回の説明会では、「産業廃棄物を含む土が、問題となっている地域以外の学校のグランドに運びこまれていた」ことが、判明しました。記事では単に「運び込まれた」とありますが、県が「ボーリング調査を行なう」としている点から考えると、おそらく「そのまま埋設されているのでは、・・・」と思われます。
これは問題となっている地域が拡大した事を意味し、この点からもただ単に一部の地域の問題ではなく、ニュータウン全体の問題だと思います。なので私は、「近い時期に、ニュータウン住民全体を対象とした説明会を行なうべきだ」と思います。
この説明会の告知ページを、見つけました。
・桃花台城山地区住民説明会について(愛知県庁 建設部住宅計画課)
このページによると、この説明会の対象となったのは、タウン城山(地区名)とグリーンテラス城山(地区名)に住んでいる人たちだったようです。
*****************************
愛知県独自のボーリング調査、年内開始へ(地盤沈下と土壌汚染問題)
「桃花台ニュータウン」における地盤沈下問題で、「愛知県」は、年内にも県独自のボーリング調査を開始するそうです。
調査内容は下記の通りです。
・地盤沈下地点を中心にして同心円状に住宅を1軒ずつ行なう。
・この調査によって、有害物質が含まれる土壌の範囲を特定する。
※旧「住宅・都市整備公団」(現『都市再生機構』)以外が販売した土地に関しても、調査を行なう。
記事にある「地盤沈下地点」とは、地盤沈下が発覚し住宅が解体され、今年(2006年)の夏に都市再生機構によって土壌調査が行なわれた地点に、ほぼ間違いないと思われます。
・愛知県知事が、県独自の調査を明言(地盤沈下問題)(桃花台新聞)
追記(11月19日)
上記のインターネット版と同じ内容の記事が、中日新聞の紙面の方にも、掲載されていました。
(※11月18日(土)朝刊 32面)
追記(11月22日)
この件に関する記事を、新たに見つけました。
新しい情報としては、下記の通りです。
・行なわれる調査は、あくまで地盤沈下の調査ではなく有害物質を含む土壌の範囲を特定するために行なう。
・有害物質を含む土壌を含んだ造成中の残土を、ニュータウン内の3校の小中学校のグランドに埋めた。その為そのグランドも、調査範囲に加わる(調査範囲の拡大)。
・調査結果は、来年(2007年)3月までにまとめる予定。
*****************************
桃花台ニュータウンの地盤沈下問題について
【記者】
小牧の桃花台ニュータウンの地盤沈下の件ですが、先日、県で分析した結果が出て、その中で、基準値が以上か以下かということは別にして、化学物質が出てきている。この件については、都市再生機構が県を提訴し、その主張の中で県が造成をちゃんとやってなかったのではないかと言っておられるようですが、化学物質が出てきたことは、都市再生機構の主張を裏付けるようなことではないかと思うのですが、あのような結果なり、化学物質が存在したということについて、どのようにお考えですか。また、今後、改めて県として調査をするつもりがあるのか、併せてお伺いします。
【知事】
この前の現地での調査のサンプルで、調査、解析を進めて、一部の物質が少し基準値をオーバーしていたということはご指摘のとおりです。特に、深刻なものではありませんけれども、一部の物質でオーバーしていたことは事実であります。したがって、そういう事実が出た以上は、もう少しきちんとした調査を実施しようということでおります。そういう基本的な考え方でおります。
そのことと、県が売り主になり都市再生機構の方へ売った法的な責任とは、直接はつながらないと思っております。
いずれにしても、これは訴訟を起こされておりますので、そういうことも含めて、今、弁護士の方に対応をお願いをしておりますけれども、その契約の問題とは別の問題だろうと、今のところ我々は考えております。
ただ、いずれにしても、そのような物質があったことは事実でありますから、地域の皆さん方に、いろいろ不安を持たれたり、心配が拡大することがあってはいけませんので、これから、より厳密に調査をするという方針でおります。
http://www.pref.aichi.jp/koho/kaiken/2006/11.06.html#6
*****************************
土壌調査の結果公表(愛知県、小牧市)
10月26日(木)、「愛知県」と「小牧市」は、それぞれが行なった地盤沈下で解体された土地の下から採取した土壌の調査結果を、公表したそうです。
・土壌調査:愛知県造成の住宅団地からヒ素検出(毎日新聞)
記事によると、調査結果は下記のようなものだったようです。
< 愛知県 >
・「環境基準」を上回る有害物質は、検出されなかった。
(※環境基準以下の「ヒ素」と「ジクロロメタン」は、検出されたようです。)
・愛知県側の主張は、「(検出された)原因は不明だが、直ちに健康被害につながる数値ではない。」。
< 小牧市 >
・環境基準を上回る「ヒ素」と「ジクロロメタン」を検出。「ヒ素」が環境基準の3.6倍、「ジクロロメタン」が1.85倍※1 。
・通常の土壌ではほとんど検出されない、油分4.8%を検出。
※1. 記事では「県は・・・公表した」となっているので、愛知県側の調査結果とも取れますが、その後の文章の中に「県の結果は基準以下」と言う所があるので、おそらく小牧市の調査結果だと思われます。たぶん「愛知県側が、小牧市と愛知県の両方の結果を公表した」のだと思います。
*****************************
桃花台の地盤沈下問題をあつかったテレビ番組の特集 - その2(中京テレビ)
8月25日(金)、「中京テレビ」の報道番組「NEWS リアルタイム」で、「桃花台ニュータウン」の地盤沈下問題の特集が、放送されていたようです。番組の公式サイトには、この時放送された特集をまとめたページが、作成されていました。
・記者の目 “沈む住宅街”で何が…?(中京テレビ:「NEWS リアルタイム」)
このまとめページには、実際地盤沈下が起こっている家の状況や、「都市再生機構」が行なっていた土壌調査地点の様子、「愛知県庁 住宅計画課」の課長へのインタビューの様子などが掲載されていました。
愛知県庁 住宅計画課の課長の発言は、正直「ひどいものだ」と思いました。城山5丁目の元地主や当時造成に立ち会った愛知県庁のOBが、「産業廃棄物」の存在を認めているにも関わらず、「あれは天然の土だ」とか「製紙カス(産業廃棄物)なんてなかった」なんて発言しています。
ただ冷静になって読めば、もしこの発言をしたのが事実であれば、愛知県がこれまで行なってきた「自分たち(愛知県)は、それら(産業廃棄物)を取り除いた」とか「住宅都市整備公団(現『都市再生機構』)には、廃棄物に関する資料を渡した」と言う主張が、根底から覆る事になります。なぜなら存在を知らなかったのであれば、土壌を取り除く事はないですし、また資料を渡すはずがないからです。
自から墓穴を掘ったのか、それともこの課長が適当に発言したのかは判かりませんが、愛知県庁の立場がどんどん悪くなっているのは、事実だと思います。
*****************************
愛知県が公開質問状に回答(地盤沈下と土壌汚染問題)10月6日(金)
「愛知県」は、9月15日(金)に住民が愛知県知事に対して提出した「公開質問状」に対し、回答したそうです。
・造成は適切と県強調 桃花台の地盤沈下(中日新聞)
記事によると愛知県側は、
・「造成工事を行った当時から、産業廃棄物処分場跡地との認識はない」
・「造成工事を行った当時はダンプカーなどの重機が作業しても支障のない十分な硬さがあり、軟弱な地盤ではなかったと聞いている」
と回答しているそうです。
ちなみに、この記事は、「中日新聞」の紙面の方にも掲載されていました。
(※10月7日(土)朝刊 20面)
この件に関しては、「県OB職員談」として、以前別の記事で「愛知県は造成時に、廃棄物と見られる粘土が大量に堆積していた事を確認し、除去した」と報じられています。
この事を踏まえると、経緯は以下のようなものになります。
1957年〜1971年
王春工業が、王子製紙の工場から出る「沈殿カス」などを投棄。
↓
1971年
愛知県が土地を購入
↓
1983年〜1985年
土地を造成
・大量の廃棄物を確認 → 除去
・「産業廃棄物処分場 跡地」と認識せず。
・造成工事中は、問題なかった。
↓
旧「住宅・都市整備公団」(現『都市再生機構』)に売却
< 売却時の廃棄物に関する認識について >
愛知県側の主張:
造成された土地の売買の際に、「大量の廃棄物が捨てられていた事」に関する資料※ のやりとりがあったはず。
都市再生機構側の主張:
愛知県から、「大量の廃棄物が持ち込まれた場所だった」とは聞いていない。
※資料は、現在残っていないそうです。
最後に、今回の愛知県の回答についての感想を、書こうと思います。
「不思議だな」と思ったのが、愛知県が大量の廃棄物を確認しておきながら、産業廃棄物処分場跡地だと認識しなかった点。この点、うがった見方をすれば、「産業廃棄物処分場跡地と認識しなかったから公団に報告しなかったのでは・・・」なんて思います。
ただ「売買の際の資料が現存していない」と言う事らしいので、この点を証明する事は非常に難しいのですが・・・。
あと気になるのが、「造成工事中は、問題なかった」と言う点。私は「地盤沈下」に関して詳しくないのですが、工事の最中に様々な機材や車両が問題の地盤の上に置かれたり通ったりしたと思うのですが、「そういった事と住宅が何年も建っている事との間に、どれくらい差があるのか?」と言う事が気になりました。「素人考え」だと、「『住宅』と言う重たい『物体』が、何年にも渡って地盤を押し続ける力」と、「一時的に機材や車両が押し続ける力」には、大きな差があると思うのですが・・・。
*****************************
桃花台の地盤沈下問題をあつかったテレビ番組の特集(TBS)
「桃花台ニュータウンで、地盤沈下!?」のコメントを読んで知ったのですが、9月17日(日)、「TBS」のテレビ番組「噂の東京マガジン」で、「桃花台ニュータウン」の「地盤沈下」問題が、取り上げられたそうです。 (^^)/ )
それと、番組の公式サイトには、都市再生機構が土壌調査していた地点のレポート記事が、掲載されていました。
・住民激怒!地盤沈下で消えた住宅(TBS:噂の東京マガジン)
*****************************
*****************************
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その7(愛知県)
桃花台ニュータウン在住の愛知県議会議員・天野まさきさんの公式ブログを見て知ったのですが、09年11月18日(水)に愛知県が、9月末に実施した桃花台ニュータウン内・城山地区と光ヶ丘小学校および大城小学校グランドに埋設されている、産業廃棄物による地下水汚染の調査結果を、公表したそうです。
それによると、相変わらず光ヶ丘および大城両小学校では、環境基準を上回る汚染物質は確認されなかったそうです。しかし城山地区の2ヶ所の井戸では、今まででもっとも高い、最大で環境基準の"8.6倍"の総水銀が検出されたそうです。
最後に感想を少し。
「今年(2009年)になってから、(愛知県が)調査結果をなかなか報じないなぁ・・・」なんて思っていたのですが、調査結果を見てみると、去年(2008年)は全4回行われていますが、今年は2月に行われた調査結果と合わせて、2回しか行われていません。昨年も最終が9月だった事から、おそらく今年はこれ以上調査結果が発表される事はないのではないかと。
この点(調査回数が減らされた事)については、疑問です。「問題ある物質が検出されない」、または「検出されてもその量は安定している」と言うのであれば別ですが、実際検出されていますし、その量は決して安定していません。今回の調査で総水銀が環境基準を上回った2地点(NO.1と2)について言えば、検出される量は回を重ねるごとに増えていますし、前回の調査で検出された「NO.5」については、今回は検出されていません。
このように、調査結果が安定していない状態で検査回数を減らす事は、"問題を未然に防ぐ"(例えばどこかの地点で急激に環境基準を上回る物質の量が増えたり、あるいは別に地点へと移動が認められるするような危険を事前に速やかに察知する)と言う観点から、問題があると思います。
*****************************
桃花台を含む日本の産業廃棄物処理問題について書かれた書籍が発刊(世界思想社)
『土壌・底質汚染と健康被害ラーニング』と言うブログの記事を読んで知ったのですが、桃花台ニュータウンを含む日本の様々な地域で問題となっている産業廃棄物の処分問題について書かれた書籍が、先月(10月)発売されたそうです。
・出版案内:『廃棄物列島・日本−深刻化する廃棄物問題と政策提言−』(土壌・底質汚染と健康被害ラーニング)
・廃棄物列島・日本 ― 深刻化する廃棄物問題と政策提言(世界思想社)・・・出版社の書籍案内ページ。
書籍には桃花台ニュータウンで問題となっている「産業廃棄物の問題」だけでなく、桃花台周辺でも埋設が確認され最近撤去された石原産業の「フェロシルト問題」も取り上げられています。
興味のある方は、読んでみてはいかがでしょう?
ちなみに、この書籍発刊と関係していると思われる講演会が、大阪府大阪市にあるおおさかATCグリーンエコプラザで、12月18日(金)に行われるそうです。
・ATCセミナー 土壌・地下水汚染の社会的問題の事例(案)(EICネット)
この講演会では、桃花台ニュータウンの事例も取り上げられるようです。興味のある方は行ってみてはいかがでしょう?
(・・・と言っても大阪なので、なかなか気軽には行けませんが・・・(^^; )
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その6(愛知県)3月18日(水)、
愛知県が2月6日(金)に城山地区で実施した地下水調査の結果を、発表しました。それによると、5つの観測地点のうち3つから、また環境基準を上回る「総水銀」が検出されたそうです。そのうちの1つからは、これまでで最大の、環境基準"約7.8倍"の総水銀が検出されたそうです。
なお、光ヶ丘小学校と大城小学校の地下水質調査は、過去4回の調査で一度も環境基準を上回る物質が検出されなかった事から、今回は行わなかったそうです。
*****************************
地盤沈下問題の裁判で都市再生機構が敗訴(愛知県)
3年前の2006年に、都市再生機構(別称「UR都市機構」、旧・住宅・都市整備公団)が愛知県に対し「城山5丁目地区で起きた地盤沈下の責任は愛知県にある」として、住民に対し機構側が支払った補償費用や調査費用などを請求する裁判を、名古屋地裁に起こしました。その裁判が、3月26日(木)に結審したそうです。
裁判官は「機構には地盤を十分に調査する責任があった。」として、機構側の訴えを棄却(機構側が敗訴)したそうです。
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その5(愛知県)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、11月11日(火)に愛知県が、9月末に実施した桃花台ニュータウン内・城山地区と光ヶ丘小学校および大城小学校グランドに埋設されている、産業廃棄物による地下水汚染の調査結果を、公表したそうです。
それによると、相変わらず光ヶ丘および大城両小学校では、環境基準を上回る汚染物質は確認されなかったそうです。しかし城山地区の2ヶ所の井戸では、前回を上回る、最大で環境基準の"7.6倍"の総水銀が検出されたそうです。
(※11月12日(水)朝刊 18面)
ただ、前回の調査(6月採取、8月結果発表)と前々回(4月採取、5月結果発表)で環境基準を上回る総水銀が見つかった、城山地区の3地点の内の1地点では、今回は環境基準を上回る汚染物質は、見つからなかったそうです。
*****************************
住民が愛知県と都市再生機構を提訴 - その3(地盤沈下と土壌汚染問題)
去年(2007年)の10月、埋設している産業廃棄物が原因で地盤沈下が起きている城山地区に住む一部住民が、愛知県や都市再生機構を相手取って、損害賠償を求める裁判を起こしましたが、それとは別の住民8世帯12人が、11月10日(月)、同じく愛知県や都市再生機構を相手取って、廃棄物の除去や総額1億2000万円の損害賠償を求める裁判を、名古屋地裁に起こしたそうです。
(※中日新聞 11月11日(火)朝刊 30面)
*****************************
公害調停が決裂(地盤沈下と土壌汚染問題)
今年(2008年)の春から桃花台ニュータウン住民と愛知県、都市再生機構などが参加して行なわれた公害調停での話し合いが決裂したそうです。
・桃花台ニュータウン地盤沈下問題:公害調停が決裂 住民側、民事訴訟の方針(毎日jp)
・桃花台地盤沈下 調停を打ち切り(YOMIURI ONLINE)
また記事によると、今後住民側は「国の公害等調整委員会に対し裁定を求める申請を行うとともに、愛知県と都市再生機構を相手取って新たに民事訴訟を起こす方針」との事。
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その4(愛知県)
8月5日(火)、愛知県が、6月に行った、桃花台ニュータウン内の城山地区と3つの学校グラウンドに埋設している産業廃棄物による地下水汚染を調べた4回目の調査結果を、公表したそうです。
前回(4月)の調査で環境基準を上回る"総水銀"が見つかった城山地区の3地点の地下水で、最大で環境基準の"6.6倍"(前回との比較では最大"約2.4倍")の"総水銀"が検出されたそうです。
(※8月6日(水)朝刊 16面)
また城山地区の3ヶ所の数値が増えた理由について、愛知県庁住宅計画課の担当者は、「丘陵地であり、地下水面が季節によって変動したためではないか」と言っているそうです。
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その3(愛知県)
今年(2008年)の2月に行なわれた地下水調査で環境基準を上回る有害物質が見つかった城山5丁目地区。当初3回目の調査は6月に行なわれる予定でしたが、この結果を受けて4月に前倒しになりました。その調査結果が、5月21日(水)に公開されたそうです。それによると、今回もまた、最大で環境基準の3倍の総水銀が検出されたそうです。
(※中日新聞紙面 5月22日(木)朝刊 18面)
*****************************
署名活動への協力求む!(桃花台ニュータウン区長会)
ずいぶん前から署名活動が行なわれているのを知ってはいたのですが、記事にするのをずっと忘れていました・・・。 (^^;
桃花台ニュータウン区長会が中心となって、愛知県と都市再生機構に対する要望書への署名活動が、現在行なわれています。
・地盤沈下問題(桃花台ニュータウン区長会)
回覧版等で周ってきてご存知の方もいるかもしれませんが、あらためて詳しく書こうと思います。
2者に対して要望している内容は、主に以下の3つです。
・第三者機関を設置し、原因究明と問題解決にあたる事。
・問題が発覚した土地の全ての土壌を撤去し、きちんと賠償する事。
・情報をきちんと開示する事。
署名に使われている用紙は、各地区の区長をやられている方の方に問い合わせれば、たぶん貰えると思います。「実物を見てみたい」と言う方は、あおい交通や名鉄バスの「光ヶ丘2丁目」停留所北側にある掲示板に貼られているので、行って見てみて下さい。
*****************************
土壌から環境基準を大幅に上回るヒ素!(エコーガーデン桃花台)
中日新聞の記事を読んで知ったのですが、昨年(2007年)10月から土壌調査を行なっていた、小牧市古雅3丁目に整備予定の住宅地「エコーガーデン桃花台」の敷地内にある土壌から、環境基準を大幅に上回るヒ素が見つかったそうです。
(※4月5日(土)朝刊 20面)
記事によると、調査結果は、以下のようなものだったそうです。
有害物質が見つかった場所:全121戸の内の7戸の宅地
見つかった有害物質:最高で環境基準の7倍の「ヒ素」、環境基準をやや上回る「フッ素」
汚染されている土の量:約2万m?
汚染された原因:不明
なお、汚染された土壌は以前愛知県住宅公社の人が言っていた通り、全て撤去するそうです。またその分新しい土を持ってきて、掘り出した部分を埋めるそうです。
あと記事にはこの場所に関する歴史も、少し書かれていました。それと私が知っている情報をまとめると、以下のような経緯があるようです。
1970年代頃:元々山林や原野だった土地を愛知県が購入。
(県は1989年頃まで、暫定調整池として利用。)
↓
1999年3月:愛知県住宅供給公社が愛知県から土地を購入。
(土地は主に駐車場として利用される。なお駐車場の管理は、桃花台新交通(※2006年9月頃まで)や(財)桃花台センター(※2007年3月末日まで)が行なっていた。)
↓
2007年4月:エコーガーデン桃花台の整備工事開始
↓
2007年10月:公社が土壌調査を開始
↓
現在に到る
この件に関する感想を、書こうと思います。
エコーガーデンの場合「汚染された土壌を全て撤去する」との事なので、今後健康被害や地盤沈下が起きる可能性は低いと思いますが、・・・
気になるのが、「なぜ汚染されたのか?」と言う点です。なぜなら公社は今のところ「原因は不明」と発表していますが、もしその原因が"調整池の埋め立て"に利用した土にあるとしたら、汚染されている地域が更に広がる可能性があるからです。
書籍『桃花台 まちの記録』によると、過去に桃花台ニュータウン内で調整池だった場所が、実はもう1つあります。それはニュータウン最北部の篠岡3丁目地区です。ちょどWikipediaに公開されている画像に、この2つの地域が調整池だった頃の航空写真があるので、興味のある方は見てみて下さい。
この場所も、長らくずっと空き地のままでした。調整池だった場所はしばらく土地を"寝かせて"地盤を固める必要がある為、このように放置されていたのだとか。
ちなみに去年(2007年)の夏頃から住宅の建設が始められ、今空き地はほとんど残っていません。
元・調整池があった場所が汚染されていたからと言って、必ずしもこの場所の土壌も汚染されているとは言えません。しかし「同じ土が運ばれた」とか、あるいは「同じ業者が埋め立て工事を行なっている」と言う可能性は、十分考えられます。そうなれば必然的に、汚染されている可能性も高くなります。
なので私は、あらためて愛知県庁に強く求めたい!
「すぐにでも、ニュータウン全地区の土壌調査をするべきだ!!」
そもそも「自治体」と言うのは、住民の健康や幸せ、財産を守る為の組織なのではないでしょう?それが住民と争うと言うのは、根本的に間違っていると思います。
それと現在県庁で働いている人は、ニュータウンの整備事業に携わった人ではないかもしれません。なので個人としての責任は、まったくないかもしれません。
しかし県庁で働いている人も、"一個人"として、この問題を考えて欲しい。もし自分が数十年ものローンを組んで購入した住宅の地下に、「産業廃棄物や有害物質が埋まっている」と判かったら、どんな気持ちがするのかという事を。
*****************************
公害調停(地盤沈下と土壌汚染問題)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、3月18日(火)、愛知県庁三の丸庁舎で、桃花台ニュータウン住民が公害紛争処理法に基づき愛知県の公害審議会に申請した、「公害調停」の1回目が行なわれたそうです。
(※3月19日(水)朝刊 18面)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、3月18日(火)、愛知県庁三の丸庁舎で、桃花台ニュータウン住民が公害紛争処理法に基づき愛知県の公害審議会に申請した、「公害調停」の1回目が行なわれたそうです。
(※3月19日(水)朝刊 18面)
*****************************
「公害調停」とは、「公害問題で当事者間の話し合いで解決しない時、行政(都道府県や国)が間に入り調停する事」のようです。
ただ今回は愛知県も"当事者"なので、話し合いには桃花台ニュータウン住民と桃花台ニュータウンの造成を行なった愛知県、そして住宅を販売した旧・住宅都市整備公団(現・都市再生機構)などと、審議会の委員による4者で行なわれたようです。
記事によると、話し合い後の記者会見で住民側が言うには、今回の会合では当事者である3者の主張は、以下のようなものだったそうです。
住民側:地盤沈下の原因をはっきりさせる為、中立公正な立場の機関による土壌調査を要請。
愛知県:調停の打ち切りを要請。
都市再生機構など:「調停には応じられない」、「当社には責任はない」(※恐らく住宅メーカーも含まれているのではないかと思われます。)
*****************************
地下水調査の結果を公表 - その2(愛知県)
小牧市の公式サイトを見て知ったのですが、2月6日(水)・7日(木)の2日間、産業廃棄物の埋設が発覚している城山地区と光ヶ丘小学校、大城小学校の敷地内で、2回目の地下水調査が行なわれたそうです。その結果が今日(3月7日(金))、愛知県によって発表されたそうです。
それによると、城山地区の1つの観測用の井戸から、環境基準の"3.4倍"にあたる「総水銀」が検出されたそうです。
土壌調査地点を見に行ってきました! - その2(小牧市城山5丁目)
先日再度、小牧市城山5丁目にある土壌調査地点を見に行ってきました。以前は金属の壁で覆われていましたがそれは取り除かれ、その代わりに低い垣根が作られていました。
*****************************
住民が愛知県と都市再生機構を提訴 - その2(地盤沈下と土壌汚染問題)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、今年(2007年)10月に城山地区住民が愛知県と都市再生機構を相手取って起こした損害賠償訴訟の第1回口頭弁論が、12月6日(木)に、名古屋地裁で行なわれたそうです。
(※12月7日(金)朝刊 34面)
記事によると、住民側の主張は、以下の通りです。
住民:
「県は有害物質の存在を知りながら造成した。機構は必要な地盤調査や廃棄物撤去をしないまま分譲した結果、居住環境が損なわれた。」
これに対し愛知県と都市再生機構(UR都市機構)は、以下のように反論し、自分たちの賠償責任を否定したそうです。
愛知県:
「地中に有害物質があるとの認識はなく、造成は適切だった。」
都市再生機構:
「健康への影響はなく、住宅の欠陥はない。」
最後に、この裁判に関する感想を書こうと思います。
愛知県と都市再生機構が上記のような反応を示すのは、当然だと思います。と言うのも、両者は桃花台ニュータウンの地盤沈下と土壌汚染問題に関する別の裁判でも、お互いの責任を争っているからです。
この問題、愛知県・都市再生機構双方ともに責任があると思います。
愛知県の方は土地購入の段階で、この地に産業廃棄物が埋められていた事を知っていた可能性があります。仮に知らなかったとしても、造成工事の段階で、当時の愛知県庁職員が「廃棄物と見られる粘土が、大量に堆積していた事を確認」したと話している(そのため愛知県の「有害物質があるとの認識がない」と言う発言は嘘の可能性があると思います。)以上、少なくとも問題があると思われる土壌の調査・分析を行なうべきだったと思いますし、それらを適切に除去すべきだったと思うからです。
また都市再生機構の方は、住民側の「住宅を建てる前の段階で地盤調査を行なうべきだった」と言う主張が正しいと思うから、彼らにも責任があると思います。
ただ上記でも書きましたが、愛知県と都市再生機構は別の裁判でもこの問題を争っている以上、どうあっても、お互い責任を認めないでしょう。なので住民側は、もう少しこの裁判の行方を見守ってから、愛知県と都市再生機構のどちらか一方(都市再生機構が勝てば愛知県、訴えが否決されれば都市再生機構)を訴えた方が良かったのではないかとも・・・思います。
*****************************
調査に関する感想を書こうと思います。
率直に言って、愛知県の調査は信用できないので、小牧市か、別の第三者機関に調査を依頼するべきだと思います。と言うのも、先日発覚した小牧市大草で地下水が水銀で汚染されていた件に関しても、一度フェロシルトの関係で調査した時は「有害物質が見つからなかった」としているからです。
この件について愛知県にメールで確認をしたところ、「フェロシルトの分析結果からフェロシルト中には水銀が含まれていないことがわかっていたため、水銀については調査していまかった。」との返信がありましたが、果たしてそれが本当なのかどうか・・・。
それに愛知県は、城山5丁目の土壌調査結果を一度は「有害物質は検出されなかった」と言っていますし・・・。
(ちなみに同じ土壌を調査した小牧市の結果では、環境基準を上回る"ヒ素"と"ジクロロメタン"が検出されています。)
・土壌調査の結果公表(愛知県、小牧市)(桃花台新聞)
それと今回の調査方法は、少しおかしいと思います。確かに愛知県の調査では、光ヶ丘小学校と大城小学校では鉛しか見つかっていませんが、城山地区と同じ産業廃棄物が埋設されているのなら、当然"ヒ素"や"総水銀"に関しても行なうべきだと思います。
それこそ場所が小学校だけに、後になって「検出対象から外していたから」では済まされないと思うからです。
あと、上記でも書きましたが、去年(2006年)10月に発表された小牧市の調査では、城山5丁目の土壌から"ジクロロメタン"が検出されています。そのため、この物質も調査対象にして、改めて調査すべきだと思います。
*****************************
住民が愛知県と都市再生機構を提訴(地盤沈下と土壌汚染問題)
10月12日(金)、城山地区の住民が、愛知県と都市再生機構(UR都市機構、旧・都市整備公団)に対し、「適切な地盤調査や廃棄物の撤去をしないまま分譲され、居住環境が損なわれた」として、住宅の購入代金分(総額約9300万円)の損害賠償を求める裁判を起こしたそうです。
(※11月3日(土)朝刊 38面)
最初にこの記事を読んで思ったのが、愛知県側の対応の"まずさ"でした。こと桃花台ニュータウンの地盤沈下と土壌汚染問題に関して、「県独自の調査はしない」と言ったり、埋設されているものが明らかに産業廃棄物だと判かった後でもそれを「黒い土」と表現してみたり・・・。
今回も記事によると、住宅計画課の担当者が「地中の物質は健康への影響がなく、撤去の必要もなかった。造成工事は適正だった」と話しているそうです。
一応付け加えておくと、現在住宅計画課で働いている職員が、撤去しないままの造成を指示した訳ではないでしょう。なので、直接彼らの責任ではないだろうけど、・・・
環境基準を越える有害物質(水銀や鉛、ヒ素など)が見つかっている以上、どう考えても撤去せず住宅地の造成を行なうのはおかしいと思います。確かに現在までは、健康被害が出ていないようですが、今後どうなるのかはまったく解かりません。
それにもし安全だと言うのであれば、住宅計画課の職員の人達に対して言いたいのは、「ではあなた達は、この場所に数千万円のお金を払って住めますか?」と言うことです。
現在地盤沈下と土壌汚染が問題となっている城山5丁目地区には、数千万円払って一戸建て住宅を購入した人が住んでいます。その事をもっと考えて、発言すべきだろうと思います。
一方、都市再生機構の対応ですが、今回の記事によると「係争中でコメントは差し控えたい」と発言しているそうです。上記の愛知県庁職員のコメントと比較すると、(こういう表現が適切かどうか解かりませんが)「非常に大人の対応だなぁ・・・」と思います。
あと今回の裁判で気になったのが、住民側が求めた損害賠償請求額です。総額約9300万円との事ですが、「5人が提訴した」とあるので、そうなると1人辺り約1860万円にしかなりません。
桃花台ニュータウン内の新築一戸建て住宅の購入価格は、だいたい3000万円〜5000万円くらい(ちなみに、そのうちの約100万円は、法律的根拠がまったくない、違法な桃花台線の建設費用分です)。
なので、「さすがにこの額は低すぎるのではないか・・・」と思いました。
ただこの点については、"同じ世帯の住民が複数参加している"とか"法律上請求できる額面の上限が規定されているから"などの理由があるのかもしれませんが・・・果たして?
*****************************
産業廃棄物最終処分場周辺で地下水汚染!(春日井市神屋町〜小牧市大草)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、春日井市神屋町と小牧市大草にまたがる産業廃棄物最終処分場近くの井戸水から、最大で環境基準の5.8倍の水銀が検出されたそうです。
(※10月31日(水)朝刊 20面)
いずれの井戸も飲料用ではなく工業用で、健康被害などは出ていないそうです。
また原因ですが、周辺で水銀の使用が確認されなかったことなどから、調査した愛知県庁と春日井市役所は、「地層・地質に由来するもの」と考えているようです。
この記事を読んで一番最初に感じたのは、記事でも調査結果でもまったく触れられていませんが、この最終処分場のすぐ南側でフェロシルトの埋設が確認されているので、その事との因果関係です。一応他の埋設場所からも水銀が見つかっていないようなので、これは私の考え違いで、まったく関係ないのかもしれません。
ただ気になるのが、その時行なわれた調査結果です。上記の場所でフェロシルトが見つかった以後、愛知県庁と春日井市役所は、周辺地区の土壌や河川、地下水(井戸)などを調査しました。その時の調査結果は、土壌から環境基準の9.6倍の六価クロムが見つかったものの、「周辺河川や井戸などからは、環境基準を上回る有害物質は見つからなかった」となっているからです。
フェロシルトに関する調査で水銀が見つからなかった件について、愛知県庁にメールで問い合わせてみました。すると、「フェロシルトの分析結果からフェロシルト中には水銀が含まれていないことがわかっていたため、水銀については調査していまかった。」との返信がありました。
ただ気になるのが・・・「本当にそうなのか?」と言う事です。と言うのも、桃花台ニュータウン内で起こっている地盤沈下と土壌汚染問題で、愛知県は当初「(問題となっている土地から)環境基準を上回る有害物質は見つからなかった」としていたのですが、小牧市や都市再生機構の調査では、環境基準を上回る有害物質が見つかっていたからです。
その後に行なわれた愛知県の調査では、有害物質が見つかっています。更にこの調査結果では、問題のある土壌がニュータウン内の学校グラウンド地下に埋設されている事も解かっています。そのため今度は「なぜ最初の調査で見つからなかったのか?」、「どうして学校地下に埋設されている事が解かったのか?」と言う疑問が残ります。
果たして、今回の調査もニュータウン内の土壌汚染の調査も、愛知県は本当にちゃんとした調査を行なったのか、・・・。
あと気になるのが、地下水が流れ込む先の太良池や八田川は、農業用水に利用されています。そして小牧市大草地区は米や桃、ぶどうなどの生産が盛んな地域です。そのため、今回の地下水汚染は農業への影響も十分考えられます。
そのため愛知県は、今後この地下水調査を、継続的にしっかりと行なうべきだと思います。ただ愛知県だけでは調査が不安なので、第三者機関にも調査を依頼した方が良いのではないかとも思います。
*****************************
固定資産税の減免措置(小牧市城山5丁目)
共産党の小牧市委員会が発行している広報誌「民報こまき 07年8月号外」を読んで知ったのですが、地盤沈下と土壌汚染の問題が起こっている桃花台ニュータウンの城山地区での固定資産税の減免が、小牧市議会で決定したそうです。
詳しい適用範囲や減免額などは書かれていなかったので判からないのですが、適用範囲はおそらく問題が起こっている城山5丁目になると思われます。
減免措置の詳細について小牧市役所に問い合わせたところ、先日メールで回答がありました。それによると、対象となるのは、やはり「城山5丁目の地盤沈下の被害を受けている住宅」なのだそうです。
また減免される期間は、「平成15年度(2003年度)〜19年度(2007年度)までの5年間」とのこと。なので、おそらく最近決まった事ではなくずいぶん前に決定したか、あるいは過去に遡って行なわれるようです。
なお減免される額は、それぞれ住宅によって傾き具合などが異なるそうで、それぞれの住宅の傾き具合(都市再生機構が調査)を応じて、土地・家屋を合わせて2割から8割の幅で、行なわれるそうです。
この件の詳細に関し共産党の小牧市委員会に問い合わせたところ、固定資産税減免措置は、今年(2007年)6月の市議会で、市側が実施を表明したものなのだそうです。その後8月に、対象者となった都市再生機構が建設した105戸のうち50戸の家庭に対し、市が個別訪問。それぞれの家庭で説明を行なったそうです。
なお、2008年度以降については、「新しいルールで実施予定」との事。
この件に関する記載が、「小牧市議会だより 2月1日号」に掲載されていました。それによると、固定資産税の減免措置が行なわれたのは、48世帯だったそうです。
また現在、都市再生機構が家屋の再調査を行なっているそうで、その結果被害が新たに確認された世帯に対しても、同様の減免措置を行なうそうです。
*****************************
住民が愛知県に公開質問状を提出 - その2(地盤沈下と土壌汚染問題)
中日新聞の紙面を読んで知ったのですが、7月6日(金)、桃花台ニュータウン住民が愛知県庁に対し、地盤沈下と土壌汚染問題に関する3回目の公開質問状を提出したそうです。
(※7月7日(土)朝刊 24面)
記事によると、「(愛知県が今年初めに行なった土壌調査の結果について)この発表のみで"安全"とされても、納得できない」とした上で、以下のような質問だったそうです。
*****************************
土壌調査結果に関する住民説明会(城山会館、愛知県)
07年4月29日(日)、城山会館で、愛知県庁による城山地区に住む一部の住民を対象とした土壌調査結果の説明会が、行なわれるそうです。
時間:午後1時 から 午後3時
この件に関する問い合わせ先は、愛知県庁 建設部 建築担当局住宅計画課です。
これまで「住民説明会」と称して行なわれてきたものは、いずれも問題となっている地域住民だけとなっています。しかし実際は、光ヶ丘小学校や大城小学校でも、土壌汚染が確認されています。そのため私は、「これらの学校に通っている生徒やその保護者、ならびに学校周辺地域の住民に対しても、説明会を開催すべきだ」と思います。
また、「城山地区以外の場所でも地盤沈下が起こっている」と言う話を、何回か聞いた事があります。土壌汚染に関しては、「実際自分の家の下にも埋まっているのではないか」と心配している人もいることでしょう。
なので私は、「愛知県は、一部地域住民を対象とした説明会だけでなく、桃花台ニュータウン住民全員を対象とした説明会を開催するべきだ」とも思います。
この説明会に関する記事が、中日新聞の紙面に掲載されていました。
(4月30日(月)朝刊 15面)
記事によると、出席したのは、愛知県側が県庁住宅計画課などの担当者9人、住民側が70人だったそうです。そして事前に戸別に配布された調査結果を、あらためて説明したそうです。
会では「県側がこれまでと同じ主張を繰り返し、住民側とが厳しく追及する」と言ったやりとりが、また行なわれたようです。それと相変わらず、県側は、産業廃棄物を「黒っぽい土」と表現し、住民側ともめたようです。
あと、記事の最後には城山区長の談話として、「疑惑のある土地は県の責任で撤去すべきであり、地域でまとまって裁判に訴えることも考えねばならない」と言う発言が、掲載されていました。
*****************************
壌調査の結果公表 - その3(愛知県)
4月12日(木)、愛知県が、小学校グランドと地盤沈下が問題となっている地域の土壌調査の結果を、公表したそうです。
それによると、今回の調査結果は以下のようなものでした。
調査期間:
2006年12月〜2007年3月
調査対象地域:
例.地域および施設名(調:、黒:、環:)
・調・・・調査対象地域および施設での全調査地点数
・黒・・・調査地点のうち、黒い土が見つかった場所
・環・・・調査地点のうち、環境基準を上回る物質が見つかった場所
・光ヶ丘小学校(調:14、黒:14、環:5)
・光ヶ丘中学校(調:14、黒:4、環:0)
・大城小学校(調:13、黒:4、環:2)
・タウン城山(調:55、黒:21、環:7)
・グリーンテラス城山(調:41、黒:2、環:0)
調査結果:
・全ての調査地域で、黒い土を確認。
・黒い土が見つかった全ての地点で、油分を確認。
・全ての調査地域で、環境基準を超えるダイオキシンは検出されず。
・光ヶ丘中学校とグリーンテラス城山では、環境基準を超える物質は検出されず。
・光ヶ丘小学校と大城小学校では、調査した全27地点のうち7地点から、環境基準の〜2.2倍の鉛が検出。
・タウン城山では、調査した55地点のうち7地点から、環境基準の〜6.9倍の鉛、1.2倍の総水銀、1.5倍のヒ素が検出。
・環境基準を超えた物質が見つかった場所では、黒い土の上に〜2.5メートルの土がある。
この調査結果に対し、愛知県は、環境基準を上回る物質が見つかった場所は土で覆われており、なおかつ地下水を飲料水として利用していないことから、住民に対し「人体への健康への影響はない」と言っているそうです。
また検出された理由は判からないけれど、造成当時は黒い土に匂いも油膜もなく、「造成は適切だった」として、あらためて自らの責任を否定したそうです。
あと今後ですが、「念のため、周辺地域で地下水調査を行うことを検討する」そうです。
*****************************
土壌調査の結果公表 - その2(都市再生機構)
「中日新聞」の紙面と「メ〜テレニュース」の記事を読んで知ったのですが、06年11月26日(日)に「都市再生機構」が、地盤沈下が問題となっている地域住民を対象とした説明会を開き、これまで判かった調査結果を公表したそうです。
(11月27日(月)朝刊 29面)
これら記事によると、調査結果は下記のようなものだったそうです。
・地盤沈下が問題となっている地域の土壌から、「産業廃棄物」の残存が、科学的に確認された。
・産業廃棄物が含まれる土壌から、基準値の170倍の「鉛」を含む5種類の有害物質が検出された。また油分や木片、ガラス片、ビニール袋、繊維のようなもの、地下水ではない「たまり水」なども確認された。
・地盤沈下の原因は、産業廃棄物層とその上部にある覆土層がそれぞれ沈下した事が原因である。「愛知県」が行なった造成工事の際、土を固める作業が不十分な地盤があり、その為覆土層に雨水が浸透し、覆土層が沈下した。その結果産業廃棄物層にかかる荷重が増え、産業廃棄物層も沈下した。
・今後覆土層が沈下する可能性は非常に低く、産業廃棄物層の沈下もほぼ終了している為、今後沈下はほとんど発生しない。
また都市再生機構は今後の対策として、「一軒ごとの建物の傾きを調べ、場合によっては、ジャッキアップ工法で建物や外構の修復工事をする」としたそうです。また修復工事の開始時期については、「愛知県の調査結果と見解の発表後」としたそうです。
これに対し住民側からは、「産廃が残っている以上、いくら宅地地盤の強度があると言っても、対策は不十分」として、「産業排気武具の完全撤去」を求める意見が相次いだそうです。いっぽう都市再生機構はこの点について、「愛知県の調査結果を待ってから検討する」としたそうです。
*****************************
有害物質を含む土壌が埋設された可能性のある学校(大城小学校、光ヶ丘小・中学校)
愛知県による地盤沈下に関する住民説明会で明らかになった、城山5丁目の土壌(小牧市の調査で、環境基準を大きく上回る有害物質が発見された)が造成時に桃花台ニュータウン内の3つの学校グランドに運び込まれた問題について、どの学校なのか「愛知県庁」に問い合わせたところ、グラウンドに運び込まれた学校は、以下の3校なのだそうです。
・大城小学校
・光ヶ丘小学校
・光ヶ丘中学校
なお今のところ、「グラウンドのどの辺りに、どの程度の規模で埋められたのか」と言う点については、まだ判かっていないそうです。その為、この点も含めて今後の調査で明らかにしていくそうです。
*****************************
知県知事、情報開示を明言(地盤沈下と土壌汚染問題)
11月20日(月)の定例記者会見で、神田真秋 愛知県知事が、土壌調査の際に採取する、「地盤沈下」の原因と関係する「地耐力」に関する情報を、住民に開示する事を明言したそうです。
*****************************
地盤沈下に関する住民説明会 - その2(小牧勤労センター、愛知県)
11月19日(日)、「小牧勤労会館(小牧勤労センター)」で、地盤沈下が問題となっている城山5丁目の住民を対象とした、「愛知県庁」による説明会が行なわれたそうです。
新しい情報としては、以下の通りです。
・有害物質を含む土壌を含む造成の際に出た残土を、ニュータウン内の小中学校の内の3校のグランドに埋めた。
・土を運び込んだ小中学校のグランドも、調査範囲に含む。
・今後行なわれる調査は、「地盤沈下」の原因究明とは関係無く、あくまで環境基準の観点から、有害物質の範囲を特定するために行なう。
・新たに始める調査は年内に開始し、来年(2007年)の3月までに結果をまとめる予定。
ちなみに、この件に関する記事は、「中日新聞」の紙面にも掲載されています。
(※11月20日(月)朝刊 14面)
今回の説明会について、私は「やる予定だ」と言う情報は知っていましたが、いつどこでやるのかはまったく知りませんでした。正直その点から、少し違和感を憶えます。実際地盤沈下が起こっている地域や場所は、「桃花台ニュータウン」の一部の地域に過ぎません。しかしニュースなどで「桃花台ニュータウンで地盤沈下が・・・」と報じられている以上、ニュータウン住民全体の問題だとも言えます。その点を考えても、「住民全体に対して説明会を行なうべきだ」と思います。
また今回の説明会では、「産業廃棄物を含む土が、問題となっている地域以外の学校のグランドに運びこまれていた」ことが、判明しました。記事では単に「運び込まれた」とありますが、県が「ボーリング調査を行なう」としている点から考えると、おそらく「そのまま埋設されているのでは、・・・」と思われます。
これは問題となっている地域が拡大した事を意味し、この点からもただ単に一部の地域の問題ではなく、ニュータウン全体の問題だと思います。なので私は、「近い時期に、ニュータウン住民全体を対象とした説明会を行なうべきだ」と思います。
この説明会の告知ページを、見つけました。
・桃花台城山地区住民説明会について(愛知県庁 建設部住宅計画課)
このページによると、この説明会の対象となったのは、タウン城山(地区名)とグリーンテラス城山(地区名)に住んでいる人たちだったようです。
*****************************
愛知県独自のボーリング調査、年内開始へ(地盤沈下と土壌汚染問題)
「桃花台ニュータウン」における地盤沈下問題で、「愛知県」は、年内にも県独自のボーリング調査を開始するそうです。
調査内容は下記の通りです。
・地盤沈下地点を中心にして同心円状に住宅を1軒ずつ行なう。
・この調査によって、有害物質が含まれる土壌の範囲を特定する。
※旧「住宅・都市整備公団」(現『都市再生機構』)以外が販売した土地に関しても、調査を行なう。
記事にある「地盤沈下地点」とは、地盤沈下が発覚し住宅が解体され、今年(2006年)の夏に都市再生機構によって土壌調査が行なわれた地点に、ほぼ間違いないと思われます。
・愛知県知事が、県独自の調査を明言(地盤沈下問題)(桃花台新聞)
追記(11月19日)
上記のインターネット版と同じ内容の記事が、中日新聞の紙面の方にも、掲載されていました。
(※11月18日(土)朝刊 32面)
追記(11月22日)
この件に関する記事を、新たに見つけました。
新しい情報としては、下記の通りです。
・行なわれる調査は、あくまで地盤沈下の調査ではなく有害物質を含む土壌の範囲を特定するために行なう。
・有害物質を含む土壌を含んだ造成中の残土を、ニュータウン内の3校の小中学校のグランドに埋めた。その為そのグランドも、調査範囲に加わる(調査範囲の拡大)。
・調査結果は、来年(2007年)3月までにまとめる予定。
*****************************
桃花台ニュータウンの地盤沈下問題について
【記者】
小牧の桃花台ニュータウンの地盤沈下の件ですが、先日、県で分析した結果が出て、その中で、基準値が以上か以下かということは別にして、化学物質が出てきている。この件については、都市再生機構が県を提訴し、その主張の中で県が造成をちゃんとやってなかったのではないかと言っておられるようですが、化学物質が出てきたことは、都市再生機構の主張を裏付けるようなことではないかと思うのですが、あのような結果なり、化学物質が存在したということについて、どのようにお考えですか。また、今後、改めて県として調査をするつもりがあるのか、併せてお伺いします。
【知事】
この前の現地での調査のサンプルで、調査、解析を進めて、一部の物質が少し基準値をオーバーしていたということはご指摘のとおりです。特に、深刻なものではありませんけれども、一部の物質でオーバーしていたことは事実であります。したがって、そういう事実が出た以上は、もう少しきちんとした調査を実施しようということでおります。そういう基本的な考え方でおります。
そのことと、県が売り主になり都市再生機構の方へ売った法的な責任とは、直接はつながらないと思っております。
いずれにしても、これは訴訟を起こされておりますので、そういうことも含めて、今、弁護士の方に対応をお願いをしておりますけれども、その契約の問題とは別の問題だろうと、今のところ我々は考えております。
ただ、いずれにしても、そのような物質があったことは事実でありますから、地域の皆さん方に、いろいろ不安を持たれたり、心配が拡大することがあってはいけませんので、これから、より厳密に調査をするという方針でおります。
http://www.pref.aichi.jp/koho/kaiken/2006/11.06.html#6
*****************************
土壌調査の結果公表(愛知県、小牧市)
10月26日(木)、「愛知県」と「小牧市」は、それぞれが行なった地盤沈下で解体された土地の下から採取した土壌の調査結果を、公表したそうです。
・土壌調査:愛知県造成の住宅団地からヒ素検出(毎日新聞)
記事によると、調査結果は下記のようなものだったようです。
< 愛知県 >
・「環境基準」を上回る有害物質は、検出されなかった。
(※環境基準以下の「ヒ素」と「ジクロロメタン」は、検出されたようです。)
・愛知県側の主張は、「(検出された)原因は不明だが、直ちに健康被害につながる数値ではない。」。
< 小牧市 >
・環境基準を上回る「ヒ素」と「ジクロロメタン」を検出。「ヒ素」が環境基準の3.6倍、「ジクロロメタン」が1.85倍※1 。
・通常の土壌ではほとんど検出されない、油分4.8%を検出。
※1. 記事では「県は・・・公表した」となっているので、愛知県側の調査結果とも取れますが、その後の文章の中に「県の結果は基準以下」と言う所があるので、おそらく小牧市の調査結果だと思われます。たぶん「愛知県側が、小牧市と愛知県の両方の結果を公表した」のだと思います。
*****************************
桃花台の地盤沈下問題をあつかったテレビ番組の特集 - その2(中京テレビ)
8月25日(金)、「中京テレビ」の報道番組「NEWS リアルタイム」で、「桃花台ニュータウン」の地盤沈下問題の特集が、放送されていたようです。番組の公式サイトには、この時放送された特集をまとめたページが、作成されていました。
・記者の目 “沈む住宅街”で何が…?(中京テレビ:「NEWS リアルタイム」)
このまとめページには、実際地盤沈下が起こっている家の状況や、「都市再生機構」が行なっていた土壌調査地点の様子、「愛知県庁 住宅計画課」の課長へのインタビューの様子などが掲載されていました。
愛知県庁 住宅計画課の課長の発言は、正直「ひどいものだ」と思いました。城山5丁目の元地主や当時造成に立ち会った愛知県庁のOBが、「産業廃棄物」の存在を認めているにも関わらず、「あれは天然の土だ」とか「製紙カス(産業廃棄物)なんてなかった」なんて発言しています。
ただ冷静になって読めば、もしこの発言をしたのが事実であれば、愛知県がこれまで行なってきた「自分たち(愛知県)は、それら(産業廃棄物)を取り除いた」とか「住宅都市整備公団(現『都市再生機構』)には、廃棄物に関する資料を渡した」と言う主張が、根底から覆る事になります。なぜなら存在を知らなかったのであれば、土壌を取り除く事はないですし、また資料を渡すはずがないからです。
自から墓穴を掘ったのか、それともこの課長が適当に発言したのかは判かりませんが、愛知県庁の立場がどんどん悪くなっているのは、事実だと思います。
*****************************
愛知県が公開質問状に回答(地盤沈下と土壌汚染問題)10月6日(金)
「愛知県」は、9月15日(金)に住民が愛知県知事に対して提出した「公開質問状」に対し、回答したそうです。
・造成は適切と県強調 桃花台の地盤沈下(中日新聞)
記事によると愛知県側は、
・「造成工事を行った当時から、産業廃棄物処分場跡地との認識はない」
・「造成工事を行った当時はダンプカーなどの重機が作業しても支障のない十分な硬さがあり、軟弱な地盤ではなかったと聞いている」
と回答しているそうです。
ちなみに、この記事は、「中日新聞」の紙面の方にも掲載されていました。
(※10月7日(土)朝刊 20面)
この件に関しては、「県OB職員談」として、以前別の記事で「愛知県は造成時に、廃棄物と見られる粘土が大量に堆積していた事を確認し、除去した」と報じられています。
この事を踏まえると、経緯は以下のようなものになります。
1957年〜1971年
王春工業が、王子製紙の工場から出る「沈殿カス」などを投棄。
↓
1971年
愛知県が土地を購入
↓
1983年〜1985年
土地を造成
・大量の廃棄物を確認 → 除去
・「産業廃棄物処分場 跡地」と認識せず。
・造成工事中は、問題なかった。
↓
旧「住宅・都市整備公団」(現『都市再生機構』)に売却
< 売却時の廃棄物に関する認識について >
愛知県側の主張:
造成された土地の売買の際に、「大量の廃棄物が捨てられていた事」に関する資料※ のやりとりがあったはず。
都市再生機構側の主張:
愛知県から、「大量の廃棄物が持ち込まれた場所だった」とは聞いていない。
※資料は、現在残っていないそうです。
最後に、今回の愛知県の回答についての感想を、書こうと思います。
「不思議だな」と思ったのが、愛知県が大量の廃棄物を確認しておきながら、産業廃棄物処分場跡地だと認識しなかった点。この点、うがった見方をすれば、「産業廃棄物処分場跡地と認識しなかったから公団に報告しなかったのでは・・・」なんて思います。
ただ「売買の際の資料が現存していない」と言う事らしいので、この点を証明する事は非常に難しいのですが・・・。
あと気になるのが、「造成工事中は、問題なかった」と言う点。私は「地盤沈下」に関して詳しくないのですが、工事の最中に様々な機材や車両が問題の地盤の上に置かれたり通ったりしたと思うのですが、「そういった事と住宅が何年も建っている事との間に、どれくらい差があるのか?」と言う事が気になりました。「素人考え」だと、「『住宅』と言う重たい『物体』が、何年にも渡って地盤を押し続ける力」と、「一時的に機材や車両が押し続ける力」には、大きな差があると思うのですが・・・。
*****************************
桃花台の地盤沈下問題をあつかったテレビ番組の特集(TBS)
「桃花台ニュータウンで、地盤沈下!?」のコメントを読んで知ったのですが、9月17日(日)、「TBS」のテレビ番組「噂の東京マガジン」で、「桃花台ニュータウン」の「地盤沈下」問題が、取り上げられたそうです。 (^^)/ )
それと、番組の公式サイトには、都市再生機構が土壌調査していた地点のレポート記事が、掲載されていました。
・住民激怒!地盤沈下で消えた住宅(TBS:噂の東京マガジン)
*****************************
*****************************
2009年11月23日
小鳥が丘団地救済協議会のブログ転載
小鳥が丘団地救済協議会のブログ

ATCグリーンエコプラザで講演した桃花台や小鳥が丘の住民達

大阪市大の畑明郎先生と環境カウンセラーの藤原きよみさん
******************************
2009年10月23日(金)
小鳥が丘住宅団地土壌汚染第13回裁判
2009年10月20日(火)16時から岡山地方裁判所353号法廷で第13回口頭弁論準備手続きが行われました。
今回は原告住民3名の陳述書を裁判所に提出しました。
前回ブログ掲載以降の裁判経過ですが、
住民訴訟第一次(3世帯)は環境総合研究所に現地地質調査分析を依頼し2009年6月13日に職員を現地に派遣してもらい住民による調査サンプル採取を行いました。
(モニター井戸水質3か所、原告敷地駐車場土壌1か所、沼川護岸擁護壁付着物1か所、合計5か所)
7月9日に調査分析報告書が送られてきましたが、護岸の付着物もはっきりと油分が検出されていました。いずれも汚染の程度は著しいものとなっていましたので早速、調査報告書は証拠として裁判所に提出しました。
裁判長は冒頭、住民訴訟第二次(18世帯)は、現在、(不動産)鑑定準備中ですと述べた後、
(裁判長)
こちら(住民訴訟第一次3世帯)は、今までの準備資料で結審に向かっていいですね。
瑕疵担保責任・不法行為で争うのですね。
当該物件は原告3名共、被告から取得したものですか?
第二次(18世帯)には時効の問題がある人がいますが、こちらは時効の問題はありませんね。
(原告代理人河田弁護士)
先日提出した各原告の陳述書で全てです。
原告2名は土地建物すべて新築物件として被告から取得したものですが、原告1名だけは、被告の仲介で、中古物件として取得していますので瑕疵担保責任ではなく不法行為で争います。
時効の問題は原告3名共ありません。
(裁判長)
では次回は原告本人尋問を、一人30分程度行い、被告反対尋問を予定します。
午前中では時間が足らないことがあるので午後の時間帯に行います。
以上のような質疑応答があり、日程調整の結果、次回は12月8日(火)13時30分〜16時30分に決まりました。
住民訴訟第二次(18世帯)は、前回原告住民が土壌改良の為の土壌調査を求めて学者の土壌調査方法等の資料を提出しましたが、調査費用の見積もりが高額になり(約7千万円)とても負担しきれない事が判明したので、調査範囲を絞り込むなどして再度調査方法を検討し費用7百万円を見積もり、原告住民と被告両備ホールディングスで折半負担を提案しました。
裁判所も被告両備に鑑定費用を半分持てという勧告を出しましたが両備側は固辞したようです。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後5年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス?の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯も続いて提訴し係争中です。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
******************************
2009年4月15日(水)
環境委員会で小鳥が丘土壌汚染問題!
参議院環境委員会2009年4月14日で「岡山市小鳥が丘団地土壌汚染問題」が取り上げられました。
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」に関する参考人の意見聴取で、川田龍平議員の質問に参考人の畑 明朗氏(大阪市立大学大学院特任教授、日本環境学会会長)が答えました。
映像は参議院ホームページ
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/consider.php
「カレンダー」から「2009年4月14日」を選び
「環境委員会」を選び
「動画形式」から再生し
(02:35:10)時間中
(02:26:10)から(02:29:33)の部分です。
質問要旨は、川田龍平議員ホームページ
http://ryuheikawada.seesaa.net/article/117456885.html
2009年4月14日です。
******************************
2008年12月28日(日)
不思議なテレビ放映中止報道ステーション!その1
2007年1月の事、テレビ朝日報道番組「報道ステーション」から取材の申し込みが来ました。
他の環境汚染現場の取材中に「岡山市小鳥が丘団地」土壌汚染の情報を聞いたとのことでした。
承諾すると、ディレクターが下見として視察し2007年2月1日10時頃から翌日2月2日の2日間に渡り住民聞き取り調査・現場撮影・地層掘削段取り等行いました。
正式な取材日程は決まり次第連絡するとのことでした。
数日後、連絡があり、スケジュール表が送られてきて数日にわたり取材が行われました。
住民へのインタビュー、学者による地質調査、20年前の汚染発生時を知る人の聞き取り調査等、学者、ニュースキャスターや最大2組のマイクとカメラマンを動員しての大がかりな取材でした。
土壌汚染改良方法については異なる意見がある住民も、何とかしなくてはという気持ちは同じで、ほとんどの住民が取材に協力しました。
小鳥が丘団地の取材を終え、テレビディレクターはニュース公平性のため次週は宅地造成販売した両備バス?を取材するとのことでした。
しかし2〜3日後、両備バス?を取材しているはずなのに、テレビディレクターから放映を延期すると連絡が入りました。
理由は土壌汚染に対する住民の意見がまとまっていないからだということでしたが納得がいきませんでした。
次回「報道ステーション」から送られてきた取材スケジュール表を掲載します。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20081228
不思議なテレビ放映中止報道ステーション!その2
2007年2月、テレビ朝日報道番組「報道ステーション」取材内容を掲載します。
(報道ステーションディレクターから小鳥が丘団地救済協議会に送られてきたスケジュール表です)
「小鳥が丘団地・地質汚染」撮影スケジュール
2月9日(金曜日)
○○(報道ステーションディレクター氏名)・岡山入り。
12日に重機を入れる△△△△(会社名)の○○氏が岩野宅下見。
13時 岩野氏と取材打ち合わせ。
夕方○○氏(取材を受ける別の住民)と取材打ち合わせ。
2月10日(土曜日)
旭油化元関係者、当時の様子を知る周辺住民に聞き取り取材。
2月11日(日曜日)
夕方、長野智子(ながの・ともこ)キャスター 楡井久先生、 岡山前のり。
17時ごろから、岩野氏宅 ・ ○○氏宅
現在の状況、健康被害などを長野智子キャスターが聞き取り取材。
2月12日(月曜日・祝日)
8時過ぎめど
地表のガス噴出検査。
午後から岩野宅、庭を掘り起こし
NPO「日本地質汚染審査機構」 楡井久(にれい・ひさし)先生の立会いで検査を行います。
長野智子キャスターも立会い。
不思議なテレビ放映中止報道ステーション!その3
前回掲載の、テレビ朝日報道番組「報道ステーション」取材スケジュール表に記載された地質調査で、庭を掘削中、あたりに悪臭が漂い、「クサイ」を通り越して鼻が痛くなる程の刺激臭で、その場に居られなくて逃げ出すほどでした。
汚染調査を行っていた地質学者の楡井教授にインタビューしていたニュースキャスターの長野智子氏は、あまりの悪臭に「マスクを買ってきて!」と、その場にシャガミ込みました。
その場にいた人は誰でも尋常な臭気ではないと認識したはずです。
掘削用敷地の提供、インタビューの応答、情報提供、20年前の汚染発生時の証人取材の道案内等、取材には住民も全面的に協力しました。
それでもテレビ放映中断となったのです。放映の中断はテレビ局の都合としても、地質調査分析の結果報告を要望しましたが、それも断られました。
複数の住民が放映希望の連絡を入れましたが、そのうち連絡が取れなくなりました。テレビ局が多額の費用をかけて取材したものを何故途中で中断したのか、今でも疑念が晴れません。
結
******************************
2008年11月20日(木)
小鳥が丘土壌汚染第9回裁判!その1
2008年11月17(月)13時30分から岡山地方裁判所で第9回口頭弁論準備手続きが行われました。
裁判所は詳細な土壌汚染実態を把握したい意向ですが多額の費用を要する土壌調査を原告住民に求めても非現実的である事は承知しているようです。
裁判長は、午前中に行われた18世帯住民の口頭弁論で原告住民から、土壌改良の為に学者の土壌調査方法等の資料、が提出され、被告両備ホールディングスにも応分の費用負担を求めたが、被告側から拒否されたとの事でした。
住民3世帯の原告代理人弁護士は、「小鳥が丘団地」が土壌汚染である事は今までの資料でも、また裁判所現地検証でも明らかであり、こちらの原告住民は立証提出資料の通り自費で自宅の土壌調査をし、汚染物質が検出されている、住宅地としてその目的を達することのできない欠陥住宅地である、住宅地として問題ないと言うならそれを立証すべきと答弁した。
今回は住民18世帯が求めている土壌調査の推移を待つ事になった。
被告両備ホールディングスは原告立証の原則により被告側は何もする気は無い趣旨の答弁があった。
小鳥が丘土壌汚染第9回裁判!その2
2008年11月17(月)13時30分から行われた第9回裁判に原告側(3世帯住民)が提出した準備書面を掲載します。
平成19年(ワ)第1352号損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
準 備 書 面
平成20年11月17日
岡山地方裁判所 第1民事部 御中
原告代理人弁護士 河 田 英 正
第1,被告の故意、過失について
1,原告等の居住する団地は、被告会社が宅地造成し原告等に販売した(争いのない事実)。
2,本件土地は被告会社が、旭油化工業株式会社から購入したものである(争いのない事実)。
3,本件土地を被告会社が購入して宅地造成することになったのは、当時、旭油化株式会社が既にその工場内に大量の汚泥や産業廃棄物を放置し、周辺に悪臭を漂わせ、河川には死魚が浮かぶなどの公害が発生していて、社会問題になっていたことにある(甲1号証の1,2,甲10号証の1ないし7)。旭油化株式会社は廃油貯蔵タンクの底から直接土中に油分を吸収させるなど無謀な処理をしていて、敷地内はこの油泥で汚染されていた。油泥の一部は、産業不法投棄事件で有名になった豊島にも運ばれるなど不法な処理がなされていた。
4,昭和57年7月27日に岡山簡易裁判所において、隣接する土地を小鳥の森団地として販売していた被告会社と旭油化株式会社はこの悪臭などの公害問題に関し和解を成立させ(甲3号証)、実質的には、この汚泥等の処理費用を全額被告会社が負担して、旭油化工業は本件土地を明け渡し、被告会社がこの土地を取得した。
この時点で被告会社は、旭油化株式会社が、これら汚泥などを自力で撤去することは不可能であることを前提で和解を成立させている。つまり、被告会社が同社の工場等の撤去費用は、被告会社が負担し、旭油化に支払うが、約束が守られなければ損害賠償金として支払った撤去費用以上の金額の損害金を請求できるとしていた。このとき、被告会社は、油泥が土中に浸透し、汚染が工場跡地の土中に拡大していた本件土地の汚染の実態は十分に認識があった。
なお、本件土地から立ち退いた旭油化工業株式会社は別会社を設立し、赤磐郡吉井町草生地区で新たに操業を始めたが、同様の不法な処理を繰り返したため、直ちに悪臭などの公害問題を地域周辺に発生させ、その地区から退去せざるを得なくなっていた(甲7号証)。
(第1,被告の故意、過失について)
5,このような激しい汚染の実態があったにも関わらず、ごく一部の土壌を搬出除去し、表層土に生石灰を混入させて中和凝固させただけの簡便な対策にとどめたままで宅地造成し、原告等に販売した。
この対策が十分でなかったことは、現在生じている汚染の実態からも明白である。土中に浸透していた油泥が拡散し、覆土したはずの表層土にまでその汚染がでてきたため、宅地を掘ればすぐに油分を含んだ黒く変色した土壌が露出してきている(甲15号証)。
当時の汚染の実態からみると、事前に十分な汚染の実態を調査し、この宅地の油泥となって地中に浸透した土壌の成分をしっかりと把握して、その危険な成分を含む土壌を完全に搬出除去すべきであったにも関わらず、簡単に覆土をして一見なんら問題のない住宅地として仮装して販売した。
これらの事実を知らない原告らに汚染の実態についてなんら説明しないまま、四六時中生活し生涯の住居として住み続けなければならない住宅地として販売し、原告等は自然豊かな環境に恵まれた被告会社の販売する優良な住宅地であると誤信して購入した。
被告会社は、十分なる有害物質除去が行われなければ、住宅地としての安全が害されることになる現在の状況は認識すべきであり、被告会社の過失の存在は従前から述べているとおり明らかである。
また、土壌汚染の被害が出ないと軽信していたのであれば、前記のような経過をたどって販売された住宅地なのだから、販売後もその汚染が広がらないように常に監視し、その汚染が顕在化すれば、ただちにその汚染の経緯を原告等購入者に説明し、汚染が拡大しないよう汚染除去などをする義務があるというべきである。
第2,証拠上明らかとなっている汚染の実態
1,株式会社ニッテクリサーチが平成19年4月に実施した『調査結果報告書(土壌汚染状況調査業務)』(甲4号証の1,2)から少なくとも以下のことが明らかにされている。
?表層土壌ガス調査の結果、全ての調査位置においてベンゼンが検出され、土壌中からベンゼンが揮発している。
?土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素などが土壌溶出基準を超えており、土壌がこれらの有害物質で汚染されている。
?土壌調査の結果、土壌含有量基準を満足しているが、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素などの有害物質が検出されている。
?したがって小鳥が丘団地の土壌はベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素などの有害物質で汚染されていると言える。
(第2,証拠上明らかとなっている汚染の実態)
2,乙第5〜18号証について
?岡山市役所環境規制課実施の『地下水・土壌分析結果』2004年7月(乙第5・6号証)によれば、○○宅付近の地下水からヒ素が環境基準の15倍、ベンゼンが31倍検出され、土壌からヒ素、ふっ素、ほう素が環境基準以下ながら検出された。
?株式会社三友土質エンジニアリングの『南古都概況調査分析結果』2004年9月(乙第7号証)によれば、3箇所のボーリング調査(深さ1〜5m)でヒ素が土壌溶出基準の1.7〜3.2倍、ベンゼンが0.5〜26倍、トリクロロエチレンが約27倍、シス-1・2-ジクロロエチレンが約6倍検出された。また、油分が1.3〜1.9重量%検出され、油で汚染されている。
?同『南古都表層土壌調査分析結果について』2004年10月(乙第10号証)によれば、ベンゼンが34箇所中8箇所で土壌溶出基準を超え、最高11倍検出された。トリクロロエチレンは1箇所、シス-1・2-ジクロロエチレンは2箇所、ヒ素は5箇所が基準を超え、最高3倍程度だった。
?財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内ガス調査業務』2004年12月(乙第14号証)によれば、表層土壌ガス調査ですべての地点でベンゼンが検知されたほか、特定の地点でジクロロメタン、シス-1・2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、などが検出され、土壌からベンゼンなどの揮発性物質(VOC)が揮発している。
硫化水素に加えてメタンがすべての地点で比較的高濃度(3.2〜68%)で検出されたことから、地層内では有機物の嫌気制分解が相当程度進行しており、硫化水素の毒性や、メタンが引火・爆発する危険性がある。
環境大気調査では、大気環境基準以下であるが、ベンゼン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの揮発性物質が検出されており、環境大気が汚染されている。
?応用地質?の『電気探査結果』2004年12月(乙第15号証)によれば、全体に低比抵抗であり、1%以上の油分によるとしている。とくに、タンク跡は油の漏洩を示している。
?財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)』2005年3月(乙第18号証)によれば、ヘキサン抽出物質量(油分)が0.1〜10%検出され、含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。つまり、油分、水分、塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。
?旭油化は、廃油の処理を貯蔵タンクから直接、工場敷地に投入していた事実があったと原告は主張しているが、電気探査の結果(甲15号証)からもタンク跡は油の漏洩があること、タンク跡にタテ型の低比抵抗ゾーンは上に尖った形状を呈するものがあるなどそのことが推認される結果となっている。
(第2,証拠上明らかとなっている汚染の実態)
3,甲15号証 平成20年5月30日に行われた現地での検証の様子を記録したものである。本件団地のどこを掘っても、表層土が黒くなっていて、深く掘るに従ってその汚染度が激しくなっていて、異臭が漂うことが確認された。汚染は、本件団地全体に広がっていることが明らかとなっている。
(第2,証拠上明らかとなっている汚染の実態)
4,被告調査による判断の問題点
?南古都?環境対策委員会の『表層土壌調査(10/4〜6)に対する意見書』(乙第9号証)は、
「地域の一部の表層土壌から検出された物質は、以前敷地内に立地していた旭油化の機械洗浄の溶剤である可能性が高い。」
とするが、機械洗浄の溶剤とする根拠はない。
また、
「一部の検体に基準値を超えるものがあるが、非常に高濃度ということではないこと、かつ34検体中8点と全体に拡散していないこと、土中にあること、周辺の地下水の汚染がないこと等を勘案すれば、日常生活上今すぐ重大な問題になるとは考えにくい。」
とするが、
「基準値を超える汚染土壌が約4分の1に存在すること、団地内の地下水汚染が存在すること、周辺の地下水汚染は充分調査されていないこと、ベンゼン、トリクロロエチレンなどの揮発性物質は、日常的に揮発し、人体に発ガンなどの悪影響があること」
から、将来、健康影響が出る可能性は否定できない。
?南古都?環境対策委員会の『2004年11月2日付の小鳥が丘環境対策委員会に対する回答書』(乙第13号証)は、
「これらの基準は、動物実験や工場での作業労働者が化学物質に暴露されて健康影響が出る値に安全率(通常数十倍や数千倍の単位)値を掛けて策定されているので、基準値を超えたからといってすぐに健康影響(急性中毒症状や発ガン)が出るものでない。・・・住宅の下にある土壌から健康影響が出る可能性は低いと考えられる」
とするが、ベンゼンなどの発ガン物質の環境基準値は、10万人に一人が発ガンすること、そもそも環境基準は急性中毒でなく慢性中毒を起こすレベルとして設定されていること、汚染土壌は住宅の下だけでなく、住宅周辺の庭などに存在し、土ぼこりとして人体に摂取されることなどから、環境基準を超える土壌に接すると長期的に健康に悪影響を与えると考えられる。悪臭のする庭で子供たちが土いじりなどして遊ぶことによる人体への影響は、極めて危険な状態である。
?南古都?環境対策委員会の2004年12月27日付け『意見書』(乙第16号証)は、「汚染源は、汚染原因者である旭油化工業株式会社が設置した(タンク等の)施設から漏洩した汚染物質や、同社が表土を開削して廃棄した汚染物質である可能性が高い。これらの汚染物質が表層土から浸透し、地中に拡散したものと推測される」とし、乙9号証における「機械洗浄の溶剤原因説」を自ら否定する結果となっている。
?南古都?環境対策委員会の2005年3月28日付『意見書』(乙第17号証)は、「現状の生活環境においては異臭による不快感はあるものの、健康への影響が直ちに懸念されるものではない」とするが、「汚染土壌から日常的に揮発するベンゼン、トリクロロエチレンなどの発ガン物質、急性毒性のある硫化水素が発生、引火性や爆発の危険性のあるメタンの高濃度発生」などを考慮すると、異臭による不快感だけでなく、長期的な健康への悪影響が懸念される。
?岡山市環境規制課実施の『古都地区周辺環境調査一覧表』(乙第20号証)は、「井戸の深さが不明であること、地下水脈の調査がされていないこと」などから、地下水汚染調査としては不十分であり、これをもって「周辺の地下水汚染がない」と結論できない。
結
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20081120
******************************
小鳥が丘住宅団地土壌汚染第7回裁判
2008年7月9日(水)15時から岡山地方裁判所353号法廷で第7回口頭弁論準備手続きが行われました。
2008年5月30日に行われた裁判所現地視察で、住民が5箇所の宅地を掘削し、いずれの箇所も油分で汚染された真っ黒い地層と刺激臭のある油系の悪臭が、浅い地層から確認されました。
この事でも明らかなように住宅地としてはその目的を達することのできない欠陥住宅地であるとの準備書面と5月30日現地視察の録画DVDを裁判所に提出しました。
裁判所としては複数の公平な学者の意見を参考にしたいので、その前提として被告両備ホールディングス株式会社が主張し証拠資料とした「意見書」を答申した、両備バス?設立の「南古都?環境対策検討委員会」、の会議録原本を提出することを打診しています。
被告両備ホールディングス株式会社は、会議録は持っていないし提出すべき文書ではないと拒否しています。
そのため裁判所で提出命令ができる文書か検討し8月8日までに決定するとの事。(要件該当文書であれば8月9日に裁判所が文書提出命令を出します)
「南古都?環境対策検討委員会」
住民不在の両備バス?私設委員会
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/sisetsuiinkai01.html
もう一件の住民18世帯の裁判と同期進行したいので、次回の第8回口頭弁論準備手続きは2008年9月29日(月)に決まりました。
******************************
裁判所による小鳥が丘団地土壌汚染現場検証
2008年5月30日13時30分から裁判所による「小鳥が丘団地」土壌汚染現場検証が行われました。
裁判官、原告住民および弁護士や学者、被告弁護士が、多くのマスコミや関係者の見守るなか、小鳥が丘団地内を見て回りました。
各家庭の庭や駐車場を住民が削岩機で3箇所、ユンボで2箇所を掘削しましたが、どこの庭や駐車場も少し掘れば真黒い土と頭が痛くなるような刺激臭がありました。
油にまみれた土壌が目詰まりした時のように雨水や地下水の浸透を妨げているようでした。
あと地盤沈下で下がった塀や、油や石灰と思われる液体が滲み出ている擁癖や、玄関前側溝から可燃性ガス(2005年11月に地元消防署が確認)の泡が吹き出している箇所を住民が説明し15時30分頃終了しました。
******************************
川田龍平議員が環境委員会で質問
参議院環境委員会「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」審議で川田龍平議員の質問に「小鳥が丘団地土壌汚染問題」が取り上げられていましたので転載します。
http://ryuheikawada.seesaa.net/article/97567775.html#more
2008年5月22日(木)
テーマ:「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」
0 改正案について・・・・・・・
実際に、全国でこうした類似ケースや土壌汚染による紛争も多発しており、土壌汚染対策法の改正が求められていることは確かです。静岡県沼津市のJR高架化にともなう駅周辺事業の区画整理事業でもJR用地の鉛汚染や愛知県小牧市や千葉県八千代市の都市再生機構開発の住宅開発に伴う重金属土壌汚染、岡山市も小鳥が丘でのトリクロロエチレン汚染など、新聞を見ていても数多くの事件が報道されています。
1 岡山市トリクロロエチレン
岡山市の小鳥が丘団地のケースのような、過去の売買後住宅が建設され20年経過後に水道工事の際に、石鹸会社のトリクロロエチレンの土壌汚染が明らかとなり、訴訟に至っているケースがあります。こうしたケースは現行法での対応と改正法ではどのような対応となるのか?・・・・・・・
映像は参議院ホームページ
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/consider.php
「カレンダー」から「5月22日」を選び
「環境委員会」を選び
「動画形式」から再生し
(02:45:40)時間中
(02:17:08)から(02:25:51)の部分です。
******************************
小牧市桃花台地盤沈下問題でテレビ報道番組
住宅地土壌汚染・地盤沈下問題の同じ被害者として闘っている愛知県小牧市「桃花台城山地区地盤沈下問題を考える会」からテレビ報道されるとの連絡が入りました。
2008年5月25日、日本テレビ報道番組 【バンキシャ!】で桃花台の地盤沈下問題が取り上げられます。地盤沈下問題が起きている地区の一地域としての放映です。
関心のある方は是非、見てください。
愛知県小牧市桃花台「土壌汚染・地盤沈下問題を考える会」代表は小鳥が丘団地に何度か訪問され、小鳥が丘土壌汚染フォーラムに出席・現地報告もしていただきました。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20071102
2008年5月30日に行われる裁判所の小鳥が丘団地現地検証にも立会いされます。
******************************
小鳥が丘団地汚染問題掲載記事2008年5月その7
岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染は、発覚後4年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス?の考えが平行線のままで裁判に発展しています。住民3世帯が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯も続いて提訴し係争中です。小鳥が丘団地土壌汚染公害問題を扱った記事を転載します。
若井たつこ市会議員、岡山市議会にて2008年3月6日個人質問
小鳥が丘団地の土壌汚染に関して、固定資産税の減免措置について
http://wakai-wakai.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_d733.html
個人質問
小鳥が丘団地の土壌汚染に関して、固定資産税の減免をお願いしましたが「規定がないので国の法整備を待って」とにべもない答弁でした。
愛知県の小牧市では減免措置をとってますし、岡山市税条例50条にも当てはまる言葉があります。開発した民間企業と裁判になり、長期化する様相なのに、困っている市民に冷たいですよね。小牧市の減免は2割、小鳥が丘は34軒しかありません。「東京から終の住家と引っ越したのに…」と肩を落とした初老の女性の姿が目に焼き付いています。
******************************
小鳥が丘団地汚染問題掲載記事2008年5月その1
岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染は、発覚後4年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス?の考えが平行線のままで裁判に発展しています。住民3世帯が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯も続いて提訴し係争中です。小鳥が丘団地土壌汚染公害問題を扱った記事を転載します。
環境新聞2008年3月5日
土壌汚染現場の最前線 1 小鳥が丘からの手紙編?
打開の道見えぬまま3年半 汚染原因者不在のまま 住民と開発業者で民訴
土壌汚染対策法が施行されて五年が経過した状況の中、土対法を始めとした関連制度では改善できないケースや土対法が制定された当初想定されなかった問題が各方面で表面化している。土対法の見直しの検討も進められているが、土壌汚染を巡る現場ではどのようなことが起きているのか。
この連載では土壌汚染を巡る様々な課題を現場の取材などを通じて紹介していく。一回目のシリーズでは、汚染原因者不在のまま住民と宅地開発業者の民事訴訟にまで発展してしまった岡山市の「小鳥が丘団地」土壌汚染問題に焦点を当てる。
(2008/03/05)
http://www.kankyo-news.co.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=56&NCODE=293
環境新聞2008年3月12日
土壌汚染現場の最前線 2 小鳥が丘からの手紙編?
原因者不在が混乱の要因 急がれる健康被害と汚染の関係解明
関係者間の温度差が生じている「小鳥が丘団地」土壌汚染問題は、汚染原因者不在が混乱の要因となっている。この土壌汚染がどのように発生したのかとともに、現在の現地で具体的にどのような問題が起きているのかを紹介する。
問題の原因そもそもこの土壌汚染は何なのか。「小鳥が丘団地」の住民らが集めた資料写真には、雑然とした衛生的とは言えない状態の土地が撮影されている。同団地造成前に存在した事業場の写真だ。
両備バス(現・両備ホールディングス)が一九八二年に開発する前、一九七四年に廃棄物処理業の許可を取得した事業者が所有し、この場所で廃油などから石鹸やペンキの原料を製造していたという。こうした事実は開発業者の両備バスも把握しているが、「実際にはどのような行為が行われていたかは分からない」と両備ホールディングスグループの両備不動産担当者は話す。
http://www.kankyo-news.co.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=56&NCODE=298
環境新聞2008年3月19日
土壌汚染現場の最前線 3 小鳥が丘からの手紙編?
健康リスク以外にも波及 現行の制度では解消難しい問題
土壌汚染問題は、汚染地での健康問題とともに地下水などを通じて周辺地域への拡散による健康リスクの問題も抱えるほか、不動産価値など土地に関係する様々な分野にも大きな影響を及ぼす。小鳥が丘団地土壌汚染問題も例外ではなく、現行の制度では解消が難しい様々な問題を抱え、もがいている。
http://www.kankyo-news.co.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=56&NCODE=303
環境新聞 2008年3月26日
土壌汚染現場の最前線 4 小鳥が丘からの手紙編?
救済に至らない土対法の現状 横たわる費用負担問題 揮発系リスクでも提起
市街地土壌汚染問題の解決に向けた法制度には土壌汚染対策法があるが、小鳥が丘団地土壌汚染問題の救済には今のところ至らず、土対法の課題も浮き彫りにしていると言える。個人の土地所有者を考慮した費用負担のあり方や現在基準が設定されていない揮発系の健康リスクなどが浮かび上がる。(2008/03/26)
環境新聞 2008年4月9日
土壌汚染現場の最前線 5 小鳥が丘からの手紙編?
開発業者の認識がポイント 予見困難と請求却下した判例も
小鳥が丘団地を巡る土壌汚染は住民と両備ホールディングス(HD)の民事訴訟に発展し、今月四日には第五回口頭弁論も行われた。裁判の焦点は責任の所在。それを巡り混迷するこの訴訟は、小鳥が丘団地が開発された一九八二年当時、健康被害にまで影響する可能性がある土壌汚染の概念を開発業者が認識できたかどうかがポイントになりそうだ。(名古屋悟)
http://www.kankyo-news.co.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=56&NCODE=324
環境新聞 2008年4月16日
土壌汚染現場の最前線 6 小鳥が丘からの手紙編?
リスコミの重要性と難しさ 土地の将来のあり方 当初から考えに相違
住民、両備ホールディングス(両備HD)双方の話を聞くとその考え方や動きでの温度差が色濃く伝わってくる。「小鳥が丘団地」土壌汚染問題は、明確化されていない責任所在のあり方とともに、リスクコミュニケーションの重要性と難しさも浮き彫りにしている。
******************************
2008年2月18日(月)
岡山地裁で土壌汚染の民事裁判始まる!その1
岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染公害問題は、以前産業廃棄物を工場敷地内に投棄していた公害工場跡地を取得した両備バス株式会社が廃棄物を除去せず宅地造成し、住民に説明せずに販売したのが原因です。
公害工場操業時には地面に大量の廃油を長期間垂れ流し工場敷地内は油泥のような土壌となり隣接する川に油膜が張り死んだ魚が浮くようになって深刻な公害を発生させていました。
その有害物質が撤去されず造成され現在も宅地表層に存在し、そのため土地建物の資産価値は無くなるのみならず住民に健康被害が発生しています。両備バスは抜本的な対策を取ろうとせず住民が2007年8月31日に民事提訴した経緯は、“両備バスを岡山地裁に提訴!”(住民たちのブログ2007年11月20日〜)に記載しましたが、その後の経過です。
2007年11月13日に第1回口頭弁論が岡山地方裁判所において始まりました。
10時15分裁判官3名が着座し、原告側は代理人河田英正弁護士が、被告側は代理人菊池捷男弁護士を含む3名が法廷に立ち、私たちを含む30名弱が傍聴しました。
口頭弁論の様子です。
原告代理人は、予め提出した訴状の通りですと述べました。
(住民たちのブログ2007年11月25日〜 “両備バスを岡山地裁に提訴その6!〜”掲載)
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20071125
++++++++++++++++++++++++++++++
訴状
平成19年8月31日
岡山地方裁判所民事部 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田 英正
同 大本 崇
〒709−0632 岡山市南古都×××
原告 藤原 康 〒709−0632 岡山市南古都×××
原告 ○○○○ 〒709−0611 岡山市楢原×××
原告 ○○○○
〒700−0816 岡山市富田町二丁目7番8号 石橋第3ビル3階
河田英正法律事務所(送達場所)
上記訴訟代理人弁護士 河田 英正
同 大本 崇
電話 086−231−
FAX 086−231−
〒704−8112 岡山市西大寺上1丁目1番50号
被告 両備ホールディングス株式会社
被告代表者代表取締役 小嶋光信
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 227,898,580円
ちょう用印紙額 704,000円
第1 請求の趣旨
1、被告は、原告○○○○に対して58,897,520円、同○○○○に対して58,759,670円、同○○○○に対して110,241,390円とそれぞれこれに対する平成16年9月28日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え
2、訴訟費用は被告の負担とする
3、仮執行宣言
第2 請求の原因
1、当事者
一 被告会社は、昭和11年5月25日に両備バス株式会社として設立され、平成19年4月1日に両備ホールディングス株式会社と商号変更された資本金4億円の株式会社であり、自動車、船舶による旅客、貨物の運送業、観光事業、不動産の所有・売買・賃貸仲介などを業務としている。
二 原告らは、両備バス株式会社が造成した小鳥が丘団地に住居を有し、居住している者である。
2、小鳥が丘団地造成前
一 本件造成地には、廃油等を利用して石鹸を製造していた旭油化工業株式会社の工場があった。
二 同社は、業績不振のなか、昭和49年11月19日に新たに廃棄物処理業の許可を取り阪神、北九州方面の企業から産業廃棄物としての廃油を集めてその処理を始めた。その頃から、廃油処理工場からは廃油処理の黒煙が不気味に立ち上っていた。地域周辺に悪臭がたちこめ、近くを流れる沼川には油膜が張ったり、死んだ魚が浮き上がってくるなどの現象が見られた。廃油を貯蔵していたタンクが設置されていたが、その装置は単に土壌に廃油を吸い込ませる装置であったようであり、タンクの底は直接土壌に接して廃油が不法に処分されていた。そのタンクの位置は土壌への吸収が悪くなると敷地内で場所が移動されていた。そして、工場敷地内には腐敗した油脂を入れたドラム缶が散乱して放置されていて、その腐敗した油脂が敷地内の土地にこびりつき、恒常的に悪臭を発生させていた。
三 両備バス株式会社は、この旭油化工業株式会社の工場北側に既に団地(小鳥の森団地)を造成し、住民が居住していた。その住民からも旭油化株式会社の産業廃棄物処理業を始めたことによる悪臭などの環境悪化の苦情が造成・販売した両備バス株式会社などに苦情が寄せられるようになった。このころ岡山県や岡山市の公害課が何度も行政指導を繰り返していたが、何ら対策が講じられなかった。
3、両備バス株式会社の本件土地の宅地造成
一 両備バス株式会社は、上記のとおり旭油化株式会社が操業している土地の北側に小鳥の森団地(37000平方メートル)を造成・販売していた。この分譲地を購入して居住している住民から、上記のとおり苦情が寄せられるようになり、両備バス株式会社は旭油化株式会社に対して強く改善方を要求していたが、一向に改善されることはなかった。両備バス株式会社の小鳥の森団地の販売が困難な状況となっていた。
(1)旭油化株式会社は昭和57年10月31日限り操業を停止し、同年12月31日までに本件土地上の全ての建物および地下工作物を撤去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
(2)両備バス株式会社は、旭油化株式会社に対して建物撤去費用、移転補償などとして6690万円を支払う。
(3)両備バス株式会社は、旭油化株式会社の工場跡地を一坪あたり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
四 こうして、旭油化株式会社の工場跡地を取得した両備バス株式会社は、このそのままでは宅地造成地には適さない工場跡地を昭和62、3年ごろから3区画に分けて有害物質に汚染されたままで宅地に造成し、平成元年頃から分譲を始めた。
4、宅地から有害物質検出の経緯
一 平成16年7月に岡山市から上水道の鉛製給水管をポリエチレン管に取り替えたいとの連絡があり、7月29日に取り替え工事がなされた。取り替えのため給水管を掘り起こしたところ、油分を多量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥状のなかに水道管が埋められていることが判明した。
そして化学反応の安定性が高いと言われる鉛管の給水管の一部が腐蝕して穴があいている箇所も発見された。岡山市の調査によればこの時の地下水と土壌から硫酸イオンが検出された。
二 両備バス株式会社は、原告ら住民の不安の訴えに対し、土壌汚染の原因を探るべく、土地履歴の調査、ボーリングによる土壌調査などの申し入れがなされ、調査が実施された。同年9月28日原告らに土壌汚染の実態と原因が知らされた。同社の報告によっても、3地点のボーリング調査の結果は、環境基準値の約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、6倍のシスー1,2−ジクロロエチレンが検出された。
また、地下約5メートル付近では金属片やボロ切れなどが発見された。同年12月に実施された電気探査の結果によれば、地盤が不安定で地盤沈下を起こしやすい状況となっていることが判明している。平成19年4月9日、原告岩野方の敷地を、敷地内において検査機関に土壌調査を私的に依頼し実施したところ
(1)表層土壌ガス調査の結果、全ての調査位置においてベンゼンが検出された。
(2)土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が土壌溶出基準を超えていたこと
(3)土壌調査の結果、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が指定基準を超えていたこと等々が明らかとなった。
三 本件団地内においては表層土においてガスが発生して臭気が漂い、土壌の性状が不安定となっていて地盤沈下の畏れがある。その臭気には発ガン性物質であるベンゼンが含まれているなど健康被害が懸念されている。
有害物質を含んだ地盤の安定しない宅地であり、そもそも人が安心して安全に暮らせる団地ではない。地盤からのこのガスの発生で、原告○○方のガス漏れ警報器が作動することもあり、安心して居住できる環境にない。
5、被告会社の責任
一 被告会社は、旭油化株式会社が汚染し続けた土壌はもはや操業をやめさせるしかないほど危険な回復しがたいものであり、そのままでは小鳥の森団地の販売を継続することはできないと認識し、旭油化株式会社の操業中止とその敷地を購入して旭油化を退去させてその問題解決を図った。
そして、その土壌が有害物質で汚染されていることを十分に認識して旭油化株式会社の敷地を買収した。
二 そのような有害で危険な土壌であることを認識しながら宅地として危険物質を残したまま造成し、分譲を続けた。購入者にはこのような危険な土壌であり住宅地として不適なことを秘匿して分譲した。そして、発ガン物質を含むガスが発生して危険な状況になっていても放置したままであった。
三 平成16年7月に、岡山市水道局による水道工事によって、本件団地が有害物質で汚染された危険な造成地であることが表面化しても、直ちに健康に被害をもたらすものではないと抜本的な対策をとろうとしなかった。
6、原告の損害
別紙原告の損害記載のとおり
7、被告会社は、抜本的な無害化工事を実施しなければとうてい造成地としてはならない汚染土壌のある旭油化の工場敷地を、危険な有害物質に汚染された土壌に表層土を盛り土して造成しただけで販売した。さらに、そのように危険な造成地であるから管理を継続し、危険な兆候があれば直ちに対応しなければならないのにこれを怠り、最後までこの事実を隠蔽したまま何らの管理もしないで販売を継続した。
汚染の事実が表面化しても危険はないと断言して、原告らに対して何らの対策をとろうとしなかった。これらその都度の方針は被告会社の方針として取締役会で決定されて実行され、あるいは不作為となったものである。その結果、各原告は6項記載の通りの損害を被った。
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の返書として「両備ホールディングス株式会社は法廷で全面的に争う」との2007年7月28日付け回答書を受けて岡山地方裁判所へ提訴しました。訴状の続きです。
よって、被告は、不法行為を原因とし(民法44条1項、同709条)、各原告に発生した損害の支払いと原告が被告会社の加害行為による被害であると認識した平成16年9月28日から完済に至るまで年5分の割合による金員の支払いを求める。
附属書類
1 訴状副本 1通
2 商業登記現在事項証明書 1通
3 訴訟委任状 3通
<別紙>
原告損害目録
1、原告 ○○○○
宅地購入年月日 平成2年8月30日
居住開始年月日 平成3年5月3日
居住状況
入居当初は、両親、長男の4人で居住していたが、平成9年に長男が県外に就職のため家を出て、平成12年に父が死亡し、平成14年に母が死亡し、以後一人で居住している。
損害額 58,897,520円
内訳
不動産取得費等 28,897,520円
慰謝料 25,000,000円
弁護士費用 5,000,000円
2、原告 ○○○○
宅地購入年月日 平成5年1月30日
居住開始年月日 平成5年3月16日
居住状況
居住当初から現在まで、妻、長男、長女の4人家族で居住している。
損害額 58,759,670円
内訳 不動産取得費等 28,759,670円
慰謝料 25,000,000円
弁護士費用 5,000,000円
慰謝料、その他の損害発生状況は原告○○と同様。平成6年頃から家族がアレルギー性鼻炎にかかるなどの症状がではじめた。原告は庭での作業中に土壌から発生する有害ガスの影響で倒れ、救急車で病院に搬送されたこともある。原因不明のめまい、頭痛に悩まされてきていた。
3、原告 ○○○○
宅地購入年月日 平成2年6月29日
居住開始年月日 平成3年3月末頃
居住状況
広島に居住していたが、環境の良いところで過ごしたいと考え、本件団地を入手して居住を始めた。夫、長男、長女の4人家族であった。居住用とともに本件建物は夫、長女が整骨院を営むためのものでもあった。現在は、夫は平成15年1月に死亡し、長女夫婦が整骨院を営業している。平成11年頃から、娘夫婦らは別に居住するようになっているが、職場は本件住居に変わりはない。業務の性格上、本件土地での業務継続は困難となっている。
損害額 110,241,390円
内訳 不動産取得費等 80,241,390円
慰謝料 20,000,000円
弁護士費用 10,000,000円
慰謝料、その他の損害発生状況は原告○○と同様。長女、孫らは本件住居に居住していた間は、原因不明の頭痛・皮膚炎などに悩まされていた。長女の夫は、原因不明の咳に悩まされている。
<別紙>
事件番号 平成19年(ワ)第 号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
証拠説明書
平成19年8月31日
岡山地方裁判所 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田英正
番号 標目(原本写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 備考
1の1 新聞記事 写し S57.6.4 山陽新聞社 造成前の本件土地の状況
1の2 同上 写し S57.7.28 朝日新聞社 汚染土壌の被告の造成方針
1の3 同上 原本 H16.9.30 山陽新聞社 土壌汚染表面化の経緯
1の4 同上 写し H16.9.30 山陽新聞社 同上
1の5 同上 原本 H16.10.1 朝日新聞社 本件土地から有害物質が検出された事実
1の6 同上 原本 H16.10.5 同上 同上
1の7 同上 原本 H16.10.31 山陽新聞社 同上
1の8 同上 原本 H18.6.8 読売新聞社 土壌汚染による健康被害
1の9 同上 原本 H19.5.30 読売新聞社 同上
2の1 週刊金曜日 原本 H18.9.23 株式会社金曜日 本件土壌の汚染と被害の実態
2の2 同上 原本 H18.12.8 株式会社金曜日 同上
3 和解調書 写し S57.7.27 岡山簡易裁判所 被告会社が本件土壌汚染実態を知っていた事実
汚染された土壌の上に居住し、長年にわたり健康に危険な状況にさらされながら日々過ごさざるを得ず、宅地としての価値も無価値となり、本件土地に居住を継続することができなくなった。こうした不安な日々を長期間に家族とともに送らなければならなかった精神的な損害は3000万円を超える。
また新たな安全な居住地に移転しなければならず、本件土地の購入費とこの土地に建物を建築した費用は全く無駄になり、原告に生じた損害である。なお、慰謝料には被害を訴えて懸命に対処を要望したにも関わらず、被告会社の利益を優先して原告らの訴えを無視したので本件訴えを起こさざるをえなかった被告の理不尽な対応に対する精神的損害も含む。
悪臭の漂う住宅地であり、原因不明の頭痛に襲われることがあった。
++++++++++++++++++++++++++++++
被告代理人は、予め提出した答弁書の通りですと述べました。
(住民たちのブログ2007年12月10日〜 “両備バスを岡山地裁に提訴その21!〜”掲載)
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20071210
++++++++++++++++++++++++++++++
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
答弁書
平成19年10月31日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
〒700−0807 岡山市南方1丁目8番14号
菊池総合法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人
弁護士 菊池 捷男・首藤 和司・財津 唯行・安達 祐一・井田千津子
電話 086−231 FAX 086−225
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求をいずれも棄却する
2 訴訟費用は原告らの負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 第1項は認める。
2(1)第2項一は認める。正確に言うと、訴外旭油化工業株式会社(以下「旭油化」という)は、大手食用油会社から出る使用済み活性白土(廃白土)を原料として、石鹸やペンキの元となる油を生成する工場である。
(2)同項二は不知。
(3)同項三は認める。但し、「既に」がいつを指すのか不明であるので念のため主張するが、小鳥の森団地は、昭和50年に土地の造成完了、土地の販売開始が同年9月で、住民の居住開始が昭和51年3月ころからである。なお誤解のないように指摘するが、岡山県や岡山市が行政指導を行っていたのは旭油化に対してである。
3
(1)第3項一の事実のうち、両備バス株式会社(以下「両備バス」という。)の小鳥の森団地の販売が困難な状況となっていたとの事実は否認し、その余は認める。
既に昭和56年12月までの段階で、小鳥の森団地全体の約84%にも及ぶ219区画が販売済みだったものであり、同団地の住民から悪臭の苦情が増加したのでこれに対応したものであって、小鳥の森団地の販売が困難な状況になっていたわけではない。
(2)同項二は認める。
(3)同項三は認める。
(4)同項四記載の事実のうち、両備バスが、旭油化から工場跡地を取得したこと、昭和62年頃から3回(但し、正確には「3期」と言うべきである)に渡って宅地造成を行い、順次分譲を行ったことは認め、その余は否認する。
「そのままでは宅地造成地には適さない工場跡地」
とあるが、これが有害物質が存在し、両備バスがそれを認識していたとの趣旨であれば否認する。当時は悪臭のみが問題とされていたものであり、地中に有害物質が存在するとか、まして両備バスがそれを認識していたなどという状況ではなかった。また、両備バスは同土地につき、後記の通り土壌改良工事として必要な対策を採り、その上で分譲を始めているのであって、工場跡地をそのままの状態で売却したのではない。
4
(1)第4項一記載の事実のうち、平成16年7月に岡山市から上水道の鉛管給水管をポリエチレン管に取り換えたいとの連絡があったこと、取り替え工事がなされたこと(但し工事を行ったのは7月27日である)、悪臭を放つ油を含んだ土壌が出てきたこと、岡山市の調査により、地下水と土壌から硫酸イオンが検出されたことは認め、鉛管給水管の一部が腐食していたことは不知、その余は否認する。
(2)同項二第1ないし第4文は認める。
第5文は否認する。
第6文の、「全ての調査位置においてベンゼンが検出された」との点についてであるが、実際には、この調査における調査位置は2箇所のみであり、しかも接近した地点であるので、「近接した2箇所の調査位置からベンゼンが検出された。」というのが正確である。
また、この土壌ガス調査及び土壌調査によると、トリクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレンについてはいずれも定量下限値以下の量しか検出されなかったことも付言する。さらに、含有量試験の結果によると、シアン化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、の含有量値は指定基準を満たしていた。
特にシアン化合物は、通常0.1?/L未満であれば、本来、測定値欄に「検出せず」と記載されるものであるが、この時は「0.01?/L」と表記されているものであり、本来なら「検出せず」の扱いを受けるものであることを付言しておく。
また、原告の指摘する(2)と(3)は内容が重複している。
(3)同項三は否認し争う。
5
(1)第5項一は否認する。両備バスが旭油化から土地を購入したのは、旭油化が度重なる行政指導にもかかわらず、付近に悪臭をまき散らしていたため、旭油化が排出する悪臭を絶つには操業を辞めさせる以外にないと判断したから、またそうするよう付近住民からの強い要望があったからであり、土壌汚染のことについては知る由もなかった。
(2)同項二は否認する。危険な土壌であるとの認識はなかったし、もちろん住宅地として不適なことを秘匿して分譲したなどという事実もない。また、現在の状況についても後述の通り放置したわけではない。
(3)同項三は否認する。
6 別紙原告の損害について
(1)1項記載に事実のうち宅地購入年月日は認め、居住開始年月日及び居住状況は不知、損害額は否認し争う。
ア 不動産取得費等について内容について釈明を求める。
イ 慰謝料について長年にわたり健康に危険な状況にさらされたことを慰謝料請求の根拠としているが、まず本件土壌の汚染が原告に発覚するまでの時点においては原告に精神的損害は発生しえないし、身体的損害が生じていたのならそれを損害として金銭に評価すべきである。
また、汚染発覚後についても、被告は住民の不安を除去するための方策をいくつも講じているから、原告の精神的損害は因果関係がない。
また、原告は訴訟を提起せざるをえなかったこと自体が精神的損害であるかのように述べているが、そこに金銭をもって慰謝すべき精神的損害はない(原告の論によれば、およそ民事訴訟の被告は常に損害賠償義務を負うことになる)。また、原因不明の頭痛は原因不明であるが故に本件とは関係がない。
(2)2項記載の事実のうち、宅地購入年月日は認め、居住開始年月日及び居住状況は不知、損害額は否認し争う。
ア 不動産取得費等について(1)に同じ。
イ 慰謝料について同上。アレルギー性鼻炎、めまい、頭痛は原因不明とあるように本件とは関係がない。
(3)3項記載の事実のうち、宅地購入年月日は認め、居住開始年月日及び居住状況は不知、損害額は否認し争う。
ア 不動産取得費等について(1)に同じ。
イ 慰謝料について同上。頭痛、皮膚炎、咳は原因不明とあるように本件とは関係がない。
7 第7項は否認し争う。
8 よって書きは争う。また、原告の主張を前提にしても、遅延損害金は平成16年9月29日から付すのが正しい。
第3 被告の主張
1 本件土地の現状について
(1)両備バスは本件発生後、住民の不安を解消するために、以下のような調査を行っている。
ア 平成16年9月6日ないし11日、団地内3カ所においてボーリング調査及び土壌分析。
イ 平成16年10月4日ないし6日、団地内34カ所において表層土壌調査及び分析。
ウ 平成16年12月に団地内土壌ガス調査及び環境大気調査。
エ 同月に団地内土壌電気探査。
オ 平成17年2月17日及び18日に団地内土壌化学性状調査。また、この間に、岡山市において以下のような調査を行っている。
カ 平成16年8月26日ないし10月7日に井戸水調査。
キ 平成16年11月4日に河川における油状物質調査。
(2)また、両備バスは、平成16年10月15日、問題の詳細調査・研究及び上記調査結果の分析、問題の解決方法の検討を、南古都?環境対策検討委員会(以下「委員会」という)に委任した。当該委員会は、農学博士千葉喬三(岡山大学学長)を委員長とし、工学博士、農学博士、医学博士、を構成員に迎え、オブザーバーとして岡山市環境保全部部長・岡山市保健所所長も加えた上で結成された専門家集団であり、両備バスも、その後両備ホールディングス株式会社となった現被告も、その調査内容・分析・意見書の作成等に何らの口出しもしていない。
(3)委員会は前記の調査結果等を踏まえて、平成16年10月30日、12月27日、平成17年3月28日の3度にわたって、意見書を作成しているが、それによると
?土壌汚染については、一部検体に基準値を超えるものがあるが、非常な高濃度というものでもなく、団地全体に拡散しているわけでもないこと、土中にあること、地下水の汚染がないことを考えれば、日常生活上重大な問題になるとは考えにくい、
?環境大気調査は環境基準値を満たしており、問題はない、
?異臭の原因は土中の硫化水素と思われ、また土中にガスが多量に集中して存在する可能性は低く、今後減衰していくものである、
?土中に空洞やドラム缶などが存在する可能性はほとんどない、とのことである。
また異臭による不快感についても、委員会から対策工事案が提出されているため、それに従った工事を行うことを前提に、費用の一部を支弁することを、原告らを含む団地住民に提案している。
2 本件土地購入時の対策について
両備バスは、本件土地の取得当時、本件団地は植物油の精製工場の跡地であると認識していたため、土壌が有害物質で汚染されていることについては知る由もなかったため、不法行為に関する故意はない。
また、たしかに、本件土地は取得当時から悪臭が問題になっていたため、両備バスは昭和59年に土壌改良工事として、3673万2000円をかけて埋没されていたドラム缶や油分の多い土壌を搬出除去し、表層土に生石灰を混入することで中和凝固させ、消臭剤の噴霧等の施工を行うなど、必要な対策をとった。また、宅地として分譲する際には、岡山市の開発許可を得て造成を行った上で分譲しており、当時は完全に合法的な売買だったのである。そうでなければ、営利団体である両備バスが、通常の地価より高い価額(全体で2億円以上)で取得するはずがない。
従って、造成工事時及び売買契約時に、上記対策工事方法では将来土壌汚染等の問題の惹起を予見することは不可能であったから、過失もない。
3 よって、原告ら主張の不法行為は成立しない。
以上
++++++++++++++++++++++++++++++
これをもって2007年11月13日に第1回口頭弁論が岡山地方裁判所において始まりました。
結
++++++++++++++++++++++++++++++
第2回口頭弁論が2007年12月11日、10時15分岡山地方裁判所開廷の予定で、前もって、被告側から被告会社が2004年実施した土壌調査報告書を、原告側から住民が2007年実施した土壌調査報告書他を裁判所に提出しました。
2007年12月11日開廷の第2回口頭弁論の前に原告側が提出した資料を説明する準備書面の内容です。
++++++++++++++++++++++++++++++
平成19年(ワ)第1352号損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
準備書面
平成19年12月10日
岡山地方裁判所 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田 英正
第1,本件土地の土壌汚染の激しさ
1,甲10号証の1,2は、旭油化が、操業によって周辺に悪臭を放ち、沼川に油膜が張って、死んだ魚が浮くようになっていた昭和56年5月の状況である。工場周辺にはドラム缶が散乱し、敷地内は油泥のような土壌となっていた。
2,旭油化が操業を中止して被告会社に土地を引き渡す前の昭和57年12月1日の旭油化の工場の状況を撮影したのが甲10号証の5,6,7である。廃油が入ったままのドラム缶が積み上げられていたり、底の抜けた廃油貯蔵タンクが無残な姿を見せている。廃油を処理しないで、土壌に直接吸収させていた実態が明らかとなっている。また、旭油化が集めた廃油類の一部は、処理されないまま産廃不法投棄事件の現場である豊島に運搬されていた。
3,旭油化は、被告会社と和解(甲3号証)が成立した後に、本件場所での操業を中止し、同様の廃油処理業務を昭和57年吉井町草生地区で三和開発の看板を掲げて始めた。
操業を始めるや否や、直ちに周辺住民から異臭や河川、地下水の汚染などの苦情が寄せられた。ここでも、廃油などを素掘りの穴に直接投棄するなどのことをしていて、敷地土壌は、油泥に覆われるようになっていた。旭油化の操業の実態と異なることのない操業方法を繰り返していたのである。
吉井町の厳しい行政指導があり、数ヶ月で操業をやめ、投棄油の回収、工場内の汚染土石類が搬出された。吉井町は、この土壌の安全性を確保するために、汚染土壌の搬出などほぼ1年をかけて地下水の汚染の影響の調査を継続するなどのことが続けられた
(甲8号証、甲9号証)。
本件被告会社が造成販売した住宅地の土壌の汚染は、日本で最大規模のものではないかと言われているのはこうした旭油化の操業の実態と悪質性が背景にある。
第2,被告会社の故意、過失
1,被告会社は、本件土地を取得するようになった経緯からも上記の本件土壌の汚染の実態は十分に認識していたし、認識すべきであった。
旭油化が廃業し、新たに旭油化と代表者を同じくする瑞穂産業が吉井町草生地区で三和開発と称して操業を始めていた廃油処理も、素掘りの穴に直接に廃油類を流し込むという激しいものであった。さらに、破産手続きに入るなど財政的基盤がなく、全く誠意のみられない対応であった。
2,このように汚染された土壌に対して、汚染土壌を完全に搬出するなどの措置をとらず、一部ドラム缶や工場の残滓なども埋めたままで造成をしている。その結果、本件造成土壌全般に汚染が広がっている実情がある。
3,被告会社が、本件土地の取得をめぐって昭和57年に岡山簡裁で和解をしている(甲3号証)。和解条項3項では、建物撤去、構造物撤去は旭油化側の責任で行い、その費用6690万円を被告会社側が負担し、さらに土地代として1310万円を旭油化に支払うという約束をしている。
しかし、一方において第11項では、旭油化が本和解条項に違反したときは旭油化に対して上記各金額の合計額である8000万円の損害賠償請求権が旭油化に対して発生すると取り決めている。
被告会社はもともと旭油化が和解条項など守る能力も意思もないことを予測しながら、基本的には旭油化に建物の撤去責任を持たせようとしたのである。
結局、当初から双方が実質的に合意していたように被告会社は、土地の売買代金のうち1310万円と建物撤去費用6690万円の合計8000万円は損害賠償金と相殺し、これを支払わないで処理しているのである。
4,被告会社は旭油化が、公害発生企業であり、無法な操業をして土壌の激しい汚染を起こしていて、その原状回復の能力も意思もないことを知りながら、本件造成地を一部損害賠償金と相殺するなどして取得し、簡単に一部の土を搬出し、汚染土壌のまま造成工事をした。
第3,汚染の実態
1,原告らの居住する本件造成地に行けば、全体に石油臭がしている。この臭いは、梅雨時、夏場に強い傾向がある。沼川のコンクリート擁癖には黒い染みが出ていて、土壌からの油類による汚染の存在が目に見える。このことだけで住宅地としてはその目的を達することのできない欠陥住宅地である。
2,地表(表層土)からガスが発生していて、ガス漏れ警報器が作動することもある。土を掘ればすぐに黒い油分を含んだ土が出てくる。健康被害も出ている。
3,検査の結果も広範囲な激しい土壌汚染を推測させる内容となっている。
?平成16年7月末、岡山市は本件造成地内における水道管取り換え工事の際に出てきた油分を含んだ水を検査した。ベンゼン、ヒ素が検出された。
?平成16年8月、岡山市が本件造成地周辺の川、井戸の水質検査を行った。井戸で基準値を超えたヒ素を検出している。
?平成16年9月、被告側でボーリング調査。基準値を超えるトリクロロエチレン、シス―1、2―ジクロロエチレン、ベンゼンなどが検出されている。
?平成16年10月、被告側で表層土調査がなされている。基準値を超えるシス―1、2―ジクロロエチレン、ベンゼンなどが検出されている。
?平成16年10月被告側で土壌ガス調査。ベンゼン、硫化水素が全地点で検出され、メタンも高濃度で検出された。
?平成16年12月、被告側で電気探査を実施(甲6号証)。
低比抵抗値を示す部分が旧地形推定線より下側に存在し、広範囲に油類等の汚染の実情が推測される。
深度4.45メートル〜5.80メートルで金属片が発見されている。ドラム缶が存在する可能性も否定されていない。
?平成19年4月、原告○○方において表層土壌ガス、土壌調査を原告側で行った(甲4号証1,2)。
全地点においてベンゼンが検知され、基準値を超えるベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素が土壌から検出された。
4,上記の汚染実態が存在するだけでも、住宅地として使用の目的に耐えない。
被告会社の責任で本件造成地の汚染土壌を完全に搬出し、汚染物質を除去できない以上、原告らは新たな住宅地を他に求めて、新たに住宅を建築するしか方法がなくなっている。
(平成14年9月27日東京地裁判決 油類による土壌汚染は宅地の瑕疵に該当)
<別紙>
事件番号 平成19年(ワ)第1352号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
証拠説明書
平成19年12月7日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田英正
番号 標目(原本写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨
4の1 調査結果報告書 原本 H19.4 株式会社ニッテクリサーチ 本件土地内の土壌汚染の実態について
4の2 測定データ 原本 H19.4 株式会社ニッテクリサーチ 本件土地内の地表大気にベンゼン系土壌汚染を疑わしめるデータが存したこと
5 被告会社グループのホームページ 写し H16.9.30 被告会社企業グループ 被告会社と岡山大学とは包括連携協力関係にあり、乙1号証ないし4号証の評価に関する記事は公正さを欠いていること
6 岡山市南古都住宅地調査電気探査結果資料 写し H16.12 被告会社・応用地質株式会社 表層土全域に1%以上の油分が確認されていること。標高8m付近にLNAPLの可能性があり、油汚染が拡大している状況
7 山陽新聞記事 写し S58.5頃 山陽新聞社 旭油化が本件土地からの移転先でもすぐに土壌汚染問題を起こしていた事実
8 メモ 写し S58.5頃 吉井町 同上(旭油化の悪質性)
9 草生地区公害処理経過報告書 写し S58.7頃 吉井町 同上
10の1 写真 写し S56.5頃 旭油化工業の操業状況を撮影したもの
10の2 同上 写し S56.5頃 同上
10の3 同上 写し S56.8.23 旭油化工業の公害問題調査が行われている状況を撮影したもの
10の4 同上 写し S57.1.21 旭油化工業の操業状況
10の5 同上 写し S57.12.1 昭和57年12月1日の本件土地の状況
10の6 同上 写し 同上 同上
10の7 同上 写し 同上 同上
11の1 無機シアン化合物(「化学物質ファクトシート」から) 原本 H17.8 環境省 無機シアン化合物の毒性等健康影響について
11の2 トリクロロエチレン(「化学物質ファクトシート」から) 原本 H17.9 環境省 トリクロロエチレンの毒性等健康影響について
11の3 ベンゼン(「化学物質ファクトシート」から) 原本 H17.10 環境省 ベンゼンの毒性(発ガン物質)、健康影響について
++++++++++++++++++++++++++++++
予め、被告側から被告会社が2004年実施した土壌調査報告書を、原告側から住民が2007年実施した土壌調査報告書他(前回掲載)を提出して、2007年12月11日、10時15分岡山地方裁判所で第2回口頭弁論がありました。
裁判官は調査地点等の団地全体位置関係が今一つ把握できないようで、要請があり、次回までに原告側から位置の分かる地図を作成することになりました。
次回口頭弁論は2008年1月29日(火)10時20分と定め10時22分終了しました。
++++++++++++++++++++++++++++++
前回口頭弁論では裁判官より小鳥が丘団地内土壌汚染調査の位置の分かる地図等の要請があり、予め原告側から土壌調査資料用地図・住宅地図及び空中写真地図等を提出し、2008年1月29日、10時20分岡山地方裁判所で第3回口頭弁論がありました。
原告代理人河田英正弁護士および大本 崇弁護士、被告代理人首藤和司弁護士他1名が法廷に立ちました。
裁判官は提出した地図のうち1枚を、おおもとの図面にしたい旨発言がありました。
そのあと裁判官は、小鳥が丘団地土壌汚染の別件初回口頭弁論が3月4日にあるので次回はその後にしたい旨発言がありました。
「小鳥が丘団地住民」23名が2007年12月27日に両備ホールディングスを提訴したのです。
以前、原告代理人河田英正弁護士から、別の小鳥が丘団地住民から依頼された弁護士から情報提供の要請があるので提供してもいいか?との打診があったので了解していました。
裁判官は、被告代理人弁護士に対し、同じ事件だと思うので被告の資料は同じものは資料番号を同じにしてもらいたい。被告答弁は同じでしょう?
との発言に、被告代理人弁護士は、違う個所もあるので、その答弁は別にして、同じ答弁の箇所は番号を揃える。
との答弁がありました。
裁判官は、各々の裁判は個々に並行して行うと述べ、次回第4回口頭弁論は2008年3月11日(火)13時10分からと定め10時30分終了しました。
今回は愛知県小牧市桃花台ニュータウン地盤沈下問題を考える会代表の丸山直希氏も傍聴に来られていて、裁判所に提出した公害工場操業当時の空中写真を見せたところ、現在の小鳥が丘団地の空中写真と重ね合わせたら状況が良く分かるのではないかとの提案で、最近の小鳥が丘団地空中写真を調査するために、環瀬戸内海会議事務局長の松本宣崇氏とともに岡山県立図書館に行きました。
最近のものは平成4年の空中写真があったので、重ね合わせ加工は丸山氏にお願いし、2日後重ね合わせ写真が送られてきたので、弁護士に届けました。
河田弁護士は、工場操業時配置と現在の住宅団地の位置関係が良く分かるので早速裁判所に提出するとの事でした。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20080229
++++++++++++++++++++++++++++++
原告代理人は、両備バスの答弁書「第3、被告の主張」で両備の実施した調査につき答弁しているのだからその資料の提出を要求し、また原告側独自の調査資料もあるから提出すると述べました。
裁判官は、追加資料を原告被告とも提出してから審議を行う方がよいだろうと述べ、第2回口頭弁論を平成19年12月11日の10時15分からと定め10時25分終了しました。
******************************
岡山県警本部へ提出した告訴状!その1
日本で最大規模のものではないかといわれている岡山市小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染は、宅地造成販売した両備バス株式会社が抜本的な土壌汚染対策を取ろうとせず、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題長く放置されています。以前住民たちのブログで紹介した“両備グループを刑事告訴!” (2007年2月11日〜2月22日)の告訴状2名分を掲載します。告訴状の書き方など全く分かりませんでしたが、アドバイスを受けながら住民だけで告訴状を作成し2006年11月1日に岡山県警本部へ告訴しました。
両備バスが立ち上げた岡山大学の先生を中心とする両備バス私設委員会「南古都?環境対策検討委員会」が最終意見書(第3回目意見書)を2005年3月28日に提出して以来、両備バスは追加土壌調査も住民との話し合いも拒否し、「裁判以外は相手にしない!」としか言わなくなりました。
この時点で最終的には民事裁判になるかもしれないと思いましたが、一般住民が健康と財産の被害を受けていて、公的機関が何もしないはずは無いと思い、各関係諸機関に相談に回っていました。
警察へは地元の岡山県警、西大寺支所へ何度も相談に行きましたが被害届けの意思を示しても要領を得ません。そこで岡山県警本部へ刑事告訴をしようと研究を始めました。
弁護士に依頼するのが一番手っ取り早いのですが資金に限りがあるので住民だけで告訴しようと調べましたが告訴状など見たことがないので告訴状を作成してもらおうと司法書士を訪ねました。
しかし1か月以上かかるとの事なので、いろいろな人に聞きながら不十分ですが住民だけで告訴状を書き上げ、ともかく2006年11月1日に岡山県警本部へ提出しました。
告訴状提出当日の様子は前に掲載したとおりです。
2007年2月11日(日) 両備グループを刑事告訴!その1
両備グループを宅建法の土壌汚染重要事項説明違反で告訴
平成18年11月1日11時に小鳥が丘団地住民2名で岡山県警生活環境課に宅地建物取引業法違反の告訴状を提出しました。
出向くと11時前からテレビ局や新聞記者が数社待ち構えていました。
゛記者会見はどこですか?゛の質問に、県庁内会見室や県庁記者クラブ会見室を交渉しましたが、了解が得られず、建物外なら良いとの事で、゛県庁中庭にします。゛と答えました。
記者の大まかな質問が終わると11時5分前だったので、県警本部の建物に入ろうと歩きかけると記者の人に、゛11時と聞いているので皆にその様に連絡しているので11時丁度まで待ってください。゛
と言われました。
11時丁度になったので、゛行きますよ。゛と言うと、カメラマンが、゛向こうの方からゆっくり歩いて入ってください。゛
と言いながら、その様子を撮影していました。
県警本部受付に用件を伝えると、再び表に出て分庁舎の生活環境課に案内してくれましたが、記者やカメラマンは県警本部玄関前に足止めをされた様でした。
県警本部の分庁舎4Fの生活環境課に入ると、次長と他に1名職員が応対してくれました。
事情説明の後、2名分の告訴状と疎明資料を提出すると、丁寧に内容を見ていただきました。短い質問をしながら読み終えると
、゛内容は良く分かりました。゛と言いながら、
゛弁護士に依頼されていれば予め分かったと思いますが、刑事上の時効が成立しています。゛といわれました。
私達は、売買契約の時に土壌汚染があった工場跡地の宅地であった説明を受けていないし、両備グループが土壌汚染地であると認識をしていたのは裁判調書でも明白なので、
故意に事実を告げなかった場合は時効の特例があるのでは?との質問に、
゛特例は有りません。゛ さらに付け加えて゛事情はよく分かりますが、法律上、刑事事件としての時効が成立している以上、受理できません。゛
゛我々は法律上でしか、行動できません。゛との回答でした。
そこで、我々小鳥が丘団地の場合の時効は何年ですか?と質問しました。
゛犯罪事実に適用する罰条の法定刑によって1年、3年となりますが、この場合には3年です。゛との回答でした。
岡山県警生活環境課の説明では、小鳥が丘団地土壌汚染の重要事項説明違反の時効は、3年との事でしたが、土壌汚染は見た目には分からないし、長期間経過した後に何かの原因で発覚するのが普通なので、建物のように購入者が1年や3年で地下の汚染を発見するのは難しいと思います。
法律の不備を感じます。
犯罪の種類によっては時効が完成していない場合もあると思われますので、その時は相談に乗ってくださいとお願いして退出しました。時計を見ると1時間以上も経過して昼を過ぎていましたので、
゛記者も昼食で解散しているかもしれないな゛と思いながら県庁中庭に行ってみると、まだ皆さん待っていました。
私達を見つけると、走り寄ってきて周りを取り囲まれ、質問責めに遭いました。
記者会見で、告訴状提出の内容を説明した後、追加の質疑応答は次のようなものです。
(記者)
現在、両備グループと話し合い継続中なのでは?
(住民)
両備グループは、法的責任がないと住民が認めない限り、話し合いにも、応じないと主張しています。 しかし認めても解決実施の確約は有りません。
つまり両備グループは話し合いだけして、何もしないで良い事にすらなりかねず、とうてい容認できません。
(記者)
両備グループは当時の法律に基づいて小鳥が丘団地を開発・販売し、土壌汚染の認識はなかったといっていますが?
(住民)
当時、両備グループが旭油化工業跡地を取得する時、有害物質の除去を条件とし、違反した時の損害賠償金を明記して買収した、裁判記録が残っていますので、土壌汚染を認識していたのは明白です。
(記者)
今後どうするのですか?重要事項説明違反以外の理由でも告訴出来るのでは?
(住民)
時効が成立してない何か別の違反を知っていれば教えてもらいたいぐらいです。別の告訴も模索していきますが、刑事事件の時効は短いですから、見付けられない場合には、最終的に民事訴訟に成らざるを得ません。
朝から忙しい1日でしたが、あっという間に過ぎてしまいました。
しかし、いくら時効になったとしても、両備グループの不正は不正であり、不正の事実が消える事は有りません。
これからも不正の事実を訴え続けていかなければなりません。
そして、行政はこの問題に対して消極的ですが、社会問題としてこれから頻発するであろう土壌汚染問題に、行政としてどう取り組むのかを問いつづけていこうと思っています。 結
++++++++++++++++++++++++++++++
住民Aの告訴状です。
告訴状
告訴人
岡山市南古都××× ○○○○ 昭和××年××月××日生
被告訴人
岡山市西大寺上1丁目1番50号 両備バス株式会社 宅地建物取引主任者 ○○○○
岡山市錦町7番23号 両備バス株式会社 代表取締役社長 小嶋 光信
宅地建物取引業法違反告訴事件
1.告訴の主旨
被告訴人らの犯罪事実に記載した行為は、宅地建物取引における重要な事項について、故意に事実を告げず販売し、売買契約の不法行為により被害を受けたことは、宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号に違反するので、捜査の上、厳重に処罰されるようここに告訴いたします。
2.犯罪事実
(1)被告訴人の○○○○は、両備バス株式会社の宅地建物取引主任者である。告訴人が居住する小鳥が丘団地の自宅、宅地面積203.82?及び、延べ床面積建物110.95?の取引につき、平成5年1月30日に仲介業者として重要事項説明をし、仲介業者である被告訴人らを通して売買契約を交わし告訴人はこれを購入した。
(2)平成18年6月5日に倉庫工事の為、告訴人が自宅庭を掘削したところ地下15cm〜40cm部分から黒い刺激臭のする土壌が出てきた。現地確認をしてもらう為、仲介業者であり、土地の造成販売業者でもある被告訴人らに連絡をしたところ、被告訴人らは現地確認を拒否し、現地はそのままの状態だった。
(3)平成18年10月13日、告訴人は、自宅庭が掘削されたままの状態であった為に自家用車を外部駐車場に置いていたが、自宅庭に、駐車する場所を確保しようと、掘削跡の埋め戻しや堆積した土壌を移動中に、15時頃自宅庭で倒れ、救急車で病院に搬送され治療を受けた。
原因は庭の掘削跡に水が常時溜まっていて、移動中の堆積した黒い土壌と反応して発生したガスを吸い込み身体に異変を生じた為で、病名は亜硫酸ガス中毒である。庭の土壌は通常生活を営むうえで健康被害を及ぼす有害物質である事が確認された。
(4)被告訴人らは本団地の土地を取得する際、昭和57年7月27日岡山簡易裁判所において和解をしている(相手方、旭油化工業)。和解条項に本件土地上のすべての建物及び地下工作物を収去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及び、アスファルト部分を除去し、本件土地上の油脂付着物を除去して、と明記しているが、現状を見るに、廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去をしていない。
(5)告訴人は売買契約時、被告訴人ら、から売買契約対象物件が土壌汚染された土地であった事実の重要事項説明を受けておらず、被告訴人らは本団地の土壌汚染が問題になった平成16年当時、汚染土壌を石灰で中和させたと申し立てているが、廃白土等除去に替えて石灰で中和させ土壌改良したのであれば、告訴人ら土地購入者にとって、これも重要事項であるにもかかわらず、売買契約時に、説明を受けていない。
(6)被告訴人らは裁判で和解をする時、和解条項に廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去を明記しているのだから、土壌が汚染されており、除去しなければならない、と認識していたことは明白である。
(7)よって当該契約対象物件の売買契約時に、被告訴人らは告訴人に土壌汚染の履歴のある宅地である旨の重要事項説明をすべきところ、被告訴人らは宅地建物を円滑に販売する為、故意に事実を告げず、告訴人は事実を知らず購入した。これは宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号違反である。
3.補足経緯
(1)最初に問題になったのは、岡山市水道局が進めている鉛製給水本管の取替工事中である。本団地が開発された昭和62年に埋没された鉛製給水本管を取り替える為、平成16年7月27日に水道工事業者が本団地内道路を掘削したところ、悪臭と油が出てきた。
(2)宅地を造成販売した両備バス株式会社と担当行政の岡山市に調査及び改善を求めたところ、3箇所のボーリング調査他の調査を実施し、環境基準値を超える有害物質が検出され、本団地造成前に操業していた公害工場の旭油化工業の廃棄物が原因と判断されたが、両備バス?が設立した、千葉 岡大副学長(当時、現岡大学長)を中心とする「南古都? 環境対策検討委員会」の意見書により、住民の健康への影響が直ちに懸念されるものではない、と回答し、住民が要求しても、その後の住民との話し合いも、住民の不安を払拭する為の追加調査も実施していない。
(3)告訴人は、体調が悪いのは、土壌が原因ではないかと思い、庭の表層土の入れ替えを自ら実施しようと、平成18年10月5日に岡山市環境保全課に出向き、廃棄土壌の指定場所を求めたところ、土壌の汚染はあるので指定区域から搬出される汚染土壌と同様に適正に処分する様に指導された為、告訴人は本団地の土壌は汚染されているとの認識をもった。
(4)汚染原因者の旭油化工業は近郊の赤磐郡吉井町(現あかいわ市)の工場で、当地と同様に廃油を垂れ流して土壌汚染を引き起こした為、吉井町ではこの公害工場を昭和58年1月に撤退させ跡地を調査し土壌汚染が深刻と判断し土壌入替えを行っている。被告訴人らは本団地を造成する前に、吉井町で同一企業が同様の工場を操業した跡地の吉井町の土壌入替え対策を知り得たはずであるから、操業期間から推定しても、地上及び地中の汚染は吉井町以上の疑いがあると認識していた、と考えるのが妥当である。
(5)被告訴人らは、これらの完全除去を確認せずして用地を取得し告訴人らに販売したのであり、除去してない廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の汚染により、その後の告訴人が受けた被害の責任は被告訴人にある。
4.両罰に関する規定
被告訴人両備バス株式会社は告訴人らに対し重要な事項について、故意に事実を告げず宅地を販売したのであるから、宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号違反について、第八十条(罰則)、第八十四条(両罰規定)により、処罰の対象である。
5.違反条文
○宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号
6.罰条
○宅地建物取引業法第八十条
○宅地建物取引業法第八十四条(両罰規定)
7.疎明資料
(1) 上申書 一通
(2) 重要事項説明書 一通
(3) 不動産売買契約書 一通
(4) 鉛製給水管使用について(回答)書 一通
(5) ボーリング調査濃度計量証明書(No3地点) 一通
(6) 表層土調査濃度計量証明書(土壌14) 一通
(7) 両備バス? 南古都?環境対策検討委員会 意見書 一通
(8) 告訴人自宅庭を掘削した写真 一枚
(9) 岡山市環境保全課の汚染土壌の処分方法について 一通
(10) 告訴人の病状退院証明書 一通
(11) 昭和57年7月27日の和解調書 一通
(12) 吉井町公害企業施設撤去新聞記事 一通
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20080317
++++++++++++++++++++++++++++++
次に住民Bの告訴状です。
告訴状
告訴人
岡山市南古都×××× ○○○○
昭和××年××月××日生
被告訴人
岡山市西大寺上1丁目1番50号 両備バス株式会社 宅地建物取引主任者 ○○○○
岡山市錦町7番23号 両備バス株式会社 代表取締役社長 小嶋 光信
宅地建物取引業法違反告訴事件
1.告訴の主旨
被告訴人らの犯罪事実に記載した行為は、宅地建物取引における重要な事項について、故意に事実を告げず販売し売買契約の不法行為により被害を受けたことは、宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号に違反するので、捜査の上、厳重に処罰されるようここに告訴いたします。
平成18年11月1日
岡山県警察本部 県警本部長 殿
告訴人 ○○○○ 印
2.犯罪事実
(1) 被告訴人の○○○○は、両備バス株式会社の宅地建物取引主任者である。告訴人が居住する小鳥が丘団地の自宅、宅地面積159.72?売買代金9,101,000円及び、延べ床面積105.58?請負代金16,375,970円(消費税込み)の建物につき、平成2年8月30日に重要事項説明の後、契約を交わし告訴人はこれを購入した。
(2) 平成17年頃より突発的かつ継続的に頭痛が起こり、診断の結果、本団地内で高濃度に検出された有害物質の影響の可能性を指摘された。
(3) 平成17年10月19日に中国銀行平島支店に不動産担保融資申し込みを行なったが、告訴人自宅土地建物は売買取引が非常に難しいので担保にならない、と融資を断られた。
(4) 告訴人の自宅は、地盤沈下しており、建物の傾斜で戸の開閉が年々できなくなっている。
(5) 告訴人の自宅は、当初被告訴人ら、から購入した土地建物のみならず、その後、追加的に行なった建物付属設備や建物補修工事を含め資産価値が無くなった。
(6) 本団地内の住人、○○○○氏が平成18年10月13日に自宅庭の土壌を移動中に亜硫酸ガス中毒になっている。
(7) 被告訴人らは本団地の土地を取得する際、昭和57年7月27日岡山簡易裁判所において和解をしている。和解条項に本件土地上のすべての建物及び地下工作物を収去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及び、アスファルト部分を除去し、本件土地上の油脂付着物を除去して、と明記しているが、現状を見るに、廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去をしていない。
(8) 告訴人は売買契約時、被告訴人ら、から売買契約対象物件が土壌汚染された土地であった事実の重要事項説明を受けておらず、被告訴人らは本団地の土壌汚染が問題になった平成16年当時、汚染土壌を石灰で中和させたと申し立てているが、廃白土等除去に替えて石灰で中和させ土壌改良したのであれば、告訴人ら土地購入者にとって、これも重要事項であるにもかかわらず、売買契約時に、説明を受けていない。
(9) 被告訴人らは裁判で和解を成すにおいて、和解条項に廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去を明記しているのだから、土壌が汚染されており、除去しなければならない、と認識していたことは明白である。
(10) よって当該契約対象物件の売買契約時に、被告訴人らは告訴人に土壌汚染の履歴のある宅地である旨の重要事項説明をすべきところ、被告訴人らは宅地建物を円滑に販売する為、故意に事実を告げず、告訴人は事実を知らず購入した。これは宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号違反である。
3.両罰に関する規定
被告訴人両備バス株式会社は告訴人らに対し重要な事項について、故意に事実を告げず宅地を販売したのであるから、宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号違反について、第八十条(罰則)、第八十四条(両罰規定)により、処罰の対象である。
4.違反条文
○宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号
5.罰条
○宅地建物取引業法第八十条
○宅地建物取引業法第八十四条(両罰規定)
6.疎明資料
(1) 上申書 一通
(2) 重要事項説明書 一通
(3) 不動産売買契約書 一通
(4) 工事請負契約書 一通
(5) 鉛製給水管使用について(回答)書 一通
(6) ボーリング調査濃度計量証明書(No3地点) 一通
(7) 表層土調査濃度計量証明書(土壌14) 一通
(8) 岡山市環境保全課の汚染土壌の処分方法について 一通
(9) 告訴人の診断書 一通
(10) 昭和57年7月27日の和解調書 一通
平成18年11月1日
岡山県警察本部
県警本部長 殿
告訴人
○○○○ 印
結
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20080323
++++++++++++++++++++++++++++++
両備グループを刑事告訴!その5
両備グループを宅建法の土壌汚染重要事項説明違反で告訴
追記
今回の告訴の後で感じた事を書きます。
私たちは、民事裁判の前に、まず刑事告訴を行いました。
金持ちであれば、自前で地質調査及び分析を行い、弁護士に依頼して、すぐ民事訴訟を起こせば良いのですが、一般の庶民では資金の工面が直ちには出来ません。
まして地質汚染であれば、一般のサラリーマンにとって唯一の担保となる土地建物が無価値になり、銀行融資も受けられません。
小鳥が丘団地地質汚染問題の様な、目に見えない地中の汚染は、発覚するまで長期間かかる方が普通であり、刑事告訴の時効があまりにも短いと思いました。
そして、いくら時効になったとしても、両備グループの不正は不正であり、不正の事実が消える事は有りませんが、それよりも重大なのは、
両備グループが、非は非と認めて対応しない事であり、小鳥が丘団地地質汚染問題を含めて、このままにすると、会社のこの様な対応の仕方が変わらず、改革が出来ない事により、第2第3の地質汚染問題を引き起こしかねないと思います。
よって、これからも不正の事実を訴え続けていかなければなりません。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20070220
追記2
今回の告訴の後で感じた事を、もう一つ書きます。
それは、行政の対応です。
前に、小鳥が丘団地地質汚染問題に対して行政が消極的だと書きましたが、当地域の環境担当行政である岡山市は、住民が自宅庭で土壌を移動中にガス中毒で倒れたという健康被害にあったにもかかわらず、実態解明の土壌調査すら行なおうとしません。
岡山市は、土壌汚染対策法に照らして行政が地質調査を行なう事は出来ない(土地の所有者が行なうべきもの)と説明しています。
しかし、そもそも小鳥が丘団地ができたのが、土壌汚染対策法が公布される以前であり、土壌汚染対策法が適用される案件では無いと、専門家から聞きました。
行政が、地質汚染の事は何でも土壌汚染対策法を持ち出すのは、行政が余り関わらなくて良い法律を利用しているのではないかと疑いたくなります。
岡山市は、一番てっとり早い土壌汚染対策法を持ち出しているとしか思われません。
余談ですが、地質汚染を防止する目的で創られた土壌汚染対策法が、逆に合法的な“こまかし”に利用されたり (土壌は層を形成しているもので土対法の調査基準では全ての層を調査するものでは無い為、汚染された層をはずせば、その土地は汚染されてない事になる)、
また、全ての地質調査指定会社が、技術レベルが高い訳では無いので、ボーリング調査で地層を勘案しない機械的深度の試料採取により、かえって汚染を拡大させてしまう等の問題点も指摘されています。 (NHKテレビクローズアップ現代でも紹介)
土壌汚染対策法は、まだまだ問題点の多い法律だと考えさせられます。 以上
******************************
******************************
******************************
******************************
2007年2月25日(日)
両備バスに申入れ書!その1
両備グループ代表に土壌汚染解決の話し合い継続を明確に伝えるために申入れ書を郵送しました。
小鳥が丘団地を造成販売した両備バス株式会社が、土壌調査継続も住民との話し合いも拒否し、いくら両備バスに連絡をとっても“弁護士に任せているのでそちらに言ってくれ”の一点張りで住民の思いが伝わらない為、両備バスの意思を確認するために、過去に両備グループ代表に手紙を配達証明郵便で出しました。(このブログの平成18年9月11日、“両備グループ代表・社長の意思!”に掲載)返書が来なかったので、住民との話し合い拒否は両備グループ代表の意思と確認しましたが、
その後、 “あの手紙は何を言っているのか分からない”と両備バスが言っていると聞いたので、再度、明確に要求が分かる様に、回答期限付きで申入れ書を平成18年10月17日に内容証明郵便で出しました。
両備グループ代表に土壌汚染解決の話し合い継続を明確に伝えるために申入れ書を郵送しました。
以下、その内容です。
++++++++++++++++++++++++++++++
平成18年10月17日
〒700−8518 岡山市錦町7番23号
両備バス株式会社代表取締役社長小嶋 光信 様
小鳥が丘団地救済協議会 代 表 岩野敏幸
申し入れ書
私たち、小鳥が丘団地救済協議会は、御社が造成・販売した小鳥が丘団地で明らかになった土壌汚染問題の解決のため団地住民の有志で組織した団体です。なお、以前に御社が交渉をもっていた小鳥が丘環境対策委員会とはべつの団体です。
当協議会は、小鳥が丘の土壌汚染問題について、御社が平成17年7月に小鳥が丘団地住民に対して提出した、条件付き提案には承諾できません。
この提案は、御社と話し合いをもつための条件として、この土壌汚染の法的責任が御社にないことを確認しなければならない一方で、土壌汚染への対策実施についての保証すらありません。
これでは御社は話し合いだけして、何もしないでよいことにすらなりかねず、当協議会としてはとうてい容認できません。
しかしながら、当団地の土壌汚染問題は、発生する有毒ガスによる健康被害や地盤沈下といった被害を引き起こしていることも考えられ、そこで生活する私たち住民にとってきわめて重大です。
そうした汚染がある土地を造成し、住民には知らせずに販売した御社には当然ながら責任があるはずです。
よって当協議会は御社との話し合いおよび当協議会の合意の上での解決策の実施を求めます。
上記の申し入れに対して、平成18年10月27日までに下記の当協議会代表に文書にてご回答願います。
岡山市南古都××× 小鳥が丘団地救済協議会代表 岩野敏幸
電話:××× 携帯:×××
++++++++++++++++++++++++++++++
豊島と小鳥が丘団地は廃棄物不法投棄搬入ルートで繋がっていました。
私たち小鳥が丘団地住民は2005年3月20日に香川県豊島に現地視察に行きました。
その時、豊島に不法投棄した業者を摘発した兵庫県警の資料の中に、産廃搬入ルート先として小鳥が丘汚染原因者の岡山市旭油化工業の名前が記載されていました。
香川県豊島の産廃と岡山市小鳥が丘の産廃は繋がっていたのです。
そこで豊島公害調停選定代表人の一人として調停に参加された石井とおる氏(前香川県議会議員)から話を聞く機会を得、大変参考になりました。
石井氏には戦後最大級の不法投棄事件と言われた豊島問題を闘った先輩として、アドバイスを頂いています。
最近、石井氏が書かれた“未来の森”という本を読みました。今までの私たちであれば、信じられない内容なのですが、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題に直面している私たちにはそのままストレートに伝わってきます。
やはり信じられない行為が平然と行われていた事に深い悲しみが湧き上がってきます。
と同時に、当時ほどではないにしても現在も、その様な事が繰り返されているのです。
そこには我々一般住民の常識からは考えられない行政の対応が書かれていました。
たとえば違法操業のページで、住民が何度も香川県の職員に事業者の行為を止めさせるよう要求したが相手にされず、 “もうもうと立ち上がる野焼きの煙は県庁の窓からも見えた。県庁を訪れた住民が担当者を窓際へ連れて行き、「あの煙が見えんか!」、と指さすと、「見えん!」、と横を向いたという。”
行政が何故この様な信じられない対応になるのか、については石井氏がこの本で指摘しています。
“自治体は何故住民の言うことを聞いてくれないのでしょうか”と聞かれて、
石井氏いわく。
“そもそも、住民の言うことなど聞くようにはできていないから”
(「未来の森」より、「農事組合法人てしまむら」発行、石井とおる著)
http://www.teshimamura.com/?pid=3038282
******************************
2007年11月20日(火)
両備バスを岡山地裁に提訴!その1
岡山市小鳥が丘団地土壌汚染公害問題で両備バス?は有害物質で汚染された宅地を住民に説明せずに販売し、汚染発覚後も抜本的な対策をとろうとせず住民が被害を受けても放置したため、2007年8月31日、住民3名が両備ホールディングス株式会社を岡山地方裁判所民事部へ提訴しました。提訴の経緯を掲載します。
両備バス?は途中で調査を取りやめ、行政も土壌汚染調査をしないので土壌汚染の全容が分からず、汚染対策の検討もできません。もはや民事訴訟しかないと思いまず住民3名で提訴しました。提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ通知・催告書を郵送しました。
通知・催告書
貴社が造成販売した小鳥が丘団地の住民である岡山市南古都××× 藤原 康氏、同所××× ○○○○氏、同所××× ○○○○氏ら3名の代理人として以下のとおりご通知し、損害賠償の請求をいたします。
貴社は、本件団地の本件造成地内に、川に廃油を垂れ流したり有害廃棄物を野積みするなどして公害企業であった旭油化工業株式会社が存在していて人体に影響を及ぼす汚染物質が存在することを知りながら、これを除去することなく埋め立てて造成し、そのことを秘して藤原氏らに販売しました。
この汚染の事実が発覚してもことさらに汚染の程度の低いことを強調し、その責任をとろうとしませんでした。
本件の造成地からは黒く汚染された地下水がにじみ出ていて、表層土壌からはベンゼンを含むガスが出ていることも明らかとなっています。
さらに、そのガスの濃度はガス漏れ警報器が作動することもあり、健康への影響のみならず物理的にも危険な状況となっている箇所もあります。
また、土壌にはベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が土壌溶出量基準を超えて検出されています。
本件危険な造成地の販売は故意にとの評価できる重大な責任があります。
藤原氏らとそれぞれの家族らは、この団地を岡山を代表する貴社の企業としての評価を信頼し、終の棲家として希望をもって購入いたしました。
しかし、上記の状況であり、この土地が土壌汚染されていて、日々健康を冒され続けてきていることが明らかになり、とても安心して住める状況ではありません。住宅地として使用不可能な土地であり、他の地に移らざるをえません。
従って、このような土地を購入した代金、この土地上に建てた家の建築費用と健康被害を受け、日々不安な生活を継続してきた損害を慰謝料として評価し、これらの合計額を請求いたします。なお、○○氏は本件分譲地で、整骨院を経営していて業務に関する工事費用も損害に加えて請求いたします。
本件請求に対するご回答を平成19年7月31日までに当事務所まで書面をもって頂きますようお願いいたします。ご誠意あるご回答なき場合はやむを得ず法的手続きをとることになりますので、念のため申し添えておきます。
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の続きです。
各自の損害は以下のとおりです。
○○○○氏
不動産取得費等 28,897,520円
慰謝料 30,000,000円
○○○○氏
不動産取得費等 28,759,670円
慰謝料 30,000,000円
○○○○氏
不動産取得費等 80,241,390円
慰謝料 30,000,000円
平成19年7月13日
岡山市富田町二丁目7番8号石橋第3ビル3階
河田英正法律事務所
弁護士 河田 英正
弁護士 大本 崇 電話 086−231− FAX 086−231−
岡山市錦町7番23号
両備バス株式会社
代表取締役 小嶋光信 様
この郵便物は平成19年7月13日第29830号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
岡山中央郵便局長
******************************
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の返書として2007年7月28日付けで送られてきた両備ホールディングス株式会社の回答書です。
回答書
平成19年7月28日
岡山市富田町2丁目7番8号 石橋第3ビル3階
藤原康氏外2名代理人 弁護士 河田 英正 殿
岡山市南方1丁目8番14号
両備ホールディングス株式会社代理人
弁護士 菊池 捷男・首藤 和司・財津 唯行・安達 祐一・井田千津子
電話 086−231 FAX 086−225−8787
冠省
貴職らからの平成19年7月13日付「通知・催告書」を拝見しました。
両備ホールディングス株式会社では、平成16年7月に、小鳥が丘団地の住民の皆様から、団地内の土地を掘ったところ臭いがする、油が出てきた、など連絡を受け、真摯に、調査と地元の方々と話し合いをしてきました。また、平成17年3月までに、専門家による現地調査や地元の方々へ対策工事の提案もしてきました。
しかしながら、貴職らの依頼人らは、具体的、科学的な根拠を示すことなく、小鳥が丘団地では人は住めない等極めて誇張した表現で両備ホールディングス株式会社を非難することに終始し、真剣に対応しようとはされませんでした。その姿勢は、今回の貴職らの書面での請求額等にも現われているところです。両備ホールディングス株式会社としましては、このような貴職らの依頼人とは真摯に話し合いができるとは思えません。そのため今回の貴職らの書面に対しては、細かな認否は致しません。
貴職らは、両備ホールディングス株式会社の回答に満足しない場合は、法的手続きをとると書かれていますので、両備ホールディングス株式会社の主張は、法廷の場でさせていただきます。ただ、念のためお伝えしておきますが、両備ホールディングス株式会社は、貴職らの依頼人の主張に対し、全面的に争うことにしております。
以上回答いたします。 草々
******************************
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の返書として「両備ホールディングス株式会社は法廷で全面的に争う」との2007年7月28日付け回答書を受けて岡山地方裁判所へ提訴しました。訴状を掲載します。
訴状
平成19年8月31日
岡山地方裁判所民事部 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田 英正
同 大本 崇
〒709−0632 岡山市南古都×××
原告 藤原 康 〒709−0632 岡山市南古都×××
原告 ○○○○ 〒709−0611 岡山市楢原×××
原告 ○○○○
〒700−0816 岡山市富田町二丁目7番8号 石橋第3ビル3階
河田英正法律事務所(送達場所)
上記訴訟代理人弁護士 河田 英正
同 大本 崇
電話 086−231− FAX 086−231−
〒704−8112 岡山市西大寺上1丁目1番50号
被告 両備ホールディングス株式会社
被告代表者代表取締役 小嶋光信
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 227,898,580円
ちょう用印紙額 704,000円
第1 請求の趣旨
1、被告は、原告○○○○に対して58,897,520円、同○○○○に対して58,759,670円、同○○○○に対して110,241,390円とそれぞれこれに対する平成16年9月28日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え
2、訴訟費用は被告の負担とする
3、仮執行宣言
第2 請求の原因
1、当事者
一 被告会社は、昭和11年5月25日に両備バス株式会社として設立され、平成19年4月1日に両備ホールディングス株式会社と商号変更された資本金4億円の株式会社であり、自動車、船舶による旅客、貨物の運送業、観光事業、不動産の所有・売買・賃貸仲介などを業務としている。
二 原告らは、両備バス株式会社が造成した小鳥が丘団地に住居を有し、居住している者である。
2、小鳥が丘団地造成前
一 本件造成地には、廃油等を利用して石鹸を製造していた旭油化工業株式会社の工場があった。
二 同社は、業績不振のなか、昭和49年11月19日に新たに廃棄物処理業の許可を取り阪神、北九州方面の企業から産業廃棄物としての廃油を集めてその処理を始めた。その頃から、廃油処理工場からは廃油処理の黒煙が不気味に立ち上っていた。地域周辺に悪臭がたちこめ、近くを流れる沼川には油膜が張ったり、死んだ魚が浮き上がってくるなどの現象が見られた。廃油を貯蔵していたタンクが設置されていたが、その装置は単に土壌に廃油を吸い込ませる装置であったようであり、タンクの底は直接土壌に接して廃油が不法に処分されていた。そのタンクの位置は土壌への吸収が悪くなると敷地内で場所が移動されていた。そして、工場敷地内には腐敗した油脂を入れたドラム缶が散乱して放置されていて、その腐敗した油脂が敷地内の土地にこびりつき、恒常的に悪臭を発生させていた。
三 両備バス株式会社は、この旭油化工業株式会社の工場北側に既に団地(小鳥の森団地)を造成し、住民が居住していた。その住民からも旭油化株式会社の産業廃棄物処理業を始めたことによる悪臭などの環境悪化の苦情が造成・販売した両備バス株式会社などに苦情が寄せられるようになった。このころ岡山県や岡山市の公害課が何度も行政指導を繰り返していたが、何ら対策が講じられなかった。
3、両備バス株式会社の本件土地の宅地造成
一 両備バス株式会社は、上記のとおり旭油化株式会社が操業している土地の北側に小鳥の森団地(37000平方メートル)を造成・販売していた。
この分譲地を購入して居住している住民から、上記のとおり苦情が寄せられるようになり、両備バス株式会社は旭油化株式会社に対して強く改善方を要求していたが、一向に改善されることはなかった。両備バス株式会社の小鳥の森団地の販売が困難な状況となっていた。
二 両備バス株式会社は、昭和57年になって旭油化株式会社を相手方として悪臭を放つ汚泥とドラム缶の除去を求めて岡山簡易裁判所に対して、小鳥の森団地の販売者として調停の申立をした(岡山簡易裁判所昭和57年(イ)第67号)。そして、昭和57年7月27日、岡山簡易裁判所において両者の間で和解が成立した。
三 上記和解の内容は、本件問題を解決するには旭油化株式会社が本件土地から移転するしか方法がないというものであり、概略以下のとおりであった。
(1)旭油化株式会社は昭和57年10月31日限り操業を停止し、同年12月31日までに本件土地上の全ての建物および地下工作物を撤去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
(2)両備バス株式会社は、旭油化株式会社に対して建物撤去費用、移転補償などとして6690万円を支払う。
(3)両備バス株式会社は、旭油化株式会社の工場跡地を一坪あたり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
四 こうして、旭油化株式会社の工場跡地を取得した両備バス株式会社は、このそのままでは宅地造成地には適さない工場跡地を昭和62、3年ごろから3区画に分けて有害物質に汚染されたままで宅地に造成し、平成元年頃から分譲を始めた。
4、宅地から有害物質検出の経緯
一 平成16年7月に岡山市から上水道の鉛製給水管をポリエチレン管に取り替えたいとの連絡があり、7月29日に取り替え工事がなされた。取り替えのため給水管を掘り起こしたところ、油分を多量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥状のなかに水道管が埋められていることが判明した。そして化学反応の安定性が高いと言われる鉛管の給水管の一部が腐蝕して穴があいている箇所も発見された。岡山市の調査によればこの時の地下水と土壌から硫酸イオンが検出された。
二 両備バス株式会社は、原告ら住民の不安の訴えに対し、土壌汚染の原因を探るべく、土地履歴の調査、ボーリングによる土壌調査などの申し入れがなされ、調査が実施された。同年9月28日原告らに土壌汚染の実態と原因が知らされた。同社の報告によっても、3地点のボーリング調査の結果は、環境基準値の約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、6倍のシスー1,2−ジクロロエチレンが検出された。また、地下約5メートル付近では金属片やボロ切れなどが発見された。同年12月に実施された電気探査の結果によれば、地盤が不安定で地盤沈下を起こしやすい状況となっていることが判明している。平成19年4月9日、原告岩野方の敷地を、敷地内において検査機関に土壌調査を私的に依頼し実施したところ
(1)表層土壌ガス調査の結果、全ての調査位置においてベンゼンが検出された。
(2)土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が土壌溶出基準を超えていたこと
(3)土壌調査の結果、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が指定基準を超えていたこと等々が明らかとなった。
三 本件団地内においては表層土においてガスが発生して臭気が漂い、土壌の性状が不安定となっていて地盤沈下の畏れがある。その臭気には発ガン性物質であるベンゼンが含まれているなど健康被害が懸念されている。有害物質を含んだ地盤の安定しない宅地であり、そもそも人が安心して安全に暮らせる団地ではない。地盤からのこのガスの発生で、原告○○方のガス漏れ警報器が作動することもあり、安心して居住できる環境にない。
5、被告会社の責任
一 被告会社は、旭油化株式会社が汚染し続けた土壌はもはや操業をやめさせるしかないほど危険な回復しがたいものであり、そのままでは小鳥の森団地の販売を継続することはできないと認識し、旭油化株式会社の操業中止とその敷地を購入して旭油化を退去させてその問題解決を図った。そして、その土壌が有害物質で汚染されていることを十分に認識して旭油化株式会社の敷地を買収した。
二 そのような有害で危険な土壌であることを認識しながら宅地として危険物質を残したまま造成し、分譲を続けた。購入者にはこのような危険な土壌であり住宅地として不適なことを秘匿して分譲した。そして、発ガン物質を含むガスが発生して危険な状況になっていても放置したままであった。
三 平成16年7月に、岡山市水道局による水道工事によって、本件団地が有害物質で汚染された危険な造成地であることが表面化しても、直ちに健康に被害をもたらすものではないと抜本的な対策をとろうとしなかった。
6、原告の損害
別紙原告の損害記載のとおり
7、被告会社は、抜本的な無害化工事を実施しなければとうてい造成地としてはならない汚染土壌のある旭油化の工場敷地を、危険な有害物質に汚染された土壌に表層土を盛り土して造成しただけで販売した。
さらに、そのように危険な造成地であるから管理を継続し、危険な兆候があれば直ちに対応しなければならないのにこれを怠り、最後までこの事実を隠蔽したまま何らの管理もしないで販売を継続した。汚染の事実が表面化しても危険はないと断言して、原告らに対して何らの対策をとろうとしなかった。
これらその都度の方針は被告会社の方針として取締役会で決定されて実行され、あるいは不作為となったものである。その結果、各原告は6項記載の通りの損害を被った。
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の返書として「両備ホールディングス株式会社は法廷で全面的に争う」との2007年7月28日付け回答書を受けて岡山地方裁判所へ提訴しました。訴状の続きです。
よって、被告は、不法行為を原因とし(民法44条1項、同709条)、各原告に発生した損害の支払いと原告が被告会社の加害行為による被害であると認識した平成16年9月28日から完済に至るまで年5分の割合による金員の支払いを求める。
附属書類
1 訴状副本 1通
2 商業登記現在事項証明書 1通
3 訴訟委任状 3通
******************************
ATCグリーンエコプラザで講演した桃花台や小鳥が丘の住民達
大阪市大の畑明郎先生と環境カウンセラーの藤原きよみさん
******************************
2009年10月23日(金)
小鳥が丘住宅団地土壌汚染第13回裁判
2009年10月20日(火)16時から岡山地方裁判所353号法廷で第13回口頭弁論準備手続きが行われました。
今回は原告住民3名の陳述書を裁判所に提出しました。
前回ブログ掲載以降の裁判経過ですが、
住民訴訟第一次(3世帯)は環境総合研究所に現地地質調査分析を依頼し2009年6月13日に職員を現地に派遣してもらい住民による調査サンプル採取を行いました。
(モニター井戸水質3か所、原告敷地駐車場土壌1か所、沼川護岸擁護壁付着物1か所、合計5か所)
7月9日に調査分析報告書が送られてきましたが、護岸の付着物もはっきりと油分が検出されていました。いずれも汚染の程度は著しいものとなっていましたので早速、調査報告書は証拠として裁判所に提出しました。
裁判長は冒頭、住民訴訟第二次(18世帯)は、現在、(不動産)鑑定準備中ですと述べた後、
(裁判長)
こちら(住民訴訟第一次3世帯)は、今までの準備資料で結審に向かっていいですね。
瑕疵担保責任・不法行為で争うのですね。
当該物件は原告3名共、被告から取得したものですか?
第二次(18世帯)には時効の問題がある人がいますが、こちらは時効の問題はありませんね。
(原告代理人河田弁護士)
先日提出した各原告の陳述書で全てです。
原告2名は土地建物すべて新築物件として被告から取得したものですが、原告1名だけは、被告の仲介で、中古物件として取得していますので瑕疵担保責任ではなく不法行為で争います。
時効の問題は原告3名共ありません。
(裁判長)
では次回は原告本人尋問を、一人30分程度行い、被告反対尋問を予定します。
午前中では時間が足らないことがあるので午後の時間帯に行います。
以上のような質疑応答があり、日程調整の結果、次回は12月8日(火)13時30分〜16時30分に決まりました。
住民訴訟第二次(18世帯)は、前回原告住民が土壌改良の為の土壌調査を求めて学者の土壌調査方法等の資料を提出しましたが、調査費用の見積もりが高額になり(約7千万円)とても負担しきれない事が判明したので、調査範囲を絞り込むなどして再度調査方法を検討し費用7百万円を見積もり、原告住民と被告両備ホールディングスで折半負担を提案しました。
裁判所も被告両備に鑑定費用を半分持てという勧告を出しましたが両備側は固辞したようです。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後5年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス?の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯も続いて提訴し係争中です。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
******************************
2009年4月15日(水)
環境委員会で小鳥が丘土壌汚染問題!
参議院環境委員会2009年4月14日で「岡山市小鳥が丘団地土壌汚染問題」が取り上げられました。
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」に関する参考人の意見聴取で、川田龍平議員の質問に参考人の畑 明朗氏(大阪市立大学大学院特任教授、日本環境学会会長)が答えました。
映像は参議院ホームページ
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/consider.php
「カレンダー」から「2009年4月14日」を選び
「環境委員会」を選び
「動画形式」から再生し
(02:35:10)時間中
(02:26:10)から(02:29:33)の部分です。
質問要旨は、川田龍平議員ホームページ
http://ryuheikawada.seesaa.net/article/117456885.html
2009年4月14日です。
******************************
2008年12月28日(日)
不思議なテレビ放映中止報道ステーション!その1
2007年1月の事、テレビ朝日報道番組「報道ステーション」から取材の申し込みが来ました。
他の環境汚染現場の取材中に「岡山市小鳥が丘団地」土壌汚染の情報を聞いたとのことでした。
承諾すると、ディレクターが下見として視察し2007年2月1日10時頃から翌日2月2日の2日間に渡り住民聞き取り調査・現場撮影・地層掘削段取り等行いました。
正式な取材日程は決まり次第連絡するとのことでした。
数日後、連絡があり、スケジュール表が送られてきて数日にわたり取材が行われました。
住民へのインタビュー、学者による地質調査、20年前の汚染発生時を知る人の聞き取り調査等、学者、ニュースキャスターや最大2組のマイクとカメラマンを動員しての大がかりな取材でした。
土壌汚染改良方法については異なる意見がある住民も、何とかしなくてはという気持ちは同じで、ほとんどの住民が取材に協力しました。
小鳥が丘団地の取材を終え、テレビディレクターはニュース公平性のため次週は宅地造成販売した両備バス?を取材するとのことでした。
しかし2〜3日後、両備バス?を取材しているはずなのに、テレビディレクターから放映を延期すると連絡が入りました。
理由は土壌汚染に対する住民の意見がまとまっていないからだということでしたが納得がいきませんでした。
次回「報道ステーション」から送られてきた取材スケジュール表を掲載します。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20081228
不思議なテレビ放映中止報道ステーション!その2
2007年2月、テレビ朝日報道番組「報道ステーション」取材内容を掲載します。
(報道ステーションディレクターから小鳥が丘団地救済協議会に送られてきたスケジュール表です)
「小鳥が丘団地・地質汚染」撮影スケジュール
2月9日(金曜日)
○○(報道ステーションディレクター氏名)・岡山入り。
12日に重機を入れる△△△△(会社名)の○○氏が岩野宅下見。
13時 岩野氏と取材打ち合わせ。
夕方○○氏(取材を受ける別の住民)と取材打ち合わせ。
2月10日(土曜日)
旭油化元関係者、当時の様子を知る周辺住民に聞き取り取材。
2月11日(日曜日)
夕方、長野智子(ながの・ともこ)キャスター 楡井久先生、 岡山前のり。
17時ごろから、岩野氏宅 ・ ○○氏宅
現在の状況、健康被害などを長野智子キャスターが聞き取り取材。
2月12日(月曜日・祝日)
8時過ぎめど
地表のガス噴出検査。
午後から岩野宅、庭を掘り起こし
NPO「日本地質汚染審査機構」 楡井久(にれい・ひさし)先生の立会いで検査を行います。
長野智子キャスターも立会い。
不思議なテレビ放映中止報道ステーション!その3
前回掲載の、テレビ朝日報道番組「報道ステーション」取材スケジュール表に記載された地質調査で、庭を掘削中、あたりに悪臭が漂い、「クサイ」を通り越して鼻が痛くなる程の刺激臭で、その場に居られなくて逃げ出すほどでした。
汚染調査を行っていた地質学者の楡井教授にインタビューしていたニュースキャスターの長野智子氏は、あまりの悪臭に「マスクを買ってきて!」と、その場にシャガミ込みました。
その場にいた人は誰でも尋常な臭気ではないと認識したはずです。
掘削用敷地の提供、インタビューの応答、情報提供、20年前の汚染発生時の証人取材の道案内等、取材には住民も全面的に協力しました。
それでもテレビ放映中断となったのです。放映の中断はテレビ局の都合としても、地質調査分析の結果報告を要望しましたが、それも断られました。
複数の住民が放映希望の連絡を入れましたが、そのうち連絡が取れなくなりました。テレビ局が多額の費用をかけて取材したものを何故途中で中断したのか、今でも疑念が晴れません。
結
******************************
2008年11月20日(木)
小鳥が丘土壌汚染第9回裁判!その1
2008年11月17(月)13時30分から岡山地方裁判所で第9回口頭弁論準備手続きが行われました。
裁判所は詳細な土壌汚染実態を把握したい意向ですが多額の費用を要する土壌調査を原告住民に求めても非現実的である事は承知しているようです。
裁判長は、午前中に行われた18世帯住民の口頭弁論で原告住民から、土壌改良の為に学者の土壌調査方法等の資料、が提出され、被告両備ホールディングスにも応分の費用負担を求めたが、被告側から拒否されたとの事でした。
住民3世帯の原告代理人弁護士は、「小鳥が丘団地」が土壌汚染である事は今までの資料でも、また裁判所現地検証でも明らかであり、こちらの原告住民は立証提出資料の通り自費で自宅の土壌調査をし、汚染物質が検出されている、住宅地としてその目的を達することのできない欠陥住宅地である、住宅地として問題ないと言うならそれを立証すべきと答弁した。
今回は住民18世帯が求めている土壌調査の推移を待つ事になった。
被告両備ホールディングスは原告立証の原則により被告側は何もする気は無い趣旨の答弁があった。
小鳥が丘土壌汚染第9回裁判!その2
2008年11月17(月)13時30分から行われた第9回裁判に原告側(3世帯住民)が提出した準備書面を掲載します。
平成19年(ワ)第1352号損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
準 備 書 面
平成20年11月17日
岡山地方裁判所 第1民事部 御中
原告代理人弁護士 河 田 英 正
第1,被告の故意、過失について
1,原告等の居住する団地は、被告会社が宅地造成し原告等に販売した(争いのない事実)。
2,本件土地は被告会社が、旭油化工業株式会社から購入したものである(争いのない事実)。
3,本件土地を被告会社が購入して宅地造成することになったのは、当時、旭油化株式会社が既にその工場内に大量の汚泥や産業廃棄物を放置し、周辺に悪臭を漂わせ、河川には死魚が浮かぶなどの公害が発生していて、社会問題になっていたことにある(甲1号証の1,2,甲10号証の1ないし7)。旭油化株式会社は廃油貯蔵タンクの底から直接土中に油分を吸収させるなど無謀な処理をしていて、敷地内はこの油泥で汚染されていた。油泥の一部は、産業不法投棄事件で有名になった豊島にも運ばれるなど不法な処理がなされていた。
4,昭和57年7月27日に岡山簡易裁判所において、隣接する土地を小鳥の森団地として販売していた被告会社と旭油化株式会社はこの悪臭などの公害問題に関し和解を成立させ(甲3号証)、実質的には、この汚泥等の処理費用を全額被告会社が負担して、旭油化工業は本件土地を明け渡し、被告会社がこの土地を取得した。
この時点で被告会社は、旭油化株式会社が、これら汚泥などを自力で撤去することは不可能であることを前提で和解を成立させている。つまり、被告会社が同社の工場等の撤去費用は、被告会社が負担し、旭油化に支払うが、約束が守られなければ損害賠償金として支払った撤去費用以上の金額の損害金を請求できるとしていた。このとき、被告会社は、油泥が土中に浸透し、汚染が工場跡地の土中に拡大していた本件土地の汚染の実態は十分に認識があった。
なお、本件土地から立ち退いた旭油化工業株式会社は別会社を設立し、赤磐郡吉井町草生地区で新たに操業を始めたが、同様の不法な処理を繰り返したため、直ちに悪臭などの公害問題を地域周辺に発生させ、その地区から退去せざるを得なくなっていた(甲7号証)。
(第1,被告の故意、過失について)
5,このような激しい汚染の実態があったにも関わらず、ごく一部の土壌を搬出除去し、表層土に生石灰を混入させて中和凝固させただけの簡便な対策にとどめたままで宅地造成し、原告等に販売した。
この対策が十分でなかったことは、現在生じている汚染の実態からも明白である。土中に浸透していた油泥が拡散し、覆土したはずの表層土にまでその汚染がでてきたため、宅地を掘ればすぐに油分を含んだ黒く変色した土壌が露出してきている(甲15号証)。
当時の汚染の実態からみると、事前に十分な汚染の実態を調査し、この宅地の油泥となって地中に浸透した土壌の成分をしっかりと把握して、その危険な成分を含む土壌を完全に搬出除去すべきであったにも関わらず、簡単に覆土をして一見なんら問題のない住宅地として仮装して販売した。
これらの事実を知らない原告らに汚染の実態についてなんら説明しないまま、四六時中生活し生涯の住居として住み続けなければならない住宅地として販売し、原告等は自然豊かな環境に恵まれた被告会社の販売する優良な住宅地であると誤信して購入した。
被告会社は、十分なる有害物質除去が行われなければ、住宅地としての安全が害されることになる現在の状況は認識すべきであり、被告会社の過失の存在は従前から述べているとおり明らかである。
また、土壌汚染の被害が出ないと軽信していたのであれば、前記のような経過をたどって販売された住宅地なのだから、販売後もその汚染が広がらないように常に監視し、その汚染が顕在化すれば、ただちにその汚染の経緯を原告等購入者に説明し、汚染が拡大しないよう汚染除去などをする義務があるというべきである。
第2,証拠上明らかとなっている汚染の実態
1,株式会社ニッテクリサーチが平成19年4月に実施した『調査結果報告書(土壌汚染状況調査業務)』(甲4号証の1,2)から少なくとも以下のことが明らかにされている。
?表層土壌ガス調査の結果、全ての調査位置においてベンゼンが検出され、土壌中からベンゼンが揮発している。
?土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素などが土壌溶出基準を超えており、土壌がこれらの有害物質で汚染されている。
?土壌調査の結果、土壌含有量基準を満足しているが、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素などの有害物質が検出されている。
?したがって小鳥が丘団地の土壌はベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素などの有害物質で汚染されていると言える。
(第2,証拠上明らかとなっている汚染の実態)
2,乙第5〜18号証について
?岡山市役所環境規制課実施の『地下水・土壌分析結果』2004年7月(乙第5・6号証)によれば、○○宅付近の地下水からヒ素が環境基準の15倍、ベンゼンが31倍検出され、土壌からヒ素、ふっ素、ほう素が環境基準以下ながら検出された。
?株式会社三友土質エンジニアリングの『南古都概況調査分析結果』2004年9月(乙第7号証)によれば、3箇所のボーリング調査(深さ1〜5m)でヒ素が土壌溶出基準の1.7〜3.2倍、ベンゼンが0.5〜26倍、トリクロロエチレンが約27倍、シス-1・2-ジクロロエチレンが約6倍検出された。また、油分が1.3〜1.9重量%検出され、油で汚染されている。
?同『南古都表層土壌調査分析結果について』2004年10月(乙第10号証)によれば、ベンゼンが34箇所中8箇所で土壌溶出基準を超え、最高11倍検出された。トリクロロエチレンは1箇所、シス-1・2-ジクロロエチレンは2箇所、ヒ素は5箇所が基準を超え、最高3倍程度だった。
?財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内ガス調査業務』2004年12月(乙第14号証)によれば、表層土壌ガス調査ですべての地点でベンゼンが検知されたほか、特定の地点でジクロロメタン、シス-1・2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、などが検出され、土壌からベンゼンなどの揮発性物質(VOC)が揮発している。
硫化水素に加えてメタンがすべての地点で比較的高濃度(3.2〜68%)で検出されたことから、地層内では有機物の嫌気制分解が相当程度進行しており、硫化水素の毒性や、メタンが引火・爆発する危険性がある。
環境大気調査では、大気環境基準以下であるが、ベンゼン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの揮発性物質が検出されており、環境大気が汚染されている。
?応用地質?の『電気探査結果』2004年12月(乙第15号証)によれば、全体に低比抵抗であり、1%以上の油分によるとしている。とくに、タンク跡は油の漏洩を示している。
?財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)』2005年3月(乙第18号証)によれば、ヘキサン抽出物質量(油分)が0.1〜10%検出され、含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。つまり、油分、水分、塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。
?旭油化は、廃油の処理を貯蔵タンクから直接、工場敷地に投入していた事実があったと原告は主張しているが、電気探査の結果(甲15号証)からもタンク跡は油の漏洩があること、タンク跡にタテ型の低比抵抗ゾーンは上に尖った形状を呈するものがあるなどそのことが推認される結果となっている。
(第2,証拠上明らかとなっている汚染の実態)
3,甲15号証 平成20年5月30日に行われた現地での検証の様子を記録したものである。本件団地のどこを掘っても、表層土が黒くなっていて、深く掘るに従ってその汚染度が激しくなっていて、異臭が漂うことが確認された。汚染は、本件団地全体に広がっていることが明らかとなっている。
(第2,証拠上明らかとなっている汚染の実態)
4,被告調査による判断の問題点
?南古都?環境対策委員会の『表層土壌調査(10/4〜6)に対する意見書』(乙第9号証)は、
「地域の一部の表層土壌から検出された物質は、以前敷地内に立地していた旭油化の機械洗浄の溶剤である可能性が高い。」
とするが、機械洗浄の溶剤とする根拠はない。
また、
「一部の検体に基準値を超えるものがあるが、非常に高濃度ということではないこと、かつ34検体中8点と全体に拡散していないこと、土中にあること、周辺の地下水の汚染がないこと等を勘案すれば、日常生活上今すぐ重大な問題になるとは考えにくい。」
とするが、
「基準値を超える汚染土壌が約4分の1に存在すること、団地内の地下水汚染が存在すること、周辺の地下水汚染は充分調査されていないこと、ベンゼン、トリクロロエチレンなどの揮発性物質は、日常的に揮発し、人体に発ガンなどの悪影響があること」
から、将来、健康影響が出る可能性は否定できない。
?南古都?環境対策委員会の『2004年11月2日付の小鳥が丘環境対策委員会に対する回答書』(乙第13号証)は、
「これらの基準は、動物実験や工場での作業労働者が化学物質に暴露されて健康影響が出る値に安全率(通常数十倍や数千倍の単位)値を掛けて策定されているので、基準値を超えたからといってすぐに健康影響(急性中毒症状や発ガン)が出るものでない。・・・住宅の下にある土壌から健康影響が出る可能性は低いと考えられる」
とするが、ベンゼンなどの発ガン物質の環境基準値は、10万人に一人が発ガンすること、そもそも環境基準は急性中毒でなく慢性中毒を起こすレベルとして設定されていること、汚染土壌は住宅の下だけでなく、住宅周辺の庭などに存在し、土ぼこりとして人体に摂取されることなどから、環境基準を超える土壌に接すると長期的に健康に悪影響を与えると考えられる。悪臭のする庭で子供たちが土いじりなどして遊ぶことによる人体への影響は、極めて危険な状態である。
?南古都?環境対策委員会の2004年12月27日付け『意見書』(乙第16号証)は、「汚染源は、汚染原因者である旭油化工業株式会社が設置した(タンク等の)施設から漏洩した汚染物質や、同社が表土を開削して廃棄した汚染物質である可能性が高い。これらの汚染物質が表層土から浸透し、地中に拡散したものと推測される」とし、乙9号証における「機械洗浄の溶剤原因説」を自ら否定する結果となっている。
?南古都?環境対策委員会の2005年3月28日付『意見書』(乙第17号証)は、「現状の生活環境においては異臭による不快感はあるものの、健康への影響が直ちに懸念されるものではない」とするが、「汚染土壌から日常的に揮発するベンゼン、トリクロロエチレンなどの発ガン物質、急性毒性のある硫化水素が発生、引火性や爆発の危険性のあるメタンの高濃度発生」などを考慮すると、異臭による不快感だけでなく、長期的な健康への悪影響が懸念される。
?岡山市環境規制課実施の『古都地区周辺環境調査一覧表』(乙第20号証)は、「井戸の深さが不明であること、地下水脈の調査がされていないこと」などから、地下水汚染調査としては不十分であり、これをもって「周辺の地下水汚染がない」と結論できない。
結
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20081120
******************************
小鳥が丘住宅団地土壌汚染第7回裁判
2008年7月9日(水)15時から岡山地方裁判所353号法廷で第7回口頭弁論準備手続きが行われました。
2008年5月30日に行われた裁判所現地視察で、住民が5箇所の宅地を掘削し、いずれの箇所も油分で汚染された真っ黒い地層と刺激臭のある油系の悪臭が、浅い地層から確認されました。
この事でも明らかなように住宅地としてはその目的を達することのできない欠陥住宅地であるとの準備書面と5月30日現地視察の録画DVDを裁判所に提出しました。
裁判所としては複数の公平な学者の意見を参考にしたいので、その前提として被告両備ホールディングス株式会社が主張し証拠資料とした「意見書」を答申した、両備バス?設立の「南古都?環境対策検討委員会」、の会議録原本を提出することを打診しています。
被告両備ホールディングス株式会社は、会議録は持っていないし提出すべき文書ではないと拒否しています。
そのため裁判所で提出命令ができる文書か検討し8月8日までに決定するとの事。(要件該当文書であれば8月9日に裁判所が文書提出命令を出します)
「南古都?環境対策検討委員会」
住民不在の両備バス?私設委員会
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/sisetsuiinkai01.html
もう一件の住民18世帯の裁判と同期進行したいので、次回の第8回口頭弁論準備手続きは2008年9月29日(月)に決まりました。
******************************
裁判所による小鳥が丘団地土壌汚染現場検証
2008年5月30日13時30分から裁判所による「小鳥が丘団地」土壌汚染現場検証が行われました。
裁判官、原告住民および弁護士や学者、被告弁護士が、多くのマスコミや関係者の見守るなか、小鳥が丘団地内を見て回りました。
各家庭の庭や駐車場を住民が削岩機で3箇所、ユンボで2箇所を掘削しましたが、どこの庭や駐車場も少し掘れば真黒い土と頭が痛くなるような刺激臭がありました。
油にまみれた土壌が目詰まりした時のように雨水や地下水の浸透を妨げているようでした。
あと地盤沈下で下がった塀や、油や石灰と思われる液体が滲み出ている擁癖や、玄関前側溝から可燃性ガス(2005年11月に地元消防署が確認)の泡が吹き出している箇所を住民が説明し15時30分頃終了しました。
******************************
川田龍平議員が環境委員会で質問
参議院環境委員会「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」審議で川田龍平議員の質問に「小鳥が丘団地土壌汚染問題」が取り上げられていましたので転載します。
http://ryuheikawada.seesaa.net/article/97567775.html#more
2008年5月22日(木)
テーマ:「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」
0 改正案について・・・・・・・
実際に、全国でこうした類似ケースや土壌汚染による紛争も多発しており、土壌汚染対策法の改正が求められていることは確かです。静岡県沼津市のJR高架化にともなう駅周辺事業の区画整理事業でもJR用地の鉛汚染や愛知県小牧市や千葉県八千代市の都市再生機構開発の住宅開発に伴う重金属土壌汚染、岡山市も小鳥が丘でのトリクロロエチレン汚染など、新聞を見ていても数多くの事件が報道されています。
1 岡山市トリクロロエチレン
岡山市の小鳥が丘団地のケースのような、過去の売買後住宅が建設され20年経過後に水道工事の際に、石鹸会社のトリクロロエチレンの土壌汚染が明らかとなり、訴訟に至っているケースがあります。こうしたケースは現行法での対応と改正法ではどのような対応となるのか?・・・・・・・
映像は参議院ホームページ
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/consider.php
「カレンダー」から「5月22日」を選び
「環境委員会」を選び
「動画形式」から再生し
(02:45:40)時間中
(02:17:08)から(02:25:51)の部分です。
******************************
小牧市桃花台地盤沈下問題でテレビ報道番組
住宅地土壌汚染・地盤沈下問題の同じ被害者として闘っている愛知県小牧市「桃花台城山地区地盤沈下問題を考える会」からテレビ報道されるとの連絡が入りました。
2008年5月25日、日本テレビ報道番組 【バンキシャ!】で桃花台の地盤沈下問題が取り上げられます。地盤沈下問題が起きている地区の一地域としての放映です。
関心のある方は是非、見てください。
愛知県小牧市桃花台「土壌汚染・地盤沈下問題を考える会」代表は小鳥が丘団地に何度か訪問され、小鳥が丘土壌汚染フォーラムに出席・現地報告もしていただきました。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20071102
2008年5月30日に行われる裁判所の小鳥が丘団地現地検証にも立会いされます。
******************************
小鳥が丘団地汚染問題掲載記事2008年5月その7
岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染は、発覚後4年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス?の考えが平行線のままで裁判に発展しています。住民3世帯が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯も続いて提訴し係争中です。小鳥が丘団地土壌汚染公害問題を扱った記事を転載します。
若井たつこ市会議員、岡山市議会にて2008年3月6日個人質問
小鳥が丘団地の土壌汚染に関して、固定資産税の減免措置について
http://wakai-wakai.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_d733.html
個人質問
小鳥が丘団地の土壌汚染に関して、固定資産税の減免をお願いしましたが「規定がないので国の法整備を待って」とにべもない答弁でした。
愛知県の小牧市では減免措置をとってますし、岡山市税条例50条にも当てはまる言葉があります。開発した民間企業と裁判になり、長期化する様相なのに、困っている市民に冷たいですよね。小牧市の減免は2割、小鳥が丘は34軒しかありません。「東京から終の住家と引っ越したのに…」と肩を落とした初老の女性の姿が目に焼き付いています。
******************************
小鳥が丘団地汚染問題掲載記事2008年5月その1
岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染は、発覚後4年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス?の考えが平行線のままで裁判に発展しています。住民3世帯が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯も続いて提訴し係争中です。小鳥が丘団地土壌汚染公害問題を扱った記事を転載します。
環境新聞2008年3月5日
土壌汚染現場の最前線 1 小鳥が丘からの手紙編?
打開の道見えぬまま3年半 汚染原因者不在のまま 住民と開発業者で民訴
土壌汚染対策法が施行されて五年が経過した状況の中、土対法を始めとした関連制度では改善できないケースや土対法が制定された当初想定されなかった問題が各方面で表面化している。土対法の見直しの検討も進められているが、土壌汚染を巡る現場ではどのようなことが起きているのか。
この連載では土壌汚染を巡る様々な課題を現場の取材などを通じて紹介していく。一回目のシリーズでは、汚染原因者不在のまま住民と宅地開発業者の民事訴訟にまで発展してしまった岡山市の「小鳥が丘団地」土壌汚染問題に焦点を当てる。
(2008/03/05)
http://www.kankyo-news.co.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=56&NCODE=293
環境新聞2008年3月12日
土壌汚染現場の最前線 2 小鳥が丘からの手紙編?
原因者不在が混乱の要因 急がれる健康被害と汚染の関係解明
関係者間の温度差が生じている「小鳥が丘団地」土壌汚染問題は、汚染原因者不在が混乱の要因となっている。この土壌汚染がどのように発生したのかとともに、現在の現地で具体的にどのような問題が起きているのかを紹介する。
問題の原因そもそもこの土壌汚染は何なのか。「小鳥が丘団地」の住民らが集めた資料写真には、雑然とした衛生的とは言えない状態の土地が撮影されている。同団地造成前に存在した事業場の写真だ。
両備バス(現・両備ホールディングス)が一九八二年に開発する前、一九七四年に廃棄物処理業の許可を取得した事業者が所有し、この場所で廃油などから石鹸やペンキの原料を製造していたという。こうした事実は開発業者の両備バスも把握しているが、「実際にはどのような行為が行われていたかは分からない」と両備ホールディングスグループの両備不動産担当者は話す。
http://www.kankyo-news.co.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=56&NCODE=298
環境新聞2008年3月19日
土壌汚染現場の最前線 3 小鳥が丘からの手紙編?
健康リスク以外にも波及 現行の制度では解消難しい問題
土壌汚染問題は、汚染地での健康問題とともに地下水などを通じて周辺地域への拡散による健康リスクの問題も抱えるほか、不動産価値など土地に関係する様々な分野にも大きな影響を及ぼす。小鳥が丘団地土壌汚染問題も例外ではなく、現行の制度では解消が難しい様々な問題を抱え、もがいている。
http://www.kankyo-news.co.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=56&NCODE=303
環境新聞 2008年3月26日
土壌汚染現場の最前線 4 小鳥が丘からの手紙編?
救済に至らない土対法の現状 横たわる費用負担問題 揮発系リスクでも提起
市街地土壌汚染問題の解決に向けた法制度には土壌汚染対策法があるが、小鳥が丘団地土壌汚染問題の救済には今のところ至らず、土対法の課題も浮き彫りにしていると言える。個人の土地所有者を考慮した費用負担のあり方や現在基準が設定されていない揮発系の健康リスクなどが浮かび上がる。(2008/03/26)
環境新聞 2008年4月9日
土壌汚染現場の最前線 5 小鳥が丘からの手紙編?
開発業者の認識がポイント 予見困難と請求却下した判例も
小鳥が丘団地を巡る土壌汚染は住民と両備ホールディングス(HD)の民事訴訟に発展し、今月四日には第五回口頭弁論も行われた。裁判の焦点は責任の所在。それを巡り混迷するこの訴訟は、小鳥が丘団地が開発された一九八二年当時、健康被害にまで影響する可能性がある土壌汚染の概念を開発業者が認識できたかどうかがポイントになりそうだ。(名古屋悟)
http://www.kankyo-news.co.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=56&NCODE=324
環境新聞 2008年4月16日
土壌汚染現場の最前線 6 小鳥が丘からの手紙編?
リスコミの重要性と難しさ 土地の将来のあり方 当初から考えに相違
住民、両備ホールディングス(両備HD)双方の話を聞くとその考え方や動きでの温度差が色濃く伝わってくる。「小鳥が丘団地」土壌汚染問題は、明確化されていない責任所在のあり方とともに、リスクコミュニケーションの重要性と難しさも浮き彫りにしている。
******************************
2008年2月18日(月)
岡山地裁で土壌汚染の民事裁判始まる!その1
岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染公害問題は、以前産業廃棄物を工場敷地内に投棄していた公害工場跡地を取得した両備バス株式会社が廃棄物を除去せず宅地造成し、住民に説明せずに販売したのが原因です。
公害工場操業時には地面に大量の廃油を長期間垂れ流し工場敷地内は油泥のような土壌となり隣接する川に油膜が張り死んだ魚が浮くようになって深刻な公害を発生させていました。
その有害物質が撤去されず造成され現在も宅地表層に存在し、そのため土地建物の資産価値は無くなるのみならず住民に健康被害が発生しています。両備バスは抜本的な対策を取ろうとせず住民が2007年8月31日に民事提訴した経緯は、“両備バスを岡山地裁に提訴!”(住民たちのブログ2007年11月20日〜)に記載しましたが、その後の経過です。
2007年11月13日に第1回口頭弁論が岡山地方裁判所において始まりました。
10時15分裁判官3名が着座し、原告側は代理人河田英正弁護士が、被告側は代理人菊池捷男弁護士を含む3名が法廷に立ち、私たちを含む30名弱が傍聴しました。
口頭弁論の様子です。
原告代理人は、予め提出した訴状の通りですと述べました。
(住民たちのブログ2007年11月25日〜 “両備バスを岡山地裁に提訴その6!〜”掲載)
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20071125
++++++++++++++++++++++++++++++
訴状
平成19年8月31日
岡山地方裁判所民事部 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田 英正
同 大本 崇
〒709−0632 岡山市南古都×××
原告 藤原 康 〒709−0632 岡山市南古都×××
原告 ○○○○ 〒709−0611 岡山市楢原×××
原告 ○○○○
〒700−0816 岡山市富田町二丁目7番8号 石橋第3ビル3階
河田英正法律事務所(送達場所)
上記訴訟代理人弁護士 河田 英正
同 大本 崇
電話 086−231−
FAX 086−231−
〒704−8112 岡山市西大寺上1丁目1番50号
被告 両備ホールディングス株式会社
被告代表者代表取締役 小嶋光信
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 227,898,580円
ちょう用印紙額 704,000円
第1 請求の趣旨
1、被告は、原告○○○○に対して58,897,520円、同○○○○に対して58,759,670円、同○○○○に対して110,241,390円とそれぞれこれに対する平成16年9月28日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え
2、訴訟費用は被告の負担とする
3、仮執行宣言
第2 請求の原因
1、当事者
一 被告会社は、昭和11年5月25日に両備バス株式会社として設立され、平成19年4月1日に両備ホールディングス株式会社と商号変更された資本金4億円の株式会社であり、自動車、船舶による旅客、貨物の運送業、観光事業、不動産の所有・売買・賃貸仲介などを業務としている。
二 原告らは、両備バス株式会社が造成した小鳥が丘団地に住居を有し、居住している者である。
2、小鳥が丘団地造成前
一 本件造成地には、廃油等を利用して石鹸を製造していた旭油化工業株式会社の工場があった。
二 同社は、業績不振のなか、昭和49年11月19日に新たに廃棄物処理業の許可を取り阪神、北九州方面の企業から産業廃棄物としての廃油を集めてその処理を始めた。その頃から、廃油処理工場からは廃油処理の黒煙が不気味に立ち上っていた。地域周辺に悪臭がたちこめ、近くを流れる沼川には油膜が張ったり、死んだ魚が浮き上がってくるなどの現象が見られた。廃油を貯蔵していたタンクが設置されていたが、その装置は単に土壌に廃油を吸い込ませる装置であったようであり、タンクの底は直接土壌に接して廃油が不法に処分されていた。そのタンクの位置は土壌への吸収が悪くなると敷地内で場所が移動されていた。そして、工場敷地内には腐敗した油脂を入れたドラム缶が散乱して放置されていて、その腐敗した油脂が敷地内の土地にこびりつき、恒常的に悪臭を発生させていた。
三 両備バス株式会社は、この旭油化工業株式会社の工場北側に既に団地(小鳥の森団地)を造成し、住民が居住していた。その住民からも旭油化株式会社の産業廃棄物処理業を始めたことによる悪臭などの環境悪化の苦情が造成・販売した両備バス株式会社などに苦情が寄せられるようになった。このころ岡山県や岡山市の公害課が何度も行政指導を繰り返していたが、何ら対策が講じられなかった。
3、両備バス株式会社の本件土地の宅地造成
一 両備バス株式会社は、上記のとおり旭油化株式会社が操業している土地の北側に小鳥の森団地(37000平方メートル)を造成・販売していた。この分譲地を購入して居住している住民から、上記のとおり苦情が寄せられるようになり、両備バス株式会社は旭油化株式会社に対して強く改善方を要求していたが、一向に改善されることはなかった。両備バス株式会社の小鳥の森団地の販売が困難な状況となっていた。
(1)旭油化株式会社は昭和57年10月31日限り操業を停止し、同年12月31日までに本件土地上の全ての建物および地下工作物を撤去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
(2)両備バス株式会社は、旭油化株式会社に対して建物撤去費用、移転補償などとして6690万円を支払う。
(3)両備バス株式会社は、旭油化株式会社の工場跡地を一坪あたり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
四 こうして、旭油化株式会社の工場跡地を取得した両備バス株式会社は、このそのままでは宅地造成地には適さない工場跡地を昭和62、3年ごろから3区画に分けて有害物質に汚染されたままで宅地に造成し、平成元年頃から分譲を始めた。
4、宅地から有害物質検出の経緯
一 平成16年7月に岡山市から上水道の鉛製給水管をポリエチレン管に取り替えたいとの連絡があり、7月29日に取り替え工事がなされた。取り替えのため給水管を掘り起こしたところ、油分を多量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥状のなかに水道管が埋められていることが判明した。
そして化学反応の安定性が高いと言われる鉛管の給水管の一部が腐蝕して穴があいている箇所も発見された。岡山市の調査によればこの時の地下水と土壌から硫酸イオンが検出された。
二 両備バス株式会社は、原告ら住民の不安の訴えに対し、土壌汚染の原因を探るべく、土地履歴の調査、ボーリングによる土壌調査などの申し入れがなされ、調査が実施された。同年9月28日原告らに土壌汚染の実態と原因が知らされた。同社の報告によっても、3地点のボーリング調査の結果は、環境基準値の約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、6倍のシスー1,2−ジクロロエチレンが検出された。
また、地下約5メートル付近では金属片やボロ切れなどが発見された。同年12月に実施された電気探査の結果によれば、地盤が不安定で地盤沈下を起こしやすい状況となっていることが判明している。平成19年4月9日、原告岩野方の敷地を、敷地内において検査機関に土壌調査を私的に依頼し実施したところ
(1)表層土壌ガス調査の結果、全ての調査位置においてベンゼンが検出された。
(2)土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が土壌溶出基準を超えていたこと
(3)土壌調査の結果、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が指定基準を超えていたこと等々が明らかとなった。
三 本件団地内においては表層土においてガスが発生して臭気が漂い、土壌の性状が不安定となっていて地盤沈下の畏れがある。その臭気には発ガン性物質であるベンゼンが含まれているなど健康被害が懸念されている。
有害物質を含んだ地盤の安定しない宅地であり、そもそも人が安心して安全に暮らせる団地ではない。地盤からのこのガスの発生で、原告○○方のガス漏れ警報器が作動することもあり、安心して居住できる環境にない。
5、被告会社の責任
一 被告会社は、旭油化株式会社が汚染し続けた土壌はもはや操業をやめさせるしかないほど危険な回復しがたいものであり、そのままでは小鳥の森団地の販売を継続することはできないと認識し、旭油化株式会社の操業中止とその敷地を購入して旭油化を退去させてその問題解決を図った。
そして、その土壌が有害物質で汚染されていることを十分に認識して旭油化株式会社の敷地を買収した。
二 そのような有害で危険な土壌であることを認識しながら宅地として危険物質を残したまま造成し、分譲を続けた。購入者にはこのような危険な土壌であり住宅地として不適なことを秘匿して分譲した。そして、発ガン物質を含むガスが発生して危険な状況になっていても放置したままであった。
三 平成16年7月に、岡山市水道局による水道工事によって、本件団地が有害物質で汚染された危険な造成地であることが表面化しても、直ちに健康に被害をもたらすものではないと抜本的な対策をとろうとしなかった。
6、原告の損害
別紙原告の損害記載のとおり
7、被告会社は、抜本的な無害化工事を実施しなければとうてい造成地としてはならない汚染土壌のある旭油化の工場敷地を、危険な有害物質に汚染された土壌に表層土を盛り土して造成しただけで販売した。さらに、そのように危険な造成地であるから管理を継続し、危険な兆候があれば直ちに対応しなければならないのにこれを怠り、最後までこの事実を隠蔽したまま何らの管理もしないで販売を継続した。
汚染の事実が表面化しても危険はないと断言して、原告らに対して何らの対策をとろうとしなかった。これらその都度の方針は被告会社の方針として取締役会で決定されて実行され、あるいは不作為となったものである。その結果、各原告は6項記載の通りの損害を被った。
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の返書として「両備ホールディングス株式会社は法廷で全面的に争う」との2007年7月28日付け回答書を受けて岡山地方裁判所へ提訴しました。訴状の続きです。
よって、被告は、不法行為を原因とし(民法44条1項、同709条)、各原告に発生した損害の支払いと原告が被告会社の加害行為による被害であると認識した平成16年9月28日から完済に至るまで年5分の割合による金員の支払いを求める。
附属書類
1 訴状副本 1通
2 商業登記現在事項証明書 1通
3 訴訟委任状 3通
<別紙>
原告損害目録
1、原告 ○○○○
宅地購入年月日 平成2年8月30日
居住開始年月日 平成3年5月3日
居住状況
入居当初は、両親、長男の4人で居住していたが、平成9年に長男が県外に就職のため家を出て、平成12年に父が死亡し、平成14年に母が死亡し、以後一人で居住している。
損害額 58,897,520円
内訳
不動産取得費等 28,897,520円
慰謝料 25,000,000円
弁護士費用 5,000,000円
2、原告 ○○○○
宅地購入年月日 平成5年1月30日
居住開始年月日 平成5年3月16日
居住状況
居住当初から現在まで、妻、長男、長女の4人家族で居住している。
損害額 58,759,670円
内訳 不動産取得費等 28,759,670円
慰謝料 25,000,000円
弁護士費用 5,000,000円
慰謝料、その他の損害発生状況は原告○○と同様。平成6年頃から家族がアレルギー性鼻炎にかかるなどの症状がではじめた。原告は庭での作業中に土壌から発生する有害ガスの影響で倒れ、救急車で病院に搬送されたこともある。原因不明のめまい、頭痛に悩まされてきていた。
3、原告 ○○○○
宅地購入年月日 平成2年6月29日
居住開始年月日 平成3年3月末頃
居住状況
広島に居住していたが、環境の良いところで過ごしたいと考え、本件団地を入手して居住を始めた。夫、長男、長女の4人家族であった。居住用とともに本件建物は夫、長女が整骨院を営むためのものでもあった。現在は、夫は平成15年1月に死亡し、長女夫婦が整骨院を営業している。平成11年頃から、娘夫婦らは別に居住するようになっているが、職場は本件住居に変わりはない。業務の性格上、本件土地での業務継続は困難となっている。
損害額 110,241,390円
内訳 不動産取得費等 80,241,390円
慰謝料 20,000,000円
弁護士費用 10,000,000円
慰謝料、その他の損害発生状況は原告○○と同様。長女、孫らは本件住居に居住していた間は、原因不明の頭痛・皮膚炎などに悩まされていた。長女の夫は、原因不明の咳に悩まされている。
<別紙>
事件番号 平成19年(ワ)第 号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
証拠説明書
平成19年8月31日
岡山地方裁判所 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田英正
番号 標目(原本写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 備考
1の1 新聞記事 写し S57.6.4 山陽新聞社 造成前の本件土地の状況
1の2 同上 写し S57.7.28 朝日新聞社 汚染土壌の被告の造成方針
1の3 同上 原本 H16.9.30 山陽新聞社 土壌汚染表面化の経緯
1の4 同上 写し H16.9.30 山陽新聞社 同上
1の5 同上 原本 H16.10.1 朝日新聞社 本件土地から有害物質が検出された事実
1の6 同上 原本 H16.10.5 同上 同上
1の7 同上 原本 H16.10.31 山陽新聞社 同上
1の8 同上 原本 H18.6.8 読売新聞社 土壌汚染による健康被害
1の9 同上 原本 H19.5.30 読売新聞社 同上
2の1 週刊金曜日 原本 H18.9.23 株式会社金曜日 本件土壌の汚染と被害の実態
2の2 同上 原本 H18.12.8 株式会社金曜日 同上
3 和解調書 写し S57.7.27 岡山簡易裁判所 被告会社が本件土壌汚染実態を知っていた事実
汚染された土壌の上に居住し、長年にわたり健康に危険な状況にさらされながら日々過ごさざるを得ず、宅地としての価値も無価値となり、本件土地に居住を継続することができなくなった。こうした不安な日々を長期間に家族とともに送らなければならなかった精神的な損害は3000万円を超える。
また新たな安全な居住地に移転しなければならず、本件土地の購入費とこの土地に建物を建築した費用は全く無駄になり、原告に生じた損害である。なお、慰謝料には被害を訴えて懸命に対処を要望したにも関わらず、被告会社の利益を優先して原告らの訴えを無視したので本件訴えを起こさざるをえなかった被告の理不尽な対応に対する精神的損害も含む。
悪臭の漂う住宅地であり、原因不明の頭痛に襲われることがあった。
++++++++++++++++++++++++++++++
被告代理人は、予め提出した答弁書の通りですと述べました。
(住民たちのブログ2007年12月10日〜 “両備バスを岡山地裁に提訴その21!〜”掲載)
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20071210
++++++++++++++++++++++++++++++
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
答弁書
平成19年10月31日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
〒700−0807 岡山市南方1丁目8番14号
菊池総合法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人
弁護士 菊池 捷男・首藤 和司・財津 唯行・安達 祐一・井田千津子
電話 086−231 FAX 086−225
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求をいずれも棄却する
2 訴訟費用は原告らの負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 第1項は認める。
2(1)第2項一は認める。正確に言うと、訴外旭油化工業株式会社(以下「旭油化」という)は、大手食用油会社から出る使用済み活性白土(廃白土)を原料として、石鹸やペンキの元となる油を生成する工場である。
(2)同項二は不知。
(3)同項三は認める。但し、「既に」がいつを指すのか不明であるので念のため主張するが、小鳥の森団地は、昭和50年に土地の造成完了、土地の販売開始が同年9月で、住民の居住開始が昭和51年3月ころからである。なお誤解のないように指摘するが、岡山県や岡山市が行政指導を行っていたのは旭油化に対してである。
3
(1)第3項一の事実のうち、両備バス株式会社(以下「両備バス」という。)の小鳥の森団地の販売が困難な状況となっていたとの事実は否認し、その余は認める。
既に昭和56年12月までの段階で、小鳥の森団地全体の約84%にも及ぶ219区画が販売済みだったものであり、同団地の住民から悪臭の苦情が増加したのでこれに対応したものであって、小鳥の森団地の販売が困難な状況になっていたわけではない。
(2)同項二は認める。
(3)同項三は認める。
(4)同項四記載の事実のうち、両備バスが、旭油化から工場跡地を取得したこと、昭和62年頃から3回(但し、正確には「3期」と言うべきである)に渡って宅地造成を行い、順次分譲を行ったことは認め、その余は否認する。
「そのままでは宅地造成地には適さない工場跡地」
とあるが、これが有害物質が存在し、両備バスがそれを認識していたとの趣旨であれば否認する。当時は悪臭のみが問題とされていたものであり、地中に有害物質が存在するとか、まして両備バスがそれを認識していたなどという状況ではなかった。また、両備バスは同土地につき、後記の通り土壌改良工事として必要な対策を採り、その上で分譲を始めているのであって、工場跡地をそのままの状態で売却したのではない。
4
(1)第4項一記載の事実のうち、平成16年7月に岡山市から上水道の鉛管給水管をポリエチレン管に取り換えたいとの連絡があったこと、取り替え工事がなされたこと(但し工事を行ったのは7月27日である)、悪臭を放つ油を含んだ土壌が出てきたこと、岡山市の調査により、地下水と土壌から硫酸イオンが検出されたことは認め、鉛管給水管の一部が腐食していたことは不知、その余は否認する。
(2)同項二第1ないし第4文は認める。
第5文は否認する。
第6文の、「全ての調査位置においてベンゼンが検出された」との点についてであるが、実際には、この調査における調査位置は2箇所のみであり、しかも接近した地点であるので、「近接した2箇所の調査位置からベンゼンが検出された。」というのが正確である。
また、この土壌ガス調査及び土壌調査によると、トリクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレンについてはいずれも定量下限値以下の量しか検出されなかったことも付言する。さらに、含有量試験の結果によると、シアン化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、の含有量値は指定基準を満たしていた。
特にシアン化合物は、通常0.1?/L未満であれば、本来、測定値欄に「検出せず」と記載されるものであるが、この時は「0.01?/L」と表記されているものであり、本来なら「検出せず」の扱いを受けるものであることを付言しておく。
また、原告の指摘する(2)と(3)は内容が重複している。
(3)同項三は否認し争う。
5
(1)第5項一は否認する。両備バスが旭油化から土地を購入したのは、旭油化が度重なる行政指導にもかかわらず、付近に悪臭をまき散らしていたため、旭油化が排出する悪臭を絶つには操業を辞めさせる以外にないと判断したから、またそうするよう付近住民からの強い要望があったからであり、土壌汚染のことについては知る由もなかった。
(2)同項二は否認する。危険な土壌であるとの認識はなかったし、もちろん住宅地として不適なことを秘匿して分譲したなどという事実もない。また、現在の状況についても後述の通り放置したわけではない。
(3)同項三は否認する。
6 別紙原告の損害について
(1)1項記載に事実のうち宅地購入年月日は認め、居住開始年月日及び居住状況は不知、損害額は否認し争う。
ア 不動産取得費等について内容について釈明を求める。
イ 慰謝料について長年にわたり健康に危険な状況にさらされたことを慰謝料請求の根拠としているが、まず本件土壌の汚染が原告に発覚するまでの時点においては原告に精神的損害は発生しえないし、身体的損害が生じていたのならそれを損害として金銭に評価すべきである。
また、汚染発覚後についても、被告は住民の不安を除去するための方策をいくつも講じているから、原告の精神的損害は因果関係がない。
また、原告は訴訟を提起せざるをえなかったこと自体が精神的損害であるかのように述べているが、そこに金銭をもって慰謝すべき精神的損害はない(原告の論によれば、およそ民事訴訟の被告は常に損害賠償義務を負うことになる)。また、原因不明の頭痛は原因不明であるが故に本件とは関係がない。
(2)2項記載の事実のうち、宅地購入年月日は認め、居住開始年月日及び居住状況は不知、損害額は否認し争う。
ア 不動産取得費等について(1)に同じ。
イ 慰謝料について同上。アレルギー性鼻炎、めまい、頭痛は原因不明とあるように本件とは関係がない。
(3)3項記載の事実のうち、宅地購入年月日は認め、居住開始年月日及び居住状況は不知、損害額は否認し争う。
ア 不動産取得費等について(1)に同じ。
イ 慰謝料について同上。頭痛、皮膚炎、咳は原因不明とあるように本件とは関係がない。
7 第7項は否認し争う。
8 よって書きは争う。また、原告の主張を前提にしても、遅延損害金は平成16年9月29日から付すのが正しい。
第3 被告の主張
1 本件土地の現状について
(1)両備バスは本件発生後、住民の不安を解消するために、以下のような調査を行っている。
ア 平成16年9月6日ないし11日、団地内3カ所においてボーリング調査及び土壌分析。
イ 平成16年10月4日ないし6日、団地内34カ所において表層土壌調査及び分析。
ウ 平成16年12月に団地内土壌ガス調査及び環境大気調査。
エ 同月に団地内土壌電気探査。
オ 平成17年2月17日及び18日に団地内土壌化学性状調査。また、この間に、岡山市において以下のような調査を行っている。
カ 平成16年8月26日ないし10月7日に井戸水調査。
キ 平成16年11月4日に河川における油状物質調査。
(2)また、両備バスは、平成16年10月15日、問題の詳細調査・研究及び上記調査結果の分析、問題の解決方法の検討を、南古都?環境対策検討委員会(以下「委員会」という)に委任した。当該委員会は、農学博士千葉喬三(岡山大学学長)を委員長とし、工学博士、農学博士、医学博士、を構成員に迎え、オブザーバーとして岡山市環境保全部部長・岡山市保健所所長も加えた上で結成された専門家集団であり、両備バスも、その後両備ホールディングス株式会社となった現被告も、その調査内容・分析・意見書の作成等に何らの口出しもしていない。
(3)委員会は前記の調査結果等を踏まえて、平成16年10月30日、12月27日、平成17年3月28日の3度にわたって、意見書を作成しているが、それによると
?土壌汚染については、一部検体に基準値を超えるものがあるが、非常な高濃度というものでもなく、団地全体に拡散しているわけでもないこと、土中にあること、地下水の汚染がないことを考えれば、日常生活上重大な問題になるとは考えにくい、
?環境大気調査は環境基準値を満たしており、問題はない、
?異臭の原因は土中の硫化水素と思われ、また土中にガスが多量に集中して存在する可能性は低く、今後減衰していくものである、
?土中に空洞やドラム缶などが存在する可能性はほとんどない、とのことである。
また異臭による不快感についても、委員会から対策工事案が提出されているため、それに従った工事を行うことを前提に、費用の一部を支弁することを、原告らを含む団地住民に提案している。
2 本件土地購入時の対策について
両備バスは、本件土地の取得当時、本件団地は植物油の精製工場の跡地であると認識していたため、土壌が有害物質で汚染されていることについては知る由もなかったため、不法行為に関する故意はない。
また、たしかに、本件土地は取得当時から悪臭が問題になっていたため、両備バスは昭和59年に土壌改良工事として、3673万2000円をかけて埋没されていたドラム缶や油分の多い土壌を搬出除去し、表層土に生石灰を混入することで中和凝固させ、消臭剤の噴霧等の施工を行うなど、必要な対策をとった。また、宅地として分譲する際には、岡山市の開発許可を得て造成を行った上で分譲しており、当時は完全に合法的な売買だったのである。そうでなければ、営利団体である両備バスが、通常の地価より高い価額(全体で2億円以上)で取得するはずがない。
従って、造成工事時及び売買契約時に、上記対策工事方法では将来土壌汚染等の問題の惹起を予見することは不可能であったから、過失もない。
3 よって、原告ら主張の不法行為は成立しない。
以上
++++++++++++++++++++++++++++++
これをもって2007年11月13日に第1回口頭弁論が岡山地方裁判所において始まりました。
結
++++++++++++++++++++++++++++++
第2回口頭弁論が2007年12月11日、10時15分岡山地方裁判所開廷の予定で、前もって、被告側から被告会社が2004年実施した土壌調査報告書を、原告側から住民が2007年実施した土壌調査報告書他を裁判所に提出しました。
2007年12月11日開廷の第2回口頭弁論の前に原告側が提出した資料を説明する準備書面の内容です。
++++++++++++++++++++++++++++++
平成19年(ワ)第1352号損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
準備書面
平成19年12月10日
岡山地方裁判所 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田 英正
第1,本件土地の土壌汚染の激しさ
1,甲10号証の1,2は、旭油化が、操業によって周辺に悪臭を放ち、沼川に油膜が張って、死んだ魚が浮くようになっていた昭和56年5月の状況である。工場周辺にはドラム缶が散乱し、敷地内は油泥のような土壌となっていた。
2,旭油化が操業を中止して被告会社に土地を引き渡す前の昭和57年12月1日の旭油化の工場の状況を撮影したのが甲10号証の5,6,7である。廃油が入ったままのドラム缶が積み上げられていたり、底の抜けた廃油貯蔵タンクが無残な姿を見せている。廃油を処理しないで、土壌に直接吸収させていた実態が明らかとなっている。また、旭油化が集めた廃油類の一部は、処理されないまま産廃不法投棄事件の現場である豊島に運搬されていた。
3,旭油化は、被告会社と和解(甲3号証)が成立した後に、本件場所での操業を中止し、同様の廃油処理業務を昭和57年吉井町草生地区で三和開発の看板を掲げて始めた。
操業を始めるや否や、直ちに周辺住民から異臭や河川、地下水の汚染などの苦情が寄せられた。ここでも、廃油などを素掘りの穴に直接投棄するなどのことをしていて、敷地土壌は、油泥に覆われるようになっていた。旭油化の操業の実態と異なることのない操業方法を繰り返していたのである。
吉井町の厳しい行政指導があり、数ヶ月で操業をやめ、投棄油の回収、工場内の汚染土石類が搬出された。吉井町は、この土壌の安全性を確保するために、汚染土壌の搬出などほぼ1年をかけて地下水の汚染の影響の調査を継続するなどのことが続けられた
(甲8号証、甲9号証)。
本件被告会社が造成販売した住宅地の土壌の汚染は、日本で最大規模のものではないかと言われているのはこうした旭油化の操業の実態と悪質性が背景にある。
第2,被告会社の故意、過失
1,被告会社は、本件土地を取得するようになった経緯からも上記の本件土壌の汚染の実態は十分に認識していたし、認識すべきであった。
旭油化が廃業し、新たに旭油化と代表者を同じくする瑞穂産業が吉井町草生地区で三和開発と称して操業を始めていた廃油処理も、素掘りの穴に直接に廃油類を流し込むという激しいものであった。さらに、破産手続きに入るなど財政的基盤がなく、全く誠意のみられない対応であった。
2,このように汚染された土壌に対して、汚染土壌を完全に搬出するなどの措置をとらず、一部ドラム缶や工場の残滓なども埋めたままで造成をしている。その結果、本件造成土壌全般に汚染が広がっている実情がある。
3,被告会社が、本件土地の取得をめぐって昭和57年に岡山簡裁で和解をしている(甲3号証)。和解条項3項では、建物撤去、構造物撤去は旭油化側の責任で行い、その費用6690万円を被告会社側が負担し、さらに土地代として1310万円を旭油化に支払うという約束をしている。
しかし、一方において第11項では、旭油化が本和解条項に違反したときは旭油化に対して上記各金額の合計額である8000万円の損害賠償請求権が旭油化に対して発生すると取り決めている。
被告会社はもともと旭油化が和解条項など守る能力も意思もないことを予測しながら、基本的には旭油化に建物の撤去責任を持たせようとしたのである。
結局、当初から双方が実質的に合意していたように被告会社は、土地の売買代金のうち1310万円と建物撤去費用6690万円の合計8000万円は損害賠償金と相殺し、これを支払わないで処理しているのである。
4,被告会社は旭油化が、公害発生企業であり、無法な操業をして土壌の激しい汚染を起こしていて、その原状回復の能力も意思もないことを知りながら、本件造成地を一部損害賠償金と相殺するなどして取得し、簡単に一部の土を搬出し、汚染土壌のまま造成工事をした。
第3,汚染の実態
1,原告らの居住する本件造成地に行けば、全体に石油臭がしている。この臭いは、梅雨時、夏場に強い傾向がある。沼川のコンクリート擁癖には黒い染みが出ていて、土壌からの油類による汚染の存在が目に見える。このことだけで住宅地としてはその目的を達することのできない欠陥住宅地である。
2,地表(表層土)からガスが発生していて、ガス漏れ警報器が作動することもある。土を掘ればすぐに黒い油分を含んだ土が出てくる。健康被害も出ている。
3,検査の結果も広範囲な激しい土壌汚染を推測させる内容となっている。
?平成16年7月末、岡山市は本件造成地内における水道管取り換え工事の際に出てきた油分を含んだ水を検査した。ベンゼン、ヒ素が検出された。
?平成16年8月、岡山市が本件造成地周辺の川、井戸の水質検査を行った。井戸で基準値を超えたヒ素を検出している。
?平成16年9月、被告側でボーリング調査。基準値を超えるトリクロロエチレン、シス―1、2―ジクロロエチレン、ベンゼンなどが検出されている。
?平成16年10月、被告側で表層土調査がなされている。基準値を超えるシス―1、2―ジクロロエチレン、ベンゼンなどが検出されている。
?平成16年10月被告側で土壌ガス調査。ベンゼン、硫化水素が全地点で検出され、メタンも高濃度で検出された。
?平成16年12月、被告側で電気探査を実施(甲6号証)。
低比抵抗値を示す部分が旧地形推定線より下側に存在し、広範囲に油類等の汚染の実情が推測される。
深度4.45メートル〜5.80メートルで金属片が発見されている。ドラム缶が存在する可能性も否定されていない。
?平成19年4月、原告○○方において表層土壌ガス、土壌調査を原告側で行った(甲4号証1,2)。
全地点においてベンゼンが検知され、基準値を超えるベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素が土壌から検出された。
4,上記の汚染実態が存在するだけでも、住宅地として使用の目的に耐えない。
被告会社の責任で本件造成地の汚染土壌を完全に搬出し、汚染物質を除去できない以上、原告らは新たな住宅地を他に求めて、新たに住宅を建築するしか方法がなくなっている。
(平成14年9月27日東京地裁判決 油類による土壌汚染は宅地の瑕疵に該当)
<別紙>
事件番号 平成19年(ワ)第1352号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
証拠説明書
平成19年12月7日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田英正
番号 標目(原本写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨
4の1 調査結果報告書 原本 H19.4 株式会社ニッテクリサーチ 本件土地内の土壌汚染の実態について
4の2 測定データ 原本 H19.4 株式会社ニッテクリサーチ 本件土地内の地表大気にベンゼン系土壌汚染を疑わしめるデータが存したこと
5 被告会社グループのホームページ 写し H16.9.30 被告会社企業グループ 被告会社と岡山大学とは包括連携協力関係にあり、乙1号証ないし4号証の評価に関する記事は公正さを欠いていること
6 岡山市南古都住宅地調査電気探査結果資料 写し H16.12 被告会社・応用地質株式会社 表層土全域に1%以上の油分が確認されていること。標高8m付近にLNAPLの可能性があり、油汚染が拡大している状況
7 山陽新聞記事 写し S58.5頃 山陽新聞社 旭油化が本件土地からの移転先でもすぐに土壌汚染問題を起こしていた事実
8 メモ 写し S58.5頃 吉井町 同上(旭油化の悪質性)
9 草生地区公害処理経過報告書 写し S58.7頃 吉井町 同上
10の1 写真 写し S56.5頃 旭油化工業の操業状況を撮影したもの
10の2 同上 写し S56.5頃 同上
10の3 同上 写し S56.8.23 旭油化工業の公害問題調査が行われている状況を撮影したもの
10の4 同上 写し S57.1.21 旭油化工業の操業状況
10の5 同上 写し S57.12.1 昭和57年12月1日の本件土地の状況
10の6 同上 写し 同上 同上
10の7 同上 写し 同上 同上
11の1 無機シアン化合物(「化学物質ファクトシート」から) 原本 H17.8 環境省 無機シアン化合物の毒性等健康影響について
11の2 トリクロロエチレン(「化学物質ファクトシート」から) 原本 H17.9 環境省 トリクロロエチレンの毒性等健康影響について
11の3 ベンゼン(「化学物質ファクトシート」から) 原本 H17.10 環境省 ベンゼンの毒性(発ガン物質)、健康影響について
++++++++++++++++++++++++++++++
予め、被告側から被告会社が2004年実施した土壌調査報告書を、原告側から住民が2007年実施した土壌調査報告書他(前回掲載)を提出して、2007年12月11日、10時15分岡山地方裁判所で第2回口頭弁論がありました。
裁判官は調査地点等の団地全体位置関係が今一つ把握できないようで、要請があり、次回までに原告側から位置の分かる地図を作成することになりました。
次回口頭弁論は2008年1月29日(火)10時20分と定め10時22分終了しました。
++++++++++++++++++++++++++++++
前回口頭弁論では裁判官より小鳥が丘団地内土壌汚染調査の位置の分かる地図等の要請があり、予め原告側から土壌調査資料用地図・住宅地図及び空中写真地図等を提出し、2008年1月29日、10時20分岡山地方裁判所で第3回口頭弁論がありました。
原告代理人河田英正弁護士および大本 崇弁護士、被告代理人首藤和司弁護士他1名が法廷に立ちました。
裁判官は提出した地図のうち1枚を、おおもとの図面にしたい旨発言がありました。
そのあと裁判官は、小鳥が丘団地土壌汚染の別件初回口頭弁論が3月4日にあるので次回はその後にしたい旨発言がありました。
「小鳥が丘団地住民」23名が2007年12月27日に両備ホールディングスを提訴したのです。
以前、原告代理人河田英正弁護士から、別の小鳥が丘団地住民から依頼された弁護士から情報提供の要請があるので提供してもいいか?との打診があったので了解していました。
裁判官は、被告代理人弁護士に対し、同じ事件だと思うので被告の資料は同じものは資料番号を同じにしてもらいたい。被告答弁は同じでしょう?
との発言に、被告代理人弁護士は、違う個所もあるので、その答弁は別にして、同じ答弁の箇所は番号を揃える。
との答弁がありました。
裁判官は、各々の裁判は個々に並行して行うと述べ、次回第4回口頭弁論は2008年3月11日(火)13時10分からと定め10時30分終了しました。
今回は愛知県小牧市桃花台ニュータウン地盤沈下問題を考える会代表の丸山直希氏も傍聴に来られていて、裁判所に提出した公害工場操業当時の空中写真を見せたところ、現在の小鳥が丘団地の空中写真と重ね合わせたら状況が良く分かるのではないかとの提案で、最近の小鳥が丘団地空中写真を調査するために、環瀬戸内海会議事務局長の松本宣崇氏とともに岡山県立図書館に行きました。
最近のものは平成4年の空中写真があったので、重ね合わせ加工は丸山氏にお願いし、2日後重ね合わせ写真が送られてきたので、弁護士に届けました。
河田弁護士は、工場操業時配置と現在の住宅団地の位置関係が良く分かるので早速裁判所に提出するとの事でした。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20080229
++++++++++++++++++++++++++++++
原告代理人は、両備バスの答弁書「第3、被告の主張」で両備の実施した調査につき答弁しているのだからその資料の提出を要求し、また原告側独自の調査資料もあるから提出すると述べました。
裁判官は、追加資料を原告被告とも提出してから審議を行う方がよいだろうと述べ、第2回口頭弁論を平成19年12月11日の10時15分からと定め10時25分終了しました。
******************************
岡山県警本部へ提出した告訴状!その1
日本で最大規模のものではないかといわれている岡山市小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染は、宅地造成販売した両備バス株式会社が抜本的な土壌汚染対策を取ろうとせず、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題長く放置されています。以前住民たちのブログで紹介した“両備グループを刑事告訴!” (2007年2月11日〜2月22日)の告訴状2名分を掲載します。告訴状の書き方など全く分かりませんでしたが、アドバイスを受けながら住民だけで告訴状を作成し2006年11月1日に岡山県警本部へ告訴しました。
両備バスが立ち上げた岡山大学の先生を中心とする両備バス私設委員会「南古都?環境対策検討委員会」が最終意見書(第3回目意見書)を2005年3月28日に提出して以来、両備バスは追加土壌調査も住民との話し合いも拒否し、「裁判以外は相手にしない!」としか言わなくなりました。
この時点で最終的には民事裁判になるかもしれないと思いましたが、一般住民が健康と財産の被害を受けていて、公的機関が何もしないはずは無いと思い、各関係諸機関に相談に回っていました。
警察へは地元の岡山県警、西大寺支所へ何度も相談に行きましたが被害届けの意思を示しても要領を得ません。そこで岡山県警本部へ刑事告訴をしようと研究を始めました。
弁護士に依頼するのが一番手っ取り早いのですが資金に限りがあるので住民だけで告訴しようと調べましたが告訴状など見たことがないので告訴状を作成してもらおうと司法書士を訪ねました。
しかし1か月以上かかるとの事なので、いろいろな人に聞きながら不十分ですが住民だけで告訴状を書き上げ、ともかく2006年11月1日に岡山県警本部へ提出しました。
告訴状提出当日の様子は前に掲載したとおりです。
2007年2月11日(日) 両備グループを刑事告訴!その1
両備グループを宅建法の土壌汚染重要事項説明違反で告訴
平成18年11月1日11時に小鳥が丘団地住民2名で岡山県警生活環境課に宅地建物取引業法違反の告訴状を提出しました。
出向くと11時前からテレビ局や新聞記者が数社待ち構えていました。
゛記者会見はどこですか?゛の質問に、県庁内会見室や県庁記者クラブ会見室を交渉しましたが、了解が得られず、建物外なら良いとの事で、゛県庁中庭にします。゛と答えました。
記者の大まかな質問が終わると11時5分前だったので、県警本部の建物に入ろうと歩きかけると記者の人に、゛11時と聞いているので皆にその様に連絡しているので11時丁度まで待ってください。゛
と言われました。
11時丁度になったので、゛行きますよ。゛と言うと、カメラマンが、゛向こうの方からゆっくり歩いて入ってください。゛
と言いながら、その様子を撮影していました。
県警本部受付に用件を伝えると、再び表に出て分庁舎の生活環境課に案内してくれましたが、記者やカメラマンは県警本部玄関前に足止めをされた様でした。
県警本部の分庁舎4Fの生活環境課に入ると、次長と他に1名職員が応対してくれました。
事情説明の後、2名分の告訴状と疎明資料を提出すると、丁寧に内容を見ていただきました。短い質問をしながら読み終えると
、゛内容は良く分かりました。゛と言いながら、
゛弁護士に依頼されていれば予め分かったと思いますが、刑事上の時効が成立しています。゛といわれました。
私達は、売買契約の時に土壌汚染があった工場跡地の宅地であった説明を受けていないし、両備グループが土壌汚染地であると認識をしていたのは裁判調書でも明白なので、
故意に事実を告げなかった場合は時効の特例があるのでは?との質問に、
゛特例は有りません。゛ さらに付け加えて゛事情はよく分かりますが、法律上、刑事事件としての時効が成立している以上、受理できません。゛
゛我々は法律上でしか、行動できません。゛との回答でした。
そこで、我々小鳥が丘団地の場合の時効は何年ですか?と質問しました。
゛犯罪事実に適用する罰条の法定刑によって1年、3年となりますが、この場合には3年です。゛との回答でした。
岡山県警生活環境課の説明では、小鳥が丘団地土壌汚染の重要事項説明違反の時効は、3年との事でしたが、土壌汚染は見た目には分からないし、長期間経過した後に何かの原因で発覚するのが普通なので、建物のように購入者が1年や3年で地下の汚染を発見するのは難しいと思います。
法律の不備を感じます。
犯罪の種類によっては時効が完成していない場合もあると思われますので、その時は相談に乗ってくださいとお願いして退出しました。時計を見ると1時間以上も経過して昼を過ぎていましたので、
゛記者も昼食で解散しているかもしれないな゛と思いながら県庁中庭に行ってみると、まだ皆さん待っていました。
私達を見つけると、走り寄ってきて周りを取り囲まれ、質問責めに遭いました。
記者会見で、告訴状提出の内容を説明した後、追加の質疑応答は次のようなものです。
(記者)
現在、両備グループと話し合い継続中なのでは?
(住民)
両備グループは、法的責任がないと住民が認めない限り、話し合いにも、応じないと主張しています。 しかし認めても解決実施の確約は有りません。
つまり両備グループは話し合いだけして、何もしないで良い事にすらなりかねず、とうてい容認できません。
(記者)
両備グループは当時の法律に基づいて小鳥が丘団地を開発・販売し、土壌汚染の認識はなかったといっていますが?
(住民)
当時、両備グループが旭油化工業跡地を取得する時、有害物質の除去を条件とし、違反した時の損害賠償金を明記して買収した、裁判記録が残っていますので、土壌汚染を認識していたのは明白です。
(記者)
今後どうするのですか?重要事項説明違反以外の理由でも告訴出来るのでは?
(住民)
時効が成立してない何か別の違反を知っていれば教えてもらいたいぐらいです。別の告訴も模索していきますが、刑事事件の時効は短いですから、見付けられない場合には、最終的に民事訴訟に成らざるを得ません。
朝から忙しい1日でしたが、あっという間に過ぎてしまいました。
しかし、いくら時効になったとしても、両備グループの不正は不正であり、不正の事実が消える事は有りません。
これからも不正の事実を訴え続けていかなければなりません。
そして、行政はこの問題に対して消極的ですが、社会問題としてこれから頻発するであろう土壌汚染問題に、行政としてどう取り組むのかを問いつづけていこうと思っています。 結
++++++++++++++++++++++++++++++
住民Aの告訴状です。
告訴状
告訴人
岡山市南古都××× ○○○○ 昭和××年××月××日生
被告訴人
岡山市西大寺上1丁目1番50号 両備バス株式会社 宅地建物取引主任者 ○○○○
岡山市錦町7番23号 両備バス株式会社 代表取締役社長 小嶋 光信
宅地建物取引業法違反告訴事件
1.告訴の主旨
被告訴人らの犯罪事実に記載した行為は、宅地建物取引における重要な事項について、故意に事実を告げず販売し、売買契約の不法行為により被害を受けたことは、宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号に違反するので、捜査の上、厳重に処罰されるようここに告訴いたします。
2.犯罪事実
(1)被告訴人の○○○○は、両備バス株式会社の宅地建物取引主任者である。告訴人が居住する小鳥が丘団地の自宅、宅地面積203.82?及び、延べ床面積建物110.95?の取引につき、平成5年1月30日に仲介業者として重要事項説明をし、仲介業者である被告訴人らを通して売買契約を交わし告訴人はこれを購入した。
(2)平成18年6月5日に倉庫工事の為、告訴人が自宅庭を掘削したところ地下15cm〜40cm部分から黒い刺激臭のする土壌が出てきた。現地確認をしてもらう為、仲介業者であり、土地の造成販売業者でもある被告訴人らに連絡をしたところ、被告訴人らは現地確認を拒否し、現地はそのままの状態だった。
(3)平成18年10月13日、告訴人は、自宅庭が掘削されたままの状態であった為に自家用車を外部駐車場に置いていたが、自宅庭に、駐車する場所を確保しようと、掘削跡の埋め戻しや堆積した土壌を移動中に、15時頃自宅庭で倒れ、救急車で病院に搬送され治療を受けた。
原因は庭の掘削跡に水が常時溜まっていて、移動中の堆積した黒い土壌と反応して発生したガスを吸い込み身体に異変を生じた為で、病名は亜硫酸ガス中毒である。庭の土壌は通常生活を営むうえで健康被害を及ぼす有害物質である事が確認された。
(4)被告訴人らは本団地の土地を取得する際、昭和57年7月27日岡山簡易裁判所において和解をしている(相手方、旭油化工業)。和解条項に本件土地上のすべての建物及び地下工作物を収去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及び、アスファルト部分を除去し、本件土地上の油脂付着物を除去して、と明記しているが、現状を見るに、廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去をしていない。
(5)告訴人は売買契約時、被告訴人ら、から売買契約対象物件が土壌汚染された土地であった事実の重要事項説明を受けておらず、被告訴人らは本団地の土壌汚染が問題になった平成16年当時、汚染土壌を石灰で中和させたと申し立てているが、廃白土等除去に替えて石灰で中和させ土壌改良したのであれば、告訴人ら土地購入者にとって、これも重要事項であるにもかかわらず、売買契約時に、説明を受けていない。
(6)被告訴人らは裁判で和解をする時、和解条項に廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去を明記しているのだから、土壌が汚染されており、除去しなければならない、と認識していたことは明白である。
(7)よって当該契約対象物件の売買契約時に、被告訴人らは告訴人に土壌汚染の履歴のある宅地である旨の重要事項説明をすべきところ、被告訴人らは宅地建物を円滑に販売する為、故意に事実を告げず、告訴人は事実を知らず購入した。これは宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号違反である。
3.補足経緯
(1)最初に問題になったのは、岡山市水道局が進めている鉛製給水本管の取替工事中である。本団地が開発された昭和62年に埋没された鉛製給水本管を取り替える為、平成16年7月27日に水道工事業者が本団地内道路を掘削したところ、悪臭と油が出てきた。
(2)宅地を造成販売した両備バス株式会社と担当行政の岡山市に調査及び改善を求めたところ、3箇所のボーリング調査他の調査を実施し、環境基準値を超える有害物質が検出され、本団地造成前に操業していた公害工場の旭油化工業の廃棄物が原因と判断されたが、両備バス?が設立した、千葉 岡大副学長(当時、現岡大学長)を中心とする「南古都? 環境対策検討委員会」の意見書により、住民の健康への影響が直ちに懸念されるものではない、と回答し、住民が要求しても、その後の住民との話し合いも、住民の不安を払拭する為の追加調査も実施していない。
(3)告訴人は、体調が悪いのは、土壌が原因ではないかと思い、庭の表層土の入れ替えを自ら実施しようと、平成18年10月5日に岡山市環境保全課に出向き、廃棄土壌の指定場所を求めたところ、土壌の汚染はあるので指定区域から搬出される汚染土壌と同様に適正に処分する様に指導された為、告訴人は本団地の土壌は汚染されているとの認識をもった。
(4)汚染原因者の旭油化工業は近郊の赤磐郡吉井町(現あかいわ市)の工場で、当地と同様に廃油を垂れ流して土壌汚染を引き起こした為、吉井町ではこの公害工場を昭和58年1月に撤退させ跡地を調査し土壌汚染が深刻と判断し土壌入替えを行っている。被告訴人らは本団地を造成する前に、吉井町で同一企業が同様の工場を操業した跡地の吉井町の土壌入替え対策を知り得たはずであるから、操業期間から推定しても、地上及び地中の汚染は吉井町以上の疑いがあると認識していた、と考えるのが妥当である。
(5)被告訴人らは、これらの完全除去を確認せずして用地を取得し告訴人らに販売したのであり、除去してない廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の汚染により、その後の告訴人が受けた被害の責任は被告訴人にある。
4.両罰に関する規定
被告訴人両備バス株式会社は告訴人らに対し重要な事項について、故意に事実を告げず宅地を販売したのであるから、宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号違反について、第八十条(罰則)、第八十四条(両罰規定)により、処罰の対象である。
5.違反条文
○宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号
6.罰条
○宅地建物取引業法第八十条
○宅地建物取引業法第八十四条(両罰規定)
7.疎明資料
(1) 上申書 一通
(2) 重要事項説明書 一通
(3) 不動産売買契約書 一通
(4) 鉛製給水管使用について(回答)書 一通
(5) ボーリング調査濃度計量証明書(No3地点) 一通
(6) 表層土調査濃度計量証明書(土壌14) 一通
(7) 両備バス? 南古都?環境対策検討委員会 意見書 一通
(8) 告訴人自宅庭を掘削した写真 一枚
(9) 岡山市環境保全課の汚染土壌の処分方法について 一通
(10) 告訴人の病状退院証明書 一通
(11) 昭和57年7月27日の和解調書 一通
(12) 吉井町公害企業施設撤去新聞記事 一通
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20080317
++++++++++++++++++++++++++++++
次に住民Bの告訴状です。
告訴状
告訴人
岡山市南古都×××× ○○○○
昭和××年××月××日生
被告訴人
岡山市西大寺上1丁目1番50号 両備バス株式会社 宅地建物取引主任者 ○○○○
岡山市錦町7番23号 両備バス株式会社 代表取締役社長 小嶋 光信
宅地建物取引業法違反告訴事件
1.告訴の主旨
被告訴人らの犯罪事実に記載した行為は、宅地建物取引における重要な事項について、故意に事実を告げず販売し売買契約の不法行為により被害を受けたことは、宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号に違反するので、捜査の上、厳重に処罰されるようここに告訴いたします。
平成18年11月1日
岡山県警察本部 県警本部長 殿
告訴人 ○○○○ 印
2.犯罪事実
(1) 被告訴人の○○○○は、両備バス株式会社の宅地建物取引主任者である。告訴人が居住する小鳥が丘団地の自宅、宅地面積159.72?売買代金9,101,000円及び、延べ床面積105.58?請負代金16,375,970円(消費税込み)の建物につき、平成2年8月30日に重要事項説明の後、契約を交わし告訴人はこれを購入した。
(2) 平成17年頃より突発的かつ継続的に頭痛が起こり、診断の結果、本団地内で高濃度に検出された有害物質の影響の可能性を指摘された。
(3) 平成17年10月19日に中国銀行平島支店に不動産担保融資申し込みを行なったが、告訴人自宅土地建物は売買取引が非常に難しいので担保にならない、と融資を断られた。
(4) 告訴人の自宅は、地盤沈下しており、建物の傾斜で戸の開閉が年々できなくなっている。
(5) 告訴人の自宅は、当初被告訴人ら、から購入した土地建物のみならず、その後、追加的に行なった建物付属設備や建物補修工事を含め資産価値が無くなった。
(6) 本団地内の住人、○○○○氏が平成18年10月13日に自宅庭の土壌を移動中に亜硫酸ガス中毒になっている。
(7) 被告訴人らは本団地の土地を取得する際、昭和57年7月27日岡山簡易裁判所において和解をしている。和解条項に本件土地上のすべての建物及び地下工作物を収去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及び、アスファルト部分を除去し、本件土地上の油脂付着物を除去して、と明記しているが、現状を見るに、廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去をしていない。
(8) 告訴人は売買契約時、被告訴人ら、から売買契約対象物件が土壌汚染された土地であった事実の重要事項説明を受けておらず、被告訴人らは本団地の土壌汚染が問題になった平成16年当時、汚染土壌を石灰で中和させたと申し立てているが、廃白土等除去に替えて石灰で中和させ土壌改良したのであれば、告訴人ら土地購入者にとって、これも重要事項であるにもかかわらず、売買契約時に、説明を受けていない。
(9) 被告訴人らは裁判で和解を成すにおいて、和解条項に廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去を明記しているのだから、土壌が汚染されており、除去しなければならない、と認識していたことは明白である。
(10) よって当該契約対象物件の売買契約時に、被告訴人らは告訴人に土壌汚染の履歴のある宅地である旨の重要事項説明をすべきところ、被告訴人らは宅地建物を円滑に販売する為、故意に事実を告げず、告訴人は事実を知らず購入した。これは宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号違反である。
3.両罰に関する規定
被告訴人両備バス株式会社は告訴人らに対し重要な事項について、故意に事実を告げず宅地を販売したのであるから、宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号違反について、第八十条(罰則)、第八十四条(両罰規定)により、処罰の対象である。
4.違反条文
○宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号
5.罰条
○宅地建物取引業法第八十条
○宅地建物取引業法第八十四条(両罰規定)
6.疎明資料
(1) 上申書 一通
(2) 重要事項説明書 一通
(3) 不動産売買契約書 一通
(4) 工事請負契約書 一通
(5) 鉛製給水管使用について(回答)書 一通
(6) ボーリング調査濃度計量証明書(No3地点) 一通
(7) 表層土調査濃度計量証明書(土壌14) 一通
(8) 岡山市環境保全課の汚染土壌の処分方法について 一通
(9) 告訴人の診断書 一通
(10) 昭和57年7月27日の和解調書 一通
平成18年11月1日
岡山県警察本部
県警本部長 殿
告訴人
○○○○ 印
結
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20080323
++++++++++++++++++++++++++++++
両備グループを刑事告訴!その5
両備グループを宅建法の土壌汚染重要事項説明違反で告訴
追記
今回の告訴の後で感じた事を書きます。
私たちは、民事裁判の前に、まず刑事告訴を行いました。
金持ちであれば、自前で地質調査及び分析を行い、弁護士に依頼して、すぐ民事訴訟を起こせば良いのですが、一般の庶民では資金の工面が直ちには出来ません。
まして地質汚染であれば、一般のサラリーマンにとって唯一の担保となる土地建物が無価値になり、銀行融資も受けられません。
小鳥が丘団地地質汚染問題の様な、目に見えない地中の汚染は、発覚するまで長期間かかる方が普通であり、刑事告訴の時効があまりにも短いと思いました。
そして、いくら時効になったとしても、両備グループの不正は不正であり、不正の事実が消える事は有りませんが、それよりも重大なのは、
両備グループが、非は非と認めて対応しない事であり、小鳥が丘団地地質汚染問題を含めて、このままにすると、会社のこの様な対応の仕方が変わらず、改革が出来ない事により、第2第3の地質汚染問題を引き起こしかねないと思います。
よって、これからも不正の事実を訴え続けていかなければなりません。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20070220
追記2
今回の告訴の後で感じた事を、もう一つ書きます。
それは、行政の対応です。
前に、小鳥が丘団地地質汚染問題に対して行政が消極的だと書きましたが、当地域の環境担当行政である岡山市は、住民が自宅庭で土壌を移動中にガス中毒で倒れたという健康被害にあったにもかかわらず、実態解明の土壌調査すら行なおうとしません。
岡山市は、土壌汚染対策法に照らして行政が地質調査を行なう事は出来ない(土地の所有者が行なうべきもの)と説明しています。
しかし、そもそも小鳥が丘団地ができたのが、土壌汚染対策法が公布される以前であり、土壌汚染対策法が適用される案件では無いと、専門家から聞きました。
行政が、地質汚染の事は何でも土壌汚染対策法を持ち出すのは、行政が余り関わらなくて良い法律を利用しているのではないかと疑いたくなります。
岡山市は、一番てっとり早い土壌汚染対策法を持ち出しているとしか思われません。
余談ですが、地質汚染を防止する目的で創られた土壌汚染対策法が、逆に合法的な“こまかし”に利用されたり (土壌は層を形成しているもので土対法の調査基準では全ての層を調査するものでは無い為、汚染された層をはずせば、その土地は汚染されてない事になる)、
また、全ての地質調査指定会社が、技術レベルが高い訳では無いので、ボーリング調査で地層を勘案しない機械的深度の試料採取により、かえって汚染を拡大させてしまう等の問題点も指摘されています。 (NHKテレビクローズアップ現代でも紹介)
土壌汚染対策法は、まだまだ問題点の多い法律だと考えさせられます。 以上
******************************
******************************
******************************
******************************
2007年2月25日(日)
両備バスに申入れ書!その1
両備グループ代表に土壌汚染解決の話し合い継続を明確に伝えるために申入れ書を郵送しました。
小鳥が丘団地を造成販売した両備バス株式会社が、土壌調査継続も住民との話し合いも拒否し、いくら両備バスに連絡をとっても“弁護士に任せているのでそちらに言ってくれ”の一点張りで住民の思いが伝わらない為、両備バスの意思を確認するために、過去に両備グループ代表に手紙を配達証明郵便で出しました。(このブログの平成18年9月11日、“両備グループ代表・社長の意思!”に掲載)返書が来なかったので、住民との話し合い拒否は両備グループ代表の意思と確認しましたが、
その後、 “あの手紙は何を言っているのか分からない”と両備バスが言っていると聞いたので、再度、明確に要求が分かる様に、回答期限付きで申入れ書を平成18年10月17日に内容証明郵便で出しました。
両備グループ代表に土壌汚染解決の話し合い継続を明確に伝えるために申入れ書を郵送しました。
以下、その内容です。
++++++++++++++++++++++++++++++
平成18年10月17日
〒700−8518 岡山市錦町7番23号
両備バス株式会社代表取締役社長小嶋 光信 様
小鳥が丘団地救済協議会 代 表 岩野敏幸
申し入れ書
私たち、小鳥が丘団地救済協議会は、御社が造成・販売した小鳥が丘団地で明らかになった土壌汚染問題の解決のため団地住民の有志で組織した団体です。なお、以前に御社が交渉をもっていた小鳥が丘環境対策委員会とはべつの団体です。
当協議会は、小鳥が丘の土壌汚染問題について、御社が平成17年7月に小鳥が丘団地住民に対して提出した、条件付き提案には承諾できません。
この提案は、御社と話し合いをもつための条件として、この土壌汚染の法的責任が御社にないことを確認しなければならない一方で、土壌汚染への対策実施についての保証すらありません。
これでは御社は話し合いだけして、何もしないでよいことにすらなりかねず、当協議会としてはとうてい容認できません。
しかしながら、当団地の土壌汚染問題は、発生する有毒ガスによる健康被害や地盤沈下といった被害を引き起こしていることも考えられ、そこで生活する私たち住民にとってきわめて重大です。
そうした汚染がある土地を造成し、住民には知らせずに販売した御社には当然ながら責任があるはずです。
よって当協議会は御社との話し合いおよび当協議会の合意の上での解決策の実施を求めます。
上記の申し入れに対して、平成18年10月27日までに下記の当協議会代表に文書にてご回答願います。
岡山市南古都××× 小鳥が丘団地救済協議会代表 岩野敏幸
電話:××× 携帯:×××
++++++++++++++++++++++++++++++
豊島と小鳥が丘団地は廃棄物不法投棄搬入ルートで繋がっていました。
私たち小鳥が丘団地住民は2005年3月20日に香川県豊島に現地視察に行きました。
その時、豊島に不法投棄した業者を摘発した兵庫県警の資料の中に、産廃搬入ルート先として小鳥が丘汚染原因者の岡山市旭油化工業の名前が記載されていました。
香川県豊島の産廃と岡山市小鳥が丘の産廃は繋がっていたのです。
そこで豊島公害調停選定代表人の一人として調停に参加された石井とおる氏(前香川県議会議員)から話を聞く機会を得、大変参考になりました。
石井氏には戦後最大級の不法投棄事件と言われた豊島問題を闘った先輩として、アドバイスを頂いています。
最近、石井氏が書かれた“未来の森”という本を読みました。今までの私たちであれば、信じられない内容なのですが、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題に直面している私たちにはそのままストレートに伝わってきます。
やはり信じられない行為が平然と行われていた事に深い悲しみが湧き上がってきます。
と同時に、当時ほどではないにしても現在も、その様な事が繰り返されているのです。
そこには我々一般住民の常識からは考えられない行政の対応が書かれていました。
たとえば違法操業のページで、住民が何度も香川県の職員に事業者の行為を止めさせるよう要求したが相手にされず、 “もうもうと立ち上がる野焼きの煙は県庁の窓からも見えた。県庁を訪れた住民が担当者を窓際へ連れて行き、「あの煙が見えんか!」、と指さすと、「見えん!」、と横を向いたという。”
行政が何故この様な信じられない対応になるのか、については石井氏がこの本で指摘しています。
“自治体は何故住民の言うことを聞いてくれないのでしょうか”と聞かれて、
石井氏いわく。
“そもそも、住民の言うことなど聞くようにはできていないから”
(「未来の森」より、「農事組合法人てしまむら」発行、石井とおる著)
http://www.teshimamura.com/?pid=3038282
******************************
2007年11月20日(火)
両備バスを岡山地裁に提訴!その1
岡山市小鳥が丘団地土壌汚染公害問題で両備バス?は有害物質で汚染された宅地を住民に説明せずに販売し、汚染発覚後も抜本的な対策をとろうとせず住民が被害を受けても放置したため、2007年8月31日、住民3名が両備ホールディングス株式会社を岡山地方裁判所民事部へ提訴しました。提訴の経緯を掲載します。
両備バス?は途中で調査を取りやめ、行政も土壌汚染調査をしないので土壌汚染の全容が分からず、汚染対策の検討もできません。もはや民事訴訟しかないと思いまず住民3名で提訴しました。提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ通知・催告書を郵送しました。
通知・催告書
貴社が造成販売した小鳥が丘団地の住民である岡山市南古都××× 藤原 康氏、同所××× ○○○○氏、同所××× ○○○○氏ら3名の代理人として以下のとおりご通知し、損害賠償の請求をいたします。
貴社は、本件団地の本件造成地内に、川に廃油を垂れ流したり有害廃棄物を野積みするなどして公害企業であった旭油化工業株式会社が存在していて人体に影響を及ぼす汚染物質が存在することを知りながら、これを除去することなく埋め立てて造成し、そのことを秘して藤原氏らに販売しました。
この汚染の事実が発覚してもことさらに汚染の程度の低いことを強調し、その責任をとろうとしませんでした。
本件の造成地からは黒く汚染された地下水がにじみ出ていて、表層土壌からはベンゼンを含むガスが出ていることも明らかとなっています。
さらに、そのガスの濃度はガス漏れ警報器が作動することもあり、健康への影響のみならず物理的にも危険な状況となっている箇所もあります。
また、土壌にはベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が土壌溶出量基準を超えて検出されています。
本件危険な造成地の販売は故意にとの評価できる重大な責任があります。
藤原氏らとそれぞれの家族らは、この団地を岡山を代表する貴社の企業としての評価を信頼し、終の棲家として希望をもって購入いたしました。
しかし、上記の状況であり、この土地が土壌汚染されていて、日々健康を冒され続けてきていることが明らかになり、とても安心して住める状況ではありません。住宅地として使用不可能な土地であり、他の地に移らざるをえません。
従って、このような土地を購入した代金、この土地上に建てた家の建築費用と健康被害を受け、日々不安な生活を継続してきた損害を慰謝料として評価し、これらの合計額を請求いたします。なお、○○氏は本件分譲地で、整骨院を経営していて業務に関する工事費用も損害に加えて請求いたします。
本件請求に対するご回答を平成19年7月31日までに当事務所まで書面をもって頂きますようお願いいたします。ご誠意あるご回答なき場合はやむを得ず法的手続きをとることになりますので、念のため申し添えておきます。
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の続きです。
各自の損害は以下のとおりです。
○○○○氏
不動産取得費等 28,897,520円
慰謝料 30,000,000円
○○○○氏
不動産取得費等 28,759,670円
慰謝料 30,000,000円
○○○○氏
不動産取得費等 80,241,390円
慰謝料 30,000,000円
平成19年7月13日
岡山市富田町二丁目7番8号石橋第3ビル3階
河田英正法律事務所
弁護士 河田 英正
弁護士 大本 崇 電話 086−231− FAX 086−231−
岡山市錦町7番23号
両備バス株式会社
代表取締役 小嶋光信 様
この郵便物は平成19年7月13日第29830号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
岡山中央郵便局長
******************************
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の返書として2007年7月28日付けで送られてきた両備ホールディングス株式会社の回答書です。
回答書
平成19年7月28日
岡山市富田町2丁目7番8号 石橋第3ビル3階
藤原康氏外2名代理人 弁護士 河田 英正 殿
岡山市南方1丁目8番14号
両備ホールディングス株式会社代理人
弁護士 菊池 捷男・首藤 和司・財津 唯行・安達 祐一・井田千津子
電話 086−231 FAX 086−225−8787
冠省
貴職らからの平成19年7月13日付「通知・催告書」を拝見しました。
両備ホールディングス株式会社では、平成16年7月に、小鳥が丘団地の住民の皆様から、団地内の土地を掘ったところ臭いがする、油が出てきた、など連絡を受け、真摯に、調査と地元の方々と話し合いをしてきました。また、平成17年3月までに、専門家による現地調査や地元の方々へ対策工事の提案もしてきました。
しかしながら、貴職らの依頼人らは、具体的、科学的な根拠を示すことなく、小鳥が丘団地では人は住めない等極めて誇張した表現で両備ホールディングス株式会社を非難することに終始し、真剣に対応しようとはされませんでした。その姿勢は、今回の貴職らの書面での請求額等にも現われているところです。両備ホールディングス株式会社としましては、このような貴職らの依頼人とは真摯に話し合いができるとは思えません。そのため今回の貴職らの書面に対しては、細かな認否は致しません。
貴職らは、両備ホールディングス株式会社の回答に満足しない場合は、法的手続きをとると書かれていますので、両備ホールディングス株式会社の主張は、法廷の場でさせていただきます。ただ、念のためお伝えしておきますが、両備ホールディングス株式会社は、貴職らの依頼人の主張に対し、全面的に争うことにしております。
以上回答いたします。 草々
******************************
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の返書として「両備ホールディングス株式会社は法廷で全面的に争う」との2007年7月28日付け回答書を受けて岡山地方裁判所へ提訴しました。訴状を掲載します。
訴状
平成19年8月31日
岡山地方裁判所民事部 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河田 英正
同 大本 崇
〒709−0632 岡山市南古都×××
原告 藤原 康 〒709−0632 岡山市南古都×××
原告 ○○○○ 〒709−0611 岡山市楢原×××
原告 ○○○○
〒700−0816 岡山市富田町二丁目7番8号 石橋第3ビル3階
河田英正法律事務所(送達場所)
上記訴訟代理人弁護士 河田 英正
同 大本 崇
電話 086−231− FAX 086−231−
〒704−8112 岡山市西大寺上1丁目1番50号
被告 両備ホールディングス株式会社
被告代表者代表取締役 小嶋光信
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 227,898,580円
ちょう用印紙額 704,000円
第1 請求の趣旨
1、被告は、原告○○○○に対して58,897,520円、同○○○○に対して58,759,670円、同○○○○に対して110,241,390円とそれぞれこれに対する平成16年9月28日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え
2、訴訟費用は被告の負担とする
3、仮執行宣言
第2 請求の原因
1、当事者
一 被告会社は、昭和11年5月25日に両備バス株式会社として設立され、平成19年4月1日に両備ホールディングス株式会社と商号変更された資本金4億円の株式会社であり、自動車、船舶による旅客、貨物の運送業、観光事業、不動産の所有・売買・賃貸仲介などを業務としている。
二 原告らは、両備バス株式会社が造成した小鳥が丘団地に住居を有し、居住している者である。
2、小鳥が丘団地造成前
一 本件造成地には、廃油等を利用して石鹸を製造していた旭油化工業株式会社の工場があった。
二 同社は、業績不振のなか、昭和49年11月19日に新たに廃棄物処理業の許可を取り阪神、北九州方面の企業から産業廃棄物としての廃油を集めてその処理を始めた。その頃から、廃油処理工場からは廃油処理の黒煙が不気味に立ち上っていた。地域周辺に悪臭がたちこめ、近くを流れる沼川には油膜が張ったり、死んだ魚が浮き上がってくるなどの現象が見られた。廃油を貯蔵していたタンクが設置されていたが、その装置は単に土壌に廃油を吸い込ませる装置であったようであり、タンクの底は直接土壌に接して廃油が不法に処分されていた。そのタンクの位置は土壌への吸収が悪くなると敷地内で場所が移動されていた。そして、工場敷地内には腐敗した油脂を入れたドラム缶が散乱して放置されていて、その腐敗した油脂が敷地内の土地にこびりつき、恒常的に悪臭を発生させていた。
三 両備バス株式会社は、この旭油化工業株式会社の工場北側に既に団地(小鳥の森団地)を造成し、住民が居住していた。その住民からも旭油化株式会社の産業廃棄物処理業を始めたことによる悪臭などの環境悪化の苦情が造成・販売した両備バス株式会社などに苦情が寄せられるようになった。このころ岡山県や岡山市の公害課が何度も行政指導を繰り返していたが、何ら対策が講じられなかった。
3、両備バス株式会社の本件土地の宅地造成
一 両備バス株式会社は、上記のとおり旭油化株式会社が操業している土地の北側に小鳥の森団地(37000平方メートル)を造成・販売していた。
この分譲地を購入して居住している住民から、上記のとおり苦情が寄せられるようになり、両備バス株式会社は旭油化株式会社に対して強く改善方を要求していたが、一向に改善されることはなかった。両備バス株式会社の小鳥の森団地の販売が困難な状況となっていた。
二 両備バス株式会社は、昭和57年になって旭油化株式会社を相手方として悪臭を放つ汚泥とドラム缶の除去を求めて岡山簡易裁判所に対して、小鳥の森団地の販売者として調停の申立をした(岡山簡易裁判所昭和57年(イ)第67号)。そして、昭和57年7月27日、岡山簡易裁判所において両者の間で和解が成立した。
三 上記和解の内容は、本件問題を解決するには旭油化株式会社が本件土地から移転するしか方法がないというものであり、概略以下のとおりであった。
(1)旭油化株式会社は昭和57年10月31日限り操業を停止し、同年12月31日までに本件土地上の全ての建物および地下工作物を撤去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
(2)両備バス株式会社は、旭油化株式会社に対して建物撤去費用、移転補償などとして6690万円を支払う。
(3)両備バス株式会社は、旭油化株式会社の工場跡地を一坪あたり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
四 こうして、旭油化株式会社の工場跡地を取得した両備バス株式会社は、このそのままでは宅地造成地には適さない工場跡地を昭和62、3年ごろから3区画に分けて有害物質に汚染されたままで宅地に造成し、平成元年頃から分譲を始めた。
4、宅地から有害物質検出の経緯
一 平成16年7月に岡山市から上水道の鉛製給水管をポリエチレン管に取り替えたいとの連絡があり、7月29日に取り替え工事がなされた。取り替えのため給水管を掘り起こしたところ、油分を多量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥状のなかに水道管が埋められていることが判明した。そして化学反応の安定性が高いと言われる鉛管の給水管の一部が腐蝕して穴があいている箇所も発見された。岡山市の調査によればこの時の地下水と土壌から硫酸イオンが検出された。
二 両備バス株式会社は、原告ら住民の不安の訴えに対し、土壌汚染の原因を探るべく、土地履歴の調査、ボーリングによる土壌調査などの申し入れがなされ、調査が実施された。同年9月28日原告らに土壌汚染の実態と原因が知らされた。同社の報告によっても、3地点のボーリング調査の結果は、環境基準値の約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、6倍のシスー1,2−ジクロロエチレンが検出された。また、地下約5メートル付近では金属片やボロ切れなどが発見された。同年12月に実施された電気探査の結果によれば、地盤が不安定で地盤沈下を起こしやすい状況となっていることが判明している。平成19年4月9日、原告岩野方の敷地を、敷地内において検査機関に土壌調査を私的に依頼し実施したところ
(1)表層土壌ガス調査の結果、全ての調査位置においてベンゼンが検出された。
(2)土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が土壌溶出基準を超えていたこと
(3)土壌調査の結果、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の溶出量値が指定基準を超えていたこと等々が明らかとなった。
三 本件団地内においては表層土においてガスが発生して臭気が漂い、土壌の性状が不安定となっていて地盤沈下の畏れがある。その臭気には発ガン性物質であるベンゼンが含まれているなど健康被害が懸念されている。有害物質を含んだ地盤の安定しない宅地であり、そもそも人が安心して安全に暮らせる団地ではない。地盤からのこのガスの発生で、原告○○方のガス漏れ警報器が作動することもあり、安心して居住できる環境にない。
5、被告会社の責任
一 被告会社は、旭油化株式会社が汚染し続けた土壌はもはや操業をやめさせるしかないほど危険な回復しがたいものであり、そのままでは小鳥の森団地の販売を継続することはできないと認識し、旭油化株式会社の操業中止とその敷地を購入して旭油化を退去させてその問題解決を図った。そして、その土壌が有害物質で汚染されていることを十分に認識して旭油化株式会社の敷地を買収した。
二 そのような有害で危険な土壌であることを認識しながら宅地として危険物質を残したまま造成し、分譲を続けた。購入者にはこのような危険な土壌であり住宅地として不適なことを秘匿して分譲した。そして、発ガン物質を含むガスが発生して危険な状況になっていても放置したままであった。
三 平成16年7月に、岡山市水道局による水道工事によって、本件団地が有害物質で汚染された危険な造成地であることが表面化しても、直ちに健康に被害をもたらすものではないと抜本的な対策をとろうとしなかった。
6、原告の損害
別紙原告の損害記載のとおり
7、被告会社は、抜本的な無害化工事を実施しなければとうてい造成地としてはならない汚染土壌のある旭油化の工場敷地を、危険な有害物質に汚染された土壌に表層土を盛り土して造成しただけで販売した。
さらに、そのように危険な造成地であるから管理を継続し、危険な兆候があれば直ちに対応しなければならないのにこれを怠り、最後までこの事実を隠蔽したまま何らの管理もしないで販売を継続した。汚染の事実が表面化しても危険はないと断言して、原告らに対して何らの対策をとろうとしなかった。
これらその都度の方針は被告会社の方針として取締役会で決定されて実行され、あるいは不作為となったものである。その結果、各原告は6項記載の通りの損害を被った。
提訴に先だって2007年7月13日に両備ホールディングス株式会社へ郵送した通知・催告書の返書として「両備ホールディングス株式会社は法廷で全面的に争う」との2007年7月28日付け回答書を受けて岡山地方裁判所へ提訴しました。訴状の続きです。
よって、被告は、不法行為を原因とし(民法44条1項、同709条)、各原告に発生した損害の支払いと原告が被告会社の加害行為による被害であると認識した平成16年9月28日から完済に至るまで年5分の割合による金員の支払いを求める。
附属書類
1 訴状副本 1通
2 商業登記現在事項証明書 1通
3 訴訟委任状 3通
******************************
2009年11月22日
リスクマネジメント
リスク
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
リスク (risk) の定義にはさまざまあるが、一般的には、「ある行動に伴って(あるいは行動しないことによって)、危険に遭う可能性や損をする可能性を意味する概念」と理解されている。
日本語ではハザード (hazard) とともに"危険性"などと訳されることもあるが、ハザードは潜在的に危険の原因となりうるものすべてをいい、リスクは実際にそれが起こって現実の危険となる可能性を組み合わせた概念である。
ゆえにハザードがあるとしてもそれがまず起こりえないような事象であればリスクは低く、一方確率は低いとしても起こった場合の結果が甚大であれば、リスクは高いということになる。
語義
経済学上のリスク
経済学においては一般的に、リスクは「ある事象の変動に関する不確実性」を指し、リスク判断に結果は組み込まれない。例えば、ビルの屋上の端に立つのは危険であるが、まだ転落するか無事であるかは分からない。この状態はかなり不確実でリスクが高い。しかし、一旦転落すれば十中八九命がないとすれば、転落直後にリスクが低下することになる。
リスクの概念は、経済学の中でも金融理論においてよく用いられる。投資において、将来の収益が必ずしも確実といえない投資手段があるためである。投資におけるリスクは、分散投資を行うことによって低減させることが可能である。株式投資を例に取ると、単一銘柄に投資を行っている場合、その企業の持つ固有リスクのために、期待される収益を得るに当たっての不確実性が高い。
しかし、投資先を分散することによって企業固有のリスクを和らげることができる。投資先を可能な限り分散し、固有リスクを分散することによって、投資によるリスクは市場リスクに近づけることができる。株式投資の例に戻ると、市場リスクとは、例えばTOPIXのような市場平均を指す。
利得がある不確実性をアップサイドリスク、損失する不確実性をダウンサイドリスクと呼ぶ。リスクが高いものは損失と利得の度合いが元本に対して高くなる。そのため、高い利得を得たい者は、損失する可能性を覚悟しなくてはならない。金融工学はここに目をつけ、統計学などを利用することで、ダウンサイドリスクを低減しアップサイドリスクをより高めることを目指している。
主なリスクの種類として、価格変動リスク、デフォルトリスク、流動性リスク、インフレリスク等があげられる。
物のリスク
物のリスクは、物(物質と物品)にかかわって、その周辺物(人、生態、有形財産)が実際に被る可能性がある悪影響の大きさを示し、必ずマイナス・イメージである。プラス・イメージについてあわせて議論するときにはベネフィットという語とともに使われる。
リスク概念は「安全」概念の定義と結びつけてはじめてその概念と背景にある思想が理解できる:安全とは、リスクが小さいことである。
この背景には、リスク・ゼロ追求は現実的な安全追求の姿勢でないという反省がある。 物の不適切な取扱いの結果、周りに、その物固有の危険性が影響を及ぼして、悪い事象(危害、損傷、損害等)が出現した時、リスクが現実となってしまうことがありうる。ここで物は物質又は物品の場合がある。
また、周りとして、人、生態、有形財産の場合がある。この周りの一つとして社会を考える場合もある。ここでの危険性には、いわゆる(狭義の)危険性と有害性の両方を含むため、これをはっきりさせるために危険有害性という用語が使われる場合も多くある(英語のen:hazardが元であるので、ハザードというカタカナ表記も使われる。)。
つまり、物のリスク評価(risk assessment)を実施するときには、
1. 物固有の危険性を特定し、その程度を評価し(危険性評価、hazard assessment)、
2. その物が取り扱われている(取扱い)状態を特定し、その周り(人、生態、有形財産等)との接触(暴露等)の頻度、範囲、量等を評価し(暴露評価、exposure assessment)、
3.その組み合わせで実際に悪い事象の出現する可能性とその大きさを見積もり、その結果が不当に大きいかどうかを判断する(リスク判定、risk characterisation) ことになる。
「安全」概念を再定義すると:
「安全とは取扱う物質の固有の危険性が低いか、取扱う周辺との接触・暴露が小さいことである。」ということになる。毒物学と薬学の父であるパラケルススの「すべての物質は毒である。毒でないものない。量によって毒と薬に区別される」との言はまさにこれを示している。
物固有の危険性
機械危険性: 物品の持つ機械的特性に基づく危険性。鋭利な刃先(裂傷にかかわる)、回転機械(巻き込まれ事故に係わる)等。
物理危険性: 物の持つ熱、圧力、音など物理現象に基づく危険性。特に、燃焼性、爆発性が問題となる。
健康危険性: 物質の持つ人の生命および健康に係わる有害性。急性毒性。慢性毒性。発癌性。感作性(アレルギー)、生殖毒性、変異原性等。
環境(生態)危険性: 物質の持つ地球環境や人以外の動植物に係わる危険有害性。オゾン層破壊物質、温暖化物質; 水棲生物に対する急性・慢性毒性。陸棲生物に対する急性・慢性毒性等。
2から4についての多くはGHSによる分類と表示の国際的調和作業が進行中である。これにより危険性を類型的に処理することができるようになり、対策立案も容易になる。国際的にはこのGHSの原型ともいえるRTDGに基づいて航空輸送、海上輸送、陸上輸送の安全対策が立てられている(ただし、日本の陸上輸送の安全は国際基準に基づいていない)。
リスク削減-もっと安全を
このように考えることによって、リスク判定の結果「不当にリスクが大きい」、つまり、安全の程度が低すぎるとされた場合、どうやって安全を確保するかという課題を解決する(リスク軽減策を立てる)上で整理がしやすくなる。つまり、
1.物の持つ固有の危険性を低くする。たとえば、鋭利な部分を取り除く、切れにくくする/切れやすくする、不燃剤を混ぜる、粒子のサイズを大きくする(細かいものは粉塵爆発を引き起こす、肺の奥のほうにまで到達して悪影響を与えるなどのリスクがある)、危険有害性の低いものに替える等々。
2. 取扱い手順を見直す、たとえば、切れにくい刃物はそのまま使用せず砥いでから使用する手順とする; 換気を行う(湯沸し器による一酸化炭素中毒); 取り扱うものに合った手袋や眼鏡や前掛け等を使用する; スプレー缶は穴を開けてから捨てる; そしてなによりも取り扱う物の特性(特に危険性)をよく理解する、あるいは、GHSの目的に挙げられているように、その理解に必要な情報をわかりやすく提供する等がある。
工学上のリスク
工学においては、リスク (risk) とは、一般的に「ある事象生起の確からしさと、それによる負の結果の組合せ」をいう (JIS Z8115: 2000)。この場合、リスクの対象は限定されない。
一例として人体もしくは財産等に対するリスクに危害リスク (risk of harm) といった危害発生の確からしさ、危害の厳しさの1つの組合せなどのリスクがあり、リスクには事象が顕在化することから好ましくない影響ごとが発生されること、その事象がいつ顕在化するかが明らかではない発生不確定性があるという性質が含まれる。
システムにおけるリスク
システムにおけるリスクは、経済学と違いより良い結果が出ることはリスクとならない。損失の可能性があるものだけがリスクとみなされる。その意味では不確実性ではなく、確実な危険性といえる。
マネジメント
経営管理論
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(マネジメント から転送)
経営管理論(英: business management, Management Administration, etc.)は、組織・団体(主に企業)の管理についての実践的な技法(経営管理)の確立を目指す学問であり、経営学を構成する分野の一つ。 20世紀初頭、科学的管理法を提唱し、「経営学の父」と呼ばれたフレデリック・テイラーがその始まりとされており、また「管理原則(管理過程論)の父」と呼ばれたアンリ・ファヨールによる研究により、学問として成立。その後、主にアメリカで研究が発展した。
現在では、企業経営の大規模化・複雑化に伴って組織を構成する要素及び経営に関わる要素は多岐に亘るようになった結果、経営管理の扱う範囲がたいへん広くなり、また専門性が強くなったため、一般に、その管理対象に応じて細分化されている。例えばヒトの面の管理は人事労務管理(人事管理)論、カネの面の管理は財務管理論など。
経営管理の定義
経営管理は、広義に解釈すれば、“経営システムの維持・存続のための全成員のダイナミック(dynamic)な情報活動”であって、それは人間の頭脳活動を含む神経系統の活動に相当するものである。
経営管理とは、人に働きかけて、協働的な営みを発展させることによって、経営資源の転換効率や環境適応の能力と創造性を高めて、企業の目的を実現しようとする活動である。(中略)経営管理は、個性的で具体的な人間が組織的な人間として振る舞い、組織の活力や創造性を高めるように働きかけようとする。こうして企業の協働的な営みは組織として展開され、個人の能力の総和以上の生産を実現するのである。
また、「管理原則の父」と呼ばれるファヨールは、経営管理を計画、組織、指揮、調整、統制の5要素と定義している。
簡単にまとめると、経営管理とは、企業活動を円滑に行うとともに、企業の目的を達成するために、「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つの経営資源を調達し、効率的に配分し、適切に組み合わせる、といった諸活動のことである。特に、主体的に行動する「ヒト」(人的資源)が重要であり、これに上手く働きかけて、組織化し協働させたり、活性化させ(もしくは能力を発揮させ)たりするようなシステムを如何に構築するかということが主要な課題となる。
経営管理論の発展
19世紀後半から、第二次産業革命と呼ばれる工業化の進行・資本主義の発展や経済の拡大により、企業は経営資源を効率的に運用し、生産力を増強することを目指すようになった。そのような状況の下、20世紀初め、アメリカの技術者・テイラーが「科学的管理法」を、フランスの経営者・ファヨールが「管理過程論」の原型をそれぞれ発表、経営管理の研究が始まった。 一方、ドイツの社会学者・マックス・ヴェーバーは、組織の支配形態を分析し、合法的・合理的な組織は官僚制組織であるとした。その上で組織の合理的・機能的側面に注目、組織構造という概念を考え出し、「官僚制組織論」を提唱した。これらの3人の研究が、経営管理論の出発点と言える。
その後、人間的側面を軽視する科学的管理法への批判から、人間関係や人間の持つ欲求、特に自己実現欲求に注目する、「人間関係論」が生まれた。メイヨー、レスリスバーガーによるホーソン実験や、マズローの欲求段階説(自己実現理論)、マクレガーのXY理論などが知られる。
さらにその後、マックス・ヴェーバーの組織の理論を経営に応用し、組織全体を分析する議論(システムズ・アプローチ)がバーナードによって唱えられ、後にサイモンの意思決定論に繋がった。
一方、1960年代以降、従来の普遍的な法則を見出そうとする議論では抽象的で現実の経営に対応できないとして、経営環境に応じてそれぞれに異なる最適な組織形態・管理法が存在するとする見解(コンティンジェンシー理論)が登場した。
これらの諸議論を基礎に、リーダーシップ論、モチベーション論、組織文化論、企業間関係論など様々な議論に広がっている。
占部都美は、最近の経営管理論は、意思決定論的アプローチ、行動科学的アプローチ、システムズ・アプローチを取っているとしている。
20世紀の終わりには、マネジメントの項目は以下の6つのサブカテゴリーから成るとされていた。
人材マネジメント Human resource management
オペレーションマネジメント w:Operations or production management
戦略的マネジメント w:Strategic management
マーケティングマネジメント w:Marketing management
財務管理 w:Financial management
ITマネジメント w:Information Technology management
21世紀の現在では、この6つのカテゴリーのみでとらえることがますます困難となってきている。 多くのプロセスが同時にいくつかのカテゴリーを含んでいるためである。 現在では6つのカテゴリーの代わりに、一人が管理できる様々なプロセス、タスクおよびオブジェクトの単位で考える傾向にある。
経営管理の諸学説
H.クーンツは著書『経営の統一理論』にて、経営管理の学説を以下の6つに分類している。
管理過程学派(普遍学派)
経営管理を「組織を構成する人々に、あることをしてもらう過程」と捉え、そのための管理の諸原則を明らかにしようとする。
経験学派
経営管理に関する事例研究(ケーススタディ)を通じて、最も有効な経営管理技法を構築する。
人間行動学派
経営には多くの人々が関わっていることに着目し、構成員・関係者の行動や相互関係を研究する。行動科学や人間関係論など、心理学的アプローチ。
社会システム学派
経営管理を人やその行動からなる一つの社会システムと捉え、社会学的見地から研究する。人間的側面を重視することから、人間行動学派と共通する点を持つ。バーナードに代表される。
数理学派
数学や統計学、計測可能なデータなどを駆使して、数理的アプローチから経営管理を把握しようとする。そのための手段として代表的なものにオペレーションズ・リサーチがある。この学派の研究は経営科学とも言われる。
意思決定学派
企業内の意思決定システムを研究し、合理的な意思決定を行うにはどうすべきかを追究する。サイモンに代表される。
注釈
^ カリスマ支配、伝統的支配、合法的支配の3つ。
^ これらは「経済人モデル」に立脚した考え方である。
^ これらは、人間を欲求・感情で動く「社会人モデル」(メイヨーによる)や、自己実現を欲する「自己実現人モデル」(マズローによる)で捉えている。
^ 占部都美『経営学辞典』(中央経済社)
リスクマネジメント 提供: フリー百科事典
リスクマネジメント (Risk Management) とは、リスクを組織的にマネジメントし、ハザード(危害 (harm) の発生源・発生原因)、損失などを回避もしくは、それらの低減をはかるプロセスをいう。リスク・マネジメントとは各種の危険による不測の損害を最小の費用で効果的に処理するための経営管理手法である。
概要
近年、会社法の施行により、株式会社では「損失の危険の管理に関する体制」を整備する必要があること、また、金融商品取引法では2008年度から日本版SOX法が施行され、財務に関する分野において、リスク管理体制の整備が求められていることもあり、経営上、リスクマネジメントは脚光を浴びており、「コンプライアンスからリスクマネジメントの時代へ」とも言われている。
リスクマネジメントとは、リスクを把握・特定することから始まり、把握・特定したリスクを発生頻度と影響度の観点から評価した後、リスクの種類に応じて対策を講じる、また、仮にリスクが実際に発生した際には、リスクによる被害を最小限に抑えるという一連のプロセスをいう。どの会社においても、意思決定を行う際は、当然、暗黙の了解で、そういったことをこれまで行ってきたものと思われるが、近年、リスクマネジメントに対する意識の高まりを受け、特に、明示的に行われるケースが増えている。
大まかなプロセス:リスク分析によりリスク因子を評価し、リスクアセスメントによりリスク管理パフォーマンスを測定し、改善する(例えば、リスクの発生頻度や、リスク顕在化による被害を最小化するための新たな対策を取る)。リスクファイナンスによりリスク顕在化に備える。これらのプロセスはPDCAサイクルを取る。
近年、民間企業では、例えば環境リスクであれば、環境リスクに特化したり、不正リスクであれば、不正リスクに特化したりして、様々な種類のリスク因子を使って、より高度なリスクマネジメントを行うところが増えてきた。 また、これに伴い、従来の危機管理部門を発展させ、リスクマネジメントに特化した専門部署を置くところも多くなってきた。
リスクファイナンス
リスクファイナンスは、リスク対処の1つとして、リスクが実際に現実化した場合の損失補償を準備することである。保険も、掛けられる場合には、有効な対策の1つとなる。この場合、リスクを保険会社に移転していることになる(リスク移転)。リスク移転に対し、自らの組織で対処することをリスク保有と言う。
事例
リスクマネジメントの甘さが指摘される事例とその対処例。
社員管理の不徹底で顧客情報の漏洩が危惧される場合。
情報セキュリティポリシーの策定、組織への徹底。
大地震が想定される地域に、組織の重要な情報システム・意思決定機構が集中している場合。
リスク分散(国家で言えば首都機能分散)。ディザスタリカバリ対処の検討準備。
事故が予想される現場における、安全措置の不徹底。
現場安全マニュアルの策定・遵守。
緊急事態において、迅速な情報伝達・意思決定を行なう機構と訓練が不足している場合。
緊急事態における迅速な対処および対処責任者の明確化、訓練の徹底。
緊急事態対処訓練。身近な例では避難訓練などがある。
製造業におけるリコール発生時の事前のマスコミ対策。
常日頃から大量に広告を打ちマスコミが自主的に報道しないよう誘導する。
改善後の品質向上を大きく取り扱ってもらう。
よい例:ジャパネットたかた個人情報漏洩事件。
悪い例:雪印乳業食中毒事件。
関連項目
リスクマネジメント論
リスクアセスメント
リスク分析
安全工学
リスクヘッジ
リスクコミュニケーション
事業継続マネジメント (BCM)
事業継続計画 (BCP)
内閣危機管理監
新しいリスクマネジメント規格であるISO 31000 : 2009 及びリスクマネジメント用語に関するISO ガイドGuide 73 : 2009 について
ERM、全体的RM、トータルRM と流行語は色々ありますが、結局のところ、これ等全ては、組織が組織の目標を達成するために対処しなければならない脅威や好機を、如何に効果的に明らかにし、管理するかを記述したものです。
組織の目標を達成すること、効果的な組織統治(Governance)を確実にすること、節度を持って法対応を確立すること、及び保証を提供することといった全てのことは、リスクを確実に理解することとそれを首尾良く管理する手段に掛かっています。
ISO 31000 : 2009 及びそれと対をなすISO ガイド73
2009 は、規格の使用者が以下に記述されたことを行う時の手助けとなるように設計されています。
・リスクマネジメントとは何であるかを明確にする。
・組織統治(Governance)の意味合いに於いて、リスクを管理する効果的なプロセスを開発する。
・組織全体でリスクを管理する総合的な取り組みの必要性を理解する。
・リスクマネジメント方針とフレームワークの必要性を説明する。
・組織の中でリスクを管理するための主体者(ownership)と責任(account2abilities)を定める。
・特定のリスクマネジメント用語やプロセスが、何故、組織に合わせて調整され(tailored)なければならないかを理解する。
・組織、活動及びプロジェクトの中でリスクマネジメント活動を開発し、実施する。
・リスク対応手法を決定する。
・どの様に、リスクマネジメントプランを開発し、実施し、監視するかを理解する。
ISO 31000 : 2009 に示されている汎用的なアプローチは、組織全体でリスクを効果的にそして首尾一貫した形で管理することを確実にする助けとなります。
ISO 31000 : 2009 は、透明性があって信頼出来る方法で、リスクを管理するために不可欠な要素を実施する指針を提供しています。ISO ガイド73 : 2009 は、リスクマネジメント用語に見識(insight)を提供しています。
ISO 31000 : 2009 とISO ガイド73 は、以下のような幅広い利害関係者に使用されることを意図しています。
・組織の中でリスクマネジメントの実施に責任(responsible)のある人。
・組織がリスクを管理することを確実にする必要がある人。
・組織全体、組織の特定な領域又は特定な活動のためにリスクを管理する必要のある人;及び
・組織におけるリスクマネジメントの履行状況を評価する必要のある人。
ISO 31000 : 2009 は、特に以下の人全てに関連があります。
・公的組織であれ民間組織であれ、大きな組織であれ小さな組織であれ、全ての組織の取締役、経営管理者及びライン管理者。
・内部職員又はコンサルタントとして、リスクのマネジメントに助言を提供する審査員、会計士、コンプライアンス専門家及び法律顧問。
http://www.jsa.or.jp/stdz/mngment/pdf/iso_risk.pdf
リスク管理と危機管理
1.企業等の組織における活動には、不確実な部分が必ず含まれています。もちろん、結果的に利益や社会的評価がプラスとなる事項もありますが、損失や事故のようなマイナスの影響を及ぼす事項も潜在しています。一般的には、後者をリスクと呼びます。プラスの影響を大きくしマイナスの影響を小さくするためには、組織としてリスクを管理していくことが重要となります。
リスク管理という概念は、何を望ましくない事象として考えるかという基本的な問題提起を含むものであり、その考え方を基に施設の保守点検等の工学的安全活動をはじめ、これまでも組織ごとにリスク管理に関する様々な活動が実施されてきました。
しかし、近年では1回のトラブルでも組織の存続に関わるような事件が度々発生しています。今改めてリスク管理の必要性が強調されるようになってきている背景には、このような事件に見られるように、これまでの活動の限界が明らかになったことがあります。
2.これまでのリスク管理に関する活動の課題としては、主に4点挙げられます。
1つ目は、問題点の把握が経験的であり、問題点が明らかになってから対応を検討する傾向がある点です。
2つ目は、発生確率が小さい事象に対しては、被害が大きくなると予想される事象であっても、対応の優先順位が低くなる傾向がある点です。
3つ目は、対応が部署単位、専門単位で検討されることが多く、全組織的な優先順位や重要性を検討するシステムを持っていない点です。
4つ目は、内部における検討結果を外部に対して情報公開するシステムを持っていない点です。
1回のトラブルが組織の存続に影響を与えかねない現状では、このような課題を改善して、限られた経営資源を有効に活用するためのリスク管理システムを確立することの必要性が高まってきています。
3.組織や施設の安全を守る活動は、リスク管理と危機管理に分けることが出来ます。しかし、概念あるいは用語としてのリスク管理と危機管理の違いはそれぞれの技術分野によって若干の違いがあり、必ずしも明確ではありません。
4.リスクを低減するための活動には、事故や危機の未然防止と、事故や危機が発生した場合の拡大防止の2つのフェーズがあります。
一般的には、事故や危機がなるべく起きないように対処する活動をリスク管理と呼び、事故や危機的な状況が発生した後の活動を危機管理と呼ぶ場合が多いようです。今回も、リスク管理と危機管理をそのように区別することにします。
5. リスク管理は未然防止を含むため、保守点検等の活動のように定常的な組織において定期的に運用されるものです。一方、危機管理の場合は、専門的担当組織が定常的に存在する場合もありますが、事故や事件が発生した後、短時間での暫定組織による対応にならざるを得ない場合が多いことに特徴があります。このため、大規模地震や事故・事件などに遭遇した場合には、危機管理の必要性が強調されることが少なくありません。
リスク管理には、危機時の体制やマニュアルの整備などの危機に関する対応事項が含まれる場合もあります。危機管理についても、危機発生時にその被害や悪影響を最小に止めることに限定せずに、危機を発生させないための未然防止活動も含めて危機管理と呼ぶこともあります。
以上のように、共通の要素も多いものですが、短期間におけるリーダーシップが重要である点では、危機管理は大きな特徴を持つと言えます。
6.リスク管理と危機管理の違いを図に示しています。平常時の活動であるせまい意味でのリスク管理は重要な定常業務の一つでありますが、不測事態が発生した場合の対応である危機管理の技術を修得することも必要なことです。
7.リスク管理の具体的な内容に関しては、対象とするリスクの範囲や要求される対応内容により様々なレベルが存在します。そのため、共通するリスク管理の基本フレームを理解した上で、様々な制約条件を踏まえ、組織や目的に見合ったレベルのリスク管理を行うことが重要と言えます。
リスク管理の基本フレームは、大きく分けて4つのステップから構成されます。
1番目は、リスク対応方針です。リスク対応方針は、行動指針と基本目的から成ります。人命優先や環境被害の最小化は当然でありますが、リスク管理に関する基本的な考え方を示し、全ての活動がこの方針に従って実施されていくことを全ての組織構成員に周知・共有することが重要であります。
2番目は、リスク特定です。リスク特定では、リスクに関する情報を分析してハザードを特定することにより、組織に重大な結果をもたらす可能性のあるリスク及び結果の重大性の判断が困難なリスクを把握します。ハザードは、日本語では危険要因と訳されることが多いようです。
8.3番目は、リスクアセスメントです。リスクアセスメントの主要な内容は、リスク分析とリスク評価に分類されます。リスク分析では、まずシナリオ分析によるリスクの見積もりを行い、次いでシステム安全工学などの工学的手法によるリスク算定を行います。リスク算定は発生確率の算定と被害規模の算定の2つを実施する必要があります。
また、リスクを評価し対策方針を検討するためには、弱点分析を行い、どの部分に対策を講じることが適切かを把握します。リスクマネジメントサイクルの中で対策が必要と判断されたものに対しては、対策効果を把握するため、リスク解析により算出されたリスクがどの程度減少するかを検討する対策効果算定を行います。リスク評価では、リスク解析によりリスクの大小及びその特性によって、対応方針を決定します。対応方針には、リスクの保有、低減、回避、移転の4つが考えられます。
4番目は、リスク対策です。リスク対策では、得られたリスクの大小や特性により、リスク対応方針に基づいた様々な対策可能性の中から最適な対策を選択し実施します。対策にはコスト増や人的資源の投入が必要となるため、総合的な技術監理の視点が必要となります。
9.組織を取り巻くリスクについて触れることにします。組織にとって望ましくない事象は非常に多岐に渡り、小さなものまで含めると数限りなく存在します。リスク管理においてどの事象やリスクを対象とするかは、リスク管理の基本フレームにおけるリスク対応方針やリスク特定に関わる問題でありますが、リスク管理の対象としない場合でも潜在的な事象を把握しておくことは非常に重要なことです。
表に組織を取り巻くリスクの一例を示しましたが、望ましくない事象やリスクを整理する場合には、「まさかこんなことが起こるとは思わなかった」と言うことの無いように、表のような広い視野で整理することが重要です。今日では、被害影響として組織の社会的信頼性の低下が重要視されてきており、社会的信頼性の低下に結び付く事象についても見落としの無いようにすることが重要です。
10.また、組織を取り巻くリスクの要因についても、一つの考え方を図に整理しましたが、これまでは主に設備の故障やヒューマンエラー等を要因とする事象がリスク管理の対象とされてきました。
しかし、最近ではネットワーク犯罪や社員による情報漏洩等、人間の悪意に基づく事件が発生しており、今後はこのようなセキュリティに関する要因についても取り扱うことが必要となってきています。
1.リスク管理を理解するための準備として、リスクという言葉の概念について説明します。
リスクという概念は、使い方によって必ずしも定義が厳密に一致する訳ではありません。ただし、リスクという概念は共通の性質として次の2つの性質を含みます。
第1に、その事象が表面化すると、好ましくない影響が発生するという性質です。
第2に、その事象がいつ表面化するかが明らかでないという、発生の不確定性に関する性質です。
以上の性質を基に、リスクを関係式で表現すると、このようになります。つまり、リスクは望ましくない事象が発生した場合の被害規模とその発生確率により表現されることが分かります。
被害規模は、望ましくない事象の影響の種類と大きさを考慮して求められます。財政的な被害を見るのか、人的被害を見るのか、その両方を見るのか等によって、被害規模の内容は変わります。
また、発生確率は年に何回発生する可能性があるか、といったように定量的に把握される場合と、頻繁に発生する、時々発生する、ほとんど発生しない、といったように定性的に把握される場合があります。
リスクを被害規模と発生確率の積として捉える考え方もありますが、被害規模と発生確率の2次元のマトリックス上で捉える考え方もあります。次にリスクに関する定義の例を説明します。
2.リスクに関する定義の例として、3つの定義を示しました。
注目する対象により様々に定義されていますが、一番目に示した定義に従って、リスクを発生確率と被害規模の積として表現することが一般的です。発生確率と被害規模の積をリスク値と呼びますが、リスクの重要性を判断する場合にはリスク値の大きさだけで判断するわけではないことに注意する必要があります。次にリスク値とリスクの重要性について説明します。
3.リスクを発生確率と被害規模の積として表現することが一般的であると説明しましたが、その定義を用いる場合に単に掛け算の結果としてのリスク値のみでリスクを判断しているわけではないことに注意する必要があります。
発生確率が大きく被害規模が小さいリスクと、発生確率が小さく被害規模が大きいリスクでは、リスク値は同程度になりますが、リスクの重要性を考えた場合、これらは区別して取り扱われます。例えば、輸送または交通事故を考えた場合、発生確率が大きく被害規模が小さいリスクとしては自動車の交通事故が考えられ、発生確率が小さく被害規模が大きいリスクとしては飛行機や船舶の事故が考えられます。
よく起こる自動車の衝突事故よりも飛行機の墜落事故の方が重要なリスクと考えられることから分かるように、リスク値が同じであれば、発生確率が小さく被害規模が大きいリスクの方が、より重要なリスクと認定されます。
4.リスクが望ましくない事象の発生確率と被害規模で表現され、それらの積であるリスク値だけではリスクの重要性を判断できないことは既に説明した通りです。この点を考慮して、リスクを分かりやすく表現する方法として、リスク図がよく利用されます。
リスク図では発生確率を縦軸にとり、被害規模を横軸にとるため、両者の積として定義されるリスク値が等しいものは、図のように直角双曲線上に現れます。
対数グラフ上では、このように右下がりの直線となります。
発生確率が極小の場合を除いては、リスク値が同じ場合には発生確率が小さく被害規模が大きいリスクの方がより重要なリスクと認定されるため、右側にあるリスク程重要なリスクであることも既に説明した通りです。これは対数グラフの場合でも同様です。
5.効果的にリスク管理を行う場合に、発生確率よりも被害規模が大きいリスクから順番に対応しようとする考え方があります。この考え方は、リスク値が同じであれば発生確率が小さく被害規模が大きいリスクの方がより重要なリスクであるという先ほど説明した考え方と共通するものです。
例えば、1年に1回1万円の被害が発生する場合と、1000年に1回の確率で1000万円の被害が発生する場合では、そのリスク値はともに年間1万円となります。
しかし、その組織の資本金が100万円であった場合には、毎年1万円の被害が発生しても対応できますが、1000万円の被害が発生した場合には倒産する可能性があります。つまり、被害の大きい1000万円の被害は組織として受け入れることができないリスクとなり、1万円の場合よりもより重要なリスクとなります。
資本金が1億円の組織であれば、1000万円の被害も対応可能かもしれません。このように、リスク値が同じ場合には被害規模が大きいリスクがより重要なリスクと認定されますが、受け入れ可能なリスクであるかは、組織によって異なることに注意する必要があります。組織が受け入れ可能なリスクとそうでないリスクの境界はリスク基準によって設定されることになります。リスク基準の詳細については、後ほど説明します。
6.次に、リスク図における領域分類について説明します。リスク図は大きく分けてリスク低減領域とリスク保有領域に分かれます。
リスク図の右上に位置する発生確率が高く被害規模も大きい領域を、リスク低減領域と呼びます。例えば、死傷者や周辺への影響が発生する被害が、頻繁に発生するようなリスクがリスク低減領域に含まれます。
このような領域のリスクに対しては、被害自体を減少させるために、潜在的な危険性を取り除くことや、低減する対策や未然防止対策を実施することによって発生確率を減少させる必要があります。
そして、これらの対策によるリスクの低減が困難で、組織としてリスクを保有できない場合には、リスクを回避するために業務撤退や設備移転等を行うことも考えられます。
7.リスク削減領域に対して、発生確率は高いが被害規模が小さい領域、および被害規模は大きいが発生確率が低い領域をリスク保有領域と呼びます。発生確率は高いが被害規模が小さいリスクとしては、極めて小さい規模の事故や日常的な災害などが挙げられます。また、被害規模は大きいが発生確率が低いリスクとしては、大規模な自然災害や戦争などが挙げられます。
8.リスク保有領域のリスクに対して対策を講じることは、巨額の費用がかかり、また投資が無駄になる可能性が高いなどの理由により、リスクを保有することが合理的と判断されます。後者に対しては、保険を掛けることによるリスク移転という対策が講じられる場合もあります。
リスク(Risk)
リスクという概念は、使い方によって必ずしも定義が厳密に一致する訳ではないが、共通の性質として次の2つの性質を含む概念である。第1に、その事象が顕在化すると、好ましくない影響が発生するという性質第2に、その事象がいつ顕在化するかが明らかでないという、発生の不確定性に関する性質
リスク管理(Risk Management)
組織やプロジェクトに潜在するリスクを把握し、そのリスクに対して使用可能なリソースを用いて効果的な対処法を検討及び実施するための技術体系である。
リスク図(Risk Chart)
リスクを整理・表現する方法の1つであり、縦軸を発生確率、横軸を被害規模とする2次元平面上にリスクを表示した図である。
リスク値(Value at Risk)
リスクの重大性を表現する指標の1つであり、発生確率と被害規模の積として表される数値である。
リスク低減領域(Risk Reduction Domain)
リスク図の右上に位置する発生確率が高く被害規模も大きい領域であり、リスクの削減が必要となる領域である。
リスク保有領域(Risk Retention Domain)
リスク図における、発生確率は高いが被害規模が小さい領域、および被害規模は大きいが発生確率が低い領域などのリスク値が比較的小さい領域のこと。この領域のリスクに対しては、リスクを保有することが合理的と判断される。
ハザード(Hazard)
事故等のリスク事象を引き起こす潜在的な原因のこと。例えば、危険物の漏洩がある。
不測事態(Contingency)
人の死傷、物的損傷、財産喪失、組織に打撃を与える潜在的な事態のことを指す。不測事態が発生もしくは差し迫ったときに現れる一つの特定状態が危機である。
不確定性(Uncertainty)
リスクという概念に共通する2つの性質のうち、その事象がいつ顕在化するかが明らかでないという性質である。もう1つの共通する性質としては、その事象が顕在化すると好ましくない影響が発生するという性質がある。
被害規模(Damage Scale)
リスクの重大性を表現する指標の1つであり、望ましくない事象の影響の種類と大きさを考慮して求められる。リスクの共通の性質の1つである「その事象が顕在化すると好ましくない影響が発生する」という性質を表現する指標である。
発生確率(Occurrence Probability)
リスクの重大性を表現する指標の1つであり、定性的または定量的に求められる。リスクの共通の性質の1つである「その事象がいつ顕在化するかが明らかでない」という性質を表現する指標である。
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
リスク (risk) の定義にはさまざまあるが、一般的には、「ある行動に伴って(あるいは行動しないことによって)、危険に遭う可能性や損をする可能性を意味する概念」と理解されている。
日本語ではハザード (hazard) とともに"危険性"などと訳されることもあるが、ハザードは潜在的に危険の原因となりうるものすべてをいい、リスクは実際にそれが起こって現実の危険となる可能性を組み合わせた概念である。
ゆえにハザードがあるとしてもそれがまず起こりえないような事象であればリスクは低く、一方確率は低いとしても起こった場合の結果が甚大であれば、リスクは高いということになる。
語義
経済学上のリスク
経済学においては一般的に、リスクは「ある事象の変動に関する不確実性」を指し、リスク判断に結果は組み込まれない。例えば、ビルの屋上の端に立つのは危険であるが、まだ転落するか無事であるかは分からない。この状態はかなり不確実でリスクが高い。しかし、一旦転落すれば十中八九命がないとすれば、転落直後にリスクが低下することになる。
リスクの概念は、経済学の中でも金融理論においてよく用いられる。投資において、将来の収益が必ずしも確実といえない投資手段があるためである。投資におけるリスクは、分散投資を行うことによって低減させることが可能である。株式投資を例に取ると、単一銘柄に投資を行っている場合、その企業の持つ固有リスクのために、期待される収益を得るに当たっての不確実性が高い。
しかし、投資先を分散することによって企業固有のリスクを和らげることができる。投資先を可能な限り分散し、固有リスクを分散することによって、投資によるリスクは市場リスクに近づけることができる。株式投資の例に戻ると、市場リスクとは、例えばTOPIXのような市場平均を指す。
利得がある不確実性をアップサイドリスク、損失する不確実性をダウンサイドリスクと呼ぶ。リスクが高いものは損失と利得の度合いが元本に対して高くなる。そのため、高い利得を得たい者は、損失する可能性を覚悟しなくてはならない。金融工学はここに目をつけ、統計学などを利用することで、ダウンサイドリスクを低減しアップサイドリスクをより高めることを目指している。
主なリスクの種類として、価格変動リスク、デフォルトリスク、流動性リスク、インフレリスク等があげられる。
物のリスク
物のリスクは、物(物質と物品)にかかわって、その周辺物(人、生態、有形財産)が実際に被る可能性がある悪影響の大きさを示し、必ずマイナス・イメージである。プラス・イメージについてあわせて議論するときにはベネフィットという語とともに使われる。
リスク概念は「安全」概念の定義と結びつけてはじめてその概念と背景にある思想が理解できる:安全とは、リスクが小さいことである。
この背景には、リスク・ゼロ追求は現実的な安全追求の姿勢でないという反省がある。 物の不適切な取扱いの結果、周りに、その物固有の危険性が影響を及ぼして、悪い事象(危害、損傷、損害等)が出現した時、リスクが現実となってしまうことがありうる。ここで物は物質又は物品の場合がある。
また、周りとして、人、生態、有形財産の場合がある。この周りの一つとして社会を考える場合もある。ここでの危険性には、いわゆる(狭義の)危険性と有害性の両方を含むため、これをはっきりさせるために危険有害性という用語が使われる場合も多くある(英語のen:hazardが元であるので、ハザードというカタカナ表記も使われる。)。
つまり、物のリスク評価(risk assessment)を実施するときには、
1. 物固有の危険性を特定し、その程度を評価し(危険性評価、hazard assessment)、
2. その物が取り扱われている(取扱い)状態を特定し、その周り(人、生態、有形財産等)との接触(暴露等)の頻度、範囲、量等を評価し(暴露評価、exposure assessment)、
3.その組み合わせで実際に悪い事象の出現する可能性とその大きさを見積もり、その結果が不当に大きいかどうかを判断する(リスク判定、risk characterisation) ことになる。
「安全」概念を再定義すると:
「安全とは取扱う物質の固有の危険性が低いか、取扱う周辺との接触・暴露が小さいことである。」ということになる。毒物学と薬学の父であるパラケルススの「すべての物質は毒である。毒でないものない。量によって毒と薬に区別される」との言はまさにこれを示している。
物固有の危険性
機械危険性: 物品の持つ機械的特性に基づく危険性。鋭利な刃先(裂傷にかかわる)、回転機械(巻き込まれ事故に係わる)等。
物理危険性: 物の持つ熱、圧力、音など物理現象に基づく危険性。特に、燃焼性、爆発性が問題となる。
健康危険性: 物質の持つ人の生命および健康に係わる有害性。急性毒性。慢性毒性。発癌性。感作性(アレルギー)、生殖毒性、変異原性等。
環境(生態)危険性: 物質の持つ地球環境や人以外の動植物に係わる危険有害性。オゾン層破壊物質、温暖化物質; 水棲生物に対する急性・慢性毒性。陸棲生物に対する急性・慢性毒性等。
2から4についての多くはGHSによる分類と表示の国際的調和作業が進行中である。これにより危険性を類型的に処理することができるようになり、対策立案も容易になる。国際的にはこのGHSの原型ともいえるRTDGに基づいて航空輸送、海上輸送、陸上輸送の安全対策が立てられている(ただし、日本の陸上輸送の安全は国際基準に基づいていない)。
リスク削減-もっと安全を
このように考えることによって、リスク判定の結果「不当にリスクが大きい」、つまり、安全の程度が低すぎるとされた場合、どうやって安全を確保するかという課題を解決する(リスク軽減策を立てる)上で整理がしやすくなる。つまり、
1.物の持つ固有の危険性を低くする。たとえば、鋭利な部分を取り除く、切れにくくする/切れやすくする、不燃剤を混ぜる、粒子のサイズを大きくする(細かいものは粉塵爆発を引き起こす、肺の奥のほうにまで到達して悪影響を与えるなどのリスクがある)、危険有害性の低いものに替える等々。
2. 取扱い手順を見直す、たとえば、切れにくい刃物はそのまま使用せず砥いでから使用する手順とする; 換気を行う(湯沸し器による一酸化炭素中毒); 取り扱うものに合った手袋や眼鏡や前掛け等を使用する; スプレー缶は穴を開けてから捨てる; そしてなによりも取り扱う物の特性(特に危険性)をよく理解する、あるいは、GHSの目的に挙げられているように、その理解に必要な情報をわかりやすく提供する等がある。
工学上のリスク
工学においては、リスク (risk) とは、一般的に「ある事象生起の確からしさと、それによる負の結果の組合せ」をいう (JIS Z8115: 2000)。この場合、リスクの対象は限定されない。
一例として人体もしくは財産等に対するリスクに危害リスク (risk of harm) といった危害発生の確からしさ、危害の厳しさの1つの組合せなどのリスクがあり、リスクには事象が顕在化することから好ましくない影響ごとが発生されること、その事象がいつ顕在化するかが明らかではない発生不確定性があるという性質が含まれる。
システムにおけるリスク
システムにおけるリスクは、経済学と違いより良い結果が出ることはリスクとならない。損失の可能性があるものだけがリスクとみなされる。その意味では不確実性ではなく、確実な危険性といえる。
マネジメント
経営管理論
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(マネジメント から転送)
経営管理論(英: business management, Management Administration, etc.)は、組織・団体(主に企業)の管理についての実践的な技法(経営管理)の確立を目指す学問であり、経営学を構成する分野の一つ。 20世紀初頭、科学的管理法を提唱し、「経営学の父」と呼ばれたフレデリック・テイラーがその始まりとされており、また「管理原則(管理過程論)の父」と呼ばれたアンリ・ファヨールによる研究により、学問として成立。その後、主にアメリカで研究が発展した。
現在では、企業経営の大規模化・複雑化に伴って組織を構成する要素及び経営に関わる要素は多岐に亘るようになった結果、経営管理の扱う範囲がたいへん広くなり、また専門性が強くなったため、一般に、その管理対象に応じて細分化されている。例えばヒトの面の管理は人事労務管理(人事管理)論、カネの面の管理は財務管理論など。
経営管理の定義
経営管理は、広義に解釈すれば、“経営システムの維持・存続のための全成員のダイナミック(dynamic)な情報活動”であって、それは人間の頭脳活動を含む神経系統の活動に相当するものである。
経営管理とは、人に働きかけて、協働的な営みを発展させることによって、経営資源の転換効率や環境適応の能力と創造性を高めて、企業の目的を実現しようとする活動である。(中略)経営管理は、個性的で具体的な人間が組織的な人間として振る舞い、組織の活力や創造性を高めるように働きかけようとする。こうして企業の協働的な営みは組織として展開され、個人の能力の総和以上の生産を実現するのである。
また、「管理原則の父」と呼ばれるファヨールは、経営管理を計画、組織、指揮、調整、統制の5要素と定義している。
簡単にまとめると、経営管理とは、企業活動を円滑に行うとともに、企業の目的を達成するために、「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つの経営資源を調達し、効率的に配分し、適切に組み合わせる、といった諸活動のことである。特に、主体的に行動する「ヒト」(人的資源)が重要であり、これに上手く働きかけて、組織化し協働させたり、活性化させ(もしくは能力を発揮させ)たりするようなシステムを如何に構築するかということが主要な課題となる。
経営管理論の発展
19世紀後半から、第二次産業革命と呼ばれる工業化の進行・資本主義の発展や経済の拡大により、企業は経営資源を効率的に運用し、生産力を増強することを目指すようになった。そのような状況の下、20世紀初め、アメリカの技術者・テイラーが「科学的管理法」を、フランスの経営者・ファヨールが「管理過程論」の原型をそれぞれ発表、経営管理の研究が始まった。 一方、ドイツの社会学者・マックス・ヴェーバーは、組織の支配形態を分析し、合法的・合理的な組織は官僚制組織であるとした。その上で組織の合理的・機能的側面に注目、組織構造という概念を考え出し、「官僚制組織論」を提唱した。これらの3人の研究が、経営管理論の出発点と言える。
その後、人間的側面を軽視する科学的管理法への批判から、人間関係や人間の持つ欲求、特に自己実現欲求に注目する、「人間関係論」が生まれた。メイヨー、レスリスバーガーによるホーソン実験や、マズローの欲求段階説(自己実現理論)、マクレガーのXY理論などが知られる。
さらにその後、マックス・ヴェーバーの組織の理論を経営に応用し、組織全体を分析する議論(システムズ・アプローチ)がバーナードによって唱えられ、後にサイモンの意思決定論に繋がった。
一方、1960年代以降、従来の普遍的な法則を見出そうとする議論では抽象的で現実の経営に対応できないとして、経営環境に応じてそれぞれに異なる最適な組織形態・管理法が存在するとする見解(コンティンジェンシー理論)が登場した。
これらの諸議論を基礎に、リーダーシップ論、モチベーション論、組織文化論、企業間関係論など様々な議論に広がっている。
占部都美は、最近の経営管理論は、意思決定論的アプローチ、行動科学的アプローチ、システムズ・アプローチを取っているとしている。
20世紀の終わりには、マネジメントの項目は以下の6つのサブカテゴリーから成るとされていた。
人材マネジメント Human resource management
オペレーションマネジメント w:Operations or production management
戦略的マネジメント w:Strategic management
マーケティングマネジメント w:Marketing management
財務管理 w:Financial management
ITマネジメント w:Information Technology management
21世紀の現在では、この6つのカテゴリーのみでとらえることがますます困難となってきている。 多くのプロセスが同時にいくつかのカテゴリーを含んでいるためである。 現在では6つのカテゴリーの代わりに、一人が管理できる様々なプロセス、タスクおよびオブジェクトの単位で考える傾向にある。
経営管理の諸学説
H.クーンツは著書『経営の統一理論』にて、経営管理の学説を以下の6つに分類している。
管理過程学派(普遍学派)
経営管理を「組織を構成する人々に、あることをしてもらう過程」と捉え、そのための管理の諸原則を明らかにしようとする。
経験学派
経営管理に関する事例研究(ケーススタディ)を通じて、最も有効な経営管理技法を構築する。
人間行動学派
経営には多くの人々が関わっていることに着目し、構成員・関係者の行動や相互関係を研究する。行動科学や人間関係論など、心理学的アプローチ。
社会システム学派
経営管理を人やその行動からなる一つの社会システムと捉え、社会学的見地から研究する。人間的側面を重視することから、人間行動学派と共通する点を持つ。バーナードに代表される。
数理学派
数学や統計学、計測可能なデータなどを駆使して、数理的アプローチから経営管理を把握しようとする。そのための手段として代表的なものにオペレーションズ・リサーチがある。この学派の研究は経営科学とも言われる。
意思決定学派
企業内の意思決定システムを研究し、合理的な意思決定を行うにはどうすべきかを追究する。サイモンに代表される。
注釈
^ カリスマ支配、伝統的支配、合法的支配の3つ。
^ これらは「経済人モデル」に立脚した考え方である。
^ これらは、人間を欲求・感情で動く「社会人モデル」(メイヨーによる)や、自己実現を欲する「自己実現人モデル」(マズローによる)で捉えている。
^ 占部都美『経営学辞典』(中央経済社)
リスクマネジメント 提供: フリー百科事典
リスクマネジメント (Risk Management) とは、リスクを組織的にマネジメントし、ハザード(危害 (harm) の発生源・発生原因)、損失などを回避もしくは、それらの低減をはかるプロセスをいう。リスク・マネジメントとは各種の危険による不測の損害を最小の費用で効果的に処理するための経営管理手法である。
概要
近年、会社法の施行により、株式会社では「損失の危険の管理に関する体制」を整備する必要があること、また、金融商品取引法では2008年度から日本版SOX法が施行され、財務に関する分野において、リスク管理体制の整備が求められていることもあり、経営上、リスクマネジメントは脚光を浴びており、「コンプライアンスからリスクマネジメントの時代へ」とも言われている。
リスクマネジメントとは、リスクを把握・特定することから始まり、把握・特定したリスクを発生頻度と影響度の観点から評価した後、リスクの種類に応じて対策を講じる、また、仮にリスクが実際に発生した際には、リスクによる被害を最小限に抑えるという一連のプロセスをいう。どの会社においても、意思決定を行う際は、当然、暗黙の了解で、そういったことをこれまで行ってきたものと思われるが、近年、リスクマネジメントに対する意識の高まりを受け、特に、明示的に行われるケースが増えている。
大まかなプロセス:リスク分析によりリスク因子を評価し、リスクアセスメントによりリスク管理パフォーマンスを測定し、改善する(例えば、リスクの発生頻度や、リスク顕在化による被害を最小化するための新たな対策を取る)。リスクファイナンスによりリスク顕在化に備える。これらのプロセスはPDCAサイクルを取る。
近年、民間企業では、例えば環境リスクであれば、環境リスクに特化したり、不正リスクであれば、不正リスクに特化したりして、様々な種類のリスク因子を使って、より高度なリスクマネジメントを行うところが増えてきた。 また、これに伴い、従来の危機管理部門を発展させ、リスクマネジメントに特化した専門部署を置くところも多くなってきた。
リスクファイナンス
リスクファイナンスは、リスク対処の1つとして、リスクが実際に現実化した場合の損失補償を準備することである。保険も、掛けられる場合には、有効な対策の1つとなる。この場合、リスクを保険会社に移転していることになる(リスク移転)。リスク移転に対し、自らの組織で対処することをリスク保有と言う。
事例
リスクマネジメントの甘さが指摘される事例とその対処例。
社員管理の不徹底で顧客情報の漏洩が危惧される場合。
情報セキュリティポリシーの策定、組織への徹底。
大地震が想定される地域に、組織の重要な情報システム・意思決定機構が集中している場合。
リスク分散(国家で言えば首都機能分散)。ディザスタリカバリ対処の検討準備。
事故が予想される現場における、安全措置の不徹底。
現場安全マニュアルの策定・遵守。
緊急事態において、迅速な情報伝達・意思決定を行なう機構と訓練が不足している場合。
緊急事態における迅速な対処および対処責任者の明確化、訓練の徹底。
緊急事態対処訓練。身近な例では避難訓練などがある。
製造業におけるリコール発生時の事前のマスコミ対策。
常日頃から大量に広告を打ちマスコミが自主的に報道しないよう誘導する。
改善後の品質向上を大きく取り扱ってもらう。
よい例:ジャパネットたかた個人情報漏洩事件。
悪い例:雪印乳業食中毒事件。
関連項目
リスクマネジメント論
リスクアセスメント
リスク分析
安全工学
リスクヘッジ
リスクコミュニケーション
事業継続マネジメント (BCM)
事業継続計画 (BCP)
内閣危機管理監
新しいリスクマネジメント規格であるISO 31000 : 2009 及びリスクマネジメント用語に関するISO ガイドGuide 73 : 2009 について
ERM、全体的RM、トータルRM と流行語は色々ありますが、結局のところ、これ等全ては、組織が組織の目標を達成するために対処しなければならない脅威や好機を、如何に効果的に明らかにし、管理するかを記述したものです。
組織の目標を達成すること、効果的な組織統治(Governance)を確実にすること、節度を持って法対応を確立すること、及び保証を提供することといった全てのことは、リスクを確実に理解することとそれを首尾良く管理する手段に掛かっています。
ISO 31000 : 2009 及びそれと対をなすISO ガイド73
2009 は、規格の使用者が以下に記述されたことを行う時の手助けとなるように設計されています。
・リスクマネジメントとは何であるかを明確にする。
・組織統治(Governance)の意味合いに於いて、リスクを管理する効果的なプロセスを開発する。
・組織全体でリスクを管理する総合的な取り組みの必要性を理解する。
・リスクマネジメント方針とフレームワークの必要性を説明する。
・組織の中でリスクを管理するための主体者(ownership)と責任(account2abilities)を定める。
・特定のリスクマネジメント用語やプロセスが、何故、組織に合わせて調整され(tailored)なければならないかを理解する。
・組織、活動及びプロジェクトの中でリスクマネジメント活動を開発し、実施する。
・リスク対応手法を決定する。
・どの様に、リスクマネジメントプランを開発し、実施し、監視するかを理解する。
ISO 31000 : 2009 に示されている汎用的なアプローチは、組織全体でリスクを効果的にそして首尾一貫した形で管理することを確実にする助けとなります。
ISO 31000 : 2009 は、透明性があって信頼出来る方法で、リスクを管理するために不可欠な要素を実施する指針を提供しています。ISO ガイド73 : 2009 は、リスクマネジメント用語に見識(insight)を提供しています。
ISO 31000 : 2009 とISO ガイド73 は、以下のような幅広い利害関係者に使用されることを意図しています。
・組織の中でリスクマネジメントの実施に責任(responsible)のある人。
・組織がリスクを管理することを確実にする必要がある人。
・組織全体、組織の特定な領域又は特定な活動のためにリスクを管理する必要のある人;及び
・組織におけるリスクマネジメントの履行状況を評価する必要のある人。
ISO 31000 : 2009 は、特に以下の人全てに関連があります。
・公的組織であれ民間組織であれ、大きな組織であれ小さな組織であれ、全ての組織の取締役、経営管理者及びライン管理者。
・内部職員又はコンサルタントとして、リスクのマネジメントに助言を提供する審査員、会計士、コンプライアンス専門家及び法律顧問。
http://www.jsa.or.jp/stdz/mngment/pdf/iso_risk.pdf
リスク管理と危機管理
1.企業等の組織における活動には、不確実な部分が必ず含まれています。もちろん、結果的に利益や社会的評価がプラスとなる事項もありますが、損失や事故のようなマイナスの影響を及ぼす事項も潜在しています。一般的には、後者をリスクと呼びます。プラスの影響を大きくしマイナスの影響を小さくするためには、組織としてリスクを管理していくことが重要となります。
リスク管理という概念は、何を望ましくない事象として考えるかという基本的な問題提起を含むものであり、その考え方を基に施設の保守点検等の工学的安全活動をはじめ、これまでも組織ごとにリスク管理に関する様々な活動が実施されてきました。
しかし、近年では1回のトラブルでも組織の存続に関わるような事件が度々発生しています。今改めてリスク管理の必要性が強調されるようになってきている背景には、このような事件に見られるように、これまでの活動の限界が明らかになったことがあります。
2.これまでのリスク管理に関する活動の課題としては、主に4点挙げられます。
1つ目は、問題点の把握が経験的であり、問題点が明らかになってから対応を検討する傾向がある点です。
2つ目は、発生確率が小さい事象に対しては、被害が大きくなると予想される事象であっても、対応の優先順位が低くなる傾向がある点です。
3つ目は、対応が部署単位、専門単位で検討されることが多く、全組織的な優先順位や重要性を検討するシステムを持っていない点です。
4つ目は、内部における検討結果を外部に対して情報公開するシステムを持っていない点です。
1回のトラブルが組織の存続に影響を与えかねない現状では、このような課題を改善して、限られた経営資源を有効に活用するためのリスク管理システムを確立することの必要性が高まってきています。
3.組織や施設の安全を守る活動は、リスク管理と危機管理に分けることが出来ます。しかし、概念あるいは用語としてのリスク管理と危機管理の違いはそれぞれの技術分野によって若干の違いがあり、必ずしも明確ではありません。
4.リスクを低減するための活動には、事故や危機の未然防止と、事故や危機が発生した場合の拡大防止の2つのフェーズがあります。
一般的には、事故や危機がなるべく起きないように対処する活動をリスク管理と呼び、事故や危機的な状況が発生した後の活動を危機管理と呼ぶ場合が多いようです。今回も、リスク管理と危機管理をそのように区別することにします。
5. リスク管理は未然防止を含むため、保守点検等の活動のように定常的な組織において定期的に運用されるものです。一方、危機管理の場合は、専門的担当組織が定常的に存在する場合もありますが、事故や事件が発生した後、短時間での暫定組織による対応にならざるを得ない場合が多いことに特徴があります。このため、大規模地震や事故・事件などに遭遇した場合には、危機管理の必要性が強調されることが少なくありません。
リスク管理には、危機時の体制やマニュアルの整備などの危機に関する対応事項が含まれる場合もあります。危機管理についても、危機発生時にその被害や悪影響を最小に止めることに限定せずに、危機を発生させないための未然防止活動も含めて危機管理と呼ぶこともあります。
以上のように、共通の要素も多いものですが、短期間におけるリーダーシップが重要である点では、危機管理は大きな特徴を持つと言えます。
6.リスク管理と危機管理の違いを図に示しています。平常時の活動であるせまい意味でのリスク管理は重要な定常業務の一つでありますが、不測事態が発生した場合の対応である危機管理の技術を修得することも必要なことです。
7.リスク管理の具体的な内容に関しては、対象とするリスクの範囲や要求される対応内容により様々なレベルが存在します。そのため、共通するリスク管理の基本フレームを理解した上で、様々な制約条件を踏まえ、組織や目的に見合ったレベルのリスク管理を行うことが重要と言えます。
リスク管理の基本フレームは、大きく分けて4つのステップから構成されます。
1番目は、リスク対応方針です。リスク対応方針は、行動指針と基本目的から成ります。人命優先や環境被害の最小化は当然でありますが、リスク管理に関する基本的な考え方を示し、全ての活動がこの方針に従って実施されていくことを全ての組織構成員に周知・共有することが重要であります。
2番目は、リスク特定です。リスク特定では、リスクに関する情報を分析してハザードを特定することにより、組織に重大な結果をもたらす可能性のあるリスク及び結果の重大性の判断が困難なリスクを把握します。ハザードは、日本語では危険要因と訳されることが多いようです。
8.3番目は、リスクアセスメントです。リスクアセスメントの主要な内容は、リスク分析とリスク評価に分類されます。リスク分析では、まずシナリオ分析によるリスクの見積もりを行い、次いでシステム安全工学などの工学的手法によるリスク算定を行います。リスク算定は発生確率の算定と被害規模の算定の2つを実施する必要があります。
また、リスクを評価し対策方針を検討するためには、弱点分析を行い、どの部分に対策を講じることが適切かを把握します。リスクマネジメントサイクルの中で対策が必要と判断されたものに対しては、対策効果を把握するため、リスク解析により算出されたリスクがどの程度減少するかを検討する対策効果算定を行います。リスク評価では、リスク解析によりリスクの大小及びその特性によって、対応方針を決定します。対応方針には、リスクの保有、低減、回避、移転の4つが考えられます。
4番目は、リスク対策です。リスク対策では、得られたリスクの大小や特性により、リスク対応方針に基づいた様々な対策可能性の中から最適な対策を選択し実施します。対策にはコスト増や人的資源の投入が必要となるため、総合的な技術監理の視点が必要となります。
9.組織を取り巻くリスクについて触れることにします。組織にとって望ましくない事象は非常に多岐に渡り、小さなものまで含めると数限りなく存在します。リスク管理においてどの事象やリスクを対象とするかは、リスク管理の基本フレームにおけるリスク対応方針やリスク特定に関わる問題でありますが、リスク管理の対象としない場合でも潜在的な事象を把握しておくことは非常に重要なことです。
表に組織を取り巻くリスクの一例を示しましたが、望ましくない事象やリスクを整理する場合には、「まさかこんなことが起こるとは思わなかった」と言うことの無いように、表のような広い視野で整理することが重要です。今日では、被害影響として組織の社会的信頼性の低下が重要視されてきており、社会的信頼性の低下に結び付く事象についても見落としの無いようにすることが重要です。
10.また、組織を取り巻くリスクの要因についても、一つの考え方を図に整理しましたが、これまでは主に設備の故障やヒューマンエラー等を要因とする事象がリスク管理の対象とされてきました。
しかし、最近ではネットワーク犯罪や社員による情報漏洩等、人間の悪意に基づく事件が発生しており、今後はこのようなセキュリティに関する要因についても取り扱うことが必要となってきています。
1.リスク管理を理解するための準備として、リスクという言葉の概念について説明します。
リスクという概念は、使い方によって必ずしも定義が厳密に一致する訳ではありません。ただし、リスクという概念は共通の性質として次の2つの性質を含みます。
第1に、その事象が表面化すると、好ましくない影響が発生するという性質です。
第2に、その事象がいつ表面化するかが明らかでないという、発生の不確定性に関する性質です。
以上の性質を基に、リスクを関係式で表現すると、このようになります。つまり、リスクは望ましくない事象が発生した場合の被害規模とその発生確率により表現されることが分かります。
被害規模は、望ましくない事象の影響の種類と大きさを考慮して求められます。財政的な被害を見るのか、人的被害を見るのか、その両方を見るのか等によって、被害規模の内容は変わります。
また、発生確率は年に何回発生する可能性があるか、といったように定量的に把握される場合と、頻繁に発生する、時々発生する、ほとんど発生しない、といったように定性的に把握される場合があります。
リスクを被害規模と発生確率の積として捉える考え方もありますが、被害規模と発生確率の2次元のマトリックス上で捉える考え方もあります。次にリスクに関する定義の例を説明します。
2.リスクに関する定義の例として、3つの定義を示しました。
注目する対象により様々に定義されていますが、一番目に示した定義に従って、リスクを発生確率と被害規模の積として表現することが一般的です。発生確率と被害規模の積をリスク値と呼びますが、リスクの重要性を判断する場合にはリスク値の大きさだけで判断するわけではないことに注意する必要があります。次にリスク値とリスクの重要性について説明します。
3.リスクを発生確率と被害規模の積として表現することが一般的であると説明しましたが、その定義を用いる場合に単に掛け算の結果としてのリスク値のみでリスクを判断しているわけではないことに注意する必要があります。
発生確率が大きく被害規模が小さいリスクと、発生確率が小さく被害規模が大きいリスクでは、リスク値は同程度になりますが、リスクの重要性を考えた場合、これらは区別して取り扱われます。例えば、輸送または交通事故を考えた場合、発生確率が大きく被害規模が小さいリスクとしては自動車の交通事故が考えられ、発生確率が小さく被害規模が大きいリスクとしては飛行機や船舶の事故が考えられます。
よく起こる自動車の衝突事故よりも飛行機の墜落事故の方が重要なリスクと考えられることから分かるように、リスク値が同じであれば、発生確率が小さく被害規模が大きいリスクの方が、より重要なリスクと認定されます。
4.リスクが望ましくない事象の発生確率と被害規模で表現され、それらの積であるリスク値だけではリスクの重要性を判断できないことは既に説明した通りです。この点を考慮して、リスクを分かりやすく表現する方法として、リスク図がよく利用されます。
リスク図では発生確率を縦軸にとり、被害規模を横軸にとるため、両者の積として定義されるリスク値が等しいものは、図のように直角双曲線上に現れます。
対数グラフ上では、このように右下がりの直線となります。
発生確率が極小の場合を除いては、リスク値が同じ場合には発生確率が小さく被害規模が大きいリスクの方がより重要なリスクと認定されるため、右側にあるリスク程重要なリスクであることも既に説明した通りです。これは対数グラフの場合でも同様です。
5.効果的にリスク管理を行う場合に、発生確率よりも被害規模が大きいリスクから順番に対応しようとする考え方があります。この考え方は、リスク値が同じであれば発生確率が小さく被害規模が大きいリスクの方がより重要なリスクであるという先ほど説明した考え方と共通するものです。
例えば、1年に1回1万円の被害が発生する場合と、1000年に1回の確率で1000万円の被害が発生する場合では、そのリスク値はともに年間1万円となります。
しかし、その組織の資本金が100万円であった場合には、毎年1万円の被害が発生しても対応できますが、1000万円の被害が発生した場合には倒産する可能性があります。つまり、被害の大きい1000万円の被害は組織として受け入れることができないリスクとなり、1万円の場合よりもより重要なリスクとなります。
資本金が1億円の組織であれば、1000万円の被害も対応可能かもしれません。このように、リスク値が同じ場合には被害規模が大きいリスクがより重要なリスクと認定されますが、受け入れ可能なリスクであるかは、組織によって異なることに注意する必要があります。組織が受け入れ可能なリスクとそうでないリスクの境界はリスク基準によって設定されることになります。リスク基準の詳細については、後ほど説明します。
6.次に、リスク図における領域分類について説明します。リスク図は大きく分けてリスク低減領域とリスク保有領域に分かれます。
リスク図の右上に位置する発生確率が高く被害規模も大きい領域を、リスク低減領域と呼びます。例えば、死傷者や周辺への影響が発生する被害が、頻繁に発生するようなリスクがリスク低減領域に含まれます。
このような領域のリスクに対しては、被害自体を減少させるために、潜在的な危険性を取り除くことや、低減する対策や未然防止対策を実施することによって発生確率を減少させる必要があります。
そして、これらの対策によるリスクの低減が困難で、組織としてリスクを保有できない場合には、リスクを回避するために業務撤退や設備移転等を行うことも考えられます。
7.リスク削減領域に対して、発生確率は高いが被害規模が小さい領域、および被害規模は大きいが発生確率が低い領域をリスク保有領域と呼びます。発生確率は高いが被害規模が小さいリスクとしては、極めて小さい規模の事故や日常的な災害などが挙げられます。また、被害規模は大きいが発生確率が低いリスクとしては、大規模な自然災害や戦争などが挙げられます。
8.リスク保有領域のリスクに対して対策を講じることは、巨額の費用がかかり、また投資が無駄になる可能性が高いなどの理由により、リスクを保有することが合理的と判断されます。後者に対しては、保険を掛けることによるリスク移転という対策が講じられる場合もあります。
リスク(Risk)
リスクという概念は、使い方によって必ずしも定義が厳密に一致する訳ではないが、共通の性質として次の2つの性質を含む概念である。第1に、その事象が顕在化すると、好ましくない影響が発生するという性質第2に、その事象がいつ顕在化するかが明らかでないという、発生の不確定性に関する性質
リスク管理(Risk Management)
組織やプロジェクトに潜在するリスクを把握し、そのリスクに対して使用可能なリソースを用いて効果的な対処法を検討及び実施するための技術体系である。
リスク図(Risk Chart)
リスクを整理・表現する方法の1つであり、縦軸を発生確率、横軸を被害規模とする2次元平面上にリスクを表示した図である。
リスク値(Value at Risk)
リスクの重大性を表現する指標の1つであり、発生確率と被害規模の積として表される数値である。
リスク低減領域(Risk Reduction Domain)
リスク図の右上に位置する発生確率が高く被害規模も大きい領域であり、リスクの削減が必要となる領域である。
リスク保有領域(Risk Retention Domain)
リスク図における、発生確率は高いが被害規模が小さい領域、および被害規模は大きいが発生確率が低い領域などのリスク値が比較的小さい領域のこと。この領域のリスクに対しては、リスクを保有することが合理的と判断される。
ハザード(Hazard)
事故等のリスク事象を引き起こす潜在的な原因のこと。例えば、危険物の漏洩がある。
不測事態(Contingency)
人の死傷、物的損傷、財産喪失、組織に打撃を与える潜在的な事態のことを指す。不測事態が発生もしくは差し迫ったときに現れる一つの特定状態が危機である。
不確定性(Uncertainty)
リスクという概念に共通する2つの性質のうち、その事象がいつ顕在化するかが明らかでないという性質である。もう1つの共通する性質としては、その事象が顕在化すると好ましくない影響が発生するという性質がある。
被害規模(Damage Scale)
リスクの重大性を表現する指標の1つであり、望ましくない事象の影響の種類と大きさを考慮して求められる。リスクの共通の性質の1つである「その事象が顕在化すると好ましくない影響が発生する」という性質を表現する指標である。
発生確率(Occurrence Probability)
リスクの重大性を表現する指標の1つであり、定性的または定量的に求められる。リスクの共通の性質の1つである「その事象がいつ顕在化するかが明らかでない」という性質を表現する指標である。
2009年11月22日
民間自然環境保全活促進報告書
民間団体等による自然環境保全活動の促進に関する検討会
報告書
1.はじめに
昨年6月に制定された生物多様性基本法(平成20年法律第58号)の前文において、人類と生物多様性に関して次のように述べられている。
「人類は、生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっている。また、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている。」
しかしながら、その人類の存続の基盤となっている生物多様性は、今、人類との関わりがもたらす危機に脅かされている。
「生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、社会経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の劣化、外来種等による生態系のかく乱等の深刻な危機に直面している。」
わが国の生物多様性の現状を見てみると、例えば植生に注目すれば、急峻な山岳地、半島部、島嶼といった人為の入りにくい地域に自然植生が分布し、平地や小起伏の山地では二次林や二次草原などの代償植生や植林地、耕作地の占める割合が高くなるなど、さまざまな段階の生態系が、さまざまな緯度、標高、水環境に立地することにより、非常に豊かな生態系の多様性が存在している。こうした生態系は、わが国の気候や地史と自然へのさまざまな働きかけの結果残されてきた特徴あるものといえるが、現在では広い範囲で失われてきている。
このような状況を踏まえ、国や地方公共団体においては、自然環境保全に関連する各種法律に基づき、さまざまな保護地域を設定し、生物多様性の保全の観点も踏まえてこれらの保護地域を適切に管理しているところであるが、未だ十分な状態であるとはいえず、多様な主体との連携を進めつつ、引き続き積極的に生物多様性の保全に取り組むことが重要である。
そのような国や地方公共団体といった公的主体の取組の一方で、国民からの寄附金を用いて、自然保護のために、身近な自然の豊かな民有地を買い入れて管理を行い、保全を図っていこうとする「ナショナル・トラスト活動」や、企業等が所有地を活用してNGO等との協力により緑地を保全する活動など、民間団体等による生物多様性の保全のための取組が行われてきている。 特に「ナショナル・トラスト活動」に関しては、昭和30年代に活動がスタートした当初は、大規模な開発から自然環境を市民自らの手で守る手段としてその活動が実施されたが、最近では、相続を契機としたやむを得ない土地の売却・開発による自然環境の改変を避けるべくその活動が実施されるなど、引き続きその活動が必要な状況にある。
このような動きを受け、生物多様性基本法第21条第3項において、「国は、事業者、国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得並びにその維持及び保全のための活動その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する自発的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする」との規定が盛り込まれた。
これにより、ナショナル・トラスト活動をはじめ「様々な民間団体(NPO法人を含む。)による活動をより一層推進し国民主導の生物多様性保全のための取組を推進するため、税制優遇措置や関連制度の見直し等の必要な措置を講ずること」*1が国に求められている。
国際的な動きに目を転じると、平成22年(2010年)10月には、愛知県名古屋市において、世界中から7,000人もの参加者が見込まれる「生物多様性条約 第10回締約国会合」(COP10)が開催される。この2010年とは、平成14年の第6回締約国会合で定められた「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減?させる」という「2010年目標」の目標年であり、COP10では、2010年以降の次期目標の採択が予定されている。
すなわち、COP10は、今後の生物多様性を巡る国際的な動きを方向付ける重要な会議であり、ホスト国であるわが国としても、そのイニシアティブを強力に発揮できるよう、生物多様性の保全に向けたわが国の取り組み姿勢をしっかりとした形で打ち出していく必要がある。
このような状況を踏まえ、本検討会では、わが国における生物多様性の保全を図るため、NGO等の民間団体、企業等が行う生物多様性の保全上重要な土地の取得並びにその維持及び保全等の活動を促進するための方策について検討を行った。本報告が、そのような活動を促進する上で有益なものとなり、引いては、わが国の生物多様性の保全を図る一助となることを強く期待する。
2.民間団体等が行う土地取得等の自然環境保全活動を巡る状況・背景
(1) 生物多様性の保全の基本的考え方
生物多様性条約では、「生物多様性」をすべての生物の間に違いがあることと定義しており、具体的には、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺伝子の多様性」の3つのレベルでの多様性があるとしている。
生物多様性という差異(変異性)を保全するためには、この3つのレベルにおける構成要素である具体的な「生態系」や「種」、「個体」を保全することが重要であるが、生物はその種のみが単独で存在するのではなく、植物であれば生育に適する土壌や水環境が必要であり、動物であれば餌となる生物の存在が必要である。
つまり、健全で恵み豊かな自然環境の維持が生物多様性の保全に欠くことのできないものであることにかんがみ、生物多様性の保全は、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて保全され、適切に利用されることを旨として行われなければならない。
(2)生物多様性の保全と民間団体等による自然環境保全活動との関係
生物多様性の保全のためには、国土の地域ごとの生物学的特性を示す代表的、典型的な生態系や、多様な生物の生息・生育の場として重要な地域について、対象地域の特性に応じて十分な規模、範囲、適正な配置、規制内容、管理水準、相互の連携の確保された保護地域などの体系を設けていく必要がある。
そのため、国においては自然環境保全法、自然公園法等の法律に基づき、代表的、典型的な生態系等が成立している地域を原生自然環境保全地域、国立公園等に指定し、厳格な行為規制等を実施することにより、生物多様性の保全を図っている。また、地域において相対的に自然性の高い自然環境を保全することは、国土全体を通じて多様な生態系を確保する上で非常に重要であることから、都道府県においても地域固有の生態系や希?野生動植物の生息・生育地を都道府県自然環境保全地域等に指定し、その保全を図っている。これらの地域においては、人の手が入ることを制限することにより保全する区域だけでなく、人の手を加えることによって、自然環境の質や生物多様性が保全される区域がある。
その際、土地所有者の高齢化等により、農業や林業、里山の利用等を通じた人間の働きかけ(適切な維持管理)が行われなくなっている地域については、その土地における自然環境を良好に保つため、民間団体等が土地所有者と協働して、一定程度の維持管理を行うことが重要となっている。
さまざまな人間の働きかけを通じて形成・維持されてきた生態系は、わが国の生物多様性を構成する重要な要素であり、私たち日本人にとってかけがえのない資産である。古来より日本人は、自然を尊重し、自然と共生することを通じて、豊かな感性や美意識をつちかい、多様な文化を形成してきた。例えば、薪炭林や農用林などの二次林や採草地の二次草原は、人間活動に必要なものとして人間の働きかけを受け、そして、その働きかけが継続されることにより維持されてきた。こうした人と自然の関わりが、地域色豊かな食、工芸、祭りなど地域固有の財産ともいうべき文化の根源となるなど、地域の生態系とそれに根ざした文化の多様性は、歴史的時間の中で育まれてきた地域固有の資産である。
わが国における生物多様性の保全のためには、このような文化の多様性をもたらす地域に固有の生態系等を、人間の適切な働きかけを継続させ、地域の特性に応じて保全することが必要である。
わが国国土全体での生物多様性の保全が図られるためには、地域の生態系の保全に関わる地域の住民や民間団体等が主体となって、地域の特性に応じたきめ細かな自然環境保全活動を進めていくことが大切である。こうした取組は、地域ごとのさまざまな経験から生まれた適正な利用や管理のための智恵を活かして行われるべきものであることから、現場で活動している人々が中心となった自主的な活動を尊重し、支援していくことが必要である。
近年、NGO等の民間団体も、それぞれの地域で自然環境保全活動を行ったり、市民参加型のモニタリングを行うなど、わが国の生物多様性を保全するために各地で積極的に幅広い活動を行っており、こうした活動は、行政では十分に行えないものを市民のニーズを捉えて地域に密着して行っているものが多く、地域の特性に応じた生物多様性の保全を進める上で大変重要である。
また、企業においても、日本経済団体連合会が、平成21年3月に「日本経団連生物多様性宣言」を発表し、経済界が生物多様性の保全等に取り組む意義と使命があるとの認識を示したり、大多数の環境報告書に自然環境・生物多様性保全に係る取組が記載されるなど、自然環境・生物多様性の保全に着目した取組が進められており、社会的貢献という点も含めて生物多様性の保全のための活動に対する企業の関心は高まっている。
わが国の生物多様性の保全のためには、わが国に存在するさまざまな生物多様性を、それぞれの特性を活かしながら確実に保全することが重要であり、確実性の観点からは、公的主体が法制度等に基づき保全を行うことが望ましいが、公的主体の能力にも限界があり、また、法制度による保全は一律の基準を設けて行われるため、必ずしも地域におけるNGO、企業、地域住民など多くの主体による取組や保全の要請を反映したものとならない面がある。
国や地方公共団体は、国土の地域ごとの生物学的特性を示す代表的、典型的な生態系や、多様な生物の生息・生育の場として重要な地域について、保護地域制度を活用し、主に人の手が入ることを制限することによって直接その保護を図っている一方で、さまざまな人間の働きかけを通じて維持・保全されてきた生物多様性については、適切な維持管理を継続させ、できる限りその場所の特性に応じた保全が図られるよう、国や地方公共団体はNGO、企業、地域住民など多くの主体が協働して、それぞれの地域において多様な特性を持つ自然環境の保全に関する活動を、地域に根付いたやり方で持続的に進めることができるよう、経済的措置を含めた制度や社会的な評価の仕組みを充実することが必要である。
なお、主に人の手が入ることを制限することによって保護が図られる地域についても、代表的、典型的な生態系等を維持・再生するために、土地の取得を行う民間団体等による自然環境保全活動が行われており、このような活動の支援も必要である。
3.民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動に関する現状及び課題
(1)民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動の現状
<民間団体等の自然環境保全活動の現状>
生物多様性基本法に位置付けられている「事業者、国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得並びにその維持及び保全のための活動その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する自発的な活動」についてはさまざまなものが考えられるが、「第三次生物多様性国家戦略」(平成19年11月閣議決定)においては、国民からの寄附金を用いて、自然保護のために自然の豊かな民有地を買い入れて、管理を行い、保全を図っていこうとする「ナショナル・トラスト活動」や、企業が所有地を活用してNGOなどとの協力により緑地を保全する活動が挙げられている。
自然環境保全を目的としたナショナル・トラスト活動とは、「広く国民から寄附金、会費等を募り、又は贈与等を受け、土地、建築物の買い取り、地上権の設定、所有者との契約などによりその管理権を取得して自然環境や歴史的環境を保全することを目的とする活動」*2とされており、昭和30年代後半から全国各地にて行われている活動である。ナショナル・トラスト活動の具体的な形態としては、?活動の対象となる土地の所有権を買い取ったり、その所有権を譲り受ける“所有型”が基本的な活動形態であるが、地価の高騰等の影響を受け、?所有権の移転を伴わずに、地上権を設定したり、土地所有者との間で賃貸借等の契約を結ぶことにより、活動の対象となる土地の管理権を取得する“協定型(非所有型)”も活動形態の一つに位置付けられており、前者に関して9,150ha、後者に関して1,220haの土地が保全されている*3。このような活動は、各地域における自然環境に価値を見出し、その保全を行うことを通じて、地域におけるさまざまな生態系や種の持続的な保全・利用を可能とするものである。また、さまざまな者が民間団体への寄附やボランティアとして維持管理に参画することを通じて、それぞれの行える範囲での自然環境保全の実施を促進することに
つながっている。
このナショナル・トラスト活動が最初に行われたのは、古都鎌倉である。鎌倉の鶴岡八幡宮の裏山にある御谷おやつに業者が宅地造成を計画したことに対し、地元の住民を中心に反対運動が起こり、土地買い取りの運動が行われた。また、和歌山県田辺市の天神崎においても、同様に、開発業者が別荘地造成を計画していることに対し、土地買い取りの運動に発展していった。当初は、このように、開発により自然環境が破壊されることを未然に防止することを目的に、大規模な開発から自然環境を市民自らの手で守る手段としてナショナル・トラスト活動が行われた。しかし最近では、相続が発生した際に相続人が高額な相続税を支払うことができないため、土地等を売却して現金化せざるを得ず、その結果として、その土地等が開発業者等により改変されることとなり、その土地における自然環境が保全されなかったという事例が増加しており、このような改変を避けるべく、ナショナル・トラスト活動が行われるというケースが増えてきている。
このような活動の歴史を持つナショナル・トラスト活動であるが、その活動を実施する民間団体の数は増加傾向にあり、団体数は約50団体、面積は約1万haに及んでいるが、その活動が活発に拡大しているとは言い難い。
「土地問題に対する国民の意識に関する調査」*4の結果をみると、土地を預貯金や株式などに比べて有利な資産であると思っている者と思わない者の割合は、平成10年以前は前者が後者を大きく上回っていたが、平成10年以降はほぼ同数の割合となるなど、土地に対する国民の意識は、近年大きく変容している。また、土地所有者の高齢化や過疎化が進み、土地の維持管理を行うことが難しいといった理由により、その所有する土地を、自ら維持管理し続けるのではなく、地方公共団体等に贈与をすることにより適切に保全し続けようとする動きも増加する傾向にある。
しかしながら、地方公共団体においても、維持管理の負担を懸念して土地の寄贈を積極的に受ける傾向には無く、結果として、自然環境の保全等を目的としてナショナル・トラスト活動を行う民間団体等に対し、土地を寄附しようとする者からの相談も増えているといった状況にある。
<企業所有地における民間団体等の自然環境保全活動の現状>
わが国には広大な森林や都市部の土地等を所有している企業も?なくない。このような企業が所有する土地は、そもそも福利厚生施設や研究施設、工場等の敷地として確保されたケースが多いが、わが国の経済状況等により企業活動に直接利用されてこなかった結果、生物多様性の保全上良好な状態が維持されている山林等の土地として残っている状況にある。このよ
うな“自然環境の豊かな土地(森林、緑地等)の面積は約92万ha*5を超えている”とする調査結果もあり、こうした土地も積極的に保全の枠組みに取り込んでいくことが必要である。
近年、国民意識の変化、環境配慮の浸透等を背景として、企業の社会的責任(CSR)に対する関心が高まっており、CSR活動を実施する企業が急速に増加している。この活動の一つとして、前述した企業の所有地を積極的に活用する例が増えてきている。
具体的には、生物多様性の保全に対する意識の高まりや、地球温暖化問題に関連して森林がCO2の吸収源として認識されていること等を背景として、土地の所有者である企業が、その土地を保全しようとする意思を表明し、民間団体等と協働するなどして、森林の保全や里山の管理といったその所有する土地における自然環境そのものを保全する事例が見られるようになってきている。
しかし、そのような取組は全国的に進展しているという状況にはなく、こうした活動による保全がより効果的に行われるように誘導することが必要である。
(2)民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動を促進する上での課題
生物多様性が認められ、民間団体等が行う自然環境保全活動による保全が望ましい土地は、地価が高い都市近郊から地価の安い中山間地までさまざまな地域に存在している。現状においては、自然環境保全を目的としたナショナル・トラスト活動が活発に拡大しているという状況にはなく、また、企業の所有地における自然環境保全の取組についても十分に進展しているとまでは言えないが、それには、次のような課題が存在すると考えられる。
1)民間団体等による土地の取得・保全
? 土地の譲渡に伴う課題
ア)譲渡所得の税制優遇措置に係る課題
都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地管理機構(NPO法人は除く。)に譲渡した特別緑地保全地区内の土地については、譲渡所得について2,000万円の特別控除が認められる等の税制上の優遇措置があるが、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等へ譲渡する場合についてはそのような優遇措置がないため、民間団体等への譲渡により土地の保全を行おうとする土地所有者の行動を支援することにつながっていない。
イ)みなし譲渡課税の非課税措置に係る課題
個人である土地所有者が、その所有する土地における自然環境の保全等を図ろうとして、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等にその土地を低額又は無償で譲渡しようとする場合であっても、税制上の取扱いでは、土地は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、土地の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税される(みなし譲渡課税)。また土地所有者が法人である場合も、寄附時の時価で譲渡があったこととして課税が行われる。特に、地価が高く値上がりの程度も大きい都市近郊においては当該課税が土地を寄附する所有者の重い負担となる。このため、このような民間団体等への土地の低額又は無償での譲渡が進まず、当該土地における自然環境の保全が図られない状況にある。
このみなし譲渡課税に関し、公益社団法人及び公益財団法人(以下「公益法人」という。)等に土地の寄附を行う場合、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなどの要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、当該土地に係る譲渡所得税を非課税とする特別措置が設けられている(租税特別措置法第40条)。
しかしながら、この特別措置は、寄附をした日から4ヶ月以内に贈与者が国税庁長官の承認の申請を行い、国税庁長官から要件を満たすとして承認を受けて初めて、その適用がなされることとなる。よって、土地所有者が土地を贈与する時点では非課税になるという確証はないことから、本特例措置を活用した民間団体等への土地の贈与も進んでいない。
なお、公益法人制度改革前においては、上述の税制優遇措置の対象となる特定公益増進法人の認定に関しては、「すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人」(所得税法施行令第217条)という類型が設けられ、主務官庁の許可により認定されていたが、この類型に基づく認定団体は4団体にとどまっていた。公益法人制度改革により、公益法人の認定基準として「地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業」(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条別表第十六号)という類型が設けられ、平成20年12月から施行されている。
ウ)相続財産の寄附に関する非課税措置の手続きに係る課題
相続が発生した際、相続人が自然環境保全活動を行う民間団体等に対し相続財産である土地や現金を寄附する場合、それらの相続財産が相続税の課税対象外となるのは、
?民間団体等が公益法人や認定NPO法人、独立行政法人等である場合に限られており、
?これらの法人に寄附を行う場合であっても、相続税の申告期限内(通常、相続人の死亡の日から10ヶ月以内)に寄附を行わなければならないこととされている。
しかし実際には、相続財産を整理し、相続財産の贈与についての全相続人の意思決定を行った上で、維持管理まで任せられる適切な民間団体等へ贈与するといった一連の手続を、この申告期間内に行うことが困難なケースも多く、これらの民間団体等への寄附が進んでいない。
エ)地方公共団体への土地の寄附に係る課題
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等に対し土地を寄附する場合とは異なり、地方公共団体に土地を寄附する場合は、当該土地に係る譲渡所得税は非課税となるため、土地所有者においては、このような民間団体等ではなく地方自治体に対し土地の寄附を行うインセンティブが働くこととなる。しかしながら、行財政状況の厳しい近年では、維持管理が必要となる土地の寄附を受けることを拒む地方公共団体も?なくない。こうした場合には、地方公共団体が土地の寄附を受け入れつつ、自然環境保全活動を行う民間団体等に土地の維持管理を委託するという手法が考えられるが、その際にはその維持管理費用をいかにして調達・確保するかが問題となる。
? 民間団体等の課題
ア)維持管理の確実性に係る課題
その他、土地所有者が、その所有する土地における自然環境の保全等を図るため、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等にその土地を寄附すること等を検討している場合、当該民間団体等が、土地所有者の意思を達成しようとして、長期にわたり土地の保全を行うかどうか、適切に維持管理を行うこととなるのかどうかについて確実な保証がないことから、土地所有者も安心して当該民間団体等へ贈与等を行うことができる状況にはない。
イ)土地の購入価格に係る課題
土地等の不動産の時価評価は、その土地を最も有効に利用する方法に基づいて算定するという考え方がある。このため、土地を取得しようとする者が、土地における自然環境の保全を目的として、土地を改変することなく、管理のみ行うことを予定している場合であっても、同様に、その土地が最も有効に利用される方法に基づいて算定されることとなる。
また、開発業者等は、土地取得後の期待収益(土地を運用することにより回収が可能な費用)を加味して土地の購入価格を提示する一方、民間団体等は、そもそも財政基盤が脆弱であり、土地の恒久的な保全のために取得する土地には期待収益が発生しえないことから、期待収益を加味した土地の購入価格を提示することができない。加えて、将来その取得を行う可能性が高い近隣の土地に係る地価の高騰を誘発しないために適正な価格以上では土地を購入しないケースも多いことから、民間団体等は当該土地を落札することができていない。
これらの理由により、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等は、土地の取得等を行おうとする際、高額な実勢価格を負担しなければならない場合が生ずるが、実際には負担することができず、結果として、土地を取得することが困難となる場合が多い。
ウ)土地取得後の固定資産税等負担に係る課題
また、仮に土地を取得することができたとしても、当該土地に係る固定資産税等の税負担が将来にわたり長期間生ずることとなる。しかし、当該土地において自然環境保全活動を行おうとする民間団体等は、?その土地における自然環境を保全するため、土地を改変することなく管理のみを行い、取得した土地から収益を得ることを予定していないこと、?その主な収入が会費、寄附金等であり財政的に脆弱であることから、固定資産税等の税負担が民間団体等にとって大きな負担となり、円滑な活動の実施に支障を及ぼす可能性がある。
2)民間団体等による土地の維持・保全(土地の取得は伴わない)
? 土地の保全契約による機会費用の逸失等の負担に係る課題
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等と土地所有者とが、その所有する土地の保全のための契約を締結する場合、土地所有者はその土地の転売等を、一定の期間、自発的に行わないこととなる。
しかしながら、現状としては、これらの保全のための契約は法制度等に基づくものでなく当事者間の任意契約である場合が多いため、土地所有者に対する税制上の優遇措置等は講じられていない。また、この保全のための契約を賃貸借契約とする場合であっても、会費、寄附金等を主たる収入としている民間団体等が十分な賃料を支払うことは難しい。
このため、保全により発生する機会費用の逸失、及び契約期間中の当該土地に係る固定資産税等の税負担について、土地所有者の十分な理解を得られず、結果として、このような保全のための契約が締結されにくい状況にある。
? 民間団体等の信頼性に係る課題
また土地所有者が、これらの民間団体等との間で、その所有する土地の保全のための契約を締結しようとする場合であっても、契約の相手方となる民間団体等に関して十分な情報を持っておらず、当該民間団体等との間で協働関係を構築し、土地の維持管理を任せることに不安を感じたり、維持管理の方針等について土地所有者と民間団体等との間で認識の共有を行うことができないため、契約の締結に至らない場合がある。
? 土地の保全契約の継続性に係る課題
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等と土地所有者とが、その所有する土地の保全のための契約を締結している場合は、当該契約は当事者間の任意契約であることが多いことから、その土地所有者が亡くなり相続が発生したときは、保全契約が継続されるかどうかは相続人の意思に左右されることとなり、安定的に長期にわたり当該土地の自然環境の保全を図ることが困難である。
3)民間団体等の運営基盤
? 民間団体等の財政的安定性に係る課題
土地の取得等の自然環境保全活動を自立的に、継続して実施するためには、そのための資金を安定的に確保する必要がある。
しかしながら、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等は、その主な収入が会費、寄附金等であることから、必ずしも安定的に十分な資金を確保できている状況にはない。また、自然環境保全活動そのものやその活動の意義、その活動を行う民間団体等についての認知度が低いため、全国民的な理解と協力の下に自然環境保全活動が積極的に推進されているとは言い難い状況である。
? 自然環境の管理水準に係る課題
民間団体等が土地の管理を行う際、その管理の程度として、その土地において維持されている自然環境を引き続き適切に維持しようとするケースと、そのような土地において保全すべき自然環境が既に回復を要する状態にありその回復を図るケースが想定される。しかし、それぞれのケースにおいて、どのような水準で管理を行うべきか、民間団体等にとっては必ずしも明らかではないため、適切な管理が行われない場合がある。
? 民間団体等のスタッフ体制に係る課題
また、土地の取得等の自然環境保全活動を民間団体等が行う場合、不動産鑑定、土地の測量、契約、登記、税制等のさまざまな専門知識が必要となる。この他にも、活動の対象となる土地についての情報収集、土地の確保に向けた土地所有者との交渉等、民間団体等が行う必要のある事務も多岐にわたっている。
しかしながら、会費や寄附金等で運営するこのような民間団体等では、財政的に、そのような専門知識を有するスタッフを雇用することは難しく、また、専従のスタッフを配置することも困難な状況にある。
4.具体的な施策の考え方
上記の課題に対処するためには、促進すべき自然環境保全活動を公的機関が認定し、認定された活動に対して税制優遇を始めとする各種の支援措置を与えることが有効であると考えられる。この考え方に基づいて、国、地方公共団体及び民間団体等が、それぞれの責務にしたがって活動を促進するための仕組みを整えることが必要である。
(1)基本的な考え方
国や地方公共団体は、国土の地域ごとの生物学的特性を示す代表的、典型的な生態系や、多様な生物の生息・生育の場として重要な地域について保護地域制度を活用し、主に人の手が入ることを制限することによって直接その保護を図る。ただし、これらの地域でも、民間団体等により生態系の維持・再生のための活動が行われており、これらへの支援は必要である。
一方、さまざまな人間の働きかけを通じて維持・保全されてきた生態系については、国や地方公共団体は、できる限りその場所の特性に応じた保全が図られるよう、NGO、企業、地域住民など多くの主体の参画を促し、それらの活動を支援するため、経済的措置を含めた制度や社会的な評価の仕組みを充実することが必要である。
(2)自然環境保全活動の促進にあたっての各主体の責務
<国>
民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動の促進に当たり、国は、これらの促進をすることについてわが国の生物多様性の保全上どのような意義があるか、わが国の生物多様性の保全の観点から民間団体等によりどのような活動が行われることが望ましいか、この促進に当たっての基本的な方向性は何か、この促進のために国、地方公共団体、民間団体等がどのような連携を行っていくべきか等の基本的な考え方について、まず明らかにする必要がある。
その上で、民間団体等が行うこれらの自然環境保全活動を促進するために、民間団体等の活動状況の情報発信を国民に対して行う等の各種措置を積極的に講ずべきである。
<地方公共団体>
地方公共団体は、わが国における生物多様性の保全を図るため、国が定める基本的な考え方に基づき、地方公共団体の管轄する区域において行われる、民間団体等による土地の取得等の自然環境保全活動の促進に関する基本的な方針を定めるべきである。
また、国が行う各種措置に合わせて、民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動を促進するための各種措置を自ら講ずる必要がある。
<民間団体等>
民間団体等は、自然環境保全活動の対象となる土地における自然環境が良好に保たれるため、地域の自然的社会的条件に応じて、自然環境保全活動を長期間にわたり継続して実施することを旨として、その活動に取り組むべきである。
併せて、自らが行う土地の取得等の自然環境保全活動が、わが国における生物多様性の保全に資する取組であり、大変重要な位置にあること、この自然環境保全活動を行う原資となる資金の確保等のために、活動の意義や活動がもたらす成果等を広く一般の方々に知らしめることを通じて、多くの人々に、活動に直接的に参加し、又は、寄附金の支出等資金面での援助により間接的に参加してもらい、自然環境の保全に向けた共通の目的を持ってもらうことにより、社会をよりよい方向に変革していくことができることを、明確に認識する必要がある。企業においても、事業活動の一環として自然環境保全活動に自ら取り組む、又は他の民間団体の活動を支援することが望まれる。
そのような認識を持った上で、土地の取得等の自然環境保全活動を実践するとともに、その活動に対する支援を得るための努力を講じていくことが大変重要である。
(3)自然環境保全活動を進める上での基本的な仕組み
上記で言及した各主体の責務に基づき、自然環境保全活動の公益性を公的機関が認定し、その社会的信頼性を確保するための以下のような仕組みが考えられる。
国による基本的考え方の策定
各主体がその責務、役割等を認識した上で、民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動の促進に取り組むため、国が、民間団体等が行う自然環境保全活動の促進に関する基本的考え方を策定する。
地方公共団体による基本方針の策定
地域の実情に即したきめ細かい自然環境保全活動を支援するため、地方公共団体は、国が定める基本的考え方に基づき、民間団体等による土地の取得等の自然環境保全活動の促進に関する基本的な方針、促進の対象とする民間団体等が行う自然環境保全活動の考え方等を定める「基本方針」を生物多様性基本法の趣旨を踏まえて策定する。なお、基本方針の策定に当たっては、地域住民等の意見も聴くものとする。また、生物多様性基本法に基づく「生物多様性地域戦略」が策定されることが、望ましい。
民間団体等による自然環境保全活動計画の策定
民間団体等は、その行おうとする自然環境保全活動が、より着実に、より継続的、自立的に実施されるよう、活動地域・活動内容を明らかにし、国が定める基本的考え方及び地方公共団体が定める基本方針に照らして適切な、中長期的に持続可能な自然環境保全活動計画を策定するものとする。活動内容としては、土地の取得や、下草刈りや落ち葉かきなどの維持保全活動のほか、環境教育活動等が考えられる。これにより、当該計画に基づいて行われる自然環境保全活動が公益的な側面を有することが明らかとなる。
地方公共団体の長による自然環境保全活動計画の認定
当該計画に基づいて民間団体等が行う自然環境保全活動の公益性を担保するため、地方公共団体の長が当該計画について認定を行うこととする。その認定に当たっては、計画の内容が、国が定める基本的考え方及び地方公共団体が定める基本方針に照らして、自然環境を維持又は回復するために有効かつ適切なものであり、継続性を持って実施される活動であること等を確認するものとする。
その他
地方公共団体は、自然環境保全活動が計画に基づき適切に実施されているかどうかについて把握するため、必要に応じ報告を求めることとする。
また、わが国の生物多様性の保全が長期的に継続して図られるよう、民間団体等が行う自然環境保全活動に係る計画の実施期間はできる限り長期間で設定されること、また実施期間終了後においても、正当な理由がない限り計画を更新することが望ましい。
(4)土地を取得し、保全する活動を促進するための措置
生物多様性の保全のためには、さまざまな自然環境が存在する土地を自立的に、継続して保全することができるよう、その土地を取得することが最も有効な方法である。これまで行われてきているナショナル・トラスト活動においても、その保全の効果から、まずは、対象となる土地の所有権を取得することが目標とされてきたところである。
よって、土地を取得し、保全しようとする民間団体等の自然環境保全活動を強力に促進する必要があり、民間団体等へ土地が寄附されることを促したり、民間団体等が土地を取得しやすくなるための措置を講ずることが重要である。
?信頼性の向上
財政的基盤の弱い民間団体等が、自然環境保全活動として土地の取得等を行おうとする際、実勢価格に見合った十分な対価を支払い、その取得等を行うケースはまれであり、むしろ、土地やその土地における自然環境をできるだけ保全したい、そのような保全を全うできる者に土地を譲り渡したい、といった土地の保全を求める土地所有者から、土地を無償又は低額で譲り受ける場合が多い。
しかしながら、どの民間団体等が土地所有者の想いを着実に、継続的に実現できるものであるかどうかについて、土地の譲渡を検討している土地所有者が一般的に公開されている情報から判断することは必ずしも容易ではない。実際には、土地所有者が適切な譲渡先であると判断することができないため、譲渡が行われず、当該土地が転売される等の結果、土地が改変され、土地やその土地における自然環境の保全が実現されないこととなる場合がある。
このような事態を解消し、所有する土地を保全したいと考える土地所有者が適切な民間団体等に安心して土地を譲り渡すことを可能とするため、自然環境保全活動として土地の取得等を行おうとする民間団体等が、当該土地における自然環境の保全のための活動に関する計画を策定し、当該計画について公的機関の認定を受けることとする等、公的主体が一定の関与を行うことにより、民間団体等の行う自然環境保全活動が適切に、継続的に行われるものかどうか、その結果として土地や土地における自然環境の保全が図られるものかどうかを明らかにすることが必要である。
これにより、土地所有者は、認定を受けた計画に基づき自然環境保全活動を行おうとする民間団体等に対して、土地の譲渡を安心して行うことができることとなり、そのような譲渡が増加する結果、自然環境の保全のための取組が促進されることとなる。
?税制措置
■所得税・法人税(譲渡益に対する課税の問題)
民間団体等が、土地の取得を行い、土地における自然環境の保全を行おうとする場合、会費、寄附金等の収入を基本としている民間団体等が土地所有者に提示できる価格は、比較的低額とならざるを得ない。
このような場合に、土地所有者の譲渡益に課される所得税、法人税について対価の一定額を控除する等の優遇措置を講ずることにより、自然環境の保全を目的に、民間団体等に土地を転売しようとする土地所有者を支援することとなり、その結果として、民間団体等により自然環境の保全が図られることとなる。
■所得税(贈与、遺贈又は著しく低い対価での譲渡を行った場合の課税の問題)
個人である土地所有者がその所有する土地における自然環境の保全のため、当該土地を寄附しようとする場合、ナショナル・トラスト活動を行う民間団体等に贈与、遺贈、又は著しく低い対価での譲渡を行ったときは、時価による譲渡が行われたものとして、土地所有者に対し所得税が課税される(みなし譲渡課税)。
この「みなし譲渡課税」に関しては、公益法人に財産が贈与又は遺贈された際には、その贈与又は遺贈がなかったものとして課税されないこととされているが、そのためには、当該公益法人の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして「国税庁長官の承認」を個別に受けることが必要とされている。しかしながら、土地所有者が寄附等を行う時点では、非課税となるか否かが明らかではないことから、課税を避けたい土地所有者は、その土地の寄附を行おうとはせず、当該土地における自然環境の保全が図られない可能性がある。
これに関し、
?個別に国税庁長官の承認を得るのではなく、民間団体等が作成する自然環境保全活動に関する計画について公的な認定を受けたことをもって国税庁長官の承認に代えること、
?事前に国税庁長官の承認の可否について確認することを可能とすること、又は、
?一旦寄附を行った後、国税庁長官の承認が得られなかった場合には、当該寄附が行われなかったものとして取り扱われるための更正の請求を認めることを制度的に担保することで、土地所有者が安心して土地を寄附することができるようにすることが必要である。
■法人税(贈与又は著しく低い対価での譲渡を行った場合の課税の問題)
法人である土地所有者がその所有する土地における自然環境の保全のため、当該土地を寄附しようとする場合、ナショナル・トラスト活動を行う民間団体等に贈与又は著しく低い対価での譲渡を行ったときは、時価による譲渡が行われたものとして、土地所有者の譲渡益に対し法人税が課税される。
具体的には、法人である土地所有者が土地を贈与した場合や低額で土地を譲渡した場合、当該土地を時価で売却したという擬制の下で譲渡益が益金に計上され、法人税が課税されることとなる。特に、地価が高く値上がりの程度も大きい都市近郊における含み益の多い土地については、寄附の際に大きな税負担が発生することとなる。
よって、土地の時価相当の寄附があったものとして損金算入を認めれば、土地所有者にとっては、寄附を行おうとする大きなインセンティブとなり得る。
具体的には、寄附に係る一団の土地の価格が単年の寄附金の損金算入限度額を超える場合もあるため、認定計画に基づいて管理される土地を寄附する際、財務大臣の指定する指定寄附金と同様に、その土地の価格の全額を損金算入することができることとしたり、次年度以降に繰り延べてその全額を損金算入できることとする等の措置を検討することが必要である。
なお、土地と併せて維持管理のための財源を寄附する場合には、土地の価格と併せて、その全額の損金算入を認める等により、民間団体等が維持管理を安定的に行う基盤を確保することも必要である。
■相続税
土地の所有者が死亡し、相続が発生した場合、相続税の支払いのために土地を譲渡する等して現金化する事例は特に都市部において顕著に見られる。この場合、相続人が相続税の申告前に、相続により取得した財産を公益法人又は認定NPO法人に贈与したときは、贈与をした財産に係る相続税は非課税とされているが、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内であり、この期間内に、相続人が一連の手続を行った上で適切な相続財産の贈与先を見つけることが難しい場合もある。
このため、相続人が、自然環境保全活動に関する計画について地方公共団体の認定を受けた公益法人又は認定NPO法人へ土地等の贈与を希望し、真摯に関係者との調整を行っているものについては、申告・納付の期限を延長できるようにし、できるだけ保全が進むように促すことが望ましい。
■固定資産税等
固定資産税は、固定資産の所有者が行政サービスの恩恵を受けていることに着目し、その恩恵の量に応じて課される応益税である。したがって、地方公共団体、国等に無償で貸し付けられた土地が公用又は公共の用に供されている場合には、公益目的で使用されていることに照らし、地方税法により固定資産税及び都市計画税が非課税とされているが、民間団体等が所有権を取得して管理を行っている土地については、特段の税制上の優遇措置は講じられていない。
しかしながら、民間団体等が所有権を取得し、地方公共団体の認定を受けた自然環境保全活動に関する計画に基づいて当該土地の管理を行う場合、当該土地は、当該計画に基づき自然環境の保全のために適切に管理されることとなる。
よって、前述の地方公共団体等に貸し付けられた土地が公用等に供される場合と同様に、民間団体等が土地の所有権を取得し、当該土地について認定計画に基づき適切に管理を行う場合には、その土地の公益的な価値に着目し、固定資産税及び都市計画税に関して税制上の優遇措置を講ずることが適当である。
(5)土地を維持・保全する活動を促進するための措置
土地を所有し続けようとする意識が比較的高いわが国においては、土地の維持・保全等の自然環境保全活動を行おうとする民間団体等が、土地の所有権を取得して当該土地の管理を行う活動のほか、所有権の移転を伴わずに、土地所有者との間で土地の賃貸借契約を締結し、当該土地に係る自然環境保全活動に関する計画に基づき土地の管理を行うことにより、当該土地における自然環境を保全する活動がある。
この場合、民間団体等は、土地の管理権を得るために締結される賃貸借契約等の範囲内での賃料等を負担することによりその土地の保全が可能となることから、対価を支払い、土地の所有権を得る場合に比べればより対応しやすいものとなる。土地所有者においても、その有する土地の所有権を保持したまま自然環境の保全の取組に協力することができることから、一定の期間、その所有する土地における自然環境を保全するための活動が積極的に行われやすくなることとなる。
また、約90万haにのぼるとも言われている企業の所有地に関し、企業側は、適切に管理することによりCO2の吸収源や清らかな水源となる山林等の価値を見直し、その所有地の所有権を保持したまま、昨今求められているCSR活動の一環として所有地における自然環境の保全に積極的に取り組んでいきたいと考えている反面、現下の厳しい経済状況にあっては、所有地の管理に要する費用を支出することがなかなか難しいという実情にある。一方、山林や草原等の自然環境を適切に保全することに関心の高い民間団体等であるものの、活動するための土地を確保できていない場合も多い。
このため、これらの民間団体等が土地所有者である企業との間で一定期間、賃貸借契約等を締結し、その土地に係る管理権を得て管理を行うことにより、このような土地における自然環境の保全を図ることが想定される。
これらの状況を踏まえ、土地を所有し続けようとする意識が比較的高いわが国においては、この形態の自然環境保全活動を積極的に促進する必要があり、そのため、安定的に自然環境が保全されるための措置を講じたり、土地所有者に対し民間団体等への土地の管理権の提供に係るインセンティブを与えることが重要である。
?土地を維持・保全する活動の継続的な実施
この形態の自然環境保全活動が適切に継続して実践されるためには、民間団体等が土地所有者との間で締結する賃貸借契約等が長期間、安定的に保持される必要がある。
このため、例えば、民間団体等が土地所有者との間で自然環境保全活動の対象となる土地について賃貸借契約を締結し、契約に基づく管理権を前提として、その土地を管理するという自然環境保全活動に関する計画を定めて活動を行おうとする場合、その活動の内容を広く一般に公表し、このような計画が自然環境の保全のための活動の促進に重要である旨を公的に認定することにより、新たに、計画の対象である土地の所有者となった者に対しても、その効力を引き続き有効とすること(承継効の付与)や、土地の所有者が正当な理由なく計画の有効期間中に土地の返還を申し出てはならないこととするなど、当該土地等における自然環境の長期にわたる保全が図られるための法的その他の適切な仕組みを検討することが必要である。
?税制措置
■相続税
民間団体等が行う自然環境保全活動に関する計画に関し、その対象である土地について相続が発生した場合においても、当該土地おける自然環境の長期にわたる保全が図られるための法的その他の適切な仕組みとして承継効を付与するとした場合、当該土地の所有権が相続により土地所有者(被相続人)から相続人に移転したとしても、計画の存続期間はその土地の利活用が制限されることとなり、土地の所有権の資産価値は減?することとなる。
このため、賃借権が設定されている土地等の取扱いに照らし、当該土地に係る相続税に関して、その課税の対象となる相続財産の評価額について一定の減額が行われることが適当である。
また、こうした形態での自然環境保全活動の実施の安定性を長期に渡って確保できるよう、賃借権と比較して長期に設定できる地上権又は地役権に関して、自然環境の保全を目的として設定することの可能性について検討することが必要である。
その上で、設定された権利の内容に応じて、相続税の課税の対象となる土地の価格の減価を認めることを可能とすることが必要である。
■固定資産税等
固定資産税は、固定資産の所有者が行政サービスの恩恵を受けていることに着目し、その恩恵の量に応じて課される応益税である。したがって、地方公共団体、国等に無償で貸し付けられた土地が公用又は公共の用に供されている場合には、公益目的で使用されていることに照らし、地方税法により固定資産税及び都市計画税が非課税とされているが、民間団体等が管理権を得て管理を行っている土地については、特段の税制上の優遇措置は講じられていない。
しかしながら、民間団体等が土地所有者との間で賃貸借契約等を締結し、地方公共団体の認定を受けた自然環境保全活動に関する計画に基づいて当該土地の管理を行う場合、当該土地は、当該計画に基づき自然環境の保全のために適切に管理されることとなる。
よって、前述の地方公共団体等に貸し付けられた土地が公用等に供される場合と同様に、民間団体等が土地所有者との間で締結した賃貸借契約等の対象となる土地について認定計画に基づき適切に管理を行う場合には、その土地が公益目的で使用されていると捉え、固定資産税及び都市計画税に関して税制上の優遇措置を講ずることが適当である。
(6)土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等の運営基盤の強化等
ナショナル・トラスト活動等の自然環境保全活動を行う民間団体等は、公益法人やNPO、任意団体である場合が多いことから、活動のための資金が十分ではなく、事務局についても十分なスタッフを雇用することができないなど、その運営基盤は大変脆弱である。
わが国における生物多様性の保全のためには、さまざまな土地における自然環境を自立的に、継続して保全することができることが重要であり、そのためには、その保全を担う民間団体等が、自立的に、継続して活動できることが前提となることから、そのために必要となる措置を講ずる必要がある。
?資金の確保
民間団体等が土地の取得等の自然環境保全活動を実践するためには、まず、その活動のための資金の確保が重要である。
ナショナル・トラスト活動を行う公益法人、NPO等の民間団体については、その主な収入源は、会員からの会費や個人・企業からの寄附金、公的主体や他の民間団体からの各種助成金、自主的な事業から得られる収入や、公的団体等からの事業の受託による収入等である。このような民間団体は、その本来的な活動をより自立的に実施するため、まずは、会員からの会費、個人・企業からの寄附金といった収入を基本として自然環境保全活動のための資金を確保する必要がある。
人類共通の財産である生物の多様性を確保し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受するためには、ナショナル・トラスト活動を継続的に長期にわたり実施することが重要であり、土地の購入資金や民間団体等の活動資金に充てるべく、長期間継続的に寄附金の拠出等の支援を得る必要がある。
このため、まず、民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動自体についての理解を得ることが必要である。一時的な資金の提供ではなく、継続して資金を提供してもらうためには、わが国で顕著に見られる“気が向いたときに募金を行う”といった形の寄附では不十分である。長期間、継続的に寄附金の拠出等の支援を行ってもらうため、民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動について説明し、共感してもらうこと、そして寄附金を拠出した結果について興味を持ってもらうことがポイントとなる。このための取組として、ホームページや会報などを用いて活動状況を報告する等、積極的に情報公開することはもとより、寄附金を支出した方々の個々の行動が、直接的にどのように民間団体等の自然環境保全活動に結びついたのかについて、よりきめ細かく伝えていく必要がある。
また、寄附のしやすさを向上させることが必要である。平成12年12月に経済企画庁国民生活局が発表した「平成12年度 国民生活選好度調査 −ボランティアと国民生活−」では、寄附をしている世帯の寄附額は、調査対象となった世帯数のうち約半数の世帯で一月当たり500円以下となっており、1,000円以下の世帯が21%、5,000円以下の世帯が22%となっている。このような状況を踏まえ、寄附を受ける場合の寄附金の額の設定に当たっては、例えば1,000円や500円単位とするなど、細かく寄附することができるようにするなどの工夫が必要である。
このほか、寄附のしやすさの一助として、他の団体との連携を模索することも想定される。有名な事例として、富士ゼロックスにおいて平成3年から実施されている「端数倶楽部」というものがある。これは、富士ゼロックスで働く人々や退職者によって構成され、自発的、自主的に運営されている社会貢献活動団体が、希望者の給与や賞与の端数部分(100円未満)を天引きして寄附する仕組みであり、これまで約2億円もの額の寄附を行っている。
寄附金の支出の方法についても、これまでは郵便局や銀行での振込が用いられる場合が多かったが、寄附を行おうとする者がより簡便に寄附することができるよう、インターネットや携帯電話の活用、クレジットカードやコンビニ決済の導入等を行うことも考えられる。
より確実に多額の寄附を得るため、例えば、企業と連携を図ることも考えられる。アサヒビールが、売上げに応じて各都道府県に自然環境保全等のための資金を寄附するとのキャンペーンを行い、約2ヶ月の間に約2億2,000万円の寄附に相当する売上に達するなど、近年、企業がその売上の一部を自然環境保全活動等へ寄附することを表明することで売上が伸びる事例も報告されている。土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等についても、売上げに応じて寄附を行うといった取組を行おうとする企業と連携を行うことにより、活動資金を確保することが可能となることから、そのような連携を行いやすくすることが必要である。
このように、民間団体等がさまざまな工夫を行うことにより、継続的に安定した会費収入や寄附金収入を受けることができるよう、そのような取組への支援について検討する必要がある。
なお、前述したような取組を行うことは、単に民間団体等が活動資金を得て、その活動を長期間、継続的に実施しやすくすることをもたらすだけではなく、さまざまな人々が、これらの民間団体等がどのような考え方の下にどのような自然環境保全活動を行っているかを知り、その趣旨に賛同して会員となり会費を支払う、寄附金を出す、つまり、“多くの人々に自然環境の保全に向けた共通の目的を持ってもらうこととなり、社会をよりよい方向に変革していく”ことにもつながるものである。民間団体等においては、そのことを念頭に置いてその活動に対する支援を得るための努力を講じていくことも重要である。
?税制措置
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等の運営基盤の強化のためには、まず、適正な事業活動の実施や情報公開により会員や寄附者の理解を得るためのさまざまな取組を実施する必要がある。そして、そのような取組を補完するものとして、寄附金がより確保しやすくなるための税制上の優遇措置が考えられる。
例えば、現在、国や地方公共団体に対して寄附金を支払った場合、確定申告により一定額が所得から控除され所得税が還付されたり、寄附金の全額が損金に算入できることとされている。このほか、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた公益法人や独立行政法人等に対して寄附金を支払った場合にも、同様の優遇措置が受けられることとされている。
また、NPO法人についても、その活動資金を外部から受けやすくすることで、その活動を支援することを目的とする「認定NPO法人制度」という寄附金に係る税制上の優遇措置が講じられ、平成13年から施行されている。この「認定NPO法人」とは、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたNPO法人を指しており、累次の税制改正により認定要件の緩和等も行われているが、平成21年7月現在で95法人(特定非営利活動法人法に基づき認証されているNPO法人は37,562法人(平成21年5月末現在))にとどまっており、NPO法人の実態を踏まえた更なる見直しが必要ではないかとの問題提起がある。*6
このような状況を踏まえ、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等を支援することにより、わが国における生物多様性の保全を図るため、まず、民間団体等のうち旧民法第34条に基づく公益法人であって、公益法人改革後の公益法人への移行期間にあるものについては、できる限り公益認定を得て税制上の優遇措置を受けることができるよう、その認定に向けた支援について検討する必要がある。
また、公益法人や認定NPO法人に限らず、一定の公的な認定を受けた自然環境保全活動計画に基づいて自然環境保全活動を行う民間団体等について、当該自然環境保全活動に係る寄附金に関する税制上の優遇措置やみなし寄附金制度を適用できるようにする必要がある。
?情報の共有
民間団体等が土地の管理を行う際、その管理の程度として、その土地において維持されている自然環境を引き続き適切に維持したり、既に回復を要する自然環境について回復を図ることが想定されるが、自然環境保全分野の専門家を雇う財政的基盤を必ずしも持たない民間団体等にとっては、どのような水準で管理を行うべきか必ずしも明らかではなく、適切な管理が行われない場合には、自然環境が適切に保全されず、結果として、生物多様性の保全が図られないこととなるおそれがある。
このため、例えば、土地の種類等に応じて、その土地における自然環境の保全のための維持管理に関するノウハウや技術手法を整理し、民間団体等に情報提供することが必要である。
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等が、その活動を着実に、自立して継続的に行うためには、土地の取得に係る不動産鑑定、相続時に土地等の寄附を受ける場合の税務上の手続、寄附金等に係る税制上の優遇措置、自然環境の保全の観点からの土地の維持管理に要する専門知識など、さまざまな専門的な知見が必要となる。また、会員や寄附金を受けた者に対して行う民間団体等の活動の実施状況に関する情報の提供や、新たな会員や寄附金の獲得、活動の対象となる土地についての情報収集や土地の確保に向けた土地所有者との交渉等、民間団体等が行う必要がある事務も多岐にわたっている。
しかしながら、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等については、同一の目的を有する地域の住民等が民間団体等を立ち上げて自ら事務局として活動を行う事例が多く、また活動に必要となる資金が不足するため、不動産鑑定等の専門家を確保することが難しく、必要十分な数の職員を雇用できるような状況には無い。
このため、例えば、不動産鑑定や相続、税制等の土地に関わる専門家との連携を確保した支援センター機能を有する組織を設け、土地の取得等の自然環境保全活動を行おうとする、又は行っている民間団体等が随時相談できるようにしたり、当該組織が、過去の相談事例を整理し、これらの民間団体等がアクセスできるように情報発信することが必要である。
また、支援センター機能を有する組織が、民間団体等が情報発信するためのホームページ作成等を技術的に支援したり、遺産相続の手続の具体的内容、寄附金の額の増大のための工夫等、それぞれの民間団体等が実際に経験し、蓄積したノウハウについて収集・整理し、他の民間団体等に良好事例として情報提供することも必要である。
?共通認識の醸成
民間団体等が、土地の所有権を得たり、賃貸借契約等により土地の管理権を得るなどして、当該土地の維持管理を行おうとする場合、自然環境が適切に保全されるためには、地域の特性に応じた適切な維持管理を実施することが必要である。また、土地所有者や地域住民と維持管理のあり方について認識を共有し、相互に連携して取り組むことも大変重要である。
このため、その前提としての市民・土地所有者への普及啓発のほか、必要に応じ、土地所有者や地域住民、自然環境に関する専門知識を有する者等が維持管理のあり方について意見交換できる場や、自然環境保全の方向性の合意を図るワークショップの場を設定することが望ましい。そして、そのような場の設定が進むための支援について検討することが必要である。
5.中長期的な課題
今回の検討は、生物多様性基本法において、民間の団体等が行う生物多様性の保全のための重要な取組の一つである「ナショナル・トラスト活動」等を推進するため、税制優遇措置等を講ずることとされたこと、平成22年10月に、わが国において生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の開催が予定されていること等の生物多様性の保全に向けた諸要請を踏まえ、早急に実施すべき措置について検討してきたところであり、その検討の結果については、当面講ずべき措置として4.までにおいて取りまとめたところである。
しかしながら、本検討会としては、わが国における生物多様性の保全が真に図られるためには、生物多様性基本法で記された「自発的な活動」が十分に促進されるよう、さらにドラスティックな措置を講ずる必要があると考える。このため、以下に掲げる事項について、引き続き検討を続けるべきと考える。
(1)長期的に土地の取得等の自然環境保全活動を行う仕組み
イギリスにおけるナショナル・トラスト法においては、「譲渡不能の原則」という仕組みがある。具体的には、同法に基づき設立された「ナショナル・トラスト」に対して、その保存の対象となる資産である土地、建物等について「譲渡不能」と宣言する機会が与えられており、この宣言を受けた資産は、売却あるいは担保に供されることはなく、また、国会の特別の議決がある場合を除き、強制収用されないこととされている。
わが国においても、生物多様性の保全を図るため、日本国憲法第29条第3項において「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定されていることを踏まえつつ、英国のナショナル・トラストのように、ナショナル・トラスト活動を行う民間団体等がその所有する土地、建物等について将来にわたり保全し続けることを表明したときは、当該土地、建物等については売却や担保に供されず、また国会の議決があるなど特別の場合を除き、当該土地、建物等が強制収用されないこととする仕組みの可能性を検討することが必要である。
(2)土地の取得等の自然環境保全活動を行う主体の抜本的強化
イギリスにおいては、ナショナル・トラスト法に基づいて、国民の利益のために、美しい土地等を恒久的に保存することを目的とした法人である「ナショナル・トラスト」が設立されるとともに、この法人に対し、譲渡不能を宣言する権利が付与されたり、ナショナル・トラストに寄贈等された資産について税制上の優遇措置が講じられるなど、さまざまな特権が設けられ、その取組の推進が図られている。
わが国においても、土地の取得等の自然環境保全活動を、長期間、継続して実施し続けるため、またその活動への支援措置を講じやすくするため、英国におけるナショナル・トラストのように、自然環境保全活動の対象となっている土地等の資産を、個々の民間団体等が所有するのではなく、例えば、特定の法律により設立される法人が取りまとめて所有することも検討すべきである。なお、その土地等の維持管理に当たっては、当該特定の団体が、各地域において自然環境保全活動を行う民間団体等と協定などを締結し、当該民間団体等が維持管理に取り組むことが考えられる。
(3)土地における自然環境を保全するための新たな権利の設定
わが国においては、土地の所有権ほど強力ではないものの、土地を一定の目的の下に使用する権利として「地役権」がある。この「地役権」とは、一般的には、要役地(便益を受ける側の土地)と承役地(要役地の便益のために利用される土地)の間で設定される“付随地役権”と言われる権利である。
一方、米国においては、土地環境を保全する目的に反する活動を制限することができる権利として「保全地役権(Conservation Easement)」がある。これは地役権の一種であるが、わが国における地役権と異なり、人の便益のために他人の土地を利用する権利とされており、承役地の有無にかかわらず、土地の所有者と行政機関や公益法人等の契約により設定することが可能である。
わが国においても、民間団体等が自然環境保全活動としてより積極的に土地の保全を行うことができるよう、米国の「保全地役権」を参考に、これまで認められている “付随地役権”に限らず、人の便益のために他人の土地を利用する権利と捉える新たな地役権を設けることを検討すべきであると考える。
(4)自然環境保全活動の対象となる土地における自然環境に係る情報の整備等
わが国に存在する自然環境の基本情報については、自然環境保全基礎調査等により、縮尺5万分の1の植生図等が整備されており、また平成11年度からは、2万5千分の1の植生図への全面改訂が順次実施されている。
しかし、これまでわが国において行われてきた、自然環境保全を目的としたナショナル・トラスト活動では、数ヘクタールの土地が対象となる場合が多く、必ずしも十分な精度の情報は得られていない。
今回検討を行った民間団体等による自然環境保全活動を促進する仕組みをより充実させ、又は、その対象となっているような小規模の自然環境までを保全する措置等を検討するためには、そのような自然環境に関するより精度の高い基礎的な情報を整備することが必要である。
また、わが国における生物多様性が適切に保全されるためには、そもそも、わが国にどのような生物多様性が存在しているかといった基本的なデータが整備される必要がある。生物多様性基本法においては、地方公共団体は生物多様性地域戦略を策定するように努めることとされているところであるが、生物多様性に関する基本的なデータが整備されることにより、よりよい地域戦略が策定されることが期待される。
http://www.env.go.jp/nature/national-trust/conf_ncaco/rep0909.pdf
報告書
1.はじめに
昨年6月に制定された生物多様性基本法(平成20年法律第58号)の前文において、人類と生物多様性に関して次のように述べられている。
「人類は、生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっている。また、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている。」
しかしながら、その人類の存続の基盤となっている生物多様性は、今、人類との関わりがもたらす危機に脅かされている。
「生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、社会経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の劣化、外来種等による生態系のかく乱等の深刻な危機に直面している。」
わが国の生物多様性の現状を見てみると、例えば植生に注目すれば、急峻な山岳地、半島部、島嶼といった人為の入りにくい地域に自然植生が分布し、平地や小起伏の山地では二次林や二次草原などの代償植生や植林地、耕作地の占める割合が高くなるなど、さまざまな段階の生態系が、さまざまな緯度、標高、水環境に立地することにより、非常に豊かな生態系の多様性が存在している。こうした生態系は、わが国の気候や地史と自然へのさまざまな働きかけの結果残されてきた特徴あるものといえるが、現在では広い範囲で失われてきている。
このような状況を踏まえ、国や地方公共団体においては、自然環境保全に関連する各種法律に基づき、さまざまな保護地域を設定し、生物多様性の保全の観点も踏まえてこれらの保護地域を適切に管理しているところであるが、未だ十分な状態であるとはいえず、多様な主体との連携を進めつつ、引き続き積極的に生物多様性の保全に取り組むことが重要である。
そのような国や地方公共団体といった公的主体の取組の一方で、国民からの寄附金を用いて、自然保護のために、身近な自然の豊かな民有地を買い入れて管理を行い、保全を図っていこうとする「ナショナル・トラスト活動」や、企業等が所有地を活用してNGO等との協力により緑地を保全する活動など、民間団体等による生物多様性の保全のための取組が行われてきている。 特に「ナショナル・トラスト活動」に関しては、昭和30年代に活動がスタートした当初は、大規模な開発から自然環境を市民自らの手で守る手段としてその活動が実施されたが、最近では、相続を契機としたやむを得ない土地の売却・開発による自然環境の改変を避けるべくその活動が実施されるなど、引き続きその活動が必要な状況にある。
このような動きを受け、生物多様性基本法第21条第3項において、「国は、事業者、国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得並びにその維持及び保全のための活動その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する自発的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする」との規定が盛り込まれた。
これにより、ナショナル・トラスト活動をはじめ「様々な民間団体(NPO法人を含む。)による活動をより一層推進し国民主導の生物多様性保全のための取組を推進するため、税制優遇措置や関連制度の見直し等の必要な措置を講ずること」*1が国に求められている。
国際的な動きに目を転じると、平成22年(2010年)10月には、愛知県名古屋市において、世界中から7,000人もの参加者が見込まれる「生物多様性条約 第10回締約国会合」(COP10)が開催される。この2010年とは、平成14年の第6回締約国会合で定められた「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減?させる」という「2010年目標」の目標年であり、COP10では、2010年以降の次期目標の採択が予定されている。
すなわち、COP10は、今後の生物多様性を巡る国際的な動きを方向付ける重要な会議であり、ホスト国であるわが国としても、そのイニシアティブを強力に発揮できるよう、生物多様性の保全に向けたわが国の取り組み姿勢をしっかりとした形で打ち出していく必要がある。
このような状況を踏まえ、本検討会では、わが国における生物多様性の保全を図るため、NGO等の民間団体、企業等が行う生物多様性の保全上重要な土地の取得並びにその維持及び保全等の活動を促進するための方策について検討を行った。本報告が、そのような活動を促進する上で有益なものとなり、引いては、わが国の生物多様性の保全を図る一助となることを強く期待する。
2.民間団体等が行う土地取得等の自然環境保全活動を巡る状況・背景
(1) 生物多様性の保全の基本的考え方
生物多様性条約では、「生物多様性」をすべての生物の間に違いがあることと定義しており、具体的には、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺伝子の多様性」の3つのレベルでの多様性があるとしている。
生物多様性という差異(変異性)を保全するためには、この3つのレベルにおける構成要素である具体的な「生態系」や「種」、「個体」を保全することが重要であるが、生物はその種のみが単独で存在するのではなく、植物であれば生育に適する土壌や水環境が必要であり、動物であれば餌となる生物の存在が必要である。
つまり、健全で恵み豊かな自然環境の維持が生物多様性の保全に欠くことのできないものであることにかんがみ、生物多様性の保全は、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて保全され、適切に利用されることを旨として行われなければならない。
(2)生物多様性の保全と民間団体等による自然環境保全活動との関係
生物多様性の保全のためには、国土の地域ごとの生物学的特性を示す代表的、典型的な生態系や、多様な生物の生息・生育の場として重要な地域について、対象地域の特性に応じて十分な規模、範囲、適正な配置、規制内容、管理水準、相互の連携の確保された保護地域などの体系を設けていく必要がある。
そのため、国においては自然環境保全法、自然公園法等の法律に基づき、代表的、典型的な生態系等が成立している地域を原生自然環境保全地域、国立公園等に指定し、厳格な行為規制等を実施することにより、生物多様性の保全を図っている。また、地域において相対的に自然性の高い自然環境を保全することは、国土全体を通じて多様な生態系を確保する上で非常に重要であることから、都道府県においても地域固有の生態系や希?野生動植物の生息・生育地を都道府県自然環境保全地域等に指定し、その保全を図っている。これらの地域においては、人の手が入ることを制限することにより保全する区域だけでなく、人の手を加えることによって、自然環境の質や生物多様性が保全される区域がある。
その際、土地所有者の高齢化等により、農業や林業、里山の利用等を通じた人間の働きかけ(適切な維持管理)が行われなくなっている地域については、その土地における自然環境を良好に保つため、民間団体等が土地所有者と協働して、一定程度の維持管理を行うことが重要となっている。
さまざまな人間の働きかけを通じて形成・維持されてきた生態系は、わが国の生物多様性を構成する重要な要素であり、私たち日本人にとってかけがえのない資産である。古来より日本人は、自然を尊重し、自然と共生することを通じて、豊かな感性や美意識をつちかい、多様な文化を形成してきた。例えば、薪炭林や農用林などの二次林や採草地の二次草原は、人間活動に必要なものとして人間の働きかけを受け、そして、その働きかけが継続されることにより維持されてきた。こうした人と自然の関わりが、地域色豊かな食、工芸、祭りなど地域固有の財産ともいうべき文化の根源となるなど、地域の生態系とそれに根ざした文化の多様性は、歴史的時間の中で育まれてきた地域固有の資産である。
わが国における生物多様性の保全のためには、このような文化の多様性をもたらす地域に固有の生態系等を、人間の適切な働きかけを継続させ、地域の特性に応じて保全することが必要である。
わが国国土全体での生物多様性の保全が図られるためには、地域の生態系の保全に関わる地域の住民や民間団体等が主体となって、地域の特性に応じたきめ細かな自然環境保全活動を進めていくことが大切である。こうした取組は、地域ごとのさまざまな経験から生まれた適正な利用や管理のための智恵を活かして行われるべきものであることから、現場で活動している人々が中心となった自主的な活動を尊重し、支援していくことが必要である。
近年、NGO等の民間団体も、それぞれの地域で自然環境保全活動を行ったり、市民参加型のモニタリングを行うなど、わが国の生物多様性を保全するために各地で積極的に幅広い活動を行っており、こうした活動は、行政では十分に行えないものを市民のニーズを捉えて地域に密着して行っているものが多く、地域の特性に応じた生物多様性の保全を進める上で大変重要である。
また、企業においても、日本経済団体連合会が、平成21年3月に「日本経団連生物多様性宣言」を発表し、経済界が生物多様性の保全等に取り組む意義と使命があるとの認識を示したり、大多数の環境報告書に自然環境・生物多様性保全に係る取組が記載されるなど、自然環境・生物多様性の保全に着目した取組が進められており、社会的貢献という点も含めて生物多様性の保全のための活動に対する企業の関心は高まっている。
わが国の生物多様性の保全のためには、わが国に存在するさまざまな生物多様性を、それぞれの特性を活かしながら確実に保全することが重要であり、確実性の観点からは、公的主体が法制度等に基づき保全を行うことが望ましいが、公的主体の能力にも限界があり、また、法制度による保全は一律の基準を設けて行われるため、必ずしも地域におけるNGO、企業、地域住民など多くの主体による取組や保全の要請を反映したものとならない面がある。
国や地方公共団体は、国土の地域ごとの生物学的特性を示す代表的、典型的な生態系や、多様な生物の生息・生育の場として重要な地域について、保護地域制度を活用し、主に人の手が入ることを制限することによって直接その保護を図っている一方で、さまざまな人間の働きかけを通じて維持・保全されてきた生物多様性については、適切な維持管理を継続させ、できる限りその場所の特性に応じた保全が図られるよう、国や地方公共団体はNGO、企業、地域住民など多くの主体が協働して、それぞれの地域において多様な特性を持つ自然環境の保全に関する活動を、地域に根付いたやり方で持続的に進めることができるよう、経済的措置を含めた制度や社会的な評価の仕組みを充実することが必要である。
なお、主に人の手が入ることを制限することによって保護が図られる地域についても、代表的、典型的な生態系等を維持・再生するために、土地の取得を行う民間団体等による自然環境保全活動が行われており、このような活動の支援も必要である。
3.民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動に関する現状及び課題
(1)民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動の現状
<民間団体等の自然環境保全活動の現状>
生物多様性基本法に位置付けられている「事業者、国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得並びにその維持及び保全のための活動その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する自発的な活動」についてはさまざまなものが考えられるが、「第三次生物多様性国家戦略」(平成19年11月閣議決定)においては、国民からの寄附金を用いて、自然保護のために自然の豊かな民有地を買い入れて、管理を行い、保全を図っていこうとする「ナショナル・トラスト活動」や、企業が所有地を活用してNGOなどとの協力により緑地を保全する活動が挙げられている。
自然環境保全を目的としたナショナル・トラスト活動とは、「広く国民から寄附金、会費等を募り、又は贈与等を受け、土地、建築物の買い取り、地上権の設定、所有者との契約などによりその管理権を取得して自然環境や歴史的環境を保全することを目的とする活動」*2とされており、昭和30年代後半から全国各地にて行われている活動である。ナショナル・トラスト活動の具体的な形態としては、?活動の対象となる土地の所有権を買い取ったり、その所有権を譲り受ける“所有型”が基本的な活動形態であるが、地価の高騰等の影響を受け、?所有権の移転を伴わずに、地上権を設定したり、土地所有者との間で賃貸借等の契約を結ぶことにより、活動の対象となる土地の管理権を取得する“協定型(非所有型)”も活動形態の一つに位置付けられており、前者に関して9,150ha、後者に関して1,220haの土地が保全されている*3。このような活動は、各地域における自然環境に価値を見出し、その保全を行うことを通じて、地域におけるさまざまな生態系や種の持続的な保全・利用を可能とするものである。また、さまざまな者が民間団体への寄附やボランティアとして維持管理に参画することを通じて、それぞれの行える範囲での自然環境保全の実施を促進することに
つながっている。
このナショナル・トラスト活動が最初に行われたのは、古都鎌倉である。鎌倉の鶴岡八幡宮の裏山にある御谷おやつに業者が宅地造成を計画したことに対し、地元の住民を中心に反対運動が起こり、土地買い取りの運動が行われた。また、和歌山県田辺市の天神崎においても、同様に、開発業者が別荘地造成を計画していることに対し、土地買い取りの運動に発展していった。当初は、このように、開発により自然環境が破壊されることを未然に防止することを目的に、大規模な開発から自然環境を市民自らの手で守る手段としてナショナル・トラスト活動が行われた。しかし最近では、相続が発生した際に相続人が高額な相続税を支払うことができないため、土地等を売却して現金化せざるを得ず、その結果として、その土地等が開発業者等により改変されることとなり、その土地における自然環境が保全されなかったという事例が増加しており、このような改変を避けるべく、ナショナル・トラスト活動が行われるというケースが増えてきている。
このような活動の歴史を持つナショナル・トラスト活動であるが、その活動を実施する民間団体の数は増加傾向にあり、団体数は約50団体、面積は約1万haに及んでいるが、その活動が活発に拡大しているとは言い難い。
「土地問題に対する国民の意識に関する調査」*4の結果をみると、土地を預貯金や株式などに比べて有利な資産であると思っている者と思わない者の割合は、平成10年以前は前者が後者を大きく上回っていたが、平成10年以降はほぼ同数の割合となるなど、土地に対する国民の意識は、近年大きく変容している。また、土地所有者の高齢化や過疎化が進み、土地の維持管理を行うことが難しいといった理由により、その所有する土地を、自ら維持管理し続けるのではなく、地方公共団体等に贈与をすることにより適切に保全し続けようとする動きも増加する傾向にある。
しかしながら、地方公共団体においても、維持管理の負担を懸念して土地の寄贈を積極的に受ける傾向には無く、結果として、自然環境の保全等を目的としてナショナル・トラスト活動を行う民間団体等に対し、土地を寄附しようとする者からの相談も増えているといった状況にある。
<企業所有地における民間団体等の自然環境保全活動の現状>
わが国には広大な森林や都市部の土地等を所有している企業も?なくない。このような企業が所有する土地は、そもそも福利厚生施設や研究施設、工場等の敷地として確保されたケースが多いが、わが国の経済状況等により企業活動に直接利用されてこなかった結果、生物多様性の保全上良好な状態が維持されている山林等の土地として残っている状況にある。このよ
うな“自然環境の豊かな土地(森林、緑地等)の面積は約92万ha*5を超えている”とする調査結果もあり、こうした土地も積極的に保全の枠組みに取り込んでいくことが必要である。
近年、国民意識の変化、環境配慮の浸透等を背景として、企業の社会的責任(CSR)に対する関心が高まっており、CSR活動を実施する企業が急速に増加している。この活動の一つとして、前述した企業の所有地を積極的に活用する例が増えてきている。
具体的には、生物多様性の保全に対する意識の高まりや、地球温暖化問題に関連して森林がCO2の吸収源として認識されていること等を背景として、土地の所有者である企業が、その土地を保全しようとする意思を表明し、民間団体等と協働するなどして、森林の保全や里山の管理といったその所有する土地における自然環境そのものを保全する事例が見られるようになってきている。
しかし、そのような取組は全国的に進展しているという状況にはなく、こうした活動による保全がより効果的に行われるように誘導することが必要である。
(2)民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動を促進する上での課題
生物多様性が認められ、民間団体等が行う自然環境保全活動による保全が望ましい土地は、地価が高い都市近郊から地価の安い中山間地までさまざまな地域に存在している。現状においては、自然環境保全を目的としたナショナル・トラスト活動が活発に拡大しているという状況にはなく、また、企業の所有地における自然環境保全の取組についても十分に進展しているとまでは言えないが、それには、次のような課題が存在すると考えられる。
1)民間団体等による土地の取得・保全
? 土地の譲渡に伴う課題
ア)譲渡所得の税制優遇措置に係る課題
都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地管理機構(NPO法人は除く。)に譲渡した特別緑地保全地区内の土地については、譲渡所得について2,000万円の特別控除が認められる等の税制上の優遇措置があるが、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等へ譲渡する場合についてはそのような優遇措置がないため、民間団体等への譲渡により土地の保全を行おうとする土地所有者の行動を支援することにつながっていない。
イ)みなし譲渡課税の非課税措置に係る課題
個人である土地所有者が、その所有する土地における自然環境の保全等を図ろうとして、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等にその土地を低額又は無償で譲渡しようとする場合であっても、税制上の取扱いでは、土地は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、土地の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税される(みなし譲渡課税)。また土地所有者が法人である場合も、寄附時の時価で譲渡があったこととして課税が行われる。特に、地価が高く値上がりの程度も大きい都市近郊においては当該課税が土地を寄附する所有者の重い負担となる。このため、このような民間団体等への土地の低額又は無償での譲渡が進まず、当該土地における自然環境の保全が図られない状況にある。
このみなし譲渡課税に関し、公益社団法人及び公益財団法人(以下「公益法人」という。)等に土地の寄附を行う場合、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなどの要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、当該土地に係る譲渡所得税を非課税とする特別措置が設けられている(租税特別措置法第40条)。
しかしながら、この特別措置は、寄附をした日から4ヶ月以内に贈与者が国税庁長官の承認の申請を行い、国税庁長官から要件を満たすとして承認を受けて初めて、その適用がなされることとなる。よって、土地所有者が土地を贈与する時点では非課税になるという確証はないことから、本特例措置を活用した民間団体等への土地の贈与も進んでいない。
なお、公益法人制度改革前においては、上述の税制優遇措置の対象となる特定公益増進法人の認定に関しては、「すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人」(所得税法施行令第217条)という類型が設けられ、主務官庁の許可により認定されていたが、この類型に基づく認定団体は4団体にとどまっていた。公益法人制度改革により、公益法人の認定基準として「地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業」(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条別表第十六号)という類型が設けられ、平成20年12月から施行されている。
ウ)相続財産の寄附に関する非課税措置の手続きに係る課題
相続が発生した際、相続人が自然環境保全活動を行う民間団体等に対し相続財産である土地や現金を寄附する場合、それらの相続財産が相続税の課税対象外となるのは、
?民間団体等が公益法人や認定NPO法人、独立行政法人等である場合に限られており、
?これらの法人に寄附を行う場合であっても、相続税の申告期限内(通常、相続人の死亡の日から10ヶ月以内)に寄附を行わなければならないこととされている。
しかし実際には、相続財産を整理し、相続財産の贈与についての全相続人の意思決定を行った上で、維持管理まで任せられる適切な民間団体等へ贈与するといった一連の手続を、この申告期間内に行うことが困難なケースも多く、これらの民間団体等への寄附が進んでいない。
エ)地方公共団体への土地の寄附に係る課題
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等に対し土地を寄附する場合とは異なり、地方公共団体に土地を寄附する場合は、当該土地に係る譲渡所得税は非課税となるため、土地所有者においては、このような民間団体等ではなく地方自治体に対し土地の寄附を行うインセンティブが働くこととなる。しかしながら、行財政状況の厳しい近年では、維持管理が必要となる土地の寄附を受けることを拒む地方公共団体も?なくない。こうした場合には、地方公共団体が土地の寄附を受け入れつつ、自然環境保全活動を行う民間団体等に土地の維持管理を委託するという手法が考えられるが、その際にはその維持管理費用をいかにして調達・確保するかが問題となる。
? 民間団体等の課題
ア)維持管理の確実性に係る課題
その他、土地所有者が、その所有する土地における自然環境の保全等を図るため、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等にその土地を寄附すること等を検討している場合、当該民間団体等が、土地所有者の意思を達成しようとして、長期にわたり土地の保全を行うかどうか、適切に維持管理を行うこととなるのかどうかについて確実な保証がないことから、土地所有者も安心して当該民間団体等へ贈与等を行うことができる状況にはない。
イ)土地の購入価格に係る課題
土地等の不動産の時価評価は、その土地を最も有効に利用する方法に基づいて算定するという考え方がある。このため、土地を取得しようとする者が、土地における自然環境の保全を目的として、土地を改変することなく、管理のみ行うことを予定している場合であっても、同様に、その土地が最も有効に利用される方法に基づいて算定されることとなる。
また、開発業者等は、土地取得後の期待収益(土地を運用することにより回収が可能な費用)を加味して土地の購入価格を提示する一方、民間団体等は、そもそも財政基盤が脆弱であり、土地の恒久的な保全のために取得する土地には期待収益が発生しえないことから、期待収益を加味した土地の購入価格を提示することができない。加えて、将来その取得を行う可能性が高い近隣の土地に係る地価の高騰を誘発しないために適正な価格以上では土地を購入しないケースも多いことから、民間団体等は当該土地を落札することができていない。
これらの理由により、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等は、土地の取得等を行おうとする際、高額な実勢価格を負担しなければならない場合が生ずるが、実際には負担することができず、結果として、土地を取得することが困難となる場合が多い。
ウ)土地取得後の固定資産税等負担に係る課題
また、仮に土地を取得することができたとしても、当該土地に係る固定資産税等の税負担が将来にわたり長期間生ずることとなる。しかし、当該土地において自然環境保全活動を行おうとする民間団体等は、?その土地における自然環境を保全するため、土地を改変することなく管理のみを行い、取得した土地から収益を得ることを予定していないこと、?その主な収入が会費、寄附金等であり財政的に脆弱であることから、固定資産税等の税負担が民間団体等にとって大きな負担となり、円滑な活動の実施に支障を及ぼす可能性がある。
2)民間団体等による土地の維持・保全(土地の取得は伴わない)
? 土地の保全契約による機会費用の逸失等の負担に係る課題
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等と土地所有者とが、その所有する土地の保全のための契約を締結する場合、土地所有者はその土地の転売等を、一定の期間、自発的に行わないこととなる。
しかしながら、現状としては、これらの保全のための契約は法制度等に基づくものでなく当事者間の任意契約である場合が多いため、土地所有者に対する税制上の優遇措置等は講じられていない。また、この保全のための契約を賃貸借契約とする場合であっても、会費、寄附金等を主たる収入としている民間団体等が十分な賃料を支払うことは難しい。
このため、保全により発生する機会費用の逸失、及び契約期間中の当該土地に係る固定資産税等の税負担について、土地所有者の十分な理解を得られず、結果として、このような保全のための契約が締結されにくい状況にある。
? 民間団体等の信頼性に係る課題
また土地所有者が、これらの民間団体等との間で、その所有する土地の保全のための契約を締結しようとする場合であっても、契約の相手方となる民間団体等に関して十分な情報を持っておらず、当該民間団体等との間で協働関係を構築し、土地の維持管理を任せることに不安を感じたり、維持管理の方針等について土地所有者と民間団体等との間で認識の共有を行うことができないため、契約の締結に至らない場合がある。
? 土地の保全契約の継続性に係る課題
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等と土地所有者とが、その所有する土地の保全のための契約を締結している場合は、当該契約は当事者間の任意契約であることが多いことから、その土地所有者が亡くなり相続が発生したときは、保全契約が継続されるかどうかは相続人の意思に左右されることとなり、安定的に長期にわたり当該土地の自然環境の保全を図ることが困難である。
3)民間団体等の運営基盤
? 民間団体等の財政的安定性に係る課題
土地の取得等の自然環境保全活動を自立的に、継続して実施するためには、そのための資金を安定的に確保する必要がある。
しかしながら、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等は、その主な収入が会費、寄附金等であることから、必ずしも安定的に十分な資金を確保できている状況にはない。また、自然環境保全活動そのものやその活動の意義、その活動を行う民間団体等についての認知度が低いため、全国民的な理解と協力の下に自然環境保全活動が積極的に推進されているとは言い難い状況である。
? 自然環境の管理水準に係る課題
民間団体等が土地の管理を行う際、その管理の程度として、その土地において維持されている自然環境を引き続き適切に維持しようとするケースと、そのような土地において保全すべき自然環境が既に回復を要する状態にありその回復を図るケースが想定される。しかし、それぞれのケースにおいて、どのような水準で管理を行うべきか、民間団体等にとっては必ずしも明らかではないため、適切な管理が行われない場合がある。
? 民間団体等のスタッフ体制に係る課題
また、土地の取得等の自然環境保全活動を民間団体等が行う場合、不動産鑑定、土地の測量、契約、登記、税制等のさまざまな専門知識が必要となる。この他にも、活動の対象となる土地についての情報収集、土地の確保に向けた土地所有者との交渉等、民間団体等が行う必要のある事務も多岐にわたっている。
しかしながら、会費や寄附金等で運営するこのような民間団体等では、財政的に、そのような専門知識を有するスタッフを雇用することは難しく、また、専従のスタッフを配置することも困難な状況にある。
4.具体的な施策の考え方
上記の課題に対処するためには、促進すべき自然環境保全活動を公的機関が認定し、認定された活動に対して税制優遇を始めとする各種の支援措置を与えることが有効であると考えられる。この考え方に基づいて、国、地方公共団体及び民間団体等が、それぞれの責務にしたがって活動を促進するための仕組みを整えることが必要である。
(1)基本的な考え方
国や地方公共団体は、国土の地域ごとの生物学的特性を示す代表的、典型的な生態系や、多様な生物の生息・生育の場として重要な地域について保護地域制度を活用し、主に人の手が入ることを制限することによって直接その保護を図る。ただし、これらの地域でも、民間団体等により生態系の維持・再生のための活動が行われており、これらへの支援は必要である。
一方、さまざまな人間の働きかけを通じて維持・保全されてきた生態系については、国や地方公共団体は、できる限りその場所の特性に応じた保全が図られるよう、NGO、企業、地域住民など多くの主体の参画を促し、それらの活動を支援するため、経済的措置を含めた制度や社会的な評価の仕組みを充実することが必要である。
(2)自然環境保全活動の促進にあたっての各主体の責務
<国>
民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動の促進に当たり、国は、これらの促進をすることについてわが国の生物多様性の保全上どのような意義があるか、わが国の生物多様性の保全の観点から民間団体等によりどのような活動が行われることが望ましいか、この促進に当たっての基本的な方向性は何か、この促進のために国、地方公共団体、民間団体等がどのような連携を行っていくべきか等の基本的な考え方について、まず明らかにする必要がある。
その上で、民間団体等が行うこれらの自然環境保全活動を促進するために、民間団体等の活動状況の情報発信を国民に対して行う等の各種措置を積極的に講ずべきである。
<地方公共団体>
地方公共団体は、わが国における生物多様性の保全を図るため、国が定める基本的な考え方に基づき、地方公共団体の管轄する区域において行われる、民間団体等による土地の取得等の自然環境保全活動の促進に関する基本的な方針を定めるべきである。
また、国が行う各種措置に合わせて、民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動を促進するための各種措置を自ら講ずる必要がある。
<民間団体等>
民間団体等は、自然環境保全活動の対象となる土地における自然環境が良好に保たれるため、地域の自然的社会的条件に応じて、自然環境保全活動を長期間にわたり継続して実施することを旨として、その活動に取り組むべきである。
併せて、自らが行う土地の取得等の自然環境保全活動が、わが国における生物多様性の保全に資する取組であり、大変重要な位置にあること、この自然環境保全活動を行う原資となる資金の確保等のために、活動の意義や活動がもたらす成果等を広く一般の方々に知らしめることを通じて、多くの人々に、活動に直接的に参加し、又は、寄附金の支出等資金面での援助により間接的に参加してもらい、自然環境の保全に向けた共通の目的を持ってもらうことにより、社会をよりよい方向に変革していくことができることを、明確に認識する必要がある。企業においても、事業活動の一環として自然環境保全活動に自ら取り組む、又は他の民間団体の活動を支援することが望まれる。
そのような認識を持った上で、土地の取得等の自然環境保全活動を実践するとともに、その活動に対する支援を得るための努力を講じていくことが大変重要である。
(3)自然環境保全活動を進める上での基本的な仕組み
上記で言及した各主体の責務に基づき、自然環境保全活動の公益性を公的機関が認定し、その社会的信頼性を確保するための以下のような仕組みが考えられる。
国による基本的考え方の策定
各主体がその責務、役割等を認識した上で、民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動の促進に取り組むため、国が、民間団体等が行う自然環境保全活動の促進に関する基本的考え方を策定する。
地方公共団体による基本方針の策定
地域の実情に即したきめ細かい自然環境保全活動を支援するため、地方公共団体は、国が定める基本的考え方に基づき、民間団体等による土地の取得等の自然環境保全活動の促進に関する基本的な方針、促進の対象とする民間団体等が行う自然環境保全活動の考え方等を定める「基本方針」を生物多様性基本法の趣旨を踏まえて策定する。なお、基本方針の策定に当たっては、地域住民等の意見も聴くものとする。また、生物多様性基本法に基づく「生物多様性地域戦略」が策定されることが、望ましい。
民間団体等による自然環境保全活動計画の策定
民間団体等は、その行おうとする自然環境保全活動が、より着実に、より継続的、自立的に実施されるよう、活動地域・活動内容を明らかにし、国が定める基本的考え方及び地方公共団体が定める基本方針に照らして適切な、中長期的に持続可能な自然環境保全活動計画を策定するものとする。活動内容としては、土地の取得や、下草刈りや落ち葉かきなどの維持保全活動のほか、環境教育活動等が考えられる。これにより、当該計画に基づいて行われる自然環境保全活動が公益的な側面を有することが明らかとなる。
地方公共団体の長による自然環境保全活動計画の認定
当該計画に基づいて民間団体等が行う自然環境保全活動の公益性を担保するため、地方公共団体の長が当該計画について認定を行うこととする。その認定に当たっては、計画の内容が、国が定める基本的考え方及び地方公共団体が定める基本方針に照らして、自然環境を維持又は回復するために有効かつ適切なものであり、継続性を持って実施される活動であること等を確認するものとする。
その他
地方公共団体は、自然環境保全活動が計画に基づき適切に実施されているかどうかについて把握するため、必要に応じ報告を求めることとする。
また、わが国の生物多様性の保全が長期的に継続して図られるよう、民間団体等が行う自然環境保全活動に係る計画の実施期間はできる限り長期間で設定されること、また実施期間終了後においても、正当な理由がない限り計画を更新することが望ましい。
(4)土地を取得し、保全する活動を促進するための措置
生物多様性の保全のためには、さまざまな自然環境が存在する土地を自立的に、継続して保全することができるよう、その土地を取得することが最も有効な方法である。これまで行われてきているナショナル・トラスト活動においても、その保全の効果から、まずは、対象となる土地の所有権を取得することが目標とされてきたところである。
よって、土地を取得し、保全しようとする民間団体等の自然環境保全活動を強力に促進する必要があり、民間団体等へ土地が寄附されることを促したり、民間団体等が土地を取得しやすくなるための措置を講ずることが重要である。
?信頼性の向上
財政的基盤の弱い民間団体等が、自然環境保全活動として土地の取得等を行おうとする際、実勢価格に見合った十分な対価を支払い、その取得等を行うケースはまれであり、むしろ、土地やその土地における自然環境をできるだけ保全したい、そのような保全を全うできる者に土地を譲り渡したい、といった土地の保全を求める土地所有者から、土地を無償又は低額で譲り受ける場合が多い。
しかしながら、どの民間団体等が土地所有者の想いを着実に、継続的に実現できるものであるかどうかについて、土地の譲渡を検討している土地所有者が一般的に公開されている情報から判断することは必ずしも容易ではない。実際には、土地所有者が適切な譲渡先であると判断することができないため、譲渡が行われず、当該土地が転売される等の結果、土地が改変され、土地やその土地における自然環境の保全が実現されないこととなる場合がある。
このような事態を解消し、所有する土地を保全したいと考える土地所有者が適切な民間団体等に安心して土地を譲り渡すことを可能とするため、自然環境保全活動として土地の取得等を行おうとする民間団体等が、当該土地における自然環境の保全のための活動に関する計画を策定し、当該計画について公的機関の認定を受けることとする等、公的主体が一定の関与を行うことにより、民間団体等の行う自然環境保全活動が適切に、継続的に行われるものかどうか、その結果として土地や土地における自然環境の保全が図られるものかどうかを明らかにすることが必要である。
これにより、土地所有者は、認定を受けた計画に基づき自然環境保全活動を行おうとする民間団体等に対して、土地の譲渡を安心して行うことができることとなり、そのような譲渡が増加する結果、自然環境の保全のための取組が促進されることとなる。
?税制措置
■所得税・法人税(譲渡益に対する課税の問題)
民間団体等が、土地の取得を行い、土地における自然環境の保全を行おうとする場合、会費、寄附金等の収入を基本としている民間団体等が土地所有者に提示できる価格は、比較的低額とならざるを得ない。
このような場合に、土地所有者の譲渡益に課される所得税、法人税について対価の一定額を控除する等の優遇措置を講ずることにより、自然環境の保全を目的に、民間団体等に土地を転売しようとする土地所有者を支援することとなり、その結果として、民間団体等により自然環境の保全が図られることとなる。
■所得税(贈与、遺贈又は著しく低い対価での譲渡を行った場合の課税の問題)
個人である土地所有者がその所有する土地における自然環境の保全のため、当該土地を寄附しようとする場合、ナショナル・トラスト活動を行う民間団体等に贈与、遺贈、又は著しく低い対価での譲渡を行ったときは、時価による譲渡が行われたものとして、土地所有者に対し所得税が課税される(みなし譲渡課税)。
この「みなし譲渡課税」に関しては、公益法人に財産が贈与又は遺贈された際には、その贈与又は遺贈がなかったものとして課税されないこととされているが、そのためには、当該公益法人の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして「国税庁長官の承認」を個別に受けることが必要とされている。しかしながら、土地所有者が寄附等を行う時点では、非課税となるか否かが明らかではないことから、課税を避けたい土地所有者は、その土地の寄附を行おうとはせず、当該土地における自然環境の保全が図られない可能性がある。
これに関し、
?個別に国税庁長官の承認を得るのではなく、民間団体等が作成する自然環境保全活動に関する計画について公的な認定を受けたことをもって国税庁長官の承認に代えること、
?事前に国税庁長官の承認の可否について確認することを可能とすること、又は、
?一旦寄附を行った後、国税庁長官の承認が得られなかった場合には、当該寄附が行われなかったものとして取り扱われるための更正の請求を認めることを制度的に担保することで、土地所有者が安心して土地を寄附することができるようにすることが必要である。
■法人税(贈与又は著しく低い対価での譲渡を行った場合の課税の問題)
法人である土地所有者がその所有する土地における自然環境の保全のため、当該土地を寄附しようとする場合、ナショナル・トラスト活動を行う民間団体等に贈与又は著しく低い対価での譲渡を行ったときは、時価による譲渡が行われたものとして、土地所有者の譲渡益に対し法人税が課税される。
具体的には、法人である土地所有者が土地を贈与した場合や低額で土地を譲渡した場合、当該土地を時価で売却したという擬制の下で譲渡益が益金に計上され、法人税が課税されることとなる。特に、地価が高く値上がりの程度も大きい都市近郊における含み益の多い土地については、寄附の際に大きな税負担が発生することとなる。
よって、土地の時価相当の寄附があったものとして損金算入を認めれば、土地所有者にとっては、寄附を行おうとする大きなインセンティブとなり得る。
具体的には、寄附に係る一団の土地の価格が単年の寄附金の損金算入限度額を超える場合もあるため、認定計画に基づいて管理される土地を寄附する際、財務大臣の指定する指定寄附金と同様に、その土地の価格の全額を損金算入することができることとしたり、次年度以降に繰り延べてその全額を損金算入できることとする等の措置を検討することが必要である。
なお、土地と併せて維持管理のための財源を寄附する場合には、土地の価格と併せて、その全額の損金算入を認める等により、民間団体等が維持管理を安定的に行う基盤を確保することも必要である。
■相続税
土地の所有者が死亡し、相続が発生した場合、相続税の支払いのために土地を譲渡する等して現金化する事例は特に都市部において顕著に見られる。この場合、相続人が相続税の申告前に、相続により取得した財産を公益法人又は認定NPO法人に贈与したときは、贈与をした財産に係る相続税は非課税とされているが、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内であり、この期間内に、相続人が一連の手続を行った上で適切な相続財産の贈与先を見つけることが難しい場合もある。
このため、相続人が、自然環境保全活動に関する計画について地方公共団体の認定を受けた公益法人又は認定NPO法人へ土地等の贈与を希望し、真摯に関係者との調整を行っているものについては、申告・納付の期限を延長できるようにし、できるだけ保全が進むように促すことが望ましい。
■固定資産税等
固定資産税は、固定資産の所有者が行政サービスの恩恵を受けていることに着目し、その恩恵の量に応じて課される応益税である。したがって、地方公共団体、国等に無償で貸し付けられた土地が公用又は公共の用に供されている場合には、公益目的で使用されていることに照らし、地方税法により固定資産税及び都市計画税が非課税とされているが、民間団体等が所有権を取得して管理を行っている土地については、特段の税制上の優遇措置は講じられていない。
しかしながら、民間団体等が所有権を取得し、地方公共団体の認定を受けた自然環境保全活動に関する計画に基づいて当該土地の管理を行う場合、当該土地は、当該計画に基づき自然環境の保全のために適切に管理されることとなる。
よって、前述の地方公共団体等に貸し付けられた土地が公用等に供される場合と同様に、民間団体等が土地の所有権を取得し、当該土地について認定計画に基づき適切に管理を行う場合には、その土地の公益的な価値に着目し、固定資産税及び都市計画税に関して税制上の優遇措置を講ずることが適当である。
(5)土地を維持・保全する活動を促進するための措置
土地を所有し続けようとする意識が比較的高いわが国においては、土地の維持・保全等の自然環境保全活動を行おうとする民間団体等が、土地の所有権を取得して当該土地の管理を行う活動のほか、所有権の移転を伴わずに、土地所有者との間で土地の賃貸借契約を締結し、当該土地に係る自然環境保全活動に関する計画に基づき土地の管理を行うことにより、当該土地における自然環境を保全する活動がある。
この場合、民間団体等は、土地の管理権を得るために締結される賃貸借契約等の範囲内での賃料等を負担することによりその土地の保全が可能となることから、対価を支払い、土地の所有権を得る場合に比べればより対応しやすいものとなる。土地所有者においても、その有する土地の所有権を保持したまま自然環境の保全の取組に協力することができることから、一定の期間、その所有する土地における自然環境を保全するための活動が積極的に行われやすくなることとなる。
また、約90万haにのぼるとも言われている企業の所有地に関し、企業側は、適切に管理することによりCO2の吸収源や清らかな水源となる山林等の価値を見直し、その所有地の所有権を保持したまま、昨今求められているCSR活動の一環として所有地における自然環境の保全に積極的に取り組んでいきたいと考えている反面、現下の厳しい経済状況にあっては、所有地の管理に要する費用を支出することがなかなか難しいという実情にある。一方、山林や草原等の自然環境を適切に保全することに関心の高い民間団体等であるものの、活動するための土地を確保できていない場合も多い。
このため、これらの民間団体等が土地所有者である企業との間で一定期間、賃貸借契約等を締結し、その土地に係る管理権を得て管理を行うことにより、このような土地における自然環境の保全を図ることが想定される。
これらの状況を踏まえ、土地を所有し続けようとする意識が比較的高いわが国においては、この形態の自然環境保全活動を積極的に促進する必要があり、そのため、安定的に自然環境が保全されるための措置を講じたり、土地所有者に対し民間団体等への土地の管理権の提供に係るインセンティブを与えることが重要である。
?土地を維持・保全する活動の継続的な実施
この形態の自然環境保全活動が適切に継続して実践されるためには、民間団体等が土地所有者との間で締結する賃貸借契約等が長期間、安定的に保持される必要がある。
このため、例えば、民間団体等が土地所有者との間で自然環境保全活動の対象となる土地について賃貸借契約を締結し、契約に基づく管理権を前提として、その土地を管理するという自然環境保全活動に関する計画を定めて活動を行おうとする場合、その活動の内容を広く一般に公表し、このような計画が自然環境の保全のための活動の促進に重要である旨を公的に認定することにより、新たに、計画の対象である土地の所有者となった者に対しても、その効力を引き続き有効とすること(承継効の付与)や、土地の所有者が正当な理由なく計画の有効期間中に土地の返還を申し出てはならないこととするなど、当該土地等における自然環境の長期にわたる保全が図られるための法的その他の適切な仕組みを検討することが必要である。
?税制措置
■相続税
民間団体等が行う自然環境保全活動に関する計画に関し、その対象である土地について相続が発生した場合においても、当該土地おける自然環境の長期にわたる保全が図られるための法的その他の適切な仕組みとして承継効を付与するとした場合、当該土地の所有権が相続により土地所有者(被相続人)から相続人に移転したとしても、計画の存続期間はその土地の利活用が制限されることとなり、土地の所有権の資産価値は減?することとなる。
このため、賃借権が設定されている土地等の取扱いに照らし、当該土地に係る相続税に関して、その課税の対象となる相続財産の評価額について一定の減額が行われることが適当である。
また、こうした形態での自然環境保全活動の実施の安定性を長期に渡って確保できるよう、賃借権と比較して長期に設定できる地上権又は地役権に関して、自然環境の保全を目的として設定することの可能性について検討することが必要である。
その上で、設定された権利の内容に応じて、相続税の課税の対象となる土地の価格の減価を認めることを可能とすることが必要である。
■固定資産税等
固定資産税は、固定資産の所有者が行政サービスの恩恵を受けていることに着目し、その恩恵の量に応じて課される応益税である。したがって、地方公共団体、国等に無償で貸し付けられた土地が公用又は公共の用に供されている場合には、公益目的で使用されていることに照らし、地方税法により固定資産税及び都市計画税が非課税とされているが、民間団体等が管理権を得て管理を行っている土地については、特段の税制上の優遇措置は講じられていない。
しかしながら、民間団体等が土地所有者との間で賃貸借契約等を締結し、地方公共団体の認定を受けた自然環境保全活動に関する計画に基づいて当該土地の管理を行う場合、当該土地は、当該計画に基づき自然環境の保全のために適切に管理されることとなる。
よって、前述の地方公共団体等に貸し付けられた土地が公用等に供される場合と同様に、民間団体等が土地所有者との間で締結した賃貸借契約等の対象となる土地について認定計画に基づき適切に管理を行う場合には、その土地が公益目的で使用されていると捉え、固定資産税及び都市計画税に関して税制上の優遇措置を講ずることが適当である。
(6)土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等の運営基盤の強化等
ナショナル・トラスト活動等の自然環境保全活動を行う民間団体等は、公益法人やNPO、任意団体である場合が多いことから、活動のための資金が十分ではなく、事務局についても十分なスタッフを雇用することができないなど、その運営基盤は大変脆弱である。
わが国における生物多様性の保全のためには、さまざまな土地における自然環境を自立的に、継続して保全することができることが重要であり、そのためには、その保全を担う民間団体等が、自立的に、継続して活動できることが前提となることから、そのために必要となる措置を講ずる必要がある。
?資金の確保
民間団体等が土地の取得等の自然環境保全活動を実践するためには、まず、その活動のための資金の確保が重要である。
ナショナル・トラスト活動を行う公益法人、NPO等の民間団体については、その主な収入源は、会員からの会費や個人・企業からの寄附金、公的主体や他の民間団体からの各種助成金、自主的な事業から得られる収入や、公的団体等からの事業の受託による収入等である。このような民間団体は、その本来的な活動をより自立的に実施するため、まずは、会員からの会費、個人・企業からの寄附金といった収入を基本として自然環境保全活動のための資金を確保する必要がある。
人類共通の財産である生物の多様性を確保し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受するためには、ナショナル・トラスト活動を継続的に長期にわたり実施することが重要であり、土地の購入資金や民間団体等の活動資金に充てるべく、長期間継続的に寄附金の拠出等の支援を得る必要がある。
このため、まず、民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動自体についての理解を得ることが必要である。一時的な資金の提供ではなく、継続して資金を提供してもらうためには、わが国で顕著に見られる“気が向いたときに募金を行う”といった形の寄附では不十分である。長期間、継続的に寄附金の拠出等の支援を行ってもらうため、民間団体等が行う土地の取得等の自然環境保全活動について説明し、共感してもらうこと、そして寄附金を拠出した結果について興味を持ってもらうことがポイントとなる。このための取組として、ホームページや会報などを用いて活動状況を報告する等、積極的に情報公開することはもとより、寄附金を支出した方々の個々の行動が、直接的にどのように民間団体等の自然環境保全活動に結びついたのかについて、よりきめ細かく伝えていく必要がある。
また、寄附のしやすさを向上させることが必要である。平成12年12月に経済企画庁国民生活局が発表した「平成12年度 国民生活選好度調査 −ボランティアと国民生活−」では、寄附をしている世帯の寄附額は、調査対象となった世帯数のうち約半数の世帯で一月当たり500円以下となっており、1,000円以下の世帯が21%、5,000円以下の世帯が22%となっている。このような状況を踏まえ、寄附を受ける場合の寄附金の額の設定に当たっては、例えば1,000円や500円単位とするなど、細かく寄附することができるようにするなどの工夫が必要である。
このほか、寄附のしやすさの一助として、他の団体との連携を模索することも想定される。有名な事例として、富士ゼロックスにおいて平成3年から実施されている「端数倶楽部」というものがある。これは、富士ゼロックスで働く人々や退職者によって構成され、自発的、自主的に運営されている社会貢献活動団体が、希望者の給与や賞与の端数部分(100円未満)を天引きして寄附する仕組みであり、これまで約2億円もの額の寄附を行っている。
寄附金の支出の方法についても、これまでは郵便局や銀行での振込が用いられる場合が多かったが、寄附を行おうとする者がより簡便に寄附することができるよう、インターネットや携帯電話の活用、クレジットカードやコンビニ決済の導入等を行うことも考えられる。
より確実に多額の寄附を得るため、例えば、企業と連携を図ることも考えられる。アサヒビールが、売上げに応じて各都道府県に自然環境保全等のための資金を寄附するとのキャンペーンを行い、約2ヶ月の間に約2億2,000万円の寄附に相当する売上に達するなど、近年、企業がその売上の一部を自然環境保全活動等へ寄附することを表明することで売上が伸びる事例も報告されている。土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等についても、売上げに応じて寄附を行うといった取組を行おうとする企業と連携を行うことにより、活動資金を確保することが可能となることから、そのような連携を行いやすくすることが必要である。
このように、民間団体等がさまざまな工夫を行うことにより、継続的に安定した会費収入や寄附金収入を受けることができるよう、そのような取組への支援について検討する必要がある。
なお、前述したような取組を行うことは、単に民間団体等が活動資金を得て、その活動を長期間、継続的に実施しやすくすることをもたらすだけではなく、さまざまな人々が、これらの民間団体等がどのような考え方の下にどのような自然環境保全活動を行っているかを知り、その趣旨に賛同して会員となり会費を支払う、寄附金を出す、つまり、“多くの人々に自然環境の保全に向けた共通の目的を持ってもらうこととなり、社会をよりよい方向に変革していく”ことにもつながるものである。民間団体等においては、そのことを念頭に置いてその活動に対する支援を得るための努力を講じていくことも重要である。
?税制措置
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等の運営基盤の強化のためには、まず、適正な事業活動の実施や情報公開により会員や寄附者の理解を得るためのさまざまな取組を実施する必要がある。そして、そのような取組を補完するものとして、寄附金がより確保しやすくなるための税制上の優遇措置が考えられる。
例えば、現在、国や地方公共団体に対して寄附金を支払った場合、確定申告により一定額が所得から控除され所得税が還付されたり、寄附金の全額が損金に算入できることとされている。このほか、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた公益法人や独立行政法人等に対して寄附金を支払った場合にも、同様の優遇措置が受けられることとされている。
また、NPO法人についても、その活動資金を外部から受けやすくすることで、その活動を支援することを目的とする「認定NPO法人制度」という寄附金に係る税制上の優遇措置が講じられ、平成13年から施行されている。この「認定NPO法人」とは、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたNPO法人を指しており、累次の税制改正により認定要件の緩和等も行われているが、平成21年7月現在で95法人(特定非営利活動法人法に基づき認証されているNPO法人は37,562法人(平成21年5月末現在))にとどまっており、NPO法人の実態を踏まえた更なる見直しが必要ではないかとの問題提起がある。*6
このような状況を踏まえ、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等を支援することにより、わが国における生物多様性の保全を図るため、まず、民間団体等のうち旧民法第34条に基づく公益法人であって、公益法人改革後の公益法人への移行期間にあるものについては、できる限り公益認定を得て税制上の優遇措置を受けることができるよう、その認定に向けた支援について検討する必要がある。
また、公益法人や認定NPO法人に限らず、一定の公的な認定を受けた自然環境保全活動計画に基づいて自然環境保全活動を行う民間団体等について、当該自然環境保全活動に係る寄附金に関する税制上の優遇措置やみなし寄附金制度を適用できるようにする必要がある。
?情報の共有
民間団体等が土地の管理を行う際、その管理の程度として、その土地において維持されている自然環境を引き続き適切に維持したり、既に回復を要する自然環境について回復を図ることが想定されるが、自然環境保全分野の専門家を雇う財政的基盤を必ずしも持たない民間団体等にとっては、どのような水準で管理を行うべきか必ずしも明らかではなく、適切な管理が行われない場合には、自然環境が適切に保全されず、結果として、生物多様性の保全が図られないこととなるおそれがある。
このため、例えば、土地の種類等に応じて、その土地における自然環境の保全のための維持管理に関するノウハウや技術手法を整理し、民間団体等に情報提供することが必要である。
土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等が、その活動を着実に、自立して継続的に行うためには、土地の取得に係る不動産鑑定、相続時に土地等の寄附を受ける場合の税務上の手続、寄附金等に係る税制上の優遇措置、自然環境の保全の観点からの土地の維持管理に要する専門知識など、さまざまな専門的な知見が必要となる。また、会員や寄附金を受けた者に対して行う民間団体等の活動の実施状況に関する情報の提供や、新たな会員や寄附金の獲得、活動の対象となる土地についての情報収集や土地の確保に向けた土地所有者との交渉等、民間団体等が行う必要がある事務も多岐にわたっている。
しかしながら、土地の取得等の自然環境保全活動を行う民間団体等については、同一の目的を有する地域の住民等が民間団体等を立ち上げて自ら事務局として活動を行う事例が多く、また活動に必要となる資金が不足するため、不動産鑑定等の専門家を確保することが難しく、必要十分な数の職員を雇用できるような状況には無い。
このため、例えば、不動産鑑定や相続、税制等の土地に関わる専門家との連携を確保した支援センター機能を有する組織を設け、土地の取得等の自然環境保全活動を行おうとする、又は行っている民間団体等が随時相談できるようにしたり、当該組織が、過去の相談事例を整理し、これらの民間団体等がアクセスできるように情報発信することが必要である。
また、支援センター機能を有する組織が、民間団体等が情報発信するためのホームページ作成等を技術的に支援したり、遺産相続の手続の具体的内容、寄附金の額の増大のための工夫等、それぞれの民間団体等が実際に経験し、蓄積したノウハウについて収集・整理し、他の民間団体等に良好事例として情報提供することも必要である。
?共通認識の醸成
民間団体等が、土地の所有権を得たり、賃貸借契約等により土地の管理権を得るなどして、当該土地の維持管理を行おうとする場合、自然環境が適切に保全されるためには、地域の特性に応じた適切な維持管理を実施することが必要である。また、土地所有者や地域住民と維持管理のあり方について認識を共有し、相互に連携して取り組むことも大変重要である。
このため、その前提としての市民・土地所有者への普及啓発のほか、必要に応じ、土地所有者や地域住民、自然環境に関する専門知識を有する者等が維持管理のあり方について意見交換できる場や、自然環境保全の方向性の合意を図るワークショップの場を設定することが望ましい。そして、そのような場の設定が進むための支援について検討することが必要である。
5.中長期的な課題
今回の検討は、生物多様性基本法において、民間の団体等が行う生物多様性の保全のための重要な取組の一つである「ナショナル・トラスト活動」等を推進するため、税制優遇措置等を講ずることとされたこと、平成22年10月に、わが国において生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の開催が予定されていること等の生物多様性の保全に向けた諸要請を踏まえ、早急に実施すべき措置について検討してきたところであり、その検討の結果については、当面講ずべき措置として4.までにおいて取りまとめたところである。
しかしながら、本検討会としては、わが国における生物多様性の保全が真に図られるためには、生物多様性基本法で記された「自発的な活動」が十分に促進されるよう、さらにドラスティックな措置を講ずる必要があると考える。このため、以下に掲げる事項について、引き続き検討を続けるべきと考える。
(1)長期的に土地の取得等の自然環境保全活動を行う仕組み
イギリスにおけるナショナル・トラスト法においては、「譲渡不能の原則」という仕組みがある。具体的には、同法に基づき設立された「ナショナル・トラスト」に対して、その保存の対象となる資産である土地、建物等について「譲渡不能」と宣言する機会が与えられており、この宣言を受けた資産は、売却あるいは担保に供されることはなく、また、国会の特別の議決がある場合を除き、強制収用されないこととされている。
わが国においても、生物多様性の保全を図るため、日本国憲法第29条第3項において「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定されていることを踏まえつつ、英国のナショナル・トラストのように、ナショナル・トラスト活動を行う民間団体等がその所有する土地、建物等について将来にわたり保全し続けることを表明したときは、当該土地、建物等については売却や担保に供されず、また国会の議決があるなど特別の場合を除き、当該土地、建物等が強制収用されないこととする仕組みの可能性を検討することが必要である。
(2)土地の取得等の自然環境保全活動を行う主体の抜本的強化
イギリスにおいては、ナショナル・トラスト法に基づいて、国民の利益のために、美しい土地等を恒久的に保存することを目的とした法人である「ナショナル・トラスト」が設立されるとともに、この法人に対し、譲渡不能を宣言する権利が付与されたり、ナショナル・トラストに寄贈等された資産について税制上の優遇措置が講じられるなど、さまざまな特権が設けられ、その取組の推進が図られている。
わが国においても、土地の取得等の自然環境保全活動を、長期間、継続して実施し続けるため、またその活動への支援措置を講じやすくするため、英国におけるナショナル・トラストのように、自然環境保全活動の対象となっている土地等の資産を、個々の民間団体等が所有するのではなく、例えば、特定の法律により設立される法人が取りまとめて所有することも検討すべきである。なお、その土地等の維持管理に当たっては、当該特定の団体が、各地域において自然環境保全活動を行う民間団体等と協定などを締結し、当該民間団体等が維持管理に取り組むことが考えられる。
(3)土地における自然環境を保全するための新たな権利の設定
わが国においては、土地の所有権ほど強力ではないものの、土地を一定の目的の下に使用する権利として「地役権」がある。この「地役権」とは、一般的には、要役地(便益を受ける側の土地)と承役地(要役地の便益のために利用される土地)の間で設定される“付随地役権”と言われる権利である。
一方、米国においては、土地環境を保全する目的に反する活動を制限することができる権利として「保全地役権(Conservation Easement)」がある。これは地役権の一種であるが、わが国における地役権と異なり、人の便益のために他人の土地を利用する権利とされており、承役地の有無にかかわらず、土地の所有者と行政機関や公益法人等の契約により設定することが可能である。
わが国においても、民間団体等が自然環境保全活動としてより積極的に土地の保全を行うことができるよう、米国の「保全地役権」を参考に、これまで認められている “付随地役権”に限らず、人の便益のために他人の土地を利用する権利と捉える新たな地役権を設けることを検討すべきであると考える。
(4)自然環境保全活動の対象となる土地における自然環境に係る情報の整備等
わが国に存在する自然環境の基本情報については、自然環境保全基礎調査等により、縮尺5万分の1の植生図等が整備されており、また平成11年度からは、2万5千分の1の植生図への全面改訂が順次実施されている。
しかし、これまでわが国において行われてきた、自然環境保全を目的としたナショナル・トラスト活動では、数ヘクタールの土地が対象となる場合が多く、必ずしも十分な精度の情報は得られていない。
今回検討を行った民間団体等による自然環境保全活動を促進する仕組みをより充実させ、又は、その対象となっているような小規模の自然環境までを保全する措置等を検討するためには、そのような自然環境に関するより精度の高い基礎的な情報を整備することが必要である。
また、わが国における生物多様性が適切に保全されるためには、そもそも、わが国にどのような生物多様性が存在しているかといった基本的なデータが整備される必要がある。生物多様性基本法においては、地方公共団体は生物多様性地域戦略を策定するように努めることとされているところであるが、生物多様性に関する基本的なデータが整備されることにより、よりよい地域戦略が策定されることが期待される。
http://www.env.go.jp/nature/national-trust/conf_ncaco/rep0909.pdf
2009年11月22日
岡山県小鳥が丘団地の土地・地下水汚染問題の経緯
岡山県小鳥が丘団地の土地・地下水汚染問題の経緯
〜リスクコミュニケーション〜
おおさかATCグリーンエコプラザで
「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」と題する講演が
平成21年12月18日(金) 14:00 〜 17:20
にあります。
地下水上昇・護岸擁壁の黒い液体の浸み出しやふくらみ・皮膚炎・鼻炎・頭痛・トリクロロエチレン・ベンゼン・食塩など混入?・
地表から浸透した有機汚染物質?地下水の上昇・擁壁のはらみ出し
不適切な記載や、事実と異なる表現、追記事項等のご意見がありましたら↓のコメント欄に記載下さいますようお願いします。
http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/38388679.html
西暦 元号 月日 行政 両備 住民等
2009年 22年 12/18
ATCセミナー 土壌汚染の社会問題で講演 〜豊洲・桃花台・小鳥が丘の事例〜
各地で市民が行政や大企業等を相手にした土壌汚染係争案件が多発しています。たとえば、岡山市小鳥が丘団地住民の開発業者である両備を相手にした油工場跡地の裁判や、小牧市桃花台における地盤沈下や土壌・地下水汚染について愛知県や都市再生機構との公害調停や民事裁判さらに、東京都江東区豊洲の埋立地におけるガス製造工場跡地の土壌汚染調査データ公開遅れが問題にされ、採取した調査試料を廃棄しようとする東京都に対し市民が提訴しています。
今回はこれらの問題に大変詳しい講師を招きし、土壌汚染対策法の改正を控え今後の土壌・地下水汚染や廃棄物問題を考える良い機会にしたくご案内いたします。
開催日時
平成21年12月18日(金) 14:00 〜 17:20
プログラム
講演1:「東京都豊洲地区の土壌汚染」〜実態と問題点〜
講師:日本環境学会 土壌汚染ワーキンググループ長 坂巻 幸雄 氏
講演2:「豊洲の土壌汚染の実態について」
講 師:NPO法人 「市場を考える会」総務・環境問題理事 野末 誠 氏
講演3:「(仮題)桃花台の地盤沈下と土壌・地下水汚染問題について」
講 師:桃花台地盤沈下問題を考える会 代表 丸山 直希 氏
講演4:「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」
講 師:小鳥が丘団地救済協議会 藤原 康 氏 岩野 敏幸 氏
総合質疑応答
主 催
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会
受講料
1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)
会 場
おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ
定 員
100名(先着順 ※受付確認はセミナー開催約10日前迄にFAXまたはE-mailでお送りします。)
お申し込み
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp
12/8
岡山地方裁判所13時30分〜16時30分
10/20
岡山地方裁判所353号法廷で第13回口頭弁論準備手続きが行われ、原告住民3名の陳述書を裁判所に提出した。
裁判長は住民訴訟第二次(18世帯)は、現在、(不動産)鑑定準備中ですと述べた。
住民訴訟第二次(18世帯)は、前回原告住民が土壌改良の為の土壌調査を求めて学者の土壌調査方法等の資料を提出しましたが、調査費用の見積もりが高額になり(約7千万円)とても負担しきれない事が判明したので、調査範囲を絞り込むなどして再度調査方法を検討し費用7百万円を見積もり、原告住民と被告両備ホールディングスで折半負担を提案しました。
裁判所も被告両備に鑑定費用を半分持てという勧告を出しましたが両備側は固辞したようです。
7/9
調査分析報告書が送られてきて、護岸の付着物もはっきりと油分が検出されていた。いずれも汚染の程度は著しいものとなっていたので早速、調査報告書は証拠として裁判所に提出した。
6/13
住民訴訟第一次(3世帯)は環境総合研究所に現地地質調査分析を依頼し、職員を現地に派遣してもらい住民による調査サンプル採取を行った。(モニター井戸水質3か所、原告敷地駐車場土壌1か所、沼川護岸擁護壁付着物1か所、合計5か所)
2008年
11/17
第9回口頭弁論準備手続き岡山地方裁判所で(非公開)。
7/9
第7回口頭弁論準備手続き。住宅地としてはその目的を達することのできない欠陥住宅地であるとの準備書面と5月30日現地視察の録画DVDを裁判所に提出。
裁判所としては複数の公平な学者の意見を参考にしたいので、その前提として被告両備ホールディングスが主張し証拠資料とした「意見書」を答申した両備バス設立の「南古都?環境対策検討委員会」の会議録原本を提出することを打診。被告両備ホールディングス株式会社は、会議録は持っていないし提出すべき文書ではないと拒否。
6/9
環境goo「小鳥が丘団地土壌汚染で強い臭気を確認――岡山地裁が現地視察」掲載
6/6.7
赤旗に「岡山・小鳥が丘団地 汚染訴訟 〜立ち上がる住民〜」が掲載される
6/4
環境新聞 「小鳥が丘団地 強い臭気と黒い土確認 岡山地裁 現地視察 数カ所で廃棄物も」報道
5/31
毎日新聞現地調査を報道
5/30
裁判所による「小鳥が丘団地」現地検証土壌汚染問題裁判・公開調査 。
13時30分から裁判所による「小鳥が丘団地」土壌汚染現場検証が行われました。裁判官、原告住民および弁護士や学者、被告弁護士が、多くのマスコミや関係者の見守るなか、小鳥が丘団地内を見て回りました。各家庭の庭や駐車場を住民が削岩機で3箇所、ユンボで2箇所を掘削しましたが、どこの庭や駐車場も少し掘れば真黒い土と頭が痛くなるような刺激臭がありました。 あと地盤沈下で下がった塀や、油や石灰と思われる液体が滲み出ている擁癖や、玄関前側溝から可燃性ガス(2005年11月に地元消防署が確認)の泡が吹き出している箇所を住民が説明し15時30分頃終了しました。
5/22
参議院環境委員会「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」審議で「小鳥が丘団地土壌汚染問題」が取り上げられる
5/19
(3世帯裁判)第6回口頭弁論準備手続き(非公開)がに岡山地方裁判所であります。
4/22
(18世帯裁判)第2回口頭弁論準備手続き(非公開)が岡山地方裁判所であります。
4/9
環境新聞 土壌汚染現場の最前線 5 小鳥が丘からの手紙編? 開発業者の認識がポイント 予見困難と請求却下した判例も
4/4
(3世帯裁判) 第5回口頭弁論
3/26
環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 4 小鳥が丘からの手紙編? 救済に至らない土対法の現状 横たわる費用負担問題 揮発系リスクでも提起
3/19
環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 3 小鳥が丘からの手紙編? 健康リスク以外にも波及 現行の制度では解消難しい問題
3/12
環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 2 小鳥が丘からの手紙編? 原因者不在が混乱の要因 急がれる健康被害と汚染の関係解明
3/11
(3世帯裁判)第4回口頭弁論
3/6
若井たつこ市会議員、岡山市議会にて「小鳥が丘団地の土壌汚染に関して、固定資産税の減免措置について」個人質問
3/5
環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 1 小鳥が丘からの手紙編? 打開の道見えぬまま3年半 汚染原因者不在のまま住民と開発業者で民訴
3/4
18世帯裁判 初回口頭弁論
3/6
若井たつこ市会議員、岡山市議会にて小鳥が丘団地の、固定資産税の減免措置について質問する
1/29
(3世帯裁判)第3回口頭弁論(岡山地裁)
1/22
毎日新聞掲載 土壌汚染・岡山の団地、資産価値ゼロ
2007年
12/28
毎日新聞掲載 提訴:宅地の土壌汚染で住民らが−−岡山・小鳥が丘団地
12/27
住民18世帯が「両備ホールディングス」を相手取り、賠償を求めて岡山地裁に提訴する
12/11
(3世帯裁判)第2回口頭弁論(岡山地裁)
11/13
(3世帯裁判)第1回口頭弁論(岡山地裁)
10/28
フォーラム開催 後援:環瀬戸内海会議 同窓会 日本共産党岡山市議 竹永みつえ参加 「小鳥が丘団地で何が起きた!」
岡山市立上道公民館
日本環境学会会長 大阪市大 畑明郎 教授 が 講演
10/28
午前 見学者が現場を確認する
道路の観測井戸 宅地の観測井戸
地下水位:地盤高−約20cm 井戸の直径:約12cm程度
ガスが湧き、引火した玄関
油がにじみ出し、はらみ出しているブロック積み擁壁(はらみ出し場所と油のにじみ出る場所が一致している)
10月
おおさかATCグリーンエコプラザで土壌地下水汚染について討議される
京都地方裁判所において、排水路改良工事において,市が不適切な工法を選択したことにより,建物の損傷が拡大したとして,市に適切な工法選択義務違反の過失を認め,業者と市に共同不法行為が成立するとした事例 (損害賠償請求事件 判例)
8/31
自治体は「民間の問題なので調査する法律がない」と言う。もはや民事訴訟しかないと思い団地住民に呼びかたが、裁判となると決断が難しく、まず3名が先兵との思いでに両備ホールディングス?(旧両備バス?)を岡山地裁に提訴した。
「ネット街宣」に「両備バス(現、両備ホールディングス)小嶋社長の責任を問う?」*問題解決は急務*と掲載される
8/23
おおさかATCグリーンエコプラザでOAPや東京豊洲の土壌汚染問題等についてのセミナーが開催され、
大阪市大 畑明郎教授(日本環境学会理事長)や楡井久(NPO法人日本地質汚染審査機構)理事長が講演する。
小鳥が丘団地救済協議会が参加する
8/13
両備が調査用に開けた穴。猛烈に臭い。 ある家の庭に開けられた調査用の穴。油膜が張り、ガスがブクブク湧いていた
週刊プレイボーイに「産廃に沈む住宅地」掲載される。
7/28
両備ホールディングス株式会社代理人 弁護士:菊池捷男、首藤和司、財津 唯行、安達祐一、井田千津子から回答書
7/13
住民代理人弁護士:河田英正、大本崇が通知・催告書出す
7/3
18時40分頃、また住民民家でガス漏れ警報器が鳴る
7/10
住民、公害調停を申請
6/25
住民が西大寺支所建設課に空洞化の確認を要請すると。
「・・・近くを通る時はチェックしている。県民局職員は水の流れる音は聞いてないとの事(矛盾)。現時点では心配ない。継続的に監視する。」
との西大寺支所建設課からの返答がある。
この頃 住民による土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の
溶出量値が土壌溶出基準を超えていた
6/23
両備グループ監査室 設立
両備グループは「社会正義」「お客様第一」「社員の幸せ」を理念とし、48社で構成され全従業員6,000名の会社です
両備グループ監査室長 佐藤 允彦 ?中国バス専務取締役 兼務
両備グループ監査室主任監査役 窪田 新治
両備グループ監査室主任監査役 桑原 彰一郎
両備グループ監査室分析統括監査役 福間 和興
6/22
21時ごろ住民民家でガス漏れ警報器が鳴る
6/16〜17
環瀬戸内海会議第18回総会で、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題を報告する
6/13
16時ごろ、西大寺消防署上道出張所が岡山市から連絡を受けて調査に来る
6/11
22時ごろ住民民家でガス漏れ警報器が鳴る
5/30
読売新聞社が土壌汚染による健康被害を報道
5/14
岡山県に調査結果を報告・・・現在岡山市が管轄しているので県では何もできないと回答。
5/14
岡山市に調査結果を報告し詳細調査を要請・・・表層に有害物質がある事が証明されたが、岡山市は実態解明調査は行わないと回答
5/12
岡山シティーホテル桑田町で記者会見し畑明郎教授が「住民による土壌調査結果」を報告
5/12
近隣の住民から旭油化工業撤退前に所有地で井戸用にボーリングしたら油が出たとの証言あり
4/30
大阪市立大学の畑明郎教授(日本環境学会会長)から意見書がメール来る
サンプル数は少ないものの、土壌ガスから発がん性のベンゼンが、土壌溶出量基準を超えるベンゼン、猛毒のシアン、発がん性のある鉛やヒ素が検出されており、危険で有害な土壌であることが証明されたと思います。
ベンゼンや鉛は、廃油や廃溶剤などからと考えられますが、シアンやヒ素の原因は不明です。応急対策として、敷地土壌のアスファルトやセメントによる被覆が早急に必要と考えます。
4/28
土壌汚染調査結果報告書を畑明郎教授に郵送し意見を伺う
4/27
兵庫県の民間土壌分析会社が調査報告書を持参
4/20
住民が片山 虎之助 参議院議員に公開質問状を送る
4/15
大阪市立大学の畑 明郎 教授が現地視察
4/9
兵庫県の民間土壌分析会社が土壌調査を実施
4/4
兵庫県の民間土壌分析会社に土壌調査を発注
4/1
両備バスと両備運輸が合併し社名を「両備ホールディングス」に変更。
4月
(住宅敷地内において)表層土壌ガス調査の結果、2箇所の調査位置においてベンゼンが検出された
3/23
ENVIROASIAや JanJanに「いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!」掲載される
3/13
住民側が岡山地方法務局の人権相談事務所で相談する。
質問:土壌汚染の分譲住宅地を知らずに購入して、健康被害に遭い宅地建物の価値も無くなったのに、連絡しても放置されたことは人権侵害だと思う。
回答:司法手続きの検討しかないと思う。岡山市には相談があった事は連絡しておきます。
3/15
岡山県倉敷市の民間土壌分析会社が調査を辞退
3/13
岡山県倉敷市の民間土壌分析会社が2007年3月26日予定で土壌調査実施を受託
2/13
岡山県土木部都市局建築指導課から回答書 (宅地建物取引業法の公訴時効は3年、行政処分を行える期間は原則として後5年)
2/13
岡山県生活環境部 環境管理課 循環型社会推進課から「岡山市と協議するように」と回答書
2/9〜12
テレビ朝日のニュース番組「報道ステーション」取材チームが取材に入る、しかし、テレビ朝日は一方的に放映中止
2/7
岡山市西大寺支所建設課が膨れている擁壁や道路を現地調査
「・・・普通の道路保全だけでは無いので(土壌汚染の関係もあるので)事情を確認してから連絡する。」
2/7
高谷 茂男 岡山市長「土壌汚染調査について(回答)」が来る 岡市み第249号
平成19年2月7日
小鳥が丘団地救済協議会 代表 ○○ 様
岡山市長 高谷 茂男
土壌汚染調査について(回答) (抜粋)
平素から、市政発展のためにご理解とご協力をいただきありがとうございます。さて、平成19年1月30日付けで提出された標記要望書に対して、下記のとおり回答いたします。
記
1.当団地の土壌汚染の実態を把握する為、市主導で、私達の信頼できる環境省指定の民間調査機関と共に徹底した土壌調査を実施することについて
(回答)
両備バス?が設立した環境対策検討委員会(以下、「委員会」と記す。)での審議の結果、平成17年3月28日付けで、
(1)現状の生活環境においては、異臭による不快感はあるものの、健康への影響が直ちに懸念されるものではないこと、
(2)MNA等による居住環境の改善対策案が示されたこと、等が提示されました。
本市としましては、平成17年3月24日付け 岡協市第108号 にて回答しているとおり、委員会から提示された対策案について、住民の皆様、両備バス?、市の3者で協議の上、対応してまいりたいと考えております。
また上記のとおり、健康への影響が直ちに懸念されるものではないと判断されていることから、現時点では、市が主導して土壌調査等を実施することは考えておりませんが、住民の皆様が安心して暮らしていけるよう、周辺環境調査等できることは実施していきたいと考えております。
なお、団地内にお住まいの方で、本件に関して健康面でご心配の事項がありましたら、引き続き岡山市保健所を窓口として健康に関する相談に応じる方針です。
(自宅庭で、ガス中毒で倒れた岩野氏が岡山市保健所に相談に行ったところ、保健所では対処できないので、岡山市環境保全課に相談して下さいとの回答でした。つまり何処の窓口に行っても健康診断には対応してくれません)
5.
一部省略
(エ)小鳥が丘団地の土壌調査は実施しないとする環境保全課の考え方について(回答)
住宅地等における土壌汚染問題については、土壌汚染対策法が適用される案件を除き、原則、造成・販売等に関わった当事者間による話し合い等により解決されるべき問題であり、土壌汚染対策法が適用される案件では、調査の実施主体は土地所有者等であると認識しております。
同様の調査は、本市においても次のとおり実施し、住民の皆様にすでに報告しているところであります。
?平成16年7月29日、地下水調査(カドミウム等、全21項目)
?平成16年8月12日、土壌溶出量調査(カドミウム等、全25項目)
?平成16年8月26日、表層ガス調査(ベンゼン等、全3項目)
<問い合わせ先>
○土壌汚染に関すること、環境局環境保全課、TEL(086)803−1281
○健康相談に関すること、保健所健康づくり課、TEL(086)803−1267
○開発許可に関すること、都市整備局開発指導課、TEL(086)803−1452
2/5
岡山県備前県民局建設部が擁壁から廃油が流れていて膨らんでいる事について現場確認する。
2/5
岡山県循環型社会推進課、河川課、建築指導課、環境調整課が住民に説明
1/30
住民が岡山市長に土壌汚染調査要望書を提出する
平成19年1月30日
岡山市長 高谷 茂男 様
小鳥が丘団地救済協議会 代 表 ○○
要望書
土壌汚染調査について
貴職におかれましては、日々、岡山市発展の為、御尽力いただき、心より敬意を表します。
さて私達 「小鳥が丘団地救済協議会」 は当団地で平成16年7月に発覚した土壌汚染の問題が長く放置され、発覚当初想像さえしなかった住宅地表層近くから広範囲に刺激臭のする黒い土壌が発見され尋常でない事に危機感を持つ団地住民の有志で組織した団体です。
何度となく岡山市、岡山県、警察、等に足を運び相談をして参りましたが、地下数メートルには環境規準値の20数倍の有害物質は有るが地上で生活する住民に健康への影響が直ちに懸念されるものではないと言われ、危険と判断されぬまま放置されましたが、その後そのガスを吸い込んだ住民が自宅庭で倒れ、救急車で病院に運ばれ緊急入院の事態に成りました。診断結果はガス中毒です。
市民がこの様な健康被害に遭い、土地建物の資産価値は無くなり、この環境を将来世代に引き継ぐ事をも懸念しています。岡山市環境保全条例の基本理念―環境の保全及び創造は,健康で快適な生活の確保が,すべての市民がその生活を営む上で欠くことができない基盤であるという認識のもと,その環境を良好なまま,子孫へと手渡していくことを目指して行われなければならない。―に掲げられている通り、このまま放置すれば汚点を残す事になりかねません。
無論、話し合いにも応じず現地確認さえ拒否する宅地開発販売業者には裁判で正否を決める事もやむなしと思っていますが、岡山市は現在当地区環境の担当行政として、また当団地の2期3期住宅地開発行為許可権者として、当団地の開発における最初に宅地埋め立て造成の許可を出した岡山県と共に、当然土壌調査を実施し専門的見地から今後この様な被害は無いのかを明らかにする社会的責任があると考えます。
市窓口の環境保全課に相談を重ねましたが、当課は市が土壌調査をすべき法律がないとの理由で要望が受け入れられません。
今回、愛知県が宅地造成した小牧市桃花台ニュータウンで土壌汚染が発覚し、小牧市も土壌調査を実施した事を知り、当課に要望したところ視察を実施されましたが岡山市では土壌調査は実施しないとの回答です。その理由は、愛知県が宅地造成の土地を買収する前に小牧市が測量等、関与しているので土壌調査を実施しているが、岡山市は土地に関与してない為との説明です。
しかし、岡山市は小鳥が丘団地2期3期住宅地開発行為許可権者です。関与の重みから言えば小牧市以上だと思いますし、たとえ小牧市が土壌調査を実施しなくても岡山市が土壌調査を実施しても何の不思議も無いと思いますので再考して頂きたく存じます。
小牧市を視察してなお土壌調査を実施しないと回答された環境保全課に、これ以上要望しても希望が持てないと判断し、今回直接市長殿に要望書を提出いたしました。
そこで次の事柄を岡山市に要望致します。
(1) 当団地の土壌汚染の実態を把握する為、市主導で、私達の信頼出来る環境省指定の民間調査機関と共に徹底した土壌調査をお願い致します。
(2) 前記の調査方法・調査内容を、広く公開する事を要望します。
(3) 調査をするに当り、事前に地元住民や周辺住民の意見を聞く場を設け、様々な意見交換をして頂きたいと思います。
(4) その調査結果に基づいて、環境の保全対策を検討して頂きたいと思います。
(5)
一部省略
(エ) 小鳥が丘団地の土壌調査は実施しないとする環境保全課の考え方
上記要望に対して平成19年2月6日までに標記当協議会代表に文書にてご回答をお願いします。
私たちが居住する「小鳥が丘団地」は、土壌汚染が発覚してから、現在に至るまでも相当の悪臭や地中から発生するガスによる健康被害に怯え、開発当時設置した水道管(鉛管)が腐食した事に因る交換工事も全住民が要望した工事がされず、一部中断したままで、安心して水道水も利用出来ない状況にあります。
また、平成16年に行なった部分的な地下ボーリング調査結果から環境規準値を超える有害物質が検出されていますが、この分布状況や質量によっては周辺の汚染拡大も十分考えられ懸念しています。
私たちは、過去の経歴の中で、汚染原因者と思われる旭油化工業が京阪神地方から搬入し不法投棄した廃油等が何らの分析も行われていない事から、ダイオキシン・PCBを含む相当な有害物質が、当団地の地下や河川に不法投棄されている可能性があるものと考えています。
市長に於かれましては、私達の窮状・惨状を御理解頂くと伴に、今後全国的な大問題になるであろう土壌汚染問題に、しかも住民が生活を営む団地の足下に有害物質が有るという環境に、行政として岡山県と共に全国に先駆けて如何に解決に導くかの先導的役割を担って頂きたく、市の過去の道義的・社会的責任において、本要望に対し、前向きに検討して頂きたいと熱望いたします。 以上
1/24
住民が 石井 正弘岡山県知事に要望書を提出する
1/18
岡山市環境保全課による小牧市視察が実施された
不詳 不詳 宅地開発業者(現、両備ホールディングス)の不動産部総務部長の富田氏が
住民に対して 「だまされたのは住人の責任」 と発言する。
2006年 平成18年
12/28
岡山市環境保全課,金安審議官らが住民宅で、事情聴取する
12/8
株式会社金曜日が土壌汚染と被害の実態を報道
12/7
法務省刑事局から回答書
12/1
環境省から回答書が住民に送付
11月
住民、宅建法違反で両備を告訴するが、時効を理由に不受理
11/24
住民が長勢甚遠法務大臣に質問状を送付
11/24
住民が“宅地建物取引業免許の適性について(両備バスの行政指導について)”の申立書を岡山県建築指導課に提出する
11/17
住民が環境大臣に質問状を送付する送付する
11/16
岡山県建築指導課は「 “この書類の中の、両備バスが用地買収した時の裁判記録を見ると、
汚染土壌と分かっているにもかかわらず、売買契約の時に何故購入者に説明しなかったのかを
両備バスに聞きたいと思うので、申立書を提出して下さい。”」と住民に説明する
11/15
国土交通省が「 “書類を見る限りでは、有害物質の除去を含めて、権利・義務の全てを、両備バスが引 き継いだ事になります。”」「 “汚染原因者と同じ立場になります。”」と住民電話連絡する
11/14
住民が環境保全課に対し、愛知県小牧市桃花台ニュータウンの事例を話し、小牧市も土壌調査を行った例を伝え、事例研究として現地視察を要請し、岡山市秘書広報室長にも再度要請し、小牧市視察が決定された。
11/1
住民、宅建法違反で両備を告訴するが、時効を理由に不受理
11/10
住民が、冬柴 鐵三 国土交通大臣に質問状を送る
10/30
両備バス代理人 菊地弁護士ほか計6名の弁護士連名で「ご連絡」書面
両備バス代理人、菊地弁護士ほか計6名の弁護士連名により
“ご連絡”、
平成18年10月30日付
○○ 個人あて、
? 少?職らは、両備バス株式会社の顧問弁護士を務める者で、あなたの申入書を拝見しました。この件に関しましては、当初より、当職らが両備バス株式会社の代理人として関与しておりますので、あなたの申入書に対して、当職らから回答をさせていただきます。
? これまで、この件に関しましては、小鳥が丘環境対策委員会(住民有志で構成する委員会)との間で種々交渉がなされ、両備バス株式会社の考え方につきましては、すでに委員会におつたえしている通りです。
? 今般、あなたが小鳥が丘団地救済協議会代表の肩書きで書面を送られてきておりますが、両備バス株式会社としましては、この件に関し複数の団体から申入れがあることに大変困惑しております。
? もしあなたが、団地の方々全員を代理する者であればお話を聞く事にやぶさかではありませんが、そうでなければ、今回の申入書はあなた個人のご意見として承っておきます。
10/27
岡山市環境保全課は“南古都?環境対策検討委員会は、両備バスの委員会であり、意見書は両備バス意見書だから両備バスが代読したものと考える”と回答する。
10月
岡山市、団地の土壌は、汚染指定区域と同等の方法で行うことを指示
10/17
住民側が両備バスに申し入れ書を送る
平成18年10月17日
岡山市錦町7番23号
両備バス株式会社代表取締役社長 小嶋 光信 様
小鳥が丘団地救済協議会 代 表 ○○○○
申し入れ書
私たち、小鳥が丘団地救済協議会は、御社が造成・販売した小鳥が丘団地で明らかになった土壌汚染問題の解決のため団地住民の有志で組織した団体です。なお、以前に御社が交渉をもっていた小鳥が丘環境対策委員会とはべつの団体です。
当協議会は、小鳥が丘の土壌汚染問題について、御社が平成17年7月に小鳥が丘団地住民に対して提出した、条件付き提案には承諾できません。
この提案は、御社と話し合いをもつための条件として、この土壌汚染の法的責任が御社にないことを確認しなければならない一方で、土壌汚染への対策実施についての保証すらありません。
これでは御社は話し合いだけして、何もしないでよいことにすらなりかねず、当協議会としてはとうてい容認できません。
しかしながら、当団地の土壌汚染問題は、発生する有毒ガスによる健康被害や地盤沈下といった被害を引き起こしていることも考えられ、そこで生活する私たち住民にとってきわめて重大です。 そうした汚染がある土地を造成し、住民には知らせずに販売した御社には当然ながら責任があるはずです。
よって当協議会は御社との話し合いおよび当協議会の合意の上での解決策の実施を求めます。
上記の申し入れに対して、平成18年10月27日までに下記の当協議会代表に文書にてご回答願います。
岡山市南古都××× 小鳥が丘団地救済協議会
10/13
住民、庭の土壌移動時にガスを吸引して倒れる
10/9
週刊金曜日ジャーナリスト井部正之氏と桃花台ニュータウンの丸山氏・木下氏が、現地視察する
8/31
環境省中四国地方環境事務所から電話連絡が入り「検討したが難しい」との事。
住民から
「土壌汚染対策法は、工場跡地等の土壌汚染から人間の健康被害を防止する法律でしょう。今現在、自宅庭から有害物質が出ていて健康が冒されているんですよ。」との質問に対し、環境省中四国地方環境事務所は「無言」
7/26
「岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結について」
(両備グループ代表 小嶋 光信) 写真:千葉学長(左)と小嶋代表
「・・・地域産業にいかに貢献するかが大学の使命であり、またそうしなければ企業からの献金を増やすことが出来ず、大学は経営難になるなど、地域の発展が即大学の経営に反映してくるのです。」
7/13
住民が環境省中四国地方環境事務所へ事情説明と今後の相談に行く。環境省の担当者は、「裁判するしかないだろう。こちらで調査をするのは難しい」との事。
7/5
小鳥が丘救済協議会がホームページを開設する
6/24
廃棄物処分場問題全国ネットワーク事務局長 が岩野氏宅の庭を訪れた
6/20
午後15時30分に友實課長と環境規制課の職員1名が岩野宅庭を視察に訪れる。手にはリトマス試験紙があった。住民がが質問する。「調査はしてもらえないんですね。?」
課長:「するかしないかは、これから検討していきます。」と言葉を濁した。
6/20
市の秘書広報室秘書課の 友實 課長を訪ね、環境規制課の件について相談する。市の秘書広報室秘書課の 友實 課長「今の段階では調査不足なので対応できない。此方で話を聞き調査をするので告訴は待ってほしい」
この頃 住民が西大寺署生活安全課で、事情を説明し被害届の手続きを希望すると「時効の問題もあるし、調査が不十分で内容も把握できない理由で、被害届の受け取りを拒否」
6/12
住民が市長へ面会求めるが面会を拒否される。
6/8
読売新聞社会面で今回の事が掲載される
午前中に読売新聞の記者「坊」氏が、岩野氏宅を取材に訪れ、庭先へ案内する。坊氏は慣れてない為か、特にせきが酷く気の毒であった。
6/7
小鳥が丘救済協議会の岩野氏、藤原氏と住民の方が3人で、西大寺署へ刑事告訴についての相談に行く。
生活安全課は最後に、「地元の警察署で相談して、それでも対応に納得いかないのであれば、県民相談課へ相談しにきなさい。」と言ってくれた。
6/7
岡山市の金安部長が両備バス?に連絡を入れると、「弁護士に任せているので、そちらに連絡してくれ。」との事
6/5
警官が 「このままでは危険なので、立ち入り禁止にし、埋め戻すかシートをかけなさい。水と反応すると亜硫酸ガスがでる。」と指導する。警官は、警察での土壌の分析を行うとの事で、ビニール袋に試料を入れ持ち返る。
6/5
岡山市の環境規制課 金安部長が駆けつけたので、両備バス?へ連絡を受ける。
6/5
岩野氏宅の倉庫工事の為、庭先の土壌を業者が掘削したところ、15〜40cm程度から下に真っ黒な刺激臭のする土壌の層が出てきた。西大寺警察、開発許可をだした市に連絡する。
小鳥が丘団地救済協議会 HPより
5/2
独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター医師が 湿疹 鼻炎と有害物質の関係について診断書 を発行
4/1
両備バスと両備運輸が対等合併して両備ホールディングスが発足する。
3/26
住民が表町商店街、岡山市表町(天満屋)百貨店前で署名活動
3/26
小笠原賢二が表町商店街の天満屋前で住民有志の皆様の活動に参加し、応援演説する
3/23
住民が岡山県庁前で署名活動を行う
3/17
3/10
3/5
住民が表町商店街、岡山市表町(天満屋)百貨店前で署名活動
2/14
岡山市水道事業管理者 植松健氏が、
「廃油処理工場跡地を造成するとの申し出があったので、ポリエチレン管は変質するので、鉛管を使用した」との返答
1/23
住民が岡山県議会議員会館を訪問し岡山県議会議員55名に土壌汚染問題請願書を提出する
2/13
岡山県より県庁にて口頭回答あり。(H18年1月16日提出の要望書の回答)
質問:土壌汚染調査等要望書について。
回答:(産業廃棄物対策課)岡山市内における環境問題は岡山市が行政権を持っており、県は動くべきでない。
質問;宅地開発許可について (回答者:建築指導課)
Q1,公害企業として何度も行政指導をしても廃油の垂れ流しを改善されなかった旭油化工場跡地を、昭和62年当時、宅地として許可した理由は?
A1,都市計画法に沿い技術基準(住宅に耐える土壌の強度があるか)に合っていれば良く、他の問題(有害物質等)は対象外であり、宅地開発許可は合法である。
質問;砂川河川敷地と両備所有団地敷地交換の経緯について。(回答者:河川課)
Q1,汚染が激しいと想定される国有河川敷地を懸念なく民間の両備に交換譲渡したのか?また公文書開示請求により2005年(H17年)11月8日に開示された「一級河川旭川水系砂川の河川敷地の公用廃止(昭和63年12月9日付け岡山県告示第973号)の起案文書」に掲載されている両備の行った「河川法20条の河川工事」とは何の工事か?
A1,「河川法20条の工事」の別紙内訳書は書類保管期限切れのため、処分したので内容は分からない。この程度の案件では調査するつもりは無い。
1/16
住民が署名3382名分を添えて要望書を、岡山県に提出しました。
2005年 平成17年
11/20
住民が沢田の柿祭り、岡山市沢田の百間川で署名活動
11/12
住民が東岡山駅で署名活動を行う
11/5
11月 雨が降った翌日、住宅の玄関ポーチと道路の境にコンクリートの割れ目から“ブツブツ”とアワが出て、火をつけると、“サーァー”と青白い炎が走る。西大寺消防署から隊員が可燃性ガスが出ている事を確認
10/28
岡山県産業廃棄物対策課(現・循環型社会推進課)が住民に対して2005年10月20日の質問に対して一部を回答する。
回答1:旭油化撤退後(1983年)に廃棄物撤去確認調査は「目視にて現状を確認したが、搬出物内容は確認してない。」
回答2:「宅地開発許可に当た開発課からの問合せ確認があったかどうかは聞いていない。」 岡山県 循環型社会推進課
産業廃棄物班 086-226-7308 FAX番号:086-224-2271 担当に問い合わせる
10/22・29
住民がスーパーマルナカ平島店及び東岡山駅で署名活動
10/20
住民側が岡山県産業廃棄物対策課(現・循環型社会推進課)に対し質問と要求を行う。
質問1:旭油化撤退後(1983年)に廃棄物撤去確認調査で有害物質の撤去を確認したのか?
質問2:宅地開発許可に当たり開発課から問い合わせ確認はなかったのか?
要求1:1983年(S58年)当時の県の実例集に記載された旭油化跡地撤去完了確認の内容開示を要求する。
「廃棄物処理法施行令」改正(埋立跡地における指定区域の指定)
10/8
高谷茂男後援会事務所から回答書が返送される
回答書です。
質問:公害企業の跡地で、土壌汚染が明らかな土地に対して、対策が不十分なまま開発許可を与えた岡山市の責任は?
答え;土壌汚染が明らかであるとの確証が得られる書面がありませんので、岡山市の責任問題についてコメントができません。
10/5
高谷茂男候補に質問書を提出する
10月
銀行から小鳥が丘団地の土地、建物は担保にならないと連絡が来る
9/25
住民が東岡山駅で署名活動
9/23
株式会社金曜日が土壌汚染と被害の実態を報道
9/18
住民がJR東岡山駅で署名活動
9/4
住民が小鳥の森フェスタ、岡山市上道公民館一帯で署名活動
7月
両備、住民との交渉継続の条件として、両備の法的責任なしの確認を含む3条件を住民に提示
6月
日本共産党 竹永みつえ岡山市議 が市議会で質問
? 委員会が現場を視察に訪れたことも住民の声を聞くこともなく解散した
3月
両備、MNA、土壌ガス吸引、水平ボーリングの3案の汚染対策案提示
3/24
岡協市第108号 ???文面は
3/29
第20回小鳥が丘環境対策委員会が(上道公民館)
主な内容は、南古都?環境対策委員会(岡山大学の教授などで構成)の意見書の説明でした。
しかし、委員会構成メンバーの参加はなく、説明は両備の担当者が「意見書」を読み上げて終わりました。
小鳥が丘の住民からは、質問状が文書で出されたほか、「子どもたちと土いじりができなくなった、安全な環境でなくなった」、「夫の病気により、実家に戻りたいが、土地と家の処分もできず、本当に困っている」などの意見が出されました。
どれも、回答は後日文書で行うとのことです。
環境対策委員会の顧問に就任した香川県議、石井亨さんから
「南古都?環境対策委員会への住民の参加を拒んだのは、委員会の委員なのか、それとも両備なのか」
との質問に対して、両備側が全く的はずれの回答をしたことは、参加されたみなさんの印象に強く残ったことでしょう。
また、リスクコミュニケーションが大切だと言いながら、この会に姿を見せなかった岡山市の態度は、問題があると思います。 ???左記の回答はどうなったのでしょうか???
3月28日
「環境対策検討委員会」が意見書
平成17年3月28日
意 見 書
南古都?環境対策検討委員会
委員長 千葉 喬三
先に行った電気探査において低比抵抗値を示した場所に存在する物質の化学的分析の結果について検討を加えた。また、本団地における調査は今回をもって完結したと考えられるので、これまでに行った調査結果をも参考にして、対策案を提案する。
1.土壌化学性状分析について
これまでに行われた土壌調査、土中ガス調査及び地下電気探査調査の各結果より、調査対象地内にパッチ状に特異な地層(団塊)の存在が推定されたことから、それら部分の性状を把握することを目的とした。
電気探査調査において低比抵抗値を示した部分の内の2ヶ所についてボーリングを実施し、採取した不攪乱試料(コアサンプル)について必要な化学的性状分析を実施した。その結果の詳細は、添付した環境保全事業団の報告書のとおりである。
2ヶ所のコアサンプルの含水量、含イオン濃度、ECの測定の結果、当該部分には通常の土壌には含有されない物質が存在することがわかった。
これは、先に実施された電気探査調査の結果と一致し、当該部分が何らかの人為的攪乱を受けていることは明らかとなった。電気探査調査における低い比抵抗値は、当該部分が電気を通しやすくなっていることを表しており、今回の調査のサンプルの含イオン濃度、ECの測定結果はそのことを裏付けている。
すなわち、当該部分になんらかの電解物質(たとえば食塩など)が相当量混入し(投棄され)、そのことにより比抵抗値が低下していると推測される。
また、サンプルの有機物含量(強熱減量値)が高く、これは何らかの有機物材料(たとえば石けん材料の油脂物質)が投棄混入されていることを推測させる。このような有機物は水の移動を抑制するため、含水率が高くなり、比抵抗値を下げる一因にもなっている可能性がある。
混入有機物は比較的深部に埋没されたかたちになっているので、嫌気的な微生物分解をうけつつ減量している過程にあるものと考えられる。
また、硫黄を含む物質は比較的地表に近いところに多く存在するので、硫黄臭に関しては有機物臭よりも短期間で消失することが期待できる。
2.居住環境の改善対策
以上の調査結果より、当委員会が提示する対策工の案は別紙のとおりである。工法の選定にあたっては、当該地が住宅団地であることを考慮し、住民の日々の生活を阻害しないことに重点を置いた。
対策の目的は、土中のガスを揮散させ、臭気の低減を図ることにより、住民の不快感ならびに不安感を解消することである。そのため、対策工は住民の大多数が不快感を抱かなくなるまで継続することが望ましい。
なお、当委員会はこの対策工の提案をもって役割を終えるが、工事の実施にあたって技術的な助言が必要であれば別途意見を申し述べることとする。
これまでの調査によって、現状の生活環境においては臭気による不快感はあるものの、健康への影響が直ちに懸念されるものではないことは、既に申しあげたとおりです。しかし、よりよい居住環境を現出するため、ここに提案しました対策工案を参考にされ、できるだけ早く改善対策を実施されることをお奨めします。 以上
2/17〜18
両備が団地内土壌化学性状調査を行う
2/25
松岡 利勝 主査質問
双方がより強い当事者意識というか責任意識の中でトラブル回避のために努力をするということに自然となっていくわけですから、そういう意味では、環境を整えていく、システムをつくっていくというのは、これはやはり国政の重要な役割なのかなという気がいたします。
竹中国務大臣 答弁
「御指摘の岡山市の事例については、私も承知をしております。これは大変重要な事案であるというふうに思っております。」と答弁
第162回国会 予算委員会第一分科会
2/20
中地氏意見書
1.はじめに
2.小鳥が丘団地の土壌汚染をどう考えるのか
・環境対策委員会の調査について
3.リスクコミュニケーションの欠如について
2/13
中地重晴氏現地視察
1/24
住民が岡山県建築指導課を訪ねる
1月
両備が住民宅を戸別訪問
1/7
江本匡氏『平成16年12月27日の意見書に対するが意見書に対して』と題して意見書を提出。意見書全体について
まず、人への健康影響がほとんどないことをいろいろな面からの調査方法を用いて説明する必要がある。
1.汚染状況
1-1 土地履歴調査
1-2 ボーリング調査
・地点が3点と少ないが
・地下水位は比較的浅い
・No1
・No2:深度1.4mよりトリクロロエチレン・ベンゼン(高濃度)・トルエン・キシレンが検出されている。
・No3:4.45〜5.8で金属片が発見されている。この部分でベンゼンが高い、
・No3:4.45〜5.8で同様の(トリクロロエチレン・トルエン・キシレン・油分等)の調査を行ってもらいたい。
1-3 表層土壌調査
・ベンゼン基準超過が9軒(内1軒は第二溶出量超過)、団地の中央部を中心にし北側にも4軒超過している。
・委員会意見書の「汚染は主として団地の南側部分に限られる」は整合しない
1-4 表層ガス調査
・調査地点を表層土壌調査で汚染物質が検出された場所に限定している??
・全地点でベンゼンが検出されている
・硫化水素やメタンが検出されている
・全軒の調査が必要
・各戸のメタンガスや有害物質の床下調査を全戸ですべき
1-5電気探査
・北半分では南北方向の電気探査が行われていない
1-6環境大気調査
1-7汚染箇所の推定について
・汚染範囲が団地外に広がっていないかどうかの確認が早急に必要
1-9 汚染物質
2.人の健康への影響について
3.今後の対応
<意見書>
・低比抵抗値を示す部分の化学分析
・硫化水素やメタン生成量及びモニタリング
<加えて>
・密度を高めたトルエン、キシレン等のガス調査
・深度方向調査
・ボーリング調査で発見された金属片
・床下ガス調査(夏場に実施)
・地下水観測
・亜硫酸ガス調査
・健康診断
2004年 平成16年
12/27
「南古都?環境対策検討委員会」が第二回意見書概要
1.汚染状況について
・今後浄化対策を明らかにするために化学分析を実施し、内容を特定する必要がある。
2.人の健康への影響について
・土壌ガス調査で、硫化水素やメタンが高濃度で検知された。
・当該地域は比較的地下水位が高くなりやすい。
・地表から浸透した有機汚染物質?!
・すみやかに、ガスの生成量や今後の生成可能量を把握するためのモニタリンクが必要である。
3.今後の対応
・今後、調査を行い、その結果をもとに調査を行う事となる。
・対応策は物理的、化学的、生物学的な手法を採用する
12月
両備が団地内土壌電気探査調査を行う
12月
両備不動産が土曜日に仮設の相談窓口を設ける
12月
両備が団地内土壌ガス調査及び環境大気調査を行う
10/30
下市(しもいち)このみがブログ掲載
10/13
山陽新聞社が報道
岡山市は県が撤去確認調査を実施していたと報告
10/30
「南古都?環境対策検討委員会」が第一回意見書を作成
10/23
住民説明会
10/17
住民が両備バス株式会社代表取締役社長小嶋 光信 に申し入れ書
10/15
両備が南古都?環境対策検討委員会に委任した 委員長 千葉喬三 岡山大学 副学長
委 員: 河原長美(岡山大学保健環境センター教授)、笹岡英司(岡山大学環境理工学部教授)、 西垣誠(岡山大学環境理工学部教授) 西村伸一(岡山大学保健環境センター助教授)、竹内文章(岡山大学保健環境センター助教授)、 山本秀樹(岡山大学医学部 講師)、オブザーバー:金安利和(岡山市環境保全部 部長)、中瀬克己(保健所 所長)
両備バス(株) 南古都?土壌汚染対策案について (抜粋)
今の調査をもとに、さらにこの詳細調査・研究及び問題点の解決方法についての見当を千葉喬三先生に依頼して、委員会を設立して頂き、その指導、ご提言を賜りながら対処することと致しましたので、お知らせいたします。・・今回の地域問題について産・官・学が連携して取組む体制になっております。
・・この、資料の問い合わせは両備グループ広報室山木までお願いします。
委員会は非公開で、住民は傍聴すらできず、議事録の閲覧すら拒否された。
山陽新聞報道
10/4〜6
両備が団地内34ヵ所で表土調査、環境基準を超えてベンゼン等を検出
10/5
朝日新聞社が報道する
10/1
9/30
山陽新聞社が報道
「廃棄物処理法施行令」改正(指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の指定、旧処分場、ミニ処分場等廃棄物処理に関する基準の強化・明確化等)
9/28
土壌汚染調査報告:ボーリング調査3地点、環境基準値の約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、
6倍のシスー1,2−ジクロロエチレンが検出された。
地下約5メートル付近では金属片やボロ切れなどが発見されたことを岡山市の出席のもとに公表する
9/6〜11
両備の実施した市道部分の3ヵ所ボーリング調査で環境基準を超えるトリクロロエチレン等を検出
8月
岡山市が健康相談を実施、
65人中42人が皮膚炎(15人)、鼻炎(12人)、頭痛(11人)等を訴える
8/26
岡山市が表層ガス調査(ベンゼン等、全3項目)を実施する
8/16
第一回住民説明会開催
8月
岡山市が団地周辺の井戸、川で水質検査実施
8/12
岡山市が土壌溶出量調査(カドミウム等、全25項目)を実施する
7月
岡山市の調査で地下水と土壌から硫酸イオンが検出された
7/29
岡山市が地下水調査(カドミウム等、全21項目)を実施し、住民に報告する
7/29
岡山市水道局の鉛製給水管解消事業に伴う上水道鉛管取替工事始まる
右の写真は、油性の黒い液体が湧き出し、ポンプで排水している状況
この頃 小嶋光信(両備バス元会長の故松田基の娘婿)が 岡山大学理事に就任。
2/27
厚生労働省健康局が、「室内空気質健康影響研究会報告書:〜シックハウス症候群に関する医学的知見の整理〜」を公表する
(研究会のメンバー:岡山大学大学院医歯学総合研究科岩月啓教授)
2003年 平成15年
2/15
土壌汚染対策法 施行
「産廃特措法」公布(平成10 年6月以前に不適正処分された産業廃棄物の支障の除去のための財政支援)
2000年 平成12年 12月 児島湾(乙)阿津沖のメナダ(ボラの一種)に含まれるダイオキシン類が16pg-TEQ/gと高い値であったを環境白書で公表
(国)ダイオキシン類対策特別措置法施行
「廃棄物処理法」改正 不適正処分の現状回復措置命令
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部改正
1996年 平成8年
(国)水質汚濁防止法に地下水の浄化措置及び油に係る事故等の措置が追加される
(県)岡山県公害防止条例(水質関係)の地下浸透を禁止する物質にPCB など16物質が追加される
1995年 平成7年
「廃棄物処理法」改正不法投棄に対する罰則の大幅強化
1992年 平成4年
9/18 廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について 公布
1991年 平成3年
「廃棄物処理法」改正罰則の強化 廃棄物処理業者、廃棄物処理施設の規制強化
1989年 平成元年
(国)「水質汚濁防止法」に地下浸透規制を追加
1987年 昭和62年
両備、小鳥が丘団地分譲開始 ? 上水道鉛管埋設工事
10/1
松本一岡山市長が両備バス(代表取締役 松田基)に開発行為許可 工事施工者 (株)東山工務店(代表取締役 荒木貞次)
2/23
長岡士郎岡山県知事が両備バス(代表取締役 松田基)に開発行為許可 工事施工者 (株)東山工務店(代表取締役 荒木冨美子)
1984年 昭和59年
8/22
トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針公布
2/23
岡山県環境保健部長から吉井町長宛て報告書で、環境保全措置のおおむね完了と、水質汚染拡散監視の為の水質定期検査の終了を連絡する。(吉井町公害対策特別委員会議事録より)
1983年 昭和58年
6月
吉井町・管財人・岡山県環境衛生課の3者で協議し、公害処理作業完了。
4月
吉井町が石灰散布を実施
2月
吉井町が瑞穂産業?工場内の汚染土石類の搬出
1月
吉井町が瑞穂産業?跡地投棄油の回収等を行い1月末までに回収
吉井町が瑞穂産業?を操業停止・撤退させる。この頃、吉井町は当地旭油化工業?跡地を現地視察する。
岡山県が廃棄物処理法に基づく廃棄物処理廃止時における汚泥の撤去の確認調査を実施
1982年 昭和57年
11月
旭油化工業(代表者小寺正志)は近郊の赤磐郡吉井町(現あかいわ市)に瑞穂産業?と変え工場を設置し、同様の廃油処理業務を始める。瑞穂産業?が吉井町草生地区で三和開発の看板を掲げて操業開始する。
10月
旭油化工業の設備解体開始 旭油化が行政指導を受ける
7/27
岡山簡易裁判所において、当時の開発業者、両備バス?松田 基代表取締役と旭油化工業?小寺 正志 代表取締役とが和解、両備バスが旭油化工業の土地7,891m2を購入する
6/14
岡山県が旭油化工業に対して廃掃法に基づく汚泥除去の処理命令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について (各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
(土地造成)
問19 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり、この者は「自ら利用」するのであるから法が適用されないと主張するが、廃棄物の埋立処分であり法が適用されると解してよいか。
答 お見込みのとおり。なお、次の点に留意されたい。「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しない。また、土地造成は廃棄物・有価物たるとを問わず固形状、でい状であれば可能であるが、廃棄物による土地造成は埋立処分に該当する。
5月
岡山市が旭油化工業に対して悪臭防止法に基づく改善勧告
1981年 昭和56年
5月
旭油化工業が、産業廃棄物処理業の廃止届け
両備、小鳥の森団地分譲開始
当時の県や市も何度か旭油化に行政指導を行い、立会い検査を行っています。その調査によると、工場の門を入ると既に敷地一体が黒い沼のようにドロドロとしており、長靴で入っても足のすね当たりまで埋まるような状況だったそうです。
1980年 昭和55年
岡山市が鉛製給水管の使用を通常は中止する
1978年 昭和53年 -
県市が行政指導 苦情多発 小鳥の森団地分譲中
1977年 昭和52年
県が、産業廃棄物処理基本計画を策定
「廃棄物処理法施行令」改正、「共同命令」公布(最終処分場の3類型(安定型・管理型・遮断型)の導入、燃えがら,ばいじんの規制)「廃棄物処理施設構造指針」
3/15
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
(52年3月15日施行)
1976年 昭和51年
「廃棄物処理法」「廃棄物処理施設整備緊急措置法」改正
(処理施設の届け出義務、廃棄物の最終処分場に関する構造基準及び維持管理基準)
不法投棄、不適正処理が後を絶たず、廃棄物中の有害物による環境汚染防止の枠組みを定めた産業廃棄物が埋められている土地の売買廃棄物の最終処分場が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって位置づけられたのは1976年の同法改正によってです。
1976年改正以前であれば、『この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による』とされているため、遡及しません。
岡山県産業廃棄物対策懇談会が発足
1975年 昭和50年 -
産業廃棄物処理規制の強化等を内容とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正(50年6月16日公布)
県市が行政指導 小鳥の森団地分譲開始
1975年 昭和50年 -
県市が行政指導
10/5
住居地域指定
「廃棄物処理法施行令」改正
(PCB・有機塩素化合物を含む廃棄物の処分基準、廃酸・廃アルカリの海洋投入処分基準の設定)
1974年 昭和49年
市が「水質汚濁防止法」の政令市となる
1973年 昭和48年 -
県が行政指導 悪臭被害出始まる 市が主要工場等と公害防止協定締結開始
瀬戸内海環境保全特別措置法
「廃棄物処理法施行令」改正(有害な産業廃棄物の判定基準の設定(「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」))
1972年 昭和47年
岡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行旭油化が行政指導を受ける
事業者の責任を強化して被害者の円滑な救済を図るため、民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法および水質汚濁防止法で無過失責任制度導入された。伝統的な不法行為理論を修正し、無過失賠償責任論に基づく原則が採用された。
1971年 昭和46年
水質汚濁防止法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃掃令 廃掃則 上道町合併
岡山県公害防止条例を改正 岡山県環境部に公害苦情処理局を設置
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】公布
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 施行
1970年 昭和45年
市 衛生局に公害課設置 岡山市公害対策本部設置
「廃棄物処理法」公布(昭和46 年9月施行)
(生活環境の保全を目的化、産業廃棄物と一般廃棄物の区別、産業廃棄物の処理責任の明確化、有害な産業廃棄物などの処理処分の技術的基準の設定)
1969年 昭和44年
1968年 昭和43年
1967年 昭和42年 - (国)「公害対策基本法」施行 旭油化が土地を購入
1966年 昭和41年 「岡山市公害防止条例」制定、公害審議会設置
1965年 昭和40年
1964年 昭和39年
1963年 昭和38年 生活環境施設整備緊急措置法公布
1962年 昭和37年 衛生部保健衛生課に公害係設置
1961年 昭和36年 岡山市公害対策審議会設置
宅地造成等規制法 宅地造成等規制法施行規則 宅地造成等規制法施行令
1960年 昭和35年 岡山県公害対策調査会を設置
明治33年 法律第31号 汚物掃除法 第六条 常時吏員ハ掃除ノ實況ヲ監視シ必要ナル事項ヲ施行スル為其ノ事由ヲ告知シテ私人ノ土地ニ立入ルコトヲ得
リンク(工事中)
小鳥が丘団地救済協議会
小鳥が丘救済協議会の掲示板
小鳥が丘団地救済協議会のブログ
小鳥が丘団地で土壌汚染!(小笠原賢二)
竹永みつえblog 小鳥が丘団地土壌汚染問題
若井たつこ活動日記: 2007年10月
地域・いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!
環境ニュース -ENVIROASIA いまだかつてない分譲住宅地の土緒・・?I
産廃に沈む住宅地週刊プレイボーイに加筆
岡山地方気象台
(岡山県HP)シックハウス症候群の主な症状について
シックハウス症候群は、さまざまな症状が現れます。
そして、その症状は、個人差が大きく、診断を難しくしています。
住まい(住宅)が、住んでいる私たちを病気にしてしまうことがあります。
この病気は、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
下記HPでは、あなたの住まいを「シックハウス症候群」から防ぐための原因と対策等について説明しています。
シックハウス対策
● 第1章 土壌汚染とリスクコミュニケーション
● 第2章 土壌汚染に関するリスクコミュニケーションの進め方
● 第3章 住民説明会の開催について
● 第4章 参考事例
● 資料編
自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン(案)について
油汚染対策ガイドライン
土壌汚染対策に対する助成制度について
助成金交付スキームについて 【参考例:都道府県又は政令市の助成率が3/4のケース】
揮発性有機化合物による地下水汚染対策に関するパンフレット「地下水をきれいにするために」
宅地造成等規制法の概要
宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)
我が家の擁壁チェックシート(案)
ふくらみ
リスクコミュニケーターは企業の顧問弁護士では無理があると思います。
企業の顧問弁護士に任すと益々問題が難しくなると思います。
日弁連 - 弁護士職務基本規程
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
第一章基本倫理
(使命の自覚)
第一条弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
(信義誠実)
第五条弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(違法行為の助長)
(依頼の勧誘等)
第十条弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。
第十四条弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(非弁護士との提携)
第十一条弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(不利益事項の説明)
第三十二条弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければならない。
懲戒制度の概要
弁護士法
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
南古都?環境対策検討委員会の委員が、意見書を発表する場に姿を見せなかったことは、分かるような気がします。
最後までご覧下さいましてありがとうございました。
不適切な記載や追記事項等のご意見がありましたら↓のコメント欄に記載下さいますようお願いします。
http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/38388679.html
多くの皆様のデーターを利用させて頂き誠にありがとうございました。
産廃に沈む住宅地 より
団地脇の川には謎の黒い油が流出している ある家の庭に開けられた調査用の穴。油膜が張り、ガスがブクブク湧いていた
「空中写真閲覧サービス(試験公開)」より 昭和55年
http://beauty.geocities.jp/oecacasa/kotorigaokanorekisi.htm
〜リスクコミュニケーション〜
おおさかATCグリーンエコプラザで
「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」と題する講演が
平成21年12月18日(金) 14:00 〜 17:20
にあります。
地下水上昇・護岸擁壁の黒い液体の浸み出しやふくらみ・皮膚炎・鼻炎・頭痛・トリクロロエチレン・ベンゼン・食塩など混入?・
地表から浸透した有機汚染物質?地下水の上昇・擁壁のはらみ出し
不適切な記載や、事実と異なる表現、追記事項等のご意見がありましたら↓のコメント欄に記載下さいますようお願いします。
http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/38388679.html
西暦 元号 月日 行政 両備 住民等
2009年 22年 12/18
ATCセミナー 土壌汚染の社会問題で講演 〜豊洲・桃花台・小鳥が丘の事例〜
各地で市民が行政や大企業等を相手にした土壌汚染係争案件が多発しています。たとえば、岡山市小鳥が丘団地住民の開発業者である両備を相手にした油工場跡地の裁判や、小牧市桃花台における地盤沈下や土壌・地下水汚染について愛知県や都市再生機構との公害調停や民事裁判さらに、東京都江東区豊洲の埋立地におけるガス製造工場跡地の土壌汚染調査データ公開遅れが問題にされ、採取した調査試料を廃棄しようとする東京都に対し市民が提訴しています。
今回はこれらの問題に大変詳しい講師を招きし、土壌汚染対策法の改正を控え今後の土壌・地下水汚染や廃棄物問題を考える良い機会にしたくご案内いたします。
開催日時
平成21年12月18日(金) 14:00 〜 17:20
プログラム
講演1:「東京都豊洲地区の土壌汚染」〜実態と問題点〜
講師:日本環境学会 土壌汚染ワーキンググループ長 坂巻 幸雄 氏
講演2:「豊洲の土壌汚染の実態について」
講 師:NPO法人 「市場を考える会」総務・環境問題理事 野末 誠 氏
講演3:「(仮題)桃花台の地盤沈下と土壌・地下水汚染問題について」
講 師:桃花台地盤沈下問題を考える会 代表 丸山 直希 氏
講演4:「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」
講 師:小鳥が丘団地救済協議会 藤原 康 氏 岩野 敏幸 氏
総合質疑応答
主 催
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会
受講料
1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)
会 場
おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ
定 員
100名(先着順 ※受付確認はセミナー開催約10日前迄にFAXまたはE-mailでお送りします。)
お申し込み
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp
12/8
岡山地方裁判所13時30分〜16時30分
10/20
岡山地方裁判所353号法廷で第13回口頭弁論準備手続きが行われ、原告住民3名の陳述書を裁判所に提出した。
裁判長は住民訴訟第二次(18世帯)は、現在、(不動産)鑑定準備中ですと述べた。
住民訴訟第二次(18世帯)は、前回原告住民が土壌改良の為の土壌調査を求めて学者の土壌調査方法等の資料を提出しましたが、調査費用の見積もりが高額になり(約7千万円)とても負担しきれない事が判明したので、調査範囲を絞り込むなどして再度調査方法を検討し費用7百万円を見積もり、原告住民と被告両備ホールディングスで折半負担を提案しました。
裁判所も被告両備に鑑定費用を半分持てという勧告を出しましたが両備側は固辞したようです。
7/9
調査分析報告書が送られてきて、護岸の付着物もはっきりと油分が検出されていた。いずれも汚染の程度は著しいものとなっていたので早速、調査報告書は証拠として裁判所に提出した。
6/13
住民訴訟第一次(3世帯)は環境総合研究所に現地地質調査分析を依頼し、職員を現地に派遣してもらい住民による調査サンプル採取を行った。(モニター井戸水質3か所、原告敷地駐車場土壌1か所、沼川護岸擁護壁付着物1か所、合計5か所)
2008年
11/17
第9回口頭弁論準備手続き岡山地方裁判所で(非公開)。
7/9
第7回口頭弁論準備手続き。住宅地としてはその目的を達することのできない欠陥住宅地であるとの準備書面と5月30日現地視察の録画DVDを裁判所に提出。
裁判所としては複数の公平な学者の意見を参考にしたいので、その前提として被告両備ホールディングスが主張し証拠資料とした「意見書」を答申した両備バス設立の「南古都?環境対策検討委員会」の会議録原本を提出することを打診。被告両備ホールディングス株式会社は、会議録は持っていないし提出すべき文書ではないと拒否。
6/9
環境goo「小鳥が丘団地土壌汚染で強い臭気を確認――岡山地裁が現地視察」掲載
6/6.7
赤旗に「岡山・小鳥が丘団地 汚染訴訟 〜立ち上がる住民〜」が掲載される
6/4
環境新聞 「小鳥が丘団地 強い臭気と黒い土確認 岡山地裁 現地視察 数カ所で廃棄物も」報道
5/31
毎日新聞現地調査を報道
5/30
裁判所による「小鳥が丘団地」現地検証土壌汚染問題裁判・公開調査 。
13時30分から裁判所による「小鳥が丘団地」土壌汚染現場検証が行われました。裁判官、原告住民および弁護士や学者、被告弁護士が、多くのマスコミや関係者の見守るなか、小鳥が丘団地内を見て回りました。各家庭の庭や駐車場を住民が削岩機で3箇所、ユンボで2箇所を掘削しましたが、どこの庭や駐車場も少し掘れば真黒い土と頭が痛くなるような刺激臭がありました。 あと地盤沈下で下がった塀や、油や石灰と思われる液体が滲み出ている擁癖や、玄関前側溝から可燃性ガス(2005年11月に地元消防署が確認)の泡が吹き出している箇所を住民が説明し15時30分頃終了しました。
5/22
参議院環境委員会「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」審議で「小鳥が丘団地土壌汚染問題」が取り上げられる
5/19
(3世帯裁判)第6回口頭弁論準備手続き(非公開)がに岡山地方裁判所であります。
4/22
(18世帯裁判)第2回口頭弁論準備手続き(非公開)が岡山地方裁判所であります。
4/9
環境新聞 土壌汚染現場の最前線 5 小鳥が丘からの手紙編? 開発業者の認識がポイント 予見困難と請求却下した判例も
4/4
(3世帯裁判) 第5回口頭弁論
3/26
環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 4 小鳥が丘からの手紙編? 救済に至らない土対法の現状 横たわる費用負担問題 揮発系リスクでも提起
3/19
環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 3 小鳥が丘からの手紙編? 健康リスク以外にも波及 現行の制度では解消難しい問題
3/12
環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 2 小鳥が丘からの手紙編? 原因者不在が混乱の要因 急がれる健康被害と汚染の関係解明
3/11
(3世帯裁判)第4回口頭弁論
3/6
若井たつこ市会議員、岡山市議会にて「小鳥が丘団地の土壌汚染に関して、固定資産税の減免措置について」個人質問
3/5
環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 1 小鳥が丘からの手紙編? 打開の道見えぬまま3年半 汚染原因者不在のまま住民と開発業者で民訴
3/4
18世帯裁判 初回口頭弁論
3/6
若井たつこ市会議員、岡山市議会にて小鳥が丘団地の、固定資産税の減免措置について質問する
1/29
(3世帯裁判)第3回口頭弁論(岡山地裁)
1/22
毎日新聞掲載 土壌汚染・岡山の団地、資産価値ゼロ
2007年
12/28
毎日新聞掲載 提訴:宅地の土壌汚染で住民らが−−岡山・小鳥が丘団地
12/27
住民18世帯が「両備ホールディングス」を相手取り、賠償を求めて岡山地裁に提訴する
12/11
(3世帯裁判)第2回口頭弁論(岡山地裁)
11/13
(3世帯裁判)第1回口頭弁論(岡山地裁)
10/28
フォーラム開催 後援:環瀬戸内海会議 同窓会 日本共産党岡山市議 竹永みつえ参加 「小鳥が丘団地で何が起きた!」
岡山市立上道公民館
日本環境学会会長 大阪市大 畑明郎 教授 が 講演
10/28
午前 見学者が現場を確認する
道路の観測井戸 宅地の観測井戸
地下水位:地盤高−約20cm 井戸の直径:約12cm程度
ガスが湧き、引火した玄関
油がにじみ出し、はらみ出しているブロック積み擁壁(はらみ出し場所と油のにじみ出る場所が一致している)
10月
おおさかATCグリーンエコプラザで土壌地下水汚染について討議される
京都地方裁判所において、排水路改良工事において,市が不適切な工法を選択したことにより,建物の損傷が拡大したとして,市に適切な工法選択義務違反の過失を認め,業者と市に共同不法行為が成立するとした事例 (損害賠償請求事件 判例)
8/31
自治体は「民間の問題なので調査する法律がない」と言う。もはや民事訴訟しかないと思い団地住民に呼びかたが、裁判となると決断が難しく、まず3名が先兵との思いでに両備ホールディングス?(旧両備バス?)を岡山地裁に提訴した。
「ネット街宣」に「両備バス(現、両備ホールディングス)小嶋社長の責任を問う?」*問題解決は急務*と掲載される
8/23
おおさかATCグリーンエコプラザでOAPや東京豊洲の土壌汚染問題等についてのセミナーが開催され、
大阪市大 畑明郎教授(日本環境学会理事長)や楡井久(NPO法人日本地質汚染審査機構)理事長が講演する。
小鳥が丘団地救済協議会が参加する
8/13
両備が調査用に開けた穴。猛烈に臭い。 ある家の庭に開けられた調査用の穴。油膜が張り、ガスがブクブク湧いていた
週刊プレイボーイに「産廃に沈む住宅地」掲載される。
7/28
両備ホールディングス株式会社代理人 弁護士:菊池捷男、首藤和司、財津 唯行、安達祐一、井田千津子から回答書
7/13
住民代理人弁護士:河田英正、大本崇が通知・催告書出す
7/3
18時40分頃、また住民民家でガス漏れ警報器が鳴る
7/10
住民、公害調停を申請
6/25
住民が西大寺支所建設課に空洞化の確認を要請すると。
「・・・近くを通る時はチェックしている。県民局職員は水の流れる音は聞いてないとの事(矛盾)。現時点では心配ない。継続的に監視する。」
との西大寺支所建設課からの返答がある。
この頃 住民による土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の
溶出量値が土壌溶出基準を超えていた
6/23
両備グループ監査室 設立
両備グループは「社会正義」「お客様第一」「社員の幸せ」を理念とし、48社で構成され全従業員6,000名の会社です
両備グループ監査室長 佐藤 允彦 ?中国バス専務取締役 兼務
両備グループ監査室主任監査役 窪田 新治
両備グループ監査室主任監査役 桑原 彰一郎
両備グループ監査室分析統括監査役 福間 和興
6/22
21時ごろ住民民家でガス漏れ警報器が鳴る
6/16〜17
環瀬戸内海会議第18回総会で、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題を報告する
6/13
16時ごろ、西大寺消防署上道出張所が岡山市から連絡を受けて調査に来る
6/11
22時ごろ住民民家でガス漏れ警報器が鳴る
5/30
読売新聞社が土壌汚染による健康被害を報道
5/14
岡山県に調査結果を報告・・・現在岡山市が管轄しているので県では何もできないと回答。
5/14
岡山市に調査結果を報告し詳細調査を要請・・・表層に有害物質がある事が証明されたが、岡山市は実態解明調査は行わないと回答
5/12
岡山シティーホテル桑田町で記者会見し畑明郎教授が「住民による土壌調査結果」を報告
5/12
近隣の住民から旭油化工業撤退前に所有地で井戸用にボーリングしたら油が出たとの証言あり
4/30
大阪市立大学の畑明郎教授(日本環境学会会長)から意見書がメール来る
サンプル数は少ないものの、土壌ガスから発がん性のベンゼンが、土壌溶出量基準を超えるベンゼン、猛毒のシアン、発がん性のある鉛やヒ素が検出されており、危険で有害な土壌であることが証明されたと思います。
ベンゼンや鉛は、廃油や廃溶剤などからと考えられますが、シアンやヒ素の原因は不明です。応急対策として、敷地土壌のアスファルトやセメントによる被覆が早急に必要と考えます。
4/28
土壌汚染調査結果報告書を畑明郎教授に郵送し意見を伺う
4/27
兵庫県の民間土壌分析会社が調査報告書を持参
4/20
住民が片山 虎之助 参議院議員に公開質問状を送る
4/15
大阪市立大学の畑 明郎 教授が現地視察
4/9
兵庫県の民間土壌分析会社が土壌調査を実施
4/4
兵庫県の民間土壌分析会社に土壌調査を発注
4/1
両備バスと両備運輸が合併し社名を「両備ホールディングス」に変更。
4月
(住宅敷地内において)表層土壌ガス調査の結果、2箇所の調査位置においてベンゼンが検出された
3/23
ENVIROASIAや JanJanに「いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!」掲載される
3/13
住民側が岡山地方法務局の人権相談事務所で相談する。
質問:土壌汚染の分譲住宅地を知らずに購入して、健康被害に遭い宅地建物の価値も無くなったのに、連絡しても放置されたことは人権侵害だと思う。
回答:司法手続きの検討しかないと思う。岡山市には相談があった事は連絡しておきます。
3/15
岡山県倉敷市の民間土壌分析会社が調査を辞退
3/13
岡山県倉敷市の民間土壌分析会社が2007年3月26日予定で土壌調査実施を受託
2/13
岡山県土木部都市局建築指導課から回答書 (宅地建物取引業法の公訴時効は3年、行政処分を行える期間は原則として後5年)
2/13
岡山県生活環境部 環境管理課 循環型社会推進課から「岡山市と協議するように」と回答書
2/9〜12
テレビ朝日のニュース番組「報道ステーション」取材チームが取材に入る、しかし、テレビ朝日は一方的に放映中止
2/7
岡山市西大寺支所建設課が膨れている擁壁や道路を現地調査
「・・・普通の道路保全だけでは無いので(土壌汚染の関係もあるので)事情を確認してから連絡する。」
2/7
高谷 茂男 岡山市長「土壌汚染調査について(回答)」が来る 岡市み第249号
平成19年2月7日
小鳥が丘団地救済協議会 代表 ○○ 様
岡山市長 高谷 茂男
土壌汚染調査について(回答) (抜粋)
平素から、市政発展のためにご理解とご協力をいただきありがとうございます。さて、平成19年1月30日付けで提出された標記要望書に対して、下記のとおり回答いたします。
記
1.当団地の土壌汚染の実態を把握する為、市主導で、私達の信頼できる環境省指定の民間調査機関と共に徹底した土壌調査を実施することについて
(回答)
両備バス?が設立した環境対策検討委員会(以下、「委員会」と記す。)での審議の結果、平成17年3月28日付けで、
(1)現状の生活環境においては、異臭による不快感はあるものの、健康への影響が直ちに懸念されるものではないこと、
(2)MNA等による居住環境の改善対策案が示されたこと、等が提示されました。
本市としましては、平成17年3月24日付け 岡協市第108号 にて回答しているとおり、委員会から提示された対策案について、住民の皆様、両備バス?、市の3者で協議の上、対応してまいりたいと考えております。
また上記のとおり、健康への影響が直ちに懸念されるものではないと判断されていることから、現時点では、市が主導して土壌調査等を実施することは考えておりませんが、住民の皆様が安心して暮らしていけるよう、周辺環境調査等できることは実施していきたいと考えております。
なお、団地内にお住まいの方で、本件に関して健康面でご心配の事項がありましたら、引き続き岡山市保健所を窓口として健康に関する相談に応じる方針です。
(自宅庭で、ガス中毒で倒れた岩野氏が岡山市保健所に相談に行ったところ、保健所では対処できないので、岡山市環境保全課に相談して下さいとの回答でした。つまり何処の窓口に行っても健康診断には対応してくれません)
5.
一部省略
(エ)小鳥が丘団地の土壌調査は実施しないとする環境保全課の考え方について(回答)
住宅地等における土壌汚染問題については、土壌汚染対策法が適用される案件を除き、原則、造成・販売等に関わった当事者間による話し合い等により解決されるべき問題であり、土壌汚染対策法が適用される案件では、調査の実施主体は土地所有者等であると認識しております。
同様の調査は、本市においても次のとおり実施し、住民の皆様にすでに報告しているところであります。
?平成16年7月29日、地下水調査(カドミウム等、全21項目)
?平成16年8月12日、土壌溶出量調査(カドミウム等、全25項目)
?平成16年8月26日、表層ガス調査(ベンゼン等、全3項目)
<問い合わせ先>
○土壌汚染に関すること、環境局環境保全課、TEL(086)803−1281
○健康相談に関すること、保健所健康づくり課、TEL(086)803−1267
○開発許可に関すること、都市整備局開発指導課、TEL(086)803−1452
2/5
岡山県備前県民局建設部が擁壁から廃油が流れていて膨らんでいる事について現場確認する。
2/5
岡山県循環型社会推進課、河川課、建築指導課、環境調整課が住民に説明
1/30
住民が岡山市長に土壌汚染調査要望書を提出する
平成19年1月30日
岡山市長 高谷 茂男 様
小鳥が丘団地救済協議会 代 表 ○○
要望書
土壌汚染調査について
貴職におかれましては、日々、岡山市発展の為、御尽力いただき、心より敬意を表します。
さて私達 「小鳥が丘団地救済協議会」 は当団地で平成16年7月に発覚した土壌汚染の問題が長く放置され、発覚当初想像さえしなかった住宅地表層近くから広範囲に刺激臭のする黒い土壌が発見され尋常でない事に危機感を持つ団地住民の有志で組織した団体です。
何度となく岡山市、岡山県、警察、等に足を運び相談をして参りましたが、地下数メートルには環境規準値の20数倍の有害物質は有るが地上で生活する住民に健康への影響が直ちに懸念されるものではないと言われ、危険と判断されぬまま放置されましたが、その後そのガスを吸い込んだ住民が自宅庭で倒れ、救急車で病院に運ばれ緊急入院の事態に成りました。診断結果はガス中毒です。
市民がこの様な健康被害に遭い、土地建物の資産価値は無くなり、この環境を将来世代に引き継ぐ事をも懸念しています。岡山市環境保全条例の基本理念―環境の保全及び創造は,健康で快適な生活の確保が,すべての市民がその生活を営む上で欠くことができない基盤であるという認識のもと,その環境を良好なまま,子孫へと手渡していくことを目指して行われなければならない。―に掲げられている通り、このまま放置すれば汚点を残す事になりかねません。
無論、話し合いにも応じず現地確認さえ拒否する宅地開発販売業者には裁判で正否を決める事もやむなしと思っていますが、岡山市は現在当地区環境の担当行政として、また当団地の2期3期住宅地開発行為許可権者として、当団地の開発における最初に宅地埋め立て造成の許可を出した岡山県と共に、当然土壌調査を実施し専門的見地から今後この様な被害は無いのかを明らかにする社会的責任があると考えます。
市窓口の環境保全課に相談を重ねましたが、当課は市が土壌調査をすべき法律がないとの理由で要望が受け入れられません。
今回、愛知県が宅地造成した小牧市桃花台ニュータウンで土壌汚染が発覚し、小牧市も土壌調査を実施した事を知り、当課に要望したところ視察を実施されましたが岡山市では土壌調査は実施しないとの回答です。その理由は、愛知県が宅地造成の土地を買収する前に小牧市が測量等、関与しているので土壌調査を実施しているが、岡山市は土地に関与してない為との説明です。
しかし、岡山市は小鳥が丘団地2期3期住宅地開発行為許可権者です。関与の重みから言えば小牧市以上だと思いますし、たとえ小牧市が土壌調査を実施しなくても岡山市が土壌調査を実施しても何の不思議も無いと思いますので再考して頂きたく存じます。
小牧市を視察してなお土壌調査を実施しないと回答された環境保全課に、これ以上要望しても希望が持てないと判断し、今回直接市長殿に要望書を提出いたしました。
そこで次の事柄を岡山市に要望致します。
(1) 当団地の土壌汚染の実態を把握する為、市主導で、私達の信頼出来る環境省指定の民間調査機関と共に徹底した土壌調査をお願い致します。
(2) 前記の調査方法・調査内容を、広く公開する事を要望します。
(3) 調査をするに当り、事前に地元住民や周辺住民の意見を聞く場を設け、様々な意見交換をして頂きたいと思います。
(4) その調査結果に基づいて、環境の保全対策を検討して頂きたいと思います。
(5)
一部省略
(エ) 小鳥が丘団地の土壌調査は実施しないとする環境保全課の考え方
上記要望に対して平成19年2月6日までに標記当協議会代表に文書にてご回答をお願いします。
私たちが居住する「小鳥が丘団地」は、土壌汚染が発覚してから、現在に至るまでも相当の悪臭や地中から発生するガスによる健康被害に怯え、開発当時設置した水道管(鉛管)が腐食した事に因る交換工事も全住民が要望した工事がされず、一部中断したままで、安心して水道水も利用出来ない状況にあります。
また、平成16年に行なった部分的な地下ボーリング調査結果から環境規準値を超える有害物質が検出されていますが、この分布状況や質量によっては周辺の汚染拡大も十分考えられ懸念しています。
私たちは、過去の経歴の中で、汚染原因者と思われる旭油化工業が京阪神地方から搬入し不法投棄した廃油等が何らの分析も行われていない事から、ダイオキシン・PCBを含む相当な有害物質が、当団地の地下や河川に不法投棄されている可能性があるものと考えています。
市長に於かれましては、私達の窮状・惨状を御理解頂くと伴に、今後全国的な大問題になるであろう土壌汚染問題に、しかも住民が生活を営む団地の足下に有害物質が有るという環境に、行政として岡山県と共に全国に先駆けて如何に解決に導くかの先導的役割を担って頂きたく、市の過去の道義的・社会的責任において、本要望に対し、前向きに検討して頂きたいと熱望いたします。 以上
1/24
住民が 石井 正弘岡山県知事に要望書を提出する
1/18
岡山市環境保全課による小牧市視察が実施された
不詳 不詳 宅地開発業者(現、両備ホールディングス)の不動産部総務部長の富田氏が
住民に対して 「だまされたのは住人の責任」 と発言する。
2006年 平成18年
12/28
岡山市環境保全課,金安審議官らが住民宅で、事情聴取する
12/8
株式会社金曜日が土壌汚染と被害の実態を報道
12/7
法務省刑事局から回答書
12/1
環境省から回答書が住民に送付
11月
住民、宅建法違反で両備を告訴するが、時効を理由に不受理
11/24
住民が長勢甚遠法務大臣に質問状を送付
11/24
住民が“宅地建物取引業免許の適性について(両備バスの行政指導について)”の申立書を岡山県建築指導課に提出する
11/17
住民が環境大臣に質問状を送付する送付する
11/16
岡山県建築指導課は「 “この書類の中の、両備バスが用地買収した時の裁判記録を見ると、
汚染土壌と分かっているにもかかわらず、売買契約の時に何故購入者に説明しなかったのかを
両備バスに聞きたいと思うので、申立書を提出して下さい。”」と住民に説明する
11/15
国土交通省が「 “書類を見る限りでは、有害物質の除去を含めて、権利・義務の全てを、両備バスが引 き継いだ事になります。”」「 “汚染原因者と同じ立場になります。”」と住民電話連絡する
11/14
住民が環境保全課に対し、愛知県小牧市桃花台ニュータウンの事例を話し、小牧市も土壌調査を行った例を伝え、事例研究として現地視察を要請し、岡山市秘書広報室長にも再度要請し、小牧市視察が決定された。
11/1
住民、宅建法違反で両備を告訴するが、時効を理由に不受理
11/10
住民が、冬柴 鐵三 国土交通大臣に質問状を送る
10/30
両備バス代理人 菊地弁護士ほか計6名の弁護士連名で「ご連絡」書面
両備バス代理人、菊地弁護士ほか計6名の弁護士連名により
“ご連絡”、
平成18年10月30日付
○○ 個人あて、
? 少?職らは、両備バス株式会社の顧問弁護士を務める者で、あなたの申入書を拝見しました。この件に関しましては、当初より、当職らが両備バス株式会社の代理人として関与しておりますので、あなたの申入書に対して、当職らから回答をさせていただきます。
? これまで、この件に関しましては、小鳥が丘環境対策委員会(住民有志で構成する委員会)との間で種々交渉がなされ、両備バス株式会社の考え方につきましては、すでに委員会におつたえしている通りです。
? 今般、あなたが小鳥が丘団地救済協議会代表の肩書きで書面を送られてきておりますが、両備バス株式会社としましては、この件に関し複数の団体から申入れがあることに大変困惑しております。
? もしあなたが、団地の方々全員を代理する者であればお話を聞く事にやぶさかではありませんが、そうでなければ、今回の申入書はあなた個人のご意見として承っておきます。
10/27
岡山市環境保全課は“南古都?環境対策検討委員会は、両備バスの委員会であり、意見書は両備バス意見書だから両備バスが代読したものと考える”と回答する。
10月
岡山市、団地の土壌は、汚染指定区域と同等の方法で行うことを指示
10/17
住民側が両備バスに申し入れ書を送る
平成18年10月17日
岡山市錦町7番23号
両備バス株式会社代表取締役社長 小嶋 光信 様
小鳥が丘団地救済協議会 代 表 ○○○○
申し入れ書
私たち、小鳥が丘団地救済協議会は、御社が造成・販売した小鳥が丘団地で明らかになった土壌汚染問題の解決のため団地住民の有志で組織した団体です。なお、以前に御社が交渉をもっていた小鳥が丘環境対策委員会とはべつの団体です。
当協議会は、小鳥が丘の土壌汚染問題について、御社が平成17年7月に小鳥が丘団地住民に対して提出した、条件付き提案には承諾できません。
この提案は、御社と話し合いをもつための条件として、この土壌汚染の法的責任が御社にないことを確認しなければならない一方で、土壌汚染への対策実施についての保証すらありません。
これでは御社は話し合いだけして、何もしないでよいことにすらなりかねず、当協議会としてはとうてい容認できません。
しかしながら、当団地の土壌汚染問題は、発生する有毒ガスによる健康被害や地盤沈下といった被害を引き起こしていることも考えられ、そこで生活する私たち住民にとってきわめて重大です。 そうした汚染がある土地を造成し、住民には知らせずに販売した御社には当然ながら責任があるはずです。
よって当協議会は御社との話し合いおよび当協議会の合意の上での解決策の実施を求めます。
上記の申し入れに対して、平成18年10月27日までに下記の当協議会代表に文書にてご回答願います。
岡山市南古都××× 小鳥が丘団地救済協議会
10/13
住民、庭の土壌移動時にガスを吸引して倒れる
10/9
週刊金曜日ジャーナリスト井部正之氏と桃花台ニュータウンの丸山氏・木下氏が、現地視察する
8/31
環境省中四国地方環境事務所から電話連絡が入り「検討したが難しい」との事。
住民から
「土壌汚染対策法は、工場跡地等の土壌汚染から人間の健康被害を防止する法律でしょう。今現在、自宅庭から有害物質が出ていて健康が冒されているんですよ。」との質問に対し、環境省中四国地方環境事務所は「無言」
7/26
「岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結について」
(両備グループ代表 小嶋 光信) 写真:千葉学長(左)と小嶋代表
「・・・地域産業にいかに貢献するかが大学の使命であり、またそうしなければ企業からの献金を増やすことが出来ず、大学は経営難になるなど、地域の発展が即大学の経営に反映してくるのです。」
7/13
住民が環境省中四国地方環境事務所へ事情説明と今後の相談に行く。環境省の担当者は、「裁判するしかないだろう。こちらで調査をするのは難しい」との事。
7/5
小鳥が丘救済協議会がホームページを開設する
6/24
廃棄物処分場問題全国ネットワーク事務局長 が岩野氏宅の庭を訪れた
6/20
午後15時30分に友實課長と環境規制課の職員1名が岩野宅庭を視察に訪れる。手にはリトマス試験紙があった。住民がが質問する。「調査はしてもらえないんですね。?」
課長:「するかしないかは、これから検討していきます。」と言葉を濁した。
6/20
市の秘書広報室秘書課の 友實 課長を訪ね、環境規制課の件について相談する。市の秘書広報室秘書課の 友實 課長「今の段階では調査不足なので対応できない。此方で話を聞き調査をするので告訴は待ってほしい」
この頃 住民が西大寺署生活安全課で、事情を説明し被害届の手続きを希望すると「時効の問題もあるし、調査が不十分で内容も把握できない理由で、被害届の受け取りを拒否」
6/12
住民が市長へ面会求めるが面会を拒否される。
6/8
読売新聞社会面で今回の事が掲載される
午前中に読売新聞の記者「坊」氏が、岩野氏宅を取材に訪れ、庭先へ案内する。坊氏は慣れてない為か、特にせきが酷く気の毒であった。
6/7
小鳥が丘救済協議会の岩野氏、藤原氏と住民の方が3人で、西大寺署へ刑事告訴についての相談に行く。
生活安全課は最後に、「地元の警察署で相談して、それでも対応に納得いかないのであれば、県民相談課へ相談しにきなさい。」と言ってくれた。
6/7
岡山市の金安部長が両備バス?に連絡を入れると、「弁護士に任せているので、そちらに連絡してくれ。」との事
6/5
警官が 「このままでは危険なので、立ち入り禁止にし、埋め戻すかシートをかけなさい。水と反応すると亜硫酸ガスがでる。」と指導する。警官は、警察での土壌の分析を行うとの事で、ビニール袋に試料を入れ持ち返る。
6/5
岡山市の環境規制課 金安部長が駆けつけたので、両備バス?へ連絡を受ける。
6/5
岩野氏宅の倉庫工事の為、庭先の土壌を業者が掘削したところ、15〜40cm程度から下に真っ黒な刺激臭のする土壌の層が出てきた。西大寺警察、開発許可をだした市に連絡する。
小鳥が丘団地救済協議会 HPより
5/2
独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター医師が 湿疹 鼻炎と有害物質の関係について診断書 を発行
4/1
両備バスと両備運輸が対等合併して両備ホールディングスが発足する。
3/26
住民が表町商店街、岡山市表町(天満屋)百貨店前で署名活動
3/26
小笠原賢二が表町商店街の天満屋前で住民有志の皆様の活動に参加し、応援演説する
3/23
住民が岡山県庁前で署名活動を行う
3/17
3/10
3/5
住民が表町商店街、岡山市表町(天満屋)百貨店前で署名活動
2/14
岡山市水道事業管理者 植松健氏が、
「廃油処理工場跡地を造成するとの申し出があったので、ポリエチレン管は変質するので、鉛管を使用した」との返答
1/23
住民が岡山県議会議員会館を訪問し岡山県議会議員55名に土壌汚染問題請願書を提出する
2/13
岡山県より県庁にて口頭回答あり。(H18年1月16日提出の要望書の回答)
質問:土壌汚染調査等要望書について。
回答:(産業廃棄物対策課)岡山市内における環境問題は岡山市が行政権を持っており、県は動くべきでない。
質問;宅地開発許可について (回答者:建築指導課)
Q1,公害企業として何度も行政指導をしても廃油の垂れ流しを改善されなかった旭油化工場跡地を、昭和62年当時、宅地として許可した理由は?
A1,都市計画法に沿い技術基準(住宅に耐える土壌の強度があるか)に合っていれば良く、他の問題(有害物質等)は対象外であり、宅地開発許可は合法である。
質問;砂川河川敷地と両備所有団地敷地交換の経緯について。(回答者:河川課)
Q1,汚染が激しいと想定される国有河川敷地を懸念なく民間の両備に交換譲渡したのか?また公文書開示請求により2005年(H17年)11月8日に開示された「一級河川旭川水系砂川の河川敷地の公用廃止(昭和63年12月9日付け岡山県告示第973号)の起案文書」に掲載されている両備の行った「河川法20条の河川工事」とは何の工事か?
A1,「河川法20条の工事」の別紙内訳書は書類保管期限切れのため、処分したので内容は分からない。この程度の案件では調査するつもりは無い。
1/16
住民が署名3382名分を添えて要望書を、岡山県に提出しました。
2005年 平成17年
11/20
住民が沢田の柿祭り、岡山市沢田の百間川で署名活動
11/12
住民が東岡山駅で署名活動を行う
11/5
11月 雨が降った翌日、住宅の玄関ポーチと道路の境にコンクリートの割れ目から“ブツブツ”とアワが出て、火をつけると、“サーァー”と青白い炎が走る。西大寺消防署から隊員が可燃性ガスが出ている事を確認
10/28
岡山県産業廃棄物対策課(現・循環型社会推進課)が住民に対して2005年10月20日の質問に対して一部を回答する。
回答1:旭油化撤退後(1983年)に廃棄物撤去確認調査は「目視にて現状を確認したが、搬出物内容は確認してない。」
回答2:「宅地開発許可に当た開発課からの問合せ確認があったかどうかは聞いていない。」 岡山県 循環型社会推進課
産業廃棄物班 086-226-7308 FAX番号:086-224-2271 担当に問い合わせる
10/22・29
住民がスーパーマルナカ平島店及び東岡山駅で署名活動
10/20
住民側が岡山県産業廃棄物対策課(現・循環型社会推進課)に対し質問と要求を行う。
質問1:旭油化撤退後(1983年)に廃棄物撤去確認調査で有害物質の撤去を確認したのか?
質問2:宅地開発許可に当たり開発課から問い合わせ確認はなかったのか?
要求1:1983年(S58年)当時の県の実例集に記載された旭油化跡地撤去完了確認の内容開示を要求する。
「廃棄物処理法施行令」改正(埋立跡地における指定区域の指定)
10/8
高谷茂男後援会事務所から回答書が返送される
回答書です。
質問:公害企業の跡地で、土壌汚染が明らかな土地に対して、対策が不十分なまま開発許可を与えた岡山市の責任は?
答え;土壌汚染が明らかであるとの確証が得られる書面がありませんので、岡山市の責任問題についてコメントができません。
10/5
高谷茂男候補に質問書を提出する
10月
銀行から小鳥が丘団地の土地、建物は担保にならないと連絡が来る
9/25
住民が東岡山駅で署名活動
9/23
株式会社金曜日が土壌汚染と被害の実態を報道
9/18
住民がJR東岡山駅で署名活動
9/4
住民が小鳥の森フェスタ、岡山市上道公民館一帯で署名活動
7月
両備、住民との交渉継続の条件として、両備の法的責任なしの確認を含む3条件を住民に提示
6月
日本共産党 竹永みつえ岡山市議 が市議会で質問
? 委員会が現場を視察に訪れたことも住民の声を聞くこともなく解散した
3月
両備、MNA、土壌ガス吸引、水平ボーリングの3案の汚染対策案提示
3/24
岡協市第108号 ???文面は
3/29
第20回小鳥が丘環境対策委員会が(上道公民館)
主な内容は、南古都?環境対策委員会(岡山大学の教授などで構成)の意見書の説明でした。
しかし、委員会構成メンバーの参加はなく、説明は両備の担当者が「意見書」を読み上げて終わりました。
小鳥が丘の住民からは、質問状が文書で出されたほか、「子どもたちと土いじりができなくなった、安全な環境でなくなった」、「夫の病気により、実家に戻りたいが、土地と家の処分もできず、本当に困っている」などの意見が出されました。
どれも、回答は後日文書で行うとのことです。
環境対策委員会の顧問に就任した香川県議、石井亨さんから
「南古都?環境対策委員会への住民の参加を拒んだのは、委員会の委員なのか、それとも両備なのか」
との質問に対して、両備側が全く的はずれの回答をしたことは、参加されたみなさんの印象に強く残ったことでしょう。
また、リスクコミュニケーションが大切だと言いながら、この会に姿を見せなかった岡山市の態度は、問題があると思います。 ???左記の回答はどうなったのでしょうか???
3月28日
「環境対策検討委員会」が意見書
平成17年3月28日
意 見 書
南古都?環境対策検討委員会
委員長 千葉 喬三
先に行った電気探査において低比抵抗値を示した場所に存在する物質の化学的分析の結果について検討を加えた。また、本団地における調査は今回をもって完結したと考えられるので、これまでに行った調査結果をも参考にして、対策案を提案する。
1.土壌化学性状分析について
これまでに行われた土壌調査、土中ガス調査及び地下電気探査調査の各結果より、調査対象地内にパッチ状に特異な地層(団塊)の存在が推定されたことから、それら部分の性状を把握することを目的とした。
電気探査調査において低比抵抗値を示した部分の内の2ヶ所についてボーリングを実施し、採取した不攪乱試料(コアサンプル)について必要な化学的性状分析を実施した。その結果の詳細は、添付した環境保全事業団の報告書のとおりである。
2ヶ所のコアサンプルの含水量、含イオン濃度、ECの測定の結果、当該部分には通常の土壌には含有されない物質が存在することがわかった。
これは、先に実施された電気探査調査の結果と一致し、当該部分が何らかの人為的攪乱を受けていることは明らかとなった。電気探査調査における低い比抵抗値は、当該部分が電気を通しやすくなっていることを表しており、今回の調査のサンプルの含イオン濃度、ECの測定結果はそのことを裏付けている。
すなわち、当該部分になんらかの電解物質(たとえば食塩など)が相当量混入し(投棄され)、そのことにより比抵抗値が低下していると推測される。
また、サンプルの有機物含量(強熱減量値)が高く、これは何らかの有機物材料(たとえば石けん材料の油脂物質)が投棄混入されていることを推測させる。このような有機物は水の移動を抑制するため、含水率が高くなり、比抵抗値を下げる一因にもなっている可能性がある。
混入有機物は比較的深部に埋没されたかたちになっているので、嫌気的な微生物分解をうけつつ減量している過程にあるものと考えられる。
また、硫黄を含む物質は比較的地表に近いところに多く存在するので、硫黄臭に関しては有機物臭よりも短期間で消失することが期待できる。
2.居住環境の改善対策
以上の調査結果より、当委員会が提示する対策工の案は別紙のとおりである。工法の選定にあたっては、当該地が住宅団地であることを考慮し、住民の日々の生活を阻害しないことに重点を置いた。
対策の目的は、土中のガスを揮散させ、臭気の低減を図ることにより、住民の不快感ならびに不安感を解消することである。そのため、対策工は住民の大多数が不快感を抱かなくなるまで継続することが望ましい。
なお、当委員会はこの対策工の提案をもって役割を終えるが、工事の実施にあたって技術的な助言が必要であれば別途意見を申し述べることとする。
これまでの調査によって、現状の生活環境においては臭気による不快感はあるものの、健康への影響が直ちに懸念されるものではないことは、既に申しあげたとおりです。しかし、よりよい居住環境を現出するため、ここに提案しました対策工案を参考にされ、できるだけ早く改善対策を実施されることをお奨めします。 以上
2/17〜18
両備が団地内土壌化学性状調査を行う
2/25
松岡 利勝 主査質問
双方がより強い当事者意識というか責任意識の中でトラブル回避のために努力をするということに自然となっていくわけですから、そういう意味では、環境を整えていく、システムをつくっていくというのは、これはやはり国政の重要な役割なのかなという気がいたします。
竹中国務大臣 答弁
「御指摘の岡山市の事例については、私も承知をしております。これは大変重要な事案であるというふうに思っております。」と答弁
第162回国会 予算委員会第一分科会
2/20
中地氏意見書
1.はじめに
2.小鳥が丘団地の土壌汚染をどう考えるのか
・環境対策委員会の調査について
3.リスクコミュニケーションの欠如について
2/13
中地重晴氏現地視察
1/24
住民が岡山県建築指導課を訪ねる
1月
両備が住民宅を戸別訪問
1/7
江本匡氏『平成16年12月27日の意見書に対するが意見書に対して』と題して意見書を提出。意見書全体について
まず、人への健康影響がほとんどないことをいろいろな面からの調査方法を用いて説明する必要がある。
1.汚染状況
1-1 土地履歴調査
1-2 ボーリング調査
・地点が3点と少ないが
・地下水位は比較的浅い
・No1
・No2:深度1.4mよりトリクロロエチレン・ベンゼン(高濃度)・トルエン・キシレンが検出されている。
・No3:4.45〜5.8で金属片が発見されている。この部分でベンゼンが高い、
・No3:4.45〜5.8で同様の(トリクロロエチレン・トルエン・キシレン・油分等)の調査を行ってもらいたい。
1-3 表層土壌調査
・ベンゼン基準超過が9軒(内1軒は第二溶出量超過)、団地の中央部を中心にし北側にも4軒超過している。
・委員会意見書の「汚染は主として団地の南側部分に限られる」は整合しない
1-4 表層ガス調査
・調査地点を表層土壌調査で汚染物質が検出された場所に限定している??
・全地点でベンゼンが検出されている
・硫化水素やメタンが検出されている
・全軒の調査が必要
・各戸のメタンガスや有害物質の床下調査を全戸ですべき
1-5電気探査
・北半分では南北方向の電気探査が行われていない
1-6環境大気調査
1-7汚染箇所の推定について
・汚染範囲が団地外に広がっていないかどうかの確認が早急に必要
1-9 汚染物質
2.人の健康への影響について
3.今後の対応
<意見書>
・低比抵抗値を示す部分の化学分析
・硫化水素やメタン生成量及びモニタリング
<加えて>
・密度を高めたトルエン、キシレン等のガス調査
・深度方向調査
・ボーリング調査で発見された金属片
・床下ガス調査(夏場に実施)
・地下水観測
・亜硫酸ガス調査
・健康診断
2004年 平成16年
12/27
「南古都?環境対策検討委員会」が第二回意見書概要
1.汚染状況について
・今後浄化対策を明らかにするために化学分析を実施し、内容を特定する必要がある。
2.人の健康への影響について
・土壌ガス調査で、硫化水素やメタンが高濃度で検知された。
・当該地域は比較的地下水位が高くなりやすい。
・地表から浸透した有機汚染物質?!
・すみやかに、ガスの生成量や今後の生成可能量を把握するためのモニタリンクが必要である。
3.今後の対応
・今後、調査を行い、その結果をもとに調査を行う事となる。
・対応策は物理的、化学的、生物学的な手法を採用する
12月
両備が団地内土壌電気探査調査を行う
12月
両備不動産が土曜日に仮設の相談窓口を設ける
12月
両備が団地内土壌ガス調査及び環境大気調査を行う
10/30
下市(しもいち)このみがブログ掲載
10/13
山陽新聞社が報道
岡山市は県が撤去確認調査を実施していたと報告
10/30
「南古都?環境対策検討委員会」が第一回意見書を作成
10/23
住民説明会
10/17
住民が両備バス株式会社代表取締役社長小嶋 光信 に申し入れ書
10/15
両備が南古都?環境対策検討委員会に委任した 委員長 千葉喬三 岡山大学 副学長
委 員: 河原長美(岡山大学保健環境センター教授)、笹岡英司(岡山大学環境理工学部教授)、 西垣誠(岡山大学環境理工学部教授) 西村伸一(岡山大学保健環境センター助教授)、竹内文章(岡山大学保健環境センター助教授)、 山本秀樹(岡山大学医学部 講師)、オブザーバー:金安利和(岡山市環境保全部 部長)、中瀬克己(保健所 所長)
両備バス(株) 南古都?土壌汚染対策案について (抜粋)
今の調査をもとに、さらにこの詳細調査・研究及び問題点の解決方法についての見当を千葉喬三先生に依頼して、委員会を設立して頂き、その指導、ご提言を賜りながら対処することと致しましたので、お知らせいたします。・・今回の地域問題について産・官・学が連携して取組む体制になっております。
・・この、資料の問い合わせは両備グループ広報室山木までお願いします。
委員会は非公開で、住民は傍聴すらできず、議事録の閲覧すら拒否された。
山陽新聞報道
10/4〜6
両備が団地内34ヵ所で表土調査、環境基準を超えてベンゼン等を検出
10/5
朝日新聞社が報道する
10/1
9/30
山陽新聞社が報道
「廃棄物処理法施行令」改正(指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の指定、旧処分場、ミニ処分場等廃棄物処理に関する基準の強化・明確化等)
9/28
土壌汚染調査報告:ボーリング調査3地点、環境基準値の約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、
6倍のシスー1,2−ジクロロエチレンが検出された。
地下約5メートル付近では金属片やボロ切れなどが発見されたことを岡山市の出席のもとに公表する
9/6〜11
両備の実施した市道部分の3ヵ所ボーリング調査で環境基準を超えるトリクロロエチレン等を検出
8月
岡山市が健康相談を実施、
65人中42人が皮膚炎(15人)、鼻炎(12人)、頭痛(11人)等を訴える
8/26
岡山市が表層ガス調査(ベンゼン等、全3項目)を実施する
8/16
第一回住民説明会開催
8月
岡山市が団地周辺の井戸、川で水質検査実施
8/12
岡山市が土壌溶出量調査(カドミウム等、全25項目)を実施する
7月
岡山市の調査で地下水と土壌から硫酸イオンが検出された
7/29
岡山市が地下水調査(カドミウム等、全21項目)を実施し、住民に報告する
7/29
岡山市水道局の鉛製給水管解消事業に伴う上水道鉛管取替工事始まる
右の写真は、油性の黒い液体が湧き出し、ポンプで排水している状況
この頃 小嶋光信(両備バス元会長の故松田基の娘婿)が 岡山大学理事に就任。
2/27
厚生労働省健康局が、「室内空気質健康影響研究会報告書:〜シックハウス症候群に関する医学的知見の整理〜」を公表する
(研究会のメンバー:岡山大学大学院医歯学総合研究科岩月啓教授)
2003年 平成15年
2/15
土壌汚染対策法 施行
「産廃特措法」公布(平成10 年6月以前に不適正処分された産業廃棄物の支障の除去のための財政支援)
2000年 平成12年 12月 児島湾(乙)阿津沖のメナダ(ボラの一種)に含まれるダイオキシン類が16pg-TEQ/gと高い値であったを環境白書で公表
(国)ダイオキシン類対策特別措置法施行
「廃棄物処理法」改正 不適正処分の現状回復措置命令
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部改正
1996年 平成8年
(国)水質汚濁防止法に地下水の浄化措置及び油に係る事故等の措置が追加される
(県)岡山県公害防止条例(水質関係)の地下浸透を禁止する物質にPCB など16物質が追加される
1995年 平成7年
「廃棄物処理法」改正不法投棄に対する罰則の大幅強化
1992年 平成4年
9/18 廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について 公布
1991年 平成3年
「廃棄物処理法」改正罰則の強化 廃棄物処理業者、廃棄物処理施設の規制強化
1989年 平成元年
(国)「水質汚濁防止法」に地下浸透規制を追加
1987年 昭和62年
両備、小鳥が丘団地分譲開始 ? 上水道鉛管埋設工事
10/1
松本一岡山市長が両備バス(代表取締役 松田基)に開発行為許可 工事施工者 (株)東山工務店(代表取締役 荒木貞次)
2/23
長岡士郎岡山県知事が両備バス(代表取締役 松田基)に開発行為許可 工事施工者 (株)東山工務店(代表取締役 荒木冨美子)
1984年 昭和59年
8/22
トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針公布
2/23
岡山県環境保健部長から吉井町長宛て報告書で、環境保全措置のおおむね完了と、水質汚染拡散監視の為の水質定期検査の終了を連絡する。(吉井町公害対策特別委員会議事録より)
1983年 昭和58年
6月
吉井町・管財人・岡山県環境衛生課の3者で協議し、公害処理作業完了。
4月
吉井町が石灰散布を実施
2月
吉井町が瑞穂産業?工場内の汚染土石類の搬出
1月
吉井町が瑞穂産業?跡地投棄油の回収等を行い1月末までに回収
吉井町が瑞穂産業?を操業停止・撤退させる。この頃、吉井町は当地旭油化工業?跡地を現地視察する。
岡山県が廃棄物処理法に基づく廃棄物処理廃止時における汚泥の撤去の確認調査を実施
1982年 昭和57年
11月
旭油化工業(代表者小寺正志)は近郊の赤磐郡吉井町(現あかいわ市)に瑞穂産業?と変え工場を設置し、同様の廃油処理業務を始める。瑞穂産業?が吉井町草生地区で三和開発の看板を掲げて操業開始する。
10月
旭油化工業の設備解体開始 旭油化が行政指導を受ける
7/27
岡山簡易裁判所において、当時の開発業者、両備バス?松田 基代表取締役と旭油化工業?小寺 正志 代表取締役とが和解、両備バスが旭油化工業の土地7,891m2を購入する
6/14
岡山県が旭油化工業に対して廃掃法に基づく汚泥除去の処理命令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について (各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
(土地造成)
問19 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり、この者は「自ら利用」するのであるから法が適用されないと主張するが、廃棄物の埋立処分であり法が適用されると解してよいか。
答 お見込みのとおり。なお、次の点に留意されたい。「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しない。また、土地造成は廃棄物・有価物たるとを問わず固形状、でい状であれば可能であるが、廃棄物による土地造成は埋立処分に該当する。
5月
岡山市が旭油化工業に対して悪臭防止法に基づく改善勧告
1981年 昭和56年
5月
旭油化工業が、産業廃棄物処理業の廃止届け
両備、小鳥の森団地分譲開始
当時の県や市も何度か旭油化に行政指導を行い、立会い検査を行っています。その調査によると、工場の門を入ると既に敷地一体が黒い沼のようにドロドロとしており、長靴で入っても足のすね当たりまで埋まるような状況だったそうです。
1980年 昭和55年
岡山市が鉛製給水管の使用を通常は中止する
1978年 昭和53年 -
県市が行政指導 苦情多発 小鳥の森団地分譲中
1977年 昭和52年
県が、産業廃棄物処理基本計画を策定
「廃棄物処理法施行令」改正、「共同命令」公布(最終処分場の3類型(安定型・管理型・遮断型)の導入、燃えがら,ばいじんの規制)「廃棄物処理施設構造指針」
3/15
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
(52年3月15日施行)
1976年 昭和51年
「廃棄物処理法」「廃棄物処理施設整備緊急措置法」改正
(処理施設の届け出義務、廃棄物の最終処分場に関する構造基準及び維持管理基準)
不法投棄、不適正処理が後を絶たず、廃棄物中の有害物による環境汚染防止の枠組みを定めた産業廃棄物が埋められている土地の売買廃棄物の最終処分場が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって位置づけられたのは1976年の同法改正によってです。
1976年改正以前であれば、『この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による』とされているため、遡及しません。
岡山県産業廃棄物対策懇談会が発足
1975年 昭和50年 -
産業廃棄物処理規制の強化等を内容とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正(50年6月16日公布)
県市が行政指導 小鳥の森団地分譲開始
1975年 昭和50年 -
県市が行政指導
10/5
住居地域指定
「廃棄物処理法施行令」改正
(PCB・有機塩素化合物を含む廃棄物の処分基準、廃酸・廃アルカリの海洋投入処分基準の設定)
1974年 昭和49年
市が「水質汚濁防止法」の政令市となる
1973年 昭和48年 -
県が行政指導 悪臭被害出始まる 市が主要工場等と公害防止協定締結開始
瀬戸内海環境保全特別措置法
「廃棄物処理法施行令」改正(有害な産業廃棄物の判定基準の設定(「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」))
1972年 昭和47年
岡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行旭油化が行政指導を受ける
事業者の責任を強化して被害者の円滑な救済を図るため、民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法および水質汚濁防止法で無過失責任制度導入された。伝統的な不法行為理論を修正し、無過失賠償責任論に基づく原則が採用された。
1971年 昭和46年
水質汚濁防止法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃掃令 廃掃則 上道町合併
岡山県公害防止条例を改正 岡山県環境部に公害苦情処理局を設置
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】公布
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 施行
1970年 昭和45年
市 衛生局に公害課設置 岡山市公害対策本部設置
「廃棄物処理法」公布(昭和46 年9月施行)
(生活環境の保全を目的化、産業廃棄物と一般廃棄物の区別、産業廃棄物の処理責任の明確化、有害な産業廃棄物などの処理処分の技術的基準の設定)
1969年 昭和44年
1968年 昭和43年
1967年 昭和42年 - (国)「公害対策基本法」施行 旭油化が土地を購入
1966年 昭和41年 「岡山市公害防止条例」制定、公害審議会設置
1965年 昭和40年
1964年 昭和39年
1963年 昭和38年 生活環境施設整備緊急措置法公布
1962年 昭和37年 衛生部保健衛生課に公害係設置
1961年 昭和36年 岡山市公害対策審議会設置
宅地造成等規制法 宅地造成等規制法施行規則 宅地造成等規制法施行令
1960年 昭和35年 岡山県公害対策調査会を設置
明治33年 法律第31号 汚物掃除法 第六条 常時吏員ハ掃除ノ實況ヲ監視シ必要ナル事項ヲ施行スル為其ノ事由ヲ告知シテ私人ノ土地ニ立入ルコトヲ得
リンク(工事中)
小鳥が丘団地救済協議会
小鳥が丘救済協議会の掲示板
小鳥が丘団地救済協議会のブログ
小鳥が丘団地で土壌汚染!(小笠原賢二)
竹永みつえblog 小鳥が丘団地土壌汚染問題
若井たつこ活動日記: 2007年10月
地域・いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!
環境ニュース -ENVIROASIA いまだかつてない分譲住宅地の土緒・・?I
産廃に沈む住宅地週刊プレイボーイに加筆
岡山地方気象台
(岡山県HP)シックハウス症候群の主な症状について
シックハウス症候群は、さまざまな症状が現れます。
そして、その症状は、個人差が大きく、診断を難しくしています。
住まい(住宅)が、住んでいる私たちを病気にしてしまうことがあります。
この病気は、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
下記HPでは、あなたの住まいを「シックハウス症候群」から防ぐための原因と対策等について説明しています。
シックハウス対策
● 第1章 土壌汚染とリスクコミュニケーション
● 第2章 土壌汚染に関するリスクコミュニケーションの進め方
● 第3章 住民説明会の開催について
● 第4章 参考事例
● 資料編
自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン(案)について
油汚染対策ガイドライン
土壌汚染対策に対する助成制度について
助成金交付スキームについて 【参考例:都道府県又は政令市の助成率が3/4のケース】
揮発性有機化合物による地下水汚染対策に関するパンフレット「地下水をきれいにするために」
宅地造成等規制法の概要
宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)
我が家の擁壁チェックシート(案)
ふくらみ
リスクコミュニケーターは企業の顧問弁護士では無理があると思います。
企業の顧問弁護士に任すと益々問題が難しくなると思います。
日弁連 - 弁護士職務基本規程
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
第一章基本倫理
(使命の自覚)
第一条弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
(信義誠実)
第五条弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(違法行為の助長)
(依頼の勧誘等)
第十条弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。
第十四条弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(非弁護士との提携)
第十一条弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(不利益事項の説明)
第三十二条弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければならない。
懲戒制度の概要
弁護士法
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
南古都?環境対策検討委員会の委員が、意見書を発表する場に姿を見せなかったことは、分かるような気がします。
最後までご覧下さいましてありがとうございました。
不適切な記載や追記事項等のご意見がありましたら↓のコメント欄に記載下さいますようお願いします。
http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/38388679.html
多くの皆様のデーターを利用させて頂き誠にありがとうございました。
産廃に沈む住宅地 より
団地脇の川には謎の黒い油が流出している ある家の庭に開けられた調査用の穴。油膜が張り、ガスがブクブク湧いていた
「空中写真閲覧サービス(試験公開)」より 昭和55年
http://beauty.geocities.jp/oecacasa/kotorigaokanorekisi.htm
2009年11月22日
土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等
地方公共団体における土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等の制定状況
1.都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道公害防止条例 ?
岩手県 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例 ?????
宮城県公害防止条例 ?
秋田県汚染土壌の処分に関する指導要綱 ??
山形県生活環境の保全等に関する条例 ????
福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例 ??福島県土壌汚染対策事務処理要領 ??
茨城県生活環境の保全等に関する条例 ?
栃木県生活環境の保全等に関する条例 ?
群馬県の生活環境を保全する条例 ????
埼玉県生活環境保全条例 ????
千葉県 千葉県環境保全条例 ?
東京都 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ????東京都土壌汚染対策指針 ?
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 ??????
新潟県生活環境の保全等に関する条例 ????
石川県 ふるさと石川の環境を守り育てる条例 ?
福井県公害防止条例 ?
山梨県 工場等における地下水汚染防止対策指導指針 ?
静岡県 生活環境の保全等に関する条例 ?
愛知県 県民の生活環境の保全等に関する条例 ????愛知県土壌汚染等対策指針 ??汚染土壌浄化施設の認定手続き等に関する要綱 ?
三重県生活環境の保全に関する条例 ????三重県汚染土壌浄化施設認定実施要領 ?
滋賀県 公害防止条例 ??? 改正土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針 ?
京都府環境を守り育てる条例 ?
大阪府生活環境の保全等に関する条例 ????????
兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 ?
奈良県 生活環境保全条例 ?
和歌山県公害防止条例 ?
鳥取県公害防止条例 ?
岡山県環境への負荷の低減に関する条例 ??
広島県生活環境の保全等に関する条例 ???
山口県土壌汚染対策法事務処理要領 ?
徳島県生活環境保全条例 ??
香川県生活環境の保全に関する条例 ???? 改正
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 ?
熊本県 土壌汚染対策法に係る事務処理要領 ?
宮崎県 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 ?
札幌市生活環境の確保に関する条例 ??
秋田市汚染土壌の処理に関する指導要綱 ? 改正
いわき市土壌汚染指定区域台帳等の閲覧に関する事務取扱要綱 ?
水戸市公害防止条例 ?
前橋市 土壌及び地下水汚染対策要綱 ?
高崎市公害防止条例 ?
草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例 ??
千葉市環境基本条例 ?千葉市環境保全条例 ?千葉市土壌汚染対策指導要綱 ?????
市川市環境保全条例 ????????
船橋市環境保全条例 ?
柏市環境保全条例 ?
市原市生活環境保全条例 ?市原市民の環境を守る基本条例 ?
横浜市公共用地等取得に係る土壌汚染対策事務処理要綱 ??横浜市生活環境の保全等に関する条例 ???????土壌汚染対策法に基づく汚染土壌浄化施設認定要綱 ?
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 ????川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する要綱 ?
汚染土壌浄化施設認定等検討会議要綱 ?川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する環境影響調査指針 ?
横須賀市適正な土地利用の調整に関する条例 ??
新潟市生活環境の保全等に関する条例 ?
金沢市環境保全条例 ?
福井市公害防止条例 ?
長野市公害防止条例 ???
岐阜市地下水保全条例 ??
浜松市土壌・地下水汚染の防止及び浄化に関する要綱 ???
名古屋市 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 ??????
岡崎市生活環境保全条例 ???
春日井市土壌汚染対策法施行細則 ?春日井生活環境の保全に関する条例 ? 新規
豊田市土壌汚染対策法施行要綱 ?
高槻市環境影響評価条例 ??
枚方市公害防止条例 ?
八尾市公害防止条例 ?
東大阪市生活環境保全等に関する条例 ?
姫路市汚染土壌浄化施設の認定の手続等に関する要綱 ? 新規
尼崎市の環境を守る条例 ? 工場跡地に関する取扱要綱 ?
北九州市土壌汚染対策指導要領 ??
佐世保市環境保全条例 ?
熊本市 土壌汚染対策法の施行に係る事務処理要領 ?
(注)
? 有害物質使用特定施設以外の有害物質を取り扱う施設等の廃止時に土壌汚染の調査を行わせるもの
? 土地改変時、用途転換・再開発等の際に土壌汚染の有無の確認を行わせるもの
? 上記調査の結果、土壌汚染が判明した場合に汚染原因者に所要の対策を行わせる、又は対策のための費用を汚染原因者
に負担させるもの
? 土地所有者等が行う自発的な土壌汚染の調査の結果を自治体に報告させるもの
? 土壌汚染の存在する場所の情報の登録、管理等を行うもの
? 土壌汚染の調査・対策に関する技術的な事項を示したもの
? 土壌の汚染の有無の判断基準として、法の指定基準以外の独自の基準を設けているもの
? 土壌汚染の防止、有害物質の地下浸透規制に関する訓示的条項を含むもの
? その他土壌汚染に係る調査・対策を円滑に行うための行政内の関係部局の取決め等
? 外部から搬入される土砂の分析を土地所有者等に行わせ、土壌汚染の未然防止を図るもの
? 土壌汚染への調査・対策を行う者に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
? 汚染土壌浄化施設に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
2.土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道 帯広市 帯広市公害防止条例 ?
苫小牧市公害防止条例 ?
登別市公害防止条例 ?
恵庭市公害防止条例 ?
伊達市公害防止条例 ?
石狩市公害防止条例 ?
福島町公害防止条例 ?
長万部町公害防止条例 ?
余市町公害防止条例 ?
下川町環境保全条例 ?
遠軽町環境基本条例 ?
豊浦町公害防止条例 ?
音更町公害防止条例 ?
幕別町公害防止条例 ?
厚岸町公害防止並びに環境保全に関する条例 ?
標津町公害防止条例 ?
芽室町公害防止条例 ?
中富良野町生活環境保全条例 ?
北斗市公害防止条例 ?
倶知安町環境基本条例 ?
安平町環境基本条例 ?
洞爺湖町公害防止条例 ?
江別市公害防止条例 ?
秋田県 大館市環境保全条例 ?大館市土壌搬入協議要綱 ?
東京都 荒川区市街地整備指導要綱 ?
江東区マンション等建設指導要綱 ?
大田区土壌汚染防止指導要綱 ??
板橋区土壌汚染調査・処理要綱 ???
江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例 ??
西東京市工場・指定作業場が自主的に行う土壌汚染調査等に係る事務取扱指針??
長野県 岡谷市公害防止条例 ?
伊那市 環境保全条例 ?
中野市環境保全及び公害防止に関する条例 ?
辰野町公害防止条例 ?
飯島町さわやか環境保全条例 ?
宮田村環境保全条例 ?
岐阜県 御嵩町環境基本条例 ?御嵩町公共事業における環境配慮指針 ?
福岡県 大牟田市環境基本条例 ?
小郡市環境保全条例 ?
古賀市環境基本条例 ?
宮若市環境基本条例 ?
嘉麻市環境基本条例 ?
那珂川町環境基本条例 ?
二丈町環境基本条例 ?
(注)
? 有害物質使用特定施設以外の有害物質を取り扱う施設等の廃止時に土壌汚染の調査を行わせるもの
? 土地改変時、用途転換・再開発等の際に土壌汚染の有無の確認を行わせるもの
? 上記調査の結果、土壌汚染が判明した場合に汚染原因者に所要の対策を行わせる、又は対策のための費用を汚染原因者
に負担させるもの
? 土地所有者等が行う自発的な土壌汚染の調査の結果を自治体に報告させるもの
? 土壌汚染の存在する場所の情報の登録、管理等を行うもの
? 土壌汚染の調査・対策に関する技術的な事項を示したもの
? 土壌の汚染の有無の判断基準として、法の指定基準以外の独自の基準を設けているもの
? 土壌汚染の防止、有害物質の地下浸透規制に関する訓示的条項を含むもの
? その他土壌汚染に係る調査・対策を円滑に行うための行政内の関係部局の取決め等
? 外部から搬入される土砂の分析を土地所有者等に行わせ、土壌汚染の未然防止を図るもの
? 土壌汚染への調査・対策を行う者に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
? 汚染土壌浄化施設に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
3.都道府県・土壌汚染対策法政令市が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例等
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
岐阜県埋立て等の規制に関する条例
兵庫県 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例
淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱
徳島県生活環境保全条例(土砂等の埋立て等に関する環境保全)
香川県 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例
秋田市汚染土壌の処理に関する指導要綱(施設を設置する際の基準や県外から搬入される汚染土壌保管の届出)
水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例
川越市土砂のたい積等の規制に関する条例
所沢市土砂のたい積の規制に関する条例
千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
柏市埋立事業規制条例
市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
相模原市盛土等の規制に関する条例
4.土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例等
秋田県 大館市 大館市環境保全条例(土壌等の搬入及び処理、処分に関する制限)
茨城県 日立市、高萩市、北茨木市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、
東海村、大子町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
常陸太田市、小美玉市
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
栃木県
大田原市、矢板市、上三川町、壬生町、下野市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、
真岡市、西方町、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、藤岡町、岩舟町、都賀町、塩谷町、
高根沢町、那須町、大平町、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、那珂川町
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例
野木町うるおいのあるまちづくり条例
群馬県 桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例
板倉町残土等による土地の埋立て盛土又はたい積行為に関する指導要綱
板倉町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例
邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
埼玉県 東松山市、滑川町
土砂等による土地の埋立て等及び不法投棄の規制に関する条例
飯能市、加須市、日高市、ときがわ町
環境保全条例
熊谷市、春日部市、秩父市、桶川市、幸手市、北本市、和光市、越生町、鳩山町、横瀬町
土砂等のたい積の規制に関する条例
狭山市、入間市、蓮田市、行田市、羽生市、久喜市、菖蒲町、嵐山町、小鹿野町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
毛呂山町 土地の埋立て等の規制に関する条例
神奈川県 秦野市、伊勢原市、大井町
土地の埋立て等の規制に関する条例
南足柄市、中井町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
千葉県
佐倉市、神崎町
土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例
銚子市、成田市、東金市、八街市
土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
館山市、大網白里町
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
木更津市、茂原市、旭市、習志野市、流山市、八千代市、君津市、富津市、四街道市、袖ヶ浦市、
印西市、白井市、酒々井町、横芝光町
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
野田市、勝浦市、鴨川市、鎌ヶ谷市、富里市、南房総市、香取市、いすみ市、印旛村、本埜村、栄町、
多古町、東庄町、九十九里町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町
小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
我孫子市 埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
匝瑳市 土砂等の小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
山武市 残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例
芝山町 残土等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
鋸南町 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
長野県 信濃町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例
岐阜県 美濃市 住みたいまち美濃市の環境を守る条例
愛知県 三好町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
犬山市埋立て等による地下水の汚染の防止に関する条例
大口町 地下水の水質保全に関する条例
一色町土砂等の埋立て等による汚染及び災害の発生防止に関する条例
阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
京都府 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土たい積行為及び切土の規制に関する条例
八幡市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制並び土砂採取事業の規制に関する条例
京田辺市土砂等による埋立事業規制に関する条例
京丹波町の環境保全等に関する条例
城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例
大阪府 河内長野市 土砂埋立等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例
富田林市 土砂埋立て等による土壌汚染及び災害を防止するための規制条例
岬町 土砂等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為の規制に関する条例
柏原市 土壌等による土地の埋立等の規制に関する条例
羽曳野市 土砂等による土地の埋立等に関する指導要綱
兵庫県 洲本市、南あわじ市
土砂等の埋立て等に災害及び土壌汚染の防止に関する条例
淡路市における残土埋立事業の適正化に関する条例
徳島県 阿南市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
勝浦町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
愛媛県 伊予市 土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱
今冶市 吉海町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(吉海町に限定)
福岡県 豊前市、吉富町、上毛町
土砂のたい積の規制に関する条例
築上町土砂等による土地や埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
熊本県 南関町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
大分県 豊後高田市 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
杵築市、日出町、国東市、佐伯市、中津市、姫島村、宇佐市
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
鹿児島県 志布志市 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について規制(許可制)
5.土壌汚染対策基金による助成を受けることができる助成制度
6.土壌汚染対策基金以外で、土壌汚染の調査や回復対策に利用できる基金
高崎市 地球環境改善資金
千葉県 ちば環境再生基金
岐阜県環境浄化機材貸出要領
7.都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている補助・融資制度
北海道 中小企業総合振興基金
宮城県 中小企業融資制度(環境安全管理対策資金)
福島県環境創造資金融資制度
栃木県環境保全資金融資制度
群馬県環境生活保全創造資金融資
埼玉県 環境みらい資金貸付制度
東京都 <チャレンジ支援>特定取組支援融資「審査会必要型」
神奈川県 中小企業制度融資−フロンティア資金
石川県環境保全資金融資制度
静岡県 環境保全資金利子補給制度
愛知県 環境対策資金融資制度
三重県中小企業融資制度(環境保全資金)
大阪府中小企業公害防止資金特別融資
岡山県中小企業向け制度融資(事業資金)
広島県県費預託融資制度(環境保全資金融資)
愛媛県環境保全資金貸付利子補給金交付制度
福岡県環境保全施設等整備資金融資制度
仙台市中小企業融資制度の環境保全促進資金
高崎市 中小企業地球環境改善資金融資制度
船橋市 船橋市中小企業融資制度
さいたま市土壌汚染対策事業助成金交付要綱
大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱
柏市中小企業資金融資制度
横浜市 中小企業金融制度
川崎市 土壌汚染対策資金融資
平塚市中小企業融資制度
金沢市産業振興資金
長野市 環境保全対策資金
静岡市環境保全資金借入金利子補給金
浜松市 中小企業の実施する環境にやさしい事業活動を促進するための補助制度
沼津市環境保全資金利子補給制度
富士市 環境保全資金利子補給制度
名古屋市環境保全設備資金あっせん融資
豊田市環境保全設備等整備資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
福山市環境保全融資資金
福岡市商工金融資金制度(公害防止資金)
宮崎市環境改善資金利子補給要綱
http://www.env.go.jp/water/report/h20-06/04ref.pdf
1.都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道公害防止条例 ?
岩手県 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例 ?????
宮城県公害防止条例 ?
秋田県汚染土壌の処分に関する指導要綱 ??
山形県生活環境の保全等に関する条例 ????
福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例 ??福島県土壌汚染対策事務処理要領 ??
茨城県生活環境の保全等に関する条例 ?
栃木県生活環境の保全等に関する条例 ?
群馬県の生活環境を保全する条例 ????
埼玉県生活環境保全条例 ????
千葉県 千葉県環境保全条例 ?
東京都 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ????東京都土壌汚染対策指針 ?
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 ??????
新潟県生活環境の保全等に関する条例 ????
石川県 ふるさと石川の環境を守り育てる条例 ?
福井県公害防止条例 ?
山梨県 工場等における地下水汚染防止対策指導指針 ?
静岡県 生活環境の保全等に関する条例 ?
愛知県 県民の生活環境の保全等に関する条例 ????愛知県土壌汚染等対策指針 ??汚染土壌浄化施設の認定手続き等に関する要綱 ?
三重県生活環境の保全に関する条例 ????三重県汚染土壌浄化施設認定実施要領 ?
滋賀県 公害防止条例 ??? 改正土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針 ?
京都府環境を守り育てる条例 ?
大阪府生活環境の保全等に関する条例 ????????
兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 ?
奈良県 生活環境保全条例 ?
和歌山県公害防止条例 ?
鳥取県公害防止条例 ?
岡山県環境への負荷の低減に関する条例 ??
広島県生活環境の保全等に関する条例 ???
山口県土壌汚染対策法事務処理要領 ?
徳島県生活環境保全条例 ??
香川県生活環境の保全に関する条例 ???? 改正
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 ?
熊本県 土壌汚染対策法に係る事務処理要領 ?
宮崎県 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 ?
札幌市生活環境の確保に関する条例 ??
秋田市汚染土壌の処理に関する指導要綱 ? 改正
いわき市土壌汚染指定区域台帳等の閲覧に関する事務取扱要綱 ?
水戸市公害防止条例 ?
前橋市 土壌及び地下水汚染対策要綱 ?
高崎市公害防止条例 ?
草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例 ??
千葉市環境基本条例 ?千葉市環境保全条例 ?千葉市土壌汚染対策指導要綱 ?????
市川市環境保全条例 ????????
船橋市環境保全条例 ?
柏市環境保全条例 ?
市原市生活環境保全条例 ?市原市民の環境を守る基本条例 ?
横浜市公共用地等取得に係る土壌汚染対策事務処理要綱 ??横浜市生活環境の保全等に関する条例 ???????土壌汚染対策法に基づく汚染土壌浄化施設認定要綱 ?
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 ????川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する要綱 ?
汚染土壌浄化施設認定等検討会議要綱 ?川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する環境影響調査指針 ?
横須賀市適正な土地利用の調整に関する条例 ??
新潟市生活環境の保全等に関する条例 ?
金沢市環境保全条例 ?
福井市公害防止条例 ?
長野市公害防止条例 ???
岐阜市地下水保全条例 ??
浜松市土壌・地下水汚染の防止及び浄化に関する要綱 ???
名古屋市 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 ??????
岡崎市生活環境保全条例 ???
春日井市土壌汚染対策法施行細則 ?春日井生活環境の保全に関する条例 ? 新規
豊田市土壌汚染対策法施行要綱 ?
高槻市環境影響評価条例 ??
枚方市公害防止条例 ?
八尾市公害防止条例 ?
東大阪市生活環境保全等に関する条例 ?
姫路市汚染土壌浄化施設の認定の手続等に関する要綱 ? 新規
尼崎市の環境を守る条例 ? 工場跡地に関する取扱要綱 ?
北九州市土壌汚染対策指導要領 ??
佐世保市環境保全条例 ?
熊本市 土壌汚染対策法の施行に係る事務処理要領 ?
(注)
? 有害物質使用特定施設以外の有害物質を取り扱う施設等の廃止時に土壌汚染の調査を行わせるもの
? 土地改変時、用途転換・再開発等の際に土壌汚染の有無の確認を行わせるもの
? 上記調査の結果、土壌汚染が判明した場合に汚染原因者に所要の対策を行わせる、又は対策のための費用を汚染原因者
に負担させるもの
? 土地所有者等が行う自発的な土壌汚染の調査の結果を自治体に報告させるもの
? 土壌汚染の存在する場所の情報の登録、管理等を行うもの
? 土壌汚染の調査・対策に関する技術的な事項を示したもの
? 土壌の汚染の有無の判断基準として、法の指定基準以外の独自の基準を設けているもの
? 土壌汚染の防止、有害物質の地下浸透規制に関する訓示的条項を含むもの
? その他土壌汚染に係る調査・対策を円滑に行うための行政内の関係部局の取決め等
? 外部から搬入される土砂の分析を土地所有者等に行わせ、土壌汚染の未然防止を図るもの
? 土壌汚染への調査・対策を行う者に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
? 汚染土壌浄化施設に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
2.土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道 帯広市 帯広市公害防止条例 ?
苫小牧市公害防止条例 ?
登別市公害防止条例 ?
恵庭市公害防止条例 ?
伊達市公害防止条例 ?
石狩市公害防止条例 ?
福島町公害防止条例 ?
長万部町公害防止条例 ?
余市町公害防止条例 ?
下川町環境保全条例 ?
遠軽町環境基本条例 ?
豊浦町公害防止条例 ?
音更町公害防止条例 ?
幕別町公害防止条例 ?
厚岸町公害防止並びに環境保全に関する条例 ?
標津町公害防止条例 ?
芽室町公害防止条例 ?
中富良野町生活環境保全条例 ?
北斗市公害防止条例 ?
倶知安町環境基本条例 ?
安平町環境基本条例 ?
洞爺湖町公害防止条例 ?
江別市公害防止条例 ?
秋田県 大館市環境保全条例 ?大館市土壌搬入協議要綱 ?
東京都 荒川区市街地整備指導要綱 ?
江東区マンション等建設指導要綱 ?
大田区土壌汚染防止指導要綱 ??
板橋区土壌汚染調査・処理要綱 ???
江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例 ??
西東京市工場・指定作業場が自主的に行う土壌汚染調査等に係る事務取扱指針??
長野県 岡谷市公害防止条例 ?
伊那市 環境保全条例 ?
中野市環境保全及び公害防止に関する条例 ?
辰野町公害防止条例 ?
飯島町さわやか環境保全条例 ?
宮田村環境保全条例 ?
岐阜県 御嵩町環境基本条例 ?御嵩町公共事業における環境配慮指針 ?
福岡県 大牟田市環境基本条例 ?
小郡市環境保全条例 ?
古賀市環境基本条例 ?
宮若市環境基本条例 ?
嘉麻市環境基本条例 ?
那珂川町環境基本条例 ?
二丈町環境基本条例 ?
(注)
? 有害物質使用特定施設以外の有害物質を取り扱う施設等の廃止時に土壌汚染の調査を行わせるもの
? 土地改変時、用途転換・再開発等の際に土壌汚染の有無の確認を行わせるもの
? 上記調査の結果、土壌汚染が判明した場合に汚染原因者に所要の対策を行わせる、又は対策のための費用を汚染原因者
に負担させるもの
? 土地所有者等が行う自発的な土壌汚染の調査の結果を自治体に報告させるもの
? 土壌汚染の存在する場所の情報の登録、管理等を行うもの
? 土壌汚染の調査・対策に関する技術的な事項を示したもの
? 土壌の汚染の有無の判断基準として、法の指定基準以外の独自の基準を設けているもの
? 土壌汚染の防止、有害物質の地下浸透規制に関する訓示的条項を含むもの
? その他土壌汚染に係る調査・対策を円滑に行うための行政内の関係部局の取決め等
? 外部から搬入される土砂の分析を土地所有者等に行わせ、土壌汚染の未然防止を図るもの
? 土壌汚染への調査・対策を行う者に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
? 汚染土壌浄化施設に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
3.都道府県・土壌汚染対策法政令市が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例等
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
岐阜県埋立て等の規制に関する条例
兵庫県 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例
淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱
徳島県生活環境保全条例(土砂等の埋立て等に関する環境保全)
香川県 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例
秋田市汚染土壌の処理に関する指導要綱(施設を設置する際の基準や県外から搬入される汚染土壌保管の届出)
水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例
川越市土砂のたい積等の規制に関する条例
所沢市土砂のたい積の規制に関する条例
千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
柏市埋立事業規制条例
市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
相模原市盛土等の規制に関する条例
4.土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例等
秋田県 大館市 大館市環境保全条例(土壌等の搬入及び処理、処分に関する制限)
茨城県 日立市、高萩市、北茨木市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、
東海村、大子町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
常陸太田市、小美玉市
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
栃木県
大田原市、矢板市、上三川町、壬生町、下野市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、
真岡市、西方町、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、藤岡町、岩舟町、都賀町、塩谷町、
高根沢町、那須町、大平町、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、那珂川町
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例
野木町うるおいのあるまちづくり条例
群馬県 桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例
板倉町残土等による土地の埋立て盛土又はたい積行為に関する指導要綱
板倉町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例
邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
埼玉県 東松山市、滑川町
土砂等による土地の埋立て等及び不法投棄の規制に関する条例
飯能市、加須市、日高市、ときがわ町
環境保全条例
熊谷市、春日部市、秩父市、桶川市、幸手市、北本市、和光市、越生町、鳩山町、横瀬町
土砂等のたい積の規制に関する条例
狭山市、入間市、蓮田市、行田市、羽生市、久喜市、菖蒲町、嵐山町、小鹿野町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
毛呂山町 土地の埋立て等の規制に関する条例
神奈川県 秦野市、伊勢原市、大井町
土地の埋立て等の規制に関する条例
南足柄市、中井町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
千葉県
佐倉市、神崎町
土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例
銚子市、成田市、東金市、八街市
土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
館山市、大網白里町
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
木更津市、茂原市、旭市、習志野市、流山市、八千代市、君津市、富津市、四街道市、袖ヶ浦市、
印西市、白井市、酒々井町、横芝光町
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
野田市、勝浦市、鴨川市、鎌ヶ谷市、富里市、南房総市、香取市、いすみ市、印旛村、本埜村、栄町、
多古町、東庄町、九十九里町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町
小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
我孫子市 埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
匝瑳市 土砂等の小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
山武市 残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例
芝山町 残土等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
鋸南町 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
長野県 信濃町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例
岐阜県 美濃市 住みたいまち美濃市の環境を守る条例
愛知県 三好町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
犬山市埋立て等による地下水の汚染の防止に関する条例
大口町 地下水の水質保全に関する条例
一色町土砂等の埋立て等による汚染及び災害の発生防止に関する条例
阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
京都府 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土たい積行為及び切土の規制に関する条例
八幡市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制並び土砂採取事業の規制に関する条例
京田辺市土砂等による埋立事業規制に関する条例
京丹波町の環境保全等に関する条例
城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例
大阪府 河内長野市 土砂埋立等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例
富田林市 土砂埋立て等による土壌汚染及び災害を防止するための規制条例
岬町 土砂等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為の規制に関する条例
柏原市 土壌等による土地の埋立等の規制に関する条例
羽曳野市 土砂等による土地の埋立等に関する指導要綱
兵庫県 洲本市、南あわじ市
土砂等の埋立て等に災害及び土壌汚染の防止に関する条例
淡路市における残土埋立事業の適正化に関する条例
徳島県 阿南市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
勝浦町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
愛媛県 伊予市 土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱
今冶市 吉海町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(吉海町に限定)
福岡県 豊前市、吉富町、上毛町
土砂のたい積の規制に関する条例
築上町土砂等による土地や埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
熊本県 南関町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
大分県 豊後高田市 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
杵築市、日出町、国東市、佐伯市、中津市、姫島村、宇佐市
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
鹿児島県 志布志市 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について規制(許可制)
5.土壌汚染対策基金による助成を受けることができる助成制度
6.土壌汚染対策基金以外で、土壌汚染の調査や回復対策に利用できる基金
高崎市 地球環境改善資金
千葉県 ちば環境再生基金
岐阜県環境浄化機材貸出要領
7.都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている補助・融資制度
北海道 中小企業総合振興基金
宮城県 中小企業融資制度(環境安全管理対策資金)
福島県環境創造資金融資制度
栃木県環境保全資金融資制度
群馬県環境生活保全創造資金融資
埼玉県 環境みらい資金貸付制度
東京都 <チャレンジ支援>特定取組支援融資「審査会必要型」
神奈川県 中小企業制度融資−フロンティア資金
石川県環境保全資金融資制度
静岡県 環境保全資金利子補給制度
愛知県 環境対策資金融資制度
三重県中小企業融資制度(環境保全資金)
大阪府中小企業公害防止資金特別融資
岡山県中小企業向け制度融資(事業資金)
広島県県費預託融資制度(環境保全資金融資)
愛媛県環境保全資金貸付利子補給金交付制度
福岡県環境保全施設等整備資金融資制度
仙台市中小企業融資制度の環境保全促進資金
高崎市 中小企業地球環境改善資金融資制度
船橋市 船橋市中小企業融資制度
さいたま市土壌汚染対策事業助成金交付要綱
大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱
柏市中小企業資金融資制度
横浜市 中小企業金融制度
川崎市 土壌汚染対策資金融資
平塚市中小企業融資制度
金沢市産業振興資金
長野市 環境保全対策資金
静岡市環境保全資金借入金利子補給金
浜松市 中小企業の実施する環境にやさしい事業活動を促進するための補助制度
沼津市環境保全資金利子補給制度
富士市 環境保全資金利子補給制度
名古屋市環境保全設備資金あっせん融資
豊田市環境保全設備等整備資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
福山市環境保全融資資金
福岡市商工金融資金制度(公害防止資金)
宮崎市環境改善資金利子補給要綱
http://www.env.go.jp/water/report/h20-06/04ref.pdf
2009年11月21日
土壌汚染地における土地の有効利用等に関する中間とりまとめ
土壌汚染地における土地の有効利用等に関する研究会中間とりまとめ
平成20 年4 月
国土交通省土地・水資源局 土地政策課土地市場企画室
中間とりまとめのポイント
土壌汚染が実際に存在する土地で、原則として掘削除去以外の浄化措置を行うとともにその後の土地利用の計画を策定した上で、その成功要因等を分析・研究するという「サクセスモデル」を構築・公開することが、土壌汚染地を有効活用するための有効策になりうる。
土壌汚染地の資産評価の適正化と土壌汚染地に係る安全かつ円滑な利用や取引を促進するため、土壌汚染の専門業者が行う調査の標準化とそれを通じた専門業者の標準化を進める必要がある。
不動産鑑定の実務面では運用指針の策定や研修等が行われているが、社会経済情勢の変化に対応しうるよう、引き続き不動産鑑定士が行うべき土壌汚染状況の確認範囲等を明確化し、鑑定評価に適切に反映するステップについて検討を深めていく必要がある。
また、スティグマについての評価方法や、掘削除去以外の措置を前提とした鑑定評価方法についてもさらに検討する必要がある。
個別の土壌汚染サイトに関する情報はなかなか公にならない現状があることから、下記の課題を検討するための前提として今後も企業や地方公共団体等へのヒアリングや調査等による情報収集が必要である。
更なる実態・状況の把握
土壌汚染情報は、土壌汚染地の近隣住民等も利害関係を有する情報であるから、全国的な土壌汚染情報をデータベース化し、広く情報を共有することができれば、土地取引の円滑化や浄化措置の促進及び早期化等に資することになる。
しかし、我が国においては土壌汚染情報の収集が十分でなく、情報の収集方法等も検討しなければならないため、すぐにはそういったデータベースの作成に取りかかることは困難であることから、公的なリーダーシップの元にフェーズ?程度の地歴調査を行った上で、過去に工場が立地している等の理由により土壌汚染の可能性が高いサイトや地区を地図上に記載した「土壌汚染要調査マップ」をひとまず作成することも有効と考えられる。
また、自然由来の土壌汚染についてデータベースを作成することも検討する必要がある。
土壌汚染情報のデータベース化
土壌汚染においては原因者負担が原則ではあるが、原因者に資力が無い場合や原因者が浄化しただけでは十分な開発が困難な場合であって、当該土地を活用して地域活性化等の施策を講じる必要が有る場合には、補助金や基金の創設、税制優遇等について検討することも考えられるので、実態把握の上、更なる検討・検証を進める。
公的支援の必要性
サクセスモデルの構築
資産評価の一層の適正化
その他の有効利用促進策
今後も市場の動向を注視しつつ、信託やファンド、保険等の活用については引き続き検討を進める必要がある。
また、土地所有者、開発業者、建設業者、さらには行政担当者等の関係者が土壌汚染について必要な知識を有していれば、必要に応じて調査等の対策を講じることが可能になるため、同業者の会合や講習等を通じ正確な知識を周知するとともに、土地取引に関する不正の防止に努める必要がある。
さらに、官民の連携を進めるため、自治体の環境部局のみならず、建築部局や都市開発部局といった関係部署においても土壌汚染が土地取引やまちづくり等の大きな阻害要因となっている旨を認識し、自治体内部で一丸となって取り組む態勢づくりが必要である。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030404/03.pdf
目 次
1.はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.土壌汚染の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1 土壌汚染の現状認識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1.1 現状認識
2.1.2 土壌汚染の可能性のある土地
2.2 土壌汚染の調査・対策の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2.2.1 土壌汚染対策法に基づく調査・対策の実施状況
2.2.2 条例・要綱等に基づく土壌汚染の調査・対策の実施状況
2.2.3 民間の自主的な調査・対策の実施状況
2.3 ヒアリング等による土壌汚染の実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2.3.1 土壌汚染の発生状況と対策
2.3.2 デベロッパー
2.3.3 ハウスメーカー
2.3.4 総合建設会社
2.3.5 外資系不動産ファンド
2.3.6 産業用不動産特化型REIT 運用会社
2.3.7 大規模土地所有企業
2.3.8 地方公共団体
3.土壌汚染に係る現行制度と諸問題・取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3.1 土壌汚染の調査と情報収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3.1.1 土壌汚染調査 /3.1.2 情報収集と活用
3.2 土壌汚染の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
3.2.1 用途別基準 /3.2.2 自然由来の汚染
3.3 土壌汚染の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
3.3.1 責任負担者
3.3.2 法令上の要求措置と実態の乖離
3.4 土壌汚染の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
3.5 土壌汚染がある土地取引のリスクと財政的支援・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
3.5.1 土壌汚染に係るリスクとリスク分担
3.5.2 低利融資等
3.5.3 保険
3.5.4 保証
3.5.5 買取り
3.5.6 信託
3.6 土壌汚染地の資産評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
3.6.1 土地の資産評価の枠組み
3.6.2 不動産鑑定評価の実務における土壌汚染地評価の基本的考え方
3.6.3 スティグマの評価
3.6.4 エンジニアリングレポートの重要性
3.6.5 課税関係
4.諸外国の制度・取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
4.1 米国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
4.1.1 スーパーファンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ
4.1.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み /4.1.3 浄化修復目標の設定
4.1.4 制度的管理
4.1.5 財政支援施策
4.1.6 環境負債免除制度
4.2 ドイツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
4.2.1 連邦土壌保護法制定の経緯
4.2.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
4.2.3 浄化修復目標の設定
4.2.4 制度的管理
4.2.5 公的関与
5.土壌汚染地における土地の有効利用促進等に向けた課題・・・・・・・・・・・・・・・ 63
5.1 更なる実態・影響の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
5.2 土壌汚染情報のデータベース化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
5.2.1 土壌汚染情報データベースの構築
5.2.2 土壌汚染要調査マップの作成
5.2.3 自然由来の土壌汚染データベースの構築
5.3 公的支援の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
5.4 サクセスモデルの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
5.4.1 サクセスモデルの構築 /5.4.2 官民の連携
5.5 資産評価の一層の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
5.6 その他の有効利用促進策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
5.6.1 信託、ファンド、保険等のリスク軽減策
5.6.2 土壌汚染の正確な知識の周知と土地取引の不正防止
1 はじめに
日本の限られた国土において、土地は国民共通の財産であり、土地の適切かつ有効な利用を
実現するためには、土地を有効利用しようとする者に対し円滑に土地を移転しやすくすること
を通じた土地取引の活性化を図ることが必要である。土地取引が円滑に行われることは、国土
の適正な利用につながると考えられる。
土壌汚染問題については、土壌汚染対策法施行後注目が集まっているところであり、土地取
引市場においても、そのリスクが近年強く意識されるようになっている。国土交通省では、土
壌汚染対策法施行以前の平成14 年10 月に「宅地公共用地に関する土壌汚染対策研究会」を設
置し、翌年6 月に土地取引の安全性と円滑化の確保を目的とした土地売買契約に当たっての留
意事項や、土地建物取引業者の留意事項に関する基本的な事項等を体系的にとりまとめ、公表
してきたところである。
しかしながら、土壌汚染の判明した土地については、依然として土地取引が忌避され、土地
の有効利用や再開発、まちづくりの観点から支障が生じる事態になっている。土壌汚染の問題
は、ともすれば土地所有者が汚染事実の公表に消極的となるので、土地の有効利用にとって、
どれだけ重要な問題であるかということが社会的に十分理解されていないのではないかという
指摘もある。実態として、土壌汚染が土地取引にどれだけの影響を与え、取引を阻害している
のかを、具体的なケースを含めて、調査、把握することが必要である。
さらには、土壌汚染土地の取引に係る様々な事項について、具体的な課題を抽出・整理し、
具体的な方策の検討につなげていくことが重要である。日本では、関係者が土壌汚染リスクに
敏感となり、法的には必ずしも要求されていない土壌汚染の完全除去を実施するケースが多く、
社会的コストの増加につながっている。また、土壌汚染土地の調査については、公的に利用可
能な情報基盤や調査・評価の枠組みに、整備改善の可能性があるという指摘が多い。土壌汚染
土地の取引に係るリスク分担を整理し、保険等のリスクヘッジのスキームを充実していくこと
が、土壌汚染土地の取引活性化につながるという意見もある。
一方、コンバージェンスの一環として、減損会計の導入等の時価会計への一本化等も進めら
れており、土壌汚染地における鑑定評価の重要性が高まるなど、土地政策の観点から土壌汚染
について検討することが強く求められている。
上記の問題意識を踏まえ、土地取引の円滑化による土地の有効利用促進等の観点から、土壌
汚染土地について現状と課題を整理し、具体的な方策につながる検討を行うことを目的として、
本研究会が設置された。本研究会においては、土壌汚染土地の取引に関係する民間企業や地方
自治体へのヒアリング、米国とドイツの事例の研究を行うと共に、本研究会委員及び土壌汚染
に関する専門的な知識を有する実務者からの発表を受けた議論を行い、今後、土壌汚染地にお
ける土地の有効利用方策を検討する際の課題を整理したところである。
2.土壌汚染の現状
2.1 土壌汚染の現状認識
2.1.1 現状認識
土壌汚染の現状に関して、土壌汚染対策法や各自治体の条例・要綱等に基づく調査・対策
の報告状況の他に、民間の自主的な実施状況に関するアンケート調査等の既存資料がある。
しかしながら、土地所有者等にとって、土壌汚染の判明は新たな調査・対策費用が必要と
なったり、近隣地域との軋轢が発生するおそれが高まったり、また土地資産評価の減価要因
になりうることなどから、自ら公表しづらいという問題を抱えているため、我が国では秘匿
されがちで、個別サイトに関する土壌汚染情報を入手することはきわめて困難な状況にある。
個別サイトに関する汚染情報を把握するためには、土壌汚染の土地を取り扱うデベロッパ
ーや不動産ファンド、このような土地を所有している企業、土壌汚染に関する相談・指導を
行う地方公共団体等に個別にヒアリング等を実施することが現状では有効と考えられる。
2.1.2 土壌汚染の可能性のある土地
? 土壌汚染の発生原因
土壌汚染の代表的な発生原因として、以下の4 つがある。
・工場などで使用していた有害物質が、不適切な取扱いや老朽化等による施設、設備の破損により漏えい、流出、飛散して土壌に浸透するという事業活動が原因の汚染
・産業廃棄物が埋立処分された土地で発生するという廃棄物が原因の汚染
・事故や災害により施設、設備が故障、破損等することにより有害物質が漏えい、流出、飛散等して土壌に浸透するという、事故や災害が起因の汚染
・重金属を含む岩石や地層が風化、流出して河川や平野部、海岸に堆積した自然の土壌中に存在する自然由来の汚染
? 工場等産業用地の土壌汚染
土壌汚染は日本の産業発展に伴って発生した過去の大きな負の遺産であり、水質汚濁防止
法による規制が行われる以前は、現在では汚染物質といわれる物質の一部も合法的に土壌に
浸透させることが可能であった。現在、有害物質使用特定施設として該当する土地は全国で
27,000 箇所といわれており、またカソリンスタンドやクリーニング事業等により土壌が汚染
されている可能性のある箇所は30 万箇所を越えるといわれている。
? 廃棄物処分地の土壌汚染
過去に廃棄物で埋め立てられた土地において、土壌汚染が見つかっている。
? 幹線道路沿道の土壌汚染
幹線道路沿道の土地では、自動車からの排気ガスに含まれている鉛などによる汚染が指摘
されており、土壌汚染は日常の生活空間のまわりで広く発生していると考えられる。
? 臨海部等埋立造成地の土壌汚染
過去に埋め立てられた臨海部の土地においては、砒素などが含まれる河川や浅海域の底質
の浚渫土砂等が埋め立てに使われていることが多いことから、土壌汚染の可能性が指摘され
ている。
臨海部以外の低・平地部の埋立造成地においても、持ち込まれた土が原因の汚染が見つか
っている。
なお、当該地域以外から持ち込まれた盛土材や廃棄物により埋立造成された場合には、土
壌汚染対策法の対象となる。
? 自然的原因の土壌汚染
自然に存在する岩石、地層に含まれる重金属が風化や水の流出に伴って拡散し、低・平地
部に自然堆積した場合や、これらを含む河床や海底での堆積土砂などにより埋め立てられた
場合は、自然的原因の土壌汚染と見なされる。自然的原因の可能性のある物質として、砒素、
鉛、フッ素、ホウ素、水銀、カドミウム、セレン、六価クロムなどがある。
自然的原因による高濃度の特定有害物質を含む土壌又は水底土砂が、周辺地域において盛
土や海面を埋め立てることにより造成された土地は、自然的原因により指定基準を超過した
ものとし、土壌汚染対策法の対象とはならないが、当該地域以外の土地から持ち込まれ、専
ら自然的原因により指定基準を超過する土壌は、土壌汚染対策法の対象となり、土壌を持ち
込んだ者が汚染原因者と見なされる。持ち込んだものが不明の場合は土地所有者が必要に応
じて措置を行うことになっている。
都市部においては、本来の河川堆積物による土壌汚染に、過去からの都市活動により河川
域の汚染原因者が不特定多数で特定できない人為的な汚染が混在しているという問題がある。
自然的原因による土壌汚染を判断することは可能であるが、人為的汚染と混在した場合に
それを区分することはかなり作業が必要となる。
その区分を把握するためには、自然的汚染は含有量が一定の範囲内にあり、広域で観測され
て局在性がないなどの特色を持っているこ
とから、広域的な視点からバックグラウンド濃度などのデータを収集して分布特性等を見て
判断していくことが必要である。
2.2 土壌汚染の調査・対策の実施状況
2.2.1 土壌汚染対策法に基づく調査・対策の実施状況
土壌汚染対策法が平成15 年2 月から施行されて以後の4 年間での法適用案件は622 件で
ある。このうち、土壌汚染の指定区域に指定されたものは172 件(28%)あり、措置済みが
91 件(15%)、措置実施中・検討中が69 件(11%)あり、未処置はわずかに12 件(2%)
である。
具体的に実施された措置としては、掘削除去が最も多く76%を占め、次いで原位置浄化が
18%、舗装措置が4%、立入禁止措置が3%の順である。
図2.2.1 指定区域の状況(平成15 年2 月15 日〜平成19 年2 月14 日)
(資料:環境省「平成19 年度版環境白書・循環型社会白書」)
2.2.2 条例・要綱等に基づく土壌汚染の調査・対策の実施状況
土壌汚染対策法が施行されて以降、多くの地方公共団体で条例や要綱等が改正され、その
中に土壌汚染に関する調査・対策の実施義務や届出措置が盛り込まれた。
都道府県調べによる年度別の土壌汚染調査件数及び判明件数は図2.2.2 に示すとおりであ
り、平成15 年2 月に土壌汚染対策法が施行されて以来、土壌汚染調査件数及び判明件数は大
きく増加している。
東京都条例に基づく土壌汚染調査の対象は、
・工場、指定作業所を設置して有害物質を取り扱い、又は取り扱った者、
・3,000 ?以上の敷地内で土地の切り盛り、掘削等土地の改変を行う者である。
また、新潟県では、平成16 年9 月から施行された新潟県生活環境の保全等に関する条例に
基づき有害物質を扱う事業所については5 年に1 回土壌汚染調査の実施を義務付けているが、
まだ届出件数はわずかである。
図2.2.2 年度別土壌汚染判明件数
(資料:環境省水・大気環境局「平成16 年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」)
2.2.3 民間の自主的な調査・対策の実施状況
? 民間の自主的な調査・対策の実施件数の増加傾向
土壌汚染の調査・対策は、健康被害を防止することよりも、むしろ土地資産価値の劣化を
防止する目的で実施されることが多い。土壌汚染対策法や条例・要綱によらない民間の自主
的な調査・対策の実施件数が増加してきており、(社)土壌環境センターの会員企業に対する
アンケート調査結果によれば、土壌汚染の調査及び対策の実施件数は平成17 年度で10,812
件に及んでおり、このうち土壌汚染調査の約8 割の件数が民間の自主的なものとなっている。
土壌汚染対策法や条例・要綱に基づく調査は約2 割である。
図2.2.3 土壌汚染調査の対象
? 土地取引を契機とした自主的な調査・対策が多い
調査及び対策の実施件数の多くは土地取引を契機としたものとなっており、土地取引に際
して土壌汚染の存在の有無の確認、存在する場合の調査・対策を求めるケースが増えている
ことがうかがえる。
図2.2.4 土壌汚染調査・対策の受託件数及び受託金額の推移
表2.2.1 土壌汚染調査・対策の契機となった理由
図2.2.5 自主調査を行う契機となった理由
図2.2.6 自主対策を行う契機となった理由
2.3 ヒアリング等による土壌汚染の実態
デベロッパー3 社、ハウスメーカー1 社、総合建設会社1 社、外資系不動産ファンド1 社、
産業用不動産特化型REIT 運用会社2 社、大規模土地所有企業3 社、地方公共団体6 団体に対
するヒアリング調査等から判明した土壌汚染の実態は、以下に示すとおりである。
2.3.1 土壌汚染の発生状況と対策
? 土壌汚染の発生状況
土壌汚染は、古くから操業を行っていた工場跡地、操業中の工場用地、市街地内のメッキ
工場やクリーニング工場、ガソリンスタンド、臨海部の埋立地、廃棄物により埋め立てられ
た土地、自然由来と思われる商業地等において判明している。
? 大都市と地方との比較
ア.大都市における土壌汚染と対策
東京のような大都市内においては、土地取引や都市開発の際に土壌汚染が判明しても、
土地価格が高いことから、掘削除去などの浄化対策費用を吸収可能であることから、ブラ
ウンフィールド化している事例はほとんど聞かれなかった。
マンション開発などの際には、土地所有者による掘削除去による対策がほとんどである。
なお、大都市内において、土地履歴調査で汚染のおそれのない土地において工事中の段
階で、搬出土調査等により汚染が判明するケースが出てきている。こうした場合は、売主
と買主との間で訴訟になるケースも見られた。
イ.地方における土壌汚染と対策
新潟市や盛岡市などの地方中核都市の市内においては、最近マンション開発などの際の
調査で土壌汚染が判明したケースが見られるが、その場合は主に掘削除去による浄化対策
が実施されており、土地取引や都市開発がストップしたような事例は聞かれなかった。
なお、新潟市内において、マンション開発の際に掘削除去と併せて封じ込め措置による
対策を併せて実施している事例もあり、また住宅以外の商業施設等の立地の場合は封じ込
め措置による対策も行われている。
しかし、それ以外のエリア、又は汚染の程度が広範囲に及んでいる場合は、土地価格に
比して相対的に土壌汚染対策費用が高いことから、汚染拡散防止措置のみを行っている事
例も見られた。こうした場合は、開発を断念したり、土地取引において買主と売主との間
でトラブルになるケースが生じている。
ウ.小規模な事業用地における土壌汚染と対策
地方都市内のメッキ工場やクリーニング用地において土壌汚染が判明した場合に、土地
所有者に対策コストを負担する資金的能力が低いことから、土地取引ができずにそのまま
となっている土地が存在しているケースが見られる。こうした土地では汚染拡散防止程度
の措置が実施されている。
クリーニング工場やメッキ工場などの小規模な事業所の汚染では、対策費用の比率が高
くなり、また資力もないことから、利用促進上のハードルが高くなって、ブラウンフィー
ルド化の懸念が高まっている。
大規模な再開発の中での小規模な土壌汚染の存在については、再開発事業の中で対処す
ることが考えられるが、市街地内で単独で残っている場合は、調査すらされずにそのまま
残されてしまうケースの発生が懸念される。
なお、ガソリンスタンドが廃止又は改修する際に油による土壌汚染が判明したケースが
あるが、系列の大手会社が前面に出て調査・対策を実施しているため、問題は生じていな
い。
? その他
ア.土壌汚染情報の秘匿
今回のヒアリングは、各企業や地方公共団体による土壌汚染問題への取組みを調べるの
みならず、個々のサイトの土壌汚染情報についても把握し、今後の検討に役立てることを
も意図したものだったが、あまり個別のサイトの土壌汚染情報は聞くことができなかった。
イ.土壌汚染が判明した場合の汚染原因者でない土地所有者の困惑
土地所有者が関与していない、いわゆる自然由来、埋立由来、もらい汚染と考えられる
土壌汚染が判明した場合に、とりわけ資金負担能力の低い土地所有者にとっては、対策を
行うことが困難であるため、相当深刻な事態となっている。
ウ.調査実施後に新たな汚染が判明したケースの発生
土地履歴調査を実施して汚染がないと判断して、土地を買収して開発する際に土壌汚染
が新たに判明したケースが生じており、売主と買主との間でトラブルになったり、デベロ
ッパー側に何らかの負担を強いられている。
2.3.2 デベロッパー3社
? 土壌汚染への対応
大手のデベロッパーは、事業用地の取得に際して土壌汚染に対処する独自の調査・判定ル
ールを設けて用地取得の可否を選別している。すべての案件についてフェーズ?調査は必須
としており、土壌汚染の可能性がある場合はフェーズ?調査を実施して、取得の可否を判断
している。
土壌汚染物件の住居系への開発・転売については、原則として掘削除去など完全浄化が可
能なものである場合が多い。但し、物流施設や商業施設への転用のケースでは法令要件を満
たせば、完全浄化でなくても受け入れるケースがある。
土地取得に際しては、自然由来による汚染も含め環境基準超過土壌は完全除去を行うこと
を基本としている。
? 特徴的な事例
ア.大都市内の都市開発可能用地において土壌汚染のため都市開発を断念したケース
大都市内の都市開発が可能な土地は、通常土地価格が高いことから、土壌汚染が判明し
ても掘削除去による対策費を吸収することが可能であるが、土壌汚染が重篤な場合や、土
壌汚染が相当にあると考えられリスク評価できない場合、周辺の状況から対策ができない
場合、また土地所有者が瑕疵担保責任を負わない場合には、開発を断念するケースがある。
イ.工事中の調査で新たな汚染が判明するケース
土地引渡し前の調査では土壌汚染が判明していないが、工事中の調査で汚染が見つかっ
たケースが出てきており、事前調査の信頼性が揺らいでいる。
こうした場合は売主・買主の間で責任の範囲についてトラブルに発展しやすい。瑕疵担
保期間が過ぎた場合や売主が全く知らない場合もあり、事業者側の新たな負担となる。ま
た、追加対策のために事業スケジュールが伸びると、契約期間内の引渡しが困難になる、
金利負担が増大するなどの影響がでる。
? 意見・感想等
ア.土壌汚染問題は地方都市ほど都市開発に影響を与えるため、対策面での工夫が必要
地方都市で、ブラウンフィールドが発生する可能性は高い。地方になればなるほど土地
価格が下がり、その対策費を土地価格で吸収できなくなる。掘削除去以外の封じ込めなど
の対策を模索していくことが必要となる。
札幌市や新潟市での開発事例(分譲マンション開発)では、土壌汚染対策費は土地価格
と同程度となって負担が大きく、掘削除去による対策では採算が合わない事態が生じてい
る。このため、深さ1m まで掘削除去、1m 以深の汚染については封じ込め措置を行って開
発したケースがある。購入者に対しては土壌汚染の調査・対策の状況を十分に説明して了
解を得ている。なお、封じ込め措置による土地価格の減価は行っていない。
イ.土壌汚染処理のための新たな基準づくりについて
現在の土壌汚染の環境基準では対策が過大になりがちで、そこまで浄化処理する必要が
あるのか、疑問の声が聞かれた。土地利用に合わせて、もっと緩やかな基準があってもよ
く、行政側で新たな基準づくりが行われることが望ましい。一般に広く理解が得られ、資
産評価にも影響しないようなものが出来るとよい。
法や条例の改正により新たな項目が環境基準に追加されると既存不適格となってしまう
土地が生じ、新たな対応が求められることになり、このような土地が多いことが指摘された。
ウ.土地取引のリスクを軽減する保険制度について
瑕疵担保保険は、保険料が高いため現在利用されていない。事業者のリスクを軽減でき
るような保険があればよいとする意見や、なくてもよいとする意見があった。
エ.地方や中小の工業等事業者への支援について
土壌汚染問題で身動きのとれないで困っている地方や中小の工業等事業者に対する支援
措置があれば、望ましい。
オ.土壌汚染地を開発する際のインセンティブ
土壌汚染地を開発する場合に、開発者側のリスクを緩和するような措置や自然由来の汚
染など原因者が不明の場合については固定資産税減免などの支援措置があれば、望ましい。
<参考>
(社)不動産協会作成の「マンション開発事業における土壌汚染対策に関する留意事項」
【マンション事業における土壌汚染対策に関する留意事項】(平成14 年11 月(社)不動産協会作成)
(社)不動産協会では、平成14 年11 月に、分譲マンション事業においてデベロッパーとし
てのリスク管理の観点から考え方を示したガイドラインである「マンション事業における土壌汚
染対策に関する留意事項」を定めた。詳細は以下のとおりである。
・ 土地履歴等調査については、売主に詳細な情報の提供を求めるとともに、買主自らも土壌汚
染情報の収集を行う。
・ マンション事業用地の売買契約において、土地履歴等調査で汚染がないことが確実な場合を
除いて、土壌汚染に関する調査を売主の負担と責任において約定し、また汚染が認められない
として引渡しを受けた後に買主の調査で汚染が発見された場合は、売主に対して責任を追及で
きる旨の特約を明確に約定する。
・ マンション事業用地の土壌汚染については、売買契約において浄化処理・汚染拡散防止措置
等を売主の負担と責任において引渡し日までに実施する旨、また引渡し後に買主の調査で汚染
が発見され、買主が浄化等の措置を行った場合についても、その費用並びに損害賠償を売主に
対して請求できる旨を明確に約定する。
・ 土地引渡し後の土壌汚染の発見に備えて、売買契約書には、所有権の移転時期、土壌汚染に
関する瑕疵担保責任及び売主による浄化措置の実施義務等の条項を必ず記載する。
・ 敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を実施した場合は、購入者に対して重要事項説
明書に基づいて正確に説明し、また購入者にその報告書(写)を交付し、併せて管理組合に原
本を引き渡す。
2.3.3 ハウスメーカー1社
? 土壌汚染への対応
大手の開発案件については、独自の調査マニュアルに基づき、すべての案件で土地履歴調
査を実施している。工場についてはすべてリスクありと判断し、また、資材置き場、倉庫、
作業場等についても詳細が不明な場合はリスクありと判断して土壌調査を実施している。
マンション用地では履歴上のリスクの有無にかかわらず全案件でより厳格なリスク評価を
行っており、汚染が判明した場合は原則として掘削除去等の完全浄化を実施している。年に
数件、汚染が重篤な場合や土地価格に見合わない場合として土地取得を断念している。
商業系や駐車場用途の場合で低濃度汚染の場合は、掘削除去以外の封じ込め又はバイオ手
法などによる長期浄化の対策もありうる。
土壌汚染リスクのある土地に対しては、跡地利用に併せて調査及び浄化対策を同時に検討
することにより、最適利用しましょうという提案をし始めている。
なお、汚染があった土地を販売する場合には、完全浄化後であっても重要事項として顧客
に説明を実施している。説明後の顧客の反応は比較的良好であった。汚染の程度が比較的低
濃度で対策も掘削除去とわかりやすい内容であったこと、積極的なリスクコミュニケーショ
ンを実施したこと等から、顧客の理解が得られた。
? 特徴的な事例
ア.建設時に新たな汚染が判明するケース
造成時の盛土や廃棄物埋設による汚染は土地履歴調査では発見することが困難であり、
マンション建設時の搬出残土の調査(残土条例や残土業者の自主調査)で汚染が判明する
事例が増えている。売買契約時に瑕疵担保を定めていても、売主の経済力などの問題で回
収できず、瑕疵担保が効果を発揮しないケースが増えてきている。
イ.施設建設後のモニタリング調査で汚染が判明するケース
特別なケースとして、過去に廃棄物により埋め立てられた土地を商業開発する際に土壌
汚染が判明したため、封じ込め措置を行って施設を建設したが、オープン後のモニタリン
グ調査で汚染地下水の流出が判明したことから、土地所有者が再度流出防止対策を実施し
た事例がある。
2.3.4 総合建設会社1社
土壌汚染を抱える開発案件の最近の情報や相談事例から、土壌汚染に関して以下のような
指摘があった。
? 土壌汚染地に対する土地所有者・土地購入者の意識
土地所有者の意識として、汚染があると買手が見つからないので、売却するためには完全
浄化をせざるをえないが、対策費用が工事費の30%を超えると、売却益が見込めなくなって
売却を断念するケースが多くなり、土地保有を継続して土地利用していくこととなる。
土地購入者としては、汚染がない、又は完全に浄化された土地を購入したい、という意識
が強い。背景として、土地利用上の制約がない、後々の問題を抱えたくない、風評が心配、
再売却時に問題を残したくない、という理由がある。
? 小規模事業所のブラウンフィールド化の懸念
大都市圏では、最近の土地価格の上昇傾向もあって土壌汚染対策費用を捻出できるケース
が大半である。しかし、クリーニング工場やメッキ工場などの小規模な事業所の汚染では、
対策費用の比率が高くなり、また資力もないことから、利用促進上のハードルが高くなって、
ブラウンフィールド化の懸念が高いケースがあるように感じられる。こうした場合では、調
査や対策もされずにそのまま残されてしまうような懸念がある。
? 商業施設や倉庫における封じ込め措置の例
商業施設や倉庫については、封じ込め措置により利用している事例が出てきている。
? 地方都市におけるブラウンフィールド化の事例
地方都市の工場等跡地において売却の際の自主調査で土壌汚染が判明し、土地価格に比し
て汚染対策費用が高額になるため、売却を断念して拡散防止措置のみを行ったうえで、駐車
場等に暫定利用又は放置されている、事例が数例ある。
・ 工場を閉鎖して土地を売却する際の自主調査で土壌汚染が判明しため、重金属による汚染
部分を掘削除去して、地下水汚染のない約半分の土地を売却し、残りの半分は売却を断念し
た事例
・ 工場跡地を購入して一部の土地を売却した後に自主調査により汚染が判明したが、対策費
用が多額になるため拡散防止対策(舗装及び揚水処理)のみを実施したが、新たな土地購入
者を確保できないため、駐車場として暫定利用している事例
・ 工場用地の一部を開発事業者に売却する際の自主調査で重金属汚染が判明したが、土地価
格に比して対策費用が過大になるため、売却を断念して舗装状態のままで利用用途を検討し
ている事例
・ 製油所跡地に公共的施設を誘致する際の自主調査で重金属、VOCs 及び油による広範囲な
土壌汚染が判明したが、土壌汚染対策費用が多額となるため、売却を断念してゴルフ練習場
などとして利用している事例
・ 工場跡地の売却の際の自主調査で重金属及びVOCs による汚染が判明したため、社会的責
任の見地から土地所有者は掘削除去を実施したが、土地の売却はやめて商業施設及び駐車場
として賃貸している事例
2.3.5 外資系不動産ファンド1社
? 土壌汚染への対応
受け入れ基準は厳格で、フェーズ?調査で土壌汚染の可能性が確認されれば、土地購入の
対象としていない。土地購入の対象となる不動産は汚染がない土地である。
今後の事業展開において、土壌汚染地を扱う可能性はあるとしているが、土壌汚染地を扱
う場合にはリスクを定量評価できることが必要であり、技術面のリスク・テイクをするゼネ
コン等の関与が必要である。
? 意見・感想等
フェーズ?調査のコスト低減、確度の向上につながる情報の開示は歓迎する。
2.3.6 産業用不動産特化型REIT 運用会社2社
? 土壌汚染への対応
商業・物流REIT では、汚染リスクが残置する物件を取得するケースもあるようである。
土壌汚染地の取得に関して自主基準に基づいて判断しており、ある社では、
?適切に対策され周囲への影響がないこと、
?将来の汚染対策費が予測可能であること、
?将来売却する場合に資産価値の大幅な下落がないこと、
の3 点を投資対象の要件としている。投資の持ち込み物件には土壌汚染地が多いが、
検討の優先順位は低くなる。
しかし、一方で投資の検討対象として土壌汚染地を避けて通るのは難しい。
? 特徴的な事例
産業用不動産については、産業用地としての利用の継続性が投資対象を選択する基準であ
ることから、掘削除去にこだわる必要はなく、その他の対策も実施可能である。
将来の改築の際に発生する汚染残土処理費用や土壌改良費を見込み、土地価格から減価す
ることで、土地取引を実施している例もある。
? 意見・感想等
ア.汚染情報の開示と活用について
元来REIT では、土壌汚染情報を開示する義務がある。検討対象物件の土壌汚染情報を
得られることは歓迎するが、コストが必要な場合はコスト・パフォーマンスで判断する。
イ.エンジニアリングレポート(ER)の信頼性の確保が必要
特別な資格を有しない者が作成するER に基づいて不動産鑑定士が土地評価を行うこと
には、問題があると思われる。
ウ.埋立由来や原因者が特定できない汚染の場合についての行政側の適切な支援
埋立由来や原因者が特定できない場合は行政側の適切な支援を行う制度の構築が望まし
い。
また、優遇税制、補助金などの制度化に向けての検討を期待する。
エ.政府による用途別基準づくり
土壌汚染地の土地取引についての自主基準は持っているが、政府による用途別の基準が
あることが望ましい。
2.3.7 大規模土地所有企業3社
? 土壌汚染への対応
所有地の土壌汚染については、自主的な調査・対策を実施している。
東京都内の工場跡地を都市開発する場合は、掘削除去による土壌汚染対策を実施している。
住民・マスコミ等風評リスクを恐れる企業も少なくなく、情報開示に必ずしも積極的では
ないという企業がある一方、自らホームページ等で公開に努めている企業もあった。
関西のある企業では、関西圏に広く散在している工場跡地の十数ヶ所で土壌汚染が判明し
たため、土壌汚染のリスク管理措置として、汚染拡散防止、地下水監視などの用地管理強化、
土壌の改善措置(盛土や舗装による表層追加被覆、汚染土壌中心部の掘削除去、土壌ガス吸
引などの原位置浄化)を実施している。
? 特徴的な事例
ア.土壌汚染地の自社利用等をしているケース
土壌汚染地については、掘削除去による浄化措置を実施して用地を売却した場合や、売
却しないで自社利用している場合がある。
後者については、汚染を残した状態では土地を売却できないものの、土壌汚染対策費が
高額になることから、やむをえず研究施設、倉庫、事務所、訓練所等として自社利用して
いる面もある。
関西のある企業が所有する京都市内の工場跡地のような立地条件の良い場所はグループ
会社で都市開発している。この場合も土地は売らずに施設を建設して賃貸している。建物
基礎部分は掘削除去を実施している。
イ.土壌汚染が土地活用を阻害しているケース
立地条件のよくない工場跡地では、土地利用ニーズがあまり期待できないことや土壌汚
染対策費がかかりすぎることがネックとなって土地活用の阻害要因となっていることがあ
る。
? 意見・感想等
ア.埋立地の土壌汚染対策に係る所有者責任について
臨海部の土地は埋立由来と考えられる汚染が必ずあり、土地を購入した所有者がすべて
対策をしなければならないことに対して、疑問を感じる。
イ.原因別、用途別の基準づくりが望まれる
現在の環境基準が厳しすぎるきらいがある。埋立由来や自然由来と思われる汚染、地下
水の直接摂取の可能性が低い汚染に対しては、基準に少し配慮があっても良いのではないか。
ウ.土壌汚染地を開発する際のインセンティブが望まれる
もらい汚染、埋立由来の汚染など土地所有者が原因者でなく、原因者が特定できない汚
染に対しては、対策費用の一部補助や税の減免措置などの支援が望ましい。
地方の土地価格の安い土地の汚染については、土地が売るに売れない厳しい環境にある
と思われるため、このような土地の有効利用を促進するための支援が望ましい。
エ.土壌汚染に対する心理的抵抗感の払拭が必要
土壌汚染に対して過剰反応しすぎる面があり、リスク管理措置でも大丈夫であるという
認識が広まるように努めてほしい。
2.3.8 地方公共団体
(1)岩手県、盛岡市
? 土壌汚染への対応
行政に報告されている土壌汚染については、法や条例に基づくもの以外の民間の自主調査
によって汚染が判明したものが多い。報告のあった件については、法や条例等に基づいて相
談・指導を実施している。なお、地下水汚染が判明した場合は、行政側で周辺の地下水調査
を実施して汚染の拡大の有無を確認している。
開発区域内のクリーニング工場跡地で溶剤漏出による汚染が判明したため、土壌浄化対策
を実施している。また、地下水モニタリングを実施する必要があることから、そのスケジュ
ールが遅延するおそれがある。
? 特徴的な事例
ア.市内のマンション開発を契機とした自主調査で土壌汚染が判明
盛岡市内でマンション開発が進んでおり、開発を契機とした民間の自主調査で土壌汚染
が判明したケースが出てきている。
マンション開発の場合は土地所有者が掘削除去で対処している。
また、かつて商用地として利用され、土地履歴で土壌汚染のおそれの少ない土地を買収
した後に、買主側の自主調査で土壌汚染が判明(盛土造成による汚染の可能性が高い)し
たケースもある。こういった場合、マンション開発のため全量掘削除去したくとも、その
対策費が多額になるため、費用負担の割合をめぐって売主と買主との間で訴訟になるおそ
れが生じている。
イ.油汚染の事例
自動車整備工場による油汚染の事例や灯油流出汚染の事例が報告されている。
? 意見・感想等
岩手県内(盛岡市除く)では、工場は継続操業されており、土壌汚染問題が生じている工
場跡地は今のところ見当たらない。工場の自主調査で土壌汚染が見つかった場合は必要な対
策が実施されている。
なお、盛岡市内を除いたエリアでは、都市開発ニーズが乏しいことから、工業の継続的な
土地利用が余儀なくされている面もあると考えられる。
(2)埼玉県
? 土壌汚染への対応
土壌汚染が見つかった場合は、事業者に公表を勧めている。事業所敷地外への地下水汚染
が考えられる場合には、行政側で周辺の地下水調査を実施している。
? 意見・感想
・ 土壌汚染対策法第3 条ただし書きで調査が猶予されているケースも多く、土壌汚染が発覚
しないことがあると思われる。土壌汚染の対策としては、掘削除去がほとんどである。
・ 小規模な事業所が多いクリーニング業は、調査が行われることが少ない。同じ小規模な事
業所でもガソリンスタンドは業界の補助金制度を活用して汚染を除去している例が見られる。
・ 埼玉県内の比較的交通便利な場所では、都市開発が進みつつあるが、土地価格の上昇によ
り掘削除去対策でも採算がとれるようになってきている。
(3)新潟県・新潟市
? 土壌汚染の状況と対応
新潟県生活環境の保全等に関する条例(平成16 年9 月施行)に基づき、有害物質を扱う事
業所については5 年に1 回土壌汚染調査を義務付けている。汚染が確認された場合は県等へ
の報告が必要であるが、まだ報告件数はわずかである。
調査義務対象外の事業場の自主調査により土壌汚染が判明し届出されたものは30 件以上
であるが、その調査の契機は土地取引に際してのものが多い。土壌汚染は、金属製品製造業
等によるものが多く、またガソリンスタンドの廃止又はタンク改修によるものも5〜6 件ある。
土壌汚染は、工場跡地に限らず、商業地等においても見られる。新潟市の場合は、地質の
特性から自然由来といわれる砒素などによる汚染が見られる。また、新潟地域には油田が埋
蔵されており、また石油産業の立地が多いため、先の地震による液状化の影響で油汚染が判
明する可能性がある。
マンションなど住宅開発の場合は掘削除去による対策が最も行われている。但し、マンシ
ョン開発の場合でも、汚染が敷地の広い範囲に及んでいるケースでは、建物基礎及び含有量
基準をオーバーしている汚染箇所を掘削除去し、溶出量基準をオーバーしている箇所等は封
じ込め措置がとられているケースがある。
住宅以外の商業施設、工業系施設の場合は、掘削除去は費用がかかるため、汚染拡散防止
措置がとられるケースが多い。敷地内の他の場所に汚染土壌を移動してアスファルト舗装等
による拡散防止措置が実施されている。
なお、新潟市内において、土壌汚染のために土地取引や土地利用が停滞しているような事
例は聞いていない。また、土壌汚染地の土地取引において問題が発生しているような事例も
見当たらない。
? 特徴的な事例
ア.工場跡地等で開発等がストップしている事例
・ 自治体がかなり以前に工場跡地を取得したが、土壌汚染が判明したため、土地利用が進
まないケースがある。原因者は撤退しており、汚染拡散防止のために土地所有者である自
治体が地下水モニタリングを実施しているが、土地は未利用のままである。
・ 工場が廃止された跡地に商業施設が立地し、その商業施設を改築する際に土壌汚染が判
明したため、商業施設が改築を断念、撤退して未利用地のまま残されているケースがある。
・ 小規模なメッキ工場の廃止に際して土壌汚染が判明したが、浄化対策を実施することは
困難であるため、土地は拡散防止程度の措置をして未利用のまま残されているケースがあ
る。借地していた工場側と土地所有者との間で原状回復についての話し合いが続けられている。
イ.小規模な工場用地等の汚染の事例
小規模な工場用地の汚染の事例として、金属製品製造業の用地の汚染、クリーニング工
場用地の汚染、ガソリンスタンドの汚染が発生している。
金属製品製造業の工場用地でトリクロロエチレンによる土壌汚染(地下水汚染もあり)
が判明しているが、対策費用の関係で浄化は無理で拡散防止措置を実施している。
クリーニング工場の廃止に伴って汚染が判明した事例は2 件あり、この内の1 件は立地
条件がよい場所であったため、掘削除去による対策を実施した後に土地を売却している。
他の1 件は浄化対策が実施されたという報告は受けていない。
ガソリンスタンドの廃止又はタンクの改修に際して、ベンゼン及び油による土壌汚染が
見つかっている事例が5〜6 件ある。ガソリンスタンドのほとんどは大手の系列店であり、
大手企業が前面に出て土壌汚染調査・対策を実施している。
? 意見・感想等
新潟県内では、金属製品等製造業の中小規模事業所が多いことから、今後土壌汚染が判明
しても、自前で浄化措置を実施できないケースが出てくることが想定される。また、浄化対
策に長期間かかることや費用面の問題から、工場の操業中から汚染対策を実施していかない
と、対策ができなくなる可能性がある。
自然由来など土壌汚染の原因者が不明の場合に、対策が実施できないようなケースが出て
くる可能性がある。
(4)福島県
? 土壌汚染の状況
民間の自主調査で土壌汚染が発見された場合については、自発的に県への報告を依頼して
いる。県への報告・相談の件数は、自主調査によるものが年間数件程度、土壌汚染対策法に
基づくものは、年間0〜3 件である。
報告があった事例については情報を保管しているが、情報の公開は難しい。土壌汚染情報
全般については、現在稼動している事業所など大企業は自主調査を行っているようだが、県
で全ての結果を把握しているわけではない。
? 特徴的な事例
ア.土壌汚染地の土地利用が円滑に進んでいない事例
住宅地開発の中で、一部の土壌汚染地が未利用のままとなっている事例がある。
従前の利用は資材置き場であったが、宅地開発を行う段階で土壌汚染が発見されたが、
汚染原因者と考えられる企業が倒産したため、汚染除去費用を開発者が負担すると事業が
成立しないので、立ち入り禁止措置がとられている。
イ.土壌汚染地の土地取引・土地利用に際して問題が生じた事例
・ 工場の移転の際の自主調査によりVOC 類の汚染が発見されたため、事業者による浄化
措置が完了した後、教育施設用地として福島県が購入した。その後、県が施設を建設する
工事を行う過程で新たにフッ素による汚染も発見されたが、フッ素は事業者が行った調査
の項目に含まれていなかった。県では、教育施設用地としての土地利用を考慮して安全性
を重視して掘削除去を実施したが、汚染浄化費用は事業者と福島県で折半された。
・ 駅前広場整備工事中に土壌汚染(地下水汚染はない)が発見されたが、用地取得が土壌
汚染対策法施行前で瑕疵担保による負担金を求めることが出来なかったため、福島県が掘
削除去による対策費用を負担した。
? 意見・感想等
福島県の制度として環境創造資金という名称で公害対策用の低利融資制度を設けているが、
市中の銀行とそれほど利子が変わらないこともあって、あまり利用されていない。土壌汚染
対策を推進するために、この融資制度を広く周知し、制度が効果的に利用されるように図っ
ていく必要がある。
今後、県が公共事業土地を購入する際には、工場などの場合は土壌汚染について確認して、
契約段階で土壌汚染の浄化を附則として盛り込むことが必要かもしれない。
3.土壌汚染に係る現行制度と諸問題・取組み
3.1 土壌汚染の調査と情報収集
3.1.1 土壌汚染調査
(1)土壌汚染調査の目的及び契機
土壌が有害物質により汚染されると、汚染土壌の直接摂取や、汚染土壌から有害物質が溶
出した地下水の飲用等により人の健康に影響を及ぼすおそれがある。汚染原因者等の責任の
明確化と土壌汚染による健康被害の防止が求められる中、土壌汚染対策の法的な拠り所とし
て、平成15 年に土壌汚染対策法が施行された。同法のもとでは、特定の有害物質を取り扱っ
た工場や、事業所の敷地であった土地の所有者に土壌汚染の調査と、その結果の報告が義務
づけられている。
また、独自に条例を定め、土壌汚染調査に関して、より厳格な規定を設け
ている自治体もある。たとえば、東京都は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
において土壌汚染に関する規定を設け、3000 ?以上の土地の改変を行う場合又は有害物質
取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合、調査を実施し報告することを
義務付けている。
しかし、前述の土壌汚染対策法や自治体の条例に基づく調査は、土壌汚染調査実施例の約
2 割を占めるにすぎない。土壌汚染対策法が施行されて以来、法や条例に基づかない民間の
自主的な土壌汚染調査が増えている。企業は、環境マネジメントや資産マネジメントにおけ
る重要な活動として、汚染の可能性のある土地の実態把握、自然由来やもらい汚染の可能性
の把握などを目的とした土壌汚染調査を実施している。また、不動産取引を契機とした土壌
汚染調査も、活発に実施されるようになった。
(2)土壌汚染調査の対象物質
「土壌汚染」状況は千差万別であり、サイト毎に最適な調査・対策方法を検討し、実施し
ていくことが重要である。また、「土壌汚染対策法」が 対象とする土壌汚染は、特定有害物
質26 項目(鉛、砒素など重金属等15 項目 、およびトリクロロエチレンなど揮発性有機化
合物11 項目)であるが、その他の規制物質や規制はされていなくとも土地利用の障害となり
うる可能性のある物質もあり、注意が必要である。ガソリン、重油、潤滑油、灯油等の油分、
ダイオキシン類、その他の化学物質(条例等において特に規制されている物質、臭気の強い
物質及び色のある物質等)、要監視項目(22 項目)等の規制対象候補の物質などが調査対象
となりうる。土地取引に際しての調査では、購入用途が住宅系である場合、履歴にかかわら
【土壌汚染対策法に基づく調査の概要】
(目的) 国民の健康保護
(対象物質) 特定有害物質(重金属、揮発性有機化合物等26 項目)
(対象:調査の契機)
? 使用がず「特定有害物質(農薬類を除く)」「油分」「ダイオキシン類」を調査対象とするケースが多
い。(社)日本不動産鑑定協会策定の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」では、
「特定有害物質を中心に各自冶体の条例等およびダイオキシン類対策特別措置法において対
象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば価格形成に大きな影響があるもの
とする。」とし、法令等による調査義務がないことのみで土壌汚染が無いとはできないとして
いる。
(3)土壌汚染調査の手順と標準化
土壌汚染調査は、土壌が汚染されているかどうか、さらに汚染されている場合にどの程度
の汚染であるか、を把握するために行われるものである。しかし、土地取引や対策計画立案
など、調査実施主体が調査結果を使用する目的に応じて、調査に必要とする精度や正確さは
異なる。したがって、日本において法や条例に基づかない民間の自主的な土壌汚染調査は、
法令に基づく調査に準拠して進められることが多いが、必ずしも統一された基準のもとに実
施されているわけではない。一般的な土壌汚染調査のフローを図3.1.1 に示す。
? フェーズ?調査
地歴等調査(フェーズ?)は、土地利用履歴調査(登記簿、閉鎖謄本、古地図、空中写真
等)、地形・地質に関する調査(ボーリングデータ、地形図等)、現地視察調査(周辺状況や
対象地の現況を把握)などに基づき、土壌汚染の有無について定性的に判断する調査である。
アメリカでは2005 年にEPA(連邦政府環境保護庁)がフェーズ?調査の標準となるAAI
(All Appropriate Inquiry:あらゆる適正な調査)を改め、これに基づきASTM(米国材料
検査協会)がフェーズ?調査の仕様を改定した。AAI とは、土地の所有者、新規購入予定者
がスーパーファンド法に基づき浄化義務を免れるために実施する必要がある調査である。
改定の目的は、浄化義務を免除された後で土壌汚染が顕在化するリスクを軽減するために、資
料等調査における質の向上及び調査内容(水準)における差異の低減を図ることであった。
AAI における従来標準からの重要な変更点は、環境専門家の資格明記、聞き取り調査の対象
者拡大、資料調査の対象拡大、土壌調査報告書の有効期限設定である。
一方、日本では、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)が土地取引時に作成され
るエンジニアリングレポート(ER)のガイドラインを定め、その中で土壌汚染のフェーズ?
調査手法を提案するなどの取り組みがあるが、統一された土壌汚染調査仕様が規定されるに
至っていない。法令等に準じたフェーズ?調査を実施することによって、土壌汚染リスクが
回避されるという一般認識が存在している。簡易なフェーズ?調査で土壌汚染の可能性が完
全に否定される場合を除き、フェーズ?調査による評価が求められる傾向が強い。したがっ
て、現状では、フェーズ?調査を実施することを想定し、日本におけるフェーズ?調査の水
準はAAI が要求する水準より低めに設定されている。
土壌汚染対策法の規定に基づく調査は、環境大臣(地方環境事務所長)が指定する指定調
査機関が実施することとされており、平成20 年1 月23 日現在、1,661 機関が指定されてい
る。東京都等の自治体の条例に基づく土壌汚染状況調査についても、原則として土壌汚染対
策法に基づく指定調査機関に実施させることが定められている。ただし、指定調査機関の認
定要件は届出による簡易な書面審査が中心であることに加え、土壌汚染対策法や条例が適用
されない調査では、土壌汚染の専門家以外でも調査の実施が可能なことから、調査結果の信
頼性を問題視する意見もある。
フェーズ?調査段階では、比較的簡単に入手できる情報のみに基づく調査であることから、
調査結果に不確実性が存在する。フェーズ?調査は、汚染の可能性を調査するものであるが、
汚染の可能性がないと判断した場合でも、不十分な調査により、対象地に存在する土壌汚染
を見逃している場合があり、留意する必要がある。ある不動産関連企業が独自に実施した調
査によれば、フェーズ?調査で汚染可能性が低いと判断した土地のうち、かなりの割合で土
壌汚染が検出された。特に、造成地において、外部から搬入された盛土部から検出されたと
想定される例が多くあり、フェーズ?調査の結果を評価する上での課題となっている。
? フェーズ?及びフェーズ?調査
フェーズ?調査で汚染の可能性があると判断された場合は、概況調査(フェーズ?)を実
施する。概況調査は、土壌汚染対策法に基づく汚染状況調査に相当するものであり、表層付
近のデータを採取し、汚染の存在を確認するとともに、平面的に汚染の存在するエリアを絞
り込むものである。この調査は、環境省監修・(社)土壌環境センター編「土壌汚染対策法に
基づく調査及び措置の技術的手法の解説」に示される方法に準じて、土壌ガス調査、5地点
混合法表層土壌調査が行われる。
詳細調査(フェーズ?)は、概況調査で絞り込んだエリアについて、ボーリングにより汚
染範囲を確定する。汚染対策の実施を前提として行われる調査であり、汚染の範囲・深さ・
程度を三次元的に把握して、対策の必要性、範囲を設定し、対策費用と期間を検討するため
に行うものである。汚染範囲が広い場合は、調査にかなりの費用と期間を要する。
土地利用の変更や土地取引に際して更地の状態で調査する場合には問題とはならないが、
開発検討段階の調査や権利置換型の事業では、調査段階で従前建物が存在(権利者が生活若
しくは営業)している場合が多い。このようなケースでは、可能な範囲でしか調査できない
ため、汚染リスクの見極めが困難となり、事業成立性の判断に影響を及ぼすことが懸念され
ている。
(4)土壌汚染調査の費用
調査のフェーズを重ねるごとに土壌汚染状況の把握の確実性は高まるが、それに伴って調
査費用も増大する。フェーズ?調査の費用は、40〜50 万円/物件であるが、フェーズ?調査
では対象範囲が大きいとその費用も多額になり、資金的余裕のない土地所有者にとっては大
きな負担となる。その費用は対象地を1,000 ?と仮定した場合、概況調査で1〜2 百万円/物
件、 詳細調査は数百万/物件となる。こうした高額の調査費用は、土地取引や開発計画を断
念したり、従来の土地利用をしたりする一因となる。また、不動産の競売入札において、土
壌汚染に関する調査を考慮に入れた上で入札する良い入札参加者ではなく、土壌汚染の可能
性を無視する悪い入札参加者が選ばれる逆選択の問題が生じているという懸念がある。
3.1.2 情報収集と活用
フェーズ?調査を実施する際には現地踏査やインタビュー、依頼者から提供される書類記
録等のレビューの他に、公的機関が保有する環境情報を精査する。次章で触れるように、ア
メリカでは、汚染サイトや浄化中のサイト、埋立地や処分場、貯蔵タンク等の情報が法や制
度によって登録されており、フェーズ?調査の実施時にはこれらの情報を評価の材料として
いる。
一方、日本でも同様の手法でフェーズ?調査が実施されているが、アメリカのような法や
制度がない。環境省と一部の自治体は、それぞれ土壌汚染対策法と自治体条例が適用された
土壌汚染地の調査・改善措置に関する情報を収集し、情報提供しているケースもあるが、こ
れらの情報を制度的に集約する機関がないため、公的機関から多くの環境情報を得ることは
できない。また、法や条例の適用を受けず、自主的に実施された調査や改善措置が、土壌汚
染調査実施数の大半を占めているものの、それらを共有できる仕組みが構築されていないこ
とも課題である。土壌汚染に関して参照できる情報、資料の蓄積が少ないため、調査の案件
毎に始めから調査を実施する必要が生じている。
調査を実施して汚染が判明すると、対策の実施や公表を迫られ、企業の業績への影響やイ
メージの低下につながる事態をおそれて、調査を実施しないケースも存在する。土壌汚染に
対する社会的な見方は変わりつつあるとはいえ、自主的な調査の結果の提供については、企
業サイドも消極的となることが想定される中で、効果的な情報収集を図ることが重要である。
フェーズ?調査を実施する際には、住宅地図、不動産登記簿、土壌汚染に係る地域の基礎
的情報(土地利用履歴、過去の地形図、漏出事故・汚染記録、潜在的汚染源の位置、地下水
水質等の環境情報など)、その他、地方自治体や各省庁が所管する基礎的情報が活用される。
これらの基礎的情報が、未整備もしくは個別に収集、管理されているために、データ収集の
非効率が生じている。これらの基礎的情報・データがアクセスしやすいように整備されるこ
とが望ましい。
土壌汚染に関する情報インフラが整備されることによる効果は、前述のとおりフェーズ?
調査の品質確保や効率的な調査に資するものであり、生産性の向上にも結びつくものである。
そして、土地取引等に当たっての保険活用や担保評価に資する有用な情報となる。また、情
報インフラが整備されることにより、土壌汚染地の譲渡等があった場合、次の管理者等が土
地の情報を引き継ぐことができる。これにより土壌汚染による環境リスクの制度的管理につ
いても、次の管理者等へ承継できる。
3.2 土壌汚染の基準
3.2.1 用途別基準
住宅や産業用地といった土地の用途に関わらず、土壌汚染が環境基準の数倍でも1,000 倍
でも、環境基準を超えていれば、土壌汚染地として同様に扱われることが、土壌汚染地対策
を非効率なものとしているという指摘が多い。健康被害の防止を前提として、土地利用と関
連付けた基準作りを望む意見も聞かれるところである。しかし、一方で、土地利用と関連付
けた基準の導入においては、土地の用途変更に際して対応する仕組みづくりが必要となる。
土壌・地下水汚染対策の目標は相当にレベルが高いため、目標水準まで浄化する場合の対
策費用は高額となる。将来、土地利用の用途に合わせた基準などが設定されれば、対策費用
の低減が可能になると考えられる。
3.2.2 自然由来の汚染
明確な自然的原因は、種々の資料もあり、データがあれば正確な判断と基準設定も可能で
あると考えられる。例えば、鉱床地帯・その周辺などの鉱染地帯や変質岩帯の地域から発生
する汚染土壌(道路工事など)については、広域地質図、一部の地域の鉱染マップ、採石資
源分布図を使って類推はできる。一方、都市部の土壌を考えると、本来の自然的原因の汚染
土壌と、過去の人間活動(不特定多数の人間活動を含む。)に起因する汚染者特定不可能な汚
染土壌などが混在しており、濃度的な問題や分布の問題の挙動が同じでも、汚染者負担の公
平性から考えると、負担者の面からも安易な分類ができない場合もある。
上記のとおり、自然由来の土壌汚染に対する基準については、さらなる科学的データの蓄
積、公開が重要である。こうした視点で、地質情報、自然起源汚染情報、人為汚染情報など
の全国規模の各種地圏情報をGIS 化して情報提供するシステムとしての「地圏環境インフォ
マティクス」構築の取り組みが東北大学を中心に行われている。この中では、日本の重金属
バックグラウンドの把握、地域によるバックグラウンドの差異の把握方法の開発、地質と環
境因子との関連性の把握と、これらを共通のプラットフォームで把握する試みが進められて
いる。
現行の法規制においては、自然的原因による有害物質含有の土壌は、「人の活動に伴って
生ずる相当範囲にわたる土壌汚染」(環境基本法第2条第3号)ではないことから、同号の「公
害」には該当せず、環境基準の適用においては「汚染が専ら自然的原因によることが明らか
であると認められる場所においては適用しない」こととされているため、中央環境審議会の
2002年1月答申「今後の土壌環境保全対策の在り方について」の中で、「自然的原因により
有害物質が含まれる土壌については、人の活動に伴って生じる土壌汚染ではなく、したがっ
て環境基本法で定める公害とは言えないことから、この制度の対象とはせず、別途検討され
るべき課題であると考える。」こととされている。
専ら自然的原因により高濃度の特定有害物質を含む土壌又は水底土砂が、同様の土壌又は水底土砂の存する周辺の地域において盛土や海面埋立等により土地の造成に用いられた場合には、造成された土地は自然的原因により基準に適合しなくなったものとされ、土壌汚染対策法や条例の適用対象とはならないものとされている。
一方、土地の造成に伴い当該地域とは異なる土地から持ち込まれた土壌については、それ
が専ら自然的原因により指定基準を超過するものであっても、平成15年2月15日環水土第24
号通知「指定区域以外の土地から搬出される汚染土壌の取扱指針について」の中で、土壌汚
染対策法の指定区域以外から搬出される汚染土壌についても、同法の考え方に即した取扱い
が望ましいこととされており、土壌を持ち込んだ者が汚染原因者と見なされる。持ち込んだ
者が不明等の場合には、土壌汚染対策法第7条第1項に基づき土地の所有者が必要に応じて措
置を行うこととされている。
土壌汚染が自然由来であるかについては、環境省が土壌汚染対策法施行時に地方公共団体
宛発出した「土壌汚染対策法の施行について(平成15年2月環水土第20号)」における「土
壌中の特定有害物質が自然的要因によるものかどうかの判定法」に基づいて判断が行われる。
具体的には土壌溶出量基準を超過する場合の判断基準として、
?対象物質の種類等、
?対象物質の含有量の範囲等、
?当該特定有害物質の分布特性、
の3項目から検討することとされ、また含有量基準を超過する場合の判断基準として、
?バックグラウンド濃度又は化合物形態等、
?使用履歴場所等との関連性、
の2項目から検討することとされている。
しかし、一般的に、土地取得に際しては、自然由来による汚染も含め環境基準超過土壌は
完全除去を行うことが原則とされている。自然由来による土壌汚染が深い部分まで及んでお
り、完全除去が事実上不可能もしくは売主に完全除去を求めることが不適当と判断される場
合は、建物の根切り深さに相当する一定の深さまでの除去を求め、それより深い部分の汚染
は免責とされるケースもある。
3.3 土壌汚染の対策
3.3.1 責任負担者
土壌汚染対策法では、汚染が判明した土壌は都道府県が「指定区域」として指定・公示し、
指定区域内の土壌が健康被害を招く恐れがある場合には、汚染原因者が特定できるケースを
除き、原則として土地所有者に対策を義務づけている。土壌汚染対策法では、土地所有者等
が汚染除去等の措置をした場合に、汚染原因者に対して措置費用の請求ができることとされ
ているが、汚染原因者が不明又は破産して費用負担できない場合には、土地所有者がすべて
対応しなければならない。
現在の諸制度は、使用者や用途が変更される通常の土地取引に対応したものである。昨今
不動産証券化にてよく行われているセール&リースバックにおいては、売買取引後のテナン
トによる汚染をモニタリングすることが重要である。モニタリングの手続きや内容は賃貸借
契約に反映されることとなるが、売主と売買取引後のテナントが異なるケースについて、売
主とテナントの間のリスク分担に係る対応が難しいという指摘がある。
3.3.2 法令上の要求措置と実態の乖離
汚染の除去等の措置には立ち入り禁止、覆土、舗装(直接摂取の場合)、汚染土壌の封じ込
め、掘削除去があるが、掘削除去が選択されることが多い。これは、土壌汚染対策法上「汚
染の除去等の措置」(同法第7 条第1 項)以外では台帳から指定地域の抹消をされないこと、
将来売却する場合に、掘削除去以外の措置では価格の減価程度が予測できないこと、土壌汚
染が完全に除去されないと、封じ込め等の措置が必要になり、その間の管理コストや土地利
用への影響があるなどの課題を長期間抱え込むことになるおそれがあることなどが、掘削除
去を求められる理由である。実に、国内で実施されている措置のうち80%強が「掘削除去」
か「現位置浄化」を選択している。
掘削除去は費用が高額となるため、土地の売却益の中で吸収できる場合は実施可能である
が、そうでない場合は厳しく、土地所有者にとって売却を断念せざるを得ない事態が生じる
可能性がある。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が土地価格を上回るケースもある。とり
わけ資金力のない中小事業者や土地価格の安い地方都市において、このような事態が生じる
可能性があり、いわゆるブラウンフィールドの発生につながると考えられる。
一方、土壌汚染対策法や自治体の条例は、掘削除去措置まで求めているわけではない。例
えば、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の第114条では、対象地内
の土壌汚染により「大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に係る被害が生じ、又は
生じるおそれがある」と認められる場合は、対象地内のすべての汚染土壌について指針の定
めるところにより汚染処理を行うこととされており、また、同条例に基づく東京都土壌汚染
対策指針において、周辺環境に土壌汚染の影響が顕在化していないこと、及び掘削する場所
以外に存在する汚染土壌が外部に拡散しないことを前提として、汚染拡散防止措置を行うも
のとされており、必ずしも掘削除去が求められていない。
なお、土地取引によらない場合は土地所有者が自己利用又は土地を賃貸することになるた
め対策コストの高い掘削除去よりは封じ込めなどの対策がしやすいものと考えられる。土壌
汚染の対策コストが多額で土地を売却できない場合には、汚染の封じ込め措置をして倉庫や
駐車場等として自己利用、又は土地を賃貸して商業施設や駐車場等への利用が見られる。ま
た、産業用途の不動産取引では、自主基準を作成し、それに沿った形で土壌汚染地取得の意
思決定が行われ、完全浄化を実施せず適切に管理している例も見られる。
3.4 土壌汚染の管理
土壌汚染が発見された場合、実態として完全除去されることが多いが、土壌汚染対策法や
自治体の条例では、完全な除去まで求めているわけではない。当該敷地および敷地以外の周
辺環境において、人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれが顕在化していなければ、
完全除去ではなく、土壌汚染が周辺環境に影響を及ぼさないように汚染拡散防止措置を実施
することで対策とすることができる。そして、法や条例の適用対象とならない場合にも、こ
の基本的な考え方は適用できる。土壌汚染を残置することによって、土地所有者は土壌汚染
リスクを将来にわたって適切に管理することが求められるが、経済的な対策を選択できる余
地が広がることとなる。
土地取引においては、土地購入者にとって、封じ込め措置などの汚染が残存する土地は割
安な価格で購入することが可能であるが、一方で封じ込めた汚染土壌に係る管理などに追加
費用を要することに加え、土地の使い勝手が大きく損なわれるおそれがある。したがって、
汚染土壌を一部エリアに封じ込める措置を採用する場合は、土地利用をあらかじめ考慮した
措置とすることによって、土地の利用価値低減をできるだけ限定的なものとすることが重要
であると考えられる。たとえば、土壌汚染地の地下利用制限などの部分的制限によって、掘
削除去以外の土壌汚染対策が容易になるだろう。また、将来、土壌汚染の封じ込め措置を行
った土地を売却する場合には、利用用途が限定される可能性があることから、売却先を探す
際にマイナス要因となりうることにも留意しなければならない。
このように、健康への潜在的な被害に考慮しつつ、土地の適切な利用を確保していくため
に、官民の間で取り決めを設ける手法は、制度的管理(Institutional Control)と呼ばれアメ
リカなどで活用されている。制度的管理は、土壌汚染された土地を、土地利用制限や継続的
モニタリングなどによって、適切に管理する手法である。制度的管理は、制度の特徴から、
土地利用用途別の基準と関連付けられることも多い。
日本での適用例は少ないが、豊中市のマンション敷地において、「深い基礎が必要な高い建
物は建てず、土壌汚染の事情を知らない第三者に転売しない」という協定を市と不動産業者
が結ぶことを条件に分譲するという方式が採用されている。また、倉庫等の産業用地を対象
とした不動産証券化ファンドにおいても、部分的な利用制限や将来の建て替え時の制限を設
け、完全浄化を行っていない例が増えている。
なお、本節で取り上げた土壌汚染の管理手法は、マンション用地など個人向け不動産に適
用する上では、十分な検討が必要となる。欧米では、管理された土壌汚染地は住宅等購入者
にとって、住宅等が比較的安く取得できるというメリットが認知されている。
しかし、掘削除去以外の対策により汚染が残存している場合は、汚染土壌の継続的なリスク管理が必要と
なり、その負担を個人に求めることができるのかという不安がある。当然のことながら、所
有権の移転があれば、その役割は新しい所有者に適切に引き継がれなければならない。また、
個人レベルで、土壌汚染の存在することによる土地資産の減価リスクの適切な判断が求められる。
3.5 土壌汚染がある土地取引のリスクと財政的支援
3.5.1 土壌汚染に係るリスクとリスク分担
(1)リスクの概要
土壌汚染によるリスクについては、人の健康リスクが重要であることは言うまでもない。
しかしながら、土壌汚染地の取引に関連して、その資産価値にかかるリスクも、予測が困難
であり、リスクが顕在化した場合の影響は大きい。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が
土地価格を上回るケースもある。汚染を完全に除去しなければ、土地に残る土壌汚染の管理
が必要となり、将来、想定外のコストが発生したり、将来売却する場合に想定以上の減価が
生じる懸念もある。さらに将来の法改正で、規制対象物質が増えたり、基準が強化され、予
測できない大きな負担が生じる可能性がある。
土壌汚染された土地に係るリスク
● 措置状態の管理/監視義務対応管理/監視結果の報告義務対応
● 第三者賠償請求(近隣住民の健康被害・財産権の侵害)
● 土地利用中の再措置命令対応(濃度上昇等による)やモニタリング井戸の追加等行政指導
● 再措置命令対応による休業損害補償
● 土地利用中の法規制の変更に伴う調査・措置の再実施に関わる費用負担
● 措置済み土地で計画する形質変更が実施できない、 あるいは計画変更を求められるリスク(計画遅延含む)
● 措置計画が行政および近隣住民からの同意が得られないリスク
● 風評リスク
(2)リスク分担
日本では、土壌汚染対策法で土地所有者等に汚染除去が求められており、同法では、土地
所有者等が対策を実施した場合に、汚染原因者に対して対策費用の請求ができることとされ
ている。しかし、汚染原因者が特定できない場合や、特定できても破産して費用負担できな
い場合には、土地所有者が負担しなければならないことになる。このように、土壌汚染があ
る土地の取引においては、土地所有者(売主)と買主が負担するリスクが大きく、円滑な取
引を阻害する要因となっている。
土地所有者(売主)と買主の間のリスク分担については、民法で瑕疵担保責任が規定され
ている。しかし、瑕疵担保責任は、二者間の契約で変更が可能であるため、土地所有者(売
主)と買主のリスク分担は、二者の関係によって変わることになる。したがって、土地所有
者(売主)が優位な場合には、無過失の買主がリスクを負担しなければならないこともある。
(3)リスク軽減の考え方
土壌汚染がある土地の取引において、リスクが顕在化した場合のコスト(つまり浄化費用)
は、莫大なものとなる可能性がある。アメリカで実際に導入されている事例からも、浄化融
資ファンドや公的な保険など、様々なタイプの支援や仕組みが、土地取引関係者のリスク軽
減とリスクヘッジに寄与するものと考えられる。零細汚染責任者のように責任者に責任を負
わせることができない場合について、修復の資金供給のための適切なメカニズムを構築する
ことを望む意見も聞かれるところである。たとえば、日本にも4万箇所以上のドライクリーニ
ング施設があり、経営主体は個人が約70%弱になる。経営規模は年間売り上げベースで3000
万円未満が8割と零細層が中心であり、対策は実質的に困難であると考えられる。こうした零
細企業の所有地を再開発する場合に、開発者にインセンティブを与えることは効果的である。
(4)リスク評価
土壌汚染に係るデータベースを用いて、統計的に土壌汚染による損失を評価する手法は、
一部の金融機関で実施されている。しかし、この手法は、金融機関の数多くの担保物件を対
象として、土壌汚染による減価の総額を把握する手法であり、個別物件のリスク評価に用い
るには精度的に不十分であった。これに対し、個別物件の土壌汚染リスクを評価するツール
開発の取り組みが行われている。
土壌汚染の可能性がある土地の取引や不動産開発を検討する際、土壌汚染の実態把握のた
めに、初期段階にて多大の費用がかかる調査等を行うと、事業リスクは大きくなる。また、
将来発生する詳細調査や対策の費用の不確実性が高いために、初期の調査に踏み出せず事業
自体が断念されるケースも多い。土地開発の採算性や実現可能性を検討するような構想段階
においては、多額の調査費用を費やし、詳細な土壌汚染調査を実施することは合理的ではな
い。むしろ、地歴調査、表土調査等の簡易調査に基づいて土壌汚染対策費用のリスク評価を
実施し、マーケットリスク等を含めて不動産開発の妥当性を検討することが必要である。
しかし、地歴調査、表土調査等の簡易調査のみが実施された段階で、土壌汚染の実態を確定的
に把握することは極めて困難であるため、特に初期構想段階では、土壌汚染に係るリスクを
評価し意思決定することが重要となる。
この点に関して、評価ツールとして期待値による評価と確率分布による評価が考えられる
が、期待値で評価をしても事業キャッシュフローに関する問題点が明確にならないケースも
ある。例えば、1000 分の1 の確率で100 億円の支出が生じる場合、期待値の上での影響は
1000 万円でしかない。しかし、ダウンサイドのリスクが顕在化し多額の資金需要が一度に生
じた場合、事業が頓挫する可能性もある。そこで、こうしたリスクを評価するためには期待
値ではなく、確率分布の形を評価することが有効である。また、人は確実に100 円の利益が
得られる場合と、期待値は100 円でもリスクのある場合とでは、その事象に見出す価値が異
なる。したがって、確率分布で理解することは、リスクコミュニケーションにおいても重要
となる。さらに、多様な資金調達や保険の活用、そして先進的な不動産プロジェクトで用い
られるようになったリアルオプションには分散に関する情報が不可欠であり、当該ツールに
よって得られる確率分布は極めて有効である。
3.5.2 低利融資等
土壌汚染対策に係る低利融資制度については、政府系金融機関(日本政策投資銀行)に
よる貸付制度がある。但し、この融資制度も包括的な制度設計に至っておらず、例えば調
査費用が対象とされなかったり、自主的な調査及び改善措置費用が対象とされなかったり
等、その適用範囲は限定的なものであるため、当該制度の利用実績は低調なものに留まっ
ている。
また、その他の公的支援制度として土壌汚染対策基金が挙げられる。この基金は、土壌汚
染対策法に基づき、汚染原因行為に関与していない資力に乏しい土地所有者等に対して汚染
の除去等の費用を助成するものであり、都道府県又は政令市を通じて実施される。
当該制度についても、資力の乏しい小規模事業者等にとっては有効な支援策であるものの、厳格な適
用要件等によりこれまでほとんど利用されてこなかった。
これら低利融資及び基金については、適用要件の緩和等、より弾力的な運用を施行するこ
とで、さらなる利用促進を図ることが望まれる。
3.5.3 保険
(1)土壌汚染地に関する保険の役割
保険の役割は、関係者または特定の土地に対し、通常の事業又は浄化工事請負作業中にお
いて、汚染が顕在化した場合の浄化費用を補償するものである。土壌汚染についてリスクを
負担することができない場合に、保険を付保することによって、リスクを移転することがで
き、費用を確定し収益性の判断がつけやすくなる。また、制度的管理(Institutional control)
を採用する場合には、潜在的な環境負債者の将来にわたる長期修繕費用の支払い能力が求め
られるが、もし適切な支払い能力がないと判断された場合、当事者は債権や保険等を利用し
て財政的な裏づけを確実に得ることもできる。アメリカでは、保険を活用することにより、
土壌汚染地の浄化を伴う再開発に民間資金が集まり、再開発が促進されるという効果を上げ
ている。
(2)土壌汚染に関する保険の種別
日本国内でも、海外と同様、汚染が顕在化した場合の浄化費用を補償する土壌浄化保険
をはじめとして、第三者土壌浄化賠償責任保険などの土壌汚染関連保険が開発されている。
これらの保険商品を分類すると、事業者に対して付保する保険と、土地に付保する保険がある。
事業者に対する保険は、開発、建築等の事業の過程で土壌汚染を発生させたことに起因
する賠償費用を補償するものや、土壌汚染対策などの請負作業において汚染を発生させた
場合に、賠償費用を補償するものがある。一方、土地に対する保険としては、結果として
土地所有者等が負担した対策費用に加え、地下水汚染等により発生する周辺住民の健康被
害などの対人、対物の損害賠償費用を補償するものがほとんどである。また、土壌汚染対
策費用の超過分を補償するコストキャップ保険(超過浄化費用保険)は、対策費の上限を
予測できるため有効である(3.5.4を参照)。
(3)土壌汚染保険の普及に向けた課題
日本国内では、土壌汚染に関連した保険の普及が進んでいない。普及が進まない最大の理
由は、保険料の高さと保険引受条件の厳しさにあるようである。仮に数を集めたところで発
生要件の規則性が見いだせない(=大数の法則が成立しない)からこそ保険料が高くなり、
加えて、逆選択(土壌汚染のリスクを抱えているのが明確な人ほど保険に入ろうとする)が
生じ、最悪の場合モラルハザードにつながるため、保険の利用が進まないという側面がある。
そして、保険の利用が進まないために、大数の法則の適用が困難となり、結果として保険料
が高くなり、引受条件が厳しくなるという悪循環が生じている。さらに、保険料に加えて、
保険引受のための高額の調査費用を、被保険者が負担することが一般的となっており、この
ことも保険が利用されていない一因となっている。
リスクを定量化するためのデータの蓄積は、保険商品の開発にとって重要である。しか
しながら、日本では、土壌汚染がある土地の調査事例や対策事例に関して、入手可能な情
報が不十分であることから、土壌汚染に関する事例の蓄積を進めていくことが必要である。
また、保険の利点や内容が理解されていないことも課題である。
(4)土壌汚染に関する保険の拡充
我が国では、土壌汚染保険やコストキャップ保険をはじめとする損害保険はあるものの、
情報の非対象性を一つの大きな理由として、必ずしも保険会社が積極的にリスクの引き受け
に応じていないのが実態であるが、海外では「ファイナイト(Finite)」といわれる従来型
の保険に代わるリスク移転手段が導入されている。
ファイナイトは、「リスクの保有」と「リスクの移転」を組み合わせ、企業と保険会社の間
でリスクをシェアする機能を有するリスク・ファイナンス手法であるといえる。ファイナイ
トにはニーズに応じた様々な形態があるが、土壌汚染問題に対する適用に関しては次の例を
想定することができる。
たとえば、ある工場の経営者が、当該工場の敷地に土壌汚染の存在が発覚したため、将来、
当該工場を閉鎖し、土地を売却する場合に備えて、その浄化費用の対策を考えた。売却の際
には、汚染地の浄化が必要になるが、その対策費が1 億円から7 億円の範囲内となることが
想定され、このときファイナイト契約を5 年間で構成することした。なお、5 年以内に当該
土地の売却・浄化してしまった場合でも契約は5 年間継続させるために、対象となる土地は
売却予定以外の複数の土地を含んだ契約となり、以下のようになる。
? 初の保険金支払い事由となる浄化工事の場合の支払限度額は7 億円、免責は1 億円、2
番目以降はそれぞれ3 億円、10 億円とする。また、毎年の保険料は1 億円で変更なしとする。
? 毎年の保険料が毎年積み立てられた場合5 年間で積立て額は5 億円となる。
? 仮に3 年目で土地の売却、浄化工事が行われ、その費用が5 億円であった場合、保険
会社から1 億円の免責額を除いた4 億円が保険金として支払われる。
? 契約は5 年目まで継続し、2 件目以降の保険金支払い事由の発生がない場合、保険料
の積立て額は5 億円、保険会社からの支払額は4 億円となる。この差額のある程度の
割合は予め約定された割合に基づき、契約者に優良戻しということで 返還されること
が多い。
? 仮に3 年目行われた浄化工事が8 億円かかった場合、保険料の積立て額は5 億円、一
方、保険金の受取額は7 億円となる。
ファイナイトのメリットは、浄化費用の発生タイミングと規模に係るリスクを抑えること
ができる点である。具体的には、積み立ての場合、積立て額は段階的にしか積み上がらない
のに対し、ファイナイトであれば1 年目から最大7 億円の浄化費用の手当てができる。また、
浄化費用の額についても、上記の例で8 億円までに収まった場合、保険料としての拠出額の
合計である5 億円に免責額の1 億円を加えた範囲内に抑えることができる。
保険会社からすると、保険料の積立て額が保険支払額よりも上回った場合は、その一部を
契約者に払い戻す構成としているため、契約者がリスクを軽減するモチベーションを持ち続
けることを期待することができるため、ある程度モラルハザードを抑制することが可能とな
る。
3.5.4 保証
保証は、保険と同様に、土壌汚染リスクをヘッジする目的で活用される。保証には、浄化
工事のコストの増加分を保証する「コストキャップ保証」型、フェーズ?調査後、汚染の可
能性が極めて低いと判断した土地に対し、調査会社が自社の調査に基づく土壌汚染がない旨
の評価に対して保証する「調査後のシロ保証型」、主として土地取引の契約書の記載事項を表
明保証する「表明保証」型などがある。
浄化工事の保証は、工事の請負契約に加え、対象地、対象期間、対象物質、工事請負金
額、工事の着工および完了予定時期、保証内容、免責事項などを記載した保証書を差し入
れることによってなされるのが一般的である。浄化工事の保証内容の例について、次に一
例を示す。
浄化工事の保証内容の例
・計画土量増加および処分時の比重増加に伴うコストの負担。
・高濃度汚染の存在などにより処理方法の変更、追加が生じた場合の費用の負担。
・対策計画の範囲内に存在する廃棄物や地中構造物の撤去に関わる費用の負担。
・地下水モニタリングに関わる費用一式の負担。
3.5.5 買取り
民間ファンド等が土壌汚染リスクのある不動産を買い取り、浄化を実施後に売却することに
よって、リスクヘッジするスキームも土壌汚染土地の取引活性化に有効であると考えられる。
土壌汚染がある土地の所有者(売主)にとっては、事業地を売却したくとも、調査費用や対策
費用の捻出が困難であったり、対策工事の工期の関係で困難であったりするケースや、風評
リスクが懸念され、売却をためらうケース、さらには、売却後の瑕疵担保責任を負いたくな
いようなケースも考えられるが、買取りスキームは、こうした土地所有者のニーズに応える
ものであり、土壌汚染調査と対策の実施負担が不要で、早期に売却収入が確定し、決済が可能
となるというメリットがある。
また、魅力的な物件だが、汚染が解消できなければ買収の意思決定ができないと躊躇う
買主側にとっても、浄化された土地として検討できるというメリット
がある。
さらには、買主と売主の双方にとって、土壌汚染に絡み流動化を阻害する問題が軽
減されることになる。ただし、民間ファンド等が中間的に買い取る行為が経済的に成立する
ためには、リスクを適切に評価することが可能であり、減価して買い取ることが条件となる。
3.5.6 信託
(1)信託の現状
信託は、委託者が、その保有する財産を受託者に引渡し、一定の目的(信託目的)に従い、
特定の受益者または公益のために、その財産(信託財産)を受託者に管理、処分してもらう
制度である。国内の信託財産残高は2007年3月末で744兆円と5年で1.9倍に増加し、この内、
不動産信託も5年間で残高3.8倍(6,257件)、件数9.0倍(22兆6千億円)と増加基調を示して
いる。(データ出典:(社)信託協会ホームページ)
不動産の信託においては、土壌汚染問題に受託者が直面することがある。例えば、
? 土地取引に際し土壌調査を行うことが慣行化する前に設定した信託受益権を信託期間中に譲渡す
る際に土壌調査を実施して、信託設定時に認識していなかった土壌汚染が発覚する場合、
?信託財産の隣接地等で実施された土壌調査によって、隣接地で汚染が見つかり、信託財産の
汚染が懸念されるような場合、
? 土壌調査の対象地に建物などがあったために汚染物質を見落とす場合、
?調査方法の選択ミスや精度の問題で、事前調査では分からなかった問題が発覚する場合等が想定される。
(2)旧信託法下での土壌汚染問題への対応方法
こうした場合に対応するため、旧信託法下においても「限定責任特約」を当事者間で締結
するというという方法があった。これは、受託者が信託事務に関する取引から生じた債務に
ついて、責任財産を信託財産に限定することを個別に特約として結ぶというものであったが、
土壌汚染に関しては、受託者に過失がなかった(無過失)としても受託者に対し以下の請求
が可能だったため、信託設定や信託財産の管理を適切に遂行したにもかかわらず、受託者が
最終的に個人負担する可能性があった。
・所有者の工作物(「汚染物質を放出した建物および構築物」)責任(民法717条)
・被害を受けた土地所有者からの妨害排除請求権に基づく汚染物質の排除請求
・受託者が土地の名義人であることによる土壌汚染対策法に基づく土壌改善等の措置命令
(土壌汚染対策法第7条第1項)
(3)改正信託法下での対応方法
そこで、仮に信託不動産に土壌汚染が存在することが発覚したとしても、その責任を限定
する手法として、平成19年に施行された改正信託法で制定された限定責任信託制度の利用が
考えられる。限定責任信託とは、「受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務につい
て信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託」(同法第2条第12項)のこ
とである。限定責任信託では、受託者の対外的な責任限定の対象者を拡大し、従来の責任限
定特約とは異なり、取引関係にない者との間でも限定責任が適用される。
しかしながら、同法第217条第1項において、「信託財産責任債務」から同法第21条第1項
第8号に掲げる権利に係る債務が除かれており、「受託者が信託事務を処理するについてした
不法行為によって生じた権利」に該当する行為の範囲が問題となるが、現時点で、土壌汚染
対策法等に基づく土壌汚染に関する責任(すなわち信託法に基づかない責任)が、信託財産
を充てるべき責任なのかどうか、又は、両者の責任が分断されるのかどうかといった点が明
確にされていないことから、現時点で土壌汚染に関する責任を限定する目的で限定責任信託
を活用するのは困難であると思われる。
仮に、信託法における責任と信託法に基づかない責任が分断できるとしても、大きな土壌
汚染に対する限定責任信託の活用については、社会的なコンセンサスを得られるのか疑問が
あり、今回の法改正で土壌汚染地の信託が急増することは想定し難いと考えられる。
3.6 土壌汚染地の資産評価
3.6.1 土地の資産評価の枠組み
現在、土地の資産価値の評価については、公の機関や業界団体が関わり、考え方や算定方
法などが規定されているものだけでも、以下に示すとおり多岐にわたっており、様々な分野
でその分野のニーズ・目的に応じた評価がなされている。それぞれ評価の目的が異なるため、
当然のことながら、土壌汚染に関しても異なる取り扱いが規定されている。民間企業によっ
ては、独自の考え方で評価を行い、内部の意思決定に活用していることもある。
3.6.2 不動産鑑定評価の実務における土壌汚染地評価の基本的考え方
平成15 年1 月1 日より、土壌汚染を土地の個別的要因の一つとして、評価項目に追加し
た改正不動産鑑定評価基準が施行された。土壌汚染調査が経済的・法的・物理的な物件調査
の1 項目として、明確に位置づけられたものであるといえる。
実務上は、原則として土壌汚染対策法第2 条第1 項に規定されている特定有害物質を中心
として、各自治体の条例等及びダイオキシン類対策特別措置法及び各自治体の環境条例等に
おいて対象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば、価格形成に大きな影響
を与える可能性が生ずると理解される。
上記の土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法及び各自治体の環境条例等は、人
の活動に伴う人への健康に係る被害の防止の観点から規定されている一方で、不動産鑑定評
価において考慮すべきは、土壌汚染が価格形成に影響を及ぼす場合であることから、自然に
由来する土壌汚染も考慮にいれる必要があり、法令等による調査等の義務がないことをもっ
て、土壌汚染がないということはできない。
現状では対策が掘削除去中心であることから鑑定評価もそれを前提にする場合が一般的で
あるが、今後掘削除去以外の措置が講じられるようになれば、それらを的確に反映するよう
な鑑定評価を行う必要があり、必要に応じた実務面の見直しと普及が必要である。
既に、 (社)日本不動産鑑定協会作成の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針
(以下「運用指針」という。)?、?」がガイドラインとして示されている。運用指針Iでは、
鑑定士が行うべき独自調査のあり方が記載されており、運用指針?では、土壌汚染地におけ
る対応のステップが示されている。
運用指針では、土壌汚染の疑いのある場合には、不動産鑑定士が独自調査を行った上で、
その結果と、既存の土壌汚染調査結果を明記し、汚染の分布状況、除去等に要する費用等を
他の専門家が行った調査結果等を活用して鑑定評価を行うものとされている。
これまでのところ、土壌汚染地の鑑定依頼件数は少なく、したがって土壌汚染土地の鑑定
評価の経験を積んだ不動産鑑定士は少ない。また、土壌汚染に関する鑑定評価が可能なレベ
ルの調査が実施されていない段階で、鑑定評価を依頼されるケースも多いのが現状である。
<参考>現在の取組み
・ 土壌汚染地に係る鑑定評価については、平成14 年の鑑定評価基準の改正時において、
土壌汚染が価格形成要因の一つに位置づけられたところである。実務面においても、(社)
日本不動産鑑定協会で「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」の策定・改定、
それに基づく研修等が実施されている。また、土壌汚染の鑑定評価の実務に関するワー
キンググループが設置され、継続的にケーススタディー等の検討が行われている。
3.6.3 スティグマの評価
土壌汚染の存在(過去に存在したこと)に起因する心理的な嫌悪感等から生ずる減価要因
をスティグマという。また、広義には、前述の心理的要因に加え、土壌汚染に起因して将来
追加コストが発生するリスクを加えた減価の根拠をいうこともある。土壌汚染地の資産評価
は、概念的には次式で表現されている。
個別の土壌汚染地及び評価時点により、スティグマの程度・内容は異なるので、評価ごと
に、求めるべきスティグマを勘案する必要性が生ずる。
日本におけるスティグマの調査事例としては、住宅用地に関する市民アンケート調査((財)
日本不動産研究所、明海大学2003 年実施)がある。当該調査結果によれば、いずれも浄化
後を想定した質問を行ったところ、汚染対策が行われたとしても購入を控えるという回答が
多く、スティグマが存在することがわかった。スティグマの大きさは、購入の場合も、賃貸
の場合も、20%から30%が最も多く、次に50%というものであった。
これに対し、デベロッパー、銀行、不動産仲介業者側は異なる考え方を示している。国土
交通省実施の「民間土地取引に係る土壌汚染地の取扱実態に関する調査」によれば、デベロ
ッパーは、マンションも、オフィスも原則として掘削除去を実施後スティグマなしで販売し
ており、スティグマを斟酌しない考え方が一般的である。また、マンション開発で、掘削除
去を実施していない場合においても、十分なリスクコミュニケーションを販売前に行うこと
によって、スティグマを考慮せずに販売価格を設定している例もある。
銀行は、担保評価上、浄化措置が前提であり、浄化後のスティグマに関しては、対応が分かれている。不動産仲介
業者は、用途等を踏まえて取扱い、浄化後スティグマを考慮に入れた上で対応を行っている。
以上のように、スティグマについては誰が土地を取り扱うかで対応が分かれており、不動
産市場で、スティグマによる減価の取扱いについて、今後のさらなる検討が必要である。
3.6.4 エンジニアリングレポートの重要性
平成19年4月に改正された不動産鑑定評価基準においては、証券化対象不動産の鑑定評価
にあたり、鑑定士は、土壌汚染について、エンジニアリングレポート(以下「ER」という。)
や鑑定士の独自調査により的確に判断しなければならないとされている。
一方、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)は、平成19年4月に新しいERのガ
イドラインを作成した。BELCAのガイドラインによれば、ERは「建物状況調査報告書」、「建
物環境リスク評価報告書(フェーズ?)」、「土壌汚染リスク評価報告書(フェーズ?)」、
「地震リスク評価報告書」の4つの報告書から構成される。
建物環境リスクにおいて、土壌汚染に関しては、フェーズ?調査が標準として位置づけ
られ、REC(Recognized Environmental Condition:使用履歴のある有害物質や石油製品
等が、現時点で漏洩している状態にある、過去に漏洩した履歴がある、あるいは将来にお
いて漏洩が発生することが十分に懸念され、土壌や地下水に影響を引き起こすような状況
のこと。)の有無及び内容を結論として提示することとされている。一方、証券化対象不
動産の鑑定評価においては、汚染リスクの価格に対する結論が要求される。
BELCAのガイドラインでは、フェーズ?でRECやデータギャップが指摘されたら、それ
を定量的に評価することとされており、これはフェーズ?で汚染がないことが完全に示さ
れない限り、フェーズ?が必要となるとも理解される。
しかしながら、BELCAのガイドラインには拘束力はなく、エンジニアリングレポートに
は様々なレベルのものが見受けられるため、鑑定評価に活用するという視点から必要とさ
れる内容等について検討し、整理していくことが必要である。
このため、(社)日本不動産鑑定協会において、エンジニアリングレポート関係者との
共同研究会や、エンジニアリングレポート関係者の協力による研修などが実施され、実務
面での取組みが進められており、今後は、これらの取組みを継続・発展させ、着実に実務
に反映させることが重要である。
この際、不動産鑑定とエンジニアリングレポートの制度面の差異やエンジニアリングレ
ポートの提出は鑑定士ではなく、鑑定評価の依頼者に対してであるなどの難しさはあるが、
両者の連携により、それらの課題を克服することが強く求められる。
3.6.5 課税関係
土壌汚染された土地についての課税関係における評価では、減額項目を見込むか否かの考
え方において税による差異が存在する。
固定資産税については、何万筆もの土地を同時に評価するという大量、一括性に特徴を有
すると同時に、課税のための評価であることから評価の均衡、公平の確保が重要である。「土
地に関する調査研究(平成18 年3 月)−土壌汚染対策法と固定資産税評価について−(資産
評価システム研究センター)」によれば、汚染の除去等の措置費用を減価要因とすることは必
ずしも適当ではなく、当該土壌汚染地の現況に着目し、当該土地の利用の制限を減価要素と
することとしている。また、心理的要因については、その影響の有無が不確定であること等
から、基本的には考慮しなくても一般的には差し支えないと考えられるとしている。
一方、相続税については、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」(平成16 年7
月5 日付国税庁課税部資産評価企画官情報第3 号、資産課税課情報第13 号)が示されてい
る。相続税における土壌汚染地の評価額は、土壌汚染がないものとした価額から、浄化費用、
使用収益制限による減価、心理的要因による減価を考慮することとされている。相続税等の
財産評価においては、課税時期において、評価対象地の土壌汚染の状況が判明している土地
を土壌汚染地としており、土壌汚染の可能性があるなどの潜在的な段階では土壌汚染地とし
て評価することはできないものとしている。
なお、相続税を公示価格を用いて評価する場合には、評価が公示価格の80%を基準として
いることから、減価は土壌汚染浄化額の80%としている。また、土壌汚染の原因が被相続人
であり、第三者からの損害賠償請求により債務が確定しているときは、債務として計上でき
る場合もある。相続開姶後に土壌汚染が判明した場合であって、土壌汚染の原因を第三者に
特定することができ、除去費用について、当該第三者に求償権を有するときは当該求償権を
資産計上する。
4.諸外国の制度・取り組み
諸外国として、土壌汚染問題関連の情報が比較的多く収集されている米国とドイツの二ヶ
国を対象とし、それぞれの国の土壌汚染問題への取り組み状況について、以下の5 つの視点
から分析整理した。
各国のはじめで、取り組み状況の分析整理の前提として、米国に関しては、スーパーファ
ンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ及びそれぞれの法制度の概要につい
て整理し、また、ドイツに関しては連邦土壌保護法制定の経緯について整理した。
なお、ドイツに関しては、「財政支援施策」及び「環境負債免除制度」の項目に関しては、
詳細な情報が不足しているため分析対象から除外した。
【分析整理の視点】
・ 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
・ 浄化修復目標の設定
・ 制度的管理
・ 財政支援施策
・ 環境負債免除制度
4.1 米国
4.1.1 スーパーファンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ
(1)スーパーファンド法
1)立法に至る背景
米国では、1970 年後半から有害廃棄物汚染による環境災害が立て続けに発生し、災害によ
っては国家非常事態宣言の発動もあった。しかし、それまでの法制度では、土壌、地下水、
地表、水、大気の汚染に対して、連邦政府が直接関与できる法的権限はなかった。このため、
有害物質汚染災害や土壌汚染から国民と環境を保護するための新たな法制度の整備が必要と
なり、1980 年に連邦議会が「包括的環境対処・補償・責任法」(以下「スーパーファンド法」
という。)を成立させた。これ以降、連邦環境保護庁(以下「EPA」という。)が主担当官庁
となって、連邦政府レベルでの取り組みを開始した。
その後、1986 年にスーパーファンド改正・再承認法(以下「SARA」 という。)が施行さ
れ、スーパーファンド法の立法内容の強化・拡充がなされている。
2)スーパーファンド法の概要 (注1)
? 汚染者負担主義
スーパーファンド法の基本的考え方は、汚染者負担主義であり、当該サイトの汚染に何ら
かの関わりがあったあらゆる個人ないし企業を潜在的責任当事者とし、サイトの浄化及び住
民の健康や自然環境に与えた損傷への補償責任を求めた。潜在的責任当事者とは、汚染物質
の排出者、運搬者、貯蔵者、投棄・処理者等有害物質の放出または放出のおそれに関与して
いる者をいい、判例により汚染物質を廃棄している施設の所有者や創業者に対して融資を行
っている金融機関等直接的に問題となる汚染に繋がっていない者も、汚染修復の資金負担責
任を抱えることになった。また、スーパーファンド法施行以前の関与の責任も負わねばなら
ないという極めて厳しい責任原則主義が基本となっていた。
? 財源の手当て
EPAは2つの財源を手当てしており、1つは責任者負担によるサイトの浄化と補償であり、
もう1つは責任主体に支払い能力が無い場合や責任主体が不在となる場合への対応のため、
危険物質を製造したり、あるいは利用する産業に目的税を課し、これを基金化(有害廃棄物
信託基金(トラスト資金))して、遊休地化したり、放棄されているサイトの浄化資金とした。
(ただし、この税制は制定後15 年間で失効した。)
? 措置の種類
スーパーファンド法では、有害物質のリスクの程度に応じ、短期又は長期のいずれかの対
応がなされる。
・ 除去措置(Removal Action):短期の対応。健康被害と緊急の環境リスクに対応するもの。
・ 浄化措置(Remedial Action):長期の対応。通常の浄化措置の流れを追って実施するもの。
? CERCRIS とNPL
CERCRIS(the Comprehensive Environmental Response, Compensation,and Liability
Information System)とは、米国内の有害物質による汚染の懸念のあるサイトと当該サイト
における調査等の状況が全て登録されている連邦政府作成のデータベースである。CERCRIS
に掲載されているサイトは、一定の手続きを経た後、連邦政府や州のスーパーファンドサイ
トとして登録される可能性のあるサイトである。
このうち、最も深刻な汚染サイトとして、早急に浄化措置を行うべきサイトに優先順位を
つけてリスト化したものがNPL(National Priority List:国家緊急リスト)である。
? スーパーファンド法による問題と対応
スーパーファンド法の責任原則に関連してさまざまな問題が発生し、それらの問題を改善
するために、さまざまな運用上の工夫や修正を加えて今日に至っている。
a.関係当事者間による訴訟の多発
汚染サイトの浄化コストが高額になるため、同じサイトの潜在的責任当事者同士に責任
分担の訴訟が多発し、訴訟問題で資金を浪費し、また、訴訟が長期化し、浄化事業の遅延
化を招いた。
この問題への対応として、1986 年に施行されたSARA において、小規模の当事者で、「寄
与割合が僅少の」または「寄与割合が極小の」当事者は、早期に和解できることとした。
「寄与割合が極小の」当事者については、負担無しで和解できることとした。
SARA のその他の主な改正内容は以下のとおりである。(注2)
・ 「無実の土地所有者保護措置」の創設とその適用要件としての「全ての適切な質問」の規定
・ 資金調達方法の改良(トラスト資金の増額)
・ 浄化に関する永続的な改良策の開発、利用の強調
・ 地域住民への重度汚染化学薬品の存在に関する情報公開の義務付け
b.環境リスクをカバーする保険商品の普及
潜在的責任当事者と保険会社の間でも浄化コストの資金的埋め合わせをめぐって訴訟が
多発したが、スーパーファンド法への対応について、保険の必要性も高まり、施設の被害、
浄化費用負担、プロジェクト遅延、ビジネス中断、担保価値下落、風評被害、契約不備等
のあらゆる環境リスクをカバーする保険商品が契約可能になっている。これらの保険商品
が開発されたことにより、リスクを潜在的に抱えているサイトの売買、浄化、開発が容易
になってきている。
c.不動産業界への影響
スーパーファンド法により不動産業界はネガティブな影響を大きく受けた。不動産開発
業者は、潜在的責任当事者になることを恐れて、環境リスクのある不動産取引を敬遠し、
汚染サイトの遊休地化、放置化が促進されてしまった。
この問題に対して、EPA と各州政府は、再開発を促進するために、税制や補助金、融資
などの財政支援の充実化や環境負債免除制度などの規制面の保護政策強化への対応措置を
講じてきている。これらの措置により、汚染サイトは、不動産業者にとって割安であり、
かつ立地条件も良いことなどから、経済的メリットのある開発適地へと蘇生される可能性
が高まる方向となった。
(2)ブラウンフィールド法
1)立法に至る背景
スーパーファンド法の施行以降、土壌浄化の汚染者負担原則及び浄化の義務付けが明確化
されたが、この法的責任に関連して、他の汚染主体との浄化コスト負担に関する訴訟の多発
や、浄化リスク発生を嫌って、土壌汚染サイトの土地取引の停滞等の問題が発生し、EPA で
はさまざまな改善策を講じてきたが、より効率的な浄化プロセスの構築と再開発促進を狙い
として、ブラウンフィールド法(小規模事業者の責任免除及びブラウンフィールド再活性化
法)が2002 年に施行された。
2)ブラウンフィールド法の概要 (注3)
ブラウンフィールド法では、浄化プロセス効率化の観点から、浄化修復事業の長期化・遅
延化の一因となっていた小規模零細企業の責任問題への対応を図り、また、ブラウンフィー
ルドの土地取引活性化への観点から、浄化後のサイト所有への免責保護の規定の明確化及び
財政支援策の拡充を図った。
? 小規模企業の浄化責任保護
スーパーファンドサイトの浄化責任を負っている企業のうち、以下の条件を満たす事業者
は免責される。
a.産業廃棄物の排出事業者または、収集運搬業者
有害物質の取り扱い量が液体100 ガロン、固体200 ポンド以下で、全ての廃棄、取り扱い、
輸送を2001 年4 月1 日以前に行っていた場合
b.生活系廃棄物(身の回りで出るごみ)の排出者以下の条件を満たす場合、免責される。
・住宅地の所有者、管理者、借地人である場合
・潜在的浄化責任の通知が届けられてから、さかのぼって3 年間の平均従業員数が100 人
以下で商業活動を営んでいて、かつ法律による小規模企業体に該当する場合
・廃棄物を発生させたNPO で、前の年の従業員数が100 人以下の場合
? ブラウンフィールド再活性化と環境修復
a.ブラウンフィールド再活性のための財政援助(補助金及びブラウンフィールド再活性化ファンド)
以下の財政支援関連施策が盛り込まれた。
・ 総額で年間2億ドルの財政援助(うち、5,000 万ドルまたは25%を石油関連物質のブラウンフィールドサイトに充当する)
・ ブラウンフィールドサイトの再定義
以下のように再定義し、ブラウンフィールドの範囲を拡張した。
「有害物質や汚染物質の存在、もしくは潜在的に存在しうることが確認されていること
により、増築や再開発、または再利用が困難と思われる土地」と定義し、産業用地以外の
土地、例えば住宅地や商用地等において過去の土地履歴等により土壌汚染が存在する可能
性がある場合の再開発時においても、財政支援の優遇措置を適用できることとなった。
・ ファンドの対象拡大
石油及び石油関連製品を対象に追加
・ ファンドから支出できる用途の拡大
サイト調査に対して20 万ドル以下、浄化に対して100 万ドル以下を対象として追加
b.ブラウンフィールド責任の明確化
以下の主体に対する責任を免除した。
・ 隣接所有者をスーパーファンド法の責任から免除(流れ汚染に対する保護措置)
・ スーパーファンドサイトの買い手の保護
・ 善意の土地所有者(適切な商習慣に従った土地の取得で、全ての適切な調査(AAI)を行っ
た上で土壌汚染の事実を知る余地がなかった場合)の保護
・ AAI の定義(AAI 自体はSARA で創設されたものであるが、何をどの程度行えばいいの
かが不明確であった。このため、ブラウンフィールド法が出来るまでのアメリカにおいて
は、環境アセスメントビジネスが発達し、フェーズ?調査として結実することとなる。)
c.州のブラウンフィールド対策プログラムへの支援
・ 毎年5,000 万ドルまでの補助金を州対策プログラムに支出
・ 対象サイトの拡大
4.1.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
土壌汚染情報は土地の安全性を知らせる公益的な情報として位置づけられ、米国では、
多くの州が土壌汚染情報に関するデータベースを作成し、ウェブサイトでの一般公開を行っ
ている。ここでは、ニューヨーク市とオクラホマ州の取り組みについて取り上げた。
(1)ニューヨーク市
ニューヨーク市のブラウンフィールド問題への取り組みの12 の具体的な内容の一つとし
て、「潜在的なブラウンフィールドを把握するための過去からの土地利用のテータベースの作
成」が掲げられている。
【目的】
以下の3 点が示されている。
・ 潜在的でかつ優先的な取り組みが必要なブラウンフィールドを見つけること
・ 地区ごとのブラウンフィールドの再開発計画への基本的な情報を提供すること
・ すべての土壌汚染地の浄化と再利用活動の目標を明確にすること
【データベース作成方法】
以下の2つの方法が示されている。
・ 各種情報の収集
(環境関連の発行物・データベース、歴史的な地図、電話帳、財務記録などからの情報収集)
・ 年ごとのブラウンフィールド関連環境アセスメントへの要望についての問い合わせ
(2)オクラホマ州
社会環境の保全のためにブラウンフィールドの制度的管理が重要であるとの認識の下に、
オクラホマ州環境局では、ブラウンフィールドを含めた土地利用の管理に向けて法制度を整
備している。
土地利用管理の具体的な内容として、ブラウンフィールドの制度的管理についてのデータ
ベースをくまなく蓄積している。
4.1.3 浄化修復目標の設定
ブラウンフィールドの浄化修復目標に関しては、汚染されている土壌の位置(地表からの
距離)、汚染の程度、その跡地における将来の用途などを考慮して、人体に対する曝露の危険
性(リスク)を計算し、そのリスクに応じて、環境浄化修復手法を選択する「リスクベース
基準」に基づき設定する方法が一般的になっている。
跡地が工場用途になる場合と幼稚園の砂場など子供が土で遊ぶ場所とでは、当然に浄化修
復レベルは異るという考え方をとっており、そのために必要な事業方法、費用も異なる。
このため、リスクベース基準の適用においては、跡地の用途が将来にわたって遵守される
必要があり、基準の設定とともに用途制限措置の設定が重要となる。
(1)浄化修復目標の設定及び適用方法に関する分類
米国の各州の浄化修復目標の設定及び適用方法は大きく、表4.1.1 に示す3つに分類され
る。また、それぞれの分類のうち、一つの州ずつ、内容の把握整理を行った。
表4.1.1 米国各州の浄化修復目標の設定及び適用方法の状況
(2)マサチューセッツ州
マサチューセッツ州の浄化修復目標の設定にあたっては、汚染された土壌や地下水の人体
及び環境への曝露の程度とともに、将来の跡地利用方法を密接に考慮して設定しており、こ
のため、土壌汚染が存在する土地に対して、その用途制限も行っている。
1)土壌の環境基準
土壌環境基準は3 つの土壌分類によって異なる基準が定められている。分類は、土壌に対
する可触可能性、受容者の存在の性質、土地の利用頻度、土地の利用の強さの4 つの土地固
有の要素によって分類される。これらの土壌分類は、土壌の受容者に対する曝露の程度を規
定しているものであり、これらの分類は互いに排他的である。
【マサチューセッツ州の土壌の環境基準】
S-1:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい(主に住宅・学校など)
現在又は将来において人間が摂取する野菜や果物を育てるため利用することができる
子供の頻繁な利用または、熱心な利用が行われる可能性が高い土壌はS-1 に準ずる
大人の頻繁かつ熱心な利用が行われる可能性が高い土壌はS-1 に準ずる
S-2:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい
子供の頻繁な利用も熱心な利用も双方とも行われる可能性が低い土壌はS-2に準ずる
子供が対象地に立ち入らず、大人の頻繁な利用又は熱心な利用が行われる可能性が高い土
壌はS-2 に準ずる
S-3:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい(駐車場の下など)
子供が対象地に立ち入らず、大人の頻繁な利用または熱心な利用が両方とも行われる可能
性が低い土壌はS-3 に準ずる
表4.1.2 マサチューセッツ州危機管理計画の土壌カテゴリー
2)地下水の環境基準
地下水環境基準は、地下水の汚染の結果に由来する異なる曝露の可能性を規定する3 つの
地下水分類によって定められている。これらの分類が異なる曝露の可能性を規定しているた
め、地下水の分類は互いに排他的ではない。すべての地下水は最終的に地表水に流れ出す可
能性があると考えられるため、すべての地下水はGW-3 の分類の水質基準を遵守する必要が
ある。土地固有の要素により、GW-1 やGW-2 に分類される可能性がある。
【マサチューセッツ州の地下水の環境基準】
GW-1:飲料水としての現在または将来の利用の可能性に基づき保護されるべき分類
GW-2:屋内の空気に対する揮発の水源となってもよいとされる分類
GW-3:石油や危険物質を地表水に対して放出する可能性がある分類
(2)カリフォルニア州
カリフォルニア州のブラウンフィールド浄化修復活動への要請事項は、NCP(国家石油及
び危険物汚染緊急対策)と連邦政府のスーパーファンド法の規定に準拠している。NCP の浄
化目標では、土壌別の基準というよりも発癌性の物質では10-4 から10-6 までの範囲に収まる
よう浄化修復を達成することといった基準であり、特定のサイトごとのリスク分析に基づい
て目標水準を設定し、跡地の土地利用に関係なく永続的な浄化修復を行うことを推奨している。
一方、EPA では、このような目標水準の実行可能性や、商業や産業用途の再開発が多い中
で、一律に住宅用途に対応した浄化修復を行うことは必要以上の対応であるとの判断を持っ
ており、跡地の土地利用に対応した浄化修復目標の設定を許容している。これは、リスクベ
ースのアプローチといわれており、浄化修復コストや健康リスク、跡地の土地利用、地域コ
ミュニティの許容性、技術的可能性などのさまざまな要因のバランスの下に浄化修復目標を
設定する方式である。
しかし、この方式は多くの環境上の判断を必要とし、恣意的に水準が適用される場合もあ
り、また、費用を節約するために必要とされる水準以下の浄化修復を行うことにより、汚染
物質が残存する問題も生じている。
これらの点から、カリフォルニア州としては、一律的な浄化修復目標水準の設定は難しい
と判断し、汚染地域の浄化修復事業に対して、以下の3 つの戦略により対応している。
【浄化修復目標水準設定の戦略】
a.バックグラウンドレベル(汚染されていない状態)までの浄化修復に向けての水準
バックグラウンドレベルについての一定不変の水準を持っている訳ではなく、各部局で
個別に設定している。
b.個別汚染地域ごとのリスクアセスメントに基づく浄化目標水準の設定
個別汚染地域ごとのリスクアセスメントに基づく浄化目標水準を設定し適用することを、
カリフォルニア州の基本的アプローチとしている。
c.州全体からのリスクベースの浄化目標水準の設定
以下の要因によるタイプ別リスクの想定に基づき、浄化目標水準を設定する。
開発事業者はまず、これらのタイプ別水準から控えめな水準との比較を行い、より高い
水準で比較する場合には、汚染地域ごとに実施するリスクアセスメントに基づく浄化目標
水準を適用する。
【タイプ別リスク設定の要因】
・汚染物質の人体への取り込みかた(摂取、吸入、皮膚からの感染)
・汚染源(土壌、空気、地下水)
・周辺土地利用(住宅地、商業地、工業地)
(3)ニュージャージー州
ニュージャージー州では浄化修復活動を行う上での目標水準として、リスクベースの基準
に基づき、以下の3 ケースに分けて、土壌と地下水に分けて設定している。
【浄化修復の目標水準】
a.無制限の跡地利用に対応する水準
b.条件付きの跡地利用に対応する水準
c.自然の自己回復力を考慮した条件付きの跡地利用に対応する水準
【浄化修復の目標水準の適用上の留意点】
・ これらのどの分類についても、汚染原因物質は除去されなければならない。
・ 土壌汚染物質については、発癌性のあるもの、非発癌性のものに分けて設定している。
・ 土壌の浄化修復においては、リスクアセスメントに基づいて設定された特定ケースの基
準の適用も認めている。
・ 適用される水準がそのサイトの周辺地区の水準よりも低い場合は、周辺地区の水準を適
用する。
・ そのサイトの土地利用が制限されている場合は、特別の注意書きを表示する必要がある。
4.1.4 制度的管理
制度的管理とは、ブラウンフィールドに対して、土地利用制限及び法的な管理により、健
康や自然環境への潜在的な被害を最小限にしつつ、ブラウンフィールドの有効利用を適切に
確保する法的措置等の取り決めを意味し、以下に示すブラウンフィールドの環境改善の一般
的プロセスのうち、段階5 に位置づけられる。
【環境改善の一般的プロセス】
段階1:地歴調査・聞き取り調査予備的な調査及び環境関連部局への通知と早期リスク削減措置の必要性の判断
段階2:包括的な土壌調査(アセスメント)、用途に対応したリスク影響調査アセスメントの実施により、汚染の原因、特性、程度、潜在的な影響の把握
段階3:環境改善計画の立案浄化計画とプロセスの評価、決定
段階4:浄化修復事業の実施
段階5:制度的管理継続的な浄化水準の維持管理
一部の州では、土壌汚染処理コストを低減させて土地の再利用、用途転換を円滑にするた
めに、人体の健康に対するリスクがない範囲において封じ込め等の部分的な処理を認めてい
る。このような完全浄化以外の対策が実施される場合には、土壌汚染による人体への暴露リ
スクを低減するために、一般の用途地区に上乗せするかたちで、土地利用制限などの制度的
管理が行われる。
制度的管理の目的は、土壌や地下水に含まれる未処理の汚染が人体に対して暴露する危険
性を管理するために、ブラウンフィールド再開発後の用途及び活動を限定して汚染土壌の封
じ込めを維持するためのものである。
(1)活動用途制限
マサチューセッツ州では、全米でもいち早く土壌汚染の制度的管理手法を導入しており、
AUL(Activity and Use Limitations)と呼ばれている活動用途制限を設けている。このAUL
は、現在及び将来の土地所有者に対してその土地で許容される活動や利用が示されており、
許容されていない用途に変更する場合は、新しい用途に応じたリスクの評価と追加的な浄化
が求められる。
この制度は、土壌汚染を全て除去するためには多額の費用がかかり、跡地利用にとって現
実的な解決策ではないため、汚染土壌を地下に残したまま人体に対して暴露されることを防
ぐために、土壌汚染が存在する土地に対して用途制限を行う制度である。
許容される土壌汚染の暴露の程度は汚染された土地の跡地利用によって異なるため、跡地
利用に応じて到達すべき浄化目標を設定して、その目標達成に適した方法で浄化を行う。こ
の浄化は、汚染自体の濃度を下げることのみでなく、汚染に対する暴露を取り除く、もしく
は最小化することでもよい。完全浄化によらず、汚染が残された場合には、活動利用制限を
設定して将来にわたり汚染の暴露状態が変わらないように継続的に土地を管理していくこと
になる。
マサチューセッツ州では、図4.1.1 に示す体制でAUL を実施している。用途制限されてい
る土地のAUL に係る情報は、州環境保護局のほかに自治体と郡不動産登記所で管理してお
り、この土地の再開発や土地取引に際しては、環境通知書によって土壌汚染の扱いが確認さ
れている。
図4.1.1 マサチューセッツ州の土壌環境情報管理体制
(2)制度的管理の実施方法に関する分類
米国の各州の制度的管理の実施方法で分類すると、多くの州では長期間モニタリングを実
施してブラウンフィールドを管理しているが、データベースを構築して経過追跡のみにとど
まっている州もみられる。表4.1.3 に示す分類のうち、カリフォルニア州及びルイジアナ州
における制度的管理の内容を以下に示す。
表4.1.3 米国各州の制度的管理の実施方法の状況
(3)カリフォルニア州の制度的管理の内容
カリフォルニア州毒物管理局(DISC)では、すべての浄化修復活動を長期間管理する方針
であり、以下の事項について実施している。
この中で、浄化修復用地の用途制限については、いろいろなメディアを用いて、情報を公
表しており、もし、用途制限をする必要がないレベルまで浄化修復された場合は、用地リス
トから除外し、逆に用途に見合ったレベルまで浄化修復されていない場合は、必要なレベル
までの浄化修復を行う財政的な裏付けを要求する。また、浄化修復活動が完了していない場
合は、継続的に浄化修復活動を行っているかどうか定期的に検査する。
【カリフォルニア州の制度的管理の内容】
・浄化修復活動完了時の検査
・モニタリング(契約事項の遵守徹底)
・インターネット上での浄化修復用地の用途制限の公表
・浄化修復用地周辺地区への掲示板での通知
・周辺住民への郵便による通知
・新聞紙上での注意広告
(4)ルイジアナ州の制度的管理の内容
ルイジアナ州環境管理局(DEQ)では、用途制限のある自主的な浄化修復活動については、
インターネット上で公表できるデータベースにより追跡的に監視している。
このデータベースでは、当該サイトの住所、用途制限、過去からの土地所有者、用途の履
歴とともに危険物取扱いの有無の情報が、土地所有者からの届出に基づき、登録されており、
DEQ の承認が無ければデータベースから除外できない。また、正確な情報が登録されていな
い場合は、当該サイトの取引契約を買い手側が解約できる根拠ともなる。
4.1.5 財政支援施策
ブラウンフィールドの浄化修復は、土地の安全性の改善や土地取引の活発化、都市の活性
化といった効果が見込まれる反面、多大な費用を要するため、当該用地の保有者が浄化修復
によるメリットが見込まれない場合は、そのまま土地利用の停滞状態が続く可能性もある。
このため、ブラウンフィールドの浄化修復を促進するために、用地の保有者や開発事業者
に財政的支援を講ずることは有効な施策となる。
ブラウンフィールド浄化修復再生事業に対する財政的な支援策としては、補助と融資、税
制措置に大別される。
ここでは、まず、米国の各州の財政支援策を総括的に捉え、次いで補助と融資について、
連邦政府の適用条件、主要な州の支援内容、適用条件について整理する。
(1)米国の財政支援策の分類
ブラウンフィールドの浄化修復事業への補助については、ブラウンフィールド再開発への
補助を行っている州が最も多い。融資については、零細事業者向けとして、ドライクリーニ
ング事業者への融資を行っている州が最も多い。また、税制措置に関しては、固定資産税の
軽減措置を講じている州が最も多い。
表4.1.4 米国各州の財政支援策の制定状況
(2)連邦政府のブラウンフィールド支援プログラム
連邦政府のブラウンフィールド支援プログラムは主にEPA(環境保護庁)とHUD(住宅
都市開発省)によって行われている。特にEPA は、常に連邦のブラウンフィールド政策のイ
ニシアチブをとり続けてきた機関であり、多くの支援プログラムを用意している。
1)EPA のブラウンフィールド補助プログラムの概要
地域に根ざした環境保護の手段としてブラウンフィールド問題に対応するために、1994 年
からEPA は、官民のパートナーシップを促進し、ブラウンフィールドサイトを評価した上で
浄化し、かつ、再開発するための革新的・創造的な方法の構築を促進することを目的として、
ブラウンフィールド問題に対応した補助金プログラムを開始した。EPA は「州・部族・自治
体の環境・経済開発職員が、ブラウンフィールド活動を概観し、また地域の問題に対して地
域固有の解決策を実行するための支援を行う」ことを目的としており、自治体を中心に自治
体・地域が主導するブラウンフィールド再生の取り組みを支援する姿勢に徹している。また、
EPA は、またブラウンフィールド再生による経済的な利益が地域に維持され続けるようにす
るため、地域の環境職業訓練プログラムを作成するための資金を提供している。
EPA のブラウンフィールド補助金は、以下の4 つが主要なものである。
・ アセスメント補助金
・ 浄化補助金
・ リボルビング・ローン・ファンド補助金
・ 職業訓練補助金
2)EPA のブラウンフィールド補助金の申請要件
【内容】
アセスメント
リボルビング・ファンド(RLF)
浄化対策
【規模】
2007 年10 月申請分 7,200 万ドル、200 件を予定
【対象】
a.ブラウンフィールド(危険物質や汚染の存在あるいは存在可能性により、再開発や再利
用に問題が生じうる不動産)
b.ブラウンフィールド以外の追加適用対象
・規制薬物によって汚染されたサイト
・石油または石油製品によって汚染されたサイト
・廃鉱など鉱物資源の跡が残るサイト
【資格要件】
a.申請者の要件
・ 浄化したいとする土地を所有している団体(大学やNPO を含む)
表4.1.5 補助対象別の申請者タイプ
b.適用除外土地
以下のサイトは、補助金受給資格を有さない。ただし、2)から5)については、個別判断に
基づき対象とすることができる。
1) NPL に現在リストされているか、リストに向け提案されている土地
2) CERCLA の下で計画あるいは進行中の浄化がある土地
3) 閉鎖計画または許認可に規定される要件に従い、RCRA 閉鎖通知を提出した処分場である土地
4) PCB の漏出があった施設
5) 漏出地下タンク信託基金から資金を受けている施設
【補助金の使用制限】
補助金は下記の支払いに使用できない
・ 罰金
・ 連邦経費分担要求(例えば他の連邦基金で要求される分担金)
・ 一般管理費
・ 潜在的責任者として対応するための費用
・ 土壌汚染浄化関連法以外の任意の連邦法に対する遵法費用
・ ロビー活動費用など
3)ブラウンフィールド・モデル地域
ブラウンフィールド・モデル地域(Brownfield Showcase Community)は、20 以上の連
邦機関のパートナーシップ(注4)のもとで1998 年から行われたブラウンフィールド再生のモ
デル事業である。環境修復から地域開発まで多岐にわたるブラウンフィールド問題を解決す
るための、省庁間協力の事例として注目される。
1997 年5 月に、ゴア副大統領は、15 を越える連邦機関の資源を集めるためにブラウンフ
ィールド連邦パートナーシップ(BFP)を発表、1998 年3 月に、この連邦パートナーシップ
は、ブラウンフィールド上の共同作業の利点を実証するモデルとして、16 ヶ所のブラウンフ
ィールド・モデル地域を選定した。さらに2000 年10 月には、イニシアチブの成功を継続す
るために12 の追加のブラウンフィールド・モデル地域を選定している。
選定は基本的に都市レベルまたは地域レベルで行われ、対象都市のなかでもブラウンフィ
ールドを多く抱える特定の地区に対して、特に重点的に資金を投入している。ブラウンフィ
ールド・モデル地域は規模、資源および地域のタイプなど多岐にわたるが、古い工業地帯が
広がる米国北東部に特に集中している。
図4.1.2 モデル地域事業に指定された自治体の位置
? モデル地域事業の目標
1.ブラウンフィールドのアセスメント、浄化および持続可能な再利用を通して環境保護お
よび回復、経済再開発、雇用創出、コミュニティ再生および公衆衛生保護を促進する。
2.ブラウンフィールドを修復し再利用する地域の努力を支援する連邦、州、地域・民間の
動きを結びつける。
3.ブラウンフィールドに取り組む際に、行政と民間が協働することによって、よい結果が
得られることを実証する全国的なモデルを開発する。
連邦政府が1980 年代から取り組んできたスーパーファンド法にはじまる環境修復の取り
組みが、土壌汚染をはじめとする環境浄化に主眼をおいてきたのに対し、90 年代のブラウン
フィールド再生事業には、単なる土壌汚染の浄化にとどまらず、環境問題に関する市民の教
育から、周辺地区の再生、地域の雇用創出に至るまで、多面的な取り組みが求められるよう
になってきた。
スーパーファンドサイト(注5)は、その多くは浄化の優先順位付けから資金確保・浄化の
管理に至るまで連邦直轄で行われてきたが、ブラウンフィールド再生事業はスーパーファン
ドほど汚染の程度は深刻ではなく、土壌汚染の浄化と同程度、もしくはそれ以上に都市・地
区の再生と経済開発に主眼が置かれている。結果として、その実施は連邦機関(特にEPA)
だけで実施できるものではなく、すべてのレベルの政府、民間部門および非政府組織の間に、
より多くの協力と調整が求められた。
モデル地域事業は、土壌汚染の浄化から工場跡地さらには疲弊した工業都市全体の再生を
目指すブラウンフィールド事業へと展開するためのノウハウを連邦・州・自治体が一体とな
って作り上げるための重要なプロセスであった。
? 対象地域の利点
ブラウンフィールド・モデル地域に指定されることで、自治体は連邦からの重点的な支援
を受けることができる。自治体は、ターゲットとされた技術的・財政的援助から直接的な利
益を得ることができる。
中でも連邦政府の職員(主にEPA の職員)が、対象の自治体に出向し、技術的・財政的援
助の調整を支援する制度である。政府間要員配置(IPA)スタッフと呼ばれ、環境面の知識
や制度・補助金に不慣れな自治体職員を助け、2 年から3 年にわたって、対象自治体の職員
として地域のブラウンフィールド再生に取り組んだことの意義が大きかった。(注6)
(3)主な州のブラウンフィールド関連財政支援策の概要
1)マサチューセッツ州の財政支援策
マサチューセッツ州では産業開発局や環境保護局などの部局ごとにさまざまなブラウンフ
ィールド関連の財政支援策が用意されているが、補助に関しては、対象が自治体または非営
利団体に限られており、一般のブラウンフィールドについては低利融資の利用に限定されて
いる。
VCP(自主浄化活動)サイト数は、2006 年7 月までに34,312 件のサイトが報告されてお
り、このうち、4,735 件は現在、実施中である。毎年、概ね1,800 件の新規サイトが申請さ
れる。
? マサチューセッツ州産業開発局(Mass Development)が管轄する助成策
a.ブラウンフィールド再開発基金(BRF)(融資)
再開発を伴うブラウンフィールドサイトに対して、以下の融資が提供されている。
【財政支援規模】
・連邦政府からのブラウンフィールド補助金の10%が、サイトを指定したアセスメントや
再開発を誘導する浄化事業(Cleaning Projects)に使われている。
・2006 年 7 月時点で、15 箇所のサイトの調査と2 箇所のサイトの浄化事業に取り組んで
いる。
【融資の内容】
・ブラウンフィールドサイトの調査への低利融資
サイトの調査に対しては、上限10 万ドルまでの低利融資が提供される。
〈資格要件〉
・EDA(Economically Distressed Areas)地域内に位置していること
以下のどれかの条件を満たすこと
・ETA(Economic Target Area)地域として指定された地域または自治体であること
・ETA 地域としては指定されていないが、ETA 指定条件を満たしていること
・以前の用途がガス製造プラントであったこと
・申請者はサイトの所有者か浄化の実施者であること
・マサチューセッツ州の規定により認可されたサイトであること
・浄化事業への低利融資
サイトの浄化、修復に対しては、上限 50 万ドルまでの低利融資が提供される。
特に、優先プロジェクトについては、調査と浄化事業に対して上限200 万ドルまで融資
される。
〈資格要件〉
・EDA 地域内に位置していること
・申請者はサイトの所有者であること
・抵当保証が設定できること
? マサチューセッツ州環境保護局(Mass DEP)が管轄する助成策
Mass DEP のブラウンフィールド関連の助成策としては、以下のように対象が限定される。
a.水質浄化リボルビングファンド(SRF)(融資)
水質を改善するプロジェクトを対象に,期間20 年の低利融資(2%)が提供される。
b.調査及び浄化事業への補助(補助)
連邦環境保護庁(EPA)の補助の下、自治体や非営利団体を対象として、荒地となって
いるサイトの調査及び浄化事業に補助される。
【財政支援規模】
・2006 年の上半期で、概算で600 万ドル支援
このうち、110 万ドルは連邦政府から指定されているサイト
・2006 年 7 月時点で、4,200 万ドルが契約中
・1983 年以降で、累計1 億8,300 万ドルを支援
? マサチューセッツ州住宅・コミュニティ開発局(DHCD)が管轄する助成策
DHCD は連邦政府の住宅都市開発省、コミュニティ開発基金プログラムを実施する機関で
あり、人口5 万人以下の市や町を対象とし、低所得者居住地区のスラム化や環境悪化の防止、
緊急対応事業などに助成する。
ブラウンフィールド関連の助成策は以下のとおりである。
a.コミュニティ開発基金(補助)
自治体を対象に、プランニング、予備的な開発計画の検討、用地の取得、調査、浄化事
業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
b.Mini−Entitlement Program(補助)
自治体のMini−Entitlement 事業を対象に、プランニング、予備的な開発計画の検討、
用地の取得、調査、浄化事業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
c.産業開発基金(補助)
自治体の産業開発事業に補助され、プランニング、予備的な開発計画の検討、用地の取
得、調査、浄化事業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
d.コミュニティ開発行動基金(補助)
自治体を対象に、市や町の経済活性化や投資の活発化、長期の雇用創出、低所得者居住
地区の環境改善に資するプロジェクトに補助され、市街地整備の様々な事業に使われる。
e.優先的開発基金(計画立案等への補助)
自治体を対象に、計画立案、ゾーニング、住宅整備への教育・指導などに上限で5 万ド
ルまで補助される。多くの市や町では、住宅開発を誘発する計画立案のコンサルタント費
用として使われている。
? マサチューセッツ州税務局(Mass DOR)が管轄する助成策
a.地下埋設タンクプログラム(補助)
自治体を対象に、地下埋設タンクからの漏洩対策や地下埋設タンクの閉鎖などの活動に
補助される。
2)カリフォルニア州の財政支援策
カリフォルニア州では、環境調査に関して連邦政府からの補助が受けられる。浄化事業に
関する補助は特定のプログラム(下記の?)に限定されている。一般事業者の浄化事業に関
しては、専ら低利融資が受けられる。
VCP(自主浄化活動)のサイト数について、カリフォルニア州毒物管理局(DTSC)は平
均して常に300 箇所のサイトを指導・監督している。また、毎年、平均して125 箇所のサイ
トの浄化事業を完了している。
? ブラウンフィールドサイトの環境調査への補助
連邦政府環境保護庁(EPA)から、カリフォルニア州毒物管理局(DTSC)の支援を通じて応
募者に環境調査費用への補助が行われる。
? 自主浄化事業(VCP)への低利融資
・融資額
サイトの特性把握:最大 10 万ドル
サイトの浄化活動:最大 250 万ドル
〈VCP として認定される資格要件〉
・連邦政府や州政府のスーパーファンド法による対策地域、軍事施設、DTSC の
管轄外のサイトでないこと
〈融資の適用条件〉
・事業用の用地であること
・産業、商業、非営利団体・スモールビジネスの立地が予定される再開発用地であること
? 浄化事業への補助等
以下のプログラムが用意されている。
・再開発局環境監視協定プログラム(EOA)
・学校用地の環境評価・浄化プログラム
・地下埋設タンク浄化基金プログラム(UST)
・毒物管理会計(TSCA)
3)ニュージャージー州の財政支援策
ニュージャージー州では、一般事業者の浄化事業に関しては、専ら低利融資が主要な助成
策となっている。革新的技術で浄化した場合などの特定の条件を満たす場合には、補助も行
われている。
以下の財政支援プログラムの下に、多数のサイトが浄化事業を実施中である。2002 年には、
危険物放出サイト修復基金では、156 サイトの浄化事業を完了しており、総額で1,500 万ド
ル以上の融資や補助が実施された。また、200 サイトが検査中である。
NJDEP では、常に23 千箇所の汚染サイトを監視しており、その内の1 万箇所は潜在的な
ブラウンフィールドサイトである。
? 危険物放出サイト修復基金(低利融資、補助)
・一般のサイト(低利融資)
危険性の高いサイトの修復に関しては、一般のサイトでは最大で100 万ドルまで融資
・地方自治体(補助)
地方自治体に対しては、所有者のはっきりしないサイトや無償譲渡されたサイトなどの浄
化のために、最大で200 万ドルまでの補助または融資
? 水資源関連のブラウンフィールドサイト浄化に対するニュージャージー州インフラ基金に
よる低利融資
? 革新的技術で浄化した場合や制限無しまたは一部制限付き再利用が可能なサイトの浄化費
用への補助(25%まで)
4.1.6 環境負債免除制度
米国における最初の土壌汚染に関する法律としてのスーパーファンド法(包括的環境対処
・補償責任法)は、不可逆的な環境汚染の拡散の防止のために、非常に厳しい規制を課して
いる。その最も厳しい点として、土壌汚染の浄化責任を現在及び過去の土地所有者に求めて
おり、現在の土地所有者が汚染の原因者でなくても浄化責任を求められる可能性があること
があげられるが、その影響として、土壌汚染浄化の可能性がある土地については浄化コスト
のリスクを伴うため、都市部の再開発から取り残されてしまうという問題を生じさせてしま
っていた。このような問題を改善し、土壌汚染地の開発を積極化していくための制度として、
以下の制度がつくられている。
○ 自発的修復制度(VCP:Voluntary Cleanup Program)
スーパーファンド法による浄化義務発生リスクを回避し、土壌汚染地の再開発を促進す
ることを目的としており、浄化修復事業は民間側が主導的にすすめることができるよう前
項で記述した各種財政支援策が用意されている。
○ 環境負債免除制度
民間側の浄化修復事業が事前に州当局と協議した計画に基づき実施され、完了した場合
に、州政府は修復完了を承認し、将来にわたる環境負債を免除するものとして、以下の証
明書を発行する。
・ 修復完了証(No-Further-Action letter)
浄化の完了及び追加的な浄化措置が不要であることを証明する
・ 訴追免除証(Covenants-Not-To-Sue)
将来にわたって同一理由による汚染修復責任を求める訴追を原則として受けなくてよい
ことを証明する
以下で各州の環境負債免除制度及び小規模事業者責任免除制度について把握整理する。
(1)環境負債免除制度
ブラウンフィールドへの取り組みとして、ほとんどの州が自発的修復制度及び環境負債免
除制度を関連法制度に盛り込んでいる。それらの州のうち、マサチューセッツ州、カリフォ
ルニア州について、その概要を整理する。
1)マサチューセッツ州の環境負債免除制度
マサチューセッツ州の環境負債免除制度の特徴は、責任軽減制度の導入と浄化管理の民間
化によって、効率的で迅速なプロセスを実現している点にある。マサチューセッツ州は、汚
染責任者に対して厳格な連帯責任を課している。汚染責任者は、自主的に土地を浄化するこ
とが認められており、もし自主的な浄化が行われない場合には、マサチューセッツ州開発局
(MADEP)が浄化を代行し、かかった費用を回収することができる。
実際に、自主的浄化の割合が95%と非常に高い。これは、マサチューセッツ州開発局の
担当者が、積極的にインセンティブ活用を推進するブラウンフィールド・コーディネーター
となり、民間事業者の側に立って自主浄化を促していることもあげられる。
? 責任免除制度の提供
責任免除制度は、民間事業者が再生事業に参加する際に最も重要になる制度である。マ
サチューセッツ州は、全米でも早い時期に責任免除制度を創設、提供を開始した州である。
? 訴訟免除契約書の発効
ウースター市のメディカル・シティ・プロジェクトの過程で、ウースター再開発公社か
ら、民間事業者に土地を売却する際に、州政府が発行したCNTS がその原型とされる。ブ
ラウンフィールド訴訟避止誓約書は、1998 年のブラウンフィールド法によって正式に制度
として認められた。現在はマサチューセッツ州法務局によって、各々の関係者に合わせた
責任免除措置が与えられている。
? 跡地利用制限がある場合の責任免除制度
土壌汚染がある土地を浄化する際に、経済的な理由から全ての汚染を除去せずに、一定
の汚染を残したまま、封じ込めなどの処理する場合がある。この場合、跡地の活動用途制
限(AUL)が土地に付加される。AUL のある土地に対してもAUL の変更を行なわない場
合、責任免除制度の適用が可能である。
2)カリフォルニア州の環境負債免除制度
カリフォルニア州のブラウンフィールド対策の基本として自発的修復制度(VCP)が位
置づけられている。浄化修復事業者は、浄化事業中はカリフォルニア州毒物管理局(DTSC)
の監督を受け、修復が完了した時点で、以下の2種類の証明書のどちらかを発行する。
しかし、これらの保証があっても将来時点で第三者機関による浄化活動を除外しない。ま
た、浄化活動が進行中であっても、事業の完了と維持管理が確保されるとの合意があれば保
証書は発行される。
・ 修復完了証(No-Further-Action letter)
一部、汚染が残っていても、人体や環境にほとんど影響が無いレベルまで浄化された場合に発行される
・ 完結終了証(Certificate of Completion)
浄化目標水準を完全に達成した場合に発行される
(2)小規模事業者責任免除制度
小規模事業者責任免除制度は、ブラウンフィールドプログラムのより効率的な実施と再開
発促進のため、連邦政府環境保護局により2002 年に法律が施行された。この法律での小規
模事業者とは、有害物質の保有量が液体100 ガロンまたは固体200 ポンド以下で、2001 年
4月1日以前にすべての有害物質の廃棄、取り扱い、輸送を行っていた事業者である。
各州の小規模事業者責任免除制度に対応する取り組みをみると、ドライクリーニング事業
者の汚染サイトに対する環境対策プログラムとして制度化されており、どの州でも財政イン
センティブが合わせて講じられている。
【小規模事業者責任免除制度を持つ州】
・ ウィスコンシン州 −ドライクリーニング環境対策プログラム
(ドライクリーニング環境対策ファンド)
・ サウスカロライナ州−ドライクリーニング事業者のための環境指導書
(ドライクリーニング修繕トラストファンド)
・ フロリダ州 −ドライクリーニング有機溶剤浄化プログラム
(ガソリンスタンド、ドライクリーニング店向け浄化ファンド)
・ カンザス州 −ドライクリーナー環境対策プログラム
(ドライクリーニングファンド)
・ テキサス州 −ドライクリーニングによる汚染サイト対策プログラム
(ドライクリーニング浄化支援プログラム)
・ ミズーリ州 −ドライクリーニングによる汚染サイトの再利用活性化支援プログラム
(ドライクリーニング信託投資ファンド)
4.2ドイツ
4.2.1 連邦土壌保護法制定の経緯
ドイツにおいても、1980 年代から土壌汚染問題への対応が本格化したが、当時は、個々の
法律(州レベルの土壌保護法、州レベルの廃棄物法など)ごとの個別的な対応であったり、
州ごとにばらばらな規制を行っていたりして、規制の不整合の問題が生じていた。しかし、
1999 年3 月に連邦土壌保護法、同年7月に連邦土壌保護土壌汚染令の施行により土壌汚染リ
スク管理が統一された。
4.2.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
ドイツにおいては、都市計画決定の権限や土壌汚染地の浄化修復についての自治体の役割
は極めて大きい。このため、土地利用計画の安定性を担保するためにも、土壌汚染情報の収
集は重要となっている。土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動してい
るため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしている。
具体的には、自治体レベルで土壌汚染の可能性のあるサイトを把握して土壌汚染情報をマ
ップに落として公表しており、また、土壌汚染に関する統計データも自治体から、州、連邦
政府へと段階的に上げられて整備され、公表されている。
ドイツにおいては、ブラウンフィールドは最終処分場跡地と産業跡地という広い意味で用
いられており、統計によれば、この該当サイトは231 千箇所あり、また土壌汚染が特定された
サイトは11 千箇所、浄化が終了しているサイトは14 千箇所、リスク評価が終了しているサ
イトは37 千箇所と集計されている。
ドイツにおいては、図4.2.1 に示すとおり法がカバーしている土壌汚染の範囲は広く、「予
防」段階から「危険防止」段階に分かれ、法的に対策が求められるのは「危険防止」段階以
上となる。ただし、「危険防止」段階でも、土地利用用途ごとの基準値と照らし合わせて、概
況調査で終わってよいもの、詳細調査まで進むべきものに分けられていく。
図4.2.1 土壌汚染の規制体系
【統計データにおける「土壌汚染」の分類】
・ ブラウンフィールドが疑われるサイト
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち旧堆積場
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち産業跡地
・ ブラウンフィールド
・ 浄化完了サイト
・ リスク評価完了サイト
・ 浄化中サイト
・ モニタリング中サイト
4.2.3 浄化修復目標の設定
ドイツにおいては、ブラウンフィールドサイト毎に「浄化計画」を作成し、目標水準は個
別に設定することを基本とする。その目標水準は、開発用途などを総合的に考慮して決定さ
れるため、米国の各州で基本的考え方となっているリスクベースの浄化修復目標水準の設定
と同様に経済合理性の視点が取り込まれている。
また、ドイツは都市計画決定に関して市町村が強力な権限を持っており、浄化修復目標の
設定や跡地の利用形態の決定に市町村が全面的に関与している。ブラウンフィールドに関連
して、健康的な居住や就労環境の確保は都市計画を定める中で、重要な配慮項目となってい
る。
(1)浄化計画と行政契約
土壌汚染の存在が確認された土地では、まず浄化のための概況調査が実施され、浄化目標、
浄化手段、費用などが定められた浄化計画が作成される。この浄化計画は、事業者側で作成
し、行政当局に提出して、公法上の手続きである行政契約によって合意形成される。
浄化後のネットバリューがマイナスになった場合、その相応額を行政が補助金で負担する。
また、浄化後の取引価格が顕著に上回った場合は、逆に費用返還請求できる制度となって
いる。
行政契約のメリットとして、行政手続きリスクの減少と手続きの迅速化があげられる。
浄化計画で定められる事項は以下のとおりであり、浄化方法、費用だけでなく、都市計画、
建築、水質保全、公害防止など都市開発に伴う関連許認可項目が網羅的に含まれている。
【タイプ別リスク設定の要因】
・ リスク評価の概要
・ 浄化対象用地の旧来そして将来の用途
・ 浄化目標
・ 費用見積り、資金計画
・ 浄化目標の達成に必要な除去、隔離、制限、自己管理措置 等
・ 浄化、品質保証のモニタリングコンセプト・一連の手続きに要する期間 等
(2)用途別基準の設定
ドイツでは詳細調査や浄化対策の必要性の判断を行うために、用途別基準が設定されてい
る。一度決められた土地利用計画は将来変わることは少ないと固定的にとらえられているた
め、経済合理性のある用途別基準が重みを持って用いられている。
調査値は、用途別汚染物質別に設定されているが、対策値はダイオキシン/フランのみし
か設定されていない。対策値は地域の特殊性を考慮して設定することが基本となっている。
【用途の分類】
・ 子供の遊び場
・ 住宅地域
・ 公園・レジャー施設
・ 工業、産業用地
4.2.4 制度的管理
ドイツでは、市町村が強力な都市計画決定権限を有しており、都市計画制度が土地利用用
途を厳格に管理している。F―プランといわれる行政内部の長期的な土地利用計画とB―プラ
ンといわれる私権を制限する強制力のある地区詳細計画があるが、計画策定に当たっては、
健康的な居住・就労環境の確保が重要な配慮事項とされている。各土壌汚染サイトの浄化レ
ベルは、開発用途等を総合的に勘案した上で個別に作成される浄化計画によって決められる
ため、都市計画と連結している。
また、浄化修復後の浄化水準チェックのためのモニタリングの方針を浄化計画に定める事
項としており、制度的管理においてモニタリングが重要な位置づけにある。
土壌汚染対策の流れは図4.2.2 に示すとおりであり、以下の点に特色がある。
・ 土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動しているため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしていること
・ リスク評価の段階で用途別の基準値を用いていること
・ 浄化とモニタリングの段階では目標が一律に定められておらず、それぞれのサイト毎に
浄化目標と浄化計画を定める浄化契約を自治体と結んで、対策及びモニタリングが実施さ
れていること
図4.2.2 土壌汚染対策の流れ図
4.2.5 公的関与
ブラウンフィールドの再開発において、採算がとりにくく民間が手を出しにくい土地に対し
ては官主導の色彩が濃くなり、自治体が基本的に公費で土壌汚染対策を実施して民間投資を誘
発して再開発を行い、開発後に得た開発利益を官民で分けている。フランクフルト西港開発の
事例では、市が土壌汚染を除去して用地をデベロッパーに売却し、開発・販売・分譲により得
た開発利益を市とデベロッパーとで折半する契約となっている。また、ノルトホルン再開発事
業の事例では、相当深刻な土壌汚染があって開発計画は一時頓挫していたが、市が様々な工夫
によって浄化対策を行って民間投資を呼び込んでいる。誘発された民間投資が大きいというこ
とで、市による公費投入が正当化されている。
(出所) Umweltbundesamt 資料、Osnabrueck 市資料より作成
5.土壌汚染地における土地の有効利用促進等に向けた課題
2.2でも述べたように、土壌汚染問題に対する一般的理解が不足していることから、我が国
においては土壌汚染に関する情報は秘匿されがちであり、容易に公にはならず、一般社会では土
壌汚染が特別なものだと思われている。その結果として、土壌汚染が公表された場合には、報道
等でことさら大きく取り上げられ、それが仮に軽微であっても、社会的には過剰反応しがちであ
る。また、この現象により土地所有者などは公表を拒むこととなり、結果的に悪循環となってい
る。
しかしながら、我が国は火山国である事から、重金属の自然含有レベルは高く、時に環境基準
を超過する土壌があることや、現在では汚染責任的には容易に対処のしようがない過去の含有レ
ベルの高い臨海の埋立地の土壌などの存在は、決して特別なものではない。それらの土地を健康
リスクの観点から見た場合、多くは他のリスクと比較して過剰反応するほどの大きなものでなく、
対応は充分可能なレベルであると考えられる。
土壌汚染が社会問題化するのは、土壌汚染自体が新しい概念であり、それらを大きな問題とし
ていない考え方や商習慣であった土地利用や土地取引への仕組みが充分に対応しきれていないこ
とによる。すなわち、対象とする物質は工場内等で管理されてきた事に対して一般的には積極的
にオープンにされていなかったにもかかわらず、その情報を求める必要性のある土地利用や土地
取引とのやりとりにまだ大きなギャップがあるまま、社会が動いてしまっているためである。
以上のような現象は、我が国よりも早くから土壌汚染の概念を導入してきた諸外国においても
見られており、それぞれの国の法令や、都市計画などの仕組みの中で対処されてきた事実も、本
年度の検討で明らかになった。特に安易に土壌汚染を放置することなく積極的に管理を行ってい
く取り組みはブラウンフィールドの対処法に関して多くの示唆があった。
現在我が国で起こっているギャップを埋めるためには、海外の取り組みも参考にしながら、単
なる規制ではなく、国民が土壌汚染の実態を認識した上で、土壌汚染の問題に対して適切な対応
をし、土地取引における問題の解消と我が国なりの法令、仕組みや国民性に適応した合理的な土
地利用を促進する必要がある。
5.1 更なる実態・影響の把握
土壌汚染に関する情報については、土壌汚染対策法が、民間の事業者が自主的に行った調査
結果の届け出を義務づけていないことに加え、自治体によって、自主調査結果についても届
け出を義務づけた上で公開するところ、できるだけ届け出るよう指導するところ、そもそも
届け出を義務づけていないところなど、そういった自主調査結果に対する取扱いが異なるこ
とから、個別の土壌汚染サイトに関する情報(調査、対策の状況やその所在地等)は、なか
なか公にならない現状がある。
土壌汚染に係る施策の必要性等を検討するためには、土壌汚染が土地取引や再開発等の支障
となっている事例を当該事例における土壌汚染の管理の実態と併せて可能な限り多く把握
し、その原因等を分析することが必要である。しかし、現時点ではそのような事例を十分に
把握しているとは言い難いことから、今後も企業や地方公共団体等へのヒアリングや調査等
を積み重ねていく必要がある。特に、どうしようもなく動かなくなった土地は商取引の場か
ら外れることにより非常に顕在化されにくいという意見が多く、5.2以下に掲げる課題を
検討し、次のステップに進むための前提としても、さらなる情報収集が必要である。
5.2 土壌汚染情報のデータベース化
5.2.1 土壌汚染情報データベースの構築
前述したとおり、基本的な土壌汚染情報が不在又はアクセス困難であるため、マンション購
入後に土壌汚染が発覚し問題となったり、再開発計画を着手後に見直さざるを得なくなる等
の支障が生じている。しかし、土壌汚染情報は、土壌汚染地の周辺住民や購入者にとっても
利害関係を有するという意味では、土地の安全性に関する情報として公益的な側面を有する
ものであるから、広く情報を共有することを検討すべきである。
この点米国では、4.1.2で述べたように、多くの州が自ら情報を収集したり、届け出や
問い合わせがあった情報を元にして、土壌汚染情報のデータベースを作成し、インターネッ
トで公開している。
これを踏まえわが国でも、全国的な土壌汚染情報をデータベース化し、インターネット等に
よりその時点の状況を誰もが閲覧できる仕組みが存在すれば、土地取引の円滑化や浄化措置
の促進・早期化等に資することになるとも考えられる。
ただし、こういったデータベースを構築・公表する場合、そもそも情報の入手手段が限られ
ており、また、情報の正確性に細心の注意を図る必要があることから、引き続き、情報の入
手源や入手方法について検討すると共に、その情報の元となる調査の信頼性及び正確性をい
かに担保するかという点や万が一公表した情報が誤っていた場合に、当該データベース作成
者の責任の射程及び当該情報を利用した結果他者に危害を与えてしまった者の責任の射程に
ついても併せて検討しておく必要がある。
なお、土壌汚染情報データベースの一類型として、浄化が完了したサイトに関し、当該サイ
トの土質や浄化が完了した旨を公表するようなデータベースを構築することも、土地取引の
円滑化等に資すると考えられることから、こうした点についても検討する必要がある。
5.2.2 土壌汚染要調査マップの作成
しかし、わが国においては、5.2.1で述べたように情報の収集方法等を検討しなければ
ならず、土壌汚染情報データベースの構築はすぐには開始できない。
この点ドイツにおいては、4.2.2で述べたように、土壌汚染が存在する結果開発がスト
ップしているサイトに関する情報のみならず、産業跡地である等の理由により土壌汚染が存
在する恐れがあるサイトに関する情報を収集し、地図上に落とし込んで公表している。
そこでわが国においても、個別サイトを対象にしたデータベースを構築するための前提とし
て、公的なリーダーシップのもとにフェーズ?程度の地歴調査を行ったうえで、過去に工場
が立地している等の理由により、土壌汚染されているおそれが高いサイトや地区を地図上に
記載した、「土壌汚染要調査マップ」をリスクアセスメント手法を活用しながらひとまず作
成することも有効であると考えられる。
「土壌汚染要調査マップ」の作成により土壌汚染要調査情報が世の中に浸透すれば、土壌汚
染に関する情報を公開することに抵抗を感じにくい土壌の醸成につながり、土地取引・土地
利用における土壌汚染の存在を特別視しないで行えることが期待される。結果として、比較
的スムーズに土壌汚染情報データベースが世の中に受け入れられ、より効率的な土壌汚染へ
の対応が可能になるものと考えられる。
5.2.3 自然由来の土壌汚染データベースの構築
自然由来の土壌汚染については、地質的に一定の地域内に幅広く分布する等の事情により、
その地域固有の特性と考えて対応する必要がある。すなわち、仮に掘削除去による完全浄化
をするとしても、どこまで掘っても汚染土壌が出てきてきりがないという場合がありうる。
したがって、対策をすべき土地とそうではない土地の線引きを可能にするため、自然由来の
土壌汚染についてデータベースを構築することは、有用であると考えられる。またこれによ
り、汚染土壌による地下水への影響や残土の処理方法等を調査、検討することも可能になる。
なお、自然由来の土壌汚染は、汚染原因者がいないことから、いわゆる「汚染者負担の原則」
により浄化費用等を負担させることは困難であるが、情報の公開によって影響を受ける関係
者も少ないことが想定されるため、自然由来の土壌汚染データベースの構築・公開に対する
抵抗感は少ないものと思われる。
しかし、自然由来の土壌汚染については、前述したようにある地域内の土地全体に当てはま
る特性であることから、個別サイトごとの状況を考慮に入れれば足りる一般の土壌汚染の場
合とは異なり、面的に土壌汚染の状況を把握する必要がある。
こうした点からすると、自然由来の土壌汚染に関する情報を収集するためには一般の土壌汚
染の場合とは異なった方法が必要であると考えられることから、引き続き検討をしていく必
要がある。
5.3 公的支援の必要性
米国等においては、土地取引の活発化や地域の活性化が図られると期待される場合には、土
壌汚染地に対し、公的主体が浄化費用の一部を補助し、また、土壌汚染地について浄化を開
始又は完了したような場合には固定資産税の軽減を行う等の財政的支援を行っている。
一方わが国においては、土壌汚染が土地取引や再開発やまちづくりに影響を与えていると考
えられる具体的局面として次の場合が挙げられる。
・ 一般的に、大都市部においては、地価が高いため対策費を拠出することが可能であり、
現時点では土壌汚染が土地取引や再開発の支障となっている事例は多くないようである
が、地方部においては対策費の負担が大きければ土地取引や再開発が断念され、地域活性
化を阻害するおそれがある。
・ 小規模事業所等の場合、土地所有者に資力がないことが多いため、調査及び対策が困難
となる結果、土地取引や再開発に支障が生じるおそれがある。
土壌汚染においては、原因者負担が原則ではあるが、原因者に資力が無い場合や原因者が浄
化しただけでは十分な開発等が困難な場合であって、なおかつ、当該土地を活用して地域活
性化等の施策を講ずる必要がある場合には、上記のような局面について、米国等の例を参考
に、補助金、公的資金を投入した基金、税制優遇、公的主体による浄化措置等を検討するこ
とも考えられる。しかしながら、本研究会では具体事例の収集が十分にできず、具体的な検
討には至らなかったところである。
今後検討する前提として、上記に掲げるようなケースごとの実態を十分に把握・分析した上
で、公的支援の公益性及び必要性について検証・検討し、問題点を明確化するとともに、背
景となる事情や制度が我が国と異なることに留意しつつ諸外国の事例を大いに参考にすべき
である。諸外国の事例を検討するに際しては、公的資金の投入等により浄化をした結果とし
ての雇用創出の程度や税収増の割合といった当該施策の効果についても分析を加え、より効
果的なものを参考にすることが望ましい。
なお、地域活性化等の観点から公的資金の投入が難しい場合であっても、地域住民に健康被
害が生じている場合等は、別の観点から検討をしていくことが必要である。
5.4 サクセスモデルの構築
5.4.1 サクセスモデルの構築
2.2.2で述べたように、現在、土壌汚染を浄化する際には、掘削除去による完全浄化が
ほとんどである。掘削除去には莫大な費用がかかることから、特に地方部においては、都市
部と比べて、掘削除去費用が地価を超えてしまうことも往々にしてあり得、結果として土壌
汚染の存在する土地が開発、利用されずに放置されてしまうという事態がありうる。
そこで、地方部においても土壌汚染が存在する土地の有効活用が少しでも図られるよう、土
壌汚染が実際に存在する土地を取り上げ、原則として掘削除去以外の浄化措置を行うと共に
その後の土地利用の計画を策定した上で、その成功要因等を分析・研究するという「サクセ
スモデル」を構築・公開し、その構築が一定程度完了した時点で当該モデルを「ひな型」と
してまとめ、公表することが、土壌汚染地の有効活用のための現実的な有効策となり得ると
考えられる。
この際、例えば、昔は工場等が集積していたが今後は住宅地・商業地として再開発の可能性
が高い一定の駅裏等を対象に、調査、データベースの整備・公開、非完全浄化を含めた対策
等の一連の対応を実験的に行うことの必要性や実現可能性について検討する必要がある。
なお、掘削除去以外の浄化方法を選択した上で再開発等を行った海外の事例について研究
し、場合によってはその事例自体を「サクセスモデル」の参考として提示することもあって
良いと考えられる。
5.4.2 官民の連携
なお、「サクセスモデル」の構築に当たっては、土地の開発、建築、浄化等を行う民間事業
者と土地利用の計画を策定する公共主体がそれぞれバラバラに取り組むのではなく、計画の
段階から実際に浄化した上で開発する段階、さらには土地利用の状況をモニタリングする段
階に至るまで官民一体となって両者が連携、協働することが必要である。
その際、浄化方法と土地利用の方法がどのように対応できるか等、民間業者と公的主体のそ
れぞれがノウハウを蓄積させるとともに、そのために必要な人材を育成していく必要がある。
5.5 資産評価の一層の適正化
時価会計への一本化や今後の資産除去債務の導入等社会経済情勢の変化に伴い、不動産の経
済的価値を正確に評価することが一層求められている。
このためには、土壌汚染の専門業者が行う調査の標準化とそれを通じた専門業者の標準化を
進める必要がある。これにより、土壌汚染地の資産評価の適正化と、さらには、土壌汚染地
に係る安全で円滑な利用や取引が促進される。
一般的に不動産鑑定士は、土壌汚染について専門の業者と同じレベルの知識は有していない
ため、土壌汚染地に係る鑑定評価においては、専門の業者が作成したER の活用が重要となる。
また、不動産鑑定の実務面においても、運用指針の策定や研修、さらなる研究・検討が行わ
れているところではあるが、社会経済情勢の変化に対応し得るよう、引き続き不動産鑑定士
が土壌汚染状況の確認範囲等を明確化し鑑定評価に適切に反映するステップについて検討を
深めていく必要がある。あわせて、様々な汚染状況や対策方法に応じた評価を一層客観的に
行うことを求められることが想定され、スティグマについての評価方法や、掘削除去以外の
措置を前提とした鑑定評価の方法についてもさらに検討する必要がある。
5.6 その他の有効利用促進策
5.6.1 信託、ファンド、保険等のリスク軽減策
なお、土壌汚染リスクの適切な移転・軽減を図る方策として、限定責任信託、土壌汚染地
を買い取った上で浄化するファンド、適切な保険料による保険商品等の活用が考えられる
が、土壌汚染の実態を把握するための十分な調査が行われていないことなどから、いずれも
現時点では具体的な提案をし得る検討状況にはない。しかしながら、いずれも重要なツール
であり、今後リスク評価が進み、具体的な方策を検討しうると考えられることから、今後も
引き続き市場における状況を注視しつつ、必要に応じ活用方策を検討する価値がある。
5.6.2 土壌汚染の正確な知識の周知と土地取引の不正防止
欧米と異なり、我が国では、例えば工業用地から住宅地への用途変更が容易であることか
ら、少なくともその機会を捉えた土壌汚染状況の確認を行うことが重要である。また、土壌
汚染の可能性がある土地について、土地取引が行われる場合には、必要な情報が新たな所有
者に十分伝達されない恐れがある。さらに、土壌汚染に関わる不公正な土地取引が散見され
るところである。
ここで、このような用途変更や土地取引に際して、土地所有者、開発業者、建設業者等の
関係者、さらにはこれに関係する行政担当者等が土壌汚染について必要な知識を有していれ
ば、必要に応じて調査その他の対策を講じることが可能となることから、これらの関係者に
対し、同業者の会合や必要に応じた講習等を通じ、土壌汚染についての正確な知識を周知す
るとともに、土地取引に関する不正の防止に努めていくことが必要である。
また、5.4.2で述べたような官民の連携を進めていく前提として、官の側も土壌汚染
について必要な知識をもつことが必要である。そこで、自治体の環境部局のみならず、建築
部局、都市開発部局といった関係部署においても、土壌汚染が土地取引やまちづくり等を行
う際に大きな阻害要因となっている旨を認識した上で、土壌汚染問題に適切な対応ができ、
ひいては民間に対しリーダーリップを発揮出来るよう、自治体内部で一丸となって取り組む
態勢づくりが必要である。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030404/02.pdf
平成20 年4 月
国土交通省土地・水資源局 土地政策課土地市場企画室
中間とりまとめのポイント
土壌汚染が実際に存在する土地で、原則として掘削除去以外の浄化措置を行うとともにその後の土地利用の計画を策定した上で、その成功要因等を分析・研究するという「サクセスモデル」を構築・公開することが、土壌汚染地を有効活用するための有効策になりうる。
土壌汚染地の資産評価の適正化と土壌汚染地に係る安全かつ円滑な利用や取引を促進するため、土壌汚染の専門業者が行う調査の標準化とそれを通じた専門業者の標準化を進める必要がある。
不動産鑑定の実務面では運用指針の策定や研修等が行われているが、社会経済情勢の変化に対応しうるよう、引き続き不動産鑑定士が行うべき土壌汚染状況の確認範囲等を明確化し、鑑定評価に適切に反映するステップについて検討を深めていく必要がある。
また、スティグマについての評価方法や、掘削除去以外の措置を前提とした鑑定評価方法についてもさらに検討する必要がある。
個別の土壌汚染サイトに関する情報はなかなか公にならない現状があることから、下記の課題を検討するための前提として今後も企業や地方公共団体等へのヒアリングや調査等による情報収集が必要である。
更なる実態・状況の把握
土壌汚染情報は、土壌汚染地の近隣住民等も利害関係を有する情報であるから、全国的な土壌汚染情報をデータベース化し、広く情報を共有することができれば、土地取引の円滑化や浄化措置の促進及び早期化等に資することになる。
しかし、我が国においては土壌汚染情報の収集が十分でなく、情報の収集方法等も検討しなければならないため、すぐにはそういったデータベースの作成に取りかかることは困難であることから、公的なリーダーシップの元にフェーズ?程度の地歴調査を行った上で、過去に工場が立地している等の理由により土壌汚染の可能性が高いサイトや地区を地図上に記載した「土壌汚染要調査マップ」をひとまず作成することも有効と考えられる。
また、自然由来の土壌汚染についてデータベースを作成することも検討する必要がある。
土壌汚染情報のデータベース化
土壌汚染においては原因者負担が原則ではあるが、原因者に資力が無い場合や原因者が浄化しただけでは十分な開発が困難な場合であって、当該土地を活用して地域活性化等の施策を講じる必要が有る場合には、補助金や基金の創設、税制優遇等について検討することも考えられるので、実態把握の上、更なる検討・検証を進める。
公的支援の必要性
サクセスモデルの構築
資産評価の一層の適正化
その他の有効利用促進策
今後も市場の動向を注視しつつ、信託やファンド、保険等の活用については引き続き検討を進める必要がある。
また、土地所有者、開発業者、建設業者、さらには行政担当者等の関係者が土壌汚染について必要な知識を有していれば、必要に応じて調査等の対策を講じることが可能になるため、同業者の会合や講習等を通じ正確な知識を周知するとともに、土地取引に関する不正の防止に努める必要がある。
さらに、官民の連携を進めるため、自治体の環境部局のみならず、建築部局や都市開発部局といった関係部署においても土壌汚染が土地取引やまちづくり等の大きな阻害要因となっている旨を認識し、自治体内部で一丸となって取り組む態勢づくりが必要である。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030404/03.pdf
目 次
1.はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.土壌汚染の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1 土壌汚染の現状認識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1.1 現状認識
2.1.2 土壌汚染の可能性のある土地
2.2 土壌汚染の調査・対策の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2.2.1 土壌汚染対策法に基づく調査・対策の実施状況
2.2.2 条例・要綱等に基づく土壌汚染の調査・対策の実施状況
2.2.3 民間の自主的な調査・対策の実施状況
2.3 ヒアリング等による土壌汚染の実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2.3.1 土壌汚染の発生状況と対策
2.3.2 デベロッパー
2.3.3 ハウスメーカー
2.3.4 総合建設会社
2.3.5 外資系不動産ファンド
2.3.6 産業用不動産特化型REIT 運用会社
2.3.7 大規模土地所有企業
2.3.8 地方公共団体
3.土壌汚染に係る現行制度と諸問題・取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3.1 土壌汚染の調査と情報収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3.1.1 土壌汚染調査 /3.1.2 情報収集と活用
3.2 土壌汚染の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
3.2.1 用途別基準 /3.2.2 自然由来の汚染
3.3 土壌汚染の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
3.3.1 責任負担者
3.3.2 法令上の要求措置と実態の乖離
3.4 土壌汚染の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
3.5 土壌汚染がある土地取引のリスクと財政的支援・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
3.5.1 土壌汚染に係るリスクとリスク分担
3.5.2 低利融資等
3.5.3 保険
3.5.4 保証
3.5.5 買取り
3.5.6 信託
3.6 土壌汚染地の資産評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
3.6.1 土地の資産評価の枠組み
3.6.2 不動産鑑定評価の実務における土壌汚染地評価の基本的考え方
3.6.3 スティグマの評価
3.6.4 エンジニアリングレポートの重要性
3.6.5 課税関係
4.諸外国の制度・取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
4.1 米国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
4.1.1 スーパーファンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ
4.1.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み /4.1.3 浄化修復目標の設定
4.1.4 制度的管理
4.1.5 財政支援施策
4.1.6 環境負債免除制度
4.2 ドイツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
4.2.1 連邦土壌保護法制定の経緯
4.2.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
4.2.3 浄化修復目標の設定
4.2.4 制度的管理
4.2.5 公的関与
5.土壌汚染地における土地の有効利用促進等に向けた課題・・・・・・・・・・・・・・・ 63
5.1 更なる実態・影響の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
5.2 土壌汚染情報のデータベース化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
5.2.1 土壌汚染情報データベースの構築
5.2.2 土壌汚染要調査マップの作成
5.2.3 自然由来の土壌汚染データベースの構築
5.3 公的支援の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
5.4 サクセスモデルの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
5.4.1 サクセスモデルの構築 /5.4.2 官民の連携
5.5 資産評価の一層の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
5.6 その他の有効利用促進策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
5.6.1 信託、ファンド、保険等のリスク軽減策
5.6.2 土壌汚染の正確な知識の周知と土地取引の不正防止
1 はじめに
日本の限られた国土において、土地は国民共通の財産であり、土地の適切かつ有効な利用を
実現するためには、土地を有効利用しようとする者に対し円滑に土地を移転しやすくすること
を通じた土地取引の活性化を図ることが必要である。土地取引が円滑に行われることは、国土
の適正な利用につながると考えられる。
土壌汚染問題については、土壌汚染対策法施行後注目が集まっているところであり、土地取
引市場においても、そのリスクが近年強く意識されるようになっている。国土交通省では、土
壌汚染対策法施行以前の平成14 年10 月に「宅地公共用地に関する土壌汚染対策研究会」を設
置し、翌年6 月に土地取引の安全性と円滑化の確保を目的とした土地売買契約に当たっての留
意事項や、土地建物取引業者の留意事項に関する基本的な事項等を体系的にとりまとめ、公表
してきたところである。
しかしながら、土壌汚染の判明した土地については、依然として土地取引が忌避され、土地
の有効利用や再開発、まちづくりの観点から支障が生じる事態になっている。土壌汚染の問題
は、ともすれば土地所有者が汚染事実の公表に消極的となるので、土地の有効利用にとって、
どれだけ重要な問題であるかということが社会的に十分理解されていないのではないかという
指摘もある。実態として、土壌汚染が土地取引にどれだけの影響を与え、取引を阻害している
のかを、具体的なケースを含めて、調査、把握することが必要である。
さらには、土壌汚染土地の取引に係る様々な事項について、具体的な課題を抽出・整理し、
具体的な方策の検討につなげていくことが重要である。日本では、関係者が土壌汚染リスクに
敏感となり、法的には必ずしも要求されていない土壌汚染の完全除去を実施するケースが多く、
社会的コストの増加につながっている。また、土壌汚染土地の調査については、公的に利用可
能な情報基盤や調査・評価の枠組みに、整備改善の可能性があるという指摘が多い。土壌汚染
土地の取引に係るリスク分担を整理し、保険等のリスクヘッジのスキームを充実していくこと
が、土壌汚染土地の取引活性化につながるという意見もある。
一方、コンバージェンスの一環として、減損会計の導入等の時価会計への一本化等も進めら
れており、土壌汚染地における鑑定評価の重要性が高まるなど、土地政策の観点から土壌汚染
について検討することが強く求められている。
上記の問題意識を踏まえ、土地取引の円滑化による土地の有効利用促進等の観点から、土壌
汚染土地について現状と課題を整理し、具体的な方策につながる検討を行うことを目的として、
本研究会が設置された。本研究会においては、土壌汚染土地の取引に関係する民間企業や地方
自治体へのヒアリング、米国とドイツの事例の研究を行うと共に、本研究会委員及び土壌汚染
に関する専門的な知識を有する実務者からの発表を受けた議論を行い、今後、土壌汚染地にお
ける土地の有効利用方策を検討する際の課題を整理したところである。
2.土壌汚染の現状
2.1 土壌汚染の現状認識
2.1.1 現状認識
土壌汚染の現状に関して、土壌汚染対策法や各自治体の条例・要綱等に基づく調査・対策
の報告状況の他に、民間の自主的な実施状況に関するアンケート調査等の既存資料がある。
しかしながら、土地所有者等にとって、土壌汚染の判明は新たな調査・対策費用が必要と
なったり、近隣地域との軋轢が発生するおそれが高まったり、また土地資産評価の減価要因
になりうることなどから、自ら公表しづらいという問題を抱えているため、我が国では秘匿
されがちで、個別サイトに関する土壌汚染情報を入手することはきわめて困難な状況にある。
個別サイトに関する汚染情報を把握するためには、土壌汚染の土地を取り扱うデベロッパ
ーや不動産ファンド、このような土地を所有している企業、土壌汚染に関する相談・指導を
行う地方公共団体等に個別にヒアリング等を実施することが現状では有効と考えられる。
2.1.2 土壌汚染の可能性のある土地
? 土壌汚染の発生原因
土壌汚染の代表的な発生原因として、以下の4 つがある。
・工場などで使用していた有害物質が、不適切な取扱いや老朽化等による施設、設備の破損により漏えい、流出、飛散して土壌に浸透するという事業活動が原因の汚染
・産業廃棄物が埋立処分された土地で発生するという廃棄物が原因の汚染
・事故や災害により施設、設備が故障、破損等することにより有害物質が漏えい、流出、飛散等して土壌に浸透するという、事故や災害が起因の汚染
・重金属を含む岩石や地層が風化、流出して河川や平野部、海岸に堆積した自然の土壌中に存在する自然由来の汚染
? 工場等産業用地の土壌汚染
土壌汚染は日本の産業発展に伴って発生した過去の大きな負の遺産であり、水質汚濁防止
法による規制が行われる以前は、現在では汚染物質といわれる物質の一部も合法的に土壌に
浸透させることが可能であった。現在、有害物質使用特定施設として該当する土地は全国で
27,000 箇所といわれており、またカソリンスタンドやクリーニング事業等により土壌が汚染
されている可能性のある箇所は30 万箇所を越えるといわれている。
? 廃棄物処分地の土壌汚染
過去に廃棄物で埋め立てられた土地において、土壌汚染が見つかっている。
? 幹線道路沿道の土壌汚染
幹線道路沿道の土地では、自動車からの排気ガスに含まれている鉛などによる汚染が指摘
されており、土壌汚染は日常の生活空間のまわりで広く発生していると考えられる。
? 臨海部等埋立造成地の土壌汚染
過去に埋め立てられた臨海部の土地においては、砒素などが含まれる河川や浅海域の底質
の浚渫土砂等が埋め立てに使われていることが多いことから、土壌汚染の可能性が指摘され
ている。
臨海部以外の低・平地部の埋立造成地においても、持ち込まれた土が原因の汚染が見つか
っている。
なお、当該地域以外から持ち込まれた盛土材や廃棄物により埋立造成された場合には、土
壌汚染対策法の対象となる。
? 自然的原因の土壌汚染
自然に存在する岩石、地層に含まれる重金属が風化や水の流出に伴って拡散し、低・平地
部に自然堆積した場合や、これらを含む河床や海底での堆積土砂などにより埋め立てられた
場合は、自然的原因の土壌汚染と見なされる。自然的原因の可能性のある物質として、砒素、
鉛、フッ素、ホウ素、水銀、カドミウム、セレン、六価クロムなどがある。
自然的原因による高濃度の特定有害物質を含む土壌又は水底土砂が、周辺地域において盛
土や海面を埋め立てることにより造成された土地は、自然的原因により指定基準を超過した
ものとし、土壌汚染対策法の対象とはならないが、当該地域以外の土地から持ち込まれ、専
ら自然的原因により指定基準を超過する土壌は、土壌汚染対策法の対象となり、土壌を持ち
込んだ者が汚染原因者と見なされる。持ち込んだものが不明の場合は土地所有者が必要に応
じて措置を行うことになっている。
都市部においては、本来の河川堆積物による土壌汚染に、過去からの都市活動により河川
域の汚染原因者が不特定多数で特定できない人為的な汚染が混在しているという問題がある。
自然的原因による土壌汚染を判断することは可能であるが、人為的汚染と混在した場合に
それを区分することはかなり作業が必要となる。
その区分を把握するためには、自然的汚染は含有量が一定の範囲内にあり、広域で観測され
て局在性がないなどの特色を持っているこ
とから、広域的な視点からバックグラウンド濃度などのデータを収集して分布特性等を見て
判断していくことが必要である。
2.2 土壌汚染の調査・対策の実施状況
2.2.1 土壌汚染対策法に基づく調査・対策の実施状況
土壌汚染対策法が平成15 年2 月から施行されて以後の4 年間での法適用案件は622 件で
ある。このうち、土壌汚染の指定区域に指定されたものは172 件(28%)あり、措置済みが
91 件(15%)、措置実施中・検討中が69 件(11%)あり、未処置はわずかに12 件(2%)
である。
具体的に実施された措置としては、掘削除去が最も多く76%を占め、次いで原位置浄化が
18%、舗装措置が4%、立入禁止措置が3%の順である。
図2.2.1 指定区域の状況(平成15 年2 月15 日〜平成19 年2 月14 日)
(資料:環境省「平成19 年度版環境白書・循環型社会白書」)
2.2.2 条例・要綱等に基づく土壌汚染の調査・対策の実施状況
土壌汚染対策法が施行されて以降、多くの地方公共団体で条例や要綱等が改正され、その
中に土壌汚染に関する調査・対策の実施義務や届出措置が盛り込まれた。
都道府県調べによる年度別の土壌汚染調査件数及び判明件数は図2.2.2 に示すとおりであ
り、平成15 年2 月に土壌汚染対策法が施行されて以来、土壌汚染調査件数及び判明件数は大
きく増加している。
東京都条例に基づく土壌汚染調査の対象は、
・工場、指定作業所を設置して有害物質を取り扱い、又は取り扱った者、
・3,000 ?以上の敷地内で土地の切り盛り、掘削等土地の改変を行う者である。
また、新潟県では、平成16 年9 月から施行された新潟県生活環境の保全等に関する条例に
基づき有害物質を扱う事業所については5 年に1 回土壌汚染調査の実施を義務付けているが、
まだ届出件数はわずかである。
図2.2.2 年度別土壌汚染判明件数
(資料:環境省水・大気環境局「平成16 年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」)
2.2.3 民間の自主的な調査・対策の実施状況
? 民間の自主的な調査・対策の実施件数の増加傾向
土壌汚染の調査・対策は、健康被害を防止することよりも、むしろ土地資産価値の劣化を
防止する目的で実施されることが多い。土壌汚染対策法や条例・要綱によらない民間の自主
的な調査・対策の実施件数が増加してきており、(社)土壌環境センターの会員企業に対する
アンケート調査結果によれば、土壌汚染の調査及び対策の実施件数は平成17 年度で10,812
件に及んでおり、このうち土壌汚染調査の約8 割の件数が民間の自主的なものとなっている。
土壌汚染対策法や条例・要綱に基づく調査は約2 割である。
図2.2.3 土壌汚染調査の対象
? 土地取引を契機とした自主的な調査・対策が多い
調査及び対策の実施件数の多くは土地取引を契機としたものとなっており、土地取引に際
して土壌汚染の存在の有無の確認、存在する場合の調査・対策を求めるケースが増えている
ことがうかがえる。
図2.2.4 土壌汚染調査・対策の受託件数及び受託金額の推移
表2.2.1 土壌汚染調査・対策の契機となった理由
図2.2.5 自主調査を行う契機となった理由
図2.2.6 自主対策を行う契機となった理由
2.3 ヒアリング等による土壌汚染の実態
デベロッパー3 社、ハウスメーカー1 社、総合建設会社1 社、外資系不動産ファンド1 社、
産業用不動産特化型REIT 運用会社2 社、大規模土地所有企業3 社、地方公共団体6 団体に対
するヒアリング調査等から判明した土壌汚染の実態は、以下に示すとおりである。
2.3.1 土壌汚染の発生状況と対策
? 土壌汚染の発生状況
土壌汚染は、古くから操業を行っていた工場跡地、操業中の工場用地、市街地内のメッキ
工場やクリーニング工場、ガソリンスタンド、臨海部の埋立地、廃棄物により埋め立てられ
た土地、自然由来と思われる商業地等において判明している。
? 大都市と地方との比較
ア.大都市における土壌汚染と対策
東京のような大都市内においては、土地取引や都市開発の際に土壌汚染が判明しても、
土地価格が高いことから、掘削除去などの浄化対策費用を吸収可能であることから、ブラ
ウンフィールド化している事例はほとんど聞かれなかった。
マンション開発などの際には、土地所有者による掘削除去による対策がほとんどである。
なお、大都市内において、土地履歴調査で汚染のおそれのない土地において工事中の段
階で、搬出土調査等により汚染が判明するケースが出てきている。こうした場合は、売主
と買主との間で訴訟になるケースも見られた。
イ.地方における土壌汚染と対策
新潟市や盛岡市などの地方中核都市の市内においては、最近マンション開発などの際の
調査で土壌汚染が判明したケースが見られるが、その場合は主に掘削除去による浄化対策
が実施されており、土地取引や都市開発がストップしたような事例は聞かれなかった。
なお、新潟市内において、マンション開発の際に掘削除去と併せて封じ込め措置による
対策を併せて実施している事例もあり、また住宅以外の商業施設等の立地の場合は封じ込
め措置による対策も行われている。
しかし、それ以外のエリア、又は汚染の程度が広範囲に及んでいる場合は、土地価格に
比して相対的に土壌汚染対策費用が高いことから、汚染拡散防止措置のみを行っている事
例も見られた。こうした場合は、開発を断念したり、土地取引において買主と売主との間
でトラブルになるケースが生じている。
ウ.小規模な事業用地における土壌汚染と対策
地方都市内のメッキ工場やクリーニング用地において土壌汚染が判明した場合に、土地
所有者に対策コストを負担する資金的能力が低いことから、土地取引ができずにそのまま
となっている土地が存在しているケースが見られる。こうした土地では汚染拡散防止程度
の措置が実施されている。
クリーニング工場やメッキ工場などの小規模な事業所の汚染では、対策費用の比率が高
くなり、また資力もないことから、利用促進上のハードルが高くなって、ブラウンフィー
ルド化の懸念が高まっている。
大規模な再開発の中での小規模な土壌汚染の存在については、再開発事業の中で対処す
ることが考えられるが、市街地内で単独で残っている場合は、調査すらされずにそのまま
残されてしまうケースの発生が懸念される。
なお、ガソリンスタンドが廃止又は改修する際に油による土壌汚染が判明したケースが
あるが、系列の大手会社が前面に出て調査・対策を実施しているため、問題は生じていな
い。
? その他
ア.土壌汚染情報の秘匿
今回のヒアリングは、各企業や地方公共団体による土壌汚染問題への取組みを調べるの
みならず、個々のサイトの土壌汚染情報についても把握し、今後の検討に役立てることを
も意図したものだったが、あまり個別のサイトの土壌汚染情報は聞くことができなかった。
イ.土壌汚染が判明した場合の汚染原因者でない土地所有者の困惑
土地所有者が関与していない、いわゆる自然由来、埋立由来、もらい汚染と考えられる
土壌汚染が判明した場合に、とりわけ資金負担能力の低い土地所有者にとっては、対策を
行うことが困難であるため、相当深刻な事態となっている。
ウ.調査実施後に新たな汚染が判明したケースの発生
土地履歴調査を実施して汚染がないと判断して、土地を買収して開発する際に土壌汚染
が新たに判明したケースが生じており、売主と買主との間でトラブルになったり、デベロ
ッパー側に何らかの負担を強いられている。
2.3.2 デベロッパー3社
? 土壌汚染への対応
大手のデベロッパーは、事業用地の取得に際して土壌汚染に対処する独自の調査・判定ル
ールを設けて用地取得の可否を選別している。すべての案件についてフェーズ?調査は必須
としており、土壌汚染の可能性がある場合はフェーズ?調査を実施して、取得の可否を判断
している。
土壌汚染物件の住居系への開発・転売については、原則として掘削除去など完全浄化が可
能なものである場合が多い。但し、物流施設や商業施設への転用のケースでは法令要件を満
たせば、完全浄化でなくても受け入れるケースがある。
土地取得に際しては、自然由来による汚染も含め環境基準超過土壌は完全除去を行うこと
を基本としている。
? 特徴的な事例
ア.大都市内の都市開発可能用地において土壌汚染のため都市開発を断念したケース
大都市内の都市開発が可能な土地は、通常土地価格が高いことから、土壌汚染が判明し
ても掘削除去による対策費を吸収することが可能であるが、土壌汚染が重篤な場合や、土
壌汚染が相当にあると考えられリスク評価できない場合、周辺の状況から対策ができない
場合、また土地所有者が瑕疵担保責任を負わない場合には、開発を断念するケースがある。
イ.工事中の調査で新たな汚染が判明するケース
土地引渡し前の調査では土壌汚染が判明していないが、工事中の調査で汚染が見つかっ
たケースが出てきており、事前調査の信頼性が揺らいでいる。
こうした場合は売主・買主の間で責任の範囲についてトラブルに発展しやすい。瑕疵担
保期間が過ぎた場合や売主が全く知らない場合もあり、事業者側の新たな負担となる。ま
た、追加対策のために事業スケジュールが伸びると、契約期間内の引渡しが困難になる、
金利負担が増大するなどの影響がでる。
? 意見・感想等
ア.土壌汚染問題は地方都市ほど都市開発に影響を与えるため、対策面での工夫が必要
地方都市で、ブラウンフィールドが発生する可能性は高い。地方になればなるほど土地
価格が下がり、その対策費を土地価格で吸収できなくなる。掘削除去以外の封じ込めなど
の対策を模索していくことが必要となる。
札幌市や新潟市での開発事例(分譲マンション開発)では、土壌汚染対策費は土地価格
と同程度となって負担が大きく、掘削除去による対策では採算が合わない事態が生じてい
る。このため、深さ1m まで掘削除去、1m 以深の汚染については封じ込め措置を行って開
発したケースがある。購入者に対しては土壌汚染の調査・対策の状況を十分に説明して了
解を得ている。なお、封じ込め措置による土地価格の減価は行っていない。
イ.土壌汚染処理のための新たな基準づくりについて
現在の土壌汚染の環境基準では対策が過大になりがちで、そこまで浄化処理する必要が
あるのか、疑問の声が聞かれた。土地利用に合わせて、もっと緩やかな基準があってもよ
く、行政側で新たな基準づくりが行われることが望ましい。一般に広く理解が得られ、資
産評価にも影響しないようなものが出来るとよい。
法や条例の改正により新たな項目が環境基準に追加されると既存不適格となってしまう
土地が生じ、新たな対応が求められることになり、このような土地が多いことが指摘された。
ウ.土地取引のリスクを軽減する保険制度について
瑕疵担保保険は、保険料が高いため現在利用されていない。事業者のリスクを軽減でき
るような保険があればよいとする意見や、なくてもよいとする意見があった。
エ.地方や中小の工業等事業者への支援について
土壌汚染問題で身動きのとれないで困っている地方や中小の工業等事業者に対する支援
措置があれば、望ましい。
オ.土壌汚染地を開発する際のインセンティブ
土壌汚染地を開発する場合に、開発者側のリスクを緩和するような措置や自然由来の汚
染など原因者が不明の場合については固定資産税減免などの支援措置があれば、望ましい。
<参考>
(社)不動産協会作成の「マンション開発事業における土壌汚染対策に関する留意事項」
【マンション事業における土壌汚染対策に関する留意事項】(平成14 年11 月(社)不動産協会作成)
(社)不動産協会では、平成14 年11 月に、分譲マンション事業においてデベロッパーとし
てのリスク管理の観点から考え方を示したガイドラインである「マンション事業における土壌汚
染対策に関する留意事項」を定めた。詳細は以下のとおりである。
・ 土地履歴等調査については、売主に詳細な情報の提供を求めるとともに、買主自らも土壌汚
染情報の収集を行う。
・ マンション事業用地の売買契約において、土地履歴等調査で汚染がないことが確実な場合を
除いて、土壌汚染に関する調査を売主の負担と責任において約定し、また汚染が認められない
として引渡しを受けた後に買主の調査で汚染が発見された場合は、売主に対して責任を追及で
きる旨の特約を明確に約定する。
・ マンション事業用地の土壌汚染については、売買契約において浄化処理・汚染拡散防止措置
等を売主の負担と責任において引渡し日までに実施する旨、また引渡し後に買主の調査で汚染
が発見され、買主が浄化等の措置を行った場合についても、その費用並びに損害賠償を売主に
対して請求できる旨を明確に約定する。
・ 土地引渡し後の土壌汚染の発見に備えて、売買契約書には、所有権の移転時期、土壌汚染に
関する瑕疵担保責任及び売主による浄化措置の実施義務等の条項を必ず記載する。
・ 敷地に対して浄化処理・汚染拡散防止措置等を実施した場合は、購入者に対して重要事項説
明書に基づいて正確に説明し、また購入者にその報告書(写)を交付し、併せて管理組合に原
本を引き渡す。
2.3.3 ハウスメーカー1社
? 土壌汚染への対応
大手の開発案件については、独自の調査マニュアルに基づき、すべての案件で土地履歴調
査を実施している。工場についてはすべてリスクありと判断し、また、資材置き場、倉庫、
作業場等についても詳細が不明な場合はリスクありと判断して土壌調査を実施している。
マンション用地では履歴上のリスクの有無にかかわらず全案件でより厳格なリスク評価を
行っており、汚染が判明した場合は原則として掘削除去等の完全浄化を実施している。年に
数件、汚染が重篤な場合や土地価格に見合わない場合として土地取得を断念している。
商業系や駐車場用途の場合で低濃度汚染の場合は、掘削除去以外の封じ込め又はバイオ手
法などによる長期浄化の対策もありうる。
土壌汚染リスクのある土地に対しては、跡地利用に併せて調査及び浄化対策を同時に検討
することにより、最適利用しましょうという提案をし始めている。
なお、汚染があった土地を販売する場合には、完全浄化後であっても重要事項として顧客
に説明を実施している。説明後の顧客の反応は比較的良好であった。汚染の程度が比較的低
濃度で対策も掘削除去とわかりやすい内容であったこと、積極的なリスクコミュニケーショ
ンを実施したこと等から、顧客の理解が得られた。
? 特徴的な事例
ア.建設時に新たな汚染が判明するケース
造成時の盛土や廃棄物埋設による汚染は土地履歴調査では発見することが困難であり、
マンション建設時の搬出残土の調査(残土条例や残土業者の自主調査)で汚染が判明する
事例が増えている。売買契約時に瑕疵担保を定めていても、売主の経済力などの問題で回
収できず、瑕疵担保が効果を発揮しないケースが増えてきている。
イ.施設建設後のモニタリング調査で汚染が判明するケース
特別なケースとして、過去に廃棄物により埋め立てられた土地を商業開発する際に土壌
汚染が判明したため、封じ込め措置を行って施設を建設したが、オープン後のモニタリン
グ調査で汚染地下水の流出が判明したことから、土地所有者が再度流出防止対策を実施し
た事例がある。
2.3.4 総合建設会社1社
土壌汚染を抱える開発案件の最近の情報や相談事例から、土壌汚染に関して以下のような
指摘があった。
? 土壌汚染地に対する土地所有者・土地購入者の意識
土地所有者の意識として、汚染があると買手が見つからないので、売却するためには完全
浄化をせざるをえないが、対策費用が工事費の30%を超えると、売却益が見込めなくなって
売却を断念するケースが多くなり、土地保有を継続して土地利用していくこととなる。
土地購入者としては、汚染がない、又は完全に浄化された土地を購入したい、という意識
が強い。背景として、土地利用上の制約がない、後々の問題を抱えたくない、風評が心配、
再売却時に問題を残したくない、という理由がある。
? 小規模事業所のブラウンフィールド化の懸念
大都市圏では、最近の土地価格の上昇傾向もあって土壌汚染対策費用を捻出できるケース
が大半である。しかし、クリーニング工場やメッキ工場などの小規模な事業所の汚染では、
対策費用の比率が高くなり、また資力もないことから、利用促進上のハードルが高くなって、
ブラウンフィールド化の懸念が高いケースがあるように感じられる。こうした場合では、調
査や対策もされずにそのまま残されてしまうような懸念がある。
? 商業施設や倉庫における封じ込め措置の例
商業施設や倉庫については、封じ込め措置により利用している事例が出てきている。
? 地方都市におけるブラウンフィールド化の事例
地方都市の工場等跡地において売却の際の自主調査で土壌汚染が判明し、土地価格に比し
て汚染対策費用が高額になるため、売却を断念して拡散防止措置のみを行ったうえで、駐車
場等に暫定利用又は放置されている、事例が数例ある。
・ 工場を閉鎖して土地を売却する際の自主調査で土壌汚染が判明しため、重金属による汚染
部分を掘削除去して、地下水汚染のない約半分の土地を売却し、残りの半分は売却を断念し
た事例
・ 工場跡地を購入して一部の土地を売却した後に自主調査により汚染が判明したが、対策費
用が多額になるため拡散防止対策(舗装及び揚水処理)のみを実施したが、新たな土地購入
者を確保できないため、駐車場として暫定利用している事例
・ 工場用地の一部を開発事業者に売却する際の自主調査で重金属汚染が判明したが、土地価
格に比して対策費用が過大になるため、売却を断念して舗装状態のままで利用用途を検討し
ている事例
・ 製油所跡地に公共的施設を誘致する際の自主調査で重金属、VOCs 及び油による広範囲な
土壌汚染が判明したが、土壌汚染対策費用が多額となるため、売却を断念してゴルフ練習場
などとして利用している事例
・ 工場跡地の売却の際の自主調査で重金属及びVOCs による汚染が判明したため、社会的責
任の見地から土地所有者は掘削除去を実施したが、土地の売却はやめて商業施設及び駐車場
として賃貸している事例
2.3.5 外資系不動産ファンド1社
? 土壌汚染への対応
受け入れ基準は厳格で、フェーズ?調査で土壌汚染の可能性が確認されれば、土地購入の
対象としていない。土地購入の対象となる不動産は汚染がない土地である。
今後の事業展開において、土壌汚染地を扱う可能性はあるとしているが、土壌汚染地を扱
う場合にはリスクを定量評価できることが必要であり、技術面のリスク・テイクをするゼネ
コン等の関与が必要である。
? 意見・感想等
フェーズ?調査のコスト低減、確度の向上につながる情報の開示は歓迎する。
2.3.6 産業用不動産特化型REIT 運用会社2社
? 土壌汚染への対応
商業・物流REIT では、汚染リスクが残置する物件を取得するケースもあるようである。
土壌汚染地の取得に関して自主基準に基づいて判断しており、ある社では、
?適切に対策され周囲への影響がないこと、
?将来の汚染対策費が予測可能であること、
?将来売却する場合に資産価値の大幅な下落がないこと、
の3 点を投資対象の要件としている。投資の持ち込み物件には土壌汚染地が多いが、
検討の優先順位は低くなる。
しかし、一方で投資の検討対象として土壌汚染地を避けて通るのは難しい。
? 特徴的な事例
産業用不動産については、産業用地としての利用の継続性が投資対象を選択する基準であ
ることから、掘削除去にこだわる必要はなく、その他の対策も実施可能である。
将来の改築の際に発生する汚染残土処理費用や土壌改良費を見込み、土地価格から減価す
ることで、土地取引を実施している例もある。
? 意見・感想等
ア.汚染情報の開示と活用について
元来REIT では、土壌汚染情報を開示する義務がある。検討対象物件の土壌汚染情報を
得られることは歓迎するが、コストが必要な場合はコスト・パフォーマンスで判断する。
イ.エンジニアリングレポート(ER)の信頼性の確保が必要
特別な資格を有しない者が作成するER に基づいて不動産鑑定士が土地評価を行うこと
には、問題があると思われる。
ウ.埋立由来や原因者が特定できない汚染の場合についての行政側の適切な支援
埋立由来や原因者が特定できない場合は行政側の適切な支援を行う制度の構築が望まし
い。
また、優遇税制、補助金などの制度化に向けての検討を期待する。
エ.政府による用途別基準づくり
土壌汚染地の土地取引についての自主基準は持っているが、政府による用途別の基準が
あることが望ましい。
2.3.7 大規模土地所有企業3社
? 土壌汚染への対応
所有地の土壌汚染については、自主的な調査・対策を実施している。
東京都内の工場跡地を都市開発する場合は、掘削除去による土壌汚染対策を実施している。
住民・マスコミ等風評リスクを恐れる企業も少なくなく、情報開示に必ずしも積極的では
ないという企業がある一方、自らホームページ等で公開に努めている企業もあった。
関西のある企業では、関西圏に広く散在している工場跡地の十数ヶ所で土壌汚染が判明し
たため、土壌汚染のリスク管理措置として、汚染拡散防止、地下水監視などの用地管理強化、
土壌の改善措置(盛土や舗装による表層追加被覆、汚染土壌中心部の掘削除去、土壌ガス吸
引などの原位置浄化)を実施している。
? 特徴的な事例
ア.土壌汚染地の自社利用等をしているケース
土壌汚染地については、掘削除去による浄化措置を実施して用地を売却した場合や、売
却しないで自社利用している場合がある。
後者については、汚染を残した状態では土地を売却できないものの、土壌汚染対策費が
高額になることから、やむをえず研究施設、倉庫、事務所、訓練所等として自社利用して
いる面もある。
関西のある企業が所有する京都市内の工場跡地のような立地条件の良い場所はグループ
会社で都市開発している。この場合も土地は売らずに施設を建設して賃貸している。建物
基礎部分は掘削除去を実施している。
イ.土壌汚染が土地活用を阻害しているケース
立地条件のよくない工場跡地では、土地利用ニーズがあまり期待できないことや土壌汚
染対策費がかかりすぎることがネックとなって土地活用の阻害要因となっていることがあ
る。
? 意見・感想等
ア.埋立地の土壌汚染対策に係る所有者責任について
臨海部の土地は埋立由来と考えられる汚染が必ずあり、土地を購入した所有者がすべて
対策をしなければならないことに対して、疑問を感じる。
イ.原因別、用途別の基準づくりが望まれる
現在の環境基準が厳しすぎるきらいがある。埋立由来や自然由来と思われる汚染、地下
水の直接摂取の可能性が低い汚染に対しては、基準に少し配慮があっても良いのではないか。
ウ.土壌汚染地を開発する際のインセンティブが望まれる
もらい汚染、埋立由来の汚染など土地所有者が原因者でなく、原因者が特定できない汚
染に対しては、対策費用の一部補助や税の減免措置などの支援が望ましい。
地方の土地価格の安い土地の汚染については、土地が売るに売れない厳しい環境にある
と思われるため、このような土地の有効利用を促進するための支援が望ましい。
エ.土壌汚染に対する心理的抵抗感の払拭が必要
土壌汚染に対して過剰反応しすぎる面があり、リスク管理措置でも大丈夫であるという
認識が広まるように努めてほしい。
2.3.8 地方公共団体
(1)岩手県、盛岡市
? 土壌汚染への対応
行政に報告されている土壌汚染については、法や条例に基づくもの以外の民間の自主調査
によって汚染が判明したものが多い。報告のあった件については、法や条例等に基づいて相
談・指導を実施している。なお、地下水汚染が判明した場合は、行政側で周辺の地下水調査
を実施して汚染の拡大の有無を確認している。
開発区域内のクリーニング工場跡地で溶剤漏出による汚染が判明したため、土壌浄化対策
を実施している。また、地下水モニタリングを実施する必要があることから、そのスケジュ
ールが遅延するおそれがある。
? 特徴的な事例
ア.市内のマンション開発を契機とした自主調査で土壌汚染が判明
盛岡市内でマンション開発が進んでおり、開発を契機とした民間の自主調査で土壌汚染
が判明したケースが出てきている。
マンション開発の場合は土地所有者が掘削除去で対処している。
また、かつて商用地として利用され、土地履歴で土壌汚染のおそれの少ない土地を買収
した後に、買主側の自主調査で土壌汚染が判明(盛土造成による汚染の可能性が高い)し
たケースもある。こういった場合、マンション開発のため全量掘削除去したくとも、その
対策費が多額になるため、費用負担の割合をめぐって売主と買主との間で訴訟になるおそ
れが生じている。
イ.油汚染の事例
自動車整備工場による油汚染の事例や灯油流出汚染の事例が報告されている。
? 意見・感想等
岩手県内(盛岡市除く)では、工場は継続操業されており、土壌汚染問題が生じている工
場跡地は今のところ見当たらない。工場の自主調査で土壌汚染が見つかった場合は必要な対
策が実施されている。
なお、盛岡市内を除いたエリアでは、都市開発ニーズが乏しいことから、工業の継続的な
土地利用が余儀なくされている面もあると考えられる。
(2)埼玉県
? 土壌汚染への対応
土壌汚染が見つかった場合は、事業者に公表を勧めている。事業所敷地外への地下水汚染
が考えられる場合には、行政側で周辺の地下水調査を実施している。
? 意見・感想
・ 土壌汚染対策法第3 条ただし書きで調査が猶予されているケースも多く、土壌汚染が発覚
しないことがあると思われる。土壌汚染の対策としては、掘削除去がほとんどである。
・ 小規模な事業所が多いクリーニング業は、調査が行われることが少ない。同じ小規模な事
業所でもガソリンスタンドは業界の補助金制度を活用して汚染を除去している例が見られる。
・ 埼玉県内の比較的交通便利な場所では、都市開発が進みつつあるが、土地価格の上昇によ
り掘削除去対策でも採算がとれるようになってきている。
(3)新潟県・新潟市
? 土壌汚染の状況と対応
新潟県生活環境の保全等に関する条例(平成16 年9 月施行)に基づき、有害物質を扱う事
業所については5 年に1 回土壌汚染調査を義務付けている。汚染が確認された場合は県等へ
の報告が必要であるが、まだ報告件数はわずかである。
調査義務対象外の事業場の自主調査により土壌汚染が判明し届出されたものは30 件以上
であるが、その調査の契機は土地取引に際してのものが多い。土壌汚染は、金属製品製造業
等によるものが多く、またガソリンスタンドの廃止又はタンク改修によるものも5〜6 件ある。
土壌汚染は、工場跡地に限らず、商業地等においても見られる。新潟市の場合は、地質の
特性から自然由来といわれる砒素などによる汚染が見られる。また、新潟地域には油田が埋
蔵されており、また石油産業の立地が多いため、先の地震による液状化の影響で油汚染が判
明する可能性がある。
マンションなど住宅開発の場合は掘削除去による対策が最も行われている。但し、マンシ
ョン開発の場合でも、汚染が敷地の広い範囲に及んでいるケースでは、建物基礎及び含有量
基準をオーバーしている汚染箇所を掘削除去し、溶出量基準をオーバーしている箇所等は封
じ込め措置がとられているケースがある。
住宅以外の商業施設、工業系施設の場合は、掘削除去は費用がかかるため、汚染拡散防止
措置がとられるケースが多い。敷地内の他の場所に汚染土壌を移動してアスファルト舗装等
による拡散防止措置が実施されている。
なお、新潟市内において、土壌汚染のために土地取引や土地利用が停滞しているような事
例は聞いていない。また、土壌汚染地の土地取引において問題が発生しているような事例も
見当たらない。
? 特徴的な事例
ア.工場跡地等で開発等がストップしている事例
・ 自治体がかなり以前に工場跡地を取得したが、土壌汚染が判明したため、土地利用が進
まないケースがある。原因者は撤退しており、汚染拡散防止のために土地所有者である自
治体が地下水モニタリングを実施しているが、土地は未利用のままである。
・ 工場が廃止された跡地に商業施設が立地し、その商業施設を改築する際に土壌汚染が判
明したため、商業施設が改築を断念、撤退して未利用地のまま残されているケースがある。
・ 小規模なメッキ工場の廃止に際して土壌汚染が判明したが、浄化対策を実施することは
困難であるため、土地は拡散防止程度の措置をして未利用のまま残されているケースがあ
る。借地していた工場側と土地所有者との間で原状回復についての話し合いが続けられている。
イ.小規模な工場用地等の汚染の事例
小規模な工場用地の汚染の事例として、金属製品製造業の用地の汚染、クリーニング工
場用地の汚染、ガソリンスタンドの汚染が発生している。
金属製品製造業の工場用地でトリクロロエチレンによる土壌汚染(地下水汚染もあり)
が判明しているが、対策費用の関係で浄化は無理で拡散防止措置を実施している。
クリーニング工場の廃止に伴って汚染が判明した事例は2 件あり、この内の1 件は立地
条件がよい場所であったため、掘削除去による対策を実施した後に土地を売却している。
他の1 件は浄化対策が実施されたという報告は受けていない。
ガソリンスタンドの廃止又はタンクの改修に際して、ベンゼン及び油による土壌汚染が
見つかっている事例が5〜6 件ある。ガソリンスタンドのほとんどは大手の系列店であり、
大手企業が前面に出て土壌汚染調査・対策を実施している。
? 意見・感想等
新潟県内では、金属製品等製造業の中小規模事業所が多いことから、今後土壌汚染が判明
しても、自前で浄化措置を実施できないケースが出てくることが想定される。また、浄化対
策に長期間かかることや費用面の問題から、工場の操業中から汚染対策を実施していかない
と、対策ができなくなる可能性がある。
自然由来など土壌汚染の原因者が不明の場合に、対策が実施できないようなケースが出て
くる可能性がある。
(4)福島県
? 土壌汚染の状況
民間の自主調査で土壌汚染が発見された場合については、自発的に県への報告を依頼して
いる。県への報告・相談の件数は、自主調査によるものが年間数件程度、土壌汚染対策法に
基づくものは、年間0〜3 件である。
報告があった事例については情報を保管しているが、情報の公開は難しい。土壌汚染情報
全般については、現在稼動している事業所など大企業は自主調査を行っているようだが、県
で全ての結果を把握しているわけではない。
? 特徴的な事例
ア.土壌汚染地の土地利用が円滑に進んでいない事例
住宅地開発の中で、一部の土壌汚染地が未利用のままとなっている事例がある。
従前の利用は資材置き場であったが、宅地開発を行う段階で土壌汚染が発見されたが、
汚染原因者と考えられる企業が倒産したため、汚染除去費用を開発者が負担すると事業が
成立しないので、立ち入り禁止措置がとられている。
イ.土壌汚染地の土地取引・土地利用に際して問題が生じた事例
・ 工場の移転の際の自主調査によりVOC 類の汚染が発見されたため、事業者による浄化
措置が完了した後、教育施設用地として福島県が購入した。その後、県が施設を建設する
工事を行う過程で新たにフッ素による汚染も発見されたが、フッ素は事業者が行った調査
の項目に含まれていなかった。県では、教育施設用地としての土地利用を考慮して安全性
を重視して掘削除去を実施したが、汚染浄化費用は事業者と福島県で折半された。
・ 駅前広場整備工事中に土壌汚染(地下水汚染はない)が発見されたが、用地取得が土壌
汚染対策法施行前で瑕疵担保による負担金を求めることが出来なかったため、福島県が掘
削除去による対策費用を負担した。
? 意見・感想等
福島県の制度として環境創造資金という名称で公害対策用の低利融資制度を設けているが、
市中の銀行とそれほど利子が変わらないこともあって、あまり利用されていない。土壌汚染
対策を推進するために、この融資制度を広く周知し、制度が効果的に利用されるように図っ
ていく必要がある。
今後、県が公共事業土地を購入する際には、工場などの場合は土壌汚染について確認して、
契約段階で土壌汚染の浄化を附則として盛り込むことが必要かもしれない。
3.土壌汚染に係る現行制度と諸問題・取組み
3.1 土壌汚染の調査と情報収集
3.1.1 土壌汚染調査
(1)土壌汚染調査の目的及び契機
土壌が有害物質により汚染されると、汚染土壌の直接摂取や、汚染土壌から有害物質が溶
出した地下水の飲用等により人の健康に影響を及ぼすおそれがある。汚染原因者等の責任の
明確化と土壌汚染による健康被害の防止が求められる中、土壌汚染対策の法的な拠り所とし
て、平成15 年に土壌汚染対策法が施行された。同法のもとでは、特定の有害物質を取り扱っ
た工場や、事業所の敷地であった土地の所有者に土壌汚染の調査と、その結果の報告が義務
づけられている。
また、独自に条例を定め、土壌汚染調査に関して、より厳格な規定を設け
ている自治体もある。たとえば、東京都は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
において土壌汚染に関する規定を設け、3000 ?以上の土地の改変を行う場合又は有害物質
取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合、調査を実施し報告することを
義務付けている。
しかし、前述の土壌汚染対策法や自治体の条例に基づく調査は、土壌汚染調査実施例の約
2 割を占めるにすぎない。土壌汚染対策法が施行されて以来、法や条例に基づかない民間の
自主的な土壌汚染調査が増えている。企業は、環境マネジメントや資産マネジメントにおけ
る重要な活動として、汚染の可能性のある土地の実態把握、自然由来やもらい汚染の可能性
の把握などを目的とした土壌汚染調査を実施している。また、不動産取引を契機とした土壌
汚染調査も、活発に実施されるようになった。
(2)土壌汚染調査の対象物質
「土壌汚染」状況は千差万別であり、サイト毎に最適な調査・対策方法を検討し、実施し
ていくことが重要である。また、「土壌汚染対策法」が 対象とする土壌汚染は、特定有害物
質26 項目(鉛、砒素など重金属等15 項目 、およびトリクロロエチレンなど揮発性有機化
合物11 項目)であるが、その他の規制物質や規制はされていなくとも土地利用の障害となり
うる可能性のある物質もあり、注意が必要である。ガソリン、重油、潤滑油、灯油等の油分、
ダイオキシン類、その他の化学物質(条例等において特に規制されている物質、臭気の強い
物質及び色のある物質等)、要監視項目(22 項目)等の規制対象候補の物質などが調査対象
となりうる。土地取引に際しての調査では、購入用途が住宅系である場合、履歴にかかわら
【土壌汚染対策法に基づく調査の概要】
(目的) 国民の健康保護
(対象物質) 特定有害物質(重金属、揮発性有機化合物等26 項目)
(対象:調査の契機)
? 使用がず「特定有害物質(農薬類を除く)」「油分」「ダイオキシン類」を調査対象とするケースが多
い。(社)日本不動産鑑定協会策定の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」では、
「特定有害物質を中心に各自冶体の条例等およびダイオキシン類対策特別措置法において対
象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば価格形成に大きな影響があるもの
とする。」とし、法令等による調査義務がないことのみで土壌汚染が無いとはできないとして
いる。
(3)土壌汚染調査の手順と標準化
土壌汚染調査は、土壌が汚染されているかどうか、さらに汚染されている場合にどの程度
の汚染であるか、を把握するために行われるものである。しかし、土地取引や対策計画立案
など、調査実施主体が調査結果を使用する目的に応じて、調査に必要とする精度や正確さは
異なる。したがって、日本において法や条例に基づかない民間の自主的な土壌汚染調査は、
法令に基づく調査に準拠して進められることが多いが、必ずしも統一された基準のもとに実
施されているわけではない。一般的な土壌汚染調査のフローを図3.1.1 に示す。
? フェーズ?調査
地歴等調査(フェーズ?)は、土地利用履歴調査(登記簿、閉鎖謄本、古地図、空中写真
等)、地形・地質に関する調査(ボーリングデータ、地形図等)、現地視察調査(周辺状況や
対象地の現況を把握)などに基づき、土壌汚染の有無について定性的に判断する調査である。
アメリカでは2005 年にEPA(連邦政府環境保護庁)がフェーズ?調査の標準となるAAI
(All Appropriate Inquiry:あらゆる適正な調査)を改め、これに基づきASTM(米国材料
検査協会)がフェーズ?調査の仕様を改定した。AAI とは、土地の所有者、新規購入予定者
がスーパーファンド法に基づき浄化義務を免れるために実施する必要がある調査である。
改定の目的は、浄化義務を免除された後で土壌汚染が顕在化するリスクを軽減するために、資
料等調査における質の向上及び調査内容(水準)における差異の低減を図ることであった。
AAI における従来標準からの重要な変更点は、環境専門家の資格明記、聞き取り調査の対象
者拡大、資料調査の対象拡大、土壌調査報告書の有効期限設定である。
一方、日本では、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)が土地取引時に作成され
るエンジニアリングレポート(ER)のガイドラインを定め、その中で土壌汚染のフェーズ?
調査手法を提案するなどの取り組みがあるが、統一された土壌汚染調査仕様が規定されるに
至っていない。法令等に準じたフェーズ?調査を実施することによって、土壌汚染リスクが
回避されるという一般認識が存在している。簡易なフェーズ?調査で土壌汚染の可能性が完
全に否定される場合を除き、フェーズ?調査による評価が求められる傾向が強い。したがっ
て、現状では、フェーズ?調査を実施することを想定し、日本におけるフェーズ?調査の水
準はAAI が要求する水準より低めに設定されている。
土壌汚染対策法の規定に基づく調査は、環境大臣(地方環境事務所長)が指定する指定調
査機関が実施することとされており、平成20 年1 月23 日現在、1,661 機関が指定されてい
る。東京都等の自治体の条例に基づく土壌汚染状況調査についても、原則として土壌汚染対
策法に基づく指定調査機関に実施させることが定められている。ただし、指定調査機関の認
定要件は届出による簡易な書面審査が中心であることに加え、土壌汚染対策法や条例が適用
されない調査では、土壌汚染の専門家以外でも調査の実施が可能なことから、調査結果の信
頼性を問題視する意見もある。
フェーズ?調査段階では、比較的簡単に入手できる情報のみに基づく調査であることから、
調査結果に不確実性が存在する。フェーズ?調査は、汚染の可能性を調査するものであるが、
汚染の可能性がないと判断した場合でも、不十分な調査により、対象地に存在する土壌汚染
を見逃している場合があり、留意する必要がある。ある不動産関連企業が独自に実施した調
査によれば、フェーズ?調査で汚染可能性が低いと判断した土地のうち、かなりの割合で土
壌汚染が検出された。特に、造成地において、外部から搬入された盛土部から検出されたと
想定される例が多くあり、フェーズ?調査の結果を評価する上での課題となっている。
? フェーズ?及びフェーズ?調査
フェーズ?調査で汚染の可能性があると判断された場合は、概況調査(フェーズ?)を実
施する。概況調査は、土壌汚染対策法に基づく汚染状況調査に相当するものであり、表層付
近のデータを採取し、汚染の存在を確認するとともに、平面的に汚染の存在するエリアを絞
り込むものである。この調査は、環境省監修・(社)土壌環境センター編「土壌汚染対策法に
基づく調査及び措置の技術的手法の解説」に示される方法に準じて、土壌ガス調査、5地点
混合法表層土壌調査が行われる。
詳細調査(フェーズ?)は、概況調査で絞り込んだエリアについて、ボーリングにより汚
染範囲を確定する。汚染対策の実施を前提として行われる調査であり、汚染の範囲・深さ・
程度を三次元的に把握して、対策の必要性、範囲を設定し、対策費用と期間を検討するため
に行うものである。汚染範囲が広い場合は、調査にかなりの費用と期間を要する。
土地利用の変更や土地取引に際して更地の状態で調査する場合には問題とはならないが、
開発検討段階の調査や権利置換型の事業では、調査段階で従前建物が存在(権利者が生活若
しくは営業)している場合が多い。このようなケースでは、可能な範囲でしか調査できない
ため、汚染リスクの見極めが困難となり、事業成立性の判断に影響を及ぼすことが懸念され
ている。
(4)土壌汚染調査の費用
調査のフェーズを重ねるごとに土壌汚染状況の把握の確実性は高まるが、それに伴って調
査費用も増大する。フェーズ?調査の費用は、40〜50 万円/物件であるが、フェーズ?調査
では対象範囲が大きいとその費用も多額になり、資金的余裕のない土地所有者にとっては大
きな負担となる。その費用は対象地を1,000 ?と仮定した場合、概況調査で1〜2 百万円/物
件、 詳細調査は数百万/物件となる。こうした高額の調査費用は、土地取引や開発計画を断
念したり、従来の土地利用をしたりする一因となる。また、不動産の競売入札において、土
壌汚染に関する調査を考慮に入れた上で入札する良い入札参加者ではなく、土壌汚染の可能
性を無視する悪い入札参加者が選ばれる逆選択の問題が生じているという懸念がある。
3.1.2 情報収集と活用
フェーズ?調査を実施する際には現地踏査やインタビュー、依頼者から提供される書類記
録等のレビューの他に、公的機関が保有する環境情報を精査する。次章で触れるように、ア
メリカでは、汚染サイトや浄化中のサイト、埋立地や処分場、貯蔵タンク等の情報が法や制
度によって登録されており、フェーズ?調査の実施時にはこれらの情報を評価の材料として
いる。
一方、日本でも同様の手法でフェーズ?調査が実施されているが、アメリカのような法や
制度がない。環境省と一部の自治体は、それぞれ土壌汚染対策法と自治体条例が適用された
土壌汚染地の調査・改善措置に関する情報を収集し、情報提供しているケースもあるが、こ
れらの情報を制度的に集約する機関がないため、公的機関から多くの環境情報を得ることは
できない。また、法や条例の適用を受けず、自主的に実施された調査や改善措置が、土壌汚
染調査実施数の大半を占めているものの、それらを共有できる仕組みが構築されていないこ
とも課題である。土壌汚染に関して参照できる情報、資料の蓄積が少ないため、調査の案件
毎に始めから調査を実施する必要が生じている。
調査を実施して汚染が判明すると、対策の実施や公表を迫られ、企業の業績への影響やイ
メージの低下につながる事態をおそれて、調査を実施しないケースも存在する。土壌汚染に
対する社会的な見方は変わりつつあるとはいえ、自主的な調査の結果の提供については、企
業サイドも消極的となることが想定される中で、効果的な情報収集を図ることが重要である。
フェーズ?調査を実施する際には、住宅地図、不動産登記簿、土壌汚染に係る地域の基礎
的情報(土地利用履歴、過去の地形図、漏出事故・汚染記録、潜在的汚染源の位置、地下水
水質等の環境情報など)、その他、地方自治体や各省庁が所管する基礎的情報が活用される。
これらの基礎的情報が、未整備もしくは個別に収集、管理されているために、データ収集の
非効率が生じている。これらの基礎的情報・データがアクセスしやすいように整備されるこ
とが望ましい。
土壌汚染に関する情報インフラが整備されることによる効果は、前述のとおりフェーズ?
調査の品質確保や効率的な調査に資するものであり、生産性の向上にも結びつくものである。
そして、土地取引等に当たっての保険活用や担保評価に資する有用な情報となる。また、情
報インフラが整備されることにより、土壌汚染地の譲渡等があった場合、次の管理者等が土
地の情報を引き継ぐことができる。これにより土壌汚染による環境リスクの制度的管理につ
いても、次の管理者等へ承継できる。
3.2 土壌汚染の基準
3.2.1 用途別基準
住宅や産業用地といった土地の用途に関わらず、土壌汚染が環境基準の数倍でも1,000 倍
でも、環境基準を超えていれば、土壌汚染地として同様に扱われることが、土壌汚染地対策
を非効率なものとしているという指摘が多い。健康被害の防止を前提として、土地利用と関
連付けた基準作りを望む意見も聞かれるところである。しかし、一方で、土地利用と関連付
けた基準の導入においては、土地の用途変更に際して対応する仕組みづくりが必要となる。
土壌・地下水汚染対策の目標は相当にレベルが高いため、目標水準まで浄化する場合の対
策費用は高額となる。将来、土地利用の用途に合わせた基準などが設定されれば、対策費用
の低減が可能になると考えられる。
3.2.2 自然由来の汚染
明確な自然的原因は、種々の資料もあり、データがあれば正確な判断と基準設定も可能で
あると考えられる。例えば、鉱床地帯・その周辺などの鉱染地帯や変質岩帯の地域から発生
する汚染土壌(道路工事など)については、広域地質図、一部の地域の鉱染マップ、採石資
源分布図を使って類推はできる。一方、都市部の土壌を考えると、本来の自然的原因の汚染
土壌と、過去の人間活動(不特定多数の人間活動を含む。)に起因する汚染者特定不可能な汚
染土壌などが混在しており、濃度的な問題や分布の問題の挙動が同じでも、汚染者負担の公
平性から考えると、負担者の面からも安易な分類ができない場合もある。
上記のとおり、自然由来の土壌汚染に対する基準については、さらなる科学的データの蓄
積、公開が重要である。こうした視点で、地質情報、自然起源汚染情報、人為汚染情報など
の全国規模の各種地圏情報をGIS 化して情報提供するシステムとしての「地圏環境インフォ
マティクス」構築の取り組みが東北大学を中心に行われている。この中では、日本の重金属
バックグラウンドの把握、地域によるバックグラウンドの差異の把握方法の開発、地質と環
境因子との関連性の把握と、これらを共通のプラットフォームで把握する試みが進められて
いる。
現行の法規制においては、自然的原因による有害物質含有の土壌は、「人の活動に伴って
生ずる相当範囲にわたる土壌汚染」(環境基本法第2条第3号)ではないことから、同号の「公
害」には該当せず、環境基準の適用においては「汚染が専ら自然的原因によることが明らか
であると認められる場所においては適用しない」こととされているため、中央環境審議会の
2002年1月答申「今後の土壌環境保全対策の在り方について」の中で、「自然的原因により
有害物質が含まれる土壌については、人の活動に伴って生じる土壌汚染ではなく、したがっ
て環境基本法で定める公害とは言えないことから、この制度の対象とはせず、別途検討され
るべき課題であると考える。」こととされている。
専ら自然的原因により高濃度の特定有害物質を含む土壌又は水底土砂が、同様の土壌又は水底土砂の存する周辺の地域において盛土や海面埋立等により土地の造成に用いられた場合には、造成された土地は自然的原因により基準に適合しなくなったものとされ、土壌汚染対策法や条例の適用対象とはならないものとされている。
一方、土地の造成に伴い当該地域とは異なる土地から持ち込まれた土壌については、それ
が専ら自然的原因により指定基準を超過するものであっても、平成15年2月15日環水土第24
号通知「指定区域以外の土地から搬出される汚染土壌の取扱指針について」の中で、土壌汚
染対策法の指定区域以外から搬出される汚染土壌についても、同法の考え方に即した取扱い
が望ましいこととされており、土壌を持ち込んだ者が汚染原因者と見なされる。持ち込んだ
者が不明等の場合には、土壌汚染対策法第7条第1項に基づき土地の所有者が必要に応じて措
置を行うこととされている。
土壌汚染が自然由来であるかについては、環境省が土壌汚染対策法施行時に地方公共団体
宛発出した「土壌汚染対策法の施行について(平成15年2月環水土第20号)」における「土
壌中の特定有害物質が自然的要因によるものかどうかの判定法」に基づいて判断が行われる。
具体的には土壌溶出量基準を超過する場合の判断基準として、
?対象物質の種類等、
?対象物質の含有量の範囲等、
?当該特定有害物質の分布特性、
の3項目から検討することとされ、また含有量基準を超過する場合の判断基準として、
?バックグラウンド濃度又は化合物形態等、
?使用履歴場所等との関連性、
の2項目から検討することとされている。
しかし、一般的に、土地取得に際しては、自然由来による汚染も含め環境基準超過土壌は
完全除去を行うことが原則とされている。自然由来による土壌汚染が深い部分まで及んでお
り、完全除去が事実上不可能もしくは売主に完全除去を求めることが不適当と判断される場
合は、建物の根切り深さに相当する一定の深さまでの除去を求め、それより深い部分の汚染
は免責とされるケースもある。
3.3 土壌汚染の対策
3.3.1 責任負担者
土壌汚染対策法では、汚染が判明した土壌は都道府県が「指定区域」として指定・公示し、
指定区域内の土壌が健康被害を招く恐れがある場合には、汚染原因者が特定できるケースを
除き、原則として土地所有者に対策を義務づけている。土壌汚染対策法では、土地所有者等
が汚染除去等の措置をした場合に、汚染原因者に対して措置費用の請求ができることとされ
ているが、汚染原因者が不明又は破産して費用負担できない場合には、土地所有者がすべて
対応しなければならない。
現在の諸制度は、使用者や用途が変更される通常の土地取引に対応したものである。昨今
不動産証券化にてよく行われているセール&リースバックにおいては、売買取引後のテナン
トによる汚染をモニタリングすることが重要である。モニタリングの手続きや内容は賃貸借
契約に反映されることとなるが、売主と売買取引後のテナントが異なるケースについて、売
主とテナントの間のリスク分担に係る対応が難しいという指摘がある。
3.3.2 法令上の要求措置と実態の乖離
汚染の除去等の措置には立ち入り禁止、覆土、舗装(直接摂取の場合)、汚染土壌の封じ込
め、掘削除去があるが、掘削除去が選択されることが多い。これは、土壌汚染対策法上「汚
染の除去等の措置」(同法第7 条第1 項)以外では台帳から指定地域の抹消をされないこと、
将来売却する場合に、掘削除去以外の措置では価格の減価程度が予測できないこと、土壌汚
染が完全に除去されないと、封じ込め等の措置が必要になり、その間の管理コストや土地利
用への影響があるなどの課題を長期間抱え込むことになるおそれがあることなどが、掘削除
去を求められる理由である。実に、国内で実施されている措置のうち80%強が「掘削除去」
か「現位置浄化」を選択している。
掘削除去は費用が高額となるため、土地の売却益の中で吸収できる場合は実施可能である
が、そうでない場合は厳しく、土地所有者にとって売却を断念せざるを得ない事態が生じる
可能性がある。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が土地価格を上回るケースもある。とり
わけ資金力のない中小事業者や土地価格の安い地方都市において、このような事態が生じる
可能性があり、いわゆるブラウンフィールドの発生につながると考えられる。
一方、土壌汚染対策法や自治体の条例は、掘削除去措置まで求めているわけではない。例
えば、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の第114条では、対象地内
の土壌汚染により「大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に係る被害が生じ、又は
生じるおそれがある」と認められる場合は、対象地内のすべての汚染土壌について指針の定
めるところにより汚染処理を行うこととされており、また、同条例に基づく東京都土壌汚染
対策指針において、周辺環境に土壌汚染の影響が顕在化していないこと、及び掘削する場所
以外に存在する汚染土壌が外部に拡散しないことを前提として、汚染拡散防止措置を行うも
のとされており、必ずしも掘削除去が求められていない。
なお、土地取引によらない場合は土地所有者が自己利用又は土地を賃貸することになるた
め対策コストの高い掘削除去よりは封じ込めなどの対策がしやすいものと考えられる。土壌
汚染の対策コストが多額で土地を売却できない場合には、汚染の封じ込め措置をして倉庫や
駐車場等として自己利用、又は土地を賃貸して商業施設や駐車場等への利用が見られる。ま
た、産業用途の不動産取引では、自主基準を作成し、それに沿った形で土壌汚染地取得の意
思決定が行われ、完全浄化を実施せず適切に管理している例も見られる。
3.4 土壌汚染の管理
土壌汚染が発見された場合、実態として完全除去されることが多いが、土壌汚染対策法や
自治体の条例では、完全な除去まで求めているわけではない。当該敷地および敷地以外の周
辺環境において、人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれが顕在化していなければ、
完全除去ではなく、土壌汚染が周辺環境に影響を及ぼさないように汚染拡散防止措置を実施
することで対策とすることができる。そして、法や条例の適用対象とならない場合にも、こ
の基本的な考え方は適用できる。土壌汚染を残置することによって、土地所有者は土壌汚染
リスクを将来にわたって適切に管理することが求められるが、経済的な対策を選択できる余
地が広がることとなる。
土地取引においては、土地購入者にとって、封じ込め措置などの汚染が残存する土地は割
安な価格で購入することが可能であるが、一方で封じ込めた汚染土壌に係る管理などに追加
費用を要することに加え、土地の使い勝手が大きく損なわれるおそれがある。したがって、
汚染土壌を一部エリアに封じ込める措置を採用する場合は、土地利用をあらかじめ考慮した
措置とすることによって、土地の利用価値低減をできるだけ限定的なものとすることが重要
であると考えられる。たとえば、土壌汚染地の地下利用制限などの部分的制限によって、掘
削除去以外の土壌汚染対策が容易になるだろう。また、将来、土壌汚染の封じ込め措置を行
った土地を売却する場合には、利用用途が限定される可能性があることから、売却先を探す
際にマイナス要因となりうることにも留意しなければならない。
このように、健康への潜在的な被害に考慮しつつ、土地の適切な利用を確保していくため
に、官民の間で取り決めを設ける手法は、制度的管理(Institutional Control)と呼ばれアメ
リカなどで活用されている。制度的管理は、土壌汚染された土地を、土地利用制限や継続的
モニタリングなどによって、適切に管理する手法である。制度的管理は、制度の特徴から、
土地利用用途別の基準と関連付けられることも多い。
日本での適用例は少ないが、豊中市のマンション敷地において、「深い基礎が必要な高い建
物は建てず、土壌汚染の事情を知らない第三者に転売しない」という協定を市と不動産業者
が結ぶことを条件に分譲するという方式が採用されている。また、倉庫等の産業用地を対象
とした不動産証券化ファンドにおいても、部分的な利用制限や将来の建て替え時の制限を設
け、完全浄化を行っていない例が増えている。
なお、本節で取り上げた土壌汚染の管理手法は、マンション用地など個人向け不動産に適
用する上では、十分な検討が必要となる。欧米では、管理された土壌汚染地は住宅等購入者
にとって、住宅等が比較的安く取得できるというメリットが認知されている。
しかし、掘削除去以外の対策により汚染が残存している場合は、汚染土壌の継続的なリスク管理が必要と
なり、その負担を個人に求めることができるのかという不安がある。当然のことながら、所
有権の移転があれば、その役割は新しい所有者に適切に引き継がれなければならない。また、
個人レベルで、土壌汚染の存在することによる土地資産の減価リスクの適切な判断が求められる。
3.5 土壌汚染がある土地取引のリスクと財政的支援
3.5.1 土壌汚染に係るリスクとリスク分担
(1)リスクの概要
土壌汚染によるリスクについては、人の健康リスクが重要であることは言うまでもない。
しかしながら、土壌汚染地の取引に関連して、その資産価値にかかるリスクも、予測が困難
であり、リスクが顕在化した場合の影響は大きい。土壌汚染の程度によっては、浄化費用が
土地価格を上回るケースもある。汚染を完全に除去しなければ、土地に残る土壌汚染の管理
が必要となり、将来、想定外のコストが発生したり、将来売却する場合に想定以上の減価が
生じる懸念もある。さらに将来の法改正で、規制対象物質が増えたり、基準が強化され、予
測できない大きな負担が生じる可能性がある。
土壌汚染された土地に係るリスク
● 措置状態の管理/監視義務対応管理/監視結果の報告義務対応
● 第三者賠償請求(近隣住民の健康被害・財産権の侵害)
● 土地利用中の再措置命令対応(濃度上昇等による)やモニタリング井戸の追加等行政指導
● 再措置命令対応による休業損害補償
● 土地利用中の法規制の変更に伴う調査・措置の再実施に関わる費用負担
● 措置済み土地で計画する形質変更が実施できない、 あるいは計画変更を求められるリスク(計画遅延含む)
● 措置計画が行政および近隣住民からの同意が得られないリスク
● 風評リスク
(2)リスク分担
日本では、土壌汚染対策法で土地所有者等に汚染除去が求められており、同法では、土地
所有者等が対策を実施した場合に、汚染原因者に対して対策費用の請求ができることとされ
ている。しかし、汚染原因者が特定できない場合や、特定できても破産して費用負担できな
い場合には、土地所有者が負担しなければならないことになる。このように、土壌汚染があ
る土地の取引においては、土地所有者(売主)と買主が負担するリスクが大きく、円滑な取
引を阻害する要因となっている。
土地所有者(売主)と買主の間のリスク分担については、民法で瑕疵担保責任が規定され
ている。しかし、瑕疵担保責任は、二者間の契約で変更が可能であるため、土地所有者(売
主)と買主のリスク分担は、二者の関係によって変わることになる。したがって、土地所有
者(売主)が優位な場合には、無過失の買主がリスクを負担しなければならないこともある。
(3)リスク軽減の考え方
土壌汚染がある土地の取引において、リスクが顕在化した場合のコスト(つまり浄化費用)
は、莫大なものとなる可能性がある。アメリカで実際に導入されている事例からも、浄化融
資ファンドや公的な保険など、様々なタイプの支援や仕組みが、土地取引関係者のリスク軽
減とリスクヘッジに寄与するものと考えられる。零細汚染責任者のように責任者に責任を負
わせることができない場合について、修復の資金供給のための適切なメカニズムを構築する
ことを望む意見も聞かれるところである。たとえば、日本にも4万箇所以上のドライクリーニ
ング施設があり、経営主体は個人が約70%弱になる。経営規模は年間売り上げベースで3000
万円未満が8割と零細層が中心であり、対策は実質的に困難であると考えられる。こうした零
細企業の所有地を再開発する場合に、開発者にインセンティブを与えることは効果的である。
(4)リスク評価
土壌汚染に係るデータベースを用いて、統計的に土壌汚染による損失を評価する手法は、
一部の金融機関で実施されている。しかし、この手法は、金融機関の数多くの担保物件を対
象として、土壌汚染による減価の総額を把握する手法であり、個別物件のリスク評価に用い
るには精度的に不十分であった。これに対し、個別物件の土壌汚染リスクを評価するツール
開発の取り組みが行われている。
土壌汚染の可能性がある土地の取引や不動産開発を検討する際、土壌汚染の実態把握のた
めに、初期段階にて多大の費用がかかる調査等を行うと、事業リスクは大きくなる。また、
将来発生する詳細調査や対策の費用の不確実性が高いために、初期の調査に踏み出せず事業
自体が断念されるケースも多い。土地開発の採算性や実現可能性を検討するような構想段階
においては、多額の調査費用を費やし、詳細な土壌汚染調査を実施することは合理的ではな
い。むしろ、地歴調査、表土調査等の簡易調査に基づいて土壌汚染対策費用のリスク評価を
実施し、マーケットリスク等を含めて不動産開発の妥当性を検討することが必要である。
しかし、地歴調査、表土調査等の簡易調査のみが実施された段階で、土壌汚染の実態を確定的
に把握することは極めて困難であるため、特に初期構想段階では、土壌汚染に係るリスクを
評価し意思決定することが重要となる。
この点に関して、評価ツールとして期待値による評価と確率分布による評価が考えられる
が、期待値で評価をしても事業キャッシュフローに関する問題点が明確にならないケースも
ある。例えば、1000 分の1 の確率で100 億円の支出が生じる場合、期待値の上での影響は
1000 万円でしかない。しかし、ダウンサイドのリスクが顕在化し多額の資金需要が一度に生
じた場合、事業が頓挫する可能性もある。そこで、こうしたリスクを評価するためには期待
値ではなく、確率分布の形を評価することが有効である。また、人は確実に100 円の利益が
得られる場合と、期待値は100 円でもリスクのある場合とでは、その事象に見出す価値が異
なる。したがって、確率分布で理解することは、リスクコミュニケーションにおいても重要
となる。さらに、多様な資金調達や保険の活用、そして先進的な不動産プロジェクトで用い
られるようになったリアルオプションには分散に関する情報が不可欠であり、当該ツールに
よって得られる確率分布は極めて有効である。
3.5.2 低利融資等
土壌汚染対策に係る低利融資制度については、政府系金融機関(日本政策投資銀行)に
よる貸付制度がある。但し、この融資制度も包括的な制度設計に至っておらず、例えば調
査費用が対象とされなかったり、自主的な調査及び改善措置費用が対象とされなかったり
等、その適用範囲は限定的なものであるため、当該制度の利用実績は低調なものに留まっ
ている。
また、その他の公的支援制度として土壌汚染対策基金が挙げられる。この基金は、土壌汚
染対策法に基づき、汚染原因行為に関与していない資力に乏しい土地所有者等に対して汚染
の除去等の費用を助成するものであり、都道府県又は政令市を通じて実施される。
当該制度についても、資力の乏しい小規模事業者等にとっては有効な支援策であるものの、厳格な適
用要件等によりこれまでほとんど利用されてこなかった。
これら低利融資及び基金については、適用要件の緩和等、より弾力的な運用を施行するこ
とで、さらなる利用促進を図ることが望まれる。
3.5.3 保険
(1)土壌汚染地に関する保険の役割
保険の役割は、関係者または特定の土地に対し、通常の事業又は浄化工事請負作業中にお
いて、汚染が顕在化した場合の浄化費用を補償するものである。土壌汚染についてリスクを
負担することができない場合に、保険を付保することによって、リスクを移転することがで
き、費用を確定し収益性の判断がつけやすくなる。また、制度的管理(Institutional control)
を採用する場合には、潜在的な環境負債者の将来にわたる長期修繕費用の支払い能力が求め
られるが、もし適切な支払い能力がないと判断された場合、当事者は債権や保険等を利用し
て財政的な裏づけを確実に得ることもできる。アメリカでは、保険を活用することにより、
土壌汚染地の浄化を伴う再開発に民間資金が集まり、再開発が促進されるという効果を上げ
ている。
(2)土壌汚染に関する保険の種別
日本国内でも、海外と同様、汚染が顕在化した場合の浄化費用を補償する土壌浄化保険
をはじめとして、第三者土壌浄化賠償責任保険などの土壌汚染関連保険が開発されている。
これらの保険商品を分類すると、事業者に対して付保する保険と、土地に付保する保険がある。
事業者に対する保険は、開発、建築等の事業の過程で土壌汚染を発生させたことに起因
する賠償費用を補償するものや、土壌汚染対策などの請負作業において汚染を発生させた
場合に、賠償費用を補償するものがある。一方、土地に対する保険としては、結果として
土地所有者等が負担した対策費用に加え、地下水汚染等により発生する周辺住民の健康被
害などの対人、対物の損害賠償費用を補償するものがほとんどである。また、土壌汚染対
策費用の超過分を補償するコストキャップ保険(超過浄化費用保険)は、対策費の上限を
予測できるため有効である(3.5.4を参照)。
(3)土壌汚染保険の普及に向けた課題
日本国内では、土壌汚染に関連した保険の普及が進んでいない。普及が進まない最大の理
由は、保険料の高さと保険引受条件の厳しさにあるようである。仮に数を集めたところで発
生要件の規則性が見いだせない(=大数の法則が成立しない)からこそ保険料が高くなり、
加えて、逆選択(土壌汚染のリスクを抱えているのが明確な人ほど保険に入ろうとする)が
生じ、最悪の場合モラルハザードにつながるため、保険の利用が進まないという側面がある。
そして、保険の利用が進まないために、大数の法則の適用が困難となり、結果として保険料
が高くなり、引受条件が厳しくなるという悪循環が生じている。さらに、保険料に加えて、
保険引受のための高額の調査費用を、被保険者が負担することが一般的となっており、この
ことも保険が利用されていない一因となっている。
リスクを定量化するためのデータの蓄積は、保険商品の開発にとって重要である。しか
しながら、日本では、土壌汚染がある土地の調査事例や対策事例に関して、入手可能な情
報が不十分であることから、土壌汚染に関する事例の蓄積を進めていくことが必要である。
また、保険の利点や内容が理解されていないことも課題である。
(4)土壌汚染に関する保険の拡充
我が国では、土壌汚染保険やコストキャップ保険をはじめとする損害保険はあるものの、
情報の非対象性を一つの大きな理由として、必ずしも保険会社が積極的にリスクの引き受け
に応じていないのが実態であるが、海外では「ファイナイト(Finite)」といわれる従来型
の保険に代わるリスク移転手段が導入されている。
ファイナイトは、「リスクの保有」と「リスクの移転」を組み合わせ、企業と保険会社の間
でリスクをシェアする機能を有するリスク・ファイナンス手法であるといえる。ファイナイ
トにはニーズに応じた様々な形態があるが、土壌汚染問題に対する適用に関しては次の例を
想定することができる。
たとえば、ある工場の経営者が、当該工場の敷地に土壌汚染の存在が発覚したため、将来、
当該工場を閉鎖し、土地を売却する場合に備えて、その浄化費用の対策を考えた。売却の際
には、汚染地の浄化が必要になるが、その対策費が1 億円から7 億円の範囲内となることが
想定され、このときファイナイト契約を5 年間で構成することした。なお、5 年以内に当該
土地の売却・浄化してしまった場合でも契約は5 年間継続させるために、対象となる土地は
売却予定以外の複数の土地を含んだ契約となり、以下のようになる。
? 初の保険金支払い事由となる浄化工事の場合の支払限度額は7 億円、免責は1 億円、2
番目以降はそれぞれ3 億円、10 億円とする。また、毎年の保険料は1 億円で変更なしとする。
? 毎年の保険料が毎年積み立てられた場合5 年間で積立て額は5 億円となる。
? 仮に3 年目で土地の売却、浄化工事が行われ、その費用が5 億円であった場合、保険
会社から1 億円の免責額を除いた4 億円が保険金として支払われる。
? 契約は5 年目まで継続し、2 件目以降の保険金支払い事由の発生がない場合、保険料
の積立て額は5 億円、保険会社からの支払額は4 億円となる。この差額のある程度の
割合は予め約定された割合に基づき、契約者に優良戻しということで 返還されること
が多い。
? 仮に3 年目行われた浄化工事が8 億円かかった場合、保険料の積立て額は5 億円、一
方、保険金の受取額は7 億円となる。
ファイナイトのメリットは、浄化費用の発生タイミングと規模に係るリスクを抑えること
ができる点である。具体的には、積み立ての場合、積立て額は段階的にしか積み上がらない
のに対し、ファイナイトであれば1 年目から最大7 億円の浄化費用の手当てができる。また、
浄化費用の額についても、上記の例で8 億円までに収まった場合、保険料としての拠出額の
合計である5 億円に免責額の1 億円を加えた範囲内に抑えることができる。
保険会社からすると、保険料の積立て額が保険支払額よりも上回った場合は、その一部を
契約者に払い戻す構成としているため、契約者がリスクを軽減するモチベーションを持ち続
けることを期待することができるため、ある程度モラルハザードを抑制することが可能とな
る。
3.5.4 保証
保証は、保険と同様に、土壌汚染リスクをヘッジする目的で活用される。保証には、浄化
工事のコストの増加分を保証する「コストキャップ保証」型、フェーズ?調査後、汚染の可
能性が極めて低いと判断した土地に対し、調査会社が自社の調査に基づく土壌汚染がない旨
の評価に対して保証する「調査後のシロ保証型」、主として土地取引の契約書の記載事項を表
明保証する「表明保証」型などがある。
浄化工事の保証は、工事の請負契約に加え、対象地、対象期間、対象物質、工事請負金
額、工事の着工および完了予定時期、保証内容、免責事項などを記載した保証書を差し入
れることによってなされるのが一般的である。浄化工事の保証内容の例について、次に一
例を示す。
浄化工事の保証内容の例
・計画土量増加および処分時の比重増加に伴うコストの負担。
・高濃度汚染の存在などにより処理方法の変更、追加が生じた場合の費用の負担。
・対策計画の範囲内に存在する廃棄物や地中構造物の撤去に関わる費用の負担。
・地下水モニタリングに関わる費用一式の負担。
3.5.5 買取り
民間ファンド等が土壌汚染リスクのある不動産を買い取り、浄化を実施後に売却することに
よって、リスクヘッジするスキームも土壌汚染土地の取引活性化に有効であると考えられる。
土壌汚染がある土地の所有者(売主)にとっては、事業地を売却したくとも、調査費用や対策
費用の捻出が困難であったり、対策工事の工期の関係で困難であったりするケースや、風評
リスクが懸念され、売却をためらうケース、さらには、売却後の瑕疵担保責任を負いたくな
いようなケースも考えられるが、買取りスキームは、こうした土地所有者のニーズに応える
ものであり、土壌汚染調査と対策の実施負担が不要で、早期に売却収入が確定し、決済が可能
となるというメリットがある。
また、魅力的な物件だが、汚染が解消できなければ買収の意思決定ができないと躊躇う
買主側にとっても、浄化された土地として検討できるというメリット
がある。
さらには、買主と売主の双方にとって、土壌汚染に絡み流動化を阻害する問題が軽
減されることになる。ただし、民間ファンド等が中間的に買い取る行為が経済的に成立する
ためには、リスクを適切に評価することが可能であり、減価して買い取ることが条件となる。
3.5.6 信託
(1)信託の現状
信託は、委託者が、その保有する財産を受託者に引渡し、一定の目的(信託目的)に従い、
特定の受益者または公益のために、その財産(信託財産)を受託者に管理、処分してもらう
制度である。国内の信託財産残高は2007年3月末で744兆円と5年で1.9倍に増加し、この内、
不動産信託も5年間で残高3.8倍(6,257件)、件数9.0倍(22兆6千億円)と増加基調を示して
いる。(データ出典:(社)信託協会ホームページ)
不動産の信託においては、土壌汚染問題に受託者が直面することがある。例えば、
? 土地取引に際し土壌調査を行うことが慣行化する前に設定した信託受益権を信託期間中に譲渡す
る際に土壌調査を実施して、信託設定時に認識していなかった土壌汚染が発覚する場合、
?信託財産の隣接地等で実施された土壌調査によって、隣接地で汚染が見つかり、信託財産の
汚染が懸念されるような場合、
? 土壌調査の対象地に建物などがあったために汚染物質を見落とす場合、
?調査方法の選択ミスや精度の問題で、事前調査では分からなかった問題が発覚する場合等が想定される。
(2)旧信託法下での土壌汚染問題への対応方法
こうした場合に対応するため、旧信託法下においても「限定責任特約」を当事者間で締結
するというという方法があった。これは、受託者が信託事務に関する取引から生じた債務に
ついて、責任財産を信託財産に限定することを個別に特約として結ぶというものであったが、
土壌汚染に関しては、受託者に過失がなかった(無過失)としても受託者に対し以下の請求
が可能だったため、信託設定や信託財産の管理を適切に遂行したにもかかわらず、受託者が
最終的に個人負担する可能性があった。
・所有者の工作物(「汚染物質を放出した建物および構築物」)責任(民法717条)
・被害を受けた土地所有者からの妨害排除請求権に基づく汚染物質の排除請求
・受託者が土地の名義人であることによる土壌汚染対策法に基づく土壌改善等の措置命令
(土壌汚染対策法第7条第1項)
(3)改正信託法下での対応方法
そこで、仮に信託不動産に土壌汚染が存在することが発覚したとしても、その責任を限定
する手法として、平成19年に施行された改正信託法で制定された限定責任信託制度の利用が
考えられる。限定責任信託とは、「受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務につい
て信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託」(同法第2条第12項)のこ
とである。限定責任信託では、受託者の対外的な責任限定の対象者を拡大し、従来の責任限
定特約とは異なり、取引関係にない者との間でも限定責任が適用される。
しかしながら、同法第217条第1項において、「信託財産責任債務」から同法第21条第1項
第8号に掲げる権利に係る債務が除かれており、「受託者が信託事務を処理するについてした
不法行為によって生じた権利」に該当する行為の範囲が問題となるが、現時点で、土壌汚染
対策法等に基づく土壌汚染に関する責任(すなわち信託法に基づかない責任)が、信託財産
を充てるべき責任なのかどうか、又は、両者の責任が分断されるのかどうかといった点が明
確にされていないことから、現時点で土壌汚染に関する責任を限定する目的で限定責任信託
を活用するのは困難であると思われる。
仮に、信託法における責任と信託法に基づかない責任が分断できるとしても、大きな土壌
汚染に対する限定責任信託の活用については、社会的なコンセンサスを得られるのか疑問が
あり、今回の法改正で土壌汚染地の信託が急増することは想定し難いと考えられる。
3.6 土壌汚染地の資産評価
3.6.1 土地の資産評価の枠組み
現在、土地の資産価値の評価については、公の機関や業界団体が関わり、考え方や算定方
法などが規定されているものだけでも、以下に示すとおり多岐にわたっており、様々な分野
でその分野のニーズ・目的に応じた評価がなされている。それぞれ評価の目的が異なるため、
当然のことながら、土壌汚染に関しても異なる取り扱いが規定されている。民間企業によっ
ては、独自の考え方で評価を行い、内部の意思決定に活用していることもある。
3.6.2 不動産鑑定評価の実務における土壌汚染地評価の基本的考え方
平成15 年1 月1 日より、土壌汚染を土地の個別的要因の一つとして、評価項目に追加し
た改正不動産鑑定評価基準が施行された。土壌汚染調査が経済的・法的・物理的な物件調査
の1 項目として、明確に位置づけられたものであるといえる。
実務上は、原則として土壌汚染対策法第2 条第1 項に規定されている特定有害物質を中心
として、各自治体の条例等及びダイオキシン類対策特別措置法及び各自治体の環境条例等に
おいて対象とする有害物質が各法令等の基準値を超えて存在すれば、価格形成に大きな影響
を与える可能性が生ずると理解される。
上記の土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法及び各自治体の環境条例等は、人
の活動に伴う人への健康に係る被害の防止の観点から規定されている一方で、不動産鑑定評
価において考慮すべきは、土壌汚染が価格形成に影響を及ぼす場合であることから、自然に
由来する土壌汚染も考慮にいれる必要があり、法令等による調査等の義務がないことをもっ
て、土壌汚染がないということはできない。
現状では対策が掘削除去中心であることから鑑定評価もそれを前提にする場合が一般的で
あるが、今後掘削除去以外の措置が講じられるようになれば、それらを的確に反映するよう
な鑑定評価を行う必要があり、必要に応じた実務面の見直しと普及が必要である。
既に、 (社)日本不動産鑑定協会作成の「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針
(以下「運用指針」という。)?、?」がガイドラインとして示されている。運用指針Iでは、
鑑定士が行うべき独自調査のあり方が記載されており、運用指針?では、土壌汚染地におけ
る対応のステップが示されている。
運用指針では、土壌汚染の疑いのある場合には、不動産鑑定士が独自調査を行った上で、
その結果と、既存の土壌汚染調査結果を明記し、汚染の分布状況、除去等に要する費用等を
他の専門家が行った調査結果等を活用して鑑定評価を行うものとされている。
これまでのところ、土壌汚染地の鑑定依頼件数は少なく、したがって土壌汚染土地の鑑定
評価の経験を積んだ不動産鑑定士は少ない。また、土壌汚染に関する鑑定評価が可能なレベ
ルの調査が実施されていない段階で、鑑定評価を依頼されるケースも多いのが現状である。
<参考>現在の取組み
・ 土壌汚染地に係る鑑定評価については、平成14 年の鑑定評価基準の改正時において、
土壌汚染が価格形成要因の一つに位置づけられたところである。実務面においても、(社)
日本不動産鑑定協会で「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針」の策定・改定、
それに基づく研修等が実施されている。また、土壌汚染の鑑定評価の実務に関するワー
キンググループが設置され、継続的にケーススタディー等の検討が行われている。
3.6.3 スティグマの評価
土壌汚染の存在(過去に存在したこと)に起因する心理的な嫌悪感等から生ずる減価要因
をスティグマという。また、広義には、前述の心理的要因に加え、土壌汚染に起因して将来
追加コストが発生するリスクを加えた減価の根拠をいうこともある。土壌汚染地の資産評価
は、概念的には次式で表現されている。
個別の土壌汚染地及び評価時点により、スティグマの程度・内容は異なるので、評価ごと
に、求めるべきスティグマを勘案する必要性が生ずる。
日本におけるスティグマの調査事例としては、住宅用地に関する市民アンケート調査((財)
日本不動産研究所、明海大学2003 年実施)がある。当該調査結果によれば、いずれも浄化
後を想定した質問を行ったところ、汚染対策が行われたとしても購入を控えるという回答が
多く、スティグマが存在することがわかった。スティグマの大きさは、購入の場合も、賃貸
の場合も、20%から30%が最も多く、次に50%というものであった。
これに対し、デベロッパー、銀行、不動産仲介業者側は異なる考え方を示している。国土
交通省実施の「民間土地取引に係る土壌汚染地の取扱実態に関する調査」によれば、デベロ
ッパーは、マンションも、オフィスも原則として掘削除去を実施後スティグマなしで販売し
ており、スティグマを斟酌しない考え方が一般的である。また、マンション開発で、掘削除
去を実施していない場合においても、十分なリスクコミュニケーションを販売前に行うこと
によって、スティグマを考慮せずに販売価格を設定している例もある。
銀行は、担保評価上、浄化措置が前提であり、浄化後のスティグマに関しては、対応が分かれている。不動産仲介
業者は、用途等を踏まえて取扱い、浄化後スティグマを考慮に入れた上で対応を行っている。
以上のように、スティグマについては誰が土地を取り扱うかで対応が分かれており、不動
産市場で、スティグマによる減価の取扱いについて、今後のさらなる検討が必要である。
3.6.4 エンジニアリングレポートの重要性
平成19年4月に改正された不動産鑑定評価基準においては、証券化対象不動産の鑑定評価
にあたり、鑑定士は、土壌汚染について、エンジニアリングレポート(以下「ER」という。)
や鑑定士の独自調査により的確に判断しなければならないとされている。
一方、(社)建築・設備維持保全推進協会(BELCA)は、平成19年4月に新しいERのガ
イドラインを作成した。BELCAのガイドラインによれば、ERは「建物状況調査報告書」、「建
物環境リスク評価報告書(フェーズ?)」、「土壌汚染リスク評価報告書(フェーズ?)」、
「地震リスク評価報告書」の4つの報告書から構成される。
建物環境リスクにおいて、土壌汚染に関しては、フェーズ?調査が標準として位置づけ
られ、REC(Recognized Environmental Condition:使用履歴のある有害物質や石油製品
等が、現時点で漏洩している状態にある、過去に漏洩した履歴がある、あるいは将来にお
いて漏洩が発生することが十分に懸念され、土壌や地下水に影響を引き起こすような状況
のこと。)の有無及び内容を結論として提示することとされている。一方、証券化対象不
動産の鑑定評価においては、汚染リスクの価格に対する結論が要求される。
BELCAのガイドラインでは、フェーズ?でRECやデータギャップが指摘されたら、それ
を定量的に評価することとされており、これはフェーズ?で汚染がないことが完全に示さ
れない限り、フェーズ?が必要となるとも理解される。
しかしながら、BELCAのガイドラインには拘束力はなく、エンジニアリングレポートに
は様々なレベルのものが見受けられるため、鑑定評価に活用するという視点から必要とさ
れる内容等について検討し、整理していくことが必要である。
このため、(社)日本不動産鑑定協会において、エンジニアリングレポート関係者との
共同研究会や、エンジニアリングレポート関係者の協力による研修などが実施され、実務
面での取組みが進められており、今後は、これらの取組みを継続・発展させ、着実に実務
に反映させることが重要である。
この際、不動産鑑定とエンジニアリングレポートの制度面の差異やエンジニアリングレ
ポートの提出は鑑定士ではなく、鑑定評価の依頼者に対してであるなどの難しさはあるが、
両者の連携により、それらの課題を克服することが強く求められる。
3.6.5 課税関係
土壌汚染された土地についての課税関係における評価では、減額項目を見込むか否かの考
え方において税による差異が存在する。
固定資産税については、何万筆もの土地を同時に評価するという大量、一括性に特徴を有
すると同時に、課税のための評価であることから評価の均衡、公平の確保が重要である。「土
地に関する調査研究(平成18 年3 月)−土壌汚染対策法と固定資産税評価について−(資産
評価システム研究センター)」によれば、汚染の除去等の措置費用を減価要因とすることは必
ずしも適当ではなく、当該土壌汚染地の現況に着目し、当該土地の利用の制限を減価要素と
することとしている。また、心理的要因については、その影響の有無が不確定であること等
から、基本的には考慮しなくても一般的には差し支えないと考えられるとしている。
一方、相続税については、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」(平成16 年7
月5 日付国税庁課税部資産評価企画官情報第3 号、資産課税課情報第13 号)が示されてい
る。相続税における土壌汚染地の評価額は、土壌汚染がないものとした価額から、浄化費用、
使用収益制限による減価、心理的要因による減価を考慮することとされている。相続税等の
財産評価においては、課税時期において、評価対象地の土壌汚染の状況が判明している土地
を土壌汚染地としており、土壌汚染の可能性があるなどの潜在的な段階では土壌汚染地とし
て評価することはできないものとしている。
なお、相続税を公示価格を用いて評価する場合には、評価が公示価格の80%を基準として
いることから、減価は土壌汚染浄化額の80%としている。また、土壌汚染の原因が被相続人
であり、第三者からの損害賠償請求により債務が確定しているときは、債務として計上でき
る場合もある。相続開姶後に土壌汚染が判明した場合であって、土壌汚染の原因を第三者に
特定することができ、除去費用について、当該第三者に求償権を有するときは当該求償権を
資産計上する。
4.諸外国の制度・取り組み
諸外国として、土壌汚染問題関連の情報が比較的多く収集されている米国とドイツの二ヶ
国を対象とし、それぞれの国の土壌汚染問題への取り組み状況について、以下の5 つの視点
から分析整理した。
各国のはじめで、取り組み状況の分析整理の前提として、米国に関しては、スーパーファ
ンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ及びそれぞれの法制度の概要につい
て整理し、また、ドイツに関しては連邦土壌保護法制定の経緯について整理した。
なお、ドイツに関しては、「財政支援施策」及び「環境負債免除制度」の項目に関しては、
詳細な情報が不足しているため分析対象から除外した。
【分析整理の視点】
・ 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
・ 浄化修復目標の設定
・ 制度的管理
・ 財政支援施策
・ 環境負債免除制度
4.1 米国
4.1.1 スーパーファンド法の制定からブラウンフィールド法制定までの流れ
(1)スーパーファンド法
1)立法に至る背景
米国では、1970 年後半から有害廃棄物汚染による環境災害が立て続けに発生し、災害によ
っては国家非常事態宣言の発動もあった。しかし、それまでの法制度では、土壌、地下水、
地表、水、大気の汚染に対して、連邦政府が直接関与できる法的権限はなかった。このため、
有害物質汚染災害や土壌汚染から国民と環境を保護するための新たな法制度の整備が必要と
なり、1980 年に連邦議会が「包括的環境対処・補償・責任法」(以下「スーパーファンド法」
という。)を成立させた。これ以降、連邦環境保護庁(以下「EPA」という。)が主担当官庁
となって、連邦政府レベルでの取り組みを開始した。
その後、1986 年にスーパーファンド改正・再承認法(以下「SARA」 という。)が施行さ
れ、スーパーファンド法の立法内容の強化・拡充がなされている。
2)スーパーファンド法の概要 (注1)
? 汚染者負担主義
スーパーファンド法の基本的考え方は、汚染者負担主義であり、当該サイトの汚染に何ら
かの関わりがあったあらゆる個人ないし企業を潜在的責任当事者とし、サイトの浄化及び住
民の健康や自然環境に与えた損傷への補償責任を求めた。潜在的責任当事者とは、汚染物質
の排出者、運搬者、貯蔵者、投棄・処理者等有害物質の放出または放出のおそれに関与して
いる者をいい、判例により汚染物質を廃棄している施設の所有者や創業者に対して融資を行
っている金融機関等直接的に問題となる汚染に繋がっていない者も、汚染修復の資金負担責
任を抱えることになった。また、スーパーファンド法施行以前の関与の責任も負わねばなら
ないという極めて厳しい責任原則主義が基本となっていた。
? 財源の手当て
EPAは2つの財源を手当てしており、1つは責任者負担によるサイトの浄化と補償であり、
もう1つは責任主体に支払い能力が無い場合や責任主体が不在となる場合への対応のため、
危険物質を製造したり、あるいは利用する産業に目的税を課し、これを基金化(有害廃棄物
信託基金(トラスト資金))して、遊休地化したり、放棄されているサイトの浄化資金とした。
(ただし、この税制は制定後15 年間で失効した。)
? 措置の種類
スーパーファンド法では、有害物質のリスクの程度に応じ、短期又は長期のいずれかの対
応がなされる。
・ 除去措置(Removal Action):短期の対応。健康被害と緊急の環境リスクに対応するもの。
・ 浄化措置(Remedial Action):長期の対応。通常の浄化措置の流れを追って実施するもの。
? CERCRIS とNPL
CERCRIS(the Comprehensive Environmental Response, Compensation,and Liability
Information System)とは、米国内の有害物質による汚染の懸念のあるサイトと当該サイト
における調査等の状況が全て登録されている連邦政府作成のデータベースである。CERCRIS
に掲載されているサイトは、一定の手続きを経た後、連邦政府や州のスーパーファンドサイ
トとして登録される可能性のあるサイトである。
このうち、最も深刻な汚染サイトとして、早急に浄化措置を行うべきサイトに優先順位を
つけてリスト化したものがNPL(National Priority List:国家緊急リスト)である。
? スーパーファンド法による問題と対応
スーパーファンド法の責任原則に関連してさまざまな問題が発生し、それらの問題を改善
するために、さまざまな運用上の工夫や修正を加えて今日に至っている。
a.関係当事者間による訴訟の多発
汚染サイトの浄化コストが高額になるため、同じサイトの潜在的責任当事者同士に責任
分担の訴訟が多発し、訴訟問題で資金を浪費し、また、訴訟が長期化し、浄化事業の遅延
化を招いた。
この問題への対応として、1986 年に施行されたSARA において、小規模の当事者で、「寄
与割合が僅少の」または「寄与割合が極小の」当事者は、早期に和解できることとした。
「寄与割合が極小の」当事者については、負担無しで和解できることとした。
SARA のその他の主な改正内容は以下のとおりである。(注2)
・ 「無実の土地所有者保護措置」の創設とその適用要件としての「全ての適切な質問」の規定
・ 資金調達方法の改良(トラスト資金の増額)
・ 浄化に関する永続的な改良策の開発、利用の強調
・ 地域住民への重度汚染化学薬品の存在に関する情報公開の義務付け
b.環境リスクをカバーする保険商品の普及
潜在的責任当事者と保険会社の間でも浄化コストの資金的埋め合わせをめぐって訴訟が
多発したが、スーパーファンド法への対応について、保険の必要性も高まり、施設の被害、
浄化費用負担、プロジェクト遅延、ビジネス中断、担保価値下落、風評被害、契約不備等
のあらゆる環境リスクをカバーする保険商品が契約可能になっている。これらの保険商品
が開発されたことにより、リスクを潜在的に抱えているサイトの売買、浄化、開発が容易
になってきている。
c.不動産業界への影響
スーパーファンド法により不動産業界はネガティブな影響を大きく受けた。不動産開発
業者は、潜在的責任当事者になることを恐れて、環境リスクのある不動産取引を敬遠し、
汚染サイトの遊休地化、放置化が促進されてしまった。
この問題に対して、EPA と各州政府は、再開発を促進するために、税制や補助金、融資
などの財政支援の充実化や環境負債免除制度などの規制面の保護政策強化への対応措置を
講じてきている。これらの措置により、汚染サイトは、不動産業者にとって割安であり、
かつ立地条件も良いことなどから、経済的メリットのある開発適地へと蘇生される可能性
が高まる方向となった。
(2)ブラウンフィールド法
1)立法に至る背景
スーパーファンド法の施行以降、土壌浄化の汚染者負担原則及び浄化の義務付けが明確化
されたが、この法的責任に関連して、他の汚染主体との浄化コスト負担に関する訴訟の多発
や、浄化リスク発生を嫌って、土壌汚染サイトの土地取引の停滞等の問題が発生し、EPA で
はさまざまな改善策を講じてきたが、より効率的な浄化プロセスの構築と再開発促進を狙い
として、ブラウンフィールド法(小規模事業者の責任免除及びブラウンフィールド再活性化
法)が2002 年に施行された。
2)ブラウンフィールド法の概要 (注3)
ブラウンフィールド法では、浄化プロセス効率化の観点から、浄化修復事業の長期化・遅
延化の一因となっていた小規模零細企業の責任問題への対応を図り、また、ブラウンフィー
ルドの土地取引活性化への観点から、浄化後のサイト所有への免責保護の規定の明確化及び
財政支援策の拡充を図った。
? 小規模企業の浄化責任保護
スーパーファンドサイトの浄化責任を負っている企業のうち、以下の条件を満たす事業者
は免責される。
a.産業廃棄物の排出事業者または、収集運搬業者
有害物質の取り扱い量が液体100 ガロン、固体200 ポンド以下で、全ての廃棄、取り扱い、
輸送を2001 年4 月1 日以前に行っていた場合
b.生活系廃棄物(身の回りで出るごみ)の排出者以下の条件を満たす場合、免責される。
・住宅地の所有者、管理者、借地人である場合
・潜在的浄化責任の通知が届けられてから、さかのぼって3 年間の平均従業員数が100 人
以下で商業活動を営んでいて、かつ法律による小規模企業体に該当する場合
・廃棄物を発生させたNPO で、前の年の従業員数が100 人以下の場合
? ブラウンフィールド再活性化と環境修復
a.ブラウンフィールド再活性のための財政援助(補助金及びブラウンフィールド再活性化ファンド)
以下の財政支援関連施策が盛り込まれた。
・ 総額で年間2億ドルの財政援助(うち、5,000 万ドルまたは25%を石油関連物質のブラウンフィールドサイトに充当する)
・ ブラウンフィールドサイトの再定義
以下のように再定義し、ブラウンフィールドの範囲を拡張した。
「有害物質や汚染物質の存在、もしくは潜在的に存在しうることが確認されていること
により、増築や再開発、または再利用が困難と思われる土地」と定義し、産業用地以外の
土地、例えば住宅地や商用地等において過去の土地履歴等により土壌汚染が存在する可能
性がある場合の再開発時においても、財政支援の優遇措置を適用できることとなった。
・ ファンドの対象拡大
石油及び石油関連製品を対象に追加
・ ファンドから支出できる用途の拡大
サイト調査に対して20 万ドル以下、浄化に対して100 万ドル以下を対象として追加
b.ブラウンフィールド責任の明確化
以下の主体に対する責任を免除した。
・ 隣接所有者をスーパーファンド法の責任から免除(流れ汚染に対する保護措置)
・ スーパーファンドサイトの買い手の保護
・ 善意の土地所有者(適切な商習慣に従った土地の取得で、全ての適切な調査(AAI)を行っ
た上で土壌汚染の事実を知る余地がなかった場合)の保護
・ AAI の定義(AAI 自体はSARA で創設されたものであるが、何をどの程度行えばいいの
かが不明確であった。このため、ブラウンフィールド法が出来るまでのアメリカにおいて
は、環境アセスメントビジネスが発達し、フェーズ?調査として結実することとなる。)
c.州のブラウンフィールド対策プログラムへの支援
・ 毎年5,000 万ドルまでの補助金を州対策プログラムに支出
・ 対象サイトの拡大
4.1.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
土壌汚染情報は土地の安全性を知らせる公益的な情報として位置づけられ、米国では、
多くの州が土壌汚染情報に関するデータベースを作成し、ウェブサイトでの一般公開を行っ
ている。ここでは、ニューヨーク市とオクラホマ州の取り組みについて取り上げた。
(1)ニューヨーク市
ニューヨーク市のブラウンフィールド問題への取り組みの12 の具体的な内容の一つとし
て、「潜在的なブラウンフィールドを把握するための過去からの土地利用のテータベースの作
成」が掲げられている。
【目的】
以下の3 点が示されている。
・ 潜在的でかつ優先的な取り組みが必要なブラウンフィールドを見つけること
・ 地区ごとのブラウンフィールドの再開発計画への基本的な情報を提供すること
・ すべての土壌汚染地の浄化と再利用活動の目標を明確にすること
【データベース作成方法】
以下の2つの方法が示されている。
・ 各種情報の収集
(環境関連の発行物・データベース、歴史的な地図、電話帳、財務記録などからの情報収集)
・ 年ごとのブラウンフィールド関連環境アセスメントへの要望についての問い合わせ
(2)オクラホマ州
社会環境の保全のためにブラウンフィールドの制度的管理が重要であるとの認識の下に、
オクラホマ州環境局では、ブラウンフィールドを含めた土地利用の管理に向けて法制度を整
備している。
土地利用管理の具体的な内容として、ブラウンフィールドの制度的管理についてのデータ
ベースをくまなく蓄積している。
4.1.3 浄化修復目標の設定
ブラウンフィールドの浄化修復目標に関しては、汚染されている土壌の位置(地表からの
距離)、汚染の程度、その跡地における将来の用途などを考慮して、人体に対する曝露の危険
性(リスク)を計算し、そのリスクに応じて、環境浄化修復手法を選択する「リスクベース
基準」に基づき設定する方法が一般的になっている。
跡地が工場用途になる場合と幼稚園の砂場など子供が土で遊ぶ場所とでは、当然に浄化修
復レベルは異るという考え方をとっており、そのために必要な事業方法、費用も異なる。
このため、リスクベース基準の適用においては、跡地の用途が将来にわたって遵守される
必要があり、基準の設定とともに用途制限措置の設定が重要となる。
(1)浄化修復目標の設定及び適用方法に関する分類
米国の各州の浄化修復目標の設定及び適用方法は大きく、表4.1.1 に示す3つに分類され
る。また、それぞれの分類のうち、一つの州ずつ、内容の把握整理を行った。
表4.1.1 米国各州の浄化修復目標の設定及び適用方法の状況
(2)マサチューセッツ州
マサチューセッツ州の浄化修復目標の設定にあたっては、汚染された土壌や地下水の人体
及び環境への曝露の程度とともに、将来の跡地利用方法を密接に考慮して設定しており、こ
のため、土壌汚染が存在する土地に対して、その用途制限も行っている。
1)土壌の環境基準
土壌環境基準は3 つの土壌分類によって異なる基準が定められている。分類は、土壌に対
する可触可能性、受容者の存在の性質、土地の利用頻度、土地の利用の強さの4 つの土地固
有の要素によって分類される。これらの土壌分類は、土壌の受容者に対する曝露の程度を規
定しているものであり、これらの分類は互いに排他的である。
【マサチューセッツ州の土壌の環境基準】
S-1:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい(主に住宅・学校など)
現在又は将来において人間が摂取する野菜や果物を育てるため利用することができる
子供の頻繁な利用または、熱心な利用が行われる可能性が高い土壌はS-1 に準ずる
大人の頻繁かつ熱心な利用が行われる可能性が高い土壌はS-1 に準ずる
S-2:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい
子供の頻繁な利用も熱心な利用も双方とも行われる可能性が低い土壌はS-2に準ずる
子供が対象地に立ち入らず、大人の頻繁な利用又は熱心な利用が行われる可能性が高い土
壌はS-2 に準ずる
S-3:土壌は以下の条件で表面土壌に利用してよい(駐車場の下など)
子供が対象地に立ち入らず、大人の頻繁な利用または熱心な利用が両方とも行われる可能
性が低い土壌はS-3 に準ずる
表4.1.2 マサチューセッツ州危機管理計画の土壌カテゴリー
2)地下水の環境基準
地下水環境基準は、地下水の汚染の結果に由来する異なる曝露の可能性を規定する3 つの
地下水分類によって定められている。これらの分類が異なる曝露の可能性を規定しているた
め、地下水の分類は互いに排他的ではない。すべての地下水は最終的に地表水に流れ出す可
能性があると考えられるため、すべての地下水はGW-3 の分類の水質基準を遵守する必要が
ある。土地固有の要素により、GW-1 やGW-2 に分類される可能性がある。
【マサチューセッツ州の地下水の環境基準】
GW-1:飲料水としての現在または将来の利用の可能性に基づき保護されるべき分類
GW-2:屋内の空気に対する揮発の水源となってもよいとされる分類
GW-3:石油や危険物質を地表水に対して放出する可能性がある分類
(2)カリフォルニア州
カリフォルニア州のブラウンフィールド浄化修復活動への要請事項は、NCP(国家石油及
び危険物汚染緊急対策)と連邦政府のスーパーファンド法の規定に準拠している。NCP の浄
化目標では、土壌別の基準というよりも発癌性の物質では10-4 から10-6 までの範囲に収まる
よう浄化修復を達成することといった基準であり、特定のサイトごとのリスク分析に基づい
て目標水準を設定し、跡地の土地利用に関係なく永続的な浄化修復を行うことを推奨している。
一方、EPA では、このような目標水準の実行可能性や、商業や産業用途の再開発が多い中
で、一律に住宅用途に対応した浄化修復を行うことは必要以上の対応であるとの判断を持っ
ており、跡地の土地利用に対応した浄化修復目標の設定を許容している。これは、リスクベ
ースのアプローチといわれており、浄化修復コストや健康リスク、跡地の土地利用、地域コ
ミュニティの許容性、技術的可能性などのさまざまな要因のバランスの下に浄化修復目標を
設定する方式である。
しかし、この方式は多くの環境上の判断を必要とし、恣意的に水準が適用される場合もあ
り、また、費用を節約するために必要とされる水準以下の浄化修復を行うことにより、汚染
物質が残存する問題も生じている。
これらの点から、カリフォルニア州としては、一律的な浄化修復目標水準の設定は難しい
と判断し、汚染地域の浄化修復事業に対して、以下の3 つの戦略により対応している。
【浄化修復目標水準設定の戦略】
a.バックグラウンドレベル(汚染されていない状態)までの浄化修復に向けての水準
バックグラウンドレベルについての一定不変の水準を持っている訳ではなく、各部局で
個別に設定している。
b.個別汚染地域ごとのリスクアセスメントに基づく浄化目標水準の設定
個別汚染地域ごとのリスクアセスメントに基づく浄化目標水準を設定し適用することを、
カリフォルニア州の基本的アプローチとしている。
c.州全体からのリスクベースの浄化目標水準の設定
以下の要因によるタイプ別リスクの想定に基づき、浄化目標水準を設定する。
開発事業者はまず、これらのタイプ別水準から控えめな水準との比較を行い、より高い
水準で比較する場合には、汚染地域ごとに実施するリスクアセスメントに基づく浄化目標
水準を適用する。
【タイプ別リスク設定の要因】
・汚染物質の人体への取り込みかた(摂取、吸入、皮膚からの感染)
・汚染源(土壌、空気、地下水)
・周辺土地利用(住宅地、商業地、工業地)
(3)ニュージャージー州
ニュージャージー州では浄化修復活動を行う上での目標水準として、リスクベースの基準
に基づき、以下の3 ケースに分けて、土壌と地下水に分けて設定している。
【浄化修復の目標水準】
a.無制限の跡地利用に対応する水準
b.条件付きの跡地利用に対応する水準
c.自然の自己回復力を考慮した条件付きの跡地利用に対応する水準
【浄化修復の目標水準の適用上の留意点】
・ これらのどの分類についても、汚染原因物質は除去されなければならない。
・ 土壌汚染物質については、発癌性のあるもの、非発癌性のものに分けて設定している。
・ 土壌の浄化修復においては、リスクアセスメントに基づいて設定された特定ケースの基
準の適用も認めている。
・ 適用される水準がそのサイトの周辺地区の水準よりも低い場合は、周辺地区の水準を適
用する。
・ そのサイトの土地利用が制限されている場合は、特別の注意書きを表示する必要がある。
4.1.4 制度的管理
制度的管理とは、ブラウンフィールドに対して、土地利用制限及び法的な管理により、健
康や自然環境への潜在的な被害を最小限にしつつ、ブラウンフィールドの有効利用を適切に
確保する法的措置等の取り決めを意味し、以下に示すブラウンフィールドの環境改善の一般
的プロセスのうち、段階5 に位置づけられる。
【環境改善の一般的プロセス】
段階1:地歴調査・聞き取り調査予備的な調査及び環境関連部局への通知と早期リスク削減措置の必要性の判断
段階2:包括的な土壌調査(アセスメント)、用途に対応したリスク影響調査アセスメントの実施により、汚染の原因、特性、程度、潜在的な影響の把握
段階3:環境改善計画の立案浄化計画とプロセスの評価、決定
段階4:浄化修復事業の実施
段階5:制度的管理継続的な浄化水準の維持管理
一部の州では、土壌汚染処理コストを低減させて土地の再利用、用途転換を円滑にするた
めに、人体の健康に対するリスクがない範囲において封じ込め等の部分的な処理を認めてい
る。このような完全浄化以外の対策が実施される場合には、土壌汚染による人体への暴露リ
スクを低減するために、一般の用途地区に上乗せするかたちで、土地利用制限などの制度的
管理が行われる。
制度的管理の目的は、土壌や地下水に含まれる未処理の汚染が人体に対して暴露する危険
性を管理するために、ブラウンフィールド再開発後の用途及び活動を限定して汚染土壌の封
じ込めを維持するためのものである。
(1)活動用途制限
マサチューセッツ州では、全米でもいち早く土壌汚染の制度的管理手法を導入しており、
AUL(Activity and Use Limitations)と呼ばれている活動用途制限を設けている。このAUL
は、現在及び将来の土地所有者に対してその土地で許容される活動や利用が示されており、
許容されていない用途に変更する場合は、新しい用途に応じたリスクの評価と追加的な浄化
が求められる。
この制度は、土壌汚染を全て除去するためには多額の費用がかかり、跡地利用にとって現
実的な解決策ではないため、汚染土壌を地下に残したまま人体に対して暴露されることを防
ぐために、土壌汚染が存在する土地に対して用途制限を行う制度である。
許容される土壌汚染の暴露の程度は汚染された土地の跡地利用によって異なるため、跡地
利用に応じて到達すべき浄化目標を設定して、その目標達成に適した方法で浄化を行う。こ
の浄化は、汚染自体の濃度を下げることのみでなく、汚染に対する暴露を取り除く、もしく
は最小化することでもよい。完全浄化によらず、汚染が残された場合には、活動利用制限を
設定して将来にわたり汚染の暴露状態が変わらないように継続的に土地を管理していくこと
になる。
マサチューセッツ州では、図4.1.1 に示す体制でAUL を実施している。用途制限されてい
る土地のAUL に係る情報は、州環境保護局のほかに自治体と郡不動産登記所で管理してお
り、この土地の再開発や土地取引に際しては、環境通知書によって土壌汚染の扱いが確認さ
れている。
図4.1.1 マサチューセッツ州の土壌環境情報管理体制
(2)制度的管理の実施方法に関する分類
米国の各州の制度的管理の実施方法で分類すると、多くの州では長期間モニタリングを実
施してブラウンフィールドを管理しているが、データベースを構築して経過追跡のみにとど
まっている州もみられる。表4.1.3 に示す分類のうち、カリフォルニア州及びルイジアナ州
における制度的管理の内容を以下に示す。
表4.1.3 米国各州の制度的管理の実施方法の状況
(3)カリフォルニア州の制度的管理の内容
カリフォルニア州毒物管理局(DISC)では、すべての浄化修復活動を長期間管理する方針
であり、以下の事項について実施している。
この中で、浄化修復用地の用途制限については、いろいろなメディアを用いて、情報を公
表しており、もし、用途制限をする必要がないレベルまで浄化修復された場合は、用地リス
トから除外し、逆に用途に見合ったレベルまで浄化修復されていない場合は、必要なレベル
までの浄化修復を行う財政的な裏付けを要求する。また、浄化修復活動が完了していない場
合は、継続的に浄化修復活動を行っているかどうか定期的に検査する。
【カリフォルニア州の制度的管理の内容】
・浄化修復活動完了時の検査
・モニタリング(契約事項の遵守徹底)
・インターネット上での浄化修復用地の用途制限の公表
・浄化修復用地周辺地区への掲示板での通知
・周辺住民への郵便による通知
・新聞紙上での注意広告
(4)ルイジアナ州の制度的管理の内容
ルイジアナ州環境管理局(DEQ)では、用途制限のある自主的な浄化修復活動については、
インターネット上で公表できるデータベースにより追跡的に監視している。
このデータベースでは、当該サイトの住所、用途制限、過去からの土地所有者、用途の履
歴とともに危険物取扱いの有無の情報が、土地所有者からの届出に基づき、登録されており、
DEQ の承認が無ければデータベースから除外できない。また、正確な情報が登録されていな
い場合は、当該サイトの取引契約を買い手側が解約できる根拠ともなる。
4.1.5 財政支援施策
ブラウンフィールドの浄化修復は、土地の安全性の改善や土地取引の活発化、都市の活性
化といった効果が見込まれる反面、多大な費用を要するため、当該用地の保有者が浄化修復
によるメリットが見込まれない場合は、そのまま土地利用の停滞状態が続く可能性もある。
このため、ブラウンフィールドの浄化修復を促進するために、用地の保有者や開発事業者
に財政的支援を講ずることは有効な施策となる。
ブラウンフィールド浄化修復再生事業に対する財政的な支援策としては、補助と融資、税
制措置に大別される。
ここでは、まず、米国の各州の財政支援策を総括的に捉え、次いで補助と融資について、
連邦政府の適用条件、主要な州の支援内容、適用条件について整理する。
(1)米国の財政支援策の分類
ブラウンフィールドの浄化修復事業への補助については、ブラウンフィールド再開発への
補助を行っている州が最も多い。融資については、零細事業者向けとして、ドライクリーニ
ング事業者への融資を行っている州が最も多い。また、税制措置に関しては、固定資産税の
軽減措置を講じている州が最も多い。
表4.1.4 米国各州の財政支援策の制定状況
(2)連邦政府のブラウンフィールド支援プログラム
連邦政府のブラウンフィールド支援プログラムは主にEPA(環境保護庁)とHUD(住宅
都市開発省)によって行われている。特にEPA は、常に連邦のブラウンフィールド政策のイ
ニシアチブをとり続けてきた機関であり、多くの支援プログラムを用意している。
1)EPA のブラウンフィールド補助プログラムの概要
地域に根ざした環境保護の手段としてブラウンフィールド問題に対応するために、1994 年
からEPA は、官民のパートナーシップを促進し、ブラウンフィールドサイトを評価した上で
浄化し、かつ、再開発するための革新的・創造的な方法の構築を促進することを目的として、
ブラウンフィールド問題に対応した補助金プログラムを開始した。EPA は「州・部族・自治
体の環境・経済開発職員が、ブラウンフィールド活動を概観し、また地域の問題に対して地
域固有の解決策を実行するための支援を行う」ことを目的としており、自治体を中心に自治
体・地域が主導するブラウンフィールド再生の取り組みを支援する姿勢に徹している。また、
EPA は、またブラウンフィールド再生による経済的な利益が地域に維持され続けるようにす
るため、地域の環境職業訓練プログラムを作成するための資金を提供している。
EPA のブラウンフィールド補助金は、以下の4 つが主要なものである。
・ アセスメント補助金
・ 浄化補助金
・ リボルビング・ローン・ファンド補助金
・ 職業訓練補助金
2)EPA のブラウンフィールド補助金の申請要件
【内容】
アセスメント
リボルビング・ファンド(RLF)
浄化対策
【規模】
2007 年10 月申請分 7,200 万ドル、200 件を予定
【対象】
a.ブラウンフィールド(危険物質や汚染の存在あるいは存在可能性により、再開発や再利
用に問題が生じうる不動産)
b.ブラウンフィールド以外の追加適用対象
・規制薬物によって汚染されたサイト
・石油または石油製品によって汚染されたサイト
・廃鉱など鉱物資源の跡が残るサイト
【資格要件】
a.申請者の要件
・ 浄化したいとする土地を所有している団体(大学やNPO を含む)
表4.1.5 補助対象別の申請者タイプ
b.適用除外土地
以下のサイトは、補助金受給資格を有さない。ただし、2)から5)については、個別判断に
基づき対象とすることができる。
1) NPL に現在リストされているか、リストに向け提案されている土地
2) CERCLA の下で計画あるいは進行中の浄化がある土地
3) 閉鎖計画または許認可に規定される要件に従い、RCRA 閉鎖通知を提出した処分場である土地
4) PCB の漏出があった施設
5) 漏出地下タンク信託基金から資金を受けている施設
【補助金の使用制限】
補助金は下記の支払いに使用できない
・ 罰金
・ 連邦経費分担要求(例えば他の連邦基金で要求される分担金)
・ 一般管理費
・ 潜在的責任者として対応するための費用
・ 土壌汚染浄化関連法以外の任意の連邦法に対する遵法費用
・ ロビー活動費用など
3)ブラウンフィールド・モデル地域
ブラウンフィールド・モデル地域(Brownfield Showcase Community)は、20 以上の連
邦機関のパートナーシップ(注4)のもとで1998 年から行われたブラウンフィールド再生のモ
デル事業である。環境修復から地域開発まで多岐にわたるブラウンフィールド問題を解決す
るための、省庁間協力の事例として注目される。
1997 年5 月に、ゴア副大統領は、15 を越える連邦機関の資源を集めるためにブラウンフ
ィールド連邦パートナーシップ(BFP)を発表、1998 年3 月に、この連邦パートナーシップ
は、ブラウンフィールド上の共同作業の利点を実証するモデルとして、16 ヶ所のブラウンフ
ィールド・モデル地域を選定した。さらに2000 年10 月には、イニシアチブの成功を継続す
るために12 の追加のブラウンフィールド・モデル地域を選定している。
選定は基本的に都市レベルまたは地域レベルで行われ、対象都市のなかでもブラウンフィ
ールドを多く抱える特定の地区に対して、特に重点的に資金を投入している。ブラウンフィ
ールド・モデル地域は規模、資源および地域のタイプなど多岐にわたるが、古い工業地帯が
広がる米国北東部に特に集中している。
図4.1.2 モデル地域事業に指定された自治体の位置
? モデル地域事業の目標
1.ブラウンフィールドのアセスメント、浄化および持続可能な再利用を通して環境保護お
よび回復、経済再開発、雇用創出、コミュニティ再生および公衆衛生保護を促進する。
2.ブラウンフィールドを修復し再利用する地域の努力を支援する連邦、州、地域・民間の
動きを結びつける。
3.ブラウンフィールドに取り組む際に、行政と民間が協働することによって、よい結果が
得られることを実証する全国的なモデルを開発する。
連邦政府が1980 年代から取り組んできたスーパーファンド法にはじまる環境修復の取り
組みが、土壌汚染をはじめとする環境浄化に主眼をおいてきたのに対し、90 年代のブラウン
フィールド再生事業には、単なる土壌汚染の浄化にとどまらず、環境問題に関する市民の教
育から、周辺地区の再生、地域の雇用創出に至るまで、多面的な取り組みが求められるよう
になってきた。
スーパーファンドサイト(注5)は、その多くは浄化の優先順位付けから資金確保・浄化の
管理に至るまで連邦直轄で行われてきたが、ブラウンフィールド再生事業はスーパーファン
ドほど汚染の程度は深刻ではなく、土壌汚染の浄化と同程度、もしくはそれ以上に都市・地
区の再生と経済開発に主眼が置かれている。結果として、その実施は連邦機関(特にEPA)
だけで実施できるものではなく、すべてのレベルの政府、民間部門および非政府組織の間に、
より多くの協力と調整が求められた。
モデル地域事業は、土壌汚染の浄化から工場跡地さらには疲弊した工業都市全体の再生を
目指すブラウンフィールド事業へと展開するためのノウハウを連邦・州・自治体が一体とな
って作り上げるための重要なプロセスであった。
? 対象地域の利点
ブラウンフィールド・モデル地域に指定されることで、自治体は連邦からの重点的な支援
を受けることができる。自治体は、ターゲットとされた技術的・財政的援助から直接的な利
益を得ることができる。
中でも連邦政府の職員(主にEPA の職員)が、対象の自治体に出向し、技術的・財政的援
助の調整を支援する制度である。政府間要員配置(IPA)スタッフと呼ばれ、環境面の知識
や制度・補助金に不慣れな自治体職員を助け、2 年から3 年にわたって、対象自治体の職員
として地域のブラウンフィールド再生に取り組んだことの意義が大きかった。(注6)
(3)主な州のブラウンフィールド関連財政支援策の概要
1)マサチューセッツ州の財政支援策
マサチューセッツ州では産業開発局や環境保護局などの部局ごとにさまざまなブラウンフ
ィールド関連の財政支援策が用意されているが、補助に関しては、対象が自治体または非営
利団体に限られており、一般のブラウンフィールドについては低利融資の利用に限定されて
いる。
VCP(自主浄化活動)サイト数は、2006 年7 月までに34,312 件のサイトが報告されてお
り、このうち、4,735 件は現在、実施中である。毎年、概ね1,800 件の新規サイトが申請さ
れる。
? マサチューセッツ州産業開発局(Mass Development)が管轄する助成策
a.ブラウンフィールド再開発基金(BRF)(融資)
再開発を伴うブラウンフィールドサイトに対して、以下の融資が提供されている。
【財政支援規模】
・連邦政府からのブラウンフィールド補助金の10%が、サイトを指定したアセスメントや
再開発を誘導する浄化事業(Cleaning Projects)に使われている。
・2006 年 7 月時点で、15 箇所のサイトの調査と2 箇所のサイトの浄化事業に取り組んで
いる。
【融資の内容】
・ブラウンフィールドサイトの調査への低利融資
サイトの調査に対しては、上限10 万ドルまでの低利融資が提供される。
〈資格要件〉
・EDA(Economically Distressed Areas)地域内に位置していること
以下のどれかの条件を満たすこと
・ETA(Economic Target Area)地域として指定された地域または自治体であること
・ETA 地域としては指定されていないが、ETA 指定条件を満たしていること
・以前の用途がガス製造プラントであったこと
・申請者はサイトの所有者か浄化の実施者であること
・マサチューセッツ州の規定により認可されたサイトであること
・浄化事業への低利融資
サイトの浄化、修復に対しては、上限 50 万ドルまでの低利融資が提供される。
特に、優先プロジェクトについては、調査と浄化事業に対して上限200 万ドルまで融資
される。
〈資格要件〉
・EDA 地域内に位置していること
・申請者はサイトの所有者であること
・抵当保証が設定できること
? マサチューセッツ州環境保護局(Mass DEP)が管轄する助成策
Mass DEP のブラウンフィールド関連の助成策としては、以下のように対象が限定される。
a.水質浄化リボルビングファンド(SRF)(融資)
水質を改善するプロジェクトを対象に,期間20 年の低利融資(2%)が提供される。
b.調査及び浄化事業への補助(補助)
連邦環境保護庁(EPA)の補助の下、自治体や非営利団体を対象として、荒地となって
いるサイトの調査及び浄化事業に補助される。
【財政支援規模】
・2006 年の上半期で、概算で600 万ドル支援
このうち、110 万ドルは連邦政府から指定されているサイト
・2006 年 7 月時点で、4,200 万ドルが契約中
・1983 年以降で、累計1 億8,300 万ドルを支援
? マサチューセッツ州住宅・コミュニティ開発局(DHCD)が管轄する助成策
DHCD は連邦政府の住宅都市開発省、コミュニティ開発基金プログラムを実施する機関で
あり、人口5 万人以下の市や町を対象とし、低所得者居住地区のスラム化や環境悪化の防止、
緊急対応事業などに助成する。
ブラウンフィールド関連の助成策は以下のとおりである。
a.コミュニティ開発基金(補助)
自治体を対象に、プランニング、予備的な開発計画の検討、用地の取得、調査、浄化事
業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
b.Mini−Entitlement Program(補助)
自治体のMini−Entitlement 事業を対象に、プランニング、予備的な開発計画の検討、
用地の取得、調査、浄化事業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
c.産業開発基金(補助)
自治体の産業開発事業に補助され、プランニング、予備的な開発計画の検討、用地の取
得、調査、浄化事業、建造物の取り壊しなどの活動に補助される。
d.コミュニティ開発行動基金(補助)
自治体を対象に、市や町の経済活性化や投資の活発化、長期の雇用創出、低所得者居住
地区の環境改善に資するプロジェクトに補助され、市街地整備の様々な事業に使われる。
e.優先的開発基金(計画立案等への補助)
自治体を対象に、計画立案、ゾーニング、住宅整備への教育・指導などに上限で5 万ド
ルまで補助される。多くの市や町では、住宅開発を誘発する計画立案のコンサルタント費
用として使われている。
? マサチューセッツ州税務局(Mass DOR)が管轄する助成策
a.地下埋設タンクプログラム(補助)
自治体を対象に、地下埋設タンクからの漏洩対策や地下埋設タンクの閉鎖などの活動に
補助される。
2)カリフォルニア州の財政支援策
カリフォルニア州では、環境調査に関して連邦政府からの補助が受けられる。浄化事業に
関する補助は特定のプログラム(下記の?)に限定されている。一般事業者の浄化事業に関
しては、専ら低利融資が受けられる。
VCP(自主浄化活動)のサイト数について、カリフォルニア州毒物管理局(DTSC)は平
均して常に300 箇所のサイトを指導・監督している。また、毎年、平均して125 箇所のサイ
トの浄化事業を完了している。
? ブラウンフィールドサイトの環境調査への補助
連邦政府環境保護庁(EPA)から、カリフォルニア州毒物管理局(DTSC)の支援を通じて応
募者に環境調査費用への補助が行われる。
? 自主浄化事業(VCP)への低利融資
・融資額
サイトの特性把握:最大 10 万ドル
サイトの浄化活動:最大 250 万ドル
〈VCP として認定される資格要件〉
・連邦政府や州政府のスーパーファンド法による対策地域、軍事施設、DTSC の
管轄外のサイトでないこと
〈融資の適用条件〉
・事業用の用地であること
・産業、商業、非営利団体・スモールビジネスの立地が予定される再開発用地であること
? 浄化事業への補助等
以下のプログラムが用意されている。
・再開発局環境監視協定プログラム(EOA)
・学校用地の環境評価・浄化プログラム
・地下埋設タンク浄化基金プログラム(UST)
・毒物管理会計(TSCA)
3)ニュージャージー州の財政支援策
ニュージャージー州では、一般事業者の浄化事業に関しては、専ら低利融資が主要な助成
策となっている。革新的技術で浄化した場合などの特定の条件を満たす場合には、補助も行
われている。
以下の財政支援プログラムの下に、多数のサイトが浄化事業を実施中である。2002 年には、
危険物放出サイト修復基金では、156 サイトの浄化事業を完了しており、総額で1,500 万ド
ル以上の融資や補助が実施された。また、200 サイトが検査中である。
NJDEP では、常に23 千箇所の汚染サイトを監視しており、その内の1 万箇所は潜在的な
ブラウンフィールドサイトである。
? 危険物放出サイト修復基金(低利融資、補助)
・一般のサイト(低利融資)
危険性の高いサイトの修復に関しては、一般のサイトでは最大で100 万ドルまで融資
・地方自治体(補助)
地方自治体に対しては、所有者のはっきりしないサイトや無償譲渡されたサイトなどの浄
化のために、最大で200 万ドルまでの補助または融資
? 水資源関連のブラウンフィールドサイト浄化に対するニュージャージー州インフラ基金に
よる低利融資
? 革新的技術で浄化した場合や制限無しまたは一部制限付き再利用が可能なサイトの浄化費
用への補助(25%まで)
4.1.6 環境負債免除制度
米国における最初の土壌汚染に関する法律としてのスーパーファンド法(包括的環境対処
・補償責任法)は、不可逆的な環境汚染の拡散の防止のために、非常に厳しい規制を課して
いる。その最も厳しい点として、土壌汚染の浄化責任を現在及び過去の土地所有者に求めて
おり、現在の土地所有者が汚染の原因者でなくても浄化責任を求められる可能性があること
があげられるが、その影響として、土壌汚染浄化の可能性がある土地については浄化コスト
のリスクを伴うため、都市部の再開発から取り残されてしまうという問題を生じさせてしま
っていた。このような問題を改善し、土壌汚染地の開発を積極化していくための制度として、
以下の制度がつくられている。
○ 自発的修復制度(VCP:Voluntary Cleanup Program)
スーパーファンド法による浄化義務発生リスクを回避し、土壌汚染地の再開発を促進す
ることを目的としており、浄化修復事業は民間側が主導的にすすめることができるよう前
項で記述した各種財政支援策が用意されている。
○ 環境負債免除制度
民間側の浄化修復事業が事前に州当局と協議した計画に基づき実施され、完了した場合
に、州政府は修復完了を承認し、将来にわたる環境負債を免除するものとして、以下の証
明書を発行する。
・ 修復完了証(No-Further-Action letter)
浄化の完了及び追加的な浄化措置が不要であることを証明する
・ 訴追免除証(Covenants-Not-To-Sue)
将来にわたって同一理由による汚染修復責任を求める訴追を原則として受けなくてよい
ことを証明する
以下で各州の環境負債免除制度及び小規模事業者責任免除制度について把握整理する。
(1)環境負債免除制度
ブラウンフィールドへの取り組みとして、ほとんどの州が自発的修復制度及び環境負債免
除制度を関連法制度に盛り込んでいる。それらの州のうち、マサチューセッツ州、カリフォ
ルニア州について、その概要を整理する。
1)マサチューセッツ州の環境負債免除制度
マサチューセッツ州の環境負債免除制度の特徴は、責任軽減制度の導入と浄化管理の民間
化によって、効率的で迅速なプロセスを実現している点にある。マサチューセッツ州は、汚
染責任者に対して厳格な連帯責任を課している。汚染責任者は、自主的に土地を浄化するこ
とが認められており、もし自主的な浄化が行われない場合には、マサチューセッツ州開発局
(MADEP)が浄化を代行し、かかった費用を回収することができる。
実際に、自主的浄化の割合が95%と非常に高い。これは、マサチューセッツ州開発局の
担当者が、積極的にインセンティブ活用を推進するブラウンフィールド・コーディネーター
となり、民間事業者の側に立って自主浄化を促していることもあげられる。
? 責任免除制度の提供
責任免除制度は、民間事業者が再生事業に参加する際に最も重要になる制度である。マ
サチューセッツ州は、全米でも早い時期に責任免除制度を創設、提供を開始した州である。
? 訴訟免除契約書の発効
ウースター市のメディカル・シティ・プロジェクトの過程で、ウースター再開発公社か
ら、民間事業者に土地を売却する際に、州政府が発行したCNTS がその原型とされる。ブ
ラウンフィールド訴訟避止誓約書は、1998 年のブラウンフィールド法によって正式に制度
として認められた。現在はマサチューセッツ州法務局によって、各々の関係者に合わせた
責任免除措置が与えられている。
? 跡地利用制限がある場合の責任免除制度
土壌汚染がある土地を浄化する際に、経済的な理由から全ての汚染を除去せずに、一定
の汚染を残したまま、封じ込めなどの処理する場合がある。この場合、跡地の活動用途制
限(AUL)が土地に付加される。AUL のある土地に対してもAUL の変更を行なわない場
合、責任免除制度の適用が可能である。
2)カリフォルニア州の環境負債免除制度
カリフォルニア州のブラウンフィールド対策の基本として自発的修復制度(VCP)が位
置づけられている。浄化修復事業者は、浄化事業中はカリフォルニア州毒物管理局(DTSC)
の監督を受け、修復が完了した時点で、以下の2種類の証明書のどちらかを発行する。
しかし、これらの保証があっても将来時点で第三者機関による浄化活動を除外しない。ま
た、浄化活動が進行中であっても、事業の完了と維持管理が確保されるとの合意があれば保
証書は発行される。
・ 修復完了証(No-Further-Action letter)
一部、汚染が残っていても、人体や環境にほとんど影響が無いレベルまで浄化された場合に発行される
・ 完結終了証(Certificate of Completion)
浄化目標水準を完全に達成した場合に発行される
(2)小規模事業者責任免除制度
小規模事業者責任免除制度は、ブラウンフィールドプログラムのより効率的な実施と再開
発促進のため、連邦政府環境保護局により2002 年に法律が施行された。この法律での小規
模事業者とは、有害物質の保有量が液体100 ガロンまたは固体200 ポンド以下で、2001 年
4月1日以前にすべての有害物質の廃棄、取り扱い、輸送を行っていた事業者である。
各州の小規模事業者責任免除制度に対応する取り組みをみると、ドライクリーニング事業
者の汚染サイトに対する環境対策プログラムとして制度化されており、どの州でも財政イン
センティブが合わせて講じられている。
【小規模事業者責任免除制度を持つ州】
・ ウィスコンシン州 −ドライクリーニング環境対策プログラム
(ドライクリーニング環境対策ファンド)
・ サウスカロライナ州−ドライクリーニング事業者のための環境指導書
(ドライクリーニング修繕トラストファンド)
・ フロリダ州 −ドライクリーニング有機溶剤浄化プログラム
(ガソリンスタンド、ドライクリーニング店向け浄化ファンド)
・ カンザス州 −ドライクリーナー環境対策プログラム
(ドライクリーニングファンド)
・ テキサス州 −ドライクリーニングによる汚染サイト対策プログラム
(ドライクリーニング浄化支援プログラム)
・ ミズーリ州 −ドライクリーニングによる汚染サイトの再利用活性化支援プログラム
(ドライクリーニング信託投資ファンド)
4.2ドイツ
4.2.1 連邦土壌保護法制定の経緯
ドイツにおいても、1980 年代から土壌汚染問題への対応が本格化したが、当時は、個々の
法律(州レベルの土壌保護法、州レベルの廃棄物法など)ごとの個別的な対応であったり、
州ごとにばらばらな規制を行っていたりして、規制の不整合の問題が生じていた。しかし、
1999 年3 月に連邦土壌保護法、同年7月に連邦土壌保護土壌汚染令の施行により土壌汚染リ
スク管理が統一された。
4.2.2 土壌汚染情報のデータベース化の取り組み
ドイツにおいては、都市計画決定の権限や土壌汚染地の浄化修復についての自治体の役割
は極めて大きい。このため、土地利用計画の安定性を担保するためにも、土壌汚染情報の収
集は重要となっている。土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動してい
るため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしている。
具体的には、自治体レベルで土壌汚染の可能性のあるサイトを把握して土壌汚染情報をマ
ップに落として公表しており、また、土壌汚染に関する統計データも自治体から、州、連邦
政府へと段階的に上げられて整備され、公表されている。
ドイツにおいては、ブラウンフィールドは最終処分場跡地と産業跡地という広い意味で用
いられており、統計によれば、この該当サイトは231 千箇所あり、また土壌汚染が特定された
サイトは11 千箇所、浄化が終了しているサイトは14 千箇所、リスク評価が終了しているサ
イトは37 千箇所と集計されている。
ドイツにおいては、図4.2.1 に示すとおり法がカバーしている土壌汚染の範囲は広く、「予
防」段階から「危険防止」段階に分かれ、法的に対策が求められるのは「危険防止」段階以
上となる。ただし、「危険防止」段階でも、土地利用用途ごとの基準値と照らし合わせて、概
況調査で終わってよいもの、詳細調査まで進むべきものに分けられていく。
図4.2.1 土壌汚染の規制体系
【統計データにおける「土壌汚染」の分類】
・ ブラウンフィールドが疑われるサイト
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち旧堆積場
・ ブラウンフィールドが疑われるサイトのうち産業跡地
・ ブラウンフィールド
・ 浄化完了サイト
・ リスク評価完了サイト
・ 浄化中サイト
・ モニタリング中サイト
4.2.3 浄化修復目標の設定
ドイツにおいては、ブラウンフィールドサイト毎に「浄化計画」を作成し、目標水準は個
別に設定することを基本とする。その目標水準は、開発用途などを総合的に考慮して決定さ
れるため、米国の各州で基本的考え方となっているリスクベースの浄化修復目標水準の設定
と同様に経済合理性の視点が取り込まれている。
また、ドイツは都市計画決定に関して市町村が強力な権限を持っており、浄化修復目標の
設定や跡地の利用形態の決定に市町村が全面的に関与している。ブラウンフィールドに関連
して、健康的な居住や就労環境の確保は都市計画を定める中で、重要な配慮項目となってい
る。
(1)浄化計画と行政契約
土壌汚染の存在が確認された土地では、まず浄化のための概況調査が実施され、浄化目標、
浄化手段、費用などが定められた浄化計画が作成される。この浄化計画は、事業者側で作成
し、行政当局に提出して、公法上の手続きである行政契約によって合意形成される。
浄化後のネットバリューがマイナスになった場合、その相応額を行政が補助金で負担する。
また、浄化後の取引価格が顕著に上回った場合は、逆に費用返還請求できる制度となって
いる。
行政契約のメリットとして、行政手続きリスクの減少と手続きの迅速化があげられる。
浄化計画で定められる事項は以下のとおりであり、浄化方法、費用だけでなく、都市計画、
建築、水質保全、公害防止など都市開発に伴う関連許認可項目が網羅的に含まれている。
【タイプ別リスク設定の要因】
・ リスク評価の概要
・ 浄化対象用地の旧来そして将来の用途
・ 浄化目標
・ 費用見積り、資金計画
・ 浄化目標の達成に必要な除去、隔離、制限、自己管理措置 等
・ 浄化、品質保証のモニタリングコンセプト・一連の手続きに要する期間 等
(2)用途別基準の設定
ドイツでは詳細調査や浄化対策の必要性の判断を行うために、用途別基準が設定されてい
る。一度決められた土地利用計画は将来変わることは少ないと固定的にとらえられているた
め、経済合理性のある用途別基準が重みを持って用いられている。
調査値は、用途別汚染物質別に設定されているが、対策値はダイオキシン/フランのみし
か設定されていない。対策値は地域の特殊性を考慮して設定することが基本となっている。
【用途の分類】
・ 子供の遊び場
・ 住宅地域
・ 公園・レジャー施設
・ 工業、産業用地
4.2.4 制度的管理
ドイツでは、市町村が強力な都市計画決定権限を有しており、都市計画制度が土地利用用
途を厳格に管理している。F―プランといわれる行政内部の長期的な土地利用計画とB―プラ
ンといわれる私権を制限する強制力のある地区詳細計画があるが、計画策定に当たっては、
健康的な居住・就労環境の確保が重要な配慮事項とされている。各土壌汚染サイトの浄化レ
ベルは、開発用途等を総合的に勘案した上で個別に作成される浄化計画によって決められる
ため、都市計画と連結している。
また、浄化修復後の浄化水準チェックのためのモニタリングの方針を浄化計画に定める事
項としており、制度的管理においてモニタリングが重要な位置づけにある。
土壌汚染対策の流れは図4.2.2 に示すとおりであり、以下の点に特色がある。
・ 土壌汚染情報の把握の段階では、都市計画制度と密接に連動しているため、基礎自治体である市町村が大きな役割を果たしていること
・ リスク評価の段階で用途別の基準値を用いていること
・ 浄化とモニタリングの段階では目標が一律に定められておらず、それぞれのサイト毎に
浄化目標と浄化計画を定める浄化契約を自治体と結んで、対策及びモニタリングが実施さ
れていること
図4.2.2 土壌汚染対策の流れ図
4.2.5 公的関与
ブラウンフィールドの再開発において、採算がとりにくく民間が手を出しにくい土地に対し
ては官主導の色彩が濃くなり、自治体が基本的に公費で土壌汚染対策を実施して民間投資を誘
発して再開発を行い、開発後に得た開発利益を官民で分けている。フランクフルト西港開発の
事例では、市が土壌汚染を除去して用地をデベロッパーに売却し、開発・販売・分譲により得
た開発利益を市とデベロッパーとで折半する契約となっている。また、ノルトホルン再開発事
業の事例では、相当深刻な土壌汚染があって開発計画は一時頓挫していたが、市が様々な工夫
によって浄化対策を行って民間投資を呼び込んでいる。誘発された民間投資が大きいというこ
とで、市による公費投入が正当化されている。
(出所) Umweltbundesamt 資料、Osnabrueck 市資料より作成
5.土壌汚染地における土地の有効利用促進等に向けた課題
2.2でも述べたように、土壌汚染問題に対する一般的理解が不足していることから、我が国
においては土壌汚染に関する情報は秘匿されがちであり、容易に公にはならず、一般社会では土
壌汚染が特別なものだと思われている。その結果として、土壌汚染が公表された場合には、報道
等でことさら大きく取り上げられ、それが仮に軽微であっても、社会的には過剰反応しがちであ
る。また、この現象により土地所有者などは公表を拒むこととなり、結果的に悪循環となってい
る。
しかしながら、我が国は火山国である事から、重金属の自然含有レベルは高く、時に環境基準
を超過する土壌があることや、現在では汚染責任的には容易に対処のしようがない過去の含有レ
ベルの高い臨海の埋立地の土壌などの存在は、決して特別なものではない。それらの土地を健康
リスクの観点から見た場合、多くは他のリスクと比較して過剰反応するほどの大きなものでなく、
対応は充分可能なレベルであると考えられる。
土壌汚染が社会問題化するのは、土壌汚染自体が新しい概念であり、それらを大きな問題とし
ていない考え方や商習慣であった土地利用や土地取引への仕組みが充分に対応しきれていないこ
とによる。すなわち、対象とする物質は工場内等で管理されてきた事に対して一般的には積極的
にオープンにされていなかったにもかかわらず、その情報を求める必要性のある土地利用や土地
取引とのやりとりにまだ大きなギャップがあるまま、社会が動いてしまっているためである。
以上のような現象は、我が国よりも早くから土壌汚染の概念を導入してきた諸外国においても
見られており、それぞれの国の法令や、都市計画などの仕組みの中で対処されてきた事実も、本
年度の検討で明らかになった。特に安易に土壌汚染を放置することなく積極的に管理を行ってい
く取り組みはブラウンフィールドの対処法に関して多くの示唆があった。
現在我が国で起こっているギャップを埋めるためには、海外の取り組みも参考にしながら、単
なる規制ではなく、国民が土壌汚染の実態を認識した上で、土壌汚染の問題に対して適切な対応
をし、土地取引における問題の解消と我が国なりの法令、仕組みや国民性に適応した合理的な土
地利用を促進する必要がある。
5.1 更なる実態・影響の把握
土壌汚染に関する情報については、土壌汚染対策法が、民間の事業者が自主的に行った調査
結果の届け出を義務づけていないことに加え、自治体によって、自主調査結果についても届
け出を義務づけた上で公開するところ、できるだけ届け出るよう指導するところ、そもそも
届け出を義務づけていないところなど、そういった自主調査結果に対する取扱いが異なるこ
とから、個別の土壌汚染サイトに関する情報(調査、対策の状況やその所在地等)は、なか
なか公にならない現状がある。
土壌汚染に係る施策の必要性等を検討するためには、土壌汚染が土地取引や再開発等の支障
となっている事例を当該事例における土壌汚染の管理の実態と併せて可能な限り多く把握
し、その原因等を分析することが必要である。しかし、現時点ではそのような事例を十分に
把握しているとは言い難いことから、今後も企業や地方公共団体等へのヒアリングや調査等
を積み重ねていく必要がある。特に、どうしようもなく動かなくなった土地は商取引の場か
ら外れることにより非常に顕在化されにくいという意見が多く、5.2以下に掲げる課題を
検討し、次のステップに進むための前提としても、さらなる情報収集が必要である。
5.2 土壌汚染情報のデータベース化
5.2.1 土壌汚染情報データベースの構築
前述したとおり、基本的な土壌汚染情報が不在又はアクセス困難であるため、マンション購
入後に土壌汚染が発覚し問題となったり、再開発計画を着手後に見直さざるを得なくなる等
の支障が生じている。しかし、土壌汚染情報は、土壌汚染地の周辺住民や購入者にとっても
利害関係を有するという意味では、土地の安全性に関する情報として公益的な側面を有する
ものであるから、広く情報を共有することを検討すべきである。
この点米国では、4.1.2で述べたように、多くの州が自ら情報を収集したり、届け出や
問い合わせがあった情報を元にして、土壌汚染情報のデータベースを作成し、インターネッ
トで公開している。
これを踏まえわが国でも、全国的な土壌汚染情報をデータベース化し、インターネット等に
よりその時点の状況を誰もが閲覧できる仕組みが存在すれば、土地取引の円滑化や浄化措置
の促進・早期化等に資することになるとも考えられる。
ただし、こういったデータベースを構築・公表する場合、そもそも情報の入手手段が限られ
ており、また、情報の正確性に細心の注意を図る必要があることから、引き続き、情報の入
手源や入手方法について検討すると共に、その情報の元となる調査の信頼性及び正確性をい
かに担保するかという点や万が一公表した情報が誤っていた場合に、当該データベース作成
者の責任の射程及び当該情報を利用した結果他者に危害を与えてしまった者の責任の射程に
ついても併せて検討しておく必要がある。
なお、土壌汚染情報データベースの一類型として、浄化が完了したサイトに関し、当該サイ
トの土質や浄化が完了した旨を公表するようなデータベースを構築することも、土地取引の
円滑化等に資すると考えられることから、こうした点についても検討する必要がある。
5.2.2 土壌汚染要調査マップの作成
しかし、わが国においては、5.2.1で述べたように情報の収集方法等を検討しなければ
ならず、土壌汚染情報データベースの構築はすぐには開始できない。
この点ドイツにおいては、4.2.2で述べたように、土壌汚染が存在する結果開発がスト
ップしているサイトに関する情報のみならず、産業跡地である等の理由により土壌汚染が存
在する恐れがあるサイトに関する情報を収集し、地図上に落とし込んで公表している。
そこでわが国においても、個別サイトを対象にしたデータベースを構築するための前提とし
て、公的なリーダーシップのもとにフェーズ?程度の地歴調査を行ったうえで、過去に工場
が立地している等の理由により、土壌汚染されているおそれが高いサイトや地区を地図上に
記載した、「土壌汚染要調査マップ」をリスクアセスメント手法を活用しながらひとまず作
成することも有効であると考えられる。
「土壌汚染要調査マップ」の作成により土壌汚染要調査情報が世の中に浸透すれば、土壌汚
染に関する情報を公開することに抵抗を感じにくい土壌の醸成につながり、土地取引・土地
利用における土壌汚染の存在を特別視しないで行えることが期待される。結果として、比較
的スムーズに土壌汚染情報データベースが世の中に受け入れられ、より効率的な土壌汚染へ
の対応が可能になるものと考えられる。
5.2.3 自然由来の土壌汚染データベースの構築
自然由来の土壌汚染については、地質的に一定の地域内に幅広く分布する等の事情により、
その地域固有の特性と考えて対応する必要がある。すなわち、仮に掘削除去による完全浄化
をするとしても、どこまで掘っても汚染土壌が出てきてきりがないという場合がありうる。
したがって、対策をすべき土地とそうではない土地の線引きを可能にするため、自然由来の
土壌汚染についてデータベースを構築することは、有用であると考えられる。またこれによ
り、汚染土壌による地下水への影響や残土の処理方法等を調査、検討することも可能になる。
なお、自然由来の土壌汚染は、汚染原因者がいないことから、いわゆる「汚染者負担の原則」
により浄化費用等を負担させることは困難であるが、情報の公開によって影響を受ける関係
者も少ないことが想定されるため、自然由来の土壌汚染データベースの構築・公開に対する
抵抗感は少ないものと思われる。
しかし、自然由来の土壌汚染については、前述したようにある地域内の土地全体に当てはま
る特性であることから、個別サイトごとの状況を考慮に入れれば足りる一般の土壌汚染の場
合とは異なり、面的に土壌汚染の状況を把握する必要がある。
こうした点からすると、自然由来の土壌汚染に関する情報を収集するためには一般の土壌汚
染の場合とは異なった方法が必要であると考えられることから、引き続き検討をしていく必
要がある。
5.3 公的支援の必要性
米国等においては、土地取引の活発化や地域の活性化が図られると期待される場合には、土
壌汚染地に対し、公的主体が浄化費用の一部を補助し、また、土壌汚染地について浄化を開
始又は完了したような場合には固定資産税の軽減を行う等の財政的支援を行っている。
一方わが国においては、土壌汚染が土地取引や再開発やまちづくりに影響を与えていると考
えられる具体的局面として次の場合が挙げられる。
・ 一般的に、大都市部においては、地価が高いため対策費を拠出することが可能であり、
現時点では土壌汚染が土地取引や再開発の支障となっている事例は多くないようである
が、地方部においては対策費の負担が大きければ土地取引や再開発が断念され、地域活性
化を阻害するおそれがある。
・ 小規模事業所等の場合、土地所有者に資力がないことが多いため、調査及び対策が困難
となる結果、土地取引や再開発に支障が生じるおそれがある。
土壌汚染においては、原因者負担が原則ではあるが、原因者に資力が無い場合や原因者が浄
化しただけでは十分な開発等が困難な場合であって、なおかつ、当該土地を活用して地域活
性化等の施策を講ずる必要がある場合には、上記のような局面について、米国等の例を参考
に、補助金、公的資金を投入した基金、税制優遇、公的主体による浄化措置等を検討するこ
とも考えられる。しかしながら、本研究会では具体事例の収集が十分にできず、具体的な検
討には至らなかったところである。
今後検討する前提として、上記に掲げるようなケースごとの実態を十分に把握・分析した上
で、公的支援の公益性及び必要性について検証・検討し、問題点を明確化するとともに、背
景となる事情や制度が我が国と異なることに留意しつつ諸外国の事例を大いに参考にすべき
である。諸外国の事例を検討するに際しては、公的資金の投入等により浄化をした結果とし
ての雇用創出の程度や税収増の割合といった当該施策の効果についても分析を加え、より効
果的なものを参考にすることが望ましい。
なお、地域活性化等の観点から公的資金の投入が難しい場合であっても、地域住民に健康被
害が生じている場合等は、別の観点から検討をしていくことが必要である。
5.4 サクセスモデルの構築
5.4.1 サクセスモデルの構築
2.2.2で述べたように、現在、土壌汚染を浄化する際には、掘削除去による完全浄化が
ほとんどである。掘削除去には莫大な費用がかかることから、特に地方部においては、都市
部と比べて、掘削除去費用が地価を超えてしまうことも往々にしてあり得、結果として土壌
汚染の存在する土地が開発、利用されずに放置されてしまうという事態がありうる。
そこで、地方部においても土壌汚染が存在する土地の有効活用が少しでも図られるよう、土
壌汚染が実際に存在する土地を取り上げ、原則として掘削除去以外の浄化措置を行うと共に
その後の土地利用の計画を策定した上で、その成功要因等を分析・研究するという「サクセ
スモデル」を構築・公開し、その構築が一定程度完了した時点で当該モデルを「ひな型」と
してまとめ、公表することが、土壌汚染地の有効活用のための現実的な有効策となり得ると
考えられる。
この際、例えば、昔は工場等が集積していたが今後は住宅地・商業地として再開発の可能性
が高い一定の駅裏等を対象に、調査、データベースの整備・公開、非完全浄化を含めた対策
等の一連の対応を実験的に行うことの必要性や実現可能性について検討する必要がある。
なお、掘削除去以外の浄化方法を選択した上で再開発等を行った海外の事例について研究
し、場合によってはその事例自体を「サクセスモデル」の参考として提示することもあって
良いと考えられる。
5.4.2 官民の連携
なお、「サクセスモデル」の構築に当たっては、土地の開発、建築、浄化等を行う民間事業
者と土地利用の計画を策定する公共主体がそれぞれバラバラに取り組むのではなく、計画の
段階から実際に浄化した上で開発する段階、さらには土地利用の状況をモニタリングする段
階に至るまで官民一体となって両者が連携、協働することが必要である。
その際、浄化方法と土地利用の方法がどのように対応できるか等、民間業者と公的主体のそ
れぞれがノウハウを蓄積させるとともに、そのために必要な人材を育成していく必要がある。
5.5 資産評価の一層の適正化
時価会計への一本化や今後の資産除去債務の導入等社会経済情勢の変化に伴い、不動産の経
済的価値を正確に評価することが一層求められている。
このためには、土壌汚染の専門業者が行う調査の標準化とそれを通じた専門業者の標準化を
進める必要がある。これにより、土壌汚染地の資産評価の適正化と、さらには、土壌汚染地
に係る安全で円滑な利用や取引が促進される。
一般的に不動産鑑定士は、土壌汚染について専門の業者と同じレベルの知識は有していない
ため、土壌汚染地に係る鑑定評価においては、専門の業者が作成したER の活用が重要となる。
また、不動産鑑定の実務面においても、運用指針の策定や研修、さらなる研究・検討が行わ
れているところではあるが、社会経済情勢の変化に対応し得るよう、引き続き不動産鑑定士
が土壌汚染状況の確認範囲等を明確化し鑑定評価に適切に反映するステップについて検討を
深めていく必要がある。あわせて、様々な汚染状況や対策方法に応じた評価を一層客観的に
行うことを求められることが想定され、スティグマについての評価方法や、掘削除去以外の
措置を前提とした鑑定評価の方法についてもさらに検討する必要がある。
5.6 その他の有効利用促進策
5.6.1 信託、ファンド、保険等のリスク軽減策
なお、土壌汚染リスクの適切な移転・軽減を図る方策として、限定責任信託、土壌汚染地
を買い取った上で浄化するファンド、適切な保険料による保険商品等の活用が考えられる
が、土壌汚染の実態を把握するための十分な調査が行われていないことなどから、いずれも
現時点では具体的な提案をし得る検討状況にはない。しかしながら、いずれも重要なツール
であり、今後リスク評価が進み、具体的な方策を検討しうると考えられることから、今後も
引き続き市場における状況を注視しつつ、必要に応じ活用方策を検討する価値がある。
5.6.2 土壌汚染の正確な知識の周知と土地取引の不正防止
欧米と異なり、我が国では、例えば工業用地から住宅地への用途変更が容易であることか
ら、少なくともその機会を捉えた土壌汚染状況の確認を行うことが重要である。また、土壌
汚染の可能性がある土地について、土地取引が行われる場合には、必要な情報が新たな所有
者に十分伝達されない恐れがある。さらに、土壌汚染に関わる不公正な土地取引が散見され
るところである。
ここで、このような用途変更や土地取引に際して、土地所有者、開発業者、建設業者等の
関係者、さらにはこれに関係する行政担当者等が土壌汚染について必要な知識を有していれ
ば、必要に応じて調査その他の対策を講じることが可能となることから、これらの関係者に
対し、同業者の会合や必要に応じた講習等を通じ、土壌汚染についての正確な知識を周知す
るとともに、土地取引に関する不正の防止に努めていくことが必要である。
また、5.4.2で述べたような官民の連携を進めていく前提として、官の側も土壌汚染
について必要な知識をもつことが必要である。そこで、自治体の環境部局のみならず、建築
部局、都市開発部局といった関係部署においても、土壌汚染が土地取引やまちづくり等を行
う際に大きな阻害要因となっている旨を認識した上で、土壌汚染問題に適切な対応ができ、
ひいては民間に対しリーダーリップを発揮出来るよう、自治体内部で一丸となって取り組む
態勢づくりが必要である。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030404/02.pdf
2009年11月19日
ATCセミナー 土壌・地下水汚染の社会的問題の事例
■ATCセミナー 土壌・地下水汚染の社会的問題の事例■
〜豊洲・桃花台・小鳥が丘の事例〜
土壌・地下水汚染問題は、改正土壌汚染対策法の成立をはじめ、岡山市小鳥が丘団地住民の開発業者である両備を相手にした油工場跡地の裁判や、小牧市桃花台の地盤沈下や土壌・地下水汚染についも多くの住民が愛知県や都市再生機構と裁判をしていました。
また、東京都江東区豊洲の埋立地のガス工場跡地の土壌汚染調査における情報公開遅れが問題にされ、採取した調査試料を廃棄しようとする東京都に対し市民が提訴しています。
このように、本年はマイホームの土壌・地下水汚染等の問題で多くの住民が行政や大企業を相手に裁判で戦っている節目となる年ではないでしょうか。
今回はこれらの問題に大変詳しい講師を招きし、今後の土壌・地下水汚染を考える良い機会になると思いますので、奮ってお申込ください。

■開催日時■
平成21年12月18日(金)14時〜17時20分
■プログラム■
講演1:「東京都豊洲地区の土壌汚染」〜実態と問題点〜
講師:日本環境学会 土壌汚染ワーキンググループ長 坂巻 幸雄 氏
講演2:「豊洲の土壌汚染の実態について」
講 師:NPO法人 「市場を考える会」総務・環境問題理事 野末 誠 氏
講演3:「(仮題)桃花台の地盤沈下と土壌・地下水汚染問題について」
講 師:桃花台地盤沈下問題を考える会 代表 丸山 直希 氏
講演4:「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」
講 師:小鳥が丘団地救済協議会 藤原 康 氏 岩野 敏幸 氏
総合質疑応答
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://atcwsr.earthblog.jp/
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html
■受講料■
1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)
■会 場■
おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■定 員■
100名
■申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp
http://www.e-being.jp/work/concierge.htm
詳しくはブログで
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51081846.html

■土壌・地下水汚染の参考リンク■
桃花台新聞
http://toukadai.exblog.jp/i15/
桃花台ニュータウンの軟弱地層及産業廃棄物による沈下問題に関する愛知県知事への公開質問状
http://eritokyo.jp/independent/komaki-col0001.html
桃花台の地盤沈下と土壌汚染
http://atcwsr.earthblog.jp/c2837.html
小鳥が丘団地救済協議会
http://www.geocities.co.jp/kotorigaoka/
ATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
Concept
Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.
As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.
A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.
Osaka ATC Green Eco Plaza
2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City
11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)
Phone: 06-6615-5888 Fax: 06-6615-5890
?施理念
通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。
大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。
大阪ATC?色?保广?
大阪市住之江区南港北2丁目1-10
ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?
??:06-6615-5888 ?真:06-6615-5890
?? ???
?? ????? ?? ? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?????.
??, ?, ??, ???, ??? ?, ??? ?? ?? ??? ??? ????? ???, ??? ?? ??? ???????? ??? ???? ? ?????. ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ATC ?? ?? ??????. ?? ?? ????? ? ?? ??????, ?? ???? ??? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ???????. ?? ATC? ?? 900? ?? ???? ?? ???? ???? ??????, ???? ????? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ?????. ?? ??? ??? ? ????? ???, ??? ?? ???, ????? ?? ??? ?, ??? ??? ?? ? ??? ??? ??? ????? ???? ????. ??? ATC ?? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ?????. ??? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????. ??? ATC ?? ?? ???? ?? ??????????? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ?????? ????? ?? ?????.
??? ATC ?? ?? ???
???? ????? ???? 2?? 1-10
ATC [??? ??? ??????]?ITM? 11? ??
TEL: 06-6615-5888 FAX: 06-6615-5890
〜豊洲・桃花台・小鳥が丘の事例〜
土壌・地下水汚染問題は、改正土壌汚染対策法の成立をはじめ、岡山市小鳥が丘団地住民の開発業者である両備を相手にした油工場跡地の裁判や、小牧市桃花台の地盤沈下や土壌・地下水汚染についも多くの住民が愛知県や都市再生機構と裁判をしていました。
また、東京都江東区豊洲の埋立地のガス工場跡地の土壌汚染調査における情報公開遅れが問題にされ、採取した調査試料を廃棄しようとする東京都に対し市民が提訴しています。
このように、本年はマイホームの土壌・地下水汚染等の問題で多くの住民が行政や大企業を相手に裁判で戦っている節目となる年ではないでしょうか。
今回はこれらの問題に大変詳しい講師を招きし、今後の土壌・地下水汚染を考える良い機会になると思いますので、奮ってお申込ください。

■開催日時■
平成21年12月18日(金)14時〜17時20分
■プログラム■
講演1:「東京都豊洲地区の土壌汚染」〜実態と問題点〜
講師:日本環境学会 土壌汚染ワーキンググループ長 坂巻 幸雄 氏
講演2:「豊洲の土壌汚染の実態について」
講 師:NPO法人 「市場を考える会」総務・環境問題理事 野末 誠 氏
講演3:「(仮題)桃花台の地盤沈下と土壌・地下水汚染問題について」
講 師:桃花台地盤沈下問題を考える会 代表 丸山 直希 氏
講演4:「小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過」
講 師:小鳥が丘団地救済協議会 藤原 康 氏 岩野 敏幸 氏
総合質疑応答
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://atcwsr.earthblog.jp/
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html
■受講料■
1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)
■会 場■
おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトープ・プラザ
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■定 員■
100名
■申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 水・土壌セミナー係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:md@e-being.jp
http://www.e-being.jp/work/concierge.htm
詳しくはブログで
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51081846.html

■土壌・地下水汚染の参考リンク■
桃花台新聞
http://toukadai.exblog.jp/i15/
桃花台ニュータウンの軟弱地層及産業廃棄物による沈下問題に関する愛知県知事への公開質問状
http://eritokyo.jp/independent/komaki-col0001.html
桃花台の地盤沈下と土壌汚染
http://atcwsr.earthblog.jp/c2837.html
小鳥が丘団地救済協議会
http://www.geocities.co.jp/kotorigaoka/
ATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
Concept
Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.
As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.
A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.
Osaka ATC Green Eco Plaza
2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City
11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)
Phone: 06-6615-5888 Fax: 06-6615-5890
?施理念
通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。
大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。
大阪ATC?色?保广?
大阪市住之江区南港北2丁目1-10
ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?
??:06-6615-5888 ?真:06-6615-5890
?? ???
?? ????? ?? ? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?????.
??, ?, ??, ???, ??? ?, ??? ?? ?? ??? ??? ????? ???, ??? ?? ??? ???????? ??? ???? ? ?????. ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ATC ?? ?? ??????. ?? ?? ????? ? ?? ??????, ?? ???? ??? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ???????. ?? ATC? ?? 900? ?? ???? ?? ???? ???? ??????, ???? ????? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ?????. ?? ??? ??? ? ????? ???, ??? ?? ???, ????? ?? ??? ?, ??? ??? ?? ? ??? ??? ??? ????? ???? ????. ??? ATC ?? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ?????. ??? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????. ??? ATC ?? ?? ???? ?? ??????????? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ?????? ????? ?? ?????.
??? ATC ?? ?? ???
???? ????? ???? 2?? 1-10
ATC [??? ??? ??????]?ITM? 11? ??
TEL: 06-6615-5888 FAX: 06-6615-5890
2009年11月19日
汚染土壌処理業の許可の申請の手続について
環水大土発第091104003号
平成2 1 年1 1 月4 日
都道府県・政令市土壌環境保全担当部局長あて
環境省水・大気環境局土壌環境課長
汚染土壌処理業の許可の申請の手続について
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21 年法律第23 号。以下「改正法」とい
う。)により創設された汚染土壌処理業の許可の申請は、改正法附則第2条の規定に基づ
き、改正法の施行の前においても、改正法第22 条第2項の規定の例により行うことがで
きることとされているところ、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定め
る政令(平成21 年政令第245 号)により、附則第2条の規定の施行日は、平成21 年10
月23 日とされたところである。
また、当該手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及
び図面のほか、汚染土壌処理業の許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(以下「省令」という。)を、平成21
年10 月22 日に制定し、公布したところである。
改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「法」という。)の体系的な解説は、後日、
施行通知により示す予定であるが、省令の公布に併せ、申請書記載事項並びに添付書類
及び図面について申請者並びに都道府県及び政令市が参考とすべき事項を下記のとおり
まとめたので、貴職におかれては、これを参照して汚染土壌処理業の許可の申請の手続
に対応されたい。
なお、省令に規定するもののほか、法第4章第2節の規定を実施するために必要な環
境省令及び環境大臣告示については、追って整備することとしており、それまでの間に
申請があった場合は申請書並びに添付書類及び図面に記載される事項のうち当該環境省
令及び環境大臣告示によりその内容が確定する事項については、追加して記載し、又は
添付すれば足りるものとして、取り扱われたい。
記
1 申請書の様式及び記載事項
申請書の様式は、省令の別記に示したとおりであり、その記載事項欄には、以下の内
容を記載させること。
? 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称(省令第3条第1号)
「○○株式会社□□工場」等具体的に記載させること。
? 申請者の事務所の所在地(同)
申請者の事務所は、汚染土壌処理業の許可がされた後は、法第54 条第4項により
都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成14 年政令第336 号)第8条に規定する
市の長を含む。以下同じ。)の立入検査の対象となるため、すべての事務所の所在地
及び連絡先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の設置の場所(法第22 条第2項第2号)
汚染土壌処理施設に係る事業場の所在地及び連絡先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の種類(法第22 条第2項第3号)
省令第1条各号に掲げる種類のいずれかを記載させること。なお、同一の敷地内
において、汚染土壌処理施設を構成する設備のうちに、浄化等、セメント製造、埋
立て及び分別等のうち異なる方法を採用する設備がある場合には、全体として一の
汚染土壌処理施設と解し、申請行為は一回で足りるが、当該採用する方法に応じた
汚染土壌処理施設の種類を記載させること。
さらに浄化等処理施設にあっては、浄化、溶融又は不溶化の別を括弧書で併記さ
せること。
? 汚染土壌処理施設の構造(同)
汚染土壌処理施設の構造を記載させること。構造の例としては、材質、屋根の有
無及び階数が想定されること。
? 汚染土壌処理施設の処理能力(同)
汚染土壌処理施設(埋立処理施設を除く。)の1時間当たりの処理量及び稼働時間
並びにこれらを乗じて得た1日当たりの処理量を記載させること。
埋立処理施設にあっては、埋立地の面積及び埋立容量を記載させること。
? 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(法
第22 条第2項第4号)
汚染土壌処理施設が処理することのできる汚染土壌の特定有害物質の種類を記載
させるとともに、処理することの出来る汚染土壌の濃度の上限値を定めている場合
には当該上限値を記載させること。
? 汚染土壌の処理の方法(省令第3条第3号)
汚染土壌の処理の方法として、熱分解方式、加熱・揮発方式、洗浄方式、化学分
解方式等を記載させること。
また、汚染土壌の処理の一連の作業の手順及び内容を記載させること。ここにい
う「汚染土壌の処理の一連の作業」は、汚染土壌の受入れから、保管、処理までを
意味するが、処理された汚染土壌であっても土壌汚染対策法施行規則(平成14 年環
境省令第29 号)第18 条第1項又は第2項の基準に適合しない場合における当該汚
染土壌を保管する過程までを含むものであること。また、セメント製造施設にあっ
ては、製造されたセメントが製品として出荷するに足りる品質を有することが確認
されるまでの過程を記載させること。
「一連の作業の手順及び内容」は具体的に記載させることを要するが、このうち
「一連の作業の内容」の記載内容の例としては、受入れについては当該受入れを行
う場所、熱分解を行う場合には分解温度及び揮発温度並びに汚染土壌の冷却方法、
洗浄を行う場合には分級、沈殿、ろ過等濃縮の方法や使用する薬剤の種類、化学分
解を行う場合には使用する薬剤の種類や添加の方法等が想定されること。
併せて、浄化等処理施設にあっては、本欄に記載した処理の方法により、?の欄
に記載した汚染土壌を処理することが可能であることを証明する実験の方法及び結
果を記載させること。
? セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法(省令第3条第4号)
以下の内容を記載させること。
イ製造するセメントの製品規格と製造方法
ロ製造するセメントの品質管理の方法
ハ製造されたセメントに含まれる特定有害物質の量の測定方法並びに当該量の上
限値の目安及びその上限の目安の設定根拠
? 保管設備の場所及び容量(省令第3条第5号)
保管設備ごとに場所と容量を記載させること。
なお、保管設備の場所は、省令第2条第2項第2号の添付図面により明らかにさ
せること。
? 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地、再処理汚染土壌処理施設の許可番号、種類及び処理能力(省令第3条第7号)
上記に準じて記載させること。
2 申請書添付書類及び図面
汚染土壌処理業の許可の申請書に添付しなければならない書類及び図面については、
以下によること。
? 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類(省令第2条第2項第1号)
以下の事項を記載させた書類を添付させること。
イ汚染土壌処理施設を稼働させる時間、汚染土壌処理施設の休止日、汚染土壌の
処理の事業を行うための組織及び当該事業に従事する従業員数
ロ汚染土壌処理施設の維持管理(省令第5条第22 号の点検及び機能検査を含む。)
の体制及び計画
? 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設
計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明
らかにする書類及び図面(省令第2条第2項第3号)
汚染土壌処理施設を構成する設備について、当該設備ごとに、平面図、立面図、
断面図、構造図及び設計計算書を添付させること。
なお、設計計算書は、汚染土壌処理施設が、自重、積載荷重その他の加重、地震
及び温度変化に対して構造耐力上安全であることを証明するに足りる内容を備える
必要があること。
? 汚染土壌の処理工程図(省令第2条第2項第4号)
汚染土壌の処理の一連の作業の手順をフロー図により示させること。ここにいう
「汚染土壌の処理の一連の作業」とは、1?に準ずること。
? 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、
当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類(省令第2条第5号)
汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地の登記事項証明書及び公図の写しを添付さ
せること。所有権を有しない場合には、当該敷地について申請者のために賃借権が
設定されたことを証する書類及び公図の写しを添付させること。
? 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(省令第2条第2項第7号)
以下の書類を添付させること。
イ汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有
する者(省令第4条第2号イ)の氏名及び役職並びに当該者が当該業務を統括管
理する権限を有することを確認することのできる管理体制系統図
ロ汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及
び技能を有する者(省令第4条第2号ロ)に係る次の書類
(1) 汚染土壌処理施設に配置されていることを確認することのできる書類
(2) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について3年以上の実務経験を有す
ることを証明する書類
(3) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有することを証明
する書類として次に掲げる書類
(イ) 大気の汚染に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類と
して次に掲げる書類のうちいずれかの書類
(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・大気管理)
に合格したことを証する証書(技術士法施行規則(昭和59 年総理府令第25
号)様式第4)の写し
(?) 大気関係第一種公害防止管理者試験又は大気関係第二種公害防止管理
者試験の合格証書(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施
行規則(昭和46 年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第3号)
様式第5)の写し
(?) 大気関係第一種公害防止管理者又は大気関係第二種公害防止管理者の
資格を得るための講習の修了証書(特定工場における公害防止組織の整備
に関する法律施行規則様式第7)の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46 年法律第
107 号)第8条の2第1項の指定試験機関(平成21 年10 月29 日現在、社
団法人産業環境管理協会)が発行する公害防止管理者等国家試験試験結果
通知書の写し(大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の
科目に合格していることが確認できるものであること)
(?) 省令第4条第2号ロ(イ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ロ) 水質の汚濁に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類とし
て次に掲げる書類のうちいずれかの書類
(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・水質管理)に
合格したことを証する証書の写し
(?) 水質関係第一種公害防止管理者試験又は水質関係第二種公害防止管理者
試験の合格証書の写し
(?) 水質関係第一種公害防止管理者又は水質関係第二種公害防止管理者の資
格を得るための講習の修了証書の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(水質概論及び水質
有害物質特論の科目に合格していることが確認できるものであること)
(?) 省令第4条第2号ロ(ロ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平
成11 年法律第105 号)第2条第1項のダイオキシン類をいう。)を生ずる可能
性のある汚染土壌処理施設にあっては、次のいずれかの書類
(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者試験の合格証書の写し
(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者の資格を得るための講習の修了証書の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(ダイオキシン類概
論及びダイオキシン類特論の科目に合格していることが確認できるものであ
ること)
? 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載
した書類(省令第2条第2項第8号)
汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額については、当該事業の開始及
び継続に必要となる一切の資金の総額を記載させること。具体的には、資本金の額
のほか、当該事業の用に供する汚染土壌処理施設の整備に要する費用、損害賠償保
険の保険料の額等が想定される。
汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の調達方法については、資本金の調達
方法、借入先、借入残高、年間返済額、返済期限、利率等資金の調達に関する一切
の事項を記載させること。利益をもって資金に充てるものについては、その見込額
を記載させること。
? 申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
る書面(省令第2条第2項第13 号)
申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
るため、その旨の誓約書を作成させ、申請者の氏名又は名称及び住所並びに申請者
が法人である場合にはその代表者の氏名を記名し、押印させた上で、添付させるこ
と。なお、申請者が法人である場合には、法第22 条第3項第2号ハのその事業を行
う役員についても、同旨の誓約書を作成し、添付させること。これらの誓約書を作
成する場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
? 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに
汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排
出水に係る用水の系統を説明する書類(省令第2条第2項第15 号)
汚水の処理の方法を示したフロー図及び設置する汚水の処理設備の構造及び能力
を記載した書類並びに排出水に係る用水及び排出水の経路図を添付させること。
? 排水口における排出水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第16号)
排出水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第17 号)
地下水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透
を防止する方法を記載した書類(省令第2条第2項第18 号)
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散等及び地下への浸透を防止するための当該汚染土壌処理施設の
構造並びにそのために設けられた設備の構造及び能力を記載させること。
また、汚染土壌の搬入及び搬出時以外の閉扉等施設管理により当該防止を図る場
合には、当該施設管理の方法を記載した書類を添付させること。
さらに、地下浸透防止措置(省令第4条第1号リ)が講じられている汚染土壌処
理施設にあっては、当該地下浸透防止措置が同号リの環境大臣が定める措置に該当
することを証明する書類を添付させること。
? 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、
排出口から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有
害物質の量の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第19 号)
発生してから排出口から大気中に排出されるまでの大気有害物質の排出経路、大
気有害物質の処理設備の構造、能力及び設置場所、大気有害物質の処理フロー図、
大気中に排出される大気有害物質の量の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及
び時間を記載した書類を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 法第27 条第1項に規定する措置(以下「廃止措置」という。)に要する費用の見
積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面(省令
第2条第2項第20 号)
法第27 条第1項の環境省令で定める廃止措置の内容に応じ、それぞれの廃止措置
に要する費用の見積額及びその算定根拠並びに当該見積額の総計の額の調達方法及
び当該調達方法が実現可能性のあるものであることを説明する書類を添付させること。
この記載に当たっては、?に準じてできる限り詳細に記載させること。
? 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者
がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況
の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項
又は第2項の基準に適合しないときの法第14 条第1項の申請を行うことについての
当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
(省令第2条第2項21 号)
廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷
地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項又は第2項の基準に適
合しないときは、汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地にいる申請者以外の所有者、
管理者又は占有者が法第14 条第1項の申請を行うことについて同意する旨の書類の
写しを添付させること。当該書類には、当該所有者、管理者又は占有者に記名し、
押印させること。この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
? 再処理汚染土壌処理施設について法第22 条第1項の許可を受けた者の当該処理を
受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書
類(省令第2条第2項22 号)
当該処理を受託することについての再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌処理
業者の同意書及び当該再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌の処理の事業の許可
証の写しを添付させること。当該同意書には、当該者に記名し、押印させること。
この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
なお、平成22 年3月31 日までに汚染土壌処理業の許可の申請をする場合には、
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受けることはないことから、再処理汚染土壌
処理施設に処理を委託することはないものとして、当該許可の申請を行わせ、当該
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受け次第、その旨の変更の届出(法第23 条第
3項)をさせること。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
平成2 1 年1 1 月4 日
都道府県・政令市土壌環境保全担当部局長あて
環境省水・大気環境局土壌環境課長
汚染土壌処理業の許可の申請の手続について
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21 年法律第23 号。以下「改正法」とい
う。)により創設された汚染土壌処理業の許可の申請は、改正法附則第2条の規定に基づ
き、改正法の施行の前においても、改正法第22 条第2項の規定の例により行うことがで
きることとされているところ、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定め
る政令(平成21 年政令第245 号)により、附則第2条の規定の施行日は、平成21 年10
月23 日とされたところである。
また、当該手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及
び図面のほか、汚染土壌処理業の許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(以下「省令」という。)を、平成21
年10 月22 日に制定し、公布したところである。
改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「法」という。)の体系的な解説は、後日、
施行通知により示す予定であるが、省令の公布に併せ、申請書記載事項並びに添付書類
及び図面について申請者並びに都道府県及び政令市が参考とすべき事項を下記のとおり
まとめたので、貴職におかれては、これを参照して汚染土壌処理業の許可の申請の手続
に対応されたい。
なお、省令に規定するもののほか、法第4章第2節の規定を実施するために必要な環
境省令及び環境大臣告示については、追って整備することとしており、それまでの間に
申請があった場合は申請書並びに添付書類及び図面に記載される事項のうち当該環境省
令及び環境大臣告示によりその内容が確定する事項については、追加して記載し、又は
添付すれば足りるものとして、取り扱われたい。
記
1 申請書の様式及び記載事項
申請書の様式は、省令の別記に示したとおりであり、その記載事項欄には、以下の内
容を記載させること。
? 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称(省令第3条第1号)
「○○株式会社□□工場」等具体的に記載させること。
? 申請者の事務所の所在地(同)
申請者の事務所は、汚染土壌処理業の許可がされた後は、法第54 条第4項により
都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成14 年政令第336 号)第8条に規定する
市の長を含む。以下同じ。)の立入検査の対象となるため、すべての事務所の所在地
及び連絡先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の設置の場所(法第22 条第2項第2号)
汚染土壌処理施設に係る事業場の所在地及び連絡先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の種類(法第22 条第2項第3号)
省令第1条各号に掲げる種類のいずれかを記載させること。なお、同一の敷地内
において、汚染土壌処理施設を構成する設備のうちに、浄化等、セメント製造、埋
立て及び分別等のうち異なる方法を採用する設備がある場合には、全体として一の
汚染土壌処理施設と解し、申請行為は一回で足りるが、当該採用する方法に応じた
汚染土壌処理施設の種類を記載させること。
さらに浄化等処理施設にあっては、浄化、溶融又は不溶化の別を括弧書で併記さ
せること。
? 汚染土壌処理施設の構造(同)
汚染土壌処理施設の構造を記載させること。構造の例としては、材質、屋根の有
無及び階数が想定されること。
? 汚染土壌処理施設の処理能力(同)
汚染土壌処理施設(埋立処理施設を除く。)の1時間当たりの処理量及び稼働時間
並びにこれらを乗じて得た1日当たりの処理量を記載させること。
埋立処理施設にあっては、埋立地の面積及び埋立容量を記載させること。
? 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(法
第22 条第2項第4号)
汚染土壌処理施設が処理することのできる汚染土壌の特定有害物質の種類を記載
させるとともに、処理することの出来る汚染土壌の濃度の上限値を定めている場合
には当該上限値を記載させること。
? 汚染土壌の処理の方法(省令第3条第3号)
汚染土壌の処理の方法として、熱分解方式、加熱・揮発方式、洗浄方式、化学分
解方式等を記載させること。
また、汚染土壌の処理の一連の作業の手順及び内容を記載させること。ここにい
う「汚染土壌の処理の一連の作業」は、汚染土壌の受入れから、保管、処理までを
意味するが、処理された汚染土壌であっても土壌汚染対策法施行規則(平成14 年環
境省令第29 号)第18 条第1項又は第2項の基準に適合しない場合における当該汚
染土壌を保管する過程までを含むものであること。また、セメント製造施設にあっ
ては、製造されたセメントが製品として出荷するに足りる品質を有することが確認
されるまでの過程を記載させること。
「一連の作業の手順及び内容」は具体的に記載させることを要するが、このうち
「一連の作業の内容」の記載内容の例としては、受入れについては当該受入れを行
う場所、熱分解を行う場合には分解温度及び揮発温度並びに汚染土壌の冷却方法、
洗浄を行う場合には分級、沈殿、ろ過等濃縮の方法や使用する薬剤の種類、化学分
解を行う場合には使用する薬剤の種類や添加の方法等が想定されること。
併せて、浄化等処理施設にあっては、本欄に記載した処理の方法により、?の欄
に記載した汚染土壌を処理することが可能であることを証明する実験の方法及び結
果を記載させること。
? セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法(省令第3条第4号)
以下の内容を記載させること。
イ製造するセメントの製品規格と製造方法
ロ製造するセメントの品質管理の方法
ハ製造されたセメントに含まれる特定有害物質の量の測定方法並びに当該量の上
限値の目安及びその上限の目安の設定根拠
? 保管設備の場所及び容量(省令第3条第5号)
保管設備ごとに場所と容量を記載させること。
なお、保管設備の場所は、省令第2条第2項第2号の添付図面により明らかにさ
せること。
? 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地、再処理汚染土壌処理施設の許可番号、種類及び処理能力(省令第3条第7号)
上記に準じて記載させること。
2 申請書添付書類及び図面
汚染土壌処理業の許可の申請書に添付しなければならない書類及び図面については、
以下によること。
? 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類(省令第2条第2項第1号)
以下の事項を記載させた書類を添付させること。
イ汚染土壌処理施設を稼働させる時間、汚染土壌処理施設の休止日、汚染土壌の
処理の事業を行うための組織及び当該事業に従事する従業員数
ロ汚染土壌処理施設の維持管理(省令第5条第22 号の点検及び機能検査を含む。)
の体制及び計画
? 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設
計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明
らかにする書類及び図面(省令第2条第2項第3号)
汚染土壌処理施設を構成する設備について、当該設備ごとに、平面図、立面図、
断面図、構造図及び設計計算書を添付させること。
なお、設計計算書は、汚染土壌処理施設が、自重、積載荷重その他の加重、地震
及び温度変化に対して構造耐力上安全であることを証明するに足りる内容を備える
必要があること。
? 汚染土壌の処理工程図(省令第2条第2項第4号)
汚染土壌の処理の一連の作業の手順をフロー図により示させること。ここにいう
「汚染土壌の処理の一連の作業」とは、1?に準ずること。
? 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、
当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類(省令第2条第5号)
汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地の登記事項証明書及び公図の写しを添付さ
せること。所有権を有しない場合には、当該敷地について申請者のために賃借権が
設定されたことを証する書類及び公図の写しを添付させること。
? 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(省令第2条第2項第7号)
以下の書類を添付させること。
イ汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有
する者(省令第4条第2号イ)の氏名及び役職並びに当該者が当該業務を統括管
理する権限を有することを確認することのできる管理体制系統図
ロ汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及
び技能を有する者(省令第4条第2号ロ)に係る次の書類
(1) 汚染土壌処理施設に配置されていることを確認することのできる書類
(2) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について3年以上の実務経験を有す
ることを証明する書類
(3) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有することを証明
する書類として次に掲げる書類
(イ) 大気の汚染に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類と
して次に掲げる書類のうちいずれかの書類
(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・大気管理)
に合格したことを証する証書(技術士法施行規則(昭和59 年総理府令第25
号)様式第4)の写し
(?) 大気関係第一種公害防止管理者試験又は大気関係第二種公害防止管理
者試験の合格証書(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施
行規則(昭和46 年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第3号)
様式第5)の写し
(?) 大気関係第一種公害防止管理者又は大気関係第二種公害防止管理者の
資格を得るための講習の修了証書(特定工場における公害防止組織の整備
に関する法律施行規則様式第7)の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46 年法律第
107 号)第8条の2第1項の指定試験機関(平成21 年10 月29 日現在、社
団法人産業環境管理協会)が発行する公害防止管理者等国家試験試験結果
通知書の写し(大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の
科目に合格していることが確認できるものであること)
(?) 省令第4条第2号ロ(イ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ロ) 水質の汚濁に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類とし
て次に掲げる書類のうちいずれかの書類
(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・水質管理)に
合格したことを証する証書の写し
(?) 水質関係第一種公害防止管理者試験又は水質関係第二種公害防止管理者
試験の合格証書の写し
(?) 水質関係第一種公害防止管理者又は水質関係第二種公害防止管理者の資
格を得るための講習の修了証書の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(水質概論及び水質
有害物質特論の科目に合格していることが確認できるものであること)
(?) 省令第4条第2号ロ(ロ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平
成11 年法律第105 号)第2条第1項のダイオキシン類をいう。)を生ずる可能
性のある汚染土壌処理施設にあっては、次のいずれかの書類
(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者試験の合格証書の写し
(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者の資格を得るための講習の修了証書の写し
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(ダイオキシン類概
論及びダイオキシン類特論の科目に合格していることが確認できるものであ
ること)
? 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載
した書類(省令第2条第2項第8号)
汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額については、当該事業の開始及
び継続に必要となる一切の資金の総額を記載させること。具体的には、資本金の額
のほか、当該事業の用に供する汚染土壌処理施設の整備に要する費用、損害賠償保
険の保険料の額等が想定される。
汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の調達方法については、資本金の調達
方法、借入先、借入残高、年間返済額、返済期限、利率等資金の調達に関する一切
の事項を記載させること。利益をもって資金に充てるものについては、その見込額
を記載させること。
? 申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
る書面(省令第2条第2項第13 号)
申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
るため、その旨の誓約書を作成させ、申請者の氏名又は名称及び住所並びに申請者
が法人である場合にはその代表者の氏名を記名し、押印させた上で、添付させるこ
と。なお、申請者が法人である場合には、法第22 条第3項第2号ハのその事業を行
う役員についても、同旨の誓約書を作成し、添付させること。これらの誓約書を作
成する場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
? 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに
汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排
出水に係る用水の系統を説明する書類(省令第2条第2項第15 号)
汚水の処理の方法を示したフロー図及び設置する汚水の処理設備の構造及び能力
を記載した書類並びに排出水に係る用水及び排出水の経路図を添付させること。
? 排水口における排出水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第16号)
排出水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第17 号)
地下水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透
を防止する方法を記載した書類(省令第2条第2項第18 号)
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散等及び地下への浸透を防止するための当該汚染土壌処理施設の
構造並びにそのために設けられた設備の構造及び能力を記載させること。
また、汚染土壌の搬入及び搬出時以外の閉扉等施設管理により当該防止を図る場
合には、当該施設管理の方法を記載した書類を添付させること。
さらに、地下浸透防止措置(省令第4条第1号リ)が講じられている汚染土壌処
理施設にあっては、当該地下浸透防止措置が同号リの環境大臣が定める措置に該当
することを証明する書類を添付させること。
? 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、
排出口から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有
害物質の量の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第19 号)
発生してから排出口から大気中に排出されるまでの大気有害物質の排出経路、大
気有害物質の処理設備の構造、能力及び設置場所、大気有害物質の処理フロー図、
大気中に排出される大気有害物質の量の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及
び時間を記載した書類を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。
? 法第27 条第1項に規定する措置(以下「廃止措置」という。)に要する費用の見
積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面(省令
第2条第2項第20 号)
法第27 条第1項の環境省令で定める廃止措置の内容に応じ、それぞれの廃止措置
に要する費用の見積額及びその算定根拠並びに当該見積額の総計の額の調達方法及
び当該調達方法が実現可能性のあるものであることを説明する書類を添付させること。
この記載に当たっては、?に準じてできる限り詳細に記載させること。
? 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者
がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況
の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項
又は第2項の基準に適合しないときの法第14 条第1項の申請を行うことについての
当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
(省令第2条第2項21 号)
廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷
地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項又は第2項の基準に適
合しないときは、汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地にいる申請者以外の所有者、
管理者又は占有者が法第14 条第1項の申請を行うことについて同意する旨の書類の
写しを添付させること。当該書類には、当該所有者、管理者又は占有者に記名し、
押印させること。この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
? 再処理汚染土壌処理施設について法第22 条第1項の許可を受けた者の当該処理を
受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書
類(省令第2条第2項22 号)
当該処理を受託することについての再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌処理
業者の同意書及び当該再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌の処理の事業の許可
証の写しを添付させること。当該同意書には、当該者に記名し、押印させること。
この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
なお、平成22 年3月31 日までに汚染土壌処理業の許可の申請をする場合には、
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受けることはないことから、再処理汚染土壌
処理施設に処理を委託することはないものとして、当該許可の申請を行わせ、当該
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受け次第、その旨の変更の届出(法第23 条第
3項)をさせること。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
2009年11月19日
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令
(平成二十一年十月二十二日環境省令第十号)
(汚染土壌処理施設の種類)
第一条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 浄化等処理施設 汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号。以下「規則」という。)第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二 セメント製造施設 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三 埋立処理施設 汚染土壌の埋立てを行うための施設
四 分別等処理施設 汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設
(汚染土壌処理業の許可の申請)
第二条 法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 汚染土壌の処理工程図
五 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六 埋立処理施設にあっては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う場合における当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
七 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
九 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十三 申請者が法第二十二条第三項第二号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
十四 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十五 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十六 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第四条第一号ト、第五条第十三号において同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。第四条第一号チ及び第五条第十四号において同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十七 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類
十八 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
十九 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(次条第二号において「令」という。)第一条第七号、第十一号、第十二号、第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロ(2)(ハ)において同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十 法第二十七条第一項に規定する措置(次号及び第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面
二十一 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しないときの法第十四条第一項の申請を行うことについての当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
二十二 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合における当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該処理を受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書類
3 法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第七号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。
第三条 法第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
二 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
三 汚染土壌の処理の方法
四 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
五 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
六 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の氏名及び住所
七 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
イ 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
(汚染土壌処理業の許可の基準)
第四条 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に関する基準
イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体、汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
ト 排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第十三号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
(イ) 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(ロ) ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(2) ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備
チ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における排出水の水質を下水道法施行令 第九条の四第一項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第十二条の二第三項の規定により同令第九条の五第一項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第十四号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
(2) 下水道法施行令第九条の四第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第十四号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備
リ 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第十五号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヌ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっ ては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、(6)に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
(1) カドミウム及びその化合物 一・〇ミリグラム
(2) 塩素 三十ミリグラム
(3) 塩化水素 七百ミリグラム
(4) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 十ミリグラム
(5) 鉛及びその化合物 二十ミリグラム
(6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
二 申請者の能力に関する基準
イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
(1) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者
(2) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止 するための知識を有する者として次に掲げる者
(イ) 大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(?) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者
(?) (?)から(?)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ロ) 水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(?) 技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
(?) (?)から(?)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
(汚染土壌の処理に関する基準)
第五条 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
三 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
四 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第五条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第十八条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第二十四条第一項第一号に規定する第二溶出量基準をいう。第八号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
五 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
六 浄化等処理施設にあっては、申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
七 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
八 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。
九 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
十 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
十一 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十二 汚水を地下に浸透させてはならないこと。
十三 排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第一号ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
十四 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
十五 汚染土壌処理施設が設置されている場所にある地下水の下流側の当該汚染土壌処理施設の周縁において、三月に一回以上地下水を採取し、当該地下水の水質を規則第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第六条第一項に規定する地下水基準をいう。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
十六 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ 前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が、排出口において、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超える大気有害物質を排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、大気有害物質(前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質を除く。)の量を一年に一回以上、同号ヌの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
十七 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、法第十六条第一項の環境省令で定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合しているものを搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
十八 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
十九 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者にあっては、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、当該処理を終了したときは、法第二十条第四項の規定の例により、当該処理を委託した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
二十 前号の処理を委託した汚染土壌処理業者にあっては、同号の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者にその写しを送付しなければならないこと。
二十一 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二十二 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
二十三 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第三条 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
2 改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
(平成二十一年十月二十二日環境省令第十号)
(汚染土壌処理施設の種類)
第一条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 浄化等処理施設 汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号。以下「規則」という。)第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二 セメント製造施設 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三 埋立処理施設 汚染土壌の埋立てを行うための施設
四 分別等処理施設 汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設
(汚染土壌処理業の許可の申請)
第二条 法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、別記様式のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 汚染土壌の処理工程図
五 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六 埋立処理施設にあっては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う場合における当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
七 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
九 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十三 申請者が法第二十二条第三項第二号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
十四 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十五 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十六 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第四条第一号ト、第五条第十三号において同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。第四条第一号チ及び第五条第十四号において同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十七 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類
十八 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
十九 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(次条第二号において「令」という。)第一条第七号、第十一号、第十二号、第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロ(2)(ハ)において同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十 法第二十七条第一項に規定する措置(次号及び第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面
二十一 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しないときの法第十四条第一項の申請を行うことについての当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類
二十二 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合における当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該処理を受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書類
3 法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第七号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。
第三条 法第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
二 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
三 汚染土壌の処理の方法
四 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
五 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
六 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の氏名及び住所
七 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
イ 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
(汚染土壌処理業の許可の基準)
第四条 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に関する基準
イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体、汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
ト 排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第十三号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
(イ) 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(ロ) ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第二の下欄に掲げる許容限度(ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(2) ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定するための設備
チ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における排出水の水質を下水道法施行令 第九条の四第一項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第十二条の二第三項の規定により同令第九条の五第一項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。次条第十四号イにおいて「排除基準」という。)に適合させるために必要な処理設備
(2) 下水道法施行令第九条の四第二項の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第十四号ロにおいて「下水道測定方法」という。)により排出水の水質を測定するための設備
リ 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第十五号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヌ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっ ては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、(6)に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
(1) カドミウム及びその化合物 一・〇ミリグラム
(2) 塩素 三十ミリグラム
(3) 塩化水素 七百ミリグラム
(4) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 十ミリグラム
(5) 鉛及びその化合物 二十ミリグラム
(6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
二 申請者の能力に関する基準
イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
(1) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について三年以上の実務経験を有する者
(2) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止 するための知識を有する者として次に掲げる者
(イ) 大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(?) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として大気管理を選択した者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)別表第二の一の項の下欄に規定する大気関係第一種有資格者又は同表の二の項の下欄に規定する大気関係第二種有資格者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)別表第三に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者
(?) (?)から(?)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ロ) 水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(?) 技術士法による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の五の項の下欄に規定する水質関係第一種有資格者又は同表の六の項の下欄に規定する水質関係第二種有資格者に限る。)
(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
(?) (?)から(?)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する公害防止管理者の資格を有する者(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第二の十二の項の下欄に規定する者に限る。)又は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第三に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
(汚染土壌の処理に関する基準)
第五条 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
三 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
四 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第五条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。)以外の規則第十八条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第二十四条第一項第一号に規定する第二溶出量基準をいう。第八号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
五 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
六 浄化等処理施設にあっては、申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
七 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
八 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。
九 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
十 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
十一 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十二 汚水を地下に浸透させてはならないこと。
十三 排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第一号ト(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
十四 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
十五 汚染土壌処理施設が設置されている場所にある地下水の下流側の当該汚染土壌処理施設の周縁において、三月に一回以上地下水を採取し、当該地下水の水質を規則第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第六条第一項に規定する地下水基準をいう。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
十六 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ 前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が、排出口において、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超える大気有害物質を排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、大気有害物質(前条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質を除く。)の量を一年に一回以上、同号ヌの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
十七 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、法第十六条第一項の環境省令で定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第十八条第一項及び第二項の基準に適合しているものを搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
十八 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
十九 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者にあっては、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、当該処理を終了したときは、法第二十条第四項の規定の例により、当該処理を委託した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
二十 前号の処理を委託した汚染土壌処理業者にあっては、同号の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者にその写しを送付しなければならないこと。
二十一 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二十二 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
二十三 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第三条 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
2 改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
2009年11月19日
改正後の土壌汚染対策法
土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域(第六条―第十条)
第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
第三節 雑則(第十四条・第十五条)
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りではない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域
(要措置区域の指定等)
第六条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(汚染の除去等の措置)
第七条 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもの(以下「指示措置等」という。)を講じなければならない。
4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公示しなければならない。
6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。
ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(適用除外)
第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
第二節 形質変更時要届出区域
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(適用除外)
第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第三節 雑則
(指定の申請)
第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(台帳)
第十五条 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(運搬に関する基準)
第十七条 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(措置命令)
第十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(管理票)
第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。
3 汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第二節 汚染土壌処理業
(汚染土壌処理業)
第二十二条 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 汚染土壌処理施設の設置の場所
三 汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
四 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
五 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 法人であって、その事業を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
4 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
6 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
7 汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。
8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
9 汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の許可等)
第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前条第三項の規定は、前項の許可について準用する。
3 汚染土壌処理業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(改善命令)
第二十四条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第二十二条第六項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第二十五条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十二条第三項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。
二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。
(名義貸しの禁止)
第二十六条 汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。
(許可の取消し等の場合の措置義務)
第二十七条 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第二十五条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(環境省令への委任)
第二十八条 この節に定めるもののほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第五章 指定調査機関
(指定の申請)
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三十二条 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
第三十三条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの(次条において「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第三十七条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第四十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第三条第一項の指定をしたとき。
二 第三十二条第一項の規定により第三条第一項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。
三 第三十五条(同条の環境省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は第四十条の規定による届出を受けたとき。
第六章 指定支援法人
(指定)
第四十四条 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、支援業務を行う者として指定することができる。
2 前項の指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(業務)
第四十五条 指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 要措置区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
二 次に掲げる事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
イ 土壌汚染状況調査
ロ 要措置区域等内の土地における汚染の除去等の措置
ハ 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更
三 前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行う
(基金)
第四十六条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(次条において単に「基金」という。)を設け、同条の規定により交付を受けた補助金と支援業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
(基金への補助金)
第四十七条 政府は、予算の範囲内において、指定支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
(事業計画等)
第四十八条 指定支援法人は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援法人は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第四十九条 指定支援法人は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(秘密保持義務)
第五十条 指定支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十五条第一号若しくは第二号に掲げる業務又は同条第四号に掲げる業務(同条第一号又は第二号に掲げる業務に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監督命令)
第五十一条 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第五十二条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。
一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 不正の手段により第四十四条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第五十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第四十四条第一項の指定をしたとき。
二 第四十四条第二項の規定による届出を受けたとき。
三 前条の規定により第四十四条第一項の指定を取り消したとき。
第七章 雑則
(報告及び検査)
第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第五十六条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第五十七条 環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第三条第一項ただし書の確認に関する事務
二 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条第二項の命令に関する事務
三 第三条第五項の確認の取消しに関する事務
四 第五条第二項の調査に関する事務
五 第六条第一項の指定に関する事務
六 第六条第二項の公示に関する事務
七 第六条第四項の指定の解除に関する事務
八 第七条第一項の指示に関する事務
九 第七条第五項の指示措置に関する事務
十 前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
(経過措置)
第六十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第六十三条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 第三条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十条から第十二条まで及び第十五条の規定の例により行うことができる。
2 第二十条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第三条 第三条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第三条 新法第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過する日以後に土地の形質の変更(同項に規定する土地の形質の変更をいう。附則第八条において同じ。)に着手する者について適用する。
(指定区域の指定に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている土地の区域は、新法第十一条第一項の規定により指定された同条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなす。
(指定区域台帳に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する旧法第六条第一項の規定による指定区域の台帳は、新法第十五条第一項の規定による形質変更時要届出区域の台帳とみなす。
(措置命令に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした旧法第七条第一項又は第二項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による命令を受けた者に係る旧法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第八条 施行日以後の日に附則第四条の規定により新法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧法第九条第一項の規定による届出をした者は、新法第十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)
第九条 新法第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。
(指定調査機関の指定に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
(変更の届出に関する経過措置)
第十一条 新法第三十五条の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする指定調査機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。
(適合命令に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前に旧法第十六条の規定によりした命令は、新法第三十九条の規定によりした命令とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域(第六条―第十条)
第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
第三節 雑則(第十四条・第十五条)
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りではない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域
(要措置区域の指定等)
第六条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(汚染の除去等の措置)
第七条 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもの(以下「指示措置等」という。)を講じなければならない。
4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公示しなければならない。
6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。
ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(適用除外)
第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
第二節 形質変更時要届出区域
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(適用除外)
第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第三節 雑則
(指定の申請)
第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(台帳)
第十五条 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(運搬に関する基準)
第十七条 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(措置命令)
第十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(管理票)
第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。
3 汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第二節 汚染土壌処理業
(汚染土壌処理業)
第二十二条 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 汚染土壌処理施設の設置の場所
三 汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
四 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
五 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 法人であって、その事業を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
4 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
6 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
7 汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。
8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
9 汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の許可等)
第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前条第三項の規定は、前項の許可について準用する。
3 汚染土壌処理業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(改善命令)
第二十四条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第二十二条第六項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第二十五条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十二条第三項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。
二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。
(名義貸しの禁止)
第二十六条 汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。
(許可の取消し等の場合の措置義務)
第二十七条 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第二十五条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(環境省令への委任)
第二十八条 この節に定めるもののほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第五章 指定調査機関
(指定の申請)
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三十二条 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
第三十三条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの(次条において「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第三十七条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第四十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第三条第一項の指定をしたとき。
二 第三十二条第一項の規定により第三条第一項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。
三 第三十五条(同条の環境省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は第四十条の規定による届出を受けたとき。
第六章 指定支援法人
(指定)
第四十四条 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、支援業務を行う者として指定することができる。
2 前項の指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(業務)
第四十五条 指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 要措置区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
二 次に掲げる事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
イ 土壌汚染状況調査
ロ 要措置区域等内の土地における汚染の除去等の措置
ハ 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更
三 前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行う
(基金)
第四十六条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(次条において単に「基金」という。)を設け、同条の規定により交付を受けた補助金と支援業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
(基金への補助金)
第四十七条 政府は、予算の範囲内において、指定支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
(事業計画等)
第四十八条 指定支援法人は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援法人は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第四十九条 指定支援法人は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(秘密保持義務)
第五十条 指定支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十五条第一号若しくは第二号に掲げる業務又は同条第四号に掲げる業務(同条第一号又は第二号に掲げる業務に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監督命令)
第五十一条 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第五十二条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。
一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 不正の手段により第四十四条第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第五十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第四十四条第一項の指定をしたとき。
二 第四十四条第二項の規定による届出を受けたとき。
三 前条の規定により第四十四条第一項の指定を取り消したとき。
第七章 雑則
(報告及び検査)
第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第五十六条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第五十七条 環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第三条第一項ただし書の確認に関する事務
二 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条第二項の命令に関する事務
三 第三条第五項の確認の取消しに関する事務
四 第五条第二項の調査に関する事務
五 第六条第一項の指定に関する事務
六 第六条第二項の公示に関する事務
七 第六条第四項の指定の解除に関する事務
八 第七条第一項の指示に関する事務
九 第七条第五項の指示措置に関する事務
十 前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
(経過措置)
第六十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第六十三条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 第三条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十条から第十二条まで及び第十五条の規定の例により行うことができる。
2 第二十条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第三条 第三条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第三条 新法第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過する日以後に土地の形質の変更(同項に規定する土地の形質の変更をいう。附則第八条において同じ。)に着手する者について適用する。
(指定区域の指定に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている土地の区域は、新法第十一条第一項の規定により指定された同条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなす。
(指定区域台帳に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する旧法第六条第一項の規定による指定区域の台帳は、新法第十五条第一項の規定による形質変更時要届出区域の台帳とみなす。
(措置命令に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした旧法第七条第一項又は第二項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による命令を受けた者に係る旧法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第八条 施行日以後の日に附則第四条の規定により新法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧法第九条第一項の規定による届出をした者は、新法第十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)
第九条 新法第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。
(指定調査機関の指定に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
(変更の届出に関する経過措置)
第十一条 新法第三十五条の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする指定調査機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。
(適合命令に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前に旧法第十六条の規定によりした命令は、新法第三十九条の規定によりした命令とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
2009年11月19日
改正土壌汚染対策法の解説
改正土壌汚染対策法の解説
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(第171回国会内閣提出第59号)については、衆議院においてその一部が修正された上で、4月17日、参議院において可決され、成立したところであり、4月24日、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)として公布され、平成22年4月1日に施行の予定である(平成21年政令第245号)。
本稿では、法案提出の契機となった土壌汚染対策の現状と課題について触れた上で、本法による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)について説明する。
なお、新法の条文、新旧対照表等は、環境省ホームページ* に掲載されているので、御参照いただきたい。
1 現状と課題
昨年12月、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、「今後の土壌汚染対策の在り方について」の答申がなされ、この中で、土壌汚染対策の現状と課題として、
? 法に基づかない自主的な調査による土壌汚染の発見が増加しており、このような土壌汚染地については、情報が開示され、適切かつ確実に管理・対策を進めることが必要
? 最近の土壌汚染対策としては、健康被害のおそれの有無にかかわらず掘削除去が選択されることが多いが、掘削除去は汚染の拡散のリスクを伴うものであることから、汚染の程度等に応じて必要な対策の基準を明確化し、指定区域を健康被害のおそれの有無に応じて分類することが必要
? 汚染土壌の不適正処理の事例が発見されており、汚染土壌の適正処理の確保が必要
との指摘を受けたところである。
環境省は、これを踏まえて土壌汚染対策法を改正することとし、そのための法案を国会に提出した。
2 新法の概要
以下、新法について、主要な条項を解説する。条項については、特に断りがない限り、新法の条項である。
(1)土壌汚染状況調査
? 第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法の変更時の届出義務
第3条第1項ただし書の確認の制度は、土地の利用の方法からみて健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けた場合に同項の土壌汚染状況調査・報告義務を免れることとするものである。しかしながら、当該確認を受けた土地の利用の方法が変更されることにより、当該土地の所有者や従業員以外の者が立ち入ることが可能となり、健康被害が生じるおそれがある場合もあり得る。
このため、当該確認を受けた土地の所有者等に対し、当該土地の利用の方法を変更する前に、変更後の土地の利用の方法を届け出させるとともに(第3条第4項)、都道府県知事は、変更後の土地の利用の方法からみて健康被害が生ずるおそれがないと認められない場合には、当該確認を取り消すこととした(同条第5項)。この取消しにより、当該土地の所有者等は、改めて同条第1項の調査・報告義務を負うこととなる。
? 土壌汚染のおそれがある土地の形質が変更される場合の調査命令
土地の形質の変更は、それが行われる土地に土壌汚染が存在する場合には、掘削工事に伴う汚染土壌の飛散、汚染土壌が帯水層に接することによる地下水汚染の発生をもたらし得るものであるし、掘削された汚染土壌が搬出されて埋立材に利用されることがあるなど、汚染の拡散のリスクを伴うものである。一方、現行法においては、指定区域外における土地の形質の変更について、何ら規制がない。
このため、土地の形質の変更(当該変更に係る部分の面積が環境省令で定める規模以上のものに限る。)をしようとする者は、当該形質の変更に着手する日の30日前までに、当該形質の変更の場所、着手予定日等を都道府県知事に届け出なければならないこととし(第4条第1項。ただし、後述する形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。第13条)、都道府県知事は、当該届出を受けた場合において、その土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、その土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査・報告を命ずることとした(第4条第2項)。
なお、「土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準」としては、
?有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地、
?特定有害物質が土壌に漏洩した土地、
?法に基づかない自主的な調査により汚染が確認されている土地、等を想定している。
(2)区域の指定等
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれの有無にかかわらず一定の基準を超過する土壌汚染地を一律に指定区域に指定する現行制度の下においては、指定区域は健康被害が生ずるおそれがあり、危険な区域であるという安全サイドに立った判断が行われることにより、必ずしも汚染の除去等の措置を講ずる必要のない区域においても、掘削除去が行われることが多い。しかし、掘削除去は、大量の汚染土壌の搬出を伴うため、環境リスクの観点から望ましいものではない。
このため、一定の基準を超過する土壌汚染が存在する土地を、健康被害が生ずるおそれの有無に応じて分類して指定するとともに、健康被害が生ずるおそれのある区域については、都道府県知事が健康被害の防止の観点から最低限必要な措置を明示することとした。
? 要措置区域
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、かつ、当該土地に人の立入りがあったり、当該土地又はその周辺の土地において地下水が飲用に供されている等、当該汚染により健康被害が生ずるおそれがある場合には、当該土地の区域を、要措置区域として指定することとした(第6条第1項)。都道府県知事は、要措置区域の指定をした場合には、当該土地の所有者等又は汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとし(第7条第1項)、この指示をするときは、講ずべき措置及びその理由等を示さなければならないこととした(同条第2項)。
この指示を受けた者は、指示された汚染の除去等の措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置を講ずる義務を負い(同条第3項)、都道府県知事は、この義務の不履行があれば、履行すべきことを命ずることができることとした(同条第4項)。
要措置区域内においては、都道府県知事から指示を受けた者が行う汚染の除去等の措置に伴うもの等を除き、土地の形質の変更を禁止することとした(第9条)。
? 形質変更時要届出区域
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないが、当該汚染により健康被害が生ずるおそれがない場合には、当該土地の区域を、形質変更時要届出区域として指定することとした(第11条第1項)。形質変更時要届出区域内については、土地の形質の変更を行うことによる新たな環境リスクの発生を防止するため、現行法第9条と同様に、土地の形質の変更時の届出等を義務付けることとした(第12条)。
(3) 指定の申請
現在では、土地取引等の際に広く自主的な調査が行われ、土壌汚染が発見されているが、このような法に基づかない調査により発見された土壌汚染地は、指定区域に指定されることはなく、法の規制の下で管理がなされていなかった。
このため、土地の所有者等は、自主的に土壌の汚染の状況について調査した結果、一定の基準を超過する土壌汚染が存在すると思料するときは、都道府県知事に対し、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定することを申請することができることとした(第14条第1項)。都道府県知事は、当該申請に係る調査が公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該自主的な調査を法に基づく調査とみなし、当該調査の結果に基づき、当該土地の区域を要措置区域等に指定することができることとした(同条第3項)。
(4) 汚染土壌の搬出等に関する規制
? 汚染土壌の搬出時の届出
要措置区域等内の土地の土壌(環境省令で定める方法により調査した結果、汚染状態が(2)?の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、都道府県知事に、当該搬出に着手する日の14日前までに、当該汚染土壌の汚染状態、体積、運搬の方法、当該汚染土壌を処理する施設の所在地等を届け出なければならないこととした(第16条第1項)。都道府県知事は、届出の内容が?に違反していると認めるときは、計画の変更を命ずることができることとした(同条第4項)。なお、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合や汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合には、届出の対象外とするが(同条第1項ただし書)、前者については事後届出が必要であることとした(同条第3項)。
? 搬出汚染土壌の運搬及び処理
搬出した汚染土壌を要措置区域等外において運搬する者は、環境省令で定める基準に従って運搬しなければならないこととした(第17条)。
また、汚染土壌を搬出する者は、自らが?の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)であって当該汚染土壌を自ら処理する場合等を除き、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないこととした(第18条第1項)。
? 措置命令
都道府県知事は、汚染土壌を運搬した者が?に違反した場合、又は汚染土壌を要措置区域等外へ搬出した者が?に違反した場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を命ずることができることとした(第19条)。
? 管理票
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者がその汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、当該者は、管理票を用いて、当該汚染土壌が適正に運搬、処理されたことを確認しなければならないこととした(第20条)。また、虚偽の管理票が交付されること等により、汚染土壌の運搬及び処理の確認に支障が生じることとなることから、虚偽の管理票の交付等を禁止することとした(第21条)。
? 汚染土壌処理業
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないこととした(第22条第1項)。また、汚染土壌の処理が確実に行われることを担保するため、都道府県知事は、
1) 汚染土壌処理施設及び申請者の能力が、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること
2) この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること等の欠格事由に該当しないこと
に適合しているときでなければ、許可してはならないこととした(同条第3項)。汚染土壌処理業の許可については、5年間の有効期間を設け、更新を受けなければ失効することとした(同条第4項)。
さらに、汚染土壌処理業者は、環境省令で定める基準に従って汚染土壌の処理を行い(同条第6項)、汚染土壌処理施設に汚染土壌の処理に関する記録を備え置き、利害関係者に閲覧させ(同条第8項)、汚染土壌処理施設における事故が発生したときにその旨を届け出る(同条第9項)義務を負うこととした。
また、都道府県知事は、汚染土壌処理業者により処理基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした(第24条)。都道府県知事は、汚染土壌処理業者が1)又は2)に適合しなくなったとき等に該当する場合には、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができることとした(第25条)。
また、汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は当該事業の許可が取り消された汚染土壌処理業者は、汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならないこととし(第27条第1項)、都道府県知事は、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該施設を事業の用に供した者に対し、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした(同条第2項)。
なお、汚染土壌処理業の許可の申請手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及び図面のほか、当該許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等について定めた、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(平成21年環境省令第10号)が平成21年10月22日に制定・公布されたので、こちらも併せて御参照いただきたい* 。
(5) 指定調査機関
? 指定の更新
指定調査機関の指定に5年間の有効期間を設け、更新を受けなければ失効することとした(第32条第1項)。環境大臣は、この更新の際に、指定調査機関が経理的基礎及び技術的能力を有するか否か等を確認し、基準に適合していると認められない指定調査機関は、更新を受けられないこととした(同条第2項により準用される第31条)。
? 技術管理者の設置
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等に精通した技術者として環境省令で定める基準に適合するものを技術管理者として選任し、土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督を技術管理者にさせなければならないこととした(第33条及び第34条)。また、指定調査機関が技術管理者の選任義務に違反した場合には、環境大臣は、その指定を取り消すことができることとした(第42条第2号)。
(6) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めることとした(第61条第1項)。この規定により、土壌汚染の状況に関する調査や講じられた汚染の除去等の措置(いずれも法に基づくものであると否とを問わない。)に関する情報等が収集されることになり、第4条第2項や第5条第1項の命令が適切に行われること等が期待される。
また、都道府県知事は、公園等の公共施設や学校、卸売市場等の公益的施設等を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地の土壌汚染のおそれの有無を把握させるよう努めることとした(同条第2項)。
(7) 施行期日、経過措置
? 施行期日
本法は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行するが(附則第1条本文)、汚染土壌処理業の許可を受けようとする者は、本法の施行前においても、第22条第2項に準じてその申請を行うことができることとし、この規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされた(附則第1条ただし書、附則第2条)。
これらの施行期日については、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成21年政令第245号)により、それぞれ、平成22年4月1日及び平成21年10月23日と定められた。
? 経過措置
現行法の指定区域は、本法施行後、形質変更時要届出区域とみなし(附則第4条)、現行法の指定区域台帳は、形質変更時要届出区域の台帳とみなすこととした(附則第5条)。現行法の指定調査機関は、本法施行日に、新法第3条第1項の指定を受けたものとみなすこととした(附則第10条)。
以上が新法の概要である。環境省としては、引き続き、省令の改正等所要の準備を行い、新法の円滑な施行を図っていくこととしている。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(第171回国会内閣提出第59号)については、衆議院においてその一部が修正された上で、4月17日、参議院において可決され、成立したところであり、4月24日、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)として公布され、平成22年4月1日に施行の予定である(平成21年政令第245号)。
本稿では、法案提出の契機となった土壌汚染対策の現状と課題について触れた上で、本法による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)について説明する。
なお、新法の条文、新旧対照表等は、環境省ホームページ* に掲載されているので、御参照いただきたい。
1 現状と課題
昨年12月、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、「今後の土壌汚染対策の在り方について」の答申がなされ、この中で、土壌汚染対策の現状と課題として、
? 法に基づかない自主的な調査による土壌汚染の発見が増加しており、このような土壌汚染地については、情報が開示され、適切かつ確実に管理・対策を進めることが必要
? 最近の土壌汚染対策としては、健康被害のおそれの有無にかかわらず掘削除去が選択されることが多いが、掘削除去は汚染の拡散のリスクを伴うものであることから、汚染の程度等に応じて必要な対策の基準を明確化し、指定区域を健康被害のおそれの有無に応じて分類することが必要
? 汚染土壌の不適正処理の事例が発見されており、汚染土壌の適正処理の確保が必要
との指摘を受けたところである。
環境省は、これを踏まえて土壌汚染対策法を改正することとし、そのための法案を国会に提出した。
2 新法の概要
以下、新法について、主要な条項を解説する。条項については、特に断りがない限り、新法の条項である。
(1)土壌汚染状況調査
? 第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法の変更時の届出義務
第3条第1項ただし書の確認の制度は、土地の利用の方法からみて健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けた場合に同項の土壌汚染状況調査・報告義務を免れることとするものである。しかしながら、当該確認を受けた土地の利用の方法が変更されることにより、当該土地の所有者や従業員以外の者が立ち入ることが可能となり、健康被害が生じるおそれがある場合もあり得る。
このため、当該確認を受けた土地の所有者等に対し、当該土地の利用の方法を変更する前に、変更後の土地の利用の方法を届け出させるとともに(第3条第4項)、都道府県知事は、変更後の土地の利用の方法からみて健康被害が生ずるおそれがないと認められない場合には、当該確認を取り消すこととした(同条第5項)。この取消しにより、当該土地の所有者等は、改めて同条第1項の調査・報告義務を負うこととなる。
? 土壌汚染のおそれがある土地の形質が変更される場合の調査命令
土地の形質の変更は、それが行われる土地に土壌汚染が存在する場合には、掘削工事に伴う汚染土壌の飛散、汚染土壌が帯水層に接することによる地下水汚染の発生をもたらし得るものであるし、掘削された汚染土壌が搬出されて埋立材に利用されることがあるなど、汚染の拡散のリスクを伴うものである。一方、現行法においては、指定区域外における土地の形質の変更について、何ら規制がない。
このため、土地の形質の変更(当該変更に係る部分の面積が環境省令で定める規模以上のものに限る。)をしようとする者は、当該形質の変更に着手する日の30日前までに、当該形質の変更の場所、着手予定日等を都道府県知事に届け出なければならないこととし(第4条第1項。ただし、後述する形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。第13条)、都道府県知事は、当該届出を受けた場合において、その土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、その土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査・報告を命ずることとした(第4条第2項)。
なお、「土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準」としては、
?有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地、
?特定有害物質が土壌に漏洩した土地、
?法に基づかない自主的な調査により汚染が確認されている土地、等を想定している。
(2)区域の指定等
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれの有無にかかわらず一定の基準を超過する土壌汚染地を一律に指定区域に指定する現行制度の下においては、指定区域は健康被害が生ずるおそれがあり、危険な区域であるという安全サイドに立った判断が行われることにより、必ずしも汚染の除去等の措置を講ずる必要のない区域においても、掘削除去が行われることが多い。しかし、掘削除去は、大量の汚染土壌の搬出を伴うため、環境リスクの観点から望ましいものではない。
このため、一定の基準を超過する土壌汚染が存在する土地を、健康被害が生ずるおそれの有無に応じて分類して指定するとともに、健康被害が生ずるおそれのある区域については、都道府県知事が健康被害の防止の観点から最低限必要な措置を明示することとした。
? 要措置区域
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、かつ、当該土地に人の立入りがあったり、当該土地又はその周辺の土地において地下水が飲用に供されている等、当該汚染により健康被害が生ずるおそれがある場合には、当該土地の区域を、要措置区域として指定することとした(第6条第1項)。都道府県知事は、要措置区域の指定をした場合には、当該土地の所有者等又は汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとし(第7条第1項)、この指示をするときは、講ずべき措置及びその理由等を示さなければならないこととした(同条第2項)。
この指示を受けた者は、指示された汚染の除去等の措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置を講ずる義務を負い(同条第3項)、都道府県知事は、この義務の不履行があれば、履行すべきことを命ずることができることとした(同条第4項)。
要措置区域内においては、都道府県知事から指示を受けた者が行う汚染の除去等の措置に伴うもの等を除き、土地の形質の変更を禁止することとした(第9条)。
? 形質変更時要届出区域
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないが、当該汚染により健康被害が生ずるおそれがない場合には、当該土地の区域を、形質変更時要届出区域として指定することとした(第11条第1項)。形質変更時要届出区域内については、土地の形質の変更を行うことによる新たな環境リスクの発生を防止するため、現行法第9条と同様に、土地の形質の変更時の届出等を義務付けることとした(第12条)。
(3) 指定の申請
現在では、土地取引等の際に広く自主的な調査が行われ、土壌汚染が発見されているが、このような法に基づかない調査により発見された土壌汚染地は、指定区域に指定されることはなく、法の規制の下で管理がなされていなかった。
このため、土地の所有者等は、自主的に土壌の汚染の状況について調査した結果、一定の基準を超過する土壌汚染が存在すると思料するときは、都道府県知事に対し、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定することを申請することができることとした(第14条第1項)。都道府県知事は、当該申請に係る調査が公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該自主的な調査を法に基づく調査とみなし、当該調査の結果に基づき、当該土地の区域を要措置区域等に指定することができることとした(同条第3項)。
(4) 汚染土壌の搬出等に関する規制
? 汚染土壌の搬出時の届出
要措置区域等内の土地の土壌(環境省令で定める方法により調査した結果、汚染状態が(2)?の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、都道府県知事に、当該搬出に着手する日の14日前までに、当該汚染土壌の汚染状態、体積、運搬の方法、当該汚染土壌を処理する施設の所在地等を届け出なければならないこととした(第16条第1項)。都道府県知事は、届出の内容が?に違反していると認めるときは、計画の変更を命ずることができることとした(同条第4項)。なお、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合や汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合には、届出の対象外とするが(同条第1項ただし書)、前者については事後届出が必要であることとした(同条第3項)。
? 搬出汚染土壌の運搬及び処理
搬出した汚染土壌を要措置区域等外において運搬する者は、環境省令で定める基準に従って運搬しなければならないこととした(第17条)。
また、汚染土壌を搬出する者は、自らが?の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)であって当該汚染土壌を自ら処理する場合等を除き、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないこととした(第18条第1項)。
? 措置命令
都道府県知事は、汚染土壌を運搬した者が?に違反した場合、又は汚染土壌を要措置区域等外へ搬出した者が?に違反した場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を命ずることができることとした(第19条)。
? 管理票
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者がその汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、当該者は、管理票を用いて、当該汚染土壌が適正に運搬、処理されたことを確認しなければならないこととした(第20条)。また、虚偽の管理票が交付されること等により、汚染土壌の運搬及び処理の確認に支障が生じることとなることから、虚偽の管理票の交付等を禁止することとした(第21条)。
? 汚染土壌処理業
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないこととした(第22条第1項)。また、汚染土壌の処理が確実に行われることを担保するため、都道府県知事は、
1) 汚染土壌処理施設及び申請者の能力が、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること
2) この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること等の欠格事由に該当しないこと
に適合しているときでなければ、許可してはならないこととした(同条第3項)。汚染土壌処理業の許可については、5年間の有効期間を設け、更新を受けなければ失効することとした(同条第4項)。
さらに、汚染土壌処理業者は、環境省令で定める基準に従って汚染土壌の処理を行い(同条第6項)、汚染土壌処理施設に汚染土壌の処理に関する記録を備え置き、利害関係者に閲覧させ(同条第8項)、汚染土壌処理施設における事故が発生したときにその旨を届け出る(同条第9項)義務を負うこととした。
また、都道府県知事は、汚染土壌処理業者により処理基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした(第24条)。都道府県知事は、汚染土壌処理業者が1)又は2)に適合しなくなったとき等に該当する場合には、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができることとした(第25条)。
また、汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は当該事業の許可が取り消された汚染土壌処理業者は、汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならないこととし(第27条第1項)、都道府県知事は、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該施設を事業の用に供した者に対し、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした(同条第2項)。
なお、汚染土壌処理業の許可の申請手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及び図面のほか、当該許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等について定めた、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(平成21年環境省令第10号)が平成21年10月22日に制定・公布されたので、こちらも併せて御参照いただきたい* 。
(5) 指定調査機関
? 指定の更新
指定調査機関の指定に5年間の有効期間を設け、更新を受けなければ失効することとした(第32条第1項)。環境大臣は、この更新の際に、指定調査機関が経理的基礎及び技術的能力を有するか否か等を確認し、基準に適合していると認められない指定調査機関は、更新を受けられないこととした(同条第2項により準用される第31条)。
? 技術管理者の設置
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等に精通した技術者として環境省令で定める基準に適合するものを技術管理者として選任し、土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督を技術管理者にさせなければならないこととした(第33条及び第34条)。また、指定調査機関が技術管理者の選任義務に違反した場合には、環境大臣は、その指定を取り消すことができることとした(第42条第2号)。
(6) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めることとした(第61条第1項)。この規定により、土壌汚染の状況に関する調査や講じられた汚染の除去等の措置(いずれも法に基づくものであると否とを問わない。)に関する情報等が収集されることになり、第4条第2項や第5条第1項の命令が適切に行われること等が期待される。
また、都道府県知事は、公園等の公共施設や学校、卸売市場等の公益的施設等を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地の土壌汚染のおそれの有無を把握させるよう努めることとした(同条第2項)。
(7) 施行期日、経過措置
? 施行期日
本法は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行するが(附則第1条本文)、汚染土壌処理業の許可を受けようとする者は、本法の施行前においても、第22条第2項に準じてその申請を行うことができることとし、この規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされた(附則第1条ただし書、附則第2条)。
これらの施行期日については、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成21年政令第245号)により、それぞれ、平成22年4月1日及び平成21年10月23日と定められた。
? 経過措置
現行法の指定区域は、本法施行後、形質変更時要届出区域とみなし(附則第4条)、現行法の指定区域台帳は、形質変更時要届出区域の台帳とみなすこととした(附則第5条)。現行法の指定調査機関は、本法施行日に、新法第3条第1項の指定を受けたものとみなすこととした(附則第10条)。
以上が新法の概要である。環境省としては、引き続き、省令の改正等所要の準備を行い、新法の円滑な施行を図っていくこととしている。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html
2009年11月15日
健全な地下水の保全・利用に向けて
健全な地下水の保全・利用に向けて−「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」報告−(抜粋)
平成19年3月
今後の地下水利用のあり方に関する懇談会
はじめに
近年、地下水を取り巻く環境は大きく変化してきている。かつて高度経済成長期に深刻であった地下水の過剰採取による地盤沈下は、一部現在も引き続き対策が必要な地域もあるが、地下水採取規制、代替水源の確保等により、沈静化しつつある。 一方で、かつては地盤沈下が深刻であった大都市地域で地下水採取規制等により地下水位が回復・上昇し、地下構造物や地下水環境への新たな悪影響・弊害を引き起こしている事例もある。また、地下水質の面で環境基準を超える浅層地下水汚染が顕在化している。
地下水は地球水循環系を構成する重要な要素であり、地下水の保全及び利用が水循環系全体に与える影響を把握していくことが重要である。
本懇談会は、平成10年に国土庁水資源部に設置され、“地下水の利用と制度のあり方”について、専門の立場より幅広く検討を進めてきた。平成12年3月には、地下水をめぐる現状、今後の地下水利用のあり方について中間報告としてとりまとめ
た。
つづいて平成15年3月に日本で開催された第3回世界水フォーラムにおいて「今後の地下水利用のあり方」をテーマに分科会を主催し国際的視野に立った議論を行った。
今般、地下水をめぐる最近の動向と保全・利用に向けた課題、地下水利用のあるべき基本的な考え方を整理し、今後の地下水利用のあり方に関する提言を報告書にまとめた。
本報告は、その前半では「地下水をめぐる現況、最近の国内外の動向、及び保全・利用に係る課題」を論点とし、後半で「今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法」に言及し、最後に、当初目指した「今後の地下水利用のあり方」を提言している。
その新しい視点は、地下水資源に軸足を置いてマネジメントする必要性に向けられている。これまでの永い地下水利用の歴史を踏まえて、地下水資源マネジメントの指針と方法をより実践的にまとめたものであり、今後、本提言が国や各地域での取り
組みに反映されることを期待するものである。
平成19年3月
今後の地下水利用のあり方に関する懇談会座長
埼玉大学名誉教授佐藤邦明
「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」委員
小尻利治京都大学防災研究所水資源研究センター教授
佐藤邦明埼玉大学名誉教授(座長)
七戸克彦九州大学大学院法学研究院教授
大東憲二大同工業大学工学部都市環境デザイン学科教授
田中正筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
中杉修身上智大学大学院地球環境学研究科教授
守田優芝浦工業大学工学部土木工学科教授
目 次
第1章 地下水をめぐる現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.1 地下水の特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2 地下水利用の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1.3 地下水障害・地下水水質・汚染の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
1.4 地下水に関する法制度の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第2章 地下水をめぐる最近の動向と地下水の保全・利用に係る課題・・・・ 29
2.1 わが国の水需給に関する動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
2.2 新たな地下水障害と地下水源開発の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
2.3 地震災害等、緊急水資源需要への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
2.4 水に関する世界情勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
2.5 地下水の保全・利用に向けた課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
第3章 今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法・・・・・・・・・・・・・・・ 55
3.1 健全な水循環系の構築における今後の地下水利用の基本的な考え方・・・・・・・・ 55
3.2 地下水資源マネジメントの考え方と手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
第4章 今後の地下水利用のあり方に関する提言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 4
4.1 地下水資源マネジメントの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
4.2 地下水資源マネジメントの運用方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
4.3 地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
第1章 地下水をめぐる現状
1.1 地下水の特性
(1)地下水の水循環上の特性
科学的にみると、地下水は陸水の地下にある水の総称である。それは、降水が地下に浸透して海洋へ地下流出するプロセスにある、いわゆる「地下水」と、陸地の地形・地質が形成される際に地下深くに閉じこめられた化石水や、岩石・溶岩の形成時に生成される初生水のように「循環に乏しい地下水」に分けられる。一般に、淡水資源や温泉水は、それらを持続的かつ健全に利用できる循環している地下水であることが前提となる。以下、このような視点に基づき、議論を展開する。
地下水の源は降水であり、地表水とともに水循環を構成する。降水の一部は、直接流出として河道に流出する。直接流出は、地表から河道に流れる表面流出と、一度地中に浸透した後に浅い地下水流として河道に流出する中間流出に分けることができる。直接流出しない降水は、窪地などに一時的に貯留されるか、土壌に浸透する。土壌に浸透した降水の一部は重力によって下方に浸透し、地下水となる。
地下水は地表水に比べて、地中をゆっくりと流れる。そして、やがて河川・湖沼や地表面に再び流出し、地表水に合流する。平均滞留時間は数百〜数千年といわれている(表1-1-1参照)。
このような水循環を図示したものが図1-1-1(○a ,○b )である。水循環の過程においては、大気事象や大地の影響を強く受けている。例えば、地下水涵養は降水量に支配され、地下水循環は地質や地形によって規定される。また、蒸発は気温や湿度、植生などの影響を受けている。さらに、採取量(揚水量)や土地利用などの人為的な要因も水循環に影響を与えている。

資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)をもとに加筆
図1-1-1 水循環とその規定要因の概念図
表1-1-1 地球の水量と滞留時間
貯留量(?3) 平均滞留時間
海 洋 1,349,929,000 3,200 年
氷 雪 24,230,000 9,600 年
地下水 10,100,000 830 年
土壌水 25,000 0.3 年
湖沼水 219,000 数年〜数百年
河川水 1,200 13 日
水蒸気 13,000 10 日
資料)建設産業調査会『改訂地下水ハンドブック』(1998 年)
(2)地下水の水資源としての潜在特性
一般に水資源としての地下水は、表1-1-2に示すように、利用の簡便性、経済性、良質な水質、恒温性という特性を有している。
表1-1-2 地下水の利用特性
このような地下水の自然特性を活かし、地下水は、生活用水(飲料用、調理用、浴用等)、工業用水(冷却用、洗浄用等)、農業用水(農作物栽培用等)、積雪地域の消雪用など多様な用途に利用されている(図1-1-2参照)。
図1-1-2 地下水特性からみた用途の内訳
1.北海道地方
(3)地下水の潜在分布状況
図1-1-3は、わが国における地下水盆の賦存地形類型と主な地下水区の分布を示している。わが国における地下水は、地形・地質上、平野型、盆地型等のいくつかに分類できる。

図1-1-3 わが国における地下水盆の類型と主な地下水文区
それぞれに分類される地下水の特徴を以下に要約する。
?堆積平野の地下水
a)平野・台地
関東平野など主要な地下水盆は、地質年代では新生代新第三紀末から第四紀の地層が堆積する平野、低平地に分布しており、特に第四紀完新世の沖積平野のうち、中〜上部更新統・完新統の新しい地質が主な帯水層となっている。地層が軟弱な沖積平野では、地下水の過剰なくみ上げが地盤沈下を引き起こしやすい。
b)盆地
わが国の盆地には、平野と同様に新生代新第三紀末から第四紀の地層が堆積しており、更新世末から完新世の地質をもつ段丘や扇状地が有力な帯水層となっている。盆地の帯水層は、豊富な地下水を有していることが多いが、地下水の過剰なくみ上げによって地下水位の低下や枯渇を起こすことがある。
?岩の地下水
地下水は溶岩体や深成岩地帯にれっか水(裂罅水:fissure water、「地質事典」平凡社、1990)や割れ目水として帯水している。
a)山地
山地では、造岩塊や固結岩の亀裂や浸透性の高い地層に地下水が含まれており、トンネル掘削時に湧水として流出することがあるが、環境への影響や採水の経済性を考慮すると、大規模な採取は困難である。
b)火山地域
火山地域は、溶岩・火山砕屑物など浸透性の高い地層から構成されているため、阿蘇カルデラ、シラス台地など有力な帯水層が多い。山麓部末端では湧水群が分布し、古くから農業用水、生活用水に利用されてきた。
c)石灰岩地帯
石灰岩中のれっかや鍾乳洞には地下水を有することが多く、日本では、例えば、栃木県の佐野市(弁天池)や山口県の秋吉台などに見られる。また、南西諸島では、琉球石灰岩が分布し、自然の地下水帯となっているため、近年、地下ダムによる地下水貯留が行われる例がある。
図1-1-4 日本の地質図
1.2 地下水利用の現状
(1)わが国における水使用量の推移
2003 年(平成15 年)におけるわが国の水使用量(取水ベース)は、都市用水と農業用水を合わせ、839 億m3 であり、そのうち、都市用水(生活用水と工業用水の合計)は282 億m3 である。都市用水の使用量は、図1-2-1に示すように1987 年(昭和62 年)以降、やや増加したが、その後微減の傾向にある。また、農業用水の使用量についても、昨今やや減少しており、2003 年は557 億m3となっている。
図1-2-1 全国の水使用量の推移
(2)わが国における地下水利用の特徴
?水使用量に占める地下水の割合
2003 年(平成15 年)における取水ベースの水使用量839 億m3 の水源内訳をみると、図1-2-2のように、河川水が735 億m3、地下水が104 億m3 であり、地下水依存率は約12.4%となっている。

図1-2-2 水使用量に占める地下水の割合
?地下水使用量の用途別割合
上述の地下水使用量104 億m3 に加え、養魚用水として約13 億m3/年、建築物用等として約7億m3/年の地下水が使用されており、全地下水使用量は約124億m3/年と推計されている。
2003 年(平成15 年)における地下水の用途別割合は、生活用水が35.5 億m3で全体の28.6%、工業用水が35.9 億m3 で28.9%、農業用水が33.0 億m3 で26.6%となっている(図1-2-3参照)。
用途別地下水使用量の推移をみると、図1-2-4に示すように、生活用水はほぼ横ばいであるが、工業用水は減少傾向にある。

図1-2-3 地下水の用途別割合
?用途別にみる地下水利用の地域性
地下水利用は、地形・地質や降水といった自然条件と、都市化や人口といった人的な条件の影響を強く受け、決して全国一律ではなく、地域性が多様である。以下、用途別に地下水源への依存の地域性を述べる。
□工業用水
地下水は、水質が良く、水温が一定であり、取水費用が安いという特徴から、工業用水に多く使用されており、特に、化学工業、鉄鋼業、パルプ・紙・食品加工など製造業で、製造、洗浄、冷却水などとして地下水使用量が多くなっている。
図1-2-5に示すように、工業用水の地下水依存率は、全国の合計でみると約3割(29.5%)である。地域別にみると、北陸で最も高く6割超(62.7%)である。また、近畿内陸(54.8%)、関東内陸(46.0%)、東海(45.0%)などでも高くなっている。
工業用水用の地下水は、戦後昭和20 年代以降、深井戸による被圧地下水が使われているが、工場等の立地は沖積平野に多いことから、地盤沈下、塩水化などの地下水障害を引き起こし、今日に至っている。
図1-2-5 地域別用途別地下水依存率(工業用水)
□生活用水
生活用水の地下水依存率は、全国の合計でみると2割強(22.1%)である。図1-2-6に示すように、地域別にみると、南九州(54.3%)や山陰地域(51.9%)で生活用水の地下水依存率が高く、5割を超えている。次いで、四国(41.5%)、関東内陸(41.0%)、北陸(39.8%)などでも高い。一方で、北海道(6.0%)、沖縄(8.5%)では、生活用水の地下水依存率が低い。
図1-2-6 地域別用途別地下水依存率(生活用水)
□農業用水
わが国では、農業用水として主に地表水が利用されてきた。地下水は、補助水源、渇水時の応急用水源として利用されてきたことから、農業用水に占める地下水の割合は概して低い(図1-2-7参照)。
図1-2-7 地域別用途別地下水依存率(農業用水)
□その他の用途
水産用にマス、ウナギなどの養殖で利用される地下水の量の統計では、上述の3つ(工業・生活・農業)の用途に次いで多く、個別的であるが、湧水、温泉水などが報告されている。
また、消雪用に地下水を利用する方法は、気温が氷点下にならない豪雪地で有効であり、消雪パイプは1961 年に新潟県長岡市で始まり、全国的には2004 年度の消雪パイプ使用水量の約83%(374 百万m3/年)が地下水を利用している。地下水は水温の季節変動が小さいため、消雪効果があり、東北、北陸などでも利用されている。しかし、狭い場所で集中的に大量の地下水をくみ上げるため、地下水位の低下、地盤沈下などの地下水障害をもたらした。
わが国では、温泉水として利用される地下水も多い。浴用以外にも、ハウス園芸用熱源、発電など多目的に利用される事例がある。井戸の掘削深度がかなり深く1,000m以上の深さのものもある。
1.3 地下水障害・地下水水質・汚染の現状
(1)地下水位の異常低下、井戸枯れ
わが国における地下水位の異常低下、井戸枯れは、戦後(1945 年)以後1950 年代後半〜1960年代前半にかけて最も激しい地下水被害をもたらした。高度成長期には地下水を大量に揚水したことによって、都市部を中心に地下水位の低下、井戸枯れが起こった。また、地下掘削工事やトンネル掘削によって、周辺の地下水位が低下し、井戸枯れが起こる例も見られた。
しかし、1950 年代後半〜1970 年代前半に揚水の法的規制等が行われたことにより採取量は減少し、全国的にみると地盤沈下は沈静化し、近年は地下水位が回復しているところもみられる。
(2)地盤沈下
(3)塩水化
わが国における地下水の塩水化は、ほとんどが海岸域で発生している(図1-1-1)。地下水の過剰なくみ上げが原因で、地下水位が海水面より低下し、帯水層に海水が浸入することによって発生する。1960 年以降、製紙業の盛んな静岡県富士市のほか多数の臨海域で発生しており、塩水化した地下水は、飲料水として利用できず、工業用水としての不適合、農作物への塩害などがみられた。八戸、石巻、気仙沼などでは、現在もその塩害が継続している。
表1-3-1 塩水化地域に対する対策の状況

(4)地下水の水質と汚染
?地下水質の評価指標
古来、地下水といえば、水温の安定した清廉な水という通念がある。地下水の水質は、地形・地質の成り立ちや地下水の由来、流動、気候、生態系などの自然条件の影響を受け、その地域性や深さによって大きく異なる。例えば、表1-3-2は日本の名水に指定されている水質の例を示す。地下水質は、主要溶存化学成分9項目、陽イオン(ナトリウムNa+、カリウムK+、カルシウムCa2+、マグネシウムMg2+)、陰イオン(重炭酸HCO3-、塩素Cl-、硫酸SO4-、硝酸NO3-、シリカSiO2)に加え、電気伝導度、水温、pH などにより判断され、必要に応じて用途や関係する水質(環境)基準項目を加味した上で評価される。
表1-3-2 名水の水質例
自然の地下水質は、元来多様な理化学的特性を持つ。言うまでもなく、ある地下水が水質上良いか悪いかを漠然と判断することはできない。通常、ある対象・目的に対して、人や環境に有害であると考えられる数値を水質評価指標(水質検査項目)の基準値(水質基準)として設定し、利用の可否を決めることになる。
したがって、自然のままで地下水質がある検査基準(例えば、水道水の検査基準)に適合しない場合がありうる(以下、仮に「自然由来の汚染」と呼ぶこととする)。なお、水質検査の項目自体も水質基準の種類(対象・目的)に応じて異なるものが必要となる。
一般に水質汚染とは、自然の地下水質が人為的に汚染された(=水質基準に不適合の検査項目がある)人為由来のものを指す。自然由来の汚染は主に深層の地下水で、人為由来の汚染は主に浅層の地下水で発生する。深層の地下水汚染は除去が困難であり、水資源として利用することができない。以下では、人為由来の地下水汚染を中心に述べる。
?地下水汚染に関する環境基準とその超過率
高度成長期以降、工場や事業所等が原因となって地下水汚染が発生し、化学合成物である揮発性有機塩素化合物による地下水汚染が深刻となった。
このため、1971 年(昭和46 年)に「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」の2つからなる「水質汚濁に係る環境基準」が定められた。「人の健康の保護に関する環境基準」は、全公共用水域に対し、カドミウム、シアン等9項目についての基準を定めていたが、1993 年(平成5年)3月に項目が追加され23 項目となった。さらに近年、農業、畜産排水による硝酸性窒素汚染が顕在化してきたことから、1999 年(平成11 年)には、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ほう素」及び「ふっ素」の3項目が追加され、現在では26 項目の基準が定められている。
国と都道府県では「地下水の水質汚濁に関わる環境基準」に定められた26 項目を調査対象物質として毎年地下水質測定を行っている(表1-3-3、図1-3-5参照)。
地下水は、一度汚染されると、汚染の継続は長期間に及ぶ。水資源の安全な利用の観点からも、地下水質の継続的な監視が求められることとなる。
表1-3-3 地下水の水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)
図1-3-5 環境基準超過率の推移
?揮発性有機塩素化合物による地下水汚染
揮発性有機塩素化合物は、土壌汚染や浅層地下水汚染を引き起こす原因となっている。その主要な原因となっているのは、金属関連産業や半導体産業などの洗浄溶剤として使用されるトリクロロエチレンと、クリーニングや金属等の脱脂洗浄、代替フロンの原料として使用されるテトラクロロエチレンであるが、近年、製造・使用量は減ってきており、環境基準超過率は減少傾向にある。
揮発性有機塩素化合物は、
?重い、
?水に溶けにくい、
?土壌に吸着しにくい、
?低粘性、
?揮発性が高い、
?分解されにくい、といった特徴を有しているため、いったん地下に進入すると、
鉛直方向には容易に重力浸透する。一方で、横方向への拡散は少ないため、高濃度の原液による局地的な地下水汚染、土壌汚染を引き起こす特徴を持っている。揮発性有機塩素化合物は、まず土壌に浸透し、少しずつその下の帯水層に重力沈降しつつ溶け出して地下水を汚染する。
溶解汚染した地下水の移流流動及び分散によって、汚染地域は拡大する。
揮発性有機塩素化合物は、麻痺や呼吸障害、貧血、肝臓障害、発ガン性があるなど、人体に悪影響を及ぼすことが分かっている。
?硝酸性窒素による地下水汚染
硝酸性窒素汚染は、農薬、畜産排水などが汚染源となっているため、野菜、果樹、茶の栽培に利用されることの多い扇状地や、畜産、野菜栽培に利用されることの多い火山山麓で拡大している。
環境基準では、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素ともに10mg/?と定められているが、基準を超える井戸も全国各地で見つかっている。
揮発性有機塩素化合物の汚染は汚染地域が局所的であるのに対し、硝酸性窒素汚染はその性格上、汚染地域が広範に及ぶ上、現状ではその改善に決定的に有効な対策が見当たらないことから、今後、被害の拡大も懸念されている。硝酸性窒素は過剰に摂取すると、乳児がメトヘモグロビン血症注) 等を起こすことが知られているが、日本ではそれによる発症例は報告されていない。

図1-3-6 平成9〜16 度(1997〜2004 年度)地下水汚染マップ(環境基準26 項目)
1.4 地下水に関する法制度の現状
わが国の現行法では、ヨーロッパの国々に見られる地下水の基本法や総合法(例えば、後述するEU水枠組み指令)のような上位法はなく、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(いわゆる「ビル用水法」)のような地盤沈下対策としての井戸揚水規制に関する法律、土壌汚染対策法や水質汚濁防止法、水質汚染防止に関する法律など、地下水に関連するさまざまな個別法が実効している。
多くの都道府県や市町村では、これら国の法律を受け、地域の実情に応じた独自の条例や要綱等を制定している。
(1)地下水揚水の規制
現在、地盤沈下対策としては「工業用水法」(1956 年(昭和31 年)施行、1962 年(昭和37 年)改正)及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(以下、「ビル用水法」、1962 年(昭和37年)施行)の2法が地下水揚水施設に適用されている。規制の対象となる指定地域は、表1-4-1及び表1-4-2に示すとおり、工業用水法は10 都府県、ビル用水法は4都府県にわたっている。
表1-4-1 「工業用水法」に基づく指定地域
(2)地盤沈下防止等対策要綱
法律や政省令ではないが、地盤沈下に伴う被害の著しい濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部の3地域については、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議(1981 年(昭和56 年)設置)において、「地盤沈下防止等対策要綱」が決定され、発効している。
これらの要綱は、指定3地域を対象とした重点的地下水の採取規制、代替水源の確保及び代替水の供給を行い、地下水を保全するとともに、地盤沈下によるたん水被害の防止及び被害の復旧等、地域の実情に応じた総合的な対策の根拠を与えている。
3地域の地盤沈下防止等対策要綱及び対象地域は表1-4-3に示すとおりである。
表1-4-3 地盤沈下防止等対策要綱の概要
また、各地域の近況は以下のとおりである。
□濃尾平野
2004 年度(平成16 年度)の地下水採取量は1.7 億m3 であり、目標採取量(2.7 億m3)を下回った。当該年度(2003 年11 月1 日〜2004 年11 月1 日)の水準測量結果によると、年間1?以上の地盤沈下が認められた面積は約9? 2 であった。
□筑後・佐賀平野
佐賀地区及び白石地区における2004 年度(平成16 年度)の地下水採取量はそれぞれ3.8 百万m3、4.2 百万m3 であり、佐賀地区では目標採取量(6百万m3)を下回ったものの白石地区では目標採取量(3 百万m3)を上回った。当該年度(2004 年2 月1 日〜2005 年2 月1 日)の水準測量結果によると、年間1cm 以上の地盤沈下はこれら両地区共に認められなかった。
□関東平野北部
2004 年度(平成16 年度)の年間採取量は4.9 億m3 であり、目標採取量(4.8 億m3)を上回った。当該年度(2004 年1 月1 日〜2005 年1 月1 日)の水準測量結果によると、地盤沈下は年間1?以上の沈下が認められた面積は約419 ? 2 であり、うち2?以上の沈下面積は約26 ? 2 であった。
(3)地方自治体における地下水に関する条例・要綱等の制定状況
地域の特性に応じ各地方自治体(都道府県、市町村)で、個別の地下水に関する条例・要綱等が制定されている。それらの法的性格は以下のとおり。
条 例:地方自治体の議会の議決などにより制定される法規で、法的拘束力を持つ。
要綱等:地方自治体が議会の議決を経ずに定める内規で、法的拘束力を持たない。
これらは、おおむね遵守されており、地域の特性に見合った地下水の利用・保全に大いに貢献していると考えられる。
ただし、同一の地下水盆が複数の地方自治体にまたがる場合、地方自治体によって規制の条件、条例・要綱等の内容が異なり、地下水盆全体としての整合した対応が必ずしもとれていない。
地方自治体の条例・要綱等による規制等の対象地域を定めても、対象地域以外では、たとえ同一の地下水盆であっても全くの自由に委ねられている点(いわゆる反対解釈)等の課題をもっているものもある。
?都道府県における制定状況
都道府県の地下水に関する条例・要綱等について、名称別に分類した(表1-4-4参照)。また、都道府県の62 件の条例・要綱等について、その名称と目的・対策等を地図上に示した(図1-4-1参照)。

表1-4-4 都道府県の地下水に関する条例・要綱等の名称による分類(2004 年7月現在)
図1-4-1 都道府県の地下水に関する条例・要綱等の制定状況と規定内容
これらのほとんどは、「公害防止条例」「生活環境保全条例」「環境基本条例」といった公害や環境全般を対象とする条例であり、地下水については、その一部として取り扱われている。
こうしたことから、地下水が、主に公害対策の一環として、地盤沈下対策の側面から規制の対象として取り扱われてきた経緯がうかがえる。一方、地下水そのものを主たる対象とする条例は5つ制定されている。それらは、以下のように要約される。
a)「公害防止条例」「環境条例」及びそれに類する条例における取り扱い(表1-4-4中の分類?〜?)
これらの中で、水質保全については、すべての都道府県において項目として掲げられ、その対策として汚水排出に関する規定が定められている。これは地下水の汚染にも関係するが、主に地表水の汚染との関わりが深い。一方、地盤沈下防止についてもすべての都道府県が目的として掲げているものの、その主要な対策である採取に関する許可・届出義務等の規定については、地域により規定のあるところと、そうでないところがある。
b)「地下水採取・地下水保全条例」及びそれに類する条例における取り扱い(表1-4-4中の分類?)
地下水の採取・保全に関する条例を制定しているのは、山形県、茨城県、富山県、静岡県、熊本県の5県である。その多くは「地下水の採取の適正化に関する条例」及びそれに類する名称を付し、熊本県のみが「地下水保全条例」の名称を持つ。これらのすべてが採取に関する許可・届出義務等の規定を定めており、公害や環境全般を対象とする条例を補完している。
c)地下水の採取に関する許可
公害や環境全般を対象とする条例もしくは地下水に関する条例において、採取に関する許可・届出義務等を規定している都道府県は、南東北、関東、北陸、東海地方に分布しているのに対し、北海道、北東北、甲信、近畿以西では、その選択的内容もしくは一部にとどまっている。
こうしたことから、採取に関する許可・届出義務等の規定は、人口が密集し、水需要の大きい大都市圏や、水資源における地下水依存率が高い関東内陸、北陸等、比較的広域的な対応の必要性の高い地域に制定されていることがわかる。
d)地下水涵養
地下水涵養の人為促進については、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、奈良県、熊本県の条例の中に規定があり、塩水化については、山形県、茨城県、富山県、静岡県、徳島県の5県で規定されている。
e)地下水に関する要綱等(表1-4-4中の分類?〜?)
要綱レベルのものでは、山梨県や徳島県において地下水の採取の適正化に関する要綱が定められているほか、埼玉県、千葉県、福井県において、地盤地下防止を目的とした要綱等が制定されている。埼玉県の「地盤沈下緊急時対策要綱」は、地盤沈下緊急時に知事が地下水利用者に対し、地下水の採取を抑制できるとするものであり、千葉県の「地盤沈下防止協定」は、天然ガスかん水地上排水基準等について県と天然ガス採取企業との間で個別的に締結された協定である。
?市町村における制定状況
市町村の地下水に関する条例・要綱等については、330 件の存在が確認できたが、その半数強の181 件は「公害防止条例」「生活環境保全条例」「環境基本条例」といった公害や環境全般を対象とする条例であり、地下水は、その一部の項目・内容で取り扱われている。
これらを除いた149 件は、名称別に分類した(表1-4-5参照)。また、分類対象とした149 件の市町村の条例・要綱等について、その名称と目的・対策等を地図上に示した(図1-4-2参照)。
表1-4-5 市町村の地下水に関する条例・要綱等の名称による分類(2004 年7月現在)
条例の名称 制定数
?地下水の採取・保全・保護に関する条例 76
?地下水の採取・保全・保護に関する要綱・規約 23
?水資源の保全・保護に関する条例 4
?水道水源の保全・保護に関する条例・要綱 12
?地盤沈下防止に関する要綱・指針 3
?自家用天然ガスの採取規制に関する条例 12
?地下水の汚染防止に関する条例 1
?水環境の保全に関する条例 1
?開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱 16
?地下水の涵養推進に関する要綱 1
合計 149
注)制定数は原則としてデータベース更新時のものであり、その後の市町村合併等による変更を反映していない。
資料)三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成
注)市町村名は2004 年7月現在のもの

図1-4-2 市町村における条例・要綱等の制定状況
a)名称による分類
分類対象とした条例・要綱等は、地下水採取の適正化や地下水の保全・保護、もしくはその双方を名称に含むもの(同じ内容の要件であっても重要度や取扱い方により違うもの)が多く、計99 件(うち条例が76、要綱・規約が23)が該当する。
水資源の側面からの条例・要綱等としては、地下水だけでなく、水資源や水道水源全般の保全・保護に関する条例・要綱で、地下水の採取に関する規定を含むものが計16 件ある。
また、地盤沈下防止に関する要綱・指針は3件あるが、このほか地盤沈下に関連して、自家用天然ガスの採取規制に関する条例が12 件制定されている。
地盤沈下以外の環境面に関するものとしては、地下水の汚染防止と水環境の保全に関する条例が各1件ある。また、開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱のうち、地下水の採取に関する規定を含むものが16 件ある。このほか、地下水の涵養推進に特化した要綱が1件制定されている。
b)条例・要綱の内容の概要
市町村の条例・要綱等について、その内容を概観すると、井戸の設置者や工場・事務所等の設置者に対し、地下水の採取について事前の届出等を義務づけたり、設備の設置基準等を定めたりするなど、採取に関する許可・届出義務や設備設置の基準に関する規定を定めるものがほとんどである。
これらの多くは地盤沈下防止もしくは水源保護を目的としているが、都道府県の場合と異なり、目的が明記されず、対策のみが定められているものも多い。また、一部の市町村では、採取に関する規定と併せて、汚水排出に関する規定や涵養に関する規定も定めている。
c)地域別の分類
地域別に制定状況をみると、新潟県が最も多く30 市町村、次いで、長野県が20 市町村、山梨県が17 市町村となっている。
このうち、新潟県については、自家用天然ガスの採取に関する条例が多いほか、地下水の採取に関する条例・要綱等の中で、消雪用地下水の保全や用水量の削減について規定しているものが多い。消雪に関する規定は豪雪地帯である石川県や福井県でもみられる。
また、長野県や山梨県では、開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱等において地下水に関する規定を設けているものが多く、リゾート開発等に対応したものと考えられる。
これ以外の条例・要綱等の制定状況を地域別にみると、山梨県や静岡県の富士山麓、山梨県や長野県の八ヶ岳山麓、長崎県の雲仙山麓、熊本県の阿蘇山麓など大規模な火山の山麓地域や、山梨県や京都府のような盆地地形の卓越する地域、鹿児島県や沖縄県の島嶼地域において、地下水に関する条例・要綱等を持つ市町村が多い。
国の地盤沈下防止等対策要綱や都道府県の条例の制定状況と合わせてみると、広域的な地下水利用が行われている大規模な平野等では、国もしくは都道府県レベルの条例・要綱等が制定され、盆地や火山山麓、島嶼など比較的狭い範囲での地下水利用が活発な地域や、消雪対策、天然ガス採取、リゾート開発など固有の問題への対応が必要な地域においては、
市町村レベルで条例・要綱等が独自に制定されている。
一方、北海道、北東北、中国、四国では、道県、市町村いずれのレベルにおいても、地下水に関する条例・要綱等の制定が少ない。
これまでにみたように、地方自治体(都道府県、市町村)では、さまざまな条例・要綱等が制定されており、それらの中には規制を伴うものもあるが、地域の実情に即した形で地元に定着し、地下水の地域特性に応じた地下水の保全・利用への取り組みに寄与しているものと考えられる。
第2章 地下水をめぐる最近の動向と地下水保全・利用に係る課題
ここでは、地下水をめぐる最近の動向を調査し、その結果を通して必要な課題を把握する。
まず、わが国の水をめぐる諸問題、水需給全般の状況や、近年の地下水障害等の状況について整理する。次いで、水に関する世界情勢とわが国との関係及び動向が整理される。
2.1 わが国の水需給に関する動向
(1)わが国の水需給動向
?水需給の見通し
わが国の水資源政策の推移をみると、食料の確保と国土の保全が最優先された戦後復興期を経て、高度成長期には、都市部の人口急増や急速な経済発展に伴い都市用水を中心として水需要が急増し、これに対応するために本格的な水資源開発が進められたが、水質汚染や地盤沈下等新たな公害や環境問題が発生した。水資源開発が需要に追いつかない状況は、わが国の経済が安定成長期に入った後も継続した。このように戦後のわが国の水資源政策には、一貫して需要増加に対応した供給拡大が求められてきた。
近年は、水資源施設の充実、人口増加率(出生率)の低下(図2-1-1、図2-1-2 参照)、経済の安定・成熟や国民生活の質的向上等に伴い、渇水等の異常気象時を除き平常時の水需給のギャップは縮小しつつある。また、総人口の減少局面を迎えたことから、水需給の将来に対し、短絡的に楽観視する声もある。
しかし、気象変動に伴う利水安全度の低下や、都市域への人口の緩やかな集中が続くことが予想されることから、平常時はもちろんのこと、特に異常渇水、災害等緊急時の対応の充実が必要である。さらに、水の重要性を国際的視点から鑑みれば、長期的に国家戦略として水資源を総合的かつ戦略的に確保・管理していく必要がある。
図2-1-1 わが国の総人口の推移と予測
図2-1-2 わが国の年齢3区分別人口割合の推移と予測(中位推計)
?安全で良質な水供給への要請
健康志向や安全・安心への関心の高まりの中で、安全で良質な水供給への国民の要請はさらに増大している。その要請の一つは飲料水の消費に現れている。最近、市販ミネラルウォーターの生産量と輸入量が急増している(図2-1-3 参照)。2004 年をみると、国内生産量と輸入量をあわせ1,627 千キロリットルが消費されており、10 年前の消費量の約3倍である。
これを一人あたりに換算すると、年間で一人約13 リットルのミネラルウォーターを使用していることとなる。一人一日あたり飲料水必要量を3リットル(市町村等で防災上必要な備蓄量の目安とされる値)として計算すると、年間の飲料水必要量の約1%に相当する。
図2-1-3 ミネラルウォーター類国内生産及び輸入量の推移
(2)水需給に関する安定性
?気象変動に伴う利水安全度の低下への対応
近年、少雨年と多雨年の変動幅が次第に増加し、渇水年の年降水量が減少傾向にあるのみならず、年最大連続無降雨日数(降水のない日が連続する最も長い期間)も長くなる傾向が認められている。こうしたことから、ダム等の水資源開発施設が計画された当時の開発水量を安定して供給できないなど、水供給の利水安全度(実力)が低下しており、気候変動が国内の水需給バランスに与える影響が顕在化しつつある(図2-1-4 参照)。
今後も、こうした降水特性の変化や地球温暖化等に起因する気候変動により、水供給の能力低下が一層加速する恐れがあるとともに、これまでの計画規模以上の渇水の危険度も増加している(図2-1-5 参照)。
図2-1-4 日本の年降水量の経年変化
図2-1-5 気象変化による水資源開発水量の利水安全度(実力)低下(木曽川水系の例)
?大都市圏域への人口集中への対応
わが国の総人口は、2025 年時点でも全国で1.2 億人前後と1980 年代の水準にあると予測されることから、年齢別人口構成の変動はあるものの生活の質の向上志向や都市型生活の利便性を容認する限り、水需要が急減することは考えにくい。現状の地方圏の実情では人口減少が避けられないだろうが、地方ブロックの中枢都市以上の大都市圏域では、統計資料の外挿の上で、人口の緩やかな集中が続くと予測されている(図2-1-6 参照)。
大都市圏域は、圏域内外より供給できる1人あたり水資源量が少ないことに加え、社会基盤の高度化や高齢化、生活様式の変化等により、給水制限や断水時の社会的影響も増大している。大都市圏域では、利水安全度の低下が高度化した都市機能の持続と維持に深刻な影響を及ぼす恐れがあり、危機管理の視点から対応の必要性が高まっている。
図2-1-6 都市と地方の人口の推移と予測
(3)地下水資源の需給見通し
これまでに述べたわが国の水需給状況と今後の動向を踏まえると、将来の地下水資源の需給見通しは以下のように考えられよう。
* 安全で良質な水供給の要請から地下水資源への需要が高まる可能性がある。
* 気象変動を踏まえた利水安全度の確保や、都市部の住民生活や都市機能の持続・維持の観点から、地下水資源への需要が高まる可能性がある。
2.2 新たな地下水障害と地下水源開発の動向
これまで地下水障害といえば、地下水の広域かつ長期にわたる揚水利用によって生じる地盤沈下、井戸枯れ、塩水化などを指したが、近年、渇水時の短期に集中する地下水利用に伴う地盤沈下が新たに問題となってきた。ここでは都市地下構造部への地下水の悪影響や新しい地下水開発・利用によるインパクト等も含め、主として量的側面に焦点を当てて広い視野で検討を加える。
(1)渇水時の地下水位(水頭)低下と地盤沈下
多くの地域では地盤沈下が沈静化し、地下水位・水頭(被圧帯水層)の大幅な低下はみられなくなってきているが、数年に一度生じる渇水時(図2-1-4)には、主要な都市域で短期的な低下がみられる(図2-2-2、図2-2-3参照)。これは、地表水が減少して河川水の取水制限が行われ、代替水源として地下水の利用量が増加することや、少雨により涵養量が少なくなることが要因と考えられている。
地下水位・水頭の低下は、地盤沈下などの不可逆かつ蓄積する障害を招く恐れがあり、一度生じると回復は容易ではなく、将来にわたる大きな問題となることから、渇水時には以下のように対応し、地下水位・水頭の低下を防ぐことが求められる。
1) 渇水時における地下水利用状況の把握・地下水位低下の要因特定
従来の年単位の地下水採取量の把握に加えて、渇水が起こりやすい地域、渇水が起こりやすい時期には、月単位などより詳細な地下水採取量の把握を行うとともに、地下水位の低下の要因を特定する必要がある。
2) 渇水時における地下水採取抑制・自粛の要請
渇水時における地下水位低下の要因を特定した上で、地下水利用の限界採取量あるいは管理基準地下水位を設定し、基準を超えた際には、利用者に対して地下水採取の抑制を要請する仕組みづくりが求められる。
例えば、生活用水の地下水依存率が高い福井県大野市では、扇状地の水田の水がなくなる11 月頃の地下水位が最も低くなり、これまでに大規模な井戸枯れが生じた経緯から、独自の地下水警報発令基準を設けている。近年、地下水位の低下が著しく、たびたび節水を呼びかける警報が出されている。
図2-2-1 渇水時の地下水位低下のメカニズム
図2-2-2 渇水年における地盤沈下の進行
図2-2-3 要綱地区(筑後・佐賀平野)における地盤沈下面積と地下水採取量
(2)地下水位(水頭)上昇による地下構造物への揚圧力による障害
揚水規制や地下水環境の保全意識の高まりにより、近年では、地盤沈下地域の数、面積ともに減少し、地盤沈下は沈静化しつつある。
しかし、首都圏では、地下水採取の法的規制によって、逆に地下水位が回復・上昇し、東京駅や上野駅などの鉄道駅の地下部分が浮き上がる等の新たな問題が発生し、JR東日本ではアンカーを埋めるなどの地下水位上昇対策工事(東京駅:1999 年、上野駅:1997年)を行った。また、大阪市では、地盤沈下を防ぐため地下水の採取を規制してきたが、現在は逆に地下水位が上昇し建物が浮いたり、地下街や地下鉄のトンネルへの湧水増等の事例が出てきている。
地下水位の上昇は地震災害時に液状化を引き起こす可能性など、防災上の問題も指摘されている。
このように、東京都や大阪市など大都市圏の限られた地域の問題ではあるものの、地下水位の上昇に伴い、地下水位が大幅に低下した時期に計画・建設された地下構造物が浮き上がるなどの障害がみられ、所有者や管理者による対策が実施されている。今後、このような国土の脆弱化をもたらす地下水位の上昇を防ぐために、地下水環境保全を促す地下水位を定めた上で、利用可能な範囲内で地下水採取を行うなど、一定の地下水位を維持する施策が求められる。
(3)ミネラルウォーターの生産拡大の動向
ミネラルウォーター市場の拡大に伴い、大手飲料メーカーだけでなく、全国各地で地下水を活用した飲料水ビジネスが活発化している。現在、国内で約400 社、450 銘柄のミネラルウォーターの飲料水があると推計されている。
現在、国内生産されているミネラルウォーターの生産量は、国内で使用されている地下水使用量全体(124.1 億?)の約0.01%にとどまり、現時点ではその占有率は低いが、大量採取が行われているような地域においては、この割合は今後高くなると想定される。
大手飲料メーカー等は山間部などの水源を確保し、地下水の大量採取を行っているが、現在のところ、この新たな地下水採取によって、周辺の地下水利用者への影響や、地下水障害等は特に報告されていない。この動向に対して行政は、水源地下水の状況や利用可能量を見極めた上で、必要な対応が求められる。
また、全国で最もミネラルウォーターの生産量が多い山梨県では、自治体が地域資源からの恩恵を受けている事業者に対して税負担(例えば、1リットルあたり0.5〜1円の税率で、2.5〜5億円の税収見込み)を求めることを検討した事例もある。
(4)地下水新ビジネスの参入
近年、水質改善膜ろ過技術や井戸の小口径高揚程ポンプの開発に伴い、企業、農漁業団体、サービス業、公的機関等の専用(自己)水道による地下水利用が新たに増加している。
特に、ホテルや病院、ショッピングセンターなど、緊急時の自己水源確保を求められる個別水道利用施設で導入が進んでいる。
この個別水道利用施設の地下水利用では、20〜30mの浅層家庭用井戸と異なり、100m以深の深井戸からのくみ上げが目立つ。浄水膜ろ過プラントは小型な設備であれば3,000万円程度の投資で済み、また、揚水機のリースであれば投資リスクを負う必要が無いなど、利用者にとって初期負担が比較的小さいことも普及の要因となっているものと思われる。
地下水の採取規制などがない地域では、利用者にとっては、水質に問題がなければ揚水コストを削減することができる。さらに、地震などの災害時に備え2つの自己水供給システムを有することができるというメリットもある。
現在のところ、これらに伴う地下水障害は顕在化していないが、規制対象から外れた地下水揚水施設については、現行法制度では利用実態の把握が困難であり、採取量が把握できない状況となっている。
また、水道事業を行う自治体において、この種の地下水採取に伴い、水道水の利用量減少による減収が懸念されている。
(5)深層地下水の開発
地下水資源は、淡水そのものを利用の対象とするのみならず、温泉・鉱業や深層水の新規開発にも拡大して目が向けられている。とりわけ都市型の商業施設や娯楽施設では深層地下水が多目的に活用されている。
(6)地下水の発展的利用・可能性へ向けた議論の動向
昨今、地下水の都市ヒートアイランド現象軽減のための利用など、いくつかの新しい発展的活用へ向けた議論がなされている。
2.3 地震災害等、緊急水資源需要への対応
(1)地震災害時における問題点
わが国では、1995 年の阪神・淡路大震災をはじめ、2004 年新潟中越地震、2005 年福岡県西方沖地震など、大きな被害を伴う大地震が発生している。これらの地震災害時には、各用途に応じた緊急的な水の確保が問題となった。阪神・淡路大震災においては、井戸や湧水を雑用水として利用したケースが報告された。また、震災時には揚水ポンプが停止し、急激な地下水帯水層の水圧力上昇により水があふれ出たが、この水が震災時のトイレ用水や復旧工事の際の散水などに活用された注)。
その他に新潟中越地震では、液状化による被害や消雪パイプの破損も問題となった。
表2-3-1 阪神・淡路大震災における水利用に関して報告された問題点
分類 分類 問題点
用途別 消火活動 ・消火栓が使用できず、消火活動の大きな障害になった。
医療活動 ・病院には特別に給水活動を行う必要があった。
飲料・炊事 ・市民は、飲料用水として、市販の水を確保した。
トイレ洗浄 ・量を必要とするトイレ用水は、その確保とともに運搬も大きな問題だった。
表2-3-2 新潟中越地震における水需要及び地下水利用に関する問題点
・被災地すべての避難所で県が実施した生活実態調査によると、「トイレが不便」という避難所が3割に達した。
・地震による液状化現象により、マンホールが浮き上がったり、路面が割れて盛り上がるなどの被害が生じている。これにより除雪車が走行できない等の問題が生じた。
・消雪パイプが破損したが、ガスや水道の復旧作業が優先されるため、消雪パイプの復旧が遅れ、雪対策が遅れる等の問題が生じた。
なお、地下水位の上昇による大地震発生時の液状化現象の危険拡大も指摘されている。液状化現象とは、地下水で満たされた地層(地盤)が地震動によりその体積を減じ、その分、間隙にあった水が上方に放出され、地盤内に余剰の水があふれた結果、地層が液状流動化することを言う。これにより、地上・地下のライフライン、構造物等が重大な被害を受ける可能性がある。
さらに、地球温暖化による海水面の上昇が、沿岸・臨海域の地下水位上昇や地盤の液状化強度の低下をもたらす可能性も指摘されている。
注)震災時の水の確保に関する研究会「大都市における大規模震災時の「水」の確保について(案)」(阪神・淡路大震災での状況)参照
(2)地震災害への対応
?緊急水需要
a)経過日数でみた水需要
大規模震災時に想定される水需要を、用途及び発生場所の点から経過日数に即して整理したものが図2-3-1 である。災害直後から3日目頃は消火用水、医療用水及び生命の維持に必要となる最小限の飲料水の確保が不可欠となる。また、被災生活が開始されると、飲料水だけでなく炊事、トイレなどのための水需要が発生するほか、入浴や洗濯のための生活用水が必要となる。
さらに、災害後概ね4日目以降で復旧作業が開始されると、生活用水の拡充とともに、産業復活や防塵、復旧工事用の水需要が発生する。
図2-3-1 地震被災時における水需要
b)用途別にみた水需要
地震災害時における水需要はその用途に応じて、必要となる水量や水質は異なる。例えば、災害直後に多量に必要となる消火活動や、生活用水の中でもトイレ洗浄用水は水質への要求度は高くない。一方、医療活動の水や飲料・炊事用水は清浄な水質が求められる。
表2-3-3 地震災害時における用途別にみた水需要
?応急水供給
地震災害時に利用が想定される、都市における水の所在は以下の通りとなっている。河川・池・湖沼水や海水などは大量に供給可能だが、水質が保証されず、取水ポイントが限定される。また、雨水や再生水は比較的良質な水であろうが、専用の設備が整備されていることが必要となる。
このような中で、地下水は、清浄な水質が期待できる身近な水資源として、飲料や医療用途に活用できる可能性があるが、事前の十分な水質検査や、地震時における地下水脈への影響等を考慮して利用する必要がある。
表2-3-4 地震災害時における水供給源別にみた特徴
2.4 水に関する世界情勢
情報、経済、物流のグローバル化が進む現在、それらを支える基盤である水資源や水政策が今後の日本でいかにあるべきかを考えることは、時代の要請と言えよう。ここでは世界的な水問題について、米国の水事情概況及び地表水・地下水を合わせた総合的な水資源管理をめざす欧州の取り組みを紹介する。
(1)世界的な水問題とわが国の関係
?世界的な水需要の拡大と地下水障害の発生
18 世紀産業革命以降の世界人口の増加や、農業、とりわけ灌漑農業の発展は、淡水の消費を飛躍的に増加させた。例えば、中国・黄河の過剰取水による流況異変、中央アジア・アラル海の灌漑取水による水位低下が招く湖面積の縮小など、世界各地で水が不足する状態を生じさせている。
米国は図2-4-1に示すように、西経100 度と120 度に挟まれた全国土(936.3 万k ?)の約4割が年降水量500mm 程度の乾燥地帯であり、西経100 度以東は降水量に恵まれた(例えば、ニューオーリンズの年降水量1,584mm)温帯多雨国土である。この東西を二分する気候は、地形と地質が相まって固有の農業を発展させてきた。図中の乾燥地帯はシェラネバダ山脈とロッキー山脈に挟まれた高地グレートベースンとロッキー山脈の東側グレートプレーンズに拡がり、小麦生産や遊牧業及び人工灌漑農業が広大な農地で行われた。
多量の水を必要とする灌漑農業には、化石水ともいえる深層地下水が利用されている。図中ではこの地域の水不足分布が概観されている。
地下水についても、米国・グレートプレーンズでは深刻な地下水位の低下が生じている。
この「センターピボット(Center Pivot)方式」では、1つの井戸で毎分10 ?の地下水を揚水し、井戸の本数が数千本にもなるため、年間約7,500 万?もの地下水を利用するが、涵養量は年間約800 万?にとどまるため、過去30 年間で地下水位は平均12m、最大30mも低下した。この結果、耕地面積は1978 年〜1988 年の10 年間で100 万ha 減少した。
図2-4-1 米国の水不足地域の分布状況
?世界的な水問題とわが国の関係
国連環境計画や国連人間居住委員会、ユネスコなど23 の国際機関などが共同で発表した「世界水開発報告書」(2003 年3月)によると、半世紀後には最悪の場合で世界人口の8割にあたる70 億人が淡水不足に直面すると予測しており、水問題は21 世紀の世界的な課題だと警告している。
島国日本は、当面、水需給ギャップが縮小傾向にあり、国際河川や国際湖沼も当然ながら存在しないため、直接的な水に係わる国際紛争はないが、無関心ではいられない。その理由は、例えば、水資源に直結するわが国の食料自給率は熱量換算で2000 年には約40%まで低下しており、フランス、アメリカ、ドイツなどの食料自給国と比較して非常に低い。
食料の生産には水が使用されることから、わが国は食料等の輸入を通じ間接的に海外の大量の水を消費しており、その総量は年間640 億?と見積られている(図2-4-3参照)。
世界的な水危機の状況が、今後ますます激化すると予想される中、これに関する世界の経済、社会活動の変化とりわけ食料問題は、物流・経済を通じて日本経済や社会問題に直結している。今後の水資源政策は、このような実情も視野に入れながら、より好ましい水資源を総合的かつ戦略的に確保、管理していかなければならない。
図2-4-3 日本の仮想投入水総輸入量
(2)EU政策「水枠組み指令」
世界的な水危機に伴い、総合的・戦略的な水資源政策が求められる中で、わが国の地下水保全・利用のあり方を検討する際の参考に資するため、ここでは、特に地下水利用の長い欧州における取り組みを紹介する。
欧州では、古代ローマ時代から地表水よりも地下水を優先して使用してきた経緯がある。その伝統は、現在でも特に生活用水において継承されており(鯖田、岩波新書、2001)、
その宗教的とも言える思想は、地下水源の保全に向けた欧州先進国の取り組みの中で継承されている。
近年、EUでは、加盟国に統一した指令として、流域単位での水管理を目指す「水枠組み指令」が新たに発効された。ここではそれに着目して、その背景や考え方、水政策と地下水に関する動向等について言及する。
?「水枠組み指令」(EU Water Framework Directive)の背景
a)EUの概要
欧州連合(EU:European Union)は、「経済的な統合を中心に発展してきた欧州共同体(EC)を基礎に、欧州連合条約(マーストリヒト条約)(1993 年発効)に従い、経済通貨統合を進めるとともに、共通外交安全保障政策、司法・内務協力等のより幅広い協力をも目指す政治・経済統合体」である。従来の国際機関などとは大きく異なり、構成国からの国家主権の一部の委譲を前提に、域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成し、政治的にも「一つの声」で発言する等、いわば連合国家に準ずる存在である点が大きな特徴である。
表2-4-1 EUの概要(2007 年1月現在)
b)欧州における水問題の状況
「水枠組み指令」制定の背景となった欧州における水問題の状況について、「水枠組み指令」では以下の各点があげられている。
*欧州連合の全地表水の20%は、深刻な汚染の危機にさらされている。
*欧州の飲料水の約65%は、地下水でまかなわれている。
*欧州の都市の60%は、地下水資源を過剰に採取している。
*湿地帯の50%は、地下水の過剰開発により「危機的状況」にある。
*1985 年以降、南欧の灌漑地が20%増加している。
EUにおいては、これまでにも主に水を保護するための政策や法律が策定されてきたが、「欧州連合の環境−1995」では、上記のような背景を踏まえ、EU内の水について、量的のみならず質的にも保護アクションが必要であることが指摘されている。
?「水枠組み指令」の概要
水域を良好な状況にすることを目的として制定された「水枠組み指令」(EU WaterFramework Directive)は、正式名称を「水政策分野での共同体アクション枠組みを構築する2000 年10 月23 日の欧州議会及び評議会指令2000/60/EC」(Directive 2000/60/EC ofthe European Parliament and of the Council establishing a framework for the Communityaction in the field of water policy)と言い、2000 年12 月に発効した。
「水枠組み指令」は、地表水や地下水などすべての水資源を対象としており、欧州全体で、地下水と地表水の統合的な管理を示した初の指令である。「水枠組み指令」を受けて、各EU加盟国は、地域性に応じたマネジメント計画等を作成し、それに基づく対策を講じることで、EU全体で水環境の保全・管理を進めていく仕組みとなっている。地下水の位置づけは地表水と同等であり、特に、第17 条では地下水に特化して汚染対策が記載されている。
「水枠組み指令」の特徴として、政治・行政的境界ではなく、河川流域単位での浄化及び管理の取り組みを導入していることがあげられる。各国はまず指令の対象となる河川流域を指定し、適切な管轄当局を含む行政整備を行うことが義務づけられている。国際河川流域についても、関係国間で調整し、同様の指定を行わなければならない。これらの河川流域には、言うまでもなく地下水が含まれる。
また、「水枠組み指令」では、水環境の維持と改善を目的としており、主な対象は水質である。水量のコントロールは水質対策の付随的な要素とされており、良質な水を確保するためには、各国で、質と同時に量に関する対策も実施すべきであるとされている。良好な地下水状態とは地下水の量的状態、化学的状態の両方が良好であることを指すとされて
いる。
以下に、「水枠組み指令」の構成及び概要を示す。
a)「水枠組み指令」の構成
「水枠組み指令」は以下のような条文から構成されている。
第1条 目的
第2条 定義
第3条 河川流域地区内での行政整備の調整
第4条 環境目的
第5条 河川流域の特徴、人間活動による環境影響のレビュー、水使用の経済分析
第6条 保護地区の登録
第7条 飲料水の対象とする水域
第8条 地表水状態、地下水状態、保護地域のモニタリング
第9条 水サービスの費用の回収
第10条 点源、拡散源についての組み合わせアプローチ
第11条 対策プログラム
第12条 加盟国のレベルで対処することができない問題
第13条 河川流域マネジメント計画
第14条 情報公開とコンサルティング
第15条 報告
第16条 水汚染に対する戦略
第17条 地下水の汚染防止、コントロールに関する戦略
第18条 委員会報告
第19条 将来の共同体対策計画
第20条 本指令に対する技術的な調整
第21条 規制委員会
第22条 廃止及び過渡的条項
第23条 罰則
第24条 実施
第25条 効力発生
第26条 送付先
付録
b)「水枠組み指令」の特徴
上述に構成されている「水枠組み指令」について、ここでは主な特徴を整理する。
■環境目的
主な環境目的は、すべての水域を2015 年までに良好な水質状態にすることである。
□地表水について
・加盟国は、地表水全体の劣化を防止するための必要な対策を実行しなければならない。
・加盟国は、すべての地表水体(bodies of surface water)を保護、整備、修復しなくてはならず、本指令発効(2000 年12 月)後少なくとも15 年間は良好な地表水状態を達成しなければならない。
・加盟国は、良好な生態的潜在力、良好な地表水化学状態を保つために、本指令発効後少なくとも15 年間は、人工的あるいは大幅に改良した地表水体を保護し整備しなくてはならない。
・加盟国は、重点物質による汚染を徐々に減らし、優先的危険物質の排出、放流、損害を排除、あるいは徐々に排除するために、必要な対策を講じなければならない。
□地下水について
・加盟国は、汚染物質が地下水に入ることを防ぎ、あるいは制限し、地下水全体の状態が悪化しないようにするために必要な対策を講じなければならない。
・加盟国は、本指令発効後少なくとも15 年間は良好な地下水状態を達成することを目的として、すべての地下水体を保護、整備、修復し、地下水の揚水量と涵養量のバランスを確実にしなくてはならない。
・加盟国は、地下水の汚染を徐々に減少させるために、人間活動の影響により地下水中の汚染物質の濃度が著しくあるいは持続的に増加する傾向にある場合、それを修復するために必要な対策を講じなければならない。
■現状把握
本指令を受けて、各河川流域地区で以下の事項を実施しなければならない。
○河川流域の特性把握
○地表水あるいは地下水に対する人間活動の影響の把握
○水使用の経済分析
○飲料水として抽出する水(1日平均供給量が10 ?超または50 人超に供給)または将来飲料水として使用される水のモニタリングなお、飲料水として抽出する水源は保護地域として登録が義務づけられる。
本指令を受けて、各国は2006 年までに(発効後6年以内)水状態のモニタリング・プログラムを設定し、実施しなければならない。地下水については、化学的状態及び量的状態の把握が求められている。
■水サービスのコスト
本指令では、水は商用製品とは異なり、むしろ遺産のように保護しなければならないとされているが、同時に水サービスコストの回収も考慮すべきと明記されている。加盟国は2010 年までに以下の実施が求められている。
?水料金政策によって水使用者が効率的使用を行った場合には、適切なインセンティブを与えられるようにして、環境目的に貢献するようにすること。
?経済分析に基づき、汚染者負担の原則を考慮して、産業、家庭、農業の異なる水利用者が、水サービスコストを適切に負担すること。
■対策
各国は、河川流域地区ごとに目的を達成するため、対策プログラムを実施しなければならない。このプログラムでは、国内レベルでの既存の法令に基づく対策の中から、本指令で求められている基準を定められた期限内に達成することができる活動を特定し、採用することができる。
■流域マネジメント計画
各国は、河川流域地区ごとに河川流域マネジメント計画を2009 年までに作成し、運用しなければならない。複数の国にまたがる国際河川流域マネジメント計画は単一の作成が義務づけられている。河川流域マネジメント計画は6年ごとにレビュー・更新される。その際には情報公開を徹底しなければならない。
■水汚染に対する戦略
欧州議会と欧州評議会は汚染物質あるいは汚染物質グループによる水汚染に対して対策を講じなければならない。欧州委員会は汚染の要因となる重点物質や重点危険物質を明確にし、それに対する対策について提案が義務づけられている。
これを受けて、欧州委員会は2001 年1月、新水枠組み指令の最初の規制対象として指定する32 種類の「優先物質」リストを提案、同年11 月に採択された。特定の有害物質については、20 年以内に水域への排出を段階的に停止することとされている。
地下水については、第17 条の中で記述され、地下水の汚染防止、コントロールに対する戦略として、欧州議会と評議会は、
?良好な地下水化学状態を評価するための基準、
?重大な継続的上昇傾向の確認及び傾向が逆転した地点の定義、を含む提案を行うこと
が義務づけられている。
また、第8条では、各国が策定する水状態のモニタリング・プログラムの対象として、地下水については化学的状態、量的状態があげられている。
■スケジュール
EU加盟各国は、2003 年12 月までに本指令の遵守に必要な法律、規制、行政条項の発効が義務づけられている。本指令の主要事項における期限は以下の通りである。
期限 内容
2003.12 ・本指令の遵守に必要な法律、規制、行政事項などを発効・流域連携の組織化
2004.12 ・水への影響分析を完了(経済分析を含む)
2006.12 ・水マネジメントの基盤となるモニタリング・プログラムの実施
2008.12 ・河川流域マネジメント計画が市民に公表される
2009.12 ・最初の河川流域マネジメント計画が発効される
2015.12 ・良質な状態の水となる
?「水枠組み指令」を補完する地下水に関する指令及び動向
2003 年9月、欧州委員会は、水枠組み指令の第17 条に基づき、地下水汚染防止に関するEU指令案(Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of groundwater against pollution 2003/0210(COD))(以下「地下水指令」)を発表した。「地下水指令」は加盟国に対し、地下水質のモニタリングを義務づけ、EUの既存の法令基準(窒素分、植物保護剤、殺生物性製品など)の遵守状況を把握するよう求めている。EUの法令で対象とされていない物質については、加盟国が2006年6月までに上限値を設定することとされている。汚染の程度が、「期間」と「環境上の重大性」の観点からみて、一定のレベルを超える場合には、加盟国は汚染悪化を防止する対策を講じなければならない。
水質基準値または上限値の75%を超える場合は、環境上重大な状況にあるとされる。この他、地下水汚染を防ぐため、有害物質の間接的な排出(地面や土壌中への排出)を禁止または制限する条項も盛り込まれている。
地下水指令の構成は以下の通りである。
第1条 内容
第2条 定義
第3条 地下水の良い化学状態を評価する基準
第4条 閾値いきち*1
第5条 重大かつ悪化傾向の判断基準及び修復を行う出発点の定義
第6条 地下水への間接的な排出を防ぐまたは制限する施策
第7条 過渡的なアレンジメント
第8条 技術的な適合
第9条 実施
第10条 効力発生
第11条 実施者
付録
備考*1)EU の各加盟国が定める、地下水帯に危険な影響を及ぼすと見なされる汚染物質の限界値。国レベル、流域レベルまたは地下水帯レベルで定めることができる。
このほか、「水枠組み指令」に基づく2005〜2006 年の作業プログラムとして、地下水、環境状況、統合的流域管理、調査報告をテーマとする4つのワーキンググループが設置され、水枠組み指令の実施にあたって解決すべき課題の検討がなされている。
?わが国の地下水利用のあり方への示唆
このように、EU「水枠組み指令」では地下水と地表水を総括した水資源全体での統合的な管理を推進している。地下水を含めた流域圏を一つの単位として、行政的な境界を超えて水資源管理を行うことが求められており、2009 年までに河川流域マネジメント計画を発効することが予定されている。
わが国においても複数の自治体にまたがる広域的な地下水マネジメントを実践する上で、行政計画策定や実践に向けた方法や手順策定の参考となろう。
2.5 地下水の保全・利用に向けた課題
(1)水資源需要多様化と地下水への期待
これまでに述べたように、わが国の水需給は、将来の人口減少や経済成長の鈍化に伴いおおむねバランスする方向にあり、一方で、安全で良質な水供給に対する要請はますます強まる動向にある。他方、少雨傾向など気候変動に伴う渇水が従来以上に頻発かつ大規模化する傾向があり、利水安全度の低下がより懸念される大都市圏域を中心として、危機管理の視点からの備えの必要性が高まっている。大規模地震災害時には、まず水の確保が重要な課題となるが、身近にある地下水は、それに即応できる重要な水源となりうる。
さらに、地球規模の水危機の深刻化にあって、安全保障の観点や食糧確保等を念頭に世界の水問題へ対応していく必要がある。
今日、淡水資源そのものを支える降水量とその地域分布が地球規模の気候変動によって大きく変容しつつある中で、水資源需給の多様化や安全性を満たす新しい水政策の構築が国家戦略として急務である。そのためには、河川水や湖沼水を含む地表水資源と地下水資源の量的・質的特性を活かしつつ、両者を調和的に利用しうる方法論が必要である。
ここでは、以上の観点から、過去の地下水過剰利用とその障害を教訓にしつつ、地球時代における地下水資源のあり方の議論に先行して、考えられる課題を以下に整理する。
(2)水資源としての地下水の保全・利用に向けた課題
地下水の保全・利用のあり方を考えるにあたって、まず、地下水が重要な水資源であることの共通認識が不可欠である。その上で、水循環系の構成要素として地表水と地下水のデータ整備や利用実態の把握を行うこと、水資源として保全と持続的利用の最適なマネジメントを考えること、また、地下水の分布や利用形態は地域的に多様性に富むことから、地域特性に即した保全・利用のあり方を実現していくことが大切である。
?水資源としての共通認識の醸成
わが国では、高度経済成長期に過剰な地下水の採取が深刻な地盤沈下を招いた経験から、それが広域的な地盤沈下の要因となることについては共通認識が得られている。しかし、地下水は地形・地質の構成要素であり、土地所有状況とは関係なく個別の地下水利用が多かれ少なかれ他に影響を及ぼすといった地下水資源特有の性質は十分理解されていない。
また、地下水は地表水と比較してデータ整備や実態把握が個別的であるため、地下水資源マネジメントに結びつく情報として定着していない。
こうしたことから、今後、地下水を水資源として捉え、その保全・利用を図っていくための共通認識を醸成していくことが課題である。
?水循環系の構成要素としての地下水に関するデータ整備・実態把握
降水を源とする地下水は、地表水とともに水循環系の構成要素であることから、水資源として重要であるだけでなく、流域地表水の基底流量の安定化や洪水流出の緩和に寄与したり、豊かな水辺環境の保全・再生に重要な役割を果たしたりするなど、水循環系において多面的な役割を担っている。
EU「水枠組み指令」(2000 年)によると、地表水や地下水などすべての水資源を対象として、流域単位での統合的な水の管理をめざす取り組みが進められている。一方、わが国でも「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」のもとで、流域全体を視野に入れた水循環系の健全化に向けた取り組みが芽生えている。
こうしたことから、水循環系の構成要素として地下水の保全・利用を行っていく必要はあるが、地下水は地表水と比較して各種定量データが十分に整備されておらず、行政上も組織的にデータ蓄積・分析する仕組みが確立されていないことから、現状では、水循環系全体として、地表水に呼応して地下水を統合的に保全・利用できる状況にはない。
このため、地下水に関する定量データを整備しうる仕組み、例えば、地下水の水資源と
しての基本データ(地下水位・水頭、採取量、地質柱状図、利用実態、水文等)の電子デ
ータ化の推進が時代の要請となっている。その定量データに基づき、科学的な地下水資源・
保全計画を立てて、水循環系の構成要素としての地下水の位置づけや特性を明らかにした
上で、適切な保全・利用を図っていくことが課題となる。
?持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現
地下水は、一般に水質が良好かつ水温変化が少なく、大規模な貯水・取水・給水施設を
必要とせず安価に利用できることから、わが国では、特に経済復興・高度成長期の水需要
に応え、大量に利用され、地盤沈下問題が深刻化した。その対策として国や地方自治体に
よるさまざまな取り組みが進められた結果、地盤沈下はおおむね沈静化している。
以下に示す観点から、今後とも地下水障害を未然に防止するための十分な配慮が必要で
ある。
1) 依然として、長期的には地盤沈下が沈静化している大都市でも、渇水時に短期的・
局所的な地下水位の低下が地盤沈下を招いた(平成6年渇水等)。近年、少雨年の
降水量が減少傾向にあることや、年最大連続無降雨日数(降水のない日が連続する
最も長い期間)が長くなる傾向が認められることから、今後も渇水に伴う地下水位
低下が懸念されている。
2) 深刻な地盤沈下を経験してきた地域(東京、名古屋、大阪等)は、地下水の採取量
を抑制してきた結果、地下水位が回復、上昇に転じ、地下街や地下駅などの既設地
下構造物が浮き上がる問題が生じている。
3) 地下水はいったん汚染されるとその浄化が困難であることから、有機塩素系溶剤や
硝酸性窒素など地下水汚染が多様化していることを踏まえた地下水資源の水質保全
について、特に留意が必要である。
4) ミネラルウォーター生産のための地下水利用、揚水・ろ過技術の新技術を背景とし
た個別水道利用施設における地下水利用等が拡大している。
地下水は水循環系において一般的に滞留時間が長く、地盤沈下や水質汚染などの地下水
障害は、いったん生じると復旧が不可能であるか、もしくは長い年月を要する。このこと
から、持続可能性という観点に立ち、地下水をめぐる新たな動向が及ぼす影響についての
解明も進めつつ、地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染等を生じさせず、地下水の保全と
利用の最適なマネジメントを実現していくことが課題となる。
?地域特性に即した保全・利用のあり方の実現
地下水資源の分布や利用形態は、地形、地質、気候、植生等の自然条件や、人口、土地
利用、産業、歴史・文化等の社会経済条件によって地域ごとに大きく異なっており、多様
性・固有性に富んでいる。
例えば、わが国では、主要な地下水盆は平野や盆地に分布しているが、関東平野のよう
に複数の都県にまたがる大規模なものから、単一市町村にとどまる小規模な平地や扇状地
まであり、このほかに火山地域や石灰岩地帯にも帯水層が存在し、それぞれで地下水が利
用されている。また、水利用全体における地下水への依存度や、生活用水、工業用水、農
業用水といった地下水利用の用途別割合も、地域によってさまざまである。
このように地下水資源の分布や利用形態が異なれば、地下水資源の開発可能性や地下水
障害・汚染等の発生状況も千差万別である。このため、地下水の保全・利用に向けた取り
組みにあたっては、それぞれの地域特性に則した考え方や方法・体制等に基づいて対応す
ることが重要な課題となる(図2-5-1参照)。
地下水への期待と動向
■水資源としての地下水への期待
* 安全で良質な水供給への要請
* 気候変動等に伴う利水安全度の低下への対応
* 大規模地震災害時の水源確保
* 長期的な安全保障の観点からの水資源確保の必要性
■地下水をめぐる最近の動向
* 広域的な地盤沈下は概ね沈静化
* 渇水時には短期的・局所的な地下水位低下、 地盤沈下が発生
* 一部地域では地下水位上昇により地下構造物への影響も発生
* 地下水質汚染
* 新たな地下水利用形態( ミネラルウォーター、 地下水ビジネス)の拡大 等地下水の保全・利用の課題
* 水資源としての共通認識の醸成
* 水循環系の構成要素としてのデータ整備・実態把握
* 持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現
* 地域特性に即した保全・利用のあり方の実現問題の所在
* 水資源としての地下水、 および水循環の構成要素としての地下水についての共通認識が得られていない
* 地下水の諸問題について、 科学的な見地からの実態解明・要因分析が十分になされていない
* 水資源としての地下水資源の保全と利用の調和の社会的合意や理念が形成されていない
* 地下水の現状・動向は、 地域ごとの多様性が高く、 全国画一的な対応が困難
図2-5-1 地下水の保全・利用に向けた課題の概観
第3章 今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法
第2章では、地下水資源の保全・利用に向けた課題として、水資源としての共通認識の醸成、水循環系の構成要素としてのデータ整備・実態把握、持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現、地域特性に即した保全・利用のあり方の実現、という4つが抽出された。
これらの解決における科学的論拠は「健全な水循環系の構築」(新しい全国総合水資源
計画(ウォータープラン21)、国土庁、1999 年)に置かれる。ここではまず、健全な水循
環系の構築における地下水の位置づけや、水循環系の構成要素としての地下水の特性を踏
まえ、課題解決に向けた基本的な考え方を示す。
次に、これらを踏まえた地下水の適正な保全・利用を実現するための新しい方法論とし
て、「地下水資源マネジメント」の考え方を提案し、その具体的な手順について述べる。
さらに、その計画・実践にあたり、地域ごとの多様性、地下水の特性、特に地域規模と
の関係に着目し、地域規模に基づく類型別「地下水資源マネジメント」を提唱する。
3.1 健全な水循環系の構築における今後の地下水利用の基本的な考え方
ここでは、健全な水循環系の構築にあたって地下水の位置づけを明らかにし、地下水の
特性を地表水と比較検討した後、これらを踏まえ、課題解決に向けた今後の地下水利用の
基本的な考え方を提示する。
(1)健全な水循環系の構築における地下水の位置づけ
?健全な水循環系構築の背景
「健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて」(2003 年10 月、健全な水循環系構
築に関する関係省庁連絡会議公表)では、「健全な水循環系」とは「流域を中心とした一連
の水の流れの過程において、人間社会の営みと環境の保全に果たす水の機能が、適切なバ
ランスの下にともに確保されている状態」と定義づけられている。その具体的な姿は地域
ごとに多様であり、例えば、地下水障害や地下水資源の枯渇を生じない範囲で地下水が最
大限利用されている状態や、歴史的・文化的に重要な湧水の復活・維持といったような目
標の設定や地域特性に依る。
近年の都市化の進展は、降水の浸透機能を低下させ、都市型水害や、地下水の涵養力低
下を招いている。また、地域の文化資産ともいえる古くからの湧水を枯渇させたり、河道
への地下水からの涵養を減少させ、平常時の河川流量の減少も招いている。地下水採取・
利用とも重なって、水循環系の健全性が損なわれている。
こうしたことから、今後の地下水資源の保全・利用のあり方を考える上で、健全な水循
環系の構築という視点の重要性がきわめて高くなっている。
?水循環系における地表水と地下水の特性比較
地表水と地下水はいずれも水循環系の構成要素であるが、今後の地下水資源の保全・利
用の検討にあたって、水循環系における地表水と地下水の特性の違いに留意する必要がある。
両者の特性を概略比較したものが表3-1-1であるが、地表水との比較における地下水の
重要な相違点として、滞留時間の長さと実態把握の困難さ(時間・経費増、遅れ等)があ
げられる。滞留時間の長さは、過剰揚水等による井戸枯れ・塩水化等の地下水障害や地下
水質の汚染が一度生じると、その回復・改善に長期間を要することの要因となる。また、
実態把握の困難性や遅れは、水循環系全体として、地表水に呼応して地下水を統合的に保
全・利用できない要因となっている。
表3-1-1 水循環系における地表水と地下水の特性比較
(2)今後の地下水利用の基本的な考え方
?地下水資源マネジメントの論点
地下水に関するマネジメント注)は、広域の地下水資源利用に焦点を当てた「地下水資源
マネジメント」と個別の土地開発や地下空間開発によって起こり得る地下水環境に与える
悪影響の防止・軽減を目的とする「地下水環境マネジメント」の2つに分けられる(図3-1-1
参照)。なお、地下水資源マネジメントは図3-1-1 青色に示す。
健全な水循環系の構成要素をなす地下水は、流域地下水文区のもつ水源地域から平野部
までさまざまな地域特性を踏まえ、量・質及び環境を考慮し、総合的な観点に立った検討
が必要である。
そこで、本報告書では、健全な水循環系の構築という視点から、主に量的な側面に軸足
を置いた「地下水資源マネジメント」について、今後の地下水利用の基本的な考え方を示
すこととする。今後、各地域で地下水資源マネジメントの取り組みをそれぞれの地域で具
体化・実践するにあたっては、各地域の諸条件や水需給に適合した検討が必要であること
は言うまでもない。以下の議論は日本で典型的な平野地形を念頭に置いている。
地下水マネジメント
地下水資源マネジメント地下水環境マネジメント
量的な側面における地下水資源マネジメント
*持続的に利用可能な範囲での利用
*地盤沈下等の地下水障害の未然防止等
地下水理・水文環境の保全
*湧水の保全・復活
*都市再開発
*地下空間開発
*大規模土地開発等
地下水質環境の保全
*汚染源・物質の特定
*汚染対策
*モニタリング等
質的な側面も含めた地下水資源マネジメント
*用途別の水質への要請を踏まえた利用等
図3-1-1 地下水資源マネジメントの主な検討対象
地下水も水資源の1つと見れば、こういった水資源マネジメントの考え方は思想上の符
号はあっても、地下水資源マネジメント(groundwater resource management)では、地表
水と同様のマネジメント手法には馴染まず、いくつか違った点がある。
1) 地下水は帯水層が自然の貯水池の役割を持つため、地表水のダムや人造湖のように
人工的な貯水施設を構築することはほとんどない(地下ダムや人工涵養施設は限ら
れた条件でしか効果を発揮しないため、事例は非常に少ない)。
2) 地下水の利用計画、管理、調整作業は、地下水盆の構造・地質の多様性や利用規則
欠如の面もあって、地表水に比べはるかに複雑である。
3) 地下水管理の要となる効果的な地下水モニタリングが地表水のそれと比べ容易でな
い。
以上を踏まえ、第2章で抽出された課題の解決に向けた今後の地下水利用の基本的な考
え方を以下に示す。
?地下水資源の最適なマネジメント実現に向けた方法論と指針の必要性
地下水は一般に水質が良好で水温の変化が少なく、大規模な貯水・取水・給水施設を要
しない等の優れた特性を有していることから、多用途に利用される重要な水資源となって
いる。今後も安定した水資源として、また災害時の緊急水源として保全・利用していくこ
とが期待されている。
地下水資源は水循環系における回復可能な水資源でもあり、地下水収支のバランス(あ
る区域内における一定期間内の地下水の流入・流出の均衡状態)が保たれる範囲内で持続
的に利用していくことが可能である。
一方、地下水資源の利用がかつて深刻な地盤沈下等の問題を招いたことから、行政によ
る採取規制とともに地表水への水源転換が積極的に進められてきた。今日、全国的にみて
地下水資源の利用による広域的な地盤沈下はおおむね沈静化しているが、渇水時等におけ
る短期的・局所的な地下水位の低下や地盤沈下等の地下水障害は、復旧に長い年月を要す。
こうしたことから、地下水資源と国土を保全することに加え、持続的に利用可能な範囲
内で利用し、地盤沈下や塩水化等の地下水障害を招かないように、地下水資源の保全・利
用をマネジメントしていくことが昨今の要請となっている。
一方、地下水資源のマネジメントを推進する前提として、地下水は同じ水循環系の構成
要素である地表水と比較して、適正に保全・利用すべき水資源としての認識が醸成されに
くく、データ整備や実態把握が十分に進んでいるとは言えない状況にある。
こうした状況にあって、地下水資源の保全と利用のマネジメントを推進していくために
は、その方法論を明らかにするとともに、地下水管理者となる地方自治体の計画担当者に
対して、どのようにして地下水に関する意識啓発や広報・指導、地下水のデータ整備や実
態把握を行い、必要な施策を計画・実践・運用していくべきかをわかりやすく示す指針(ガ
イドライン)が必要である。
?適正採取量に基づく地下水資源の保全・利用のマネジメント
地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染等を生じさせず、持続可能な形で地下水の保全と
利用を最適にマネジメントしていくためには、以下に述べる「適正採取量」に基づき、そ
の範囲内で地下水資源の保全と利用の最適なマネジメントを実現していくことが肝要であ
る。
ある地下水盆において、ある一定の期間に利用可能な地下水の量(おおむね涵養量より
小さく地下水障害を起こさない量)を「適正採取量」とすれば、適正採取量と(実際の)
採取量の関係は、図3-1-2上で説明できよう。採取量が適正採取量を上回る場合には地下
水障害や地下水資源の枯渇が懸念され、採取量が適正採取量を超えない範囲内で利用して
いくことが必要条件となる。一方で、地域によっては、地下水位が上がりすぎないように
マネジメントしていくことも重要な課題となる。
一般に、地下水は特段の規制をしなければ、安価な水資源として利用ニーズが拡大する
傾向を採る。このため、地下水の涵養能力や地下水障害の発生しやすさなどにより決まる
適正採取量より実際の採取量が少ない状態にあることが好ましい。また、地
下水の適正採取量そのものの維持・拡大には、地下水涵養策や地下水資源の保全策を実施
する必要がある。
図3-1-2 適正採取量と採取量の関係からみた地下水の保全と利用の説明
?地域規模等の類型に即した地下水資源のマネジメント
地域の地下水に関する状況は、自然条件(地形、地質、気候等)や社会経済条件(人口、
土地利用、産業、歴史・文化、法制度等)に応じて地域ごとの多様性・固有性がきわめて
強いことから、地域特性に即した対応が必要である。特に、適正採取量に基づく地下水資
源の保全・利用のマネジメントにあたっては、地下水盆や帯水層の規模が重要な尺度とな
る。その規模は1市町村内で完結するものから複数の都府県にまたがるものまで大小さま
ざまであり、こうした規模の違いによってマネジメントの目的や方法にも違いが生じる。
また、地下水資源のマネジメントでは、行政が中心的な役割を果たすことが期待される
ため、都道府県や市町村といった行政単位との関係も重要である。
こうしたことから、地下水盆や帯水層の規模と行政単位に着目していくつかの地域単位
の分類を設けることで、多種多様な地域特性を類型化し、地下水資源マネジメントの目的、
方法等を明らかにすることが可能となる。具体的には図3-1-3に示すように、局所(地区
レベル)・小規模(市町村レベル)・中規模(都府県レベル)・大規模(複数の都府県レ
ベル)という4つの類型が想定される。
資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)をもとに作成
図3-1-3 地域類型に応じた地下水資源マネジメント等の概観
3.2 地下水資源マネジメントの考え方と手順
ここでは、3.1節に述べた今後の地下水利用の基本的な考え方を踏まえ、地下水の保
全・利用の方法論として地下水資源マネジメントを提案し、その考え方と具体的な手順を
示す。
(1)地下水資源マネジメントの定義と特徴
「地下水資源マネジメント注1)」とは、3.1節に述べた今後の地下水利用の基本的な
考え方を具現化するための手段であり、「健全な地下水文循環にあって、地下水障害や枯
渇を発生させない範囲で、地下水を水資源として持続的に保全・利用しうる採取(揚水)・
運営・管理の方法」と定義する。
その特徴は、科学的な知見に基づき、実態把握、計画策定、揚水マネジメント、観測・
モニタリング、評価・見直しを定量的に行うことにあり、そのプロセスの中核を成すのは、
その適正配分数値シミュレーションモデルを活用した対象地下水盆の適正採取量の数量化
と地下水位に基づいた管理・モニタリングにある。また、もう1つの特徴として、PDC
Aサイクルに基づく継続的な見直しを行い、科学的・定量的なマネジメントの精度を向上
させていくことがあげられる。
?数値シミュレーションモデルを活用した適正採取量の数量化
地下水資源マネジメントにあたっては、持続的にどの程度の地下水が利用可能であるの
かの定量的把握に基づいた計画の作成が必要となる。そのためには対象地下水盆の数値シ
ミュレーションモデルを構築し、これを用いて地下水障害を発生させず、かつ健全な地下
水収支を保つ地下水位のもとで、総採取量とその地域配分を科学的な手法で数量化するこ
とが求められる。
このように、数値シミュレーションモデルは、地下水資源マネジメントの根幹を成すも
のであり、揚水事業者と地下水管理者 注2)(国や地方自治体)の両者が地下水の保全・利
用に関する計画を策定する際に有用である。
数値シミュレーションモデルの作成にあたっては、計画対象地域における地下水に関す
る各種データを経年的に収集し、地下水や水文の実態把握、地質調査・分析を行うことが
前提として必要となる。
?井内地下水位・水頭を用いた地下水管理・モニタリング
地下水の保全・利用に関する計画を実際に運用し、地下水の管理に役立てていくために
は、適切な管理・モニタリングの手法が必要となる。地下水位の変動と地下水採取量とが
密接に関係していることに注目すれば、テレメーターシステムを活用することにより、リ
アルタイムで地下水位をモニタリングして採取量を適正に制御できる。
こうした視点から、地下水資源マネジメントにおける地下水管理・モニタリングの指標
として井内地下水位を用いることが有効と考えられる。地下水位の常時観測を行い、その
変化に応じて地下水利用者に採取量の抑制を要請すること等により、過剰揚水を緩和し、
地盤沈下等の地下水障害を未然に防止ないし軽減することが可能となる。また、地下水位
を用いた地下水管理・モニタリングは、即時的かつ容易に対策を実施できるという点で優
れ、予想外の水需要に伴う緊急的対策にも対応可能である(例えば、渇水時の地下水採取
量急増による地下水位の短期異常低下の回避対策、既存の水源の水質事故に伴う振り替え
水源確保等)。さらに、地域によっては、地下水位が上がりすぎないよう適切に管理する
ことにも活用できる。
地下水位を用いた地下水管理・モニタリングは、渇水時等において地盤沈下防止のため
の地下水採取量を緊急抑制する施策にも適している。
?PDCAサイクルによる継続的な取り組みのプロセス
地下水資源マネジメントは、調査・計画(P)→実行・観測・モニタリング(D)→評価(C)
→見直し(A)というプロセス(PDCAサイクル)をある程度反復しながら、継続的に取り
組んでマネジメントの精度を高めていくことが必要となろう。
一般に、地下水に関するデータ整備や実態把握がどの地下水盆でも十分に進んでいると
は言えず、数値シミュレーションモデルを用いた地下水資源マネジメントの実践例も限ら
れていることから、地下水資源マネジメントの実施当初から精度の高い将来予測を行える
わけではない。また、地下水涵養量や帯水層水理パラメータの事前の把握は簡単ではなく、
推算せざるを得ないこともあり、シミュレーションモデルは、実際に運用しながら改良を
加えていくことで、精度を高めていく必要がある。
このため、地下水資源マネジメントの実施にあたっては、当初はある程度、実測値や経
験則に基づいて計画を策定し、実際に運用しながら評価・見直しを重ねていくことで、シ
ミュレーションモデルの精度を高めたり、計画の実効性を高めていったりするといった、
継続した取り組みが必要である。
(2)地域類型別にみた地下水資源マネジメントの方向性
地下水資源マネジメントのコンセプトは、地域特性に即した取り組みが重要であること
から、前述した地域規模による4つの地域類型(図3-1-3参照)に沿って以下に示す。
?局所規模レベルの地下水資源マネジメント
局所規模(1km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に小規模な地下水源の確保(井
戸のさく井)にあたって、個別の揚水井の配置や採取量の設定が対象となる。この場合、
対象となる地域の広がりは、地下水盆というより帯水層と呼ぶのが相応しい地区レベルの
規模である。
小規模な地下水源の確保においては、必要な採取量が継続的に確保できることと、地下
水資源開発による影響(周辺井戸の枯渇、地盤沈下の発生等)が周辺に及ばないようにす
ることの2点が重要である。
このため、既存の周辺井戸の影響や地盤沈下を防止しつつ、必要な採取量を確保するに
あたって、揚水井の適正深度や適正配置(適正な井戸間の距離)、個々の井戸の適正採取
量を算定し、井戸設置の申請に対してどのような許可制度や許可基準を設定するかという
ことが重要となる。これらの検討方法としては、水収支と水理学的な検討が求められ、揚
水井戸理論を用いた定量的検討が想定される。観測・モニタリングにあたっては、採取量、
地下水位、地盤変動量等が指標となる。
?小規模レベルの地下水資源マネジメント
小規模(数km2〜数十km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に市町村(単一の市町
村もしくは複数の市町村による組合等)の行政区域内で完結している地下水盆が対象とな
るが、近隣市町村にまたがる平野や盆地の一部地域が対象となることもある。
局所レベルのような個別井戸ごとではなく、一定の広がりをもつ地域を対象として、複
数の揚水井を集合体として捉え、対象地域内での地下水収支や地下水採取量の地域配分等
を取り扱うことになり、対象地域外の近隣市町村に地下水資源開発の影響を及ぼさないよ
うにしつつ、必要な採取量を確保することが地下水資源マネジメントの要点となる。
このため、地下水収支バランスの保たれる範囲内の適正採取量とともに、対象地域内で
の適正な地域配分や用途別配分、採取許可方法等を明らかにする必要がある。検討方法と
しては、数値シミュレーションモデルを用いて地下水盆や帯水層をモデル化した上で、水
需給の現状や将来見通しに基づくシミュレーションを用いて、利用可能地下水資源量や適
正採取量、揚水井の分布密度、安全地下水頭・採取量等を設定する。
また、観測・モニタリングの方法としては、テレメーターによって地下水位や地盤変動
量をリアルタイムで把握するとともに、渇水時等の短期的な地下水位低下に対する対応と
して、管理水位を設定し、警報・注意報の発令による地下水採取者への採取量抑制の要請
を行うこと等が考えられる。
?中規模レベルの地下水資源マネジメント
中規模(数十〜数百km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に都府県レベルで完結
している中規模な地下水盆(熊本地域等)が対象となる。
地下水資源マネジメントにあたっては、対象となる都府県の地域内において、地下水収
支バランスの保たれる範囲内で、かつ地下水資源開発に伴って地下水障害等の悪影響を防
止しつつ、必要な採取量を確保することが重要となる。
このため、計画においては、地下水資源量とその地域配分を適正化することや、広域的
な地下水の観測・モニタリング(地下水位、地盤変動量等)を通じた地盤沈下の防止対策
が重要な課題となる。検討方法については、?で述べた小規模地下水資源マネジメントの
定量的な延長検討とほぼ同様に考えることができる。
?大規模レベルの地下水資源マネジメント
大規模の地下水資源マネジメントにおいては、複数の都府県にまたがる広がりを持つ大
規模な地下水盆の分布する地域(関東平野、濃尾平野、大阪平野、筑後・佐賀平野等)が
対象となる。ここでの重点は中規模の地下水資源マネジメントとおおむね一致するが、都
府県をまたがる対応が必要となるため、国の関係府省と関係地方自治体が連携して対策を
行っている「地盤沈下防止等対策要綱」の対象地域のように、体制・制度面で広域的な取
り組みが必要となる。
(3)地下水資源マネジメントの企画・検討手順
地下水資源マネジメントの目的や手順は、その対象とする地下水盆の地形・地質特性、
特に地域の規模によって異なってくるが、ここでは地域特性にかかわらず共通する基本的
な企画・検討手順について、適宜代表的な事例を紹介しながら、図3-2-1に沿って示す。
資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)
図3-2-1 地下水資源マネジメントの企画・検討手順
?予備調査
a)対象・目的の設定
はじめに、地下水資源マネジメントを行う対象・目的の設定を行う。
対象となる地域は、局所的な1〜2k?の狭い範囲において個別の井戸の設置可否等を
対象とするような場合を除き、行政上の視点から設定されることが多いが、その規模は単
独の市町村にとどまるものから、同一都道府県内で複数の市町村にまたがるもの、複数の
都府県にまたがる盆地や平野規模までさまざまである。こうした対象地域は、地下水の保
全・利用に関する課題や問題意識を共有する圏域として設定され、地理的条件、特に帯水
層や地下水盆の分布状況・規模に応じた地域となる。
目的の設定は、地下水資源の保全、地盤沈下等の地下水障害の防止、地下水環境の保全
など、対象地下水盆における地下水の保全・利用上の課題や問題意識等に応じて設定され
る。また、地下水の保全・利用に関する総合的な計画の場合と、特定の課題に特化した計
画の場合で、目的の設定や力点が異なってくる。以下にその事例を示す。
【総合的な利用・保全の目的を掲げる事例】(熊本地域地下水総合保全管理計画)
生活用水をすべて地下水で賄っている熊本地域では、地下水資源を次世代に引き継ぐ
ことを目的に、地下水の保全を優先している。
本計画は地下水の保全・利用に関する総合的な計画であることから、計画で定めてい
る保全目標は、地下水資源の量・質両面での維持に加え、地域のシンボルともなってい
る豊かな湧水の維持・復元、地下水障害の防止等にも置かれている。
【特定課題の目的を掲げる事例】(埼玉県地盤沈下緊急時対策要綱)
かつて深刻な地盤沈下を経験し、現在も地盤沈下が懸念される埼玉県では、地下水の
過剰なくみ上げによる地盤沈下を防止することを、地下水対策の優先目的としている。
地下水の保全・利用全般については「埼玉県生活環境保全条例」に定められているこ
とから、本要綱では、緊急的な地盤沈下対策に特化して目的が設定されている。
b)調査内容・検討手順の検討
設定された対象・目的に基づき、実態把握や計画の策定、及び運用・評価にあたって必
要な調査内容や検討手順を構築する。その際には、地下水資源マネジメントの対象・目的
のほか、利用可能な予算、計画策定までの期間、取組体制等も考慮する。
?地下水に関する実態把握
対象・目的に応じた地下水・水文調査(地形・地質、水文、土地利用、水利用実態、地
下水障害、地下水流、地下水質、法制度等)を行い、対象地域の地下水に関する問題点の
要因分析を行うとともに、対象・目的に応じて適当な数値シミュレーションモデルを用い
ながら、地下水盆や帯水層をモデル化し、適正採取量の数量化を行う。
地下水資源マネジメントの実施にあたって、地下水に関する実態把握、特に採取量の把
握や地下水収支の数量化は、地下水の保全・利用に関する計画の策定・運用の前提となる
きわめて重要な要素である。同時に、実施にあたっては、適正採取量の数量化のために必
要な時間・労力と知識・経験の蓄積、また、地下水採取量把握にあたっての利用者の理解
と協力が必要である。
a)地下水・水文調査
地下水・水文調査の調査項目として、以下のようなものがあげられるが、実施する項目
や精度は、地下水資源マネジメントの対象・目的等に応じて、個別に設定する。
* 地形、地質、水文、土地利用、水利用実態
* 地下水障害、地下水流、地下水質、関係法令
【地下水・水文調査の調査項目の例】(熊本地域地下水総合調査)
「熊本地域地下水総合調査」では、以下の項目について調査を実施している。
・ 地形・地質:地質平面図・断面図、地下水位断面図等を作成
・ 土地利用:涵養域・非涵養域別土地利用、生産調整率(米作減反率)の推移を把握
・ 水利用実態:条例に基づき採取者から報告されたデータを活用
・ 地下水流:既存井戸の一斉測水調査を実施し、帯水層別地下水位等高線図を作成
・ 地下水質:水質汚染防止法に基づく地下水の水質汚濁状況の常時監視を170 地点あ
まりで実施するとともに、河川水5地点、湧水10 地点、地下水86 地点でイオン分
析を実施等
【地下水利用実態電子データの例】(茨城県)
以下に示す茨城県の検討例では、現行の揚水実態、井戸分布、地形・土地利用の情報
を一目で知ることができ、それぞれの井戸の地質情報や採取量が判る。
b)地下水数値シミュレーション解析による適正採取量の数量化
水収支は地表の水収支と地下の水収支が連成・構成されるが、地下水収支は、地下水の
涵養量と採取量によって地表水収支と結びついている。帯水層・地下水盆が対象地域を越
えて分布している場合には、隣接する地域との間において、地下水同士の流入・流出が生
じうるが、帯水層・地下水盆が対象地域内で閉じている場合には、涵養量と採取量が把握
できれば、地下水収支を数量化できることになる。
地下水収支モデルが検定・修正できれば、水需給の現状や将来見通しを外生的に入力し、
数値シミュレーションモデルを活用して地下水の挙動の将来予測を行うこと 注)、さらにそ
の現地適用への論拠とすることが可能となる。
* 地下水盆のモデル化
* 地下水涵養の数量化
* 水理定数
* 地下水流動解析・内挿検定・パラメータ同定
* 数値シミュレーションモデルによる適正採取量や水収支の数量化
* 将来予測
* 地下水採取量の適正配分・揚水井分布
* 安全水頭・採取量の設定
【地下水収支の数量化の例】(座間市地下水総合調査)
「座間市地下水総合調査」においては、過去20 年間におけるデータに基づき、地下
水収支シミュレーションモデルを構築し、揚水条件(地下水揚水量)、涵養条件(平水
年と渇水年の涵養量)、河川改修条件の組み合わせによって、7ケースについて地下水
位変動や水収支予測を行い、台地部、低地部、市全体のそれぞれについて、水収支が±
0となる揚水量を適正揚水量として設定している。
また、市内の代表観測井において地下水の揚水に支障のない地下水位として、第1段
階水位(注意)と第2段階水位(警戒)の2段階の管理水位を設定している。
?地下水の保全・利用に関する計画の策定
対象地域における地下水資源マネジメントの目的や枠組みに基づき、必要に応じて数値
シミュレーションモデルによる将来予測の結果を活用しながら、適正な地下水利用を実現
するための考え方、適正採取量、管理水位、利用規則や、地下水の観測・モニタリングの
方法、行政担当者向けの管理マニュアル等を検討・策定する。
a)地下水適正利用のあり方
数量化された地下水収支やその将来予測を参考にしながら、地下水の保全・利用に関す
る計画の根幹を成す地下水適正利用のあり方を検討する。
* 適正利用のコンセプト
地下水障害を招くことなく、地下水収支のバランスが保たれる範囲内で地下水資源
を保全しながら持続的に利用できること前提として、地下水資源の適正な利用にあ
たってのコンセプト、基本目標を設定する。地域内において、ある一定の期間に利
用可能な地下水の量(おおむね涵養量より小さく地下水障害を起こさない量)を「適
正採取量」とするとき、以下のようなケースが想定される。
<採取量が適正採取量を上回っていない場合>
採取量が適正採取量の範囲内にある状態を維持していくため、涵養量の維持に向け
た取り組みを行うとともに、規制・誘導等により採取量を抑制する必要がある。
<採取量が適正採取量を上回っている場合>
採取量の抑制と適正採取量の拡大が考えられるが、地下水涵養策による利用可能量
の拡大には限界があることから、主に規制・誘導等により採取量を適正採取量の範
囲内に抑制する方策が求められる。
* 用途別配分・利用方式
数値シミュレーションモデルによる適正採取量の将来予測結果や適正利用のコン
セプト、水資源の需給事情等に基づき、総採取量の中での利水用途別配分(農業用
水、工業用水、生活用水等)や、地下水の利用方式(各用途における地下水と地表
水の組み合わせ利用の考え方)等について検討する。
* 利用規則・井戸の設置許可等
必要に応じて、地下水の採取・利用にあたっての規則や揚水井の設置基準・設置条
件等のルール(法律・条例等)を検討する必要がある。例えば、茨城県地下水適正
利用条例では、新規の井戸設置は許可が必要である。
b)適正利用を実現するための方策
地下水適正利用のあり方の検討結果に基づき、これを実現させるための方策(地下水管
理の方式、具体的方法等)について検討する。
* 地下水管理の方式
気象の平穏な平常時、気象の不順な渇水期、自然災害時等の状況に応じた地下水管
理の方式を検討する。具体的には、総適正採取量の範囲で地下水位・水頭や地盤変
動、採取量等の各種データを総合的に分析して管理する方式や、経験的に得られた
採取量配分と地下水位の経時的な相関関係の分析に基づき、地下水位のモニタリン
グを通じて過剰揚水を抑制する方式(警報・注意報の発令による地下水採取者への
採取量抑制の要請等)が選定される。
* 観測井の構造・配置・数
地下水収支の数量化の結果等を踏まえ、地下水管理を行うために必要な地下水位・
水頭や地盤変動量等を観測する観測井の構造・配置・数を決定する。
近年ではテレメーターの実用化が進み、通信回線を活用して観測データをリアルタ
イムで観測・収集することが可能となっている。
* 管理マニュアル
担当者の異動等があっても継続的に地下水資源マネジメントが行えるよう、地下水
の保全・利用に関する計画の管理者や地下水採取者等が地下水管理をどのように行
っていくのかをまとめた管理マニュアルを作成する。
* 地下水管理者・採取者への情報伝達方法
地下水管理者となる地方自治体、地下水採取者となる企業、水道事業者、個人等に
対して、地下水資源マネジメントにあたって必要な情報を迅速に伝達する方法は、
インターネットをはじめとする電子媒体によることができる。
* 広報・指導
地下水資源は採取者や利用者が多岐・多数にわたることから、地下水資源マネジメ
ントにあたって重要な情報は、採取者のみならず、広く利用者一般に対して公表・
提供し、地下水の保全・利用に関する意識啓発を図る。
【適正利用を実現するための方策の事例】(埼玉県地盤沈下緊急時対策要綱)
埼玉県では、「埼玉県地盤沈下緊急対策要綱」に基づき、地下水位の著しい低下によ
り、地盤沈下が生じる恐れがあると認められる時には、一定量以上の地下水採取者に対
して、各地域の地下水位の程度に応じて、地下水採取の抑制等を要請する「地盤沈下注
意報」「地盤沈下警報」が発令される。
?地下水の保全・利用に関する計画の運用・評価
a)地下水の観測・モニタリング
計画に定められた適正利用を実現するための方策に基づき、地下水位、採取量、地盤変
動量についての報告を採取者に求めたり、観測井を用いて観測したりした上で、そのデー
タを収集・処理するとともに、必要に応じて地下水障害等を未然に防止するための対策(新
規揚水井の許可制等)を実施する。地下水資源マネジメントは、地下水位・水質、採取量、
降水、地下水障害(地盤沈下量等)といった観測データによってなされることから、観測
データの迅速かつ正確な収集・伝達・処理が重要である。
* 採取量・水位報告
地下水資源マネジメントには採取量や地下水位の把握が不可欠であることから、一
定量以上を採取する採取者に対して、記入書式を用意し、採取量や地下水位の報告
を義務づけること等により、これらを把握する。
b)計画の評価・見直し
地下水の観測・モニタリングを一定期間継続し、データの蓄積が図られた時点で、策定
した計画の妥当性、観測・モニタリングの有効性等を評価し、その結果に基づいて必要な
修正・変更を行う。特に、地下水収支の数量化と将来予測に用いる数値シミュレーション
モデルの精度を高めていくことが重要である。
* 評価
計画の評価は、地下水資源マネジメントのPDCAサイクルの「C」に相当し、計
画内容の有効性や成果を計る「政策評価」と、計画の執行段階での効率性や進捗度
を計る「執行評価」を適切に組み合わせて実施することが望ましい。
評価に用いる指標と、最低限達成すべき水準、おおむね成功と評価できる水準、可
能ならば達成したい水準というような目標を、計画策定段階で予め設定をしておく
ことで、評価の精度が高まる。
* 見直し
計画の見直しは、地下水資源マネジメントのPDCAサイクルの「A」に相当し、
上記の評価結果に基づいて行う。必要に応じて、地下水適正利用のあり方を見直す
とともに、適正利用を実現するための方策については、評価結果に応じ、継続・改
善・中止のいずれかを検討する。
【評価・見直しの例】(熊本市地下水量保全プラン)
「熊本市地下水量保全プラン」の場合、毎年度プランの評価・見直しを行い、その進
捗状況をホームページで公表することとしている。評価にあたっては、評価結果等の説
明や市民の意見聴取のため、「熊本市節水推進パートナーシップ会議」を設置している。
(4)地下水資源マネジメントの検討・策定方法と策定・運用主体
地下水資源マネジメントを円滑に実施・運用するためには、地下水利用事業者の参加及
び地下水管理者との共同歩調が欠かせない。したがって、行政だけでなく、対象地域の主
要な地下水採取者が参画し、地域全体が連携して取り組んでいくことができる体制づくり
が求められる。このため、計画の策定・運用主体は、地下水資源マネジメントを主体的か
つ効率的・効果的に実施できる体制を整備する必要がある。
現行の行政管理体制では、行政区画単位でのマネジメントが実用的と考えられることか
ら、行政や協議会の長が地下水管理者として、計画の策定・運用主体となろう。具体的に
は、対象地域が単独の市町村にとどまる場合、同一都道府県内で複数の市町村にまたがる
場合、複数の都府県にまたがる場合といったように、各地域の事情に即して個別に判断さ
れるべきである。なお、複数の都府県にまたがる「地盤沈下防止等対策要綱」の対象地域
については、国の関係府省連絡会議が設置されている。
第4章 今後の地下水利用のあり方に関する提言
本報告では、
?「健全な水循環系構築」のための計画づくりの一環において、地下水について計画作成担当者に向けた提言
?地下水障害を発生させないことを前提とした適正な管理により利用する仕組みの構築に向けた具体的な提言
?国際比較の中でのわが国の地下水の特性及び利用のあり方
の3点に重点を置いて検討してきた。
地下水は重要な水資源であり、水循環系の構成要素であることから、本来、地表水と一
体化させ、環境面を含めて捉え、計画的に保全・利用されるべきものと考えられる。これ
までは、水資源の需給バランスの相互補完や地下水障害等の直面する課題の解決の面から
のみ地下水が捉えられてきたが、今後は地下水と地表水の役割分担や最適な両者の利用配
分の実現をめざした施策展開が必要な段階になってきている。こういった今日的なニーズ
に応え、本報告は、地下水資源マネジメントの手法論を展開した。
ここでは、第1章から第3章で述べた検討の結果を踏まえ、今後の地下水利用のあり方
に関する基本的な考え方やその実現にあたって求められる取り組みを提言として以下にと
りまとめる。
国の関係府省、地方自治体、企業、利水受益者等、地下水の保全・利用にかかわる各関
係主体には、本提言を踏まえ、それぞれの立場から、健全な水循環系の構築と持続可能な
地下水の保全・利用に向けた積極的な取り組みが期待される。
4.1 地下水資源マネジメントの推進
(1)健全な水循環系の構築に向けた地下水資源マネジメントの必要性
現在、わが国では、都市域における雨水浸透機能の低下、地表水と地下水の自然相互依
存の阻害等といった水循環系の健全性が損なわれていることに起因して、平常時の河川流
量の減少、湧水の枯渇、各種排水による水質汚濁、都市型水害等の問題が顕著となってき
ている。地表水とともに水循環系の重要な構成要素である地下水においても、健全な水循
環系の構築が重要な課題となっている。さらに、多量の水資源を水文収支域外より集積し、
消費・排出する都市の人工水循環系の健全化・保全を推進していく必要がある。
そのため、適正採取量の数量化や将来予測に基づき、地下水に係わる地域の諸条件に応
じて、地盤沈下などの地下水障害を未然に防止し、地下水収支バランスが保たれる範囲内
で、持続的に地下水を水資源として利用していくための適正利用のあり方とその実現方策
を検討し、地下水保全・利用に関する計画を策定・運用する必要がある。計画の策定・実
践・運用にあたっては、実態把握、計画策定、観測・モニタリング、評価・見直しという
継続的な試行プロセスを通じて、地域の諸条件に応じた持続的な地下水資源の保全・利用
のあり方を実現していくという「地下水資源マネジメント」の考え方が重要である。
例えば、関東平野を例にとると、図4-1-1に示すように、昭和20 年代より広域地下水利
用がなされ、地下水位(水頭)は低下したが、法律の規制(昭和31 年以降)によって回復・
上昇し、今は過去の自然地下水位に近づきつつある。将来の地下水資源のマネジメントに
は、健全な地下水環境・国土保全を目標に、安全水位を管理値に保持するよう人工制御す
ることが目指すところとなる。
図4-1-1 地下水資源マネジメントの説明図
(2)地下水資源マネジメントの推進に向けた支援環境整備
地下水資源マネジメントの実践・普及に向けた支援環境整備として、以下のような取り
組みを進めるべきである。
?地下水の実態把握に向けた採取量をはじめとするデータ整備の推進
地下水資源マネジメントの実践にあたっては、地下水の実態把握や問題点の要因分析等
を行う必要がある。地下水に関する調査としては、
1)地下水位及び地盤変動に関する調査、
2)水質に関する調査、
3)採取量に関する調査、
4)地形・地質に関する調査等があるが、以上のような観測データは、その地域の地下水解析に欠くことのできないものであるため、精度の高い長期的な観測を継続する必要がある。しかし、地表水と異なり、地下水はその
実態把握に時間・労力・経費がかかり、地下水の実態把握を行うための各種観測データが
十分に整備されていない。特に、地下水採取量は、地下水収支の数量化や将来予測、計画
の運用、観測・モニタリング等のさまざまな面で有用であるにもかかわらず、データの収
集整備(特に電子データ化)が進んでいない地域も多い。
採取量をはじめとする各種観測データの収集には、利用者の協力が不可欠であることか
ら、関係者間での協議、条例等の制度面での対応、データ収集・処理体制の整備などにす
みやかに着手することが求められる。
国においては、各地域において収集されたデータを全国共通に活用できるよう、データ
の収集項目や定義、収集方法等についての統一的な基準を作成し、各地方自治体に対して
データ収集を積極的に取り組むよう、普及啓発活動を実施することが必要である。また、
収集されたデータを蓄積・活用するためのデータベースについては、一元的な電子データ
ベース化を図り、データの効果的・効率的・実践的な活用を推進していくことが期待され
る。地質情報を全国で共有するための全国電子地盤図システム構築の構想も動き始めてお
り、こうしたシステムの活用も検討する必要がある。
?地下水実態・観測の数値情報共有・活用の推進
地下水資源マネジメントの推進を図るため、地方自治体の担当者をはじめ、地下水資源
マネジメントに関係する人が、全国各地域で策定された地下水保全・利用計画やその運用
状況、地下水に関する各種データ(降水量、地質、地下水採取量等)、地方自治体の地下
水に関する条例・要綱等、各地域の取組事例を情報交換し、活用しやすくなるよう情報環
境整備が必要である。そうすることによって地域性に富み、かつ水需給事情の異なる地下
水資源採取者や管理者が、より適正な地下水資源開発計画や運用方策を実践することが出
来よう。地下水資源のように多数の採取者が分散して各自揚水している場合、そのマネジ
メントの実行主体は採取者の側にあることを銘記したい。したがって、採取者の理解と協
力がマネジメントの運用に不可欠である。その実施・推進にあたって、地下水資源の所管
(地方自治体や各種機関)を通じて、地下水資源マネジメントの趣旨や方法について地下
水採取者(例えば利用協議会等)に対する講習会やポスター配布等により予め周知する必
要がある。
?実証モデルケースによる地下水資源マネジメントの推進〜取り組みの牽引役として〜
すでにいくつかの地域で、地下水資源マネジメントの先駆となる取り組み(例えば、埼
玉県、熊本県、栃木県野木町等)が行われているものの、現状ではその数は限られている。
そこで、地下水資源マネジメントの考え方に基づき、地下水保全・利用計画を策定・運
用しようとしている地域(例えば、現行の地盤沈下防止等対策要綱の対象地域等)に実証
モデルケースを選定し、地下水管理者と揚水事業者の連携のもとで採取量の把握、地下水
収支の数量化と将来予測に支援された地下水資源マネジメントを試行・実践し、その応用
性の実証や問題の解決後、有効性を普及していく必要がある。
先進地下水資源マネジメントの事例や方法を公表・情報提供していくことで、より多く
の地域で地下水資源マネジメントの経験・実績・有効性が認識されるようになり、その前
提となる採取量の把握に向けた採取者の理解と協力も得やすくなっていくことが期待され
る。
国においては、地下水資源マネジメントを推進するための新たなモデル事業を先導し、
実証モデルケースとなる地域の取り組みに対して、財政面での支援や専門的見地からの助
言を行うとともに、その成果を広く情報提供することはもとより、解析作業の中核を成す
汎用性の高い数値シミュレーションモデルの普及(例えば、米国地質調査所(USGS)の
MODFLOW.2005 等が国際的に普及)を行うことが期待される。
4.2 地下水資源マネジメントの運用方策
地下水資源マネジメントには、管理する際不可欠なマネジメント条件(あるいは制約条
件)が課されることになるが、その条件や制約指標(例えば、観測地下水位、採取量、地
下水障害)は、次の5つが要点となる。
?ある対象地下水盆(あるいは地下水文区)に涵養される地下水総量より広域総採取
量が小さいこと(地下水収支条件)
?観測地下水位が管理目標限界地下水位より高いこと(あるいは、管理目標地下水位
の上限と下限の範囲内にあること)(安全地下水位保全条件)
?広域総採取量をその構成地域採取配分量の和とすると、それら配分量がそれぞれの
管理目標地域採取量を超えないこと(安全地下水採取量条件)
?地下水障害(地盤沈下、地下水塩水化等)の誘発防止(地下水障害防止条件)
?異常な井戸水位低下、井戸干渉を招かず、かつ揚水井間距離が適正であること
(揚水井適正配置条件)
以上の制約条件を満足させるよう地下水資源をマネジメントすることになるが、?と?
は健全な地下水環境を保証すべき必須条件であり、観測地下水位や採取量の適正化によっ
て満たされ、過去の経験や実測データ及び数値シミュレーションによって解析しうる。し
かし、即時的な地下水資源マネジメントの指標としては、観測地下水位が実用的である。
今日、?を満たすようマネジメントを行うことが運用しやすい。その具体的な仕様は以下
に示す。
地下水揚水の適正化とは、広域地下水盆における地表水と降水による涵養の範囲内で、地下水
障害が発生しない最適揚水量を地域ごとに決め、急激な揚水は避けながら地下水資源を効果的に
利用することにある。地下水揚水抑制の具体的な実践には、過去の地下水・地盤沈下の観測デー
タを解析し、従来の揚水実績を十分検討した上で、段階的に分けた管理基準(限界値)水位を予
め設定しておき、注意報・警報といった情報を地下水利用者の合意の下で実践するのが合理的と
考える。設定された(目標)基準(限界)水位を下回るような地下水揚水は回避されなければな
らない。
地下水位と地盤沈下の観測方法は、二重管構造の観測井を使用するのが主流で、地下水位はフ
ロート式で地盤沈下は管頭変位量を機械的に測定している。近年オンライン化されたテレメータ
観測システムを利用し、地盤沈下を防止しつつマネジメントする方法が開発されている。図4-2-1
はそのシステム概念を示す。最近、このシステムが地盤沈下対策のみならず、経済性向上や省力
化に向けた地下水資源の保全にも普及しつつある。
図4-2-1 テレメータによる地下水マネジメントシステム概念図
また、地下水位を用いた地下水管理をより推進するため、即時的かつ容易に対策を実施
できるという点で有利なテレメーターシステム等の導入が必要であり、財政面での支援を
行うとともに、その成果を広く全国に情報提供していくことが期待される。
4.3 地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項
地下水資源マネジメントの推進や地下水資源の利用にあたって重要と考えられる事項
を以下に提言する。
(1)水資源の視点からの地下水の水質確保・保全
地下水の水質面については、これまでの汚染対策としての視点に加え、水資源政策の視
点から捉え、多様な地下水の利用ニーズに対応した用途別の水質確保・保全のあり方につ
いて検討する必要がある。その際には、地下水資源マネジメントの実施にあたって、量的
な側面だけでなく、水質面もその対象とすることで地域の諸条件に応じた地下水利用のあ
り方を実現していくことが適切である。
また、その前提として、浅層のみならず深層も含めた水質汚染に関するデータや情報の
整備が求められることから、まずは量的な側面に限って地下水資源マネジメントを実施す
る際にも、水質面の観測・モニタリングを同時に行い、データ整備を進めていくことが欠
かせない。
(2)地下水の震災対策
大規模地震災害時において、水の確保が重要な課題であることがこれまでの震災の経験
から指摘されており、発生直後から時間の経過に応じた各種水需要に適切に対応するため、
利用可能な水源とその特徴(水量、水質、設備・運搬の必要性等)を踏まえた水利用シス
テムを検討・構築しておく必要がある。
地下水は、身近で入手の容易な水資源であり、一般に水質もよいことから、大規模地震
災害時の利活用性が高く、地域の特性に応じた地下水の利用方策(用途・利用方法・制度
等)を検討・構築する必要がある。その際には、シミュレーション結果に基づき、各避難
所に緊急時に使える井戸を積極的に設置するという地域の取り組み等も踏まえつつ、耐震
性の高い井戸の分布状況の把握、災害時に民間井戸を利用可能とする権限の担保方法、少
なくとも災害発生直後の緊急・応急水供給に向けた別水源への振り替えのあり方等に留意
し、安全・安心な災害時地下水利用システムを構築することが求められる。
(3)地下水資源マネジメントの社会的合意形成への取り組み
?社会的関心向上の必要性
これまでわが国においては、地下水の過剰採取が深刻な地盤沈下を招いた経験から、一
般に地下水は地盤沈下と結びついたイメージが強く定着し、地下水の採取が、採取者の所
有する土地内にとどまらず、広域的な地盤沈下の原因となることについては、共通の理解
が得られていると思われる。
今後、地下水を水資源として管理しながら利用していくにあたって、社会的な合意が必
要な内容(地下水は水資源として、また環境面においてどのような役割を担うべきか、地
下水は平常時・緊急時にそれぞれどの程度利用してよいか、等)を定量化し、その意義の
普及・啓発を図っていく必要がある。
?法制度に関する検討の必要性
現在、わが国では地下水に関する重要な紛争や係争が生じている状況にない。これは、
工業用水法などの個別法や条例の適切な運用に負うところも大きいと考えられる。
しかし、現在も長期的、短期的な地下水をめぐる課題が存在しており、また条例等を施
行する自治体においては、いわゆる反対解釈の問題や強制力の不足による公平性の確保の
困難さ等、施策の実効性不足の声も聞かれている。さらに、地下水に関する社会的合意を
具現化するため、わが国における地下水に関する法制度について、法制化を行うべきかど
うかも含め、検討を行うことも必要と考えられる。
その際、全国一律的な法律と、各地域の特性に応じた条例の関係については、地域によ
る多様性に富むという地下水の特性やこれまでの各地域における取り組みを踏まえつつ、
法の機能と特長をいかに適切に組み合わせていくかが重要な論点となる。
また、国外に目を転じると、EU(欧州連合)では、基本法とも言える水枠組み指令と
これに対応した各国の法律が制定されており、こうした海外の事例も参考にしながら、国
際的な視点に立って、わが国の自然特性や社会の実情に即した法制度のあり方を検討する
必要がある。
「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」報告要旨【平成19年3月】
地下水の特性と保全・利用に係る課題
・水循環系における滞留時間が長い
・涵養に時間がかかるが潜在賦存量は多い
・地下水資源利用の広域定着と安定化
・渇水時の揚水増による地下水位低下
・採取量等のデータ整備と実態把握の遅れ
・地下水の保全・利用に関する全般的取り組みの遅れ
・水収支バランスが保たれる範囲内での利用
・緊急時の応急水源としての利用方策
・広域地盤沈下は沈静化傾向のまま継続・残存
・短期的、集中的な地盤沈下は今後も懸念
・科学的、定量的処理と電子情報化が必要
・社会への啓発と関係者の意識向上
特性課題
・「持続的かつ健全に利用できる循環している地下水」が利用の前提
・一般に、水資源としての地下水は、利用の簡便性、経済性、良質な水質、恒温性を有する
・わが国の水使用量における地下水依存率は約12%
・各種法令による地下水採取規制等により、広域的な地盤沈下は概ね沈静化
・しかし、渇水時には短期的・局所的な地下水位低下、地盤沈下が発生
・一部地域では地下水位上昇により地下構造物への影響が発生
・地下水汚染の多様化
・新たな地下水利用形態(ミネラルウォーター、地下水ビジネス)の拡大
地下水をめぐる現状と最近の動向
?地下水資源マネジメントの推進
・地下水障害を未然に防止し、地下水収支バランスが保たれる範囲内で、持続的な地下水資源の適正利用のあり方とその実現方策を検討し、地下水保全・利用に関する計画を策定・運用する必要がある。
・計画に基づく施策の実施にあたっては、数値シミュレーションモデルの活用により地下水収支を定量化し、実態把握、計画策定、観測・モニタリング、評価・見直しのというプロセスを反復しながら継続的に取り組み、地域の諸条件に即した最適なマネジメントを実現することが重要である。
?地下水資源マネジメントの運用方策
・マネジメントにあたっては、目標とすべき地下水位を定め、地下水位を常時観測していくことにより管理していくことが実用的である。
・マネジメントの推進に必要となるデータを収集するため、観測井戸、観測機器、テレメーターシステム
等の整備が必要である。
?地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項
・水資源の視点からの地下水の水質確保・保全のあり方を検討する必要がある。
・大規模地震災害時における地下水の利用方策を検討する必要がある。
・地下水資源マネジメントの社会的合意形成への取り組みを推進する必要
http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/f_
groundwater/25/houkokusyo.pdf
平成19年3月
今後の地下水利用のあり方に関する懇談会
はじめに
近年、地下水を取り巻く環境は大きく変化してきている。かつて高度経済成長期に深刻であった地下水の過剰採取による地盤沈下は、一部現在も引き続き対策が必要な地域もあるが、地下水採取規制、代替水源の確保等により、沈静化しつつある。 一方で、かつては地盤沈下が深刻であった大都市地域で地下水採取規制等により地下水位が回復・上昇し、地下構造物や地下水環境への新たな悪影響・弊害を引き起こしている事例もある。また、地下水質の面で環境基準を超える浅層地下水汚染が顕在化している。
地下水は地球水循環系を構成する重要な要素であり、地下水の保全及び利用が水循環系全体に与える影響を把握していくことが重要である。
本懇談会は、平成10年に国土庁水資源部に設置され、“地下水の利用と制度のあり方”について、専門の立場より幅広く検討を進めてきた。平成12年3月には、地下水をめぐる現状、今後の地下水利用のあり方について中間報告としてとりまとめ
た。
つづいて平成15年3月に日本で開催された第3回世界水フォーラムにおいて「今後の地下水利用のあり方」をテーマに分科会を主催し国際的視野に立った議論を行った。
今般、地下水をめぐる最近の動向と保全・利用に向けた課題、地下水利用のあるべき基本的な考え方を整理し、今後の地下水利用のあり方に関する提言を報告書にまとめた。
本報告は、その前半では「地下水をめぐる現況、最近の国内外の動向、及び保全・利用に係る課題」を論点とし、後半で「今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法」に言及し、最後に、当初目指した「今後の地下水利用のあり方」を提言している。
その新しい視点は、地下水資源に軸足を置いてマネジメントする必要性に向けられている。これまでの永い地下水利用の歴史を踏まえて、地下水資源マネジメントの指針と方法をより実践的にまとめたものであり、今後、本提言が国や各地域での取り
組みに反映されることを期待するものである。
平成19年3月
今後の地下水利用のあり方に関する懇談会座長
埼玉大学名誉教授佐藤邦明
「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」委員
小尻利治京都大学防災研究所水資源研究センター教授
佐藤邦明埼玉大学名誉教授(座長)
七戸克彦九州大学大学院法学研究院教授
大東憲二大同工業大学工学部都市環境デザイン学科教授
田中正筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
中杉修身上智大学大学院地球環境学研究科教授
守田優芝浦工業大学工学部土木工学科教授
目 次
第1章 地下水をめぐる現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.1 地下水の特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2 地下水利用の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1.3 地下水障害・地下水水質・汚染の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
1.4 地下水に関する法制度の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第2章 地下水をめぐる最近の動向と地下水の保全・利用に係る課題・・・・ 29
2.1 わが国の水需給に関する動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
2.2 新たな地下水障害と地下水源開発の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
2.3 地震災害等、緊急水資源需要への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
2.4 水に関する世界情勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
2.5 地下水の保全・利用に向けた課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
第3章 今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法・・・・・・・・・・・・・・・ 55
3.1 健全な水循環系の構築における今後の地下水利用の基本的な考え方・・・・・・・・ 55
3.2 地下水資源マネジメントの考え方と手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
第4章 今後の地下水利用のあり方に関する提言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 4
4.1 地下水資源マネジメントの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
4.2 地下水資源マネジメントの運用方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
4.3 地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
第1章 地下水をめぐる現状
1.1 地下水の特性
(1)地下水の水循環上の特性
科学的にみると、地下水は陸水の地下にある水の総称である。それは、降水が地下に浸透して海洋へ地下流出するプロセスにある、いわゆる「地下水」と、陸地の地形・地質が形成される際に地下深くに閉じこめられた化石水や、岩石・溶岩の形成時に生成される初生水のように「循環に乏しい地下水」に分けられる。一般に、淡水資源や温泉水は、それらを持続的かつ健全に利用できる循環している地下水であることが前提となる。以下、このような視点に基づき、議論を展開する。
地下水の源は降水であり、地表水とともに水循環を構成する。降水の一部は、直接流出として河道に流出する。直接流出は、地表から河道に流れる表面流出と、一度地中に浸透した後に浅い地下水流として河道に流出する中間流出に分けることができる。直接流出しない降水は、窪地などに一時的に貯留されるか、土壌に浸透する。土壌に浸透した降水の一部は重力によって下方に浸透し、地下水となる。
地下水は地表水に比べて、地中をゆっくりと流れる。そして、やがて河川・湖沼や地表面に再び流出し、地表水に合流する。平均滞留時間は数百〜数千年といわれている(表1-1-1参照)。
このような水循環を図示したものが図1-1-1(○a ,○b )である。水循環の過程においては、大気事象や大地の影響を強く受けている。例えば、地下水涵養は降水量に支配され、地下水循環は地質や地形によって規定される。また、蒸発は気温や湿度、植生などの影響を受けている。さらに、採取量(揚水量)や土地利用などの人為的な要因も水循環に影響を与えている。

資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)をもとに加筆
図1-1-1 水循環とその規定要因の概念図
表1-1-1 地球の水量と滞留時間
貯留量(?3) 平均滞留時間
海 洋 1,349,929,000 3,200 年
氷 雪 24,230,000 9,600 年
地下水 10,100,000 830 年
土壌水 25,000 0.3 年
湖沼水 219,000 数年〜数百年
河川水 1,200 13 日
水蒸気 13,000 10 日
資料)建設産業調査会『改訂地下水ハンドブック』(1998 年)
(2)地下水の水資源としての潜在特性
一般に水資源としての地下水は、表1-1-2に示すように、利用の簡便性、経済性、良質な水質、恒温性という特性を有している。
表1-1-2 地下水の利用特性
このような地下水の自然特性を活かし、地下水は、生活用水(飲料用、調理用、浴用等)、工業用水(冷却用、洗浄用等)、農業用水(農作物栽培用等)、積雪地域の消雪用など多様な用途に利用されている(図1-1-2参照)。
図1-1-2 地下水特性からみた用途の内訳
1.北海道地方
(3)地下水の潜在分布状況
図1-1-3は、わが国における地下水盆の賦存地形類型と主な地下水区の分布を示している。わが国における地下水は、地形・地質上、平野型、盆地型等のいくつかに分類できる。

図1-1-3 わが国における地下水盆の類型と主な地下水文区
それぞれに分類される地下水の特徴を以下に要約する。
?堆積平野の地下水
a)平野・台地
関東平野など主要な地下水盆は、地質年代では新生代新第三紀末から第四紀の地層が堆積する平野、低平地に分布しており、特に第四紀完新世の沖積平野のうち、中〜上部更新統・完新統の新しい地質が主な帯水層となっている。地層が軟弱な沖積平野では、地下水の過剰なくみ上げが地盤沈下を引き起こしやすい。
b)盆地
わが国の盆地には、平野と同様に新生代新第三紀末から第四紀の地層が堆積しており、更新世末から完新世の地質をもつ段丘や扇状地が有力な帯水層となっている。盆地の帯水層は、豊富な地下水を有していることが多いが、地下水の過剰なくみ上げによって地下水位の低下や枯渇を起こすことがある。
?岩の地下水
地下水は溶岩体や深成岩地帯にれっか水(裂罅水:fissure water、「地質事典」平凡社、1990)や割れ目水として帯水している。
a)山地
山地では、造岩塊や固結岩の亀裂や浸透性の高い地層に地下水が含まれており、トンネル掘削時に湧水として流出することがあるが、環境への影響や採水の経済性を考慮すると、大規模な採取は困難である。
b)火山地域
火山地域は、溶岩・火山砕屑物など浸透性の高い地層から構成されているため、阿蘇カルデラ、シラス台地など有力な帯水層が多い。山麓部末端では湧水群が分布し、古くから農業用水、生活用水に利用されてきた。
c)石灰岩地帯
石灰岩中のれっかや鍾乳洞には地下水を有することが多く、日本では、例えば、栃木県の佐野市(弁天池)や山口県の秋吉台などに見られる。また、南西諸島では、琉球石灰岩が分布し、自然の地下水帯となっているため、近年、地下ダムによる地下水貯留が行われる例がある。
図1-1-4 日本の地質図
1.2 地下水利用の現状
(1)わが国における水使用量の推移
2003 年(平成15 年)におけるわが国の水使用量(取水ベース)は、都市用水と農業用水を合わせ、839 億m3 であり、そのうち、都市用水(生活用水と工業用水の合計)は282 億m3 である。都市用水の使用量は、図1-2-1に示すように1987 年(昭和62 年)以降、やや増加したが、その後微減の傾向にある。また、農業用水の使用量についても、昨今やや減少しており、2003 年は557 億m3となっている。
図1-2-1 全国の水使用量の推移
(2)わが国における地下水利用の特徴
?水使用量に占める地下水の割合
2003 年(平成15 年)における取水ベースの水使用量839 億m3 の水源内訳をみると、図1-2-2のように、河川水が735 億m3、地下水が104 億m3 であり、地下水依存率は約12.4%となっている。

図1-2-2 水使用量に占める地下水の割合
?地下水使用量の用途別割合
上述の地下水使用量104 億m3 に加え、養魚用水として約13 億m3/年、建築物用等として約7億m3/年の地下水が使用されており、全地下水使用量は約124億m3/年と推計されている。
2003 年(平成15 年)における地下水の用途別割合は、生活用水が35.5 億m3で全体の28.6%、工業用水が35.9 億m3 で28.9%、農業用水が33.0 億m3 で26.6%となっている(図1-2-3参照)。
用途別地下水使用量の推移をみると、図1-2-4に示すように、生活用水はほぼ横ばいであるが、工業用水は減少傾向にある。

図1-2-3 地下水の用途別割合
?用途別にみる地下水利用の地域性
地下水利用は、地形・地質や降水といった自然条件と、都市化や人口といった人的な条件の影響を強く受け、決して全国一律ではなく、地域性が多様である。以下、用途別に地下水源への依存の地域性を述べる。
□工業用水
地下水は、水質が良く、水温が一定であり、取水費用が安いという特徴から、工業用水に多く使用されており、特に、化学工業、鉄鋼業、パルプ・紙・食品加工など製造業で、製造、洗浄、冷却水などとして地下水使用量が多くなっている。
図1-2-5に示すように、工業用水の地下水依存率は、全国の合計でみると約3割(29.5%)である。地域別にみると、北陸で最も高く6割超(62.7%)である。また、近畿内陸(54.8%)、関東内陸(46.0%)、東海(45.0%)などでも高くなっている。
工業用水用の地下水は、戦後昭和20 年代以降、深井戸による被圧地下水が使われているが、工場等の立地は沖積平野に多いことから、地盤沈下、塩水化などの地下水障害を引き起こし、今日に至っている。
図1-2-5 地域別用途別地下水依存率(工業用水)
□生活用水
生活用水の地下水依存率は、全国の合計でみると2割強(22.1%)である。図1-2-6に示すように、地域別にみると、南九州(54.3%)や山陰地域(51.9%)で生活用水の地下水依存率が高く、5割を超えている。次いで、四国(41.5%)、関東内陸(41.0%)、北陸(39.8%)などでも高い。一方で、北海道(6.0%)、沖縄(8.5%)では、生活用水の地下水依存率が低い。
図1-2-6 地域別用途別地下水依存率(生活用水)
□農業用水
わが国では、農業用水として主に地表水が利用されてきた。地下水は、補助水源、渇水時の応急用水源として利用されてきたことから、農業用水に占める地下水の割合は概して低い(図1-2-7参照)。
図1-2-7 地域別用途別地下水依存率(農業用水)
□その他の用途
水産用にマス、ウナギなどの養殖で利用される地下水の量の統計では、上述の3つ(工業・生活・農業)の用途に次いで多く、個別的であるが、湧水、温泉水などが報告されている。
また、消雪用に地下水を利用する方法は、気温が氷点下にならない豪雪地で有効であり、消雪パイプは1961 年に新潟県長岡市で始まり、全国的には2004 年度の消雪パイプ使用水量の約83%(374 百万m3/年)が地下水を利用している。地下水は水温の季節変動が小さいため、消雪効果があり、東北、北陸などでも利用されている。しかし、狭い場所で集中的に大量の地下水をくみ上げるため、地下水位の低下、地盤沈下などの地下水障害をもたらした。
わが国では、温泉水として利用される地下水も多い。浴用以外にも、ハウス園芸用熱源、発電など多目的に利用される事例がある。井戸の掘削深度がかなり深く1,000m以上の深さのものもある。
1.3 地下水障害・地下水水質・汚染の現状
(1)地下水位の異常低下、井戸枯れ
わが国における地下水位の異常低下、井戸枯れは、戦後(1945 年)以後1950 年代後半〜1960年代前半にかけて最も激しい地下水被害をもたらした。高度成長期には地下水を大量に揚水したことによって、都市部を中心に地下水位の低下、井戸枯れが起こった。また、地下掘削工事やトンネル掘削によって、周辺の地下水位が低下し、井戸枯れが起こる例も見られた。
しかし、1950 年代後半〜1970 年代前半に揚水の法的規制等が行われたことにより採取量は減少し、全国的にみると地盤沈下は沈静化し、近年は地下水位が回復しているところもみられる。
(2)地盤沈下
(3)塩水化
わが国における地下水の塩水化は、ほとんどが海岸域で発生している(図1-1-1)。地下水の過剰なくみ上げが原因で、地下水位が海水面より低下し、帯水層に海水が浸入することによって発生する。1960 年以降、製紙業の盛んな静岡県富士市のほか多数の臨海域で発生しており、塩水化した地下水は、飲料水として利用できず、工業用水としての不適合、農作物への塩害などがみられた。八戸、石巻、気仙沼などでは、現在もその塩害が継続している。
表1-3-1 塩水化地域に対する対策の状況

(4)地下水の水質と汚染
?地下水質の評価指標
古来、地下水といえば、水温の安定した清廉な水という通念がある。地下水の水質は、地形・地質の成り立ちや地下水の由来、流動、気候、生態系などの自然条件の影響を受け、その地域性や深さによって大きく異なる。例えば、表1-3-2は日本の名水に指定されている水質の例を示す。地下水質は、主要溶存化学成分9項目、陽イオン(ナトリウムNa+、カリウムK+、カルシウムCa2+、マグネシウムMg2+)、陰イオン(重炭酸HCO3-、塩素Cl-、硫酸SO4-、硝酸NO3-、シリカSiO2)に加え、電気伝導度、水温、pH などにより判断され、必要に応じて用途や関係する水質(環境)基準項目を加味した上で評価される。
表1-3-2 名水の水質例
自然の地下水質は、元来多様な理化学的特性を持つ。言うまでもなく、ある地下水が水質上良いか悪いかを漠然と判断することはできない。通常、ある対象・目的に対して、人や環境に有害であると考えられる数値を水質評価指標(水質検査項目)の基準値(水質基準)として設定し、利用の可否を決めることになる。
したがって、自然のままで地下水質がある検査基準(例えば、水道水の検査基準)に適合しない場合がありうる(以下、仮に「自然由来の汚染」と呼ぶこととする)。なお、水質検査の項目自体も水質基準の種類(対象・目的)に応じて異なるものが必要となる。
一般に水質汚染とは、自然の地下水質が人為的に汚染された(=水質基準に不適合の検査項目がある)人為由来のものを指す。自然由来の汚染は主に深層の地下水で、人為由来の汚染は主に浅層の地下水で発生する。深層の地下水汚染は除去が困難であり、水資源として利用することができない。以下では、人為由来の地下水汚染を中心に述べる。
?地下水汚染に関する環境基準とその超過率
高度成長期以降、工場や事業所等が原因となって地下水汚染が発生し、化学合成物である揮発性有機塩素化合物による地下水汚染が深刻となった。
このため、1971 年(昭和46 年)に「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」の2つからなる「水質汚濁に係る環境基準」が定められた。「人の健康の保護に関する環境基準」は、全公共用水域に対し、カドミウム、シアン等9項目についての基準を定めていたが、1993 年(平成5年)3月に項目が追加され23 項目となった。さらに近年、農業、畜産排水による硝酸性窒素汚染が顕在化してきたことから、1999 年(平成11 年)には、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ほう素」及び「ふっ素」の3項目が追加され、現在では26 項目の基準が定められている。
国と都道府県では「地下水の水質汚濁に関わる環境基準」に定められた26 項目を調査対象物質として毎年地下水質測定を行っている(表1-3-3、図1-3-5参照)。
地下水は、一度汚染されると、汚染の継続は長期間に及ぶ。水資源の安全な利用の観点からも、地下水質の継続的な監視が求められることとなる。
表1-3-3 地下水の水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)
図1-3-5 環境基準超過率の推移
?揮発性有機塩素化合物による地下水汚染
揮発性有機塩素化合物は、土壌汚染や浅層地下水汚染を引き起こす原因となっている。その主要な原因となっているのは、金属関連産業や半導体産業などの洗浄溶剤として使用されるトリクロロエチレンと、クリーニングや金属等の脱脂洗浄、代替フロンの原料として使用されるテトラクロロエチレンであるが、近年、製造・使用量は減ってきており、環境基準超過率は減少傾向にある。
揮発性有機塩素化合物は、
?重い、
?水に溶けにくい、
?土壌に吸着しにくい、
?低粘性、
?揮発性が高い、
?分解されにくい、といった特徴を有しているため、いったん地下に進入すると、
鉛直方向には容易に重力浸透する。一方で、横方向への拡散は少ないため、高濃度の原液による局地的な地下水汚染、土壌汚染を引き起こす特徴を持っている。揮発性有機塩素化合物は、まず土壌に浸透し、少しずつその下の帯水層に重力沈降しつつ溶け出して地下水を汚染する。
溶解汚染した地下水の移流流動及び分散によって、汚染地域は拡大する。
揮発性有機塩素化合物は、麻痺や呼吸障害、貧血、肝臓障害、発ガン性があるなど、人体に悪影響を及ぼすことが分かっている。
?硝酸性窒素による地下水汚染
硝酸性窒素汚染は、農薬、畜産排水などが汚染源となっているため、野菜、果樹、茶の栽培に利用されることの多い扇状地や、畜産、野菜栽培に利用されることの多い火山山麓で拡大している。
環境基準では、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素ともに10mg/?と定められているが、基準を超える井戸も全国各地で見つかっている。
揮発性有機塩素化合物の汚染は汚染地域が局所的であるのに対し、硝酸性窒素汚染はその性格上、汚染地域が広範に及ぶ上、現状ではその改善に決定的に有効な対策が見当たらないことから、今後、被害の拡大も懸念されている。硝酸性窒素は過剰に摂取すると、乳児がメトヘモグロビン血症注) 等を起こすことが知られているが、日本ではそれによる発症例は報告されていない。

図1-3-6 平成9〜16 度(1997〜2004 年度)地下水汚染マップ(環境基準26 項目)
1.4 地下水に関する法制度の現状
わが国の現行法では、ヨーロッパの国々に見られる地下水の基本法や総合法(例えば、後述するEU水枠組み指令)のような上位法はなく、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(いわゆる「ビル用水法」)のような地盤沈下対策としての井戸揚水規制に関する法律、土壌汚染対策法や水質汚濁防止法、水質汚染防止に関する法律など、地下水に関連するさまざまな個別法が実効している。
多くの都道府県や市町村では、これら国の法律を受け、地域の実情に応じた独自の条例や要綱等を制定している。
(1)地下水揚水の規制
現在、地盤沈下対策としては「工業用水法」(1956 年(昭和31 年)施行、1962 年(昭和37 年)改正)及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(以下、「ビル用水法」、1962 年(昭和37年)施行)の2法が地下水揚水施設に適用されている。規制の対象となる指定地域は、表1-4-1及び表1-4-2に示すとおり、工業用水法は10 都府県、ビル用水法は4都府県にわたっている。
表1-4-1 「工業用水法」に基づく指定地域
(2)地盤沈下防止等対策要綱
法律や政省令ではないが、地盤沈下に伴う被害の著しい濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部の3地域については、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議(1981 年(昭和56 年)設置)において、「地盤沈下防止等対策要綱」が決定され、発効している。
これらの要綱は、指定3地域を対象とした重点的地下水の採取規制、代替水源の確保及び代替水の供給を行い、地下水を保全するとともに、地盤沈下によるたん水被害の防止及び被害の復旧等、地域の実情に応じた総合的な対策の根拠を与えている。
3地域の地盤沈下防止等対策要綱及び対象地域は表1-4-3に示すとおりである。
表1-4-3 地盤沈下防止等対策要綱の概要
また、各地域の近況は以下のとおりである。
□濃尾平野
2004 年度(平成16 年度)の地下水採取量は1.7 億m3 であり、目標採取量(2.7 億m3)を下回った。当該年度(2003 年11 月1 日〜2004 年11 月1 日)の水準測量結果によると、年間1?以上の地盤沈下が認められた面積は約9? 2 であった。
□筑後・佐賀平野
佐賀地区及び白石地区における2004 年度(平成16 年度)の地下水採取量はそれぞれ3.8 百万m3、4.2 百万m3 であり、佐賀地区では目標採取量(6百万m3)を下回ったものの白石地区では目標採取量(3 百万m3)を上回った。当該年度(2004 年2 月1 日〜2005 年2 月1 日)の水準測量結果によると、年間1cm 以上の地盤沈下はこれら両地区共に認められなかった。
□関東平野北部
2004 年度(平成16 年度)の年間採取量は4.9 億m3 であり、目標採取量(4.8 億m3)を上回った。当該年度(2004 年1 月1 日〜2005 年1 月1 日)の水準測量結果によると、地盤沈下は年間1?以上の沈下が認められた面積は約419 ? 2 であり、うち2?以上の沈下面積は約26 ? 2 であった。
(3)地方自治体における地下水に関する条例・要綱等の制定状況
地域の特性に応じ各地方自治体(都道府県、市町村)で、個別の地下水に関する条例・要綱等が制定されている。それらの法的性格は以下のとおり。
条 例:地方自治体の議会の議決などにより制定される法規で、法的拘束力を持つ。
要綱等:地方自治体が議会の議決を経ずに定める内規で、法的拘束力を持たない。
これらは、おおむね遵守されており、地域の特性に見合った地下水の利用・保全に大いに貢献していると考えられる。
ただし、同一の地下水盆が複数の地方自治体にまたがる場合、地方自治体によって規制の条件、条例・要綱等の内容が異なり、地下水盆全体としての整合した対応が必ずしもとれていない。
地方自治体の条例・要綱等による規制等の対象地域を定めても、対象地域以外では、たとえ同一の地下水盆であっても全くの自由に委ねられている点(いわゆる反対解釈)等の課題をもっているものもある。
?都道府県における制定状況
都道府県の地下水に関する条例・要綱等について、名称別に分類した(表1-4-4参照)。また、都道府県の62 件の条例・要綱等について、その名称と目的・対策等を地図上に示した(図1-4-1参照)。

表1-4-4 都道府県の地下水に関する条例・要綱等の名称による分類(2004 年7月現在)
図1-4-1 都道府県の地下水に関する条例・要綱等の制定状況と規定内容
これらのほとんどは、「公害防止条例」「生活環境保全条例」「環境基本条例」といった公害や環境全般を対象とする条例であり、地下水については、その一部として取り扱われている。
こうしたことから、地下水が、主に公害対策の一環として、地盤沈下対策の側面から規制の対象として取り扱われてきた経緯がうかがえる。一方、地下水そのものを主たる対象とする条例は5つ制定されている。それらは、以下のように要約される。
a)「公害防止条例」「環境条例」及びそれに類する条例における取り扱い(表1-4-4中の分類?〜?)
これらの中で、水質保全については、すべての都道府県において項目として掲げられ、その対策として汚水排出に関する規定が定められている。これは地下水の汚染にも関係するが、主に地表水の汚染との関わりが深い。一方、地盤沈下防止についてもすべての都道府県が目的として掲げているものの、その主要な対策である採取に関する許可・届出義務等の規定については、地域により規定のあるところと、そうでないところがある。
b)「地下水採取・地下水保全条例」及びそれに類する条例における取り扱い(表1-4-4中の分類?)
地下水の採取・保全に関する条例を制定しているのは、山形県、茨城県、富山県、静岡県、熊本県の5県である。その多くは「地下水の採取の適正化に関する条例」及びそれに類する名称を付し、熊本県のみが「地下水保全条例」の名称を持つ。これらのすべてが採取に関する許可・届出義務等の規定を定めており、公害や環境全般を対象とする条例を補完している。
c)地下水の採取に関する許可
公害や環境全般を対象とする条例もしくは地下水に関する条例において、採取に関する許可・届出義務等を規定している都道府県は、南東北、関東、北陸、東海地方に分布しているのに対し、北海道、北東北、甲信、近畿以西では、その選択的内容もしくは一部にとどまっている。
こうしたことから、採取に関する許可・届出義務等の規定は、人口が密集し、水需要の大きい大都市圏や、水資源における地下水依存率が高い関東内陸、北陸等、比較的広域的な対応の必要性の高い地域に制定されていることがわかる。
d)地下水涵養
地下水涵養の人為促進については、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、奈良県、熊本県の条例の中に規定があり、塩水化については、山形県、茨城県、富山県、静岡県、徳島県の5県で規定されている。
e)地下水に関する要綱等(表1-4-4中の分類?〜?)
要綱レベルのものでは、山梨県や徳島県において地下水の採取の適正化に関する要綱が定められているほか、埼玉県、千葉県、福井県において、地盤地下防止を目的とした要綱等が制定されている。埼玉県の「地盤沈下緊急時対策要綱」は、地盤沈下緊急時に知事が地下水利用者に対し、地下水の採取を抑制できるとするものであり、千葉県の「地盤沈下防止協定」は、天然ガスかん水地上排水基準等について県と天然ガス採取企業との間で個別的に締結された協定である。
?市町村における制定状況
市町村の地下水に関する条例・要綱等については、330 件の存在が確認できたが、その半数強の181 件は「公害防止条例」「生活環境保全条例」「環境基本条例」といった公害や環境全般を対象とする条例であり、地下水は、その一部の項目・内容で取り扱われている。
これらを除いた149 件は、名称別に分類した(表1-4-5参照)。また、分類対象とした149 件の市町村の条例・要綱等について、その名称と目的・対策等を地図上に示した(図1-4-2参照)。
表1-4-5 市町村の地下水に関する条例・要綱等の名称による分類(2004 年7月現在)
条例の名称 制定数
?地下水の採取・保全・保護に関する条例 76
?地下水の採取・保全・保護に関する要綱・規約 23
?水資源の保全・保護に関する条例 4
?水道水源の保全・保護に関する条例・要綱 12
?地盤沈下防止に関する要綱・指針 3
?自家用天然ガスの採取規制に関する条例 12
?地下水の汚染防止に関する条例 1
?水環境の保全に関する条例 1
?開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱 16
?地下水の涵養推進に関する要綱 1
合計 149
注)制定数は原則としてデータベース更新時のものであり、その後の市町村合併等による変更を反映していない。
資料)三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成
注)市町村名は2004 年7月現在のもの

図1-4-2 市町村における条例・要綱等の制定状況
a)名称による分類
分類対象とした条例・要綱等は、地下水採取の適正化や地下水の保全・保護、もしくはその双方を名称に含むもの(同じ内容の要件であっても重要度や取扱い方により違うもの)が多く、計99 件(うち条例が76、要綱・規約が23)が該当する。
水資源の側面からの条例・要綱等としては、地下水だけでなく、水資源や水道水源全般の保全・保護に関する条例・要綱で、地下水の採取に関する規定を含むものが計16 件ある。
また、地盤沈下防止に関する要綱・指針は3件あるが、このほか地盤沈下に関連して、自家用天然ガスの採取規制に関する条例が12 件制定されている。
地盤沈下以外の環境面に関するものとしては、地下水の汚染防止と水環境の保全に関する条例が各1件ある。また、開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱のうち、地下水の採取に関する規定を含むものが16 件ある。このほか、地下水の涵養推進に特化した要綱が1件制定されている。
b)条例・要綱の内容の概要
市町村の条例・要綱等について、その内容を概観すると、井戸の設置者や工場・事務所等の設置者に対し、地下水の採取について事前の届出等を義務づけたり、設備の設置基準等を定めたりするなど、採取に関する許可・届出義務や設備設置の基準に関する規定を定めるものがほとんどである。
これらの多くは地盤沈下防止もしくは水源保護を目的としているが、都道府県の場合と異なり、目的が明記されず、対策のみが定められているものも多い。また、一部の市町村では、採取に関する規定と併せて、汚水排出に関する規定や涵養に関する規定も定めている。
c)地域別の分類
地域別に制定状況をみると、新潟県が最も多く30 市町村、次いで、長野県が20 市町村、山梨県が17 市町村となっている。
このうち、新潟県については、自家用天然ガスの採取に関する条例が多いほか、地下水の採取に関する条例・要綱等の中で、消雪用地下水の保全や用水量の削減について規定しているものが多い。消雪に関する規定は豪雪地帯である石川県や福井県でもみられる。
また、長野県や山梨県では、開発事業等の基準・指導に関する条例・要綱等において地下水に関する規定を設けているものが多く、リゾート開発等に対応したものと考えられる。
これ以外の条例・要綱等の制定状況を地域別にみると、山梨県や静岡県の富士山麓、山梨県や長野県の八ヶ岳山麓、長崎県の雲仙山麓、熊本県の阿蘇山麓など大規模な火山の山麓地域や、山梨県や京都府のような盆地地形の卓越する地域、鹿児島県や沖縄県の島嶼地域において、地下水に関する条例・要綱等を持つ市町村が多い。
国の地盤沈下防止等対策要綱や都道府県の条例の制定状況と合わせてみると、広域的な地下水利用が行われている大規模な平野等では、国もしくは都道府県レベルの条例・要綱等が制定され、盆地や火山山麓、島嶼など比較的狭い範囲での地下水利用が活発な地域や、消雪対策、天然ガス採取、リゾート開発など固有の問題への対応が必要な地域においては、
市町村レベルで条例・要綱等が独自に制定されている。
一方、北海道、北東北、中国、四国では、道県、市町村いずれのレベルにおいても、地下水に関する条例・要綱等の制定が少ない。
これまでにみたように、地方自治体(都道府県、市町村)では、さまざまな条例・要綱等が制定されており、それらの中には規制を伴うものもあるが、地域の実情に即した形で地元に定着し、地下水の地域特性に応じた地下水の保全・利用への取り組みに寄与しているものと考えられる。
第2章 地下水をめぐる最近の動向と地下水保全・利用に係る課題
ここでは、地下水をめぐる最近の動向を調査し、その結果を通して必要な課題を把握する。
まず、わが国の水をめぐる諸問題、水需給全般の状況や、近年の地下水障害等の状況について整理する。次いで、水に関する世界情勢とわが国との関係及び動向が整理される。
2.1 わが国の水需給に関する動向
(1)わが国の水需給動向
?水需給の見通し
わが国の水資源政策の推移をみると、食料の確保と国土の保全が最優先された戦後復興期を経て、高度成長期には、都市部の人口急増や急速な経済発展に伴い都市用水を中心として水需要が急増し、これに対応するために本格的な水資源開発が進められたが、水質汚染や地盤沈下等新たな公害や環境問題が発生した。水資源開発が需要に追いつかない状況は、わが国の経済が安定成長期に入った後も継続した。このように戦後のわが国の水資源政策には、一貫して需要増加に対応した供給拡大が求められてきた。
近年は、水資源施設の充実、人口増加率(出生率)の低下(図2-1-1、図2-1-2 参照)、経済の安定・成熟や国民生活の質的向上等に伴い、渇水等の異常気象時を除き平常時の水需給のギャップは縮小しつつある。また、総人口の減少局面を迎えたことから、水需給の将来に対し、短絡的に楽観視する声もある。
しかし、気象変動に伴う利水安全度の低下や、都市域への人口の緩やかな集中が続くことが予想されることから、平常時はもちろんのこと、特に異常渇水、災害等緊急時の対応の充実が必要である。さらに、水の重要性を国際的視点から鑑みれば、長期的に国家戦略として水資源を総合的かつ戦略的に確保・管理していく必要がある。
図2-1-1 わが国の総人口の推移と予測
図2-1-2 わが国の年齢3区分別人口割合の推移と予測(中位推計)
?安全で良質な水供給への要請
健康志向や安全・安心への関心の高まりの中で、安全で良質な水供給への国民の要請はさらに増大している。その要請の一つは飲料水の消費に現れている。最近、市販ミネラルウォーターの生産量と輸入量が急増している(図2-1-3 参照)。2004 年をみると、国内生産量と輸入量をあわせ1,627 千キロリットルが消費されており、10 年前の消費量の約3倍である。
これを一人あたりに換算すると、年間で一人約13 リットルのミネラルウォーターを使用していることとなる。一人一日あたり飲料水必要量を3リットル(市町村等で防災上必要な備蓄量の目安とされる値)として計算すると、年間の飲料水必要量の約1%に相当する。
図2-1-3 ミネラルウォーター類国内生産及び輸入量の推移
(2)水需給に関する安定性
?気象変動に伴う利水安全度の低下への対応
近年、少雨年と多雨年の変動幅が次第に増加し、渇水年の年降水量が減少傾向にあるのみならず、年最大連続無降雨日数(降水のない日が連続する最も長い期間)も長くなる傾向が認められている。こうしたことから、ダム等の水資源開発施設が計画された当時の開発水量を安定して供給できないなど、水供給の利水安全度(実力)が低下しており、気候変動が国内の水需給バランスに与える影響が顕在化しつつある(図2-1-4 参照)。
今後も、こうした降水特性の変化や地球温暖化等に起因する気候変動により、水供給の能力低下が一層加速する恐れがあるとともに、これまでの計画規模以上の渇水の危険度も増加している(図2-1-5 参照)。
図2-1-4 日本の年降水量の経年変化
図2-1-5 気象変化による水資源開発水量の利水安全度(実力)低下(木曽川水系の例)
?大都市圏域への人口集中への対応
わが国の総人口は、2025 年時点でも全国で1.2 億人前後と1980 年代の水準にあると予測されることから、年齢別人口構成の変動はあるものの生活の質の向上志向や都市型生活の利便性を容認する限り、水需要が急減することは考えにくい。現状の地方圏の実情では人口減少が避けられないだろうが、地方ブロックの中枢都市以上の大都市圏域では、統計資料の外挿の上で、人口の緩やかな集中が続くと予測されている(図2-1-6 参照)。
大都市圏域は、圏域内外より供給できる1人あたり水資源量が少ないことに加え、社会基盤の高度化や高齢化、生活様式の変化等により、給水制限や断水時の社会的影響も増大している。大都市圏域では、利水安全度の低下が高度化した都市機能の持続と維持に深刻な影響を及ぼす恐れがあり、危機管理の視点から対応の必要性が高まっている。
図2-1-6 都市と地方の人口の推移と予測
(3)地下水資源の需給見通し
これまでに述べたわが国の水需給状況と今後の動向を踏まえると、将来の地下水資源の需給見通しは以下のように考えられよう。
* 安全で良質な水供給の要請から地下水資源への需要が高まる可能性がある。
* 気象変動を踏まえた利水安全度の確保や、都市部の住民生活や都市機能の持続・維持の観点から、地下水資源への需要が高まる可能性がある。
2.2 新たな地下水障害と地下水源開発の動向
これまで地下水障害といえば、地下水の広域かつ長期にわたる揚水利用によって生じる地盤沈下、井戸枯れ、塩水化などを指したが、近年、渇水時の短期に集中する地下水利用に伴う地盤沈下が新たに問題となってきた。ここでは都市地下構造部への地下水の悪影響や新しい地下水開発・利用によるインパクト等も含め、主として量的側面に焦点を当てて広い視野で検討を加える。
(1)渇水時の地下水位(水頭)低下と地盤沈下
多くの地域では地盤沈下が沈静化し、地下水位・水頭(被圧帯水層)の大幅な低下はみられなくなってきているが、数年に一度生じる渇水時(図2-1-4)には、主要な都市域で短期的な低下がみられる(図2-2-2、図2-2-3参照)。これは、地表水が減少して河川水の取水制限が行われ、代替水源として地下水の利用量が増加することや、少雨により涵養量が少なくなることが要因と考えられている。
地下水位・水頭の低下は、地盤沈下などの不可逆かつ蓄積する障害を招く恐れがあり、一度生じると回復は容易ではなく、将来にわたる大きな問題となることから、渇水時には以下のように対応し、地下水位・水頭の低下を防ぐことが求められる。
1) 渇水時における地下水利用状況の把握・地下水位低下の要因特定
従来の年単位の地下水採取量の把握に加えて、渇水が起こりやすい地域、渇水が起こりやすい時期には、月単位などより詳細な地下水採取量の把握を行うとともに、地下水位の低下の要因を特定する必要がある。
2) 渇水時における地下水採取抑制・自粛の要請
渇水時における地下水位低下の要因を特定した上で、地下水利用の限界採取量あるいは管理基準地下水位を設定し、基準を超えた際には、利用者に対して地下水採取の抑制を要請する仕組みづくりが求められる。
例えば、生活用水の地下水依存率が高い福井県大野市では、扇状地の水田の水がなくなる11 月頃の地下水位が最も低くなり、これまでに大規模な井戸枯れが生じた経緯から、独自の地下水警報発令基準を設けている。近年、地下水位の低下が著しく、たびたび節水を呼びかける警報が出されている。
図2-2-1 渇水時の地下水位低下のメカニズム
図2-2-2 渇水年における地盤沈下の進行
図2-2-3 要綱地区(筑後・佐賀平野)における地盤沈下面積と地下水採取量
(2)地下水位(水頭)上昇による地下構造物への揚圧力による障害
揚水規制や地下水環境の保全意識の高まりにより、近年では、地盤沈下地域の数、面積ともに減少し、地盤沈下は沈静化しつつある。
しかし、首都圏では、地下水採取の法的規制によって、逆に地下水位が回復・上昇し、東京駅や上野駅などの鉄道駅の地下部分が浮き上がる等の新たな問題が発生し、JR東日本ではアンカーを埋めるなどの地下水位上昇対策工事(東京駅:1999 年、上野駅:1997年)を行った。また、大阪市では、地盤沈下を防ぐため地下水の採取を規制してきたが、現在は逆に地下水位が上昇し建物が浮いたり、地下街や地下鉄のトンネルへの湧水増等の事例が出てきている。
地下水位の上昇は地震災害時に液状化を引き起こす可能性など、防災上の問題も指摘されている。
このように、東京都や大阪市など大都市圏の限られた地域の問題ではあるものの、地下水位の上昇に伴い、地下水位が大幅に低下した時期に計画・建設された地下構造物が浮き上がるなどの障害がみられ、所有者や管理者による対策が実施されている。今後、このような国土の脆弱化をもたらす地下水位の上昇を防ぐために、地下水環境保全を促す地下水位を定めた上で、利用可能な範囲内で地下水採取を行うなど、一定の地下水位を維持する施策が求められる。
(3)ミネラルウォーターの生産拡大の動向
ミネラルウォーター市場の拡大に伴い、大手飲料メーカーだけでなく、全国各地で地下水を活用した飲料水ビジネスが活発化している。現在、国内で約400 社、450 銘柄のミネラルウォーターの飲料水があると推計されている。
現在、国内生産されているミネラルウォーターの生産量は、国内で使用されている地下水使用量全体(124.1 億?)の約0.01%にとどまり、現時点ではその占有率は低いが、大量採取が行われているような地域においては、この割合は今後高くなると想定される。
大手飲料メーカー等は山間部などの水源を確保し、地下水の大量採取を行っているが、現在のところ、この新たな地下水採取によって、周辺の地下水利用者への影響や、地下水障害等は特に報告されていない。この動向に対して行政は、水源地下水の状況や利用可能量を見極めた上で、必要な対応が求められる。
また、全国で最もミネラルウォーターの生産量が多い山梨県では、自治体が地域資源からの恩恵を受けている事業者に対して税負担(例えば、1リットルあたり0.5〜1円の税率で、2.5〜5億円の税収見込み)を求めることを検討した事例もある。
(4)地下水新ビジネスの参入
近年、水質改善膜ろ過技術や井戸の小口径高揚程ポンプの開発に伴い、企業、農漁業団体、サービス業、公的機関等の専用(自己)水道による地下水利用が新たに増加している。
特に、ホテルや病院、ショッピングセンターなど、緊急時の自己水源確保を求められる個別水道利用施設で導入が進んでいる。
この個別水道利用施設の地下水利用では、20〜30mの浅層家庭用井戸と異なり、100m以深の深井戸からのくみ上げが目立つ。浄水膜ろ過プラントは小型な設備であれば3,000万円程度の投資で済み、また、揚水機のリースであれば投資リスクを負う必要が無いなど、利用者にとって初期負担が比較的小さいことも普及の要因となっているものと思われる。
地下水の採取規制などがない地域では、利用者にとっては、水質に問題がなければ揚水コストを削減することができる。さらに、地震などの災害時に備え2つの自己水供給システムを有することができるというメリットもある。
現在のところ、これらに伴う地下水障害は顕在化していないが、規制対象から外れた地下水揚水施設については、現行法制度では利用実態の把握が困難であり、採取量が把握できない状況となっている。
また、水道事業を行う自治体において、この種の地下水採取に伴い、水道水の利用量減少による減収が懸念されている。
(5)深層地下水の開発
地下水資源は、淡水そのものを利用の対象とするのみならず、温泉・鉱業や深層水の新規開発にも拡大して目が向けられている。とりわけ都市型の商業施設や娯楽施設では深層地下水が多目的に活用されている。
(6)地下水の発展的利用・可能性へ向けた議論の動向
昨今、地下水の都市ヒートアイランド現象軽減のための利用など、いくつかの新しい発展的活用へ向けた議論がなされている。
2.3 地震災害等、緊急水資源需要への対応
(1)地震災害時における問題点
わが国では、1995 年の阪神・淡路大震災をはじめ、2004 年新潟中越地震、2005 年福岡県西方沖地震など、大きな被害を伴う大地震が発生している。これらの地震災害時には、各用途に応じた緊急的な水の確保が問題となった。阪神・淡路大震災においては、井戸や湧水を雑用水として利用したケースが報告された。また、震災時には揚水ポンプが停止し、急激な地下水帯水層の水圧力上昇により水があふれ出たが、この水が震災時のトイレ用水や復旧工事の際の散水などに活用された注)。
その他に新潟中越地震では、液状化による被害や消雪パイプの破損も問題となった。
表2-3-1 阪神・淡路大震災における水利用に関して報告された問題点
分類 分類 問題点
用途別 消火活動 ・消火栓が使用できず、消火活動の大きな障害になった。
医療活動 ・病院には特別に給水活動を行う必要があった。
飲料・炊事 ・市民は、飲料用水として、市販の水を確保した。
トイレ洗浄 ・量を必要とするトイレ用水は、その確保とともに運搬も大きな問題だった。
表2-3-2 新潟中越地震における水需要及び地下水利用に関する問題点
・被災地すべての避難所で県が実施した生活実態調査によると、「トイレが不便」という避難所が3割に達した。
・地震による液状化現象により、マンホールが浮き上がったり、路面が割れて盛り上がるなどの被害が生じている。これにより除雪車が走行できない等の問題が生じた。
・消雪パイプが破損したが、ガスや水道の復旧作業が優先されるため、消雪パイプの復旧が遅れ、雪対策が遅れる等の問題が生じた。
なお、地下水位の上昇による大地震発生時の液状化現象の危険拡大も指摘されている。液状化現象とは、地下水で満たされた地層(地盤)が地震動によりその体積を減じ、その分、間隙にあった水が上方に放出され、地盤内に余剰の水があふれた結果、地層が液状流動化することを言う。これにより、地上・地下のライフライン、構造物等が重大な被害を受ける可能性がある。
さらに、地球温暖化による海水面の上昇が、沿岸・臨海域の地下水位上昇や地盤の液状化強度の低下をもたらす可能性も指摘されている。
注)震災時の水の確保に関する研究会「大都市における大規模震災時の「水」の確保について(案)」(阪神・淡路大震災での状況)参照
(2)地震災害への対応
?緊急水需要
a)経過日数でみた水需要
大規模震災時に想定される水需要を、用途及び発生場所の点から経過日数に即して整理したものが図2-3-1 である。災害直後から3日目頃は消火用水、医療用水及び生命の維持に必要となる最小限の飲料水の確保が不可欠となる。また、被災生活が開始されると、飲料水だけでなく炊事、トイレなどのための水需要が発生するほか、入浴や洗濯のための生活用水が必要となる。
さらに、災害後概ね4日目以降で復旧作業が開始されると、生活用水の拡充とともに、産業復活や防塵、復旧工事用の水需要が発生する。
図2-3-1 地震被災時における水需要
b)用途別にみた水需要
地震災害時における水需要はその用途に応じて、必要となる水量や水質は異なる。例えば、災害直後に多量に必要となる消火活動や、生活用水の中でもトイレ洗浄用水は水質への要求度は高くない。一方、医療活動の水や飲料・炊事用水は清浄な水質が求められる。
表2-3-3 地震災害時における用途別にみた水需要
?応急水供給
地震災害時に利用が想定される、都市における水の所在は以下の通りとなっている。河川・池・湖沼水や海水などは大量に供給可能だが、水質が保証されず、取水ポイントが限定される。また、雨水や再生水は比較的良質な水であろうが、専用の設備が整備されていることが必要となる。
このような中で、地下水は、清浄な水質が期待できる身近な水資源として、飲料や医療用途に活用できる可能性があるが、事前の十分な水質検査や、地震時における地下水脈への影響等を考慮して利用する必要がある。
表2-3-4 地震災害時における水供給源別にみた特徴
2.4 水に関する世界情勢
情報、経済、物流のグローバル化が進む現在、それらを支える基盤である水資源や水政策が今後の日本でいかにあるべきかを考えることは、時代の要請と言えよう。ここでは世界的な水問題について、米国の水事情概況及び地表水・地下水を合わせた総合的な水資源管理をめざす欧州の取り組みを紹介する。
(1)世界的な水問題とわが国の関係
?世界的な水需要の拡大と地下水障害の発生
18 世紀産業革命以降の世界人口の増加や、農業、とりわけ灌漑農業の発展は、淡水の消費を飛躍的に増加させた。例えば、中国・黄河の過剰取水による流況異変、中央アジア・アラル海の灌漑取水による水位低下が招く湖面積の縮小など、世界各地で水が不足する状態を生じさせている。
米国は図2-4-1に示すように、西経100 度と120 度に挟まれた全国土(936.3 万k ?)の約4割が年降水量500mm 程度の乾燥地帯であり、西経100 度以東は降水量に恵まれた(例えば、ニューオーリンズの年降水量1,584mm)温帯多雨国土である。この東西を二分する気候は、地形と地質が相まって固有の農業を発展させてきた。図中の乾燥地帯はシェラネバダ山脈とロッキー山脈に挟まれた高地グレートベースンとロッキー山脈の東側グレートプレーンズに拡がり、小麦生産や遊牧業及び人工灌漑農業が広大な農地で行われた。
多量の水を必要とする灌漑農業には、化石水ともいえる深層地下水が利用されている。図中ではこの地域の水不足分布が概観されている。
地下水についても、米国・グレートプレーンズでは深刻な地下水位の低下が生じている。
この「センターピボット(Center Pivot)方式」では、1つの井戸で毎分10 ?の地下水を揚水し、井戸の本数が数千本にもなるため、年間約7,500 万?もの地下水を利用するが、涵養量は年間約800 万?にとどまるため、過去30 年間で地下水位は平均12m、最大30mも低下した。この結果、耕地面積は1978 年〜1988 年の10 年間で100 万ha 減少した。
図2-4-1 米国の水不足地域の分布状況
?世界的な水問題とわが国の関係
国連環境計画や国連人間居住委員会、ユネスコなど23 の国際機関などが共同で発表した「世界水開発報告書」(2003 年3月)によると、半世紀後には最悪の場合で世界人口の8割にあたる70 億人が淡水不足に直面すると予測しており、水問題は21 世紀の世界的な課題だと警告している。
島国日本は、当面、水需給ギャップが縮小傾向にあり、国際河川や国際湖沼も当然ながら存在しないため、直接的な水に係わる国際紛争はないが、無関心ではいられない。その理由は、例えば、水資源に直結するわが国の食料自給率は熱量換算で2000 年には約40%まで低下しており、フランス、アメリカ、ドイツなどの食料自給国と比較して非常に低い。
食料の生産には水が使用されることから、わが国は食料等の輸入を通じ間接的に海外の大量の水を消費しており、その総量は年間640 億?と見積られている(図2-4-3参照)。
世界的な水危機の状況が、今後ますます激化すると予想される中、これに関する世界の経済、社会活動の変化とりわけ食料問題は、物流・経済を通じて日本経済や社会問題に直結している。今後の水資源政策は、このような実情も視野に入れながら、より好ましい水資源を総合的かつ戦略的に確保、管理していかなければならない。
図2-4-3 日本の仮想投入水総輸入量
(2)EU政策「水枠組み指令」
世界的な水危機に伴い、総合的・戦略的な水資源政策が求められる中で、わが国の地下水保全・利用のあり方を検討する際の参考に資するため、ここでは、特に地下水利用の長い欧州における取り組みを紹介する。
欧州では、古代ローマ時代から地表水よりも地下水を優先して使用してきた経緯がある。その伝統は、現在でも特に生活用水において継承されており(鯖田、岩波新書、2001)、
その宗教的とも言える思想は、地下水源の保全に向けた欧州先進国の取り組みの中で継承されている。
近年、EUでは、加盟国に統一した指令として、流域単位での水管理を目指す「水枠組み指令」が新たに発効された。ここではそれに着目して、その背景や考え方、水政策と地下水に関する動向等について言及する。
?「水枠組み指令」(EU Water Framework Directive)の背景
a)EUの概要
欧州連合(EU:European Union)は、「経済的な統合を中心に発展してきた欧州共同体(EC)を基礎に、欧州連合条約(マーストリヒト条約)(1993 年発効)に従い、経済通貨統合を進めるとともに、共通外交安全保障政策、司法・内務協力等のより幅広い協力をも目指す政治・経済統合体」である。従来の国際機関などとは大きく異なり、構成国からの国家主権の一部の委譲を前提に、域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成し、政治的にも「一つの声」で発言する等、いわば連合国家に準ずる存在である点が大きな特徴である。
表2-4-1 EUの概要(2007 年1月現在)
b)欧州における水問題の状況
「水枠組み指令」制定の背景となった欧州における水問題の状況について、「水枠組み指令」では以下の各点があげられている。
*欧州連合の全地表水の20%は、深刻な汚染の危機にさらされている。
*欧州の飲料水の約65%は、地下水でまかなわれている。
*欧州の都市の60%は、地下水資源を過剰に採取している。
*湿地帯の50%は、地下水の過剰開発により「危機的状況」にある。
*1985 年以降、南欧の灌漑地が20%増加している。
EUにおいては、これまでにも主に水を保護するための政策や法律が策定されてきたが、「欧州連合の環境−1995」では、上記のような背景を踏まえ、EU内の水について、量的のみならず質的にも保護アクションが必要であることが指摘されている。
?「水枠組み指令」の概要
水域を良好な状況にすることを目的として制定された「水枠組み指令」(EU WaterFramework Directive)は、正式名称を「水政策分野での共同体アクション枠組みを構築する2000 年10 月23 日の欧州議会及び評議会指令2000/60/EC」(Directive 2000/60/EC ofthe European Parliament and of the Council establishing a framework for the Communityaction in the field of water policy)と言い、2000 年12 月に発効した。
「水枠組み指令」は、地表水や地下水などすべての水資源を対象としており、欧州全体で、地下水と地表水の統合的な管理を示した初の指令である。「水枠組み指令」を受けて、各EU加盟国は、地域性に応じたマネジメント計画等を作成し、それに基づく対策を講じることで、EU全体で水環境の保全・管理を進めていく仕組みとなっている。地下水の位置づけは地表水と同等であり、特に、第17 条では地下水に特化して汚染対策が記載されている。
「水枠組み指令」の特徴として、政治・行政的境界ではなく、河川流域単位での浄化及び管理の取り組みを導入していることがあげられる。各国はまず指令の対象となる河川流域を指定し、適切な管轄当局を含む行政整備を行うことが義務づけられている。国際河川流域についても、関係国間で調整し、同様の指定を行わなければならない。これらの河川流域には、言うまでもなく地下水が含まれる。
また、「水枠組み指令」では、水環境の維持と改善を目的としており、主な対象は水質である。水量のコントロールは水質対策の付随的な要素とされており、良質な水を確保するためには、各国で、質と同時に量に関する対策も実施すべきであるとされている。良好な地下水状態とは地下水の量的状態、化学的状態の両方が良好であることを指すとされて
いる。
以下に、「水枠組み指令」の構成及び概要を示す。
a)「水枠組み指令」の構成
「水枠組み指令」は以下のような条文から構成されている。
第1条 目的
第2条 定義
第3条 河川流域地区内での行政整備の調整
第4条 環境目的
第5条 河川流域の特徴、人間活動による環境影響のレビュー、水使用の経済分析
第6条 保護地区の登録
第7条 飲料水の対象とする水域
第8条 地表水状態、地下水状態、保護地域のモニタリング
第9条 水サービスの費用の回収
第10条 点源、拡散源についての組み合わせアプローチ
第11条 対策プログラム
第12条 加盟国のレベルで対処することができない問題
第13条 河川流域マネジメント計画
第14条 情報公開とコンサルティング
第15条 報告
第16条 水汚染に対する戦略
第17条 地下水の汚染防止、コントロールに関する戦略
第18条 委員会報告
第19条 将来の共同体対策計画
第20条 本指令に対する技術的な調整
第21条 規制委員会
第22条 廃止及び過渡的条項
第23条 罰則
第24条 実施
第25条 効力発生
第26条 送付先
付録
b)「水枠組み指令」の特徴
上述に構成されている「水枠組み指令」について、ここでは主な特徴を整理する。
■環境目的
主な環境目的は、すべての水域を2015 年までに良好な水質状態にすることである。
□地表水について
・加盟国は、地表水全体の劣化を防止するための必要な対策を実行しなければならない。
・加盟国は、すべての地表水体(bodies of surface water)を保護、整備、修復しなくてはならず、本指令発効(2000 年12 月)後少なくとも15 年間は良好な地表水状態を達成しなければならない。
・加盟国は、良好な生態的潜在力、良好な地表水化学状態を保つために、本指令発効後少なくとも15 年間は、人工的あるいは大幅に改良した地表水体を保護し整備しなくてはならない。
・加盟国は、重点物質による汚染を徐々に減らし、優先的危険物質の排出、放流、損害を排除、あるいは徐々に排除するために、必要な対策を講じなければならない。
□地下水について
・加盟国は、汚染物質が地下水に入ることを防ぎ、あるいは制限し、地下水全体の状態が悪化しないようにするために必要な対策を講じなければならない。
・加盟国は、本指令発効後少なくとも15 年間は良好な地下水状態を達成することを目的として、すべての地下水体を保護、整備、修復し、地下水の揚水量と涵養量のバランスを確実にしなくてはならない。
・加盟国は、地下水の汚染を徐々に減少させるために、人間活動の影響により地下水中の汚染物質の濃度が著しくあるいは持続的に増加する傾向にある場合、それを修復するために必要な対策を講じなければならない。
■現状把握
本指令を受けて、各河川流域地区で以下の事項を実施しなければならない。
○河川流域の特性把握
○地表水あるいは地下水に対する人間活動の影響の把握
○水使用の経済分析
○飲料水として抽出する水(1日平均供給量が10 ?超または50 人超に供給)または将来飲料水として使用される水のモニタリングなお、飲料水として抽出する水源は保護地域として登録が義務づけられる。
本指令を受けて、各国は2006 年までに(発効後6年以内)水状態のモニタリング・プログラムを設定し、実施しなければならない。地下水については、化学的状態及び量的状態の把握が求められている。
■水サービスのコスト
本指令では、水は商用製品とは異なり、むしろ遺産のように保護しなければならないとされているが、同時に水サービスコストの回収も考慮すべきと明記されている。加盟国は2010 年までに以下の実施が求められている。
?水料金政策によって水使用者が効率的使用を行った場合には、適切なインセンティブを与えられるようにして、環境目的に貢献するようにすること。
?経済分析に基づき、汚染者負担の原則を考慮して、産業、家庭、農業の異なる水利用者が、水サービスコストを適切に負担すること。
■対策
各国は、河川流域地区ごとに目的を達成するため、対策プログラムを実施しなければならない。このプログラムでは、国内レベルでの既存の法令に基づく対策の中から、本指令で求められている基準を定められた期限内に達成することができる活動を特定し、採用することができる。
■流域マネジメント計画
各国は、河川流域地区ごとに河川流域マネジメント計画を2009 年までに作成し、運用しなければならない。複数の国にまたがる国際河川流域マネジメント計画は単一の作成が義務づけられている。河川流域マネジメント計画は6年ごとにレビュー・更新される。その際には情報公開を徹底しなければならない。
■水汚染に対する戦略
欧州議会と欧州評議会は汚染物質あるいは汚染物質グループによる水汚染に対して対策を講じなければならない。欧州委員会は汚染の要因となる重点物質や重点危険物質を明確にし、それに対する対策について提案が義務づけられている。
これを受けて、欧州委員会は2001 年1月、新水枠組み指令の最初の規制対象として指定する32 種類の「優先物質」リストを提案、同年11 月に採択された。特定の有害物質については、20 年以内に水域への排出を段階的に停止することとされている。
地下水については、第17 条の中で記述され、地下水の汚染防止、コントロールに対する戦略として、欧州議会と評議会は、
?良好な地下水化学状態を評価するための基準、
?重大な継続的上昇傾向の確認及び傾向が逆転した地点の定義、を含む提案を行うこと
が義務づけられている。
また、第8条では、各国が策定する水状態のモニタリング・プログラムの対象として、地下水については化学的状態、量的状態があげられている。
■スケジュール
EU加盟各国は、2003 年12 月までに本指令の遵守に必要な法律、規制、行政条項の発効が義務づけられている。本指令の主要事項における期限は以下の通りである。
期限 内容
2003.12 ・本指令の遵守に必要な法律、規制、行政事項などを発効・流域連携の組織化
2004.12 ・水への影響分析を完了(経済分析を含む)
2006.12 ・水マネジメントの基盤となるモニタリング・プログラムの実施
2008.12 ・河川流域マネジメント計画が市民に公表される
2009.12 ・最初の河川流域マネジメント計画が発効される
2015.12 ・良質な状態の水となる
?「水枠組み指令」を補完する地下水に関する指令及び動向
2003 年9月、欧州委員会は、水枠組み指令の第17 条に基づき、地下水汚染防止に関するEU指令案(Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of groundwater against pollution 2003/0210(COD))(以下「地下水指令」)を発表した。「地下水指令」は加盟国に対し、地下水質のモニタリングを義務づけ、EUの既存の法令基準(窒素分、植物保護剤、殺生物性製品など)の遵守状況を把握するよう求めている。EUの法令で対象とされていない物質については、加盟国が2006年6月までに上限値を設定することとされている。汚染の程度が、「期間」と「環境上の重大性」の観点からみて、一定のレベルを超える場合には、加盟国は汚染悪化を防止する対策を講じなければならない。
水質基準値または上限値の75%を超える場合は、環境上重大な状況にあるとされる。この他、地下水汚染を防ぐため、有害物質の間接的な排出(地面や土壌中への排出)を禁止または制限する条項も盛り込まれている。
地下水指令の構成は以下の通りである。
第1条 内容
第2条 定義
第3条 地下水の良い化学状態を評価する基準
第4条 閾値いきち*1
第5条 重大かつ悪化傾向の判断基準及び修復を行う出発点の定義
第6条 地下水への間接的な排出を防ぐまたは制限する施策
第7条 過渡的なアレンジメント
第8条 技術的な適合
第9条 実施
第10条 効力発生
第11条 実施者
付録
備考*1)EU の各加盟国が定める、地下水帯に危険な影響を及ぼすと見なされる汚染物質の限界値。国レベル、流域レベルまたは地下水帯レベルで定めることができる。
このほか、「水枠組み指令」に基づく2005〜2006 年の作業プログラムとして、地下水、環境状況、統合的流域管理、調査報告をテーマとする4つのワーキンググループが設置され、水枠組み指令の実施にあたって解決すべき課題の検討がなされている。
?わが国の地下水利用のあり方への示唆
このように、EU「水枠組み指令」では地下水と地表水を総括した水資源全体での統合的な管理を推進している。地下水を含めた流域圏を一つの単位として、行政的な境界を超えて水資源管理を行うことが求められており、2009 年までに河川流域マネジメント計画を発効することが予定されている。
わが国においても複数の自治体にまたがる広域的な地下水マネジメントを実践する上で、行政計画策定や実践に向けた方法や手順策定の参考となろう。
2.5 地下水の保全・利用に向けた課題
(1)水資源需要多様化と地下水への期待
これまでに述べたように、わが国の水需給は、将来の人口減少や経済成長の鈍化に伴いおおむねバランスする方向にあり、一方で、安全で良質な水供給に対する要請はますます強まる動向にある。他方、少雨傾向など気候変動に伴う渇水が従来以上に頻発かつ大規模化する傾向があり、利水安全度の低下がより懸念される大都市圏域を中心として、危機管理の視点からの備えの必要性が高まっている。大規模地震災害時には、まず水の確保が重要な課題となるが、身近にある地下水は、それに即応できる重要な水源となりうる。
さらに、地球規模の水危機の深刻化にあって、安全保障の観点や食糧確保等を念頭に世界の水問題へ対応していく必要がある。
今日、淡水資源そのものを支える降水量とその地域分布が地球規模の気候変動によって大きく変容しつつある中で、水資源需給の多様化や安全性を満たす新しい水政策の構築が国家戦略として急務である。そのためには、河川水や湖沼水を含む地表水資源と地下水資源の量的・質的特性を活かしつつ、両者を調和的に利用しうる方法論が必要である。
ここでは、以上の観点から、過去の地下水過剰利用とその障害を教訓にしつつ、地球時代における地下水資源のあり方の議論に先行して、考えられる課題を以下に整理する。
(2)水資源としての地下水の保全・利用に向けた課題
地下水の保全・利用のあり方を考えるにあたって、まず、地下水が重要な水資源であることの共通認識が不可欠である。その上で、水循環系の構成要素として地表水と地下水のデータ整備や利用実態の把握を行うこと、水資源として保全と持続的利用の最適なマネジメントを考えること、また、地下水の分布や利用形態は地域的に多様性に富むことから、地域特性に即した保全・利用のあり方を実現していくことが大切である。
?水資源としての共通認識の醸成
わが国では、高度経済成長期に過剰な地下水の採取が深刻な地盤沈下を招いた経験から、それが広域的な地盤沈下の要因となることについては共通認識が得られている。しかし、地下水は地形・地質の構成要素であり、土地所有状況とは関係なく個別の地下水利用が多かれ少なかれ他に影響を及ぼすといった地下水資源特有の性質は十分理解されていない。
また、地下水は地表水と比較してデータ整備や実態把握が個別的であるため、地下水資源マネジメントに結びつく情報として定着していない。
こうしたことから、今後、地下水を水資源として捉え、その保全・利用を図っていくための共通認識を醸成していくことが課題である。
?水循環系の構成要素としての地下水に関するデータ整備・実態把握
降水を源とする地下水は、地表水とともに水循環系の構成要素であることから、水資源として重要であるだけでなく、流域地表水の基底流量の安定化や洪水流出の緩和に寄与したり、豊かな水辺環境の保全・再生に重要な役割を果たしたりするなど、水循環系において多面的な役割を担っている。
EU「水枠組み指令」(2000 年)によると、地表水や地下水などすべての水資源を対象として、流域単位での統合的な水の管理をめざす取り組みが進められている。一方、わが国でも「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」のもとで、流域全体を視野に入れた水循環系の健全化に向けた取り組みが芽生えている。
こうしたことから、水循環系の構成要素として地下水の保全・利用を行っていく必要はあるが、地下水は地表水と比較して各種定量データが十分に整備されておらず、行政上も組織的にデータ蓄積・分析する仕組みが確立されていないことから、現状では、水循環系全体として、地表水に呼応して地下水を統合的に保全・利用できる状況にはない。
このため、地下水に関する定量データを整備しうる仕組み、例えば、地下水の水資源と
しての基本データ(地下水位・水頭、採取量、地質柱状図、利用実態、水文等)の電子デ
ータ化の推進が時代の要請となっている。その定量データに基づき、科学的な地下水資源・
保全計画を立てて、水循環系の構成要素としての地下水の位置づけや特性を明らかにした
上で、適切な保全・利用を図っていくことが課題となる。
?持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現
地下水は、一般に水質が良好かつ水温変化が少なく、大規模な貯水・取水・給水施設を
必要とせず安価に利用できることから、わが国では、特に経済復興・高度成長期の水需要
に応え、大量に利用され、地盤沈下問題が深刻化した。その対策として国や地方自治体に
よるさまざまな取り組みが進められた結果、地盤沈下はおおむね沈静化している。
以下に示す観点から、今後とも地下水障害を未然に防止するための十分な配慮が必要で
ある。
1) 依然として、長期的には地盤沈下が沈静化している大都市でも、渇水時に短期的・
局所的な地下水位の低下が地盤沈下を招いた(平成6年渇水等)。近年、少雨年の
降水量が減少傾向にあることや、年最大連続無降雨日数(降水のない日が連続する
最も長い期間)が長くなる傾向が認められることから、今後も渇水に伴う地下水位
低下が懸念されている。
2) 深刻な地盤沈下を経験してきた地域(東京、名古屋、大阪等)は、地下水の採取量
を抑制してきた結果、地下水位が回復、上昇に転じ、地下街や地下駅などの既設地
下構造物が浮き上がる問題が生じている。
3) 地下水はいったん汚染されるとその浄化が困難であることから、有機塩素系溶剤や
硝酸性窒素など地下水汚染が多様化していることを踏まえた地下水資源の水質保全
について、特に留意が必要である。
4) ミネラルウォーター生産のための地下水利用、揚水・ろ過技術の新技術を背景とし
た個別水道利用施設における地下水利用等が拡大している。
地下水は水循環系において一般的に滞留時間が長く、地盤沈下や水質汚染などの地下水
障害は、いったん生じると復旧が不可能であるか、もしくは長い年月を要する。このこと
から、持続可能性という観点に立ち、地下水をめぐる新たな動向が及ぼす影響についての
解明も進めつつ、地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染等を生じさせず、地下水の保全と
利用の最適なマネジメントを実現していくことが課題となる。
?地域特性に即した保全・利用のあり方の実現
地下水資源の分布や利用形態は、地形、地質、気候、植生等の自然条件や、人口、土地
利用、産業、歴史・文化等の社会経済条件によって地域ごとに大きく異なっており、多様
性・固有性に富んでいる。
例えば、わが国では、主要な地下水盆は平野や盆地に分布しているが、関東平野のよう
に複数の都県にまたがる大規模なものから、単一市町村にとどまる小規模な平地や扇状地
まであり、このほかに火山地域や石灰岩地帯にも帯水層が存在し、それぞれで地下水が利
用されている。また、水利用全体における地下水への依存度や、生活用水、工業用水、農
業用水といった地下水利用の用途別割合も、地域によってさまざまである。
このように地下水資源の分布や利用形態が異なれば、地下水資源の開発可能性や地下水
障害・汚染等の発生状況も千差万別である。このため、地下水の保全・利用に向けた取り
組みにあたっては、それぞれの地域特性に則した考え方や方法・体制等に基づいて対応す
ることが重要な課題となる(図2-5-1参照)。
地下水への期待と動向
■水資源としての地下水への期待
* 安全で良質な水供給への要請
* 気候変動等に伴う利水安全度の低下への対応
* 大規模地震災害時の水源確保
* 長期的な安全保障の観点からの水資源確保の必要性
■地下水をめぐる最近の動向
* 広域的な地盤沈下は概ね沈静化
* 渇水時には短期的・局所的な地下水位低下、 地盤沈下が発生
* 一部地域では地下水位上昇により地下構造物への影響も発生
* 地下水質汚染
* 新たな地下水利用形態( ミネラルウォーター、 地下水ビジネス)の拡大 等地下水の保全・利用の課題
* 水資源としての共通認識の醸成
* 水循環系の構成要素としてのデータ整備・実態把握
* 持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現
* 地域特性に即した保全・利用のあり方の実現問題の所在
* 水資源としての地下水、 および水循環の構成要素としての地下水についての共通認識が得られていない
* 地下水の諸問題について、 科学的な見地からの実態解明・要因分析が十分になされていない
* 水資源としての地下水資源の保全と利用の調和の社会的合意や理念が形成されていない
* 地下水の現状・動向は、 地域ごとの多様性が高く、 全国画一的な対応が困難
図2-5-1 地下水の保全・利用に向けた課題の概観
第3章 今後の地下水利用に向けた基本的な考え方と方法
第2章では、地下水資源の保全・利用に向けた課題として、水資源としての共通認識の醸成、水循環系の構成要素としてのデータ整備・実態把握、持続可能性の観点からみた保全と利用の最適なマネジメントの実現、地域特性に即した保全・利用のあり方の実現、という4つが抽出された。
これらの解決における科学的論拠は「健全な水循環系の構築」(新しい全国総合水資源
計画(ウォータープラン21)、国土庁、1999 年)に置かれる。ここではまず、健全な水循
環系の構築における地下水の位置づけや、水循環系の構成要素としての地下水の特性を踏
まえ、課題解決に向けた基本的な考え方を示す。
次に、これらを踏まえた地下水の適正な保全・利用を実現するための新しい方法論とし
て、「地下水資源マネジメント」の考え方を提案し、その具体的な手順について述べる。
さらに、その計画・実践にあたり、地域ごとの多様性、地下水の特性、特に地域規模と
の関係に着目し、地域規模に基づく類型別「地下水資源マネジメント」を提唱する。
3.1 健全な水循環系の構築における今後の地下水利用の基本的な考え方
ここでは、健全な水循環系の構築にあたって地下水の位置づけを明らかにし、地下水の
特性を地表水と比較検討した後、これらを踏まえ、課題解決に向けた今後の地下水利用の
基本的な考え方を提示する。
(1)健全な水循環系の構築における地下水の位置づけ
?健全な水循環系構築の背景
「健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて」(2003 年10 月、健全な水循環系構
築に関する関係省庁連絡会議公表)では、「健全な水循環系」とは「流域を中心とした一連
の水の流れの過程において、人間社会の営みと環境の保全に果たす水の機能が、適切なバ
ランスの下にともに確保されている状態」と定義づけられている。その具体的な姿は地域
ごとに多様であり、例えば、地下水障害や地下水資源の枯渇を生じない範囲で地下水が最
大限利用されている状態や、歴史的・文化的に重要な湧水の復活・維持といったような目
標の設定や地域特性に依る。
近年の都市化の進展は、降水の浸透機能を低下させ、都市型水害や、地下水の涵養力低
下を招いている。また、地域の文化資産ともいえる古くからの湧水を枯渇させたり、河道
への地下水からの涵養を減少させ、平常時の河川流量の減少も招いている。地下水採取・
利用とも重なって、水循環系の健全性が損なわれている。
こうしたことから、今後の地下水資源の保全・利用のあり方を考える上で、健全な水循
環系の構築という視点の重要性がきわめて高くなっている。
?水循環系における地表水と地下水の特性比較
地表水と地下水はいずれも水循環系の構成要素であるが、今後の地下水資源の保全・利
用の検討にあたって、水循環系における地表水と地下水の特性の違いに留意する必要がある。
両者の特性を概略比較したものが表3-1-1であるが、地表水との比較における地下水の
重要な相違点として、滞留時間の長さと実態把握の困難さ(時間・経費増、遅れ等)があ
げられる。滞留時間の長さは、過剰揚水等による井戸枯れ・塩水化等の地下水障害や地下
水質の汚染が一度生じると、その回復・改善に長期間を要することの要因となる。また、
実態把握の困難性や遅れは、水循環系全体として、地表水に呼応して地下水を統合的に保
全・利用できない要因となっている。
表3-1-1 水循環系における地表水と地下水の特性比較
(2)今後の地下水利用の基本的な考え方
?地下水資源マネジメントの論点
地下水に関するマネジメント注)は、広域の地下水資源利用に焦点を当てた「地下水資源
マネジメント」と個別の土地開発や地下空間開発によって起こり得る地下水環境に与える
悪影響の防止・軽減を目的とする「地下水環境マネジメント」の2つに分けられる(図3-1-1
参照)。なお、地下水資源マネジメントは図3-1-1 青色に示す。
健全な水循環系の構成要素をなす地下水は、流域地下水文区のもつ水源地域から平野部
までさまざまな地域特性を踏まえ、量・質及び環境を考慮し、総合的な観点に立った検討
が必要である。
そこで、本報告書では、健全な水循環系の構築という視点から、主に量的な側面に軸足
を置いた「地下水資源マネジメント」について、今後の地下水利用の基本的な考え方を示
すこととする。今後、各地域で地下水資源マネジメントの取り組みをそれぞれの地域で具
体化・実践するにあたっては、各地域の諸条件や水需給に適合した検討が必要であること
は言うまでもない。以下の議論は日本で典型的な平野地形を念頭に置いている。
地下水マネジメント
地下水資源マネジメント地下水環境マネジメント
量的な側面における地下水資源マネジメント
*持続的に利用可能な範囲での利用
*地盤沈下等の地下水障害の未然防止等
地下水理・水文環境の保全
*湧水の保全・復活
*都市再開発
*地下空間開発
*大規模土地開発等
地下水質環境の保全
*汚染源・物質の特定
*汚染対策
*モニタリング等
質的な側面も含めた地下水資源マネジメント
*用途別の水質への要請を踏まえた利用等
図3-1-1 地下水資源マネジメントの主な検討対象
地下水も水資源の1つと見れば、こういった水資源マネジメントの考え方は思想上の符
号はあっても、地下水資源マネジメント(groundwater resource management)では、地表
水と同様のマネジメント手法には馴染まず、いくつか違った点がある。
1) 地下水は帯水層が自然の貯水池の役割を持つため、地表水のダムや人造湖のように
人工的な貯水施設を構築することはほとんどない(地下ダムや人工涵養施設は限ら
れた条件でしか効果を発揮しないため、事例は非常に少ない)。
2) 地下水の利用計画、管理、調整作業は、地下水盆の構造・地質の多様性や利用規則
欠如の面もあって、地表水に比べはるかに複雑である。
3) 地下水管理の要となる効果的な地下水モニタリングが地表水のそれと比べ容易でな
い。
以上を踏まえ、第2章で抽出された課題の解決に向けた今後の地下水利用の基本的な考
え方を以下に示す。
?地下水資源の最適なマネジメント実現に向けた方法論と指針の必要性
地下水は一般に水質が良好で水温の変化が少なく、大規模な貯水・取水・給水施設を要
しない等の優れた特性を有していることから、多用途に利用される重要な水資源となって
いる。今後も安定した水資源として、また災害時の緊急水源として保全・利用していくこ
とが期待されている。
地下水資源は水循環系における回復可能な水資源でもあり、地下水収支のバランス(あ
る区域内における一定期間内の地下水の流入・流出の均衡状態)が保たれる範囲内で持続
的に利用していくことが可能である。
一方、地下水資源の利用がかつて深刻な地盤沈下等の問題を招いたことから、行政によ
る採取規制とともに地表水への水源転換が積極的に進められてきた。今日、全国的にみて
地下水資源の利用による広域的な地盤沈下はおおむね沈静化しているが、渇水時等におけ
る短期的・局所的な地下水位の低下や地盤沈下等の地下水障害は、復旧に長い年月を要す。
こうしたことから、地下水資源と国土を保全することに加え、持続的に利用可能な範囲
内で利用し、地盤沈下や塩水化等の地下水障害を招かないように、地下水資源の保全・利
用をマネジメントしていくことが昨今の要請となっている。
一方、地下水資源のマネジメントを推進する前提として、地下水は同じ水循環系の構成
要素である地表水と比較して、適正に保全・利用すべき水資源としての認識が醸成されに
くく、データ整備や実態把握が十分に進んでいるとは言えない状況にある。
こうした状況にあって、地下水資源の保全と利用のマネジメントを推進していくために
は、その方法論を明らかにするとともに、地下水管理者となる地方自治体の計画担当者に
対して、どのようにして地下水に関する意識啓発や広報・指導、地下水のデータ整備や実
態把握を行い、必要な施策を計画・実践・運用していくべきかをわかりやすく示す指針(ガ
イドライン)が必要である。
?適正採取量に基づく地下水資源の保全・利用のマネジメント
地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染等を生じさせず、持続可能な形で地下水の保全と
利用を最適にマネジメントしていくためには、以下に述べる「適正採取量」に基づき、そ
の範囲内で地下水資源の保全と利用の最適なマネジメントを実現していくことが肝要であ
る。
ある地下水盆において、ある一定の期間に利用可能な地下水の量(おおむね涵養量より
小さく地下水障害を起こさない量)を「適正採取量」とすれば、適正採取量と(実際の)
採取量の関係は、図3-1-2上で説明できよう。採取量が適正採取量を上回る場合には地下
水障害や地下水資源の枯渇が懸念され、採取量が適正採取量を超えない範囲内で利用して
いくことが必要条件となる。一方で、地域によっては、地下水位が上がりすぎないように
マネジメントしていくことも重要な課題となる。
一般に、地下水は特段の規制をしなければ、安価な水資源として利用ニーズが拡大する
傾向を採る。このため、地下水の涵養能力や地下水障害の発生しやすさなどにより決まる
適正採取量より実際の採取量が少ない状態にあることが好ましい。また、地
下水の適正採取量そのものの維持・拡大には、地下水涵養策や地下水資源の保全策を実施
する必要がある。
図3-1-2 適正採取量と採取量の関係からみた地下水の保全と利用の説明
?地域規模等の類型に即した地下水資源のマネジメント
地域の地下水に関する状況は、自然条件(地形、地質、気候等)や社会経済条件(人口、
土地利用、産業、歴史・文化、法制度等)に応じて地域ごとの多様性・固有性がきわめて
強いことから、地域特性に即した対応が必要である。特に、適正採取量に基づく地下水資
源の保全・利用のマネジメントにあたっては、地下水盆や帯水層の規模が重要な尺度とな
る。その規模は1市町村内で完結するものから複数の都府県にまたがるものまで大小さま
ざまであり、こうした規模の違いによってマネジメントの目的や方法にも違いが生じる。
また、地下水資源のマネジメントでは、行政が中心的な役割を果たすことが期待される
ため、都道府県や市町村といった行政単位との関係も重要である。
こうしたことから、地下水盆や帯水層の規模と行政単位に着目していくつかの地域単位
の分類を設けることで、多種多様な地域特性を類型化し、地下水資源マネジメントの目的、
方法等を明らかにすることが可能となる。具体的には図3-1-3に示すように、局所(地区
レベル)・小規模(市町村レベル)・中規模(都府県レベル)・大規模(複数の都府県レ
ベル)という4つの類型が想定される。
資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)をもとに作成
図3-1-3 地域類型に応じた地下水資源マネジメント等の概観
3.2 地下水資源マネジメントの考え方と手順
ここでは、3.1節に述べた今後の地下水利用の基本的な考え方を踏まえ、地下水の保
全・利用の方法論として地下水資源マネジメントを提案し、その考え方と具体的な手順を
示す。
(1)地下水資源マネジメントの定義と特徴
「地下水資源マネジメント注1)」とは、3.1節に述べた今後の地下水利用の基本的な
考え方を具現化するための手段であり、「健全な地下水文循環にあって、地下水障害や枯
渇を発生させない範囲で、地下水を水資源として持続的に保全・利用しうる採取(揚水)・
運営・管理の方法」と定義する。
その特徴は、科学的な知見に基づき、実態把握、計画策定、揚水マネジメント、観測・
モニタリング、評価・見直しを定量的に行うことにあり、そのプロセスの中核を成すのは、
その適正配分数値シミュレーションモデルを活用した対象地下水盆の適正採取量の数量化
と地下水位に基づいた管理・モニタリングにある。また、もう1つの特徴として、PDC
Aサイクルに基づく継続的な見直しを行い、科学的・定量的なマネジメントの精度を向上
させていくことがあげられる。
?数値シミュレーションモデルを活用した適正採取量の数量化
地下水資源マネジメントにあたっては、持続的にどの程度の地下水が利用可能であるの
かの定量的把握に基づいた計画の作成が必要となる。そのためには対象地下水盆の数値シ
ミュレーションモデルを構築し、これを用いて地下水障害を発生させず、かつ健全な地下
水収支を保つ地下水位のもとで、総採取量とその地域配分を科学的な手法で数量化するこ
とが求められる。
このように、数値シミュレーションモデルは、地下水資源マネジメントの根幹を成すも
のであり、揚水事業者と地下水管理者 注2)(国や地方自治体)の両者が地下水の保全・利
用に関する計画を策定する際に有用である。
数値シミュレーションモデルの作成にあたっては、計画対象地域における地下水に関す
る各種データを経年的に収集し、地下水や水文の実態把握、地質調査・分析を行うことが
前提として必要となる。
?井内地下水位・水頭を用いた地下水管理・モニタリング
地下水の保全・利用に関する計画を実際に運用し、地下水の管理に役立てていくために
は、適切な管理・モニタリングの手法が必要となる。地下水位の変動と地下水採取量とが
密接に関係していることに注目すれば、テレメーターシステムを活用することにより、リ
アルタイムで地下水位をモニタリングして採取量を適正に制御できる。
こうした視点から、地下水資源マネジメントにおける地下水管理・モニタリングの指標
として井内地下水位を用いることが有効と考えられる。地下水位の常時観測を行い、その
変化に応じて地下水利用者に採取量の抑制を要請すること等により、過剰揚水を緩和し、
地盤沈下等の地下水障害を未然に防止ないし軽減することが可能となる。また、地下水位
を用いた地下水管理・モニタリングは、即時的かつ容易に対策を実施できるという点で優
れ、予想外の水需要に伴う緊急的対策にも対応可能である(例えば、渇水時の地下水採取
量急増による地下水位の短期異常低下の回避対策、既存の水源の水質事故に伴う振り替え
水源確保等)。さらに、地域によっては、地下水位が上がりすぎないよう適切に管理する
ことにも活用できる。
地下水位を用いた地下水管理・モニタリングは、渇水時等において地盤沈下防止のため
の地下水採取量を緊急抑制する施策にも適している。
?PDCAサイクルによる継続的な取り組みのプロセス
地下水資源マネジメントは、調査・計画(P)→実行・観測・モニタリング(D)→評価(C)
→見直し(A)というプロセス(PDCAサイクル)をある程度反復しながら、継続的に取り
組んでマネジメントの精度を高めていくことが必要となろう。
一般に、地下水に関するデータ整備や実態把握がどの地下水盆でも十分に進んでいると
は言えず、数値シミュレーションモデルを用いた地下水資源マネジメントの実践例も限ら
れていることから、地下水資源マネジメントの実施当初から精度の高い将来予測を行える
わけではない。また、地下水涵養量や帯水層水理パラメータの事前の把握は簡単ではなく、
推算せざるを得ないこともあり、シミュレーションモデルは、実際に運用しながら改良を
加えていくことで、精度を高めていく必要がある。
このため、地下水資源マネジメントの実施にあたっては、当初はある程度、実測値や経
験則に基づいて計画を策定し、実際に運用しながら評価・見直しを重ねていくことで、シ
ミュレーションモデルの精度を高めたり、計画の実効性を高めていったりするといった、
継続した取り組みが必要である。
(2)地域類型別にみた地下水資源マネジメントの方向性
地下水資源マネジメントのコンセプトは、地域特性に即した取り組みが重要であること
から、前述した地域規模による4つの地域類型(図3-1-3参照)に沿って以下に示す。
?局所規模レベルの地下水資源マネジメント
局所規模(1km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に小規模な地下水源の確保(井
戸のさく井)にあたって、個別の揚水井の配置や採取量の設定が対象となる。この場合、
対象となる地域の広がりは、地下水盆というより帯水層と呼ぶのが相応しい地区レベルの
規模である。
小規模な地下水源の確保においては、必要な採取量が継続的に確保できることと、地下
水資源開発による影響(周辺井戸の枯渇、地盤沈下の発生等)が周辺に及ばないようにす
ることの2点が重要である。
このため、既存の周辺井戸の影響や地盤沈下を防止しつつ、必要な採取量を確保するに
あたって、揚水井の適正深度や適正配置(適正な井戸間の距離)、個々の井戸の適正採取
量を算定し、井戸設置の申請に対してどのような許可制度や許可基準を設定するかという
ことが重要となる。これらの検討方法としては、水収支と水理学的な検討が求められ、揚
水井戸理論を用いた定量的検討が想定される。観測・モニタリングにあたっては、採取量、
地下水位、地盤変動量等が指標となる。
?小規模レベルの地下水資源マネジメント
小規模(数km2〜数十km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に市町村(単一の市町
村もしくは複数の市町村による組合等)の行政区域内で完結している地下水盆が対象とな
るが、近隣市町村にまたがる平野や盆地の一部地域が対象となることもある。
局所レベルのような個別井戸ごとではなく、一定の広がりをもつ地域を対象として、複
数の揚水井を集合体として捉え、対象地域内での地下水収支や地下水採取量の地域配分等
を取り扱うことになり、対象地域外の近隣市町村に地下水資源開発の影響を及ぼさないよ
うにしつつ、必要な採取量を確保することが地下水資源マネジメントの要点となる。
このため、地下水収支バランスの保たれる範囲内の適正採取量とともに、対象地域内で
の適正な地域配分や用途別配分、採取許可方法等を明らかにする必要がある。検討方法と
しては、数値シミュレーションモデルを用いて地下水盆や帯水層をモデル化した上で、水
需給の現状や将来見通しに基づくシミュレーションを用いて、利用可能地下水資源量や適
正採取量、揚水井の分布密度、安全地下水頭・採取量等を設定する。
また、観測・モニタリングの方法としては、テレメーターによって地下水位や地盤変動
量をリアルタイムで把握するとともに、渇水時等の短期的な地下水位低下に対する対応と
して、管理水位を設定し、警報・注意報の発令による地下水採取者への採取量抑制の要請
を行うこと等が考えられる。
?中規模レベルの地下水資源マネジメント
中規模(数十〜数百km2 程度)の地下水資源マネジメントは、主に都府県レベルで完結
している中規模な地下水盆(熊本地域等)が対象となる。
地下水資源マネジメントにあたっては、対象となる都府県の地域内において、地下水収
支バランスの保たれる範囲内で、かつ地下水資源開発に伴って地下水障害等の悪影響を防
止しつつ、必要な採取量を確保することが重要となる。
このため、計画においては、地下水資源量とその地域配分を適正化することや、広域的
な地下水の観測・モニタリング(地下水位、地盤変動量等)を通じた地盤沈下の防止対策
が重要な課題となる。検討方法については、?で述べた小規模地下水資源マネジメントの
定量的な延長検討とほぼ同様に考えることができる。
?大規模レベルの地下水資源マネジメント
大規模の地下水資源マネジメントにおいては、複数の都府県にまたがる広がりを持つ大
規模な地下水盆の分布する地域(関東平野、濃尾平野、大阪平野、筑後・佐賀平野等)が
対象となる。ここでの重点は中規模の地下水資源マネジメントとおおむね一致するが、都
府県をまたがる対応が必要となるため、国の関係府省と関係地方自治体が連携して対策を
行っている「地盤沈下防止等対策要綱」の対象地域のように、体制・制度面で広域的な取
り組みが必要となる。
(3)地下水資源マネジメントの企画・検討手順
地下水資源マネジメントの目的や手順は、その対象とする地下水盆の地形・地質特性、
特に地域の規模によって異なってくるが、ここでは地域特性にかかわらず共通する基本的
な企画・検討手順について、適宜代表的な事例を紹介しながら、図3-2-1に沿って示す。
資料)佐藤邦明編著「地下水環境・資源マネージメント」埼玉大学出版会(2005 年)
図3-2-1 地下水資源マネジメントの企画・検討手順
?予備調査
a)対象・目的の設定
はじめに、地下水資源マネジメントを行う対象・目的の設定を行う。
対象となる地域は、局所的な1〜2k?の狭い範囲において個別の井戸の設置可否等を
対象とするような場合を除き、行政上の視点から設定されることが多いが、その規模は単
独の市町村にとどまるものから、同一都道府県内で複数の市町村にまたがるもの、複数の
都府県にまたがる盆地や平野規模までさまざまである。こうした対象地域は、地下水の保
全・利用に関する課題や問題意識を共有する圏域として設定され、地理的条件、特に帯水
層や地下水盆の分布状況・規模に応じた地域となる。
目的の設定は、地下水資源の保全、地盤沈下等の地下水障害の防止、地下水環境の保全
など、対象地下水盆における地下水の保全・利用上の課題や問題意識等に応じて設定され
る。また、地下水の保全・利用に関する総合的な計画の場合と、特定の課題に特化した計
画の場合で、目的の設定や力点が異なってくる。以下にその事例を示す。
【総合的な利用・保全の目的を掲げる事例】(熊本地域地下水総合保全管理計画)
生活用水をすべて地下水で賄っている熊本地域では、地下水資源を次世代に引き継ぐ
ことを目的に、地下水の保全を優先している。
本計画は地下水の保全・利用に関する総合的な計画であることから、計画で定めてい
る保全目標は、地下水資源の量・質両面での維持に加え、地域のシンボルともなってい
る豊かな湧水の維持・復元、地下水障害の防止等にも置かれている。
【特定課題の目的を掲げる事例】(埼玉県地盤沈下緊急時対策要綱)
かつて深刻な地盤沈下を経験し、現在も地盤沈下が懸念される埼玉県では、地下水の
過剰なくみ上げによる地盤沈下を防止することを、地下水対策の優先目的としている。
地下水の保全・利用全般については「埼玉県生活環境保全条例」に定められているこ
とから、本要綱では、緊急的な地盤沈下対策に特化して目的が設定されている。
b)調査内容・検討手順の検討
設定された対象・目的に基づき、実態把握や計画の策定、及び運用・評価にあたって必
要な調査内容や検討手順を構築する。その際には、地下水資源マネジメントの対象・目的
のほか、利用可能な予算、計画策定までの期間、取組体制等も考慮する。
?地下水に関する実態把握
対象・目的に応じた地下水・水文調査(地形・地質、水文、土地利用、水利用実態、地
下水障害、地下水流、地下水質、法制度等)を行い、対象地域の地下水に関する問題点の
要因分析を行うとともに、対象・目的に応じて適当な数値シミュレーションモデルを用い
ながら、地下水盆や帯水層をモデル化し、適正採取量の数量化を行う。
地下水資源マネジメントの実施にあたって、地下水に関する実態把握、特に採取量の把
握や地下水収支の数量化は、地下水の保全・利用に関する計画の策定・運用の前提となる
きわめて重要な要素である。同時に、実施にあたっては、適正採取量の数量化のために必
要な時間・労力と知識・経験の蓄積、また、地下水採取量把握にあたっての利用者の理解
と協力が必要である。
a)地下水・水文調査
地下水・水文調査の調査項目として、以下のようなものがあげられるが、実施する項目
や精度は、地下水資源マネジメントの対象・目的等に応じて、個別に設定する。
* 地形、地質、水文、土地利用、水利用実態
* 地下水障害、地下水流、地下水質、関係法令
【地下水・水文調査の調査項目の例】(熊本地域地下水総合調査)
「熊本地域地下水総合調査」では、以下の項目について調査を実施している。
・ 地形・地質:地質平面図・断面図、地下水位断面図等を作成
・ 土地利用:涵養域・非涵養域別土地利用、生産調整率(米作減反率)の推移を把握
・ 水利用実態:条例に基づき採取者から報告されたデータを活用
・ 地下水流:既存井戸の一斉測水調査を実施し、帯水層別地下水位等高線図を作成
・ 地下水質:水質汚染防止法に基づく地下水の水質汚濁状況の常時監視を170 地点あ
まりで実施するとともに、河川水5地点、湧水10 地点、地下水86 地点でイオン分
析を実施等
【地下水利用実態電子データの例】(茨城県)
以下に示す茨城県の検討例では、現行の揚水実態、井戸分布、地形・土地利用の情報
を一目で知ることができ、それぞれの井戸の地質情報や採取量が判る。
b)地下水数値シミュレーション解析による適正採取量の数量化
水収支は地表の水収支と地下の水収支が連成・構成されるが、地下水収支は、地下水の
涵養量と採取量によって地表水収支と結びついている。帯水層・地下水盆が対象地域を越
えて分布している場合には、隣接する地域との間において、地下水同士の流入・流出が生
じうるが、帯水層・地下水盆が対象地域内で閉じている場合には、涵養量と採取量が把握
できれば、地下水収支を数量化できることになる。
地下水収支モデルが検定・修正できれば、水需給の現状や将来見通しを外生的に入力し、
数値シミュレーションモデルを活用して地下水の挙動の将来予測を行うこと 注)、さらにそ
の現地適用への論拠とすることが可能となる。
* 地下水盆のモデル化
* 地下水涵養の数量化
* 水理定数
* 地下水流動解析・内挿検定・パラメータ同定
* 数値シミュレーションモデルによる適正採取量や水収支の数量化
* 将来予測
* 地下水採取量の適正配分・揚水井分布
* 安全水頭・採取量の設定
【地下水収支の数量化の例】(座間市地下水総合調査)
「座間市地下水総合調査」においては、過去20 年間におけるデータに基づき、地下
水収支シミュレーションモデルを構築し、揚水条件(地下水揚水量)、涵養条件(平水
年と渇水年の涵養量)、河川改修条件の組み合わせによって、7ケースについて地下水
位変動や水収支予測を行い、台地部、低地部、市全体のそれぞれについて、水収支が±
0となる揚水量を適正揚水量として設定している。
また、市内の代表観測井において地下水の揚水に支障のない地下水位として、第1段
階水位(注意)と第2段階水位(警戒)の2段階の管理水位を設定している。
?地下水の保全・利用に関する計画の策定
対象地域における地下水資源マネジメントの目的や枠組みに基づき、必要に応じて数値
シミュレーションモデルによる将来予測の結果を活用しながら、適正な地下水利用を実現
するための考え方、適正採取量、管理水位、利用規則や、地下水の観測・モニタリングの
方法、行政担当者向けの管理マニュアル等を検討・策定する。
a)地下水適正利用のあり方
数量化された地下水収支やその将来予測を参考にしながら、地下水の保全・利用に関す
る計画の根幹を成す地下水適正利用のあり方を検討する。
* 適正利用のコンセプト
地下水障害を招くことなく、地下水収支のバランスが保たれる範囲内で地下水資源
を保全しながら持続的に利用できること前提として、地下水資源の適正な利用にあ
たってのコンセプト、基本目標を設定する。地域内において、ある一定の期間に利
用可能な地下水の量(おおむね涵養量より小さく地下水障害を起こさない量)を「適
正採取量」とするとき、以下のようなケースが想定される。
<採取量が適正採取量を上回っていない場合>
採取量が適正採取量の範囲内にある状態を維持していくため、涵養量の維持に向け
た取り組みを行うとともに、規制・誘導等により採取量を抑制する必要がある。
<採取量が適正採取量を上回っている場合>
採取量の抑制と適正採取量の拡大が考えられるが、地下水涵養策による利用可能量
の拡大には限界があることから、主に規制・誘導等により採取量を適正採取量の範
囲内に抑制する方策が求められる。
* 用途別配分・利用方式
数値シミュレーションモデルによる適正採取量の将来予測結果や適正利用のコン
セプト、水資源の需給事情等に基づき、総採取量の中での利水用途別配分(農業用
水、工業用水、生活用水等)や、地下水の利用方式(各用途における地下水と地表
水の組み合わせ利用の考え方)等について検討する。
* 利用規則・井戸の設置許可等
必要に応じて、地下水の採取・利用にあたっての規則や揚水井の設置基準・設置条
件等のルール(法律・条例等)を検討する必要がある。例えば、茨城県地下水適正
利用条例では、新規の井戸設置は許可が必要である。
b)適正利用を実現するための方策
地下水適正利用のあり方の検討結果に基づき、これを実現させるための方策(地下水管
理の方式、具体的方法等)について検討する。
* 地下水管理の方式
気象の平穏な平常時、気象の不順な渇水期、自然災害時等の状況に応じた地下水管
理の方式を検討する。具体的には、総適正採取量の範囲で地下水位・水頭や地盤変
動、採取量等の各種データを総合的に分析して管理する方式や、経験的に得られた
採取量配分と地下水位の経時的な相関関係の分析に基づき、地下水位のモニタリン
グを通じて過剰揚水を抑制する方式(警報・注意報の発令による地下水採取者への
採取量抑制の要請等)が選定される。
* 観測井の構造・配置・数
地下水収支の数量化の結果等を踏まえ、地下水管理を行うために必要な地下水位・
水頭や地盤変動量等を観測する観測井の構造・配置・数を決定する。
近年ではテレメーターの実用化が進み、通信回線を活用して観測データをリアルタ
イムで観測・収集することが可能となっている。
* 管理マニュアル
担当者の異動等があっても継続的に地下水資源マネジメントが行えるよう、地下水
の保全・利用に関する計画の管理者や地下水採取者等が地下水管理をどのように行
っていくのかをまとめた管理マニュアルを作成する。
* 地下水管理者・採取者への情報伝達方法
地下水管理者となる地方自治体、地下水採取者となる企業、水道事業者、個人等に
対して、地下水資源マネジメントにあたって必要な情報を迅速に伝達する方法は、
インターネットをはじめとする電子媒体によることができる。
* 広報・指導
地下水資源は採取者や利用者が多岐・多数にわたることから、地下水資源マネジメ
ントにあたって重要な情報は、採取者のみならず、広く利用者一般に対して公表・
提供し、地下水の保全・利用に関する意識啓発を図る。
【適正利用を実現するための方策の事例】(埼玉県地盤沈下緊急時対策要綱)
埼玉県では、「埼玉県地盤沈下緊急対策要綱」に基づき、地下水位の著しい低下によ
り、地盤沈下が生じる恐れがあると認められる時には、一定量以上の地下水採取者に対
して、各地域の地下水位の程度に応じて、地下水採取の抑制等を要請する「地盤沈下注
意報」「地盤沈下警報」が発令される。
?地下水の保全・利用に関する計画の運用・評価
a)地下水の観測・モニタリング
計画に定められた適正利用を実現するための方策に基づき、地下水位、採取量、地盤変
動量についての報告を採取者に求めたり、観測井を用いて観測したりした上で、そのデー
タを収集・処理するとともに、必要に応じて地下水障害等を未然に防止するための対策(新
規揚水井の許可制等)を実施する。地下水資源マネジメントは、地下水位・水質、採取量、
降水、地下水障害(地盤沈下量等)といった観測データによってなされることから、観測
データの迅速かつ正確な収集・伝達・処理が重要である。
* 採取量・水位報告
地下水資源マネジメントには採取量や地下水位の把握が不可欠であることから、一
定量以上を採取する採取者に対して、記入書式を用意し、採取量や地下水位の報告
を義務づけること等により、これらを把握する。
b)計画の評価・見直し
地下水の観測・モニタリングを一定期間継続し、データの蓄積が図られた時点で、策定
した計画の妥当性、観測・モニタリングの有効性等を評価し、その結果に基づいて必要な
修正・変更を行う。特に、地下水収支の数量化と将来予測に用いる数値シミュレーション
モデルの精度を高めていくことが重要である。
* 評価
計画の評価は、地下水資源マネジメントのPDCAサイクルの「C」に相当し、計
画内容の有効性や成果を計る「政策評価」と、計画の執行段階での効率性や進捗度
を計る「執行評価」を適切に組み合わせて実施することが望ましい。
評価に用いる指標と、最低限達成すべき水準、おおむね成功と評価できる水準、可
能ならば達成したい水準というような目標を、計画策定段階で予め設定をしておく
ことで、評価の精度が高まる。
* 見直し
計画の見直しは、地下水資源マネジメントのPDCAサイクルの「A」に相当し、
上記の評価結果に基づいて行う。必要に応じて、地下水適正利用のあり方を見直す
とともに、適正利用を実現するための方策については、評価結果に応じ、継続・改
善・中止のいずれかを検討する。
【評価・見直しの例】(熊本市地下水量保全プラン)
「熊本市地下水量保全プラン」の場合、毎年度プランの評価・見直しを行い、その進
捗状況をホームページで公表することとしている。評価にあたっては、評価結果等の説
明や市民の意見聴取のため、「熊本市節水推進パートナーシップ会議」を設置している。
(4)地下水資源マネジメントの検討・策定方法と策定・運用主体
地下水資源マネジメントを円滑に実施・運用するためには、地下水利用事業者の参加及
び地下水管理者との共同歩調が欠かせない。したがって、行政だけでなく、対象地域の主
要な地下水採取者が参画し、地域全体が連携して取り組んでいくことができる体制づくり
が求められる。このため、計画の策定・運用主体は、地下水資源マネジメントを主体的か
つ効率的・効果的に実施できる体制を整備する必要がある。
現行の行政管理体制では、行政区画単位でのマネジメントが実用的と考えられることか
ら、行政や協議会の長が地下水管理者として、計画の策定・運用主体となろう。具体的に
は、対象地域が単独の市町村にとどまる場合、同一都道府県内で複数の市町村にまたがる
場合、複数の都府県にまたがる場合といったように、各地域の事情に即して個別に判断さ
れるべきである。なお、複数の都府県にまたがる「地盤沈下防止等対策要綱」の対象地域
については、国の関係府省連絡会議が設置されている。
第4章 今後の地下水利用のあり方に関する提言
本報告では、
?「健全な水循環系構築」のための計画づくりの一環において、地下水について計画作成担当者に向けた提言
?地下水障害を発生させないことを前提とした適正な管理により利用する仕組みの構築に向けた具体的な提言
?国際比較の中でのわが国の地下水の特性及び利用のあり方
の3点に重点を置いて検討してきた。
地下水は重要な水資源であり、水循環系の構成要素であることから、本来、地表水と一
体化させ、環境面を含めて捉え、計画的に保全・利用されるべきものと考えられる。これ
までは、水資源の需給バランスの相互補完や地下水障害等の直面する課題の解決の面から
のみ地下水が捉えられてきたが、今後は地下水と地表水の役割分担や最適な両者の利用配
分の実現をめざした施策展開が必要な段階になってきている。こういった今日的なニーズ
に応え、本報告は、地下水資源マネジメントの手法論を展開した。
ここでは、第1章から第3章で述べた検討の結果を踏まえ、今後の地下水利用のあり方
に関する基本的な考え方やその実現にあたって求められる取り組みを提言として以下にと
りまとめる。
国の関係府省、地方自治体、企業、利水受益者等、地下水の保全・利用にかかわる各関
係主体には、本提言を踏まえ、それぞれの立場から、健全な水循環系の構築と持続可能な
地下水の保全・利用に向けた積極的な取り組みが期待される。
4.1 地下水資源マネジメントの推進
(1)健全な水循環系の構築に向けた地下水資源マネジメントの必要性
現在、わが国では、都市域における雨水浸透機能の低下、地表水と地下水の自然相互依
存の阻害等といった水循環系の健全性が損なわれていることに起因して、平常時の河川流
量の減少、湧水の枯渇、各種排水による水質汚濁、都市型水害等の問題が顕著となってき
ている。地表水とともに水循環系の重要な構成要素である地下水においても、健全な水循
環系の構築が重要な課題となっている。さらに、多量の水資源を水文収支域外より集積し、
消費・排出する都市の人工水循環系の健全化・保全を推進していく必要がある。
そのため、適正採取量の数量化や将来予測に基づき、地下水に係わる地域の諸条件に応
じて、地盤沈下などの地下水障害を未然に防止し、地下水収支バランスが保たれる範囲内
で、持続的に地下水を水資源として利用していくための適正利用のあり方とその実現方策
を検討し、地下水保全・利用に関する計画を策定・運用する必要がある。計画の策定・実
践・運用にあたっては、実態把握、計画策定、観測・モニタリング、評価・見直しという
継続的な試行プロセスを通じて、地域の諸条件に応じた持続的な地下水資源の保全・利用
のあり方を実現していくという「地下水資源マネジメント」の考え方が重要である。
例えば、関東平野を例にとると、図4-1-1に示すように、昭和20 年代より広域地下水利
用がなされ、地下水位(水頭)は低下したが、法律の規制(昭和31 年以降)によって回復・
上昇し、今は過去の自然地下水位に近づきつつある。将来の地下水資源のマネジメントに
は、健全な地下水環境・国土保全を目標に、安全水位を管理値に保持するよう人工制御す
ることが目指すところとなる。
図4-1-1 地下水資源マネジメントの説明図
(2)地下水資源マネジメントの推進に向けた支援環境整備
地下水資源マネジメントの実践・普及に向けた支援環境整備として、以下のような取り
組みを進めるべきである。
?地下水の実態把握に向けた採取量をはじめとするデータ整備の推進
地下水資源マネジメントの実践にあたっては、地下水の実態把握や問題点の要因分析等
を行う必要がある。地下水に関する調査としては、
1)地下水位及び地盤変動に関する調査、
2)水質に関する調査、
3)採取量に関する調査、
4)地形・地質に関する調査等があるが、以上のような観測データは、その地域の地下水解析に欠くことのできないものであるため、精度の高い長期的な観測を継続する必要がある。しかし、地表水と異なり、地下水はその
実態把握に時間・労力・経費がかかり、地下水の実態把握を行うための各種観測データが
十分に整備されていない。特に、地下水採取量は、地下水収支の数量化や将来予測、計画
の運用、観測・モニタリング等のさまざまな面で有用であるにもかかわらず、データの収
集整備(特に電子データ化)が進んでいない地域も多い。
採取量をはじめとする各種観測データの収集には、利用者の協力が不可欠であることか
ら、関係者間での協議、条例等の制度面での対応、データ収集・処理体制の整備などにす
みやかに着手することが求められる。
国においては、各地域において収集されたデータを全国共通に活用できるよう、データ
の収集項目や定義、収集方法等についての統一的な基準を作成し、各地方自治体に対して
データ収集を積極的に取り組むよう、普及啓発活動を実施することが必要である。また、
収集されたデータを蓄積・活用するためのデータベースについては、一元的な電子データ
ベース化を図り、データの効果的・効率的・実践的な活用を推進していくことが期待され
る。地質情報を全国で共有するための全国電子地盤図システム構築の構想も動き始めてお
り、こうしたシステムの活用も検討する必要がある。
?地下水実態・観測の数値情報共有・活用の推進
地下水資源マネジメントの推進を図るため、地方自治体の担当者をはじめ、地下水資源
マネジメントに関係する人が、全国各地域で策定された地下水保全・利用計画やその運用
状況、地下水に関する各種データ(降水量、地質、地下水採取量等)、地方自治体の地下
水に関する条例・要綱等、各地域の取組事例を情報交換し、活用しやすくなるよう情報環
境整備が必要である。そうすることによって地域性に富み、かつ水需給事情の異なる地下
水資源採取者や管理者が、より適正な地下水資源開発計画や運用方策を実践することが出
来よう。地下水資源のように多数の採取者が分散して各自揚水している場合、そのマネジ
メントの実行主体は採取者の側にあることを銘記したい。したがって、採取者の理解と協
力がマネジメントの運用に不可欠である。その実施・推進にあたって、地下水資源の所管
(地方自治体や各種機関)を通じて、地下水資源マネジメントの趣旨や方法について地下
水採取者(例えば利用協議会等)に対する講習会やポスター配布等により予め周知する必
要がある。
?実証モデルケースによる地下水資源マネジメントの推進〜取り組みの牽引役として〜
すでにいくつかの地域で、地下水資源マネジメントの先駆となる取り組み(例えば、埼
玉県、熊本県、栃木県野木町等)が行われているものの、現状ではその数は限られている。
そこで、地下水資源マネジメントの考え方に基づき、地下水保全・利用計画を策定・運
用しようとしている地域(例えば、現行の地盤沈下防止等対策要綱の対象地域等)に実証
モデルケースを選定し、地下水管理者と揚水事業者の連携のもとで採取量の把握、地下水
収支の数量化と将来予測に支援された地下水資源マネジメントを試行・実践し、その応用
性の実証や問題の解決後、有効性を普及していく必要がある。
先進地下水資源マネジメントの事例や方法を公表・情報提供していくことで、より多く
の地域で地下水資源マネジメントの経験・実績・有効性が認識されるようになり、その前
提となる採取量の把握に向けた採取者の理解と協力も得やすくなっていくことが期待され
る。
国においては、地下水資源マネジメントを推進するための新たなモデル事業を先導し、
実証モデルケースとなる地域の取り組みに対して、財政面での支援や専門的見地からの助
言を行うとともに、その成果を広く情報提供することはもとより、解析作業の中核を成す
汎用性の高い数値シミュレーションモデルの普及(例えば、米国地質調査所(USGS)の
MODFLOW.2005 等が国際的に普及)を行うことが期待される。
4.2 地下水資源マネジメントの運用方策
地下水資源マネジメントには、管理する際不可欠なマネジメント条件(あるいは制約条
件)が課されることになるが、その条件や制約指標(例えば、観測地下水位、採取量、地
下水障害)は、次の5つが要点となる。
?ある対象地下水盆(あるいは地下水文区)に涵養される地下水総量より広域総採取
量が小さいこと(地下水収支条件)
?観測地下水位が管理目標限界地下水位より高いこと(あるいは、管理目標地下水位
の上限と下限の範囲内にあること)(安全地下水位保全条件)
?広域総採取量をその構成地域採取配分量の和とすると、それら配分量がそれぞれの
管理目標地域採取量を超えないこと(安全地下水採取量条件)
?地下水障害(地盤沈下、地下水塩水化等)の誘発防止(地下水障害防止条件)
?異常な井戸水位低下、井戸干渉を招かず、かつ揚水井間距離が適正であること
(揚水井適正配置条件)
以上の制約条件を満足させるよう地下水資源をマネジメントすることになるが、?と?
は健全な地下水環境を保証すべき必須条件であり、観測地下水位や採取量の適正化によっ
て満たされ、過去の経験や実測データ及び数値シミュレーションによって解析しうる。し
かし、即時的な地下水資源マネジメントの指標としては、観測地下水位が実用的である。
今日、?を満たすようマネジメントを行うことが運用しやすい。その具体的な仕様は以下
に示す。
地下水揚水の適正化とは、広域地下水盆における地表水と降水による涵養の範囲内で、地下水
障害が発生しない最適揚水量を地域ごとに決め、急激な揚水は避けながら地下水資源を効果的に
利用することにある。地下水揚水抑制の具体的な実践には、過去の地下水・地盤沈下の観測デー
タを解析し、従来の揚水実績を十分検討した上で、段階的に分けた管理基準(限界値)水位を予
め設定しておき、注意報・警報といった情報を地下水利用者の合意の下で実践するのが合理的と
考える。設定された(目標)基準(限界)水位を下回るような地下水揚水は回避されなければな
らない。
地下水位と地盤沈下の観測方法は、二重管構造の観測井を使用するのが主流で、地下水位はフ
ロート式で地盤沈下は管頭変位量を機械的に測定している。近年オンライン化されたテレメータ
観測システムを利用し、地盤沈下を防止しつつマネジメントする方法が開発されている。図4-2-1
はそのシステム概念を示す。最近、このシステムが地盤沈下対策のみならず、経済性向上や省力
化に向けた地下水資源の保全にも普及しつつある。
図4-2-1 テレメータによる地下水マネジメントシステム概念図
また、地下水位を用いた地下水管理をより推進するため、即時的かつ容易に対策を実施
できるという点で有利なテレメーターシステム等の導入が必要であり、財政面での支援を
行うとともに、その成果を広く全国に情報提供していくことが期待される。
4.3 地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項
地下水資源マネジメントの推進や地下水資源の利用にあたって重要と考えられる事項
を以下に提言する。
(1)水資源の視点からの地下水の水質確保・保全
地下水の水質面については、これまでの汚染対策としての視点に加え、水資源政策の視
点から捉え、多様な地下水の利用ニーズに対応した用途別の水質確保・保全のあり方につ
いて検討する必要がある。その際には、地下水資源マネジメントの実施にあたって、量的
な側面だけでなく、水質面もその対象とすることで地域の諸条件に応じた地下水利用のあ
り方を実現していくことが適切である。
また、その前提として、浅層のみならず深層も含めた水質汚染に関するデータや情報の
整備が求められることから、まずは量的な側面に限って地下水資源マネジメントを実施す
る際にも、水質面の観測・モニタリングを同時に行い、データ整備を進めていくことが欠
かせない。
(2)地下水の震災対策
大規模地震災害時において、水の確保が重要な課題であることがこれまでの震災の経験
から指摘されており、発生直後から時間の経過に応じた各種水需要に適切に対応するため、
利用可能な水源とその特徴(水量、水質、設備・運搬の必要性等)を踏まえた水利用シス
テムを検討・構築しておく必要がある。
地下水は、身近で入手の容易な水資源であり、一般に水質もよいことから、大規模地震
災害時の利活用性が高く、地域の特性に応じた地下水の利用方策(用途・利用方法・制度
等)を検討・構築する必要がある。その際には、シミュレーション結果に基づき、各避難
所に緊急時に使える井戸を積極的に設置するという地域の取り組み等も踏まえつつ、耐震
性の高い井戸の分布状況の把握、災害時に民間井戸を利用可能とする権限の担保方法、少
なくとも災害発生直後の緊急・応急水供給に向けた別水源への振り替えのあり方等に留意
し、安全・安心な災害時地下水利用システムを構築することが求められる。
(3)地下水資源マネジメントの社会的合意形成への取り組み
?社会的関心向上の必要性
これまでわが国においては、地下水の過剰採取が深刻な地盤沈下を招いた経験から、一
般に地下水は地盤沈下と結びついたイメージが強く定着し、地下水の採取が、採取者の所
有する土地内にとどまらず、広域的な地盤沈下の原因となることについては、共通の理解
が得られていると思われる。
今後、地下水を水資源として管理しながら利用していくにあたって、社会的な合意が必
要な内容(地下水は水資源として、また環境面においてどのような役割を担うべきか、地
下水は平常時・緊急時にそれぞれどの程度利用してよいか、等)を定量化し、その意義の
普及・啓発を図っていく必要がある。
?法制度に関する検討の必要性
現在、わが国では地下水に関する重要な紛争や係争が生じている状況にない。これは、
工業用水法などの個別法や条例の適切な運用に負うところも大きいと考えられる。
しかし、現在も長期的、短期的な地下水をめぐる課題が存在しており、また条例等を施
行する自治体においては、いわゆる反対解釈の問題や強制力の不足による公平性の確保の
困難さ等、施策の実効性不足の声も聞かれている。さらに、地下水に関する社会的合意を
具現化するため、わが国における地下水に関する法制度について、法制化を行うべきかど
うかも含め、検討を行うことも必要と考えられる。
その際、全国一律的な法律と、各地域の特性に応じた条例の関係については、地域によ
る多様性に富むという地下水の特性やこれまでの各地域における取り組みを踏まえつつ、
法の機能と特長をいかに適切に組み合わせていくかが重要な論点となる。
また、国外に目を転じると、EU(欧州連合)では、基本法とも言える水枠組み指令と
これに対応した各国の法律が制定されており、こうした海外の事例も参考にしながら、国
際的な視点に立って、わが国の自然特性や社会の実情に即した法制度のあり方を検討する
必要がある。
「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」報告要旨【平成19年3月】
地下水の特性と保全・利用に係る課題
・水循環系における滞留時間が長い
・涵養に時間がかかるが潜在賦存量は多い
・地下水資源利用の広域定着と安定化
・渇水時の揚水増による地下水位低下
・採取量等のデータ整備と実態把握の遅れ
・地下水の保全・利用に関する全般的取り組みの遅れ
・水収支バランスが保たれる範囲内での利用
・緊急時の応急水源としての利用方策
・広域地盤沈下は沈静化傾向のまま継続・残存
・短期的、集中的な地盤沈下は今後も懸念
・科学的、定量的処理と電子情報化が必要
・社会への啓発と関係者の意識向上
特性課題
・「持続的かつ健全に利用できる循環している地下水」が利用の前提
・一般に、水資源としての地下水は、利用の簡便性、経済性、良質な水質、恒温性を有する
・わが国の水使用量における地下水依存率は約12%
・各種法令による地下水採取規制等により、広域的な地盤沈下は概ね沈静化
・しかし、渇水時には短期的・局所的な地下水位低下、地盤沈下が発生
・一部地域では地下水位上昇により地下構造物への影響が発生
・地下水汚染の多様化
・新たな地下水利用形態(ミネラルウォーター、地下水ビジネス)の拡大
地下水をめぐる現状と最近の動向
?地下水資源マネジメントの推進
・地下水障害を未然に防止し、地下水収支バランスが保たれる範囲内で、持続的な地下水資源の適正利用のあり方とその実現方策を検討し、地下水保全・利用に関する計画を策定・運用する必要がある。
・計画に基づく施策の実施にあたっては、数値シミュレーションモデルの活用により地下水収支を定量化し、実態把握、計画策定、観測・モニタリング、評価・見直しのというプロセスを反復しながら継続的に取り組み、地域の諸条件に即した最適なマネジメントを実現することが重要である。
?地下水資源マネジメントの運用方策
・マネジメントにあたっては、目標とすべき地下水位を定め、地下水位を常時観測していくことにより管理していくことが実用的である。
・マネジメントの推進に必要となるデータを収集するため、観測井戸、観測機器、テレメーターシステム
等の整備が必要である。
?地下水資源マネジメントの実施に際しての重要留意事項
・水資源の視点からの地下水の水質確保・保全のあり方を検討する必要がある。
・大規模地震災害時における地下水の利用方策を検討する必要がある。
・地下水資源マネジメントの社会的合意形成への取り組みを推進する必要
http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/f_
groundwater/25/houkokusyo.pdf
2009年11月15日
ATCセミナー〜平成20年関西エコオフィス大賞受賞者発表会〜
おおさかATCグリーンエコプラザ
循環型社会形成推進セミナー
〜平成20年関西エコオフィス大賞受賞者発表会〜
関西広域機構(KU)では、身近なところからの省エネルギー等の取組みを通じて、地球温暖化対策を実施する「関西エコオフィス運動」を進めており、この運動への参加オフィスや各種の環境マネジメントシステムの認証・登録を受けているオフィ
スの中から、顕著な効果を挙げているオフィスを、「関西エコオフィス大賞」として毎年表彰しています。 平成20年度は、これらの中から特に先導的で優れた取り組みを行っているオフィスを、「平成20年度関西エコオフィス大賞・奨励賞」として、6事業所を選定しました。
今回の発表会では、まず関西広域機構(KU)から「関西エコオフィス大賞」の主旨、目的、経緯等をご説明頂き、その後に大賞受賞の2事業所と奨励賞受賞の2事業所にそれぞれの優れた先導的な取り組み内容を紹介していただきます。今回のセミナーで、これらの環境行動内容を広く参加者に理解していただくことにより、関西における先導的な優れた環境行動の普及・推進を図っていく。
開催日時
平成21年12月11日(金)13:30〜17:00
内容
主旨説明「関西エコオフィス大賞について」
講 師:関西広域機構環境・防災部長早金孝氏
発表1 「京都ビール工場の環境活動『エコ・ブルワリーの実現』」(大賞*1)
講 師:サントリー酒類株式会社 京都ビール工場 技師長 高田純一氏
発表2 「山金工業株式会社森田工場のCO2・VOC排出量削減活動」(大賞*2)
講 師:山金工業株式会社 森田工場 製造部 ISO委員会事務局 担当課長 山腰喜勇氏
発表3 「エプソンイメージングデバイス株式会社の環境施策について」(奨励賞*1)
講師:エプソンイメージングデバイス株式会社 経営管理部部長 上條光一 氏
発表4 「くらこんの継続した環境活動」(奨励賞*2)
講師:株式会社くらこん枚方工場 常務取締役製造本部長 松井隆史 氏
*1:大企業部門*2:中小企業・団体部門
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)・ビジネス交流会
協力
関西広域機構(KU)
受講料
無料
会場
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」
定員
100名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までにFAX またはE-mail でお送りします。)
お申し込み
おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで
〈事務局〉〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ関西エコオフィス大賞発表会(12月11日)係TEL:06-6615-5688
お申し込みはE−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください
E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890
http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar091211.pdf
参考セミナーレポート
環境経営の最新動向 〜リスクをチャンスに変える知と情〜
■講師
日本環境経営大賞表彰委員会 審査委員 東北大学大学院
生命科学研究科 生態適応グローバルCOE 特任教授 竹本徳子氏
【第1章】日本環境経営大賞08年の審査結果
(1)日本環境経営大賞の概要
日本環境経営大賞は、「持続可能な社会の構築」に向けて、あらゆる組織の環境文化を醸成し環境経営を促進することを目的として設けられたもので、今年で8年目を迎えました。
名前からすると政府が主催しているように思われるかも知れませんが、これは三重県が主催している表彰制度で、事業規模の大小・業種・業態にかかわらず、全国から誰でも応募でき、環境経営の"さきがけ"となる活動や優れた成果をあげた組織を表彰しています。自治体として、行政としてこうした事業に取り組んでこられていて、いろいろご苦労もおありかと思いますが、この制度があることで三重県の企業さんが大変グリーンになっている。これはまず三重県さんが表彰されるべきじゃないかと思うほどです。
(2)各部門の評価基準
これまでに1094件の応募があり、109の組織が表彰されました。08年の日本環境経営大賞は「環境経営部門」「環境価値創造部門」「CO2削減部門」の3つの部門に分かれています。
まず、持続可能性、つまり環境・経済・社会の3側面で総合的にバランスがとれているかどうか、本当に経営トップが環境にコミットメントしているか、実践体制が整備されているか、そしてその取り組みがきっちり成果としてでているか、ということを見ていくのが「環境経営部門」です。「環境価値創造部門」は、これまでの「環境プロジェクト賞」と「環境連携賞」をひとつにまとめたもので、ライフスタイルをどうチェンジしていくのか、楽しくファッショナブルで素敵な価値創造でエコを広めていくのにどれだけ貢献しているか、を見ます。目的がはっきりしていること、新規性・創造性はあるか、連携の実効性はどうか、実績や効果はどうか、などが評価基準となっています。「CO2削減部門」は新設です。
本気で削減目標をたてているか、経営トップがコミットメントしているか、実際に削減実績がでているか、費用対効果はどうなのか、サプライチェーンも含めて皆さんに伝える姿勢があるか、取り組みの先進性・持続性・発展性も評価の対象です。
(3)応募の推移
応募件数の推移ですが、第1回は149件の応募があり、第4回のときに賞を統合しまして214件になりました。第5回180件、第6回145件と減少してきましたので、ここでCO2部門を増やして160件の応募をいただきました。
環境価値創造に86件、環境経営に38件、CO2削減に36件という内訳です。地域別では事業者数の多い関東が一番なのは当然ですが、東海・近畿からも多いのは、やはり三重県さんから各企業に応募を呼び掛けることで環境度をあげていく、そういう取り組みが効果をもたらしているのだと思います。組織別では中小企業からの応募が増加しました。
(4)第7回「日本環境経営大賞」受賞者
【環境経営パール大賞】
・トヨタ自動車株式会社 堤工場(愛知県)
持続性あるバランスのとれた経営が評価されました。
・速水林業(三重県)
日本で最初に国際森林認証(FSC)を取得された企業です。
【環境価値創造パール大賞】
・おひさま進歩エネルギー株式会社(長野県)
市民ファンドの会社で、新しいお金の流れを作っていく点が評価されました。
【CO2削減パール大賞】
・レンゴー株式会社(大阪府)
段ボールメーカー。中期で削減目標をたてて本気で取り組んでおられます。
受賞された企業は、いずれも本気でトップがコミットメントされ、本気で未来の持続可能な経営を、あるいは社会を考えて取り組んでおられるところだったと思います。
【第2章】環境経営の最新動向
(1)環境経営に関わるトレンドの変化
●環境経営部門
長いあいだ省エネとか省資源とかいわゆる3R(リユース、リデュース、リサイクル)のようなテーマが多かったと思います。ISOに取り組んだところでもよく継続的改善って何するの、という話を聞きますが、次に何をしようかなんて考えなくても問題は次から次へとやってくる。
CO2の排出量削減だとか、さらに創エネまで踏み込んでやらなくてはならない。また生物多様性の保全という取り組みも始まっていて、問題は山積みという感じです。一方で病院や学校でのEMS(環境マネジメントシステム)導入も増えてきています。
●環境プロジェクト
●環境連携
・・・野呂三重県知事がいわれた「新しい時代の公」(公共領域を担う多様な主体間の関係づくり)の理念・・・・
(2)経営環境の劇的変化
・・・グリーンニューディールがいまブームのようになっています。環境によって経済を立て直す、という考え方です。その流れにどのくらい乗っていけるかが試されているわけです。
・・・脱化石燃料化を図らないと、経済に少しブレーキをかけてでも削減目標を達成しないと、子供たちになにも残らなくなってしまいます。「地球温暖化対策を強力に推進する」というマニフェストを発表した・・・
【第3章】低炭素社会への移行
(1)経済と環境について
経済とは、「物資の生産・流通・交換・分配とその消費・蓄積の全過程、およびその中で営まれる社会的諸関係の総体」。
また、金儲けをすることではなく「世を治め、民の生活を安定させること。"経世済民"」から・・
つまり経済とは、本来民を救うためのものだったのです。
一方、環境とは何か。何かを「取り囲んでいる周りの世界」。「人間や生物の周囲にあって、意識や行動の面でそれらと何らかの相互作用を及ぼし合うもの」つまりつながりです。あるいは関係性のことだといえるでしょう。
(2)トリプルボトムライン
トリプルボトムラインといいますのは、企業活動を経済面、社会面及び環境面という3つの側面から評価しようとする考え方で、この3つがバランスよく好循環をしていることが今世紀の企業に求められるというものです。3つをちゃんと報告することがCSR(企業の社会的責任)あるいはサステナビリティ・レポートと呼ばれるようになって、きちんと説明責任を果たしていることが企業価値を高めるといわれています。
私はそうではなくて、環境というのはイコール生態系のこと、生態系とは人間を含むすべてつまり地球です。地球の上で経済活動を行い、社会活動をやっている。この土台がなくなったら何の意味があるのでしょう。環境の上に経済と社会がありその真中にソーシャルビジネスが今生まれつつあるのではないでしょうか。
「おひさまファンド」などがその例だと思います。定年退職されてお金も力もある方が、ソーシャルビジネスをされれば、地域は良くなるのではないですか。そのことによって行政の負担も軽くすることができる、そういう制度ができるといいなと思っています。
(3)「持続可能性」サステナビリティとは
この定義としては、まずブルントラント委員会(環境と開発に関する世界委員会'87)の「Our Common Future」という本の中に書かれているもので、「持続可能な開発とは将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」というのがあります。
二つ目は経済学者・ハーマン・デイリーがいっている3原則で、「資源利用と廃棄物の排出において、持続可能な利用速度が(再生・代用・無害化できる)速度をこえてはならない」
たとえばCO2は森林が吸収していますが、この範囲をこえてCO2の排出をしているので、いま温暖化がおこっている、だからブレーキを踏みましょうというわけです。
もうひとつ科学者の視点としては、スウェーデンの小児科医・カール・ヘンリク=ロベール博士がいったナチュラル・ステップという国際NGOの4つのシステム条件があります。「地殻からの物質の濃度・化学物質・物理的劣化を増やさない。基本的ニーズを妨げない」というもので、分解できないものはつくらないとか、森林を切りすぎない、魚を獲りすぎないということと、どこにいても基本的ニーズは妨げられないということです。
山奥にいたらGDPがあがっても誰も幸せになれない。地球にダメージを与えることなく山奥の人の基本的ニーズを満たすにはどうすればいいかを考えなければなりません。いまや都市人口、つまり消費人口が50%をこえました。生産が追いつかなくなったらどうなるのか。それで持続可能な社会といえるのでしょうか。
(4)20世紀型経済成長論の破綻
何故そんなことが起こったのか。大量生産・大量消費・大量廃棄、つまり消費が増えて生産が増えれば、雇用が増えて貧困はなくなるという夢物語がありました。実際は人口が増え、ゴミが増え、そして格差も増大したわけです。しかもそれだけではなく、生物の多様性も喪失してしまった。生態系サービスも劣化してしまった。これは何かというと、乱獲や汚染、開発といった人間の活動によって自然の恵みが得られなくなっている、ということなのです。
気候変動や自然災害は人間が原因であると考えるかどうか。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)はかなりの程度まで人間が原因であると述べています。では生態系の劣化は人間生活にどう影響するのでしょう。生態系サービスには、食糧や水、木材、燃料などを供給する「物質供給サービス」と、気候の調節や洪水の調節、病気や害虫の制御、浄水作用といった「調節的サービス」、そして美的文化、精神文化、教育といった「文化的サービス」の3つがあげられます。物質供給サービスも調節的サービスも、人間生活の安全性やベターライフ、健康などに必要なものを与えてくれます。しかしながらこうした生態系サービスの多くが低下してきていると国連の「ミレニアム生態系評価」は報告しています。
-
【第4章】リスクをチャンスに変える知と情
(1)生態系サービスの傾向から生じるリスクとチャンス
こうした状況を受けてリスクとチャンスをどう捉えるか。たとえば工場を持っている企業では、リスクとしては原材料が減ってくる、生産性の低下が起きる、生産量が減る、ひどい場合は業務の中断も起きる、といったことになります。 ・・・・といったチャンスが生まれるでしょう。
(2)本業のリスクをチャンスに変える知と情
皆さんの本業に対するリスクは何なのか、これをまずしっかり知ることが大事です。生物多様性もそうですし、環境影響評価をきっちりやってください。・・・・・実は本大賞の3年前の環境プロジェクト賞受賞企業です。
【第5章】生物多様性保全について
(1)生物多様性ガイドラインと宣言
日本では05年に鹿島建設さんが、「鹿島生態系保全行動指針」を出したのを皮切りに、企業の宣言が相次ぎ、生物多様性保全のさまざまな取り組みがなされてきました。09年3月には日本経団連が宣言。09年8月には環境省の「生物多様性民間参画ガイドライン」が作成されました。
キーは、生物多様性の保全ということと、生物多様性の構成要素の持続可能な利用ということです。取り組みの方向としては、事業活動とのかかわりを把握するよう努めるということと、生物多様性に及ぼす影響の低減を図り、そのための措置をとる、そして持続可能な利用に努めるということです。またそのための推進体制を整備するよう努める、となっています。
(2)環境激変への生態適応に向けた教育研究
・・・一緒に実践活動を行っています。
【まとめ】
環境経営に取り組む際の課題
・まずトップが持続可能な社会を目指すという覚悟をする。トップの覚悟なくしては何も始りません。その時に「知」と「情」のバランスをうまくとることが大切でしょう。
・自分たちの活動・製品・サービスを化学的にきっちり評価する。そしてこういう不確実な時代の複雑系に生きているわけですから、柔軟に現実に即して真摯に見直す姿勢が大事です。
・温暖化対策と生物多様性保全対策は別々のものではありません。3Rにしても限られた資源を持続可能に使っていくか、生態系サービスをどう護るのかということと同じことですので、対策もこれらを融合化していくことが有効だと思います。
・最後に自分たちだけでなく、周りの地域・サプライヤー・行政を巻き込みながら進めることです。巻き込むことができれば自信が得られます。プライドが得られます。それは従業員の満足につながり、そこで企業価値がつくられていくのではないでしょうか。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/seminar_report.html
■鹿島生物多様性行動指針■
鹿島は、「鹿島生態系保全行動指針」を2005年8月に定め、2009年7月には「鹿島生物多様性行動指針」として改訂を行い、それに基づいたさまざまな活動を進めています。
■基本理念
鹿島は、「100年をつくる会社」として、将来にわたり豊かな環境を維持し、良質な社会基盤を整備していくことを使命としている。
地球規模での環境への影響が顕在化するなか、生物多様性の劣化は地球温暖化と並ぶ重要な課題であり、その解決には企業として果たすべき役割も大きい。
鹿島は、生物多様性に関し建設事業を通じてその保全と持続可能な利用に取り組み、人と自然が共生する社会の実現に貢献していく。
■行動指針
全社員の参加
鹿島は、自然の恵みに対する社員の意識を高め、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する知識を普及展開し、全社的に取組みを推進する。
■建設事業への展開
鹿島は、生物多様性に関する情報・技術を活用した提案、工事における環境配慮を推進することで、生物多様性の保全と持続可能な利用を目指す。
■調達における配慮
鹿島は、調達において生物多様性への影響を考慮し、その回避・低減を図る。
■研究開発の推進
鹿島は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する情報や技術的知見を集積し、関連する研究・技術開発を推進する。
■社会的要請の尊重
鹿島は、生物多様性に関する法令等の遵守にとどまらず、関連施策や社会的要請を把握し、その知見を事業活動に反映させるよう努める。
■コミュニケーションの促進
鹿島は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する活動、研究内容を開示し、顧客、地域社会、行政、研究機関、企業、NGO等との連携・対話を図る。
http://www.kajima.co.jp/csr/environment/problem4/index-j.html#seitaikei
との循環型社会の構築と環境ビジネス、環境・CSR経営
■講師
おおさかATCグリーンエコプラザ顧問 同志社大学 経済学部教授
郡嶌 孝氏
はじめに
ドイツの社会学者、ウルリッヒ・ベックは、今日の近代社会をリスク社会と呼んでいます。我々の社会は、現在、成功しているがゆえに新たな課題、リスクを生んでいます。今日は、私たちがこの新しい課題である環境危機に今後どう対応していくべきなのか、温暖化問題を含めてお話していきます。
21世紀の環境問題と各国の動き
危機という漢字は、“危”険と“機”会が組み合わさっています。まさに環境危機とは、日本においてはリスクを伴いながら、一方ではビジネスチャンスになったりするのが特徴であるかもしれません。
21世紀の環境問題は、廃棄物および温暖化の問題がとりわけ大きくなってきました。そんな中、先進国の取組みは、温暖化よりも廃棄物問題への取組みの方が少し早かったようです。
G8のサミットで初めて循環型社会について取り上げられたのは、2003年の、フランス、エビアンでのサミットです。エビアンでは循環型社会を実現する上での、先進国のマテリアルリサイクルについて話し合われました。その後、アメリカのシーアイランドでのサミットでは、小泉前総理の提唱により3Rイニシアチブが合意され、国際会議が行われるようになりました。
実はこれらの契機となったのは2002年のヨハネスブルグサミットです。1992年の地球サミットより10年が経過したこの年、持続可能な生産・開発を約束した「アジェンダ21」の進捗状況を確かめるとともに、次の「持続可能な生産・消費」に取り組む10年のフレームワークを策定することとなりました。
アジアとの循環型社会の構築
昨年、エコプラザ前館長と共に、大阪市と上海の環境問題対話のために上海に行ったのですが、アジアで環境ビジネスを行うのは難しいことがわかりました。中国にとって日本は、再生資源の原料輸入国としてしか位置づけられていないようです。対話の中で、環境用語は、ほぼドイツ語に占められていたことからも、すでにドイツとの環境ビジネスが進んでいることは明らかです。ここに入り込むのは、なかなか容易ではないでしょう。
では、当面、商売よりも日本の経験の中でどう環境と経済を両立するかということが重要となります。中国をはじめ、海外でも両立しなけれならないという意識はありますが、そのための技術や経験が不足しています。彼らが、技術・経験を身につけた後、開放的調整計画による協力関係が生まれると考えられます。しかしそのためには、まずトレーサビリティが最重要です。
現在、日本のマテリアルフローは、とりわけ静脈産業におけるフローの把握が非常に弱い状況にあります。例えばどのように資源が回収され、資源化され、どう使われているのか。消えた資源は廃棄されたのか、海外に輸出されたのか。廃棄自動車の例を挙げると、多くは海外に輸出されていることはわかっていますが、その後、部品として使われているのか、車のままなのか、海外で何が起こっているのか、トレーサビリティが全く把握できていません。家電についても同様です。
我々は環境の問題を“見える化”するためには、まずは数値化し、その実態をとらえられるようにしなければなりません。そしてグローバル化の中で循環経済圏を作ることはまだまだ難しい状態にありますが、日本の経験は必ず中国に役立つはずであり、必ずそこにビジネスチャンスはあると考えられます。
エコイノベーションとソーシャルイノベーション
また、エコイノベーションという面から言うと、今後は次第に製品を売ることから、機能やサービスを売るプロダクトサービスシステム(サービスサイジング)への変換が必要になってきます。
我々が3年前に地球環境戦略機関で研究を始めて以来、経済産業省でもサービスサイジング事業推進委員会が作られ、少しずつサービスサイジングの流れが生まれています。これを大きな流れにするべく、主要産業におけるサービスサイジングの促進を進めていかなければなりません。
これからは、まさに大企業の中で、サービスサイジングを動脈産業として変えていかねばなりません。
また環境ビジネスとしては、中間組織の支援をしながら、さらに市民社会における環境への取組みを進めていく必要があります。日本の強みを生かし、環境重視、人間重視の、技術革新・社会革新の実現こそが、経済産業省が描いている環境大国へのビジョンです。まさに我々はエコイノベーションと同時に、ソーシャルイノベーションも伴わなくてはいけません。
その中で、環境をどう価値化するか。皆が見えないCO2をどう見えるようにするかが非常に重要です。まずは環境問題を経済的な価値として見えるようにして、キャップをはめることが大事なのです。
たとえば社内では、部署ごとに排出権取引、環境税などで規制すれば良いでしょう。企業の中における評価を、売上高や経済価値だけでなく、環境の価値も“見える化”して評価対象にすれば、皆も取り組むようになるかもしれません。経験こそ重要な資産となるでしょう。
それぞれに何ができるか、環境と経済の両立の中で、今日お話された他の企業の皆さんのお話も参考にして取り組んでいただければ、これも、開放的調整政策のひとつといえるでしょう。どうもありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190801/index.html
循環型社会形成推進セミナー
〜平成20年関西エコオフィス大賞受賞者発表会〜
関西広域機構(KU)では、身近なところからの省エネルギー等の取組みを通じて、地球温暖化対策を実施する「関西エコオフィス運動」を進めており、この運動への参加オフィスや各種の環境マネジメントシステムの認証・登録を受けているオフィ
スの中から、顕著な効果を挙げているオフィスを、「関西エコオフィス大賞」として毎年表彰しています。 平成20年度は、これらの中から特に先導的で優れた取り組みを行っているオフィスを、「平成20年度関西エコオフィス大賞・奨励賞」として、6事業所を選定しました。
今回の発表会では、まず関西広域機構(KU)から「関西エコオフィス大賞」の主旨、目的、経緯等をご説明頂き、その後に大賞受賞の2事業所と奨励賞受賞の2事業所にそれぞれの優れた先導的な取り組み内容を紹介していただきます。今回のセミナーで、これらの環境行動内容を広く参加者に理解していただくことにより、関西における先導的な優れた環境行動の普及・推進を図っていく。
開催日時
平成21年12月11日(金)13:30〜17:00
内容
主旨説明「関西エコオフィス大賞について」
講 師:関西広域機構環境・防災部長早金孝氏
発表1 「京都ビール工場の環境活動『エコ・ブルワリーの実現』」(大賞*1)
講 師:サントリー酒類株式会社 京都ビール工場 技師長 高田純一氏
発表2 「山金工業株式会社森田工場のCO2・VOC排出量削減活動」(大賞*2)
講 師:山金工業株式会社 森田工場 製造部 ISO委員会事務局 担当課長 山腰喜勇氏
発表3 「エプソンイメージングデバイス株式会社の環境施策について」(奨励賞*1)
講師:エプソンイメージングデバイス株式会社 経営管理部部長 上條光一 氏
発表4 「くらこんの継続した環境活動」(奨励賞*2)
講師:株式会社くらこん枚方工場 常務取締役製造本部長 松井隆史 氏
*1:大企業部門*2:中小企業・団体部門
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、ATC、日本経済新聞社)・ビジネス交流会
協力
関西広域機構(KU)
受講料
無料
会場
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟、おおさかATCグリーンエコプラザ゙内「ビオトーププラザ」
定員
100名(先着順※受付確認はセミナー開催約10 日前までにFAX またはE-mail でお送りします。)
お申し込み
おおさかATCグリーンエコプラザ事務局まで
〈事務局〉〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ関西エコオフィス大賞発表会(12月11日)係TEL:06-6615-5688
お申し込みはE−mailで、もしくは下記にご記入後FAXで、お送りください
E−mail:office@ecoplaza.gr.jp FAX送付先06−6615−5890
http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar091211.pdf
参考セミナーレポート
環境経営の最新動向 〜リスクをチャンスに変える知と情〜
■講師
日本環境経営大賞表彰委員会 審査委員 東北大学大学院
生命科学研究科 生態適応グローバルCOE 特任教授 竹本徳子氏
【第1章】日本環境経営大賞08年の審査結果
(1)日本環境経営大賞の概要
日本環境経営大賞は、「持続可能な社会の構築」に向けて、あらゆる組織の環境文化を醸成し環境経営を促進することを目的として設けられたもので、今年で8年目を迎えました。
名前からすると政府が主催しているように思われるかも知れませんが、これは三重県が主催している表彰制度で、事業規模の大小・業種・業態にかかわらず、全国から誰でも応募でき、環境経営の"さきがけ"となる活動や優れた成果をあげた組織を表彰しています。自治体として、行政としてこうした事業に取り組んでこられていて、いろいろご苦労もおありかと思いますが、この制度があることで三重県の企業さんが大変グリーンになっている。これはまず三重県さんが表彰されるべきじゃないかと思うほどです。
(2)各部門の評価基準
これまでに1094件の応募があり、109の組織が表彰されました。08年の日本環境経営大賞は「環境経営部門」「環境価値創造部門」「CO2削減部門」の3つの部門に分かれています。
まず、持続可能性、つまり環境・経済・社会の3側面で総合的にバランスがとれているかどうか、本当に経営トップが環境にコミットメントしているか、実践体制が整備されているか、そしてその取り組みがきっちり成果としてでているか、ということを見ていくのが「環境経営部門」です。「環境価値創造部門」は、これまでの「環境プロジェクト賞」と「環境連携賞」をひとつにまとめたもので、ライフスタイルをどうチェンジしていくのか、楽しくファッショナブルで素敵な価値創造でエコを広めていくのにどれだけ貢献しているか、を見ます。目的がはっきりしていること、新規性・創造性はあるか、連携の実効性はどうか、実績や効果はどうか、などが評価基準となっています。「CO2削減部門」は新設です。
本気で削減目標をたてているか、経営トップがコミットメントしているか、実際に削減実績がでているか、費用対効果はどうなのか、サプライチェーンも含めて皆さんに伝える姿勢があるか、取り組みの先進性・持続性・発展性も評価の対象です。
(3)応募の推移
応募件数の推移ですが、第1回は149件の応募があり、第4回のときに賞を統合しまして214件になりました。第5回180件、第6回145件と減少してきましたので、ここでCO2部門を増やして160件の応募をいただきました。
環境価値創造に86件、環境経営に38件、CO2削減に36件という内訳です。地域別では事業者数の多い関東が一番なのは当然ですが、東海・近畿からも多いのは、やはり三重県さんから各企業に応募を呼び掛けることで環境度をあげていく、そういう取り組みが効果をもたらしているのだと思います。組織別では中小企業からの応募が増加しました。
(4)第7回「日本環境経営大賞」受賞者
【環境経営パール大賞】
・トヨタ自動車株式会社 堤工場(愛知県)
持続性あるバランスのとれた経営が評価されました。
・速水林業(三重県)
日本で最初に国際森林認証(FSC)を取得された企業です。
【環境価値創造パール大賞】
・おひさま進歩エネルギー株式会社(長野県)
市民ファンドの会社で、新しいお金の流れを作っていく点が評価されました。
【CO2削減パール大賞】
・レンゴー株式会社(大阪府)
段ボールメーカー。中期で削減目標をたてて本気で取り組んでおられます。
受賞された企業は、いずれも本気でトップがコミットメントされ、本気で未来の持続可能な経営を、あるいは社会を考えて取り組んでおられるところだったと思います。
【第2章】環境経営の最新動向
(1)環境経営に関わるトレンドの変化
●環境経営部門
長いあいだ省エネとか省資源とかいわゆる3R(リユース、リデュース、リサイクル)のようなテーマが多かったと思います。ISOに取り組んだところでもよく継続的改善って何するの、という話を聞きますが、次に何をしようかなんて考えなくても問題は次から次へとやってくる。
CO2の排出量削減だとか、さらに創エネまで踏み込んでやらなくてはならない。また生物多様性の保全という取り組みも始まっていて、問題は山積みという感じです。一方で病院や学校でのEMS(環境マネジメントシステム)導入も増えてきています。
●環境プロジェクト
●環境連携
・・・野呂三重県知事がいわれた「新しい時代の公」(公共領域を担う多様な主体間の関係づくり)の理念・・・・
(2)経営環境の劇的変化
・・・グリーンニューディールがいまブームのようになっています。環境によって経済を立て直す、という考え方です。その流れにどのくらい乗っていけるかが試されているわけです。
・・・脱化石燃料化を図らないと、経済に少しブレーキをかけてでも削減目標を達成しないと、子供たちになにも残らなくなってしまいます。「地球温暖化対策を強力に推進する」というマニフェストを発表した・・・
【第3章】低炭素社会への移行
(1)経済と環境について
経済とは、「物資の生産・流通・交換・分配とその消費・蓄積の全過程、およびその中で営まれる社会的諸関係の総体」。
また、金儲けをすることではなく「世を治め、民の生活を安定させること。"経世済民"」から・・
つまり経済とは、本来民を救うためのものだったのです。
一方、環境とは何か。何かを「取り囲んでいる周りの世界」。「人間や生物の周囲にあって、意識や行動の面でそれらと何らかの相互作用を及ぼし合うもの」つまりつながりです。あるいは関係性のことだといえるでしょう。
(2)トリプルボトムライン
トリプルボトムラインといいますのは、企業活動を経済面、社会面及び環境面という3つの側面から評価しようとする考え方で、この3つがバランスよく好循環をしていることが今世紀の企業に求められるというものです。3つをちゃんと報告することがCSR(企業の社会的責任)あるいはサステナビリティ・レポートと呼ばれるようになって、きちんと説明責任を果たしていることが企業価値を高めるといわれています。
私はそうではなくて、環境というのはイコール生態系のこと、生態系とは人間を含むすべてつまり地球です。地球の上で経済活動を行い、社会活動をやっている。この土台がなくなったら何の意味があるのでしょう。環境の上に経済と社会がありその真中にソーシャルビジネスが今生まれつつあるのではないでしょうか。
「おひさまファンド」などがその例だと思います。定年退職されてお金も力もある方が、ソーシャルビジネスをされれば、地域は良くなるのではないですか。そのことによって行政の負担も軽くすることができる、そういう制度ができるといいなと思っています。
(3)「持続可能性」サステナビリティとは
この定義としては、まずブルントラント委員会(環境と開発に関する世界委員会'87)の「Our Common Future」という本の中に書かれているもので、「持続可能な開発とは将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」というのがあります。
二つ目は経済学者・ハーマン・デイリーがいっている3原則で、「資源利用と廃棄物の排出において、持続可能な利用速度が(再生・代用・無害化できる)速度をこえてはならない」
たとえばCO2は森林が吸収していますが、この範囲をこえてCO2の排出をしているので、いま温暖化がおこっている、だからブレーキを踏みましょうというわけです。
もうひとつ科学者の視点としては、スウェーデンの小児科医・カール・ヘンリク=ロベール博士がいったナチュラル・ステップという国際NGOの4つのシステム条件があります。「地殻からの物質の濃度・化学物質・物理的劣化を増やさない。基本的ニーズを妨げない」というもので、分解できないものはつくらないとか、森林を切りすぎない、魚を獲りすぎないということと、どこにいても基本的ニーズは妨げられないということです。
山奥にいたらGDPがあがっても誰も幸せになれない。地球にダメージを与えることなく山奥の人の基本的ニーズを満たすにはどうすればいいかを考えなければなりません。いまや都市人口、つまり消費人口が50%をこえました。生産が追いつかなくなったらどうなるのか。それで持続可能な社会といえるのでしょうか。
(4)20世紀型経済成長論の破綻
何故そんなことが起こったのか。大量生産・大量消費・大量廃棄、つまり消費が増えて生産が増えれば、雇用が増えて貧困はなくなるという夢物語がありました。実際は人口が増え、ゴミが増え、そして格差も増大したわけです。しかもそれだけではなく、生物の多様性も喪失してしまった。生態系サービスも劣化してしまった。これは何かというと、乱獲や汚染、開発といった人間の活動によって自然の恵みが得られなくなっている、ということなのです。
気候変動や自然災害は人間が原因であると考えるかどうか。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)はかなりの程度まで人間が原因であると述べています。では生態系の劣化は人間生活にどう影響するのでしょう。生態系サービスには、食糧や水、木材、燃料などを供給する「物質供給サービス」と、気候の調節や洪水の調節、病気や害虫の制御、浄水作用といった「調節的サービス」、そして美的文化、精神文化、教育といった「文化的サービス」の3つがあげられます。物質供給サービスも調節的サービスも、人間生活の安全性やベターライフ、健康などに必要なものを与えてくれます。しかしながらこうした生態系サービスの多くが低下してきていると国連の「ミレニアム生態系評価」は報告しています。
-
【第4章】リスクをチャンスに変える知と情
(1)生態系サービスの傾向から生じるリスクとチャンス
こうした状況を受けてリスクとチャンスをどう捉えるか。たとえば工場を持っている企業では、リスクとしては原材料が減ってくる、生産性の低下が起きる、生産量が減る、ひどい場合は業務の中断も起きる、といったことになります。 ・・・・といったチャンスが生まれるでしょう。
(2)本業のリスクをチャンスに変える知と情
皆さんの本業に対するリスクは何なのか、これをまずしっかり知ることが大事です。生物多様性もそうですし、環境影響評価をきっちりやってください。・・・・・実は本大賞の3年前の環境プロジェクト賞受賞企業です。
【第5章】生物多様性保全について
(1)生物多様性ガイドラインと宣言
日本では05年に鹿島建設さんが、「鹿島生態系保全行動指針」を出したのを皮切りに、企業の宣言が相次ぎ、生物多様性保全のさまざまな取り組みがなされてきました。09年3月には日本経団連が宣言。09年8月には環境省の「生物多様性民間参画ガイドライン」が作成されました。
キーは、生物多様性の保全ということと、生物多様性の構成要素の持続可能な利用ということです。取り組みの方向としては、事業活動とのかかわりを把握するよう努めるということと、生物多様性に及ぼす影響の低減を図り、そのための措置をとる、そして持続可能な利用に努めるということです。またそのための推進体制を整備するよう努める、となっています。
(2)環境激変への生態適応に向けた教育研究
・・・一緒に実践活動を行っています。
【まとめ】
環境経営に取り組む際の課題
・まずトップが持続可能な社会を目指すという覚悟をする。トップの覚悟なくしては何も始りません。その時に「知」と「情」のバランスをうまくとることが大切でしょう。
・自分たちの活動・製品・サービスを化学的にきっちり評価する。そしてこういう不確実な時代の複雑系に生きているわけですから、柔軟に現実に即して真摯に見直す姿勢が大事です。
・温暖化対策と生物多様性保全対策は別々のものではありません。3Rにしても限られた資源を持続可能に使っていくか、生態系サービスをどう護るのかということと同じことですので、対策もこれらを融合化していくことが有効だと思います。
・最後に自分たちだけでなく、周りの地域・サプライヤー・行政を巻き込みながら進めることです。巻き込むことができれば自信が得られます。プライドが得られます。それは従業員の満足につながり、そこで企業価値がつくられていくのではないでしょうか。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/seminar_report.html
■鹿島生物多様性行動指針■
鹿島は、「鹿島生態系保全行動指針」を2005年8月に定め、2009年7月には「鹿島生物多様性行動指針」として改訂を行い、それに基づいたさまざまな活動を進めています。
■基本理念
鹿島は、「100年をつくる会社」として、将来にわたり豊かな環境を維持し、良質な社会基盤を整備していくことを使命としている。
地球規模での環境への影響が顕在化するなか、生物多様性の劣化は地球温暖化と並ぶ重要な課題であり、その解決には企業として果たすべき役割も大きい。
鹿島は、生物多様性に関し建設事業を通じてその保全と持続可能な利用に取り組み、人と自然が共生する社会の実現に貢献していく。
■行動指針
全社員の参加
鹿島は、自然の恵みに対する社員の意識を高め、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する知識を普及展開し、全社的に取組みを推進する。
■建設事業への展開
鹿島は、生物多様性に関する情報・技術を活用した提案、工事における環境配慮を推進することで、生物多様性の保全と持続可能な利用を目指す。
■調達における配慮
鹿島は、調達において生物多様性への影響を考慮し、その回避・低減を図る。
■研究開発の推進
鹿島は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する情報や技術的知見を集積し、関連する研究・技術開発を推進する。
■社会的要請の尊重
鹿島は、生物多様性に関する法令等の遵守にとどまらず、関連施策や社会的要請を把握し、その知見を事業活動に反映させるよう努める。
■コミュニケーションの促進
鹿島は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する活動、研究内容を開示し、顧客、地域社会、行政、研究機関、企業、NGO等との連携・対話を図る。
http://www.kajima.co.jp/csr/environment/problem4/index-j.html#seitaikei
との循環型社会の構築と環境ビジネス、環境・CSR経営
■講師
おおさかATCグリーンエコプラザ顧問 同志社大学 経済学部教授
郡嶌 孝氏
はじめに
ドイツの社会学者、ウルリッヒ・ベックは、今日の近代社会をリスク社会と呼んでいます。我々の社会は、現在、成功しているがゆえに新たな課題、リスクを生んでいます。今日は、私たちがこの新しい課題である環境危機に今後どう対応していくべきなのか、温暖化問題を含めてお話していきます。
21世紀の環境問題と各国の動き
危機という漢字は、“危”険と“機”会が組み合わさっています。まさに環境危機とは、日本においてはリスクを伴いながら、一方ではビジネスチャンスになったりするのが特徴であるかもしれません。
21世紀の環境問題は、廃棄物および温暖化の問題がとりわけ大きくなってきました。そんな中、先進国の取組みは、温暖化よりも廃棄物問題への取組みの方が少し早かったようです。
G8のサミットで初めて循環型社会について取り上げられたのは、2003年の、フランス、エビアンでのサミットです。エビアンでは循環型社会を実現する上での、先進国のマテリアルリサイクルについて話し合われました。その後、アメリカのシーアイランドでのサミットでは、小泉前総理の提唱により3Rイニシアチブが合意され、国際会議が行われるようになりました。
実はこれらの契機となったのは2002年のヨハネスブルグサミットです。1992年の地球サミットより10年が経過したこの年、持続可能な生産・開発を約束した「アジェンダ21」の進捗状況を確かめるとともに、次の「持続可能な生産・消費」に取り組む10年のフレームワークを策定することとなりました。
アジアとの循環型社会の構築
昨年、エコプラザ前館長と共に、大阪市と上海の環境問題対話のために上海に行ったのですが、アジアで環境ビジネスを行うのは難しいことがわかりました。中国にとって日本は、再生資源の原料輸入国としてしか位置づけられていないようです。対話の中で、環境用語は、ほぼドイツ語に占められていたことからも、すでにドイツとの環境ビジネスが進んでいることは明らかです。ここに入り込むのは、なかなか容易ではないでしょう。
では、当面、商売よりも日本の経験の中でどう環境と経済を両立するかということが重要となります。中国をはじめ、海外でも両立しなけれならないという意識はありますが、そのための技術や経験が不足しています。彼らが、技術・経験を身につけた後、開放的調整計画による協力関係が生まれると考えられます。しかしそのためには、まずトレーサビリティが最重要です。
現在、日本のマテリアルフローは、とりわけ静脈産業におけるフローの把握が非常に弱い状況にあります。例えばどのように資源が回収され、資源化され、どう使われているのか。消えた資源は廃棄されたのか、海外に輸出されたのか。廃棄自動車の例を挙げると、多くは海外に輸出されていることはわかっていますが、その後、部品として使われているのか、車のままなのか、海外で何が起こっているのか、トレーサビリティが全く把握できていません。家電についても同様です。
我々は環境の問題を“見える化”するためには、まずは数値化し、その実態をとらえられるようにしなければなりません。そしてグローバル化の中で循環経済圏を作ることはまだまだ難しい状態にありますが、日本の経験は必ず中国に役立つはずであり、必ずそこにビジネスチャンスはあると考えられます。
エコイノベーションとソーシャルイノベーション
また、エコイノベーションという面から言うと、今後は次第に製品を売ることから、機能やサービスを売るプロダクトサービスシステム(サービスサイジング)への変換が必要になってきます。
我々が3年前に地球環境戦略機関で研究を始めて以来、経済産業省でもサービスサイジング事業推進委員会が作られ、少しずつサービスサイジングの流れが生まれています。これを大きな流れにするべく、主要産業におけるサービスサイジングの促進を進めていかなければなりません。
これからは、まさに大企業の中で、サービスサイジングを動脈産業として変えていかねばなりません。
また環境ビジネスとしては、中間組織の支援をしながら、さらに市民社会における環境への取組みを進めていく必要があります。日本の強みを生かし、環境重視、人間重視の、技術革新・社会革新の実現こそが、経済産業省が描いている環境大国へのビジョンです。まさに我々はエコイノベーションと同時に、ソーシャルイノベーションも伴わなくてはいけません。
その中で、環境をどう価値化するか。皆が見えないCO2をどう見えるようにするかが非常に重要です。まずは環境問題を経済的な価値として見えるようにして、キャップをはめることが大事なのです。
たとえば社内では、部署ごとに排出権取引、環境税などで規制すれば良いでしょう。企業の中における評価を、売上高や経済価値だけでなく、環境の価値も“見える化”して評価対象にすれば、皆も取り組むようになるかもしれません。経験こそ重要な資産となるでしょう。
それぞれに何ができるか、環境と経済の両立の中で、今日お話された他の企業の皆さんのお話も参考にして取り組んでいただければ、これも、開放的調整政策のひとつといえるでしょう。どうもありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190801/index.html
2009年11月15日
ATC農商工連携による価値の創造 〜植物工場の可能性〜
おおさかATCグリーンエコプラザ 食と環境ビジネスフォーラム

農商工連携による価値の創造 〜植物工場の可能性〜
植物工場が注目されています。農商工連携による相乗効果を期待できる植物工場は、地域経済活性化の大きな可能性があり、経済産業省と農林水産省も、様々な支援を行っています。
植物工場の現状と課題、今後の展望について、最新情報をお持ちの日本有数の講師陣をお招きして熱く語っていただきます。講演、パネルディスカッションだけでなく、植物工場の見学や試食もございます。多数のご参加をお待ち申し上げます。
開催日時
2009年12月17日(木)13:00〜17:50
開催場所
大阪南港ATC ITM棟12階 ITMホール(&11階おおさかATCグリーンエコプラザ)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
プログラム(予定)
総合司会: 大阪大学大学院 工学研究科 准教授 加藤 悟氏
13:00《ご 挨 拶》
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会 委員長 石?良也
13:10《講 演》「国家的プロジェクト植物工場普及・拡大に向けての経済産業省の取組み」
経済産業省 地域経済産業政策課 課長補佐 杉本敬次氏
13:40《基調講演》「植物工場の将来展望」
財団法人社会開発研究センター理事
農商工連携研究会植物工場ワーキンググループ座長 高辻正基氏
14:30《見学タイム》
植物工場見学、展示ブース見学、機能性野菜リーフレタスの試食
15:00《分 科 会》
テーマ1.技術開発、生産コスト削減
植物工場の多様なシステムとビジネス展開、最新技術とコストパフォーマンスについてのパネルディスカッション
〈パネリスト〉
エスペックミック株式会社 環境モニタリング事業部部長 中村謙治氏
日本アドバンストアグリ株式会社 代表取締役社長 辻 昭久氏
徳寿工業株式会社 常務取締役 坂谷英志郎氏
株式会社演算工房 代表取締役 林 稔氏
〈コーディネーター〉 加籐 悟氏
テーマ2.販路の拡大、新事業展開
販路拡大のポイント、植物工場を活用した地域活性化、新しいカテゴリーとしての植物工場産野菜の役割りなどについての
パネルディスカッション
〈パネリスト〉
ステラグリーン株式会社 専務取締役 野澤歸价氏
株式会社イズミヤ総研 代表取締役 清水正博氏
早稲田商店会 代表研究員 藤村望洋氏
鹿児島市宇宿商店街振興組合理事長 河井達志氏
日本経済新聞社(予定)
〈コーディネーター〉 高辻正基氏
16:40《総 合 討 議》
17:50終了
主 催 : アジア太平洋トレードセンター株式会社
参加料 : 無 料
お申し込み : 裏面をご覧のうえ、e-mailまたはFAXにて。
会 場 : メイン会場 ITMホール (ATCビルITM棟12F)
分科会会場 ATCグリーンエコプラザ内ビオトーププラザほか (ATCビルITM棟11F)
定 員 : 300名
お申し込み
下記にご記入の上、FAXでお申込下さい。(または、同内容を、E-mailでお送り下さい。)
FAX送付先: 06−6614−1801 E−mail:091217@e-being.jp



参考:セミナーレポート
アグリビジネスの成長戦略とその可能性
講師
株式会社日本総合研究所 総合研究部門
食・農基本戦略クラスタークラスター長 主任研究員 大澤信一氏
1.21世紀 食と環境ビジネスの可能性
本日は、日本の農業の全体像を概観し、アグリビジネスの課題を展望し成長戦略を考えるというテーマでお話をさせていただきます。
日本の農業は、粗生産額8.4兆円弱、その大半は、畜産、米、野菜、果実、花木です。各地域の特性にあわせたアグリビジネスの展開が基本であり、最終的には成長の鍵を握っていると言えるでしょう。
日本の農家の耕地面積は、津軽海峡を境として、北海道はEU平均よりも大きい約17haであるのに対し、本州の平均は約1.6haと、大きく差があります。それぞれ展開するアグリビジネスも別物として考える必要があるでしょう。
各地域の特徴としては、欧米型の大型農業の北海道、稲作中心の東北・北陸。そして首都圏の野菜の供給基地であり、産出額ベースで全国2位、3位を争う千葉と茨城からなる東関東。施設園芸は愛知、静岡、そして畜産は南九州が核となっています。また、近畿圏は、産出額は少ないものの、伝統野菜などもあり、食文化が優れています。アグリビジネスとしてはチャンスがあると言えるでしょう。・・・・・・・・
また日本は、食品ビジネスの海外展開が遅れています。今後、国内では高齢化が進み、ひとりあたりの食べる量が減っていくことが予想されることからも、各企業の積極的な海外展開が期待されます。また日本の農業技術は、世界でも非常に優れており、世界でマーケットを作るということも十分考えられるでしょう。
2.日本農業の概況
1980年代中ごろまでは、日本の農業産出額の割合は、米、畜産、野菜がほぼ25%ずつでした。BSE騒動以降、一時は牛肉の消費が落ちましたが、現在は、どこの牧場の肉であるかトレースができるようになり、さらに消費が拡大し、農林水産省による「平成17年農業産出額」によると、畜産が31%、米が21%、野菜が25%となっています。逆に米は、どんどん単価が下がっています。40年くらい前まで、日本では年間ひとり120kgほどの米の消費がありました。しかし米の輸入自由化、なおかつ日本人のライフスタイルも変わったことで米以外のものを食べる機会も多くなりました。政府は米の消費拡大をと言っていますが、もはや1年でひとり60kgくらいが限度でしょう。そんな中、個性的な米を作り、単価が下がらないようにする工夫も必要でないかと思います。
・・・・・・・・
農政改革の象徴として、農業への企業の新規参入の許可、農地の利用権を重視する農地法改革、それと農協改革の三つが挙げられます。しかし企業の参入は、現実的には細かい規制が残り難しい状況にあります。実質的な規制緩和、民間開放が必要です。農地法改革については所有権より利用権という形で工夫されており、あとは現場がどのように実施していくかというところまで来ていると思います。そして農業の構造改革として第2クールの2005年に打ち出された、“大規模化(品目横断的経営所得安定対策)”は、今、日本にある約290万の様々な規模の農家を、平成27年を目途に、約40万の大規模な農家に集約していくという計画です。しかし、現実的に、中小規模の250万の農家はどうするかという説明がわかりにくく、頓挫状態と言っても良い状況にあります。
3.アグリビジネスの課題と展望
アグリビジネスをとりまく環境は大きく変わっています。1990年代の構造変化から、21世紀にかけて、従来のキャッチアップ型から、新しい価値を作りマーケットを先導するという時代へ変わってきました。少子高齢化や消費者のライフスタイルの変化、ニーズの変化、また不況の影響などもありますが、では実際どうしたら良いかと言うと、経済の上でも、マーケティングの上でも、考え方を切り替えるのはなかなか難しいのが現状です。そんな中、すでに成功している直売所には、新しい時代にマッチしたアグリビジネスの色々なヒントがあるのではないかと考えています。・・・・
・・・・そのほかにも、農業は高齢化が進んでおり、直売所でも平均年齢75歳のところもあるなど、問題は山積みです。農業の課題として、先に述べたように、流通加工分野へ進出することも重要です。そのために、例えば企業を引退したノウハウある人材を仲間に入れるという方法もあると思います。このような問題を、5年10年の短いスパン、30年ほどの長いスパンで戦略を立て、解決していかなければなりません。
私個人としては、中小規模の農家は、特に直売所を上手く利用していくべきではないかと考えています。本日は直売所を中心に話をしましたが、農業の大規模化にもやはりチャンスがあると思います。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/210804/index.html

農商工連携による価値の創造 〜植物工場の可能性〜
植物工場が注目されています。農商工連携による相乗効果を期待できる植物工場は、地域経済活性化の大きな可能性があり、経済産業省と農林水産省も、様々な支援を行っています。
植物工場の現状と課題、今後の展望について、最新情報をお持ちの日本有数の講師陣をお招きして熱く語っていただきます。講演、パネルディスカッションだけでなく、植物工場の見学や試食もございます。多数のご参加をお待ち申し上げます。
開催日時
2009年12月17日(木)13:00〜17:50
開催場所
大阪南港ATC ITM棟12階 ITMホール(&11階おおさかATCグリーンエコプラザ)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
プログラム(予定)
総合司会: 大阪大学大学院 工学研究科 准教授 加藤 悟氏
13:00《ご 挨 拶》
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会 委員長 石?良也
13:10《講 演》「国家的プロジェクト植物工場普及・拡大に向けての経済産業省の取組み」
経済産業省 地域経済産業政策課 課長補佐 杉本敬次氏
13:40《基調講演》「植物工場の将来展望」
財団法人社会開発研究センター理事
農商工連携研究会植物工場ワーキンググループ座長 高辻正基氏
14:30《見学タイム》
植物工場見学、展示ブース見学、機能性野菜リーフレタスの試食
15:00《分 科 会》
テーマ1.技術開発、生産コスト削減
植物工場の多様なシステムとビジネス展開、最新技術とコストパフォーマンスについてのパネルディスカッション
〈パネリスト〉
エスペックミック株式会社 環境モニタリング事業部部長 中村謙治氏
日本アドバンストアグリ株式会社 代表取締役社長 辻 昭久氏
徳寿工業株式会社 常務取締役 坂谷英志郎氏
株式会社演算工房 代表取締役 林 稔氏
〈コーディネーター〉 加籐 悟氏
テーマ2.販路の拡大、新事業展開
販路拡大のポイント、植物工場を活用した地域活性化、新しいカテゴリーとしての植物工場産野菜の役割りなどについての
パネルディスカッション
〈パネリスト〉
ステラグリーン株式会社 専務取締役 野澤歸价氏
株式会社イズミヤ総研 代表取締役 清水正博氏
早稲田商店会 代表研究員 藤村望洋氏
鹿児島市宇宿商店街振興組合理事長 河井達志氏
日本経済新聞社(予定)
〈コーディネーター〉 高辻正基氏
16:40《総 合 討 議》
17:50終了
主 催 : アジア太平洋トレードセンター株式会社
参加料 : 無 料
お申し込み : 裏面をご覧のうえ、e-mailまたはFAXにて。
会 場 : メイン会場 ITMホール (ATCビルITM棟12F)
分科会会場 ATCグリーンエコプラザ内ビオトーププラザほか (ATCビルITM棟11F)
定 員 : 300名
お申し込み
下記にご記入の上、FAXでお申込下さい。(または、同内容を、E-mailでお送り下さい。)
FAX送付先: 06−6614−1801 E−mail:091217@e-being.jp



参考:セミナーレポート
アグリビジネスの成長戦略とその可能性
講師
株式会社日本総合研究所 総合研究部門
食・農基本戦略クラスタークラスター長 主任研究員 大澤信一氏
1.21世紀 食と環境ビジネスの可能性
本日は、日本の農業の全体像を概観し、アグリビジネスの課題を展望し成長戦略を考えるというテーマでお話をさせていただきます。
日本の農業は、粗生産額8.4兆円弱、その大半は、畜産、米、野菜、果実、花木です。各地域の特性にあわせたアグリビジネスの展開が基本であり、最終的には成長の鍵を握っていると言えるでしょう。
日本の農家の耕地面積は、津軽海峡を境として、北海道はEU平均よりも大きい約17haであるのに対し、本州の平均は約1.6haと、大きく差があります。それぞれ展開するアグリビジネスも別物として考える必要があるでしょう。
各地域の特徴としては、欧米型の大型農業の北海道、稲作中心の東北・北陸。そして首都圏の野菜の供給基地であり、産出額ベースで全国2位、3位を争う千葉と茨城からなる東関東。施設園芸は愛知、静岡、そして畜産は南九州が核となっています。また、近畿圏は、産出額は少ないものの、伝統野菜などもあり、食文化が優れています。アグリビジネスとしてはチャンスがあると言えるでしょう。・・・・・・・・
また日本は、食品ビジネスの海外展開が遅れています。今後、国内では高齢化が進み、ひとりあたりの食べる量が減っていくことが予想されることからも、各企業の積極的な海外展開が期待されます。また日本の農業技術は、世界でも非常に優れており、世界でマーケットを作るということも十分考えられるでしょう。
2.日本農業の概況
1980年代中ごろまでは、日本の農業産出額の割合は、米、畜産、野菜がほぼ25%ずつでした。BSE騒動以降、一時は牛肉の消費が落ちましたが、現在は、どこの牧場の肉であるかトレースができるようになり、さらに消費が拡大し、農林水産省による「平成17年農業産出額」によると、畜産が31%、米が21%、野菜が25%となっています。逆に米は、どんどん単価が下がっています。40年くらい前まで、日本では年間ひとり120kgほどの米の消費がありました。しかし米の輸入自由化、なおかつ日本人のライフスタイルも変わったことで米以外のものを食べる機会も多くなりました。政府は米の消費拡大をと言っていますが、もはや1年でひとり60kgくらいが限度でしょう。そんな中、個性的な米を作り、単価が下がらないようにする工夫も必要でないかと思います。
・・・・・・・・
農政改革の象徴として、農業への企業の新規参入の許可、農地の利用権を重視する農地法改革、それと農協改革の三つが挙げられます。しかし企業の参入は、現実的には細かい規制が残り難しい状況にあります。実質的な規制緩和、民間開放が必要です。農地法改革については所有権より利用権という形で工夫されており、あとは現場がどのように実施していくかというところまで来ていると思います。そして農業の構造改革として第2クールの2005年に打ち出された、“大規模化(品目横断的経営所得安定対策)”は、今、日本にある約290万の様々な規模の農家を、平成27年を目途に、約40万の大規模な農家に集約していくという計画です。しかし、現実的に、中小規模の250万の農家はどうするかという説明がわかりにくく、頓挫状態と言っても良い状況にあります。
3.アグリビジネスの課題と展望
アグリビジネスをとりまく環境は大きく変わっています。1990年代の構造変化から、21世紀にかけて、従来のキャッチアップ型から、新しい価値を作りマーケットを先導するという時代へ変わってきました。少子高齢化や消費者のライフスタイルの変化、ニーズの変化、また不況の影響などもありますが、では実際どうしたら良いかと言うと、経済の上でも、マーケティングの上でも、考え方を切り替えるのはなかなか難しいのが現状です。そんな中、すでに成功している直売所には、新しい時代にマッチしたアグリビジネスの色々なヒントがあるのではないかと考えています。・・・・
・・・・そのほかにも、農業は高齢化が進んでおり、直売所でも平均年齢75歳のところもあるなど、問題は山積みです。農業の課題として、先に述べたように、流通加工分野へ進出することも重要です。そのために、例えば企業を引退したノウハウある人材を仲間に入れるという方法もあると思います。このような問題を、5年10年の短いスパン、30年ほどの長いスパンで戦略を立て、解決していかなければなりません。
私個人としては、中小規模の農家は、特に直売所を上手く利用していくべきではないかと考えています。本日は直売所を中心に話をしましたが、農業の大規模化にもやはりチャンスがあると思います。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/210804/index.html
2009年11月14日
ATC中国環境ビジネスビジネスの成功に向けて
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会
アジア環境ビジネス研究部会(第3回)
中国環境ビジネスセミナー? 〜ビジネスの成功に向けて〜のご案内

環境ビジネスに限らず、中国でのビジネスの展開は、ますます注目を浴びております。世界経済をリードすべく立場の経済力を誇る中国ではありますが、国民性などの違いにより、実際のビジネス展開は紆余曲折しております。
今回のアジア環境ビジネス研究部会では、中国での環境ビジネスの問題点、実際のビジネスによる商習慣の違いなど、具体的な問題点を取り上げ、中国ビジネスのサクセスストーリーをシリーズ化してセミナーを開催し、講演終了後には懇親会において講師の先生方に参加して頂きますので、中国ビジネスにおける人脈作り及び中国ビジネスのトラブル解消の一環として、皆様のご参加をお待ちしております。
■開催日時■
2009年12月10日(木)
セミナー: 14:00 〜 16:30
交流会: 16:40 〜 18:00
■プログラム■
【講演1】中国の環境政策と環境ビジネス(14:05〜15:05
講師:福井県立大学名誉教授
(社)日中科学技術文化センター 理事長 凌 星光 氏
http://www.jcst.or.jp/
【講演2】山東省沿海地域の環境ビジネス(予定)(15:20〜16:20)
講師:ハルピン大学 教授
威海ハイテク産業開発区 副主任 王 政玉 氏
【交流会】 質疑応答・名詞交換は交流会会場で行います。(16:40〜18:00)
(会費3,000円/人)
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア環境ビジネス研究部会
水・土壌汚染研究部会 循環型社会ビジネス研究部会
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会
■受 講 料■
2000円/人
(但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、アジア環境ビジネス研究部会会員、
水・土壌汚染研究部会会員、循環型社会ビジネス研究部会会員は無料)
■会 場■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス ビオトープ・プラザ
(アジアトレードセンター ITM棟11F おおさかATCグリーンエコプラザ内)
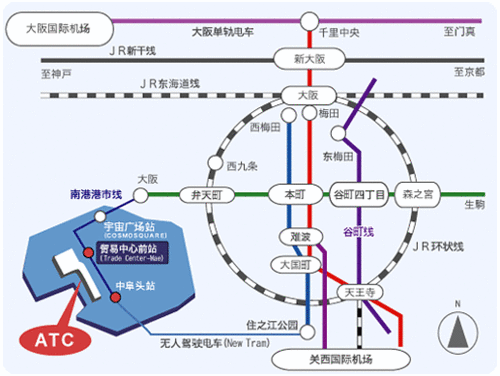
■定 員■
80名(先着順 ※受付確認はセミナー開催約10日前迄にFAXまたはE-mailでお送りします。)
■お申し込み■
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア研究部会セミナー係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:asia@e-being.jp
■交 流 会■
セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(3000 円/人)
おおさかATCグリーンエコプラザの中国語↓
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html
アジア太平洋トレードセンター株式会社↓
http://www.atc-estate.com/language/chinese/index.htm



ATCグリーンエコプラザセミナーレポート
エネルギー環境からみた日中協力の新たな可能性
講師
立命館大学 政策科学部 教授 周生
日中関係は、協力か、競争か、それとも対立か。エネルギー・環境分野においては、協力できることが多々あると考えています。今日は日中比較を通じて、エネルギー・環境分野における日中協力の可能性と課題について、私が把握している範囲でお話します。
産業革命と社会システムの変化
産業革命と社会システムの変化により、人類の歴史は三つの時代に分けることができます。まず、産業革命以前は、人間の生活活動や生産活動による環境に与える負荷が低く、人間が自然資源を採取する能力が低かった為、自然の力で循環できる社会を形成していました。これを「自然的循環型社会」といいます。しかし、18世紀末の第一次産業革命(石炭エネルギー,製鉄,鉄道など) 以来、第二次産業革命(19世紀末、プラスチックなどの新素材,石油,電気エネルギー,自動車,家電製品など )、第三次産業革命(20世紀末、近代産業社会、高度情報化社会、産業の情報化,電子化−デジタル革命など)を経て、技術革新が進み、我々人間が自然資源を採取する能力が飛躍的向上し、そして環境負荷が、遥かに自然の自浄能力を上回る状態となりました。その結果、資源の枯渇性問題や、公害などローカルな環境問題から地球温暖化などグローバルな環境問題まで顕在化してきたといえます。私はこれを「一方通行型社会」と呼んでおり、このような社会システムでは地球が持続不可能な状態になります。
そうなると、今後は自然の力では循環ができない、なんらかの人為的な力で循環させるという「人為的循環型社会」、いわゆる第四次産業革命がくるのではと思っています。
特にシンボルとなる技術としてIT,BT(バイオテクノロジー)、ET(エネルギー技術)、ET(環境回復・健康産業技術)、NT(ナノテクノロジー)という技術が挙げられ、その中でも、いかに資源・環境負荷を最小化するかという技術が、これからの社会で一番大きなポイントになるでしょう。これからの技術・産業は、循環型をキーワードとして対応していかなければいけないと考えます。すなわち、循環型技術システム、循環型産業システム、循環型経済システム、循環型社会システムの構築が求められています。
私達が色々な環境問題に直面しているのは、以下のような重要な3原則を犯しているという根本的な問題からです。
これらは人類文明が持続可能であるための最低限の必要条件です。
(1)再生可能な資源の消費量<再生力(現在の砂漠化、森林減少はこの原則を犯している典型)
(2)非再生可能な資源の消費量<再生可能資源の開発力(現在は全くこの原則を無視)
(3)汚染物質の排出量<環境の吸収力(自浄能力)(大気中CO2濃度の増大はこの原則を犯している典型)。
人為的に、技術やライフスタイルの変革によっていかに環境負荷を小さくしていくかが、今後の課題です。
中国が抱える問題
ご存知のように、中国の経済は、1980年代から、世界のほとんどの予想を裏切って、20年余りをかけて、年平均9%を超える高成長を続けてきました。この急成長による中国のエネルギー消費量の急増も世界を驚かせています。例えば、ここ5年間のエネルギー消費量の増加は、1981〜2000年の20年間の総量を超え、少なくとも国際機関や中国国内エネルギー研究機関の予測より10年早まりました。
さらに、中国は2000年のGDPを10年後に2倍、20年後に4倍に増やすという国家目標を発表しました。この目標は、21世紀の最初の20年間における年平均経済成長率を7%という高水準に維持することを意味しますが、この目標を達成するためには、経済活動を支えるエネルギーの安定供給が大前提となります。この膨大なエネルギー消費量をどこまで安定的に供給できるかの問題は、中国一国の問題のみならず、世界全体の経済発展とエネルギー安全保障にも大きなインパクトを与えるものなのです。
その象徴的な事例としては以下の三つを挙げることができます。
(1)深刻な電力不足
近年、電力の不足は中国全土特に沿岸地域において深刻な問題となっており、例えば2003年の電力使用量は1兆9000億kwh、発電設備容量は3億8000万kw。電力不足は2000万kwとなりました。徐々に改善はしていますが、長期的にみれば、再び大きな問題となる可能性は高いでしょう。
また、2010年に使用量が3兆5000億kwh、発電設備容量は6億7000万kw以上になります。2020年がそれぞれ4兆5000億kwhと9億5000万kwになり、03年の2倍余りになります。中国の電力需要は、世界の色々な機関が予測していますが、EIA(米エネルギー情報局)、IEA(国際エネルギー機関)などが発表していた値は全て大きくはずれています。実際のエネルギー消費量は予測値より10年も早まっています。
(2)原油輸入の急増
近年中国では環境制約等により自国の石炭消費を抑制する動きがある一方で、原油輸入が急増しており、エネルギー供給に関するリスクが高まっています。中国の石油消費量は2003年に2億6千万トンとなり、日本を抜きアメリカに次ぐ世界第2位となりました。中国統計局によると、2004年度の原油輸入量は1億2000万トン(2003年は9112万トン)に達しました。
また中国の石油輸入の中東依存度は50%(日本は85%)に達しています。その輸入先の大半は日本と同じく中東に依存しているので、いかに中国のエネルギー消費量を削減するかという点においては、日中両国に共通な利益があり、協力できるポテンシャルも非常に高いと考えています。中国の原油輸入拡大は世界の原油市況にも大きな影響を及ぼしそうであると同時に原油価格の値上がりによる自国経済への影響も大きいものと見られています。
(3)環境負荷の増大
中国には今、公害の発生や河川の渇水、国土の広い範囲での砂漠化など深刻な環境問題に見舞われています。その中、周辺諸国及び地球環境や気候変動にもっとも深刻な影響を及ぼしているのはともにエネルギーの消費から排出する二酸化硫黄(SO2)による酸性雨の広範囲発生及び二酸化炭素(CO2)の大量排出等が挙げられます。中国の場合、国民一人当たりでみた環境負荷は決して大きくありません。1人当たりのCO2排出量は世界平均値の半分以下にすぎません。
しかし、その大きな人口、急速な経済成長、石炭中心としたエネルギー消費構造のため、CO2排出量は急速に増加し、総量ではアメリカに次ぐ世界第2位となっています。この酸性雨越境汚染問題とCO2排出問題を解決するには、中国自身の努力はもちろんのこと、先進国とりわけ日本との協力は不可欠であると考えられます。
また中国が抱える大きな環境問題としては、水の問題があります。現在の中国の水問題は、足りない・汚い・危ないという3つの言葉で表すことができます。中国の水消費量は先進国と比較して非常に多い状態にあり、GDP1000ドルあたりの水消費量は日本の10倍に及ぶため、日本が節水技術を提供できれば大きなビジネスになるでしょう。
それ以外に、新たなビジネスとしては、CO2排出削減技術があり、中国はすでに136のCDMプロジェクトが動いています。
中国の取り組み
中国の第11次五ヵ年計画には二つの数値目標を掲げられました。ひとつは2010年のGDPを2000年の倍増、もう1つが省エネ目標、すなわち2010年のGDPあたりのエネルギー消費量を2006年時点の20%カットをする、ということです。実はこれは、かつてブッシュ政権が提示した、京都議定書の代替案と似たものなのです。エネルギー効率を上げるという国内での取り組みにおいて、結果として中国もCO2削減に取り組んでいると言えます。
中国の経済社会の特徴
中国を分析するときは、先進地域(一人あたりGDP2000米ドル以上)・中進地域(一人あたりGDP800米ドル〜2000米ドル)・後進地域(一人当たりGDP800米ドル未満)の三つの地域にわけると、地域ごとに特徴が表れます。国土面積4%・人口19%の先進地域(東部沿岸部)に、GDPの約3割と、対外貿易8割、外国産業の6割が集中しています。一方、人口が中国全土の約5割を占める中進地域(東北・華北など)は、GDPは約4割、対外貿易、外国産業は先進地域に次ぐ値となっています。最後に国土面積の72%を占める後進地域の人口は約3割を占めますがGDPは17%程度しかありません。
もうひとつのデータとして、中国には三大経済圏があります。ひとつは人口4億8千万人にのぼる都市部です。その規模は日米独三カ国人口のトータルに相当し、毎年10%の勢いで成長しています。それは広東省地域、上海市を中心とした長江デルタ地域、北京・天津を中心とする勃海湾地域です。
グローバルリサイクルシステム
今、私達の研究室では、リサイクルのあり方として、グローバルリサイクルシステムを提唱しています。リサイクルには小循環・中循環・大循環があります。できれば廃棄物を工場内で処分・リサイクルできればいいのですが、できない場合は隣接地域などの広域で行い、さらに国内で無理な場合は国境を越えて行うというものです。資源廃棄物を生かしてビジネスにする静脈産業、これは、資源・エネルギー効率の最大化(投入・排出の最小化)、事業者・消費者・行政のパートナーシップ(社会全体としての便益の最大化)、新たな産業技術体系の確立(循環型技術体系の確立)、環境関連産業の発展(新規産業フロンティアの開拓、企業の競争力強化)を中心とした広域循環型経済システムであると考えています。実際、今までも多くの資源廃棄物を輸出入している会社はあり、資源の最大限利用と廃棄物排出の最小化を目指すものとして、静脈産業としてこれからはまだ大きな発展を達成していくことと思います。
特に東北アジア地域は、世界で有数の流動性、多様性をもつ地域です。先進国の日本、そして北朝鮮や中国の僻地など最も貧しく遅れた地域が共存し、また韓国や上海など、人口、経済成長がめざましい地域もあります。このような富める国と貧しい国が隣り合って暮らす地域では、お互いが環境問題の重荷を共有し、その解決のため、地域間の協力が必要となります。互いにうまく協力できればWin-Winの関係になれると考えています。
中国で生まれた新しい言葉
近年、中国には新しい言葉が生まれているので、少しご紹介しておきます。
鄧小平氏が言った「小康社会(しょうかんしゃかい)」とは、衣食を確保できる最低限度の生活レベルと、豊かな生活との間のステップを指し、経済水準だけではなく、社会・教育・文化などを含んだ幅広い概念を含んでいます。そして江沢民時代に言われた「全面小康社会」は、鄧小平時代の効率一辺倒の政策により、国民生活は改善された反面、経済格差などの不均衡が生まれたことから、よりゆとりのある生活だけでなく、より平等的な所得分配をも意味して名づけられました。
そして、現在の「和諧社会」は、胡錦濤政権が定めた新しいスローガンで、和諧とは調和がとれているという意味です。都市と農村の発展の調和、地域の発展の調和、経済と社会の発展の調和、人と自然の調和ある発展、国内発展と対外開放の調和という5つの調和で構成されています。中国に戻ったときに、和諧社会のイメージとは何かを中国人に聞いてみると、皆わからないと答えます。しかし私は、社会制度・医療・保険・教育制度など色々な面で、日本にこの和諧社会のモデルがあると思っています。日本の社会制度をもっと研究すべきと考えられます。その他、韓国の農村建設なども大変良いモデルになると考えています。
中国のエコビジネス
中国におけるエコビジネスの市場は非常に膨大です。さきほど述べた水問題に加え、都市部の廃棄物問題など、さまざまな環境問題を抱えており、第11次5ヵ年計画(2006〜2010年)期間中、環境保全関連の投資総額は、1兆3千億元(約18兆円)となる見込みです。その重点事業としては、火力発電所の脱硫装置や廃棄物処分など、技術面では日本が大幅にリードしている分野となっているため、日中間の環境ビジネスのさらなる商機拡大の局面を迎えているといえます。
今までは脱硫により二割ほどコストがあがるため、多くの企業において脱硫装置はほとんど導入されていない状態でしたが、近年中国政府の規制も強化され、状況は徐々に改善されています。中国の市場においては、日本より効率が低くても、簡易で安価な脱硫装置を開発できれば大きな需要があると言えるでしょう。
もうひとつの大きな市場として、廃棄物の問題があります。中国は今、産業廃棄物の問題に直面したばかりです。これはローテクで解決できる問題なので、多くの事例をもつ日本が中国に協力することでぜひビジネスチャンスに変えていただきたいと思います。
また新ビジネスとして注目されているのは、大気ビジネス、酸性雨、公害物質に関するビジネスです。それに加え、中国の炭鉱ガスは潜在埋蔵量が多く、クリーンなエネルギーとして今後の開発が期待されています。
中国において申請受理したCDMプロジェクトの数は現在136で、風力、水力、炭鉱ガスの順に多くなっていますが、CO2削減の量でみるとHFC(代替フロン)がもっとも効果があります。しかし残念ながら、現在のところ省エネのCDMはほとんどありません。
そんな中、今、我々が推進しているのはCDMとESCOを合併するということです。CDMの利益はCO2へ、ESCOの利益は省エネへ換算されます。CDMをするときは省エネの利益を換算せず、ESCOを行うときは、CO2の利益を無視するため、これら両方の利益を組み合わせると省エネの利益は更に大きくなり、取り組む企業が増えるのではないかと考えています。
中国の省エネポテンシャル
中国の場合は省エネポテンシャルがたぶん非常に大きいと考えられています。GDP1000米ドルあたりで中国が消費するエネルギーは日本の約9.7倍(2004年ですが、しかしこれを購買力平価PPP換算すれば、およそ2倍程度の値となります。ですから中国の省エネのポテンシャルは、上限は日本の10倍、下限はその2倍程度だと思われます。また可能性としては、単位製品あたりの省エネ、またシステム的な省エネに効果があると思われます。我々の計算では、もし中国がGDPあたりの消費量を日本並みに達成できれば、エネルギー消費量を半減できることとなります。
今後の日中協力に向けて
今後、日中協力のためには二つの視点があります。まず中国におけるエコビジネスを考えるときには、経済活動のグローバル化の中で生産基地として成長する中国を通して、どのように日本が循環型経済社会の形成を推進できるか。そして二つ目には、日本の十倍以上と言われる中国の経済市場の中で、どのように環境に配慮して生産活動を行い、将来的に循環型経済社会の構築に貢献できるかの二点です。
中国等の発展途上国は、欧州諸国が産業革命以来200年余りをかけ、日本が100年余りをかけた工業化のステップを半世紀に満たない短期間に一挙に経験する道を歩んでいます。このため、経済の成熟した段階で徐々に環境問題に取組んできた先進国とはことなり、貧困問題、公害問題と地球環境問題の三方に同時に取り組まなければならない状態にあります。このため、途上国は「後発者利益」を十分に活かすのみならず、多様な経済発展レベルに応じた環境政策を組み込んだ新たな「持続可能な開発」モデルを考察しなければなりません。これを実現するためには、中国等の途上国自身における独自の技術開発と環境産業の育成が必要であることはいうまでもありませんが,世界各国との協力も必要としており,アジア最大の先進工業国である日本との協力はとりわけ重要です。
今後,中国のエネルギー需要と環境負荷の増大をなだらかなものとしていくためには,先進国が,持続可能な循環社会実現に向けたビジョン作りに協力し,その実現の為に経済的・技術的協力を併せて行っていくことも重要でしょう。
これらを配慮した上で、今後も日中での協力を進め、エコビジネスを推進していただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190105/index.html
アジアとの循環型社会の構築と環境ビジネス、環境・CSR経営
■講師
おおさかATCグリーンエコプラザ顧問 同志社大学 経済学部教授
郡嶌 孝氏
はじめに
ドイツの社会学者、ウルリッヒ・ベックは、今日の近代社会をリスク社会と呼んでいます。我々の社会は、現在、成功しているがゆえに新たな課題、リスクを生んでいます。今日は、私たちがこの新しい課題である環境危機に今後どう対応していくべきなのか、温暖化問題を含めてお話していきます。
21世紀の環境問題と各国の動き
危機という漢字は、“危”険と“機”会が組み合わさっています。まさに環境危機とは、日本においてはリスクを伴いながら、一方ではビジネスチャンスになったりするのが特徴であるかもしれません。
21世紀の環境問題は、廃棄物および温暖化の問題がとりわけ大きくなってきました。そんな中、先進国の取組みは、温暖化よりも廃棄物問題への取組みの方が少し早かったようです。
G8のサミットで初めて循環型社会について取り上げられたのは、2003年の、フランス、エビアンでのサミットです。エビアンでは循環型社会を実現する上での、先進国のマテリアルリサイクルについて話し合われました。その後、アメリカのシーアイランドでのサミットでは、小泉前総理の提唱により3Rイニシアチブが合意され、国際会議が行われるようになりました。
実はこれらの契機となったのは2002年のヨハネスブルグサミットです。1992年の地球サミットより10年が経過したこの年、持続可能な生産・開発を約束した「アジェンダ21」の進捗状況を確かめるとともに、次の「持続可能な生産・消費」に取り組む10年のフレームワークを策定することとなりました。
アジアとの循環型社会の構築
昨年、エコプラザ前館長と共に、大阪市と上海の環境問題対話のために上海に行ったのですが、アジアで環境ビジネスを行うのは難しいことがわかりました。中国にとって日本は、再生資源の原料輸入国としてしか位置づけられていないようです。対話の中で、環境用語は、ほぼドイツ語に占められていたことからも、すでにドイツとの環境ビジネスが進んでいることは明らかです。ここに入り込むのは、なかなか容易ではないでしょう。
では、当面、商売よりも日本の経験の中でどう環境と経済を両立するかということが重要となります。中国をはじめ、海外でも両立しなけれならないという意識はありますが、そのための技術や経験が不足しています。彼らが、技術・経験を身につけた後、開放的調整計画による協力関係が生まれると考えられます。しかしそのためには、まずトレーサビリティが最重要です。
現在、日本のマテリアルフローは、とりわけ静脈産業におけるフローの把握が非常に弱い状況にあります。例えばどのように資源が回収され、資源化され、どう使われているのか。消えた資源は廃棄されたのか、海外に輸出されたのか。廃棄自動車の例を挙げると、多くは海外に輸出されていることはわかっていますが、その後、部品として使われているのか、車のままなのか、海外で何が起こっているのか、トレーサビリティが全く把握できていません。家電についても同様です。
我々は環境の問題を“見える化”するためには、まずは数値化し、その実態をとらえられるようにしなければなりません。そしてグローバル化の中で循環経済圏を作ることはまだまだ難しい状態にありますが、日本の経験は必ず中国に役立つはずであり、必ずそこにビジネスチャンスはあると考えられます。
エコイノベーションとソーシャルイノベーション
また、エコイノベーションという面から言うと、今後は次第に製品を売ることから、機能やサービスを売るプロダクトサービスシステム(サービスサイジング)への変換が必要になってきます。
我々が3年前に地球環境戦略機関で研究を始めて以来、経済産業省でもサービスサイジング事業推進委員会が作られ、少しずつサービスサイジングの流れが生まれています。これを大きな流れにするべく、主要産業におけるサービスサイジングの促進を進めていかなければなりません。
これからは、まさに大企業の中で、サービスサイジングを動脈産業として変えていかねばなりません。
また環境ビジネスとしては、中間組織の支援をしながら、さらに市民社会における環境への取組みを進めていく必要があります。日本の強みを生かし、環境重視、人間重視の、技術革新・社会革新の実現こそが、経済産業省が描いている環境大国へのビジョンです。まさに我々はエコイノベーションと同時に、ソーシャルイノベーションも伴わなくてはいけません。
その中で、環境をどう価値化するか。皆が見えないCO2をどう見えるようにするかが非常に重要です。まずは環境問題を経済的な価値として見えるようにして、キャップをはめることが大事なのです。
たとえば社内では、部署ごとに排出権取引、環境税などで規制すれば良いでしょう。企業の中における評価を、売上高や経済価値だけでなく、環境の価値も“見える化”して評価対象にすれば、皆も取り組むようになるかもしれません。経験こそ重要な資産となるでしょう。
それぞれに何ができるか、環境と経済の両立の中で、今日お話された他の企業の皆さんのお話も参考にして取り組んでいただければ、これも、開放的調整政策のひとつといえるでしょう。どうもありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190801/index.html
?施理念
通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。
大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html
Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.
As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.
A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.
?施概要
名称 大阪?境??振?中心[大阪ATC?色?保广?]
?置方 大阪市 ?洲太平洋?易中心株式会社
主? 大阪?境??振?中心?行委?会
?大阪市
??洲太平洋?易中心株式会社
?日本???社
会? ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?
地址 大阪市住之江区南港北2丁目1-10
会?面? 4,500m2
???? 上午10?30分〜下午5?30分
休?日 星期一(星期六、日、?假日也?放)
?? 同志社大学 ??系教授 郡? 孝
后援 ????省 ?境省 大阪府
大阪工商会?所 ?西???合会 ?西??同友会
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/profile.html
Overview
Name Osaka Center for the Promotion of Eco Industry
(Osaka ATC Green Eco Plaza)
Founded by Osaka City Asia Pacific Trade Center Corporation
Sponsors Osaka Center for the Promotion of Eco Industry Organizing Committee
・ Osaka City
・ Asia Pacific Trade Center Corporation
・ Nikkei Inc.
Location 11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)
Address 2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City
Floor Space 4,500 m2
Hours 10:30 am to 5:30 pm
Closed Mondays (open Saturdays, Sundays, and national holidays)
Advisor Professor Takashi Gunjima, Faculty of Economics, Doshisha University
Support Ministry of Economy, Trade and Industry
Ministry of the Environment
Osaka Prefecture
Osaka Chamber of Commerce and Industry
Kansai Economic Federation (Keidanren)
Kansai Association of Corporate Executives
アジア環境ビジネス研究部会(第3回)
中国環境ビジネスセミナー? 〜ビジネスの成功に向けて〜のご案内

環境ビジネスに限らず、中国でのビジネスの展開は、ますます注目を浴びております。世界経済をリードすべく立場の経済力を誇る中国ではありますが、国民性などの違いにより、実際のビジネス展開は紆余曲折しております。
今回のアジア環境ビジネス研究部会では、中国での環境ビジネスの問題点、実際のビジネスによる商習慣の違いなど、具体的な問題点を取り上げ、中国ビジネスのサクセスストーリーをシリーズ化してセミナーを開催し、講演終了後には懇親会において講師の先生方に参加して頂きますので、中国ビジネスにおける人脈作り及び中国ビジネスのトラブル解消の一環として、皆様のご参加をお待ちしております。
■開催日時■
2009年12月10日(木)
セミナー: 14:00 〜 16:30
交流会: 16:40 〜 18:00
■プログラム■
【講演1】中国の環境政策と環境ビジネス(14:05〜15:05
講師:福井県立大学名誉教授
(社)日中科学技術文化センター 理事長 凌 星光 氏
http://www.jcst.or.jp/
【講演2】山東省沿海地域の環境ビジネス(予定)(15:20〜16:20)
講師:ハルピン大学 教授
威海ハイテク産業開発区 副主任 王 政玉 氏
【交流会】 質疑応答・名詞交換は交流会会場で行います。(16:40〜18:00)
(会費3,000円/人)
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア環境ビジネス研究部会
水・土壌汚染研究部会 循環型社会ビジネス研究部会
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会
■受 講 料■
2000円/人
(但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、アジア環境ビジネス研究部会会員、
水・土壌汚染研究部会会員、循環型社会ビジネス研究部会会員は無料)
■会 場■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス ビオトープ・プラザ
(アジアトレードセンター ITM棟11F おおさかATCグリーンエコプラザ内)
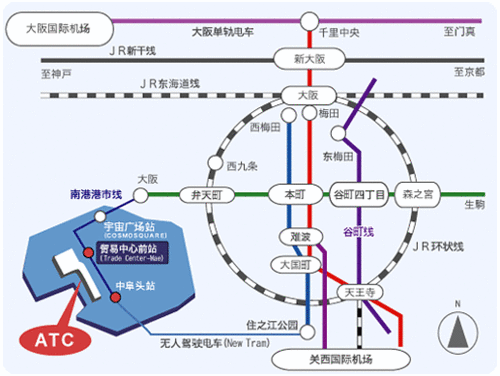
■定 員■
80名(先着順 ※受付確認はセミナー開催約10日前迄にFAXまたはE-mailでお送りします。)
■お申し込み■
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア研究部会セミナー係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:asia@e-being.jp
■交 流 会■
セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(3000 円/人)
おおさかATCグリーンエコプラザの中国語↓
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html
アジア太平洋トレードセンター株式会社↓
http://www.atc-estate.com/language/chinese/index.htm



ATCグリーンエコプラザセミナーレポート
エネルギー環境からみた日中協力の新たな可能性
講師
立命館大学 政策科学部 教授 周生
日中関係は、協力か、競争か、それとも対立か。エネルギー・環境分野においては、協力できることが多々あると考えています。今日は日中比較を通じて、エネルギー・環境分野における日中協力の可能性と課題について、私が把握している範囲でお話します。
産業革命と社会システムの変化
産業革命と社会システムの変化により、人類の歴史は三つの時代に分けることができます。まず、産業革命以前は、人間の生活活動や生産活動による環境に与える負荷が低く、人間が自然資源を採取する能力が低かった為、自然の力で循環できる社会を形成していました。これを「自然的循環型社会」といいます。しかし、18世紀末の第一次産業革命(石炭エネルギー,製鉄,鉄道など) 以来、第二次産業革命(19世紀末、プラスチックなどの新素材,石油,電気エネルギー,自動車,家電製品など )、第三次産業革命(20世紀末、近代産業社会、高度情報化社会、産業の情報化,電子化−デジタル革命など)を経て、技術革新が進み、我々人間が自然資源を採取する能力が飛躍的向上し、そして環境負荷が、遥かに自然の自浄能力を上回る状態となりました。その結果、資源の枯渇性問題や、公害などローカルな環境問題から地球温暖化などグローバルな環境問題まで顕在化してきたといえます。私はこれを「一方通行型社会」と呼んでおり、このような社会システムでは地球が持続不可能な状態になります。
そうなると、今後は自然の力では循環ができない、なんらかの人為的な力で循環させるという「人為的循環型社会」、いわゆる第四次産業革命がくるのではと思っています。
特にシンボルとなる技術としてIT,BT(バイオテクノロジー)、ET(エネルギー技術)、ET(環境回復・健康産業技術)、NT(ナノテクノロジー)という技術が挙げられ、その中でも、いかに資源・環境負荷を最小化するかという技術が、これからの社会で一番大きなポイントになるでしょう。これからの技術・産業は、循環型をキーワードとして対応していかなければいけないと考えます。すなわち、循環型技術システム、循環型産業システム、循環型経済システム、循環型社会システムの構築が求められています。
私達が色々な環境問題に直面しているのは、以下のような重要な3原則を犯しているという根本的な問題からです。
これらは人類文明が持続可能であるための最低限の必要条件です。
(1)再生可能な資源の消費量<再生力(現在の砂漠化、森林減少はこの原則を犯している典型)
(2)非再生可能な資源の消費量<再生可能資源の開発力(現在は全くこの原則を無視)
(3)汚染物質の排出量<環境の吸収力(自浄能力)(大気中CO2濃度の増大はこの原則を犯している典型)。
人為的に、技術やライフスタイルの変革によっていかに環境負荷を小さくしていくかが、今後の課題です。
中国が抱える問題
ご存知のように、中国の経済は、1980年代から、世界のほとんどの予想を裏切って、20年余りをかけて、年平均9%を超える高成長を続けてきました。この急成長による中国のエネルギー消費量の急増も世界を驚かせています。例えば、ここ5年間のエネルギー消費量の増加は、1981〜2000年の20年間の総量を超え、少なくとも国際機関や中国国内エネルギー研究機関の予測より10年早まりました。
さらに、中国は2000年のGDPを10年後に2倍、20年後に4倍に増やすという国家目標を発表しました。この目標は、21世紀の最初の20年間における年平均経済成長率を7%という高水準に維持することを意味しますが、この目標を達成するためには、経済活動を支えるエネルギーの安定供給が大前提となります。この膨大なエネルギー消費量をどこまで安定的に供給できるかの問題は、中国一国の問題のみならず、世界全体の経済発展とエネルギー安全保障にも大きなインパクトを与えるものなのです。
その象徴的な事例としては以下の三つを挙げることができます。
(1)深刻な電力不足
近年、電力の不足は中国全土特に沿岸地域において深刻な問題となっており、例えば2003年の電力使用量は1兆9000億kwh、発電設備容量は3億8000万kw。電力不足は2000万kwとなりました。徐々に改善はしていますが、長期的にみれば、再び大きな問題となる可能性は高いでしょう。
また、2010年に使用量が3兆5000億kwh、発電設備容量は6億7000万kw以上になります。2020年がそれぞれ4兆5000億kwhと9億5000万kwになり、03年の2倍余りになります。中国の電力需要は、世界の色々な機関が予測していますが、EIA(米エネルギー情報局)、IEA(国際エネルギー機関)などが発表していた値は全て大きくはずれています。実際のエネルギー消費量は予測値より10年も早まっています。
(2)原油輸入の急増
近年中国では環境制約等により自国の石炭消費を抑制する動きがある一方で、原油輸入が急増しており、エネルギー供給に関するリスクが高まっています。中国の石油消費量は2003年に2億6千万トンとなり、日本を抜きアメリカに次ぐ世界第2位となりました。中国統計局によると、2004年度の原油輸入量は1億2000万トン(2003年は9112万トン)に達しました。
また中国の石油輸入の中東依存度は50%(日本は85%)に達しています。その輸入先の大半は日本と同じく中東に依存しているので、いかに中国のエネルギー消費量を削減するかという点においては、日中両国に共通な利益があり、協力できるポテンシャルも非常に高いと考えています。中国の原油輸入拡大は世界の原油市況にも大きな影響を及ぼしそうであると同時に原油価格の値上がりによる自国経済への影響も大きいものと見られています。
(3)環境負荷の増大
中国には今、公害の発生や河川の渇水、国土の広い範囲での砂漠化など深刻な環境問題に見舞われています。その中、周辺諸国及び地球環境や気候変動にもっとも深刻な影響を及ぼしているのはともにエネルギーの消費から排出する二酸化硫黄(SO2)による酸性雨の広範囲発生及び二酸化炭素(CO2)の大量排出等が挙げられます。中国の場合、国民一人当たりでみた環境負荷は決して大きくありません。1人当たりのCO2排出量は世界平均値の半分以下にすぎません。
しかし、その大きな人口、急速な経済成長、石炭中心としたエネルギー消費構造のため、CO2排出量は急速に増加し、総量ではアメリカに次ぐ世界第2位となっています。この酸性雨越境汚染問題とCO2排出問題を解決するには、中国自身の努力はもちろんのこと、先進国とりわけ日本との協力は不可欠であると考えられます。
また中国が抱える大きな環境問題としては、水の問題があります。現在の中国の水問題は、足りない・汚い・危ないという3つの言葉で表すことができます。中国の水消費量は先進国と比較して非常に多い状態にあり、GDP1000ドルあたりの水消費量は日本の10倍に及ぶため、日本が節水技術を提供できれば大きなビジネスになるでしょう。
それ以外に、新たなビジネスとしては、CO2排出削減技術があり、中国はすでに136のCDMプロジェクトが動いています。
中国の取り組み
中国の第11次五ヵ年計画には二つの数値目標を掲げられました。ひとつは2010年のGDPを2000年の倍増、もう1つが省エネ目標、すなわち2010年のGDPあたりのエネルギー消費量を2006年時点の20%カットをする、ということです。実はこれは、かつてブッシュ政権が提示した、京都議定書の代替案と似たものなのです。エネルギー効率を上げるという国内での取り組みにおいて、結果として中国もCO2削減に取り組んでいると言えます。
中国の経済社会の特徴
中国を分析するときは、先進地域(一人あたりGDP2000米ドル以上)・中進地域(一人あたりGDP800米ドル〜2000米ドル)・後進地域(一人当たりGDP800米ドル未満)の三つの地域にわけると、地域ごとに特徴が表れます。国土面積4%・人口19%の先進地域(東部沿岸部)に、GDPの約3割と、対外貿易8割、外国産業の6割が集中しています。一方、人口が中国全土の約5割を占める中進地域(東北・華北など)は、GDPは約4割、対外貿易、外国産業は先進地域に次ぐ値となっています。最後に国土面積の72%を占める後進地域の人口は約3割を占めますがGDPは17%程度しかありません。
もうひとつのデータとして、中国には三大経済圏があります。ひとつは人口4億8千万人にのぼる都市部です。その規模は日米独三カ国人口のトータルに相当し、毎年10%の勢いで成長しています。それは広東省地域、上海市を中心とした長江デルタ地域、北京・天津を中心とする勃海湾地域です。
グローバルリサイクルシステム
今、私達の研究室では、リサイクルのあり方として、グローバルリサイクルシステムを提唱しています。リサイクルには小循環・中循環・大循環があります。できれば廃棄物を工場内で処分・リサイクルできればいいのですが、できない場合は隣接地域などの広域で行い、さらに国内で無理な場合は国境を越えて行うというものです。資源廃棄物を生かしてビジネスにする静脈産業、これは、資源・エネルギー効率の最大化(投入・排出の最小化)、事業者・消費者・行政のパートナーシップ(社会全体としての便益の最大化)、新たな産業技術体系の確立(循環型技術体系の確立)、環境関連産業の発展(新規産業フロンティアの開拓、企業の競争力強化)を中心とした広域循環型経済システムであると考えています。実際、今までも多くの資源廃棄物を輸出入している会社はあり、資源の最大限利用と廃棄物排出の最小化を目指すものとして、静脈産業としてこれからはまだ大きな発展を達成していくことと思います。
特に東北アジア地域は、世界で有数の流動性、多様性をもつ地域です。先進国の日本、そして北朝鮮や中国の僻地など最も貧しく遅れた地域が共存し、また韓国や上海など、人口、経済成長がめざましい地域もあります。このような富める国と貧しい国が隣り合って暮らす地域では、お互いが環境問題の重荷を共有し、その解決のため、地域間の協力が必要となります。互いにうまく協力できればWin-Winの関係になれると考えています。
中国で生まれた新しい言葉
近年、中国には新しい言葉が生まれているので、少しご紹介しておきます。
鄧小平氏が言った「小康社会(しょうかんしゃかい)」とは、衣食を確保できる最低限度の生活レベルと、豊かな生活との間のステップを指し、経済水準だけではなく、社会・教育・文化などを含んだ幅広い概念を含んでいます。そして江沢民時代に言われた「全面小康社会」は、鄧小平時代の効率一辺倒の政策により、国民生活は改善された反面、経済格差などの不均衡が生まれたことから、よりゆとりのある生活だけでなく、より平等的な所得分配をも意味して名づけられました。
そして、現在の「和諧社会」は、胡錦濤政権が定めた新しいスローガンで、和諧とは調和がとれているという意味です。都市と農村の発展の調和、地域の発展の調和、経済と社会の発展の調和、人と自然の調和ある発展、国内発展と対外開放の調和という5つの調和で構成されています。中国に戻ったときに、和諧社会のイメージとは何かを中国人に聞いてみると、皆わからないと答えます。しかし私は、社会制度・医療・保険・教育制度など色々な面で、日本にこの和諧社会のモデルがあると思っています。日本の社会制度をもっと研究すべきと考えられます。その他、韓国の農村建設なども大変良いモデルになると考えています。
中国のエコビジネス
中国におけるエコビジネスの市場は非常に膨大です。さきほど述べた水問題に加え、都市部の廃棄物問題など、さまざまな環境問題を抱えており、第11次5ヵ年計画(2006〜2010年)期間中、環境保全関連の投資総額は、1兆3千億元(約18兆円)となる見込みです。その重点事業としては、火力発電所の脱硫装置や廃棄物処分など、技術面では日本が大幅にリードしている分野となっているため、日中間の環境ビジネスのさらなる商機拡大の局面を迎えているといえます。
今までは脱硫により二割ほどコストがあがるため、多くの企業において脱硫装置はほとんど導入されていない状態でしたが、近年中国政府の規制も強化され、状況は徐々に改善されています。中国の市場においては、日本より効率が低くても、簡易で安価な脱硫装置を開発できれば大きな需要があると言えるでしょう。
もうひとつの大きな市場として、廃棄物の問題があります。中国は今、産業廃棄物の問題に直面したばかりです。これはローテクで解決できる問題なので、多くの事例をもつ日本が中国に協力することでぜひビジネスチャンスに変えていただきたいと思います。
また新ビジネスとして注目されているのは、大気ビジネス、酸性雨、公害物質に関するビジネスです。それに加え、中国の炭鉱ガスは潜在埋蔵量が多く、クリーンなエネルギーとして今後の開発が期待されています。
中国において申請受理したCDMプロジェクトの数は現在136で、風力、水力、炭鉱ガスの順に多くなっていますが、CO2削減の量でみるとHFC(代替フロン)がもっとも効果があります。しかし残念ながら、現在のところ省エネのCDMはほとんどありません。
そんな中、今、我々が推進しているのはCDMとESCOを合併するということです。CDMの利益はCO2へ、ESCOの利益は省エネへ換算されます。CDMをするときは省エネの利益を換算せず、ESCOを行うときは、CO2の利益を無視するため、これら両方の利益を組み合わせると省エネの利益は更に大きくなり、取り組む企業が増えるのではないかと考えています。
中国の省エネポテンシャル
中国の場合は省エネポテンシャルがたぶん非常に大きいと考えられています。GDP1000米ドルあたりで中国が消費するエネルギーは日本の約9.7倍(2004年ですが、しかしこれを購買力平価PPP換算すれば、およそ2倍程度の値となります。ですから中国の省エネのポテンシャルは、上限は日本の10倍、下限はその2倍程度だと思われます。また可能性としては、単位製品あたりの省エネ、またシステム的な省エネに効果があると思われます。我々の計算では、もし中国がGDPあたりの消費量を日本並みに達成できれば、エネルギー消費量を半減できることとなります。
今後の日中協力に向けて
今後、日中協力のためには二つの視点があります。まず中国におけるエコビジネスを考えるときには、経済活動のグローバル化の中で生産基地として成長する中国を通して、どのように日本が循環型経済社会の形成を推進できるか。そして二つ目には、日本の十倍以上と言われる中国の経済市場の中で、どのように環境に配慮して生産活動を行い、将来的に循環型経済社会の構築に貢献できるかの二点です。
中国等の発展途上国は、欧州諸国が産業革命以来200年余りをかけ、日本が100年余りをかけた工業化のステップを半世紀に満たない短期間に一挙に経験する道を歩んでいます。このため、経済の成熟した段階で徐々に環境問題に取組んできた先進国とはことなり、貧困問題、公害問題と地球環境問題の三方に同時に取り組まなければならない状態にあります。このため、途上国は「後発者利益」を十分に活かすのみならず、多様な経済発展レベルに応じた環境政策を組み込んだ新たな「持続可能な開発」モデルを考察しなければなりません。これを実現するためには、中国等の途上国自身における独自の技術開発と環境産業の育成が必要であることはいうまでもありませんが,世界各国との協力も必要としており,アジア最大の先進工業国である日本との協力はとりわけ重要です。
今後,中国のエネルギー需要と環境負荷の増大をなだらかなものとしていくためには,先進国が,持続可能な循環社会実現に向けたビジョン作りに協力し,その実現の為に経済的・技術的協力を併せて行っていくことも重要でしょう。
これらを配慮した上で、今後も日中での協力を進め、エコビジネスを推進していただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190105/index.html
アジアとの循環型社会の構築と環境ビジネス、環境・CSR経営
■講師
おおさかATCグリーンエコプラザ顧問 同志社大学 経済学部教授
郡嶌 孝氏
はじめに
ドイツの社会学者、ウルリッヒ・ベックは、今日の近代社会をリスク社会と呼んでいます。我々の社会は、現在、成功しているがゆえに新たな課題、リスクを生んでいます。今日は、私たちがこの新しい課題である環境危機に今後どう対応していくべきなのか、温暖化問題を含めてお話していきます。
21世紀の環境問題と各国の動き
危機という漢字は、“危”険と“機”会が組み合わさっています。まさに環境危機とは、日本においてはリスクを伴いながら、一方ではビジネスチャンスになったりするのが特徴であるかもしれません。
21世紀の環境問題は、廃棄物および温暖化の問題がとりわけ大きくなってきました。そんな中、先進国の取組みは、温暖化よりも廃棄物問題への取組みの方が少し早かったようです。
G8のサミットで初めて循環型社会について取り上げられたのは、2003年の、フランス、エビアンでのサミットです。エビアンでは循環型社会を実現する上での、先進国のマテリアルリサイクルについて話し合われました。その後、アメリカのシーアイランドでのサミットでは、小泉前総理の提唱により3Rイニシアチブが合意され、国際会議が行われるようになりました。
実はこれらの契機となったのは2002年のヨハネスブルグサミットです。1992年の地球サミットより10年が経過したこの年、持続可能な生産・開発を約束した「アジェンダ21」の進捗状況を確かめるとともに、次の「持続可能な生産・消費」に取り組む10年のフレームワークを策定することとなりました。
アジアとの循環型社会の構築
昨年、エコプラザ前館長と共に、大阪市と上海の環境問題対話のために上海に行ったのですが、アジアで環境ビジネスを行うのは難しいことがわかりました。中国にとって日本は、再生資源の原料輸入国としてしか位置づけられていないようです。対話の中で、環境用語は、ほぼドイツ語に占められていたことからも、すでにドイツとの環境ビジネスが進んでいることは明らかです。ここに入り込むのは、なかなか容易ではないでしょう。
では、当面、商売よりも日本の経験の中でどう環境と経済を両立するかということが重要となります。中国をはじめ、海外でも両立しなけれならないという意識はありますが、そのための技術や経験が不足しています。彼らが、技術・経験を身につけた後、開放的調整計画による協力関係が生まれると考えられます。しかしそのためには、まずトレーサビリティが最重要です。
現在、日本のマテリアルフローは、とりわけ静脈産業におけるフローの把握が非常に弱い状況にあります。例えばどのように資源が回収され、資源化され、どう使われているのか。消えた資源は廃棄されたのか、海外に輸出されたのか。廃棄自動車の例を挙げると、多くは海外に輸出されていることはわかっていますが、その後、部品として使われているのか、車のままなのか、海外で何が起こっているのか、トレーサビリティが全く把握できていません。家電についても同様です。
我々は環境の問題を“見える化”するためには、まずは数値化し、その実態をとらえられるようにしなければなりません。そしてグローバル化の中で循環経済圏を作ることはまだまだ難しい状態にありますが、日本の経験は必ず中国に役立つはずであり、必ずそこにビジネスチャンスはあると考えられます。
エコイノベーションとソーシャルイノベーション
また、エコイノベーションという面から言うと、今後は次第に製品を売ることから、機能やサービスを売るプロダクトサービスシステム(サービスサイジング)への変換が必要になってきます。
我々が3年前に地球環境戦略機関で研究を始めて以来、経済産業省でもサービスサイジング事業推進委員会が作られ、少しずつサービスサイジングの流れが生まれています。これを大きな流れにするべく、主要産業におけるサービスサイジングの促進を進めていかなければなりません。
これからは、まさに大企業の中で、サービスサイジングを動脈産業として変えていかねばなりません。
また環境ビジネスとしては、中間組織の支援をしながら、さらに市民社会における環境への取組みを進めていく必要があります。日本の強みを生かし、環境重視、人間重視の、技術革新・社会革新の実現こそが、経済産業省が描いている環境大国へのビジョンです。まさに我々はエコイノベーションと同時に、ソーシャルイノベーションも伴わなくてはいけません。
その中で、環境をどう価値化するか。皆が見えないCO2をどう見えるようにするかが非常に重要です。まずは環境問題を経済的な価値として見えるようにして、キャップをはめることが大事なのです。
たとえば社内では、部署ごとに排出権取引、環境税などで規制すれば良いでしょう。企業の中における評価を、売上高や経済価値だけでなく、環境の価値も“見える化”して評価対象にすれば、皆も取り組むようになるかもしれません。経験こそ重要な資産となるでしょう。
それぞれに何ができるか、環境と経済の両立の中で、今日お話された他の企業の皆さんのお話も参考にして取り組んでいただければ、これも、開放的調整政策のひとつといえるでしょう。どうもありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190801/index.html
?施理念
通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。
大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html
Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.
As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.
A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.
?施概要
名称 大阪?境??振?中心[大阪ATC?色?保广?]
?置方 大阪市 ?洲太平洋?易中心株式会社
主? 大阪?境??振?中心?行委?会
?大阪市
??洲太平洋?易中心株式会社
?日本???社
会? ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?
地址 大阪市住之江区南港北2丁目1-10
会?面? 4,500m2
???? 上午10?30分〜下午5?30分
休?日 星期一(星期六、日、?假日也?放)
?? 同志社大学 ??系教授 郡? 孝
后援 ????省 ?境省 大阪府
大阪工商会?所 ?西???合会 ?西??同友会
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/profile.html
Overview
Name Osaka Center for the Promotion of Eco Industry
(Osaka ATC Green Eco Plaza)
Founded by Osaka City Asia Pacific Trade Center Corporation
Sponsors Osaka Center for the Promotion of Eco Industry Organizing Committee
・ Osaka City
・ Asia Pacific Trade Center Corporation
・ Nikkei Inc.
Location 11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)
Address 2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City
Floor Space 4,500 m2
Hours 10:30 am to 5:30 pm
Closed Mondays (open Saturdays, Sundays, and national holidays)
Advisor Professor Takashi Gunjima, Faculty of Economics, Doshisha University
Support Ministry of Economy, Trade and Industry
Ministry of the Environment
Osaka Prefecture
Osaka Chamber of Commerce and Industry
Kansai Economic Federation (Keidanren)
Kansai Association of Corporate Executives