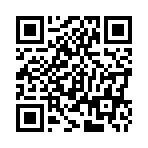2009年11月14日
ATC中国環境ビジネスビジネスの成功に向けて
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会
アジア環境ビジネス研究部会(第3回)
中国環境ビジネスセミナー? 〜ビジネスの成功に向けて〜のご案内

環境ビジネスに限らず、中国でのビジネスの展開は、ますます注目を浴びております。世界経済をリードすべく立場の経済力を誇る中国ではありますが、国民性などの違いにより、実際のビジネス展開は紆余曲折しております。
今回のアジア環境ビジネス研究部会では、中国での環境ビジネスの問題点、実際のビジネスによる商習慣の違いなど、具体的な問題点を取り上げ、中国ビジネスのサクセスストーリーをシリーズ化してセミナーを開催し、講演終了後には懇親会において講師の先生方に参加して頂きますので、中国ビジネスにおける人脈作り及び中国ビジネスのトラブル解消の一環として、皆様のご参加をお待ちしております。
■開催日時■
2009年12月10日(木)
セミナー: 14:00 〜 16:30
交流会: 16:40 〜 18:00
■プログラム■
【講演1】中国の環境政策と環境ビジネス(14:05〜15:05
講師:福井県立大学名誉教授
(社)日中科学技術文化センター 理事長 凌 星光 氏
http://www.jcst.or.jp/
【講演2】山東省沿海地域の環境ビジネス(予定)(15:20〜16:20)
講師:ハルピン大学 教授
威海ハイテク産業開発区 副主任 王 政玉 氏
【交流会】 質疑応答・名詞交換は交流会会場で行います。(16:40〜18:00)
(会費3,000円/人)
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア環境ビジネス研究部会
水・土壌汚染研究部会 循環型社会ビジネス研究部会
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会
■受 講 料■
2000円/人
(但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、アジア環境ビジネス研究部会会員、
水・土壌汚染研究部会会員、循環型社会ビジネス研究部会会員は無料)
■会 場■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス ビオトープ・プラザ
(アジアトレードセンター ITM棟11F おおさかATCグリーンエコプラザ内)
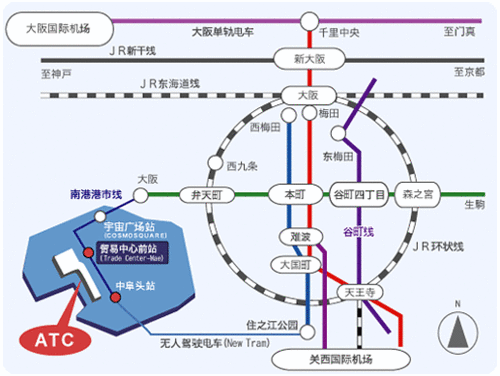
■定 員■
80名(先着順 ※受付確認はセミナー開催約10日前迄にFAXまたはE-mailでお送りします。)
■お申し込み■
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア研究部会セミナー係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:asia@e-being.jp
■交 流 会■
セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(3000 円/人)
おおさかATCグリーンエコプラザの中国語↓
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html
アジア太平洋トレードセンター株式会社↓
http://www.atc-estate.com/language/chinese/index.htm



ATCグリーンエコプラザセミナーレポート
エネルギー環境からみた日中協力の新たな可能性
講師
立命館大学 政策科学部 教授 周生
日中関係は、協力か、競争か、それとも対立か。エネルギー・環境分野においては、協力できることが多々あると考えています。今日は日中比較を通じて、エネルギー・環境分野における日中協力の可能性と課題について、私が把握している範囲でお話します。
産業革命と社会システムの変化
産業革命と社会システムの変化により、人類の歴史は三つの時代に分けることができます。まず、産業革命以前は、人間の生活活動や生産活動による環境に与える負荷が低く、人間が自然資源を採取する能力が低かった為、自然の力で循環できる社会を形成していました。これを「自然的循環型社会」といいます。しかし、18世紀末の第一次産業革命(石炭エネルギー,製鉄,鉄道など) 以来、第二次産業革命(19世紀末、プラスチックなどの新素材,石油,電気エネルギー,自動車,家電製品など )、第三次産業革命(20世紀末、近代産業社会、高度情報化社会、産業の情報化,電子化−デジタル革命など)を経て、技術革新が進み、我々人間が自然資源を採取する能力が飛躍的向上し、そして環境負荷が、遥かに自然の自浄能力を上回る状態となりました。その結果、資源の枯渇性問題や、公害などローカルな環境問題から地球温暖化などグローバルな環境問題まで顕在化してきたといえます。私はこれを「一方通行型社会」と呼んでおり、このような社会システムでは地球が持続不可能な状態になります。
そうなると、今後は自然の力では循環ができない、なんらかの人為的な力で循環させるという「人為的循環型社会」、いわゆる第四次産業革命がくるのではと思っています。
特にシンボルとなる技術としてIT,BT(バイオテクノロジー)、ET(エネルギー技術)、ET(環境回復・健康産業技術)、NT(ナノテクノロジー)という技術が挙げられ、その中でも、いかに資源・環境負荷を最小化するかという技術が、これからの社会で一番大きなポイントになるでしょう。これからの技術・産業は、循環型をキーワードとして対応していかなければいけないと考えます。すなわち、循環型技術システム、循環型産業システム、循環型経済システム、循環型社会システムの構築が求められています。
私達が色々な環境問題に直面しているのは、以下のような重要な3原則を犯しているという根本的な問題からです。
これらは人類文明が持続可能であるための最低限の必要条件です。
(1)再生可能な資源の消費量<再生力(現在の砂漠化、森林減少はこの原則を犯している典型)
(2)非再生可能な資源の消費量<再生可能資源の開発力(現在は全くこの原則を無視)
(3)汚染物質の排出量<環境の吸収力(自浄能力)(大気中CO2濃度の増大はこの原則を犯している典型)。
人為的に、技術やライフスタイルの変革によっていかに環境負荷を小さくしていくかが、今後の課題です。
中国が抱える問題
ご存知のように、中国の経済は、1980年代から、世界のほとんどの予想を裏切って、20年余りをかけて、年平均9%を超える高成長を続けてきました。この急成長による中国のエネルギー消費量の急増も世界を驚かせています。例えば、ここ5年間のエネルギー消費量の増加は、1981〜2000年の20年間の総量を超え、少なくとも国際機関や中国国内エネルギー研究機関の予測より10年早まりました。
さらに、中国は2000年のGDPを10年後に2倍、20年後に4倍に増やすという国家目標を発表しました。この目標は、21世紀の最初の20年間における年平均経済成長率を7%という高水準に維持することを意味しますが、この目標を達成するためには、経済活動を支えるエネルギーの安定供給が大前提となります。この膨大なエネルギー消費量をどこまで安定的に供給できるかの問題は、中国一国の問題のみならず、世界全体の経済発展とエネルギー安全保障にも大きなインパクトを与えるものなのです。
その象徴的な事例としては以下の三つを挙げることができます。
(1)深刻な電力不足
近年、電力の不足は中国全土特に沿岸地域において深刻な問題となっており、例えば2003年の電力使用量は1兆9000億kwh、発電設備容量は3億8000万kw。電力不足は2000万kwとなりました。徐々に改善はしていますが、長期的にみれば、再び大きな問題となる可能性は高いでしょう。
また、2010年に使用量が3兆5000億kwh、発電設備容量は6億7000万kw以上になります。2020年がそれぞれ4兆5000億kwhと9億5000万kwになり、03年の2倍余りになります。中国の電力需要は、世界の色々な機関が予測していますが、EIA(米エネルギー情報局)、IEA(国際エネルギー機関)などが発表していた値は全て大きくはずれています。実際のエネルギー消費量は予測値より10年も早まっています。
(2)原油輸入の急増
近年中国では環境制約等により自国の石炭消費を抑制する動きがある一方で、原油輸入が急増しており、エネルギー供給に関するリスクが高まっています。中国の石油消費量は2003年に2億6千万トンとなり、日本を抜きアメリカに次ぐ世界第2位となりました。中国統計局によると、2004年度の原油輸入量は1億2000万トン(2003年は9112万トン)に達しました。
また中国の石油輸入の中東依存度は50%(日本は85%)に達しています。その輸入先の大半は日本と同じく中東に依存しているので、いかに中国のエネルギー消費量を削減するかという点においては、日中両国に共通な利益があり、協力できるポテンシャルも非常に高いと考えています。中国の原油輸入拡大は世界の原油市況にも大きな影響を及ぼしそうであると同時に原油価格の値上がりによる自国経済への影響も大きいものと見られています。
(3)環境負荷の増大
中国には今、公害の発生や河川の渇水、国土の広い範囲での砂漠化など深刻な環境問題に見舞われています。その中、周辺諸国及び地球環境や気候変動にもっとも深刻な影響を及ぼしているのはともにエネルギーの消費から排出する二酸化硫黄(SO2)による酸性雨の広範囲発生及び二酸化炭素(CO2)の大量排出等が挙げられます。中国の場合、国民一人当たりでみた環境負荷は決して大きくありません。1人当たりのCO2排出量は世界平均値の半分以下にすぎません。
しかし、その大きな人口、急速な経済成長、石炭中心としたエネルギー消費構造のため、CO2排出量は急速に増加し、総量ではアメリカに次ぐ世界第2位となっています。この酸性雨越境汚染問題とCO2排出問題を解決するには、中国自身の努力はもちろんのこと、先進国とりわけ日本との協力は不可欠であると考えられます。
また中国が抱える大きな環境問題としては、水の問題があります。現在の中国の水問題は、足りない・汚い・危ないという3つの言葉で表すことができます。中国の水消費量は先進国と比較して非常に多い状態にあり、GDP1000ドルあたりの水消費量は日本の10倍に及ぶため、日本が節水技術を提供できれば大きなビジネスになるでしょう。
それ以外に、新たなビジネスとしては、CO2排出削減技術があり、中国はすでに136のCDMプロジェクトが動いています。
中国の取り組み
中国の第11次五ヵ年計画には二つの数値目標を掲げられました。ひとつは2010年のGDPを2000年の倍増、もう1つが省エネ目標、すなわち2010年のGDPあたりのエネルギー消費量を2006年時点の20%カットをする、ということです。実はこれは、かつてブッシュ政権が提示した、京都議定書の代替案と似たものなのです。エネルギー効率を上げるという国内での取り組みにおいて、結果として中国もCO2削減に取り組んでいると言えます。
中国の経済社会の特徴
中国を分析するときは、先進地域(一人あたりGDP2000米ドル以上)・中進地域(一人あたりGDP800米ドル〜2000米ドル)・後進地域(一人当たりGDP800米ドル未満)の三つの地域にわけると、地域ごとに特徴が表れます。国土面積4%・人口19%の先進地域(東部沿岸部)に、GDPの約3割と、対外貿易8割、外国産業の6割が集中しています。一方、人口が中国全土の約5割を占める中進地域(東北・華北など)は、GDPは約4割、対外貿易、外国産業は先進地域に次ぐ値となっています。最後に国土面積の72%を占める後進地域の人口は約3割を占めますがGDPは17%程度しかありません。
もうひとつのデータとして、中国には三大経済圏があります。ひとつは人口4億8千万人にのぼる都市部です。その規模は日米独三カ国人口のトータルに相当し、毎年10%の勢いで成長しています。それは広東省地域、上海市を中心とした長江デルタ地域、北京・天津を中心とする勃海湾地域です。
グローバルリサイクルシステム
今、私達の研究室では、リサイクルのあり方として、グローバルリサイクルシステムを提唱しています。リサイクルには小循環・中循環・大循環があります。できれば廃棄物を工場内で処分・リサイクルできればいいのですが、できない場合は隣接地域などの広域で行い、さらに国内で無理な場合は国境を越えて行うというものです。資源廃棄物を生かしてビジネスにする静脈産業、これは、資源・エネルギー効率の最大化(投入・排出の最小化)、事業者・消費者・行政のパートナーシップ(社会全体としての便益の最大化)、新たな産業技術体系の確立(循環型技術体系の確立)、環境関連産業の発展(新規産業フロンティアの開拓、企業の競争力強化)を中心とした広域循環型経済システムであると考えています。実際、今までも多くの資源廃棄物を輸出入している会社はあり、資源の最大限利用と廃棄物排出の最小化を目指すものとして、静脈産業としてこれからはまだ大きな発展を達成していくことと思います。
特に東北アジア地域は、世界で有数の流動性、多様性をもつ地域です。先進国の日本、そして北朝鮮や中国の僻地など最も貧しく遅れた地域が共存し、また韓国や上海など、人口、経済成長がめざましい地域もあります。このような富める国と貧しい国が隣り合って暮らす地域では、お互いが環境問題の重荷を共有し、その解決のため、地域間の協力が必要となります。互いにうまく協力できればWin-Winの関係になれると考えています。
中国で生まれた新しい言葉
近年、中国には新しい言葉が生まれているので、少しご紹介しておきます。
鄧小平氏が言った「小康社会(しょうかんしゃかい)」とは、衣食を確保できる最低限度の生活レベルと、豊かな生活との間のステップを指し、経済水準だけではなく、社会・教育・文化などを含んだ幅広い概念を含んでいます。そして江沢民時代に言われた「全面小康社会」は、鄧小平時代の効率一辺倒の政策により、国民生活は改善された反面、経済格差などの不均衡が生まれたことから、よりゆとりのある生活だけでなく、より平等的な所得分配をも意味して名づけられました。
そして、現在の「和諧社会」は、胡錦濤政権が定めた新しいスローガンで、和諧とは調和がとれているという意味です。都市と農村の発展の調和、地域の発展の調和、経済と社会の発展の調和、人と自然の調和ある発展、国内発展と対外開放の調和という5つの調和で構成されています。中国に戻ったときに、和諧社会のイメージとは何かを中国人に聞いてみると、皆わからないと答えます。しかし私は、社会制度・医療・保険・教育制度など色々な面で、日本にこの和諧社会のモデルがあると思っています。日本の社会制度をもっと研究すべきと考えられます。その他、韓国の農村建設なども大変良いモデルになると考えています。
中国のエコビジネス
中国におけるエコビジネスの市場は非常に膨大です。さきほど述べた水問題に加え、都市部の廃棄物問題など、さまざまな環境問題を抱えており、第11次5ヵ年計画(2006〜2010年)期間中、環境保全関連の投資総額は、1兆3千億元(約18兆円)となる見込みです。その重点事業としては、火力発電所の脱硫装置や廃棄物処分など、技術面では日本が大幅にリードしている分野となっているため、日中間の環境ビジネスのさらなる商機拡大の局面を迎えているといえます。
今までは脱硫により二割ほどコストがあがるため、多くの企業において脱硫装置はほとんど導入されていない状態でしたが、近年中国政府の規制も強化され、状況は徐々に改善されています。中国の市場においては、日本より効率が低くても、簡易で安価な脱硫装置を開発できれば大きな需要があると言えるでしょう。
もうひとつの大きな市場として、廃棄物の問題があります。中国は今、産業廃棄物の問題に直面したばかりです。これはローテクで解決できる問題なので、多くの事例をもつ日本が中国に協力することでぜひビジネスチャンスに変えていただきたいと思います。
また新ビジネスとして注目されているのは、大気ビジネス、酸性雨、公害物質に関するビジネスです。それに加え、中国の炭鉱ガスは潜在埋蔵量が多く、クリーンなエネルギーとして今後の開発が期待されています。
中国において申請受理したCDMプロジェクトの数は現在136で、風力、水力、炭鉱ガスの順に多くなっていますが、CO2削減の量でみるとHFC(代替フロン)がもっとも効果があります。しかし残念ながら、現在のところ省エネのCDMはほとんどありません。
そんな中、今、我々が推進しているのはCDMとESCOを合併するということです。CDMの利益はCO2へ、ESCOの利益は省エネへ換算されます。CDMをするときは省エネの利益を換算せず、ESCOを行うときは、CO2の利益を無視するため、これら両方の利益を組み合わせると省エネの利益は更に大きくなり、取り組む企業が増えるのではないかと考えています。
中国の省エネポテンシャル
中国の場合は省エネポテンシャルがたぶん非常に大きいと考えられています。GDP1000米ドルあたりで中国が消費するエネルギーは日本の約9.7倍(2004年ですが、しかしこれを購買力平価PPP換算すれば、およそ2倍程度の値となります。ですから中国の省エネのポテンシャルは、上限は日本の10倍、下限はその2倍程度だと思われます。また可能性としては、単位製品あたりの省エネ、またシステム的な省エネに効果があると思われます。我々の計算では、もし中国がGDPあたりの消費量を日本並みに達成できれば、エネルギー消費量を半減できることとなります。
今後の日中協力に向けて
今後、日中協力のためには二つの視点があります。まず中国におけるエコビジネスを考えるときには、経済活動のグローバル化の中で生産基地として成長する中国を通して、どのように日本が循環型経済社会の形成を推進できるか。そして二つ目には、日本の十倍以上と言われる中国の経済市場の中で、どのように環境に配慮して生産活動を行い、将来的に循環型経済社会の構築に貢献できるかの二点です。
中国等の発展途上国は、欧州諸国が産業革命以来200年余りをかけ、日本が100年余りをかけた工業化のステップを半世紀に満たない短期間に一挙に経験する道を歩んでいます。このため、経済の成熟した段階で徐々に環境問題に取組んできた先進国とはことなり、貧困問題、公害問題と地球環境問題の三方に同時に取り組まなければならない状態にあります。このため、途上国は「後発者利益」を十分に活かすのみならず、多様な経済発展レベルに応じた環境政策を組み込んだ新たな「持続可能な開発」モデルを考察しなければなりません。これを実現するためには、中国等の途上国自身における独自の技術開発と環境産業の育成が必要であることはいうまでもありませんが,世界各国との協力も必要としており,アジア最大の先進工業国である日本との協力はとりわけ重要です。
今後,中国のエネルギー需要と環境負荷の増大をなだらかなものとしていくためには,先進国が,持続可能な循環社会実現に向けたビジョン作りに協力し,その実現の為に経済的・技術的協力を併せて行っていくことも重要でしょう。
これらを配慮した上で、今後も日中での協力を進め、エコビジネスを推進していただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190105/index.html
アジアとの循環型社会の構築と環境ビジネス、環境・CSR経営
■講師
おおさかATCグリーンエコプラザ顧問 同志社大学 経済学部教授
郡嶌 孝氏
はじめに
ドイツの社会学者、ウルリッヒ・ベックは、今日の近代社会をリスク社会と呼んでいます。我々の社会は、現在、成功しているがゆえに新たな課題、リスクを生んでいます。今日は、私たちがこの新しい課題である環境危機に今後どう対応していくべきなのか、温暖化問題を含めてお話していきます。
21世紀の環境問題と各国の動き
危機という漢字は、“危”険と“機”会が組み合わさっています。まさに環境危機とは、日本においてはリスクを伴いながら、一方ではビジネスチャンスになったりするのが特徴であるかもしれません。
21世紀の環境問題は、廃棄物および温暖化の問題がとりわけ大きくなってきました。そんな中、先進国の取組みは、温暖化よりも廃棄物問題への取組みの方が少し早かったようです。
G8のサミットで初めて循環型社会について取り上げられたのは、2003年の、フランス、エビアンでのサミットです。エビアンでは循環型社会を実現する上での、先進国のマテリアルリサイクルについて話し合われました。その後、アメリカのシーアイランドでのサミットでは、小泉前総理の提唱により3Rイニシアチブが合意され、国際会議が行われるようになりました。
実はこれらの契機となったのは2002年のヨハネスブルグサミットです。1992年の地球サミットより10年が経過したこの年、持続可能な生産・開発を約束した「アジェンダ21」の進捗状況を確かめるとともに、次の「持続可能な生産・消費」に取り組む10年のフレームワークを策定することとなりました。
アジアとの循環型社会の構築
昨年、エコプラザ前館長と共に、大阪市と上海の環境問題対話のために上海に行ったのですが、アジアで環境ビジネスを行うのは難しいことがわかりました。中国にとって日本は、再生資源の原料輸入国としてしか位置づけられていないようです。対話の中で、環境用語は、ほぼドイツ語に占められていたことからも、すでにドイツとの環境ビジネスが進んでいることは明らかです。ここに入り込むのは、なかなか容易ではないでしょう。
では、当面、商売よりも日本の経験の中でどう環境と経済を両立するかということが重要となります。中国をはじめ、海外でも両立しなけれならないという意識はありますが、そのための技術や経験が不足しています。彼らが、技術・経験を身につけた後、開放的調整計画による協力関係が生まれると考えられます。しかしそのためには、まずトレーサビリティが最重要です。
現在、日本のマテリアルフローは、とりわけ静脈産業におけるフローの把握が非常に弱い状況にあります。例えばどのように資源が回収され、資源化され、どう使われているのか。消えた資源は廃棄されたのか、海外に輸出されたのか。廃棄自動車の例を挙げると、多くは海外に輸出されていることはわかっていますが、その後、部品として使われているのか、車のままなのか、海外で何が起こっているのか、トレーサビリティが全く把握できていません。家電についても同様です。
我々は環境の問題を“見える化”するためには、まずは数値化し、その実態をとらえられるようにしなければなりません。そしてグローバル化の中で循環経済圏を作ることはまだまだ難しい状態にありますが、日本の経験は必ず中国に役立つはずであり、必ずそこにビジネスチャンスはあると考えられます。
エコイノベーションとソーシャルイノベーション
また、エコイノベーションという面から言うと、今後は次第に製品を売ることから、機能やサービスを売るプロダクトサービスシステム(サービスサイジング)への変換が必要になってきます。
我々が3年前に地球環境戦略機関で研究を始めて以来、経済産業省でもサービスサイジング事業推進委員会が作られ、少しずつサービスサイジングの流れが生まれています。これを大きな流れにするべく、主要産業におけるサービスサイジングの促進を進めていかなければなりません。
これからは、まさに大企業の中で、サービスサイジングを動脈産業として変えていかねばなりません。
また環境ビジネスとしては、中間組織の支援をしながら、さらに市民社会における環境への取組みを進めていく必要があります。日本の強みを生かし、環境重視、人間重視の、技術革新・社会革新の実現こそが、経済産業省が描いている環境大国へのビジョンです。まさに我々はエコイノベーションと同時に、ソーシャルイノベーションも伴わなくてはいけません。
その中で、環境をどう価値化するか。皆が見えないCO2をどう見えるようにするかが非常に重要です。まずは環境問題を経済的な価値として見えるようにして、キャップをはめることが大事なのです。
たとえば社内では、部署ごとに排出権取引、環境税などで規制すれば良いでしょう。企業の中における評価を、売上高や経済価値だけでなく、環境の価値も“見える化”して評価対象にすれば、皆も取り組むようになるかもしれません。経験こそ重要な資産となるでしょう。
それぞれに何ができるか、環境と経済の両立の中で、今日お話された他の企業の皆さんのお話も参考にして取り組んでいただければ、これも、開放的調整政策のひとつといえるでしょう。どうもありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190801/index.html
?施理念
通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。
大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html
Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.
As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.
A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.
?施概要
名称 大阪?境??振?中心[大阪ATC?色?保广?]
?置方 大阪市 ?洲太平洋?易中心株式会社
主? 大阪?境??振?中心?行委?会
?大阪市
??洲太平洋?易中心株式会社
?日本???社
会? ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?
地址 大阪市住之江区南港北2丁目1-10
会?面? 4,500m2
???? 上午10?30分〜下午5?30分
休?日 星期一(星期六、日、?假日也?放)
?? 同志社大学 ??系教授 郡? 孝
后援 ????省 ?境省 大阪府
大阪工商会?所 ?西???合会 ?西??同友会
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/profile.html
Overview
Name Osaka Center for the Promotion of Eco Industry
(Osaka ATC Green Eco Plaza)
Founded by Osaka City Asia Pacific Trade Center Corporation
Sponsors Osaka Center for the Promotion of Eco Industry Organizing Committee
・ Osaka City
・ Asia Pacific Trade Center Corporation
・ Nikkei Inc.
Location 11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)
Address 2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City
Floor Space 4,500 m2
Hours 10:30 am to 5:30 pm
Closed Mondays (open Saturdays, Sundays, and national holidays)
Advisor Professor Takashi Gunjima, Faculty of Economics, Doshisha University
Support Ministry of Economy, Trade and Industry
Ministry of the Environment
Osaka Prefecture
Osaka Chamber of Commerce and Industry
Kansai Economic Federation (Keidanren)
Kansai Association of Corporate Executives
アジア環境ビジネス研究部会(第3回)
中国環境ビジネスセミナー? 〜ビジネスの成功に向けて〜のご案内

環境ビジネスに限らず、中国でのビジネスの展開は、ますます注目を浴びております。世界経済をリードすべく立場の経済力を誇る中国ではありますが、国民性などの違いにより、実際のビジネス展開は紆余曲折しております。
今回のアジア環境ビジネス研究部会では、中国での環境ビジネスの問題点、実際のビジネスによる商習慣の違いなど、具体的な問題点を取り上げ、中国ビジネスのサクセスストーリーをシリーズ化してセミナーを開催し、講演終了後には懇親会において講師の先生方に参加して頂きますので、中国ビジネスにおける人脈作り及び中国ビジネスのトラブル解消の一環として、皆様のご参加をお待ちしております。
■開催日時■
2009年12月10日(木)
セミナー: 14:00 〜 16:30
交流会: 16:40 〜 18:00
■プログラム■
【講演1】中国の環境政策と環境ビジネス(14:05〜15:05
講師:福井県立大学名誉教授
(社)日中科学技術文化センター 理事長 凌 星光 氏
http://www.jcst.or.jp/
【講演2】山東省沿海地域の環境ビジネス(予定)(15:20〜16:20)
講師:ハルピン大学 教授
威海ハイテク産業開発区 副主任 王 政玉 氏
【交流会】 質疑応答・名詞交換は交流会会場で行います。(16:40〜18:00)
(会費3,000円/人)
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア環境ビジネス研究部会
水・土壌汚染研究部会 循環型社会ビジネス研究部会
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会
■受 講 料■
2000円/人
(但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、アジア環境ビジネス研究部会会員、
水・土壌汚染研究部会会員、循環型社会ビジネス研究部会会員は無料)
■会 場■
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス ビオトープ・プラザ
(アジアトレードセンター ITM棟11F おおさかATCグリーンエコプラザ内)
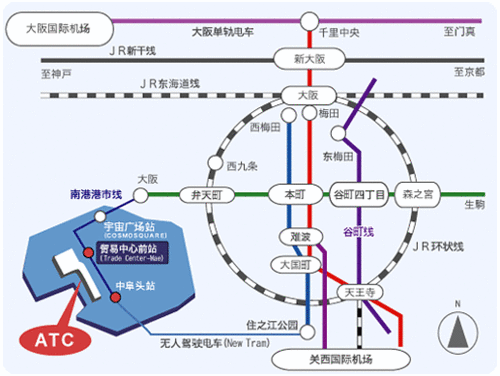
■定 員■
80名(先着順 ※受付確認はセミナー開催約10日前迄にFAXまたはE-mailでお送りします。)
■お申し込み■
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 アジア研究部会セミナー係
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801 E-mail:asia@e-being.jp
■交 流 会■
セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(3000 円/人)
おおさかATCグリーンエコプラザの中国語↓
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html
アジア太平洋トレードセンター株式会社↓
http://www.atc-estate.com/language/chinese/index.htm



ATCグリーンエコプラザセミナーレポート
エネルギー環境からみた日中協力の新たな可能性
講師
立命館大学 政策科学部 教授 周生
日中関係は、協力か、競争か、それとも対立か。エネルギー・環境分野においては、協力できることが多々あると考えています。今日は日中比較を通じて、エネルギー・環境分野における日中協力の可能性と課題について、私が把握している範囲でお話します。
産業革命と社会システムの変化
産業革命と社会システムの変化により、人類の歴史は三つの時代に分けることができます。まず、産業革命以前は、人間の生活活動や生産活動による環境に与える負荷が低く、人間が自然資源を採取する能力が低かった為、自然の力で循環できる社会を形成していました。これを「自然的循環型社会」といいます。しかし、18世紀末の第一次産業革命(石炭エネルギー,製鉄,鉄道など) 以来、第二次産業革命(19世紀末、プラスチックなどの新素材,石油,電気エネルギー,自動車,家電製品など )、第三次産業革命(20世紀末、近代産業社会、高度情報化社会、産業の情報化,電子化−デジタル革命など)を経て、技術革新が進み、我々人間が自然資源を採取する能力が飛躍的向上し、そして環境負荷が、遥かに自然の自浄能力を上回る状態となりました。その結果、資源の枯渇性問題や、公害などローカルな環境問題から地球温暖化などグローバルな環境問題まで顕在化してきたといえます。私はこれを「一方通行型社会」と呼んでおり、このような社会システムでは地球が持続不可能な状態になります。
そうなると、今後は自然の力では循環ができない、なんらかの人為的な力で循環させるという「人為的循環型社会」、いわゆる第四次産業革命がくるのではと思っています。
特にシンボルとなる技術としてIT,BT(バイオテクノロジー)、ET(エネルギー技術)、ET(環境回復・健康産業技術)、NT(ナノテクノロジー)という技術が挙げられ、その中でも、いかに資源・環境負荷を最小化するかという技術が、これからの社会で一番大きなポイントになるでしょう。これからの技術・産業は、循環型をキーワードとして対応していかなければいけないと考えます。すなわち、循環型技術システム、循環型産業システム、循環型経済システム、循環型社会システムの構築が求められています。
私達が色々な環境問題に直面しているのは、以下のような重要な3原則を犯しているという根本的な問題からです。
これらは人類文明が持続可能であるための最低限の必要条件です。
(1)再生可能な資源の消費量<再生力(現在の砂漠化、森林減少はこの原則を犯している典型)
(2)非再生可能な資源の消費量<再生可能資源の開発力(現在は全くこの原則を無視)
(3)汚染物質の排出量<環境の吸収力(自浄能力)(大気中CO2濃度の増大はこの原則を犯している典型)。
人為的に、技術やライフスタイルの変革によっていかに環境負荷を小さくしていくかが、今後の課題です。
中国が抱える問題
ご存知のように、中国の経済は、1980年代から、世界のほとんどの予想を裏切って、20年余りをかけて、年平均9%を超える高成長を続けてきました。この急成長による中国のエネルギー消費量の急増も世界を驚かせています。例えば、ここ5年間のエネルギー消費量の増加は、1981〜2000年の20年間の総量を超え、少なくとも国際機関や中国国内エネルギー研究機関の予測より10年早まりました。
さらに、中国は2000年のGDPを10年後に2倍、20年後に4倍に増やすという国家目標を発表しました。この目標は、21世紀の最初の20年間における年平均経済成長率を7%という高水準に維持することを意味しますが、この目標を達成するためには、経済活動を支えるエネルギーの安定供給が大前提となります。この膨大なエネルギー消費量をどこまで安定的に供給できるかの問題は、中国一国の問題のみならず、世界全体の経済発展とエネルギー安全保障にも大きなインパクトを与えるものなのです。
その象徴的な事例としては以下の三つを挙げることができます。
(1)深刻な電力不足
近年、電力の不足は中国全土特に沿岸地域において深刻な問題となっており、例えば2003年の電力使用量は1兆9000億kwh、発電設備容量は3億8000万kw。電力不足は2000万kwとなりました。徐々に改善はしていますが、長期的にみれば、再び大きな問題となる可能性は高いでしょう。
また、2010年に使用量が3兆5000億kwh、発電設備容量は6億7000万kw以上になります。2020年がそれぞれ4兆5000億kwhと9億5000万kwになり、03年の2倍余りになります。中国の電力需要は、世界の色々な機関が予測していますが、EIA(米エネルギー情報局)、IEA(国際エネルギー機関)などが発表していた値は全て大きくはずれています。実際のエネルギー消費量は予測値より10年も早まっています。
(2)原油輸入の急増
近年中国では環境制約等により自国の石炭消費を抑制する動きがある一方で、原油輸入が急増しており、エネルギー供給に関するリスクが高まっています。中国の石油消費量は2003年に2億6千万トンとなり、日本を抜きアメリカに次ぐ世界第2位となりました。中国統計局によると、2004年度の原油輸入量は1億2000万トン(2003年は9112万トン)に達しました。
また中国の石油輸入の中東依存度は50%(日本は85%)に達しています。その輸入先の大半は日本と同じく中東に依存しているので、いかに中国のエネルギー消費量を削減するかという点においては、日中両国に共通な利益があり、協力できるポテンシャルも非常に高いと考えています。中国の原油輸入拡大は世界の原油市況にも大きな影響を及ぼしそうであると同時に原油価格の値上がりによる自国経済への影響も大きいものと見られています。
(3)環境負荷の増大
中国には今、公害の発生や河川の渇水、国土の広い範囲での砂漠化など深刻な環境問題に見舞われています。その中、周辺諸国及び地球環境や気候変動にもっとも深刻な影響を及ぼしているのはともにエネルギーの消費から排出する二酸化硫黄(SO2)による酸性雨の広範囲発生及び二酸化炭素(CO2)の大量排出等が挙げられます。中国の場合、国民一人当たりでみた環境負荷は決して大きくありません。1人当たりのCO2排出量は世界平均値の半分以下にすぎません。
しかし、その大きな人口、急速な経済成長、石炭中心としたエネルギー消費構造のため、CO2排出量は急速に増加し、総量ではアメリカに次ぐ世界第2位となっています。この酸性雨越境汚染問題とCO2排出問題を解決するには、中国自身の努力はもちろんのこと、先進国とりわけ日本との協力は不可欠であると考えられます。
また中国が抱える大きな環境問題としては、水の問題があります。現在の中国の水問題は、足りない・汚い・危ないという3つの言葉で表すことができます。中国の水消費量は先進国と比較して非常に多い状態にあり、GDP1000ドルあたりの水消費量は日本の10倍に及ぶため、日本が節水技術を提供できれば大きなビジネスになるでしょう。
それ以外に、新たなビジネスとしては、CO2排出削減技術があり、中国はすでに136のCDMプロジェクトが動いています。
中国の取り組み
中国の第11次五ヵ年計画には二つの数値目標を掲げられました。ひとつは2010年のGDPを2000年の倍増、もう1つが省エネ目標、すなわち2010年のGDPあたりのエネルギー消費量を2006年時点の20%カットをする、ということです。実はこれは、かつてブッシュ政権が提示した、京都議定書の代替案と似たものなのです。エネルギー効率を上げるという国内での取り組みにおいて、結果として中国もCO2削減に取り組んでいると言えます。
中国の経済社会の特徴
中国を分析するときは、先進地域(一人あたりGDP2000米ドル以上)・中進地域(一人あたりGDP800米ドル〜2000米ドル)・後進地域(一人当たりGDP800米ドル未満)の三つの地域にわけると、地域ごとに特徴が表れます。国土面積4%・人口19%の先進地域(東部沿岸部)に、GDPの約3割と、対外貿易8割、外国産業の6割が集中しています。一方、人口が中国全土の約5割を占める中進地域(東北・華北など)は、GDPは約4割、対外貿易、外国産業は先進地域に次ぐ値となっています。最後に国土面積の72%を占める後進地域の人口は約3割を占めますがGDPは17%程度しかありません。
もうひとつのデータとして、中国には三大経済圏があります。ひとつは人口4億8千万人にのぼる都市部です。その規模は日米独三カ国人口のトータルに相当し、毎年10%の勢いで成長しています。それは広東省地域、上海市を中心とした長江デルタ地域、北京・天津を中心とする勃海湾地域です。
グローバルリサイクルシステム
今、私達の研究室では、リサイクルのあり方として、グローバルリサイクルシステムを提唱しています。リサイクルには小循環・中循環・大循環があります。できれば廃棄物を工場内で処分・リサイクルできればいいのですが、できない場合は隣接地域などの広域で行い、さらに国内で無理な場合は国境を越えて行うというものです。資源廃棄物を生かしてビジネスにする静脈産業、これは、資源・エネルギー効率の最大化(投入・排出の最小化)、事業者・消費者・行政のパートナーシップ(社会全体としての便益の最大化)、新たな産業技術体系の確立(循環型技術体系の確立)、環境関連産業の発展(新規産業フロンティアの開拓、企業の競争力強化)を中心とした広域循環型経済システムであると考えています。実際、今までも多くの資源廃棄物を輸出入している会社はあり、資源の最大限利用と廃棄物排出の最小化を目指すものとして、静脈産業としてこれからはまだ大きな発展を達成していくことと思います。
特に東北アジア地域は、世界で有数の流動性、多様性をもつ地域です。先進国の日本、そして北朝鮮や中国の僻地など最も貧しく遅れた地域が共存し、また韓国や上海など、人口、経済成長がめざましい地域もあります。このような富める国と貧しい国が隣り合って暮らす地域では、お互いが環境問題の重荷を共有し、その解決のため、地域間の協力が必要となります。互いにうまく協力できればWin-Winの関係になれると考えています。
中国で生まれた新しい言葉
近年、中国には新しい言葉が生まれているので、少しご紹介しておきます。
鄧小平氏が言った「小康社会(しょうかんしゃかい)」とは、衣食を確保できる最低限度の生活レベルと、豊かな生活との間のステップを指し、経済水準だけではなく、社会・教育・文化などを含んだ幅広い概念を含んでいます。そして江沢民時代に言われた「全面小康社会」は、鄧小平時代の効率一辺倒の政策により、国民生活は改善された反面、経済格差などの不均衡が生まれたことから、よりゆとりのある生活だけでなく、より平等的な所得分配をも意味して名づけられました。
そして、現在の「和諧社会」は、胡錦濤政権が定めた新しいスローガンで、和諧とは調和がとれているという意味です。都市と農村の発展の調和、地域の発展の調和、経済と社会の発展の調和、人と自然の調和ある発展、国内発展と対外開放の調和という5つの調和で構成されています。中国に戻ったときに、和諧社会のイメージとは何かを中国人に聞いてみると、皆わからないと答えます。しかし私は、社会制度・医療・保険・教育制度など色々な面で、日本にこの和諧社会のモデルがあると思っています。日本の社会制度をもっと研究すべきと考えられます。その他、韓国の農村建設なども大変良いモデルになると考えています。
中国のエコビジネス
中国におけるエコビジネスの市場は非常に膨大です。さきほど述べた水問題に加え、都市部の廃棄物問題など、さまざまな環境問題を抱えており、第11次5ヵ年計画(2006〜2010年)期間中、環境保全関連の投資総額は、1兆3千億元(約18兆円)となる見込みです。その重点事業としては、火力発電所の脱硫装置や廃棄物処分など、技術面では日本が大幅にリードしている分野となっているため、日中間の環境ビジネスのさらなる商機拡大の局面を迎えているといえます。
今までは脱硫により二割ほどコストがあがるため、多くの企業において脱硫装置はほとんど導入されていない状態でしたが、近年中国政府の規制も強化され、状況は徐々に改善されています。中国の市場においては、日本より効率が低くても、簡易で安価な脱硫装置を開発できれば大きな需要があると言えるでしょう。
もうひとつの大きな市場として、廃棄物の問題があります。中国は今、産業廃棄物の問題に直面したばかりです。これはローテクで解決できる問題なので、多くの事例をもつ日本が中国に協力することでぜひビジネスチャンスに変えていただきたいと思います。
また新ビジネスとして注目されているのは、大気ビジネス、酸性雨、公害物質に関するビジネスです。それに加え、中国の炭鉱ガスは潜在埋蔵量が多く、クリーンなエネルギーとして今後の開発が期待されています。
中国において申請受理したCDMプロジェクトの数は現在136で、風力、水力、炭鉱ガスの順に多くなっていますが、CO2削減の量でみるとHFC(代替フロン)がもっとも効果があります。しかし残念ながら、現在のところ省エネのCDMはほとんどありません。
そんな中、今、我々が推進しているのはCDMとESCOを合併するということです。CDMの利益はCO2へ、ESCOの利益は省エネへ換算されます。CDMをするときは省エネの利益を換算せず、ESCOを行うときは、CO2の利益を無視するため、これら両方の利益を組み合わせると省エネの利益は更に大きくなり、取り組む企業が増えるのではないかと考えています。
中国の省エネポテンシャル
中国の場合は省エネポテンシャルがたぶん非常に大きいと考えられています。GDP1000米ドルあたりで中国が消費するエネルギーは日本の約9.7倍(2004年ですが、しかしこれを購買力平価PPP換算すれば、およそ2倍程度の値となります。ですから中国の省エネのポテンシャルは、上限は日本の10倍、下限はその2倍程度だと思われます。また可能性としては、単位製品あたりの省エネ、またシステム的な省エネに効果があると思われます。我々の計算では、もし中国がGDPあたりの消費量を日本並みに達成できれば、エネルギー消費量を半減できることとなります。
今後の日中協力に向けて
今後、日中協力のためには二つの視点があります。まず中国におけるエコビジネスを考えるときには、経済活動のグローバル化の中で生産基地として成長する中国を通して、どのように日本が循環型経済社会の形成を推進できるか。そして二つ目には、日本の十倍以上と言われる中国の経済市場の中で、どのように環境に配慮して生産活動を行い、将来的に循環型経済社会の構築に貢献できるかの二点です。
中国等の発展途上国は、欧州諸国が産業革命以来200年余りをかけ、日本が100年余りをかけた工業化のステップを半世紀に満たない短期間に一挙に経験する道を歩んでいます。このため、経済の成熟した段階で徐々に環境問題に取組んできた先進国とはことなり、貧困問題、公害問題と地球環境問題の三方に同時に取り組まなければならない状態にあります。このため、途上国は「後発者利益」を十分に活かすのみならず、多様な経済発展レベルに応じた環境政策を組み込んだ新たな「持続可能な開発」モデルを考察しなければなりません。これを実現するためには、中国等の途上国自身における独自の技術開発と環境産業の育成が必要であることはいうまでもありませんが,世界各国との協力も必要としており,アジア最大の先進工業国である日本との協力はとりわけ重要です。
今後,中国のエネルギー需要と環境負荷の増大をなだらかなものとしていくためには,先進国が,持続可能な循環社会実現に向けたビジョン作りに協力し,その実現の為に経済的・技術的協力を併せて行っていくことも重要でしょう。
これらを配慮した上で、今後も日中での協力を進め、エコビジネスを推進していただければと思います。
ご清聴ありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190105/index.html
アジアとの循環型社会の構築と環境ビジネス、環境・CSR経営
■講師
おおさかATCグリーンエコプラザ顧問 同志社大学 経済学部教授
郡嶌 孝氏
はじめに
ドイツの社会学者、ウルリッヒ・ベックは、今日の近代社会をリスク社会と呼んでいます。我々の社会は、現在、成功しているがゆえに新たな課題、リスクを生んでいます。今日は、私たちがこの新しい課題である環境危機に今後どう対応していくべきなのか、温暖化問題を含めてお話していきます。
21世紀の環境問題と各国の動き
危機という漢字は、“危”険と“機”会が組み合わさっています。まさに環境危機とは、日本においてはリスクを伴いながら、一方ではビジネスチャンスになったりするのが特徴であるかもしれません。
21世紀の環境問題は、廃棄物および温暖化の問題がとりわけ大きくなってきました。そんな中、先進国の取組みは、温暖化よりも廃棄物問題への取組みの方が少し早かったようです。
G8のサミットで初めて循環型社会について取り上げられたのは、2003年の、フランス、エビアンでのサミットです。エビアンでは循環型社会を実現する上での、先進国のマテリアルリサイクルについて話し合われました。その後、アメリカのシーアイランドでのサミットでは、小泉前総理の提唱により3Rイニシアチブが合意され、国際会議が行われるようになりました。
実はこれらの契機となったのは2002年のヨハネスブルグサミットです。1992年の地球サミットより10年が経過したこの年、持続可能な生産・開発を約束した「アジェンダ21」の進捗状況を確かめるとともに、次の「持続可能な生産・消費」に取り組む10年のフレームワークを策定することとなりました。
アジアとの循環型社会の構築
昨年、エコプラザ前館長と共に、大阪市と上海の環境問題対話のために上海に行ったのですが、アジアで環境ビジネスを行うのは難しいことがわかりました。中国にとって日本は、再生資源の原料輸入国としてしか位置づけられていないようです。対話の中で、環境用語は、ほぼドイツ語に占められていたことからも、すでにドイツとの環境ビジネスが進んでいることは明らかです。ここに入り込むのは、なかなか容易ではないでしょう。
では、当面、商売よりも日本の経験の中でどう環境と経済を両立するかということが重要となります。中国をはじめ、海外でも両立しなけれならないという意識はありますが、そのための技術や経験が不足しています。彼らが、技術・経験を身につけた後、開放的調整計画による協力関係が生まれると考えられます。しかしそのためには、まずトレーサビリティが最重要です。
現在、日本のマテリアルフローは、とりわけ静脈産業におけるフローの把握が非常に弱い状況にあります。例えばどのように資源が回収され、資源化され、どう使われているのか。消えた資源は廃棄されたのか、海外に輸出されたのか。廃棄自動車の例を挙げると、多くは海外に輸出されていることはわかっていますが、その後、部品として使われているのか、車のままなのか、海外で何が起こっているのか、トレーサビリティが全く把握できていません。家電についても同様です。
我々は環境の問題を“見える化”するためには、まずは数値化し、その実態をとらえられるようにしなければなりません。そしてグローバル化の中で循環経済圏を作ることはまだまだ難しい状態にありますが、日本の経験は必ず中国に役立つはずであり、必ずそこにビジネスチャンスはあると考えられます。
エコイノベーションとソーシャルイノベーション
また、エコイノベーションという面から言うと、今後は次第に製品を売ることから、機能やサービスを売るプロダクトサービスシステム(サービスサイジング)への変換が必要になってきます。
我々が3年前に地球環境戦略機関で研究を始めて以来、経済産業省でもサービスサイジング事業推進委員会が作られ、少しずつサービスサイジングの流れが生まれています。これを大きな流れにするべく、主要産業におけるサービスサイジングの促進を進めていかなければなりません。
これからは、まさに大企業の中で、サービスサイジングを動脈産業として変えていかねばなりません。
また環境ビジネスとしては、中間組織の支援をしながら、さらに市民社会における環境への取組みを進めていく必要があります。日本の強みを生かし、環境重視、人間重視の、技術革新・社会革新の実現こそが、経済産業省が描いている環境大国へのビジョンです。まさに我々はエコイノベーションと同時に、ソーシャルイノベーションも伴わなくてはいけません。
その中で、環境をどう価値化するか。皆が見えないCO2をどう見えるようにするかが非常に重要です。まずは環境問題を経済的な価値として見えるようにして、キャップをはめることが大事なのです。
たとえば社内では、部署ごとに排出権取引、環境税などで規制すれば良いでしょう。企業の中における評価を、売上高や経済価値だけでなく、環境の価値も“見える化”して評価対象にすれば、皆も取り組むようになるかもしれません。経験こそ重要な資産となるでしょう。
それぞれに何ができるか、環境と経済の両立の中で、今日お話された他の企業の皆さんのお話も参考にして取り組んでいただければ、これも、開放的調整政策のひとつといえるでしょう。どうもありがとうございました。
http://www.ecoplaza.gr.jp/event/eco_seminar_report/report/190801/index.html
?施理念
通?培?和振??境商?,???更加美好的社会?献力量。
大气、水、噪音、?弃物、能源等与?境相?的各???正逐年?向??化,?于市民、企?和自治体而言是?尽快解决的??。大阪ATC?色?保广?正是在????境??的???得越来越重要的情况下?运而生的。其?立的目的是通?广泛地介?最新的?境商?,?求尚?于萌芽期的?境商?的活性化,??造循?型社会?献力量。ATC?年聚集900万人的市民,?日本首屈一指的集客?施,是作?大阪城市副中心而正在推?基??施建?的宇宙广?地区的中心?施。此外,以福利?主?的健康中心、??振?广?、?件??广?等?求新型??的培?与振?的基地也正在依次建?中。大阪ATC?色?保广?通??境商??解决?境???献力量,是大众的广?。以企??主,众多市民和自治体的共同思考和共同行?是必不可少的。我???大阪ATC?色?保广?将孕育市民、企?、行政??一体共同致力于?境??的理想的三角?系。
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/index.html
Osaka ATC Green Eco Plaza seeks to achieve a better society through the cultivation and promotion of eco-business.
As they grow more complex with each passing year, environmental problems involving the atmosphere, water, noise, waste products, and energy demand quick movement on solutions by citizens, corporations, and local government. Osaka ATC Green Eco Plaza was conceived in the recognition that dealing with environmental problems such as these is becoming an increasingly critical imperative. The Plaza was founded to contribute to the realization of a sustainable, recycling-based society while stimulating the development of nascent eco-businesses by introducing a broad selection of cutting-edge, ecologically responsible business opportunities and practices.
A leading attraction visited by some 9 million citizens every year, ATC is one of the anchor facilities in the Cosmo Square zone, which is being developed as a new subcenter of Osaka. A growing number of facilities devoted to cultivating and promoting new industries are springing up in Cosmo Square, including the social welfare-based ATC Ageless Center, Osaka Design Promotion Plaza, and Software Industry Plaza. Osaka ATC Green Eco Plaza is a gathering place for citizens who are committed to contributing to the resolution of environmental problems through the pursuit of eco-businesses. It was founded in recognition of the need for corporations, citizens, and local government to think and act together, and in the hope that these groups will come together to form an “ideal triangle” of activism in addressing the environmental challenges facing our society.
?施概要
名称 大阪?境??振?中心[大阪ATC?色?保广?]
?置方 大阪市 ?洲太平洋?易中心株式会社
主? 大阪?境??振?中心?行委?会
?大阪市
??洲太平洋?易中心株式会社
?日本???社
会? ATC[?洲太平洋?易中心]?ITM大厦11楼西?
地址 大阪市住之江区南港北2丁目1-10
会?面? 4,500m2
???? 上午10?30分〜下午5?30分
休?日 星期一(星期六、日、?假日也?放)
?? 同志社大学 ??系教授 郡? 孝
后援 ????省 ?境省 大阪府
大阪工商会?所 ?西???合会 ?西??同友会
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/profile.html
Overview
Name Osaka Center for the Promotion of Eco Industry
(Osaka ATC Green Eco Plaza)
Founded by Osaka City Asia Pacific Trade Center Corporation
Sponsors Osaka Center for the Promotion of Eco Industry Organizing Committee
・ Osaka City
・ Asia Pacific Trade Center Corporation
・ Nikkei Inc.
Location 11th Floor West, ITM Wing, ATC (Asia Pacific Trade Center)
Address 2-1-10 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City
Floor Space 4,500 m2
Hours 10:30 am to 5:30 pm
Closed Mondays (open Saturdays, Sundays, and national holidays)
Advisor Professor Takashi Gunjima, Faculty of Economics, Doshisha University
Support Ministry of Economy, Trade and Industry
Ministry of the Environment
Osaka Prefecture
Osaka Chamber of Commerce and Industry
Kansai Economic Federation (Keidanren)
Kansai Association of Corporate Executives
2009年11月14日
2009ATCグリーンエコプラザ環境ビジネスシーズ発表会
おおさかATCグリーンエコプラザ環境ビジネスシーズ発表会
開催日時
平成21年12月9日(水) 13:00−19:00
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、アジア太平洋トレードセンター株式会社、日本経済新聞社
協力
地方独立行政法人大阪市立工業研究所
場所
おおさかATCグリーンエコプラザ(ニュートラム「トレードセンター前」駅下車すぐ)
(大阪市住之江区南港北2丁目1−10 ATCビルITM棟11F)


プレゼンテーション一覧
分野NOテーマ研究者名(○は発表者)所属プレゼン時間
1 異形TiO2微粒子光触媒の調製法日置 亜也子大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部
2 Fe(III)酸化鉄を用いる環境中有機化合物浄化法の開発林 寛一○、中島 陽一太田 清久大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部三重大学大学院 工学研究科
3 ラジカル測定による光触媒の評価岩崎 和弥○林 寛一、日置 亜也子大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部
4 水溶液中の微量有害陰イオン種(As、Se,Cr、B)の吸着除去村山 憲弘関西大学 環境都市工学部 専任講師
5 森林におけるCO2交換量の評価植山 雅仁大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 助教
6 三価クロム系化成皮膜からのCr(V1)の溶出挙動中島 陽一○、林 寛一西村 崇大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部大阪府立産業技術総合研究所 機械金属部15:10-15:20
7 生分解性プラスチックの継続的使用による土壌環境への影響評価増井 昭彦○井川 聡、藤原 信明大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部平井 宏昭大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科
8 触媒の回収・再使用が容易な酸化反応を用いた化成品原料の合成中井 猛夫大阪市立工業研究所 有機材料研究部
9 植物ポリフェノールをもちいたタンパク質ゲルの開発山内 朝夫大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部
10 グリセリンを原料とするポリカーボネート合成水野 卓巳大阪市立工業研究所 有機材料研究部15:50-16:00
11 ラジカル反応を利用する新規分解性ポリマー材料の設計松本 章一大阪市立大学大学院 工学研究科 教授
パネルディスカッションにおける発表者のテーマ
12 バイオマスプラスチック・ポリ乳酸の軟質フイルムの開発酒井 清文○上利 泰幸大阪市立工業研究所 環境技術研究部大阪市立工業研究所 有機材料研究部
13 都市域における海陸一体型バイオマス有効利用システム大塚 耕司大阪府立大学大学院 工学研究科 教授
14 ヒートアイランド抑制のための都市表面温度低減技術と評価−保水性舗装の性能指標−西岡 真稔大阪市立大学大学院 工学研究科 教授
15 下水汚泥焼却灰のコンクリート材料としての有効利用鶴田 浩章関西大学 環境都市工学部 准教授
ポスター発表
16 都市を冷やす“日射照り返し抑制効果を持つ太陽熱高反射材の開発”酒井 英樹大阪市立大学大学院 生活科学研究科 講師
17 都市の熱さましのためのモリタリング技術鍋島 美奈子大阪市立大学大学院 工学研究科 講師
※当日、発表者のご都合により、代理の方によるプレゼンテーション、あるいは、ポスター資料のみのご提供になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
開催日時
平成21年12月9日(水) 13:00−19:00
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市、アジア太平洋トレードセンター株式会社、日本経済新聞社
協力
地方独立行政法人大阪市立工業研究所
場所
おおさかATCグリーンエコプラザ(ニュートラム「トレードセンター前」駅下車すぐ)
(大阪市住之江区南港北2丁目1−10 ATCビルITM棟11F)


プレゼンテーション一覧
分野NOテーマ研究者名(○は発表者)所属プレゼン時間
1 異形TiO2微粒子光触媒の調製法日置 亜也子大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部
2 Fe(III)酸化鉄を用いる環境中有機化合物浄化法の開発林 寛一○、中島 陽一太田 清久大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部三重大学大学院 工学研究科
3 ラジカル測定による光触媒の評価岩崎 和弥○林 寛一、日置 亜也子大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部
4 水溶液中の微量有害陰イオン種(As、Se,Cr、B)の吸着除去村山 憲弘関西大学 環境都市工学部 専任講師
5 森林におけるCO2交換量の評価植山 雅仁大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 助教
6 三価クロム系化成皮膜からのCr(V1)の溶出挙動中島 陽一○、林 寛一西村 崇大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部大阪府立産業技術総合研究所 機械金属部15:10-15:20
7 生分解性プラスチックの継続的使用による土壌環境への影響評価増井 昭彦○井川 聡、藤原 信明大阪府立産業技術総合研究所 化学環境部平井 宏昭大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科
8 触媒の回収・再使用が容易な酸化反応を用いた化成品原料の合成中井 猛夫大阪市立工業研究所 有機材料研究部
9 植物ポリフェノールをもちいたタンパク質ゲルの開発山内 朝夫大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部
10 グリセリンを原料とするポリカーボネート合成水野 卓巳大阪市立工業研究所 有機材料研究部15:50-16:00
11 ラジカル反応を利用する新規分解性ポリマー材料の設計松本 章一大阪市立大学大学院 工学研究科 教授
パネルディスカッションにおける発表者のテーマ
12 バイオマスプラスチック・ポリ乳酸の軟質フイルムの開発酒井 清文○上利 泰幸大阪市立工業研究所 環境技術研究部大阪市立工業研究所 有機材料研究部
13 都市域における海陸一体型バイオマス有効利用システム大塚 耕司大阪府立大学大学院 工学研究科 教授
14 ヒートアイランド抑制のための都市表面温度低減技術と評価−保水性舗装の性能指標−西岡 真稔大阪市立大学大学院 工学研究科 教授
15 下水汚泥焼却灰のコンクリート材料としての有効利用鶴田 浩章関西大学 環境都市工学部 准教授
ポスター発表
16 都市を冷やす“日射照り返し抑制効果を持つ太陽熱高反射材の開発”酒井 英樹大阪市立大学大学院 生活科学研究科 講師
17 都市の熱さましのためのモリタリング技術鍋島 美奈子大阪市立大学大学院 工学研究科 講師
※当日、発表者のご都合により、代理の方によるプレゼンテーション、あるいは、ポスター資料のみのご提供になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
2009年11月14日
水道水源の保全
水道水源の保全
水道事業体内容
仙台市水道局
● 水源かん養林の保全、育成
仙台市の水道専用ダム「青下ダム」の周辺及び上流域には、約86ha の水源かん養林があります。この水源かん養林を適切に保全・管理し、青下ダム周辺や上流域の良好な水源地の確保を図っています。
● 水源流域保全に関する協定の締結
水源流域内に設置された産業廃棄物処分場及びゴルフ場と「水源流域保全に関する協定」を締結し、これらの施設からの放流水の水質監視や、定期的な施設状況の調査などを行っています。
● 釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画への参画
釜房ダムでは、水源保全のため、「湖沼水質保全特別措置法」の指定に基づき、「釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画」を宮城県が策定し、国、県、川崎町などの関係機関が実施しています。仙台市水道局では、この計画に対して財政的な協力や、水質保全に対する各種調査・研究などに参画しています。
● 川崎町公共下水道整備に対する財政援助
生活排水などによる釜房ダムの水質汚濁を抑制するため、ダム上流域に位置している
川崎町の公共下水道整備事業に対して、財政支援を行っています。
● 水質保全に関する各種協議会への参画
「名取川水質汚濁防止連絡協議会」や「釜房ダム水質保全対策協議会」などに参加し、
国土交通省をはじめとする各関係機関と協力して、水質保全の対策を図っています。
● 水源流域の清掃活動
良好な水源流域を確保するため、市民の皆さまと水道局の職員が一体となって、ダム
周辺などの清掃活動を行っています。
出典)仙台市水道局ウェブサイト
http://www.suidou.city.sendai.jp/03_suisitu/03.html
山形市水道部水源涵養林は、水源地の周辺に位置し、保水や洪水緩和、さらには自然の自浄作用
による水質浄化など「緑のダム」とも呼ばれる重要な役割を果たしており、良質な水
源を将来に渡って確保していくために必要な森林です。山形市では、松原浄水場の水
源の一つとして、馬見ヶ崎川の上流にあり、蔵王連峰の北東部を源とする不動沢の流
域部に72.825ha の水源涵養林を所有して、計画的な整備と環境の保全を図っています。
平成8 年2 月に山形市水道部では、恒久的に安全でおいしい水を市民に供給するた
め、山形市水源涵養林経営計画書を策定し、樹種にあった施業や拡大を図り、本市自
らが厳正な管理、経営を行い、水資源保全に努めています。
具体的には、標高の低い箇所でのスギとケヤキ(落葉量が多く水源林に好適)の混交
林を、また、標高の高い箇所では、スギ、カラマツとブナ(水源林としては最適樹種)
の混交林の造成を実施しています。
出典)山形市水道部ウェブサイト
http://suidou.yamagata.yamagata.jp/suidou/kankyo/kanyo.html
宇都宮市上下水道局
○水源地域・流域地域との連携
水源であるダムや地下水の所在地域や、河川の流域地域と連携し水源水質の保全を図る。
出典)宇都宮市上下水道局ウェブサイト(第2 次宇都宮市上水道基本計画)
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/news/010617.html
さいたま市水道局
出典)さいたま市水道局ウェブサイト(さいたま市水道事業長期構想)
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1188536455432/index.html
東京都水道局(1)水道水源林の管理による水源水質の保全
東京都の水道水源林は、多摩川上流域の東西31km、南北20km に及んでいます。面積
は東京都区部の約35%に当たる21,630ha です。
東京都の水道水源林の管理は、明治34 年(1901 年)、東京府が多摩川水源地の森林
荒廃を原因とする洪水や渇水に対処するために森林管理を始めたのがその第一歩で、平
成13 年(2001 年)に100 周年を迎えました。
水源林の持つ様々な機能を維持・向上させ、小河内貯水池の水質保全や、安定した河
川流量の確保を図るため、水道局では計画的な管理を行っています。
出典)東京都水道局ウェブサイト(環境報告書平成19 年版)
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html
横浜市水道局
出典)横浜市水道局ウェブサイト(平成20 年版環境報告書)
http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/kyoku/torikumi/kankyo-hozen/kankyo-houkokusyo.html
横須賀市上下水道局
出典)横須賀市上下水道局ウェブサイト(平成18 年度環境レポート)
http://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/ir/index.html
川崎市水道局
出典)川崎市水道局ウェブサイト(平成19 年度決算版環境報告書)
http://www.city.kawasaki.jp/80/80syomu/home/manage/19k_houkoku.htm
神奈川県企業庁
出典)神奈川県企業庁ウェブサイト(環境報告書(平成19 年度決算版))
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/kankyo/index.htm
新潟市水道局水源保全に係るお客様の理解や意識の高揚を図るため、広報の充実やイベントの開催
などを行います。
また「信濃川・阿賀野川両水系水質協議会」、「信濃川水系水質汚濁対策連絡協議会」、
「阿賀野川水系水質汚濁対策連絡協議会」や上流域との連携を深め、水源水質の保全活
動を推進していきます。
【事業・取組み】
・信濃川・阿賀野川両水系水質協議会等との連携
・水源保全の啓発活動の実施
出典)新潟市水道局ウェブサイト(新潟市水道事業中長期経営計画)
http://www.city.niigata.jp/info/suido/somu/master_plan.htm
金沢市企業局水道水源である犀川ダム、内川ダムの水質保全のため、水源保全条例の制定、広報活
動の充実等に取り組み、関係機関とお客さまが一体となった水道水源の涵養を積極的に
進める。
【行動計画】
・水道水源の保全
・水源涵養林の整備
・水源調査や広報活動の充実等
出典)金沢市企業局ウェブサイト(金沢市企業局中長期基本計画(マスタープラン
2006))
http://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/web/about/about_public_02.html
浜松市上下水道部
出典)浜松市上下水道部ウェブサイト(浜松市上水道事業基本計画)
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/policy/suidou/index.htm
静岡市水道部
出典)静岡市水道部ウェブサイト(静岡市水道事業基本構想・基本計画)
http://www.city.shizuoka.jp/deps/suidosomu/basicplan.html
豊田市上下水道局
○水道業務上での負担軽減
ISO14001 により、燃料・紙の削減や資源の有効利用・再利用を進めます。
また、豊田水道水源保全基金を活用して水源の森を整備し、CO2 削減に寄与します。
お客様には、水道使用料のほか水量1? につき1 円をご負担いただいていることから、
CO2 削減に貢献し地球温暖化対策に参加していただいています。
出典)豊田市上下水道局ウェブサイト(豊田市水道ビジョン)
http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/ca00/ca03/tanto/suidouvision/index.html
大阪市水道局
出典)大阪市水道局ウェブサイト(平成19 年度版環境報告書)
http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html
豊中市上下水道局
○水源の保全
猪名川水系の利水団体や住民などと連携を図り、流域単位の水質監視を行っていきます。
出典)豊中市上下水道局ウェブサイト(豊中市水道事業長期基本計画)
http://www.tcct.zaq.ne.jp/toyonaka_suidou/06_annai/index.htm
吹田市水道部水源環境保全への取り組み
出典)吹田市水道部ウェブサイト(吹田市水道部中期経営計画)
http://www.city.suita.osaka.jp/kakuka/suido/suido/index.htm
高槻市水道部関係機関と連携し、水源涵養事業と環境保全に努めます。
出典)高槻市水道部ウェブサイト(高槻市水道事業基本計画)
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/suido/fr-jigyo_keikaku.html
枚方市水道局
○広域連携による環境保全の推進
水源である琵琶湖・淀川水系の河川の水質・環境を守るためには、日本水道協会をは
じめ、国、関係府県、周辺自治体及び水源管理者など関係団体との協力が不可欠であり、
連携を密にし、環境保全に係る取り組みを推進します。
出典)枚方市水道局ウェブサイト(枚方市水道ビジョン)
http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyousei/SUIDOU/work/bijyonsakutei.htm
神戸市水道局
出典)神戸市水道局ウェブサイト(神戸水道ビジョン2017)
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/51/01/2008/20080925.html
http://www.mhlw.go.jp/za/0723/c02/dl/c02-02-17.pdf
奈良市水道局
出典)奈良市水道局ウェブサイト(奈良市水道事業中長期計画)
http://www.h2o.nara.nara.jp/jigyo/vision.htm
岡山市水道局
出典)岡山市水道局ウェブサイト(岡山市水道事業総合基本計画(アクアプラン2007))
http://www.water.okayama.okayama.jp/jigyo/kadai1.htm
広島市水道局
広島市水道局ウェブサイト(環境会計(平成19 年度決算版))
http://www.water.city.hiroshima.jp/jigyo/kaikei/index.html
高松市水道局水源地のボランティア清掃(早明浦ダム・地元水源地各1 回/年)を継続実施します。
水道水源の水質保全の観点に立ち、全市的な水源保護条例の制定について検討します。
高松市水道局ウェブサイト(高松市水道事業基本計画(高松市水道ビジョン))
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/9433.html
北九州市水道局
北九州市水道局ウェブサイト(北九州市水道事業基本計画)
http://water-kitakyushu.icek.jp/suidou/menu06/keikaku.html
福岡市水道局
水源かん養林の整備
● 概要
水源のかん養機能を高め、水質保全を図る目的で、ダム周辺の森林を購入し整備しています。
● 環境保全効果
かん養林の光合成によって大気中のCO2 を吸収します。かん養林は緑のダムといわれ、その貯水能
力による水源かん養効果や、土砂流出防止効果があります。
空気揚水筒ダム設置
● 概要
ダムの貯留水をコンプレッサーでかくはんし、異臭の原因となる藻類の発生を抑制します。
● 環境保全効果
水道原水の水質向上により薬品の使用量が削減されるので、薬品製造時に発生するCO2 等の温室効
果ガスの排出を削減できます。
植樹祭等による植林
● 概要
水源地域や流域の人々との相互理解を深めるため、水源地域で開催される植樹祭等の行事に参加
しています。
● 環境保全効果
植樹祭等で植栽された樹木の光合成によりCO2 を吸収します。
上下流地域の相互理解と連携を深めるため、平成9年度に福岡市水道水源かん養事業基金を設置
し、事業を推進しています。
■ 福岡市水道水源かん養事業基金運営委員会
基金の使い方について協議するため、学識経験者や市民の参加を得て、運営委員会を設置してい
ます。
● 福岡都市圏流域連携基金負担金
福岡都市圏広域行政事業組合が設置する基金へ負担金を支出し、都市圏自治体と協力して都市圏
共通の水源地域への各種取り組みを行っています。
■ 水源の森基金等への参画
(財)福岡県水源の森基金及び(財)筑後川水源地域対策基金に参画し、水源地域への支援等を行っ
ています。
福岡市水道局ウェブサイト
http://www.city.fukuoka.lg.jp/suidou/index.html
熊本市水道局
熊本市水道局ウェブサイト(熊本市水道事業経営基本計画)
http://www.kumamoto-waterworks.jp/gaiyou/column.html?clmnno=638
大分市水道局
○水源の水質保全
森からのきれいな水が守られ、良質な飲み水となってお客さまのもとに届けられるよ
う、お客さまや流域で生活する人々と一緒になって森を育み、きれいな水を守る運動を
進めるなど、河川流域の住民や大分県・関係自治体など関係機関等との連携を図り、水
源水質の保全に向けた取組みを推進します。
大分市水道局ウェブサイト(大分市水道事業基本計画)
http://www.city.oita.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::27236
宮崎市上下水道局
宮崎市上下水道局ウェブサイト(水道事業経営計画)
http://www.suidou-miyazaki.jp/outline/keiei.html
水道事業体内容(地下水から表流水への転換)
茨城県保健福祉部生活衛生課水道整備グループ
限られた資源である地下水については,「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例」
の指定地域を中心に,地下水の保全とその適正な利用に努め,引き続き,地表水(受水
を含む)への転換を進めていく必要がある。
また,約39 万人の県民が自家用井戸等に依存しているが,飲用井戸水の水質検査の適
合率は30〜40%台と低いため,水道水への切り替えを促進する必要がある。
出典)茨城県保健福祉部生活衛生課水道整備グループウェブサイト(茨城県水道整備基本構想21)
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seiei/suido/01guide/0100.html
水道事業体内容(水質汚濁防止)
千葉県水道局
水質検査における廃液及び原水水質自動監視装置からの廃液の無害化
浄水場や水質センターでの水質検査や、取水場での原水水質自動監視装置では試薬とし
て薬品を使用します。その廃液は産業廃棄物として委託先の処理工場で無害化され、環境
に負荷を与えないように適切に廃棄されています。
出典)千葉県水道局ウェブサイト(平成19 年度環境報告書)
http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/zigyougaiyou/kankyoukaikei/houkokusho19.html
奈良県水道局
○水質汚濁等の防止
土砂・汚濁等の流入防止対策として、雨水調整池を設置することにより、土砂を沈殿
させ雨水を放流することにより、水道用地外に影響を与えないようにします。
出典)奈良県水道局ウェブサイト(環境会計平成18 年度決算)
http://www.pref.nara.jp/suido/
化学物質の適正管理(塩素・PCB 等)
水道事業体内容(化学物質の適正管理(塩素・PCB 等))東京都水道局
出典)東京都水道局ウェブサイト(環境報告書平成19 年版)
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html
その他環境保全
その他公害防止
1) 建設工事の環境対策・ガイドラインの作成
水道事業体内容(建設工事の環境対策・ガイドラインの作成)
札幌市水道局
出典)札幌市水道局ウェブサイト(平成20 年(2008 年)版環境報告書)
http://www.city.sapporo.jp/suido/c03/c03third/08_03_10.html
札幌市水道局
出典)札幌市水道局ウェブサイト(平成20 年(2008 年)版環境報告書)
http://www.city.sapporo.jp/suido/c03/c03third/08_03_10.html
東京都水道局
出典)東京都水道局ウェブサイト(環境報告書平成19 年版)
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html
神奈川県企業庁
○環境に配慮した公共工事の推進
企業庁では、計画、設計、積算、実施の各段階で「環境配慮チェックリスト」により
環境配慮項目の確認を行ない、環境に配慮した公共工事を推進するとともに、再生資源
(アスファルト合材など)を積極的に利用しています。
出典)神奈川県企業庁ウェブサイト(環境報告書(平成19 年度決算版))
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/kankyo/index.htm
浜松市上下水道部
出典)浜松市上下水道部ウェブサイト(浜松市上水道事業基本計画)
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/policy/suidou/index.htm
大阪市水道局
出典)大阪市水道局ウェブサイト(平成19 年度版環境報告書)
http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html
東大阪市上下水道局
出典)東大阪市上下水道局ウェブサイト
http://www.suidou.city.higashiosaka.osaka.jp/topics/iso/index.html
水道事業体内容
仙台市水道局
● 水源かん養林の保全、育成
仙台市の水道専用ダム「青下ダム」の周辺及び上流域には、約86ha の水源かん養林があります。この水源かん養林を適切に保全・管理し、青下ダム周辺や上流域の良好な水源地の確保を図っています。
● 水源流域保全に関する協定の締結
水源流域内に設置された産業廃棄物処分場及びゴルフ場と「水源流域保全に関する協定」を締結し、これらの施設からの放流水の水質監視や、定期的な施設状況の調査などを行っています。
● 釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画への参画
釜房ダムでは、水源保全のため、「湖沼水質保全特別措置法」の指定に基づき、「釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画」を宮城県が策定し、国、県、川崎町などの関係機関が実施しています。仙台市水道局では、この計画に対して財政的な協力や、水質保全に対する各種調査・研究などに参画しています。
● 川崎町公共下水道整備に対する財政援助
生活排水などによる釜房ダムの水質汚濁を抑制するため、ダム上流域に位置している
川崎町の公共下水道整備事業に対して、財政支援を行っています。
● 水質保全に関する各種協議会への参画
「名取川水質汚濁防止連絡協議会」や「釜房ダム水質保全対策協議会」などに参加し、
国土交通省をはじめとする各関係機関と協力して、水質保全の対策を図っています。
● 水源流域の清掃活動
良好な水源流域を確保するため、市民の皆さまと水道局の職員が一体となって、ダム
周辺などの清掃活動を行っています。
出典)仙台市水道局ウェブサイト
http://www.suidou.city.sendai.jp/03_suisitu/03.html
山形市水道部水源涵養林は、水源地の周辺に位置し、保水や洪水緩和、さらには自然の自浄作用
による水質浄化など「緑のダム」とも呼ばれる重要な役割を果たしており、良質な水
源を将来に渡って確保していくために必要な森林です。山形市では、松原浄水場の水
源の一つとして、馬見ヶ崎川の上流にあり、蔵王連峰の北東部を源とする不動沢の流
域部に72.825ha の水源涵養林を所有して、計画的な整備と環境の保全を図っています。
平成8 年2 月に山形市水道部では、恒久的に安全でおいしい水を市民に供給するた
め、山形市水源涵養林経営計画書を策定し、樹種にあった施業や拡大を図り、本市自
らが厳正な管理、経営を行い、水資源保全に努めています。
具体的には、標高の低い箇所でのスギとケヤキ(落葉量が多く水源林に好適)の混交
林を、また、標高の高い箇所では、スギ、カラマツとブナ(水源林としては最適樹種)
の混交林の造成を実施しています。
出典)山形市水道部ウェブサイト
http://suidou.yamagata.yamagata.jp/suidou/kankyo/kanyo.html
宇都宮市上下水道局
○水源地域・流域地域との連携
水源であるダムや地下水の所在地域や、河川の流域地域と連携し水源水質の保全を図る。
出典)宇都宮市上下水道局ウェブサイト(第2 次宇都宮市上水道基本計画)
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/news/010617.html
さいたま市水道局
出典)さいたま市水道局ウェブサイト(さいたま市水道事業長期構想)
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1188536455432/index.html
東京都水道局(1)水道水源林の管理による水源水質の保全
東京都の水道水源林は、多摩川上流域の東西31km、南北20km に及んでいます。面積
は東京都区部の約35%に当たる21,630ha です。
東京都の水道水源林の管理は、明治34 年(1901 年)、東京府が多摩川水源地の森林
荒廃を原因とする洪水や渇水に対処するために森林管理を始めたのがその第一歩で、平
成13 年(2001 年)に100 周年を迎えました。
水源林の持つ様々な機能を維持・向上させ、小河内貯水池の水質保全や、安定した河
川流量の確保を図るため、水道局では計画的な管理を行っています。
出典)東京都水道局ウェブサイト(環境報告書平成19 年版)
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html
横浜市水道局
出典)横浜市水道局ウェブサイト(平成20 年版環境報告書)
http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/kyoku/torikumi/kankyo-hozen/kankyo-houkokusyo.html
横須賀市上下水道局
出典)横須賀市上下水道局ウェブサイト(平成18 年度環境レポート)
http://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/ir/index.html
川崎市水道局
出典)川崎市水道局ウェブサイト(平成19 年度決算版環境報告書)
http://www.city.kawasaki.jp/80/80syomu/home/manage/19k_houkoku.htm
神奈川県企業庁
出典)神奈川県企業庁ウェブサイト(環境報告書(平成19 年度決算版))
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/kankyo/index.htm
新潟市水道局水源保全に係るお客様の理解や意識の高揚を図るため、広報の充実やイベントの開催
などを行います。
また「信濃川・阿賀野川両水系水質協議会」、「信濃川水系水質汚濁対策連絡協議会」、
「阿賀野川水系水質汚濁対策連絡協議会」や上流域との連携を深め、水源水質の保全活
動を推進していきます。
【事業・取組み】
・信濃川・阿賀野川両水系水質協議会等との連携
・水源保全の啓発活動の実施
出典)新潟市水道局ウェブサイト(新潟市水道事業中長期経営計画)
http://www.city.niigata.jp/info/suido/somu/master_plan.htm
金沢市企業局水道水源である犀川ダム、内川ダムの水質保全のため、水源保全条例の制定、広報活
動の充実等に取り組み、関係機関とお客さまが一体となった水道水源の涵養を積極的に
進める。
【行動計画】
・水道水源の保全
・水源涵養林の整備
・水源調査や広報活動の充実等
出典)金沢市企業局ウェブサイト(金沢市企業局中長期基本計画(マスタープラン
2006))
http://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/web/about/about_public_02.html
浜松市上下水道部
出典)浜松市上下水道部ウェブサイト(浜松市上水道事業基本計画)
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/policy/suidou/index.htm
静岡市水道部
出典)静岡市水道部ウェブサイト(静岡市水道事業基本構想・基本計画)
http://www.city.shizuoka.jp/deps/suidosomu/basicplan.html
豊田市上下水道局
○水道業務上での負担軽減
ISO14001 により、燃料・紙の削減や資源の有効利用・再利用を進めます。
また、豊田水道水源保全基金を活用して水源の森を整備し、CO2 削減に寄与します。
お客様には、水道使用料のほか水量1? につき1 円をご負担いただいていることから、
CO2 削減に貢献し地球温暖化対策に参加していただいています。
出典)豊田市上下水道局ウェブサイト(豊田市水道ビジョン)
http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/ca00/ca03/tanto/suidouvision/index.html
大阪市水道局
出典)大阪市水道局ウェブサイト(平成19 年度版環境報告書)
http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html
豊中市上下水道局
○水源の保全
猪名川水系の利水団体や住民などと連携を図り、流域単位の水質監視を行っていきます。
出典)豊中市上下水道局ウェブサイト(豊中市水道事業長期基本計画)
http://www.tcct.zaq.ne.jp/toyonaka_suidou/06_annai/index.htm
吹田市水道部水源環境保全への取り組み
出典)吹田市水道部ウェブサイト(吹田市水道部中期経営計画)
http://www.city.suita.osaka.jp/kakuka/suido/suido/index.htm
高槻市水道部関係機関と連携し、水源涵養事業と環境保全に努めます。
出典)高槻市水道部ウェブサイト(高槻市水道事業基本計画)
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/suido/fr-jigyo_keikaku.html
枚方市水道局
○広域連携による環境保全の推進
水源である琵琶湖・淀川水系の河川の水質・環境を守るためには、日本水道協会をは
じめ、国、関係府県、周辺自治体及び水源管理者など関係団体との協力が不可欠であり、
連携を密にし、環境保全に係る取り組みを推進します。
出典)枚方市水道局ウェブサイト(枚方市水道ビジョン)
http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyousei/SUIDOU/work/bijyonsakutei.htm
神戸市水道局
出典)神戸市水道局ウェブサイト(神戸水道ビジョン2017)
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/51/01/2008/20080925.html
http://www.mhlw.go.jp/za/0723/c02/dl/c02-02-17.pdf
奈良市水道局
出典)奈良市水道局ウェブサイト(奈良市水道事業中長期計画)
http://www.h2o.nara.nara.jp/jigyo/vision.htm
岡山市水道局
出典)岡山市水道局ウェブサイト(岡山市水道事業総合基本計画(アクアプラン2007))
http://www.water.okayama.okayama.jp/jigyo/kadai1.htm
広島市水道局
広島市水道局ウェブサイト(環境会計(平成19 年度決算版))
http://www.water.city.hiroshima.jp/jigyo/kaikei/index.html
高松市水道局水源地のボランティア清掃(早明浦ダム・地元水源地各1 回/年)を継続実施します。
水道水源の水質保全の観点に立ち、全市的な水源保護条例の制定について検討します。
高松市水道局ウェブサイト(高松市水道事業基本計画(高松市水道ビジョン))
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/9433.html
北九州市水道局
北九州市水道局ウェブサイト(北九州市水道事業基本計画)
http://water-kitakyushu.icek.jp/suidou/menu06/keikaku.html
福岡市水道局
水源かん養林の整備
● 概要
水源のかん養機能を高め、水質保全を図る目的で、ダム周辺の森林を購入し整備しています。
● 環境保全効果
かん養林の光合成によって大気中のCO2 を吸収します。かん養林は緑のダムといわれ、その貯水能
力による水源かん養効果や、土砂流出防止効果があります。
空気揚水筒ダム設置
● 概要
ダムの貯留水をコンプレッサーでかくはんし、異臭の原因となる藻類の発生を抑制します。
● 環境保全効果
水道原水の水質向上により薬品の使用量が削減されるので、薬品製造時に発生するCO2 等の温室効
果ガスの排出を削減できます。
植樹祭等による植林
● 概要
水源地域や流域の人々との相互理解を深めるため、水源地域で開催される植樹祭等の行事に参加
しています。
● 環境保全効果
植樹祭等で植栽された樹木の光合成によりCO2 を吸収します。
上下流地域の相互理解と連携を深めるため、平成9年度に福岡市水道水源かん養事業基金を設置
し、事業を推進しています。
■ 福岡市水道水源かん養事業基金運営委員会
基金の使い方について協議するため、学識経験者や市民の参加を得て、運営委員会を設置してい
ます。
● 福岡都市圏流域連携基金負担金
福岡都市圏広域行政事業組合が設置する基金へ負担金を支出し、都市圏自治体と協力して都市圏
共通の水源地域への各種取り組みを行っています。
■ 水源の森基金等への参画
(財)福岡県水源の森基金及び(財)筑後川水源地域対策基金に参画し、水源地域への支援等を行っ
ています。
福岡市水道局ウェブサイト
http://www.city.fukuoka.lg.jp/suidou/index.html
熊本市水道局
熊本市水道局ウェブサイト(熊本市水道事業経営基本計画)
http://www.kumamoto-waterworks.jp/gaiyou/column.html?clmnno=638
大分市水道局
○水源の水質保全
森からのきれいな水が守られ、良質な飲み水となってお客さまのもとに届けられるよ
う、お客さまや流域で生活する人々と一緒になって森を育み、きれいな水を守る運動を
進めるなど、河川流域の住民や大分県・関係自治体など関係機関等との連携を図り、水
源水質の保全に向けた取組みを推進します。
大分市水道局ウェブサイト(大分市水道事業基本計画)
http://www.city.oita.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::27236
宮崎市上下水道局
宮崎市上下水道局ウェブサイト(水道事業経営計画)
http://www.suidou-miyazaki.jp/outline/keiei.html
水道事業体内容(地下水から表流水への転換)
茨城県保健福祉部生活衛生課水道整備グループ
限られた資源である地下水については,「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例」
の指定地域を中心に,地下水の保全とその適正な利用に努め,引き続き,地表水(受水
を含む)への転換を進めていく必要がある。
また,約39 万人の県民が自家用井戸等に依存しているが,飲用井戸水の水質検査の適
合率は30〜40%台と低いため,水道水への切り替えを促進する必要がある。
出典)茨城県保健福祉部生活衛生課水道整備グループウェブサイト(茨城県水道整備基本構想21)
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seiei/suido/01guide/0100.html
水道事業体内容(水質汚濁防止)
千葉県水道局
水質検査における廃液及び原水水質自動監視装置からの廃液の無害化
浄水場や水質センターでの水質検査や、取水場での原水水質自動監視装置では試薬とし
て薬品を使用します。その廃液は産業廃棄物として委託先の処理工場で無害化され、環境
に負荷を与えないように適切に廃棄されています。
出典)千葉県水道局ウェブサイト(平成19 年度環境報告書)
http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/zigyougaiyou/kankyoukaikei/houkokusho19.html
奈良県水道局
○水質汚濁等の防止
土砂・汚濁等の流入防止対策として、雨水調整池を設置することにより、土砂を沈殿
させ雨水を放流することにより、水道用地外に影響を与えないようにします。
出典)奈良県水道局ウェブサイト(環境会計平成18 年度決算)
http://www.pref.nara.jp/suido/
化学物質の適正管理(塩素・PCB 等)
水道事業体内容(化学物質の適正管理(塩素・PCB 等))東京都水道局
出典)東京都水道局ウェブサイト(環境報告書平成19 年版)
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html
その他環境保全
その他公害防止
1) 建設工事の環境対策・ガイドラインの作成
水道事業体内容(建設工事の環境対策・ガイドラインの作成)
札幌市水道局
出典)札幌市水道局ウェブサイト(平成20 年(2008 年)版環境報告書)
http://www.city.sapporo.jp/suido/c03/c03third/08_03_10.html
札幌市水道局
出典)札幌市水道局ウェブサイト(平成20 年(2008 年)版環境報告書)
http://www.city.sapporo.jp/suido/c03/c03third/08_03_10.html
東京都水道局
出典)東京都水道局ウェブサイト(環境報告書平成19 年版)
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html
神奈川県企業庁
○環境に配慮した公共工事の推進
企業庁では、計画、設計、積算、実施の各段階で「環境配慮チェックリスト」により
環境配慮項目の確認を行ない、環境に配慮した公共工事を推進するとともに、再生資源
(アスファルト合材など)を積極的に利用しています。
出典)神奈川県企業庁ウェブサイト(環境報告書(平成19 年度決算版))
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/kankyo/index.htm
浜松市上下水道部
出典)浜松市上下水道部ウェブサイト(浜松市上水道事業基本計画)
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/policy/suidou/index.htm
大阪市水道局
出典)大阪市水道局ウェブサイト(平成19 年度版環境報告書)
http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html
東大阪市上下水道局
出典)東大阪市上下水道局ウェブサイト
http://www.suidou.city.higashiosaka.osaka.jp/topics/iso/index.html
2009年11月14日
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
(平成六年三月四日法律第八号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
(目的)
第一条 この法律は、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水道事業者」とは、水道法 第六条第一項 の規定による認可を受けて同法第三条第二項 に規定する水道事業(同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第五項 に規定する水道用水供給事業者をいう。
2 この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業(水道法第三条第四項 に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。)のための原水をいう。
3 この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
4 この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 下水道法 第二条第二号 に規定する下水道の整備に関する事業
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第八条第一項 に規定するし尿処理施設(市町村が同法第六条の二第一項 の規定によりし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)の整備に関する事業
三 浄化槽法 第二条第一号 に規定する浄化槽(次号において「浄化槽」という。)であって、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業
四 浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業
五 畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
六 水道法第三条第一項 に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
七 特別会計に関する法律 第百九十八条第二項第一号 に掲げる河川に関する事業のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。)
八 その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの
(基本方針)
第三条 主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項
二 水道原水水質保全事業の内容に関する事項
三 水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項
四 水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項
五 その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
3 基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。)第三条第一項 に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(水道事業者等の要請等)
第四条 水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業(第二条第一項の水道事業又は同法第三条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第二項 に規定する水道事業をいう。次項において同じ。)の給水区域(同法第三条第十二項 に規定する給水区域をいう。次項において同じ。)をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。
2 水道事業者が特別措置法第四条第二項 の規定による要請をしたとき(同項 の都府県が同項 の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県(以下この項において「給水対象都府県」という。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る。)は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。
3 都府県は、第一項の規定による要請があった場合において、当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業(河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該区域をその区域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次条第一項の都道府県計画を定めることを要請することができる。
4 都道府県は、第一項の規定による要請があったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川(河川法 第三条第一項 に規定する河川(同法第百条 の規定により同法 の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第七条第二項において同じ。)を管理する河川管理者(同法第七条 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に対し通知するとともに、対象水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施の促進に関する意見を述べるものとする。
(都道府県計画)
第五条 都道府県は、前条第一項又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
3 都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。
4 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第七項において「負担予定額」という。)
五 その他地域水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
5 負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
6 都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項 に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。
7 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、関係市町村及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意(負担予定額に係る部分に限る。)及び対象水道事業者の同意を得なければならない。
8 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告し、かつ、関係地方公共団体、関係河川管理者及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
9 主務大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
10 前三項の規定は、都道府県計画の変更について準用する。
(下水道整備事業に係る案の提出等)
第六条 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項 に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の三第一項 に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
2 前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
(河川管理者事業計画)
第七条 河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。
3 河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
4 河川管理者は、第一項及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。
5 河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第八項において「負担予定額」という。)
五 その他河川水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
6 負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
7 河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。
8 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。
9 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係地方公共団体及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
10 前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。
(事業の実施)
第八条 都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(協議会)
第九条 事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。
5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等)
第十条 計画水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。
2 計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項 の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
3 都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。
(都道府県計画の作成のための援助)
第十一条 国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
(資金の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO008.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
(平成六年四月二十二日政令第百三十四号)
最終改正:平成一二年九月一三日政令第四二四号
内閣は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第四条第一項 、第三項 及び第四項 、第五条第五項 、第七条第六項 、第十三条第二項 、第十四条第三項 並びに第十六条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(水道事業者の都道府県に対する要請)
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の取水地点の位置
二 前号の取水地点における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録
三 当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「要請水道事業者」という。)が第一号の取水地点における対象水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
四 要請水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
五 要請水道事業者が第三号の措置を講じた場合においても、対象水道原水に係る水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由
(都府県の他の都府県に対する要請)
第二条 法第四条第三項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
二 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項 に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由
2 前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(都道府県の河川管理者に対する通知)
第三条 法第四条第四項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 対象水道原水の取水地点の位置
二 当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
2 前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(負担予定額を定める際に勘案する事情)
第四条 法第五条第五項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
第五条 法第七条第六項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号 に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
(国庫補助)
第六条 法第十三条第二項 の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号 に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE134.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
(平成六年四月二十八日厚生省令第三十六号)
最終改正:平成一五年九月一七日厚生労働省令第一四〇号
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第十条第一項 の規定に基づき、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項 の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち法第五条第一項 の都道府県計画又は法第七条第一項 の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号 又は法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
第二条 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
一 水質基準に関する省令 (平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項 同令 に規定する厚生労働大臣が定める方法
二 その他の事項 厚生労働大臣が定める方法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03601000036.html
(平成六年三月四日法律第八号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
(目的)
第一条 この法律は、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水道事業者」とは、水道法 第六条第一項 の規定による認可を受けて同法第三条第二項 に規定する水道事業(同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第五項 に規定する水道用水供給事業者をいう。
2 この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業(水道法第三条第四項 に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。)のための原水をいう。
3 この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
4 この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 下水道法 第二条第二号 に規定する下水道の整備に関する事業
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第八条第一項 に規定するし尿処理施設(市町村が同法第六条の二第一項 の規定によりし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)の整備に関する事業
三 浄化槽法 第二条第一号 に規定する浄化槽(次号において「浄化槽」という。)であって、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業
四 浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業
五 畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
六 水道法第三条第一項 に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
七 特別会計に関する法律 第百九十八条第二項第一号 に掲げる河川に関する事業のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。)
八 その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの
(基本方針)
第三条 主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項
二 水道原水水質保全事業の内容に関する事項
三 水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項
四 水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項
五 その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
3 基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。)第三条第一項 に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(水道事業者等の要請等)
第四条 水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業(第二条第一項の水道事業又は同法第三条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第二項 に規定する水道事業をいう。次項において同じ。)の給水区域(同法第三条第十二項 に規定する給水区域をいう。次項において同じ。)をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。
2 水道事業者が特別措置法第四条第二項 の規定による要請をしたとき(同項 の都府県が同項 の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県(以下この項において「給水対象都府県」という。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る。)は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。
3 都府県は、第一項の規定による要請があった場合において、当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業(河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該区域をその区域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次条第一項の都道府県計画を定めることを要請することができる。
4 都道府県は、第一項の規定による要請があったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川(河川法 第三条第一項 に規定する河川(同法第百条 の規定により同法 の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第七条第二項において同じ。)を管理する河川管理者(同法第七条 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に対し通知するとともに、対象水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施の促進に関する意見を述べるものとする。
(都道府県計画)
第五条 都道府県は、前条第一項又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
3 都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。
4 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第七項において「負担予定額」という。)
五 その他地域水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
5 負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
6 都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項 に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。
7 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、関係市町村及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意(負担予定額に係る部分に限る。)及び対象水道事業者の同意を得なければならない。
8 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告し、かつ、関係地方公共団体、関係河川管理者及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
9 主務大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
10 前三項の規定は、都道府県計画の変更について準用する。
(下水道整備事業に係る案の提出等)
第六条 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項 に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の三第一項 に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
2 前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
(河川管理者事業計画)
第七条 河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。
3 河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
4 河川管理者は、第一項及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。
5 河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第八項において「負担予定額」という。)
五 その他河川水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
6 負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
7 河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。
8 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。
9 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係地方公共団体及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
10 前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。
(事業の実施)
第八条 都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(協議会)
第九条 事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。
5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等)
第十条 計画水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。
2 計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項 の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
3 都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。
(都道府県計画の作成のための援助)
第十一条 国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
(資金の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO008.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
(平成六年四月二十二日政令第百三十四号)
最終改正:平成一二年九月一三日政令第四二四号
内閣は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第四条第一項 、第三項 及び第四項 、第五条第五項 、第七条第六項 、第十三条第二項 、第十四条第三項 並びに第十六条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(水道事業者の都道府県に対する要請)
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の取水地点の位置
二 前号の取水地点における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録
三 当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「要請水道事業者」という。)が第一号の取水地点における対象水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
四 要請水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
五 要請水道事業者が第三号の措置を講じた場合においても、対象水道原水に係る水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由
(都府県の他の都府県に対する要請)
第二条 法第四条第三項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
二 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項 に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由
2 前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(都道府県の河川管理者に対する通知)
第三条 法第四条第四項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 対象水道原水の取水地点の位置
二 当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
2 前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(負担予定額を定める際に勘案する事情)
第四条 法第五条第五項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
第五条 法第七条第六項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号 に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
(国庫補助)
第六条 法第十三条第二項 の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号 に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE134.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
(平成六年四月二十八日厚生省令第三十六号)
最終改正:平成一五年九月一七日厚生労働省令第一四〇号
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第十条第一項 の規定に基づき、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項 の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち法第五条第一項 の都道府県計画又は法第七条第一項 の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号 又は法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
第二条 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
一 水質基準に関する省令 (平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項 同令 に規定する厚生労働大臣が定める方法
二 その他の事項 厚生労働大臣が定める方法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03601000036.html
2009年11月14日
平成17(2005)年度 水道統計 水質分布表(原水)最高値
平成17(2005)年度 水道統計 水質分布表(原水)最高値
水 質 項 目計 区 分
鉛及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
表流水1,029 886 52 25 17 11 10 4 9 4 1 10
ダム湖沼310 276 18 7 6 0 2 0 0 1 0 0
地下水3,115 2,966 76 30 17 7 8 3 2 4 0 2
その他784 752 16 4 5 1 2 1 2 0 0 1
注:読み方 鉛の環境基準0.01mg/Lを超過している水道原水が
表流水:10ヶ所
ダム湖沼: 010ヶ所
地下水: 210ヶ所
その他: 110ヶ所
あります。
一般細菌〜10 〜50 〜100 〜500 〜1000 〜5000 〜10000 〜50000 〜100000 〜500000 500001〜
表流水1,033 80 102 93 209 96 214 71 125 29 14 0
ダム湖沼315 15 29 31 110 47 59 10 13 0 1 0
地下水3,119 2,552 250 90 131 39 38 9 7 1 2 0
その他798 618 89 22 33 10 13 6 5 1 1 0
大腸菌(定量)(MPN/100ml) 〜0.0 〜10.0 〜20.0 〜50.0 〜100.0 〜200.0 〜500.0 〜1000.0 〜5000.0 〜10000.0 10000.1〜
表流水391 28 46 10 29 20 39 45 39 72 17 46
ダム湖沼140 17 30 13 27 4 8 9 3 10 3 16
地下水682 604 39 5 9 4 5 5 4 3 2 2
その他148 105 20 4 5 3 2 4 1 1 0 3
カドミウム及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
地下水3,113 3,106 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
水銀及びその化合物〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00020 〜0.00025 〜0.00030 〜0.00035 〜0.00040 〜0.00045 〜0.00050 0.00051〜
表流水1,031 1,028 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
地下水3,113 3,107 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
セレン及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
地下水3,113 3,109 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ヒ素及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
表流水1,031 799 138 44 16 6 6 8 4 0 0 10
ダム湖沼310 265 30 7 1 4 0 2 1 0 0 0
地下水3,115 2,681 203 84 43 32 29 11 8 5 2 17
その他779 677 46 22 9 8 3 1 2 5 3 3
六価クロム化合物〜0.005 〜0.010 〜0.015 〜0.020 〜0.025 〜0.030 〜0.035 〜0.040 〜0.045 〜0.050 0.051〜
地下水3,114 3,108 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
シアン化物イオン及び塩化シアン〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
地下水3,106 3,103 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素〜0.50 〜1.00 〜2.00 〜3.00 〜4.00 〜5.00 〜6.00 〜7.00 〜8.00 〜10.00 10.01〜
全体5,259 2,079 1,197 1,049 403 221 111 81 34 32 28 24
表流水1,036 428 312 230 32 21 6 5 1 0 0 1
ダム湖沼315 173 87 42 9 2 1 1 0 0 0 0
地下水3,118 1,107 639 653 314 166 85 57 28 25 25 19
その他790 371 159 124 48 32 19 18 5 7 3 4
フッ素及びその化合物〜0.08 〜0.16 〜0.24 〜0.32 〜0.40 〜0.48 〜0.56 〜0.64 〜0.72 〜0.80 0.81〜
表流水1,034 687 263 42 20 6 6 4 1 1 1 3
ダム湖沼310 178 100 19 6 4 1 0 0 0 2 0
地下水3,117 2,029 745 192 64 38 12 13 3 6 3 12
その他787 564 173 31 5 5 3 0 1 0 2 3
ホウ素及びその化合物〜0.1 〜0.2 〜0.3 〜0.4 〜0.5 〜0.6 〜0.7 〜0.8 〜0.9 〜1.0 1.1〜
表流水1,024 984 16 13 2 3 3 1 1 0 0 1
地下水3,101 2,951 67 29 16 16 6 5 6 5 0 0
その他765 738 8 6 4 3 1 2 0 0 1 2
四塩化炭素〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0008 〜0.0010 〜0.0012 〜0.0014 〜0.0016 〜0.0018 〜0.0020 0.0021〜
表流水1,028 1,027 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
地下水3,114 3,106 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0
1,4−ジオキサン〜0.005 〜0.010 〜0.015 〜0.020 〜0.025 〜0.030 〜0.035 〜0.040 〜0.045 〜0.050 0.051〜
地下水3,107 3,098 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0
シス−1,2−ジクロロエチレン〜0.004 〜0.008 〜0.012 〜0.016 〜0.020 〜0.024 〜0.028 〜0.032 〜0.036 〜0.040 0.041〜
地下水3,114 3,104 4 2 0 1 1 0 1 0 0 1
テトラクロロエチレン〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
地下水3,114 3,076 8 7 4 11 1 1 0 1 1 4
その他786 777 2 0 1 3 0 1 0 0 0 2
トリクロロエチレン〜0.003 〜0.006 〜0.009 〜0.012 〜0.015 〜0.018 〜0.021 〜0.024 〜0.027 〜0.030 0.031〜
地下水3,114 3,079 7 8 4 2 3 2 4 0 0 5
その他786 778 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0
臭素酸〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
ダム湖沼53 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
地下水286 272 7 1 2 0 0 1 0 0 2 1
その他185 168 5 9 2 0 0 0 0 0 0 1
総トリハロメタン〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.060 〜0.070 〜0.080 〜0.090 〜0.100 0.101〜
表流水153 149 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
ダム湖沼36 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
地下水170 160 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0
その他164 55 47 23 27 10 1 1 0 0 0 0
ブロモジクロロメタン〜0.003 〜0.006 〜0.009 〜0.012 〜0.015 〜0.018 〜0.021 〜0.024 〜0.027 〜0.030 0.031〜
表流水153 148 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
ダム湖沼38 35 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
地下水168 163 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
その他164 66 43 24 14 15 2 0 0 0 0 0
ブロモホルム〜0.009 〜0.018 〜0.027 〜0.036 〜0.045 〜0.054 〜0.063 〜0.072 〜0.081 〜0.090 0.091〜
地下水167 163 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ホルムアルデヒド〜0.008 〜0.016 〜0.024 〜0.032 〜0.040 〜0.048 〜0.056 〜0.064 〜0.072 〜0.080 0.081〜
地下水119 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
亜鉛及びその化合物〜0.02 〜0.04 〜0.06 〜0.08 〜0.10 〜0.20 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 1.01〜
地下水3,115 2,953 55 43 14 23 16 10 0 0 1 0
アルミニウム及びその化合物〜0.02 〜0.05 〜0.10 〜0.15 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 1.01〜
表流水1,029 276 139 114 87 43 70 56 65 38 33 108
ダム湖沼313 49 58 49 28 31 25 16 16 17 7 17
地下水3,112 2,888 111 51 16 10 12 12 2 2 1 7
その他788 621 78 52 8 7 6 4 3 2 1 6
鉄及びその化合物〜0.03 〜0.05 〜0.10 〜0.15 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 1.01〜
表流水1,036 263 57 115 60 63 94 46 84 61 47 146
ダム湖沼314 24 9 40 51 26 47 23 29 14 12 39
地下水3,118 2,392 133 170 75 50 54 25 56 27 20 116
その他796 653 27 31 16 12 19 0 14 5 2 17
ナトリウム及びその化合物〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜40.0 〜60.0 〜80.0 〜100.0 〜120.0 〜150.0 〜200.0 200.1〜
表流水1,031 290 397 265 63 13 3 0 0 0 0 0
ダム湖沼310 50 141 85 31 2 0 1 0 0 0 0
地下水3,116 461 1,224 996 327 68 22 9 6 0 3 0
その他787 221 276 184 76 21 5 0 1 1 0 2
マンガン及びその化合物〜0.005 〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.100 〜0.200 〜0.300 〜0.500 0.501〜
表流水1,036 325 71 118 78 79 62 160 97 19 20 7
ダム湖沼314 30 10 32 31 26 16 79 51 14 15 10
地下水3,122 2,303 104 109 87 58 34 125 130 59 57 56
その他796 653 13 14 13 12 4 30 34 10 8 5
塩化物イオン〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜40.0 〜60.0 〜80.0 〜100.0 〜120.0 〜150.0 〜200.0 200.1〜
表流水1,037 331 276 257 153 11 1 3 3 0 1 1
ダム湖沼315 46 93 130 33 10 0 0 2 1 0 0
地下水3,121 863 1,013 830 287 64 23 13 8 10 6 4
その他801 329 198 137 82 34 7 6 3 1 3 1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 〜10 〜20 〜40 〜60 〜80 〜100 〜150 〜200 〜250 〜300 301〜
表流水1,027 56 140 377 243 94 45 53 7 4 1 7
ダム湖沼315 16 34 120 78 29 11 20 2 3 0 2
地下水3,123 68 135 752 832 615 327 263 67 26 6 32
その他788 34 88 263 176 84 58 60 12 6 4 3
蒸発残留物〜30 〜50 〜100 〜150 〜200 〜250 〜300 〜350 〜400 〜500 501〜
表流水1,022 38 86 440 267 95 38 33 11 2 5 7
ダム湖沼312 6 29 156 70 21 16 7 4 0 2 1
地下水3,118 40 63 818 1,083 663 240 107 37 33 20 14
その他792 27 50 294 191 101 69 30 11 4 7 8
陰イオン界面活性剤〜0.02 〜0.04 〜0.06 〜0.08 〜0.10 〜0.15 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.50 0.51〜
全体5,210 5,140 34 19 7 6 2 2 0 0 0 0
表流水1,025 980 24 10 3 5 2 1 0 0 0 0
ダム湖沼309 304 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水3,108 3,103 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
その他768 753 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0
ジェオスミン〜0.000002 〜0.000004 〜0.000006 〜0.000008 〜0.000010 〜0.000015 〜0.000020 〜0.000030 〜0.000040 〜0.000050 0.000051〜
全体4,605 4,207 154 87 50 28 20 11 13 12 2 21
表流水950 711 102 60 34 18 7 3 2 2 0 11
ダム湖沼304 203 28 19 8 6 9 3 7 9 2 10
地下水2,666 2,648 2 3 5 2 1 4 1 0 0 0
その他685 645 22 5 3 2 3 1 3 1 0 0
2−メチルイソボルネオール〜0.000002 〜0.000004 〜0.000006 〜0.000008 〜0.000010 〜0.000020 〜0.000030 〜0.000040 〜0.000050 〜0.000100 0.000101〜
表流水950 806 55 33 19 16 13 0 2 0 1 5
ダム湖沼302 244 14 13 5 2 11 3 0 0 3 7
地下水2,666 2,649 4 3 1 3 5 0 0 0 0 1
その他685 643 27 6 0 3 3 0 0 0 2 1
非イオン界面活性剤〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.010 〜0.012 〜0.015 〜0.020 〜0.030 〜0.040 0.041〜
表流水1,025 942 9 10 12 15 11 3 10 11 0 2
ダム湖沼311 298 2 3 0 4 0 0 2 1 0 1
地下水3,101 3,089 1 0 2 4 1 1 3 0 0 0
その他768 752 3 2 0 4 2 2 3 0 0 0
フェノール類〜0.0005 〜0.0006 〜0.0007 〜0.0008 〜0.0009 〜0.0010 〜0.0020 〜0.0030 〜0.0040 〜0.0050 0.0051〜
表流水1,025 1,004 3 1 3 0 2 2 2 0 7 1
ダム湖沼313 311 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
地下水3,106 3,077 0 4 3 0 2 1 0 0 18 1
その他775 771 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
有機物(TOCの量) 〜0.5 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜6.0 〜7.0 〜8.0 〜10.0 10.1〜
表流水1,009 212 201 261 174 85 28 15 7 8 11 7
ダム湖沼311 18 45 127 58 35 10 7 4 0 5 2
地下水3,072 2,517 366 146 26 6 3 1 3 0 1 3
その他770 544 103 95 18 2 3 1 1 2 0 1
pH値〜5.8 〜6.0 〜6.3 〜6.6 〜6.9 〜7.2 〜7.5 〜7.8 〜8.2 〜8.6 8.7〜
表流水1,037 12 0 2 17 43 154 268 320 135 50 36
ダム湖沼315 3 0 2 10 20 60 79 53 29 19 40
地下水3,124 39 25 186 442 582 550 462 428 301 94 15
その他802 21 3 15 49 67 150 188 189 97 17 6
色度〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜10.0 〜15.0 〜20.0 〜50.0 〜100.0 100.1〜
表流水1,037 117 96 81 68 54 198 113 80 142 61 27
ダム湖沼315 10 7 17 21 27 81 56 33 44 15 4
地下水3,121 2,426 190 118 56 46 140 60 22 49 10 4
その他802 644 39 21 11 19 34 12 8 9 4 1
濁度〜0.1 〜0.2 〜0.5 〜1.0 〜2.0 〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜50.0 〜100.0 100.1〜
表流水1,037 94 26 79 94 116 121 113 130 124 54 86
ダム湖沼315 6 2 7 18 22 81 73 54 25 14 13
地下水3,125 2,390 179 205 97 83 70 49 35 12 4 1
その他801 642 34 38 25 9 16 13 10 8 4 2
アンチモン及びその化合物〜0.0015 〜0.0030 〜0.0045 〜0.0060 〜0.0075 〜0.0090 〜0.0105 〜0.0120 〜0.0135 〜0.0150 0.0151〜
表流水459 455 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
その他130 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウラン及びその化合物〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0008 〜0.0010 〜0.0012 〜0.0014 〜0.0016 〜0.0018 〜0.0020 0.0021〜
表流水451 417 16 11 1 3 0 0 0 0 2 1
ダム湖沼144 132 7 3 0 1 0 0 0 0 0 1
地下水661 625 18 6 3 2 1 2 1 0 1 2
その他135 128 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3
ニッケル及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
表流水452 344 47 17 15 6 5 8 1 6 2 1
ダム湖沼151 120 20 6 2 1 0 1 0 0 0 1
地下水668 608 25 12 10 8 3 0 1 1 0 0
その他148 134 8 4 1 0 0 0 0 1 0 0
亜硝酸態窒素〜0.005 〜0.010 〜0.015 〜0.020 〜0.025 〜0.030 〜0.035 〜0.040 〜0.045 〜0.050 0.051〜
表流水470 258 45 28 20 17 17 10 12 7 17 39
ダム湖沼158 88 18 12 10 5 3 3 3 1 1 14
地下水650 591 22 8 3 1 1 3 1 1 1 18
その他147 130 0 5 4 2 1 0 1 0 0 4
1,2−ジクロロエタン〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0016 〜0.0020 〜0.0024 〜0.0028 〜0.0032 〜0.0036 〜0.0040 0.0041〜
地下水723 721 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) 〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.060 〜0.070 〜0.080 〜0.090 〜0.100 0.101〜
その他123 122 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
塩素酸〜0.06 〜0.12 〜0.18 〜0.24 〜0.30 〜0.36 〜0.42 〜0.48 〜0.54 〜0.60 0.61〜
地下水40 37 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ジクロロアセトニトリル〜0.004 〜0.008 〜0.012 〜0.016 〜0.020 〜0.024 〜0.028 〜0.032 〜0.036 〜0.040 0.041〜
その他48 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
抱水クロラール〜0.003 〜0.006 〜0.009 〜0.012 〜0.015 〜0.018 〜0.021 〜0.024 〜0.027 〜0.030 0.031〜
ダム湖沼20 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水121 118 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他48 39 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
農薬類〜0.01 〜0.02 〜0.03 〜0.05 〜0.10 〜0.20 〜0.30 〜0.50 〜0.70 〜1.00 1.01〜
表流水307 208 7 5 13 23 27 8 13 0 2 1
ダム湖沼111 100 3 1 2 0 3 0 2 0 0 0
地下水396 388 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0
その他85 79 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0
遊離炭酸〜2.0 〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 80.1〜
表流水317 107 154 42 12 1 1 0 0 0 0 0
ダム湖沼124 50 49 19 3 3 0 0 0 0 0 0
地下水537 82 100 97 108 57 32 18 16 14 6 7
その他125 29 49 18 15 6 2 4 1 0 1 0
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE) 〜0.002 〜0.004 〜0.006 〜0.008 〜0.010 〜0.012 〜0.014 〜0.016 〜0.018 〜0.020 0.021〜
表流水399 398 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜7.0 〜10.0 〜15.0 〜20.0 〜30.0 30.1〜
表流水434 42 49 41 36 37 46 65 62 21 11 24
ダム湖沼151 4 3 17 23 23 32 21 15 4 4 5
地下水723 512 136 34 15 6 14 6 0 0 0 0
その他193 94 40 28 4 7 10 5 2 2 1 0
臭気強度(TON) 0 1 2 3 4 5 〜8 〜10 〜20 〜30 31〜
表流水319 60 41 34 34 15 23 25 14 30 18 25
ダム湖沼130 16 19 13 12 9 8 9 7 14 8 15
地下水399 241 97 14 19 6 7 6 1 4 1 3
その他76 26 18 14 3 4 3 1 0 3 1 3
腐食性(ランゲリア指数) 〜-4.0 〜-3.5 〜-3.0 〜-2.5 〜-2.0 〜-1.5 〜-1.0 〜-0.5 〜0.0 〜0.5 0.6〜
表流水289 3 0 1 7 57 65 70 44 19 8 15
ダム湖沼103 3 0 1 12 16 22 19 11 6 6 7
地下水496 13 0 10 32 103 124 88 64 27 14 21
その他109 5 0 0 3 22 19 24 19 14 1 2
水温(℃) 〜10.0 〜12.0 〜14.0 〜16.0 〜18.0 〜20.0 〜22.0 〜24.0 〜26.0 〜28.0 28.1〜
表流水783 42 18 40 45 72 93 86 92 118 94 83
ダム湖沼244 3 2 3 4 6 18 34 35 49 30 60
地下水2,093 52 85 209 357 514 368 229 161 72 34 12
その他601 71 64 73 72 79 68 31 30 31 37 45
アンモニア態窒素〜0.05 〜0.10 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.50 〜0.60 〜0.80 〜1.00 〜1.50 1.51〜
表流水431 243 62 44 23 25 9 7 8 6 4 0
ダム湖沼163 109 29 8 8 4 1 0 3 0 1 0
地下水661 504 35 21 22 13 9 8 12 8 10 19
その他189 152 3 4 1 3 3 2 1 6 8 6
生物化学的酸素要求量(BOD) 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜6.0 〜7.0 〜8.0 〜9.0 〜10.0 10.1〜
表流水248 46 116 48 17 7 10 1 2 0 0 1
ダム湖沼86 41 32 10 0 1 1 0 1 0 0 0
地下水35 19 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0
その他20 6 9 2 1 1 0 0 0 1 0 0
化学的酸素要求量(COD) 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜6.0 〜7.0 〜8.0 〜9.0 〜10.0 10.1〜
表流水126 6 18 24 22 20 11 6 4 3 2 10
ダム湖沼86 1 8 23 16 10 8 5 4 1 3 7
地下水21 11 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
その他18 5 0 3 4 2 0 1 1 0 0 2
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 〜0.040 〜0.080 〜0.120 〜0.160 〜0.200 〜0.240 〜0.280 〜0.320 〜0.360 〜0.400 0.401〜
表流水129 22 18 4 11 7 9 16 7 5 3 27
ダム湖沼60 8 8 4 9 6 5 2 4 6 1 7
地下水40 24 4 3 0 1 1 0 2 0 2 3
その他30 5 17 4 0 1 2 1 0 0 0 0
浮遊物質(SS) 〜5 〜10 〜15 〜20 〜25 〜30 〜35 〜40 〜45 〜50 51〜
表流水226 49 44 20 22 17 11 4 2 15 4 38
ダム湖沼93 44 19 9 5 1 2 1 1 3 1 7
その他17 6 5 0 1 0 0 0 2 0 0 3
侵食性遊離炭酸〜2.5 〜5.0 〜7.5 〜10.0 〜12.5 〜15.0 〜17.5 〜20.0 〜22.5 〜25.0 25.1〜
表流水80 32 36 7 0 1 3 0 1 0 0 0
ダム湖沼31 10 14 4 2 0 0 0 0 0 0 1
地下水237 36 12 13 20 17 15 17 19 12 10 66
その他48 14 7 1 6 5 1 3 1 2 0 8
全窒素〜0.10 〜0.20 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 〜1.50 〜2.00 〜3.00 〜5.00 5.01〜
表流水192 0 4 13 26 29 10 53 29 13 13 2
ダム湖沼106 1 3 12 19 17 17 15 11 6 5 0
地下水41 3 2 3 5 8 3 7 3 2 3 2
その他24 0 0 4 3 0 1 8 5 2 1 0
全リン〜0.010 〜0.020 〜0.040 〜0.060 〜0.080 〜0.100 〜0.200 〜0.300 〜0.500 〜1.000 1.001〜
表流水195 12 32 40 22 21 6 34 14 14 0 0
ダム湖沼106 16 29 19 13 6 5 11 6 1 0 0
地下水61 7 7 10 10 7 4 6 5 3 2 0
その他25 3 4 6 4 1 1 3 1 1 1 0
リン酸イオン〜0.010 〜0.020 〜0.040 〜0.060 〜0.080 〜0.100 〜0.200 〜0.300 〜0.500 〜1.000 1.001〜
表流水81 34 3 5 2 5 1 21 4 3 3 0
ダム湖沼30 16 4 2 1 2 1 3 1 0 0 0
地下水117 48 8 5 8 5 2 6 14 8 8 5
その他44 23 3 3 1 0 0 2 1 1 6 4
トリハロメタン生成能〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.060 〜0.070 〜0.080 〜0.090 〜0.100 0.101〜
表流水143 1 14 17 24 23 19 8 5 11 9 12
ダム湖沼67 2 4 8 15 8 3 10 4 3 2 8
地下水38 15 8 3 5 0 1 0 1 0 3 2
その他27 11 4 0 3 3 1 2 0 1 1 1
アルカリ度〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 〜90.0 〜100.0 100.1〜
表流水356 2 35 96 68 70 45 16 7 8 2 7
ダム湖沼115 5 10 23 28 12 10 11 6 2 3 5
地下水345 2 8 22 64 61 59 40 30 23 12 24
その他94 1 9 14 15 22 13 5 1 5 4 5
溶存酸素〜1.0 〜2.0 〜4.0 〜6.0 〜8.0 〜10.0 〜12.0 〜14.0 〜16.0 〜18.0 18.1〜
表流水173 0 0 0 0 2 9 37 112 12 0 1
ダム湖沼60 0 1 0 0 0 2 29 22 5 1 0
地下水44 1 0 1 13 18 6 4 1 0 0 0
その他10 0 0 0 0 0 1 3 4 2 0 0
硫酸イオン〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 〜90.0 90.1〜
表流水184 10 34 74 35 18 5 5 0 0 1 2
ダム湖沼49 5 13 15 10 3 1 1 1 0 0 0
地下水232 48 56 49 14 38 12 7 1 1 2 4
その他74 23 14 14 2 8 3 9 1 0 0 0
溶性ケイ酸〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 〜90.0 90.1〜
表流水66 1 4 28 21 4 4 2 2 0 0 0
ダム湖沼27 2 1 14 9 0 0 1 0 0 0 0
地下水102 2 3 18 17 10 17 13 12 8 2 0
その他24 2 1 4 3 3 2 2 4 3 0 0
生物(n/ml) 〜10.0 〜50.0 〜100.0 〜500.0 〜1000.0 〜5000.0 〜10000.0 〜50000.0 〜100000.0 〜500000.0 500000.1〜
表流水94 0 0 1 9 20 37 11 16 0 0 0
ダム湖沼66 0 0 1 6 7 21 9 15 5 2 0
地下水14 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
その他10 2 0 0 0 3 1 1 2 1 0 0
チウラム〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
表流水309 307 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水411 405 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
シマジン (CAT) 〜0.00003 〜0.00006 〜0.00009 〜0.00015 〜0.00021 〜0.00030 〜0.00090 〜0.00150 〜0.00210 〜0.00300 0.00301〜
表流水303 292 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ダム湖沼101 98 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チオベンカルブ〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
表流水317 306 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0
1, 3−ジクロロプロペン (D−D) 〜0.00002 〜0.00004 〜0.00006 〜0.00010 〜0.00014 〜0.00020 〜0.00060 〜0.00100 〜0.00140 〜0.00200 0.00201〜
表流水287 285 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
地下水394 393 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
イソキサチオン〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
ダム湖沼103 101 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
地下水432 431 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ダイアジノン〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水338 316 10 6 5 1 0 0 0 0 0 0
ダム湖沼113 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フェニトロチオン (MEP) 〜0.00003 〜0.00006 〜0.00009 〜0.00015 〜0.00021 〜0.00030 〜0.00090 〜0.00150 〜0.00210 〜0.00300 0.00301〜
表流水369 333 16 3 6 0 1 9 0 0 0 1
ダム湖沼128 120 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
地下水566 564 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他93 91 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
イソプロチオラン (IPT) 〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水317 292 16 3 1 2 1 2 0 0 0 0
プロピザミド〜0.0005 〜0.0010 〜0.0015 〜0.0025 〜0.0035 〜0.0050 〜0.0150 〜0.0250 〜0.0350 〜0.0500 0.0501〜
表流水263 261 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ジクロルボス (DDVP) 〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
表流水318 314 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水470 469 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
フェノブカルブ (BPMC) 〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水317 311 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
クロルニトロフェン (CNP):失効農薬〜0.000001 〜0.000002 〜0.000003 〜0.000005 〜0.000007 〜0.000010 〜0.000030 〜0.000050 〜0.000070 〜0.000100 0.000101〜
表流水229 226 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
地下水321 317 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
CNP−アミノ体〜0.000001 〜0.000002 〜0.000003 〜0.000005 〜0.000007 〜0.000010 〜0.000030 〜0.000050 〜0.000070 〜0.000100 0.000101〜
表流水162 161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
地下水232 230 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
イプロベンホス (IBP) 〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
表流水291 251 14 13 5 1 2 4 1 0 0 0
ダム湖沼98 91 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPN 〜0.00006 〜0.00012 〜0.00018 〜0.00030 〜0.00042 〜0.00060 〜0.00180 〜0.00300 〜0.00420 〜0.00600 0.00601〜
表流水276 269 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ダム湖沼97 94 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
カルボフラン(カルボスルファン代謝物) 〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水243 233 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ダム湖沼89 85 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
トリクロピル〜0.00006 〜0.00012 〜0.00018 〜0.00030 〜0.00042 〜0.00060 〜0.00180 〜0.00300 〜0.00420 〜0.00600 0.00601〜
表流水246 233 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ダム湖沼91 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
アセフェート〜0.0008 〜0.0016 〜0.0024 〜0.0040 〜0.0056 〜0.0080 〜0.0240 〜0.0400 〜0.0560 〜0.0800 0.0801〜
表流水295 294 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イソフェンホス〜0.00001 〜0.00002 〜0.00003 〜0.00005 〜0.00007 〜0.00010 〜0.00030 〜0.00050 〜0.00070 〜0.00100 0.00101〜
表流水227 221 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水321 320 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
トリクロルホン (DEP) 〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水296 293 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ピリダフェンチオン〜0.00002 〜0.00004 〜0.00006 〜0.00010 〜0.00014 〜0.00020 〜0.00060 〜0.00100 〜0.00140 〜0.00200 0.00201〜
表流水271 267 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水343 342 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ペンシクロン〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水294 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
メコプロップ (MCPP) 〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水264 257 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
メチルダイムロン〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水222 221 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
カルバリル (NAC) 〜0.0005 〜0.0010 〜0.0015 〜0.0025 〜0.0035 〜0.0050 〜0.0150 〜0.0250 〜0.0350 〜0.0500 0.0501〜
地下水336 334 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) 〜0.00006 〜0.00012 〜0.00018 〜0.00030 〜0.00042 〜0.00060 〜0.00180 〜0.00300 〜0.00420 〜0.00600 0.00601〜
表流水291 288 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ピロキロン〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水300 275 10 4 7 1 0 0 3 0 0 0
ダム湖沼101 99 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水384 380 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
フサライド〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.005 〜0.007 〜0.010 〜0.030 〜0.050 〜0.070 〜0.100 0.101〜
表流水322 321 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
メフェナセット〜0.00009 〜0.00018 〜0.00027 〜0.00045 〜0.00063 〜0.00090 〜0.00270 〜0.00450 〜0.00630 〜0.00900 0.00901〜
表流水334 276 12 14 16 9 3 4 0 0 0 0
ダム湖沼109 103 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0
地下水445 442 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
プレチラクロール〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水323 312 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
ダム湖沼110 106 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水433 431 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
メチダチオン (DMTP) 〜0.00004 〜0.00008 〜0.00012 〜0.00020 〜0.00028 〜0.00040 〜0.00120 〜0.00200 〜0.00280 〜0.00400 0.00401〜
表流水277 275 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水373 372 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロモブチド〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水289 230 27 20 5 3 2 2 0 0 0 0
ダム湖沼100 97 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
地下水361 354 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0
モリネート〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水297 249 4 10 16 4 6 6 0 1 0 1
ダム湖沼95 92 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
その他49 48 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
アニロホス〜0.00003 〜0.00006 〜0.00009 〜0.00015 〜0.00021 〜0.00030 〜0.00090 〜0.00150 〜0.00210 〜0.00300 0.00301〜
表流水209 204 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
ダラポン〜0.0008 〜0.0016 〜0.0024 〜0.0040 〜0.0056 〜0.0080 〜0.0240 〜0.0400 〜0.0560 〜0.0800 0.0801〜
地下水252 251 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ジクワット〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水245 240 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ダム湖沼95 93 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
地下水365 359 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
その他50 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
フェンチオン (MPP) 〜0.00001 〜0.00002 〜0.00003 〜0.00005 〜0.00007 〜0.00010 〜0.00030 〜0.00050 〜0.00070 〜0.00100 0.00101〜
表流水299 284 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0
ベノミル〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
表流水251 236 8 3 1 0 3 0 0 0 0 0
ダム湖沼97 95 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ベンフラカルブ〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水245 243 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
シメトリン〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水304 288 11 2 2 0 1 0 0 0 0 0
ダム湖沼100 99 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
エスプロカルブ〜0.0001 〜0.0002 〜0.0003 〜0.0005 〜0.0007 〜0.0010 〜0.0030 〜0.0050 〜0.0070 〜0.010 0.0101〜
全体787 769 15 2 0 0 1 0 0 0 0 0
表流水288 272 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ダム湖沼100 98 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ビフェノックス〜0.002 〜0.004 〜0.006 〜0.010 〜0.0140 〜0.020 〜0.060 〜0.100 〜0.140 〜0.200 0.201〜
ダム湖沼90 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トリシクラゾール〜0.0008 〜0.0016 〜0.0024 〜0.0040 〜0.0056 〜0.0080 〜0.0240 〜0.0400 〜0.0560 〜0.0800 0.0801〜
その他41 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ピペロホス〜0.000009 〜0.000018 〜0.000027 〜0.000045 〜0.000063 〜0.000090 〜0.000270 〜0.000450 〜0.000630 〜0.000900 0.000901〜
表流水223 221 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水291 290 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ジメタメトリン〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
表流水258 257 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
イミノクタジン酢酸塩〜0.00006 〜0.00012 〜0.00018 〜0.00030 〜0.00042 〜0.00060 〜0.00180 〜0.00300 〜0.00420 〜0.00600 0.00601〜
表流水187 184 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
その他37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ポリカーバメート〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水156 152 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
カフェンストロール〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
表流水303 281 7 4 6 1 2 2 0 0 0 0
ダム湖沼104 101 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
http://www.jwwa.or.jp/mizu/pdf/2005-b-01gen-01max.pdf
水 質 項 目計 区 分
鉛及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
表流水1,029 886 52 25 17 11 10 4 9 4 1 10
ダム湖沼310 276 18 7 6 0 2 0 0 1 0 0
地下水3,115 2,966 76 30 17 7 8 3 2 4 0 2
その他784 752 16 4 5 1 2 1 2 0 0 1
注:読み方 鉛の環境基準0.01mg/Lを超過している水道原水が
表流水:10ヶ所
ダム湖沼: 010ヶ所
地下水: 210ヶ所
その他: 110ヶ所
あります。
一般細菌〜10 〜50 〜100 〜500 〜1000 〜5000 〜10000 〜50000 〜100000 〜500000 500001〜
表流水1,033 80 102 93 209 96 214 71 125 29 14 0
ダム湖沼315 15 29 31 110 47 59 10 13 0 1 0
地下水3,119 2,552 250 90 131 39 38 9 7 1 2 0
その他798 618 89 22 33 10 13 6 5 1 1 0
大腸菌(定量)(MPN/100ml) 〜0.0 〜10.0 〜20.0 〜50.0 〜100.0 〜200.0 〜500.0 〜1000.0 〜5000.0 〜10000.0 10000.1〜
表流水391 28 46 10 29 20 39 45 39 72 17 46
ダム湖沼140 17 30 13 27 4 8 9 3 10 3 16
地下水682 604 39 5 9 4 5 5 4 3 2 2
その他148 105 20 4 5 3 2 4 1 1 0 3
カドミウム及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
地下水3,113 3,106 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
水銀及びその化合物〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00020 〜0.00025 〜0.00030 〜0.00035 〜0.00040 〜0.00045 〜0.00050 0.00051〜
表流水1,031 1,028 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
地下水3,113 3,107 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
セレン及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
地下水3,113 3,109 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ヒ素及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
表流水1,031 799 138 44 16 6 6 8 4 0 0 10
ダム湖沼310 265 30 7 1 4 0 2 1 0 0 0
地下水3,115 2,681 203 84 43 32 29 11 8 5 2 17
その他779 677 46 22 9 8 3 1 2 5 3 3
六価クロム化合物〜0.005 〜0.010 〜0.015 〜0.020 〜0.025 〜0.030 〜0.035 〜0.040 〜0.045 〜0.050 0.051〜
地下水3,114 3,108 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
シアン化物イオン及び塩化シアン〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
地下水3,106 3,103 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素〜0.50 〜1.00 〜2.00 〜3.00 〜4.00 〜5.00 〜6.00 〜7.00 〜8.00 〜10.00 10.01〜
全体5,259 2,079 1,197 1,049 403 221 111 81 34 32 28 24
表流水1,036 428 312 230 32 21 6 5 1 0 0 1
ダム湖沼315 173 87 42 9 2 1 1 0 0 0 0
地下水3,118 1,107 639 653 314 166 85 57 28 25 25 19
その他790 371 159 124 48 32 19 18 5 7 3 4
フッ素及びその化合物〜0.08 〜0.16 〜0.24 〜0.32 〜0.40 〜0.48 〜0.56 〜0.64 〜0.72 〜0.80 0.81〜
表流水1,034 687 263 42 20 6 6 4 1 1 1 3
ダム湖沼310 178 100 19 6 4 1 0 0 0 2 0
地下水3,117 2,029 745 192 64 38 12 13 3 6 3 12
その他787 564 173 31 5 5 3 0 1 0 2 3
ホウ素及びその化合物〜0.1 〜0.2 〜0.3 〜0.4 〜0.5 〜0.6 〜0.7 〜0.8 〜0.9 〜1.0 1.1〜
表流水1,024 984 16 13 2 3 3 1 1 0 0 1
地下水3,101 2,951 67 29 16 16 6 5 6 5 0 0
その他765 738 8 6 4 3 1 2 0 0 1 2
四塩化炭素〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0008 〜0.0010 〜0.0012 〜0.0014 〜0.0016 〜0.0018 〜0.0020 0.0021〜
表流水1,028 1,027 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
地下水3,114 3,106 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0
1,4−ジオキサン〜0.005 〜0.010 〜0.015 〜0.020 〜0.025 〜0.030 〜0.035 〜0.040 〜0.045 〜0.050 0.051〜
地下水3,107 3,098 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0
シス−1,2−ジクロロエチレン〜0.004 〜0.008 〜0.012 〜0.016 〜0.020 〜0.024 〜0.028 〜0.032 〜0.036 〜0.040 0.041〜
地下水3,114 3,104 4 2 0 1 1 0 1 0 0 1
テトラクロロエチレン〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
地下水3,114 3,076 8 7 4 11 1 1 0 1 1 4
その他786 777 2 0 1 3 0 1 0 0 0 2
トリクロロエチレン〜0.003 〜0.006 〜0.009 〜0.012 〜0.015 〜0.018 〜0.021 〜0.024 〜0.027 〜0.030 0.031〜
地下水3,114 3,079 7 8 4 2 3 2 4 0 0 5
その他786 778 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0
臭素酸〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
ダム湖沼53 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
地下水286 272 7 1 2 0 0 1 0 0 2 1
その他185 168 5 9 2 0 0 0 0 0 0 1
総トリハロメタン〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.060 〜0.070 〜0.080 〜0.090 〜0.100 0.101〜
表流水153 149 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
ダム湖沼36 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
地下水170 160 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0
その他164 55 47 23 27 10 1 1 0 0 0 0
ブロモジクロロメタン〜0.003 〜0.006 〜0.009 〜0.012 〜0.015 〜0.018 〜0.021 〜0.024 〜0.027 〜0.030 0.031〜
表流水153 148 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
ダム湖沼38 35 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
地下水168 163 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
その他164 66 43 24 14 15 2 0 0 0 0 0
ブロモホルム〜0.009 〜0.018 〜0.027 〜0.036 〜0.045 〜0.054 〜0.063 〜0.072 〜0.081 〜0.090 0.091〜
地下水167 163 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ホルムアルデヒド〜0.008 〜0.016 〜0.024 〜0.032 〜0.040 〜0.048 〜0.056 〜0.064 〜0.072 〜0.080 0.081〜
地下水119 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
亜鉛及びその化合物〜0.02 〜0.04 〜0.06 〜0.08 〜0.10 〜0.20 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 1.01〜
地下水3,115 2,953 55 43 14 23 16 10 0 0 1 0
アルミニウム及びその化合物〜0.02 〜0.05 〜0.10 〜0.15 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 1.01〜
表流水1,029 276 139 114 87 43 70 56 65 38 33 108
ダム湖沼313 49 58 49 28 31 25 16 16 17 7 17
地下水3,112 2,888 111 51 16 10 12 12 2 2 1 7
その他788 621 78 52 8 7 6 4 3 2 1 6
鉄及びその化合物〜0.03 〜0.05 〜0.10 〜0.15 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 1.01〜
表流水1,036 263 57 115 60 63 94 46 84 61 47 146
ダム湖沼314 24 9 40 51 26 47 23 29 14 12 39
地下水3,118 2,392 133 170 75 50 54 25 56 27 20 116
その他796 653 27 31 16 12 19 0 14 5 2 17
ナトリウム及びその化合物〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜40.0 〜60.0 〜80.0 〜100.0 〜120.0 〜150.0 〜200.0 200.1〜
表流水1,031 290 397 265 63 13 3 0 0 0 0 0
ダム湖沼310 50 141 85 31 2 0 1 0 0 0 0
地下水3,116 461 1,224 996 327 68 22 9 6 0 3 0
その他787 221 276 184 76 21 5 0 1 1 0 2
マンガン及びその化合物〜0.005 〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.100 〜0.200 〜0.300 〜0.500 0.501〜
表流水1,036 325 71 118 78 79 62 160 97 19 20 7
ダム湖沼314 30 10 32 31 26 16 79 51 14 15 10
地下水3,122 2,303 104 109 87 58 34 125 130 59 57 56
その他796 653 13 14 13 12 4 30 34 10 8 5
塩化物イオン〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜40.0 〜60.0 〜80.0 〜100.0 〜120.0 〜150.0 〜200.0 200.1〜
表流水1,037 331 276 257 153 11 1 3 3 0 1 1
ダム湖沼315 46 93 130 33 10 0 0 2 1 0 0
地下水3,121 863 1,013 830 287 64 23 13 8 10 6 4
その他801 329 198 137 82 34 7 6 3 1 3 1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 〜10 〜20 〜40 〜60 〜80 〜100 〜150 〜200 〜250 〜300 301〜
表流水1,027 56 140 377 243 94 45 53 7 4 1 7
ダム湖沼315 16 34 120 78 29 11 20 2 3 0 2
地下水3,123 68 135 752 832 615 327 263 67 26 6 32
その他788 34 88 263 176 84 58 60 12 6 4 3
蒸発残留物〜30 〜50 〜100 〜150 〜200 〜250 〜300 〜350 〜400 〜500 501〜
表流水1,022 38 86 440 267 95 38 33 11 2 5 7
ダム湖沼312 6 29 156 70 21 16 7 4 0 2 1
地下水3,118 40 63 818 1,083 663 240 107 37 33 20 14
その他792 27 50 294 191 101 69 30 11 4 7 8
陰イオン界面活性剤〜0.02 〜0.04 〜0.06 〜0.08 〜0.10 〜0.15 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.50 0.51〜
全体5,210 5,140 34 19 7 6 2 2 0 0 0 0
表流水1,025 980 24 10 3 5 2 1 0 0 0 0
ダム湖沼309 304 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水3,108 3,103 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
その他768 753 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0
ジェオスミン〜0.000002 〜0.000004 〜0.000006 〜0.000008 〜0.000010 〜0.000015 〜0.000020 〜0.000030 〜0.000040 〜0.000050 0.000051〜
全体4,605 4,207 154 87 50 28 20 11 13 12 2 21
表流水950 711 102 60 34 18 7 3 2 2 0 11
ダム湖沼304 203 28 19 8 6 9 3 7 9 2 10
地下水2,666 2,648 2 3 5 2 1 4 1 0 0 0
その他685 645 22 5 3 2 3 1 3 1 0 0
2−メチルイソボルネオール〜0.000002 〜0.000004 〜0.000006 〜0.000008 〜0.000010 〜0.000020 〜0.000030 〜0.000040 〜0.000050 〜0.000100 0.000101〜
表流水950 806 55 33 19 16 13 0 2 0 1 5
ダム湖沼302 244 14 13 5 2 11 3 0 0 3 7
地下水2,666 2,649 4 3 1 3 5 0 0 0 0 1
その他685 643 27 6 0 3 3 0 0 0 2 1
非イオン界面活性剤〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.010 〜0.012 〜0.015 〜0.020 〜0.030 〜0.040 0.041〜
表流水1,025 942 9 10 12 15 11 3 10 11 0 2
ダム湖沼311 298 2 3 0 4 0 0 2 1 0 1
地下水3,101 3,089 1 0 2 4 1 1 3 0 0 0
その他768 752 3 2 0 4 2 2 3 0 0 0
フェノール類〜0.0005 〜0.0006 〜0.0007 〜0.0008 〜0.0009 〜0.0010 〜0.0020 〜0.0030 〜0.0040 〜0.0050 0.0051〜
表流水1,025 1,004 3 1 3 0 2 2 2 0 7 1
ダム湖沼313 311 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
地下水3,106 3,077 0 4 3 0 2 1 0 0 18 1
その他775 771 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
有機物(TOCの量) 〜0.5 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜6.0 〜7.0 〜8.0 〜10.0 10.1〜
表流水1,009 212 201 261 174 85 28 15 7 8 11 7
ダム湖沼311 18 45 127 58 35 10 7 4 0 5 2
地下水3,072 2,517 366 146 26 6 3 1 3 0 1 3
その他770 544 103 95 18 2 3 1 1 2 0 1
pH値〜5.8 〜6.0 〜6.3 〜6.6 〜6.9 〜7.2 〜7.5 〜7.8 〜8.2 〜8.6 8.7〜
表流水1,037 12 0 2 17 43 154 268 320 135 50 36
ダム湖沼315 3 0 2 10 20 60 79 53 29 19 40
地下水3,124 39 25 186 442 582 550 462 428 301 94 15
その他802 21 3 15 49 67 150 188 189 97 17 6
色度〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜10.0 〜15.0 〜20.0 〜50.0 〜100.0 100.1〜
表流水1,037 117 96 81 68 54 198 113 80 142 61 27
ダム湖沼315 10 7 17 21 27 81 56 33 44 15 4
地下水3,121 2,426 190 118 56 46 140 60 22 49 10 4
その他802 644 39 21 11 19 34 12 8 9 4 1
濁度〜0.1 〜0.2 〜0.5 〜1.0 〜2.0 〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜50.0 〜100.0 100.1〜
表流水1,037 94 26 79 94 116 121 113 130 124 54 86
ダム湖沼315 6 2 7 18 22 81 73 54 25 14 13
地下水3,125 2,390 179 205 97 83 70 49 35 12 4 1
その他801 642 34 38 25 9 16 13 10 8 4 2
アンチモン及びその化合物〜0.0015 〜0.0030 〜0.0045 〜0.0060 〜0.0075 〜0.0090 〜0.0105 〜0.0120 〜0.0135 〜0.0150 0.0151〜
表流水459 455 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
その他130 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウラン及びその化合物〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0008 〜0.0010 〜0.0012 〜0.0014 〜0.0016 〜0.0018 〜0.0020 0.0021〜
表流水451 417 16 11 1 3 0 0 0 0 2 1
ダム湖沼144 132 7 3 0 1 0 0 0 0 0 1
地下水661 625 18 6 3 2 1 2 1 0 1 2
その他135 128 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3
ニッケル及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
表流水452 344 47 17 15 6 5 8 1 6 2 1
ダム湖沼151 120 20 6 2 1 0 1 0 0 0 1
地下水668 608 25 12 10 8 3 0 1 1 0 0
その他148 134 8 4 1 0 0 0 0 1 0 0
亜硝酸態窒素〜0.005 〜0.010 〜0.015 〜0.020 〜0.025 〜0.030 〜0.035 〜0.040 〜0.045 〜0.050 0.051〜
表流水470 258 45 28 20 17 17 10 12 7 17 39
ダム湖沼158 88 18 12 10 5 3 3 3 1 1 14
地下水650 591 22 8 3 1 1 3 1 1 1 18
その他147 130 0 5 4 2 1 0 1 0 0 4
1,2−ジクロロエタン〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0016 〜0.0020 〜0.0024 〜0.0028 〜0.0032 〜0.0036 〜0.0040 0.0041〜
地下水723 721 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) 〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.060 〜0.070 〜0.080 〜0.090 〜0.100 0.101〜
その他123 122 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
塩素酸〜0.06 〜0.12 〜0.18 〜0.24 〜0.30 〜0.36 〜0.42 〜0.48 〜0.54 〜0.60 0.61〜
地下水40 37 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ジクロロアセトニトリル〜0.004 〜0.008 〜0.012 〜0.016 〜0.020 〜0.024 〜0.028 〜0.032 〜0.036 〜0.040 0.041〜
その他48 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
抱水クロラール〜0.003 〜0.006 〜0.009 〜0.012 〜0.015 〜0.018 〜0.021 〜0.024 〜0.027 〜0.030 0.031〜
ダム湖沼20 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水121 118 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他48 39 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
農薬類〜0.01 〜0.02 〜0.03 〜0.05 〜0.10 〜0.20 〜0.30 〜0.50 〜0.70 〜1.00 1.01〜
表流水307 208 7 5 13 23 27 8 13 0 2 1
ダム湖沼111 100 3 1 2 0 3 0 2 0 0 0
地下水396 388 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0
その他85 79 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0
遊離炭酸〜2.0 〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 80.1〜
表流水317 107 154 42 12 1 1 0 0 0 0 0
ダム湖沼124 50 49 19 3 3 0 0 0 0 0 0
地下水537 82 100 97 108 57 32 18 16 14 6 7
その他125 29 49 18 15 6 2 4 1 0 1 0
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE) 〜0.002 〜0.004 〜0.006 〜0.008 〜0.010 〜0.012 〜0.014 〜0.016 〜0.018 〜0.020 0.021〜
表流水399 398 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜7.0 〜10.0 〜15.0 〜20.0 〜30.0 30.1〜
表流水434 42 49 41 36 37 46 65 62 21 11 24
ダム湖沼151 4 3 17 23 23 32 21 15 4 4 5
地下水723 512 136 34 15 6 14 6 0 0 0 0
その他193 94 40 28 4 7 10 5 2 2 1 0
臭気強度(TON) 0 1 2 3 4 5 〜8 〜10 〜20 〜30 31〜
表流水319 60 41 34 34 15 23 25 14 30 18 25
ダム湖沼130 16 19 13 12 9 8 9 7 14 8 15
地下水399 241 97 14 19 6 7 6 1 4 1 3
その他76 26 18 14 3 4 3 1 0 3 1 3
腐食性(ランゲリア指数) 〜-4.0 〜-3.5 〜-3.0 〜-2.5 〜-2.0 〜-1.5 〜-1.0 〜-0.5 〜0.0 〜0.5 0.6〜
表流水289 3 0 1 7 57 65 70 44 19 8 15
ダム湖沼103 3 0 1 12 16 22 19 11 6 6 7
地下水496 13 0 10 32 103 124 88 64 27 14 21
その他109 5 0 0 3 22 19 24 19 14 1 2
水温(℃) 〜10.0 〜12.0 〜14.0 〜16.0 〜18.0 〜20.0 〜22.0 〜24.0 〜26.0 〜28.0 28.1〜
表流水783 42 18 40 45 72 93 86 92 118 94 83
ダム湖沼244 3 2 3 4 6 18 34 35 49 30 60
地下水2,093 52 85 209 357 514 368 229 161 72 34 12
その他601 71 64 73 72 79 68 31 30 31 37 45
アンモニア態窒素〜0.05 〜0.10 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.50 〜0.60 〜0.80 〜1.00 〜1.50 1.51〜
表流水431 243 62 44 23 25 9 7 8 6 4 0
ダム湖沼163 109 29 8 8 4 1 0 3 0 1 0
地下水661 504 35 21 22 13 9 8 12 8 10 19
その他189 152 3 4 1 3 3 2 1 6 8 6
生物化学的酸素要求量(BOD) 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜6.0 〜7.0 〜8.0 〜9.0 〜10.0 10.1〜
表流水248 46 116 48 17 7 10 1 2 0 0 1
ダム湖沼86 41 32 10 0 1 1 0 1 0 0 0
地下水35 19 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0
その他20 6 9 2 1 1 0 0 0 1 0 0
化学的酸素要求量(COD) 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜6.0 〜7.0 〜8.0 〜9.0 〜10.0 10.1〜
表流水126 6 18 24 22 20 11 6 4 3 2 10
ダム湖沼86 1 8 23 16 10 8 5 4 1 3 7
地下水21 11 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
その他18 5 0 3 4 2 0 1 1 0 0 2
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 〜0.040 〜0.080 〜0.120 〜0.160 〜0.200 〜0.240 〜0.280 〜0.320 〜0.360 〜0.400 0.401〜
表流水129 22 18 4 11 7 9 16 7 5 3 27
ダム湖沼60 8 8 4 9 6 5 2 4 6 1 7
地下水40 24 4 3 0 1 1 0 2 0 2 3
その他30 5 17 4 0 1 2 1 0 0 0 0
浮遊物質(SS) 〜5 〜10 〜15 〜20 〜25 〜30 〜35 〜40 〜45 〜50 51〜
表流水226 49 44 20 22 17 11 4 2 15 4 38
ダム湖沼93 44 19 9 5 1 2 1 1 3 1 7
その他17 6 5 0 1 0 0 0 2 0 0 3
侵食性遊離炭酸〜2.5 〜5.0 〜7.5 〜10.0 〜12.5 〜15.0 〜17.5 〜20.0 〜22.5 〜25.0 25.1〜
表流水80 32 36 7 0 1 3 0 1 0 0 0
ダム湖沼31 10 14 4 2 0 0 0 0 0 0 1
地下水237 36 12 13 20 17 15 17 19 12 10 66
その他48 14 7 1 6 5 1 3 1 2 0 8
全窒素〜0.10 〜0.20 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 〜1.50 〜2.00 〜3.00 〜5.00 5.01〜
表流水192 0 4 13 26 29 10 53 29 13 13 2
ダム湖沼106 1 3 12 19 17 17 15 11 6 5 0
地下水41 3 2 3 5 8 3 7 3 2 3 2
その他24 0 0 4 3 0 1 8 5 2 1 0
全リン〜0.010 〜0.020 〜0.040 〜0.060 〜0.080 〜0.100 〜0.200 〜0.300 〜0.500 〜1.000 1.001〜
表流水195 12 32 40 22 21 6 34 14 14 0 0
ダム湖沼106 16 29 19 13 6 5 11 6 1 0 0
地下水61 7 7 10 10 7 4 6 5 3 2 0
その他25 3 4 6 4 1 1 3 1 1 1 0
リン酸イオン〜0.010 〜0.020 〜0.040 〜0.060 〜0.080 〜0.100 〜0.200 〜0.300 〜0.500 〜1.000 1.001〜
表流水81 34 3 5 2 5 1 21 4 3 3 0
ダム湖沼30 16 4 2 1 2 1 3 1 0 0 0
地下水117 48 8 5 8 5 2 6 14 8 8 5
その他44 23 3 3 1 0 0 2 1 1 6 4
トリハロメタン生成能〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.060 〜0.070 〜0.080 〜0.090 〜0.100 0.101〜
表流水143 1 14 17 24 23 19 8 5 11 9 12
ダム湖沼67 2 4 8 15 8 3 10 4 3 2 8
地下水38 15 8 3 5 0 1 0 1 0 3 2
その他27 11 4 0 3 3 1 2 0 1 1 1
アルカリ度〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 〜90.0 〜100.0 100.1〜
表流水356 2 35 96 68 70 45 16 7 8 2 7
ダム湖沼115 5 10 23 28 12 10 11 6 2 3 5
地下水345 2 8 22 64 61 59 40 30 23 12 24
その他94 1 9 14 15 22 13 5 1 5 4 5
溶存酸素〜1.0 〜2.0 〜4.0 〜6.0 〜8.0 〜10.0 〜12.0 〜14.0 〜16.0 〜18.0 18.1〜
表流水173 0 0 0 0 2 9 37 112 12 0 1
ダム湖沼60 0 1 0 0 0 2 29 22 5 1 0
地下水44 1 0 1 13 18 6 4 1 0 0 0
その他10 0 0 0 0 0 1 3 4 2 0 0
硫酸イオン〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 〜90.0 90.1〜
表流水184 10 34 74 35 18 5 5 0 0 1 2
ダム湖沼49 5 13 15 10 3 1 1 1 0 0 0
地下水232 48 56 49 14 38 12 7 1 1 2 4
その他74 23 14 14 2 8 3 9 1 0 0 0
溶性ケイ酸〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 〜90.0 90.1〜
表流水66 1 4 28 21 4 4 2 2 0 0 0
ダム湖沼27 2 1 14 9 0 0 1 0 0 0 0
地下水102 2 3 18 17 10 17 13 12 8 2 0
その他24 2 1 4 3 3 2 2 4 3 0 0
生物(n/ml) 〜10.0 〜50.0 〜100.0 〜500.0 〜1000.0 〜5000.0 〜10000.0 〜50000.0 〜100000.0 〜500000.0 500000.1〜
表流水94 0 0 1 9 20 37 11 16 0 0 0
ダム湖沼66 0 0 1 6 7 21 9 15 5 2 0
地下水14 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
その他10 2 0 0 0 3 1 1 2 1 0 0
チウラム〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
表流水309 307 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水411 405 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
シマジン (CAT) 〜0.00003 〜0.00006 〜0.00009 〜0.00015 〜0.00021 〜0.00030 〜0.00090 〜0.00150 〜0.00210 〜0.00300 0.00301〜
表流水303 292 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ダム湖沼101 98 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チオベンカルブ〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
表流水317 306 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0
1, 3−ジクロロプロペン (D−D) 〜0.00002 〜0.00004 〜0.00006 〜0.00010 〜0.00014 〜0.00020 〜0.00060 〜0.00100 〜0.00140 〜0.00200 0.00201〜
表流水287 285 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
地下水394 393 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
イソキサチオン〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
ダム湖沼103 101 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
地下水432 431 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ダイアジノン〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水338 316 10 6 5 1 0 0 0 0 0 0
ダム湖沼113 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フェニトロチオン (MEP) 〜0.00003 〜0.00006 〜0.00009 〜0.00015 〜0.00021 〜0.00030 〜0.00090 〜0.00150 〜0.00210 〜0.00300 0.00301〜
表流水369 333 16 3 6 0 1 9 0 0 0 1
ダム湖沼128 120 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
地下水566 564 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他93 91 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
イソプロチオラン (IPT) 〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水317 292 16 3 1 2 1 2 0 0 0 0
プロピザミド〜0.0005 〜0.0010 〜0.0015 〜0.0025 〜0.0035 〜0.0050 〜0.0150 〜0.0250 〜0.0350 〜0.0500 0.0501〜
表流水263 261 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ジクロルボス (DDVP) 〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
表流水318 314 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水470 469 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
フェノブカルブ (BPMC) 〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水317 311 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
クロルニトロフェン (CNP):失効農薬〜0.000001 〜0.000002 〜0.000003 〜0.000005 〜0.000007 〜0.000010 〜0.000030 〜0.000050 〜0.000070 〜0.000100 0.000101〜
表流水229 226 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
地下水321 317 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
CNP−アミノ体〜0.000001 〜0.000002 〜0.000003 〜0.000005 〜0.000007 〜0.000010 〜0.000030 〜0.000050 〜0.000070 〜0.000100 0.000101〜
表流水162 161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
地下水232 230 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
イプロベンホス (IBP) 〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
表流水291 251 14 13 5 1 2 4 1 0 0 0
ダム湖沼98 91 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPN 〜0.00006 〜0.00012 〜0.00018 〜0.00030 〜0.00042 〜0.00060 〜0.00180 〜0.00300 〜0.00420 〜0.00600 0.00601〜
表流水276 269 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ダム湖沼97 94 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
カルボフラン(カルボスルファン代謝物) 〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水243 233 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ダム湖沼89 85 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
トリクロピル〜0.00006 〜0.00012 〜0.00018 〜0.00030 〜0.00042 〜0.00060 〜0.00180 〜0.00300 〜0.00420 〜0.00600 0.00601〜
表流水246 233 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ダム湖沼91 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
アセフェート〜0.0008 〜0.0016 〜0.0024 〜0.0040 〜0.0056 〜0.0080 〜0.0240 〜0.0400 〜0.0560 〜0.0800 0.0801〜
表流水295 294 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イソフェンホス〜0.00001 〜0.00002 〜0.00003 〜0.00005 〜0.00007 〜0.00010 〜0.00030 〜0.00050 〜0.00070 〜0.00100 0.00101〜
表流水227 221 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水321 320 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
トリクロルホン (DEP) 〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水296 293 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ピリダフェンチオン〜0.00002 〜0.00004 〜0.00006 〜0.00010 〜0.00014 〜0.00020 〜0.00060 〜0.00100 〜0.00140 〜0.00200 0.00201〜
表流水271 267 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水343 342 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ペンシクロン〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水294 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
メコプロップ (MCPP) 〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水264 257 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
メチルダイムロン〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水222 221 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
カルバリル (NAC) 〜0.0005 〜0.0010 〜0.0015 〜0.0025 〜0.0035 〜0.0050 〜0.0150 〜0.0250 〜0.0350 〜0.0500 0.0501〜
地下水336 334 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) 〜0.00006 〜0.00012 〜0.00018 〜0.00030 〜0.00042 〜0.00060 〜0.00180 〜0.00300 〜0.00420 〜0.00600 0.00601〜
表流水291 288 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ピロキロン〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水300 275 10 4 7 1 0 0 3 0 0 0
ダム湖沼101 99 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水384 380 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
フサライド〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.005 〜0.007 〜0.010 〜0.030 〜0.050 〜0.070 〜0.100 0.101〜
表流水322 321 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
メフェナセット〜0.00009 〜0.00018 〜0.00027 〜0.00045 〜0.00063 〜0.00090 〜0.00270 〜0.00450 〜0.00630 〜0.00900 0.00901〜
表流水334 276 12 14 16 9 3 4 0 0 0 0
ダム湖沼109 103 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0
地下水445 442 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
プレチラクロール〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水323 312 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
ダム湖沼110 106 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水433 431 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
メチダチオン (DMTP) 〜0.00004 〜0.00008 〜0.00012 〜0.00020 〜0.00028 〜0.00040 〜0.00120 〜0.00200 〜0.00280 〜0.00400 0.00401〜
表流水277 275 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
地下水373 372 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロモブチド〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水289 230 27 20 5 3 2 2 0 0 0 0
ダム湖沼100 97 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
地下水361 354 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0
モリネート〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水297 249 4 10 16 4 6 6 0 1 0 1
ダム湖沼95 92 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
その他49 48 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
アニロホス〜0.00003 〜0.00006 〜0.00009 〜0.00015 〜0.00021 〜0.00030 〜0.00090 〜0.00150 〜0.00210 〜0.00300 0.00301〜
表流水209 204 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
ダラポン〜0.0008 〜0.0016 〜0.0024 〜0.0040 〜0.0056 〜0.0080 〜0.0240 〜0.0400 〜0.0560 〜0.0800 0.0801〜
地下水252 251 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ジクワット〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
表流水245 240 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ダム湖沼95 93 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
地下水365 359 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
その他50 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
フェンチオン (MPP) 〜0.00001 〜0.00002 〜0.00003 〜0.00005 〜0.00007 〜0.00010 〜0.00030 〜0.00050 〜0.00070 〜0.00100 0.00101〜
表流水299 284 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0
ベノミル〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
表流水251 236 8 3 1 0 3 0 0 0 0 0
ダム湖沼97 95 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ベンフラカルブ〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
表流水245 243 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
シメトリン〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水304 288 11 2 2 0 1 0 0 0 0 0
ダム湖沼100 99 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
エスプロカルブ〜0.0001 〜0.0002 〜0.0003 〜0.0005 〜0.0007 〜0.0010 〜0.0030 〜0.0050 〜0.0070 〜0.010 0.0101〜
全体787 769 15 2 0 0 1 0 0 0 0 0
表流水288 272 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ダム湖沼100 98 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ビフェノックス〜0.002 〜0.004 〜0.006 〜0.010 〜0.0140 〜0.020 〜0.060 〜0.100 〜0.140 〜0.200 0.201〜
ダム湖沼90 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トリシクラゾール〜0.0008 〜0.0016 〜0.0024 〜0.0040 〜0.0056 〜0.0080 〜0.0240 〜0.0400 〜0.0560 〜0.0800 0.0801〜
その他41 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ピペロホス〜0.000009 〜0.000018 〜0.000027 〜0.000045 〜0.000063 〜0.000090 〜0.000270 〜0.000450 〜0.000630 〜0.000900 0.000901〜
表流水223 221 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
地下水291 290 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ジメタメトリン〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
表流水258 257 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
イミノクタジン酢酸塩〜0.00006 〜0.00012 〜0.00018 〜0.00030 〜0.00042 〜0.00060 〜0.00180 〜0.00300 〜0.00420 〜0.00600 0.00601〜
表流水187 184 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
その他37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ポリカーバメート〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
表流水156 152 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
カフェンストロール〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
表流水303 281 7 4 6 1 2 2 0 0 0 0
ダム湖沼104 101 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
http://www.jwwa.or.jp/mizu/pdf/2005-b-01gen-01max.pdf
2009年11月14日
水道統計(水質編)における調査対象項目の解説
● 水道統計(水質編)における調査対象項目の解説
A 水質基準項目(50項目)
水道により供給される水は、水道法第4 条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に
適合することが必要です。
なお、水質基準については、厚生労働大臣により諮問を受け厚生労働審議会において検討がなされました。
その検討経緯は、 に公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/shingikai.html
項目 基準値 解説
1 一般細菌
1ml の検水で形成される集落数が100 以下であること
一般細菌とは、標準寒天培地を用いて36±1℃で24±2時間培養したとき、培地に集落を形成する細菌のことをいう。分類学的に特定のグループを意味するものではない。
一般細菌として検出される細菌の多くは病原菌ではないが、汚染された水ほど多く検出される。
2 大腸菌
検出されないこと
ここでいう大腸菌(Escherichia coli)とは、特定酵素基質培地法によってβ−グルクロニダーゼ活性を有すると判定された好気性又は通性嫌気性の細菌のことをいう。
大腸菌はヒトや温血動物の腸管に常在し、環境中での増殖はまれなため、糞便由来でない細菌も含む大腸菌群と比べて糞便汚染の指標としてより信頼できる。
他の糞便指標細菌と比較すると自然界では生存期間が短いといわれている。飲料水中に大腸菌が存在することは、直ちに対応が必要とされる危険な汚染である可能性を示している。塩素消毒が完全であれば検出されない。
3 カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して、0.01mg/L 以下
カドミウムは、亜鉛とともに自然界にごく微量であるが存在していることが多い。 地表水、地下水中に亜鉛含量の1%以下の割合で存在しているといわれる。
カドミウムの用途は充電式電池、ビニル安定剤のステアリン酸カドミウムなどと広い。
富山県の神通川流域に多発したイタイイタイ病は、鉱山排水中のカドミウムが主な原因とされ、昭和43年(1968)5月8日に
公害病に認定された。慢性中毒では肺気腫、腎障害、骨変化、タンパク尿の症状がみられる。
4 水銀及びその化合物
水銀の量に関して、0.0005mg/L 以下
一般に無機水銀と有機水銀に分けられる。総水銀とは両者の合計量をいう。 主要鉱物は辰砂(HgS)。 常温で唯一の液体金属。
温度計、気圧計などの計器類の他に、各種水銀化合物の原料として、また電極、触媒、水銀灯など、幅広い用途がある。
水銀による急性中毒は口内炎、下痢、腎障害、慢性中毒では貧血、白血球減少を起こし、さらに手足の知覚喪失、精神異常となる。 水俣病の原因は、工場排水中のメチル水銀を摂取した魚介類を食したためである。
5 セレン及びその化合物
セレンの量に関して、0.01mg/L 以下
硫黄鉱床などから産出。周期表では硫黄と同族であるが金属性が大きい。光伝導性のある半導体で多くの同素体がある。光電池、整流器、複写機感光体などの電気材料、有機合成化学の触媒、色ガラス、顔料など、各種部門に広く用途がある。金属セレンの毒性は少ないが、化合物には猛毒のものが多い。
粘膜に刺激を与え、胃腸障害、肺炎などの症状を起こし、全身けいれんから死に至ることがある。
6 鉛及びその化合物
鉛の量に関して、0.01mg/L 以下
方鉛鉱、白鉛鉱を原料鉱として得られる。軟らかく加工しやすい金属なので、昔から水道管として使用されてきた。近年は水道メータの前後など一部に限られている。かつては鉛の表面に酸化被膜ができ、鉛は溶けにくいといわれたが、最近その溶出が問題視され、水道事業体ではステンレス管などに切り替える傾向にある。
鉛は神経系の障害や、貧血、頭痛、食欲不振、鉛疝痛などの中毒症状を呈することが知られている。
7 ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下
自然界では銅、鉄、水銀、鉛、ニッケルなどの鉱物と共存し自然水中に溶出するほか、鉱山排水や工場排水、ヒ酸石灰やヒ酸鉛などの農薬の混入によっても水中に含まれることがある。ヒ素化合物の毒性はその結合形によって異なる。
通常、3価および5価のヒ素化合物として存在し、いずれも毒性を持つが、3価のヒ素の方が5価のヒ素よりも毒性が強い。可溶性無機ヒ素化合物を摂取すると急速に吸収され、肝臓、腎臓、消化管などに強く作用する。
8 六価クロム化合物
六価クロムの量に関して、0.05mg/L 以下
6価の形で存在しているクロムのこと。水に溶けてクロム酸および重クロム酸を生成する。メッキ廃水に多量に含まれる。6価クロム塩を多量に摂取した場合、嘔吐、下痢、尿毒症などを引き起こす。致死量は成人の場合K2CrO7で0.5〜1gである。
9 シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して、0.01mg/L 以下
シアン化合物には、シアン化ナトリウム、シアン化カリウムのように水中でシアンイオン、シアン化水素を容易に生成する遊離型シアンと、フェリシアン化カリウム、フェロシアン化カリウムのように金属錯化合物を形成する錯塩シアンがある。
シアンは、めっき、鉄鋼製造、金銀の選鉱や多くの化学合成工業で使用される。シアンは自然中にはほとんど存在しない。シアン化合物を含んだ工場排水の混入によって水中に見いだされる。
また、含窒素化合物の燃焼によってもシアンが生じる場合がある。シアン化合物には強い毒性がある。ヒトの体内にはいると、粘膜から吸収され、頭痛、吐き気などを引き起こし、死亡する場合もある。
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/L 以下 (硝酸態窒素)
水中の硝酸イオン(NO3−)および硝酸塩に含まれている窒素のことである。硝酸イオンは有機および無機の窒素化合物の最終的酸化形である。
硝酸態窒素を多量に含む水を摂取した場合、体内で細菌により硝酸塩は亜硝酸塩へと代謝され、亜硝酸塩は血液中でメトヘモグロビンを生成して呼吸酵素の働きを阻害しメトヘモグロビン血症を起こす。
(亜硝酸態窒素)
水中の亜硝酸イオン(NO2−)または亜硝酸塩に含まれている窒素のことである。水に混入したアンモニア態窒素が酸化されて生ずる場合が多いが、硝酸態窒素の還元によって生じる場合も多い。
亜硝酸塩は赤血球のヘモグロビン(体内組織へ酸素を運搬する)と反応してメトヘモグロビンを生成し、呼吸酵素の働きを阻害するメトヘモグロビン血症を起こす。
体内で硝酸態窒素は亜硝酸態窒素へと速やかに変化するため、水道水質基準は硝酸態窒素および亜硝酸態窒素の合計量となる。
11 フッ素及びその化合物
フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下
水中のフッ素は、主として地質や工場排水の混入などに起因する。自然界に広く分布しているホタル石はフッ化カリウムが主成分であるため、日本でも特に温泉地帯の地下水や河川水に多く含まれることがある。
フッ素を適量に含んだ水を飲用した場合には「う歯」(むし歯)の予防に効果があるといわれているが、多量に含まれていると斑状歯(歯牙の慢性フッ素中毒)の原因となる。
12
ホウ素及びその化合物
ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下
ホウ素は、自然中に含まれることはまれであるが、火山地域の地下水、温泉水にはメタホウ酸の形で含まれることがある。また、金属の表面加工処理剤、ガラス、エナメル工業などで使用されるので、これらの工業排水に混入することがある。
ホウ酸を少量摂取した場合には緩和な生理作用を示すに過ぎないが、多量のときには消化器、神経中枢等に影響を及ぼす。ホウ素による中毒症状は、一般に胃腸障害、皮膚紅疹、抑うつ症を伴う中枢神経刺激の症状である。
13 四塩化炭素
0.002mg/L 以下
テトラクロロメタン、ベンジノホルムともいう。比重1.59(20℃)。融点−23℃、沸点76.5℃の無色透明な液体。水に対する溶解度は800mg/L(25℃)で、アルコール、エーテル、クロロホルムなどに混和する。蒸気圧115mmHg(25℃)。主な用途はフロンガスの製造原料、薫蒸殺菌剤、金属洗浄用溶剤などある。
液化塩素に不純物として存在することがある。その毒性は肝臓の感受性が最も高く、脂肪浸潤、肝細胞内酵素の遊離、細
胞内酵素活性の抑制、炎症が起こり、最終的に肝細胞壊死を引き起こす。
14 1,4-ジオキサン
0.05mg/L 以下
1,4-ジオキサンは、特異的な臭気のある無色の液体である。溶剤や1,1,1−トリクロロエタン安定剤などの用途に使用されるほか、ポリエキシエチレン系非イオン界面活性剤及びその硫酸エステルの製造工程において副生し、洗剤などの製品中に不純物として存在する。その毒性は目に強い刺激性を有し、肝臓、腎臓、中枢神経に影響を与え、また皮膚の脱脂を起こすことがある。
ヒトに対しては、弱い遺伝毒性しか示されていないが、多臓器での腫瘍を誘発することが報告されている。IARC では、ヒトへの発ガン性の可能性があるとして、Group2B に分類している。
15 1,1-ジクロロエチレン
0.02mg/L 以下 1,1,−ジクロロエチレンは、揮発性有機塩素化合物であるが、蒸気は空気より重い。酸化されやすく、酸素と接触すると過酸化物を生成する。
1,1−ジクロロエチレンの環境への放出は、製造過程及びポリマー製造の原料として使用されている際に起きる。揮発性のため、ほとんどが大気中へ移行していき、地表水を汚染した1,1−ジクロロエチレンも速やかに揮発する。
地下水では、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びこれらの分解成物である1,2−ジクロロエチレンや塩化ビニルと共存することが知られている。
主たる用途は、塩化ビニリデン樹脂の製造原料である。塩化ビニリデン樹脂は、家庭用ラップ、食品包装用フィルム、紙やプラスチックの表面コーティング等に使用される。ヒトでは、神経症状、肝機能障害、頭痛、視覚障害等がある。
16 シス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下 化学合成品はシス体とトランス体の混合物である。水には難溶であるが、各種の有機溶剤には易溶である。化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用される。ヒトに対して麻酔作用がある以外に報告例がない。
シス-1,2-ジクロロエチレンの環境中への放出は、製造過程及び溶剤として使用する過程で起きる。揮発性のため、多くが大気中に移行する。
地表水を汚染したシス-1,2-ジクロロエチレンは速やかに大気中に揮散する。土壌に浸透すると吸着されにくく、地下水中に長期間滞留する。地中のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが還元状態で微生物分解を受けると、シス-1,2-ジクロロエチレンが生成される。地下水中では、多くの場合トリクロロエチレンと共存している。
シス体とトランス体の混合物の毒性はLD50(ラット,経口)770mg/kgで、単回投与によりラットの肝アルカリホスファターゼが顕著に増加した。多量に摂取した場合には、腹痛、咳、咽頭痛、めまい、吐き気、嗜眠、脱力感、意識喪失、嘔吐等の急性症状がみられる。
17 ジクロロメタン
0.02mg/L 以下
沸点40℃の無色の液体。合成有機化学物質であり、自然界には存在しない。殺虫剤、塗料、ニス、塗料剥離剤、食品加工中の脱脂処理および洗浄液などとして使われる。
表流水中に排出されたジクロロメタンは大気中に揮散し数日から数週間で分解するが、地上に排出されたジクロロメタンは容易に地下水に移行し、長期間残留する。
ジクロロメタンの毒性はLD50(ラット,経口)2,121mg/kg、(マウス,経口)1,987mg/kgである。また、1.3mg/kg体重の単回投与では、呼吸困難、運動失調、チアノーゼ及び昏睡が認められた。多量に摂取した場合には、腹痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感、意識喪失の急性症状がみられる。
18 テトラクロロエチレン
0.01mg/L 以下
テトラクロロエテン、パークレン、パークロロエチレンともいう。比重1.62(20℃)、融点22.4℃、沸点121.2℃の液体。蒸気圧19mmHg。水に対する溶解度150mg/L(25℃)。主な用途はドライクリーニング溶剤,金属用脱脂剤など。
この物質は使用後排出され、土壌中を移行して直ちに地下水中に入り、地下水汚染物質の一つとなっている。地下水中では数カ月から数年間にわたって残留する。
トリクロロエチレンに比べて尿中代謝物排泄ははるかに少ない。その毒性はLD50(ラット,経口)8.85g/kgで、肝
腎障害や中枢神経抑制作用があり、また、肝ガンの発生も認められている。多量に摂取した場合には、腹痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感、意識喪失の急性症状がみられる。
19 トリクロロエチレン
0.03mg/L 以下
TCE、トリクレン、トリクロロエテンともいう。比重1.4 (25℃)、融点−86.4℃、沸点86.7℃の無色透明の液体。蒸気圧77mmHg(25℃)。
水に対する溶解度1g/L(20℃)。主な用途は金属の脱脂剤である。環境に放出されて地下水汚染を超こす。地下水中に長期間残留 し、分解してジクロロエチレンや塩化ビニルになる。
また,テトラクロロエチレンの分解によって生成することもある。体内吸収では抱水クロラールを経てトリクロロ酢酸に代謝される。毒性はLD50(ラット,経口)4.92g/kgで、発ガン性も認められる。多量に摂取した場合の急性症状は、腹痛、めまい、し眠、頭痛、脱力感、吐き気、意識喪失がある。
20 ベンゼン
0.01mg/L 以下
揮発性のある無色の液体で、芳香族特有の芳香があり、引火性が大きい。エタノールおよびエーテルとはすべての割合で混合するほか、多くの有機溶媒に可溶である。
水には難溶。置換、付加および開裂の三つの反応が起こり、多種の芳香族化合物を生成する。溶剤、燃料、アルコール変性剤などとしても重要である。
発ガン性を有する。その毒性はLD50(ラット、マウス,経口)1〜10g/kgで、発ガン性や骨髄形成不全、リンパ球減少症
も認められる。多量に摂取した場合の急性症状は、腹痛、咽頭痛、嘔吐がある。
21 クロロ酢酸
0.02mg/L 以下
クロロ酢酸は、刺激臭のある無色の結晶である。除草剤、チューインガム可塑剤、塩化ビニル可塑剤、医薬品、アミン酸等合成、香料、キレート剤、界面活性剤として使用される。
クロロ酢酸などのハロゲン化酢酸類は、水道水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒
副生成物の一つである。その毒性はLD50(ラット,経口)55mg/kgで、皮
膚や鼻、目の粘膜を腐食する。変異原性が認められる。
22 クロロホルム
0.06mg/L 以下
比重1.49(20℃)。融点−63.5℃、沸点61.2℃の無色透明の液体で、甘い刺激臭がある。水に対する溶解度は0.28g/100g(20℃)で,エタノール、エーテルなどには易溶である。
主な用途として医薬品、溶剤、有機合成の原料などがある。クロロホルムは、浄水処理における塩素消毒によって生成するトリハロメタンの主成分である。クロロホルムには強い麻酔作用があり、肝臓、腎細尿管、心臓などに細胞毒として作用する。
また、動物実験によって腎腫瘍や肝癌などの発癌性が確認されている。低濃度の慢性毒性では胃腸、肝腎障害が起こり、高濃度では反射機能の喪失、感覚麻痺、呼吸停止などが起こる。
23 ジクロロ酢酸
0.04mg/L 以下
ジクロロ酢酸は、刺激臭のある無色の液体である。ジクロロ酢酸などのハロゲン化酢酸類は、浄水過程において水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物物質の一つである。
マウスに75週にわたってジクロロ酢酸を飲水投与した結果、最大無作用量は50mg/kg/日である。慢性試験で発ガン性を示す根拠は認められていない。IARC では、ヒト発ガン性物質として分類できないとして、Group3に分類されている。
24 ジブロモクロロメタン
0.1mg/L 以下
浄水処理過程で使われる消毒剤の塩素と水中のフミン質などの有機物質が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。生成量は原水中の臭素イオンに大きく影響される。
写真工業の排水や海水の影響を受けやすいところ、また塩分を含む地下水で臭素化トリハロメタンが多い。その毒性はLD50(雄マウス,経口)800mg/kg、(雌マウス,経口)1200mg/kgである。参考文献:アメリカ国家毒性プログラムNTP(1985)ではマウスによる2 年間の経口投与実験では、肝の脂肪変性、腎ネフローゼが認められた。
25 臭素酸
0.01mg/L 以下
臭素酸の最も一般的な形態が臭素酸カリウムと臭素酸ナトリウムである。臭素酸カリウムは小麦粉改良材として、臭素酸ナトリウムは分析用試薬、毛髪のコールドウェーブ用薬品等に使用される。
浄水処理においてオゾンを使用する場合、臭素イオンから消毒副生成物として生成される。また、消毒剤としての次亜塩素酸ナトリウム生成時に、不純物の臭素が酸化され、臭素酸が生成される。
毒性影響には、腹痛、中枢神経系の機能低下、呼吸困難、肺浮腫、腎機能低下、聴覚障害等及び発ガン性が報告されている。
ヒトが摂取すると消化管から速やかに吸収され、肝臓でグルタチオン抱合された後臭化物に還元される。IARC では、実験動物の発ガン性に関しては十分な証拠があるとして、Group2B に分類している。
26 総トリハロメタン
0.1mg/L 以下
メタン(CH4)の水素原子3個が、塩素、臭素、あるいはヨウ素に置換された有機ハロゲン化合物の総称。THMと略称される。これらのうち、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の合計を総トリハロメタン(TTHM)と呼ぶ。
水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に存在するフミン質などの有機物を前駆物質として、塩素処理によって生成する。なかでもクロロホルムは発ガン物質であることが明らかとなっている。
27 トリクロロ酢酸
0.2mg/L 以下
トリクロロ酢酸は、刺激臭のある無色で吸湿性の結晶である。医薬品の原料、除草剤、腐食剤、角質溶解剤、塗装剥離剤、除タンパク剤、生体内タンパク・脂質の分画剤として使用される。水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物質の一つである。
マウスで肝腫瘍を引き起こすが、変異原性や染色異常などのin vitro 系の試験では陰性及び陽性の結果が混在して報告されており、IARC ではヒト発ガン性物質として分類できないとしてGroup3に分類されている。
28 ブロモジクロロメタン
0.03mg/L 以下
浄水処理過程で使われる消毒剤の塩素と水中のフミン質などの有機物質が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。生成量は原水中の臭素イオンに大きく影響される。写真工業の排水や海水の影響を受けやすいところ、また塩分を含む地下水で臭素化トリハロメタンが多い。
その毒性はLD50(雄マウス,経口)450mg/kg、(雌マウス,経口)900mg/kgである。参考文献:アメリカ国家毒性プログラムNTP(1987)では、マウスによる2 年間の経口投与実験では、腎細胞肥大、肝の脂肪変性のほか腎臓の腺腫と腺がん、肝細胞の腺腫と腺がんがみられた。
29 ブロモホルム
0.09mg/L 以下
同上
30 ホルムアルデヒド
0.08mg/L 以下
ホルムアルデヒドは、特徴的な臭気のある気体で、有機溶媒に易溶である。浄水過程で、水中のアミン等の有機物質と塩素、オゾン等の消毒剤が反応して生成される。
主要な構成物資として、ホルムアルデヒドとアセトアルデヒド等がある。エポキシ樹脂塗料及びアクリル樹脂塗料の原料として
使用される。土壌燻蒸剤として線虫等の駆除に使用される。
野菜、樹木の苗木などの防除に使用される。ヒトへの健康影響としては、内服したとき、呼吸困難、めまい、嘔吐、口腔及び胃に炎症が起きる。
吸入曝露試験では発ガン性を示し、鼻と喉の灼熱感、頭痛、吐き気などが起こり、短期暴露の場合、眼、皮膚、気道に対して腐食性があり、肺水腫を起こすこともある。
高濃度で死に至ることもある。経口曝露では明らかな発ガン性は示さない。
31 亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下
自然水中に微量に含まれるが、高濃度の亜鉛は鉱山排水や工場排水などによる汚染が原因であることが多い。水道水で高濃度の亜鉛が検出される場合は、そのほとんどが給水管などの亜鉛引き鋼管からの溶出による。
水道水に高濃度の亜鉛が含まれていると白濁して、いわゆる白水の原因となる。また5mg/L以上含まれると収れん味を呈する。毒性は比較的弱いが、高濃度の場合には腹痛、嘔吐、下痢などの中毒症状をもたらすことがある。
32 アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下
地球の表面に存在する元素で3番目に多く、金属では最も多い。比重が2.6で、さびにくく、かなり丈夫なので航空機、自動車、建築物などに使われている。
アルミニウムの化合物である明ばんは昔から水の清澄剤として、また,硫酸アルミニウム、ポリ塩化アルミニウムも水道水の水処理剤として用いられている。
濃度が高いと、白濁水の原因となる。
33 鉄及びその化合物
鉄の量に関して、0.3mg/L 以下
クラーク数は4.7で、酸素、ケイ素、アルミニウムについで地球で4番目に多い元素である。地表水中ではFe(OH)3として懸濁して存在している。
また,泥炭地などの有機物の多いところではコロイド性の有機錯体として存在する。自然水中に含まれる鉄は、地質に起因するもののほか鉱山排水、工場排水などからの場合もある。0.3mg/L以上溶解すると、水に色がつきはじめ赤水の原因となり、臭気や苦味を与える(0.5mg/L)。
鉄は栄養上,1人1日当たり約10mg以上必要とされている。鉄塩の毒性はLD50(マウス,経口)300〜600mg/kg、LD50(ラット,経口)800〜2,000mg/kgである。
急性毒性は、うつ病、昏睡、呼吸障害や心拍停止などである。
34 銅 及びその化合物
銅の量に関して、1.0mg/L 以下
天然には主として硫化物(黄銅鉱、班銅鉱、輝銅鉱)の形で産出する。電線、合金、貨幣、彫刻、メッキ、農薬など、多くの分野に用いられる。
銅イオンを1.0mg/L以上含む水は金属味を帯び、着色(青色)を与える。ヒトにとって銅は必須元素であり、成人の必要量は1日に約2mgとされている。
銅化合物は藻類、カビ類、無脊椎動物に対しては強い毒物であるが、哺乳類に対しては蓄積性が認められないので慢性中毒のおそれは少ない。
35 ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下
地殻中に広く分布。海水中には約10g/L含まれ、また岩塩として巨大な鉱床をつくる。ナトリウムは自然水中に広く存在する元素であるが、海水、工場排水の混入、水処理時のカセイソーダによるpH調整などに由来することもある。
ナトリウムイオンは動物体内の生理に重要な役割を果たしている。ナトリウムと高血圧との関係はよく論じられるが、1日1.6〜9.6gの摂取量では人の健康に何ら影響はないとみられている。
36 マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下
マンガンは地殻中に広く分布しており、軟マンガン鉱などに多く含まれる。生理的に不可欠の元素で、炭水化物の代謝などに関与する。水道水中にマンガンが多いと、浄水に黒い色をつけるので好ましくない。
過剰摂取すると全身倦怠感、頭痛、不眠、言語不明瞭などの中毒症状を起こす。
37 塩化物イオン
200mg/L 以下
水中に溶存している塩化物中の塩素のこと。自然水は常に多少の塩化物イオンを含んでいるが、これは地質に由来するもので、特に海岸地帯では海水や送風塩の影響によることが大きい。
しかし、塩化物イオンは下水系、生活系および産業系などの各排水や、屎尿処理水などの混入によっても増加する。したがって、塩化物イオンは水質汚濁の指標の一つともなっている。
硝酸銀と反応して塩化銀の白色沈澱を生ずるため、測定にはこの性質を利用した硝酸銀法(モール法)がある。多量の塩化物イオンは水に味をつけたり、鉄管などの腐食を促進する傾向がある。塩化物の毒性は陽イオンの種類によって異なっており、塩化物イオン自体の毒性は知られていない。
しかしながら、2.5mg/L 以上の濃度の塩化ナトリウムを含む飲料水を過剰に飲用していると高血圧症を引き起こすと報告されている。
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
300mg/L 以下 (カルシウム)
アルカリ土壌金属の一つで、展性・延性がある。自然界には遊離状態で産出されず、炭酸塩およびケイ酸塩として広く多量に存在する。水中ではカルシウムイオン(Ca2+)と して存在し、硬度の主体をなしている。その起源は地質によるものが主であるが、他にコンクリート構造物からの溶出、海水、工場排水および温泉などの混入に由来するものがある。
原子吸光分析法により波長422.7nmの吸光度を測定する方法やカルシウム硬度による測定方法(EDTA法)などがある。
(マグネシウム)
アルカリ土類金属の一つ。自然界では単体としては存在せず、炭酸塩、ケイ酸塩、硫酸塩および塩化物などとして広く多量に存在する。
水中にはマグネシウムイオンとして存在し、カルシウムイオンとともに硬度の主体をなしている。その成因は主に地質に由来するが、鉱山排水、工場排水、海水および温泉などの混入によることもある。原子吸光分析法により波長285.2nmで吸光度を測定する方法や総硬度とカルシウム硬度の差から求める測定法がある。
健康障害としては、硬度が高すぎると胃腸を害して下痢を起こすことがある。
39 蒸発残留物
500mg/L 以下
水を蒸発乾固したときに残る物質。具体的には、一定量の検水を蒸発皿に入れて水浴上で蒸発乾固し、残った物質量を求める。濁質のある検水をそのまま蒸発乾固すれば、浮遊物質と溶解性物質との総和となる。
水道水の主な蒸発残留物の成分は、カルシウム、マグネシウム、シリカ、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物である。健康への影響はほとんど生じない。
40 陰イオン界面活性剤
0.2mg/L 以下
界面活性剤のうち、水溶液中で電離して活性剤の主体が陰イオンになるもの。工場排水、家庭下水などの混入に由来し、水中に存在すると泡立ちの原因となり、汚濁の重要な指標である。
また、陰イオン界面活性剤に付随するリン酸塩による水源の富栄養化が問題となっている。その毒性はほとんど認められない。
41ジェオスミン
0.00001mg/L 以下
ジェオスミンは、湖沼等で富栄養化現象に伴って発せするかび臭(異臭味)の原因物質である。藍藻類のアナベナにより産生される。その毒性はほとんど認められない。
42 2−メチルイソボルネオール
0.00001mg/L 以下
2−メチルイソボルネオールは、湖沼等で富栄養化現象に伴って発せするかび臭(異臭味)の原因物質である。藍藻類のフォルミディウムやオッシラトリアにより産生される。その毒性はほとんど認められない。
43 非イオン界面活性剤
0.02mg/L 以下
非イオン界面活性剤とは、界面活性剤のうち、イオンに解離する基を持たない物質の総称である。エーテル型、エーテルエステル型、エステル型、含窒素型が知られている。
洗浄剤、乳化剤、分散剤、消泡剤、潤滑油、化粧品、流出油の処理剤等に使用される。その毒性は、一般に陰イオン界
面活性剤に比べ低く、健康への影響はほとんど生じない。
44 フェノール類
フェノールの量に換算して、0.005mg/L 以下
芳香族化合物のベンゼン環の水素が、水酸基で置換された化合物の総称で、環境汚染に関連するものは主としてフェノール(石炭酸)、ο−,m−,p−クレゾール、クロロフェノールなどである。合成樹脂、界面活性剤などの原料として大量に使用されている。
フェノール類は、天然水中には存在しないが、化学工場排水、ガス製造工場排水などに含まれる。フェノール類が含まれていると水の塩素処理過程でクロロフェノール類が生成し、水に著しい異臭味を与えるので、厳しい排水基準が示されている。
45有機物(全有機炭素(TOC)の量)
5mg/L 以下
水中の全有機炭素(TOC : Total Organic Carbon)は、種々の有機化合物から構成されていて、これらの有機化合物に含まれている炭素量をいう。全有機炭素は、水中に含まれる有機物総量の指標として用いることができるため、原水の有機性汚濁の状況や浄水処理過程における水の処理性評価に利用することができる。
また、溶存有機炭素(DOC)も有機性汚濁の指標として用いられている。
46 pH値
5.8 以上8.6以下
水素イオンのモル濃度(水素イオン濃度)の逆数の常用対数値。pH7は中性、pH7より値が小さくなるほど酸性が強くなり、値が大きくなるほどアルカリ性(塩基性)が強くなる。
水道法に基づく水質基準は5.8以上8.6以下であること、また、水質管理目標設定項目としての目標値は7.5程度
とされている。水の基本的な指標の一つであり、理化学的水質、生物学的水質、浄水処理効果、管路の腐食などに関係する重要な因子である。
測定法はガラス電極法(pH計)がある。
47 味
異常でないこと
水の味は、水に溶存する物質の種類・濃度によって感じ方が異なる。味の原因には、下水、工場排水等による汚染、生物や細菌類の繁殖、また、海岸地帯では海水の影響をうけ塩味を感じることもある。
異常な味は不快感を与えるので飲用には適さない。
48 臭気
異常でないこと
水の臭気は水に溶解している種々の物質が原因となっています。水道において問題となる臭気物質は、藻類や放線菌等の生物に起因するかび臭物質、フェノールなどの有機化合物が主です。異常な臭気は不快感を与え
るので飲用には適しません。
49 色度
5 度以下
水中に含まれる溶解性物質およびコロイド性物質が呈する黄褐色の程度をいう。原水においては、主に地質に由来するフミン質、フミン酸鉄による呈色と同じ色調の色について測定される。水道水においては配管等からの鉄の溶出などによって色度が高くなることがある。
精製水1L中に白金イオン1mgおよびコバルトイオン0.5mgを含むときの呈色に相当するものを1度としている。
50 濁度
2 度以下
濁度は、水の濁りをポリスチレン系粒子(5種類)を濁質の標準液とし、これと比較して測定する。水道において、原水濁度は浄水処理に大きな影響を与え,浄水管理上の指標となる。
また、給水栓中の濁りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要である。
B 水質管理目標設定項目(27項目)
水質基準とするにいたりませんが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目、必要に応じ水質検査を実施する項目です。このうち農薬類については、全国の検出状況や使用量などを考慮して、101項目がリストアップされ、「総農薬方式」とよばれる考え方で設定されています。
項目 目標値 解説
1 アンチモン及びその化合物
アンチモンの量に関して、0.015mg/L 以下
アンチモンは、半導体材料、潤滑剤、弾薬、陶器、硝子など材料成分として主に使われている。三価アンチモンは容易に赤血球に取り込まれるが、五価アンチモンは取り込まれない。飲料水中のアンチモンの形態が毒性のキー決定要因であるが、飲料水中のアンチモンはほとんどが、弱毒性型の五価アンチモン、オキソ-陰イオン型と思われる。
ヒトへの健康影響では、嘔吐、下痢が知られていて、三価アンチモンの発ガン性はグループ2Bに分類されているが、この判断となった知見のほとんどは、水に不溶な粒子による吸入暴露によるものであり、水溶性アンチモンの経口摂取による発ガン性を示す知見は知られていない。
2 ウラン及びその化合物
ウランの量に関して、0.002mg/L 以下(暫定)
ウラン化合物はガラス・磁器の着色剤、光電管にも使用されているが、主に原子炉の燃料として使用されている。ごく微量であるが、地球の表面の近くの岩石(特に花崗岩)及び海水中に広く分布している。
ウランを含む鉱石や廃棄された選鉱くずからの溶出、核物質使用工場からの排出、石炭及び他の燃料の燃焼、ウランを含むリン酸肥料の使用になどにより環境中に放出される。
ウランの健康影響としては化学毒性による眼粘膜刺激、催涙及び結膜炎、吸入による気道刺激、腎障害などがある。また、放射線障害による肺ガン、リンパ腫の増加などがある。
3ニッケル及びその化合物
ニッケルの量に関して、0.01mg/L 以下(暫定)
ニッケルは、ステンレス綱、めっき、貨幣、顔料、触媒原料などに使用されている。ニッケルの化合物は不溶性のものが多いので、自然水中に存在することはまれであるが、鉱山排水、工場排水あるいはニッケルめっきの溶出などから混入することがある。また、水道では管材及びその他の材料の腐食による汚染がある。
大量に摂取するとめまい、嘔吐、急性胃腸炎を引き起こす。発ガン性の評価については、金属ニッケルではIARCグル
プ2B、ニッケル化合物ではグループ1にそれぞれ分類されている。
4亜硝酸態窒素
0.05mg/L 以下(暫定)
水中に含まれる亜硝酸イオン中の窒素の量であり、窒素肥料、腐敗した動植物、家庭排水等に由来する。これらに含まれる窒素化合物は、環境中で化学的・微生物学的に酸化及び還元を受け、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素等になる。
摂取すると体内で食物中のタンパク質に含まれるアミン類と結合し、発ガン物質であるニトロソアミンを生成したり、急性毒性を引き起こす危険性がある。
塩素処理により容易に硝酸態窒素へと酸化されるので、通常の浄水処理により除去され、残留塩素のある浄水には存在しな
い。
5 1,2-ジクロロエタン
0.004mg/L 以下
主に塩化ビニルモノマーの原料として使用されるほか、有機溶剤、殺虫剤、金属の脱脂洗浄等に使用されている。環境中には、貯蔵タンクからの漏出や工場排水等により放出されるおそれがある。地表水を汚染した場合は比較的容易に大気中に揮散するが、土壌吸着性は低く、土壌を浸透し地下水に進入すると安定な形で閉じこめられるため長期間にわたり汚染が継続する。
健康影響はめまい、吐き気、嘔吐などがある。
6 トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下
シス体との混合物で使用され、化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用されている。また、トリクロロエチレンの分解物でもある。吐き気、眠気、疲労感、めまい等の中枢神経系への影響がある。
7 1,1,2-トリクロロエタン
0.006mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレンの製造原料、油脂、ワックス、天然樹脂の溶剤として使用されている。土壌吸着性は低く、地下水中に長時間残留する。長期暴露では慢性胃炎、肝臓への脂肪蓄積、肺障害など、上記暴露では呼吸器と眼に対する刺激作用がある。
8 トルエン
0.2mg/以下
染料、香料、有機顔料、ポリウレタン、合成繊維などの原料として、また、樹脂や塗料の溶剤として使用されている。石油成分の一つで石油分留生成で得られる。
健康影響としては、急性暴露により、頭痛、吐き気、錯乱などの症状を引き起こす。
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
0.1mg/L 以下
可塑剤として、ポリ塩化ビニルフィルム、シート、レザー、ホース、機械器具部品、日用雑貨などに使われ、また農薬、化粧品、染料、印刷インクなどの溶剤や保留剤としても使用されている。
大量摂取により、胃腸、肝臓障害などの報告例がある。
10亜塩素酸 0.6mg/L 以下
11塩素酸 0.6mg/L 以下
12二酸化塩素 0.6mg/L 以下
主に漂白剤として使用されている。二酸化塩素を浄水過程で酸化剤として使用した場合に検査を行うことが望ましいとされている項目である。
亜塩素酸塩、塩素酸塩から合成される二酸化塩素を処理水中に投入した場合に分解生成物として亜塩素酸イオン、塩素酸イオンが生成する。
赤血球中のヘモグロビンが亜塩素酸塩により酸化され、メトヘモグロビンを形成することによる中毒症が知られている。
13 ジクロロアセトニトリル
0.04mg/L 以下(暫定)
塩素処理の際に遊離塩素とフミン物質、藻類、アミン酸が反応してできる副生成物の1 つである。時間の経過とともに、また水温が高いほど生成量は増加するが、トリハロメタンほど顕著ではない。土壌や汚泥等にはあまり吸着せず、生物への濃縮もあまり大きくないと考えられている。
14 抱水クロラール
0.03mg/L 以下(暫定)
塩素消毒の際に遊離塩素とフミン質、酸化シアンが反応してできる副生成物の1つである。鎮静剤、睡眠薬等の医療用として、医薬品や農薬の原料として使用されている。
15 農薬類
検出値と目標値の比の和として、1 以下
水源上流などにおける農薬の使用状況により、使用されている薬剤について検査を行うこととされている。計101 種類の農薬が対象になっていて、総農薬方式として評価される。
16 残留塩素
1mg/L 以下
水中に塩素を注入することによって水中に残留した有効塩素をいい、次亜塩素酸などの遊離有効塩素(遊離残留塩素)とクロラミンのような結合有効塩素(結合残留塩素)に区分される。残留塩素の測定にはDPD法、ポーラログラフ法及び吸光光度法がある。
衛生上の措置として給水の残留塩素を遊離残留塩素として0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するよう規定している。
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
10mg/L 以上
100mg/L 以下
水質基準項目 38 を参照。
18マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.01mg/L 以下
水質基準項目 36 を参照。
19 遊離炭酸
20mg/L 以下
水中に溶解している二酸化炭素(CO2)のこと。遊離炭酸は炭酸塩や有機物質が分解して発生した二酸化炭素や空気中の二酸化炭素などが水中に溶解することに起因する。
地下水では有機物の分解などにより、一般に多く存在する。遊離炭酸には水中のアルカリ化合物と反応して炭酸化合
物を生成させるような腐食性のある侵食性遊離炭酸と、腐食性のない従属性遊離炭酸がある。
20 1,1,1-トリクロロエタン
0.3mg/L 以下
ドライクリーニング用溶剤、金属の脱脂洗浄剤、繊維のしみ抜き剤などに使用されている。健康影響としては、吐き気、下痢、めまい、ふらつきなどの症状がある。
21メチル-t- ブチルエーテル
0.02mg/L 以下
ガソリンのオクタン価向上剤、アンチノック剤、ラッカー混合溶剤の混和性改良材などに使用されている。健康影響については、毒性評価が詳細にされていないのが現状であるが、地下水で一過的に高濃度で検出されるとの情報もある。
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)
3mg/L 以下
水中の有機物や還元性物質(被酸化性物質)の量を、酸化させるのに必要な過マンガン酸カリウムの量として表したもので、一般に有機物の含有量の指標になっている。
土壌に由来するフミン質を多く含む場合や水道水源にし尿、下水又は工場排水が混入した場合に増加する。有機物の多い
水は渋みがあり、また、消毒に用いる塩素の消費量も多くなり、その点で水の味を損なう原因になる。
23 臭気強度(TON)
3 以下
検水の臭気をほとんど感知できなくなるまで無臭味水で希釈し、その希釈倍率によって示される臭気の強さのこと。TON ともいう。臭気に対する感受性は個人差があり、また、同一人でも測定時の状態で差異を生じるため、複数人数による試験が望ましい。
24 蒸発残留物
30mg /L 以上
200mg/L 以下
水質基準項目 39 を参照
25 濁度
1 度以下
水質基準項目 50 を参照
26 pH 値
7.5 程度
水質基準項目 46 を参照
27 腐食性(ランゲリア指数)
−1 程度以上とし、極力0に近づける
水のpH 値、カルシウムイオン量、総アルカリ度及び溶解性物質から求められるもので、水のpH値とその水の理論的pH 値との差を表す。指数が正の値で絶対値の大きいほど炭酸カルシウムの析出が起こりやすくなる。
また、負の値では炭酸カルシウム被膜が形成されず、その絶対値が大きくなるほど水の腐食傾向は強くなる。
C その他の項目
水質基準・水質管理目標設定項目ではありませんが、水道に関連する項目です。
項目 解説
1 水温
水温は、地表水の場合、気温の影響を受けやすく、湖沼や貯水池の場合、水温の変化によって、比重が変わり、水の停滞や循環などの原因となる。また、水温の上昇は物質の溶解性、生物の消長、河川での自浄作用などに影響を与える。
2 アンモニア態窒素
水中のアンモニウムイオン(NH4+)に含まれる窒素のこと。有機窒素化合物の分解、工場排水、下水および屎尿の混入によって生ずる場合が多い。土壌や水中の細菌により亜硝酸態窒素、硝酸態窒素へと酸化され、嫌気性状態では逆に硝酸態窒素、亜硝酸態窒素が還元されてアンモニア態窒素となる。
浄水処理では塩素処理や、緩速濾過のような生物化学処理によって分解され減少するので、処理工程の管理指標としても重要な項目である。測定方法にはインドフェノール法、ネスラー法、α−ナフトール法、蒸留比色法がある。
3 生物化学的酸素要求量(BOD)
水中の有機物が生物化学的に酸化されるのに必要な酸素量のことで、生物化学的酸素要求量ともいう。生物化学的酸化とは、水中の好気性微生物が有機物を栄養源とし、水中の酸素を消費してエネルギー化、生命維持・増殖するとき、有機物が生物学的に酸化分解されることをいい、有機物が多いほど消費される酸素量が多くなる。
したがって、BODが高いことはその水中に有機物が多いことを示し、化学的酸素要求量(COD)とともに水質汚濁を示す重要な指標である。生物化学的酸素要求量は試料を20℃、5日間静置し、静置前と後の溶存酸素量をウィンクラー法で測定し、その間に消費された溶存酸素量(mg/L)で表す。
4 化学的酸素要求量(COD)
化学的酸素要求量のこと。水中の被酸化性物質(有機物)を酸化剤で化学的に酸化したときに消費される酸化剤の量を酸素に換算したもの。CODが高いことはその水中に有機物が多いことを示し、生物化学的酸素要求量(BOD)とともに水質汚濁を示す重要な指標である。
測定方法には酸性過マンガン酸カリウム法があるが、酸化剤として重クロム酸カリウムを使用する方法もある。
5 紫外線(UV)吸光度
紫外線領域における特定波長の吸光度(紫外部吸光度、UV 吸光度)または透過率を光電的に測定し、検量線により濃度を求める方法。紫外線とは波長360〜400 以下1nm 程度までの電磁波を指すが、200nm 以下の波長域は空気による吸収があり、真空中で測定する必要があるため真空紫外線とよんでいる。
光源には石英水銀灯、重水素放電管、セキノンランプなどが用いられている。測定には紫外線領域に吸収の少ない石英セルを使用する。
6 浮遊物質(SS)
水中に懸濁している粒径1μm〜2mm 程度の不溶解性物質のことをいう。SSと記すこともある。上水試験方法では、網目2mm のふるいを通過した一定量の試料を1μm のメンブレンフィルターでろ過し、その残留物105〜110℃で2 時間乾燥し、秤量して求める重量法を定めている。
濁度との相関が議論されることがあるが、厳密な意味での相関関係はない。浄水処理、排水処理などに影響を及ぼす。
7 侵食性遊離炭酸
水中のアルカリ化合物と反応して炭酸化合物を生成させるような腐食性のある水中に溶解している二酸化炭素(CO2)のこと。
8 全窒素
水中に含まれる窒素化合物の総量のことで、窒素量で表す。窒素はリンとともに水源の富栄養化の原因物質の一つといわれ、湖沼やダム湖などの閉鎖性水域での富栄養化による藻類などの増加は、浄水操作上の障害や藻類に由来する臭気物質による水道水の異臭味問題などを引き起こすことがある。
測定方法にはカドミウム・銅カラム還元法,紫外線吸光光度法がある。
9 全リン
水中に含まれるリン化合物の総量をいい、リン量で表す。水中のリン化合物は、正リン酸(オルトリン酸)、メタリン酸、ピロリン酸、ポリリン酸などの無機リン酸塩と、農薬、エステル、リン脂質などの有機リン化合物があり、これらが溶存状態または懸濁状態で存在している。リンは地質中に広く存在し、あらゆる動植物にも含まれている。
したがって自然水中にも含まれるが、リン化合物は屎尿、肥料、農薬、合成洗剤などにも含まれているため、水中のリン化合物の増加は生活排水、工場排水、農業排水などの混入に由来する場合が多い。リン化合物の増加は湖沼・海域の富栄養化を促進する一因とされている。
測定は、加熱分解または高圧分解した後にモリブデン青法で行う。
10 リン酸イオン
リン化合物は、総リン、リン酸イオンおよび加水分解性リン化合物に区別して測定され、いずれもリン酸イオン量で表示される。リン酸には、メタリン酸、ピロリン酸、オルトリン酸、三リン酸、四リン酸などがあり、普通はオルトリン酸を単にリン酸または正リン酸という。オルトリン酸は水中で解離してオルトリン酸イオンとなる。測定方法には、モリブデン青法、モリブデン青抽出法がある。
11 トリハロメタン生成能
20℃、pH7.0±0.2 の条件下で、24±2 時間静置後、残留塩素が1〜2mg/L となるように塩素処理した検水のトリハロメタン濃度のことで、トリハロメタン前駆物質量の指標となる。THMFP、THM 生成能ともいわれる。
トリハロメタンの前駆物質として種々の有機物が認められているが、そのすべてが明らかではないので、前駆物質を直接測定することはできない。またトリハロメタンの低減方法として、塩素処理を行う前に前駆物質を除去する手法が効果的であるため、トリハロメタン生成能はその除去効果の評価手法として、広く利用されている。
12 生物
水道の場合、水源から給水栓水に至る水中に懸濁している微少な植物及び動物を指し、魚類など大型の生物は含まない。
試験結果は、水源の状況の監視、適切で効率のよい浄水処理方法の選択、生物障害予防及び対策に利用する。
13 アルカリ度
水中に含まれている炭酸水素塩、水酸化物および炭酸塩などを中和するのに必要な酸の量に相当するアルカリ量を炭酸カルシウム(CaCO3) のmg/Lで表したもので、酸消費量ともいう。中和点のpH値によりP−アルカリ度(フェノールフタレイン変色点pH8.3)とM−アルカリ度(メチルレッド混合指示薬変色点pH約4.8)に区別される。M−アルカリ度は総アルカリ度とも呼ばれる。
構成成分により炭酸水素塩によるものを炭酸水素アルカリ度(重炭酸アルカリ度)、水酸化物によるものを水酸基アルカリ度、炭酸塩によるものを炭酸アルカリ度という。
14 溶存酸素
水中に溶解している酸素のこと。DO ともいう。供給源の多くは大気であるが、藻類の光合成により発生した酸素のこともある。酸素の溶解度は気圧、水温、塩分などによって影響される。有機物で汚濁した水中では、生物化学的酸化により酸素が消費されるため溶存酸素が減少する。
水温が急激に上昇したり藻類が著しく繁殖した場合には、過飽和となることもある。
15 硫酸イオン
水中に溶解している硫酸塩中の硫酸分のこと。例えば硫酸カルシウムのような硫酸塩は水に溶けるとカルシウムイオンと硫酸イオンになる。硫酸塩は地殻中に広く分布しており、これが溶けて硫酸イオンとなるため、自然水中には常に多少の硫酸イオンが含まれている。これは主に地質に起因するが、化学肥料、硫黄泉、鉱山排水、工場排水、屎尿を含む下水排水および海水などの混入により増加することもある。
また、浄水処理において凝集剤に硫酸アルミニウムを使用すると若干増加する。硫酸イオンが多量に含まれると水の味が悪くなり、鉄管などの腐食を促進する傾向がある。
16 溶性ケイ酸
自然水中のケイ酸の形態は非常に複雑で、イオン、コロイドおよび分子状のものやケイ酸塩または生物体に含まれるものなど各種ある。測定上から大別して、溶性ケイ酸と総ケイ酸があり、溶性ケイ酸は水中における溶解性のケイ酸のことである。
分析法は、ろ過した試料水に酸性でモリブデン酸アンモニウムを加えるとモリブデン黄の帯緑色となるので、これを吸光光度法により波長410nm 付近の吸光度を測定する方法である。
http://www.jwwa.or.jp/mizu/pdf/2007-kaisetsu.pdf
A 水質基準項目(50項目)
水道により供給される水は、水道法第4 条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に
適合することが必要です。
なお、水質基準については、厚生労働大臣により諮問を受け厚生労働審議会において検討がなされました。
その検討経緯は、 に公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/shingikai.html
項目 基準値 解説
1 一般細菌
1ml の検水で形成される集落数が100 以下であること
一般細菌とは、標準寒天培地を用いて36±1℃で24±2時間培養したとき、培地に集落を形成する細菌のことをいう。分類学的に特定のグループを意味するものではない。
一般細菌として検出される細菌の多くは病原菌ではないが、汚染された水ほど多く検出される。
2 大腸菌
検出されないこと
ここでいう大腸菌(Escherichia coli)とは、特定酵素基質培地法によってβ−グルクロニダーゼ活性を有すると判定された好気性又は通性嫌気性の細菌のことをいう。
大腸菌はヒトや温血動物の腸管に常在し、環境中での増殖はまれなため、糞便由来でない細菌も含む大腸菌群と比べて糞便汚染の指標としてより信頼できる。
他の糞便指標細菌と比較すると自然界では生存期間が短いといわれている。飲料水中に大腸菌が存在することは、直ちに対応が必要とされる危険な汚染である可能性を示している。塩素消毒が完全であれば検出されない。
3 カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して、0.01mg/L 以下
カドミウムは、亜鉛とともに自然界にごく微量であるが存在していることが多い。 地表水、地下水中に亜鉛含量の1%以下の割合で存在しているといわれる。
カドミウムの用途は充電式電池、ビニル安定剤のステアリン酸カドミウムなどと広い。
富山県の神通川流域に多発したイタイイタイ病は、鉱山排水中のカドミウムが主な原因とされ、昭和43年(1968)5月8日に
公害病に認定された。慢性中毒では肺気腫、腎障害、骨変化、タンパク尿の症状がみられる。
4 水銀及びその化合物
水銀の量に関して、0.0005mg/L 以下
一般に無機水銀と有機水銀に分けられる。総水銀とは両者の合計量をいう。 主要鉱物は辰砂(HgS)。 常温で唯一の液体金属。
温度計、気圧計などの計器類の他に、各種水銀化合物の原料として、また電極、触媒、水銀灯など、幅広い用途がある。
水銀による急性中毒は口内炎、下痢、腎障害、慢性中毒では貧血、白血球減少を起こし、さらに手足の知覚喪失、精神異常となる。 水俣病の原因は、工場排水中のメチル水銀を摂取した魚介類を食したためである。
5 セレン及びその化合物
セレンの量に関して、0.01mg/L 以下
硫黄鉱床などから産出。周期表では硫黄と同族であるが金属性が大きい。光伝導性のある半導体で多くの同素体がある。光電池、整流器、複写機感光体などの電気材料、有機合成化学の触媒、色ガラス、顔料など、各種部門に広く用途がある。金属セレンの毒性は少ないが、化合物には猛毒のものが多い。
粘膜に刺激を与え、胃腸障害、肺炎などの症状を起こし、全身けいれんから死に至ることがある。
6 鉛及びその化合物
鉛の量に関して、0.01mg/L 以下
方鉛鉱、白鉛鉱を原料鉱として得られる。軟らかく加工しやすい金属なので、昔から水道管として使用されてきた。近年は水道メータの前後など一部に限られている。かつては鉛の表面に酸化被膜ができ、鉛は溶けにくいといわれたが、最近その溶出が問題視され、水道事業体ではステンレス管などに切り替える傾向にある。
鉛は神経系の障害や、貧血、頭痛、食欲不振、鉛疝痛などの中毒症状を呈することが知られている。
7 ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下
自然界では銅、鉄、水銀、鉛、ニッケルなどの鉱物と共存し自然水中に溶出するほか、鉱山排水や工場排水、ヒ酸石灰やヒ酸鉛などの農薬の混入によっても水中に含まれることがある。ヒ素化合物の毒性はその結合形によって異なる。
通常、3価および5価のヒ素化合物として存在し、いずれも毒性を持つが、3価のヒ素の方が5価のヒ素よりも毒性が強い。可溶性無機ヒ素化合物を摂取すると急速に吸収され、肝臓、腎臓、消化管などに強く作用する。
8 六価クロム化合物
六価クロムの量に関して、0.05mg/L 以下
6価の形で存在しているクロムのこと。水に溶けてクロム酸および重クロム酸を生成する。メッキ廃水に多量に含まれる。6価クロム塩を多量に摂取した場合、嘔吐、下痢、尿毒症などを引き起こす。致死量は成人の場合K2CrO7で0.5〜1gである。
9 シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して、0.01mg/L 以下
シアン化合物には、シアン化ナトリウム、シアン化カリウムのように水中でシアンイオン、シアン化水素を容易に生成する遊離型シアンと、フェリシアン化カリウム、フェロシアン化カリウムのように金属錯化合物を形成する錯塩シアンがある。
シアンは、めっき、鉄鋼製造、金銀の選鉱や多くの化学合成工業で使用される。シアンは自然中にはほとんど存在しない。シアン化合物を含んだ工場排水の混入によって水中に見いだされる。
また、含窒素化合物の燃焼によってもシアンが生じる場合がある。シアン化合物には強い毒性がある。ヒトの体内にはいると、粘膜から吸収され、頭痛、吐き気などを引き起こし、死亡する場合もある。
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/L 以下 (硝酸態窒素)
水中の硝酸イオン(NO3−)および硝酸塩に含まれている窒素のことである。硝酸イオンは有機および無機の窒素化合物の最終的酸化形である。
硝酸態窒素を多量に含む水を摂取した場合、体内で細菌により硝酸塩は亜硝酸塩へと代謝され、亜硝酸塩は血液中でメトヘモグロビンを生成して呼吸酵素の働きを阻害しメトヘモグロビン血症を起こす。
(亜硝酸態窒素)
水中の亜硝酸イオン(NO2−)または亜硝酸塩に含まれている窒素のことである。水に混入したアンモニア態窒素が酸化されて生ずる場合が多いが、硝酸態窒素の還元によって生じる場合も多い。
亜硝酸塩は赤血球のヘモグロビン(体内組織へ酸素を運搬する)と反応してメトヘモグロビンを生成し、呼吸酵素の働きを阻害するメトヘモグロビン血症を起こす。
体内で硝酸態窒素は亜硝酸態窒素へと速やかに変化するため、水道水質基準は硝酸態窒素および亜硝酸態窒素の合計量となる。
11 フッ素及びその化合物
フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下
水中のフッ素は、主として地質や工場排水の混入などに起因する。自然界に広く分布しているホタル石はフッ化カリウムが主成分であるため、日本でも特に温泉地帯の地下水や河川水に多く含まれることがある。
フッ素を適量に含んだ水を飲用した場合には「う歯」(むし歯)の予防に効果があるといわれているが、多量に含まれていると斑状歯(歯牙の慢性フッ素中毒)の原因となる。
12
ホウ素及びその化合物
ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下
ホウ素は、自然中に含まれることはまれであるが、火山地域の地下水、温泉水にはメタホウ酸の形で含まれることがある。また、金属の表面加工処理剤、ガラス、エナメル工業などで使用されるので、これらの工業排水に混入することがある。
ホウ酸を少量摂取した場合には緩和な生理作用を示すに過ぎないが、多量のときには消化器、神経中枢等に影響を及ぼす。ホウ素による中毒症状は、一般に胃腸障害、皮膚紅疹、抑うつ症を伴う中枢神経刺激の症状である。
13 四塩化炭素
0.002mg/L 以下
テトラクロロメタン、ベンジノホルムともいう。比重1.59(20℃)。融点−23℃、沸点76.5℃の無色透明な液体。水に対する溶解度は800mg/L(25℃)で、アルコール、エーテル、クロロホルムなどに混和する。蒸気圧115mmHg(25℃)。主な用途はフロンガスの製造原料、薫蒸殺菌剤、金属洗浄用溶剤などある。
液化塩素に不純物として存在することがある。その毒性は肝臓の感受性が最も高く、脂肪浸潤、肝細胞内酵素の遊離、細
胞内酵素活性の抑制、炎症が起こり、最終的に肝細胞壊死を引き起こす。
14 1,4-ジオキサン
0.05mg/L 以下
1,4-ジオキサンは、特異的な臭気のある無色の液体である。溶剤や1,1,1−トリクロロエタン安定剤などの用途に使用されるほか、ポリエキシエチレン系非イオン界面活性剤及びその硫酸エステルの製造工程において副生し、洗剤などの製品中に不純物として存在する。その毒性は目に強い刺激性を有し、肝臓、腎臓、中枢神経に影響を与え、また皮膚の脱脂を起こすことがある。
ヒトに対しては、弱い遺伝毒性しか示されていないが、多臓器での腫瘍を誘発することが報告されている。IARC では、ヒトへの発ガン性の可能性があるとして、Group2B に分類している。
15 1,1-ジクロロエチレン
0.02mg/L 以下 1,1,−ジクロロエチレンは、揮発性有機塩素化合物であるが、蒸気は空気より重い。酸化されやすく、酸素と接触すると過酸化物を生成する。
1,1−ジクロロエチレンの環境への放出は、製造過程及びポリマー製造の原料として使用されている際に起きる。揮発性のため、ほとんどが大気中へ移行していき、地表水を汚染した1,1−ジクロロエチレンも速やかに揮発する。
地下水では、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びこれらの分解成物である1,2−ジクロロエチレンや塩化ビニルと共存することが知られている。
主たる用途は、塩化ビニリデン樹脂の製造原料である。塩化ビニリデン樹脂は、家庭用ラップ、食品包装用フィルム、紙やプラスチックの表面コーティング等に使用される。ヒトでは、神経症状、肝機能障害、頭痛、視覚障害等がある。
16 シス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下 化学合成品はシス体とトランス体の混合物である。水には難溶であるが、各種の有機溶剤には易溶である。化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用される。ヒトに対して麻酔作用がある以外に報告例がない。
シス-1,2-ジクロロエチレンの環境中への放出は、製造過程及び溶剤として使用する過程で起きる。揮発性のため、多くが大気中に移行する。
地表水を汚染したシス-1,2-ジクロロエチレンは速やかに大気中に揮散する。土壌に浸透すると吸着されにくく、地下水中に長期間滞留する。地中のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが還元状態で微生物分解を受けると、シス-1,2-ジクロロエチレンが生成される。地下水中では、多くの場合トリクロロエチレンと共存している。
シス体とトランス体の混合物の毒性はLD50(ラット,経口)770mg/kgで、単回投与によりラットの肝アルカリホスファターゼが顕著に増加した。多量に摂取した場合には、腹痛、咳、咽頭痛、めまい、吐き気、嗜眠、脱力感、意識喪失、嘔吐等の急性症状がみられる。
17 ジクロロメタン
0.02mg/L 以下
沸点40℃の無色の液体。合成有機化学物質であり、自然界には存在しない。殺虫剤、塗料、ニス、塗料剥離剤、食品加工中の脱脂処理および洗浄液などとして使われる。
表流水中に排出されたジクロロメタンは大気中に揮散し数日から数週間で分解するが、地上に排出されたジクロロメタンは容易に地下水に移行し、長期間残留する。
ジクロロメタンの毒性はLD50(ラット,経口)2,121mg/kg、(マウス,経口)1,987mg/kgである。また、1.3mg/kg体重の単回投与では、呼吸困難、運動失調、チアノーゼ及び昏睡が認められた。多量に摂取した場合には、腹痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感、意識喪失の急性症状がみられる。
18 テトラクロロエチレン
0.01mg/L 以下
テトラクロロエテン、パークレン、パークロロエチレンともいう。比重1.62(20℃)、融点22.4℃、沸点121.2℃の液体。蒸気圧19mmHg。水に対する溶解度150mg/L(25℃)。主な用途はドライクリーニング溶剤,金属用脱脂剤など。
この物質は使用後排出され、土壌中を移行して直ちに地下水中に入り、地下水汚染物質の一つとなっている。地下水中では数カ月から数年間にわたって残留する。
トリクロロエチレンに比べて尿中代謝物排泄ははるかに少ない。その毒性はLD50(ラット,経口)8.85g/kgで、肝
腎障害や中枢神経抑制作用があり、また、肝ガンの発生も認められている。多量に摂取した場合には、腹痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感、意識喪失の急性症状がみられる。
19 トリクロロエチレン
0.03mg/L 以下
TCE、トリクレン、トリクロロエテンともいう。比重1.4 (25℃)、融点−86.4℃、沸点86.7℃の無色透明の液体。蒸気圧77mmHg(25℃)。
水に対する溶解度1g/L(20℃)。主な用途は金属の脱脂剤である。環境に放出されて地下水汚染を超こす。地下水中に長期間残留 し、分解してジクロロエチレンや塩化ビニルになる。
また,テトラクロロエチレンの分解によって生成することもある。体内吸収では抱水クロラールを経てトリクロロ酢酸に代謝される。毒性はLD50(ラット,経口)4.92g/kgで、発ガン性も認められる。多量に摂取した場合の急性症状は、腹痛、めまい、し眠、頭痛、脱力感、吐き気、意識喪失がある。
20 ベンゼン
0.01mg/L 以下
揮発性のある無色の液体で、芳香族特有の芳香があり、引火性が大きい。エタノールおよびエーテルとはすべての割合で混合するほか、多くの有機溶媒に可溶である。
水には難溶。置換、付加および開裂の三つの反応が起こり、多種の芳香族化合物を生成する。溶剤、燃料、アルコール変性剤などとしても重要である。
発ガン性を有する。その毒性はLD50(ラット、マウス,経口)1〜10g/kgで、発ガン性や骨髄形成不全、リンパ球減少症
も認められる。多量に摂取した場合の急性症状は、腹痛、咽頭痛、嘔吐がある。
21 クロロ酢酸
0.02mg/L 以下
クロロ酢酸は、刺激臭のある無色の結晶である。除草剤、チューインガム可塑剤、塩化ビニル可塑剤、医薬品、アミン酸等合成、香料、キレート剤、界面活性剤として使用される。
クロロ酢酸などのハロゲン化酢酸類は、水道水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒
副生成物の一つである。その毒性はLD50(ラット,経口)55mg/kgで、皮
膚や鼻、目の粘膜を腐食する。変異原性が認められる。
22 クロロホルム
0.06mg/L 以下
比重1.49(20℃)。融点−63.5℃、沸点61.2℃の無色透明の液体で、甘い刺激臭がある。水に対する溶解度は0.28g/100g(20℃)で,エタノール、エーテルなどには易溶である。
主な用途として医薬品、溶剤、有機合成の原料などがある。クロロホルムは、浄水処理における塩素消毒によって生成するトリハロメタンの主成分である。クロロホルムには強い麻酔作用があり、肝臓、腎細尿管、心臓などに細胞毒として作用する。
また、動物実験によって腎腫瘍や肝癌などの発癌性が確認されている。低濃度の慢性毒性では胃腸、肝腎障害が起こり、高濃度では反射機能の喪失、感覚麻痺、呼吸停止などが起こる。
23 ジクロロ酢酸
0.04mg/L 以下
ジクロロ酢酸は、刺激臭のある無色の液体である。ジクロロ酢酸などのハロゲン化酢酸類は、浄水過程において水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物物質の一つである。
マウスに75週にわたってジクロロ酢酸を飲水投与した結果、最大無作用量は50mg/kg/日である。慢性試験で発ガン性を示す根拠は認められていない。IARC では、ヒト発ガン性物質として分類できないとして、Group3に分類されている。
24 ジブロモクロロメタン
0.1mg/L 以下
浄水処理過程で使われる消毒剤の塩素と水中のフミン質などの有機物質が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。生成量は原水中の臭素イオンに大きく影響される。
写真工業の排水や海水の影響を受けやすいところ、また塩分を含む地下水で臭素化トリハロメタンが多い。その毒性はLD50(雄マウス,経口)800mg/kg、(雌マウス,経口)1200mg/kgである。参考文献:アメリカ国家毒性プログラムNTP(1985)ではマウスによる2 年間の経口投与実験では、肝の脂肪変性、腎ネフローゼが認められた。
25 臭素酸
0.01mg/L 以下
臭素酸の最も一般的な形態が臭素酸カリウムと臭素酸ナトリウムである。臭素酸カリウムは小麦粉改良材として、臭素酸ナトリウムは分析用試薬、毛髪のコールドウェーブ用薬品等に使用される。
浄水処理においてオゾンを使用する場合、臭素イオンから消毒副生成物として生成される。また、消毒剤としての次亜塩素酸ナトリウム生成時に、不純物の臭素が酸化され、臭素酸が生成される。
毒性影響には、腹痛、中枢神経系の機能低下、呼吸困難、肺浮腫、腎機能低下、聴覚障害等及び発ガン性が報告されている。
ヒトが摂取すると消化管から速やかに吸収され、肝臓でグルタチオン抱合された後臭化物に還元される。IARC では、実験動物の発ガン性に関しては十分な証拠があるとして、Group2B に分類している。
26 総トリハロメタン
0.1mg/L 以下
メタン(CH4)の水素原子3個が、塩素、臭素、あるいはヨウ素に置換された有機ハロゲン化合物の総称。THMと略称される。これらのうち、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の合計を総トリハロメタン(TTHM)と呼ぶ。
水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に存在するフミン質などの有機物を前駆物質として、塩素処理によって生成する。なかでもクロロホルムは発ガン物質であることが明らかとなっている。
27 トリクロロ酢酸
0.2mg/L 以下
トリクロロ酢酸は、刺激臭のある無色で吸湿性の結晶である。医薬品の原料、除草剤、腐食剤、角質溶解剤、塗装剥離剤、除タンパク剤、生体内タンパク・脂質の分画剤として使用される。水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物質の一つである。
マウスで肝腫瘍を引き起こすが、変異原性や染色異常などのin vitro 系の試験では陰性及び陽性の結果が混在して報告されており、IARC ではヒト発ガン性物質として分類できないとしてGroup3に分類されている。
28 ブロモジクロロメタン
0.03mg/L 以下
浄水処理過程で使われる消毒剤の塩素と水中のフミン質などの有機物質が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。生成量は原水中の臭素イオンに大きく影響される。写真工業の排水や海水の影響を受けやすいところ、また塩分を含む地下水で臭素化トリハロメタンが多い。
その毒性はLD50(雄マウス,経口)450mg/kg、(雌マウス,経口)900mg/kgである。参考文献:アメリカ国家毒性プログラムNTP(1987)では、マウスによる2 年間の経口投与実験では、腎細胞肥大、肝の脂肪変性のほか腎臓の腺腫と腺がん、肝細胞の腺腫と腺がんがみられた。
29 ブロモホルム
0.09mg/L 以下
同上
30 ホルムアルデヒド
0.08mg/L 以下
ホルムアルデヒドは、特徴的な臭気のある気体で、有機溶媒に易溶である。浄水過程で、水中のアミン等の有機物質と塩素、オゾン等の消毒剤が反応して生成される。
主要な構成物資として、ホルムアルデヒドとアセトアルデヒド等がある。エポキシ樹脂塗料及びアクリル樹脂塗料の原料として
使用される。土壌燻蒸剤として線虫等の駆除に使用される。
野菜、樹木の苗木などの防除に使用される。ヒトへの健康影響としては、内服したとき、呼吸困難、めまい、嘔吐、口腔及び胃に炎症が起きる。
吸入曝露試験では発ガン性を示し、鼻と喉の灼熱感、頭痛、吐き気などが起こり、短期暴露の場合、眼、皮膚、気道に対して腐食性があり、肺水腫を起こすこともある。
高濃度で死に至ることもある。経口曝露では明らかな発ガン性は示さない。
31 亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下
自然水中に微量に含まれるが、高濃度の亜鉛は鉱山排水や工場排水などによる汚染が原因であることが多い。水道水で高濃度の亜鉛が検出される場合は、そのほとんどが給水管などの亜鉛引き鋼管からの溶出による。
水道水に高濃度の亜鉛が含まれていると白濁して、いわゆる白水の原因となる。また5mg/L以上含まれると収れん味を呈する。毒性は比較的弱いが、高濃度の場合には腹痛、嘔吐、下痢などの中毒症状をもたらすことがある。
32 アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下
地球の表面に存在する元素で3番目に多く、金属では最も多い。比重が2.6で、さびにくく、かなり丈夫なので航空機、自動車、建築物などに使われている。
アルミニウムの化合物である明ばんは昔から水の清澄剤として、また,硫酸アルミニウム、ポリ塩化アルミニウムも水道水の水処理剤として用いられている。
濃度が高いと、白濁水の原因となる。
33 鉄及びその化合物
鉄の量に関して、0.3mg/L 以下
クラーク数は4.7で、酸素、ケイ素、アルミニウムについで地球で4番目に多い元素である。地表水中ではFe(OH)3として懸濁して存在している。
また,泥炭地などの有機物の多いところではコロイド性の有機錯体として存在する。自然水中に含まれる鉄は、地質に起因するもののほか鉱山排水、工場排水などからの場合もある。0.3mg/L以上溶解すると、水に色がつきはじめ赤水の原因となり、臭気や苦味を与える(0.5mg/L)。
鉄は栄養上,1人1日当たり約10mg以上必要とされている。鉄塩の毒性はLD50(マウス,経口)300〜600mg/kg、LD50(ラット,経口)800〜2,000mg/kgである。
急性毒性は、うつ病、昏睡、呼吸障害や心拍停止などである。
34 銅 及びその化合物
銅の量に関して、1.0mg/L 以下
天然には主として硫化物(黄銅鉱、班銅鉱、輝銅鉱)の形で産出する。電線、合金、貨幣、彫刻、メッキ、農薬など、多くの分野に用いられる。
銅イオンを1.0mg/L以上含む水は金属味を帯び、着色(青色)を与える。ヒトにとって銅は必須元素であり、成人の必要量は1日に約2mgとされている。
銅化合物は藻類、カビ類、無脊椎動物に対しては強い毒物であるが、哺乳類に対しては蓄積性が認められないので慢性中毒のおそれは少ない。
35 ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下
地殻中に広く分布。海水中には約10g/L含まれ、また岩塩として巨大な鉱床をつくる。ナトリウムは自然水中に広く存在する元素であるが、海水、工場排水の混入、水処理時のカセイソーダによるpH調整などに由来することもある。
ナトリウムイオンは動物体内の生理に重要な役割を果たしている。ナトリウムと高血圧との関係はよく論じられるが、1日1.6〜9.6gの摂取量では人の健康に何ら影響はないとみられている。
36 マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下
マンガンは地殻中に広く分布しており、軟マンガン鉱などに多く含まれる。生理的に不可欠の元素で、炭水化物の代謝などに関与する。水道水中にマンガンが多いと、浄水に黒い色をつけるので好ましくない。
過剰摂取すると全身倦怠感、頭痛、不眠、言語不明瞭などの中毒症状を起こす。
37 塩化物イオン
200mg/L 以下
水中に溶存している塩化物中の塩素のこと。自然水は常に多少の塩化物イオンを含んでいるが、これは地質に由来するもので、特に海岸地帯では海水や送風塩の影響によることが大きい。
しかし、塩化物イオンは下水系、生活系および産業系などの各排水や、屎尿処理水などの混入によっても増加する。したがって、塩化物イオンは水質汚濁の指標の一つともなっている。
硝酸銀と反応して塩化銀の白色沈澱を生ずるため、測定にはこの性質を利用した硝酸銀法(モール法)がある。多量の塩化物イオンは水に味をつけたり、鉄管などの腐食を促進する傾向がある。塩化物の毒性は陽イオンの種類によって異なっており、塩化物イオン自体の毒性は知られていない。
しかしながら、2.5mg/L 以上の濃度の塩化ナトリウムを含む飲料水を過剰に飲用していると高血圧症を引き起こすと報告されている。
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
300mg/L 以下 (カルシウム)
アルカリ土壌金属の一つで、展性・延性がある。自然界には遊離状態で産出されず、炭酸塩およびケイ酸塩として広く多量に存在する。水中ではカルシウムイオン(Ca2+)と して存在し、硬度の主体をなしている。その起源は地質によるものが主であるが、他にコンクリート構造物からの溶出、海水、工場排水および温泉などの混入に由来するものがある。
原子吸光分析法により波長422.7nmの吸光度を測定する方法やカルシウム硬度による測定方法(EDTA法)などがある。
(マグネシウム)
アルカリ土類金属の一つ。自然界では単体としては存在せず、炭酸塩、ケイ酸塩、硫酸塩および塩化物などとして広く多量に存在する。
水中にはマグネシウムイオンとして存在し、カルシウムイオンとともに硬度の主体をなしている。その成因は主に地質に由来するが、鉱山排水、工場排水、海水および温泉などの混入によることもある。原子吸光分析法により波長285.2nmで吸光度を測定する方法や総硬度とカルシウム硬度の差から求める測定法がある。
健康障害としては、硬度が高すぎると胃腸を害して下痢を起こすことがある。
39 蒸発残留物
500mg/L 以下
水を蒸発乾固したときに残る物質。具体的には、一定量の検水を蒸発皿に入れて水浴上で蒸発乾固し、残った物質量を求める。濁質のある検水をそのまま蒸発乾固すれば、浮遊物質と溶解性物質との総和となる。
水道水の主な蒸発残留物の成分は、カルシウム、マグネシウム、シリカ、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物である。健康への影響はほとんど生じない。
40 陰イオン界面活性剤
0.2mg/L 以下
界面活性剤のうち、水溶液中で電離して活性剤の主体が陰イオンになるもの。工場排水、家庭下水などの混入に由来し、水中に存在すると泡立ちの原因となり、汚濁の重要な指標である。
また、陰イオン界面活性剤に付随するリン酸塩による水源の富栄養化が問題となっている。その毒性はほとんど認められない。
41ジェオスミン
0.00001mg/L 以下
ジェオスミンは、湖沼等で富栄養化現象に伴って発せするかび臭(異臭味)の原因物質である。藍藻類のアナベナにより産生される。その毒性はほとんど認められない。
42 2−メチルイソボルネオール
0.00001mg/L 以下
2−メチルイソボルネオールは、湖沼等で富栄養化現象に伴って発せするかび臭(異臭味)の原因物質である。藍藻類のフォルミディウムやオッシラトリアにより産生される。その毒性はほとんど認められない。
43 非イオン界面活性剤
0.02mg/L 以下
非イオン界面活性剤とは、界面活性剤のうち、イオンに解離する基を持たない物質の総称である。エーテル型、エーテルエステル型、エステル型、含窒素型が知られている。
洗浄剤、乳化剤、分散剤、消泡剤、潤滑油、化粧品、流出油の処理剤等に使用される。その毒性は、一般に陰イオン界
面活性剤に比べ低く、健康への影響はほとんど生じない。
44 フェノール類
フェノールの量に換算して、0.005mg/L 以下
芳香族化合物のベンゼン環の水素が、水酸基で置換された化合物の総称で、環境汚染に関連するものは主としてフェノール(石炭酸)、ο−,m−,p−クレゾール、クロロフェノールなどである。合成樹脂、界面活性剤などの原料として大量に使用されている。
フェノール類は、天然水中には存在しないが、化学工場排水、ガス製造工場排水などに含まれる。フェノール類が含まれていると水の塩素処理過程でクロロフェノール類が生成し、水に著しい異臭味を与えるので、厳しい排水基準が示されている。
45有機物(全有機炭素(TOC)の量)
5mg/L 以下
水中の全有機炭素(TOC : Total Organic Carbon)は、種々の有機化合物から構成されていて、これらの有機化合物に含まれている炭素量をいう。全有機炭素は、水中に含まれる有機物総量の指標として用いることができるため、原水の有機性汚濁の状況や浄水処理過程における水の処理性評価に利用することができる。
また、溶存有機炭素(DOC)も有機性汚濁の指標として用いられている。
46 pH値
5.8 以上8.6以下
水素イオンのモル濃度(水素イオン濃度)の逆数の常用対数値。pH7は中性、pH7より値が小さくなるほど酸性が強くなり、値が大きくなるほどアルカリ性(塩基性)が強くなる。
水道法に基づく水質基準は5.8以上8.6以下であること、また、水質管理目標設定項目としての目標値は7.5程度
とされている。水の基本的な指標の一つであり、理化学的水質、生物学的水質、浄水処理効果、管路の腐食などに関係する重要な因子である。
測定法はガラス電極法(pH計)がある。
47 味
異常でないこと
水の味は、水に溶存する物質の種類・濃度によって感じ方が異なる。味の原因には、下水、工場排水等による汚染、生物や細菌類の繁殖、また、海岸地帯では海水の影響をうけ塩味を感じることもある。
異常な味は不快感を与えるので飲用には適さない。
48 臭気
異常でないこと
水の臭気は水に溶解している種々の物質が原因となっています。水道において問題となる臭気物質は、藻類や放線菌等の生物に起因するかび臭物質、フェノールなどの有機化合物が主です。異常な臭気は不快感を与え
るので飲用には適しません。
49 色度
5 度以下
水中に含まれる溶解性物質およびコロイド性物質が呈する黄褐色の程度をいう。原水においては、主に地質に由来するフミン質、フミン酸鉄による呈色と同じ色調の色について測定される。水道水においては配管等からの鉄の溶出などによって色度が高くなることがある。
精製水1L中に白金イオン1mgおよびコバルトイオン0.5mgを含むときの呈色に相当するものを1度としている。
50 濁度
2 度以下
濁度は、水の濁りをポリスチレン系粒子(5種類)を濁質の標準液とし、これと比較して測定する。水道において、原水濁度は浄水処理に大きな影響を与え,浄水管理上の指標となる。
また、給水栓中の濁りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要である。
B 水質管理目標設定項目(27項目)
水質基準とするにいたりませんが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目、必要に応じ水質検査を実施する項目です。このうち農薬類については、全国の検出状況や使用量などを考慮して、101項目がリストアップされ、「総農薬方式」とよばれる考え方で設定されています。
項目 目標値 解説
1 アンチモン及びその化合物
アンチモンの量に関して、0.015mg/L 以下
アンチモンは、半導体材料、潤滑剤、弾薬、陶器、硝子など材料成分として主に使われている。三価アンチモンは容易に赤血球に取り込まれるが、五価アンチモンは取り込まれない。飲料水中のアンチモンの形態が毒性のキー決定要因であるが、飲料水中のアンチモンはほとんどが、弱毒性型の五価アンチモン、オキソ-陰イオン型と思われる。
ヒトへの健康影響では、嘔吐、下痢が知られていて、三価アンチモンの発ガン性はグループ2Bに分類されているが、この判断となった知見のほとんどは、水に不溶な粒子による吸入暴露によるものであり、水溶性アンチモンの経口摂取による発ガン性を示す知見は知られていない。
2 ウラン及びその化合物
ウランの量に関して、0.002mg/L 以下(暫定)
ウラン化合物はガラス・磁器の着色剤、光電管にも使用されているが、主に原子炉の燃料として使用されている。ごく微量であるが、地球の表面の近くの岩石(特に花崗岩)及び海水中に広く分布している。
ウランを含む鉱石や廃棄された選鉱くずからの溶出、核物質使用工場からの排出、石炭及び他の燃料の燃焼、ウランを含むリン酸肥料の使用になどにより環境中に放出される。
ウランの健康影響としては化学毒性による眼粘膜刺激、催涙及び結膜炎、吸入による気道刺激、腎障害などがある。また、放射線障害による肺ガン、リンパ腫の増加などがある。
3ニッケル及びその化合物
ニッケルの量に関して、0.01mg/L 以下(暫定)
ニッケルは、ステンレス綱、めっき、貨幣、顔料、触媒原料などに使用されている。ニッケルの化合物は不溶性のものが多いので、自然水中に存在することはまれであるが、鉱山排水、工場排水あるいはニッケルめっきの溶出などから混入することがある。また、水道では管材及びその他の材料の腐食による汚染がある。
大量に摂取するとめまい、嘔吐、急性胃腸炎を引き起こす。発ガン性の評価については、金属ニッケルではIARCグル
プ2B、ニッケル化合物ではグループ1にそれぞれ分類されている。
4亜硝酸態窒素
0.05mg/L 以下(暫定)
水中に含まれる亜硝酸イオン中の窒素の量であり、窒素肥料、腐敗した動植物、家庭排水等に由来する。これらに含まれる窒素化合物は、環境中で化学的・微生物学的に酸化及び還元を受け、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素等になる。
摂取すると体内で食物中のタンパク質に含まれるアミン類と結合し、発ガン物質であるニトロソアミンを生成したり、急性毒性を引き起こす危険性がある。
塩素処理により容易に硝酸態窒素へと酸化されるので、通常の浄水処理により除去され、残留塩素のある浄水には存在しな
い。
5 1,2-ジクロロエタン
0.004mg/L 以下
主に塩化ビニルモノマーの原料として使用されるほか、有機溶剤、殺虫剤、金属の脱脂洗浄等に使用されている。環境中には、貯蔵タンクからの漏出や工場排水等により放出されるおそれがある。地表水を汚染した場合は比較的容易に大気中に揮散するが、土壌吸着性は低く、土壌を浸透し地下水に進入すると安定な形で閉じこめられるため長期間にわたり汚染が継続する。
健康影響はめまい、吐き気、嘔吐などがある。
6 トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下
シス体との混合物で使用され、化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用されている。また、トリクロロエチレンの分解物でもある。吐き気、眠気、疲労感、めまい等の中枢神経系への影響がある。
7 1,1,2-トリクロロエタン
0.006mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレンの製造原料、油脂、ワックス、天然樹脂の溶剤として使用されている。土壌吸着性は低く、地下水中に長時間残留する。長期暴露では慢性胃炎、肝臓への脂肪蓄積、肺障害など、上記暴露では呼吸器と眼に対する刺激作用がある。
8 トルエン
0.2mg/以下
染料、香料、有機顔料、ポリウレタン、合成繊維などの原料として、また、樹脂や塗料の溶剤として使用されている。石油成分の一つで石油分留生成で得られる。
健康影響としては、急性暴露により、頭痛、吐き気、錯乱などの症状を引き起こす。
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
0.1mg/L 以下
可塑剤として、ポリ塩化ビニルフィルム、シート、レザー、ホース、機械器具部品、日用雑貨などに使われ、また農薬、化粧品、染料、印刷インクなどの溶剤や保留剤としても使用されている。
大量摂取により、胃腸、肝臓障害などの報告例がある。
10亜塩素酸 0.6mg/L 以下
11塩素酸 0.6mg/L 以下
12二酸化塩素 0.6mg/L 以下
主に漂白剤として使用されている。二酸化塩素を浄水過程で酸化剤として使用した場合に検査を行うことが望ましいとされている項目である。
亜塩素酸塩、塩素酸塩から合成される二酸化塩素を処理水中に投入した場合に分解生成物として亜塩素酸イオン、塩素酸イオンが生成する。
赤血球中のヘモグロビンが亜塩素酸塩により酸化され、メトヘモグロビンを形成することによる中毒症が知られている。
13 ジクロロアセトニトリル
0.04mg/L 以下(暫定)
塩素処理の際に遊離塩素とフミン物質、藻類、アミン酸が反応してできる副生成物の1 つである。時間の経過とともに、また水温が高いほど生成量は増加するが、トリハロメタンほど顕著ではない。土壌や汚泥等にはあまり吸着せず、生物への濃縮もあまり大きくないと考えられている。
14 抱水クロラール
0.03mg/L 以下(暫定)
塩素消毒の際に遊離塩素とフミン質、酸化シアンが反応してできる副生成物の1つである。鎮静剤、睡眠薬等の医療用として、医薬品や農薬の原料として使用されている。
15 農薬類
検出値と目標値の比の和として、1 以下
水源上流などにおける農薬の使用状況により、使用されている薬剤について検査を行うこととされている。計101 種類の農薬が対象になっていて、総農薬方式として評価される。
16 残留塩素
1mg/L 以下
水中に塩素を注入することによって水中に残留した有効塩素をいい、次亜塩素酸などの遊離有効塩素(遊離残留塩素)とクロラミンのような結合有効塩素(結合残留塩素)に区分される。残留塩素の測定にはDPD法、ポーラログラフ法及び吸光光度法がある。
衛生上の措置として給水の残留塩素を遊離残留塩素として0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するよう規定している。
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
10mg/L 以上
100mg/L 以下
水質基準項目 38 を参照。
18マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.01mg/L 以下
水質基準項目 36 を参照。
19 遊離炭酸
20mg/L 以下
水中に溶解している二酸化炭素(CO2)のこと。遊離炭酸は炭酸塩や有機物質が分解して発生した二酸化炭素や空気中の二酸化炭素などが水中に溶解することに起因する。
地下水では有機物の分解などにより、一般に多く存在する。遊離炭酸には水中のアルカリ化合物と反応して炭酸化合
物を生成させるような腐食性のある侵食性遊離炭酸と、腐食性のない従属性遊離炭酸がある。
20 1,1,1-トリクロロエタン
0.3mg/L 以下
ドライクリーニング用溶剤、金属の脱脂洗浄剤、繊維のしみ抜き剤などに使用されている。健康影響としては、吐き気、下痢、めまい、ふらつきなどの症状がある。
21メチル-t- ブチルエーテル
0.02mg/L 以下
ガソリンのオクタン価向上剤、アンチノック剤、ラッカー混合溶剤の混和性改良材などに使用されている。健康影響については、毒性評価が詳細にされていないのが現状であるが、地下水で一過的に高濃度で検出されるとの情報もある。
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)
3mg/L 以下
水中の有機物や還元性物質(被酸化性物質)の量を、酸化させるのに必要な過マンガン酸カリウムの量として表したもので、一般に有機物の含有量の指標になっている。
土壌に由来するフミン質を多く含む場合や水道水源にし尿、下水又は工場排水が混入した場合に増加する。有機物の多い
水は渋みがあり、また、消毒に用いる塩素の消費量も多くなり、その点で水の味を損なう原因になる。
23 臭気強度(TON)
3 以下
検水の臭気をほとんど感知できなくなるまで無臭味水で希釈し、その希釈倍率によって示される臭気の強さのこと。TON ともいう。臭気に対する感受性は個人差があり、また、同一人でも測定時の状態で差異を生じるため、複数人数による試験が望ましい。
24 蒸発残留物
30mg /L 以上
200mg/L 以下
水質基準項目 39 を参照
25 濁度
1 度以下
水質基準項目 50 を参照
26 pH 値
7.5 程度
水質基準項目 46 を参照
27 腐食性(ランゲリア指数)
−1 程度以上とし、極力0に近づける
水のpH 値、カルシウムイオン量、総アルカリ度及び溶解性物質から求められるもので、水のpH値とその水の理論的pH 値との差を表す。指数が正の値で絶対値の大きいほど炭酸カルシウムの析出が起こりやすくなる。
また、負の値では炭酸カルシウム被膜が形成されず、その絶対値が大きくなるほど水の腐食傾向は強くなる。
C その他の項目
水質基準・水質管理目標設定項目ではありませんが、水道に関連する項目です。
項目 解説
1 水温
水温は、地表水の場合、気温の影響を受けやすく、湖沼や貯水池の場合、水温の変化によって、比重が変わり、水の停滞や循環などの原因となる。また、水温の上昇は物質の溶解性、生物の消長、河川での自浄作用などに影響を与える。
2 アンモニア態窒素
水中のアンモニウムイオン(NH4+)に含まれる窒素のこと。有機窒素化合物の分解、工場排水、下水および屎尿の混入によって生ずる場合が多い。土壌や水中の細菌により亜硝酸態窒素、硝酸態窒素へと酸化され、嫌気性状態では逆に硝酸態窒素、亜硝酸態窒素が還元されてアンモニア態窒素となる。
浄水処理では塩素処理や、緩速濾過のような生物化学処理によって分解され減少するので、処理工程の管理指標としても重要な項目である。測定方法にはインドフェノール法、ネスラー法、α−ナフトール法、蒸留比色法がある。
3 生物化学的酸素要求量(BOD)
水中の有機物が生物化学的に酸化されるのに必要な酸素量のことで、生物化学的酸素要求量ともいう。生物化学的酸化とは、水中の好気性微生物が有機物を栄養源とし、水中の酸素を消費してエネルギー化、生命維持・増殖するとき、有機物が生物学的に酸化分解されることをいい、有機物が多いほど消費される酸素量が多くなる。
したがって、BODが高いことはその水中に有機物が多いことを示し、化学的酸素要求量(COD)とともに水質汚濁を示す重要な指標である。生物化学的酸素要求量は試料を20℃、5日間静置し、静置前と後の溶存酸素量をウィンクラー法で測定し、その間に消費された溶存酸素量(mg/L)で表す。
4 化学的酸素要求量(COD)
化学的酸素要求量のこと。水中の被酸化性物質(有機物)を酸化剤で化学的に酸化したときに消費される酸化剤の量を酸素に換算したもの。CODが高いことはその水中に有機物が多いことを示し、生物化学的酸素要求量(BOD)とともに水質汚濁を示す重要な指標である。
測定方法には酸性過マンガン酸カリウム法があるが、酸化剤として重クロム酸カリウムを使用する方法もある。
5 紫外線(UV)吸光度
紫外線領域における特定波長の吸光度(紫外部吸光度、UV 吸光度)または透過率を光電的に測定し、検量線により濃度を求める方法。紫外線とは波長360〜400 以下1nm 程度までの電磁波を指すが、200nm 以下の波長域は空気による吸収があり、真空中で測定する必要があるため真空紫外線とよんでいる。
光源には石英水銀灯、重水素放電管、セキノンランプなどが用いられている。測定には紫外線領域に吸収の少ない石英セルを使用する。
6 浮遊物質(SS)
水中に懸濁している粒径1μm〜2mm 程度の不溶解性物質のことをいう。SSと記すこともある。上水試験方法では、網目2mm のふるいを通過した一定量の試料を1μm のメンブレンフィルターでろ過し、その残留物105〜110℃で2 時間乾燥し、秤量して求める重量法を定めている。
濁度との相関が議論されることがあるが、厳密な意味での相関関係はない。浄水処理、排水処理などに影響を及ぼす。
7 侵食性遊離炭酸
水中のアルカリ化合物と反応して炭酸化合物を生成させるような腐食性のある水中に溶解している二酸化炭素(CO2)のこと。
8 全窒素
水中に含まれる窒素化合物の総量のことで、窒素量で表す。窒素はリンとともに水源の富栄養化の原因物質の一つといわれ、湖沼やダム湖などの閉鎖性水域での富栄養化による藻類などの増加は、浄水操作上の障害や藻類に由来する臭気物質による水道水の異臭味問題などを引き起こすことがある。
測定方法にはカドミウム・銅カラム還元法,紫外線吸光光度法がある。
9 全リン
水中に含まれるリン化合物の総量をいい、リン量で表す。水中のリン化合物は、正リン酸(オルトリン酸)、メタリン酸、ピロリン酸、ポリリン酸などの無機リン酸塩と、農薬、エステル、リン脂質などの有機リン化合物があり、これらが溶存状態または懸濁状態で存在している。リンは地質中に広く存在し、あらゆる動植物にも含まれている。
したがって自然水中にも含まれるが、リン化合物は屎尿、肥料、農薬、合成洗剤などにも含まれているため、水中のリン化合物の増加は生活排水、工場排水、農業排水などの混入に由来する場合が多い。リン化合物の増加は湖沼・海域の富栄養化を促進する一因とされている。
測定は、加熱分解または高圧分解した後にモリブデン青法で行う。
10 リン酸イオン
リン化合物は、総リン、リン酸イオンおよび加水分解性リン化合物に区別して測定され、いずれもリン酸イオン量で表示される。リン酸には、メタリン酸、ピロリン酸、オルトリン酸、三リン酸、四リン酸などがあり、普通はオルトリン酸を単にリン酸または正リン酸という。オルトリン酸は水中で解離してオルトリン酸イオンとなる。測定方法には、モリブデン青法、モリブデン青抽出法がある。
11 トリハロメタン生成能
20℃、pH7.0±0.2 の条件下で、24±2 時間静置後、残留塩素が1〜2mg/L となるように塩素処理した検水のトリハロメタン濃度のことで、トリハロメタン前駆物質量の指標となる。THMFP、THM 生成能ともいわれる。
トリハロメタンの前駆物質として種々の有機物が認められているが、そのすべてが明らかではないので、前駆物質を直接測定することはできない。またトリハロメタンの低減方法として、塩素処理を行う前に前駆物質を除去する手法が効果的であるため、トリハロメタン生成能はその除去効果の評価手法として、広く利用されている。
12 生物
水道の場合、水源から給水栓水に至る水中に懸濁している微少な植物及び動物を指し、魚類など大型の生物は含まない。
試験結果は、水源の状況の監視、適切で効率のよい浄水処理方法の選択、生物障害予防及び対策に利用する。
13 アルカリ度
水中に含まれている炭酸水素塩、水酸化物および炭酸塩などを中和するのに必要な酸の量に相当するアルカリ量を炭酸カルシウム(CaCO3) のmg/Lで表したもので、酸消費量ともいう。中和点のpH値によりP−アルカリ度(フェノールフタレイン変色点pH8.3)とM−アルカリ度(メチルレッド混合指示薬変色点pH約4.8)に区別される。M−アルカリ度は総アルカリ度とも呼ばれる。
構成成分により炭酸水素塩によるものを炭酸水素アルカリ度(重炭酸アルカリ度)、水酸化物によるものを水酸基アルカリ度、炭酸塩によるものを炭酸アルカリ度という。
14 溶存酸素
水中に溶解している酸素のこと。DO ともいう。供給源の多くは大気であるが、藻類の光合成により発生した酸素のこともある。酸素の溶解度は気圧、水温、塩分などによって影響される。有機物で汚濁した水中では、生物化学的酸化により酸素が消費されるため溶存酸素が減少する。
水温が急激に上昇したり藻類が著しく繁殖した場合には、過飽和となることもある。
15 硫酸イオン
水中に溶解している硫酸塩中の硫酸分のこと。例えば硫酸カルシウムのような硫酸塩は水に溶けるとカルシウムイオンと硫酸イオンになる。硫酸塩は地殻中に広く分布しており、これが溶けて硫酸イオンとなるため、自然水中には常に多少の硫酸イオンが含まれている。これは主に地質に起因するが、化学肥料、硫黄泉、鉱山排水、工場排水、屎尿を含む下水排水および海水などの混入により増加することもある。
また、浄水処理において凝集剤に硫酸アルミニウムを使用すると若干増加する。硫酸イオンが多量に含まれると水の味が悪くなり、鉄管などの腐食を促進する傾向がある。
16 溶性ケイ酸
自然水中のケイ酸の形態は非常に複雑で、イオン、コロイドおよび分子状のものやケイ酸塩または生物体に含まれるものなど各種ある。測定上から大別して、溶性ケイ酸と総ケイ酸があり、溶性ケイ酸は水中における溶解性のケイ酸のことである。
分析法は、ろ過した試料水に酸性でモリブデン酸アンモニウムを加えるとモリブデン黄の帯緑色となるので、これを吸光光度法により波長410nm 付近の吸光度を測定する方法である。
http://www.jwwa.or.jp/mizu/pdf/2007-kaisetsu.pdf
EARTH BLOG スペシャルブログ
地球で起きている数々のドラマを伝える人、その向こうを見る人を応援します。