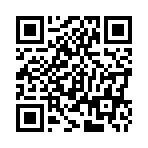2009年11月14日
水道統計(水質編)における調査対象項目の解説
● 水道統計(水質編)における調査対象項目の解説
A 水質基準項目(50項目)
水道により供給される水は、水道法第4 条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に
適合することが必要です。
なお、水質基準については、厚生労働大臣により諮問を受け厚生労働審議会において検討がなされました。
その検討経緯は、 に公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/shingikai.html
項目 基準値 解説
1 一般細菌
1ml の検水で形成される集落数が100 以下であること
一般細菌とは、標準寒天培地を用いて36±1℃で24±2時間培養したとき、培地に集落を形成する細菌のことをいう。分類学的に特定のグループを意味するものではない。
一般細菌として検出される細菌の多くは病原菌ではないが、汚染された水ほど多く検出される。
2 大腸菌
検出されないこと
ここでいう大腸菌(Escherichia coli)とは、特定酵素基質培地法によってβ−グルクロニダーゼ活性を有すると判定された好気性又は通性嫌気性の細菌のことをいう。
大腸菌はヒトや温血動物の腸管に常在し、環境中での増殖はまれなため、糞便由来でない細菌も含む大腸菌群と比べて糞便汚染の指標としてより信頼できる。
他の糞便指標細菌と比較すると自然界では生存期間が短いといわれている。飲料水中に大腸菌が存在することは、直ちに対応が必要とされる危険な汚染である可能性を示している。塩素消毒が完全であれば検出されない。
3 カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して、0.01mg/L 以下
カドミウムは、亜鉛とともに自然界にごく微量であるが存在していることが多い。 地表水、地下水中に亜鉛含量の1%以下の割合で存在しているといわれる。
カドミウムの用途は充電式電池、ビニル安定剤のステアリン酸カドミウムなどと広い。
富山県の神通川流域に多発したイタイイタイ病は、鉱山排水中のカドミウムが主な原因とされ、昭和43年(1968)5月8日に
公害病に認定された。慢性中毒では肺気腫、腎障害、骨変化、タンパク尿の症状がみられる。
4 水銀及びその化合物
水銀の量に関して、0.0005mg/L 以下
一般に無機水銀と有機水銀に分けられる。総水銀とは両者の合計量をいう。 主要鉱物は辰砂(HgS)。 常温で唯一の液体金属。
温度計、気圧計などの計器類の他に、各種水銀化合物の原料として、また電極、触媒、水銀灯など、幅広い用途がある。
水銀による急性中毒は口内炎、下痢、腎障害、慢性中毒では貧血、白血球減少を起こし、さらに手足の知覚喪失、精神異常となる。 水俣病の原因は、工場排水中のメチル水銀を摂取した魚介類を食したためである。
5 セレン及びその化合物
セレンの量に関して、0.01mg/L 以下
硫黄鉱床などから産出。周期表では硫黄と同族であるが金属性が大きい。光伝導性のある半導体で多くの同素体がある。光電池、整流器、複写機感光体などの電気材料、有機合成化学の触媒、色ガラス、顔料など、各種部門に広く用途がある。金属セレンの毒性は少ないが、化合物には猛毒のものが多い。
粘膜に刺激を与え、胃腸障害、肺炎などの症状を起こし、全身けいれんから死に至ることがある。
6 鉛及びその化合物
鉛の量に関して、0.01mg/L 以下
方鉛鉱、白鉛鉱を原料鉱として得られる。軟らかく加工しやすい金属なので、昔から水道管として使用されてきた。近年は水道メータの前後など一部に限られている。かつては鉛の表面に酸化被膜ができ、鉛は溶けにくいといわれたが、最近その溶出が問題視され、水道事業体ではステンレス管などに切り替える傾向にある。
鉛は神経系の障害や、貧血、頭痛、食欲不振、鉛疝痛などの中毒症状を呈することが知られている。
7 ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下
自然界では銅、鉄、水銀、鉛、ニッケルなどの鉱物と共存し自然水中に溶出するほか、鉱山排水や工場排水、ヒ酸石灰やヒ酸鉛などの農薬の混入によっても水中に含まれることがある。ヒ素化合物の毒性はその結合形によって異なる。
通常、3価および5価のヒ素化合物として存在し、いずれも毒性を持つが、3価のヒ素の方が5価のヒ素よりも毒性が強い。可溶性無機ヒ素化合物を摂取すると急速に吸収され、肝臓、腎臓、消化管などに強く作用する。
8 六価クロム化合物
六価クロムの量に関して、0.05mg/L 以下
6価の形で存在しているクロムのこと。水に溶けてクロム酸および重クロム酸を生成する。メッキ廃水に多量に含まれる。6価クロム塩を多量に摂取した場合、嘔吐、下痢、尿毒症などを引き起こす。致死量は成人の場合K2CrO7で0.5〜1gである。
9 シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して、0.01mg/L 以下
シアン化合物には、シアン化ナトリウム、シアン化カリウムのように水中でシアンイオン、シアン化水素を容易に生成する遊離型シアンと、フェリシアン化カリウム、フェロシアン化カリウムのように金属錯化合物を形成する錯塩シアンがある。
シアンは、めっき、鉄鋼製造、金銀の選鉱や多くの化学合成工業で使用される。シアンは自然中にはほとんど存在しない。シアン化合物を含んだ工場排水の混入によって水中に見いだされる。
また、含窒素化合物の燃焼によってもシアンが生じる場合がある。シアン化合物には強い毒性がある。ヒトの体内にはいると、粘膜から吸収され、頭痛、吐き気などを引き起こし、死亡する場合もある。
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/L 以下 (硝酸態窒素)
水中の硝酸イオン(NO3−)および硝酸塩に含まれている窒素のことである。硝酸イオンは有機および無機の窒素化合物の最終的酸化形である。
硝酸態窒素を多量に含む水を摂取した場合、体内で細菌により硝酸塩は亜硝酸塩へと代謝され、亜硝酸塩は血液中でメトヘモグロビンを生成して呼吸酵素の働きを阻害しメトヘモグロビン血症を起こす。
(亜硝酸態窒素)
水中の亜硝酸イオン(NO2−)または亜硝酸塩に含まれている窒素のことである。水に混入したアンモニア態窒素が酸化されて生ずる場合が多いが、硝酸態窒素の還元によって生じる場合も多い。
亜硝酸塩は赤血球のヘモグロビン(体内組織へ酸素を運搬する)と反応してメトヘモグロビンを生成し、呼吸酵素の働きを阻害するメトヘモグロビン血症を起こす。
体内で硝酸態窒素は亜硝酸態窒素へと速やかに変化するため、水道水質基準は硝酸態窒素および亜硝酸態窒素の合計量となる。
11 フッ素及びその化合物
フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下
水中のフッ素は、主として地質や工場排水の混入などに起因する。自然界に広く分布しているホタル石はフッ化カリウムが主成分であるため、日本でも特に温泉地帯の地下水や河川水に多く含まれることがある。
フッ素を適量に含んだ水を飲用した場合には「う歯」(むし歯)の予防に効果があるといわれているが、多量に含まれていると斑状歯(歯牙の慢性フッ素中毒)の原因となる。
12
ホウ素及びその化合物
ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下
ホウ素は、自然中に含まれることはまれであるが、火山地域の地下水、温泉水にはメタホウ酸の形で含まれることがある。また、金属の表面加工処理剤、ガラス、エナメル工業などで使用されるので、これらの工業排水に混入することがある。
ホウ酸を少量摂取した場合には緩和な生理作用を示すに過ぎないが、多量のときには消化器、神経中枢等に影響を及ぼす。ホウ素による中毒症状は、一般に胃腸障害、皮膚紅疹、抑うつ症を伴う中枢神経刺激の症状である。
13 四塩化炭素
0.002mg/L 以下
テトラクロロメタン、ベンジノホルムともいう。比重1.59(20℃)。融点−23℃、沸点76.5℃の無色透明な液体。水に対する溶解度は800mg/L(25℃)で、アルコール、エーテル、クロロホルムなどに混和する。蒸気圧115mmHg(25℃)。主な用途はフロンガスの製造原料、薫蒸殺菌剤、金属洗浄用溶剤などある。
液化塩素に不純物として存在することがある。その毒性は肝臓の感受性が最も高く、脂肪浸潤、肝細胞内酵素の遊離、細
胞内酵素活性の抑制、炎症が起こり、最終的に肝細胞壊死を引き起こす。
14 1,4-ジオキサン
0.05mg/L 以下
1,4-ジオキサンは、特異的な臭気のある無色の液体である。溶剤や1,1,1−トリクロロエタン安定剤などの用途に使用されるほか、ポリエキシエチレン系非イオン界面活性剤及びその硫酸エステルの製造工程において副生し、洗剤などの製品中に不純物として存在する。その毒性は目に強い刺激性を有し、肝臓、腎臓、中枢神経に影響を与え、また皮膚の脱脂を起こすことがある。
ヒトに対しては、弱い遺伝毒性しか示されていないが、多臓器での腫瘍を誘発することが報告されている。IARC では、ヒトへの発ガン性の可能性があるとして、Group2B に分類している。
15 1,1-ジクロロエチレン
0.02mg/L 以下 1,1,−ジクロロエチレンは、揮発性有機塩素化合物であるが、蒸気は空気より重い。酸化されやすく、酸素と接触すると過酸化物を生成する。
1,1−ジクロロエチレンの環境への放出は、製造過程及びポリマー製造の原料として使用されている際に起きる。揮発性のため、ほとんどが大気中へ移行していき、地表水を汚染した1,1−ジクロロエチレンも速やかに揮発する。
地下水では、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びこれらの分解成物である1,2−ジクロロエチレンや塩化ビニルと共存することが知られている。
主たる用途は、塩化ビニリデン樹脂の製造原料である。塩化ビニリデン樹脂は、家庭用ラップ、食品包装用フィルム、紙やプラスチックの表面コーティング等に使用される。ヒトでは、神経症状、肝機能障害、頭痛、視覚障害等がある。
16 シス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下 化学合成品はシス体とトランス体の混合物である。水には難溶であるが、各種の有機溶剤には易溶である。化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用される。ヒトに対して麻酔作用がある以外に報告例がない。
シス-1,2-ジクロロエチレンの環境中への放出は、製造過程及び溶剤として使用する過程で起きる。揮発性のため、多くが大気中に移行する。
地表水を汚染したシス-1,2-ジクロロエチレンは速やかに大気中に揮散する。土壌に浸透すると吸着されにくく、地下水中に長期間滞留する。地中のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが還元状態で微生物分解を受けると、シス-1,2-ジクロロエチレンが生成される。地下水中では、多くの場合トリクロロエチレンと共存している。
シス体とトランス体の混合物の毒性はLD50(ラット,経口)770mg/kgで、単回投与によりラットの肝アルカリホスファターゼが顕著に増加した。多量に摂取した場合には、腹痛、咳、咽頭痛、めまい、吐き気、嗜眠、脱力感、意識喪失、嘔吐等の急性症状がみられる。
17 ジクロロメタン
0.02mg/L 以下
沸点40℃の無色の液体。合成有機化学物質であり、自然界には存在しない。殺虫剤、塗料、ニス、塗料剥離剤、食品加工中の脱脂処理および洗浄液などとして使われる。
表流水中に排出されたジクロロメタンは大気中に揮散し数日から数週間で分解するが、地上に排出されたジクロロメタンは容易に地下水に移行し、長期間残留する。
ジクロロメタンの毒性はLD50(ラット,経口)2,121mg/kg、(マウス,経口)1,987mg/kgである。また、1.3mg/kg体重の単回投与では、呼吸困難、運動失調、チアノーゼ及び昏睡が認められた。多量に摂取した場合には、腹痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感、意識喪失の急性症状がみられる。
18 テトラクロロエチレン
0.01mg/L 以下
テトラクロロエテン、パークレン、パークロロエチレンともいう。比重1.62(20℃)、融点22.4℃、沸点121.2℃の液体。蒸気圧19mmHg。水に対する溶解度150mg/L(25℃)。主な用途はドライクリーニング溶剤,金属用脱脂剤など。
この物質は使用後排出され、土壌中を移行して直ちに地下水中に入り、地下水汚染物質の一つとなっている。地下水中では数カ月から数年間にわたって残留する。
トリクロロエチレンに比べて尿中代謝物排泄ははるかに少ない。その毒性はLD50(ラット,経口)8.85g/kgで、肝
腎障害や中枢神経抑制作用があり、また、肝ガンの発生も認められている。多量に摂取した場合には、腹痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感、意識喪失の急性症状がみられる。
19 トリクロロエチレン
0.03mg/L 以下
TCE、トリクレン、トリクロロエテンともいう。比重1.4 (25℃)、融点−86.4℃、沸点86.7℃の無色透明の液体。蒸気圧77mmHg(25℃)。
水に対する溶解度1g/L(20℃)。主な用途は金属の脱脂剤である。環境に放出されて地下水汚染を超こす。地下水中に長期間残留 し、分解してジクロロエチレンや塩化ビニルになる。
また,テトラクロロエチレンの分解によって生成することもある。体内吸収では抱水クロラールを経てトリクロロ酢酸に代謝される。毒性はLD50(ラット,経口)4.92g/kgで、発ガン性も認められる。多量に摂取した場合の急性症状は、腹痛、めまい、し眠、頭痛、脱力感、吐き気、意識喪失がある。
20 ベンゼン
0.01mg/L 以下
揮発性のある無色の液体で、芳香族特有の芳香があり、引火性が大きい。エタノールおよびエーテルとはすべての割合で混合するほか、多くの有機溶媒に可溶である。
水には難溶。置換、付加および開裂の三つの反応が起こり、多種の芳香族化合物を生成する。溶剤、燃料、アルコール変性剤などとしても重要である。
発ガン性を有する。その毒性はLD50(ラット、マウス,経口)1〜10g/kgで、発ガン性や骨髄形成不全、リンパ球減少症
も認められる。多量に摂取した場合の急性症状は、腹痛、咽頭痛、嘔吐がある。
21 クロロ酢酸
0.02mg/L 以下
クロロ酢酸は、刺激臭のある無色の結晶である。除草剤、チューインガム可塑剤、塩化ビニル可塑剤、医薬品、アミン酸等合成、香料、キレート剤、界面活性剤として使用される。
クロロ酢酸などのハロゲン化酢酸類は、水道水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒
副生成物の一つである。その毒性はLD50(ラット,経口)55mg/kgで、皮
膚や鼻、目の粘膜を腐食する。変異原性が認められる。
22 クロロホルム
0.06mg/L 以下
比重1.49(20℃)。融点−63.5℃、沸点61.2℃の無色透明の液体で、甘い刺激臭がある。水に対する溶解度は0.28g/100g(20℃)で,エタノール、エーテルなどには易溶である。
主な用途として医薬品、溶剤、有機合成の原料などがある。クロロホルムは、浄水処理における塩素消毒によって生成するトリハロメタンの主成分である。クロロホルムには強い麻酔作用があり、肝臓、腎細尿管、心臓などに細胞毒として作用する。
また、動物実験によって腎腫瘍や肝癌などの発癌性が確認されている。低濃度の慢性毒性では胃腸、肝腎障害が起こり、高濃度では反射機能の喪失、感覚麻痺、呼吸停止などが起こる。
23 ジクロロ酢酸
0.04mg/L 以下
ジクロロ酢酸は、刺激臭のある無色の液体である。ジクロロ酢酸などのハロゲン化酢酸類は、浄水過程において水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物物質の一つである。
マウスに75週にわたってジクロロ酢酸を飲水投与した結果、最大無作用量は50mg/kg/日である。慢性試験で発ガン性を示す根拠は認められていない。IARC では、ヒト発ガン性物質として分類できないとして、Group3に分類されている。
24 ジブロモクロロメタン
0.1mg/L 以下
浄水処理過程で使われる消毒剤の塩素と水中のフミン質などの有機物質が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。生成量は原水中の臭素イオンに大きく影響される。
写真工業の排水や海水の影響を受けやすいところ、また塩分を含む地下水で臭素化トリハロメタンが多い。その毒性はLD50(雄マウス,経口)800mg/kg、(雌マウス,経口)1200mg/kgである。参考文献:アメリカ国家毒性プログラムNTP(1985)ではマウスによる2 年間の経口投与実験では、肝の脂肪変性、腎ネフローゼが認められた。
25 臭素酸
0.01mg/L 以下
臭素酸の最も一般的な形態が臭素酸カリウムと臭素酸ナトリウムである。臭素酸カリウムは小麦粉改良材として、臭素酸ナトリウムは分析用試薬、毛髪のコールドウェーブ用薬品等に使用される。
浄水処理においてオゾンを使用する場合、臭素イオンから消毒副生成物として生成される。また、消毒剤としての次亜塩素酸ナトリウム生成時に、不純物の臭素が酸化され、臭素酸が生成される。
毒性影響には、腹痛、中枢神経系の機能低下、呼吸困難、肺浮腫、腎機能低下、聴覚障害等及び発ガン性が報告されている。
ヒトが摂取すると消化管から速やかに吸収され、肝臓でグルタチオン抱合された後臭化物に還元される。IARC では、実験動物の発ガン性に関しては十分な証拠があるとして、Group2B に分類している。
26 総トリハロメタン
0.1mg/L 以下
メタン(CH4)の水素原子3個が、塩素、臭素、あるいはヨウ素に置換された有機ハロゲン化合物の総称。THMと略称される。これらのうち、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の合計を総トリハロメタン(TTHM)と呼ぶ。
水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に存在するフミン質などの有機物を前駆物質として、塩素処理によって生成する。なかでもクロロホルムは発ガン物質であることが明らかとなっている。
27 トリクロロ酢酸
0.2mg/L 以下
トリクロロ酢酸は、刺激臭のある無色で吸湿性の結晶である。医薬品の原料、除草剤、腐食剤、角質溶解剤、塗装剥離剤、除タンパク剤、生体内タンパク・脂質の分画剤として使用される。水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物質の一つである。
マウスで肝腫瘍を引き起こすが、変異原性や染色異常などのin vitro 系の試験では陰性及び陽性の結果が混在して報告されており、IARC ではヒト発ガン性物質として分類できないとしてGroup3に分類されている。
28 ブロモジクロロメタン
0.03mg/L 以下
浄水処理過程で使われる消毒剤の塩素と水中のフミン質などの有機物質が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。生成量は原水中の臭素イオンに大きく影響される。写真工業の排水や海水の影響を受けやすいところ、また塩分を含む地下水で臭素化トリハロメタンが多い。
その毒性はLD50(雄マウス,経口)450mg/kg、(雌マウス,経口)900mg/kgである。参考文献:アメリカ国家毒性プログラムNTP(1987)では、マウスによる2 年間の経口投与実験では、腎細胞肥大、肝の脂肪変性のほか腎臓の腺腫と腺がん、肝細胞の腺腫と腺がんがみられた。
29 ブロモホルム
0.09mg/L 以下
同上
30 ホルムアルデヒド
0.08mg/L 以下
ホルムアルデヒドは、特徴的な臭気のある気体で、有機溶媒に易溶である。浄水過程で、水中のアミン等の有機物質と塩素、オゾン等の消毒剤が反応して生成される。
主要な構成物資として、ホルムアルデヒドとアセトアルデヒド等がある。エポキシ樹脂塗料及びアクリル樹脂塗料の原料として
使用される。土壌燻蒸剤として線虫等の駆除に使用される。
野菜、樹木の苗木などの防除に使用される。ヒトへの健康影響としては、内服したとき、呼吸困難、めまい、嘔吐、口腔及び胃に炎症が起きる。
吸入曝露試験では発ガン性を示し、鼻と喉の灼熱感、頭痛、吐き気などが起こり、短期暴露の場合、眼、皮膚、気道に対して腐食性があり、肺水腫を起こすこともある。
高濃度で死に至ることもある。経口曝露では明らかな発ガン性は示さない。
31 亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下
自然水中に微量に含まれるが、高濃度の亜鉛は鉱山排水や工場排水などによる汚染が原因であることが多い。水道水で高濃度の亜鉛が検出される場合は、そのほとんどが給水管などの亜鉛引き鋼管からの溶出による。
水道水に高濃度の亜鉛が含まれていると白濁して、いわゆる白水の原因となる。また5mg/L以上含まれると収れん味を呈する。毒性は比較的弱いが、高濃度の場合には腹痛、嘔吐、下痢などの中毒症状をもたらすことがある。
32 アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下
地球の表面に存在する元素で3番目に多く、金属では最も多い。比重が2.6で、さびにくく、かなり丈夫なので航空機、自動車、建築物などに使われている。
アルミニウムの化合物である明ばんは昔から水の清澄剤として、また,硫酸アルミニウム、ポリ塩化アルミニウムも水道水の水処理剤として用いられている。
濃度が高いと、白濁水の原因となる。
33 鉄及びその化合物
鉄の量に関して、0.3mg/L 以下
クラーク数は4.7で、酸素、ケイ素、アルミニウムについで地球で4番目に多い元素である。地表水中ではFe(OH)3として懸濁して存在している。
また,泥炭地などの有機物の多いところではコロイド性の有機錯体として存在する。自然水中に含まれる鉄は、地質に起因するもののほか鉱山排水、工場排水などからの場合もある。0.3mg/L以上溶解すると、水に色がつきはじめ赤水の原因となり、臭気や苦味を与える(0.5mg/L)。
鉄は栄養上,1人1日当たり約10mg以上必要とされている。鉄塩の毒性はLD50(マウス,経口)300〜600mg/kg、LD50(ラット,経口)800〜2,000mg/kgである。
急性毒性は、うつ病、昏睡、呼吸障害や心拍停止などである。
34 銅 及びその化合物
銅の量に関して、1.0mg/L 以下
天然には主として硫化物(黄銅鉱、班銅鉱、輝銅鉱)の形で産出する。電線、合金、貨幣、彫刻、メッキ、農薬など、多くの分野に用いられる。
銅イオンを1.0mg/L以上含む水は金属味を帯び、着色(青色)を与える。ヒトにとって銅は必須元素であり、成人の必要量は1日に約2mgとされている。
銅化合物は藻類、カビ類、無脊椎動物に対しては強い毒物であるが、哺乳類に対しては蓄積性が認められないので慢性中毒のおそれは少ない。
35 ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下
地殻中に広く分布。海水中には約10g/L含まれ、また岩塩として巨大な鉱床をつくる。ナトリウムは自然水中に広く存在する元素であるが、海水、工場排水の混入、水処理時のカセイソーダによるpH調整などに由来することもある。
ナトリウムイオンは動物体内の生理に重要な役割を果たしている。ナトリウムと高血圧との関係はよく論じられるが、1日1.6〜9.6gの摂取量では人の健康に何ら影響はないとみられている。
36 マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下
マンガンは地殻中に広く分布しており、軟マンガン鉱などに多く含まれる。生理的に不可欠の元素で、炭水化物の代謝などに関与する。水道水中にマンガンが多いと、浄水に黒い色をつけるので好ましくない。
過剰摂取すると全身倦怠感、頭痛、不眠、言語不明瞭などの中毒症状を起こす。
37 塩化物イオン
200mg/L 以下
水中に溶存している塩化物中の塩素のこと。自然水は常に多少の塩化物イオンを含んでいるが、これは地質に由来するもので、特に海岸地帯では海水や送風塩の影響によることが大きい。
しかし、塩化物イオンは下水系、生活系および産業系などの各排水や、屎尿処理水などの混入によっても増加する。したがって、塩化物イオンは水質汚濁の指標の一つともなっている。
硝酸銀と反応して塩化銀の白色沈澱を生ずるため、測定にはこの性質を利用した硝酸銀法(モール法)がある。多量の塩化物イオンは水に味をつけたり、鉄管などの腐食を促進する傾向がある。塩化物の毒性は陽イオンの種類によって異なっており、塩化物イオン自体の毒性は知られていない。
しかしながら、2.5mg/L 以上の濃度の塩化ナトリウムを含む飲料水を過剰に飲用していると高血圧症を引き起こすと報告されている。
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
300mg/L 以下 (カルシウム)
アルカリ土壌金属の一つで、展性・延性がある。自然界には遊離状態で産出されず、炭酸塩およびケイ酸塩として広く多量に存在する。水中ではカルシウムイオン(Ca2+)と して存在し、硬度の主体をなしている。その起源は地質によるものが主であるが、他にコンクリート構造物からの溶出、海水、工場排水および温泉などの混入に由来するものがある。
原子吸光分析法により波長422.7nmの吸光度を測定する方法やカルシウム硬度による測定方法(EDTA法)などがある。
(マグネシウム)
アルカリ土類金属の一つ。自然界では単体としては存在せず、炭酸塩、ケイ酸塩、硫酸塩および塩化物などとして広く多量に存在する。
水中にはマグネシウムイオンとして存在し、カルシウムイオンとともに硬度の主体をなしている。その成因は主に地質に由来するが、鉱山排水、工場排水、海水および温泉などの混入によることもある。原子吸光分析法により波長285.2nmで吸光度を測定する方法や総硬度とカルシウム硬度の差から求める測定法がある。
健康障害としては、硬度が高すぎると胃腸を害して下痢を起こすことがある。
39 蒸発残留物
500mg/L 以下
水を蒸発乾固したときに残る物質。具体的には、一定量の検水を蒸発皿に入れて水浴上で蒸発乾固し、残った物質量を求める。濁質のある検水をそのまま蒸発乾固すれば、浮遊物質と溶解性物質との総和となる。
水道水の主な蒸発残留物の成分は、カルシウム、マグネシウム、シリカ、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物である。健康への影響はほとんど生じない。
40 陰イオン界面活性剤
0.2mg/L 以下
界面活性剤のうち、水溶液中で電離して活性剤の主体が陰イオンになるもの。工場排水、家庭下水などの混入に由来し、水中に存在すると泡立ちの原因となり、汚濁の重要な指標である。
また、陰イオン界面活性剤に付随するリン酸塩による水源の富栄養化が問題となっている。その毒性はほとんど認められない。
41ジェオスミン
0.00001mg/L 以下
ジェオスミンは、湖沼等で富栄養化現象に伴って発せするかび臭(異臭味)の原因物質である。藍藻類のアナベナにより産生される。その毒性はほとんど認められない。
42 2−メチルイソボルネオール
0.00001mg/L 以下
2−メチルイソボルネオールは、湖沼等で富栄養化現象に伴って発せするかび臭(異臭味)の原因物質である。藍藻類のフォルミディウムやオッシラトリアにより産生される。その毒性はほとんど認められない。
43 非イオン界面活性剤
0.02mg/L 以下
非イオン界面活性剤とは、界面活性剤のうち、イオンに解離する基を持たない物質の総称である。エーテル型、エーテルエステル型、エステル型、含窒素型が知られている。
洗浄剤、乳化剤、分散剤、消泡剤、潤滑油、化粧品、流出油の処理剤等に使用される。その毒性は、一般に陰イオン界
面活性剤に比べ低く、健康への影響はほとんど生じない。
44 フェノール類
フェノールの量に換算して、0.005mg/L 以下
芳香族化合物のベンゼン環の水素が、水酸基で置換された化合物の総称で、環境汚染に関連するものは主としてフェノール(石炭酸)、ο−,m−,p−クレゾール、クロロフェノールなどである。合成樹脂、界面活性剤などの原料として大量に使用されている。
フェノール類は、天然水中には存在しないが、化学工場排水、ガス製造工場排水などに含まれる。フェノール類が含まれていると水の塩素処理過程でクロロフェノール類が生成し、水に著しい異臭味を与えるので、厳しい排水基準が示されている。
45有機物(全有機炭素(TOC)の量)
5mg/L 以下
水中の全有機炭素(TOC : Total Organic Carbon)は、種々の有機化合物から構成されていて、これらの有機化合物に含まれている炭素量をいう。全有機炭素は、水中に含まれる有機物総量の指標として用いることができるため、原水の有機性汚濁の状況や浄水処理過程における水の処理性評価に利用することができる。
また、溶存有機炭素(DOC)も有機性汚濁の指標として用いられている。
46 pH値
5.8 以上8.6以下
水素イオンのモル濃度(水素イオン濃度)の逆数の常用対数値。pH7は中性、pH7より値が小さくなるほど酸性が強くなり、値が大きくなるほどアルカリ性(塩基性)が強くなる。
水道法に基づく水質基準は5.8以上8.6以下であること、また、水質管理目標設定項目としての目標値は7.5程度
とされている。水の基本的な指標の一つであり、理化学的水質、生物学的水質、浄水処理効果、管路の腐食などに関係する重要な因子である。
測定法はガラス電極法(pH計)がある。
47 味
異常でないこと
水の味は、水に溶存する物質の種類・濃度によって感じ方が異なる。味の原因には、下水、工場排水等による汚染、生物や細菌類の繁殖、また、海岸地帯では海水の影響をうけ塩味を感じることもある。
異常な味は不快感を与えるので飲用には適さない。
48 臭気
異常でないこと
水の臭気は水に溶解している種々の物質が原因となっています。水道において問題となる臭気物質は、藻類や放線菌等の生物に起因するかび臭物質、フェノールなどの有機化合物が主です。異常な臭気は不快感を与え
るので飲用には適しません。
49 色度
5 度以下
水中に含まれる溶解性物質およびコロイド性物質が呈する黄褐色の程度をいう。原水においては、主に地質に由来するフミン質、フミン酸鉄による呈色と同じ色調の色について測定される。水道水においては配管等からの鉄の溶出などによって色度が高くなることがある。
精製水1L中に白金イオン1mgおよびコバルトイオン0.5mgを含むときの呈色に相当するものを1度としている。
50 濁度
2 度以下
濁度は、水の濁りをポリスチレン系粒子(5種類)を濁質の標準液とし、これと比較して測定する。水道において、原水濁度は浄水処理に大きな影響を与え,浄水管理上の指標となる。
また、給水栓中の濁りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要である。
B 水質管理目標設定項目(27項目)
水質基準とするにいたりませんが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目、必要に応じ水質検査を実施する項目です。このうち農薬類については、全国の検出状況や使用量などを考慮して、101項目がリストアップされ、「総農薬方式」とよばれる考え方で設定されています。
項目 目標値 解説
1 アンチモン及びその化合物
アンチモンの量に関して、0.015mg/L 以下
アンチモンは、半導体材料、潤滑剤、弾薬、陶器、硝子など材料成分として主に使われている。三価アンチモンは容易に赤血球に取り込まれるが、五価アンチモンは取り込まれない。飲料水中のアンチモンの形態が毒性のキー決定要因であるが、飲料水中のアンチモンはほとんどが、弱毒性型の五価アンチモン、オキソ-陰イオン型と思われる。
ヒトへの健康影響では、嘔吐、下痢が知られていて、三価アンチモンの発ガン性はグループ2Bに分類されているが、この判断となった知見のほとんどは、水に不溶な粒子による吸入暴露によるものであり、水溶性アンチモンの経口摂取による発ガン性を示す知見は知られていない。
2 ウラン及びその化合物
ウランの量に関して、0.002mg/L 以下(暫定)
ウラン化合物はガラス・磁器の着色剤、光電管にも使用されているが、主に原子炉の燃料として使用されている。ごく微量であるが、地球の表面の近くの岩石(特に花崗岩)及び海水中に広く分布している。
ウランを含む鉱石や廃棄された選鉱くずからの溶出、核物質使用工場からの排出、石炭及び他の燃料の燃焼、ウランを含むリン酸肥料の使用になどにより環境中に放出される。
ウランの健康影響としては化学毒性による眼粘膜刺激、催涙及び結膜炎、吸入による気道刺激、腎障害などがある。また、放射線障害による肺ガン、リンパ腫の増加などがある。
3ニッケル及びその化合物
ニッケルの量に関して、0.01mg/L 以下(暫定)
ニッケルは、ステンレス綱、めっき、貨幣、顔料、触媒原料などに使用されている。ニッケルの化合物は不溶性のものが多いので、自然水中に存在することはまれであるが、鉱山排水、工場排水あるいはニッケルめっきの溶出などから混入することがある。また、水道では管材及びその他の材料の腐食による汚染がある。
大量に摂取するとめまい、嘔吐、急性胃腸炎を引き起こす。発ガン性の評価については、金属ニッケルではIARCグル
プ2B、ニッケル化合物ではグループ1にそれぞれ分類されている。
4亜硝酸態窒素
0.05mg/L 以下(暫定)
水中に含まれる亜硝酸イオン中の窒素の量であり、窒素肥料、腐敗した動植物、家庭排水等に由来する。これらに含まれる窒素化合物は、環境中で化学的・微生物学的に酸化及び還元を受け、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素等になる。
摂取すると体内で食物中のタンパク質に含まれるアミン類と結合し、発ガン物質であるニトロソアミンを生成したり、急性毒性を引き起こす危険性がある。
塩素処理により容易に硝酸態窒素へと酸化されるので、通常の浄水処理により除去され、残留塩素のある浄水には存在しな
い。
5 1,2-ジクロロエタン
0.004mg/L 以下
主に塩化ビニルモノマーの原料として使用されるほか、有機溶剤、殺虫剤、金属の脱脂洗浄等に使用されている。環境中には、貯蔵タンクからの漏出や工場排水等により放出されるおそれがある。地表水を汚染した場合は比較的容易に大気中に揮散するが、土壌吸着性は低く、土壌を浸透し地下水に進入すると安定な形で閉じこめられるため長期間にわたり汚染が継続する。
健康影響はめまい、吐き気、嘔吐などがある。
6 トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下
シス体との混合物で使用され、化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用されている。また、トリクロロエチレンの分解物でもある。吐き気、眠気、疲労感、めまい等の中枢神経系への影響がある。
7 1,1,2-トリクロロエタン
0.006mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレンの製造原料、油脂、ワックス、天然樹脂の溶剤として使用されている。土壌吸着性は低く、地下水中に長時間残留する。長期暴露では慢性胃炎、肝臓への脂肪蓄積、肺障害など、上記暴露では呼吸器と眼に対する刺激作用がある。
8 トルエン
0.2mg/以下
染料、香料、有機顔料、ポリウレタン、合成繊維などの原料として、また、樹脂や塗料の溶剤として使用されている。石油成分の一つで石油分留生成で得られる。
健康影響としては、急性暴露により、頭痛、吐き気、錯乱などの症状を引き起こす。
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
0.1mg/L 以下
可塑剤として、ポリ塩化ビニルフィルム、シート、レザー、ホース、機械器具部品、日用雑貨などに使われ、また農薬、化粧品、染料、印刷インクなどの溶剤や保留剤としても使用されている。
大量摂取により、胃腸、肝臓障害などの報告例がある。
10亜塩素酸 0.6mg/L 以下
11塩素酸 0.6mg/L 以下
12二酸化塩素 0.6mg/L 以下
主に漂白剤として使用されている。二酸化塩素を浄水過程で酸化剤として使用した場合に検査を行うことが望ましいとされている項目である。
亜塩素酸塩、塩素酸塩から合成される二酸化塩素を処理水中に投入した場合に分解生成物として亜塩素酸イオン、塩素酸イオンが生成する。
赤血球中のヘモグロビンが亜塩素酸塩により酸化され、メトヘモグロビンを形成することによる中毒症が知られている。
13 ジクロロアセトニトリル
0.04mg/L 以下(暫定)
塩素処理の際に遊離塩素とフミン物質、藻類、アミン酸が反応してできる副生成物の1 つである。時間の経過とともに、また水温が高いほど生成量は増加するが、トリハロメタンほど顕著ではない。土壌や汚泥等にはあまり吸着せず、生物への濃縮もあまり大きくないと考えられている。
14 抱水クロラール
0.03mg/L 以下(暫定)
塩素消毒の際に遊離塩素とフミン質、酸化シアンが反応してできる副生成物の1つである。鎮静剤、睡眠薬等の医療用として、医薬品や農薬の原料として使用されている。
15 農薬類
検出値と目標値の比の和として、1 以下
水源上流などにおける農薬の使用状況により、使用されている薬剤について検査を行うこととされている。計101 種類の農薬が対象になっていて、総農薬方式として評価される。
16 残留塩素
1mg/L 以下
水中に塩素を注入することによって水中に残留した有効塩素をいい、次亜塩素酸などの遊離有効塩素(遊離残留塩素)とクロラミンのような結合有効塩素(結合残留塩素)に区分される。残留塩素の測定にはDPD法、ポーラログラフ法及び吸光光度法がある。
衛生上の措置として給水の残留塩素を遊離残留塩素として0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するよう規定している。
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
10mg/L 以上
100mg/L 以下
水質基準項目 38 を参照。
18マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.01mg/L 以下
水質基準項目 36 を参照。
19 遊離炭酸
20mg/L 以下
水中に溶解している二酸化炭素(CO2)のこと。遊離炭酸は炭酸塩や有機物質が分解して発生した二酸化炭素や空気中の二酸化炭素などが水中に溶解することに起因する。
地下水では有機物の分解などにより、一般に多く存在する。遊離炭酸には水中のアルカリ化合物と反応して炭酸化合
物を生成させるような腐食性のある侵食性遊離炭酸と、腐食性のない従属性遊離炭酸がある。
20 1,1,1-トリクロロエタン
0.3mg/L 以下
ドライクリーニング用溶剤、金属の脱脂洗浄剤、繊維のしみ抜き剤などに使用されている。健康影響としては、吐き気、下痢、めまい、ふらつきなどの症状がある。
21メチル-t- ブチルエーテル
0.02mg/L 以下
ガソリンのオクタン価向上剤、アンチノック剤、ラッカー混合溶剤の混和性改良材などに使用されている。健康影響については、毒性評価が詳細にされていないのが現状であるが、地下水で一過的に高濃度で検出されるとの情報もある。
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)
3mg/L 以下
水中の有機物や還元性物質(被酸化性物質)の量を、酸化させるのに必要な過マンガン酸カリウムの量として表したもので、一般に有機物の含有量の指標になっている。
土壌に由来するフミン質を多く含む場合や水道水源にし尿、下水又は工場排水が混入した場合に増加する。有機物の多い
水は渋みがあり、また、消毒に用いる塩素の消費量も多くなり、その点で水の味を損なう原因になる。
23 臭気強度(TON)
3 以下
検水の臭気をほとんど感知できなくなるまで無臭味水で希釈し、その希釈倍率によって示される臭気の強さのこと。TON ともいう。臭気に対する感受性は個人差があり、また、同一人でも測定時の状態で差異を生じるため、複数人数による試験が望ましい。
24 蒸発残留物
30mg /L 以上
200mg/L 以下
水質基準項目 39 を参照
25 濁度
1 度以下
水質基準項目 50 を参照
26 pH 値
7.5 程度
水質基準項目 46 を参照
27 腐食性(ランゲリア指数)
−1 程度以上とし、極力0に近づける
水のpH 値、カルシウムイオン量、総アルカリ度及び溶解性物質から求められるもので、水のpH値とその水の理論的pH 値との差を表す。指数が正の値で絶対値の大きいほど炭酸カルシウムの析出が起こりやすくなる。
また、負の値では炭酸カルシウム被膜が形成されず、その絶対値が大きくなるほど水の腐食傾向は強くなる。
C その他の項目
水質基準・水質管理目標設定項目ではありませんが、水道に関連する項目です。
項目 解説
1 水温
水温は、地表水の場合、気温の影響を受けやすく、湖沼や貯水池の場合、水温の変化によって、比重が変わり、水の停滞や循環などの原因となる。また、水温の上昇は物質の溶解性、生物の消長、河川での自浄作用などに影響を与える。
2 アンモニア態窒素
水中のアンモニウムイオン(NH4+)に含まれる窒素のこと。有機窒素化合物の分解、工場排水、下水および屎尿の混入によって生ずる場合が多い。土壌や水中の細菌により亜硝酸態窒素、硝酸態窒素へと酸化され、嫌気性状態では逆に硝酸態窒素、亜硝酸態窒素が還元されてアンモニア態窒素となる。
浄水処理では塩素処理や、緩速濾過のような生物化学処理によって分解され減少するので、処理工程の管理指標としても重要な項目である。測定方法にはインドフェノール法、ネスラー法、α−ナフトール法、蒸留比色法がある。
3 生物化学的酸素要求量(BOD)
水中の有機物が生物化学的に酸化されるのに必要な酸素量のことで、生物化学的酸素要求量ともいう。生物化学的酸化とは、水中の好気性微生物が有機物を栄養源とし、水中の酸素を消費してエネルギー化、生命維持・増殖するとき、有機物が生物学的に酸化分解されることをいい、有機物が多いほど消費される酸素量が多くなる。
したがって、BODが高いことはその水中に有機物が多いことを示し、化学的酸素要求量(COD)とともに水質汚濁を示す重要な指標である。生物化学的酸素要求量は試料を20℃、5日間静置し、静置前と後の溶存酸素量をウィンクラー法で測定し、その間に消費された溶存酸素量(mg/L)で表す。
4 化学的酸素要求量(COD)
化学的酸素要求量のこと。水中の被酸化性物質(有機物)を酸化剤で化学的に酸化したときに消費される酸化剤の量を酸素に換算したもの。CODが高いことはその水中に有機物が多いことを示し、生物化学的酸素要求量(BOD)とともに水質汚濁を示す重要な指標である。
測定方法には酸性過マンガン酸カリウム法があるが、酸化剤として重クロム酸カリウムを使用する方法もある。
5 紫外線(UV)吸光度
紫外線領域における特定波長の吸光度(紫外部吸光度、UV 吸光度)または透過率を光電的に測定し、検量線により濃度を求める方法。紫外線とは波長360〜400 以下1nm 程度までの電磁波を指すが、200nm 以下の波長域は空気による吸収があり、真空中で測定する必要があるため真空紫外線とよんでいる。
光源には石英水銀灯、重水素放電管、セキノンランプなどが用いられている。測定には紫外線領域に吸収の少ない石英セルを使用する。
6 浮遊物質(SS)
水中に懸濁している粒径1μm〜2mm 程度の不溶解性物質のことをいう。SSと記すこともある。上水試験方法では、網目2mm のふるいを通過した一定量の試料を1μm のメンブレンフィルターでろ過し、その残留物105〜110℃で2 時間乾燥し、秤量して求める重量法を定めている。
濁度との相関が議論されることがあるが、厳密な意味での相関関係はない。浄水処理、排水処理などに影響を及ぼす。
7 侵食性遊離炭酸
水中のアルカリ化合物と反応して炭酸化合物を生成させるような腐食性のある水中に溶解している二酸化炭素(CO2)のこと。
8 全窒素
水中に含まれる窒素化合物の総量のことで、窒素量で表す。窒素はリンとともに水源の富栄養化の原因物質の一つといわれ、湖沼やダム湖などの閉鎖性水域での富栄養化による藻類などの増加は、浄水操作上の障害や藻類に由来する臭気物質による水道水の異臭味問題などを引き起こすことがある。
測定方法にはカドミウム・銅カラム還元法,紫外線吸光光度法がある。
9 全リン
水中に含まれるリン化合物の総量をいい、リン量で表す。水中のリン化合物は、正リン酸(オルトリン酸)、メタリン酸、ピロリン酸、ポリリン酸などの無機リン酸塩と、農薬、エステル、リン脂質などの有機リン化合物があり、これらが溶存状態または懸濁状態で存在している。リンは地質中に広く存在し、あらゆる動植物にも含まれている。
したがって自然水中にも含まれるが、リン化合物は屎尿、肥料、農薬、合成洗剤などにも含まれているため、水中のリン化合物の増加は生活排水、工場排水、農業排水などの混入に由来する場合が多い。リン化合物の増加は湖沼・海域の富栄養化を促進する一因とされている。
測定は、加熱分解または高圧分解した後にモリブデン青法で行う。
10 リン酸イオン
リン化合物は、総リン、リン酸イオンおよび加水分解性リン化合物に区別して測定され、いずれもリン酸イオン量で表示される。リン酸には、メタリン酸、ピロリン酸、オルトリン酸、三リン酸、四リン酸などがあり、普通はオルトリン酸を単にリン酸または正リン酸という。オルトリン酸は水中で解離してオルトリン酸イオンとなる。測定方法には、モリブデン青法、モリブデン青抽出法がある。
11 トリハロメタン生成能
20℃、pH7.0±0.2 の条件下で、24±2 時間静置後、残留塩素が1〜2mg/L となるように塩素処理した検水のトリハロメタン濃度のことで、トリハロメタン前駆物質量の指標となる。THMFP、THM 生成能ともいわれる。
トリハロメタンの前駆物質として種々の有機物が認められているが、そのすべてが明らかではないので、前駆物質を直接測定することはできない。またトリハロメタンの低減方法として、塩素処理を行う前に前駆物質を除去する手法が効果的であるため、トリハロメタン生成能はその除去効果の評価手法として、広く利用されている。
12 生物
水道の場合、水源から給水栓水に至る水中に懸濁している微少な植物及び動物を指し、魚類など大型の生物は含まない。
試験結果は、水源の状況の監視、適切で効率のよい浄水処理方法の選択、生物障害予防及び対策に利用する。
13 アルカリ度
水中に含まれている炭酸水素塩、水酸化物および炭酸塩などを中和するのに必要な酸の量に相当するアルカリ量を炭酸カルシウム(CaCO3) のmg/Lで表したもので、酸消費量ともいう。中和点のpH値によりP−アルカリ度(フェノールフタレイン変色点pH8.3)とM−アルカリ度(メチルレッド混合指示薬変色点pH約4.8)に区別される。M−アルカリ度は総アルカリ度とも呼ばれる。
構成成分により炭酸水素塩によるものを炭酸水素アルカリ度(重炭酸アルカリ度)、水酸化物によるものを水酸基アルカリ度、炭酸塩によるものを炭酸アルカリ度という。
14 溶存酸素
水中に溶解している酸素のこと。DO ともいう。供給源の多くは大気であるが、藻類の光合成により発生した酸素のこともある。酸素の溶解度は気圧、水温、塩分などによって影響される。有機物で汚濁した水中では、生物化学的酸化により酸素が消費されるため溶存酸素が減少する。
水温が急激に上昇したり藻類が著しく繁殖した場合には、過飽和となることもある。
15 硫酸イオン
水中に溶解している硫酸塩中の硫酸分のこと。例えば硫酸カルシウムのような硫酸塩は水に溶けるとカルシウムイオンと硫酸イオンになる。硫酸塩は地殻中に広く分布しており、これが溶けて硫酸イオンとなるため、自然水中には常に多少の硫酸イオンが含まれている。これは主に地質に起因するが、化学肥料、硫黄泉、鉱山排水、工場排水、屎尿を含む下水排水および海水などの混入により増加することもある。
また、浄水処理において凝集剤に硫酸アルミニウムを使用すると若干増加する。硫酸イオンが多量に含まれると水の味が悪くなり、鉄管などの腐食を促進する傾向がある。
16 溶性ケイ酸
自然水中のケイ酸の形態は非常に複雑で、イオン、コロイドおよび分子状のものやケイ酸塩または生物体に含まれるものなど各種ある。測定上から大別して、溶性ケイ酸と総ケイ酸があり、溶性ケイ酸は水中における溶解性のケイ酸のことである。
分析法は、ろ過した試料水に酸性でモリブデン酸アンモニウムを加えるとモリブデン黄の帯緑色となるので、これを吸光光度法により波長410nm 付近の吸光度を測定する方法である。
http://www.jwwa.or.jp/mizu/pdf/2007-kaisetsu.pdf
A 水質基準項目(50項目)
水道により供給される水は、水道法第4 条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に
適合することが必要です。
なお、水質基準については、厚生労働大臣により諮問を受け厚生労働審議会において検討がなされました。
その検討経緯は、 に公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/shingikai.html
項目 基準値 解説
1 一般細菌
1ml の検水で形成される集落数が100 以下であること
一般細菌とは、標準寒天培地を用いて36±1℃で24±2時間培養したとき、培地に集落を形成する細菌のことをいう。分類学的に特定のグループを意味するものではない。
一般細菌として検出される細菌の多くは病原菌ではないが、汚染された水ほど多く検出される。
2 大腸菌
検出されないこと
ここでいう大腸菌(Escherichia coli)とは、特定酵素基質培地法によってβ−グルクロニダーゼ活性を有すると判定された好気性又は通性嫌気性の細菌のことをいう。
大腸菌はヒトや温血動物の腸管に常在し、環境中での増殖はまれなため、糞便由来でない細菌も含む大腸菌群と比べて糞便汚染の指標としてより信頼できる。
他の糞便指標細菌と比較すると自然界では生存期間が短いといわれている。飲料水中に大腸菌が存在することは、直ちに対応が必要とされる危険な汚染である可能性を示している。塩素消毒が完全であれば検出されない。
3 カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して、0.01mg/L 以下
カドミウムは、亜鉛とともに自然界にごく微量であるが存在していることが多い。 地表水、地下水中に亜鉛含量の1%以下の割合で存在しているといわれる。
カドミウムの用途は充電式電池、ビニル安定剤のステアリン酸カドミウムなどと広い。
富山県の神通川流域に多発したイタイイタイ病は、鉱山排水中のカドミウムが主な原因とされ、昭和43年(1968)5月8日に
公害病に認定された。慢性中毒では肺気腫、腎障害、骨変化、タンパク尿の症状がみられる。
4 水銀及びその化合物
水銀の量に関して、0.0005mg/L 以下
一般に無機水銀と有機水銀に分けられる。総水銀とは両者の合計量をいう。 主要鉱物は辰砂(HgS)。 常温で唯一の液体金属。
温度計、気圧計などの計器類の他に、各種水銀化合物の原料として、また電極、触媒、水銀灯など、幅広い用途がある。
水銀による急性中毒は口内炎、下痢、腎障害、慢性中毒では貧血、白血球減少を起こし、さらに手足の知覚喪失、精神異常となる。 水俣病の原因は、工場排水中のメチル水銀を摂取した魚介類を食したためである。
5 セレン及びその化合物
セレンの量に関して、0.01mg/L 以下
硫黄鉱床などから産出。周期表では硫黄と同族であるが金属性が大きい。光伝導性のある半導体で多くの同素体がある。光電池、整流器、複写機感光体などの電気材料、有機合成化学の触媒、色ガラス、顔料など、各種部門に広く用途がある。金属セレンの毒性は少ないが、化合物には猛毒のものが多い。
粘膜に刺激を与え、胃腸障害、肺炎などの症状を起こし、全身けいれんから死に至ることがある。
6 鉛及びその化合物
鉛の量に関して、0.01mg/L 以下
方鉛鉱、白鉛鉱を原料鉱として得られる。軟らかく加工しやすい金属なので、昔から水道管として使用されてきた。近年は水道メータの前後など一部に限られている。かつては鉛の表面に酸化被膜ができ、鉛は溶けにくいといわれたが、最近その溶出が問題視され、水道事業体ではステンレス管などに切り替える傾向にある。
鉛は神経系の障害や、貧血、頭痛、食欲不振、鉛疝痛などの中毒症状を呈することが知られている。
7 ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下
自然界では銅、鉄、水銀、鉛、ニッケルなどの鉱物と共存し自然水中に溶出するほか、鉱山排水や工場排水、ヒ酸石灰やヒ酸鉛などの農薬の混入によっても水中に含まれることがある。ヒ素化合物の毒性はその結合形によって異なる。
通常、3価および5価のヒ素化合物として存在し、いずれも毒性を持つが、3価のヒ素の方が5価のヒ素よりも毒性が強い。可溶性無機ヒ素化合物を摂取すると急速に吸収され、肝臓、腎臓、消化管などに強く作用する。
8 六価クロム化合物
六価クロムの量に関して、0.05mg/L 以下
6価の形で存在しているクロムのこと。水に溶けてクロム酸および重クロム酸を生成する。メッキ廃水に多量に含まれる。6価クロム塩を多量に摂取した場合、嘔吐、下痢、尿毒症などを引き起こす。致死量は成人の場合K2CrO7で0.5〜1gである。
9 シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して、0.01mg/L 以下
シアン化合物には、シアン化ナトリウム、シアン化カリウムのように水中でシアンイオン、シアン化水素を容易に生成する遊離型シアンと、フェリシアン化カリウム、フェロシアン化カリウムのように金属錯化合物を形成する錯塩シアンがある。
シアンは、めっき、鉄鋼製造、金銀の選鉱や多くの化学合成工業で使用される。シアンは自然中にはほとんど存在しない。シアン化合物を含んだ工場排水の混入によって水中に見いだされる。
また、含窒素化合物の燃焼によってもシアンが生じる場合がある。シアン化合物には強い毒性がある。ヒトの体内にはいると、粘膜から吸収され、頭痛、吐き気などを引き起こし、死亡する場合もある。
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/L 以下 (硝酸態窒素)
水中の硝酸イオン(NO3−)および硝酸塩に含まれている窒素のことである。硝酸イオンは有機および無機の窒素化合物の最終的酸化形である。
硝酸態窒素を多量に含む水を摂取した場合、体内で細菌により硝酸塩は亜硝酸塩へと代謝され、亜硝酸塩は血液中でメトヘモグロビンを生成して呼吸酵素の働きを阻害しメトヘモグロビン血症を起こす。
(亜硝酸態窒素)
水中の亜硝酸イオン(NO2−)または亜硝酸塩に含まれている窒素のことである。水に混入したアンモニア態窒素が酸化されて生ずる場合が多いが、硝酸態窒素の還元によって生じる場合も多い。
亜硝酸塩は赤血球のヘモグロビン(体内組織へ酸素を運搬する)と反応してメトヘモグロビンを生成し、呼吸酵素の働きを阻害するメトヘモグロビン血症を起こす。
体内で硝酸態窒素は亜硝酸態窒素へと速やかに変化するため、水道水質基準は硝酸態窒素および亜硝酸態窒素の合計量となる。
11 フッ素及びその化合物
フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下
水中のフッ素は、主として地質や工場排水の混入などに起因する。自然界に広く分布しているホタル石はフッ化カリウムが主成分であるため、日本でも特に温泉地帯の地下水や河川水に多く含まれることがある。
フッ素を適量に含んだ水を飲用した場合には「う歯」(むし歯)の予防に効果があるといわれているが、多量に含まれていると斑状歯(歯牙の慢性フッ素中毒)の原因となる。
12
ホウ素及びその化合物
ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下
ホウ素は、自然中に含まれることはまれであるが、火山地域の地下水、温泉水にはメタホウ酸の形で含まれることがある。また、金属の表面加工処理剤、ガラス、エナメル工業などで使用されるので、これらの工業排水に混入することがある。
ホウ酸を少量摂取した場合には緩和な生理作用を示すに過ぎないが、多量のときには消化器、神経中枢等に影響を及ぼす。ホウ素による中毒症状は、一般に胃腸障害、皮膚紅疹、抑うつ症を伴う中枢神経刺激の症状である。
13 四塩化炭素
0.002mg/L 以下
テトラクロロメタン、ベンジノホルムともいう。比重1.59(20℃)。融点−23℃、沸点76.5℃の無色透明な液体。水に対する溶解度は800mg/L(25℃)で、アルコール、エーテル、クロロホルムなどに混和する。蒸気圧115mmHg(25℃)。主な用途はフロンガスの製造原料、薫蒸殺菌剤、金属洗浄用溶剤などある。
液化塩素に不純物として存在することがある。その毒性は肝臓の感受性が最も高く、脂肪浸潤、肝細胞内酵素の遊離、細
胞内酵素活性の抑制、炎症が起こり、最終的に肝細胞壊死を引き起こす。
14 1,4-ジオキサン
0.05mg/L 以下
1,4-ジオキサンは、特異的な臭気のある無色の液体である。溶剤や1,1,1−トリクロロエタン安定剤などの用途に使用されるほか、ポリエキシエチレン系非イオン界面活性剤及びその硫酸エステルの製造工程において副生し、洗剤などの製品中に不純物として存在する。その毒性は目に強い刺激性を有し、肝臓、腎臓、中枢神経に影響を与え、また皮膚の脱脂を起こすことがある。
ヒトに対しては、弱い遺伝毒性しか示されていないが、多臓器での腫瘍を誘発することが報告されている。IARC では、ヒトへの発ガン性の可能性があるとして、Group2B に分類している。
15 1,1-ジクロロエチレン
0.02mg/L 以下 1,1,−ジクロロエチレンは、揮発性有機塩素化合物であるが、蒸気は空気より重い。酸化されやすく、酸素と接触すると過酸化物を生成する。
1,1−ジクロロエチレンの環境への放出は、製造過程及びポリマー製造の原料として使用されている際に起きる。揮発性のため、ほとんどが大気中へ移行していき、地表水を汚染した1,1−ジクロロエチレンも速やかに揮発する。
地下水では、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びこれらの分解成物である1,2−ジクロロエチレンや塩化ビニルと共存することが知られている。
主たる用途は、塩化ビニリデン樹脂の製造原料である。塩化ビニリデン樹脂は、家庭用ラップ、食品包装用フィルム、紙やプラスチックの表面コーティング等に使用される。ヒトでは、神経症状、肝機能障害、頭痛、視覚障害等がある。
16 シス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下 化学合成品はシス体とトランス体の混合物である。水には難溶であるが、各種の有機溶剤には易溶である。化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用される。ヒトに対して麻酔作用がある以外に報告例がない。
シス-1,2-ジクロロエチレンの環境中への放出は、製造過程及び溶剤として使用する過程で起きる。揮発性のため、多くが大気中に移行する。
地表水を汚染したシス-1,2-ジクロロエチレンは速やかに大気中に揮散する。土壌に浸透すると吸着されにくく、地下水中に長期間滞留する。地中のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが還元状態で微生物分解を受けると、シス-1,2-ジクロロエチレンが生成される。地下水中では、多くの場合トリクロロエチレンと共存している。
シス体とトランス体の混合物の毒性はLD50(ラット,経口)770mg/kgで、単回投与によりラットの肝アルカリホスファターゼが顕著に増加した。多量に摂取した場合には、腹痛、咳、咽頭痛、めまい、吐き気、嗜眠、脱力感、意識喪失、嘔吐等の急性症状がみられる。
17 ジクロロメタン
0.02mg/L 以下
沸点40℃の無色の液体。合成有機化学物質であり、自然界には存在しない。殺虫剤、塗料、ニス、塗料剥離剤、食品加工中の脱脂処理および洗浄液などとして使われる。
表流水中に排出されたジクロロメタンは大気中に揮散し数日から数週間で分解するが、地上に排出されたジクロロメタンは容易に地下水に移行し、長期間残留する。
ジクロロメタンの毒性はLD50(ラット,経口)2,121mg/kg、(マウス,経口)1,987mg/kgである。また、1.3mg/kg体重の単回投与では、呼吸困難、運動失調、チアノーゼ及び昏睡が認められた。多量に摂取した場合には、腹痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感、意識喪失の急性症状がみられる。
18 テトラクロロエチレン
0.01mg/L 以下
テトラクロロエテン、パークレン、パークロロエチレンともいう。比重1.62(20℃)、融点22.4℃、沸点121.2℃の液体。蒸気圧19mmHg。水に対する溶解度150mg/L(25℃)。主な用途はドライクリーニング溶剤,金属用脱脂剤など。
この物質は使用後排出され、土壌中を移行して直ちに地下水中に入り、地下水汚染物質の一つとなっている。地下水中では数カ月から数年間にわたって残留する。
トリクロロエチレンに比べて尿中代謝物排泄ははるかに少ない。その毒性はLD50(ラット,経口)8.85g/kgで、肝
腎障害や中枢神経抑制作用があり、また、肝ガンの発生も認められている。多量に摂取した場合には、腹痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感、意識喪失の急性症状がみられる。
19 トリクロロエチレン
0.03mg/L 以下
TCE、トリクレン、トリクロロエテンともいう。比重1.4 (25℃)、融点−86.4℃、沸点86.7℃の無色透明の液体。蒸気圧77mmHg(25℃)。
水に対する溶解度1g/L(20℃)。主な用途は金属の脱脂剤である。環境に放出されて地下水汚染を超こす。地下水中に長期間残留 し、分解してジクロロエチレンや塩化ビニルになる。
また,テトラクロロエチレンの分解によって生成することもある。体内吸収では抱水クロラールを経てトリクロロ酢酸に代謝される。毒性はLD50(ラット,経口)4.92g/kgで、発ガン性も認められる。多量に摂取した場合の急性症状は、腹痛、めまい、し眠、頭痛、脱力感、吐き気、意識喪失がある。
20 ベンゼン
0.01mg/L 以下
揮発性のある無色の液体で、芳香族特有の芳香があり、引火性が大きい。エタノールおよびエーテルとはすべての割合で混合するほか、多くの有機溶媒に可溶である。
水には難溶。置換、付加および開裂の三つの反応が起こり、多種の芳香族化合物を生成する。溶剤、燃料、アルコール変性剤などとしても重要である。
発ガン性を有する。その毒性はLD50(ラット、マウス,経口)1〜10g/kgで、発ガン性や骨髄形成不全、リンパ球減少症
も認められる。多量に摂取した場合の急性症状は、腹痛、咽頭痛、嘔吐がある。
21 クロロ酢酸
0.02mg/L 以下
クロロ酢酸は、刺激臭のある無色の結晶である。除草剤、チューインガム可塑剤、塩化ビニル可塑剤、医薬品、アミン酸等合成、香料、キレート剤、界面活性剤として使用される。
クロロ酢酸などのハロゲン化酢酸類は、水道水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒
副生成物の一つである。その毒性はLD50(ラット,経口)55mg/kgで、皮
膚や鼻、目の粘膜を腐食する。変異原性が認められる。
22 クロロホルム
0.06mg/L 以下
比重1.49(20℃)。融点−63.5℃、沸点61.2℃の無色透明の液体で、甘い刺激臭がある。水に対する溶解度は0.28g/100g(20℃)で,エタノール、エーテルなどには易溶である。
主な用途として医薬品、溶剤、有機合成の原料などがある。クロロホルムは、浄水処理における塩素消毒によって生成するトリハロメタンの主成分である。クロロホルムには強い麻酔作用があり、肝臓、腎細尿管、心臓などに細胞毒として作用する。
また、動物実験によって腎腫瘍や肝癌などの発癌性が確認されている。低濃度の慢性毒性では胃腸、肝腎障害が起こり、高濃度では反射機能の喪失、感覚麻痺、呼吸停止などが起こる。
23 ジクロロ酢酸
0.04mg/L 以下
ジクロロ酢酸は、刺激臭のある無色の液体である。ジクロロ酢酸などのハロゲン化酢酸類は、浄水過程において水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物物質の一つである。
マウスに75週にわたってジクロロ酢酸を飲水投与した結果、最大無作用量は50mg/kg/日である。慢性試験で発ガン性を示す根拠は認められていない。IARC では、ヒト発ガン性物質として分類できないとして、Group3に分類されている。
24 ジブロモクロロメタン
0.1mg/L 以下
浄水処理過程で使われる消毒剤の塩素と水中のフミン質などの有機物質が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。生成量は原水中の臭素イオンに大きく影響される。
写真工業の排水や海水の影響を受けやすいところ、また塩分を含む地下水で臭素化トリハロメタンが多い。その毒性はLD50(雄マウス,経口)800mg/kg、(雌マウス,経口)1200mg/kgである。参考文献:アメリカ国家毒性プログラムNTP(1985)ではマウスによる2 年間の経口投与実験では、肝の脂肪変性、腎ネフローゼが認められた。
25 臭素酸
0.01mg/L 以下
臭素酸の最も一般的な形態が臭素酸カリウムと臭素酸ナトリウムである。臭素酸カリウムは小麦粉改良材として、臭素酸ナトリウムは分析用試薬、毛髪のコールドウェーブ用薬品等に使用される。
浄水処理においてオゾンを使用する場合、臭素イオンから消毒副生成物として生成される。また、消毒剤としての次亜塩素酸ナトリウム生成時に、不純物の臭素が酸化され、臭素酸が生成される。
毒性影響には、腹痛、中枢神経系の機能低下、呼吸困難、肺浮腫、腎機能低下、聴覚障害等及び発ガン性が報告されている。
ヒトが摂取すると消化管から速やかに吸収され、肝臓でグルタチオン抱合された後臭化物に還元される。IARC では、実験動物の発ガン性に関しては十分な証拠があるとして、Group2B に分類している。
26 総トリハロメタン
0.1mg/L 以下
メタン(CH4)の水素原子3個が、塩素、臭素、あるいはヨウ素に置換された有機ハロゲン化合物の総称。THMと略称される。これらのうち、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の合計を総トリハロメタン(TTHM)と呼ぶ。
水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に存在するフミン質などの有機物を前駆物質として、塩素処理によって生成する。なかでもクロロホルムは発ガン物質であることが明らかとなっている。
27 トリクロロ酢酸
0.2mg/L 以下
トリクロロ酢酸は、刺激臭のある無色で吸湿性の結晶である。医薬品の原料、除草剤、腐食剤、角質溶解剤、塗装剥離剤、除タンパク剤、生体内タンパク・脂質の分画剤として使用される。水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物質の一つである。
マウスで肝腫瘍を引き起こすが、変異原性や染色異常などのin vitro 系の試験では陰性及び陽性の結果が混在して報告されており、IARC ではヒト発ガン性物質として分類できないとしてGroup3に分類されている。
28 ブロモジクロロメタン
0.03mg/L 以下
浄水処理過程で使われる消毒剤の塩素と水中のフミン質などの有機物質が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ。生成量は原水中の臭素イオンに大きく影響される。写真工業の排水や海水の影響を受けやすいところ、また塩分を含む地下水で臭素化トリハロメタンが多い。
その毒性はLD50(雄マウス,経口)450mg/kg、(雌マウス,経口)900mg/kgである。参考文献:アメリカ国家毒性プログラムNTP(1987)では、マウスによる2 年間の経口投与実験では、腎細胞肥大、肝の脂肪変性のほか腎臓の腺腫と腺がん、肝細胞の腺腫と腺がんがみられた。
29 ブロモホルム
0.09mg/L 以下
同上
30 ホルムアルデヒド
0.08mg/L 以下
ホルムアルデヒドは、特徴的な臭気のある気体で、有機溶媒に易溶である。浄水過程で、水中のアミン等の有機物質と塩素、オゾン等の消毒剤が反応して生成される。
主要な構成物資として、ホルムアルデヒドとアセトアルデヒド等がある。エポキシ樹脂塗料及びアクリル樹脂塗料の原料として
使用される。土壌燻蒸剤として線虫等の駆除に使用される。
野菜、樹木の苗木などの防除に使用される。ヒトへの健康影響としては、内服したとき、呼吸困難、めまい、嘔吐、口腔及び胃に炎症が起きる。
吸入曝露試験では発ガン性を示し、鼻と喉の灼熱感、頭痛、吐き気などが起こり、短期暴露の場合、眼、皮膚、気道に対して腐食性があり、肺水腫を起こすこともある。
高濃度で死に至ることもある。経口曝露では明らかな発ガン性は示さない。
31 亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下
自然水中に微量に含まれるが、高濃度の亜鉛は鉱山排水や工場排水などによる汚染が原因であることが多い。水道水で高濃度の亜鉛が検出される場合は、そのほとんどが給水管などの亜鉛引き鋼管からの溶出による。
水道水に高濃度の亜鉛が含まれていると白濁して、いわゆる白水の原因となる。また5mg/L以上含まれると収れん味を呈する。毒性は比較的弱いが、高濃度の場合には腹痛、嘔吐、下痢などの中毒症状をもたらすことがある。
32 アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下
地球の表面に存在する元素で3番目に多く、金属では最も多い。比重が2.6で、さびにくく、かなり丈夫なので航空機、自動車、建築物などに使われている。
アルミニウムの化合物である明ばんは昔から水の清澄剤として、また,硫酸アルミニウム、ポリ塩化アルミニウムも水道水の水処理剤として用いられている。
濃度が高いと、白濁水の原因となる。
33 鉄及びその化合物
鉄の量に関して、0.3mg/L 以下
クラーク数は4.7で、酸素、ケイ素、アルミニウムについで地球で4番目に多い元素である。地表水中ではFe(OH)3として懸濁して存在している。
また,泥炭地などの有機物の多いところではコロイド性の有機錯体として存在する。自然水中に含まれる鉄は、地質に起因するもののほか鉱山排水、工場排水などからの場合もある。0.3mg/L以上溶解すると、水に色がつきはじめ赤水の原因となり、臭気や苦味を与える(0.5mg/L)。
鉄は栄養上,1人1日当たり約10mg以上必要とされている。鉄塩の毒性はLD50(マウス,経口)300〜600mg/kg、LD50(ラット,経口)800〜2,000mg/kgである。
急性毒性は、うつ病、昏睡、呼吸障害や心拍停止などである。
34 銅 及びその化合物
銅の量に関して、1.0mg/L 以下
天然には主として硫化物(黄銅鉱、班銅鉱、輝銅鉱)の形で産出する。電線、合金、貨幣、彫刻、メッキ、農薬など、多くの分野に用いられる。
銅イオンを1.0mg/L以上含む水は金属味を帯び、着色(青色)を与える。ヒトにとって銅は必須元素であり、成人の必要量は1日に約2mgとされている。
銅化合物は藻類、カビ類、無脊椎動物に対しては強い毒物であるが、哺乳類に対しては蓄積性が認められないので慢性中毒のおそれは少ない。
35 ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下
地殻中に広く分布。海水中には約10g/L含まれ、また岩塩として巨大な鉱床をつくる。ナトリウムは自然水中に広く存在する元素であるが、海水、工場排水の混入、水処理時のカセイソーダによるpH調整などに由来することもある。
ナトリウムイオンは動物体内の生理に重要な役割を果たしている。ナトリウムと高血圧との関係はよく論じられるが、1日1.6〜9.6gの摂取量では人の健康に何ら影響はないとみられている。
36 マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下
マンガンは地殻中に広く分布しており、軟マンガン鉱などに多く含まれる。生理的に不可欠の元素で、炭水化物の代謝などに関与する。水道水中にマンガンが多いと、浄水に黒い色をつけるので好ましくない。
過剰摂取すると全身倦怠感、頭痛、不眠、言語不明瞭などの中毒症状を起こす。
37 塩化物イオン
200mg/L 以下
水中に溶存している塩化物中の塩素のこと。自然水は常に多少の塩化物イオンを含んでいるが、これは地質に由来するもので、特に海岸地帯では海水や送風塩の影響によることが大きい。
しかし、塩化物イオンは下水系、生活系および産業系などの各排水や、屎尿処理水などの混入によっても増加する。したがって、塩化物イオンは水質汚濁の指標の一つともなっている。
硝酸銀と反応して塩化銀の白色沈澱を生ずるため、測定にはこの性質を利用した硝酸銀法(モール法)がある。多量の塩化物イオンは水に味をつけたり、鉄管などの腐食を促進する傾向がある。塩化物の毒性は陽イオンの種類によって異なっており、塩化物イオン自体の毒性は知られていない。
しかしながら、2.5mg/L 以上の濃度の塩化ナトリウムを含む飲料水を過剰に飲用していると高血圧症を引き起こすと報告されている。
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
300mg/L 以下 (カルシウム)
アルカリ土壌金属の一つで、展性・延性がある。自然界には遊離状態で産出されず、炭酸塩およびケイ酸塩として広く多量に存在する。水中ではカルシウムイオン(Ca2+)と して存在し、硬度の主体をなしている。その起源は地質によるものが主であるが、他にコンクリート構造物からの溶出、海水、工場排水および温泉などの混入に由来するものがある。
原子吸光分析法により波長422.7nmの吸光度を測定する方法やカルシウム硬度による測定方法(EDTA法)などがある。
(マグネシウム)
アルカリ土類金属の一つ。自然界では単体としては存在せず、炭酸塩、ケイ酸塩、硫酸塩および塩化物などとして広く多量に存在する。
水中にはマグネシウムイオンとして存在し、カルシウムイオンとともに硬度の主体をなしている。その成因は主に地質に由来するが、鉱山排水、工場排水、海水および温泉などの混入によることもある。原子吸光分析法により波長285.2nmで吸光度を測定する方法や総硬度とカルシウム硬度の差から求める測定法がある。
健康障害としては、硬度が高すぎると胃腸を害して下痢を起こすことがある。
39 蒸発残留物
500mg/L 以下
水を蒸発乾固したときに残る物質。具体的には、一定量の検水を蒸発皿に入れて水浴上で蒸発乾固し、残った物質量を求める。濁質のある検水をそのまま蒸発乾固すれば、浮遊物質と溶解性物質との総和となる。
水道水の主な蒸発残留物の成分は、カルシウム、マグネシウム、シリカ、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物である。健康への影響はほとんど生じない。
40 陰イオン界面活性剤
0.2mg/L 以下
界面活性剤のうち、水溶液中で電離して活性剤の主体が陰イオンになるもの。工場排水、家庭下水などの混入に由来し、水中に存在すると泡立ちの原因となり、汚濁の重要な指標である。
また、陰イオン界面活性剤に付随するリン酸塩による水源の富栄養化が問題となっている。その毒性はほとんど認められない。
41ジェオスミン
0.00001mg/L 以下
ジェオスミンは、湖沼等で富栄養化現象に伴って発せするかび臭(異臭味)の原因物質である。藍藻類のアナベナにより産生される。その毒性はほとんど認められない。
42 2−メチルイソボルネオール
0.00001mg/L 以下
2−メチルイソボルネオールは、湖沼等で富栄養化現象に伴って発せするかび臭(異臭味)の原因物質である。藍藻類のフォルミディウムやオッシラトリアにより産生される。その毒性はほとんど認められない。
43 非イオン界面活性剤
0.02mg/L 以下
非イオン界面活性剤とは、界面活性剤のうち、イオンに解離する基を持たない物質の総称である。エーテル型、エーテルエステル型、エステル型、含窒素型が知られている。
洗浄剤、乳化剤、分散剤、消泡剤、潤滑油、化粧品、流出油の処理剤等に使用される。その毒性は、一般に陰イオン界
面活性剤に比べ低く、健康への影響はほとんど生じない。
44 フェノール類
フェノールの量に換算して、0.005mg/L 以下
芳香族化合物のベンゼン環の水素が、水酸基で置換された化合物の総称で、環境汚染に関連するものは主としてフェノール(石炭酸)、ο−,m−,p−クレゾール、クロロフェノールなどである。合成樹脂、界面活性剤などの原料として大量に使用されている。
フェノール類は、天然水中には存在しないが、化学工場排水、ガス製造工場排水などに含まれる。フェノール類が含まれていると水の塩素処理過程でクロロフェノール類が生成し、水に著しい異臭味を与えるので、厳しい排水基準が示されている。
45有機物(全有機炭素(TOC)の量)
5mg/L 以下
水中の全有機炭素(TOC : Total Organic Carbon)は、種々の有機化合物から構成されていて、これらの有機化合物に含まれている炭素量をいう。全有機炭素は、水中に含まれる有機物総量の指標として用いることができるため、原水の有機性汚濁の状況や浄水処理過程における水の処理性評価に利用することができる。
また、溶存有機炭素(DOC)も有機性汚濁の指標として用いられている。
46 pH値
5.8 以上8.6以下
水素イオンのモル濃度(水素イオン濃度)の逆数の常用対数値。pH7は中性、pH7より値が小さくなるほど酸性が強くなり、値が大きくなるほどアルカリ性(塩基性)が強くなる。
水道法に基づく水質基準は5.8以上8.6以下であること、また、水質管理目標設定項目としての目標値は7.5程度
とされている。水の基本的な指標の一つであり、理化学的水質、生物学的水質、浄水処理効果、管路の腐食などに関係する重要な因子である。
測定法はガラス電極法(pH計)がある。
47 味
異常でないこと
水の味は、水に溶存する物質の種類・濃度によって感じ方が異なる。味の原因には、下水、工場排水等による汚染、生物や細菌類の繁殖、また、海岸地帯では海水の影響をうけ塩味を感じることもある。
異常な味は不快感を与えるので飲用には適さない。
48 臭気
異常でないこと
水の臭気は水に溶解している種々の物質が原因となっています。水道において問題となる臭気物質は、藻類や放線菌等の生物に起因するかび臭物質、フェノールなどの有機化合物が主です。異常な臭気は不快感を与え
るので飲用には適しません。
49 色度
5 度以下
水中に含まれる溶解性物質およびコロイド性物質が呈する黄褐色の程度をいう。原水においては、主に地質に由来するフミン質、フミン酸鉄による呈色と同じ色調の色について測定される。水道水においては配管等からの鉄の溶出などによって色度が高くなることがある。
精製水1L中に白金イオン1mgおよびコバルトイオン0.5mgを含むときの呈色に相当するものを1度としている。
50 濁度
2 度以下
濁度は、水の濁りをポリスチレン系粒子(5種類)を濁質の標準液とし、これと比較して測定する。水道において、原水濁度は浄水処理に大きな影響を与え,浄水管理上の指標となる。
また、給水栓中の濁りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要である。
B 水質管理目標設定項目(27項目)
水質基準とするにいたりませんが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目、必要に応じ水質検査を実施する項目です。このうち農薬類については、全国の検出状況や使用量などを考慮して、101項目がリストアップされ、「総農薬方式」とよばれる考え方で設定されています。
項目 目標値 解説
1 アンチモン及びその化合物
アンチモンの量に関して、0.015mg/L 以下
アンチモンは、半導体材料、潤滑剤、弾薬、陶器、硝子など材料成分として主に使われている。三価アンチモンは容易に赤血球に取り込まれるが、五価アンチモンは取り込まれない。飲料水中のアンチモンの形態が毒性のキー決定要因であるが、飲料水中のアンチモンはほとんどが、弱毒性型の五価アンチモン、オキソ-陰イオン型と思われる。
ヒトへの健康影響では、嘔吐、下痢が知られていて、三価アンチモンの発ガン性はグループ2Bに分類されているが、この判断となった知見のほとんどは、水に不溶な粒子による吸入暴露によるものであり、水溶性アンチモンの経口摂取による発ガン性を示す知見は知られていない。
2 ウラン及びその化合物
ウランの量に関して、0.002mg/L 以下(暫定)
ウラン化合物はガラス・磁器の着色剤、光電管にも使用されているが、主に原子炉の燃料として使用されている。ごく微量であるが、地球の表面の近くの岩石(特に花崗岩)及び海水中に広く分布している。
ウランを含む鉱石や廃棄された選鉱くずからの溶出、核物質使用工場からの排出、石炭及び他の燃料の燃焼、ウランを含むリン酸肥料の使用になどにより環境中に放出される。
ウランの健康影響としては化学毒性による眼粘膜刺激、催涙及び結膜炎、吸入による気道刺激、腎障害などがある。また、放射線障害による肺ガン、リンパ腫の増加などがある。
3ニッケル及びその化合物
ニッケルの量に関して、0.01mg/L 以下(暫定)
ニッケルは、ステンレス綱、めっき、貨幣、顔料、触媒原料などに使用されている。ニッケルの化合物は不溶性のものが多いので、自然水中に存在することはまれであるが、鉱山排水、工場排水あるいはニッケルめっきの溶出などから混入することがある。また、水道では管材及びその他の材料の腐食による汚染がある。
大量に摂取するとめまい、嘔吐、急性胃腸炎を引き起こす。発ガン性の評価については、金属ニッケルではIARCグル
プ2B、ニッケル化合物ではグループ1にそれぞれ分類されている。
4亜硝酸態窒素
0.05mg/L 以下(暫定)
水中に含まれる亜硝酸イオン中の窒素の量であり、窒素肥料、腐敗した動植物、家庭排水等に由来する。これらに含まれる窒素化合物は、環境中で化学的・微生物学的に酸化及び還元を受け、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素等になる。
摂取すると体内で食物中のタンパク質に含まれるアミン類と結合し、発ガン物質であるニトロソアミンを生成したり、急性毒性を引き起こす危険性がある。
塩素処理により容易に硝酸態窒素へと酸化されるので、通常の浄水処理により除去され、残留塩素のある浄水には存在しな
い。
5 1,2-ジクロロエタン
0.004mg/L 以下
主に塩化ビニルモノマーの原料として使用されるほか、有機溶剤、殺虫剤、金属の脱脂洗浄等に使用されている。環境中には、貯蔵タンクからの漏出や工場排水等により放出されるおそれがある。地表水を汚染した場合は比較的容易に大気中に揮散するが、土壌吸着性は低く、土壌を浸透し地下水に進入すると安定な形で閉じこめられるため長期間にわたり汚染が継続する。
健康影響はめまい、吐き気、嘔吐などがある。
6 トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下
シス体との混合物で使用され、化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用されている。また、トリクロロエチレンの分解物でもある。吐き気、眠気、疲労感、めまい等の中枢神経系への影響がある。
7 1,1,2-トリクロロエタン
0.006mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレンの製造原料、油脂、ワックス、天然樹脂の溶剤として使用されている。土壌吸着性は低く、地下水中に長時間残留する。長期暴露では慢性胃炎、肝臓への脂肪蓄積、肺障害など、上記暴露では呼吸器と眼に対する刺激作用がある。
8 トルエン
0.2mg/以下
染料、香料、有機顔料、ポリウレタン、合成繊維などの原料として、また、樹脂や塗料の溶剤として使用されている。石油成分の一つで石油分留生成で得られる。
健康影響としては、急性暴露により、頭痛、吐き気、錯乱などの症状を引き起こす。
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
0.1mg/L 以下
可塑剤として、ポリ塩化ビニルフィルム、シート、レザー、ホース、機械器具部品、日用雑貨などに使われ、また農薬、化粧品、染料、印刷インクなどの溶剤や保留剤としても使用されている。
大量摂取により、胃腸、肝臓障害などの報告例がある。
10亜塩素酸 0.6mg/L 以下
11塩素酸 0.6mg/L 以下
12二酸化塩素 0.6mg/L 以下
主に漂白剤として使用されている。二酸化塩素を浄水過程で酸化剤として使用した場合に検査を行うことが望ましいとされている項目である。
亜塩素酸塩、塩素酸塩から合成される二酸化塩素を処理水中に投入した場合に分解生成物として亜塩素酸イオン、塩素酸イオンが生成する。
赤血球中のヘモグロビンが亜塩素酸塩により酸化され、メトヘモグロビンを形成することによる中毒症が知られている。
13 ジクロロアセトニトリル
0.04mg/L 以下(暫定)
塩素処理の際に遊離塩素とフミン物質、藻類、アミン酸が反応してできる副生成物の1 つである。時間の経過とともに、また水温が高いほど生成量は増加するが、トリハロメタンほど顕著ではない。土壌や汚泥等にはあまり吸着せず、生物への濃縮もあまり大きくないと考えられている。
14 抱水クロラール
0.03mg/L 以下(暫定)
塩素消毒の際に遊離塩素とフミン質、酸化シアンが反応してできる副生成物の1つである。鎮静剤、睡眠薬等の医療用として、医薬品や農薬の原料として使用されている。
15 農薬類
検出値と目標値の比の和として、1 以下
水源上流などにおける農薬の使用状況により、使用されている薬剤について検査を行うこととされている。計101 種類の農薬が対象になっていて、総農薬方式として評価される。
16 残留塩素
1mg/L 以下
水中に塩素を注入することによって水中に残留した有効塩素をいい、次亜塩素酸などの遊離有効塩素(遊離残留塩素)とクロラミンのような結合有効塩素(結合残留塩素)に区分される。残留塩素の測定にはDPD法、ポーラログラフ法及び吸光光度法がある。
衛生上の措置として給水の残留塩素を遊離残留塩素として0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するよう規定している。
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
10mg/L 以上
100mg/L 以下
水質基準項目 38 を参照。
18マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.01mg/L 以下
水質基準項目 36 を参照。
19 遊離炭酸
20mg/L 以下
水中に溶解している二酸化炭素(CO2)のこと。遊離炭酸は炭酸塩や有機物質が分解して発生した二酸化炭素や空気中の二酸化炭素などが水中に溶解することに起因する。
地下水では有機物の分解などにより、一般に多く存在する。遊離炭酸には水中のアルカリ化合物と反応して炭酸化合
物を生成させるような腐食性のある侵食性遊離炭酸と、腐食性のない従属性遊離炭酸がある。
20 1,1,1-トリクロロエタン
0.3mg/L 以下
ドライクリーニング用溶剤、金属の脱脂洗浄剤、繊維のしみ抜き剤などに使用されている。健康影響としては、吐き気、下痢、めまい、ふらつきなどの症状がある。
21メチル-t- ブチルエーテル
0.02mg/L 以下
ガソリンのオクタン価向上剤、アンチノック剤、ラッカー混合溶剤の混和性改良材などに使用されている。健康影響については、毒性評価が詳細にされていないのが現状であるが、地下水で一過的に高濃度で検出されるとの情報もある。
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)
3mg/L 以下
水中の有機物や還元性物質(被酸化性物質)の量を、酸化させるのに必要な過マンガン酸カリウムの量として表したもので、一般に有機物の含有量の指標になっている。
土壌に由来するフミン質を多く含む場合や水道水源にし尿、下水又は工場排水が混入した場合に増加する。有機物の多い
水は渋みがあり、また、消毒に用いる塩素の消費量も多くなり、その点で水の味を損なう原因になる。
23 臭気強度(TON)
3 以下
検水の臭気をほとんど感知できなくなるまで無臭味水で希釈し、その希釈倍率によって示される臭気の強さのこと。TON ともいう。臭気に対する感受性は個人差があり、また、同一人でも測定時の状態で差異を生じるため、複数人数による試験が望ましい。
24 蒸発残留物
30mg /L 以上
200mg/L 以下
水質基準項目 39 を参照
25 濁度
1 度以下
水質基準項目 50 を参照
26 pH 値
7.5 程度
水質基準項目 46 を参照
27 腐食性(ランゲリア指数)
−1 程度以上とし、極力0に近づける
水のpH 値、カルシウムイオン量、総アルカリ度及び溶解性物質から求められるもので、水のpH値とその水の理論的pH 値との差を表す。指数が正の値で絶対値の大きいほど炭酸カルシウムの析出が起こりやすくなる。
また、負の値では炭酸カルシウム被膜が形成されず、その絶対値が大きくなるほど水の腐食傾向は強くなる。
C その他の項目
水質基準・水質管理目標設定項目ではありませんが、水道に関連する項目です。
項目 解説
1 水温
水温は、地表水の場合、気温の影響を受けやすく、湖沼や貯水池の場合、水温の変化によって、比重が変わり、水の停滞や循環などの原因となる。また、水温の上昇は物質の溶解性、生物の消長、河川での自浄作用などに影響を与える。
2 アンモニア態窒素
水中のアンモニウムイオン(NH4+)に含まれる窒素のこと。有機窒素化合物の分解、工場排水、下水および屎尿の混入によって生ずる場合が多い。土壌や水中の細菌により亜硝酸態窒素、硝酸態窒素へと酸化され、嫌気性状態では逆に硝酸態窒素、亜硝酸態窒素が還元されてアンモニア態窒素となる。
浄水処理では塩素処理や、緩速濾過のような生物化学処理によって分解され減少するので、処理工程の管理指標としても重要な項目である。測定方法にはインドフェノール法、ネスラー法、α−ナフトール法、蒸留比色法がある。
3 生物化学的酸素要求量(BOD)
水中の有機物が生物化学的に酸化されるのに必要な酸素量のことで、生物化学的酸素要求量ともいう。生物化学的酸化とは、水中の好気性微生物が有機物を栄養源とし、水中の酸素を消費してエネルギー化、生命維持・増殖するとき、有機物が生物学的に酸化分解されることをいい、有機物が多いほど消費される酸素量が多くなる。
したがって、BODが高いことはその水中に有機物が多いことを示し、化学的酸素要求量(COD)とともに水質汚濁を示す重要な指標である。生物化学的酸素要求量は試料を20℃、5日間静置し、静置前と後の溶存酸素量をウィンクラー法で測定し、その間に消費された溶存酸素量(mg/L)で表す。
4 化学的酸素要求量(COD)
化学的酸素要求量のこと。水中の被酸化性物質(有機物)を酸化剤で化学的に酸化したときに消費される酸化剤の量を酸素に換算したもの。CODが高いことはその水中に有機物が多いことを示し、生物化学的酸素要求量(BOD)とともに水質汚濁を示す重要な指標である。
測定方法には酸性過マンガン酸カリウム法があるが、酸化剤として重クロム酸カリウムを使用する方法もある。
5 紫外線(UV)吸光度
紫外線領域における特定波長の吸光度(紫外部吸光度、UV 吸光度)または透過率を光電的に測定し、検量線により濃度を求める方法。紫外線とは波長360〜400 以下1nm 程度までの電磁波を指すが、200nm 以下の波長域は空気による吸収があり、真空中で測定する必要があるため真空紫外線とよんでいる。
光源には石英水銀灯、重水素放電管、セキノンランプなどが用いられている。測定には紫外線領域に吸収の少ない石英セルを使用する。
6 浮遊物質(SS)
水中に懸濁している粒径1μm〜2mm 程度の不溶解性物質のことをいう。SSと記すこともある。上水試験方法では、網目2mm のふるいを通過した一定量の試料を1μm のメンブレンフィルターでろ過し、その残留物105〜110℃で2 時間乾燥し、秤量して求める重量法を定めている。
濁度との相関が議論されることがあるが、厳密な意味での相関関係はない。浄水処理、排水処理などに影響を及ぼす。
7 侵食性遊離炭酸
水中のアルカリ化合物と反応して炭酸化合物を生成させるような腐食性のある水中に溶解している二酸化炭素(CO2)のこと。
8 全窒素
水中に含まれる窒素化合物の総量のことで、窒素量で表す。窒素はリンとともに水源の富栄養化の原因物質の一つといわれ、湖沼やダム湖などの閉鎖性水域での富栄養化による藻類などの増加は、浄水操作上の障害や藻類に由来する臭気物質による水道水の異臭味問題などを引き起こすことがある。
測定方法にはカドミウム・銅カラム還元法,紫外線吸光光度法がある。
9 全リン
水中に含まれるリン化合物の総量をいい、リン量で表す。水中のリン化合物は、正リン酸(オルトリン酸)、メタリン酸、ピロリン酸、ポリリン酸などの無機リン酸塩と、農薬、エステル、リン脂質などの有機リン化合物があり、これらが溶存状態または懸濁状態で存在している。リンは地質中に広く存在し、あらゆる動植物にも含まれている。
したがって自然水中にも含まれるが、リン化合物は屎尿、肥料、農薬、合成洗剤などにも含まれているため、水中のリン化合物の増加は生活排水、工場排水、農業排水などの混入に由来する場合が多い。リン化合物の増加は湖沼・海域の富栄養化を促進する一因とされている。
測定は、加熱分解または高圧分解した後にモリブデン青法で行う。
10 リン酸イオン
リン化合物は、総リン、リン酸イオンおよび加水分解性リン化合物に区別して測定され、いずれもリン酸イオン量で表示される。リン酸には、メタリン酸、ピロリン酸、オルトリン酸、三リン酸、四リン酸などがあり、普通はオルトリン酸を単にリン酸または正リン酸という。オルトリン酸は水中で解離してオルトリン酸イオンとなる。測定方法には、モリブデン青法、モリブデン青抽出法がある。
11 トリハロメタン生成能
20℃、pH7.0±0.2 の条件下で、24±2 時間静置後、残留塩素が1〜2mg/L となるように塩素処理した検水のトリハロメタン濃度のことで、トリハロメタン前駆物質量の指標となる。THMFP、THM 生成能ともいわれる。
トリハロメタンの前駆物質として種々の有機物が認められているが、そのすべてが明らかではないので、前駆物質を直接測定することはできない。またトリハロメタンの低減方法として、塩素処理を行う前に前駆物質を除去する手法が効果的であるため、トリハロメタン生成能はその除去効果の評価手法として、広く利用されている。
12 生物
水道の場合、水源から給水栓水に至る水中に懸濁している微少な植物及び動物を指し、魚類など大型の生物は含まない。
試験結果は、水源の状況の監視、適切で効率のよい浄水処理方法の選択、生物障害予防及び対策に利用する。
13 アルカリ度
水中に含まれている炭酸水素塩、水酸化物および炭酸塩などを中和するのに必要な酸の量に相当するアルカリ量を炭酸カルシウム(CaCO3) のmg/Lで表したもので、酸消費量ともいう。中和点のpH値によりP−アルカリ度(フェノールフタレイン変色点pH8.3)とM−アルカリ度(メチルレッド混合指示薬変色点pH約4.8)に区別される。M−アルカリ度は総アルカリ度とも呼ばれる。
構成成分により炭酸水素塩によるものを炭酸水素アルカリ度(重炭酸アルカリ度)、水酸化物によるものを水酸基アルカリ度、炭酸塩によるものを炭酸アルカリ度という。
14 溶存酸素
水中に溶解している酸素のこと。DO ともいう。供給源の多くは大気であるが、藻類の光合成により発生した酸素のこともある。酸素の溶解度は気圧、水温、塩分などによって影響される。有機物で汚濁した水中では、生物化学的酸化により酸素が消費されるため溶存酸素が減少する。
水温が急激に上昇したり藻類が著しく繁殖した場合には、過飽和となることもある。
15 硫酸イオン
水中に溶解している硫酸塩中の硫酸分のこと。例えば硫酸カルシウムのような硫酸塩は水に溶けるとカルシウムイオンと硫酸イオンになる。硫酸塩は地殻中に広く分布しており、これが溶けて硫酸イオンとなるため、自然水中には常に多少の硫酸イオンが含まれている。これは主に地質に起因するが、化学肥料、硫黄泉、鉱山排水、工場排水、屎尿を含む下水排水および海水などの混入により増加することもある。
また、浄水処理において凝集剤に硫酸アルミニウムを使用すると若干増加する。硫酸イオンが多量に含まれると水の味が悪くなり、鉄管などの腐食を促進する傾向がある。
16 溶性ケイ酸
自然水中のケイ酸の形態は非常に複雑で、イオン、コロイドおよび分子状のものやケイ酸塩または生物体に含まれるものなど各種ある。測定上から大別して、溶性ケイ酸と総ケイ酸があり、溶性ケイ酸は水中における溶解性のケイ酸のことである。
分析法は、ろ過した試料水に酸性でモリブデン酸アンモニウムを加えるとモリブデン黄の帯緑色となるので、これを吸光光度法により波長410nm 付近の吸光度を測定する方法である。
http://www.jwwa.or.jp/mizu/pdf/2007-kaisetsu.pdf
Posted by 大阪水・土壌研究会員 at 12:57│Comments(0)
│水は命の母